解説記事2025年03月17日 解説 グループ通算制度についての一考察(2025年3月17日号・№1067) —個別的否認規定の不当性要件を考える—
解説
グループ通算制度についての一考察
—個別的否認規定の不当性要件を考える—
弁護士・元国税審判官 向笠太郎(脚注1)
1 はじめに
グループ通算制度は、令和2年度税制改正(令和2年法律第8号)で連結納税制度に代わって導入され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。国税庁の公表資料によると、令和5年度の通算法人数は1万8937法人(親法人が2049法人、子法人が1万6888法人)とのことである(脚注2)。
ごく簡単に述べれば、グループ通算制度(法人税法64条の5以下)は、完全支配関係(脚注3)にある企業グループ内で、損益通算等は行いつつ申告自体は各法人が個々に行うというものである。また、制度の簡素化という観点から、後発的に修更正(修正申告又は更正・決定)事由が生じた場合は原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みが採用されている(図表1参照)。さらに、一連の行為の中で損益通算等の要素を利用した多様な租税回避行為が想定されることから、包括的な租税回避行為防止規定として、同法132条の3が規定されている(脚注4)。
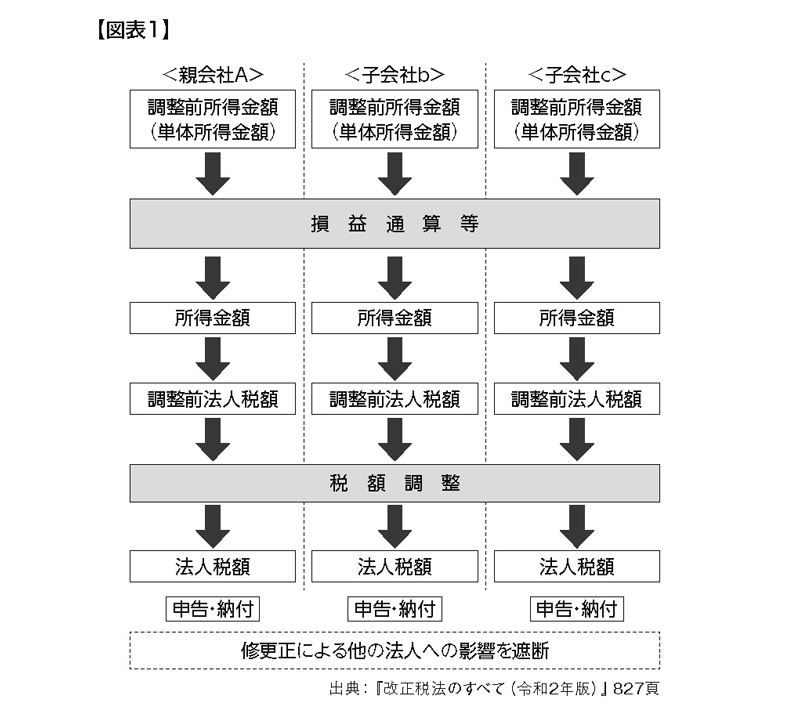
もっとも、グループ通算制度では、包括的否認規定に加えて個別的否認規定もあり(法人税法65条の5第8項)、後述のとおり、不当性要件を具備すれば遮断措置の適用が排除される。では、この個別的否認規定の不当性要件は、包括的否認規定のそれと同様に解してよいのだろうか。
管見の限りでは、本日(令和7年3月)現在、この個別的否認規定が争われた裁判例や裁決例は存在せず、また、この点について詳しく検討した論文等も見当たらない。しかし、グループ通算制度の特徴の1つである遮断措置を排除する効果を有する個別的否認規定の不当性要件について検討しておくのは、意義があることと考える。
そこで、本稿では、以上の点について筆者なりの考察を行ってみたい。
2 検討の前提−グループ通算制度における損益通算等について
本稿の検討のためには、グループ通算制度の損益通算等についての理解が重要であるから、まずは、その点について説明を行う。
(1)損益通算等について(脚注5)
ア 損益通算
(ア)所得がある通算法人の場合
通算法人(A社)の所得事業年度(脚注6)終了の日(基準日)において、その通算法人(A社)との間に通算完全支配関係(脚注7)がある他の通算法人(B社)の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(脚注8)が生ずる場合、その通算法人(A社)の所得事業年度の通算対象欠損金額は、その所得事業年度の損金の額に算入される(法人税法64条の5第1項)。つまり、通算グループ内の欠損法人の欠損金額の合計額が、所得法人の所得金額の比で配分され、その配分された通算対象欠損金額が所得法人の損金の額に算入されることとなる。
なお、通算対象欠損金額とは、以下の算式により計算されたものをいう(同条2項)。
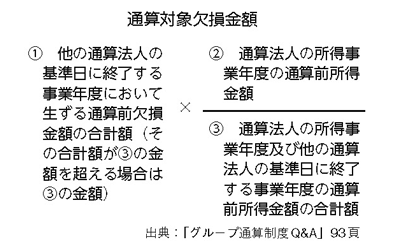
(イ)欠損金がある通算法人の場合
通算法人(A社)の欠損事業年度(脚注9)終了の日(基準日)において、その通算法人(A社)との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(B社)の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生じる場合、その通算法人(A社)の欠損事業年度の通算対象所得金額は、その欠損事業年度の益金の額に算入される(法人税法64条の5第3項)。つまり、上記(ア)で所得法人において損金算入された金額の合計額と同額の所得の金額が、欠損法人の欠損金額の比で各欠損法人に配分され、その配分された通算対象所得金額が欠損法人の益金の額に算入されることとなる。
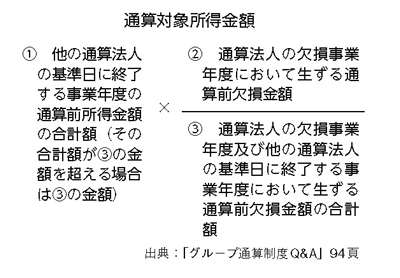
なお、通算対象所得金額とは、上記の算式により計算されたものをいう(同条4項)。
(ウ)具体的な計算方法
以上で述べたことについて、「グループ通算制度Q&A」94頁以下を参考に、具体例を用いて説明したい。
a 通算前所得金額の合計額が通算前欠損金額の合計額より多い場合
完全支配関係にあるP社(親法人)、S1社(子法人)、S2社(子法人)及びS3社(子法人)において、以下のとおりであったとする。
P 社: 500(所得)
S1社: 100(所得)
S2社: ▲ 50(欠損)
S3社: ▲250(欠損)
このように、通算前所得金額の合計額(600)が通算前欠損金額の合計額(▲300)よりも多い場合、損益通算は図表2のように行われる。
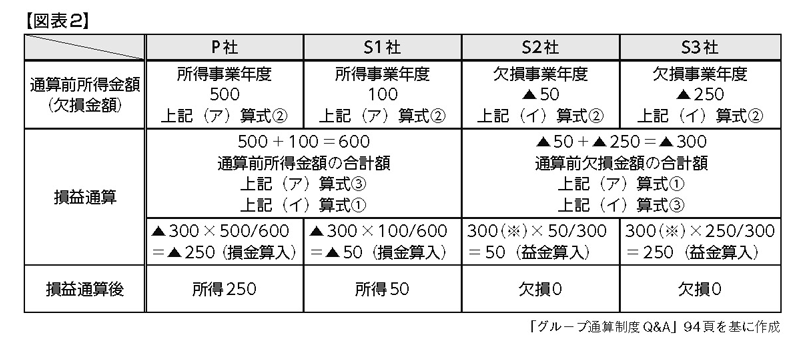
S2社及びS3社において、「他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額」が300となっているのは(図表2の「※」部分)、通算前所得金額の合計額600が通算前欠損金額▲300を超えることから、通算前欠損金額の合計額▲300が上限となるためである(法人税法64条の5第4項1号括弧書)。
b 通算前欠損金額の合計額が通算前所得金額の合計額より多い場合
上記aと異なり、完全支配関係にあるP社(親法人)、S1社(子法人)、S2社(子法人)及びS3社(子法人)において、以下のとおりであったとする。
P 社: 250(所得)
S1社: 50(所得)
S2社: ▲500(欠損)
S3社: ▲100(欠損)
このように、通算前欠損金額の合計額(▲600)が通算前所得金額の合計額(300)よりも多い場合、損益通算は図表3のように行われる。
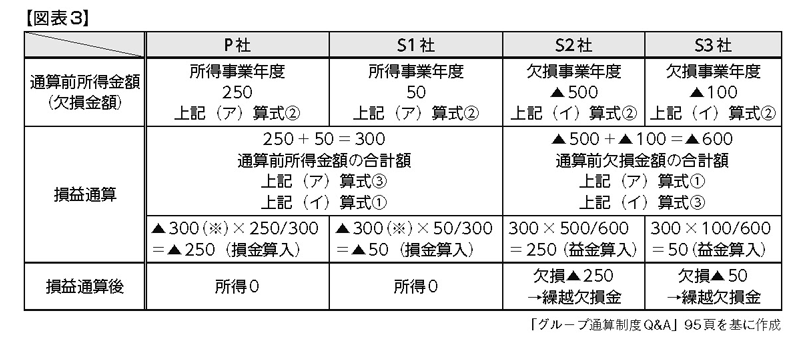
P社及びS1社において、「他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前欠損金額の合計額」が▲300となっているのは(図表3の「※」部分)、通算前欠損金額の合計額▲600が通算前所得金額300を超えることから、通算前所得金額の合計額300が上限となるためである(法人税法64条の5第2項1号括弧書)。
(エ)損益通算の遮断措置
上記(ア)の通算法人の所得事業年度若しくは他の通算法人の基準日に終了する事業年度又は上記(イ)の通算法人の欠損事業年度若しくは他の通算法人の基準日に終了する事業年度(通算事業年度)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当初申告額と異なるときは、それぞれの当初申告額がその通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなされる(法人税法64条の5第5項)。
これにより、原則として、修更正事由が生じた通算法人以外の通算法人への影響が遮断され、その修更正事由が生じた通算法人の申告のみが是正されることとなる。連結納税制度においては、修更正事由が生じた場合に時間がかかり過ぎるという指摘があったことから(脚注10)、グループ通算制度下でこのような遮断措置が採用され、事務負担の軽減が図られることとなったのである。
イ 欠損金の通算
上記アでは、各通算法人において繰越欠損金がない場合を前提としていたが、通算法人が繰越欠損金額を有する場合、以下のように一定の調整を行う必要がある(法人税法64条の7、57条1項)(脚注11)。
(ア)欠損金の繰越控除額の計算
a 通算法人の適用事業年度(脚注12)開始の日前10年以内に開始した各事業年度に生じた欠損金額は、特定欠損金額(脚注13)と非特定欠損金額(脚注14)の合計額とされる(法人税法64条の7第1項2号)。
非特定欠損金額は、通算グループ全体の非特定欠損金額の合計額が、過年度において損金算入された欠損金額及び特定欠損金額を控除した後の損金算入限度額の比で配分される(同項3号ロ)。
b 各通算法人の繰越控除額は、それぞれ以下の金額が限度とされる(法人税法64条の7第1項3号)。
① 特定欠損金額
各通算法人の損金算入限度額の合計額を各通算法人の特定欠損金額のうち欠損控除前所得金額(脚注15)に達するまでの金額の比で配分した金額
② 非特定欠損金額
各通算法人の特定欠損金額の繰越控除後の損金算入限度額の合計額を各通算法人の上記アによる配分後の非特定欠損金額の比で配分した金額
(イ)欠損金の通算の遮断措置
欠損金の通算についても、損益通算の場合と同様に遮断措置がある。
a まず、上記(ア)の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度(以下「他の事業年度」という。)の損金算入限度額又は過年度の欠損金額が当初申告額と異なるときは、それらの当初申告額が当該他の事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額等とみなされる(法人税法64条の7第4項)。
これは、通算グループ内の他の通算法人に修更正事由が生じた場合、欠損金の通算に用いる金額を当初申告額に固定することで、その通算法人への影響を遮断するものである。
b また、上記(ア)の場合において、通算法人の適用事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額等が当初申告額と異なるときは、欠損金額及び損金算入限度額で当初の期限内申告において通算グループ内で他の通算法人との間で配分し又は配分された金額を固定する調整等をした上で、その通算法人のみで欠損金額の損金算入額等が再計算される(法人税法64条の7第5項から第7項)。
ウ 遮断措置の不適用
以上のとおり、グループ通算制度には遮断措置があるが、税務署長は、遮断の規定(法人税法64条の5第8項及び法人税法施行令131条の7第2項)(脚注16)を適用したならば以下の(ア)、(イ)の事実その他の事実(脚注17)が生じ、通算法人又は他の通算法人の事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認める場合は、当該事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、損益通算の遮断措置の規定(法人税法64条の5第5項)を適用しないことができる(同条第8項、64条の7第8項2号)。つまり、この場合、損益通算及び欠損金の通算の規定の計算に用いる所得の金額及び欠損金額を当初申告額に固定せずに、通算グループ全体で再計算が可能、ということである(脚注18)。
(ア)その通算法人が当該各事業年度前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(欠損金の通算における遮断措置(法人税法64条の7第4項)の規定を適用したならば当該各事業年度において同法57条1項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
(イ)その通算法人又は他の通算法人のうちに通算承認の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、その通算法人又は他の通算法人に法人税法57条1項の規定の適用がある欠損金額があること。
3 個別的否認規定の不当性要件について
(1)問題の所在
このように、法人税法64条の5第8項は、「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」場合、すなわち、不当性要件を満たす場合には、遮断措置の規定を適用しない旨規定している。上記1のとおり、グループ通算制度に係る包括的な行為計算否認規定は同法132条の3が別に規定しており、同法64条の5第8項は、個別的否認規定である。
では、この個別的否認規定の不当性要件はどのように解すべきか。
(2)不当性要件の意味
『改正税法のすべて(令和2年版)』834頁には、法人税法64条の5第8項は、報告書(脚注19)に記載された「『例外的に、欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を持たせるためにあえて誤った当初申告を行うなど、法人税の負担を不当に減少させることとなると認められるときは、職権更正において、プロラタ方式で全体を再計算することができるようにする必要がある。』との考え方に沿ったもの」とある。また、同項1号が「欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱する」を、同項2号が「離脱法人に欠損金を持たせる」場面とされている。
この内容からすると、「欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を持たせるためにあえて誤った当初申告を行う」ことが、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるとき」の具体例であるといえる。そして、この具体例からすれば、同法64条の5第8項の不当性要件は、遮断措置を濫用している場合(脚注20)を意味すると解される。
それでは、このように解した場合、遮断措置を濫用しているかどうかの判断基準はどのように考えるべきか。
(3)濫用の判断基準について
ア この点、グループ通算制度に係る包括的否認規定(法人税法132条の3)における不当性要件が、組織再編成に係る包括的否認規定(同法132条の2)における不当性要件の判断基準と同様の濫用基準であることを前提に、同法64条の5第8項の不当性要件も濫用基準であるという考え方があり得よう(脚注21)。
すなわち、同法132条の2は、組織再編成を利用した租税回避行為には多様なものが考えられることから、適正な課税が行えるようにするために、個別的否認規定に加えて導入されたものである(脚注22)。一方、同法132条の3は、元々は、連結納税制度の仕組みを利用したり、あるいは、連結納税制度と単体納税制度の違いを利用した租税回避行為についても多様なものが考えられることから、適正な課税が行えるようにするために導入されたものである(脚注23)。その後、グループ通算制度導入に際し、連結納税制度の場合と同様の趣旨で維持されている(脚注24)。
このようなことからして、同法132条の2の立法趣旨と同法132条の3の立法趣旨は同じということができ、そうであれば、同法132条の2の不当性要件の判断基準として濫用基準(後記イ参照)が採用されているのであれば、同法132条の3の不当性要件の判断基準も濫用基準を採用するのがよいと考えられる。
そして、その上で、法解釈の統一性を重視すると、同法132条の3の不当性要件について濫用基準を採用する以上、グループ通算制度に係る個別的否認規定である同法64条の5第8項の不当性要件についても濫用基準を採用するのが好ましい、となると思われる。
イ しかし、法人税法64条の5第8項が想定する「濫用」と、濫用基準にいう「濫用」は同じといえるだろうか。
すなわち、ヤフー事件(最判平28.2.29民集70巻2号242頁)では、同法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、「法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」とされている。
ヤフー事件において定立された基準は「濫用基準」といわれるところ、同事件では、濫用の有無は、不自然性や不合理性を考慮した上で、「当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様」であったかを判断するとされている。この不自然性、不合理性という考慮要素からすれば、ヤフー事件では、濫用を、程度を超えた利用といった内容で捉えているように思われる(脚注25)。
一方、法人税法64条の5第8項の想定される適用場面(上記(2))を改めて見ると、遮断措置を悪用に近い形で利用している場合といえる。
そうすると、ヤフー事件にいう「濫用」と法人税法64条の5第8項が想定している「濫用」では、その内容が異なっていると考えられる(脚注26)。そして、このように考えると、同法132条の2で採用された濫用基準を同法64条の5第8項の基準として採用すべき必然性はないように思われる(脚注27)し、むしろ、同項に濫用基準を持ち込むのは適切ではないといえよう。
ウ 法人税法64条の5第8項の不当性要件について考える場合、どちらかといえば、りそな外税控除事件(最判平17.12.19民集59巻10号2964頁)が参考になるのではないだろうか。同事件では、法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条が規定する外国税額控除の適用が争われたところ、最高裁は、納税者が行った取引について、「我が国の外国税額控除制度をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ、我が国において納付されるべき法人税額を減少させた上、この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が享受するために、取引自体によっては外国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本件取引をあえて行うというものであって、我が国ひいては我が国の納税者の負担の下に取引関係者の利益を図るものというほかない。」「そうすると、本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用するものであり、さらには、税負担の公平を著しく害するものとして許されないというべきである。」と判示している。
りそな外税控除事件では、包括的否認規定がない状況下で、外国税額控除余裕枠の流用について、上記のとおり「我が国の外国税額控除制度をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ」ることが同制度の濫用に当たるとして、法人税法69条の適用を認めなかったのである。
ヤフー事件の調査官解説には、「制度の濫用」の意味内容についてはりそな外税控除事件が参考になる、とある(脚注28)。しかし、ヤフー事件が「本来の趣旨及び目的から逸脱する態様」であるかを問題とするのに対し、りそな外税控除事件は、「本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様」であるかを問題にしている(下線部筆者)。この「著しく」という表現をあえて入れていることや、りそな外税控除事件においては「税負担の公平を著しく害するものとして許されない」というヤフー事件には見られない厳しい表現があることからすれば、りそな外税控除事件にいう「濫用」は、外国税額控除制度の悪用又は悪用に近い場合を意味していると解される(脚注29)。
そうすると、りそな外税控除事件は、個別的な制度について、悪用に近い形での濫用がある場合にはその制度の適用を排除する場合があることを認めたといえる。他方、法人税法64条の5第8項は、悪用に近い形で遮断措置の濫用がある場合には、遮断措置の適用を排除することを明文化したとみることができるので、同項の不当性要件(濫用該当性の判断基準)は、りそな外税控除事件における濫用の判断を参考に、遮断措置をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れる場合、と解するのがよいと考える。
エ もっとも、このように考えると、同一文言について統一的解釈ができなくなる、といった問題はある。しかし、仮に法人税法64条の5第8項の不当性要件も濫用基準であると解すると、その適用場面は、同法132条の3の適用場面とほぼ重なり、同法64条の5第8項を独自に設けた意義が失われてしまいかねない。「欠損金の繰越期間に関する制限を人為的に回避するなど」の「租税回避行為を防止するための規定は個別に設ける必要がある」として同項が創設された趣旨(脚注30)を踏まえれば、やはり、同項には個別的否認規定としての独自の意味があると考えるべきであり、同項の存在意義が失われてしまいかねない解釈は適切ではないように思われる。
このことからしても、同項の不当性要件は、同法132条の3のそれとは異なると解すべきである。
4 具体例に基づく要件事実的検討
以上を踏まえ、法人税法64条の5第8項の不当性要件が争われた場合に、誰が、どのようなことを主張立証すべきであるかについて、以下の事例を用いつつ簡単に検討したい。
(1)事例
グループ通算制度の適用を受ける完全親会社X社並びに完全子会社Y社及びZ社が、令和7年3月期におけるX社の通算前所得金額が1000万円、Y社の通算前所得金額が500万円、Z社の通算前欠損金額が600万円であること、同月期に期限が到来するX社の特定欠損金が600万円あること及び同月期に期限が到来する非特定欠損金が300万円あるとして、図表4のとおり損益通算等をした上で、それぞれ所得0円で法人税(以下「本件法人税」という。)の確定申告(以下「本件各当初申告」といい、X社に係るものは「本件X社当初申告」という。)を行った。
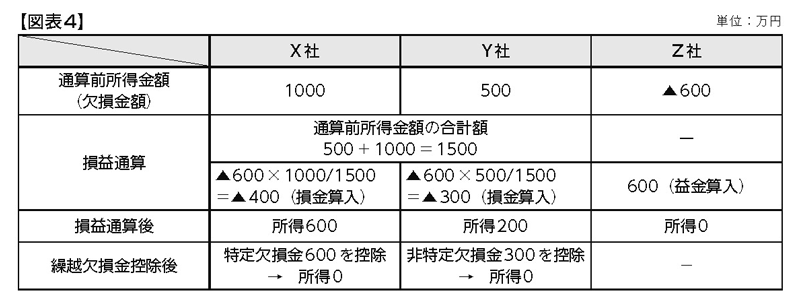
その後、X社は、令和7年●月●日、本件X社当初申告について、通算前所得金額が0円であったとして、通算前所得金額を1000万円減額する更正の請求を行った(以下「本件更正の請求」という。)。なお、Y社及びZ社は、遮断措置(法人税法64条の5第5項)が適用されることを前提に、特段の対応をしていない。
これに対してW税務署長は、本件更正の請求のとおりに減額更正を行い、X社の通算前所得金額1000万円を0円として再計算すると、令和7年3月期に期限切れとなるはずだったX社の特定欠損金600万円が非特定欠損金として生まれ変わることになるので、グループ全体での再計算が必要であると判断した。そのため、W税務署長は、令和7年■月■日、本件更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った(以下「本件通知処分」という。)。
また、W税務署長は、令和8年▲月▲日、X社、Y社及びZ社に対し、法人税法64条の5第8項1号に基づきグループ全体で再計算をすると図表5のとおりになるとして、本件法人税の各更正処分(以下「本件各更正処分」といい、X社に係るものは「本件X社更正処分」という。)を行った。その結果、特定欠損金600万円及び非特定欠損金300万円は、いずれも、期限切れにより消失することとなった。
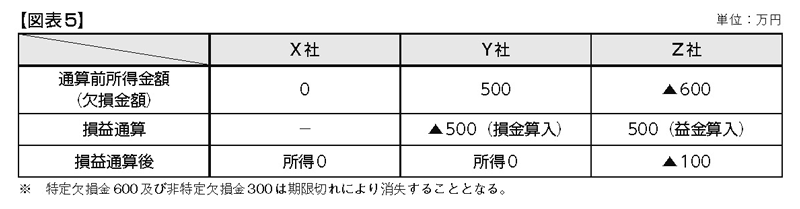
そこで、X社、Y社及びZ社は、それぞれ、国税不服審判所に対する審査請求(棄却裁決)を経て、国に対し、本件各更正処分の取消訴訟を提起した(以下では、X社に係る取消訴訟を検討する。)。
(2)検討
ア この事例は、財務省「説明資料〔連結納税制度〕平成31年4月18日(木)」(脚注31)7頁を参考に筆者が作成した架空のものである。
事例では、本件通知処分後に本件各更正処分がなされており、両処分の関係も問題となる。紙幅の関係上、詳細な検討は控えるが、本件通知処分は本件X社更正処分に吸収され、独立の取消訴訟の対象とはならないと考える(吸収説)(脚注32)。
イ 次に、課税処分は、国民の権利を侵害する侵害処分であることから、課税庁が、当該課税処分の正当な理由についての評価根拠事実について主張立証責任を負うと解すべきである(侵害処分・授益処分説)(脚注33)。そうすると、本件X社更正処分は、X社にとって典型的な侵害処分であるので、その手続上及び実体上の適法要件全てに該当する事実については、国が抗弁として立証責任を負うこととなる。
その結果、法人税法64条の5第8項の不当性要件を具備していることを基礎付ける事実、すなわち、遮断措置をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れることを基礎付ける事実についても、国側が主張立証すべき、となる。そして、同項1号に該当する事実が生じる場合であれば、欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱する目的があるためにあえて誤った当初申告を行っていること、となると解する。
したがって、上記事例の場合、国側は、X社が期限の切れてしまう特定欠損金600万円を非特定欠損金として生まれ変わらせるために、本件X社当初申告において通算前所得金額をあえて1000万円としていたことを主張立証すべきとなる。
ウ なお、X社は、本件X社当初申告で通算前所得金額を1000万円としたのは単なる計算ミスであったこと等を反論することが考えられるが、これは、国側の抗弁と両立しない事実である。そうすると、納税者が主張立証責任を負う再抗弁ではなく、国側の抗弁の積極否認になると考える(脚注34)。
5 終わりに
以上、法人税法64条の5第8項の不当性要件について、筆者なりの考察を加えてみた。グループ通算制度は、実務上の運用も、また、理論的な研究も、これから進んでいくものと思われるところ、本稿がその一助となるのであれば望外の喜びである。
脚注
1 本稿執筆時に、岡村勲弁護士の訃報に接した。筆者は、岡村弁護士が代表を務める法律事務所に在籍していた当時、幸いなことに岡村弁護士から多くのご指導を賜った。筆者が今日あるのも、ひとえに岡村弁護士のお陰である。この場を借りて深く感謝申し上げるとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
2 国税庁「令和5事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」(令和6年10月)
3 グループ通算制度における「完全支配関係」は、完全支配関係のうち法人税法64条の9第1項3号から10号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして法人税法施行令131条の11第2項で定める関係に限られる。なお、適用対象となる法人については、法人税法64条の9第1項及び法人税法施行令131条の11第1項参照
4 内藤景一朗ほか『改正税法のすべて(令和2年版)』(大蔵財務協会、2020年)(以下『改正税法のすべて(令和2年版)』という。)1001頁
5 グループ通算制度についての解説は、国税庁「グループ通算制度の概要」(令和2年4月)及び国税庁「グループ通算制度に関するQ&A(令和2年6月(令和2年8月・令和3年6月・令和4年7月改訂))」(以下「グループ通算制度Q&A」という。)によるところが大きい。その点につきご承知おきいただきたい。
6 通算前所得金額の生ずる事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。なお、「通算前所得金額」とは、欠損金の控除及び損益通算前の所得の金額をいう。
7 通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(法人税法施行令131条の11第2項で定める関係に限る。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう(法人税法2条12号の7の7)。
8 損益通算前の欠損金額をいう。
9 通算前欠損金額の生ずる事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。
10 『改正税法のすべて(令和2年版)』821頁以下
11 欠損金の通算についてのより詳しい説明や具体的な計算方法等については、「グループ通算制度Q&A」105頁以下を参照されたい。
12 法人税法57条1項の適用を受ける事業年度をいい、その通算法人が通算子法人である場合には、その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。
13 通算法人の最初通算事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額等をいう(法人税法67条の4第2項)。要するに、通算制度開始前や通算グループ加入前に生じた繰越欠損金等が特定欠損金額であり、これは、その通算法人の所得の金額のみから控除できる。
14 欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額をいう(法人税法64条の7第1項3号ロ)。典型的には、グループ通算制度適用後に通算グループで生じた欠損金が挙げられる。
15 法人税法57条1項本文を適用せず、かつ同法59条3項、4項及び62条の5第5項を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得から一定の金額を控除した金額をいう(同法64条の7第1項3号イ1つ目の括弧書)。
16 遮断の規定としては、例えば以下のようなものがある。
・損益通算における遮断措置(法人税法64条の5第5項)
・欠損金の通算における遮断措置(同法64条の7第4項から第7項まで)
・外国税額控除における遮断措置(同法69条15項又は19項)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における遮断措置(租税特別措置法42条の4第8項4号から第7号まで、第12項又は14項(これらを18項で準用する場合を含む。))
17 「その他の事実」とあることから分かるように、本文に掲げた2つ(法人税法64条の5第8項各号)は例示である。したがって、これら以外の事実が生じた場合でも、同項が適用される可能性がある。
18 『改正税法のすべて(令和2年版)』833頁、884頁。なお、この場合のほか、通算グループ全体では所得金額がないにもかかわらず当初申告額に固定することで所得金額が発生する法人がないようにする、という観点からグループ全体で再計算をする旨の規定もある(法人税法64条の5第6項、64条の7第8項1号。『改正税法のすべて(令和2年版)』832頁、884頁)。
19 令和元年8月27日の税制調査会総会に提出された「連結納税制度の見直しについて」と題する報告書を指す(『改正税法のすべて(令和2年版)』822頁)。
20 「濫用」とは、みだりに用いることである(新村出編『広辞苑〔第7版〕』(岩波書店、2018年)3067頁)。
21 小塚真啓「連結納税制度の改革を評価する」(税研2020年5月号(211号))50頁の注(13)では、ヤフー事件で示された濫用基準が法人税法64条の5第8項の「適用基準として採用される可能性が高い。」という指摘がある。ただし、その理由は特に記載されていない。
22 中尾睦ほか『改正税法のすべて(平成13年版)』(大蔵財務協会、2001年)244頁
23 柴崎澄哉ほか『改正税法のすべて(平成14年版)』(大蔵財務協会、2002年)370頁
24 前掲注4
25 渡辺徹也「法人税法132条の2にいう不当性要件とヤフー事件最高裁判決〔下〕」(旬刊商事法務2113号24頁及び29頁の(注56)、岡村忠生「租税回避否認への柔らかな対応−ヤフー事件最高裁判決−」WLJ判例コラム77号)参照
26 「濫用」の通常の意味(注20)からすれば、制度を悪用に近い形で利用する場合も、程度を超えて利用する場合も、いずれも「濫用」には当たるといえよう。
27 なお、法人税法132条1項の不当性要件の判断基準については、経済的合理性基準と呼ばれるものが採用されている(ユニバーサルミュージック事件(最判令4.4.21民集76巻4号480頁))。この経済的合理性基準と濫用基準に違いがあるのかどうかについては、評者によっても見解が分かれるところであるが、いずれにしろ、包括的否認規定であっても、不当性要件について全く同じ解釈が採用されているわけではないから、個別的否認規定である法人税法64条の5第8項の不当性要件について同じ解釈をすべき、という理由はないように思われる。
28 法曹会編『最高裁判所判例解説民事平成28年度』110頁〔徳地淳=林史高〕
29 岡村・前掲注25
30 前掲注4
31 税制調査会の第3回連結納税制度に関する専門家会合(平成31年4月18日開催)に提出された資料
32 伊藤滋夫=岩崎政明=河村浩『要件事実で構成する所得税法』(中央経済社、2019年)233頁〔河村〕及びそこに挙がっている文献参照
33 詳細は、伊藤滋夫=岩崎政明編『租税訴訟における要件事実論の展開』(青林書院、2016年)19頁以下〔伊藤〕参照
34 抗弁と(積極)否認の違いについては、例えば、河村浩『行政事件における要件事実と訴訟実務−実務の正当化根拠を求めて』(中央経済社、2021年)11頁参照
向笠太郎 (むかさ たろう)
2009年上智大学法科大学院修了。10年弁護士登録。18年から22年まで東京国税不服審判所において任期付公務員(国税審判官)として勤務し、現在は、弁護士法人日本クレアス法律事務所所属。最近の著書、論文として、『対話でわかる租税「法律家」入門』(共著、中央経済社、2024年)、『免税事業者との取引条件見直しの実務』(共著、中央経済社、2024年)、「実質所得者課税原則に基づく判断の結果納税者が勝訴した事例」本誌1002号13頁(2023年)、「租税分野における私法関係(契約関係)の重要性−南御堂参道事件を題材に−」本誌1026号12頁(2024年)等がある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























