解説記事2025年03月31日 巻頭特集 トランプ第2次政権の国際課税改革への影響と今後の展望(2025年3月31日号・№1068)
巻頭特集
OECD租税政策・税務行政センター 元局長パスカル・サンタマン氏に聞く
トランプ第2次政権の国際課税改革への影響と今後の展望
OECDが主導してきた国際課税のルール作りとそれを支えて来た国際協調が岐路に立っている。トランプ政権が大統領令により、OECD主導の国際課税改革の枠組みからの離脱に加え、米国企業に対するミニマムタックス課税を許容しないなどのメッセージを発する一方、国連では税の枠組み条約に関する検討が始まり、OECDに代わって国連が国際課税の主要なルール形成の場となる可能性も指摘されている。
そこで本誌では、OECDの租税政策・税務行政センター(CTPA=Centre for Tax Policy and Administration)の局長時代、BEPSプロジェクト、自動的情報交換、デジタル課税、包摂的枠組みの立ち上げ等、国際課税分野における歴史的な重要課題解決に多大な貢献を果たし、現在は世界的に有名な戦略コンサルティング会社 ブランズウィック・グループのパートナーを務めるパスカル・サンタマン氏に、トランプ政権の動き、第1・2の柱の行方、国連における議論がOECDの取組みに与える影響、税制に関する各国間の緊張が高まる中での企業の対処法、日本政府が果すべき役割、さらには経済のグローバル化の問題点まで、幅広いテーマについてお話をうかがった。(文中、敬称略)
トランプ政権
現時点ではトランプ政権の真の狙いは見えず
本誌:1月20日にトランプ政権が公表したGlobal Tax Dealに関する大統領令では、OECD主導の国際課税改革に対し、前政権が交わしたいかなる約束も米国議会での承認がない限りは米国内で効力を持たないとされています。サンタマンさんは、第1次トランプ政権時にOECD CTPA局長を務めていましたが、過去の経験を踏まえ、今回のトランプ政権の自国優先主義的な動きについてどのような印象をお持ちでしょうか。
サンタマン: まず、トランプ政権は1期目と2期目ではかなり違うということを申し上げたいと思います。大統領令の内容を見れば分かるように、今回のトランプ政権は税に対して高い関心を持っています。大統領令を就任初日に出したということは、政権発足前から準備が進められていたということです。
大統領令では、3つの点で非常に強い、強硬なメッセージが示されました。1点目は、米国はOECDとのディールから離脱するということ、2点目は、他国による米国企業に対するミニマムタックスの課税を許容しないということ、3点目は、もし各国がDST(デジタルサービス税)を導入するのであれば、貿易面で制裁を科すということです。そして、大統領令を出してから60日以内に、①米国との租税条約に違反する、あるいは域外適用的ないし米国企業がターゲットになるような外国の課税措置(可能性を含む)を特定し、②そのような措置に対応するために米国がとるべき保護的措置の選択肢を提言するためのレポートを公表すると言っています。
本誌:間もなく出て来るレポートのどのような点が注目されますでしょうか。
サンタマン:まず前提として、米国は第1・2の柱を国内で実施していません。そのような段階で米国はOECDとのディールから離脱すると言っていますが、米国が最終的に第2の柱で何を目指すのかが見えない点、また、DSTはダメだと言っていますが、では米国としては第1の柱で何を達成したいのかがはっきりしないという点が注目されます。
このように現在は非常に不確実性が高い状況となっていますが、これはトランプ氏の戦略の一環とも言えます。つまり、ひとまず爆弾を落としてみて皆を右往左往させる、それがトランプ氏の交渉のアプローチの一つだということです。したがって、先行きがどうなるかを判断するには時期尚早であり、まずは米国からの追加的な説明を注視する必要があります。私としては、2月下旬に南アフリカで開催されたG20の会合で米国の立場がより明確に説明されると思っていたのですが、そうはなりませんでした。4月下旬にワシントンDCで予定されているIMF・世界銀行の春季会合で、米国がもう少し明確な立場を説明するのではないかと予想しています。
第1の柱
第1の柱に関する「プロセス」の継続には各国のDST導入を抑止する効果
本誌: 第1の柱については多国間協定がいまだに合意に至らず、米国の反対もあり、検討が進展していない状況にあります。トランプ政権の4年間の下では、第1の柱・利益Aの進展は難しいでしょうか。第1の柱・利益Aが進展しない場合、各国でDSTを導入する動きが活発化するおそれがあります。今後どのような展開になると考えますか。
サンタマン: 最も利益率が高い大企業の利益を、課税権の問題として、より適切に配分できるように交渉していくというのが第1の柱の目的です。したがって、第1の柱の実施にあたっては、どうしても多国間協定が必要になってきます。これまで第1の柱は、DSTを含め各国が一方的な措置を取ることを回避するための「プロセス」として交渉が継続されてきました。米国以外の国は第1の柱のプロセスを生かしておきたいと考えています。
米国では、議会上院の3分の2の支持を得なければ多国間協定に比準することができませんが、もしトランプ政権が本当に真剣に第1の柱を“殺す”ということであるならば、このプロセスも“死ぬ”ことになります。そして、このプロセスが死んでしまうということは、米国以外の国が、DSTを含め一方的な措置を取らざるを得ない状況に追い込まれるということを意味します。それは当然、米国からの報復を招くでしょう。結果として、ネガティブな悪循環が始まってしまうことになります。
今回の大統領令を見ただけでは、米国がこの交渉の過程に関与し続けるのか、それとも関与することさえやめてしまうのか、はっきりとは分かりません。ただ、トランプ政権は様々な分野で極端なアプローチをとっているので、非常に厳しい対応を取ってくる可能性は排除できないでしょう。
第2の柱
第2の柱は維持される可能性が高い
本誌: ご指摘のあったGlobal Tax Dealに関する大統領令の対抗措置について、第2の柱のミニマム課税、とりわけUTPR(軽課税所得ルール)が租税条約に違反するとして、日本を含む各国のUTPRに対して対抗措置が実施される可能性はあると思いますか。
サンタマン:前提として、第1の柱と異なり、第2の柱については、米国の賛同がなくても、他国は実施可能です。大統領令を見る限り、第2の柱についてトランプ政権が具体的に何を解決しようとしているのかは分かりません。ただ、一つはっきりしたのは、ミニマム課税が導入されて以来ずっと共和党がとってきた立場と同様、トランプ政権も、たとえ米国国内において過少課税になっていたとしても、米国の多国籍企業の米国国内の利益に対して他国が課税するのは絶対に許さないということです。
もっとも、米国以外の低税率国において、米国企業の利益に対してUTPRが適用されることについてまで米国が反対の立場なのかどうかは、まだ分かりません。もし、トランプ政権が米国国内における米国企業の利益だけに関心を持っているということであるならば、一つの解決策があるかもしれないと思っています。つまり、OECDがUTPRセーフハーバーを延長するなどして、米国国内にある米国企業の利益に対しシェルターを作ってあげることです。
一方、トランプ政権が目指しているのが米国国内にある米国企業の利益だけではなく、例えばケイマンのような無税国における米国企業の利益にもシェルターを適用したいということになると、問題はもっと深刻になります。なぜなら、ルールそのものを変え、UTPRをなくすことが必要になるからです。UTPRがなければ、ミニマムタックス課税は成り立ち得ないわけですから。
いずれにせよ、米国がUTPRをすべてダメにしたいというのであれば、ルールを変える必要性が出てきます。この場合、欧州ではEU指令を変える必要が出てきます。しかし、EUが指令を変えるということになると手続き上加盟国の全会一致での賛成が必要になりますので、EUがそれに合意するはずがないと思います。EUが指令を変えなければ、結果として第2の柱は生き残ることになります。最初のオプション、すなわち米国企業の米国国内の利益を守るというオプションであれば、米国が米国企業に係る法人税率を大きく引き下げて米国自体がタックスヘイブンになるということでない限り、UTPRセーフハーバーの延長などにより対応できると思います。第2の柱を巡り今後緊張が高まるのは間違いありませんが、たとえ緊張が高まったとしても、第2の柱は維持されるだろうというのが私の見通しです。
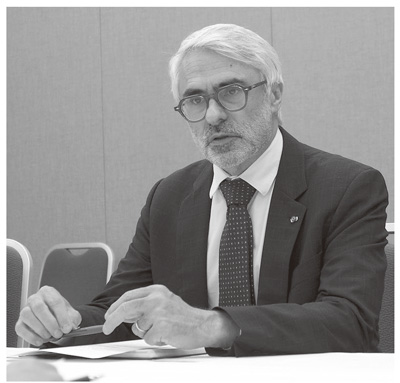
OECD
「有志連合 対 米国」という構図になるおそれも
本誌:米国のトランプ政権の動きにOECDはどのように対応し、国際課税について検討を進めていくべきでしょうか。
サンタマン:OECDの対応については、「OECD事務局」と「OECD加盟国」を切り分けて考える必要があります。事務局ができることには当然ながら限界があります。なぜなら、事務局はあくまでも加盟各国に従うという立場にあるからです。加盟国の中の大国である米国が止めろと言っている中で、事務局がイニシアチブを取ることはできません。したがって、OECD事務局の私のかつての同僚たちは、今後国際的な議論を円滑に進めることができるよう、様々なサポートに徹するということになります。
一方、加盟国の反応は今後米国がどれくらい広範な“戦争”を仕掛けてくるかということによって決まってくると思います。つまり、米国が第2の柱そのものを“殺したい”と思っているのか、それとも米国国内の米国企業に対する課税に対してセーフハーバーを確保したいと思っているだけなのか、それによって加盟国の反応は変わってくるだろうということです。
今後の方向性としては2つのパターンが考えられると思います。1つ目は、建設的な議論を通じて共通のルール、国際的な協力、協調を維持していくということです。2つ目は、もっと対立的な状況に陥ってしまうということです。つまり、米国が真に目指すところが「破壊する」ことにあり、代替的な解決策にも全く応じようとしないということであれば、日本も含め米国以外の国々もより強い、強硬な立場をとっていくしかなくなってしまい、各国間の力と力が正面から衝突をするという状況になります。そうなった場合に、有志連合対米国という構図になるのか、それとも、米国も含め国際的に建設的な議論が進んでいくのか、これは今後数週間で明らかになるであろう米国のポジションがはっきりしてからでないと分かりません。
本誌:現在の状況に日本はどのように関与していくべきでしょうか。
サンタマン:日本政府は適切な対応をしてきていると思います。直近のG20でも、日本は米国の動きを受けて、国際協調の維持を積極的に訴えかけています。
一方で、米国の真の狙いは何なのか、どのようなアプローチを考えているのかを探るのも日本の役割です。日本は米国との間に特別な関係がありますので、米国が本当は何を目指しているのか理解し得る立場にある国なのではないかと思います。
国 連
国連がOECDに取って代わることはない
本誌:国連でも税の枠組み条約に関する検討が行われています。今後は、OECDに代わって、国連が国際課税の主要なルール形成の場となる可能性は考えられますか。
サンタマン:国連は20年間にわたって国際課税の議論への関与を強めようとしてきましたが、やっとここに来てその努力が日の目を見つつあります。一方で、G7諸国、特に欧州諸国とアフリカとの間には大きな意見の相違が生じています。では国連がOECDに取って代われるかと言えば、答えはNoです。なぜなら、OECDの意思決定はコンセンサス方式であるのに対して、国連は多数決によって意思決定を行う機関であるからです。このため、国連は、各国がそれぞれ意見表明を行う場ではありますが、それ以上のものではありません。租税は国家主権に直結するので、こうしたやり方で国際課税に関するルール形成はできません。
しかしながら、国連における国際課税の議論は現実のものとなっていますし、この議論は今後も続いていくでしょう。もしかしたら、国連が「マジョリティの国々はこう思っている」ということを表明する場になるかもしれませんし、OECDの取組みとは異なる、あるいはそれに代わり得る様々な規定を国連が出してくるということもあり得ますが、国連において全会一致がなければ、直接的に国際課税の分野にインパクトを及ぼす可能性は低いでしょう。ただ、長期的には各国間での議論が国連の場において進んでいくことはあり得ますので、議論の内容には各国政府、各国経済界ともに注目していく必要がありますし、国連における議論を無視することはできない以上、日本政府もこれまで以上に、しっかりと議論に関わっていくことが重要です。
本誌:途上国が国連の議論を主導する一方で、先進国の間でも対応に差異が生じているように見受けられますが、特にEUはどのように対応しようとしているとお考えですか。
サンタマン:途上国もそうですし、先進国もここにきてフラストレーションが溜まってきています。特にアフリカ諸国とEUの間には大きな対立が生まれています。そして、米国が議論から離脱してしまいました。こうした中、各国ができることとしては、米国以外の国々で連携の道を探るということです。実際に連携が実現するかどうかは分かりませんが、少なくとも今よりも敵対的な姿勢を弱めてくれればと願っています。
企業のリスク
企業には税制面のみならず貿易面での不確実性も
本誌:関税の問題も含め、税制に関する議論を巡り各国間で緊張が高まる中で、企業が認識しておくべきリスクと、それに対処する方策についてお考えをお聞かせください。
サンタマン:まず挙げられるのは、15年間かけて築き上げてきた国際課税における各国間の非常に強い協力、国際協調がサバイブするのか(生き残るのか)どうかということです。税の分野における国際協力は各国にとって共通の利益となってきました。しかし、米国がそこから離脱するとの発言を繰り返していることに加え、地政学的な分断、相互不信、そして関税戦争と言われる環境の中でサバイブし得るのかが不透明となり、それは企業にとってもリスクとなっています。税制面のみならず、貿易面での不確実性もにらみながら、しっかりと情報を集め、分析し、状況をモニタリングした上で、万が一の偶発事態に対する備えを怠らないことが、日本企業も含めすべての国の企業に求められていると思います。
本誌:企業には具体的にどのような備えが必要になるとお考えでしょうか。
サンタマン:非常に不確実性が高い状況ですが、想定され得るあらゆるリスクに備え、準備しておく必要があります。具体的には、シナリオ・プランニングを行い、貿易面に関して言えば、バリューチェーンはどうなっているのか、代替的な調達先はあるのかなど、自社が置かれた状況をいま一度棚卸しして、場合によっては見直す必要があると思います。
税制面では、第1・2の柱のそれぞれについて、米国がどこまでの対応を求めるのか、それに対して各国がどのような対抗措置を取るのか、さらに米国の報復はどうなるのか、といったシナリオを立てて、日本企業にどのような影響が出てくるのかをシミュレーションした上で、取り得るあらゆるアクションを考えておく必要があります。
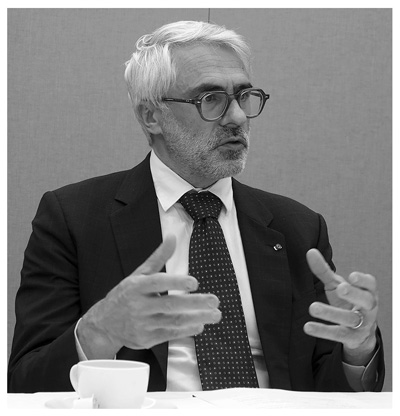
日本政府の役割
“大人”として日本が議論のファシリテーターに
本誌:現在のような状況の中で、日本政府はどのような役割を果していくべきでしょうか。
サンタマン:日本政府は、これまで国際課税に関する国際的な合意形成において、大きな役割を果たしてきました。
極めて難しい環境ですが、引き続き、G7、OECDという議論の場において、議論のファシリテーターとしての役割を果たし、円滑な議論が行われるように力を尽くすことではないでしょうか。米国が税の分野にどのような戦争を仕掛けようとしているのか、妥協の余地はあるのか、解決策が見つかるのかはまだ見えませんが、“大人”として日本が議論をまとめながら、ルールの健全性、ルールの完全性を担保するための議論を重ね、さらにあり得る妥協策を探っていくという役割が日本政府に期待されると思います。
グローバル化
グローバル化にも一定の規制やルールが必要
本誌:現在の国際課税を巡る混乱の根本的な原因は経済のグローバル化にあるとの指摘もあります。
サンタマン:もちろんグローバル化には様々な良い面もありますが、一方で、グローバル化の帰結として、中産階級の不信感というのが非常に高まってしまったということがあります。“勝者総取り”と言われる富の集中により、一握りの個人や企業が富を独占した結果、格差が広がり、社会に不均衡が生まれ、現在のポピュリズムの台頭につながっています。
今後は格差の解消や不均衡を調整することが優先されなければならないにもかかわらず、現在の米国は、規制緩和や公共サービスの削減によりむしろ格差が広がる方向に進んでしまっています。歴史を振り返っても、1930年に米国が大幅に関税を引き上げたことがきっかけとなって、報復措置の応酬による大きな悪循環が生まれ、それが最終的にどういう結果を招いたかということは皆さん良くご存じだと思います。歴史の教訓にも学ばなければなりません。
我々は今こそ最大限、最善の努力を尽くし、国際協力、国際協調によって中産階級がグローバル化の恩恵を受けられるような世の中を築いていく必要があります。米国は嫌がりますが、グローバル化にも一定の規制やルールが必要なんだということを、いかに各国の国民に理解してもらうかということが重要になってくると思います。
パスカル・サンタマン (Pascal Saint-Amans)
企業のステークホルダー対応への支援を行う戦略コンサルティング会社であるブランズウィック・グループのパートナー。税務関係を含む政策・規制に関する重要課題について、グローバルな視点から数多くの多国籍企業にアドバイスを行っている。
2022年にブランズウィック・グループに参画する以前は、仏財務省を経て、2012年にOECDの租税政策・税務行政センター(CTPA:Centre for Tax Policy and Administration)局長に就任し、以降10年間にわたり、OECD・G20によるBEPS(税源浸食と利益移転)をはじめとする国際課税改革プロジェクトを主導した。
スイスのローザンヌ大学教授を兼任。2023年11月に、日本政府より旭日中綬章を受章。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























