解説記事2025年04月21日 法令解説 金融商品取引法施行令等の改正金融商品取引法施行令等の改正−スタートアップへの資金供給の促進関係−(2025年4月21日号・№1071)
法令解説
金融商品取引法施行令等の改正金融商品取引法施行令等の改正
−スタートアップへの資金供給の促進関係−
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 鳥屋尾大介
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 小林法之
弁護士・元金融庁企画市場局企業開示課 専門官 鈴木彬史
金融庁企画市場局企業開示課 専門官 齋藤隆慶
金融庁企画市場局企業開示課 係員 藤岡桃子
一 はじめに
わが国経済の持続的成長のためには、株式投資等を通じて、スタートアップ企業等への成長資金の供給が活性化されていくことが不可欠であり、また、それによる運用対象の多様化は、機関投資家等によるさらなる収益機会や分散投資の機会の拡大を図ることにつながるものであると考えられる。このような観点から、2023年12月12日に公表された、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書(脚注1)(以下「TF報告書」という。)では、
・株式報酬に係る開示規制の整備
・特定投資家私募制度に関する利用促進や必要に応じた見直しに向けた検討
・少額募集に係る有価証券届出書の開示内容の簡素化
等が提言された。
そして、今般、これらの事項について制度的対応を行うことを目的とする「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第40号。以下金融商品取引法施行令を「政令」といい、特に本改正による改正後の金融商品取引法施行令を「改正政令」という)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和7年内閣府令第13号。以下企業内容等の開示に関する内閣府令を「開示府令」といい、特に本改正による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令を「改正開示府令」という)が2025年2月21日に公布され、一部を除き、同月25日から施行された(脚注2)。併せて、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が改正され(以下改正後の同ガイドラインを「改正ガイドライン」という)、同日から適用された。
本稿では、改正政令、改正開示府令等の概要について、パブリックコメントに対する金融庁の考え方なども踏まえて解説する(本改正の概要は、図表1を参照。なお、本稿では、図表1の1と2①・②について解説する)。なお、本稿において、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解であることをあらかじめ申し添えておく。
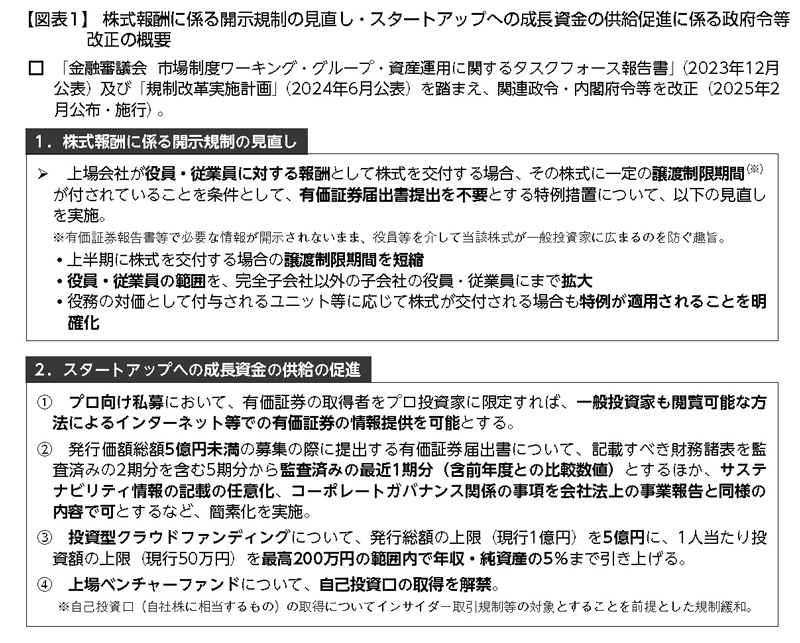
二 改正の概要
1 株式報酬に係る開示規制の見直し
(1)譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間の見直し
① 改正前の制度概要
金融商品取引法(以下「法」という)では、発行価額総額または売出価額総額(以下「発行価額総額等」という)が1億円以上である有価証券の募集または売出しを行おうとするときは、投資者に対し投資判断に必要な情報を提供する観点から、有価証券届出書の提出が必要とされている(脚注3)。他方、有価証券届出書の提出が必要となる募集または売出しであっても、その相手方が有価証券届出書に記載すべき情報を既に取得し、または容易に取得することが可能と考えられる場合、具体的には、発行会社及びその完全子会社・完全孫会社(以下「発行会社等」という)の取締役、会計参与、監査役、執行役または使用人(以下「取締役等」という)を相手方として、
ⅰ)金融商品取引所に上場されている株券等(脚注4)であって、一定期間の譲渡制限が付されているもの(譲渡制限付株式。以下「RS」という)の募集または売出し
ⅱ)新株予約権証券等(脚注5)であって、譲渡を禁止する旨の制限が付されているものの募集または売出し
については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出をもって募集または売出しを行うことができるとの特例(以下「本特例」という)が設けられている(脚注6)。このうちⅰ)については、2019年の政令等の改正(脚注7)で導入された制度であるが、譲渡制限の要件は、発行会社等の取締役等が交付を受けた株券等を一般の投資者に譲渡する際は、両者の情報の非対称性を解消した上で行うこととすることが適当との考え方により設けられているものである。具体的には、有価証券報告書が提出されれば、情報の非対称性が解消され得るとの考え方の下で、有価証券報告書の法定提出期間を念頭に、「取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月(脚注8)を超える期間」譲渡が禁止される旨の制限が当該株券等に付されていることを求めていた。
② 改正の背景
「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(以下「実施計画」という)において、「RSに関し、特例の活用が可能となる、交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月(外国会社にあっては6月)を超える期間(中略)譲渡が禁止される旨の制限という要件について、所定期間の合理性の有無を検証し見直しを行う」と提言されていたところである。
③ 改正内容
RSの譲渡制限の趣旨は、①に記載したとおり、発行会社等の取締役等と一般の投資者との情報の非対称性が解消された上で株券等の譲渡を可能とすることにある。この点、本特例の対象となる、金融商品取引所に上場されている株券等の発行会社は、有価証券報告書の提出義務のみならず、半期報告書の提出義務も負っており(脚注9)、半期報告書が提出されることによっても、発行会社等の取締役等と一般の投資者との間の情報の非対称性は解消され得ることを踏まえれば、半期報告書の提出をもって、RSに係る譲渡制限を解除することができるとしても上記譲渡制限の趣旨に反するものではないと考えられる。
かかる観点を踏まえ、本改正では、RSに係る譲渡制限期間を、
・事業年度の上半期に株券等を交付した場合には、交付日の属する事業年度の半期報告書が提出されるまで
・事業年度の下半期に株券等を交付した場合には、交付日の属する事業年度の有価証券報告書が提出されるまで
とすることとした(脚注10)。これにより、上半期に株券等を交付した場合の譲渡制限期間は改正前よりも短縮されることとなる。
(2)本特例の対象となる相手方の範囲の拡大
① 改正前の制度概要
本特例が適用される有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等(以下「取得勧誘等」という)の相手方の範囲は、発行会社の情報を既に取得し、または容易に取得することができる範囲の者として、発行会社の完全子会社または完全孫会社(脚注11)の取締役等と規定されていた。
② 改正の背景
近時、企業グループ全体の企業価値向上を図る観点から、労働に対する報酬として、発行会社の株券等を完全子会社以外の子会社の取締役等にも交付する例がみられるところである。また、必ずしも完全子会社でなくとも、子会社である限り、その取締役等は、発行会社の情報を既に取得し、または容易に取得することができるとも考えられる。
しかしながら、改正前の制度上は、完全子会社・完全孫会社ではない子会社の取締役等を含む株券等の取得勧誘等は、本特例の適用外としていたことから、かかる取締役等を交付対象とした株券等の取得勧誘等については、有価証券届出書の提出が必要とされていた。
このような状況を踏まえ、実施計画においても、「特例の活用が可能となる付与対象者の範囲について、現行、発行企業と発行企業の完全子会社の役職員に限定されているところ、戦略的な企業経営の実態も考慮し、完全子会社ではない子会社の役職員にも拡張する」と提言されていた。
③ 改正内容
本改正では、本特例が適用される株券等または新株予約権証券等の取得勧誘等の相手方の範囲を、発行会社の「子会社」の取締役等にまで拡大している(改正開示府令第2条第1項、第3項)。ここで、「子会社」とは、開示府令第1条第27号において、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社、つまり実質支配力基準による子会社をいうとされている。また、同項に「親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす」とあることから、「子会社」の中に発行会社の孫会社も含まれることとなる。なお、株券等やストック・オプションの活用によって企業グループ全体の企業価値の向上を図るとの観点は、連結・非連結の別によって差異はないと考えられるため、子会社の定義上、連結・非連結を問わないこととしている。
(3)事後交付型株式に係る解釈の明確化
① 背景
近時、企業の中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与するために株式報酬を導入する企業が増加傾向にある中で、あらかじめ役員・従業員に対して、発行会社の株券等の付与を受けることができるポイント、ユニット等を付与し、一定期間の勤務継続等の条件を達成した場合に実際に株券等を付与するという報酬制度(以下「事後交付型株式」という)の導入事例も認められるところである。
しかしながら、事後交付型株式については、現行実務上、情報開示のタイミングや開示書類に差異が見られ、開示規制の解釈をめぐる企業の実務が安定していないことから導入しづらいとの指摘がなされていた。かかる指摘を踏まえ、TF報告書において、以下の提言がなされている。
・株式報酬導入の開始時点である「株式報酬規程等を定めて取締役等に通知を行う行為」を有価証券の取得勧誘の端緒と捉え、当該行為が、有価証券の募集等に該当すると整理することが適当
・事後交付型株式は、会社から取締役等に対して他者へ譲渡できない形で報酬を前払いするという点でストック・オプションやRS(譲渡制限付株式)の経済的性質と類似していることを踏まえ、ストック・オプション及びRSと同様、有価証券届出書の提出に代えて臨時報告書の提出を認める特例を設けることが適当
また、実施計画においても、「特例の活用が可能となる株式報酬について、現行の譲渡制限付株式(RS)、ストック・オプションに加え、これらと同等の経済的意義がある譲渡制限付株式ユニット(RSU)、パフォーマンスシェアユニット(PSU)、信託型株式報酬、従業員株式所有制度といった株式報酬類型を新設する」旨が提言されている。
② 改正内容
本改正では、以下のとおり、事後交付型株式における株券等の募集または売出しについても、本特例が適用されることを明確化している(改正開示ガイドライン4−2−2)。
i.発行会社が、発行会社またはその子会社の取締役等に対し、所定の時期に確定した数の株券等を交付する旨を定めて通知その他の方法により当該定めの内容を知らせることは、改正政令第2条の12第1号に規定する取得勧誘等に該当し得ること(「解釈i」)(脚注12)
ii.取締役等が、通知その他の方法により事後交付型株式に係る定めの内容を知ることとなる日が、改正政令第2条の12第1号に規定する「交付日」に相当し、当該定めに基づいて、当該取締役等が現実に株券等の交付を受けることとなる日はこれに相当しないこと(「解釈ii」)
解釈iは、上記①のTF報告書における提言を踏まえたものである。
また、解釈iiの結果、事後交付型株式における株券等の取得勧誘等については、株券等について「取締役等が通知その他の方法により事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知ることとなる日」の属する事業年度に係る有価証券報告書(または半期報告書)が提出されるまでの期間、株券等の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合には、本特例の要件を満たすことになる。すなわち、取得勧誘等の対象となる株券等に譲渡制限が付されている必要はあるため、株券等の交付予定日が当該譲渡制限期間内である場合のほか、何らかの事情により株券等が当該譲渡制限期間内に交付される場合(脚注13)には、譲渡が制限されることとなる。他方、当該譲渡制限期間の経過後に株券等が交付される場合には、その株券等自体は譲渡制限なく譲渡することが可能ということになる(脚注14)(事後交付型株式の「交付日」と譲渡制限の関係については、図表2を参照)。
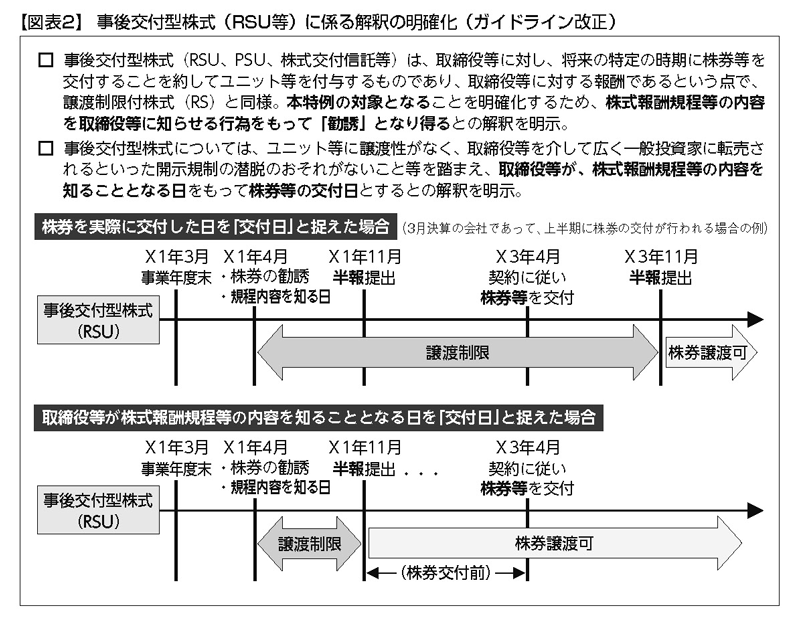
(4)臨時報告書等の記載事項の追加
① 改正内容
信託や持株会を通じて株券等を交付する類型の事後交付型株式がみられることも踏まえ、本特例が適用される場合の臨時報告書の記載事項を追加している。具体的には下表のとおりである(改正開示府令第19条第2項第2号の2イ(7)・(8))。
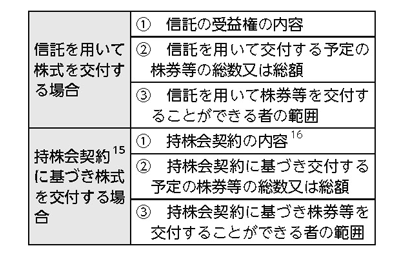
② 改正に伴う解釈の整理
ア.臨時報告書やその訂正報告書の提出の要否の考え方
改正開示府令第19条第2項第2号の2の規定による臨時報告書の提出要件は、改正政令第2条の12の適用のある取得勧誘等のうち発行価額総額等が1億円以上であるものについて取締役会決議等があった場合としている。
この点、事後交付型株式については、(3)②の解釈ⅰのとおり、所定の時期に確定した数の株券等を交付する旨を定めて、発行会社またはその子会社の取締役等に、通知その他の方法により当該定めの内容を知らせる行為を取得勧誘等と捉えているところ、一般に、当該日から実際に株券等を交付するまでの期間が長期にわたるため、臨時報告書の提出後に株券等の数の増減や株券等の総額の増減が生じることが予想される。
こうした事後交付型株式の性質を踏まえ、臨時報告書やその訂正報告書の提出の要否について、以下のような考え方を示している。
・事後交付型株式の発行数や発行価額総額等については、取得勧誘等についての決定が行われた時点で合理的に見込まれる数(脚注17)を記載
・株価の騰貴のみを理由として発行価額総額等が1億円以上となった場合には、臨時報告書の提出は不要(ただし、発行数または売出数の増加を伴う場合には、臨時報告書の提出が必要)(脚注18)
・臨時報告書の提出後、株価下落により1億円未満となることが見込まれる場合でも、訂正臨時報告書の提出は不要(脚注19)
・株券等の交付対象者の増加があった場合、原則として、その者に対して新たに取得勧誘等があったものと考えられるが、その者に対する株券等の発行価額総額等が1億円未満である場合には、臨時報告書の提出は不要(脚注20)
イ.信託型の事後交付型株式に係る解釈の明確化
信託を用いた事後交付型株式においては、交付対象となる発行会社の株券等を信託会社等が調達する方法として、発行会社が信託会社等に対して新規発行または自己株式処分をする方法と、信託会社等が金融商品市場から調達する方法とがある。この点、(3)②の解釈ⅰにより、信託型の事後交付型株式についても、発行会社による発行会社またはその子会社の取締役等に対する取得勧誘等に該当するものと整理されたことに伴い、次のような解釈の明確化を行っている。
・発行会社が信託会社等に対して新規発行または自己株式処分を行う方法:
従前、発行会社により、信託会社等を相手方とする開示府令第19条第2項第1号ヲの「第三者割当」に該当する募集または売出しが行われているものと整理され、有価証券届出書において、割当予定先の状況等の「第三者割当の場合の特記事項」の開示が求められてきた(脚注21)が、本改正後は、信託会社等を相手方とする第三者割当としては構成されないこととなる(脚注22)。
・信託会社等が交付予定の株券等のすべてを金融商品市場から調達する方法:
従前、発行会社による信託会社等に対する勧誘が行われていないと解されてきたが、本改正後は、発行会社による発行会社またはその子会社の取締役等に対する売付け勧誘等が行われていると整理されることになる(脚注23)。
なお、後者の場合は、発行済株式総数が増えるわけではなく、議決権の希薄化が生じないことから、臨時報告書の提出を不要とするため、改正開示府令第19条第2項第2号の2柱書においてその旨を明文化している。
(5)有価証券報告書の記載事項の追加
(4)②アのとおり、事後交付型株式の発行数や発行価額総額等については、取得勧誘等についての決定が行われた時点で合理的に見込まれる数が臨時報告書に記載されるため、臨時報告書の開示内容からは、実際に交付された株券等の数を知ることはできない。
このため、事後交付型株式としての株券等の交付により、発行済株式総数、資本金、資本準備金が増加した場合には、有価証券報告書において、事業年度ごとに、それぞれの合計額の記載と事後交付型株式の交付によるものである旨の欄外注記を求めることとした(脚注24)(改正開示府令第三号様式記載上の注意(23)b等)。
2 インターネット等を利用した特定投資家私募における情報提供の範囲の拡大
① 改正前の制度概要
インターネット、新聞、雑誌等により、有価証券に係る広告をすることは、勧誘対象者が不特定多数に及ぶことから、有価証券の募集または売出しに該当するとされていた。もっとも、インターネット広告が適格機関投資家・特定投資家(脚注25)のみがアクセスできるウェブページを用いて行われる場合には、他の私募・私売出しの要件(脚注26)を満たす限り、有価証券の募集または売出しに該当しないと整理されていた(2022年6月の開示ガイドライン改正(脚注27))。
② 改正の背景
スタートアップによる資金調達手段としての特定投資家私募制度に関する課題として、TF報告書では、「特定投資家私募制度については、実際のニーズや投資家保護の観点も踏まえ、利用促進や必要に応じた見直しに向けた検討を行うことが適当」と提言されていた。また、金融庁も、「2024事務年度金融行政方針」(2024年8月公表)(脚注28)において、「特定投資家私募制度における勧誘時の規制の見直し」として、「特定投資家私募の勧誘時に特定投資家以外の者も含めてインターネット閲覧を認めることを検討する」との方向性を示していた。
③ 改正内容
一般投資家が閲覧できる方法でインターネット、新聞、雑誌等による広告が行われるとしても、特定投資家以外の者が当該有価証券を取得できないような合理的措置が講じられている場合であれば、公衆縦覧型の開示規制により、一般投資家の保護を図る必要性は乏しいと考えられる。また、特定投資家私募・私売出しは、金融商品取引業者等が顧客からの委託を受けて、または自己のために行うものであることが法律上の要件とされているところである(脚注29)。さらに、金融商品取引業者等には、自己を特定投資家として取り扱うよう申出をした個人が特定投資家の要件に該当するか否かを確認する義務が課されている(脚注30)ことも踏まえると、特定投資家私募・私売出しについては、金融商品取引業者を通じた前記「合理的措置」の実効性の担保が期待できる。
こうしたことから、有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的な措置が取られている限り、インターネット、新聞、雑誌等により広く有価証券の取得勧誘等を行うような場合であっても、「特定投資家のみを相手方として行う」勧誘であると考えることができ、他の要件(脚注31)を満たす限り、特定投資家私募・私売出しに該当するとの解釈を明確化した(改正開示ガイドライン4−1−3)。
そして、有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的措置が講じられている場合としては、例えば、次に掲げる要件のすべてを満たしている場合としている(改正開示ガイドライン4−1−4)。
・当該取得勧誘等は特定投資家のみを相手方とするものであって、特定投資家以外の者は当該有価証券を取得し、または買い付けることができない旨を表示すること
・金融商品取引業者等が有価証券の取得勧誘等に係る申込みを受け付けるための仕組を整備していること
なお、有価証券の取得者を適格機関投資家に限定するための措置を講じていれば、「適格機関投資家のみを相手方として行う」勧誘も成立し得るようにも考えられる。しかしながら、適格機関投資家私募・私売出しは、特定投資家私募・私売出しと異なり、その成立要件として金融商品取引業者等の介在が要求されておらず(脚注32)、前記「合理的措置」の実効性が担保されないおそれがある。このため、適格機関投資家私募・私売出しについては本改正の対象としておらず、インターネット広告を用いて適格機関投資家私募を行おうとする場合には、従前どおり、適格機関投資家のみがアクセスできるウェブページにて行う必要があることに留意が必要である。
3 少額募集に係る有価証券届出書の開示内容の簡素化
① 改正前の制度概要
発行価額総額が1億円以上である有価証券の募集は、有価証券届出書を提出している場合でなければ、することができない(脚注33)。原則的な届出書様式は、連結財務諸表等の連結情報の開示を必要としているが、発行価額総額が1億円以上5億円未満の募集(以下「少額募集」という)については、連結情報の開示を不要とする簡易な様式(開示府令第二号の五様式)を使用することができるとされている(脚注34)。
② 改正の背景
少額募集に係る有価証券届出書の利用状況は、直近10年間で5件程度と限られているところ、TF報告書では、少額募集に係る有価証券届出書においても、スタートアップにとって開示負担が大きい項目が存在しているものと考えられ、スタートアップの資金調達に係る情報開示の負担軽減・合理化の観点から、開示内容等をより簡素化することが適当との提言が行われている。具体的には、以下の見直しを行う方向で検討を進める必要があるとされていた。
・「サステナビリティ情報」の記載欄について、開示を任意化する
・最近5事業年度の財務諸表の記載を不要とし、最近2事業年度の財務諸表のみとする
・非財務情報部分についても、例えば「コーポレート・ガバナンスの概要」等の項目について会社法上の事業報告における記載内容と同程度とする
また、実施計画においても、「現行の金融商品取引法第5条第2項に基づく少額募集について、金融庁が現在検討している開示の簡素化を早期に実施する」とされていた。
③ 改正内容
TF報告書における提言を踏まえ、少額募集に係る有価証券届出書の様式(開示府令第二号の五様式)を以下のとおり簡素化することとした。
・「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載を任意化する
・「主要な経営指標等の推移」の記載対象事業年度を5事業年度から2事業年度に縮減するほか、記載項目を削減する
・「コーポレート・ガバナンスの概要」のうちの取締役会等の活動状況、「役員の状況」のうちの社外取締役等の選任状況、「監査の状況」のうちの監査役会等の活動状況の記載を不要とするほか、「株式等の状況」のうちの「所有者別状況」の項目、「株式の保有状況」の項目を削除する
・「事業の内容」、「株式等の状況」、「コーポレート・ガバナンスの状況等」及び「設備の状況」の各項目については、会社法上の事業報告に準じて記載することを可能とする
また、従前、少額募集に係る有価証券届出書の「経理の状況」の項目においては、原則として最近事業年度に係る財務諸表(比較情報(脚注35)を含む)を、他の届出書または有価証券報告書に最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が記載されていない場合(脚注36)には、最近2事業年度に係る財務諸表を記載することとされており、それぞれ、最近事業年度分とその前事業年度分の財務諸表の監査証明が求められていた(脚注37)。さらに、「特別情報」の「最近の財務諸表」の項目において、最近5事業年度の財務諸表のうち「経理の状況」に記載した財務諸表以外の財務諸表の記載も求められており、合計5事業年度に係る財務諸表の記載が求められていた。
三 おわりに
本改正では、スタートアップ等の小規模な非上場企業における監査負担を軽減する観点から、本改正後に少額募集に係る有価証券届出書に記載すべき財務諸表は、常に最近事業年度に係る財務諸表(比較情報を含む)のみとしている(改正開示府令第二号の五様式記載上の注意(46)aにおいて準じて記載することとする第二号様式記載上の注意(67)a本文)。そして、その結果として、監査対象期についても、現行の2期分から常に最近1期分となる。
ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表について法第193条の2第1項の監査証明を受けていない場合(脚注38)には、最近事業年度の財務諸表に係る比較情報について監査証明を受けていないことを記載することを求めている(改正開示府令第二号の五様式記載上の注意(46)b)。
本改正は、株式報酬に係る開示規制の見直しとともに、スタートアップへの成長資金の供給の促進を内容とするものである。本改正が、今後、インセンティブ報酬の拡大による企業の中長期的な企業価値向上とともに、プロ投資家によるスタートアップへの成長資金の供給の促進につながることを期待したい。
脚注
1 「金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書の公表について」(2023年12月12日公表)(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20231212.html)
2 改正政令、改正開示府令等の内容については、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(スタートアップへの資金供給の促進関係)(2025年2月21日公表)を参照(https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250221/20250221.html)。
3 法第4条第1項、第5条第1項
4 株券(金融商品取引所に上場されているものまたは店頭売買有価証券に該当するものに限る。)または外国の者の発行する証券等のうち株券の性質を有するものを指す。以下同じ。
5 新株予約権証券または外国の者の発行する証券等のうち新株予約権証券の性質を有するものを指す。以下同じ。なお、取締役等が提供する役務に対する対価として交付されるものは、ストック・オプションといわれている。
6 法第4条第1項第1号、政令第2条の12、開示府令第19条第2項第2号の2
7 金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(2019年6月21日)(https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190621.html)
8 政令第2条の12第1号。外国会社にあっては6月とされている(法第24条1項本文、政令第3条の4本文)。
9 法第24条の5第1項
10 本改正前は、「取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月を超える期間」と具体的な期間をもって譲渡制限期間を規定していたが、発行会社等の取締役等と一般の投資者との間の情報の非対称性が解消された時点をもって譲渡制限を解除可能であることをより明確化する観点から、本改正では、有価証券報告書または半期報告書が提出されるまで譲渡制限が付されていることを求めている。
改正後における譲渡制限の設定の仕方としては、株券等の交付日の属する事業年度に係る有価証券報告書等が提出されるまでとするほか、従前どおり有期の譲渡制限期間として、例えば、有価証券報告書等を提出すると合理的に推測される日までとすることも考えられる。ただし、後者の場合、仮に何らかの理由で、当初想定していた日程で有価証券報告書等を提出することができず、結果的に有価証券報告書等の提出前に譲渡制限期間が終了することとなる場合には、本特例の要件を満たしていないこととなり、有価証券届出書を提出せずに募集または売出しを行ったものとして扱われることに留意が必要となる。
11 完全子会社については、株券等または新株予約権証券等の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社、完全孫会社については、株券等または新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社または完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社と定義されていた(改正前の開示府令第2条第1項、第3項)。
12 なお、この解釈は、本特例が適用されない事後交付型株式の取得勧誘または売付け勧誘等についても及ぶものと考えられる(前掲注2の別紙1「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」という。)No.83及び84を参照)。
13 死亡その他正当な理由による退任・退職があった場合や組織再編成等が行われた場合を除く(改正開示ガイドライン4−2−3)。
14 パブコメ回答No.18から22参照。事後交付型株式の場合、本文中の譲渡制限期間内に株券等が交付されることは通常想定されないと考えられるが、何らかの事情により当該期間内に株券等が交付される場合は、その期間経過後まで譲渡制限が付されるよう割当契約等において対応しておくことが考えられる。なお、当該制限期間内に株券等が交付される場合においてはRSと同様に、譲渡制限が付されていない他の株券等と分別して管理される必要がある(改正開示府令第19条2項2号の2イ(6)、改正開示ガイドライン24の5−14−3)。
15 発行会社またはその子会社の取締役等が、当該発行会社等の他の取締役等と共同して、株式の買付けを一定の計画に従って個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約であり、一般には民法上の組合として組成される持株会に加入するための組合契約等を指している(パブコメ回答No.64参照)。
16 信託を用いて株券等を交付するときは、信託の受益権の内容を含む。
17 合理的に見込まれる数として、株式報酬規程等に基づき業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数や発行価額総額等が多くなる場合)を想定した数を記載することも問題ないと考えられる(パブコメ回答No.121参照)。
18 パブコメ回答No.115から120参照。また、開示ガイドライン24の5−14−5に明記。
19 パブコメ回答No.115から120参照。
20 パブコメ回答No.103参照。
21 開示府令第二号様式記載上の注意(23−2)等
22 パブコメ回答No.33参照。
23 パブコメ回答No.92から95参照。
24 半期報告書には、当中間会計期間中における状況の記載を求めている(改正開示府令第四号の三様式記載上の注意(14)b等)。
25 法第2条第31項は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金等を「特定投資家」と定義している。なお、法第34条の3第6項及び第34条の4第6項により特定投資家とみなされる特定投資家以外の者も含まれる。
26 例えば、株券に係る適格機関投資家私募に該当するためには、同一の内容の株券について有価証券報告書の提出義務を負っていないこと、同一種類の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこと、株券の取得者が当該株券を適格機関投資家以外の者に譲渡しないことを条件として、取得勧誘が行われることとの要件を満たす必要がある(政令第1条の4第1号)。
27 「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(2022年6月17日)(https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2.html)
28 「2024事務年度金融行政方針について」(2024年8月30日)(https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240830/20240830.html)
29 法第2条第3項第2号ロ(1)、第4項第2号ロ(1)
30 法第34条の4第2項
31 株券を例にとると、金融商品取引業者等が顧客からの委託を受けて、または自己のために行う取得勧誘であることのほか、同一種類の有価証券について有価証券報告書の提出義務を負っていないこと、発行者と取得者の間、勧誘を行う者と取得者の間で、取得者が取得した株券を特定投資家等以外の者に譲渡しない旨の契約を締結することを取得の条件として取得勧誘が行われることとの要件を満たす場合には、特定投資家私募に該当する(法第2条第3項第2号ロ、施行令第1条の5の2第2項第1号)。また、特定投資家私募を行う場合には、あらかじめ、特定証券情報を提供または公表する必要がある(法第27条の31第1項)。以上について、特定投資家私売出しも同様。
32 法第2条第3項第2号イ、第4項第2号イ
33 法第4条第1項第5号を参照。
34 法第5条第2項。売出しについても同様。
35 比較情報とは、「当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいう」とされ、財務諸表は、比較情報を含めて作成しなければならないとされている(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の2の2)。
日本公認会計士協会「監査基準委員会報告書710 過年度の比較情報−対応数値と比較財務諸表」は、
・当年度の財務諸表に不可分の一部として含まれ、当年度に関する金額及び注記事項と関連付けて読まれることのみを意図している場合の比較情報を「対応数値」、
・当年度の財務諸表と同程度の比較情報が含まれており、比較情報について監査が実施されている場合に、比較情報に対する監査意見が当年度の監査報告書に記載されるときの比較情報を「比較財務諸表」
と定義し、比較情報が対応数値として表示される場合には、監査意見において対応数値に言及してはならないとしている。これに関連して、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2010年3月26日)では、我が国においては、対応数値方式の方が監査実務になじみやすく、投資者の理解にも資するとして、この考え方に基づき、所要の制度の整備を行うことが適当とされていたところである。
なお、上記の監査基準委員会報告書では、監査人は、比較情報が財務諸表に含まれているかどうか、当該情報が適切に表示及び分類されているかどうかを判断しなければならないとされている。
36 端的には、初めて有価証券届出書を提出する場合など、他の開示書類において最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が開示されていない場合が考えられる。
37 法第193条の2第1項本文、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条第1号
38 前掲注36と同様。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















