解説記事2025年05月12日 ニュース特集 当局、金融機関等に対するCRS報告書検査を強化(2025年5月12日号・№1073)
ニュース特集
開発特官等が法定監査と併せて実施
当局、金融機関等に対するCRS報告書検査を強化
国税当局が近年、CRS報告書検査を強化しているもようだ。CRS報告書検査は、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の適正な執行を図るために開発調査担当特官等が金融機関等(銀行、証券会社、保険会社、組合、信託等)に対して実施するもの。当該報告義務がある金融機関等は、特定取引を行った者が報告対象契約を締結している場合、報告対象契約ごとに特定対象者の氏名(名称)、住所(本店所在地等)、特定居住地国及び報告対象契約に係る資産の価額などの報告事項を所轄税務署長に提供しなければならない。なお、令和5事務年度においては、国税庁から外国居住者のCRS情報約51万件(口座残高約5.6兆円)が外国税務当局(80か国・地域)に提供されている(本誌1061号12頁参照)。
本特集では、令和6事務年度におけるCRS報告書検査について、国税庁指示文書等に基づきQ&A形式で紹介する。
Q
CRS報告書検査が導入された経緯は分かりますか?
A
「非居住者の金融口座情報に係る報告書検査」(CRS報告書検査)について、大阪局は、令和3事務年度に報告書検査を実施して以降、報告書検査の件数が年々増加傾向にあることから、令和5事務年度において開発調査部門(開発調査担当特官及び付職員)の事務マニュアルに報告書検査事務の項目を新設したとしています。また、同局は令和6事務年度の開発調査部門の事務運営方針の中で「報告書検査の充実」を明記しています。
名古屋局も、令和5事務年度から開発調査担当特官が実施する事務に「CRS報告書検査」を加えています。
Q
検査対象者の選定はどの部署が担当しますか?
A
令和6事務年度の報告書検査事務に係る国税庁指示文書では、局課税総括課等(各局等の課税総括課(東京局・大阪局は資料総括課)、東京局資料情報担当統括国税実査官)及び開発調査部門が報告書検査の必要性を検討し、検査対象者(租税条約実施特例法施行令6条の7に規定された報告金融機関等)の選定及び実施方針を決定するとしています。
また、国税庁が検査対象者を指定し、各局に報告書検査の実施を指示するケースもあるようです。
※租税条約実施特例法:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
Q
報告書検査の実施担当者は決められていますか?
A
報告書検査は局課税総括課等及び開発調査部門が実施します。実施に当たっては国税庁や他局の課税総括課等と連携し、相互に支援を行うようです。
なお、開発調査担当特官は、①資料源開発、②法定監査(金融機関や証券会社を中心に法定資料の提出に関する調査を実施)、③CRS報告書検査を行いますが、CRS報告書検査については、法定監査と併せて実施するなど、効率化を図っています。
Q
報告書検査では金融機関等に事前通知が行われますか?
A
報告書検査は、租税条約実施特例法等に定められた質問検査権に基づいて実施される「調査」であるため、国税通則法上の事前通知は必要ないとされています。
ただし、国税当局は、運用上、検査先の金融機関等に対して検査開始日前に相当の時間的余裕をおいて、あらかじめ検査日時等の調整を行うとしています。この事前連絡は原則として電話で行われます。
また、事前連絡を行った場合、国税当局は法定監査の実施手続に準じて「報告書検査等手続チェックシート」(事前連絡の際の報告書検査を実施する旨の明示、提出物件の留置きに係る手続等を確認)、「報告書検査等経過記録書」(検査・監査事項、応接状況等の復命事項等を記載)を作成します。
なお、日程調整の連絡の際、金融機関等に対しては、国税庁ホームページに掲載されている「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関するセルフチェックシート」の作成及び手続の実施に当たって使用している帳簿書類等の準備が依頼されるようです。報告書検査の実施担当者は、当該チェックシートを活用して、検査対象者選定時に決定した実施方針に基づく検査を実施します。
Q
報告書検査に当たり実施担当者が留意している点は?
A
報告書検査を実施する場合、実施担当者は身分証明書(国税職務証票が交付されている場合は国税職務証票)及び報告事項の提供に関する質問検査章を必ず携行し、質問検査等の相手となる者に提示して報告書検査のために臨場した旨を明らかにするとともに、報告書検査に対する理解と協力を得た上で検査を実施するとしています。
また、報告書検査において、報告書検査上有効な情報を把握した場合は、「調査情報連絡せん」(特定の不正取引や不正経理等から発見した有効資料源・有効な調査手法を広くかつ組織的に活用して調査効率の向上に役立てるためのもの)の作成が必要とされています。なお、当該連絡せんは、国税庁課税総括課を通じて関係局の課税総括課等に連絡されます。
Q
報告書検査における検査項目は分かりますか?
A
検査終了後に実施担当者が作成する「検査事績書」(下掲参照)には、「把握した非違等の状況」として、①事務フロー及びプロセス等の整備状況、②システム設計の問題の有無、③新規届出書の入手漏れ(任意届出書・異動届出書の要求漏れ)、④居住地国等の特定が適切でなかった特定取引に係る契約数などの「検査項目」が記載されています。
上記③については、現物確認により検査対象者(特に投資事業体)が新規届出書を確実に入手しているか確認を行い、その結果、新規届出書が入手漏れとなっていた特定取引に係る契約件数を「検査項目の適否又は非違等に係る契約数」欄に記載するとしています。
なお、検査の結果、検査対象者が報告したデータに誤りがあった場合、その報告データの修正に関する指導が行われ、修正報告データの報告までに要する期間が聴取されます。聴取した期限までに検査対象者が報告をしなかった場合は、局課税総括課等が検査対象者の作業状況について確認を行います。
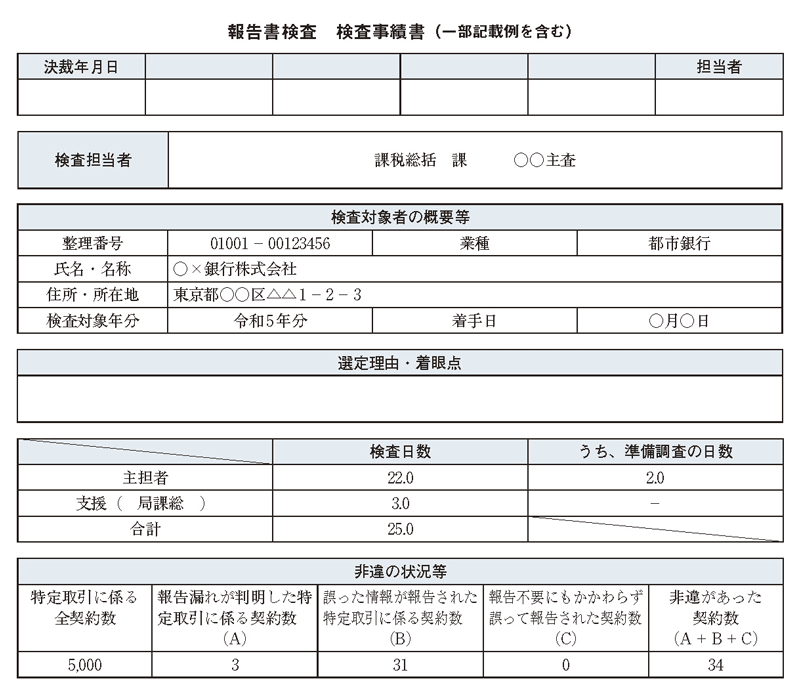

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























