解説記事2025年06月23日 税制改正解説 令和7年度における相続税・贈与税関係の改正について(2025年6月23日号・№1079)
税制改正解説
令和7年度における相続税・贈与税関係の改正について
大内大地
相続税法の改正
一 相続税の物納制度の見直し
1 改正の内容
物納制度は、納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合についてのみ、その納付を困難とする金額を限度(この限度額を以下「物納許可限度額」という。)として申請をすることができる(相法41①)。
この物納許可限度額の計算方法について、納税者の支払能力を的確に勘案した物納制度となるよう、次のとおり物納許可限度額の計算方法が見直されている。
延納期間終了後における当面の生活費等に配慮する観点から、物納許可限度額〔(A)納付すべき相続税額−(B)即納可能額(注1)−(C)延納可能額(注2)〕の計算において、(D)延納期間終了後の当面の生活費等を加算することとされた(相令17三)。また、この見直しに伴い、物納申請書等の記載事項についても規定が整備されている(相規22①)。
なお、(D)延納期間終了後の当面の生活費等を加算した結果、物納許可限度額が計算上算出されることになり、延納を使わずに「即納+物納」が可能となる場合が生じるように見えるが、そもそも物納は、「延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」(相法41①)に適用されるものであるという点については改正がない。そのため、即納可能額が納付すべき相続税額を超える場合には、そもそも納期限において金銭で納付することを困難とする事由があるとはいえないため、引き続き物納の許可を受けることはできない。
(注1)即納可能額とは、現金・預貯金その他換価の容易な財産の額から3月分の生活費及び事業を継続するために必要な当面の運転資金を控除して算出した金額をいう。
(注2)延納可能額とは、延納期間中の収入から延納期間中の生活費及び運転資金を控除して算出した金額をいう。
※ 特定物納(相法48の2①)の許可限度額の計算についても同様の見直しがされている(相令25の7①、相規28)。
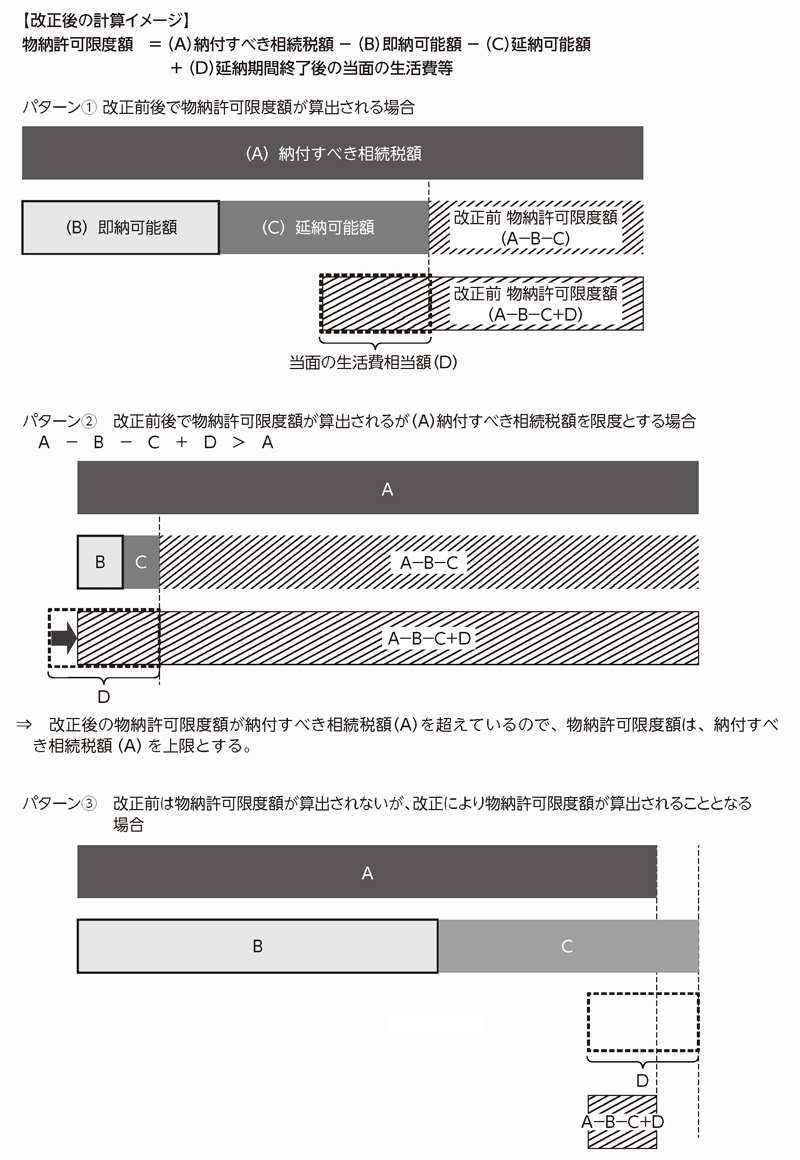
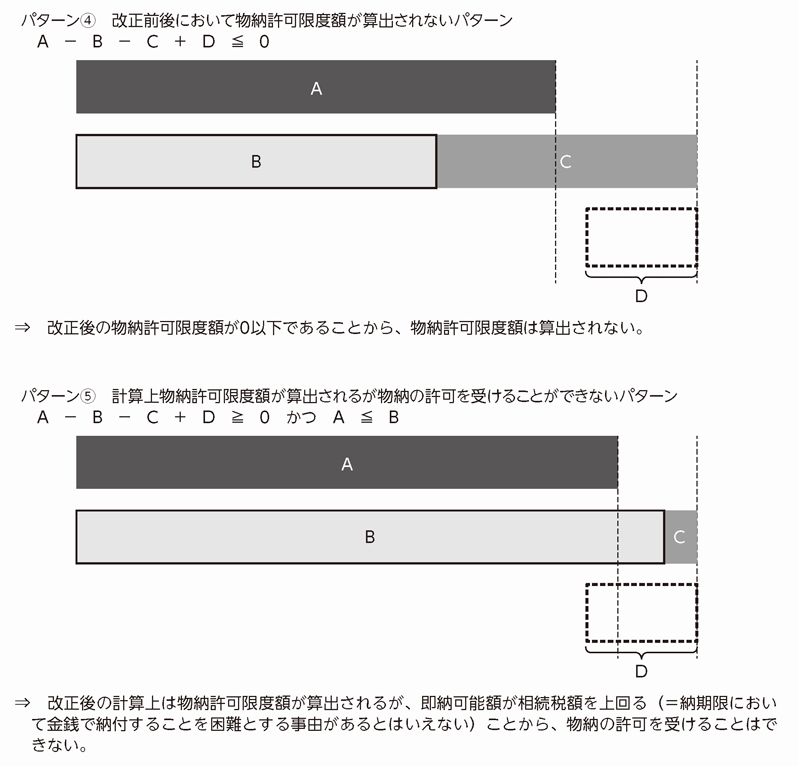
2 適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、従前どおりとされている(改正相令附則②)。
租税特別措置法の改正(相続税・贈与税関係)
一 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の延長
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、利用件数が低迷する等の状況にあり、若年世代への資産移転を通じた経済活性化や少子化対策という政策目的に寄与しているとは評価できず、本来的には制度の廃止を検討すべきである。
しかしながら、令和8年度までは「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)の集中取組期間の最中にあり、こども・子育て政策を総動員する時期にあることを踏まえ、本措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された(措法70の2の3①)。
(参考)令和7年度与党税制改正大綱(抄)
第一 令和7年度税制改正の基本的考え方
3.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
(2)子育て世帯への支援
② 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、令和5年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討する」とされた後も、利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを巡る給付と負担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである。他方、現在、「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)の最中にあり、こども・子育て政策を総動員する時期にある。このため、本措置は、特に集中取組期間であることを勘案し、適用期限を2年延長する。
二 農地等に係る贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付けの要件の見直し
1 改正の内容
農地等に係る贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由のうち、受贈者が贈与税の申告書の提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障について、「介護医療院への入所により農業に従事することができなくなる故障」として市町村長又は特別区の区長が認定したものが追加された(平成25年4月農林水産省告示第803号)。
(参考)「介護医療院」とは、要介護者であって主として長期にわたり療養が必要である者に対し施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として都道府県知事の許可を受けたものをいう(介護保険法8 )。
)。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に営農困難時貸付けをする場合に適用される(令和7年4月農林水産省告示第509号)。
三 農地等に係る相続税の納税猶予制度における営農困難時貸付けの要件の見直し
1 改正の内容
農地等に係る贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付けと同様に、農地等に係る相続税の納税猶予制度における営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由のうち、相続人が相続税の申告書の提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障について、「介護医療院への入所により農業に従事することができなくなる故障」として市町村長又は特別区の区長が認定したものが追加された(平成25年4月農林水産省告示第803号)。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に営農困難時貸付けをする場合に適用される(令和7年4月農林水産省告示第509号)。
四 山林に係る相続税の納税猶予制度における経営困難時委託特例の要件の見直し
1 改正の内容
農地等に係る贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付けと同様に、山林に係る相続税の納税猶予制度における経営困難時委託特例についても、本特例の適用を受けることができる事由のうち、林業経営相続人が相続税の申告書の提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障について、「介護医療院への入所により山林の経営を行うことができなくなる故障」として市町村長が認定したものが追加された(平成29年3月農林水産省告示第511号)。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に経営困難時委託を行う場合に適用される(令和7年4月農林水産省告示第510号)。
五 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例制度の改正
1 改正の内容
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けようとする特例経営承継受贈者は、「贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特例認定贈与承継会社の役員等でなければならないこと(以下「役員等就任要件」という。)」とされていたが、特例の適用期限である令和9年12月31日から逆算すると遅くとも令和6年12月末までには特例認定贈与承継会社の役員等でなければならないこととなる。そこで適用期間内におけるこの特例の最大限の活用を促すため、この役員等就任要件を「贈与の直前において役員等であること」に見直すこととされた(措法70の7の5②六ヘ)。
なお、いわゆる一般措置についても役員等就任要件があるが、この役員等就任要件については見直しを行わず、従来通り贈与前3年以上の役員等就任要件が課せられている(措法70の7②三ヘ)。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得をする非上場株式等に係る贈与税について適用され、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、従前どおりとされている(改正法附則55)。
六 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除制度の改正
1 改正の内容
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例よりも1年遅れて創設された個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除は、その適用期限が令和10年12月31日とされていることから、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例のような差し迫った状況にはないが、個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除についても適用期間内に最大限の活用を促すため、「贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたこと」とされていた要件を「贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこと」に見直すこととされた(措法70の6の8②二ハ)。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得をする特定事業用資産に係る贈与税について適用され、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、従前どおりとされている(改正法附則55)。
租税特別措置法等の改正(登録免許税関係)
一 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置の改正
1 改正の内容
信用保証協会、農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金、漁業信用基金協会又は日本酒造組合中央会(以下「信用保証協会等(注)」という。)が、債務保証業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税の軽減税率を1,000分の2(改正前:1,000分の1.5)に引き上げた上、適用期限を令和10年3月31日まで3年延長することとされた。
(注)信用保証協会等は、中小企業者や農林漁業者等が金融機関から事業資金を調達する際に信用保証を付けることで、中小企業者等の信用力を補完する機関である。
2 適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用される(改正法附則1)。
二 認定事業再編計画等(産業競争力強化法)に基づき行う登記の税率の軽減措置の改正
1 改正の内容
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(改正後:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律。以下「食品等持続的供給法」という。)の改正を踏まえ、認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減措置の適用対象となる登記の範囲に、産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けたものとみなされる食品等持続的供給法の認定計画(安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画及び消費者選択支援事業活動計画)に基づき行う会社の設立等の登記が追加された(措法80①)。
2 適用関係
上記2の改正は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用される(改正法附則1十三)。
三 選定実施計画(情報処理の促進に関する法律)に基づき行う登記の税率の軽減措置の創設
1 特例制度の内容
情報処理の促進に関する法律の規定により選定された選定事業者(注1)が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、その資本金の額の増加が、選定実施計画(注2)に係るものであるときは、その登記に係る登録免許税の税率は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から令和9年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、1,000分の3.5(本則:1,000分の7)とされる(措法80④)。
(注1)選定事業者とは、情報処理の高度化に特に必要な半導体として経済産業大臣が指定した高速情報処理用半導体(以下「指定高速情報処理用半導体」という。)の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取り組み(以下「特定取組」という。)を最も適正に実施することができると認められる者として一定のプロセスを経て経済産業大臣に選定された者をいう。
(注2)選定実施計画とは、選定事業者になろうとする者が経済産業大臣の選定プロセスにおいて同大臣に提出する特定取組の実施に関する計画のうち、選定事業者として選定された者が提出した実施計画(変更の承認又は変更の届出があった場合には、その変更後のもの。)をいう。
2 適用関係
この特例は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第30号)の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用される(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則1)。
四 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減措置の改正
1 改正の内容
(1)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)又は適格特例投資家限定事業者が、同法に規定する不動産特定共同事業契約のうち一定のものに係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合のその不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しが行われた上、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。
イ 特定建築物(注1)の新築等に着手するまでの期限について、取得後3年以内(改正前:2年以内)に緩和(措令43の3①三)。
ロ 特定建築物の新築等の前提となる建替え等が必要な建築物の築年数要件について、築15年超(改正前:10年超)であることとする(措令43の3②一)。
(2)不動産特定共同事業法に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物の新築、改築又は特例増築等(注2)をした場合のその建築物(特例増築等の場合には、その特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。
(注1)特例建築物とは、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(路外駐車場に限る。)、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫の用に供する建築物をいう。ただし、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の用に供するものは除く(措令43の3⑦)。
(注2)特例増築等とは、特例建築物とするために行う一定の増築、修繕又は模様替をいう。
2 適用関係
上記1(1)の改正は、令和7年4月1日以後に締結する不動産特定共同事業契約に係る不動産の取得をする場合の所有権の移転登記又は当該不動産特定共同事業契約に係る建築物の新築等若しくは特定増築等をする場合の所有権の保存登記に係る登録免許税について適用され、同日前に不動産特定共同事業契約を締結した場合については、従前どおりとされている(改正措令附則22)。
五 社会保険診療報酬支払基金の改組に伴う所要の措置
1 改正の内容
登録免許税法別表第3に掲げる者が自己のために受ける一定の登記等については登録免許税を課さないこととされているが(登法4②)、この別表第3に掲げる者の範囲から社会保険診療報酬支払基金が削除されるとともに、同表に掲げる者の範囲に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が追加され、同機構が受ける同機構の事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記については、登録免許税が課されないこととされた(旧登法別表第3の11の項、登法別表第3の1の項)。
2 適用関係
上記2の改正は、医療法等の一部を改正する法律(注)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が受ける登記に係る登録免許税について適用される(改正法附則1八ハ)。
(注)第217回国会(常会)に提出されており、令和7年6月18日現在、衆議院で審議中
六 租税特別措置等の適用期限の延長・廃止
1 次に掲げる租税特別措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。
(1)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減措置(措法83の2の2)
(2)相続に係る所有権の移転登記等の免税措置(措法84の2の3)
2 帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止された(旧震災税特法40の4)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























