解説記事2025年06月30日 SCOPE 総則6項適用事案、高裁で国が逆転勝訴(2025年6月30日号・№1080)
“持株外し、比準要素1の会社外し”を問題視
総則6項適用事案、高裁で国が逆転勝訴
総則6項の適用を巡っては、国の敗訴が確定した高裁判決(令和6年8月28日東京高裁判決。本誌1042号)に続き、令和7年1月17日、東京地裁でも国が敗訴していた(本誌1061号)。こうした中、同地裁判決の控訴審の行方が注目を集めていたが、東京高裁第4民事部(鹿子木康裁判長)は令和7年6月19日、一転、原判決を取り消し、国が逆転勝訴した。
原判決が、相続税額の減少は新株発行等だけが原因ではなく評価方法の選択にも基因するとし、原告らの行為は相続税の負担を著しく減少させるものとはいえないとしたのに対し、東京高裁は、軽減される相続税の額や原告らの行為から相続税の負担を著しく減少させるものであるとして、地裁判決とは正反対の判断を下した。
相続税減税スキームを実行と認定、総則6項適用は平等原則に違反せず
総則6項の適用の可否については、「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反すると言うべき事情」(特段の事情)があるかどうかが判断のポイントとされている。
本件は、原告(被控訴人)らが相続により取得したX社(小会社)株式の評価方法が争われた事案である。X社は、本件相続開始前に、本件被相続人への第三者割当てによる募集株式発行(本件新株発行)及び株主(被相続人の実子ら)への配当を行った。
国は、原告らが本件新株発行等を行ったのは、X社が併用方式よりも評価額が高くなる「株式保有特定会社」(評基通189(2))に該当しないようにするためであると主張。原告A氏(被相続人の子)及び本件被相続人が、本件新株発行等が原告らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待していたから、上記「特段の事情」があるとして、総則6項を適用して純資産価額方式により更正処分等を行っていた。
地裁、相続税減少は評価方法の選択に基因
これに対し東京地裁は、相続税の総額等の減少は、本件新株発行等を行ったことにより直ちに生ずるものではなく、評価通達179(3)が、小会社の株式の価額の評価方法について、純資産価額方式と併用方式の選択を認めていることにも基因すると指摘した上で、本件株式の価額を評価通達の定める方法(併用方式)により評価した額と、本件各更正処分価額(純資産価額方式)などとの間に大きなかい離があることをもって、「特段の事情」があるということはできないとしていた。
また、本件新株発行等を行っても減少の割合は5割未満にとどまり、相続税の総額はなお相当高額であること、本件被相続人の遺言や遺産分割協議の内容からも、2割加算がされる行為もしていることなども含めて、全体としてみれば、原告A氏及び被相続人の行為が、それにより原告らの相続税の負担が著しく軽減されるものであると評価することまではできないとの考えも示していた。
相続税の負担を著しく軽減する行為と認定
東京高裁も東京地裁と同様に、本件新株発行等がされたことにより、課税価格の合計額は44.6%、相続税額は48.1%軽減されたと認定したが(表参照)、「相続税額の軽減割合が5割に満たず、相続税の負担が著しく軽減されることにはならない」という被控訴人の主張に対し、「軽減される相続税の額を総合的に考慮して判断すると、被控訴人らの相続税の負担は著しく軽減されることになる」とその“額”に着目して地裁とは異なる判断を下した。
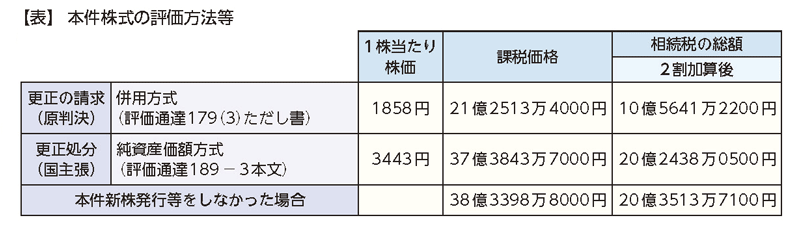
また、A氏が相続開始の3か月前に証券会社の担当者に相続税の節税対策を相談し、その後、X社が「株式保有特定会社」(評価通達189(2))及び「比準要素数1の会社」(評価通達189(1))に該当しないための方策を含め、本件新株発行等を用いた相続税減税スキームなどについて担当者と協議を重ねて同スキームを実行したと指摘。これらの経緯から、A氏らが、本件新株発行等が近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において被控訴人らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件新株発行等を行ったことは明らかとの判断を示した。
更正処分の評価額は合理的
なお、地裁判決では、平等原則に違反する(争点2)として更正処分等が取り消されたため、「本件各更正処分価額が本件株式の客観的な交換価値を上回り、本件各更正処分が相続税法22条に違反するか否か」(争点1)については判断が示されなかったが、東京高裁は争点1についても以下のとおり判断を示している。
具体的には、本件各更正処分価額は、①純資産価額方式による評価額(1株当たり3,443円)及び②監査法人による本件報告書における評価額(1株当たり3,488円)のうち、より評価額が低い上記①の評価額を採用したものであり、上記①及び②の各評価額の算定方法に不合理な点は認められないところ、上記①及び②の各評価額が近似していることは、各評価額の合理性を裏付けるものとした。
被控訴人らは、「上記②の本件報告書における評価額が、非流動性ディスカウントやマイノリティ・ディスカウントをしていない点で、不合理である」と主張したが認められなかった。
以上を踏まえて、東京高裁は、総則6項を適用した更正処分等を適法と判断し、地裁判決を取り消した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























