解説記事2025年07月07日 ニュース特集 インサイダーや課徴金引上げなど、来年の通常国会で金商法を改正へ(2025年7月7日号・№1081)
ニュース特集
虚偽記載に対する開示の見直しも
インサイダーや課徴金引上げなど、来年の通常国会で金商法を改正へ
早ければ来年の通常国会に金融商品取引法等の改正案が提出されることになりそうだ。金融審議会は6月25日に総会を開催。加藤勝信金融担当大臣の諮問を受け、①不公正取引規制の強化等、②企業情報の開示のあり方、③暗号資産を巡る制度のあり方、④地域金融力の強化に関する4つのワーキンググループの設置を決めた。不公正取引規制等の強化では、公開買付者等関係者に係るインサイダー取引規制の対象者の拡大や、大量保有報告制度違反に係る課徴金の引き上げなどについて検討。また、企業情報の開示のあり方では、サステナビリティ情報等の虚偽記載等に対するセーフハーバー・ルールなどを導入する方向で検討する。暗号資産に関しては、金融商品取引法上の枠組みとし、金融商品として位置付けるかどうかなどを検討する。仮に金融商品となれば税制も申告分離課税となる可能性が高まることになる。
現行、TOB対象企業のアドバイザーからの情報漏洩は規制の対象外
昨今では、既存の法令では違反行為として捕捉できない不正事例や、課徴金の額が低く、抑止効果が不十分な事例があることを踏まえ、証券取引等監視委員会では、6月20日に内閣総理大臣及び金融庁長官に対し金融庁設置法21条に基づく建議を行っている。建議では、公開買付者等関係者の範囲等の拡大や、課徴金水準の引き上げ及び対象の拡大などの措置を講じるよう求めており、金融審議会に設置される市場制度ワーキンググループでも、証券監視委の建議を踏まえ、不公正取引規制を強化する方向で検討が行われる。
TOBによるインサイダーが多数
インサイダー取引規制に関する見直しでは、公開買付者等関係者に係る対象者の範囲を拡大する。証券監視委によると、インサイダー取引に係る課徴金勧告事案で最も件数が多いのが公開買付け等事実に係る事案である。平成17年度の課徴金制度導入後から令和6年度までの勧告件数408件のうち、公開買付け等事実は25.5%(104件)を占める。公開買付けは、公表後に株価が上昇する可能性が高いことや、制度上、公表前に多数の関係者に情報共有する必要があり情報管理が難しいことなどから、違反行為が多くなっているのが現状だ。
公開買付けに係るインサイダー取引規制では、公開買付者だけでなく、被買付企業、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)やリーガル・アドバイザー(LA)などの公開買付者と契約を締結する者についても、公開買付者等関係者として規制の対象としているが、限定列挙となっているため(金商法167条1項)、法令に規定されていない者については規制の対象外となる。最近では、TOBを行う際には事前交渉が行われるのが通常だが、例えば、被買付企業の契約締結者については、公開買付者等関係者と同等の情報を有しているにもかかわらず、対象とはなっていないため、FAやLAからインサイダー情報を得た者については、第二次情報受領者となり、インサイダー規制の対象外となっている点が問題視されている(図参照)。
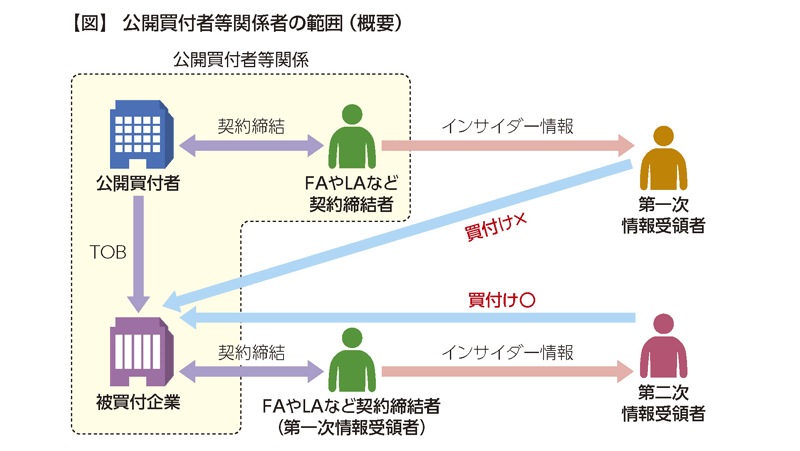
また、抑止力を高めるとしてTOBに係る課徴金の引き上げも検討する。なお、現行の課徴金の算出方法は、「(公開買付等事実公表後2週間における最大の価格−買付けをした価格)×数量」となっている。
他人名義口座による不公正取引にメス
課徴金に関しては、他人名義口座によるインサイダー取引規制も見直しの対象だ。
従来から証券監視委においても注視されているが、他人名義口座の提供を受けるなどして取引を行う事案は後を絶たない。令和元年度から令和6年度においては、インサイダー取引を行った58人中21人、相場操縦を行った24人中8人が他人名義の口座で取引を行っていたという。なかには、提供先の不正取引を認識した上で口座を提供しているにもかかわらず課徴金の対象とならない協力者もいるとされており、抑止力が働くような制度の見直しが検討されることになる。
1万円未満の場合は課徴金勧告できず
また、高頻度取引、いわゆるHFT(High Frequency Trading)による注文を通じて相場操縦を行う事案が発生しているが、課徴金の認定を行うのが難しいのが現状である。HFTとは、アルゴリズムを用いて高速、高頻度かつ自動的に行うという取引のことだが、薄利の取引を大量に行っているため、1銘柄・1日当たりの利益金額の大半は1万円未満にすぎず、金商法176条1項の規定では、1万円未満の金額は課徴金納付命令が出せないからだ。
このため、高速かつ高頻度である取引行為の性質を踏まえた課徴金額の算定方法を新たに措置する方向で検討がなされることになる。
大量保有報告書の不提出に対応
大量保有報告書等は、提出事由が生じた日から5日以内に提出する義務があるが、提出遅延も多いことから、2008年の金融商品取引法の改正により、大量保有報告書等の不提出及び不実記載が課徴金制度の対象となったところ。しかし、その後も大量保有報告書等の提出遅延は後を絶たず、現在も年間平均で約1,500件が提出遅延となっている。一方、課徴金納付命令の発出件数は課徴金制度導入以来、わずか13件にすぎない。加えて、課徴金納付命令が勧告された事案でも、課徴金額は数十万円にとどまるなど、決して抑止力の高いものとはなっていない。現行法上、課徴金額は対象企業の時価総額の10万分の1とされているが、この算定方法を見直すこととしている。
調査協力の度合いで課徴金の減算率を決定
そのほかでは、課徴金の減算制度について、より調査の実効性を高めるための見直しが行われる方向だ。現行、有価証券報告書の虚偽記載等に関し調査開始前に違反事実の報告を行った場合には、課徴金の額を50%減額する仕組みが導入されている。ただし、違反事実の報告を行ったにもかかわらず、調査に対し協力的でなくなるケースも想定されるため、独占禁止法において導入されている調査協力減算制度と同じような仕組みを導入する考えだ。調査協力減算制度とは、課徴金減免申請で行った事実の報告及び資料の提出の内容も含めて、報告等事業者による協力が事件の真相の解明に資する程度を評価し、課徴金の減算率を決定するというものである。
EMMoUの署名に向け出頭権限を追加へ
日本企業がグローバルに展開する中、海外子会社の役職員が日本の上場会社等の重要事実等を知る機会も多く、上場会社等においては、インサイダー情報の管理体制及び法令遵守体制の整備を海外子会社等にまで徹底することが求められている。
証券監視委では、海外の金融規制当局に対し多国間情報交換覚書(MMoU)に基づく情報提供を依頼し、調査を実施。海外居住者が日本や居住国以外の第三国に開設した自己名義ではない口座を利用して取引を行ったとしても、違反行為を特定し、不公正取引として摘発している。
ただ、IOSCO(証券監督者国際機構)が2016年に作成した多国間情報交換覚書(EMMoU)では、証言のために出頭を強制すること、資産を凍結すること、裁判所の関係当局を通じて既存のインターネットサービスプロバイダの記録を入手し、共有することなどの実効性の強い権限が追加されており、日本においてもEMMoUに署名することができるよう、出頭命令の権限を追加するなどの措置を加える方向だ。
虚偽記載に対するセーフハーバー・ルールを法令に規定へ
企業情報の開示のあり方については、ディスクロージャーワーキンググループで検討が行われる。サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)については、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に2027年3月期から適用される方向だが、1つ懸念されるのはサステナビリティ情報が見積りなどを伴う点である。特に温室効果ガス(GHG)のScope3排出量の開示では、会社のバリュー・チェーンの上流及び下流の主体から提供されたデータ、データプロバイダーから提供されるデータ、投融資に帰属する排出量(ファイナンスド・エミッション)等の企業の統制の及ばない第三者から取得した情報や見積りによる情報開示が求められており、事後的に誤りであったという可能性が生じるからだ。このため、仮にScope3排出量に関する定量情報が事後的に誤りであることが発覚しても、①統制の及ばない第三者から取得した情報を利用することの適切性、②見積りの合理性について会社内部で適切な検討が行われたことが説明されている場合であること、③その開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合には、虚偽記載等の責任を負わないとすることが適当であるとし、金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、開示ガイドラインを改正する考え方が示されるとともに、法律改正も視野に入れ、引き続き検討していくこととされている。
このため、ディスクロージャーWGでは、法令に明記するため、セーフハーバーの内容、適用要件、適用範囲、行政罰や刑事罰といった効果などについて検討が行われる。
有価証券報告書の記載事項を整理
そのほか、加藤勝信金融担当大臣がすべての上場企業に対し、株主総会前に有価証券報告書を開示することを要請したことなどを踏まえ、有価証券報告書の記載事項のうち、相対的に有用性が低下している事項の有無を検証し、必要に応じて整理を行うとしている。
また、上場会社が役員・従業員に対する報酬として株式を交付する場合には、その株式に一定の譲渡制限期間が付されていることを条件に、有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提出をもって募集又は売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)が設けられているが、スタートアップ等の非上場会社がその役員・従業員に株券を交付する場合や、外国企業が日本子会社の役員・従業員に株券を交付する場合についても臨報特例の適用ができるよう検討する。
暗号資産、金融商品となれば申告分離課税に変更も
暗号資産に関しては、資金決済法上の支払・決済手段の1つとなっているが、暗号資産制度に関するワーキンググループでは、金融商品取引法上の枠組みとし、金融商品として位置付けるかどうかなどを検討する。政府が6月13日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」において、「暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品として業法において位置付けるとともに、投資家保護のための制度を整備する法案の早期国会提出を図りつつ、税務当局への報告義務の整備などを行った上で、分離課税の導入を含めた税制面の見直しの検討も併せて行う。」とされたことなどを踏まえたもの。税制については、現行、個人が暗号資産取引により得た利益は原則として雑所得に該当するが、仮に金融商品として位置付けられることになれば、申告分離課税となる可能性も高まることになる(本誌1071号14頁参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























