解説記事2025年07月14日 税制改正解説 令和7年度における法人税関係の改正について(2025年7月14日号・№1082)
税制改正解説
令和7年度における法人税関係の改正について
中澤和真
はじめに
令和7年度税制改正においては、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行うこととされ、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等を引き上げることとされ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充することとされ、国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行うこととされ、これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとされ、関係法令の改正が行われた。
このうち法人税法関係(国際課税関係を除く。)の改正では、リースに関する会計基準を踏まえたオペレーティング・リースの借手における賃借費用の損金算入規定の創設等税制上の整備、一定の協同組合組織が共同で事業を行うための合併及び分割型分割の適格要件の見直し、無対価の非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の算定方法の適正化等の改正が行われ、租税特別措置法等の改正では、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の改正、地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の改正、認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の適用期限の延長等が行われる一方で、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(5G導入促進税制)の廃止等、既存の租税特別措置の整理合理化が行われた。
さらに、令和7年度税制改正においては、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、防衛特別法人税の創設、たばこ税の税率の特例等の創設が行われた。法人税法(以下「法法」という。)、租税特別措置法(以下「措法」という。)及び防衛特別法人税の創設等のための、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「防衛財確法」という。)等の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」は、去る3月31日に参議院本会議で可決・成立し、同日に令和7年法律第13号として公布された。
Ⅰ 法人税法の改正
一 リースに関する会計基準等への対応
(1)賃貸借取引に係る費用の損金算入
法人が賃貸借取引によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づきその法人が支払うこととされている金額があるときは、その支払うこととされている金額のうちその各事業年度において債務の確定した部分の金額は、その各事業年度において損金の額に算入することとする別段の定めが設けられた(法法53)。
① 賃貸借取引
本制度の対象となる賃貸借取引は、資産の賃貸借で法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引以外のもの(いわゆるオペレーティング・リース取引)とされている(法法53①)。
② 対象金額
本制度の対象となる金額は、賃貸借取引に係る契約に基づき支払うこととされている金額とされている(法法53①)。すなわち、付随費用を含む借手の支払リース料が本制度の対象となる。
ただし、次の金額は、対象金額から除くものとされている。
イ 収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
これらの原価の額は、会計上収益に対応させて経理した金額が損金算入されることとなる(法法22③④)。
ロ 法人税法上の固定資産及び繰延資産として計上される費用の額
これらの額は、各事業年度において減価償却資産及び繰延資産の償却費として会計上経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金算入されることとなる(法法31①、32①)。
③ 損金算入額
上記①の賃貸借取引に係る上記②の対象金額がある場合には、その対象金額のうちその賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において債務の確定した部分の金額を、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされている(法法53①)。
(2)リース資産の償却限度額等
① リース期間定額法
所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされるリース資産の償却限度額の計算上選定することとされるリース期間定額法の計算の基礎となるリース資産の取得価額について、その所有権移転外リース取引に係る契約が令和9年3月31日後に締結されたものにあっては、その取得価額に含まれる残価保証額に相当する金額を控除しないこととされた(法令48の2①六)。
また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされるリース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合のその評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度におけるリース期間定額法の計算の基礎となるリース資産のその評価換え等の直後の帳簿価額について、その所有権移転外リース取引に係る契約が令和9年3月31日後に締結されたものにあっては、その取得価額に含まれる残価保証額に相当する金額を控除しないこととされた(法令48の2④)。
上記の改正に伴い、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされるリース資産でその所有権移転外リース取引に係る契約が令和9年3月31日後に締結されたものの償却可能限度額が、その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額(改正前:その取得価額からその減価償却資産に係る残価保証額を控除した金額に相当する金額)とされた(法令61①二イ)。すなわち、その所有権移転外リース取引に係る契約が同日後に締結されたリース資産については、リース期間内において定額で1円(備忘価額)まで償却できることとなる。
(注)令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る。)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置が講じられた(改正法令附則7②~⑦、改正法規附則2)。
② 所有権移転外リース取引の範囲
所有権移転外リース取引の要件のうち目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利(以下「割安購入権」という。)に関する要件について、賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を買い取る権利が与えられており、かつ、その権利が割安購入権であることその他の事情によりその権利が行使されることが確実であると見込まれるものであることとされた(法令48の2⑤五ロ)。
③ リース資産につき賃借人が損金経理をした金額
法人税法第64条の2第1項の規定により売買があったものとされたリース資産につき賃借人がそのリース資産を賃借するために支出した費用として損金経理をした金額(賃借料として損金経理をした金額を除く。)は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされた(法令131の2③)。同条第2項の規定により金銭の貸付けがあったものとされた場合の賃借に係る資産につき譲渡人がその資産を賃借するために支出した費用として損金経理をした金額(賃借料として損金経理をした金額を除く。)についても、同様である。
(3)リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
制度が廃止された(旧法法63、旧法令124~128)。これにより、リース取引によるリース資産の引渡しを行った場合には、原則として、法人税法第22条及び第22条の2の規定により、そのリース資産の引渡しに係る収益の額及び費用の額をその引渡しの日の属する事業年度において益金の額及び損金の額に算入することとなる。また、本制度の廃止に伴い、所要の整備が行われた。
なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置が講じられた(改正法附則17③~⑦)。
二 組織再編税制
(1)一定の協同組合組織が共同で事業を行うための合併及び分割型分割の適格要件の見直し
共同で事業を行うための組織再編成のうち合併及び分割型分割(以下「共同事業合併等」という。)に係る適格要件について、その共同事業合併等に係る当事者が「法人税法別表第2又は別表第3に掲げる法人のうち、その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体」(以下「対象組合」という。)のみである場合には、事業規模要件及び特定役員引継要件を除外することとされた(法令4の3④⑧)。
対象組合とは、具体的には、次の法人をいう(法規3の2)。
① 法人税法別表第2に掲げる法人(公益法人等)のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合
② 法人税法別表第3に掲げる法人(協同組合等)のうち、次のもの以外のもの
イ 漁業生産組合
ロ 生活衛生同業組合
ハ 生活衛生同業組合連合会
ニ 生産森林組合
ホ 農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行うものに限る。)
(注)上記①の「農業協同組合連合会」には、公的医療機関に該当する病院等を設置する一定の厚生農業協同組合連合会のほか、法人税法別表第2に掲げる法人とみなされている特例農業協同組合中央会(法法附則19の2①)についても該当する。
(2)通算法人の行う分割型分割及び株式分配に係る減少資本金額等の計算方法の整備
通算法人の行った分割型分割及び株式分配(以下「分割型分割等」という。)について、その分割型分割等により通算子法人が通算グループから離脱することとなる場合の資本金等の額、みなし配当及び所有株式の部分譲渡損益の計算方法が見直された。
① 資本金等の額から減少する金額
通算法人が行った分割型分割等により調整対象通算法人の株式等を分割承継法人に移転し、又は現物分配法人の株主等に交付する場合には、その分割型分割等に係る調整対象通算法人の株式等の帳簿価額については修正前帳簿価額及び修正帳簿価額により調整した金額を用いて、資本金等の額から減少する金額を計算することとされた(法令8①十五・十七②)。
② 所有株式に対応する資本金等の額
通算法人が行った分割型分割等により調整対象通算法人の株式等を分割承継法人に移転し、又は現物分配法人の株主等に交付する場合には、その分割型分割等に係る調整対象通算法人の株式等の帳簿価額については修正前帳簿価額及び修正帳簿価額により調整した金額を用いて、みなし配当の額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額を計算することとされた(法令23①二・三②)。
③ 所有株式の譲渡原価
上記②の改正により、通算法人である分割法人等の株主等である法人が分割型分割等により分割承継法人又は完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、その分割法人等が分割型分割等の直前の時において調整対象通算法人の株式等を有するときは、その株主等である法人が有する分割法人等の株式等の部分譲渡損益の計算に係る譲渡原価は、その分割型分割等の直前のその有する分割法人等の株式等の帳簿価額に、その分割型分割等に係る上記②の調整後の分割移転割合及び分配移転割合を乗じて計算した金額となる(法令119の8①、119の8の2①)。
また、通算法人である分割法人等が分割型分割等を行った場合にその株主等である法人に通知しなければならない割合についても同様である(法令119の8②、119の8の2②)。
(3)無対価の非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の算定方法の適正化
① 移転を受けた資産及び負債が債務超過である場合において非適格合併等対価額が0であるときの資産調整勘定の金額の算定方法の適正化
資産調整勘定の金額の算定について、移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額が、その移転を受けた資産の取得価額の合計額からその移転を受けた負債の額の合計額を減算した金額とすることとされた(法法62の8①)。なお、差額負債調整勘定の金額の算定についてもこの時価純資産価額を用いることとなる(法法62の8③)。
② 対価の交付が省略されたと認められる非適格合併等に係る調整勘定の算定方法の適正化
非適格合併等により被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた法人が株式その他の資産を交付しなかった場合の資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額の算定について、その対象となる非適格合併等が、無対価合併で一定の関係があるもの又は無対価分割で一定の関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式等(その分割承継法人が有する自己の株式等を除く。)の全部を保有する関係があるもの、いわゆる対価の交付が省略されたと認められる非適格合併等に限ることとされた(法法62の8⑫、法令123の10⑯)。
また、対価の交付が省略されたと認められる非適格合併等の場合の資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額の算定方法が次のとおりとされた(法令123の10⑯)。
イ その非適格合併等に際して一定の資産評定を行っている場合(ロの場合を除く。)
(イ)の金額が(ロ)の金額以上である場合のその差額に相当する金額((イ)の金額が(ロ)の金額と同額である場合には、0)を資産調整勘定の金額とし、(ロ)の金額が(イ)の金額を超える場合のその超える部分の金額を差額負債調整勘定の金額とすることとされた(法令123の10⑯一)。
(イ)その非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権(独立取引営業権を除く。)のその一定の資産評定による価額(改正前と同様。)
(ロ)その非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務でその履行に係る負担の引受けをしたものの額(改正前と同様。)
ロ 次の(イ)及び(ロ)の場合
資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、ないものとされた(法令123の10⑯二)。
(イ)その非適格合併等に際して上記イの一定の資産評定を行っていない場合において、その非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。(ロ)において同じ。)の取得価額の合計額がその非適格合併等により移転を受けた負債の額(退職給与債務引受額及び短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額及び上記イ(ロ)の金額を含む。(ロ)において同じ。)の合計額以上であるとき
(ロ)その非適格合併等により移転を受けた資産の取得価額(その非適格合併等に際して上記イの資産評定を行っている場合には、上記イ (イ)の営業権の価額を含む。)の合計額がその非適格合併等により移転を受けた負債の額の合計額に満たない場合(改正前と同様。)
三 その他
1 公共法人の範囲
公共法人の範囲について、次の改正が行われた。
① 社会保険診療報酬支払基金の名称及び根拠法の題名について、所要の改正が行われた(法法別表1)。
② 公共法人となる独立行政法人の範囲から、国立研究開発法人国立国際医療研究センターが除外された。
2 公益法人等の範囲及び収益事業から除外される事業の範囲
① 公益法人等の範囲
イ 公益法人等の追加・除外
(イ)日本学術会議法により設立される日本学術会議が追加された(法法別表2)。
(ロ)石炭鉱業年金基金法の廃止に伴い、石炭鉱業年金基金が除外された(法法別表2)。
ロ 非営利型法人の範囲の見直し
非営利型法人の要件のうち残余財産の帰属先に関する要件について、その帰属先の範囲に「その残余財産が公益信託の信託財産とされる場合におけるその公益信託の受託者」が追加された(法令3①二②五)。
ハ 社会医療法人に対する税制上の措置
社会医療法人の認定要件のうち次の要件について、医療法施行規則の改正により、それぞれ次の見直しが行われた。
(イ)社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件
A 社会保険診療等に係る収入金額の範囲に、補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含めることとされた。
B 全収入金額を医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)とすることとされた。
(ロ)医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であることとの要件
従前の医療診療による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを法令上明確化するとともに、医療診療による収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額のうち本来業務に係るものを含めることとされた。具体的には、「病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうちその業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、その業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること」とされた。
(ハ)本来業務に係る費用の額が経常費用の額の100分の60を超えることとの要件
従前の本来業務に係る費用の額及び経常費用の額の範囲に係る取扱いを法令上明確化するとともに、下限となる割合が100分の63とされた。具体的には、「病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)が全ての業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)の100分の63を超えること」とされた。
ニ マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置
(イ)マンション除却組合に対する税制上の措置
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正により、改正後のマンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「マンション再生法」という。)により設立されるマンション除却組合を公益法人等とみなし、収益事業から生ずる所得についてのみ課税することとされた。また、マンション除却組合に適用される税率は普通法人と同様とするほか、みなし寄附金の規定は適用しないこととされた(法法2六、37、66、マンション再生法163の32①)。
(ロ)マンション建替組合及びマンション敷地売却組合の改組
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正により、マンションの再生をより円滑にするための事業類型が追加されるなど、公益法人等とみなすこととされている同法により設立されるマンション建替組合及びマンション敷地売却組合の事業手続等が整備され、これに伴い、それぞれ「マンション再生組合」及び「マンション等売却組合」に改組された(マンション再生法44①、139①)。
② 収益事業から除外される事業の範囲
収益事業から除外される事業の範囲について、次の見直しが行われた(法令5①)。
イ 不動産販売業及び不動産貸付業
収益事業から除外される民間都市開発推進機構が参加業務(民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定に基づく業務)として行う不動産販売業及び不動産貸付業に、都市再生特別措置法第71条第1項第1号に規定する緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に要する費用の一部を負担して行うものが追加された(法令5①二ホ・五ト)。
ロ 医療保健業
(イ)収益事業から除外される医師会法人等がその開設する病院又は診療所において行う医療保健業(法令5①二十九ヲ)の要件のうち公的な事業運営等に係る要件(法規5六)における社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の60を超えることとの基準について、次の見直しが行われた。
A 社会保険診療等に係る収入金額の範囲に、補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含めることとされた。
B 全収入金額を医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)とすることとされた。
(ロ)収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する一定の厚生農業協同組合連合会が行う医療保健業(法令5①二十九ワ)の要件のうち公的な事業運営等に係る要件(法規5の2①三)における社会保険診療等に係る収入金額の合計額が事業収益の額の100分の80を超えることとの基準について、次の見直しが行われた。
A 社会保険診療等に係る収入金額の範囲に、補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含めることとされた。
B 事業収益の額を医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)とすることとされた。
(ハ)収益事業から除外される無料又は低額な料金による診療事業等を行う公益法人等が行う医療保健業(法令5①二十九ヨ)の要件のうち公的な事業運営等に係る要件(法規6七)における社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの基準について、次の見直しが行われた。
A 社会保険診療等に係る収入金額の範囲に、補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含めることとされた。
B 全収入金額を医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)とすることとされた。
ハ 請負業
収益事業から除外される国民健康保険団体連合会が一定の者の委託を受けて行う請負業について、一定の者である社会保険診療報酬支払基金の名称が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に変更された(法令5①十ホ(3))。
3 減価償却資産
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の試掘権(以下「貯留試掘権」という。)に関する規定の施行に伴い、貯留試掘権について、次のとおり整備が行われた。
① 減価償却資産の範囲の見直し
貯留試掘権が、減価償却資産(無形固定資産)とされた(法令13八ロ)。
② 貯留試掘権の償却方法
貯留試掘権の償却方法は、定額法とされている(法令48の2①四)。
③ 貯留試掘権の耐用年数
貯留試掘権の耐用年数は、6年とされている(耐用年数省令1②二イ)。
4 寄附金の損金不算入
① 特定公益増進法人の範囲
特定公益増進法人の範囲に、国立健康危機管理研究機構が追加された(法令77二)。
② 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例における損金算入限度額の計算の基礎となる公益目的事業の実施のために必要な金額の算出方法の見直し
公益社団法人又は公益財団法人の一般の寄附金の損金算入限度額の計算の特例における公益法人特別限度額の計算の基礎となる公益目的事業の実施のために必要な金額の算出方法が見直された(法規22の5①)。
5 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
対象となる国庫補助金等に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第3号の2に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の補助金が追加された(法令79三)。
6 不正行為等に係る費用等の損金不算入
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の制定による課徴金制度(自社OSを通じたアプリストアの限定、他社のアプリストアの利用妨害等の禁止行為をした特定ソフトウェア事業者に対して公正取引委員会がその行為に係る商品又は役務の売上額の20%相当額を課徴金として納付することを命ずる制度)の導入に伴い、損金不算入の対象となる費用等に同法の規定による課徴金及び延滞金が追加された(法法55⑤八)。
7 有価証券の譲渡損益
特定受益証券発行信託の元本の払戻しがあった場合における受益権の譲渡損益の計算方法等の整備が行われた。
① 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入
法人がその有する特定受益証券発行信託の受益権(①において「所有受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の元本の払戻し(以下「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合における所有受益権の譲渡損益の計算については、その譲渡原価は、その所有受益権の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として計算した金額とすることとされた(法法61の2⑳)。
イ 特定受益証券発行信託の元本の払戻し
上記の特定受益証券発行信託の元本の払戻しは、その特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除くこととされている(法法61の2⑳)。
ロ 元本の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として計算した金額
上記の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として計算した金額は、具体的には、上記の払戻しの直前のその所有受益権の帳簿価額に次の割合(元本減少割合)を乗じて計算した金額とされている(法令119の9の2①)。
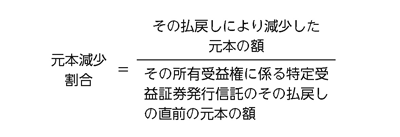
(注)上記の割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。
ハ 元本減少割合の通知
上記の所有受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、払戻しを行った場合には、その所有受益権を有していた法人に対し、上記ロの元本減少割合を通知しなければならないこととされた(法令119の9の2②)。
ニ 譲渡損益の益金又は損金算入時期
特定受益証券発行信託の元本の払戻しとして金銭の交付を受けたことによるその特定受益証券発行信託に係る受益権の譲渡損益の益金又は損金算入時期が、その元本の払戻しの日の属する事業年度とされた(法規27の3十八)。
② 特定受益証券発行信託の元本の払戻しがあった場合の有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法
法人がその有する特定受益証券発行信託の受益権(②において「旧受益権」という。)に係る払戻しとして金銭の交付を受けた場合で、その旧受益権につき1単位当たりの帳簿価額の算出方法として移動平均法を採用しているときは、その1単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその交付の直前の帳簿価額から上記①ロの金額(譲渡原価)を控除した金額を所有受益権の数で除して計算した金額とすることとされた(法令119の3 )。
)。
また、法人が旧受益権に係る払戻しとして金銭の交付を受けた場合で、その旧受益権につき1単位当たりの帳簿価額の算出方法として総平均法を採用しているときは、その1単位当たりの帳簿価額は、事業年度開始の時からその交付の直前の時までの期間(以下「交付前期間」という。)及びその交付の時から事業年度終了の時までの期間(以下「交付後期間」という。)をそれぞれ1事業年度とみなして総平均法により算出することとされた(法令119の4①)。この場合において、その交付後期間の開始の時における所有受益権の帳簿価額は、その交付前期間を1事業年度とみなして総平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額にその交付前期間の終了の時における旧受益権の数を乗じて計算した金額をその旧受益権のその交付の直前の帳簿価額とみなして上記の移動平均法の計算の例により算出したその交付の直後のその1単位当たりの帳簿価額に、その所有受益権の数を乗じて計算した金額とすることとされている(法令119の4①後段)。
Ⅱ 租税特別措置法の改正
第一 税額控除等関係
一 中小企業者等の法人税率の特例
(1)適用税率の見直し
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、その事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%(改正前:15%)とされた(措法42の3の2①)。
法人又は人格のない社団等の事業年度が1年に満たない場合には、上記の「年10億円」は、10億円を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額とすることとされている(措法42の3の2③)。
なお、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)が認定を取り消された場合において、租税特別措置法第66条の11の3第4項の適用を受けるときは、その適用を受ける事業年度が1年に満たない場合であっても、上記の月数按分は行わないこととされた(措法66の11の3④)。
(2)対象法人の除外
対象法人から通算法人が除外された(措法42の3の2①②旧③)。
(3)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法42の3の2①②)。
二 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)
特別研究機関等との共同研究及び特別研究機関等に対する委託研究について、特別研究機関等に国立健康危機管理研究機構が追加された(措令27の4 一ニ)。
一ニ)。
また、対象となる金額は、試験研究費の額のうちその試験研究に要した費用(その試験研究に係る契約又は協定においてその法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額で、その金額が生じた事業年度の確定申告書等にその認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とされた(措規20 一・二)。
一・二)。
三 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(中小企業投資促進税制)
(1)対象法人の見直し
① 対象となる中小企業者から除くこととされる発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人及びその発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人から、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1を超える数又は金額の株式又は出資が一定の承認会社の所有に属している農地所有適格法人を除くこととされた(措法42の6①、措令27の6①)。すなわち、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の農地所有適格法人のうち、その農地所有適格法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1を超える数又は金額の株式又は出資が一定の承認会社の所有に属するものは、その一定の承認会社が大規模法人に該当する場合であっても、中小企業者に該当し、その農地所有適格法人が適用除外事業者に該当する場合を除き、この制度の適用を受けることができる。
② 対象となる中小企業者等の範囲から特定認定を受けた特定事業者等に該当するもののうちその特定認定に係る特定経営力向上計画に一定の減価償却資産が記載されているものを除くこととされた(措法42の6①)。
(2)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法42の6①)。
四 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度
(1)対象施設の見直し
観光地形成促進地域に係る措置の対象施設から、国際健康管理・増進施設(その施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)が除外された(措規20の4①二②三)。
(2)対象事業の見直し
制度の対象となる事業について、次の見直しが行われた。
① 情報通信産業振興地域に係る措置の対象事業から、パッケージソフトウェア業が除外された(措令27の9⑤)。
② 産業イノベーション促進地域に係る措置の対象事業から、デザイン業が除外された(措令27の9⑦)。
(3)対象地域の見直し
国際物流拠点産業集積地域に係る措置の対象地域(国際物流拠点産業集積地域の区域)について、次の見直しが行われた。
① 対象地域に、津嘉山地区、照屋地区及び神里地区(南風原町)並びに友寄地区(八重瀬町)が追加された。
② その全域が対象であった那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市及び糸満市の区域について、国際物流拠点産業の集積が見込まれる地区に限定された。
(4)その他
① 措置期間の見直し
観光地形成促進地域に係る措置、情報通信産業振興地域に係る措置、産業イノベーション促進地域に係る措置及び国際物流拠点産業集積地域に係る措置における主務大臣の確認要件に係る措置期間(措置開始事業年度の初日から措置終了事業年度の末日までの期間)について、措置開始事業年度が対象資産を事業の用に供した日の属する事業年度(改正前:対象措置の実施期間の開始の日の属する事業年度)に変更されるなど、その適正化が行われた。
② 対象資産に係る改正
5G導入促進税制の廃止に伴い、対象資産のうち特定高度情報通信技術活用システム(5G情報通信システム)に該当するものについて5G導入促進税制の対象となるものに限ることとしていた規定が削除された(措法42の9①)。
(5)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法42の9①、措令27の9①一~五)。
五 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
(1)特別償却割合の引下げ
機械及び装置並びに器具及び備品の特別償却割合が、35%(改正前:40%)に引き下げられた(措法42の11の2①一)。
(2)投資規模要件の引上げ
特定地域経済牽引事業施設等に係る投資規模要件が1億円以上(改正前:2,000万円以上)に引き上げられた(措令27の11の2①)。
(3)特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係る措置の見直し
特別償却割合を50%に、税額控除割合を5%に、それぞれ引き上げる措置(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものである場合の基準)について、次の見直しが行われた。
① 措置の対象に、その承認地域経済牽引事業について、評価委員会において先進的であると認められた場合で、かつ、次のいずれにも該当する場合が追加された。なお、計画承認日が令和7年4月1日以後である必要がある。
イ 承認地域経済牽引事業が次のいずれかに該当すること。
(イ)指定業種に該当すること。
指定業種とは、その承認地域経済牽引事業計画の承認(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の承認をいう。以下同じ。)の際に適合すると認められた同意基本計画(同法第6条に規定する同意基本計画をいう。以下同じ。)において同法第4条第1項に規定する市町村及び同項に規定する都道府県が基本方針(地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(令和2年9月総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)をいう。)第一ハ(2)に基づき指定した業種をいう。
(ロ)対象事業の特定取引先(その対象事業に関する直接の取引先であってその対象事業の出荷額又は仕入額のうちにその取引先に対する出荷額又はその取引先からの仕入額の占める割合が50%を超える場合におけるその取引先をいう。)の行う対象事業者からの仕入れ(その対象事業に係るものに限る。)又は対象事業者に対する出荷(その対象事業に係るものに限る。)に係る事業(その対象事業に係る承認の際に適合すると認められた同意基本計画の促進区域(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。)内において行われるものに限る。)が指定業種に該当するものであること。
ロ 承認地域経済牽引事業が1億円以上の付加価値額を創出すると見込まれるものであること。
ハ 減価償却資産の取得予定価額の合計額が10億円以上であること。
ニ 承認地域経済牽引事業について、減価償却資産を事業の用に供した事業年度から5年間の労働生産性の伸び率の年平均が5%以上(対象事業者が下記③の見直し後の中小企業者である場合にあっては、4%以上)となることが見込まれること及び減価償却資産を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から5年間の投資収益率の年平均が5%以上となることが見込まれること。
② 本措置の適用要件に、「承認地域経済牽引事業が1億円以上の付加価値額を創出すると見込まれるものであること」が追加された。
③ 本措置の適用要件に係る労働生産性の伸び率の年平均が4%以上とされる中小企業者について、中小企業基本法の中小企業者から地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の中小企業者にその範囲が変更された。
(4)地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準の見直し
① 先進性に係る要件について、次の運用の改善が行われた。
イ 「労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定水準以上となることが見込まれること」の確認が不要とされた。
ロ 先進性が認められない事業の明確化その他の評価委員の評価精度の向上に向けた次の措置が講じられた。
(イ)ガイドラインにおいて示されている先進性が認められないものの類型について、評価委員は、担当する全ての案件についてその類型に該当するか否かを明確に判断して、その内容を書面で提出することとされた。その上で、評価委員の1名以上がその類型に該当するものとして先進性が無いと評価した場合には、他の評価委員の評価にかかわらず、その対象事業を先進性が無いものとして取り扱うこととされた。
(ロ)上記(イ)の場合以外の場合において、評価委員の1名以上が、その対象事業について先進性が無いと評価したときは、その対象事業につき評価を担当した評価委員において合議を行った上で、最終的な先進性の有無を改めて評価することとされた。その際、評価委員は、再評価の詳細及び最終評価を書面で提出することとされている。
(ハ)評価委員は、先進性を有すると評価する場合には、ガイドラインで示されている先進性の類型のどの類型に該当するのかについて評価し、その評価の詳細を書面で提出することとされた。また、評価委員は、専門家として独立した立場で、独自の調査・検討を基にその先進性を評価すべきであることが、ガイドラインにおいて明記された。なお、その評価の際は、評価委員の先進性評価の補助を目的として経済産業省にて措置されている委託事業を、積極的に活用することとされている。
(ニ)確認申請に係る申請書の様式が改定され、確認申請をする承認地域経済牽引事業者は、その承認地域経済牽引事業が先進性を有することについて、自らも説明を要することとされた。
② 対象となる事業類型からサプライチェーン類型が除外された。
③ 承認地域経済牽引事業について、次のいずれかに該当することとの要件が追加された。
イ 減価償却資産を事業の用に供した事業年度から5年間の対象事業の労働生産性の伸び率の年平均が4%以上となることが見込まれること。
ロ 減価償却資産を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から5年間の対象事業の投資収益率の年平均が5%以上となることが見込まれること。
④ 減価償却資産の取得予定価額の合計額に係る規模要件が1億円以上(改正前:2,000万円以上)に引き上げられた。
⑤ 対象事業者が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額がその対象事業者の前事業年度における減価償却費の額の20%以上の額であることとの要件について、次の見直しが行われた。
イ 対象事業者の直接又は間接の出資者のうちに外国法人等が含まれている場合で、かつ、その外国法人等が直接又は間接に有する対象事業者の議決権の数のその対象事業者の議決権の総数のうちに占める割合が50%を超える場合(その対象事業者が連結会社に該当する場合を除く。)には、その対象事業者の前事業年度における減価償却費の額は、その減価償却費の額(事業年度の期間が1年未満である場合にあっては、その減価償却費の額を1年当たりの額に換算した額)に、その外国法人等の前事業年度における減価償却費の額(事業年度の期間が1年未満である場合にあっては、その減価償却費の額を1年当たりの額に換算した額)の合計額を加えて得た額とすることとされた。
ロ 前事業年度における減価償却費の額に乗ずる割合が25%(改正前:20%)に引き上げられた。
(5)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和10年3月31日まで3年延長された(措法42の11の2①)。
六 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度
(1)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和10年3月31日まで3年延長された(措法42の12の2①)。
(2)その他関係法令の改正
① 寄附活用事業に係る執行上のチェック機能の強化
寄附活用事業を実施した認定地方公共団体は、寄附活用事業の完了の時及び各会計年度終了の時に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととされた。ただし、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の日以後速やかに内閣総理大臣にまち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施状況確認結果報告書を提出しなければならないこととされている。
イ 寄附活用事業の企画・立案に、その認定地方公共団体以外の者が関与している場合において、その者とその寄附活用事業に関連する寄附金を支出した法人又はその法人の関係会社(以下「寄附法人等」という。)との間に取引等の関係があるとき……その寄附金を支出した法人からその寄附活用事業に関連する寄附金を受領した日
ロ 寄附活用事業の企画・立案に、その認定地方公共団体以外の者が関与している場合において、その者がその寄附活用事業に係る事業の契約の相手方となったとき……その契約の締結の日
ハ 寄附活用事業に係る事業の歳出予算がその認定地方公共団体の議会において議決される前にその寄附活用事業に関連する寄附金を受領した場合……その寄附金を受領した日
② 寄附活用事業の実施状況の透明化
イ 認定地方公共団体が、その実施する寄附活用事業に関連する寄附金を受領した場合において、その寄附活用事業に係る契約等が次のいずれかに該当するときは、その認定地方公共団体は内閣総理大臣にその寄附金を支出した法人の名称を報告するとともに、その寄附金を支出した法人の名称を公表することとされた。ただし、寄附金を支出した法人がその名称の公表を希望しない場合であって、その公表を希望しない理由が正当であることについて、その寄附金を受領した認定地方公共団体が第三者を含む審議会等の確認を受けたときは、公表しないことができることとされている。
(イ)その寄附活用事業に係る事業の入札において応札者が一の者又は一の者とその者の関係者のみであり、かつ、その事業に係る契約者等が寄附法人等である場合
(ロ)その寄附活用事業に係る事業に関する契約が随意契約(少額のものを除く。)であり、かつ、その事業に係る契約者等が寄附法人等である場合
(ハ)その寄附活用事業に係る補助金の交付申請者が一の者又は一の者とその関係者のみであり、かつ、その補助金の交付先等が寄附法人等である場合
(ニ)その寄附活用事業に係る負担金の拠出先が一の者又は一の者とその関係者のみであり、かつ、その負担金の拠出先等が寄附法人等である場合
ロ 上記イの報告を受けた内閣総理大臣は、その報告を受けた寄附活用事業及び寄附金を支出した法人の名称(その名称を公表しない場合は、その理由)を公表することとされた。
ハ 認定地方公共団体は、寄附活用事業に係る事業について、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約(少額のものを除く。)により契約の相手方を選定した場合には、その寄附活用事業に係る契約の相手方を公表することとされた。
③ 地域再生計画の認定取消しを受けた場合の再申請に係る欠格期間の創設
地域再生計画の認定の取消しを受けた地方公共団体は、その取消しの日から起算して2年を経過するまでは、地域再生計画の認定を受けることができないこととされた。ただし、地方公共団体が自ら認定の取消しを申し出たことにより地域再生計画の認定が取り消された場合(地域再生計画の認定が取り消されることを予見して申し出た場合を除く。)は、この限りではない。
七 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
(1)適用対象法人の見直し
対象となる中小企業者の範囲が、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者(改正前:同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者)とされた(措法42の12の4①)。
具体的には、対象となる中小企業者から除かれる発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人及びその発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人から、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一定の承認会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1を超える数又は金額の株式又は出資を有する農地所有適格法人を除くこととされた(措法42の6①、42の12の4①、措令27の6①)。
(2)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定を受けた場合の手続のワンストップ化
改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「食品等持続的供給法」という。)において、新たに計画認定制度が創設され、食品等事業者は、食品等持続的供給法の安定取引関係確立事業活動計画等につき農林水産大臣の認定を受けることができることとされた。
安定取引関係確立事業活動計画等には、それぞれの計画に中小企業等経営強化法第2条第10項に規定する経営力向上に関する事項として同法第17条第2項各号及び第4項第2号に掲げる事項(以下「経営力向上に関する事項」という。)を記載することができることとされており、この経営力向上に関する事項の記載のある安定取引関係確立事業活動計画等につき食品等持続的供給法の認定を受ける場合には、中小企業等経営強化法の認定要件を満たす必要があることとされている。また、その安定取引関係確立事業活動計画等(経営力向上に関する事項が記載されているものに限る。以下同じ。)につき食品等持続的供給法の認定を受けた場合については、「中小企業等経営強化法の特例」が設けられており、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定があったものとみなして同法の規定を適用することとされている。すなわち、この「中小企業等経営強化法の特例」の適用がある場合においては、同法の経営力向上計画につき同法の認定を受けた場合と同様の効果・結果となるように措置されているものと考えられる。
これを踏まえ、手続のワンストップ化の観点から、上記の「中小企業等経営強化法の特例」の適用がある場合において、その安定取引関係確立事業活動計画等につき食品等持続的供給法の認定を受けた食品等事業者を本制度の対象となる法人とし、生産等設備を構成する減価償却資産でその認定に係る安定取引関係確立事業活動計画等(食品等持続的供給法第7条第1項の規定又は食品等持続的供給法第8条第7項、第9条第8項若しくは第10条第7項において準用する食品等持続的供給法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された資産を本制度の対象となる資産とすることとされた(措法42の12の4①)。
(3)対象資産の追加
① 対象資産に、次のイからニまでの減価償却資産で、中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする場合におけるその建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する一定のものに限る。)に該当するもの(以下「特定機械装置等」という。)のうちその中小企業者等の特定認定に係る特定経営力向上計画に記載されたものが追加された(措法42の12の4①)。なお、対象資産は、次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の規模のものとされている(措法42の12の4①、措令27の12の4②二)。
イ 機械及び装置……1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ 工具、器具及び備品……1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ 建物及びその附属設備……一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,000万円以上のもの
ニ 一定のソフトウエア……一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの
なお、中小企業者等が上記ハの建物及びその附属設備を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度がその建物及びその附属設備に係る計画確認を受けた投資計画(以下「確認投資計画」という。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度に該当しないときは、その事業の用に供した建物及びその附属設備は、上記の「経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する一定のもの」には該当しないこととされている(措規20の9③)。すなわち、建物及びその附属設備を事業の用に供した事業年度において、確認投資計画に記載した給与支給額増加目標を達成できなかったときは、その事業の用に供した建物及びその附属設備については、特別償却又は法人税額の特別控除の規定の適用を受けることができない。
② 特定機械装置等の特別償却限度額及び税額控除限度額は、次のとおりとされている。
イ 特別償却限度額……次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額とされている(措法42の12の4①二)。
(イ)機械及び装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア……基準取得価額から普通償却限度額に相当する金額を控除した金額(即時償却)(措法42の12の4①二イ)
(ロ)建物及びその附属設備……基準取得価額の15%(特定建物等については、基準取得価額の25%)相当額(措法42の12の4①二ロ)
ロ 税額控除限度額……次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額とされている(措法42の12の4②)。
(イ)上記イ(イ)の減価償却資産……基準取得価額の7%(中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人等がその指定事業の用に供したものについては、10%)相当額(措法42の12の4②一)
(ロ)上記イ(ロ)の減価償却資産……基準取得価額の1%(特定建物等については、2%)相当額(措法42の12の4②二)
(4)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法42の12の4①)。
(5)その他関係法令の改正
中小企業等経営強化法施行規則が改正され、対象資産である中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等について、次の見直しが行われた。
① 対象となる設備等から、暗号資産マイニング業の用に供する設備等が除外された。
② 生産性向上設備の要件のうち経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであることとの要件について、単位時間当たりの生産量、歩留まり率又は投入コストの指標が年平均1%以上向上しているものであることとされた。
③ 収益力強化設備の要件のうち事業者が策定した投資計画における年平均の投資利益率の要件について、事業者が策定した投資計画における年平均の投資利益率が7%(改正前:5%)以上となることが見込まれるものであることとされた。
④ デジタル化設備が対象となる設備等から除外された。
八 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(5G導入促進税制)
適用期限(令和7年3月31日)の到来をもって制度が廃止された(旧措法42の12の6、旧措令27の12の6、旧措規20の10の2)。
九 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度(改正後:生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
(1)デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の廃止
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制は、適用期限(令和7年3月31日)の到来をもって廃止された(旧措法42の12の7①②④⑤、旧措令27の12の7①②、旧措規20の10の3①②)。
(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制に係る手続のワンストップ化
改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「食品等持続的供給法」という。)において、新たに計画認定制度が創設され、食品等事業者は、食品等持続的供給法第9条第1項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき農林水産大臣の認定を受けることができることとされた。
この環境負荷低減事業活動計画には、その食品等事業者が行う産業競争力強化法に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事項として同法第21条の22第3項各号に掲げる事項(以下「エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事項」という。)を記載することができることとされており、このエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事項を記載した環境負荷低減事業活動計画につき食品等持続的供給法の認定を受ける場合には、産業競争力強化法の認定要件を満たす必要があることとされている。また、その環境負荷低減事業活動計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事項が記載されているものに限る。以下同じ。)につき食品等持続的供給法の認定を受けた場合については、「産業競争力強化法の特例」が設けられており、産業競争力強化法第21条の22第1項の認定があったものとみなして同法の規定を適用することとされている。すなわち、この「産業競争力強化法の特例」の適用がある場合においては、同法の事業適応計画につき同法の認定を受けた場合と同様の効果・結果となるように措置されているものと考えられる。
これを踏まえ、手続のワンストップ化の観点から、上記の「産業競争力強化法の特例」の適用がある場合において、その環境負荷低減事業活動計画につき食品等持続的供給法の認定を受けた食品等事業者を本制度の対象となる法人とし、その認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等持続的供給法第9条第8項において準用する食品等持続的供給法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として導入する生産工程効率化等設備の取得等をする場合のその生産工程効率化等設備を本制度の対象となる資産とすることとされた(措法42の12の6①②)。
第二 特別償却関係
一 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度
(1)研究所用の施設の取得等資金に係る要件の引上げ
適用対象となる研究所用の施設の取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額に係る要件が、4億5,000万円以上(改正前:4億円以上)に引き上げられた(措令28の4①一)。
(2)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法44①)。
二 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度
制度の適用の前提となる事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法44の2①)。
三 共同利用施設の特別償却制度
(1)建物の取得価額要件の引上げ
共同利用施設のうち建物の取得価額要件が、650万円以上(改正前:600万円以上)に引き上げられた(措令28の6)。
(2)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法44の3①)。
四 再資源化事業等高度化設備の特別償却制度(創設)
制度の内容
(1)適用対象法人
適用対象となる法人は、青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「再資源化事業等高度化法」という。)第11条第1項又は第16条第1項の認定(以下「認定」という。)を受けたものとされた(措法44の6①)。
(2)適用期間
適用期間は、再資源化事業等高度化法の施行の日から令和10年3月31日までの期間とされた(措法44の6①)。
(3)適用対象資産
適用対象となる資産は、再資源化事業等高度化設備とされた(措法44の6①)。
再資源化事業等高度化設備は、その認定に係る認定計画(認定高度再資源化事業計画又は認定高度分離・回収事業計画をいう。以下同じ。)に記載された廃棄物処理施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、再資源化事業等高度化法第2条第2項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資する一定のもので、一定の規模のものとされた(措法44の6①)。
再資源化事業等高度化法第2条第2項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資する一定のものは、認定計画に記載された廃棄物処理施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定するものとされた(措令28の8の2①)。
また、一定の規模のものは、機械及び装置にあっては、1台又は1基の取得価額が2,000万円以上のものとし、器具及び備品にあっては、1台又は1基の取得価額が200万円以上のものとされた(措令28の8の2②)。
(4)適用対象事業
適用対象となる事業は、高度再資源化事業又は高度分離・回収事業とされた(措法44の6①)。
(5)適用対象事業年度
適用対象となる事業年度は、適用対象法人が、適用期間内に、再資源化事業等高度化設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再資源化事業等高度化設備を製作して、これをその適用対象法人の適用対象事業の用に供した場合におけるその用に供した日を含む事業年度とされた(措法44の6①)。
(6)特別償却限度額
特別償却限度額は、その再資源化事業等高度化設備の取得価額の35%相当額とされた(措法44の6①)。
ただし、その認定計画に従って行う適用対象事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円にその適用対象事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の35%相当額とされた(措法44の6①)。すなわち、特別償却の対象となる再資源化事業等高度化設備の取得価額は、認定計画ごとに20億円が上限となる。
(7)申告要件等
この制度は、確定申告書等に再資源化事業等高度化設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しないこととされた(措法44の6②、43②)。
また、法人が、その取得し、又は製作した機械及び装置並びに器具及び備品(以下「機械等」という。)につき本制度の適用を受ける場合には、その機械等につき本制度の適用を受ける事業年度の確定申告書等にその機械等が再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類を添付しなければならないこととされた(措令28の8の2③)。
(8)特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例
他の特別償却制度と同様に、特別償却不足額については、1年間の繰越しができることとされた(措法52の2)。
(9)準備金方式による特別償却(特別償却準備金)制度
他の特別償却制度と同様に、特別償却の方法として、特別償却の適用を受けることに代えて、準備金方式による特別償却制度の適用(特別償却準備金の積立て)ができるとともに、特別償却準備金積立不足額については、1年間の繰越しができることとされた(措法52の3)。
(10)他の特別償却制度等との重複適用の排除
法人の有する減価償却資産が上記(5)の事業年度において租税特別措置法の規定による特別償却又は税額控除制度等及び震災税特法の規定による特別償却又は税額控除制度のうち、2以上の制度の適用を受けることができるものである場合には、その減価償却資産については、これらの特別償却又は税額控除制度等のうちいずれか一の制度のみを適用することとされた(措法53、61の3④、64⑦、64の2⑭、65⑫、65の7⑦、65の8⑯、67の4⑫、67の5①、震災税特法18の7、措令32、震災税特令18の6)。
五 特定地域における工業用機械等の特別償却制度
(1)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却制度の改正
① 対象事業の見直し
産業イノベーション促進地域に係る措置の対象事業から、デザイン業が除外された(措令28の9④)。
② 対象地域の見直し
国際物流拠点産業集積地域に係る措置の対象地域(国際物流拠点産業集積地域の区域)について、次の見直しが行われた。
イ 対象地域に、津嘉山地区、照屋地区及び神里地区(南風原町)並びに友寄地区(八重瀬町)が追加された。
ロ その全域が対象であった那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市及び糸満市の区域について、国際物流拠点産業の集積が見込まれる地区に限定された。
③ その他
イ 措置期間の見直し
産業イノベーション促進地域に係る措置及び国際物流拠点産業集積地域に係る措置における主務大臣の確認要件に係る措置期間(措置開始事業年度の初日から措置終了事業年度の末日までの期間)について、措置開始事業年度が対象資産を事業の用に供した日の属する事業年度(改正前:対象措置の実施期間の開始の日の属する事業年度)に変更されるなど、その適正化が行われた。
ロ 対象資産に係る改正
5G導入促進税制の廃止に伴い、対象資産のうち特定高度情報通信技術活用システム(5G情報通信システム)に該当するものについて5G導入促進税制の対象となるものに限ることとしていた規定が削除された(措法45①)。
④ 適用期限の延長
各地域に係る措置の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法45①、措令28の9①一~三)。
(2)沖縄の離島において旅館業用建物等を取得した場合の特別償却制度の適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法45②、措令28の9⑧)。
(3)特定地域において産業振興機械等を取得した場合の割増償却制度の改正
① 対象事業の見直し
半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係る措置の対象事業から、コールセンター及び市場等に関する調査の業務並びにその業務により得られた情報の整理等の業務に係る事業が除外された(措令28の9 、措規20の16⑨)。
、措規20の16⑨)。
② 適用期限の延長
半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係る措置の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法45③、措令28の9⑮二・三)。
六 医療用機器等の特別償却制度
(1)医療用機器に係る措置の対象機器の見直し(6機器)
医療用機器のうち高度な医療の提供に資する機器について、対象機器から次の機器が除外された。
内視鏡ビデオ画像システム、超音波軟性十二指腸鏡、歯科用オプション追加型ユニット、据置型アナログ式乳房用X線診断装置、レーザー処置用能動器具及び気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム
(2)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法45の2①~③)。
第三 準備金等関係
一 保険会社等の異常危険準備金制度
(1)保険の種類の見直し
① 異常災害損失の計算における見直し
異常災害損失の計算において、特定保険については、特定保険区分ごとに計算することとされた(措法57の5②)。
なお、特定保険区分に係る異常災害損失が生じた場合に取り崩す異常危険準備金の金額は、特定保険区分に係る異常危険準備金の金額であることが明らかにされている(措法57の5⑥)。
② 洗替保証限度額の計算における見直し
洗替保証限度額の計算において、特定保険については、特定保険区分ごとに計算することとされた(措令33の2⑮)。
③ 火災保険等に係る積立率の特例における見直し
火災保険等に係る積立率の特例において、事業年度終了の日において法人の行う特定保険に係る異常危険準備金の金額がその特定保険の当年度保険料等に30%を乗じて計算した金額を超える場合のその事業年度を特例の対象事業年度から除外することとされた(措令33の2 )。
)。
(2)異常災害損失率の見直し
特定保険の異常災害損失率が55%(改正前:50%)に引き上げられた(措令33の2⑩二)。
(3)適用期限の延長
火災保険等に係る積立率の特例及び火災等共済組合等の共済に係る積立率の特例の適用期限が、令和10年3月31日まで3年延長された(措令33の2
 )。
)。
二 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度
(1)積立限度額の見直し
① 探鉱準備金制度における積立限度額について、その適用を受ける事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかった場合には、改正前の積立限度額から、次のイの金額からロの金額を控除した残額(その残額が改正前の積立限度額に25%を乗じて計算した金額を超える場合には、その計算した金額)を控除することとされた(措法58①)。
イ 当該事業年度における次の金額の合計額
(イ)積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した探鉱準備金の取崩しにより益金の額に算入される金額
(ロ)探鉱準備金の任意の取崩しにより益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額
ロ 当該事業年度において支出する鉱物に係る新鉱床探鉱費の額及び当該事業年度の探鉱用機械設備の償却額の合計額
② 海外探鉱準備金制度における積立限度額について、その適用を受ける事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかった場合には、改正前の積立限度額から、次のイの金額からロの金額を控除した残額(その残額が改正前の積立限度額に25%を乗じて計算した金額を超える場合には、その計算した金額)を控除することとされた(措法58②)。
イ 当該事業年度における次の金額の合計額
(イ)積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した海外探鉱準備金の取崩しにより益金の額に算入される金額
(ロ)海外探鉱準備金の任意の取崩しにより益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額
ロ 当該事業年度において支出する国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の額及び当該事業年度の海外探鉱用機械設備の償却額の合計額
(2)国内鉱業者に準ずる法人の認定に係る要件の見直し
海外探鉱準備金制度の対象となる国内鉱業者に準ずる法人の認定に係る要件のうち、国外子会社への役員及び技術者の派遣に係る要件について、次の見直しが行われた(措令34⑨)。
① その法人の役員の派遣に代えてその法人の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣され、及びその法人又は他の会社の技術者が派遣されている場合にも、本要件を満たすこととされた。
② 技術者から重要な使用人が除外された。
(3)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和10年3月31日まで3年延長された(措法58①②)。
三 農業経営基盤強化準備金制度
(1)積立限度額の見直し
積立限度額の計算の基礎となる金額のうち農用地の取得に充てるための金額について、農用地のうち農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)の区域においてその法人の利用が見込まれるものの取得に充てるための金額(改正前:農用地の取得に充てるための金額)に限定することとされた(措令37の2①一)。
(2)農用地を取得した場合の準備金の取崩事由の整備
次の農用地を取得した場合に、その取得をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得をした農用地の取得価額に相当する金額を益金の額に算入することとされた(措法61の2③二)。
① 認定計画の定めるところにより取得をする租税特別措置法第61条の3第1項に規定する農用地(措法61の2③二イ)
② 農用地(認定計画の定めるところにより取得をするものを除く。)(措法61の2③二ロ)
(3)添付すべき証明書に係る改正
確定申告書等に添付することとされている農林水産大臣の証明書について、その証明書の原本の添付のほか、その写しの添付が可能とされた(措規21の18の2③)。
(4)適用期限の延長
制度の適用期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法61の2①)。
四 農用地等を取得した場合の課税の特例
(1)対象となる農用地の見直し
対象となる農用地が、認定計画の定めるところにより取得をする農用地で農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)にその法人が利用するものとして定められたもの(改正前:認定計画の定めるところにより取得をする農用地)に限定された(措法61の3①)。
(2)圧縮限度額の計算の基礎となる金額の整備
圧縮限度額の計算の基礎となる金額について、その事業年度において交付を受けた交付金等の額のうち、その認定計画に記載された次の固定資産の取得に充てるための金額であって農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額であることにつき農林水産大臣の当該金額である旨の証明書を確定申告書等に添付することにより証明がされた金額とされた(措令37の3③)。
① 農用地で地域計画の区域においてその法人の利用が見込まれるもの
② 特定農業用機械等
(3)添付すべき証明書に係る改正
確定申告書等に添付することとされている農林水産大臣の証明書について、その証明書の原本の添付のほか、その写しの添付が可能とされた(措規21の18の3②③)。
第四 その他の特別措置関係
一 沖縄の認定法人の課税の特例
(1)対象事業の見直し
情報通信産業特別地区に係る措置の対象事業から、パッケージソフトウェア業が除外された。
(2)対象区域の見直し
国際物流拠点産業集積地域に係る措置の対象区域(国際物流拠点産業集積地域の区域)について、次の見直しが行われた。
① 対象区域に、津嘉山地区、照屋地区及び神里地区(南風原町)並びに友寄地区(八重瀬町)が追加された。
② その全域が対象であった那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市及び糸満市の区域について、国際物流拠点産業の集積が見込まれる地区に限定された。
(3)確認期限及び認定期限の延長
情報通信産業特別地区に係る措置及び国際物流拠点産業集積地域に係る措置並びに経済金融活性化特別地区に係る措置の適用の前提となる内国法人の確認期限及び認定期限が、令和9年3月31日まで2年延長された(措法60①②)。
二 特定の医療法人の法人税率の特例
国税庁長官の承認及び承認の取消しの要件のうち厚生労働大臣の証明書の交付に係る要件(措令39の25①一)における次の基準について、それぞれ次の見直しが行われた。
(1)社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの基準
① 社会保険診療等に係る収入金額の範囲に、補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含めることとされた。
② 全収入金額を医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)とすることとされた。
(2)医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であることとの基準
従前の医療診療による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを法令上明確化するとともに、医療診療による収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額のうち本来業務に係るものを含めることとされた。具体的には、「病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうちその業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、その業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること」とされた。
三 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
対象法人から特定認定を受けた特定事業者等に該当するもののうちその特定認定に係る特定経営力向上計画に一定の減価償却資産が記載されているものを除くこととされた(措法67の5①)。
四 特定の公共的施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
本制度は、廃止された(旧措法67の5の2、旧措令39の29)。
五 農業協同組合等の合併に係る課税の特例
適用期限(令和7年3月31日)の到来をもって、制度が廃止された(旧措法68の2、旧措令39の34の2、旧措規22の19の5)。
六 特定目的信託に係る受託法人の課税の特例
超過分配事業年度以後の各事業年度の「金銭の分配の額が分配可能額の90%超であること」とする要件における超過分配額について、その受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額がその受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額(改正前:元本の額)を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額とされた(措令39の35の2⑧一)。
第五 その他
リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(旧法人税法第63条)の廃止に伴い、土地の譲渡等がある場合の特別税率(租税特別措置法第62条の3)における譲渡利益額の計算の基礎となる土地の譲渡等による収益の額、その収益に係る原価の額及びその土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額について、その収益の額、原価の額及び経費の額につきリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の適用を受けているときは特例を適用して計算した金額によることとする措置が廃止された(措令38の4③⑤⑥)。
第六 震災税特法関係
帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等
本制度は廃止された(旧震災税特法18の10、旧震災税特令18の8、旧震災税特規7)。
Ⅲ 防衛特別法人税の創設
1 制度の内容
(1)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があることとされている(防衛財確法8)。防衛特別法人税は、実質的には各事業年度の所得に対する法人税の付加税といえるものであり、納税義務者は各事業年度の所得に対する法人税の納税義務者と同範囲である。したがって、公共法人、収益事業を行わない公益法人等などは防衛特別法人税の納税義務を負わない。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む(防衛財確法7①)。
(2)課税の対象
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課することとされている(防衛財確法9)。
(注)課税事業年度は、法人の令和8年4月1日以後に開始する課税事業年度をいう(防衛財確法11)。
(3)税額の計算
① 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じて計算した金額とされている(防衛財確法14①)。ただし、特定同族会社の特別税率(留保金課税)により、課税標準法人税額に留保金課税により加算された金額(以下「留保税額」という。)が含まれている場合の課税標準法人税額は、下記②イの金額(加算前基準法人税額から基礎控除額を控除した金額)とされている。つまり、留保金課税により加算された法人税の額を除いた基準法人税額に対して防衛特別法人税の額を計算し、この計算した防衛特別法人税の額をもって留保金課税における課税留保金額を算出することとなる(防衛財確法14②)。
② 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とされている(防衛財確法13②一)。ただし、各課税事業年度の基準法人税額に留保税額がある場合の課税標準法人税額は、次のイ及びロの金額の合計額とされている(防衛財確法13②二)。
イ その課税事業年度の加算前基準法人税額から基礎控除額を控除した金額
(注)加算前基準法人税額とは、基準法人税額から留保税額を控除した金額をいう(防衛財確法13②二イ)。
ロ その課税事業年度の基準法人税加算額から基礎控除残額を控除した金額
(注)基準法人税加算額とは、基準法人税額のうち留保税額をいい(防衛財確法13②二ロ)、基礎控除残額とは、基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額をいう(防衛財確法13④)。
③ 留保金課税の適用がある法人の防衛特別法人税の額は、上記①により計算した防衛特別法人税の額に、上記②ロの金額(基準法人税加算額から基礎控除残額を控除した金額)に4%を乗じて計算した金額を加算した金額とされている(防衛財確法15)。
④ 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とされている。ただし、附帯税の額を除く(防衛財確法10)。
イ 所得税額の控除(法法68)
ロ 外国税額の控除(法法69)
ハ 分配時調整外国税相当額の控除(法法69の2)
ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除(法法70)
ホ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除(租法42の12の6⑥⑦)及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額(同法42の12の14①④(同法42の12の6⑥⑦に係る部分に限る))
ヘ 控除対象所得税額等相当額の控除(租法66の7④、66の9の3③)
⑤ 基礎控除額は、年500万円とされている(防衛財確法13③一)。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額又は加算前基準法人税額の比で配分した金額とされている(防衛財確法13③二)。
(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
⑥ 次のイ~ニの順序により税額控除を行うこととされている。
イ 分配時調整外国税相当額の控除(防衛財確法17)
ロ 控除対象所得税額等相当額の控除(防衛財確法18)
ハ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除(防衛財確法19)
ニ 外国税額の控除(防衛財確法16)
(4)申告及び納付等
① 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない(防衛財確法21①)。ただし、法人税中間申告書の提出義務のない公益法人等は提出義務がない。
また、法人税中間申告書に記載すべき中間申告に係る法人税の額が10万円以下であることや、法人税の額がないことにより、法人税中間申告書の提出を要しない場合も、防衛特別法人税の中間申告書の提出は不要とされている。
さらに、いわゆる仮決算を行って所得の金額又は欠損金額を計算して、その所得の金額又は欠損金額、所得の金額につき計算した法人税の額等を記載した中間申告書を提出する法人は、防衛特別法人税においても、同様に仮決算による法人税の額を課税標準とする中間申告書を提出しなければならないこととされている(防衛財確法22①)。
なお、これらの提出すべき防衛特別法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その提出すべき防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなされ、納付すべき防衛特別法人税の中間納付額が確定する(防衛財確法24)。
② 防衛特別法人税の納税地、申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の納税地、申告期限及び納期限と同一である(防衛財確法12、21、25、29及び30)。すなわち、防衛特別法人税の申告をする法人は、中間申告の場合は、各課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、確定申告の場合は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、所定の事項を記載した申告書を提出し、税額の記載がある場合はその申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。
また、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合には、税務署長は期日を指定して申告期限を延長できることとされているほか、定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより期末後2月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にある場合には、申告期限を延長できることとされている。防衛特別法人税は法人税の額を基礎として計算するものであることから、法人税において申告期限が延長される場合には、防衛特別法人税の申告期限も自動的に法人税の申告期限まで延長することとされている(防衛財確法25④)。
③ 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様である。すなわち、特定法人である内国法人が提出する防衛特別法人税中間申告書若しくは防衛特別法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書及び添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を、電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより、行わなければならないこととされている(防衛財確法27①)。具体的には、e-Taxによる電子申告を行うこととなる。
なお、令和8年4月1日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度(特定法人でなかったその内国法人について通算承認の効力が生じた場合におけるその通算承認の効力が生じた日の属する課税事業年度を除く。)開始の日において特定法人であるものは、同日以後1月以内に電子申告の開始届出を行わなければならないこととされているが、令和8年4月1日前に既に法人税の申告について電子情報処理組織による申告を行う旨の届出をしている内国法人は、開始届出を行うことを要しないこととされている(防衛特別法人税に関する省令附則②)。
(注)特定法人とは、その課税事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等一定の大規模法人を指し、その範囲は法人税及び地方法人税と同様である。
④ 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額を還付することとされている(防衛財確法32①)。
⑤ 各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付することとされている(防衛財確法33①)。つまり、法人税における欠損金の繰戻し還付の請求をすることにより、請求額に相当する防衛特別法人税の還付も受けられることとなる。
(5)その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずることとされている(防衛財確法42、44~48)。
2 適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされている(改正法附則62①)。ただし、防衛特別法人税の中間申告に係る規定は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされている(改正法附則62②)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























