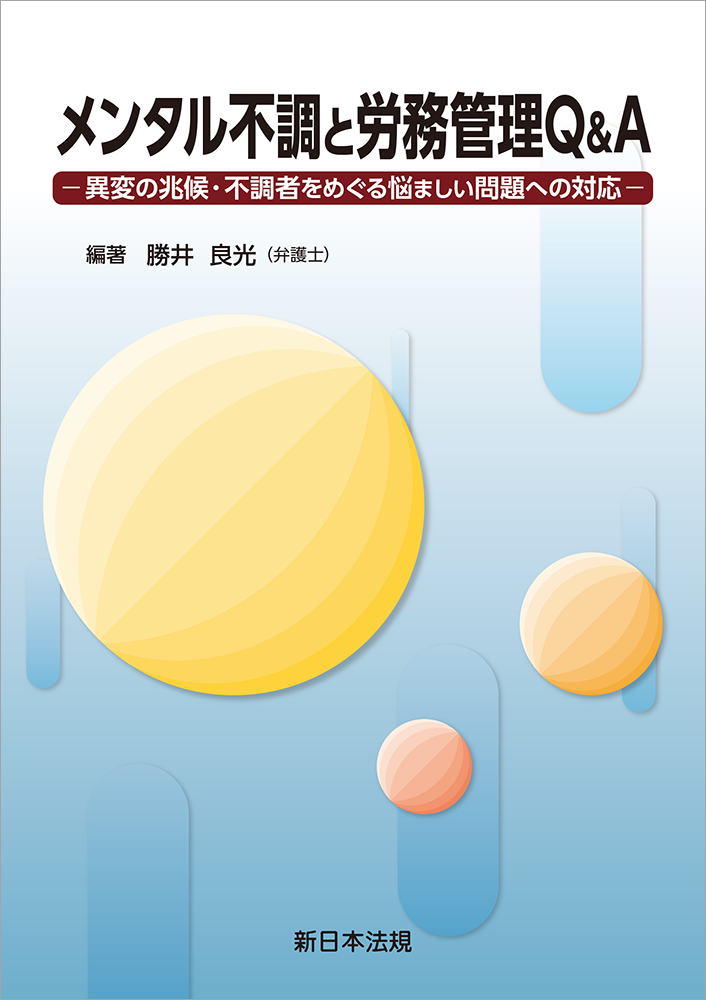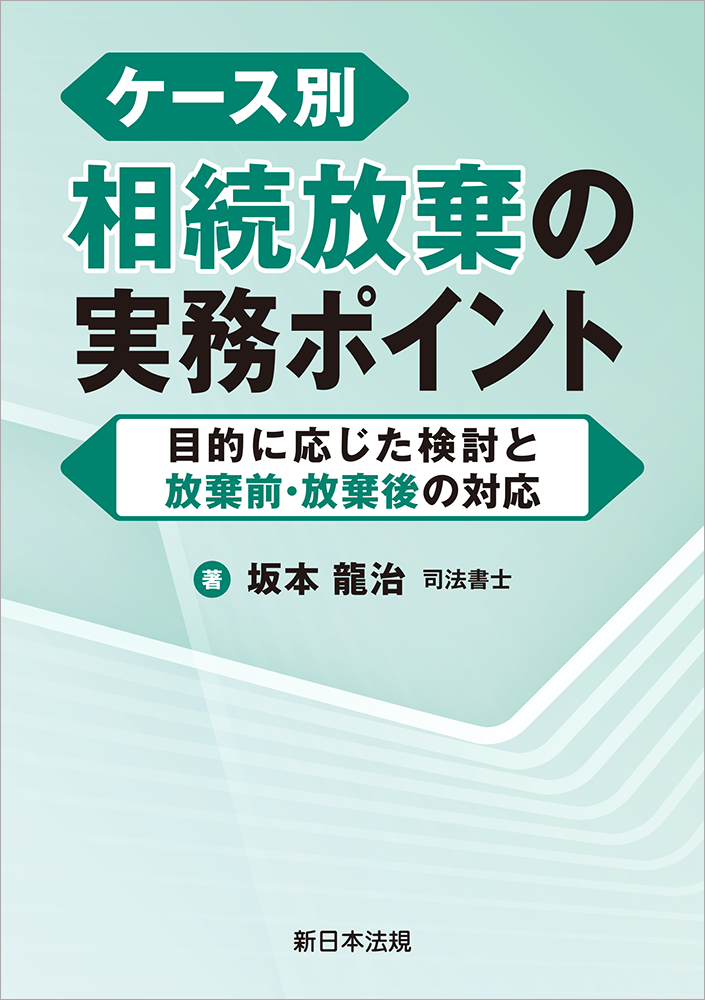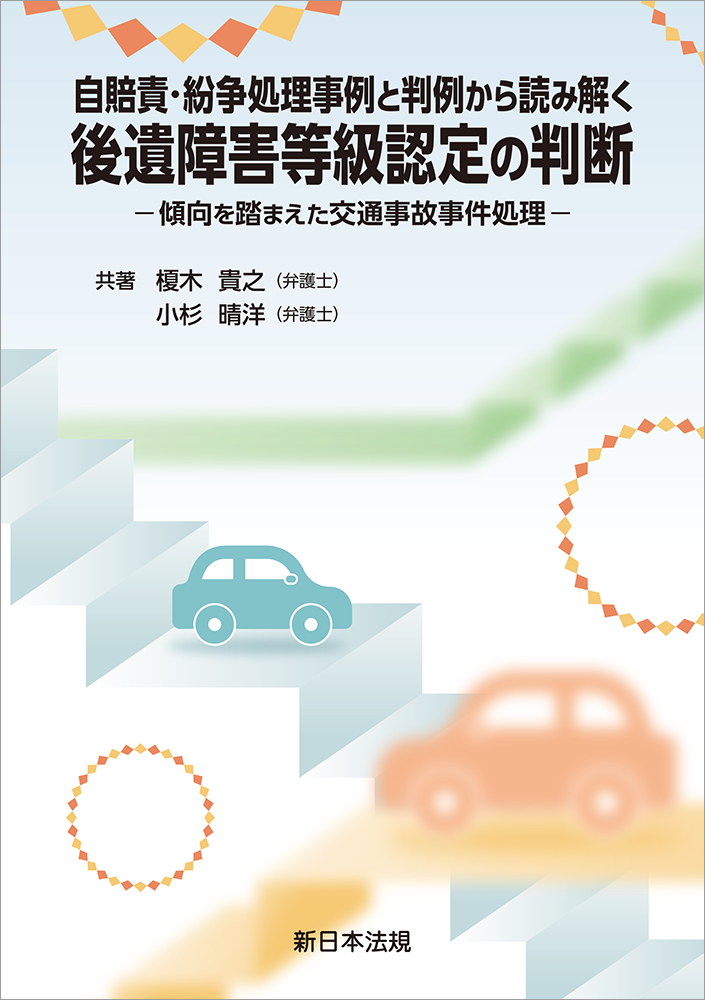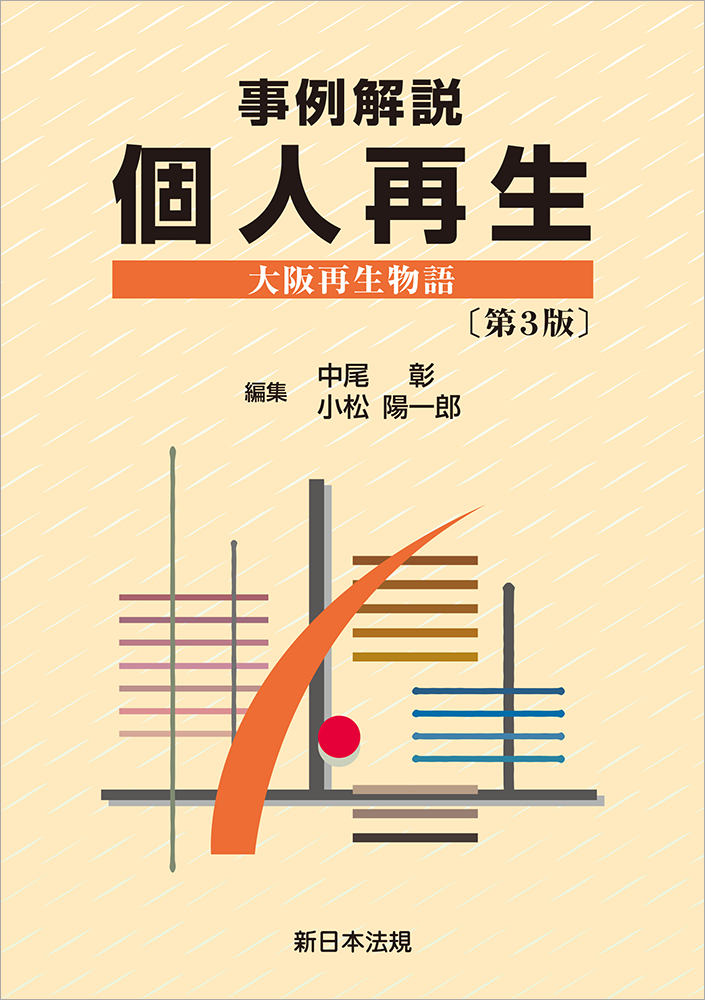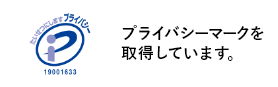解説記事2025年10月27日 解説 株主の同族会社に対する低利息貸付は経済的合理性を欠くとして所得税法157条1項を適用して未発生の利息収入(雑所得)を認定した課税処分を支持した裁決の検証(その1)(2025年10月27日号・№1096)
解説
株主の同族会社に対する低利息貸付は経済的合理性を欠くとして所得税法157条1項を適用して未発生の利息収入(雑所得)を認定した課税処分を支持した裁決の検証(その1)
中央大学名誉教授 税理士 大淵博義
はじめに
昨年6月に個人(株主)の同族会社に対する低利息貸付が租税回避に当たるとして所得税法157条1項が適用され、個人が収入していない利息収入が雑所得として課税された裁決が専門誌に紹介された(本誌No.1065 40頁)。同族会社の営利法人にとって経済的合理性のある有利な行為計算の否認は許されないという認識から、この問題点については疑問を提起していたところである。今回、本誌編集部からこの裁決について評釈の依頼があり、本稿で、従前の拙稿の総まとめの思いから、2回に亘り論考を執筆させていただくことにした。
Ⅰ 事案の概要と裁決の要旨
1 事案の概要
国税不服審判所長(大阪国税不服審判所)は、令和6年5月15日裁決(タインズコード番号FO−1−1688、以下「本裁決」という。)において、同族会社の代表取締役等の審査請求人ら(請求人、弟、亡父、母、以下「請求人ら」という。)が同族会社に対して貸し付けた金利が低利率であると認定、所得税法157条1項(同族会社の行為計算の否認)を適用して適正利率による利息収入を認定して雑所得とした課税処分を適法として、請求人らの審査請求を棄却した(脚注1)。
この事案は、同族会社が発行した社債を引き受けていた請求人らは、同族会社の社債償還期限前の償還の要請に応じて社債の払込金額の償還を受けた。その後、その資金を主たる原資として同族会社に対して81億円余を低利率で貸し付けた。これに対して原処分庁は、請求人らの低利息貸付は経済的合理性を欠くとして、日本銀行の貸出約定金利(0.791%~0.886%)を適正利率として、その低利率と適正利率との差額に相当する利息を雑所得として加算する課税処分を行った。
これに対して、本裁決は、次の理由により本件課税処分を適法としたものである。
2 裁決要旨
(1)「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
「同族会社の行為又は計算」のうち、①経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち、経済的合理性を欠くものであって、②当該株主等の所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。そして、③同族会社の行為又は計算が、独立当事者間の通常の取引との比較において異常又は変則的であり、かつ、当該行為又は計算を行ったことにつき租税回避以外に正当で合理的な理由や目的があったとは認められない場合には、当該行為又は計算が経済的合理性を欠くと評価されるというべきである。
(2)本件消費貸借が異常又は変則的な行為か
本件低利息貸付が本件貸付金(合計81億6,000万円)の多額な金員を、①弁済期限を定めず、無担保で貸し付けたこと、②本件貸付利率は国内銀行における貸出約定平均金利の約100分の1又は約500分の1にすぎないこと、③金員の貸付け(本件消費貸借)の原資の大部分(78億円)は、同族会社が発行した社債の償還金であり、本件貸付利率は、社債の年利率と比較して、著しく低くなっていること、以上からすれば、④本件貸付利率による本件消費貸借は、独立当事者間の通常の取引との比較において、明らかに異常又は変則的であるといわざるを得ない。
(3)本件消費貸借が租税回避か
本件消費貸借は、税制改正によって請求人らに新たに生ずることが予定されていた所得税の負担を回避することを主たる目的として行われたものであると推認される。
以上によると、本件消費貸借は経済的合理性を欠くもので、これを容認した場合には、請求人らの所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるから、所得税法157条1項を適用することができる。
Ⅱ 問題点の所在とその本質的理解に向けて~営利法人として経済的合理性のある無利息借入れが租税回避として否認される不可解な実相~
1 本件の争点と検証範囲~個人の情愛による行動と「独立当事者間取引基準」とのかい離~
本件事件の争点は、同族会社の株主が無利息貸付等(無利息及び低利息をいう。)により、同族会社に対して利息相当額の経済的利益を供与した場合、その個人(株主)に対して、法人と同様に利息相当額の収益が生ずるかということが唯一の争点である。すなわち、個人(株主)と同族会社との間の取引に独立当事者間取引基準を採用することの是非がここでの検証の射程である。
この検証は、個人と個人の取引に独立当事者間取引基準が適用さるかという論点の検証にも影響するものであるが、個人の行為により、その経済的合理性を判断すれば、その取引が個人のビジネスとして行われている場合を除けば、その大半の取引が独立当事者間取引基準に違背するであろう。それは、個人は経済的合理性を求めてのみ行動するものではなく、法人にはない個人の情愛という思いからの情義、厚誼又は哀れみ、喜びの感情の下で行動するものである。そのことが仮に経済的に不合理といえるものであるとしても、個人の属性からの自然な姿であり、これを税法が規制して制裁を課すことなど許されるものではない。
そうであれば、個人(株主)が、自ら支配する同族会社に対する無利息貸付等は、その関係を前提とした個人の同族会社に対する支援であり、問題視するのは不自然、不合理であることはいうまでもない。
ちなみに、本裁決は、請求人らは税制改正による将来の租税負担を考慮して早期償還に応じた上で、その資金で本件貸付を行ったもので、それは、請求人らの「所得税の負担を回避することを主たる目的として行われたもの」と認定している。しかしながら、請求人らが有利な税制を利用するというのは、いわば「節税」の範囲であり、同族会社の行為計算の否認規定の対象とされる「租税回避」とは全く性質の異なるものである(脚注2)。
本裁決は、「節税」と「租税回避」の法的な意義を混同して誤認し、その検討も行っていない。また、本裁決は、個人が一人又は本件のように近しい親族の株主の同族会社に対する貸付は、無担保で弁済期限も明示していない消費貸借を不合理としている。しかし、一般社会生活における個人間の行為として、すでに触れた個人の情愛という特性からの行動として格別、異常、不合理な行為でないことは自然な認識と言えよう。税務がそれを特別取り上げて論難するのはかえって不自然である。
そこで、ここでの論考は、「同族会社の個人(株主)が、当該同族会社に無利息貸付等した場合に、その個人(株主)にあるべき利率による利息収入(雑所得)を認定することが、実定法の解釈として適法かという論点」に絞って、そこから生ずる矛盾点等を指摘し検証することとする。
2 所得税法157条1項(同族会社の行為計算の否認)の判例等の解釈適用の矛盾点
(1)課税当局の否認法理の解釈適用の推移と平和事件判決の登場による課税実務の混迷
ア 従前の課税実務の実相
所得税法157条1項は、「同族会社の行為又は計算により株主の所得税を不当に減少することになったと認められる場合」に税務署長に認められた特別の課税権である。したがって、無利息貸付等が、①個人が個人に対して、②個人(株主)がその非同族会社に対して、また、③非株主の代表取締役等(雇われ社長等)が同族会社に対して、行われた場合には、同族会社の行為計算ではなく、その株主でもないから、この規定により収受していない利息収入の認定課税が行われることはない。
そうであれば、個人(株主)と同族会社に限定して、しかも、支配株主(同族株主)でもない少数株主と同族会社との間の無利息貸付等についても同様に、当該個人(株主)に対して、当該否認規定によって収入していない利息を収入しているという実体(事実)とは異なる課税要件事実を擬制して課税することができるのか、その法益は奈辺にあるのかという素朴な疑問は今でも解消されていない。
また、同族会社の行為計算の否認規定は憲法違反という問題がある。この点につき訴訟が提起されたが、その判決では、「少数の株主等で支配されている同族会社であるが故に、租税軽減のために不合理不自然な行為計算を行い易いことから、その同族会社及び株主等の租税負担の回避を否認して、課税の不公平を是正するためのものであり、憲法違反とはいえない。」(要旨)と判示している(東京高裁昭和53.11.30判決・訟務月報25巻4号1145頁)。
その判決によれば、営利法人の同族会社が株主から無利息融資を受けることは、同族会社の行為として経済的合理性のある行為であるから、「同族会社の(不合理な)行為又は計算」により、その株主の所得税を不当に減少する場合には当たらない。
個人(株主)が自らの意思で、自己が支配する同族会社に無利息貸付等を行ったこと、すなわち、個人(株主)が同族会社の利益のために無利息貸付等を行ったことが、所得税法157条1項の否認対象とされる「同族会社の行為又は計算により」という文理には該当しないと思料する(脚注3)。
つまり、本裁決の事案のように、営利法人である同族会社にとって経済的に最も合理的な無利息又は低利息融資(借入)を受けたことに対して、税務当局が当該借入行為を異常不合理として、その株主に対して収受していない利息認定をする課税実務は、従前の長い課税実務の世界では、考えられてもいなかったのである(脚注4)。
換言すれば、個人から個人、個人(株主)から非同族会社に対する無利息貸付等については否認されない法律と課税実務との整合性に照らしても、個人(株主)から同族会社に対する無利息貸付等に限定して、利息収入の存在をフィクション(擬制)して課税する差別課税の合理的理由の説明は本裁決にもみられない。そうであれば、平等課税の視座からも、株主の同族会社に対する無利息貸付等について、貸主の株主が収受していない利息収入を課税対象とすることは誤りであると解すべきである。
イ 平和事件判決の登場と課税及び司法における実務の混迷
かかる課税実務に対して衝撃を与えたのが、平和事件判決である(脚注5)。筆者は個人(株主)の同族会社に対する無利息貸付等については、前述したように、所得税法157条1項は適用できないという理解の下で、長年に亘り平和事件判決を批判してきた(脚注6)。
この平和事件の下級審判決が納税者勝訴で確定し、最高裁では過少申告加算税賦課決定処分のみが争われ、その決定処分が適法とされて、控訴審判決が取り消した加算税賦課決定が、最高裁判決により適法として復活した。このことから、直截的ではないとしても、最高裁は本件利息認定の処分は適法という前提の下で、加算税賦課決定を適法としたと判断したということができる。この平和事件判決により、従前の課税実務は一変するかに見えた。
ところが、平和事件判決は、株主の同族会社に対する3,455億円の多額な無利息貸付けが問題とされた事件であり、しかも、平成元年の有価証券譲渡所得の原則課税とする税制改正の施行日の15日前に行った平和株式の譲渡であったという特殊な要因がある。
しかし、そのことは、税務上は問題はないところ、大きくマスコミにとり上げられたのである。その実態は、(株)平和の代表取締役が、その保有する平和株式を時価(3,455億円)で同人の資産管理会社に譲渡、その管理会社の譲受代金の支払資金として、上記金額を銀行11行から借り入れて無利息で管理会社に貸し付けたという事例である。その上で、本件株主は、当該金員を管理会社から当該株式の譲渡代金として回収し、即座に11行の借入先の銀行に借入金の返済を行ったというものである。それを1日で実行したものであるが、その1日の借入金の銀行に支払った支払利息が1千数百万円、さらに有価証券取引税が19億円と記憶している。
かかる事案の特殊性に鑑み、国税当局は、その勝訴判決を積極的に活用して否認する課税実務の執行は消極的であったように思われる(脚注7)。しかしながら、かかる無償貸付等による個人(株主)の同族会社への利益供与について、利息発生もその収受もしていない利息収入にも関わらず、「収入すべき金額」と認定することは、「現実に発生している法的、経済的成果と異なる事実をフィクション(擬制)して課税する」ものであり、その租税負担能力の欠如はもとより、実質課税の原則にも違背するという基本的な問題点の検討が等閑視されている。
それが平和事件の課税処分の背景にあり、そして、課税庁はもとより、本裁決及び税務判決が、この事件の数々の税務上の問題点の存在を失念し(脚注8)、その論点の検証を閑却した結果が本裁決の判断に至ったといえよう。また、控訴審判決が加算税賦課決定処分を取り消したことの是非が争われた最高裁の判決は、控訴審判決を取り消して加算税の賦課決定処分を適法とした(脚注9)。また平和事件判決が影響したと思われる本裁決は、ここで指摘した論点について議論の対象としていないのは、真に遺憾という以外に言葉もない。
そこで、筆者の視座からの問題点の検証を捨象した本裁決及び以前の平和事件判決の結論は疑問(誤判)と評価せざるを得ない具体的根拠について論証することとする。
(2)同族会社の行為計算の否認規定の創設の経緯及び趣旨目的からの検証
平和事件判決及び本裁決の判断は、同否認規定の創設の経緯とその趣旨目的を全く無視して捨象していることに基因していると考えている。そこで、以下、この点について明らかにしておく。
ア 所得税・法人税の同族会社の行為計算の否認規定の趣旨・沿革との齟齬
わが国の現行税制の所得税法及び法人税法における同族会社の行為計算の否認規定に相当する規定が創設されたのは、大正12年の所得税法一部改正においてである。当時の所得税法は、個人及び法人の所得に対する課税制度が所得税法に一本化されて規定されていた。法人税は第一種所得税、個人の公債、社債の利子が第二種所得税、事業所得等のその他の所得が第三種所得税として規定されていた。
その改正において、所得税法73条ノ2では同族会社の留保金課税が創設され、同73条ノ3では、同族会社と株主等との間における行為の否認規定が創設された(脚注10)。
かかる留保金課税や行為計算の否認規定の創設は、大正9年の所得税法改正により、それまで非課税とされていた配当所得が個人の段階で総合課税の対象とされることとなったことに伴い、その総合課税による配当所得の所得税負担の増加を回避するため、同族関係者からなる家族的な会社(財産保全会社)を組織し、その財産保全会社に利益を留保して配当を行わないこととする事例が続出した。
例えば、財産保全会社と株主等との間に、財産保全会社であるがゆえに行われやすい税負担の軽減を意図とした種々の形態の恣意的な取引(隠れたる利益処分)が見受けられるようになってきた、という当時の状況を背景とするもので、同族会社の留保金課税制度とともに、これらの租税回避行為を防止・是正するための措置として法制化されたものといわれている(脚注11)。
かかる創設の趣旨について、当時の立法当局者の解説では、次のように述べられている。
「同族会社の租税回避の常套手段は、個人と法人との所得の計算方法の相違する点を逆用することにあるやに認められる。即ち個人の営利に属せざる一時の所得が非課税とせらるるにかかわらず法人の所得計算上普通所得を構成し、個人の所得計算に於いては所得を得るに必要なる経費の範囲が限定せらるるに反し、法人の所得計算に於てはその範囲が制限せられない等の故に、法人をして積極的又は消極的に、個人に一時的利益を与ふる目的を以て、出捐又は犠牲を為さしむること−最も単純な例を挙ぐれば贈与其の他の無償の行為を以て、事ある毎に法人の利益の減殺を図り、因って個人に利益を与ふる等、容易に租税の回避が企図せらるるのである。茲に於て、税務執行官庁に対し行為計算の否認権が付与せられ、其の否認権運用の目標は専ら此等の贈与又は贈与類似の利益供与の関係を客観的照準に依り是正せんとするにある。」(脚注12)。
このような立法の経緯と趣旨からすれば、同族会社の行為計算の否認規定は、営利法人の同族会社にとって、資産の減少をもたらす贈与(寄附金)等を損金の額に算入し、他方、その贈与を受けた個人(株主)は非課税とされていたことにより(脚注13)、法人及び所得税の負担を回避する租税回避を防止するために、この否認規定が創設されたということである。
この制度創設の趣旨目的に鑑みれば、この租税回避否認規定が否認対象としているのは、営利法人としての同族会社が経済的不合理な行為計算を行い、同族会社の利益を個人(株主)に移転する場合を課税対象とするものである(脚注14)。したがって、平和事件判決及び本裁決のように、個人(株主)がその同族会社に対して、無利息貸付等により個人(株主)の利益を移転することを予定したものでないことは明白であろう。
仮に、所得税法157条1項が、本裁決のような事例を否認する規定であるというのであれば、個人(株主)が非同族会社に対して、また個人が個人に対して無利息貸付等を行った場合には、その貸主の個人には利息認定ができない現行制度の下では、同族会社の個人(株主)に限定して、所得税法157条1項を適用して収受していない利息収入の存在をフィクション(擬制)して所得税の課税対象とすることは、不平等課税の憲法違反の問題が復活することになる。また「所得なきところに課税なし」違反、ひいては実質課税の原則に違反することになり、課税の合理的根拠は見いだせないのである。
ここでの結論は、所得税法157条1項は、同族会社の無償行為等により個人(株主)に対する利益移転の租税回避を課税対象とするものであり、個人(株主)の同族会社への利益移転を課税の対象とするものではないということである。本裁決及及び平和事件判決は、この立法の趣旨目的からの検証を閑却したところに、その判断の誤りに気づいていないでいるというのが、ここでの結論である。
(3)所得税法157条1項により個人(株主)に収入金額を認定した本裁決と現実の課税制度等との齟齬・矛盾についての検証
本裁決の否認の法理が適法であるというためには、個人は営利を追求する合理的経済人であるという事実を証明する必要がある。しかし、それは不可能である。
何故ならば、個人の生活主体は、消費生活と業務生活の二面性を有しているから、消費生活主体は、利益追求とはかけ離れた情誼、厚誼又は恩義という特別な感情から行われる支援があり得るのである。そこが営利追求主体たる法人とは本質的に異なるところである。
例えば、親族関係における無利息貸付等や友人関係に対する同様の行為は、むしろ無償又は低率の貸付で支援することが常態とも言えるのが個人間の支援行為といえよう。そこに税務が入り込む余地がないのが所得税法である。
他方、法人組織は、営利を追求する主体として機能し、株主等の構成員の利益追求目的のために組織された法人としての属性は、個人のそれとは全く異なる存在であるにもかかわらず、本裁決や平和事件判決は、この自然人の「人」としての本質的な属性の相違、そのことによる所得税と法人税の法律自体に幾つかの相違があることを看過しているという点にこそ問題の本質がある。そのために、判決等の判断には、かかる個人と法人の「人としての属性」の相違による税法規定の相違を捨象して解釈している点にこそ、多くの齟齬・矛盾が露呈していることの考察の欠落が、本裁決及び平和事件判決である。
このような理解を捨象した結果、本裁決は、下記のような現行所得税法による課税実務との矛盾齟齬が指摘できる。
① みなし譲渡課税制度(所法59①)と個人(株主)の同族会社の無利息貸付等に限定した利息認定との齟齬
すでに(1)で述べたように、所得税法59条1項は時価10億円のマンション等をその2分の1以上の5億1,000万円で譲渡した場合には、4億9,000万円の含み益の所得課税は行われないのが所得税法である。それは個人の属性故の譲渡価額の選択の幅を許容したということである。かかる所得税制度の存在を前提として検証すると、この規定とは無関係の本裁決の個人(株主)の同族会社に対する低利息貸付につき、その借主が同族会社の場合に限定して適正利息に引き直して、収受していない利息収入を収受しているとフィクション(擬制)して課税を行うことは、制度相互間の矛盾であり齟齬を来していることになる。具体的には次のとおりである。
個人(株主)の同族会社に対する無利息貸付等を否認するのであれば、みなし譲渡課税の時価の2分の1未満と同様に、通常の適正利率の2分の1未満の低利息貸付に限定して否認の対象とする個別規定を措定して対応するのが課税の公平原則に適うものであり、法律相互間の整合性を保持することでもある。かかる規定が不存在である所得税法の下では、個人(株主)の同族会社に対する無償等の役務提供に対するみなし収入は、個人の特性を考慮して課税対象とはしていないという制度として理解するのが素直な解釈であり、前記の立法趣旨とも整合的である。
それは、平和事件判決以前は、個人(株主)が同族会社の支援のための無利息貸付等の役務提供は枚挙に暇がないほど多数行われていたことは多言を要しない。しかるに、過去、それが全く問題視されていなかったのは、個人から同族会社に対する利益供与は所得税法157条1項の射程範囲ではなく容認されていたからにほかならない。それは筆者の課税当局における体験からの認識である。
しかるに、本件の低利息貸付を所得税法157条1項の同族会社の行為計算の否認規定の特殊な規制規定の射程と捉えて、利息等の収入の取得をフィクション(擬制)して課税することは解釈の限界を超えており許されないと考えている。このことは、以下に述べる点からも、そのことの正当性が証明されるであろう。
② 同族会社の経済的合理的行為を否認対象とする基礎的理論との齟齬と矛盾~「同族会社の行為又は計算」と「独立当事者間取引基準」の齟齬について~
ア 同族会社の経済的合理的な行為計算を否認した本裁決の誤謬
所得税法157条1項のここ数年の課税実態は、個人(株主)の同族会社に対する無償等の役務提供に限定されて否認されている。しかるに、無償等の金銭の貸付等の役務提供により利益を享受する同族会社にとって、かかる無償又は低利息融資を受けることは同族会社のみならず非同族会社も含む営利法人が求めている融資であり、「同族会社の行為計算」として何ら非難を受けるものではない。
同規定の「不当減少」の判断基準の一つとして、「非同族会社比準説」(非同族会社では行われない行為計算か否か)があるが、それによれば、非同族会社においても無利息借入等は経済的、合理的なものであることは論ずるまでもないことであり、したがって、ここでの「不当減少」に当たらないことは明白である。
本裁決は、その経済的合理的な行為計算を、異常、不合理と判断したということであるが、それは、本裁決が多くの問題点のある平和事件判決を無条件に受け入れたというのがその原因であろう。
本裁決は、かかる基本的な疑問点について全く検討していないのは、単に、失念したものとは思えない。すでに紹介したように、平和事件判決以後、田中治大阪府立大学名誉教授が数多くの論考を発表されているが、平和事件判決の無利息貸付は利息収入が発生していないので、所得税法157条1項により有利息貸付に置き換えて利息収入を認定するのは、許されないと述べておられる(脚注15)。それは、「講学上の租税回避行為」の定義とは異なるからである(その詳細は後述する。)。
権利救済機関たる国税不服審判所長が、その論考を把握していないということは考え難い。しかして、本裁決はこの論点の議論を意図的に閑却したという批判を甘受せざるをえないであろう。
そして、本裁決の登場は、平和事件の3,455億円の無利息貸付から一挙に81億円の無利息貸付等にまで引き下げられて否認されるという先例が発生したということである。
このことは、個人から無利息貸付等による同族会社への支援が否認対象となるのか、という予測可能性が全く担保されなくなったということである。税務執行として、納税者に最も不信感を抱かせる事態であるということを課税当局はもとより、裁判所等の権利救済機関は自覚して欲しいものである。
イ 本件個人(株主)の同族会社に対する低利息貸付の合理性の判断基準に「独立当事者間取引基準」を持ち込むことの不合理性
ところで、本裁決は、「弁済期も定めず、無担保での低利利息貸付」は、独立当事者間の通常の取引においては、極めて異常又は変則的であるとし、また、本件同族会社の行為又は計算は、税制改正(社債利子が分離課税から総合課税に移行)による将来の所得税負担を回避するためのもので、それ以外に正当で合理的な理由や目的があったとは認められないから、経済的合理性を欠くものというべきである、と結論付けている。
この本裁決の法解釈と事実認定の前提こそが、不合理な唯我独尊の見解であり、一般的社会通念(社会常識)と齟齬を来たし乖離しているものである。税制改正により租税負担が増加することを回避するために、社債の早期償還に応じてその資金により本件貸付を行なうこと自体に、格別、問題はない。ここでの問題は、請求人らの同族会社への低利息貸付であるが、それ自体も何ら問題はないということを論じることにする。
このことについては、一人株主の典型的な同族会社の例で説明しよう。
貸主の一人株主が同族会社に無利息貸付を行った場合には、その無利息融資で同族会社が受けた利息相当額の利益は、その一人株主が、当該株式を通じて間接的に所有するという関係にある。すなわち、両者の関係は「同族会社=株主」という実態である。このことは、同族会社の財産は配当又は同族会社の解散によりその一人株主が全ての財産を保有することができるという関係を考えれば、通常の利率で融資することにより、その雑所得の所得税を納税することを回避することは一人株主の個人として当然のことである。このことが非難されるいわれはない。
すなわち、株主が同族会社に対して、無利息貸付等を行うことは、株主責任としての支援であり、その株主としての行為として経済的合理性が認められるということができる。端的に言えば、同族会社の所有者である株主が、同族会社の支援として無利息貸付等を行うことが不自然、不合理とはいえないということでもある。
しかも、所得税法上問題にされない友人関係における無利息融資の支援は課税対象外であり、他方で、親密な関係の一人株主の同族会社に対する合理的な行為が否認される不合理は明らかである。
しかるに、平和事件判決が、営利追求の主体である株式会社等の行為の経済的合理性の判断基準とされる「独立当事者間取引基準」を採用した合理的根拠を、その判決文からは見い出すことができない。
ただ、同判決は、「本件規定は、その制定の沿革からすれば、(略)『所得税の負担を不当に減少させる結果となる』という文言から、本件規定の適用対象が客観的な租税回避行為に限られるとまで解すべき理由はない。」と判示した。しかしながら、その解釈は、いかなる根拠により導き出せるのか、その根拠が明確に示されているわけではない。また、かかる解釈を打ち出す前に、同族会社の行為計算の否認規定の創設の趣旨目的を検討すべきことは当然であるにもかかわらず、その検証は皆無である。しかして、「不当に減少している」という要件が、いかなる要件を充足しているのかを明確に示すべきところ、なんら触れるところではない。
しかも、請求人らは、原処分の認定した利息収入を収受していないのであるから、所得税を不当に減少していることにならないことは多言を要しない当然の道理である。租税回避における「不当減少」とは、ほぼ同様の経済的成果を得ながら、異常不合理な行為計算を選択した納税者が租税を減免され、他方、経済的合理的な通常行われる行為計算を選択した納税者は、より多くの租税負担を行なっている、という現状を「不当減少」ということを理解していないのである。
本裁決の請求人らが現実に収入した利息は、低利率の約定による利息収入であるから、それと請求人らが通常の利率で貸付けた場合の仮定の利息とを比較して「不当減少」というのは、租税回避の不当減少とは異質のものであり、本末転倒した論理である。
請求人らは、株主の立場からの租税節減という節税を行ったに過ぎないし、その株主としての役員は、当然の支援を行ったにすぎない。
ところで、この「独立当事者間取引基準」は、株主等の構成員の利潤獲得の手段としての法人という法的組織では、利害相反する独立した第三者間取引で成立した取引関係は客観的合理性を有するという観念の下で成立した概念である。すなわち、その基準は、利益追求主体たる法人の行為計算の合理性の判断基準であるのに対して、厚誼、情義等の感情により損得を度外視して行動する個人の行為計算の合理性につき、「独立当事者間取引基準」により判断するということは不適切、不合理であることは明白である(脚注16)。
平和事件判決は、この点において重大な誤謬を犯しているということを指摘しておく。
(つづく)
脚注
1 この裁決の1か月後に、所得税法157条1項により利息認定を行った令和6年6月10日裁決(タインズF0−1−1683)がある。その貸付金額はマスキングされ不明であるが、その裁決の中身は本裁決と同様である。
2 後に触れるが、「講学上の租税回避」は、一定の法的経済的成果を得るために、通常行われる経済的合理的な行為の選択に代え不合理な行為を選択して、その得られた経済的成果に相応する租税負担を回避することをいうが、「節税」は、既存の税制度等を利用して租税負担を軽減するという合法的ものであり、租税回避のような制限は伴わないものである。
3 それはその制度の立法の経緯、趣旨目的からも明らかであることは後に論ずることとする。
4 このことは、筆者の国税庁及び国税局で訴訟事務に従事した14年間を含む33年間の税務当局の勤務経験において、検討の対象にもなっていないことからの結論でもある。
5 一審・東京地裁平成9年4月25日判決(判例時報第1625号23頁)及び控訴審・東京高裁平成11年5月31日判決(訟務月報51巻8号2135頁)。なお、最高裁平成16年7月20日判決(訟務月報51巻2126)は、加算税の賦課決定処分の是非が争われている。
6 税務事例32巻5号(2000年)1頁、同巻6号1頁、同巻7号1頁参照。税務会計研究学会租税回避行為研究特別委員会・最終報告(委員長大淵博義・委員 岸田貞夫・野田秀三)「租税回避行為−その否認の現状の問題点と課題−」税務会計研究第 20号(2009年)165頁~194頁。
7 そのような消極的な対応は、国税庁の会議で伝達されたということを仄聞しているが、その真偽は不明である。しかし、その後、平和事件判決(平成9年)から本裁決(令和6年)までの間、本件事案のような課税処分の争訟事案は発生していないことに鑑みれば、少なくとも当時、課税当局は抑制的な税務執行を実践していたと思われる。しかしながら、このことについては、争訟事案は発生していないが、地方局では10億円未満の無利息貸付の課税事案(修正申告)の発生も仄聞しているし、その他にも、散発的に類似の課税事案が発生していると推測している。かかる現状は、本稿で指摘した問題点を認識している調査官は無利息貸付等の納税者の事案を容認しているものと思われるが、それは、国税庁のこれまでの不分明なスタンスによるもので、税務執行の不平等課税という憲法違反の事態を招来しているということがいえよう。これを是正するためには、課税当局の問題認識による反省と執行の是正、税務行政の権利救済機関である国税不服審判所の裁決による処分取消又は司法の税務判決の取消以外にはない。しかしながら、少なくとも、これまではその是正の兆候は全くみられないことから、今後も、さらに拡大する方向で推移することを懸念している。それを最低限に抑えるのは、研究者や税理士等の税務専門家による積極的な否認課税の批判的論考の展開と議論が行われることが肝要である。最近では、以前とは異なり、かかる研究者等の議論の展開が極端に減少しているのは遺憾なことである。
8 この判決の多くの問題点を指摘し検討している文献に、田中治『田中治税法著作集』所収「所得税における同族会社の行為計算の否認規定」清文社(2021年)154頁以下参照。なお、拙稿「『所得なきところに課税なし』の原則と同族会社の行為計算の否認」税理40巻9号(1997年)71頁も参照。
9 最高裁判決の結論は、所得税法における同族会社の行為計算の否認規定の立法の経緯及び趣旨に関する検討が欠落していることの証左であり遺憾なことである。この立法の趣旨に適う納税者の無利息貸付に係る申告には「正当な理由」があるということは言うまでもないことである。
10 大正15年に取引を同族会社と株主間の取引に限定しない旨の改正が行われている。この規定は、基本的には現在の規定と異なるところはない。
11 この点の規定創設の経緯については、村上泰治「同族会社の行為計算否認規定の沿革からの考察」税務大学論叢11号(1977年)228頁に詳しく論じられている。
12 片岡政一『増徴新税 税務会計原理』文精社(1935年・昭和10年)283頁以下。なお、山本貞作『営業収益税法釈義』自治館(1927年・昭和2年)378~379頁も同旨。
13 当時の税制の下では、法人からの個人に対する贈与(寄附金)は、法人では損金算入とされ(昭和17年に寄附金課税創設)、贈与を受けた個人は所得源泉説の下では非課税とされていたものである(現在の一時所得は非課税)。
14 それは所得税法157条1項の場合であり、法人の場合には株主に限定されずに、その同族会社以外の法人及び個人に対する行為計算が対象とされる。
15 田中治「同族会社の行為計算否認規定(所得税法157条)の射程」税務事例研究(Vol89(2006年)46頁(日本税務研究センター)。
16 ちなみに、平和事件訴訟では、国側は、「株主と同族会社との間の取引を一体として(全体としてみて)『独立当事者間取引基準』により合理性を判断すべきである。」と主張しているが、それを本裁決は無条件に採用したというのが実態であろう。
大淵博義 (おおふち ひろよし)
1970年中央大学商学部卒業。東京国税局直税部訟務官室、東京国税局法人税課審理係、国税庁直税部審理室訟務専門官、税務大学校教授、中央大学教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2015年税理士登録。著書に『法人税法解釈の検証と実践的展開(第Ⅰ巻)改訂増補版、(第Ⅱ巻)、(第Ⅲ巻)』(税務経理協会)、『寄附金課税の実務』(共著)(新日本法規出版)、『最新判例による法人税法の解釈と実務』(大蔵財務協会)ほか多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -