解説記事2020年05月25日 最新判決研究 個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(同族株主等判定の時期)(2020年5月25日号・№835)
最新判決研究
個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(同族株主等判定の時期)
最高裁令和2年3月24日第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第422号)
東京高裁平成30年7月19日判決(平成29年(行コ)第283号)
東京地裁平成29年8月30日判決(平成24年(行ウ)第185号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)甲は、A社の代表取締役を務めていたが、平成19年8月1日、A社の株式72万5000株(以下「本件株式」という。)を、B社に対し、代金1株当たり75円、合計5437万円余で譲渡し(以下「本件株式譲渡」という。)、同年12月26日に死亡した。甲の相続人は、配偶者であるX1、子であるX2、X3、X4及びX5(原告、控訴人及び被上告人、以下「Xら」という。)並びに代襲相続人であるAの6名であり、同人らは、甲を相続した(以下「本件相続」という。)。
Xらは、本件相続に伴い、平成20年3月13日、所轄税務署長に対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)188−2に定める配当還元方式による評価額(1株当たり75円)によって算定し、所得税の準確定申告書を提出した(以下「本件申告」という。)。
所轄税務署長は、平成22年4月20日、Xらに対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式の価額は評価通達180に定める類似業種比準方式による評価額1株当たり2990円であるとして、各更正等(以下「本件各更正等」という。)をした。Xらは、本件各更正等を不服として、国(被告、被控訴人及び上告人)に対し、それらの取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)A社は、昭和25年9月に設立され、金属製品等の製造、販売等を業とする資本金4億6000万円の株式会社であり、平成19年1月期の売上金額は約236億円、従業員数は449人である。また、A社は、本件株式譲渡時の発行済株式総数は920万株であり、株主は1株につき1個の議決権を有し、定款において、その株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めていた。
本件株式譲渡の時点において、A社は、評価通達178に定める「大会社」に該当し、A社の株式は、所得税基本通達23〜35共−9(4)二に定める比準すべき売買実例のない株式に、また、評価通達に定める取引相場のない株式に該当する。
B社は、平成16年2月に金銭の貸付業、株式投資業等を目的として設立されたものであるが、A社の持株会の補完的機能を有している。
なお、本件に関しては、本件相続に係るXの相続税につき、本件相続によってXが取得したA社の株式の相続税法上の「時価」が幾許であるかが別訴で争われ、本判決と同日に判決(東京地裁平成24年(行ウ)第184号、平成29年8月30日判決)が下されている。同判決は、相続税については配当還元方式の適用を認めている。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の主たる争点は、本件株式譲渡が所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるか否か(本件株式の価額を配当還元方式によって評価すべきか類似業種比準方式によって評価すべきか)であり、具体的には、次の2点にある。
(1)所得税基本通達59−6の(1)の条件下における評価通達188の議決権割合の判定方法
(2)本件株式譲渡における譲渡代金額をもって時価といえるか。
2 国の主張
(1)所得税基本通達59−6の(1)の趣旨は、譲渡人に帰属する資産の保有期間中の増加益を所得として課税する点にあることからすれば、その増加益は株式の譲渡人の譲渡直前の議決権割合により判定することが最も合理的といえるためである。本件株式譲渡の直前において、甲及びその同族関係者は、A社の議決権総数の15%以上(22.79%)の議決権を有し、かつ、甲個人も、A社の議決権総数の5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当せず、評価通達178本文、179の(1)により、原則的評価方法である類似業種比準方式により評価すべきことになる。
(2)甲は、A社の株主でもあるC社及びA社の役員らが甲の実効支配下にあったことなどから、A社のみならず、A社の役員らが株主であるB社においても極めて強い権限を有しており、これらの会社では、本件株式譲渡の前後を通じて株主総会や取締役会が開催されたことはなく、株式の移動や人事、報酬などの株主総会や取締役会で決定される事項は、全て甲が意思決定をするという甲に実効支配体制が確立していた。
そして、本件株式譲渡の譲渡価額を決定するに当たり、甲やB社において合理的な検討はされておらず、本件株式譲渡は、甲一族が有するA社の議決権割合を15%未満にして相続税負担を軽減させることを目的に行われたものである。
以上によれば、本件株式譲渡における譲渡価額は、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して算定されたものではなく、譲渡の時の価額の2分の1に満たない金額によるものであるから、所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たる。
3 Xらの主張
(1)評価通達188の(3)のうち、「同族株主のいない会社」であるかどうかの判定は、所得税基本通達59−6の(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行うことになるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定は、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当である。このような評価通達の文言に忠実な解釈は、実務上、通達も法律に準じ広く一般に周知され、納税者の指針となっていることに鑑みれば、租税法律主義の下で課税に関する予測可能性を保障するという要請に適うものといえる。
(2)本件株式譲渡は、利害相反する第三者間で行われたものである。そして、A社の少数株主となるにすぎないB社にとって、本件株式の実質的な経済的価値は配当への期待のみであり、このような買主の主観的事情を考慮すれば、本件株式を配当還元方式により評価することは当然であるから、本件株式譲渡は「時価」によりなされたものである。
三、一審判決要旨
請求棄却。
(1)所得税基本通達59−6が上記の評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の一定の条件として規定した内容の合理性について検討すると、そもそもそのような一定の条件を設けたのは、評価通達が本来的には相続税や贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであって、譲渡所得の収入金額の計算とは適用場面が異なることから、評価通達を譲渡所得の収入金額の計算の趣旨に則して用いることを可能にするためであると解される。
すなわち、相続税や贈与税が、相続や贈与による財産の移転があった場合にその財産の価額を課税価格としてその財産の取得した者に課される税であるのに対し、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として、その資産が所得者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算してその譲渡人である元の所有者に課税する趣旨のものと解されるのであって、そのような課税の趣旨からすれば、譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当である。
(2)以上によれば、前記前提事実のとおり、本件株式譲渡直前の時点において、A社には合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がおらず、A社は「同族株主のいない会社」に当たるから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式には該当しない。また、本件株式譲渡直前の時点において、譲渡人である甲及びその同族関係者である甲親族らは、合計して15%以上(22.79%)の議決権を有し、甲個人も5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。よって、本件株式は、評価通達188の株式のいずれにも該当しないから、類似業種比準方式により評価すべきこととなり、その評価額は1株当たり2505円となることが認められる。
四、控訴審判決要旨
原判決取消し(請求認容)
(1)所得税基本通達59−6の(1)は、評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の条件として、「財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」と定めている。これは、評価通達188の(1)は、「同族株主」につき、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上等である場合におけるその株主及びその同族関係者としているところ、その文理解釈だけでは、30%以上等である場合が、株式譲渡前の議決権について述べているのか、譲渡後の議決権について述べているのかは必ずしも明らかではないため、譲渡所得に対する課税が、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するという趣旨から、30%以上等という基準は、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権割合により判定すべきことを定めたということができ、このこと自体の合理性は認めることができる。
(2)ところが、国は、更に進んで、譲渡所得に対する課税の上記の趣旨から、評価通達188の(2)から(4)までに係る株主区分の判定についても、譲渡人の株式譲渡直前の議決権割合により判定する旨を主張している。しかし、租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことは許されないと解されるところ、所得税基本通達及び評価通達は租税法規そのものではないものの、課税庁による租税法規の解釈適用の統一に極めて重要な役割を果たしており、一般にも公開されて納税者が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば、課税に関する納税者の信頼及び予見可能性を確保する見地から、上記各通達の意味内容についてもその文理に忠実に解釈するのが相当であり、通達の文言を殊更に読み替えて異なる内容のものとして適用することは許されないというべきである。本件においては、本件株式が評価通達188の(3)の株式に該当するかどうかが争われているところ、上記のとおり、所得税基本通達59−6の(1)が、評価通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかについて株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権の数により判定する旨を定める一方で、同(2)から(4)までについて何ら触れていないことからすれば、同(3)の「同族株主のいない会社」に当たるかどうかの判定(会社区分の判定)については、それが同(1)の「同族株主のいる会社」の対概念として定められていることに照らし、所得税基本通達59−6の(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行われるものと解されるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定(株主区分の判定)については、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により判定されるものと解するのが相当である。
五、上告審判決要旨
原判決中上告人敗訴部分破棄(原審差戻し)
(1)譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものである(最高裁昭和41年(行ツ)第8号同43年10月31日第一小法廷判決・裁判集民事92号797頁、最高裁同41年(行ツ)第102号同47年12月26日第三小法廷判決・民集26巻10号2083頁等参照)。すなわち、譲渡所得に対する課税においては、資産の譲渡は課税の機会にすぎず、その時点において所有者である譲渡人の下に生じている増加益に対して課税されることとなるところ、所得税法59条1項は、同項各号に掲げる事由により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に当該資産についてその時点において生じている増加益の全部又は一部に対して課税できなくなる事態を防止するため、「その時における価額」に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなすこととしたものと解される。
(2)所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき、所得税基本通達59−6は、譲渡所得の基因となった資産が取引相場のない株式である場合には、同通達59−6の(1)〜(4)によることを条件に評価通達の例により算定した価額とする旨を定める。評価通達は、相続税及び贈与税の課税における財産の評価に関するものであるところ、取引相場のない株式の評価方法について、原則的な評価方法を定める一方、事業経営への影響の少ない同族株主の一部や従業員株主等においては、会社への支配力が乏しく、単に配当を期待するにとどまるという実情があることから、評価手続の簡便性をも考慮して、このような少数株主が取得した株式については、例外的に配当還元方式によるものとする。そして、評価通達は、株式を取得した株主の議決権の割合により配当還元方式を用いるか否かを判定するものとするが、これは、相続税や贈与税は、相続等により財産を取得した者に対し、取得した財産の価額を課税価格として課されるものであることから、株式を取得した株主の会社への支配力に着目したものということができる。
これに対し、本件のような株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、当該譲渡における譲受人の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を及ぼすものではないのであって、前記の譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される。
そうすると、譲渡所得に対する課税の場面においては、相続税や贈与税の課税の場面を前提とする評価通達の前記の定めをそのまま用いることはできず、所得税法の趣旨に則し、その差異に応じた取扱いがされるべきである。所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式の評価につき、少数株主に該当するか否かの判断の前提となる「同族株主」に該当するかどうかは株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること等を条件に、評価通達の例により算定した価額とする旨を定めているところ、この定めは、上記のとおり、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株式を譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる。
ところが、原審は、本件株式の譲受人であるCが評価通達188の(3)の少数株主に該当することを理由として、本件株式につき配当還元方式により算定した額が本件株式譲渡の時における価額であるとしたものであり、この原審の判断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。
(3)以上によれば、原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、本件株式譲渡の時における本件株式の価額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官宇賀克也、同宮崎裕子の各補足意見がある。
(4)裁判官宇賀克也の補足意見は、次のとおりである。
通達は、法規命令ではなく、講学上の行政規則であり、下級行政庁は原則としてこれに拘束されるものの、国民を拘束するものでも裁判所を拘束するものでもない。
もっとも、租税法律主義は課税要件明確主義も内容とするものであり、所得税法に基づく課税処分について、相続税法に関する通達の読替えを行うという方法が、国民にとって分かりにくいことは否定できない。課税に関する予見可能性の点についての原審の判示及び被上告人らの主張には首肯できる面があり、より理解しやすい仕組みへの改善がされることが望ましいと思われる。
(5)裁判官宮崎裕子の補足意見は、次のとおりである。
私は、法廷意見に賛成であるとともに、宇賀裁判官の補足意見に同調するものであるが、さらに以下の点を敷衍しておきたい。
法廷意見で指摘しているとおり、所得税法に基づく譲渡所得に対する課税と相続税法に基づく相続税、贈与税の課税とでは、課税根拠となる法律を異にし、それぞれの法律に定められた課税を受けるべき主体、課税対象、課税標準の捉え方等の課税要件も異にするという差異がある。その点を踏まえると、所得税法適用のための通達の作成に当たり、相続税法適用のための通達を借用し、しかもその借用を具体的にどのように行うかを必ずしも個別に明記しないという所得税基本通達59−6で採られている通達作成手法には、通達の内容を分かりにくいものにしているという点において問題があるといわざるを得ない。本件は、そのような通達作成手法の問題点が顕在化した事案であったということができる。租税法の通達は課税庁の公的見解の表示として広く国民に受け入れられ、納税者の指針とされていることを踏まえるならば、そのような通達作成手法については、分かりやすさという観点から改善が望まれることはいうまでもない。
六、解説
はじめに
本件は、会社の代表取締役が、自社の株式(非上場株式、本件株式)を関係会社に対して、評価通達に定める配当還元価額で譲渡した場合に、当該譲渡価額が所得税法59条1項2号に定める「著しく低い価額」に当たるとする課税処分が行われ、当該課税処分の適否が争われたものである。会社役員等の個人と当該個人の関係会社に対する資産の売買については、所得税法59条1項2号の適用の可否がまま問題となるが、その場合に、最も問題となるのが、当該売買価額が当該資産の同項に定める「その時における価額」に当たるかであり、当該価額をどう評価すべきかである。
特に、本件のように、当該資産が非上場株式である場合には、元々、市場価格が存在していないだけに、「その時における価額」の評価が困難となる。そのため、実務においては、所得税基本通達と評価通達の取扱いに依存することになるが、当該通達の取扱いの適用のあり方が問題になることがある。しかも、本件に関しては、本件株式を譲渡した甲が、当該譲渡約4月後に死亡し、その相続税に関しても、本件株式と同じ会社の株式の評価額の是非が別訴で争われることになったのであるが、それぞれの税目の違いを反映することとなった(注1)。
そこで、本稿では、上記の各問題に関し、本件に即して、関係する法律、通達等を検討し、所得税法59条1項に定める「その時における価額」の解釈について論じることとする。
1 非上場株式の譲渡における所得税法上の「価額」
(1)かつて、シャウプ勧告は、「生前によると死亡によるとを問わず、資産が無償移転された場合、その時までにその資産につき生じた利得又は損失は、その年の所得税申告書に計上しなくてはならない」旨を勧告し(注2)、それを受けて昭和25年の所得税法改正では、相続、遺贈又は贈与により資産の移転があった場合にも、その時の時価により譲渡があったものとして、譲渡所得等の課税を行うこととした。しかし、このような課税が納税者の理解を得られ難かったことや税務執行が困難であったことから、上記課税制度は、徐々に変更され、昭和48年以降、現行の所得税法59条及び60条の規定となり、限定的にみなし譲渡課税が行われることとなった。そして、当該みなし譲渡課税が行われていない場合には、当該資産の取得価額の引継ぎが行われることとなった(注3)。
すなわち、所得税法59条1項は、「次に掲げる事由により居住者の有する山林(〈略〉)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。」と定めている。そして、本件に即すると、その2号に「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)」と定めている。そして、所得税法施行令169条は、「法第59条第1項第2号(〈略〉)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。」と定めている(注4)。
(2)かくして、上記条項の解釈については、本件に即すると、本件株式の「その時における価額」が問題となる。この「価額」の意義については、判例等において、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち客観的交換価値(客額的交換価額)であると解されている(注5)。そして、この「価額」の意義については、相続税法上の「時価」(同法7、22)及び法人税法上の「価額」に共通するものと解されている(注6)。
しかしながら、当該「価額」を客観的交換価値であると解し得るとしても、特に、非上場株式のように、市場取引がない資産については、それのみでは「価額」の解釈(認定)が困難である。そこで、所得税基本通達23〜35共−9(4)では、いわゆる非上場株式の「価額」については、次に掲げる区分に応じて、次のように評価する旨定めている。
① 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額(注7)
② 公開途上にある株式 公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
③ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
④ ①から③までに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3)所得税法上の非上場株式の譲渡における「価額」は、上記の取扱いによって評価されるのであるが、実務上は当該取扱いのうち④に該当する場合が最も多いと言えるところ、「……通常取引されると認められる価額」が定かでないため、所得税基本通達59−6では、次のように取り扱うとしている。
「法第59条第1項の規定の適用について、譲渡所得の基因となる株式(〈略〉)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23〜35共−9に準じて算定した価額による。この場合、23〜35共−9の(4)二に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189−7まで(〈略〉)の例により算定した価額とする。」
この規定により、評価通達上の取引相場のない株式の評価方法によって評価することができる条件を4つ定めているが、本件に関しては、「評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」である。この場合、後述するように、評価通達188では、(1)から(4)まで株主の態様に関する定めがあるところ、本訴では、「(1)に定める」という限定した文言をめぐって紛糾することになった。
かくして、所得税法において非上場株式の価額を評価する場合にも、原則として、相続税法において適用される評価通達の評価方法に準ずる場合が多いが、当該評価通達の評価方法は、次のとおりである。
2 評価通達における取引相場のない株式の評価方法
(1)評価通達では、株式等の評価単位につき、上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式を「取引相場のない株式」として区分し(評基通168(1)〜(3))、取引相場のない株式の評価区分につき、当該株式の発行会社(以下「評価会社」という。)を大会社、中会社又は小会社に区分する(評基通178)。そして、大会社の株式の価額は、原則として、類似業種比準価額(純資産価額も可)で評価し、中会社の株式の価額は、類似業種比準価額と純資産価額の折衷方式(価額)で評価し、小会社の株式の価額は、原則として、純資産価額(類似業種比準価額の2分の1併用も可)で評価する(評基通179)。
ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ評価通達188又は189の定めにより、配当還元方式又は純資産価額方式等によって評価する(評基通178ただし書)。
かくして、本件に即すると、本件株式の発行会社であるA社が上記の大会社に区分されることについては、当事者間に争いがないが、甲が上記の「同族株主以外の株主等」に該当し、本件株式の価額を配当還元価額で評価し得るか否かが、問題となる。よって、「同族株主以外の株主等」の範囲を明らかにする必要がある。
(2)評価通達188は、「178(〈略〉)の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。」と定めている。上記の株式は、次のとおりである。
① 同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(〈略〉)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
② 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令71条1項1号、2号及び4号に掲げる者をいう。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株式の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻続(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
③ 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
④ 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(②の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。
以上の取扱いにおいて、特に、問題となるのが、「同族関係者」の範囲及び議決権数の数え方であるが、それらの問題は、本件に直接関係がないので、別稿に譲る(注8)。
(3)次に、前記取扱いによって、「同族株主以外の株主等が取得した株式」と区分された株式の価額については、配当還元方式によって評価されるのであるが、当該配当還元方式は、次のとおりである(評基通188−2)。
すなわち、当該株式の価額は、その株式に係る年配当金額(評価通達183の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を評価通達179に定める原則的評価方式によって計算した金額を超える場合には、当該原則的評価方式によって計算した金額によって評価する。
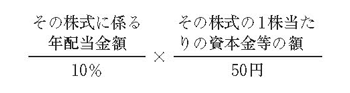
上記の配当還元方式は、元々、額面株式の額面額が50円であったことが主流であったことに起因し、当該株式の価額は、1割配当であれば50円で評価することになる。ただし、平成18年の評価通達の改正によって、「資本金の額」を「資本金等の額」に変更したため、配当還元価額が類似業種比準価額を上回ることが生じるようになった(注9)。
3 本件株式の価額の評価
(1)本件においては、A社の代表取締役を務めていた甲が、平成19年8月1日、関係会社であるB社に対し、本件株式(A社株式)を1株当たり75円(配当還元価額)、総額5437万円余で譲渡(本件株式譲渡)し、同年12月26日に死亡した場合に、本件株式の譲渡価額が所得税法上適正であるか否かが問題となったものである。
前記1で述べたように、所得税法59条によれば、個人が法人に対し資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡価額が当該資産の価額の2分の1に満たないときには、当該資産の「その時における価額」によって譲渡したものとみなされる。かくして、個人が法人に資産を譲渡した場合には、特に、それが関係会社に対して行われると、当該資産の「その時における価額」が幾許であるかが問題となる。特に、本件のような非上場株式については、所得税法及び他の税法が「価額(時価)」の解釈基準としている「客観的交換価値」が容易に把握し難いため、一層問題となる。
そうなると、実務では、「その時における価額」の解釈について、国税庁が定めた通達にその評価方法(評価額)が定めていることと、当該評価方法(評価額)に従って評価しておけば納税申告が否認されることはないということで、当該通達の取扱いを基準にする(従う)ことになる。また、非上場株式等の資産の「その時における価額」が法廷で解われる場合にも、多くの裁判例が当該通達の合理性を容認し、それに基づく評価額が「その時における価額」に相当する旨容認しているところである。
(2)かくして、本件株式譲渡についても、「その時における価額」の解釈につき、前記1で述べたように、所得税基本通達23〜35共−9(4)は、適正と認められる売買実例価額等がなければ、1株当たりの「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によって評価することとしている。しかし、非上場株式の譲渡については、上記の「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」が評価(算定)し難いこともあるので、その場合には、所得税基本通達59−6が、原則として、所定の条件の下に、評価通達が定める評価方法(評価額)の例によって評価(算定)することを認めている。その所定の条件のうち、本件に関するものが、「評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」という定めである。
ところで、評価通達188は、前記2で述べたように、配当還元方式が適用される「同族株主以外の株主等」に該当するか否かについて、(1)(前記2(2)の①)から(4)(同前④)までに規定している。本件において、Aの本件株式譲渡前におけるA社の議決権数割合は、A個人で15.88%、A及び同族関係者の合計で22.79%となる。そうすると、本件株式譲渡前の議決権数割合によって評価通達188の(1)から(4)までを適用すると、Aは、(3)又は(4)の規定によって、「同族株主以外の株主等」に該当しないため、配当還元方式は適用できないことになる。しかし、所得税基本通達59−6は、前記1で述べたように、評価通達188の(1)に定める「同族株主」の判定についてのみ譲渡直前の議決権数割合による旨を定めているので、同通達の文字どおり解すると、評価通達188の(2)から(4)までの各株主の判定は、評価通達の文言どおり、当該株式の取得後(譲渡後)において行われることになる。そうすると、各通達の文言をそのまま適用する限りでは、Xらの主張に理があるように考えられる。しかし、所得税法59条が資産の低額譲渡等におけるキャピタル・ゲインを適正に算定しようとしている法の趣旨からすると、上記形式解釈には疑問を残すことになる。
(3)かくして、一審判決は、前記三で述べたように、「譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所得者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算してその譲渡人である元の所有者課税する趣旨」であることを重視して、評価通達188の(1)〜(4)の各定め中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株式の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当である旨判示し、本件各更正等を適法と認めた。
これに対し、控訴審判決は、前述のように、「租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことは許されないと解されるところ、〈略〉課税に関する納税者の信頼及び予見可能性を確保する見地から、上記各通達の意味内容についてもその文理に忠実に解釈するのが相当であ」ると判示し、原判決を取り消した。
かくして、上告審判決は、前述のように、所得税法における譲渡所得に対する課税の趣旨と同法59条所定の「その時における価額」の評価のあり方(譲渡人の会社への支配力の重視)を判示した上で、「譲渡所得に対する課税の場面においては、相続税や贈与税の課税の場面を前提とする評価通達の前記の定めをそのまま用いることはできず、所得税法の趣旨に則し、その差異に応じた取扱いがされるべきである。所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式の評価につき、少数株主に該当するか否かの判断の前提となる「同族株主」に該当するかどうかは株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること等を条件に、評価通達の例により算定した価額とする旨を定めているところ、この定めは、上記のとおり、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株式を譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる。」と判示した。次いで、同判決は、「原審の判断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。」と判示し、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、本件株式の価額等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した。
(4)以上のように、本件の各判決は、所得税法59条所定の「その時における価額」の解釈と所得税基本通達59−6及び評価通達188の適用のあり方につき、三者三様の判断を示したことになる。その中で、特に、控訴審判決と上告審判決の差異は、前者が、租税法規の文理解釈の重要性を説き、それが税務通達に及ぶことから、所得税基本通達59−6の文言を重視したことに対し、後者が、譲渡所得課税の制度の趣旨を重視し所得税と相続税及び贈与税との違いから、所得税基本通達59−6が評価通達188(1)所定の「同族株主」の判定においてのみ譲渡直前の支配関係であると定めているのはいわば例示的なものと捕え、その考え方は同通達の(2)から(4)まで及ぶ旨判示した、ことにある。
このような考え方の差異については、元々、所得税基本通達59−6が同通達23〜35共−9(4)二の定めを補完的に定めたものであるところ、基となる後者の取扱いが、「1株当たりの純資産価額等を参酌して通達取引されると認められる価額」と規定しているので、仮に、当該「価額」を評価通達185に定める純資産価額であるとすると、同価額が本件各更正等に適用されている類似業種比準価額より通常相当高いと想定されるところから、結論としては、上告審判決の方が妥当であるものと考えられる。いずれにしても、本件は、差し戻された東京高等裁判所において、再度、本件株式譲渡の時における本件株式の価額等について審理されることになるが、控訴審判決が認めた配当還元方式の適用が再び認められることは考えられないであろう。
4 本件各判決の意義と問題点
種々のタックス・プランニング等において、会社役員等の個人が、関係会社等の法人に対して、関係する非上場株式を譲渡することはよくあることである。その場合、当該譲渡の価額をどうするかが、関係者間でよく問題になる。その問題は、当該個人の資金関係であったり、当該法人の経営戦略に関わることも多いこともあって、所得税基本通達59−6の取扱いをクリアできるか否かが最大の関心事となる。
その場合、実務では、課税上の安全を考慮してか、所得税基本通達59−6が評価通達188(1)の「同族株主」の判定に限定して譲渡直前の議決権数によると定めていることについては、同通達の(2)から(4)まで及ぶものとして処理する場合が多いものと考えられる。しかし、所得税基本通達59−6の文理からすると、本件におけるXらのような考え方があるわけであり、それらの考え方の対立が最高裁まで争われたことは、関係者間で大いに注目されたところであるので、大変意義のあることである。
本件については、差戻し審においてどのような判断が下されるかが問題となろうが、大筋は最高裁判所の考え方に沿った判断が下されるであろう。しかし、各裁判官の補足意見で指摘されているところでもあり、所得税基本通達59−6の文理については、然るべき改正が行われるものと想定される。
(注1)東京地方裁判所民事3部(裁判官も同じ。)は、本件の一審判決と同時に、本件と原告が同じである相続税事件については、配当還元方式を認める判決を下している。この事件においては、評価通達の取扱いを文字通り解釈すれば、配当還元方式が適用されるところ、所轄税務署長が評価通達6を適用して類似業種比準方式によって評価した課税処分を行ったため、当該処分の適法性が争われていた。結局、同じ裁判官は、本件の所得税事件については、通達の文言よりも、譲渡所得における譲渡価額の実質を重視し、別件の相続税事件については、通達の文言を重視したことになる。
(注2)シャウプ使節団「日本税制報告書」第1編第5章第13節参照。
(注3)このような課税制度の変遷については、品川芳宣「資産の無償等譲渡をめぐる課税と徴収の交錯(1)」税理2004年1月号24頁等参照。
(注4)このみなし譲渡課税の趣旨、問題点については、前出(注3)25頁参照。なお、同族会社等に対する低額譲渡については、2分の1を上回ってもみなし譲渡課税が行われることがある(所基通59−3参照)。
(注5)所得税法に関する裁判例として、名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、神戸地裁昭和54年5月29日判決(同105号461頁)、東京地裁平成2年2月27日判決(同175号802頁)、東京地裁平成11年11月30日判決(同245号576頁)等参照。
(注6)相続税法に関するものとして、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等を、法人税法に関するものとして、大阪地裁昭和53年5月11日判決(行裁例集39巻5号943頁)、東京高裁平成6年2月26日判決(税資200号815頁)等を参照。
(注7)法人税基本通達4−1−5及び同9−1−13においては、所得税基本通達23〜35共−9(4)と同様の規定を設けているところ、所得税基本通達の方が「最近」と抽象的に定めているのに対し、具体的に「前6月」と定めている。そのため、国は、係争事案につき、所得税についても「前6月」に限定すべき旨主張しているが、その主張は否定されている(大分地裁平成13年9月25日判決・税資251号順号8982参照。同判決については、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)246頁等参照)。
(注8)これらの問題については、品川芳宣編著「資産・事業承継対策の現状と課題」(大蔵財務協会 平成28年)(第14章事業承継と取引相場のない株式の評価)529頁以下参照。
(注9)詳細については、前出(注8)582頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















