解説記事2020年06月08日 ニュース特集 特集 外国事業体の法人該当性(2020年6月8日号・№837)
ニュース特集
いまだ安定しない実務 デラウェアLPS最高裁判決の他事案への適用には要注意
特集 外国事業体の法人該当性
外国法に基づいて設立された事業体が日本の租税法上「法人」に該当するかは、法人の意義を定義した規定がないために度々争いとなってきた。特に問題となってきたのが、事業体の損失を出資者の他の所得と損益通算するケースだ。
現在の実務では、米国デラウェア州LPSが法人に該当するとし、外国事業体の法人該当性について最高裁として初めて判断基準を示した平成27年7月17日最高裁判決が同種の事案の判断基準となっているが、当該判決の射程についてはいまだ専門家の間でも議論がある。また、平成29年2月9日に国税庁が公表した情報に対しても、判決との整合性等についての疑問の声が挙がっており、いまだ実務は安定していない状況にある。
外国事業体の法人該当性を巡る事案では、法人該当性をどのような基準で判断するのかという「法令解釈」の問題と、その判断基準に事実を当てはめた場合に法人に該当するかという「事実の認定・評価」の問題の2つがポイントとなる。そこで本特集では、判断基準の違いと事実関係の違いについて、デラウェア州LPS最高裁判決の前後の事案、特に、法人該当性が肯定されたデラウェア州LPS最高裁判決と、同日に上告不受理となり法人該当性が否定されたバミューダLPS事案との違いを中心に整理した上で、デラウェア州LPS最高裁判決の影響についての専門家の指摘等についても紹介する。
01 外国事業体への投資を巡る問題
投資家が海外不動産に投資する場合、不動産事業を営むどのような事業体に投資するかについては、様々な選択肢がある。
株式会社に投資する場合、株主の責任は出資額を限度とする有限責任となるが、税制上は事業体に対して法人税が課される一方、株主には課税後の利益が分配され、それに対してさらに所得税が課されるという二重課税が発生する。これに対し、組合(パートナーシップ、GPS)は組合員が共同で事業を営む事業体であり、組合員の責任は無限責任であるが、組合自体には課税されず直接組合員に課税され二重課税は生じない。そこで、投資を活発にするため、出資者の責任は有限責任でありながら、二重課税を排除するために、事業体段階では課税されず構成員段階のみで課税(パススルー課税)されることとなる“株式会社とパートナーシップの中間の性質”を持つ様々な事業体(ビークル)が作られている。
例えば、LLC(Limited Liability Company)、LLP(Limited Liability Partnership)、LPS(Limited Partnership)などである。米国LLCは、米国各州が制定するLLC法に基づいて設立される事業体で、Corporationと同様に法的に独立した存在と言われており、出資者は有限責任であるが、米国税制上、チェック・ザ・ボックス規則により構成員課税か団体課税かを選択することができる。LLPは、組合員の責任は有限であるが全員が業務を執行し、税制上は構成員課税が適用され、我が国でも任意組合契約と同様に取り扱われている。LPSは、無限責任を負い業務を執行するジェネラル・パートナー(GP)と有限責任のリミテッド・パートナー(LP)から構成され、税制上は、構成員課税か団体課税かを選択でき、LLCとLLPの中間的な存在とも言われている。
このような事業体は投資促進に寄与することとなったが、その一方で、パススルー課税(導管性)を利用した租税回避という問題を引き起こした。具体的には、海外不動産の減価償却費を日本で得た他の所得と損益通算するという手法である。外国法を準拠法とする事業体が日本の租税法上法人に該当するかについては、日本の租税法上、「法人」の意義について定義した規定がないために度々争いとなり、国際課税の根本的な問題とされてきた。事業体が法人に該当すれば、事業体から生じた損失は事業体自体に帰属するため、出資者の側での損失計上は認められないが、法人に該当しなければ、その損失は出資者に直接帰属し、他の所得と損益通算することによる節税メリットを享受することができるからである。また、米国で構成員課税が選択されていても、日本の税法上法人として扱われる場合には、日本国内と国外で税務上の取扱いが異なるというハイブリッドミスマッチの問題も生じている。
02 ニューヨーク州LLC-法人格肯定
外国事業体の法人該当性について検討する出発点として、まず、米国で構成員課税が選択されていたニューヨーク州LLCが法人に該当するか否か(その不動産賃貸業の損益が当該LLCに帰属するか否か)が争われた訴訟を取り上げる(さいたま地裁平成19年5月16日判決、東京高裁平成19年10月10日判決)。本訴訟の判決で示された判断基準は、後の事案に影響を与えることになるからである。
本事案で、原審のさいたま地裁は、法人該当性の判断基準と当てはめについて、表1のとおり判示した(控訴審である東京高裁もこれを引用)。
【表1】
| 法人該当性の判断基準 |
| 外国の法令に準拠して設立された社団や財団の法人格の有無の判定に当たっては、基本的に当該外国の法令の内容と団体の実質に従って判断するのが相当であり、本件LLC は、ニューヨークLLC 法に準拠して設立され、その事業の本拠を同州に置いているのであるから、本件LLC が法人格を有するか否かについては、法の内容と本件LLCの実質に基づき判断するのが相当である。 そして、英米法における法人格を有する団体の要素は、①訴訟当事者になること、②法人の名において財産を取得し処分すること、③法人の名において契約を締結すること、④法人印(corporate seal)を使用することの4つであり、これらの性質を有する場合はわが国の租税法上の法人に該当する。 |
| 本件ニューヨーク州LLCへの当てはめ |
| ニューヨークLLC法の規定やLLCの契約などから、本件LLCは上記の①②③の3つの性質を有する。 本件LLC はニューヨークLLC 法上、法人格を有する団体として規定されており、自然人とは異なる人格を認められた上で、実際、自己の名において、契約をするなど、(中略)独立した法的実在として存在していることが認められる。 |
表1のとおり、本件ではニューヨーク州LLCの法人該当性が肯定されたが、国は、デラウェア州LPSを巡る裁判で、法人該当性の判断基準として、①構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か、②契約を締結し、権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か、③訴訟当事者となり得るか否かの3要素を挙げ、デラウェア州LPS法には、ニューヨーク州LLC法と同趣旨または類似の規定があると主張していた。この“3要素基準”は大阪地裁では認められたが、大阪高裁及び名古屋地裁では否定された。また、名古屋地裁は、ニューヨーク州LLCは、デラウェア州LPSとはその成り立ち、構成員の責任、組織運営等が異なり、両者の類似性を根拠とする国側の主張は前提自体が間違っているとも指摘している。
なお、国税庁は平成13年、同庁のホームページ上で、下記のとおり米国LLCに係る税務上の取扱いを公表している(要旨)。(国税庁が示した下記の基準は、後述するデラウェア州LPS最高裁判決の「権利義務帰属主体基準」と実質的には変わらないとする専門家の意見もある。)
米国LLCに係る税務上の取扱い
我が国の税務上、外国法人として取り扱うか否かは、当該事業体が我が国の私法上、外国法人に該当するか否かで判断する。
米国LLCについては、以下の理由等から、原則的には我が国の私法上、外国法人に該当する。
① 商行為をなす目的で米国の各州のLLC法に準拠して設立された事業体であり、外国の商事会社であると認められること
② 設立に伴い商号等の登録(登記)等が行われること
③ 事業体自らが訴訟の当事者等になれるといった法的主体となることが認められていること
④ 統一LLC法においては、「LLCは構成員(member)と別個の法的主体(a legal entity)である」「LLCは事業活動を行うための必要かつ十分な、個人と同等の権利能力を有する」と規定されていること
03 バミューダLPS-法人格否定
次に、法人該当性が否定された事案としてバミューダLPSを取り上げる。
この事案(東京地裁平成24年8月30日判決、東京高裁平成26年2月5日判決)は、匿名組合契約に基づく利益分配金(国内源泉所得であることを前提)をバミューダLPSが収受したことに対して、同LPSが外国法人として課税されたことから争いになったものであり、まさに真正面からLPSの法人該当性が争われた事案といえる(なお、匿名組合の利益分配金については平成14年度税制改正で源泉所得税が課されることとなり、PEがない外国法人に対する法人税の課税所得であるいわゆる資産の運用所得からは除かれたが、本件は当該改正前の事案である)。
東京地裁及び東京高裁が判示した判断基準と当てはめは表2のとおりである。
【表2】
| 法人該当性の判断基準 |
| 外国法令により組成された事業体が日本の租税法上、法人に該当するか否かについて、①準拠法である外国の法令によって法人格を付与する旨が規定されているか否か、②当該外国の法令が規定するその設立、組織、運営及び管理等の内容に着目して経済的、実質的に見れば、その事業体が日本の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否かを検討する必要があり、②の点が肯定される場合に限り、日本の租税法上の法人に該当すると解すべきである。 |
| 本件バミューダLPSへの当てはめ |
| ①の基準について バミューダ法の規定内容によれば、1883年LPS法、1902年PS法および1992年EPS法上、特例パートナーシップに関して、法人格を付与する旨の規定は存在しない。 なお、1902年PS法の2006年改正により、特例パートナーシップの選択により法人格を取得することが認められることとされたが、本件事業年度は上記の法律改正の前に終了しているから、改正後の条文が適用されることはなく、改正の前後を通じて原告は法人格の取得を選択していないため、上記の規定により原告が法人格を取得することはあり得ない。 ②の基準について ・バミューダのPS法では、全てのパートナーが事業の資本資産及び事業から生ずる利益につき等しく持分の権利を有するとし、また全てのパートナーは資本資産の損失その他のパートナーシップが被った損失を等しく負担しなければならないと規定している。そして、本件LPS契約では、損益は、各パートナーの持分割合に応じて各パートナーに比例配分されるものとすると規定している。 ・上記の各規定に照らすと、原告のような特例パートナーシップを通じた事業の損益は、法令および契約上各パートナーに直接帰属するとされ、すなわち原告自体に損益が帰属するものではないと認められる。 |
この事案は、東京高裁判決で法人該当性が否定され納税者側が勝訴し、さらに平成27年7月17日、最高裁が国の上告受理申立てを不受理としたため、法人に該当しないことが確定した。
ただ、ここで注意しておきたいのが、最高裁は上告受理申立てを不受理としたに過ぎず、公に判断を示したわけではないため、結論に至る判断理由は明らかではないということだ。この事案は、法人該当性が肯定されたデラウェア州LPS最高裁判決と同日に上告不受理が決定され、同一の小法廷に係属していたことから、その影響があるものと考えられている。本件の東京高裁の判断基準は、デラウェア州LPS最高裁判決で破棄された名古屋高裁と同じ判断基準であることから、本件の東京高裁の判断基準によって法人該当性が否認されたとは必ずしも言えず、デラウェア州LPS最高裁判決と同じ基準によってバミューダLPSの法人該当性を否定するという判断がされた可能性がある。
04 デラウェア州LPS-法人格肯定
デラウェア州LPSの法人該当性が争われた事案は、デラウェア州LPSが行う不動産賃貸業から発生した損失が納税者(出資者)に帰属するか否か(損益通算の可否)が問題となったものである。
なお、平成17年度の税制改正によって、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例(措置法41条の4の2)が措置され、現在では、個人がLPSから生ずる不動産所得を有する場合において、原則として、当該不動産所得の損失と他の所得との損益通算をすることができなくなり、組合事業による中古不動産投資等の節税スキームは実質的に封じ込められている。一連の訴訟は、改正措置法が適用される前の事案である。しかしながら、デラウェア州LPSは米国投資に際しての一般的なビークルであるため、引き続き、実務上の取扱いには注意が必要だ。
下級審における法人該当性の判断基準
この事案の東京、大阪、名古屋の下級審判決においては、表3のとおり、その判断基準及び結論はそれぞれ異なっている。東京地裁、名古屋地裁及び名古屋高裁の判断基準はバミューダLPS事案の判断基準と同じであり、大阪地裁の判断基準はニューヨーク州LLC事案の判断基準と類似している。
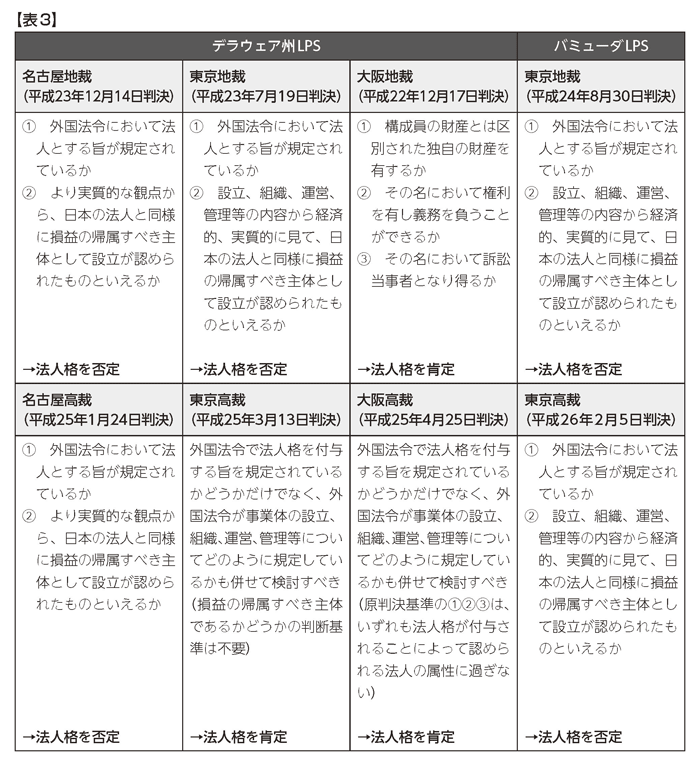
名古屋高裁の上告審である平成27年7月17日最高裁判決が示した表4の判断基準は、表3のいずれとも異なっており、特に、名古屋高裁判決が判断基準とした「損益帰属主体基準」が否定された点で影響が大きいとする専門家が多い(なお、最高裁判決の・の判断基準と東京高裁判決の判断基準の類似性を指摘する専門家の声もある)。
【表4】
| 法人該当性の判断基準 |
| ① 対象となる外国の組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討し(判断方法①より客観的かつ一義的な判定が可能な基準)、これができない場合には、 ② 当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否か、具体的には、当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から、当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否か(判断方法②より実質的な判断基準)を検討すべき |
| 本件デラウェア州LPSへの当てはめ |
| 判断方法①について デラウェア州LPS法は、同法に基づいて設立されるリミテッド・パートナーシップがその設立により「separate legal entity」となるものと定めているところ、デラウェア州法を含む外国の法令において「legal entity」が日本法上の法人に相当する法的地位を指すものであるか否かは明確でなく、また、「separate legal entity」であるとされる組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価することができるか否かについても明確ではない。 そして、デラウェア州一般会社法における株式会社(corporation) については、「a body corporate」という文言が用いられ、「separate legal entity」との文言は用いられていないことなども併せ考慮すると、州LPS法においてLPSが「separate legal entity」となるものと定められていることをもって、本件各LPSに日本法上の法人に相当する法的地位が付与されているか否かを疑義のない程度に明白であるとすることは困難である。 判断方法②について (1)デラウェア州LPS 法は、リミテッド・パートナーシップにつき、営利目的か否かを問わず、一定の例外を除き、いかなる合法的な事業、目的又は活動をも実施することができる旨を定めるとともに、同法若しくはその他の法律又は当該リミテッド・パートナーシップのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限を保有し、それを行使することができる旨定めているとし、 (2)かかる州LPS法の定めに照らせば、同法は、LPSにその名義で法律行為をする権利又は権限を付与するとともに、LPS名義でされた法律行為の効果がLPS自身に帰属することを前提とするものと解され、 (3)このことは、同法において、パートナーシップ持分がそれ自体として人的財産と称される財産権の一類型であるとされ、かつ、構成員であるパートナーが特定のリミテッド・パートナーシップ財産について持分を有しないとされていることとも整合する。 (4)上記のような州LPS法の定め等に鑑みると、本件各LPSは、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が本件各LPSに帰属するものということができるから、権利義務の帰属主体であると認められる。 |
専門家からの指摘等
最高裁が示した上記の判断基準に対して、専門家からは様々な指摘がなされたが、最高裁はこれらの判断基準を採用した理由について次のとおり述べている。
①の基準の理由
諸外国の多くにおいても、その制度の内容の詳細には相違があるにせよ、一定の範囲の組織体にその構成員とは別個の人格を承認し、これを権利義務の帰属主体とするという我が国の法人制度と同様の機能を有する制度が存在することや、国際的な法制の調和の要請等を踏まえると、外国法に基づいて設立された組織体につき、設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、日本法上の法人に相当する法的地位が付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である場合には、そのことをもって当該組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当する旨又は該当しない旨の判断をすることが相当である。
②の基準の理由
(1)外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かは、当該組織体が日本法上の法人との対比において我が国の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否かとの観点から判断することが予定されているものということができる、(2)そして、我が国においては、ある組織体が権利義務の帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性であり、そのような属性を有することは我が国の租税法において法人が独立して事業を行い得るものとしてその構成員とは別個に納税義務者とされていることの主たる根拠であると考えられる上、納税義務者とされる者の範囲は客観的に明確な基準により決せられるべきであること等を考慮すると、(3)外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かについては、上記の属性の有無に即して、当該組織体が権利義務の帰属主体とされているか否かを基準として判断することが相当であると解される。
最高裁の判決文では、上記のうち、まず②が述べられ、次に①が述べられている。この順番からすると、最高裁は②の考え方が「原則」であり、①の考え方は「例外」と位置付けているように見える。だとすれば、法人であるか否かは、まず「日本の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否か」により判断し、法人が構成員とは別個の納税義務者である根拠として、「組織体が権利義務の帰属主体であること」が挙げられているということになる。このような判断枠組みによれば、外国の組織体のそれぞれについて、日本法上の法人に相当するか否か(権利義務の帰属主体か)を個別に判断すべきこととなるが、本判決は、「国際的な法制の調和」を図るため、「設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから」形式的な判断を行う“例外”として①の基準をまず置き、次いで②の基準を置くという二段階の方法をとったとみる専門家の指摘がある。
この判断枠組みについて、専門家の間では、最高裁は「法人」を借用概念論(租税法に「法人」という語が定義も何もなく用いられていれば、特別の事情がない限り、私法上の法人を意味するという考え方)を離れて、固有概念(税法独自の概念)として捉えているとする意見もあれば、借用概念論を離れたわけではない、あるいは、離れたかどうかは必ずしも明らかではないとする意見もあり、見解が分かれている。
また、二段階の判断基準についても、そもそも①の判断基準は必要なのか、という疑問の声も多い。実務上は、法人該当性に疑義が生じるような事業体は①の判断基準では判断できないようなケースが多いと思われ、結局、②の基準で判断することになるのではないかと言われている。そうなると、結局のところ「疑義のない程度に明白」とはどの程度なのか、実際には外国法の文言や法制の仕組みをどう捉えるかという実質判断になり、その見極めは難しいという声もある。
さらに、「ある組織体が権利義務の帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性」という点についても、法人であれば権利義務の帰属主体であると言えるが、権利義務の帰属主体であれば法人であると言っていいのか、という疑問の声も挙がっている。法人でなくても権利義務の帰属主体となり得る事業体があり、例えば、諸外国の中では、日本の民法上の組合に相当する組織体に対しても権利能力を認める判例法理が形成されていると言われている。
また、「権利義務の帰属主体」という基準についても、「権利義務」の範囲、程度等が具体的に示されているわけではないため、結局のところ「権利義務の帰属主体」であるかどうかの実質判断は難しいということを懸念する声は多い。特に、米国GPS(ジェネラル・パートナーシップ)に対する判断は微妙なものになるのではないかとの指摘が聞かれる。米国GPSの準拠法には最高裁が判示したような権利義務帰属主体基準を満たす条項があり、権利義務帰属主体基準によれば法人に該当することになるのであろうが、構成員全員が無限責任を持ち日本の任意組合のような特徴を有する米国GPSをそのように判断するのが正しいのかどうか悩ましいと言われている。
課税関係への影響
また、デラウェア州LPSの法人該当性が肯定されたことにより、外国子会社配当益金不算入制度、タックス・ヘイブン対策税制、日米租税条約の適用など、他の課税関係への影響が懸念されるようになり、課税当局が実務上の混乱を防止するため何らかの指針を示す可能性が指摘されていた。特に、デラウェア州LPSが日本の税法上「法人」として取り扱われる場合に、日本の居住者が投資から得られる所得(配当、利子等)に対する米国での源泉徴収について日米租税条約の軽減税率又は免税措置を適用することができないのではないかという懸念が大きかった。これに対し国税庁は、日本の居住者による日米租税条約上の特典享受を可能とすることを主な目的として平成29年2月9日、ホームページ上に「The tax treatment under Japanese law of items of income derived through a U.S. Limited Partnership by Japanese resident partners」(英文のみ)と題する情報を公開し、平成17年度税制改正(外国パートナーシップの損金算入制限措置の新設)に照らし、「構成員たる居住者が米国LPSを通じて得る所得について構成員課税の取扱いによったとしても、今後、国税庁はこれを否定しない。(ただし米国税法上、法人課税を選択(チェック・ザ・ボックス規則)した場合を除く)」との見解を明らかにした。
結果として、米国LPSについては、構成員課税か法人課税かを選択できる方式が認められることになったということもできるが、米国LPSを日本の税法上構成員課税(パススルー)として扱うことは、最高裁判決の法解釈とは整合しない。国税庁情報は、結びとして、日米租税条約の適用関係にのみ言及しており、他の税制における米国LPSの取扱いにまで射程が及ぶかは明らかではなく、専門家の見解も分かれている。
05 ワシントン州LPS-法人格肯定
デラウェア州LPS最高裁判決後の事案としては、ワシントン州LPSの法人該当性が争われた事件が3件あるが(東京地裁平成28年4月27日判決、東京地裁平成28年12月22日判決、東京地裁平成29年1月24日判決)、まさに当該最高裁判決が示した判断基準によって当てはめを行なって、法人に該当するという判断がなされた。
3つの判決のうち、平成28年12月22日判決及び平成29年1月24日判決は、表5のとおり、デラウェア州LPS最高裁判決の2つの基準の当てはめを行なっている。
【表5】
| 本件ワシントン州LPSへの当てはめ |
| 判断基準①について 米国ワシントン州のLPS法においては、LPSは「パートナーとは別個の主体」(an entity distinct from its partners)である旨のエンティティ規定が定められているところ、米国の法令において「entity」が日本法上の法人に相当する法的地位を指すものであるか否かは明確でなく、また、パートナーとは別個の主体とされていることをもって直ちに日本法上の法人に相当するということはできないから、「an entity distinct from its partners」であるとされる組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価することができるか否かについても明確ではない。 そして、ワシントン州事業法人法において、LPSは「corporation」であるとはされておらず、同法の「corporation」の定義規定においても「an entity distinct from」等の文言は用いられていないことなども併せ考慮すると、州LPS法等においてLPSが「an entity distinct from its partners」となるものと定められていることをもって、本件LPSに日本法上の法人に相当する法的地位が付与されていることが疑義のない程度に明白であるとすることは困難である。 他方で、ワシントン州のLPS法において、パートナーシップが「個人」や「corporation」等と並んで「法的又は商業上の主体(entity)」とされていることを前提とした上で、LPSが「パートナーとは別個の主体」(an entity distinct from its partners)とされており、これらの規定は法人の法的地位と抵触しない内容のものであることなどからすれば、本件LPSに日本法上の法人に相当する法的地位が付与されていないことが疑義のない程度に明白であるとすることも困難である。 判断基準②について (1)LPSの法律行為の権限等及びその効果の帰属に関する州LPS法等の規律 本件各LPSの設立根拠法令である州LPS法等は、LPSに自らの名義で法律行為をする権限を付与するとともに、LPSの名義でされた法律行為の効果がLPS自身に帰属することを前提としているものと解するのが相当である。 (2)LPSに係るパートナーシップの持分に関する規律 州LPS法等の定めの内容等に照らせば、LPSのパートナーは、LPSに属する個々の財産に対して割合的な権利を具体的に有していないものとみるのが相当であるから、上記(1)のLPSの法律行為の権限及びその効果の帰属に関する規律は、LPSに係るパートナーシップの持分に関する州LPS法等の規律とも整合する。 (3)本件各LPS契約の内容 本件各LPS契約における、本件各LPSが営む事業の主要な目的及び一般的な特徴、各LPが清算その他の場合に本件各LPSに対し現金以外の形式での分配を要求したり受領したりするいかなる権利を有しないとされていること、その他の本件各LPS契約の各条項は、上記(1)(2)と整合する。 |
06 他の事業体への適用について
上記のとおり、デラウェア州LPS最高裁判決後の事案であるワシントン州LPSは、最高裁判決の基準で判断され、法人該当性が肯定される結果となった。
では、ケイマンLPSやバミューダLPSのような英国型のパートナーシップの場合はどうだろうか。ケイマンLPSについては、ケイマンLPSを通じて行われた船舶賃貸事業に係る組合参加契約が民法上の組合契約かそれとも利益配当契約となるのか(損益通算の可否)が争われた事案(いわゆる船舶リース事件)(名古屋高裁平成19年3月8日判決、平成20年3月27日上告不受理決定)があるが、これらの判決では「ケイマン法に基づいて成立された特例LPSである本件パートナーシップは、我が国の民法における組合の要件を満たしうる」との判断が示された(ただし、船舶リース事件は民法上の組合かどうかが争われたもので、法人該当性が真正面から問われたものではないとの声もある)。また、バミューダLPSについては、上記のとおり、損益帰属主体基準によって法人該当性が否定されたところである。しかし、おそらく最高裁判決の基準によったとしても、やはり法人該当性は否定されるだろうというのが多くの専門家の見立てであるようだ。
その理由としては、まず①の形式的な基準については、準拠法に法人格を付与する旨の規定はなく、「corporation」や「body corporate」はもちろん、「separate legal entity」や「entity distinct from its partners」といった文言もなく「firm」との規定があるのみであり、「firm」の持つ意味からすると、法人格のないことが疑義のない程度に明白かとは言えないだろうということだ。そうすると②の基準で判断することになるが、②の権利義務帰属主体基準については、PS法に、「パートナーは専らパートナーシップの事業目的のために、かつパートナー契約に基づき、パートナーシップ財産を保有し使用しなければならない」との規定があること等から、権利義務帰属主体基準も満たさないだろうと言われている。また、LPS自体ではなくパートナー(構成員)が契約締結の法的主体とされていると指摘する声もある。
今後、外国事業体の法人該当性が争われる場合には、デラウェア州LPS最高裁判決の基準により判断されることになっていくと思われるが、当該判決は、デラウェア州LPSの法人該当性判断のアプローチを示すにとどまり、明確な基準を提示しているものではないとの指摘がある。したがって、その他のLPSや類似のパートナーシップの法人判断については、個別具体的に準拠法やパートナーシップ契約等の規定の内容を検討することが必要、というのが大方の専門家の意見であるようだ。
外国事業体の法人該当性に関連したところでは、最近も、ケイマンLPSを用いた組織再編事案である塩野義製薬事件について、令和2年3月11日に東京地裁から判決が出されている(本誌830号40頁参照)。当該事案では、ケイマンLPS持分の国外子会社への現物出資が適格現物出資であるかどうかが争われ、争点は、現物出資の対象資産が国内資産であるかどうかであり、ケイマンLPSの法人該当性については争われなかった。しかし、ケイマンLPSが日本の租税法上法人として扱われる場合には、LPS持分が「株式」に当たり適格要件を満たすことになるので、納税者側には法人該当性を主張して争う余地もあったのではないかという専門家の指摘もある。
外国事業体の法人該当性を巡る実務を安定させるためには、さらなる事例の積み重ね、あるいは法整備が待たれるところだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















