解説記事2020年09月21日 未公開判決事例紹介 マンション販売事業者の仕入税額控除の用途区分(2020年9月21日号・№850)
未公開判決事例紹介
マンション販売事業者の仕入税額控除の用途区分
東京地裁、課税対応課税仕入れに区分
読者からの反響が大きかった本誌849号4頁で紹介した消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件の判決全部について、仮名処理した上で紹介する。
○住宅用賃貸部分を含むマンションの購入が「課税売上のみ要する課税仕入れ」あるいは「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ」のいずれに区分されるかが争点となった事件。東京地方裁判所(清水知恵子裁判長)は令和2年9月3日、課税処分の全部を取り消す判決を下した(平成30年(行ウ)第559号)。東京地裁は、仕入日に賃料収入が見込まれることをもって共通対応課税仕入れに区分することは事業に係る経済実態から著しくかい離するばかりでなく、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点に照らしても、相当性を欠くものといわざるを得ないと指摘。各課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものとして課税対応課税仕入れに区分するのが相当であるとし、各課税仕入れに係る消費税額はその全額が控除対象仕入税額となるとの判断を示した。
主 文
1 K税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額マイナス1465万0657円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス407万2865円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
2 K税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額マイナス689万5404円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス186万0549円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 K税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額マイナス1億2791万4478円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス3451万6505円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文1項から3項までと同旨
第2 事案の概要等
1 事案の概要
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい、他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において、将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は、消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下、本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。)、原告は、本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において、本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして、本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し、K税務署長(処分行政庁)は、本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから、本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして、平成30年7月30日付けで、原告に対し、本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。
本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
2 関係法令の定め
本件に関する消費税法の定めは別紙2−1、地方税法(平成24年法律第69号による改正前のもの。以下同じ)の定めは別紙2−2、国税通則法の定めは別紙2−3に記載のとおりである。なお、本件に関しては、平成27年法律第9号による改正前の消費税法及び平成24年法律第69号による改正前の地方税法も適用されることになるが、本件の争点との関係では実質的な差異はない。
(1)消費税の課税の対象
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう(消費税法4条1項、2条1項8号)。国内において行われる資産の譲渡等のうち、住宅の貸付けや土地の譲渡など一定のものについては、消費税を課さないこととされており(同法6条1項、別表第1)、このような非課税とされるものを除いた資産の譲渡等を、課税資産の譲渡等という(同法2条1項9号)。
(2)仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは、所定の課税標準(課税資産の譲渡等であれば、その対価の額)に税率を乗じて得た金額(課税標準額に対する消費税額)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ(事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること〔消費税法2条1項12号〕)及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における保税地域からの課税貨物の引取り(以下、これらを併せて「課税仕入れ等」という。)に係る消費税額を控除する制度である(同法30条1項)。
控除される具体的な税額(以下「控除対象仕入税額」という。)は、事業者の課税売上高が5億円を超え、又は課税売上割合(後述)が95%に満たない場合には、次のア又はイの方法で計算される(消費税法30条2項)。
ア 個別対応方式
当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき、下記①から③までの区分(以下「用途区分」という。)が明らかにされている場合には、(a)課税対応課税仕入れ(下記①)に係る消費税額の合計額に、(b)共通対応課税仕入れ(下記③)に係る消費税額の合計額に課税売上割合(当該事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として、政令で定めるところにより計算した割合〔消費税法30条6項〕)を乗じた額を加算した金額が控除対象仕入税額となる(同条2項1号)。
また、事業者は、課税売上割合に代わる合理的な割合につき所定の要件を満たすものとして所轄税務署長の承認を受けている場合、上記(b)の計算において、その承認を受けた割合(以下「課税売上割合に準ずる割合」という。)を用いることができる(消費税法30条3項)。
記
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応課税仕入れ)
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「非課税対応課税仕入れ」という。)
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応課税仕入れ)
イ 一括比例配分方式
上記ア以外の場合、当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じた金額が控除対象仕入税額となる(消費税法30条2項2号)。
3 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告の収益不動産販売事業
原告は、不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社であり、平成15年から不動産投資事業に本格参入し、平成27年以降は東京証券取引所市場第1部に上場している。原告の主要な事業のうち、収益不動産販売事業(以下「本件事業」という。)は、富裕層の個人投資家を主な顧客とする販売事業であって、賃貸収益を上げることのできる収益不動産(中古の賃貸用マンション等)を仕入れ、その資産価値及び収益力を向上させるバリューアップ(①物件に改良工事を施す「リノベーション」、②物件を良好な状態に管理する「マネジメント」のほか、③物件を適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らす「リーシング」等の方法による。)を行った上で、当該収益不動産を顧客に転売するというものである(以下、このような本件事業の枠組みを「本件ビジネスモデル」ということがある。)。(甲4、48、49、乙3)
(2)本件各課税仕入れ
原告は、本件各課税期間において、本件ビジネスモデルに基づき、バリューアップ後の転売を目的として、中古の賃貸用マンション(主に居住用であるが、一部に事務所、店舗が混在するものを含む。)である本件各マンション合計84棟(平成27年3月期及び平成28年3月期はいずれも26棟、平成29年3月期は32棟。)を購入した(本件各課税仕入れ)。
本件各マンションは、本件各課税仕入れが行われた日(以下「本件各仕入日」という。)の時点において、その一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、本件各マンションの購入によってその賃貸人たる地位を承継し、本件各マンションを転売するまでの間、その賃料を収受した。
(以上につき、甲2の1~3、50、乙4~7)
(3)本件各確定申告
原告は、本件各課税期間の消費税等について、個別対応方式で控除対象仕入税額を計算することを選択した上で、本件各課税仕入れの用途区分に関しては、建物の販売(課税資産の譲渡等)を目的にしたものであるから課税対応課税仕入れに区分すべきであるとして、本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除し、別表1−1から1−3までの各「確定申告」欄記載のとおり、法定申告期限までに確定申告を行った(以下「本件各確定申告」という。)。
なお、本件各課税期間における原告の課税売上高は5億円を超えており、課税売上割合も95%を下回っていた。また、原告は、本件各課税期間中に国内において行った課税仕入れ等について、用途区分を明らかにしていた(原告は、一部において建物賃貸業も行っているが、住宅の貸付けを目的として購入した建物については、非課税対応課税仕入れとして申告している。)。
(以上につき、甲1の1~3、甲2の1、乙1の1~3)
(4)本件各処分
K税務署長(処分行政庁)は、本件各課税仕入れの用途区分について、建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)も目的としたものであるから、共通対応課税仕入れに区分すべきであって、課税標準額に対する消費税額から控除することができるのは、本件各課税仕入れに係る消費税額に本件各課税期間に係る課税売上割合(平成27年3月期は約36%、平成28年3月期及び平成29年3月期はいずれも約34%。以下「本件各課税売上割合」という。)を乗じた金額にとどまるとして、平成30年7月30日付けで、原告に対し、別表1−1から1−3までの各「更正処分」欄記載のとおり、本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(本件各更正処分)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をした。なお、平成27年3月期に係る更正処分においては、本件各課税仕入れの用途区分が上記のとおり変更されたほか、原告が住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)を目的として購入したマンション1棟に係る課税仕入れについても、駐車場の貸付け(課税資産の譲渡等)を含むとの理由で、用途区分が非課税対応課税仕入れから共通対応課税仕入れへと変更されている。(甲2の1~3、58の1~3)
(5)本件各確定申告では、納付すべき消費税等の額がマイナスとなり、合計1億8991万0458円の還付金が生じていたのに対し、本件各更正処分では、還付金はなくなり、合計2億7731万5400円の消費税等を納付すべきことになり、差引納付すべき消費税等の額は合計4億6722万5858円となった。また、過少申告加算税の額は合計7000万8000円となった(別表1−1から1−3まで)。
なお、本件各確定申告と本件各更正処分とでこのような差が生じたのは、上記(4)のとおり本件各課税売上割合が約34~36%にとどまるためであるが、これは、原告の本件各課税期間の売上げの一部に住宅の貸付けによる収入が含まれるほか、本件ビジネスモデルの下で、中古の賃貸用マンションを転売する際に、その敷地の譲渡(土地の譲渡は非課税である。)も併せて行われるのが通常であるため、非課税売上げの金額が全体の相当部分を占めることとなるという、構造的な要因によるものである。
(6)審査請求
原告は、本件各処分を不服として、平成30年9月13日付けで審査請求をした(甲3)が、国税不服審判所長は、審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決をしなかった。
(7)本件訴訟の提起等
原告は、平成30年12月14日、国税通則法115条1項1号に基づき、国税不服審判所長の裁決を経ることなく本件訴訟を提起した。そして、原告は、平成31年3月19日、上記(6)の審査請求を取り下げた(乙8)。
4 争点
(1)本件各更正処分の適法性に関し
ア 本件各課税仕入れの用途区分(本件各課税仕入れが課税対応課税仕入れと共通対応課税仕入れのいずれに区分されるべきものであるか)(争点(1))
イ 平等取扱原則違反の有無(争点(2))
(2)本件各賦課決定処分の適法性に関し
国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無(争点(3))
5 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙3記載のとおりである。また、被告が主張する本件各処分に係る課税の根拠及び計算は、別紙4記載のとおりであるところ、原告は、上記4において争点となっている点を除き、これを争うことを明らかにしていない。なお、上記各別紙で定義した略語は、本文においても用いる。
第3 当裁判所の判断
当裁判所は、本件各課税仕入れは専ら将来における不動産の転売のためにされたものとして課税対応課税仕入れに区分すべきものであり、その消費税額の全額が控除対象仕入税額となるため、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分はいずれも違法であるから、これらの取消しを求める原告の請求は認容すべきものと判断する。その理由の詳細は、以下のとおりである。
1 争点(1)(本件各課税仕入れの用途区分)について
(1)仕入税額控除及び用途区分の趣旨等
ア 消費税の制度は、広く公平な税負担を求めるという観点から、ほとんど全ての国内における取引を課税の対象とするものであるが、これらの取引は生産や流通等の各段階に及ぶため、それぞれの取引に消費税が課される結果、製品やサービスが消費者(いわゆる最終消費者を指す。以下同じ)に購入されるまでの間に二重、三重に消費税が課されることとなって税負担が累積すると、その負担は消費者が購入する製品等の価格に転嫁されることとなる。このような税負担の累積を避け、消費者に対する税負担の適正な転嫁を実現し、もって中立かつ公平な課税の確立を図るため、消費税法は、仕入税額控除の制度を採用し、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等の消費税額(控除対象仕入税額)を控除するものとしている(30条1項。関係法令(2))。
イ もっとも、課税仕入れ(事業として行う資産の譲受け等)は、課税資産の譲渡等のために行われるばかりでなく、その他の資産の譲渡等(住宅の貸付けなど、消費税を課さないこととされている資産の譲渡等)のためにも行われることがあり、後者(その他の資産の譲渡等のために行われる課税仕入れ)については税負担の累積は生じないため、その課税仕入れに係る消費税額を控除する必要はない。そこで、消費税法は、課税売上高が5億円を超え、又は課税売上割合が95%に満たない事業者について、個別対応方式(30条2項1号)又は一括比例配分方式(同項2号)のいずれかによって控除対象仕入税額を算定とすることとしている(関係法令(2)ア、イ)。
これらのうち、個別対応方式は、事業者が当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応課税仕入れ)、②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(非課税対応課税仕入れ)、③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応課税仕入れ)のいずれかに当たるかにつき区分した場合の控除対象仕入税額の算定方法であって、 課税対応課税仕入れに区分したものについてはその消費税額の全部を、
課税対応課税仕入れに区分したものについてはその消費税額の全部を、 共通対応課税仕入れに区分したものについてはその消費税額に課税売上割合を乗じた額を、控除対象仕入税額に含めるものとされている(消費税法30条2項1号。関係法令(2)ア)。
共通対応課税仕入れに区分したものについてはその消費税額に課税売上割合を乗じた額を、控除対象仕入税額に含めるものとされている(消費税法30条2項1号。関係法令(2)ア)。
したがって、課税資産の譲渡等に要するものであることが明らかな課税仕入れ等については、課税対応課税仕入れと共通対応課税仕入れのいずれに区分されるかによって、控除対象仕入税額に当該課税仕入れ等に係る消費税額の全部を含めるのか、当該課税仕入れ等に係る消費税額に課税売上割合を乗じた額のみを含めるのかが異なることになるところ、特に、課税売上割合が低い事業形態の場合には、課税仕入れ等の用途区分による差異は大きなものとなる。
以上に鑑みると、課税仕入れの用途区分に係る判断は、税負担の累積の排除という消費税法の目的に照らし、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点から、当該課税仕入れがいかなる取引のために行われたものであるのかを、その経済実態に即して適切に行うべきものである。
ウ ところで、消費税法30条2項1号が課税仕入れ等の用途区分につき「要するもの」という文言を用いているのは、①課税仕入れ等に対応する取引(資産の譲渡等)が必ずしも当該課税期間中に行われるとは限らないことや、②課税仕入れ等が事業者による経済活動の一環として行われるものである以上、将来における一定の取引を目指したものということができ、実際に当該課税仕入れ等に対応するどのような取引が行われたか(あるいは、行われなかったか)を見るまでもなく、当該課税仕入れ等がどのような取引を目指して行われたかを見れば、用途区分を判定するのに十分であることによるものと解される。
このような消費税法30条2項1号の文言及び趣旨に鑑みると、課税仕入れ等の用途区分に係る判断は、当該課税仕入れ等を行った日(仕入日)を基準に、事業者が将来におけるどのような取引のために当該課税仕入れ等を行ったのかを認定して行うべきである。そして、かかる認定に当たっては、税負担の判断が事業者の恣意に左右されることのないよう、①当該事業者の事業内容・業務実態、②当該事業者における過去の同種の課税仕入れ等及びこれに対応して行われた取引の内容・状況、③当該課税仕入れ等と過去の同種の課税仕入れ等との異同など、仕入日に存在した客観的な諸事情に基づき認定するのが相当である。
(2)本件ビジネスモデル下における用途区分の認定について
ア 問題の所在
本件ビジネスモデルは、事業者が、中古の賃貸用マンション等の収益不動産を購入し、適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らすというリーシングを行った上で当該収益不動産を顧客に転売するというものである(前提事実(1))。したがって、本件ビジネスモデル下における課税仕入れ(収益不動産〔建物〕の購入)が、将来における当該収益不動産(建物)の売却(課税資産の譲渡等)のために行われるものであることは、明らかである。
もっとも、本件ビジネスモデル下で収益不動産を購入する事業者は、仕入日に賃借人が存在する場合に自らその賃貸人たる地位を承継することにより、また、仕入後にリーシングを行うことにより、当該収益不動産を転売するまでの間に賃料収入を得ることが見込まれるところ、住宅の貸付けは「その他の資産の譲渡等」に該当することから、仮に、当該課税仕入れの用途区分の判定において、かかる賃料収入が見込まれることをもって当該課税仕入れにつき「その他の資産の譲渡等」にも要するものと評価することとすれば、当該課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分されることとなる。
被告は、おおむね上記のような考え方に基づき、本件各課税仕入れが本件ビジネスモデル下で行われていることや、本件各仕入日において本件各マンションに賃借人が存在し、原告がその賃貸人たる地位を承継したこと(前提事実(2))から、原告が本件各マンションの賃料を収受することは確実であったものであり、そうである以上、本件各課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分すべきである旨を主張する。
イ しかしながら、本件ビジネスモデルにおいて課税仕入れの目的が収益不動産の売却にあることは明らかであるのに、当該事業における賃料収入の位置付けや、賃料収入が売上げ全体に占める割合その他の個別の事情を一切考慮せずに、将来の賃料収入が確実に見込まれるというだけで常に共通対応課税仕入れに区分すべきものと解するとすれば、経済実態と著しくかい離するおそれがあるにとどまらず、上記(1)のような税負担の累積の排除という消費税法の目的や、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点に照らしても、問題が生ずるといわざるを得ない。
殊に、本件ビジネスモデルの下では、収益不動産を転売する際に、建物だけでなく、その敷地の譲渡(土地の譲渡は非課税である。)も併せて行われるのが通常であるため、転売による売上げ全体に占める建物の売上げの割合は相対的に低いものとならざるを得ず、したがって、事業者が当該課税期間中に行う資産の譲渡等の対価のうちに課税資産の譲渡等が占める割合(課税売上割合)も、これに応じた低いものとなることを免れない(前提事実(5)。本件各課税売上割合は、約34~36%である。)。
そうすると、上記のような課税売上割合と、賃料収入額が売上げ全体に占める割合とのギャップによって、建物の取得価格に対する消費税額のうち相当部分に税負担の累積が生じてしまうこととなるが、本件ビジネスモデル下で仕入日に賃借人の存する収益不動産を購入する場合において、常にこのような税負担の累積を許すこととすれば、税負担の累積の排除という消費税法の目的を十分に達成し得ないこととなる。
なお、被告は、このような課税売上割合とのギャップの問題は、課税売上割合に準ずる割合(消費税法30条3項)の利用によって解消すべきものである旨を主張するが、課税売上割合に準ずる割合を用いるためには、合理的な計算方法を定めて事前に所轄税務署長の承認を受けておかなければならないのであって、上記のような本件ビジネスモデル下における課税売上割合とのギャップの問題が、課税売上割合に準ずる割合の利用によって解消し得るものとは直ちに解し難い。
ウ 以上のような問題点を踏まえ、翻って検討すると、一般に、事業者が課税仕入れ等を行う場合に、当該活動が本来得ることを目的としている収入(課税資産の譲渡等)のほかに、当該活動の過程で生じる他の収入(その他の資産の譲渡等)が見込まれることにより、当該課税仕入れ等が共通対応課税仕入れに区分されることとなるのか否かについては、一義的に解するのではなく、①他の収入が当該事業者の経済活動におけるどのような過程で得られ、その活動全体の中でどのように位置付けられているのか、②他の収入が見込まれることが、課税仕入れ等やこれに対応する取引にどのような影響を及ぼしているのか、③全体の収入の見込額のうちに他の収入の見込額が占める割合など、当該事業者が行う経済活動に関する個別の事情を踏まえ、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点に照らし、他の収入が見込まれることをもって当該課税仕入れ等につき「その他の資産の譲渡等」にも要するものと評価することが相当といえるか否かを考慮して判断すべきである。
エ そうすると、本件ビジネスモデル下における課税仕入れについては、仕入日に将来の賃料収入が確実に見込まれるというだけで直ちに共通対応課税仕入れに区分されるものと解すべきではなく、上記ウのような当該事業者が行う経済活動に関する個別の事情に基づく検討がされるべきであるから、被告の上記アの主張は採用することができない。
そこで、以下、原告が行う事業に関する個別の事情を認定の上、本件各課税仕入れの用途区分につき検討する。
(3)認定事実
ア 原告の事業の内容等(前提事実(1)、甲4、48、49、乙22)
(ア)概要
原告(原告のグループ会社を含む。以下、アにおいて同じ)は、富裕層の個人投資家を対象にした不動産事業を行っており、①本件ビジネスモデルに基づく収益不動産販売事業(本件事業)と、②ストック型フィービジネスの二つを主力事業としている。
(イ)本件事業の内容等
a 収益不動産販売事業(本件事業)は、個人投資家の購買ニーズの強い、首都圏に所在する5億円以下の住居系収益不動産(中古の賃貸用マンション等)を自己勘定で購入し、バリューアップを図った上でこれを顧客(個人投資家)に転売するというものである。仕入れた収益不動産については、販売用の資産であることから、棚卸資産として計上されている。
b 原告が仕入れた収益不動産のバリューアップは、①リノベーション(改良工事を施すこと)、②マネジメント(良好な状態に管理すること)及び③リーシング(適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らすこと)によって行われる。なお、リノベーションは、建物の外観や共用部分、設備等について行うものであって、現に貸し付けられている居室の内装について行うものではない。
バリューアップの方法の中でも、リーシングは、不動産の収益力を向上させるものであって、収益不動産を転売する上で重要な意義を有している。収益不動産の購入者(個人投資家)は、表面利回り(満室であるとした場合に想定される年間賃料収入を、当該収益不動産の購入価格で除した割合による利回り)に基づいて投資判断を行うのが一般的であり、空室の多い不動産(表面利回りどおりの賃料収入を得られない可能性が高い不動産)への投資をちゅうちょする傾向にあるため、リーシングにより空室を減らすことによって、売買契約の成立率や転売価格を上げる効果がある。
c 原告が収益不動産を仕入れるに当たっても、上記のようなリーシングによるバリューアップを経た上で顧客に販売することを想定しているため、満室となった場合を想定した表面利回りを前提とした想定販売価格に基づき、購入費(改修費用等を含む。)に対してどの程度の利益が見込まれるかを検討した上で、販売用資産として仕入れるか否かを決定している(甲56の3)。これに対し、当該収益不動産により原告が得る賃料収入がどれだけ見込まれるかは、仕入時の判断において考慮に入れられていない。
また、原告が収益不動産を販売するに当たっては、市況や顧客との交渉状況を踏まえつつ、想定販売価格にできるだけ近い値で販売できる状況になり次第、速やかに販売しており、賃料収入がどれだけ得られるかは販売時期の決定等においても考慮に入れられていない。
(ウ)ストック型フィービジネスの内容等
a ストック型フィービジネスは、本件事業で収益不動産を購入した顧客に対し、不動産経営に関する各種のソリューションを提供するサービス事業である。その内容は、①マネジメント業務の代行(管理、リーシング、賃料徴収等)、②不動産活用に関するコンサルティング(修繕プランの提案等)、③不動産の鑑定評価に大別される。
b 本件事業で購入した収益不動産から原告が得る賃料収入は、ストック型フィービジネスの収入として計上されている。なお、本件事業により購入した収益不動産は棚卸資産として計上され、減価償却の対象とならないため、その購入代金が上記賃料収入の費用として計上されることはない。
イ 平成24年3月期から平成26年3月期までにおける本件事業の展開状況(甲70)
(ア)原告は、本件各課税期間に先立つ平成24年3月期から平成26年3月期までの各課税期間(以下「直近3課税期間」という。)において、本件事業における転売を目的として、賃貸用マンション合計84棟(平成24年3月期が19棟、平成25年3月期が34棟、平成26年3月期が31棟)を仕入れた。これらのマンションは、仕入日において、その一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、その賃貸人たる地位を承継し、その後転売までの間に生じた賃料を収受した。
原告は、上記各マンションについてバリューアップを行い、全84棟のうち83棟を仕入価格よりも高値で転売した(平成25年12月に購入した1棟のみ、転売未了である。)。これらのマンションは、原告における会計処理上、いずれも棚卸資産に計上されていた。
(イ)直近3課税期間のそれぞれにおける、①購入時の入室率、②転売時の入室率、③転売による収入(販売収入)、④転売までの間に得た賃料収入、⑤転売までの保有期間(いずれも1棟当たりの平均値)は、次の表に記載のとおりである。
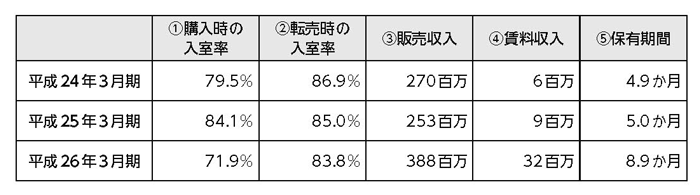
これによれば、リーシングによる入室率の上昇は、平成24年3月期が7.4%、平成25年3月期が0.9%、平成26年3月期が11.9%であり、これらを平均すると6.73%となる。なお、仕入日の稼働率が6割を下回る場合でも、リーシングにより、転売時までに稼働率が大幅に改善された例が散見される。
また、販売収入と賃料収入の総和(上記③+④)に占める賃料収入(上記④)の割合は、平成24年3月期が2.17%、平成25年3月期が3.44%、平成26年3月期が7.62%であり、これらを平均すると4.41%となる(なお、販売収入のうち建物部分を仮に3割とすると、建物の販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合は、平成24年3月期が6.90%、平成25年3月期が10.60%、平成26年3月期が21.56%であり、これらを平均すると13.02%となる。)。
なお、転売されるまでの保有期間(上記⑤)を平均すると、直近3課税期間を通じて6.27か月となる。
ウ 本件各課税期間における本件事業の展開状況(前提事実(2)、甲2の1~3、22、50)
(ア)原告は、本件各課税期間において、本件事業における転売を目的として、本件各マンション合計84棟(平成27年3月期及び平成28年3月期はいずれも26棟、平成29年3月期は32棟)を仕入れた。本件各マンションは、本件各仕入日において、その一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、その賃貸人たる地位を承継し、その後転売までの間に生じた賃料を収受した。
原告は、本件各マンションについてバリューアップを行い、全84棟のうち80棟を仕入価格よりも高値で転売した(4棟は販売未了である。)。本件各マンションは、原告における会計処理上、いずれも棚卸資産に計上されていた。
(イ)本件各課税期間のそれぞれにおける、①購入時の入室率、②転売時の入室率、③販売収入、④賃料収入、⑤転売までの保有期間(いずれも1棟当たりの平均値)は、次の表に記載のとおりである。
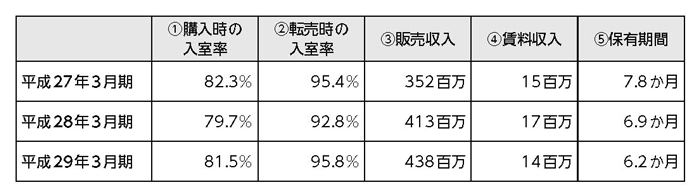
これによれば、リーシングによる入室率の上昇は、平成27年3月期が13.1%、平成28年3月期が13.1%、平成29年3月期が14.3%であり、これらを平均すると13.5%となる。なお、仕入日の稼働率が6割を下回る場合でも、リーシングにより、転売時までに稼働率が大幅に改善された例が散見される。
また、販売収入と賃料収入の総和(上記③+④)に占める賃料収入(上記④)の割合は、平成27年3月期が4.09%、平成28年3月期が3.95%、平成29年3月期が3.10%であり、これらを平均すると3.71%となる(なお、販売収入のうち建物部分を仮に3割とすると、建物の販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合は、平成27年3月期が12.44%、平成28年3月期が12.07%、平成29年3月期が9.63%であり、これらを平均すると11.38%となる。)。
なお、転売されるまでの保有期間(上記⑤)を平均すると、直近3課税期間を通じて6.97か月となる。
(4)本件各課税仕入れに係る用途区分の判定
上記(3)の認定事実を踏まえ、上記(1)及び(2)の観点に照らして、本件各課税仕入れに係る用途区分を検討する。
ア 本件事業は、富裕層の個人投資家を対象とした本件ビジネスモデルによる収益不動産販売事業であり、仕入れた収益不動産(中古の賃貸用マンション等)を転売時までにできるだけ満室に近づけるリーシングやリノベーション等のバリューアップを行うことにより、その収益力や資産価値を高め、当該収益不動産の販売による利益を得ようとするものであって、原告が仕入れた収益不動産を賃貸することは、販売のための手段として位置付けられるものである。そして、原告が得る賃料収入は、仕入れた収益不動産を賃貸することによって不可避的に発生するものであり、上記のとおり賃貸が収益不動産の販売のための手段であることに鑑みれば、収益不動産の販売による利益を得るという本件事業の目的との関係において、副産物というべきものである。
イ このような賃料収入の位置付けは、原告の会計処理にも表れている。すなわち、原告が仕入れた収益不動産を賃貸することによる賃料収入は、本件事業による収入とは扱われず、ストック型フィービジネスの収入として計上されているところ(認定事実ア(ウ)b)、ストック型フィービジネスは、本件事業で収益不動産を購入した顧客に対して展開される不動産経営に関する各種のサービス事業であり(同a)、上記賃料収入はこれらの事業とも関係がないから、実際には「その他」に近い取扱いがされているといえる。また、原告が本件事業において購入した収益不動産は、棚卸資産として計上され、減価償却の対象とならないため、その購入代金が賃料収入の費用として計上されることもない(同b)。
ウ そして、原告が収益不動産を仕入れるに当たっても、当該収益不動産による賃料収入がどれだけ見込まれるかは、仕入時の判断において考慮に入れられていない(認定事実ア(イ)c)。なお、仕入時において空室が多かったとしても、転売時までのリーシングにより稼働率を改善することができるため(直近3課税期間及び本件各課税期間における実際の稼働率の改善状況を参照〔認定事実イ(イ)、ウ(イ)〕。)、収益不動産の空室状況が仕入時の判断に及ぼす影響も小さいといえる。
エ さらに、原告が収益不動産を販売するに当たっても、上記ウと同様に、販売時期の決定等において原告が得られる賃料収入が考慮に入れられることはなく、当該収益不動産について販売できる状況が整い次第、速やかに販売されている。そのため、直近3課税期間及び本件各課税期間における転売までの保有期間も、おおむね6~7か月となっており(認定事実イ(イ))、ウ(イ))、その結果として、販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合も、直近3課税期間において4.41%、本件各課税期間において3.71%(販売収入のうち建物部分を仮に3割として計算した場合の建物の販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合は、直近3課税期間において13.02%、本件各課税期間において11.38%)にとどまっている。
オ 用途区分に係る小括
上記アからエまでに検討したところによれば、原告が本件事業において仕入れた収益不動産を賃貸して得られる賃料収入は、当該収益不動産の販売を行うための手段としての賃貸から不可避的に生じる副産物として位置付けられるものであって、このことは、原告の会計処理における取扱いや、収益不動産の仕入れ及び販売の際に原告がどれだけ賃料収入を得られるかが考慮に入れられていないことからも裏付けられるものである。そして、原告が実際に得ている賃料収入も、販売収入と賃料収入の総和に対して3課税期間の平均で5%未満(販売収入のうち建物部分を仮に3割として、建物の販売収入と賃料収入の総和に占める割合を見ても、おおむね1割程度)にとどまっている。また、これらに関しては、直近3課税期間と本件各課税期間とで有意な差が見られない。
これらの事実関係に照らせば、本件各仕入日に上記のような賃料収入が見込まれることをもって、本件各課税仕入れにつき「その他の資産の譲渡等」にも要するものとして共通対応課税仕入れに区分することは、本件事業に係る経済実態から著しくかい離するばかりでなく、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点に照らしても、相当性を欠くものといわざるを得ない。
したがって、本件各課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものとして課税対応課税仕入れに区分するのが相当であるから、本件各課税仕入れに係る消費税額は、その全額が控除対象仕入税額となる。
カ 被告の主張に関し
被告は、原告のウェブサイトに、「ストック型フィービジネスの収益には…中古物件を仕入れた後、販売するまでの間に確保できる賃料収入も含まれて」おり、「収益不動産残高の拡充を進め、賃料収入を増加させることで、安定した収益モデルへの転換を図って」いるとの記載があること(甲4)を根拠に、本件各課税仕入れは将来の転売のみならず住宅の貸付けにも要するものであったと主張する。
しかしながら、原告のウェブサイトにおける上記の記載は、いわゆるIR情報(投資家向け広報)として公にされたものであり(甲48)、原告の主力事業である収益不動産販売事業の拡大に伴い生ずる収益不動産残高の増加という事態を、投資家からネガティブに捉えられないよう説明する趣旨と理解することができるものであって、かかる記載が存在するというだけで、本件各課税仕入れが住宅の貸付けにも要するものであったと認めることはできない。そして、原告の事業に係る客観的な事実関係に照らし、本件各課税仕入れにつき共通対応課税仕入れに区分することが相当でないことは、以上に説示したとおりである。
したがって、被告の上記主張は採用することができない。
2 本件各処分の適法性について
(1)本件各更正処分に関し
上記1の判断並びに別紙4記載の被告が主張する課税の根拠及び計算(争点となっている点を除く。)によれば、本件各課税期間に係る控除対象仕入税額は、平成27年3月期については別表3−4(⑯欄)に記載のとおりとなり、平成28年3月期及び平成29年3月期については、別表3−2(⑱欄)及び3−3(⑱欄)に記載のとおり(申告額と同額)となる。そして、これらの控除対象仕入税額を前提にすれば、本件各課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額の計算は、別表2−4から2−6までに記載のとおりとなる(納付すべき税額はいずれもマイナスとなるため、上記各表の⑩欄及び⑱欄のとおり還付金が生じることとなる。)。
以上によれば、本件各更正処分のうち上記に認定した納付すべき税額を超える部分(ただし、平成27年3月期については申告額を超える部分〔原告が取消しを求める部分と同じ。〕)は、争点(2)(平等取扱原則違反の有無)について判断するまでもなく、違法であって、取消しを免れない。
(2)本件各賦課決定処分に関し
上記(1)の判断によれば、本件各更正処分によって新たに納付すべき税額は存在しないこととなるから、本件各賦課決定処分は、争点(3)(国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無)について判断するまでもなく、同条1項及び2項所定の課税要件を欠く違法なものであって、取消しを免れない。
第4 結論
以上によれば、原告の請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
裁判長裁判官 清水知恵子
裁判官村松悠史及び裁判官松原平学は、転補のため、署名押印することができない。
裁判長裁判官 清水知恵子
(別紙1、別紙2−1、2−2、2−3:略)
(別紙3)
当事者の主張の要旨
1 争点(1)(本件各課税仕入れの用途区分)について
(被告の主張の要旨)
(1)用途区分の判定基準
ア 消費税は、生産、流通過程を経て事業者から消費者に提供される物品・サービスの流れに着目し、製造、卸、小売等の各事業者が行う取引に課税することを目的とするものであるところ、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除しないと、生産、流通の各段階で二重、三重に税が課される結果となる。そこで、消費税法30条1項は、このような税の累積を避けるため、仕入税額控除の制度を設け、事業者が国内で課税仕入れ等を行った場合の納付すべき消費税額の算定に当たり、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内で行った課税仕入れ等の税額を控除することとしている。
事業者が行った仕入れが課税仕入れ等に該当するか否かは、仕入れを行った日において判断されるべきものである。そして、課税仕入れ等に該当すると判断された場合には、当該課税仕入れ等に係る消費税額は、対応する課税資産の譲渡等が実際に行われたか否かにかかわらず、仕入れを行った日の属する課税期間において、課税標準額に対する消費税額から控除されることになる。いわゆる費用収益対応の原則は、仕入税額控除においては採用されていない。
イ 控除の対象となる税額を個別対応方式に基づいて計算する場合、課税期間中に国内において行った課税仕入れ等について、その用途区分を明らかにする必要があるところ、消費税法30条2項1号は、かかる用途区分について、「…要したもの」ではなく「…要するもの」と規定しており、課税仕入れ等が実際にいかなる資産の譲渡等に用いられたかを問題としていない。
また、上記アのとおり、課税仕入れ等に該当するか否かは、仕入れを行った日において判断すべきものであるから、当該課税仕入れ等に係る用途区分についても、これと同様に、当該課税仕入れ等を行った日を基準に判定すべきである。
以上を踏まえれば、用途区分の判定に当たっては、当該課税仕入れ等を行った日の状況に基づき、その取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちどのような取引に要するものであるのかを客観的に判断すべきものと解するのが相当である。そして、このような判断は、将来の事情を想定して行わざるを得ないものであるから、当該課税仕入れ等を行った日を基準に、当該事業者における過去の同種の課税仕入れ等の状況や事業内容、あるいは当該課税仕入れ等に係る一連の事情等から考察される当該課税仕入れ等の目的・意図、さらに、客観的にみてその後に予定されているといえる取引の内容といった事情を考慮して行うのが相当である。
(2)本件各課税仕入れの用途区分
本件各課税仕入れは、後記アのとおり、将来の転売(課税資産の譲渡等)に要するものであるとともに、後記イのとおり、住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)にも要するものであるから、共通対応課税仕入れに区分すべきである。
ア 本件各課税仕入れが将来の転売(課税資産の譲渡等)に要するものであること
原告は、収益不動産を購入し、バリューアップを行った上で富裕層の個人投資家に転売するとのビジネスモデル(本件ビジネスモデル)に基づく事業を行っている。原告は、このような本件ビジネスモデルの下、本件各マンションを譲り受け、会計処理上これらを棚卸資産(通常の営業循環過程において販売又は費消される資産)として計上していたのであるから、原告は、本件各マンションを譲り受けた日(本件各仕入日)の時点において、本件各マンションを転売することを客観的に予定していたと認めるのが相当である。
したがって、本件各課税仕入れは、本件各仕入日において、原告が将来行う「課税資産の譲渡等」に要するものであったというべきである。
イ 本件各課税仕入れが住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)に要するものであること
本件各マンションは、いずれもその一部又は全部が住宅として貸し付けられていたところ、原告は、本件各マンションを譲り受けるに当たり、賃借権付売買契約により上記の貸付けに係る賃貸人たる地位を承継しているのであるから、本件各仕入日の時点において、本件各マンションから賃料を確実に収受することができる状況にあったというべきである。そして、原告が、本件各仕入日以降の賃料を現に収受していることをも併せ考えれば、原告は、本件各仕入日の時点において、本件各マンションから生ずる貸料を収受することを客観的に予定していたと認めるのが相当である。
このことは、①原告のウェブサイト(甲4)に、「ストック型フィービジネスの収益には…中古物件を仕入れた後、販売するまでの間に確保できる賃料収入も含まれて」おり、「収益不動産残高の拡充を進め、賃料収入を増加させることで、安定した収益モデルへの転換を図って」いるとの記載があることや、②原告の常務取締役CFOが、その陳述書(甲48)において、原告のいう「バリューアップ」には、「適正賃料でのリーシング(物件に賃借人をできるだけ多く付けて家賃の滞納や空室をできるだけ減らすこと)」が含まれている旨陳述していること、すなわち、原告が賃料収入を得ることを意図して事業を行っていたことからも裏付けられるというべきである。
以上のとおり、原告は、本件各マンションの譲受けに際し、本件各マンションから生ずる貸料を収受することを客観的に予定していたと認められるのであるから、本件各課税仕入れは、本件各仕入日において、原告が将来行う「その他の資産の譲渡等」たる住宅の貸付けに要するものであったというべきである。
(原告の主張の要旨)
(1)用途区分の判断基準
ア 控除対象仕入税額の計算において個別対応方式を用いる場合には、課税仕入れ等の用途区分、すなわち、当該課税仕入れ等が①「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(課税対応課税仕入れ)、②「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの」(非課税対応課税仕入れ)及び③「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(共通対応課税仕入れ)のいずれに対応するものであるかを明らかにしなければならない(消費税法30条2項1号)。
ここで、上記①及び②に共通して用いられている「にのみ要するもの」という文言を文理に即して解釈すれば、当該文言は、「その資産の譲渡等を行わないのであればそもそも事業者はその課税仕入れ等を行わなかった」という条件関係を意味するものと解される。そうすると、用途区分の判定については、その対象となる課税仕入れ等が、 課税資産の譲渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には課税対応課税仕入れに、
課税資産の譲渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には課税対応課税仕入れに、 その他の資産の譲渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には非課税対応課税仕入れに、
その他の資産の譲渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には非課税対応課税仕入れに、 その双方と条件関係を満たす場合には共通対応課税仕入れに、それぞれ区分されるものと解するのが相当である。
その双方と条件関係を満たす場合には共通対応課税仕入れに、それぞれ区分されるものと解するのが相当である。
そして、このような条件関係の判断は、課税の累積の排除という仕入税額控除の趣旨を適正に達成するため、現実に行われた個々の課税仕入れ等を前提として、当該課税仕入れ等がされた日の状況により、様々な事情を考慮して個別具体的かつ客観的に行うべきである。
イ なお、上記アの判断基準をコストの観点に引き直せば、課税対応課税仕入れとは、課税資産の譲渡等による売上げをもって課税仕入れ等のコストを回収することができる(コストについて条件関係が認められる)課税仕入れ、すなわち、「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」を意味するということになる。
また、事業者の目的(個別具体的かつ客観的に認定されるところの課税仕入れ等の目的)、という観点に引き直せば、①用途区分の判定は事業者の最終的な目的(課税資産の譲渡等が達成できないのであればそもそも事業者はその課税仕入れ等を行わなかったといえる〔すなわち条件関係が認められる〕課税資産の譲渡等)に基づいて判断すべきであり、②仮に副次的に得る対価があったとしても、その副次的に得る対価はその判断を左右しない(副次的な対価を得る資産の譲渡等が行われても行われなくても、事業者はいずれにせよその課税仕入れ等を行っていたという場合には、その資産の譲渡等との間に条件関係は認められないということができる。
(2)本件各課税仕入れの用途区分
本件各課税仕入れは、後記アのとおり、将来の転売(課税資産の譲渡等)との間では条件関係が満たされる一方、後記イのとおり、住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)との間では条件関係が満たされないから、課税対応課税仕入れに区分すべきである。
ア 本件各課税仕入れと将来の転売(課税資産の譲渡等)との間に条件関係が認められること
原告は、収益不動産を購入し、バリューアップを行った上で富裕層の個人投資家に転売するとのビジネスモデル(本件ビジネスモデル)に基づく事業を行っており、本件各マンションについても、本件ビジネスモデルの一環として将来の転売を前提に譲り受けたものである。そうすると、原告は、個人投資家への転売たる課税資産の譲渡等を行わないのであれば、そもそも本件各課税仕入れを行わなかったということができるから、本件各課税仕入れと将来の転売(課税資産の譲渡等)との間には条件関係が認められる。
イ 本件各課税仕入れと住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)との間に条件関係が認められないこと
本件各マンションは、いずれもその一部又は全部が住宅として貸し付けられていたものであり、本件各仕入日において、原告が、将来、上記貸付けを継続するとともに、空室に関してもバリューアップの一環としてのリーシングを行い、これらに係る賃料を得ていくであろうことが客観的に想定されていた。
しかし、本件ビジネスモデルにおいて、原告が仕入れた収益不動産を保有期間中に貸し付けることは、当該収益不動産のバリューアップという将来の転売のための前提ないしは手段にすぎないのであるから、かかる側面を条件関係の判断において考慮することは相当でない(かかる側面はむしろ転売との条件関係の判断において考慮すべきである。)。そして、本件ビジネスモデルに基づけば、原告は、バリューアップという観点を離れて賃料収入を得るためだけに住宅の貸付けを行うことはないのであるから、原告について、住宅の貸付けたるその他の資産の譲渡等を行わないのであれば、そもそも本件各課税仕入れを行わなかったということはできず、したがって、本件各課税仕入れと住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)との間には条件関係が認められない。
2 争点(2)(平等取扱原則違反の有無)について
(原告の主張の要旨)
(1)平等原則について規定する憲法14条1項は、法の執行段階における取扱いの平等をも要請していると解されるから(平等取扱原則)、同一の状況にある納税者のうち、一方に対しては課税処分を行いながら、他方に対して課税処分を行わないことは、かかる平等取扱原則に反し許されない。そうすると、税務当局の対応が一貫性を欠く状況下において、特定の納税者を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分が行われた場合には、当該課税処分は、平等取扱原則に反して違法となるというべきである。
(2)税務当局の現在の対応が一貫性を欠いていること
本件訴訟では、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分が問題となるところ、この点に関する税務当局の現在の対応は、およそ一貫性を欠いている。すなわち、転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分して消費税等の申告をした納税者の中には、①原告と同様に当該用途区分を一律に否認された者がいる一方、②転売までの期間の長短等で否認の範囲が限定された者や、③原告とは逆に当該用途区分を一律に是認された者も存在する(このことは、東京国税局や財務省〔旧大蔵省〕主税局での勤務経験を有する○○○○税理士の陳述書〔甲6〕や、原告訴訟代理人らが行ったアンケート調査の結果〔甲28〕等から明らかである。)。
そうすると、原告に対してされた本件各更正処分は、税務当局の対応が一貫性を欠く状況下において、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分というべきであるから、平等取扱原則に反して違法である。
(3)税務当局の対応が過去と比較して一貫性を欠いていること
税務当局は、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分について、従前は課税対応課税仕入れに区分するとの取扱いをしていたが(後記ア)、平成17年に突然これを変更し、共通対応課税仕入れに区分するとの取扱いをするようになった(後記イ)。そうすると、原告に対してされた本件各更正処分は、税務当局の対応が過去と比較して一貫性を欠く状況下において、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分というべきであるから、平等取扱原則に反して違法である。
ア 税務当局が転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたこと
国税庁は、「買い取った分譲用マンションを分譲が完了するまで一時期賃貸した」との事例における用途区分について、平成6年11月に実施した「全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議」における意見聴取を経た上で、平成7年2月16日付けで、全国の国税局及び税務署に対し、課税対応課税仕入れに区分して差支えない旨通知している(甲18、19。以下「平成7年分譲マンション事例」という。)。
また、東京国税局は、平成9年、「賃借人が居住しているマンションを転売目的でそのままの状態で購入した」との事例における用途区分について、照会元の下級行政機関に対し、「本件の場合は…マンションを転売目的で取得したことが明らかである」から課税対応課税仕入れ等に区分される旨回答している(甲21。以下「平成9年賃貸マンション事例」といい、平成7年分譲マンション事例と併せて「本件過去事例」という。)。
このような本件過去事例に照らせば、税務当局が、転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れ等に区分する取扱いをしていたことは明らかである。
イ 税務当局が平成17年を境に取扱いを変更したこと
上記アのとおり、税務当局は、元々、転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていた。
しかし、平成17年11月5日、国税庁職員が執筆する「こんなときどうする 消費税Q&A」と題する加除式の文献に「現住建造物を転売目的で購入した場合の仕入税額控除」と題する設例(事実関係は平成9年賃貸マンション事例と同様である。)が追加され、同設例における課税仕入れは「建物の転売という課税売上と住宅の家賃という非課税売上げのための課税仕入れ」であるから共通対応課税仕入れに区分されるとの見解(従前と正反対の見解)が突如として示されることとなった(甲31、乙12)。
また、上記の設例が追加された僅か5日後(平成17年11月10日)には、国税不服審判所においても、転売用マンションに係る課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分するのが相当であるとの初判断が示され(乙11の1)、その後も同種の裁決が引き続くようになった。
このような経緯に照らせば、税務当局が平成17年を境に転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分を、課税対応課税仕入れから共通対応課税仕入れへと変更したことは明らかである。
(被告の主張の要旨)
(1)ア 憲法14条1項の下、各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなければならならず(租税平等主義)、具体的には、同様の状況にあるものは同様に、異なる状況にあるものは状況に応じて異なって取り扱われる必要がある(平等取扱原則)。もっとも、租税法の執行段階においては、租税法律主義(憲法84条)の要請が働き、課税要件が充足されている限り、租税を減免する余地はないのであるから、課税要件の充足する課税処分については、その余の事情にかかわらず、平等取扱原則違反の問題は生じないというべきである。
イ これを本件についてみるに、前記1(被告の主張の要旨)及び別紙4(課税の根拠及び計算)のとおり、本件各更正処分は、消費税法所定の課税要件を充足するものであるから、同処分が平等取扱原則に反して違法となる余地はないというべきである。
(2)ア なお、税務当局(ないし被告)は、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分が争点となった他の審査請求や訴訟において、当該課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分される旨一貫して主張してきており(甲10、乙11の1~3)、つまりは、平等取扱原則に従って「同様の状況にあるものは同様に取り扱っている」のだから、上記(1)イの点を措いたとしても、本件各更正処分が平等取扱原則に反するものでないことは明らかである。
イ この点、原告は、本件過去事例の存在を根拠に、税務当局は、従前、転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたが、平成17年を境にその取扱いを変更したと主張する。
しかし、上記主張の根拠として原告が摘示する証拠(甲18、19、21)は、いずれも被告においてその存否を確認することができないものである。この点を措いたとしても、平成7年分譲マンション事例は、課税仕入れを行った日において当該マンションがいまだ貸し付けられていなかったという点で、本件とは事案を異にするものであるし、平成9年賃貸マンション事例については、過去の誤った一事例であるにすぎない。
したがって、本件過去事例の存在を根拠に、税務当局が、過去に転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたとか、平成17年を境にその取扱いを変更したなどということはできない。
3 争点(3)(国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無)について
(原告の主張の要旨)
国税通則法65条4項の「正当な理由」が認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される(最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁等参照)。
これを本件についてみると、前記2(原告の主張)(3)記載のとおり、税務当局は、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分という租税法規の解釈上微妙な点を含む問題について、平成17年を境に課税上の取扱いを変更しているが、変更後の取扱いを国民の間に定着させるための措置は何ら講じていない。このような事情に鑑みれば、原告が従前の取扱いに従って本件各課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分したことについて、その責めに帰することのできない客観的な事情があることは明らかであって、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、原告に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというべきである。
そうすると、仮に本件各更正処分が適法であるとしても、納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件各確定申告時における計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められるから、本件各賦課決定処分はその根拠を欠き違法である。
(被告の主張の要旨)
原告は、税務当局が、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分について、平成17年を境に課税上の取扱いを変更したことを前提に、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると主張しているが、前記2(被告の主張の要旨)のとおり、このような事実は認められないのであるから、原告の主張はその前提を欠き失当である。
以上
(別紙4:略)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















