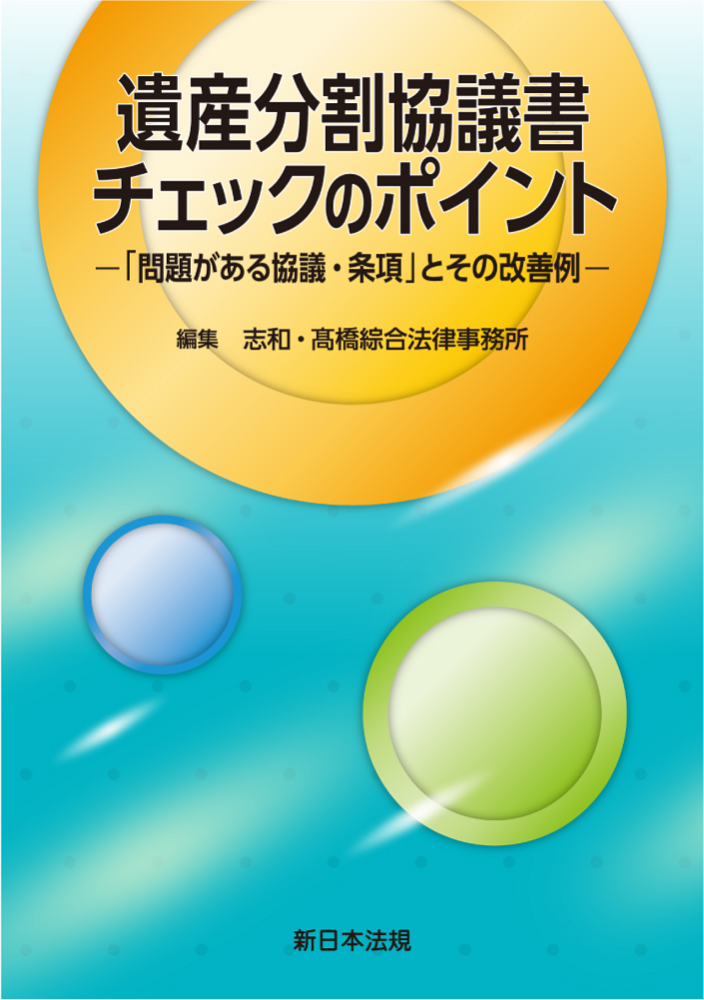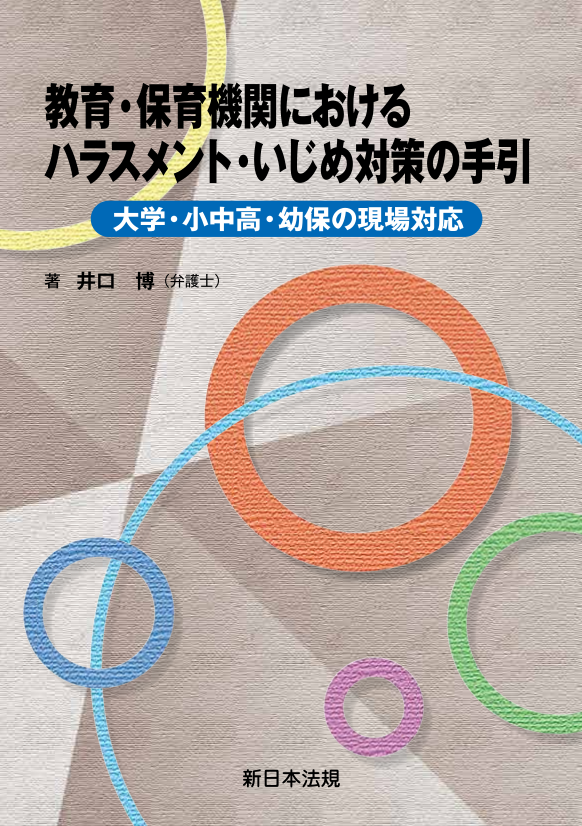民事2025年04月12日 別室登校は「権利侵害」 被害者保護へ現状に一石 いじめ判決 提供:共同通信社

いじめを受けて学校に通えなくなった子どもが別室に登校できるようになっても、本来の教室に戻れないままでは「学習権」の侵害だ―。小学校でのいじめを巡る訴訟で昨年、こうした司法判断が示された。加害者が教室に残る一方で、被害者は不登校になったり別室登校を余儀なくされたりして戻れないケースは多く、改善を求める声は根強い。現状に一石を投じる判決となりそうだ。
▽1日1こま
訴訟の原告は大阪府吹田市立小に通っていた男性と両親。小学6年だった2018年に同級生から仲間外れにされるなどのいじめを受け、学校に通えなくなった。市教育委員会は同年11月に「重大事態」と認定。男性は卒業前の2カ月間、別室に登校して1日1こまだけ授業を受けたが、教室には戻れなかった。男性らは市などに損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。
昨年5月の一審判決は「学校が適切に対処していれば、全面的ではなくても教室に復帰できた。男性の学習権は侵害された」と判断し、市の賠償責任を認定。昨年12月の大阪高裁判決も支持し、市側は最高裁に上告受理を申し立てている。
「加害者が教室にいるために教室で学べない多くの被害者にとって朗報だ」。男性の父親は教育現場の変化を期待する。いじめ問題に詳しい千葉大の藤川大祐(ふじかわ・だいすけ)教授(教育方法学)も「別室登校できていれば学習権は保障できている、という考え方が一般的だった中で、画期的な判決ではないか」と評価する。
▽0・9%
いじめ防止対策推進法は、被害者が安心して教育を受けられるよう、加害者を教室以外の場所で学習させる権限を学校に認めているが、実態は異なる。
文部科学省の23年度問題行動・不登校調査によると、小中高などで認知したいじめ計約73万件のうち、被害者に別室を提供するなどした対応は3・4%だったのに対し、加害者を別室としたのは0・9%にとどまった。
こうした現状に被害者が教室に戻れるようなルール作りを求める声も上がるが、文科省の担当者は「被害者を守るのが最優先なのは言うまでもないが、いじめにもさまざまなケースがある。加害者側にも話を聞く必要があり、しゃくし定規に対応を決めるのは難しい」と慎重姿勢だ。
藤川教授は「加害者が教室にいたままで被害者が戻れない状況はおかしいという議論はありながら、これまで対応はうやむやのままだった」と指摘。その上で「加害者をいきなり教室から出すのは難しい。いじめの訴えがあったらまずは警告を出し、再び相手が嫌がることをしたら分離する、というようなやり方も考えられるのではないか」と提案した。
(2025/04/12)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.