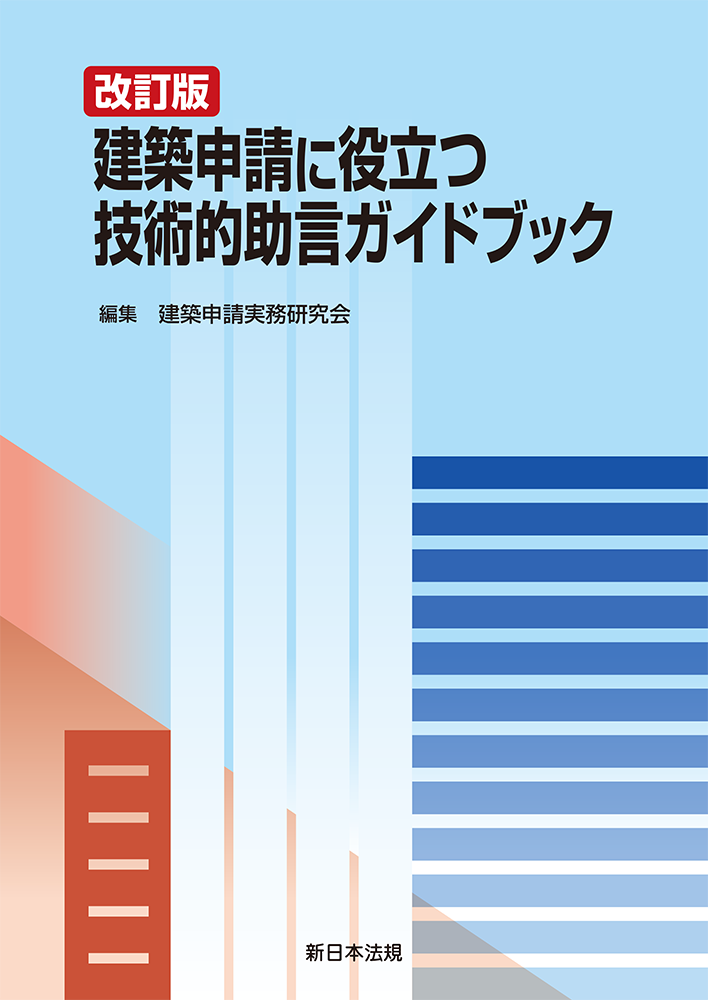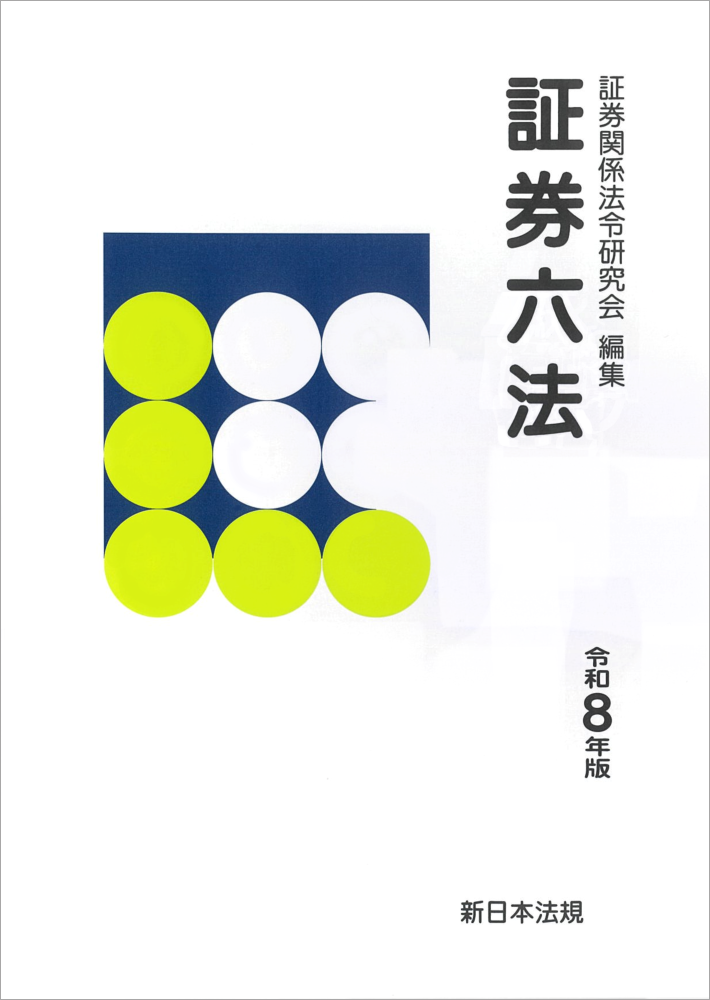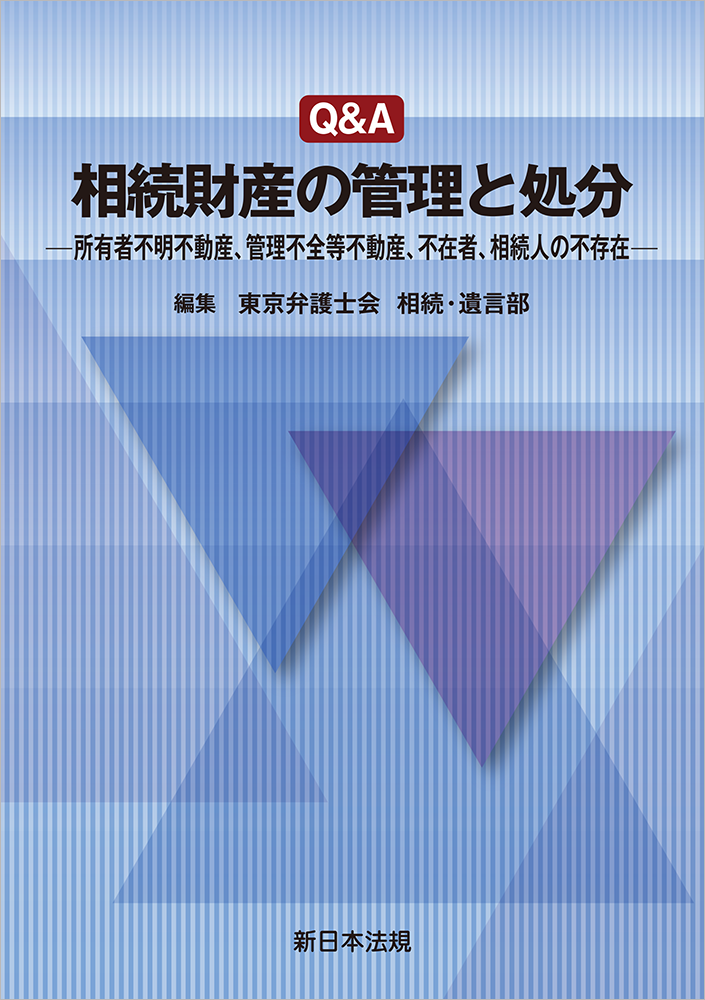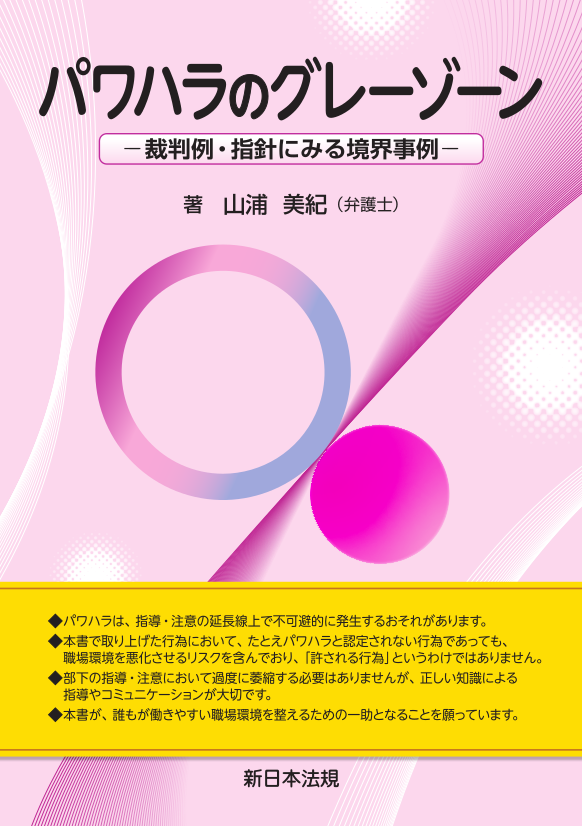民事2025年09月19日 「死人が出る」「助けて」消防パワハラで免職、処分は正しかったのか 決着まで8年半、割れた司法判断 提供:共同通信社

きっかけは、組織の窮状を訴える悲痛な声だった。「このままでは死人が出ます」「助けてください」。2017年3月、福岡県の糸島市消防本部で訓練中に同僚約30人にパワーハラスメント行為をしたとして、職員13人が懲戒免職などの処分を受けた。処分が不当だとして一部の職員が起こした訴訟が9月、約8年半の時を経て最高裁で決着。一、二審と最高裁で司法判断が分かれた法廷闘争は、どのような経緯をたどったのか。(共同通信=帯向琢磨)
▽前例のない大規模処分
糸島市消防本部では職場環境改善のため、全職員を対象に毎年度アンケートをしている。「部下に対する行き過ぎた指導、暴力、暴言が日常的に行われている」「職場にパワハラがまん延している」。2016年6月の実施分では、こういった意見が相次いだ。
さらに翌月「勇士一同」名義の文書が市長や市の顧問弁護士に届く。つづられていたのは、訓練の名を借りたいじめやしごきが横行していること。数年で若手6人が次々に退職し3人の病休者が出ており、アンケートにこうした実態を告発しても変化がない―。
市はすぐ事情聴取を開始。副市長や教育長らで構成する審査委員会は「組織全体の問題」と捉えて厳正な調査に臨んだ。9回の審議を経て、処分対象は13人となった。懲戒免職1人、分限免職1人、停職6カ月が3人、停職3カ月が1人、戒告が5人、訓告が2人。100人ほどの組織において、前例のない大規模な処分だった。
▽新入職員をロープで宙づりに
いったい、どのような行為が処分の対象になったのか。
最も重い懲戒免職となった予防課予防係長(当時)は、約13年にわたり少なくとも10人の部下に対し、法令や規則に違反する行為(非違行為)があったと認定された。
例えば、新人職員に鉄棒と体をロープで縛って懸垂をさせ、力尽きて宙づりになった状態でさらに懸垂をさせたり、ぞうきん掛け競争で負けるとペナルティーとして腕立て伏せをさせたりした。
体力の限界まで訓練をさせらせて熱中症になり、一時意識を失った職員も。「おまえは駄目だ」「ぶっ殺す」「死ね」「おまえを恐怖で支配するけん」。暴言や侮辱もあった。
処分の発表に合わせて記者会見した月形祐二市長は「消防職員の誇りを汚し、社会的に大きな影響を与えた。大変申し訳ない」と陳謝した。
▽一、二審は「処分は重すぎて違法」
処分を受けたうち4人は、取り消しを求めて裁判を起こした。調査での事実認定に不服があること、処分が重すぎることなどが理由だ。
そして、懲戒免職になった予防係長と、停職6カ月になった警防課主任の2人について、一審福岡地裁と二審福岡高裁はいずれも請求を認め、市の懲戒処分を取り消した。
長年にわたる多数の非違行為を認めたが、重大な負傷が生じておらず他の職員や社会への影響が特に大きいとは言えないこと、過去に懲戒処分歴がないことなどから「処分は重すぎて社会観念上著しく妥当性を欠き違法だ」と判断したのだ。市側が上告し、舞台は最高裁での審理に移った。
6月に開かれた、当事者双方の意見を聞く口頭弁論。市側は「パワハラで大量の離職者が出て組織が崩壊しそうだ」「ハラスメントが組織に及ぼす影響は大きい」とし、地裁と高裁の判決を覆すよう求めた。聞き取りで、職員66人が予防係長の職場復帰に拒絶の意思を示したことも明らかにし「職場への重大な悪影響があった」と訴えた。
一方、職員側は「被害者側からしか聞き取りをしておらず、ずさんな事実認定だった」「本来よりも悪く見られている可能性があり、(職場での人間関係が)修復不可能だとは思っていない」と反論した。
▽最高裁は「組織の秩序や規律を著しく乱した」
9月2日の上告審判決で最高裁第3小法廷は、一、二審の判断が「是認できない」とし、市の懲戒処分を支持した。
鉄棒と体をロープで縛って懸垂をさせ、力尽きて宙づりになった状態でさらに懸垂をするよう指示したことや、体力の限界で倒れ込んだことに対するペナルティーとしてさらに過酷なトレーニングをさせたことなどは「職場内における優位性を背景として、指示や指導の範囲を大きく逸脱する」と指弾した。
さらに、少なくとも10人の部下に、10年以上の長期にわたって不適切な指導や発言を執拗に繰り返したことは「甚だしく職場環境を害し、消防組織の秩序や規律を著しく乱した」と厳しく批判した。
▽判断分けたポイントは
最高裁の判決により、市側の逆転勝訴が確定した。判断の分かれ目はどこにあったのか。
一、二審判決も非違行為自体を否定したわけではなかったが、その程度は特段大きいわけではなかったと考えた。それに対し最高裁は、期間や回数を踏まえて「極めて重い」と一蹴した。
また、職場環境に与える影響をどのくらい考慮するかも、判断のポイントとなった。この点について、第3小法廷の裁判官の1人は「危険と隣り合わせの現場で職務を安全、確実かつ迅速に遂行するためには、職員同士の緊密な意思疎通が必要であり、そうした消防職員の職務の性質に照らしても、規律や秩序に対する悪影響は特に大きい」との補足意見を付けた。
今回の裁判は、あくまで糸島市消防本部内の出来事に対する市の処分の是非が問題であり、最高裁が普遍的な規範を示したというものではない。とはいえ、ハラスメントに厳しく向き合う社会の要請は高まっており、それを色濃く反映したものだと言えそうだ。
(2025/09/19)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -