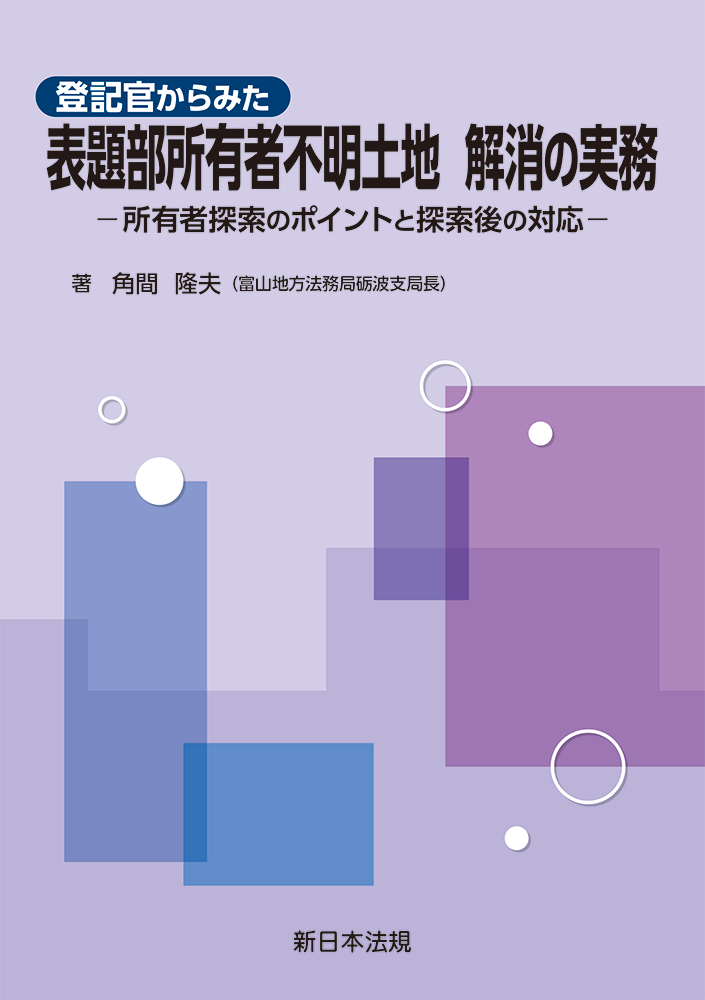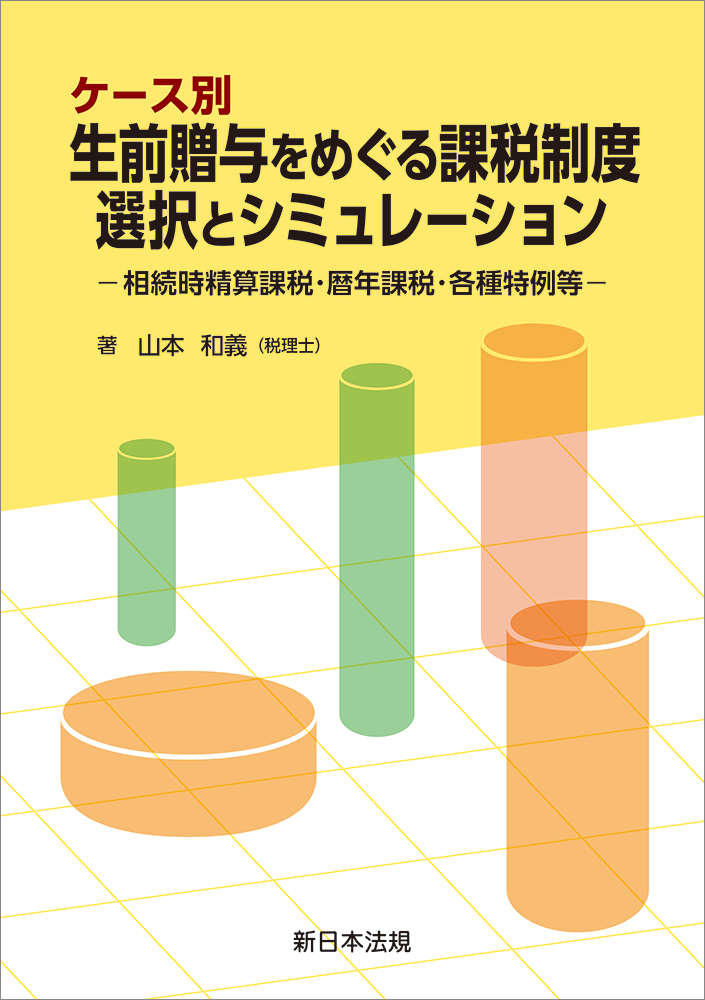一般2025年10月05日 揺れる「法の支配」―国際刑事裁判所への米制裁拡大を懸念 「遠い話ではない」日本の弁護士も強い危機感 提供:共同通信社

オランダ・ハーグにあり、戦争犯罪や人道に対する罪を裁く国際刑事裁判所(ICC、赤根智子所長)本体に対し、トランプ米政権が国内資産凍結などの制裁を科すことが懸念されている。ICC非加盟ながら国際金融ネットワークを握る米国の制裁対象になれば活動が困難になり、ICCは存続の危機に追い込まれる。国際社会で「法の支配」の一翼を担う司法機関が、それに加わっていない米国に命運を握られるという理不尽な事態だ。
「海の向こうの遠い話ではない」―。締約国は非難声明を発表し、日本国内でも、法の支配の崩壊に弁護士らが危機感を強めている。事態の打開に向け、締約国である日本政府の積極的な関与を求める声も上がっている。(共同通信=出口朋弘、小川美沙)
ICC 戦争犯罪などを犯した個人を処罰するため、2002年7月に発効したローマ規程に基づき、世界で初めて常設された国際的な刑事裁判機関。検察局も抱える。加盟国・地域は125に上るが、米国、ロシア、中国、イスラエルなどは非加盟だ。加盟国の領域内で起きた犯罪はICCが管轄権を有するため、被疑者の国籍は問われない。日本は2007年に加盟した。2024年3月からは赤根氏が日本人初の所長を務める。日本は最大の分担金拠出国で、2025年予算で14・7%を負担している。
▽テロリストと同じ
9月15日、オランダ西部ハーグにあるICCで共同通信の取材に応じた所長の赤根氏は、米国による制裁の可能性についてこう表現した。「以前は半々のイメージだったが、今はほぼ100%起きると思う」。そして、米制裁がICC所属の個人から組織全体に拡大する事態が「かなり近い将来」に迫っていると危機感を示した。
パレスチナ自治区ガザ攻撃を巡り、2024年11月に戦争犯罪と人道への罪でイスラエルのネタニヤフ首相らへの逮捕状が出たことに反発したトランプ政権は今年、ICCの裁判官や検察官に制裁を発動。裁判官18人の3分の1に当たる6人と捜査を担う検察局のトップ3人が対象となった。
米国内の資産が凍結され、国際金融システムからも事実上締め出されたため、送金やクレジットカードの利用ができなくなった。「テロリストを制裁にかけるときと同じ仕組み。相当な不便が出ている」(赤根氏)
制裁が組織全体に拡大すれば、捜査を維持できなくなるのは必至。ICCの情報通信システムを担う米企業も米国での刑事罰を恐れて取引を控えざるを得なくなるため、ICCは活動停止に追い込まれる可能性は高い。
▽「力」横行
ICCは法的独立性に厳格で、加盟国も個別の事案に口出しできない。所長であっても同じ敷地内の検察局に立ち入ることすらできない。赤根氏は「検察のこの仕事は政治的だといって制裁をかけるというのは明らかに違法だ」と指摘する。
活動停止に追い込まれれば、紛争時に民間人への組織的な攻撃が処罰されないまま放置され、戦勝国が敗戦国を裁いた第2次大戦以前の状況に戻る。「法の支配」ではなく「力の支配」が横行する世界だ。
赤根氏は分断が進む現在の国際情勢を踏まえ、ICCのような組織が「1回つぶれてしまったら、二度と同じものはつくれない」と訴える。
宇都宮大の藤井広重准教授(国際刑事法)は、米国が制裁に乗り出すことで、他国や企業もICCと距離を置こうと忖度する「チリングエフェクト(萎縮効果)」が生じることを危惧する。実際その兆候は出ている。
来年12月には赤根氏を含め、任期切れを迎える裁判官6人の後任を決める選挙がある。通常なら既に立候補表明が相次いでいる時期だが、まだ誰も名乗り出ていない。「加盟国はICCを守る行動を具体的に取ってほしい」。赤根氏の訴えは切実だ。
▽鈍い日本政府の対応
トランプ米大統領がICC関係者らへの制裁を可能とする大統領令に署名した翌日の今年2月7日、英独仏など約80カ国が共同で次のような声明を出した。「ICCの独立性、誠実さ、公平性を損なういかなる試みも遺憾に思う」。しかし、締約国で、最大の分担金拠出国でもある日本の対応は鈍く、この声明に加わらないままだった。
一方、愛知と大阪の弁護士会は3月7日、日本政府に対し、ICCの尊重や、支援を訴える会長声明を発表。愛知の声明は「制裁の実施に明確に反対する立場を示すこと」を求めた。日弁連も3月27日に会長声明を出し、同様の動きは各地の弁護士会に広がった。
▽自分の問題
愛知で会長声明の発出に尽力した一人、上松健太郎弁護士は、検事出身の赤根氏が名屋大法科大学院で教壇に立っていた時の教え子だ。当初は「海の向こうの遠い話」だと思っていたが、自身が日々向き合う法の支配を揺るがす「とんでもないこと」だと気付き、「自分の問題でもある」と思うようになった。
同じ問題意識を持つ名古屋大法科大学院修了生らと一緒にICCが扱った事件の判決について学び、実際に3月にはオランダ・ハーグにあるICCも訪問した。8月には愛知県弁護士会主催の市民向け講座を企画し、赤根氏にオンラインで講師を務めてもらったところ、小学生から高齢者まで計数百人が参加・視聴したという。
▽信頼
赤根氏は帰国した際に「日本の司法は汚職と無縁で信頼度が高い。誇るべきことだ」と話していたという。トップを日本人が務め、重大な犯罪を裁くICCについて、上松弁護士は「司法への信頼を世界に波及させる効果があるのでは」と考えている。米国の制裁がICC本体に及んだとしても「つぶれないと信じている」。未来を見据え、若い人にICCについて知ってほしいと、模擬裁判の実施を検討中だ。
非政府組織(NGO)や研究者は9月12日、共同記者会見をオンラインで開催した。ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗さんは「日本政府にはICCを守り抜く強い決意は残念ながらない。法の支配を掲げる国としてリーダーシップを取ってほしい」と訴えた。
(2025/10/05)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -