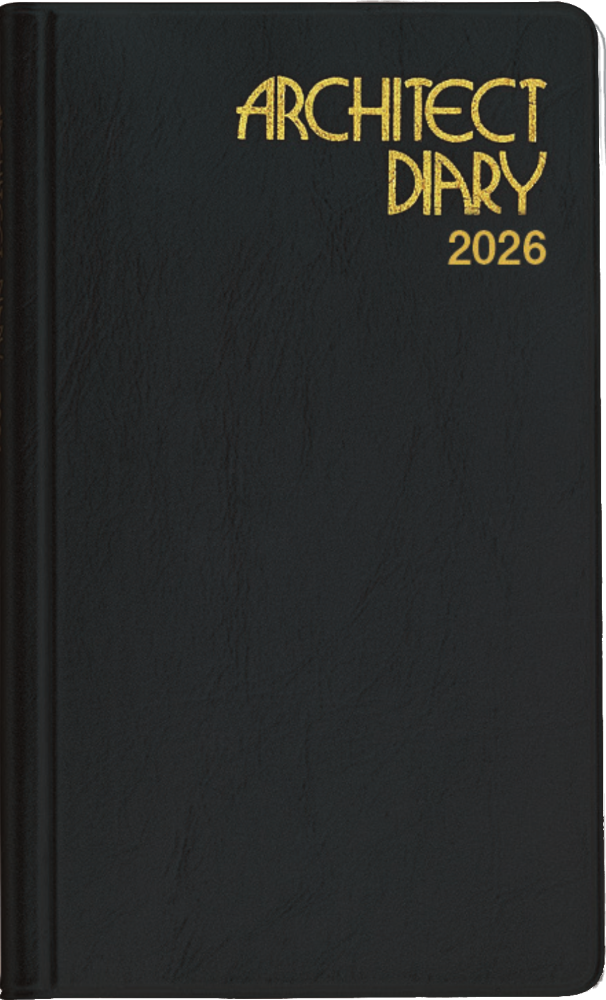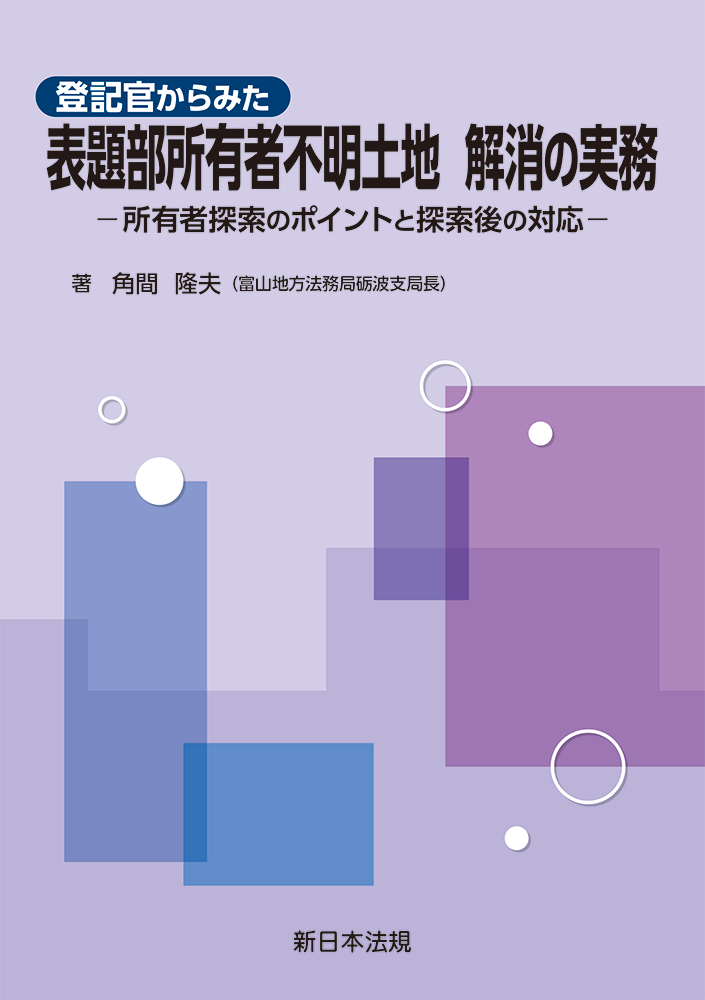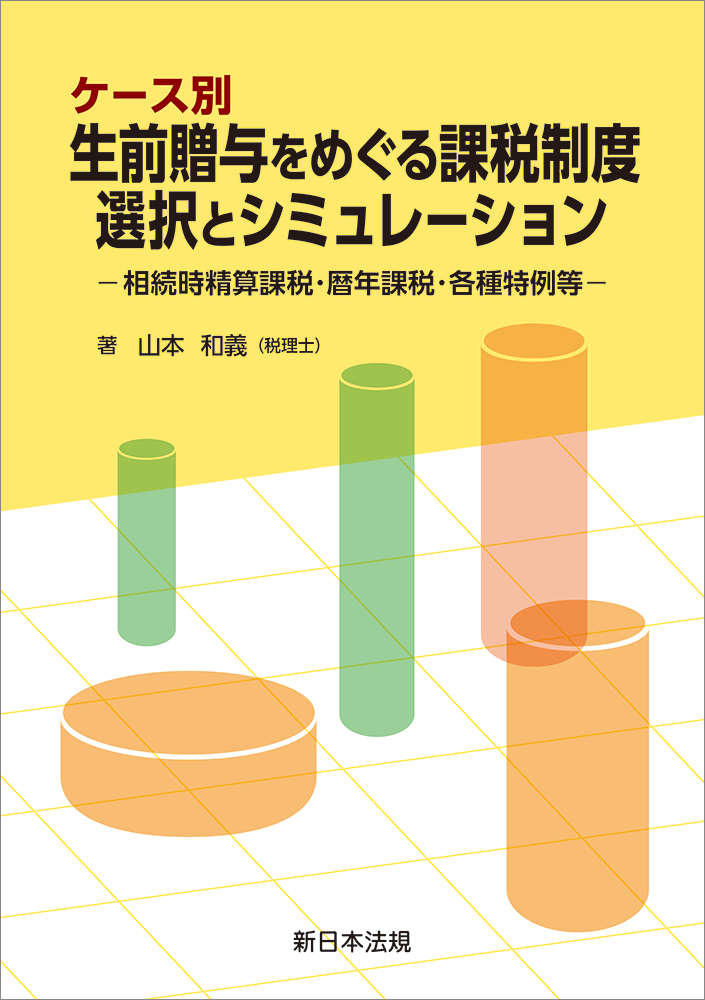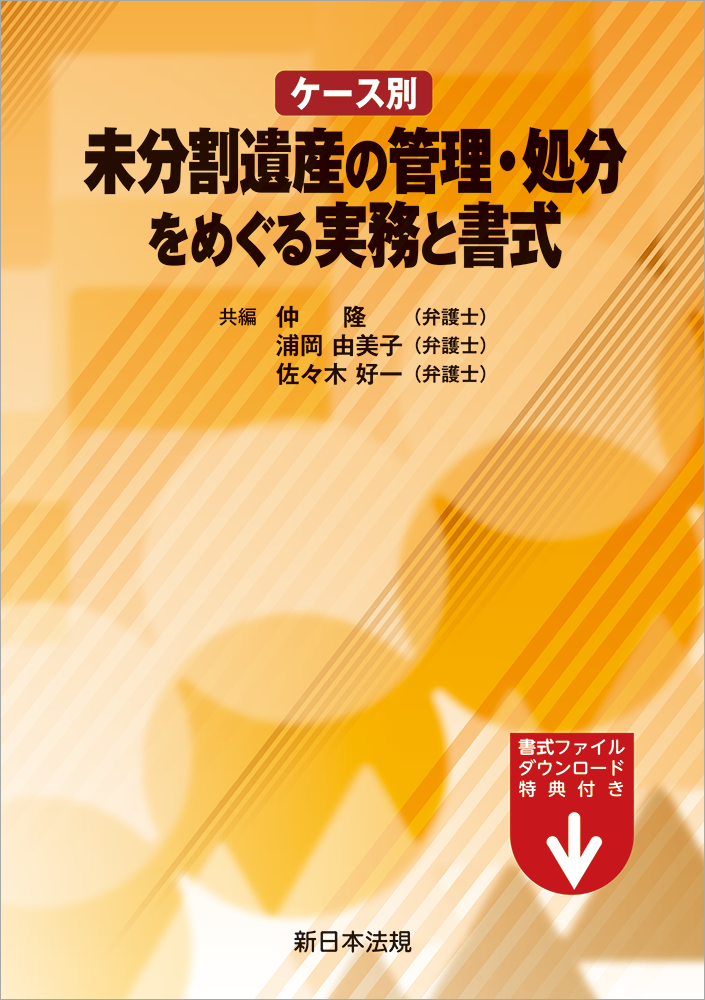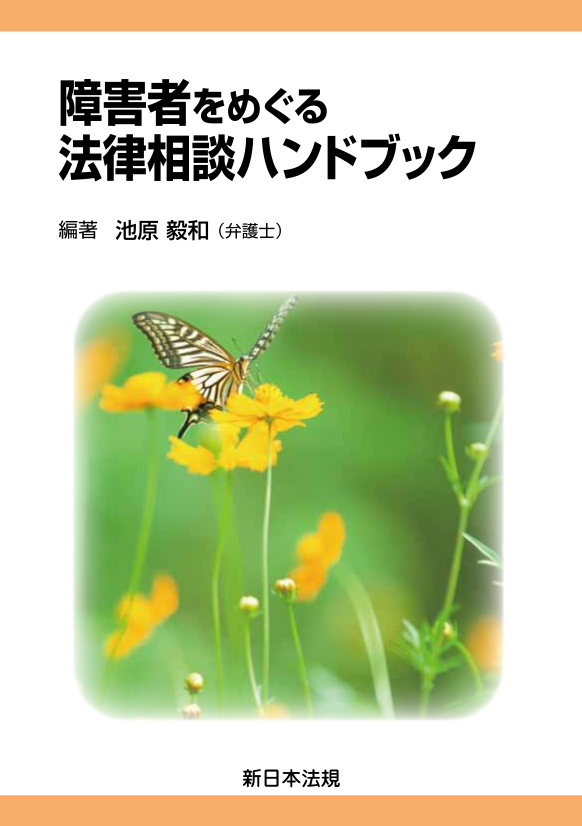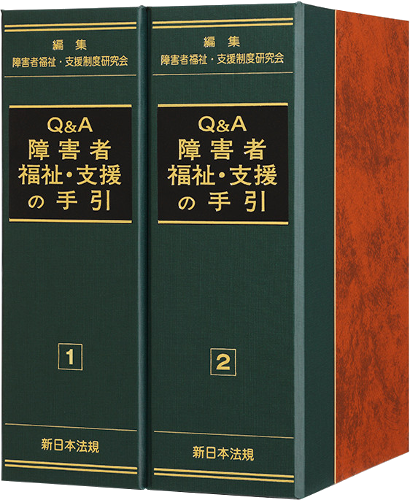福祉・保健2025年10月26日 手話、理解の広がり期待 法律やデフリンピック機に 手話施策推進法 提供:共同通信社

手話の普及や理解に向けた環境整備を国や自治体の責務とする「手話施策推進法」が6月に成立、施行された。耳の不自由な人が長年求めてきた法律だ。11月には聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が日本では初めて開かれる。聴覚障害者は、これらを機に障害や手話への理解が広がることに期待する。
▽苦労
「心から喜びを感じる」。推進法成立を受け6月に国会内で開かれた集会。弁護士で聴覚障害者の田門浩(たもん・ひろし)さん(58)は手話通訳を通じて語った。
学生や司法修習生の時に手話通訳を配置するよう交渉したと振り返り「ろう者は今まで社会生活や職場で通訳がいない、手話を自由に使えない場面が多かった」と話した。音声による情報とコミュニケーションを手話や文字に変換して提供する「情報保障」の実現を「今後は推進法を盾に、きちんと求めることができる」と述べた。
推進法は、児童や生徒が手話で教育を受けられるよう手話の技能を持つ教員や通訳者の配置を進めると規定。田門さんは「一般の学校に聞こえない子どもが通うケースもある。子どもは通訳不在で苦労している」として、改善を期待する。
国の関連施策では、文部科学省が教員らを対象とした手話を学ぶ動画の開発を推進。2026年度予算の概算要求に費用を盛り込んだ。
▽距離縮めて
全日本ろうあ連盟(東京)によると、約610自治体が手話の普及などを目的とする条例を制定した。このうち埼玉県富士見市は、手話通訳を正職員で採用するほか、星野光弘(ほしの・みつひろ)市長(68)らが地域の聴覚障害者団体と定期的に交流している。デフリンピックのキャンプ地として、セルビアの男子ハンドボール代表を11月に受け入れる。
星野市長は、自治体によって手話普及の取り組みに「濃淡がある」と言う。「行政は聴覚障害者との距離をもっと縮めるべきだ。デフリンピックは手話を知ってもらい、身近に感じてもらう大きな機会だ」と強調した。
田門さんも「デフリンピックで、聞こえない人でも環境を整備すれば聞こえる人と同じように動けることを社会に知ってもらいたい」と語った。
(2025/10/26)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -