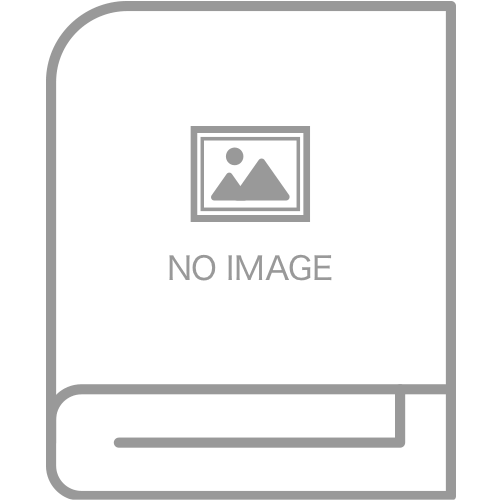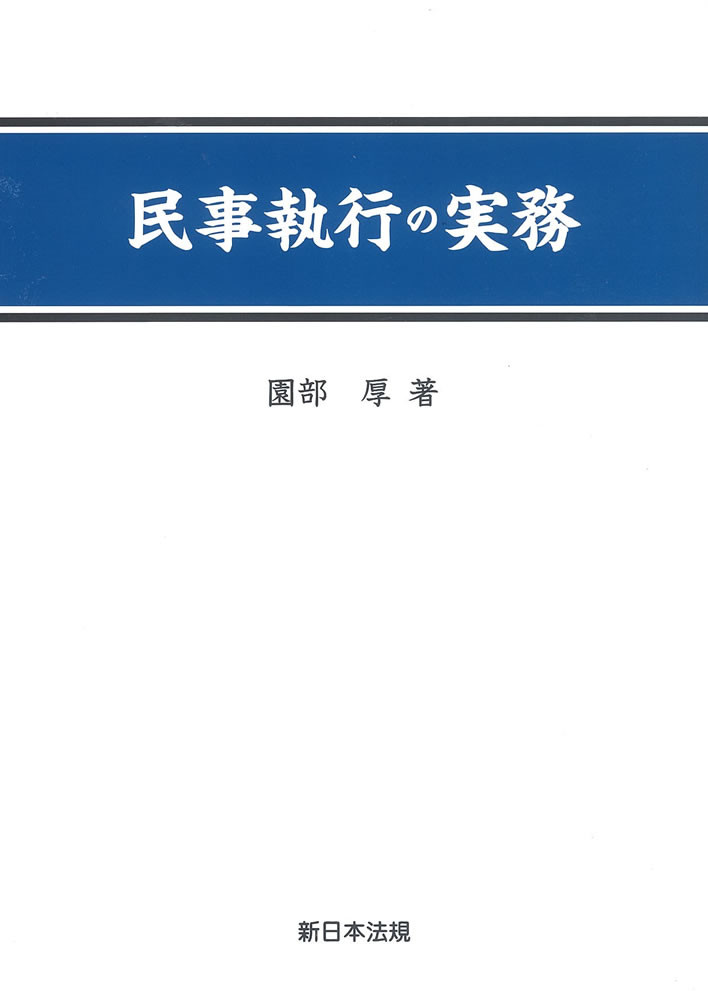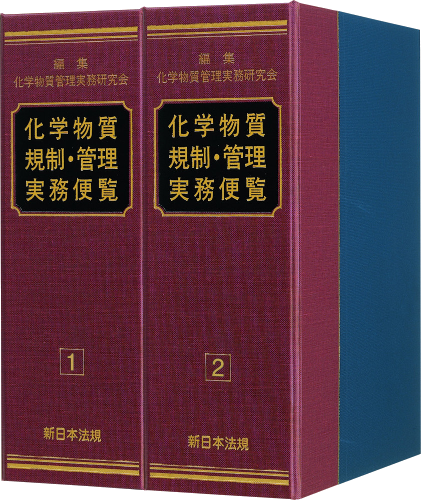PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
船舶油濁損害賠償保障法の一部改正(令和元年5月31日法律第18号 2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が 日本国について効力を生ずる日 ※令和2年10月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
昭和50年法律第95号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
昭和50年法律第95号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(法律第一八号)(国土交通省)
1 題名
題名を「船舶油濁等損害賠償保障法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 定義
(一) この法律において「燃料油条約」とは、二〇〇一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいうこととした。
(二) この法律において「難破物除去条約」とは、二〇〇七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいうこととした。
(三) この法律において「燃料油等」とは、燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいうこととした。
(四) この法律において「難破物」とは、海難により生じた次のいずれかに該当するものをいうこととした。
(1) 沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部
(2) 海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの
(3) 沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。)
(五) この法律において「船舶油濁等損害」とは、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害をいうこととした。
(六) この法律において「一般船舶等油濁損害」とは、次に掲げる損害又は費用をいい、タンカー油濁損害に該当するものを除くものをいうこととした。
(1) タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
(2) タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条(a)(ⅱ)に規定する水域内における損害
(3) (1)又は(2)に掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
㈦ この法律において「難破物除去損害」とは、我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内における難破物の位置の特定等に要する費用の負担により生ずる損害をいい、タンカー油濁損害又は一般船舶等油濁損害に該当するものを除くものをいうこととした。(第二条関係)
4 一般船舶等油濁損害賠償責任及び責任の制限
(一) 一般船舶等油濁損害が生じたときは、船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責任を負うこととした。(第三九条第一項関係)
(二) 燃料油条約の規定により管轄権を有する外国裁判所が一般船舶等油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、その効力を有することとした。(第三九条第二項関係)
(三) 一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負う船舶所有者等の責任の制限については、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の定めるところによることとした。(第四〇条関係)
5 一般船舶等油濁損害賠償保障契約等
(一) 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を拡大することとした。(第四一条及び第四二条関係)
(二) 一般船舶等油濁損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとした。(第四三条関係)
6 難破物除去損害賠償責任
(一) 難破物除去損害が生じたときは、船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負うこととした。(第四七条関係)
(二) (一)の規定に基づく訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができることとした。(第四八条関係)
7 難破物除去損害賠償保障契約等
(一) 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ、タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三〇〇トン以上のものに限る。以下「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するものは、全ての航海に従事させてはならないこととし、一般船舶(総トン数が一〇〇トン以上三〇〇トン未満のものに限る。以下「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するものは、国際航海に従事させてはならないこととした。(第四九条第一項関係)
(二) 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ、日本国籍を有しない第一種特定船舶及び第二種特定船舶は、本邦内の港に入港等してはならないこととした。(第四九条第二項関係)
(三) 難破物除去損害賠償保障契約は、難破物除去損害の賠償により船舶所有者に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とすることとした。(第五〇条関係)
(四) 難破物除去損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとした。(第五一条関係)
8 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、燃料油条約及び難破物除去条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。
1 題名
題名を「船舶油濁等損害賠償保障法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 定義
(一) この法律において「燃料油条約」とは、二〇〇一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいうこととした。
(二) この法律において「難破物除去条約」とは、二〇〇七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいうこととした。
(三) この法律において「燃料油等」とは、燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいうこととした。
(四) この法律において「難破物」とは、海難により生じた次のいずれかに該当するものをいうこととした。
(1) 沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部
(2) 海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの
(3) 沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。)
(五) この法律において「船舶油濁等損害」とは、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害をいうこととした。
(六) この法律において「一般船舶等油濁損害」とは、次に掲げる損害又は費用をいい、タンカー油濁損害に該当するものを除くものをいうこととした。
(1) タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
(2) タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条(a)(ⅱ)に規定する水域内における損害
(3) (1)又は(2)に掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
㈦ この法律において「難破物除去損害」とは、我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内における難破物の位置の特定等に要する費用の負担により生ずる損害をいい、タンカー油濁損害又は一般船舶等油濁損害に該当するものを除くものをいうこととした。(第二条関係)
4 一般船舶等油濁損害賠償責任及び責任の制限
(一) 一般船舶等油濁損害が生じたときは、船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責任を負うこととした。(第三九条第一項関係)
(二) 燃料油条約の規定により管轄権を有する外国裁判所が一般船舶等油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、その効力を有することとした。(第三九条第二項関係)
(三) 一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負う船舶所有者等の責任の制限については、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の定めるところによることとした。(第四〇条関係)
5 一般船舶等油濁損害賠償保障契約等
(一) 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を拡大することとした。(第四一条及び第四二条関係)
(二) 一般船舶等油濁損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとした。(第四三条関係)
6 難破物除去損害賠償責任
(一) 難破物除去損害が生じたときは、船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負うこととした。(第四七条関係)
(二) (一)の規定に基づく訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができることとした。(第四八条関係)
7 難破物除去損害賠償保障契約等
(一) 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ、タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三〇〇トン以上のものに限る。以下「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するものは、全ての航海に従事させてはならないこととし、一般船舶(総トン数が一〇〇トン以上三〇〇トン未満のものに限る。以下「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するものは、国際航海に従事させてはならないこととした。(第四九条第一項関係)
(二) 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ、日本国籍を有しない第一種特定船舶及び第二種特定船舶は、本邦内の港に入港等してはならないこととした。(第四九条第二項関係)
(三) 難破物除去損害賠償保障契約は、難破物除去損害の賠償により船舶所有者に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とすることとした。(第五〇条関係)
(四) 難破物除去損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとした。(第五一条関係)
8 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、燃料油条約及び難破物除去条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。
関連商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -