資料1997年09月18日 【裁決事例】 請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例(平成4年分~5年分所得税に係る各更正処分等/棄却)
(平9.9.18裁決、裁決事例集No.54 115頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
審査請求人(以下「請求人」という。)は、会社役員であるが、平成4年分及び平成5年分(以下、併せて「各年分」という。)の所得税について、確定申告書に次表のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに提出した。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
総所得金額(給与所得の金額) 10,945,000 10,945,000
納付すべき税額 △13,200 27,100
(注)「納付すべき税額」欄の△印は、還付金に相当する税額を示す。
原処分庁は、これに対し、平成8年3月8日付で各年分の所得税について、次表のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
(単位 円)
区分 項目 年分 平成4年分 平成5年分
更正処分 総所得金額 12,582,157 29,788,419
内訳
給与所得の金額 10,945,000 10,945,000
雑所得の金額 1,637,157 18,843,419
納付すべき税額 594,400 8,374,900
賦課決定処分 過少申告加算税の額 60,000 1,151,500
請求人は、これらの処分を不服として、平成8年4月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年7月4日付で棄却の異議決定をした。
請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成8年7月31日に審査請求をした。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
イ 本件更正処分について
(イ)原処分は、請求人が各年分においてF株式会社(以下「F社」という。)に委託して商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)をした際に上げた利益について課税したものであるが、請求人は、F社の取引員に欺もうされ本件先物取引を行ったものであり、この本件先物取引自体が違法性を帯び、無効あるいは取り消し得る行為なので、請求人は、平成7年11月2日にF社を相手にG地方裁判所へ損害賠償請求の訴訟(以下「本件損害賠償請求訴訟」という。)を提起し、現在争訟中である。
したがって、本件先物取引から生じた所得は請求人には帰属しないから、本件先物取引が有効であるという前提で行った原処分は違法である。
なお、F社と請求人との間には、平成6年5月31日に本件先物取引について和解がなされ、この和解の効力についても請求人は本件損害賠償請求訴訟において争っているが、このような和解契約がなされたこと自体、F社がいかに違法な取引を行ったものであったかを物語る一つの有力な証拠であり、仮に、F社と請求人との取引が全く正常なものであるならば、F社はこのような和解をするはずがない。
(ロ)原処分庁は、請求人が本件先物取引についての承諾書に署名押印した上、同承諾書をF社に対して差し入れていることをもって、本件先物取引から生じた所得が請求人に帰属するものとして課税処分を行っているが、本件先物取引はいわゆる先物取引の客殺し(請求人は、いわゆる客殺しにあった被害者である。)であって、このような客殺しが問題となるときには、形式的には承諾書にサインさせているのがほとんどすべてであり、先物取引に関する判例も、承諾書だけをもって先物取引業者に勝訴判決をした例は皆無である。
したがって、請求人が本件先物取引を開始するに際して形式的に承諾したことをもってその内容を了知したとする原処分庁の認定は経験則に反することである。
(ハ)原処分庁は、課税標準等及び税額等の計算に当たっては、その計算をする時における法的状態を基礎として算定すべきものである旨主張するが、F社の取引の違法性は、既に第三者にとっても重大であり、明白にその違法性が認識できる状態であるから、このような場合には法的状態を基礎として算出すべきではない。
したがって、本件更正処分のうち、本件先物取引に係る部分は直ちに取り消されるべきであり、本件損害賠償請求訴訟の判決を待って最終的な更正処分がなされるべきである。
(ニ)原処分のうちH株式会社(以下「H社」という。)との商品先物取引に係る雑所得の金額については争わない。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
以上のとおり、本件更正処分は違法であり、その一部を取り消すべきであるから、これに伴い過少申告加算税の賦課決定処分もその一部を取り消すべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり適法に行われており、本件審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分について
請求人は、次のとおり、本件先物取引の内容について了知していたことが認められることから、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属する。
(イ)請求人は、J工業品取引所における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J工業品取引所受託契約準則に従い、昭和61年2月20日に次の書類をF社との間で取り交わしている事実が認められる。
A 請求人はF社から「商品取引委託のしおり」を受領し、F社に対して「商品取引委託のしおりの受領について」と題する書面を署名押印の上、差し入れていること。
B 請求人は、F社から「受託契約準則」、「金スプレッド取引実施要領」、「金損失限定取引実施要領」、「貴金属ストラドル取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領し、F社に対してこれらの書面の「受領書」を署名押印の上、差し入れていること。
C 請求人は、F社に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、差し入れていること。
D 請求人は、請求人の氏名及び住所を記載した「通知書」をF社に差し入れていること。
(ロ)請求人は、J砂糖取引所(同取引所は、平成○年○月○日付でJ穀物商品取引所と合併している。)における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J砂糖取引所受託契約準則に従い、昭和63年2月5日に次の書類をF社との間で取り交わしている事実が認められる。
A 請求人はF社から「受託契約準則」、「セット売買契約条項」、「パック取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領し、F社に対してこれらの書面の「受領書」を署名押印の上、差し入れていること。
B 請求人はF社に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、差し入れていること。
(ハ)請求人は、J穀物商品取引所における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J穀物商品取引所受託契約準則に従い、平成元年2月22日に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ニ)請求人は、平成元年11月27日に売買取引の委託に係る取引所に「K生糸取引所」及び「L乾繭取引所」を付け加える旨を記載した「追加約諾書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ホ)請求人は、平成元年11月27日に「準備金による委託証拠金充当同意書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ヘ)請求人が平成4年中及び平成5年中においてF社に対して支払った委託証拠金は次表のとおりであり、また、これらの委託証拠金の支払の際には、F社から請求人に対して「委託証拠金預り証」が交付されていること。
A 農水グループ
(単位 円)
日付 金額
平成4年 3月12日 400,000
平成4年 3月16日 68,000
平成4年12月25日 5,000,000
(注)農水グループとは、J穀物商品取引所、K生糸取引所、L乾繭取引所等の農林水産省が所管する商品取引所のグループを示す。以下同じ。
B 通産グループ
(単位 円)
日付 金額
平成4年 3月 9日 500,000
平成4年 4月24日 500,000
平成4年10月30日 386,000
平成4年12月21日 10,000,000
平成5年 6月14日 3,000,000
平成5年 6月15日 4,020,000
平成5年 6月18日 350,000
(注)通産グループとは、J工業品取引所、M繊維取引所等の通商産業省が所管する商品取引所のグループを示す。以下同じ。
(ト)請求人に対しては、取引成立の都度、F社から、商品、限月、約定年月日、場節、売付け・買付けの別、新規・仕切りの別、枚数、約定値段及び総取引金額が記載された「売買報告書」が送付されていること。
(チ)請求人に対しては、反対売買決済(新規に買い付け又は売り付けた商品を限月前に仕切って精算する取引をいう。以下同じ。)の際、F社から、売買差金(商品先物取引の反対売買決済による売買差金をいう。以下同じ。)、委託手数料、消費税、取引所税、差引損益金及び返還可能額が記載された「売買報告書及び売買計算書」が送付されていること。
(リ)請求人に対しては、毎月F社から、作成日現在の建玉の内訳、委託証拠金必要額、委託証拠金現在残高、差引損益金及び返還可能額が記載された「残高照合通知書」が送付されており、請求人は記載内容についての異議等の有無等を同封の葉書により回答するものとされていること。
(ヌ)反対売買決済により差引損金が生じた場合には、F社から請求人に対して「立替金請求書」が送付されていること。
(ル)請求人は、平成5年1月21日に、F社から、委託証拠金2,367,983円の返還を受け、また、同日に帳尻金(反対売買決済による売買差金から委託手数料、消費税及び取引所税を控除した残額をいう。以下同じ。)として3,632,017円を受領し、同社に対してこれらの金員の領収証を交付していること。
(ヲ)請求人は、平成5年12月2日に、F社から、帳尻金として3,000,000円を受領し、同社に対して領収証を交付していること。
(ワ)F社が請求人からの委託に基づくものとして行った商品先物取引の売買差金の各年分の状況は、別表1ないし4のとおりであること。
(カ)上記(イ)ないし(ワ)の事実から判断すると、各年分の本件先物取引に係る売買差金は請求人に帰属するものであると認められる。
ロ 総所得金額
(イ)給与所得の金額
給与所得の金額は、各年分とも請求人が確定申告書に記載した金額で、平成4年分10,945,000円及び平成5年分10,945,000円である。
(ロ)雑所得の金額
A 商品先物取引に係る雑所得の金額は、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
総収入金額 (1) 4,844,800 34,254,000
必要経費 (2) 3,207,643 13,840,259
所得金額((1)-(2)) 1,637,157 20,413,741
(A)総収入金額は、F社及びH社に委託した商品先物取引に係る売買差金の各年分の合計金額で、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
F 社 (1) 4,528,000 34,986,800
H 社 (2) 316,800 △732,000
総収入金額((1)+(2)) 4,844,800 34,254,000
(注)△印は、売買差金が損失であることを示す。
(B)必要経費
必要経費は、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
委託手数料 (1) 3,108,000 13,401,860
消費税の額 (2) 93,238 402,040
取引所税の額 (3) 6,405 36,359
必要経費((1)+(2)+(3)) 3,207,643 13,840,259
a 委託手数料
委託手数料は、F社及びH社に対する支払額である。
b 消費税の額
消費税の額は、上記aに掲げた委託手数料に対するものである。
c 取引所税の額
新規の買付け・売付け取引及び反対売買取引の総取引金額に対するものである。
B 有価証券オプション取引に係る雑所得の金額
有価証券オプション取引に係る雑所得の金額は、請求人がN証券株式会社(以下「N証券」という。)に委託して行った有価証券オプション取引の反対売買決済により生じた損失の金額1,250,140円である。
C 雑所得の金額
以上の結果、雑所得の金額は、商品先物取引に係る雑所得の金額から有価証券オプション取引に係る雑所得の損失を控除した額で、次表のとおりである。
(図表1)
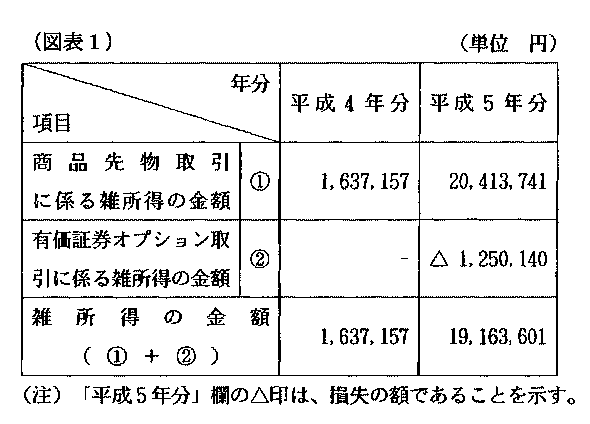
(ハ)総所得金額
各年分の総所得金額は、上記(イ)の給与所得の金額と上記(ロ)の雑所得の金額の合計額で平成4年分12,582,157円及び平成5年分30,108,601円となり、これらの金額は本件更正処分の額と同額又は上回るから、各年分の更正処分に違法はない。
なお、課税標準等及び税額等の計算に当たっては、その計算をする時における法的状態を基礎として算定すべきものであり、このことは国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第2項第1号が「課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実に対する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」には、更正の請求によって是正を求める途を開いていることからも明らかであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
ハ 過少申告加算税の賦課決定処分
過少申告加算税の賦課決定処分については、請求人の場合、通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないので、同条第1項及び第2項の規定に基づき各年分の過少申告加算税を賦課決定したことは適法である。
3 判断
本件審査請求の争点は、本件先物取引に係る所得に対する課税処分の適否であるので、以下審理する。
(1)本件更正処分について
イ 原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ)F社に対する商品先物取引の委託状況等について
請求人は、F社に商品先物取引を委託するに当たって、次のとおり、商品取引所法第94条の2《受託契約の締結前の書面の交付》で交付が義務づけられた「商品先物取引委託のしおり」及び「受託契約準則」等の書面をF社から受領し、受領した旨の書面をF社に差し入れており、また、同法第96条《受託契約準則への準拠》に規定する各取引所の定める受託契約準則に基づく各種書類等をF社との間で取り交わしていることが認められる。
A 請求人は、昭和61年2月20日に、F社から「商品取引委託のしおり」を受領した旨の「商品取引委託のしおりの受領について」と題する書面を差し入れていること。
B 請求人は、昭和61年2月20日に、F社から「受託契約準則」、「金スプレッド取引実施要領」、「金損失限定(ストップ・ロス)取引実施要領」、「貴金属ストラドル取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領した旨の「受領書」を差し入れていること。
C 請求人は、昭和61年2月20日に、J工業品取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ工業品取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
D 請求人は、昭和61年2月20日に、商品取引では元本は保証されていないこと及びF社の社員へ売買を任せることは絶対にしないということを充分承知の上取引注文をする旨記載された「お取引について」と題する書面を差し入れていること。
E 請求人は、昭和61年2月20日に、請求人の氏名及び住所を記載した「通知書」を差し入れていること。
F 請求人は、昭和63年7月5日に、J砂糖取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ砂糖取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
G 請求人は、昭和63年7月5日に、F社から「受託契約準則」、「セット売買契約条項」、「パック取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領した旨の「受領書」を差し入れていること。
H 請求人は、平成元年2月22日に、J穀物商品取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ穀物商品取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
I 請求人は、平成元年11月27日に、売買取引の委託に係る取引所にK生糸取引所及びL乾繭取引所を付け加える旨を記載した「商品取引所追加約諾書」を差し入れていること。
J 請求人は、平成元年11月27日に、「準備金による委託証拠金充当同意書」を差し入れていること。
(ロ)F社に委託した商品先物取引の状況等について
F社に委託して行った商品先物取引の状況は、次のとおりである。
A F社の営業管理本部本社営業管理部長Tは、平成9年4月8日に当審判所に対し、請求人は昭和61年2月20日から平成6年2月10日まで商品先物取引をF社に委託して取引していた旨答述していること。
また、請求人は、F社に商品先物取引を委託して取引していた期間について、本件損害賠償請求訴訟においても昭和61年2月20日から平成6年2月10日までであることを認めていること。
B 請求人が平成4年から平成6年の間にF社に委託して行った商品先物取引による売買差金は、別表1ないし5のとおりであり、商品先物取引による年間の損益としては、平成4年及び平成5年は利益が生じ、平成6年は損失となっていること。
C F社は、請求人に対して、本件先物取引に係る売買取引成立の都度、当該取引が成立した日の翌営業日に、商品、限月、約定年月日、場節、売付け・買付けの別、新規・仕切りの別、枚数、約定値段及び総取引金額が記載された「売買報告書」を送付していること。
D F社は、請求人に対して、反対売買決済の都度、その決済をした日の翌営業日に、売買差金、委託手数料、消費税、取引所税、差引損益及び返還可能額が記載された「売買計算書」を送付していること。
E F社は、請求人に対して、毎月1日(1日が休業日の場合は、その月の最初の営業日)現在の建玉の内訳、委託証拠金必要額、委託証拠金現在高、差引損益金及び返還可能額を記載した「貴口座現在高照合ご通知書」と同通知書の記載内容についての異議等の有無等を回答するための「回答書」を併せて翌営業日に送付していること。
F 請求人は、平成元年4月10日現在の残高照合表について、その内容の照合の結果を通知する「回答書」に署名押印をして、F社に送付していること。
G F社は、平成4年3月2日に反対売買決済により差引217,289円の損失が生じたため、当該金額に係る「帳尻立替金請求書」を上記Eの「貴口座現在高照合ご通知書」に同封して請求人に送付していること。
H 請求人は、平成4年3月3日に上記Gの帳尻立替金のうち50,000円をF社に支払い、F社は、請求人に対して領収証を発行していること。
I F社の営業管理本部本社営業管理部長Tは、平成9年4月8日に当審判所に対し、委託証拠金が不足した場合には、F社のW支店の担当外務員が請求人に対して委託追証拠金(委託証拠金の担保不足を補うための証拠金で、以下、「追証」という。)が必要となることを電話で連絡していた旨答述していること。
J 請求人は、F社に対して次表のとおり委託証拠金を支払っていること。
(単位 円)
支払年月日 委託証拠金 グループ
平成4年 3月 9日 500,000 通産
平成4年 3月12日 400,000 農水
平成4年 3月16日 68,000 農水
平成4年 4月24日 500,000 通産
平成4年10月30日 386,000 通産
平成4年12月21日 10,000,000 通産
平成4年12月25日 5,000,000 農水
平成5年 6月14日 3,000,000 通産
平成5年 6月15日 4,020,000 通産
平成5年 6月18日 350,000 通産
K F社は、委託証拠金の額に異動があった都度、別表6のとおり委託証拠金預り証を請求人へ送付していること。
L F社は、請求人の要請に基づき、次表のとおり委託証拠金の返還又は帳尻金の支払をしていること。
(単位 円)
返還又は支払年月日 金額 グループ 種 類 返還又は支払方法
平成4年11月 4日 11,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 1月21日 2,367,983 通産 証拠金 現金支払
平成5年 1月21日 2,834,672 通産 帳尻金 現金支払
平成5年 1月21日 797,345 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 1月26日 6,000,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 3月10日 200,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 3月10日 1,300,000 農水 証拠金 現金支払
平成5年 7月 9日 600,000 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 8月 3日 578,993 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 8月17日 250,000 農水 証拠金 現金支払
平成5年 9月 2日 377,843 農水 帳尻金 口座振込
平成5年12月 2日 3,000,000 農水 帳尻金 現金支払
M 請求人は、上記Lの表の現金で受領した金員について、署名押印した領収証をF社に差し入れていること。
N 上記Lの表の口座振込の方法で支払われた金員は、X銀行Y支店の請求人名義の普通預金(口座番号△△△)へ振り込まれていること。
ロ 上記イの事実について検討したところ、次のとおりである。
(イ)上記イの各事実から判断すると、請求人は、商品先物取引を始めるに当たり、昭和61年2月20日にF社に対して商品先物取引の委託をしていることが認められ、その際、請求人は、商品先物取引が投機的な性格が強い取引であることを十分認識し、理解して取引を行うようにとの主旨から、商品取引所法第94条の2で商品取引の委託者に交付が義務付けられた「商品先物取引委託のしおり」等の書面の交付を受けるとともに、先物取引の危険性を了知した上で取引することを承諾する旨の「承諾書」をF社に差し入れるなどしており、請求人においては、先物取引の危険性及び先物取引における注意事項や手続について十分認識した上で、自己の意思と判断の下でF社に商品先物取引を委託していたものと認められる。
(ロ)上記イの(ロ)のAないしFの事実から、請求人は、本件先物取引の個々の内容及び損益について、毎月F社から送られてくる「売買計算書」及び「貴口座現在高照合ご通知書」により随時確認できる状況にあったものと認められ、しかも、本件先物取引により利益が生じて返還可能額がある場合には、返還を求めるかどうかについて指示することができることとされており、現に請求人は、上記イの(ロ)のLのとおり帳尻金等の返還を受けていることが認められる。
また、通知された取引内容に疑義がある場合には「回答書」により、再調査の依頼ができることとされており、請求人は、平成元年4月10日現在の残高照合表について「回答書」に署名押印の上、F社に送付していることが認められる。
(ハ)上記イの(ロ)のGないしNの事実から、請求人は、本件先物取引に関して、F社から立替金や追証の請求があった都度、F社へ金員を支払っており、また、請求人は委託証拠金の返還や帳尻金の支払をF社に請求し、その都度F社から金員を受領していることが認められる。
ハ 以上のことから、請求人は、自己の意思と判断の下にF社に委託して本件先物取引を行い、本件先物取引から生じる所得を得ていたものと認められるから、原処分庁が、本件先物取引から生じた所得を請求人に帰属するものと認定したことに誤りは認められない。
なお、請求人は、先物取引を開始するに際して承諾書にサインするのは形式的なことであり、そのことをもって取引内容を了知したとするのは経験則に反する旨主張するが、本件先物取引については、承諾書にサインがあるという事実だけではなく、上述のとおり、上記イの各事実を上記ロで検討し取引内容を了知したものと認められたものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ニ 請求人は、本件先物取引は違法性を帯び、無効あるいは取り消し得る取引であるから、このような取引を課税要件の基礎としたことは誤りである旨主張する。
しかしながら、上記ハのとおり、本件先物取引は請求人がF社に委託して行った取引であり、平成4年分及び平成5年分において、本件先物取引から所得が生じており、しかも、請求人はその利益を受領したり、委託証拠金に充当するなど享受していることが明らかであるから、請求人には課税要件事実が満たされているということができる。
また、本件更正処分が行われた時点において、本件先物取引が違法又は無効なものとして、その経済的成果が失われたという証拠も認められず、しかも、本件先物取引に関して、取り消すことのできる行為が取り消されたという事実も認められないことから、原処分庁が課税処分時の本件先物取引に係る法的状態に基づいて課税をすることに違法は認められない。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ホ なお、請求人は、F社との間で和解が成立したことが、F社がいかに違法な取引をしたかの証左である旨主張するが、平成6年5月31日付のF社との和解書には、和解金2,000,000円の支払、請求人が預託している委託証拠金の返還及び和解後における請求人とF社との間の権利義務関係に関する確認など5項目について記載してあるのみで、本件先物取引に関し和解金が支払われることとなった具体的な法的評価等については何ら記載されておらず、本件和解が各年分の課税関係に変動を生じさせるものとは認められない。
したがって、本件和解によって上記ニの判断が左右されるものではない。
ヘ 請求人は、本件損害賠償請求訴訟の判決を待って最終的な更正処分がなされるべきである旨主張する。
上記ハ及びニで述べたとおり、本件先物取引は請求人の意思と判断の下で行ったものであり、また、後記チで述べるとおり、請求人には本件先物取引による所得が生じていることから、課税適状にあるというべきである。
ところで、通則法第24《更正》においては、税務署長は、「納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他課税標準等又は税額等が調査したところと異なるときは、その調査により、納税申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する」こととされている。
そして、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項で、期限内申告書に係る国税の増額更正については「更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない」と規定されており、更正処分ができる期間についての制限が設けられている。
したがって、税務署長が調査により納税者の申告した課税標準等に誤りを発見し、課税適状にある場合においては、法定申告期限から3年間はいつでも更正処分をすることができることとされているが、仮に、請求人の主張するように課税要件事実に争いがあることをもって、訴訟等によりその争いが解決された時点で課税をすべきであるとすると、争いの解決が長期化し、法定申告期限から3年を経過した日以後に解決することとなるような場合には、同条項により更正処分ができないこととなり、国は適正な賦課権の行使ができなくなる。
このようなことは、租税負担の公平の見地から容認することはできないというべきである。
また、上記のように課税要件事実に関する争いがある段階で更正処分がされ、後に、課税要件事実に関する争いが解決した場合において、先の更正処分の基礎とされた課税要件事実の全部又は一部が取り消されることになり、税額等が減少することとなった場合には、通則法第23条第2項第1号の規定により、判決等により先の更正処分の基礎とされたところと異なる事実が確定した日の翌日から起算して2月以内に、税務署長に対して更正の請求をすることにより、その是正を求めることができることとされているから、課税時期の法的状態に基づいて課税をしたとしても納税者に不当な課税を強いる結果となるものではない。
以上のとおり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ト 請求人は、請求人が形式的に承諾したことをもって本件先物取引の内容を了知していたとすることは経験則に反することである旨主張する。
しかしながら、上記ロで述べたとおり、請求人は、昭和61年2月から自己の意思と判断の下で商品先物取引を繰り返し行って、損失が生じて金員の支払が必要な場合はその都度金員を支払い、利益が生じた場合はその利益を享受しており、本件先物取引の内容について十分了知していたと認められることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
チ 総所得金額
(イ)給与所得の金額
原処分庁は請求人の各年分の給与所得の金額は、請求人が確定申告書に記載した金額で、平成4年分10,945,000円及び平成5年分10,945,000円と認定しているところ、当審判所の調査によっても原処分庁の認定額は相当と認められる。
(ロ)雑所得の金額
A 商品先物取引に係る雑所得の金額
(A)請求人が行った本件先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、 次表のとおりである。
(図表2)
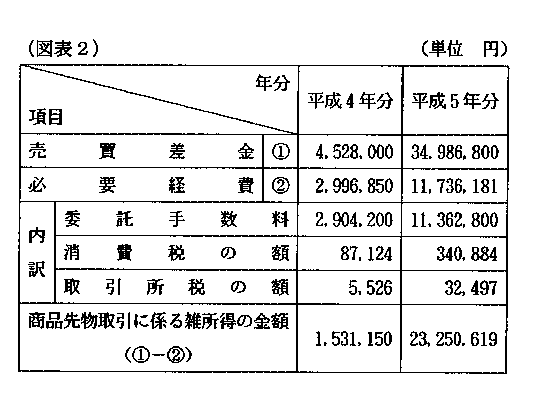
(B)請求人がH社に委託して行った商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、次表のとおりである。
(図表3)
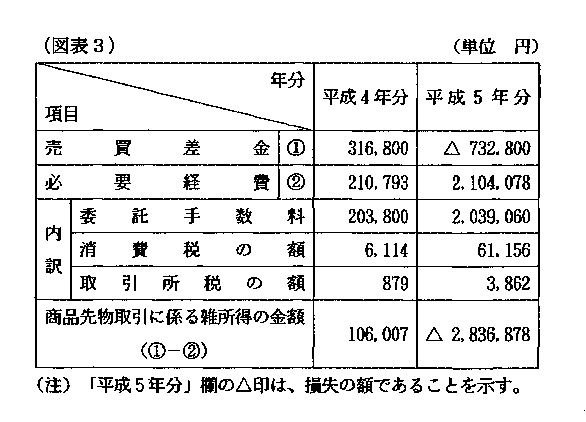
(C)請求人の商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、上記(A)と(B)の金額の合計額で、平成4年分1,637,157円及び平成5年分20,413,741円となり、これらの金額は原処分の金額と同額であるから、原処分庁が認定した商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は相当と認められる。
B 有価証券オプション取引に係る雑所得の金額
原処分庁は、請求人がN証券に委託して行った平成5年分の有価証券オプション取引による雑所得の金額は、1,250,140円の損失であると認定しているところ、当審判所の調査によっても原処分庁の認定額は相当と認められる。
C雑所得の金額
請求人の各年分の雑所得の金額は、上記Aの商品先物取引に係る雑所得の金額から上記Bの有価証券オプション取引に係る雑所得の損失額を控除した金額であり、平成4年分1,637,157円及び平成5年分19,163,601円となる。
(ハ)総所得金額
請求人の各年分の総所得金額は、上記(イ)の給与所得の金額と上記(ロ)の雑所得の金額の合計額で平成4年分12,582,157円及び平成5年分30,108,601円となり、これらの金額は原処分の金額と同額又は上回るから、本件更正処分は、適法である。
(2)過少申告加算税の賦課決定処分について
以上のとおり、本件更正処分は適法であり、また、本件更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づいてした過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(3)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。
別表1
平成4年分 農水グループ
(単位 円)
日付 売買差金
4月 9日 750,000
4月15日 166,400
5月14日 675,000
5月21日 75,000
6月24日 △168,000
6月24日 △30,000
7月 7日 △261,000
7月 7日 △130,000
7月 8日 △110,000
7月15日 △329,000
7月17日 △377,000
12月16日 71,200
12月16日 △61,600
合計 271,000
(注)△印は、売買差金が損失であることを示す。以下同じ。
別表2
平成4年分 通産グループ
(単位 円)
日付 売買差金
3月12日 △22,000
4月21日 80,000
7月17日 △796,000
8月17日 △212,500
8月27日 △402,500
11月10日 52,500
12月24日 5,557,500
合計 4,257,000
別表3
平成5年分 農水グループ
(単位 円)
日付 売買差金 日付 売買差金
1月14日 576,000 9月29日 △608,000
1月19日 600,000 10月 6日 △192,000
3月12日 150,000 10月 8日 △364,000
3月12日 275,000 10月27日 584,000
3月17日 △240,000 10月29日 100,000
4月28日 520,000 11月 8日 216,000
4月28日 △40,000 11月 8日 624,000
4月30日 650,000 11月10日 1,456,000
4月30日 △180,000 11月16日 3,080,000
5月18日 470,000 11月16日 688,000
5月18日 260,000 11月17日 △840,000
5月26日 520,000 11月17日 △744,000
6月15日 80,000 11月18日 △936,000
6月28日 150,000 11月22日 2,720,000
7月 5日 525,000 11月22日 2,600,000
7月 6日 400,000 12月 2日 3,120,000
7月28日 56,000 12月 6日 △123,200
7月29日 185,600 12月 7日 △81,600
8月10日 3,680,000 12月 7日 1,320,000
8月10日 △3,072,000 12月 8日 960,000
8月13日 △480,000 12月 8日 1,880,000
8月18日 1,184,000 12月13日 △112,000
8月18日 △796,000 12月13日 1,640,000
8月24日 120,000 12月14日 440,000
9月 6日 240,000 12月16日 400,000
9月10日 436,000 12月20日 3,120,000
9月10日 △48,000 12月20日 532,000
9月10日 △410,000 12月20日 2,200,000
9月14日 100,000 12月22日 5,040,000
9月17日 92,000 12月24日 △3,192,000
9月20日 76,000 12月30日 1,760,000
9月20日 △76,000 12月30日 1,240,000
9月28日 △92,000 小計 28,527,200
9月29日 1,240,000 合計 35,678,800
小計 7,151,600
別表4
平成5年分 通産グループ
(単位 円)
日 付 売買差金
3月22日 192,000
3月22日 62,000
3月31日 △426,000
4月28日 △408,000
4月28日 △48,000
4月28日 △64,000
合 計 △692,000
別表5
平成6年分 農水グループ
(単位 円)
日 付 売買差金
1月 4日 △2,280,000
1月25日 1,120,000
1月31日 △960,000
1月31日 △1,440,000
1月31日 △864,000
2月 1日 △5,880,000
2月 4日 △2,880,000
2月 7日 △6,520,000
2月10日 △8,480,000
合 計 △28,184,000
(図表6)
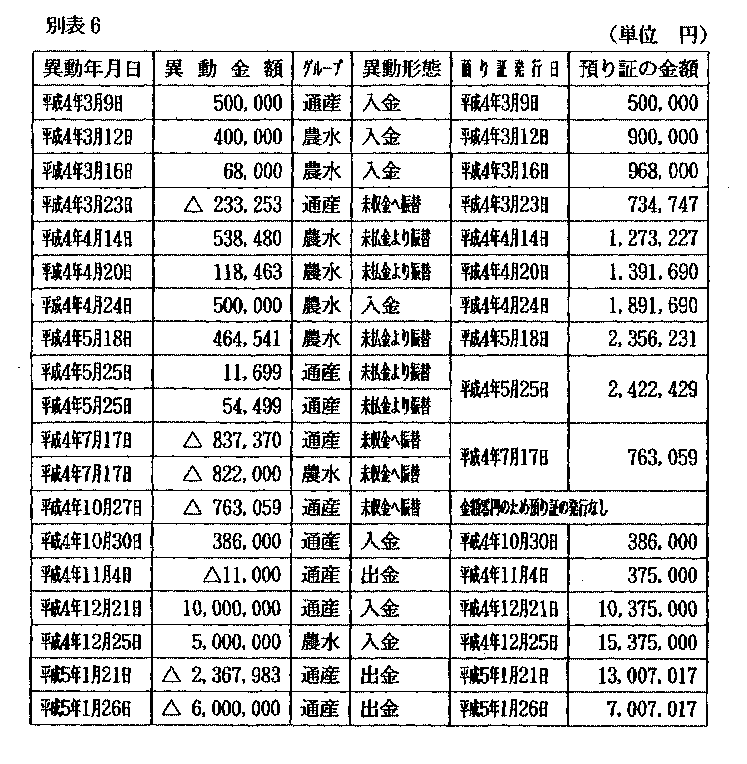
(図表6)(続き)1
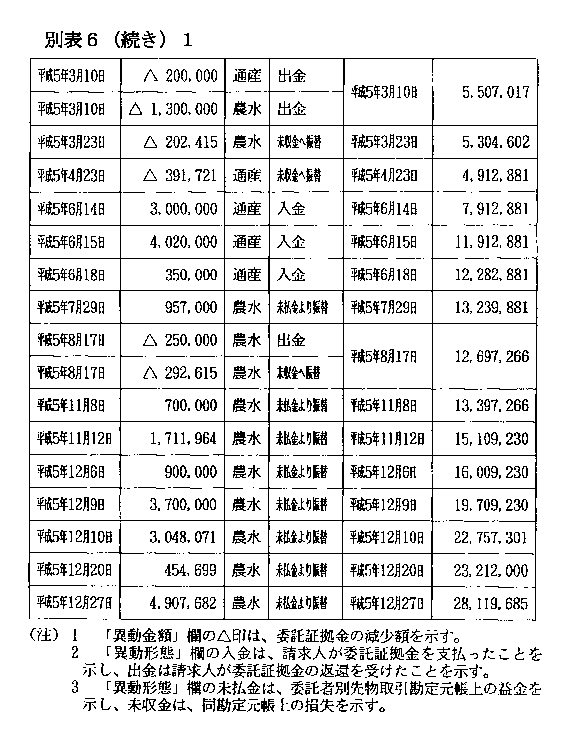
《裁決書(抄)》
1 事実
審査請求人(以下「請求人」という。)は、会社役員であるが、平成4年分及び平成5年分(以下、併せて「各年分」という。)の所得税について、確定申告書に次表のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに提出した。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
総所得金額(給与所得の金額) 10,945,000 10,945,000
納付すべき税額 △13,200 27,100
(注)「納付すべき税額」欄の△印は、還付金に相当する税額を示す。
原処分庁は、これに対し、平成8年3月8日付で各年分の所得税について、次表のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
(単位 円)
区分 項目 年分 平成4年分 平成5年分
更正処分 総所得金額 12,582,157 29,788,419
内訳
給与所得の金額 10,945,000 10,945,000
雑所得の金額 1,637,157 18,843,419
納付すべき税額 594,400 8,374,900
賦課決定処分 過少申告加算税の額 60,000 1,151,500
請求人は、これらの処分を不服として、平成8年4月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年7月4日付で棄却の異議決定をした。
請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成8年7月31日に審査請求をした。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
イ 本件更正処分について
(イ)原処分は、請求人が各年分においてF株式会社(以下「F社」という。)に委託して商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)をした際に上げた利益について課税したものであるが、請求人は、F社の取引員に欺もうされ本件先物取引を行ったものであり、この本件先物取引自体が違法性を帯び、無効あるいは取り消し得る行為なので、請求人は、平成7年11月2日にF社を相手にG地方裁判所へ損害賠償請求の訴訟(以下「本件損害賠償請求訴訟」という。)を提起し、現在争訟中である。
したがって、本件先物取引から生じた所得は請求人には帰属しないから、本件先物取引が有効であるという前提で行った原処分は違法である。
なお、F社と請求人との間には、平成6年5月31日に本件先物取引について和解がなされ、この和解の効力についても請求人は本件損害賠償請求訴訟において争っているが、このような和解契約がなされたこと自体、F社がいかに違法な取引を行ったものであったかを物語る一つの有力な証拠であり、仮に、F社と請求人との取引が全く正常なものであるならば、F社はこのような和解をするはずがない。
(ロ)原処分庁は、請求人が本件先物取引についての承諾書に署名押印した上、同承諾書をF社に対して差し入れていることをもって、本件先物取引から生じた所得が請求人に帰属するものとして課税処分を行っているが、本件先物取引はいわゆる先物取引の客殺し(請求人は、いわゆる客殺しにあった被害者である。)であって、このような客殺しが問題となるときには、形式的には承諾書にサインさせているのがほとんどすべてであり、先物取引に関する判例も、承諾書だけをもって先物取引業者に勝訴判決をした例は皆無である。
したがって、請求人が本件先物取引を開始するに際して形式的に承諾したことをもってその内容を了知したとする原処分庁の認定は経験則に反することである。
(ハ)原処分庁は、課税標準等及び税額等の計算に当たっては、その計算をする時における法的状態を基礎として算定すべきものである旨主張するが、F社の取引の違法性は、既に第三者にとっても重大であり、明白にその違法性が認識できる状態であるから、このような場合には法的状態を基礎として算出すべきではない。
したがって、本件更正処分のうち、本件先物取引に係る部分は直ちに取り消されるべきであり、本件損害賠償請求訴訟の判決を待って最終的な更正処分がなされるべきである。
(ニ)原処分のうちH株式会社(以下「H社」という。)との商品先物取引に係る雑所得の金額については争わない。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
以上のとおり、本件更正処分は違法であり、その一部を取り消すべきであるから、これに伴い過少申告加算税の賦課決定処分もその一部を取り消すべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり適法に行われており、本件審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分について
請求人は、次のとおり、本件先物取引の内容について了知していたことが認められることから、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属する。
(イ)請求人は、J工業品取引所における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J工業品取引所受託契約準則に従い、昭和61年2月20日に次の書類をF社との間で取り交わしている事実が認められる。
A 請求人はF社から「商品取引委託のしおり」を受領し、F社に対して「商品取引委託のしおりの受領について」と題する書面を署名押印の上、差し入れていること。
B 請求人は、F社から「受託契約準則」、「金スプレッド取引実施要領」、「金損失限定取引実施要領」、「貴金属ストラドル取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領し、F社に対してこれらの書面の「受領書」を署名押印の上、差し入れていること。
C 請求人は、F社に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、差し入れていること。
D 請求人は、請求人の氏名及び住所を記載した「通知書」をF社に差し入れていること。
(ロ)請求人は、J砂糖取引所(同取引所は、平成○年○月○日付でJ穀物商品取引所と合併している。)における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J砂糖取引所受託契約準則に従い、昭和63年2月5日に次の書類をF社との間で取り交わしている事実が認められる。
A 請求人はF社から「受託契約準則」、「セット売買契約条項」、「パック取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領し、F社に対してこれらの書面の「受領書」を署名押印の上、差し入れていること。
B 請求人はF社に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、差し入れていること。
(ハ)請求人は、J穀物商品取引所における商品先物取引をF社に委託するに当たり、J穀物商品取引所受託契約準則に従い、平成元年2月22日に「先物取引の危険性を了知した上で同準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ニ)請求人は、平成元年11月27日に売買取引の委託に係る取引所に「K生糸取引所」及び「L乾繭取引所」を付け加える旨を記載した「追加約諾書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ホ)請求人は、平成元年11月27日に「準備金による委託証拠金充当同意書」を署名押印の上、F社に差し入れていること。
(ヘ)請求人が平成4年中及び平成5年中においてF社に対して支払った委託証拠金は次表のとおりであり、また、これらの委託証拠金の支払の際には、F社から請求人に対して「委託証拠金預り証」が交付されていること。
A 農水グループ
(単位 円)
日付 金額
平成4年 3月12日 400,000
平成4年 3月16日 68,000
平成4年12月25日 5,000,000
(注)農水グループとは、J穀物商品取引所、K生糸取引所、L乾繭取引所等の農林水産省が所管する商品取引所のグループを示す。以下同じ。
B 通産グループ
(単位 円)
日付 金額
平成4年 3月 9日 500,000
平成4年 4月24日 500,000
平成4年10月30日 386,000
平成4年12月21日 10,000,000
平成5年 6月14日 3,000,000
平成5年 6月15日 4,020,000
平成5年 6月18日 350,000
(注)通産グループとは、J工業品取引所、M繊維取引所等の通商産業省が所管する商品取引所のグループを示す。以下同じ。
(ト)請求人に対しては、取引成立の都度、F社から、商品、限月、約定年月日、場節、売付け・買付けの別、新規・仕切りの別、枚数、約定値段及び総取引金額が記載された「売買報告書」が送付されていること。
(チ)請求人に対しては、反対売買決済(新規に買い付け又は売り付けた商品を限月前に仕切って精算する取引をいう。以下同じ。)の際、F社から、売買差金(商品先物取引の反対売買決済による売買差金をいう。以下同じ。)、委託手数料、消費税、取引所税、差引損益金及び返還可能額が記載された「売買報告書及び売買計算書」が送付されていること。
(リ)請求人に対しては、毎月F社から、作成日現在の建玉の内訳、委託証拠金必要額、委託証拠金現在残高、差引損益金及び返還可能額が記載された「残高照合通知書」が送付されており、請求人は記載内容についての異議等の有無等を同封の葉書により回答するものとされていること。
(ヌ)反対売買決済により差引損金が生じた場合には、F社から請求人に対して「立替金請求書」が送付されていること。
(ル)請求人は、平成5年1月21日に、F社から、委託証拠金2,367,983円の返還を受け、また、同日に帳尻金(反対売買決済による売買差金から委託手数料、消費税及び取引所税を控除した残額をいう。以下同じ。)として3,632,017円を受領し、同社に対してこれらの金員の領収証を交付していること。
(ヲ)請求人は、平成5年12月2日に、F社から、帳尻金として3,000,000円を受領し、同社に対して領収証を交付していること。
(ワ)F社が請求人からの委託に基づくものとして行った商品先物取引の売買差金の各年分の状況は、別表1ないし4のとおりであること。
(カ)上記(イ)ないし(ワ)の事実から判断すると、各年分の本件先物取引に係る売買差金は請求人に帰属するものであると認められる。
ロ 総所得金額
(イ)給与所得の金額
給与所得の金額は、各年分とも請求人が確定申告書に記載した金額で、平成4年分10,945,000円及び平成5年分10,945,000円である。
(ロ)雑所得の金額
A 商品先物取引に係る雑所得の金額は、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
総収入金額 (1) 4,844,800 34,254,000
必要経費 (2) 3,207,643 13,840,259
所得金額((1)-(2)) 1,637,157 20,413,741
(A)総収入金額は、F社及びH社に委託した商品先物取引に係る売買差金の各年分の合計金額で、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
F 社 (1) 4,528,000 34,986,800
H 社 (2) 316,800 △732,000
総収入金額((1)+(2)) 4,844,800 34,254,000
(注)△印は、売買差金が損失であることを示す。
(B)必要経費
必要経費は、次表のとおりである。
(単位 円)
項目 年分 平成4年分 平成5年分
委託手数料 (1) 3,108,000 13,401,860
消費税の額 (2) 93,238 402,040
取引所税の額 (3) 6,405 36,359
必要経費((1)+(2)+(3)) 3,207,643 13,840,259
a 委託手数料
委託手数料は、F社及びH社に対する支払額である。
b 消費税の額
消費税の額は、上記aに掲げた委託手数料に対するものである。
c 取引所税の額
新規の買付け・売付け取引及び反対売買取引の総取引金額に対するものである。
B 有価証券オプション取引に係る雑所得の金額
有価証券オプション取引に係る雑所得の金額は、請求人がN証券株式会社(以下「N証券」という。)に委託して行った有価証券オプション取引の反対売買決済により生じた損失の金額1,250,140円である。
C 雑所得の金額
以上の結果、雑所得の金額は、商品先物取引に係る雑所得の金額から有価証券オプション取引に係る雑所得の損失を控除した額で、次表のとおりである。
(図表1)
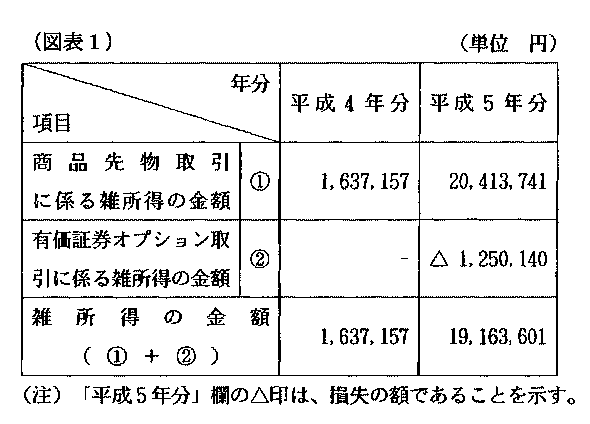
(ハ)総所得金額
各年分の総所得金額は、上記(イ)の給与所得の金額と上記(ロ)の雑所得の金額の合計額で平成4年分12,582,157円及び平成5年分30,108,601円となり、これらの金額は本件更正処分の額と同額又は上回るから、各年分の更正処分に違法はない。
なお、課税標準等及び税額等の計算に当たっては、その計算をする時における法的状態を基礎として算定すべきものであり、このことは国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第2項第1号が「課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実に対する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」には、更正の請求によって是正を求める途を開いていることからも明らかであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
ハ 過少申告加算税の賦課決定処分
過少申告加算税の賦課決定処分については、請求人の場合、通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないので、同条第1項及び第2項の規定に基づき各年分の過少申告加算税を賦課決定したことは適法である。
3 判断
本件審査請求の争点は、本件先物取引に係る所得に対する課税処分の適否であるので、以下審理する。
(1)本件更正処分について
イ 原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ)F社に対する商品先物取引の委託状況等について
請求人は、F社に商品先物取引を委託するに当たって、次のとおり、商品取引所法第94条の2《受託契約の締結前の書面の交付》で交付が義務づけられた「商品先物取引委託のしおり」及び「受託契約準則」等の書面をF社から受領し、受領した旨の書面をF社に差し入れており、また、同法第96条《受託契約準則への準拠》に規定する各取引所の定める受託契約準則に基づく各種書類等をF社との間で取り交わしていることが認められる。
A 請求人は、昭和61年2月20日に、F社から「商品取引委託のしおり」を受領した旨の「商品取引委託のしおりの受領について」と題する書面を差し入れていること。
B 請求人は、昭和61年2月20日に、F社から「受託契約準則」、「金スプレッド取引実施要領」、「金損失限定(ストップ・ロス)取引実施要領」、「貴金属ストラドル取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領した旨の「受領書」を差し入れていること。
C 請求人は、昭和61年2月20日に、J工業品取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ工業品取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
D 請求人は、昭和61年2月20日に、商品取引では元本は保証されていないこと及びF社の社員へ売買を任せることは絶対にしないということを充分承知の上取引注文をする旨記載された「お取引について」と題する書面を差し入れていること。
E 請求人は、昭和61年2月20日に、請求人の氏名及び住所を記載した「通知書」を差し入れていること。
F 請求人は、昭和63年7月5日に、J砂糖取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ砂糖取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
G 請求人は、昭和63年7月5日に、F社から「受託契約準則」、「セット売買契約条項」、「パック取引実施要領」及び「危険開示告知書」を受領した旨の「受領書」を差し入れていること。
H 請求人は、平成元年2月22日に、J穀物商品取引所における売買取引の委託をするについて「先物取引の危険性を了知した上でJ穀物商品取引所の受託契約準則に従って取引を行うことを承諾する」旨を記載した「承諾書」を差し入れていること。
I 請求人は、平成元年11月27日に、売買取引の委託に係る取引所にK生糸取引所及びL乾繭取引所を付け加える旨を記載した「商品取引所追加約諾書」を差し入れていること。
J 請求人は、平成元年11月27日に、「準備金による委託証拠金充当同意書」を差し入れていること。
(ロ)F社に委託した商品先物取引の状況等について
F社に委託して行った商品先物取引の状況は、次のとおりである。
A F社の営業管理本部本社営業管理部長Tは、平成9年4月8日に当審判所に対し、請求人は昭和61年2月20日から平成6年2月10日まで商品先物取引をF社に委託して取引していた旨答述していること。
また、請求人は、F社に商品先物取引を委託して取引していた期間について、本件損害賠償請求訴訟においても昭和61年2月20日から平成6年2月10日までであることを認めていること。
B 請求人が平成4年から平成6年の間にF社に委託して行った商品先物取引による売買差金は、別表1ないし5のとおりであり、商品先物取引による年間の損益としては、平成4年及び平成5年は利益が生じ、平成6年は損失となっていること。
C F社は、請求人に対して、本件先物取引に係る売買取引成立の都度、当該取引が成立した日の翌営業日に、商品、限月、約定年月日、場節、売付け・買付けの別、新規・仕切りの別、枚数、約定値段及び総取引金額が記載された「売買報告書」を送付していること。
D F社は、請求人に対して、反対売買決済の都度、その決済をした日の翌営業日に、売買差金、委託手数料、消費税、取引所税、差引損益及び返還可能額が記載された「売買計算書」を送付していること。
E F社は、請求人に対して、毎月1日(1日が休業日の場合は、その月の最初の営業日)現在の建玉の内訳、委託証拠金必要額、委託証拠金現在高、差引損益金及び返還可能額を記載した「貴口座現在高照合ご通知書」と同通知書の記載内容についての異議等の有無等を回答するための「回答書」を併せて翌営業日に送付していること。
F 請求人は、平成元年4月10日現在の残高照合表について、その内容の照合の結果を通知する「回答書」に署名押印をして、F社に送付していること。
G F社は、平成4年3月2日に反対売買決済により差引217,289円の損失が生じたため、当該金額に係る「帳尻立替金請求書」を上記Eの「貴口座現在高照合ご通知書」に同封して請求人に送付していること。
H 請求人は、平成4年3月3日に上記Gの帳尻立替金のうち50,000円をF社に支払い、F社は、請求人に対して領収証を発行していること。
I F社の営業管理本部本社営業管理部長Tは、平成9年4月8日に当審判所に対し、委託証拠金が不足した場合には、F社のW支店の担当外務員が請求人に対して委託追証拠金(委託証拠金の担保不足を補うための証拠金で、以下、「追証」という。)が必要となることを電話で連絡していた旨答述していること。
J 請求人は、F社に対して次表のとおり委託証拠金を支払っていること。
(単位 円)
支払年月日 委託証拠金 グループ
平成4年 3月 9日 500,000 通産
平成4年 3月12日 400,000 農水
平成4年 3月16日 68,000 農水
平成4年 4月24日 500,000 通産
平成4年10月30日 386,000 通産
平成4年12月21日 10,000,000 通産
平成4年12月25日 5,000,000 農水
平成5年 6月14日 3,000,000 通産
平成5年 6月15日 4,020,000 通産
平成5年 6月18日 350,000 通産
K F社は、委託証拠金の額に異動があった都度、別表6のとおり委託証拠金預り証を請求人へ送付していること。
L F社は、請求人の要請に基づき、次表のとおり委託証拠金の返還又は帳尻金の支払をしていること。
(単位 円)
返還又は支払年月日 金額 グループ 種 類 返還又は支払方法
平成4年11月 4日 11,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 1月21日 2,367,983 通産 証拠金 現金支払
平成5年 1月21日 2,834,672 通産 帳尻金 現金支払
平成5年 1月21日 797,345 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 1月26日 6,000,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 3月10日 200,000 通産 証拠金 現金支払
平成5年 3月10日 1,300,000 農水 証拠金 現金支払
平成5年 7月 9日 600,000 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 8月 3日 578,993 農水 帳尻金 現金支払
平成5年 8月17日 250,000 農水 証拠金 現金支払
平成5年 9月 2日 377,843 農水 帳尻金 口座振込
平成5年12月 2日 3,000,000 農水 帳尻金 現金支払
M 請求人は、上記Lの表の現金で受領した金員について、署名押印した領収証をF社に差し入れていること。
N 上記Lの表の口座振込の方法で支払われた金員は、X銀行Y支店の請求人名義の普通預金(口座番号△△△)へ振り込まれていること。
ロ 上記イの事実について検討したところ、次のとおりである。
(イ)上記イの各事実から判断すると、請求人は、商品先物取引を始めるに当たり、昭和61年2月20日にF社に対して商品先物取引の委託をしていることが認められ、その際、請求人は、商品先物取引が投機的な性格が強い取引であることを十分認識し、理解して取引を行うようにとの主旨から、商品取引所法第94条の2で商品取引の委託者に交付が義務付けられた「商品先物取引委託のしおり」等の書面の交付を受けるとともに、先物取引の危険性を了知した上で取引することを承諾する旨の「承諾書」をF社に差し入れるなどしており、請求人においては、先物取引の危険性及び先物取引における注意事項や手続について十分認識した上で、自己の意思と判断の下でF社に商品先物取引を委託していたものと認められる。
(ロ)上記イの(ロ)のAないしFの事実から、請求人は、本件先物取引の個々の内容及び損益について、毎月F社から送られてくる「売買計算書」及び「貴口座現在高照合ご通知書」により随時確認できる状況にあったものと認められ、しかも、本件先物取引により利益が生じて返還可能額がある場合には、返還を求めるかどうかについて指示することができることとされており、現に請求人は、上記イの(ロ)のLのとおり帳尻金等の返還を受けていることが認められる。
また、通知された取引内容に疑義がある場合には「回答書」により、再調査の依頼ができることとされており、請求人は、平成元年4月10日現在の残高照合表について「回答書」に署名押印の上、F社に送付していることが認められる。
(ハ)上記イの(ロ)のGないしNの事実から、請求人は、本件先物取引に関して、F社から立替金や追証の請求があった都度、F社へ金員を支払っており、また、請求人は委託証拠金の返還や帳尻金の支払をF社に請求し、その都度F社から金員を受領していることが認められる。
ハ 以上のことから、請求人は、自己の意思と判断の下にF社に委託して本件先物取引を行い、本件先物取引から生じる所得を得ていたものと認められるから、原処分庁が、本件先物取引から生じた所得を請求人に帰属するものと認定したことに誤りは認められない。
なお、請求人は、先物取引を開始するに際して承諾書にサインするのは形式的なことであり、そのことをもって取引内容を了知したとするのは経験則に反する旨主張するが、本件先物取引については、承諾書にサインがあるという事実だけではなく、上述のとおり、上記イの各事実を上記ロで検討し取引内容を了知したものと認められたものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ニ 請求人は、本件先物取引は違法性を帯び、無効あるいは取り消し得る取引であるから、このような取引を課税要件の基礎としたことは誤りである旨主張する。
しかしながら、上記ハのとおり、本件先物取引は請求人がF社に委託して行った取引であり、平成4年分及び平成5年分において、本件先物取引から所得が生じており、しかも、請求人はその利益を受領したり、委託証拠金に充当するなど享受していることが明らかであるから、請求人には課税要件事実が満たされているということができる。
また、本件更正処分が行われた時点において、本件先物取引が違法又は無効なものとして、その経済的成果が失われたという証拠も認められず、しかも、本件先物取引に関して、取り消すことのできる行為が取り消されたという事実も認められないことから、原処分庁が課税処分時の本件先物取引に係る法的状態に基づいて課税をすることに違法は認められない。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ホ なお、請求人は、F社との間で和解が成立したことが、F社がいかに違法な取引をしたかの証左である旨主張するが、平成6年5月31日付のF社との和解書には、和解金2,000,000円の支払、請求人が預託している委託証拠金の返還及び和解後における請求人とF社との間の権利義務関係に関する確認など5項目について記載してあるのみで、本件先物取引に関し和解金が支払われることとなった具体的な法的評価等については何ら記載されておらず、本件和解が各年分の課税関係に変動を生じさせるものとは認められない。
したがって、本件和解によって上記ニの判断が左右されるものではない。
ヘ 請求人は、本件損害賠償請求訴訟の判決を待って最終的な更正処分がなされるべきである旨主張する。
上記ハ及びニで述べたとおり、本件先物取引は請求人の意思と判断の下で行ったものであり、また、後記チで述べるとおり、請求人には本件先物取引による所得が生じていることから、課税適状にあるというべきである。
ところで、通則法第24《更正》においては、税務署長は、「納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他課税標準等又は税額等が調査したところと異なるときは、その調査により、納税申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する」こととされている。
そして、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項で、期限内申告書に係る国税の増額更正については「更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない」と規定されており、更正処分ができる期間についての制限が設けられている。
したがって、税務署長が調査により納税者の申告した課税標準等に誤りを発見し、課税適状にある場合においては、法定申告期限から3年間はいつでも更正処分をすることができることとされているが、仮に、請求人の主張するように課税要件事実に争いがあることをもって、訴訟等によりその争いが解決された時点で課税をすべきであるとすると、争いの解決が長期化し、法定申告期限から3年を経過した日以後に解決することとなるような場合には、同条項により更正処分ができないこととなり、国は適正な賦課権の行使ができなくなる。
このようなことは、租税負担の公平の見地から容認することはできないというべきである。
また、上記のように課税要件事実に関する争いがある段階で更正処分がされ、後に、課税要件事実に関する争いが解決した場合において、先の更正処分の基礎とされた課税要件事実の全部又は一部が取り消されることになり、税額等が減少することとなった場合には、通則法第23条第2項第1号の規定により、判決等により先の更正処分の基礎とされたところと異なる事実が確定した日の翌日から起算して2月以内に、税務署長に対して更正の請求をすることにより、その是正を求めることができることとされているから、課税時期の法的状態に基づいて課税をしたとしても納税者に不当な課税を強いる結果となるものではない。
以上のとおり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ト 請求人は、請求人が形式的に承諾したことをもって本件先物取引の内容を了知していたとすることは経験則に反することである旨主張する。
しかしながら、上記ロで述べたとおり、請求人は、昭和61年2月から自己の意思と判断の下で商品先物取引を繰り返し行って、損失が生じて金員の支払が必要な場合はその都度金員を支払い、利益が生じた場合はその利益を享受しており、本件先物取引の内容について十分了知していたと認められることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
チ 総所得金額
(イ)給与所得の金額
原処分庁は請求人の各年分の給与所得の金額は、請求人が確定申告書に記載した金額で、平成4年分10,945,000円及び平成5年分10,945,000円と認定しているところ、当審判所の調査によっても原処分庁の認定額は相当と認められる。
(ロ)雑所得の金額
A 商品先物取引に係る雑所得の金額
(A)請求人が行った本件先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、 次表のとおりである。
(図表2)
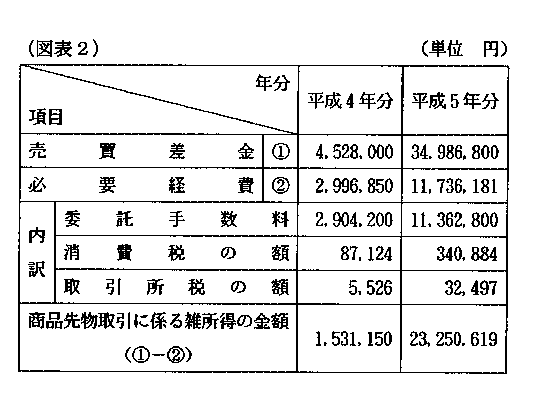
(B)請求人がH社に委託して行った商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、次表のとおりである。
(図表3)
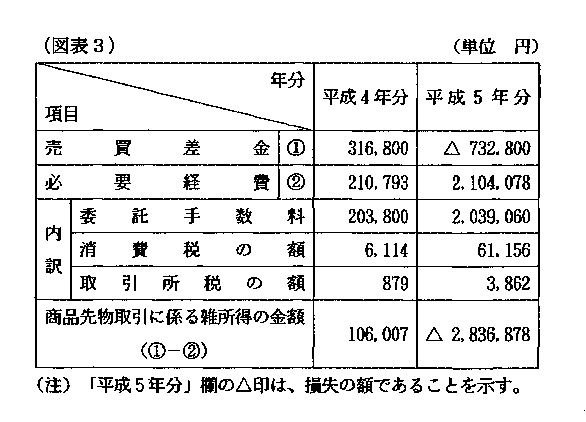
(C)請求人の商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は、上記(A)と(B)の金額の合計額で、平成4年分1,637,157円及び平成5年分20,413,741円となり、これらの金額は原処分の金額と同額であるから、原処分庁が認定した商品先物取引に係る各年分の雑所得の金額は相当と認められる。
B 有価証券オプション取引に係る雑所得の金額
原処分庁は、請求人がN証券に委託して行った平成5年分の有価証券オプション取引による雑所得の金額は、1,250,140円の損失であると認定しているところ、当審判所の調査によっても原処分庁の認定額は相当と認められる。
C雑所得の金額
請求人の各年分の雑所得の金額は、上記Aの商品先物取引に係る雑所得の金額から上記Bの有価証券オプション取引に係る雑所得の損失額を控除した金額であり、平成4年分1,637,157円及び平成5年分19,163,601円となる。
(ハ)総所得金額
請求人の各年分の総所得金額は、上記(イ)の給与所得の金額と上記(ロ)の雑所得の金額の合計額で平成4年分12,582,157円及び平成5年分30,108,601円となり、これらの金額は原処分の金額と同額又は上回るから、本件更正処分は、適法である。
(2)過少申告加算税の賦課決定処分について
以上のとおり、本件更正処分は適法であり、また、本件更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づいてした過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(3)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。
別表1
平成4年分 農水グループ
(単位 円)
日付 売買差金
4月 9日 750,000
4月15日 166,400
5月14日 675,000
5月21日 75,000
6月24日 △168,000
6月24日 △30,000
7月 7日 △261,000
7月 7日 △130,000
7月 8日 △110,000
7月15日 △329,000
7月17日 △377,000
12月16日 71,200
12月16日 △61,600
合計 271,000
(注)△印は、売買差金が損失であることを示す。以下同じ。
別表2
平成4年分 通産グループ
(単位 円)
日付 売買差金
3月12日 △22,000
4月21日 80,000
7月17日 △796,000
8月17日 △212,500
8月27日 △402,500
11月10日 52,500
12月24日 5,557,500
合計 4,257,000
別表3
平成5年分 農水グループ
(単位 円)
日付 売買差金 日付 売買差金
1月14日 576,000 9月29日 △608,000
1月19日 600,000 10月 6日 △192,000
3月12日 150,000 10月 8日 △364,000
3月12日 275,000 10月27日 584,000
3月17日 △240,000 10月29日 100,000
4月28日 520,000 11月 8日 216,000
4月28日 △40,000 11月 8日 624,000
4月30日 650,000 11月10日 1,456,000
4月30日 △180,000 11月16日 3,080,000
5月18日 470,000 11月16日 688,000
5月18日 260,000 11月17日 △840,000
5月26日 520,000 11月17日 △744,000
6月15日 80,000 11月18日 △936,000
6月28日 150,000 11月22日 2,720,000
7月 5日 525,000 11月22日 2,600,000
7月 6日 400,000 12月 2日 3,120,000
7月28日 56,000 12月 6日 △123,200
7月29日 185,600 12月 7日 △81,600
8月10日 3,680,000 12月 7日 1,320,000
8月10日 △3,072,000 12月 8日 960,000
8月13日 △480,000 12月 8日 1,880,000
8月18日 1,184,000 12月13日 △112,000
8月18日 △796,000 12月13日 1,640,000
8月24日 120,000 12月14日 440,000
9月 6日 240,000 12月16日 400,000
9月10日 436,000 12月20日 3,120,000
9月10日 △48,000 12月20日 532,000
9月10日 △410,000 12月20日 2,200,000
9月14日 100,000 12月22日 5,040,000
9月17日 92,000 12月24日 △3,192,000
9月20日 76,000 12月30日 1,760,000
9月20日 △76,000 12月30日 1,240,000
9月28日 △92,000 小計 28,527,200
9月29日 1,240,000 合計 35,678,800
小計 7,151,600
別表4
平成5年分 通産グループ
(単位 円)
日 付 売買差金
3月22日 192,000
3月22日 62,000
3月31日 △426,000
4月28日 △408,000
4月28日 △48,000
4月28日 △64,000
合 計 △692,000
別表5
平成6年分 農水グループ
(単位 円)
日 付 売買差金
1月 4日 △2,280,000
1月25日 1,120,000
1月31日 △960,000
1月31日 △1,440,000
1月31日 △864,000
2月 1日 △5,880,000
2月 4日 △2,880,000
2月 7日 △6,520,000
2月10日 △8,480,000
合 計 △28,184,000
(図表6)
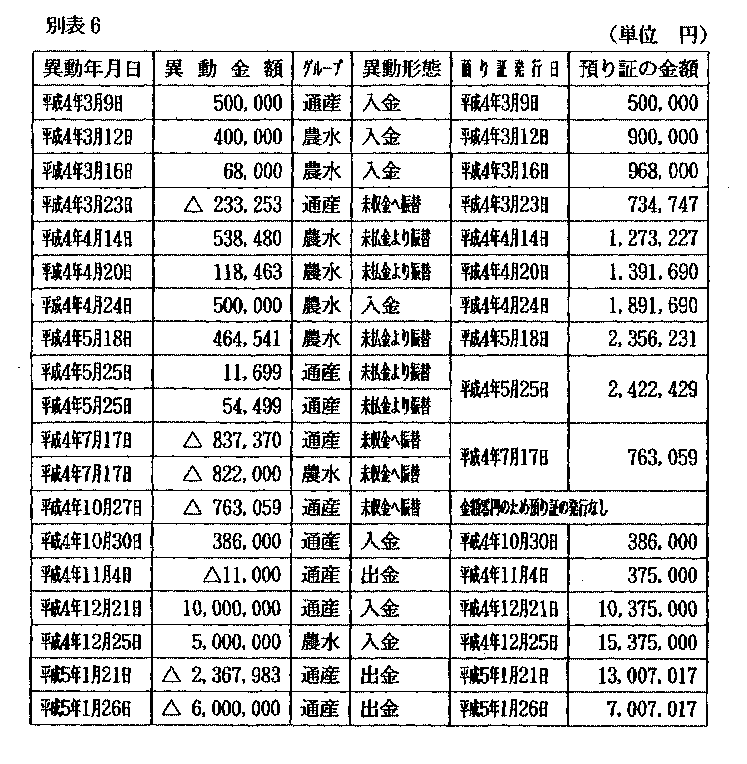
(図表6)(続き)1
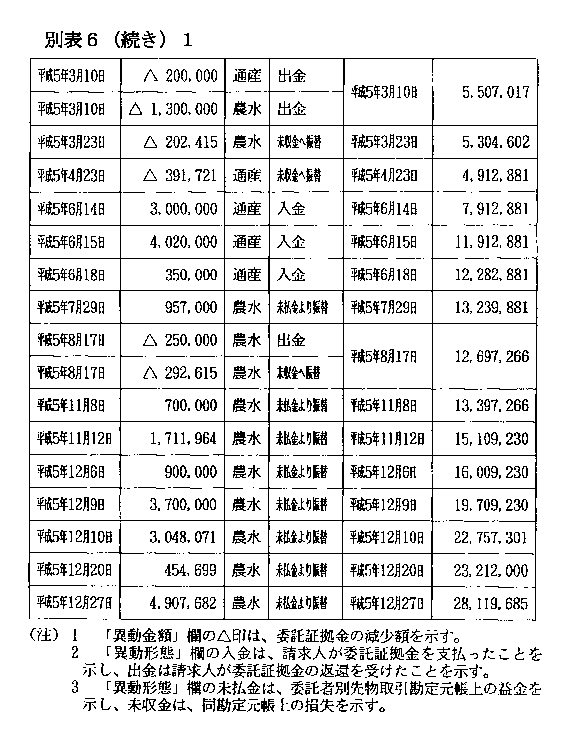
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















