税務ニュース2003年12月08日 公的年金等控除・老年者控除の縮減などを明記 ニュース特集 政府税調・平成16年度の税制改正に関する中間報告を公表
ニュース特集
公的年金等控除・老年者控除の縮減などを明記
どうなる!?来年の税制改正
政府税調・平成16年度の税制改正に関する中間報告を公表
政府税制調査会(会長:石弘光一橋大学学長)は11月27日、「平成16年度の税制改正に関する中間報告」(以下:中間報告)をとりまとめ、公表しました。今回の中間報告は、例年における答申に該当するものですが、答申の起草段階(11月21日)において、小泉純一郎首相から「16年度の税源移譲についても、国庫補助負担金の改革と併せて検討すること」が指示されたため、これまでの議論を中間報告としてまとめることになったもの。今回の特集では、この中間報告の概要についてご紹介します。なお、政府税制調査会では、引き続き「平成16年度の税源移譲」について検討を行い、「平成16年度の税制改正に関する答申」として、12月中旬に取りまとめを行う予定です。
中間報告の原文はこちら⇒http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/151127a.pdf
中間報告の概要
今回の中間報告での個別税目の改正についての要約は以下の通り。順次、主だった点についてみていきます。ただ、実際には、これらをベースに自民党税制調査会で検討されますので、最終的には自民党(与党)税制改正大綱のとりまとめを待つ必要があります。
なお、中間報告に盛り込まれなかった意見としては、個人所得税の定率減税廃止などの他、消費税率の引き上げは、小泉首相が任期中の税率引上げを否定しているため、来年度の課題にはされていません。
公的年金等控除と老年者控除の縮減
今回注目すべき点として挙げられるのは公的年金等控除と老年者控除の縮減です。低所得者に配慮しつつも、高齢者に対して経済力に応じた負担を求めるということです。
公的年金等控除について、現行制度では、65歳以上であれば、最低140万円までの場合は非課税となっています(65歳未満は最低70万円まで非課税)。 また、老年者控除とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の人を対象に、所得税の計算に当り、所得控除として50万円を控除できるというものです。1,000万円という所得要件を見直すのか、又は控除額を半分にするといった案があるようです。
ただ、これら二つの制度の縮減を同時に行うことは難しいとされている他、来年は、参議院選挙を控えていることもあり、実際にどの程度縮減されるかは、現時点では不透明な状況です。
住宅ローン減税の縮減
現行の住宅ローン減税制度では、最大で500万円までの減税が今年末で期限切れとなります。また、平成16年度税制改正において、何らかの手当てがなされないとすると、平成16年入居者分については、最大で150万円の控除となります。この最大150万円の控除制度自体も法律上では、来年でなくなってしまいます。
最大控除額は300万円~400万円?
中間報告では、現行制度を継続すれば、1兆円程度の減収が見込まれるとして、景気情勢に配慮しつつ、同制度の縮減を打ち出しています。最大控除額は300万円から400万円程度になる案が有力のようです。しかし、自民党内においては住宅ローン減税の縮減に慎重な意見も強いようです。このため、延長期間や控除額は自民党税制調査会で決定されることになります。
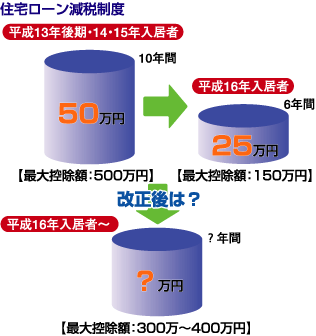
個人住民税の均等割の見直し
個人住民税の均等割の税率については、低い水準にとどまっていることから、人口段階に応じた税率区分の廃止とともに税率を引き上げる必要があるとしています。
現在、市長村民税均等割については、人口に応じて2,000円から3,000円とされていますが、これを統一し、都道府県民税1,000円と合わせて均等割は4,000円から5,000円になりそうな状況です。
また、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻については、現在、非課税とされていますが、この措置を撤廃すると明記されています。
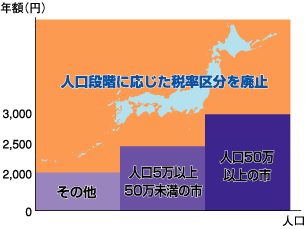
不良債権処理に係る税制面の対応
中間報告では不良債権処理に関する税制面の対応(いわゆる金融3点セット)について、言及しています。このうち、無税償却基準の見直しと欠損金の繰越期間の延長については実現の見込みです。欠損金の繰越期間の延長については、慎重に検討すべきとしていますが、実際には新規分で7年という案が浮上しています。
ただ、金融庁などが要望していた16年間の欠損金の繰戻還付については、実質的に金融機関への公的資金の供与には他ならず、課税の公平性を著しく欠くものとして却下されています。
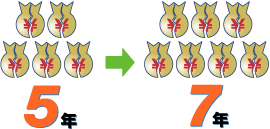
その他
その他の項目をみると、まず、連結納税制度における連結付加税については、厳しい財政状況に鑑み平成14年度から2年間の時限措置として講じられたものであるため、基本的には廃止すべきであると、当初予定通りの撤廃の方針が明確にされています。 また、先日、新しい日米租税条約が署名されたことにより、これに伴う国内法令の見直しを速やかに行うべきであるとしています。中間報告では、今回の新条約を、わが国の租税条約交渉のモデルとすべきものと位置付けています。
公的年金等控除・老年者控除の縮減などを明記
どうなる!?来年の税制改正
政府税調・平成16年度の税制改正に関する中間報告を公表
政府税制調査会(会長:石弘光一橋大学学長)は11月27日、「平成16年度の税制改正に関する中間報告」(以下:中間報告)をとりまとめ、公表しました。今回の中間報告は、例年における答申に該当するものですが、答申の起草段階(11月21日)において、小泉純一郎首相から「16年度の税源移譲についても、国庫補助負担金の改革と併せて検討すること」が指示されたため、これまでの議論を中間報告としてまとめることになったもの。今回の特集では、この中間報告の概要についてご紹介します。なお、政府税制調査会では、引き続き「平成16年度の税源移譲」について検討を行い、「平成16年度の税制改正に関する答申」として、12月中旬に取りまとめを行う予定です。
中間報告の原文はこちら⇒http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/151127a.pdf
中間報告の概要
今回の中間報告での個別税目の改正についての要約は以下の通り。順次、主だった点についてみていきます。ただ、実際には、これらをベースに自民党税制調査会で検討されますので、最終的には自民党(与党)税制改正大綱のとりまとめを待つ必要があります。
なお、中間報告に盛り込まれなかった意見としては、個人所得税の定率減税廃止などの他、消費税率の引き上げは、小泉首相が任期中の税率引上げを否定しているため、来年度の課題にはされていません。
| 中間報告のポイント ○公的年金等控除、老年者控除の縮減を図るべきである。 ○住宅ローン減税については、景気情勢に配慮しつつ、縮減すべきである。 ○個人住民税均等割について、生計同一の妻に対する非課税措置の廃止、税率の引き上げ及び人口段階に応じた税率区分の廃止を行うべきである。 ○不良債権処理に係る税制面の対応は、以下の考え方に沿って、具対化を図るべきである。 ・無税償却基準は、金融機関に与える影響を見極め、企業会計との差異が小さくなるよう見直しの具体化を図るべきである。 ・16年間分の繰戻還付は、実質的に金融機関への公的資金の供与にほかならず、課税の公平性を著しく欠くものであり、到底とりえない。 ・繰越期間の延長は、産業構造の改革や不良債権処理の加速という政策課題に真に有効な措置となるかどうか、慎重に検討すべきである。 ○連結付加税については、基本的には廃止すべきである。 ○新たな日米租税条約を実施する環境整備のため、国内法令を速やかに見直すべきである。 |
公的年金等控除と老年者控除の縮減
今回注目すべき点として挙げられるのは公的年金等控除と老年者控除の縮減です。低所得者に配慮しつつも、高齢者に対して経済力に応じた負担を求めるということです。
公的年金等控除について、現行制度では、65歳以上であれば、最低140万円までの場合は非課税となっています(65歳未満は最低70万円まで非課税)。 また、老年者控除とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の人を対象に、所得税の計算に当り、所得控除として50万円を控除できるというものです。1,000万円という所得要件を見直すのか、又は控除額を半分にするといった案があるようです。
ただ、これら二つの制度の縮減を同時に行うことは難しいとされている他、来年は、参議院選挙を控えていることもあり、実際にどの程度縮減されるかは、現時点では不透明な状況です。
現行の公的年金等に係る雑所得の速算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン減税の縮減
現行の住宅ローン減税制度では、最大で500万円までの減税が今年末で期限切れとなります。また、平成16年度税制改正において、何らかの手当てがなされないとすると、平成16年入居者分については、最大で150万円の控除となります。この最大150万円の控除制度自体も法律上では、来年でなくなってしまいます。
最大控除額は300万円~400万円?
中間報告では、現行制度を継続すれば、1兆円程度の減収が見込まれるとして、景気情勢に配慮しつつ、同制度の縮減を打ち出しています。最大控除額は300万円から400万円程度になる案が有力のようです。しかし、自民党内においては住宅ローン減税の縮減に慎重な意見も強いようです。このため、延長期間や控除額は自民党税制調査会で決定されることになります。
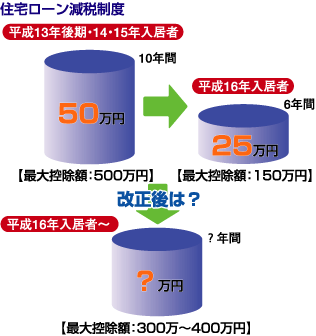
個人住民税の均等割の見直し
個人住民税の均等割の税率については、低い水準にとどまっていることから、人口段階に応じた税率区分の廃止とともに税率を引き上げる必要があるとしています。
現在、市長村民税均等割については、人口に応じて2,000円から3,000円とされていますが、これを統一し、都道府県民税1,000円と合わせて均等割は4,000円から5,000円になりそうな状況です。
また、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻については、現在、非課税とされていますが、この措置を撤廃すると明記されています。
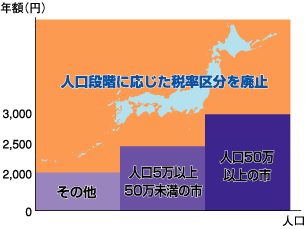
不良債権処理に係る税制面の対応
中間報告では不良債権処理に関する税制面の対応(いわゆる金融3点セット)について、言及しています。このうち、無税償却基準の見直しと欠損金の繰越期間の延長については実現の見込みです。欠損金の繰越期間の延長については、慎重に検討すべきとしていますが、実際には新規分で7年という案が浮上しています。
ただ、金融庁などが要望していた16年間の欠損金の繰戻還付については、実質的に金融機関への公的資金の供与には他ならず、課税の公平性を著しく欠くものとして却下されています。
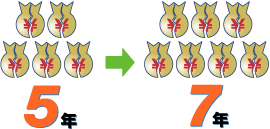
その他
その他の項目をみると、まず、連結納税制度における連結付加税については、厳しい財政状況に鑑み平成14年度から2年間の時限措置として講じられたものであるため、基本的には廃止すべきであると、当初予定通りの撤廃の方針が明確にされています。 また、先日、新しい日米租税条約が署名されたことにより、これに伴う国内法令の見直しを速やかに行うべきであるとしています。中間報告では、今回の新条約を、わが国の租税条約交渉のモデルとすべきものと位置付けています。
| 自民党税制調査会の幹部決定 |
| 自民党の税制調査会は11月28日に総会を開催。税調幹部を正式決定し、本格議論をスタートさせました。会長には津島雄二議員が就任しています。自民党税制調査会でも12月16日を目処に税制改正大綱をまとめる予定です。ただ、税源移譲の問題の他、従来のインナーと呼ばれるで幹部会が廃止されたこともあり、今後の自民党税制調査会の決定方法も現段階では不透明な状況です。 【自民党税制調査会幹部】 [会長]津島雄二 [最高顧問]山中貞則 [顧問]武藤嘉文、片山虎之助、柳澤伯夫 [小委員長]町村信孝 [副会長]甘利明、伊吹文明、尾身幸次、亀井久興、高村正彦、自見庄三郎、丹羽雄哉、野田毅、野呂田芳成、村井仁、谷津義男、与謝野馨、久世公堯、陣内孝雄、保坂三蔵 [幹事]塩崎恭久、滝実、宮路和明、林芳正(敬称略) |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















