解説記事2003年10月20日 【解説】 退職給付会計の概要(2003年10月20日号・№039)
解説
退職給付会計の概要
株式会社ビジネストラスト
吉木伸彦
野田茂樹
1. 序章
1) 背景
平成12年4月1日以降に開始する事業年度から「退職給付に係る会計基準」が適用されています。以前は退職給与引当金の計上として、「期末自己都合要支給額(期末に全社員が自己都合で退職した場合に支給される退職金額)」に基づき引当金として計上していましたが、国際的には将来の退職金給付額に、給付する確率と現在価値計算を加味して退職給付債務(Projected Benefit Obligation 一般的には「PBO」と呼ばれている)を計算し、退職金給付用に積み立てられた年金資産との差額で退職給付引当金を計上する形に変わっています。
この退職給付会計は以前の退職給与引当金の計上とは異なり、将来予測をしなければならないという点で若干複雑な計算を必要とします。ここでは会計処理の概要と退職給付債務の計算について解説します。
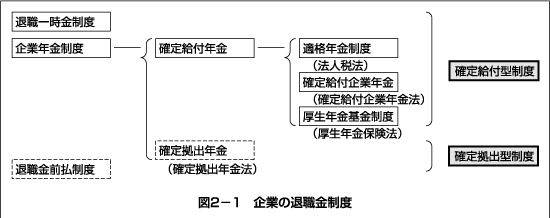
2. 退職金制度
1) 企業の退職金制度
退職金は本来、従業員が退職した場合に労働契約や就業規則等の規程に基づいて企業または企業より退職金管理を委託された生命保険会社や信託銀行等の受託機関から支払われるものです。
退職金制度は、退職時に一時金として給付される退職一時金制度のほか、一定期間にわたって分割給付される企業年金制度などがあり、退職給付会計の観点からは図2-1のように分類されます。
確定給付型制度は従来から退職金制度として用いられてきた制度であり、従業員は資産の運用結果にかかわらず規程や規約に定められた額を受け取ることができ、運用リスクは企業が負います。この制度には、社内積立型の制度として退職一時金制度や社内年金制度、社外積立型として外部に運営管理を委託している適格退職年金制度や厚生年金基金制度などがあります。
一方、確定拠出型制度は確定拠出型年金法案が平成13年6月に制定されています。この確定拠出型制度は定められた額を毎期企業から従業員に拠出し、その後の運用リスクは従業員が負います。この制度は拠出時に企業の年金の給付義務が履行され企業に対して財務的な影響を及ぼさないため、近年多くの企業で採用されてきています。
2) 退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員の退職時に労働契約や就業規則等に基づいて一時金として退職金を給付する制度であり、企業は従業員の退職に備えて財源を社内に積立てておかなければなりません。従来は、退職時の給与と勤続年数に比例して退職金が支給される支給倍率型の退職金制度が多く用いられてきましたが、最近では業績主義に沿った人事制度への見直しが行われ職能や考課などをポイントとして反映させていくポイント型退職金制度へ変わってきています。
3) 適格退職年金制度
適格年金制度は事業主である企業が運用管理を行う幹事会社に一定の契約に従って掛金を拠出し、幹事会社ではその掛金を運用し、その資産をもとに退職者に一時金や年金を給付する制度であり、図2-2のような形で運営されます。この適格退職年金制度は税務上も拠出額を損金経理できるなどのメリットがあります。
しかし、この適格退職年金制度は平成24年3月までに廃止されることが決定しており、今後は他の制度への移行が行われるものと思われます。
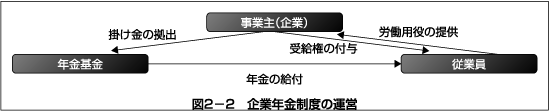
4) 厚生年金基金制度
厚生年金基金制度は国で行っている厚生年金の一部を運営し、さらに独自の上乗せ部分を含めて年金として退職者に給付する制度です。これは図2-3のような形の制度になります。この制度は比較的大規模な企業で運営される単独型基金、企業グループで運営される連合型基金、同種の企業が集まって共同運営される総合型基金があります。以前の運用状況が良い時代には資産を独自運用する形で行われていましたが、近年の運用利回りの低下に伴い、国の代行部分を国に返上するケースも見受けられます。
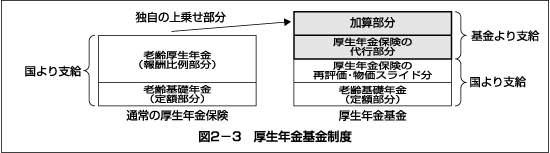
3. 退職給付会計の概要
1) 退職給付引当金の計算
退職給付引当金は次の3つの段階を経て計算されます。
Part1: 退職給付債務を計算する。
Part2: 年金資産を公正評価する。
Part3: 退職給付債務から年金資産を差し
引いて退職給付引当金を求める。
《Part1:退職給付債務を計算する。》
まず、その企業が負うべき退職給付債務の計算が必要になります。退職給付債務の計算方法については後述しますが、その計算方法は煩雑な処理になります。退職給付会計の導入当初はその計算の煩雑さから退職給付債務の計算を生命保険会社や信託銀行、債務計算コンサルティング会社などに委託するケースが多く見受けられていました。しかし、情報開示の早期化や中期経営計画の資料として、計算コストの軽減化のため計算ソフトを購入し自社内で退職給付債務を計算する形に移り変わってきています。
《Part2:年金資産を公正評価する。》
企業年金制度を採用している場合、退職給付引当金は退職給付債務から年金資産を差し引いて算出するため、期末日時点の年金資産を確定させる必要があります。年金資産とは企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている資産のことをいいます。
年金資産とされたものは、期末時点で公正な評価額により測定されます。ここで、公正な評価額とは、十分な知識と情報を得ている者同士が自発的に取引を行う場合に成立する価格のことをいいます。公正な評価額は、取引を行う市場が十分に発達しているのであれば時価で計上します。実務上は各運用先に期末時点の年金資産の評価額を問い合わせ、資産運用報告書をもとに計上していきます。
《Part3:退職給付引当金を求める。》
退職給付引当金は図3-1のように期末時点の退職給付債務(PBO)から期末時点の年金資産を差し引いて求められます。ただし、会計上一定の要件を満たす未認識差異については退職給付引当金の計上の際に調整を行います。
退職給付引当金=退職給付債務(PBO)
-年金資産-未認識数理計算上の差異
-未認識過去勤務債務
-未認識会計基準変更時差異
①未認識数理計算上の差異
退職給付会計では退職給付債務の計算において昇給率、退職率、死亡率などの確率計算の要素を用いて行っています。また、退職給付費用の算定において、年金資産の運用による期待運用収益を過去の運用結果をもとに予定計上していきます。それらの確率計算による予定と実績の差額から生ずる差異と年金資産の運用予測と実績の差額から生ずる差異は、退職給付会計上は数理計算上の差異といいます。数理計算上の差異は一旦、未認識数理計算上の差異としてオフバランスで処理し、一定期間にわたって費用として処理することができます。この未認識数理計算上の差異は平均残存勤務期間以内の一定の期間で費用化し、退職給付費用に振り替えていくことになります。
②未認識過去勤務債務
過去勤務債務とは、企業の退職金規程を変更した場合に生ずる変更前の退職給付債務と変更後の退職給付債務との差額になります。退職給付会計上はその差額を未認識過去勤務債務としてオフバランスで処理することができます。この未認識過去勤務債務も未認識数理計算上の差異と同様に一定期間にわたって費用処理を行っていきます。
③未認識会計基準変更時差異
この退職給付会計は平成12年4月から始まる年度から適用されましたが、以前の退職給与引当金とは計算方法が変更され、多くの企業で引当金の積み立て不足が発生しました。そのため、経過的に退職給付会計導入による退職給与引当金と退職給付債務との差額を会計基準変更時差異として計上する形になっております。この会計基準変更時差異は一旦、未認識会計基準変更時差異としてオフバランスとしておき、15年以内の一定期間にわたって費用処理を行っていきます。
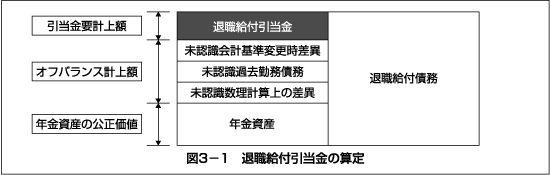
2) 退職給付費用の計算
退職給付費用は様々な要素から成り立ちますが、その内訳は勤務費用、利息費用、期待運用収益等で構成されます。退職給付費用は次のような算式から求められます。
退職給付費用=勤務費用+利息費用
-期待運用収益
+数理計算上の差異の費用処理額
+過去勤務債務の費用処理額
+会計基準変更時差異の費用処理額
①勤務費用
勤務費用は、一定の労働の対価として当期に発生すると認められる費用のことです。
これは退職給付債務と同様、割引計算によって算定されます。
②利息費用
退職給付債務の算定では割引計算を行っています。そのため、期首における退職給付債務と期末における退職給付債務では1年間の割引計算の差額が発生します。これは時の経過に応じて生じた計算上の利息であることから、利息費用と呼ばれています。利息費用は期首の退職給付債務に割引率を乗じて求めることができます。
③期待運用収益
年金資産は当期中に運用により運用収益を得ることができます。退職給付費用の算定上は過去の運用実績に基づいて当期中の運用予定収益額を期待運用収益としてその期の費用から控除することになります。
④数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異の費用処理額
数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異は1)の退職給付引当金の算定上オフバランスとされているものを定額法または定率法により一定の期間で費用として計上していきます。
3) 差異の費用処理
退職給付会計では退職給付債務と年金資産の差額のうち、数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異についてはオフバランスとして退職給付引当金を計上しないことができます。数理計算上の差異、過去勤務債務は平均残存勤務期間を算定し、その期間以内の年数で定率法または定額法により、発生年度ごとに退職給付費用に含めて計上していきます。会計基準変更時差異については15年以内の一定の期間にわたり、毎期均等額を退職給付費用に含めて計算していきます。
4. 退職給付債務の計算
退職給付会計の実務上最も複雑な部分がこの退職給付債務の計算になります。この退職給付債務は対象者数が300名以上となる企業では必ず昇給率や退職率などの確率計算を反映させる原則法という方法により計上しなければなりません。300名未満の企業については、期末自己都合要支給額をもとに計算する簡便法という計算方法によって計上することも認められております。
1) 原則法による退職給付債務の計算
退職給付債務は、退職給付を従業員の労働の対価の後払いと考えて、将来の退職給付を企業の負担として捉えたものです。具体的には
①「退職時」に見込まれる退職給付(これを退職給付見込額といいます。)のうち、
②期末までに発生したと認められる額の、
③割引現在価値
になります。
①退職給付見込額の計算
まず、退職給付見込額については将来退職した場合に見込まれる退職給付といっても、来年退職する場合も考えられますし、数年後に退職する場合も考えられます。そのため、退職給付見込額は期末時点から定年年齢に至る各時点(予想退職時期)ごとに、その時点で退職した場合の退職給付額を算定し、その時点で退職する確率を乗じて計算します。
例えば55歳での生存退職金が10,000,000円、死亡退職金が15,000,000円、生存退職する確率が3%、死亡退職する確率が0.3%とすると、55歳の退職給付見込額は
退職給付見込額=10,000,000円×3%
+15,000,000円×0.3%=345,000円
となります。
②期末発生額の計算
次にそれぞれの退職時点までの期間のうち、当期末までに負担する分を算定します。この負担額の計算方法は勤務期間の比で算定する方法(期間定額基準)、給与支給額の比で算定する方法(給与基準)などの数種類の算定方法が認められていますが、期間定額基準が原則とされています。
期間定額基準は、①の事例の退職時の勤続年数が20年、当期末の勤続年数が10年としますと、
期末発生額=345,000円×10年/20年
=172,500円
となります。
③割引現在価値の計算
さらに、退職金は数年後または数十年後の価値になりますので、これを現在価値に換算します。当期末から退職時まで10年間、割引率を3%としますと
割引現在価値=172,500円/(1+0.03)10
=128,356円
この金額は55歳で退職する場合の退職給付債務の計算になりますが、現在の年齢から定年退職する年齢までの各年齢で同様の計算を行い、その総額が一人の社員の退職給付債務ということになります。
2) 簡便法による退職給付債務の計算
退職給付会計では昇給率や退職率などの基礎率については各企業の実績をもとに算定し、それらの基礎率を用いて退職給付債務を算定します。しかし、社員数が少ない企業については基礎率算定の母数が少なくなるため、簡便法を用いて債務計算を行うことができます。簡便法の計算方法については次の3通りの計算方法が認められています。
《退職一時金制度》
①比較指数法
退職給付会計適用初年度における退職給付債務と自己都合要支給額との比較指数を算定します。その後の年度においては期末の自己都合要支給額に比較指数を乗じて求められた金額を退職給付債務とする方法です。
②係数法
この方法は退職給付に係る期末自己都合要支給額に日本公認会計士協会より公表されている「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の中で提示されている平均残存勤務期間に対応する割引率および昇給率の各係数を乗じた額を退職給付債務とする方法です。
③要支給額法
この方法は期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法です。この方法は3通りの方法の中でも最も簡便な方法になりますが、基礎率の影響が全く反映されませんので原則法の退職給付債務と大きくかけ離れてしまう危険性があります。
《企業年金制度》
①比較指数法
退職一時金制度の①の方法と同様の計算方法になります。
退職給付会計適用初年度における退職給付債務と年金財政計算上の責任準備金との比較指数を算定し、その後の年度においては直近の年金財政計算における責任準備金にその比較指数を乗じて求められた金額を退職給付債務とする方法です。
②係数法
これは現従業員については退職一時金制度の②または③の方法を用いて退職給付債務の計算を行い、その金額に年金受給者の責任準備金を加算する方法です。
③責任準備金法
直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職給付債務とする方法です。これは退職一時金制度と同様に最も簡便的な方法になりますが、予定利率が現状の市場利率と比較して高く設定されている場合もあります。その場合には原則法による計算結果と大きくかけ離れた債務額になる可能性があります。
3) 計算基礎の設定
退職給付債務の計算には割引率や昇給率、退職率などの基礎率の設定が必要になります。この基礎率は退職給付債務の金額に大きな影響を及ぼします。
①割引率
割引率は、企業が退職給付として支給すべき将来の金額負担を現時点の価値に割り戻す際に使用する率になります。具体的には、退職給付見込額から退職給付債務や勤務費用を算定する割引計算や利息費用の計算に使用されます。この割引率を高く設定した場合には将来の給付額が高額であっても高い利率で割り引かれるため退職給付債務は小さくなります。逆に割引率を低く設定した場合には退職給付債務は高くなります。大まかには1%の割引率の低下により退職給付債務は20%程度増加するものといわれています。
「退職給付に係る会計基準」では、割引率を安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定するものとしていますが、実務上は過去5年程度の長期国債の利回りの平均をベースに割引率を設定しています。
②予定昇給率
予定昇給率は、退職給付債務の計算上将来の給与水準を推定する場合に用いられる基礎率になります。予定昇給率が高い場合には退職給付債務が高くなります。
この予定昇給率は、給与規程、平均給与の実態分布および過去の昇給実績などに基づいて、確実に見込まれるものを合理的に推定して算定することとされています。実務上は一定時点の社員の給与の年齢別平均を算定し、さらに最小自乗法などの補正をかけて算定されます。
③退職率、死亡率
退職率は各年齢で翌1年間に生存退職する率、死亡率は翌1年間に死亡退職する率になります。これらの基礎率は各年齢での退職給付額から退職給付見込額を算定する際に使用します。
退職率は一定時点以前3年間以上の退職者から各年齢の退職者割合を算定し、5点平均法などの補正をかけて算定されます。死亡率は厚生労働省から開示される国民生命表などを使用するケースが一般的です。
4) 債務計算の手段
退職給付債務の計算は確率計算や割引計算など、その計算に煩雑さを伴うため、実務では次のいずれかの方法により計算されています。
①債務計算ソフト
これは市販されている退職給付債務計算用のソフトを使用し、社内で計算する方法です。債務の計算には期末日時点の社員データと年金受給者のデータを取り込み、自社の退職金規程に合わせて設定した計算方法に従って自動計算されます。
②の委託計算に比べて計算期間が短縮されるほか、毎期の債務計算費用や予算用の債務計算費用が抑えられるメリットがあります。
②委託計算
これは、生命保険会社や信託銀行、コンサルティング会社に人事データを提出し、退職給付債務の計算結果報告書を受け取り、会計処理を行う方法です。通常は3ヶ月程度の期間が必要になるため、期末日より数ヶ月前に計算を委託し、受け取った計算結果に退職者等の債務の控除を行い、計上します。
委託先が主導して計算を行いますが、自社で計算する場合に比べて費用が高くなることや計算期間の長期化などでデメリットがあります。
5. 今後の動向
1) 適格年金の廃止
適格退職年金は、平成24年3月をもって廃止される予定になっています。そのため、現在適格退職年金制度を採用している企業は今後数年間で新たな確定給付企業年金法に基づいた年金制度に変更するか、または確定拠出型年金制度へ変更することになります。
2) 代行返上
厚生年金基金制度は本来、国の厚生年金制度の一部の資産管理と運用を代行し、独自の上乗せ部分を設定して運営しております。しかし、近年の運用状況の悪化により、企業の財務に対する影響が大きいため、厚生年金の代行部分の資産を国に返上し、資産と債務を圧縮する基金が増えてきています。
3) 割引率の見直し
近年、市場利子率の低下に伴い、割引率の見直しを求められるケースが増加してきております。先に述べたように、割引率の低下は退職給付債務の増加につながり、結果的に退職給付費用が増加します。
数年前には3.5%程度の割引率で債務計算を行う企業が多く見受けられましたが、2003年3月期では2.0~2.5%での計算が主流になってきております。今後も平均市場利率が低下することが予想されるため、その場合の退職給付債務の予測が必要になると思われます。また最近は、企業の財務に対する退職給付債務の影響を削減するため、退職金制度自体の見直しを進める企業も増えてきています。
退職給付会計の概要
株式会社ビジネストラスト
吉木伸彦
野田茂樹
1. 序章
1) 背景
平成12年4月1日以降に開始する事業年度から「退職給付に係る会計基準」が適用されています。以前は退職給与引当金の計上として、「期末自己都合要支給額(期末に全社員が自己都合で退職した場合に支給される退職金額)」に基づき引当金として計上していましたが、国際的には将来の退職金給付額に、給付する確率と現在価値計算を加味して退職給付債務(Projected Benefit Obligation 一般的には「PBO」と呼ばれている)を計算し、退職金給付用に積み立てられた年金資産との差額で退職給付引当金を計上する形に変わっています。
この退職給付会計は以前の退職給与引当金の計上とは異なり、将来予測をしなければならないという点で若干複雑な計算を必要とします。ここでは会計処理の概要と退職給付債務の計算について解説します。
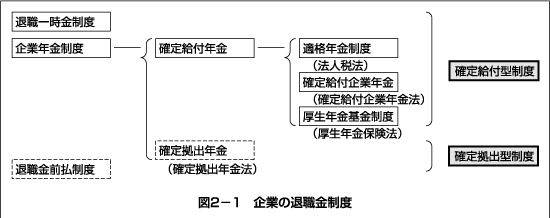
2. 退職金制度
1) 企業の退職金制度
退職金は本来、従業員が退職した場合に労働契約や就業規則等の規程に基づいて企業または企業より退職金管理を委託された生命保険会社や信託銀行等の受託機関から支払われるものです。
退職金制度は、退職時に一時金として給付される退職一時金制度のほか、一定期間にわたって分割給付される企業年金制度などがあり、退職給付会計の観点からは図2-1のように分類されます。
確定給付型制度は従来から退職金制度として用いられてきた制度であり、従業員は資産の運用結果にかかわらず規程や規約に定められた額を受け取ることができ、運用リスクは企業が負います。この制度には、社内積立型の制度として退職一時金制度や社内年金制度、社外積立型として外部に運営管理を委託している適格退職年金制度や厚生年金基金制度などがあります。
一方、確定拠出型制度は確定拠出型年金法案が平成13年6月に制定されています。この確定拠出型制度は定められた額を毎期企業から従業員に拠出し、その後の運用リスクは従業員が負います。この制度は拠出時に企業の年金の給付義務が履行され企業に対して財務的な影響を及ぼさないため、近年多くの企業で採用されてきています。
2) 退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員の退職時に労働契約や就業規則等に基づいて一時金として退職金を給付する制度であり、企業は従業員の退職に備えて財源を社内に積立てておかなければなりません。従来は、退職時の給与と勤続年数に比例して退職金が支給される支給倍率型の退職金制度が多く用いられてきましたが、最近では業績主義に沿った人事制度への見直しが行われ職能や考課などをポイントとして反映させていくポイント型退職金制度へ変わってきています。
3) 適格退職年金制度
適格年金制度は事業主である企業が運用管理を行う幹事会社に一定の契約に従って掛金を拠出し、幹事会社ではその掛金を運用し、その資産をもとに退職者に一時金や年金を給付する制度であり、図2-2のような形で運営されます。この適格退職年金制度は税務上も拠出額を損金経理できるなどのメリットがあります。
しかし、この適格退職年金制度は平成24年3月までに廃止されることが決定しており、今後は他の制度への移行が行われるものと思われます。
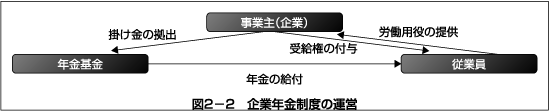
4) 厚生年金基金制度
厚生年金基金制度は国で行っている厚生年金の一部を運営し、さらに独自の上乗せ部分を含めて年金として退職者に給付する制度です。これは図2-3のような形の制度になります。この制度は比較的大規模な企業で運営される単独型基金、企業グループで運営される連合型基金、同種の企業が集まって共同運営される総合型基金があります。以前の運用状況が良い時代には資産を独自運用する形で行われていましたが、近年の運用利回りの低下に伴い、国の代行部分を国に返上するケースも見受けられます。
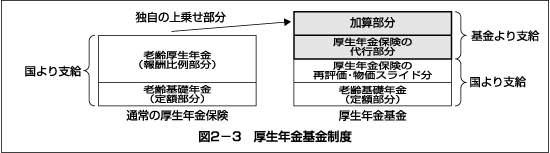
3. 退職給付会計の概要
1) 退職給付引当金の計算
退職給付引当金は次の3つの段階を経て計算されます。
Part1: 退職給付債務を計算する。
Part2: 年金資産を公正評価する。
Part3: 退職給付債務から年金資産を差し
引いて退職給付引当金を求める。
《Part1:退職給付債務を計算する。》
まず、その企業が負うべき退職給付債務の計算が必要になります。退職給付債務の計算方法については後述しますが、その計算方法は煩雑な処理になります。退職給付会計の導入当初はその計算の煩雑さから退職給付債務の計算を生命保険会社や信託銀行、債務計算コンサルティング会社などに委託するケースが多く見受けられていました。しかし、情報開示の早期化や中期経営計画の資料として、計算コストの軽減化のため計算ソフトを購入し自社内で退職給付債務を計算する形に移り変わってきています。
《Part2:年金資産を公正評価する。》
企業年金制度を採用している場合、退職給付引当金は退職給付債務から年金資産を差し引いて算出するため、期末日時点の年金資産を確定させる必要があります。年金資産とは企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている資産のことをいいます。
年金資産とされたものは、期末時点で公正な評価額により測定されます。ここで、公正な評価額とは、十分な知識と情報を得ている者同士が自発的に取引を行う場合に成立する価格のことをいいます。公正な評価額は、取引を行う市場が十分に発達しているのであれば時価で計上します。実務上は各運用先に期末時点の年金資産の評価額を問い合わせ、資産運用報告書をもとに計上していきます。
《Part3:退職給付引当金を求める。》
退職給付引当金は図3-1のように期末時点の退職給付債務(PBO)から期末時点の年金資産を差し引いて求められます。ただし、会計上一定の要件を満たす未認識差異については退職給付引当金の計上の際に調整を行います。
退職給付引当金=退職給付債務(PBO)
-年金資産-未認識数理計算上の差異
-未認識過去勤務債務
-未認識会計基準変更時差異
①未認識数理計算上の差異
退職給付会計では退職給付債務の計算において昇給率、退職率、死亡率などの確率計算の要素を用いて行っています。また、退職給付費用の算定において、年金資産の運用による期待運用収益を過去の運用結果をもとに予定計上していきます。それらの確率計算による予定と実績の差額から生ずる差異と年金資産の運用予測と実績の差額から生ずる差異は、退職給付会計上は数理計算上の差異といいます。数理計算上の差異は一旦、未認識数理計算上の差異としてオフバランスで処理し、一定期間にわたって費用として処理することができます。この未認識数理計算上の差異は平均残存勤務期間以内の一定の期間で費用化し、退職給付費用に振り替えていくことになります。
②未認識過去勤務債務
過去勤務債務とは、企業の退職金規程を変更した場合に生ずる変更前の退職給付債務と変更後の退職給付債務との差額になります。退職給付会計上はその差額を未認識過去勤務債務としてオフバランスで処理することができます。この未認識過去勤務債務も未認識数理計算上の差異と同様に一定期間にわたって費用処理を行っていきます。
③未認識会計基準変更時差異
この退職給付会計は平成12年4月から始まる年度から適用されましたが、以前の退職給与引当金とは計算方法が変更され、多くの企業で引当金の積み立て不足が発生しました。そのため、経過的に退職給付会計導入による退職給与引当金と退職給付債務との差額を会計基準変更時差異として計上する形になっております。この会計基準変更時差異は一旦、未認識会計基準変更時差異としてオフバランスとしておき、15年以内の一定期間にわたって費用処理を行っていきます。
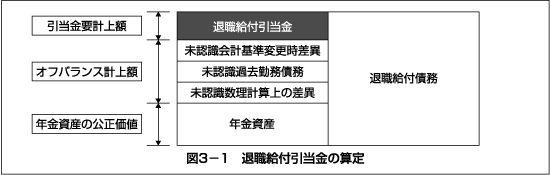
2) 退職給付費用の計算
退職給付費用は様々な要素から成り立ちますが、その内訳は勤務費用、利息費用、期待運用収益等で構成されます。退職給付費用は次のような算式から求められます。
退職給付費用=勤務費用+利息費用
-期待運用収益
+数理計算上の差異の費用処理額
+過去勤務債務の費用処理額
+会計基準変更時差異の費用処理額
①勤務費用
勤務費用は、一定の労働の対価として当期に発生すると認められる費用のことです。
これは退職給付債務と同様、割引計算によって算定されます。
②利息費用
退職給付債務の算定では割引計算を行っています。そのため、期首における退職給付債務と期末における退職給付債務では1年間の割引計算の差額が発生します。これは時の経過に応じて生じた計算上の利息であることから、利息費用と呼ばれています。利息費用は期首の退職給付債務に割引率を乗じて求めることができます。
③期待運用収益
年金資産は当期中に運用により運用収益を得ることができます。退職給付費用の算定上は過去の運用実績に基づいて当期中の運用予定収益額を期待運用収益としてその期の費用から控除することになります。
④数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異の費用処理額
数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異は1)の退職給付引当金の算定上オフバランスとされているものを定額法または定率法により一定の期間で費用として計上していきます。
3) 差異の費用処理
退職給付会計では退職給付債務と年金資産の差額のうち、数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異についてはオフバランスとして退職給付引当金を計上しないことができます。数理計算上の差異、過去勤務債務は平均残存勤務期間を算定し、その期間以内の年数で定率法または定額法により、発生年度ごとに退職給付費用に含めて計上していきます。会計基準変更時差異については15年以内の一定の期間にわたり、毎期均等額を退職給付費用に含めて計算していきます。
4. 退職給付債務の計算
退職給付会計の実務上最も複雑な部分がこの退職給付債務の計算になります。この退職給付債務は対象者数が300名以上となる企業では必ず昇給率や退職率などの確率計算を反映させる原則法という方法により計上しなければなりません。300名未満の企業については、期末自己都合要支給額をもとに計算する簡便法という計算方法によって計上することも認められております。
1) 原則法による退職給付債務の計算
退職給付債務は、退職給付を従業員の労働の対価の後払いと考えて、将来の退職給付を企業の負担として捉えたものです。具体的には
①「退職時」に見込まれる退職給付(これを退職給付見込額といいます。)のうち、
②期末までに発生したと認められる額の、
③割引現在価値
になります。
①退職給付見込額の計算
まず、退職給付見込額については将来退職した場合に見込まれる退職給付といっても、来年退職する場合も考えられますし、数年後に退職する場合も考えられます。そのため、退職給付見込額は期末時点から定年年齢に至る各時点(予想退職時期)ごとに、その時点で退職した場合の退職給付額を算定し、その時点で退職する確率を乗じて計算します。
例えば55歳での生存退職金が10,000,000円、死亡退職金が15,000,000円、生存退職する確率が3%、死亡退職する確率が0.3%とすると、55歳の退職給付見込額は
退職給付見込額=10,000,000円×3%
+15,000,000円×0.3%=345,000円
となります。
②期末発生額の計算
次にそれぞれの退職時点までの期間のうち、当期末までに負担する分を算定します。この負担額の計算方法は勤務期間の比で算定する方法(期間定額基準)、給与支給額の比で算定する方法(給与基準)などの数種類の算定方法が認められていますが、期間定額基準が原則とされています。
期間定額基準は、①の事例の退職時の勤続年数が20年、当期末の勤続年数が10年としますと、
期末発生額=345,000円×10年/20年
=172,500円
となります。
③割引現在価値の計算
さらに、退職金は数年後または数十年後の価値になりますので、これを現在価値に換算します。当期末から退職時まで10年間、割引率を3%としますと
割引現在価値=172,500円/(1+0.03)10
=128,356円
この金額は55歳で退職する場合の退職給付債務の計算になりますが、現在の年齢から定年退職する年齢までの各年齢で同様の計算を行い、その総額が一人の社員の退職給付債務ということになります。
2) 簡便法による退職給付債務の計算
退職給付会計では昇給率や退職率などの基礎率については各企業の実績をもとに算定し、それらの基礎率を用いて退職給付債務を算定します。しかし、社員数が少ない企業については基礎率算定の母数が少なくなるため、簡便法を用いて債務計算を行うことができます。簡便法の計算方法については次の3通りの計算方法が認められています。
《退職一時金制度》
①比較指数法
退職給付会計適用初年度における退職給付債務と自己都合要支給額との比較指数を算定します。その後の年度においては期末の自己都合要支給額に比較指数を乗じて求められた金額を退職給付債務とする方法です。
②係数法
この方法は退職給付に係る期末自己都合要支給額に日本公認会計士協会より公表されている「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の中で提示されている平均残存勤務期間に対応する割引率および昇給率の各係数を乗じた額を退職給付債務とする方法です。
③要支給額法
この方法は期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法です。この方法は3通りの方法の中でも最も簡便な方法になりますが、基礎率の影響が全く反映されませんので原則法の退職給付債務と大きくかけ離れてしまう危険性があります。
《企業年金制度》
①比較指数法
退職一時金制度の①の方法と同様の計算方法になります。
退職給付会計適用初年度における退職給付債務と年金財政計算上の責任準備金との比較指数を算定し、その後の年度においては直近の年金財政計算における責任準備金にその比較指数を乗じて求められた金額を退職給付債務とする方法です。
②係数法
これは現従業員については退職一時金制度の②または③の方法を用いて退職給付債務の計算を行い、その金額に年金受給者の責任準備金を加算する方法です。
③責任準備金法
直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職給付債務とする方法です。これは退職一時金制度と同様に最も簡便的な方法になりますが、予定利率が現状の市場利率と比較して高く設定されている場合もあります。その場合には原則法による計算結果と大きくかけ離れた債務額になる可能性があります。
3) 計算基礎の設定
退職給付債務の計算には割引率や昇給率、退職率などの基礎率の設定が必要になります。この基礎率は退職給付債務の金額に大きな影響を及ぼします。
①割引率
割引率は、企業が退職給付として支給すべき将来の金額負担を現時点の価値に割り戻す際に使用する率になります。具体的には、退職給付見込額から退職給付債務や勤務費用を算定する割引計算や利息費用の計算に使用されます。この割引率を高く設定した場合には将来の給付額が高額であっても高い利率で割り引かれるため退職給付債務は小さくなります。逆に割引率を低く設定した場合には退職給付債務は高くなります。大まかには1%の割引率の低下により退職給付債務は20%程度増加するものといわれています。
「退職給付に係る会計基準」では、割引率を安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定するものとしていますが、実務上は過去5年程度の長期国債の利回りの平均をベースに割引率を設定しています。
②予定昇給率
予定昇給率は、退職給付債務の計算上将来の給与水準を推定する場合に用いられる基礎率になります。予定昇給率が高い場合には退職給付債務が高くなります。
この予定昇給率は、給与規程、平均給与の実態分布および過去の昇給実績などに基づいて、確実に見込まれるものを合理的に推定して算定することとされています。実務上は一定時点の社員の給与の年齢別平均を算定し、さらに最小自乗法などの補正をかけて算定されます。
③退職率、死亡率
退職率は各年齢で翌1年間に生存退職する率、死亡率は翌1年間に死亡退職する率になります。これらの基礎率は各年齢での退職給付額から退職給付見込額を算定する際に使用します。
退職率は一定時点以前3年間以上の退職者から各年齢の退職者割合を算定し、5点平均法などの補正をかけて算定されます。死亡率は厚生労働省から開示される国民生命表などを使用するケースが一般的です。
4) 債務計算の手段
退職給付債務の計算は確率計算や割引計算など、その計算に煩雑さを伴うため、実務では次のいずれかの方法により計算されています。
①債務計算ソフト
これは市販されている退職給付債務計算用のソフトを使用し、社内で計算する方法です。債務の計算には期末日時点の社員データと年金受給者のデータを取り込み、自社の退職金規程に合わせて設定した計算方法に従って自動計算されます。
②の委託計算に比べて計算期間が短縮されるほか、毎期の債務計算費用や予算用の債務計算費用が抑えられるメリットがあります。
②委託計算
これは、生命保険会社や信託銀行、コンサルティング会社に人事データを提出し、退職給付債務の計算結果報告書を受け取り、会計処理を行う方法です。通常は3ヶ月程度の期間が必要になるため、期末日より数ヶ月前に計算を委託し、受け取った計算結果に退職者等の債務の控除を行い、計上します。
委託先が主導して計算を行いますが、自社で計算する場合に比べて費用が高くなることや計算期間の長期化などでデメリットがあります。
5. 今後の動向
1) 適格年金の廃止
適格退職年金は、平成24年3月をもって廃止される予定になっています。そのため、現在適格退職年金制度を採用している企業は今後数年間で新たな確定給付企業年金法に基づいた年金制度に変更するか、または確定拠出型年金制度へ変更することになります。
2) 代行返上
厚生年金基金制度は本来、国の厚生年金制度の一部の資産管理と運用を代行し、独自の上乗せ部分を設定して運営しております。しかし、近年の運用状況の悪化により、企業の財務に対する影響が大きいため、厚生年金の代行部分の資産を国に返上し、資産と債務を圧縮する基金が増えてきています。
3) 割引率の見直し
近年、市場利子率の低下に伴い、割引率の見直しを求められるケースが増加してきております。先に述べたように、割引率の低下は退職給付債務の増加につながり、結果的に退職給付費用が増加します。
数年前には3.5%程度の割引率で債務計算を行う企業が多く見受けられましたが、2003年3月期では2.0~2.5%での計算が主流になってきております。今後も平均市場利率が低下することが予想されるため、その場合の退職給付債務の予測が必要になると思われます。また最近は、企業の財務に対する退職給付債務の影響を削減するため、退職金制度自体の見直しを進める企業も増えてきています。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















