解説記事2004年01月26日 【実務解説】 非公開会社における証券取引法の規制(2004年1月26日号・№051)
実務解説
非公開会社における証券取引法の規制
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1.はじめに
非公開会社においても、「有価証券」の発行において、証券取引法の規制に該当すると開示義務が生ずる場合があります。具体的には、証券取引法上に規定する「有価証券」、すなわち株券、社債券、新株予約権証券等を発行する場合、証券取引法上の規制に該当すると、「有価証券届出書」または「有価証券通知書」の提出義務が生じます。
「有価証券届出書」は、その作成にはかなりの手間とコストがかかります。相当な準備期間がないと急な提出は困難を極めるもので、しかも一度提出するとその後継続開示義務が生じます。すなわち毎年「有価証券報告書」(半期には「半期報告書」)の提出義務が生じてしまいます。
発行においては、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するか否か。」に留意が必要です。募集人数(50名以上)には6ヶ月間の通算ルールがあり、また1億円未満の発行でも募集(50名以上)に該当すると、以後新たな募集を行いそれら発行価額の合計が2年間通算で1億円以上になると、ここに届出義務が生じます。
なお、4.に後述する既発有価証券の「売出し」についても、証券取引法は開示規制を設けていますが、今回は新規発行を中心に取扱います。
また、これら届出義務とは別に、株主数が500名以上になると、原則として有価証券報告書の継続開示義務が生じますので注意が必要です。
なお、以降の文中における、証券取引法の開示制度に係る法体系とその凡例は以下の通りです。
① 証券取引法(証法)
② 証券取引法施行令(証令)
③ 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(定義府令)
④ 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
⑤ 企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)
⑥ 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子手続ガイドライン)
2.開示義務対象となる有価証券
証券取引法上の有価証券は第2条1項に具体的に規定されています。これらを1億円以上発行し、かつ後述する「募集」に該当すると、証券取引法上の開示義務として「有価証券届出書等」の提出義務が生じますが、この規制が課される有価証券はそれら全ての有価証券ではなく、以下に限定されます。
(1)社債券(証法2①四)
これには普通社債の他に、新株予約権付社債券も含まれます。
(2)株券、新株引受権証書、新株予約権証券(証法2①六)
(3)コマーシャル・ペーパー(証法2①八)
(4)カバーワラント(証法2①十の三)
(5)預託証券(証法2①十の三)
3.発行市場における届出制度の概要
企業が1億円以上の2.の有価証券の「募集」又は「売出し」を行うと(「募集」「売出し」の定義は4.にて後述)、有価証券届出書等の提出義務が生じ、公衆の縦覧に供されます。この発行市場における企業内容等の開示制度は、一般投資家の自己責任による投資判断を可能とするよう、有価証券届出書等により有価証券の内容や発行者の財務内容等を開示するというものです。
この開示書類は、①有価証券届出書、②発行登録書、③目論見書をいい、①及び②を有価証券発行前に財務局に提出して公衆の縦覧に供し、③も事前に投資家に直接交付します。①には、当該募集または売出しに関する「証券情報(10~20頁程度)」並びに発行会社の企業集団及び当該会社の事業内容や財務内容に関する「企業情報(100頁程度)」の2つの情報が記載されます。③は①とほぼ同様のものです。
この有価証券届出書等を提出すると、その後毎期、有価証券報告書(半期には半期報告書)を継続開示する義務が生じます。この有価証券報告書は、有価証券届出書の「企業情報」部分を記載したものです。有価証券届出書並びに有価証券報告書には、連結財務諸表規則に準拠した2期間の連結財務諸表の記載と、それらに対する公認会計士または監査法人の2期間の監査証明も必要で、その作成には相当の準備期間と手間並びにコストがかかります。非公開会社においては、その作成は簡単なものではありません。
4.「募集」「売出し」の意味
「募集」とは何か。証券取引法上、「多数の者を相手に新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う。」ことを有価証券の「募集」と定義しています(証法2③)。この募集に該当するか否かは、勧誘対象者の人数と属性を考慮して判断されます。
(1)人数基準
「多数の者」は「50名以上の者」とされています(証令1の4)。したがって、50名未満の場合には「募集」には該当せず「私募」として開示義務は免除されます。ただし、50名未満を相手とする場合であっても、その有価証券が取得者から多数の者に譲渡されるおそれがある場合は「募集」とみなされます(証法2③二)。
なおここで、50名というのは、勧誘された者の数で実際に有価証券を取得した者の数ではありません。
(2)属性基準
「勧誘対象者」が、有価証券投資に係る専門的な知識・経験を有している者(「適格機関投資家」という)のみに限定される場合には、当該勧誘には開示義務は課されません(証法2③一かっこ書)。これは、適格機関投資家はその専門知識・経験に基づいて自ら投資判断することが可能なため、一般投資家と同様のディスクロージャーによる保護は必要ないという考えによっています。
ただし、適格機関投資家のみを相手方とする場合でも、有価証券が取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれがある場合には「募集」とみなされます(証法2③二)。
このように、勧誘の相手方が適格機関投資家か否かによって開示が必要か否かが決まるので、これを属性基準といいます。
以上、新規発行有価証券の「募集」について説明しましたが、「売出し」といって、既に発行された有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みのうち、均一の条件で50名以上の者を相手方としてこれを行う場合、同様の開示義務が生じます(証法2④、証法4)。
5.届出義務の判定ルール
前述の通り、企業が1億円以上の上記有価証券の募集又は売出しを行うと、原則として有価証券届出書等の提出義務が生じます。
すなわち、届出義務が生ずる発行は、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」です。1回の発行がこれに該当すると届出義務が生じます。
これは、今回の発行が1億円以上でも、募集に該当しなければ届出義務は生じませんし、また募集に該当しても1億円未満の発行ならば届出義務は生じないということでもあります。
しかし、これには次の「6ヶ月間人数通算ルール」並びに「2年間金額通算ルール」があるので注意が必要です。
(1)「6ヶ月間人数通算」ルール
届出義務が生ずる発行は前述の通り、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」です。すると、今回の発行価額の総額が1億円以上でも、募集に該当させない、すなわち50名未満に勧誘を行えば届出義務は生じません。
しかしこの点に関しては、今回発行の勧誘相手先が50名未満でも、以降6ヶ月間に更に発行を行い、同一有価証券の勧誘対象者合計が50名以上になると、50名以上となった当該発行が「募集」に該当します。これが6ヶ月間人数通算ルールです(証法2③二ロかっこ書、証令1の6)。
例えば、今回35名に1億円の株式の発行(第三者割当増資または株主割当増資)を行い、6ヶ月以内に18名に同じ種類の3千万円の株式発行を行うと、後者に届出義務が生じます。
(2)「2年間金額通算」ルール
今回の発行が募集(50名以上勧誘)に該当しても、発行価額の総額が1億円未満であれば届出義務は生じません。しかし、一度募集(同上)に該当すると、同一種類の有価証券について2年以内に次の募集(同上)を行い、その発行価額の合計が1億円以上になると、当該募集(同上)に届出義務が生じます(開示府令2二、開示ガイドライン4-6)。
例えば、届出義務を伴わない7千万円の募集(同上)による発行の後、2年以内に3千万円の募集(同上)による発行が行われた場合、後者に届出義務が生じます。
6.勧誘相手先により異なる届出義務
(1)一般投資家向け勧誘
一般投資家向け勧誘の場合、前述の「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」がそのまま適用されます。これに該当しない場合は「少人数私募」として開示義務は生じません。
(2)適格機関投資家のみへの勧誘
適格機関投資家のみに勧誘を行った場合、上記「属性基準」が適用され、「プロ私募」として届出義務は課されません(証法2③一かっこ書)。ここに「適格機関投資家」とは、証券会社、銀行、信用金庫、保険会社、農業協同組合等をいい、平成15年4月1日からはその範囲拡大として、ベンチャー・キャピタル会社(資本金5億円以上で金融庁長官に届出を行った者)、中小企業等投資事業有限責任組合等が含まれることとなりました。
(3)一般投資家並びに適格機関投資家への勧誘
一般投資家並びに適格機関投資家へ勧誘を行った場合、従来は50名の人数基準に適格機関投資家の数を含めて計算していましたが、平成15年4月1日から250名以下の適格機関投資家(他の適格機関投資家に譲渡しない旨の転売制限を付する等の条件付)については人数基準から除外されることになりました。
この改正の結果、例えば一般投資家49名及び250名以下の適格機関投資家(上記の転売制限等の条件付)を相手方とする勧誘は募集に該当せず、私募扱いとなりました。
7.ストック・オプション特例について
新株予約権をストック・オプションとして発行した場合には、有価証券届出書等の提出を要しない特例が設けられています(証令1の4③、1の8②、開示ガイドライン2-2)。特例対象となるためには次の条件を満たす必要があり、これを満たした場合は、50名の人数基準に該当する者の人数を含ませないことができます。
① その譲渡につき取締役会の承認を要すること。
② その付与対象者が、発行会社及び当該発行会社が日本国内に設立した100%子会社の取締役、執行役、監査役または使用人のみに限定していること。
③ 非公開会社の場合は、付与の直前期の商法施行規則により作成した計算書類を使用人に書類又は電磁的方法により交付すること。
8.継続開示義務が生ずる場合とは
有価証券届出書等を提出すると、その後毎期継続的に「有価証券報告書(半期は「半期報告書」)」の提出義務が生ずるのは前述の通りです。ここに、有価証券報告書の継続開示義務者を整理すると以下の通りです。
① 証券取引所に上場している会社(証法24①一)
② 店頭登録会社(証法24①二)
③ その募集または売出しにつき有価証券届出書等を提出した会社(上場会社及び店頭登録会社を除く)(証法24①三)
④ 株券または優先出資証券の所有者が事業年度末にて500名以上の場合(証法24①四)。ただし、事業年度末の資本の額が5億円未満の会社は免除されます(証法24①ただし書き)。
非公開会社では、上記③及び④が該当します。とりわけ④では、5年間の継続開示となりますが、300名未満になった場合にはその年度について開示義務が中断されます(証法24①ただし書、証令3の6①)。
①、②及び③においては、いったん継続開示会社となると、その後継続開示義務が中断できるのは次の事由に該当し、金融庁長官に所定の承認申請を提出した場合のみに限られます。
・清算中の者(証令4②一)
・相当の期間営業を休止している者(証令4②二)
・その募集または売出しにつき届出をした有価証券の所有者が25名未満である者(証令4②三、開示府令16②)
提出義務中断の承認を受けた発行会社は、申請後4年間毎事業年度経過後3ヶ月以内に、次の書類を金融庁長官に提出しなければなりません(証令4③、開示府令16④、⑤)。
① 事業年度末の株主名簿の写し
② 定時総会の承認を受けた商法283①の計算書類等
9.新株発行等の届出義務チェックシート
株券、社債券、新株予約権証券の新規発行等の届出義務に関するチェックシートをこの後に示します。
10.有価証券通知書の事例
非公開会社でもチェックシートにあるように、有価証券通知書を提出するケースは珍しくありません。そこで、そのフォーマットを事例としてチェックシートの後に示します。
参考文献:内山正次、小谷融著『証券取引法ディスクロージャー実務Q&A(初版)』税務研究会出版局、2002年
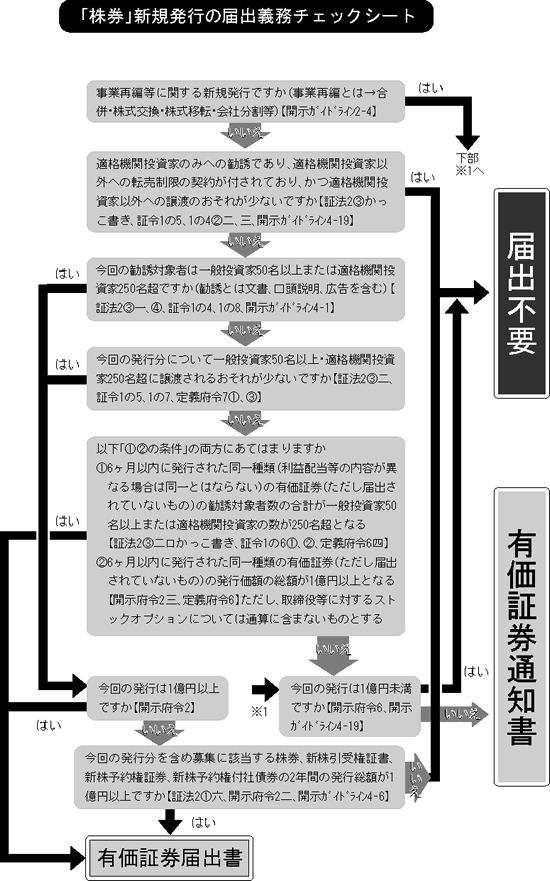
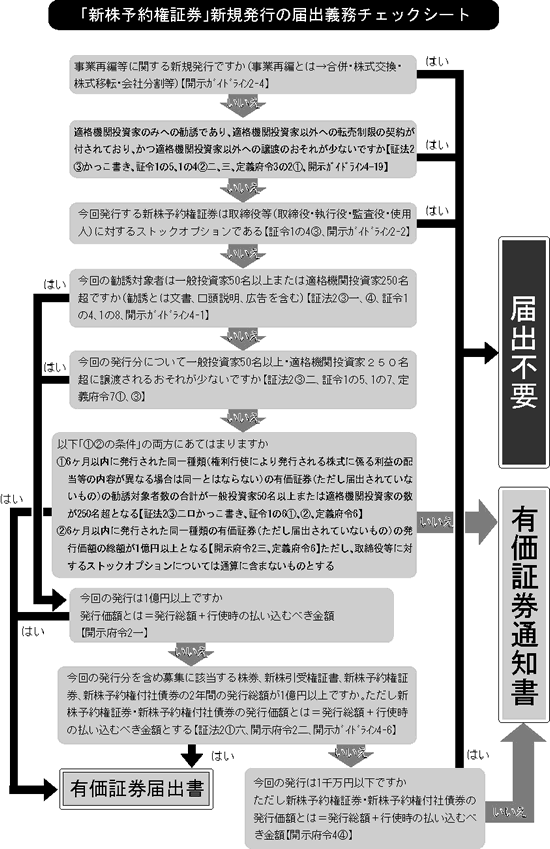
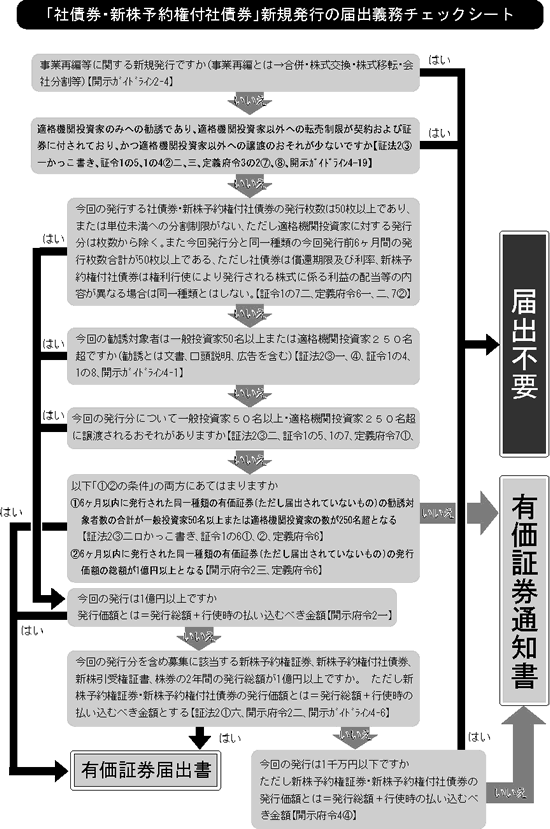
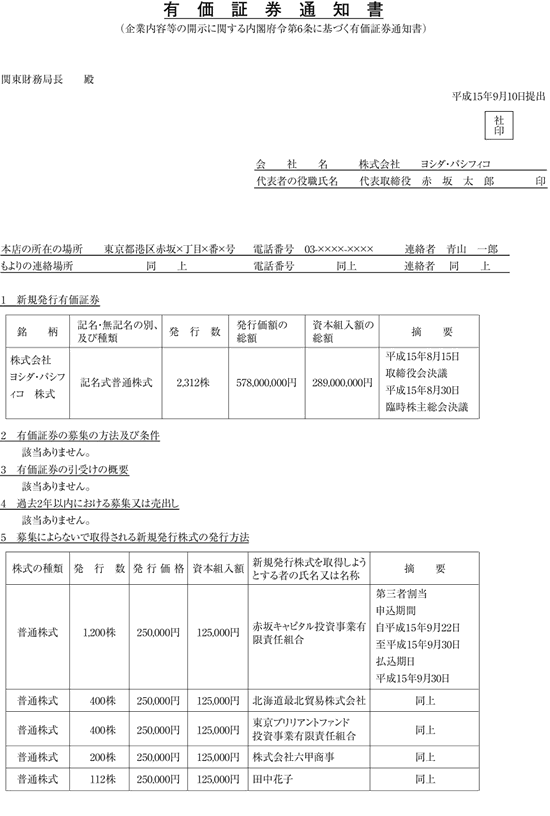
非公開会社における証券取引法の規制
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1.はじめに
非公開会社においても、「有価証券」の発行において、証券取引法の規制に該当すると開示義務が生ずる場合があります。具体的には、証券取引法上に規定する「有価証券」、すなわち株券、社債券、新株予約権証券等を発行する場合、証券取引法上の規制に該当すると、「有価証券届出書」または「有価証券通知書」の提出義務が生じます。
「有価証券届出書」は、その作成にはかなりの手間とコストがかかります。相当な準備期間がないと急な提出は困難を極めるもので、しかも一度提出するとその後継続開示義務が生じます。すなわち毎年「有価証券報告書」(半期には「半期報告書」)の提出義務が生じてしまいます。
発行においては、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するか否か。」に留意が必要です。募集人数(50名以上)には6ヶ月間の通算ルールがあり、また1億円未満の発行でも募集(50名以上)に該当すると、以後新たな募集を行いそれら発行価額の合計が2年間通算で1億円以上になると、ここに届出義務が生じます。
なお、4.に後述する既発有価証券の「売出し」についても、証券取引法は開示規制を設けていますが、今回は新規発行を中心に取扱います。
また、これら届出義務とは別に、株主数が500名以上になると、原則として有価証券報告書の継続開示義務が生じますので注意が必要です。
なお、以降の文中における、証券取引法の開示制度に係る法体系とその凡例は以下の通りです。
① 証券取引法(証法)
② 証券取引法施行令(証令)
③ 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(定義府令)
④ 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
⑤ 企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)
⑥ 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子手続ガイドライン)
2.開示義務対象となる有価証券
証券取引法上の有価証券は第2条1項に具体的に規定されています。これらを1億円以上発行し、かつ後述する「募集」に該当すると、証券取引法上の開示義務として「有価証券届出書等」の提出義務が生じますが、この規制が課される有価証券はそれら全ての有価証券ではなく、以下に限定されます。
(1)社債券(証法2①四)
これには普通社債の他に、新株予約権付社債券も含まれます。
(2)株券、新株引受権証書、新株予約権証券(証法2①六)
(3)コマーシャル・ペーパー(証法2①八)
(4)カバーワラント(証法2①十の三)
(5)預託証券(証法2①十の三)
3.発行市場における届出制度の概要
企業が1億円以上の2.の有価証券の「募集」又は「売出し」を行うと(「募集」「売出し」の定義は4.にて後述)、有価証券届出書等の提出義務が生じ、公衆の縦覧に供されます。この発行市場における企業内容等の開示制度は、一般投資家の自己責任による投資判断を可能とするよう、有価証券届出書等により有価証券の内容や発行者の財務内容等を開示するというものです。
この開示書類は、①有価証券届出書、②発行登録書、③目論見書をいい、①及び②を有価証券発行前に財務局に提出して公衆の縦覧に供し、③も事前に投資家に直接交付します。①には、当該募集または売出しに関する「証券情報(10~20頁程度)」並びに発行会社の企業集団及び当該会社の事業内容や財務内容に関する「企業情報(100頁程度)」の2つの情報が記載されます。③は①とほぼ同様のものです。
この有価証券届出書等を提出すると、その後毎期、有価証券報告書(半期には半期報告書)を継続開示する義務が生じます。この有価証券報告書は、有価証券届出書の「企業情報」部分を記載したものです。有価証券届出書並びに有価証券報告書には、連結財務諸表規則に準拠した2期間の連結財務諸表の記載と、それらに対する公認会計士または監査法人の2期間の監査証明も必要で、その作成には相当の準備期間と手間並びにコストがかかります。非公開会社においては、その作成は簡単なものではありません。
4.「募集」「売出し」の意味
「募集」とは何か。証券取引法上、「多数の者を相手に新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う。」ことを有価証券の「募集」と定義しています(証法2③)。この募集に該当するか否かは、勧誘対象者の人数と属性を考慮して判断されます。
(1)人数基準
「多数の者」は「50名以上の者」とされています(証令1の4)。したがって、50名未満の場合には「募集」には該当せず「私募」として開示義務は免除されます。ただし、50名未満を相手とする場合であっても、その有価証券が取得者から多数の者に譲渡されるおそれがある場合は「募集」とみなされます(証法2③二)。
なおここで、50名というのは、勧誘された者の数で実際に有価証券を取得した者の数ではありません。
(2)属性基準
「勧誘対象者」が、有価証券投資に係る専門的な知識・経験を有している者(「適格機関投資家」という)のみに限定される場合には、当該勧誘には開示義務は課されません(証法2③一かっこ書)。これは、適格機関投資家はその専門知識・経験に基づいて自ら投資判断することが可能なため、一般投資家と同様のディスクロージャーによる保護は必要ないという考えによっています。
ただし、適格機関投資家のみを相手方とする場合でも、有価証券が取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれがある場合には「募集」とみなされます(証法2③二)。
このように、勧誘の相手方が適格機関投資家か否かによって開示が必要か否かが決まるので、これを属性基準といいます。
以上、新規発行有価証券の「募集」について説明しましたが、「売出し」といって、既に発行された有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みのうち、均一の条件で50名以上の者を相手方としてこれを行う場合、同様の開示義務が生じます(証法2④、証法4)。
5.届出義務の判定ルール
前述の通り、企業が1億円以上の上記有価証券の募集又は売出しを行うと、原則として有価証券届出書等の提出義務が生じます。
すなわち、届出義務が生ずる発行は、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」です。1回の発行がこれに該当すると届出義務が生じます。
これは、今回の発行が1億円以上でも、募集に該当しなければ届出義務は生じませんし、また募集に該当しても1億円未満の発行ならば届出義務は生じないということでもあります。
しかし、これには次の「6ヶ月間人数通算ルール」並びに「2年間金額通算ルール」があるので注意が必要です。
(1)「6ヶ月間人数通算」ルール
届出義務が生ずる発行は前述の通り、「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」です。すると、今回の発行価額の総額が1億円以上でも、募集に該当させない、すなわち50名未満に勧誘を行えば届出義務は生じません。
しかしこの点に関しては、今回発行の勧誘相手先が50名未満でも、以降6ヶ月間に更に発行を行い、同一有価証券の勧誘対象者合計が50名以上になると、50名以上となった当該発行が「募集」に該当します。これが6ヶ月間人数通算ルールです(証法2③二ロかっこ書、証令1の6)。
例えば、今回35名に1億円の株式の発行(第三者割当増資または株主割当増資)を行い、6ヶ月以内に18名に同じ種類の3千万円の株式発行を行うと、後者に届出義務が生じます。
(2)「2年間金額通算」ルール
今回の発行が募集(50名以上勧誘)に該当しても、発行価額の総額が1億円未満であれば届出義務は生じません。しかし、一度募集(同上)に該当すると、同一種類の有価証券について2年以内に次の募集(同上)を行い、その発行価額の合計が1億円以上になると、当該募集(同上)に届出義務が生じます(開示府令2二、開示ガイドライン4-6)。
例えば、届出義務を伴わない7千万円の募集(同上)による発行の後、2年以内に3千万円の募集(同上)による発行が行われた場合、後者に届出義務が生じます。
6.勧誘相手先により異なる届出義務
(1)一般投資家向け勧誘
一般投資家向け勧誘の場合、前述の「同一種類の有価証券について発行価額の総額が1億円以上かつ募集に該当するもの。」がそのまま適用されます。これに該当しない場合は「少人数私募」として開示義務は生じません。
(2)適格機関投資家のみへの勧誘
適格機関投資家のみに勧誘を行った場合、上記「属性基準」が適用され、「プロ私募」として届出義務は課されません(証法2③一かっこ書)。ここに「適格機関投資家」とは、証券会社、銀行、信用金庫、保険会社、農業協同組合等をいい、平成15年4月1日からはその範囲拡大として、ベンチャー・キャピタル会社(資本金5億円以上で金融庁長官に届出を行った者)、中小企業等投資事業有限責任組合等が含まれることとなりました。
(3)一般投資家並びに適格機関投資家への勧誘
一般投資家並びに適格機関投資家へ勧誘を行った場合、従来は50名の人数基準に適格機関投資家の数を含めて計算していましたが、平成15年4月1日から250名以下の適格機関投資家(他の適格機関投資家に譲渡しない旨の転売制限を付する等の条件付)については人数基準から除外されることになりました。
この改正の結果、例えば一般投資家49名及び250名以下の適格機関投資家(上記の転売制限等の条件付)を相手方とする勧誘は募集に該当せず、私募扱いとなりました。
7.ストック・オプション特例について
新株予約権をストック・オプションとして発行した場合には、有価証券届出書等の提出を要しない特例が設けられています(証令1の4③、1の8②、開示ガイドライン2-2)。特例対象となるためには次の条件を満たす必要があり、これを満たした場合は、50名の人数基準に該当する者の人数を含ませないことができます。
① その譲渡につき取締役会の承認を要すること。
② その付与対象者が、発行会社及び当該発行会社が日本国内に設立した100%子会社の取締役、執行役、監査役または使用人のみに限定していること。
③ 非公開会社の場合は、付与の直前期の商法施行規則により作成した計算書類を使用人に書類又は電磁的方法により交付すること。
8.継続開示義務が生ずる場合とは
有価証券届出書等を提出すると、その後毎期継続的に「有価証券報告書(半期は「半期報告書」)」の提出義務が生ずるのは前述の通りです。ここに、有価証券報告書の継続開示義務者を整理すると以下の通りです。
① 証券取引所に上場している会社(証法24①一)
② 店頭登録会社(証法24①二)
③ その募集または売出しにつき有価証券届出書等を提出した会社(上場会社及び店頭登録会社を除く)(証法24①三)
④ 株券または優先出資証券の所有者が事業年度末にて500名以上の場合(証法24①四)。ただし、事業年度末の資本の額が5億円未満の会社は免除されます(証法24①ただし書き)。
非公開会社では、上記③及び④が該当します。とりわけ④では、5年間の継続開示となりますが、300名未満になった場合にはその年度について開示義務が中断されます(証法24①ただし書、証令3の6①)。
①、②及び③においては、いったん継続開示会社となると、その後継続開示義務が中断できるのは次の事由に該当し、金融庁長官に所定の承認申請を提出した場合のみに限られます。
・清算中の者(証令4②一)
・相当の期間営業を休止している者(証令4②二)
・その募集または売出しにつき届出をした有価証券の所有者が25名未満である者(証令4②三、開示府令16②)
提出義務中断の承認を受けた発行会社は、申請後4年間毎事業年度経過後3ヶ月以内に、次の書類を金融庁長官に提出しなければなりません(証令4③、開示府令16④、⑤)。
① 事業年度末の株主名簿の写し
② 定時総会の承認を受けた商法283①の計算書類等
9.新株発行等の届出義務チェックシート
株券、社債券、新株予約権証券の新規発行等の届出義務に関するチェックシートをこの後に示します。
10.有価証券通知書の事例
非公開会社でもチェックシートにあるように、有価証券通知書を提出するケースは珍しくありません。そこで、そのフォーマットを事例としてチェックシートの後に示します。
参考文献:内山正次、小谷融著『証券取引法ディスクロージャー実務Q&A(初版)』税務研究会出版局、2002年
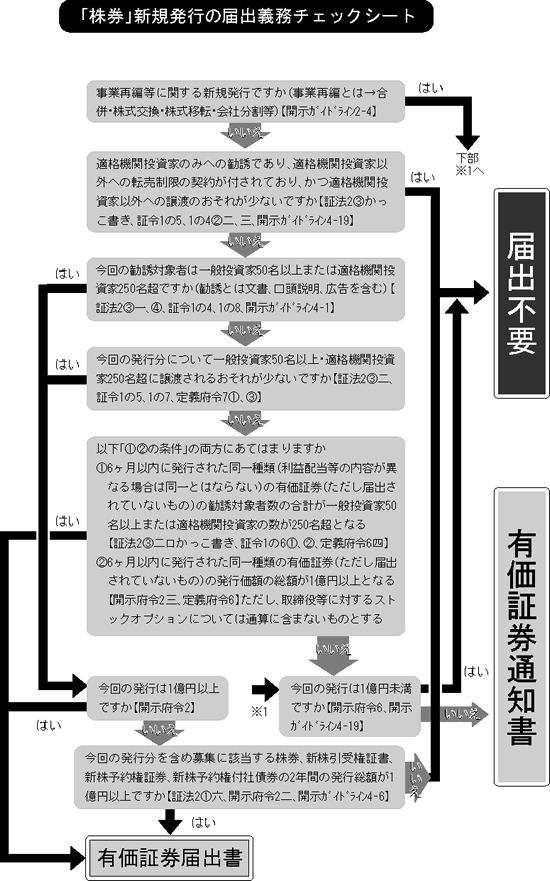
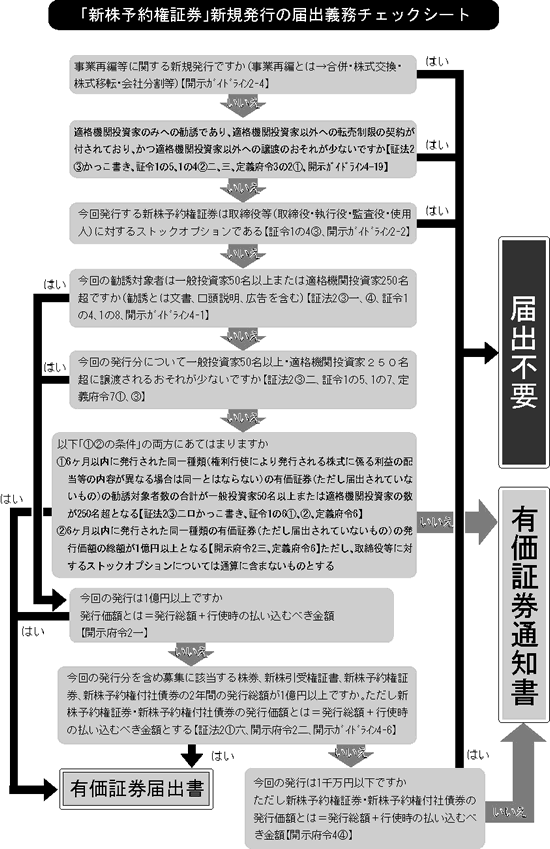
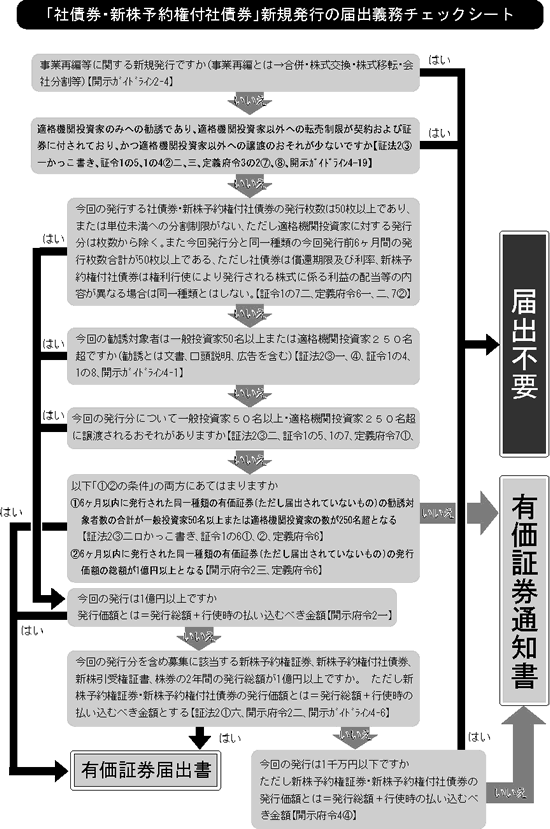
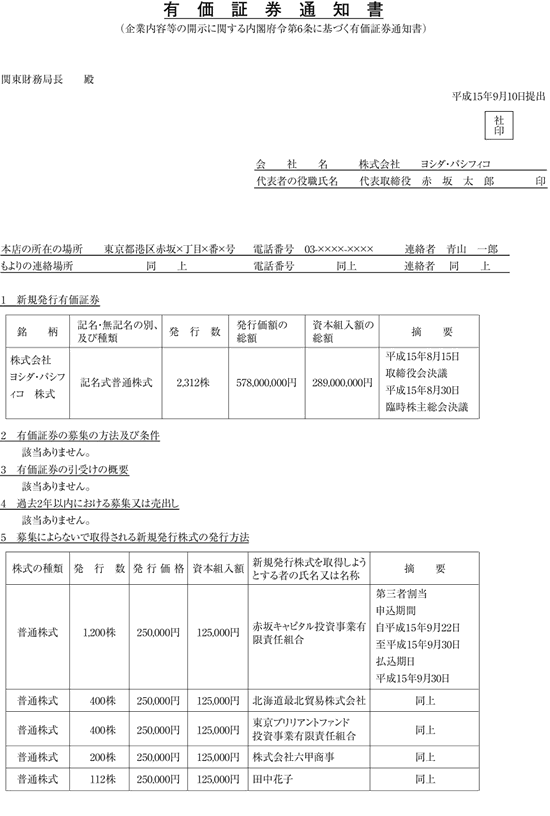
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















