解説記事2004年03月29日 【編集部解説】 連結納税の申告書を作成してみましょう!(第11回)(2004年3月29日号・№060)
連結納税の申告書を作成してみましょう!(第11回)
編集部
連結法人が各連結事業年度において利子、配当等の支払を受ける場合には、これらについて源泉徴収された所得税額は、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除することができます(法法81の14)。連結法人が、連結事業年度における所得税額の控除等の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除等の金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法法81の7)。
連結納税の所得税額控除は、連結グループを一体として計算を行います。連結グループ内の法人間で元本が移転した場合には元本所有期間を通算し、「原則法」又は「簡便法」の選択は、「公社債」・「株式及び出資」・「投資信託等の受益証券」等に区分された元本について、連結グループ全体で行うことになります。
連結グループ全体で計算された「法人税額から控除される所得税額」は、政令(法令155の44)の定めにより計算された各連結法人ごとの個別帰属額に配分します。
設例
(1)各連結法人の連結事業年度における受取利子・受取配当の額及び源泉徴収された所得税額・住民税利子割額は次表のとおりです。受取配当の計算期間はそれぞれ1年間(12月)とし、その計算期間のすべてにわたり、その元本である株式を所有していたものとします。
① P(株)
② A(株)
③ B(株)
連結事業年度における所得税額控除の取扱い
(1) 連結事業年度における所得税額の控除
連結法人が各連結事業年度において所得税法等に規定する利子、配当等の支払を受ける場合には、これらについて源泉徴収された所得税額は、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除することができます(法法81の14)。
連結法人税額から控除する所得税額の計算は、原則的に単体の規定(法令140の2「法人税額から控除する所得税額の計算」)を準用することとなっています(法令155の26①)が、単体の規定と以下の2点で異なる取扱いとなります。
① 元本所有期間対応分の所得税額の計算には、原則(個別)法と銘柄別簡便法の2つの方法があり、利子・配当等の元本をi)公社債、ii)株式及び出資、iii)投資信託等の受益証券の3種類に区分し、さらにその元本を当該利子配当等の計算の基礎となった期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分して、それぞれの区分ごとに原則法と銘柄別簡便法のいずれかの方法を選択することになりますが、連結法人全体で選択することになります(法令155の26③)。
② 次の理由により、計算期間の中途で利子配当等の元本の移転を受けた場合には、移転元の法人(以下の理由ごとに記載したそれぞれの法人)が元本を所有していた期間を自己の所有期間とみなすこととされています(法令155の26④)。
i 適格合併 被合併法人
ii 適格分割 分割法人
iii 適格現物出資 現物出資法人
iv 特別の法律に基づく承継 被承継法人
v 連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転 当該他の連結法人
(2) 連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入
連結法人が、「連結事業年度における所得税額の控除」、「連結確定申告による所得税額等の還付」、「確定申告又は連結確定申告に係る更正所得税額等の還付」の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法法81の7)。
この損金不算入額のうち、各連結法人に帰せられる金額(個別帰属額)は、連結法人税から控除する所得税額の個別帰属額の計算(後記(5)参照)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額となります(法法81の7②、法令155の17)。
(3) 連結別表(別表六の二(一))の記載の内容について
連結納税における所得税額の控除の内容を明らかにするため、「別表六の二(一)・連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」が規定されました。
この明細書は、単体申告における所得税額の控除(別表六(一))の記載内容に個別帰属額の計算欄を付加したものとなりました。個別帰属額の計算は、各連結法人ごとに別葉に記載しますから、別表六の二(一)は、連結法人の数の枚数の明細書を記載することになります。
個別帰属額の計算以外の記載は、所得税額の控除が連結グループ全体で計算しますので、連結グループ全体の金額を記載します。各連結法人ごとの明細書では、共通する内容になります。
(4)連結別表(別表六の二(一))の記載の要領について
この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の各欄から記載し、次に上段の各欄を記載します。
設例では、元本の所有期間に対応する金額を計算するものは、「株式及び出資」だけであり、配当の計算期間は1年で、その期間すべてにわたって所有していますので、「個別法」による計算だけを行っています。銘柄別の利子配当等の計算は、連結グループ全体の合計額を記載します。
「公社債の利子」など、他の区分で計算方法(原則法・銘柄別簡便法)を選択する場合には、連結法人全体で原則法あるいは、銘柄別簡便法を選択することができます。
中段で集計した「公社債の利子等」の合計額は、上段の公社債の利子等(「2」欄)へ、「利益の配当及び剰余金の分配」の合計額は、上段の利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当を除く。)(「3」欄)へ、「投資信託及び特定目的信託の収益の分配」の合計額は、上段の投資信託及び特定目的信託の収益の分配(「4」欄)へ転記します。
所得税法174条3号から10号までに規定する給付補てん金等並びに懸賞金等及びみなし配当等がある場合には、中段下部の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に記載して、その合計額を上段のその他(「5」欄)へ転記します。
別表六の二(一)上段の計(「6欄」)③は、別表一の二(一)「各連結事業年度の連結所得にかかる申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分」の所得税の額(「41」欄)へ転記され、税額控除の対象となった所得税額は、別表四の二「連結所得金額の計算に関する明細書」の法人税額から控除される所得税額(「37」欄)に転記されて、損金不算入(加算・その他)の取扱いとなります。
(5) 個別帰属額の計算
所得税額控除の各連結法人の個別帰属額の計算は、元本所有期間対応部分のみが控除対象となる「公社債の利子」「利益の配当及び剰余金の分配」「投資信託等の収益の分配」とその全額が控除対象となるその他に区分して計算し、その合計額となります(法令155の44)。
① 元本所有期間対応部分のみが控除対象となるもの
ア 原則(個別)法により計算した場合
原則法により計算した金額の合計額
イ 銘柄別簡便法により計算した場合
次の算式で計算された銘柄別の個別帰属額の合計額
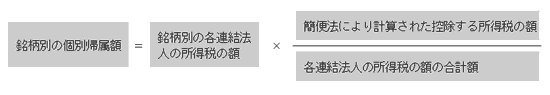
② 預貯金の利子その他その全額が控除対象となるもの
その所得税の額の全額
③ 各連結法人の個別帰属額
①+②
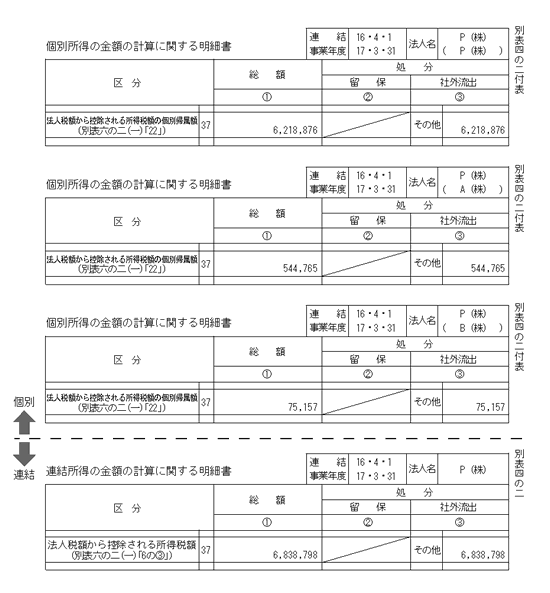
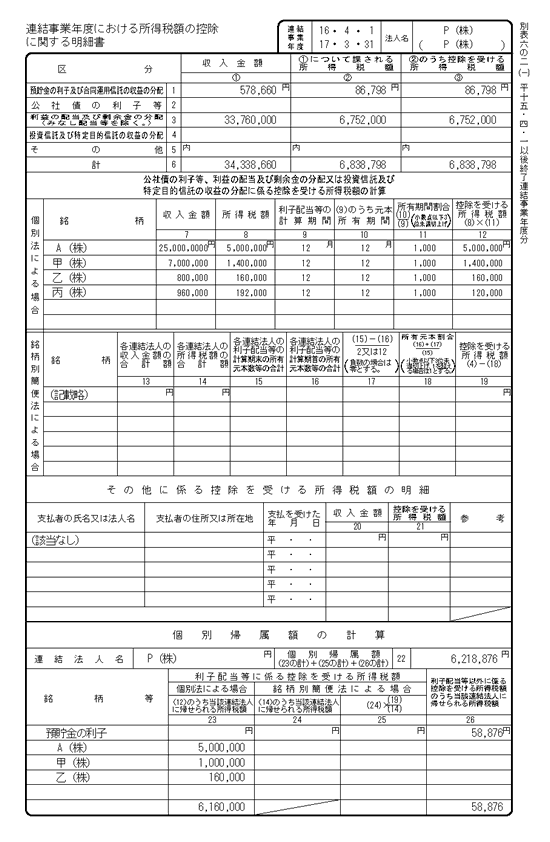
別表上の個別帰属額の計算は、別表六の二(一)下段の個別帰属額の計算で次のように行います。
① 元本所有期間対応部分のみが控除対象となるもの
ア 原則(個別)法により計算したもの
当該連結法人が課されたものについて、別表六の二(一)の「23」欄で集計します。
イ 銘柄別簡便法により計算したもの
各連結法人の所得税額を「24」欄に記載し、銘柄別の個別帰属額を「25」欄で計算・集計します。
② 預貯金の利子その他でその全額が控除対象となるもの
「26」欄で集計します。
③ 各連結法人の個別帰属額
「23」の計・「25」の計・「26」の計の合計額を個別帰属額(「22」欄)に記載します。
各連結法人の個別帰属額は、各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書の所得税の額の個別帰属額(「33」欄)及び個別所得の金額に関する明細書(別表四の二付表)の法人税額から控除される所得税額の個別帰属額(「37」欄)に転記します。
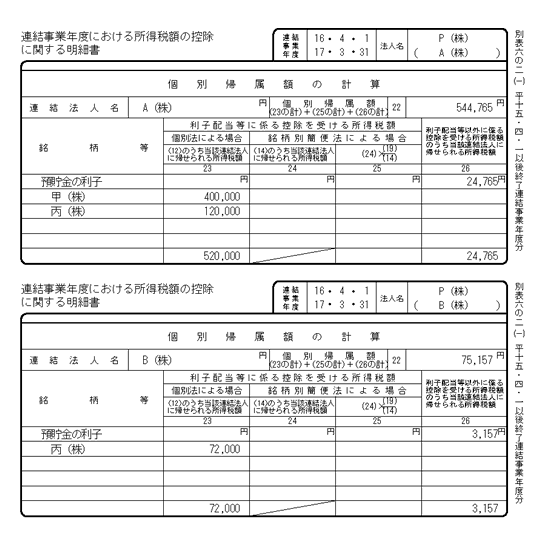
編集部
連結法人が各連結事業年度において利子、配当等の支払を受ける場合には、これらについて源泉徴収された所得税額は、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除することができます(法法81の14)。連結法人が、連結事業年度における所得税額の控除等の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除等の金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法法81の7)。
連結納税の所得税額控除は、連結グループを一体として計算を行います。連結グループ内の法人間で元本が移転した場合には元本所有期間を通算し、「原則法」又は「簡便法」の選択は、「公社債」・「株式及び出資」・「投資信託等の受益証券」等に区分された元本について、連結グループ全体で行うことになります。
連結グループ全体で計算された「法人税額から控除される所得税額」は、政令(法令155の44)の定めにより計算された各連結法人ごとの個別帰属額に配分します。
設例
(1)各連結法人の連結事業年度における受取利子・受取配当の額及び源泉徴収された所得税額・住民税利子割額は次表のとおりです。受取配当の計算期間はそれぞれ1年間(12月)とし、その計算期間のすべてにわたり、その元本である株式を所有していたものとします。
① P(株)
種類・銘柄 | 収入金額 | 所得税額 | 住民税利子割額 |
| 預貯金の利子 | 392,509 | 58,876 | 19,625 |
| 配当・A(株) | 25,000,000 | 5,000,000 | |
| 配当・甲(株) | 5,000,000 | 1,000,000 | |
| 配当・乙(株) | 800,000 | 160,000 | |
合 計 | 31,192,509 | 6,218,876 | 19,625 |
② A(株)
種類・銘柄 | 収入金額 | 所得税額 | 住民税利子割額 |
| 預貯金の利子 | 165,103 | 24,765 | 8,254 |
| 配当・甲(株) | 2,000,000 | 400,000 | |
| 配当・丙(株) | 600,000 | 120,000 | |
合 計 | 2,765,103 | 544,765 | 8,254 |
③ B(株)
種類・銘柄 | 収入金額 | 所得税額 | 住民税利子割額 |
| 預貯金の利子 | 21,048 | 3,157 | 1,052 |
| 配当・丙(株) | 360,000 | 72,000 | |
合 計 | 381,048 | 75,157 | 1,052 |
連結事業年度における所得税額控除の取扱い
(1) 連結事業年度における所得税額の控除
連結法人が各連結事業年度において所得税法等に規定する利子、配当等の支払を受ける場合には、これらについて源泉徴収された所得税額は、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除することができます(法法81の14)。
連結法人税額から控除する所得税額の計算は、原則的に単体の規定(法令140の2「法人税額から控除する所得税額の計算」)を準用することとなっています(法令155の26①)が、単体の規定と以下の2点で異なる取扱いとなります。
① 元本所有期間対応分の所得税額の計算には、原則(個別)法と銘柄別簡便法の2つの方法があり、利子・配当等の元本をi)公社債、ii)株式及び出資、iii)投資信託等の受益証券の3種類に区分し、さらにその元本を当該利子配当等の計算の基礎となった期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分して、それぞれの区分ごとに原則法と銘柄別簡便法のいずれかの方法を選択することになりますが、連結法人全体で選択することになります(法令155の26③)。
② 次の理由により、計算期間の中途で利子配当等の元本の移転を受けた場合には、移転元の法人(以下の理由ごとに記載したそれぞれの法人)が元本を所有していた期間を自己の所有期間とみなすこととされています(法令155の26④)。
i 適格合併 被合併法人
ii 適格分割 分割法人
iii 適格現物出資 現物出資法人
iv 特別の法律に基づく承継 被承継法人
v 連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転 当該他の連結法人
(2) 連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入
連結法人が、「連結事業年度における所得税額の控除」、「連結確定申告による所得税額等の還付」、「確定申告又は連結確定申告に係る更正所得税額等の還付」の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法法81の7)。
この損金不算入額のうち、各連結法人に帰せられる金額(個別帰属額)は、連結法人税から控除する所得税額の個別帰属額の計算(後記(5)参照)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額となります(法法81の7②、法令155の17)。
(3) 連結別表(別表六の二(一))の記載の内容について
連結納税における所得税額の控除の内容を明らかにするため、「別表六の二(一)・連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」が規定されました。
この明細書は、単体申告における所得税額の控除(別表六(一))の記載内容に個別帰属額の計算欄を付加したものとなりました。個別帰属額の計算は、各連結法人ごとに別葉に記載しますから、別表六の二(一)は、連結法人の数の枚数の明細書を記載することになります。
個別帰属額の計算以外の記載は、所得税額の控除が連結グループ全体で計算しますので、連結グループ全体の金額を記載します。各連結法人ごとの明細書では、共通する内容になります。
(4)連結別表(別表六の二(一))の記載の要領について
この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の各欄から記載し、次に上段の各欄を記載します。
設例では、元本の所有期間に対応する金額を計算するものは、「株式及び出資」だけであり、配当の計算期間は1年で、その期間すべてにわたって所有していますので、「個別法」による計算だけを行っています。銘柄別の利子配当等の計算は、連結グループ全体の合計額を記載します。
「公社債の利子」など、他の区分で計算方法(原則法・銘柄別簡便法)を選択する場合には、連結法人全体で原則法あるいは、銘柄別簡便法を選択することができます。
中段で集計した「公社債の利子等」の合計額は、上段の公社債の利子等(「2」欄)へ、「利益の配当及び剰余金の分配」の合計額は、上段の利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当を除く。)(「3」欄)へ、「投資信託及び特定目的信託の収益の分配」の合計額は、上段の投資信託及び特定目的信託の収益の分配(「4」欄)へ転記します。
所得税法174条3号から10号までに規定する給付補てん金等並びに懸賞金等及びみなし配当等がある場合には、中段下部の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に記載して、その合計額を上段のその他(「5」欄)へ転記します。
別表六の二(一)上段の計(「6欄」)③は、別表一の二(一)「各連結事業年度の連結所得にかかる申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分」の所得税の額(「41」欄)へ転記され、税額控除の対象となった所得税額は、別表四の二「連結所得金額の計算に関する明細書」の法人税額から控除される所得税額(「37」欄)に転記されて、損金不算入(加算・その他)の取扱いとなります。
(5) 個別帰属額の計算
所得税額控除の各連結法人の個別帰属額の計算は、元本所有期間対応部分のみが控除対象となる「公社債の利子」「利益の配当及び剰余金の分配」「投資信託等の収益の分配」とその全額が控除対象となるその他に区分して計算し、その合計額となります(法令155の44)。
① 元本所有期間対応部分のみが控除対象となるもの
ア 原則(個別)法により計算した場合
原則法により計算した金額の合計額
イ 銘柄別簡便法により計算した場合
次の算式で計算された銘柄別の個別帰属額の合計額
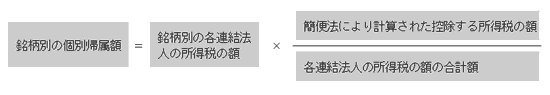
② 預貯金の利子その他その全額が控除対象となるもの
その所得税の額の全額
③ 各連結法人の個別帰属額
①+②
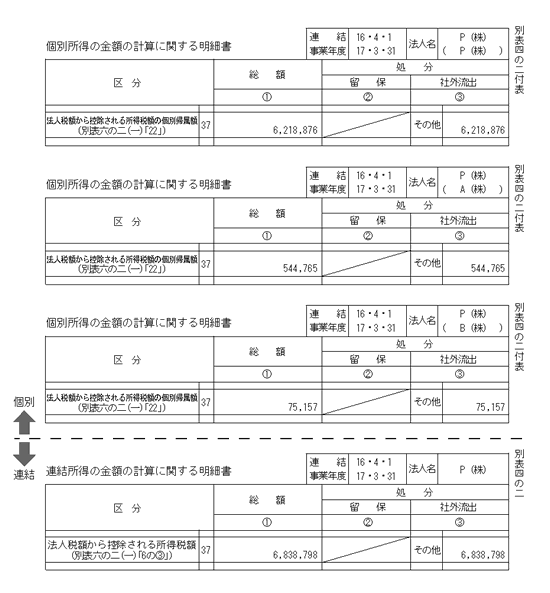
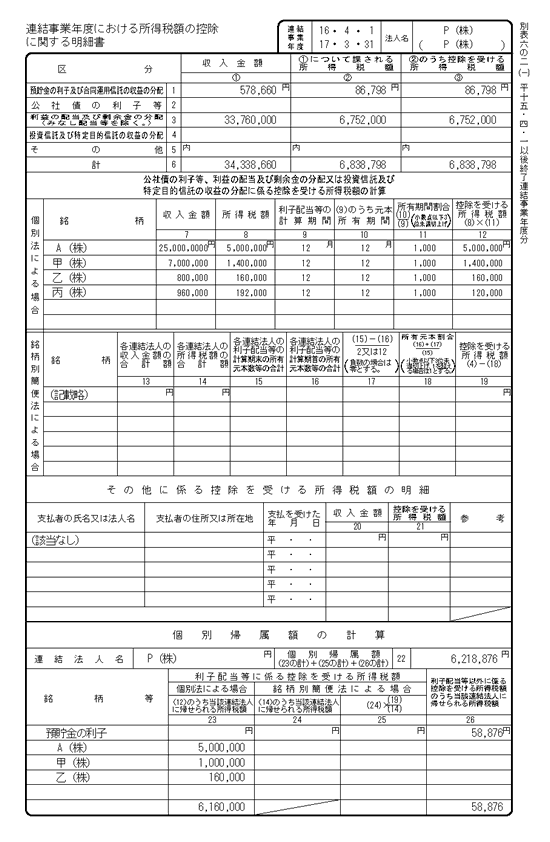
別表上の個別帰属額の計算は、別表六の二(一)下段の個別帰属額の計算で次のように行います。
① 元本所有期間対応部分のみが控除対象となるもの
ア 原則(個別)法により計算したもの
当該連結法人が課されたものについて、別表六の二(一)の「23」欄で集計します。
イ 銘柄別簡便法により計算したもの
各連結法人の所得税額を「24」欄に記載し、銘柄別の個別帰属額を「25」欄で計算・集計します。
② 預貯金の利子その他でその全額が控除対象となるもの
「26」欄で集計します。
③ 各連結法人の個別帰属額
「23」の計・「25」の計・「26」の計の合計額を個別帰属額(「22」欄)に記載します。
各連結法人の個別帰属額は、各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書の所得税の額の個別帰属額(「33」欄)及び個別所得の金額に関する明細書(別表四の二付表)の法人税額から控除される所得税額の個別帰属額(「37」欄)に転記します。
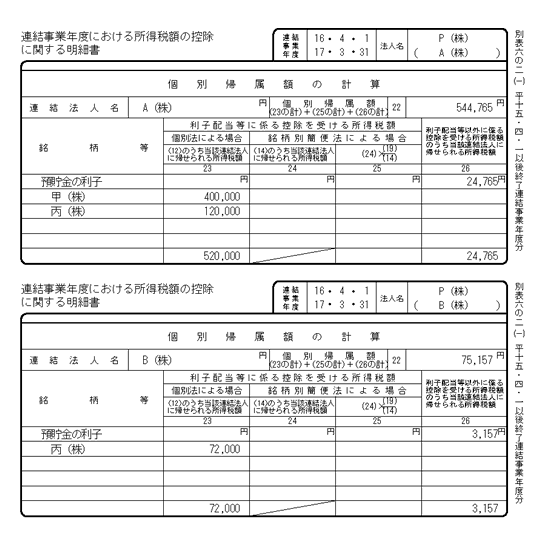
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























