解説記事2004年04月05日 【相続税務に必要な民法のミニ知識】 相続時精算課税制度と遺留分の関係は?(2004年4月5日号・№061)
実務解説
相続税務に必要な民法のミニ知識1
相続時精算課税制度と遺留分の関係は?
税理士・公認会計士 田中義幸
相続時精算課税制度を適用して親が特定の子に生前贈与をする。そんなとき民法の遺留分の関係はどうなるのか、ちょっと気になるところです。
1 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、相続による財産の移転を前倒しで実行した場合に、2,500万円の特別控除をした上で20%の贈与税を予め課しておいて、後の相続時に行う相続税の計算でそれを精算するという制度です。
相続時精算課税制度は、年齢65歳以上の者から20歳以上の直系卑属で推定相続人に該当する者が贈与により財産を取得した場合に、その財産を取得した者の選択により、その贈与により取得した財産に対する贈与税及び相続税について適用されます(相21の9~21の18)。
2 相続時精算課税制度を適用した場合の違い
この相続時精算課税制度を用いた場合と用いなかった場合とで、相続税の総額に違いがあるかどうかですが、相続税の課税標準となる課税価格には相続又は遺贈により取得した財産だけでなく、相続時精算課税制度を適用した財産も含めることになりますので、この制度の適用いかんによって相続税の総額に違いが生じないことは言うまでもありません。
ただし、相続時精算課税制度の適用を受けると、贈与を受けた時の財産の価額が相続税の課税価格になってきますので、評価額の変動があれば相続税の総額も影響を受けて変わってくることになります。そうなった場合には、相続時精算課税制度の適用を受けたことによるプラス面を誰が享受し、マイナス面を誰が負うかという問題が生じるかもしれません。
3 遺留分とは
次に遺留分の問題です。個人の財産は自由に処分できるのが原則ですが、相続の場合には一定の制限が設けられています。最小限度の相続財産を、配偶者や子供に残さなければならないからです。これを「遺留分」といい、直系尊属のみが相続人であるときは財産の3分の1、その他の場合は財産の2分の1と決められています。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません(民1028)。遺留分権利者である子供や配偶者が、この遺留分をもらえない状態になっているときは、贈与や遺贈によって受取っている者に対して、その財産の返還や金銭による弁償を請求することができます(民1031、1041)。
この「遺留分減殺請求権」は、相続が開始して遺留分が侵害されていることが現実のものとなったときにはじめて行使できることになります。相続開始前には、遺留分を侵害することが明らかな贈与がなされる場合であっても、減殺を請求することはできません。
遺留分は、相続税の観点からすれば、受贈者や受遺者、相続人の間の相続財産の分割に関する問題に過ぎません。相続財産を法定相続分で分割したものとして計算される相続税の総額においては遺留分の問題は生じません。つまり、遺留分の減殺があろうとなかろうと、相続税の総額は変わらないのです。
4 遺留分算定の基礎
遺留分の算定は、被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額にその贈与した財産の価額を足して、債務の全額を引いたものがベースになります(民1029)。
遺留分算定の基礎に算入する贈与は原則として相続開始前の1年内にしたものに限りますが、遺留分を侵害することを知っていたときは、1年前以前の分であっても遺留分算定の基礎に加えることとされています(民1030)。
相続時精算課税制度を適用して生前贈与された財産について、どのように取扱うことになるかですが、この制度がそもそも贈与と相続の一体化措置として設けられ、生前贈与と相続との資産移転の時期の選択に対する税制の中立性を維持するという趣旨に基づくものであることからすれば、相続時精算課税制度を適用して生前贈与された財産は遺留分算定の基礎に加えられるものと考えるのが相当でしょう。
5 相続時精算課税制度はどう絡むか
相続時精算課税制度の適用を受けた相続人が遺留分を返還した場合に、その返還した財産に対応する税額は負担しなくていいことになるわけですが、その返還した財産の評価額とそれに係る税額はどう計算するのかという問題があります。一方、遺留分権利者の方では取得した遺留分に見合う税額を負担することになりますが、そのときの評価額は贈与時の評価額になるとすると、これとの対称性を考えると、遺留分を返還した受贈者又は受遺者の方の減額になる評価額も贈与時の評価額になると考えられます。
課税上は、相続税の総額に変わりありませんのであまり問題にならないようですが、相続人同士の間では相続時精算課税制度の適用を受けたことによるプラス面マイナス面をどうするかという点も含めて、評価額をどの時点のものとして税額の精算をするかが問題になるケースもあるでしょう。
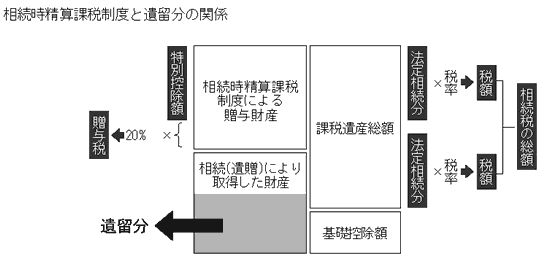
相続税務に必要な民法のミニ知識1
相続時精算課税制度と遺留分の関係は?
税理士・公認会計士 田中義幸
相続時精算課税制度を適用して親が特定の子に生前贈与をする。そんなとき民法の遺留分の関係はどうなるのか、ちょっと気になるところです。
1 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、相続による財産の移転を前倒しで実行した場合に、2,500万円の特別控除をした上で20%の贈与税を予め課しておいて、後の相続時に行う相続税の計算でそれを精算するという制度です。
相続時精算課税制度は、年齢65歳以上の者から20歳以上の直系卑属で推定相続人に該当する者が贈与により財産を取得した場合に、その財産を取得した者の選択により、その贈与により取得した財産に対する贈与税及び相続税について適用されます(相21の9~21の18)。
2 相続時精算課税制度を適用した場合の違い
この相続時精算課税制度を用いた場合と用いなかった場合とで、相続税の総額に違いがあるかどうかですが、相続税の課税標準となる課税価格には相続又は遺贈により取得した財産だけでなく、相続時精算課税制度を適用した財産も含めることになりますので、この制度の適用いかんによって相続税の総額に違いが生じないことは言うまでもありません。
ただし、相続時精算課税制度の適用を受けると、贈与を受けた時の財産の価額が相続税の課税価格になってきますので、評価額の変動があれば相続税の総額も影響を受けて変わってくることになります。そうなった場合には、相続時精算課税制度の適用を受けたことによるプラス面を誰が享受し、マイナス面を誰が負うかという問題が生じるかもしれません。
3 遺留分とは
次に遺留分の問題です。個人の財産は自由に処分できるのが原則ですが、相続の場合には一定の制限が設けられています。最小限度の相続財産を、配偶者や子供に残さなければならないからです。これを「遺留分」といい、直系尊属のみが相続人であるときは財産の3分の1、その他の場合は財産の2分の1と決められています。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません(民1028)。遺留分権利者である子供や配偶者が、この遺留分をもらえない状態になっているときは、贈与や遺贈によって受取っている者に対して、その財産の返還や金銭による弁償を請求することができます(民1031、1041)。
この「遺留分減殺請求権」は、相続が開始して遺留分が侵害されていることが現実のものとなったときにはじめて行使できることになります。相続開始前には、遺留分を侵害することが明らかな贈与がなされる場合であっても、減殺を請求することはできません。
遺留分は、相続税の観点からすれば、受贈者や受遺者、相続人の間の相続財産の分割に関する問題に過ぎません。相続財産を法定相続分で分割したものとして計算される相続税の総額においては遺留分の問題は生じません。つまり、遺留分の減殺があろうとなかろうと、相続税の総額は変わらないのです。
4 遺留分算定の基礎
遺留分の算定は、被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額にその贈与した財産の価額を足して、債務の全額を引いたものがベースになります(民1029)。
遺留分算定の基礎に算入する贈与は原則として相続開始前の1年内にしたものに限りますが、遺留分を侵害することを知っていたときは、1年前以前の分であっても遺留分算定の基礎に加えることとされています(民1030)。
相続時精算課税制度を適用して生前贈与された財産について、どのように取扱うことになるかですが、この制度がそもそも贈与と相続の一体化措置として設けられ、生前贈与と相続との資産移転の時期の選択に対する税制の中立性を維持するという趣旨に基づくものであることからすれば、相続時精算課税制度を適用して生前贈与された財産は遺留分算定の基礎に加えられるものと考えるのが相当でしょう。
5 相続時精算課税制度はどう絡むか
相続時精算課税制度の適用を受けた相続人が遺留分を返還した場合に、その返還した財産に対応する税額は負担しなくていいことになるわけですが、その返還した財産の評価額とそれに係る税額はどう計算するのかという問題があります。一方、遺留分権利者の方では取得した遺留分に見合う税額を負担することになりますが、そのときの評価額は贈与時の評価額になるとすると、これとの対称性を考えると、遺留分を返還した受贈者又は受遺者の方の減額になる評価額も贈与時の評価額になると考えられます。
課税上は、相続税の総額に変わりありませんのであまり問題にならないようですが、相続人同士の間では相続時精算課税制度の適用を受けたことによるプラス面マイナス面をどうするかという点も含めて、評価額をどの時点のものとして税額の精算をするかが問題になるケースもあるでしょう。
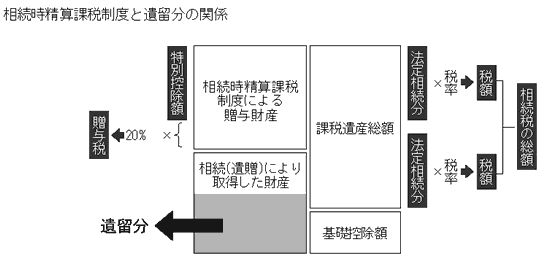
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















