資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税徴収法基本通達 第5章 滞納処分
第5章 滞納処分
第1節 財産の差押え
第1款 通 則
第47条関係 差押えの要件
違法性の承継
(滞納処分相互間)
1 督促又は差押処分の違法性は、その後おける差押え、換価又は配当処分に承継される(大正15.7.20行判、昭和9.7.24行判)。
(賦課処分との関係)
2 賦課処分と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、賦課処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、賦課処分が取り消すことのできるものであっても、その処分が取り消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また賦課処分が取り消されても、その取消し前に完結した滞納処分の効力には影響がない(昭和26.2.28鳥取地判、昭和26.7.4広島高判、昭和39.4.16仙台高判)。
(納付通知書による告知との関係)
3 第二次納税義務者及び保証人に対する納付通知書による告知(以下3において「告知」という。)と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、告知処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、告知処分が取り消すことのできるものであっても、その処分が取消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また告知処分が取り消されても、その取消し前に完結した滞納処分の効力には影響がない(昭和37.3.23大阪地判)。
差押えをすることができる者
4 法第47条の「徴収職員」とは、法第2条第11号((徴収職員の定義))に掲げる徴収職員のうち、差押えをする際における納税者の国税の納税地を所轄する税務署に所属する徴収職員をいい(通則法43条1項)、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる徴収職員をいう。なお、滞納処分の引継ぎ(法182条2項、183条2項、3項)を受けた税務署、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)又は税関(沖縄地区税関を含む。以下同じ。)に所属する徴収職員も、法第47条の「徴収職員」に含まれる。 (1) 通則法第43条第2項((納税地の移動があった場合の国税の徴収の所轄庁))の規定により税務署長が国税の徴収に係る処分をする場合その税務署に所属する徴収職員
(2) 通則法第43条第3項((徴収の引継ぎ))又は第44条第1項((徴収の引継ぎ))の規定により税務署長、国税局長又は税関長が徴収の引継ぎを受けた場合その引継ぎを受けた税務署、国税局又は税関に所属する徴収職員
(3)
通則法第43条第1項ただし書((税関長が課する消費税等の徴収の所轄庁))の規定により税関長が消費税等の徴収をする場合 その税関に所属する徴収職員
差押えの対象となる財産
(財産の帰属)
5 差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に帰属しているものでなければならない(20参照)。
(財産の所在)
6 差押えの対象となる財産は、法施行地域内にあるものでなければならない。
なお、財産の所在については、相続税法第10条((財産の所在))に定めるところに準ずるものとする。
(財産が金銭的価値を有すること)
7 差押えの対象となる財産は、金銭的価値を有するものでなければならない。
なお、次のことに留意する。 (1) 金銭又は物の給付を目的としない行為(例えば、演奏をすること)又は不作為(例えば、競業をしないこと)を目的とする債権は、差押えの対象とならない。ただし、これらの債権が債務不履行等により損害賠償請求権となった場合には、差し押さえることができる。
(2) 金銭又は物を第三者に給付することを請求する債権は、納税者にとって金銭的価値を有しないから、差押えの対象とならない。ただし、これらの債権が債務不履行等により納税者の損害賠償請求権となった場合には、差し押さえることができる。
(財産が譲渡又は取立てができるものであること)
8 差押えの対象となる財産は、譲渡又は取立てができるものでなければならない。
なお、次のことに留意する。 (1) 有価証券のうち、指図禁止の手形及び小切手については、手形法第11条第2項((指図禁止の場合の譲渡の方式等))又は小切手法第14条第2項((指図禁止の場合の譲渡の方式等))の規定により、指名債権の譲渡に関する方式に従い、かつ、その効力をもってだけ譲渡することができる(民法467条、468条参照)。したがって、当該手形等に係る債権は、法第62条((差押の手続及び効力発生時期))の規定により差し押さえることができる。
(2) 相続権、扶養請求権、慰謝料請求権、財産分与請求権等は、納税者の一身に専属する権利であるから、譲渡することができない。ただし、その権利の行使により、金銭債権等の具体的債権となったときは、その債権を差し押さえることができる。
(3) 要役地の所有権に従たる地役権又は債権に従たる留置権、先取特権、質権若しくは抵当権は、主たる権利とともにするのでなければ譲渡することができない。したがって、これらの権利は、独立したものとして差し押さえることができない。 (注)1 抵当権については、民法第375条((抵当権の処分))の規定により譲渡することができるが、この譲渡には、滞納処分による権利の移転は含まれない。
2 根抵当権は、民法第398条ノ2((根抵当権の譲渡))の規定により元本の確定前は根抵当権設定者の承諾を得て譲渡することができるが、この譲渡には、滞納処分による権利の移転は含まれない。
(譲渡禁止の特約がある財産の差押え)
9 譲渡禁止の特約がある財産でも、差し押さえることができる。 (注) 譲渡禁止の特約が登記されている永小作権の換価は、永小作権設定者の同意を得てその特約の登記を抹消した後でなければ、することができない(民法272条ただし書、不動産登記法112条)。
差押えができる場合
(督促をした場合)
10 法第47条第1項第1号の「督促」とは、通則法第37条((督促))の規定による督促状による督促及び法第32条第2項((納付催告書による督促))又は通則法第52条第3項((納付催告書による督促))の規定による納付催告書による督促をいう(法47条3項参照)。滞納者がこの督促を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。
(公示送達による場合)
11 督促状又は納付催告書を公示送達により送達した場合は、通則法第14条第2項((公示送達の場合の掲示))の掲示を始めた日から起算して10日を経過した日までに督促に係る国税が完納されないときに、差押えができるものとする。
(納期限)
12 法第47条第1項第2号の「納期限」とは、次に掲げるものをいう。
なお、延滞税及び利子税の納期限は、その計算の基礎となる国税の納期限とされている(通則法37条1項本文)。 (1) 繰上請求がされた国税(通則法38条1項)繰上請求に係る期限 (注) 繰上請求は、繰上げに係る期限等を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で、納税の告知がされていないものについては、その請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う(通則法38条2項)。
(2) 繰上保全差押金額の決定の基因となった国税(通則法38条3項前段参照) その国税の納期限
(3) 保全差押金額の決定の基因となった国税(法159条1項前段参照) その国税の納期限 (例) 保全差押金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60万円
確定した国税(各種加算税を含む。第159条関係21の
(注)1参照)の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
この場合の決定の基因となった国税は、100万円である。
(4) 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税(第2条関係21参照)納税告知書に記載された納期限
(完納しないとき)
13 法第47条第1項の「完納しないとき」とは、納税者又は滞納者その他第三者の納付又は充当により、国税の全額が納付されていない場合のほか、免除又は賦課の取消し等により、徴収しようとする金額に係る国税の全額が消滅していないときをいう。なお、本税額の全額が納付され、延滞税又は利子税だけが未納である場合には、督促がされている延滞税又は利子税だけについて差し押さえることができる(通則法37条1項、3項)。
(繰上差押え)
14 法第47条第2項の繰上差押えについては、次のことに留意する。 (1) 「直ちにその財産を差し押さえることができる」とは、督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日以前でも督促に係る国税につき納税者の財産を差し押さえることができることをいう。
(2) 「国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたとき」には、督促以前に生じた事実が督促後まで継続しているときも含まれる。
(3) 繰上差押えをする場合には、差押調書又は差押書の「備考」欄にその旨を付記するものとする。
(賦課等の処分が争われている場合の差押え)
15 課税に関する処分、告知又は督促について、不服申立て又は訴訟が係属中であつても、その処分の取消しがされるまでは、その不服申立て又は訴訟に係る国税についての差押えをすることができる(通則法105条1項、行政事件訴訟法25条1項)。
差押えができない場合
16 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる期間内は、新たな差押えをすることができない。
なお、納税者が、保全差押金額又は繰上保全金額に相当する担保を提供して、保全差押え等をしないことを求めたときは差押えをすることができず(法159条4項、通則法38条4項)、また、換価の猶予に伴い差押えを猶予した場合又は不服申立てに伴い差押えを猶予した場合には差押えをすることができない(法151条2項、通則法105条3項、6項)。 (1) 納税の猶予(通則法46条1項から3項まで、会社更生法122条1項)又は徴収の猶予(通則法23条5項、105条2項、6項、所得税法118条、相続税法40条1項、42条5項、資産再評価法87条5項、会社更生法122条1項等)をしている場合 その猶予に係る国税につきその猶予期間
(2) 滞納処分の停止(法153条)をしている場合 その停止に係る国税につきその停止期間
(3) 滞納処分等の中止命令がされた場合(会社更生法37条2項、3項)又は更生手続の開始決定に伴う滞納処分等の中止の場合(同法67条2項、3項) その国税につき滞納処分の中止期間
(4) 企業担保権の実行手続の開始決定があった場合(企業担保法28条参照) その係属期間
(5) 破産宣告を受けた場合(37参照) その係属期間
財産の選択
17 差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量によるが、次に掲げる事項に十分留意して選択を行うものとする。この場合において、差し押さえるべき財産について滞納者の申出があるときは、諸般の事情を十分考慮の上、滞納処分の執行に支障がない限り、その申出に係る財産を差し押さえるものとする。 (1) 第三者の権利を害することが少ない財産であること(第49条関係参照)。
(2) 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。
(3) 換価に便利な財産であること。
(4) 保管又は引揚げに便利な財産であること。
(5) 価額の変動が少ない財産であること。
差押えの時期
(着手前の催告)
18 督促状もくしくは納付催告書又は譲渡担保権者に対する告知書を発した後6月以上を経て差押えをする場合には、あらかじめ、催告をするものとする。
(夜間、休日の差押え)
19 夜間及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日において個人の住居に立ち入つて行う差押えについては、特に必要があると認められる場合のほかは、これらの時間は又は日において行わないものとする(執行法8条1項参照)。
財産帰属の認定
(一般の帰属認定)
20 財産が滞納者に帰属するかどうかの判定は、次に掲げる事項を参考として行うものとする(5参照)。 (1) 動産及び有価証券にあつては、滞納者が所持していること(民法186条参照)。ただし、他人の所有に属することが明らかなものを除くこと。
なお、有価証券の所持人が取立委任裏書又は質入裏書の被裏書人である場合には、その所持人の財産としてその有価証券を差し押さえることはできないこと。
(2) 登録公社債等にあっては、登録名義が滞納者であること(国債二関スル法律3条、社債等登録法5条1項)。
(3) 登記された不動産、船舶、建設機械、自動車、航空機及び電話加入権、地上権、鉱業権等の権利並びに特許権その他の無体財産権等については、登記の名義人が滞納者であること。
(4) 未登記の不動産所有権その他の不動産に関する権利及び未登録の著作権については、その占有の事実、家屋補充課税台帳(又は家屋台帳)、土地補充課税台帳(又は土地台帳)その他帳簿書類の記載等により滞納者に帰属すると認められること。
(5) 合名会社及び合資会社の社員の持分については、定款又は商業登記簿における社員の名義が滞納者であること(商法12条、63条、64条、67条、147条、商業登記法60条、71条、74条等参照)。
(6) 有限会社の社員の持分については、定款又は社員名簿における名義人が滞納者であること(有限会社法6条、20条)。
(7) 債権については、借用証書、預金通帳、売掛帳その他取引関係帳簿書類等により、滞納者に帰属すると認められること。
(滞納者の名義でない場合の帰属認定)
21 20の(1)から(3)までに掲げる財産並びに(5)及び(6)に掲げる財産については、所持している者又は登記の名義人(以下21において「名義人等」という。)が滞納者でない場合であつても、帳簿書類、当事者の陳述等に基づき次に掲げる事項が明らかであるときは、その財産は、滞納者に帰属しているのであるから、滞納者の財産として差し押さえることができる。この場合においては、登記の名義を滞納者に変更させる必要がある。 (1) その財産が売買、贈与、交換、出資、代物弁済等により、滞納者に譲渡されたこと。
(2) 滞納者がその財産を仮装売買等無効な法律行為により、名義人等に譲渡したこと。
(3) 相続、包括遺贈又は合併に基づく一般承継により、財産の所有権が滞納者に移転していること。
(4) 上記を除くほか、権利が滞納者に帰属しているにもかかわらず、登記の名義が滞納者以外の者となつていること。 (注) 農地の所有権を移転する場合には、農業委員会又は都道府県知事の許可がない限りその効力を生じないが、この許可を得ている場合においても、虚偽表示により所有名義人となっているにすぎない者は、農地の所有権を取得しない(昭和52.2.17最高判参照)。
(夫婦又は同居の親族の財産の帰属認定)
22 滞納者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下(3)及び(4)において同じ。)又は同居の親族が主として滞納者の資産又は収入によって生計を維持している場合には、その滞納者の住居にある財産は、その滞納者に帰属するものと認定して差し支えない。ただし、次に掲げる財産はこの限りでない。 (1) 配偶者が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名において得た財産(民法762条1項)
(2) 配偶者が登記された夫婦財産契約に基づき所有する財産(民法756条、夫婦財産契約登記取扱手続参照)
(3) (1)及び(2)に掲げる財産以外の財産で配偶者又は親族が専ら使用する財産(昭和12.6.17行判)
(4) 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産についての配偶者の持分(民法762条2項参照)
特殊な財産の差押え
(共有財産)
23 差し押さえるべき財産が法律の規定又は当事者の意思表示により共有となっている場合において、それぞれの持分が定まっていないとき(持分が明らかでないときを含む。)は、その持分は等しいものと推定して差し押さえることができる(民法250条参照)。
(取消しうべき法律行為又は契約の解除の目的となった財産)
24 滞納者が、その財産について、売買、贈与その他による譲渡又は権利の設定等をした場合において、その譲渡等の行為が取消しうべき行為(民法4条2項、9条、12条3項、96条1項及び2項等)であるとき又は契約を解除(同法541条、542条、543条等)できるときは、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者の代位))の規定により滞納者に代位してその行為を取り消し、又はその契約を解除し、その財産を滞納者の財産として差し押さえることができる。ただし、その行為の取消し又は契約の解除の効果を第三者に対して主張できない場合がある(民法96条3項、545条1項ただし書等参照)。
(条件付又は期限付の譲渡の目的となった財産)
25 差し押さえた財産が、差押えの当時条件付又は期限付の売買、贈与等の譲渡の目的となつていた場合(民法129条参照)においては、差押え後、その条件の成就又は期限の到来により権利を取得した者は、その権利の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができない(大正6.4.10行判)。ただし、その権利を保全する仮登記が差押え前からあるときは、その権利の取得をもって差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(売買予約の目的となった財産)
26 差し押さえた財産が、差押えの当時売買予約の目的となっていた場合には、差押え後におけるその売買を完結する意思表示により所有権を取得した者は、その所有権を持って差押債権者である国に対抗することができない。ただし、その権利を保全する仮登記が差押え前からあるときは、その所有権の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(買戻しの特約等の目的となった財産)
27 差し押さえた財産が、差押えの当時買戻しの特約又は再売買の予約の目的となっていても、差押え後における買戻権の行使又は再売買の予約完結権の行使による所有権の取得をもって、差押債権者である国に対抗することができない。ただし、買戻の特約の登記(民法581条1項、不動産登記法37条、59条ノ2)又は再売買の予約に係る所有権移転請求権の仮登記(不動産登記法2条2号)が差押え前にあるときは、その所有権の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(譲渡担保財産)
28 譲渡担保財産は、譲渡担保権者に属する財産としてその譲渡担保権者の滞納国税につき差し押さえることができ、またその譲渡人の滞納国税につき法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により差し押さえることができる(令9条参照)。
(信託の目的となつた財産)
29 信託の目的となつた財産は、信託の終了又は解除があったときは、信託財産の帰属権利者の財産として差し押さえることができる(信託法61条、62条参照)。
なお、信託法第57条((信託の解除))の規定に該当する場合には、委託者又はその相続人の滞納国税を徴収するため、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者の代位))の規定により委託者又はその相続人に代位して信託を解除することができ、また信託法第58条((信託の解除))の規定に該当する場合には、受益者の滞納国税を徴収するため、受益者に代位して、裁判所に対し信託の解除を請求することができる。 (注) 納税者(委託者)が、国税の差押えを免れるため自己の財産を信託の目的とした場合には、信託法第12条((信託による詐害行為の取消し))の規定により、その信託契約の取消しを裁判所に請求することができる。この場合においては、譲受人(受託者)が善意であっても取消しを請求することができる。
(担保のための仮登記のある財産)
30 25から27までにおける仮登記が担保のための仮登記である場合には、法第23条((法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等))及び第52条の2((担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力))の規定が適用される。
(仮差押え又は仮処分の目的となった財産)
31 仮差押え又は仮処分の目的となっている財産については、法第140条((仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力))の規定により、滞納処分をすることができる。
(強制管理の目的となった財産)
32 強制管理の開始決定(執行法93条)の目的となつた不動産及び当該不動産の果実についても、滞納処分をすることができる。
(滞調法の適用を受ける財産)
33 強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている財産についても、滞調法の規定(21条、29条、35条等)により、滞納処分をすることができる。
(和議の開始された者の財産)
34 和議の開始された者の財産については、国税は和議債権ではないし(和議法42条参照)、また滞納処分ができない旨の規定がないので(同法40条参照)、滞納処分をすることができる。
(整理又は特別清算の開始された会社の財産)
35 商法第381条((整理の開始))又は第431条((特別清算の開始))の規定による整理又は特別清算の開始があつた場合の会社の財産については、国税は同法第383条第2項((破産、和議、強制執行、保全処分等の中止))(433条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないから、滞納処分をすることができる。
(法令等による譲渡制限がある財産)
36 麻薬類、銃砲・刀剣類等その譲渡若しくは所有等について法令上制限が付されている財産(第89条関係14から27まで参照)又は定款によつて譲渡制限の付されている株式(商法204条1項、204条ノ5)についても、滞納処分をすることができる。
(留置権による競売の開始された財産)
37 滞納者の財産について留置権による競売が開始された場合には(執行法195条参照)、滞納者が留置権者に対して有する残余金の交付請求権を差し押さえるものとする。 (注) 留置権による競売に対しては、交付要求をすることができない(第2条関係26の(注)参照)。
(未分離の果実)
38 農作物等土地から分離する前の天然果実については、おおむね1月以内に収穫することが確実であるものを除き、差押えをしないものとする(執行法122条1項参照)。
破産宣告を受けた者の財産に対する滞納処分
(破産管財人に対する交付要求)
39 滞納者が破産宣告を受けた場合(破産法1条参照)には、その滞納者の破産財団(同法6条参照)に属する財産に対しては、財団債権である国税による新たな滞納処分は行わないものとし、破産管財人に対して交付要求をする(昭和45.7.16最高判参照)。 (注)1 財団債権である国税とは、破産宣告前の原因に基づく国税及び破産宣告後の原因に基づく国税のうち破産財団に関して生じたものをいう(破産法47条2号)。
2 破産管財人が交付要求に応じない場合には、破産裁判所に破産管財人に対する監督権の発動を促し、必要に応じ、破産管財人に対する損害賠償の責任を追及する(破産法161条、164条参照)。
(滞納処分の続行)
40 破産財団に属する財産について、破産宣告前に滞納処分に着手しているときは、破産宣告後も、その続行をすることができる(破産法71条1項)。この続行できる滞納処分には、破産宣告前に行つた参加差押え、債権の二重差押え(第62条関係6参照)及び滞調法の規定による二重差押えが含まれる。 (注) 破産宣告前に滞納処分の前提となる行為に着手している場合には、それに引き続いてする滞納処分、例えば、破産宣告前に捜索に着手した場合におけるそれに引き続いて行う差押え、詐害行為取消訴訟を提起した後に破産宣告があった場合におけるその勝訴に基づく差押え(昭5.11.29大判)は、破産宣告によって妨げられない。
(行政機関等に対する交付要求)
41 行政機関等が破産宣告前に着手した滞納処分を破産宣告後に続行する場合には、その行政機関等に対して交付要求を行い、参加差押えは行わないものとする。
(別除権の行使)
42 国税の担保として提供されている財産については、破産宣告後においても、別除権の行使として、通則法第52条第1項((担保の処分))の規定に基づく滞納処分の例による差押えをすることができる(破産法95条、203条1項参照)。
なお、私債権者の申立てにより別除権の行使として担保権の実行手続が開始された場合には、その執行機関に対して交付要求をする。また、行政機関等が、担保の処分として滞納処分の例による差押えをした場合においては、交付要求を行い、参加差押えは行わないものとする。 (注) 別除権とは、次のものをいう。 1 破産財団に属する財産について存する特別の先取特権、質権及び抵当権(電話加入権質に関する臨時特例法、工場抵当法等の特別法によるものも含む。)(破産法92条)
2 破産財団に属する財産について存する商法上の留置権(破産法93条)
3 共有者の一人が破産の宣告を受けた場合において、分割によりその破産者に帰すべき共有財産の部分について、他の共有者が破産者に対して有する共有に関する債権(破産法94条)
4 破産財団に属する財産について存する担保仮登記に係る権利(仮登記担保法19条1項)
(破産後取得した財産)
43 破産宣告を受けた者が破産宣告後取得した財産については、破産財団に属さないから、滞納処分をすることができる。
なお、破産者は、国税については免責されない(破産法366条ノ12第1号)。
会社更生法の適用を受ける会社の財産に対する滞納処分
(開始決定前の滞納処分等の中止命令)
44 更生手続開始の申立てがあつた場合において、更生裁判所は、必要があると認めるときは、あらかじめ税務署長に意見を聞いた上で滞納処分又は国税の担保のために提供された物件の処分(以下45及び47において「滞納処分等」という。)の中止を命ずることができる(会社更生法37条2項)。ただし、その中止命令は、更生手続開始の申立てにつき決定があったとき又は中止の決定の日から2月を経過したときは、その効力を失う(同法37条3項)。
(開始決定による滞納処分等の中止等)
45 更生手続開始の決定があつたときは、その決定の日から更生計画認可若しくは更生手続終了までの間又はその決定の日から1年間(税務署長に同意を得た上で伸長されることがある。会社更生法67条3項、4項)か、いずれか短い期間内は、共益債権となる国税(48の(注)参照)を除き滞納処分等はすることができず、既にされている滞納処分等は中止される(同法67条2項)。
なお、更生裁判所は、中止した滞納処分等の続行又は取消しを命ずることができる(会社更生法67条6項)。 (注) 更生手続終了とは、開始決定の取消し(会社更生法51条)、更生手続の廃止(同法273条、273条の2,274条、277条)及び更生計画の不認可(同法238条)の各決定をいい、その効力は、公告の最終の掲載があつた日の翌日から生ずる(同法12条2項)。
(更生計画における納税の猶予、減免等)
46 更生計画において、国税について納税の猶予、換価の猶予、減免、承継その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、税務署長の意見を聞かなければならないとき(例えば、3年以下の期間の納税の猶予又は換価の猶予の定めをする場合等)と、その同意を得なければならないとき(例えば3年を超える期間の納税の猶予又は換価の猶予の定めをする場合等)とがある(会社更生法122条1項から3項まで)。
(共益債権となる国税以外の国税の徴収)
47 更生会社に対する共益債権である国税以外の国税については、原則として更生手続により弁済を受けることになるので(会社更生法112条)、税務署長は、遅滞なくその額、原因及び担保権の内容を更生裁判所に届け出なければならない(同法157条1項。241条参照)。
なお、滞納処分等又はその続行が許される場合等においては、更生手続によらずに弁済等を受けることがでできる(同法112条ただし書、112条の2第4項)。ただし、更生会社の財産が共益債権の総額を弁済するに足りないことが明らかになつた後は、新たな滞納処分等又は中止していた滞納処分等の続行は行わないものとする(昭和56.5.6大阪高判)。また、共益債権である国税以外の国税について、更生会社が税務署長に対して行つた担保の供与又は債務の消滅に関する行為は、否認権の対象とならない(同法78条2項)。 (注) 共益債権となる国税以外の国税としては、更生債権となる国税(更生手続開始前の原因に基づいて生じた国税。会社更生法102条)、更生担保権となる国税(更生債権となる国税又は更生手続開始前の原因に基づいて生じた更生会社以外の者に対する国税で、更生手続き開始当時更生会社財産の上に存する担保権によつて担保される国税。同法123条1項)及び劣後的更生債権となる国税(更生債権となる国税のうち、更生手続開始前の脱税が摘発され、開始後に刑罰に処せられ又は国税犯則取締法による通告処分を履行した場合におけるほ脱国税で届出のないもの。会社更生法121条1項6号)がある。
(共益債権となる国税の徴収)
48 共益債権となる国税については、更生手続によらないで更生債権及び更生担保権に先立つて随時弁済されるが(会社更生法209条)、更生管財人がこの弁済に応じないときは、更生手続中であつても滞納処分をすることができる(この場合における差押登記の嘱託の受理については、昭和42.9.7付民事甲第2,524号法務省民事局長通達参照)。ただし、更生会社の財産が共益債権の総額を弁済するに足りないことが明らかになつたときは、担保権によつて担保されるものを除き、まだ弁済されていない共益債権の債権額の割合に応じて弁済されることになるので(同法210条)、滞納処分はできないことに留意する(昭和54.2.16大阪地判)。
なお、共益債権である国税に劣後する担保権により、その実行手続が開始された場合には、その国税について執行機関に交付要求をする(同法210条参照)。 (注) 共益債権となる国税としては、次のものがある。 1 更生債権のうち、源泉徴収にかかる所得税、消費税、酒税等で、更生手続開始当時まだ具体的納期限の到来していないもの(同法119条前段、昭和49.7.22最高判)
2 更生手続開始後の会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用に該当する国税(例えば、更生手続開始後の原因に基づいて生じた法人税等。同法208条2号)
差押えの効力
(処分の禁止)
49 差押えは、滞納者の特定財産の法律上又は事実上の処分を禁止する効力を有するものである。したがつて、差押え後におけるその財産の譲渡又は権利設定等の法律上の処分は、差押債権者である国に対抗することができない。この場合において、差押えにより禁止される法律上又は事実上の処分は、差押債権者である国に不利益となる処分に限られるから、例えば、差押財産についての賃貸借契約の解除、差押財産の改良等の処分はこれに含まれない。なお、債権の差押えに当たっては、法第62条第2項((債権差押の手続))の規定により、処分禁止の趣旨を特に明示することとなつている。
(効力の保証)
50 差押えによる法律上又は事実上の処分の禁止は、法第187条((罰則))若しくは第189条((罰則))又は刑法第96条((封印破棄の罪))、第115条((放火の罪))、第120条第2項((溢水の罪))、第242条((窃盗及び強盗の罪)、第251条((詐欺及び恐喝の罪))、第252条第2項((横領の罪))若しくは第262条((毀棄の罪))の各規定により間接的に保証されている。
(効力の制限)
51 差押えによる法律上又は事実上の処分の禁止は、国、地方公共団体等の土地収用法、農地法等の規定に基づく土地収用、農地買収(未墾地等の買収に限る。)、没収(刑法19条等)等の処分を妨げるものでなく、かつ、これらの処分があつたときは、差押えの効力は失われる。
(差押え財産の消滅)
52 加入電話加入契約の解除により、電話加入権が消滅する場合(公衆電気通信法42条1項)、民法第958条((相続人捜索の公告))に規定する期間内に相続人である権利を主張する者がないことにより特許権が消滅する場合(特許法76条)等においては、その財産に係る差押えの効力は消滅することがある(実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条等)。
(時効の中断)
53 差押えに係る国税については、その差押えが効力を生じた時に時効が中断する(通則法72条3項、民法147条2号)。この場合における中断事由は、差押財産を換価した場合にはその権利が買受人に移転した時(債権取立てのときは弁済の効力が生じた時)まで、差押財産が滅失した場合(法53条1項の規定の適用がある場合を除く。)にはその滅失した時まで、差押えを解除した場合にはその解除をした時まで、それぞれ継続する。ただし、その差押えの手続が不適法を理由として取り消されたときは、時効中断の効力を生じない(民法154条)。
なお、第三者の占有する動産若しくは有価証券、物上保証人の財産若しくは法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により譲渡担保財産を差し押さえた場合又は法第22条第3項((質権等の代位実行))の規定により質権若しくは抵当権を実行した場合は、差押調書の謄本が滞納者に交付されたとき等差し押さえた旨等が滞納者に通知された時に時効が中断する(通則法72条3項、民法155条)。
(従 物)
54 主物を差し押さえたときは、その差押えの効力は従物に及ぶ(民法87条参照)。したがって、家屋を差し押さえた場合には、差押えの効力は、その家屋の従物となっている畳、建具等に及ぶ(第56条関係9参照)。
(果 実)
55 元物を差し押さえたときは、その差押えの効力は、原則として、天然果実に及ぶが、法定果実には及ばない(法52条)。
(相続等があった場合)
56 滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅した場合には、その滞納処分を続行することができるし、また滞納者の死亡を知らないで、滞納者の名義の財産を差し押さえた場合には、その差押えは、その財産を有する相続人に対してされたものとみなされる(法139条)。
(継続的な収入)
57 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入に対する債権の差押えの効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金額に及ぶ(法66条)。
(保険に付されている財産)
58 差押財産が損害保険に付され、又は火災共済協同組合の火災共済等の目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない(法53条1項)。
差押え財産を譲り受けた者に対する滞納処分
59 不動産に対し強制競売若しくは担保権の実行としての競売による差押え、仮差押え又は滞納処分による差押え(保全差押金額又は繰上保全差押金額に係る差押えを含む。以下59において同じ。)の登記があるまま、第三者に所有権移転の登記がされた場合には、当該第三者の国税を徴収するため、当該不動産に対し滞納処分による差押え(参加差押え又は滞調法29条の規定により行うことができる滞納処分による差押えで、当該第三者を滞納者とするものを含む。以下59において同じ。)をすることができる(この場合における差押登記の嘱託の受理については、昭和42.5.15付民事甲第299号法務省民事局長通達参照)。 (注) 上記の場合において、当該第三者を滞納者として行つた滞納処分による差押えに基づく換価は、譲渡人に対する差押え等の効力が失われるまでは行わない取扱いとする。
なお、次に掲げる事項に留意する。
(1) 不動産以外の登記を要する全ての財産についても、不動産と同様である。
(2) 所有権移転の登記が数次にわたつてされた場合において、その各譲受人が所有者である間に行う滞納処分についても同様である。
担保物処分の場合の差押え
60 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定による担保物の処分にあつては、督促を要しないで滞納処分の例による差押えをすることができる。
滞納処分費の差押え
61 滞納処分費だけが滞納となっている場合には、法第138条((滞納処分費の納入の告知))の規定による納入の告知の納期限後、督促を要しないで差押えをすることができる。
第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
超過差押えの禁止
(意 義)
1 法第48条第1項の規定は、徴収職員が第47条関係17の財産の選択基準に従い差押えをする場合において、国税の徴収に十分な価額の財産を選択し、差し押さえた時は、それ以外の財産の差押えをしてはならないことを定めたものである。
(財産の価額の計算)
2 1の財産の価額は、差し押さえようとする時の処分予定価額によるものとし、差押えに係る国税に優先する他の国税、地方税、公課その他の債権がある場合には、その処分予定価額からこれらの優先すると認められる債権の額に相当する金額を控除した後の価額によるものとする。
(不可分物)
3 差押財産が不可分物である場合には、その財産の価額が差押えに係る国税の額を超過するときであつても、その差押えは違法でない。
なお、上記の不可分物とは、おおむね次に掲げるものをいう。 (1) 物の性状から分割することができないもの(例えば、1個の動産)
(2) 分割することはできるが、分割することにより物の経済的価値を著しく害するもの(例えば、1棟の家屋)
(3) 法律上分割して売却することができないもの(例えば、工場財団の組成物件)
(滞納処分の引継ぎをしている場合の判定)
4 滞納処分の引継ぎをしている場合において、その引継ぎを受けた税務署長が差し押さえた財産がある時は、滞納処分の引継ぎをした税務署長が、当該財産を含めたところで超過差押えの有無を判定する取扱いとする。
無益な差押えの禁止
(財産の価額等)
5 法第48条第2項の「差し押さえることができる財産の価額」とは差押えをしようとする時における差押えの対象となる財産の処分予定価額を、「差押えに係る滞納処分費」とは差し押さえようとする財産に係る滞納処分費の見込額を、「徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額」とは差押えをしようとする時においてその差押えに係る国税に優先すると認められる他の国税、地方税、公課その他の債権のその時における債権額を、それぞれいうものとする。
(個別財産についての判定)
6 法第48条第2項の「合計額を超える見込がないとき」とは、差押えの対象となる財産についてそれぞれ個別に判定すると合計額を超える見込みがない場合をいうものとするが、これらの財産の全部又は一部を一体として判定すると合計額を超える見込みがある場合を含まないものとする。例えば、数個の不動産上に国税に優先する共同担保権が設定されている場合に、その不動産について個別に判定すると差押えに係る滞納処分費及びその被担保債権の合計額を超える見込みはないが、その数個の不動産の全部又は一部を一体として判定すると、その合計額を超える見込みのある場合は、無益な差押えにはならない。
第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
差し押さえる場合
1 法第49条の「差し押える」とは、法第47条((差押の要件))の規定により差押えをすることのほか、法第24条第3項((譲渡担保財産についての滞納処分))、第159条第1項((保全差押えによる差押え))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押えによる差押え))の規定による差押えをすることをいう。 (注) 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定に基づく滞納処分の例による差押えに当たつても、法第49条の規定の趣旨により取り扱うものとする。
滞納処分の執行上の支障
2 法第49条の「支障」とは、おおむね次に掲げる事項をいう。 (1) 第三者の権利がある財産以外に、差押えをすることができる適当な財産がないこと。
(2) 第三者の権利がある財産以外の差押えができる財産が、すべて換価の著しく困難な財産だけであること(第50条関係12参照)。
第三者の権利の保護
(第三者の権利)
3 法第49条の「第三者が有する権利」とは、第三者が有する質権、抵当権、先取特権、留置権、貸借権、使用貸借権、地上権、永小作権、地役権、租鉱権、入漁権、買戻権、出版権、特許権についての専用実施権、実用新案権についての専用実施権、意匠権についての専用実施権、商標権についての専用使用権等の権利をいう。
なお、上記の先取特権は、法第50条第1項((第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求))に規定する先取特権に限られない。
(権利の保護)
4 法第49条の「害さないように努めなければならない」とは、徴収職員が差押えをするに当たって通常の調査によって知った第三者の権利を害さないように努めることをいうのであって、第三者の権利を害さないための特別の調査までも行わなければならないことをいうものではない。
第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
差押換えの請求
(差押換えの意義)
1 法第50条第1項の「差押換」とは、第三者の権利(差押え前に取得したものに限る。)の目的となっている財産を差し押さえた場合において、次に掲げる要件を満たすときに、その第三者からの請求により国税の全額を徴収できる財産を差し押さえ、かつ、その第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除することをいう。 (1) 滞納者が他に換価の容易な財産で、請求者以外の第三者の権利(差押換えの請求以後に生じたものを含む。)の目的となっていないものを有していること。
(2) その財産により滞納者の国税の全額を徴収することができること。
(賃借権)
2 法第50条の「賃借権」とは、当事者の一方(賃貸人)が他方(賃借人)に対してある物を使用収益させることを約し、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約する契約(民法601条)により、賃借人が取得する権利をいう。
(その他第三者の権利)
3 法第50条第1項の「その他第三者の権利」とは、地上権、永小作権、地役権、租鉱権、入漁権、使用貸借権、出版権、買戻権その他滞納者の財産上に第三者が有する権利をいう。
(これらの先取特権)
4 法第50条第1項の「これらの先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))又は第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいう。
(換価の容易な財産)
5 法第50条第1項の「換価の容易な財産」とは、評価が容易であり、かつ、滞納処分との関係において市場性のある財産をいうが、その財産は、換価をするために直ちに差押えをすることができるものに限られる。
なお、債権については、確実に取り立てることができると認められるものも、換価の容易な財産に含まれるものとする。 (注) 上記の「債権」については、法第50条第3項及び第4項の規定が適用されることはない。
(滞納者の財産)
6 通則法第50条第6号の保証人の保証は、法第50条第1項の滞納者の財産には当たらない(昭和47.2.25広島高松江支判参照)。
(請求者以外の第三者の権利)
7 法第50条の「他の第三者の権利」とは、第49条関係3に掲げる権利(法19条1項各号及び20条1項各号に掲げる先取特権以外の先取特権を除く。)のうち、差押換えの請求をした者(以下第50条関係において「請求者」という。)以外の第三者の権利をいう。
(国税の全額)
8 法第50条第1項の「国税の全額」とは、法第50条第1項の権利を有する者が差押換えの請求をする時の滞納者の国税の全額をいう。したがって、差押えに係る国税だけでなく、差押え後に発生した国税で差押換えの請求のあった時に滞納になっているものも含まれる。 (注) 上記の国税には、延滞税も含まれることに留意する。
(請求の方法及び期限)
9 法第50条第1項の規定による差押換えの請求は、令第19条第1項各号((差押換えの請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、その請求に係る請求者の権利の目的となっている財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合にはその売却決定の時、また、その財産が金銭による取立ての方法により換価するものである場合にはその取立てが終わる時)までにしなければならない。
(請求を相当と認めるとき)
10 法第50条第2項の差押換えの「請求を相当と認めるとき」とは、請求者が差し押さえるべきことを請求した財産により滞納国税の全額を徴収することができると認められるときをいうが、次に掲げるときは、その請求を相当と認めるものとする。 (1) 滞納国税について他に差し押さえた財産がある場合において、その財産と請求者が差し押さえるべきことを請求した財産とにより滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(2) 差押換えの請求に係る差押えのほか、交付要求をしている場合において、その交付要求に基づく配当が比較的近い時期において確実に得られ、滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(3) 徴収職員において、新たに換価容易であり、かつ、第三者の権利の目的となっていないもので滞納国税の全額を徴収することができる財産を発見したとき。
(4) 請求者が2人以上いる場合において、各請求者が差し押さえるべきことを請求した財産を合計することにより、滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(請求を相当と認めないとき)
11 税務署長は、法第50条第1項の規定による差押換えの請求を相当と認めないときは、その旨を請求者に通知しなければならない(法50条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
換価の申立てと換価制限
(申立ての方法及び期限)
12 法第50条第3項の規定による換価の申立ては、同条第2項の通知(11参照)を受けた請求者が、令第19条第2項各号((換価の申立ての方法))に掲げる事項を記載した書面により、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までにしなければならない(令19条2項)。なお、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法10条2項)。
(換価の著しく困難なもの)
13 法第50条第3項の「換価の著しく困難なもの」とは、その評価、換価手続、買受人への権利移転手続等が通常の換価の場合に比べて社会通念上著しく困難である財産をいい、換価をするための前提としての差押えが著しく困難なものも含まれる。
(換価に付した)
14 法第50条第3項の「換価に付した」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開いたことをいう。 (注) 公売期日を開いた場合には、入札者の有無を問わず「換価に付した」ことになることに留意する。
(法第48条との関係)
15 法第50条第1項の規定による差押換えの請求に基づく差押えのため一時的に超過差押えとなっても、法第48条第1項((超過差押えの禁止))の規定に反するものではない。
換価の申立てに応じない場合の措置
(前項の場合)
16 法第50条第4項の「前項の場合」とは、法第50条第2項の通知があった場合で、その通知を受けた請求者が、法第50条第3項の期限までに差し押さえるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てた場合において、その財産が換価の著しく困難なものでなく、かつ、他の第三者の権利(換価の申立てがあった後に生じたものを含む。)の目的となっていないときをいう。
(換価に付さない)
17 法第50条第4項の「換価に付さない」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開かないことをいう。
(通則法第1O条第1項との関係)
18 法第50条第4項の「申立てがあった日から2月」は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。
(換価について制限があるもの)
19 法第50条第4項の「国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするもの」については、第89条関係6と同様である。 (注) 上記の「国税に関する法律」とは、法その他の法律で、差押財産の換価の制限を規定しているすべての法律をいう。
(ただし書の意義)
20 法50条第3項の申立てがあった場合において、その申立てのあった日から2月の期間内に、申立てに係る財産の差押え及び換価が可能となったときは、法第50条第4項ただし書の規定は適用されない。
滞納処分の制限の解除
21 差押換えをしようとする場合に新たな差押え又は換価の申立てに係る財産の新たな差押えは、通則法その他国税に関する法律の規定により新たな差押えをすることができない場合であっても(第47条関係16参照)、することができる(法50条5項)。
第51条関係 相続があった場合の差押え
相続があった場合の差押え
(法第49条との関係)
1 法第51条の規定による相続人の権利と第三者の権利とが競合する場合には、第三者の権利を尊重するものとする(法49条、50条参照)。
(滞納処分の執行上の支障)
2 法第51条第1項の「支障」とは、おおむね次に掲げる事項をいう。 (1) 第三者の権利の目的となっている相続財産以外に、差押えをすることができる適当な相続財産がないこと。
(2) 第三者の権利の目的となっている相続財産以外の差押えができる相続財産が、すべて換価の著しく困難な財産(差押え困難なものを含む。)だけであること。 (注) 上記の「換価の著しく困難な財産」とは、例えば、弁済期が長期にわたるためその取立てが困難な債権、山間へき地にあたるため物理的に差押えが困難な土地、訴訟により所有権の帰属が争われており法律的に問題のある財産等をいう。
(限定承認等との関係)
3 限定承認(民法922条)があったときは、被相続人の国税の弁済の責任は相続財産の範囲に限定されるため(通則法5条1項後段)、その国税によって相続人の固有財産が滞納処分を受けることはない。 (注) 相続の放棄(民法938条)をした者については、被相続人の国税を承継しないため、法第51条の規定は適用がないことに留意する。
差押換えの請求
(換価が容易な相続財産)
4 法第51条第2項の「換価が容易な相続財産」については、第50条関係5と同様である。
(第三者の権利)
5 法第51条第2項の「第三者の権利」とは、第49条関係3に掲げる権利(法19条1項各号及び20条1項各号に掲げる先取特権以外の先取特権を除く。)このうち、差押換えの請求をした相続人以外の第三者の権利をいう。
(国税の全額)
6 法第51条第2項の「国税の全額」とは、納税義務の承継をした被相続人の国税の全額であり、納付責任のある国税も含まれる。
(請求の方法及び期限)
7 法第51条第2項の規定による差押換えの請求は、令第20条各号((差押換えの請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により相続人の固有財産で差し押さえられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合にはその売却決定の時、また、その財産が金銭による取立ての方法により換価するものである場合にはその取立てが終わる時)までにしなければならない。
(請求を相当と認めるとき)
8 法第51条第3項の差押換えの「請求を相当と認めるとき」とは、相続人が差し押さえるべきことを請求した相続財産により被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるときをいうが、次に掲げるときは、その請求を相当と認めるもとのする。 (1) 被相続人の国税について他に差し押さえた相続財産がある場合において、その財産と相続人が差し押さえるべきことを請求した相続財産とにより、被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(2) 差押換えの請求に係る差押えのほか、交付要求をしている場合において、その交付要求に基づく配当が比較的近い時期において確実に得られ、被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(3) 徴収職員において、新たに、換価容易であり、かつ、第三者の権利の目的となっていないもので被相続人の国税の全額を徴収することができる相続財産を発見したとき。
(4) 2人以上の相続人がそれぞれ差押換えを請求した場合において、差し押さえるべきことを請求した相続財産の価額が被相続人の国税に満たないときにおいても、その相続財産を一括換価(第89条関係5参照)することにより被相続人の国税を徴収することができると認められるとき。
(請求を相当と認めないとき)
9 税務署長は、法第51条第2項の規定による差押換えの請求を相当と認めないときは、その旨を差押換えを請求した相続人に通知しなければならない(法51条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(法第48条との関係)
10 法第51条第2項の規定による差押換えの請求に基づく差押えのため一時的に超過差押えとなっても、法第48条第1項((超過差押えの禁止))の規定に反するものではない。
(滞納処分の制限の解除)
11 差押換えをしようとする場合に新たな差押えは、通則法その他国税に関する法律の規定により新たな差押えをすることができない場合であっても(第47条関係16参照)、することができる(法51条3項、50条5項)。
第52条関係 果実に対する差押えの効力
天然果実に対する差押えの効力
(天然果実の意義)
1 法第52条第1項の「天然果実」とは、元物の用法に従い収取する産出物をいい(民法88条1項)、例えば、果実、野菜、牛乳、鶏卵、羊毛、動物の子又は石山から採取される石材等がある。
(天然果実に及ぶ)
2 法第52条第1項の「天然果実に及ぶ」とは、元物を差し押さえた場合には、新たな差押手続をすることなく、その差押えの効力が天然果実に及ぶことをいう。したがって、元物の差押えに基づきその天然果実の収取手続ができる。
(差押えの効力と果実の帰属)
3 天然果実に対して差押えの効力が及ぶのは、その果実が滞納者に帰属する場合に限られる。したがって、法律又は契約の定めるところに従って、その果実が滞納者以外の第三者に帰属する場合には、差押えの効力は及ばない。例えば、第三者が永小作権、賃借権等正当な権限により滞納者の土地を利用して収得する果実、野菜等の天然果実、不動産質権者が民法第356条((使用収益権))の規定により使用及び収益をすることができる場合の天然果実等には、差押えの効力は及ばない。
(差押時期との関係)
4 天然果実に対する差押えの効力は、差押え時における未分離の果実及び差押え時以後において生ずる果実に対して及ぶが、既に差押え時において分離されている果実に対しては及ばない。
なお、差押え時に既に分離されている天然果実は、元物とは別個の動産として差し押さえることができる。
(譲渡又は差押えのあった果実)
5 差押え時における未分離の天然果実には、次に掲げる場合には、差押えの効力が及ばない。 (1) 天然果実が差押え時に既に動産として譲渡され、明認方法によりその対抗要件を備えている場合
(2) 天然果実が差押え時に既に動産として差し押さえられ、明認方法によりその対抗要件を備えている場合
(差押財産を使用収益できる場合)
6 法第52条第1項の「滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合」とは、次に掲げる場合をいう。 (1) 滞納者又は使用若しくは収益をする権利を有する第三者が、法第61条第1項又は第2項((差し押さえた動産の使用収益))の規定により、差押動産の使用又は収益を許可された場合
(2) 滞納者又は使用若しくは収益をする権利を有する第三者が、法第69条第1項及び第2項((差押不動産の使用収益))の規定により、差押不動産につき使用又は収益をすることができる場合
(3) 動産の引渡命令を受けた第三者(動産の引渡しを拒まなかった第三者を含む。)で、使用又は収益をする権利を有する者が、法第59条第2項((引渡命令を受けた第三者の使用収益権))又は第4項((引渡しを拒まなかった第三者の権利の保護))の規定により、差押動産につき使用又は収益をすることができる場合
(換価財産の権利移転の時)
7 法第52条第1項の「その財産の換価による権利の移転の時」とは、換価財産の買受人が買受代金の全額を納付し換価財産を取得したときをいう(法116条1項、第116条関係2)。
(明認方法)
8 天然果実を収取する場合において、明認方法による対抗要件を必要とするもの(例えば、みかん等)については、立札、縄張その他適当な方法をもって明認方法を施すものとする。
(収取を必要としない場合)
9 天然果実を生ずる財産を差し押さえる場合で、元物だけで徴収すべき滞納国税を確保できると認められるとき、天然果実の収取が困難であると認められるときその他徴収上天然果実の収取の必要がないと認められるときは、天然果実に対して差押えの効力を及ぼさないことができる(昭和32.6.4前橋地判)。なお、天然果実に対し差押えの効力を及ぼさないこととする場合は、その旨を差押調書に明記するものとする。
(収取の方法)
10 天然果実を収取する場合には、徴収職員が白ら収取を行うこともでき、又は滞納者若しくは第三者をして収取させることもできる。この場合において、みかん等の果実は、成熟した後等通常の取引に適するようになってから収取するものとする(法90条1項、執行規則112条参照)。なお、天然果実を収取して搬出する場合の手続については、差押動産の搬出をする場合の手続と同様である(令26条の2参照)。
(捜索、出入禁止及び質問検査)
11 天然果実の収取行為は、差押えに付随する行為であるから、質問及び検査並びに捜索等をする場合には、法第5章第6節第2款((財産の調査))の規定が適用される。
(収取に伴う費用)
12 収取行為に伴う必要な費用は、財産の差押えに関する費用であるから、法136条((滞納処分費の範囲))の規定により滞納処分費として徴収することができる。
(未分離果実の換価)
13 未分離の天然果実は、元物とともに、又は元物とは別に換価することができる。ただし、みかん等の果実が元物から分離していない場合には、その果実が未成熟等通常の取引に適しない間は、法第90条第1項((換価の制限))の規定によりこれらの天然果実だけを換価することができないが、元物から分離した天然果実は、それだけを元物とは別に換価することができる。
法定果実に対する差押えの効力
(法定果実の意義)
14 法52条第2項の「法定果実」とは、元物の使用の対価として収取される金銭その他の物、例えば、家賃、地代、小作料、利息等をいう(民法88条2項)。
(利息)
15 法第52条第2項の「利息」とは、一定の元本債権から付随的に生ずる所得であって、元本債権に対する一定の利率をもって定期的に計算される金銭等をいい、元本の弁済期以後における遅延利息等利息の性質を有するものはこれに含まれるが、建設利息(商法291条)、終身定期金(民法689条)等はこれには含まれない。
(利息に対する差押えの効力)
16 元本債権の差押えの効力は、その差押え後に生ずる利息債権にも及ぶが(法52条2項ただし書)、差押え時までに発生した利息債権は、別に差し押さえない限り差押えの効力は及ばない(大正5.3.8大判参照)。したがって、利息支払時期前に差押えをした場合における利息債権に対する差押えの効力は、差押え後に発生する部分についてだけ効力が及ぶ(民法89条2項)。
(法定果実に対する差押え)
17 差押えの効力は、差押財産(債権を除く。)から生ずる法定果実に及ばないから、元物の差押えとは別に債権差押えの方法により法定果実の差押えを行う必要がある(法52条2項参照)。
(利息制限法による利息の制限)
18 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が一定の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は無効となるから(利息制限法1条1項)、その部分の支払を請求することはできない。
なお、契約成立の際に第三債務者が利息として上記の超過部分の金額を前払しても元本に充てたものとみなされ(利息制限法2条)、また、第三債務者から超過分の任意の支払を受けたときは、その超過部分は、残存元本に充当(民法491条)され、元本充当の結果、計算上元利合計を超える部分の金額については、利息制限法第1条第2項及び第4条第2項の適用はなく、第三債務者は、民法の規定するところにより、債権者(滞納者)に対し、不当利得の返還を請求することができる(昭和43.11.13最高判、昭和44.11.25最高判)。 (注)1 金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、上記の「利息」に含まれる(利息制限法3条)。
2 利息制限法所定の制限を超える利息の定めのある金銭消費貸借において、遅延損害金について特約がないときのその利率は、同法第1条第1項所定の利率にまで減縮される(昭和43.7.17最高判、昭和50.2.25最高判)。
3 数個の債務がある場合における法定利息超過部分については、順次に利息及び元本に充当される(民法491条1項)。
(利息の取立て手続)
19 元物である債権を差押え、利息の取立てもしようとするときは、第三債務者に送付する債権差押通知書に、利息もあわせて国に支払うべき旨を記載するものとする。
第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
担保のための仮登記がある財産に対する滞納処分
(滞納処分の続行)
1 担保のための仮登記(第23条関係2参照)がある財産を差し押さえた場合において、その差押えの効力が発生したとき(第68条関係46)が清算期間の経過前または清算金の支払若しくは供託前(清算金がないときは、清算期間の経過前)であるときは、仮登記担保権者は、その仮登記に基づく本登記(本登録を含む。以下同じ。)の請求をすることができない(法52条の2、仮登記担保法2条1項、15条1項、20条)。したがって、税務署長は、当該財産について滞納処分を続行することができる。ただし、その差押えについて、不服申立て又は訴訟が提起されたときは、財産の換価は制限されることとなる(通則法105条1項、法90条3項)。 (注) 「担保のための仮登記がある財産」が特許権、意匠権、実用新案権又は商標権のような不動産登記法の適用又は準用のない財産であるときは、利害関係人の承諾を要しないでその仮登録に基づく本登録をすることができるが、差押え後になされたその本登録は、換価により消滅することに留意する(法124条1項)。
(滞納処分の制限)
2 清算期間経過後、正当な清算金の支払又は供託がされた後(清算金がないときは、清算期間の経過後)においては、担保のための仮登記がある財産に対する差押えは、行うことができない(法52条の2、仮登記担保法15条2項、20条)。
第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
損害保険
(意義)
1 法第53条第1項の「損害保険」とは、当事者の一方(保険者)が偶然な一定の事故(以下第53条関係において「保険事故」という。)によって差押財産について生ずることがあるかもしれない損害をてん補することを約し、相手方(保険契約者)が保険者に対して報酬(保険料)を支払うことを約する契約に関する保険をいうものである(商法629条参照)。これらの保険には、例えば、商法に規定する火災保険、運送保険及び海上保険のほか、物についての盗難保険、ガラス保険、自動車保険、航空保険、ボイラー・ターボセット保険、家畜保険、風水害保険、動産総合保険等及び債権についての信用保険、抵当保険、有価証券保険等がある。
(当事名の意思によらない損害保険契約の終了)
2 損害保険契約の終了については、当事者の意志による場合とよらない場合とがあるが、次に掲げる場合には、当事者の意思表示を待たず当然に終了する。 (1) 保険期間の満了の場合保険者は保険期間中に起こった保険事故による損害をてん補するものであるから、保険事故の発生を見ずに保険期間が満了したときは、保険契約は原則として消滅する。ただし、保険契約の継続について、特別の定めをしているときは、この限りでない。
(2) 被保険利益の消滅の場合損害保険契約は、損害のてん補を目的とするから被保険利益の存在を前提とする。したがって、保険者の負担すべき保険事故以外の理由により保険の目的の全部又は一部が滅失し、被保険利益の全部又は一部が消滅した場合(危険が消滅した場合を含む。)には、その部分についての保険契約は効力を失う。
(3) 危険の著しい変更又は増加の場合保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰すべき理由により著しく変更又は増加したときは、その契約は当然に効力を失う(商法656条)。 (注) 危険の変更又は増加とは、保険期間中における危険に関する事情の変更で、契約当時に予定された以上に危険発生の可能性が増加することをいう。
(4) 保険者の破産の後3月を経過した場合保険者が破産の宣告を受けたときは、保険契約者はその契約を解除することができるが(商法651条1項、破産法59条)、保険契約者が商法第651条第1項((保険者の破産))の規定による解除をしない場合において、破産宣告の後3月を経過したときは、その保険契約は当然にその効力を失う(同条2項)。
(当事者の意思による損害保険契約の終了)
3 損害保険契約は、次に掲げる場合には、契約当事者の意志によって終了させることができる。 (1) 保険者の責任開始前(商法649条2項6号参照)における保険契約者による任意解除の場合保険者の責任が始まる前においては、保険契約者は自由に保険契約の全部又は一部を解除することができる(商法653条)。
(2) 保険者の破産の場合における保険契約者による解除の場合保険者が破産の宣告を受けたときは、保険契約者は将来に向かって契約を解除することができる(商法651条1項)。
(3) 告知義務違反の場合における保険者による解除の場合保険契約者が、告知義務に違反した場合には、保険者は、一定の要件(商法644条1項ただし書、2項、645条参照)のもとにその契約を解除することができる(同法644条1項本文)。
(4) 危険の著しい変更又は増加の場合における保険者による解除の場合保険者は、保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない理由によって著しく変更又は増加した場合には、将来に向かってその契約を解除することができる(商法657条1項)。 (注) 危険の変更又は増加については、2の(3)の(注)と同様である。
(5) 保険者による失効宣言の場合保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない理由によって著しく変更又は増加した場合において、これを知った保険契約者又は被保険者が遅滞なくこれを保険者に通知することを怠ったときは、保険者は危険の変更又は増加の時から契約がその効力を失ったものとみなすことができる(商法657条2項)。 (注) 危険の変更又は増加については、2の(3)の(注)と同様である。
(6) 約款の規定による解除の場合保険約款に、一定の要件があるときに、その契約を解除することができる旨の定めがある場合において、その要件に該当するときは、その保険契約を解除することができる。
(保険契約の終了又は無効と差押えの効力)
4 2又は3により差押財産に係る損害保険契約が終了した場合又は保険契約の全部又は一部が無効である場合には、その差押えの効力は、その終了又は無効であることにより生ずる保険料等の返還を受ける権利(商法643条、654条等参照)には及ばない。したがって、この返還請求権は、別個の債権として差し押さえる必要がある。
火災共済協同組合の火災共済
(火災共済の意義)
5 法第53条第1項の「中小企業等協同組合法第9条の7の2第1項第1号(火災共済協同組合の火災共済事業)に規定する共済」とは、火災共済協同組合員が火災又は落雷等の偶然な事故によりその所有財産等について受けた損害をてん補するために、その火災共済組合が行う共済をいう。
(共済金額の制限)
6 共済金額については、中小企業等協同組合法第9条の7の3((共済金額の制限))の規定により、共済契約者1人につき共済金額の総額の制限がある。
(商法等の準用)
7 火災共済協同組合が締結する火災共済契約については、商法第3編第10章第1節第1款(同法650条1項及び664条を除く.)((損害保険の総則))及び第2款((火災保険))の規定が適用されるので、共済契約の終了等については、2から4までに準ずる(中小企業等協同組合法9条の7の5)。
(これに類する共済)
8 法第53条第1項の「その他法律の規定による共済でこれに類するもの」には、次に掲げるものがある。 (1) 農業協同組合法の規定による共済(同法10条1項8号、10条の2、農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済事業に係る責任準備金の積立に関する省令参照)
(2) 水産業協同組合法の規定による共済(同法100条の2,100条の4,100条の10,100条の14、商法3編10章参照)
(3) 消費生活協同組合法の規定による共済(同法10条1項4号、26条の3参照)
保険等の目的
(目的)
9 保険又は共済の目的とは、保険契約又は共済契約の対象とされているものをいう。例えば、建物の火災保険の場合は、その建物をいう(商法641条、649条、650条等参照)。 (注) 保険契約の目的とは、被保険利益のことをいう(商法630条、631条参照)。
(目的物の範囲)
10 損害保険、火災共済その他の共済の目的物及びその範囲は、各損害保険契約の約款又は共済契約により定められる。
保険金又は共済金
(保険金)
11 法第53条の「保険金」とは、保険事故が発生したことにより保険契約に基づく保険価額及び保険金額の範囲内で、実際に生じた損害額につき、被保険者が保険者から損害のてん補として受ける金銭をいう。
なお、普通保険約款で、現品の交付、修繕その他の方法によるてん補も定めることができる。 (注)1 保険価額とは、保険契約の目的の評価額をいい、保険金額とは、保険者が、保険事故による損害の発生の際にてん補すべき金額の最高限度額で契約締結時に保険者と保険契約者の間で約定されるものをいう。
2 約定保険金額が保険価額を超える場合又は数人の保険者との間に、保険事故、被保険者及び被保険利益が同一で保険期間を共通にする数個の保険契約が存在し、しかもその各契約の保険金額の合計が保険価額を超過する場合には、保険価額を超える部分の保険金額については、その支払を受けることができない(商法631条、632条1項参照)。
(共済金)
12 法第53条の「共済金」とは、共済事故が発生したことにより共済契約に基づく共済金額の範囲内で、実際に生じた損害額につき、共済契約者が共済事業者から損害のてん補として受ける金銭をいう。
保険金又は共済金に係る差押えの効力
(差押え前に差押財産が保険等に付されている場合)
13 保険に付され、又は共済の目的となっている財産に対する差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶから、一定の事故が生じた場合には、改めて保険金又は共済金の支払を受ける権利の差押えをすることなく保険者又は共済事業者は、保険金又は共済金を差押債権者である国に対して支払うこととなる。ただし、保険者又は共済事業者に対し財産を差し押さえた旨を通知することが必要である(法53条1項ただし書)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
なお、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権等がある場合は、上記の通知をしたときにその質権等の権利者に法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知をするものとする。
(差押え後に差押財産が保険等に付された場合)
14 差押え後にその差押財産が保険又は共済に付された場合における差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶものとする。ただし、このためには、保険又は共済の付された財産を差し押さえている旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない(法53条1項ただし書)。 (注) 財産差押え後、その財産の譲渡があり、新たに譲受人を受取人とする保険契約又は共済契約がされた場合には、差押えの効力は保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ばない。
(保険の目的の譲渡と差押えの効力)
15 保険の目的物が譲渡された場合には、その譲渡により危険の著しい変更又は増加を生じない限り、商法第650条((保険の目的の譲渡))の規定により、保険契約によって生じた権利も譲渡されたものと推定される。したがって、その譲受財産を譲受人の滞納処分として差し押さえた場合には、その差押えの効力は、その保険金の支払を受ける権利に及ぶことになる。これに対し、保険に付されている財産を差押え、法第53条第1項ただし書の通知をした後にその差押財産が譲渡された場合には、その財産の譲渡に伴う保険契約に係る権利の譲渡は、その差押えに対抗することができない。 (注) 保険の目的につき、相続又は会社の合併による包括承継があったときは、これに関する保険契約の被保険者の地位もまた、原則として、包括承継の対象となる。
(保険契約の継続と差押えの効力)
16 保険事故の発生を見ないで保険期間が満了した場合において、保険証券を新たに発行せず、保険契約継続証を従来の保険証券に添付し、新証券として保険契約が継続されたときは、改めて法第53条第1項ただし書の差押えの通知をする必要はない(昭和37.8.10名古屋高判参照)。
(共済の目的の譲渡と差押えの効力)
17 火災共済契約の目的財産が譲渡された場合(相続又は合併による場合を含む。)においては、中小企業等協同組合法第9条の7の4((火災共済の目的の譲渡等))の規定により、譲受人は火災共済協同組合の承諾を得て、その目的財産に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができるので、この場合の譲渡と差押えの効力との関係については、15と同様である。
なお、火災共済契約の共済の目的財産の譲受人が火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族、組合員たる法人の役員、組合員の使用人又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下17及び18において「組合員等」という。)でなくなった場合においても、火災共済契約期間内は、その契約につき組合員等の財産とみなされる(中小企業等協同組合法9条の7の4第1項後段)。
(被共済者が組合員等でなくなった場合の差押えの効力)
18 火災共済協同組合の組合員等が組合員等でなくなった場合において、その際締結されていた火災共済契約の目的物のうち、その組合員等でなくなったことにより組合員等の財産でなくなった財産がある場合は、中小企業等協同組合法第9条の7の4第3項((火災共済の目的の譲渡等))の規定により、その財産に係る火災共済契約の期間内は、その契約につき組合員等の財産とみなされるので、差押えの効力は、その組合員等でなくなった者の共済金の支払を受ける権利に及ぶ。
保険又は共済の事故
(事故)
19 法第53条第2項の「保険又は共済に係る事故」とは、保険者又は共済事業者が保険又は共済の目的につき、偶然な一定の事故によって生ずる損害をてん補することを契約している場合において、その保険者又は共済事業者のてん補すべき義務を具体化させる事故をいう(商法629条、642条参照)。
(保険事故と免責事由)
20 保険に係る事故については、それぞれの保険契約で約定されたところによるが、事故が生じても、それが次に掲げる原因によるときは、保険者は損害てん補義務を免れる。
なお、保険者は、普通保険約款に、免責される事故又は損害の態様を特約事項として定めることができる。 (1) 変乱より生じた損害は、商法第640条((保険者の法定免責事由))の規定により、特約がなければ、保険者はその損害をてん補する責めを負わないこと。
(2) 保険の目的物の性質若しくはかし、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失により生じた損害は、商法第641条((保険者の法定免責事由))の規定により、保険者はその損害をてん補する責めを負わないこと。又この場合は、特約をもってこの損害のてん補を定めることができないこと。
(共済事故)
21 共済に係る事故としては、火災共済協同組合が締結するものについては火災又は落雷等の偶然の事故、農業協同組合が締結するものについては共済規程に定める事故、水産業協同組合が締結するものについては共済規程に定める事故及び消費生活協同組合が締結するものについては規約に定める事故等がある(中小企業等協同組合法9条の7の2、農業協同組合法10条の2、水産業協同組合法100条の10、消費生活協同組合法26条の3参照)。
差押財産上の抵当権等と差押え国税との関係
(差押財産上の抵当権等の物上代位)
22 差押財産が保険又は共済及び抵当権、質権又は先取特権(以下第53条関係において「抵当権等」という。)この目的となっている場合において、徴収職員がその財産についてその保険金又は共済金の支払を受けたときは、法第53条第2項の規定により、その抵当権者、質権者又は先取特権者(以下第53条関係において「抵当権者等」という。)がその支払前にその保険金又は共済金の支払を受ける権利について、民法第304条第1項ただし書((物上代位))、第350条((留置権等の規定の準用))、第372条((他の担保物件の規定の準用))、自動車抵当法第8条((物上代位))、建設機械抵当法第12条((物上代位))等の規定による差押えをしたものとみなされるので、その抵当権者等は、物上代位のための要件としての差押手続を要せず、その権利の行使をしたと同様の関係になる。
(保険金等の配当)
23 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合のその保険金又は共済金に係る金銭は、法第128条第2号((配当すべき金銭))の規定による配当すべき金銭に該当する。
(差押財産上の抵当権等と差押え国税)
24 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産上に法第53条第2項の抵当権等があったときのその抵当権等の被担保債権とその差押えに係る国税との優先関係については、その保険金又は共済金が差押財産の換価代金に相当するものとして、法第2章第3節((国税と被担保債権との調整))等の規定を適用するものとする。
なお、上記の場合における抵当権等の被担保債権の優先についての証明は、令第4条第3項((優先質権等の証明の期限))の規定により、保険金又は共済金についての配当計算書の作成の日の前日までにしなければならない。
保険金の請求権上の質権と差押財産上の抵当権等と差押国税との競合
(質権と抵当権等との競合)
25 保険金又は共済金の支払を受ける権利について設定された質権の被担保債権と差押財産上にある法第53条第2項の抵当権等の被担保債権との優先順位は、法第53条第2項の規定により、これらの抵当権等を有する者が保険金又は共済金の支払を受ける権利を差し押さえたとみなされるときと保険金又は共済金の支払を受ける権利について質権を設定した時とを比較して、これらの古い順序に従って優先順位を定めるものとする(昭和32.8.30福岡高判)。 (注)1 法第53条第2項の規定により差押えをしたものとみなされた場合において、抵当権等が2以上ある時は、その抵当権等相互間については、民法その他の法律の規定によりその順位を定めるものとする。
2 法第53条第1項の規定により、差押財産に対する差押えの効力が保険金又は共済金の支払を受ける権利に及んだ時以後に、その請求権上に設定した質権については、配当しないものとする。
(質権と抵当権等と差押国税との競合)
26 徴収職員が、差押財産に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その保険金又は共済金の請求権につき設定されていた質権の被担保債権と法第53条第2項の抵当権等の被担保債権と差押えに係る国税とが競合した場合のその保険金又は共済金の配当等については、次に掲げるところによるものとする。 (1) 差押えに係る国税が質権の被担保債権及び抵当権等の被担保債権に優先する場合は、第1順位差押えに係る国税、第2順位質権の被担保債権、第3順位抵当権等の被担保債権、の順位により配当する。
(2) 差押えに係る国税が質権の被担保債権及び抵当権等の被担保債権に後れる場合は、第1順位質権の被担保債権、第2順位抵当権等の被担保債権、第3順位差押えに係る国税、の順位により配当する。
(3) 差押えに係る国税が、質権の被担保債権に後れ、抵当権等の被担保債権に優先する場合は、第1順位質権の被担保債権、第2順位差押えに係る国税、第3順位抵当権等の被担保債権、の順位により配当する。
(4) 差押えに係る国税が、抵当権等の被担保債権に後れ、質権の被担保債権に優先する場合は、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定を類推適用して、配当するものとする。 〔例〕 滞納処分費 (不動産の差押えに関する費用、保険金受領に関する費用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
差押え国税 (法定納期限等 昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・・11万円
抵当権の被担保債権額(設定登記昭和57. 1.30)・・・・・・・・・8万円
(保険金請求権の発生した日 昭和58. 5.30)
質権の被担保債権額 (設定 昭和58. 4.30)・・・・・・・・・・・6万円
保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21万円
※配当額の計算 イ 法第26条第1号の規定により、滞納処分費の1万円に充てる。
ロ 法第26条第2号の規定により、法定納期限等、質権の設定及び抵当権の設定登記の古い順に従って国税及び私債権に充てるべき金額の総額(21万円-1万円)を定めると、抵当権の設定登記が昭和57.1.30、差押国税の法定納期限が昭和58.3.15、質権の設定が昭和58.4.30であるから、(1)抵当権8万円、(2)国税11万円、(3)質権1万円(保険金額21万円-イの1万円-(1)の8万円-(2)の11万円)となり、私債権の総額9万円((1)の8万円十(3)の1万円)、国税11万円となる。
ハ 法第26条第3号の規定により国税に充てるべき金額は、11万円となる。
ニ 法第26条第4号の規定により、質権の設定が昭和58.4.30で抵当権者が保険金の支払を受ける権利を差し押さえたとみなされるときより早いから、質権に6万円、抵当権に3万円充てる(25参照)。
ホ 上記の結果、配当額は次のとおりとなる。
滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
質権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
参加差押え及び交付要求との関係
(参加差押え又は交付要求をした者への配当)
27 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その差押えに係る財産につき、参加差押え又は交付要求がされていたときは、これらの参加差押え又は交付要求に係る国税、地方税又は公課に対しても配当する。
なお、上記の場合においては、法第2章第2節((国税及び地方税の調整))の規定が適用される。
(参加差押えに係る差押えについての保険者等への通知)
28 保険又は共済の目的となっている財産の参加差押えをした場合には、参加差押えをした旨を保険者又は共済事業者に通知するものとする。この通知をしていない場合において、先行の差押えが解除されたことにより参加差押えが差押えの効力を生じたときは、改めて保険者又は共済事業者に対し差し押さえた旨を通知しない限り、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない。
なお、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権等がある場合には、その質権等の権利者に対する通知をするものとする。
保険金等の支払いを受ける権利の差押えと法第53条第2項との関係
29 法第53条第1項の保険金又は共済金の支払を受ける権利を滞納処分により差し押さえた場合において、その差押えに基づきその保険金又共済金の支払を受けたときにおいても、法第53条第2項の規定の適用があるものとする。
担保の処分としての差押えと法第53条との関係
30 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により、滞納処分の例により担保物の差押えをする場合において、その財産が保険に付され、又は共済の目的となっているときは、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権を設定しているときを除き、その財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知する(法53条1項ただし書)。
第54条関係 差押調書
差押調書
(意義)
1 法第54条の「差押調書」とは、差押えの事績を記録証明するために作成する文書であって、令第21条第1項各号((差押調書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第3号書式による。
なお、差押調書の作成は、差押えの効力発生要件ではない。
(動産及び有価証券)
2 法第54条第1号の「動産」とは、民法第86条第2項及び第3項((動産の定義等)))に規定する動産のうち、法第70条又は第71条((船舶、航空機等の差押え))の規定の適用を受ける船舶、航空機、自動車及び建設機械並びに無記名債権を除いたもの(以下「動産」という。)をいい、「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、無記名債権も含まれる(第56条関係13参照)。
(債権)
3 法第54条第2号の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいい、電話加入権、賃借権その他取り立てることができない債権は含まれない(第62条関係1参照)。
(電話加入権等)
4 法第54条第3号の「第73条(電話加入権等の差押)の規定の適用を受ける財産」とは、無体財産権等のうち、電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産をいう(第73条関係1参照)。
(搬出又は取上げの場合)
5 差押財産を搬出する場合において、差押財産を搬出した旨を差押調書に付記したときは、滞納者又は第三者にその謄本を交付しなければならない(令26条の2、22条1項ただし書)。
なお、債権証書等を取り上げた場合において、債権証書等を取り上げた旨を差押調書に付記したときは、滞納者又はその処分を受けた者に、その謄本を交付しなければならない(令28条)。
(署名又は記名)
6 令第21条第1項((差押調書の記載事項))の「署名」とは、徴収職員が自らその氏名を記載することをいい、「記名」とは、署名に代えて、印判、謄写、印刷等によってその氏名を表示することをいう。
(性質)
7 令第21条第1項第3号((差押調書の記載事項))の「性質」とは、例えば、自動車については、年式、製造者名、色、新旧の別、車台番号、登録番号等通常の場合において、社会通念上他の同種物品と識別することができる程度の性状、機能、特徴等をいう。
(所在)
8 令第21条第1項第3号((差押調書の記載事項))の「所在」については、社会通念上その財産の特定のために必要な所在場所に関する事項を記載するものとする。
(捜索した場合)
9 令第21条第2項((捜索調書を作成しない場合の差押調書の記載事項))の規定により差押調書に記載する捜索した「日時及び場所」とは、捜索して差押えをした場合における捜索を開始した日時及び終了した日時並びに社会通念上特定するに足りる程度の捜索した場所の表示(例えば、個人の場合には、居間、台所等、法人の場合には、事務室、倉庫、工場、応接室等)をいう。
(参加差押えの場合)
10 法第87条第1項((参加差押えに係る差押えの効力の発生時期等))の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、差押調書を作成することを要しない。
(保全差押え等の場合)
11 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定により差し押さえたときは、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして差押調書を作成するものとする。この場合において、令第21条第1項第2号((差押調書の記載事項))に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令56条、通則令9条、規則3条別紙第3号書式備考2)。
(担保物処分の場合)
12 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により担保を滞納処分の例により処分するため差し押さえた場合において、その差押えの時にその財産が滞納者以外の者に帰属しているときは、その帰属している者を滞納者としてみなして、差押調書に準ずる調書を作成するものとする。
差押調書の謄本
(謄本)
13 法第54条の差押調書の「謄本」とは、差押調書と同一の文字符号を用いて、差押調書の内容を完全に写し取った書面をいう。この書面は、謄写したものであると筆写したものであるとを問わないが、謄本である旨を記載するものとする。
(作 成)
14 差押調書の謄本は、立会人を要しない場合及び滞納者が立会人である場合には1通を、滞納者以外の者が立会人である場合には滞納者及び立会人に交付すべき数に相当するものを、それぞれ作成する。
(交 付)
15 法第54条の「交付」とは、謄本を相手方に渡すことをいい、直接の手交に限らず、通則法第1章第4節((送達))の規定による送達を含む。
なお、謄本の交付を要しないときも、差押調書は作成しなければならない。
(債権を差し押さえた場合)
16 債権を差し押さえた場合には、法第62条第2項((差し押さえた債権の処分禁止))の規定により、その債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を差押調書の謄本に付記しなければならない(令21条3項)。
この場合の付記については、別に定めるところによる。
第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
差押えの通知
(知れている者)
1 法第55条の「知れている者」とは、同条第1号から第3号までに掲げる者のうち、徴収職員がその差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者をいう。
(その他必要な事項)
2 法第55条の「その他必要な事項」とは、次に掲げる事項をいう(令22条1項)。 (1) 滞納者の氏名及び住所又は居所
(2) 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
(3) 差押財産の名称、数量、性質及び所在
(4) 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
(5) 担保のための仮登記(第23条関係2参照)の権利者に対しては、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められる旨
(通知の方法)
3 法第55の規定による通知は、令第22条第1項各号((質権者等に対する差押通知書の記載事項))に掲げる事項(2参照)を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、法第55条第1号及び第2号に掲げる権利者に対する差押えの通知書は、登記簿(又は登録簿)に登記されている住所又は居所あてに送付することとして差し支えない。 (注) 担保物を滞納処分の例により差し押さえたときは、法第55条の規定に準じて通知しなければならない。
(保全差押え等をした場合の通知)
4 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定による差押えをした場合には、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして、法第55条の規定による差押えの通知をしなければならない。この場合において、令第22条第1項第1号((質権者等に対する差押通知書))において準用する第21条第1項第2号((差押調書の記載事項))に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令56条・通則令9条)。
(保全差押えに係る国税が確定した場合の通知)
5 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定による差押え後、その差押えに係る国税が確定しても、法第55条の規定による差押えの通知は必要ではない。
(捜索又は取り上げた場合)
6 法第55条の規定による通知を受けるべき者が、法第146条第3項((捜索調書の作成))の規定により差押調書の謄本を受けた者であるときは、その者に対しては、差押えの通知をすることを要しない(令22条2項)。
なお、質権者等の第三者が占有する債権証書等を取り上げた場合において、取上調書に代えて差押調書の謄本にその旨を付記して交付したときは、その者に対しては法第55条の規定による差押えの通知を要しないものとする(令28条、22条1項ただし書参照)。
(参加差押えの場合)
7 法第87条第1項((参加差押えに係る差押えの効力の発生時期))の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、改めて、法第55条の規定による差押えの通知をすることを要しない(法81条、86条4項参照)。
(質権、抵当権、先取特権)
8 法第55条第1号の「質権、抵当権、先取特権」は、保全仮登記がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(仮登記)
9 法第55条第2号の「仮登記」とは、担保のための仮登記(第23条関係2参照)その他すべての仮登記をいう。
(仮差押え)
10 法第55条第3号の「仮差押え」とは、裁判所の決定に係る仮差押えをいい、保全法による強制執行を保全するための仮差押えに限らず、破産法第155条((破産宣告前の保全処分))、和議法第20条((和議開始決定前の保全処分))、会社更生法第39条((更生手続開始決定前の保全処分))、商法第386条第1項第1号((会社の整理開始命令後の保全処分))、第454条第1項第1号((会社の特別清算開始命令後の保全処分))等の規定による仮差押えも含まれる。
この仮差押えの執行は、次に掲げる財産ごとに、それぞれの執行機関が行う。 (1) 動産又は有価証券目的物の所在地を管轄する地方裁判所所属の執行官(保全法49条1項、執行官法4条)
(2) 債権仮差押命令を発した裁判所(保全法50条2項)
(3) 不動産仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法47条2項)。強制管理の方法による仮差押えの執行については、不動産の所在地を管轄する地方裁判所(保全法47条5項、執行法44条1項)
(4) 船舶又は航空機仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法48条2項、民事保全規則(以下「保全規則」という。)34条)。執行官に対して船舶国籍証書等又は航空機登録証明書等を取り上げて執行官に提出すべきことを命ずる方法による仮差押えの執行については、船舶又は航空機の所在地を管轄する地方裁判所(保全法48条2項、保全規則34条)
(5) 自動車又は建設機械仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全規則38条、39条、保全法48条2項)。執行官に対し自動車又は建設機械を取り上げて保管すべき旨を命ずる方法による仮差押えの執行については、自動車又は建設機械の所在地を管轄する地方裁判所(保全規則38条、39条、保全法48条2項)
(6) 預託株券等仮差押命令を発した裁判所(保全規則42条2項、保全法50条2項) (注) 預託株券等とは、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「株券保管振替法」という。)第14条第1項((保管振替機関への預託))(同法39条1項((株券以外の有価証券))において準用する場合を含む。)の規定により保管振替機関に預託された株券その他の有価証券をいう(執行規則150条の2参照)。
(7) (1)から(6)までに掲げる財産権以外の財産権仮差押命令を発した裁判所(保全法50条4項)
(仮処分)
11 法第55条第3号の「仮処分」とは、裁判所の決定に係る仮処分をいい、保全法第23条第1項(係争物に関する仮処分命令)の規定に限らず、仮差押えと同様に10に掲げる破産法第155条、和議法第20条等の規定による仮処分も含まれる。この仮処分の執行機関については、10に準ずる(保全法52条1項、保全規則45条)。
なお、次に掲げるような仮の地位を定める仮処分等は、金銭給付を内容とする滞納処分との競合が生じないので、法第55条第3号の仮処分には含まれない。 (1) 仮の地位を定める仮処分(保全法23条2項)
(2) 取締役及び監査役の職務執行停止又は職務代行者の選任の仮処分(商法270条、280条)
(3) 子の看護その他の仮処分(人事訴訟手続法16条)
(4) 仮登記のための仮処分(不動産登記法32条、33条1項)
第2款 動産又は有価証券の差押え
第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
動産
(土地に付着した物)
1 土地の定着物は不動産であるが、仮植中の草木、小規模の工事で土地に固定されたもの、例えば、使用中の動揺を防ぐためボールト、くぎ、スパイク等で固定しただけの機械類等単に土地に付着しているだけのものは、定着物とはいえないから、動産として差し押さえる(大正10.8.10大判、昭和4.10.19大判)。
(未完成の建物)
2 建物は不動産であるが、その使用の目的に応じて使用可能な程度に完成していなければ建物とはいえないから、例えば、木材を組み立てて地上に定着させ、屋根をふきあげただけのもの等は、動産として差し押さえる(大正15.2.22大判)。 (注) 建物が完成した場合には、改めて不動産としての差押えの手続をとる必要がある。
(未分離の果実等)
3 未分離の果実等は、土地の定着物である樹木と一体をなすものであって、本来動産ではないが、動産として取引されるもの(おおむね1月以内に収穫することが確実であるもの。執行法122条1項参照)は、独立した動産として差し押さえることができる(大正9.5.5大判)。
(登記されない船舶)
4 法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる船舶は、動産として差し押さえる。 (1) 端舟その他若しくはかいだけで運転し、又は主として若しくはかいだけで運転する舟(商法684条2項、船舶法20条)
(2) 総トン数20トン未満の船舶(商法686条2項、船舶法20条)
(3) 推進器を有しないしゆんせつ(凌渫)船(船舶法施行細則2条)
(4) 外国船舶(執行法121条) (注) 外国船舶とは、船舶法第1条((日本船舶の要件))に規定する日本船舶以外の船舶をいう。
(5) 製造中の船舶(抵当権の登記がされている船舶を含む。第70条関係1の(2)参照)
(登録のない航空機等)
5 法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる航空機は、動産として差し押さえる。 (1) 滑空機及び飛行船(登録のあるものを含む。) (注) 滑空機及び飛行船その他航空法施行令で定める航空の用に供することができる機器は、登録をしてもその登録は第三者に対する対抗要件ではなく(航空法2条1項、3条の3参照)、法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。
(2) 未登録の飛行機及び回転翼航空機
(登録のない自動車)
6 法第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる自動車は、動産として差押さえる(道路運送車両法4条参照)。 (1) 軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車。例えば、オートバイ、スクーター、サイドカー等(道路運送車両法3条、4条、道路運送車両法施行規則2条の規定による別表第1号参照)
(2) 未登録の自動車。例えば、商品として陳列されている自動車、登録を抹消されている自動車等(道路運送車両法4条、15条、16条参照)
(3) 建設機械としての登記がない大型特殊自動車(道路運送車両法5条2項、自動車抵当法2条ただし書参照)
(登記のない建設機械)
7 所有権保存登記のない建設機械は、記号の打刻の有無にかかわらず、法第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。 (注) 建設機械を動産として差し押さえている場合には、所有権保存の登記がされても差押債権者に対しては効力を生じない(建設機械抵当法3条2項)から、動産として滞納処分の続行をすることができる。
(外国通貨)
8 外国通貨(本邦通貨以外の通貨。)は、動産として差し押さえる。この場合において、徴収職員は、速やかに、差し押さえた外国通貨を外国為替公認銀行(同法11条)又は両替商(同法14条)において本邦通貨と交換した上、金銭を差し押さえた場合と同様に処理するものとする(27、28参照)。 (注) 本邦通貨とは、日本円を単位とする通貨をいう(外国為替及び外国貿易管理法6条1項3号)。
(従物である動産)
9 従物である動産(例えば、建物に備え付けられた畳、建具、冷暖房器、空調器等。昭和55.1.28東京地判)の差押えについては、次のことに留意する。 (1) 従物は、独立の動産として差し押さえることができる。ただし、他に滞納国税に見合う適当な財産がない場合又は主物の利用関係を著しく害しない場合に限って差し押さえるものとする。
なお、雨戸、建具、入口の戸扉その他建物の内外を遮断する建具類は、これらが建物に備え付けられた後は建物の一部を構成し、従物ではないから、その取外しの難易にかかわらず、独立した動産として差し押さえることができない(昭和5.12.18大判)。
(2) 畳、建具等の従物の差押禁止については、法第75条第1項第1号、第13号及び第2項((一般の差押禁止財産))の規定がある。
(3) 担保権の効力が及んでいる従物は、担保権者の同意のない限り、独立の動産として差し押さえないものとする(昭和18.2.13東京控判参照)。
(4) 船舶の属具目録に記載された動産は、従物と推定されるから(商法685条)、原則として、(1)及び(3)に準じて差し押さえる。
(工場抵当との関係)
10 工場抵当法による工場抵当(工場財団を組成しない工場抵当)の目的となっている土地又は建物に備え付けられている機械、器具その他工場の用に供されている動産(以下10において「備付物」という。)については、次のことに留意する。 (1) 備付物については、工場抵当法第7条第2項((抵当権の目的である物に対する差押え等))の規定により、土地又は建物と別個に差し押さえることができない。ただし、同法第2条第1項ただし書((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による抵当権の設定行為に別段の定めがある場合及び同法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録に記載されていない場合の備付物については、この限りでない。
(2) 滞納者(工場所有者)が、工場抵当法第6条第2項((抵当権の目的物の分離))の規定により抵当権者の同意を得て分離した備付物は、動産として差し押さえることができる。この場合において、その備付物が同法第3条((抵当権の目的物の分離))の規定による目録に記載されているときは、目録の変更の登記をする必要がある。
(3) 滞納者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、かつ、抵当権者もその事情を知って備え付けた備付物については、工場抵当法第2条第1項ただし書((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定により抵当権の効力はその備付物に及ばないから、動産として差し押さえることができる
(4) 滞納者の所有する動産が工場抵当の目的となっている他人の工場の備付物である場合には、工場抵当法第3条((抵当権の目的物の分離))に規定する目録に記載されている場合であっても、抵当権の効力は及んでいないから、滞納者の動産として差し押さえることができる(昭和35.8.3名古屋高判。昭和37.5.10最高判参照)。
(5) 工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))に規定する目録に記載されている備付物については、滞納処分により差し押さえたときに既に第三者が譲渡等により備付物の引渡しを受けているときにおいても、その備付物に対し差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。5条1項参照)。ただし、税務署長は、当該第三者が即時取得の要件を満たしているときは、差押えの効力を主張することはできない(同法5条2項)。
(財団に属する動産)
11 工場財団、鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団、鉄道財団、軌道財団、運河財団又は観光施設財団に属する動産は、これらの財団が1個の財産とみなされているから、個々の動産として差し押さえることができない。ただし、抵当権者の同意を得て分離した動産については、この限りでない(工場抵当法15条、鉱業抵当法3条、漁業財団抵当法6条、道路交通事業抵当法19法、港湾運送事業法26条、鉄道抵当法20条、軌道ノ抵当二関スル法律1条、運河法13条、観光施設財団抵当法11条)。
(貨物引換証等の発行されている物品)
12 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券が発行されている物品については、動産として差し押さえることはできず、これらの証券を有価証券として差し押さえるものとする(商法573条、604条、776条参照)。
有価証券
(意義)
13 法第56条第1項の「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、民法上動産とみなされている無記名債権(20参照)も含まれる(法54条1号参照)が、次に掲げる証券は、有価証券ではない。 (1) 借用証書若しくは受取証券のような証拠証券又は銀行預金証書のような免責証券 (注) 上記の場合には、債権の差押えを行い、上記の証拠証券又は免責証券は債権証書として取り上げる(第65条関係3参照)。
(2) 郵便切手又は収入印紙のように、証券自体が特定の金銭的価値を有し、金銭の代用となる金券 (注) 上記の金券は、動産の差押手続に従って差し押さえる。
(有価証券の種類)
14 「有価証券」には、手形、小切手、国債証券、地方債証券、社債券、株券(株主会員制によるゴルフ会員権に係るものを含む。)、出資証券、信託の無記名受益証券、抵当証券(抵当証券法14条、15条参照)、倉庫証券、貨物引換証(商法571条参照)、船荷証券(同法767条、768条参照)、商品券、劇場入場券等がある。
(社債券)
15 14の「社債券」は、商法の規定により社債について発行された債券だけでなく、特別の法律により設立された法人の発行する債券(例えば、電信電話債券、鉄道債権、放送債券、商工債券、農林債券等)及び会社が特別の法律により発行する債券(例えば、興業債券、長期信用債券等)をも含むものとし、これに準ずる外国の社債券についても同様とする。
(権利株等)
16 株式の引受けによる権利(いわゆる権利株)を表わす株式の申込証拠金領収証、株券発行前の株式を表わす株式払込金領収証及び新株の引受権を表わす割当通知書は、株券の受領のための委任状及び株式の譲渡を証する書面(譲渡のための委任状を含む。)が添付されているときは、株券に準じて取り扱うものとする(昭和26.2.9東京地判、昭和27.1.28東京地判)。
(出資証券)
17 14の「出資証券」とは、日本銀行及び日本原子力研究所の出資証券をいい、合名会社及び合資会社の出資に関する証券は、有価証券ではない。
(信託の無記名受益証券)
18 14の「信託の無記名受益証券」とは、証券投資信託又は貸付信託の無記名受益証券をいう。 (注) 信託の記名式の受益証券は、有価証券ではなく証拠証券である(証券投資信託法5条2項、貸付信託法8条1項参照)。
(倉庫証券)
19 14の「倉庫証券」には、預証券、質入証券及び倉荷証券の3種があるが、なお次のことに留意する。 (1) 預証券は、寄託物返還請求権を表彰する有価証券であり、質入証券とともに発行され(商法598条)、質入れ前は質入証券とともに流通するが(同法603条2項)、質入れ後は分離して流通し、預証券の所持人は、質入れに際して証券に記載された債券額と利息を支払う義務を負い(同法607条)、また、原則としてその債権額と利息を質入証券の所持人に支払って質入証券を取得しなければ、寄託物の返還を請求できない(同法620条から622条まで)。
(2) 質入債権は、質入れ後は証券記載の債券とこれを担保する質権とを表彰する。
(3) 倉荷証券は、預証券及び質入証券に代えて発行する有価証券であって(商法627条)、この証券で寄託物の譲渡、質入れその他の処分をすることができる。
(無記名債権)
20 「無記名債権」とは、証券面に債権者の名を記載せず、その正当な所持人に弁済すべき証券的債権をいい、具体的には、商品券、乗車券、無記名公債のように、債権が証券に化体し、その成立、存続、行使等に、原則として証券を必要とするものをいう。
差押手続
(占有による差押え)
21 法第56条第1項の「占有して行う」とは、徴収職員がその財産を差押えの意思をもって客観的な事実上の支配下に置き、滞納者の処分の可能性を排除することをいう。この場合の占有は、公法上の占有であり、私法上の権利関係の効力には影響を及ぼさない。
(差押調書の作成等)
22 徴収職員が動産又は有価証券を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付しなければならない(法54条)。
(未完成の手形等)
23 未完成の手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものを差し押さえたときは、直ちに滞納者に対し、当該未完成の手形等に記載すべき事項を補充させるものとする(執行規則103条2項参照)。
(有価証券の保管)
24 差し押さえた有価証券(物品の給付を目的とする権利を表彰する船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等を除く。)は、政府保管有価証券取扱規定第2条((政府保管有価証券の寄託))の規定により、原則として日本銀行に寄託するものとするが、近い将来において換価をする予定のもの又は法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により取立てをするため必要があるものについては、政府保管有価証券取扱規程第2条第1項ただし書の規定により、日本銀行に寄託することなく、税務署長がこれを保管しても差し支えない。 (注) 税務署長は、船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等の物品の給付を目的とする権利を表彰する有価証券を保管するに当たっては、保管上の必要に応じ、貸金庫等を利用するものとする。
差押えの効力
25 動産又は有価証券の差押えは、徴収職員がこれらの財産を占有した時にその効力を生ずる。したがって、占有を欠くとき、例えば、差押調書の作成又は差押調書の謄本の交付だけをしたとき等の場合には、差押えの効力は生じない。
なお、法第60条第1項((差し押さえた動産等の保管))の規定により滞納者又は第三者に差押財産を保管させたときは、封印、公示書、その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生じる(法60条2項)。
金銭の差押え
(金銭)
26 法第56条第3項の「金銭」とは、財貨の交換の媒介物として国家がその価格を一定した物のうち、日本円を単位とする通貨(本邦通貨)及び国税の納付に使用することができる有価証券をいう(証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律1条、2条参照)。 (注)1 上記の「通貨」とは、強制通用力のある支払手段をいい、鋳造貨幣(金貨、銀貨、銅貨、ニッケル貨等の貨幣)のほか、紙幣及び銀行券を含み(貨幣法3条、臨時通貨法2条、3条、日本銀行法29条、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律1条参照)、小切手等は含まない。
2 強制通用力を有しない本邦通貨とは、1円未満の貨幣及び紙幣並びに新円切換前の通貨等の古銭及び元来が強制通用力を有するものであったが模様の認識しがたいもの又は私に極印をする等故意に損傷したと認められるもの等貨幣の効用がなくなったものをいう(貨幣法13条)。
(徴収したものとみなす)
27 法第56条第3項の「徴収したものとみなす」とは、金銭(26参照)を差し押さえたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
なお、国税の納付に使用することができる有価証券を差し押さえた場合において、その支払がなかったときは、滞納者の国税の納税義務は消滅しない(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律2条参照)。
(差押金銭の受入れ)
28 差し押さえた金銭は、直ちに歳入歳出外現金出納官吏の資格において、受け入れる(昭和58.5.31付徴管3-32ほか6課共同「管理事務提要(現金出納編)の制定について」通達の別冊(以下「管理事務提要(現金出納編)」という。)第131参照)。
差押財産の保管責任と損害賠償
(動産等の保管)
29 差し押さえた動産又は有価証券(法60条1項の規定により、滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)については、税務署長は、善良な管理者の注意をもって管理し、帳簿を備え、その動産及び有価証券の出納を記載しなければならない(令23条)。この帳簿については、別に定めるところによる。 (注) 善良な管理者の注意とは、差し押さえた動産又は有価証券を保管する税務署長として、一般に要求される程度の相当の注意をいう。
(損害賠償)
30 税務署長が、その職務を行うについて故意又は過失により違法に差押財産を亡失し、又はき損し、滞納者等に損害を与えたときは、国は国家賠償法第1条第1項((国等の損害賠償責任))の規定により、滞納者等に対してその損害を賠償する責めを負う。
(管理)
31 令第23条の「管理」とは、税務署長が差し押さえた動産及び有価証券を保管し、その滅失、き損、侵奪、腐敗、変質等を防ぐことをいう。
第57条関係 有価証券に係る債権の取立て
有価証券の取立て
(金銭債権)
1 法第57条第1項の「有価証券に係る金銭債権」とは、差し押さえた有価証券に基づいて行使することができる債権のうち、金銭の給付を目的とするものをいう。したがって、金銭の給付を目的とする債権以外の債権、例えば、物品の給付を目的とする債権を表彰する有価証券(倉庫証券等)については、代位取立てをしないで、直接その有価証券を換価に付するものとする。
(取立ての意義)
2 法第57条第1項の「取立」とは、徴収職員が差し押さえた有価証券の本来の性質、内容に従って、金銭の給付を受けることをいう。
(取立てをする場合)
3 法第57条第1項の規定による取立てをする有価証券は、その有価証券に係る金銭債権の履行期日が既に到来しているもの又は近い将来において履行期日が到来するものであって、換価をするよりもその債権の取立てをする方が徴収上有利であると認められるものに限るものとする(法89条2項参照)。
(取立ての名義)
4 法第57条第1項の規定による取立ては、滞納者の名において行うのではなく、徴収職員の名において行う。
(取立ての範囲)
5 法第57条第1項の規定による取立ては、差押えに係る国税の額にかかわらず、有価証券の券面金額の全額についてするものとする(第67条関係2参照)。
(取立ての手続)
6 法第57条第1項の規定による取立てに当たっては、原則として、その有価証券に「徴収法第56条第1項の規定により差し押さえ、同法第57条第1項の規定により取り立てる」旨を記載し、徴収職員が署名押印するものとする。
なお、次のことに留意する。 (1) 小切手又は手形(金融機関を通じて取り立てることができるものに限る。)については、通則法第55条((納付委託))の場合における取立ての方法に準じ、取り立てるものとする。
(2) (1)に掲げるもの以外の有価証券については、その有価証券を呈示し、直接取り立てる。
(取立て効果)
7 法第57条第2項の「徴収したものとみなす」とは、金銭を取り立てたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
(遡及権の行使)
8 手形又は小切手について満期又は支払呈示の日に支払がないときは、徴収職員は、振出人、裏書人及びこれらの保証人並びに参加引受人に対して手形又は小切手の金額とその満期以後の利息及び拒絶証書の作成・遡及の通知等のための諸費用を請求することができる(手形法43条、48条1項、77条1項、小切手法39条、44条)。 (注) 遡及権を行使する場合には、支払人等が取引停止処分を受けている場合であっても、支払のための手形又は小切手の呈示が必要であることに留意する。
第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
引渡し
1 法第58条の「引渡」とは、滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が、動産又は有価証券を徴収職員に、占有して差し押さえることができるように提供することをいう。
差押えの制限
(親族その他の特殊関係者の判定)
2 法第58条第1項の「親族その他の特殊関係者」に該当するかどうかの判定は、差押えをしようとする時の現況によるものとする。 (注) 「親族その他の特殊関係者」とは、令第13条各号に掲げる者をいう(法38条参照)。
(第三者が占有している財産でないものとみなす場合)
3 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる者は、法第58条第1項の規定による差押えについての制約を受けない(令24条4項、5項)。 (1) 法第24条第3項((譲渡担保財産の滞納処分))の規定により譲渡担保財産につき差押えをする場合、その譲渡担保財産を占有する滞納者又はその親族その他の特殊関係者
(2) 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税の滞納処分として、その者の財産につき差押えをする場合その財産を占有する滞納者(主たる滞納者)又はその親族その他の特殊関係者
(執行官が動産等を占有する場合)
4 執行官が滞納者の動産又は有価証券を仮差押え又は仮処分により占有している場合においても、差し押さえることができる(法140条参照。強制執行又は競売による差押えがされている場合には、滞調法が適用される。)。ただし、その動産又は有価証券につき法第58条第1項の第三者が占有権を有しているときは、その第三者との関係においては、法第58条及び第59条((第三者が占有する動産等の差押手続等))等の規定が適用される。
(占有)
5 法第58条第1項の「占有」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的に継続及びその主体の意思を問わない(大正3.1O.22大判)。
(引渡しの拒否)
6 法第58条第1項の「引渡を拒む」とは、徴収職員が動産又は有価証券を占有して差し押さえようとすることを拒むことをいう。
引渡命令
(発付の要件)
7 引渡命令は、次に掲げる要件を満たしたときに発することができる(法58条2項前段)。これらの要件に該当するかどうかの判定は、引渡命令を発する時の現況によるものとする。 (1) 滞納者の動産又は有価証券を占有する滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が引渡しを拒むとき。
(2) 滞納者が他に換価が容易であり(第50条関係5参照)、かつ、その滞納に係る国税の全額(第50条関係8参照)を徴収することができる財産を有しないと認められるとき。
(期限の指定)
8 法第58条第2項前段の「期限」は、引渡しを命ずる書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。この場合の「7日を経過した日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってこの期限とみなされる(通則法10条2項)。
(期限の繰上げ)
9 令第24条第3項の「通則法第38条第1項第1号の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるとき」とは、第三者につき同法第38条第1項各号に該当する事実が生じた場合等で、かつ、引渡命令に係る期限後においてはその財産の差押えをすることができないと認められるとき(ただし、期限内に引渡しがあると認められるときを除く。)をいう。
(引渡命令)
10 法第58条第2項前段の規定による引渡命令は、その命令に係る動産又は有価証券を差し押さえるための前提要件である。この引渡命令は、令第24条第1項各号((引渡命令書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(滞納者に対する通知)
11 法第58条第2項後段の規定による滞納者に対する通知は、令第24条第2項各号((引渡命令に係る通知の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
引渡命令書を送達した後他の第三考に占有が移転している場合
12 法第58条第2項前段の引渡命令書を送達した後、他の第三者に占有が移転している場合の差押えについては、次のことに留意する。 (1) 占有の移転により、引渡命令に係る滞納者の動産又は有価証券を現に占有する第三者がその引渡しを拒むときは、(2)の場合を除き、その第三者に対して改めて引渡命令を発しなければならない。
(2) 占有の移転が相続、法人の合併等の包括承継による場合には、引渡命令を再び発する必要はない。
差押動産等の搬出の制限
13 法第58条第2項前段の規定による引渡命令を受けた第三者が、その引渡命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その引渡命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、その財産を搬出することができない(法172条)。この場合において、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、第90条関係10の「訴訟の係属する間」に準じ、その財産の搬出を行わないものとする。
第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
動産を使用又は収益する権利
(賃借権)
1 法第59条第1項の「滞納者との契約による賃借権」には、買取権付賃貸借契約による割賦払約款付売買も含まれる。
(使用貸借権)
2 法第59条第1項の「使用貸借権」とは、当事者の一方(借主)の相手方(貸主である滞納者)からある動産を無償で借りて使用及び収益をした後、その物を返還することを約する契約(使用貸借)により、借主が取得する権利をいう(民法593条)。
(その他動産の使用又は収益をする権利)
3 法第59条第1項の「その他動産の使用又は収益をする権利」とは、例えば、受寄者が寄託者(滞納者)の承諾を得て受寄物を使用する場合(民法658条1項)、賃貸借、使用貸借等の混合契約に基づき使用又は収益をする場合等におけるその使用又は収益をする権利をいう。
契約の解除
(意義)
4 法第59条第1項の「契約を解除することができる」とは、契約の内容いかんにかかわらず、その契約を一方的に解除することができることをいう(民法540条1項、543条、620条参照)。 (注) 法律の規定(民法548条参照)又は契約により、法第59条第1項の規定にかかわらず、契約の解除ができない場合がある。
(占有の目的)
5 法第59条第1項の「占有の目的を達することができなくなる」とは、その動産を、その占有の基礎となった契約の内容どおり使用又は収益することができなくなることをいう。
(契約解除の通知)
6 引渡命令を受けた第三者は、引渡命令に係る動産の差押えの時までに、その引渡しを命じた税務署長に対して、法第59条第1項前段の規定による契約の解除をした旨の通知を、書面によりしなければならない(令25条1項)。
損害賠償請求権
(意義)
7 法第59条第1項の「滞納者に対して取得する損害賠償請求権」は、債務不履行、不法行為その他契約に基づく損害賠償請求権であって、その行使は、契約の解除によって影響を受けるものではない(民法415条、709条、545条3項。昭和6.4.28大判、昭和8.2.24大判参照)。
(賠償請求の範囲)
8 法第59条第1項後段の損害賠償請求権による求償の範囲は、原則として、民法第415条((債務不履行))及び第416条(損害賠償の範囲)その他の規定によるものであって、債務の不履行によって被ったいわゆる積極的損害のほか、不履行のなかった場合の得べかりし利益の喪失たるいわゆる消極的損害も含まれる。
(売却代金)
9 法第59条第1項後段の「売却代金」は、法第94条((公売))、第109条((随意契約による売却))又は第110条((国による買入れ))の規定により換価した引渡命令に係る動産の売却代金に限られる。
(配当の方法)
10 法第59条第1項後段の「残余のうちから配当を受けることができる」とは、9の動産の売却代金を法第129条第1項((配当の原則))に掲げる国税その他の債権(法59条1項後段及び4項の損害賠償請求権を除く。)に配当し、その残余のうちから、配当を受けることができることをいう。
(配当の請求)
11 損害賠償請求権による配当の請求は、その動産の売却決定の日の前日までに、債権現在額申立書を税務署長に提出することによってしなければならない(法130条1項。令48条1項参照)。
(配当が受けられない場合)
12 動産の引渡しを命ぜられた第三者は、その動産の差押え時までに、法第59条第1項の規定による契約の解除をした旨の通知をしないときは、動産の差押え後にその通知をしたことについて相当の理由があると認められるときを除き、法第59条第1項の規定による配当を受けることができない(令25条2項、3項)。
なお、この場合には、次のことに留意する。 (1) 令第25条第3項((みなし使用又は収益の請求の不適用))に該当する場合であっても、引渡しに係る動産の売却代金の交付期日までに契約の解除をした旨の通知をしなければ配当を受けることができないこと。
(2) 令第25条第3項の「相当の理由があると認められるとき」とは、その動産を引き渡すべき期限を繰り上げて引渡命令を発したとき(令24条3項)又は通知の遅延が火災、風水害等の理由によるとき等をいうこと。 (注) この場合における令第25条第1項の通知は、引渡命令を発した日又は火災、風水害等のやんだ日からおおむね7日以内にしなければならないものとする。
使用又は収益
(請求)
13 法第59条第2項の「請求」は、その請求に係る動産の差押え時までにしなければならない(令25条1項)。
(使用又は収益の請求)
14 引渡しを命ぜられた第三者がする法第59条第2項の規定による動産の使用又は収益の請求は、書面によりしなければならない(令25条1項)。
なお、引渡しを命ぜられた第三者が、その命令に係る動産の差押え時までに、法第59条第1項の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第2項の請求をしないときは、同条同項の請求があったものとみなされる(令25条2項前段)。
(使用又は収益できる期間)
15 法第59条第2項の「その期限がその動産を差し押えた日から3月を経過した日より遅いときは、その日」とは、契約の期間の末日が、その動産を差し押さえた日から3月を経過した日より遅いときは、その経過した日をいう。この場合の「3月を経過した日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日または通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法10条2項)。
(使用又は収益をさせる場合の第三者の保管)
16 法第59条第2項の規定により第三者に動産の使用または収益をさせる場合には、その動産をその第三者に保管させるものとする。
前払借賃を支払った第三者の配当請求
(配当請求)
17 法第58条第2項の規定により動産の引渡しを命ぜられた第三者が、法第59条第1項前段の規定により賃貸借契約を解除し、かつ、その引渡命令があった時前にその後の期間分の借賃を支払っているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で差押えの日後の期間に係るもの(3月分に相当する金額を限度とする。)の配当を請求することができる(法59条3項前段)。
なお、法第59条第3項の「借賃」とは、賃貸借契約に基づいて支払われる賃借料をいい、その名称のいかんを問わない。
(請求額)
18 配当の請求額については、次のことに留意する。 (1) 差押えの日後の期間分の前払借賃について1月未満に係るものがある場合には、日割りにより計算すること。
(2) 差押えの日後の期日分の前払借賃の金額が借賃の3月分相当額を超えるときは、その3月分の金額とすること。
(配当の順位)
19 法第59条第3項前段の前払借賃の配当順位は、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぎ、かつ、船舶債権者の先取特権等法第19条の適用を受ける債権に先立つことに留意する(法26条1号参照)。
参加差押えをした行政機関等に対する配当請求
20 税務署長が、法第87条第2項((参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置))の規定により、参加差押えをした行政機関等に動産を引き渡した場合には、その動産に係る法第59条第1項又は第3項の規定によりその売却代金から配当を受けることができる権利は、その行政機関等に対して行使することができる(令41条3項)。
動産の引渡しを拒まなかった第三者
(契約解除の通知)
21 動産の引渡しを拒まなかった第三者が、差押え後(引渡し後)であっても相当の期間内(おおむね7日以内)に、契約の解除をした旨の通知をしたときは、法第59条第1項及び第3項の規定による配当を受けることができる(法59条4項、令25条3項)。この場合の配当の方法及び順位については、10及び20に準ずる。
(使用又は収益の請求)
22 動産の引渡しを拒まなかった第三者については、差押え後(引渡し後)であっても、相当の期間内(おおむね7日以内)は使用又は収益の請求ができるが、この請求は書面によりさせるものとする(法59条4項、令25条3項)。
(参加差押えをした行政機関等に対する配当請求)
23 税務署長が法第87条第2項((参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置))の規定により、参加差押えをした行政機関等に動産を引き渡した場合には、その動産に係る法第59条第4項の規定によりその売却代金から配当を受けることができる権利は、その行政機関等に対して行使することができる(令41条3項)。
第60条関係 差し押さえた動産等の保管
保管
1 法第60条の「保管」とは、差し押さえられた動産又は有価証券を自己の勢力範囲内に保持して、その滅失又はき損を防ぐことをいう。
保管責任
(滞納者が差押財産を亡失し、又はき損した場合)
2 滞納者が保管中の財産を滅失し、亡失し、又はき損したときは、その保管人としての注意義務を怠ったと怠らなかったとにかかわらず、一切の損害をその滞納者が負担する。
なお、故意に差押財産を滅失し、亡失し、又はき損した場合には、法第187条((罰則))、刑法第252条第2項((横領の罪))、第262条((毀棄の罪))等の規定が適用されることがある。
(第三者の保管責任)
3 法第60条第1項の第三者は、滞納者に対しては、滞納者の財産を占有している原因である賃貸借契約、寄託契約等の内容に従って注意義務を負い、また国に対しては、保管者として一般に要求される程度の相当の注意義務を負う。
なお、第三者が、故意に又は注意義務を怠ったことにより、保管中の財産を滅失し、亡失し、又はき損したときは、滞納者又は国に対してその損害を賠償する責めを負う。
(滞納者及び占有する第三者以外の第三者の保管責任)
4 法第60条第1項の第三者以外の第三者は、差押財産の保管について、特約のない限り、次に掲げる注意義務を負い、故意に又はその注意義務を怠ったことにより、保管中の財産を減失し、亡失し、又はき損したときは、国に対してその損害を賠償する責めを負う。 (1) 無償で保管する場合((3)の場合を除く。)には、自己の財産におけると同一の注意をもって保管する義務(民法659条)
(2) 有償で保管する場合には、善管注意義務(民法400条)
(3) 保管者が倉庫営業者その他営業の範囲内で保管する商人(例えば、差押財産の運送を依頼した場合の運送人)である場合には、善管注意義務(商法593条、597条、569条、559条参照)
(天災等による差押財産の滅失)
5 差押財産の保管中に、天災その他の不可抗力により、その財産が滅失し、亡失し、又はき損したときは、その損害はすべて滞納者が負担する。
財産を占有する第三者
6 法第60条第1項の「財産を占有する第三者」には、法第58条第1項((第三者が占有する動産等の差押手続))の滞納者の親族その他の特殊関係者で、滞納者の財産を占有する者も含まれる。
保管させることができる場合
7 法第60条第1項の「必要があると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。 (1) 法第59条第2項((引渡しを命ぜられた第三者の使用収益))及び第4項((引渡しを拒まなかった第三者の使用収益))の規定により、これらの第三者に、差し押さえた動産の使用又は収益をさせる場合
(2) 法第61条((差し押さえた動産の使用収益))の規定により、滞納者又は差し押さえた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者に、その動産を保管させる場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難である場合
(4) 差し押さえた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることが滞納処分の執行上適当であると認める場合
滞納者に保管させる場合
8 法第60条第1項の規定により差し押さえた動産又は有価証券を滞納者に保管させる場合には、その滞納者に、その財産を保管すべきことを命じなければならない。この保管命令は、差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
第三者に保管させる場合
(保管命令)
9 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難である場合において、これらを占有する第三者に保管させるときは、その第三者に、その財産を保管すべきことを命じなければならない(法60条1項)。この保管命令は、差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
(運搬が困難であるとき)
10 法第60条第1項ただし書の「その運搬が困難であるとき」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。 (1) 差し押さえた動産又は有価証券の量、型、据付け状態により、その運搬が物理的に困難である場合
(2) 差し押さえた動産又は有価証券が山間へき地にあること等により、交通機関、運搬費等の関係でその運搬が困難である場合
(3) 法第172条((差押動産等の搬出の制限))又は行政事件訴訟法第25条第2項((執行停止)))の規定による停止命令等により搬出が法律上制限されている場合
(同意が得られなかった場合)
11 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難でない場合で、これらを占有する第三者に保管をさせようとする場合において、その第三者の同意が得られなかったときは、徴収職員がその差押財産の直接占有を継続しなければならない。
(保管の同意書)
12 差し押さえた動産又は有価証券を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、差押調書の余白に無償で保管する旨を記載して第三者の署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をさせるものとする。 (注) 有価証券の保管を命じた場合の保管証については、印紙税は課税しない取扱いとされている(昭和52.4.7付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊の別表第1の第18号文書4関係((差押物件等の保管証)))。また、動産の保管を命じた場合の保管証は、課税文書に該当しない。
差押えを明白にする方法
(封印)
13 法第60条第2項の「封印」とは、差押財産であることを表示する令第26条((差押動産等の表示))に定める事項を記載した標識をいう。この封印の様式は、別に定めるところによる。
(公示書)
14 法第60条第2項の「公示書」とは、差押財産であることを一般に周知させるために公示し、公衆がこれを知りうる状態におくための令第26条((差押動産等の表示))に定める事項を記載した書面をいう。この公示書の様式は、別に定めるところによる。
(その他の方法)
15 法第60条第2項の「その他差押を明白にする方法」とは、例えば、縄張、立札、木札等により第三者に対し差押財産であることを明白にする方法をいう(昭和28.1.30広島高松江支判)。
差押えの効力
(差押えの効力発生の時期)
16 徴収職員がその動産又は有価証券を占有した時に、法第56条第2項((差押えの効力の発生時期))の規定によりその差押えの効力が生ずるのであるが、その差押財産を滞納者又は第三者の保管に移したときは、封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生ずる(法60条2項)。
(封印等の効果)
17 封印その他の表示は、徴収職員が差押財産を占有していることを明らかにする方法であって、徴収職員の現実の占有に代わる支配力を有するものであるから、封印その他の表示がされているときは、その財産の譲受けはその差押えに対抗することができない。
(封印と差押えとの関係)
18 封印等の標識は、第三者が通常容易に認識できるようにするものとする。また、差押えの効力の持続のためには、これらの標識の存続は必要ではなく、それが損壊され、自然に脱落し、又は消滅することがあっても、差押えの効力は消滅しない。ただし、徴収職員は、封印等の損壊、脱落又は消滅を発見したときは、速やかに修復するものとする。
差押財産の搬出手続
19 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、令第26条の2第1項((差押財産搬出の手続))に定める事項を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその第三者にその謄本を交付しなければならない。この書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 差押えと同時に差押財産を搬出する場合には、差押調書に差押財産を搬出した旨を付記し、この書面は作成しなくてもよいこと及び差押財産の搬出に際し捜索をした場合には、捜索調書を作成し、この書面は作成しないことに留意する(令26条の2第2項)。
第61条関係 差し押さえた動産の使用収益
滞納者の使用収益
(国税の徴収上支障がないと認めるとき)
1 法第61条第1項の「国税の徴収上支障がないと認めるとき」とは、その動産の使用又は収益をさせてもほとんど減耗を来さないとき、多少減耗はあっても国税の徴収が確実であると認めるとき等国税の徴収に支障がない場合をいう。
(滞納者の申立て)
2 差押動産を保管させた場合における使用又は収益の許可は、滞納者の申立てにより行うものとする。この場合における申立ては、口頭又は書面のいずれの方法によっても差し支えない。 (注) 滞納者から使用又は収益の許可を求める旨の積極的な申立てがなくても、黙示の申立てがあったとみられる場合があることに留意する。
(許 可)
3 法第61条第1項の使用又は収益の許可は、通常の用法により従来の使用又は収益を継続する程度の範囲において行うものとする。
(通 知)
4 法第61条第1項の規定により滞納者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を滞納者に通知するものとする。この場合における通知は、口頭又は差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
第三者の使用収益
(第三者)
5 法第61条第2項の「使用又は収益をする権利を有する第三者」とは、差押え時において第59条関係1から3までに掲げる権利を有する第三者をいう(昭和49.4.30名古屋地判)。
(通知)
6 法第61条第2項の規定により第三者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を第三者及び滞納者に通知するものとする。
第3款 債権の差押え
第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
債 権
1 法第62条の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいう。
なお、将来生ずべき債権であっても、差押え時においてその原因が確立しており、かつ、その発生が確実であると認められるもの(例えば、将来受けるべき給料債権、社員又は株主の有する決議前の利益配当請求権(大正2.11.19大判)、社会保険に基づく将来の診療報酬債権(昭和54.9.19東京高決。昭和53.12.15最高判参照)等)は、差し押さえることができる。 (注) 本来の性質が債権であっても、その性質上取立てに適さず、換価手続によるべきもの(例えば、電話加入権、賃借権等)は、法第73条((電話加入権等の差押の手続及び効力発生時期))の規定により差し押さえる(法54条2号)。
連帯債務者のある債権
2 2人以上の債務者のある債権で、それらの債務者が連帯債務を負っているものを差し押さえる場合には、すべての債務者を第三債務者として差し押さえるものとする。この場合において、第三債務者が任意に履行しないときは、いずれの債務者に対しても執行法の規定による強制執行を行うことができる(民法432条から445条まで参照)。
保証人のある債権
(差押手続)
3 保証人のある債権を差し押さえる場合は、主たる債権の差押えと同時に、保証人を第三債務者として、その保証人に対する債権を別個に差し押さえるものとする。この場合において、その保証が連帯保証であるとき又は保証人が2人以上であり、かつ、保証人相互間では連帯債務であるときの保証人に対する履行の請求については、2の後段と同様である。
(催告及び検索の抗弁権)
4 保証人のある債権の差押え及びこれに基づく強制執行については、次のことに留意する。 (1) 主たる債権の差押えをすることなく、保証人に対する債権を差し押さえたときは、法第62条の規定による差押えは支払の請求を含むものであるから、保証人は催告の抗弁権を有する(民法452条)。
(2) 主たる債権及び保証人に対する債権を差し押さえた後、主たる債務者及び保証人が任意に履行しない場合において、主たる債務者に対して執行法の規定により強制執行をすることなく、保証人に対して強制執行をしたときは、保証人は検索の抗弁権を有する(民法453条)。
(3) 保証人が催告又は検索の抗弁権を行使したにもかかわらず、国が主たる債務者に対して差押え又は強制執行をすることを怠ったため、主たる債務者から全部の弁済を受けることができなかった場合は、保証人は、国が直ちに主たる債務者に対して差押え又は強制執行をすれば弁済を受けることができた限度において、その弁済の責めを免れる(民法455条)。
(連帯保証の場合)
5 保証人の保証が連帯保証である場合は、その保証人は、4に掲げる催告及び検索の抗弁権を有しない(民法454条。商法511条2項参照)。
差押えがされている債権
(滞納処分による差押えがされている債権)
6 滞納処分による差押えがされている債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下(1)及び(3)において同じ。)に対する滞納処分による差押え(以下(1)から(5)までにおいて「二重差押え」という。)については、次に掲げるところによる。 (1) 既にされている差押え(以下(2)から(5)までにおいて「先順位の差押え」という。)が債権の全部又は一部についてされているかどうかを問わず、原則として、二重差押えを行うものとする(昭和33.10.10最高判、昭和32.7.2福岡地決参照)。
(2) 先順位の差押えがある間は、二重差押えに基づいて換価(取立てを含む。)をすることができない。
なお、第三債務者が先順位の差押えに係る行政機関等に対して全額履行したときは、二重差押えは効力を失う。
(3) 二重差押えを行う場合においては、法の規定による債権の差押えの手続によるほか、二重差押えを行った旨を先順位の差押え(その差押えが2以上あるときは、原則としてその全部。以下(4)及び(5)において同じ。)に係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えを行った旨通知は、(4)の交付要求書に付記することにより行う。
(4) 二重差押えを行う場合においては、併せて先順位の差押えに係る行政機関等に対して交付要求をするものとする。
(5) 先順位の差押えがある間に、二重差押えを解除したときは、その旨を先順位の差押えに係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えの解除の通知は、交付要求解除通知書に付記することにより行う。
(強制執行等による差押えがされている債権)
7 強制執行又は担保権の実行若しくは行使による差押えがされている債権に対する滞納処分による差押えについては、滞調法及び昭和56.2.7付徴徴4-2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」通達の別冊(以下「滞調法逐条通達」という。)に定めるところによる。 (注) 担保権の行使とは、担保権者が目的物の売却その他により滞納者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によってするその権利の行使をいう(執行法193条)。
期限の定めのない債権
8 期限の定めのない債権を差し押さえる場合には、徴収職員は、債権差押通知書の「履行期限」欄に、原則として即時と記載するものとする(民法412条3項参照)。
なお、その債権が消費貸借に係るものであるときは、契約の目的、金額その他の事情を考慮して履行期限を定めるものとする(同法591条参照)。
交互計算の特約のある債権
9 特約により交互計算に組み入れられることとなる債権は、計算期間中は独立して差し押さえることができないから、計算期間末に発生すべき残額の支払請求権を差し押さえる。この場合において、他に適当な財産がないときは、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者代位権))の規定による債権者代位権により、滞納者に代位して交互計算の契約を解除し、直ちに残額の支払を請求することができる(商法529条から534条まで参照)。
対抗要件を欠いて譲渡された債権
10 指名債権の譲渡は、確定日付のある証書(民法施行法5条)により譲渡人がこれを債務者に通知し又は債務者がこれを承諾しなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条)ので、この要件を欠いている場合には、譲渡人の債権として差し押さえることができる。 (注) 債権譲渡の通知は譲渡人がすべきであり、譲受人は譲渡人から委任を受けている場合を除き、譲渡人に代位して通知することができない(昭和46.3.25最高判)。
代理受領の目的となっている債権
11 代理受領の目的となっている債権であっても、その契約は差押債権者に対抗できないから(昭和43.3.22大阪高判参照)、当該債権に対して滞納処分をすることができる。 (注) 代理受領とは、債権者が、その債権の確保のために、債務者(滞納者)が第三債務者に対して有する債権について、債務者から取立ての委任を受け、受領した金員を直接自らの債権の弁済に充当する方法による債権担保手段をいう。
譲渡禁止の特約のある債権
(譲渡禁止の特約のある債権の差押え)
12 指名債権につき、当事者間の特約によりその譲渡が禁止されている場合においても、当該債権を滞納処分により差し押さえることができる(第47条関係9、昭和34.9.14東京地判。昭和45.4.10最高判参照)。
(譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合)
13 譲渡禁止の特約のある指名債権につき、譲受人がその特約を知っているときは、その譲渡は無効であるから(民法466条2項)、譲渡人の債権として差し押さえることができる。ただし、その譲渡について第三債務者が承諾を与えているときは、譲渡人の債権として差し押さえることはできない(昭和52.3.17最高判)。
手形又は小切手の振り出されている債権
14 債権について手形又は小切手が振り出されている場合には、その債権の差押えは、次による。 (1) 第三債務者が債務の弁済に代えて手形又は小切手を振り出している場合には、代物弁済によりその債務は弁済されたことになるから、債権の差押えをすることはできない。したがって、この場合には、その手形又は小切手を、法第56条第1項((動産等の差押え))の規定により差し押さえる。
(2) 第三債務者が債務の弁済のために手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているから、その手形又は小切手とは別個にその債権を差し押さえることができる。ただし、手形又は小切手が時効その他の理由により効力を失うまでは、第三債務者は、手形又は小切手が返却されなければ、本来の債務の履行を拒むことができる(昭和13.11.19大判)。
なお、手形又は小切手の振出について特に代物弁済の意思表示がなかったときは、その手形又は小切手は、支払のために振り出されたものと推定される(昭和3.2.15大判)。
敷 金
15 物の賃貸借において、賃借人が賃貸人に交付する敷金の差押えについては、次のことに留意する。
なお、敷金とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的であらかじめ賃貸人に交付される金銭であり、その名称のいかんを間わない。 (1) 賃貸借が継続している間は、賃借人は、敷金の返還請求権を有せず、また、敷金は、賃貸借存続中の賃料債権のみならず賃貸借終了後目的物の明渡義務の履行までに生ずる質料相当損害金の債権その他賃借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのあるべき一切の債権を担保する。したがって、敷金は、将来目的物の明渡しの際に生ずべき返還請求権として差し押さえる(昭和48.2.2最高判)。
(2) 賃貸人が賃貸借の目的物を譲渡した場合には、特約があるときを除き、敷金は、当事者が現実に敷金の引継ぎをしたかどうかにかかわらず、被担保債権を控除した残額について、新たな賃貸人に引き継がれる(昭和2.12.22大判、昭和44.7.17最高判)。
(3) 賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転した場合においては、旧賃借人が新賃借人に敷金を譲渡するなど特段の事情のない限り、敷金は新賃借人に承継されない(昭和53.12.22最高判)。
権利金
16 借地契約又は借家契約に伴い貸主が借主から受領した借地権利金又は借家権利金は、地代家賃統制令第12条の2((権利金の受領禁止))の規定に違反するから、その権利金の返還請求権を差し押さえることができる。ただし、同令第23条((適用除外))の規定に該当する場合には、権利金の返還請求権がない。
無記名預金等
17 無記名預金、他人名義又は架空名義の預金の差押えについては、次のことに留意する。 (1) これらの預金については、自らの出えんによって、自らの預金とする意思で自ら又は使者等を通じて預金契約をした者が預金者となる(昭和32.12.19最高判、昭和53.2.28最高判)。
(2) 無記名預金は、氏名を特定しない一種の指名債権であって、無記名債権ではないから(昭和32.12.19最高判)、法第56条第1項((動産等の差押え))の規定によっては差し押さえることができず、法第62条の規定により債権として差し押さえる。この場合においては、その預金の名称、預金金額、預金証書番号、無記名である旨、使用印影の表示をすること等によって、被差押債権を特定させるものとし、また、その債権の取立てに当たっては、できる限り使用印影を押なつした預金証書を呈示するものとする。
(3) 他人名義又は架空名義で預金をしている場合であっても、その真の権利者に対する滞納処分としてその預金を差し押さえることができる。この場合においては、預金名義人の住所、氏名、預金の種類、名称、預金金額、預金証書番号等によって被差押債権を特定するとともに、真の権利者が滞納者である旨を表示する(例えば、何某(預金名義人氏名)こと何某(滞納者氏名)のように表示するものとする。)。
国又は地方公共団体に対する債権
18 国又は地方公共団体に対する債権を差し押さえる場合には、直接その支払の権限を有する支出官、資金前渡官吏等を第三債務者として差し押さえる(政府ノ債務ニ対シ差押命令ヲ受クル場合二於ケル会計上ノ規程参照)。この場合において、その支払の権限を有する者が判明しないときは、その行政機関の長を第三債務者として差し押さえても差し支えない。 (注) 供託金について債権差押えをする場合には、第三債務者を国とし、その代表者を供託官とし、供託官あてに債権差押通知書を送達する(昭和26.4.18付民事甲第61号最高裁判所民事局長回答参照)。
郵便貯金
19 郵便貯金を差し押さえる場合には、次により、直接その支払の権限を有する者を第三債務者として差し押さえる。 (1) 即時払いを請求できる場合(貯金を預け入れた郵便局においてその郵便局に預け入れた貯金の現在高を超えない金額の貯金の払戻しを請求する場合等。郵便貯金規則51条2項、3項)には、払戻しを請求すべき郵便局の局長を第三債務者とする。
(2) (1)以外の場合には、払戻証書による払戻しの方法によることになるから(郵便貯金規則54条1項)、その郵便貯金の貯金原簿を所管する地方貯金局又は沖縄郵政管理事務所の長を第三債務者とする。この場合においては、その所管庁は、差押金額について払戻証書を作成し、徴収職員に送付することとなっているから、徴収職員は、その払戻証書により特定の郵便局(債権差押通知書に指定すること。)において払戻しを受けるものとする。 (注)1 郵便貯金の払戻しを受けるに当たっては、貯金通帳又は貯金証書を呈示することとなっているから、これらの通帳等を、法第65条((債権証書の取上げ))の規定により、債権に関する証書として取り上げるものとする。
2 郵便貯金を差し押さえた場合は、債権差押通知書に令第27条第4号((債権差押通知書の記載事項))の事項の記載があることにより、その払戻しの請求をしたこととなるが、この払戻しの請求は、貯金通帳又は貯金証書を呈示してしなければならない(郵便貯金規則51条1項、52条、54条2項から4項まで)。
不渡異議申立預託金
20 手形又は小切手の振出人等が、その不渡りによる取引停止処分を回避するため支払銀行に預託する不渡異議申立預託金については、支払銀行に対して有する不渡異議申立預託金返還請求権を差し押さえる。この不渡異議申立預託金返還請求権の弁済期は、支払銀行が手形交換所から不渡異議申立提供金の返還を受けた時である(昭和45.6.18最高判)。 (注) 不渡異議申立提供金とは、支払銀行が手形又は小切手の支払を拒絶した振出人等に支払の資力があり、不渡りがその信用に関しないものであることを明らかにすることにより、取引停止処分を回避するために手形交換所に提供する手形又は小切手の金額相当額の金員をいう(東京手形交換所規則66条参照)。
公示催告中の手形等に係る債権
21 公示催告中の手形又は小切手に係る債権については、その手形金等の支払請求権を差し押さえることができる(昭和51.4.8最高判参照)。 (注) この手形金等の支払請求権は、将来の除権判決の取得を停止条件として権利行使ができる一種の条件付債権である。
換地の所有権の移転があった場合の清算金交付請求権
22 土地区画整理事業による換地の所有権が移転した場合における当該換地に係る清算金交付請求権は、当事者間で特段の合意がなされない限り、当該換地の譲受人には移転しないから(昭和37.12.26最高判、昭和48.12.21最高判)、清算金交付請求権は、当該換地の譲渡人に帰属するものとして差し押さえることができる。
差押手続
(第三債務者)
23 法第62条の「第三債務者」とは、滞納者に対して金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債務を負う者をいう。
(債権の特定)
24 債権の差押えに当たっては、債権者(滞納者)、第三債務者、債権の数額、給付の内容等を表示することによって被差押債権を特定しなければならない。
なお、被差押債権の表示については、具体的事実によって第三債務者が被差押債権を確知できる程度に表示されておれば、その債権の差押えは有効である(昭和13.7.2大判、昭和30.5.19大阪高決。昭和46.11.30最高判参照)。
(債権の範囲)
25 差し押さえる債権の範囲は、原則として、その債権の全額である(法63条)。 (注) 社会保険に基づく将来の診療報酬債権については、近い将来の範囲(おおむね1年以内とする。)に限り、その始期と終期を定めて差し押さえるものとする(昭和54.9.19東京高決参照)。
(債権差押通知書)
26 法第62条第1項の「債権差押通知書」とは、令第27条各号((債権差押通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第4号書式による。この債権差押通知書には、被差押債権の弁済期までに履行すべき旨又は弁済期が既に到来しているものについては直ちに履行すべき旨を記載する。
(差押調書)
27 債権を差し押さえたときは、法第54条の規定により、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付する。この謄本には、債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を付記しなければならない(法62条2項、令21条3項)。
(債権証書の取上げ)
28 徴収職員は、債権の差押えのため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる(法65条)。
差押えの効力
(効力発生の時期)
29 債権の差押えは、債権差押通知書が第三債務者に送達された時にその効力を生ずる(法62条3項)。
なお、滞納者に対する差押調書の謄本の交付は、差押えの効力発生要件ではない。
(履行の禁止)
30 第三債務者は、債権の差押えを受けたときは、その範囲において滞納者に対する履行が禁止される。したがって、債権差押通知書の送達を受けた後に、第三債務者が滞納者に対して履行をしても、その履行をもって差押債権者である国に対抗することができない(民法481条参照)。
(相殺の禁止)
31 第三債務者の有する反対債権と被差押債権との相殺については、次のことに留意する。 (1) 被差押債権及び反対債権の弁済期が差押え時以前に到来している場合並びにこの場合以外で被差押債権の弁済期以前に反対債権の弁済期が到来する場合には、差押え後においても、第三債務者は、相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(2) 差押え前に取得した反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より後に到来する場合において、第三債務者が履行しないことについて正当な理由があるときに限り、第三債務者は、相殺をもって差押債権者に対抗することができる(昭和45.6.24最高判)。
なお、滞納者と第三債務者との間において、差押え前に、期限の利益の喪失の特約又は債務不履行があった場合等一定の条件の下に第三債務者が相殺の予約完結権を行使できる旨の特約がされている場合には、反対債権が差押え後に取得されたものでない限り(民法511条)、第三債務者は、当該特約に基づく相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(3) 民法第509条((不法行為による債権の相殺))、商法第200条第2項((相殺禁止))、有限会社法第57条((資本増加に関する準用規定))等の法令の規定により、相殺が禁止される場合がある。
(債権の譲渡等)
32 第三債務者が債権の差押えを受けたときは、滞納者が被差押債権の譲渡、免除、期限の猶予等をしても、第三債務者は、これらの行為にかかわらず、差押債権者に弁済をしなければならない(法62条2項参照)。
(債権譲渡と差押えとの優劣)
33 指名債権の譲渡と滞納処分による差押えの優劣は、確定日付のある譲渡通知書が第三債務者に到達した日時又は確定日付のある第三債務者の承諾の日時と、債権差押通知書が第三債務者に到達した日時との先後により判定する(昭和49.3.7最高判参照)。この場合において、これらの日時が同一であることにより優劣の判定ができないときは、債権譲受人及び差押債権者は、それぞれ第三債務者に対しその履行を請求することができる(昭和55.1.11最高判参照)。
(同時履行の抗弁権又は選択権の行使)
34 第三債務者が同時履行の抗弁権を有する場合(民法533条)又は第三債務者若しくは第三者が選択権を有する場合(同法406条から411条まで参照)には、差押え後であっても、これらの権利を行使することができる。
(継続的な収入)
35 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押えの効力は、差押えに係る国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金額に及ぶ(法66条)。
(法定果実)
36 債権を差し押さえた場合には、その差押えの効力は、差押え後に生ずる利息に及ぶが、その他の法定果実には及ばない(法52条2項、第52条関係16,17参照)。
(時効中断)
37 債権の差押えは、通則法第72条第3項((時効についての民法の規定の準用))において準用する民法第147条第2号((差押え等の時効中断の事由))の規定により、その差押えに係る国税については時効中断の効力を有する。また被差押債権については、時効中断の効力を生ぜず、催告としての効力を有するから(大正10.1.26大判)、債権差押え後6月内に裁判上の請求その他の行為(民法153条参照)をすれば、その催告による時効中断の効力がある。 (注) 時効期間は一般の債権が10年(民法167条1項)、商事の債権が5年(商法522条)であるが、なお、短期消滅時効の定めがあることに留意する(民法169条から174条まで、商法567条、手形法70条等)。
差押えの登録の嘱託
(登録を要する債権)
38 法第62条第4項の「移転につき登録を要するもの」には、社債等登録法第3条((登録をする場合))の規定により登録された社債のほか、地方債、特別の法令により設立された法人で会社でないものが発行する債券等で、同法第14条((地方債等への準用))において準用する同法第3条の規定に基づき登録されたものがある(これらについては、債券は発行されていない。同法4条)。
なお、登録国債については、次に掲げる書類を日本銀行(国債局)に送達することにより、差し押さえるものとする。 (1) 第三債務者を国とし、その代表者を大蔵大臣と記載した債権差押通知書
(2) 日本銀行総裁をあて先とする登録国債差押登録嘱託書
(登録社債等の差押えの登録の嘱託)
39 登録社債等を差し押さえたときは、社債等登録法施行令に定める手続に従って、関係機関(登録機関)に対して差押えの登録の嘱託をしなければならない(法62条4項)。この場合において、その登録社債等の発行機関が同令第1条((登録機関))に規定する登録機関と異なるときは、その発行機関に対して差押えの通知をするものとする(社債等登録法5条、同法施行令13条、18条1項)。
第63条関係 差し押さえる債権の範囲
差し押さえる債権の範囲
(全額の差押え)
1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法63条本文)。
(一部の差押え)
2 法第63条ただし書の「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる要件を満たすときをいうものとする。 (1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。
(2) 弁済期日が明確であること。
(3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと。
一部差押えの手続
3 債権の一部を差し押さえる場合には、債権差押通知書の「差押債権」欄に、その債権のうち一部を差し押さえる旨を明記する(令27条3号参照)。
第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
債権差押えの登記の嘱託
(登記の嘱託)
1 抵当権(根抵当権を含む。昭和55.12.24付民三第7,176号法務省民事局長通達。以下3及び4において同じ。)又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権を差し押さえた場合(債権差押え後に、その債権を被担保債権として担保権が設定された場合を含む。昭和42.1.30付民事甲第206号法務省民事局長通達)には、税務署長は、債権差押えの登記を関係機関に嘱託する。この関係機関については、第68条関係44、第70条関係5、第71条関係5、第72条関係19及び第73関係52と同様である。この債権差押えの登記は、担保権の登記の付記登記としてなされる(不動産登記法施行細則55条、56条)。
なお、債権差押えの登記は、債権差押えの効力要件ではないが、その登記をすることにより、その抵当権、質権又は先取特権に差押えの効力が及んでいることについて対抗要件を具備することとなる。 (注) 登記の嘱託とは、官公署が法令の規定に従って関係機関に対して登記の依頼を行うことをいう。
嘱託による登記の手続には、原則として申請による登記に関する規定が準用される(不動産登記法25条2項、船舶登記規則1条、航空機登録令8条、自動車登録令9条、建設機械登記令9条、特許登録令15条等)。
(登録免許税の非課税)
2 税務署長が債権の差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
債権譲渡又は担保権の処分と差押えとの関係
3 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権の譲渡と滞納処分による差押えとの優劣は、その担保権の移転の登記又は債権差押えの登記との先後によってではなく、債権譲渡の対抗要件である確定日付のある通知又は承諾と債権差押通知書の送達との先後によって定まる(法62条関係33)。したがって、債権譲渡が優先する場合には、債権差押えの登記をしても、債権譲受人に対し担保権につき差押えの効力を主張できず(大正1.11.26大判)、また、差押えが優先する場合においては、既に担保権の移転の登記がされていても、その抹消を求めることができる(昭和35.4.28高知地判、昭和35.9.28松山地判)。
なお、被担保債権と別個になされる抵当権のみの譲渡、順位譲渡その他の抵当権の処分と差押えとの優劣は、抵当権の処分の登記と債権差押えの登記との先後によって定まることに留意する(民法177条、375条参照)。
債権差押えの通知
(質権又は抵当権が設定されている場合)
4 税務署長は、1の嘱託をしたときは、その質権又は抵当権が設定されている財産の権利者(第三債務者を除く。)に対して、債権差押えをした旨を通知しなければならない(法64条後段)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(先取特権がある場合)
5 税務署長は、1の嘱託をしたときは、その先取特権がある財産の権利者に対して4の通知をしなければならない。この場合において、その権利者がその被差押債権の第三債務者であるときは、この通知は要しない(法64条後段)。
他の担保権のある債権の差押え
(動産質等のある場合の差押手続)
6 動産について質権又は留置権のある債権を差し押さえた場合には、その質権又は留置権に差押えの効力が及ぶから、その質権又は留置権の目的となっている財産の権利者(第三債務者を除く。)に対し、4に準じて債権差押えをした旨を通知する。この場合には、滞納者の所持する質物又は留置物を動産差押えの手続に準ずる方法により、徴収職員が直接占有するものとする。この場合において、その質物又は留置物を滞納者以外の第三者が所持している場合の徴収職員の占有の手続については、法第56条第1項、第58条及び第60条第1項本文((動産の差押手続、保管等))の規定による手続を準用する。
なお、不動産留置権のある債権を差し押さえた場合においても、上記の手続に準ずる。
(債権質のある場合の差押手続)
7 債権質のある債権を差し押さえた場合(8の場合を除く。)には、その債権質の目的となっている債権の債務者(第三債務者を除く。)に対して、4に準じて主たる債権(その債権質によって担保されている被差押債権)を差し押さえた旨を通知するものとする。この場合において、主たる債権の債権者(滞納者)の占有する債権に関する証書があるときは、法第65条((債権証書の取上げ))の規定によりその証書を取り上げることができる。 (注) 債権をもって質権の目的とする場合において、その債権につき証書があるときは、質権の設定の効力は、その証書を交付しなければ生じない(民法363条)。
(有価証券質のある場合の差押手続)
8 有価証券を目的とする質権のある債権を差し押さえた場合には、その質権の設定者(第三債務者を除く。)に対して、4に準じて債権差押えをした旨を通知するほか、滞納者が占有するその質権の目的である有価証券を、法第65条((債権証書の取上げ))の規定により徴収職員が占有する。この場合において、その有価証券が記名社債又は記名株式であるときは、その有価証券質に差押えの効力が及んでいることの対抗要件を具備するために、その有価証券を発行した者に債権差押えをした旨を通知する(民法365条、商法209条参照)。 (注) 上記の場合において、有価証券を滞納者以外の第三者が所持している場合の徴収職員の占有の手続については、法第56条第1項、第58条及び第60条第1項本文((動産の差押手続、保管等))の規定による手続に準ずる。
(その他の権利質のある場合の差押手続)
9 7及び8以外の権利質のある債権を差し押さえた蝪合には、その権利質の目的となっている財産権の性質に従い、主たる債権の差押えの登記の嘱託、第三債務者に準ずる者への通知等7及び8に準じて必要な手続をとるものとする。
第65条関係 債権証書の取上げ
債権証書の取上げ
(取上げができる場合)
1 法第65条の「差押のため必要があるとき」には、債権差押えをしようとする場合において、債権の存否、債権の数額の確認等のため必要と認められるときのほか、債権の差押え、取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれる。
(取上げができる証書)
2 法第65条の「債権に関する証書」とは、債権の発生、変更を証する文書のほか、債権の差押え、被差押債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められる文書をいい、例えば、郵便貯金通帳、銀行預金通帳、銀行預金証書、供託書正本(官庁又は公署が保管している場合に限る。供託規則24条、25条参照)、供託通知書、公正証書、確定判決、和解調書等がある。
(取上げの手続)
3 法第65条の「取り上げる」とは、徴収職員が、その債権に関する証書の取上げの意思をもって客観的な事実上の支配下に置くことをいう。この場合において、その証書を滞納者及びその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有し、その引渡しを拒むときは、法第58条((第三者が占有する動産等の差押手続))の規定の準用がある(法65条後段)。
(取上調書の作成)
4 債権に関する証書を取り上げた場合は、令第28条第1項((債権証書等を取り上げた場合の調書))の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した調書を作成して署名押印し、その謄本を滞納者その他その処分を受けた者に交付しなければならない。この調書は、別に定めるところによる。ただし、上記の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成した場合において、これらの調書に取り上げる証書の名称、数量その他その証書を特定するに足りる必要な事項を付記したときは、取上調書の作成を要しない(令28条2項)。
債権証書の返還等
5 債権の差押えを解除する場合において、取り上げた債権に関する証書があるときの措置については、法第80条第2項第1号及び第4項((差押の解除の手続))の規定が準用される(法80条5項)。
第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
継続的な収入
1 法第66条の「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」とは、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給料に係る債権(法76条1項参照)並びに継続的給付を目的とする契約関係から発生する収入を請求する権利、例えば、賃貸借契約に基づく地代、家賃の請求権等をいう。
差押えの効力の及ぶ範囲
(差押え後に収入すべき金額)
2 継続収入の債権を差し押さえた場合には、特に制限した場合(例えば、「何月分の給料又は家賃」というように制限した場合等)を除いては、差押えに係る国税を限度として、差押え後に支払われるべき金額のすべてに差押えの効力が及ぶ。したがって、各支払期ごとの金額を各別に差し押さえる必要はない。
(差押えの効力の存続)
3 法第66条の継続的な収入に対する差押えの効力は、第三債務者が同一であり、かつ、滞納者と第三債務者との間の基本の法律関係に変更がない限り、その後に変更があった収入にも及ぶ。 (注) 滞納者が退職した後再雇用されている場合には、執行を免れるため仮装したと認められるときを除き、退職前に行われた給料に対する差押えの効力は、再雇用後の給料には及ばない(昭和55.1.18最高判参照)。
第67条関係 差し押さえた債権の取立て
取立て
(意 義)
1 法第67条第1項の「取立」とは、徴収職員が、被差押債権の本来の性質、内容に従って、金銭又は換価に適する財産の給付を受けることをいう。
(取立ての範囲)
2 債権を差し押さえたときは、差押えに係る国税の額にかかわらず、被差押債権の全額を取り立てるものとする(法67条1項)。
(取立権取得の効果)
3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、差し押さえた債権の取立てに必要な滞納者の有する権利を行使することができる。したがって、支払命令の申立て、給付の訴えの提起、配当要求、破産手続又は会社更生手続への参加、担保権の実行、保証人に対する請求等の行為をすることができるが、債務の免除、譲渡、弁済期限の変更等取立ての目的を超える行為をすることはできない。 (注)1 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合においても、被差押債権の取立ては制限をうけない(通則法105条1項参照)。
2 債権差押えに基づく取立訴訟において、第三債務者は、差押えに係る国税の存否を争うことはできない(昭和52.1.28広島地判。昭和45.6.11最高判参照)。
(取立ての方法)
4 第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行しないときは、徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずるものとする。
なお、必要に応じ仮差押え又は仮処分の申請をすることができる。 (注) 被差押債権の取立てについては、給付の訴えの提起、支払命令の申立て、仮差押え又は仮処分の申請等をする必要がある場合には、法務省の関係部局に依頼して行う(法務大臣の権限法1条)。
(担保権のある債権の取立手続)
5 抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合において、第三債務者が被差押債権の取立てに応じないときは、次に掲げるところによる。 (1) 抵当権、質権(権利質及び注に掲げるものを除く。)、先取特権又は留置権の目的となっている財産については、執行法その他の法律の規定により担保権の実行をする。 (注) 流質契約のある商事質又は営業質の目的となっている財産については、流質期限の経過後は、滞納者の財産として差し押さえる。
(2) 債権質の目的となっている債権については、その債権の債務者(第四債務者)から直接取り立てる(民法367条)。
なお、上記の債務者が取立てに応じないときは、執行法第193条((債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等))の規定により担保権の実行又は行使をする。
(3) 不動産物権の上の質権については、抵当権実行の方法に準じて、その不動産物権について競売の申立てをする。
(4) (2)及び(3)に掲げる以外の権利質については、執行法第193条の規定により担保権の実行又は行使をする。
(取立ての責任)
6 徴収職員が被差押債権の取立てに当たって故意又は過失により違法に滞納者に損害を与えたときは、国は、国家賠償法第1条第1項((公権力の行使に基づく損害の賠償責任))の規定により、滞納者に対してその損害を賠償しなければならない場合がある。
(給付の受領の資格)
7 第三債務者から取り立てた金銭は、歳入歳出外現金出納官吏の資格において、受け入れる(管理事務提要(現金出納編)第131参照)。
(履行の場所)
8 被差押債権の履行場所は、原則として(民法664条、商法608条参照)、次に掲げるところによる。
なお、被差押債権が持参債務であるときは、税務署の所在地が履行場所となる(9の(2)のただし書参照)。 (注) 滞納者と第三債務者との間で金融機関に振込入金することにより履行することになっている場合であっても、同様である。 (1) 商行為により生じた債務(商法516条参照) イ 行為の性質又は当事者の意思表示で定まっているときは、その定められている場所
ロ イ以外の場合には次による。 (イ) 特定物の引渡しを目的とする債務については、行為の当時その物の存在した場所
(ロ) 特定物の引渡し以外の給付を目的とする債務については、履行する時の債権者の営業所(営業所がないときは住所) (注) 支店でした取引については、その支店が営業所とみなされる(商法516条3項)。
(2) (1)以外の債務(民法484条参照) イ 取引の慣行又は意思表示で定まっているときは、その定められている場所
ロ イ以外の場合には次による。 (イ) 特定物の引渡しを目的とする債務については、債権発生の当時その物の存在した場所
(ロ) 特定物の引渡し以外の給付を目的とする債務については、履行する時の債権者の場所 (注) 売買代金について、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所が履行場所となる(民法574条)。
(履行の費用)
9 被差押債権の履行の費用については、次による(民法485条参照)。 (1) 取立債務であるときは、その取立てに要する費用は滞納処分費として支出する。ただし、第三債務者が取立てに要する費用を支出し、その費用を債務の額から差し引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えない。この場合においては、第三債務者に対し、その費用に相当する額については履行の請求をしないものとする。
(2) 持参債務であるときは、その取立てに要する費用は第三債務者に負担させる。ただし、本来の履行場所である滞納者の住所又は営業所と税務署の所在地とが異なるため費用が増加した場合における増加費用については、(1)に準ずる。
(3) 履行場所が特約によって定まっているときは、その履行場所からの取立てに要する費用については、(1)に準ずる。
(4) 弁済の費用について特約があるときは、その特約の定めるところに従い、(1)から(3)までに準ずる。
取立不能の判定
10 第三債務者に弁済の資力がなく取立不能と認められる場合には、債権の差押えを解除するものとする。この場合において、取立不能の判定は、原則としては強制執行等の強制的な取立手続をした後において行うが、第三債務者の資力その他の状況により、その債権が取立不能と認められるときは、強制的な取立て手続をすることなく判定して差し支えない。
取立財産の差押え
11 第三債務者から取り立てた金銭(第56条関係26参照)以外の財産については、その財産の種類に応じて、法第56条((差押の手続及び効力発生時期等))、第68条((不動産の差押の手続及び効力発生時期))、第70条((船舶又は航空機の差押))又は第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定による差押えの手続をとらなければならない(法67条2項)。
徴収したものとみなす
12 法第67条第3項の「徴収したものとみなす」とは、金銭(第56条関係26参照)を取り立てたときは、その限度において、滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
なお、国税の納付に使用することができる有価証券を取り立てた場合において、その支払がなかったときは、滞納者の国税の納税義務は消滅しない(証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律2条参照)。
弁済の委託
(意 義)
13 法第67条第4項の「弁済の委託」とは、第三債務者が有価証券の現金化及びその現金による被差押債権の弁済手続を、弁済受託に関する証書に記載された税務署長が定める条件により、徴収職員に委任することをいう。
なお、弁済委託により受領した証券は債権の弁済に代えて受領するものではないから、第三債務者の債務(被差押債権)は、弁済委託により直ちに消滅するものではない。
(弁済受託に関する証書)
14 弁済受託に関する証書は、通則規則第5条((書式))に規定する別紙第6号書式の納付受託証書を補正の上使用する(規則3条2項参照)。 (注) 徴収職員は、弁済の委託を受けたときは、弁済受託に関する証書を弁済の委託をした者に交付しなければならない(法67条4項、通則法55条2項)。
(証書に記載する延滞税の金額)
15 弁済受託に関する証書に記載する延滞税の金額は、弁済委託を受けた証券の種類により、それぞれ次に掲げる目までの金額とする。
なお、次のそれぞれに掲げる日の翌日以後の延滞税については、通則法第63条第5項第1号((納付委託に係る延滞税の免除))の規定に準じて、免除することができるものとする。 (1) 証券が一覧払いのものであるときは、その委託を受けた日
(2) 証券が先日付小切手であるときは、その振出日として記載された日
(3) 証券が(1)以外の手形であるときは、その満期日
(弁済委託に使用できる証券)
16 弁済委託に使用することができる証券は、証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律の規定に基づき国税及び歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券のうち、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限る取扱いとする(令67条4項、通則法55条1項参照)。
なお、証券の券面金額が差押えに係る国税の額を超える場合であっても、被差押債権の金額を超えない限り、その証券による弁済の委託を受けることができる。 (1) 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下16において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの (注) 信用金庫、農業協同組合等は、小切手ノ適用二付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ足ムルノ件により、小切手法の適用については銀行と同視されているので、これらのもののうち、手形交換所に代理交換の認められているものは、手形交換所に加入している銀行として取り扱う。 イ 振出人が弁済委託をする者であるときは、弁済委託を受ける徴収職員の所属する税務署長を受取人とする記名式のもの
ロ 振出人が弁済委託をする者以外の者であるときは、弁済委託をする者が税務署長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの イ 約束手形については振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)については支払人が、それぞれ弁済委託をする者であるときは、税務署長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
ロ 約束手形については振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人が、それぞれ弁済委託をする者以外の者であるときは、弁済委託をする者が税務署長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする(1)及び(2)に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(弁済委託を受けることができる場合)
17 弁済委託を受けることができる場合は、最近において取立てが確実と認められる16の証券を提供した場合で、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するときに限る取扱いとする(法67条4項、通則法55条1項参照)。 (1) 第三債務者の提供した証券の支払期日が、被差押債権の弁済期以前であるとき。
(2) 第三債務者の提供した証券の支払期日が弁済期後となるときは、その証券の支払期日まで弁済期限を猶予することを滞納者が承認したことを証する書面を、併せて提出したとき(18、令29条参照)。
(滞納者の承認)
18 法第67条第4項ただし書の「滞納者の承認」とは、滞納者が被差押債権の弁済期限の猶予を承認することをいう。この場合における弁済期限の猶予は、差押債権者である国と滞納者との間には影響を及ぼさない。
(取立ての費用)
19 弁済委託を受けた証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を第三債務者から併せて提供させなければならないが(法67条4項、通則法55条1項後段参照)、この場合における費用とは、銀行に再委託した場合における取立手数料その他銀行が取立てをするために要する費用(例えば、取立済通知を電信で受けるように依頼して取立委託をする場合の実費等)をいう。
なお、取立費用は、徴収職員としての資格ではなく、歳入歳出外現金出納官吏の資格において受領するものである(管理事務提要(現金出納編)第131参照)。
(再委託)
20 弁済委託を受けた証券は、その取立てのため、徴収職員が確実と認める金融機関に再委託をすることができる(法67条4項、通則法55条3項)。
(納付委託に関する規定の準用)
21 弁済委託については、通則法第55条第1項から第3項((納付委託))までの規定が準用される(法67条4項)。
第4款 不動産等の差押え
第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
法第68条の適用を受ける財産
1 法第68条の適用を受ける財産は、次に掲げる財産(以下「不動産」という。)である。 (1) 民法上の不動産土地及び土地の定着物
(2) 不動産を目的とする物権(所有権を除く。)地上権及び永小作権
(3) 不動産とみなされる財産立木法による立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団及び観光施設財団
(4) 不動産に関する規定の準用がある財産鉱業権、特定鉱業権、漁業権、入漁権、採石権及びダム使用権
(5) 不動産として取り扱う財産鉄道財団、軌道財団及び運河財団
民法上の不動産
(土地及び土地の定着物)
2 土地及び土地の定着物は、民法第86条第1項((不動産の定義))に規定する不動産であるが、なお次のことに留意する。 (1) 土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶが(民法207条)、鉱業法において、鉱物として列挙されたもので、未採掘のものを取得する権利等は国により賦与されるので、その権利の賦与がない限り、その鉱物には土地の所有権が及ばない(鉱業法2条、3条)。
(2) 土地の定着物とは、土地に付着させられ、かつ、取引上の性質としてその土地に継続的に付着させられた状態で使用されるもの(例えば、建物その他の工作物、植栽された樹木、大規模な基礎工事によって土地に固着させられた機械等)をいい、土地の一部として土地の差押えの効力が及ぶが、建物及び立木法による立木は、取引上及び登記簿上、土地と別個の不動産として取り扱われ、その差押えには別個の差押手続を必要とする。 (注) 登記することができない土地の定着物は、民事執行の手続の上では、動産執行の対象となる(執行法43条1項、122条1項)。
(3) 仮植中の樹木、簡単な方法で土地に据え付けた機械、灯ろう等は独立の動産であって、土地の定着物ではない。
(4) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による工場抵当の目的となっている土地の備付物には、その土地に対する差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。4参照)。
(建 物)
3 建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい(不動産登記事務取扱手続準則(昭和52.9.3付民三第4,472号法務省民事局長通達)136条1項)、取引上及び登記簿上、土地から独立した不動産とされ、土地には別個に差し押えなければならないが、なお次のことに留意する。 (1) 不動産登記手続上次のイの建造物は建物として取り扱われるとして例示されているが、ロの建造物は建物として取り扱われないこととされている(不動産登記事務取扱手続準則136条2項)。 イ 建物として取り扱うもの (イ) 停車場の乗降場及び荷物積卸場(ただし、上屋を有する部分に限る。)
(ロ) 野球場、競馬場の観覧席(ただし、屋根を有する部分に限る。)
(ハ) ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
(ニ) 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物
(ホ) 園芸、農耕用の温床施設(ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。)
ロ 建物として取り扱わないもの (イ) 瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク
(ロ) 機械上に建設した建造物(ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。)
(ハ) 浮船を利用したもの(ただし、固定しているものを除く。)
(ニ) アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
(ホ) 容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等
(2) 建築中の建物のうち、建物の使用の目的からみて使用可能な程度に完成していないものは、動産として差押さえる(大正15.2.22大判参照)。この場合において、その後通常建物として使用することができる程度(屋根、周壁及び床を備える状態)に完成した場合には、改めて不動産としての差押えの上、動産としての差押えを解除するものとする。
なお、建築中の建物については、不動産工事の先取特権の登記がある場合であっても、建物としての差押え及びその登記をすることはできない(不動産登記法136条参照)。
(3) プレハブ式建物については、その土台を土地に付着させしめるような特別の付加工事を施した場合又は土地に永続的に付着した状態で一定の用途に供されるものであると取引観念上も認めうるような特段の事情がない限り、動産として差し押さえる(昭和54.3.27釧路地判参照)。 (注) プレハブ式建物とは、屋根、周壁等によって構成され、一時的あるいは場所的な移動を必要とする用供する目的で移設に適するような構造に製作された建物をいう(昭和54.3.27釧路地判参照)。
(4) 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(建物の区分所有等に関する法律1条参照)があるときは、その各部分について独立した不動産として差し押さえる(不動産登記法15条ただし書、16条ノ2参照)。
(5) 同一の建物につき2以上の表示の登記がされている場合には、先にされた表示の登記が建物の現況と符号している以上、後にされた表示の登記は無効である(昭和37.10.4付民事甲第2,820号法務省民事局長通達参照)。
(6) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による工場抵当の目的となっている建物の備付物には、その建物に対する差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。4参照)。
財団を組成しない工場抵当の目的となっている土地又は建物
(差押えの効力が及ぶ財産)
4 工場抵当法第7条((差押え等の及ぶ範囲))の規定により、抵当権の目的となっている土地又は建物についての差押えの効力は、その土地又は建物に付加してこれと一体となっている物及びその土地又は建物に備え付けた機械器具その他工場の用に供する物に及び、その備え付けた時期が抵当権の設定又は差押えの前であると後であるとを問わない(大正9.12.3大判)。
(差押えの効力が及ばない財産)
5 工場抵当法第1条((工場の定義))にいう工場の土地又は建物についての抵当権の効力は、次に掲げる物には及ばないから、その土地又は建物についての差押えの効力も及ばない。したがって、これらの物件が同法第3条((抵当権の目的物の目録))の目録に記載されている場合においても、その記載は効力がない(同法3条2項、35条参照)。 (1) 土地を差し押さえた場合の建物及び建物を差し押さえた場合の土地(工場抵当法2条)
(2) 備付物のうち、設定行為で抵当権の効力が及ばない旨の特約の登記のある物(工場抵当法2条1項ただし書、2項)
(3) 抵当権設定者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、抵当権者もその事情を知りながら備え付けた物(工場抵当法2条1項ただし書、2項。民法424条参照)
(4) 他人の所有物(民法242条ただし書、昭和37.5.10最高判参照)
(5) 工場所有者が抵当権者の同意を得て土地又は建物から分離し、又は備付けをやめた物(工場抵当法6条)
(6) 性質上土地又は建物に備え付けられたと認められない物(例えば、車両、運搬具等)
(目録に記載されていない財産)
6 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定により抵当権の効力が当然に及ぶ物であっても、同法第3条((抵当権の目的物の目録))に規定する目録にその記載がない場合には、これらの物についての抵当権の効力は第三者に対抗することができないから、これらの財産の差押えも第三者に対抗することができない。したがって、この場合には、滞納者に代位して、抵当権者の同意を得て目録記載の変更登記をするか、又はこれらの財産を独立の動産として差し押さえる(同法3条2項、38条、大正9.12.3大判)。
(差押え後の抵当権の設定)
7 土地又は建物を差し押さえた後、その土地又は建物について工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の抵当権が設定された場合には、その抵当権の設定は、差押債権者である国に対抗することができない。
地上権
(意 義)
8 地上権は、工作物(建物等を含む。)又は竹木を所有する目的のため他人の土地を使用する権利をいい(民法265条)、所有すべき目的物のない土地の上にも設定することができ、また、地下又は空間について、その上下の範囲を限って設定することもできる(民法269条ノ2)。 (注) 地上権の処分の効力は、立木法による立木には及ばない(同法2条3項)。
(農地等の上の地上権)
9 農地又は採草放牧地(以下第68条関係において「農地等」という。)の上の地上権の移転については、原則として、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。
永小作権
(意 義)
10 永小作権は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利をいう(民法270条)。
(譲渡禁止の特約がある永小作権)
11 永小作権については、設定行為によって権利の譲渡を禁ずることができ、その特約が登記されている場合には、第三者に対抗することができるが、差押えをすることは妨げられない。
ただし、換価については、永小作権設定者の同意を得て特約の登記を抹消した後てなければ、することができない(民法272条、不動産登記法112条)。
(農地等の上の永小作権)
12 農地等の上の永小作権の移転については、原則として、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。
立木法による立木
13 立木とは、立木法第1条((定義))の規定により登記した樹木の集団をいい、独立した不動産とみなされるから(同法2条1項)、土地と別個に差し押さえなければならないが、なお次のことに留意する。 (1) 明治42年法律第22号第1条第2項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件により、立木法の規定の適用を受ける樹木の集団で、その所有者が同法の規定により所有権の保存の登記をしたものは、土地から独立した不動産となり、1筆の土地又はその一部分の土地の上に生立する集団ごとに、1単位の立木として差し押さえる。
(2) 滞納処分の前提として、滞納者に代位してする立木の保存登記の申請は、受理されない(昭和33.7.2付民事甲第1,328号法務省民事局長心得通達)。この場合においては、(3)により処理する。
(3) 登記をしない樹木の集団及び独立の取引価値がある個々の樹木は、通常の土地の定着物としてその土地の差押えの効力が及ぶのであるが、それらの樹木について立札、縄張等の明認方法を施すことによって、土地から独立した不動産として差し押さえることができる(大正10.4.14大判、昭和46.6.24最高判参照)。
(4) 植栽された樹木の集団は、果実の採取を目的とするものであっても、立木としての保存登記をすることができる(明治42年法律第22号第1条第2項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件1条ただし書、昭和30.6.10付民事甲第1,175号法務省民事局長通達)。
工場財団
(意 義)
14 工場財団とは、工場抵当法により物品の製造等の工場の施設としての土地、建物、機械、器具その他の物的設備のみならず、そのための地上権、賃借権、工業所有権又はダム使用権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法8条、9条、11条)。工場所有者が工場財団登記簿に所有権保存の登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされる(同法14条1項)。
なお、工場抵当法第22条((工場財団目録))の工場財団目録に記載された不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、動産、無体財産権その他の財団組成物件は、個々の物又は権利として差し押さえることができない(同法13条2項、昭和7.12.21法曹会決議)。
(差し押さえた動産が工場財団に組み入れられた場合)
15 差し押さえられた動産は工場財団に属させることができないが(工場抵当法13条1項)、滞納処分により差し押さえた動産について工場財団の所有権保存の登記の申請があったときは、登記官は、登記のない動産については、1月以上3月以内の期間を指定してその間に権利の申出をすべき旨を官報に公告するから(同法24条1項)、徴収職員は、その期間内に、その動産が滞納処分による差押えの対象財産である旨を登記官に申し出なければならない。 (注) 上記の公告期間中にその申出をしないときは、工場財団の所有権保存登記後6月内に抵当権設定の登記がされなかったためにその登記が効力を失う場合を除いて、その差押えは効力を失うことに留意する(同法25条、10条)。
(差し押さえた不動産等が工場財団に組み入れられた場合)
16 不動産、地上権、賃借権、工業所有権、ダム使用権及び登記のある動産について差押えの登記をした後は、これらの物件を工場財団に組み入れることができないが(工場抵当法13条1項)、差押えの登記前にこれらの物件について工場財団の所有権保存の登記の申請があった旨の登記がされた場合において(同法23条)、工場財団について抵当権設定登記があったときは、差押えの登記はその効力を失うから(同法31条、32条)、改めて工場財団として差し押さえるものとする。
(保存登記申請後の差押え)
17 不動産、地上権、賃借権、工業所有権、ダム使用権及び登記のある動産については、工場財団の所有権保存登記の申請があった旨の登記があった後においても、その不動産等を差し押さえてその登記を嘱託すことができるが、所有権保存登記の申請が却下されない間及びその登記が効力を失わない間は換価をすることができず(工場抵当法30条)、また工場財団について抵当権設定登記がされたときは、差押えの登記はその効力を失うから(同法31条)、改めて工場財団として差し押さえるものとする。
なお、工場財団に属する登記のない動産についても、工場抵当法第24条第1項((利害関係人に対する公告))に規定する公告がされた後の差押えについては、上記と同様である(同法33条)。
(保存登記があった後の差押え)
18 工場財団について所有権保存登記があった後は、工場財団としての差押えをすることができるが、その保存登記後6月内に抵当権設定の登記がされないときは、その保存登記は効力を失うから、個々の財団組成物件について新たに差押えをしなければならない(工場抵当法10条参照)。また、抵当権が全部抹消された後若しくは分割により消滅した後6月内は工場財団は消滅しないから、この期間中は、工場財団として差し押さえることができるが、6月内に新たな抵当権の設定の登記がないときは、個々の財団組成物件について、新たに差押えをしなければならない(同法8条3項参照)。
鉱業財団等
(鉱業財団)
19 鉱業財団とは、鉱業抵当法により鉱業権、土地、機械、器具及びその他の物的設備のほか、地上権、賃借権又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法1条、2条、3条)。採掘権者が鉱業財団登記簿に所有権保存の登記をした鉱業財団には、同法第3条((工場財団の規定の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(漁業財団)
20 漁業財団とは、漁業財団抵当法により定置漁業権又は区画漁業権、船舶、漁具及びその他の物的設備のほか地上権、水面の使用に関する権利又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法1条、2条、6条)。定置漁業権者、区画漁業権者又は漁業の用に供する登記した船舶若しくは水産物の養殖場の所有者が、漁業財団登記簿に所有権保存の登記をした漁業財団には、同法第6条((工場財団に関する規定の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(道路交通事業財団)
21 道路交通事業財団とは、道路交通事業抵当法により、自動車、土地、機械、器具及び軽車両等のほか、地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法3条、4条、6条)。道路運送事業者又は通運業者が道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をした道路交通事業財団は、同法第8条((事業財団の性質))の規定により1個の不動産とみなされ、工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用される(同法19条)。
(港湾運送事業財団)
22 港湾運送事業財団とは、港湾運送事業法により、港湾運送事業に関する上屋、荷役機械、はしけ、事務所及び港湾運送事業の経営のため必要な器具等のほか地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法23条、24条、26条)。港湾運送事業者が港湾運送事業財団登記簿に所有権保存の登記をした港湾運送事業財団には、同法第26条((工場抵当法の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(観光施設財団)
23 観光施設財団とは、観光施設財団抵当法により観光施設に属する土地、機械、動物、植物、展示物、船舶、車両及び航空機等のほか、地上権、貸借権、温泉を利用する権利等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法3条、4条、7条)。観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者が、観光施設財団登記簿に所有権保存の登記をした観光施設財団は、同法第8条((財団の性質))の規定により、1個の不動産とみなされ、工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用される(同法11条)。
(鉱業財団等の差押え)
24 鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団及び観光施設財団の差押えについては、15から18までに定めるところによる。
鉱業権
(意 義)
25 鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、取得する試掘権及び採掘権をいい(鉱業法5条、11条)、所轄経済産業局長が設定の許可をし(同法21条)、鉱業原簿に登録することによって成立する(同法59条、60条。この権利は、物権とみなされ、鉱業法に別段の規定がある場合を除き不動産に関する規定が準用される(同法12条、13条)。
なお、鉱業法には鉱業権とともに租鉱権についての規定がある。租鉱権とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、自己の所有物とする権利をいい(鉱業法6条)、相続その他の一般承継の目的となるほか、権利の目的となることができないから、差し押さえることができない(同法72条)。
(試掘権及び採掘権)
26 試掘権とは、一定の鉱区において主として鉱物の探鉱を内容とする鉱業権をいい、採掘権とは、一定の鉱区において主として鉱物を掘採し、自己の所有物とすることを内容とする鉱業権をいう。
特定鉱業権
27 特定鉱業権とは、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定第2条第1項に規定する大陸棚の区域(共同開発区域)内の登録を受けた一定の区域において天然資源の探査又は採掘をし及び掘採された天然質源を取得する権利をいい、(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措法(以下「大陸棚特別措置法」という。)2条3項)、経済産業大臣がその設定の許可をし(同法12条)、特定鉱業原簿に登録することによって効力を生ずる(同法32条3項)。
特定鉱業権には、探査権と採掘権とがあり(大陸棚特別措置法4条)、特定鉱業権は物権とみなされ、大陸棚特別措置法に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定が準用される(同法6条)。
漁業権
(意 義)
28 漁業権とは、定置漁業権(定置漁業を営む権利)、区画漁業権(区画漁業を営む権利)及び共同漁業権(共同漁業を営む権利)をいい(漁業法6条)、物権とみなされ、土地に関する規定が準用される(同法23条1項)。
(漁業権の移転等)
29 定置漁業権及び区画漁業権について移転ができるのは、次の場合であるが、(2)から(4)までの場合には、買受人は、都道府県知事の認可を受けなければならない(漁業法26条1項)。
なお、共同漁業権は、相続又は法人の合併による場合を除き、移転の目的となることができず(漁業法26条1項本文)、滞納処分はできないものとする(同法6条参照)。 (1) 相続又は法人の合併による場合
(2) 滞納処分による場合
(3) 先取特権者又は抵当権者がその権利を実行する場合
(4) 漁業法第28条第2項((漁業権を取り消す旨の通知))の通知を受けた者が譲渡する場合
入漁権
(意 義)
30 入漁権とは、設定行為に基づいて、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、そう類養殖業、真珠母貝養殖業、小割り式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行う水産動物の養殖業をいう。)、かき養殖業若しくは第三種区画漁業権である貝類養殖業を内容とする区画漁業権に属する漁場において、その漁業権の内容である漁業の全部又は一部を営む権利をいい(漁業法7条)、物権とみなされる(同法43条1項)。
(取得及び譲渡の制限)
31 入漁権は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は取得することができず(漁業法42条の2)、漁業権者の同意がなければ譲渡することができない(同法43条3項)。
なお、入漁権を差し押さえたときは、漁業権者に対しても、差押えの通知をするものとする。
採石権
32 採石権とは、設定行為に基づき、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利をいい(採石法4条1項)、採石法によって認められる物権であり、地上権に関する規定が準用される(同法4条3項)。
ダム使用権
(意 義)
33 ダム使用権とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいい(特定多目的ダム法2条2項)、ダム使用権又はダム使用権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限は、ダム使用権登録簿に登録することによって成立する(同法26条)。この権利は、物権とみなされ、特定多目的ダム法に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定が準用される(同法20条)。
(処分の制限)
34 ダム使用権は、国土交通大臣の許可を受けなければ、移転(相続、法人の合併その他の一般承継によるものを除く。)の目的とし、分割し、合併し、又はその設定の目的を変更することができない(特定多目的ダム法22条)。
鉄道財団等
(鉄道財団)
35 鉄道財団は、鉄道抵当法によって抵当権の設定を認められる財団で、地方鉄道の全部又は一部について設定され、鉄道事業経営に関する物的設備と地上権、地役権、登記した賃借権をその内容とし、1個の物とみなされる(同法2条、2条ノ2,3条、4条、13条ノ4参照)。 (注) 鉄道財団についての滞納処分に関しては、鉄道抵当法第65条本文((競落代金の支払))、第66条((競落による権利の移転))、第67条第1項及び第2項((競落を許す決定の取消し))、第68条((競落代金の配当、競売申立ての登録の抹消))、第70条((財団の分割競売))、第71条第1項((分割競売の手続))、第73条((競落人の許可申請))、第74条((競落人が会社の発起人であるときの許可申請手続))、第76条((監督官庁の許可義務))並びに第77条((競落人の許可の効力))の規定が準用される(同法77条ノ2)。
(軌道財団)
36 軌道財団は、軌道ノ抵当ニ関スル法律によって抵当権の設定を認められる財団であり、別段の規定がある場合を除いて鉄道抵当法が準用され(同法1条)、財団の組成物件も鉄道財団とおおむね同様である(同法2条参照)。
(運河財団)
37 運河財団は、運河法によって抵当権の設定を認められる財団で、運河事業に関する物的設備と地上権、地役権、登記した賃借権をその内容とし、1個の物とみなされる(同法14条、13条)。
(鉄道財団等の差押え)
38 鉄道財団、軌道財団及び運河財団の差押えについては、15から18までに定めるところに準ずる。
不動産の共有持分
39 不動産の共有持分とは、共有者がその不動産に対して有する量的に制限された所有権をいい、特約がなければ各共有者の持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
差押手続
(差押書)
40 法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法68条2項)。
(差押調書)
41 法第68条第1項の不動産を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
42 不動産を差し押さえたときは、税務署長は、差押えの登記を関係機関(44参照)に嘱託しなければならない(法68条3項)。
なお、差押えの登記の嘱託等については、次のことに留意する。 (1) 登記原因を証する書面は差押調書の正本又は謄本であり、登記権利者は財務省、登記を嘱託することができる者は国税局長、税務署長又は税関長である(不動産登記法35条3項、財務省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令)。
(2) 不動産登記法第26条第1項((当事者の出頭))の規定にかかわらず、差押登記嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、管轄登記所に提出することができる(同法25条2項、通則法12条1項)。
(3) 差押登記嘱託書には、工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録又は工場財団の目録の添付を要しない。
(4) 工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録に、他人の物件が記載されている場合には、その物件を除外して差押えの登記を嘱託して差し支えない(昭和31.6.14付民事甲第1,273号法務省民事局長通達参照)。
(5) 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産の差押えの登記を嘱託する場合には、同一の嘱託書をもって差押えの登記を嘱託することができる(不動産登記法25条2項、46条)。
(6) 表示登記又は所有権の保存登記がされていない不動産について、差押えの登記を嘱託した場合には、登記官は、職権で、表示登記がないときは表示登記及び保存登記を、保存登記がないときは保存登記をそれぞれ行った上、差押えの登記をする(不動産登記法104条、102条)。
(7) 土地区画整理法第103条第4項((換地処分の公告))の規定により国土交通大臣又は都道府県知事による換地処分の公告があった後においては、同法第107条第3項本文((換地処分の公告後の登記の制限))の規定により、同条第2項((事業の施行による変動に係る登記等))に規定する土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでの期間は、差押えの登記の嘱託をすることができない。 (注) 換地処分の公告の日前に差押えの登記原因が生じているときは、上記の期間中であっても、差押えの登記の嘱託をすることができる(土地区画整理法107条3項ただし書)。
(未登記不動産と民法第177条)
43 未登記不動産についても民法第177条((不動産物権の対抗要件))の適用があり、その取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に所有権を取得して登記を経た第三者に対し、自己の所有権の取得を主張することができない(昭和57.2.18最高判)。
(関係機関)
44 法第68条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
(登録免許税の非課税)
45 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
46 法第68条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが(法68条2項)、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合には、その登記がされた時に差押えの効力が生ずる(法68条4項)。
なお、鉱業権又は特定鉱業権の差押えの効力は、上記にかかわらず、差押えの登録がされた時に生ずる(法68条5項、鉱業法60条、大陸棚特別措置法32条、同法施行令5条)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
各別の所有者に属する工場を含む工場財団の差押え
47 各別の所有者に属する工場について1個の工場財団が設定されている場合には、その所有者のうちの1人に対する滞納処分として、その財団全体を差し押さえることはできないから、次によるものとする(工場抵当法8条1項参照)。 (1) 抵当権者に対し、滞納者の所有に属する工場財団の分割と、分割された工場財団についての抵当権の消滅の承諾を得、その承諾を証する書面を添付して、他の工場所有者と共同して分割の登記を求め、その登記を了したときに、その滞納者に属する分割された工場財団を差し押さえる(工場抵当法42条ノ2,42条ノ4,42条ノ5)。
(2) 抵当権者から(1)の承諾が得られないときは、滞納者の有する財団持分を差し押さえる。この場合における持分とは、土地、建物等の共有持分とは異なり、その滞納者の所有に係る工場等をいうものであるから、差押えに当たっては、財団持分の差押えである旨及びその内容であるその工場等の表示を明らかに記載するものとする。
第69条関係 差押不動産の使用収益
使用又は収益の制限
(価値が著しく減耗する行為)
1 法第69条第1項の「価値が著しく減耗する行為」とは、通常の用法に従っているが、差し押さえられた不動産の価値を著しく減耗する行為をいう。この減耗は、物理的な減耗に限られることなく、法律的に減耗するもの、例えば、差し押さえた更地の上に建物を新築する行為も含まれる(昭和41.12.24新潟地長岡支決参照)。
(使用収益の制限)
2 法第69条第1項の「使用又は収益を制限する」方法は、かぎをかけ、立入禁止を宣言する等の事実行為又は命令行為によるものとする。
第70条関係 船舶又は航空機の差押え
船舶又は航空機
(登記される船舶)
1 法第70条第1項の「登記される船舶」とは、船舶登記簿に登記することができる船舶(以下「船舶」という。)をいい(商法686条、船舶法5条1項参照)、その差押えについては、次のことに留意する。 (1) 第56条関係4の(1)から(4)までに掲げる船舶は、登記することができないから、法第70条の船舶に該当せず、動産として差し押さえる。
(2) 建造中の船舶で、船舶として航行の用に供することができる程度に完成していないものは、抵当権の登記がされている場合であっても、船舶としての差押え及びその登記をすることはできないから、動産として差し押さえる(商法851条、848条、船舶登記規則32条参照)。
(3) 製造中の船舶を動産として差し押さえた後に、航行することができる程度に完成した場合には、改めて法第70条の規定による船舶としての差押手続をとる。
(登録を受けた航空機)
2 法第70条第1項の「登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機又は回転翼航空機であって、航空法第3条((登録))の規定により国土交通大臣の管掌する航空機登録原簿に登録を受けたもの(以下「航空機」という。)をいう。
差押手続
(差押書)
3 法第70条第1項において準用する法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法70条1項、68条2項)。 (注) 発航の準備が終了した船舶は、商法第689条((船舶の差押え及び仮差押えの執行の制限))の規定により、差押え又は仮差押え(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)をすることができないが、この規定は、滞納処分による差押えには適用されないことに留意する。
(差押調書)
4 法第70条第1項の船舶又は航空機を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
5 税務署長は、船舶を差し押さえたときは船籍港を管轄する法務局、地方法務局又はその支局若しくは出張所に、航空機を差し押さえたときは国土交通省航空局に、それぞれ差押えの登記を嘱託しなければならない(法70条1項、68条3項、船舶登記規則2条、航空機登録規則3条)。 (注) 不動産登記法第26条1項((当事者の出頭))又は航空機登録令第9条((登録の申請))の規定にかかわらず、差押登記嘱託書又は差押登録嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、管轄登記所又は国土交通省航空局に提出することができる(法70条1項、68条3項、船舶登記規則1条、不動産登記法25条2項、通則法12条1項)。
(監守保存処分との関係)
6 法第70条第3項の「監守及び保存のため必要な処分」(14から16まで参照)をしたことにより差押えの効力が生じた場合においては、遅滞なく3から5までに掲げる手続をとらなければならない。
(登録免許税の非課税)
7 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
(効力発生の時期)
8 法第70条第1号の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合にはその差押えの登記がされた時に、差押書の送達前に監守及び保存のため必要な処分をした場合にはその処分をした時に、それぞれ差押えの効力が生ずる(法70条1項、4項、68条2項、4項)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
(船舶の属具)
9 船舶の属具目録に記載されたものは、船舶の従物と推定されるから(商法685条)、原則として、船舶に対する差押えの効力が属具に及ぶ。
停 泊
(意 義)
10 法第70条第2項の「停泊」とは、船舶又は航空機が、その所在する場所に停止又は停留することをいう。
(滞納処分のため必要があるとき)
11 法第70条第2項の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、航行による損壊、き減の防止、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(発航の準備)
12 法第70条第2項の「発航の準備が終った」かどうかの判定は、船舶航行の計画又は契約の成立によって行わず、専ら貨客の運送に必要であり、かつ、客観的には相当な整備がされたかどうか(例えば、船員及び船客の乗組み、貨物、燃料、食料及び飲料の積込み、出港及び渡航手続が完了したかどうか)等によって行うものとする。
なお、航空機の発航の準備が終わったかどうかの判定については、上記に準ずるものとする。
監守保存の処分
(滞納処分のため必要があるとき)
13 法第70条第3項の「滞納処分のため必要があるとき」とは、11と同様である。
(監 守)
14 法第70条第3項の「監守」とは、主として、所在を変えることを防止するための処置をいう。
(保 存)
15 法第70条第3項の「保存」とは、主として、目的物の効用を維持するための処置をいう。
(必要な処分)
16 法第70条第3項の「必要な処分」には、縄張をすること、係留すること、格納庫へ入庫させること、管理人を置くこと、船舶国籍証書又は航空機登録証明書その他船舶又は航空機の航行のために必要な文書(船舶法5条、6条、船員法18条、航空法59条等参照)を取り上げること等があり、これらの処分は、監守又は保存のいずれか一つのために必要なものであれば、することができる。
なお、船航国籍証書等の取上げについては、債権証書に準じて取り扱うものとする(第65条関係参照)。
航行の許可
(営業上の必要その他相当の理由があるとき)
17 法第70条第5項の「営業上の必要その他相当の理由があるとき」とは、航行を許可することにより営業上の利益が見込まれ、徴収上有利な結果をもたらすときをいい、例えば、現に行っている運送契約に債務不履行が生ずることを避け、航行による収益を滞納者に得させる必要があるとき等をいう。
(申立て)
18 法第70条第5項の規定による航行の許可の申立ては、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が、令第31条各号((船舶等の航行許可申立書の記載事項))に掲げる事項を記載して連署した書面でしなければならない。この場合の連署については、上記の一部の利害関係人の連署がとれないとき等には、その同意書又は承諾書を添付して行わせることとしても差し支えない。
(許 可)
19 法第70条第5項の航行の許可の申立てがあった場合には、徴収上支障のない限り、航行を許可して差し支えない。この許可は、原則として別に定める書面により行うものとする。
共有持分の差押え
20 法第70条の規定の適用を受ける船舶又は航空機の共有持分を差し押さえたときは、その共有持分の差押えの登記を5の関係機関に嘱託しなければならない(法70条1項、68条3項)。(注)船舶共有者間に組合関係がある場合には、船舶管理人の有する共有持分は、他の共有者の同意を得なければ譲渡することができない(商法698条ただし書)。
第71条関係 自動車又は建設機械の差押え
自動車又は建設機械
(登録を受けた自動車)
1 法第71条第1項の「登録を受けた自動車」とは、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車で、道路運送車両法第2章((自動車の登録))の規定により、運輸大臣が管理する自動車登録ファイルに登録を受けたもの(自動車抵当法2条ただし書に規定する大型特殊自動車で、建設機械抵当法2条に規定する建設機械であるものを除く(道路運送車両法5条2項)。以下「自動車」という。)をいう。
(登記を受けた建設機械)
2 法第71条第1項の「登記を受けた建設機械」とは、建設業法第2条第1項((建設工事の定義))に規定する建設工事の川に供される機械類で建設機械抵当法施行令第1条((建設機械の範囲))の規定による別表に掲げるもの(例えば、ブルドーザー、トラクター、コンクリートミキサー等)のうち、建設業者(建設業法2条3項)が国土交通大臣又は都道府県知事の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けた後、建設機械登記簿に保存登記をしたもの(以下「建設機械」という。)をいう(建設機械抵当法2条、4条1項。建設機械登記令5条、建設機械抵当法施行令9条1項参照)。
差押手続
(差押書)
3 法第71条第1項において準用する法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式をいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法71条1項、68条2項)。
(差押調書)
4 法第71条第1項の自動車又は建設機械を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
5 税務署長は、自動車を差し押さえたときはその自動車の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事(運輸局陸運支局)に、建設機械を差し押さえたときはその機械の打刻された記号によって表示された都道府県の区域内にある法務局又は地方法務局(北海道にあっては、札幌法務局)に、それぞれ差押えの登記を嘱託しなければならない(法71条1項、68条3項。逆路運送車両法施行令8条2項、建設機械登記令1条参照)。 (注) 自動車登録令第10条((共同申請))又は不動産登記法第26条第1項((当事者の出頭))の規定にかかわらず、差押登録嘱託書又は差押登記嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、都道府県知事(運輸局陸運支局)又は管轄登記所に提出することができる(法71条1項、68条3項、自動車登録令9条、不動産登記法25条2項、通則法12条1項)。
(登録免許税の非課税)
6 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
(効力発生の時期)
7 法第71条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合にはその差押えの登記がされた時に、差押書の送達前に監守及び保存のため必要な処分をした場合にはその処分をした時に、それぞれ差押えの効力が生ずる(法71条1項、2項、68条2項、4項、70条4項)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
(差押えの効力が及ぶ範囲)
8 抵当権の目的となっている自動車又は建設機械の差押えの効力は、その自動車又は建設機械に付加して一体となっている物に及ぶが、これらの物のうち、抵当権設定行為で抵当権の効力が及ばない旨の特約の登記をしたもの及び自動車又は建設機械の所有者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、抵当権者もその事情を知りながら付加したものには、差押えの効力は及ばない(自動車抵当法6条、建設機械抵当法10条)。
(差押え後に保存登記がされた建設機械)
9 所有権保存登記のない建設機械を動産として差し押さえた後にその建設機械について所有権保存の登記があっても、その登記は差押債権者である国に対しては効力を生じないから、新たに差押えの登記を嘱託する必要がないことはもちろん、登記簿上その建設機械について権利を取得した第三者も、その権利をもって差押債権者である国に対抗することができない(建設機械抵当法3条2項)。
(差押え後に抵当権設定の登記がされない建設機械)
10 建設機械の所有権保存登記後30日以内に抵当権設定の登記がされない場合又は抵当権の登記が全部抹消された後30日以内に新たな抵当権設定の登記がされない場合には、その建設機械の登記用紙は閉鎖されるが、その期間内に差押えの登記をした場合には、その登記用紙は閉鎖されないから、法第71条の規定により建設機械としてした差押えの効力は妨げられない(建設機械抵当法8条)。
自動車検査証の占有
11 換価による所有権の移転登録には、自動車検査証の呈示を必要とし(道路運送車両法13条3項、12条2項)、かつ、自動車検査証を備えなければ自動車を運行の用に供することができないから(同法66条1項)、自動車の差押えに当たっては、自動車検査証を動産の差押手続に準じて占有するものとする。
監守保存の処分
12 自動車及び建設機械の監守保存のため必要な処分については、第70条関係13から16までに準ずる。
徴収職員の占有
(引渡命令)
13 自動車又は建設機械を差し押さえた場合には、税務署長は、滞納者に対してその引渡しを命じ、徴収職員にそれを占有させることができる(法71条3項)。この場合には、徴収職員は、次に掲げるところにより占有するものとする。
なお、滞納者が引渡命令に応じないときは、法第142条((捜索の権限及び方法))の規定により、捜索その他の処分を行うことができる。 (1) 滞納者が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を滞納者が占有している場合には、税務署長は、滞納者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員にその引渡しがされたとき及びその引渡しをしないときは、徴収職員は直ちにその占有ができる(法71条4項、56条1項)。
(2) 特殊関係者等が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を滞納者の親族その他の特殊関係者(第38条関係1から8まで参照)が占有している場合には、税務署長は、滞納者及びその第三者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員は(1)に準じて直ちにその占有ができる(法71条4項、56条1項)。
(3) 第三者が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を第三者((2)の第三者を除く。)が占有している場合には、税務署長は、滞納者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員にその引渡しがされたときは直ちに占有するが、その引渡しをしないときで占有する第三者もその引渡しを拒むときは、その第三者に対し引渡しを命じ、その引渡しがされたとき及びその第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡しをしないときは、直ちにその占有力ができる(法71条4項、58条2項、3項)。この場合には、次のことに留意する。 イ 法第58条第2項((第三者が占有する動産等の差押手続))の規定のうち「滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り」の事項は、占有のための引渡命令についての要件に当たらないものである。
ロ 法第59条第2項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))に規定する「その期限が、その動産を差し押さえた日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで」は、「その期限がその自動車又は建設機械を占有した日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで」として準用する。
ハ 法第59条第3項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))に規定する「同条第3項の規定による差押の日後の期間に係るもの」は、「法第71条第4項において準用する第58条第3項の規定による占有の日後の期間に係るもの」として準用する。
(保 管)
14 法第71条第5項前段の規定により、自動車又は建設機械を滞納者又は第三者に保管させる場合には、第60条関係8,9及び12に定めるところに準ずる。
(封印その他の公示方法)
15 法第71条第5項後段の「封印その他の公示方法」は、第60条関係13から15までと同様であり(令32条、26条)、また、これらの公示方法は差押えの効力発生要件ではない。
(適当な措置)
16 法第71条第5項後段の「適当な措置」とは、運行又は使用を禁ずるための措置、例えば、ハンドルの封印、立札、縄張等の方法による措置をいう。
(運行又は使用の許可)
17 法第71条第6項の規定による自動車又は建設機械の運行又は使用の許可については、第70条関係17から19までと同様である(令32条、31条)。
共有持分の差押え
18 法第71条の規定の適用を受ける自動車又は建設機械の共有持分を差し押さえたときは、その共有持分の差押えの登記を5の関係機関に嘱託する。
なお、上記の場合には、徴収職員は目的物を占有することができないものとする(民法249条参照)。
第5款 無体財産権等の差押え
第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がない無体財産権等
1 法第72条第1項の規定により差し押さえる財産は、特許権及び著作権のほか法第5章第1節第2款((動産又は有価証券の差押))、第3款((債権の差押))及び第4款((不動産等の差押))の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち、第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)がない財産であり、おおむね次の財産がこれに該当する。 (1) 工業所有権である実用新案権、意匠権及び商標権
(2) 工業所有権以外の無体財産権である著作隣接権
(3) 源泉権
特許権
(意 義)
2 特許権とは、物の特許発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利を、方法の特許発明にあっては、その方法を使用する独占的排他的な権利を、物を生産する方法の特許発明にあっては、上記に該当するもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利を、それぞれいい(特許法2条。68条参照)、特許庁長官の管掌する特許原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法66条1項)。
(存続期間)
3 特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年を超えることができない(特許法67条1項)。
実用新案権
(意 義)
4 実用新案権とは、実用新案登録を受けている考案(自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。)に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利をいい(実用新案法2条。16条参照)、特許庁長官の管掌する実用新案原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法14条1項)。
(存続期間)
5 実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年をもって終了する。ただし、実用新案登録出願の日から15年を超えることができない(実用新案法15条1項)。
意匠権
(意 義)
6 意匠権とは、意匠登録を受けている意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。)に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利をいい(意匠法2条。23条参照)、特許庁長官の管掌する意匠原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法20条1項)。
(存続期間)
7 意匠権の存続期間は、設定の登録の日から15年をもって終了する(意匠法21条)。
商標権
(意 義)
8 商標権とは、指定商品について商標登録を受けている商標(文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下8において「標章」という。)であって、業として商品を生産し、加工し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものをいう。)を使用(商品又は商品の包装に標章を付する行為、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為及び商品に関する公告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為をいう。)する独占的排他的な権利をいい(商標法2条。25条参照)、特許庁長官の管掌する商標原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法18条1項)。
(存続期間)
9 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する(商標法19条1項)。
著作権
(意 義)
10 著作権とは、著作者がその著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。)についての複製権、上演権、演奏権、放送権、有線放送権、口述権、展示権、上映権、頒布権、翻訳権、翻案権及び第二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を専有する独占的排他的な権利をいい(著作権法2条、17条1項。21条から28条まで参照)、著作者の著作により当然に発生し、登録を要しない。著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下10において同じ。)又は処分の制限及び著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、文化庁長官が管掌する著作権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法77条、78条1項)。
(存続期間)
11 著作権の存続期間は、おおむね次のとおりである。 (1) 著作権は、著作者が著作物を創作した時に始まり、(2)から(5)までに掲げる場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。(2)において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条)。
(2) 無名又は変名の著作物の著作権は、原則として、その著作物の公表後50年(著作者の死後50年を経過していると認められるときは、死後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法52条)。
(3) 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、原則として、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条)。
(4) 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法54条1項)。
(5) 写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法55条1項)。 (注)1 (2)から(5)までにおける公表の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとされ、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、原則として、最終部分の公表の時によるものとされる(著作権法56条)。
2 (1)から(5)までにおいて、著作者の死後50年又は著作物の公表後50年若しくは創作後50年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算される(著作権法57条)。
(未発表の著作権)
12 まだ発行、興行等公にしていない著作物の原本及びその著作権は、差し押さえることができない(法75条1項11号)。
著作隣接権
(意 義)
13 著作隣接権とは、実演家、レコード製作者及び放送事業者に与えられた著作権に準ずる権利をいう(著作権法91条から100条まで)。著作隣接権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下13において同じ。)又は処分の制限及び著作隣接権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作隣接権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、文化庁長官が管掌する著作隣接権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法104条、77条、78条1項)。
(存続期間) 編注21
14 著作隣接権は、実演及び放送についてはその行われた日の属する年の翌年から起算して20年、レコードについてはその音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過するまでの間、存続する(著作権法101条)。
共有特許権等
15 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権の共有持分の譲渡については、他の共有者の同意を必要とする(特許法73条1項、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条、著作権法65条、103条)。
源泉権
16 源泉権(温泉所有権、温泉専用権、湯口権、温泉権又は鉱泉権ともいう。)とは、地中からゆう出する温泉を利用、管理、処分する権利で、源泉地所有権とは別個独立の権利として自由に処分できるものをいう(昭和15.9.18大判、昭和33.7.1最高判)。
源泉権者は、源泉権の効力として、温泉所在地及びその周辺土地のうち温泉の採取、利用、管理のために必要とする範囲において、その使用権限を有する(昭和45.12.19東京地判)。
差押手続
(差押書)
17 法第72条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法72条2項)。
(差押調書)
18 法第72条第1項の財産を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登録の嘱託)
19 法第72条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
なお、源泉権にあっては、その地方の慣行に従った公示方法(例えば、温泉組合等に対する登録の依頼、立札その他の標識の掲示)を講ずるものとする(昭和15.9.18大判、昭和45.12.19東京地判参照)。
(登録免許税の非課税)
20 税務署長が差押えの登録を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
21 法第72条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが(法72条2項)、その前に差押えの登録がされた場合には、その差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法72条4項)。ただし、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については、差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法72条5項。特許法98条1項、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条参照)。 (注) 差押えの登録がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がある無体財産権等
1 法第73条第1項の規定により差し押さえる財産は、電話加入権、合名会社の社員の持分のほか第三債務者等がある無体財産権等であり、おおむね次の財産がこれに該当する。 (1) 合資会社及び有限会社の社員の持分
(2) 中小企業等協同組合法、水産業協同組合法、農業協同組合法、森林組合法、農住組合法等による各種の組合等の組合員等の持分
(3) 信用金庫の会員の持分
(4) 中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の会員の持分
(5) 民法上の組合の組合員の持分
(6) 無尽講又はたのもし講の講員の持口
(7) 営業無尽の加入者の権利
(8) 動産の共有持分
(9) 賃借権
(10) 買戻権
(11) 仮登記(保全仮登記を除く。以下73条関係において同じ。)に係る権利
(12) 特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権及び通常実施権並びに商標権についての専用使用権及び通常使用権
(13) 出版権
(14) 引湯権
(15) ゴルフ会員権(預託金会員制ゴルフ会員権をいう。以下第73条関係において同じ。)
電話加入権
(意 義)
2 電話加入権とは、日本電信電話公社(以下第73条関係において「公社」という。)と加入契約を結んだ者が、その契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう(公衆電気通信法31条3号かつこ書)。
なお、電話加入権の譲渡は、公社の承認がなければその効力を生じない(公衆電気通信法38条1項)。
(差押えと譲渡等との優劣)
3 電話加入権に対する差押えとその譲渡等との優劣の関係は、次のとおりである(公衆電気通信法38条の3第3項、電話加入権質に関する臨時特例法6条2項)。 (1) 電話加入権の譲渡の承認があったときは、その譲渡承認の請求書を所轄の電話取扱局が受け取った時と、当該電話取扱局が電話加入権の差押通知書を受け取った時との先後により、その優劣が定まる。
(2) 電話加入権の質権の登録があったときは、その質権の登録請求書を所轄の電話取扱局が受け取った時と、当該電話取扱局が電話加入権の差押通知書を受け取った時との先後により、その優劣が定まる。
(差押え後の譲渡禁止)
4 公社は、電話加入権の差押えの通知を受けた後は、その電話加入権の譲渡承認の請求があっても、承認しないことになっている。
(差押え後の契約解除)
5 公社は、差押えを受けた電話加入権についても、公衆電気通信法第42条(通話の停止及び加入電話加入契約の解除)の規定により、加入契約を解除することができる。
(地域団体加入電話等の差押除外)
6 地域団体加入電話に関する権利及びその組合員の持分は、差押えをしない取扱いとする(加入電話等利用規程69条参照)。 (注) 地域団体加入電話とは、一定の地域内に居住する者が公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的として組合を設立し、その組合と公社との契約によって設置する電話である(公衆電気通信法25条2号、43条の2から43条の4まで参照)。
合名会社及び合資会社の社員の持分
(意 義)
7 合名会社及び合資会社の社員の持分とは、社員がその資格において会社に対して有する権利義務の総体、すなわち、社員権をいう。
なお、社員の持分は、無限責任社員の同意がなければ、譲渡することができない(商法73条、147条、154条)。
(利益配当請求権等に対する差押えの効力)
8 社員の持分の差押えの効力は、社員の会社に対する将来の利益配当請求権及び持分払戻請求権に及ぶ(商法90条、147条)ほか、残余財産分配請求権にも及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとる必要はなく、会社に対して、決算確定の場合には利益の配当を、退社の場合には持分の払戻しを、会社の解散の場合には残余財産の分配を、それぞれ請求することができる(56参照)。
(退社の告知権)
9 社員の持分を差し押さえた場合には、商法第91条(持分差押債権者による退社)及び第147条(合名会社の規定の準用)の規定により、営業年度の終了する6月前に会社及びその社員に予告した上、営業年度の終わりにおいてその社員を退社させることができる。この場合においては、営業年度の終わりにおいて当然に退社の効力を生ずる。
なお、上記の予告は、社員が相当の担保を提供したときは、その効力を失う(商法91条2項、147条)。この場合には、担保として提供された社員の財産を差し押さえるものとする。
(持分払戻請求権の保全)
10 9の告知権を行使したときは、会社の本店所在地の地方裁判所に対して、持分払戻請求権の保全に関し必要な処分をすることを請求できる(非訟事件手続法135条ノ10)。
(差押え後の任意清算)
11 社員の持分の差押えの通知を受けた合名会社又は合資会社が任意清算しようとするときは、会社財産の処分方法について差押債権者である国の同意を要する(商法117条4項、147条)。会社が同意を受けないで財産を処分したときは、会社に対してその持分に相当する金額の支払を請求し、又はその処分の取消しを裁判所に請求することができる(同法118条、119条、147条)。
有限会社の社員の持分
(意 義)
12 有限会社の社員の持分とは、社員がその資格において会社に対して有する権利義務の総体、すなわち、社員権をいい、各社員はその出資の口数に応じて持分を有する(有限会社法18条)。
なお、社員の持分の移転は、社員名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない(有限会社法20条)。
(残余財産分配請求権の取立て)
13 有限会社の社員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権にも及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
(持分払戻請求権のないこと)
14 有限会社の社員は、株式会社の株主と同様、持分の払戻しを請求することができない。
(利益配当請求権の差押え)
15 有限会社の社員の持分を差し押さえた場合において、利益の配当を受けようとするときは、その利益配当請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
(利益配当請求権等と持分の質入れとの関係)
16 社員の持分が質入れされ、社員名簿に質入れの記載がされている場合には、利益配当請求権及び残余財産分配請求についても、その質権の効力が及ぶ(有限会社法24条1項、商法209条1項)。
協同組合等の組合員等の持分
(意 義)
17 中小企業等協同組合法による組合等1の(2)に掲げるものの組合員等の持分とは、組合員等がその資格において組合等に対して有する権利義務の総体をいう。
なお、組合員等の持分は、組合等の承諾がなければ譲渡することができず、また組合員等以外の者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない(中小企業等協同組合法17条、水産業協同組合法20条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法14条、森林組合法30条、農住組合法17条等)。
(持分の一部払戻請求)
18 組合員等の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の払戻しを請求できるときがある。
(残余財産分配請求権等の取立て)
19 組合員等の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法74条の規定による一部の払戻しのほか、法定脱退による払戻しを含む。)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。
(剰余金配当請求権の差押え)
20 組合員等の持分を差し押さえた場合において、剰余金の配当を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
信用金庫の会員の持分
(意 義)
21 信用金庫の会員の持分とは、会員がその地位に基づいて信用金庫に対して有する権利義務の総体をいう。.
なお、会員の持分は、信用金庫の承諾がなければ、他の会員又は会員の資格を有する者にも譲渡することができない(信用金庫法15条)。
(持分の一部の譲受請求)
22 会員の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の譲受けを請求できるときがある(第74条関係7参照)。
(残余財産分配請求権等の取立て)
23 会員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法定脱退によるもの)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
(剰余金配当請求権の差押え)
24 会員の持分を差し押さえた場合において、剰余金の配当を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
漁業信用基金協会の会員の持分
(意 義)
25 漁業信用基金協会の会員の持分とは、会員がその地位に基づいて漁業信用基金協会に対して有する権利義務の総体をいう。
なお、会員の持分は、漁業信用基金協会の承認を得なければ譲渡することができず、会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない(中小漁業融資保証法12条1項、2項)。
(持分の一部の払戻請求)
26 会員の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の払戻しを請求できるときがある。
(残余財産分配請求権等の取立て)
27 会員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法74条の規定による一部の払戻しのほか、法定脱退による払戻しを含む。)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。
なお、漁業信用基金協会が剰余金を配当することはない(中小漁業融資保証法44条)。
民法による組合の組合員の持分
(意 義)
28 民法第667条(組合契約)の規定に基づいて設立された組合の組合員の持分とは、組合員として有する財産的地位をいう。
なお、組合員の持分の譲渡については、他の組合員全員の同意を必要とされているが(民法667条参照)、契約によって特別の定めがされているときは、その定めに従う。 (注) 組合員としての地位に基づいて組合財産を構成する個々の物又は権利について有する共有の権利をも持分というが、この持分の処分は、組合及び組合と取引をした第三者に対抗できないから(民法676条)、この持分を差し押さえることはできない。
(残余財産分配請求権等の取立て)
29 組合員等の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。 (注) 組合員の持分を換価処分によって換価することができない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、脱退の意思表示をさせた後、持分払戻請求権の取立てをすることに留意する。
(利益分配請求権の差押え)
30 組合員の持分を差し押さえた場合において、利益の分配を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
無尽講又はたのもし講の講員の持口
(意 義)
31 無尽講又はたのもし講は、慣習によって成立したものであるが、実質的には組合であるから、民法の組合に関する規定の適用があり、講員(加入者)は、その拠出した金銭又は物の価額に応じて持口を有する。
なお、講員の持口は、講規約に特約がないときは、他の講員全員の同意がなければ、譲渡することができない。 (注) 講員の持口は、未給付口については積極財産であって差し押さえることができるが、給付口については消極財産であって差押えの対象とならない。
(給付請求権等の取立て)
32 講員の持口の差押えの効力は、当せん、落札等の給付原因によって生じた給付金請求権及び脱退によって生じた払戻請求権に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
なお、上記の取立てについては、次のことに留意する。 (1) 講員の持口を換価処分により換価できない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、脱退の意思表示をさせた後、払戻請求権の取立てをするように取り扱うものとする(民法678条2項参照)。
(2) 講規約によって、担保を供しなければ給付を行わないこと、脱退者に対する払戻しは満講までは行わないこと等を定めているときは、これらの要件を満たさなければ、給付又は払戻しを受けることができない。
営業無尽の加入者の権利
(意 義)
33 営業無尽の加入者の権利とは、加入者が無尽契約、相互掛金契約又は物品無尽契約に基づき、相互銀行又は無尽会社に対して有する権利義務の総体(例えば、掛金払込義務、給付受領権利等)をいう。
なお、加入者の権利の譲渡について会社の承認を要する旨の契約があるときは、会社の承認がなければ、権利を譲渡することができない。 (注) 営業無尽の加入者の権利の給付口及び未給付口については31と同様であるが、無尽講と異なり、加入者相互間には法律関係を生じない。
(給付金請求権等の取立て)
34 給付金請求権又は払戻請求権の取立てについては、32に定めるところと同様である。
動産の共有持分
(意 義)
35 共有動産の持分とは、共有者がその動産に対して有する量的に制限された所有権をいい、特約がなければ各共有者の持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
なお、共有持分は、他の共有者の同意を得ないで、自由に譲渡することができる。
(差押えと目的物の占有との関係)
36 共有動産の持分を差し押さえた場合でも、徴収職員が目的物を占有することはしないものとする(民法249条参照)。
(持分の分割の請求)
37 共有動産の持分の換価ができないときは、次の方法によるものとする。 (1) 分割禁止の特約がない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、滞納者に代位して(通則法42条、民法423条)、他の共有者の全員に対して共有物の分割を請求し(民法256条1項本文)、滞納者の分割物の引渡請求権の取立て(56参照)を行う。
(2) (1)により分割の請求をした場合において、分割の協議が調わないときは、滞納者に代位して、訴えにより裁判所に分割の請求をする(民法258条1項)。
(3) 分割禁止の特約がある場合には、その禁止期間は分割を請求することができない(民法256条1項ただし書)。
なお、共有物の分割禁止の特約は、5年を超えて定めることができず(民法256条1項)、また持分の差押えを受けた後は、差押えの効力として、特約の更新(同条2項)をしても、差押債権者である国に対抗することができない。
買戻権
(意 義)
38 買戻権とは、不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約(民法579条参照)により買主が支払った代金及び契約の費用を償還して当初の売買を解除し、目的物を取り戻すことができる権利(所有権移転請求権としての財産権)をいう。
(買戻権の換価)
39 買戻権の換価に当たっては、当該換価による買戻権を取得した買受人が、期間の点で買戻権を行使することができる余裕があるように考慮する。 (注) 買戻権は、有効な約定期間内に権利行使ができるが、この期間は10年を超えるときは10年に短縮される(民法580条1項)し、また、その期間を定めないときは最長5年とされている(同条3項)。
特許権の実施権等
(特許権の実施権)
40 特許権についてのいわゆる実施権には、専用実施権と通常実施権とがあり、特許権者以外の者が特許発明を一定の目的に利用することができる権利である。これらの実施権は差し押さえることができるが、専用実施権については、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合を除いては、移転することができず(特許法77条3項)、通常実施権の移転については、特許法第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項(裁定の請求)、実用新案法第22条第3項(裁定の請求)又は意匠法第33条第3項(裁定の請求)の裁定による通常実施権を除き、上記と同様(承諾については、専用実施権についての通常実施権にあっては特許権者及び専用実施権者の承諾)である(特許法94条1項)。
(実用新案権の実施権)
41 実用新案権についての専用実施権及び通常実施権の性質は、おおむね40と同様である(実用新案法18条3項、24条1項、特許法77条3項)。
(意匠権の実施権)
42 意匠権についての専用実施権及び通常実施権の性質は、おおむね40と同様である(意匠法27条3項、34条1項、特許法77条3項)。
(商標権の使用権)
43 商標権についてのいわゆる使用権には、専用使用権と通常使用権とがあり、商標権者以外の者が指定商品について登録商標を使用することができる権利である。これらの権利は差し押さえることができるが、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般継承の場合を除いては、移転することができない(商標法30条3項、31条3項)。
出版権
44 出版権とは、設定行為の定めるところによって、頒布の目的をもって、著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する独占的排他的な権利をいい(著作権法80条1項)、その設定、移転(相続その他の一般継承によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)若しくは処分の制限又は出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)若しくは処分の制限は、文化庁長官が管掌する出版権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法88条)。
なお、出版権は、著作者の承諾がなければ、譲渡することができない(著作権法87条)。
共有専用実施権等
45 特許権、実用新案権及び意匠権の専用実施権及び通常実施権並びに商標権の専用使用権及び通常使用権の共有持分の譲渡については、他の共有者の同意を必要とする(特許法77条5項、94条5項、実用新案法18条3項、19条3項、意匠法27条3項、28条3項、商標法30条4項、31条4項)。
引湯権
46 引湯権とは、源泉権(第72条関係16)を有する者との契約に基づいて、継続的に一定量の温泉の給湯を受ける権利をいう(昭和2.5.3静岡地沼津支判、昭和43.11.25山形地判参照)。
ゴルフ会員権
(意 義)
47 ゴルフ会員権とは、ゴルフ場を経営する株式会社等に対するゴルフ場及びその付属施設の優先的利用権、年会費納付等の義務、据置期間経過後退会時の預託金返還請求権の三つの権利義務から成る契約上の地位をいう(昭和48.12.18東京高判)。
(差押えの効力)
48 ゴルフ会員権の差押えの効力は、預託金返還請求にも及ぶから、別個に債権差押えの手続をとることなく、規約等に定めるところにより、その取立てができる(56参照)。 (注) 差押通知書の「差押財産」欄には、ゴルフ場及びその付属施設の優先的利用権及び預託金返還請求権(金額を明示する。)がある旨を併記するものとする。
差押手続
(第三債務者等)
49 法第73条の「第三債務者等」とは、おおむね次に掲げる者をいう。 (1) 電話加入権については、公社
(2) 合名会社の社員の持分及び1の(1)に掲げる会社の社員の持分については、その会社
(3) 中小企業等協同組合法による組合等1の(2)に掲げる組合等の組合員等の持分については、その組合等
(4) 信用金庫の会員の持分については、その信用金庫
(5) 漁業信用基金協会の会員の持分については、その漁業信用基金協会
(6) 民法上の組合の組合員の持分については、その組合(業務を執行する組合員があるときはその者、業務を執行する組合員の定めがないときは他の組合員全員)
(7) 無尽講又はたのもし講の講員の持口については、その講の講元(講親)
(8) 営業無尽の加入者の権利については、その相互銀行又は無尽会社
(9) 動産の共有持分については、他の共有者
(10) 賃借権については、その貸主
(11) 買戻権については、その買戻権のある財産の差押え時における所有者
(12) 仮登記に係る権利については、その仮登記時における登記義務者
(13) 特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権及び通常実施権並びに商標権についての専用使用権及び通常使用権については、その特許権者、実用新案権者、意匠権者又は商標権者
(14) 出版権については、その著作権者
(15) 引湯権については、その源泉権者
(16) ゴルフ会員権については、そのゴルフ場を経営する株式会社等
(差押通知書)
50 法第73条第1項の「差押通知書」とは、令第30条第2項((差押通知書の記載事項))に定める事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第6号書式をいい、これを第三債務者等に送達することによって差押えの効力を生ずる(法73条2項)。
(差押調書)
51 法第73条1項の財産を差し押さえた場合には、差押調書を作成し、滞納者に対して、差押調書の謄本を交付しなければならない。(法54条)。
(差押えの登記の嘱託)
52 法第73条第3項の「その権利の移転につき登記を要するもの」とは、1に掲げる財産のうち、登記を第三者対抗要件とする賃借権、登記した買戻権及び(1)から(13)までに掲げる権利をいうが、法第73条第3項において準用する法第72条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
なお、引湯権にあっては、その地方の慣行に従った公示方法(例えば、温泉組合等に対する登録の依頼、立札その他の標識の掲示)を講ずるものとする。 (注) 賃借権、買戻権又は仮登記に係る権利の差押えの登記は、付記登記により行われる(不動産登記法施行細則56条)。
(登録免許税の非課税)
53 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
54 法第73条第1項の規定による差押えの効力は、差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずるが(法73条2項)、その前に差押えの登記がされた場合には、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる(法73条3項、72条4項)。ただし、特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権並びに商標権についての専用使用権については、差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法73条4項、72条5項。特許法98条1項、実用新案法18条3項、意匠法27条3項、商標法30条4項参照)。
預託証書等の取上げ
55 徴収職員は、第三債務者等がある無体財産権等の差押えのため必要があるときは、預託証書、会員証書等その財産権に関する証書を取り上げることができるが(法73条5項)、この場合の手続等については、第65条関係3から5までに準ずる。
取立て
56 法第73条第5項において準用する法第67条((差し押えた債権の取立))の規定により取立てができる財産は、合名会社等の社員の利益配当請求権及び持分払戻請求権、ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権、法第74条((差し押えた持分の払戻の請求))の規定により請求できる持分払戻請求権等差押えに基因して請求できる債権並びに有限会社の社員の残余財産分配請求権等差押えの効力が及ぶ債権に限られる。
第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
払戻し等の請求ができる組合等
1 法第74条第1項の規定により持分の一部の払戻し等を請求できる法人は、組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社及び合資会社を除く。)をいい、中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫のほか、おおむね次に掲げるもの(以下第74条関係において「組合等」という。)である。 (1) 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法18条)
(2) 漁業協同組合(水産業協同組合法26条)、漁業生産組合(同法86条1項)、漁業協同組合連合会(同法92条2項)、水産加工業協同組合(同法96条2項)及び水産加工業協同組合連合会(同法100条2項)
(3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法21条)
(4) 森林組合(森林組合法36条)、生産森林組合(同法100条1項)及び森林組合連合会(同法109条2項)
(5) 農住組合(農住組合法22条)
(6) 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(消費生活協同組合法19条)
(7) 漁業信用基金協会(中小漁業融資保証法17条1項、2項)
払戻し等の請求ができる場合
(不足すると認められるとき)
2 法第74条第1項の「徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様であるただし、不足するかどうかの判定は、法第74条第1項の「請求する」時の現況によるものとする。
(買受人がない場合)
3 法第74条第1項第1号の「買受人がない」とは、売却決定を受けた者がない場合及び売却決定が取り消された場合をいう。
(譲渡ができない場合)
4 法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき法律に制限があるため、譲渡することができない」ときとは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、持分譲渡につき組合等の承諾又は承認を要する場合において、その承諾又は承認が得られないとき(換価処分前に承諾又は承認しない旨の意思表示があったときを含む。)をいう(中小企業等協同組合法17条1項、水産業協同組合法20条1項、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法14条1項、森林組合法30条1項、100条1項、109条2項、農住組合法17条1項、信用金庫法15条1項、中小漁業融資保証法12条1項等)。
なお、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき定款に制限があるため、譲渡することができない」ときに該当することはない。
払戻し等の請求
(持分の一部)
5 法第74条第1項の「持分の一部」とは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、1口の出資を除外した残りの持分をいう。
(持分の払戻し)
6 法第74条第1項の「払戻」とは、第73条関係1の(2)及び(4)に掲げる持分の一部について、脱退があったと仮定した場合における中小企業等協同組合法等の規定により持分の払戻しをいい、その持分の金額は、脱退を仮定した事業年度の終わりにおける組合等の財産によって定まる(中小企業等協同組合法20条、水産業協同組合法28条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法23条、森林組合法38条、100条1項、109条2項、農住組合法24条、中小漁業融資保証法18条1項等)。この場合における財産の評価は、帳簿価格ではなく、その組合等の事業の継続を前提として一括譲渡するときの価額が標準になる(昭和44.12.11最高判)。 (注) 組合等の構成員である滞納者が組合等に対して債務を負っているときは、その債務を完済するまでは、組合等は持分の払戻しを停止することができる(中小企業等協同組合法22条、水産業協同組合法30条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法26条、森林組合法40条、100条1項、109条2項、農住組合法27条、中小漁業融資保証法18条2項等)。
(信用金庫の場合の特例)
7 法第74条第1項の「組合等による譲受が認められている持分」とは、信用金庫の会員の持分をいい、その「譲受」とは、会員の持分の一部について信用金庫法第16条((自由脱退))の規定による脱退を仮定した場合における同条の規定による持分の譲受け(会員から信用金庫への譲渡)をいう。
なお、持分の譲受けの請求をする場合において、1万円(出資の1口の金額で1万円を整除することができないときは、1万円を超え1万円に最も近い整除できる金額とする。)以下の金額の部分については、その譲受けの請求をしないものとする。 (注)1 信用金庫の会員は、持分の全部の譲渡によって脱退することができるが(信用金庫法16条前段)、この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員から信用金庫に対して、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求できることになっており(同法16条後段)、その反面、この自由脱退の場合には、持分の払戻しの制度はない。
2 信用金庫の会員が信用金庫法第17条第1項第1号から第4号まで又は第2項((法定脱退事由))の規定により脱退したときは、同法第18条((脱退者の持分の払戻))の規定により、持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。
3 信用金庫は、脱退した会員が信用金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる(信用金庫法20条)。
(予告期間)
8 法第74条第2項の「組合等からの脱退につき、法律又は定款の定により、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするもの」及び「その期間」は、おおむね次のとおりである。 (1) 中小企業等協同組合法及び消費生活協同組合法による組合等については、事業年度終了の90日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(中小企業等協同組合法18条、消費生活協同組合法19条)
(2) 水産業協同組合法、農業協同組合法、森林組合法及び農住組合法による組合等については、事業年度終了の60日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(水産業協同組合法26条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法21条、森林組合法36条、100条1項、109条2項、農住組合法22条)
(3) 中小漁業融資保証法による漁業信用基金協会については、事業年度終了の6月前まで(同法17条2項)。
(請求及び予告の手続)
9 法第74条第1項の規定による請求は、30日(これと異なる予告期間が定められている場合には、その期間。8参照)前に、令第33条第2項各号((払戻等請求の予告通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、その予告をした後、令第33条第1項各号((払戻し等の請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。これらの書面の様式は、別に定めるところによる。
債権者代位による払戻請求等との関係
10 法第74条の規定により差し押さえた持分の払戻し又は譲受けの請求ができる場合には、債権者代位権(通則法42条、民法423条)により滞納者に代位して行う持分の払戻し又は譲受けの請求をしないものとする。
第75条関係 一般の差押禁止財産
第1条関係 目 的
差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものである。したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに無効となるものではない。
第1号の財産
(生計を一にする親族)
2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び三親等内の姻族(民法725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に取り扱うものとする(執行法97条1項参照)。
(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは、滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下第75条関係において「生計を一にする親族」という。)が、最低限度の生活を維持するに必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具(以下3において「衣服等」という。)をいう。
なお、滞納者の所有に属さない衣服等(例えば、配偶者の所有に属する衣服等)は、差押えの対象財産とならないことはもちろんである。
第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びその者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料をいう。
第3号の財産
(農業を営む者)
5 法第75条第1項第3号の「主として自己の労力により農業を営む者」とは、生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、農業により生計を維持している者をいい、自作、小作の別を問わない。
(器具等)
6 法第75条第1項第3号の「農業に欠くことができない器具」等とは、5に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族が農業を行うため必要最低限の器具等をいう。この場合において、農業を行うため必要最低限のものであるかどうかは、滞納者の営む農業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する(昭和42.5.25鳥取地裁参照)。
(類する農産物)
7 法第75条第1項第3号の「その他これに類する農産物」とは、地下茎、球根、種芋等をいう。
第4号の財産
(漁業を営む者)
8 法第75条第1項第4号の「主として自己の労力により漁業を営む者」とは、生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、漁業により生計を維持している者をいい、舟、漁網その他の漁具を有する者も含まれる。
(漁網その他の漁具等)
9 法第75条第1項第4号の「水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具」等とは、8に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族が漁業を行うため必要最低限の漁網、漁衣、釣りざおその他の漁具等をいう。
(これに類する水産物)
10 法第75条第1項第4号の「これに類する水産物」とは、真珠貝、種のり、養殖用の卵、種がき、えさとして飼育している小魚等をいう。
第5号の財産
(職業又は営業に従事する者)
11 法第75条第1項第5号の「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者」とは、技術者、職人、労務者、弁護士、給与生活者、僧りよ、画家、著述家、小規摸な企業主等で生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、自己の知的又は肉体的な労働を主とする職業又は営業により生計を維持している者をいう(昭和46.5.18東京高決参照)。この場合においては、これらの者が独立して営業を営む場合であると、他に雇用される場合であるとを問わない(昭和8.2.10大決)。
(器具その他の物)
12 法第75条第1項第5号の「業務に欠くことができない器具その他の物」とは、11に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族がその職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものをいう。この場合において、その職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものであるかどうかは、滞納者の職業又は営業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する。
(商品の除外)
13 法第75条第1項第5号の「商品を除く」とは、商品は換価を目的とするものであるから、たとえ業務上欠くことのできないものであっても、同号の差押禁止財産から除外することをいう。
第6号の財産
(実 印)
14 法第75条第1項第6号の「実印」とは、個人にあっては市町村条例等により市区町村役場に、会社の代表者にあっては登記所に、それぞれ届け出た印鑑で、市区町村役場又は登記所から印鑑証明書の交付を受けられるものをいう(商業登記法12条、20条参照)。
(職業に欠くことのできないもの)
15 法第75条第1項第6号の「職業に欠くことができないもの」とは、官公吏、会社員、弁護士、公証人等が職務上使用する印、会社の社印、画家及び書家の落款等の職業に必要な印章で、現に使用中のものをいう。
第7号の財産
16 法第75条第1項第7号の「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」とは、神体、神具、仏具等で、現に信仰又は礼拝の対象となっているもの及びこれに必要なものをいう。したがって、仏像、仏壇等であっても礼拝の対象としないで商品、骨とう品等となっているものには、法第75条第1項第7号の規定の適用がなく、また寺院の本堂、くり(庫裡)、神社の拝殿、社務所等は、礼拝に直接必要と認められないから、同号の規定の適用がない(昭和6.12.23大判、昭和11.3.19大判)。
第8号の財産
17 法第75条第1項第8号の「滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類」とは、滞納者が書画、骨とう等として有しているものを除き、滞納者自身又はその親族その他滞納者と特殊な関係にある者の系譜、日記、書簡等をいう。
第9号の財産
18 法第75条第1項第9号の「勲章」とは、勲功に対する名誉を表彰するものであって、内国のものであると外国のものであると問わず、また、はい(佩)授及び略章も含まれる。また、「その他名誉の章票」とは、勲章以外のもので、その所持が本人の名誉を表示するものであって、競技、学芸、技芸等が優秀なために授与された賞杯等をいう。
なお、法第75条第1項第9号は、いずれも本人又はその親族、第子等その本人と特殊な関係にある者が所持している場合に限って適用され、美術品、骨とう品等として第三者が所有している場合には適用がない。
第10号の財産
19 法第75条第1項第10号の「学習に必要な書籍及び器具」とは、学校教育法第1条((学校の範囲))に規定する学校において教育を受け、又はこれと同程度の修学をするために必要と認められる書籍、器具をいう。この場合における「書籍」とは、教科書、参考書、辞書、帳簿等をいい、「器具」とは、机、本箱、文房具等をいう。
第11号の財産
(発明等)
20 法第75条第1項第11号の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい(特許法2条1項参照)、「著作に係るもの」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、10条参照)。
(公 表)
21 法第75条第1項第11号の「公表」とは、発明につき特許を受けたとき若しくは発明に係るものを展示等し(特許法29条参照)、又は著作に係るものを発行、演奏、展示等すること(著作権法4条1項参照)をいう。
第12号の財産
22 法第75条第1項第12号の「その他の身体の補足に供する物」とは、盲人安全つえ、補聴器、車いす、義眼、眼鏡、人工こう(喉)頭及び松葉づえ等をいう。
第13号の財産
(工作物)
23 法第75条第1項第13号の「工作物」とは、人為的な労作を加えることによって通常土地に固定して設備された物をいい、「その他の工作物」には、塀、門、井戸、煙突等がある。
(消防用の機械等)
24 法第75条第1項第13号の「災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械」等とは、消防法第17条((学校等の消火器等設備義務))の規定に基づく市町村条例等により工場、事業場、学校、百貨店、旅館、飲食店、興業場等に備え付けなければならない消防自動車、消火器その他の消防用機械、器具又は避難器具、鉱山保安法第10条((保安規程))の規定による金属鉱山等保安規則第89条((防火設備等))、第98条((坑外建築物の消火設備))、第110条((防止施設))、石炭鉱山保安規則第152条((防火及び消火))、石油鉱山保安規則第240条((消火施設))等の規定により設備しなければならない各種鉱山の保安施設等をいう。
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによる。
第76条関係 給与の差押禁止
給料等の差押禁止とその範囲
(これらの性質を有する給与)
1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、日直料、宿直料、通勤手当等をいう。
(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法36条1項、2項)。
(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の基礎となる期間が1月未満のときは100円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。 (1) 給料等の金額については、切り捨てる。
(2) 法第76条第1項各号に掲げる金額については、切り上げる。
(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項((差押禁止債権))の規定により差押えが禁止されている債権(法76条及び77条の規定により差押えが禁止されるものを除く。)については、その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項に規定する差押禁止額の限度においても、その差押を行わないものとする。
(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額」とは、これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せず、同法第222条((不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等))の規定により給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金額になる。
(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
なお、道府県民税及び市町村民税については、地方税法第41条第1項((個人の道府県民税の賦課徴収))及び第321条の3の規定により普通徴収の方法により徴収する場合もあるが、この場合には、法第76条第1項第2号の規定に該当する金額がない。
(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第78条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、5と同様である。
(その他の法律)
8 法第75条第1項第3号の「その他の法令」とは、日雇労働者健康保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、港湾労働法、農業者年金基金法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法、恩給法、国会議員互助年金法及び国民年金法をいう。
(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
9 同一期間につきAとBとの支払先から給料等の支給を受ける場合において、これらの給料等につき差押えをした場合の法第76条第1項第4号(以下9において「第4号」という。)及び第5号(以下9において「第5号」という。)の金額計算は、次のいずれかの方法によるものとする。 (1) Aの給料等につき、第4号及び第5号の金額を計算し、次にAとBとの給料等の合計額について第4号及び第5号の金額を計算し、その合計額から、Aの給料等の第4号及び第5号の金額を控除したものをもって、Bの給料等の第4号及び第5号の金額とする方法 〔例〕 Aの給料
支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
法第76条第1項第1号から第3号まで(以下9において「第1号から第3号まで」という。)の金額 ・・・・・・50,000円
Bの給料
支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
第1号から第3号までの金額 ・・・・・・・・・・・・・5,000円
(注) 滞納者の家族構成は、配偶者と扶養親族2人である。
※AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額の計算 イ Aの給料の第4号の金額は170,000円(滞納者分65,O00円十配偶者・扶養親族分35,000円×3人)、第5号の金額は16,000円((支給額300,000円-第1号から第3号までの金額50,000円-第4号の金額170,000円)×20/100)、その合計額は186,000円となる。
ロ AとBとの給料の合計額350,000円についての第4号の金額は170,000円(滞納者分65,000円十配偶者・扶養親族分35,000円×3人)、第5号の金額は25,000円((350,000円-Aの第1号から第3号までの金額50,000円-Bの第1号から第3号までの金額5,000円-AとBとの給料の合計額についての第4号の金額170,000円)x×20/100)、その合計額は195,000円となる。
ハ Bの給料の第4号及び第5号の金額の合計額は9,OOO円(ロの第4号及び第5号の合計額195,000円-イの第4号及び第5号の合計額186,000円)となる。このうち、Bの給料の第4号の金額は0円(AとBとの給料の合計額についての第4号の金額170,000円-Aの給料の第4号の金額170,000円)、Bの給料の第5号の金額は9,000円(Bの給料の第4号及び第5号の金額9,000円-Bの給料の第4号の金額O円)となる。
ニ 以上の結果、AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額は次のとおりとなる。 Aの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・170,000円
Aの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・16,000円
Bの給料の第4号の金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
Bの給料の第5号の金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円
(2) AとBとの給料等の合計額につき、第4号及び第5号の金額を計算し、そのそれぞれの金額をそれぞれの給料等の金額から第1号から第3号までの金額を控除した残額に相当する金額であん分した金額をもって、それぞれの給料等の第4号及び第5号の金額とする方法 〔例〕 設例は(1)と同じ
※AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額の計算 イ AとBとの給料の合計額350,000円についての第4号の金額は170,000円、第5号の金額は25,000円となる((1)のロ参照)。
ロ Aの給料の金額から、第1号から第3号までの金額を控除した金額は250,000円(300,000円-50,000円)となる。
ハ Bの給料の金額から、第1号から第3号までの金額を控除した金額は450,005円(50,000円-5,000円)となる。
ニ イの第4号の金額をロの金額とハの金額であん分すると、Aの給料の第4号の金額は
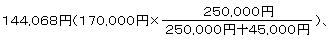
Bの給料の第4号の金額は
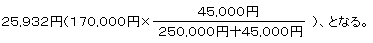
ホ イの第5号の金額をロの金額とハの金額であん分すると、Aの給料の第5号の金額は
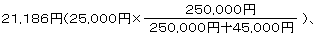
Bの給料の第5号の金額は
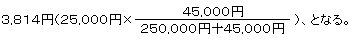
ヘ したがって、AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額は、次のとおりとなる(第76条関係3参照)。 Aの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・145,000円
Aの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円
Bの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,000円
Bの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
給料等に基づき支払を受けた金銭の差押禁止
(現物給与)
10 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」は、給料等に基づき支払を受けた金銭だけをいうのであるから、現物給与として受けた者については、同項の規定の適用がない。
なお、徴収上支障がないと認められる場合には、同項の規定に準じて取り扱うことができる。
(差押禁止額)
11 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数(30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額(150,000円x20/30=100,000円)である。
賞与等及び退職手当等の差押禁止
(賞与等の差押禁止額の判定)
12 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法76条3項前段)。
なお、上記の場合において法第76条第1項第4号又は第5号に掲げる金額についての限度を計算するときは、その支給の基礎となった期間は1月であるものとみなして判定する(法76条3項後段)。
(退職手当等の場合の加算額の計算)
13 法第76条第4項第4号の規定による差押禁止額に加算すべき金額を計算する場合において、同号の「5年をこえる場合には、そのこえる年数1年」に1年未満の端数があるときは、すべて切り上げて計算する取扱いとする。
滞納考の承諾がある場合の差押え
(承 諾)
14 法第76条第5項の「滞納者の承諾」とは、徴収職員が同条第1項、第2項及び第4項の規定を適用しないで給料等又は給料等に基づき支払を受けた金銭の差押えをすることに、滞納者が同意することをいう。この滞納者の承諾は、書面により徴するものとする。 (注) 滞納者が提出する承諾書には、印紙税は課されない(印紙税法2条参照)。
(差押えのできる範囲)
15 法第76条第1項(同項1号から3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項1号及び2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないのであるから(法76条5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内において、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えができる。
なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押えができるものとする。
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
退職年金等に係る債権
1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(法人税法第84条第3項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職年金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。
退職一時金等に係る債権
2 法第77条第1項の「退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(当該適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。
第78条関係 条件付差押禁止財産
条件付差押禁止
(国税の全額を徴収することができる財産)
1 法第78条の「国税の全額を徴収することができる財産」とは、滞納者の差押えをしようとするときにおける滞納国税の全額を徴収することができる財産をいい、その財産の処分予定価額がその国税の全額以上である財産をいう。
なお、上記の「滞納国税の全額を徴収することができる」かどうかの判定については、滞納国税につき既に差押えをした財産があるときは、その財産の処分により徴収できると見込まれる金額を除いたものにより判定するものとする。
(提 供)
2 法第78条の「提供」とは、徴収職員が直ちに差押えができる状態におくことをいう(昭和32.6.26高松高判)。したがって、滞納者が提供しようとする財産の権利関係が明らかではなく又はその財産が著しく遠隔地にあるなどにより、調査するために日時を要する場合には、法第78条の「提供」には該当しない。
(その選択により)
3 法第78条の「その選択により」とは、滞納者の選択によることをいう。
条件付差押禁止財産
(第1号の財産)
4 法第78条第1号の「農業に必要な機械」等とは、現に農業を営んでいる者が、その機械等を差し押さえられることにより、現在程度の農業の継続維持に支障を来すと認められる程度に農業に関係を有する機械等をいう。したがって、例えば、現に農業に従事していない者の所有する機械等は該当しないが、農業を営む者の所有する機械等のうち使用人が使用している機械等は含まれる。
(農 地)
5 法第78条第1号の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう(農地法2条1項、土地改良法2条1項)。この場合における「耕作」とは、一般に、土地に労力を加え、肥料を施して作物を栽培することをいう。
(採草放牧地)
6 法第78条第1号の「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう(農地法2条1項参照)。
(第2号の財産)
7 法第78条第2号の「漁業に必要な漁網」等とは、現に漁業を営んでいる者が、その漁網等を差し押さえられることにより、現在程度の漁業の継続維持に支障を来すと認められる程度に漁業に関係を有する漁網等をいう。したがって、例えば、現に漁業に従事していない者の所有する漁網等は該当しないが、漁業を営む者の所有する漁網等のうち使用人が使用している漁網等は含まれる。
(第3号の財産)
8 法第78条第3号の「職業又は事業の継続に必要な機械」等とは、4及び7に準じ、現に職業又は事業(農業及び漁業を除く。)に従事している者が、その機械等を差し押さえられることにより、現在程度の職業又は事業の継続維持に支障があると認められる程度に職業又は事業に関係を有する機械等をいう(昭和32.6.26高松高判)。
(その他棚卸しをすべき資産)
9 法第78条第3号の「その他たな卸をすべき資産」とは、商品、製品、半製品、仕掛品、副産物、建築用又は修理用資材(例えば、セメント、鉄くず、木材、レール、まくら木、電線、電柱、機械部品等)、消耗品(例えば、油、くぎ、包装材料その他事務用品等)及びその他の貯蔵品をいう。
第7款 差押えの解除
第79条関係 差押えの解除の要件
差押えを解除しなければならない場合
(納 付)
1 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「納付」とは、通則法第34条((納付の手続))の規定による納付をいう。
なお、上記の納付には、同法第41条第1項((第三者の納付))の規定による第三者の納付も含まれる。
(充 当)
2 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「充当」とは、通則法第57条((充当))の規定による充当をいう。
(更正の取消し)
3 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「更正の取消」とは、通則法第24条((更正))等の規定による賦課処分が取り消されることをいう。
(その他の理由)
4 法第79条第1項第1号の「その他の理由」とは、差し押さえた金銭又は交付要求による交付を受けた金銭を差押えに係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項((配当の原則))の規定により差押えに係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除、法律の規定の変更等により差押えに係る国税の全額が消滅したことをいう。
(差押えに係る滞納処分費)
5 法第79条第1項第2号の「差押に係る滞納処分費」とは、差押えに係る国税の滞納処分費のうち、その差押えに係る財産についての滞納処分費をいう(法10条参照)。
(金銭的価値が失われたとき)
6 差押財産の金銭的価値が全く失われたときは、法第79条第1項第2号に該当するものとして取り扱う。
差押えを解除することができる場合
(その他の理由)
7 法第79条第2項第1号の「その他の理由」とは、差押えに係る国税に優先する他の国税、地方税又は公課の交付要求が解除されたこと、差押えに係る国税に優先する債権が弁済されたこと、差押財産の改良等によりその価値が増加したこと等をいう。
(差押超過による解除)
8 法第79条第2項第1号の規定により差押えを解除する場合におけるその解除する財産は、その超過する価額に相当する範囲を超えないものとし、差押財産が不可分物である場合には、その差押えは解除しないものとする。
差押えの解除の効力
9 差押えの解除は、差押えによる処分の禁止の効力を将来に向かって失わせるものである。したがって、例えば、継続収入の債権の差押えに基づいて、差押解除前に一部の取立て及び国税への充当がされていた場合には、差押えの解除は、既にされていた取立て等の処分には影響を及ぼさない。
他の規定による差押えの解除
10 差押えの解除には、法第79条の規定によるもののほか、法第50条第2項若しくは第4項((差押換えの請求等に基づく差押解除))、第51条第3項((差押換えの請求に基づく差押解除))、第151条第2項((換価の猶予に係る差押解除))、第153条第3項((滞納処分の停止に係る差押解除))又は第159条第5項若しくは第6項((保全差押えに係る差押解除))、通則法第48条第2項((納税の猶予に係る差押解除))、第105条第3項((不服申立てに係る差押解除))等の規定によるものがある。
差押国税の一部解除
11 2以上の滞納国税により、同一の差押調書で差し押さえている場合において、ある国税に対応する差押えを解除する必要があるとき(例えば、不服申立てに伴う換価制限があるとき)は、税務署長は、差押えに係る国税の一部を解除することができる。この場合には、その旨を滞納者及び法第81条((質権者等への差押解除の通知))に規定する者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第80条関係 差押えの解除の手続
解除の手続
1 差押えの解除は、その旨を滞納者に通知することによって行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押えの解除は、その旨を第三債務者等に通知することによって行う(法80条1項)。これらの通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
解除に伴う措置
(滞納者への通知)
2 債権又は第三債務者等がある無体財産権等の差押えを解除したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない(法80条2項2号)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(その財産を占有する第三者)
3 法第80条第2項の「その財産を占有する第三者」とは、差押えを解除した時においてその解除した財産を占有している第三者をいう。
(引渡し)
4 法第80条の「引渡」は、現実の引渡しに限らず、指図による占有の移転を含むものとする(民法184条参照)。
(差押えの登記の抹消の嘱託)
5 税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法80条3項)。この関係機関は、差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。 (注) 法第80条第3項の「差押の登記」には、法第87条第1項((参加差押えの効力))の規定により差押えの効力を生じた参加差押えの登記が含まれる。
(引き渡さなければならない)
6 法第80条第4項の「引き渡さなければならない」とは、差押えの時に第三者が占有していた動産又は有価証券については、その第三者が滞納者に引渡しをすべきことを申し出ない限り、解除時にその第三者がその財産を占有することができる権限を有しているかどうかを問わず、その第三者に引き渡さなければならず、またその第三者に引き渡せば免責されることをいう。
(供 託)
7 差押えを解除した場合に、滞納者が所在不明、受領を拒否していること等により、解除した動産又は有価証券の引渡しができないときは、通則法第121条((供託))の規定により供託することができる。
(国の責めに帰すべき理由)
8 法第80条第4項第1号の「国の責に帰すべき理由」とは、更正又は徴収に関する処分に、差押えの解除の直接の理由となった違法性があることをいう。したがって、更正の一部の取消しがあった後残額が納付されたことにより差押えを解除する場合等は、この理由に該当しない。
(参加差押えがある場合の差押えの解除等)
9 解除する差押えにつき参加差押えがある場合又は滞調法の規定の適用がある場合の差押えの解除については、法第87条第2項((参加差押えの効力)の規定((令39条から41条まで参照))又は滞調法第5条第1項本文((滞納処分による差押えの解除時の処置))、第11条第1項本文((仮差押えの執行))、第14条((滞納処分による差押の解除の通知))、第19条((船舶に対する強制執行及び仮差押の執行))、第20条((競売))及び滞調法令第3条第1項((滞納処分による差押えの解除時の処置))、第12条の2((航空機に対する強制執行等))、第12条の3((自動車等に対する強制執行及び競売))、第12条の4((自動車等に対する仮差押えの執行))等の特別の規定がある。
(第三者債務者が供託した後における差押えの解除)
10 滞納処分による差押えをした金銭債権につき強制執行による差押えがされ、第三債務者が供託した場合において(滞調法20条の6参照)、税務署長がその払渡手続前に差押えの解除をするときにおける法第80条第1項ただし書の規定による第三債務者に対する通知は、供託所に対して行うものとする。
差押えの取消しの手続
11 税務署長が、差押えの全部又は一部を取り消す場合(不服申立てに対する取消しの決定又は裁決があった場合を含む。)の手続については、法第80条の規定に準ずるものとする。
第81条関係 質権者等への差押解除の通知
差押解除の通知
(通 知)
1 税務署長は、差押えを解除した場合において、法第55条各号((質権者等に対する差押の通知))に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法81条)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(通知の相手方)
2 交付要求(参加差押えを含む。)をしている者以外の通知すべき相手方は、差押えの解除の時において、法第55条各号((差押えの通知をすべき相手方))に掲げる者に該当する者のうち知れている者である。したがって、同条の規定により差押えの通知をした者と同一の範囲に限られるものではない。
(その他必要な事項)
3 法第80条の「その他必要な事項」とは、滞納者の氏名、住所又は居所、差押えを解除した財産の名称、数量、性質、所在、差押年月日、差押解除の年月日等をいう。
第2節 交付要求
第82条関係 交付要求の手続
交付要求ができる国税
1 法第82条第1項の「滞納」とは、法第2条第9号((滞納者の定義))にいう「納付の期限までに国税を納付しない」ことをいう。
なお、滞納に係る国税については、次のことに留意する。 (1) 督促(納付催告書による督促を含む。)をしていない国税についても、交付要求をすることができる。
(2) 納税の猶予又は徴収の猶予に係る国税について、その猶予期間内であっても、交付要求をすることができる(通則法48条1項参照)。
(3) 滞納者の財産について差押えをした後、滞納者が死亡したときは、その差押えを受けた財産の相続人の固有の滞納国税について、交付要求をすることができる。
(4) 国税につき徴している第三者の担保財産を滞納処分の例により処分する場合には、その差押え時における第三者の国税につき交付要求をすることができる。 (注) 担保権の設定時において納税者に帰属していたが、差押え時には第三者に帰属している財産も上記の第三者の財産に含まれる。
交付要求ができる時期
2 次に掲げる場合には、交付要求は、それぞれに掲げる時までに行うものとする。 (1) 滞納処分の場合には、売却決定の日の前日(換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時)(法130条1項、令48条2項参照)
(2) 不動産(執行法43条1項((不動産執行の方法))に規定する不動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制執行又は不動産を目当てとする担保権の実行としての競売の場合には、執行裁判所の定める配当要求の終期(執行法49条1項、2項、87条1項2号、188条) (注) 執行法第49条第3項((配当要求の終期の延期))又は第52条((配当要求の終期の変更))の規定により、配当要求の終期が延期された場合等には、当初の配当要求の終期後においても、延期等後の配当要求の終期までの間は交付要求をすることができる。
(3) 不動産に対する強制管理の場合には、執行裁判所が定める期間の終期(執行法107条1項、4項) (注) 上記の場合には、執行裁判所が定める期間ごとに配当等(執行法84条3項参照)が実施されるので、当該期間の満了までに交付要求をしなければ、既に収取されている収益の配当を受けることはできない。
(4) 船舶(執行法112条((船舶執行の方法))に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車又は建設機械に対する強制執行又はこれらの財産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、(2)に準ずる時(執行法121条、189条、執行規則84条、97条、98条、175条から177条まで)
(5) 動産(執行法122条1項((動産執行の開始))に規定する動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制執行又は動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、次に掲げる時 イ 売得金については、執行官がその交付を受ける時(執行法137条((執行停止中の売却))又は保全法49条3項((動産に対する仮差押えの執行))の規定により供託された売得金については、動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売が続行されることとなった時)
ロ 手形等(執行法136条参照)の支払金については、執行官がその支払を受ける時(同法140条)
(6) 金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行の場合には、次に掲げる時(執行法165条)。ただし、金銭の支払を目的とする債権につき管理命令が発せられている場合には、上記(3)に準ずる(同法166条1項、161条1項、6項、107条4項参照)。 イ 第三債務者が執行法第156条第1項又は第2項((第三債務者の供託))の規定による供託をした時
ロ 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
ハ 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
ニ 動産引渡請求権の差押えの場合にあっては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
(7) (2)から(6)までに掲げる財産権以外の財産権に対する強制執行又はこれらの財産権を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、特別の定めがあるもののほか、(6)に準ずる時(執行法167条1項、193条2項)
(8) 企業担保権の実行手続が開始された場合には、一括競売により換価をするときは競落期日の終了時、任意売却により換価をするときは裁判所が定めて公告した日(企業担保法51条の2)
(9) 破産宣告があった場合には、破産終結の決定(破産法282条1項)、強制和議の認可決定(同法321条)又は破産廃止の決定(同法347条参照)がある時 (注) 破産宣告後に確定した財団債権である国税については、上記にかかわらず、直ちに交付要求をするものとする(破産法286条参照)。
担保財産につき強制換価手続が開始された場合
3 国税の担保財産につき強制換価手続が開始された場合には、次のことに留意する。 (1) 裁判所書記官から債権届出の催告を受けたときは、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない(執行法49条2項、50条1項、121条、執行規則97条、98条)。また、その届出に係る国税の額に変更があったときは、その旨の届出をしなければならない(執行法50条2項、121条、執行規則97条、98条)。
(2) 担保を徴した国税が、次に掲げる場合に該当するため、法第15条((法定納期限等以前に設定された質権の優先))又は第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定を適用して、国税としての優先権を主張する必要があるときは、交付要求をするものとする。
なお、この場合における交付要求書には、担保を徴した国税に係る交付要求である旨を付記するものとする。 イ 国税の担保権の設定が、その担保財産上に設定された質権又は抵当権の設定に後れる場合
ロ 抵当権の設定に係る国税の利子税又は延滞税が、民法第374条((抵当権の被担保債権の範囲))の規定により、その抵当権の満期となった最後の2年分に制限されるため、国税債権額の満足を得ることができない場合
交付要求の手続
(交付要求書)
4 法第82条第1項の「交付要求書」とは、令第36条第1項各号((交付要求書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第7号書式による。
(滞納者への通知)
5 交付要求をしたときは、令第36条第2項各号((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、滞納者に通知しなければならない(法82条2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(質権者等への通知)
6 交付要求をしたときは、令第36条第3項((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に定める事項を記載した書面により、質権者等に通知しなければならないが(法82条3項)、これについては第55条関係と同様とする。ただし、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、通知をする必要がない(令36条4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
交付要求の効果
7 交付要求の効果については、次のことに留意する。 (1) 交付要求は、その交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行(担保権の実行としての競売を含む。以下同じ。)の手続が解除され、又は取り消された場合には、その効力を失う。
(2) 交付要求は、交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行の手続が解除されず、又は取り消されない限り、その処分の目的となった財産について差押え後に権利の移転があっても、その交付要求により配当を受けることができる(昭和27.12.9浦和地判、昭和28.6.30東京高判)。
(3) 交付要求は、時効中断の効力を有する(通則法73条1項5号、2項)。
滞調法の規定により二重差押えがされている場合
8 滞納者の財産について、滞調法の規定により滞納処分と強制執行とが競合している場合には、滞納処分をしている行政機関等に対して交付要求(参加差押えの要件を満たしている場合には、参加差押え)をするととともに、強制執行の執行機関に対しても交付要求をするものとする。 (注) 強制執行に先行して滞納処分による差押えをしている場合において、強制執行続行の決定があったときは、当該差押えに係る国税につき、強制執行の執行機関に対して交付要求をすることに留意する(滞調法10条3項等)。
交付要求に係る強制執行につき続行決定があった場合
9 交付要求に係る強制執行について、その続行決定があつた場合には、交付要求をした国税を徴収するため改めて交付要求をする必要はない。
第83条関係 交付要求の制限
交付要求の制限の意義
1 法第83条は、滞納者が他に換価容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によって国税の全額を徴収できると認められるときは、利害関係人の利益を害することがないよう交付要求をしないことを定めた訓示規定である(昭和49.8.6.最高判)。
換価の容易な財産
2 法第83条の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。
徴収できると認められる場合
3 法第83条の「徴収することができると認められる」かどうかの判定については、第22条関係4と同様である。
第84条関係 交付要求の解除
その他の理由
1 法第84条第1項第1号の「その他の理由」とは、交付要件により交付を受けた金銭を交付要求に係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項((配当の原則))の規定により交付要求に係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除、法律の規定の変更等により交付要求に係る国税の全額が消滅したことをいう。
交付要求の解除手続
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う(法84条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
関係者への通知
(滞納者への通知)
3 交付要求を解除した場合には、その旨を滞納者に通知しなければならない(法84条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(質権者等への通知)
4 交付要求を解除した場合は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときを除き、その旨を質権者等に通知しなければならないが(法84条3項、令36条4項)、この通知については、第55条関係に準ずる(第81条関係1参照)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第85条関係 交付要求の解除の請求
解除の請求ができる者
1 法第85条第1項の「配当を受けることができる債権者」とは、交付要求の解除の請求をした時において、強制換価手続により配当を受けることができる債権者をいい、配当受領のための手続を必要とする債権につきその手続をとっていない債権者は含まれない。
解除の請求ができる場合
(債権の弁済を受けられないこと)
2 法第85条第1項第1号の「弁済を受けることができない」とは、交付要求がなければ弁済を受けることができたにかかわらず、交付要求がされたために、債権の全部又は一部の弁済を受けることができなくなることをいう。したがって、交付要求の有無にかかわらず弁済を受けることができない場合は、法第85条第1項第1号には該当しない。
(換価の容易な財産)
3 法第85条第1項第2号の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。
(徴収できることの判定)
4 法第85条第1項第2号の「徴収することができる」かどうかの判定については、第22条関係4と同様である。
(解除の請求手続)
5 法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求は、令第37条各号に掲げる事項を記載した書面により、交付要求ができる時期(第82条関係2参照)までにしなければならないものとする(昭和49.8.6最高判)。
請求に対する措置
(請求を相当と認めるとき)
6 法第85条第2項の「相当と認めるとき」は、第50条関係10とおおむね同様である。
なお、交付要求ができる時期(第82条関係2参照)が経過した後に交付要求の解除の請求があった場合においても、相当と認められるときは、交付要求の解除をするものとする。
(請求を相当と認めないとき)
7 税務署長は、法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない(法85条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第86条関係 参加差押えの手続
参加差押えの手続
(参加差押えの意義)
1 法第86条から第88条((参加差押えの制限、解除等))までに規定する参加差押えは、交付要求の一つとして行われるものであるから、参加差押えを受けた差押えが解除されるまでの効力は交付要求の効力と同様であるが、その参加差押えを受けた差押えが解除されると参加差押えをした時等にさかのぼって差押えの効力を生じ、その後はその差押えに基づき参加差押財産の換価処分ができる効力を有する。
(差押えができる場合)
2 法第86条第1項の「第47条(差押の要件)の規定により差押をすることができる場合」とは差押えの要件を定める法第47条の規定に基づく差押えができる場合をいい、次に掲げる場合を含むものとする。
なお、法第47条第2項((繰上差押え))の規定により繰上差押えができる場合にも、法第86条第1項の規定により繰上参加差押えをすることができる(第47条関係14参照)。 (1) 法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分の要件))に規定する同条第2項((譲渡担保権者に対する告知))の告知書を発した日から1O日を経過した日までに法第24条の規定により徴収しようとする金額が完納されていない場合
(2) 法第159条第3項((保全差押金額の通知))の規定による保全差押金額の通知を納税義務があると認められる者にした場合
(3) 通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定による繰上保全差押金額の通知を納税者にした場合
(4) 通則法第52条(担保の処分)に規定により担保の処分をする場合。
(5) 法第138条((滞納処分費の納入の告知))の規定による納入告知により指定された納期限までに、その納入告知書により告知された滞納処分費を完納しない場合
(参加差押書)
3 法第86条第1項の「参加差押書」とは、令第36条第1項各号((交付要求書の記載事項))に掲げる事項に準ずる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第8号書式による。
(滞納者への通知)
4 参加差押えをしたときは、令第36条第2項各号((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に掲げる事項に準ずる事項を記載した書面(参加差押通知書)により、滞納者に通知しなければならない(法86条2項前段)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(第三債務者への通知)
5 電話加入権について参加差押えをしたときは、令第36条第3項に定める事項に準ずる事項を記載した書面により、第三債務者(日本電信電話公社)に通知しなければならない(法88条2項後段)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(差押財産が譲渡された場合)
6 滞納者(甲)の所有財産がその者の滞納処分により差し押さえられ、その後その差押財産が第三者(乙)に譲渡された場合において、滞納者(甲)の国税につき参加差押えをすることはできないし(昭和37.6.29付民事甲第1,838号法務省民事局長電報回答)(交付要求はできる。)、また、第三者(乙)の国税につき参加差押え(交付要求を含む。)をすることもできない(第47条関係59参照)。
(譲渡担保財産である場合)
7 譲渡担保権者の国税により差押えがされている譲渡担保財産について、法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分))の規定により譲渡担保設定者(譲渡担保財産を譲渡担保権者に譲渡した者をいう。)の国税により参加差押えをすることができるし、また譲渡担保設定者の国税により差押えがされている譲渡担保財産について譲渡担保権者の国税により参加差押えをすることもできる(令9条参照)。
登記の嘱託
8 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械につき参加差押えをしたときは、参加差押えの登記を、参加差押調書謄本を添えて(昭和35.9.19付民事甲第2,304号法務省民事局長通達)、関係機関に嘱託しなければならない(法86条3項)。この関係機関については、第68条関係44、第70条関係5及び第71条関係5と同様である。
なお、参加差押えの登記は、参加差押えの効力要件ではないが、法第87条((参加差押の効力))の規定による差押えを第三者に対抗するための要件である。
質権者等への通知
9 税務署長は、法第86条第1項の規定により参加差押えをしたときは、法第55条((質権者等に対する差押えの通知))に掲げる者のうち、徴収職員がその参加差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対して、令第36条第3項((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に定める事項に準ずる事項を記載した書面により通知しなければならない(法86条4項、令38条)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
第87条関係 参加差押えの効力
参加差押えに係る差押えの効力
(参加差押えの効力)
1 参加差押えは、次に掲げる効力を有する。
なお、(2)及び(3)に掲げる効力は、参加差押えが2以上ある場合は、そのうち最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え)に限られる(法87条1項)。 (1) 参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対する交付要求の効力
(2) 参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、参加差押財産について、3に掲げる時にさかのぼって生ずる差押えの効力
(3) 参加差押財産が動産、有価証券、自動車又は建設機械であって、その参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、その差押えを解除した行政機関等からその財産の引渡しを受けることができる効力
(差押えの効力が生ずる参加差押え)
2 参加差押えを受けた差押えが解除されたときにおいて、差押えの効力を生ずる参加差押えは、次のとおりである(法87条1項)。 (1) 参加差押えが一つである場合には、その参加差押え
(2) 参加差押えが2以上ある場合には、参加差押えを受けた差押えが解除されたときにされている参加差押えのうち、最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え) (注)1 参加差押えを最も先にしたものであっても、参加差押えを受けた差押えが解除される時までに解除したときの参加差押えは、差押えの効力を生じないし、また上記の差押えの効力を生ずる参加差押え以外の参加差押えは、差押えの効力を生じない。
2 差押えの解除後、その抹消登記前にした参加差押えは、効力を生じない。
(差押えの効力を生ずる時期)
3 参加差押えが差押えの効力を生ずる時は、次のそれぞれに掲げる時である(法87条1項、大陸棚特別措置法施行令5条)。 (1) 参加差押財産が動産及び有価証券である場合には、その参加差押書が参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に交付された時
(2) 参加差押財産が不動産(鉱業権及び特定鉱業権を除く。)、船舶、航空機、自動車及び建設機械である場合には、その参加差押通知書が滞納者に送達された時。ただし、参加差押えの登記が、参加差押通知書の滞納者への送達前にされた場合には、その登記がされた時
(3) 参加差押財産が鉱業権又は特定鉱業権である場合には、参加差押えの登録がされた時
(4) 参加差押財産が電話加入権である場合には、その参加差押通知書が第三債務者である日本電信電話公社に送達された時
動産等の引渡し
(差押えを解除すべきときの順序)
4 参加差押えがされている動産、有価証券、自動車又は建設機械(以下第87条関係において「動産等」という。)について、参加差押えを受けている差押えを解除すべきとき又は差押えの解除ができるときは、税務署長は、その動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡し、その後において差押えを解除するものとする。
(動産等の引渡しの通知)
5 法第87条第2項の規定により動産等を差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等(以下第87条関係において「参加差押えの行政機関等」という。)に引き渡すべきときは、税務署長は、次によりその参加差押えの行政機関等にその旨を通知しなければならない(令39条1項、2項)。 (1) 令第39条第1項各号((参加差押えに係る動産等の引渡しの通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面による。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(2) 徴収職員以外の者で動産等の保管をしている者に直接引渡しをさせようとする場合には、その旨を(1)の書面に付記するとともに、その保管者にあてた参加差押えの行政機関等へ動産等の引渡しをすべき旨の書面を添付する。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(権利書等の引渡し)
6 税務署長は、法第65条((債権証書の取上げ))又は第73条第4項((権利証書の取上げ))の規定の趣旨により取り上げた権利証書等がある場合及び動産等を占有している第三者が提出した法第59条第1項又は第3項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)に規定する損害賠償請求権又は前払借賃に関する書類その他必要なもの(令48条の債権現在額申立書を含む。)がある場合には、これらの権利証書及び書類を、参加差押えの行政機関等に引き渡すものとする(令41条1項、3項、4項)。
(差押えを解除したときの措置)
7 税務署長は、参加差押えを受けた差押えを解除したときは、法第80条第2項及び第3項((差押解除の措置))並びに第81条((質権者等への差押解除の通知))の規定による手続をするほか、次に掲げる措置をしなければならない。 (1) 2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされている参加差押えを除き、他の参加差押えに係る参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち、滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を参加差押えの行政機関等に引き渡す(令41条1項)。この場合においては、別に定める書面を添付するものとする。
なお、滞納処分による差押え等に関する書類の引渡しについては、一つの参加差押えだけがある場合においても、同様に取り扱う。
(2) (1)により参加差押えの行政機関等に引き渡す参加差押書又はその写しには、差押えの解除をした税務署におけるその参加差押書の受付順序を明白に表示する。
(3) 参加差押えの行政機関等以外の参加差押えをしていた行政機関等又は法第55条((質権者等に対する差押えの通知))に規定する質権者等に対し、参加差押えの行政機関等の名称及びその行政機関等に差押財産を引き渡した旨を法第81条の規定による通知書に付記する(令39条3項参照)。
(4) 法第59条第2項(同条4項において準用する場合を含む。)の規定により、差し押さえた財産の使用又は収益をしている者及び法第129条第1項第4号((配当を受ける損害賠償請求権等に係る債権))に掲げる債権を有する者に対し、(3)に準じて通知するものとする。
(引渡しをした動産等の保管費用)
8 徴収職員が動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡した場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書が参加差押えの行政機関等に送達された日までの保管に関する費用は、その動産等の引渡しをした国(税務署長)の負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令40条5項参照)。
(差押解除後の参加差押えの効力)
9 行政機関等が、参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を、参加差押えの行政機関等に引き渡した場合には、それらの参加差押書に係る参加差押えは、行政機関等にそれらの参加差押書が送達された時に、それらの参加差押書に係る参加差押えの順序に従い、参加差押えの行政機関等に対して参加差押えをしたものとみなされ、引渡しがされたその他の書類は、その行政機関等に提出されたものとみなされる(令41条2項)。
(動産等の引渡しを受けた場合の措置)
10 参加差押えが差押えの効力を生じた場合において、徴収職員が差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面の送付を受けたときは、次の措置をしなければならない。 (1) 徴収職員は、差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面に記載されている事項に基づき、遅滞なく、その通知に係る動産等の引渡しを受ける(令40条1項前段)。この場合において、その通知に係る動産等を徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)以外の者でその動産等の保管をしている者から受け取るときは、その保管をしている者に対し、送付を受けたその保管者あての動産等の引渡しをすべき旨の書面を交付する(令40条1項後段)。
(2) 徴収職員は、必要があると認めるときは、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させることができるので、保管については通常の差押財産と同様に処理する(令40条2項本文)。この場合において、第三者に保管させるときは、その動産等の運搬が困難であるときを除き、その第三者の同意を得なければならない(令40条2項ただし書)。
(3) 徴収職員は、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させた場合には、封印、公示書その他の方法により差押えを明白にしなければならない(令40条3項)。
(4) 徴収職員は、動産等の引渡しを受けたときは、引渡しをした行政機関等に対し、引渡動産等の引渡しを受けた旨を通知する(令40条4項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(引渡しを受けた動産等の保管)
11 令第40条第2項((引渡しを受けた動産等の保管))の「必要があると認めるとき」、「財産を占有する第三者」及び「運搬が困難であるとき」は、第60条関係7,6及び10と、それぞれ同様である。
なお、上記の場合における令第40条第3項((保管させた場合の措置))の規定による封印、公示書その他の方法により差押えを明白にすることは、差押えの効力発生の要件ではなく、徴収職員が差押財産を占有していることを明らかにする方法にすぎない。
(賃料債権等の権利行使)
12 法第59条第1項又は第3項((引渡命令を受けた第三者の権利保護))(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対して配当を請求することができる権利は、差押えの効力を生ずべき参加差押えをしている税務署長に対して行使することができる(令41条3項、4項)。
(引渡しを受けた動産等の保管費用)
13 徴収職員が、他の行政機関等から徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)から動産等の引渡しを受けた場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書がその徴収職員の所属する税務署に送達された日の翌日からの保管に関する費用は、その引渡しを受けた税務署の13負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令40条5項)。
換価の催告
14 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる(法87条3項)。この催告は、原則として別に定める書面により行うものとする。
換価の催告を受けた場合
15 差押えをした税務署長が、その差押えに対して参加差押えをした行政機関等から、差押財産について換価すべき旨の催告を受けた場合は(法87条3項)、法律で換価が制限されているときその他相当な理由により換価ができない場合を除き、速やかに換価するものとする。
上記の理由に該当しない場合において、差押財産の換価をしないときは、その理由を催告した行政機関等に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第88条関係 参加差押えの制限、解除等
参加差押えの制限
1 参加差押えの制限については、第83条関係1から3までに準ずる(法88条1項参照)。
参加差押えの解除
2 参加差押えの解除については、第84条関係1から4までに準ずる(法88条1項参照)。
なお、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を日本電信電話公社に通知しなければならない(法88条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
参加差押えの登記の抹消の嘱託
3 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法88条2項)。この関係機関は、参加差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。
参加差押えの解除の請求
4 参加差押えの解除の請求については、第85条関係1から7までに準ずる(法88条1項参照)。
第3節 財産の換価
第1款 通則
第89条関係 換価する財産の範囲
差押財産
1 法第89条第1項の「差押財産」とは、差し押さえた財産のうち、次に掲げるものを除いた財産をいうものとする。 (1) 金銭及び債権
(2) 法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により取り立てる場合の有価証券
(3) 法第73条第5項((差し押さえた債権の取立て等の準用))において準用する第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取り立てる場合の無体財産権等
換価することができる債権
2 次に掲げる債権は、法第89条第2項の規定により換価することができる。 (1) 差し押さえた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取立てをしようとする時から6月以内に到来しないもの。この場合において、6月の計算の始期は、差押えの効力の発生した日とする。
(2) 取立てをすることが著しく困難であると認められるもの。この場合において、著しく困難とは、差し押さえた債権が、不確定期限のついたもの、条件の付けられたもの、反対給付に係るもの等で、かつ、取立てまでに要する期間、条件その他債権の内容により取立てをすることが社会通念上著しく困難なことをいう。なお、6月以内に取立ての見込まれないことが明白な債権は取立てが著しく困難なものとして換価できるものとする。
一括換価
(一括換価をする場合)
3 次の財産については、原則として、それぞれに定めるところに従い、一括して換価する。 (1) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定の適用を受ける財産については、土地又は建物とともに換価する。
(2) 工場財団その他の財団の組成物件については、工場財団その他の財団として換価する。ただし、財団として売却することが困難である場合には、工場抵当法第46条((個々のものの競売又は入札))の規定の趣旨に従い、抵当権者等の同意を得て、個々の物件として換価することができる。
(3) 担保権の目的となっている財産の従物については、主物とともに換価する。ただし、担保権者の同意がある場合には、主物と別個に換価することができる。
(一括換価をすることができる場合)
4 同一の滞納者の所有に係る複数の財産について、次のいずれにも該当するときは、当該財産を一括して換価することができる(昭和49.1.17東京高決参照)。 (1) 財産が、客観的かつ経済的にみて、有機的に結合された一体をなすと認められること。
(2) 一括換価をすることにより高価有利に売却できること。
(3) 一括換価することを不当とする事由(例えば、担保権者に対する配当に支障を来すこと。)がないこと。
(4) 売却決定が同一の日であること。
(共有に係る不動産の一括換価)
5 共有に係る不動産については、その共有者の全員が滞納しており、かつ、各滞納者について国税への配当金額がある場合に限り、当該不動産を一括して換価することができる(第129条関係17参照)。
換価ができない場合
6 次に掲げる国税については、原則として、それぞれに掲げる期間内は、換価をすることができない。なお、果実等については、法第90条第1項及び第2項((果実等の換価の制限))の規定の適用がある。 (1) 納税者の国税を第二次納税義務者又は保証人から徴収する場合におけるその第二次納税義務者及び保証人の納付すべき国税その納税者の財産を換価に付すまでの期間(法32条4項、通則法52条5項)又は第二次納税義務者若しくは保証人が、納付通知書による告知、納税催告書による督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(2) 担保のための仮登記がされた財産を差し押さえた場合の法第55条第2号((仮登記の権利者に対する差押えの通知))の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る国税同条第2号の通知に係る差押えにつき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(3) 法第24条第1項((譲渡担保財産からの国税の徴収))の規定により譲渡担保財産から徴収する納税者の国税その納税者の財産を換価に付すまでの期間(法24条3項、32条4項)又はその譲渡担保権者が同条第2項の告知(同条4項の規定による場合のものを含む。)若しくはこれに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(4) 法第50条第3項((第三者による換価の申立てと換価の制限))の申立てがあった場合において、その申立てに係る財産が換価の著しく困難なもの又はその申立て者以外の第三者(滞納者を除く。)の権利の目的となっているもの以外のものであるときの、その申立てに係る財産についてのその国税その申立てがあった時からその申立てに係る財産を換価に付すまでの期間
(5) 法第151条第1項((換価の猶予の要件))の規定による換価の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(6) 通則法第23条第5項ただし書((更正の請求があった場合の徴収の猶予))又は第105条第2項及び第6項((不服申立てに係る徴収の猶予等))の規定による徴収の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(7) 通則法第46条第1項、第2項及び第3項((納税の猶予の要件))の規定による納税の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間(同法48条1項)
(8) 不服申立てに係る国税その不服申立てについての決定又は裁決があるまでの期間(通則法105条1項ただし書)
(9) 通則法第105条第2項及び第6項((不服申立てに係る滞納処分の続行の停止等))の規定により滞納処分の続行が停止されている場合におけるその停止に係る国税その続行の停止期間
(10) 滞納法第10条((強制執行続行の決定))等の規定により強制執行等の続行の決定があった場合のその滞納処分による差押えに係る国税その強制執行等の係属する期間
(11) 会社更生法第37条第2項((滞納処分の中止命令等))の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合におけるその中止に係る国税その中止期間
(12) 会社更生法第102条((更生債権))の規定により更生債権となった国税同法第67条第2項((滞納処分の中止等))の規定による滞納処分の中止期間
(13) 会社更生法第122条第1項((租税等の請求権))の規定による猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(14) 行政事件訴訟法第25条第2項((執行停止))の規定により執行の停止を命ぜられた処分に係る国税その停止期間
(15) 企業担保権の実行手続の開始があった株式会社に係る国税その実行手続の係属する期間(企業担保法28条)
(16) 予定納税額に係る所得税その年分の所得税に係る確定申告期限までの期間(所得税法117条)
換価の効果
(承継取得)
7 換価は、滞納者と買受人との間に売買契約を成立させるものであるから、買受人の権利の取得は、原始取得ではなく、承継取得である(昭和8.12.2大判、昭和32.4.24岐阜地判)。
(担保権等の消滅)
8 買受人が買受代金の納付により換価に係る権利を取得したときは、換価財産の上にあつた質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、消滅する(法124条1項前段)。ただし、法第124条第2項((担保権の引受け))の規定による担保権の引受けがあったときは、その引受けに係る担保権は、消滅しない(法124条2項後段)。
なお、法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により譲渡担保財産に対して滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権も、上記と同様に消滅する(法124条1項後段)。
(用益物権等の存続)
9 換価財産が不動産その他の登記を権利移転の対抗要件又は効力要件とする財産であって、その財産上に差押えの登記前に第三者に対抗できる地上権その他の用益物権、買戻権、賃借権、仮登記(担保のための仮登記を除く。)等(以下「用益物権等」という。)がある場合には、その用益物権等は、換価によっては消滅しない。ただし、第三者に対抗できる用益物権等であっても、それらの権利の設定前に換価によって消滅する質権、抵当権、先取特権、留置権、買戻権又は担保のための仮登記がある場合には、その用益物権等も消滅する。 (注) 換価によって消滅する担保権等の後に設定された用益物権等が消滅するのは、これらの用益物権等が担保権等に対抗できないことによるものであるから、民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない登記された賃貸借(登記なしで対抗できるものを含む。借家法1条等)は、消滅しない(民法395条)。
(賃借権等の消滅)
10 差押え前に換価財産上に賃借権(9に定めるものを除く。)、使用貸借権等の権利が設定されている場合においても、換価による買受人に対抗できないから、これらの権利は消滅する。
(土地の賃借権の存続)
11 換価により建物の所有を目的とする賃借地上の建物の所有権を取得した買受人は、その土地の賃借権も取得する(借地法9条の3,9条の4、昭和47.7.18最高判参照)。
(仮差押え等の消滅)
12 換価財産上にある仮差押え及び仮処分の消滅については、第140条関係3及び12から21までに定めるとおりである。
(差押え後の権利の消滅)
13 換価財産につき差押え後に取得した所有権、担保権、用益物権等を有していた者は、その換価財産の買受人に対して所有権等の権利を主張することができない。
譲渡の制限
(たばこ専売法)
14 たばこ種子、たばこ苗及び葉たばこについては、たばこ専売法の規定に基づく譲渡制限等があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) たばこ種子は、日本専売公社(以下「専売公社」という。)又は耕作者でなければ所有できない(たばこ専売法11条1項)。
(2) たばこ苗は、専売公社又は耕作者でなければ育成できない(たばこ専売法12条1項)。
なお、耕作者に譲渡するときは、専売公社の許可を受けなければならない(たばこ専売法12条4項)。
(3) 葉たばこ及び製造たばこ用巻紙は、専売公社に対してでなければ譲渡できない(たばこ専売法18条1項、54条1項)。
(4) 農薬用たばこ耕作者の収穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供するときは、あらかじめ専売公社の承認を要する(たばこ専売法26条の3)。
(5) 製造たばこの換価は、たばこ専売法第29条第2項((製造たばこの販売制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(6) 製造たばこの換価に際しては、一般消費者が買受人となることができることはもちろん、小売人は、たばこ専売法第37条第1項第2号((買受販売制限の除外))の規定により買受人となることができる。
(7) 小売人の所有する製造たばこを換価する場合においては、たばこ専売法第34条第3項((定価))の規定の適用はないから、小売定価によらないで換価することができる。
(塩専売法)
15 塩及びかん水については、塩専売法の規定に基づく譲渡制限等があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) 塩の製造者が製造して所有する塩は、原則として専売公社に対してでなければ譲渡できない(塩専売法5条1項、14条1項参照)。
(2) 塩専売法第29条第1項((特別価格による売却))の規定により特別価格で買い受けた塩は、専売公社の許可を受けなければ譲渡できない(同法29条4項)。
(3) 輸出のため専売公社から買い受けた塩は、専売公社の許可を受けなければ、輸出前には譲渡できない(塩専売法41条2項)。
(4) かん水は、塩の製造者に対してでなければ譲渡できない。ただし、専売公社の許可を受けた場合には、この限りでない(塩専売法43条1項)。
(5) 塩の換価は、塩専売法第23条第2項本文((販売の制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(6) 塩の換価に際しては、一般消費者が買受人となることができることはもちろん、小売人は、塩専売法第34条第1項第2号((買受販売制限の除外))の規定により買受人となることができる。
(アルコール専売法)
16 アルコールの換価については、アルコール専売法の規定に基づく譲渡制限があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) アルコールを製造している者の製造したアルコールは、政府に対してでなければ譲渡できない(アルコール専売法13条)。
(2) 売さばき人又は消費者の所有するアルコールの換価は、アルコール専売法第28条第1項((販売の制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(飼料需給安定法)
17 政府は、輸入飼料を売り渡す場合には、飼料需給安定法第6条((売渡の附帯条件))の規定により、その相手方に対し、譲渡に関し地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
(大麻取締法)
18 大麻(大麻取締法1条に規定する大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)を除く。)は、同法第3条第1項((譲渡等の制限))の規定により、大麻取扱者に対してでなければ譲渡することができない。
(火薬類取締法)
19 火薬類(火薬類取締法2条に掲げる黒色火薬、ニトログリセリン、実砲等の火薬、爆薬及び火工品をいう。)の譲渡については、同法第17条第1項((譲渡等の許可))の規定により、同項各号のいずれかに該当する場合以外の場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(毒物及び劇物取締法)
20 毒物(黄りん、ひ(砒)素等の毒物及び劇物取締法2条1項の規定による別表第1に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)又は劇物(塩酸、硝酸等同法2条2項の規定による別表第2に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)の製造業又は輸入業の登録を受けた者で、販売業の登録を受けていない者は、同法第3条第3項((販売等の制限))の規定により、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業の登録を受けた者に対してでなければ、毒物又は劇物を譲渡することができない。
(覚せい剤取締法)
21 覚せい剤(覚せい剤取締法2条に掲げるフェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン等をいう。)の製造業者が、その製造して所有する覚せい剤は、同法第17条((譲渡及び譲受の制限及び禁止))の規定により、覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
(麻薬取締法)
22 麻薬(コカ葉、モルヒネ等麻薬取締法2条1号の規定による別表に掲げるものをいう。)は、同法第26条((譲受))の規定により、麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に対してでなければ、譲り渡してはならない(同法24条参照)。
(あへん法)
23 あへん(あへん法3条2号に規定するけしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。)は、同法第7条第1項((譲渡等の禁止))の規定により、国に対してでなければ譲渡することができず、また、けしがら(同法3条3号に規定するけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。)は、同条第2項((譲渡等の制限))の規定により、けし栽培者、麻薬製造者又は麻薬研究施設の設置者に対してでなければ、譲渡することができない。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律)
24 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社又は有限会社の株式又は持分については、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第1条((株式の譲渡制限等))及び第5条((有限会社の準用))の規定により、定款をもって定められた場合に限り、株式又は持分の譲受人を、その株式会社又は有限会社の事業に関係のある者に限ることができる。
(日本航空株式会社法)
25 日本航空株式会社法第2条第2項((株式の譲渡制限))の規定により、航空法第4条第1項各号((航空機登録の要件))に掲げる者が議決権の3分の1以上を占めることとならないようにするため、定款で定められた場合に限り、株式の譲受人を制限することができる。
(海上運送法)
26 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下26において「日本の国籍を有する者等」という。)が、その所有する船舶(海上運送法施行規則44条1項各号((譲渡等の許可を受けることを要しない船舶等))に定めるものを除く。)を日本の国籍を有する者等以外の者に譲渡しようとするときは、海上運送法第44条の2第1項((船舶の譲受けの許可))の規定により、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(漁港法)
27 漁港施設の譲渡については、漁港法第37条第1項((漁港施設の処分の制限))の規定により、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(銃砲刀剣類所持等取締法)
28 銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法2条1項((定義))に規定するけん銃、小銃、機関銃等をいう。)又は刀剣類(同法2条2項((定義))に規定する刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり等をいう。)の譲渡については、同法第21条の2((譲渡の制限))の規定による制限がある。
第90条関係 換価の制限
換価手続の制限
(未成熟の果実等の場合)
1 法第90条第1項及び第2項の規定により換価が制限されている場合には、その制限がされている間は公売公告以後の換価手続は行わないものとする。
(納付通知等の処分に関する訴訟係属中の場合)
2 法第90条第3項に規定する換価の制限に該当することとなった場合には、その換価の制限がされている間は公売公告以後の換価手続は行わないものとする。なお、公売公告後、買受代金の納付期限前に上記の換価の制限に該当することとなった場合においては、それが売却決定前であるときは売却決定を行わないものとし、売却決定後、買受代金の納付期限前であるときは買受代金を受領することができないものとする。
果実等の換価制限
(果 実)
3 法第90条第1項の「果実」とは、植物の果実をいい、いわゆる果物のほか、馬鈴しょ、落花生等の野菜類等をいう。
なお、不動産等と果実とを一体として換価する場合には、法第90条の規定は適用されない。
(成 熟)
4 法第90条第1項の「成熟」とは、通常の取引に適する状態になることをいう。
仕掛品等の換価制限
(生産工程中)
5 法第90条第2項の「生産工程中」とは、生産の作業が完成品となる前段階にあり、まだ作業が継続していることをいう。したがって、事業の休廃止等に係る仕掛品については、法第90条第2項の規定は適用されない。
(仕掛品)
6 法第90条第2項の「仕掛品」とは、一定時点において、製品、半製品、部分品の生産のために現に仕掛中又は加工中のものをいい、なお製造過程中にあって、製品又は半製品となる前段階にあり、まだ販売に適しないものをいう。
(栽培品等)
7 法第90条第2項の「その他これらに類するもの」とは、仕掛品に類するもの及び栽培品に類する稚魚、ひな等をいう。
(完成品)
8 法第90条第2項の「完成品」とは、その生産等の作業により通常の取引に適する状態になった物をいう。 (注) 完成品とならなくても、著しく低額にならない物(例えば、塗装だけが終わっていない机等)は換価することができる。
訴訟係属中の換価制限
(訴えの提起)
9 法第90条第3項の「訴えを提起したとき」とは、訴状が裁判所から税務署長に送達されたときをいうものとする(民事訴訟法229条参照)。
(訴訟の係属する間)
10 法第90条第3項の「訴訟の係属する間」とは、訴えの提起から裁判の確定までの期間をいい、適法な上訴(控訴又は上告)の期間中は「訴訟の係属する間」に含まれる(民事訴訟法229条、237条、498条参照)。
不服申立て中の換価制限
11 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合には、その国税の徴収のため差し押さえた財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、することができない(通則法105条1項)。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、10の「訴訟の係属する間」と同様に取り扱うものとする。
第91条関係 自動車等の換価前の占有
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車又は建設機械の評価、買受希望者の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
第92条関係 買受人の制限
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。 (1) 通則法第52条((担保の処分))の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法49条、92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局又は税務署に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判)。
第93条関係 修理等の処分
差押財産の修理等
(必要があると認めるとき)
1 法第93条の「必要があると認めるとき」とは、修理等の処分をしなければ買受けを希望する者がないと認められるとき、修理等の処分をすることによって滞納国税に充てるべき額が増加すると認められるとき等をいう。
(滞納者の同意)
2 法第93条の規定による修理等の処分をしようとするときの滞納者の同意は、書面により徴するものとする。この書面の様式は別に定めるところによる。
(修理その他その価額を増加する処分)
3 法第93条の「修理その他その価額を増加する処分」とは、差押財産の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等その処分の結果、その処分に要した費用の額以上にその価額が増加するものをいう。
(修理等の処分の費用)
4 修理等の処分の費用は、滞納処分費として滞納者から徴収する(法136条)。
第2款 公売
第94条関係 公売
公売の原則
1 法第94条第1項の「公売に付さなければならない」とは、差押財産を換価するときは、公売しなければならないことをいう。ただし、法第109条第1項((随意契約による売却))又は第110条((国による買入れ))の規定により、公売に代えて、随意契約による売却又は国による買入れができる場合がある。
公売の方法
(入 札)
2 法第94条第2項の「入札」とは、差押財産を換価しようとする場合において、その財産の買受けの申込者に、各自入札価額その他必要な事項を記載した入札書で買受けの申出をさせ、見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める方法をいう。
(入札の方法)
3 入札には、入札期日において、入札書を徴収職員に提出させた後、開札を行う方法(以下「入札」という。)と入札期間(第95条関係9参照)内に、入札書を徴収職員に提出させて、開札期日に開札を行う方法(以下「期間入札」という。)とがある。
(競り売り)
4 法第94条第2項の「せり売」とは、差押財産を換価しようとする場合において、その財産の買受けの申込者に、口頭等で順次高価な買受けの申出をさせ、見積価額以上の申込者のうち、最高の価額による申込者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める方法をいう。
(期間入札)
5 期間入札の手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、入札と同様である。
第95条 関係公売公告
公売公告の手続
(公売公告)
1 公売公告は、法第95条第1項各号に掲げる事項を記載した別に定める書面により行うものとする。
(公売公告の時期)
2 公売公告は、法第95条第1項の規定により、公売の日(期間入札の場合には、入札書を提出することができる始期の属する日)の前日を第1日として逆算し、10日目に当たる日の前日以前にしなければならない。
なお、上記の10日目に当たる日の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日に公告をするものとする。
(公売公告期間の短縮ができる場合)
3 税務署長は、公売財産が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、法第95条第1項本文の公売公告期間を短縮することができる(法95条1項ただし書)。ただし、法第99条第1項((見積価額の公告))の規定により見積価額の公告をしなければならないときは、その公告期間より短い公売公告期間とすることはできない。
(不相応の保存費)
4 法第95条第1項の「不相応の保存費を要し」とは、公売財産の価額と比べ多額の保存費を要することをいう。例えば、相当量のき損品、半製品等その価額が低廉なもので、これらのものを引き揚げて保管倉庫等に保管するとすれば相当の保存費を要するような場合及び生鮮食料品、腐敗変質するおそれがある化学薬品等で、特殊の保管設備を要し、このため相当高額の保存費を要するような場合がこれに当たる。
(価額を著しく減少するおそれがあるもの)
5 法第95条第1項の「価額を著しく減少するおそれがある」とは、公売財産を速やかに換価しないと、その価額が著しく減少するおそれがあることをいう。例えば、鮮魚、野菜等の生鮮食料品及びクリスマス用品等の季節用品等のようなものを公売する場合がこれに当たる。
(公告の継続)
6 法第95条第1項の公告は、公告をした日から公売する日まで掲示するものとする。したがつて、公告後掲示板等から公告に係る書類等がとれた場合には、速やかに掲示するものとするが、この場合においても、法第95条第1項の10日の期間計算は、通常、当初の公告の掲示日を基準として計算するものとする。
公告をすべき事項
(公売財産の名称等)
7 法第95条第1項第1号の「公売財産の名称、数量、性質及び所在」は、買受希望者が、公売財産を特定することができ、かつ、その現況を把握できる程度に記載する。したがって、例えば、建物につき登記簿上の表示と現況とに著しく差異のある場合には、登記簿上の表示のほか現況を併記する(昭和51.8.30名古屋高決、昭和55.8.6東京高決参照)。
(公売の方法)
8 法第95条第1項第2号の「公売の方法」とは、入札、期間入札又は競り売りの方法をいう(法94条2項)。
なお、入札又は期間入札の場合に、最高価申込者を決定するに際して複数落札入札制(法105条参照)によることとしたときは、その旨を公売公告に記載するものとする。
(公売の日時)
9 法第95条第1項第3号の「公売の日時」とは、入札及び期間入札については、入札書を提出することができる始期から終期までを、競り売りについては、競り売りを開始することができる始期をいう。
なお、期間入札による場合の入札書を提出することができる始期から終期まで(以下「入札期間」という。)については、7日以上で税務署長が相当と認める期間を定める。
(公売の場所)
10 法第95条第1項第3号の「公売の場所」とは、入札又は期間入札については、入札書を提出する場所を、競り売りについては、競り売りを行う場所をいう。
(売却決定の日時)
11 法第95条第1項第4号の「売却決定の日時」とは、売却決定をすることができる始期をいい、この売却決定には、次順位買受申込者に対する売却決定(法113条2項)が含まれる。
(買受代金の納付の期限)
12 法第95条第1項第6号の「買受代金の納付の期限」は、法第115条((買受代金の納付の期限等))の規定により税務署長が定めた期限である(第115条関係4、5参照)。 (注)1 次順位買受申込者に係る買受代金の納付の期限は、法第113条第2項に定める売却決定の日から起算して7目を経過した日となる(法115条1項かつこ書)。
2 法第115条第2項((買受代金の納付の期限の延長))の規定による期限の延長は、公売公告に記載しなければできないものとする。
(一定の資格を要する場合)
13 法第95条第1項第7号の「一定の資格を必要とするとき」とは、公売財産を買い受けるために、法令その他の規定により一定の資格を要する場合をいい、例えば、次に掲げる差押財産の公売については、次に掲げる資格を要することをいう。 (1) たばこ種子専売公社又は耕作者(たばこ専売法11条1項)
(2) たばこ苗専売公社又は耕作者(たばこ専売法12条1項)(耕作者に譲渡するときは、専売公社の許可を要する。同条4項)
(3) かん水塩の製造者(塩専売法1項。専売公社の許可を受けた場合は、塩の製造者以外の者でもよい。)
(4) 大麻(大麻取締法1条に規定する大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)を除く。)大麻取扱者(同法3条1項)
(5) 製造し、又は輸入した毒物(黄りん、ひ(砒)素等の毒物及び劇物取締法別表第1に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)又は劇物(塩酸、硝酸等の同法別表第2に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(同法3条参照)
(6) 覚せい剤(覚せい剤取締法2条に掲げるフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン等をいう。)覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者(同法17条1項)
(7) 麻薬(コカ葉、モルヒネ等の麻薬取締法別表に掲げるものをいう。)麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同法26条1項)
(8) けしがら(あへん法3条に規定するけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。)けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者(同法7条2項)
(その他の要件を要する場合)
14 法第95条第1項第7号の「その他の要件を必要とするとき」とは、公売財産の買受けのために関係官庁の承認、許可を要する場合をいう。例えば、農地又は採草放牧地を公売する場合における当該財産の買受けの申込みをしようとする者は、農業委員会、都道府県知事又は農林水産大臣の買受適格証明書の交付を受けなければならない場合をいう。
(配当を受ける権利者)
15 法第95条第1項第8号の「その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者」とは、法第129条((配当の原則))の規定により、交付要求(参加差押えを含む。)をした者、法第59条第1項後段、第3項又は第4項((損害賠償請求権等への配当))(これらの規定を法71条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権を有する者をいう。
(権利の内容)
16 法第95条第1項第8号の「その内容」とは、債権の元本、利息、弁済期限その他の権利の内容をいい、おおむね、債権現在額申立書(第130条関係1)に記載すべき事項をいう。
(重要と認める事項)
17 法第95条第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項」とは、次に掲げる事項をいうものとする。 (1) 買受人が公売財産の所有権を取得する時期が、法第116条((買受代金の納付の効果))に規定するものと異なる場合は、その事項(鉱業法60条、特許法98条1項、実用新案法26条、意匠法36条)
(2) 公売財産の所有権の移転につき農地法その他法令の規定により関係官庁等の許可、承認等を必要とする場合は、その旨(農地法3条、漁業法26条、公衆電気通信法38条1項等)
(3) 買受人に対抗することができる公売財産上の負担がある場合は、その負担(法124条2項等)
(4) 公売財産の権利の移転について登記を要するものについては、買受代金を納付するほか、一定の期間内に登録免許税額に相当する印紙若しくは現金の領収証書を提出すべき旨(登録免許税法23条)、また、自ら権利移転の手続を行う必要がある場合は、その旨
(5) 開札の日時及び場所
(6) 一括換価の方法により公売する場合は、その旨
(7) 期間入札の方法により公売する場合は、その旨及び期間入札に関し重要と認められる事項
(8) 建物等(土地及びその上にある建物又は立木をいう。以下同じ。)の公売によって、その建物等につき法定地上権(法127条1項、民法388条、立木法5条等)又は法定賃借権(法127条2項)が成立する場合は、その旨
(9) その他、例えば、公売財産の権利移転に伴う危険負担の時期等公売に関して重要と認められる事項
公売公告の掲示等
(税務署の掲示場)
18 法第95条第2項の「税務署の掲示場」とは、公売をする税務署の掲示場をいい、常設公売場の掲示場も含まれる。
(その他の掲示場)
19 法第95条第2項の「その他税務署内の公衆の見やすい場所」とは、税務署内において公衆が自由に出入りでき、かつ、公衆の見やすい場所をいう。
(適当な場所)
20 法第95条第2項の「他の適当な場所」とは、公売財産の所在する市町村の役場の掲示場、その他公売財産につき買受けを希望すると認められる者が集合する場所等公売することを公衆に知らせるのに適当と税務署長が認める場所をいう。
(その他の方法)
21 法第95条第2項の「その他の方法」とは、公売財産につき買受けを希望すると思われる者に知らせるのに適する業界新聞に掲載すること、買受けを希望すると思われる者に勧誘書を送付すること等買受希望者を募るのに適した方法をいう。
第96条関係 公売の通知
質権者等に対する公売の通知
(公売通知書の送違)
1 税務署長は、公売公告をしたときは、法第95条第1項各号(8号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を次に掲げる者に通知しなければならない(法96条1項)。この通知は、別に定める書面により行うものとする。 (1) 滞納者
(2) 公売財産につき交付要求をした者
(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者
(公売に係る国税の額)
2 法第96条第1項の「公売に係る国税の額」とは、公売公告に係る公売財産につき、公売処分の基因となっている国税の額をいう。
(知れている者)
3 法第96条第1項第1号の公売財産につさ交付要求をした者及び第2号の質権等の権利を有する者のうち徴収職員が公売の通知をするに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対しては、公売の通知をしなければならない。
(質権、抵当権、先取特権)
4 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(その他の権利)
5 法第96条第1項第2号の「その他の権利」とは、永小作権、地役権、採石権、仮登記(担保のための仮登記を含む。)に係る権利、法第59条第1項後段若しくは第3項又は第4項((第三者の損害賠償請求権等への配当))(これらの規定を法71条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は前払借賃に係る債権等をいう。 (注)1 法第19条及び第20条((不動産保存の先取特権等の優先等))に規定する先取特権以外の先取特権者は、「その他の権利」を有する者に含まれる。
2 仮差押えの債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする(滞調法逐条通達第11条関係1の(1)等参照)。
3 不動産の使用若しくは収益をする権利の移転又は担保権の移転についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(保全法53条1項)がされている場合において、当該不動産につき公売公告をしたときは、当該仮処分の債権者に対しても法第96条の通知をするものとする。また、不動産に関する権利以外の権利でその権利の処分の制限について登記又は登録を効力発生要件又は対抗要件とするもの(保全法54条)についても同様とする。
4 滞調法の規定による二重差押えに係る差押債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする。
5 動産の共有に係る持分を公売する場合は、他の共有者に対しても、公売の通知をするものとする。
(差押えに対抗できない権利者)
6 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者」には、差押債権者に対抗できないこれらの権利を有する者は含まれない。
債権現在額申立書の提出の催告
(催告すべき者)
7 法第96条第2項の規定により催告しなければならない者は、法第96条第1項各号に掲げる者で、かつ、法第129条第1項第2号から第4号((配当すべき債権))までに掲げる債権を有する者のうち知れている者に限られる(第95条関係15参照)。
(売却決定をする日)
8 法第96条第2項の「売却決定をする日」とは、法第111条((動産等の売却決定))又は第113条((不動産等の売却決定))の規定による売却決定をする日をいう。 (注) 売却決定をする日の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条6号)。
第97条関係 公売の場所
公売をする場所
(公売財産の所在する市町村)
1 法第97条の「公売財産の所在する市町村」とは、公売財産が現に所在する市町村をいう。したがって、公売財産を公売するために税務署等(常設公売場、合同公売場等を含む。以下1において同じ。)に搬入した場合の「公売財産の所在する市町村」とは、税務署等の所在する市町村をいう。
(必要と認めるとき)
2 法第97条の「必要と認めるとき」とは、例えば、公売財産の運搬が困難である場合において、その所在する市町村では適当な買受人が求められないようなとき等公売財産をその所在する市町村で公売することが不適当であると税務署長が認めるときをいう。
第98条関係 見積価額の決定
見積価額の意義
1 法第98条の「見積価額」とは、財産の公売に際し、税務署長が公売財産の客観的な時価を基準とし、公売の特殊性を考慮して見積った価額をいい、公売財産の最低公売価額としての意義を有する(法104条1項参照)。
鑑定人による評価
(必要と認めるとき)
2 法第98条の「必要と認めるとき」とは、公売財産が不動産、船舶、鉱業権、骨とう品、貴金属、特殊機械等である場合において、その価額が高価又は評価困難と認められるとき、公売財産の見積価額について紛争を生ずるおそれがあると認められるとき等税務署長が鑑定人に評価させることが適当であると認めるときをいう。
(鑑定人の評価と見積価額の決定との関係)
3 法第98条の「その評価額を参考とすることができる」とは、単純に、鑑定人の評価額をもって見積価額とすることなく、税務署長が、その評価額を参考として見積価額を決定することをいう。
第99条関係 見積価額の公告等
見積価額の公告
1 税務署長は、法第99条第1項各号に掲げる財産を公売に付するときは、それぞれ同項各号に掲げる日までに、見積価額を公告しなければならない(法99条1項、3項本文、95条2項)。ただし、公売財産が動産である場合には、その財産に見積価額を記載した用紙をちよう付して、この公告に代えることができる(法99条3項ただし書)。これらの見積価額の公告の方法については、別に定めるところによる。
見積価額の公告の時期
(3日前の日)
2 法第99条第1項第1号の規定による見積価額の公告は、公売の日の前日を第1日として逆算して3日前に当たる日の前日以前にしなければならない。
なお、上記の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日に公告する取扱いとする。
(前日等)
3 法第99条第1項第2号及び第3号の「公売の日の前日」までに公告しなければならないとは、公売の日の前日に当たる日のうちには、公告しなければならないことをいい、また、第2号の「公売の日」までに公告しなければならないとは、公売する時前までに公告しなければならないことをいい、これらの日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条5号)。
(期間入札による場合)
4 期間入札の方法により公売を行う場合における法第99条第1項に規定する「公売の日」は、入札期間の始期の属する日をいう。
見積価額の公告の方法
5 見積価額の公告は、公売公告と併せて行っても差し支えないものとする。
不動産等についての賃借権等の公告
(公告すべき事項)
6 法第99条第4項の「その存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容」とは、公売により財産を買い受けようとする者がその財産を評価するに当たって重要と認められる事項とし、前払いの借賃若しくは地代又は敷金があるときは、これらに関する事項を含むものとする。
(公売公告との関係)
7 法第99条第4項の規定により公告すべき事項を公売公告と同時に公告した後見積価額の公告をする場合には、重ねて、法第99条第4項の規定による公告をする必要はないものとする。
見積価額を公告しない場合
(公売をする場所)
8 法第99条第2項の「公売をする場所」とは、入札をする場所であって、入札者が、見積価額を記載した書面の入っている封筒の状況を見ることができる場所をいう。
(開札後の非公開)
9 見積価額を公告しない場合には、開札後であっても、見積価額を公開しないものとする。
第100条関係 公売保証金
公売保証金の納付に使用できる小切手
(小切手)
1 法第100条第1項の「国税の納付に使用することができる小切手」とは、証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律に基づき租税及び歳入の納付に使用できる証券のうちの小切手をいうが、このうち呈示期間の満了までに5日以上の期間のないものは、受領を拒否することができるものとする(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件1条2項、執行規則40条1項2号、3号参照)。
(銀 行)
2 法第100条第1項の「銀行」とは、銀行法に基づく銀行をいうが、相互銀行、信用金庫及び郵便局を含むものとして取り扱う。
(銀行振出のもの)
3 法第100条第1項の「銀行の振出に係るもの」とは、銀行が振り出した小切手で、その銀行にあてたもの(いわゆる預金小切手)をいう。
(支払保証のあるもの)
4 法第100条第1項の「その支払保証のあるもの」とは、小切手法第53条(支払保証の方式)の規定により、支払人である銀行が支払保証をしたものをいう。
公売保証金の買受代金への充当
5 公売保証金を買受代金へ充てるのは、買受人の意思表示によるが(法100条3項本文)、その充てた場合における買受代金への納付の効果は、買受代金のうち、買受代金へ充てた公売保証金を控除した額の全額の納付があった時に生ずるものとする。
公売保証金の国税への充当等
(充てる場合)
6 法第100条第3項ただし書の規定により、公売保証金を公売に係る国税に充てることができるのは、その公売財産の買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないために、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定によって売却決定が取り消された場合である。
なお、法第108条第2項((最高価申込者とする決定等の取消し))の規定により最高価申込者とする決定の取消し等の処分ができる場合には(同条1項4号参照)、法第100条第3項ただし書の規定を適用しないものとする(第108条関係24参照)。
(公売に係る国税)
7 法第100条第3項ただし書の「公売に係る国税」とは、公売保証金の納付を受けた公売処分の執行の基礎となった国税をいい、交付要求に係る国税等へは充てることができない。
(残余金を交付すべき者)
8 法第100条第3項ただし書の「滞納者」とは、公売の基因となった国税を滞納していた者(譲渡担保権者及び物上保証人を含む。)であって、公売財産の差押え時における権利者をいう。
(滞納者への通知)
9 法第100条第3項ただし書の規定により公売保証金を国税へ充てた場合及びその残余を滞納者に交付すべき場合には、その旨を滞納者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
公売保証金の返還
(法第105条第2項との関係)
10 法第105条第2項((複数落札入札において入札がなかったものとされる場合))の規定により入札がなかったものとされた場合において、入札がなかったものとされた者が納付した公売保証金があるときは、入札がなかったものとされた入札数量に相当するその公売保証金について、法第100条第4項第1号に該当したときの公売保証金と同様に取り扱う。
(その他の理由により最高価申込者を定めることができなかった場合)
11 法第100条第4項第2号の「その他の理由により最高価申込者を定めることができなかった場合」には、例えば、換価制限に関する規定(法90条3項、通則法105条1項ただし書等)に該当し、公売をとりやめた場合、災害その他やむを得ない事情により公売財産の入札等(公売財産の入札又は競り売りに係る買受けの申込みをいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「入札者等」という。)の全員について入札等がなかった場合等がある。
(法第108条第3項との関係)
12 法第108条第3項((公売保証金の国庫帰属))の規定によって公売保証金が国庫に帰属する場合には、法第100条第4項の規定は適用されず(法108条3項後段、第108条関係23)、したがって、公売保証金は返還しない。
(法第117条との関係)
13 換価財産に係る国税が完納され、最高価申込者の決定を取り消した場合(第104条関係6)には、最高価申込者が納付した公売保証金は、遅滞なく返還する(法100条4項5号参照)。
第101条関係 入札及び開札
入札書の提出
(入札書の記載)
1 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項(例えば、種類、員数、売却区分等)を入札書に記載しなければならない(法101条1項)。入札書の様式については、別に定めるところによる。
(期間入札による場合)
2 期間入札による場合の入札書の提出は、入札書を開札の日時を記載した封筒に入れて封をし、これを徴収職員に提出する方法により行う。
(提 出)
3 入札をしようとする者は、税務署長が指定した時間内又は入札期間内に、入札書を徴収職員に提出しなければならない(法101条1項参照)。
(二重入札)
4 入札をしようとする者が、一つの公売財産について複数の入札書を提出した場合には、いずれの入札書も無効なものとする。
入札書の引換え等の禁止
(引換え)
5 法第101条第2項の「引換」とは、入札者が既に徴収職員に差し出した入札書と引換えに、新たな入札書を差し出すことをいう。
(変 更)
6 法第101条第2項の「変更」とは、入札価額又は入札者名を変更する等既に徴収職員に差し出した入札書の記載事項の全部又は一部を改変することをいう。
(取消し)
7 法第101条第2項の「取消」とは、既に徴収職員に差し出した入札書による入札を取り消す旨の意思を表示することをいう。
開札及び立会い
(開 札)
8 徴収職員は、入札書の提出を締め切った後、公売公告に記載した開札の場所及び日時において入札書を開かなければならない。
(立会い)
9 徴収職員は、次により立会人を置き、その面前で開札を行わなければならない(法101条3項参照)。 (1) 開札の場所に入札者がいるときは、その1人以上の入札者
(2) 開札の場所に入札者がいないとき又は立会いに応じないときは、税務署所属の他の職員
第102条関係 再度入札
再度入札
(再度入札ができる場合)
1 再度入札ができる場合は、入札の方法により公売財産を公売する場合において、入札者がないとき又は見積価額に達した入札価額の入札がないときに限る(法102条前段)。
なお、法第108条第2項((公売実施の適正化のための措置))の規定により、入札がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条((入札又は競り売りの終了の告知等))の規定による入札終了の告知をしている場合を除き、再度入札ができる。
(公売保証金との関係)
2 再度入札の場合においては、先に納付した公売保証金を再度入札の公売保証金とするものとする。
なお、再度入札に参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に納付した公売保証金を払い渡さなければならない(法100条4項2号)。
第103条関係 競り売り
競り売りの方法
(買受申込みの催告)
1 徴収職員は、競り売りをしようとするときは、公売をしようとする財産を指定して、買受けの申込みを催告し、順次申込価額を競り上げさせるよう促すものとする(法103条1項参照)。
(買受けの申込みをした者)
2 買受けの申込みをした者は、より高額の買受けの申込みがあるまで、その申込価額に拘束される(執行規則50条2項参照)。
(競り売り人を選任した場合)
3 法第103条第2項の規定により競り売り人に競り売りをさせる場合においても、徴収職員が必ず競り売りの場所に立ち会うものとする。 (注) 競り売り人を選任して競り売りを取り扱わせた場合においても、徴収職員が最高価申込者を決定しなければならない(法104条1項)。
再度競り売り
(再度競り売りができる場合)
4 再度競り売りができる場合は、競り売りの方法により差押財産を公売する場合において、買受申込者がないときに限る(法103条3項、法102条)。
なお、法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定により、入札等がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定による競り売りの終了の告知をしている場合を除き、再度競り売りができる。
(公売保証金との関係)
5 再度競り売りの場合においては、先に納付した公売保証金を再度競り売りの公売保証金とするものとする。
なお、再度競り売りに参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に納付した公売保証金を払い渡さなければならない(法100条4項2号)。
第104条関係 最高価申込者の決定
最高価申込者の決定
(売却区分ごとの決定)
1 最高価申込者は、公売財産の売却区分ごとに決定する。したがって、一括入札を売却条件とした場合には、一括入札価額により最高価申込者を決定し、個別売却とした場合には、個別の入札価額により最高価申込者を決定する。 (注) 競り売りの場合において、買受申込価額が最高であるかどうかの決定は、順次買受申込価額を競り上げ、最後の最高価額を3回呼び上げて、それ以上の高価の買受申込みのない場合に、その価額を最高の価額とするものとする(執行規則50条3項参照)。
(決定の条件)
2 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、最高価申込者とする決定をしないものとする(法104条1項参照)。 (1) 最高価申込者とする決定をしようとする者の入札価額又は買受申込価額が見積価額以上であり、かつ、最高の価額であること。
(2) 公売保証金を納付させる場合においては、所定の公売保証金を納付していること。
(3) 法第92条((買受人の制限))又は第108条((公売実施の適正化のための措置))等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。
(4) 法第95条第1項第7号((公売公告の記載事項))の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
追加入札等
(追加入札等をする場合)
3 開札又は競り売りの結果、最高価申込者となるべき者が2人以上あるときは、更に入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下第104条関係において「追加入札等」という。)をさせなければならない(法104条2項)。この場合の追加入札等の申込価額は、その追加入札等の基因となった入札等の価額以上でなければならない。
(法第108条との関係)
4 追加入札等をすべき者が追加入札等をしなかった場合又はその追加入札等の基因となった入札等の価額に満たない価額で追加入札等をした場合は、法第108条((公売実施の適正化のための措置))の規定が適用されることがある。
(くじによる決定)
5 追加入札等の結果、なおその追加入札等の価額が同額の場合は、抽せんにより当せんした者を最高価申込者として決定する(法104条2項)。この場合における抽せんは、これらの者が直接抽せんをすることができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法(例えば、宝くじの抽せん方法類似のもの)により抽せんを行うものとする。
国税の完納による最高価申込者の決定の取消し
6 公売財産に係る国税の完納の事実が、最高価申込者の決定後、売却決定までの間に確認されたときは、その最高価申込者の決定を取り消すものとする。
第104条の2関係 次順位買受申込者の決定
公売保証金の不徴収との関係
1 公売保証金の納付を要しないこととして公売する場合(法100条1項ただし書)には、最高の価額の入札者が2人以上あり、くじで最高価申込者を定めた場合に限り次順位買受申込者制度が適用される。
次順位による買受けの申込み
(申込みの催告)
2 最高価申込者の決定をした場合には、徴収職員は、最高入札価額に次く高い価額による入札者に対し、次順位による買受けの申込みの催告をするものとする。
(申込みの方法)
3 次順位による買受けの申込みは、既に徴収職員に提出している入札書の余白に、その旨を明らかにさせる方法により行わせる。
なお、この申込みは、2の申込みの催告前にすることはできない。
次順位買受申込者の決定
(決定の条件)
4 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、次順位買受申込者として決定をしないものとする(法104条の2第1項参照)。 (1) 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。)であること。
(2) 公売保証金を納付させる場合においては、所定の公売保証金を納付していること。
(3) 法第92条((買受人の制限))又は第108条((公売実施の適正化のための措置))等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。
(4) 法第95条第1項第7号((公売公告の記載事項))の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
(くじによる決定)
5 最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2人以上あり、これらの者から次順位による買受けの申込みがある場合は、抽せんにより当せんした者を次順位買受申込者として決定する(法104条の2第3項)。これらの場合における抽せんは、これらの者が直接抽せんすることができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法(例えば、宝くじの抽せん方法類似のもの)により抽せんを行うものとする。
第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
複数落札入札制
(意 義)
1 種類及び価額が同じ財産(例えば、同一銘柄、同一規格の商品又は同一銘柄の証券、社債等の有価証券)を一時に多量に入札の方法により公売する場合においては、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる(法105条1項前段)。
(最高価申込者の決定方法)
2 複数落札入札制による最高価申込者の決定は、次による。 (1) 入札は、公売財産の数量の範囲内において、入札しようとする者の希望する買受数量及び単価を入札書に記載して行わせる(法105条1項前段)。
(2) 見積価額は、単価について定める(法105条1項前段、106条1項参照)。
(3) 最高価申込者の決定は、見積価額以上の価額の入札者のうち、高額の入札者から順次にその財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とすることにより行う(法105条1項前段)。
(4) (3)により最高価申込者を決定する場合において、同価の入札者が2人以上あったときは、入札数量の多い者を先順位の入札者とし、また入札数量が同量であったときはくじにより先順位の入札者を定める(法105条1項後段)。
(5) (3)により最高価申込者を決定する場合において、最後の順位の最高価申込者の入札数量が他の最高価申込者の数量と併せて公売財産の数量を超えるときは、その超える入札数量については入札がなかったものとする(法105条2項)。
(6) 最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内で、(5)により入札がなかったものとされた入札数量について入札があったものとする。この場合において、買受代金を納付しない買受人に(5)により入札がなかったものとされた入札数量があるときは、その入札数量は除かれる(法105条3項前段)。
(7) (6)によって最高価申込者を決定しても、なお公売財産に残余を生ずるときは、(4)により最高価申込者とならなかった者を最高価申込者とする(法105条3項前段)。
(8) (7)により最高価申込者の決定をする場合において、(4)により最高価申込者とならなかった者が2人以上あるときは、(4)に準じてその順位を決定する(法105条3項後段)。
(9) (8)により最高価申込者を決定する場合において、最後の順位の最高価申込者の入札数量が他の最高価申込者の数量と併せて公売財産の数量を超えるときは、(5)に準ずる(法105条3項後段)。
公売保証金との関係
3 2の(4)から(9)までに掲げる場合において入札数量の一部についてだけ入札があったものとされた者は、数量の不足を理由として、買受けの申込みを取り消すことはできない(第100条関係10参照)。
第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
入札又は競り売りの終了の告知
(氏名及び価額の呼び上げ)
1 最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を決定したときは、直ちにその氏名及び入札等の価額を呼び上げなければならない。ただし、複数落札入札制による場合には、最高価申込者のすべての氏名並びにその数量及び単価を呼び上げなければならない(法106条1項)。
(終了の告知)
2 徴収職員は、1の呼び上げ後、入札又は競り売りの終了を、口頭又は掲示等により、告知しなければならない(法106条1項)。この場合において、口頭による告知は、その入札又は競り売りを終了する旨を発言する程度で足りる(法106条1項)。
終了の通知及び公告
(通知及び公告)
3 入札又は競り売りの終了を告知した場合において、公売した財産が不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)であるときは、税務署長は、遅滞なく、最高価申込者等の氏名、その価額(複数落札入札制による場合は、その数量及び単価)並びに売却決定をする日時(法113条2項に定める日時を含む。)及び場所を、滞納者及び法第96条第1項各号((公売の通知))に掲げる者(以下「利害関係人」という。)で知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない(法106条2項)。この通知及び公告は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(通知の相手方)
4 法第106条第2項の通知は、次に掲げるすべての者に対してしなければならない(法106条2項)。 (1) 滞納者
(2) 公売財産につき交付要求をした者
(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者
(公告の期間)
5 法第106条第2項の公告の期間は、法第113条((不動産等の売却決定))に規定する売却決定期日までとするものとする。
第107条関係 再公売
再公売ができる場合
1 税務署長は、次のいずれか一つに該当する場合においては、同一の財産を更に公売に付する(法107条1項参照)。 (1) 公売に付しても入札者等がないとき。
(2) 入札等の価額のうち見積価額に達するものがないとき。
(3) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第108条第2項((公売実施の適正化のための措置))の規定により、入札等がなかったものとされ、又は最高価申込者とする決定が取り消されたことによって、売却決定を取り消したとき。
(4) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定により、売却決定を取り消したとき。
(5) 次順位買受申込者に対して売却決定をした場合において、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定により、売却決定を取り消したとき。
再公売の手続
(その他の公売条件の変更)
2 法第107条第2項の「その他公売の条件の変更」とは、公売の場所、公売の方法、売却区分、公売保証金の額等につき、公売財産の状況等に応じて、直前の公売における売却条件を変更することをいう。
(期間入札による場合)
3 期間入札の方法により公売を行った場合における法第107条第3項の「公売期日」は、入札期間の始期の属する日をいう。
(見積価額の公告期間の短縮)
4 再公売に付する場合において、公売財産が、不動産、船舶又は航空機である場合は、公売の日の前日までに見積価額を公告する(法107条4項)。
なお、上記の場合における「公売の日の前日」は、第99条関係3と同様である。
第108条関係 公売実施の適正化のための措置
公売参加の制限を受ける者
(制限を受ける者の範囲)
1 法第108条第1項の規定により公売への参加を制限させる者は、次に掲げる者である。 (1) 法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者
(2) 法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を、使用人その他の従業者として使用する者。この場合における「使用人その他の従業者」とは、事務員、工員、よう人その他雇用契約等に基づき従業している者をいう。
(3) (1)及び(2)に掲げる者を、入札等の代理人とする者
(公売への参加を妨げた者)
2 法第108条第1項第1号の「公売への参加を妨げた者」とは、公売が中止又は延期されたと偽り他の者をして公売に参加させなかった者、公売に参加すれば暴行を加えると脅迫した者、公売の場所への入場を威力をもって妨げた者等をいう。この場合においては、妨害の結果として、妨害を受けた者が公売に参加したかどうかを問わない。
(入札等を妨げた者)
3 法第108条第1項第1号の「入札等を妨げた者」とは、入札に当たって入札書の記載を妨げた者、大声を発して競り売りについての買受けの申込みを妨げた者等をいう。
(最高価申込者等の決定を妨げた者)
4 法第108条第1項第1号の「最高価申込者等の決定を妨げた者」とは、徴収職員に暴行を加えて最高価申込者等の決定を妨げた者、最高価申込者等を定めるための「くじ」(法104条2項、104条の2第3項、105条1項後段、同条3項参照)を引く者を脅迫して「くじ」に参加させなかった者等をいう。
(買受代金の納付を妨げた者)
5 法第108条第1項第1号の「買受代金の納付を妨げた者」とは、買受代金を納付すれば暴行を加えると脅迫した者、買受代金を納付することが極めて不利益であると欺いた者等をいう。
(不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者)
6 法第108条第1項第2号の「不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者」とは、公売に際し、価額を引き下げるため、競争による公正な価額の形成を妨げる意思をもって、入札等を行う者相互間で、ある価額以上の入札を行わず、ある特定の者に低額で買い受けさせるように合意約定した者をいう。
なお、上記の場合においては、利益の一部に相当する金額を配分することが多いと考えられるが、その合意約定について利益配分の目的がないとき及び現実の入札等がなく単に合意約定したにとどまるときにおいても、上記に該当する。
(偽りの名義で買受申込みをした者)
7 法第108条第1項第3号の「偽りの名義で買受申込みをした者」には、架空の人物の名義を用いた者だけではなく、実在する他の人物の名義を勝手に用いて、買受申込みをした者も含まれる。
(正当な理由)
8 法第108条第1項第4号の「正当な理由」とは、換価処分を妨げる意思又は換価処分を妨げる結果となることを知りながら故意に買受代金を納付しないこと以外の理由をいう。
(故意に財産を損傷した者)
9 法第108条第1項第5号の「故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者」とは、公売財産の価額を減少させる意思をもって、財産の形状、性質等をそこなった者はもちろん、その結果を生ずることを知りながら財産を損傷して価額を減少させた者をいい、過失によって公売財産を損傷し、その価額を減少させた者は含まれない。
(公売等の実施を妨げる行為をした者)
10 法第108条第1項第6号の「公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者」とは、法第108条第1項第1号から第5号に該当する者以外の者であって、公売又は随意契約による売却手続が、公正かつ円滑に行われることを妨げた者をいい、例えば、暴力をもって開札を妨げた者、随意契約により買い受けることは不利益であると欺いた者等をいう。
公売への参加制限
(制限の内容)
11 法第108条第1項の規定による公売への参加制限は、公売の場所へ入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことによって行うが、この場合における「公売の場所」とは、入札又は競り売りを実施するための場所、公売財産のある場所等上記の制限をしなければ、公売手続の公正かつ円滑な執行が害される場所をいう。
(制限できる期間)
12 法第108条第1項の規定により公売への参加を制限できる期間は、法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実のあった時から2年間である。
(参加を制限する公売)
13 法第108条第1項の規定による公売への参加制限については、法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があったときの公売の後に行われる公売への参加制限はもちろん、その事実があったときの公売のその後の手続への参加も制限することができる。
(入札者等の身分の証明)
14 税務署長は、法第108条第1項の規定による公売への参加制限をするために必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる(法108条4項)。
(刑罰法規との関係)
15 法第108条第1項各号に掲げる者については、刑法第96条ノ3第1項((競売入札妨害))、同条第2項((談合行為))等の刑罰法規による処罰の有無にかかわらず、公売への参加を制限することができる。
最高価申込者の決定の取消し等
(第1項に該当する者)
16 法第108条第2項の「前項の規定に該当する者」とは、法第108条第1項の規定により税務署長が公売への参加制限ができる者をいい、法第108条第1項の規定によって公売への参加を制限したかどうかは関係がない。
(入札者等への通知)
17 税務署長が、法第108条第2項の規定により「入札等がなかったものとする」場合には、その入札者等に対して、原則として、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(最高価申込者等の決定の取消し)
18 法第108条第2項の「その決定を取り消す」とは、最高価申込者等が16に掲げる者である場合には、その最高価申込者等とする決定を取り消すことをいう。この場合においては、19により売却決定を取り消したときを除き、最高価申込者等及び利害関係人(滞納者を含む。)に対してその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(売却決定の取消し)
19 売却決定後において、法第108条第2項の規定により最高価申込者等とする決定を取り消すときは、その売却決定も取り消すものとする。この場合においては、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
公売保証金の国庫帰属
(入札等がなかったものとされた者等)
20 法第108条第3項の「同項の処分を受けた者」とは、法第108条第2項の規定によって入札等がなかったものとされ、又は最高価申込者とする決定を取り消された者をいう。
(国庫に帰属する公売保証金)
21 法第108条第3項の「その公売保証金」とは、20に掲げた者の納付した公売保証金をいうが、法第100条第3項又は第4項((公売保証金の買受代金への充当等))の規定によって公売保証金が既に買受代金納付としての効果を生じているとき(第100条関係5参照)、買受人へ交付されているとき等は、法第108条第3項の規定により国庫に帰属すべき公売保証金はないものとする。
(国庫への帰属)
22 法第108条第3項の「国庫に帰属する」とは、同条第2項の規定によって入札等をなかったものとし、又は最高価申込者等とする決定を取り消した場合には、その処分をした時に、当然に公売保証金が国庫に帰属することをいう。
なお、17から19までに定める通知に当たっては、上記の旨を、併せて通知するものとする。
(法第100条第4項との関係)
23 法第108条第3項の「第100条第4項(公売保証金の返還)の規定は、適用しない」とは、法第108条第3項の規定により公売保証金が国庫に帰属する場合には、法第100条第4項の規定による公売保証金の返還をしないことを明らかにしたものである。
(法第100条第3項との関係)
24 法第108条第1項第4号に該当する者(正当な理由がなく買受代金を納付しない者)の公売保証金が、法第108条第3項の規定により国庫に帰属する場合においては、法第100条第3項ただし書((公売保証金の国税への充当等))の規定により公売保証金を国税へ充てること又はその残余を滞納者に交付することは、行わないものとする(第100条関係6参照)。
第3款 随意契約による売却
第109条関係 随意契約による売却
随意契約の意義
1 法第109条の「随意契約」とは、差押財産の換価に当たり、入札又は競り売りの方法によることなく、税務署長が、買受人及び価額を決定して売却する契約をいう。
随意契約により売却できる場合
(買受人の適格を有する者が1人であるとき)
2 法第109条第1項第1号の「法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人であるとき」とは、たばこ専売法第18条第1項((納付))の規定により耕作者の収穫した葉たばこをすべて専売公社に対して納付しなければならないとされているとき等をいう。
(財産の最高価額が定められているとき)
3 法第109条1項第1号の「その財産の最高価額が定められている場合」とは、物価統制令等の規定に基づいて財産の最高価額が定められている場合をいう。
なお、最高価額が定められている財産を、その価額未満の価額で売却するときは、法第109条第1項第1号には該当しない。
(公益上適当でないと認められるとき)
4 法第109条第1項第1号の「その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき」とは、例えば、次に掲げる場合をいう。 (1) 麻薬取締法等の法令の規定により譲渡の相手方が制限されている場合において、その法令の規定により、譲受けが認められている者に対してその財産を譲渡しようとするとき。
(2) 土地収用法、都市計画法等の規定に基づいて土地を収用できる者から、差し押さえた土地を買い受けたい旨の申出があったとき(大正9.7.23大判、昭和26.10.24高知地判参照)。
(3) 公売財産が私有道路、公園、排水溝、下水処理槽等である場合において、その利用者又は地方公共団体等から、その私有道路等を買い受けたい旨の申出があったとき。
(取引所の相場がある財産)
5 法第109条第1項第2号の「取引所の相場がある財産」とは、証券取引所又は商品取引所における相場のある財産、例えば、株券、社債券、生糸、ゴム、金等(証券取引法2条1項、商品取引所法2条2項、同法施行令1条)をいう。
売却する場合の通知等
(売却の通知)
6 随意契約による売却をする場合には、7の場合を除き、売却をする日の7日前までに、法第96条((公売の通知))に準ずる通知書を発しなければならないが(法109条4項)、この通知等については、第96条関係で定めるところに準ずる。 (注) 上記の「7日前までに通知書を発しなければならない」とは、売却する日の前日を第1日として7日目に当たる日の前日以前に通知書を発しなければならないことをいう。
なお、上記の「7日目に当たる日の前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日にする取扱いとする。
(通知をしない場合)
7 随意契約による売却をする場合において、その売却の期日が、直前の公売期日又は直前の随意契約による売却の期日から10日以内であるときは、6の通知等をする必要がない(法109条4項、107条3項)。この場合の10日は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。
売却の場所
8 随意契約による売却を行う場所については、法第97条((公売の場所))に準ずるものとする。
見積価額
(見積価額を決定する場合)
9 随意契約により売却する財産については、次に掲げる場合を除き、その財産の見積価額を決定しなければならない(法109条2項前段、98条)。 (1) 最高価額が定められている財産をその価額で売却するとき(3参照)。
(2) 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき(5参照)。
(直前の公売の見積価額との関係)
10 法第109条第1項第3号((公売に付しても入札等がなかった場合等))該当として随意契約により売却する場合における財産の見積価額は、その売却の直前の公売における見積価額と同額又はそれを超える額てなければならない(法109条2項後段)。
(見積価額の決定)
11 随意契約により売却する財産の見積価額の決定については、10の制約があるほか、第98条関係で定めるところに準ずる。 (注) 上記により決定した見積価額は、公告をしなければならないものではない。
公売保証金の不必要
12 差押財産を随意契約により売却する場合には、その売却手続に参加するための公売保証金を納付させることはできない。
あらかじめ公告した価額による売却
13 法第109条第1項第3号((公売に付しても入札等がなかった場合等))該当として随意契約により売却する場合において、その財産が動産であるときは、その売却価額(見積価額以上の額で、売却しようとする価額)をあらかじめ公告し、その価額によって売却(随意契約による売却)することができる(法109条3項)。この場合における公告については、法第99条第3項ただし書((見積価額の公告の特例))の規定の適用があるものとする。
買受人となるべき者の決定の通知及び公告
14 随意契約による売却について、買受人となるべき者を定めた場合には、法第106条第2項及び第3項((最高価申込者等を決定した場合の利害関係人に対する通知及び公告))の規定が準用されるから(法109条4項)、この通知及び公告については、第106条関係3から5までに準ずる。
第110条関係 国による買入れ
農地法等との関係
1 国が農地法第34条((公売の特例))の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条((買入れしよう却))の規定により行う国債の買入れしよう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
第4款 売却決定
第111条関係 動産等の売却決定
売却の決定
(公売をする日)
1 法第111条の「公売をする日」とは、公売により売却する場合には法第95条第1項第3号((公売公告))の「公売の日時」の属する日(期間入札の場合には、入札書を提出することができる終期の属する日)を、随意契約により売却する場合にはその売却する日(以下これらを「公売期日等」という。)を、それぞれいう。
(最高価申込者)
2 法第111条の「最高価申込者」とは、法第104条((最高価申込者の決定))若しくは第105条((複数落札入札制による最高価申込者の決定))の規定により最高価申込者としての決定を受けた者又は随意契約により売却する場合における買受人となるべき者をいう。
(売却決定)
3 法第111条の「売却決定」とは、公売期日等において、2に掲げる者(以下「最高価申込者」という。)に対して、その買受けの申込みをした財産を売却することに決定する処分をいう。
売却決定の効果
4 売却決定は、換価に付した財産について滞納者(法24条の譲渡担保権者、物上保証人等を含む。)と最高価申込者との聞における売買契約成立の効果を生ずる。
第112条関係 動産等の売却決定の取消し
売却決定の取消しと善意の買受人との関係
(善意の買受人)
1 法第112条第1項の「善意の買受人」とは、その換価処分について、買受人が換価困難につき取り消すべき違法又は不当があることを知らずに買受代金を納付して、その換価財産を取得した買受人をいう。
(対抗することができない)
2 法第112条第1項の「対抗することができない」とは、換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消しがあった場合においても、その取消しの効果を、買受代金を納付した善意の買受人に対して主張することができないことをいう。
損害賠償責任
(故意及び過失)
3 法第112条第2項の「故意」とは、自己の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容する心理状態のことをいい、また「過失」とは、一定の事実を認識すべきにかかわらず不注意で認識しないことをいい、軽過失であるか重過失であるかの別を問わない。この場合における故意又は過失の挙証責任は、国が負う。
(通常生ずべき損失)
4 法第112条第2項の「通常生ずべき損失」とは、売却決定の取消しをした財産について、事物自然の成り行きからして普通に生ずべき損害の額をいい、それが通常生ずべきものであるかどうかは、社会通念によって判定するものとする。したがって、特別の事情によって生じた損害は含まれない。
(賠償責任)
5 法第112条第2項の「賠償する責に任ずる」とは、国に故意又は過失がない場合においても、その損害賠償の責めを負うことをいう(国家賠償法1条参照)。
(求償権の行使)
6 法第112条第2項の「求償権の行使」とは、国が損害賠償をした場合において、その損害賠償の基因となる行為が他人の行為による場合には、国がその負担した賠償額の範囲において、その者に対して求償権を行使することをいう。
第113条関係 不動産等の売却決定
売却決定期日
1 法第113条の「起算して7日を経過した日」については、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない(通則令2条6号参照)。
売却決定に伴う処理
2 次順位買受申込者に対し売却決定をした場合には、当該申込者に対し、書面又は口頭によりその旨及び買受代金の納付の期限を通知するものとする。また、公売の通知をした者のうち知れている者についても同様に取り扱うものとする。
なお、上記の書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 上記の書面は、法第118条((売却決定通知書の交付))に規定する売却決定通知書とは異なることに留意する。
第114条関係 買受申込み等の取消し
滞納処分の続行停止
(意 義)
1 法第114条の「滞納処分の続行の停止」とは、一定の事実の発生により、最高価申込者等の決定又は売却決定に続く後行の処分の執行が差し止められることをいう。
(滞納処分の続行の停止があったとき)
2 法第114条の「国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があったとき」とは、換価財産について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、次に掲げる場合に該当するときをいう。 (注) 法第32条第4項((第二次納税義務者の財産の換価の制限))、所得税法第117条((予定納税額の滞納処分の特例))、第118条((予定納税額の徴収猶予))等の規定のように、もともと換価をすることが期待できない場合は、法第114条の規定を適用する余地がない。 (1) 通則法第23条第5項ただし書((更正の請求があった場合の徴収の猶予))の規定により、国税の徴収が猶予されたとき。
(2) 通則法第46条((納税の猶予の要件等))の規定により、国税の納税が猶予されたとき。
(3) 通則法第105条第1項ただし書((不服申立てがあった場合の処分の制限))の規定により、換価ができないこととなったとき。
(4) 行政事件訴訟法第25条第2項本文((執行停止))の規定に基づき滞納処分の続行の停止命令があったとき。
(5) 訴えの提起により法第90条第3項((訴訟係属中の換価の制限))の規定に該当することとなったとき。
(6) 法第50条第3項((換価の制限))の請求財産の換価の申立てがあった場合で、かつ、同項の規定により請求財産の換価ができないときに該当するとき。
(7) 会社更生法第37条第2項((滞納処分等の中止命令))の規定により滞納処分の中止命令があったとき。
(8) 更生手続開始の決定があったとき(会社更生法67条2項)。
(9) 納税の猶予又は換価の猶予が更生計画により認められたとき(会社更生法232条、122条、236条等参照)。
入札等又は買受けの取消しに伴う措置
(取消しの効力の発生と手続等)
3 法第114条の「その入札等又は買受けを取り消すことができる」については、最高価申込者等又は買受人からの入札等又は買受けの取消しの申出により、その効力が生ずるのであるが、これらの申出があった場合には、税務署長は、最高価申込者等の決定の取消し又は売却決定の取消しの手続をとるものとする。この場合において、税務署長は、知れている利害関係人(滞納者を含む。)に対してその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(公売保証金の返還)
4 最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の納付した公売保証金があるときは、遅滞なく、その公売保証金をその納付した者に返還しなければならない(法100条4項3号)。
再公売との関係
5 滞納処分の続行の停止が解除された後においては、その続行の停止に係る公売を前提とする再公売(法107条)をすることはできない。
第5款 代金納付及び権利移転
第115条関係 買受代金の納付の期限等
納付の期限
(売却決定の日)
1 法第115条第1項の「売却決定の日」とは、動産、有価証券又は電話加入権については法第111条((動産等の売却決定))の公売期日等をいい、不動産等については法第113条第1項((不動産等の売却決定))の売却決定期日をいう。
(期 間)
2 法第115条第2項の「期間」は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。 (注) 法第115条第2項の規定によって期限を延長するときは、1O日以内の日のうち日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たる日は、指定しないものとする。
(買受人が次順位買受申込者である場合)
3 法第115条第2項の「前項の期限」には、買受人が次順位買受申込者である場合の売却決定の日から起算して7日を経過した日が含まれる(法115条1項)。
(公売公告と期限の延長)
4 法第115条第2項の規定による期限の延長は、必ず公売公告に記載して行う取扱いとする(第95条関係12参照)。
買受代金の納付
(第1項の期限)
5 法第115条第3項及び第4項の「第1項の期限」には、法第115条第2項の規定により延長された期限が含まれる。
(納付の手続)
6 換価財産の買受人は、買受代金に、買受けに係る財産の名称、数量、性質、所在及び買受代金の額を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない(令42条の3)。
売却決定の取消し及び通知
(売却決定の取消し)
7 買受人が買受代金を期限までに納付しないときは、速やかに売却決定を取り消すものとする。ただし、次順位買受申込者が定められていない場合において、期限までに納付できないことの理由がやむをえないものであって、しかもそれが継続しており、かつ、取消しをしな.いでいることが徴収上有利であると認められるときにあっては、相当の期間に限って取消しが遅れても差し支えないものとする。
(取消しの通知)
8 法第115条第4項の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
法第108条との関係
9 法第115条第4項及び法第108条第2項((最高価申込者等とする決定の取消し等))の規定をともに適用することができる場合には、すべて法第108条第2項の規定を適用するものとする。
第116条関係 買受代金の納付の効果
換価財産の取得
1 法第116条第1項の「換価財産を取得する」とは、買受人が滞納者から換価財産を承継的に取得することをいう(第89条関係7参照)。
権利移転の時期
2 換価財産の権利移転の時期は、買受人が買受代金の全額を納付した時である(法116条1項)。
なお、おおむね次に掲げる財産については、それぞれに掲げる要件を満たさなければ権利移転の効力が生じない。 (1) 鉱業権又は特定鉱業権の移転については登録(鉱業法60条、大陸棚特別措置法32条1項1号)
(2) 特許権、実用新案権及び意匠権並びにこれらについての専用実施権の移転については登録(特許法98条1項、実用新案法26条、18条3項、意匠法36条、27条3項)
(3) 商標権及びその専用使用権の移転については登録(商標法35条、30条4項)
(4) 電話加入権の譲渡については、日本電信電話公社の承認(公衆電気通信法38条1項)
(5) 農地又は採草放牧地の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転については、農業委員会の許可(買受人がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地についてこれらの権利を取得する場合には、都道府県知事の許可)(農地法3条1項、4項)
危険負担の移転の時期
3 買受人が買受代金の全額を納付した場合は、その時に換価財産の権利が移転するから、換価財産の換価に伴う危険負担もその時に買受人に移転する。したがって、換価財産の買受人から買受代金の納付を受ける前において、その財産上に生じた危険(例えば、焼失、盗難等)は、滞納者が負担する。また、換価財産の買受人から買受代金の納付があった後において、その財産上に生じた危険は、その財産の登記の手続の既未済又は現実の引渡しの有無にかかわらず、買受人が負担する。
徴収したものとみなす
4 法第116条第2項の「徴収したものとみなす」とは、徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者の換価に係る国税の納税義務を消滅させることをいう。
第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
国税の完納の証明
(国税の完納)
1 法第117条の「国税の完納」とは、換価の基因となっている国税の全額が消滅することをいい、納付、更正の取消し、免除又は還付金等の充当等その消滅の理由のいかんを問わない。
(事実の証明)
2 法第117条の「国税の完納の事実」の証明は、納税者又は第三者から、売却決定をした税務署長に対し、国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面(収納機関がその完納の事実を証する書面)を呈示することによってしなければならない(令43条)。
なお、税務署長は、収納機関から送付された領収済通知書又は領収済報告書により、換価の基因となっている国税の完納の事実が確認できたときは、証明を待つまでもなく、直ちに売却決定を取り消すものとする。
売却決定の取消し
(取消しの通知)
3 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(取消しの効果)
4 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、滞納者と買受人との間の売買契約は、売却決定の時にさかのぼって消滅するから、税務署長は、買受人の納付した公売保証金があるときは、遅滞なく、これを買受人に返還しなければならない(法100条4項5号)。
第118条関係 売却決定通知書の交付
売却決定通知書
1 法第118条の「売却決定通知書」とは、令第44条各号((売却決定通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第9号書式による。
交付しない場合
(動産の場合)
2 動産を換価した場合において、その動産を公売の場所に引き揚げているとき、買受人が占有しているとき、その他直接買受人に引渡しができるとき等売却決定通知書を交付する必要がないと認めるときは、売却決定通知書の交付をしないものとする(法118条ただし書)。
(有価証券の場合)
3 有価証券を換価した場合においては、法第118条の売却決定通知書の交付を要しない(法118条本文)。
第119条関係 動産等の引渡し
引渡しの方法
(徴収職員が占有した場合の引渡し)
1 法第119条第1項の「引き渡さなければならない」とは、換価した動産、有価証券又は自動車若しくは建設機械(徴収職員が占有したものに限る。以下第119条関係において.「動産等」という。)を買受人に現実に引き渡すことをいう。ただし、その動産等を2の者以外の第三者に保管させている場合には、民法第184条((指図による占有の移転))の規定により引き渡すことができる。
(滞納考又は第三者に保管させている場合の引渡し)
2 換価した動産等を、滞納者又は第三者に保管させている場合の引渡しは、売却決定通知書にその引渡しをする旨並びにその引渡しに係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を付記して買受人に交付すること(令45条1項)によって行う(法119条2項前段)。この場合においては、税務署長は、その動産等を保管している滞納者又は第三者に対し、令第45条第2項各号((保管している動産等を引き渡す場合の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、通知しなければならない(法119条2項後段、令45条2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 保管者がその動産等の現実の引渡しを拒否しても、国はその現実の引渡しを行う義務を負わない。
第120条関係 有価証券の裏書等
期限の指定
1 法第120条第1項の規定により指定する期限は、換価した有価証券の内容、数量等を考慮して定めるものとする。
なお、記名株式を換価した場合の権利移転の手続は、株券の交付のみで足りるから(商法205条参照)、法第120条に規定する手続をとる必要はない。
税務署長による裏書等
2 滞納者が、法第120条第1項の期限までに、換価した有価証券に係る権利の移転につき必要な手続をとらないときは、税務署長は、滞納者に代わり、次の手続をとるものとする(法120条2項)。 (1) 権利移転につき裏書を必要とする有価証券については、「国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡する」旨をその証券の裏面に記載し、税務署長がこれに署名押印する。
(2) 権利移転につき名義変更を必要とする有価証券については、「公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡したから、国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、名義変更を請求する」旨を記載した書面に、税務署長が署名押印する。 (注) 上記の書面の交付を受けた買受人は、その証券の発行者(名義書換代理人を含む。)に対して名義変更を請求するが、この場合における費用は、買受人の負担とする(法123条)。
第121条関係 権利移転の登記の嘱託
法第121条の規定による場合
(財 産)
1 法第121条の規定により、権利の移転の登記を嘱託する財産は、権利の移転につき登記を要する財産のうち、4及び5によるもの以外の財産、すなわち、鉱業権、特定鉱業権、漁業権、入漁権、ダム使用権、航空機、自動車、特許権、特許実施権、実用新案権、実用新案実施権、意匠権、意匠実施権、商標権、著作権、著作隣接権、出版権、登録公社債等に係る債権等である。
(権利移転の手続)
2 税務署長は、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、権利移転の登記の嘱託書に買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本を添付して、関係機関にその権利の移転の登記を嘱託しなければならない(令46条)。この関係機関は、差押えの登記の嘱託をした関係機関と同様である。
なお、次のことに留意する。 (1) 自動車の権利移転の登録を嘱託するときは、嘱託書に売却決定通知書又はその謄本を添付するほか自動車検査証を呈示しなければならない(道路運送車両法13条3項)。
この場合において、その自動車の使用本拠の位置が変更となり、かつ、買受人の自動車の使用本拠の位置が、自動車の保管場所の確保等の関する法律の適用を受ける地域(同法施行令2条別表参照)内にあるときは、自動車保管場所証明書(自動車の保管場所の確保を証する書面に関する命令1条別記様式参照)を添付しなければならない(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条)。
(2) 買受人が売却決定通知書を紛失等したことにより提出できないときは、税務署長にその再交付を求め、交付を受けた売却決定通知書を提出して登記の嘱託を請求することができる(昭和50,3.28大阪地判参照)。
(消滅する権利との関係)
3 換価に伴い消滅する権利及び換価に係る差押えの登記の抹消の登記の嘱託については、法第125条((換価に伴い消滅する権利の登記のまつ梢の嘱託))に定めるところによる。
不動産登記法等の規定による場合
4 不動産登記法第29条((公売処分による登記))の規定の適用がある場合(不動産とみなされることにより同条の適用がある場合を含む。工場抵当法14条1項、鉱業抵当法3条、漁業財団抵当法6条、道路交通事業抵当法8条、港湾運送事業法26条、立木法2条1項、観光施設財団抵当法8条参照)並びに船舶登記規則第1条((不動産登記法の準用))及び建設機械登記令第9条((不動産登記法の準用))の規定により不動産登記法第29条の規定が準用される場合において、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、税務署長は、次の登記を、それぞれの書類を添付して嘱託しなければならない。 (1) 換価による権利移転の登記買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本
(2) 換価に係る差押えの登記の抹消の登記買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本
(3) 換価により消滅した権利(第89条関係8から13まで参照)の登記の抹消の登記配当計算書の謄本(令46条) (注) 上記の場合における抹消の登記については、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
鉄道抵当法等の規定による場合
5 鉄道抵当法の規定に基づく鉄道財団、軌道財団及び運河財団の権利移転の登記等の嘱託については、4に準じて取り扱う(鉄道抵当法77条ノ2、68条、軌道ノ抵当ニ関スル法律1条、運河法13条、法121条)。
第122条関係 債権等の権利移転の手続
換価した債権等の権利移転の手続
(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項((債権の換価))の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法122条1項。第118条関係1参照)。
第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
権利移転に伴う費用
(有価証券の代位裏書等の費用)
1 法第123条の「第120条第2項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用」とは、換価した有価証券の名義変更手数料等、名義の変更に伴って生ずる費用等をいう。
(登録免許税)
2 法第123条の「第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税」とは、権利移転の登記の嘱託により登記を受ける場合に納付すべき登録免許税をいう(登録免許税法2条参照)。
(その他の費用)
3 法第123条の「その他の費用」とは、所有権移転登記の嘱託書を郵送する場合の郵送料等をいう。
買受人の負担
4 法第123条の「買受人の負担とする」とは、1から3までに掲げる費用は、買受人が前払いしなければならないことをいう。
第124条関係 担保権の消滅又は引受け
担保権等の消滅
(先取特権)
1 法第124条第1項の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権、先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。また、同項の「先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいう(法50条1項参照)。
(担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利)
2 法第124条第1項の「担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利」とは、担保のための仮登記のある財産が滞納処分により差し押さえられた後、仮登記担保契約に基づく本登記をしたものに係る権利をいう。 (注) 担保のための仮登録のある財産が、不動産登記法の適用又は準用のない財産である場合には、利害関係人の承諾を要しないで仮登録に基づく本登録をすることができる。
(再売買の予約の仮登記)
3 法第124条の「再売買の予約の仮登記」とは、再売買の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記をいう。
(担保権が消滅しない場合)
4 法第124条第2項の規定による担保権の引受けがあった場合は、その担保権については、法第124条第1項の規定は適用されず(法124条2項後段)、したがって、その担保権は消滅しない。
担保権の引受け
(登記されている先取特権)
5 法第124条第2項の「先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいうが、法第124条第2項の規定による引受けができる先取特権は、そのうちの登記をしているものに限られる。
(負担の引受け)
6 法第124条第2項の「負担を買受人に引き受けさせる」とは、法第124条第2項の担保権のある財産の換価に当たって、その担保権を消滅させず、その担保権の負担のある財産として買受人に売却することをいう。
(国税が劣後するとき)
7 法第124条第2項第1号の「次いで徴収するものであるとき」とは、差押国税のうち、法第10条((直接の滞納処分費の優先))の規定の適用を受ける滞納処分費を除いた国税の全額が、法第124条第2項の担保権に劣後するとき(法15条から20条まで参照)をいうものとする。
(担保権者の申出)
8 法第124条第2項第3号の「申出」は、令第47条((担保権の引受けによる換価の申出))の規定により、同条各号に掲げる事項を記載した書面をもって公売公告の日又は随意契約により売却する日の前日までに、しなければならない。この場合において、その申出の期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令に定める日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条7号)。
(引受けを認めない場合)
9 法第124条第2項各号のすべてに該当する場合であっても、次に掲げるときは、担保権の引受けをさせないものとする。 (1) 最も先順位の担保権に対抗できない用益物権、賃借権等の権利があるとき。
(2) 仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権であるとき。
(3) 担保権の引受けをさせることとした場合には見積価額の決定に煩さな手続を要すると認められるときその他税務署長が担保権の引受けをさせることが徴収上適当でないと認めるとき。
第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
消滅する権利の抹消の登記の嘱託
(嘱託をする場合)
1 法第125条の規定による抹消の登記の嘱託は、法第121条((権利移転の登記の嘱託))の規定により権利移転の登記を嘱託する場合に行うものであり、不動産登記法その他の法令に別段の定めがあるときは、これらの規定に基づいて抹消の登記を嘱託する(第121条関係4、5参照)。
なお、法第125条の関係機関については、第121条関係2と同様である。
(消滅する権利)
2 法第125条の「換価に伴い消滅する権利に係る登記」とは、法第124条((担保権の消滅又は引受け))の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等(第89条関係8から13まで参照)に係る登記及び差押え(参加差押えを含む。)の登記をいう。 (注) 滞調法の規定により二重差押えがされた不動産、船舶、航空機、自動車、建設機関、債権又はその他の財産権を滞納処分により換価し、権利移転の登記をしたときは、強制執行による差押えの登記は、登記官により職権で抹消される(滞調法16条、19条、20条、20条の8、20条の11、滞調令12条の2、12条の3、12条の10)。
(嘱託書の添付書類)
3 法第125条に規定する換価に伴い消滅する権利(差押えを含む。)に係る登記の抹消の登記の嘱託をする場合には、嘱託書に配当計算書(法131条参照)の謄本を添付しなければならない(令46条)。
登録免許税の非課税
4 法第125条の規定により抹消の登記の嘱託をする場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
第126条関係 担保責任
民法第568条の規定の準用
(民法第568条第1項の規定の準用)
1 差押財産を換価した場合において、民法第561条本文((売主の担保責任))、第563条第1項若しくは第2項((権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任))、第565条((数量の不足又は物の一部滅失の場合の売主の担保責任))又は第566条第1項若しくは第2項((用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任))に規定する場合に該当する場合があるときは、その財産の買受人は、これらの規定に準じ、滞納者に対してその契約を解除し、又は買受代金の減額を請求することができる。この場合における買受人の権利の行使については、同法第564条((権利行使の除斥期間))及び第566条第3項((権利行使の除斥期限))の規定が準用される。
(民法第568条第2項の規定の準用)
2 1の場合において、滞納者が無資力であるときは、換価財産の買受人は、換価代金等の配当を受けた債権者に対して、買受代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法568条2項)。この場合における請求は、滞納者に対して解除権又は買受代金減額請求権を行使した上で、滞納者が無資力であることを証明したときにすることができる(大正8.5.3大判)。
(民法第568条第3項の規定の準用)
3 1又は2の場合において、滞納者が当初から物又は権利のけんけつ(欠缺)を知っていながらこれを申し出なかったときは、換価財産の買受人は、滞納者に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法568条3項)。
第127条関係 法定地上権等の設定
法定地上権
(成立要件)
1 法第127条第1項の「地上権が設定されたものとみなす」とは、法第127条第1項の規定により、設定契約を締結しなくても、法律上当然に地上権が成立することをいう。
なお、上記の地上権の成立については、次のことに留意する。 (1) 滞納者の所有に属する土地若しくは建物等に抵当権の設定があり、その後滞納処分による差押え及び換価をした場合において、民法第388条((法定地上権))、立木法第5条((法定地上権))、工場抵当法第16条第1項((民法388条の準用))等の規定の類推適用(昭和37.9.4最高判参照)によって法定地上権が成立するときは、法第127条の法定地上権は成立しない。
(2) 差押えの当初から滞納者所有の土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。差押えの当初から滞納者所有の土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。 (注) 土地を差し押さえた時に建物が存在し、その後にその土地の上の建物が滅失(取壊し、焼失等)して再築された場合でも、法定地上権は成立する(昭和10.8.10大判参照)。
(3) 土地と建物等との所有者を異にするに至ったことの理由が換価であることを要する。
(地上権の及ぶ範囲)
2 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権は、建物等の利用に必要かつ十分な程度の広さに及ぶ(大正9.5.5大判、昭和35.12.15大阪高判参照)。
(法定地上権の対抗力)
3 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の対抗力は、次のとおりである。 (1) 土地を換価し、地上権が設定されたものとみなされた場合には、建物等の所有者である滞納者がその地上権を土地の買受人以外の第三者に対抗するためには、地上権の登記又は建物等の登記があることが必要である(民法177条、建物保護二関スル法律1条、昭和8.12.23大判参照)。
なお、滞納者は、土地の買受人に対しては、なんらの手続を要せず、法定地上権を主張することができる。
(2) 建物等を換価し、地上権が設定されたものとみなされた場合には、建物等の買受人がその地上権を第三者に対抗するためには、地上権の登記又は建物等の取得の登記をすることが必要である(民法177条、建物保護二関スル法律1条、昭和8.12.23大判参照)。なお、買受人は、土地の所有者である滞納者に対しては、なんらの手続を要せず、法定地上権を主張することができる。
(存続期間)
4 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の存続期間は、まず当事者の協議によって定まるのであるが、協議が調わない場合には、法第127条第3項の規定により、当事者の請求によって裁判所がこれを定める。この場合において、建物の地上権の存続期間については、借地法の規定の適用がある(同法2条1項参照)。
(地 代)
5 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の地代は、まず当事者の協議によって定まるが、協議が調わない場合には、法第127条第3項の規定により、当事者の請求によって裁判所がこれを定める。
法定賃借権
(地上権の存続期間)
6 法第127条第2項の「地上権の存続期間」とは、次に掲げる期間をいう。 (1) 建物所有を目的とする地上権に基づいてその土地の上に存在する建物については、借地権設定契約に存続期間の定めがある場合でその存続期間が借地法第2条第2項((借地権の存続期間))の規定に抵触しないものであるときはその期間(同法6条又は7条の規定に該当する場合を除く。)、設定契約に存続期間の定めがない場合においては同法第2条第1項((借地権の存続期間))に規定する存続期間(同法6条又は7条の規定に該当する場合を除く。) (注)1 建物所有を目的とする地上権の設定契約に存続期間の定めがある場合において、その地上権の存続期間を借地法第2条第2項((借地権の存続期間))の存続期間よりも短期とする特約がある場合においては、同法第11条((強行規定))の規定により、その存続期間の定めがなかったものとされる。
2 契約をもって建物所有を目的とする地上権を設定する場合の地上権の存続期間については、借地法第3条((借地権の存続期間))の規定がある。
(2) 立木の所有を目的とする地上権に基づいてその土地の上に存在する立木については、地上権設定契約に存続期間の定めがある場合においてはその期間、設定契約に存続期間の定めがない場合においては民法第268条((地上権の存続期間))に規定する存続期間
(みなし賃貸借)
7 法第127条第2項の「土地の賃貸借をした」ものとみなすとは、法第127条第2項の規定により、設定契約を締結しなくても、法律上当然に賃借権が成立することをいう。
なお、上記の賃借権の成立については、次のことに留意する。 (1) 差押えの当初から滞納者に帰属する地上権の目的となっている土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。
(2) 地上権者と建物等の所有権者とを異にするに至ったことの理由が換価であることを要する。
(賃借権の及ぶ範囲等)
8 法第127条第2項の規定により賃借権が設定されたものとみなされた場合におけるその賃借権の及ぶ範囲、対抗力、存続期間及び借賃については、それぞれ2から5までに定めるところに準ずる。
第4節 換価代金等の配当
第128条関係 配当すべき金銭
差押財産の売却代金
1 法第128条第1号の「差押財産の売却代金」とは、法第89条((換価する財産の範囲))の規定により公売に付し、又は随意契約により売却(国による買入れを含む。)した差押財産の売却代金をいう。
なお、土地収用法第96条第1項((差押えがある場合の補償金の払渡し))の規定に基づき払渡しを受けた金銭は、上記の売却代金に含まれることに留意する(同法96条2項参照)。
給付を受けた金銭
(有価証券)
2 法第128条第2号の「有価証券」とは、有価証券のうち、法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により金銭債権の取立てをしたものをいう。
(債 権)
3 法第128条第2号の「債権」とは、法第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取立てをした債権のうち、金銭債権をいう。
(無体財産権等)
4 法第128条第2号の「無体財産権等」とは、無体財産権等で、法第73条第5項((債権に関する規定の準用))において準用する第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取立てをしたもののうち、金銭債権に係るものをいう。
(保険金、持分の払戻金等)
5 法第128条第2号の「金銭」には、法第53条第1項((保険に付されている財産に対する差押えの効力))の規定の適用を受ける差押えに基づき給付を受けた金銭及び同法第74条第1項((差し押さえた持分の払戻し等の請求))の規定に基づき給付を受けた金銭が含まれるものとする。
交付要求によリ交付を受けた金銭
6 法第128条第4号の「交付要求により交付を受けた金銭」には、国税につき担保を徴した財産が強制換価手続により換価され交付を受けた金銭及び法第22条第3項((担保権の代位実行))の規定により税務署長が担保権者に代位実行することによって交付を受けた金銭が含まれるものとする。
第129条関係 配当の原則
配当する債権
(質権、抵当権、先取特権)
1 法第129条第1項第3号の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。また、同号の「先取特権」とは、法第19条第1号各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいい、これらの先取特権以外の先取特権は、配当を受けることができない。
(担保権の引受けとの関係)
2 法第124条第2項((担保権の引受け))の規定により質権、抵当権又は先取特権に関する負担を買受人に引き受けさせた場合には、その引受けに係る担保権の被担保債権については、配当をしない。
(損害賠償請求権又は借賃に係る債権)
3 法第129条第1項第4号の「損害賠償請求権又は借賃に係る債権」については、次のことに留意する。 (1) 動産の引渡しを命ぜられた第三者がその動産の差押え時までに法第59条第1項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))の規定による契約の解除をした旨を通知しないときは、その第三者は、契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権について配当を受けることができない(令25条2項)。ただし、その第三者がその動産の差押え後にその通知をした場合において、相当の理由があると認められるとき(第59条関係6参照)は、この限りでない(令25条3項)。
(2) 参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対して、法第59条第1項又は第3項(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)の規定により配当を請求することができた権利は、法第87条第2項((参加差押えに係る動産等の引渡し))の規定により参加差押えに係る財産の引渡しがされた場合には、その引渡しを受けた行政機関等に対して行使することができる(令41条3項、4項)。
国税に充てること
(国税に充てたことの効果)
4 法第129条第2項の規定により国税に充てたときは、滞納者の納税義務は、その充てられた範囲において消滅する。
なお、上記の場合には、配当計算書が作成されないので、滞納者に対しては、その充てた旨の通知をするものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(国税に充てるべき時期)
5 差押財産の売却代金又は有価証券、債権若しくは無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭(以下「換価代金等」という。)又は差押さえた金銭若しくは交付要求により交付を受けた金銭(第128条関係6に規定する金銭を含む。)を国税に充てるべき時期については、次に掲げる時によるものとする。 (1) 差し押さえた金銭については、その差押えの時
(2) 第三債務者等から給付を受けた金銭(第128条関係2から5まで参照)については、その給付を受けた時
(3) 売却代金については、それを受領した時
(4) 交付要求(参加差押えを含む。)により交付を受けた金銭については、その交付を受けた時
滞納者等への交付
(滞納者への交付)
6 法第129条第3項の規定により、滞納者に残余の金銭を交付する場合には、次のことに留意する。 (1) 換価した財産が譲渡担保財産又は物上保証に係るものである場合は、配当した金銭の残余は、譲渡担保権者又は差押え時における担保物の所有者に交付する。
(2) 差押財産が、差押え後に譲渡された場合において、配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、差押え時の所有者である滞納者に交付するものとする(法129条3項、昭和35.1.29大阪高判)。
(交付要求をした国税に係る延滞税の免除)
7 交付要求(参加差押えを含む。)により交付を受けた金銭を国税に充てた場合には、交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の延滞税は、免除する(通則法63条5項4号、通則令26条の2第1号)。この場合において、交付要求が滞調法第36条の10第1項((みなし交付要求))の規定に係るものであるときは、第三債務者が同法第36条の6第1項((第三債務者の供託義務))の規定により供託した日が、上記の「受領した日」に当たるものとして延滞税を免除する。
(破産宣告があった場合等)
8 滞納者に交付すべき金銭は、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる者に交付するものとする。 (1) 滞納者につき破産の宣告がされている場合破産管財人(破産法7条)
(2) 滞納者である株式会社につき更生手続の開始決定があった場合管財人(会社更生法53条)
(3) 会社整理の命令があり、会社財産の管理命令があった場合管理人(商法398条2項)
(4) 滞納者が死亡し、相続人があることが明らかでない場合相続財産管理人(民法953条)
(5) 滞納者である株式会社につき企業担保権の実行手続の開始決定があった場合管財人(企業担保法32条1項)
(6) 滞調法の規定の適用がある場合その執行官又は執行裁判所(同法6条1項、17条等)
(7) 滞納者が不在者(民法25条参照)に該当する場合管理人(同法25条、26条)
(残余金について差押え等があった場合)
9 滞納者に交付すべき残余金額について、差押え等があった場合には、次に定めるところによるものとする。 (1) 執行法の規定による差押命令又は保全法の規定による仮差押命令の送達がされたときは、滞納者に対しては交付しない(執行法145条、保全法50条参照)。
この場合においては、差押え又は仮差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭は供託することができる(執行法156条1項、保全法50条5項)。また、債務者(滞納者)に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、他に競合する債権者がいない場合に限り((3)参照)、その差押債権者に対して交付することになる。 (注)1 上記により供託したときは、その事情を執行裁判所又は保全執行裁判所に届け出なければならない(執行法156条3項、保全法50条5項)。
2 交付又は供託するまでの間は、その金銭は、保管金として処理する(出納官吏事務規程61条参照)。
3 債務者(滞納者)に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したか否かは、送達通知書(執行規則134条)等により確認するものとする。
(2) 執行法の規定による差押命令及び転付命令の送達があった場合には、転付命令の確定(同法159条5項)及びその他の差押命令若しくは仮差押命令の送達又は配当要求がないこと(同法159条3項)を確認した上、この命令を得た債権者に交付する(同法160条参照)。
(3) 差押え若しくは仮差押えが競合し(仮差押えと仮差押えが競合した場合を除く。)、又は配当要求があったときは、その金額の全部又は一部を供託し、その事情を差押命令を発した執行裁判所に届け出なければならない(執行法156条2項、3項、保全法50条5項参照)。
(4) 滞納処分による債権差押えの通知書の送達を受けたときは、差押えをした行政機関等へ交付する(法62条、67条等)。
(5) 滞納者から確定日付のある証書をもって債権譲渡の通知があったときは、その債権の譲受人に交付する(民法467条参照)。
(換価財産について強制執行による差押え等がされている場合)
10 換価財産について、強制執行による差押え等がされている場合には、次に定めるところによる。 (1) 換価財産について、滞納処分による差押え後に強制執行による差押え又は担保権の実行としての競売が開始されている場合には、滞納者に交付すべき残余金は、執行官又は執行裁判所に交付しなければならない(滞調法6条1項、11条の2、17条、19条、20条、20条の8第1項、20条の10、20条の11第1項、滞調令12条の2、12条の3第1項)。
(2) 換価財産について、仮差押えの執行がされている場合には、滞納者に交付すべき残余金は、執行官又は執行裁判所に交付しなければならない(滞調法11条1項、18条2項、19条、20条の9第1項、20条の11第1項、滞調令12条の2、12条の4)。
配 当
(転質又は転抵当がある場合)
11 転質又は転抵当がある場合には、原質又は原抵当によって担保される債権額の範囲内で、その転質又は転抵当により担保される債権額について、まず転質権者又は転抵当権者に配当し、なお配当すべき残余があるときは、次いで原質権者又は原抵当権者に配当する(昭和7.8.29大判)。
なお、転質権者又は転抵当権者には、転質又は転抵当について保全仮登記をした仮処分の債権者が含まれる(第133条3項、令50条4項参照)。
(共同抵当権がある場合)
12 同一債権の担保として数個の財産上に抵当権の設定がある場合(共同抵当の場合)において、その財産を換価したときは、次のことに留意する。 (1) 共同抵当の目的となっている財産の一部について後順位の抵当権がある場合で、その財産の全部を換価したときは、抵当権者に交付すべき金額は、各財産の売却価額(その財産を一括して換価したときは各財産の見積価額によってあん分した価額)に応じて、共同抵当によって担保される債権額をあん分した金額である(民法392条1項)。
(2) 共同抵当の目的となっている財産の一部を換価した場合においては、その換価した財産について後順位の抵当権があるときでも、先順位の抵当権者に交付すべき金額は、担保される債権額の全額である(民法392条2項)。
(抵当権の譲渡等があった場合)
13 抵当権の譲渡等があった場合においては、次のように配当する。
この場合、抵当権の譲渡等を受けた者がその譲渡等を第三者に対抗するためには、付記登記することが必要であるから、付記登記のない場合は、これらの処分はなかったものとして配当する。
また、抵当権の順位の譲渡又は抵当権の順位の放棄についての保全仮登記がされている場合には、保全仮登記がされた抵当権により担保される債権に対して配当を行う(法133条3項、令50条4項参照)。 〔例〕 第1順位抵当権者(甲)の債権の額・・・・・・・・・・・・・4万円
第2順位抵当権者(乙)の債権の額・・・・・・・・・・・・・5万円
第3順位担当権者(丙)の債権の額・・・・・・・・・・・・・8万円
無担保権者(丁)の債権の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
1 甲が丁のために抵当権の譲渡をした場合
丁は甲の債権(4万円)の範囲内で甲の抵当権者としての地位を取得することになり、丁の債権額(6万円)の範囲内で甲が受けるべき債権額が配当され、乙、丙の配当額には影響がない。
したがって、(1)丁に4万円、(2)乙に5万円、(3)丙に2万円(11万円-4万円-5万円)配当される。
2 甲が丙のために抵当権の順位の譲渡をした場合
抵当権の順位の譲渡がないとした場合に丙が受くべき債権額は2万円(11万円-4万円-5万円)であるから、甲の4万円と丙の2万円の合計額6万円の範囲内で丙の債権額に先に配当され、乙の配当額には影響がない。
したがって、(1)丙に6万円、(2)乙に5万円配当される。
3 甲から丁のために抵当権の放棄があった場合
甲は丁に対し優先権を持たなくなるため、甲と丁とは抵当権の放棄がないとした場合に甲が受くべき債権額4万円につき、それぞれの債権額によりあん分して配当され、乙、丙には影響がない。
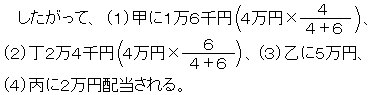
4 甲から丙のために抵当権の順位の放棄があった場合
甲は丙に対し優先権を持たなくなるから、抵当権の順位の譲渡がないとした場合の甲と丙が配当を受くべき債権額6万円(甲の4万円と丙の2万円(11万円-甲の4万円-乙の5万円))について甲・丙それぞれの債権額によりあん分(4:8)して配当され乙には影響がない。
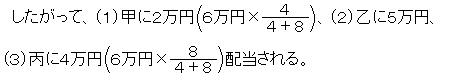
(仮差押えの執行後に担保権が設定された財産を換価した場合)
14 仮差押えの執行後に担保権が設定された財産を差し押さえ、換価した場合において、その配当時に仮差押えに係る本案訴訟の確定判決がない等のため配当額が定まらないときは、その定まらない部分に相当する金銭は供託しなければならない(滞調法34条2項、執行法87条2項、91条1項6号、92条)。この場合において、仮差押えに係る本案訴訟が確定したこと等により、配当額が確定したときの配当手続は、滞調法逐条通達第33条関係8に定めるところによる。
(差押え後に担保権が設定された財産を換価した場合)
15 滞納処分又は強制執行による差押え後に設定した担保権については、配当しないものとする(6の(2)参照)。
ただし、執行停止に係る強制執行による差押え後に登記された担保権については、滞調法逐条通達第33条関係7及び8に定めるところによる。
(担保権の目的となっている財産と、なっていない財産とをともに換価した場合)
16 担保権の目的となっている財産と、なっていない財産とをともに換価した場合において、その担保権の被担保債権が国税に優先しないときは、その担保権の目的となっていない財産の売却代金から順次国税に配当するものとする。
(不動産の共有持分を換価した場合)
17 担保権の設定後に共有となった不動産の共有持分を換価した場合には、担保権者に対しては、担保権の被担保債権に対する共有持分の割合に相当する金額を配当する。 (注) 上記の場合における担保権の登記の抹消は、嘱託書に抹消すべき登記として、「昭和○年○月○日受付第○号担保権設定登記のうち共有者○の持分に対する担保権」と記載する(昭和4.7.24付民第6,250号司法省民事局長回答)
不服申立て等の期限の特例
18 換価代金等の配当処分に対する不服申立て又は訴えの提起については、法第171条第1項又は第2項((滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例))の規定による期限の制限がある。
附帯税等の徴収
19 配当された金銭を国税に充てる場合には、まず徴収の基因となった国税(延滞税、利子税及び加算税を除く。)に充て、その後延滞税、利子税及び加算税に充てるものとする(法129条6項参照)。
なお、配当された金銭を複数の国税のいずれに充てるかは、税務署長の裁量による(大正5.3.9行判)が、この場合においては、民法第488条((当事者の指定による弁済の充当))、第489条第2号及び第3号((法定弁済充当))の規定に準じて処理するものとする。
第130条関係 債権額の確認方法
債権現在額の申立て
(債権現在額申立書)
1 法第130条第1項の「債権現在額申立書」とは、法第129条第1項第2号((配当の原則))に規定する国税、地方税又は公課を徴収する者及び法第129条第1項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者が、配当を受けるために、差押財産を換価した税務署長に提出する書面をいう。
(提出期限)
2 法第130条第1項の「売却決定の日の前日まで」とは、法第111条((動産等の売却決定))又は第113条((不動産等の売却決定))の規定による売却決定の日の前日までをいう。この場合において、その「前日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条6号)。
なお、差し押さえた債権等を取り立てた場合の配当に伴う債権現在額申立書については、法第130条第1項の債権を有する者は、その取立ての日までに税務署長に提出しなければならない。この場合において、法第130条第3項に規定する者がその取立ての時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない(令48条2項)。 (注) 次順位買受申込者に対し売却決定をした場合における法第130条第1項の「売却決定の日」は、法第113条第2項各号((次順位買受申込者に対する売却決定))に掲げる日である。
(債権現在額申立書に記載する債権の範囲)
3 法第130条第1項の債権現在額申立書に記載すべき債権現在額は、次のとおりである。この場合におけるその債権の債権現在額とは、その債権の元本、利息、損害金、費用その他附帯する債権額の総額をいう。 (1) 配当を受けるべき債権が国税、地方税又は公課の場合には、換価代金等の受領の時現在における債権現在額
(2) 配当を受けるべき債権が(1)以外の債権の場合には、換価代金等の交付期日現在における債権現在額
債権の確認
(申立書が提出された場合)
4 法第130条第2項前段の規定による債権の確認は、法第130条第1項の規定により提出された債権現在額申立書を形式審査して行うものとする。ただし、法第129条第1項第3号又は第4号((差押財産に係る質権等の被担保債権等))に掲げる債権で国税に優先するものがあるときは、その債権の存否、金額、順位等について実質審査を行い、これを確認するものとする。
(申立書が提出されない場合)
5 法第130条第2項後段の規定による確認は、その債権の存否、金額、順位等について実質審査を行い、これを確認するものとする。ただし、法第130条第2項第1号に掲げる債権のうち国税に優先しないものについては、登記事項を形式審査してこれを確認しても差し支えない。
(知れているもの)
6 法第130条第2項第2号及び第3号の「知れているもの」とは、徴収職員が法第131条((配当計算書))の配当計算書の謄本を発送する時までに知ることができたものをいう。
配当が受けられない場合
7 法第130条第3項の規定の適用を受ける「債権」とは、登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権のうち知れていないもので、かつ、売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を税務署長に提出しないものをいい、その債権は配当を受けることができない。
なお、上記の債権を有する者が法第130条第1項に規定する期限の経過後売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を提出したときにおけるその債権の額の確認は、その提出した債権現在額申立書を実質審査して行うものとする。
第131条関係 配当計算書
配当計算書
1 法第131条の「配当計算書」とは、令第49条第1項各号((配当計算書の記載事項等))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第10号書式による。
配当計算書の記載事項
2 配当計算書に記載する令第49条第1項第3号の「国税の金額」は、換価代金等の受領の時現在における金額をいい、同項第4号の「債権金額」は、換価代金等の交付期日現在における金額をいう(第130条関係3参照)。
配当計算書の謄本の交付
(謄本の発送)
3 配当計算書の謄本は、配当金額がない債権者に対しても、法第131条の規定により、発送しなければならない。
(発送の期限)
4 法第131条の「納付の日から3日以内」及び令第49条第2項((金銭による取立てに係るものの配当計算書の謄本の発送期限))の「取立ての日から3日以内」の「3日」の期間計算については、初日は算入しない(通則法10条1項)。
(第1号に掲げる者)
5 法第131条第1号の「債権現在額申立書を提出した者」とは、法第130条第1項((債権現在額申立書の提出期限))の期限までに債権現在額申立書を提出した者及び同条第3項((債権現在額申立書の提出と配当との関係))に規定する者で、同条第3項の期限までに債権現在額申立書を提出した者をいう。
(滞納者)
6 法第131条第3号の「滞納者」には、法第24条第2項前段((譲渡担保権者に対する告知))の譲渡担保権者が含まれる(法49条)ほか、差押え時における担保財産の所有者を含むものとする。この場合においては、本来の滞納者に対しては、配当された金銭を国税に充てた旨の通知をするものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第132条関係 換価代金等の交付期日
交付期日
(交付期日が休日に当たる場合)
1 法第132条第2項本文の「換価代金等の交付期日」については、その日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない。
(期間を短縮することができる場合)
2 法第132条第2項ただし書の「前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合」とは、差押えをした国税を有する行政機関、交付要求に係る国税、地方税及び公課を有する行政機関等並びに滞納者以外に配当手続に参加している者がない場合をいう。
なお、法第132条第2項ただし書の規定により期間を短縮する場合においても、滞納者及び交付要求をしている行政機関等が、法第133条第2項((配当計算書に関する異議))又は第171条((滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例))の規定による異議の申出又は不服申立てをすることができるだけの期間はおくものとする。
第133条関係 換価代金等の交付
配当計算書
1 法第133条第1項の「配当計算書」とは、法第131条((配当計算書))の配当計算書をいう。ただし、法第133条第2項の規定により更正されたときは、更正後の配当計算書をいう。
配当計算書に関する異議
(異議の範囲)
2 法第133条第2項の「配当計算書に関する異議」とは、配当計算書に記載された金額についての異議をいう。
(不服申立てとの関係)
3 換価代金等の配当に関して異議を有する者が、通則法の規定による不服申立てとの法第133条の異議の申出とを併せてした場合において、法第133条の異議の申出が認められなかったときは、不服申立てだけが審理されることとなる。
なお、不服申立てだけがされた場合において、その申立ての内容が法第133条の異議に当たるときは、その部分については、法第133条の異議の申出が併せてされたものとして取り扱う。
(異議の申出者)
4 法第133条第2項の規定により異議の申出をすることができる者は、滞納者及びその異議が認められることによって配当される金額が増加することとなる者である。
(配当計算書の更正)
5 法第133条第2項各号の規定により配当計算書を更正したときは、その旨を配当計算書に関する異議に関係を有する者及び滞納者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第1号の異議
(異議の内容)
6 法第133条第2項第1号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるとき」とは、異議が配当計算書に配当すべき金額として現に記載されている国税、地方税又は公課の金額についてのその金額の存否又は多少に関するものであるときをいい、行政機関等から異議の申出があったことにより、国税、地方税又は公課以外の債権に影響を与えることとなるときも含まれる。
(行政機関等)
7 法第133条第2項第1号の「その行政機関等」とは、配当計算書に関し、法第133条第2項第1号に規定する異議の申出があった場合において、その異議の目的となった配当金額を受けるべき行政機関等をいう。
(行政機関等からの通知)
8 法第133条第2項第1号の「行政機関等からの通知に従い」とは、異議の内容が7の行政機関等の権限に係るものである場合には、その行政機関等からその異議に関する通知を受け、その通知に従うことをいう。
第2号の異議
(異議の内容)
9 法第133条第2項第2号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合」とは、異議を認めても配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に影響を与えない場合をいう。
(異議の関係者)
10 法第133条第2項第2号の「その異議に関係を有する者」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる債権者をいう。
(合 意)
11 法第133条第2項第2号の「その他の方法で合意したとき」とは、10の債権者と滞納者が、配当計算書に記載された金額以外の配当金額によることを合意したときをいう。
(供 託)
12 法第133条第2項第2号の異議を正当と認めないとき又はその他の方法による合意がないことにより換価代金等を交付することができないときは、税務署長は、換価代金等を供託しなければならない(法133条3項、令50条1項)。この供託及び供託後の手続については、19に定めるところによる。
第3号の異議
(異議の内容)
13 法第133条第2項第3号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合」とは、異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課に対する直接の異議ではなく、これら以外の債権の配当金額に関するものであって、その異議を認めることにより、国税、地方税又は公課の配当金額に影響を与えることとなる場合をいう。
(異議の関係者)
14 法第133条第2項第3号の「異議に関係を有する者」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる債権者及び行政機関等をいう。
(合 意)
15 法第133条第2項第3号の「その他の方法で合意したとき」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる行政機関等及び債権者並びに滞納者が、配当計算書に記載された金額以外の金額によることを合意したときをいう。
(異議の参酌)
16 法第133条第2項第3号の「その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し」とは、税務署長がその異議について客観的にみて合理的な理由があると認めるときは、その異議の内容を参酌して配当金額を定め、配当計算書を更正して、換価代金等を交付することをいう。
(供託等)
17 法第133条第2項第3号の異議を正当と認めないとき又はその他の方法による合意がないときで、税務署長が異議につき相当の理由がないと認める場合の配当については、次による。 (1) 国税、地方税又は公課の金額は、直ちに交付する(法133条2項3号)。
(2) (1)以外の異議に関係を有する者に配当すべき換価代金等は、供託しなければならない(法133条3項、令50条1項)。この供託の手続及び供託後の手続については、19に定めるところによる。
特殊な場合の供託
(停止条件)
18 法第133条第3項の「停止条件」とは、その成就まで法律行為の効力の発生を停止する条件をいう(民法127条)。
(供託等の手続)
19 法第133条第3項に掲げる場合における換価代金等の交付については、次に掲げるところによる。 (1) 法第133条第2項の規定により換価代金等を交付することができない場合には、税務署長は、その換価代金等を供託(第134条関係5,6参照)し、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない(令50条1項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
なお、滞納者に対しては、異議に関係のないときであっても、上記に準じて通知するものとする。
(2) (1)の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになったときは、これに従って配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、(1)により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない(令50条2項)。この配当額支払証及び支払委託書は、別に定めるところによる。
(3) (2)による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、(2)の支払委託書に基づいて行われる(令50条3項)。
(4) 換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付については、(1)から(3)までに準ずる(令50条4項)。
滞調法の規定による供託
20 執行停止に係る強制執行による差押え後に登記された担保権がある場合又は仮差押え後に担保権が設定されている場合の換価代金の交付については、滞調法に規定するところにより供託しなければならない(同法33条2項、34条2項。第129条関係14,15参照)。
第134条関係 換価代金等の供託
換価代金等の供託
(保全差押え等に係る交付要求がある場合)
1 法第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))又は同項の規定を準用する通則法第38条第4項((保全差押えに関する規定の準用))の規定による交付要求を受けている場合において、その保全差押金額又は繰上保全差押金額に係る確定した国税の納期限が到来していないときは、法第134条第1項の規定により供託しなければならない。
(供託の対象となる金額)
2 法第134条第1項の「その債権者に交付すべき金額」とは、法第133条第1項((換価代金等の交付))の規定により債権者に交付すべき金額をいう。
(供託)
3 法第134条第1項の「供託」とは、税務署長が、債権者に交付すべき金額に相当する金銭を、その債権者のために、供託所に供託することをいう。
(配当手続の終了)
4 法第134条第1項の規定によって供託した場合には、その供託に係る部分について、換価代金等の配当手続は終了する(民法494条参照)。
供託の手続
(供託所)
5 法第134条第1項の規定により供託すべき供託所は、換価代金等を配当する行政機関等の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは法務大臣の指定する出張所である(供託法1条)。
(供託の手続)
6 供託の手続は、供託法第2条((供託手続))又は供託規則の定めるところによる。
(供託の通知)
7 法第134条第2項の規定による債権者に対する供託した旨の通知は、供託官が供託に係る金銭を受領したとき又は日本銀行から供託に係る金銭を受領した旨の証書の交付を受けたときにおいて、供託官が、あらかじめ税務署長から提出を受けている供託通知書(供託規則第20号書式)を送付することによって行われることに留意する。
第135条関係 売却決定の取消しに伴う措置
売却決定を取り消したとき
1 法第135条第1項の「売却決定を取り消したとき」とは、買受人が買受代金を納付した後に、その売却決定を取り消したときをいう。
なお、法第112条第1項((動産等の売却決定の取消し))の規定により、その取消しをもって買受人に対抗することができないときは、法第135条の規定の適用はない(法135条1項ただし書)。
抹消の登記の嘱託
2 法第135条第1項第2号の「第121条(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利」とは、換価に伴い移転の登記を嘱託した権利をいい、「まつ消の嘱託」は、上記の権利移転の登記についての抹消の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。
回復の登記の嘱託
(質権等の回復の登記)
3 法第135条第1項第3号の「第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権その他の権利」とは、法第124条((担保権の消滅又は引受))の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等をいい、「回復の登記の嘱託」は、上記の抹消された質権、抵当権その他の権利についての回復の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。 (注) 抹消した登記の回復の登記を申請する場合において、登記上利害関係がある第三者があるときは、申請書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する必要がある(不動産登記法67条参照)。
(差押えの登記の回復)
4 換価に伴い抹消された滞納処分による差押え又は参加差押えの登記についても、法第135条第1項第3号の規定による回復の登記の嘱託ができる。この場合において、売却決定の取消しが差押処分自体の違法を理由とするものであるときは、回復の登記の嘱託をしないで、新たな滞納処分を行うものとする。
(交付した金額の返還の請求)
5 税務署長は、売却決定を取り消したときは、換価代金等の交付を受けた者に対して、交付した金額の返還を請求する。この場合において、交付すべき金額を供託しているときは、供託規則に定めるところにより取り戻す。 (注) 交付した金額の返還の請求は、国の債権の管理等に関する法律の定めるところによる。
代 位
(意 義)
6 法第135条第2項の「代位」とは、5の請求を受けた担保権者が返還しない金額を限度として、その担保権に係る権利が税務署長に移転することをいう。
(付記登記)
7 法第135条第2項の規定により税務署長が代位したときは、その代位に係る付記登記をすることができる。この場合において、税務署長が付記登記を嘱託(又は申請)するときは、「登記原因ヲ証スル書面」等として、嘱託書(又は申請書)に配当計算書の謄本及び代位される担保権者の承諾書を、添付しなければならない(不動産登記法31条、建設機械登記令9条、自動車登録令55条、56条、14条(申請書に担保権者の署名押印があるときは、承諾書の添付は要しない。17条)等参照)。 (注) 税務署長は、全部代位するときは債権に関する証書の交付を、一部代位するときは債権に関する証書に代位の旨の記入を、それぞれの代位される担保権者にさせることができるほか、付記登記についての承諾書の交付を求めること等ができる(民法503条参照)。
第5節 滞納処分費
第136条関係 滞納処分費の範囲
滞納処分費の範囲
(差押えに関する費用)
1 法第136条の「差押に関する費用」とは、おおむね次に掲げる費用をいう。 (1) 差押財産の収集、整理等のために要した縄代、人夫賃等の費用
(2) 差押えの登記をするために、登記簿上の記載事項の更正、変更若しくは抹消の登記又は新たな事項の登記を嘱託した場合に要した登録手数料、名義変更料及び登記簿の調査に要する費用
(交付要求に関する費用)
2 法第136条の「交付要求に関する費用」とは、おおむね次に掲げる費用をいう。 (1) 交付要求をするために要した執行機関等の書類の閲覧に関する費用
(2) 参加差押えをするために要した登記簿等の調査に関する費用
(保管に関する費用)
3 法第136条の「保管に関する費用」とは、差押財産の維持管理のために支出し、又は支出すべきことの確定した費用をいい、おおむね次に掲げるものがある。 (1) 保管人に対する報酬
(2) 倉敷料等の保管料
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、その財産の維持管理に要した費用、例えば、動物の飼育費、船舶のけい船料、監守人の日当等
(運搬に関する費用)
4 法第136条の「運搬に関する費用」とは、差押財産をその所在の場所から税務署、保管人の住所等の保管場所に引き揚げ、又は保管の場所を移し、若しくは保管場所から公売場に搬入するために支出し、又は支出すべきことの確定した費用をいい、おおむね次に掲げるものがある。 (1) 荷造りに要する費用
(2) 運搬に要する人夫賃
(3) 運送費、例えば、自動車の借上科、運転手の日当、運賃等
(換価に関する費用)
5 法第136条の「換価に関する費用」とは、おおむね次に掲げるものをいう。 (1) 公売公告(見積価額の公告を含む。)の新聞掲載料 (注) 複数の滞納者の公売財産に係る公売公告の新聞掲載料は、掲載に要した紙面のうち、各々の滞納者分として使用した部分に相当する掲載料とそれ以外の部分に相当する掲載料を当該滞納者に均分した掲載料との合計額を、各滞納者に負担させる。
(2) 鑑定人の鑑定料、旅費、日当等
(3) 競り売り人の旅費、日当、現地案内人の謝金、測量手数料等
(4) 公売の場所の使用料、整理費等
(修理等の処分に関する費用)
6 法第136条の「第93条(修理等の処分)の規定による処分に関する費用」とは、差押財産の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等の費用をいう。
(有価証券の取立てに関する費用)
7 法第136条の「有価証券の取立に関する費用」とは、金融機関に取立てを依頼した場合における取立手数料等の費用をいう。
(債権の取立てに関する費用)
8 法第136条の「債権の取立に関する費用」とは、被差押債権の取立てに要した人夫賃等の費用をいう。
(無体財産権等の取立てに関する費用)
9 法第136条の「無体財産権等の取立に関する費用」とは、法第73条第5項((債権に関する規定の準用))の規定による無体財産権等の取立てに要した人夫賃等の費用をいう。
(配当に関する費用)
10 法第136条の「配当に関する費用」とは、法第130条第2項((債権額の確認方法))の規定による債権現在額の確認のための調査に要した費用等をいう。
滞納処分費として徴収できないもの
11 通知書その他の書類の送達に要する費用は、滞納処分費として徴収することができない(法136条)。また、次に掲げる費用は、滞納処分費として徴収しないものとする。 (1) 滞納処分に従事する徴収職員の俸給、旅費、手当等
(2) 滞納処分に関する書類(差押調書、公売公告等)の用紙代、税務署等の自動車によって差押財産を引き揚げた場合の燃料費等
(3) 公売公告の取消しに要する費用
(4) 行政上の措置として行った手続に要する費用
(5) 滞納処分に臨場した場合において、滞納税金の完納、納税の猶予の許可、差押えをすることができる財産がない等の理由によって差押えをしなかったときに要した費用
滞納処分費として徴収しない場合
12 次の事実が生じた場合には、それぞれに掲げる費用は、滞納処分費として徴収しないものとする。 (1) 徴収に関する処分が取り消された場合においては、その取り消された処分に要した費用
(2) 賦課処分の全部又は一部の取消しに基づき、徴収に関する処分が解除又は取消しされた場合においては、その解除又は取消しされた処分に要した費用
(3) 法第50条第2項((差押換えの請求に対する措置))又は第51条第3項((相続に係る差押換えの請求に対する措置))の規定により差押換えをした場合においては、解除に係る差押処分に要した費用
第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
徴収の基因となった国税
1 法第137条の「その徴収の基因となった国税」とは、滞納処分費を要する原因となった国税をいい、滞納処分費が個々のどの差押財産から生じたものであるかを問わない。 (注) 滞納処分費は、その徴収の基因となった国税には先立つが、他の国税には後れることもある。 〔例〕 甲国税によりA財産とB財産を差し押さえ、A財産を換価した場合の法第10条((直接の滞納処分費の優先))と法第137条との関係は、次のようになる。 A財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
B財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800万円
A財産の換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
この場合には、法第10条((直接の滞納処分費の優先))の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、差押国税590万円に配当する。次いで600万円の配当を受けた税務署長は、法第137条の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、B財産に係る滞納処分費5万円、差押国税585万円の配当をし、それぞれの国税に充てることになる。
第138条関係 滞納処分費の納入の告知
徴収手続
(納入の告知を要する場合)
1 滞納処分費につき納入の告知を要する場合は、本税及び附帯税のすべてが完納され、滞納処分費だけについて滞納者の財産を差し押さえようとする場合である(法138条)。
なお、納入の告知をした滞納処分費については、督促をしないで直ちに差押えをすることができる。
(納入の告知を要しない場合)
2 1以外の場合、例えば完納されていない本税若しくは附帯税と滞納処分費とについて差押えをするとき又は一つの国税について滞納処分費だけが残っており、他の国税の本税若しくは附帯税とともに差押えをするときは、納入の告知を要しない。
(納入告知書)
3 法第138条の「納入の告知」は、口頭による場合のほかは、令第51条各号((納入告知書の記載事項等))に掲げる事項を記載した通則規則第5条((書式))に規定する別紙第2号書式に、同書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えた(規則3条3項)納入告知書を、滞納者に送達して行う。
(口頭による告知)
4 令第51条ただし書((口頭による納入の告知))の規定は、例えば、徴収職員が滞納処分のために臨戸した場合において、本税及び附帯税が完納され、その滞納処分費だけ残っていることが判明したとき等、その滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、口頭により納入の告知をすることができることを定めたものである。この場合には、令第51条各号((納入告知書に記載すべき事項))に掲げる事項のほか、滞納処分費の納入の告知である旨を明確にして告知する。
(納期限)
5 令第51条第3号((納入告知書の記載事項))の「納期限」は、国税収納金整理資金事務取扱規則第18条((納付期限))の規定により調査決定の日から20日以内の日として適宜定める。
なお、上記の納付期限は、納入告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日以後とする(通則令8条1項参照)。
第6節 雑則
第1款 滞納処分の効力
第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
滞納処分の続行
1 法第139条第1項の「滞納処分を続行することができる」とは、被相続人又は被合併法人に対してした滞納処分の効力が、別段の手続をとることなく当然に相続人又は合併法人に及ぶことをいう。
なお、滞納処分による換価に伴う買受人への権利移転に当たっては、税務署長は、買受人に代わって相続人又は合併法人への権利移転の登記の嘱託をした後、買受人のために権利移転の登記の嘱託するものとする(昭和43.6.5付民事甲第1,835号法務省民事局長回答)。
承継財産についての執行
(死 亡)
2 法第139条第1項の「死亡」には、失そう宣告により死亡したものとみなされる場合(民法31条)も含まれる。
(法 人)
3 法第139条第1項の「法人」には、人格のない社団等も含まれる(法3条)。
(合 併)
4 法第139条第1項の「合併により消滅したとき」とは、吸収合併又は新設合併により法人が解散して消滅した場合及び人格のない社団等でこれに準ずる場合をいう。
滞納者名義の財産に対する執行
(滞納者の名義の財産)
5 法第139条第2項本文の「滞納者の名義の財産」とは、差押えに当たり、徴収職員が財産の帰属を名義によって判断する財産、例えば、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械又は各種記名式有価証券で滞納者の名義となっている財産に限られず、社会通念上滞納者の名義の財産と認められるものをいう。
(死亡を知っていた)
6 法第139条第2項ただし書の「死亡を知っていた」かどうかについては、5の財産に対してした差押えの時の現況による。
第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
仮差えの意義
1 法第140条の「仮差押」とは、裁判所の決定に係る仮差押えをいう(第55条関係10参照)。
仮処分の意義
2 法第140条の「仮処分」とは、裁判所の決定に係る仮処分をいう(第55条関係11参照)。
滞納処分と仮差押えとの関係
(仮差押えの効力)
3 仮差押えを受けた財産についても、法第140条の規定により滞納処分による差押えをすることができる。この場合における仮差押えの効力は、滞納処分による差押えによって消滅するものではないが、その財産が換価された場合には消滅する(第125条関係2参照)。
なお、仮差押えを受けた財産を滞納処分により換価した場合においては、換価代金等の残余は、当該財産に対する強制執行について管轄権を有する地方裁判所又は仮差押えをした執行官に交付する(滞調法28条、6条1項、34条1項、18条2項等)。 (注) 仮差押えについては交付要求及び参加差押えはできないが、仮差押えがされている財産につき滞納処分がされている場合には、その滞納処分につき交付要求及び参加差押えができるし、これらの処分は、仮差押えにより妨げられない。
(仮差押えを受けた動産又は有価証券の差押え)
4 仮差押えを受けている動産又は有価証券については、法第56条第1項((動産又は有価証券の差押手続))の規定によりその差押えを行うことができる(第58条関係4参照)。この場合において、その動産又は有価証券に対し執行官による仮差押えの旨の封印その他の表示がしてあるときは、それらの表示を破棄しないものとする。
(供託された金銭の差押え)
5 仮差押えの執行に係る金銭(保全法49条2項)、仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、若しくはその保管のために不相応な費用を要するため売却した売得金(同法49条3項)、強制管理の方法によるときの配当等に充てるべき金銭(同法47条4項)、強制競売による配当金(執行法91条1項2号)、又は滞納処分の行政機関等から交付を受けた金銭で売得金若しくは売却代金とみなされる金銭(滞調法11条3項、18条2項3項、19条参照)が供託されている場合(保全法49条2項、3項、47条4項、執行法91条1項)には、執行官又は裁判所にその供託金の払戻しを請求し、その払戻しがされた金銭について、法第56条第1項((動産又は有価証券の差押手続))の規定により差し押さえる。
(仮差押えを受けた動産等以外の財産の差押え)
6 仮差押えを受けている動産又は有価証券以外の財産については、その財産の種類に応じて、法第62条第1項及び第2項((債権の差押手続))、第68条第1項及び第3項((不動産の差押手続))、第70条第1項((船舶又は航空機の差押手続))、第71条第1項((自動車又は建設機械の差押手続))、第72条第1項及び第3項((特許権等の差押手続))又は第73条第1項及び第3項((電話加入権等の差押手続))の規定により、それぞれ差し押さえる。
(仮差押解放金の差押え)
7 仮差押えの執行停止のため、又は既に執行した仮差押えの取消しのため、仮差押債務者(滞納者)が仮差押決定の記載に従い供託した金銭(仮差押えによって保全される金銭債権の額に相当する金銭。以下7及び8において「仮差押解放金」という。保全法22条)については、滞納者の有する供託金取戻請求権を差し押さえるものとする。
また、第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭債権の額に相当する金銭を供託した場合において、保全法第50条第3項((みなす仮差押解放金))の規定により「仮差押解放金」とみなされる供託した金銭については、滞納者の有する供託金還付請求権を差し押さえるものとする。
(仮差押解放金の取立て)
8 7により供託金取戻請求権又は供託金還付請求権を差し押さえたときは、税務署長は、直ちに供託金の払渡しの請求をすることができる(平成2.11.13付民四第5,002号法務省民事局長通達)。
(差押えの通知)
9 保全法の規定により仮差押えがされている財産を差し押さえたときは、法第55条第3号((仮差押え等をした保全執行裁判所等に対する差押えの通知))の規定により、保全執行裁判所又は執行官に差し押さえた旨その他必要な事項を通知しなければならない。
(差押解除の通知)
10 仮差押えがされている財産について滞納処分による差押えを解除した場合においては、仮差押えをした保全執行裁判所又は執行官にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法81条)。
(公売等による仮差押えの登記の抹消の嘱託)
11 不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械に対する仮差押えの執行が、仮差押えの登記(強制管理の開始決定に係る仮差押えの登記を含む。)をすることにより行われている場合において、その仮差押えの登記のある財産を換価し、その権利移転の登記を関係機関に嘱託するときは(法121条等参照)、法第125条((換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託))等の規定により、併せて、仮差押えの登記の抹消を嘱託するものとする。
滞納処分と仮処分との関係
(仮処分が執行された財産の差押え)
12 仮処分が執行された財産についても、滞納処分による差押えをすることができる。この場合における仮処分の効力は、滞納処分による差押えによって消滅しない(保全法58条1項、2項参照)。
なお、仮処分が執行された財産を差し押さえた場合における換価については、この条関係13から20までに定めるところによる。 (注) 仮処分について交付要求及び参加差押えはできないが、仮処分がされている財産につき滞納処分がされている場合には、その滞納処分につき交付要求及び参加差押えができる。
(不動産の所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
13 所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、滞納処分による差押えは仮処分債権者に対抗することができない(保全法58条1項、2項)。
したがって、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする。 (注)1 所有権についての登記とは、所有権又は共有持分の登記名義人を実質的に変更する登記であり、例えば、所有権の移転の登記、保存若しくは移転の登記の抹消、移転の登記の抹消回復の登記又は持分の更正の登記をいう。
2 処分禁止の仮処分とは、仮処分債務者に対して係争物(不動産、動産、債権等)に係る権利の処分(所有権の移転、担保権の設定等)を禁止することを内容とする仮処分(保全法24条)をいう。
3 不動産とは、不動産登記法第1条の不動産(土地及び建物)及び特別法において不動産とみなされるもの(立木(立木法2条)、工場財団(工場抵当法14条)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)漁業財団(漁業財団抵当法6条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法26条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法8条)及び観光施設財団(観光施設財団抵当法8条))をいう。
4 所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行われる(保全法53条1項)。したがって、仮処分の執行と滞納処分による差押えの先後は、処分禁止の登記と差押えの登記の先後によって定まる。
5 仮処分債権者は、所有権の登記を申請する場合において、これと同時に申請するときに限り、その仮処分の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる(保全法58条2項、不動産登記法146条ノ2第1項)。この場合、仮処分債権者は、あらかじめ、その登記の権利者に対し、登記を抹消する旨の通知をしなければならない(保全法59条、不動産登記法146条ノ2第2項)。また、差押登記が抹消されたときは登記官から抹消した旨の通知がされることとされている(保全法59条、平成2.11.8付民三第5,000号法務省民事局長通達)。
6 処分禁止の登記より後順位の登記のうち、仮処分債権者の保全すべき登記請求権の登記に係る権利の取得又は消滅に抵触しないものは、仮処分債権者に対抗することができる。例えば、処分禁止の登記の前にされた国税の担保のための抵当権に基づく担保物処分のための差押え(通則法52条1項)の登記、仮処分の登記前に登記された抵当権の登記名義人を申立人とする競売開始決定に係る差押えの登記(昭和58,6.22付民三第3,672号法務省民事局長通達)、仮処分の債務者に対する破産(破産法70条)、和議開始(和議法40条2項、58条)、株式会社の整理開始に伴う保全処分(商法383条、386条1項)、更生手続開始(会社更生法67条1項、246条1項)又は企業担保権の実行手続の開始(企業担保法28条)の各登記がこれに当たる。
7 本案(保全法1条参照)の帰すうの形態としては、仮処分債権者の勝訴判決又は敗訴判決の確定、和解及び仮処分債権者と仮処分債務者との共同申請による登記の実現等がある。
(不動産の所有権以外の権利の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
14 所有権以外の権利の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合には、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条1項)。ただし、差押えに基づく換価は、当該不動産を仮処分の負担付きで換価できる場合等を除き、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(89条関係9、124条関係6参照)。 (注)1 不動産の所有権以外の権利の移転の登記とは、当該権利の全部又は一部の名義人を実質的に変更する登記で保存又は設定の登記に変更を加えないものをいい、例えば、抵当権若しくは地上権の全部若しくは一部の移転の登記、移転の更正の登記又は移転の抹消回復の登記をいう。
2 不動産の所有権以外の権利の消滅の登記とは、当該権利の全部又は一部が設定者との関係において実質的に消滅する登記をいい、例えば、抵当権抹消の登記、一部弁済による抵当権変更の登記又は被担保債権額を減額する抵当権更正の登記をいう。
(不動産の所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
15 所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合には、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条1項)。この場合、当該仮処分が担保権の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分であるときは換価を行うことができるが、当該仮処分が不動産の使用又は収益をする権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分であるときは、本案の帰すうが定まるまでの間は換価を行わないものとする(法133条3項、令50条4項参照)。 (注)1 所有権以外の権利の保存、設定又は変更の登記とは、実質的に新たに権利を設定する登記をいい、例えば、先取特権の保存の登記、抵当権若しくは地上権設定の登記、その抹消回復の登記、根抵当権の極度額を増額する変更若しくは更正の登記又は民法第375条による抵当権の処分の登記をいう。
2 担保権の保存、設定又は変更の登記とは、1に掲げたもののうち、担保権に関する登記をいう。
3 上記の仮処分の執行は、処分禁止の登記とともに保全仮登記をする方法により行われる(保全法53条2項)。この場合、処分禁止の登記は、処分禁止の対象が所有権である場合には甲区に、所有権以外である場合には乙区にされ、保全仮登記は乙区にされる(平成2.11.8付民三第5,000号法務省民事局長通達参照)。
4 担保権の保存、設定又は変更登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分が執行された後に新たな担保権が設定された財産を差し押さえて換価した場合においては、仮処分の執行後における担保権の設定は有効であるから、当該新たな担保権により担保される債権に対しても配当を行う(保全法58条1項、3項参照)。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
16 不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについて、登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分がされている場合の仮処分と滞納処分との関係については、第140条関係13から15までに準ずるものとする(保全法54条、61条参照)。 (注) 不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものには、例えば、特許権(特許法66条)、実用新案権(実用新案法14条)、意匠権(意匠法20条)、商標権(商標法18条)、自動車の所有権及び抵当権(道路運送車両法5条、自動車抵当法5条)、航空機の所有権及び抵当権(航空法3条の3、航空機抵当法5条)、建設機械の所有権及び抵当権(建設機械抵当法7条)並びに船舶の所有権及び抵当権(商法686条、687条、703条、848条)等がある。
(その他の財産に対する処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
17 不動産及び不動産以外の権利でその処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするもの以外の財産について処分禁止の仮処分がされている場合における滞納処分については、第140条関係13から15までに準じて取り扱うものとする。
(物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための占有移転禁止の仮処分と滞納処分との関係)
18 物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するため、債務者に対し、その物の占有の移転を禁止し、及びその占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずるとともに、執行官にその物の保管をさせ、かつ、債務者がその物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官がその物を保管している旨を公示させることを目的とする仮処分(以下「占有移転禁止の仮処分」という。保全法62条)がされた物を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者が、本案の債務名義に基づいて、その物の引渡し又は明渡しの強制執行をしたときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条、62条参照)。
(2) 仮処分債権者は、本案の債務名義に基づいて、仮処分の執行がされたことを知ってその物を占有した者に対し、その物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるから、差押えに基づく換価は本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(保全法62条参照)。 (注) 占有移転禁止の仮処分は、所有者が不法占拠者に目的物の返還を請求する場合、売買契約・賃貸借契約に基づき買主・賃借人が目的物の引渡しを請求する場合、賃貸借契約終了により賃貸人が目的物の返還を請求する場合等において、占有関係が転々とするのを防止するために行われる。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
19 建物収去土地明渡請求権を保全するための処分禁止の仮処分(保全法55条)がされた建物を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者は、差押登記の抹消を請求することはできない(保全法58条、64条参照)が、本案の債務名義に基づいて、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行を行うことができる(保全法64条参照)。
(2) 仮処分債権者は、本案の債務名義に基づき、処分禁止の登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行を行うことができるから、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(保全法64条参照)。
(その他の仮処分と滞納処分との関係)
20 係争物に関する仮処分(保全法23条1項)のうち、第140条関係13から19までに掲げた以外の仮処分がされた財産を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者が、本案の債務名義に基づいて、強制執行をした場合においても、滞納処分による差押えは効力を失わない。
(2) 当該仮処分の効力は、滞納処分による換価によって消滅しないから、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする。 (注) 上記の仮処分には、滞納者名義の土地につき第三者が所有権に基づいて立入禁止の仮処分をする場合及び滞納者の所有建物につき第三者が賃借権に基づいて占有使用妨害禁止の仮処分をする場合等がある。
(差押え後に仮処分が執行された場合における滞納処分と仮処分との関係)
21 滞納処分による差押え後に係争物に関する仮処分(保全法23条1項)が執行された場合、処分禁止の仮処分等差押えに対抗することができない仮処分の効力は、滞納処分による換価によって消滅する(執行法59条3項参照)。
ただし、仮処分債権者が、本案において係争物に係る実体上の所有権を主張しているときは、本案の帰すうが定まるまでの間は換価を行わないものとする。 (注) 建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分等係争物に係る権利の処分を禁止する効力を有しない仮処分については、滞納処分による換価によって効力が消滅しない場合があることに留意する。
(仮差押えの準用)
22 仮処分を受けた動産の差押え、仮処分を受けた動産以外の財産の差押え、仮処分を受けた財産に対する差押えの通知及び仮処分を受けた財産に対する差押えの解除については、4及び6並びに9から11までに定めるところに準じて行うものとする。
(仮処分解放金の差押え)
23 仮処分の執行の停止のため又は既にした仮処分の執行の取消しのため、仮処分命令の決定書の記載に従い仮処分債務者が供託した金額(保全法25条。以下「仮処分解放金」という。)の差押えは、次のより行うものとする。 (1) 一般の仮処分に基づく仮処分解放金(以下「一般型仮処分解放金」という。)が供託された場合には、仮処分債権者が滞納者であるときは供託金還付請求権を、仮処分債務者が滞納者であるときは供託金取戻請求権を、それぞれ差し押さえる。
(2) 詐害行為取消権(民法424条1項)を保全するための仮処分に基づく仮処分解放金(以下「特殊型仮処分解放金」という。)が供託された場合には、民法第424条第1項の債務者(以下「詐害行為の債務者」という。)が滞納者であるときは供託金還付請求権(保全法65条)を、仮処分債務者が滞納者であるときは供託金取戻請求権を、それぞれ差し押さえる。 (注)1 供託書中の「被供託者」欄に仮処分債権者が記載されている場合には一般型仮処分解放金に係る供託と、仮処分債権者以外の者が記載されている場合には特殊型仮処分解放金に係る供託と判断して差し支えない(平成2.11.13付民四第5002号法務省民事局長通達参照)。
2 一般型仮処分解放金の供託は、所有権留保付売買契約における代金債務の不履行による目的物の引渡請求権を保全するための占有移転禁止の仮処分及び譲渡担保契約における金銭債務の不履行による担保目的物の引渡請求権保全のための仮処分等に基づいて行われる。
3 特殊型仮処分解放金が供託された場合には、仮処分債権者は供託金還付請求権を有しない(保全法65条参照)。
(仮処分解放金の取立て)
24 23により供託金還付請求権又は供託金取戻請求権を差し押さえた場合においては、次により取り立てるものとする(平成2.11.13付民四第5002号法務省民事局長通達参照)。 (1) 一般型仮処分解放金に係る供託金還付請求権を差し押さえた場合において、仮処分債権者の本案訴訟の勝訴が確定したとき又は勝訴判決と同一内容の和解又は調停が成立したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に、確定判決の正本及びその確定証明書(保全規則13条2項参照)又は和解調書、調停調書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物の同一性を証する書面(仮処分申立書、仮処分命令決定書等をいう。以下(2)から(4)までにおいて同じ。)を添付する(民事訴訟法151条3項、保全法5条1項参照)。
(2) 一般型仮処分解放金に係る供託金取戻請求権を差し押さえた場合において、仮処分の本案判決の確定前に仮処分の申立てが取り下げられたとき、仮処分債権者の本案訴訟の敗訴が確定したとき又は仮処分債権者が本案訴訟で勝訴し仮処分の目的物に対して強制執行したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。この場合、供託物払渡請求書に、仮処分の申立てが取り下げられたことを証する書面又は本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面を添付する。
(3) 特殊型仮処分解放金に係る供託金還付請求権を差し押さえた場合においては、次により取り立てるものとする。 イ 仮処分の執行が保全法第57条第1項((仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し))の規定により取り消され、かつ、本案訴訟の判決が確定した後に仮処分債権者が詐害行為の債務者の有する供託金還付請求権に対して強制執行をしたときは、執行裁判所から支払証明書の交付を受け、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる(保全法65条)。
この場合、供託物払渡請求書に当該支払証明書を添付する。
ロ 仮処分債権者が供託金還付請求権に対する強制執行の申立てを取り下げたときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に、本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面及び仮処分債権者の強制執行の申立てが取り下げられたことを証する書面を添付する。
(4) 特殊型仮処分解放金に係る供託金取戻請求権を差し押さえた場合において、本案の勝訴判決の確定前に仮処分の申立てが取り下げられたとき又は仮処分債権者が本案訴訟で敗訴したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に仮処分の申立てが取り下げられたことを証する書面又は本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分債権者が本案訴訟で敗訴した場合においては仮処分の被保全権利と本案の訴訟物の同一性を証する書面を、それぞれ添付する。
担保の差押え
25 保全法第32条第3項((保全異議の申立てについての決定))、第38条第1項((事情の変更による保全取消し))、第39条((特別の事情による保全取消し))等の規定により仮差押え又は仮処分の取消しのための担保として金銭又は有価証券が供託されているとき(同法4条)は、滞納者の有する供託物取戻請求権を差し押さえることができる。
第2款 財産の調査
第141条関係 質問及び検査
質問及び検査をすることができる場合
1 法第141条の「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため、滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等(以下第141条関係において「財産の状況等」という。)を明らかにするため調査する必要があるときをいう。この場合において、質問の内容及び検査の方法等は、財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。
質問又は検査の相手方
(滞納者の財産を占有する第三者)
2 法第141条第2号の「滞納者の財産を占有する第三者」とは、正当な権限の有無にかかわらず、滞納者の財産を自己の占有に移し、事実上支配している第三者をいう。
(相当の理由)
3 法第141条第2号及び第3号の「相当の理由がある」場合には、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、滞納者の財産を占有し、又は滞納者と債権債務の関係を有し、若しくは滞納者から財産を取得したと認められる場合が含まれる。
(滞納者が株主又は出資者である法人)
4 法第141条第4号の「滞納者が株主又は出資者である法人」とは、滞納者が株主である株式会社又は滞納者が出資者である合名会社、合資会社、有限会社、各種協同組合、信用金庫、人格のない社団等をいう。
質問又は検査の方法
(質 問)
5 法第141条の「質問」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。この場合において、口頭による質問の内容が重要な事項であるときは、必ずてん末を記録することとし、そのでん末を記載した書類には答弁者の署名押印を求め、その者が署名押印をしないときは、その旨を付記しておくものとする。
(検査する帳簿書類)
6 法第141条の「財産に関する帳簿若しくは書類」とは、法第141条第1号から第4号までに掲げる者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の債権若しくは債務又は財産の状況等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類をいう。
(検査の時間の制限)
7 法第141条の「検査」には、捜索の場合と異なり、その時間の制限はないが、特に必要がある場合を除き、捜索の場合の時間の制限に準ずるものとする(第143条関係1から3まで参照)。
(身分証明書の呈示)
8 法第141条の質問又は検査に当たって関係者の請求があったときは、規則第3条(書式)に規定する別紙第12号書式の徴収職員証票を呈示しなければならない(法147条1項)。
罰則の適用
9 法第141条の質問及び検査については、法第188条及び第189条の規定による罰則の適用がある。
第142条関係 捜索の権限及び方法
捜索ができる場合
(滞納処分のため必要があるとき)
1 法第142条の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、差押財産の引揚げ、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(所 持)
2 法第142条第2項の「所持」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的継続及びその主体の意思を問わない(大正3.10.22大判)。
(引渡し)
3 法第142条第2項の「引渡をしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に引き渡さないときをいい、法第58条第2項((第三者が占有する動産の引渡命令))の規定により引渡命令を受けた者又は第60条第1項((差押動産の保管))の規定により保管する者が引渡しをしないときに限られない。
(相当の理由)
4 法第142条第2項第2号の「相当の理由がある場合」には、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、財産を所持すると認められる場合が含まれる。
捜索ができる物及び場所
(滞納者又は第三者の物)
5 捜索ができる「物」には、滞納者又は上記3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、長持、封筒等がある。
(滞納者又は第三者の住居その他の場所)
6 捜索ができる「場所」には、滞納者又は上記3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、工場、納屋、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋があり、また建物の敷地はもちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置されるものが含まれるものとする。
また、解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索ができる「場所」に含まれる(昭和45.4.14東京高判参照)。
捜索の方法
(戸、金庫等の開扉)
7 徴収職員は、滞納者又は上記3に規定する者の物又は住居等の捜索に当たり、閉鎖してある戸、扉、金庫等を開かせなければ捜索の目的を達することができない場合には、その滞納者又は上記3に規定する者に開かせ、又は自ら開くことができる(法142条3項)。ただし、徴収職員が自ら開くのは、滞納者又は上記3に規定する者が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るものとする。
(必要な処分)
8 法第142条第3項の「必要な処分」とは、徴収職員が自ら開扉するための錠の除去等をいう。この場合の錠の除去等は、必要に応じて第三者(上記3に規定する者を除く。)にさせることができる。
なお、これらの処分をするに当たっては、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。
(立会人)
9 捜索をする場合には、法第144条((捜索の立会人))の規定により、立会人を置かなければならない。
(捜索調書)
10 捜索をした場合における捜索調書の作成等については、第146条関係に定めるところによる。
時効の中断
11 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判)。この場合において、法第142条第2項の規定により第三者の住居等を捜索したときは、捜索をした旨を捜索調書の謄本等により滞納者に対して通知しなければ、時効中断の効力を生じない(通則法72条、民法155条)。
刑法との関係
12 捜索に際して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条((公務執行妨害等))の規定の適用がある。
第143条関係 捜索の時間制限
捜索の時間の制限
(日出と日没)
1 法第143条第1項の「日出」又は「日没」とは、太陽面の最上点が地平線上に見える時刻を標準とするものであって、その地方の暦の日の出入をいう(明治34.10.7大判、大正11.6.24大判)。
(捜索の継続)
2 日没前に捜索に着手した場合には、その捜索に着手した物又は住居その他の場所の捜索は、日没後まで継続することができる(法143条1項ただし書)。
(休日の捜索)
3 日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日その他一般の休日において個人の住居に立ち入って行う捜索については、特に必要があると認められる場合のほかは、行わないものとする(執行法8条1項、第47条関係19参照)。
日没後の捜索
(捜索ができる場所)
4 法第143条第2項の「夜間でも公衆が出入することができる場所」とは、旅館及び飲食店のほか、次に掲げるものを含む。 (1) 待合、バー及びキャバレー
(2) 映画館、演劇場その他の興行場
(捜索ができる場合)
5 法第143条第2項の「滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるとき」とは、例えば、捜索の相手方が夜間だけ在宅又は営業し、あるいは、財産が夜間だけ蔵置されている等の事情が明らかである場合又は滞納者が海外に出国することが前日に判明した場合等滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由がある場合をいう。
(公開した時間内)
6 法第143条第2項の「公開した時間内」は、営業時間内に限られるものではない。
第144条関係 捜索の立会人
立会人を置くべき場合
1 法第144条の「捜索」とは、法第142条の((捜索の権限及び方法))の規定による捜索処分をいい、捜索をする場合には、必ず立会人を置かなければならないが、捜索を必要としない不動産その他の財産の差押えに当たっては、立会人を必要としない。
立会人の範囲
(滞納者、第三者等)
2 法第144条の「滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者」とは、法第142条第1項((滞納者の住居等の捜索))の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける滞納者又は滞納者の同居の親族若しくは滞納者の使用人その他の従業者をいい、同条第2項((第三者の住居等の捜索))の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける第三者又はその第三者の同居の親族若しくはその第三者の使用人その他の従業者をいう。
(同居の親族)
3 法第144条の「同居の親族」とは、滞納者又は第三者と同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。
(使用人その他の従業者)
4 法第144条の「使用人その他の従業者」とは、事務員、工員、よう人その他滞納者又は第三者との雇用契約等に基づき従業している者をいう。
(相当のわきまえのあるもの)
5 法第144条の「相当のわきまえのある」とは、上記3及び4に規定する者が捜索の立会いについての事理を弁識することのできる相当の能力を有することをいい、成年に達した者であることを要しない。
(市町村の吏員)
6 法第144条の「市町村の吏員」とは、捜索をする場所の所在する市町村(特別区を含む。)における地方自治法第173条((吏員の種類))に規定する吏員をいう。したがって、都道府県の吏員はこれに該当しない。
(警察官)
7 法第144条の「警察官」は、なるべく捜索をする場所を管轄する警察署(下部機構を含む。警察法53条参照)の警察官(同法55条参照)とするものとする。
(税務署の職員)
8 税務署の職員については、他に立会人を求めることができない場合等真にやむを得ない事情がある場合を除き、立会人としないものとする。
第145条関係 出入禁止
出入禁止をすることができる場合
1 法第145条の「これらの処分をする間」とは、捜索、差押処分又は搬出をする場合において、これらの行為に必要な手続が完了するまでの間をいう。
なお、差押財産の搬出は、差押処分後直ちに財産の搬出をする場合に限らず、差押財産を滞納者又は第三者に保管させた後においてその財産の搬出をする場合をも含むものとする。
出入りが認められる者
(差押財産を保管する第三者)
2 法第145条第2号の「差押に係る財産を保管する第三者」とは、法第60条((差し押えた動産等の保管))、第71条第5項(占有した自動車等の保管)等の規定により差押財産を保管させている第三者をいう。
(同居の親族)
3 法第145条第3号の「同居の親族」とは、滞納者又は法第145条第2号の第三者と、それぞれ同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。
(滞納者を代理する権限を有する者)
4 法第145条第4号の「国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者」とは、課税標準等の申告、納税の猶予等の申請、不服申立て又は訴えの提起等、税務に関する事項について、契約又は法律により滞納者に代理してその行為ができる者をいい、例えば、その滞納者から委任を受けた税理士、弁護士、納税管理人等又は法律の規定により定められた親権者、後見人等をいう(民法818条、839条から842条まで、破産法157条等参照)。
出入禁止の方法
(出入禁止の意義)
5 法第145条の「出入することを禁止することができる」とは、徴収職員の許可を得ないで捜索、差押処分又は搬出を行う場所へ出入りすることを禁止すること及びその場所にいる者を退去させることができることをいう。
(出入禁止の掲示)
6 徴収職員は、出入りを禁止した場合には、掲示、口頭その他の方法により、出入りを禁止した旨を明らかにするものとする。
(出入禁止に従わない場合)
7 徴収職員の出入禁止命令に従わない者に対しては、扉を閉鎖する等必要な処置をとることができるものとするが、身体の拘束はできない。
刑法との関係
8 徴収職員の出入禁止命令に関連して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条((公務執行妨害等))の規定の適用がある。
第146条関係 捜索調書の作成
捜索調書の作成
(捜索調書)
1 法第146条第1項の「捜索調書」とは、令第52条第1項各号((捜索調書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第11号書式による。
(記載事項の省略)
2 令第52条第1項ただし書((捜索調書の記載事項の省略))の規定により同項第2号に掲げる事項の記載を省略する場合は、差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書が滞納者又は第三者に交付された後に、差押財産の搬出をするために捜索をした場合等である。
(その他必要な事項)
3 令第52条第1項第5号((捜索調書の記載事項))の「その他必要な事項」とは、捜索した物又は住居その他の場所を特定するために必要な事項(名称又は所在を除く。)をいう。
(立会人の署名押印)
4 捜索調書を作成する場合には、捜索調書に法第144条((捜索の立会人))の立会人の署名押印を求めなければならず、また立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない(令52条2項)。
(差押財産を搬出した場合の捜索調書)
5 滞納者又は第三者が保管している差押財産を搬出するに当たって捜索した場合には、捜索調書に差押財産の搬出をした旨を付記しなければならない(令26条の2第2項)。
捜索調書を作成しない場合
6 法第54条((差押調書))の規定により差押調書を作成する場合には、法第146条第1項の規定による捜索調書の作成及び同条第2項の規定による謄本の交付の必要はない(法146条3項前段)。この場合には、差押調書の謄本を、捜索を受けた第三者及びその第三者以外の立会人があるときはその立会人に、交付しなければならない(法146条3項後段)。
第147条関係 身分証明書の呈示等
身分証明書の呈示
(差押え等の場合の身分証明書の呈示)
1 法第147条の規定の適用がある場合以外で、差押えをしようとするとき等においても、滞納者等から請求があったときは、身分証明書を呈示するよう取り扱うものとする。
(身分を示す証明書)
2 法第147条第1項の「身分を示す証明書」とは、規則第2条第1項((身分証明書の交付))の規定により交付を受けた規則第3条((書式))に規定する別紙第12号書式の「徴収職員証票」をいう。
(関係者の範囲)
3 法第147条第1項の「関係者」とは、法第141条((質問及び検査))の規定による質問若しくは検査又は第142条((捜索の権限及び方法))の規定による捜索を受ける者をいう。
なお、出入禁止を受けた者、立会人等上記の処分に直接の関係を有する者から請求があった場合にも、身分証明書を呈示する。
(請求と呈示)
4 関係者が身分証明書の呈示を求めず、捜索等に応じたときは、その呈示がなくてもその処分は違法ではないが、関係者が身分証明書の呈示を求めたときは、それを呈示しなければその処分を執行することができない。
第1節 財産の差押え
第1款 通 則
第47条関係 差押えの要件
違法性の承継
(滞納処分相互間)
1 督促又は差押処分の違法性は、その後おける差押え、換価又は配当処分に承継される(大正15.7.20行判、昭和9.7.24行判)。
(賦課処分との関係)
2 賦課処分と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、賦課処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、賦課処分が取り消すことのできるものであっても、その処分が取り消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また賦課処分が取り消されても、その取消し前に完結した滞納処分の効力には影響がない(昭和26.2.28鳥取地判、昭和26.7.4広島高判、昭和39.4.16仙台高判)。
(納付通知書による告知との関係)
3 第二次納税義務者及び保証人に対する納付通知書による告知(以下3において「告知」という。)と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、告知処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、告知処分が取り消すことのできるものであっても、その処分が取消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また告知処分が取り消されても、その取消し前に完結した滞納処分の効力には影響がない(昭和37.3.23大阪地判)。
差押えをすることができる者
4 法第47条の「徴収職員」とは、法第2条第11号((徴収職員の定義))に掲げる徴収職員のうち、差押えをする際における納税者の国税の納税地を所轄する税務署に所属する徴収職員をいい(通則法43条1項)、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる徴収職員をいう。なお、滞納処分の引継ぎ(法182条2項、183条2項、3項)を受けた税務署、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)又は税関(沖縄地区税関を含む。以下同じ。)に所属する徴収職員も、法第47条の「徴収職員」に含まれる。 (1) 通則法第43条第2項((納税地の移動があった場合の国税の徴収の所轄庁))の規定により税務署長が国税の徴収に係る処分をする場合その税務署に所属する徴収職員
(2) 通則法第43条第3項((徴収の引継ぎ))又は第44条第1項((徴収の引継ぎ))の規定により税務署長、国税局長又は税関長が徴収の引継ぎを受けた場合その引継ぎを受けた税務署、国税局又は税関に所属する徴収職員
(3)
通則法第43条第1項ただし書((税関長が課する消費税等の徴収の所轄庁))の規定により税関長が消費税等の徴収をする場合 その税関に所属する徴収職員
差押えの対象となる財産
(財産の帰属)
5 差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に帰属しているものでなければならない(20参照)。
(財産の所在)
6 差押えの対象となる財産は、法施行地域内にあるものでなければならない。
なお、財産の所在については、相続税法第10条((財産の所在))に定めるところに準ずるものとする。
(財産が金銭的価値を有すること)
7 差押えの対象となる財産は、金銭的価値を有するものでなければならない。
なお、次のことに留意する。 (1) 金銭又は物の給付を目的としない行為(例えば、演奏をすること)又は不作為(例えば、競業をしないこと)を目的とする債権は、差押えの対象とならない。ただし、これらの債権が債務不履行等により損害賠償請求権となった場合には、差し押さえることができる。
(2) 金銭又は物を第三者に給付することを請求する債権は、納税者にとって金銭的価値を有しないから、差押えの対象とならない。ただし、これらの債権が債務不履行等により納税者の損害賠償請求権となった場合には、差し押さえることができる。
(財産が譲渡又は取立てができるものであること)
8 差押えの対象となる財産は、譲渡又は取立てができるものでなければならない。
なお、次のことに留意する。 (1) 有価証券のうち、指図禁止の手形及び小切手については、手形法第11条第2項((指図禁止の場合の譲渡の方式等))又は小切手法第14条第2項((指図禁止の場合の譲渡の方式等))の規定により、指名債権の譲渡に関する方式に従い、かつ、その効力をもってだけ譲渡することができる(民法467条、468条参照)。したがって、当該手形等に係る債権は、法第62条((差押の手続及び効力発生時期))の規定により差し押さえることができる。
(2) 相続権、扶養請求権、慰謝料請求権、財産分与請求権等は、納税者の一身に専属する権利であるから、譲渡することができない。ただし、その権利の行使により、金銭債権等の具体的債権となったときは、その債権を差し押さえることができる。
(3) 要役地の所有権に従たる地役権又は債権に従たる留置権、先取特権、質権若しくは抵当権は、主たる権利とともにするのでなければ譲渡することができない。したがって、これらの権利は、独立したものとして差し押さえることができない。 (注)1 抵当権については、民法第375条((抵当権の処分))の規定により譲渡することができるが、この譲渡には、滞納処分による権利の移転は含まれない。
2 根抵当権は、民法第398条ノ2((根抵当権の譲渡))の規定により元本の確定前は根抵当権設定者の承諾を得て譲渡することができるが、この譲渡には、滞納処分による権利の移転は含まれない。
(譲渡禁止の特約がある財産の差押え)
9 譲渡禁止の特約がある財産でも、差し押さえることができる。 (注) 譲渡禁止の特約が登記されている永小作権の換価は、永小作権設定者の同意を得てその特約の登記を抹消した後でなければ、することができない(民法272条ただし書、不動産登記法112条)。
差押えができる場合
(督促をした場合)
10 法第47条第1項第1号の「督促」とは、通則法第37条((督促))の規定による督促状による督促及び法第32条第2項((納付催告書による督促))又は通則法第52条第3項((納付催告書による督促))の規定による納付催告書による督促をいう(法47条3項参照)。滞納者がこの督促を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。
(公示送達による場合)
11 督促状又は納付催告書を公示送達により送達した場合は、通則法第14条第2項((公示送達の場合の掲示))の掲示を始めた日から起算して10日を経過した日までに督促に係る国税が完納されないときに、差押えができるものとする。
(納期限)
12 法第47条第1項第2号の「納期限」とは、次に掲げるものをいう。
なお、延滞税及び利子税の納期限は、その計算の基礎となる国税の納期限とされている(通則法37条1項本文)。 (1) 繰上請求がされた国税(通則法38条1項)繰上請求に係る期限 (注) 繰上請求は、繰上げに係る期限等を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で、納税の告知がされていないものについては、その請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う(通則法38条2項)。
(2) 繰上保全差押金額の決定の基因となった国税(通則法38条3項前段参照) その国税の納期限
(3) 保全差押金額の決定の基因となった国税(法159条1項前段参照) その国税の納期限 (例) 保全差押金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60万円
確定した国税(各種加算税を含む。第159条関係21の
(注)1参照)の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
この場合の決定の基因となった国税は、100万円である。
(4) 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税(第2条関係21参照)納税告知書に記載された納期限
(完納しないとき)
13 法第47条第1項の「完納しないとき」とは、納税者又は滞納者その他第三者の納付又は充当により、国税の全額が納付されていない場合のほか、免除又は賦課の取消し等により、徴収しようとする金額に係る国税の全額が消滅していないときをいう。なお、本税額の全額が納付され、延滞税又は利子税だけが未納である場合には、督促がされている延滞税又は利子税だけについて差し押さえることができる(通則法37条1項、3項)。
(繰上差押え)
14 法第47条第2項の繰上差押えについては、次のことに留意する。 (1) 「直ちにその財産を差し押さえることができる」とは、督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日以前でも督促に係る国税につき納税者の財産を差し押さえることができることをいう。
(2) 「国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたとき」には、督促以前に生じた事実が督促後まで継続しているときも含まれる。
(3) 繰上差押えをする場合には、差押調書又は差押書の「備考」欄にその旨を付記するものとする。
(賦課等の処分が争われている場合の差押え)
15 課税に関する処分、告知又は督促について、不服申立て又は訴訟が係属中であつても、その処分の取消しがされるまでは、その不服申立て又は訴訟に係る国税についての差押えをすることができる(通則法105条1項、行政事件訴訟法25条1項)。
差押えができない場合
16 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる期間内は、新たな差押えをすることができない。
なお、納税者が、保全差押金額又は繰上保全金額に相当する担保を提供して、保全差押え等をしないことを求めたときは差押えをすることができず(法159条4項、通則法38条4項)、また、換価の猶予に伴い差押えを猶予した場合又は不服申立てに伴い差押えを猶予した場合には差押えをすることができない(法151条2項、通則法105条3項、6項)。 (1) 納税の猶予(通則法46条1項から3項まで、会社更生法122条1項)又は徴収の猶予(通則法23条5項、105条2項、6項、所得税法118条、相続税法40条1項、42条5項、資産再評価法87条5項、会社更生法122条1項等)をしている場合 その猶予に係る国税につきその猶予期間
(2) 滞納処分の停止(法153条)をしている場合 その停止に係る国税につきその停止期間
(3) 滞納処分等の中止命令がされた場合(会社更生法37条2項、3項)又は更生手続の開始決定に伴う滞納処分等の中止の場合(同法67条2項、3項) その国税につき滞納処分の中止期間
(4) 企業担保権の実行手続の開始決定があった場合(企業担保法28条参照) その係属期間
(5) 破産宣告を受けた場合(37参照) その係属期間
財産の選択
17 差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量によるが、次に掲げる事項に十分留意して選択を行うものとする。この場合において、差し押さえるべき財産について滞納者の申出があるときは、諸般の事情を十分考慮の上、滞納処分の執行に支障がない限り、その申出に係る財産を差し押さえるものとする。 (1) 第三者の権利を害することが少ない財産であること(第49条関係参照)。
(2) 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。
(3) 換価に便利な財産であること。
(4) 保管又は引揚げに便利な財産であること。
(5) 価額の変動が少ない財産であること。
差押えの時期
(着手前の催告)
18 督促状もくしくは納付催告書又は譲渡担保権者に対する告知書を発した後6月以上を経て差押えをする場合には、あらかじめ、催告をするものとする。
(夜間、休日の差押え)
19 夜間及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日において個人の住居に立ち入つて行う差押えについては、特に必要があると認められる場合のほかは、これらの時間は又は日において行わないものとする(執行法8条1項参照)。
財産帰属の認定
(一般の帰属認定)
20 財産が滞納者に帰属するかどうかの判定は、次に掲げる事項を参考として行うものとする(5参照)。 (1) 動産及び有価証券にあつては、滞納者が所持していること(民法186条参照)。ただし、他人の所有に属することが明らかなものを除くこと。
なお、有価証券の所持人が取立委任裏書又は質入裏書の被裏書人である場合には、その所持人の財産としてその有価証券を差し押さえることはできないこと。
(2) 登録公社債等にあっては、登録名義が滞納者であること(国債二関スル法律3条、社債等登録法5条1項)。
(3) 登記された不動産、船舶、建設機械、自動車、航空機及び電話加入権、地上権、鉱業権等の権利並びに特許権その他の無体財産権等については、登記の名義人が滞納者であること。
(4) 未登記の不動産所有権その他の不動産に関する権利及び未登録の著作権については、その占有の事実、家屋補充課税台帳(又は家屋台帳)、土地補充課税台帳(又は土地台帳)その他帳簿書類の記載等により滞納者に帰属すると認められること。
(5) 合名会社及び合資会社の社員の持分については、定款又は商業登記簿における社員の名義が滞納者であること(商法12条、63条、64条、67条、147条、商業登記法60条、71条、74条等参照)。
(6) 有限会社の社員の持分については、定款又は社員名簿における名義人が滞納者であること(有限会社法6条、20条)。
(7) 債権については、借用証書、預金通帳、売掛帳その他取引関係帳簿書類等により、滞納者に帰属すると認められること。
(滞納者の名義でない場合の帰属認定)
21 20の(1)から(3)までに掲げる財産並びに(5)及び(6)に掲げる財産については、所持している者又は登記の名義人(以下21において「名義人等」という。)が滞納者でない場合であつても、帳簿書類、当事者の陳述等に基づき次に掲げる事項が明らかであるときは、その財産は、滞納者に帰属しているのであるから、滞納者の財産として差し押さえることができる。この場合においては、登記の名義を滞納者に変更させる必要がある。 (1) その財産が売買、贈与、交換、出資、代物弁済等により、滞納者に譲渡されたこと。
(2) 滞納者がその財産を仮装売買等無効な法律行為により、名義人等に譲渡したこと。
(3) 相続、包括遺贈又は合併に基づく一般承継により、財産の所有権が滞納者に移転していること。
(4) 上記を除くほか、権利が滞納者に帰属しているにもかかわらず、登記の名義が滞納者以外の者となつていること。 (注) 農地の所有権を移転する場合には、農業委員会又は都道府県知事の許可がない限りその効力を生じないが、この許可を得ている場合においても、虚偽表示により所有名義人となっているにすぎない者は、農地の所有権を取得しない(昭和52.2.17最高判参照)。
(夫婦又は同居の親族の財産の帰属認定)
22 滞納者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下(3)及び(4)において同じ。)又は同居の親族が主として滞納者の資産又は収入によって生計を維持している場合には、その滞納者の住居にある財産は、その滞納者に帰属するものと認定して差し支えない。ただし、次に掲げる財産はこの限りでない。 (1) 配偶者が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名において得た財産(民法762条1項)
(2) 配偶者が登記された夫婦財産契約に基づき所有する財産(民法756条、夫婦財産契約登記取扱手続参照)
(3) (1)及び(2)に掲げる財産以外の財産で配偶者又は親族が専ら使用する財産(昭和12.6.17行判)
(4) 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産についての配偶者の持分(民法762条2項参照)
特殊な財産の差押え
(共有財産)
23 差し押さえるべき財産が法律の規定又は当事者の意思表示により共有となっている場合において、それぞれの持分が定まっていないとき(持分が明らかでないときを含む。)は、その持分は等しいものと推定して差し押さえることができる(民法250条参照)。
(取消しうべき法律行為又は契約の解除の目的となった財産)
24 滞納者が、その財産について、売買、贈与その他による譲渡又は権利の設定等をした場合において、その譲渡等の行為が取消しうべき行為(民法4条2項、9条、12条3項、96条1項及び2項等)であるとき又は契約を解除(同法541条、542条、543条等)できるときは、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者の代位))の規定により滞納者に代位してその行為を取り消し、又はその契約を解除し、その財産を滞納者の財産として差し押さえることができる。ただし、その行為の取消し又は契約の解除の効果を第三者に対して主張できない場合がある(民法96条3項、545条1項ただし書等参照)。
(条件付又は期限付の譲渡の目的となった財産)
25 差し押さえた財産が、差押えの当時条件付又は期限付の売買、贈与等の譲渡の目的となつていた場合(民法129条参照)においては、差押え後、その条件の成就又は期限の到来により権利を取得した者は、その権利の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができない(大正6.4.10行判)。ただし、その権利を保全する仮登記が差押え前からあるときは、その権利の取得をもって差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(売買予約の目的となった財産)
26 差し押さえた財産が、差押えの当時売買予約の目的となっていた場合には、差押え後におけるその売買を完結する意思表示により所有権を取得した者は、その所有権を持って差押債権者である国に対抗することができない。ただし、その権利を保全する仮登記が差押え前からあるときは、その所有権の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(買戻しの特約等の目的となった財産)
27 差し押さえた財産が、差押えの当時買戻しの特約又は再売買の予約の目的となっていても、差押え後における買戻権の行使又は再売買の予約完結権の行使による所有権の取得をもって、差押債権者である国に対抗することができない。ただし、買戻の特約の登記(民法581条1項、不動産登記法37条、59条ノ2)又は再売買の予約に係る所有権移転請求権の仮登記(不動産登記法2条2号)が差押え前にあるときは、その所有権の取得をもつて差押債権者である国に対抗することができる(不動産登記法7条2項)。
(譲渡担保財産)
28 譲渡担保財産は、譲渡担保権者に属する財産としてその譲渡担保権者の滞納国税につき差し押さえることができ、またその譲渡人の滞納国税につき法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により差し押さえることができる(令9条参照)。
(信託の目的となつた財産)
29 信託の目的となつた財産は、信託の終了又は解除があったときは、信託財産の帰属権利者の財産として差し押さえることができる(信託法61条、62条参照)。
なお、信託法第57条((信託の解除))の規定に該当する場合には、委託者又はその相続人の滞納国税を徴収するため、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者の代位))の規定により委託者又はその相続人に代位して信託を解除することができ、また信託法第58条((信託の解除))の規定に該当する場合には、受益者の滞納国税を徴収するため、受益者に代位して、裁判所に対し信託の解除を請求することができる。 (注) 納税者(委託者)が、国税の差押えを免れるため自己の財産を信託の目的とした場合には、信託法第12条((信託による詐害行為の取消し))の規定により、その信託契約の取消しを裁判所に請求することができる。この場合においては、譲受人(受託者)が善意であっても取消しを請求することができる。
(担保のための仮登記のある財産)
30 25から27までにおける仮登記が担保のための仮登記である場合には、法第23条((法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等))及び第52条の2((担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力))の規定が適用される。
(仮差押え又は仮処分の目的となった財産)
31 仮差押え又は仮処分の目的となっている財産については、法第140条((仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力))の規定により、滞納処分をすることができる。
(強制管理の目的となった財産)
32 強制管理の開始決定(執行法93条)の目的となつた不動産及び当該不動産の果実についても、滞納処分をすることができる。
(滞調法の適用を受ける財産)
33 強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている財産についても、滞調法の規定(21条、29条、35条等)により、滞納処分をすることができる。
(和議の開始された者の財産)
34 和議の開始された者の財産については、国税は和議債権ではないし(和議法42条参照)、また滞納処分ができない旨の規定がないので(同法40条参照)、滞納処分をすることができる。
(整理又は特別清算の開始された会社の財産)
35 商法第381条((整理の開始))又は第431条((特別清算の開始))の規定による整理又は特別清算の開始があつた場合の会社の財産については、国税は同法第383条第2項((破産、和議、強制執行、保全処分等の中止))(433条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないから、滞納処分をすることができる。
(法令等による譲渡制限がある財産)
36 麻薬類、銃砲・刀剣類等その譲渡若しくは所有等について法令上制限が付されている財産(第89条関係14から27まで参照)又は定款によつて譲渡制限の付されている株式(商法204条1項、204条ノ5)についても、滞納処分をすることができる。
(留置権による競売の開始された財産)
37 滞納者の財産について留置権による競売が開始された場合には(執行法195条参照)、滞納者が留置権者に対して有する残余金の交付請求権を差し押さえるものとする。 (注) 留置権による競売に対しては、交付要求をすることができない(第2条関係26の(注)参照)。
(未分離の果実)
38 農作物等土地から分離する前の天然果実については、おおむね1月以内に収穫することが確実であるものを除き、差押えをしないものとする(執行法122条1項参照)。
破産宣告を受けた者の財産に対する滞納処分
(破産管財人に対する交付要求)
39 滞納者が破産宣告を受けた場合(破産法1条参照)には、その滞納者の破産財団(同法6条参照)に属する財産に対しては、財団債権である国税による新たな滞納処分は行わないものとし、破産管財人に対して交付要求をする(昭和45.7.16最高判参照)。 (注)1 財団債権である国税とは、破産宣告前の原因に基づく国税及び破産宣告後の原因に基づく国税のうち破産財団に関して生じたものをいう(破産法47条2号)。
2 破産管財人が交付要求に応じない場合には、破産裁判所に破産管財人に対する監督権の発動を促し、必要に応じ、破産管財人に対する損害賠償の責任を追及する(破産法161条、164条参照)。
(滞納処分の続行)
40 破産財団に属する財産について、破産宣告前に滞納処分に着手しているときは、破産宣告後も、その続行をすることができる(破産法71条1項)。この続行できる滞納処分には、破産宣告前に行つた参加差押え、債権の二重差押え(第62条関係6参照)及び滞調法の規定による二重差押えが含まれる。 (注) 破産宣告前に滞納処分の前提となる行為に着手している場合には、それに引き続いてする滞納処分、例えば、破産宣告前に捜索に着手した場合におけるそれに引き続いて行う差押え、詐害行為取消訴訟を提起した後に破産宣告があった場合におけるその勝訴に基づく差押え(昭5.11.29大判)は、破産宣告によって妨げられない。
(行政機関等に対する交付要求)
41 行政機関等が破産宣告前に着手した滞納処分を破産宣告後に続行する場合には、その行政機関等に対して交付要求を行い、参加差押えは行わないものとする。
(別除権の行使)
42 国税の担保として提供されている財産については、破産宣告後においても、別除権の行使として、通則法第52条第1項((担保の処分))の規定に基づく滞納処分の例による差押えをすることができる(破産法95条、203条1項参照)。
なお、私債権者の申立てにより別除権の行使として担保権の実行手続が開始された場合には、その執行機関に対して交付要求をする。また、行政機関等が、担保の処分として滞納処分の例による差押えをした場合においては、交付要求を行い、参加差押えは行わないものとする。 (注) 別除権とは、次のものをいう。 1 破産財団に属する財産について存する特別の先取特権、質権及び抵当権(電話加入権質に関する臨時特例法、工場抵当法等の特別法によるものも含む。)(破産法92条)
2 破産財団に属する財産について存する商法上の留置権(破産法93条)
3 共有者の一人が破産の宣告を受けた場合において、分割によりその破産者に帰すべき共有財産の部分について、他の共有者が破産者に対して有する共有に関する債権(破産法94条)
4 破産財団に属する財産について存する担保仮登記に係る権利(仮登記担保法19条1項)
(破産後取得した財産)
43 破産宣告を受けた者が破産宣告後取得した財産については、破産財団に属さないから、滞納処分をすることができる。
なお、破産者は、国税については免責されない(破産法366条ノ12第1号)。
会社更生法の適用を受ける会社の財産に対する滞納処分
(開始決定前の滞納処分等の中止命令)
44 更生手続開始の申立てがあつた場合において、更生裁判所は、必要があると認めるときは、あらかじめ税務署長に意見を聞いた上で滞納処分又は国税の担保のために提供された物件の処分(以下45及び47において「滞納処分等」という。)の中止を命ずることができる(会社更生法37条2項)。ただし、その中止命令は、更生手続開始の申立てにつき決定があったとき又は中止の決定の日から2月を経過したときは、その効力を失う(同法37条3項)。
(開始決定による滞納処分等の中止等)
45 更生手続開始の決定があつたときは、その決定の日から更生計画認可若しくは更生手続終了までの間又はその決定の日から1年間(税務署長に同意を得た上で伸長されることがある。会社更生法67条3項、4項)か、いずれか短い期間内は、共益債権となる国税(48の(注)参照)を除き滞納処分等はすることができず、既にされている滞納処分等は中止される(同法67条2項)。
なお、更生裁判所は、中止した滞納処分等の続行又は取消しを命ずることができる(会社更生法67条6項)。 (注) 更生手続終了とは、開始決定の取消し(会社更生法51条)、更生手続の廃止(同法273条、273条の2,274条、277条)及び更生計画の不認可(同法238条)の各決定をいい、その効力は、公告の最終の掲載があつた日の翌日から生ずる(同法12条2項)。
(更生計画における納税の猶予、減免等)
46 更生計画において、国税について納税の猶予、換価の猶予、減免、承継その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、税務署長の意見を聞かなければならないとき(例えば、3年以下の期間の納税の猶予又は換価の猶予の定めをする場合等)と、その同意を得なければならないとき(例えば3年を超える期間の納税の猶予又は換価の猶予の定めをする場合等)とがある(会社更生法122条1項から3項まで)。
(共益債権となる国税以外の国税の徴収)
47 更生会社に対する共益債権である国税以外の国税については、原則として更生手続により弁済を受けることになるので(会社更生法112条)、税務署長は、遅滞なくその額、原因及び担保権の内容を更生裁判所に届け出なければならない(同法157条1項。241条参照)。
なお、滞納処分等又はその続行が許される場合等においては、更生手続によらずに弁済等を受けることがでできる(同法112条ただし書、112条の2第4項)。ただし、更生会社の財産が共益債権の総額を弁済するに足りないことが明らかになつた後は、新たな滞納処分等又は中止していた滞納処分等の続行は行わないものとする(昭和56.5.6大阪高判)。また、共益債権である国税以外の国税について、更生会社が税務署長に対して行つた担保の供与又は債務の消滅に関する行為は、否認権の対象とならない(同法78条2項)。 (注) 共益債権となる国税以外の国税としては、更生債権となる国税(更生手続開始前の原因に基づいて生じた国税。会社更生法102条)、更生担保権となる国税(更生債権となる国税又は更生手続開始前の原因に基づいて生じた更生会社以外の者に対する国税で、更生手続き開始当時更生会社財産の上に存する担保権によつて担保される国税。同法123条1項)及び劣後的更生債権となる国税(更生債権となる国税のうち、更生手続開始前の脱税が摘発され、開始後に刑罰に処せられ又は国税犯則取締法による通告処分を履行した場合におけるほ脱国税で届出のないもの。会社更生法121条1項6号)がある。
(共益債権となる国税の徴収)
48 共益債権となる国税については、更生手続によらないで更生債権及び更生担保権に先立つて随時弁済されるが(会社更生法209条)、更生管財人がこの弁済に応じないときは、更生手続中であつても滞納処分をすることができる(この場合における差押登記の嘱託の受理については、昭和42.9.7付民事甲第2,524号法務省民事局長通達参照)。ただし、更生会社の財産が共益債権の総額を弁済するに足りないことが明らかになつたときは、担保権によつて担保されるものを除き、まだ弁済されていない共益債権の債権額の割合に応じて弁済されることになるので(同法210条)、滞納処分はできないことに留意する(昭和54.2.16大阪地判)。
なお、共益債権である国税に劣後する担保権により、その実行手続が開始された場合には、その国税について執行機関に交付要求をする(同法210条参照)。 (注) 共益債権となる国税としては、次のものがある。 1 更生債権のうち、源泉徴収にかかる所得税、消費税、酒税等で、更生手続開始当時まだ具体的納期限の到来していないもの(同法119条前段、昭和49.7.22最高判)
2 更生手続開始後の会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用に該当する国税(例えば、更生手続開始後の原因に基づいて生じた法人税等。同法208条2号)
差押えの効力
(処分の禁止)
49 差押えは、滞納者の特定財産の法律上又は事実上の処分を禁止する効力を有するものである。したがつて、差押え後におけるその財産の譲渡又は権利設定等の法律上の処分は、差押債権者である国に対抗することができない。この場合において、差押えにより禁止される法律上又は事実上の処分は、差押債権者である国に不利益となる処分に限られるから、例えば、差押財産についての賃貸借契約の解除、差押財産の改良等の処分はこれに含まれない。なお、債権の差押えに当たっては、法第62条第2項((債権差押の手続))の規定により、処分禁止の趣旨を特に明示することとなつている。
(効力の保証)
50 差押えによる法律上又は事実上の処分の禁止は、法第187条((罰則))若しくは第189条((罰則))又は刑法第96条((封印破棄の罪))、第115条((放火の罪))、第120条第2項((溢水の罪))、第242条((窃盗及び強盗の罪)、第251条((詐欺及び恐喝の罪))、第252条第2項((横領の罪))若しくは第262条((毀棄の罪))の各規定により間接的に保証されている。
(効力の制限)
51 差押えによる法律上又は事実上の処分の禁止は、国、地方公共団体等の土地収用法、農地法等の規定に基づく土地収用、農地買収(未墾地等の買収に限る。)、没収(刑法19条等)等の処分を妨げるものでなく、かつ、これらの処分があつたときは、差押えの効力は失われる。
(差押え財産の消滅)
52 加入電話加入契約の解除により、電話加入権が消滅する場合(公衆電気通信法42条1項)、民法第958条((相続人捜索の公告))に規定する期間内に相続人である権利を主張する者がないことにより特許権が消滅する場合(特許法76条)等においては、その財産に係る差押えの効力は消滅することがある(実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条等)。
(時効の中断)
53 差押えに係る国税については、その差押えが効力を生じた時に時効が中断する(通則法72条3項、民法147条2号)。この場合における中断事由は、差押財産を換価した場合にはその権利が買受人に移転した時(債権取立てのときは弁済の効力が生じた時)まで、差押財産が滅失した場合(法53条1項の規定の適用がある場合を除く。)にはその滅失した時まで、差押えを解除した場合にはその解除をした時まで、それぞれ継続する。ただし、その差押えの手続が不適法を理由として取り消されたときは、時効中断の効力を生じない(民法154条)。
なお、第三者の占有する動産若しくは有価証券、物上保証人の財産若しくは法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により譲渡担保財産を差し押さえた場合又は法第22条第3項((質権等の代位実行))の規定により質権若しくは抵当権を実行した場合は、差押調書の謄本が滞納者に交付されたとき等差し押さえた旨等が滞納者に通知された時に時効が中断する(通則法72条3項、民法155条)。
(従 物)
54 主物を差し押さえたときは、その差押えの効力は従物に及ぶ(民法87条参照)。したがって、家屋を差し押さえた場合には、差押えの効力は、その家屋の従物となっている畳、建具等に及ぶ(第56条関係9参照)。
(果 実)
55 元物を差し押さえたときは、その差押えの効力は、原則として、天然果実に及ぶが、法定果実には及ばない(法52条)。
(相続等があった場合)
56 滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅した場合には、その滞納処分を続行することができるし、また滞納者の死亡を知らないで、滞納者の名義の財産を差し押さえた場合には、その差押えは、その財産を有する相続人に対してされたものとみなされる(法139条)。
(継続的な収入)
57 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入に対する債権の差押えの効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金額に及ぶ(法66条)。
(保険に付されている財産)
58 差押財産が損害保険に付され、又は火災共済協同組合の火災共済等の目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない(法53条1項)。
差押え財産を譲り受けた者に対する滞納処分
59 不動産に対し強制競売若しくは担保権の実行としての競売による差押え、仮差押え又は滞納処分による差押え(保全差押金額又は繰上保全差押金額に係る差押えを含む。以下59において同じ。)の登記があるまま、第三者に所有権移転の登記がされた場合には、当該第三者の国税を徴収するため、当該不動産に対し滞納処分による差押え(参加差押え又は滞調法29条の規定により行うことができる滞納処分による差押えで、当該第三者を滞納者とするものを含む。以下59において同じ。)をすることができる(この場合における差押登記の嘱託の受理については、昭和42.5.15付民事甲第299号法務省民事局長通達参照)。 (注) 上記の場合において、当該第三者を滞納者として行つた滞納処分による差押えに基づく換価は、譲渡人に対する差押え等の効力が失われるまでは行わない取扱いとする。
なお、次に掲げる事項に留意する。
(1) 不動産以外の登記を要する全ての財産についても、不動産と同様である。
(2) 所有権移転の登記が数次にわたつてされた場合において、その各譲受人が所有者である間に行う滞納処分についても同様である。
担保物処分の場合の差押え
60 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定による担保物の処分にあつては、督促を要しないで滞納処分の例による差押えをすることができる。
滞納処分費の差押え
61 滞納処分費だけが滞納となっている場合には、法第138条((滞納処分費の納入の告知))の規定による納入の告知の納期限後、督促を要しないで差押えをすることができる。
第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
超過差押えの禁止
(意 義)
1 法第48条第1項の規定は、徴収職員が第47条関係17の財産の選択基準に従い差押えをする場合において、国税の徴収に十分な価額の財産を選択し、差し押さえた時は、それ以外の財産の差押えをしてはならないことを定めたものである。
(財産の価額の計算)
2 1の財産の価額は、差し押さえようとする時の処分予定価額によるものとし、差押えに係る国税に優先する他の国税、地方税、公課その他の債権がある場合には、その処分予定価額からこれらの優先すると認められる債権の額に相当する金額を控除した後の価額によるものとする。
(不可分物)
3 差押財産が不可分物である場合には、その財産の価額が差押えに係る国税の額を超過するときであつても、その差押えは違法でない。
なお、上記の不可分物とは、おおむね次に掲げるものをいう。 (1) 物の性状から分割することができないもの(例えば、1個の動産)
(2) 分割することはできるが、分割することにより物の経済的価値を著しく害するもの(例えば、1棟の家屋)
(3) 法律上分割して売却することができないもの(例えば、工場財団の組成物件)
(滞納処分の引継ぎをしている場合の判定)
4 滞納処分の引継ぎをしている場合において、その引継ぎを受けた税務署長が差し押さえた財産がある時は、滞納処分の引継ぎをした税務署長が、当該財産を含めたところで超過差押えの有無を判定する取扱いとする。
無益な差押えの禁止
(財産の価額等)
5 法第48条第2項の「差し押さえることができる財産の価額」とは差押えをしようとする時における差押えの対象となる財産の処分予定価額を、「差押えに係る滞納処分費」とは差し押さえようとする財産に係る滞納処分費の見込額を、「徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額」とは差押えをしようとする時においてその差押えに係る国税に優先すると認められる他の国税、地方税、公課その他の債権のその時における債権額を、それぞれいうものとする。
(個別財産についての判定)
6 法第48条第2項の「合計額を超える見込がないとき」とは、差押えの対象となる財産についてそれぞれ個別に判定すると合計額を超える見込みがない場合をいうものとするが、これらの財産の全部又は一部を一体として判定すると合計額を超える見込みがある場合を含まないものとする。例えば、数個の不動産上に国税に優先する共同担保権が設定されている場合に、その不動産について個別に判定すると差押えに係る滞納処分費及びその被担保債権の合計額を超える見込みはないが、その数個の不動産の全部又は一部を一体として判定すると、その合計額を超える見込みのある場合は、無益な差押えにはならない。
第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
差し押さえる場合
1 法第49条の「差し押える」とは、法第47条((差押の要件))の規定により差押えをすることのほか、法第24条第3項((譲渡担保財産についての滞納処分))、第159条第1項((保全差押えによる差押え))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押えによる差押え))の規定による差押えをすることをいう。 (注) 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定に基づく滞納処分の例による差押えに当たつても、法第49条の規定の趣旨により取り扱うものとする。
滞納処分の執行上の支障
2 法第49条の「支障」とは、おおむね次に掲げる事項をいう。 (1) 第三者の権利がある財産以外に、差押えをすることができる適当な財産がないこと。
(2) 第三者の権利がある財産以外の差押えができる財産が、すべて換価の著しく困難な財産だけであること(第50条関係12参照)。
第三者の権利の保護
(第三者の権利)
3 法第49条の「第三者が有する権利」とは、第三者が有する質権、抵当権、先取特権、留置権、貸借権、使用貸借権、地上権、永小作権、地役権、租鉱権、入漁権、買戻権、出版権、特許権についての専用実施権、実用新案権についての専用実施権、意匠権についての専用実施権、商標権についての専用使用権等の権利をいう。
なお、上記の先取特権は、法第50条第1項((第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求))に規定する先取特権に限られない。
(権利の保護)
4 法第49条の「害さないように努めなければならない」とは、徴収職員が差押えをするに当たって通常の調査によって知った第三者の権利を害さないように努めることをいうのであって、第三者の権利を害さないための特別の調査までも行わなければならないことをいうものではない。
第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
差押換えの請求
(差押換えの意義)
1 法第50条第1項の「差押換」とは、第三者の権利(差押え前に取得したものに限る。)の目的となっている財産を差し押さえた場合において、次に掲げる要件を満たすときに、その第三者からの請求により国税の全額を徴収できる財産を差し押さえ、かつ、その第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除することをいう。 (1) 滞納者が他に換価の容易な財産で、請求者以外の第三者の権利(差押換えの請求以後に生じたものを含む。)の目的となっていないものを有していること。
(2) その財産により滞納者の国税の全額を徴収することができること。
(賃借権)
2 法第50条の「賃借権」とは、当事者の一方(賃貸人)が他方(賃借人)に対してある物を使用収益させることを約し、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約する契約(民法601条)により、賃借人が取得する権利をいう。
(その他第三者の権利)
3 法第50条第1項の「その他第三者の権利」とは、地上権、永小作権、地役権、租鉱権、入漁権、使用貸借権、出版権、買戻権その他滞納者の財産上に第三者が有する権利をいう。
(これらの先取特権)
4 法第50条第1項の「これらの先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))又は第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいう。
(換価の容易な財産)
5 法第50条第1項の「換価の容易な財産」とは、評価が容易であり、かつ、滞納処分との関係において市場性のある財産をいうが、その財産は、換価をするために直ちに差押えをすることができるものに限られる。
なお、債権については、確実に取り立てることができると認められるものも、換価の容易な財産に含まれるものとする。 (注) 上記の「債権」については、法第50条第3項及び第4項の規定が適用されることはない。
(滞納者の財産)
6 通則法第50条第6号の保証人の保証は、法第50条第1項の滞納者の財産には当たらない(昭和47.2.25広島高松江支判参照)。
(請求者以外の第三者の権利)
7 法第50条の「他の第三者の権利」とは、第49条関係3に掲げる権利(法19条1項各号及び20条1項各号に掲げる先取特権以外の先取特権を除く。)のうち、差押換えの請求をした者(以下第50条関係において「請求者」という。)以外の第三者の権利をいう。
(国税の全額)
8 法第50条第1項の「国税の全額」とは、法第50条第1項の権利を有する者が差押換えの請求をする時の滞納者の国税の全額をいう。したがって、差押えに係る国税だけでなく、差押え後に発生した国税で差押換えの請求のあった時に滞納になっているものも含まれる。 (注) 上記の国税には、延滞税も含まれることに留意する。
(請求の方法及び期限)
9 法第50条第1項の規定による差押換えの請求は、令第19条第1項各号((差押換えの請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、その請求に係る請求者の権利の目的となっている財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合にはその売却決定の時、また、その財産が金銭による取立ての方法により換価するものである場合にはその取立てが終わる時)までにしなければならない。
(請求を相当と認めるとき)
10 法第50条第2項の差押換えの「請求を相当と認めるとき」とは、請求者が差し押さえるべきことを請求した財産により滞納国税の全額を徴収することができると認められるときをいうが、次に掲げるときは、その請求を相当と認めるものとする。 (1) 滞納国税について他に差し押さえた財産がある場合において、その財産と請求者が差し押さえるべきことを請求した財産とにより滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(2) 差押換えの請求に係る差押えのほか、交付要求をしている場合において、その交付要求に基づく配当が比較的近い時期において確実に得られ、滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(3) 徴収職員において、新たに換価容易であり、かつ、第三者の権利の目的となっていないもので滞納国税の全額を徴収することができる財産を発見したとき。
(4) 請求者が2人以上いる場合において、各請求者が差し押さえるべきことを請求した財産を合計することにより、滞納国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(請求を相当と認めないとき)
11 税務署長は、法第50条第1項の規定による差押換えの請求を相当と認めないときは、その旨を請求者に通知しなければならない(法50条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
換価の申立てと換価制限
(申立ての方法及び期限)
12 法第50条第3項の規定による換価の申立ては、同条第2項の通知(11参照)を受けた請求者が、令第19条第2項各号((換価の申立ての方法))に掲げる事項を記載した書面により、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までにしなければならない(令19条2項)。なお、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法10条2項)。
(換価の著しく困難なもの)
13 法第50条第3項の「換価の著しく困難なもの」とは、その評価、換価手続、買受人への権利移転手続等が通常の換価の場合に比べて社会通念上著しく困難である財産をいい、換価をするための前提としての差押えが著しく困難なものも含まれる。
(換価に付した)
14 法第50条第3項の「換価に付した」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開いたことをいう。 (注) 公売期日を開いた場合には、入札者の有無を問わず「換価に付した」ことになることに留意する。
(法第48条との関係)
15 法第50条第1項の規定による差押換えの請求に基づく差押えのため一時的に超過差押えとなっても、法第48条第1項((超過差押えの禁止))の規定に反するものではない。
換価の申立てに応じない場合の措置
(前項の場合)
16 法第50条第4項の「前項の場合」とは、法第50条第2項の通知があった場合で、その通知を受けた請求者が、法第50条第3項の期限までに差し押さえるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てた場合において、その財産が換価の著しく困難なものでなく、かつ、他の第三者の権利(換価の申立てがあった後に生じたものを含む。)の目的となっていないときをいう。
(換価に付さない)
17 法第50条第4項の「換価に付さない」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開かないことをいう。
(通則法第1O条第1項との関係)
18 法第50条第4項の「申立てがあった日から2月」は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。
(換価について制限があるもの)
19 法第50条第4項の「国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするもの」については、第89条関係6と同様である。 (注) 上記の「国税に関する法律」とは、法その他の法律で、差押財産の換価の制限を規定しているすべての法律をいう。
(ただし書の意義)
20 法50条第3項の申立てがあった場合において、その申立てのあった日から2月の期間内に、申立てに係る財産の差押え及び換価が可能となったときは、法第50条第4項ただし書の規定は適用されない。
滞納処分の制限の解除
21 差押換えをしようとする場合に新たな差押え又は換価の申立てに係る財産の新たな差押えは、通則法その他国税に関する法律の規定により新たな差押えをすることができない場合であっても(第47条関係16参照)、することができる(法50条5項)。
第51条関係 相続があった場合の差押え
相続があった場合の差押え
(法第49条との関係)
1 法第51条の規定による相続人の権利と第三者の権利とが競合する場合には、第三者の権利を尊重するものとする(法49条、50条参照)。
(滞納処分の執行上の支障)
2 法第51条第1項の「支障」とは、おおむね次に掲げる事項をいう。 (1) 第三者の権利の目的となっている相続財産以外に、差押えをすることができる適当な相続財産がないこと。
(2) 第三者の権利の目的となっている相続財産以外の差押えができる相続財産が、すべて換価の著しく困難な財産(差押え困難なものを含む。)だけであること。 (注) 上記の「換価の著しく困難な財産」とは、例えば、弁済期が長期にわたるためその取立てが困難な債権、山間へき地にあたるため物理的に差押えが困難な土地、訴訟により所有権の帰属が争われており法律的に問題のある財産等をいう。
(限定承認等との関係)
3 限定承認(民法922条)があったときは、被相続人の国税の弁済の責任は相続財産の範囲に限定されるため(通則法5条1項後段)、その国税によって相続人の固有財産が滞納処分を受けることはない。 (注) 相続の放棄(民法938条)をした者については、被相続人の国税を承継しないため、法第51条の規定は適用がないことに留意する。
差押換えの請求
(換価が容易な相続財産)
4 法第51条第2項の「換価が容易な相続財産」については、第50条関係5と同様である。
(第三者の権利)
5 法第51条第2項の「第三者の権利」とは、第49条関係3に掲げる権利(法19条1項各号及び20条1項各号に掲げる先取特権以外の先取特権を除く。)このうち、差押換えの請求をした相続人以外の第三者の権利をいう。
(国税の全額)
6 法第51条第2項の「国税の全額」とは、納税義務の承継をした被相続人の国税の全額であり、納付責任のある国税も含まれる。
(請求の方法及び期限)
7 法第51条第2項の規定による差押換えの請求は、令第20条各号((差押換えの請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により相続人の固有財産で差し押さえられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合にはその売却決定の時、また、その財産が金銭による取立ての方法により換価するものである場合にはその取立てが終わる時)までにしなければならない。
(請求を相当と認めるとき)
8 法第51条第3項の差押換えの「請求を相当と認めるとき」とは、相続人が差し押さえるべきことを請求した相続財産により被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるときをいうが、次に掲げるときは、その請求を相当と認めるもとのする。 (1) 被相続人の国税について他に差し押さえた相続財産がある場合において、その財産と相続人が差し押さえるべきことを請求した相続財産とにより、被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(2) 差押換えの請求に係る差押えのほか、交付要求をしている場合において、その交付要求に基づく配当が比較的近い時期において確実に得られ、被相続人の国税の全額を徴収することができると認められるとき。
(3) 徴収職員において、新たに、換価容易であり、かつ、第三者の権利の目的となっていないもので被相続人の国税の全額を徴収することができる相続財産を発見したとき。
(4) 2人以上の相続人がそれぞれ差押換えを請求した場合において、差し押さえるべきことを請求した相続財産の価額が被相続人の国税に満たないときにおいても、その相続財産を一括換価(第89条関係5参照)することにより被相続人の国税を徴収することができると認められるとき。
(請求を相当と認めないとき)
9 税務署長は、法第51条第2項の規定による差押換えの請求を相当と認めないときは、その旨を差押換えを請求した相続人に通知しなければならない(法51条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(法第48条との関係)
10 法第51条第2項の規定による差押換えの請求に基づく差押えのため一時的に超過差押えとなっても、法第48条第1項((超過差押えの禁止))の規定に反するものではない。
(滞納処分の制限の解除)
11 差押換えをしようとする場合に新たな差押えは、通則法その他国税に関する法律の規定により新たな差押えをすることができない場合であっても(第47条関係16参照)、することができる(法51条3項、50条5項)。
第52条関係 果実に対する差押えの効力
天然果実に対する差押えの効力
(天然果実の意義)
1 法第52条第1項の「天然果実」とは、元物の用法に従い収取する産出物をいい(民法88条1項)、例えば、果実、野菜、牛乳、鶏卵、羊毛、動物の子又は石山から採取される石材等がある。
(天然果実に及ぶ)
2 法第52条第1項の「天然果実に及ぶ」とは、元物を差し押さえた場合には、新たな差押手続をすることなく、その差押えの効力が天然果実に及ぶことをいう。したがって、元物の差押えに基づきその天然果実の収取手続ができる。
(差押えの効力と果実の帰属)
3 天然果実に対して差押えの効力が及ぶのは、その果実が滞納者に帰属する場合に限られる。したがって、法律又は契約の定めるところに従って、その果実が滞納者以外の第三者に帰属する場合には、差押えの効力は及ばない。例えば、第三者が永小作権、賃借権等正当な権限により滞納者の土地を利用して収得する果実、野菜等の天然果実、不動産質権者が民法第356条((使用収益権))の規定により使用及び収益をすることができる場合の天然果実等には、差押えの効力は及ばない。
(差押時期との関係)
4 天然果実に対する差押えの効力は、差押え時における未分離の果実及び差押え時以後において生ずる果実に対して及ぶが、既に差押え時において分離されている果実に対しては及ばない。
なお、差押え時に既に分離されている天然果実は、元物とは別個の動産として差し押さえることができる。
(譲渡又は差押えのあった果実)
5 差押え時における未分離の天然果実には、次に掲げる場合には、差押えの効力が及ばない。 (1) 天然果実が差押え時に既に動産として譲渡され、明認方法によりその対抗要件を備えている場合
(2) 天然果実が差押え時に既に動産として差し押さえられ、明認方法によりその対抗要件を備えている場合
(差押財産を使用収益できる場合)
6 法第52条第1項の「滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合」とは、次に掲げる場合をいう。 (1) 滞納者又は使用若しくは収益をする権利を有する第三者が、法第61条第1項又は第2項((差し押さえた動産の使用収益))の規定により、差押動産の使用又は収益を許可された場合
(2) 滞納者又は使用若しくは収益をする権利を有する第三者が、法第69条第1項及び第2項((差押不動産の使用収益))の規定により、差押不動産につき使用又は収益をすることができる場合
(3) 動産の引渡命令を受けた第三者(動産の引渡しを拒まなかった第三者を含む。)で、使用又は収益をする権利を有する者が、法第59条第2項((引渡命令を受けた第三者の使用収益権))又は第4項((引渡しを拒まなかった第三者の権利の保護))の規定により、差押動産につき使用又は収益をすることができる場合
(換価財産の権利移転の時)
7 法第52条第1項の「その財産の換価による権利の移転の時」とは、換価財産の買受人が買受代金の全額を納付し換価財産を取得したときをいう(法116条1項、第116条関係2)。
(明認方法)
8 天然果実を収取する場合において、明認方法による対抗要件を必要とするもの(例えば、みかん等)については、立札、縄張その他適当な方法をもって明認方法を施すものとする。
(収取を必要としない場合)
9 天然果実を生ずる財産を差し押さえる場合で、元物だけで徴収すべき滞納国税を確保できると認められるとき、天然果実の収取が困難であると認められるときその他徴収上天然果実の収取の必要がないと認められるときは、天然果実に対して差押えの効力を及ぼさないことができる(昭和32.6.4前橋地判)。なお、天然果実に対し差押えの効力を及ぼさないこととする場合は、その旨を差押調書に明記するものとする。
(収取の方法)
10 天然果実を収取する場合には、徴収職員が白ら収取を行うこともでき、又は滞納者若しくは第三者をして収取させることもできる。この場合において、みかん等の果実は、成熟した後等通常の取引に適するようになってから収取するものとする(法90条1項、執行規則112条参照)。なお、天然果実を収取して搬出する場合の手続については、差押動産の搬出をする場合の手続と同様である(令26条の2参照)。
(捜索、出入禁止及び質問検査)
11 天然果実の収取行為は、差押えに付随する行為であるから、質問及び検査並びに捜索等をする場合には、法第5章第6節第2款((財産の調査))の規定が適用される。
(収取に伴う費用)
12 収取行為に伴う必要な費用は、財産の差押えに関する費用であるから、法136条((滞納処分費の範囲))の規定により滞納処分費として徴収することができる。
(未分離果実の換価)
13 未分離の天然果実は、元物とともに、又は元物とは別に換価することができる。ただし、みかん等の果実が元物から分離していない場合には、その果実が未成熟等通常の取引に適しない間は、法第90条第1項((換価の制限))の規定によりこれらの天然果実だけを換価することができないが、元物から分離した天然果実は、それだけを元物とは別に換価することができる。
法定果実に対する差押えの効力
(法定果実の意義)
14 法52条第2項の「法定果実」とは、元物の使用の対価として収取される金銭その他の物、例えば、家賃、地代、小作料、利息等をいう(民法88条2項)。
(利息)
15 法第52条第2項の「利息」とは、一定の元本債権から付随的に生ずる所得であって、元本債権に対する一定の利率をもって定期的に計算される金銭等をいい、元本の弁済期以後における遅延利息等利息の性質を有するものはこれに含まれるが、建設利息(商法291条)、終身定期金(民法689条)等はこれには含まれない。
(利息に対する差押えの効力)
16 元本債権の差押えの効力は、その差押え後に生ずる利息債権にも及ぶが(法52条2項ただし書)、差押え時までに発生した利息債権は、別に差し押さえない限り差押えの効力は及ばない(大正5.3.8大判参照)。したがって、利息支払時期前に差押えをした場合における利息債権に対する差押えの効力は、差押え後に発生する部分についてだけ効力が及ぶ(民法89条2項)。
(法定果実に対する差押え)
17 差押えの効力は、差押財産(債権を除く。)から生ずる法定果実に及ばないから、元物の差押えとは別に債権差押えの方法により法定果実の差押えを行う必要がある(法52条2項参照)。
(利息制限法による利息の制限)
18 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が一定の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は無効となるから(利息制限法1条1項)、その部分の支払を請求することはできない。
なお、契約成立の際に第三債務者が利息として上記の超過部分の金額を前払しても元本に充てたものとみなされ(利息制限法2条)、また、第三債務者から超過分の任意の支払を受けたときは、その超過部分は、残存元本に充当(民法491条)され、元本充当の結果、計算上元利合計を超える部分の金額については、利息制限法第1条第2項及び第4条第2項の適用はなく、第三債務者は、民法の規定するところにより、債権者(滞納者)に対し、不当利得の返還を請求することができる(昭和43.11.13最高判、昭和44.11.25最高判)。 (注)1 金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、上記の「利息」に含まれる(利息制限法3条)。
2 利息制限法所定の制限を超える利息の定めのある金銭消費貸借において、遅延損害金について特約がないときのその利率は、同法第1条第1項所定の利率にまで減縮される(昭和43.7.17最高判、昭和50.2.25最高判)。
3 数個の債務がある場合における法定利息超過部分については、順次に利息及び元本に充当される(民法491条1項)。
(利息の取立て手続)
19 元物である債権を差押え、利息の取立てもしようとするときは、第三債務者に送付する債権差押通知書に、利息もあわせて国に支払うべき旨を記載するものとする。
第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
担保のための仮登記がある財産に対する滞納処分
(滞納処分の続行)
1 担保のための仮登記(第23条関係2参照)がある財産を差し押さえた場合において、その差押えの効力が発生したとき(第68条関係46)が清算期間の経過前または清算金の支払若しくは供託前(清算金がないときは、清算期間の経過前)であるときは、仮登記担保権者は、その仮登記に基づく本登記(本登録を含む。以下同じ。)の請求をすることができない(法52条の2、仮登記担保法2条1項、15条1項、20条)。したがって、税務署長は、当該財産について滞納処分を続行することができる。ただし、その差押えについて、不服申立て又は訴訟が提起されたときは、財産の換価は制限されることとなる(通則法105条1項、法90条3項)。 (注) 「担保のための仮登記がある財産」が特許権、意匠権、実用新案権又は商標権のような不動産登記法の適用又は準用のない財産であるときは、利害関係人の承諾を要しないでその仮登録に基づく本登録をすることができるが、差押え後になされたその本登録は、換価により消滅することに留意する(法124条1項)。
(滞納処分の制限)
2 清算期間経過後、正当な清算金の支払又は供託がされた後(清算金がないときは、清算期間の経過後)においては、担保のための仮登記がある財産に対する差押えは、行うことができない(法52条の2、仮登記担保法15条2項、20条)。
第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
損害保険
(意義)
1 法第53条第1項の「損害保険」とは、当事者の一方(保険者)が偶然な一定の事故(以下第53条関係において「保険事故」という。)によって差押財産について生ずることがあるかもしれない損害をてん補することを約し、相手方(保険契約者)が保険者に対して報酬(保険料)を支払うことを約する契約に関する保険をいうものである(商法629条参照)。これらの保険には、例えば、商法に規定する火災保険、運送保険及び海上保険のほか、物についての盗難保険、ガラス保険、自動車保険、航空保険、ボイラー・ターボセット保険、家畜保険、風水害保険、動産総合保険等及び債権についての信用保険、抵当保険、有価証券保険等がある。
(当事名の意思によらない損害保険契約の終了)
2 損害保険契約の終了については、当事者の意志による場合とよらない場合とがあるが、次に掲げる場合には、当事者の意思表示を待たず当然に終了する。 (1) 保険期間の満了の場合保険者は保険期間中に起こった保険事故による損害をてん補するものであるから、保険事故の発生を見ずに保険期間が満了したときは、保険契約は原則として消滅する。ただし、保険契約の継続について、特別の定めをしているときは、この限りでない。
(2) 被保険利益の消滅の場合損害保険契約は、損害のてん補を目的とするから被保険利益の存在を前提とする。したがって、保険者の負担すべき保険事故以外の理由により保険の目的の全部又は一部が滅失し、被保険利益の全部又は一部が消滅した場合(危険が消滅した場合を含む。)には、その部分についての保険契約は効力を失う。
(3) 危険の著しい変更又は増加の場合保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰すべき理由により著しく変更又は増加したときは、その契約は当然に効力を失う(商法656条)。 (注) 危険の変更又は増加とは、保険期間中における危険に関する事情の変更で、契約当時に予定された以上に危険発生の可能性が増加することをいう。
(4) 保険者の破産の後3月を経過した場合保険者が破産の宣告を受けたときは、保険契約者はその契約を解除することができるが(商法651条1項、破産法59条)、保険契約者が商法第651条第1項((保険者の破産))の規定による解除をしない場合において、破産宣告の後3月を経過したときは、その保険契約は当然にその効力を失う(同条2項)。
(当事者の意思による損害保険契約の終了)
3 損害保険契約は、次に掲げる場合には、契約当事者の意志によって終了させることができる。 (1) 保険者の責任開始前(商法649条2項6号参照)における保険契約者による任意解除の場合保険者の責任が始まる前においては、保険契約者は自由に保険契約の全部又は一部を解除することができる(商法653条)。
(2) 保険者の破産の場合における保険契約者による解除の場合保険者が破産の宣告を受けたときは、保険契約者は将来に向かって契約を解除することができる(商法651条1項)。
(3) 告知義務違反の場合における保険者による解除の場合保険契約者が、告知義務に違反した場合には、保険者は、一定の要件(商法644条1項ただし書、2項、645条参照)のもとにその契約を解除することができる(同法644条1項本文)。
(4) 危険の著しい変更又は増加の場合における保険者による解除の場合保険者は、保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない理由によって著しく変更又は増加した場合には、将来に向かってその契約を解除することができる(商法657条1項)。 (注) 危険の変更又は増加については、2の(3)の(注)と同様である。
(5) 保険者による失効宣言の場合保険期間中に危険が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない理由によって著しく変更又は増加した場合において、これを知った保険契約者又は被保険者が遅滞なくこれを保険者に通知することを怠ったときは、保険者は危険の変更又は増加の時から契約がその効力を失ったものとみなすことができる(商法657条2項)。 (注) 危険の変更又は増加については、2の(3)の(注)と同様である。
(6) 約款の規定による解除の場合保険約款に、一定の要件があるときに、その契約を解除することができる旨の定めがある場合において、その要件に該当するときは、その保険契約を解除することができる。
(保険契約の終了又は無効と差押えの効力)
4 2又は3により差押財産に係る損害保険契約が終了した場合又は保険契約の全部又は一部が無効である場合には、その差押えの効力は、その終了又は無効であることにより生ずる保険料等の返還を受ける権利(商法643条、654条等参照)には及ばない。したがって、この返還請求権は、別個の債権として差し押さえる必要がある。
火災共済協同組合の火災共済
(火災共済の意義)
5 法第53条第1項の「中小企業等協同組合法第9条の7の2第1項第1号(火災共済協同組合の火災共済事業)に規定する共済」とは、火災共済協同組合員が火災又は落雷等の偶然な事故によりその所有財産等について受けた損害をてん補するために、その火災共済組合が行う共済をいう。
(共済金額の制限)
6 共済金額については、中小企業等協同組合法第9条の7の3((共済金額の制限))の規定により、共済契約者1人につき共済金額の総額の制限がある。
(商法等の準用)
7 火災共済協同組合が締結する火災共済契約については、商法第3編第10章第1節第1款(同法650条1項及び664条を除く.)((損害保険の総則))及び第2款((火災保険))の規定が適用されるので、共済契約の終了等については、2から4までに準ずる(中小企業等協同組合法9条の7の5)。
(これに類する共済)
8 法第53条第1項の「その他法律の規定による共済でこれに類するもの」には、次に掲げるものがある。 (1) 農業協同組合法の規定による共済(同法10条1項8号、10条の2、農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済事業に係る責任準備金の積立に関する省令参照)
(2) 水産業協同組合法の規定による共済(同法100条の2,100条の4,100条の10,100条の14、商法3編10章参照)
(3) 消費生活協同組合法の規定による共済(同法10条1項4号、26条の3参照)
保険等の目的
(目的)
9 保険又は共済の目的とは、保険契約又は共済契約の対象とされているものをいう。例えば、建物の火災保険の場合は、その建物をいう(商法641条、649条、650条等参照)。 (注) 保険契約の目的とは、被保険利益のことをいう(商法630条、631条参照)。
(目的物の範囲)
10 損害保険、火災共済その他の共済の目的物及びその範囲は、各損害保険契約の約款又は共済契約により定められる。
保険金又は共済金
(保険金)
11 法第53条の「保険金」とは、保険事故が発生したことにより保険契約に基づく保険価額及び保険金額の範囲内で、実際に生じた損害額につき、被保険者が保険者から損害のてん補として受ける金銭をいう。
なお、普通保険約款で、現品の交付、修繕その他の方法によるてん補も定めることができる。 (注)1 保険価額とは、保険契約の目的の評価額をいい、保険金額とは、保険者が、保険事故による損害の発生の際にてん補すべき金額の最高限度額で契約締結時に保険者と保険契約者の間で約定されるものをいう。
2 約定保険金額が保険価額を超える場合又は数人の保険者との間に、保険事故、被保険者及び被保険利益が同一で保険期間を共通にする数個の保険契約が存在し、しかもその各契約の保険金額の合計が保険価額を超過する場合には、保険価額を超える部分の保険金額については、その支払を受けることができない(商法631条、632条1項参照)。
(共済金)
12 法第53条の「共済金」とは、共済事故が発生したことにより共済契約に基づく共済金額の範囲内で、実際に生じた損害額につき、共済契約者が共済事業者から損害のてん補として受ける金銭をいう。
保険金又は共済金に係る差押えの効力
(差押え前に差押財産が保険等に付されている場合)
13 保険に付され、又は共済の目的となっている財産に対する差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶから、一定の事故が生じた場合には、改めて保険金又は共済金の支払を受ける権利の差押えをすることなく保険者又は共済事業者は、保険金又は共済金を差押債権者である国に対して支払うこととなる。ただし、保険者又は共済事業者に対し財産を差し押さえた旨を通知することが必要である(法53条1項ただし書)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
なお、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権等がある場合は、上記の通知をしたときにその質権等の権利者に法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知をするものとする。
(差押え後に差押財産が保険等に付された場合)
14 差押え後にその差押財産が保険又は共済に付された場合における差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶものとする。ただし、このためには、保険又は共済の付された財産を差し押さえている旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない(法53条1項ただし書)。 (注) 財産差押え後、その財産の譲渡があり、新たに譲受人を受取人とする保険契約又は共済契約がされた場合には、差押えの効力は保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ばない。
(保険の目的の譲渡と差押えの効力)
15 保険の目的物が譲渡された場合には、その譲渡により危険の著しい変更又は増加を生じない限り、商法第650条((保険の目的の譲渡))の規定により、保険契約によって生じた権利も譲渡されたものと推定される。したがって、その譲受財産を譲受人の滞納処分として差し押さえた場合には、その差押えの効力は、その保険金の支払を受ける権利に及ぶことになる。これに対し、保険に付されている財産を差押え、法第53条第1項ただし書の通知をした後にその差押財産が譲渡された場合には、その財産の譲渡に伴う保険契約に係る権利の譲渡は、その差押えに対抗することができない。 (注) 保険の目的につき、相続又は会社の合併による包括承継があったときは、これに関する保険契約の被保険者の地位もまた、原則として、包括承継の対象となる。
(保険契約の継続と差押えの効力)
16 保険事故の発生を見ないで保険期間が満了した場合において、保険証券を新たに発行せず、保険契約継続証を従来の保険証券に添付し、新証券として保険契約が継続されたときは、改めて法第53条第1項ただし書の差押えの通知をする必要はない(昭和37.8.10名古屋高判参照)。
(共済の目的の譲渡と差押えの効力)
17 火災共済契約の目的財産が譲渡された場合(相続又は合併による場合を含む。)においては、中小企業等協同組合法第9条の7の4((火災共済の目的の譲渡等))の規定により、譲受人は火災共済協同組合の承諾を得て、その目的財産に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができるので、この場合の譲渡と差押えの効力との関係については、15と同様である。
なお、火災共済契約の共済の目的財産の譲受人が火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族、組合員たる法人の役員、組合員の使用人又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下17及び18において「組合員等」という。)でなくなった場合においても、火災共済契約期間内は、その契約につき組合員等の財産とみなされる(中小企業等協同組合法9条の7の4第1項後段)。
(被共済者が組合員等でなくなった場合の差押えの効力)
18 火災共済協同組合の組合員等が組合員等でなくなった場合において、その際締結されていた火災共済契約の目的物のうち、その組合員等でなくなったことにより組合員等の財産でなくなった財産がある場合は、中小企業等協同組合法第9条の7の4第3項((火災共済の目的の譲渡等))の規定により、その財産に係る火災共済契約の期間内は、その契約につき組合員等の財産とみなされるので、差押えの効力は、その組合員等でなくなった者の共済金の支払を受ける権利に及ぶ。
保険又は共済の事故
(事故)
19 法第53条第2項の「保険又は共済に係る事故」とは、保険者又は共済事業者が保険又は共済の目的につき、偶然な一定の事故によって生ずる損害をてん補することを契約している場合において、その保険者又は共済事業者のてん補すべき義務を具体化させる事故をいう(商法629条、642条参照)。
(保険事故と免責事由)
20 保険に係る事故については、それぞれの保険契約で約定されたところによるが、事故が生じても、それが次に掲げる原因によるときは、保険者は損害てん補義務を免れる。
なお、保険者は、普通保険約款に、免責される事故又は損害の態様を特約事項として定めることができる。 (1) 変乱より生じた損害は、商法第640条((保険者の法定免責事由))の規定により、特約がなければ、保険者はその損害をてん補する責めを負わないこと。
(2) 保険の目的物の性質若しくはかし、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失により生じた損害は、商法第641条((保険者の法定免責事由))の規定により、保険者はその損害をてん補する責めを負わないこと。又この場合は、特約をもってこの損害のてん補を定めることができないこと。
(共済事故)
21 共済に係る事故としては、火災共済協同組合が締結するものについては火災又は落雷等の偶然の事故、農業協同組合が締結するものについては共済規程に定める事故、水産業協同組合が締結するものについては共済規程に定める事故及び消費生活協同組合が締結するものについては規約に定める事故等がある(中小企業等協同組合法9条の7の2、農業協同組合法10条の2、水産業協同組合法100条の10、消費生活協同組合法26条の3参照)。
差押財産上の抵当権等と差押え国税との関係
(差押財産上の抵当権等の物上代位)
22 差押財産が保険又は共済及び抵当権、質権又は先取特権(以下第53条関係において「抵当権等」という。)この目的となっている場合において、徴収職員がその財産についてその保険金又は共済金の支払を受けたときは、法第53条第2項の規定により、その抵当権者、質権者又は先取特権者(以下第53条関係において「抵当権者等」という。)がその支払前にその保険金又は共済金の支払を受ける権利について、民法第304条第1項ただし書((物上代位))、第350条((留置権等の規定の準用))、第372条((他の担保物件の規定の準用))、自動車抵当法第8条((物上代位))、建設機械抵当法第12条((物上代位))等の規定による差押えをしたものとみなされるので、その抵当権者等は、物上代位のための要件としての差押手続を要せず、その権利の行使をしたと同様の関係になる。
(保険金等の配当)
23 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合のその保険金又は共済金に係る金銭は、法第128条第2号((配当すべき金銭))の規定による配当すべき金銭に該当する。
(差押財産上の抵当権等と差押え国税)
24 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産上に法第53条第2項の抵当権等があったときのその抵当権等の被担保債権とその差押えに係る国税との優先関係については、その保険金又は共済金が差押財産の換価代金に相当するものとして、法第2章第3節((国税と被担保債権との調整))等の規定を適用するものとする。
なお、上記の場合における抵当権等の被担保債権の優先についての証明は、令第4条第3項((優先質権等の証明の期限))の規定により、保険金又は共済金についての配当計算書の作成の日の前日までにしなければならない。
保険金の請求権上の質権と差押財産上の抵当権等と差押国税との競合
(質権と抵当権等との競合)
25 保険金又は共済金の支払を受ける権利について設定された質権の被担保債権と差押財産上にある法第53条第2項の抵当権等の被担保債権との優先順位は、法第53条第2項の規定により、これらの抵当権等を有する者が保険金又は共済金の支払を受ける権利を差し押さえたとみなされるときと保険金又は共済金の支払を受ける権利について質権を設定した時とを比較して、これらの古い順序に従って優先順位を定めるものとする(昭和32.8.30福岡高判)。 (注)1 法第53条第2項の規定により差押えをしたものとみなされた場合において、抵当権等が2以上ある時は、その抵当権等相互間については、民法その他の法律の規定によりその順位を定めるものとする。
2 法第53条第1項の規定により、差押財産に対する差押えの効力が保険金又は共済金の支払を受ける権利に及んだ時以後に、その請求権上に設定した質権については、配当しないものとする。
(質権と抵当権等と差押国税との競合)
26 徴収職員が、差押財産に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その保険金又は共済金の請求権につき設定されていた質権の被担保債権と法第53条第2項の抵当権等の被担保債権と差押えに係る国税とが競合した場合のその保険金又は共済金の配当等については、次に掲げるところによるものとする。 (1) 差押えに係る国税が質権の被担保債権及び抵当権等の被担保債権に優先する場合は、第1順位差押えに係る国税、第2順位質権の被担保債権、第3順位抵当権等の被担保債権、の順位により配当する。
(2) 差押えに係る国税が質権の被担保債権及び抵当権等の被担保債権に後れる場合は、第1順位質権の被担保債権、第2順位抵当権等の被担保債権、第3順位差押えに係る国税、の順位により配当する。
(3) 差押えに係る国税が、質権の被担保債権に後れ、抵当権等の被担保債権に優先する場合は、第1順位質権の被担保債権、第2順位差押えに係る国税、第3順位抵当権等の被担保債権、の順位により配当する。
(4) 差押えに係る国税が、抵当権等の被担保債権に後れ、質権の被担保債権に優先する場合は、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定を類推適用して、配当するものとする。 〔例〕 滞納処分費 (不動産の差押えに関する費用、保険金受領に関する費用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
差押え国税 (法定納期限等 昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・・11万円
抵当権の被担保債権額(設定登記昭和57. 1.30)・・・・・・・・・8万円
(保険金請求権の発生した日 昭和58. 5.30)
質権の被担保債権額 (設定 昭和58. 4.30)・・・・・・・・・・・6万円
保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21万円
※配当額の計算 イ 法第26条第1号の規定により、滞納処分費の1万円に充てる。
ロ 法第26条第2号の規定により、法定納期限等、質権の設定及び抵当権の設定登記の古い順に従って国税及び私債権に充てるべき金額の総額(21万円-1万円)を定めると、抵当権の設定登記が昭和57.1.30、差押国税の法定納期限が昭和58.3.15、質権の設定が昭和58.4.30であるから、(1)抵当権8万円、(2)国税11万円、(3)質権1万円(保険金額21万円-イの1万円-(1)の8万円-(2)の11万円)となり、私債権の総額9万円((1)の8万円十(3)の1万円)、国税11万円となる。
ハ 法第26条第3号の規定により国税に充てるべき金額は、11万円となる。
ニ 法第26条第4号の規定により、質権の設定が昭和58.4.30で抵当権者が保険金の支払を受ける権利を差し押さえたとみなされるときより早いから、質権に6万円、抵当権に3万円充てる(25参照)。
ホ 上記の結果、配当額は次のとおりとなる。
滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
質権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
参加差押え及び交付要求との関係
(参加差押え又は交付要求をした者への配当)
27 徴収職員が、差押えに係る保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その差押えに係る財産につき、参加差押え又は交付要求がされていたときは、これらの参加差押え又は交付要求に係る国税、地方税又は公課に対しても配当する。
なお、上記の場合においては、法第2章第2節((国税及び地方税の調整))の規定が適用される。
(参加差押えに係る差押えについての保険者等への通知)
28 保険又は共済の目的となっている財産の参加差押えをした場合には、参加差押えをした旨を保険者又は共済事業者に通知するものとする。この通知をしていない場合において、先行の差押えが解除されたことにより参加差押えが差押えの効力を生じたときは、改めて保険者又は共済事業者に対し差し押さえた旨を通知しない限り、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない。
なお、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権等がある場合には、その質権等の権利者に対する通知をするものとする。
保険金等の支払いを受ける権利の差押えと法第53条第2項との関係
29 法第53条第1項の保険金又は共済金の支払を受ける権利を滞納処分により差し押さえた場合において、その差押えに基づきその保険金又共済金の支払を受けたときにおいても、法第53条第2項の規定の適用があるものとする。
担保の処分としての差押えと法第53条との関係
30 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により、滞納処分の例により担保物の差押えをする場合において、その財産が保険に付され、又は共済の目的となっているときは、保険金又は共済金の支払を受ける権利に質権を設定しているときを除き、その財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知する(法53条1項ただし書)。
第54条関係 差押調書
差押調書
(意義)
1 法第54条の「差押調書」とは、差押えの事績を記録証明するために作成する文書であって、令第21条第1項各号((差押調書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第3号書式による。
なお、差押調書の作成は、差押えの効力発生要件ではない。
(動産及び有価証券)
2 法第54条第1号の「動産」とは、民法第86条第2項及び第3項((動産の定義等)))に規定する動産のうち、法第70条又は第71条((船舶、航空機等の差押え))の規定の適用を受ける船舶、航空機、自動車及び建設機械並びに無記名債権を除いたもの(以下「動産」という。)をいい、「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、無記名債権も含まれる(第56条関係13参照)。
(債権)
3 法第54条第2号の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいい、電話加入権、賃借権その他取り立てることができない債権は含まれない(第62条関係1参照)。
(電話加入権等)
4 法第54条第3号の「第73条(電話加入権等の差押)の規定の適用を受ける財産」とは、無体財産権等のうち、電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産をいう(第73条関係1参照)。
(搬出又は取上げの場合)
5 差押財産を搬出する場合において、差押財産を搬出した旨を差押調書に付記したときは、滞納者又は第三者にその謄本を交付しなければならない(令26条の2、22条1項ただし書)。
なお、債権証書等を取り上げた場合において、債権証書等を取り上げた旨を差押調書に付記したときは、滞納者又はその処分を受けた者に、その謄本を交付しなければならない(令28条)。
(署名又は記名)
6 令第21条第1項((差押調書の記載事項))の「署名」とは、徴収職員が自らその氏名を記載することをいい、「記名」とは、署名に代えて、印判、謄写、印刷等によってその氏名を表示することをいう。
(性質)
7 令第21条第1項第3号((差押調書の記載事項))の「性質」とは、例えば、自動車については、年式、製造者名、色、新旧の別、車台番号、登録番号等通常の場合において、社会通念上他の同種物品と識別することができる程度の性状、機能、特徴等をいう。
(所在)
8 令第21条第1項第3号((差押調書の記載事項))の「所在」については、社会通念上その財産の特定のために必要な所在場所に関する事項を記載するものとする。
(捜索した場合)
9 令第21条第2項((捜索調書を作成しない場合の差押調書の記載事項))の規定により差押調書に記載する捜索した「日時及び場所」とは、捜索して差押えをした場合における捜索を開始した日時及び終了した日時並びに社会通念上特定するに足りる程度の捜索した場所の表示(例えば、個人の場合には、居間、台所等、法人の場合には、事務室、倉庫、工場、応接室等)をいう。
(参加差押えの場合)
10 法第87条第1項((参加差押えに係る差押えの効力の発生時期等))の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、差押調書を作成することを要しない。
(保全差押え等の場合)
11 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定により差し押さえたときは、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして差押調書を作成するものとする。この場合において、令第21条第1項第2号((差押調書の記載事項))に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令56条、通則令9条、規則3条別紙第3号書式備考2)。
(担保物処分の場合)
12 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により担保を滞納処分の例により処分するため差し押さえた場合において、その差押えの時にその財産が滞納者以外の者に帰属しているときは、その帰属している者を滞納者としてみなして、差押調書に準ずる調書を作成するものとする。
差押調書の謄本
(謄本)
13 法第54条の差押調書の「謄本」とは、差押調書と同一の文字符号を用いて、差押調書の内容を完全に写し取った書面をいう。この書面は、謄写したものであると筆写したものであるとを問わないが、謄本である旨を記載するものとする。
(作 成)
14 差押調書の謄本は、立会人を要しない場合及び滞納者が立会人である場合には1通を、滞納者以外の者が立会人である場合には滞納者及び立会人に交付すべき数に相当するものを、それぞれ作成する。
(交 付)
15 法第54条の「交付」とは、謄本を相手方に渡すことをいい、直接の手交に限らず、通則法第1章第4節((送達))の規定による送達を含む。
なお、謄本の交付を要しないときも、差押調書は作成しなければならない。
(債権を差し押さえた場合)
16 債権を差し押さえた場合には、法第62条第2項((差し押さえた債権の処分禁止))の規定により、その債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を差押調書の謄本に付記しなければならない(令21条3項)。
この場合の付記については、別に定めるところによる。
第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
差押えの通知
(知れている者)
1 法第55条の「知れている者」とは、同条第1号から第3号までに掲げる者のうち、徴収職員がその差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者をいう。
(その他必要な事項)
2 法第55条の「その他必要な事項」とは、次に掲げる事項をいう(令22条1項)。 (1) 滞納者の氏名及び住所又は居所
(2) 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
(3) 差押財産の名称、数量、性質及び所在
(4) 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
(5) 担保のための仮登記(第23条関係2参照)の権利者に対しては、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められる旨
(通知の方法)
3 法第55の規定による通知は、令第22条第1項各号((質権者等に対する差押通知書の記載事項))に掲げる事項(2参照)を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、法第55条第1号及び第2号に掲げる権利者に対する差押えの通知書は、登記簿(又は登録簿)に登記されている住所又は居所あてに送付することとして差し支えない。 (注) 担保物を滞納処分の例により差し押さえたときは、法第55条の規定に準じて通知しなければならない。
(保全差押え等をした場合の通知)
4 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定による差押えをした場合には、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして、法第55条の規定による差押えの通知をしなければならない。この場合において、令第22条第1項第1号((質権者等に対する差押通知書))において準用する第21条第1項第2号((差押調書の記載事項))に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令56条・通則令9条)。
(保全差押えに係る国税が確定した場合の通知)
5 法第159条第1項((保全差押金額の決定等))又は通則法第38条第3項((繰上保全差押金額の決定等))の規定による差押え後、その差押えに係る国税が確定しても、法第55条の規定による差押えの通知は必要ではない。
(捜索又は取り上げた場合)
6 法第55条の規定による通知を受けるべき者が、法第146条第3項((捜索調書の作成))の規定により差押調書の謄本を受けた者であるときは、その者に対しては、差押えの通知をすることを要しない(令22条2項)。
なお、質権者等の第三者が占有する債権証書等を取り上げた場合において、取上調書に代えて差押調書の謄本にその旨を付記して交付したときは、その者に対しては法第55条の規定による差押えの通知を要しないものとする(令28条、22条1項ただし書参照)。
(参加差押えの場合)
7 法第87条第1項((参加差押えに係る差押えの効力の発生時期))の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、改めて、法第55条の規定による差押えの通知をすることを要しない(法81条、86条4項参照)。
(質権、抵当権、先取特権)
8 法第55条第1号の「質権、抵当権、先取特権」は、保全仮登記がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(仮登記)
9 法第55条第2号の「仮登記」とは、担保のための仮登記(第23条関係2参照)その他すべての仮登記をいう。
(仮差押え)
10 法第55条第3号の「仮差押え」とは、裁判所の決定に係る仮差押えをいい、保全法による強制執行を保全するための仮差押えに限らず、破産法第155条((破産宣告前の保全処分))、和議法第20条((和議開始決定前の保全処分))、会社更生法第39条((更生手続開始決定前の保全処分))、商法第386条第1項第1号((会社の整理開始命令後の保全処分))、第454条第1項第1号((会社の特別清算開始命令後の保全処分))等の規定による仮差押えも含まれる。
この仮差押えの執行は、次に掲げる財産ごとに、それぞれの執行機関が行う。 (1) 動産又は有価証券目的物の所在地を管轄する地方裁判所所属の執行官(保全法49条1項、執行官法4条)
(2) 債権仮差押命令を発した裁判所(保全法50条2項)
(3) 不動産仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法47条2項)。強制管理の方法による仮差押えの執行については、不動産の所在地を管轄する地方裁判所(保全法47条5項、執行法44条1項)
(4) 船舶又は航空機仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法48条2項、民事保全規則(以下「保全規則」という。)34条)。執行官に対して船舶国籍証書等又は航空機登録証明書等を取り上げて執行官に提出すべきことを命ずる方法による仮差押えの執行については、船舶又は航空機の所在地を管轄する地方裁判所(保全法48条2項、保全規則34条)
(5) 自動車又は建設機械仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全規則38条、39条、保全法48条2項)。執行官に対し自動車又は建設機械を取り上げて保管すべき旨を命ずる方法による仮差押えの執行については、自動車又は建設機械の所在地を管轄する地方裁判所(保全規則38条、39条、保全法48条2項)
(6) 預託株券等仮差押命令を発した裁判所(保全規則42条2項、保全法50条2項) (注) 預託株券等とは、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「株券保管振替法」という。)第14条第1項((保管振替機関への預託))(同法39条1項((株券以外の有価証券))において準用する場合を含む。)の規定により保管振替機関に預託された株券その他の有価証券をいう(執行規則150条の2参照)。
(7) (1)から(6)までに掲げる財産権以外の財産権仮差押命令を発した裁判所(保全法50条4項)
(仮処分)
11 法第55条第3号の「仮処分」とは、裁判所の決定に係る仮処分をいい、保全法第23条第1項(係争物に関する仮処分命令)の規定に限らず、仮差押えと同様に10に掲げる破産法第155条、和議法第20条等の規定による仮処分も含まれる。この仮処分の執行機関については、10に準ずる(保全法52条1項、保全規則45条)。
なお、次に掲げるような仮の地位を定める仮処分等は、金銭給付を内容とする滞納処分との競合が生じないので、法第55条第3号の仮処分には含まれない。 (1) 仮の地位を定める仮処分(保全法23条2項)
(2) 取締役及び監査役の職務執行停止又は職務代行者の選任の仮処分(商法270条、280条)
(3) 子の看護その他の仮処分(人事訴訟手続法16条)
(4) 仮登記のための仮処分(不動産登記法32条、33条1項)
第2款 動産又は有価証券の差押え
第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
動産
(土地に付着した物)
1 土地の定着物は不動産であるが、仮植中の草木、小規模の工事で土地に固定されたもの、例えば、使用中の動揺を防ぐためボールト、くぎ、スパイク等で固定しただけの機械類等単に土地に付着しているだけのものは、定着物とはいえないから、動産として差し押さえる(大正10.8.10大判、昭和4.10.19大判)。
(未完成の建物)
2 建物は不動産であるが、その使用の目的に応じて使用可能な程度に完成していなければ建物とはいえないから、例えば、木材を組み立てて地上に定着させ、屋根をふきあげただけのもの等は、動産として差し押さえる(大正15.2.22大判)。 (注) 建物が完成した場合には、改めて不動産としての差押えの手続をとる必要がある。
(未分離の果実等)
3 未分離の果実等は、土地の定着物である樹木と一体をなすものであって、本来動産ではないが、動産として取引されるもの(おおむね1月以内に収穫することが確実であるもの。執行法122条1項参照)は、独立した動産として差し押さえることができる(大正9.5.5大判)。
(登記されない船舶)
4 法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる船舶は、動産として差し押さえる。 (1) 端舟その他若しくはかいだけで運転し、又は主として若しくはかいだけで運転する舟(商法684条2項、船舶法20条)
(2) 総トン数20トン未満の船舶(商法686条2項、船舶法20条)
(3) 推進器を有しないしゆんせつ(凌渫)船(船舶法施行細則2条)
(4) 外国船舶(執行法121条) (注) 外国船舶とは、船舶法第1条((日本船舶の要件))に規定する日本船舶以外の船舶をいう。
(5) 製造中の船舶(抵当権の登記がされている船舶を含む。第70条関係1の(2)参照)
(登録のない航空機等)
5 法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる航空機は、動産として差し押さえる。 (1) 滑空機及び飛行船(登録のあるものを含む。) (注) 滑空機及び飛行船その他航空法施行令で定める航空の用に供することができる機器は、登録をしてもその登録は第三者に対する対抗要件ではなく(航空法2条1項、3条の3参照)、法第70条((船舶又は航空機の差押))の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。
(2) 未登録の飛行機及び回転翼航空機
(登録のない自動車)
6 法第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定の適用を受けない次に掲げる自動車は、動産として差押さえる(道路運送車両法4条参照)。 (1) 軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車。例えば、オートバイ、スクーター、サイドカー等(道路運送車両法3条、4条、道路運送車両法施行規則2条の規定による別表第1号参照)
(2) 未登録の自動車。例えば、商品として陳列されている自動車、登録を抹消されている自動車等(道路運送車両法4条、15条、16条参照)
(3) 建設機械としての登記がない大型特殊自動車(道路運送車両法5条2項、自動車抵当法2条ただし書参照)
(登記のない建設機械)
7 所有権保存登記のない建設機械は、記号の打刻の有無にかかわらず、法第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。 (注) 建設機械を動産として差し押さえている場合には、所有権保存の登記がされても差押債権者に対しては効力を生じない(建設機械抵当法3条2項)から、動産として滞納処分の続行をすることができる。
(外国通貨)
8 外国通貨(本邦通貨以外の通貨。)は、動産として差し押さえる。この場合において、徴収職員は、速やかに、差し押さえた外国通貨を外国為替公認銀行(同法11条)又は両替商(同法14条)において本邦通貨と交換した上、金銭を差し押さえた場合と同様に処理するものとする(27、28参照)。 (注) 本邦通貨とは、日本円を単位とする通貨をいう(外国為替及び外国貿易管理法6条1項3号)。
(従物である動産)
9 従物である動産(例えば、建物に備え付けられた畳、建具、冷暖房器、空調器等。昭和55.1.28東京地判)の差押えについては、次のことに留意する。 (1) 従物は、独立の動産として差し押さえることができる。ただし、他に滞納国税に見合う適当な財産がない場合又は主物の利用関係を著しく害しない場合に限って差し押さえるものとする。
なお、雨戸、建具、入口の戸扉その他建物の内外を遮断する建具類は、これらが建物に備え付けられた後は建物の一部を構成し、従物ではないから、その取外しの難易にかかわらず、独立した動産として差し押さえることができない(昭和5.12.18大判)。
(2) 畳、建具等の従物の差押禁止については、法第75条第1項第1号、第13号及び第2項((一般の差押禁止財産))の規定がある。
(3) 担保権の効力が及んでいる従物は、担保権者の同意のない限り、独立の動産として差し押さえないものとする(昭和18.2.13東京控判参照)。
(4) 船舶の属具目録に記載された動産は、従物と推定されるから(商法685条)、原則として、(1)及び(3)に準じて差し押さえる。
(工場抵当との関係)
10 工場抵当法による工場抵当(工場財団を組成しない工場抵当)の目的となっている土地又は建物に備え付けられている機械、器具その他工場の用に供されている動産(以下10において「備付物」という。)については、次のことに留意する。 (1) 備付物については、工場抵当法第7条第2項((抵当権の目的である物に対する差押え等))の規定により、土地又は建物と別個に差し押さえることができない。ただし、同法第2条第1項ただし書((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による抵当権の設定行為に別段の定めがある場合及び同法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録に記載されていない場合の備付物については、この限りでない。
(2) 滞納者(工場所有者)が、工場抵当法第6条第2項((抵当権の目的物の分離))の規定により抵当権者の同意を得て分離した備付物は、動産として差し押さえることができる。この場合において、その備付物が同法第3条((抵当権の目的物の分離))の規定による目録に記載されているときは、目録の変更の登記をする必要がある。
(3) 滞納者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、かつ、抵当権者もその事情を知って備え付けた備付物については、工場抵当法第2条第1項ただし書((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定により抵当権の効力はその備付物に及ばないから、動産として差し押さえることができる
(4) 滞納者の所有する動産が工場抵当の目的となっている他人の工場の備付物である場合には、工場抵当法第3条((抵当権の目的物の分離))に規定する目録に記載されている場合であっても、抵当権の効力は及んでいないから、滞納者の動産として差し押さえることができる(昭和35.8.3名古屋高判。昭和37.5.10最高判参照)。
(5) 工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))に規定する目録に記載されている備付物については、滞納処分により差し押さえたときに既に第三者が譲渡等により備付物の引渡しを受けているときにおいても、その備付物に対し差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。5条1項参照)。ただし、税務署長は、当該第三者が即時取得の要件を満たしているときは、差押えの効力を主張することはできない(同法5条2項)。
(財団に属する動産)
11 工場財団、鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団、鉄道財団、軌道財団、運河財団又は観光施設財団に属する動産は、これらの財団が1個の財産とみなされているから、個々の動産として差し押さえることができない。ただし、抵当権者の同意を得て分離した動産については、この限りでない(工場抵当法15条、鉱業抵当法3条、漁業財団抵当法6条、道路交通事業抵当法19法、港湾運送事業法26条、鉄道抵当法20条、軌道ノ抵当二関スル法律1条、運河法13条、観光施設財団抵当法11条)。
(貨物引換証等の発行されている物品)
12 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券が発行されている物品については、動産として差し押さえることはできず、これらの証券を有価証券として差し押さえるものとする(商法573条、604条、776条参照)。
有価証券
(意義)
13 法第56条第1項の「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、民法上動産とみなされている無記名債権(20参照)も含まれる(法54条1号参照)が、次に掲げる証券は、有価証券ではない。 (1) 借用証書若しくは受取証券のような証拠証券又は銀行預金証書のような免責証券 (注) 上記の場合には、債権の差押えを行い、上記の証拠証券又は免責証券は債権証書として取り上げる(第65条関係3参照)。
(2) 郵便切手又は収入印紙のように、証券自体が特定の金銭的価値を有し、金銭の代用となる金券 (注) 上記の金券は、動産の差押手続に従って差し押さえる。
(有価証券の種類)
14 「有価証券」には、手形、小切手、国債証券、地方債証券、社債券、株券(株主会員制によるゴルフ会員権に係るものを含む。)、出資証券、信託の無記名受益証券、抵当証券(抵当証券法14条、15条参照)、倉庫証券、貨物引換証(商法571条参照)、船荷証券(同法767条、768条参照)、商品券、劇場入場券等がある。
(社債券)
15 14の「社債券」は、商法の規定により社債について発行された債券だけでなく、特別の法律により設立された法人の発行する債券(例えば、電信電話債券、鉄道債権、放送債券、商工債券、農林債券等)及び会社が特別の法律により発行する債券(例えば、興業債券、長期信用債券等)をも含むものとし、これに準ずる外国の社債券についても同様とする。
(権利株等)
16 株式の引受けによる権利(いわゆる権利株)を表わす株式の申込証拠金領収証、株券発行前の株式を表わす株式払込金領収証及び新株の引受権を表わす割当通知書は、株券の受領のための委任状及び株式の譲渡を証する書面(譲渡のための委任状を含む。)が添付されているときは、株券に準じて取り扱うものとする(昭和26.2.9東京地判、昭和27.1.28東京地判)。
(出資証券)
17 14の「出資証券」とは、日本銀行及び日本原子力研究所の出資証券をいい、合名会社及び合資会社の出資に関する証券は、有価証券ではない。
(信託の無記名受益証券)
18 14の「信託の無記名受益証券」とは、証券投資信託又は貸付信託の無記名受益証券をいう。 (注) 信託の記名式の受益証券は、有価証券ではなく証拠証券である(証券投資信託法5条2項、貸付信託法8条1項参照)。
(倉庫証券)
19 14の「倉庫証券」には、預証券、質入証券及び倉荷証券の3種があるが、なお次のことに留意する。 (1) 預証券は、寄託物返還請求権を表彰する有価証券であり、質入証券とともに発行され(商法598条)、質入れ前は質入証券とともに流通するが(同法603条2項)、質入れ後は分離して流通し、預証券の所持人は、質入れに際して証券に記載された債券額と利息を支払う義務を負い(同法607条)、また、原則としてその債権額と利息を質入証券の所持人に支払って質入証券を取得しなければ、寄託物の返還を請求できない(同法620条から622条まで)。
(2) 質入債権は、質入れ後は証券記載の債券とこれを担保する質権とを表彰する。
(3) 倉荷証券は、預証券及び質入証券に代えて発行する有価証券であって(商法627条)、この証券で寄託物の譲渡、質入れその他の処分をすることができる。
(無記名債権)
20 「無記名債権」とは、証券面に債権者の名を記載せず、その正当な所持人に弁済すべき証券的債権をいい、具体的には、商品券、乗車券、無記名公債のように、債権が証券に化体し、その成立、存続、行使等に、原則として証券を必要とするものをいう。
差押手続
(占有による差押え)
21 法第56条第1項の「占有して行う」とは、徴収職員がその財産を差押えの意思をもって客観的な事実上の支配下に置き、滞納者の処分の可能性を排除することをいう。この場合の占有は、公法上の占有であり、私法上の権利関係の効力には影響を及ぼさない。
(差押調書の作成等)
22 徴収職員が動産又は有価証券を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付しなければならない(法54条)。
(未完成の手形等)
23 未完成の手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものを差し押さえたときは、直ちに滞納者に対し、当該未完成の手形等に記載すべき事項を補充させるものとする(執行規則103条2項参照)。
(有価証券の保管)
24 差し押さえた有価証券(物品の給付を目的とする権利を表彰する船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等を除く。)は、政府保管有価証券取扱規定第2条((政府保管有価証券の寄託))の規定により、原則として日本銀行に寄託するものとするが、近い将来において換価をする予定のもの又は法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により取立てをするため必要があるものについては、政府保管有価証券取扱規程第2条第1項ただし書の規定により、日本銀行に寄託することなく、税務署長がこれを保管しても差し支えない。 (注) 税務署長は、船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等の物品の給付を目的とする権利を表彰する有価証券を保管するに当たっては、保管上の必要に応じ、貸金庫等を利用するものとする。
差押えの効力
25 動産又は有価証券の差押えは、徴収職員がこれらの財産を占有した時にその効力を生ずる。したがって、占有を欠くとき、例えば、差押調書の作成又は差押調書の謄本の交付だけをしたとき等の場合には、差押えの効力は生じない。
なお、法第60条第1項((差し押さえた動産等の保管))の規定により滞納者又は第三者に差押財産を保管させたときは、封印、公示書、その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生じる(法60条2項)。
金銭の差押え
(金銭)
26 法第56条第3項の「金銭」とは、財貨の交換の媒介物として国家がその価格を一定した物のうち、日本円を単位とする通貨(本邦通貨)及び国税の納付に使用することができる有価証券をいう(証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律1条、2条参照)。 (注)1 上記の「通貨」とは、強制通用力のある支払手段をいい、鋳造貨幣(金貨、銀貨、銅貨、ニッケル貨等の貨幣)のほか、紙幣及び銀行券を含み(貨幣法3条、臨時通貨法2条、3条、日本銀行法29条、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律1条参照)、小切手等は含まない。
2 強制通用力を有しない本邦通貨とは、1円未満の貨幣及び紙幣並びに新円切換前の通貨等の古銭及び元来が強制通用力を有するものであったが模様の認識しがたいもの又は私に極印をする等故意に損傷したと認められるもの等貨幣の効用がなくなったものをいう(貨幣法13条)。
(徴収したものとみなす)
27 法第56条第3項の「徴収したものとみなす」とは、金銭(26参照)を差し押さえたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
なお、国税の納付に使用することができる有価証券を差し押さえた場合において、その支払がなかったときは、滞納者の国税の納税義務は消滅しない(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律2条参照)。
(差押金銭の受入れ)
28 差し押さえた金銭は、直ちに歳入歳出外現金出納官吏の資格において、受け入れる(昭和58.5.31付徴管3-32ほか6課共同「管理事務提要(現金出納編)の制定について」通達の別冊(以下「管理事務提要(現金出納編)」という。)第131参照)。
差押財産の保管責任と損害賠償
(動産等の保管)
29 差し押さえた動産又は有価証券(法60条1項の規定により、滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)については、税務署長は、善良な管理者の注意をもって管理し、帳簿を備え、その動産及び有価証券の出納を記載しなければならない(令23条)。この帳簿については、別に定めるところによる。 (注) 善良な管理者の注意とは、差し押さえた動産又は有価証券を保管する税務署長として、一般に要求される程度の相当の注意をいう。
(損害賠償)
30 税務署長が、その職務を行うについて故意又は過失により違法に差押財産を亡失し、又はき損し、滞納者等に損害を与えたときは、国は国家賠償法第1条第1項((国等の損害賠償責任))の規定により、滞納者等に対してその損害を賠償する責めを負う。
(管理)
31 令第23条の「管理」とは、税務署長が差し押さえた動産及び有価証券を保管し、その滅失、き損、侵奪、腐敗、変質等を防ぐことをいう。
第57条関係 有価証券に係る債権の取立て
有価証券の取立て
(金銭債権)
1 法第57条第1項の「有価証券に係る金銭債権」とは、差し押さえた有価証券に基づいて行使することができる債権のうち、金銭の給付を目的とするものをいう。したがって、金銭の給付を目的とする債権以外の債権、例えば、物品の給付を目的とする債権を表彰する有価証券(倉庫証券等)については、代位取立てをしないで、直接その有価証券を換価に付するものとする。
(取立ての意義)
2 法第57条第1項の「取立」とは、徴収職員が差し押さえた有価証券の本来の性質、内容に従って、金銭の給付を受けることをいう。
(取立てをする場合)
3 法第57条第1項の規定による取立てをする有価証券は、その有価証券に係る金銭債権の履行期日が既に到来しているもの又は近い将来において履行期日が到来するものであって、換価をするよりもその債権の取立てをする方が徴収上有利であると認められるものに限るものとする(法89条2項参照)。
(取立ての名義)
4 法第57条第1項の規定による取立ては、滞納者の名において行うのではなく、徴収職員の名において行う。
(取立ての範囲)
5 法第57条第1項の規定による取立ては、差押えに係る国税の額にかかわらず、有価証券の券面金額の全額についてするものとする(第67条関係2参照)。
(取立ての手続)
6 法第57条第1項の規定による取立てに当たっては、原則として、その有価証券に「徴収法第56条第1項の規定により差し押さえ、同法第57条第1項の規定により取り立てる」旨を記載し、徴収職員が署名押印するものとする。
なお、次のことに留意する。 (1) 小切手又は手形(金融機関を通じて取り立てることができるものに限る。)については、通則法第55条((納付委託))の場合における取立ての方法に準じ、取り立てるものとする。
(2) (1)に掲げるもの以外の有価証券については、その有価証券を呈示し、直接取り立てる。
(取立て効果)
7 法第57条第2項の「徴収したものとみなす」とは、金銭を取り立てたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
(遡及権の行使)
8 手形又は小切手について満期又は支払呈示の日に支払がないときは、徴収職員は、振出人、裏書人及びこれらの保証人並びに参加引受人に対して手形又は小切手の金額とその満期以後の利息及び拒絶証書の作成・遡及の通知等のための諸費用を請求することができる(手形法43条、48条1項、77条1項、小切手法39条、44条)。 (注) 遡及権を行使する場合には、支払人等が取引停止処分を受けている場合であっても、支払のための手形又は小切手の呈示が必要であることに留意する。
第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
引渡し
1 法第58条の「引渡」とは、滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が、動産又は有価証券を徴収職員に、占有して差し押さえることができるように提供することをいう。
差押えの制限
(親族その他の特殊関係者の判定)
2 法第58条第1項の「親族その他の特殊関係者」に該当するかどうかの判定は、差押えをしようとする時の現況によるものとする。 (注) 「親族その他の特殊関係者」とは、令第13条各号に掲げる者をいう(法38条参照)。
(第三者が占有している財産でないものとみなす場合)
3 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる者は、法第58条第1項の規定による差押えについての制約を受けない(令24条4項、5項)。 (1) 法第24条第3項((譲渡担保財産の滞納処分))の規定により譲渡担保財産につき差押えをする場合、その譲渡担保財産を占有する滞納者又はその親族その他の特殊関係者
(2) 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税の滞納処分として、その者の財産につき差押えをする場合その財産を占有する滞納者(主たる滞納者)又はその親族その他の特殊関係者
(執行官が動産等を占有する場合)
4 執行官が滞納者の動産又は有価証券を仮差押え又は仮処分により占有している場合においても、差し押さえることができる(法140条参照。強制執行又は競売による差押えがされている場合には、滞調法が適用される。)。ただし、その動産又は有価証券につき法第58条第1項の第三者が占有権を有しているときは、その第三者との関係においては、法第58条及び第59条((第三者が占有する動産等の差押手続等))等の規定が適用される。
(占有)
5 法第58条第1項の「占有」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的に継続及びその主体の意思を問わない(大正3.1O.22大判)。
(引渡しの拒否)
6 法第58条第1項の「引渡を拒む」とは、徴収職員が動産又は有価証券を占有して差し押さえようとすることを拒むことをいう。
引渡命令
(発付の要件)
7 引渡命令は、次に掲げる要件を満たしたときに発することができる(法58条2項前段)。これらの要件に該当するかどうかの判定は、引渡命令を発する時の現況によるものとする。 (1) 滞納者の動産又は有価証券を占有する滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が引渡しを拒むとき。
(2) 滞納者が他に換価が容易であり(第50条関係5参照)、かつ、その滞納に係る国税の全額(第50条関係8参照)を徴収することができる財産を有しないと認められるとき。
(期限の指定)
8 法第58条第2項前段の「期限」は、引渡しを命ずる書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。この場合の「7日を経過した日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってこの期限とみなされる(通則法10条2項)。
(期限の繰上げ)
9 令第24条第3項の「通則法第38条第1項第1号の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるとき」とは、第三者につき同法第38条第1項各号に該当する事実が生じた場合等で、かつ、引渡命令に係る期限後においてはその財産の差押えをすることができないと認められるとき(ただし、期限内に引渡しがあると認められるときを除く。)をいう。
(引渡命令)
10 法第58条第2項前段の規定による引渡命令は、その命令に係る動産又は有価証券を差し押さえるための前提要件である。この引渡命令は、令第24条第1項各号((引渡命令書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(滞納者に対する通知)
11 法第58条第2項後段の規定による滞納者に対する通知は、令第24条第2項各号((引渡命令に係る通知の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
引渡命令書を送達した後他の第三考に占有が移転している場合
12 法第58条第2項前段の引渡命令書を送達した後、他の第三者に占有が移転している場合の差押えについては、次のことに留意する。 (1) 占有の移転により、引渡命令に係る滞納者の動産又は有価証券を現に占有する第三者がその引渡しを拒むときは、(2)の場合を除き、その第三者に対して改めて引渡命令を発しなければならない。
(2) 占有の移転が相続、法人の合併等の包括承継による場合には、引渡命令を再び発する必要はない。
差押動産等の搬出の制限
13 法第58条第2項前段の規定による引渡命令を受けた第三者が、その引渡命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その引渡命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、その財産を搬出することができない(法172条)。この場合において、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、第90条関係10の「訴訟の係属する間」に準じ、その財産の搬出を行わないものとする。
第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
動産を使用又は収益する権利
(賃借権)
1 法第59条第1項の「滞納者との契約による賃借権」には、買取権付賃貸借契約による割賦払約款付売買も含まれる。
(使用貸借権)
2 法第59条第1項の「使用貸借権」とは、当事者の一方(借主)の相手方(貸主である滞納者)からある動産を無償で借りて使用及び収益をした後、その物を返還することを約する契約(使用貸借)により、借主が取得する権利をいう(民法593条)。
(その他動産の使用又は収益をする権利)
3 法第59条第1項の「その他動産の使用又は収益をする権利」とは、例えば、受寄者が寄託者(滞納者)の承諾を得て受寄物を使用する場合(民法658条1項)、賃貸借、使用貸借等の混合契約に基づき使用又は収益をする場合等におけるその使用又は収益をする権利をいう。
契約の解除
(意義)
4 法第59条第1項の「契約を解除することができる」とは、契約の内容いかんにかかわらず、その契約を一方的に解除することができることをいう(民法540条1項、543条、620条参照)。 (注) 法律の規定(民法548条参照)又は契約により、法第59条第1項の規定にかかわらず、契約の解除ができない場合がある。
(占有の目的)
5 法第59条第1項の「占有の目的を達することができなくなる」とは、その動産を、その占有の基礎となった契約の内容どおり使用又は収益することができなくなることをいう。
(契約解除の通知)
6 引渡命令を受けた第三者は、引渡命令に係る動産の差押えの時までに、その引渡しを命じた税務署長に対して、法第59条第1項前段の規定による契約の解除をした旨の通知を、書面によりしなければならない(令25条1項)。
損害賠償請求権
(意義)
7 法第59条第1項の「滞納者に対して取得する損害賠償請求権」は、債務不履行、不法行為その他契約に基づく損害賠償請求権であって、その行使は、契約の解除によって影響を受けるものではない(民法415条、709条、545条3項。昭和6.4.28大判、昭和8.2.24大判参照)。
(賠償請求の範囲)
8 法第59条第1項後段の損害賠償請求権による求償の範囲は、原則として、民法第415条((債務不履行))及び第416条(損害賠償の範囲)その他の規定によるものであって、債務の不履行によって被ったいわゆる積極的損害のほか、不履行のなかった場合の得べかりし利益の喪失たるいわゆる消極的損害も含まれる。
(売却代金)
9 法第59条第1項後段の「売却代金」は、法第94条((公売))、第109条((随意契約による売却))又は第110条((国による買入れ))の規定により換価した引渡命令に係る動産の売却代金に限られる。
(配当の方法)
10 法第59条第1項後段の「残余のうちから配当を受けることができる」とは、9の動産の売却代金を法第129条第1項((配当の原則))に掲げる国税その他の債権(法59条1項後段及び4項の損害賠償請求権を除く。)に配当し、その残余のうちから、配当を受けることができることをいう。
(配当の請求)
11 損害賠償請求権による配当の請求は、その動産の売却決定の日の前日までに、債権現在額申立書を税務署長に提出することによってしなければならない(法130条1項。令48条1項参照)。
(配当が受けられない場合)
12 動産の引渡しを命ぜられた第三者は、その動産の差押え時までに、法第59条第1項の規定による契約の解除をした旨の通知をしないときは、動産の差押え後にその通知をしたことについて相当の理由があると認められるときを除き、法第59条第1項の規定による配当を受けることができない(令25条2項、3項)。
なお、この場合には、次のことに留意する。 (1) 令第25条第3項((みなし使用又は収益の請求の不適用))に該当する場合であっても、引渡しに係る動産の売却代金の交付期日までに契約の解除をした旨の通知をしなければ配当を受けることができないこと。
(2) 令第25条第3項の「相当の理由があると認められるとき」とは、その動産を引き渡すべき期限を繰り上げて引渡命令を発したとき(令24条3項)又は通知の遅延が火災、風水害等の理由によるとき等をいうこと。 (注) この場合における令第25条第1項の通知は、引渡命令を発した日又は火災、風水害等のやんだ日からおおむね7日以内にしなければならないものとする。
使用又は収益
(請求)
13 法第59条第2項の「請求」は、その請求に係る動産の差押え時までにしなければならない(令25条1項)。
(使用又は収益の請求)
14 引渡しを命ぜられた第三者がする法第59条第2項の規定による動産の使用又は収益の請求は、書面によりしなければならない(令25条1項)。
なお、引渡しを命ぜられた第三者が、その命令に係る動産の差押え時までに、法第59条第1項の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第2項の請求をしないときは、同条同項の請求があったものとみなされる(令25条2項前段)。
(使用又は収益できる期間)
15 法第59条第2項の「その期限がその動産を差し押えた日から3月を経過した日より遅いときは、その日」とは、契約の期間の末日が、その動産を差し押さえた日から3月を経過した日より遅いときは、その経過した日をいう。この場合の「3月を経過した日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日または通則令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法10条2項)。
(使用又は収益をさせる場合の第三者の保管)
16 法第59条第2項の規定により第三者に動産の使用または収益をさせる場合には、その動産をその第三者に保管させるものとする。
前払借賃を支払った第三者の配当請求
(配当請求)
17 法第58条第2項の規定により動産の引渡しを命ぜられた第三者が、法第59条第1項前段の規定により賃貸借契約を解除し、かつ、その引渡命令があった時前にその後の期間分の借賃を支払っているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で差押えの日後の期間に係るもの(3月分に相当する金額を限度とする。)の配当を請求することができる(法59条3項前段)。
なお、法第59条第3項の「借賃」とは、賃貸借契約に基づいて支払われる賃借料をいい、その名称のいかんを問わない。
(請求額)
18 配当の請求額については、次のことに留意する。 (1) 差押えの日後の期間分の前払借賃について1月未満に係るものがある場合には、日割りにより計算すること。
(2) 差押えの日後の期日分の前払借賃の金額が借賃の3月分相当額を超えるときは、その3月分の金額とすること。
(配当の順位)
19 法第59条第3項前段の前払借賃の配当順位は、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぎ、かつ、船舶債権者の先取特権等法第19条の適用を受ける債権に先立つことに留意する(法26条1号参照)。
参加差押えをした行政機関等に対する配当請求
20 税務署長が、法第87条第2項((参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置))の規定により、参加差押えをした行政機関等に動産を引き渡した場合には、その動産に係る法第59条第1項又は第3項の規定によりその売却代金から配当を受けることができる権利は、その行政機関等に対して行使することができる(令41条3項)。
動産の引渡しを拒まなかった第三者
(契約解除の通知)
21 動産の引渡しを拒まなかった第三者が、差押え後(引渡し後)であっても相当の期間内(おおむね7日以内)に、契約の解除をした旨の通知をしたときは、法第59条第1項及び第3項の規定による配当を受けることができる(法59条4項、令25条3項)。この場合の配当の方法及び順位については、10及び20に準ずる。
(使用又は収益の請求)
22 動産の引渡しを拒まなかった第三者については、差押え後(引渡し後)であっても、相当の期間内(おおむね7日以内)は使用又は収益の請求ができるが、この請求は書面によりさせるものとする(法59条4項、令25条3項)。
(参加差押えをした行政機関等に対する配当請求)
23 税務署長が法第87条第2項((参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置))の規定により、参加差押えをした行政機関等に動産を引き渡した場合には、その動産に係る法第59条第4項の規定によりその売却代金から配当を受けることができる権利は、その行政機関等に対して行使することができる(令41条3項)。
第60条関係 差し押さえた動産等の保管
保管
1 法第60条の「保管」とは、差し押さえられた動産又は有価証券を自己の勢力範囲内に保持して、その滅失又はき損を防ぐことをいう。
保管責任
(滞納者が差押財産を亡失し、又はき損した場合)
2 滞納者が保管中の財産を滅失し、亡失し、又はき損したときは、その保管人としての注意義務を怠ったと怠らなかったとにかかわらず、一切の損害をその滞納者が負担する。
なお、故意に差押財産を滅失し、亡失し、又はき損した場合には、法第187条((罰則))、刑法第252条第2項((横領の罪))、第262条((毀棄の罪))等の規定が適用されることがある。
(第三者の保管責任)
3 法第60条第1項の第三者は、滞納者に対しては、滞納者の財産を占有している原因である賃貸借契約、寄託契約等の内容に従って注意義務を負い、また国に対しては、保管者として一般に要求される程度の相当の注意義務を負う。
なお、第三者が、故意に又は注意義務を怠ったことにより、保管中の財産を滅失し、亡失し、又はき損したときは、滞納者又は国に対してその損害を賠償する責めを負う。
(滞納者及び占有する第三者以外の第三者の保管責任)
4 法第60条第1項の第三者以外の第三者は、差押財産の保管について、特約のない限り、次に掲げる注意義務を負い、故意に又はその注意義務を怠ったことにより、保管中の財産を減失し、亡失し、又はき損したときは、国に対してその損害を賠償する責めを負う。 (1) 無償で保管する場合((3)の場合を除く。)には、自己の財産におけると同一の注意をもって保管する義務(民法659条)
(2) 有償で保管する場合には、善管注意義務(民法400条)
(3) 保管者が倉庫営業者その他営業の範囲内で保管する商人(例えば、差押財産の運送を依頼した場合の運送人)である場合には、善管注意義務(商法593条、597条、569条、559条参照)
(天災等による差押財産の滅失)
5 差押財産の保管中に、天災その他の不可抗力により、その財産が滅失し、亡失し、又はき損したときは、その損害はすべて滞納者が負担する。
財産を占有する第三者
6 法第60条第1項の「財産を占有する第三者」には、法第58条第1項((第三者が占有する動産等の差押手続))の滞納者の親族その他の特殊関係者で、滞納者の財産を占有する者も含まれる。
保管させることができる場合
7 法第60条第1項の「必要があると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。 (1) 法第59条第2項((引渡しを命ぜられた第三者の使用収益))及び第4項((引渡しを拒まなかった第三者の使用収益))の規定により、これらの第三者に、差し押さえた動産の使用又は収益をさせる場合
(2) 法第61条((差し押さえた動産の使用収益))の規定により、滞納者又は差し押さえた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者に、その動産を保管させる場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難である場合
(4) 差し押さえた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることが滞納処分の執行上適当であると認める場合
滞納者に保管させる場合
8 法第60条第1項の規定により差し押さえた動産又は有価証券を滞納者に保管させる場合には、その滞納者に、その財産を保管すべきことを命じなければならない。この保管命令は、差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
第三者に保管させる場合
(保管命令)
9 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難である場合において、これらを占有する第三者に保管させるときは、その第三者に、その財産を保管すべきことを命じなければならない(法60条1項)。この保管命令は、差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
(運搬が困難であるとき)
10 法第60条第1項ただし書の「その運搬が困難であるとき」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。 (1) 差し押さえた動産又は有価証券の量、型、据付け状態により、その運搬が物理的に困難である場合
(2) 差し押さえた動産又は有価証券が山間へき地にあること等により、交通機関、運搬費等の関係でその運搬が困難である場合
(3) 法第172条((差押動産等の搬出の制限))又は行政事件訴訟法第25条第2項((執行停止)))の規定による停止命令等により搬出が法律上制限されている場合
(同意が得られなかった場合)
11 差し押さえた動産又は有価証券の運搬が困難でない場合で、これらを占有する第三者に保管をさせようとする場合において、その第三者の同意が得られなかったときは、徴収職員がその差押財産の直接占有を継続しなければならない。
(保管の同意書)
12 差し押さえた動産又は有価証券を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、差押調書の余白に無償で保管する旨を記載して第三者の署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をさせるものとする。 (注) 有価証券の保管を命じた場合の保管証については、印紙税は課税しない取扱いとされている(昭和52.4.7付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊の別表第1の第18号文書4関係((差押物件等の保管証)))。また、動産の保管を命じた場合の保管証は、課税文書に該当しない。
差押えを明白にする方法
(封印)
13 法第60条第2項の「封印」とは、差押財産であることを表示する令第26条((差押動産等の表示))に定める事項を記載した標識をいう。この封印の様式は、別に定めるところによる。
(公示書)
14 法第60条第2項の「公示書」とは、差押財産であることを一般に周知させるために公示し、公衆がこれを知りうる状態におくための令第26条((差押動産等の表示))に定める事項を記載した書面をいう。この公示書の様式は、別に定めるところによる。
(その他の方法)
15 法第60条第2項の「その他差押を明白にする方法」とは、例えば、縄張、立札、木札等により第三者に対し差押財産であることを明白にする方法をいう(昭和28.1.30広島高松江支判)。
差押えの効力
(差押えの効力発生の時期)
16 徴収職員がその動産又は有価証券を占有した時に、法第56条第2項((差押えの効力の発生時期))の規定によりその差押えの効力が生ずるのであるが、その差押財産を滞納者又は第三者の保管に移したときは、封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生ずる(法60条2項)。
(封印等の効果)
17 封印その他の表示は、徴収職員が差押財産を占有していることを明らかにする方法であって、徴収職員の現実の占有に代わる支配力を有するものであるから、封印その他の表示がされているときは、その財産の譲受けはその差押えに対抗することができない。
(封印と差押えとの関係)
18 封印等の標識は、第三者が通常容易に認識できるようにするものとする。また、差押えの効力の持続のためには、これらの標識の存続は必要ではなく、それが損壊され、自然に脱落し、又は消滅することがあっても、差押えの効力は消滅しない。ただし、徴収職員は、封印等の損壊、脱落又は消滅を発見したときは、速やかに修復するものとする。
差押財産の搬出手続
19 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、令第26条の2第1項((差押財産搬出の手続))に定める事項を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその第三者にその謄本を交付しなければならない。この書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 差押えと同時に差押財産を搬出する場合には、差押調書に差押財産を搬出した旨を付記し、この書面は作成しなくてもよいこと及び差押財産の搬出に際し捜索をした場合には、捜索調書を作成し、この書面は作成しないことに留意する(令26条の2第2項)。
第61条関係 差し押さえた動産の使用収益
滞納者の使用収益
(国税の徴収上支障がないと認めるとき)
1 法第61条第1項の「国税の徴収上支障がないと認めるとき」とは、その動産の使用又は収益をさせてもほとんど減耗を来さないとき、多少減耗はあっても国税の徴収が確実であると認めるとき等国税の徴収に支障がない場合をいう。
(滞納者の申立て)
2 差押動産を保管させた場合における使用又は収益の許可は、滞納者の申立てにより行うものとする。この場合における申立ては、口頭又は書面のいずれの方法によっても差し支えない。 (注) 滞納者から使用又は収益の許可を求める旨の積極的な申立てがなくても、黙示の申立てがあったとみられる場合があることに留意する。
(許 可)
3 法第61条第1項の使用又は収益の許可は、通常の用法により従来の使用又は収益を継続する程度の範囲において行うものとする。
(通 知)
4 法第61条第1項の規定により滞納者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を滞納者に通知するものとする。この場合における通知は、口頭又は差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。
第三者の使用収益
(第三者)
5 法第61条第2項の「使用又は収益をする権利を有する第三者」とは、差押え時において第59条関係1から3までに掲げる権利を有する第三者をいう(昭和49.4.30名古屋地判)。
(通知)
6 法第61条第2項の規定により第三者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を第三者及び滞納者に通知するものとする。
第3款 債権の差押え
第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
債 権
1 法第62条の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいう。
なお、将来生ずべき債権であっても、差押え時においてその原因が確立しており、かつ、その発生が確実であると認められるもの(例えば、将来受けるべき給料債権、社員又は株主の有する決議前の利益配当請求権(大正2.11.19大判)、社会保険に基づく将来の診療報酬債権(昭和54.9.19東京高決。昭和53.12.15最高判参照)等)は、差し押さえることができる。 (注) 本来の性質が債権であっても、その性質上取立てに適さず、換価手続によるべきもの(例えば、電話加入権、賃借権等)は、法第73条((電話加入権等の差押の手続及び効力発生時期))の規定により差し押さえる(法54条2号)。
連帯債務者のある債権
2 2人以上の債務者のある債権で、それらの債務者が連帯債務を負っているものを差し押さえる場合には、すべての債務者を第三債務者として差し押さえるものとする。この場合において、第三債務者が任意に履行しないときは、いずれの債務者に対しても執行法の規定による強制執行を行うことができる(民法432条から445条まで参照)。
保証人のある債権
(差押手続)
3 保証人のある債権を差し押さえる場合は、主たる債権の差押えと同時に、保証人を第三債務者として、その保証人に対する債権を別個に差し押さえるものとする。この場合において、その保証が連帯保証であるとき又は保証人が2人以上であり、かつ、保証人相互間では連帯債務であるときの保証人に対する履行の請求については、2の後段と同様である。
(催告及び検索の抗弁権)
4 保証人のある債権の差押え及びこれに基づく強制執行については、次のことに留意する。 (1) 主たる債権の差押えをすることなく、保証人に対する債権を差し押さえたときは、法第62条の規定による差押えは支払の請求を含むものであるから、保証人は催告の抗弁権を有する(民法452条)。
(2) 主たる債権及び保証人に対する債権を差し押さえた後、主たる債務者及び保証人が任意に履行しない場合において、主たる債務者に対して執行法の規定により強制執行をすることなく、保証人に対して強制執行をしたときは、保証人は検索の抗弁権を有する(民法453条)。
(3) 保証人が催告又は検索の抗弁権を行使したにもかかわらず、国が主たる債務者に対して差押え又は強制執行をすることを怠ったため、主たる債務者から全部の弁済を受けることができなかった場合は、保証人は、国が直ちに主たる債務者に対して差押え又は強制執行をすれば弁済を受けることができた限度において、その弁済の責めを免れる(民法455条)。
(連帯保証の場合)
5 保証人の保証が連帯保証である場合は、その保証人は、4に掲げる催告及び検索の抗弁権を有しない(民法454条。商法511条2項参照)。
差押えがされている債権
(滞納処分による差押えがされている債権)
6 滞納処分による差押えがされている債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下(1)及び(3)において同じ。)に対する滞納処分による差押え(以下(1)から(5)までにおいて「二重差押え」という。)については、次に掲げるところによる。 (1) 既にされている差押え(以下(2)から(5)までにおいて「先順位の差押え」という。)が債権の全部又は一部についてされているかどうかを問わず、原則として、二重差押えを行うものとする(昭和33.10.10最高判、昭和32.7.2福岡地決参照)。
(2) 先順位の差押えがある間は、二重差押えに基づいて換価(取立てを含む。)をすることができない。
なお、第三債務者が先順位の差押えに係る行政機関等に対して全額履行したときは、二重差押えは効力を失う。
(3) 二重差押えを行う場合においては、法の規定による債権の差押えの手続によるほか、二重差押えを行った旨を先順位の差押え(その差押えが2以上あるときは、原則としてその全部。以下(4)及び(5)において同じ。)に係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えを行った旨通知は、(4)の交付要求書に付記することにより行う。
(4) 二重差押えを行う場合においては、併せて先順位の差押えに係る行政機関等に対して交付要求をするものとする。
(5) 先順位の差押えがある間に、二重差押えを解除したときは、その旨を先順位の差押えに係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えの解除の通知は、交付要求解除通知書に付記することにより行う。
(強制執行等による差押えがされている債権)
7 強制執行又は担保権の実行若しくは行使による差押えがされている債権に対する滞納処分による差押えについては、滞調法及び昭和56.2.7付徴徴4-2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」通達の別冊(以下「滞調法逐条通達」という。)に定めるところによる。 (注) 担保権の行使とは、担保権者が目的物の売却その他により滞納者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によってするその権利の行使をいう(執行法193条)。
期限の定めのない債権
8 期限の定めのない債権を差し押さえる場合には、徴収職員は、債権差押通知書の「履行期限」欄に、原則として即時と記載するものとする(民法412条3項参照)。
なお、その債権が消費貸借に係るものであるときは、契約の目的、金額その他の事情を考慮して履行期限を定めるものとする(同法591条参照)。
交互計算の特約のある債権
9 特約により交互計算に組み入れられることとなる債権は、計算期間中は独立して差し押さえることができないから、計算期間末に発生すべき残額の支払請求権を差し押さえる。この場合において、他に適当な財産がないときは、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))において準用する民法第423条((債権者代位権))の規定による債権者代位権により、滞納者に代位して交互計算の契約を解除し、直ちに残額の支払を請求することができる(商法529条から534条まで参照)。
対抗要件を欠いて譲渡された債権
10 指名債権の譲渡は、確定日付のある証書(民法施行法5条)により譲渡人がこれを債務者に通知し又は債務者がこれを承諾しなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条)ので、この要件を欠いている場合には、譲渡人の債権として差し押さえることができる。 (注) 債権譲渡の通知は譲渡人がすべきであり、譲受人は譲渡人から委任を受けている場合を除き、譲渡人に代位して通知することができない(昭和46.3.25最高判)。
代理受領の目的となっている債権
11 代理受領の目的となっている債権であっても、その契約は差押債権者に対抗できないから(昭和43.3.22大阪高判参照)、当該債権に対して滞納処分をすることができる。 (注) 代理受領とは、債権者が、その債権の確保のために、債務者(滞納者)が第三債務者に対して有する債権について、債務者から取立ての委任を受け、受領した金員を直接自らの債権の弁済に充当する方法による債権担保手段をいう。
譲渡禁止の特約のある債権
(譲渡禁止の特約のある債権の差押え)
12 指名債権につき、当事者間の特約によりその譲渡が禁止されている場合においても、当該債権を滞納処分により差し押さえることができる(第47条関係9、昭和34.9.14東京地判。昭和45.4.10最高判参照)。
(譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合)
13 譲渡禁止の特約のある指名債権につき、譲受人がその特約を知っているときは、その譲渡は無効であるから(民法466条2項)、譲渡人の債権として差し押さえることができる。ただし、その譲渡について第三債務者が承諾を与えているときは、譲渡人の債権として差し押さえることはできない(昭和52.3.17最高判)。
手形又は小切手の振り出されている債権
14 債権について手形又は小切手が振り出されている場合には、その債権の差押えは、次による。 (1) 第三債務者が債務の弁済に代えて手形又は小切手を振り出している場合には、代物弁済によりその債務は弁済されたことになるから、債権の差押えをすることはできない。したがって、この場合には、その手形又は小切手を、法第56条第1項((動産等の差押え))の規定により差し押さえる。
(2) 第三債務者が債務の弁済のために手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているから、その手形又は小切手とは別個にその債権を差し押さえることができる。ただし、手形又は小切手が時効その他の理由により効力を失うまでは、第三債務者は、手形又は小切手が返却されなければ、本来の債務の履行を拒むことができる(昭和13.11.19大判)。
なお、手形又は小切手の振出について特に代物弁済の意思表示がなかったときは、その手形又は小切手は、支払のために振り出されたものと推定される(昭和3.2.15大判)。
敷 金
15 物の賃貸借において、賃借人が賃貸人に交付する敷金の差押えについては、次のことに留意する。
なお、敷金とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的であらかじめ賃貸人に交付される金銭であり、その名称のいかんを間わない。 (1) 賃貸借が継続している間は、賃借人は、敷金の返還請求権を有せず、また、敷金は、賃貸借存続中の賃料債権のみならず賃貸借終了後目的物の明渡義務の履行までに生ずる質料相当損害金の債権その他賃借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのあるべき一切の債権を担保する。したがって、敷金は、将来目的物の明渡しの際に生ずべき返還請求権として差し押さえる(昭和48.2.2最高判)。
(2) 賃貸人が賃貸借の目的物を譲渡した場合には、特約があるときを除き、敷金は、当事者が現実に敷金の引継ぎをしたかどうかにかかわらず、被担保債権を控除した残額について、新たな賃貸人に引き継がれる(昭和2.12.22大判、昭和44.7.17最高判)。
(3) 賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転した場合においては、旧賃借人が新賃借人に敷金を譲渡するなど特段の事情のない限り、敷金は新賃借人に承継されない(昭和53.12.22最高判)。
権利金
16 借地契約又は借家契約に伴い貸主が借主から受領した借地権利金又は借家権利金は、地代家賃統制令第12条の2((権利金の受領禁止))の規定に違反するから、その権利金の返還請求権を差し押さえることができる。ただし、同令第23条((適用除外))の規定に該当する場合には、権利金の返還請求権がない。
無記名預金等
17 無記名預金、他人名義又は架空名義の預金の差押えについては、次のことに留意する。 (1) これらの預金については、自らの出えんによって、自らの預金とする意思で自ら又は使者等を通じて預金契約をした者が預金者となる(昭和32.12.19最高判、昭和53.2.28最高判)。
(2) 無記名預金は、氏名を特定しない一種の指名債権であって、無記名債権ではないから(昭和32.12.19最高判)、法第56条第1項((動産等の差押え))の規定によっては差し押さえることができず、法第62条の規定により債権として差し押さえる。この場合においては、その預金の名称、預金金額、預金証書番号、無記名である旨、使用印影の表示をすること等によって、被差押債権を特定させるものとし、また、その債権の取立てに当たっては、できる限り使用印影を押なつした預金証書を呈示するものとする。
(3) 他人名義又は架空名義で預金をしている場合であっても、その真の権利者に対する滞納処分としてその預金を差し押さえることができる。この場合においては、預金名義人の住所、氏名、預金の種類、名称、預金金額、預金証書番号等によって被差押債権を特定するとともに、真の権利者が滞納者である旨を表示する(例えば、何某(預金名義人氏名)こと何某(滞納者氏名)のように表示するものとする。)。
国又は地方公共団体に対する債権
18 国又は地方公共団体に対する債権を差し押さえる場合には、直接その支払の権限を有する支出官、資金前渡官吏等を第三債務者として差し押さえる(政府ノ債務ニ対シ差押命令ヲ受クル場合二於ケル会計上ノ規程参照)。この場合において、その支払の権限を有する者が判明しないときは、その行政機関の長を第三債務者として差し押さえても差し支えない。 (注) 供託金について債権差押えをする場合には、第三債務者を国とし、その代表者を供託官とし、供託官あてに債権差押通知書を送達する(昭和26.4.18付民事甲第61号最高裁判所民事局長回答参照)。
郵便貯金
19 郵便貯金を差し押さえる場合には、次により、直接その支払の権限を有する者を第三債務者として差し押さえる。 (1) 即時払いを請求できる場合(貯金を預け入れた郵便局においてその郵便局に預け入れた貯金の現在高を超えない金額の貯金の払戻しを請求する場合等。郵便貯金規則51条2項、3項)には、払戻しを請求すべき郵便局の局長を第三債務者とする。
(2) (1)以外の場合には、払戻証書による払戻しの方法によることになるから(郵便貯金規則54条1項)、その郵便貯金の貯金原簿を所管する地方貯金局又は沖縄郵政管理事務所の長を第三債務者とする。この場合においては、その所管庁は、差押金額について払戻証書を作成し、徴収職員に送付することとなっているから、徴収職員は、その払戻証書により特定の郵便局(債権差押通知書に指定すること。)において払戻しを受けるものとする。 (注)1 郵便貯金の払戻しを受けるに当たっては、貯金通帳又は貯金証書を呈示することとなっているから、これらの通帳等を、法第65条((債権証書の取上げ))の規定により、債権に関する証書として取り上げるものとする。
2 郵便貯金を差し押さえた場合は、債権差押通知書に令第27条第4号((債権差押通知書の記載事項))の事項の記載があることにより、その払戻しの請求をしたこととなるが、この払戻しの請求は、貯金通帳又は貯金証書を呈示してしなければならない(郵便貯金規則51条1項、52条、54条2項から4項まで)。
不渡異議申立預託金
20 手形又は小切手の振出人等が、その不渡りによる取引停止処分を回避するため支払銀行に預託する不渡異議申立預託金については、支払銀行に対して有する不渡異議申立預託金返還請求権を差し押さえる。この不渡異議申立預託金返還請求権の弁済期は、支払銀行が手形交換所から不渡異議申立提供金の返還を受けた時である(昭和45.6.18最高判)。 (注) 不渡異議申立提供金とは、支払銀行が手形又は小切手の支払を拒絶した振出人等に支払の資力があり、不渡りがその信用に関しないものであることを明らかにすることにより、取引停止処分を回避するために手形交換所に提供する手形又は小切手の金額相当額の金員をいう(東京手形交換所規則66条参照)。
公示催告中の手形等に係る債権
21 公示催告中の手形又は小切手に係る債権については、その手形金等の支払請求権を差し押さえることができる(昭和51.4.8最高判参照)。 (注) この手形金等の支払請求権は、将来の除権判決の取得を停止条件として権利行使ができる一種の条件付債権である。
換地の所有権の移転があった場合の清算金交付請求権
22 土地区画整理事業による換地の所有権が移転した場合における当該換地に係る清算金交付請求権は、当事者間で特段の合意がなされない限り、当該換地の譲受人には移転しないから(昭和37.12.26最高判、昭和48.12.21最高判)、清算金交付請求権は、当該換地の譲渡人に帰属するものとして差し押さえることができる。
差押手続
(第三債務者)
23 法第62条の「第三債務者」とは、滞納者に対して金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債務を負う者をいう。
(債権の特定)
24 債権の差押えに当たっては、債権者(滞納者)、第三債務者、債権の数額、給付の内容等を表示することによって被差押債権を特定しなければならない。
なお、被差押債権の表示については、具体的事実によって第三債務者が被差押債権を確知できる程度に表示されておれば、その債権の差押えは有効である(昭和13.7.2大判、昭和30.5.19大阪高決。昭和46.11.30最高判参照)。
(債権の範囲)
25 差し押さえる債権の範囲は、原則として、その債権の全額である(法63条)。 (注) 社会保険に基づく将来の診療報酬債権については、近い将来の範囲(おおむね1年以内とする。)に限り、その始期と終期を定めて差し押さえるものとする(昭和54.9.19東京高決参照)。
(債権差押通知書)
26 法第62条第1項の「債権差押通知書」とは、令第27条各号((債権差押通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第4号書式による。この債権差押通知書には、被差押債権の弁済期までに履行すべき旨又は弁済期が既に到来しているものについては直ちに履行すべき旨を記載する。
(差押調書)
27 債権を差し押さえたときは、法第54条の規定により、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付する。この謄本には、債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を付記しなければならない(法62条2項、令21条3項)。
(債権証書の取上げ)
28 徴収職員は、債権の差押えのため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる(法65条)。
差押えの効力
(効力発生の時期)
29 債権の差押えは、債権差押通知書が第三債務者に送達された時にその効力を生ずる(法62条3項)。
なお、滞納者に対する差押調書の謄本の交付は、差押えの効力発生要件ではない。
(履行の禁止)
30 第三債務者は、債権の差押えを受けたときは、その範囲において滞納者に対する履行が禁止される。したがって、債権差押通知書の送達を受けた後に、第三債務者が滞納者に対して履行をしても、その履行をもって差押債権者である国に対抗することができない(民法481条参照)。
(相殺の禁止)
31 第三債務者の有する反対債権と被差押債権との相殺については、次のことに留意する。 (1) 被差押債権及び反対債権の弁済期が差押え時以前に到来している場合並びにこの場合以外で被差押債権の弁済期以前に反対債権の弁済期が到来する場合には、差押え後においても、第三債務者は、相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(2) 差押え前に取得した反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より後に到来する場合において、第三債務者が履行しないことについて正当な理由があるときに限り、第三債務者は、相殺をもって差押債権者に対抗することができる(昭和45.6.24最高判)。
なお、滞納者と第三債務者との間において、差押え前に、期限の利益の喪失の特約又は債務不履行があった場合等一定の条件の下に第三債務者が相殺の予約完結権を行使できる旨の特約がされている場合には、反対債権が差押え後に取得されたものでない限り(民法511条)、第三債務者は、当該特約に基づく相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(3) 民法第509条((不法行為による債権の相殺))、商法第200条第2項((相殺禁止))、有限会社法第57条((資本増加に関する準用規定))等の法令の規定により、相殺が禁止される場合がある。
(債権の譲渡等)
32 第三債務者が債権の差押えを受けたときは、滞納者が被差押債権の譲渡、免除、期限の猶予等をしても、第三債務者は、これらの行為にかかわらず、差押債権者に弁済をしなければならない(法62条2項参照)。
(債権譲渡と差押えとの優劣)
33 指名債権の譲渡と滞納処分による差押えの優劣は、確定日付のある譲渡通知書が第三債務者に到達した日時又は確定日付のある第三債務者の承諾の日時と、債権差押通知書が第三債務者に到達した日時との先後により判定する(昭和49.3.7最高判参照)。この場合において、これらの日時が同一であることにより優劣の判定ができないときは、債権譲受人及び差押債権者は、それぞれ第三債務者に対しその履行を請求することができる(昭和55.1.11最高判参照)。
(同時履行の抗弁権又は選択権の行使)
34 第三債務者が同時履行の抗弁権を有する場合(民法533条)又は第三債務者若しくは第三者が選択権を有する場合(同法406条から411条まで参照)には、差押え後であっても、これらの権利を行使することができる。
(継続的な収入)
35 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押えの効力は、差押えに係る国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金額に及ぶ(法66条)。
(法定果実)
36 債権を差し押さえた場合には、その差押えの効力は、差押え後に生ずる利息に及ぶが、その他の法定果実には及ばない(法52条2項、第52条関係16,17参照)。
(時効中断)
37 債権の差押えは、通則法第72条第3項((時効についての民法の規定の準用))において準用する民法第147条第2号((差押え等の時効中断の事由))の規定により、その差押えに係る国税については時効中断の効力を有する。また被差押債権については、時効中断の効力を生ぜず、催告としての効力を有するから(大正10.1.26大判)、債権差押え後6月内に裁判上の請求その他の行為(民法153条参照)をすれば、その催告による時効中断の効力がある。 (注) 時効期間は一般の債権が10年(民法167条1項)、商事の債権が5年(商法522条)であるが、なお、短期消滅時効の定めがあることに留意する(民法169条から174条まで、商法567条、手形法70条等)。
差押えの登録の嘱託
(登録を要する債権)
38 法第62条第4項の「移転につき登録を要するもの」には、社債等登録法第3条((登録をする場合))の規定により登録された社債のほか、地方債、特別の法令により設立された法人で会社でないものが発行する債券等で、同法第14条((地方債等への準用))において準用する同法第3条の規定に基づき登録されたものがある(これらについては、債券は発行されていない。同法4条)。
なお、登録国債については、次に掲げる書類を日本銀行(国債局)に送達することにより、差し押さえるものとする。 (1) 第三債務者を国とし、その代表者を大蔵大臣と記載した債権差押通知書
(2) 日本銀行総裁をあて先とする登録国債差押登録嘱託書
(登録社債等の差押えの登録の嘱託)
39 登録社債等を差し押さえたときは、社債等登録法施行令に定める手続に従って、関係機関(登録機関)に対して差押えの登録の嘱託をしなければならない(法62条4項)。この場合において、その登録社債等の発行機関が同令第1条((登録機関))に規定する登録機関と異なるときは、その発行機関に対して差押えの通知をするものとする(社債等登録法5条、同法施行令13条、18条1項)。
第63条関係 差し押さえる債権の範囲
差し押さえる債権の範囲
(全額の差押え)
1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法63条本文)。
(一部の差押え)
2 法第63条ただし書の「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる要件を満たすときをいうものとする。 (1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。
(2) 弁済期日が明確であること。
(3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと。
一部差押えの手続
3 債権の一部を差し押さえる場合には、債権差押通知書の「差押債権」欄に、その債権のうち一部を差し押さえる旨を明記する(令27条3号参照)。
第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
債権差押えの登記の嘱託
(登記の嘱託)
1 抵当権(根抵当権を含む。昭和55.12.24付民三第7,176号法務省民事局長通達。以下3及び4において同じ。)又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権を差し押さえた場合(債権差押え後に、その債権を被担保債権として担保権が設定された場合を含む。昭和42.1.30付民事甲第206号法務省民事局長通達)には、税務署長は、債権差押えの登記を関係機関に嘱託する。この関係機関については、第68条関係44、第70条関係5、第71条関係5、第72条関係19及び第73関係52と同様である。この債権差押えの登記は、担保権の登記の付記登記としてなされる(不動産登記法施行細則55条、56条)。
なお、債権差押えの登記は、債権差押えの効力要件ではないが、その登記をすることにより、その抵当権、質権又は先取特権に差押えの効力が及んでいることについて対抗要件を具備することとなる。 (注) 登記の嘱託とは、官公署が法令の規定に従って関係機関に対して登記の依頼を行うことをいう。
嘱託による登記の手続には、原則として申請による登記に関する規定が準用される(不動産登記法25条2項、船舶登記規則1条、航空機登録令8条、自動車登録令9条、建設機械登記令9条、特許登録令15条等)。
(登録免許税の非課税)
2 税務署長が債権の差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
債権譲渡又は担保権の処分と差押えとの関係
3 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権の譲渡と滞納処分による差押えとの優劣は、その担保権の移転の登記又は債権差押えの登記との先後によってではなく、債権譲渡の対抗要件である確定日付のある通知又は承諾と債権差押通知書の送達との先後によって定まる(法62条関係33)。したがって、債権譲渡が優先する場合には、債権差押えの登記をしても、債権譲受人に対し担保権につき差押えの効力を主張できず(大正1.11.26大判)、また、差押えが優先する場合においては、既に担保権の移転の登記がされていても、その抹消を求めることができる(昭和35.4.28高知地判、昭和35.9.28松山地判)。
なお、被担保債権と別個になされる抵当権のみの譲渡、順位譲渡その他の抵当権の処分と差押えとの優劣は、抵当権の処分の登記と債権差押えの登記との先後によって定まることに留意する(民法177条、375条参照)。
債権差押えの通知
(質権又は抵当権が設定されている場合)
4 税務署長は、1の嘱託をしたときは、その質権又は抵当権が設定されている財産の権利者(第三債務者を除く。)に対して、債権差押えをした旨を通知しなければならない(法64条後段)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(先取特権がある場合)
5 税務署長は、1の嘱託をしたときは、その先取特権がある財産の権利者に対して4の通知をしなければならない。この場合において、その権利者がその被差押債権の第三債務者であるときは、この通知は要しない(法64条後段)。
他の担保権のある債権の差押え
(動産質等のある場合の差押手続)
6 動産について質権又は留置権のある債権を差し押さえた場合には、その質権又は留置権に差押えの効力が及ぶから、その質権又は留置権の目的となっている財産の権利者(第三債務者を除く。)に対し、4に準じて債権差押えをした旨を通知する。この場合には、滞納者の所持する質物又は留置物を動産差押えの手続に準ずる方法により、徴収職員が直接占有するものとする。この場合において、その質物又は留置物を滞納者以外の第三者が所持している場合の徴収職員の占有の手続については、法第56条第1項、第58条及び第60条第1項本文((動産の差押手続、保管等))の規定による手続を準用する。
なお、不動産留置権のある債権を差し押さえた場合においても、上記の手続に準ずる。
(債権質のある場合の差押手続)
7 債権質のある債権を差し押さえた場合(8の場合を除く。)には、その債権質の目的となっている債権の債務者(第三債務者を除く。)に対して、4に準じて主たる債権(その債権質によって担保されている被差押債権)を差し押さえた旨を通知するものとする。この場合において、主たる債権の債権者(滞納者)の占有する債権に関する証書があるときは、法第65条((債権証書の取上げ))の規定によりその証書を取り上げることができる。 (注) 債権をもって質権の目的とする場合において、その債権につき証書があるときは、質権の設定の効力は、その証書を交付しなければ生じない(民法363条)。
(有価証券質のある場合の差押手続)
8 有価証券を目的とする質権のある債権を差し押さえた場合には、その質権の設定者(第三債務者を除く。)に対して、4に準じて債権差押えをした旨を通知するほか、滞納者が占有するその質権の目的である有価証券を、法第65条((債権証書の取上げ))の規定により徴収職員が占有する。この場合において、その有価証券が記名社債又は記名株式であるときは、その有価証券質に差押えの効力が及んでいることの対抗要件を具備するために、その有価証券を発行した者に債権差押えをした旨を通知する(民法365条、商法209条参照)。 (注) 上記の場合において、有価証券を滞納者以外の第三者が所持している場合の徴収職員の占有の手続については、法第56条第1項、第58条及び第60条第1項本文((動産の差押手続、保管等))の規定による手続に準ずる。
(その他の権利質のある場合の差押手続)
9 7及び8以外の権利質のある債権を差し押さえた蝪合には、その権利質の目的となっている財産権の性質に従い、主たる債権の差押えの登記の嘱託、第三債務者に準ずる者への通知等7及び8に準じて必要な手続をとるものとする。
第65条関係 債権証書の取上げ
債権証書の取上げ
(取上げができる場合)
1 法第65条の「差押のため必要があるとき」には、債権差押えをしようとする場合において、債権の存否、債権の数額の確認等のため必要と認められるときのほか、債権の差押え、取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれる。
(取上げができる証書)
2 法第65条の「債権に関する証書」とは、債権の発生、変更を証する文書のほか、債権の差押え、被差押債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められる文書をいい、例えば、郵便貯金通帳、銀行預金通帳、銀行預金証書、供託書正本(官庁又は公署が保管している場合に限る。供託規則24条、25条参照)、供託通知書、公正証書、確定判決、和解調書等がある。
(取上げの手続)
3 法第65条の「取り上げる」とは、徴収職員が、その債権に関する証書の取上げの意思をもって客観的な事実上の支配下に置くことをいう。この場合において、その証書を滞納者及びその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有し、その引渡しを拒むときは、法第58条((第三者が占有する動産等の差押手続))の規定の準用がある(法65条後段)。
(取上調書の作成)
4 債権に関する証書を取り上げた場合は、令第28条第1項((債権証書等を取り上げた場合の調書))の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した調書を作成して署名押印し、その謄本を滞納者その他その処分を受けた者に交付しなければならない。この調書は、別に定めるところによる。ただし、上記の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成した場合において、これらの調書に取り上げる証書の名称、数量その他その証書を特定するに足りる必要な事項を付記したときは、取上調書の作成を要しない(令28条2項)。
債権証書の返還等
5 債権の差押えを解除する場合において、取り上げた債権に関する証書があるときの措置については、法第80条第2項第1号及び第4項((差押の解除の手続))の規定が準用される(法80条5項)。
第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
継続的な収入
1 法第66条の「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」とは、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給料に係る債権(法76条1項参照)並びに継続的給付を目的とする契約関係から発生する収入を請求する権利、例えば、賃貸借契約に基づく地代、家賃の請求権等をいう。
差押えの効力の及ぶ範囲
(差押え後に収入すべき金額)
2 継続収入の債権を差し押さえた場合には、特に制限した場合(例えば、「何月分の給料又は家賃」というように制限した場合等)を除いては、差押えに係る国税を限度として、差押え後に支払われるべき金額のすべてに差押えの効力が及ぶ。したがって、各支払期ごとの金額を各別に差し押さえる必要はない。
(差押えの効力の存続)
3 法第66条の継続的な収入に対する差押えの効力は、第三債務者が同一であり、かつ、滞納者と第三債務者との間の基本の法律関係に変更がない限り、その後に変更があった収入にも及ぶ。 (注) 滞納者が退職した後再雇用されている場合には、執行を免れるため仮装したと認められるときを除き、退職前に行われた給料に対する差押えの効力は、再雇用後の給料には及ばない(昭和55.1.18最高判参照)。
第67条関係 差し押さえた債権の取立て
取立て
(意 義)
1 法第67条第1項の「取立」とは、徴収職員が、被差押債権の本来の性質、内容に従って、金銭又は換価に適する財産の給付を受けることをいう。
(取立ての範囲)
2 債権を差し押さえたときは、差押えに係る国税の額にかかわらず、被差押債権の全額を取り立てるものとする(法67条1項)。
(取立権取得の効果)
3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、差し押さえた債権の取立てに必要な滞納者の有する権利を行使することができる。したがって、支払命令の申立て、給付の訴えの提起、配当要求、破産手続又は会社更生手続への参加、担保権の実行、保証人に対する請求等の行為をすることができるが、債務の免除、譲渡、弁済期限の変更等取立ての目的を超える行為をすることはできない。 (注)1 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合においても、被差押債権の取立ては制限をうけない(通則法105条1項参照)。
2 債権差押えに基づく取立訴訟において、第三債務者は、差押えに係る国税の存否を争うことはできない(昭和52.1.28広島地判。昭和45.6.11最高判参照)。
(取立ての方法)
4 第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行しないときは、徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずるものとする。
なお、必要に応じ仮差押え又は仮処分の申請をすることができる。 (注) 被差押債権の取立てについては、給付の訴えの提起、支払命令の申立て、仮差押え又は仮処分の申請等をする必要がある場合には、法務省の関係部局に依頼して行う(法務大臣の権限法1条)。
(担保権のある債権の取立手続)
5 抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合において、第三債務者が被差押債権の取立てに応じないときは、次に掲げるところによる。 (1) 抵当権、質権(権利質及び注に掲げるものを除く。)、先取特権又は留置権の目的となっている財産については、執行法その他の法律の規定により担保権の実行をする。 (注) 流質契約のある商事質又は営業質の目的となっている財産については、流質期限の経過後は、滞納者の財産として差し押さえる。
(2) 債権質の目的となっている債権については、その債権の債務者(第四債務者)から直接取り立てる(民法367条)。
なお、上記の債務者が取立てに応じないときは、執行法第193条((債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等))の規定により担保権の実行又は行使をする。
(3) 不動産物権の上の質権については、抵当権実行の方法に準じて、その不動産物権について競売の申立てをする。
(4) (2)及び(3)に掲げる以外の権利質については、執行法第193条の規定により担保権の実行又は行使をする。
(取立ての責任)
6 徴収職員が被差押債権の取立てに当たって故意又は過失により違法に滞納者に損害を与えたときは、国は、国家賠償法第1条第1項((公権力の行使に基づく損害の賠償責任))の規定により、滞納者に対してその損害を賠償しなければならない場合がある。
(給付の受領の資格)
7 第三債務者から取り立てた金銭は、歳入歳出外現金出納官吏の資格において、受け入れる(管理事務提要(現金出納編)第131参照)。
(履行の場所)
8 被差押債権の履行場所は、原則として(民法664条、商法608条参照)、次に掲げるところによる。
なお、被差押債権が持参債務であるときは、税務署の所在地が履行場所となる(9の(2)のただし書参照)。 (注) 滞納者と第三債務者との間で金融機関に振込入金することにより履行することになっている場合であっても、同様である。 (1) 商行為により生じた債務(商法516条参照) イ 行為の性質又は当事者の意思表示で定まっているときは、その定められている場所
ロ イ以外の場合には次による。 (イ) 特定物の引渡しを目的とする債務については、行為の当時その物の存在した場所
(ロ) 特定物の引渡し以外の給付を目的とする債務については、履行する時の債権者の営業所(営業所がないときは住所) (注) 支店でした取引については、その支店が営業所とみなされる(商法516条3項)。
(2) (1)以外の債務(民法484条参照) イ 取引の慣行又は意思表示で定まっているときは、その定められている場所
ロ イ以外の場合には次による。 (イ) 特定物の引渡しを目的とする債務については、債権発生の当時その物の存在した場所
(ロ) 特定物の引渡し以外の給付を目的とする債務については、履行する時の債権者の場所 (注) 売買代金について、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所が履行場所となる(民法574条)。
(履行の費用)
9 被差押債権の履行の費用については、次による(民法485条参照)。 (1) 取立債務であるときは、その取立てに要する費用は滞納処分費として支出する。ただし、第三債務者が取立てに要する費用を支出し、その費用を債務の額から差し引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えない。この場合においては、第三債務者に対し、その費用に相当する額については履行の請求をしないものとする。
(2) 持参債務であるときは、その取立てに要する費用は第三債務者に負担させる。ただし、本来の履行場所である滞納者の住所又は営業所と税務署の所在地とが異なるため費用が増加した場合における増加費用については、(1)に準ずる。
(3) 履行場所が特約によって定まっているときは、その履行場所からの取立てに要する費用については、(1)に準ずる。
(4) 弁済の費用について特約があるときは、その特約の定めるところに従い、(1)から(3)までに準ずる。
取立不能の判定
10 第三債務者に弁済の資力がなく取立不能と認められる場合には、債権の差押えを解除するものとする。この場合において、取立不能の判定は、原則としては強制執行等の強制的な取立手続をした後において行うが、第三債務者の資力その他の状況により、その債権が取立不能と認められるときは、強制的な取立て手続をすることなく判定して差し支えない。
取立財産の差押え
11 第三債務者から取り立てた金銭(第56条関係26参照)以外の財産については、その財産の種類に応じて、法第56条((差押の手続及び効力発生時期等))、第68条((不動産の差押の手続及び効力発生時期))、第70条((船舶又は航空機の差押))又は第71条((自動車又は建設機械の差押))の規定による差押えの手続をとらなければならない(法67条2項)。
徴収したものとみなす
12 法第67条第3項の「徴収したものとみなす」とは、金銭(第56条関係26参照)を取り立てたときは、その限度において、滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
なお、国税の納付に使用することができる有価証券を取り立てた場合において、その支払がなかったときは、滞納者の国税の納税義務は消滅しない(証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律2条参照)。
弁済の委託
(意 義)
13 法第67条第4項の「弁済の委託」とは、第三債務者が有価証券の現金化及びその現金による被差押債権の弁済手続を、弁済受託に関する証書に記載された税務署長が定める条件により、徴収職員に委任することをいう。
なお、弁済委託により受領した証券は債権の弁済に代えて受領するものではないから、第三債務者の債務(被差押債権)は、弁済委託により直ちに消滅するものではない。
(弁済受託に関する証書)
14 弁済受託に関する証書は、通則規則第5条((書式))に規定する別紙第6号書式の納付受託証書を補正の上使用する(規則3条2項参照)。 (注) 徴収職員は、弁済の委託を受けたときは、弁済受託に関する証書を弁済の委託をした者に交付しなければならない(法67条4項、通則法55条2項)。
(証書に記載する延滞税の金額)
15 弁済受託に関する証書に記載する延滞税の金額は、弁済委託を受けた証券の種類により、それぞれ次に掲げる目までの金額とする。
なお、次のそれぞれに掲げる日の翌日以後の延滞税については、通則法第63条第5項第1号((納付委託に係る延滞税の免除))の規定に準じて、免除することができるものとする。 (1) 証券が一覧払いのものであるときは、その委託を受けた日
(2) 証券が先日付小切手であるときは、その振出日として記載された日
(3) 証券が(1)以外の手形であるときは、その満期日
(弁済委託に使用できる証券)
16 弁済委託に使用することができる証券は、証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律の規定に基づき国税及び歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券のうち、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限る取扱いとする(令67条4項、通則法55条1項参照)。
なお、証券の券面金額が差押えに係る国税の額を超える場合であっても、被差押債権の金額を超えない限り、その証券による弁済の委託を受けることができる。 (1) 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下16において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの (注) 信用金庫、農業協同組合等は、小切手ノ適用二付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ足ムルノ件により、小切手法の適用については銀行と同視されているので、これらのもののうち、手形交換所に代理交換の認められているものは、手形交換所に加入している銀行として取り扱う。 イ 振出人が弁済委託をする者であるときは、弁済委託を受ける徴収職員の所属する税務署長を受取人とする記名式のもの
ロ 振出人が弁済委託をする者以外の者であるときは、弁済委託をする者が税務署長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの イ 約束手形については振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)については支払人が、それぞれ弁済委託をする者であるときは、税務署長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
ロ 約束手形については振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人が、それぞれ弁済委託をする者以外の者であるときは、弁済委託をする者が税務署長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする(1)及び(2)に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(弁済委託を受けることができる場合)
17 弁済委託を受けることができる場合は、最近において取立てが確実と認められる16の証券を提供した場合で、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するときに限る取扱いとする(法67条4項、通則法55条1項参照)。 (1) 第三債務者の提供した証券の支払期日が、被差押債権の弁済期以前であるとき。
(2) 第三債務者の提供した証券の支払期日が弁済期後となるときは、その証券の支払期日まで弁済期限を猶予することを滞納者が承認したことを証する書面を、併せて提出したとき(18、令29条参照)。
(滞納者の承認)
18 法第67条第4項ただし書の「滞納者の承認」とは、滞納者が被差押債権の弁済期限の猶予を承認することをいう。この場合における弁済期限の猶予は、差押債権者である国と滞納者との間には影響を及ぼさない。
(取立ての費用)
19 弁済委託を受けた証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を第三債務者から併せて提供させなければならないが(法67条4項、通則法55条1項後段参照)、この場合における費用とは、銀行に再委託した場合における取立手数料その他銀行が取立てをするために要する費用(例えば、取立済通知を電信で受けるように依頼して取立委託をする場合の実費等)をいう。
なお、取立費用は、徴収職員としての資格ではなく、歳入歳出外現金出納官吏の資格において受領するものである(管理事務提要(現金出納編)第131参照)。
(再委託)
20 弁済委託を受けた証券は、その取立てのため、徴収職員が確実と認める金融機関に再委託をすることができる(法67条4項、通則法55条3項)。
(納付委託に関する規定の準用)
21 弁済委託については、通則法第55条第1項から第3項((納付委託))までの規定が準用される(法67条4項)。
第4款 不動産等の差押え
第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
法第68条の適用を受ける財産
1 法第68条の適用を受ける財産は、次に掲げる財産(以下「不動産」という。)である。 (1) 民法上の不動産土地及び土地の定着物
(2) 不動産を目的とする物権(所有権を除く。)地上権及び永小作権
(3) 不動産とみなされる財産立木法による立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団及び観光施設財団
(4) 不動産に関する規定の準用がある財産鉱業権、特定鉱業権、漁業権、入漁権、採石権及びダム使用権
(5) 不動産として取り扱う財産鉄道財団、軌道財団及び運河財団
民法上の不動産
(土地及び土地の定着物)
2 土地及び土地の定着物は、民法第86条第1項((不動産の定義))に規定する不動産であるが、なお次のことに留意する。 (1) 土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶが(民法207条)、鉱業法において、鉱物として列挙されたもので、未採掘のものを取得する権利等は国により賦与されるので、その権利の賦与がない限り、その鉱物には土地の所有権が及ばない(鉱業法2条、3条)。
(2) 土地の定着物とは、土地に付着させられ、かつ、取引上の性質としてその土地に継続的に付着させられた状態で使用されるもの(例えば、建物その他の工作物、植栽された樹木、大規模な基礎工事によって土地に固着させられた機械等)をいい、土地の一部として土地の差押えの効力が及ぶが、建物及び立木法による立木は、取引上及び登記簿上、土地と別個の不動産として取り扱われ、その差押えには別個の差押手続を必要とする。 (注) 登記することができない土地の定着物は、民事執行の手続の上では、動産執行の対象となる(執行法43条1項、122条1項)。
(3) 仮植中の樹木、簡単な方法で土地に据え付けた機械、灯ろう等は独立の動産であって、土地の定着物ではない。
(4) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による工場抵当の目的となっている土地の備付物には、その土地に対する差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。4参照)。
(建 物)
3 建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい(不動産登記事務取扱手続準則(昭和52.9.3付民三第4,472号法務省民事局長通達)136条1項)、取引上及び登記簿上、土地から独立した不動産とされ、土地には別個に差し押えなければならないが、なお次のことに留意する。 (1) 不動産登記手続上次のイの建造物は建物として取り扱われるとして例示されているが、ロの建造物は建物として取り扱われないこととされている(不動産登記事務取扱手続準則136条2項)。 イ 建物として取り扱うもの (イ) 停車場の乗降場及び荷物積卸場(ただし、上屋を有する部分に限る。)
(ロ) 野球場、競馬場の観覧席(ただし、屋根を有する部分に限る。)
(ハ) ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
(ニ) 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物
(ホ) 園芸、農耕用の温床施設(ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。)
ロ 建物として取り扱わないもの (イ) 瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク
(ロ) 機械上に建設した建造物(ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。)
(ハ) 浮船を利用したもの(ただし、固定しているものを除く。)
(ニ) アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
(ホ) 容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等
(2) 建築中の建物のうち、建物の使用の目的からみて使用可能な程度に完成していないものは、動産として差押さえる(大正15.2.22大判参照)。この場合において、その後通常建物として使用することができる程度(屋根、周壁及び床を備える状態)に完成した場合には、改めて不動産としての差押えの上、動産としての差押えを解除するものとする。
なお、建築中の建物については、不動産工事の先取特権の登記がある場合であっても、建物としての差押え及びその登記をすることはできない(不動産登記法136条参照)。
(3) プレハブ式建物については、その土台を土地に付着させしめるような特別の付加工事を施した場合又は土地に永続的に付着した状態で一定の用途に供されるものであると取引観念上も認めうるような特段の事情がない限り、動産として差し押さえる(昭和54.3.27釧路地判参照)。 (注) プレハブ式建物とは、屋根、周壁等によって構成され、一時的あるいは場所的な移動を必要とする用供する目的で移設に適するような構造に製作された建物をいう(昭和54.3.27釧路地判参照)。
(4) 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(建物の区分所有等に関する法律1条参照)があるときは、その各部分について独立した不動産として差し押さえる(不動産登記法15条ただし書、16条ノ2参照)。
(5) 同一の建物につき2以上の表示の登記がされている場合には、先にされた表示の登記が建物の現況と符号している以上、後にされた表示の登記は無効である(昭和37.10.4付民事甲第2,820号法務省民事局長通達参照)。
(6) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定による工場抵当の目的となっている建物の備付物には、その建物に対する差押えの効力が及ぶ(同法7条1項。4参照)。
財団を組成しない工場抵当の目的となっている土地又は建物
(差押えの効力が及ぶ財産)
4 工場抵当法第7条((差押え等の及ぶ範囲))の規定により、抵当権の目的となっている土地又は建物についての差押えの効力は、その土地又は建物に付加してこれと一体となっている物及びその土地又は建物に備え付けた機械器具その他工場の用に供する物に及び、その備え付けた時期が抵当権の設定又は差押えの前であると後であるとを問わない(大正9.12.3大判)。
(差押えの効力が及ばない財産)
5 工場抵当法第1条((工場の定義))にいう工場の土地又は建物についての抵当権の効力は、次に掲げる物には及ばないから、その土地又は建物についての差押えの効力も及ばない。したがって、これらの物件が同法第3条((抵当権の目的物の目録))の目録に記載されている場合においても、その記載は効力がない(同法3条2項、35条参照)。 (1) 土地を差し押さえた場合の建物及び建物を差し押さえた場合の土地(工場抵当法2条)
(2) 備付物のうち、設定行為で抵当権の効力が及ばない旨の特約の登記のある物(工場抵当法2条1項ただし書、2項)
(3) 抵当権設定者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、抵当権者もその事情を知りながら備え付けた物(工場抵当法2条1項ただし書、2項。民法424条参照)
(4) 他人の所有物(民法242条ただし書、昭和37.5.10最高判参照)
(5) 工場所有者が抵当権者の同意を得て土地又は建物から分離し、又は備付けをやめた物(工場抵当法6条)
(6) 性質上土地又は建物に備え付けられたと認められない物(例えば、車両、運搬具等)
(目録に記載されていない財産)
6 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定により抵当権の効力が当然に及ぶ物であっても、同法第3条((抵当権の目的物の目録))に規定する目録にその記載がない場合には、これらの物についての抵当権の効力は第三者に対抗することができないから、これらの財産の差押えも第三者に対抗することができない。したがって、この場合には、滞納者に代位して、抵当権者の同意を得て目録記載の変更登記をするか、又はこれらの財産を独立の動産として差し押さえる(同法3条2項、38条、大正9.12.3大判)。
(差押え後の抵当権の設定)
7 土地又は建物を差し押さえた後、その土地又は建物について工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の抵当権が設定された場合には、その抵当権の設定は、差押債権者である国に対抗することができない。
地上権
(意 義)
8 地上権は、工作物(建物等を含む。)又は竹木を所有する目的のため他人の土地を使用する権利をいい(民法265条)、所有すべき目的物のない土地の上にも設定することができ、また、地下又は空間について、その上下の範囲を限って設定することもできる(民法269条ノ2)。 (注) 地上権の処分の効力は、立木法による立木には及ばない(同法2条3項)。
(農地等の上の地上権)
9 農地又は採草放牧地(以下第68条関係において「農地等」という。)の上の地上権の移転については、原則として、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。
永小作権
(意 義)
10 永小作権は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利をいう(民法270条)。
(譲渡禁止の特約がある永小作権)
11 永小作権については、設定行為によって権利の譲渡を禁ずることができ、その特約が登記されている場合には、第三者に対抗することができるが、差押えをすることは妨げられない。
ただし、換価については、永小作権設定者の同意を得て特約の登記を抹消した後てなければ、することができない(民法272条、不動産登記法112条)。
(農地等の上の永小作権)
12 農地等の上の永小作権の移転については、原則として、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。
立木法による立木
13 立木とは、立木法第1条((定義))の規定により登記した樹木の集団をいい、独立した不動産とみなされるから(同法2条1項)、土地と別個に差し押さえなければならないが、なお次のことに留意する。 (1) 明治42年法律第22号第1条第2項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件により、立木法の規定の適用を受ける樹木の集団で、その所有者が同法の規定により所有権の保存の登記をしたものは、土地から独立した不動産となり、1筆の土地又はその一部分の土地の上に生立する集団ごとに、1単位の立木として差し押さえる。
(2) 滞納処分の前提として、滞納者に代位してする立木の保存登記の申請は、受理されない(昭和33.7.2付民事甲第1,328号法務省民事局長心得通達)。この場合においては、(3)により処理する。
(3) 登記をしない樹木の集団及び独立の取引価値がある個々の樹木は、通常の土地の定着物としてその土地の差押えの効力が及ぶのであるが、それらの樹木について立札、縄張等の明認方法を施すことによって、土地から独立した不動産として差し押さえることができる(大正10.4.14大判、昭和46.6.24最高判参照)。
(4) 植栽された樹木の集団は、果実の採取を目的とするものであっても、立木としての保存登記をすることができる(明治42年法律第22号第1条第2項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件1条ただし書、昭和30.6.10付民事甲第1,175号法務省民事局長通達)。
工場財団
(意 義)
14 工場財団とは、工場抵当法により物品の製造等の工場の施設としての土地、建物、機械、器具その他の物的設備のみならず、そのための地上権、賃借権、工業所有権又はダム使用権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法8条、9条、11条)。工場所有者が工場財団登記簿に所有権保存の登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされる(同法14条1項)。
なお、工場抵当法第22条((工場財団目録))の工場財団目録に記載された不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、動産、無体財産権その他の財団組成物件は、個々の物又は権利として差し押さえることができない(同法13条2項、昭和7.12.21法曹会決議)。
(差し押さえた動産が工場財団に組み入れられた場合)
15 差し押さえられた動産は工場財団に属させることができないが(工場抵当法13条1項)、滞納処分により差し押さえた動産について工場財団の所有権保存の登記の申請があったときは、登記官は、登記のない動産については、1月以上3月以内の期間を指定してその間に権利の申出をすべき旨を官報に公告するから(同法24条1項)、徴収職員は、その期間内に、その動産が滞納処分による差押えの対象財産である旨を登記官に申し出なければならない。 (注) 上記の公告期間中にその申出をしないときは、工場財団の所有権保存登記後6月内に抵当権設定の登記がされなかったためにその登記が効力を失う場合を除いて、その差押えは効力を失うことに留意する(同法25条、10条)。
(差し押さえた不動産等が工場財団に組み入れられた場合)
16 不動産、地上権、賃借権、工業所有権、ダム使用権及び登記のある動産について差押えの登記をした後は、これらの物件を工場財団に組み入れることができないが(工場抵当法13条1項)、差押えの登記前にこれらの物件について工場財団の所有権保存の登記の申請があった旨の登記がされた場合において(同法23条)、工場財団について抵当権設定登記があったときは、差押えの登記はその効力を失うから(同法31条、32条)、改めて工場財団として差し押さえるものとする。
(保存登記申請後の差押え)
17 不動産、地上権、賃借権、工業所有権、ダム使用権及び登記のある動産については、工場財団の所有権保存登記の申請があった旨の登記があった後においても、その不動産等を差し押さえてその登記を嘱託すことができるが、所有権保存登記の申請が却下されない間及びその登記が効力を失わない間は換価をすることができず(工場抵当法30条)、また工場財団について抵当権設定登記がされたときは、差押えの登記はその効力を失うから(同法31条)、改めて工場財団として差し押さえるものとする。
なお、工場財団に属する登記のない動産についても、工場抵当法第24条第1項((利害関係人に対する公告))に規定する公告がされた後の差押えについては、上記と同様である(同法33条)。
(保存登記があった後の差押え)
18 工場財団について所有権保存登記があった後は、工場財団としての差押えをすることができるが、その保存登記後6月内に抵当権設定の登記がされないときは、その保存登記は効力を失うから、個々の財団組成物件について新たに差押えをしなければならない(工場抵当法10条参照)。また、抵当権が全部抹消された後若しくは分割により消滅した後6月内は工場財団は消滅しないから、この期間中は、工場財団として差し押さえることができるが、6月内に新たな抵当権の設定の登記がないときは、個々の財団組成物件について、新たに差押えをしなければならない(同法8条3項参照)。
鉱業財団等
(鉱業財団)
19 鉱業財団とは、鉱業抵当法により鉱業権、土地、機械、器具及びその他の物的設備のほか、地上権、賃借権又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法1条、2条、3条)。採掘権者が鉱業財団登記簿に所有権保存の登記をした鉱業財団には、同法第3条((工場財団の規定の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(漁業財団)
20 漁業財団とは、漁業財団抵当法により定置漁業権又は区画漁業権、船舶、漁具及びその他の物的設備のほか地上権、水面の使用に関する権利又は工業所有権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法1条、2条、6条)。定置漁業権者、区画漁業権者又は漁業の用に供する登記した船舶若しくは水産物の養殖場の所有者が、漁業財団登記簿に所有権保存の登記をした漁業財団には、同法第6条((工場財団に関する規定の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(道路交通事業財団)
21 道路交通事業財団とは、道路交通事業抵当法により、自動車、土地、機械、器具及び軽車両等のほか、地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法3条、4条、6条)。道路運送事業者又は通運業者が道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をした道路交通事業財団は、同法第8条((事業財団の性質))の規定により1個の不動産とみなされ、工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用される(同法19条)。
(港湾運送事業財団)
22 港湾運送事業財団とは、港湾運送事業法により、港湾運送事業に関する上屋、荷役機械、はしけ、事務所及び港湾運送事業の経営のため必要な器具等のほか地上権、地役権等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法23条、24条、26条)。港湾運送事業者が港湾運送事業財団登記簿に所有権保存の登記をした港湾運送事業財団には、同法第26条((工場抵当法の準用))の規定により工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用されるので、1個の不動産とみなされる。
(観光施設財団)
23 観光施設財団とは、観光施設財団抵当法により観光施設に属する土地、機械、動物、植物、展示物、船舶、車両及び航空機等のほか、地上権、貸借権、温泉を利用する権利等をもって組成され、抵当権の目的とするためその所有権保存の登記によって成立する財団をいう(同法3条、4条、7条)。観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者が、観光施設財団登記簿に所有権保存の登記をした観光施設財団は、同法第8条((財団の性質))の規定により、1個の不動産とみなされ、工場抵当法のうち工場財団に関する規定が準用される(同法11条)。
(鉱業財団等の差押え)
24 鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団及び観光施設財団の差押えについては、15から18までに定めるところによる。
鉱業権
(意 義)
25 鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、取得する試掘権及び採掘権をいい(鉱業法5条、11条)、所轄経済産業局長が設定の許可をし(同法21条)、鉱業原簿に登録することによって成立する(同法59条、60条。この権利は、物権とみなされ、鉱業法に別段の規定がある場合を除き不動産に関する規定が準用される(同法12条、13条)。
なお、鉱業法には鉱業権とともに租鉱権についての規定がある。租鉱権とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、自己の所有物とする権利をいい(鉱業法6条)、相続その他の一般承継の目的となるほか、権利の目的となることができないから、差し押さえることができない(同法72条)。
(試掘権及び採掘権)
26 試掘権とは、一定の鉱区において主として鉱物の探鉱を内容とする鉱業権をいい、採掘権とは、一定の鉱区において主として鉱物を掘採し、自己の所有物とすることを内容とする鉱業権をいう。
特定鉱業権
27 特定鉱業権とは、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定第2条第1項に規定する大陸棚の区域(共同開発区域)内の登録を受けた一定の区域において天然資源の探査又は採掘をし及び掘採された天然質源を取得する権利をいい、(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措法(以下「大陸棚特別措置法」という。)2条3項)、経済産業大臣がその設定の許可をし(同法12条)、特定鉱業原簿に登録することによって効力を生ずる(同法32条3項)。
特定鉱業権には、探査権と採掘権とがあり(大陸棚特別措置法4条)、特定鉱業権は物権とみなされ、大陸棚特別措置法に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定が準用される(同法6条)。
漁業権
(意 義)
28 漁業権とは、定置漁業権(定置漁業を営む権利)、区画漁業権(区画漁業を営む権利)及び共同漁業権(共同漁業を営む権利)をいい(漁業法6条)、物権とみなされ、土地に関する規定が準用される(同法23条1項)。
(漁業権の移転等)
29 定置漁業権及び区画漁業権について移転ができるのは、次の場合であるが、(2)から(4)までの場合には、買受人は、都道府県知事の認可を受けなければならない(漁業法26条1項)。
なお、共同漁業権は、相続又は法人の合併による場合を除き、移転の目的となることができず(漁業法26条1項本文)、滞納処分はできないものとする(同法6条参照)。 (1) 相続又は法人の合併による場合
(2) 滞納処分による場合
(3) 先取特権者又は抵当権者がその権利を実行する場合
(4) 漁業法第28条第2項((漁業権を取り消す旨の通知))の通知を受けた者が譲渡する場合
入漁権
(意 義)
30 入漁権とは、設定行為に基づいて、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、そう類養殖業、真珠母貝養殖業、小割り式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行う水産動物の養殖業をいう。)、かき養殖業若しくは第三種区画漁業権である貝類養殖業を内容とする区画漁業権に属する漁場において、その漁業権の内容である漁業の全部又は一部を営む権利をいい(漁業法7条)、物権とみなされる(同法43条1項)。
(取得及び譲渡の制限)
31 入漁権は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は取得することができず(漁業法42条の2)、漁業権者の同意がなければ譲渡することができない(同法43条3項)。
なお、入漁権を差し押さえたときは、漁業権者に対しても、差押えの通知をするものとする。
採石権
32 採石権とは、設定行為に基づき、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利をいい(採石法4条1項)、採石法によって認められる物権であり、地上権に関する規定が準用される(同法4条3項)。
ダム使用権
(意 義)
33 ダム使用権とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいい(特定多目的ダム法2条2項)、ダム使用権又はダム使用権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限は、ダム使用権登録簿に登録することによって成立する(同法26条)。この権利は、物権とみなされ、特定多目的ダム法に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定が準用される(同法20条)。
(処分の制限)
34 ダム使用権は、国土交通大臣の許可を受けなければ、移転(相続、法人の合併その他の一般承継によるものを除く。)の目的とし、分割し、合併し、又はその設定の目的を変更することができない(特定多目的ダム法22条)。
鉄道財団等
(鉄道財団)
35 鉄道財団は、鉄道抵当法によって抵当権の設定を認められる財団で、地方鉄道の全部又は一部について設定され、鉄道事業経営に関する物的設備と地上権、地役権、登記した賃借権をその内容とし、1個の物とみなされる(同法2条、2条ノ2,3条、4条、13条ノ4参照)。 (注) 鉄道財団についての滞納処分に関しては、鉄道抵当法第65条本文((競落代金の支払))、第66条((競落による権利の移転))、第67条第1項及び第2項((競落を許す決定の取消し))、第68条((競落代金の配当、競売申立ての登録の抹消))、第70条((財団の分割競売))、第71条第1項((分割競売の手続))、第73条((競落人の許可申請))、第74条((競落人が会社の発起人であるときの許可申請手続))、第76条((監督官庁の許可義務))並びに第77条((競落人の許可の効力))の規定が準用される(同法77条ノ2)。
(軌道財団)
36 軌道財団は、軌道ノ抵当ニ関スル法律によって抵当権の設定を認められる財団であり、別段の規定がある場合を除いて鉄道抵当法が準用され(同法1条)、財団の組成物件も鉄道財団とおおむね同様である(同法2条参照)。
(運河財団)
37 運河財団は、運河法によって抵当権の設定を認められる財団で、運河事業に関する物的設備と地上権、地役権、登記した賃借権をその内容とし、1個の物とみなされる(同法14条、13条)。
(鉄道財団等の差押え)
38 鉄道財団、軌道財団及び運河財団の差押えについては、15から18までに定めるところに準ずる。
不動産の共有持分
39 不動産の共有持分とは、共有者がその不動産に対して有する量的に制限された所有権をいい、特約がなければ各共有者の持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
差押手続
(差押書)
40 法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法68条2項)。
(差押調書)
41 法第68条第1項の不動産を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
42 不動産を差し押さえたときは、税務署長は、差押えの登記を関係機関(44参照)に嘱託しなければならない(法68条3項)。
なお、差押えの登記の嘱託等については、次のことに留意する。 (1) 登記原因を証する書面は差押調書の正本又は謄本であり、登記権利者は財務省、登記を嘱託することができる者は国税局長、税務署長又は税関長である(不動産登記法35条3項、財務省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令)。
(2) 不動産登記法第26条第1項((当事者の出頭))の規定にかかわらず、差押登記嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、管轄登記所に提出することができる(同法25条2項、通則法12条1項)。
(3) 差押登記嘱託書には、工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録又は工場財団の目録の添付を要しない。
(4) 工場抵当法第3条((抵当権の目的物の目録))の規定による目録に、他人の物件が記載されている場合には、その物件を除外して差押えの登記を嘱託して差し支えない(昭和31.6.14付民事甲第1,273号法務省民事局長通達参照)。
(5) 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産の差押えの登記を嘱託する場合には、同一の嘱託書をもって差押えの登記を嘱託することができる(不動産登記法25条2項、46条)。
(6) 表示登記又は所有権の保存登記がされていない不動産について、差押えの登記を嘱託した場合には、登記官は、職権で、表示登記がないときは表示登記及び保存登記を、保存登記がないときは保存登記をそれぞれ行った上、差押えの登記をする(不動産登記法104条、102条)。
(7) 土地区画整理法第103条第4項((換地処分の公告))の規定により国土交通大臣又は都道府県知事による換地処分の公告があった後においては、同法第107条第3項本文((換地処分の公告後の登記の制限))の規定により、同条第2項((事業の施行による変動に係る登記等))に規定する土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでの期間は、差押えの登記の嘱託をすることができない。 (注) 換地処分の公告の日前に差押えの登記原因が生じているときは、上記の期間中であっても、差押えの登記の嘱託をすることができる(土地区画整理法107条3項ただし書)。
(未登記不動産と民法第177条)
43 未登記不動産についても民法第177条((不動産物権の対抗要件))の適用があり、その取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に所有権を取得して登記を経た第三者に対し、自己の所有権の取得を主張することができない(昭和57.2.18最高判)。
(関係機関)
44 法第68条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
(登録免許税の非課税)
45 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
46 法第68条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが(法68条2項)、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合には、その登記がされた時に差押えの効力が生ずる(法68条4項)。
なお、鉱業権又は特定鉱業権の差押えの効力は、上記にかかわらず、差押えの登録がされた時に生ずる(法68条5項、鉱業法60条、大陸棚特別措置法32条、同法施行令5条)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
各別の所有者に属する工場を含む工場財団の差押え
47 各別の所有者に属する工場について1個の工場財団が設定されている場合には、その所有者のうちの1人に対する滞納処分として、その財団全体を差し押さえることはできないから、次によるものとする(工場抵当法8条1項参照)。 (1) 抵当権者に対し、滞納者の所有に属する工場財団の分割と、分割された工場財団についての抵当権の消滅の承諾を得、その承諾を証する書面を添付して、他の工場所有者と共同して分割の登記を求め、その登記を了したときに、その滞納者に属する分割された工場財団を差し押さえる(工場抵当法42条ノ2,42条ノ4,42条ノ5)。
(2) 抵当権者から(1)の承諾が得られないときは、滞納者の有する財団持分を差し押さえる。この場合における持分とは、土地、建物等の共有持分とは異なり、その滞納者の所有に係る工場等をいうものであるから、差押えに当たっては、財団持分の差押えである旨及びその内容であるその工場等の表示を明らかに記載するものとする。
第69条関係 差押不動産の使用収益
使用又は収益の制限
(価値が著しく減耗する行為)
1 法第69条第1項の「価値が著しく減耗する行為」とは、通常の用法に従っているが、差し押さえられた不動産の価値を著しく減耗する行為をいう。この減耗は、物理的な減耗に限られることなく、法律的に減耗するもの、例えば、差し押さえた更地の上に建物を新築する行為も含まれる(昭和41.12.24新潟地長岡支決参照)。
(使用収益の制限)
2 法第69条第1項の「使用又は収益を制限する」方法は、かぎをかけ、立入禁止を宣言する等の事実行為又は命令行為によるものとする。
第70条関係 船舶又は航空機の差押え
船舶又は航空機
(登記される船舶)
1 法第70条第1項の「登記される船舶」とは、船舶登記簿に登記することができる船舶(以下「船舶」という。)をいい(商法686条、船舶法5条1項参照)、その差押えについては、次のことに留意する。 (1) 第56条関係4の(1)から(4)までに掲げる船舶は、登記することができないから、法第70条の船舶に該当せず、動産として差し押さえる。
(2) 建造中の船舶で、船舶として航行の用に供することができる程度に完成していないものは、抵当権の登記がされている場合であっても、船舶としての差押え及びその登記をすることはできないから、動産として差し押さえる(商法851条、848条、船舶登記規則32条参照)。
(3) 製造中の船舶を動産として差し押さえた後に、航行することができる程度に完成した場合には、改めて法第70条の規定による船舶としての差押手続をとる。
(登録を受けた航空機)
2 法第70条第1項の「登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機又は回転翼航空機であって、航空法第3条((登録))の規定により国土交通大臣の管掌する航空機登録原簿に登録を受けたもの(以下「航空機」という。)をいう。
差押手続
(差押書)
3 法第70条第1項において準用する法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法70条1項、68条2項)。 (注) 発航の準備が終了した船舶は、商法第689条((船舶の差押え及び仮差押えの執行の制限))の規定により、差押え又は仮差押え(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)をすることができないが、この規定は、滞納処分による差押えには適用されないことに留意する。
(差押調書)
4 法第70条第1項の船舶又は航空機を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
5 税務署長は、船舶を差し押さえたときは船籍港を管轄する法務局、地方法務局又はその支局若しくは出張所に、航空機を差し押さえたときは国土交通省航空局に、それぞれ差押えの登記を嘱託しなければならない(法70条1項、68条3項、船舶登記規則2条、航空機登録規則3条)。 (注) 不動産登記法第26条1項((当事者の出頭))又は航空機登録令第9条((登録の申請))の規定にかかわらず、差押登記嘱託書又は差押登録嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、管轄登記所又は国土交通省航空局に提出することができる(法70条1項、68条3項、船舶登記規則1条、不動産登記法25条2項、通則法12条1項)。
(監守保存処分との関係)
6 法第70条第3項の「監守及び保存のため必要な処分」(14から16まで参照)をしたことにより差押えの効力が生じた場合においては、遅滞なく3から5までに掲げる手続をとらなければならない。
(登録免許税の非課税)
7 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
(効力発生の時期)
8 法第70条第1号の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合にはその差押えの登記がされた時に、差押書の送達前に監守及び保存のため必要な処分をした場合にはその処分をした時に、それぞれ差押えの効力が生ずる(法70条1項、4項、68条2項、4項)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
(船舶の属具)
9 船舶の属具目録に記載されたものは、船舶の従物と推定されるから(商法685条)、原則として、船舶に対する差押えの効力が属具に及ぶ。
停 泊
(意 義)
10 法第70条第2項の「停泊」とは、船舶又は航空機が、その所在する場所に停止又は停留することをいう。
(滞納処分のため必要があるとき)
11 法第70条第2項の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、航行による損壊、き減の防止、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(発航の準備)
12 法第70条第2項の「発航の準備が終った」かどうかの判定は、船舶航行の計画又は契約の成立によって行わず、専ら貨客の運送に必要であり、かつ、客観的には相当な整備がされたかどうか(例えば、船員及び船客の乗組み、貨物、燃料、食料及び飲料の積込み、出港及び渡航手続が完了したかどうか)等によって行うものとする。
なお、航空機の発航の準備が終わったかどうかの判定については、上記に準ずるものとする。
監守保存の処分
(滞納処分のため必要があるとき)
13 法第70条第3項の「滞納処分のため必要があるとき」とは、11と同様である。
(監 守)
14 法第70条第3項の「監守」とは、主として、所在を変えることを防止するための処置をいう。
(保 存)
15 法第70条第3項の「保存」とは、主として、目的物の効用を維持するための処置をいう。
(必要な処分)
16 法第70条第3項の「必要な処分」には、縄張をすること、係留すること、格納庫へ入庫させること、管理人を置くこと、船舶国籍証書又は航空機登録証明書その他船舶又は航空機の航行のために必要な文書(船舶法5条、6条、船員法18条、航空法59条等参照)を取り上げること等があり、これらの処分は、監守又は保存のいずれか一つのために必要なものであれば、することができる。
なお、船航国籍証書等の取上げについては、債権証書に準じて取り扱うものとする(第65条関係参照)。
航行の許可
(営業上の必要その他相当の理由があるとき)
17 法第70条第5項の「営業上の必要その他相当の理由があるとき」とは、航行を許可することにより営業上の利益が見込まれ、徴収上有利な結果をもたらすときをいい、例えば、現に行っている運送契約に債務不履行が生ずることを避け、航行による収益を滞納者に得させる必要があるとき等をいう。
(申立て)
18 法第70条第5項の規定による航行の許可の申立ては、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が、令第31条各号((船舶等の航行許可申立書の記載事項))に掲げる事項を記載して連署した書面でしなければならない。この場合の連署については、上記の一部の利害関係人の連署がとれないとき等には、その同意書又は承諾書を添付して行わせることとしても差し支えない。
(許 可)
19 法第70条第5項の航行の許可の申立てがあった場合には、徴収上支障のない限り、航行を許可して差し支えない。この許可は、原則として別に定める書面により行うものとする。
共有持分の差押え
20 法第70条の規定の適用を受ける船舶又は航空機の共有持分を差し押さえたときは、その共有持分の差押えの登記を5の関係機関に嘱託しなければならない(法70条1項、68条3項)。(注)船舶共有者間に組合関係がある場合には、船舶管理人の有する共有持分は、他の共有者の同意を得なければ譲渡することができない(商法698条ただし書)。
第71条関係 自動車又は建設機械の差押え
自動車又は建設機械
(登録を受けた自動車)
1 法第71条第1項の「登録を受けた自動車」とは、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車で、道路運送車両法第2章((自動車の登録))の規定により、運輸大臣が管理する自動車登録ファイルに登録を受けたもの(自動車抵当法2条ただし書に規定する大型特殊自動車で、建設機械抵当法2条に規定する建設機械であるものを除く(道路運送車両法5条2項)。以下「自動車」という。)をいう。
(登記を受けた建設機械)
2 法第71条第1項の「登記を受けた建設機械」とは、建設業法第2条第1項((建設工事の定義))に規定する建設工事の川に供される機械類で建設機械抵当法施行令第1条((建設機械の範囲))の規定による別表に掲げるもの(例えば、ブルドーザー、トラクター、コンクリートミキサー等)のうち、建設業者(建設業法2条3項)が国土交通大臣又は都道府県知事の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けた後、建設機械登記簿に保存登記をしたもの(以下「建設機械」という。)をいう(建設機械抵当法2条、4条1項。建設機械登記令5条、建設機械抵当法施行令9条1項参照)。
差押手続
(差押書)
3 法第71条第1項において準用する法第68条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式をいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法71条1項、68条2項)。
(差押調書)
4 法第71条第1項の自動車又は建設機械を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登記の嘱託)
5 税務署長は、自動車を差し押さえたときはその自動車の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事(運輸局陸運支局)に、建設機械を差し押さえたときはその機械の打刻された記号によって表示された都道府県の区域内にある法務局又は地方法務局(北海道にあっては、札幌法務局)に、それぞれ差押えの登記を嘱託しなければならない(法71条1項、68条3項。逆路運送車両法施行令8条2項、建設機械登記令1条参照)。 (注) 自動車登録令第10条((共同申請))又は不動産登記法第26条第1項((当事者の出頭))の規定にかかわらず、差押登録嘱託書又は差押登記嘱託書を郵便による送達又は交付送達の方法によって、都道府県知事(運輸局陸運支局)又は管轄登記所に提出することができる(法71条1項、68条3項、自動車登録令9条、不動産登記法25条2項、通則法12条1項)。
(登録免許税の非課税)
6 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
(効力発生の時期)
7 法第71条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合にはその差押えの登記がされた時に、差押書の送達前に監守及び保存のため必要な処分をした場合にはその処分をした時に、それぞれ差押えの効力が生ずる(法71条1項、2項、68条2項、4項、70条4項)。 (注) 差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
(差押えの効力が及ぶ範囲)
8 抵当権の目的となっている自動車又は建設機械の差押えの効力は、その自動車又は建設機械に付加して一体となっている物に及ぶが、これらの物のうち、抵当権設定行為で抵当権の効力が及ばない旨の特約の登記をしたもの及び自動車又は建設機械の所有者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、抵当権者もその事情を知りながら付加したものには、差押えの効力は及ばない(自動車抵当法6条、建設機械抵当法10条)。
(差押え後に保存登記がされた建設機械)
9 所有権保存登記のない建設機械を動産として差し押さえた後にその建設機械について所有権保存の登記があっても、その登記は差押債権者である国に対しては効力を生じないから、新たに差押えの登記を嘱託する必要がないことはもちろん、登記簿上その建設機械について権利を取得した第三者も、その権利をもって差押債権者である国に対抗することができない(建設機械抵当法3条2項)。
(差押え後に抵当権設定の登記がされない建設機械)
10 建設機械の所有権保存登記後30日以内に抵当権設定の登記がされない場合又は抵当権の登記が全部抹消された後30日以内に新たな抵当権設定の登記がされない場合には、その建設機械の登記用紙は閉鎖されるが、その期間内に差押えの登記をした場合には、その登記用紙は閉鎖されないから、法第71条の規定により建設機械としてした差押えの効力は妨げられない(建設機械抵当法8条)。
自動車検査証の占有
11 換価による所有権の移転登録には、自動車検査証の呈示を必要とし(道路運送車両法13条3項、12条2項)、かつ、自動車検査証を備えなければ自動車を運行の用に供することができないから(同法66条1項)、自動車の差押えに当たっては、自動車検査証を動産の差押手続に準じて占有するものとする。
監守保存の処分
12 自動車及び建設機械の監守保存のため必要な処分については、第70条関係13から16までに準ずる。
徴収職員の占有
(引渡命令)
13 自動車又は建設機械を差し押さえた場合には、税務署長は、滞納者に対してその引渡しを命じ、徴収職員にそれを占有させることができる(法71条3項)。この場合には、徴収職員は、次に掲げるところにより占有するものとする。
なお、滞納者が引渡命令に応じないときは、法第142条((捜索の権限及び方法))の規定により、捜索その他の処分を行うことができる。 (1) 滞納者が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を滞納者が占有している場合には、税務署長は、滞納者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員にその引渡しがされたとき及びその引渡しをしないときは、徴収職員は直ちにその占有ができる(法71条4項、56条1項)。
(2) 特殊関係者等が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を滞納者の親族その他の特殊関係者(第38条関係1から8まで参照)が占有している場合には、税務署長は、滞納者及びその第三者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員は(1)に準じて直ちにその占有ができる(法71条4項、56条1項)。
(3) 第三者が占有している場合
差し押さえた自動車又は建設機械を第三者((2)の第三者を除く。)が占有している場合には、税務署長は、滞納者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員にその引渡しがされたときは直ちに占有するが、その引渡しをしないときで占有する第三者もその引渡しを拒むときは、その第三者に対し引渡しを命じ、その引渡しがされたとき及びその第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡しをしないときは、直ちにその占有力ができる(法71条4項、58条2項、3項)。この場合には、次のことに留意する。 イ 法第58条第2項((第三者が占有する動産等の差押手続))の規定のうち「滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り」の事項は、占有のための引渡命令についての要件に当たらないものである。
ロ 法第59条第2項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))に規定する「その期限が、その動産を差し押さえた日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで」は、「その期限がその自動車又は建設機械を占有した日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで」として準用する。
ハ 法第59条第3項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))に規定する「同条第3項の規定による差押の日後の期間に係るもの」は、「法第71条第4項において準用する第58条第3項の規定による占有の日後の期間に係るもの」として準用する。
(保 管)
14 法第71条第5項前段の規定により、自動車又は建設機械を滞納者又は第三者に保管させる場合には、第60条関係8,9及び12に定めるところに準ずる。
(封印その他の公示方法)
15 法第71条第5項後段の「封印その他の公示方法」は、第60条関係13から15までと同様であり(令32条、26条)、また、これらの公示方法は差押えの効力発生要件ではない。
(適当な措置)
16 法第71条第5項後段の「適当な措置」とは、運行又は使用を禁ずるための措置、例えば、ハンドルの封印、立札、縄張等の方法による措置をいう。
(運行又は使用の許可)
17 法第71条第6項の規定による自動車又は建設機械の運行又は使用の許可については、第70条関係17から19までと同様である(令32条、31条)。
共有持分の差押え
18 法第71条の規定の適用を受ける自動車又は建設機械の共有持分を差し押さえたときは、その共有持分の差押えの登記を5の関係機関に嘱託する。
なお、上記の場合には、徴収職員は目的物を占有することができないものとする(民法249条参照)。
第5款 無体財産権等の差押え
第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がない無体財産権等
1 法第72条第1項の規定により差し押さえる財産は、特許権及び著作権のほか法第5章第1節第2款((動産又は有価証券の差押))、第3款((債権の差押))及び第4款((不動産等の差押))の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち、第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)がない財産であり、おおむね次の財産がこれに該当する。 (1) 工業所有権である実用新案権、意匠権及び商標権
(2) 工業所有権以外の無体財産権である著作隣接権
(3) 源泉権
特許権
(意 義)
2 特許権とは、物の特許発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利を、方法の特許発明にあっては、その方法を使用する独占的排他的な権利を、物を生産する方法の特許発明にあっては、上記に該当するもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利を、それぞれいい(特許法2条。68条参照)、特許庁長官の管掌する特許原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法66条1項)。
(存続期間)
3 特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年を超えることができない(特許法67条1項)。
実用新案権
(意 義)
4 実用新案権とは、実用新案登録を受けている考案(自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。)に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利をいい(実用新案法2条。16条参照)、特許庁長官の管掌する実用新案原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法14条1項)。
(存続期間)
5 実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年をもって終了する。ただし、実用新案登録出願の日から15年を超えることができない(実用新案法15条1項)。
意匠権
(意 義)
6 意匠権とは、意匠登録を受けている意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。)に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する独占的排他的な権利をいい(意匠法2条。23条参照)、特許庁長官の管掌する意匠原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法20条1項)。
(存続期間)
7 意匠権の存続期間は、設定の登録の日から15年をもって終了する(意匠法21条)。
商標権
(意 義)
8 商標権とは、指定商品について商標登録を受けている商標(文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下8において「標章」という。)であって、業として商品を生産し、加工し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものをいう。)を使用(商品又は商品の包装に標章を付する行為、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為及び商品に関する公告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為をいう。)する独占的排他的な権利をいい(商標法2条。25条参照)、特許庁長官の管掌する商標原簿に設定の登録をすることによって発生する(同法18条1項)。
(存続期間)
9 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する(商標法19条1項)。
著作権
(意 義)
10 著作権とは、著作者がその著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。)についての複製権、上演権、演奏権、放送権、有線放送権、口述権、展示権、上映権、頒布権、翻訳権、翻案権及び第二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を専有する独占的排他的な権利をいい(著作権法2条、17条1項。21条から28条まで参照)、著作者の著作により当然に発生し、登録を要しない。著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下10において同じ。)又は処分の制限及び著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、文化庁長官が管掌する著作権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法77条、78条1項)。
(存続期間)
11 著作権の存続期間は、おおむね次のとおりである。 (1) 著作権は、著作者が著作物を創作した時に始まり、(2)から(5)までに掲げる場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。(2)において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条)。
(2) 無名又は変名の著作物の著作権は、原則として、その著作物の公表後50年(著作者の死後50年を経過していると認められるときは、死後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法52条)。
(3) 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、原則として、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条)。
(4) 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法54条1項)。
(5) 写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法55条1項)。 (注)1 (2)から(5)までにおける公表の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとされ、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、原則として、最終部分の公表の時によるものとされる(著作権法56条)。
2 (1)から(5)までにおいて、著作者の死後50年又は著作物の公表後50年若しくは創作後50年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算される(著作権法57条)。
(未発表の著作権)
12 まだ発行、興行等公にしていない著作物の原本及びその著作権は、差し押さえることができない(法75条1項11号)。
著作隣接権
(意 義)
13 著作隣接権とは、実演家、レコード製作者及び放送事業者に与えられた著作権に準ずる権利をいう(著作権法91条から100条まで)。著作隣接権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下13において同じ。)又は処分の制限及び著作隣接権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作隣接権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、文化庁長官が管掌する著作隣接権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法104条、77条、78条1項)。
(存続期間) 編注21
14 著作隣接権は、実演及び放送についてはその行われた日の属する年の翌年から起算して20年、レコードについてはその音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過するまでの間、存続する(著作権法101条)。
共有特許権等
15 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権の共有持分の譲渡については、他の共有者の同意を必要とする(特許法73条1項、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条、著作権法65条、103条)。
源泉権
16 源泉権(温泉所有権、温泉専用権、湯口権、温泉権又は鉱泉権ともいう。)とは、地中からゆう出する温泉を利用、管理、処分する権利で、源泉地所有権とは別個独立の権利として自由に処分できるものをいう(昭和15.9.18大判、昭和33.7.1最高判)。
源泉権者は、源泉権の効力として、温泉所在地及びその周辺土地のうち温泉の採取、利用、管理のために必要とする範囲において、その使用権限を有する(昭和45.12.19東京地判)。
差押手続
(差押書)
17 法第72条第1項の「差押書」とは、令第30条第1項各号((不動産の差押書等の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第5号書式によるものをいい、これを滞納者に送達することによって差押えの効力を生ずる(法72条2項)。
(差押調書)
18 法第72条第1項の財産を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法54条参照)。
(差押えの登録の嘱託)
19 法第72条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
なお、源泉権にあっては、その地方の慣行に従った公示方法(例えば、温泉組合等に対する登録の依頼、立札その他の標識の掲示)を講ずるものとする(昭和15.9.18大判、昭和45.12.19東京地判参照)。
(登録免許税の非課税)
20 税務署長が差押えの登録を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
21 法第72条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが(法72条2項)、その前に差押えの登録がされた場合には、その差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法72条4項)。ただし、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については、差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法72条5項。特許法98条1項、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条参照)。 (注) 差押えの登録がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がある無体財産権等
1 法第73条第1項の規定により差し押さえる財産は、電話加入権、合名会社の社員の持分のほか第三債務者等がある無体財産権等であり、おおむね次の財産がこれに該当する。 (1) 合資会社及び有限会社の社員の持分
(2) 中小企業等協同組合法、水産業協同組合法、農業協同組合法、森林組合法、農住組合法等による各種の組合等の組合員等の持分
(3) 信用金庫の会員の持分
(4) 中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の会員の持分
(5) 民法上の組合の組合員の持分
(6) 無尽講又はたのもし講の講員の持口
(7) 営業無尽の加入者の権利
(8) 動産の共有持分
(9) 賃借権
(10) 買戻権
(11) 仮登記(保全仮登記を除く。以下73条関係において同じ。)に係る権利
(12) 特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権及び通常実施権並びに商標権についての専用使用権及び通常使用権
(13) 出版権
(14) 引湯権
(15) ゴルフ会員権(預託金会員制ゴルフ会員権をいう。以下第73条関係において同じ。)
電話加入権
(意 義)
2 電話加入権とは、日本電信電話公社(以下第73条関係において「公社」という。)と加入契約を結んだ者が、その契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう(公衆電気通信法31条3号かつこ書)。
なお、電話加入権の譲渡は、公社の承認がなければその効力を生じない(公衆電気通信法38条1項)。
(差押えと譲渡等との優劣)
3 電話加入権に対する差押えとその譲渡等との優劣の関係は、次のとおりである(公衆電気通信法38条の3第3項、電話加入権質に関する臨時特例法6条2項)。 (1) 電話加入権の譲渡の承認があったときは、その譲渡承認の請求書を所轄の電話取扱局が受け取った時と、当該電話取扱局が電話加入権の差押通知書を受け取った時との先後により、その優劣が定まる。
(2) 電話加入権の質権の登録があったときは、その質権の登録請求書を所轄の電話取扱局が受け取った時と、当該電話取扱局が電話加入権の差押通知書を受け取った時との先後により、その優劣が定まる。
(差押え後の譲渡禁止)
4 公社は、電話加入権の差押えの通知を受けた後は、その電話加入権の譲渡承認の請求があっても、承認しないことになっている。
(差押え後の契約解除)
5 公社は、差押えを受けた電話加入権についても、公衆電気通信法第42条(通話の停止及び加入電話加入契約の解除)の規定により、加入契約を解除することができる。
(地域団体加入電話等の差押除外)
6 地域団体加入電話に関する権利及びその組合員の持分は、差押えをしない取扱いとする(加入電話等利用規程69条参照)。 (注) 地域団体加入電話とは、一定の地域内に居住する者が公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的として組合を設立し、その組合と公社との契約によって設置する電話である(公衆電気通信法25条2号、43条の2から43条の4まで参照)。
合名会社及び合資会社の社員の持分
(意 義)
7 合名会社及び合資会社の社員の持分とは、社員がその資格において会社に対して有する権利義務の総体、すなわち、社員権をいう。
なお、社員の持分は、無限責任社員の同意がなければ、譲渡することができない(商法73条、147条、154条)。
(利益配当請求権等に対する差押えの効力)
8 社員の持分の差押えの効力は、社員の会社に対する将来の利益配当請求権及び持分払戻請求権に及ぶ(商法90条、147条)ほか、残余財産分配請求権にも及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとる必要はなく、会社に対して、決算確定の場合には利益の配当を、退社の場合には持分の払戻しを、会社の解散の場合には残余財産の分配を、それぞれ請求することができる(56参照)。
(退社の告知権)
9 社員の持分を差し押さえた場合には、商法第91条(持分差押債権者による退社)及び第147条(合名会社の規定の準用)の規定により、営業年度の終了する6月前に会社及びその社員に予告した上、営業年度の終わりにおいてその社員を退社させることができる。この場合においては、営業年度の終わりにおいて当然に退社の効力を生ずる。
なお、上記の予告は、社員が相当の担保を提供したときは、その効力を失う(商法91条2項、147条)。この場合には、担保として提供された社員の財産を差し押さえるものとする。
(持分払戻請求権の保全)
10 9の告知権を行使したときは、会社の本店所在地の地方裁判所に対して、持分払戻請求権の保全に関し必要な処分をすることを請求できる(非訟事件手続法135条ノ10)。
(差押え後の任意清算)
11 社員の持分の差押えの通知を受けた合名会社又は合資会社が任意清算しようとするときは、会社財産の処分方法について差押債権者である国の同意を要する(商法117条4項、147条)。会社が同意を受けないで財産を処分したときは、会社に対してその持分に相当する金額の支払を請求し、又はその処分の取消しを裁判所に請求することができる(同法118条、119条、147条)。
有限会社の社員の持分
(意 義)
12 有限会社の社員の持分とは、社員がその資格において会社に対して有する権利義務の総体、すなわち、社員権をいい、各社員はその出資の口数に応じて持分を有する(有限会社法18条)。
なお、社員の持分の移転は、社員名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない(有限会社法20条)。
(残余財産分配請求権の取立て)
13 有限会社の社員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権にも及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
(持分払戻請求権のないこと)
14 有限会社の社員は、株式会社の株主と同様、持分の払戻しを請求することができない。
(利益配当請求権の差押え)
15 有限会社の社員の持分を差し押さえた場合において、利益の配当を受けようとするときは、その利益配当請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
(利益配当請求権等と持分の質入れとの関係)
16 社員の持分が質入れされ、社員名簿に質入れの記載がされている場合には、利益配当請求権及び残余財産分配請求についても、その質権の効力が及ぶ(有限会社法24条1項、商法209条1項)。
協同組合等の組合員等の持分
(意 義)
17 中小企業等協同組合法による組合等1の(2)に掲げるものの組合員等の持分とは、組合員等がその資格において組合等に対して有する権利義務の総体をいう。
なお、組合員等の持分は、組合等の承諾がなければ譲渡することができず、また組合員等以外の者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない(中小企業等協同組合法17条、水産業協同組合法20条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法14条、森林組合法30条、農住組合法17条等)。
(持分の一部払戻請求)
18 組合員等の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の払戻しを請求できるときがある。
(残余財産分配請求権等の取立て)
19 組合員等の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法74条の規定による一部の払戻しのほか、法定脱退による払戻しを含む。)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。
(剰余金配当請求権の差押え)
20 組合員等の持分を差し押さえた場合において、剰余金の配当を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
信用金庫の会員の持分
(意 義)
21 信用金庫の会員の持分とは、会員がその地位に基づいて信用金庫に対して有する権利義務の総体をいう。.
なお、会員の持分は、信用金庫の承諾がなければ、他の会員又は会員の資格を有する者にも譲渡することができない(信用金庫法15条)。
(持分の一部の譲受請求)
22 会員の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の譲受けを請求できるときがある(第74条関係7参照)。
(残余財産分配請求権等の取立て)
23 会員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法定脱退によるもの)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
(剰余金配当請求権の差押え)
24 会員の持分を差し押さえた場合において、剰余金の配当を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
漁業信用基金協会の会員の持分
(意 義)
25 漁業信用基金協会の会員の持分とは、会員がその地位に基づいて漁業信用基金協会に対して有する権利義務の総体をいう。
なお、会員の持分は、漁業信用基金協会の承認を得なければ譲渡することができず、会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない(中小漁業融資保証法12条1項、2項)。
(持分の一部の払戻請求)
26 会員の持分を差し押さえた場合においては、法第74条(差し押えた持分の払戻の請求)の規定により、持分の一部の払戻しを請求できるときがある。
(残余財産分配請求権等の取立て)
27 会員の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権(法74条の規定による一部の払戻しのほか、法定脱退による払戻しを含む。)に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。
なお、漁業信用基金協会が剰余金を配当することはない(中小漁業融資保証法44条)。
民法による組合の組合員の持分
(意 義)
28 民法第667条(組合契約)の規定に基づいて設立された組合の組合員の持分とは、組合員として有する財産的地位をいう。
なお、組合員の持分の譲渡については、他の組合員全員の同意を必要とされているが(民法667条参照)、契約によって特別の定めがされているときは、その定めに従う。 (注) 組合員としての地位に基づいて組合財産を構成する個々の物又は権利について有する共有の権利をも持分というが、この持分の処分は、組合及び組合と取引をした第三者に対抗できないから(民法676条)、この持分を差し押さえることはできない。
(残余財産分配請求権等の取立て)
29 組合員等の持分差押えの効力は、残余財産分配請求権及び持分払戻請求権に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56、第74条関係6の(注)参照)。 (注) 組合員の持分を換価処分によって換価することができない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、脱退の意思表示をさせた後、持分払戻請求権の取立てをすることに留意する。
(利益分配請求権の差押え)
30 組合員の持分を差し押さえた場合において、利益の分配を受けようとするときは、その請求権は、別個に債権として差し押さえるものとする。
無尽講又はたのもし講の講員の持口
(意 義)
31 無尽講又はたのもし講は、慣習によって成立したものであるが、実質的には組合であるから、民法の組合に関する規定の適用があり、講員(加入者)は、その拠出した金銭又は物の価額に応じて持口を有する。
なお、講員の持口は、講規約に特約がないときは、他の講員全員の同意がなければ、譲渡することができない。 (注) 講員の持口は、未給付口については積極財産であって差し押さえることができるが、給付口については消極財産であって差押えの対象とならない。
(給付請求権等の取立て)
32 講員の持口の差押えの効力は、当せん、落札等の給付原因によって生じた給付金請求権及び脱退によって生じた払戻請求権に及ぶから、これらの債権が確定したときは、別個に債権差押えの手続をとることなく、取立てができる(56参照)。
なお、上記の取立てについては、次のことに留意する。 (1) 講員の持口を換価処分により換価できない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、脱退の意思表示をさせた後、払戻請求権の取立てをするように取り扱うものとする(民法678条2項参照)。
(2) 講規約によって、担保を供しなければ給付を行わないこと、脱退者に対する払戻しは満講までは行わないこと等を定めているときは、これらの要件を満たさなければ、給付又は払戻しを受けることができない。
営業無尽の加入者の権利
(意 義)
33 営業無尽の加入者の権利とは、加入者が無尽契約、相互掛金契約又は物品無尽契約に基づき、相互銀行又は無尽会社に対して有する権利義務の総体(例えば、掛金払込義務、給付受領権利等)をいう。
なお、加入者の権利の譲渡について会社の承認を要する旨の契約があるときは、会社の承認がなければ、権利を譲渡することができない。 (注) 営業無尽の加入者の権利の給付口及び未給付口については31と同様であるが、無尽講と異なり、加入者相互間には法律関係を生じない。
(給付金請求権等の取立て)
34 給付金請求権又は払戻請求権の取立てについては、32に定めるところと同様である。
動産の共有持分
(意 義)
35 共有動産の持分とは、共有者がその動産に対して有する量的に制限された所有権をいい、特約がなければ各共有者の持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
なお、共有持分は、他の共有者の同意を得ないで、自由に譲渡することができる。
(差押えと目的物の占有との関係)
36 共有動産の持分を差し押さえた場合でも、徴収職員が目的物を占有することはしないものとする(民法249条参照)。
(持分の分割の請求)
37 共有動産の持分の換価ができないときは、次の方法によるものとする。 (1) 分割禁止の特約がない場合において、他に差し押さえるべき適当な財産がないときは、滞納者に代位して(通則法42条、民法423条)、他の共有者の全員に対して共有物の分割を請求し(民法256条1項本文)、滞納者の分割物の引渡請求権の取立て(56参照)を行う。
(2) (1)により分割の請求をした場合において、分割の協議が調わないときは、滞納者に代位して、訴えにより裁判所に分割の請求をする(民法258条1項)。
(3) 分割禁止の特約がある場合には、その禁止期間は分割を請求することができない(民法256条1項ただし書)。
なお、共有物の分割禁止の特約は、5年を超えて定めることができず(民法256条1項)、また持分の差押えを受けた後は、差押えの効力として、特約の更新(同条2項)をしても、差押債権者である国に対抗することができない。
買戻権
(意 義)
38 買戻権とは、不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約(民法579条参照)により買主が支払った代金及び契約の費用を償還して当初の売買を解除し、目的物を取り戻すことができる権利(所有権移転請求権としての財産権)をいう。
(買戻権の換価)
39 買戻権の換価に当たっては、当該換価による買戻権を取得した買受人が、期間の点で買戻権を行使することができる余裕があるように考慮する。 (注) 買戻権は、有効な約定期間内に権利行使ができるが、この期間は10年を超えるときは10年に短縮される(民法580条1項)し、また、その期間を定めないときは最長5年とされている(同条3項)。
特許権の実施権等
(特許権の実施権)
40 特許権についてのいわゆる実施権には、専用実施権と通常実施権とがあり、特許権者以外の者が特許発明を一定の目的に利用することができる権利である。これらの実施権は差し押さえることができるが、専用実施権については、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合を除いては、移転することができず(特許法77条3項)、通常実施権の移転については、特許法第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項(裁定の請求)、実用新案法第22条第3項(裁定の請求)又は意匠法第33条第3項(裁定の請求)の裁定による通常実施権を除き、上記と同様(承諾については、専用実施権についての通常実施権にあっては特許権者及び専用実施権者の承諾)である(特許法94条1項)。
(実用新案権の実施権)
41 実用新案権についての専用実施権及び通常実施権の性質は、おおむね40と同様である(実用新案法18条3項、24条1項、特許法77条3項)。
(意匠権の実施権)
42 意匠権についての専用実施権及び通常実施権の性質は、おおむね40と同様である(意匠法27条3項、34条1項、特許法77条3項)。
(商標権の使用権)
43 商標権についてのいわゆる使用権には、専用使用権と通常使用権とがあり、商標権者以外の者が指定商品について登録商標を使用することができる権利である。これらの権利は差し押さえることができるが、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般継承の場合を除いては、移転することができない(商標法30条3項、31条3項)。
出版権
44 出版権とは、設定行為の定めるところによって、頒布の目的をもって、著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する独占的排他的な権利をいい(著作権法80条1項)、その設定、移転(相続その他の一般継承によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)若しくは処分の制限又は出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)若しくは処分の制限は、文化庁長官が管掌する出版権登録原簿に登録しなければ、第三者に対抗することができない(同法88条)。
なお、出版権は、著作者の承諾がなければ、譲渡することができない(著作権法87条)。
共有専用実施権等
45 特許権、実用新案権及び意匠権の専用実施権及び通常実施権並びに商標権の専用使用権及び通常使用権の共有持分の譲渡については、他の共有者の同意を必要とする(特許法77条5項、94条5項、実用新案法18条3項、19条3項、意匠法27条3項、28条3項、商標法30条4項、31条4項)。
引湯権
46 引湯権とは、源泉権(第72条関係16)を有する者との契約に基づいて、継続的に一定量の温泉の給湯を受ける権利をいう(昭和2.5.3静岡地沼津支判、昭和43.11.25山形地判参照)。
ゴルフ会員権
(意 義)
47 ゴルフ会員権とは、ゴルフ場を経営する株式会社等に対するゴルフ場及びその付属施設の優先的利用権、年会費納付等の義務、据置期間経過後退会時の預託金返還請求権の三つの権利義務から成る契約上の地位をいう(昭和48.12.18東京高判)。
(差押えの効力)
48 ゴルフ会員権の差押えの効力は、預託金返還請求にも及ぶから、別個に債権差押えの手続をとることなく、規約等に定めるところにより、その取立てができる(56参照)。 (注) 差押通知書の「差押財産」欄には、ゴルフ場及びその付属施設の優先的利用権及び預託金返還請求権(金額を明示する。)がある旨を併記するものとする。
差押手続
(第三債務者等)
49 法第73条の「第三債務者等」とは、おおむね次に掲げる者をいう。 (1) 電話加入権については、公社
(2) 合名会社の社員の持分及び1の(1)に掲げる会社の社員の持分については、その会社
(3) 中小企業等協同組合法による組合等1の(2)に掲げる組合等の組合員等の持分については、その組合等
(4) 信用金庫の会員の持分については、その信用金庫
(5) 漁業信用基金協会の会員の持分については、その漁業信用基金協会
(6) 民法上の組合の組合員の持分については、その組合(業務を執行する組合員があるときはその者、業務を執行する組合員の定めがないときは他の組合員全員)
(7) 無尽講又はたのもし講の講員の持口については、その講の講元(講親)
(8) 営業無尽の加入者の権利については、その相互銀行又は無尽会社
(9) 動産の共有持分については、他の共有者
(10) 賃借権については、その貸主
(11) 買戻権については、その買戻権のある財産の差押え時における所有者
(12) 仮登記に係る権利については、その仮登記時における登記義務者
(13) 特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権及び通常実施権並びに商標権についての専用使用権及び通常使用権については、その特許権者、実用新案権者、意匠権者又は商標権者
(14) 出版権については、その著作権者
(15) 引湯権については、その源泉権者
(16) ゴルフ会員権については、そのゴルフ場を経営する株式会社等
(差押通知書)
50 法第73条第1項の「差押通知書」とは、令第30条第2項((差押通知書の記載事項))に定める事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第6号書式をいい、これを第三債務者等に送達することによって差押えの効力を生ずる(法73条2項)。
(差押調書)
51 法第73条1項の財産を差し押さえた場合には、差押調書を作成し、滞納者に対して、差押調書の謄本を交付しなければならない。(法54条)。
(差押えの登記の嘱託)
52 法第73条第3項の「その権利の移転につき登記を要するもの」とは、1に掲げる財産のうち、登記を第三者対抗要件とする賃借権、登記した買戻権及び(1)から(13)までに掲げる権利をいうが、法第73条第3項において準用する法第72条第3項の「関係機関」については、別に定めるところによる。
なお、引湯権にあっては、その地方の慣行に従った公示方法(例えば、温泉組合等に対する登録の依頼、立札その他の標識の掲示)を講ずるものとする。 (注) 賃借権、買戻権又は仮登記に係る権利の差押えの登記は、付記登記により行われる(不動産登記法施行細則56条)。
(登録免許税の非課税)
53 税務署長が差押えの登記を嘱託する場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
差押えの効力
54 法第73条第1項の規定による差押えの効力は、差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずるが(法73条2項)、その前に差押えの登記がされた場合には、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる(法73条3項、72条4項)。ただし、特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権並びに商標権についての専用使用権については、差押えの登録がされた時に差押えの効力が生ずる(法73条4項、72条5項。特許法98条1項、実用新案法18条3項、意匠法27条3項、商標法30条4項参照)。
預託証書等の取上げ
55 徴収職員は、第三債務者等がある無体財産権等の差押えのため必要があるときは、預託証書、会員証書等その財産権に関する証書を取り上げることができるが(法73条5項)、この場合の手続等については、第65条関係3から5までに準ずる。
取立て
56 法第73条第5項において準用する法第67条((差し押えた債権の取立))の規定により取立てができる財産は、合名会社等の社員の利益配当請求権及び持分払戻請求権、ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権、法第74条((差し押えた持分の払戻の請求))の規定により請求できる持分払戻請求権等差押えに基因して請求できる債権並びに有限会社の社員の残余財産分配請求権等差押えの効力が及ぶ債権に限られる。
第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
払戻し等の請求ができる組合等
1 法第74条第1項の規定により持分の一部の払戻し等を請求できる法人は、組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社及び合資会社を除く。)をいい、中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫のほか、おおむね次に掲げるもの(以下第74条関係において「組合等」という。)である。 (1) 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法18条)
(2) 漁業協同組合(水産業協同組合法26条)、漁業生産組合(同法86条1項)、漁業協同組合連合会(同法92条2項)、水産加工業協同組合(同法96条2項)及び水産加工業協同組合連合会(同法100条2項)
(3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法21条)
(4) 森林組合(森林組合法36条)、生産森林組合(同法100条1項)及び森林組合連合会(同法109条2項)
(5) 農住組合(農住組合法22条)
(6) 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(消費生活協同組合法19条)
(7) 漁業信用基金協会(中小漁業融資保証法17条1項、2項)
払戻し等の請求ができる場合
(不足すると認められるとき)
2 法第74条第1項の「徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様であるただし、不足するかどうかの判定は、法第74条第1項の「請求する」時の現況によるものとする。
(買受人がない場合)
3 法第74条第1項第1号の「買受人がない」とは、売却決定を受けた者がない場合及び売却決定が取り消された場合をいう。
(譲渡ができない場合)
4 法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき法律に制限があるため、譲渡することができない」ときとは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、持分譲渡につき組合等の承諾又は承認を要する場合において、その承諾又は承認が得られないとき(換価処分前に承諾又は承認しない旨の意思表示があったときを含む。)をいう(中小企業等協同組合法17条1項、水産業協同組合法20条1項、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法14条1項、森林組合法30条1項、100条1項、109条2項、農住組合法17条1項、信用金庫法15条1項、中小漁業融資保証法12条1項等)。
なお、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき定款に制限があるため、譲渡することができない」ときに該当することはない。
払戻し等の請求
(持分の一部)
5 法第74条第1項の「持分の一部」とは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、1口の出資を除外した残りの持分をいう。
(持分の払戻し)
6 法第74条第1項の「払戻」とは、第73条関係1の(2)及び(4)に掲げる持分の一部について、脱退があったと仮定した場合における中小企業等協同組合法等の規定により持分の払戻しをいい、その持分の金額は、脱退を仮定した事業年度の終わりにおける組合等の財産によって定まる(中小企業等協同組合法20条、水産業協同組合法28条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法23条、森林組合法38条、100条1項、109条2項、農住組合法24条、中小漁業融資保証法18条1項等)。この場合における財産の評価は、帳簿価格ではなく、その組合等の事業の継続を前提として一括譲渡するときの価額が標準になる(昭和44.12.11最高判)。 (注) 組合等の構成員である滞納者が組合等に対して債務を負っているときは、その債務を完済するまでは、組合等は持分の払戻しを停止することができる(中小企業等協同組合法22条、水産業協同組合法30条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法26条、森林組合法40条、100条1項、109条2項、農住組合法27条、中小漁業融資保証法18条2項等)。
(信用金庫の場合の特例)
7 法第74条第1項の「組合等による譲受が認められている持分」とは、信用金庫の会員の持分をいい、その「譲受」とは、会員の持分の一部について信用金庫法第16条((自由脱退))の規定による脱退を仮定した場合における同条の規定による持分の譲受け(会員から信用金庫への譲渡)をいう。
なお、持分の譲受けの請求をする場合において、1万円(出資の1口の金額で1万円を整除することができないときは、1万円を超え1万円に最も近い整除できる金額とする。)以下の金額の部分については、その譲受けの請求をしないものとする。 (注)1 信用金庫の会員は、持分の全部の譲渡によって脱退することができるが(信用金庫法16条前段)、この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員から信用金庫に対して、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求できることになっており(同法16条後段)、その反面、この自由脱退の場合には、持分の払戻しの制度はない。
2 信用金庫の会員が信用金庫法第17条第1項第1号から第4号まで又は第2項((法定脱退事由))の規定により脱退したときは、同法第18条((脱退者の持分の払戻))の規定により、持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。
3 信用金庫は、脱退した会員が信用金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる(信用金庫法20条)。
(予告期間)
8 法第74条第2項の「組合等からの脱退につき、法律又は定款の定により、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするもの」及び「その期間」は、おおむね次のとおりである。 (1) 中小企業等協同組合法及び消費生活協同組合法による組合等については、事業年度終了の90日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(中小企業等協同組合法18条、消費生活協同組合法19条)
(2) 水産業協同組合法、農業協同組合法、森林組合法及び農住組合法による組合等については、事業年度終了の60日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(水産業協同組合法26条、86条1項、92条2項、96条2項、100条2項、農業協同組合法21条、森林組合法36条、100条1項、109条2項、農住組合法22条)
(3) 中小漁業融資保証法による漁業信用基金協会については、事業年度終了の6月前まで(同法17条2項)。
(請求及び予告の手続)
9 法第74条第1項の規定による請求は、30日(これと異なる予告期間が定められている場合には、その期間。8参照)前に、令第33条第2項各号((払戻等請求の予告通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、その予告をした後、令第33条第1項各号((払戻し等の請求書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。これらの書面の様式は、別に定めるところによる。
債権者代位による払戻請求等との関係
10 法第74条の規定により差し押さえた持分の払戻し又は譲受けの請求ができる場合には、債権者代位権(通則法42条、民法423条)により滞納者に代位して行う持分の払戻し又は譲受けの請求をしないものとする。
第75条関係 一般の差押禁止財産
第1条関係 目 的
差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものである。したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに無効となるものではない。
第1号の財産
(生計を一にする親族)
2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び三親等内の姻族(民法725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に取り扱うものとする(執行法97条1項参照)。
(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは、滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下第75条関係において「生計を一にする親族」という。)が、最低限度の生活を維持するに必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具(以下3において「衣服等」という。)をいう。
なお、滞納者の所有に属さない衣服等(例えば、配偶者の所有に属する衣服等)は、差押えの対象財産とならないことはもちろんである。
第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びその者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料をいう。
第3号の財産
(農業を営む者)
5 法第75条第1項第3号の「主として自己の労力により農業を営む者」とは、生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、農業により生計を維持している者をいい、自作、小作の別を問わない。
(器具等)
6 法第75条第1項第3号の「農業に欠くことができない器具」等とは、5に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族が農業を行うため必要最低限の器具等をいう。この場合において、農業を行うため必要最低限のものであるかどうかは、滞納者の営む農業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する(昭和42.5.25鳥取地裁参照)。
(類する農産物)
7 法第75条第1項第3号の「その他これに類する農産物」とは、地下茎、球根、種芋等をいう。
第4号の財産
(漁業を営む者)
8 法第75条第1項第4号の「主として自己の労力により漁業を営む者」とは、生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、漁業により生計を維持している者をいい、舟、漁網その他の漁具を有する者も含まれる。
(漁網その他の漁具等)
9 法第75条第1項第4号の「水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具」等とは、8に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族が漁業を行うため必要最低限の漁網、漁衣、釣りざおその他の漁具等をいう。
(これに類する水産物)
10 法第75条第1項第4号の「これに類する水産物」とは、真珠貝、種のり、養殖用の卵、種がき、えさとして飼育している小魚等をいう。
第5号の財産
(職業又は営業に従事する者)
11 法第75条第1項第5号の「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者」とは、技術者、職人、労務者、弁護士、給与生活者、僧りよ、画家、著述家、小規摸な企業主等で生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、自己の知的又は肉体的な労働を主とする職業又は営業により生計を維持している者をいう(昭和46.5.18東京高決参照)。この場合においては、これらの者が独立して営業を営む場合であると、他に雇用される場合であるとを問わない(昭和8.2.10大決)。
(器具その他の物)
12 法第75条第1項第5号の「業務に欠くことができない器具その他の物」とは、11に掲げる滞納者及びその者と生計を一にする親族がその職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものをいう。この場合において、その職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものであるかどうかは、滞納者の職業又は営業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する。
(商品の除外)
13 法第75条第1項第5号の「商品を除く」とは、商品は換価を目的とするものであるから、たとえ業務上欠くことのできないものであっても、同号の差押禁止財産から除外することをいう。
第6号の財産
(実 印)
14 法第75条第1項第6号の「実印」とは、個人にあっては市町村条例等により市区町村役場に、会社の代表者にあっては登記所に、それぞれ届け出た印鑑で、市区町村役場又は登記所から印鑑証明書の交付を受けられるものをいう(商業登記法12条、20条参照)。
(職業に欠くことのできないもの)
15 法第75条第1項第6号の「職業に欠くことができないもの」とは、官公吏、会社員、弁護士、公証人等が職務上使用する印、会社の社印、画家及び書家の落款等の職業に必要な印章で、現に使用中のものをいう。
第7号の財産
16 法第75条第1項第7号の「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」とは、神体、神具、仏具等で、現に信仰又は礼拝の対象となっているもの及びこれに必要なものをいう。したがって、仏像、仏壇等であっても礼拝の対象としないで商品、骨とう品等となっているものには、法第75条第1項第7号の規定の適用がなく、また寺院の本堂、くり(庫裡)、神社の拝殿、社務所等は、礼拝に直接必要と認められないから、同号の規定の適用がない(昭和6.12.23大判、昭和11.3.19大判)。
第8号の財産
17 法第75条第1項第8号の「滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類」とは、滞納者が書画、骨とう等として有しているものを除き、滞納者自身又はその親族その他滞納者と特殊な関係にある者の系譜、日記、書簡等をいう。
第9号の財産
18 法第75条第1項第9号の「勲章」とは、勲功に対する名誉を表彰するものであって、内国のものであると外国のものであると問わず、また、はい(佩)授及び略章も含まれる。また、「その他名誉の章票」とは、勲章以外のもので、その所持が本人の名誉を表示するものであって、競技、学芸、技芸等が優秀なために授与された賞杯等をいう。
なお、法第75条第1項第9号は、いずれも本人又はその親族、第子等その本人と特殊な関係にある者が所持している場合に限って適用され、美術品、骨とう品等として第三者が所有している場合には適用がない。
第10号の財産
19 法第75条第1項第10号の「学習に必要な書籍及び器具」とは、学校教育法第1条((学校の範囲))に規定する学校において教育を受け、又はこれと同程度の修学をするために必要と認められる書籍、器具をいう。この場合における「書籍」とは、教科書、参考書、辞書、帳簿等をいい、「器具」とは、机、本箱、文房具等をいう。
第11号の財産
(発明等)
20 法第75条第1項第11号の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい(特許法2条1項参照)、「著作に係るもの」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、10条参照)。
(公 表)
21 法第75条第1項第11号の「公表」とは、発明につき特許を受けたとき若しくは発明に係るものを展示等し(特許法29条参照)、又は著作に係るものを発行、演奏、展示等すること(著作権法4条1項参照)をいう。
第12号の財産
22 法第75条第1項第12号の「その他の身体の補足に供する物」とは、盲人安全つえ、補聴器、車いす、義眼、眼鏡、人工こう(喉)頭及び松葉づえ等をいう。
第13号の財産
(工作物)
23 法第75条第1項第13号の「工作物」とは、人為的な労作を加えることによって通常土地に固定して設備された物をいい、「その他の工作物」には、塀、門、井戸、煙突等がある。
(消防用の機械等)
24 法第75条第1項第13号の「災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械」等とは、消防法第17条((学校等の消火器等設備義務))の規定に基づく市町村条例等により工場、事業場、学校、百貨店、旅館、飲食店、興業場等に備え付けなければならない消防自動車、消火器その他の消防用機械、器具又は避難器具、鉱山保安法第10条((保安規程))の規定による金属鉱山等保安規則第89条((防火設備等))、第98条((坑外建築物の消火設備))、第110条((防止施設))、石炭鉱山保安規則第152条((防火及び消火))、石油鉱山保安規則第240条((消火施設))等の規定により設備しなければならない各種鉱山の保安施設等をいう。
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによる。
第76条関係 給与の差押禁止
給料等の差押禁止とその範囲
(これらの性質を有する給与)
1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、日直料、宿直料、通勤手当等をいう。
(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法36条1項、2項)。
(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の基礎となる期間が1月未満のときは100円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。 (1) 給料等の金額については、切り捨てる。
(2) 法第76条第1項各号に掲げる金額については、切り上げる。
(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項((差押禁止債権))の規定により差押えが禁止されている債権(法76条及び77条の規定により差押えが禁止されるものを除く。)については、その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項に規定する差押禁止額の限度においても、その差押を行わないものとする。
(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額」とは、これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せず、同法第222条((不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等))の規定により給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金額になる。
(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
なお、道府県民税及び市町村民税については、地方税法第41条第1項((個人の道府県民税の賦課徴収))及び第321条の3の規定により普通徴収の方法により徴収する場合もあるが、この場合には、法第76条第1項第2号の規定に該当する金額がない。
(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第78条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、5と同様である。
(その他の法律)
8 法第75条第1項第3号の「その他の法令」とは、日雇労働者健康保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、港湾労働法、農業者年金基金法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法、恩給法、国会議員互助年金法及び国民年金法をいう。
(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
9 同一期間につきAとBとの支払先から給料等の支給を受ける場合において、これらの給料等につき差押えをした場合の法第76条第1項第4号(以下9において「第4号」という。)及び第5号(以下9において「第5号」という。)の金額計算は、次のいずれかの方法によるものとする。 (1) Aの給料等につき、第4号及び第5号の金額を計算し、次にAとBとの給料等の合計額について第4号及び第5号の金額を計算し、その合計額から、Aの給料等の第4号及び第5号の金額を控除したものをもって、Bの給料等の第4号及び第5号の金額とする方法 〔例〕 Aの給料
支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
法第76条第1項第1号から第3号まで(以下9において「第1号から第3号まで」という。)の金額 ・・・・・・50,000円
Bの給料
支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
第1号から第3号までの金額 ・・・・・・・・・・・・・5,000円
(注) 滞納者の家族構成は、配偶者と扶養親族2人である。
※AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額の計算 イ Aの給料の第4号の金額は170,000円(滞納者分65,O00円十配偶者・扶養親族分35,000円×3人)、第5号の金額は16,000円((支給額300,000円-第1号から第3号までの金額50,000円-第4号の金額170,000円)×20/100)、その合計額は186,000円となる。
ロ AとBとの給料の合計額350,000円についての第4号の金額は170,000円(滞納者分65,000円十配偶者・扶養親族分35,000円×3人)、第5号の金額は25,000円((350,000円-Aの第1号から第3号までの金額50,000円-Bの第1号から第3号までの金額5,000円-AとBとの給料の合計額についての第4号の金額170,000円)x×20/100)、その合計額は195,000円となる。
ハ Bの給料の第4号及び第5号の金額の合計額は9,OOO円(ロの第4号及び第5号の合計額195,000円-イの第4号及び第5号の合計額186,000円)となる。このうち、Bの給料の第4号の金額は0円(AとBとの給料の合計額についての第4号の金額170,000円-Aの給料の第4号の金額170,000円)、Bの給料の第5号の金額は9,000円(Bの給料の第4号及び第5号の金額9,000円-Bの給料の第4号の金額O円)となる。
ニ 以上の結果、AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額は次のとおりとなる。 Aの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・170,000円
Aの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・16,000円
Bの給料の第4号の金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
Bの給料の第5号の金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円
(2) AとBとの給料等の合計額につき、第4号及び第5号の金額を計算し、そのそれぞれの金額をそれぞれの給料等の金額から第1号から第3号までの金額を控除した残額に相当する金額であん分した金額をもって、それぞれの給料等の第4号及び第5号の金額とする方法 〔例〕 設例は(1)と同じ
※AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額の計算 イ AとBとの給料の合計額350,000円についての第4号の金額は170,000円、第5号の金額は25,000円となる((1)のロ参照)。
ロ Aの給料の金額から、第1号から第3号までの金額を控除した金額は250,000円(300,000円-50,000円)となる。
ハ Bの給料の金額から、第1号から第3号までの金額を控除した金額は450,005円(50,000円-5,000円)となる。
ニ イの第4号の金額をロの金額とハの金額であん分すると、Aの給料の第4号の金額は
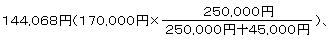
Bの給料の第4号の金額は
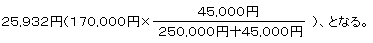
ホ イの第5号の金額をロの金額とハの金額であん分すると、Aの給料の第5号の金額は
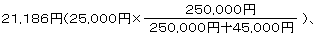
Bの給料の第5号の金額は
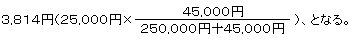
ヘ したがって、AとBとの給料のそれぞれ第4号及び第5号の金額は、次のとおりとなる(第76条関係3参照)。 Aの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・145,000円
Aの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円
Bの給料の第4号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,000円
Bの給料の第5号の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
給料等に基づき支払を受けた金銭の差押禁止
(現物給与)
10 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」は、給料等に基づき支払を受けた金銭だけをいうのであるから、現物給与として受けた者については、同項の規定の適用がない。
なお、徴収上支障がないと認められる場合には、同項の規定に準じて取り扱うことができる。
(差押禁止額)
11 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数(30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額(150,000円x20/30=100,000円)である。
賞与等及び退職手当等の差押禁止
(賞与等の差押禁止額の判定)
12 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法76条3項前段)。
なお、上記の場合において法第76条第1項第4号又は第5号に掲げる金額についての限度を計算するときは、その支給の基礎となった期間は1月であるものとみなして判定する(法76条3項後段)。
(退職手当等の場合の加算額の計算)
13 法第76条第4項第4号の規定による差押禁止額に加算すべき金額を計算する場合において、同号の「5年をこえる場合には、そのこえる年数1年」に1年未満の端数があるときは、すべて切り上げて計算する取扱いとする。
滞納考の承諾がある場合の差押え
(承 諾)
14 法第76条第5項の「滞納者の承諾」とは、徴収職員が同条第1項、第2項及び第4項の規定を適用しないで給料等又は給料等に基づき支払を受けた金銭の差押えをすることに、滞納者が同意することをいう。この滞納者の承諾は、書面により徴するものとする。 (注) 滞納者が提出する承諾書には、印紙税は課されない(印紙税法2条参照)。
(差押えのできる範囲)
15 法第76条第1項(同項1号から3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項1号及び2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないのであるから(法76条5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内において、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えができる。
なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押えができるものとする。
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
退職年金等に係る債権
1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(法人税法第84条第3項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職年金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。
退職一時金等に係る債権
2 法第77条第1項の「退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(当該適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。
第78条関係 条件付差押禁止財産
条件付差押禁止
(国税の全額を徴収することができる財産)
1 法第78条の「国税の全額を徴収することができる財産」とは、滞納者の差押えをしようとするときにおける滞納国税の全額を徴収することができる財産をいい、その財産の処分予定価額がその国税の全額以上である財産をいう。
なお、上記の「滞納国税の全額を徴収することができる」かどうかの判定については、滞納国税につき既に差押えをした財産があるときは、その財産の処分により徴収できると見込まれる金額を除いたものにより判定するものとする。
(提 供)
2 法第78条の「提供」とは、徴収職員が直ちに差押えができる状態におくことをいう(昭和32.6.26高松高判)。したがって、滞納者が提供しようとする財産の権利関係が明らかではなく又はその財産が著しく遠隔地にあるなどにより、調査するために日時を要する場合には、法第78条の「提供」には該当しない。
(その選択により)
3 法第78条の「その選択により」とは、滞納者の選択によることをいう。
条件付差押禁止財産
(第1号の財産)
4 法第78条第1号の「農業に必要な機械」等とは、現に農業を営んでいる者が、その機械等を差し押さえられることにより、現在程度の農業の継続維持に支障を来すと認められる程度に農業に関係を有する機械等をいう。したがって、例えば、現に農業に従事していない者の所有する機械等は該当しないが、農業を営む者の所有する機械等のうち使用人が使用している機械等は含まれる。
(農 地)
5 法第78条第1号の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう(農地法2条1項、土地改良法2条1項)。この場合における「耕作」とは、一般に、土地に労力を加え、肥料を施して作物を栽培することをいう。
(採草放牧地)
6 法第78条第1号の「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう(農地法2条1項参照)。
(第2号の財産)
7 法第78条第2号の「漁業に必要な漁網」等とは、現に漁業を営んでいる者が、その漁網等を差し押さえられることにより、現在程度の漁業の継続維持に支障を来すと認められる程度に漁業に関係を有する漁網等をいう。したがって、例えば、現に漁業に従事していない者の所有する漁網等は該当しないが、漁業を営む者の所有する漁網等のうち使用人が使用している漁網等は含まれる。
(第3号の財産)
8 法第78条第3号の「職業又は事業の継続に必要な機械」等とは、4及び7に準じ、現に職業又は事業(農業及び漁業を除く。)に従事している者が、その機械等を差し押さえられることにより、現在程度の職業又は事業の継続維持に支障があると認められる程度に職業又は事業に関係を有する機械等をいう(昭和32.6.26高松高判)。
(その他棚卸しをすべき資産)
9 法第78条第3号の「その他たな卸をすべき資産」とは、商品、製品、半製品、仕掛品、副産物、建築用又は修理用資材(例えば、セメント、鉄くず、木材、レール、まくら木、電線、電柱、機械部品等)、消耗品(例えば、油、くぎ、包装材料その他事務用品等)及びその他の貯蔵品をいう。
第7款 差押えの解除
第79条関係 差押えの解除の要件
差押えを解除しなければならない場合
(納 付)
1 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「納付」とは、通則法第34条((納付の手続))の規定による納付をいう。
なお、上記の納付には、同法第41条第1項((第三者の納付))の規定による第三者の納付も含まれる。
(充 当)
2 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「充当」とは、通則法第57条((充当))の規定による充当をいう。
(更正の取消し)
3 法第79条第1項第1号及び第2項第1号の「更正の取消」とは、通則法第24条((更正))等の規定による賦課処分が取り消されることをいう。
(その他の理由)
4 法第79条第1項第1号の「その他の理由」とは、差し押さえた金銭又は交付要求による交付を受けた金銭を差押えに係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項((配当の原則))の規定により差押えに係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除、法律の規定の変更等により差押えに係る国税の全額が消滅したことをいう。
(差押えに係る滞納処分費)
5 法第79条第1項第2号の「差押に係る滞納処分費」とは、差押えに係る国税の滞納処分費のうち、その差押えに係る財産についての滞納処分費をいう(法10条参照)。
(金銭的価値が失われたとき)
6 差押財産の金銭的価値が全く失われたときは、法第79条第1項第2号に該当するものとして取り扱う。
差押えを解除することができる場合
(その他の理由)
7 法第79条第2項第1号の「その他の理由」とは、差押えに係る国税に優先する他の国税、地方税又は公課の交付要求が解除されたこと、差押えに係る国税に優先する債権が弁済されたこと、差押財産の改良等によりその価値が増加したこと等をいう。
(差押超過による解除)
8 法第79条第2項第1号の規定により差押えを解除する場合におけるその解除する財産は、その超過する価額に相当する範囲を超えないものとし、差押財産が不可分物である場合には、その差押えは解除しないものとする。
差押えの解除の効力
9 差押えの解除は、差押えによる処分の禁止の効力を将来に向かって失わせるものである。したがって、例えば、継続収入の債権の差押えに基づいて、差押解除前に一部の取立て及び国税への充当がされていた場合には、差押えの解除は、既にされていた取立て等の処分には影響を及ぼさない。
他の規定による差押えの解除
10 差押えの解除には、法第79条の規定によるもののほか、法第50条第2項若しくは第4項((差押換えの請求等に基づく差押解除))、第51条第3項((差押換えの請求に基づく差押解除))、第151条第2項((換価の猶予に係る差押解除))、第153条第3項((滞納処分の停止に係る差押解除))又は第159条第5項若しくは第6項((保全差押えに係る差押解除))、通則法第48条第2項((納税の猶予に係る差押解除))、第105条第3項((不服申立てに係る差押解除))等の規定によるものがある。
差押国税の一部解除
11 2以上の滞納国税により、同一の差押調書で差し押さえている場合において、ある国税に対応する差押えを解除する必要があるとき(例えば、不服申立てに伴う換価制限があるとき)は、税務署長は、差押えに係る国税の一部を解除することができる。この場合には、その旨を滞納者及び法第81条((質権者等への差押解除の通知))に規定する者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第80条関係 差押えの解除の手続
解除の手続
1 差押えの解除は、その旨を滞納者に通知することによって行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押えの解除は、その旨を第三債務者等に通知することによって行う(法80条1項)。これらの通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
解除に伴う措置
(滞納者への通知)
2 債権又は第三債務者等がある無体財産権等の差押えを解除したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない(法80条2項2号)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(その財産を占有する第三者)
3 法第80条第2項の「その財産を占有する第三者」とは、差押えを解除した時においてその解除した財産を占有している第三者をいう。
(引渡し)
4 法第80条の「引渡」は、現実の引渡しに限らず、指図による占有の移転を含むものとする(民法184条参照)。
(差押えの登記の抹消の嘱託)
5 税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法80条3項)。この関係機関は、差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。 (注) 法第80条第3項の「差押の登記」には、法第87条第1項((参加差押えの効力))の規定により差押えの効力を生じた参加差押えの登記が含まれる。
(引き渡さなければならない)
6 法第80条第4項の「引き渡さなければならない」とは、差押えの時に第三者が占有していた動産又は有価証券については、その第三者が滞納者に引渡しをすべきことを申し出ない限り、解除時にその第三者がその財産を占有することができる権限を有しているかどうかを問わず、その第三者に引き渡さなければならず、またその第三者に引き渡せば免責されることをいう。
(供 託)
7 差押えを解除した場合に、滞納者が所在不明、受領を拒否していること等により、解除した動産又は有価証券の引渡しができないときは、通則法第121条((供託))の規定により供託することができる。
(国の責めに帰すべき理由)
8 法第80条第4項第1号の「国の責に帰すべき理由」とは、更正又は徴収に関する処分に、差押えの解除の直接の理由となった違法性があることをいう。したがって、更正の一部の取消しがあった後残額が納付されたことにより差押えを解除する場合等は、この理由に該当しない。
(参加差押えがある場合の差押えの解除等)
9 解除する差押えにつき参加差押えがある場合又は滞調法の規定の適用がある場合の差押えの解除については、法第87条第2項((参加差押えの効力)の規定((令39条から41条まで参照))又は滞調法第5条第1項本文((滞納処分による差押えの解除時の処置))、第11条第1項本文((仮差押えの執行))、第14条((滞納処分による差押の解除の通知))、第19条((船舶に対する強制執行及び仮差押の執行))、第20条((競売))及び滞調法令第3条第1項((滞納処分による差押えの解除時の処置))、第12条の2((航空機に対する強制執行等))、第12条の3((自動車等に対する強制執行及び競売))、第12条の4((自動車等に対する仮差押えの執行))等の特別の規定がある。
(第三者債務者が供託した後における差押えの解除)
10 滞納処分による差押えをした金銭債権につき強制執行による差押えがされ、第三債務者が供託した場合において(滞調法20条の6参照)、税務署長がその払渡手続前に差押えの解除をするときにおける法第80条第1項ただし書の規定による第三債務者に対する通知は、供託所に対して行うものとする。
差押えの取消しの手続
11 税務署長が、差押えの全部又は一部を取り消す場合(不服申立てに対する取消しの決定又は裁決があった場合を含む。)の手続については、法第80条の規定に準ずるものとする。
第81条関係 質権者等への差押解除の通知
差押解除の通知
(通 知)
1 税務署長は、差押えを解除した場合において、法第55条各号((質権者等に対する差押の通知))に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法81条)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(通知の相手方)
2 交付要求(参加差押えを含む。)をしている者以外の通知すべき相手方は、差押えの解除の時において、法第55条各号((差押えの通知をすべき相手方))に掲げる者に該当する者のうち知れている者である。したがって、同条の規定により差押えの通知をした者と同一の範囲に限られるものではない。
(その他必要な事項)
3 法第80条の「その他必要な事項」とは、滞納者の氏名、住所又は居所、差押えを解除した財産の名称、数量、性質、所在、差押年月日、差押解除の年月日等をいう。
第2節 交付要求
第82条関係 交付要求の手続
交付要求ができる国税
1 法第82条第1項の「滞納」とは、法第2条第9号((滞納者の定義))にいう「納付の期限までに国税を納付しない」ことをいう。
なお、滞納に係る国税については、次のことに留意する。 (1) 督促(納付催告書による督促を含む。)をしていない国税についても、交付要求をすることができる。
(2) 納税の猶予又は徴収の猶予に係る国税について、その猶予期間内であっても、交付要求をすることができる(通則法48条1項参照)。
(3) 滞納者の財産について差押えをした後、滞納者が死亡したときは、その差押えを受けた財産の相続人の固有の滞納国税について、交付要求をすることができる。
(4) 国税につき徴している第三者の担保財産を滞納処分の例により処分する場合には、その差押え時における第三者の国税につき交付要求をすることができる。 (注) 担保権の設定時において納税者に帰属していたが、差押え時には第三者に帰属している財産も上記の第三者の財産に含まれる。
交付要求ができる時期
2 次に掲げる場合には、交付要求は、それぞれに掲げる時までに行うものとする。 (1) 滞納処分の場合には、売却決定の日の前日(換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時)(法130条1項、令48条2項参照)
(2) 不動産(執行法43条1項((不動産執行の方法))に規定する不動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制執行又は不動産を目当てとする担保権の実行としての競売の場合には、執行裁判所の定める配当要求の終期(執行法49条1項、2項、87条1項2号、188条) (注) 執行法第49条第3項((配当要求の終期の延期))又は第52条((配当要求の終期の変更))の規定により、配当要求の終期が延期された場合等には、当初の配当要求の終期後においても、延期等後の配当要求の終期までの間は交付要求をすることができる。
(3) 不動産に対する強制管理の場合には、執行裁判所が定める期間の終期(執行法107条1項、4項) (注) 上記の場合には、執行裁判所が定める期間ごとに配当等(執行法84条3項参照)が実施されるので、当該期間の満了までに交付要求をしなければ、既に収取されている収益の配当を受けることはできない。
(4) 船舶(執行法112条((船舶執行の方法))に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車又は建設機械に対する強制執行又はこれらの財産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、(2)に準ずる時(執行法121条、189条、執行規則84条、97条、98条、175条から177条まで)
(5) 動産(執行法122条1項((動産執行の開始))に規定する動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制執行又は動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、次に掲げる時 イ 売得金については、執行官がその交付を受ける時(執行法137条((執行停止中の売却))又は保全法49条3項((動産に対する仮差押えの執行))の規定により供託された売得金については、動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売が続行されることとなった時)
ロ 手形等(執行法136条参照)の支払金については、執行官がその支払を受ける時(同法140条)
(6) 金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行の場合には、次に掲げる時(執行法165条)。ただし、金銭の支払を目的とする債権につき管理命令が発せられている場合には、上記(3)に準ずる(同法166条1項、161条1項、6項、107条4項参照)。 イ 第三債務者が執行法第156条第1項又は第2項((第三債務者の供託))の規定による供託をした時
ロ 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
ハ 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
ニ 動産引渡請求権の差押えの場合にあっては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
(7) (2)から(6)までに掲げる財産権以外の財産権に対する強制執行又はこれらの財産権を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、特別の定めがあるもののほか、(6)に準ずる時(執行法167条1項、193条2項)
(8) 企業担保権の実行手続が開始された場合には、一括競売により換価をするときは競落期日の終了時、任意売却により換価をするときは裁判所が定めて公告した日(企業担保法51条の2)
(9) 破産宣告があった場合には、破産終結の決定(破産法282条1項)、強制和議の認可決定(同法321条)又は破産廃止の決定(同法347条参照)がある時 (注) 破産宣告後に確定した財団債権である国税については、上記にかかわらず、直ちに交付要求をするものとする(破産法286条参照)。
担保財産につき強制換価手続が開始された場合
3 国税の担保財産につき強制換価手続が開始された場合には、次のことに留意する。 (1) 裁判所書記官から債権届出の催告を受けたときは、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない(執行法49条2項、50条1項、121条、執行規則97条、98条)。また、その届出に係る国税の額に変更があったときは、その旨の届出をしなければならない(執行法50条2項、121条、執行規則97条、98条)。
(2) 担保を徴した国税が、次に掲げる場合に該当するため、法第15条((法定納期限等以前に設定された質権の優先))又は第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定を適用して、国税としての優先権を主張する必要があるときは、交付要求をするものとする。
なお、この場合における交付要求書には、担保を徴した国税に係る交付要求である旨を付記するものとする。 イ 国税の担保権の設定が、その担保財産上に設定された質権又は抵当権の設定に後れる場合
ロ 抵当権の設定に係る国税の利子税又は延滞税が、民法第374条((抵当権の被担保債権の範囲))の規定により、その抵当権の満期となった最後の2年分に制限されるため、国税債権額の満足を得ることができない場合
交付要求の手続
(交付要求書)
4 法第82条第1項の「交付要求書」とは、令第36条第1項各号((交付要求書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第7号書式による。
(滞納者への通知)
5 交付要求をしたときは、令第36条第2項各号((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、滞納者に通知しなければならない(法82条2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(質権者等への通知)
6 交付要求をしたときは、令第36条第3項((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に定める事項を記載した書面により、質権者等に通知しなければならないが(法82条3項)、これについては第55条関係と同様とする。ただし、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、通知をする必要がない(令36条4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
交付要求の効果
7 交付要求の効果については、次のことに留意する。 (1) 交付要求は、その交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行(担保権の実行としての競売を含む。以下同じ。)の手続が解除され、又は取り消された場合には、その効力を失う。
(2) 交付要求は、交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行の手続が解除されず、又は取り消されない限り、その処分の目的となった財産について差押え後に権利の移転があっても、その交付要求により配当を受けることができる(昭和27.12.9浦和地判、昭和28.6.30東京高判)。
(3) 交付要求は、時効中断の効力を有する(通則法73条1項5号、2項)。
滞調法の規定により二重差押えがされている場合
8 滞納者の財産について、滞調法の規定により滞納処分と強制執行とが競合している場合には、滞納処分をしている行政機関等に対して交付要求(参加差押えの要件を満たしている場合には、参加差押え)をするととともに、強制執行の執行機関に対しても交付要求をするものとする。 (注) 強制執行に先行して滞納処分による差押えをしている場合において、強制執行続行の決定があったときは、当該差押えに係る国税につき、強制執行の執行機関に対して交付要求をすることに留意する(滞調法10条3項等)。
交付要求に係る強制執行につき続行決定があった場合
9 交付要求に係る強制執行について、その続行決定があつた場合には、交付要求をした国税を徴収するため改めて交付要求をする必要はない。
第83条関係 交付要求の制限
交付要求の制限の意義
1 法第83条は、滞納者が他に換価容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によって国税の全額を徴収できると認められるときは、利害関係人の利益を害することがないよう交付要求をしないことを定めた訓示規定である(昭和49.8.6.最高判)。
換価の容易な財産
2 法第83条の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。
徴収できると認められる場合
3 法第83条の「徴収することができると認められる」かどうかの判定については、第22条関係4と同様である。
第84条関係 交付要求の解除
その他の理由
1 法第84条第1項第1号の「その他の理由」とは、交付要件により交付を受けた金銭を交付要求に係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項((配当の原則))の規定により交付要求に係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除、法律の規定の変更等により交付要求に係る国税の全額が消滅したことをいう。
交付要求の解除手続
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う(法84条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
関係者への通知
(滞納者への通知)
3 交付要求を解除した場合には、その旨を滞納者に通知しなければならない(法84条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(質権者等への通知)
4 交付要求を解除した場合は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときを除き、その旨を質権者等に通知しなければならないが(法84条3項、令36条4項)、この通知については、第55条関係に準ずる(第81条関係1参照)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第85条関係 交付要求の解除の請求
解除の請求ができる者
1 法第85条第1項の「配当を受けることができる債権者」とは、交付要求の解除の請求をした時において、強制換価手続により配当を受けることができる債権者をいい、配当受領のための手続を必要とする債権につきその手続をとっていない債権者は含まれない。
解除の請求ができる場合
(債権の弁済を受けられないこと)
2 法第85条第1項第1号の「弁済を受けることができない」とは、交付要求がなければ弁済を受けることができたにかかわらず、交付要求がされたために、債権の全部又は一部の弁済を受けることができなくなることをいう。したがって、交付要求の有無にかかわらず弁済を受けることができない場合は、法第85条第1項第1号には該当しない。
(換価の容易な財産)
3 法第85条第1項第2号の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。
(徴収できることの判定)
4 法第85条第1項第2号の「徴収することができる」かどうかの判定については、第22条関係4と同様である。
(解除の請求手続)
5 法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求は、令第37条各号に掲げる事項を記載した書面により、交付要求ができる時期(第82条関係2参照)までにしなければならないものとする(昭和49.8.6最高判)。
請求に対する措置
(請求を相当と認めるとき)
6 法第85条第2項の「相当と認めるとき」は、第50条関係10とおおむね同様である。
なお、交付要求ができる時期(第82条関係2参照)が経過した後に交付要求の解除の請求があった場合においても、相当と認められるときは、交付要求の解除をするものとする。
(請求を相当と認めないとき)
7 税務署長は、法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない(法85条2項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第86条関係 参加差押えの手続
参加差押えの手続
(参加差押えの意義)
1 法第86条から第88条((参加差押えの制限、解除等))までに規定する参加差押えは、交付要求の一つとして行われるものであるから、参加差押えを受けた差押えが解除されるまでの効力は交付要求の効力と同様であるが、その参加差押えを受けた差押えが解除されると参加差押えをした時等にさかのぼって差押えの効力を生じ、その後はその差押えに基づき参加差押財産の換価処分ができる効力を有する。
(差押えができる場合)
2 法第86条第1項の「第47条(差押の要件)の規定により差押をすることができる場合」とは差押えの要件を定める法第47条の規定に基づく差押えができる場合をいい、次に掲げる場合を含むものとする。
なお、法第47条第2項((繰上差押え))の規定により繰上差押えができる場合にも、法第86条第1項の規定により繰上参加差押えをすることができる(第47条関係14参照)。 (1) 法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分の要件))に規定する同条第2項((譲渡担保権者に対する告知))の告知書を発した日から1O日を経過した日までに法第24条の規定により徴収しようとする金額が完納されていない場合
(2) 法第159条第3項((保全差押金額の通知))の規定による保全差押金額の通知を納税義務があると認められる者にした場合
(3) 通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定による繰上保全差押金額の通知を納税者にした場合
(4) 通則法第52条(担保の処分)に規定により担保の処分をする場合。
(5) 法第138条((滞納処分費の納入の告知))の規定による納入告知により指定された納期限までに、その納入告知書により告知された滞納処分費を完納しない場合
(参加差押書)
3 法第86条第1項の「参加差押書」とは、令第36条第1項各号((交付要求書の記載事項))に掲げる事項に準ずる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第8号書式による。
(滞納者への通知)
4 参加差押えをしたときは、令第36条第2項各号((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に掲げる事項に準ずる事項を記載した書面(参加差押通知書)により、滞納者に通知しなければならない(法86条2項前段)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(第三債務者への通知)
5 電話加入権について参加差押えをしたときは、令第36条第3項に定める事項に準ずる事項を記載した書面により、第三債務者(日本電信電話公社)に通知しなければならない(法88条2項後段)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(差押財産が譲渡された場合)
6 滞納者(甲)の所有財産がその者の滞納処分により差し押さえられ、その後その差押財産が第三者(乙)に譲渡された場合において、滞納者(甲)の国税につき参加差押えをすることはできないし(昭和37.6.29付民事甲第1,838号法務省民事局長電報回答)(交付要求はできる。)、また、第三者(乙)の国税につき参加差押え(交付要求を含む。)をすることもできない(第47条関係59参照)。
(譲渡担保財産である場合)
7 譲渡担保権者の国税により差押えがされている譲渡担保財産について、法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分))の規定により譲渡担保設定者(譲渡担保財産を譲渡担保権者に譲渡した者をいう。)の国税により参加差押えをすることができるし、また譲渡担保設定者の国税により差押えがされている譲渡担保財産について譲渡担保権者の国税により参加差押えをすることもできる(令9条参照)。
登記の嘱託
8 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械につき参加差押えをしたときは、参加差押えの登記を、参加差押調書謄本を添えて(昭和35.9.19付民事甲第2,304号法務省民事局長通達)、関係機関に嘱託しなければならない(法86条3項)。この関係機関については、第68条関係44、第70条関係5及び第71条関係5と同様である。
なお、参加差押えの登記は、参加差押えの効力要件ではないが、法第87条((参加差押の効力))の規定による差押えを第三者に対抗するための要件である。
質権者等への通知
9 税務署長は、法第86条第1項の規定により参加差押えをしたときは、法第55条((質権者等に対する差押えの通知))に掲げる者のうち、徴収職員がその参加差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対して、令第36条第3項((交付要求をした旨の通知書の記載事項))に定める事項に準ずる事項を記載した書面により通知しなければならない(法86条4項、令38条)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
第87条関係 参加差押えの効力
参加差押えに係る差押えの効力
(参加差押えの効力)
1 参加差押えは、次に掲げる効力を有する。
なお、(2)及び(3)に掲げる効力は、参加差押えが2以上ある場合は、そのうち最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え)に限られる(法87条1項)。 (1) 参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対する交付要求の効力
(2) 参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、参加差押財産について、3に掲げる時にさかのぼって生ずる差押えの効力
(3) 参加差押財産が動産、有価証券、自動車又は建設機械であって、その参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、その差押えを解除した行政機関等からその財産の引渡しを受けることができる効力
(差押えの効力が生ずる参加差押え)
2 参加差押えを受けた差押えが解除されたときにおいて、差押えの効力を生ずる参加差押えは、次のとおりである(法87条1項)。 (1) 参加差押えが一つである場合には、その参加差押え
(2) 参加差押えが2以上ある場合には、参加差押えを受けた差押えが解除されたときにされている参加差押えのうち、最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え) (注)1 参加差押えを最も先にしたものであっても、参加差押えを受けた差押えが解除される時までに解除したときの参加差押えは、差押えの効力を生じないし、また上記の差押えの効力を生ずる参加差押え以外の参加差押えは、差押えの効力を生じない。
2 差押えの解除後、その抹消登記前にした参加差押えは、効力を生じない。
(差押えの効力を生ずる時期)
3 参加差押えが差押えの効力を生ずる時は、次のそれぞれに掲げる時である(法87条1項、大陸棚特別措置法施行令5条)。 (1) 参加差押財産が動産及び有価証券である場合には、その参加差押書が参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に交付された時
(2) 参加差押財産が不動産(鉱業権及び特定鉱業権を除く。)、船舶、航空機、自動車及び建設機械である場合には、その参加差押通知書が滞納者に送達された時。ただし、参加差押えの登記が、参加差押通知書の滞納者への送達前にされた場合には、その登記がされた時
(3) 参加差押財産が鉱業権又は特定鉱業権である場合には、参加差押えの登録がされた時
(4) 参加差押財産が電話加入権である場合には、その参加差押通知書が第三債務者である日本電信電話公社に送達された時
動産等の引渡し
(差押えを解除すべきときの順序)
4 参加差押えがされている動産、有価証券、自動車又は建設機械(以下第87条関係において「動産等」という。)について、参加差押えを受けている差押えを解除すべきとき又は差押えの解除ができるときは、税務署長は、その動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡し、その後において差押えを解除するものとする。
(動産等の引渡しの通知)
5 法第87条第2項の規定により動産等を差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等(以下第87条関係において「参加差押えの行政機関等」という。)に引き渡すべきときは、税務署長は、次によりその参加差押えの行政機関等にその旨を通知しなければならない(令39条1項、2項)。 (1) 令第39条第1項各号((参加差押えに係る動産等の引渡しの通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面による。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(2) 徴収職員以外の者で動産等の保管をしている者に直接引渡しをさせようとする場合には、その旨を(1)の書面に付記するとともに、その保管者にあてた参加差押えの行政機関等へ動産等の引渡しをすべき旨の書面を添付する。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(権利書等の引渡し)
6 税務署長は、法第65条((債権証書の取上げ))又は第73条第4項((権利証書の取上げ))の規定の趣旨により取り上げた権利証書等がある場合及び動産等を占有している第三者が提出した法第59条第1項又は第3項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)に規定する損害賠償請求権又は前払借賃に関する書類その他必要なもの(令48条の債権現在額申立書を含む。)がある場合には、これらの権利証書及び書類を、参加差押えの行政機関等に引き渡すものとする(令41条1項、3項、4項)。
(差押えを解除したときの措置)
7 税務署長は、参加差押えを受けた差押えを解除したときは、法第80条第2項及び第3項((差押解除の措置))並びに第81条((質権者等への差押解除の通知))の規定による手続をするほか、次に掲げる措置をしなければならない。 (1) 2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされている参加差押えを除き、他の参加差押えに係る参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち、滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を参加差押えの行政機関等に引き渡す(令41条1項)。この場合においては、別に定める書面を添付するものとする。
なお、滞納処分による差押え等に関する書類の引渡しについては、一つの参加差押えだけがある場合においても、同様に取り扱う。
(2) (1)により参加差押えの行政機関等に引き渡す参加差押書又はその写しには、差押えの解除をした税務署におけるその参加差押書の受付順序を明白に表示する。
(3) 参加差押えの行政機関等以外の参加差押えをしていた行政機関等又は法第55条((質権者等に対する差押えの通知))に規定する質権者等に対し、参加差押えの行政機関等の名称及びその行政機関等に差押財産を引き渡した旨を法第81条の規定による通知書に付記する(令39条3項参照)。
(4) 法第59条第2項(同条4項において準用する場合を含む。)の規定により、差し押さえた財産の使用又は収益をしている者及び法第129条第1項第4号((配当を受ける損害賠償請求権等に係る債権))に掲げる債権を有する者に対し、(3)に準じて通知するものとする。
(引渡しをした動産等の保管費用)
8 徴収職員が動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡した場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書が参加差押えの行政機関等に送達された日までの保管に関する費用は、その動産等の引渡しをした国(税務署長)の負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令40条5項参照)。
(差押解除後の参加差押えの効力)
9 行政機関等が、参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を、参加差押えの行政機関等に引き渡した場合には、それらの参加差押書に係る参加差押えは、行政機関等にそれらの参加差押書が送達された時に、それらの参加差押書に係る参加差押えの順序に従い、参加差押えの行政機関等に対して参加差押えをしたものとみなされ、引渡しがされたその他の書類は、その行政機関等に提出されたものとみなされる(令41条2項)。
(動産等の引渡しを受けた場合の措置)
10 参加差押えが差押えの効力を生じた場合において、徴収職員が差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面の送付を受けたときは、次の措置をしなければならない。 (1) 徴収職員は、差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面に記載されている事項に基づき、遅滞なく、その通知に係る動産等の引渡しを受ける(令40条1項前段)。この場合において、その通知に係る動産等を徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)以外の者でその動産等の保管をしている者から受け取るときは、その保管をしている者に対し、送付を受けたその保管者あての動産等の引渡しをすべき旨の書面を交付する(令40条1項後段)。
(2) 徴収職員は、必要があると認めるときは、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させることができるので、保管については通常の差押財産と同様に処理する(令40条2項本文)。この場合において、第三者に保管させるときは、その動産等の運搬が困難であるときを除き、その第三者の同意を得なければならない(令40条2項ただし書)。
(3) 徴収職員は、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させた場合には、封印、公示書その他の方法により差押えを明白にしなければならない(令40条3項)。
(4) 徴収職員は、動産等の引渡しを受けたときは、引渡しをした行政機関等に対し、引渡動産等の引渡しを受けた旨を通知する(令40条4項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(引渡しを受けた動産等の保管)
11 令第40条第2項((引渡しを受けた動産等の保管))の「必要があると認めるとき」、「財産を占有する第三者」及び「運搬が困難であるとき」は、第60条関係7,6及び10と、それぞれ同様である。
なお、上記の場合における令第40条第3項((保管させた場合の措置))の規定による封印、公示書その他の方法により差押えを明白にすることは、差押えの効力発生の要件ではなく、徴収職員が差押財産を占有していることを明らかにする方法にすぎない。
(賃料債権等の権利行使)
12 法第59条第1項又は第3項((引渡命令を受けた第三者の権利保護))(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対して配当を請求することができる権利は、差押えの効力を生ずべき参加差押えをしている税務署長に対して行使することができる(令41条3項、4項)。
(引渡しを受けた動産等の保管費用)
13 徴収職員が、他の行政機関等から徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)から動産等の引渡しを受けた場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書がその徴収職員の所属する税務署に送達された日の翌日からの保管に関する費用は、その引渡しを受けた税務署の13負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令40条5項)。
換価の催告
14 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる(法87条3項)。この催告は、原則として別に定める書面により行うものとする。
換価の催告を受けた場合
15 差押えをした税務署長が、その差押えに対して参加差押えをした行政機関等から、差押財産について換価すべき旨の催告を受けた場合は(法87条3項)、法律で換価が制限されているときその他相当な理由により換価ができない場合を除き、速やかに換価するものとする。
上記の理由に該当しない場合において、差押財産の換価をしないときは、その理由を催告した行政機関等に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第88条関係 参加差押えの制限、解除等
参加差押えの制限
1 参加差押えの制限については、第83条関係1から3までに準ずる(法88条1項参照)。
参加差押えの解除
2 参加差押えの解除については、第84条関係1から4までに準ずる(法88条1項参照)。
なお、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を日本電信電話公社に通知しなければならない(法88条3項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
参加差押えの登記の抹消の嘱託
3 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法88条2項)。この関係機関は、参加差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。
参加差押えの解除の請求
4 参加差押えの解除の請求については、第85条関係1から7までに準ずる(法88条1項参照)。
第3節 財産の換価
第1款 通則
第89条関係 換価する財産の範囲
差押財産
1 法第89条第1項の「差押財産」とは、差し押さえた財産のうち、次に掲げるものを除いた財産をいうものとする。 (1) 金銭及び債権
(2) 法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により取り立てる場合の有価証券
(3) 法第73条第5項((差し押さえた債権の取立て等の準用))において準用する第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取り立てる場合の無体財産権等
換価することができる債権
2 次に掲げる債権は、法第89条第2項の規定により換価することができる。 (1) 差し押さえた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取立てをしようとする時から6月以内に到来しないもの。この場合において、6月の計算の始期は、差押えの効力の発生した日とする。
(2) 取立てをすることが著しく困難であると認められるもの。この場合において、著しく困難とは、差し押さえた債権が、不確定期限のついたもの、条件の付けられたもの、反対給付に係るもの等で、かつ、取立てまでに要する期間、条件その他債権の内容により取立てをすることが社会通念上著しく困難なことをいう。なお、6月以内に取立ての見込まれないことが明白な債権は取立てが著しく困難なものとして換価できるものとする。
一括換価
(一括換価をする場合)
3 次の財産については、原則として、それぞれに定めるところに従い、一括して換価する。 (1) 工場抵当法第2条((財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権))の規定の適用を受ける財産については、土地又は建物とともに換価する。
(2) 工場財団その他の財団の組成物件については、工場財団その他の財団として換価する。ただし、財団として売却することが困難である場合には、工場抵当法第46条((個々のものの競売又は入札))の規定の趣旨に従い、抵当権者等の同意を得て、個々の物件として換価することができる。
(3) 担保権の目的となっている財産の従物については、主物とともに換価する。ただし、担保権者の同意がある場合には、主物と別個に換価することができる。
(一括換価をすることができる場合)
4 同一の滞納者の所有に係る複数の財産について、次のいずれにも該当するときは、当該財産を一括して換価することができる(昭和49.1.17東京高決参照)。 (1) 財産が、客観的かつ経済的にみて、有機的に結合された一体をなすと認められること。
(2) 一括換価をすることにより高価有利に売却できること。
(3) 一括換価することを不当とする事由(例えば、担保権者に対する配当に支障を来すこと。)がないこと。
(4) 売却決定が同一の日であること。
(共有に係る不動産の一括換価)
5 共有に係る不動産については、その共有者の全員が滞納しており、かつ、各滞納者について国税への配当金額がある場合に限り、当該不動産を一括して換価することができる(第129条関係17参照)。
換価ができない場合
6 次に掲げる国税については、原則として、それぞれに掲げる期間内は、換価をすることができない。なお、果実等については、法第90条第1項及び第2項((果実等の換価の制限))の規定の適用がある。 (1) 納税者の国税を第二次納税義務者又は保証人から徴収する場合におけるその第二次納税義務者及び保証人の納付すべき国税その納税者の財産を換価に付すまでの期間(法32条4項、通則法52条5項)又は第二次納税義務者若しくは保証人が、納付通知書による告知、納税催告書による督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(2) 担保のための仮登記がされた財産を差し押さえた場合の法第55条第2号((仮登記の権利者に対する差押えの通知))の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る国税同条第2号の通知に係る差押えにつき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(3) 法第24条第1項((譲渡担保財産からの国税の徴収))の規定により譲渡担保財産から徴収する納税者の国税その納税者の財産を換価に付すまでの期間(法24条3項、32条4項)又はその譲渡担保権者が同条第2項の告知(同条4項の規定による場合のものを含む。)若しくはこれに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起した場合におけるその訴訟の係属する期間(法90条3項)
(4) 法第50条第3項((第三者による換価の申立てと換価の制限))の申立てがあった場合において、その申立てに係る財産が換価の著しく困難なもの又はその申立て者以外の第三者(滞納者を除く。)の権利の目的となっているもの以外のものであるときの、その申立てに係る財産についてのその国税その申立てがあった時からその申立てに係る財産を換価に付すまでの期間
(5) 法第151条第1項((換価の猶予の要件))の規定による換価の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(6) 通則法第23条第5項ただし書((更正の請求があった場合の徴収の猶予))又は第105条第2項及び第6項((不服申立てに係る徴収の猶予等))の規定による徴収の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(7) 通則法第46条第1項、第2項及び第3項((納税の猶予の要件))の規定による納税の猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間(同法48条1項)
(8) 不服申立てに係る国税その不服申立てについての決定又は裁決があるまでの期間(通則法105条1項ただし書)
(9) 通則法第105条第2項及び第6項((不服申立てに係る滞納処分の続行の停止等))の規定により滞納処分の続行が停止されている場合におけるその停止に係る国税その続行の停止期間
(10) 滞納法第10条((強制執行続行の決定))等の規定により強制執行等の続行の決定があった場合のその滞納処分による差押えに係る国税その強制執行等の係属する期間
(11) 会社更生法第37条第2項((滞納処分の中止命令等))の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合におけるその中止に係る国税その中止期間
(12) 会社更生法第102条((更生債権))の規定により更生債権となった国税同法第67条第2項((滞納処分の中止等))の規定による滞納処分の中止期間
(13) 会社更生法第122条第1項((租税等の請求権))の規定による猶予がされている場合におけるその猶予された国税その猶予期間
(14) 行政事件訴訟法第25条第2項((執行停止))の規定により執行の停止を命ぜられた処分に係る国税その停止期間
(15) 企業担保権の実行手続の開始があった株式会社に係る国税その実行手続の係属する期間(企業担保法28条)
(16) 予定納税額に係る所得税その年分の所得税に係る確定申告期限までの期間(所得税法117条)
換価の効果
(承継取得)
7 換価は、滞納者と買受人との間に売買契約を成立させるものであるから、買受人の権利の取得は、原始取得ではなく、承継取得である(昭和8.12.2大判、昭和32.4.24岐阜地判)。
(担保権等の消滅)
8 買受人が買受代金の納付により換価に係る権利を取得したときは、換価財産の上にあつた質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、消滅する(法124条1項前段)。ただし、法第124条第2項((担保権の引受け))の規定による担保権の引受けがあったときは、その引受けに係る担保権は、消滅しない(法124条2項後段)。
なお、法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により譲渡担保財産に対して滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権も、上記と同様に消滅する(法124条1項後段)。
(用益物権等の存続)
9 換価財産が不動産その他の登記を権利移転の対抗要件又は効力要件とする財産であって、その財産上に差押えの登記前に第三者に対抗できる地上権その他の用益物権、買戻権、賃借権、仮登記(担保のための仮登記を除く。)等(以下「用益物権等」という。)がある場合には、その用益物権等は、換価によっては消滅しない。ただし、第三者に対抗できる用益物権等であっても、それらの権利の設定前に換価によって消滅する質権、抵当権、先取特権、留置権、買戻権又は担保のための仮登記がある場合には、その用益物権等も消滅する。 (注) 換価によって消滅する担保権等の後に設定された用益物権等が消滅するのは、これらの用益物権等が担保権等に対抗できないことによるものであるから、民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない登記された賃貸借(登記なしで対抗できるものを含む。借家法1条等)は、消滅しない(民法395条)。
(賃借権等の消滅)
10 差押え前に換価財産上に賃借権(9に定めるものを除く。)、使用貸借権等の権利が設定されている場合においても、換価による買受人に対抗できないから、これらの権利は消滅する。
(土地の賃借権の存続)
11 換価により建物の所有を目的とする賃借地上の建物の所有権を取得した買受人は、その土地の賃借権も取得する(借地法9条の3,9条の4、昭和47.7.18最高判参照)。
(仮差押え等の消滅)
12 換価財産上にある仮差押え及び仮処分の消滅については、第140条関係3及び12から21までに定めるとおりである。
(差押え後の権利の消滅)
13 換価財産につき差押え後に取得した所有権、担保権、用益物権等を有していた者は、その換価財産の買受人に対して所有権等の権利を主張することができない。
譲渡の制限
(たばこ専売法)
14 たばこ種子、たばこ苗及び葉たばこについては、たばこ専売法の規定に基づく譲渡制限等があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) たばこ種子は、日本専売公社(以下「専売公社」という。)又は耕作者でなければ所有できない(たばこ専売法11条1項)。
(2) たばこ苗は、専売公社又は耕作者でなければ育成できない(たばこ専売法12条1項)。
なお、耕作者に譲渡するときは、専売公社の許可を受けなければならない(たばこ専売法12条4項)。
(3) 葉たばこ及び製造たばこ用巻紙は、専売公社に対してでなければ譲渡できない(たばこ専売法18条1項、54条1項)。
(4) 農薬用たばこ耕作者の収穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供するときは、あらかじめ専売公社の承認を要する(たばこ専売法26条の3)。
(5) 製造たばこの換価は、たばこ専売法第29条第2項((製造たばこの販売制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(6) 製造たばこの換価に際しては、一般消費者が買受人となることができることはもちろん、小売人は、たばこ専売法第37条第1項第2号((買受販売制限の除外))の規定により買受人となることができる。
(7) 小売人の所有する製造たばこを換価する場合においては、たばこ専売法第34条第3項((定価))の規定の適用はないから、小売定価によらないで換価することができる。
(塩専売法)
15 塩及びかん水については、塩専売法の規定に基づく譲渡制限等があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) 塩の製造者が製造して所有する塩は、原則として専売公社に対してでなければ譲渡できない(塩専売法5条1項、14条1項参照)。
(2) 塩専売法第29条第1項((特別価格による売却))の規定により特別価格で買い受けた塩は、専売公社の許可を受けなければ譲渡できない(同法29条4項)。
(3) 輸出のため専売公社から買い受けた塩は、専売公社の許可を受けなければ、輸出前には譲渡できない(塩専売法41条2項)。
(4) かん水は、塩の製造者に対してでなければ譲渡できない。ただし、専売公社の許可を受けた場合には、この限りでない(塩専売法43条1項)。
(5) 塩の換価は、塩専売法第23条第2項本文((販売の制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(6) 塩の換価に際しては、一般消費者が買受人となることができることはもちろん、小売人は、塩専売法第34条第1項第2号((買受販売制限の除外))の規定により買受人となることができる。
(アルコール専売法)
16 アルコールの換価については、アルコール専売法の規定に基づく譲渡制限があるが、これについては、次のことに留意する。 (1) アルコールを製造している者の製造したアルコールは、政府に対してでなければ譲渡できない(アルコール専売法13条)。
(2) 売さばき人又は消費者の所有するアルコールの換価は、アルコール専売法第28条第1項((販売の制限))の規定による販売ではないから、同項の規定による制限は受けない。
(飼料需給安定法)
17 政府は、輸入飼料を売り渡す場合には、飼料需給安定法第6条((売渡の附帯条件))の規定により、その相手方に対し、譲渡に関し地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
(大麻取締法)
18 大麻(大麻取締法1条に規定する大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)を除く。)は、同法第3条第1項((譲渡等の制限))の規定により、大麻取扱者に対してでなければ譲渡することができない。
(火薬類取締法)
19 火薬類(火薬類取締法2条に掲げる黒色火薬、ニトログリセリン、実砲等の火薬、爆薬及び火工品をいう。)の譲渡については、同法第17条第1項((譲渡等の許可))の規定により、同項各号のいずれかに該当する場合以外の場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(毒物及び劇物取締法)
20 毒物(黄りん、ひ(砒)素等の毒物及び劇物取締法2条1項の規定による別表第1に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)又は劇物(塩酸、硝酸等同法2条2項の規定による別表第2に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)の製造業又は輸入業の登録を受けた者で、販売業の登録を受けていない者は、同法第3条第3項((販売等の制限))の規定により、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業の登録を受けた者に対してでなければ、毒物又は劇物を譲渡することができない。
(覚せい剤取締法)
21 覚せい剤(覚せい剤取締法2条に掲げるフェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン等をいう。)の製造業者が、その製造して所有する覚せい剤は、同法第17条((譲渡及び譲受の制限及び禁止))の規定により、覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
(麻薬取締法)
22 麻薬(コカ葉、モルヒネ等麻薬取締法2条1号の規定による別表に掲げるものをいう。)は、同法第26条((譲受))の規定により、麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に対してでなければ、譲り渡してはならない(同法24条参照)。
(あへん法)
23 あへん(あへん法3条2号に規定するけしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。)は、同法第7条第1項((譲渡等の禁止))の規定により、国に対してでなければ譲渡することができず、また、けしがら(同法3条3号に規定するけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。)は、同条第2項((譲渡等の制限))の規定により、けし栽培者、麻薬製造者又は麻薬研究施設の設置者に対してでなければ、譲渡することができない。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律)
24 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社又は有限会社の株式又は持分については、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第1条((株式の譲渡制限等))及び第5条((有限会社の準用))の規定により、定款をもって定められた場合に限り、株式又は持分の譲受人を、その株式会社又は有限会社の事業に関係のある者に限ることができる。
(日本航空株式会社法)
25 日本航空株式会社法第2条第2項((株式の譲渡制限))の規定により、航空法第4条第1項各号((航空機登録の要件))に掲げる者が議決権の3分の1以上を占めることとならないようにするため、定款で定められた場合に限り、株式の譲受人を制限することができる。
(海上運送法)
26 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下26において「日本の国籍を有する者等」という。)が、その所有する船舶(海上運送法施行規則44条1項各号((譲渡等の許可を受けることを要しない船舶等))に定めるものを除く。)を日本の国籍を有する者等以外の者に譲渡しようとするときは、海上運送法第44条の2第1項((船舶の譲受けの許可))の規定により、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(漁港法)
27 漁港施設の譲渡については、漁港法第37条第1項((漁港施設の処分の制限))の規定により、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(銃砲刀剣類所持等取締法)
28 銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法2条1項((定義))に規定するけん銃、小銃、機関銃等をいう。)又は刀剣類(同法2条2項((定義))に規定する刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり等をいう。)の譲渡については、同法第21条の2((譲渡の制限))の規定による制限がある。
第90条関係 換価の制限
換価手続の制限
(未成熟の果実等の場合)
1 法第90条第1項及び第2項の規定により換価が制限されている場合には、その制限がされている間は公売公告以後の換価手続は行わないものとする。
(納付通知等の処分に関する訴訟係属中の場合)
2 法第90条第3項に規定する換価の制限に該当することとなった場合には、その換価の制限がされている間は公売公告以後の換価手続は行わないものとする。なお、公売公告後、買受代金の納付期限前に上記の換価の制限に該当することとなった場合においては、それが売却決定前であるときは売却決定を行わないものとし、売却決定後、買受代金の納付期限前であるときは買受代金を受領することができないものとする。
果実等の換価制限
(果 実)
3 法第90条第1項の「果実」とは、植物の果実をいい、いわゆる果物のほか、馬鈴しょ、落花生等の野菜類等をいう。
なお、不動産等と果実とを一体として換価する場合には、法第90条の規定は適用されない。
(成 熟)
4 法第90条第1項の「成熟」とは、通常の取引に適する状態になることをいう。
仕掛品等の換価制限
(生産工程中)
5 法第90条第2項の「生産工程中」とは、生産の作業が完成品となる前段階にあり、まだ作業が継続していることをいう。したがって、事業の休廃止等に係る仕掛品については、法第90条第2項の規定は適用されない。
(仕掛品)
6 法第90条第2項の「仕掛品」とは、一定時点において、製品、半製品、部分品の生産のために現に仕掛中又は加工中のものをいい、なお製造過程中にあって、製品又は半製品となる前段階にあり、まだ販売に適しないものをいう。
(栽培品等)
7 法第90条第2項の「その他これらに類するもの」とは、仕掛品に類するもの及び栽培品に類する稚魚、ひな等をいう。
(完成品)
8 法第90条第2項の「完成品」とは、その生産等の作業により通常の取引に適する状態になった物をいう。 (注) 完成品とならなくても、著しく低額にならない物(例えば、塗装だけが終わっていない机等)は換価することができる。
訴訟係属中の換価制限
(訴えの提起)
9 法第90条第3項の「訴えを提起したとき」とは、訴状が裁判所から税務署長に送達されたときをいうものとする(民事訴訟法229条参照)。
(訴訟の係属する間)
10 法第90条第3項の「訴訟の係属する間」とは、訴えの提起から裁判の確定までの期間をいい、適法な上訴(控訴又は上告)の期間中は「訴訟の係属する間」に含まれる(民事訴訟法229条、237条、498条参照)。
不服申立て中の換価制限
11 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合には、その国税の徴収のため差し押さえた財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、することができない(通則法105条1項)。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、10の「訴訟の係属する間」と同様に取り扱うものとする。
第91条関係 自動車等の換価前の占有
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車又は建設機械の評価、買受希望者の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
第92条関係 買受人の制限
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。 (1) 通則法第52条((担保の処分))の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法49条、92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局又は税務署に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判)。
第93条関係 修理等の処分
差押財産の修理等
(必要があると認めるとき)
1 法第93条の「必要があると認めるとき」とは、修理等の処分をしなければ買受けを希望する者がないと認められるとき、修理等の処分をすることによって滞納国税に充てるべき額が増加すると認められるとき等をいう。
(滞納者の同意)
2 法第93条の規定による修理等の処分をしようとするときの滞納者の同意は、書面により徴するものとする。この書面の様式は別に定めるところによる。
(修理その他その価額を増加する処分)
3 法第93条の「修理その他その価額を増加する処分」とは、差押財産の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等その処分の結果、その処分に要した費用の額以上にその価額が増加するものをいう。
(修理等の処分の費用)
4 修理等の処分の費用は、滞納処分費として滞納者から徴収する(法136条)。
第2款 公売
第94条関係 公売
公売の原則
1 法第94条第1項の「公売に付さなければならない」とは、差押財産を換価するときは、公売しなければならないことをいう。ただし、法第109条第1項((随意契約による売却))又は第110条((国による買入れ))の規定により、公売に代えて、随意契約による売却又は国による買入れができる場合がある。
公売の方法
(入 札)
2 法第94条第2項の「入札」とは、差押財産を換価しようとする場合において、その財産の買受けの申込者に、各自入札価額その他必要な事項を記載した入札書で買受けの申出をさせ、見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める方法をいう。
(入札の方法)
3 入札には、入札期日において、入札書を徴収職員に提出させた後、開札を行う方法(以下「入札」という。)と入札期間(第95条関係9参照)内に、入札書を徴収職員に提出させて、開札期日に開札を行う方法(以下「期間入札」という。)とがある。
(競り売り)
4 法第94条第2項の「せり売」とは、差押財産を換価しようとする場合において、その財産の買受けの申込者に、口頭等で順次高価な買受けの申出をさせ、見積価額以上の申込者のうち、最高の価額による申込者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める方法をいう。
(期間入札)
5 期間入札の手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、入札と同様である。
第95条 関係公売公告
公売公告の手続
(公売公告)
1 公売公告は、法第95条第1項各号に掲げる事項を記載した別に定める書面により行うものとする。
(公売公告の時期)
2 公売公告は、法第95条第1項の規定により、公売の日(期間入札の場合には、入札書を提出することができる始期の属する日)の前日を第1日として逆算し、10日目に当たる日の前日以前にしなければならない。
なお、上記の10日目に当たる日の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日に公告をするものとする。
(公売公告期間の短縮ができる場合)
3 税務署長は、公売財産が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、法第95条第1項本文の公売公告期間を短縮することができる(法95条1項ただし書)。ただし、法第99条第1項((見積価額の公告))の規定により見積価額の公告をしなければならないときは、その公告期間より短い公売公告期間とすることはできない。
(不相応の保存費)
4 法第95条第1項の「不相応の保存費を要し」とは、公売財産の価額と比べ多額の保存費を要することをいう。例えば、相当量のき損品、半製品等その価額が低廉なもので、これらのものを引き揚げて保管倉庫等に保管するとすれば相当の保存費を要するような場合及び生鮮食料品、腐敗変質するおそれがある化学薬品等で、特殊の保管設備を要し、このため相当高額の保存費を要するような場合がこれに当たる。
(価額を著しく減少するおそれがあるもの)
5 法第95条第1項の「価額を著しく減少するおそれがある」とは、公売財産を速やかに換価しないと、その価額が著しく減少するおそれがあることをいう。例えば、鮮魚、野菜等の生鮮食料品及びクリスマス用品等の季節用品等のようなものを公売する場合がこれに当たる。
(公告の継続)
6 法第95条第1項の公告は、公告をした日から公売する日まで掲示するものとする。したがつて、公告後掲示板等から公告に係る書類等がとれた場合には、速やかに掲示するものとするが、この場合においても、法第95条第1項の10日の期間計算は、通常、当初の公告の掲示日を基準として計算するものとする。
公告をすべき事項
(公売財産の名称等)
7 法第95条第1項第1号の「公売財産の名称、数量、性質及び所在」は、買受希望者が、公売財産を特定することができ、かつ、その現況を把握できる程度に記載する。したがって、例えば、建物につき登記簿上の表示と現況とに著しく差異のある場合には、登記簿上の表示のほか現況を併記する(昭和51.8.30名古屋高決、昭和55.8.6東京高決参照)。
(公売の方法)
8 法第95条第1項第2号の「公売の方法」とは、入札、期間入札又は競り売りの方法をいう(法94条2項)。
なお、入札又は期間入札の場合に、最高価申込者を決定するに際して複数落札入札制(法105条参照)によることとしたときは、その旨を公売公告に記載するものとする。
(公売の日時)
9 法第95条第1項第3号の「公売の日時」とは、入札及び期間入札については、入札書を提出することができる始期から終期までを、競り売りについては、競り売りを開始することができる始期をいう。
なお、期間入札による場合の入札書を提出することができる始期から終期まで(以下「入札期間」という。)については、7日以上で税務署長が相当と認める期間を定める。
(公売の場所)
10 法第95条第1項第3号の「公売の場所」とは、入札又は期間入札については、入札書を提出する場所を、競り売りについては、競り売りを行う場所をいう。
(売却決定の日時)
11 法第95条第1項第4号の「売却決定の日時」とは、売却決定をすることができる始期をいい、この売却決定には、次順位買受申込者に対する売却決定(法113条2項)が含まれる。
(買受代金の納付の期限)
12 法第95条第1項第6号の「買受代金の納付の期限」は、法第115条((買受代金の納付の期限等))の規定により税務署長が定めた期限である(第115条関係4、5参照)。 (注)1 次順位買受申込者に係る買受代金の納付の期限は、法第113条第2項に定める売却決定の日から起算して7目を経過した日となる(法115条1項かつこ書)。
2 法第115条第2項((買受代金の納付の期限の延長))の規定による期限の延長は、公売公告に記載しなければできないものとする。
(一定の資格を要する場合)
13 法第95条第1項第7号の「一定の資格を必要とするとき」とは、公売財産を買い受けるために、法令その他の規定により一定の資格を要する場合をいい、例えば、次に掲げる差押財産の公売については、次に掲げる資格を要することをいう。 (1) たばこ種子専売公社又は耕作者(たばこ専売法11条1項)
(2) たばこ苗専売公社又は耕作者(たばこ専売法12条1項)(耕作者に譲渡するときは、専売公社の許可を要する。同条4項)
(3) かん水塩の製造者(塩専売法1項。専売公社の許可を受けた場合は、塩の製造者以外の者でもよい。)
(4) 大麻(大麻取締法1条に規定する大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)を除く。)大麻取扱者(同法3条1項)
(5) 製造し、又は輸入した毒物(黄りん、ひ(砒)素等の毒物及び劇物取締法別表第1に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)又は劇物(塩酸、硝酸等の同法別表第2に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(同法3条参照)
(6) 覚せい剤(覚せい剤取締法2条に掲げるフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン等をいう。)覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者(同法17条1項)
(7) 麻薬(コカ葉、モルヒネ等の麻薬取締法別表に掲げるものをいう。)麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同法26条1項)
(8) けしがら(あへん法3条に規定するけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。)けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者(同法7条2項)
(その他の要件を要する場合)
14 法第95条第1項第7号の「その他の要件を必要とするとき」とは、公売財産の買受けのために関係官庁の承認、許可を要する場合をいう。例えば、農地又は採草放牧地を公売する場合における当該財産の買受けの申込みをしようとする者は、農業委員会、都道府県知事又は農林水産大臣の買受適格証明書の交付を受けなければならない場合をいう。
(配当を受ける権利者)
15 法第95条第1項第8号の「その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者」とは、法第129条((配当の原則))の規定により、交付要求(参加差押えを含む。)をした者、法第59条第1項後段、第3項又は第4項((損害賠償請求権等への配当))(これらの規定を法71条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権を有する者をいう。
(権利の内容)
16 法第95条第1項第8号の「その内容」とは、債権の元本、利息、弁済期限その他の権利の内容をいい、おおむね、債権現在額申立書(第130条関係1)に記載すべき事項をいう。
(重要と認める事項)
17 法第95条第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項」とは、次に掲げる事項をいうものとする。 (1) 買受人が公売財産の所有権を取得する時期が、法第116条((買受代金の納付の効果))に規定するものと異なる場合は、その事項(鉱業法60条、特許法98条1項、実用新案法26条、意匠法36条)
(2) 公売財産の所有権の移転につき農地法その他法令の規定により関係官庁等の許可、承認等を必要とする場合は、その旨(農地法3条、漁業法26条、公衆電気通信法38条1項等)
(3) 買受人に対抗することができる公売財産上の負担がある場合は、その負担(法124条2項等)
(4) 公売財産の権利の移転について登記を要するものについては、買受代金を納付するほか、一定の期間内に登録免許税額に相当する印紙若しくは現金の領収証書を提出すべき旨(登録免許税法23条)、また、自ら権利移転の手続を行う必要がある場合は、その旨
(5) 開札の日時及び場所
(6) 一括換価の方法により公売する場合は、その旨
(7) 期間入札の方法により公売する場合は、その旨及び期間入札に関し重要と認められる事項
(8) 建物等(土地及びその上にある建物又は立木をいう。以下同じ。)の公売によって、その建物等につき法定地上権(法127条1項、民法388条、立木法5条等)又は法定賃借権(法127条2項)が成立する場合は、その旨
(9) その他、例えば、公売財産の権利移転に伴う危険負担の時期等公売に関して重要と認められる事項
公売公告の掲示等
(税務署の掲示場)
18 法第95条第2項の「税務署の掲示場」とは、公売をする税務署の掲示場をいい、常設公売場の掲示場も含まれる。
(その他の掲示場)
19 法第95条第2項の「その他税務署内の公衆の見やすい場所」とは、税務署内において公衆が自由に出入りでき、かつ、公衆の見やすい場所をいう。
(適当な場所)
20 法第95条第2項の「他の適当な場所」とは、公売財産の所在する市町村の役場の掲示場、その他公売財産につき買受けを希望すると認められる者が集合する場所等公売することを公衆に知らせるのに適当と税務署長が認める場所をいう。
(その他の方法)
21 法第95条第2項の「その他の方法」とは、公売財産につき買受けを希望すると思われる者に知らせるのに適する業界新聞に掲載すること、買受けを希望すると思われる者に勧誘書を送付すること等買受希望者を募るのに適した方法をいう。
第96条関係 公売の通知
質権者等に対する公売の通知
(公売通知書の送違)
1 税務署長は、公売公告をしたときは、法第95条第1項各号(8号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を次に掲げる者に通知しなければならない(法96条1項)。この通知は、別に定める書面により行うものとする。 (1) 滞納者
(2) 公売財産につき交付要求をした者
(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者
(公売に係る国税の額)
2 法第96条第1項の「公売に係る国税の額」とは、公売公告に係る公売財産につき、公売処分の基因となっている国税の額をいう。
(知れている者)
3 法第96条第1項第1号の公売財産につさ交付要求をした者及び第2号の質権等の権利を有する者のうち徴収職員が公売の通知をするに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対しては、公売の通知をしなければならない。
(質権、抵当権、先取特権)
4 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(その他の権利)
5 法第96条第1項第2号の「その他の権利」とは、永小作権、地役権、採石権、仮登記(担保のための仮登記を含む。)に係る権利、法第59条第1項後段若しくは第3項又は第4項((第三者の損害賠償請求権等への配当))(これらの規定を法71条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は前払借賃に係る債権等をいう。 (注)1 法第19条及び第20条((不動産保存の先取特権等の優先等))に規定する先取特権以外の先取特権者は、「その他の権利」を有する者に含まれる。
2 仮差押えの債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする(滞調法逐条通達第11条関係1の(1)等参照)。
3 不動産の使用若しくは収益をする権利の移転又は担保権の移転についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(保全法53条1項)がされている場合において、当該不動産につき公売公告をしたときは、当該仮処分の債権者に対しても法第96条の通知をするものとする。また、不動産に関する権利以外の権利でその権利の処分の制限について登記又は登録を効力発生要件又は対抗要件とするもの(保全法54条)についても同様とする。
4 滞調法の規定による二重差押えに係る差押債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする。
5 動産の共有に係る持分を公売する場合は、他の共有者に対しても、公売の通知をするものとする。
(差押えに対抗できない権利者)
6 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者」には、差押債権者に対抗できないこれらの権利を有する者は含まれない。
債権現在額申立書の提出の催告
(催告すべき者)
7 法第96条第2項の規定により催告しなければならない者は、法第96条第1項各号に掲げる者で、かつ、法第129条第1項第2号から第4号((配当すべき債権))までに掲げる債権を有する者のうち知れている者に限られる(第95条関係15参照)。
(売却決定をする日)
8 法第96条第2項の「売却決定をする日」とは、法第111条((動産等の売却決定))又は第113条((不動産等の売却決定))の規定による売却決定をする日をいう。 (注) 売却決定をする日の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条6号)。
第97条関係 公売の場所
公売をする場所
(公売財産の所在する市町村)
1 法第97条の「公売財産の所在する市町村」とは、公売財産が現に所在する市町村をいう。したがって、公売財産を公売するために税務署等(常設公売場、合同公売場等を含む。以下1において同じ。)に搬入した場合の「公売財産の所在する市町村」とは、税務署等の所在する市町村をいう。
(必要と認めるとき)
2 法第97条の「必要と認めるとき」とは、例えば、公売財産の運搬が困難である場合において、その所在する市町村では適当な買受人が求められないようなとき等公売財産をその所在する市町村で公売することが不適当であると税務署長が認めるときをいう。
第98条関係 見積価額の決定
見積価額の意義
1 法第98条の「見積価額」とは、財産の公売に際し、税務署長が公売財産の客観的な時価を基準とし、公売の特殊性を考慮して見積った価額をいい、公売財産の最低公売価額としての意義を有する(法104条1項参照)。
鑑定人による評価
(必要と認めるとき)
2 法第98条の「必要と認めるとき」とは、公売財産が不動産、船舶、鉱業権、骨とう品、貴金属、特殊機械等である場合において、その価額が高価又は評価困難と認められるとき、公売財産の見積価額について紛争を生ずるおそれがあると認められるとき等税務署長が鑑定人に評価させることが適当であると認めるときをいう。
(鑑定人の評価と見積価額の決定との関係)
3 法第98条の「その評価額を参考とすることができる」とは、単純に、鑑定人の評価額をもって見積価額とすることなく、税務署長が、その評価額を参考として見積価額を決定することをいう。
第99条関係 見積価額の公告等
見積価額の公告
1 税務署長は、法第99条第1項各号に掲げる財産を公売に付するときは、それぞれ同項各号に掲げる日までに、見積価額を公告しなければならない(法99条1項、3項本文、95条2項)。ただし、公売財産が動産である場合には、その財産に見積価額を記載した用紙をちよう付して、この公告に代えることができる(法99条3項ただし書)。これらの見積価額の公告の方法については、別に定めるところによる。
見積価額の公告の時期
(3日前の日)
2 法第99条第1項第1号の規定による見積価額の公告は、公売の日の前日を第1日として逆算して3日前に当たる日の前日以前にしなければならない。
なお、上記の「前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日に公告する取扱いとする。
(前日等)
3 法第99条第1項第2号及び第3号の「公売の日の前日」までに公告しなければならないとは、公売の日の前日に当たる日のうちには、公告しなければならないことをいい、また、第2号の「公売の日」までに公告しなければならないとは、公売する時前までに公告しなければならないことをいい、これらの日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条5号)。
(期間入札による場合)
4 期間入札の方法により公売を行う場合における法第99条第1項に規定する「公売の日」は、入札期間の始期の属する日をいう。
見積価額の公告の方法
5 見積価額の公告は、公売公告と併せて行っても差し支えないものとする。
不動産等についての賃借権等の公告
(公告すべき事項)
6 法第99条第4項の「その存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容」とは、公売により財産を買い受けようとする者がその財産を評価するに当たって重要と認められる事項とし、前払いの借賃若しくは地代又は敷金があるときは、これらに関する事項を含むものとする。
(公売公告との関係)
7 法第99条第4項の規定により公告すべき事項を公売公告と同時に公告した後見積価額の公告をする場合には、重ねて、法第99条第4項の規定による公告をする必要はないものとする。
見積価額を公告しない場合
(公売をする場所)
8 法第99条第2項の「公売をする場所」とは、入札をする場所であって、入札者が、見積価額を記載した書面の入っている封筒の状況を見ることができる場所をいう。
(開札後の非公開)
9 見積価額を公告しない場合には、開札後であっても、見積価額を公開しないものとする。
第100条関係 公売保証金
公売保証金の納付に使用できる小切手
(小切手)
1 法第100条第1項の「国税の納付に使用することができる小切手」とは、証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律に基づき租税及び歳入の納付に使用できる証券のうちの小切手をいうが、このうち呈示期間の満了までに5日以上の期間のないものは、受領を拒否することができるものとする(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件1条2項、執行規則40条1項2号、3号参照)。
(銀 行)
2 法第100条第1項の「銀行」とは、銀行法に基づく銀行をいうが、相互銀行、信用金庫及び郵便局を含むものとして取り扱う。
(銀行振出のもの)
3 法第100条第1項の「銀行の振出に係るもの」とは、銀行が振り出した小切手で、その銀行にあてたもの(いわゆる預金小切手)をいう。
(支払保証のあるもの)
4 法第100条第1項の「その支払保証のあるもの」とは、小切手法第53条(支払保証の方式)の規定により、支払人である銀行が支払保証をしたものをいう。
公売保証金の買受代金への充当
5 公売保証金を買受代金へ充てるのは、買受人の意思表示によるが(法100条3項本文)、その充てた場合における買受代金への納付の効果は、買受代金のうち、買受代金へ充てた公売保証金を控除した額の全額の納付があった時に生ずるものとする。
公売保証金の国税への充当等
(充てる場合)
6 法第100条第3項ただし書の規定により、公売保証金を公売に係る国税に充てることができるのは、その公売財産の買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないために、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定によって売却決定が取り消された場合である。
なお、法第108条第2項((最高価申込者とする決定等の取消し))の規定により最高価申込者とする決定の取消し等の処分ができる場合には(同条1項4号参照)、法第100条第3項ただし書の規定を適用しないものとする(第108条関係24参照)。
(公売に係る国税)
7 法第100条第3項ただし書の「公売に係る国税」とは、公売保証金の納付を受けた公売処分の執行の基礎となった国税をいい、交付要求に係る国税等へは充てることができない。
(残余金を交付すべき者)
8 法第100条第3項ただし書の「滞納者」とは、公売の基因となった国税を滞納していた者(譲渡担保権者及び物上保証人を含む。)であって、公売財産の差押え時における権利者をいう。
(滞納者への通知)
9 法第100条第3項ただし書の規定により公売保証金を国税へ充てた場合及びその残余を滞納者に交付すべき場合には、その旨を滞納者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
公売保証金の返還
(法第105条第2項との関係)
10 法第105条第2項((複数落札入札において入札がなかったものとされる場合))の規定により入札がなかったものとされた場合において、入札がなかったものとされた者が納付した公売保証金があるときは、入札がなかったものとされた入札数量に相当するその公売保証金について、法第100条第4項第1号に該当したときの公売保証金と同様に取り扱う。
(その他の理由により最高価申込者を定めることができなかった場合)
11 法第100条第4項第2号の「その他の理由により最高価申込者を定めることができなかった場合」には、例えば、換価制限に関する規定(法90条3項、通則法105条1項ただし書等)に該当し、公売をとりやめた場合、災害その他やむを得ない事情により公売財産の入札等(公売財産の入札又は競り売りに係る買受けの申込みをいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「入札者等」という。)の全員について入札等がなかった場合等がある。
(法第108条第3項との関係)
12 法第108条第3項((公売保証金の国庫帰属))の規定によって公売保証金が国庫に帰属する場合には、法第100条第4項の規定は適用されず(法108条3項後段、第108条関係23)、したがって、公売保証金は返還しない。
(法第117条との関係)
13 換価財産に係る国税が完納され、最高価申込者の決定を取り消した場合(第104条関係6)には、最高価申込者が納付した公売保証金は、遅滞なく返還する(法100条4項5号参照)。
第101条関係 入札及び開札
入札書の提出
(入札書の記載)
1 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項(例えば、種類、員数、売却区分等)を入札書に記載しなければならない(法101条1項)。入札書の様式については、別に定めるところによる。
(期間入札による場合)
2 期間入札による場合の入札書の提出は、入札書を開札の日時を記載した封筒に入れて封をし、これを徴収職員に提出する方法により行う。
(提 出)
3 入札をしようとする者は、税務署長が指定した時間内又は入札期間内に、入札書を徴収職員に提出しなければならない(法101条1項参照)。
(二重入札)
4 入札をしようとする者が、一つの公売財産について複数の入札書を提出した場合には、いずれの入札書も無効なものとする。
入札書の引換え等の禁止
(引換え)
5 法第101条第2項の「引換」とは、入札者が既に徴収職員に差し出した入札書と引換えに、新たな入札書を差し出すことをいう。
(変 更)
6 法第101条第2項の「変更」とは、入札価額又は入札者名を変更する等既に徴収職員に差し出した入札書の記載事項の全部又は一部を改変することをいう。
(取消し)
7 法第101条第2項の「取消」とは、既に徴収職員に差し出した入札書による入札を取り消す旨の意思を表示することをいう。
開札及び立会い
(開 札)
8 徴収職員は、入札書の提出を締め切った後、公売公告に記載した開札の場所及び日時において入札書を開かなければならない。
(立会い)
9 徴収職員は、次により立会人を置き、その面前で開札を行わなければならない(法101条3項参照)。 (1) 開札の場所に入札者がいるときは、その1人以上の入札者
(2) 開札の場所に入札者がいないとき又は立会いに応じないときは、税務署所属の他の職員
第102条関係 再度入札
再度入札
(再度入札ができる場合)
1 再度入札ができる場合は、入札の方法により公売財産を公売する場合において、入札者がないとき又は見積価額に達した入札価額の入札がないときに限る(法102条前段)。
なお、法第108条第2項((公売実施の適正化のための措置))の規定により、入札がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条((入札又は競り売りの終了の告知等))の規定による入札終了の告知をしている場合を除き、再度入札ができる。
(公売保証金との関係)
2 再度入札の場合においては、先に納付した公売保証金を再度入札の公売保証金とするものとする。
なお、再度入札に参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に納付した公売保証金を払い渡さなければならない(法100条4項2号)。
第103条関係 競り売り
競り売りの方法
(買受申込みの催告)
1 徴収職員は、競り売りをしようとするときは、公売をしようとする財産を指定して、買受けの申込みを催告し、順次申込価額を競り上げさせるよう促すものとする(法103条1項参照)。
(買受けの申込みをした者)
2 買受けの申込みをした者は、より高額の買受けの申込みがあるまで、その申込価額に拘束される(執行規則50条2項参照)。
(競り売り人を選任した場合)
3 法第103条第2項の規定により競り売り人に競り売りをさせる場合においても、徴収職員が必ず競り売りの場所に立ち会うものとする。 (注) 競り売り人を選任して競り売りを取り扱わせた場合においても、徴収職員が最高価申込者を決定しなければならない(法104条1項)。
再度競り売り
(再度競り売りができる場合)
4 再度競り売りができる場合は、競り売りの方法により差押財産を公売する場合において、買受申込者がないときに限る(法103条3項、法102条)。
なお、法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定により、入札等がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定による競り売りの終了の告知をしている場合を除き、再度競り売りができる。
(公売保証金との関係)
5 再度競り売りの場合においては、先に納付した公売保証金を再度競り売りの公売保証金とするものとする。
なお、再度競り売りに参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に納付した公売保証金を払い渡さなければならない(法100条4項2号)。
第104条関係 最高価申込者の決定
最高価申込者の決定
(売却区分ごとの決定)
1 最高価申込者は、公売財産の売却区分ごとに決定する。したがって、一括入札を売却条件とした場合には、一括入札価額により最高価申込者を決定し、個別売却とした場合には、個別の入札価額により最高価申込者を決定する。 (注) 競り売りの場合において、買受申込価額が最高であるかどうかの決定は、順次買受申込価額を競り上げ、最後の最高価額を3回呼び上げて、それ以上の高価の買受申込みのない場合に、その価額を最高の価額とするものとする(執行規則50条3項参照)。
(決定の条件)
2 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、最高価申込者とする決定をしないものとする(法104条1項参照)。 (1) 最高価申込者とする決定をしようとする者の入札価額又は買受申込価額が見積価額以上であり、かつ、最高の価額であること。
(2) 公売保証金を納付させる場合においては、所定の公売保証金を納付していること。
(3) 法第92条((買受人の制限))又は第108条((公売実施の適正化のための措置))等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。
(4) 法第95条第1項第7号((公売公告の記載事項))の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
追加入札等
(追加入札等をする場合)
3 開札又は競り売りの結果、最高価申込者となるべき者が2人以上あるときは、更に入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下第104条関係において「追加入札等」という。)をさせなければならない(法104条2項)。この場合の追加入札等の申込価額は、その追加入札等の基因となった入札等の価額以上でなければならない。
(法第108条との関係)
4 追加入札等をすべき者が追加入札等をしなかった場合又はその追加入札等の基因となった入札等の価額に満たない価額で追加入札等をした場合は、法第108条((公売実施の適正化のための措置))の規定が適用されることがある。
(くじによる決定)
5 追加入札等の結果、なおその追加入札等の価額が同額の場合は、抽せんにより当せんした者を最高価申込者として決定する(法104条2項)。この場合における抽せんは、これらの者が直接抽せんをすることができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法(例えば、宝くじの抽せん方法類似のもの)により抽せんを行うものとする。
国税の完納による最高価申込者の決定の取消し
6 公売財産に係る国税の完納の事実が、最高価申込者の決定後、売却決定までの間に確認されたときは、その最高価申込者の決定を取り消すものとする。
第104条の2関係 次順位買受申込者の決定
公売保証金の不徴収との関係
1 公売保証金の納付を要しないこととして公売する場合(法100条1項ただし書)には、最高の価額の入札者が2人以上あり、くじで最高価申込者を定めた場合に限り次順位買受申込者制度が適用される。
次順位による買受けの申込み
(申込みの催告)
2 最高価申込者の決定をした場合には、徴収職員は、最高入札価額に次く高い価額による入札者に対し、次順位による買受けの申込みの催告をするものとする。
(申込みの方法)
3 次順位による買受けの申込みは、既に徴収職員に提出している入札書の余白に、その旨を明らかにさせる方法により行わせる。
なお、この申込みは、2の申込みの催告前にすることはできない。
次順位買受申込者の決定
(決定の条件)
4 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、次順位買受申込者として決定をしないものとする(法104条の2第1項参照)。 (1) 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。)であること。
(2) 公売保証金を納付させる場合においては、所定の公売保証金を納付していること。
(3) 法第92条((買受人の制限))又は第108条((公売実施の適正化のための措置))等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。
(4) 法第95条第1項第7号((公売公告の記載事項))の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
(くじによる決定)
5 最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2人以上あり、これらの者から次順位による買受けの申込みがある場合は、抽せんにより当せんした者を次順位買受申込者として決定する(法104条の2第3項)。これらの場合における抽せんは、これらの者が直接抽せんすることができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法(例えば、宝くじの抽せん方法類似のもの)により抽せんを行うものとする。
第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
複数落札入札制
(意 義)
1 種類及び価額が同じ財産(例えば、同一銘柄、同一規格の商品又は同一銘柄の証券、社債等の有価証券)を一時に多量に入札の方法により公売する場合においては、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる(法105条1項前段)。
(最高価申込者の決定方法)
2 複数落札入札制による最高価申込者の決定は、次による。 (1) 入札は、公売財産の数量の範囲内において、入札しようとする者の希望する買受数量及び単価を入札書に記載して行わせる(法105条1項前段)。
(2) 見積価額は、単価について定める(法105条1項前段、106条1項参照)。
(3) 最高価申込者の決定は、見積価額以上の価額の入札者のうち、高額の入札者から順次にその財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とすることにより行う(法105条1項前段)。
(4) (3)により最高価申込者を決定する場合において、同価の入札者が2人以上あったときは、入札数量の多い者を先順位の入札者とし、また入札数量が同量であったときはくじにより先順位の入札者を定める(法105条1項後段)。
(5) (3)により最高価申込者を決定する場合において、最後の順位の最高価申込者の入札数量が他の最高価申込者の数量と併せて公売財産の数量を超えるときは、その超える入札数量については入札がなかったものとする(法105条2項)。
(6) 最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内で、(5)により入札がなかったものとされた入札数量について入札があったものとする。この場合において、買受代金を納付しない買受人に(5)により入札がなかったものとされた入札数量があるときは、その入札数量は除かれる(法105条3項前段)。
(7) (6)によって最高価申込者を決定しても、なお公売財産に残余を生ずるときは、(4)により最高価申込者とならなかった者を最高価申込者とする(法105条3項前段)。
(8) (7)により最高価申込者の決定をする場合において、(4)により最高価申込者とならなかった者が2人以上あるときは、(4)に準じてその順位を決定する(法105条3項後段)。
(9) (8)により最高価申込者を決定する場合において、最後の順位の最高価申込者の入札数量が他の最高価申込者の数量と併せて公売財産の数量を超えるときは、(5)に準ずる(法105条3項後段)。
公売保証金との関係
3 2の(4)から(9)までに掲げる場合において入札数量の一部についてだけ入札があったものとされた者は、数量の不足を理由として、買受けの申込みを取り消すことはできない(第100条関係10参照)。
第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
入札又は競り売りの終了の告知
(氏名及び価額の呼び上げ)
1 最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を決定したときは、直ちにその氏名及び入札等の価額を呼び上げなければならない。ただし、複数落札入札制による場合には、最高価申込者のすべての氏名並びにその数量及び単価を呼び上げなければならない(法106条1項)。
(終了の告知)
2 徴収職員は、1の呼び上げ後、入札又は競り売りの終了を、口頭又は掲示等により、告知しなければならない(法106条1項)。この場合において、口頭による告知は、その入札又は競り売りを終了する旨を発言する程度で足りる(法106条1項)。
終了の通知及び公告
(通知及び公告)
3 入札又は競り売りの終了を告知した場合において、公売した財産が不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)であるときは、税務署長は、遅滞なく、最高価申込者等の氏名、その価額(複数落札入札制による場合は、その数量及び単価)並びに売却決定をする日時(法113条2項に定める日時を含む。)及び場所を、滞納者及び法第96条第1項各号((公売の通知))に掲げる者(以下「利害関係人」という。)で知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない(法106条2項)。この通知及び公告は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(通知の相手方)
4 法第106条第2項の通知は、次に掲げるすべての者に対してしなければならない(法106条2項)。 (1) 滞納者
(2) 公売財産につき交付要求をした者
(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者
(公告の期間)
5 法第106条第2項の公告の期間は、法第113条((不動産等の売却決定))に規定する売却決定期日までとするものとする。
第107条関係 再公売
再公売ができる場合
1 税務署長は、次のいずれか一つに該当する場合においては、同一の財産を更に公売に付する(法107条1項参照)。 (1) 公売に付しても入札者等がないとき。
(2) 入札等の価額のうち見積価額に達するものがないとき。
(3) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第108条第2項((公売実施の適正化のための措置))の規定により、入札等がなかったものとされ、又は最高価申込者とする決定が取り消されたことによって、売却決定を取り消したとき。
(4) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定により、売却決定を取り消したとき。
(5) 次順位買受申込者に対して売却決定をした場合において、法第115条第4項((売却決定の取消し))の規定により、売却決定を取り消したとき。
再公売の手続
(その他の公売条件の変更)
2 法第107条第2項の「その他公売の条件の変更」とは、公売の場所、公売の方法、売却区分、公売保証金の額等につき、公売財産の状況等に応じて、直前の公売における売却条件を変更することをいう。
(期間入札による場合)
3 期間入札の方法により公売を行った場合における法第107条第3項の「公売期日」は、入札期間の始期の属する日をいう。
(見積価額の公告期間の短縮)
4 再公売に付する場合において、公売財産が、不動産、船舶又は航空機である場合は、公売の日の前日までに見積価額を公告する(法107条4項)。
なお、上記の場合における「公売の日の前日」は、第99条関係3と同様である。
第108条関係 公売実施の適正化のための措置
公売参加の制限を受ける者
(制限を受ける者の範囲)
1 法第108条第1項の規定により公売への参加を制限させる者は、次に掲げる者である。 (1) 法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者
(2) 法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を、使用人その他の従業者として使用する者。この場合における「使用人その他の従業者」とは、事務員、工員、よう人その他雇用契約等に基づき従業している者をいう。
(3) (1)及び(2)に掲げる者を、入札等の代理人とする者
(公売への参加を妨げた者)
2 法第108条第1項第1号の「公売への参加を妨げた者」とは、公売が中止又は延期されたと偽り他の者をして公売に参加させなかった者、公売に参加すれば暴行を加えると脅迫した者、公売の場所への入場を威力をもって妨げた者等をいう。この場合においては、妨害の結果として、妨害を受けた者が公売に参加したかどうかを問わない。
(入札等を妨げた者)
3 法第108条第1項第1号の「入札等を妨げた者」とは、入札に当たって入札書の記載を妨げた者、大声を発して競り売りについての買受けの申込みを妨げた者等をいう。
(最高価申込者等の決定を妨げた者)
4 法第108条第1項第1号の「最高価申込者等の決定を妨げた者」とは、徴収職員に暴行を加えて最高価申込者等の決定を妨げた者、最高価申込者等を定めるための「くじ」(法104条2項、104条の2第3項、105条1項後段、同条3項参照)を引く者を脅迫して「くじ」に参加させなかった者等をいう。
(買受代金の納付を妨げた者)
5 法第108条第1項第1号の「買受代金の納付を妨げた者」とは、買受代金を納付すれば暴行を加えると脅迫した者、買受代金を納付することが極めて不利益であると欺いた者等をいう。
(不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者)
6 法第108条第1項第2号の「不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者」とは、公売に際し、価額を引き下げるため、競争による公正な価額の形成を妨げる意思をもって、入札等を行う者相互間で、ある価額以上の入札を行わず、ある特定の者に低額で買い受けさせるように合意約定した者をいう。
なお、上記の場合においては、利益の一部に相当する金額を配分することが多いと考えられるが、その合意約定について利益配分の目的がないとき及び現実の入札等がなく単に合意約定したにとどまるときにおいても、上記に該当する。
(偽りの名義で買受申込みをした者)
7 法第108条第1項第3号の「偽りの名義で買受申込みをした者」には、架空の人物の名義を用いた者だけではなく、実在する他の人物の名義を勝手に用いて、買受申込みをした者も含まれる。
(正当な理由)
8 法第108条第1項第4号の「正当な理由」とは、換価処分を妨げる意思又は換価処分を妨げる結果となることを知りながら故意に買受代金を納付しないこと以外の理由をいう。
(故意に財産を損傷した者)
9 法第108条第1項第5号の「故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者」とは、公売財産の価額を減少させる意思をもって、財産の形状、性質等をそこなった者はもちろん、その結果を生ずることを知りながら財産を損傷して価額を減少させた者をいい、過失によって公売財産を損傷し、その価額を減少させた者は含まれない。
(公売等の実施を妨げる行為をした者)
10 法第108条第1項第6号の「公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者」とは、法第108条第1項第1号から第5号に該当する者以外の者であって、公売又は随意契約による売却手続が、公正かつ円滑に行われることを妨げた者をいい、例えば、暴力をもって開札を妨げた者、随意契約により買い受けることは不利益であると欺いた者等をいう。
公売への参加制限
(制限の内容)
11 法第108条第1項の規定による公売への参加制限は、公売の場所へ入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことによって行うが、この場合における「公売の場所」とは、入札又は競り売りを実施するための場所、公売財産のある場所等上記の制限をしなければ、公売手続の公正かつ円滑な執行が害される場所をいう。
(制限できる期間)
12 法第108条第1項の規定により公売への参加を制限できる期間は、法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実のあった時から2年間である。
(参加を制限する公売)
13 法第108条第1項の規定による公売への参加制限については、法第108条第1項各号に掲げる者に該当すると認められる事実があったときの公売の後に行われる公売への参加制限はもちろん、その事実があったときの公売のその後の手続への参加も制限することができる。
(入札者等の身分の証明)
14 税務署長は、法第108条第1項の規定による公売への参加制限をするために必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる(法108条4項)。
(刑罰法規との関係)
15 法第108条第1項各号に掲げる者については、刑法第96条ノ3第1項((競売入札妨害))、同条第2項((談合行為))等の刑罰法規による処罰の有無にかかわらず、公売への参加を制限することができる。
最高価申込者の決定の取消し等
(第1項に該当する者)
16 法第108条第2項の「前項の規定に該当する者」とは、法第108条第1項の規定により税務署長が公売への参加制限ができる者をいい、法第108条第1項の規定によって公売への参加を制限したかどうかは関係がない。
(入札者等への通知)
17 税務署長が、法第108条第2項の規定により「入札等がなかったものとする」場合には、その入札者等に対して、原則として、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(最高価申込者等の決定の取消し)
18 法第108条第2項の「その決定を取り消す」とは、最高価申込者等が16に掲げる者である場合には、その最高価申込者等とする決定を取り消すことをいう。この場合においては、19により売却決定を取り消したときを除き、最高価申込者等及び利害関係人(滞納者を含む。)に対してその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(売却決定の取消し)
19 売却決定後において、法第108条第2項の規定により最高価申込者等とする決定を取り消すときは、その売却決定も取り消すものとする。この場合においては、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
公売保証金の国庫帰属
(入札等がなかったものとされた者等)
20 法第108条第3項の「同項の処分を受けた者」とは、法第108条第2項の規定によって入札等がなかったものとされ、又は最高価申込者とする決定を取り消された者をいう。
(国庫に帰属する公売保証金)
21 法第108条第3項の「その公売保証金」とは、20に掲げた者の納付した公売保証金をいうが、法第100条第3項又は第4項((公売保証金の買受代金への充当等))の規定によって公売保証金が既に買受代金納付としての効果を生じているとき(第100条関係5参照)、買受人へ交付されているとき等は、法第108条第3項の規定により国庫に帰属すべき公売保証金はないものとする。
(国庫への帰属)
22 法第108条第3項の「国庫に帰属する」とは、同条第2項の規定によって入札等をなかったものとし、又は最高価申込者等とする決定を取り消した場合には、その処分をした時に、当然に公売保証金が国庫に帰属することをいう。
なお、17から19までに定める通知に当たっては、上記の旨を、併せて通知するものとする。
(法第100条第4項との関係)
23 法第108条第3項の「第100条第4項(公売保証金の返還)の規定は、適用しない」とは、法第108条第3項の規定により公売保証金が国庫に帰属する場合には、法第100条第4項の規定による公売保証金の返還をしないことを明らかにしたものである。
(法第100条第3項との関係)
24 法第108条第1項第4号に該当する者(正当な理由がなく買受代金を納付しない者)の公売保証金が、法第108条第3項の規定により国庫に帰属する場合においては、法第100条第3項ただし書((公売保証金の国税への充当等))の規定により公売保証金を国税へ充てること又はその残余を滞納者に交付することは、行わないものとする(第100条関係6参照)。
第3款 随意契約による売却
第109条関係 随意契約による売却
随意契約の意義
1 法第109条の「随意契約」とは、差押財産の換価に当たり、入札又は競り売りの方法によることなく、税務署長が、買受人及び価額を決定して売却する契約をいう。
随意契約により売却できる場合
(買受人の適格を有する者が1人であるとき)
2 法第109条第1項第1号の「法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人であるとき」とは、たばこ専売法第18条第1項((納付))の規定により耕作者の収穫した葉たばこをすべて専売公社に対して納付しなければならないとされているとき等をいう。
(財産の最高価額が定められているとき)
3 法第109条1項第1号の「その財産の最高価額が定められている場合」とは、物価統制令等の規定に基づいて財産の最高価額が定められている場合をいう。
なお、最高価額が定められている財産を、その価額未満の価額で売却するときは、法第109条第1項第1号には該当しない。
(公益上適当でないと認められるとき)
4 法第109条第1項第1号の「その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき」とは、例えば、次に掲げる場合をいう。 (1) 麻薬取締法等の法令の規定により譲渡の相手方が制限されている場合において、その法令の規定により、譲受けが認められている者に対してその財産を譲渡しようとするとき。
(2) 土地収用法、都市計画法等の規定に基づいて土地を収用できる者から、差し押さえた土地を買い受けたい旨の申出があったとき(大正9.7.23大判、昭和26.10.24高知地判参照)。
(3) 公売財産が私有道路、公園、排水溝、下水処理槽等である場合において、その利用者又は地方公共団体等から、その私有道路等を買い受けたい旨の申出があったとき。
(取引所の相場がある財産)
5 法第109条第1項第2号の「取引所の相場がある財産」とは、証券取引所又は商品取引所における相場のある財産、例えば、株券、社債券、生糸、ゴム、金等(証券取引法2条1項、商品取引所法2条2項、同法施行令1条)をいう。
売却する場合の通知等
(売却の通知)
6 随意契約による売却をする場合には、7の場合を除き、売却をする日の7日前までに、法第96条((公売の通知))に準ずる通知書を発しなければならないが(法109条4項)、この通知等については、第96条関係で定めるところに準ずる。 (注) 上記の「7日前までに通知書を発しなければならない」とは、売却する日の前日を第1日として7日目に当たる日の前日以前に通知書を発しなければならないことをいう。
なお、上記の「7日目に当たる日の前日」が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たるときは、更にその前の日にする取扱いとする。
(通知をしない場合)
7 随意契約による売却をする場合において、その売却の期日が、直前の公売期日又は直前の随意契約による売却の期日から10日以内であるときは、6の通知等をする必要がない(法109条4項、107条3項)。この場合の10日は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。
売却の場所
8 随意契約による売却を行う場所については、法第97条((公売の場所))に準ずるものとする。
見積価額
(見積価額を決定する場合)
9 随意契約により売却する財産については、次に掲げる場合を除き、その財産の見積価額を決定しなければならない(法109条2項前段、98条)。 (1) 最高価額が定められている財産をその価額で売却するとき(3参照)。
(2) 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき(5参照)。
(直前の公売の見積価額との関係)
10 法第109条第1項第3号((公売に付しても入札等がなかった場合等))該当として随意契約により売却する場合における財産の見積価額は、その売却の直前の公売における見積価額と同額又はそれを超える額てなければならない(法109条2項後段)。
(見積価額の決定)
11 随意契約により売却する財産の見積価額の決定については、10の制約があるほか、第98条関係で定めるところに準ずる。 (注) 上記により決定した見積価額は、公告をしなければならないものではない。
公売保証金の不必要
12 差押財産を随意契約により売却する場合には、その売却手続に参加するための公売保証金を納付させることはできない。
あらかじめ公告した価額による売却
13 法第109条第1項第3号((公売に付しても入札等がなかった場合等))該当として随意契約により売却する場合において、その財産が動産であるときは、その売却価額(見積価額以上の額で、売却しようとする価額)をあらかじめ公告し、その価額によって売却(随意契約による売却)することができる(法109条3項)。この場合における公告については、法第99条第3項ただし書((見積価額の公告の特例))の規定の適用があるものとする。
買受人となるべき者の決定の通知及び公告
14 随意契約による売却について、買受人となるべき者を定めた場合には、法第106条第2項及び第3項((最高価申込者等を決定した場合の利害関係人に対する通知及び公告))の規定が準用されるから(法109条4項)、この通知及び公告については、第106条関係3から5までに準ずる。
第110条関係 国による買入れ
農地法等との関係
1 国が農地法第34条((公売の特例))の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条((買入れしよう却))の規定により行う国債の買入れしよう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
第4款 売却決定
第111条関係 動産等の売却決定
売却の決定
(公売をする日)
1 法第111条の「公売をする日」とは、公売により売却する場合には法第95条第1項第3号((公売公告))の「公売の日時」の属する日(期間入札の場合には、入札書を提出することができる終期の属する日)を、随意契約により売却する場合にはその売却する日(以下これらを「公売期日等」という。)を、それぞれいう。
(最高価申込者)
2 法第111条の「最高価申込者」とは、法第104条((最高価申込者の決定))若しくは第105条((複数落札入札制による最高価申込者の決定))の規定により最高価申込者としての決定を受けた者又は随意契約により売却する場合における買受人となるべき者をいう。
(売却決定)
3 法第111条の「売却決定」とは、公売期日等において、2に掲げる者(以下「最高価申込者」という。)に対して、その買受けの申込みをした財産を売却することに決定する処分をいう。
売却決定の効果
4 売却決定は、換価に付した財産について滞納者(法24条の譲渡担保権者、物上保証人等を含む。)と最高価申込者との聞における売買契約成立の効果を生ずる。
第112条関係 動産等の売却決定の取消し
売却決定の取消しと善意の買受人との関係
(善意の買受人)
1 法第112条第1項の「善意の買受人」とは、その換価処分について、買受人が換価困難につき取り消すべき違法又は不当があることを知らずに買受代金を納付して、その換価財産を取得した買受人をいう。
(対抗することができない)
2 法第112条第1項の「対抗することができない」とは、換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消しがあった場合においても、その取消しの効果を、買受代金を納付した善意の買受人に対して主張することができないことをいう。
損害賠償責任
(故意及び過失)
3 法第112条第2項の「故意」とは、自己の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容する心理状態のことをいい、また「過失」とは、一定の事実を認識すべきにかかわらず不注意で認識しないことをいい、軽過失であるか重過失であるかの別を問わない。この場合における故意又は過失の挙証責任は、国が負う。
(通常生ずべき損失)
4 法第112条第2項の「通常生ずべき損失」とは、売却決定の取消しをした財産について、事物自然の成り行きからして普通に生ずべき損害の額をいい、それが通常生ずべきものであるかどうかは、社会通念によって判定するものとする。したがって、特別の事情によって生じた損害は含まれない。
(賠償責任)
5 法第112条第2項の「賠償する責に任ずる」とは、国に故意又は過失がない場合においても、その損害賠償の責めを負うことをいう(国家賠償法1条参照)。
(求償権の行使)
6 法第112条第2項の「求償権の行使」とは、国が損害賠償をした場合において、その損害賠償の基因となる行為が他人の行為による場合には、国がその負担した賠償額の範囲において、その者に対して求償権を行使することをいう。
第113条関係 不動産等の売却決定
売却決定期日
1 法第113条の「起算して7日を経過した日」については、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない(通則令2条6号参照)。
売却決定に伴う処理
2 次順位買受申込者に対し売却決定をした場合には、当該申込者に対し、書面又は口頭によりその旨及び買受代金の納付の期限を通知するものとする。また、公売の通知をした者のうち知れている者についても同様に取り扱うものとする。
なお、上記の書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 上記の書面は、法第118条((売却決定通知書の交付))に規定する売却決定通知書とは異なることに留意する。
第114条関係 買受申込み等の取消し
滞納処分の続行停止
(意 義)
1 法第114条の「滞納処分の続行の停止」とは、一定の事実の発生により、最高価申込者等の決定又は売却決定に続く後行の処分の執行が差し止められることをいう。
(滞納処分の続行の停止があったとき)
2 法第114条の「国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があったとき」とは、換価財産について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、次に掲げる場合に該当するときをいう。 (注) 法第32条第4項((第二次納税義務者の財産の換価の制限))、所得税法第117条((予定納税額の滞納処分の特例))、第118条((予定納税額の徴収猶予))等の規定のように、もともと換価をすることが期待できない場合は、法第114条の規定を適用する余地がない。 (1) 通則法第23条第5項ただし書((更正の請求があった場合の徴収の猶予))の規定により、国税の徴収が猶予されたとき。
(2) 通則法第46条((納税の猶予の要件等))の規定により、国税の納税が猶予されたとき。
(3) 通則法第105条第1項ただし書((不服申立てがあった場合の処分の制限))の規定により、換価ができないこととなったとき。
(4) 行政事件訴訟法第25条第2項本文((執行停止))の規定に基づき滞納処分の続行の停止命令があったとき。
(5) 訴えの提起により法第90条第3項((訴訟係属中の換価の制限))の規定に該当することとなったとき。
(6) 法第50条第3項((換価の制限))の請求財産の換価の申立てがあった場合で、かつ、同項の規定により請求財産の換価ができないときに該当するとき。
(7) 会社更生法第37条第2項((滞納処分等の中止命令))の規定により滞納処分の中止命令があったとき。
(8) 更生手続開始の決定があったとき(会社更生法67条2項)。
(9) 納税の猶予又は換価の猶予が更生計画により認められたとき(会社更生法232条、122条、236条等参照)。
入札等又は買受けの取消しに伴う措置
(取消しの効力の発生と手続等)
3 法第114条の「その入札等又は買受けを取り消すことができる」については、最高価申込者等又は買受人からの入札等又は買受けの取消しの申出により、その効力が生ずるのであるが、これらの申出があった場合には、税務署長は、最高価申込者等の決定の取消し又は売却決定の取消しの手続をとるものとする。この場合において、税務署長は、知れている利害関係人(滞納者を含む。)に対してその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(公売保証金の返還)
4 最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の納付した公売保証金があるときは、遅滞なく、その公売保証金をその納付した者に返還しなければならない(法100条4項3号)。
再公売との関係
5 滞納処分の続行の停止が解除された後においては、その続行の停止に係る公売を前提とする再公売(法107条)をすることはできない。
第5款 代金納付及び権利移転
第115条関係 買受代金の納付の期限等
納付の期限
(売却決定の日)
1 法第115条第1項の「売却決定の日」とは、動産、有価証券又は電話加入権については法第111条((動産等の売却決定))の公売期日等をいい、不動産等については法第113条第1項((不動産等の売却決定))の売却決定期日をいう。
(期 間)
2 法第115条第2項の「期間」は、通則法第10条第1項((期間の計算))の期間に該当する。 (注) 法第115条第2項の規定によって期限を延長するときは、1O日以内の日のうち日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たる日は、指定しないものとする。
(買受人が次順位買受申込者である場合)
3 法第115条第2項の「前項の期限」には、買受人が次順位買受申込者である場合の売却決定の日から起算して7日を経過した日が含まれる(法115条1項)。
(公売公告と期限の延長)
4 法第115条第2項の規定による期限の延長は、必ず公売公告に記載して行う取扱いとする(第95条関係12参照)。
買受代金の納付
(第1項の期限)
5 法第115条第3項及び第4項の「第1項の期限」には、法第115条第2項の規定により延長された期限が含まれる。
(納付の手続)
6 換価財産の買受人は、買受代金に、買受けに係る財産の名称、数量、性質、所在及び買受代金の額を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない(令42条の3)。
売却決定の取消し及び通知
(売却決定の取消し)
7 買受人が買受代金を期限までに納付しないときは、速やかに売却決定を取り消すものとする。ただし、次順位買受申込者が定められていない場合において、期限までに納付できないことの理由がやむをえないものであって、しかもそれが継続しており、かつ、取消しをしな.いでいることが徴収上有利であると認められるときにあっては、相当の期間に限って取消しが遅れても差し支えないものとする。
(取消しの通知)
8 法第115条第4項の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
法第108条との関係
9 法第115条第4項及び法第108条第2項((最高価申込者等とする決定の取消し等))の規定をともに適用することができる場合には、すべて法第108条第2項の規定を適用するものとする。
第116条関係 買受代金の納付の効果
換価財産の取得
1 法第116条第1項の「換価財産を取得する」とは、買受人が滞納者から換価財産を承継的に取得することをいう(第89条関係7参照)。
権利移転の時期
2 換価財産の権利移転の時期は、買受人が買受代金の全額を納付した時である(法116条1項)。
なお、おおむね次に掲げる財産については、それぞれに掲げる要件を満たさなければ権利移転の効力が生じない。 (1) 鉱業権又は特定鉱業権の移転については登録(鉱業法60条、大陸棚特別措置法32条1項1号)
(2) 特許権、実用新案権及び意匠権並びにこれらについての専用実施権の移転については登録(特許法98条1項、実用新案法26条、18条3項、意匠法36条、27条3項)
(3) 商標権及びその専用使用権の移転については登録(商標法35条、30条4項)
(4) 電話加入権の譲渡については、日本電信電話公社の承認(公衆電気通信法38条1項)
(5) 農地又は採草放牧地の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転については、農業委員会の許可(買受人がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地についてこれらの権利を取得する場合には、都道府県知事の許可)(農地法3条1項、4項)
危険負担の移転の時期
3 買受人が買受代金の全額を納付した場合は、その時に換価財産の権利が移転するから、換価財産の換価に伴う危険負担もその時に買受人に移転する。したがって、換価財産の買受人から買受代金の納付を受ける前において、その財産上に生じた危険(例えば、焼失、盗難等)は、滞納者が負担する。また、換価財産の買受人から買受代金の納付があった後において、その財産上に生じた危険は、その財産の登記の手続の既未済又は現実の引渡しの有無にかかわらず、買受人が負担する。
徴収したものとみなす
4 法第116条第2項の「徴収したものとみなす」とは、徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者の換価に係る国税の納税義務を消滅させることをいう。
第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
国税の完納の証明
(国税の完納)
1 法第117条の「国税の完納」とは、換価の基因となっている国税の全額が消滅することをいい、納付、更正の取消し、免除又は還付金等の充当等その消滅の理由のいかんを問わない。
(事実の証明)
2 法第117条の「国税の完納の事実」の証明は、納税者又は第三者から、売却決定をした税務署長に対し、国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面(収納機関がその完納の事実を証する書面)を呈示することによってしなければならない(令43条)。
なお、税務署長は、収納機関から送付された領収済通知書又は領収済報告書により、換価の基因となっている国税の完納の事実が確認できたときは、証明を待つまでもなく、直ちに売却決定を取り消すものとする。
売却決定の取消し
(取消しの通知)
3 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(取消しの効果)
4 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、滞納者と買受人との間の売買契約は、売却決定の時にさかのぼって消滅するから、税務署長は、買受人の納付した公売保証金があるときは、遅滞なく、これを買受人に返還しなければならない(法100条4項5号)。
第118条関係 売却決定通知書の交付
売却決定通知書
1 法第118条の「売却決定通知書」とは、令第44条各号((売却決定通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第9号書式による。
交付しない場合
(動産の場合)
2 動産を換価した場合において、その動産を公売の場所に引き揚げているとき、買受人が占有しているとき、その他直接買受人に引渡しができるとき等売却決定通知書を交付する必要がないと認めるときは、売却決定通知書の交付をしないものとする(法118条ただし書)。
(有価証券の場合)
3 有価証券を換価した場合においては、法第118条の売却決定通知書の交付を要しない(法118条本文)。
第119条関係 動産等の引渡し
引渡しの方法
(徴収職員が占有した場合の引渡し)
1 法第119条第1項の「引き渡さなければならない」とは、換価した動産、有価証券又は自動車若しくは建設機械(徴収職員が占有したものに限る。以下第119条関係において.「動産等」という。)を買受人に現実に引き渡すことをいう。ただし、その動産等を2の者以外の第三者に保管させている場合には、民法第184条((指図による占有の移転))の規定により引き渡すことができる。
(滞納考又は第三者に保管させている場合の引渡し)
2 換価した動産等を、滞納者又は第三者に保管させている場合の引渡しは、売却決定通知書にその引渡しをする旨並びにその引渡しに係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を付記して買受人に交付すること(令45条1項)によって行う(法119条2項前段)。この場合においては、税務署長は、その動産等を保管している滞納者又は第三者に対し、令第45条第2項各号((保管している動産等を引き渡す場合の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、通知しなければならない(法119条2項後段、令45条2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。 (注) 保管者がその動産等の現実の引渡しを拒否しても、国はその現実の引渡しを行う義務を負わない。
第120条関係 有価証券の裏書等
期限の指定
1 法第120条第1項の規定により指定する期限は、換価した有価証券の内容、数量等を考慮して定めるものとする。
なお、記名株式を換価した場合の権利移転の手続は、株券の交付のみで足りるから(商法205条参照)、法第120条に規定する手続をとる必要はない。
税務署長による裏書等
2 滞納者が、法第120条第1項の期限までに、換価した有価証券に係る権利の移転につき必要な手続をとらないときは、税務署長は、滞納者に代わり、次の手続をとるものとする(法120条2項)。 (1) 権利移転につき裏書を必要とする有価証券については、「国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡する」旨をその証券の裏面に記載し、税務署長がこれに署名押印する。
(2) 権利移転につき名義変更を必要とする有価証券については、「公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡したから、国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、名義変更を請求する」旨を記載した書面に、税務署長が署名押印する。 (注) 上記の書面の交付を受けた買受人は、その証券の発行者(名義書換代理人を含む。)に対して名義変更を請求するが、この場合における費用は、買受人の負担とする(法123条)。
第121条関係 権利移転の登記の嘱託
法第121条の規定による場合
(財 産)
1 法第121条の規定により、権利の移転の登記を嘱託する財産は、権利の移転につき登記を要する財産のうち、4及び5によるもの以外の財産、すなわち、鉱業権、特定鉱業権、漁業権、入漁権、ダム使用権、航空機、自動車、特許権、特許実施権、実用新案権、実用新案実施権、意匠権、意匠実施権、商標権、著作権、著作隣接権、出版権、登録公社債等に係る債権等である。
(権利移転の手続)
2 税務署長は、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、権利移転の登記の嘱託書に買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本を添付して、関係機関にその権利の移転の登記を嘱託しなければならない(令46条)。この関係機関は、差押えの登記の嘱託をした関係機関と同様である。
なお、次のことに留意する。 (1) 自動車の権利移転の登録を嘱託するときは、嘱託書に売却決定通知書又はその謄本を添付するほか自動車検査証を呈示しなければならない(道路運送車両法13条3項)。
この場合において、その自動車の使用本拠の位置が変更となり、かつ、買受人の自動車の使用本拠の位置が、自動車の保管場所の確保等の関する法律の適用を受ける地域(同法施行令2条別表参照)内にあるときは、自動車保管場所証明書(自動車の保管場所の確保を証する書面に関する命令1条別記様式参照)を添付しなければならない(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条)。
(2) 買受人が売却決定通知書を紛失等したことにより提出できないときは、税務署長にその再交付を求め、交付を受けた売却決定通知書を提出して登記の嘱託を請求することができる(昭和50,3.28大阪地判参照)。
(消滅する権利との関係)
3 換価に伴い消滅する権利及び換価に係る差押えの登記の抹消の登記の嘱託については、法第125条((換価に伴い消滅する権利の登記のまつ梢の嘱託))に定めるところによる。
不動産登記法等の規定による場合
4 不動産登記法第29条((公売処分による登記))の規定の適用がある場合(不動産とみなされることにより同条の適用がある場合を含む。工場抵当法14条1項、鉱業抵当法3条、漁業財団抵当法6条、道路交通事業抵当法8条、港湾運送事業法26条、立木法2条1項、観光施設財団抵当法8条参照)並びに船舶登記規則第1条((不動産登記法の準用))及び建設機械登記令第9条((不動産登記法の準用))の規定により不動産登記法第29条の規定が準用される場合において、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、税務署長は、次の登記を、それぞれの書類を添付して嘱託しなければならない。 (1) 換価による権利移転の登記買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本
(2) 換価に係る差押えの登記の抹消の登記買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本
(3) 換価により消滅した権利(第89条関係8から13まで参照)の登記の抹消の登記配当計算書の謄本(令46条) (注) 上記の場合における抹消の登記については、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
鉄道抵当法等の規定による場合
5 鉄道抵当法の規定に基づく鉄道財団、軌道財団及び運河財団の権利移転の登記等の嘱託については、4に準じて取り扱う(鉄道抵当法77条ノ2、68条、軌道ノ抵当ニ関スル法律1条、運河法13条、法121条)。
第122条関係 債権等の権利移転の手続
換価した債権等の権利移転の手続
(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項((債権の換価))の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法122条1項。第118条関係1参照)。
第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
権利移転に伴う費用
(有価証券の代位裏書等の費用)
1 法第123条の「第120条第2項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用」とは、換価した有価証券の名義変更手数料等、名義の変更に伴って生ずる費用等をいう。
(登録免許税)
2 法第123条の「第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税」とは、権利移転の登記の嘱託により登記を受ける場合に納付すべき登録免許税をいう(登録免許税法2条参照)。
(その他の費用)
3 法第123条の「その他の費用」とは、所有権移転登記の嘱託書を郵送する場合の郵送料等をいう。
買受人の負担
4 法第123条の「買受人の負担とする」とは、1から3までに掲げる費用は、買受人が前払いしなければならないことをいう。
第124条関係 担保権の消滅又は引受け
担保権等の消滅
(先取特権)
1 法第124条第1項の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権、先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。また、同項の「先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいう(法50条1項参照)。
(担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利)
2 法第124条第1項の「担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利」とは、担保のための仮登記のある財産が滞納処分により差し押さえられた後、仮登記担保契約に基づく本登記をしたものに係る権利をいう。 (注) 担保のための仮登録のある財産が、不動産登記法の適用又は準用のない財産である場合には、利害関係人の承諾を要しないで仮登録に基づく本登録をすることができる。
(再売買の予約の仮登記)
3 法第124条の「再売買の予約の仮登記」とは、再売買の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記をいう。
(担保権が消滅しない場合)
4 法第124条第2項の規定による担保権の引受けがあった場合は、その担保権については、法第124条第1項の規定は適用されず(法124条2項後段)、したがって、その担保権は消滅しない。
担保権の引受け
(登記されている先取特権)
5 法第124条第2項の「先取特権」とは、法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいうが、法第124条第2項の規定による引受けができる先取特権は、そのうちの登記をしているものに限られる。
(負担の引受け)
6 法第124条第2項の「負担を買受人に引き受けさせる」とは、法第124条第2項の担保権のある財産の換価に当たって、その担保権を消滅させず、その担保権の負担のある財産として買受人に売却することをいう。
(国税が劣後するとき)
7 法第124条第2項第1号の「次いで徴収するものであるとき」とは、差押国税のうち、法第10条((直接の滞納処分費の優先))の規定の適用を受ける滞納処分費を除いた国税の全額が、法第124条第2項の担保権に劣後するとき(法15条から20条まで参照)をいうものとする。
(担保権者の申出)
8 法第124条第2項第3号の「申出」は、令第47条((担保権の引受けによる換価の申出))の規定により、同条各号に掲げる事項を記載した書面をもって公売公告の日又は随意契約により売却する日の前日までに、しなければならない。この場合において、その申出の期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令に定める日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条7号)。
(引受けを認めない場合)
9 法第124条第2項各号のすべてに該当する場合であっても、次に掲げるときは、担保権の引受けをさせないものとする。 (1) 最も先順位の担保権に対抗できない用益物権、賃借権等の権利があるとき。
(2) 仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権であるとき。
(3) 担保権の引受けをさせることとした場合には見積価額の決定に煩さな手続を要すると認められるときその他税務署長が担保権の引受けをさせることが徴収上適当でないと認めるとき。
第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
消滅する権利の抹消の登記の嘱託
(嘱託をする場合)
1 法第125条の規定による抹消の登記の嘱託は、法第121条((権利移転の登記の嘱託))の規定により権利移転の登記を嘱託する場合に行うものであり、不動産登記法その他の法令に別段の定めがあるときは、これらの規定に基づいて抹消の登記を嘱託する(第121条関係4、5参照)。
なお、法第125条の関係機関については、第121条関係2と同様である。
(消滅する権利)
2 法第125条の「換価に伴い消滅する権利に係る登記」とは、法第124条((担保権の消滅又は引受け))の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等(第89条関係8から13まで参照)に係る登記及び差押え(参加差押えを含む。)の登記をいう。 (注) 滞調法の規定により二重差押えがされた不動産、船舶、航空機、自動車、建設機関、債権又はその他の財産権を滞納処分により換価し、権利移転の登記をしたときは、強制執行による差押えの登記は、登記官により職権で抹消される(滞調法16条、19条、20条、20条の8、20条の11、滞調令12条の2、12条の3、12条の10)。
(嘱託書の添付書類)
3 法第125条に規定する換価に伴い消滅する権利(差押えを含む。)に係る登記の抹消の登記の嘱託をする場合には、嘱託書に配当計算書(法131条参照)の謄本を添付しなければならない(令46条)。
登録免許税の非課税
4 法第125条の規定により抹消の登記の嘱託をする場合には、登録免許税法第5条第11号((滞納処分に関する登記等の非課税))の規定により、登録免許税は課されない。
第126条関係 担保責任
民法第568条の規定の準用
(民法第568条第1項の規定の準用)
1 差押財産を換価した場合において、民法第561条本文((売主の担保責任))、第563条第1項若しくは第2項((権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任))、第565条((数量の不足又は物の一部滅失の場合の売主の担保責任))又は第566条第1項若しくは第2項((用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任))に規定する場合に該当する場合があるときは、その財産の買受人は、これらの規定に準じ、滞納者に対してその契約を解除し、又は買受代金の減額を請求することができる。この場合における買受人の権利の行使については、同法第564条((権利行使の除斥期間))及び第566条第3項((権利行使の除斥期限))の規定が準用される。
(民法第568条第2項の規定の準用)
2 1の場合において、滞納者が無資力であるときは、換価財産の買受人は、換価代金等の配当を受けた債権者に対して、買受代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法568条2項)。この場合における請求は、滞納者に対して解除権又は買受代金減額請求権を行使した上で、滞納者が無資力であることを証明したときにすることができる(大正8.5.3大判)。
(民法第568条第3項の規定の準用)
3 1又は2の場合において、滞納者が当初から物又は権利のけんけつ(欠缺)を知っていながらこれを申し出なかったときは、換価財産の買受人は、滞納者に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法568条3項)。
第127条関係 法定地上権等の設定
法定地上権
(成立要件)
1 法第127条第1項の「地上権が設定されたものとみなす」とは、法第127条第1項の規定により、設定契約を締結しなくても、法律上当然に地上権が成立することをいう。
なお、上記の地上権の成立については、次のことに留意する。 (1) 滞納者の所有に属する土地若しくは建物等に抵当権の設定があり、その後滞納処分による差押え及び換価をした場合において、民法第388条((法定地上権))、立木法第5条((法定地上権))、工場抵当法第16条第1項((民法388条の準用))等の規定の類推適用(昭和37.9.4最高判参照)によって法定地上権が成立するときは、法第127条の法定地上権は成立しない。
(2) 差押えの当初から滞納者所有の土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。差押えの当初から滞納者所有の土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。 (注) 土地を差し押さえた時に建物が存在し、その後にその土地の上の建物が滅失(取壊し、焼失等)して再築された場合でも、法定地上権は成立する(昭和10.8.10大判参照)。
(3) 土地と建物等との所有者を異にするに至ったことの理由が換価であることを要する。
(地上権の及ぶ範囲)
2 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権は、建物等の利用に必要かつ十分な程度の広さに及ぶ(大正9.5.5大判、昭和35.12.15大阪高判参照)。
(法定地上権の対抗力)
3 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の対抗力は、次のとおりである。 (1) 土地を換価し、地上権が設定されたものとみなされた場合には、建物等の所有者である滞納者がその地上権を土地の買受人以外の第三者に対抗するためには、地上権の登記又は建物等の登記があることが必要である(民法177条、建物保護二関スル法律1条、昭和8.12.23大判参照)。
なお、滞納者は、土地の買受人に対しては、なんらの手続を要せず、法定地上権を主張することができる。
(2) 建物等を換価し、地上権が設定されたものとみなされた場合には、建物等の買受人がその地上権を第三者に対抗するためには、地上権の登記又は建物等の取得の登記をすることが必要である(民法177条、建物保護二関スル法律1条、昭和8.12.23大判参照)。なお、買受人は、土地の所有者である滞納者に対しては、なんらの手続を要せず、法定地上権を主張することができる。
(存続期間)
4 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の存続期間は、まず当事者の協議によって定まるのであるが、協議が調わない場合には、法第127条第3項の規定により、当事者の請求によって裁判所がこれを定める。この場合において、建物の地上権の存続期間については、借地法の規定の適用がある(同法2条1項参照)。
(地 代)
5 法第127条第1項の規定により地上権が設定されたものとみなされた場合におけるその地上権の地代は、まず当事者の協議によって定まるが、協議が調わない場合には、法第127条第3項の規定により、当事者の請求によって裁判所がこれを定める。
法定賃借権
(地上権の存続期間)
6 法第127条第2項の「地上権の存続期間」とは、次に掲げる期間をいう。 (1) 建物所有を目的とする地上権に基づいてその土地の上に存在する建物については、借地権設定契約に存続期間の定めがある場合でその存続期間が借地法第2条第2項((借地権の存続期間))の規定に抵触しないものであるときはその期間(同法6条又は7条の規定に該当する場合を除く。)、設定契約に存続期間の定めがない場合においては同法第2条第1項((借地権の存続期間))に規定する存続期間(同法6条又は7条の規定に該当する場合を除く。) (注)1 建物所有を目的とする地上権の設定契約に存続期間の定めがある場合において、その地上権の存続期間を借地法第2条第2項((借地権の存続期間))の存続期間よりも短期とする特約がある場合においては、同法第11条((強行規定))の規定により、その存続期間の定めがなかったものとされる。
2 契約をもって建物所有を目的とする地上権を設定する場合の地上権の存続期間については、借地法第3条((借地権の存続期間))の規定がある。
(2) 立木の所有を目的とする地上権に基づいてその土地の上に存在する立木については、地上権設定契約に存続期間の定めがある場合においてはその期間、設定契約に存続期間の定めがない場合においては民法第268条((地上権の存続期間))に規定する存続期間
(みなし賃貸借)
7 法第127条第2項の「土地の賃貸借をした」ものとみなすとは、法第127条第2項の規定により、設定契約を締結しなくても、法律上当然に賃借権が成立することをいう。
なお、上記の賃借権の成立については、次のことに留意する。 (1) 差押えの当初から滞納者に帰属する地上権の目的となっている土地の上に滞納者所有の建物等が存在していたことを要する。
(2) 地上権者と建物等の所有権者とを異にするに至ったことの理由が換価であることを要する。
(賃借権の及ぶ範囲等)
8 法第127条第2項の規定により賃借権が設定されたものとみなされた場合におけるその賃借権の及ぶ範囲、対抗力、存続期間及び借賃については、それぞれ2から5までに定めるところに準ずる。
第4節 換価代金等の配当
第128条関係 配当すべき金銭
差押財産の売却代金
1 法第128条第1号の「差押財産の売却代金」とは、法第89条((換価する財産の範囲))の規定により公売に付し、又は随意契約により売却(国による買入れを含む。)した差押財産の売却代金をいう。
なお、土地収用法第96条第1項((差押えがある場合の補償金の払渡し))の規定に基づき払渡しを受けた金銭は、上記の売却代金に含まれることに留意する(同法96条2項参照)。
給付を受けた金銭
(有価証券)
2 法第128条第2号の「有価証券」とは、有価証券のうち、法第57条第1項((有価証券に係る債権の取立て))の規定により金銭債権の取立てをしたものをいう。
(債 権)
3 法第128条第2号の「債権」とは、法第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取立てをした債権のうち、金銭債権をいう。
(無体財産権等)
4 法第128条第2号の「無体財産権等」とは、無体財産権等で、法第73条第5項((債権に関する規定の準用))において準用する第67条第1項((差し押さえた債権の取立て))の規定により取立てをしたもののうち、金銭債権に係るものをいう。
(保険金、持分の払戻金等)
5 法第128条第2号の「金銭」には、法第53条第1項((保険に付されている財産に対する差押えの効力))の規定の適用を受ける差押えに基づき給付を受けた金銭及び同法第74条第1項((差し押さえた持分の払戻し等の請求))の規定に基づき給付を受けた金銭が含まれるものとする。
交付要求によリ交付を受けた金銭
6 法第128条第4号の「交付要求により交付を受けた金銭」には、国税につき担保を徴した財産が強制換価手続により換価され交付を受けた金銭及び法第22条第3項((担保権の代位実行))の規定により税務署長が担保権者に代位実行することによって交付を受けた金銭が含まれるものとする。
第129条関係 配当の原則
配当する債権
(質権、抵当権、先取特権)
1 法第129条第1項第3号の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。また、同号の「先取特権」とは、法第19条第1号各号((不動産保存の先取特権等))及び第20条第1項各号((不動産賃貸の先取特権等))に掲げる先取特権をいい、これらの先取特権以外の先取特権は、配当を受けることができない。
(担保権の引受けとの関係)
2 法第124条第2項((担保権の引受け))の規定により質権、抵当権又は先取特権に関する負担を買受人に引き受けさせた場合には、その引受けに係る担保権の被担保債権については、配当をしない。
(損害賠償請求権又は借賃に係る債権)
3 法第129条第1項第4号の「損害賠償請求権又は借賃に係る債権」については、次のことに留意する。 (1) 動産の引渡しを命ぜられた第三者がその動産の差押え時までに法第59条第1項((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))の規定による契約の解除をした旨を通知しないときは、その第三者は、契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権について配当を受けることができない(令25条2項)。ただし、その第三者がその動産の差押え後にその通知をした場合において、相当の理由があると認められるとき(第59条関係6参照)は、この限りでない(令25条3項)。
(2) 参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対して、法第59条第1項又は第3項(同条4項及び71条4項において準用する場合を含む。)の規定により配当を請求することができた権利は、法第87条第2項((参加差押えに係る動産等の引渡し))の規定により参加差押えに係る財産の引渡しがされた場合には、その引渡しを受けた行政機関等に対して行使することができる(令41条3項、4項)。
国税に充てること
(国税に充てたことの効果)
4 法第129条第2項の規定により国税に充てたときは、滞納者の納税義務は、その充てられた範囲において消滅する。
なお、上記の場合には、配当計算書が作成されないので、滞納者に対しては、その充てた旨の通知をするものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
(国税に充てるべき時期)
5 差押財産の売却代金又は有価証券、債権若しくは無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭(以下「換価代金等」という。)又は差押さえた金銭若しくは交付要求により交付を受けた金銭(第128条関係6に規定する金銭を含む。)を国税に充てるべき時期については、次に掲げる時によるものとする。 (1) 差し押さえた金銭については、その差押えの時
(2) 第三債務者等から給付を受けた金銭(第128条関係2から5まで参照)については、その給付を受けた時
(3) 売却代金については、それを受領した時
(4) 交付要求(参加差押えを含む。)により交付を受けた金銭については、その交付を受けた時
滞納者等への交付
(滞納者への交付)
6 法第129条第3項の規定により、滞納者に残余の金銭を交付する場合には、次のことに留意する。 (1) 換価した財産が譲渡担保財産又は物上保証に係るものである場合は、配当した金銭の残余は、譲渡担保権者又は差押え時における担保物の所有者に交付する。
(2) 差押財産が、差押え後に譲渡された場合において、配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、差押え時の所有者である滞納者に交付するものとする(法129条3項、昭和35.1.29大阪高判)。
(交付要求をした国税に係る延滞税の免除)
7 交付要求(参加差押えを含む。)により交付を受けた金銭を国税に充てた場合には、交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の延滞税は、免除する(通則法63条5項4号、通則令26条の2第1号)。この場合において、交付要求が滞調法第36条の10第1項((みなし交付要求))の規定に係るものであるときは、第三債務者が同法第36条の6第1項((第三債務者の供託義務))の規定により供託した日が、上記の「受領した日」に当たるものとして延滞税を免除する。
(破産宣告があった場合等)
8 滞納者に交付すべき金銭は、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる者に交付するものとする。 (1) 滞納者につき破産の宣告がされている場合破産管財人(破産法7条)
(2) 滞納者である株式会社につき更生手続の開始決定があった場合管財人(会社更生法53条)
(3) 会社整理の命令があり、会社財産の管理命令があった場合管理人(商法398条2項)
(4) 滞納者が死亡し、相続人があることが明らかでない場合相続財産管理人(民法953条)
(5) 滞納者である株式会社につき企業担保権の実行手続の開始決定があった場合管財人(企業担保法32条1項)
(6) 滞調法の規定の適用がある場合その執行官又は執行裁判所(同法6条1項、17条等)
(7) 滞納者が不在者(民法25条参照)に該当する場合管理人(同法25条、26条)
(残余金について差押え等があった場合)
9 滞納者に交付すべき残余金額について、差押え等があった場合には、次に定めるところによるものとする。 (1) 執行法の規定による差押命令又は保全法の規定による仮差押命令の送達がされたときは、滞納者に対しては交付しない(執行法145条、保全法50条参照)。
この場合においては、差押え又は仮差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭は供託することができる(執行法156条1項、保全法50条5項)。また、債務者(滞納者)に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、他に競合する債権者がいない場合に限り((3)参照)、その差押債権者に対して交付することになる。 (注)1 上記により供託したときは、その事情を執行裁判所又は保全執行裁判所に届け出なければならない(執行法156条3項、保全法50条5項)。
2 交付又は供託するまでの間は、その金銭は、保管金として処理する(出納官吏事務規程61条参照)。
3 債務者(滞納者)に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したか否かは、送達通知書(執行規則134条)等により確認するものとする。
(2) 執行法の規定による差押命令及び転付命令の送達があった場合には、転付命令の確定(同法159条5項)及びその他の差押命令若しくは仮差押命令の送達又は配当要求がないこと(同法159条3項)を確認した上、この命令を得た債権者に交付する(同法160条参照)。
(3) 差押え若しくは仮差押えが競合し(仮差押えと仮差押えが競合した場合を除く。)、又は配当要求があったときは、その金額の全部又は一部を供託し、その事情を差押命令を発した執行裁判所に届け出なければならない(執行法156条2項、3項、保全法50条5項参照)。
(4) 滞納処分による債権差押えの通知書の送達を受けたときは、差押えをした行政機関等へ交付する(法62条、67条等)。
(5) 滞納者から確定日付のある証書をもって債権譲渡の通知があったときは、その債権の譲受人に交付する(民法467条参照)。
(換価財産について強制執行による差押え等がされている場合)
10 換価財産について、強制執行による差押え等がされている場合には、次に定めるところによる。 (1) 換価財産について、滞納処分による差押え後に強制執行による差押え又は担保権の実行としての競売が開始されている場合には、滞納者に交付すべき残余金は、執行官又は執行裁判所に交付しなければならない(滞調法6条1項、11条の2、17条、19条、20条、20条の8第1項、20条の10、20条の11第1項、滞調令12条の2、12条の3第1項)。
(2) 換価財産について、仮差押えの執行がされている場合には、滞納者に交付すべき残余金は、執行官又は執行裁判所に交付しなければならない(滞調法11条1項、18条2項、19条、20条の9第1項、20条の11第1項、滞調令12条の2、12条の4)。
配 当
(転質又は転抵当がある場合)
11 転質又は転抵当がある場合には、原質又は原抵当によって担保される債権額の範囲内で、その転質又は転抵当により担保される債権額について、まず転質権者又は転抵当権者に配当し、なお配当すべき残余があるときは、次いで原質権者又は原抵当権者に配当する(昭和7.8.29大判)。
なお、転質権者又は転抵当権者には、転質又は転抵当について保全仮登記をした仮処分の債権者が含まれる(第133条3項、令50条4項参照)。
(共同抵当権がある場合)
12 同一債権の担保として数個の財産上に抵当権の設定がある場合(共同抵当の場合)において、その財産を換価したときは、次のことに留意する。 (1) 共同抵当の目的となっている財産の一部について後順位の抵当権がある場合で、その財産の全部を換価したときは、抵当権者に交付すべき金額は、各財産の売却価額(その財産を一括して換価したときは各財産の見積価額によってあん分した価額)に応じて、共同抵当によって担保される債権額をあん分した金額である(民法392条1項)。
(2) 共同抵当の目的となっている財産の一部を換価した場合においては、その換価した財産について後順位の抵当権があるときでも、先順位の抵当権者に交付すべき金額は、担保される債権額の全額である(民法392条2項)。
(抵当権の譲渡等があった場合)
13 抵当権の譲渡等があった場合においては、次のように配当する。
この場合、抵当権の譲渡等を受けた者がその譲渡等を第三者に対抗するためには、付記登記することが必要であるから、付記登記のない場合は、これらの処分はなかったものとして配当する。
また、抵当権の順位の譲渡又は抵当権の順位の放棄についての保全仮登記がされている場合には、保全仮登記がされた抵当権により担保される債権に対して配当を行う(法133条3項、令50条4項参照)。 〔例〕 第1順位抵当権者(甲)の債権の額・・・・・・・・・・・・・4万円
第2順位抵当権者(乙)の債権の額・・・・・・・・・・・・・5万円
第3順位担当権者(丙)の債権の額・・・・・・・・・・・・・8万円
無担保権者(丁)の債権の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
1 甲が丁のために抵当権の譲渡をした場合
丁は甲の債権(4万円)の範囲内で甲の抵当権者としての地位を取得することになり、丁の債権額(6万円)の範囲内で甲が受けるべき債権額が配当され、乙、丙の配当額には影響がない。
したがって、(1)丁に4万円、(2)乙に5万円、(3)丙に2万円(11万円-4万円-5万円)配当される。
2 甲が丙のために抵当権の順位の譲渡をした場合
抵当権の順位の譲渡がないとした場合に丙が受くべき債権額は2万円(11万円-4万円-5万円)であるから、甲の4万円と丙の2万円の合計額6万円の範囲内で丙の債権額に先に配当され、乙の配当額には影響がない。
したがって、(1)丙に6万円、(2)乙に5万円配当される。
3 甲から丁のために抵当権の放棄があった場合
甲は丁に対し優先権を持たなくなるため、甲と丁とは抵当権の放棄がないとした場合に甲が受くべき債権額4万円につき、それぞれの債権額によりあん分して配当され、乙、丙には影響がない。
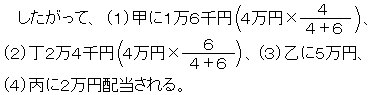
4 甲から丙のために抵当権の順位の放棄があった場合
甲は丙に対し優先権を持たなくなるから、抵当権の順位の譲渡がないとした場合の甲と丙が配当を受くべき債権額6万円(甲の4万円と丙の2万円(11万円-甲の4万円-乙の5万円))について甲・丙それぞれの債権額によりあん分(4:8)して配当され乙には影響がない。
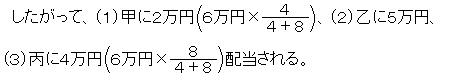
(仮差押えの執行後に担保権が設定された財産を換価した場合)
14 仮差押えの執行後に担保権が設定された財産を差し押さえ、換価した場合において、その配当時に仮差押えに係る本案訴訟の確定判決がない等のため配当額が定まらないときは、その定まらない部分に相当する金銭は供託しなければならない(滞調法34条2項、執行法87条2項、91条1項6号、92条)。この場合において、仮差押えに係る本案訴訟が確定したこと等により、配当額が確定したときの配当手続は、滞調法逐条通達第33条関係8に定めるところによる。
(差押え後に担保権が設定された財産を換価した場合)
15 滞納処分又は強制執行による差押え後に設定した担保権については、配当しないものとする(6の(2)参照)。
ただし、執行停止に係る強制執行による差押え後に登記された担保権については、滞調法逐条通達第33条関係7及び8に定めるところによる。
(担保権の目的となっている財産と、なっていない財産とをともに換価した場合)
16 担保権の目的となっている財産と、なっていない財産とをともに換価した場合において、その担保権の被担保債権が国税に優先しないときは、その担保権の目的となっていない財産の売却代金から順次国税に配当するものとする。
(不動産の共有持分を換価した場合)
17 担保権の設定後に共有となった不動産の共有持分を換価した場合には、担保権者に対しては、担保権の被担保債権に対する共有持分の割合に相当する金額を配当する。 (注) 上記の場合における担保権の登記の抹消は、嘱託書に抹消すべき登記として、「昭和○年○月○日受付第○号担保権設定登記のうち共有者○の持分に対する担保権」と記載する(昭和4.7.24付民第6,250号司法省民事局長回答)
不服申立て等の期限の特例
18 換価代金等の配当処分に対する不服申立て又は訴えの提起については、法第171条第1項又は第2項((滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例))の規定による期限の制限がある。
附帯税等の徴収
19 配当された金銭を国税に充てる場合には、まず徴収の基因となった国税(延滞税、利子税及び加算税を除く。)に充て、その後延滞税、利子税及び加算税に充てるものとする(法129条6項参照)。
なお、配当された金銭を複数の国税のいずれに充てるかは、税務署長の裁量による(大正5.3.9行判)が、この場合においては、民法第488条((当事者の指定による弁済の充当))、第489条第2号及び第3号((法定弁済充当))の規定に準じて処理するものとする。
第130条関係 債権額の確認方法
債権現在額の申立て
(債権現在額申立書)
1 法第130条第1項の「債権現在額申立書」とは、法第129条第1項第2号((配当の原則))に規定する国税、地方税又は公課を徴収する者及び法第129条第1項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者が、配当を受けるために、差押財産を換価した税務署長に提出する書面をいう。
(提出期限)
2 法第130条第1項の「売却決定の日の前日まで」とは、法第111条((動産等の売却決定))又は第113条((不動産等の売却決定))の規定による売却決定の日の前日までをいう。この場合において、その「前日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日に当たっても延長されない(通則法10条2項、通則令2条6号)。
なお、差し押さえた債権等を取り立てた場合の配当に伴う債権現在額申立書については、法第130条第1項の債権を有する者は、その取立ての日までに税務署長に提出しなければならない。この場合において、法第130条第3項に規定する者がその取立ての時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない(令48条2項)。 (注) 次順位買受申込者に対し売却決定をした場合における法第130条第1項の「売却決定の日」は、法第113条第2項各号((次順位買受申込者に対する売却決定))に掲げる日である。
(債権現在額申立書に記載する債権の範囲)
3 法第130条第1項の債権現在額申立書に記載すべき債権現在額は、次のとおりである。この場合におけるその債権の債権現在額とは、その債権の元本、利息、損害金、費用その他附帯する債権額の総額をいう。 (1) 配当を受けるべき債権が国税、地方税又は公課の場合には、換価代金等の受領の時現在における債権現在額
(2) 配当を受けるべき債権が(1)以外の債権の場合には、換価代金等の交付期日現在における債権現在額
債権の確認
(申立書が提出された場合)
4 法第130条第2項前段の規定による債権の確認は、法第130条第1項の規定により提出された債権現在額申立書を形式審査して行うものとする。ただし、法第129条第1項第3号又は第4号((差押財産に係る質権等の被担保債権等))に掲げる債権で国税に優先するものがあるときは、その債権の存否、金額、順位等について実質審査を行い、これを確認するものとする。
(申立書が提出されない場合)
5 法第130条第2項後段の規定による確認は、その債権の存否、金額、順位等について実質審査を行い、これを確認するものとする。ただし、法第130条第2項第1号に掲げる債権のうち国税に優先しないものについては、登記事項を形式審査してこれを確認しても差し支えない。
(知れているもの)
6 法第130条第2項第2号及び第3号の「知れているもの」とは、徴収職員が法第131条((配当計算書))の配当計算書の謄本を発送する時までに知ることができたものをいう。
配当が受けられない場合
7 法第130条第3項の規定の適用を受ける「債権」とは、登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権のうち知れていないもので、かつ、売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を税務署長に提出しないものをいい、その債権は配当を受けることができない。
なお、上記の債権を有する者が法第130条第1項に規定する期限の経過後売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を提出したときにおけるその債権の額の確認は、その提出した債権現在額申立書を実質審査して行うものとする。
第131条関係 配当計算書
配当計算書
1 法第131条の「配当計算書」とは、令第49条第1項各号((配当計算書の記載事項等))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第10号書式による。
配当計算書の記載事項
2 配当計算書に記載する令第49条第1項第3号の「国税の金額」は、換価代金等の受領の時現在における金額をいい、同項第4号の「債権金額」は、換価代金等の交付期日現在における金額をいう(第130条関係3参照)。
配当計算書の謄本の交付
(謄本の発送)
3 配当計算書の謄本は、配当金額がない債権者に対しても、法第131条の規定により、発送しなければならない。
(発送の期限)
4 法第131条の「納付の日から3日以内」及び令第49条第2項((金銭による取立てに係るものの配当計算書の謄本の発送期限))の「取立ての日から3日以内」の「3日」の期間計算については、初日は算入しない(通則法10条1項)。
(第1号に掲げる者)
5 法第131条第1号の「債権現在額申立書を提出した者」とは、法第130条第1項((債権現在額申立書の提出期限))の期限までに債権現在額申立書を提出した者及び同条第3項((債権現在額申立書の提出と配当との関係))に規定する者で、同条第3項の期限までに債権現在額申立書を提出した者をいう。
(滞納者)
6 法第131条第3号の「滞納者」には、法第24条第2項前段((譲渡担保権者に対する告知))の譲渡担保権者が含まれる(法49条)ほか、差押え時における担保財産の所有者を含むものとする。この場合においては、本来の滞納者に対しては、配当された金銭を国税に充てた旨の通知をするものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第132条関係 換価代金等の交付期日
交付期日
(交付期日が休日に当たる場合)
1 法第132条第2項本文の「換価代金等の交付期日」については、その日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令で定める日に当たっても延長されない。
(期間を短縮することができる場合)
2 法第132条第2項ただし書の「前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合」とは、差押えをした国税を有する行政機関、交付要求に係る国税、地方税及び公課を有する行政機関等並びに滞納者以外に配当手続に参加している者がない場合をいう。
なお、法第132条第2項ただし書の規定により期間を短縮する場合においても、滞納者及び交付要求をしている行政機関等が、法第133条第2項((配当計算書に関する異議))又は第171条((滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例))の規定による異議の申出又は不服申立てをすることができるだけの期間はおくものとする。
第133条関係 換価代金等の交付
配当計算書
1 法第133条第1項の「配当計算書」とは、法第131条((配当計算書))の配当計算書をいう。ただし、法第133条第2項の規定により更正されたときは、更正後の配当計算書をいう。
配当計算書に関する異議
(異議の範囲)
2 法第133条第2項の「配当計算書に関する異議」とは、配当計算書に記載された金額についての異議をいう。
(不服申立てとの関係)
3 換価代金等の配当に関して異議を有する者が、通則法の規定による不服申立てとの法第133条の異議の申出とを併せてした場合において、法第133条の異議の申出が認められなかったときは、不服申立てだけが審理されることとなる。
なお、不服申立てだけがされた場合において、その申立ての内容が法第133条の異議に当たるときは、その部分については、法第133条の異議の申出が併せてされたものとして取り扱う。
(異議の申出者)
4 法第133条第2項の規定により異議の申出をすることができる者は、滞納者及びその異議が認められることによって配当される金額が増加することとなる者である。
(配当計算書の更正)
5 法第133条第2項各号の規定により配当計算書を更正したときは、その旨を配当計算書に関する異議に関係を有する者及び滞納者に通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
第1号の異議
(異議の内容)
6 法第133条第2項第1号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるとき」とは、異議が配当計算書に配当すべき金額として現に記載されている国税、地方税又は公課の金額についてのその金額の存否又は多少に関するものであるときをいい、行政機関等から異議の申出があったことにより、国税、地方税又は公課以外の債権に影響を与えることとなるときも含まれる。
(行政機関等)
7 法第133条第2項第1号の「その行政機関等」とは、配当計算書に関し、法第133条第2項第1号に規定する異議の申出があった場合において、その異議の目的となった配当金額を受けるべき行政機関等をいう。
(行政機関等からの通知)
8 法第133条第2項第1号の「行政機関等からの通知に従い」とは、異議の内容が7の行政機関等の権限に係るものである場合には、その行政機関等からその異議に関する通知を受け、その通知に従うことをいう。
第2号の異議
(異議の内容)
9 法第133条第2項第2号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合」とは、異議を認めても配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に影響を与えない場合をいう。
(異議の関係者)
10 法第133条第2項第2号の「その異議に関係を有する者」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる債権者をいう。
(合 意)
11 法第133条第2項第2号の「その他の方法で合意したとき」とは、10の債権者と滞納者が、配当計算書に記載された金額以外の配当金額によることを合意したときをいう。
(供 託)
12 法第133条第2項第2号の異議を正当と認めないとき又はその他の方法による合意がないことにより換価代金等を交付することができないときは、税務署長は、換価代金等を供託しなければならない(法133条3項、令50条1項)。この供託及び供託後の手続については、19に定めるところによる。
第3号の異議
(異議の内容)
13 法第133条第2項第3号の「配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合」とは、異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課に対する直接の異議ではなく、これら以外の債権の配当金額に関するものであって、その異議を認めることにより、国税、地方税又は公課の配当金額に影響を与えることとなる場合をいう。
(異議の関係者)
14 法第133条第2項第3号の「異議に関係を有する者」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる債権者及び行政機関等をいう。
(合 意)
15 法第133条第2項第3号の「その他の方法で合意したとき」とは、異議を認めることにより配当金額に影響を受けることとなる行政機関等及び債権者並びに滞納者が、配当計算書に記載された金額以外の金額によることを合意したときをいう。
(異議の参酌)
16 法第133条第2項第3号の「その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し」とは、税務署長がその異議について客観的にみて合理的な理由があると認めるときは、その異議の内容を参酌して配当金額を定め、配当計算書を更正して、換価代金等を交付することをいう。
(供託等)
17 法第133条第2項第3号の異議を正当と認めないとき又はその他の方法による合意がないときで、税務署長が異議につき相当の理由がないと認める場合の配当については、次による。 (1) 国税、地方税又は公課の金額は、直ちに交付する(法133条2項3号)。
(2) (1)以外の異議に関係を有する者に配当すべき換価代金等は、供託しなければならない(法133条3項、令50条1項)。この供託の手続及び供託後の手続については、19に定めるところによる。
特殊な場合の供託
(停止条件)
18 法第133条第3項の「停止条件」とは、その成就まで法律行為の効力の発生を停止する条件をいう(民法127条)。
(供託等の手続)
19 法第133条第3項に掲げる場合における換価代金等の交付については、次に掲げるところによる。 (1) 法第133条第2項の規定により換価代金等を交付することができない場合には、税務署長は、その換価代金等を供託(第134条関係5,6参照)し、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない(令50条1項)。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
なお、滞納者に対しては、異議に関係のないときであっても、上記に準じて通知するものとする。
(2) (1)の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになったときは、これに従って配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、(1)により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない(令50条2項)。この配当額支払証及び支払委託書は、別に定めるところによる。
(3) (2)による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、(2)の支払委託書に基づいて行われる(令50条3項)。
(4) 換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付については、(1)から(3)までに準ずる(令50条4項)。
滞調法の規定による供託
20 執行停止に係る強制執行による差押え後に登記された担保権がある場合又は仮差押え後に担保権が設定されている場合の換価代金の交付については、滞調法に規定するところにより供託しなければならない(同法33条2項、34条2項。第129条関係14,15参照)。
第134条関係 換価代金等の供託
換価代金等の供託
(保全差押え等に係る交付要求がある場合)
1 法第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))又は同項の規定を準用する通則法第38条第4項((保全差押えに関する規定の準用))の規定による交付要求を受けている場合において、その保全差押金額又は繰上保全差押金額に係る確定した国税の納期限が到来していないときは、法第134条第1項の規定により供託しなければならない。
(供託の対象となる金額)
2 法第134条第1項の「その債権者に交付すべき金額」とは、法第133条第1項((換価代金等の交付))の規定により債権者に交付すべき金額をいう。
(供託)
3 法第134条第1項の「供託」とは、税務署長が、債権者に交付すべき金額に相当する金銭を、その債権者のために、供託所に供託することをいう。
(配当手続の終了)
4 法第134条第1項の規定によって供託した場合には、その供託に係る部分について、換価代金等の配当手続は終了する(民法494条参照)。
供託の手続
(供託所)
5 法第134条第1項の規定により供託すべき供託所は、換価代金等を配当する行政機関等の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは法務大臣の指定する出張所である(供託法1条)。
(供託の手続)
6 供託の手続は、供託法第2条((供託手続))又は供託規則の定めるところによる。
(供託の通知)
7 法第134条第2項の規定による債権者に対する供託した旨の通知は、供託官が供託に係る金銭を受領したとき又は日本銀行から供託に係る金銭を受領した旨の証書の交付を受けたときにおいて、供託官が、あらかじめ税務署長から提出を受けている供託通知書(供託規則第20号書式)を送付することによって行われることに留意する。
第135条関係 売却決定の取消しに伴う措置
売却決定を取り消したとき
1 法第135条第1項の「売却決定を取り消したとき」とは、買受人が買受代金を納付した後に、その売却決定を取り消したときをいう。
なお、法第112条第1項((動産等の売却決定の取消し))の規定により、その取消しをもって買受人に対抗することができないときは、法第135条の規定の適用はない(法135条1項ただし書)。
抹消の登記の嘱託
2 法第135条第1項第2号の「第121条(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利」とは、換価に伴い移転の登記を嘱託した権利をいい、「まつ消の嘱託」は、上記の権利移転の登記についての抹消の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。
回復の登記の嘱託
(質権等の回復の登記)
3 法第135条第1項第3号の「第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権その他の権利」とは、法第124条((担保権の消滅又は引受))の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等をいい、「回復の登記の嘱託」は、上記の抹消された質権、抵当権その他の権利についての回復の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。 (注) 抹消した登記の回復の登記を申請する場合において、登記上利害関係がある第三者があるときは、申請書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する必要がある(不動産登記法67条参照)。
(差押えの登記の回復)
4 換価に伴い抹消された滞納処分による差押え又は参加差押えの登記についても、法第135条第1項第3号の規定による回復の登記の嘱託ができる。この場合において、売却決定の取消しが差押処分自体の違法を理由とするものであるときは、回復の登記の嘱託をしないで、新たな滞納処分を行うものとする。
(交付した金額の返還の請求)
5 税務署長は、売却決定を取り消したときは、換価代金等の交付を受けた者に対して、交付した金額の返還を請求する。この場合において、交付すべき金額を供託しているときは、供託規則に定めるところにより取り戻す。 (注) 交付した金額の返還の請求は、国の債権の管理等に関する法律の定めるところによる。
代 位
(意 義)
6 法第135条第2項の「代位」とは、5の請求を受けた担保権者が返還しない金額を限度として、その担保権に係る権利が税務署長に移転することをいう。
(付記登記)
7 法第135条第2項の規定により税務署長が代位したときは、その代位に係る付記登記をすることができる。この場合において、税務署長が付記登記を嘱託(又は申請)するときは、「登記原因ヲ証スル書面」等として、嘱託書(又は申請書)に配当計算書の謄本及び代位される担保権者の承諾書を、添付しなければならない(不動産登記法31条、建設機械登記令9条、自動車登録令55条、56条、14条(申請書に担保権者の署名押印があるときは、承諾書の添付は要しない。17条)等参照)。 (注) 税務署長は、全部代位するときは債権に関する証書の交付を、一部代位するときは債権に関する証書に代位の旨の記入を、それぞれの代位される担保権者にさせることができるほか、付記登記についての承諾書の交付を求めること等ができる(民法503条参照)。
第5節 滞納処分費
第136条関係 滞納処分費の範囲
滞納処分費の範囲
(差押えに関する費用)
1 法第136条の「差押に関する費用」とは、おおむね次に掲げる費用をいう。 (1) 差押財産の収集、整理等のために要した縄代、人夫賃等の費用
(2) 差押えの登記をするために、登記簿上の記載事項の更正、変更若しくは抹消の登記又は新たな事項の登記を嘱託した場合に要した登録手数料、名義変更料及び登記簿の調査に要する費用
(交付要求に関する費用)
2 法第136条の「交付要求に関する費用」とは、おおむね次に掲げる費用をいう。 (1) 交付要求をするために要した執行機関等の書類の閲覧に関する費用
(2) 参加差押えをするために要した登記簿等の調査に関する費用
(保管に関する費用)
3 法第136条の「保管に関する費用」とは、差押財産の維持管理のために支出し、又は支出すべきことの確定した費用をいい、おおむね次に掲げるものがある。 (1) 保管人に対する報酬
(2) 倉敷料等の保管料
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、その財産の維持管理に要した費用、例えば、動物の飼育費、船舶のけい船料、監守人の日当等
(運搬に関する費用)
4 法第136条の「運搬に関する費用」とは、差押財産をその所在の場所から税務署、保管人の住所等の保管場所に引き揚げ、又は保管の場所を移し、若しくは保管場所から公売場に搬入するために支出し、又は支出すべきことの確定した費用をいい、おおむね次に掲げるものがある。 (1) 荷造りに要する費用
(2) 運搬に要する人夫賃
(3) 運送費、例えば、自動車の借上科、運転手の日当、運賃等
(換価に関する費用)
5 法第136条の「換価に関する費用」とは、おおむね次に掲げるものをいう。 (1) 公売公告(見積価額の公告を含む。)の新聞掲載料 (注) 複数の滞納者の公売財産に係る公売公告の新聞掲載料は、掲載に要した紙面のうち、各々の滞納者分として使用した部分に相当する掲載料とそれ以外の部分に相当する掲載料を当該滞納者に均分した掲載料との合計額を、各滞納者に負担させる。
(2) 鑑定人の鑑定料、旅費、日当等
(3) 競り売り人の旅費、日当、現地案内人の謝金、測量手数料等
(4) 公売の場所の使用料、整理費等
(修理等の処分に関する費用)
6 法第136条の「第93条(修理等の処分)の規定による処分に関する費用」とは、差押財産の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等の費用をいう。
(有価証券の取立てに関する費用)
7 法第136条の「有価証券の取立に関する費用」とは、金融機関に取立てを依頼した場合における取立手数料等の費用をいう。
(債権の取立てに関する費用)
8 法第136条の「債権の取立に関する費用」とは、被差押債権の取立てに要した人夫賃等の費用をいう。
(無体財産権等の取立てに関する費用)
9 法第136条の「無体財産権等の取立に関する費用」とは、法第73条第5項((債権に関する規定の準用))の規定による無体財産権等の取立てに要した人夫賃等の費用をいう。
(配当に関する費用)
10 法第136条の「配当に関する費用」とは、法第130条第2項((債権額の確認方法))の規定による債権現在額の確認のための調査に要した費用等をいう。
滞納処分費として徴収できないもの
11 通知書その他の書類の送達に要する費用は、滞納処分費として徴収することができない(法136条)。また、次に掲げる費用は、滞納処分費として徴収しないものとする。 (1) 滞納処分に従事する徴収職員の俸給、旅費、手当等
(2) 滞納処分に関する書類(差押調書、公売公告等)の用紙代、税務署等の自動車によって差押財産を引き揚げた場合の燃料費等
(3) 公売公告の取消しに要する費用
(4) 行政上の措置として行った手続に要する費用
(5) 滞納処分に臨場した場合において、滞納税金の完納、納税の猶予の許可、差押えをすることができる財産がない等の理由によって差押えをしなかったときに要した費用
滞納処分費として徴収しない場合
12 次の事実が生じた場合には、それぞれに掲げる費用は、滞納処分費として徴収しないものとする。 (1) 徴収に関する処分が取り消された場合においては、その取り消された処分に要した費用
(2) 賦課処分の全部又は一部の取消しに基づき、徴収に関する処分が解除又は取消しされた場合においては、その解除又は取消しされた処分に要した費用
(3) 法第50条第2項((差押換えの請求に対する措置))又は第51条第3項((相続に係る差押換えの請求に対する措置))の規定により差押換えをした場合においては、解除に係る差押処分に要した費用
第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
徴収の基因となった国税
1 法第137条の「その徴収の基因となった国税」とは、滞納処分費を要する原因となった国税をいい、滞納処分費が個々のどの差押財産から生じたものであるかを問わない。 (注) 滞納処分費は、その徴収の基因となった国税には先立つが、他の国税には後れることもある。 〔例〕 甲国税によりA財産とB財産を差し押さえ、A財産を換価した場合の法第10条((直接の滞納処分費の優先))と法第137条との関係は、次のようになる。 A財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
B財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800万円
A財産の換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
この場合には、法第10条((直接の滞納処分費の優先))の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、差押国税590万円に配当する。次いで600万円の配当を受けた税務署長は、法第137条の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、B財産に係る滞納処分費5万円、差押国税585万円の配当をし、それぞれの国税に充てることになる。
第138条関係 滞納処分費の納入の告知
徴収手続
(納入の告知を要する場合)
1 滞納処分費につき納入の告知を要する場合は、本税及び附帯税のすべてが完納され、滞納処分費だけについて滞納者の財産を差し押さえようとする場合である(法138条)。
なお、納入の告知をした滞納処分費については、督促をしないで直ちに差押えをすることができる。
(納入の告知を要しない場合)
2 1以外の場合、例えば完納されていない本税若しくは附帯税と滞納処分費とについて差押えをするとき又は一つの国税について滞納処分費だけが残っており、他の国税の本税若しくは附帯税とともに差押えをするときは、納入の告知を要しない。
(納入告知書)
3 法第138条の「納入の告知」は、口頭による場合のほかは、令第51条各号((納入告知書の記載事項等))に掲げる事項を記載した通則規則第5条((書式))に規定する別紙第2号書式に、同書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えた(規則3条3項)納入告知書を、滞納者に送達して行う。
(口頭による告知)
4 令第51条ただし書((口頭による納入の告知))の規定は、例えば、徴収職員が滞納処分のために臨戸した場合において、本税及び附帯税が完納され、その滞納処分費だけ残っていることが判明したとき等、その滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、口頭により納入の告知をすることができることを定めたものである。この場合には、令第51条各号((納入告知書に記載すべき事項))に掲げる事項のほか、滞納処分費の納入の告知である旨を明確にして告知する。
(納期限)
5 令第51条第3号((納入告知書の記載事項))の「納期限」は、国税収納金整理資金事務取扱規則第18条((納付期限))の規定により調査決定の日から20日以内の日として適宜定める。
なお、上記の納付期限は、納入告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日以後とする(通則令8条1項参照)。
第6節 雑則
第1款 滞納処分の効力
第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
滞納処分の続行
1 法第139条第1項の「滞納処分を続行することができる」とは、被相続人又は被合併法人に対してした滞納処分の効力が、別段の手続をとることなく当然に相続人又は合併法人に及ぶことをいう。
なお、滞納処分による換価に伴う買受人への権利移転に当たっては、税務署長は、買受人に代わって相続人又は合併法人への権利移転の登記の嘱託をした後、買受人のために権利移転の登記の嘱託するものとする(昭和43.6.5付民事甲第1,835号法務省民事局長回答)。
承継財産についての執行
(死 亡)
2 法第139条第1項の「死亡」には、失そう宣告により死亡したものとみなされる場合(民法31条)も含まれる。
(法 人)
3 法第139条第1項の「法人」には、人格のない社団等も含まれる(法3条)。
(合 併)
4 法第139条第1項の「合併により消滅したとき」とは、吸収合併又は新設合併により法人が解散して消滅した場合及び人格のない社団等でこれに準ずる場合をいう。
滞納者名義の財産に対する執行
(滞納者の名義の財産)
5 法第139条第2項本文の「滞納者の名義の財産」とは、差押えに当たり、徴収職員が財産の帰属を名義によって判断する財産、例えば、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械又は各種記名式有価証券で滞納者の名義となっている財産に限られず、社会通念上滞納者の名義の財産と認められるものをいう。
(死亡を知っていた)
6 法第139条第2項ただし書の「死亡を知っていた」かどうかについては、5の財産に対してした差押えの時の現況による。
第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
仮差えの意義
1 法第140条の「仮差押」とは、裁判所の決定に係る仮差押えをいう(第55条関係10参照)。
仮処分の意義
2 法第140条の「仮処分」とは、裁判所の決定に係る仮処分をいう(第55条関係11参照)。
滞納処分と仮差押えとの関係
(仮差押えの効力)
3 仮差押えを受けた財産についても、法第140条の規定により滞納処分による差押えをすることができる。この場合における仮差押えの効力は、滞納処分による差押えによって消滅するものではないが、その財産が換価された場合には消滅する(第125条関係2参照)。
なお、仮差押えを受けた財産を滞納処分により換価した場合においては、換価代金等の残余は、当該財産に対する強制執行について管轄権を有する地方裁判所又は仮差押えをした執行官に交付する(滞調法28条、6条1項、34条1項、18条2項等)。 (注) 仮差押えについては交付要求及び参加差押えはできないが、仮差押えがされている財産につき滞納処分がされている場合には、その滞納処分につき交付要求及び参加差押えができるし、これらの処分は、仮差押えにより妨げられない。
(仮差押えを受けた動産又は有価証券の差押え)
4 仮差押えを受けている動産又は有価証券については、法第56条第1項((動産又は有価証券の差押手続))の規定によりその差押えを行うことができる(第58条関係4参照)。この場合において、その動産又は有価証券に対し執行官による仮差押えの旨の封印その他の表示がしてあるときは、それらの表示を破棄しないものとする。
(供託された金銭の差押え)
5 仮差押えの執行に係る金銭(保全法49条2項)、仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、若しくはその保管のために不相応な費用を要するため売却した売得金(同法49条3項)、強制管理の方法によるときの配当等に充てるべき金銭(同法47条4項)、強制競売による配当金(執行法91条1項2号)、又は滞納処分の行政機関等から交付を受けた金銭で売得金若しくは売却代金とみなされる金銭(滞調法11条3項、18条2項3項、19条参照)が供託されている場合(保全法49条2項、3項、47条4項、執行法91条1項)には、執行官又は裁判所にその供託金の払戻しを請求し、その払戻しがされた金銭について、法第56条第1項((動産又は有価証券の差押手続))の規定により差し押さえる。
(仮差押えを受けた動産等以外の財産の差押え)
6 仮差押えを受けている動産又は有価証券以外の財産については、その財産の種類に応じて、法第62条第1項及び第2項((債権の差押手続))、第68条第1項及び第3項((不動産の差押手続))、第70条第1項((船舶又は航空機の差押手続))、第71条第1項((自動車又は建設機械の差押手続))、第72条第1項及び第3項((特許権等の差押手続))又は第73条第1項及び第3項((電話加入権等の差押手続))の規定により、それぞれ差し押さえる。
(仮差押解放金の差押え)
7 仮差押えの執行停止のため、又は既に執行した仮差押えの取消しのため、仮差押債務者(滞納者)が仮差押決定の記載に従い供託した金銭(仮差押えによって保全される金銭債権の額に相当する金銭。以下7及び8において「仮差押解放金」という。保全法22条)については、滞納者の有する供託金取戻請求権を差し押さえるものとする。
また、第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭債権の額に相当する金銭を供託した場合において、保全法第50条第3項((みなす仮差押解放金))の規定により「仮差押解放金」とみなされる供託した金銭については、滞納者の有する供託金還付請求権を差し押さえるものとする。
(仮差押解放金の取立て)
8 7により供託金取戻請求権又は供託金還付請求権を差し押さえたときは、税務署長は、直ちに供託金の払渡しの請求をすることができる(平成2.11.13付民四第5,002号法務省民事局長通達)。
(差押えの通知)
9 保全法の規定により仮差押えがされている財産を差し押さえたときは、法第55条第3号((仮差押え等をした保全執行裁判所等に対する差押えの通知))の規定により、保全執行裁判所又は執行官に差し押さえた旨その他必要な事項を通知しなければならない。
(差押解除の通知)
10 仮差押えがされている財産について滞納処分による差押えを解除した場合においては、仮差押えをした保全執行裁判所又は執行官にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法81条)。
(公売等による仮差押えの登記の抹消の嘱託)
11 不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械に対する仮差押えの執行が、仮差押えの登記(強制管理の開始決定に係る仮差押えの登記を含む。)をすることにより行われている場合において、その仮差押えの登記のある財産を換価し、その権利移転の登記を関係機関に嘱託するときは(法121条等参照)、法第125条((換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託))等の規定により、併せて、仮差押えの登記の抹消を嘱託するものとする。
滞納処分と仮処分との関係
(仮処分が執行された財産の差押え)
12 仮処分が執行された財産についても、滞納処分による差押えをすることができる。この場合における仮処分の効力は、滞納処分による差押えによって消滅しない(保全法58条1項、2項参照)。
なお、仮処分が執行された財産を差し押さえた場合における換価については、この条関係13から20までに定めるところによる。 (注) 仮処分について交付要求及び参加差押えはできないが、仮処分がされている財産につき滞納処分がされている場合には、その滞納処分につき交付要求及び参加差押えができる。
(不動産の所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
13 所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、滞納処分による差押えは仮処分債権者に対抗することができない(保全法58条1項、2項)。
したがって、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする。 (注)1 所有権についての登記とは、所有権又は共有持分の登記名義人を実質的に変更する登記であり、例えば、所有権の移転の登記、保存若しくは移転の登記の抹消、移転の登記の抹消回復の登記又は持分の更正の登記をいう。
2 処分禁止の仮処分とは、仮処分債務者に対して係争物(不動産、動産、債権等)に係る権利の処分(所有権の移転、担保権の設定等)を禁止することを内容とする仮処分(保全法24条)をいう。
3 不動産とは、不動産登記法第1条の不動産(土地及び建物)及び特別法において不動産とみなされるもの(立木(立木法2条)、工場財団(工場抵当法14条)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)漁業財団(漁業財団抵当法6条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法26条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法8条)及び観光施設財団(観光施設財団抵当法8条))をいう。
4 所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行われる(保全法53条1項)。したがって、仮処分の執行と滞納処分による差押えの先後は、処分禁止の登記と差押えの登記の先後によって定まる。
5 仮処分債権者は、所有権の登記を申請する場合において、これと同時に申請するときに限り、その仮処分の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる(保全法58条2項、不動産登記法146条ノ2第1項)。この場合、仮処分債権者は、あらかじめ、その登記の権利者に対し、登記を抹消する旨の通知をしなければならない(保全法59条、不動産登記法146条ノ2第2項)。また、差押登記が抹消されたときは登記官から抹消した旨の通知がされることとされている(保全法59条、平成2.11.8付民三第5,000号法務省民事局長通達)。
6 処分禁止の登記より後順位の登記のうち、仮処分債権者の保全すべき登記請求権の登記に係る権利の取得又は消滅に抵触しないものは、仮処分債権者に対抗することができる。例えば、処分禁止の登記の前にされた国税の担保のための抵当権に基づく担保物処分のための差押え(通則法52条1項)の登記、仮処分の登記前に登記された抵当権の登記名義人を申立人とする競売開始決定に係る差押えの登記(昭和58,6.22付民三第3,672号法務省民事局長通達)、仮処分の債務者に対する破産(破産法70条)、和議開始(和議法40条2項、58条)、株式会社の整理開始に伴う保全処分(商法383条、386条1項)、更生手続開始(会社更生法67条1項、246条1項)又は企業担保権の実行手続の開始(企業担保法28条)の各登記がこれに当たる。
7 本案(保全法1条参照)の帰すうの形態としては、仮処分債権者の勝訴判決又は敗訴判決の確定、和解及び仮処分債権者と仮処分債務者との共同申請による登記の実現等がある。
(不動産の所有権以外の権利の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
14 所有権以外の権利の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合には、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条1項)。ただし、差押えに基づく換価は、当該不動産を仮処分の負担付きで換価できる場合等を除き、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(89条関係9、124条関係6参照)。 (注)1 不動産の所有権以外の権利の移転の登記とは、当該権利の全部又は一部の名義人を実質的に変更する登記で保存又は設定の登記に変更を加えないものをいい、例えば、抵当権若しくは地上権の全部若しくは一部の移転の登記、移転の更正の登記又は移転の抹消回復の登記をいう。
2 不動産の所有権以外の権利の消滅の登記とは、当該権利の全部又は一部が設定者との関係において実質的に消滅する登記をいい、例えば、抵当権抹消の登記、一部弁済による抵当権変更の登記又は被担保債権額を減額する抵当権更正の登記をいう。
(不動産の所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
15 所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた不動産を差し押さえた場合には、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条1項)。この場合、当該仮処分が担保権の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分であるときは換価を行うことができるが、当該仮処分が不動産の使用又は収益をする権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分であるときは、本案の帰すうが定まるまでの間は換価を行わないものとする(法133条3項、令50条4項参照)。 (注)1 所有権以外の権利の保存、設定又は変更の登記とは、実質的に新たに権利を設定する登記をいい、例えば、先取特権の保存の登記、抵当権若しくは地上権設定の登記、その抹消回復の登記、根抵当権の極度額を増額する変更若しくは更正の登記又は民法第375条による抵当権の処分の登記をいう。
2 担保権の保存、設定又は変更の登記とは、1に掲げたもののうち、担保権に関する登記をいう。
3 上記の仮処分の執行は、処分禁止の登記とともに保全仮登記をする方法により行われる(保全法53条2項)。この場合、処分禁止の登記は、処分禁止の対象が所有権である場合には甲区に、所有権以外である場合には乙区にされ、保全仮登記は乙区にされる(平成2.11.8付民三第5,000号法務省民事局長通達参照)。
4 担保権の保存、設定又は変更登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分が執行された後に新たな担保権が設定された財産を差し押さえて換価した場合においては、仮処分の執行後における担保権の設定は有効であるから、当該新たな担保権により担保される債権に対しても配当を行う(保全法58条1項、3項参照)。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
16 不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについて、登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分がされている場合の仮処分と滞納処分との関係については、第140条関係13から15までに準ずるものとする(保全法54条、61条参照)。 (注) 不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものには、例えば、特許権(特許法66条)、実用新案権(実用新案法14条)、意匠権(意匠法20条)、商標権(商標法18条)、自動車の所有権及び抵当権(道路運送車両法5条、自動車抵当法5条)、航空機の所有権及び抵当権(航空法3条の3、航空機抵当法5条)、建設機械の所有権及び抵当権(建設機械抵当法7条)並びに船舶の所有権及び抵当権(商法686条、687条、703条、848条)等がある。
(その他の財産に対する処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
17 不動産及び不動産以外の権利でその処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするもの以外の財産について処分禁止の仮処分がされている場合における滞納処分については、第140条関係13から15までに準じて取り扱うものとする。
(物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための占有移転禁止の仮処分と滞納処分との関係)
18 物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するため、債務者に対し、その物の占有の移転を禁止し、及びその占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずるとともに、執行官にその物の保管をさせ、かつ、債務者がその物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官がその物を保管している旨を公示させることを目的とする仮処分(以下「占有移転禁止の仮処分」という。保全法62条)がされた物を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者が、本案の債務名義に基づいて、その物の引渡し又は明渡しの強制執行をしたときにおいても、滞納処分による差押えは効力を失わない(保全法58条、62条参照)。
(2) 仮処分債権者は、本案の債務名義に基づいて、仮処分の執行がされたことを知ってその物を占有した者に対し、その物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるから、差押えに基づく換価は本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(保全法62条参照)。 (注) 占有移転禁止の仮処分は、所有者が不法占拠者に目的物の返還を請求する場合、売買契約・賃貸借契約に基づき買主・賃借人が目的物の引渡しを請求する場合、賃貸借契約終了により賃貸人が目的物の返還を請求する場合等において、占有関係が転々とするのを防止するために行われる。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分と滞納処分との関係)
19 建物収去土地明渡請求権を保全するための処分禁止の仮処分(保全法55条)がされた建物を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者は、差押登記の抹消を請求することはできない(保全法58条、64条参照)が、本案の債務名義に基づいて、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行を行うことができる(保全法64条参照)。
(2) 仮処分債権者は、本案の債務名義に基づき、処分禁止の登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行を行うことができるから、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする(保全法64条参照)。
(その他の仮処分と滞納処分との関係)
20 係争物に関する仮処分(保全法23条1項)のうち、第140条関係13から19までに掲げた以外の仮処分がされた財産を差し押さえた場合における仮処分と滞納処分との関係は、次のとおりである。 (1) 仮処分債権者が、本案の債務名義に基づいて、強制執行をした場合においても、滞納処分による差押えは効力を失わない。
(2) 当該仮処分の効力は、滞納処分による換価によって消滅しないから、差押えに基づく換価は、本案の帰すうが定まるまでの間は行わないものとする。 (注) 上記の仮処分には、滞納者名義の土地につき第三者が所有権に基づいて立入禁止の仮処分をする場合及び滞納者の所有建物につき第三者が賃借権に基づいて占有使用妨害禁止の仮処分をする場合等がある。
(差押え後に仮処分が執行された場合における滞納処分と仮処分との関係)
21 滞納処分による差押え後に係争物に関する仮処分(保全法23条1項)が執行された場合、処分禁止の仮処分等差押えに対抗することができない仮処分の効力は、滞納処分による換価によって消滅する(執行法59条3項参照)。
ただし、仮処分債権者が、本案において係争物に係る実体上の所有権を主張しているときは、本案の帰すうが定まるまでの間は換価を行わないものとする。 (注) 建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分等係争物に係る権利の処分を禁止する効力を有しない仮処分については、滞納処分による換価によって効力が消滅しない場合があることに留意する。
(仮差押えの準用)
22 仮処分を受けた動産の差押え、仮処分を受けた動産以外の財産の差押え、仮処分を受けた財産に対する差押えの通知及び仮処分を受けた財産に対する差押えの解除については、4及び6並びに9から11までに定めるところに準じて行うものとする。
(仮処分解放金の差押え)
23 仮処分の執行の停止のため又は既にした仮処分の執行の取消しのため、仮処分命令の決定書の記載に従い仮処分債務者が供託した金額(保全法25条。以下「仮処分解放金」という。)の差押えは、次のより行うものとする。 (1) 一般の仮処分に基づく仮処分解放金(以下「一般型仮処分解放金」という。)が供託された場合には、仮処分債権者が滞納者であるときは供託金還付請求権を、仮処分債務者が滞納者であるときは供託金取戻請求権を、それぞれ差し押さえる。
(2) 詐害行為取消権(民法424条1項)を保全するための仮処分に基づく仮処分解放金(以下「特殊型仮処分解放金」という。)が供託された場合には、民法第424条第1項の債務者(以下「詐害行為の債務者」という。)が滞納者であるときは供託金還付請求権(保全法65条)を、仮処分債務者が滞納者であるときは供託金取戻請求権を、それぞれ差し押さえる。 (注)1 供託書中の「被供託者」欄に仮処分債権者が記載されている場合には一般型仮処分解放金に係る供託と、仮処分債権者以外の者が記載されている場合には特殊型仮処分解放金に係る供託と判断して差し支えない(平成2.11.13付民四第5002号法務省民事局長通達参照)。
2 一般型仮処分解放金の供託は、所有権留保付売買契約における代金債務の不履行による目的物の引渡請求権を保全するための占有移転禁止の仮処分及び譲渡担保契約における金銭債務の不履行による担保目的物の引渡請求権保全のための仮処分等に基づいて行われる。
3 特殊型仮処分解放金が供託された場合には、仮処分債権者は供託金還付請求権を有しない(保全法65条参照)。
(仮処分解放金の取立て)
24 23により供託金還付請求権又は供託金取戻請求権を差し押さえた場合においては、次により取り立てるものとする(平成2.11.13付民四第5002号法務省民事局長通達参照)。 (1) 一般型仮処分解放金に係る供託金還付請求権を差し押さえた場合において、仮処分債権者の本案訴訟の勝訴が確定したとき又は勝訴判決と同一内容の和解又は調停が成立したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に、確定判決の正本及びその確定証明書(保全規則13条2項参照)又は和解調書、調停調書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物の同一性を証する書面(仮処分申立書、仮処分命令決定書等をいう。以下(2)から(4)までにおいて同じ。)を添付する(民事訴訟法151条3項、保全法5条1項参照)。
(2) 一般型仮処分解放金に係る供託金取戻請求権を差し押さえた場合において、仮処分の本案判決の確定前に仮処分の申立てが取り下げられたとき、仮処分債権者の本案訴訟の敗訴が確定したとき又は仮処分債権者が本案訴訟で勝訴し仮処分の目的物に対して強制執行したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。この場合、供託物払渡請求書に、仮処分の申立てが取り下げられたことを証する書面又は本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面を添付する。
(3) 特殊型仮処分解放金に係る供託金還付請求権を差し押さえた場合においては、次により取り立てるものとする。 イ 仮処分の執行が保全法第57条第1項((仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し))の規定により取り消され、かつ、本案訴訟の判決が確定した後に仮処分債権者が詐害行為の債務者の有する供託金還付請求権に対して強制執行をしたときは、執行裁判所から支払証明書の交付を受け、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる(保全法65条)。
この場合、供託物払渡請求書に当該支払証明書を添付する。
ロ 仮処分債権者が供託金還付請求権に対する強制執行の申立てを取り下げたときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に、本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面及び仮処分債権者の強制執行の申立てが取り下げられたことを証する書面を添付する。
(4) 特殊型仮処分解放金に係る供託金取戻請求権を差し押さえた場合において、本案の勝訴判決の確定前に仮処分の申立てが取り下げられたとき又は仮処分債権者が本案訴訟で敗訴したときは、供託所に対して供託金の払渡しを請求することができる。
この場合、供託物払渡請求書に仮処分の申立てが取り下げられたことを証する書面又は本案判決の正本及びその確定証明書のほか、仮処分債権者が本案訴訟で敗訴した場合においては仮処分の被保全権利と本案の訴訟物の同一性を証する書面を、それぞれ添付する。
担保の差押え
25 保全法第32条第3項((保全異議の申立てについての決定))、第38条第1項((事情の変更による保全取消し))、第39条((特別の事情による保全取消し))等の規定により仮差押え又は仮処分の取消しのための担保として金銭又は有価証券が供託されているとき(同法4条)は、滞納者の有する供託物取戻請求権を差し押さえることができる。
第2款 財産の調査
第141条関係 質問及び検査
質問及び検査をすることができる場合
1 法第141条の「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため、滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等(以下第141条関係において「財産の状況等」という。)を明らかにするため調査する必要があるときをいう。この場合において、質問の内容及び検査の方法等は、財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。
質問又は検査の相手方
(滞納者の財産を占有する第三者)
2 法第141条第2号の「滞納者の財産を占有する第三者」とは、正当な権限の有無にかかわらず、滞納者の財産を自己の占有に移し、事実上支配している第三者をいう。
(相当の理由)
3 法第141条第2号及び第3号の「相当の理由がある」場合には、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、滞納者の財産を占有し、又は滞納者と債権債務の関係を有し、若しくは滞納者から財産を取得したと認められる場合が含まれる。
(滞納者が株主又は出資者である法人)
4 法第141条第4号の「滞納者が株主又は出資者である法人」とは、滞納者が株主である株式会社又は滞納者が出資者である合名会社、合資会社、有限会社、各種協同組合、信用金庫、人格のない社団等をいう。
質問又は検査の方法
(質 問)
5 法第141条の「質問」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。この場合において、口頭による質問の内容が重要な事項であるときは、必ずてん末を記録することとし、そのでん末を記載した書類には答弁者の署名押印を求め、その者が署名押印をしないときは、その旨を付記しておくものとする。
(検査する帳簿書類)
6 法第141条の「財産に関する帳簿若しくは書類」とは、法第141条第1号から第4号までに掲げる者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の債権若しくは債務又は財産の状況等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類をいう。
(検査の時間の制限)
7 法第141条の「検査」には、捜索の場合と異なり、その時間の制限はないが、特に必要がある場合を除き、捜索の場合の時間の制限に準ずるものとする(第143条関係1から3まで参照)。
(身分証明書の呈示)
8 法第141条の質問又は検査に当たって関係者の請求があったときは、規則第3条(書式)に規定する別紙第12号書式の徴収職員証票を呈示しなければならない(法147条1項)。
罰則の適用
9 法第141条の質問及び検査については、法第188条及び第189条の規定による罰則の適用がある。
第142条関係 捜索の権限及び方法
捜索ができる場合
(滞納処分のため必要があるとき)
1 法第142条の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章((滞納処分))の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、差押財産の引揚げ、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(所 持)
2 法第142条第2項の「所持」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的継続及びその主体の意思を問わない(大正3.10.22大判)。
(引渡し)
3 法第142条第2項の「引渡をしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に引き渡さないときをいい、法第58条第2項((第三者が占有する動産の引渡命令))の規定により引渡命令を受けた者又は第60条第1項((差押動産の保管))の規定により保管する者が引渡しをしないときに限られない。
(相当の理由)
4 法第142条第2項第2号の「相当の理由がある場合」には、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、財産を所持すると認められる場合が含まれる。
捜索ができる物及び場所
(滞納者又は第三者の物)
5 捜索ができる「物」には、滞納者又は上記3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、長持、封筒等がある。
(滞納者又は第三者の住居その他の場所)
6 捜索ができる「場所」には、滞納者又は上記3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、工場、納屋、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋があり、また建物の敷地はもちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置されるものが含まれるものとする。
また、解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索ができる「場所」に含まれる(昭和45.4.14東京高判参照)。
捜索の方法
(戸、金庫等の開扉)
7 徴収職員は、滞納者又は上記3に規定する者の物又は住居等の捜索に当たり、閉鎖してある戸、扉、金庫等を開かせなければ捜索の目的を達することができない場合には、その滞納者又は上記3に規定する者に開かせ、又は自ら開くことができる(法142条3項)。ただし、徴収職員が自ら開くのは、滞納者又は上記3に規定する者が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るものとする。
(必要な処分)
8 法第142条第3項の「必要な処分」とは、徴収職員が自ら開扉するための錠の除去等をいう。この場合の錠の除去等は、必要に応じて第三者(上記3に規定する者を除く。)にさせることができる。
なお、これらの処分をするに当たっては、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。
(立会人)
9 捜索をする場合には、法第144条((捜索の立会人))の規定により、立会人を置かなければならない。
(捜索調書)
10 捜索をした場合における捜索調書の作成等については、第146条関係に定めるところによる。
時効の中断
11 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判)。この場合において、法第142条第2項の規定により第三者の住居等を捜索したときは、捜索をした旨を捜索調書の謄本等により滞納者に対して通知しなければ、時効中断の効力を生じない(通則法72条、民法155条)。
刑法との関係
12 捜索に際して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条((公務執行妨害等))の規定の適用がある。
第143条関係 捜索の時間制限
捜索の時間の制限
(日出と日没)
1 法第143条第1項の「日出」又は「日没」とは、太陽面の最上点が地平線上に見える時刻を標準とするものであって、その地方の暦の日の出入をいう(明治34.10.7大判、大正11.6.24大判)。
(捜索の継続)
2 日没前に捜索に着手した場合には、その捜索に着手した物又は住居その他の場所の捜索は、日没後まで継続することができる(法143条1項ただし書)。
(休日の捜索)
3 日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日その他一般の休日において個人の住居に立ち入って行う捜索については、特に必要があると認められる場合のほかは、行わないものとする(執行法8条1項、第47条関係19参照)。
日没後の捜索
(捜索ができる場所)
4 法第143条第2項の「夜間でも公衆が出入することができる場所」とは、旅館及び飲食店のほか、次に掲げるものを含む。 (1) 待合、バー及びキャバレー
(2) 映画館、演劇場その他の興行場
(捜索ができる場合)
5 法第143条第2項の「滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるとき」とは、例えば、捜索の相手方が夜間だけ在宅又は営業し、あるいは、財産が夜間だけ蔵置されている等の事情が明らかである場合又は滞納者が海外に出国することが前日に判明した場合等滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由がある場合をいう。
(公開した時間内)
6 法第143条第2項の「公開した時間内」は、営業時間内に限られるものではない。
第144条関係 捜索の立会人
立会人を置くべき場合
1 法第144条の「捜索」とは、法第142条の((捜索の権限及び方法))の規定による捜索処分をいい、捜索をする場合には、必ず立会人を置かなければならないが、捜索を必要としない不動産その他の財産の差押えに当たっては、立会人を必要としない。
立会人の範囲
(滞納者、第三者等)
2 法第144条の「滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者」とは、法第142条第1項((滞納者の住居等の捜索))の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける滞納者又は滞納者の同居の親族若しくは滞納者の使用人その他の従業者をいい、同条第2項((第三者の住居等の捜索))の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける第三者又はその第三者の同居の親族若しくはその第三者の使用人その他の従業者をいう。
(同居の親族)
3 法第144条の「同居の親族」とは、滞納者又は第三者と同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。
(使用人その他の従業者)
4 法第144条の「使用人その他の従業者」とは、事務員、工員、よう人その他滞納者又は第三者との雇用契約等に基づき従業している者をいう。
(相当のわきまえのあるもの)
5 法第144条の「相当のわきまえのある」とは、上記3及び4に規定する者が捜索の立会いについての事理を弁識することのできる相当の能力を有することをいい、成年に達した者であることを要しない。
(市町村の吏員)
6 法第144条の「市町村の吏員」とは、捜索をする場所の所在する市町村(特別区を含む。)における地方自治法第173条((吏員の種類))に規定する吏員をいう。したがって、都道府県の吏員はこれに該当しない。
(警察官)
7 法第144条の「警察官」は、なるべく捜索をする場所を管轄する警察署(下部機構を含む。警察法53条参照)の警察官(同法55条参照)とするものとする。
(税務署の職員)
8 税務署の職員については、他に立会人を求めることができない場合等真にやむを得ない事情がある場合を除き、立会人としないものとする。
第145条関係 出入禁止
出入禁止をすることができる場合
1 法第145条の「これらの処分をする間」とは、捜索、差押処分又は搬出をする場合において、これらの行為に必要な手続が完了するまでの間をいう。
なお、差押財産の搬出は、差押処分後直ちに財産の搬出をする場合に限らず、差押財産を滞納者又は第三者に保管させた後においてその財産の搬出をする場合をも含むものとする。
出入りが認められる者
(差押財産を保管する第三者)
2 法第145条第2号の「差押に係る財産を保管する第三者」とは、法第60条((差し押えた動産等の保管))、第71条第5項(占有した自動車等の保管)等の規定により差押財産を保管させている第三者をいう。
(同居の親族)
3 法第145条第3号の「同居の親族」とは、滞納者又は法第145条第2号の第三者と、それぞれ同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。
(滞納者を代理する権限を有する者)
4 法第145条第4号の「国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者」とは、課税標準等の申告、納税の猶予等の申請、不服申立て又は訴えの提起等、税務に関する事項について、契約又は法律により滞納者に代理してその行為ができる者をいい、例えば、その滞納者から委任を受けた税理士、弁護士、納税管理人等又は法律の規定により定められた親権者、後見人等をいう(民法818条、839条から842条まで、破産法157条等参照)。
出入禁止の方法
(出入禁止の意義)
5 法第145条の「出入することを禁止することができる」とは、徴収職員の許可を得ないで捜索、差押処分又は搬出を行う場所へ出入りすることを禁止すること及びその場所にいる者を退去させることができることをいう。
(出入禁止の掲示)
6 徴収職員は、出入りを禁止した場合には、掲示、口頭その他の方法により、出入りを禁止した旨を明らかにするものとする。
(出入禁止に従わない場合)
7 徴収職員の出入禁止命令に従わない者に対しては、扉を閉鎖する等必要な処置をとることができるものとするが、身体の拘束はできない。
刑法との関係
8 徴収職員の出入禁止命令に関連して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条((公務執行妨害等))の規定の適用がある。
第146条関係 捜索調書の作成
捜索調書の作成
(捜索調書)
1 法第146条第1項の「捜索調書」とは、令第52条第1項各号((捜索調書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第11号書式による。
(記載事項の省略)
2 令第52条第1項ただし書((捜索調書の記載事項の省略))の規定により同項第2号に掲げる事項の記載を省略する場合は、差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書が滞納者又は第三者に交付された後に、差押財産の搬出をするために捜索をした場合等である。
(その他必要な事項)
3 令第52条第1項第5号((捜索調書の記載事項))の「その他必要な事項」とは、捜索した物又は住居その他の場所を特定するために必要な事項(名称又は所在を除く。)をいう。
(立会人の署名押印)
4 捜索調書を作成する場合には、捜索調書に法第144条((捜索の立会人))の立会人の署名押印を求めなければならず、また立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない(令52条2項)。
(差押財産を搬出した場合の捜索調書)
5 滞納者又は第三者が保管している差押財産を搬出するに当たって捜索した場合には、捜索調書に差押財産の搬出をした旨を付記しなければならない(令26条の2第2項)。
捜索調書を作成しない場合
6 法第54条((差押調書))の規定により差押調書を作成する場合には、法第146条第1項の規定による捜索調書の作成及び同条第2項の規定による謄本の交付の必要はない(法146条3項前段)。この場合には、差押調書の謄本を、捜索を受けた第三者及びその第三者以外の立会人があるときはその立会人に、交付しなければならない(法146条3項後段)。
第147条関係 身分証明書の呈示等
身分証明書の呈示
(差押え等の場合の身分証明書の呈示)
1 法第147条の規定の適用がある場合以外で、差押えをしようとするとき等においても、滞納者等から請求があったときは、身分証明書を呈示するよう取り扱うものとする。
(身分を示す証明書)
2 法第147条第1項の「身分を示す証明書」とは、規則第2条第1項((身分証明書の交付))の規定により交付を受けた規則第3条((書式))に規定する別紙第12号書式の「徴収職員証票」をいう。
(関係者の範囲)
3 法第147条第1項の「関係者」とは、法第141条((質問及び検査))の規定による質問若しくは検査又は第142条((捜索の権限及び方法))の規定による捜索を受ける者をいう。
なお、出入禁止を受けた者、立会人等上記の処分に直接の関係を有する者から請求があった場合にも、身分証明書を呈示する。
(請求と呈示)
4 関係者が身分証明書の呈示を求めず、捜索等に応じたときは、その呈示がなくてもその処分は違法ではないが、関係者が身分証明書の呈示を求めたときは、それを呈示しなければその処分を執行することができない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























