解説記事2004年10月04日 【ニュース特集】 合同会社(仮称)のしくみを図解してみました!(2004年10月4日号・№085)
要綱案の公表間近!新会社法の目玉に迫る!
パススルー課税の可否で注目を集める
合同会社(仮称)のしくみを図解してみました!
新会社法(平成18年4月より施行予定)の目玉の一つともいえるのが、合同会社(仮称)です。これはいわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)といわれるものですが、具体的イメージがなかなかわかない読者も多いのでは。そこで、特集では、要綱案(第二次案)をベースに合同会社を図解してみました。なお、要綱案(第二次案)の合同会社に関する個所については29ページに掲載していますので参照してください。
合同会社ってなに?
合同会社(仮称。以下、単に合同会社と表記)とは「社員の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される特徴を有する新たな会社類型」をいいます。ここでのキーワードは、「有限責任」「組合的規律」の2点。この2つの概念は、前者が構成員と会社債権者の関係で、後者は構成員同士の関係であり、局面が異なる以上、お互いが排他的とはいえないまでも、現行の商法のもとでは両立しにくい概念であったといえます。
有限責任とは、会社の債務について、合同会社の社員(社員とは組織の構成員のこと。従業員のことではありません。合同会社の出資者のことです。)が責任を負わない、というもの。株式会社における株主の責任がその典型といえます。社員間のつながりが希薄化し、社員の個性が喪失した、いわゆる物的会社の社員になじむ責任といえます。
一方、組合的規律とは、「原則として全員一致で定款の変更その他の会社の在り方が決定され、社員自らが会社の業務の執行に当たるという規律」をいいます。社員間のつながりが濃厚ないわゆる人的会社や組合においてなじむ規律といえます。
このように合同会社とは、物的会社の性質と人的会社の性質を融合させようとする試みであることが分かります。わが国では会社形態としては初めての試みですが、諸外国では例があり、米国ではいわゆるLLCといわれるものがそれに該当します。
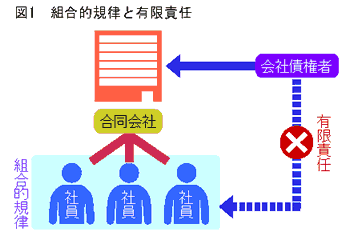
合同会社のしくみ
合同会社のしくみは上述のキーワードである「組合的規律」「有限責任」の2点から説明することができます。まず、組合的規律から導き出される規定としては、以下のようなものがあります。これらは合名会社の規律に準じているといえます。
・合同会社の成立後の定款の変更その他会社の在り方を決める際には、原則として社員全員の一致によるものとし、その意思決定に出資額の多寡は影響しない。
・合同会社成立後の社員の入社及び持分の譲渡の承認については、それぞれ原則として社員全員の一致によるものとする。
・業務執行権限は原則として社員全員にある。
なお、「合同」というと、複数の社員がいることが前提であるかのようなイメージがありますが、要綱案(第二次案)では、社員一人のみの合同会社の設立及び存続が認められています(図2)。また、合同会社の社員は法人でもよいとされています(図3)。その場合、当該法人において職務執行者の選任が必要となります(後述)。
また、有限責任に関連する規定としては
・合同会社の出資の目的は、金銭その他の財産のみに限られており、労務出資・信用出資はできない。
・合同会社の社員の出資については、全額払込主義がとられており、出資時にその全額を払い込む必要がある。
といった規定が挙げられています。
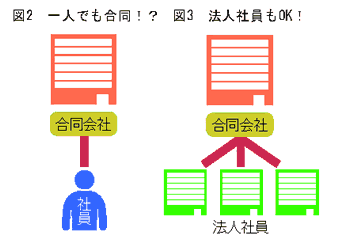
合同会社はどうやって業務執行するの?
合同会社の社員は、全員が業務執行権限を有するのが原則です(図4)。
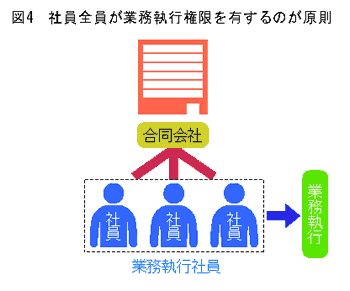
もっとも、全員が業務執行権限を有すると運営が不安定になりがちですし、経営能力の高い者に業務執行を委ねた方が効率がよいでしょう。とくに社員が有限責任であることを考慮すると、わずらわしさを排除したいというニーズもあります。そこで、合同会社では定款の定め又は社員全員の同意により、業務執行社員を選任することも認められる予定(図5及び30頁参照)。
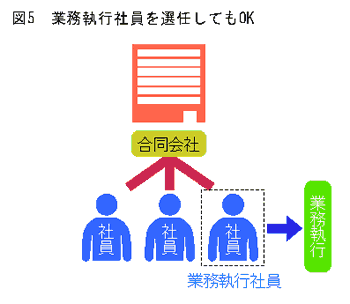
業務執行社員は、合同会社に対して民法の委任の規定に基づく善管注意義務及び忠実義務を負うこととなります。
なお、業務執行社員が法人の場合は、当該法人社員は自然人を職務執行者として選任する必要があります(図6)。
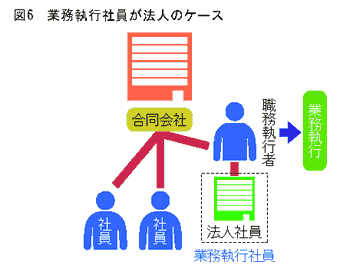
職務執行者の選任は当該法人社員が業務執行社員ではないケースでは不要です。
いずれにしろ、取締役会や監査役を置く必要はないので機動的な業務執行が可能となります。
合同会社の計算はどうなる?
合同会社では、貸借対照表・損益計算書・社員持分変動計算書を作成する必要があります。社員持分変動計算書とは聞きなれないものですが、新会社法下で株式会社に導入される予定の株主持分変動計算書(本誌082号33頁参照)に似たフォームとなるものと思われます。なお、要綱案(第二次案)では「合同会社の債権者は、その閲覧又は謄写の請求をすることができる」(30頁参照)とされていることから、決算公告までは要求されていないといえます。
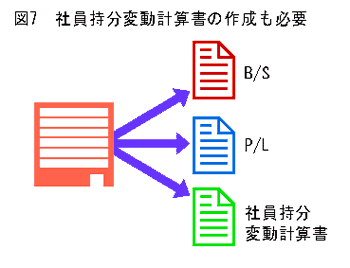
どんな組織が合同会社に向く?
合同会社は人的結合に重きを置いた会社形態であるため、合同会社に向く組織と向かない組織とがあります。他社との実験的事業の母体、既存事業の再編・共同分社化、産学協同等に伴い新設する合弁会社(ジョイント・ベンチャー)や士業、コンサルタント、デザイナー、プログラマー等の専門職の共同事務所、ファンドマネージャー等が合同会社にフィットするものと思われます。また、証券化のスキームに組み込まれることも予想されます。取締役会や監査役の設置が不要で機動的な業務執行が可能なため、株式会社ではなく合同会社として起業しておいて、IPOやM&Aといった出口が見えてから株式会社に転換するという起業スタイルも増えるものと思われます。
その他
合同会社では持分の払戻しが認められています。払戻しに伴い欠損金を計上することとなるような払戻しも債権者保護手続の実施を条件に認められています。
また、合同会社では社債を発行することもできます。さらに、合同会社や株式会社を相手方とする吸収分割若しくは株式交換に相当する行為等の企業再編行為も可能となります。
今後の検討課題
課題①:パススルー課税はどうなる?
合同会社においては、米国のLLCと同様パススルー課税(合同会社では課税されずに構成員の段階で課税されること)が導入されるかどうかが最大の焦点となっています。これについては平成18年度税制改正で議論される予定。制度の使い勝手を大きく左右するものだけに注目を集めています。財務省はパススルー課税に難色を示しており、まだまだ目が離せません。
課題②:監査はどうなる?
合同会社は有限責任であることから会社債権者の保護が重要となってきます。そこでテーマとして浮上したのが、合同会社でも大規模の会社(株式会社における大会社のような会社)については会計士の監査を必要とするのか否かです。これについては現段階では何も決まっていません。
課題③:名称はどうなる?
今一つぱっとしない名称の感がある「合同会社」ですが、現状ではあくまで仮称という位置付けです。要綱案でどのような名称となるのか、また、法律でその名称が維持されるのかは別問題といえます。現に、9月15日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会では、「協同会社」という名称が提案されています。
パススルー課税の可否で注目を集める
合同会社(仮称)のしくみを図解してみました!
新会社法(平成18年4月より施行予定)の目玉の一つともいえるのが、合同会社(仮称)です。これはいわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)といわれるものですが、具体的イメージがなかなかわかない読者も多いのでは。そこで、特集では、要綱案(第二次案)をベースに合同会社を図解してみました。なお、要綱案(第二次案)の合同会社に関する個所については29ページに掲載していますので参照してください。
合同会社ってなに?
合同会社(仮称。以下、単に合同会社と表記)とは「社員の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される特徴を有する新たな会社類型」をいいます。ここでのキーワードは、「有限責任」「組合的規律」の2点。この2つの概念は、前者が構成員と会社債権者の関係で、後者は構成員同士の関係であり、局面が異なる以上、お互いが排他的とはいえないまでも、現行の商法のもとでは両立しにくい概念であったといえます。
有限責任とは、会社の債務について、合同会社の社員(社員とは組織の構成員のこと。従業員のことではありません。合同会社の出資者のことです。)が責任を負わない、というもの。株式会社における株主の責任がその典型といえます。社員間のつながりが希薄化し、社員の個性が喪失した、いわゆる物的会社の社員になじむ責任といえます。
一方、組合的規律とは、「原則として全員一致で定款の変更その他の会社の在り方が決定され、社員自らが会社の業務の執行に当たるという規律」をいいます。社員間のつながりが濃厚ないわゆる人的会社や組合においてなじむ規律といえます。
このように合同会社とは、物的会社の性質と人的会社の性質を融合させようとする試みであることが分かります。わが国では会社形態としては初めての試みですが、諸外国では例があり、米国ではいわゆるLLCといわれるものがそれに該当します。
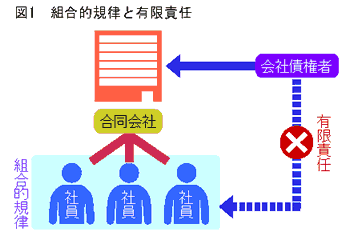
合同会社のしくみ
合同会社のしくみは上述のキーワードである「組合的規律」「有限責任」の2点から説明することができます。まず、組合的規律から導き出される規定としては、以下のようなものがあります。これらは合名会社の規律に準じているといえます。
・合同会社の成立後の定款の変更その他会社の在り方を決める際には、原則として社員全員の一致によるものとし、その意思決定に出資額の多寡は影響しない。
・合同会社成立後の社員の入社及び持分の譲渡の承認については、それぞれ原則として社員全員の一致によるものとする。
・業務執行権限は原則として社員全員にある。
なお、「合同」というと、複数の社員がいることが前提であるかのようなイメージがありますが、要綱案(第二次案)では、社員一人のみの合同会社の設立及び存続が認められています(図2)。また、合同会社の社員は法人でもよいとされています(図3)。その場合、当該法人において職務執行者の選任が必要となります(後述)。
また、有限責任に関連する規定としては
・合同会社の出資の目的は、金銭その他の財産のみに限られており、労務出資・信用出資はできない。
・合同会社の社員の出資については、全額払込主義がとられており、出資時にその全額を払い込む必要がある。
といった規定が挙げられています。
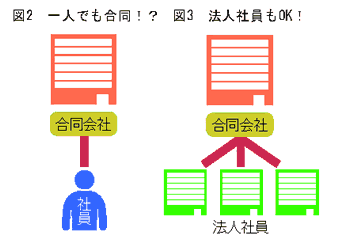
合同会社はどうやって業務執行するの?
合同会社の社員は、全員が業務執行権限を有するのが原則です(図4)。
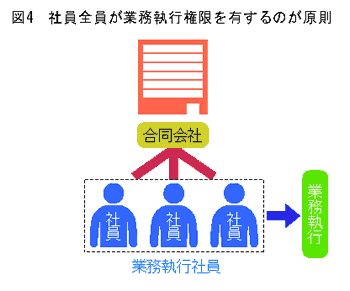
もっとも、全員が業務執行権限を有すると運営が不安定になりがちですし、経営能力の高い者に業務執行を委ねた方が効率がよいでしょう。とくに社員が有限責任であることを考慮すると、わずらわしさを排除したいというニーズもあります。そこで、合同会社では定款の定め又は社員全員の同意により、業務執行社員を選任することも認められる予定(図5及び30頁参照)。
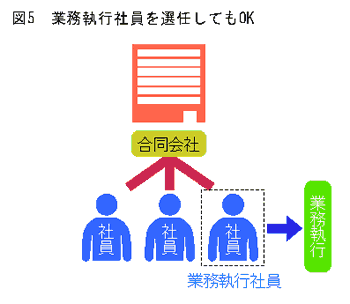
業務執行社員は、合同会社に対して民法の委任の規定に基づく善管注意義務及び忠実義務を負うこととなります。
なお、業務執行社員が法人の場合は、当該法人社員は自然人を職務執行者として選任する必要があります(図6)。
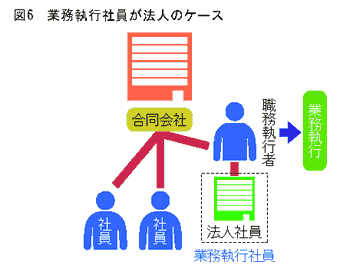
職務執行者の選任は当該法人社員が業務執行社員ではないケースでは不要です。
いずれにしろ、取締役会や監査役を置く必要はないので機動的な業務執行が可能となります。
合同会社の計算はどうなる?
合同会社では、貸借対照表・損益計算書・社員持分変動計算書を作成する必要があります。社員持分変動計算書とは聞きなれないものですが、新会社法下で株式会社に導入される予定の株主持分変動計算書(本誌082号33頁参照)に似たフォームとなるものと思われます。なお、要綱案(第二次案)では「合同会社の債権者は、その閲覧又は謄写の請求をすることができる」(30頁参照)とされていることから、決算公告までは要求されていないといえます。
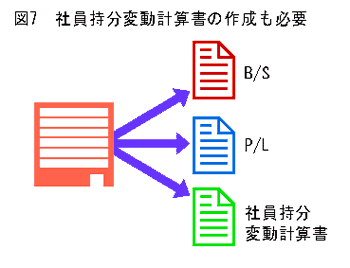
どんな組織が合同会社に向く?
合同会社は人的結合に重きを置いた会社形態であるため、合同会社に向く組織と向かない組織とがあります。他社との実験的事業の母体、既存事業の再編・共同分社化、産学協同等に伴い新設する合弁会社(ジョイント・ベンチャー)や士業、コンサルタント、デザイナー、プログラマー等の専門職の共同事務所、ファンドマネージャー等が合同会社にフィットするものと思われます。また、証券化のスキームに組み込まれることも予想されます。取締役会や監査役の設置が不要で機動的な業務執行が可能なため、株式会社ではなく合同会社として起業しておいて、IPOやM&Aといった出口が見えてから株式会社に転換するという起業スタイルも増えるものと思われます。
その他
合同会社では持分の払戻しが認められています。払戻しに伴い欠損金を計上することとなるような払戻しも債権者保護手続の実施を条件に認められています。
また、合同会社では社債を発行することもできます。さらに、合同会社や株式会社を相手方とする吸収分割若しくは株式交換に相当する行為等の企業再編行為も可能となります。
今後の検討課題
課題①:パススルー課税はどうなる?
合同会社においては、米国のLLCと同様パススルー課税(合同会社では課税されずに構成員の段階で課税されること)が導入されるかどうかが最大の焦点となっています。これについては平成18年度税制改正で議論される予定。制度の使い勝手を大きく左右するものだけに注目を集めています。財務省はパススルー課税に難色を示しており、まだまだ目が離せません。
課題②:監査はどうなる?
合同会社は有限責任であることから会社債権者の保護が重要となってきます。そこでテーマとして浮上したのが、合同会社でも大規模の会社(株式会社における大会社のような会社)については会計士の監査を必要とするのか否かです。これについては現段階では何も決まっていません。
課題③:名称はどうなる?
今一つぱっとしない名称の感がある「合同会社」ですが、現状ではあくまで仮称という位置付けです。要綱案でどのような名称となるのか、また、法律でその名称が維持されるのかは別問題といえます。現に、9月15日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会では、「協同会社」という名称が提案されています。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















