解説記事2004年10月11日 【解説】 包括外部監査と活用-2003年度「通信簿」-(2004年10月11日号・№086)
実 務 解 説
包括外部監査と活用-2003年度「通信簿」-
弁護士 井上善雄
1 包括外部監査と“通信簿”
1.包括外部監査制度の実施状況
平成11年度(1999年度)から全国の47都道府県、12政令市、25中核市、条例制定による任意実施都市2市(東京都八王子市・三重県四日市市。以下、これら条例による任意実施市区を「条例市区」という)の計86の地方公共団体(以下、「自治体」という)において、外部監査制度による包括外部監査と監査結果報告書の提示がスタートした。その後中核市や条例による任意実施の自治体が増加し、12年度は91自治体、13年度は95自治体、14年度は100自治体となり、15年度(2003年度)は、実施自治体は合計104、監査報告書は合計178テーマとなった。11年度から実施していた条例市区の四日市市(三重県)が15年度は実施していないが(条例廃止)、同市は中核市を目指しており近く再実施となろう。
なお、16年度には法定で義務付けられていない市はもちろん、神奈川県城山町が外部監査(包括・個別双方)を条例化して実施している。平成16年8月現在、全国には695市、1863町、529村の合計3087の市町村があるが、城山町の人口や財政レベルでいうと、その市町村数は900程度には達するであろう。
2.包括外部監査の趣旨(地方自治法252条の27~38)
現行法の包括外部監査(以下、「外部監査」という)とは、自治体が法2条14項と15項の趣旨を達成するため、包括外部監査人(以下、「監査人」という)の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とするものである(法252条の27第2項)。よって、地方公共団体の事務の①真実性、②適法性、③有効性、④効率性、⑤経済性が問われることになる。
外部監査は、全法令的見地からの適法性監査と、英国で採用されるVFM監査(Value For Money=人財投入に見合う価値があるか)、あるいは米国の3E監査-有効性(Effectiveness=住民福祉、公共目的への人財投入の適合性)・効率性(Efficiency=人財投入により最大限の効果をあげること)・経済性(Economy=最も少ない人財投入であること)-を含むものとして位置づけられる。
3.監査報告書の評価方法と評価基準
全国市民オンブズマン連絡会議の「包括外部監査の通信簿」は、平成11年度分から始め、市民に公表・提供された監査報告書をもとに評価している(後註)。15年度の評価も監査報告書のみに基づいている。
しかし、今回は個別報告書ごとのA~Eのランク付けをやめ、優れた監査報告書を選抜して「優秀賞」を贈ること、逆に大きな欠陥のある監査には「改善要望」を出すことにした。そして、実用性に注目した「活用賞」という評価もした。全報告書の総括評価表は従前より詳しくし、「優秀賞」の個別報告は拡充紹介し、従前のような全ての個別報告書の作成はしていない。
私達の評価の視点ないし基準は、次のとおりである。この点は、これまでと変わらない。
① 対象の選定は適切で監査結果は活用度があるか
i 具体的な目的根拠があって対象が選定されているか。
ii 監査テーマと結果が首長(自治体)が採用する有効性を持っているか。
iii 行政の改善の方向が具体化されているか。
② 監査が充実し、評価が適切であるか
i 新しい問題意識・発見があるか。
ii 適法性の監査について充実・適切であるか。
iii 3E監査について具体的な対象への適用とチェックがあるか。
iv テーマの数だけでなく質の高さがあるか。
v 行政結果の追認に終わっていないか。
③ 報告書・意見書は判りやすいか
i 市民が読んで判る記述になっているか。
ii 問題点や意見要点が明確に指摘されているか。
iii 専門用語などは解説・注釈があるか。
iv 表やデータが判りやすいものか。
4.監査対象と監査の視点
① 税・収入金・手数料
このテーマで最低限クリアすべき要件としては、事務処理の適法性や3E点検は当然として、その上で、i.個人情報保護の観点を含むシステム監査の視点、ii.課税漏れ防止手続の検証及び課税標準算定・賦課金額決定の適正手続の検証、iii.課税の公平の見地に立った賦課・徴収の適正かつ効率的執行の3点がある。
② 財産管理(公有土地・物品・現金・基金)
「土地」は、単に遊休化や見通しの甘さの指摘のみでは不十分で、そこに至る政策立案の過程や責任の所在を分析する必要がある。また、現地を実際に確かめる調査も必要である。
「物品管理」(法239条)に関しては、台帳整備や保管、棚卸点検の問題だけでなく、不実購入や必要性の乏しい購入、分割発注による随意契約の問題や期末などにまとめた大量発注等の点検が必要である。
「現金管理」は、本来、安全・正確という適法性点検が第一であり、本来は内部監査の領域であろう。
「基金」(法241条)は、当該基金の趣旨、積立、保管・運用、取崩し、利用にわたる点検が必要だが、低金利時代にどう運用すべきか、今後のあり方などの展望も必要である。
③ 施設管理
公共施設の管理は「箱もの行政」の管理問題であるものも多い。「収支不足」「赤字」の事実を指摘するだけでは不十分である。当該施設の企画段階に遡って収支見通しに問題はなかったか、その決定に関する責任の所在はどこにあるのかを検証しなければならない。
行政コスト計算は、現在の運営コストの計算だけでなく企画・建設コストまで含めたところでの妥当性を3Eの視点に立って分析する必要がある。将来に向けた収支分析も必要である。
保健・スポーツ・文化・福祉・公園の施設は、運営を自治体が出資する財団法人、株式会社等の第三セクターに委託していることが多い。施設の管理・運営を外郭団体に委託しているにもかかわらず、その外郭団体自体の「再委託」を含む経営管理の内容の点検も必要である。
平成15年6月に地方自治法が改正され、平成18年9月までに従来の「管理委託制度」は「指定管理者制度」に移行することとなり、民間委託が広がるとみられ、また、「地方独立行政法人」化の問題も検討事項になる。
④ 貸付金・債権管理・債務保証
「貸付金」は、適法性の点検は不可欠で、単に返済の滞納が多いこと等の指摘と改善だけでは不十分である。回収促進のための方策を組織・体制の点に踏み込んで具体的に提案しなければ意義ある監査とはならない。
「制度融資」は制度自体に「不正誘引」するものもあり、実際に大規模な不正事件も発生している。制度適用に問題はないか、制度自体が役割を終えたのではないかという疑問を持つことも必要である。制度維持にかかる人件費等もその政策のコストである。
「債権管理」は、的確な把握・管理だけでなく安全かつ有効で効率的な管理のチェックが必要であり、融資に伴う「損失補償」や「債務保証」も、そもそもその対象、方法、手続として適法であるかも問題である。「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」の規制についても視野に入れ適法性を判断すべきである。「隠れた債務保証」は脱法的処理ともいえ破局の際に大問題となる。
⑤ 病院事業
診療科別の損益分析、一般会計からの繰入金の分析、診療報酬の請求に関する分析、設備投資の生産性分析、医師・看護師の労働生産性分析等は必要であるが、単なる「経営コンサルティング」では評価できない。本来、公立病院は長期的な地域医療、地域福祉に関するグランドデザインの視点も必要である。適法性監査、経営分析、地域医療政策的観点の3つの要素全てにおいて高い評価のできる監査報告書でなければ満足とは言えない。
⑥ 教育・試験研究機関
専門的学究分野としての期待と現実の財務運営に落差のあるテーマであり、問題意識が重要である。保育園から大学までのそれぞれの教育機関や試験研究機関について、自治体における公共性、存在意義、有効性の視座が必要である。
⑦ 公営事業(特別会計)・企業局
公営事業も赤字のケースが多いだけに3Eの視点が欠かせない。基本的には公共政策目的、すなわち事業の有効性とその経済的投入との整合性である。赤字でも必要な事業であれば、その分費用対効果が厳密に分析されなければならない。代替可能な施策がないかも当然検討するべきである。
「上水道」の場合は、水源開発の問題は避けて通れない。「交通事業」の場合も自治体の交通政策の全体を踏まえる必要がある。「港湾事業」は現在道路とともに公共事業のあり方として反省が求められている。
「公営ギャンブル(競輪・競馬等)」は公益性としては財政収入の理由しかない。公共の福祉という観点からは百害あって一利なしと言っても過言ではなく、その百害の部分も「コスト」であるという見識が必要である。今では財政的貢献も少なく「やめる・やめない」ではなく、「どうやめるか」が問題であろう。
「環境・ゴミ・清掃」は、近年予算規模が巨大化し、企画・新設・管理の施設面と担当する人の人件費の面の双方及び将来の環境行政への視点など課題は多い。環境事業を行う一部事務組合の町村レベルは監査体制が弱く、条例化による外部監査も必要になっているといえる。
「住宅事業」は住宅政策そのものが時代とともに変わってきている現在、質・量ともに民間に劣っており必然性はなくなりつつある。存在意義は、社会的弱者に対する低廉で良好な住宅提供という政策目標以外にはない。この有効性への問題意識が必要である。
⑧ 出資団体・財政援助団体(外郭団体)
「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」という)による土地開発公社は、設立趣旨目的に照らした上での適法性監査と3E監査がポイントである。「塩漬け土地」の実態解明だけでは不十分であり、その原因に関する意思形成過程の解明と責任の所在の分析が重要である。公拡法が既に役割を終えているという認識も必要である。
行政の第三セクターへの「貸付金」や公社借入の「債務保証」も、第三セクターの破綻問題で重要となっている。不正貸付や「隠れた保証」は違法であり指摘するのは当然であるが、安易な保証はないか、そもそも必要性はどうだったのかが検証の対象である。現在の運営コストに問題がある場合には、その原因を検証した上で、実現可能な具体的改善意見を提示することが必要である。公社への補助金、委託、保証についても前記のとおりである。
外郭団体の存在理由も公益・政策目的との整合性が最大のポイントである。外郭団体の根拠は機動性や効率性・経済性(独立採算制)であるが、それも公益・政策目的との整合性があった上でのことであり、本当に効率性・経済性を実現できているのかという点が問題となる。外郭団体の経営責任の視点も重要で、役員を自治体幹部が「宛て職」「指定席」としていたり、天下り先となっていたりするケースも多い。平成14年4月に「公益法人等への一般職の地方公務の派遣等に関する法律」(以下、「派遣法」という)が施行されたが依然問題が多い。
外郭団体が議会や市民の目を覆うための「隠れ蓑」になっていることが多い。再委託や、競争入札を回避するために外郭団体が利用されていることもある。大規模な事業展開を行う外郭団体の場合は、長期的な採算性が重要な視点であるし、採算が取れていない場合(このような場合が非常に多い)は、需要予測を含めどのような根拠で決定がなされたかがポイントとなる。政策決定過程やその根拠の信頼性まで検証する必要がある。外郭団体は、i.計画・設立、ii.管理運営、iii.将来の事業展望までチェックされねばならない。
⑨ 補助金・寄付金
明確に個別ケースでの公益性や政策目的への適合性、公平性や透明性の検証が重要な要素である。自治体の予算の大きな部分を占める割には小口の多種多様な案件も多く、全体像の把握の程度や、対象の重要度を踏まえた実地調査の対象の選定も評価の要素となる。外郭団体への補助金は、意義が曖昧なまま始まったり、「前例化」「既得権化」したりしているものも多く、不透明さを伴うものが少なくない。i.合目的性・有効性、ii.比例原則、iii.公平・平等性、iv.経済・効率性、v.手続の公正性などが問われる。
⑩ 契約・入札・請負・委託
契約、委託そして公共事業の性質や意義を的確に捉え、踏み込んだ提案をしているかが問われる。入札は、真に一般入札か、指名入札その他の入札形態の是非も検討し、入札に参加した業者数、不当な参入制限がないこと、落札率等について説得力のあるデータを示す必要がある。直接的証拠の収集は困難でも、高い落札率、1位不動の状況、予定価格内1社、落札の循環性などから談合の存在に高い疑念を呈することができる。「入札回避」「競争回避」がないかも含めて調査し検証がなされなければならない。委託の場合は、何のために委託がなされるのかを問うことも必要である。「再委託」「丸投げ」や、「自己に対する委託」も要検討である。
⑪ 人件費・給与・退職金
人件費は自治体の必要的経費の中で大きなウエイトを占めており、その点検は欠かせなくなっている。民間より仕事は楽で給与は高いという市民の声がある。単に高いかどうかではなく、手当などが勤務実態に相応しているか、適法性監査と3E監査の点から説明責任を果たしているかにも視点を向けるべきであろう。
⑫ その他
外部監査の監査対象としては、これら以外にも様々なものがあるが、公金支出・債務負担行為は、全てのテーマにかかわる。また、数は少ないものの「議会・政務調査費」を取り上げたものも見られる。近時、警察の「裏金」などが大きな社会問題になっており「聖域」にしてはならない。ノーチェックの聖域は不正の温床となる。
このような一般的でない問題を取り上げた場合は、監査人の問題意識が鮮明で優れた報告書も少なくない。
⑬ まとめ
全てのテーマに共通して言えるのは、まず、問題の関連性、継続性を意識し、意思形成過程及びその責任の所在の検証をすることである。現状の問題点を指摘している監査報告書でも、原因や責任の所在まで追及しているものは意外と少ない。また、問題点を指摘するときには監査人の提案も同時に示してほしい。そういう意味で、説得力のあるシミュレーションを試みている監査報告書は高い評価ができる。改善のために付する意見は、具体的・実効的で、実行可能性のあるものでなければならない。抽象的に検討を求めるだけの監査意見には価値はない。監査人自身が実効性の検討まで行って予想される効果を提示すべきである。
適法性についての検証は全般的に甘い。形式的に手続を踏んであればよしとする傾向があり、規程や要綱は見ても根拠法まで遡って検討していない。関連する出資団体等の監査を行う場合には、まず、派遣職員の有無を確認し、職員が派遣されている場合には、派遣法の要件を充足しているか、派遣が所定の手続にしたがっているかなどを検証すべきである。
3E監査に関しては、効率性・経済性についてほとんど言及されている。一般論に終始しているものが多いが自治体が活用し得る見識と具体的意見を備えた監査報告書も増加してきている。有効性の監査は、行政の本質や公共性・公益性の評価、過去の行政の選択の是非を問うことにも係わり困難な面がある。当初の目的と客観的情勢と現在と将来の意義など検証することになる。政策を実行するための事前のアセスメントや代替案を含む政策選定の説明責任の点検といった方法もある。
外部監査の実効性を深めるためには、対象部局の説明の要点を紹介し、それに対してさらに是正措置や改善意見を述べることも有効である。
裁量とグレーゾーンの監査について、「理想」と「現実」の中での苦悶にまで達して監査しているものは、高いレベルにあることを示している。よい監査とは、事実の調査を尽くした上で、あるべきルールを細部までよく適用できるように指針を示し提言しているものである。補助金、委託契約の中には過去の「暫定処理」が続いているものも多い。火葬場、下水処理場、ごみ処理場など、従来「忌避施設」と呼ばれたものの周辺では、正面から説明や解決ができず、灰色の処理をしているケースが少なくない。
「新鮮で輝く監査報告書」は、監査人が、i.新しい視点を含め深くより広く調査し、ii.当該自治体の歴史と現実を的確に把握し、iii.自治体の採用すべきルール(時には条例改正案の提供)の細則や指針を示し、iv.個別的な事例についても是正すべき点や改善すべきことの意見を明確に示しているものである。
委託は直営による非効率や人件費の高額化による経済性の問題が根本にあり、民間ならば柔軟にできる人事・労働が直営では硬直化するというように「人」にかかわる点が大きい。直営での人件費と需用費負担と委託費負担とを、その事業の性質から配分や経済性を検討し、適法性と有効性、効率性、経済性を問うことが監査として必要となっている。
比較調査は、対象の行政が法令上の根拠や運用において同様である他の「先進」自治体の取り組みも知れるし、行政の3E点検には有効なひとつの方法になる。行政が横並び主義だけでは批判しなければならないが、先進自治体の経験も踏まえ、改革へ役立つならば、比較評価は判りやすい監査、意見になり得る。
公共性は、その有無や程度、また官としてしなければならないものかという点検が必要である。その結論は、究極的には国民・住民の決めるところとしても、その指標を整理し呈示して、市民が共同の財源から負担すべき当該行政事務の内容を法規や現在の自治体の政治責任・行政責任の所在から争いのない点で全うしているか、その行政遂行の方法を定めたルールから逸脱していないかなどの適法性監査と行政目的に照らしての3E点検が求められているのである。
5.平成15年度の評価
平成11年から5年間の監査報告書を調査してきたが、全国的にみるとその対象テーマはかなり網羅されるようになっている。監査人自身が外部(=市民)の眼を発現強化し、市民にもよくわかる監査を行い、良識ある市民との連帯関係を持つこと、そして、行政関係部局、外部団体を含めて、この監査を機に慣例遵守、既得利益固守から行政改革への道を具体的に歩むことである。
今回は、従来行ってきた全報告書のA~Eの5段階評価を改め、従来でいえばA・Bクラスの「優秀賞」と、行政と市民の双方からの活用度を検討して「活用賞」を贈り、また、従来のD・Eクラスから「改善要望」という点に特化した評価をすることにした。「改善要望」は、テーマの選定の問題、視点の欠陥、調査の充実度、わかりやすさなどで、強く改善を望むものである。
「優秀賞」は、都道府県では静岡県(業務委託)・三重県(委託料)・奈良県(補助金・貸付金)・鳥取県(観光行政)・大分県(地方債)・長崎県(補助金・貸付金)の6県、政令市以下では千葉市(廃棄物処理行政)・川崎市(教育委員会)・新潟市(業務委託)・松山市(財政援助団体)・坂出市(人件費)の5市の合計11自治体の監査報告書であった。そして、「ナンバーワン」と評価したのが新潟市のものであり、今回、「オンブズマン大賞」を贈ることにした。
活用賞は、北から順に都道府県では青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・千葉県・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・佐賀県・熊本県の25府県、政令市以下では、さいたま市・横浜市・名古屋市・広島市・北九州市・福岡市・郡山市・いわき市・宇都宮市・船橋市・横須賀市・相模原市・富山市・長野市・静岡市・浜松市・堺市・高槻市・奈良市・倉敷市・高知市・長崎市・熊本市・大分市・宮崎市・鹿児島市・文京区・目黒区・豊島区・八尾市・善通寺市の31市区、合計56自治体の62テーマの監査報告書である。
改善要望のものは、岩手県・栃木県・埼玉県・富山県・石川県・福井県・長野県・香川県・高知県・熊本県の10県と、札幌市・金沢市・姫路市・港区・八王子市の5市区の合計15自治体21テーマの監査報告書が対象である。
以上によれば、複数の監査報告書を公表された自治体では、活用賞と改善要望の2種の評価のものがあること、また結果としては「賞外」となった報告書がかなりあることになる。「賞外」は、「普通」というよりも、むしろ不満・難点が多いものである。
2 包括外部監査の活用
1.監査結果にもとづく措置
外部監査は、監査報告書が提出され、公表されることによって終わるものではない。外部監査によって、これまで自治体内部に潜んでいた問題、欠陥、損失、負債、リスクなどが明らかにされたものも少なくない。外部監査により、一般的には情報公開されない部分がまとまって整理されて市民に公開されるなどして役立つものが多い。
私達は、外部監査がその後の行政にどのように活かされたかについて、13年度から調査を始めた。この措置の公表内容の丁寧さから自治体が監査報告に具体的に対応し尊重しようとする姿勢の差や市民への説明度の差は見てとれる。自治体が指摘された点や意見に丁寧に対応しないのでは、監査人の労に報いるものではない。また、市民に対しての行政の説明責任を欠くものであり非難に値する。監査報告を受けた自治体は監査結果を真摯に受け止め、迅速かつ確実に改革を実行していくことを強く求めたい。
2.あるべき措置対応
外部監査は、行政が慣行化してきたものを具体的な対象部局の監査を通して問題点を指摘し、情報保存と公開、説明責任の分野にわたり改善方向を示すところに意義がある。行政のあるべき姿は次のとおりであろう。
① 監査結果を全庁的に受け止める…対象部局だけでなく同じ問題を抱える他部局でも措置対応する。
② 対応措置の計画化…時間と手続を要するものであっても、改善の具体的方向、日程、手法などについて対応する措置を示すべきである。
③ 首長の見解を示す…現行法制の制約、現行条例・規則の運用では対応できないもの、立法的解決をしなければならないものについては、現行法制の改正の必要がないのか行政全体の首長としてどのように考えるか見解を示すべきである。
④ 早期実行…自治体行政の取組を早期に推進する。
⑤ 措置通知と監査人の「検証」…自治体の講じる措置は、現行法上は監査人とは無関係に行われるが、監査人にとって自らの監査に対し首長や対象団体がどう対応するかは重大な関心事である。検証も一定期限を付した上で行い、検証の結果も速やかに公表されるべきである。
⑥ 以上をまとめると、次のとおり日程化できる。
i.過去・現在の是正可能事項は直ちに実施する。
ii.制度改革については6ヶ月程度で改善内容を確定する。
iii.例外的事情のない限り1年以内に全面実行開始を宣言する。
3.外部監査の今後の課題と活用法
① 市民にわかる外部監査
監査報告書は具体的でわかりやすいものにし、市民の関心をも呼ぶ工夫が求められる。報告書を公報やホームページ等に公表する際には、より市民の理解を得やすくなるよう工夫も求めたい。
② 監査人と補助者の選任
監査人の選任は外部監査の役割を左右する重要な要素である。市民によくわかる選任理由も発表し、弁護士会、公認会計士協会、税理士会が自信を持って有能な監査人を推薦できることも必要であろう。監査人や補助者の供給源としての社会的責任もある。監査人選考については、「選考委員会」を設置したり、公募方式を導入したりしている自治体等もみられる。監査人選任が市民から理解されるために透明性を確保し、合議化して選任理由を明確にすることも大切である。
③ 外部監査に対する「行政」「議会」の協力
施行5年を経て、行政側も監査人に協力的になったはずであろうが、「外部監査に対して行政が協力的でない」という苦労話が漏れ聞こえてくる。監査を受ける側と監査する側の「摩擦」は避け難いのかもしれないが、監査人への協力を首長が明確に指揮し、監査人も確固たる姿勢で望むことで克服すべきである。
④ 行政の措置義務の法定と説明責任
現行法上、監査結果にもとづく措置は義務付けられておらず、措置が講じられないときは監査委員への通知も監査委員による措置結果の公表もなされないことになる。しかし、90日以内に第1次改善措置通知、1年以内に意見を含む全項目について措置の有無についての通知を義務付けるべきである。対象部局がどうしても措置を講じられないというのであれば、措置を講じられない項目についてその理由と将来の見通し等を付して対応できない旨を通知し、監査委員はこれも公表すべきである。
⑤ 監査対象の範囲と内容
政策の是非は外部監査の対象とはされていないといわれるが、施策の適正・効率性が財務の適正・効率性にかかわっていたり、行政監査と財務監査を峻別しきれなかったりする場合が多く、その点で踏み込む必要がある。立法的には行政監査を担当できることも制度的に考えるべきである。また、決算監査も対象と考えられてよい。さらに、現在は条例により選択できる財政援助団体等の監査はその外部監査の必要性から考えて制約は無くすべきである。
⑥ 監査委員監査の改革と外部監査
監査委員監査制度には、人選・事務局など人的組織と独立性に課題がある。監査事務局は自治体職員の回り持ち、配転職となって、外部性・独立性がないと批判され、監査委員が必ずしも専門的能力や十分な独立的基盤がない「名誉職」化している自治体では、事務局主導の日常の定期的・形式的監査の処理で手一杯というところも多い。小さな市町村では監査委員の力が弱いという意見もある。監査委員は、まず本来の「光」と「力」を取り戻すべきと考える。その上で、外部監査との相互向上が必要である。
⑦ 外部監査と行財政改革
財政がひっ迫し行財政改革が求められ、増税の前に無駄な出費や不合理な支出を少しでもなくすことがこれほどまで求められている時代はない。自治体が「市民の共同船」であれば、乗客は「船賃」(税などの負担金)で安全と公正を維持して運航されているのかを知る権利がある。その説明責任は委託された船長らにある。「船」の安全性(適法性)、行き先(有効性)、行程や燃費(効率性・経済性)等については独立性のある検査・点検機関の機能強化が徹底して必要となっている。この検査を内部監査の監査委員と外部の外部監査人が十分に果たすことが求められている。
⑧ 行政での活用
これまでの政治や行財政は、予算獲得や配分決定に熱心であったが、それが「利権」につながっていた。予算が正しく使われたか、その目的を果たしたかの事後検証であるはずの決算はルーズであった。予算の決定・執行・決算により、検証手続によって行政にフィードバックし、税の適正かつ有効利用に活かすという視点があまりにも不足していた。21世紀の自治体運営は予算からの事前調査・評価の充実と執行途中の点検・見直し・修正と事後の評価・反省という検査・検証の手法を強化活用していく以外に正しい進路は選べないであろう。
⑨ 議員と監査報告書の活用
i 議会の力の「低さ」
議会は、長以下の行政を監視・監督し、市民にとって公正、有効、効率的、経済的な行政がなされているかの審理機関でもあるが、その機能を必ずしも十分には果たせていない。議会には予算審議と決算審議という重要な使命があるが、全体的にチェックしようとする議員がいても、全体像はもとより個別についてはほとんどつかみがたく、短い予算・決算審議の期間に会派議席数で時間配分される議会で問題を追求する時間的余欲は少ない。
ii 議員と監査委員
議員は意外に行政情報から閉ざされている。まして、会計分析に素人の議員が監査委員として能力をどれだけ発揮できるか、また発揮できているかについては、厳しい評価をせざるを得ない。そこにも外部監査の意義がある。
⑩ 監査報告書がわからない議員は「失格」
議員たるもの監査報告書を読めない、わからないでは、能力的に失格であろう。現状では「失格」の議員もいるであろうが、自己の自治体の監査報告書はもちろん、他の自治体の例を見るならば、共通課題、共通の不当な事実が必ず発見できるし、よい監査からは是正の方向性についても知識を得られるであろう。監査人の中には、長だけでなく議長にも報告書の説明をしている例もあるようである。しかし、議会が詳しく監査報告を聞いた例はほとんど聞かれなかった。委員会その他自由に意見を聞く機会を持つことが期待される。
⑪ 議会・議員は監査に基づく「措置」の点検をする
議会は、監査結果等のうち行政の措置によって是正事項が達成されているかを自らの見識を加えて追求する場を持ってほしい。1年たっても是正されない不当な行政など、議会にとっては絶対に見逃せないはずである。
4.市民の活用へのアクセス
以上の全体を市民がチェックすることになる。まずは、監査報告書を入手し読んでみることである。もちろん関心のあるテーマからであろうが、関心を持つ市民が一人でも多いことが、外部監査と行政の向上に貢献する。
5.市民の外部監査活用法
① わが自治体の行政実態を知る
監査報告書は特定自治体の特定部門の調査報告であるが、その調査は類似自治体、周辺自治体との相対比較をしていることも多く、比較自治体の実態をも示しているものが少なくない。また、性質上地方自治体共通のテーマが多く、具体的データは違っても検討の手法や問題点の指摘は他の地方自治体についても該当することが多い。したがって、住民、自治体の議員や行政職員にとっても、問題意識のあるテーマについて研究し比較検討する上で、監査報告書は有意義なものが多い。最近は、ほとんどの都道府県で監査報告書が公報等で全部掲載されており、自治体のホームページから入手できたり、公報を有料で販売されたりしているところもある。
② 財政状況を知る
外部監査では、具体的な財政・支出負担が明らかにされる。当該地方自治体での対象行為や部局の経済的な位置付けも金銭的数字で示される。私達市民の税金、あるいは負担がどの程度であるか、公平であるか、また他の行政需要(財政項目)との比較上どうなっているかも教えてくれる。
③ 適法性を知る
監査の第一の目的は、行政執行、財政行為の適法性の点検にある。証拠と事実の不適合は真実性に反するという一点だけで適法性を欠くものである。監査報告書を熟読すればその疑惑を窺わせたり、対象部局の協力がなかったりするための限界を示しているものもある。包括外部監査は個々の行政の不正・不当点の指摘を受けて行うものではなく、監査人の適法性の点検は結果としてまだまだ弱い。形式的な法令基準に準拠していれば合規性ありとしていることが少なくない。この点は裁量行政に極めて甘い監査となる。しかし、その弱さはあってもそのテーマの部門での適法性の所在を知る上で有益である。
④ 自治体行財政の3Eを知る
i 有効性(合目的性)
自治体の行政行為,財政支出(負担)を伴う行為には当然ながら目的がある。その目的の正当性は法令・条例に示され、目的条項や法定の要件原則から導かれる。時、場所、対象(人・ケース)等に応じた具体的合目的性が要求される。
例えば、補助金の交付は、「公益性の必要」という要件解釈にもなり、当該自治体の補助によって達成しようとする公共目的に照らし一般的に有効性を持つにとどまらず、具体的な公共目的がその補助により獲得できること、他の同種団体と比較して補助の優越性を持っていることが要件となる。
ii 効率性
自治体における効率とは、自治体の人と公金等の投入によって、より大きな目的が達成されているかという「程度」の問題である。その検証は強制力による税の限られた財源能力に照らし、どれだけ最大限の効率を目指しているか厳正に審査されなければならない。
iii 経済性
ここでの経済性とは、人と公金・資材の投入を小さくすることである。効率的運営は経済性もあるので効率性類似の領域もあるが、絶対的な出費額の点で異なる。ここでも法令の厳正な適用が問題となる。この点、過去おろそかになっていたものも少なくないことは否めない。
⑤ 個別監査報告書のテーマと活用法
5年間に取り上げたれた監査対象は今や912テーマに及ぶ。外部監査の中から参考にし、活用するものを探すことが可能である。これらを手がかりに、あるべき行政像が求められる。
(註) 全国市民オンブズマン連絡会議の「包括外部監査の通信簿」は1999年版から毎年発行され、2003年度版(本年8月発行)まで5期を重ねている。黄色の表紙で「イエローブック」と呼ばれてもいるが、2003年度版はもちろん2001年度版・2002年度版も若干の残部がある。申込み・問い合わせは、「市民オンブズマン(大阪)包括外部監査評価班事務局(電話:06-6202-5051)」まで。
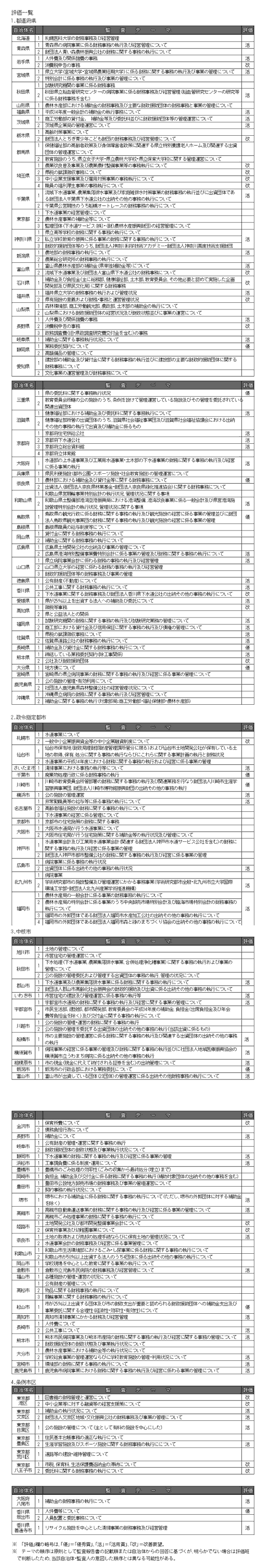
包括外部監査と活用-2003年度「通信簿」-
弁護士 井上善雄
1 包括外部監査と“通信簿”
1.包括外部監査制度の実施状況
平成11年度(1999年度)から全国の47都道府県、12政令市、25中核市、条例制定による任意実施都市2市(東京都八王子市・三重県四日市市。以下、これら条例による任意実施市区を「条例市区」という)の計86の地方公共団体(以下、「自治体」という)において、外部監査制度による包括外部監査と監査結果報告書の提示がスタートした。その後中核市や条例による任意実施の自治体が増加し、12年度は91自治体、13年度は95自治体、14年度は100自治体となり、15年度(2003年度)は、実施自治体は合計104、監査報告書は合計178テーマとなった。11年度から実施していた条例市区の四日市市(三重県)が15年度は実施していないが(条例廃止)、同市は中核市を目指しており近く再実施となろう。
なお、16年度には法定で義務付けられていない市はもちろん、神奈川県城山町が外部監査(包括・個別双方)を条例化して実施している。平成16年8月現在、全国には695市、1863町、529村の合計3087の市町村があるが、城山町の人口や財政レベルでいうと、その市町村数は900程度には達するであろう。
2.包括外部監査の趣旨(地方自治法252条の27~38)
現行法の包括外部監査(以下、「外部監査」という)とは、自治体が法2条14項と15項の趣旨を達成するため、包括外部監査人(以下、「監査人」という)の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とするものである(法252条の27第2項)。よって、地方公共団体の事務の①真実性、②適法性、③有効性、④効率性、⑤経済性が問われることになる。
外部監査は、全法令的見地からの適法性監査と、英国で採用されるVFM監査(Value For Money=人財投入に見合う価値があるか)、あるいは米国の3E監査-有効性(Effectiveness=住民福祉、公共目的への人財投入の適合性)・効率性(Efficiency=人財投入により最大限の効果をあげること)・経済性(Economy=最も少ない人財投入であること)-を含むものとして位置づけられる。
3.監査報告書の評価方法と評価基準
全国市民オンブズマン連絡会議の「包括外部監査の通信簿」は、平成11年度分から始め、市民に公表・提供された監査報告書をもとに評価している(後註)。15年度の評価も監査報告書のみに基づいている。
しかし、今回は個別報告書ごとのA~Eのランク付けをやめ、優れた監査報告書を選抜して「優秀賞」を贈ること、逆に大きな欠陥のある監査には「改善要望」を出すことにした。そして、実用性に注目した「活用賞」という評価もした。全報告書の総括評価表は従前より詳しくし、「優秀賞」の個別報告は拡充紹介し、従前のような全ての個別報告書の作成はしていない。
私達の評価の視点ないし基準は、次のとおりである。この点は、これまでと変わらない。
① 対象の選定は適切で監査結果は活用度があるか
i 具体的な目的根拠があって対象が選定されているか。
ii 監査テーマと結果が首長(自治体)が採用する有効性を持っているか。
iii 行政の改善の方向が具体化されているか。
② 監査が充実し、評価が適切であるか
i 新しい問題意識・発見があるか。
ii 適法性の監査について充実・適切であるか。
iii 3E監査について具体的な対象への適用とチェックがあるか。
iv テーマの数だけでなく質の高さがあるか。
v 行政結果の追認に終わっていないか。
③ 報告書・意見書は判りやすいか
i 市民が読んで判る記述になっているか。
ii 問題点や意見要点が明確に指摘されているか。
iii 専門用語などは解説・注釈があるか。
iv 表やデータが判りやすいものか。
4.監査対象と監査の視点
① 税・収入金・手数料
このテーマで最低限クリアすべき要件としては、事務処理の適法性や3E点検は当然として、その上で、i.個人情報保護の観点を含むシステム監査の視点、ii.課税漏れ防止手続の検証及び課税標準算定・賦課金額決定の適正手続の検証、iii.課税の公平の見地に立った賦課・徴収の適正かつ効率的執行の3点がある。
② 財産管理(公有土地・物品・現金・基金)
「土地」は、単に遊休化や見通しの甘さの指摘のみでは不十分で、そこに至る政策立案の過程や責任の所在を分析する必要がある。また、現地を実際に確かめる調査も必要である。
「物品管理」(法239条)に関しては、台帳整備や保管、棚卸点検の問題だけでなく、不実購入や必要性の乏しい購入、分割発注による随意契約の問題や期末などにまとめた大量発注等の点検が必要である。
「現金管理」は、本来、安全・正確という適法性点検が第一であり、本来は内部監査の領域であろう。
「基金」(法241条)は、当該基金の趣旨、積立、保管・運用、取崩し、利用にわたる点検が必要だが、低金利時代にどう運用すべきか、今後のあり方などの展望も必要である。
③ 施設管理
公共施設の管理は「箱もの行政」の管理問題であるものも多い。「収支不足」「赤字」の事実を指摘するだけでは不十分である。当該施設の企画段階に遡って収支見通しに問題はなかったか、その決定に関する責任の所在はどこにあるのかを検証しなければならない。
行政コスト計算は、現在の運営コストの計算だけでなく企画・建設コストまで含めたところでの妥当性を3Eの視点に立って分析する必要がある。将来に向けた収支分析も必要である。
保健・スポーツ・文化・福祉・公園の施設は、運営を自治体が出資する財団法人、株式会社等の第三セクターに委託していることが多い。施設の管理・運営を外郭団体に委託しているにもかかわらず、その外郭団体自体の「再委託」を含む経営管理の内容の点検も必要である。
平成15年6月に地方自治法が改正され、平成18年9月までに従来の「管理委託制度」は「指定管理者制度」に移行することとなり、民間委託が広がるとみられ、また、「地方独立行政法人」化の問題も検討事項になる。
④ 貸付金・債権管理・債務保証
「貸付金」は、適法性の点検は不可欠で、単に返済の滞納が多いこと等の指摘と改善だけでは不十分である。回収促進のための方策を組織・体制の点に踏み込んで具体的に提案しなければ意義ある監査とはならない。
「制度融資」は制度自体に「不正誘引」するものもあり、実際に大規模な不正事件も発生している。制度適用に問題はないか、制度自体が役割を終えたのではないかという疑問を持つことも必要である。制度維持にかかる人件費等もその政策のコストである。
「債権管理」は、的確な把握・管理だけでなく安全かつ有効で効率的な管理のチェックが必要であり、融資に伴う「損失補償」や「債務保証」も、そもそもその対象、方法、手続として適法であるかも問題である。「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」の規制についても視野に入れ適法性を判断すべきである。「隠れた債務保証」は脱法的処理ともいえ破局の際に大問題となる。
⑤ 病院事業
診療科別の損益分析、一般会計からの繰入金の分析、診療報酬の請求に関する分析、設備投資の生産性分析、医師・看護師の労働生産性分析等は必要であるが、単なる「経営コンサルティング」では評価できない。本来、公立病院は長期的な地域医療、地域福祉に関するグランドデザインの視点も必要である。適法性監査、経営分析、地域医療政策的観点の3つの要素全てにおいて高い評価のできる監査報告書でなければ満足とは言えない。
⑥ 教育・試験研究機関
専門的学究分野としての期待と現実の財務運営に落差のあるテーマであり、問題意識が重要である。保育園から大学までのそれぞれの教育機関や試験研究機関について、自治体における公共性、存在意義、有効性の視座が必要である。
⑦ 公営事業(特別会計)・企業局
公営事業も赤字のケースが多いだけに3Eの視点が欠かせない。基本的には公共政策目的、すなわち事業の有効性とその経済的投入との整合性である。赤字でも必要な事業であれば、その分費用対効果が厳密に分析されなければならない。代替可能な施策がないかも当然検討するべきである。
「上水道」の場合は、水源開発の問題は避けて通れない。「交通事業」の場合も自治体の交通政策の全体を踏まえる必要がある。「港湾事業」は現在道路とともに公共事業のあり方として反省が求められている。
「公営ギャンブル(競輪・競馬等)」は公益性としては財政収入の理由しかない。公共の福祉という観点からは百害あって一利なしと言っても過言ではなく、その百害の部分も「コスト」であるという見識が必要である。今では財政的貢献も少なく「やめる・やめない」ではなく、「どうやめるか」が問題であろう。
「環境・ゴミ・清掃」は、近年予算規模が巨大化し、企画・新設・管理の施設面と担当する人の人件費の面の双方及び将来の環境行政への視点など課題は多い。環境事業を行う一部事務組合の町村レベルは監査体制が弱く、条例化による外部監査も必要になっているといえる。
「住宅事業」は住宅政策そのものが時代とともに変わってきている現在、質・量ともに民間に劣っており必然性はなくなりつつある。存在意義は、社会的弱者に対する低廉で良好な住宅提供という政策目標以外にはない。この有効性への問題意識が必要である。
⑧ 出資団体・財政援助団体(外郭団体)
「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」という)による土地開発公社は、設立趣旨目的に照らした上での適法性監査と3E監査がポイントである。「塩漬け土地」の実態解明だけでは不十分であり、その原因に関する意思形成過程の解明と責任の所在の分析が重要である。公拡法が既に役割を終えているという認識も必要である。
行政の第三セクターへの「貸付金」や公社借入の「債務保証」も、第三セクターの破綻問題で重要となっている。不正貸付や「隠れた保証」は違法であり指摘するのは当然であるが、安易な保証はないか、そもそも必要性はどうだったのかが検証の対象である。現在の運営コストに問題がある場合には、その原因を検証した上で、実現可能な具体的改善意見を提示することが必要である。公社への補助金、委託、保証についても前記のとおりである。
外郭団体の存在理由も公益・政策目的との整合性が最大のポイントである。外郭団体の根拠は機動性や効率性・経済性(独立採算制)であるが、それも公益・政策目的との整合性があった上でのことであり、本当に効率性・経済性を実現できているのかという点が問題となる。外郭団体の経営責任の視点も重要で、役員を自治体幹部が「宛て職」「指定席」としていたり、天下り先となっていたりするケースも多い。平成14年4月に「公益法人等への一般職の地方公務の派遣等に関する法律」(以下、「派遣法」という)が施行されたが依然問題が多い。
外郭団体が議会や市民の目を覆うための「隠れ蓑」になっていることが多い。再委託や、競争入札を回避するために外郭団体が利用されていることもある。大規模な事業展開を行う外郭団体の場合は、長期的な採算性が重要な視点であるし、採算が取れていない場合(このような場合が非常に多い)は、需要予測を含めどのような根拠で決定がなされたかがポイントとなる。政策決定過程やその根拠の信頼性まで検証する必要がある。外郭団体は、i.計画・設立、ii.管理運営、iii.将来の事業展望までチェックされねばならない。
⑨ 補助金・寄付金
明確に個別ケースでの公益性や政策目的への適合性、公平性や透明性の検証が重要な要素である。自治体の予算の大きな部分を占める割には小口の多種多様な案件も多く、全体像の把握の程度や、対象の重要度を踏まえた実地調査の対象の選定も評価の要素となる。外郭団体への補助金は、意義が曖昧なまま始まったり、「前例化」「既得権化」したりしているものも多く、不透明さを伴うものが少なくない。i.合目的性・有効性、ii.比例原則、iii.公平・平等性、iv.経済・効率性、v.手続の公正性などが問われる。
⑩ 契約・入札・請負・委託
契約、委託そして公共事業の性質や意義を的確に捉え、踏み込んだ提案をしているかが問われる。入札は、真に一般入札か、指名入札その他の入札形態の是非も検討し、入札に参加した業者数、不当な参入制限がないこと、落札率等について説得力のあるデータを示す必要がある。直接的証拠の収集は困難でも、高い落札率、1位不動の状況、予定価格内1社、落札の循環性などから談合の存在に高い疑念を呈することができる。「入札回避」「競争回避」がないかも含めて調査し検証がなされなければならない。委託の場合は、何のために委託がなされるのかを問うことも必要である。「再委託」「丸投げ」や、「自己に対する委託」も要検討である。
⑪ 人件費・給与・退職金
人件費は自治体の必要的経費の中で大きなウエイトを占めており、その点検は欠かせなくなっている。民間より仕事は楽で給与は高いという市民の声がある。単に高いかどうかではなく、手当などが勤務実態に相応しているか、適法性監査と3E監査の点から説明責任を果たしているかにも視点を向けるべきであろう。
⑫ その他
外部監査の監査対象としては、これら以外にも様々なものがあるが、公金支出・債務負担行為は、全てのテーマにかかわる。また、数は少ないものの「議会・政務調査費」を取り上げたものも見られる。近時、警察の「裏金」などが大きな社会問題になっており「聖域」にしてはならない。ノーチェックの聖域は不正の温床となる。
このような一般的でない問題を取り上げた場合は、監査人の問題意識が鮮明で優れた報告書も少なくない。
⑬ まとめ
全てのテーマに共通して言えるのは、まず、問題の関連性、継続性を意識し、意思形成過程及びその責任の所在の検証をすることである。現状の問題点を指摘している監査報告書でも、原因や責任の所在まで追及しているものは意外と少ない。また、問題点を指摘するときには監査人の提案も同時に示してほしい。そういう意味で、説得力のあるシミュレーションを試みている監査報告書は高い評価ができる。改善のために付する意見は、具体的・実効的で、実行可能性のあるものでなければならない。抽象的に検討を求めるだけの監査意見には価値はない。監査人自身が実効性の検討まで行って予想される効果を提示すべきである。
適法性についての検証は全般的に甘い。形式的に手続を踏んであればよしとする傾向があり、規程や要綱は見ても根拠法まで遡って検討していない。関連する出資団体等の監査を行う場合には、まず、派遣職員の有無を確認し、職員が派遣されている場合には、派遣法の要件を充足しているか、派遣が所定の手続にしたがっているかなどを検証すべきである。
3E監査に関しては、効率性・経済性についてほとんど言及されている。一般論に終始しているものが多いが自治体が活用し得る見識と具体的意見を備えた監査報告書も増加してきている。有効性の監査は、行政の本質や公共性・公益性の評価、過去の行政の選択の是非を問うことにも係わり困難な面がある。当初の目的と客観的情勢と現在と将来の意義など検証することになる。政策を実行するための事前のアセスメントや代替案を含む政策選定の説明責任の点検といった方法もある。
外部監査の実効性を深めるためには、対象部局の説明の要点を紹介し、それに対してさらに是正措置や改善意見を述べることも有効である。
裁量とグレーゾーンの監査について、「理想」と「現実」の中での苦悶にまで達して監査しているものは、高いレベルにあることを示している。よい監査とは、事実の調査を尽くした上で、あるべきルールを細部までよく適用できるように指針を示し提言しているものである。補助金、委託契約の中には過去の「暫定処理」が続いているものも多い。火葬場、下水処理場、ごみ処理場など、従来「忌避施設」と呼ばれたものの周辺では、正面から説明や解決ができず、灰色の処理をしているケースが少なくない。
「新鮮で輝く監査報告書」は、監査人が、i.新しい視点を含め深くより広く調査し、ii.当該自治体の歴史と現実を的確に把握し、iii.自治体の採用すべきルール(時には条例改正案の提供)の細則や指針を示し、iv.個別的な事例についても是正すべき点や改善すべきことの意見を明確に示しているものである。
委託は直営による非効率や人件費の高額化による経済性の問題が根本にあり、民間ならば柔軟にできる人事・労働が直営では硬直化するというように「人」にかかわる点が大きい。直営での人件費と需用費負担と委託費負担とを、その事業の性質から配分や経済性を検討し、適法性と有効性、効率性、経済性を問うことが監査として必要となっている。
比較調査は、対象の行政が法令上の根拠や運用において同様である他の「先進」自治体の取り組みも知れるし、行政の3E点検には有効なひとつの方法になる。行政が横並び主義だけでは批判しなければならないが、先進自治体の経験も踏まえ、改革へ役立つならば、比較評価は判りやすい監査、意見になり得る。
公共性は、その有無や程度、また官としてしなければならないものかという点検が必要である。その結論は、究極的には国民・住民の決めるところとしても、その指標を整理し呈示して、市民が共同の財源から負担すべき当該行政事務の内容を法規や現在の自治体の政治責任・行政責任の所在から争いのない点で全うしているか、その行政遂行の方法を定めたルールから逸脱していないかなどの適法性監査と行政目的に照らしての3E点検が求められているのである。
5.平成15年度の評価
平成11年から5年間の監査報告書を調査してきたが、全国的にみるとその対象テーマはかなり網羅されるようになっている。監査人自身が外部(=市民)の眼を発現強化し、市民にもよくわかる監査を行い、良識ある市民との連帯関係を持つこと、そして、行政関係部局、外部団体を含めて、この監査を機に慣例遵守、既得利益固守から行政改革への道を具体的に歩むことである。
今回は、従来行ってきた全報告書のA~Eの5段階評価を改め、従来でいえばA・Bクラスの「優秀賞」と、行政と市民の双方からの活用度を検討して「活用賞」を贈り、また、従来のD・Eクラスから「改善要望」という点に特化した評価をすることにした。「改善要望」は、テーマの選定の問題、視点の欠陥、調査の充実度、わかりやすさなどで、強く改善を望むものである。
「優秀賞」は、都道府県では静岡県(業務委託)・三重県(委託料)・奈良県(補助金・貸付金)・鳥取県(観光行政)・大分県(地方債)・長崎県(補助金・貸付金)の6県、政令市以下では千葉市(廃棄物処理行政)・川崎市(教育委員会)・新潟市(業務委託)・松山市(財政援助団体)・坂出市(人件費)の5市の合計11自治体の監査報告書であった。そして、「ナンバーワン」と評価したのが新潟市のものであり、今回、「オンブズマン大賞」を贈ることにした。
活用賞は、北から順に都道府県では青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・千葉県・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・佐賀県・熊本県の25府県、政令市以下では、さいたま市・横浜市・名古屋市・広島市・北九州市・福岡市・郡山市・いわき市・宇都宮市・船橋市・横須賀市・相模原市・富山市・長野市・静岡市・浜松市・堺市・高槻市・奈良市・倉敷市・高知市・長崎市・熊本市・大分市・宮崎市・鹿児島市・文京区・目黒区・豊島区・八尾市・善通寺市の31市区、合計56自治体の62テーマの監査報告書である。
改善要望のものは、岩手県・栃木県・埼玉県・富山県・石川県・福井県・長野県・香川県・高知県・熊本県の10県と、札幌市・金沢市・姫路市・港区・八王子市の5市区の合計15自治体21テーマの監査報告書が対象である。
以上によれば、複数の監査報告書を公表された自治体では、活用賞と改善要望の2種の評価のものがあること、また結果としては「賞外」となった報告書がかなりあることになる。「賞外」は、「普通」というよりも、むしろ不満・難点が多いものである。
2 包括外部監査の活用
1.監査結果にもとづく措置
外部監査は、監査報告書が提出され、公表されることによって終わるものではない。外部監査によって、これまで自治体内部に潜んでいた問題、欠陥、損失、負債、リスクなどが明らかにされたものも少なくない。外部監査により、一般的には情報公開されない部分がまとまって整理されて市民に公開されるなどして役立つものが多い。
私達は、外部監査がその後の行政にどのように活かされたかについて、13年度から調査を始めた。この措置の公表内容の丁寧さから自治体が監査報告に具体的に対応し尊重しようとする姿勢の差や市民への説明度の差は見てとれる。自治体が指摘された点や意見に丁寧に対応しないのでは、監査人の労に報いるものではない。また、市民に対しての行政の説明責任を欠くものであり非難に値する。監査報告を受けた自治体は監査結果を真摯に受け止め、迅速かつ確実に改革を実行していくことを強く求めたい。
2.あるべき措置対応
外部監査は、行政が慣行化してきたものを具体的な対象部局の監査を通して問題点を指摘し、情報保存と公開、説明責任の分野にわたり改善方向を示すところに意義がある。行政のあるべき姿は次のとおりであろう。
① 監査結果を全庁的に受け止める…対象部局だけでなく同じ問題を抱える他部局でも措置対応する。
② 対応措置の計画化…時間と手続を要するものであっても、改善の具体的方向、日程、手法などについて対応する措置を示すべきである。
③ 首長の見解を示す…現行法制の制約、現行条例・規則の運用では対応できないもの、立法的解決をしなければならないものについては、現行法制の改正の必要がないのか行政全体の首長としてどのように考えるか見解を示すべきである。
④ 早期実行…自治体行政の取組を早期に推進する。
⑤ 措置通知と監査人の「検証」…自治体の講じる措置は、現行法上は監査人とは無関係に行われるが、監査人にとって自らの監査に対し首長や対象団体がどう対応するかは重大な関心事である。検証も一定期限を付した上で行い、検証の結果も速やかに公表されるべきである。
⑥ 以上をまとめると、次のとおり日程化できる。
i.過去・現在の是正可能事項は直ちに実施する。
ii.制度改革については6ヶ月程度で改善内容を確定する。
iii.例外的事情のない限り1年以内に全面実行開始を宣言する。
3.外部監査の今後の課題と活用法
① 市民にわかる外部監査
監査報告書は具体的でわかりやすいものにし、市民の関心をも呼ぶ工夫が求められる。報告書を公報やホームページ等に公表する際には、より市民の理解を得やすくなるよう工夫も求めたい。
② 監査人と補助者の選任
監査人の選任は外部監査の役割を左右する重要な要素である。市民によくわかる選任理由も発表し、弁護士会、公認会計士協会、税理士会が自信を持って有能な監査人を推薦できることも必要であろう。監査人や補助者の供給源としての社会的責任もある。監査人選考については、「選考委員会」を設置したり、公募方式を導入したりしている自治体等もみられる。監査人選任が市民から理解されるために透明性を確保し、合議化して選任理由を明確にすることも大切である。
③ 外部監査に対する「行政」「議会」の協力
施行5年を経て、行政側も監査人に協力的になったはずであろうが、「外部監査に対して行政が協力的でない」という苦労話が漏れ聞こえてくる。監査を受ける側と監査する側の「摩擦」は避け難いのかもしれないが、監査人への協力を首長が明確に指揮し、監査人も確固たる姿勢で望むことで克服すべきである。
④ 行政の措置義務の法定と説明責任
現行法上、監査結果にもとづく措置は義務付けられておらず、措置が講じられないときは監査委員への通知も監査委員による措置結果の公表もなされないことになる。しかし、90日以内に第1次改善措置通知、1年以内に意見を含む全項目について措置の有無についての通知を義務付けるべきである。対象部局がどうしても措置を講じられないというのであれば、措置を講じられない項目についてその理由と将来の見通し等を付して対応できない旨を通知し、監査委員はこれも公表すべきである。
⑤ 監査対象の範囲と内容
政策の是非は外部監査の対象とはされていないといわれるが、施策の適正・効率性が財務の適正・効率性にかかわっていたり、行政監査と財務監査を峻別しきれなかったりする場合が多く、その点で踏み込む必要がある。立法的には行政監査を担当できることも制度的に考えるべきである。また、決算監査も対象と考えられてよい。さらに、現在は条例により選択できる財政援助団体等の監査はその外部監査の必要性から考えて制約は無くすべきである。
⑥ 監査委員監査の改革と外部監査
監査委員監査制度には、人選・事務局など人的組織と独立性に課題がある。監査事務局は自治体職員の回り持ち、配転職となって、外部性・独立性がないと批判され、監査委員が必ずしも専門的能力や十分な独立的基盤がない「名誉職」化している自治体では、事務局主導の日常の定期的・形式的監査の処理で手一杯というところも多い。小さな市町村では監査委員の力が弱いという意見もある。監査委員は、まず本来の「光」と「力」を取り戻すべきと考える。その上で、外部監査との相互向上が必要である。
⑦ 外部監査と行財政改革
財政がひっ迫し行財政改革が求められ、増税の前に無駄な出費や不合理な支出を少しでもなくすことがこれほどまで求められている時代はない。自治体が「市民の共同船」であれば、乗客は「船賃」(税などの負担金)で安全と公正を維持して運航されているのかを知る権利がある。その説明責任は委託された船長らにある。「船」の安全性(適法性)、行き先(有効性)、行程や燃費(効率性・経済性)等については独立性のある検査・点検機関の機能強化が徹底して必要となっている。この検査を内部監査の監査委員と外部の外部監査人が十分に果たすことが求められている。
⑧ 行政での活用
これまでの政治や行財政は、予算獲得や配分決定に熱心であったが、それが「利権」につながっていた。予算が正しく使われたか、その目的を果たしたかの事後検証であるはずの決算はルーズであった。予算の決定・執行・決算により、検証手続によって行政にフィードバックし、税の適正かつ有効利用に活かすという視点があまりにも不足していた。21世紀の自治体運営は予算からの事前調査・評価の充実と執行途中の点検・見直し・修正と事後の評価・反省という検査・検証の手法を強化活用していく以外に正しい進路は選べないであろう。
⑨ 議員と監査報告書の活用
i 議会の力の「低さ」
議会は、長以下の行政を監視・監督し、市民にとって公正、有効、効率的、経済的な行政がなされているかの審理機関でもあるが、その機能を必ずしも十分には果たせていない。議会には予算審議と決算審議という重要な使命があるが、全体的にチェックしようとする議員がいても、全体像はもとより個別についてはほとんどつかみがたく、短い予算・決算審議の期間に会派議席数で時間配分される議会で問題を追求する時間的余欲は少ない。
ii 議員と監査委員
議員は意外に行政情報から閉ざされている。まして、会計分析に素人の議員が監査委員として能力をどれだけ発揮できるか、また発揮できているかについては、厳しい評価をせざるを得ない。そこにも外部監査の意義がある。
⑩ 監査報告書がわからない議員は「失格」
議員たるもの監査報告書を読めない、わからないでは、能力的に失格であろう。現状では「失格」の議員もいるであろうが、自己の自治体の監査報告書はもちろん、他の自治体の例を見るならば、共通課題、共通の不当な事実が必ず発見できるし、よい監査からは是正の方向性についても知識を得られるであろう。監査人の中には、長だけでなく議長にも報告書の説明をしている例もあるようである。しかし、議会が詳しく監査報告を聞いた例はほとんど聞かれなかった。委員会その他自由に意見を聞く機会を持つことが期待される。
⑪ 議会・議員は監査に基づく「措置」の点検をする
議会は、監査結果等のうち行政の措置によって是正事項が達成されているかを自らの見識を加えて追求する場を持ってほしい。1年たっても是正されない不当な行政など、議会にとっては絶対に見逃せないはずである。
4.市民の活用へのアクセス
以上の全体を市民がチェックすることになる。まずは、監査報告書を入手し読んでみることである。もちろん関心のあるテーマからであろうが、関心を持つ市民が一人でも多いことが、外部監査と行政の向上に貢献する。
5.市民の外部監査活用法
① わが自治体の行政実態を知る
監査報告書は特定自治体の特定部門の調査報告であるが、その調査は類似自治体、周辺自治体との相対比較をしていることも多く、比較自治体の実態をも示しているものが少なくない。また、性質上地方自治体共通のテーマが多く、具体的データは違っても検討の手法や問題点の指摘は他の地方自治体についても該当することが多い。したがって、住民、自治体の議員や行政職員にとっても、問題意識のあるテーマについて研究し比較検討する上で、監査報告書は有意義なものが多い。最近は、ほとんどの都道府県で監査報告書が公報等で全部掲載されており、自治体のホームページから入手できたり、公報を有料で販売されたりしているところもある。
② 財政状況を知る
外部監査では、具体的な財政・支出負担が明らかにされる。当該地方自治体での対象行為や部局の経済的な位置付けも金銭的数字で示される。私達市民の税金、あるいは負担がどの程度であるか、公平であるか、また他の行政需要(財政項目)との比較上どうなっているかも教えてくれる。
③ 適法性を知る
監査の第一の目的は、行政執行、財政行為の適法性の点検にある。証拠と事実の不適合は真実性に反するという一点だけで適法性を欠くものである。監査報告書を熟読すればその疑惑を窺わせたり、対象部局の協力がなかったりするための限界を示しているものもある。包括外部監査は個々の行政の不正・不当点の指摘を受けて行うものではなく、監査人の適法性の点検は結果としてまだまだ弱い。形式的な法令基準に準拠していれば合規性ありとしていることが少なくない。この点は裁量行政に極めて甘い監査となる。しかし、その弱さはあってもそのテーマの部門での適法性の所在を知る上で有益である。
④ 自治体行財政の3Eを知る
i 有効性(合目的性)
自治体の行政行為,財政支出(負担)を伴う行為には当然ながら目的がある。その目的の正当性は法令・条例に示され、目的条項や法定の要件原則から導かれる。時、場所、対象(人・ケース)等に応じた具体的合目的性が要求される。
例えば、補助金の交付は、「公益性の必要」という要件解釈にもなり、当該自治体の補助によって達成しようとする公共目的に照らし一般的に有効性を持つにとどまらず、具体的な公共目的がその補助により獲得できること、他の同種団体と比較して補助の優越性を持っていることが要件となる。
ii 効率性
自治体における効率とは、自治体の人と公金等の投入によって、より大きな目的が達成されているかという「程度」の問題である。その検証は強制力による税の限られた財源能力に照らし、どれだけ最大限の効率を目指しているか厳正に審査されなければならない。
iii 経済性
ここでの経済性とは、人と公金・資材の投入を小さくすることである。効率的運営は経済性もあるので効率性類似の領域もあるが、絶対的な出費額の点で異なる。ここでも法令の厳正な適用が問題となる。この点、過去おろそかになっていたものも少なくないことは否めない。
⑤ 個別監査報告書のテーマと活用法
5年間に取り上げたれた監査対象は今や912テーマに及ぶ。外部監査の中から参考にし、活用するものを探すことが可能である。これらを手がかりに、あるべき行政像が求められる。
(註) 全国市民オンブズマン連絡会議の「包括外部監査の通信簿」は1999年版から毎年発行され、2003年度版(本年8月発行)まで5期を重ねている。黄色の表紙で「イエローブック」と呼ばれてもいるが、2003年度版はもちろん2001年度版・2002年度版も若干の残部がある。申込み・問い合わせは、「市民オンブズマン(大阪)包括外部監査評価班事務局(電話:06-6202-5051)」まで。
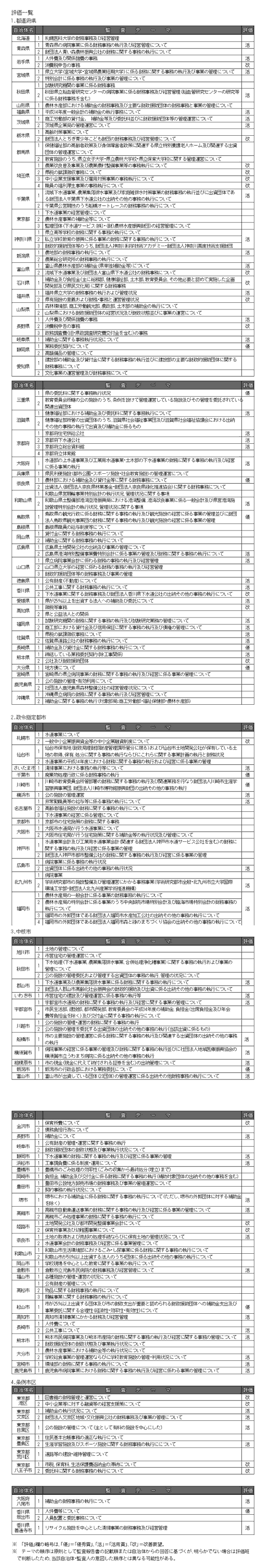
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























