解説記事2005年02月14日 【実務解説】 企業会計基準公開草案第3号「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」について(2005年2月14日号・№102)
実務解説
企業会計基準公開草案第3号
「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 豊田俊一
1 はじめに
企業会計基準委員会(ASB)では、平成13年11月の商法改正で新株予約権制度が導入され、ストック・オプションとしての利用が活発化していることから、平成14年5月にストック・オプション等専門委員会を設置し、同様の取引に関して会計基準が整備されつつあった海外の動向も視野にいれつつ(脚注1)、会計処理等につき検討を行ってきた。その過程で、わが国におけるストック・オプション制度に関する実態調査を実施するとともに、会計基準を開発する上で考慮すべき基本的な論点を整理し、平成14年12月に「ストック・オプション会計に係る論点の整理」として公表しコメントを求め、公聴会において意見を聴取した。ASBは、このようにして得られた意見や実態調査の結果を踏まえ、審議を重ねた結果を取りまとめ、平成16年12月28日に企業会計基準公開草案として公表した。本稿ではその概要を説明する。(なお、文中意見にわたる部分は私見である。)
2 適用範囲等
(1) 取扱っている範囲
上記の経緯から、会計基準開発にあたっては、従業員等に対する報酬として現金等に代えて自社株式オプションを付与するストック・オプション取引に焦点が当てられた。
ストック・オプション会計の本質は、取引の対価として自社株式オプションを用いるところにあることから、自社株式オプションを対価として用いる取引一般にも、ストック・オプションと整合的な会計的取扱いが求められると考えられる。
さらに、取引対価として自社株式を用いる取引では、ストック・オプション会計のうち、オプションを対価とすることに由来する問題については該当しないが、自社株式又はその交付に結びつく可能性のある対価を用いた取引において取得した財貨・サービスを財務諸表上認識する必要があるか否かという点に関しては共通する問題であり、両者に整合的な取扱いが求められると考えられる。このため、本基準案では、自社株式オプション又は自社株式を、財貨・サービス取得の対価として用いる取引一般を適用範囲に含めている。
なお、親会社が子会社の従業員等に自社株式オプションを付与する場合、対応して提供される追加的サービスの直接の受領者は子会社であるが、親会社はその結果子会社に対する投資価値が高まることを期待していると考えられ、親会社の付与するこのような自社株式オプションにも対価性が認められ、本基準案の適用範囲に含まれる(第20項)。
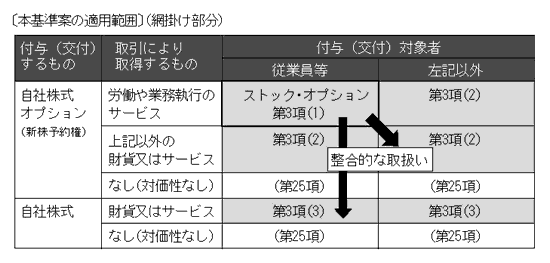
(2) 取扱っていない取引
本基準案は、対価の額が何らかの形で自社株式の市場価格に連動するものであっても、自社株式オプション又は自社株式を用いない取引は取扱っていない。また、本基準案では、企業が付与する自社株式オプションや交付する自社株式が、対価として用いられていることが前提である。経済的に合理的な行動を行う企業が付与又は交付する以上、これらは通常対価性があると考えられる。しかし、論点整理に対するコメントや公聴会での意見の中には対価性に疑問を抱く意見もあった。そこで、本基準案では、極めて稀ではあると考えられるが、対価性を有しないことを証明できる場合には、その開示を条件に適用対象外としている(第25項)。
3 一般的なストック・オプション取引
ここでは、ストック・オプション取引のイメージを説明しつつ、本基準案で用いられている用語につきおおよその意味を述べる(用語定義については第2項参照)。
(1) ストック・オプションの付与
自社株式オプションとは、一定の金額(行使価格)の支払いにより、報告企業の株式(自社株式)を取得する権利(新株予約権はこれに該当)をいい、このうち、企業がその従業員等(使用人の他、取締役、監査役及び執行役)に、報酬(労働や業務執行等のサービスの対価)として付与するものをストック・オプションという。
ストック・オプションは従業員等に付与されるが(この時点が付与日)、付与された従業員等がそのストック・オプションと報酬関係にある一定のサービス提供期間(対象勤務期間といい、明らかではない場合には、付与日から権利確定日までの期間を対象勤務期間とみなす。)にわたり勤務することが権利確定のために必要との条件(勤務条件)が付されているのが一般的である。これに加えて、ストック・オプションの権利の確定を一定の業績の達成等に関わらせている(業績条件)場合もあり、ストック・オプションの権利確定のための要件とされるこれらの条件を権利確定条件という。
付与されたストック・オプションのうち、権利確定条件が成就しないこととなった部分については、権利行使されないことが確定(失効)する。失効には、ここで述べたように、権利確定条件を成就しないことによるもの(権利不確定による失効)の他、後述の権利不行使による失効がある。
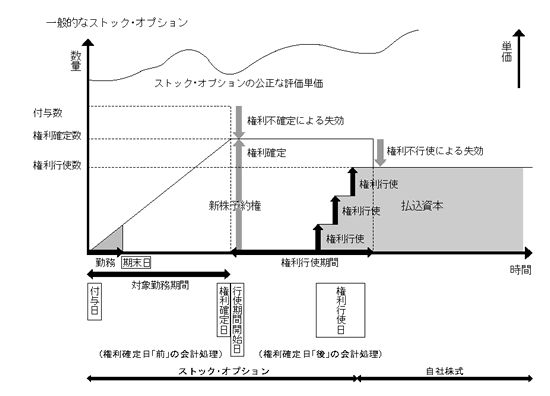
(2) 権利の確定
ストック・オプションの権利が確定すれば(この時点を権利確定日といい、明らかではない場合には、ストック・オプションを付与された従業員等がその権利を行使できる期間(権利行使期間)の開始日の前日を権利確定日とみなす。)、通常、遅滞なく権利行使期間が開始し、その期間内であれば、従業員等は株価状況等に応じ、適当と考えるタイミングで権利行使することができる。
(3) ストック・オプションの行使
従業員等がストック・オプションを行使し、行使価額に相当する金銭を払い込んだ場合には、従業員等に自社株式を交付することになる。
行使期間中に、株価が行使価格を上回る場合、従業員等は権利行使により(この時点が権利行使日)その差額分の経済的メリットを享受することができる。
一方、行使期間中に株価が行使価格を上回ることがない場合、従業員等にはストック・オプションを行使する経済的メリットがない。権利を行使しないまま行使期間を経過すると、従業員等の権利は消滅する(権利不行使による失効)。
4 ストック・オプションの会計処理と考え方
(1) 本解説で使用する設例
〔共通条件〕
A社は、X3年6月の株主総会において、従業員のうちマネージャー以上の者全員に以下の条件でストック・オプション(新株予約権)を付与することを決議した。
・付与対象者数:75人
・付与数: 1人当たり160個(合計付与数=75名×160個/人=12,000個)
・但しストック・オプション1個の行使により1株が交付される。
・各対象者に付与された160個につき、一部行使は認められない。
・行使価格(1株当たり):75,000円
・付与日: X3年7月1日
・権利確定日:X5年6月末日(権利行使期間開始日の前日)
・対象勤務期間:付与日X3年7月1日から権利確定日X5年6月末日までの24ヶ月間
・権利行使期間:X5年7月1日からX7年6月末日
・付与日のストック・オプションの公正な評価単価:8,000円/個
〔ストック・オプション数に関する見込みと実績〕
・付与時点における失効見込数:X5年6月末までに7人が退職すると見込んでいる。
・X4年3月期末:上記の見込みに修正はない。
・権利確定日:退職者累計実績は5人であった。
・年度ごとのストック・オプション数の実績は以下のとおり。
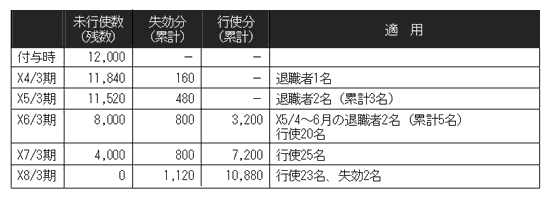
(2) 権利確定日以前の会計処理
① 取得した財貨・サービスの認識と相手勘定の表示
(i)取得した財貨・サービスの認識
ストック・オプションを用いた場合には、現金等の会社財産の流出に結びつかないため、従業員等から取得したサービスの消費を費用として認識する必要があるか否かについては従来必ずしも明らかではなく、実務上も費用としての会計処理が行われてこなかったが、本基準案では、従業員等にストック・オプションが付与され、これに対応して従業員等からサービスが提供された場合には、報酬として現金等を用いた場合と同様に、費用認識が必要となる(第4項)。
その根拠については、本基準案の結論の背景(第28項から第34項)において、主要な指摘事項を各々検討する形で述べられているが、要約すれば、従業員等に付与される自社株式オプションには、通常当該従業員等から提供されるサービスに対する対価としての性格があると考えられ、このような企業と従業員等との間の取引の結果、従業員等から企業に対して量的又は質的に追加的なサービスが提供されてこれが企業に帰属することとなり、企業に帰属するものを消費した場合には費用認識が必要となるということになる。
(ii)費用認識の相手勘定
上記の場合、相手勘定となる新株予約権については、負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上することとされた(第4項)。ストック・オプションは、失効して払込資本とならない可能性もあり、保有者は未だ株主の立場にあるとはいえない。既存基準において社債と同時に発行される等の新株引受権や新株予約権を資本とはせず負債の部に計上することとしているのも、同様の理由によると考えられる。現行の資本の部は、払込資本、留保利益の他、海外の基準にいう「その他の包括的利益」に概ね対応した資本直入項目から構成されるが、新株予約権はこれらのいずれにも該当しない。他方、新株予約権は、返済義務のある本来の負債にも該当しない。新株予約権は、行使されればその保有者を付け加えた株主の持分となり、失効すればその保有者を含まない株主の利益となり持分に付け加わるため、未だ当該企業の所有者である株主とはなっていないいわば潜在的な株主に帰属する部分とみることもできる。返済義務のある本来の負債にあたらず、かつ当該企業の所有者である株主以外の者に帰属する部分という点では少数株主持分と共通しており、ともに負債の部に表示することも、資本の部に表示することも問題があるものとして、さしあたり上記のように、少数株主持分と同様の表示方法とすることが適当とされた(第35項から第37項)。
しかし、かかる項目の性格について未だ概念上の整理が定着しているとはいえず、個別財務諸表に新たに中間区分を設けることについても慎重な検討が必要との意見も多いことから、別途早急に貸借対照表における貸方項目の区分表示のあり方全般について包括的な検討を行うこととされ、ストック・オプションに対応する金額の表示区分についても、その中で引き続き議論することとされた。
なお、ストック・オプションである新株予約権の表示区分については、既存の会計基準における社債と同時に発行される等の新株引受権や新株予約権の表示区分の取扱いとの整合を図る必要があるが、本会計基準の適用開始までに、現在の新株予約権等の表示区分を必要に応じて見直し、両者の表示区分を本会計基準の適用開始時点から一致させることとされている(第38項)。
② 各期間の会計処理
上記の考え方により、企業が財務諸表上で認識するサービスの取得価額は、付与されたストック・オプションの公正な評価額に基づいて算定する(第5項)。付与されたストック・オプションの公正な評価額は、通常、対象勤務期間中に提供されるサービス全体に対応していると考えられるため、各報告期間における費用計上額は、これを、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づいて配分して算定する(第6項)。
公正な評価額とは、一般には市場価格に基づく価額をいうが、ストック・オプションの場合、通常、市場価格が観察できないため、株式オプションの合理的な価格の見積りに広く受け入れられているブラック=ショールズ・モデルなど株式オプション価格算定モデル等の評価技法により合理的に算定された価額を用いる。ストック・オプションの単位当たりの公正な評価額を公正な評価単価といい(第2項(12)、第7項(2))、ストック・オプションの公正な評価額は、これに、ストック・オプション数を乗じて求める。
(i)ストック・オプションの公正な評価単価の算定
ストック・オプションの公正な評価単価は、付与日現在で算定しその後は見直さないこととされている(第7項(1))。これは、企業が従業員等に対し一定の契約条件を満たすサービスの提供を期待し、その提供がなされた場合に権利確定させるという条件付のストック・オプションを付与する取引においても、企業の取引が経済合理性に基づくものである以上、等価での交換が行われているはずであり、この等価性の判断において前提とされているストック・オプションの価値は、いわば条件付の契約が締結されたといえるストック・オプション付与日における価値とみるのが合理的であるとの考え方による(第41項、第46項)。
(ii)ストック・オプション数の算定及びその見直し
ストック・オプション数については、権利確定日以前においては、ストック・オプション付与数から権利不確定による失効見積数を控除した権利確定見積数により、権利確定日においては、これを権利確定数に一致させる(第8項(1)、(3))。また、権利確定日以前において権利不確定による失効の見積数に重要な変動が生じた場合には、これに応じてストック・オプション数を見直すこととされている(第8項(2))。
これは、ストック・オプションの付与日において、企業と従業員等との間で先に述べたような条件付の契約が締結されたとしても、それが取引として完結し認識の対象となるのは、当事者双方が現実に契約条件に沿った給付を果たし、ストック・オプションの権利が確定した部分であるからであり、権利確定日より前においては、そのような部分を見積って費用計上額を算定することになる(第42項)。
権利確定部分の見積りに基づいて計上した費用のうち、取引が完結せず権利が確定しないことが判明した部分については、その実績に基づいて利益への影響額を修正すべきこととなる。また、実績確定以前においても、その見積数に重要な変動が生じた場合には、ストック・オプション数を見直し、これに基づく利益の影響額をその期に修正すべきことになる(第8項(2)、(3)、第42項)。
説例による会計処理の確認
〔X4年3月期〕(費用計上の会計処理)
ストック・オプションの公正な評価額は、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価(8,000円/個)にストック・オプション数(付与数(75人×160個)-失効見込数(7人×160個))を乗じた、87,040,000円。
これを、対象勤務期間(付与日X3年7月1日より、権利確定日X5年6月末日までの24ヶ月)を基礎とする方法で当期(付与日X3年7月1日より、当期末X4年3月末日までの9ヶ月)に配分することで、当期の費用は、32,640,000円(=87,040,000円×9月/24月)と算定される。
(仕訳)
給料手当 32,640,000 / 新株予約権 32,640,000
〔X5年3月期〕(費用計上―失効の見積数に変動が生じた場合の会計処理)
(仕訳)
給料手当 44,640,000 / 新株予約権 44,640,000
期末時点で、将来の累計失効見込を6人に修正したため、ストック・オプションの公正な評価額は、8,000円/個×{(75人-6人)×160個/人}=88,320,000に修正されることになる。
この結果、当期末まで(付与日X3年7月1日より、X5年3月末日までの、21ヶ月間)に費用計上すべき額の累計は、88,320,000×21月/24月=77,280,000円であり、当期に計上すべき額は、ここから、前期の費用計上額(32,640,000円)を控除した、44,640,000円である。
〔X6年3月期(権利確定日以前の部分)〕(費用計上―権利確定日を含む期の会計処理)
ストック・オプション数は、権利確定数(75人-5人)×160個/人に一致させることになる。その結果、当期に費用計上すべき額は、当期までに計上すべき費用の累積額8,000円/個×{(75人-5人)×160個/人}×24月/24月から、前期までに実際に費用計上した累計額(32,640,000円+44,640,000円)を控除した、12,320,000円となる。
(仕訳)
給料手当 12,320,000 / 新株予約権 12,320,000
(3) 権利確定日より後の会計処理
ストック・オプションの権利が確定した後は、権利行使期間中に権利行使され、行使価格の払込みを受けて自社株式を交付(新株発行の場合と、自己株式交付の場合とがある)するか、権利行使されないまま、権利行使期間を経過して、ストック・オプションが失効するかのいずれかである。
権利行使時には、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分は、払込資本に振り替え(第9項)、権利不行使による失効時には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分は、原則として、当該失効が生じた期に利益として計上することになる(第10項)。
説例による会計処理の確認
〔X6年3月期(権利確定日より後の部分)〕(権利行使の会計処理―新株発行のケース)
20人が権利行使したため、20人×160個/人=3,200個のストック・オプションが行使されたことになる。行使価格が75,000円/個であるから、払込金額は、75,000円/個×3,200個=240,000,000円である。
また、権利行使により、払込資本に振り替るべき新株予約権の金額は、付与日の公正な評価単価8,000円/個×3,200個25,600,000円である。
(仕訳)
現金預金 240,000,000 払込資本 265,600,000
新株予約権 25,600,000
(権利行使の会計処理―自己株式交付のケース)
ストック・オプションの権利行使に対して、自己株式を交付する場合も考えられる。この場合、権利行使による払込金額および払込資本に振替るべき新株予約権の金額は、新株発行のケースと同様、それぞれ、240,000,000円および25,600,000円である。
自己株式の取得原価は、1株当たり70,000円であったとすると、160個/人×20人×70,000円=224,000,000円となり、次の会計処理となる。
(仕訳)
現金預金 240,000,000 自己株式 224,000,000
新株予約権 25,600,000 自己株式処分差益 41,600,000
〔X7年3月期の会計処理〕・〔X8年3月期〕(権利行使の会計処理)省略
〔X8年3月期〕(権利不行使による失効の会計処理)
権利行使期間において最終的に権利行使されなかった2人分の新株予約権の残額(160個/人×2人×8,000円/個=2,560,000円)を新株予約権戻入益として利益に計上する。
(仕訳)
新株予約権 2,560,000 / 新株予約権戻入益 2,560,000
5 ストック・オプションに係るその他の問題
(1) 未公開会社の取扱い
未公開会社については、ストック・オプションの公正な評価額について、損益計算に反映させるに足りるだけの信頼性をもって見積ることが困難な場合が多いと考えられる。そこで、未公開会社では一般投資家がいないことも考慮し、本則であるストック・オプションの公正な評価単価に代え、その単位当たりの本源的価値(原資産である自社株式の評価額と行使価格との差額)の見積りによることを認めることとされた(第11項、第49項から第53項)。ここで、未公開会社とは、株式を証券取引所に上場している会社又はその株式が組織された店頭市場において継続的に取引されている会社である公開会社以外の会社をいうものとされている(第2項(14))。
単位当たりの本源的価値による場合には、次のような会計処理と開示を行うことになる。
(i)会計処理
本会計基準の適用上、公正な評価単価を、単位当たりの本源的価値に読み替える。その結果、費用計上額の算定に当たっては、付与日現在でストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積り、これにストック・オプション数を乗じたものを、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づいて配分して算定することになる。
(ii)注記による開示
単位当たりの本源的価値による会計処理を選択した場合には、次の金額の開示が求められる(第15項(5))。
・当該ストック・オプションの各期末における本源的価値の合計額
・各報告期間中に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(2) 条件変更(行使価格の引下げ)の取扱い
付与後の著しい株価下落により、当初期待していたストック・オプションのインセンティブ効果が失われた場合、これを回復する目的で行使価格を引き下げることも想定される。本基準案では、このようなケースをもとに、付与されたストック・オプションに関して、当初の条件を事後的に変更した場合の会計処理についての原則的な考え方が示されている。なお、この他にも様々な条件変更が考え得るが、態様毎の個別の検討は必要に応じ適用指針で対応することとされた。
(i)条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを上回る場合
本基準案では、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく公正な評価額を配分することにより、各報告期間における費用計上額を算定することを求めているが、行使価格の引き下げが行われた場合には、これにより、ストック・オプションの公正な評価単価についての修正が行われたとみることができ、以後、修正後の公正な評価単価のベースに基づき会計処理を行うこととされた。具体的には、条件変更前から行われてきた付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく公正な評価額の配分を継続して行うことに加え、条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日における公正な評価単価より増加した部分に見合う、ストック・オプションの公正な評価額の増加額につき、以後追加的な配分計算を行う(第12項(1)、第55項)。
(ii)条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを下回る場合
以上の会計処理を、ストック・オプションの条件変更日における公正な評価単価が付与日における公正な評価単価を下回る場合にも適用すると、ストック・オプションの条件を従業員等により有利なものとしたにもかかわらず却って費用を減額させることになってしまう。このようなパラドックスを回避するため、この場合には、条件変更後においても、なお付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく条件変更前からの会計処理を継続することとした(第12項(2)、第56項)。
説例による会計処理の確認
4.(1)の設例の共通条件に加え、行使価格引下げに関する次の条件を追加する。なお、単純化のため、各期末においてその時点における実績を超える失効は見込まれないものとする。条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを上回る状況(ケース甲)と、下回る状況(ケース乙)が想定されている。
〔条件変更に係る追加条件〕
A社の株式は全体的な株式相場の下落の影響を受け、一貫して行使価格(権利行使時の1株当たりの払込額)である75,000円を大幅に下回り、インセンティブ効果が失われたと考えられたため、その回復を期して、X4年6月の株主総会において行使価格を引き下げた。
・条件変更日:X4年7月1日
・行使価格(1株当たり):75,000円から、次の価格に引き下げた。
ケース甲 31,000円
ケース乙 52,000円
・条件変更日(条件変更直後)のストック・オプションの公正な評価単価:
ケース甲 9,000円/個(> 付与日の公正な評価単価8,000円/個)
ケース乙 5,000円/個(< 付与日の公正な評価単価8,000円/個)
・条件変更直前のストック・オプションの公正な評価単価: 800円/個
年度ごとのストック・オプション数の実績は以下のとおり。
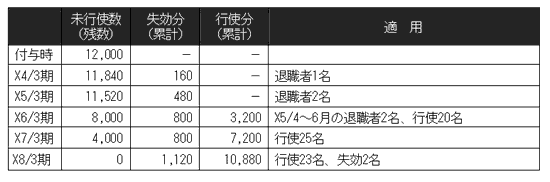
〔X4年3月期〕(条件変更より前の期)
当期の費用計上額:(75人-1人)×8,000円/個×160個/人×9月/24月=35,520,000円
(仕訳)
給料手当 35,520,000 / 新株予約権 35,520,000
〔X5年3月期〕(条件変更日を含む期)
<ケース甲>
条件変更により、ストック・オプションの公正な評価単価のベースが、8,000円/個から9,000円/個に修正されたものとして取扱う。
(1)従来の配分計算を継続する部分:対象勤務期間(X3年7月からX5年6月までの24ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×8,000円/個×160個/人×21月/24月-35,520,000円(前期までの費用計上額)=45,120,000円
(2)条件変更による追加的な配分計算:対象勤務期間の残存期間(X4年7月からX5年6月までの12ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×(9,000円/個-8,000円/個)×160個/人×9月/12月=8,640,000円
当期の費用計上額は、(1)に(2)を加えた53,760,000円(=45,120,000円+8,640,000円)となる。
(仕訳)
給料手当 53,760,000 / 新株予約権 53,760,000
<ケース乙>
条件変更日のストック・オプションの公正な評価単価(5,000円/個)が、付与日のストック・オプションの公正な評価単価(8,000円/個)を下回るので、付与日の公正な評価単価にもとづく費用配分計算を継続する。
(1)従来の配分計算を継続:対象勤務期間(X3年7月からX5年6月までの24ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×8,000円/個×160個/人×21月/24月-35,520,000円=45,120,000円
(仕訳)
給料手当 45,120,000 / 新株予約権 45,120,000
〔X6年3月期〕(費用計上の会計処理)
<ケース甲>
(1)従来の配分計算を継続する部分
(75人-5人)×8,000円/個×160個/人×24月/24月-(35,520,000円+45,120,000円)
=8,960,000円
(2)条件変更による追加的な配分計算
(75人-5人)×(9,000円/個-8,000円/個)×160個/人×12月/12月-8,640,000円
=2,560,000円
当期の費用計上額:8,960,000円(1)+2,560,000円(2)=11,520,000円
(仕訳)
給料手当 11,520,000 / 新株予約権 11,520,000
<ケース乙>
(1)従来の配分計算を継続
(75人-5人)×8,000円/個×160個/人×24月/24月-(35,520,000円+45,120,000円)
=8,960,000円
(仕訳)
給料手当 8,960,000 / 新株予約権 8,960,000
〔X6年3月期〕(権利行使の会計処理―新株発行)
<ケース甲>
払込金額:160個/人×20人×31,000円=99,200,000円
行使されたストック・オプションの金額:160個/人×20人×9,000円=28,800,000円
(仕訳)
現金預金 99,200,000 払込資本 128,000,000
新株予約権 28,800,000
<ケース乙>
払込金額:160個/人×20人×52,000円=166,400,000円
行使されたストック・オプションの金額:160個/人×20人×8,000円=25,600,000円
(仕訳)
現金預金 166,400,000 払込資本 192,000,000
新株予約権 25,600,000
(以下省略)
6 取引対価として自社株式オプションや自社株式を用いる取引
ストック・オプションに関する会計処理は、取引対価として自社株式オプションを用いる取引にも適用される。また、財貨・サービスの取得の対価として、自社株式を用いる取引においても、取得した財貨・サービスを財務諸表上認識することが求められる。これらの場合においては、取得した財貨・サービスの価値で測定することがあり得ることや、測定の基準日等について、若干の留意事項が掲げられている(第13項、第14項)。
7 開示項目
本基準案においては、開示の基本的な考え方や項目を示すにとどめ、具体的な開示の詳細や開示情報の算定方法については、本会計基準の適用指針において定めることとされている(第60項)。開示項目は次のとおりとされている(第15項)。
●本基準案の適用による財務諸表への影響額
●付与されているストック・オプションの概要
各報告期間において存在したストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
●ストック・オプション付与に伴い財務諸表上計上される数値の見積方法
●その他の項目
本基準案は、一部の注記項目を除き、平成18年4月1日以後開始する事業年度に新たに付与又は交付されるストック・オプション、自社株式オプション及び自社株式につき適用される。
8 おわりに
本基準案は公開草案として公表され、平成17年2月末日までコメントを募集している(http://www.asb.or.jp/)。本基準案の全体がコメントの対象になるが、特に議論が多かった、新株予約権の表示(費用認識の相手勘定)と、未公開会社の取扱いについては、コメントの参考として、ASBの審議等における主な指摘事項の一覧表が添付されている。また、本基準案の内容に対するコメントに加え、本基準案を基礎に会計基準を導入する場合、適用指針において実務上重要性のある項目を網羅するため、適用指針において規定が求められる事項等についても、コメントが求められている。
脚注
1 国際会計基準審議会では、平成14年11月に公表された公開草案を経て平成16年2月に国際財務報告基準書第2号「株式報酬」が公表された。
また、米国では、平成16年3月に公表された公開草案を経て、平成16年12月に米国財務会計基準書第123号の改訂版「株式報酬」が公表された。
企業会計基準公開草案第3号
「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 豊田俊一
1 はじめに
企業会計基準委員会(ASB)では、平成13年11月の商法改正で新株予約権制度が導入され、ストック・オプションとしての利用が活発化していることから、平成14年5月にストック・オプション等専門委員会を設置し、同様の取引に関して会計基準が整備されつつあった海外の動向も視野にいれつつ(脚注1)、会計処理等につき検討を行ってきた。その過程で、わが国におけるストック・オプション制度に関する実態調査を実施するとともに、会計基準を開発する上で考慮すべき基本的な論点を整理し、平成14年12月に「ストック・オプション会計に係る論点の整理」として公表しコメントを求め、公聴会において意見を聴取した。ASBは、このようにして得られた意見や実態調査の結果を踏まえ、審議を重ねた結果を取りまとめ、平成16年12月28日に企業会計基準公開草案として公表した。本稿ではその概要を説明する。(なお、文中意見にわたる部分は私見である。)
2 適用範囲等
(1) 取扱っている範囲
上記の経緯から、会計基準開発にあたっては、従業員等に対する報酬として現金等に代えて自社株式オプションを付与するストック・オプション取引に焦点が当てられた。
ストック・オプション会計の本質は、取引の対価として自社株式オプションを用いるところにあることから、自社株式オプションを対価として用いる取引一般にも、ストック・オプションと整合的な会計的取扱いが求められると考えられる。
さらに、取引対価として自社株式を用いる取引では、ストック・オプション会計のうち、オプションを対価とすることに由来する問題については該当しないが、自社株式又はその交付に結びつく可能性のある対価を用いた取引において取得した財貨・サービスを財務諸表上認識する必要があるか否かという点に関しては共通する問題であり、両者に整合的な取扱いが求められると考えられる。このため、本基準案では、自社株式オプション又は自社株式を、財貨・サービス取得の対価として用いる取引一般を適用範囲に含めている。
なお、親会社が子会社の従業員等に自社株式オプションを付与する場合、対応して提供される追加的サービスの直接の受領者は子会社であるが、親会社はその結果子会社に対する投資価値が高まることを期待していると考えられ、親会社の付与するこのような自社株式オプションにも対価性が認められ、本基準案の適用範囲に含まれる(第20項)。
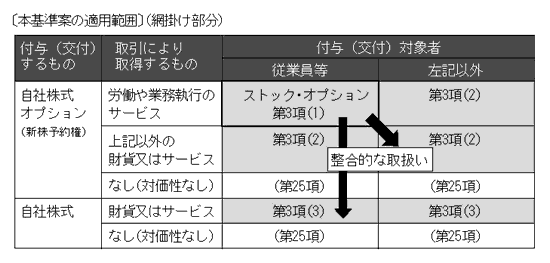
(2) 取扱っていない取引
本基準案は、対価の額が何らかの形で自社株式の市場価格に連動するものであっても、自社株式オプション又は自社株式を用いない取引は取扱っていない。また、本基準案では、企業が付与する自社株式オプションや交付する自社株式が、対価として用いられていることが前提である。経済的に合理的な行動を行う企業が付与又は交付する以上、これらは通常対価性があると考えられる。しかし、論点整理に対するコメントや公聴会での意見の中には対価性に疑問を抱く意見もあった。そこで、本基準案では、極めて稀ではあると考えられるが、対価性を有しないことを証明できる場合には、その開示を条件に適用対象外としている(第25項)。
3 一般的なストック・オプション取引
ここでは、ストック・オプション取引のイメージを説明しつつ、本基準案で用いられている用語につきおおよその意味を述べる(用語定義については第2項参照)。
(1) ストック・オプションの付与
自社株式オプションとは、一定の金額(行使価格)の支払いにより、報告企業の株式(自社株式)を取得する権利(新株予約権はこれに該当)をいい、このうち、企業がその従業員等(使用人の他、取締役、監査役及び執行役)に、報酬(労働や業務執行等のサービスの対価)として付与するものをストック・オプションという。
ストック・オプションは従業員等に付与されるが(この時点が付与日)、付与された従業員等がそのストック・オプションと報酬関係にある一定のサービス提供期間(対象勤務期間といい、明らかではない場合には、付与日から権利確定日までの期間を対象勤務期間とみなす。)にわたり勤務することが権利確定のために必要との条件(勤務条件)が付されているのが一般的である。これに加えて、ストック・オプションの権利の確定を一定の業績の達成等に関わらせている(業績条件)場合もあり、ストック・オプションの権利確定のための要件とされるこれらの条件を権利確定条件という。
付与されたストック・オプションのうち、権利確定条件が成就しないこととなった部分については、権利行使されないことが確定(失効)する。失効には、ここで述べたように、権利確定条件を成就しないことによるもの(権利不確定による失効)の他、後述の権利不行使による失効がある。
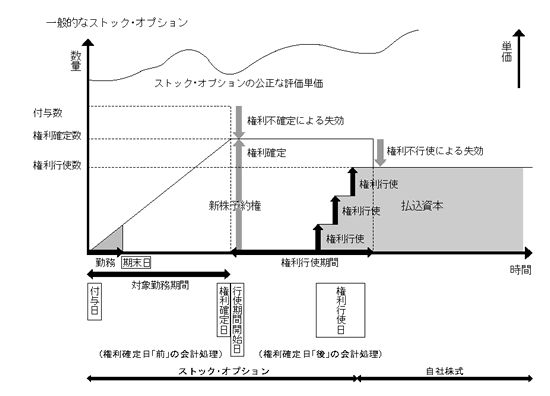
(2) 権利の確定
ストック・オプションの権利が確定すれば(この時点を権利確定日といい、明らかではない場合には、ストック・オプションを付与された従業員等がその権利を行使できる期間(権利行使期間)の開始日の前日を権利確定日とみなす。)、通常、遅滞なく権利行使期間が開始し、その期間内であれば、従業員等は株価状況等に応じ、適当と考えるタイミングで権利行使することができる。
(3) ストック・オプションの行使
従業員等がストック・オプションを行使し、行使価額に相当する金銭を払い込んだ場合には、従業員等に自社株式を交付することになる。
行使期間中に、株価が行使価格を上回る場合、従業員等は権利行使により(この時点が権利行使日)その差額分の経済的メリットを享受することができる。
一方、行使期間中に株価が行使価格を上回ることがない場合、従業員等にはストック・オプションを行使する経済的メリットがない。権利を行使しないまま行使期間を経過すると、従業員等の権利は消滅する(権利不行使による失効)。
4 ストック・オプションの会計処理と考え方
(1) 本解説で使用する設例
〔共通条件〕
A社は、X3年6月の株主総会において、従業員のうちマネージャー以上の者全員に以下の条件でストック・オプション(新株予約権)を付与することを決議した。
・付与対象者数:75人
・付与数: 1人当たり160個(合計付与数=75名×160個/人=12,000個)
・但しストック・オプション1個の行使により1株が交付される。
・各対象者に付与された160個につき、一部行使は認められない。
・行使価格(1株当たり):75,000円
・付与日: X3年7月1日
・権利確定日:X5年6月末日(権利行使期間開始日の前日)
・対象勤務期間:付与日X3年7月1日から権利確定日X5年6月末日までの24ヶ月間
・権利行使期間:X5年7月1日からX7年6月末日
・付与日のストック・オプションの公正な評価単価:8,000円/個
〔ストック・オプション数に関する見込みと実績〕
・付与時点における失効見込数:X5年6月末までに7人が退職すると見込んでいる。
・X4年3月期末:上記の見込みに修正はない。
・権利確定日:退職者累計実績は5人であった。
・年度ごとのストック・オプション数の実績は以下のとおり。
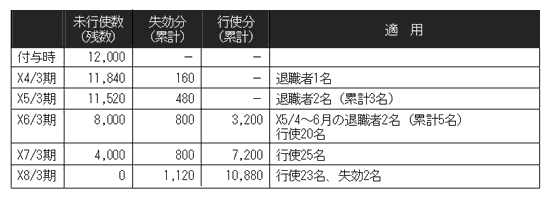
(2) 権利確定日以前の会計処理
① 取得した財貨・サービスの認識と相手勘定の表示
(i)取得した財貨・サービスの認識
ストック・オプションを用いた場合には、現金等の会社財産の流出に結びつかないため、従業員等から取得したサービスの消費を費用として認識する必要があるか否かについては従来必ずしも明らかではなく、実務上も費用としての会計処理が行われてこなかったが、本基準案では、従業員等にストック・オプションが付与され、これに対応して従業員等からサービスが提供された場合には、報酬として現金等を用いた場合と同様に、費用認識が必要となる(第4項)。
その根拠については、本基準案の結論の背景(第28項から第34項)において、主要な指摘事項を各々検討する形で述べられているが、要約すれば、従業員等に付与される自社株式オプションには、通常当該従業員等から提供されるサービスに対する対価としての性格があると考えられ、このような企業と従業員等との間の取引の結果、従業員等から企業に対して量的又は質的に追加的なサービスが提供されてこれが企業に帰属することとなり、企業に帰属するものを消費した場合には費用認識が必要となるということになる。
(ii)費用認識の相手勘定
上記の場合、相手勘定となる新株予約権については、負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上することとされた(第4項)。ストック・オプションは、失効して払込資本とならない可能性もあり、保有者は未だ株主の立場にあるとはいえない。既存基準において社債と同時に発行される等の新株引受権や新株予約権を資本とはせず負債の部に計上することとしているのも、同様の理由によると考えられる。現行の資本の部は、払込資本、留保利益の他、海外の基準にいう「その他の包括的利益」に概ね対応した資本直入項目から構成されるが、新株予約権はこれらのいずれにも該当しない。他方、新株予約権は、返済義務のある本来の負債にも該当しない。新株予約権は、行使されればその保有者を付け加えた株主の持分となり、失効すればその保有者を含まない株主の利益となり持分に付け加わるため、未だ当該企業の所有者である株主とはなっていないいわば潜在的な株主に帰属する部分とみることもできる。返済義務のある本来の負債にあたらず、かつ当該企業の所有者である株主以外の者に帰属する部分という点では少数株主持分と共通しており、ともに負債の部に表示することも、資本の部に表示することも問題があるものとして、さしあたり上記のように、少数株主持分と同様の表示方法とすることが適当とされた(第35項から第37項)。
しかし、かかる項目の性格について未だ概念上の整理が定着しているとはいえず、個別財務諸表に新たに中間区分を設けることについても慎重な検討が必要との意見も多いことから、別途早急に貸借対照表における貸方項目の区分表示のあり方全般について包括的な検討を行うこととされ、ストック・オプションに対応する金額の表示区分についても、その中で引き続き議論することとされた。
なお、ストック・オプションである新株予約権の表示区分については、既存の会計基準における社債と同時に発行される等の新株引受権や新株予約権の表示区分の取扱いとの整合を図る必要があるが、本会計基準の適用開始までに、現在の新株予約権等の表示区分を必要に応じて見直し、両者の表示区分を本会計基準の適用開始時点から一致させることとされている(第38項)。
② 各期間の会計処理
上記の考え方により、企業が財務諸表上で認識するサービスの取得価額は、付与されたストック・オプションの公正な評価額に基づいて算定する(第5項)。付与されたストック・オプションの公正な評価額は、通常、対象勤務期間中に提供されるサービス全体に対応していると考えられるため、各報告期間における費用計上額は、これを、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づいて配分して算定する(第6項)。
公正な評価額とは、一般には市場価格に基づく価額をいうが、ストック・オプションの場合、通常、市場価格が観察できないため、株式オプションの合理的な価格の見積りに広く受け入れられているブラック=ショールズ・モデルなど株式オプション価格算定モデル等の評価技法により合理的に算定された価額を用いる。ストック・オプションの単位当たりの公正な評価額を公正な評価単価といい(第2項(12)、第7項(2))、ストック・オプションの公正な評価額は、これに、ストック・オプション数を乗じて求める。
(i)ストック・オプションの公正な評価単価の算定
ストック・オプションの公正な評価単価は、付与日現在で算定しその後は見直さないこととされている(第7項(1))。これは、企業が従業員等に対し一定の契約条件を満たすサービスの提供を期待し、その提供がなされた場合に権利確定させるという条件付のストック・オプションを付与する取引においても、企業の取引が経済合理性に基づくものである以上、等価での交換が行われているはずであり、この等価性の判断において前提とされているストック・オプションの価値は、いわば条件付の契約が締結されたといえるストック・オプション付与日における価値とみるのが合理的であるとの考え方による(第41項、第46項)。
(ii)ストック・オプション数の算定及びその見直し
ストック・オプション数については、権利確定日以前においては、ストック・オプション付与数から権利不確定による失効見積数を控除した権利確定見積数により、権利確定日においては、これを権利確定数に一致させる(第8項(1)、(3))。また、権利確定日以前において権利不確定による失効の見積数に重要な変動が生じた場合には、これに応じてストック・オプション数を見直すこととされている(第8項(2))。
これは、ストック・オプションの付与日において、企業と従業員等との間で先に述べたような条件付の契約が締結されたとしても、それが取引として完結し認識の対象となるのは、当事者双方が現実に契約条件に沿った給付を果たし、ストック・オプションの権利が確定した部分であるからであり、権利確定日より前においては、そのような部分を見積って費用計上額を算定することになる(第42項)。
権利確定部分の見積りに基づいて計上した費用のうち、取引が完結せず権利が確定しないことが判明した部分については、その実績に基づいて利益への影響額を修正すべきこととなる。また、実績確定以前においても、その見積数に重要な変動が生じた場合には、ストック・オプション数を見直し、これに基づく利益の影響額をその期に修正すべきことになる(第8項(2)、(3)、第42項)。
説例による会計処理の確認
〔X4年3月期〕(費用計上の会計処理)
ストック・オプションの公正な評価額は、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価(8,000円/個)にストック・オプション数(付与数(75人×160個)-失効見込数(7人×160個))を乗じた、87,040,000円。
これを、対象勤務期間(付与日X3年7月1日より、権利確定日X5年6月末日までの24ヶ月)を基礎とする方法で当期(付与日X3年7月1日より、当期末X4年3月末日までの9ヶ月)に配分することで、当期の費用は、32,640,000円(=87,040,000円×9月/24月)と算定される。
(仕訳)
給料手当 32,640,000 / 新株予約権 32,640,000
〔X5年3月期〕(費用計上―失効の見積数に変動が生じた場合の会計処理)
(仕訳)
給料手当 44,640,000 / 新株予約権 44,640,000
期末時点で、将来の累計失効見込を6人に修正したため、ストック・オプションの公正な評価額は、8,000円/個×{(75人-6人)×160個/人}=88,320,000に修正されることになる。
この結果、当期末まで(付与日X3年7月1日より、X5年3月末日までの、21ヶ月間)に費用計上すべき額の累計は、88,320,000×21月/24月=77,280,000円であり、当期に計上すべき額は、ここから、前期の費用計上額(32,640,000円)を控除した、44,640,000円である。
〔X6年3月期(権利確定日以前の部分)〕(費用計上―権利確定日を含む期の会計処理)
ストック・オプション数は、権利確定数(75人-5人)×160個/人に一致させることになる。その結果、当期に費用計上すべき額は、当期までに計上すべき費用の累積額8,000円/個×{(75人-5人)×160個/人}×24月/24月から、前期までに実際に費用計上した累計額(32,640,000円+44,640,000円)を控除した、12,320,000円となる。
(仕訳)
給料手当 12,320,000 / 新株予約権 12,320,000
(3) 権利確定日より後の会計処理
ストック・オプションの権利が確定した後は、権利行使期間中に権利行使され、行使価格の払込みを受けて自社株式を交付(新株発行の場合と、自己株式交付の場合とがある)するか、権利行使されないまま、権利行使期間を経過して、ストック・オプションが失効するかのいずれかである。
権利行使時には、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分は、払込資本に振り替え(第9項)、権利不行使による失効時には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分は、原則として、当該失効が生じた期に利益として計上することになる(第10項)。
説例による会計処理の確認
〔X6年3月期(権利確定日より後の部分)〕(権利行使の会計処理―新株発行のケース)
20人が権利行使したため、20人×160個/人=3,200個のストック・オプションが行使されたことになる。行使価格が75,000円/個であるから、払込金額は、75,000円/個×3,200個=240,000,000円である。
また、権利行使により、払込資本に振り替るべき新株予約権の金額は、付与日の公正な評価単価8,000円/個×3,200個25,600,000円である。
(仕訳)
現金預金 240,000,000 払込資本 265,600,000
新株予約権 25,600,000
(権利行使の会計処理―自己株式交付のケース)
ストック・オプションの権利行使に対して、自己株式を交付する場合も考えられる。この場合、権利行使による払込金額および払込資本に振替るべき新株予約権の金額は、新株発行のケースと同様、それぞれ、240,000,000円および25,600,000円である。
自己株式の取得原価は、1株当たり70,000円であったとすると、160個/人×20人×70,000円=224,000,000円となり、次の会計処理となる。
(仕訳)
現金預金 240,000,000 自己株式 224,000,000
新株予約権 25,600,000 自己株式処分差益 41,600,000
〔X7年3月期の会計処理〕・〔X8年3月期〕(権利行使の会計処理)省略
〔X8年3月期〕(権利不行使による失効の会計処理)
権利行使期間において最終的に権利行使されなかった2人分の新株予約権の残額(160個/人×2人×8,000円/個=2,560,000円)を新株予約権戻入益として利益に計上する。
(仕訳)
新株予約権 2,560,000 / 新株予約権戻入益 2,560,000
5 ストック・オプションに係るその他の問題
(1) 未公開会社の取扱い
未公開会社については、ストック・オプションの公正な評価額について、損益計算に反映させるに足りるだけの信頼性をもって見積ることが困難な場合が多いと考えられる。そこで、未公開会社では一般投資家がいないことも考慮し、本則であるストック・オプションの公正な評価単価に代え、その単位当たりの本源的価値(原資産である自社株式の評価額と行使価格との差額)の見積りによることを認めることとされた(第11項、第49項から第53項)。ここで、未公開会社とは、株式を証券取引所に上場している会社又はその株式が組織された店頭市場において継続的に取引されている会社である公開会社以外の会社をいうものとされている(第2項(14))。
単位当たりの本源的価値による場合には、次のような会計処理と開示を行うことになる。
(i)会計処理
本会計基準の適用上、公正な評価単価を、単位当たりの本源的価値に読み替える。その結果、費用計上額の算定に当たっては、付与日現在でストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積り、これにストック・オプション数を乗じたものを、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づいて配分して算定することになる。
(ii)注記による開示
単位当たりの本源的価値による会計処理を選択した場合には、次の金額の開示が求められる(第15項(5))。
・当該ストック・オプションの各期末における本源的価値の合計額
・各報告期間中に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(2) 条件変更(行使価格の引下げ)の取扱い
付与後の著しい株価下落により、当初期待していたストック・オプションのインセンティブ効果が失われた場合、これを回復する目的で行使価格を引き下げることも想定される。本基準案では、このようなケースをもとに、付与されたストック・オプションに関して、当初の条件を事後的に変更した場合の会計処理についての原則的な考え方が示されている。なお、この他にも様々な条件変更が考え得るが、態様毎の個別の検討は必要に応じ適用指針で対応することとされた。
(i)条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを上回る場合
本基準案では、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく公正な評価額を配分することにより、各報告期間における費用計上額を算定することを求めているが、行使価格の引き下げが行われた場合には、これにより、ストック・オプションの公正な評価単価についての修正が行われたとみることができ、以後、修正後の公正な評価単価のベースに基づき会計処理を行うこととされた。具体的には、条件変更前から行われてきた付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく公正な評価額の配分を継続して行うことに加え、条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日における公正な評価単価より増加した部分に見合う、ストック・オプションの公正な評価額の増加額につき、以後追加的な配分計算を行う(第12項(1)、第55項)。
(ii)条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを下回る場合
以上の会計処理を、ストック・オプションの条件変更日における公正な評価単価が付与日における公正な評価単価を下回る場合にも適用すると、ストック・オプションの条件を従業員等により有利なものとしたにもかかわらず却って費用を減額させることになってしまう。このようなパラドックスを回避するため、この場合には、条件変更後においても、なお付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価に基づく条件変更前からの会計処理を継続することとした(第12項(2)、第56項)。
説例による会計処理の確認
4.(1)の設例の共通条件に加え、行使価格引下げに関する次の条件を追加する。なお、単純化のため、各期末においてその時点における実績を超える失効は見込まれないものとする。条件変更日の公正な評価単価が、付与日のそれを上回る状況(ケース甲)と、下回る状況(ケース乙)が想定されている。
〔条件変更に係る追加条件〕
A社の株式は全体的な株式相場の下落の影響を受け、一貫して行使価格(権利行使時の1株当たりの払込額)である75,000円を大幅に下回り、インセンティブ効果が失われたと考えられたため、その回復を期して、X4年6月の株主総会において行使価格を引き下げた。
・条件変更日:X4年7月1日
・行使価格(1株当たり):75,000円から、次の価格に引き下げた。
ケース甲 31,000円
ケース乙 52,000円
・条件変更日(条件変更直後)のストック・オプションの公正な評価単価:
ケース甲 9,000円/個(> 付与日の公正な評価単価8,000円/個)
ケース乙 5,000円/個(< 付与日の公正な評価単価8,000円/個)
・条件変更直前のストック・オプションの公正な評価単価: 800円/個
年度ごとのストック・オプション数の実績は以下のとおり。
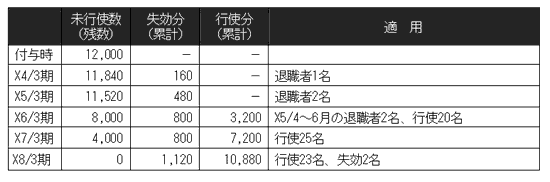
〔X4年3月期〕(条件変更より前の期)
当期の費用計上額:(75人-1人)×8,000円/個×160個/人×9月/24月=35,520,000円
(仕訳)
給料手当 35,520,000 / 新株予約権 35,520,000
〔X5年3月期〕(条件変更日を含む期)
<ケース甲>
条件変更により、ストック・オプションの公正な評価単価のベースが、8,000円/個から9,000円/個に修正されたものとして取扱う。
(1)従来の配分計算を継続する部分:対象勤務期間(X3年7月からX5年6月までの24ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×8,000円/個×160個/人×21月/24月-35,520,000円(前期までの費用計上額)=45,120,000円
(2)条件変更による追加的な配分計算:対象勤務期間の残存期間(X4年7月からX5年6月までの12ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×(9,000円/個-8,000円/個)×160個/人×9月/12月=8,640,000円
当期の費用計上額は、(1)に(2)を加えた53,760,000円(=45,120,000円+8,640,000円)となる。
(仕訳)
給料手当 53,760,000 / 新株予約権 53,760,000
<ケース乙>
条件変更日のストック・オプションの公正な評価単価(5,000円/個)が、付与日のストック・オプションの公正な評価単価(8,000円/個)を下回るので、付与日の公正な評価単価にもとづく費用配分計算を継続する。
(1)従来の配分計算を継続:対象勤務期間(X3年7月からX5年6月までの24ヶ月)を基礎として配分
(75人-3人)×8,000円/個×160個/人×21月/24月-35,520,000円=45,120,000円
(仕訳)
給料手当 45,120,000 / 新株予約権 45,120,000
〔X6年3月期〕(費用計上の会計処理)
<ケース甲>
(1)従来の配分計算を継続する部分
(75人-5人)×8,000円/個×160個/人×24月/24月-(35,520,000円+45,120,000円)
=8,960,000円
(2)条件変更による追加的な配分計算
(75人-5人)×(9,000円/個-8,000円/個)×160個/人×12月/12月-8,640,000円
=2,560,000円
当期の費用計上額:8,960,000円(1)+2,560,000円(2)=11,520,000円
(仕訳)
給料手当 11,520,000 / 新株予約権 11,520,000
<ケース乙>
(1)従来の配分計算を継続
(75人-5人)×8,000円/個×160個/人×24月/24月-(35,520,000円+45,120,000円)
=8,960,000円
(仕訳)
給料手当 8,960,000 / 新株予約権 8,960,000
〔X6年3月期〕(権利行使の会計処理―新株発行)
<ケース甲>
払込金額:160個/人×20人×31,000円=99,200,000円
行使されたストック・オプションの金額:160個/人×20人×9,000円=28,800,000円
(仕訳)
現金預金 99,200,000 払込資本 128,000,000
新株予約権 28,800,000
<ケース乙>
払込金額:160個/人×20人×52,000円=166,400,000円
行使されたストック・オプションの金額:160個/人×20人×8,000円=25,600,000円
(仕訳)
現金預金 166,400,000 払込資本 192,000,000
新株予約権 25,600,000
(以下省略)
6 取引対価として自社株式オプションや自社株式を用いる取引
ストック・オプションに関する会計処理は、取引対価として自社株式オプションを用いる取引にも適用される。また、財貨・サービスの取得の対価として、自社株式を用いる取引においても、取得した財貨・サービスを財務諸表上認識することが求められる。これらの場合においては、取得した財貨・サービスの価値で測定することがあり得ることや、測定の基準日等について、若干の留意事項が掲げられている(第13項、第14項)。
7 開示項目
本基準案においては、開示の基本的な考え方や項目を示すにとどめ、具体的な開示の詳細や開示情報の算定方法については、本会計基準の適用指針において定めることとされている(第60項)。開示項目は次のとおりとされている(第15項)。
●本基準案の適用による財務諸表への影響額
●付与されているストック・オプションの概要
各報告期間において存在したストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
●ストック・オプション付与に伴い財務諸表上計上される数値の見積方法
●その他の項目
本基準案は、一部の注記項目を除き、平成18年4月1日以後開始する事業年度に新たに付与又は交付されるストック・オプション、自社株式オプション及び自社株式につき適用される。
8 おわりに
本基準案は公開草案として公表され、平成17年2月末日までコメントを募集している(http://www.asb.or.jp/)。本基準案の全体がコメントの対象になるが、特に議論が多かった、新株予約権の表示(費用認識の相手勘定)と、未公開会社の取扱いについては、コメントの参考として、ASBの審議等における主な指摘事項の一覧表が添付されている。また、本基準案の内容に対するコメントに加え、本基準案を基礎に会計基準を導入する場合、適用指針において実務上重要性のある項目を網羅するため、適用指針において規定が求められる事項等についても、コメントが求められている。
脚注
1 国際会計基準審議会では、平成14年11月に公表された公開草案を経て平成16年2月に国際財務報告基準書第2号「株式報酬」が公表された。
また、米国では、平成16年3月に公表された公開草案を経て、平成16年12月に米国財務会計基準書第123号の改訂版「株式報酬」が公表された。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















