資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)資産の譲渡の範囲
(資産の譲渡の範囲)
1 サラリーマンが行う建物の賃付けの取扱い
2 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
3 事業者の事業用固定資産の売却
4 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
5 譲渡担保が実行された場合の課税関係
6 商品を融通し合う場合の課税
7 陳列棚の無償取得
8 ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
9 テナントから領収するビルの共益費
10 違約入居者から受け取る割増賃貸料
11 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
12 共同販売促進費の取扱い
13 共同施設に係る特別負担金
14 マンション管理組合の課税関係
15 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
16 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
17 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
18 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
19 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
20 経営指導料、フランチャイズ手数料等
21 生命保険料の引去手数料
22 お布施、戒名料、玉串料等
23 チップの支払
24 ホテルの客のタクシー代の立替払
25 実費弁償金の課税
26 印刷業者が郵便はがきに印刷を行う場合
27 早期完済割引料
28 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
29 土地に設定された抵当権の譲渡
30 土地信託と消費税
31 未経過固定資産税等の取扱い
32 不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
33 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
34 減資(株式の有償消却)
35 分割に伴って行われる資産の移転
サラリーマンが行う建物の賃付けの取扱い
【 照会要旨】
サラリーマンが行う建物の賃付けは、課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税の課税対象となる取引は、事業者が事業として行う資産の譲渡等であるから、サラリーマンが行う建物の賃付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。
なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
【 照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5-1-1(注)1)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業者の事業用固定資産の売却
【 照会要旨】
事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法2①八、4①、令2③、基通5-1-1、5-1-7)。
例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合にも課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第3項、消費税法基本通達5-1-1、5-1-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
【 照会要旨】
個人事業者が所有する資産で、事業と家事の用途に共通して使用されるものを売却した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。 (例)1. 店舗兼住宅の1階部分を店舗又は工場に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物
2. 昼は事業用、夜は家庭用として使用している電話に係る電話加入権
なお、所得税法の計算上は、家事関連費であっても業務の遂行上必要であること等の一定の要件に該当するものについては、必要経費に算入されます(所法45、所法令96)。
【 回答要旨】
事業と家事の用途に共通して使用される資産であっても、譲渡すれば事業用の部分については課税の対象となります(按分)。
ただし、例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。
【 関係法令通達】
消費税法基本通達10-1-19
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
譲渡担保が実行された場合の課税関係
【 照会要旨】
譲渡担保が実行された場合の譲渡担保設定者及び担保権者における課税関係はどうなるのでしょうか。
なお、譲渡担保には次の二つの形態があるとされています。
〔清算型〕 担保権者は、債務不履行の場合には目的物を任意に売却してその代金を元利金の弁済に充て、残余があれば債務者に返還します。
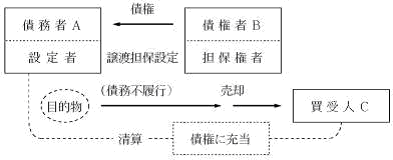
〔流質型〕 特約により弁済に代えて債権者が目的物の所有権を完全に取得します。
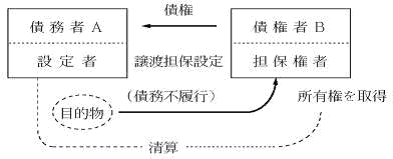
【 回答要旨】
清算型と流質型についてそれぞれ次のとおり取り扱われます。
〔 清算型〕
① 設定者A………担保権者Bが売却処分を行った時に、目的物を買受人Cに譲渡したことになります。
② 担保権者B………設定者に対する債権の弁済を受けます(消費税の課税関係は生じません。)。
③ 買受人C…………目的物の引渡しを受けた時に設定者Aから資産の譲渡を受けたことになります。 (注) 担保権者は弁済に充てるため目的物を換価するのみです。したがって、担保権者は目的物の所有権を取得せず、目的物の譲渡は直接設定者から買受人に対して行われます(このような場合、経理上も担保権者は目的物を自己の資産として計上することはありませんから、担保としての実態に即して取り扱います。)。
なお、契約において、債務不履行があった場合には担保権者が目的物の所有権を取得することとしており、経理上も自己の資産として計上している実態にあるときには、設定者から担保権者に対する譲渡として扱います。この場合、設定者に支払うべき清算金があるときには、被担保債権の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。
〔 流質型〕
① 設定者A………債務の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。
② 担保権者B……被担保債権の額に清算金を加算した金額が仕入対価の額になります。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、第4項、第28条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
商品を融通し合う場合の課税
【 照会要旨】
複数の事業者間で商品を融通し合ったときは、それぞれが資産の譲渡等に該当することになりますか。
【 回答要旨】
商品の融通が買取り又は交換に該当する場合には、資産の譲渡等に該当しますが、単に一時的に商品を融通し合い、その融通について、同種、同等、同量の物を返還し、手数料、利子、使用料その他名目のいかんを問わず一切金銭等の支払がなされないものは、資産の譲渡等には該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、消費税法基本通達5-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
陳列棚の無償取得
【 照会要旨】
百貨店の化粧品売り場にある陳列棚は、化粧品メーカーから無償で取得するものが多いですが、この陳列棚の取得に対する消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
なお、法人税法上、百貨店の当該陳列棚の取得は、化粧品メーカーが取得した価額の2/3に相当する金額から百貨店がその取得に支出した金額を控除した金額を収益に計上することとされています(法法22、法基通4-2-1)。
【 回答要旨】
法人税法上受贈益として収益に計上する必要があるものであっても、消費税法上は、課税資産の譲渡等に該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、百貨店は広告宣伝用の資産を無償で取得しても、それにより反対給付としての課税資産の譲渡等(広告宣伝という新たな負担)を行うものではありませんから、課税関係は生じません。
(注)1 化粧品メーカーが当該陳列棚の取得等に要した費用については、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除の対象とすることになります。
2 上記取引において、百貨店が一部負担金をメーカーに支出している場合には、その支出した金額は百貨店の課税仕入れとなります(メーカーにおいては、課税売上げとなります。)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
【 照会要旨】
A社は、B銀行から取得資金を借り入れ、ゴルフ会員権発行会社であるC社から預託金方式によるゴルフ会員権を取得しました。C社は、A社の銀行からの資金の借入れに際して、A社の連帯保証人となりました。
その後、A社が借入金の返済を遅延したことから、保証委託契約に基づき連帯保証人であるC社が、A社の借入金をB銀行に代位弁済し、C社はA社に対する求償権とA社が入会に際して支払った預託金とを相殺しました。
A社は代位弁済されたことにより当該ゴルフクラブの会員たる地位を失い、入会保証金証書及びその預り証は無効となりますが、この場合において、A社のゴルフ会員権の喪失は、求償権の代物弁済によるゴルフ会員権の譲渡として消費税の課税対象となるのでしょうか。
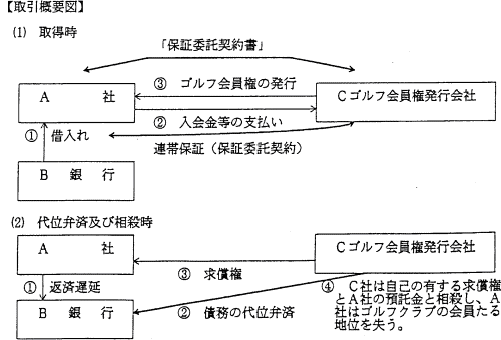
【 回答要旨】
C社が有する求償権とA社が有する預託金の相殺は、ゴルフ会員権による代物弁済に当たらず、消費税の課税の対象となりません。
( 理由)
A社は、C社がB銀行に代位弁済した時点でゴルフ会員としての地位を失い、ゴルフ場施設の優先的利用権及び年会費等の支払義務が消滅し、入会保証金証書及びその預り証は無効となり、A社は預託金返還請求権のみを有することとなると認められます。
したがって、照会の取引は、A社の預託金返還請求権とC社の求償権とを相殺したものですから、A社とC社がそれぞれ有する金銭債権が対当額で消滅したにすぎず、資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税対象外です。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
テナントから領収するビルの共益費
【 照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【 回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
違約入居者から受け取る割増賃貸料
【 照会要旨】
賃貸事務所の入居者が契約条件に従わない場合等には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料を徴収することとしていますが、この規定の賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金又は違約金的なものとして、事務所の貸付けの対価には該当しないと考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合等、一定の要件に該当する場合における割増料金としての性格を有するものと認められます。したがって、その全額が事務所の貸付けの対価に該当することとなります(基通5-2-5)。
( 参考)
供給契約に違反する受給形態等による電気、ガスの受給、電車等の不正乗車等についても通常の料金の3倍に相当する額の料金、運賃等を徴収する場合がありますが、いずれもその全額が対価の額となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
【 照会要旨】
当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。
この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。
【 回答要旨】
建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。
したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同販売促進費の取扱い
【 照会要旨】
契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために展示会等を行い、これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしている共同販売促進費の分担金についての課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
メーカー等においては課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては課税仕入れに該当します(法2①八、九、十二)。
なお、販売促進のために行った共同行事に要した費用の全額についてあらかじめ共同行事の参加者ごとの負担割合が定められていて、メーカー等において、その負担割合に応じてその共同行事を参加者が実施したものとして、その分担金収入を参加者からの預り金として経理している場合には、メーカー等は分担金収入を課税の対象としないことができます(基通5-5-7)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第9号、第12号、消費税法基本通達5-5-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同施設に係る特別負担金
【 照会要旨】
組合は、共同施設(組合会館、体育館等)の建設に際し、組合員から特別負担金を徴しています(共同施設は、組合が所有します。)。
この特別負担金収入は、共同施設の建設に要した借入金の返済に充てるものですが、課税の対象となるのでしょうか。 (注) この共同施設は、組合員以外の者にも利用させる場合がありますが、その場合、組合員と組合員以外の者とで、その利用料に差を設けています。
【 回答要旨】
質問の場合には、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であると認められますから、組合が資産の譲渡等に係る対価に該当しないとし、かつ、組合員が課税仕入れに該当しないとしている場合には、その取扱いが認められます(基通5-5-6)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-5-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
マンション管理組合の課税関係
【 照会要旨】
マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
【 照会要旨】
(1) 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。
(2) また、宿泊を希望する参加会員から別途徴収する宿泊費の実費相当額は課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
(1) 団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います。なお、法別表第三に掲げる法人の場合、この参加費収入は特定収入となります。
(2) 宿泊費として別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、当該宿泊費を預り金経理しているときは、その処理は認めるものとします。
なお、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、上記(1)と同様に取り扱います(基通5-5-3)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第60条第4項、消費税法施行令第75条、消費税法基本通達5-5-3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
【 照会要旨】
新製品の製造を開始する場合、親会社から出向契約に基づいて派遣される社員により指導を受けることがあります。その際、親会社に対して派遣社員の給料に相当する額を給与負担金として支払うほか、旅費、通勤費、日当などの実費をも支払うこととし、親会社はそれをそのまま派遣社員に支給しています。この場合、当社が負担する給与負担金及び旅費などの実費相当額は、当社の課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払は本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、子会社がその給与相当額の全部又は一部を給与負担金として親会社に支払うことがありますが、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、課税資産の譲渡等の対価にはなりません。したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません(基通5-5-10)。
また、派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに該当することになり、また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりません。
他社から社員の派遣(出向による派遣を除く。)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達5-5-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「労働者派遣」に係る労働者派遣料
【 照会要旨】
同族法人グループ間において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に規定する許可又は届出をすることなく、労働者派遣会社を設立し、当該グループ内の法人に対し労働者の派遣を行っている取引があり、その典型的な例としては、同族法人グループ内の会社を退職した社員(又は退職させた社員)を当該労働者派遣会社で雇用し、退職前の会社に派遣して退職前と同じ職務に従事させるなど派遣された労働者にとっては、派遣される以前の勤務状況と実質的に何ら変わることがない実態のものがあります。
このような場合であっても、当該労働者派遣会社と労働者の派遣を受ける会社との労働者派遣に基づく対価(労働者派遣会社で雇用している労働者の役務の提供の対価)として金銭を授受しているときは、消費税の課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働派遣法に規定する許可又は届出をすべき労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)となり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります。
〔 参 考〕
○ 事業者が支出する金銭が、「出向」に基づく給与負担金(基通5-5-10(注)の実質的に給与負担金の性格を有する経営指導料等を含む。)となるか、又は「労働者派遣」に係る労働者派遣料となるかは、当該労働者に対する雇用契約関係等の有無(事実関係)に基づき判定することとなりますが、「出向」と「労働者派遣」との関係を整理すると次のようになります(厚生労働省職業安定局編・労働者派遣法)。
① 「出向」の定義
「出向」とは、一般的に出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たに雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるとされています。
また、「出向」は出向元と労働者との関係により、「移籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係が終了し、出向先と労働者との間に一元的な雇用関係が成立する)と「在籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係を維持しつつ、出向先と労働者との間にも雇用契約関係が成立する)に区分されます。
② 「労働者派遣事業」の定義
「労働者派達事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)」とされています(労働者派遣法第2条)。
したがって、次の3つの要素からなる「労働者派遣」を業として行うことを「労働者派遣事業」といいます。 イ 「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」(派遣元が労働者を雇用する。)
ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」(派遣先が労働者を指揮命令する。)
ハ 「労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」(派遣先は労働者を雇用しない。)
以上のことから、「出向」と「労働者派遣」は、派遣先と当該労働者との間に雇用契約関係が存在するか否かにより、明確に区分されることとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号、消費税法基本通達5-5-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
【 照会要旨】
A協同組合は加盟店である組合員に対して、トレーディングスタンプを発行し、それを集めた消費者に対してそのスタンプの枚数に応じて加盟店共通の商品券と引き換えることとしていますが、スタンプと商品券の引換えに係る消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
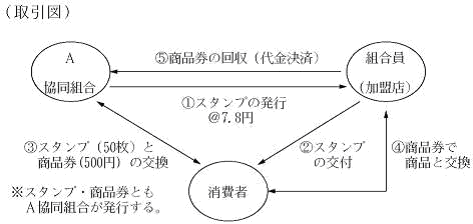
【 回答要旨】
次のとおり取り扱います。 1. 取引図①のスタンプの発行は資産の譲渡等として課税の対象となります。
(資産の譲渡の時期は発行時に全額収益計上している場合は発行時となり、所得税基本通達36・37共-13の2又は法人税基本通達2-1-39のただし書を適用している場合には、これらの規定により総収入金額又は収益として計上すべき時となります。)
2. 取引図②のスタンプの交付及び取引図⑤の商品券の回収はそれぞれ不課税取引となります。
3. 取引図③のスタンプを提示した客に商品券を引き渡す行為は、商品券の無償譲渡であり、資産の譲渡等には該当しません。
4. 取引図④の商品券と商品との交換は課税取引となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
【 照会要旨】
百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合があります。
このお買物券を使用して顧客が買物をした場合、商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、このお買物券に関する消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。 ( 参考)
お買物券を利用して買物をした場合、お買物券の券面額が商品の価格を超えている場合であっても、釣銭は出しません。
【 回答要旨】
事業者が照会のお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、当該お買物券等を交付する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等に該当しません。
また、当該お買物券を利用して買物をした場合に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品等の譲渡の対価の額となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、第28条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
経営指導料、フランチャイズ手数料等
【 照会要旨】
○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
①経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務の対価であり、また、②フランチャイズ手数料及び②ロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価です。
したがって、いずれも課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
生命保険料の引去手数料
【 照会要旨】
事業主が生命保険料の給与からの引去手数料として生命保険会社から金銭を受け取る場合には課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
生命保険料の受入れについては課税関係は生じませんが、生命保険会社から受ける生命保険料の給与からの引去手数料は、保険料受入れに係る役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
お布施、戒名料、玉串料等
【 照会要旨】
寺の住職がもらう「お布施」も課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
チップの支払
【 照会要旨】
運転手や女中等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
運転手や女中等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2①八、十二)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ホテルの客のタクシー代の立替払
【 照会要旨】
ホテルにおいて客のタクシー代や宴会のコンパニオン派遣料等を立替払した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
ホテル等が客の依頼を受けて、又は客が自らタクシーや宴会のコンパニオンを呼んだ場合においては、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものですから、ホテルが当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはなりません。また、その支払はホテルの課税仕入れにも該当しません。
なお、タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
実費弁償金の課税
【 照会要旨】
弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
【 回答要旨】
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
印刷業者が郵便はがきに印刷を行う場合
【 照会要旨】
印刷業者において、郵便はがきの印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 1 郵便局で購入した郵便はがきに、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。
2 郵便局から購入して手持ちしている郵便はがきに、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。
3 注文者が持ち込んだ郵便はがきに注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。
【 回答要旨】
1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便はがきを自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便はがきに係る対価の全額が課税の対象となります。
2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。
ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便はがきについて仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便はがきの代金と印刷代金とを区分の上、郵便はがきの代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。
3 印刷代金のみが課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
早期完済割引料
【 照会要旨】
当社では、延払販売に係る対価については、消費税法施行令第10条第3項第10号《延払販売等に係る利子等の非課税》の規定の適用を受ける場合には、本体価格と利子とを区分して得意先に明示し、得意先が繰上弁済するときには、残賦払金額の1%~3%を早期完済割引料と称して金銭を収受することとしています。
この早期完済割引料は課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
本体価格と利子とを得意先に区分明示して行った延払販売について、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する早期完済割引料は、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金としての性格を有しますので、課税の対象となりません。
なお、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する金銭が一件当たり幾ら(定額)となっているものは、解約手数料を対価とする役務の提供に該当し、課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、第6条、別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第10号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
【 照会要旨】
株式の発行、併合又は分割の場合に交付すべき株式につき1株に満たない部分があるときは、その部分は一括して売却し、その売却代金を株主に交付することとされています(商法220①)。
この場合、株式発行法人が行う端数株式の一括売却は有価証券の譲渡ですが、株式の交付が困難であるためやむを得ず譲渡するものであることから、課税売上割合の計算において、その譲渡代金の5%相当額を分母に加算しないこととしてよいでしょうか。
また、株主においては、交付を受けた売却代金を課税の対象として取り扱うことでよいでしょうか。
【 回答要旨】
株式の発行、併合又は分割において株式発行法人が一括売却する端数株式は端数株主全員の共有に属し、会社は端数株主からその処分を委託されているにすぎないものと認められますから、当該法人においては消費税の課税関係は生じません。
一方、一括売却に付された端数株式の売却代金は、株主に帰属すべきものですから、株主が交付を受けた売却代金は有価証券の譲渡の対価に該当し、課税売上割合の計算においては、株主はその5%相当額を分母の金額に算入することとなります(令48⑤)。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第48条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地に設定された抵当権の譲渡
【 照会要旨】
融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。
また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税の対象となります。
また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税の対象となります。 ( 理由)
抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第6条第1項、別表第一第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地信託と消費税
【 照会要旨】
土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについては、昭和61.7.9付直審5-6外「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(通達)が定められていますが、事業者が行う土地信託に係る取引の消費税の取扱いについては、同通達を準用することになるのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が個人事業者であるか法人であるかの区分に応じ、同通達の「第二 所得税に関する取扱い」又は「第三 法人税に関する取扱い」の規定を準用することとなります。
例えば、土地信託契約の中でも一般的な賃貸型土地信託に係る消費税の取扱いは、次のようになります。
なお、賃貸型土地信託とは、信託された土地の上に借入金等により建物を建築し、その賃貸による収益を受益者に信託配当金として交付する信託契約をいいます。 (1) 信託の規定による委託者から受託者への信託財産の移転は、資産の譲渡等に該当しません。
ただし、信託の設定により取得した信託受益権を他に譲渡した場合には、受益者が信託受益権の目的となっている信託財産の構成物の全部を一括して譲渡したものとして取り扱われるので、その譲渡等の対価の額を課税資産と非課税資産とに合理的に区分する必要があります。
(2) 借入金等により建物を建築した場合には、受益者が当該建物を取得したことになりますので、受益者の課税仕入れに該当します。
(3) 信託財産となった建物を賃貸した場合の賃貸料収入は受益者の課税売上げとなります(ただし、住宅の貸付けに係るものは非課税となります。)。
(4) 信託財産から支出される販売費、一般管理費等は個々の内容により、課税、非課税及び不課税取引に区分し、その結果課税取引となるものについては、受益者の課税仕入れに該当します。
(5) 信託期間中に受託者から受益者に交付される信託配当金は、資産の譲渡等の対価として受領したものではありませんから、課税関係は生じません。
(6) 信託の終了に伴い受託者から受益者への信託財産の移転は、資産の取得等に該当しないので、課税関係は生じません。
【 関係法令通達】
消費税法第14条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
未経過固定資産税等の取扱い
【 照会要旨】
不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
【 回答要旨】
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
【 照会要旨】
不動産の売買により引渡しを行いましたが、登記簿上名義書替えを行わなかったため、登録名義人である譲渡者が当該不動産の固定資産税を納付することとなりました。この場合に、譲受人から譲渡人に対して当該固定資産税に相当する金額を支払った場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
登記が遅れる場合としては次のようなことが考えられます。 (1) 地上げに伴い地上げ業者が登記を省略する場合(中間登記省略等)
(2) 当事者間の手違いで遅れた場合
(3) 土地の譲渡代金の相当部分を支払った段階で引渡しがあったものとして帳簿上計上するが、移転登記の日は代金の全部を支払ったときとしている場合(基通9-1-2《棚卸資産の引渡しの日の判定》)
【 回答要旨】
不動産の引渡しが行われた後、所有権移転登記が行われないことを原因として所有権移転後の課税期間に係る固定資産税が前所有者に課税された場合に、当事者で当該固定資産税相当額であることを明記して授受した場合には、当該固定資産税相当額は資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱います。
ただし、当事者間で名義借料等役務の提供の対価として授受した場合は、資産の譲渡等の対価として課税となります。 (注) 不動産を年の中途で売買した場合に授受する未経過固定資産税相当額は、資産の譲渡の対価を構成するものですから留意してください。
【 関係法令通達】
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
【 照会要旨】
他社が主催するパック旅行を仕入れて、他に販売する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
他社が主催するパック旅行を他の旅行業者が販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、質問の場合には、BがCから受領する120万円とBがAに支払う100万円の差額の20万円が代売手数料として課税の対象となります。
なお、会計処理上、 仕入 ○○○/ 売上 ○○○ として計上していても、その差額部分(代売手数料)を課税売上げとして処理して差し支えありません(基通10-1-12(2))。
【 関係法令通達】
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-12
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
減資(株式の有償消却)
【 照会要旨】
法人が株式の消却の方法で減資を実施するため、当該法人が株主に金銭を交付して自己株式を取得する場合、当該株主からの株券の引渡しは資産(有価証券)の譲渡等に該当するのでしょうか。
(注) 所得税においては、当該減資により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産の合計額については、配当及び譲渡所得等の収入金額とみなすこととしています(所法25①、租特法37の10④等)。
【 回答要旨】
有償減資による株式の消却は、出資の払戻しであり、たとえ株式の消却により交付を受ける金銭等の中に所得税法等の規定上配当及び譲渡所得等の収入金額とみなされる額が含まれているとしても、減資に伴う株式の消却は株式が喪失(消滅)するものですから、資産の譲渡等には該当しません(基通5-2-9)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-9
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
分割に伴って行われる資産の移転
【 照会要旨】
分割が行われると、分割法人の営業の全部又は一部が包括的に分割承継法人に承継され、分割承継法人の発行する株式が分割法人又は分割法人の株主に割り当てられます。
ところで、法人の設立又は増資に当たって、金銭以外の資産を出資する現物出資は資産の譲渡等に該当することとされていますが(令2①二)、分割に伴って行われる資産の移転も資産の譲渡等に該当することとなるのでしょうか。また、当該分割が、法人税法上の適格分割に該当するか否かにより、取扱いが変わることはあるのでしょうか。
【 回答要旨】
法人税法上の適格分割に該当するか否かを問わず、分割に伴って行われる資産の移転は、資産の譲渡等には該当しません。
( 理由)
会社分割は、合併の場合における被合併法人の権利義務の承継と同様の法的性格を有する包括承継であり、個々の財産の譲渡とは異なるものです。また、会社分割の際の分割法人に対する分割承継法人の発行する株式の割当ては、承継した営業に対して明確な対価性を有しているとは言い難いものです。
なお、現物出資による資産の移転は、個々の財産の譲渡ですが、新株の交付については財産の移転に対する対価であるか疑義があるところです。しかし、その経済的実質は対価を得て行う取引である変態現物出資(事後設立)と変わりがないことから、消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡の範囲》の規定により、対価を得て行う資産の譲渡に含めることとしています。
( 参考)
1 「分割の対象」
分割の対象は、営業の全部又は一部に限定されます(商法373、373の16)。
「営業」とは、営業用財産である物及び権利だけでなく、これに得意先関係、仕入先関係、販売の機会、営業上の秘訣、経営の組織等の経済的価値のある事実関係を加え、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産をいいます。また、「営業の一部」とは、会社が行っている複数の営業のうちの一部等、それ自体が営業としての内容を備えているものをいい、個々の物又は権利自体である「営業用財産」とは異なります。
このように、分割の対象が営業とされていることから、営業を構成しない財産を会社分割により分割承継法人に承継させることはできないこととされています。
2 営業譲渡との差異
会社分割と営業譲渡とは、いずれも営業を単位として権利義務が承継されるという点で共通しています。しかしながら、会社分割が商法の定める組織の再編成であるのに対し、営業譲渡は、商人が行う取引行為の一つであって、民法の売買や商法の商行為に関する規定によって要件及び効果が律せられるものです。したがって、営業譲渡においては、譲受会社から譲渡会社に対して当然に対価としての金銭が支払われます。
また、会社分割に基づく権利義務の承継は、合併と同様の包括承継に当たると解されており、法律上当然に生じることとされているのに対し、営業譲渡に基づく権利義務の承継は、法律上は特定承継としての性質を有します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法施行令第2条第1項第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 サラリーマンが行う建物の賃付けの取扱い
2 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
3 事業者の事業用固定資産の売却
4 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
5 譲渡担保が実行された場合の課税関係
6 商品を融通し合う場合の課税
7 陳列棚の無償取得
8 ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
9 テナントから領収するビルの共益費
10 違約入居者から受け取る割増賃貸料
11 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
12 共同販売促進費の取扱い
13 共同施設に係る特別負担金
14 マンション管理組合の課税関係
15 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
16 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
17 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
18 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
19 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
20 経営指導料、フランチャイズ手数料等
21 生命保険料の引去手数料
22 お布施、戒名料、玉串料等
23 チップの支払
24 ホテルの客のタクシー代の立替払
25 実費弁償金の課税
26 印刷業者が郵便はがきに印刷を行う場合
27 早期完済割引料
28 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
29 土地に設定された抵当権の譲渡
30 土地信託と消費税
31 未経過固定資産税等の取扱い
32 不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
33 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
34 減資(株式の有償消却)
35 分割に伴って行われる資産の移転
サラリーマンが行う建物の賃付けの取扱い
【 照会要旨】
サラリーマンが行う建物の賃付けは、課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税の課税対象となる取引は、事業者が事業として行う資産の譲渡等であるから、サラリーマンが行う建物の賃付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。
なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
【 照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5-1-1(注)1)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業者の事業用固定資産の売却
【 照会要旨】
事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法2①八、4①、令2③、基通5-1-1、5-1-7)。
例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合にも課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第3項、消費税法基本通達5-1-1、5-1-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
【 照会要旨】
個人事業者が所有する資産で、事業と家事の用途に共通して使用されるものを売却した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。 (例)1. 店舗兼住宅の1階部分を店舗又は工場に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物
2. 昼は事業用、夜は家庭用として使用している電話に係る電話加入権
なお、所得税法の計算上は、家事関連費であっても業務の遂行上必要であること等の一定の要件に該当するものについては、必要経費に算入されます(所法45、所法令96)。
【 回答要旨】
事業と家事の用途に共通して使用される資産であっても、譲渡すれば事業用の部分については課税の対象となります(按分)。
ただし、例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。
【 関係法令通達】
消費税法基本通達10-1-19
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
譲渡担保が実行された場合の課税関係
【 照会要旨】
譲渡担保が実行された場合の譲渡担保設定者及び担保権者における課税関係はどうなるのでしょうか。
なお、譲渡担保には次の二つの形態があるとされています。
〔清算型〕 担保権者は、債務不履行の場合には目的物を任意に売却してその代金を元利金の弁済に充て、残余があれば債務者に返還します。
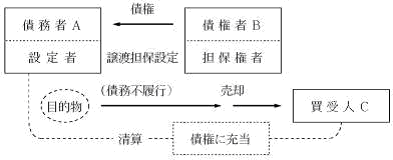
〔流質型〕 特約により弁済に代えて債権者が目的物の所有権を完全に取得します。
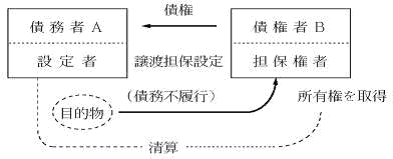
【 回答要旨】
清算型と流質型についてそれぞれ次のとおり取り扱われます。
〔 清算型〕
① 設定者A………担保権者Bが売却処分を行った時に、目的物を買受人Cに譲渡したことになります。
② 担保権者B………設定者に対する債権の弁済を受けます(消費税の課税関係は生じません。)。
③ 買受人C…………目的物の引渡しを受けた時に設定者Aから資産の譲渡を受けたことになります。 (注) 担保権者は弁済に充てるため目的物を換価するのみです。したがって、担保権者は目的物の所有権を取得せず、目的物の譲渡は直接設定者から買受人に対して行われます(このような場合、経理上も担保権者は目的物を自己の資産として計上することはありませんから、担保としての実態に即して取り扱います。)。
なお、契約において、債務不履行があった場合には担保権者が目的物の所有権を取得することとしており、経理上も自己の資産として計上している実態にあるときには、設定者から担保権者に対する譲渡として扱います。この場合、設定者に支払うべき清算金があるときには、被担保債権の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。
〔 流質型〕
① 設定者A………債務の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。
② 担保権者B……被担保債権の額に清算金を加算した金額が仕入対価の額になります。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、第4項、第28条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
商品を融通し合う場合の課税
【 照会要旨】
複数の事業者間で商品を融通し合ったときは、それぞれが資産の譲渡等に該当することになりますか。
【 回答要旨】
商品の融通が買取り又は交換に該当する場合には、資産の譲渡等に該当しますが、単に一時的に商品を融通し合い、その融通について、同種、同等、同量の物を返還し、手数料、利子、使用料その他名目のいかんを問わず一切金銭等の支払がなされないものは、資産の譲渡等には該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、消費税法基本通達5-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
陳列棚の無償取得
【 照会要旨】
百貨店の化粧品売り場にある陳列棚は、化粧品メーカーから無償で取得するものが多いですが、この陳列棚の取得に対する消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
なお、法人税法上、百貨店の当該陳列棚の取得は、化粧品メーカーが取得した価額の2/3に相当する金額から百貨店がその取得に支出した金額を控除した金額を収益に計上することとされています(法法22、法基通4-2-1)。
【 回答要旨】
法人税法上受贈益として収益に計上する必要があるものであっても、消費税法上は、課税資産の譲渡等に該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、百貨店は広告宣伝用の資産を無償で取得しても、それにより反対給付としての課税資産の譲渡等(広告宣伝という新たな負担)を行うものではありませんから、課税関係は生じません。
(注)1 化粧品メーカーが当該陳列棚の取得等に要した費用については、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除の対象とすることになります。
2 上記取引において、百貨店が一部負担金をメーカーに支出している場合には、その支出した金額は百貨店の課税仕入れとなります(メーカーにおいては、課税売上げとなります。)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
【 照会要旨】
A社は、B銀行から取得資金を借り入れ、ゴルフ会員権発行会社であるC社から預託金方式によるゴルフ会員権を取得しました。C社は、A社の銀行からの資金の借入れに際して、A社の連帯保証人となりました。
その後、A社が借入金の返済を遅延したことから、保証委託契約に基づき連帯保証人であるC社が、A社の借入金をB銀行に代位弁済し、C社はA社に対する求償権とA社が入会に際して支払った預託金とを相殺しました。
A社は代位弁済されたことにより当該ゴルフクラブの会員たる地位を失い、入会保証金証書及びその預り証は無効となりますが、この場合において、A社のゴルフ会員権の喪失は、求償権の代物弁済によるゴルフ会員権の譲渡として消費税の課税対象となるのでしょうか。
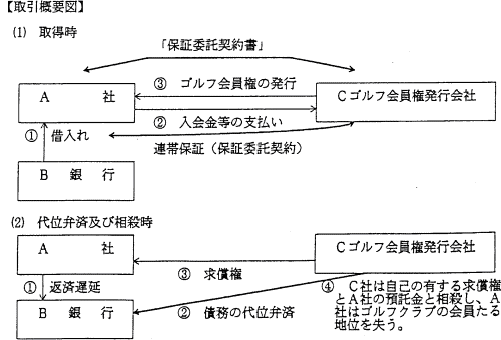
【 回答要旨】
C社が有する求償権とA社が有する預託金の相殺は、ゴルフ会員権による代物弁済に当たらず、消費税の課税の対象となりません。
( 理由)
A社は、C社がB銀行に代位弁済した時点でゴルフ会員としての地位を失い、ゴルフ場施設の優先的利用権及び年会費等の支払義務が消滅し、入会保証金証書及びその預り証は無効となり、A社は預託金返還請求権のみを有することとなると認められます。
したがって、照会の取引は、A社の預託金返還請求権とC社の求償権とを相殺したものですから、A社とC社がそれぞれ有する金銭債権が対当額で消滅したにすぎず、資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税対象外です。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
テナントから領収するビルの共益費
【 照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【 回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
違約入居者から受け取る割増賃貸料
【 照会要旨】
賃貸事務所の入居者が契約条件に従わない場合等には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料を徴収することとしていますが、この規定の賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金又は違約金的なものとして、事務所の貸付けの対価には該当しないと考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合等、一定の要件に該当する場合における割増料金としての性格を有するものと認められます。したがって、その全額が事務所の貸付けの対価に該当することとなります(基通5-2-5)。
( 参考)
供給契約に違反する受給形態等による電気、ガスの受給、電車等の不正乗車等についても通常の料金の3倍に相当する額の料金、運賃等を徴収する場合がありますが、いずれもその全額が対価の額となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
【 照会要旨】
当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。
この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。
【 回答要旨】
建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。
したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同販売促進費の取扱い
【 照会要旨】
契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために展示会等を行い、これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしている共同販売促進費の分担金についての課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
メーカー等においては課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては課税仕入れに該当します(法2①八、九、十二)。
なお、販売促進のために行った共同行事に要した費用の全額についてあらかじめ共同行事の参加者ごとの負担割合が定められていて、メーカー等において、その負担割合に応じてその共同行事を参加者が実施したものとして、その分担金収入を参加者からの預り金として経理している場合には、メーカー等は分担金収入を課税の対象としないことができます(基通5-5-7)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第9号、第12号、消費税法基本通達5-5-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同施設に係る特別負担金
【 照会要旨】
組合は、共同施設(組合会館、体育館等)の建設に際し、組合員から特別負担金を徴しています(共同施設は、組合が所有します。)。
この特別負担金収入は、共同施設の建設に要した借入金の返済に充てるものですが、課税の対象となるのでしょうか。 (注) この共同施設は、組合員以外の者にも利用させる場合がありますが、その場合、組合員と組合員以外の者とで、その利用料に差を設けています。
【 回答要旨】
質問の場合には、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であると認められますから、組合が資産の譲渡等に係る対価に該当しないとし、かつ、組合員が課税仕入れに該当しないとしている場合には、その取扱いが認められます(基通5-5-6)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-5-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
マンション管理組合の課税関係
【 照会要旨】
マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
【 照会要旨】
(1) 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。
(2) また、宿泊を希望する参加会員から別途徴収する宿泊費の実費相当額は課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
(1) 団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います。なお、法別表第三に掲げる法人の場合、この参加費収入は特定収入となります。
(2) 宿泊費として別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、当該宿泊費を預り金経理しているときは、その処理は認めるものとします。
なお、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、上記(1)と同様に取り扱います(基通5-5-3)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第60条第4項、消費税法施行令第75条、消費税法基本通達5-5-3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
【 照会要旨】
新製品の製造を開始する場合、親会社から出向契約に基づいて派遣される社員により指導を受けることがあります。その際、親会社に対して派遣社員の給料に相当する額を給与負担金として支払うほか、旅費、通勤費、日当などの実費をも支払うこととし、親会社はそれをそのまま派遣社員に支給しています。この場合、当社が負担する給与負担金及び旅費などの実費相当額は、当社の課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払は本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、子会社がその給与相当額の全部又は一部を給与負担金として親会社に支払うことがありますが、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、課税資産の譲渡等の対価にはなりません。したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません(基通5-5-10)。
また、派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに該当することになり、また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりません。
他社から社員の派遣(出向による派遣を除く。)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達5-5-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「労働者派遣」に係る労働者派遣料
【 照会要旨】
同族法人グループ間において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に規定する許可又は届出をすることなく、労働者派遣会社を設立し、当該グループ内の法人に対し労働者の派遣を行っている取引があり、その典型的な例としては、同族法人グループ内の会社を退職した社員(又は退職させた社員)を当該労働者派遣会社で雇用し、退職前の会社に派遣して退職前と同じ職務に従事させるなど派遣された労働者にとっては、派遣される以前の勤務状況と実質的に何ら変わることがない実態のものがあります。
このような場合であっても、当該労働者派遣会社と労働者の派遣を受ける会社との労働者派遣に基づく対価(労働者派遣会社で雇用している労働者の役務の提供の対価)として金銭を授受しているときは、消費税の課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働派遣法に規定する許可又は届出をすべき労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)となり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります。
〔 参 考〕
○ 事業者が支出する金銭が、「出向」に基づく給与負担金(基通5-5-10(注)の実質的に給与負担金の性格を有する経営指導料等を含む。)となるか、又は「労働者派遣」に係る労働者派遣料となるかは、当該労働者に対する雇用契約関係等の有無(事実関係)に基づき判定することとなりますが、「出向」と「労働者派遣」との関係を整理すると次のようになります(厚生労働省職業安定局編・労働者派遣法)。
① 「出向」の定義
「出向」とは、一般的に出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たに雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるとされています。
また、「出向」は出向元と労働者との関係により、「移籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係が終了し、出向先と労働者との間に一元的な雇用関係が成立する)と「在籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係を維持しつつ、出向先と労働者との間にも雇用契約関係が成立する)に区分されます。
② 「労働者派遣事業」の定義
「労働者派達事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)」とされています(労働者派遣法第2条)。
したがって、次の3つの要素からなる「労働者派遣」を業として行うことを「労働者派遣事業」といいます。 イ 「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」(派遣元が労働者を雇用する。)
ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」(派遣先が労働者を指揮命令する。)
ハ 「労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」(派遣先は労働者を雇用しない。)
以上のことから、「出向」と「労働者派遣」は、派遣先と当該労働者との間に雇用契約関係が存在するか否かにより、明確に区分されることとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号、消費税法基本通達5-5-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
【 照会要旨】
A協同組合は加盟店である組合員に対して、トレーディングスタンプを発行し、それを集めた消費者に対してそのスタンプの枚数に応じて加盟店共通の商品券と引き換えることとしていますが、スタンプと商品券の引換えに係る消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
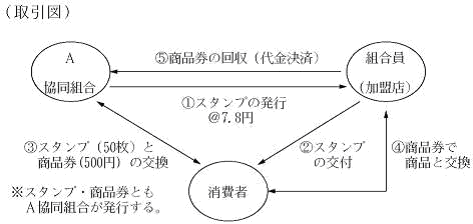
【 回答要旨】
次のとおり取り扱います。 1. 取引図①のスタンプの発行は資産の譲渡等として課税の対象となります。
(資産の譲渡の時期は発行時に全額収益計上している場合は発行時となり、所得税基本通達36・37共-13の2又は法人税基本通達2-1-39のただし書を適用している場合には、これらの規定により総収入金額又は収益として計上すべき時となります。)
2. 取引図②のスタンプの交付及び取引図⑤の商品券の回収はそれぞれ不課税取引となります。
3. 取引図③のスタンプを提示した客に商品券を引き渡す行為は、商品券の無償譲渡であり、資産の譲渡等には該当しません。
4. 取引図④の商品券と商品との交換は課税取引となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
【 照会要旨】
百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合があります。
このお買物券を使用して顧客が買物をした場合、商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、このお買物券に関する消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。 ( 参考)
お買物券を利用して買物をした場合、お買物券の券面額が商品の価格を超えている場合であっても、釣銭は出しません。
【 回答要旨】
事業者が照会のお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、当該お買物券等を交付する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等に該当しません。
また、当該お買物券を利用して買物をした場合に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品等の譲渡の対価の額となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、第28条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
経営指導料、フランチャイズ手数料等
【 照会要旨】
○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
①経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務の対価であり、また、②フランチャイズ手数料及び②ロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価です。
したがって、いずれも課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
生命保険料の引去手数料
【 照会要旨】
事業主が生命保険料の給与からの引去手数料として生命保険会社から金銭を受け取る場合には課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
生命保険料の受入れについては課税関係は生じませんが、生命保険会社から受ける生命保険料の給与からの引去手数料は、保険料受入れに係る役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
お布施、戒名料、玉串料等
【 照会要旨】
寺の住職がもらう「お布施」も課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
チップの支払
【 照会要旨】
運転手や女中等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
運転手や女中等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2①八、十二)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ホテルの客のタクシー代の立替払
【 照会要旨】
ホテルにおいて客のタクシー代や宴会のコンパニオン派遣料等を立替払した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
ホテル等が客の依頼を受けて、又は客が自らタクシーや宴会のコンパニオンを呼んだ場合においては、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものですから、ホテルが当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはなりません。また、その支払はホテルの課税仕入れにも該当しません。
なお、タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
実費弁償金の課税
【 照会要旨】
弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
【 回答要旨】
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
印刷業者が郵便はがきに印刷を行う場合
【 照会要旨】
印刷業者において、郵便はがきの印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 1 郵便局で購入した郵便はがきに、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。
2 郵便局から購入して手持ちしている郵便はがきに、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。
3 注文者が持ち込んだ郵便はがきに注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。
【 回答要旨】
1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便はがきを自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便はがきに係る対価の全額が課税の対象となります。
2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。
ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便はがきについて仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便はがきの代金と印刷代金とを区分の上、郵便はがきの代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。
3 印刷代金のみが課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
早期完済割引料
【 照会要旨】
当社では、延払販売に係る対価については、消費税法施行令第10条第3項第10号《延払販売等に係る利子等の非課税》の規定の適用を受ける場合には、本体価格と利子とを区分して得意先に明示し、得意先が繰上弁済するときには、残賦払金額の1%~3%を早期完済割引料と称して金銭を収受することとしています。
この早期完済割引料は課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
本体価格と利子とを得意先に区分明示して行った延払販売について、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する早期完済割引料は、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金としての性格を有しますので、課税の対象となりません。
なお、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する金銭が一件当たり幾ら(定額)となっているものは、解約手数料を対価とする役務の提供に該当し、課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第1項、第6条、別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第10号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
【 照会要旨】
株式の発行、併合又は分割の場合に交付すべき株式につき1株に満たない部分があるときは、その部分は一括して売却し、その売却代金を株主に交付することとされています(商法220①)。
この場合、株式発行法人が行う端数株式の一括売却は有価証券の譲渡ですが、株式の交付が困難であるためやむを得ず譲渡するものであることから、課税売上割合の計算において、その譲渡代金の5%相当額を分母に加算しないこととしてよいでしょうか。
また、株主においては、交付を受けた売却代金を課税の対象として取り扱うことでよいでしょうか。
【 回答要旨】
株式の発行、併合又は分割において株式発行法人が一括売却する端数株式は端数株主全員の共有に属し、会社は端数株主からその処分を委託されているにすぎないものと認められますから、当該法人においては消費税の課税関係は生じません。
一方、一括売却に付された端数株式の売却代金は、株主に帰属すべきものですから、株主が交付を受けた売却代金は有価証券の譲渡の対価に該当し、課税売上割合の計算においては、株主はその5%相当額を分母の金額に算入することとなります(令48⑤)。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第48条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地に設定された抵当権の譲渡
【 照会要旨】
融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。
また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税の対象となります。
また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税の対象となります。 ( 理由)
抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第6条第1項、別表第一第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地信託と消費税
【 照会要旨】
土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについては、昭和61.7.9付直審5-6外「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(通達)が定められていますが、事業者が行う土地信託に係る取引の消費税の取扱いについては、同通達を準用することになるのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が個人事業者であるか法人であるかの区分に応じ、同通達の「第二 所得税に関する取扱い」又は「第三 法人税に関する取扱い」の規定を準用することとなります。
例えば、土地信託契約の中でも一般的な賃貸型土地信託に係る消費税の取扱いは、次のようになります。
なお、賃貸型土地信託とは、信託された土地の上に借入金等により建物を建築し、その賃貸による収益を受益者に信託配当金として交付する信託契約をいいます。 (1) 信託の規定による委託者から受託者への信託財産の移転は、資産の譲渡等に該当しません。
ただし、信託の設定により取得した信託受益権を他に譲渡した場合には、受益者が信託受益権の目的となっている信託財産の構成物の全部を一括して譲渡したものとして取り扱われるので、その譲渡等の対価の額を課税資産と非課税資産とに合理的に区分する必要があります。
(2) 借入金等により建物を建築した場合には、受益者が当該建物を取得したことになりますので、受益者の課税仕入れに該当します。
(3) 信託財産となった建物を賃貸した場合の賃貸料収入は受益者の課税売上げとなります(ただし、住宅の貸付けに係るものは非課税となります。)。
(4) 信託財産から支出される販売費、一般管理費等は個々の内容により、課税、非課税及び不課税取引に区分し、その結果課税取引となるものについては、受益者の課税仕入れに該当します。
(5) 信託期間中に受託者から受益者に交付される信託配当金は、資産の譲渡等の対価として受領したものではありませんから、課税関係は生じません。
(6) 信託の終了に伴い受託者から受益者への信託財産の移転は、資産の取得等に該当しないので、課税関係は生じません。
【 関係法令通達】
消費税法第14条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
未経過固定資産税等の取扱い
【 照会要旨】
不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
【 回答要旨】
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
【 照会要旨】
不動産の売買により引渡しを行いましたが、登記簿上名義書替えを行わなかったため、登録名義人である譲渡者が当該不動産の固定資産税を納付することとなりました。この場合に、譲受人から譲渡人に対して当該固定資産税に相当する金額を支払った場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
登記が遅れる場合としては次のようなことが考えられます。 (1) 地上げに伴い地上げ業者が登記を省略する場合(中間登記省略等)
(2) 当事者間の手違いで遅れた場合
(3) 土地の譲渡代金の相当部分を支払った段階で引渡しがあったものとして帳簿上計上するが、移転登記の日は代金の全部を支払ったときとしている場合(基通9-1-2《棚卸資産の引渡しの日の判定》)
【 回答要旨】
不動産の引渡しが行われた後、所有権移転登記が行われないことを原因として所有権移転後の課税期間に係る固定資産税が前所有者に課税された場合に、当事者で当該固定資産税相当額であることを明記して授受した場合には、当該固定資産税相当額は資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱います。
ただし、当事者間で名義借料等役務の提供の対価として授受した場合は、資産の譲渡等の対価として課税となります。 (注) 不動産を年の中途で売買した場合に授受する未経過固定資産税相当額は、資産の譲渡の対価を構成するものですから留意してください。
【 関係法令通達】
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
【 照会要旨】
他社が主催するパック旅行を仕入れて、他に販売する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
他社が主催するパック旅行を他の旅行業者が販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、質問の場合には、BがCから受領する120万円とBがAに支払う100万円の差額の20万円が代売手数料として課税の対象となります。
なお、会計処理上、 仕入 ○○○/ 売上 ○○○ として計上していても、その差額部分(代売手数料)を課税売上げとして処理して差し支えありません(基通10-1-12(2))。
【 関係法令通達】
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-12
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
減資(株式の有償消却)
【 照会要旨】
法人が株式の消却の方法で減資を実施するため、当該法人が株主に金銭を交付して自己株式を取得する場合、当該株主からの株券の引渡しは資産(有価証券)の譲渡等に該当するのでしょうか。
(注) 所得税においては、当該減資により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産の合計額については、配当及び譲渡所得等の収入金額とみなすこととしています(所法25①、租特法37の10④等)。
【 回答要旨】
有償減資による株式の消却は、出資の払戻しであり、たとえ株式の消却により交付を受ける金銭等の中に所得税法等の規定上配当及び譲渡所得等の収入金額とみなされる額が含まれているとしても、減資に伴う株式の消却は株式が喪失(消滅)するものですから、資産の譲渡等には該当しません(基通5-2-9)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-9
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
分割に伴って行われる資産の移転
【 照会要旨】
分割が行われると、分割法人の営業の全部又は一部が包括的に分割承継法人に承継され、分割承継法人の発行する株式が分割法人又は分割法人の株主に割り当てられます。
ところで、法人の設立又は増資に当たって、金銭以外の資産を出資する現物出資は資産の譲渡等に該当することとされていますが(令2①二)、分割に伴って行われる資産の移転も資産の譲渡等に該当することとなるのでしょうか。また、当該分割が、法人税法上の適格分割に該当するか否かにより、取扱いが変わることはあるのでしょうか。
【 回答要旨】
法人税法上の適格分割に該当するか否かを問わず、分割に伴って行われる資産の移転は、資産の譲渡等には該当しません。
( 理由)
会社分割は、合併の場合における被合併法人の権利義務の承継と同様の法的性格を有する包括承継であり、個々の財産の譲渡とは異なるものです。また、会社分割の際の分割法人に対する分割承継法人の発行する株式の割当ては、承継した営業に対して明確な対価性を有しているとは言い難いものです。
なお、現物出資による資産の移転は、個々の財産の譲渡ですが、新株の交付については財産の移転に対する対価であるか疑義があるところです。しかし、その経済的実質は対価を得て行う取引である変態現物出資(事後設立)と変わりがないことから、消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡の範囲》の規定により、対価を得て行う資産の譲渡に含めることとしています。
( 参考)
1 「分割の対象」
分割の対象は、営業の全部又は一部に限定されます(商法373、373の16)。
「営業」とは、営業用財産である物及び権利だけでなく、これに得意先関係、仕入先関係、販売の機会、営業上の秘訣、経営の組織等の経済的価値のある事実関係を加え、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産をいいます。また、「営業の一部」とは、会社が行っている複数の営業のうちの一部等、それ自体が営業としての内容を備えているものをいい、個々の物又は権利自体である「営業用財産」とは異なります。
このように、分割の対象が営業とされていることから、営業を構成しない財産を会社分割により分割承継法人に承継させることはできないこととされています。
2 営業譲渡との差異
会社分割と営業譲渡とは、いずれも営業を単位として権利義務が承継されるという点で共通しています。しかしながら、会社分割が商法の定める組織の再編成であるのに対し、営業譲渡は、商人が行う取引行為の一つであって、民法の売買や商法の商行為に関する規定によって要件及び効果が律せられるものです。したがって、営業譲渡においては、譲受会社から譲渡会社に対して当然に対価としての金銭が支払われます。
また、会社分割に基づく権利義務の承継は、合併と同様の包括承継に当たると解されており、法律上当然に生じることとされているのに対し、営業譲渡に基づく権利義務の承継は、法律上は特定承継としての性質を有します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法施行令第2条第1項第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















