資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)運送に関する契約書(第1号の4文書)
(運送に関する契約書(第1号の4文書))
1 運送の意義
2 運送状
3 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
4 用船契約書の意義
5 定期用船契約書
6 裸用船契約書
7 送り状
8 貨物受取書
9 車両賃貸借契約書
10 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
11 リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
12 ご進物品承り票
運送の意義
【 照会要旨】
引越荷物を運ぶことを、貨物自動車を持っている人に頼んで、簡単な念書をつくりました。このようなものでも運送契約ということになるのでしょうか。
【 回答要旨】
運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は人の場所的な移動を約し、相手(依頼人)がこれに報酬(運送賃)を支払うことを約する契約ですから、それが営業として行われるものだけでなく、たまたま行われるものでも運送となります。
したがって、簡単な文書であっても運送の内容について記載され、これを証明するためのものであれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
運送状
【 照会要旨】
第1号文書の定義欄3には「運送に関する契約書には、運送状を含まないものとする。」と規定されていますが、この運送状とはどういうものでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法において、運送に関する契約書に含めないこととしている運送状とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともにその到達地に送付され、荷受人が運送品の同一性を検査し、また、着払運賃などその負担する義務の範囲を知るために利用される文書で、一般に「送り状」とも呼ばれているものです。
したがって、その文書の標題が「運送状」、「送り状」などと称する文書であっても、運送品とともに、その到達地に送付されることなく、運送契約の成立を証明するために荷送人に交付されるものは運送状には該当せず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として取り扱われることになります(基通第1号の4文書の2)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
貨物運送に関して作成される文書の取扱い
【 照会要旨】
貨物運送に関して作成される文書には、その標題をみても「運送状」、「送り状」、「発送伝票」、「運送明細書」、「貨物引受書」、「貨物受取書」、「運賃請求書」、「運賃受取書」など各種のものがありますが、これらに対する印紙税の取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
貨物運送業者が荷送人から貨物の運送を引き受けた際に荷送人に交付する文書で、その文書に運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成立の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの証としているものは、その文書の標題のいかんにかかわらず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として印紙税が課税されることになります。
なお、貨物の運送に関して作成される文書に対する印紙税の取扱いは、おおむね次表のとおりです。
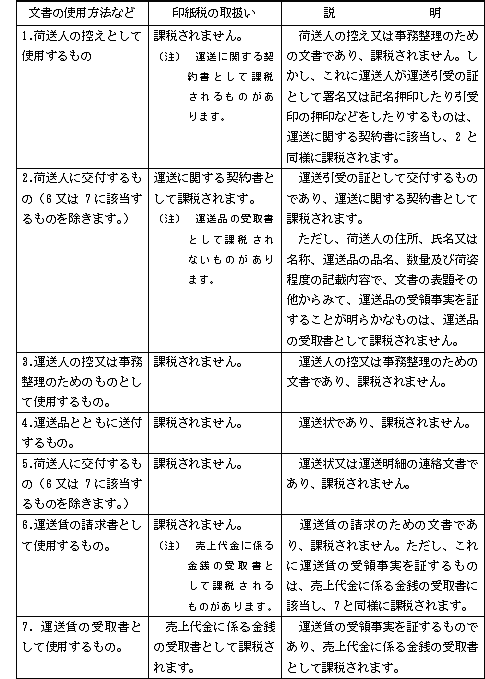
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
用船契約書の意義
【 照会要旨】
第1号の4文書(運送に関する契約書)には用船契約書を含むこととされていますが、用船契約とはどういうものでしょうか。
【 回答要旨】
「用船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これに積載した物品等を運送することを約する契約をいいますが、これには次の方法があり、いずれも用船契約に当たります(基通第1号の4文書の4)。
(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの
(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
定期用船契約書
【 照会要旨】
一定期間、船舶を乗組員付きで借受け、借主がこの船舶を用いて貨物運送を行う場合には、船主は、船舶使用料を収受するにすぎませんが、これも用船契約書ということになるのでしょうか。
【 回答要旨】
定期用船契約は、船主が一定期間船舶の全部を乗組員付きで定期用船者に貸し切るとともに、船長使用約款等に基づいて、船長をその期間内定期用船者の指示の下におく契約です。
これは、単なる船舶の賃貸借とは異なることから、印紙税法上運送に関する契約に含めることにしており、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当しますが、定期用船契約書のうち、契約期間が3月を超え、かつ、用船の目的物の種類、数量、単価、対価の支払方法等を定めるものは第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することになります(基通第1号の4文書の5)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
裸用船契約書
【 照会要旨】
第1号文書の定義欄4には、「用船契約書には、裸用船契約書を含まないものとする。」と規定されていますが、この裸用船契約書とはどういうものでしょうか。
また、裸用船契約は課税されないのでしょうか。
【 回答要旨】
定期用船契約は、船長その他の乗組員付きで船舶又は航空機を借り受けるのに対し、裸用船契約は乗組員のつかない船舶又は航空機そのものの賃貸借を内容とする契約です。
そのため、裸用船契約書は用船契約という名称を用いていますが、その実質は不課税文書である賃貸借契約書となりますから、課税物件表の第1号文書の定義欄4で第1号文書には該当しないことを念のため規定しているものです(基通第1号の4文書の6)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
送り状
【 照会要旨】
次の文書は、運送人が貨物の運送を引き受けた際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
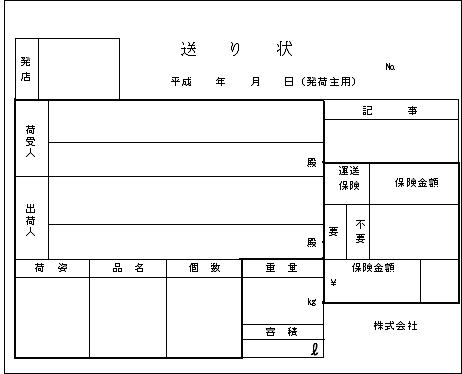
【 回答要旨】
ご質問の文書は、荷受人、出荷人及び運送保険についての事項が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく、運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、記載金額のない第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
同様の文書で、運賃額の記載のあるものは、その金額に応じて印紙税が課税されます。
なお、貨物とともに荷受人に送付される文書は、印紙税の課税対象から除かれている運送状に該当しますから、課税文書には該当しません(課税物件表第1号の4文書定義欄3)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表第1号の4文書定義欄3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
貨物受取書
【 照会要旨】
次の①及び②の文書は、運送業者が運送物品を受け取った際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
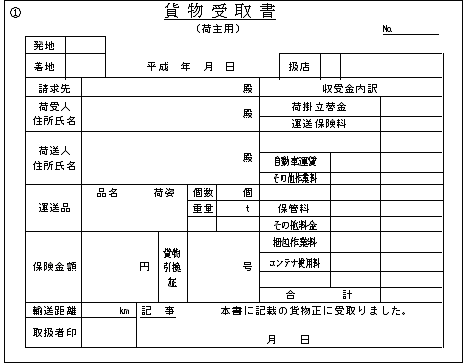
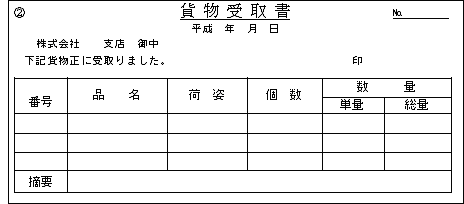
【 回答要旨】
①の文書は、標題が貨物受取書になっていますが、発地、着地、運送賃、荷受人、荷送人及び運送保険についての事項等が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
第1号の4文書の記載金額(契約金額)とは、運送料、用船料、有料道路利用料、集荷料、配達料、保管料等の運送契約の対価のすべてをいい、品代金取立料(代引手数料)、運送保険料等の運送契約とは別の代金取立委託契約、運送保険契約等の対価を含みません。また、品代金取立金(代引)、運送品価格等の金額を記載しても、これは運送契約の対価ではありませんから、記載金額にはなりません。なお、運送契約の対価に対する消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分記載されている場合は、その消費税及び地方消費税は記載金額に含めないことになります。
なお、質問の文書を交付する時点で運送料が確定できなくても明らかに運送料が1万円未満の場合に、「運送料10,000円未満」等の記載により、運送料が1万円未満である旨の記載をしたものは、記載金額1万円未満のものとして非課税文書として取り扱われます。
②の文書は、貨物の受取事実を証する事項のみの記載で、運送契約の成立の事実を証する事項の記載がありませんから、課税文書には該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
車両賃貸借契約書
【 照会要旨】
次の文書は、運転手付きの貨切バスを提供し、運送業務に従事することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。
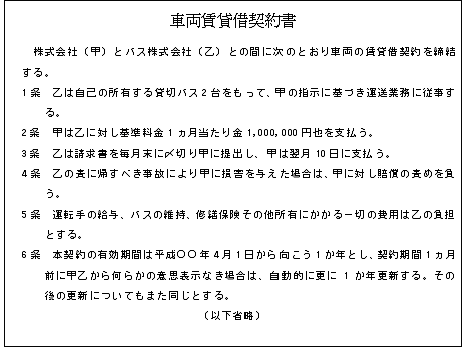
【 回答要旨】
ご質問の文書は、記載金額1,200万円の第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
(1) 文書名は車両賃貸借契約書となっていますが、この契約書は、乙の所有する貸切バスを甲が単に借りることを内容とするものではなく、乙が自己の責任のもとに運送業務を行うことを内容とするものですから、単なる賃貸借契約ではなく運送契約であるといえます。したがって、この契約書は、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
次に、この契約書は、3月を超えて継続する運送取引について、単価、対価の支払方法などを定めるものですから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します(令第26条第1号)。
(2) 記載金額は、基準料金(月額100万円)と契約期間の月数(12ケ月)を乗じて得た金額1,200万円と算出することができますから、通則3のイの規定により第1号の4文書として取り扱われることになります。
(注)1 バスだけを借入れ、運行は借主側(甲)において行う場合は、単なる自動車の賃貸借契約書ということで、不課税になります。
2 契約期間の更新の定めがある契約書の記載金額は、当初の契約期間のみを根基として算出することにし、更新後の期間は計算の対象にしません(基通第29条)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達第29条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
【 照会要旨】
次の①及び②の文書は、「車両賃貸借契約書」の一部について変更するものですが、どの号の文書として印紙税が課税されるのでしょうか。
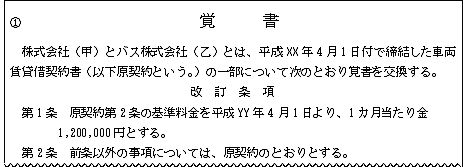
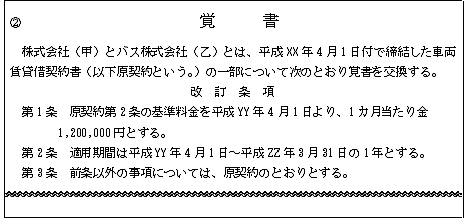
【 回答要旨】
営業者間における継続する運送取引についての運送単価(重要な事項)を変更することを定めたものですから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するほか、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、このような契約の内容の変更契約については、通則3のイの規定により、その所属を決定することになります。
したがって、①の文書は月額運送料を変更するもので、契約期間又は契約金額の記載がありませんので第7号文書となりますが、②の文書は月額運送料を変更するとともに契約期間の記載がありますから、記載金額を計算することができ第1号の4文書になります。
(②の文書の記載金額の計算) 月1,200,000円×12か月=14,400,000円
運送に関する契約書についての重要な事項を例示すると、次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
① 運送の内容(方法を含みます。)
② 運送の期日又は期限
③ 契約金額
④ 取扱数量
⑤ 単価
⑥ 契約金額の支払方法又は支払期日
⑦ 割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧ 契約期間
⑨ 契約に付される停止条件又は解除条件
⑩ 債務不履行の場合の損害賠償の方法
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
【 照会要旨】
家電リサイクル法に伴い作成される5枚複写のリサイクル券(小売業者控券受領書、小売業者回付用、指定引取場所控、排出者控、現品貼付用)の印紙税の取扱いについて、教えてください。
【 回答要旨】
1 「小売業者控券受領書」
「小売業者控券受領書」には、廃家電の品目の記載しかなく、小売業者等から運送業者等へ廃家電が引き渡された場合に、運送業者等の受領印が押印されるものであり、廃家電(物品)の受領書であることから、運送引受けの証として作成される第1号の4文書(運送に関する契約書)及びその他の課税文書には該当しません。
2 「小売業者回付用」
指定引取場所で受領印が押印された後、小売業者の控となるもので、1と同様に指定引取場所で受け入れた事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。
3 「指定引取場所控」
廃家電に添付されるもので、指定引取場所で受入れ事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。
4 「排出者控」
排出者である消費者等の控えとなるものであり、消費者等が支払を求められた「リサイクル料」又は「収集・運搬料」が記載されるものですが、家電リサイクル法に基づいた料金が確認的に記載されているにすぎないものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。
なお、当該排出者控の記載内容が、小売業者等において消費者等から上記料金を領収した事実を証するものである場合には、当該金額を記載金額とする第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。
5 「現品貼付用」
最終処分されるまで、廃家電にちょう付されるものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。
(注) 家電リサイクル法
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により、特定の家電製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)を排出する消費者等は、当該家電製品が確実にリサイクル処理されるよう、リサイクル料金及び収集・運搬料金を支払わなければなりません。
また、これを引き取る義務を負う小売業者等は、これを確実に製造業者へ引き渡す義務があり、製造業者は当該家電製品の再商品化等を行う義務があります。
この場合に、排出者と小売業者等の間で「リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)」を作成することとしています。
リサイクル券は、小売業者等は排出者にその写しを交付しなければならないこととされているほか、収集運搬業者を経由して再商品化を義務付けされた製造業者が、当該廃家電の受入れ施設として指定した引取場所へ回付されることとなっています。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ご進物品承り票
【 照会要旨】
次の「ご進物品承り票(お客様控)」は、商品の購入申込みがあった場合に、顧客に交付する文書ですが、商品の配送先及び配送料の記載があることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになりますか。
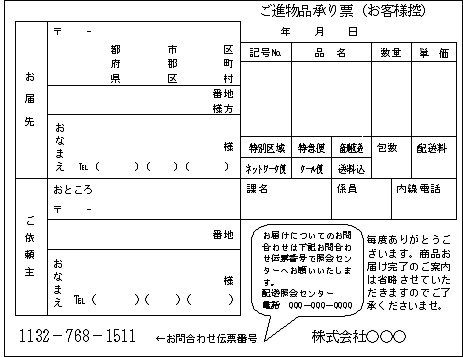
【 回答要旨】
「ご進物品承り票(お客様控)」は、契約の証として担当者が署名又は押印して顧客に交付するもので、売買契約の内容とともに、配送料が記載されていることから、不課税事項である物品の売買契約と第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのではないかとの疑義が生じますが、配送料の記載は、実費弁償としての配送料を徴するものであり、独立した運送契約ではありませんから、その全体が物品売買契約と評価され、課税文書に該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 運送の意義
2 運送状
3 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
4 用船契約書の意義
5 定期用船契約書
6 裸用船契約書
7 送り状
8 貨物受取書
9 車両賃貸借契約書
10 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
11 リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
12 ご進物品承り票
運送の意義
【 照会要旨】
引越荷物を運ぶことを、貨物自動車を持っている人に頼んで、簡単な念書をつくりました。このようなものでも運送契約ということになるのでしょうか。
【 回答要旨】
運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は人の場所的な移動を約し、相手(依頼人)がこれに報酬(運送賃)を支払うことを約する契約ですから、それが営業として行われるものだけでなく、たまたま行われるものでも運送となります。
したがって、簡単な文書であっても運送の内容について記載され、これを証明するためのものであれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
運送状
【 照会要旨】
第1号文書の定義欄3には「運送に関する契約書には、運送状を含まないものとする。」と規定されていますが、この運送状とはどういうものでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法において、運送に関する契約書に含めないこととしている運送状とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともにその到達地に送付され、荷受人が運送品の同一性を検査し、また、着払運賃などその負担する義務の範囲を知るために利用される文書で、一般に「送り状」とも呼ばれているものです。
したがって、その文書の標題が「運送状」、「送り状」などと称する文書であっても、運送品とともに、その到達地に送付されることなく、運送契約の成立を証明するために荷送人に交付されるものは運送状には該当せず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として取り扱われることになります(基通第1号の4文書の2)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
貨物運送に関して作成される文書の取扱い
【 照会要旨】
貨物運送に関して作成される文書には、その標題をみても「運送状」、「送り状」、「発送伝票」、「運送明細書」、「貨物引受書」、「貨物受取書」、「運賃請求書」、「運賃受取書」など各種のものがありますが、これらに対する印紙税の取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
貨物運送業者が荷送人から貨物の運送を引き受けた際に荷送人に交付する文書で、その文書に運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成立の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの証としているものは、その文書の標題のいかんにかかわらず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として印紙税が課税されることになります。
なお、貨物の運送に関して作成される文書に対する印紙税の取扱いは、おおむね次表のとおりです。
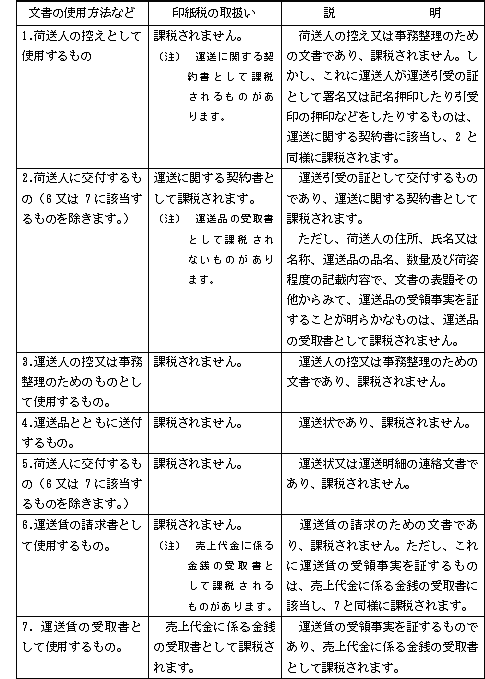
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
用船契約書の意義
【 照会要旨】
第1号の4文書(運送に関する契約書)には用船契約書を含むこととされていますが、用船契約とはどういうものでしょうか。
【 回答要旨】
「用船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これに積載した物品等を運送することを約する契約をいいますが、これには次の方法があり、いずれも用船契約に当たります(基通第1号の4文書の4)。
(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの
(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
定期用船契約書
【 照会要旨】
一定期間、船舶を乗組員付きで借受け、借主がこの船舶を用いて貨物運送を行う場合には、船主は、船舶使用料を収受するにすぎませんが、これも用船契約書ということになるのでしょうか。
【 回答要旨】
定期用船契約は、船主が一定期間船舶の全部を乗組員付きで定期用船者に貸し切るとともに、船長使用約款等に基づいて、船長をその期間内定期用船者の指示の下におく契約です。
これは、単なる船舶の賃貸借とは異なることから、印紙税法上運送に関する契約に含めることにしており、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当しますが、定期用船契約書のうち、契約期間が3月を超え、かつ、用船の目的物の種類、数量、単価、対価の支払方法等を定めるものは第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することになります(基通第1号の4文書の5)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
裸用船契約書
【 照会要旨】
第1号文書の定義欄4には、「用船契約書には、裸用船契約書を含まないものとする。」と規定されていますが、この裸用船契約書とはどういうものでしょうか。
また、裸用船契約は課税されないのでしょうか。
【 回答要旨】
定期用船契約は、船長その他の乗組員付きで船舶又は航空機を借り受けるのに対し、裸用船契約は乗組員のつかない船舶又は航空機そのものの賃貸借を内容とする契約です。
そのため、裸用船契約書は用船契約という名称を用いていますが、その実質は不課税文書である賃貸借契約書となりますから、課税物件表の第1号文書の定義欄4で第1号文書には該当しないことを念のため規定しているものです(基通第1号の4文書の6)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
送り状
【 照会要旨】
次の文書は、運送人が貨物の運送を引き受けた際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
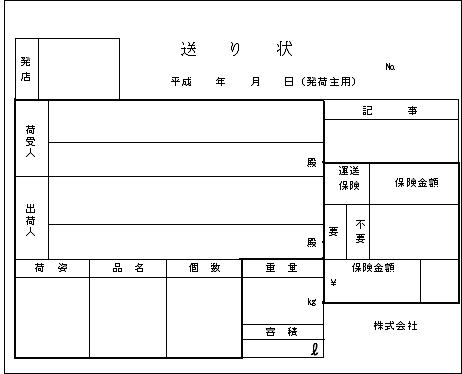
【 回答要旨】
ご質問の文書は、荷受人、出荷人及び運送保険についての事項が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく、運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、記載金額のない第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
同様の文書で、運賃額の記載のあるものは、その金額に応じて印紙税が課税されます。
なお、貨物とともに荷受人に送付される文書は、印紙税の課税対象から除かれている運送状に該当しますから、課税文書には該当しません(課税物件表第1号の4文書定義欄3)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表第1号の4文書定義欄3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
貨物受取書
【 照会要旨】
次の①及び②の文書は、運送業者が運送物品を受け取った際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
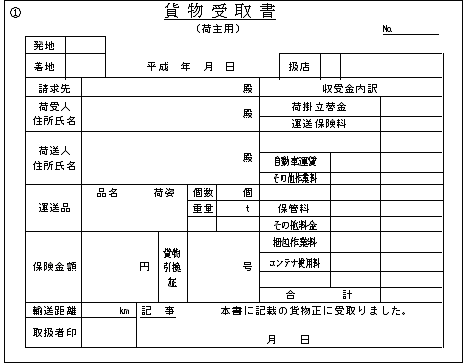
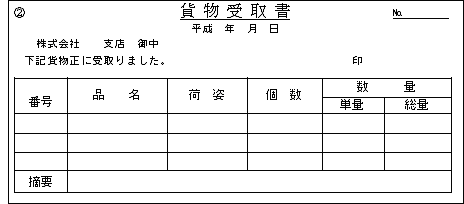
【 回答要旨】
①の文書は、標題が貨物受取書になっていますが、発地、着地、運送賃、荷受人、荷送人及び運送保険についての事項等が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
第1号の4文書の記載金額(契約金額)とは、運送料、用船料、有料道路利用料、集荷料、配達料、保管料等の運送契約の対価のすべてをいい、品代金取立料(代引手数料)、運送保険料等の運送契約とは別の代金取立委託契約、運送保険契約等の対価を含みません。また、品代金取立金(代引)、運送品価格等の金額を記載しても、これは運送契約の対価ではありませんから、記載金額にはなりません。なお、運送契約の対価に対する消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分記載されている場合は、その消費税及び地方消費税は記載金額に含めないことになります。
なお、質問の文書を交付する時点で運送料が確定できなくても明らかに運送料が1万円未満の場合に、「運送料10,000円未満」等の記載により、運送料が1万円未満である旨の記載をしたものは、記載金額1万円未満のものとして非課税文書として取り扱われます。
②の文書は、貨物の受取事実を証する事項のみの記載で、運送契約の成立の事実を証する事項の記載がありませんから、課税文書には該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
車両賃貸借契約書
【 照会要旨】
次の文書は、運転手付きの貨切バスを提供し、運送業務に従事することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。
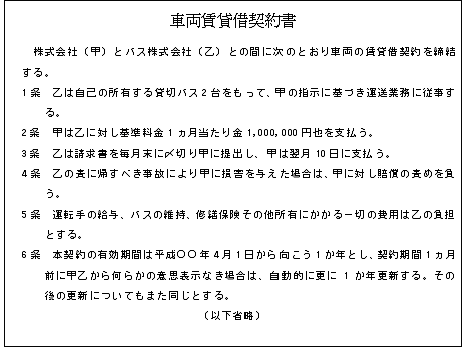
【 回答要旨】
ご質問の文書は、記載金額1,200万円の第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
(1) 文書名は車両賃貸借契約書となっていますが、この契約書は、乙の所有する貸切バスを甲が単に借りることを内容とするものではなく、乙が自己の責任のもとに運送業務を行うことを内容とするものですから、単なる賃貸借契約ではなく運送契約であるといえます。したがって、この契約書は、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
次に、この契約書は、3月を超えて継続する運送取引について、単価、対価の支払方法などを定めるものですから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します(令第26条第1号)。
(2) 記載金額は、基準料金(月額100万円)と契約期間の月数(12ケ月)を乗じて得た金額1,200万円と算出することができますから、通則3のイの規定により第1号の4文書として取り扱われることになります。
(注)1 バスだけを借入れ、運行は借主側(甲)において行う場合は、単なる自動車の賃貸借契約書ということで、不課税になります。
2 契約期間の更新の定めがある契約書の記載金額は、当初の契約期間のみを根基として算出することにし、更新後の期間は計算の対象にしません(基通第29条)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達第29条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
【 照会要旨】
次の①及び②の文書は、「車両賃貸借契約書」の一部について変更するものですが、どの号の文書として印紙税が課税されるのでしょうか。
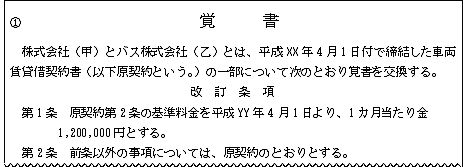
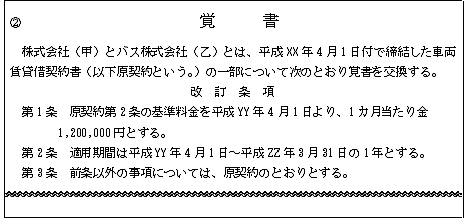
【 回答要旨】
営業者間における継続する運送取引についての運送単価(重要な事項)を変更することを定めたものですから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するほか、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、このような契約の内容の変更契約については、通則3のイの規定により、その所属を決定することになります。
したがって、①の文書は月額運送料を変更するもので、契約期間又は契約金額の記載がありませんので第7号文書となりますが、②の文書は月額運送料を変更するとともに契約期間の記載がありますから、記載金額を計算することができ第1号の4文書になります。
(②の文書の記載金額の計算) 月1,200,000円×12か月=14,400,000円
運送に関する契約書についての重要な事項を例示すると、次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
① 運送の内容(方法を含みます。)
② 運送の期日又は期限
③ 契約金額
④ 取扱数量
⑤ 単価
⑥ 契約金額の支払方法又は支払期日
⑦ 割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧ 契約期間
⑨ 契約に付される停止条件又は解除条件
⑩ 債務不履行の場合の損害賠償の方法
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
【 照会要旨】
家電リサイクル法に伴い作成される5枚複写のリサイクル券(小売業者控券受領書、小売業者回付用、指定引取場所控、排出者控、現品貼付用)の印紙税の取扱いについて、教えてください。
【 回答要旨】
1 「小売業者控券受領書」
「小売業者控券受領書」には、廃家電の品目の記載しかなく、小売業者等から運送業者等へ廃家電が引き渡された場合に、運送業者等の受領印が押印されるものであり、廃家電(物品)の受領書であることから、運送引受けの証として作成される第1号の4文書(運送に関する契約書)及びその他の課税文書には該当しません。
2 「小売業者回付用」
指定引取場所で受領印が押印された後、小売業者の控となるもので、1と同様に指定引取場所で受け入れた事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。
3 「指定引取場所控」
廃家電に添付されるもので、指定引取場所で受入れ事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。
4 「排出者控」
排出者である消費者等の控えとなるものであり、消費者等が支払を求められた「リサイクル料」又は「収集・運搬料」が記載されるものですが、家電リサイクル法に基づいた料金が確認的に記載されているにすぎないものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。
なお、当該排出者控の記載内容が、小売業者等において消費者等から上記料金を領収した事実を証するものである場合には、当該金額を記載金額とする第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。
5 「現品貼付用」
最終処分されるまで、廃家電にちょう付されるものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。
(注) 家電リサイクル法
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により、特定の家電製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)を排出する消費者等は、当該家電製品が確実にリサイクル処理されるよう、リサイクル料金及び収集・運搬料金を支払わなければなりません。
また、これを引き取る義務を負う小売業者等は、これを確実に製造業者へ引き渡す義務があり、製造業者は当該家電製品の再商品化等を行う義務があります。
この場合に、排出者と小売業者等の間で「リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)」を作成することとしています。
リサイクル券は、小売業者等は排出者にその写しを交付しなければならないこととされているほか、収集運搬業者を経由して再商品化を義務付けされた製造業者が、当該廃家電の受入れ施設として指定した引取場所へ回付されることとなっています。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ご進物品承り票
【 照会要旨】
次の「ご進物品承り票(お客様控)」は、商品の購入申込みがあった場合に、顧客に交付する文書ですが、商品の配送先及び配送料の記載があることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになりますか。
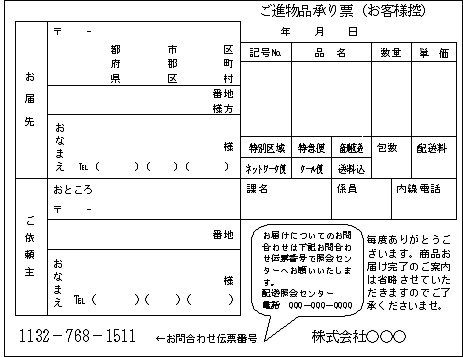
【 回答要旨】
「ご進物品承り票(お客様控)」は、契約の証として担当者が署名又は押印して顧客に交付するもので、売買契約の内容とともに、配送料が記載されていることから、不課税事項である物品の売買契約と第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのではないかとの疑義が生じますが、配送料の記載は、実費弁償としての配送料を徴するものであり、独立した運送契約ではありませんから、その全体が物品売買契約と評価され、課税文書に該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























