解説記事2005年03月21日 【解説】 消費税免税事業者判定訴訟―最高裁判決を受けて(2005年3月21日号・№107)
解説
消費税免税事業者判定訴訟
最高裁判決を受けて
平成12年(行ヒ)第126号
税理士 張江 忠
はじめに
平成17年2月1日、最高裁判所第3小法廷において、消費税の課税事業者に該当するか否かの判定に際し、当該基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の算定にあたっては、消費税相当額(当時103分の3)を控除すべきであるか否かを争ってきた裁判に判決が下された。
判決及び課税庁の主張は、地裁、高裁と同様に、当方の主張にまともに答えず、ただ、「消費税の納税義務がない者には、課されるべき消費税に相当する額がない」といういたって簡単な内容であった。
Ⅰ 最高裁判決までの経緯
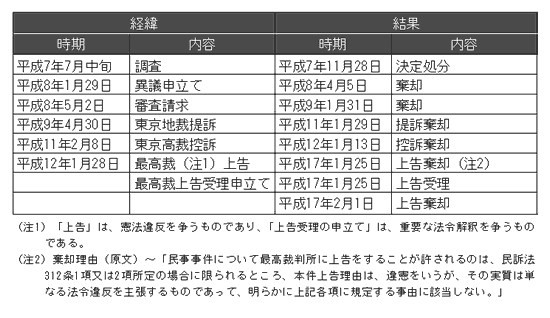
以下本稿では、「上告受理の申立て」の判決について検討する。
Ⅱ 我々が主張してきたこと
1 法9条の解釈論
(1)法9条の目的は免税事業者の弁別
法9条は、すべての事業者を対象として、単一の基準に基づいて免税事業者を弁別することを目的とする規定である。
① 法4条1項が免税事業者、課税事業者の区別なく「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」とし、4条1項の例外である6条1項には「消費税を課さない」という文言が用いられていること、法9条1項が法6条1項と異なり、「消費税を課さない」という文言ではなく、「消費税を納める義務を免除する」という文言を用いていることから、免税事業者を含むすべての事業者の取引に消費税が課され、ただし免税事業者の場合には法9条によってその税を納める義務が免除されるにすぎないと読むのが文理解釈上自然である。
② 法9条1項に定める「事業者」には、基準期間において課税事業者である事業者と免税事業者である事業者の区別をすることなく双方を含んでおり、すべての事業者に103分の3を控除した金額をもって小規模事業者性を判定すると解釈するのが自然である。
③ 消費税法施行からしばらくの問は、課税庁においても、このような解釈に基づいた運用を当然のごとくおこなっていた事実は、上告人の解釈の妥当性を何よりも示している。
(2)明確な物差しの必要性
小規模事業者への事務負担の配慮という法9条の立法趣旨からすると、小規模事業者の判定基準として最も重要なのは、争いの生じない明確な基準、可能なかぎり「明確かつ単一な物差し」であることである。
基準期間において免税・課税の区別をしない上告人の解釈は、その要請に沿うものである。
(3)「課されるべき消費税額」の意味
消費税の課税標準計算において税抜きで課税売上高を判定すること(28条1項)と、小規模事業者性の判定においてその規定を借用するということ(9条2項)とは、それぞれに条項の目的が異なることから、「課されるべき消費税に相当する額」という文言の意味内容も異なってくる。課税標準の計算という性質上、課税事業者のみが対象とされる規定である28条1項を、免税事業者を含むすべての事業者を対象とする法9条2項に借用しているのであるから、そこでの「課されるべき消費税に相当する額」の意味も、小規模事業者性の判定(納税義務の有無を問わず事業規模の大小を判定するだけの)基準であるという同上の趣旨に合致した形で解釈されなくてはならない。
従って、9条の趣旨からすれば、「当該基準期間において、すべての事業者が課税事業者であるとした場合において課されることになる消費税相当額」と解すべきこととなる。
2 小規模事業者性の判定基準としての実質的妥当性
(1)単一基準が妥当
課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、課税資産の譲渡等の対価の額から「103分の3」を控除した金額(=「基準期間における課税売上高」)を単一の基準とすることが、実質的・経済的観点からも妥当な解釈である。
(2)消費税とは何か
上記の妥当性は、第一に、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」である(東京地裁[平成2年3月26日]判決など)ということ、第二に消費税相当額を転嫁できるか否かは、各事業者の市場の競争力によって決まるという事実からも理解できよう。
(3)税制改革法11条は訓示規定
税制改革法との関係を論じれば、同法11条は、消費税が適正に転嫁されるよう、事業者および国等が適切な配慮を行うべきことを定めた規定である。しかし、前述したように、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であることから、同条は一種の訓示規定であって、そこから何ら法的な効果が発生するものではない。したがって、同条は、上記2(1)の解釈の妥当性に何らの影響を及ぼすものではないといえる。
3 本件に関する税務実務の現場の状況と多くの税理士の理解
(1)課税庁も上告人と同様の解釈
課税庁は法施行当初、明らかに上告人と同様の解釈をしていた。
法人税取扱通達平成元年3月1日直法2-1は、本文において免税事業者である法人について「税込経理方式」をとるべきことを定め、同通達第5項<免税事業者の消費税の処理>の(注)2に「これらの法人(免税事業者)が行う取引に係る消費税の額は、…」としており、免税事業者の取引にも消費税が課されることを当然の前提としていた。
(2)「税込み」か「税抜き」かの問題設定のみ
課税庁サイドが編集等している文献も、法9条の課税売上高については単に「税抜き」と記述しており「税抜きだが、免税事業者には税がないので…」との説明をしているものは存在しない。
本件調査時の現場税務職員も、根拠条文が説明するたびに異なり、最終的には国税局への確認の結果として、根拠条文は法9条でも28条でもなく、あえていえば税制改革法10条・11条であると説明した。しかも、この段階でも「税込み」なのか「税抜き」なのかという問題設定でのやりとりであった。
(3)税務署も上告人と同様の指導
税務実務の現場では、下記のような上告人の主張どおりの指導例等が散見された(最高裁に提出した事例列挙は省略)。
・税理士が自らの税務署との折衝、指導を受けた事例
・税務署主催の研修会での説明
・民間税務研修会での講師自らの説明
・税務申告時に上告人の主張どおり税務署が指導していた事例
Ⅲ 最高裁の判決文
法9条1項は、課税期間に係る基準期間(事業者が法人の場合は、法2条1項14号により、その事業年度の前々事業年度をいう。)における課税売上高が3000万円以下である事業者について、その課税期間中の課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除するものと規定する。
法9条1項に規定する「基準期間における課税売上高」とは、事業者が小規模事業者として消費税の納税義務を免除されるべきものに当たるかどうかを決定する基準であり、事業者の取引の規模を測定し、把握するためのものにほかならない。ところで、資産の譲渡等を課税の対象とする消費税の課税標準は、事業者が行う課税資産の譲渡等の対価の額であり(法28条1項)、売上高と同様の概念であって、事業者が行う取引の規模を直接示すものである。そこで、法9条2項1号は、上記の課税売上高の意義について、消費税の課税標準を定める法28条1項の規定するところに基づいてこれを定義している。
すなわち、法9条2項1号は、上記の課税売上高とは、基準期間が1年である法人の場合、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(法28条1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から所定の金額を控除した残額をいうものと規定する。そして、同項は、「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)とする。」と規定する。
法28条1項の趣旨は、課税資産の譲渡等の対価として収受された金銭等の額の中には、当該資産の譲渡等の相手方に転嫁された消費税に相当するものが含まれることから、課税標準を定めるに当たって上記のとおりこれを控除することが相当であるというものである。したがって、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者については、消費税相当額を上記のとおり控除することは、法の予定しないところというべきである。
以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当である。
前事実関係によれば、上告人は、本件基準期間において、売上総額が3,000万円を超えており、かつ、免税事業者に該当していたというのである。そうすると、上告人は、本件課税期間において、免税事業者に該当しないこととなるから、本件各決定が違法であるとはいえない。
以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
Ⅳ 判決内容の検討
1 はじめに
法解釈を求めたにもかかわらず、明確な条文解釈に欠ける残念な判決文である。最高裁が、何故、この判決を下すまでに5年もの歳月が必要だったのか、社会的常識を有すると自認する我々としてはとても理解できないところである。
そもそも、この訴訟を提起したのは、何故、我々の法解釈が誤っているのか(顧問先の納税者を説得できる解釈)を知りたいという素朴な要求からだったのである。
2 判決文の検討
『法9条1項に規定する「基準期間における課税売上高」とは、事業者が小規模事業者として消費税の納税義務を免除されるべきものに当たるかどうかを決定する基準であり、事業者の取引の規模を測定し、把握するためのものにほかならない。ところで、資産の譲渡等を課税の対象とする消費税の課税標準は、事業者が行う課税資産の譲渡等の対価の額であり(法28条1項)、売上高と同様の概念であって、事業者が行う取引の規模を直接示すものである。』
単に「基準期間における課税売上高」の説明と、法9条の小規模事業者の判定基準であることを述べているに過ぎない。
『法28条1項の趣旨は、課税資産の譲渡等の対価として収受された金銭等の額の中には、当該資産の譲渡等の相手方に転嫁された消費税に相当するものが含まれることから、課税標準を定めるに当たって上記のとおりこれを控除することが相当であるというものである。』
課税事業者が納付税額を算出するための課税標準規定の一般的な説明であり、法9条で借用される場合(小規模事業者性の判定基準)の意味が説明されていない。
「転嫁された消費税に相当するもの」の本質的な意味の説明がされていない。
『したがって、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者については、消費税相当額を上記のとおり控除することは、法の予定しないところというべきである。』
なにが「したがって」なのか?
単に納付税額を算出するための課税標準規定を説明しただけである。法9条で借用される場合(小規模事業者性の判定基準)の意味説明を全くしていない。
「転嫁された消費税に相当するもの」の本質的な意味説明もしていない。
判決文からすると、免税事業者は、事業者ではなく消費者と同じ立場であることとなる。しかしながら、免税事業者は、税制改革法上及び消費税法上でも事業者であり、又、仕入先から転嫁されている消費税もある。
『以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当である。』
なにが「以上の法9条及び28条の趣旨、目的」なのか?
上告人の主張になにも答えていない。これが司法機関の最高峰の解答なのかと首をひねるばかりである。
3 判決内容の検討
(1)判決は「免税」と「非課税」を混同
判決内容は、地裁及び高裁と同様に終始一貫して、納税義務の有無を根拠として、納税義務者が納付税額を算定するための課税標準規定として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえ、納税義務がないことをもって、免税事業者には譲渡先に転嫁する税即ち「課されるべき消費税に相当する額」がないと結論づけている。
このような司法の解釈は、善意に解釈すれば、消費税を租税債権債務関係という視点からのみとらえ、納税義務がなければ課税物件すら存在しないと考えるからであろう。しかし、そうであるならば、一般消費税である現行消費税法の構造を理解していないとしか言いようがない。
消費税法(以下「法」という)は、事業者が行う資産の譲渡等を通じて、法が予定する消費税額が商品等の価格の一部として適正に転嫁されることを予定し、最終消費者が購入品の対価の一部としてその消費税を負担することによって初めて成り立つ構造を持っている。
そうすると、すべての事業者が行う資産の譲渡等には消費税が含まれ、それが最終消費者に帰属することとなる。およそ間接税とされる税目においては、その税額は対価の額に含まれて最終消費者に転嫁されるのである。
現行法は、法4条で課税物件を限定し、その例外として法6条(非課税)を規定している。従って、法6条に列挙された非課税取引以外は全て課税取引であり、免税事業者が行う取引であっても同様に課税取引となり消費税が含まれることとなる。これは、国税通則法15条2項7号で消費税については課税資産の譲渡等をした時に納税義務が成立することを定めていることからも明らかである。
(2)本件訴訟のポイント
本件訴訟のポイントは、法9条が法28条の課税標準規定を借用する場合において、①納付税額を算定するための課税標準規定として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえる、②事業者の大小を弁別するための小規模事業者性の判定基準として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえる、という2点であろう。
① 第一のポイントについて
イ)地裁の判断
納税義務が免除された事業者は課税要件を充足していないから納税義務が発生せず、したがって、「課される消費税」はない。そして、国税通則法15条2項の規定は、納税義務の成立の時期を規定するものであり、納税義務の発生要件を規定するものではない、とした。
ロ)高裁および最高裁の判断
納税義務がないことをもってその課税資産の譲渡等の対価の額には「課されるべき消費税に相当する額」がないものとし、法9条の規定を法4条の例外規定(つまり、課税物件の人的非課税規定)とした。
ハ)上告人の反論
法9条は納税義務を免除する規定そのものであって、課税物件を規定する法4条の例外規定とはなり得ない。つまり、納税義務が免除されるだけであって、事業者の行う課税資産の譲渡等の対価の額に消費税が含まれているかどうかとは関係がない。
仮に、課税庁等が主張するように、免税事業者には課税すべき消費税相当分がもともと存在せず(非課税)、いわば最終消費者と同じであるというならば、免税事業者が課税事業者を選択することができるとする規定(法9条4項)と矛盾することとなる。又、同様に、法の各規定(7条、30条、33条、34条、37条~46条等々)において、「(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)」とわざわざカッコ書で規定する必要はないこととなる。(課税庁等は、このカッコ書きをもって、免税事業者を「法の適用のない事業者」としている。)
消費税法は、前述のとおり、すべての事業者が行なう資産の譲渡等には消費税が含まれており、それが適正に転嫁されているという仮定の論理に基づいて成り立っている。又、税制改革法の規定ぶり(特に17条3項)、法の規定ぶり、法施行当初の社会情勢等から、立法者は元々完全(百%)な転嫁は予定していないのである。現に、税制改革法(17条3項)の要請に基づいて、免税判定額及び簡易課税判定額を下げる改正が行われている。そうすると、「転嫁」ということをもって、上告人の主張を退けるのは、まとはずれな引用であることとなる。
② 第二のポイントについて
※地裁において原告はこの主張をしていない
イ)高裁の判断
法9条の趣旨及び目的にはほとんどふれることなく、租税法律主義の下では、条文の文言にない仮定の計算をするような解釈は採用できないとして簡単に退けている。
ロ)最高裁の判断
みごとなくらいに何も答えていない。
ハ)上告人の反論
この点についてだけ、何故ほとんど触れないのであろう?おそらく、当方の主張を退ける論理が構築できないのであろう。又、もし、この点について、答えていくと、課税庁等の自らの論理矛盾を露呈してしまうからではないか?と思われてしかたがない。
法9条の趣旨及び目的からすれば、第二の視点に立つ解釈こそが正当であることは、前述したとおりである。
(3)法9条で借用される法28条の意味
そもそも法28条は納付税額を算定するための課税標準規定なのだから、納税義務が免除されている免税事業者に適用することを予定していないのは当然のことだが、あえて借用しているのは、単に事業規模の大小を判定するためだけの目的であり、納付税額を算出するためではない。故に、法9条は当該基準期間にその事業者が課税事業者であったか免税事業者であったかを別段規定していないのである。当然課税事業者・免税事業者共通の判定基準でなくてはならないということになる。
(4)判決の具体的な問題点
① 売上高が毎年同一(例えば3千1万円)である場合、(同一の担税力なのに)年によって課税となったり免税となったりする、いわゆるダッジロール現象が生じる。
これは、法9条の趣旨、目的に反する
② 免税事業者の判定をする場合、その基準期間が課税か免税かを判定し、そのために又、その基準期間が課税か免税かを判定しなくてはならず、どんどん遡らなければならないこととなる。
これは法9条の趣旨、目的に反する。
③ 課税事業者については本体価格とは別個に消費税を収受し、免税事業者については本体価格のみを収受していることとなる。
これは、今日通説となっている、消費税は「価格の一部である」という見解に逆行することとなる。
④ 課税事業者と免税事業者とを別途判定することとなる。又、同一の担税力(売上高)を基準としてない。
これは、法9条の趣旨、目的に反する。
Ⅴ 終わりに
本件訴訟を通じて私が感じたことは、課税庁(行政)と裁判所(司法)に対する不信である。又、我国においては、民主主義の基本理念である「三権分立」が機能していないのではないかという懸念である。
(1)裁判所の説明責任に不信
当方の主張に対して説明責任を果たさない裁判所(特に、前述第二のポイントについては全く説明されていない)。
それにより、当方の主張を無視した裁判所独自の見解の判決文となる。従って、判決文しか読まない者には本当の訴訟内容が見えてこないこととなる。高裁の判決中の、「租税法律主義の下では、条文の文言にない仮定の計算をするような解釈は採用できない。」という表現が、よい例である。事実、多数の税理士から「いったい、どのような戦い方をしているのか?」と問われたものである。
(2)課税庁は「預り金」と「価格の一部」を都合のいいように使い分けている
消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であるとする見解が、今日では通説となっているにも拘わらず、国民の誤解(「預り金」であると考えている)を利用して、都合のいいように両見解を使い分けている。
課税庁においては、徴税の段階においては「預り金」、益税批判論に対しては「価格の一部」としている。例えば、
・「消費者が負担し事業者が預って納める税金であるから、納税しない人に対しては、売掛金を差し押さえてでも徴収する。」と言った国税庁長官の発言(平成9年11月10日[朝日新聞])。
・「消費者から預った消資税の滞納は悪質」として、平成9年秋、クリーニング会社の売掛金数十万円を差し押さえた(会社は数日後に倒産)大阪国税局の事例(平成11年8月8日[朝日新聞])。
などがあり、現在においても、少額の申告漏れでも、他の税目であれば指導ですむのに修正申告を慫慂している。
裁判所においても同様に、益税論に関しては「価格の一部」であるとして益税は生じないと解釈し、本件訴訟のような事例に関しては、「預り金」的な発想で課税事業者は本体価格とは別個に消費税を収受し、免税事業者は本体価格のみを収受していたと解釈している。
(3)税務訴訟には「信義則の原則」が機能しないのか
最近の税務判決の傾向は、税法における「信義則の原則」がないように思われる。又、例え違法な指導を課税庁が行なったとしても、課税庁の責任を裁判所は追及しない。例えば、平成17年1月25日判決(平成15年(行コ)第235号)(いわゆる「ストックオプション判決」)では、課税庁の指導のもとに行なった税務処理を3年後に否認している。(本件訴訟では、当方には該当しないが、多数の税理士が税務署から具体的個別事案で「税抜き」の指導を受けている。)
「信義則の原則」が機能しないということは、我々税理士が最終的に頼れるのは、結局のところ税法条文ということになるのであるから、本件訴訟のようにどちらともとれるような条文構成の法律は極力批判していくように働きかけなければならないであろう。
最後に、この紙面を借りて、我々の力がおよばず残念ながら敗訴となりましたお詫びと、足掛け約10年という長い間、応援協力して下さった諸先生方、一緒に戦ってきた諸先生方に対し、深く感謝の意を申し上げる。
消費税免税事業者判定訴訟
最高裁判決を受けて
平成12年(行ヒ)第126号
税理士 張江 忠
はじめに
平成17年2月1日、最高裁判所第3小法廷において、消費税の課税事業者に該当するか否かの判定に際し、当該基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の算定にあたっては、消費税相当額(当時103分の3)を控除すべきであるか否かを争ってきた裁判に判決が下された。
判決及び課税庁の主張は、地裁、高裁と同様に、当方の主張にまともに答えず、ただ、「消費税の納税義務がない者には、課されるべき消費税に相当する額がない」といういたって簡単な内容であった。
Ⅰ 最高裁判決までの経緯
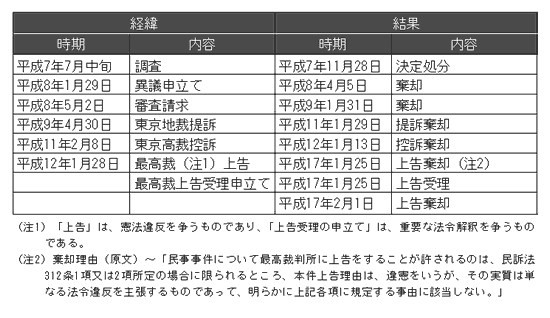
以下本稿では、「上告受理の申立て」の判決について検討する。
Ⅱ 我々が主張してきたこと
1 法9条の解釈論
(1)法9条の目的は免税事業者の弁別
法9条は、すべての事業者を対象として、単一の基準に基づいて免税事業者を弁別することを目的とする規定である。
① 法4条1項が免税事業者、課税事業者の区別なく「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」とし、4条1項の例外である6条1項には「消費税を課さない」という文言が用いられていること、法9条1項が法6条1項と異なり、「消費税を課さない」という文言ではなく、「消費税を納める義務を免除する」という文言を用いていることから、免税事業者を含むすべての事業者の取引に消費税が課され、ただし免税事業者の場合には法9条によってその税を納める義務が免除されるにすぎないと読むのが文理解釈上自然である。
② 法9条1項に定める「事業者」には、基準期間において課税事業者である事業者と免税事業者である事業者の区別をすることなく双方を含んでおり、すべての事業者に103分の3を控除した金額をもって小規模事業者性を判定すると解釈するのが自然である。
③ 消費税法施行からしばらくの問は、課税庁においても、このような解釈に基づいた運用を当然のごとくおこなっていた事実は、上告人の解釈の妥当性を何よりも示している。
(2)明確な物差しの必要性
小規模事業者への事務負担の配慮という法9条の立法趣旨からすると、小規模事業者の判定基準として最も重要なのは、争いの生じない明確な基準、可能なかぎり「明確かつ単一な物差し」であることである。
基準期間において免税・課税の区別をしない上告人の解釈は、その要請に沿うものである。
(3)「課されるべき消費税額」の意味
消費税の課税標準計算において税抜きで課税売上高を判定すること(28条1項)と、小規模事業者性の判定においてその規定を借用するということ(9条2項)とは、それぞれに条項の目的が異なることから、「課されるべき消費税に相当する額」という文言の意味内容も異なってくる。課税標準の計算という性質上、課税事業者のみが対象とされる規定である28条1項を、免税事業者を含むすべての事業者を対象とする法9条2項に借用しているのであるから、そこでの「課されるべき消費税に相当する額」の意味も、小規模事業者性の判定(納税義務の有無を問わず事業規模の大小を判定するだけの)基準であるという同上の趣旨に合致した形で解釈されなくてはならない。
従って、9条の趣旨からすれば、「当該基準期間において、すべての事業者が課税事業者であるとした場合において課されることになる消費税相当額」と解すべきこととなる。
2 小規模事業者性の判定基準としての実質的妥当性
(1)単一基準が妥当
課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、課税資産の譲渡等の対価の額から「103分の3」を控除した金額(=「基準期間における課税売上高」)を単一の基準とすることが、実質的・経済的観点からも妥当な解釈である。
(2)消費税とは何か
上記の妥当性は、第一に、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」である(東京地裁[平成2年3月26日]判決など)ということ、第二に消費税相当額を転嫁できるか否かは、各事業者の市場の競争力によって決まるという事実からも理解できよう。
(3)税制改革法11条は訓示規定
税制改革法との関係を論じれば、同法11条は、消費税が適正に転嫁されるよう、事業者および国等が適切な配慮を行うべきことを定めた規定である。しかし、前述したように、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であることから、同条は一種の訓示規定であって、そこから何ら法的な効果が発生するものではない。したがって、同条は、上記2(1)の解釈の妥当性に何らの影響を及ぼすものではないといえる。
3 本件に関する税務実務の現場の状況と多くの税理士の理解
(1)課税庁も上告人と同様の解釈
課税庁は法施行当初、明らかに上告人と同様の解釈をしていた。
法人税取扱通達平成元年3月1日直法2-1は、本文において免税事業者である法人について「税込経理方式」をとるべきことを定め、同通達第5項<免税事業者の消費税の処理>の(注)2に「これらの法人(免税事業者)が行う取引に係る消費税の額は、…」としており、免税事業者の取引にも消費税が課されることを当然の前提としていた。
(2)「税込み」か「税抜き」かの問題設定のみ
課税庁サイドが編集等している文献も、法9条の課税売上高については単に「税抜き」と記述しており「税抜きだが、免税事業者には税がないので…」との説明をしているものは存在しない。
本件調査時の現場税務職員も、根拠条文が説明するたびに異なり、最終的には国税局への確認の結果として、根拠条文は法9条でも28条でもなく、あえていえば税制改革法10条・11条であると説明した。しかも、この段階でも「税込み」なのか「税抜き」なのかという問題設定でのやりとりであった。
(3)税務署も上告人と同様の指導
税務実務の現場では、下記のような上告人の主張どおりの指導例等が散見された(最高裁に提出した事例列挙は省略)。
・税理士が自らの税務署との折衝、指導を受けた事例
・税務署主催の研修会での説明
・民間税務研修会での講師自らの説明
・税務申告時に上告人の主張どおり税務署が指導していた事例
Ⅲ 最高裁の判決文
法9条1項は、課税期間に係る基準期間(事業者が法人の場合は、法2条1項14号により、その事業年度の前々事業年度をいう。)における課税売上高が3000万円以下である事業者について、その課税期間中の課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除するものと規定する。
法9条1項に規定する「基準期間における課税売上高」とは、事業者が小規模事業者として消費税の納税義務を免除されるべきものに当たるかどうかを決定する基準であり、事業者の取引の規模を測定し、把握するためのものにほかならない。ところで、資産の譲渡等を課税の対象とする消費税の課税標準は、事業者が行う課税資産の譲渡等の対価の額であり(法28条1項)、売上高と同様の概念であって、事業者が行う取引の規模を直接示すものである。そこで、法9条2項1号は、上記の課税売上高の意義について、消費税の課税標準を定める法28条1項の規定するところに基づいてこれを定義している。
すなわち、法9条2項1号は、上記の課税売上高とは、基準期間が1年である法人の場合、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(法28条1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から所定の金額を控除した残額をいうものと規定する。そして、同項は、「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)とする。」と規定する。
法28条1項の趣旨は、課税資産の譲渡等の対価として収受された金銭等の額の中には、当該資産の譲渡等の相手方に転嫁された消費税に相当するものが含まれることから、課税標準を定めるに当たって上記のとおりこれを控除することが相当であるというものである。したがって、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者については、消費税相当額を上記のとおり控除することは、法の予定しないところというべきである。
以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当である。
前事実関係によれば、上告人は、本件基準期間において、売上総額が3,000万円を超えており、かつ、免税事業者に該当していたというのである。そうすると、上告人は、本件課税期間において、免税事業者に該当しないこととなるから、本件各決定が違法であるとはいえない。
以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
Ⅳ 判決内容の検討
1 はじめに
法解釈を求めたにもかかわらず、明確な条文解釈に欠ける残念な判決文である。最高裁が、何故、この判決を下すまでに5年もの歳月が必要だったのか、社会的常識を有すると自認する我々としてはとても理解できないところである。
そもそも、この訴訟を提起したのは、何故、我々の法解釈が誤っているのか(顧問先の納税者を説得できる解釈)を知りたいという素朴な要求からだったのである。
2 判決文の検討
『法9条1項に規定する「基準期間における課税売上高」とは、事業者が小規模事業者として消費税の納税義務を免除されるべきものに当たるかどうかを決定する基準であり、事業者の取引の規模を測定し、把握するためのものにほかならない。ところで、資産の譲渡等を課税の対象とする消費税の課税標準は、事業者が行う課税資産の譲渡等の対価の額であり(法28条1項)、売上高と同様の概念であって、事業者が行う取引の規模を直接示すものである。』
単に「基準期間における課税売上高」の説明と、法9条の小規模事業者の判定基準であることを述べているに過ぎない。
『法28条1項の趣旨は、課税資産の譲渡等の対価として収受された金銭等の額の中には、当該資産の譲渡等の相手方に転嫁された消費税に相当するものが含まれることから、課税標準を定めるに当たって上記のとおりこれを控除することが相当であるというものである。』
課税事業者が納付税額を算出するための課税標準規定の一般的な説明であり、法9条で借用される場合(小規模事業者性の判定基準)の意味が説明されていない。
「転嫁された消費税に相当するもの」の本質的な意味の説明がされていない。
『したがって、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者については、消費税相当額を上記のとおり控除することは、法の予定しないところというべきである。』
なにが「したがって」なのか?
単に納付税額を算出するための課税標準規定を説明しただけである。法9条で借用される場合(小規模事業者性の判定基準)の意味説明を全くしていない。
「転嫁された消費税に相当するもの」の本質的な意味説明もしていない。
判決文からすると、免税事業者は、事業者ではなく消費者と同じ立場であることとなる。しかしながら、免税事業者は、税制改革法上及び消費税法上でも事業者であり、又、仕入先から転嫁されている消費税もある。
『以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当である。』
なにが「以上の法9条及び28条の趣旨、目的」なのか?
上告人の主張になにも答えていない。これが司法機関の最高峰の解答なのかと首をひねるばかりである。
3 判決内容の検討
(1)判決は「免税」と「非課税」を混同
判決内容は、地裁及び高裁と同様に終始一貫して、納税義務の有無を根拠として、納税義務者が納付税額を算定するための課税標準規定として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえ、納税義務がないことをもって、免税事業者には譲渡先に転嫁する税即ち「課されるべき消費税に相当する額」がないと結論づけている。
このような司法の解釈は、善意に解釈すれば、消費税を租税債権債務関係という視点からのみとらえ、納税義務がなければ課税物件すら存在しないと考えるからであろう。しかし、そうであるならば、一般消費税である現行消費税法の構造を理解していないとしか言いようがない。
消費税法(以下「法」という)は、事業者が行う資産の譲渡等を通じて、法が予定する消費税額が商品等の価格の一部として適正に転嫁されることを予定し、最終消費者が購入品の対価の一部としてその消費税を負担することによって初めて成り立つ構造を持っている。
そうすると、すべての事業者が行う資産の譲渡等には消費税が含まれ、それが最終消費者に帰属することとなる。およそ間接税とされる税目においては、その税額は対価の額に含まれて最終消費者に転嫁されるのである。
現行法は、法4条で課税物件を限定し、その例外として法6条(非課税)を規定している。従って、法6条に列挙された非課税取引以外は全て課税取引であり、免税事業者が行う取引であっても同様に課税取引となり消費税が含まれることとなる。これは、国税通則法15条2項7号で消費税については課税資産の譲渡等をした時に納税義務が成立することを定めていることからも明らかである。
(2)本件訴訟のポイント
本件訴訟のポイントは、法9条が法28条の課税標準規定を借用する場合において、①納付税額を算定するための課税標準規定として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえる、②事業者の大小を弁別するための小規模事業者性の判定基準として「課されるべき消費税に相当する額」をとらえる、という2点であろう。
① 第一のポイントについて
イ)地裁の判断
納税義務が免除された事業者は課税要件を充足していないから納税義務が発生せず、したがって、「課される消費税」はない。そして、国税通則法15条2項の規定は、納税義務の成立の時期を規定するものであり、納税義務の発生要件を規定するものではない、とした。
ロ)高裁および最高裁の判断
納税義務がないことをもってその課税資産の譲渡等の対価の額には「課されるべき消費税に相当する額」がないものとし、法9条の規定を法4条の例外規定(つまり、課税物件の人的非課税規定)とした。
ハ)上告人の反論
法9条は納税義務を免除する規定そのものであって、課税物件を規定する法4条の例外規定とはなり得ない。つまり、納税義務が免除されるだけであって、事業者の行う課税資産の譲渡等の対価の額に消費税が含まれているかどうかとは関係がない。
仮に、課税庁等が主張するように、免税事業者には課税すべき消費税相当分がもともと存在せず(非課税)、いわば最終消費者と同じであるというならば、免税事業者が課税事業者を選択することができるとする規定(法9条4項)と矛盾することとなる。又、同様に、法の各規定(7条、30条、33条、34条、37条~46条等々)において、「(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)」とわざわざカッコ書で規定する必要はないこととなる。(課税庁等は、このカッコ書きをもって、免税事業者を「法の適用のない事業者」としている。)
消費税法は、前述のとおり、すべての事業者が行なう資産の譲渡等には消費税が含まれており、それが適正に転嫁されているという仮定の論理に基づいて成り立っている。又、税制改革法の規定ぶり(特に17条3項)、法の規定ぶり、法施行当初の社会情勢等から、立法者は元々完全(百%)な転嫁は予定していないのである。現に、税制改革法(17条3項)の要請に基づいて、免税判定額及び簡易課税判定額を下げる改正が行われている。そうすると、「転嫁」ということをもって、上告人の主張を退けるのは、まとはずれな引用であることとなる。
② 第二のポイントについて
※地裁において原告はこの主張をしていない
イ)高裁の判断
法9条の趣旨及び目的にはほとんどふれることなく、租税法律主義の下では、条文の文言にない仮定の計算をするような解釈は採用できないとして簡単に退けている。
ロ)最高裁の判断
みごとなくらいに何も答えていない。
ハ)上告人の反論
この点についてだけ、何故ほとんど触れないのであろう?おそらく、当方の主張を退ける論理が構築できないのであろう。又、もし、この点について、答えていくと、課税庁等の自らの論理矛盾を露呈してしまうからではないか?と思われてしかたがない。
法9条の趣旨及び目的からすれば、第二の視点に立つ解釈こそが正当であることは、前述したとおりである。
(3)法9条で借用される法28条の意味
そもそも法28条は納付税額を算定するための課税標準規定なのだから、納税義務が免除されている免税事業者に適用することを予定していないのは当然のことだが、あえて借用しているのは、単に事業規模の大小を判定するためだけの目的であり、納付税額を算出するためではない。故に、法9条は当該基準期間にその事業者が課税事業者であったか免税事業者であったかを別段規定していないのである。当然課税事業者・免税事業者共通の判定基準でなくてはならないということになる。
(4)判決の具体的な問題点
① 売上高が毎年同一(例えば3千1万円)である場合、(同一の担税力なのに)年によって課税となったり免税となったりする、いわゆるダッジロール現象が生じる。
これは、法9条の趣旨、目的に反する
② 免税事業者の判定をする場合、その基準期間が課税か免税かを判定し、そのために又、その基準期間が課税か免税かを判定しなくてはならず、どんどん遡らなければならないこととなる。
これは法9条の趣旨、目的に反する。
③ 課税事業者については本体価格とは別個に消費税を収受し、免税事業者については本体価格のみを収受していることとなる。
これは、今日通説となっている、消費税は「価格の一部である」という見解に逆行することとなる。
④ 課税事業者と免税事業者とを別途判定することとなる。又、同一の担税力(売上高)を基準としてない。
これは、法9条の趣旨、目的に反する。
Ⅴ 終わりに
本件訴訟を通じて私が感じたことは、課税庁(行政)と裁判所(司法)に対する不信である。又、我国においては、民主主義の基本理念である「三権分立」が機能していないのではないかという懸念である。
(1)裁判所の説明責任に不信
当方の主張に対して説明責任を果たさない裁判所(特に、前述第二のポイントについては全く説明されていない)。
それにより、当方の主張を無視した裁判所独自の見解の判決文となる。従って、判決文しか読まない者には本当の訴訟内容が見えてこないこととなる。高裁の判決中の、「租税法律主義の下では、条文の文言にない仮定の計算をするような解釈は採用できない。」という表現が、よい例である。事実、多数の税理士から「いったい、どのような戦い方をしているのか?」と問われたものである。
(2)課税庁は「預り金」と「価格の一部」を都合のいいように使い分けている
消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であるとする見解が、今日では通説となっているにも拘わらず、国民の誤解(「預り金」であると考えている)を利用して、都合のいいように両見解を使い分けている。
課税庁においては、徴税の段階においては「預り金」、益税批判論に対しては「価格の一部」としている。例えば、
・「消費者が負担し事業者が預って納める税金であるから、納税しない人に対しては、売掛金を差し押さえてでも徴収する。」と言った国税庁長官の発言(平成9年11月10日[朝日新聞])。
・「消費者から預った消資税の滞納は悪質」として、平成9年秋、クリーニング会社の売掛金数十万円を差し押さえた(会社は数日後に倒産)大阪国税局の事例(平成11年8月8日[朝日新聞])。
などがあり、現在においても、少額の申告漏れでも、他の税目であれば指導ですむのに修正申告を慫慂している。
裁判所においても同様に、益税論に関しては「価格の一部」であるとして益税は生じないと解釈し、本件訴訟のような事例に関しては、「預り金」的な発想で課税事業者は本体価格とは別個に消費税を収受し、免税事業者は本体価格のみを収受していたと解釈している。
(3)税務訴訟には「信義則の原則」が機能しないのか
最近の税務判決の傾向は、税法における「信義則の原則」がないように思われる。又、例え違法な指導を課税庁が行なったとしても、課税庁の責任を裁判所は追及しない。例えば、平成17年1月25日判決(平成15年(行コ)第235号)(いわゆる「ストックオプション判決」)では、課税庁の指導のもとに行なった税務処理を3年後に否認している。(本件訴訟では、当方には該当しないが、多数の税理士が税務署から具体的個別事案で「税抜き」の指導を受けている。)
「信義則の原則」が機能しないということは、我々税理士が最終的に頼れるのは、結局のところ税法条文ということになるのであるから、本件訴訟のようにどちらともとれるような条文構成の法律は極力批判していくように働きかけなければならないであろう。
最後に、この紙面を借りて、我々の力がおよばず残念ながら敗訴となりましたお詫びと、足掛け約10年という長い間、応援協力して下さった諸先生方、一緒に戦ってきた諸先生方に対し、深く感謝の意を申し上げる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















