解説記事2005年04月25日 【税務関連解説】 非按分型会社分割の事業承継への活用と課税上の疑問点(2005年4月25日号・№112)
実 務 解 説
非按分型会社分割の事業承継への活用と課税上の疑問点
税理士 大島一徳
1 事業承継における分割型分割制度創設の意義
平成12年の商法改正により会社分割制度が創設された。この制度は、平成9年の商法改正で合理化された合併制度や、平成11年の商法改正により創設された株式交換・株式移転制度と同様、会社がその組織を再編成するための法整備の一環として創設されたものであるが(注1)、中小企業における株主間の紛争の解決をも予定している(注2)。
中小企業においては、株主はすべて親族であることが多い。そのため、この株主間の紛争は、親族間の紛争である場合が多い。そして、この親族間の紛争は、相続を基因として発生することがある(注3)。また、事業承継は、親の世代が行なっていた事業を子の世代に承継するという性格を有するため、事業承継に係る問題を考える際には、この相続との関係を考慮することが重要である。つまり、中小企業の株主間の紛争と事業承継とは多くの接点があると考えられる。したがって、中小企業における円滑な事業承継を行なうために会社分割制度を活用することは、十分に予想されることである。
会社分割とは、会社の営業の全部又は一部を他の会社に承継させる組織法上の行為である(注4)。商法は、会社分割の形態として、まず、分割をする会社(以下「分割法人」という。)がその営業の全部又は一部を新しく設立される会社に承継させる「新設分割」と、既存の他の会社に承継させる「吸収分割」を認めている(商373、374の16)。(以下、会社分割により分割法人から営業の承継を受ける会社を「分割承継法人」という。)そして、それぞれについて、分割承継法人が会社分割に際して発行する株式を分割法人に割当てる「分社型分割」と分割法人の株主に割当てる「分割型分割」を認めている(商374②二、374の17②二参照。)。
分社型分割と同様の効果は、平成12年改正前の商法においても営業の現物出資などの方法によって実現することができた(注5)。しかし、分割型分割の効果は、平成12年の商法改正により新たに設けられたものであり、改正前の商法上の制度ではできなかったものである(注6)。
この分割型分割の創設は、事業承継に係る問題を考える上で重要な意義があるといえる。経営者が事業を行なう方法には、大きく分けて、事業用財産を個人が所有する個人事業形態と会社が所有する会社形態とがある。行なっている事業が2以上あり、そのうちのある特定の事業をある特定の承継者に承継させようとすることは、個人事業形態を採用している場合には、その承継させようとしている事業に属する財産をその承継者に移転させることにより可能である(図1参照)。しかし、会社形態を採用している場合には、事業用財産は会社の所有となっているため事業用財産を直接承継者に移転することはできず、経営者はその所有する会社の株式を承継者に移転することができるにすぎない。ある特定の事業用財産を承継者に与えようという意図でその承継者に会社の株式を移転しても、その承継者はその事業用財産を個別的に所有しているとはいえず、いわば持分的に所有しているにすぎない(図2参照)。このように、会社形態を採用している場合には、個人事業形態を採用している場合のようにある特定の事業用財産を特定の承継者に個別的に承継させることができなかった。しかし、これは、分割型分割が創設されたことにより可能となった。その方法は、まず、会社を新設分割型分割により2つに分割し、その分割後に経営者が所有することとなる分割承継法人の株式を特定の承継者に移転させることである(図3参照)。
この方法を行うと、図3のような会社形態を採用していても特定の承継者乙に特定のY事業の財産を実質的に移転することが可能となり、図1のような個人事業形態を採用している場合と同様の効果を得ることができる。
このように会社形態を採用していてもあたかも個人事業形態を採用しているのと同じように、ある特定の事業用財産を特定の承継者に個別的に承継させることができるようになったため、分割型分割制度の創設は事業承継に係る問題を考える上で重要な意義があるといえるのである。
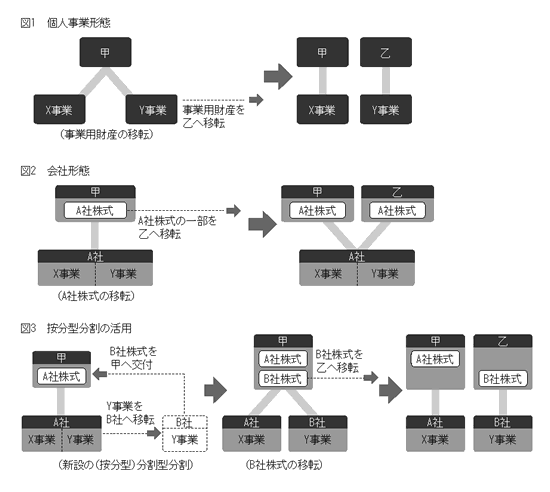
2 非按分型分割の意義と活用
分割型分割における分割承継法人の株式の交付は、商法上、株主平等の原則から、分割法人の株主が分割型分割前に有していた分割法人の株式の持分割合に応じて按分的に行なわれることが要求される(以下、分割承継法人の株式の交付が分割型分割の前における分割法人の株主の持分割合に応じて行なわれる分割型分割を「按分型分割」といい、持分割合に応じて行なわれない分割型分割を「非按分型分割」という。)。
この株主平等の原則に反する非按分型分割を行なうことが認められるかどうかについては、商法上明文規定は存在しないが、分割法人の株主全員の同意がある場合には、非按分型分割を行なうことも許されると解されている(注7)。
この非按分型分割を利用すると、図3における方法をさらに簡易に行なうことができる。A社のY事業を新設するB社に移転し、B社株式を乙にすべて交付する新設の非按分型分割を行なうと、図3において2段階で行なわれた手続を1段階で行なうことが可能となる(図4参照)(注8)。
このように、非按分型分割を利用すればさらに簡易に特定の事業用財産を特定の承継者に承継することが可能となるため、非按分型分割が事業承継の場面で活用されることは十分に予想されるであろう。
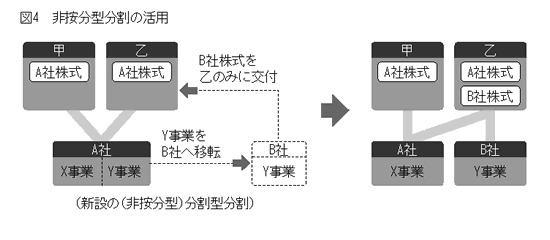
3 分割型分割の課税関係
税法においても、商法の企業間の組織再編成に係る法整備を受けて、平成13年の税制改正で、会社分割を含む組織再編税制が創設された。
税法では、会社分割に関して、商法上の区分に加えさらに適格、非適格という区分を設けている。会社分割のうち法人税法の定める一定の適格要件を満たすものを適格分割とし(法法2十二の十一)、それ以外のものを非適格分割として、その課税関係を規定している。
分割型分割を行なう場合における各当事者に対する課税関係を概観すると次のとおりである。(以下、適格要件を満たす分割型分割を「適格分割」といい、適格要件を満たさない分割型分割を「非適格分割」という。)
法人が非適格分割によりその資産等の移転を行った場合には、その資産等を時価で譲渡したものとして分割法人に対して課税を行い(法法62①前段)、適格分割によりその資産等の移転を行った場合には、その資産等は簿価により引継がれたものとされ、移転した資産等に係る譲渡損益の繰延べが行なわれる(法法62の2①前段)。
また、非適格分割により分割法人の株主が分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、一定の金額についてみなし配当課税が行われる(法法24①二、所法25①二)。適格分割の場合には、分割法人の株主に対するみなし配当課税は生じない(法法24①二、所法25①二)。
また、分割型分割に際して、分割法人の株主に金銭などの分割承継法人の株式以外の資産の交付が行われた場合には(以下、分割承継法人の株式以外の資産が交付される分割型分割を「金銭等交付分割」という。)、分割法人の株主に対して、分割法人の株式に係る時価譲渡課税が行われる(法法61の2①、③、措法37の10①、④二)。分割法人の株主に分割承継法人の株式のみが交付された場合には、分割法人の株式に係る課税の繰延べが行われる(法法61の2①、③)。
また、組織再編成に係る課税関係については、税法は個別に規定を設け、基本的にはこの個別規定に基づき課税を行なうこととしているが、さらに、組織再編成に係る包括的な租税回避防止規定が創設されている(法法132の2、所法157③、相法64③)。
4 非按分型分割の課税関係と課税上の疑問点
非按分型分割の場合には、適格分割の要件の一つである「分割承継法人の株式を按分的に交付すること」という要件を満たさないため、非適格分割とされる(法法2十二の十一)。また、非按分型分割は、分割型分割に際して分割承継法人の株式のみが交付される場合であっても、金銭等交付分割とされる(法令119の8②、所令113③)。したがって、非按分型分割が行われた場合の各当事者に対する課税関係は、前記3における分割型分割が非適格分割に該当する場合の課税関係及び金銭等交付分割に該当する場合の課税関係となる。
ここで、適格要件の一つである按分的交付要件以外の適格要件をすべて満たすと仮定した場合に、図3のような按分型分割の場合の分割法人に対する課税関係と、図4のような非按分型分割の場合の分割法人に対する課税関係とを比較すると、図3の場合には適格分割に該当するものとしてA社に対する移転資産等に係る時価譲渡課税は行われず(法法62の2①前段)、図4の場合には非適格分割に該当するものとしてA社に対する移転資産等に係る時価譲渡課税が行われる(法法62①前段)。
図3の場合と図4の場合を比較すると、分割型分割の活用前後の状況は両者ともまったく同じで(注9)、かつ、B社株式の交付方法以外の分割型分割の方法等がまったく同じであったとしても、両者のA社に対する課税関係は大きく異なる。つまり、分割型分割が按分型分割であるのか非按分型分割であるのかによって、A社に対する課税関係は大きく異なることになるのである。
すると、分割型分割が按分型分割か非按分型分割かによってなぜ分割法人に対する課税関係が大きく異なるのであろうか。この点について、次に考察を行うこととする。
5 非按分型分割が非適格分割とされる理由の考察
(1)原則と特例
非按分型分割が非適格分割とされる理由として、まず、原則論と特例という関係が考えられる。分割法人に対する移転資産等に係る課税関係の基本的な考え方として、「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的な考え方」(注10)の第一基本的な考え方(3)は、「会社分割・合併等の組織再編成に係る法人税制の検討の中心となるのは、組織再編成により移転する資産の譲渡損益の取扱いと考えられるが、法人がその有する資産を他に移転する場合には、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上するのが原則であり、この点については、組織再編成により資産を移転する場合も例外ではない。ただし、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更が無いと考えられる場合には、課税関係を継続させるのが適当と考えられる。したがって、組織再編成において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについては、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることが考えられる。」としている。
そうすると、分割型分割により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないと考えられるように行われる分割型分割を適格分割とし、そうでないものを非適格分割としているといえる。このように考えると、非按分型分割が行われる場合には、分割型分割により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更があり、そのため特例の対象とはならず、原則に立ち返り分割法人に対して移転資産に係る時価譲渡課税を行うのだともいえる。
しかし、前記4では図3と図4との比較において按分的交付要件以外の状況がすべて同じであったとして考察したが、この場合には、両者の分割型分割の活用前後の経済実態はまったく同じであると考えられる。図3のような分割型分割が適格分割と考えられる以上、図3と経済実態が同じであると考えられる図4のような分割型分割も、資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないと考えられる。したがって、非按分型分割が非適格分割とされる理由は、この原則論によってではないといえる。
(2)租税回避行為の防止
また、非按分型分割は租税回避行為が行われる可能性が高いため非適格分割とするのだという理由も考えられる。この理由によれば、租税回避行為に対応するため非按分型分割をすべて非適格分割とするのだといえる。確かに、非按分型分割が行われた場合の各当事者に対する課税関係は複雑であり、これを利用した租税回避行為が行われる可能性は十分に考えられる。だからといって、非按分型分割がすべて租税回避行為に利用されるとは限らず、非按分型分割をいわば入り口から非適格分割とする理由とはならない。非按分型分割以外の租税回避行為に利用されるものへの対応として、繰越欠損金の引継ぎに関する規定が存在する。繰越欠損金の引継ぎについては、租税回避行為に利用される可能性が高いにもかかわらず、一定の適格要件を満たす合併や合併に類似する適格分割の場合には、原則としてその引継ぎを認め(法法57②)、租税回避行為に利用される可能性が高いと認められるものについては、いわば特則的に、非常に詳細な規定を設けて一定の制限を行っている(法法57③、⑤、62の7)。つまり、原則容認、特則で否認である。非按分型分割が特則がなくすべて否認であるのとは対照的である。
また、税法は、組織再編成による租税回避行為を防止するために、包括規定をおいている(法法132の2、所法157③、相法64③)。このような一般条項的な規定を適用することは必ずしも望ましいこととはいえないが、この規定を適用すれば非按分型分割による租税回避行為に対応できるのであり、この点からも非按分型分割をすべて非適格分割とする必要がないといえる。
(3)株主間の租税回避行為の防止
また、非按分型分割は株主間での租税回避行為に利用されるおそれが高いとする見解もある(注11)。株主間での経済的価値の移転に係る租税回避行為が行われる可能性が高いため、分割法人と分割承継法人との法人間における資産等の移転に対して時価譲渡課税を行うのだと考えられる。つまり、株主間における租税回避行為を、法人間の課税関係で課税しようとするものであるといえる。この考えは、株主と法人との関係が非常に強い同族会社については説得力がある。同族会社においては、法人の資産は実質的には法人の株主のものであり、この株主において租税回避行為が行われるならばその実質的な所有物である法人の資産についても、この株主に係る原因によって課税してもかまわないのではないかとも考えられるのである。
しかし、現行法では法人と株主との関係をこのようには考えていない。組織再編税制では、法人間の資産等の移転に係る課税を繰延べる要件と株主の分割法人の株式の譲渡損益に係る課税を繰延べる要件は同じではない。つまり、株主に対する分割法人の株式の譲渡損益に係る課税を繰延べる要件を適格組織再編成とはしていないのである。この株主に対する要件を定めるにあたり、株主と法人との関係は「株主は投資家である」と考えられた(注12)。「株主は法人の実質的な所有者」ではないのである。これは、株主間の課税関係と法人間の課税関係を、ある種、区分したものであると考えられる。
このように考えるならば、株主間の経済的価値の移転については株主間の課税関係で課税を行えば十分であって、なにも法人に対して課税を行う必要はない。現に、図4のような非按分型分割と経済的実態が同じである図3のような分割型分割が行われた場合には、分割法人であるA社に対しては移転資産等の譲渡損益に係る課税は繰延べられ、株主間の経済的価値の移転について株主間の課税関係として課税が行われるのである。
したがって、非按分型分割の場合についても、分割法人に対して移転資産等の譲渡損益に係る課税を行うかどうかの判断は、按分型分割の場合と同様の要件とすべきであり(適格要件から按分的交付要件を除外し)、もし、分割型分割の際に株主間の経済的価値の移転が生ずるのであれば、それは株主間の課税関係として課税を行うことで十分なのではないか(注13)。
組織再編成にはいろいろな形態が考えられ、また、当事者も多数存在するため、課税関係が複雑である。そのため、各当事者に対してどのような課税を行うのかを考える際に議論の混乱をまねくおそれもある。このような議論の混乱をまねかないようにするためには、課税関係はできるだけ明瞭にするのが望ましい。同一の経済効果には同一の課税を、である。この意味でも、分割法人の移転資産等に係る譲渡損益に対する課税は、按分型分割と非按分型分割とを区別せず、同一の課税を行うことが望まれるのである。
6 事業承継の観点からの非按分型分割の再検討
前述の非按分型分割が非適格分割とされている理由ではないが、非按分型分割が非適格分割とされていても実務上実害はない、という考えもある。非按分型分割による効果と同様の効果を得ることは按分型分割によっても可能であり、なにも商法上の株主平等の原則に反することまで行い、また、税務上不利であると予想される非按分型分割をあえて行う必要はない、という考えである。図4の場合と同様の効果は図3の方法によっても可能である、ということである。
確かに、図4の場合と同様の効果は図3の方法によっても実現できる。したがって、非按分型分割を活用しなくとも按分型分割を活用すれば同様の効果が得られるのであるから、非按分型分割の制度は不要であるともいえる。しかし、この考えは、按分型分割が非按分型分割を完全に代替するという前提の下ではまさにそのとおりであるが、そうでない場合には再考を要する。次に事業承継という観点から、この按分型分割と非按分型分割とについて再度検討を加えたい。
按分型分割が非按分型分割を完全に代替できるのかどうかについては、事業承継の観点からは必ずしもそうとはいえない。
図3の場合と図4の場合は、確かに同様の経済的効果を得ることができるのであるが、両者の違いは、図3の場合は2段階の手続きが必要であるのに対して、図4の場合は1段階の手続きで済むということである。このことは、甲の側からみれば、図3の場合には二度の意思表示が必要であるのに対して、図4の場合には一度の意思表示で済むということである。つまり、甲は、図3の場合には、まず、A社の分割型分割に際して株主として分割型分割に賛成するか否か意思表示を行い、次いで、分割型分割後に交付されることとなるB社株式を乙に移転するという意思表示を行うこととなる。一方、図4の場合には、A社の分割型分割に際して株主としての意思表示を行うのみである。図3の場合におけるB社株式の甲から乙への移転の効果ついては、図4の場合においては商法上の会社分割の効果として当然に得られるのであり、甲がそのことについて特に意思表示をすることは必要ないからである。
事業承継の観点から検討すると、この違いは重要な意味を持つことがある。意思表示が有効に成立するためには、その意思表示の際に表意者に意思能力を有することが要求される。このことは、図3や図4のような場合も同様である。各意思表示の局面のいずれかにでも意思能力がなければ、図3や図4の活用は不可能となる。
例えば、図3の場合において、第1段階時と第2段階時の間に甲に関する相続が発生した場合のように、第2段階時の意思表示の際に甲が意思表示をすることができない場合を考えてみる。この場合には、(会社分割の効力発生前に甲の相続が発生したとすると)会社分割により交付されるB社株式は甲の共同相続人間の共有となる(民898)。このB社株式の乙への移転は、甲の意思表示によるのではなく甲の共同相続人間の遺産分割協議により行われることになる(民907)。もし、B社株式を乙に移転するという遺産分割協議が整わなかった場合には、B社株式は乙へは移転しない。したがって、事業承継の目的は達成できないのである。
事業を行っている経営者が死亡して相続が発生すると、共同相続人によりその経営者の遺産について分割の協議が行われる(民907)。この遺産分割では、民法相続法の均分相続原則(民899、900)を満たすことが要求される。その行っている事業が会社形態を採用している場合に、その経営者の遺産のほとんどがその会社の株式であるようなときは、各共同相続人が取得する株式の持分割合により均分相続原則を満たすこととなる。そしてその会社はこれらの共同相続人によって共同経営されていくのである。
しかし、この共同相続人による共同経営が後々問題となってくる場合がある。共同相続人間で意見が一致している場合には問題がないのであるが、一度共同相続人間で意見の不一致が生じると、親族である株主間で会社の経営権の争奪という紛争が発生する。そして、この経営権の争奪は株主間の紛争として表面化し(注14)(注15)、会社の意思決定に支障を生じ、最悪の場合、会社の倒産を余儀なくされる。
一方、図4の場合において、甲が分割型分割について議決権を行使したときは、その後、たとえ分割型分割の効力発生前に甲についての相続が発生してもB社株式は会社分割の効果により乙に移転するのであり、事業承継の目的は達成できるのである。その後、わが国の閉鎖会社における典型的な内部紛争の形態である共同相続人による共同経営を基因とした株主間の紛争も生じないのである。
以上のように、図3のような按分型分割を活用した方法では事業承継を完全に行なうことができない場合が想定できるのであり、その意味で按分型分割は非按分型分割を完全には代替できないのである。したがって、非按分型分割が非適格分割とされていることは、実務上実害がないとはいえないのである。
事業承継に関連した株主間の紛争の解決は非常に難しい問題である。そして、事業承継の問題が民法相続法と関連してくるため、問題がさらに複雑になってくる。図4のような非按分型分割を活用した事業承継を行なった場合に、商法上規定された会社分割の効果によりB社株式が乙に移転するといっても、これを民法相続法上どのように考えるべきか、という問題がある。この商法と民法相続法との関係については、法律家による議論の結果を待たなければならない(注16)。しかし、もし、B社の経営権を表章するB社株式自体は商法上の会社分割の効果により乙に帰属し、財産的価値の精算は民法相続法上の規定によるという結論が得られれば(注17)、財産的価値の精算が可能かどうかという問題は残るものの、少なくともB社の経営権は乙に帰属し、共同経営による株主間の紛争という事態は避けることができる。
この意味で、商法が、分割型分割制度を創設したことに加えて非按分型分割を容認したことは、事業承継においては非常に重要な意義を有する(注18)。この点からも、非按分型分割を一般的に税務上不利と考えられている非適格分割としないことが要請されるのである。
7 おわりに
以上において、非按分型分割の課税上の疑問点を挙げ、課税関係の明確化及び事業承継における重要性を中心としてその考察を行なってきた。その結果、適格要件から按分的交付要件を除外し、適格分割に該当するかどうかの判定を按分型分割と非按分型分割とを区別せず同一の基準によることが望ましいという提言を行なった。
円滑な事業承継を行なうことは社会的に強く要請されている。非按分型分割制度の創設は、その要請に答えるための重要な制度の誕生といえる。非按分型分割制度が十分に活用されることが望まれる。
また、分割型分割制度は企業組織再編成に関連するものとして創設されたが、事業承継に関連するものという側面をももつ。本論稿の提言によっても、株主間の課税関係として多額の税額が発生することが予想される。その税額を軽減すべきかどうかという議論があることが予想されるが、これは、組織再編税制の枠組みというよりむしろ事業承継税制として議論されるべき問題であると考える。今後の活発な議論を期待したい。
最後に、本論稿は安易な節税制度を設けるとか、事業承継のためには民法相続法をないがしろにしてもよい、といったことを提言するものでない。明確な課税関係の構築と円滑な事業承継を望むものであることを再度付け加えておきたい。
(注1)原田晃治『一問一答平成12年改正商法-会社分割法制-』((社)商亊法務研究会、平成12年)3頁、6頁。
(注2)原田・前掲注(1)19頁。
(注3)宍戸善一「閉鎖会社における内部紛争の解決と経済的公正(一)・(二)・(三)・(四・完)」法学協会雑誌101巻4号(昭和60年)505-668頁、法学協会雑誌101巻6号(昭和60年)795-870頁、法学協会雑誌101巻9号(昭和60年)1319-1405頁、法学協会雑誌101巻11号(昭和60年)1758-1846頁は、昭和58年9月末日までに入手し得た最高裁判所民事判例集、高等裁判所民事判例集、下級裁判所民事裁判例集及び判例時報に掲載されている判例の中から、閉鎖会社の内部紛争に関する事例を選択し、その選択した300以上の事例を27の項目により統計的分析を行い、その事例分析を行なうことによりわが国における閉鎖会社の内部紛争の実態を探求し、その解決の方策を探っている。これによると、相続・贈与と関連する争いが18件あると指摘されている(宍戸・同(一)544頁。)。
(注4)原田晃治「会社分割法制の創設について[上]-平成十二年改正商法の解説-」商事法務1563号(平成12年)9頁。
(注5)原田・前掲注(1)20頁。
(注6)原田・前掲注(1)21頁。
(注7)原田・前掲注(1)67頁。
(注8)図3と図4では会社分割前の株主構成が異なるが、これは、会社分割では分割法人及び分割法人の株主以外の者に分割承継法人の株式を交付することができないと解されているため(前田庸『会社法入門[第8版]』((株)有斐閣、平成14年)669頁。)、便宜上このような例を挙げた。図4の場合においても、会社分割後に乙の有するA社株式を甲に移転すれば図3の株式の移転後の状態になる。
(注9)図4の分割型分割後の状況については、前掲注(8)参照。
(注10)「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」(政府税制調査会、平成12年10月3日)。なお、この基本的考え方の全文については、朝長英樹=山田博志「会社分割等の組織再編成に係る税制について」租税研究2000年12月号(平成12年)69-81頁、平川忠雄『会社分割・企業組織再編税制の実務-21世紀型税制の創設と課題-』((株)税務経理協会、平成13年)212-224頁参照。
(注11)朝長英樹「会社組織再編成に係る税制について〔第3回〕」租税研究2001年7月号(平成13年)36頁、吉牟田勲「企業組織再編税制の要点と課題」税研2000年11月号(平成12年)21頁。
(注12)分割法人の株主に対する分割法人の株式の譲渡損益に係る課税の繰延べについては、株主の投資が継続しているかどうかが重視された。そして投資が継続しているかどうかについては、金銭等の交付があるかどうかで判断することとされた。これは、現行の法人税制が、株主が実質的に会社の資産を保有して事業を行っているとは考えずに、株主は「投資家」であることを前提としているためである(朝長他・前掲注(10)57頁、65頁参照。)。しかし、株主は「投資家」であると一律に決めて制度を構築するのは実態に合っていないという指摘が、将来、必ず出てくるものと考えられ、その際には見直しが必要となるが、とりあえず、株主は「投資家」という前提で今回の改正は行われた(朝長他・前掲注(10)65頁参照。)。
(注13)吉牟田・前掲注(11)21頁は、非按分型分割が親子間の相続税の節税策とされることから、今回の改正では認められなかったとしているが、相続税で明確に贈与税が課税される規定が整備されれば、法人税での非按分型分割を認める規定の導入も検討されてよいだろう、と述べている。
(注14)宍戸(一)・前掲注(3)544頁は、支配権争奪の要素を含む争いが51件、経済的利害対立の要素を含む争いが60件あると指摘している。
(注15)宍戸(四・完)・前掲注(3)1813頁は、わが国の閉鎖会社における典型的な内部紛争としての争いを、まず、相続を契機として紛争が発生し、二派に分かれて支配権の争奪をする。そして、支配権の争奪は、役員報酬及び会社資産、特に不動産の評価、帰属と関連して経済的利害対立の問題となる、と指摘している。
(注16)大野正道教授は、このような事業承継に係る法律問題を研究する法律学を、「企業形態の如何を問わず(個人営業であれ株式会社であれ)、その企業主ないし経営者の死亡によって生ずる新たな会社経営者(企業主)への経営権(およびその裏付としての持分・株式)の移転に関する法律問題を研究する商法学の一分科である」とする企業承継法として定義し(大野正道『企業承継法の研究』(信山社出版(株)、平成6年)1頁。)、そして、この企業承継法を、「民法学、特に相続法との関係は深く、商法学と民法学の交錯領域として把握」して(大野・同160頁。)、事業承継に係るさまざまな法律問題の考察を行っている。
(注17)大野正道教授は、この財産の帰属と財産的価値の精算という商法と民法相続法とに関連する問題について、「財貨(持分)の帰属は会社法の領域に属し、その財貨の把握する価値の分配は相続法の領域に属する」として二元的に解釈を構成することにより両者の関係についての結論を導き出している(大野・前掲注(16)191頁。)。
(注18)原田・前掲注(1)68頁は、非按分型分割の予想利用形態として、経営者である親が、子に事業を承継する場合を例示している。
非按分型会社分割の事業承継への活用と課税上の疑問点
税理士 大島一徳
1 事業承継における分割型分割制度創設の意義
平成12年の商法改正により会社分割制度が創設された。この制度は、平成9年の商法改正で合理化された合併制度や、平成11年の商法改正により創設された株式交換・株式移転制度と同様、会社がその組織を再編成するための法整備の一環として創設されたものであるが(注1)、中小企業における株主間の紛争の解決をも予定している(注2)。
中小企業においては、株主はすべて親族であることが多い。そのため、この株主間の紛争は、親族間の紛争である場合が多い。そして、この親族間の紛争は、相続を基因として発生することがある(注3)。また、事業承継は、親の世代が行なっていた事業を子の世代に承継するという性格を有するため、事業承継に係る問題を考える際には、この相続との関係を考慮することが重要である。つまり、中小企業の株主間の紛争と事業承継とは多くの接点があると考えられる。したがって、中小企業における円滑な事業承継を行なうために会社分割制度を活用することは、十分に予想されることである。
会社分割とは、会社の営業の全部又は一部を他の会社に承継させる組織法上の行為である(注4)。商法は、会社分割の形態として、まず、分割をする会社(以下「分割法人」という。)がその営業の全部又は一部を新しく設立される会社に承継させる「新設分割」と、既存の他の会社に承継させる「吸収分割」を認めている(商373、374の16)。(以下、会社分割により分割法人から営業の承継を受ける会社を「分割承継法人」という。)そして、それぞれについて、分割承継法人が会社分割に際して発行する株式を分割法人に割当てる「分社型分割」と分割法人の株主に割当てる「分割型分割」を認めている(商374②二、374の17②二参照。)。
分社型分割と同様の効果は、平成12年改正前の商法においても営業の現物出資などの方法によって実現することができた(注5)。しかし、分割型分割の効果は、平成12年の商法改正により新たに設けられたものであり、改正前の商法上の制度ではできなかったものである(注6)。
この分割型分割の創設は、事業承継に係る問題を考える上で重要な意義があるといえる。経営者が事業を行なう方法には、大きく分けて、事業用財産を個人が所有する個人事業形態と会社が所有する会社形態とがある。行なっている事業が2以上あり、そのうちのある特定の事業をある特定の承継者に承継させようとすることは、個人事業形態を採用している場合には、その承継させようとしている事業に属する財産をその承継者に移転させることにより可能である(図1参照)。しかし、会社形態を採用している場合には、事業用財産は会社の所有となっているため事業用財産を直接承継者に移転することはできず、経営者はその所有する会社の株式を承継者に移転することができるにすぎない。ある特定の事業用財産を承継者に与えようという意図でその承継者に会社の株式を移転しても、その承継者はその事業用財産を個別的に所有しているとはいえず、いわば持分的に所有しているにすぎない(図2参照)。このように、会社形態を採用している場合には、個人事業形態を採用している場合のようにある特定の事業用財産を特定の承継者に個別的に承継させることができなかった。しかし、これは、分割型分割が創設されたことにより可能となった。その方法は、まず、会社を新設分割型分割により2つに分割し、その分割後に経営者が所有することとなる分割承継法人の株式を特定の承継者に移転させることである(図3参照)。
この方法を行うと、図3のような会社形態を採用していても特定の承継者乙に特定のY事業の財産を実質的に移転することが可能となり、図1のような個人事業形態を採用している場合と同様の効果を得ることができる。
このように会社形態を採用していてもあたかも個人事業形態を採用しているのと同じように、ある特定の事業用財産を特定の承継者に個別的に承継させることができるようになったため、分割型分割制度の創設は事業承継に係る問題を考える上で重要な意義があるといえるのである。
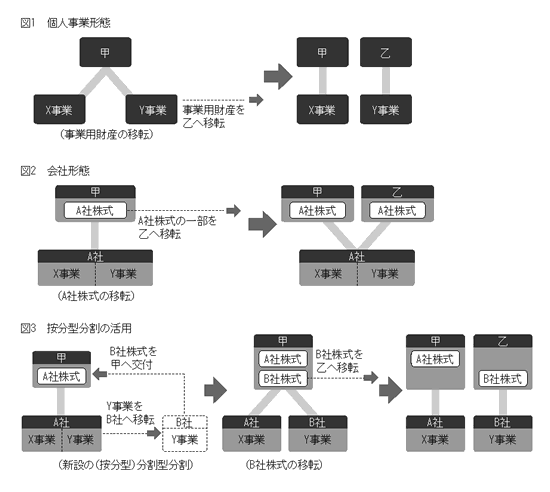
2 非按分型分割の意義と活用
分割型分割における分割承継法人の株式の交付は、商法上、株主平等の原則から、分割法人の株主が分割型分割前に有していた分割法人の株式の持分割合に応じて按分的に行なわれることが要求される(以下、分割承継法人の株式の交付が分割型分割の前における分割法人の株主の持分割合に応じて行なわれる分割型分割を「按分型分割」といい、持分割合に応じて行なわれない分割型分割を「非按分型分割」という。)。
この株主平等の原則に反する非按分型分割を行なうことが認められるかどうかについては、商法上明文規定は存在しないが、分割法人の株主全員の同意がある場合には、非按分型分割を行なうことも許されると解されている(注7)。
この非按分型分割を利用すると、図3における方法をさらに簡易に行なうことができる。A社のY事業を新設するB社に移転し、B社株式を乙にすべて交付する新設の非按分型分割を行なうと、図3において2段階で行なわれた手続を1段階で行なうことが可能となる(図4参照)(注8)。
このように、非按分型分割を利用すればさらに簡易に特定の事業用財産を特定の承継者に承継することが可能となるため、非按分型分割が事業承継の場面で活用されることは十分に予想されるであろう。
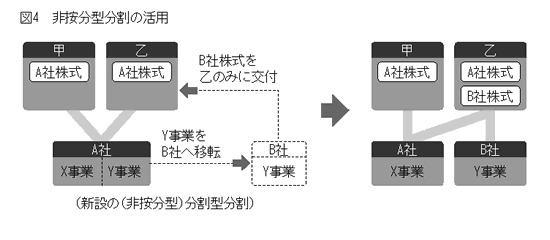
3 分割型分割の課税関係
税法においても、商法の企業間の組織再編成に係る法整備を受けて、平成13年の税制改正で、会社分割を含む組織再編税制が創設された。
税法では、会社分割に関して、商法上の区分に加えさらに適格、非適格という区分を設けている。会社分割のうち法人税法の定める一定の適格要件を満たすものを適格分割とし(法法2十二の十一)、それ以外のものを非適格分割として、その課税関係を規定している。
分割型分割を行なう場合における各当事者に対する課税関係を概観すると次のとおりである。(以下、適格要件を満たす分割型分割を「適格分割」といい、適格要件を満たさない分割型分割を「非適格分割」という。)
法人が非適格分割によりその資産等の移転を行った場合には、その資産等を時価で譲渡したものとして分割法人に対して課税を行い(法法62①前段)、適格分割によりその資産等の移転を行った場合には、その資産等は簿価により引継がれたものとされ、移転した資産等に係る譲渡損益の繰延べが行なわれる(法法62の2①前段)。
また、非適格分割により分割法人の株主が分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、一定の金額についてみなし配当課税が行われる(法法24①二、所法25①二)。適格分割の場合には、分割法人の株主に対するみなし配当課税は生じない(法法24①二、所法25①二)。
また、分割型分割に際して、分割法人の株主に金銭などの分割承継法人の株式以外の資産の交付が行われた場合には(以下、分割承継法人の株式以外の資産が交付される分割型分割を「金銭等交付分割」という。)、分割法人の株主に対して、分割法人の株式に係る時価譲渡課税が行われる(法法61の2①、③、措法37の10①、④二)。分割法人の株主に分割承継法人の株式のみが交付された場合には、分割法人の株式に係る課税の繰延べが行われる(法法61の2①、③)。
また、組織再編成に係る課税関係については、税法は個別に規定を設け、基本的にはこの個別規定に基づき課税を行なうこととしているが、さらに、組織再編成に係る包括的な租税回避防止規定が創設されている(法法132の2、所法157③、相法64③)。
4 非按分型分割の課税関係と課税上の疑問点
非按分型分割の場合には、適格分割の要件の一つである「分割承継法人の株式を按分的に交付すること」という要件を満たさないため、非適格分割とされる(法法2十二の十一)。また、非按分型分割は、分割型分割に際して分割承継法人の株式のみが交付される場合であっても、金銭等交付分割とされる(法令119の8②、所令113③)。したがって、非按分型分割が行われた場合の各当事者に対する課税関係は、前記3における分割型分割が非適格分割に該当する場合の課税関係及び金銭等交付分割に該当する場合の課税関係となる。
ここで、適格要件の一つである按分的交付要件以外の適格要件をすべて満たすと仮定した場合に、図3のような按分型分割の場合の分割法人に対する課税関係と、図4のような非按分型分割の場合の分割法人に対する課税関係とを比較すると、図3の場合には適格分割に該当するものとしてA社に対する移転資産等に係る時価譲渡課税は行われず(法法62の2①前段)、図4の場合には非適格分割に該当するものとしてA社に対する移転資産等に係る時価譲渡課税が行われる(法法62①前段)。
図3の場合と図4の場合を比較すると、分割型分割の活用前後の状況は両者ともまったく同じで(注9)、かつ、B社株式の交付方法以外の分割型分割の方法等がまったく同じであったとしても、両者のA社に対する課税関係は大きく異なる。つまり、分割型分割が按分型分割であるのか非按分型分割であるのかによって、A社に対する課税関係は大きく異なることになるのである。
すると、分割型分割が按分型分割か非按分型分割かによってなぜ分割法人に対する課税関係が大きく異なるのであろうか。この点について、次に考察を行うこととする。
5 非按分型分割が非適格分割とされる理由の考察
(1)原則と特例
非按分型分割が非適格分割とされる理由として、まず、原則論と特例という関係が考えられる。分割法人に対する移転資産等に係る課税関係の基本的な考え方として、「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的な考え方」(注10)の第一基本的な考え方(3)は、「会社分割・合併等の組織再編成に係る法人税制の検討の中心となるのは、組織再編成により移転する資産の譲渡損益の取扱いと考えられるが、法人がその有する資産を他に移転する場合には、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上するのが原則であり、この点については、組織再編成により資産を移転する場合も例外ではない。ただし、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更が無いと考えられる場合には、課税関係を継続させるのが適当と考えられる。したがって、組織再編成において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについては、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることが考えられる。」としている。
そうすると、分割型分割により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないと考えられるように行われる分割型分割を適格分割とし、そうでないものを非適格分割としているといえる。このように考えると、非按分型分割が行われる場合には、分割型分割により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更があり、そのため特例の対象とはならず、原則に立ち返り分割法人に対して移転資産に係る時価譲渡課税を行うのだともいえる。
しかし、前記4では図3と図4との比較において按分的交付要件以外の状況がすべて同じであったとして考察したが、この場合には、両者の分割型分割の活用前後の経済実態はまったく同じであると考えられる。図3のような分割型分割が適格分割と考えられる以上、図3と経済実態が同じであると考えられる図4のような分割型分割も、資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないと考えられる。したがって、非按分型分割が非適格分割とされる理由は、この原則論によってではないといえる。
(2)租税回避行為の防止
また、非按分型分割は租税回避行為が行われる可能性が高いため非適格分割とするのだという理由も考えられる。この理由によれば、租税回避行為に対応するため非按分型分割をすべて非適格分割とするのだといえる。確かに、非按分型分割が行われた場合の各当事者に対する課税関係は複雑であり、これを利用した租税回避行為が行われる可能性は十分に考えられる。だからといって、非按分型分割がすべて租税回避行為に利用されるとは限らず、非按分型分割をいわば入り口から非適格分割とする理由とはならない。非按分型分割以外の租税回避行為に利用されるものへの対応として、繰越欠損金の引継ぎに関する規定が存在する。繰越欠損金の引継ぎについては、租税回避行為に利用される可能性が高いにもかかわらず、一定の適格要件を満たす合併や合併に類似する適格分割の場合には、原則としてその引継ぎを認め(法法57②)、租税回避行為に利用される可能性が高いと認められるものについては、いわば特則的に、非常に詳細な規定を設けて一定の制限を行っている(法法57③、⑤、62の7)。つまり、原則容認、特則で否認である。非按分型分割が特則がなくすべて否認であるのとは対照的である。
また、税法は、組織再編成による租税回避行為を防止するために、包括規定をおいている(法法132の2、所法157③、相法64③)。このような一般条項的な規定を適用することは必ずしも望ましいこととはいえないが、この規定を適用すれば非按分型分割による租税回避行為に対応できるのであり、この点からも非按分型分割をすべて非適格分割とする必要がないといえる。
(3)株主間の租税回避行為の防止
また、非按分型分割は株主間での租税回避行為に利用されるおそれが高いとする見解もある(注11)。株主間での経済的価値の移転に係る租税回避行為が行われる可能性が高いため、分割法人と分割承継法人との法人間における資産等の移転に対して時価譲渡課税を行うのだと考えられる。つまり、株主間における租税回避行為を、法人間の課税関係で課税しようとするものであるといえる。この考えは、株主と法人との関係が非常に強い同族会社については説得力がある。同族会社においては、法人の資産は実質的には法人の株主のものであり、この株主において租税回避行為が行われるならばその実質的な所有物である法人の資産についても、この株主に係る原因によって課税してもかまわないのではないかとも考えられるのである。
しかし、現行法では法人と株主との関係をこのようには考えていない。組織再編税制では、法人間の資産等の移転に係る課税を繰延べる要件と株主の分割法人の株式の譲渡損益に係る課税を繰延べる要件は同じではない。つまり、株主に対する分割法人の株式の譲渡損益に係る課税を繰延べる要件を適格組織再編成とはしていないのである。この株主に対する要件を定めるにあたり、株主と法人との関係は「株主は投資家である」と考えられた(注12)。「株主は法人の実質的な所有者」ではないのである。これは、株主間の課税関係と法人間の課税関係を、ある種、区分したものであると考えられる。
このように考えるならば、株主間の経済的価値の移転については株主間の課税関係で課税を行えば十分であって、なにも法人に対して課税を行う必要はない。現に、図4のような非按分型分割と経済的実態が同じである図3のような分割型分割が行われた場合には、分割法人であるA社に対しては移転資産等の譲渡損益に係る課税は繰延べられ、株主間の経済的価値の移転について株主間の課税関係として課税が行われるのである。
したがって、非按分型分割の場合についても、分割法人に対して移転資産等の譲渡損益に係る課税を行うかどうかの判断は、按分型分割の場合と同様の要件とすべきであり(適格要件から按分的交付要件を除外し)、もし、分割型分割の際に株主間の経済的価値の移転が生ずるのであれば、それは株主間の課税関係として課税を行うことで十分なのではないか(注13)。
組織再編成にはいろいろな形態が考えられ、また、当事者も多数存在するため、課税関係が複雑である。そのため、各当事者に対してどのような課税を行うのかを考える際に議論の混乱をまねくおそれもある。このような議論の混乱をまねかないようにするためには、課税関係はできるだけ明瞭にするのが望ましい。同一の経済効果には同一の課税を、である。この意味でも、分割法人の移転資産等に係る譲渡損益に対する課税は、按分型分割と非按分型分割とを区別せず、同一の課税を行うことが望まれるのである。
6 事業承継の観点からの非按分型分割の再検討
前述の非按分型分割が非適格分割とされている理由ではないが、非按分型分割が非適格分割とされていても実務上実害はない、という考えもある。非按分型分割による効果と同様の効果を得ることは按分型分割によっても可能であり、なにも商法上の株主平等の原則に反することまで行い、また、税務上不利であると予想される非按分型分割をあえて行う必要はない、という考えである。図4の場合と同様の効果は図3の方法によっても可能である、ということである。
確かに、図4の場合と同様の効果は図3の方法によっても実現できる。したがって、非按分型分割を活用しなくとも按分型分割を活用すれば同様の効果が得られるのであるから、非按分型分割の制度は不要であるともいえる。しかし、この考えは、按分型分割が非按分型分割を完全に代替するという前提の下ではまさにそのとおりであるが、そうでない場合には再考を要する。次に事業承継という観点から、この按分型分割と非按分型分割とについて再度検討を加えたい。
按分型分割が非按分型分割を完全に代替できるのかどうかについては、事業承継の観点からは必ずしもそうとはいえない。
図3の場合と図4の場合は、確かに同様の経済的効果を得ることができるのであるが、両者の違いは、図3の場合は2段階の手続きが必要であるのに対して、図4の場合は1段階の手続きで済むということである。このことは、甲の側からみれば、図3の場合には二度の意思表示が必要であるのに対して、図4の場合には一度の意思表示で済むということである。つまり、甲は、図3の場合には、まず、A社の分割型分割に際して株主として分割型分割に賛成するか否か意思表示を行い、次いで、分割型分割後に交付されることとなるB社株式を乙に移転するという意思表示を行うこととなる。一方、図4の場合には、A社の分割型分割に際して株主としての意思表示を行うのみである。図3の場合におけるB社株式の甲から乙への移転の効果ついては、図4の場合においては商法上の会社分割の効果として当然に得られるのであり、甲がそのことについて特に意思表示をすることは必要ないからである。
事業承継の観点から検討すると、この違いは重要な意味を持つことがある。意思表示が有効に成立するためには、その意思表示の際に表意者に意思能力を有することが要求される。このことは、図3や図4のような場合も同様である。各意思表示の局面のいずれかにでも意思能力がなければ、図3や図4の活用は不可能となる。
例えば、図3の場合において、第1段階時と第2段階時の間に甲に関する相続が発生した場合のように、第2段階時の意思表示の際に甲が意思表示をすることができない場合を考えてみる。この場合には、(会社分割の効力発生前に甲の相続が発生したとすると)会社分割により交付されるB社株式は甲の共同相続人間の共有となる(民898)。このB社株式の乙への移転は、甲の意思表示によるのではなく甲の共同相続人間の遺産分割協議により行われることになる(民907)。もし、B社株式を乙に移転するという遺産分割協議が整わなかった場合には、B社株式は乙へは移転しない。したがって、事業承継の目的は達成できないのである。
事業を行っている経営者が死亡して相続が発生すると、共同相続人によりその経営者の遺産について分割の協議が行われる(民907)。この遺産分割では、民法相続法の均分相続原則(民899、900)を満たすことが要求される。その行っている事業が会社形態を採用している場合に、その経営者の遺産のほとんどがその会社の株式であるようなときは、各共同相続人が取得する株式の持分割合により均分相続原則を満たすこととなる。そしてその会社はこれらの共同相続人によって共同経営されていくのである。
しかし、この共同相続人による共同経営が後々問題となってくる場合がある。共同相続人間で意見が一致している場合には問題がないのであるが、一度共同相続人間で意見の不一致が生じると、親族である株主間で会社の経営権の争奪という紛争が発生する。そして、この経営権の争奪は株主間の紛争として表面化し(注14)(注15)、会社の意思決定に支障を生じ、最悪の場合、会社の倒産を余儀なくされる。
一方、図4の場合において、甲が分割型分割について議決権を行使したときは、その後、たとえ分割型分割の効力発生前に甲についての相続が発生してもB社株式は会社分割の効果により乙に移転するのであり、事業承継の目的は達成できるのである。その後、わが国の閉鎖会社における典型的な内部紛争の形態である共同相続人による共同経営を基因とした株主間の紛争も生じないのである。
以上のように、図3のような按分型分割を活用した方法では事業承継を完全に行なうことができない場合が想定できるのであり、その意味で按分型分割は非按分型分割を完全には代替できないのである。したがって、非按分型分割が非適格分割とされていることは、実務上実害がないとはいえないのである。
事業承継に関連した株主間の紛争の解決は非常に難しい問題である。そして、事業承継の問題が民法相続法と関連してくるため、問題がさらに複雑になってくる。図4のような非按分型分割を活用した事業承継を行なった場合に、商法上規定された会社分割の効果によりB社株式が乙に移転するといっても、これを民法相続法上どのように考えるべきか、という問題がある。この商法と民法相続法との関係については、法律家による議論の結果を待たなければならない(注16)。しかし、もし、B社の経営権を表章するB社株式自体は商法上の会社分割の効果により乙に帰属し、財産的価値の精算は民法相続法上の規定によるという結論が得られれば(注17)、財産的価値の精算が可能かどうかという問題は残るものの、少なくともB社の経営権は乙に帰属し、共同経営による株主間の紛争という事態は避けることができる。
この意味で、商法が、分割型分割制度を創設したことに加えて非按分型分割を容認したことは、事業承継においては非常に重要な意義を有する(注18)。この点からも、非按分型分割を一般的に税務上不利と考えられている非適格分割としないことが要請されるのである。
7 おわりに
以上において、非按分型分割の課税上の疑問点を挙げ、課税関係の明確化及び事業承継における重要性を中心としてその考察を行なってきた。その結果、適格要件から按分的交付要件を除外し、適格分割に該当するかどうかの判定を按分型分割と非按分型分割とを区別せず同一の基準によることが望ましいという提言を行なった。
円滑な事業承継を行なうことは社会的に強く要請されている。非按分型分割制度の創設は、その要請に答えるための重要な制度の誕生といえる。非按分型分割制度が十分に活用されることが望まれる。
また、分割型分割制度は企業組織再編成に関連するものとして創設されたが、事業承継に関連するものという側面をももつ。本論稿の提言によっても、株主間の課税関係として多額の税額が発生することが予想される。その税額を軽減すべきかどうかという議論があることが予想されるが、これは、組織再編税制の枠組みというよりむしろ事業承継税制として議論されるべき問題であると考える。今後の活発な議論を期待したい。
最後に、本論稿は安易な節税制度を設けるとか、事業承継のためには民法相続法をないがしろにしてもよい、といったことを提言するものでない。明確な課税関係の構築と円滑な事業承継を望むものであることを再度付け加えておきたい。
(注1)原田晃治『一問一答平成12年改正商法-会社分割法制-』((社)商亊法務研究会、平成12年)3頁、6頁。
(注2)原田・前掲注(1)19頁。
(注3)宍戸善一「閉鎖会社における内部紛争の解決と経済的公正(一)・(二)・(三)・(四・完)」法学協会雑誌101巻4号(昭和60年)505-668頁、法学協会雑誌101巻6号(昭和60年)795-870頁、法学協会雑誌101巻9号(昭和60年)1319-1405頁、法学協会雑誌101巻11号(昭和60年)1758-1846頁は、昭和58年9月末日までに入手し得た最高裁判所民事判例集、高等裁判所民事判例集、下級裁判所民事裁判例集及び判例時報に掲載されている判例の中から、閉鎖会社の内部紛争に関する事例を選択し、その選択した300以上の事例を27の項目により統計的分析を行い、その事例分析を行なうことによりわが国における閉鎖会社の内部紛争の実態を探求し、その解決の方策を探っている。これによると、相続・贈与と関連する争いが18件あると指摘されている(宍戸・同(一)544頁。)。
(注4)原田晃治「会社分割法制の創設について[上]-平成十二年改正商法の解説-」商事法務1563号(平成12年)9頁。
(注5)原田・前掲注(1)20頁。
(注6)原田・前掲注(1)21頁。
(注7)原田・前掲注(1)67頁。
(注8)図3と図4では会社分割前の株主構成が異なるが、これは、会社分割では分割法人及び分割法人の株主以外の者に分割承継法人の株式を交付することができないと解されているため(前田庸『会社法入門[第8版]』((株)有斐閣、平成14年)669頁。)、便宜上このような例を挙げた。図4の場合においても、会社分割後に乙の有するA社株式を甲に移転すれば図3の株式の移転後の状態になる。
(注9)図4の分割型分割後の状況については、前掲注(8)参照。
(注10)「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」(政府税制調査会、平成12年10月3日)。なお、この基本的考え方の全文については、朝長英樹=山田博志「会社分割等の組織再編成に係る税制について」租税研究2000年12月号(平成12年)69-81頁、平川忠雄『会社分割・企業組織再編税制の実務-21世紀型税制の創設と課題-』((株)税務経理協会、平成13年)212-224頁参照。
(注11)朝長英樹「会社組織再編成に係る税制について〔第3回〕」租税研究2001年7月号(平成13年)36頁、吉牟田勲「企業組織再編税制の要点と課題」税研2000年11月号(平成12年)21頁。
(注12)分割法人の株主に対する分割法人の株式の譲渡損益に係る課税の繰延べについては、株主の投資が継続しているかどうかが重視された。そして投資が継続しているかどうかについては、金銭等の交付があるかどうかで判断することとされた。これは、現行の法人税制が、株主が実質的に会社の資産を保有して事業を行っているとは考えずに、株主は「投資家」であることを前提としているためである(朝長他・前掲注(10)57頁、65頁参照。)。しかし、株主は「投資家」であると一律に決めて制度を構築するのは実態に合っていないという指摘が、将来、必ず出てくるものと考えられ、その際には見直しが必要となるが、とりあえず、株主は「投資家」という前提で今回の改正は行われた(朝長他・前掲注(10)65頁参照。)。
(注13)吉牟田・前掲注(11)21頁は、非按分型分割が親子間の相続税の節税策とされることから、今回の改正では認められなかったとしているが、相続税で明確に贈与税が課税される規定が整備されれば、法人税での非按分型分割を認める規定の導入も検討されてよいだろう、と述べている。
(注14)宍戸(一)・前掲注(3)544頁は、支配権争奪の要素を含む争いが51件、経済的利害対立の要素を含む争いが60件あると指摘している。
(注15)宍戸(四・完)・前掲注(3)1813頁は、わが国の閉鎖会社における典型的な内部紛争としての争いを、まず、相続を契機として紛争が発生し、二派に分かれて支配権の争奪をする。そして、支配権の争奪は、役員報酬及び会社資産、特に不動産の評価、帰属と関連して経済的利害対立の問題となる、と指摘している。
(注16)大野正道教授は、このような事業承継に係る法律問題を研究する法律学を、「企業形態の如何を問わず(個人営業であれ株式会社であれ)、その企業主ないし経営者の死亡によって生ずる新たな会社経営者(企業主)への経営権(およびその裏付としての持分・株式)の移転に関する法律問題を研究する商法学の一分科である」とする企業承継法として定義し(大野正道『企業承継法の研究』(信山社出版(株)、平成6年)1頁。)、そして、この企業承継法を、「民法学、特に相続法との関係は深く、商法学と民法学の交錯領域として把握」して(大野・同160頁。)、事業承継に係るさまざまな法律問題の考察を行っている。
(注17)大野正道教授は、この財産の帰属と財産的価値の精算という商法と民法相続法とに関連する問題について、「財貨(持分)の帰属は会社法の領域に属し、その財貨の把握する価値の分配は相続法の領域に属する」として二元的に解釈を構成することにより両者の関係についての結論を導き出している(大野・前掲注(16)191頁。)。
(注18)原田・前掲注(1)68頁は、非按分型分割の予想利用形態として、経営者である親が、子に事業を承継する場合を例示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















