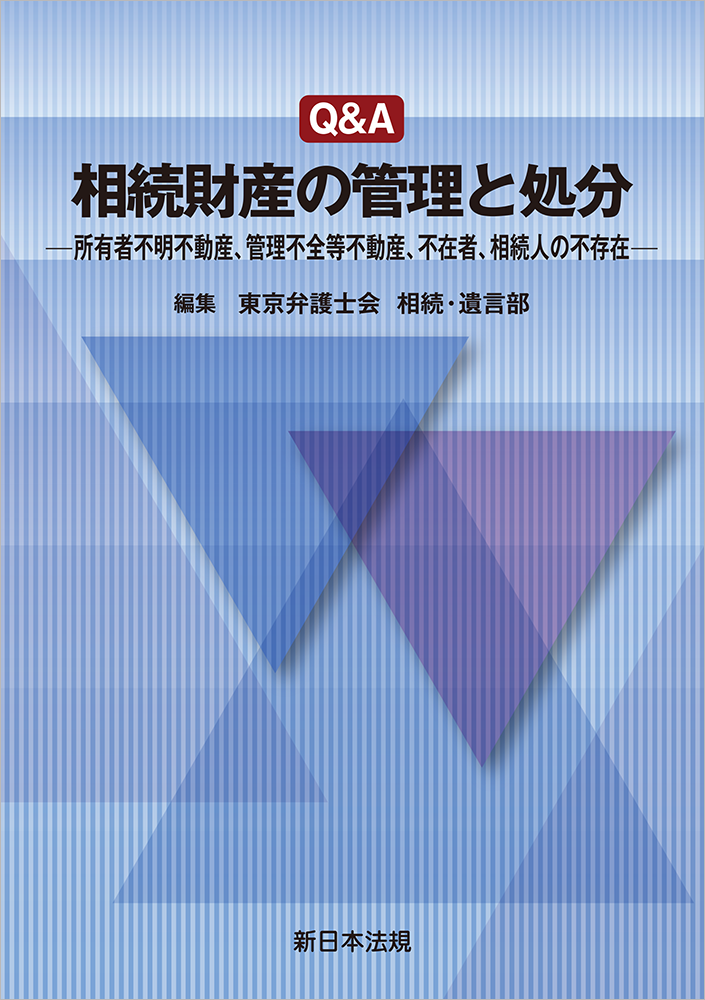資料2005年05月19日 【主要判例】 H17. 5.19 東京地方裁判所 平成11年(ワ)第28164号 損害賠償請求事件
H17. 5.19 東京地方裁判所 平成11年(ワ)第28164号 損害賠償請求事件
事件番号 :平成11年(ワ)第28164号
事件名 :損害賠償請求事件
裁判年月日 :H17. 5.19
裁判所名 :東京地方裁判所
部 :民事第8部
平成17年5月19日判決言渡
平成11年(ワ)第28164号 損害賠償請求事件
主文
1 原告及び原告訴訟引受人の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告及び原告訴訟引受人の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告
(1) 被告A,同D,同E,同B,同C及び同Fは,原告に対し,連帯して金7億円及びこれに対する同Cを除く被告らにつき平成11年12月30日から,同Cにつき同月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告D,同E,同F,同G及び同Hは,原告に対し,連帯して金3億円及びこれに対する平成11年12月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告訴訟引受人
(1) 被告A,同D,同E,同B,同C及び同Fは,原告訴訟引受人に対し,連帯して金7億円及びこれに対する同Cを除く被告らにつき平成11年12月30日から,同Cにつき同月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告D,同E,同F,同G及び同Hは,原告訴訟引受人に対し,連帯して金3億円及びこれに対する平成11年12月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告(当時の商号株式会社日本長期信用銀行)が,その取締役であった被告らに対し,以下の①及び②のとおり,被告らが商法の規定に違反した違法な配当実施に関与したと主張して損害賠償請求訴訟を提起し,その後,原告から本件各損害賠償請求権を譲り受けた原告訴訟引受人に訴訟引受けがなされた事案である。
① 被告A(以下「被告A」という。),同D(以下「D」という。),同E(以下「E」という。),同B(以下「B」という。),同C(以下「C」という。)及び同F(以下「F」という。)に対し,原告の平成9年度(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度)末(平成10年3月期)において,金71億7233万6392円を株主に配当したこと(以下「本件決算配当」という。)について,商法290条1項に違反し,配当可能利益が存在しなかったにもかかわらず,違法な本件決算配当が行われたとして,商法266条1項1号(Fについて商法266条1項5号)に基づき,上記配当額又は損害額の内金7億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(Cを除く被告らについて平成11年12月30日,Cについて同月
31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
② D,E,F,被告G(以下「G」という。)及び同H(以下「H」という。)に対し,原告の平成9年度中間期(平成9年9月期)において,金71億7564万6348円を株主に配当したこと(以下「本件中間配当」という。)について,商法293条ノ5第3項に違反し,同年度末において配当可能利益が存在しなかったにもかかわらず,違法な本件中間配当が行われたとして,商法266条1項1号に基づき,上記分配額の内金3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年12月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
第3 当事者の主張
1 原告及び原告訴訟引受人(以下「原告ら」という。)の主張
別紙1(原告らの主張)のとおり
2 被告らの主張
別紙2(被告らの主張)のとおり
第4 前提となる事実(証拠等で認定した事実については,各項末尾に証拠を摘示した。)
1 当事者
(1) 原告ら
原告は,商号を株式会社日本長期信用銀行として,長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に基づいて設立された長期信用銀行であったが,平成10年10月23日,「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号,以下「金融再生法」という。)36条1項に基づく特別公的管理の開始決定を受け,その後,株式会社新生銀行に商号変更された。
原告訴訟引受人は,預金保険機構の全額出資により設立され,預金保険機構からの委託等により破綻金融機関等からの貸付金債権等の買取り及びその管理・回収業務等を行う株式会社である。
(2) 被告ら
ア 被告A
被告Aは,昭和51年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年8月21日に退任するまでその地位にあった。その間の平成3年4月5日から平成10年8月21日まで取締役会長であった。
イ D
Dは,昭和61年6月27日に原告の取締役に就任し,平成10年9月28日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年4月28日から平成10年9月28日まで代表取締役頭取であった。
ウ E
Eは,平成元年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年4月28日から平成9年10月1日まで専務取締役,平成9年10月1日から平成10年8月21日まで取締役副頭取であった。
エ B
Bは,平成4年6月26日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年1月4日から平成10年8月21日まで常務取締役であった。
オ C
Cは,平成4年6月26日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年1月4日から平成10年8月21日まで常務取締役であった。
カ F
Fは,平成元年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年12月2日から平成9年10月1日まで専務取締役,平成9年10月1日から平成10年4月1日まで取締役副頭取であった。
キ G
Gは,平成6年6月28日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年6月から平成10年3月末まで,総合企画部長を務めていた。
ク H
Hは,平成7年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年2月から平成10年4月まで事業推進部長を務めていた。
2 原告の組織体制等
(1) 各会議体
原告には,商法上の取締役会の外,経営会議,常務会,常務役員連絡会などの各会議体が存在していた。
経営会議は,取締役会の前置機関として,原告の取締役会長が主宰し,取締役会への付議事項を議論する会議であり,常務会は,取締役頭取の諮問機関であり,会長を除く常務役員以上の取締役が構成員であって,業務執行について議論する会議であり,常務役員連絡会は,取締役頭取が招集する常務役員以上の取締役の意見交換,情報連絡の会議である。(乙100,弁論の全趣旨)
(2) 総合企画部,事業推進部
総合企画部は,原告における経営戦略(各業務戦略,資産負債構成,収益,重要投資等の計画)の企画・立案,これに関連した金融諸制度,資本市場の動向,他行の経営状況の調査等を行い,また,経営会議,常務会などの諸会議の事務局機能を担当し,さらに,経営方針に沿って,毎期・毎年の業務予算を作成し,全体としての進捗状況を管理する業務を行う部門であった。
事業推進部は,原告の不良債権の処理(いわゆる償却・引当,回収等)を実施する部門であり,不良債権の償却・引当処理を進めるほか,原告が支援していた関連ノンバンク等について,具体的な再建計画(事業化計画や不良債権処理のための財源を付与する損益支援の計画等)の立案・推進の業務を担当していた。(G本人,乙100,乙101)
3 平成9年度決算において導入された資産査定通達の概要等
(1) 早期是正措置の導入に至る経緯等
ア 早期是正措置の導入に対する検討等
金融検査・監督等に関する委員会は,平成7年12月26日,「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」と題する報告書を作成・公表し,その中で,金融機関(銀行)の経営の健全性を確保するため,自己資本比率による客観的な指標に基づき業務改善命令等の経営の早期是正を促すいわゆる早期是正措置を導入すること,そのためには,金融機関自らによる資産の査定(自己査定)とこれに基づく適正な償却(乙9ないし乙12によれば,貸出金等の債権に係る回収不能額について,直接貸借対照表から引き落とす貸倒処理をいうものと認められる。なお,法人税法上損金として処理し得る場合(無税)と損金として処理し得ない場合〔有税〕がある。)・引当の実施が前提となること,自己査定のための統一的基準を示す必要が
あることを指摘した。
その後,大蔵省(当時)銀行局長の私的研究会である「早期是正措置に関する検討会」(以下「早期是正措置検討会」という。)は,平成8年12月26日に「中間とりまとめ」を作成・公表し,その中には,自己査定については,従前の大蔵省による銀行法25条に基づく立入検査(いわゆるMOF検。以下「大蔵省検査」という。)における資産分類(Ⅰ分類ないしⅣ分類)に沿って,自己査定ガイドラインの原案を作成したこと,また,日本公認会計士協会(以下「会計士協会」という。)が示した債権の区分に従った償却・引当の計上に係る基本的な考え方により,資産査定と償却・引当の仕組みの大枠の一致が図られたこと,今後,各金融機関において,このガイドラインをベースに自己査定を行うべきことが記載されていた。(甲13ない
し甲15,乙18,弁論の全趣旨)
イ いわゆる金融3法の成立と早期是正措置の導入
また,平成8年6月21日には,「金融機関等の経営の健全化確保のための関係法律の整備に関する法律」(同年法律第94号,以下「健全性確保法」という。),「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」(同年法律第95号)及び「預金保険法の一部を改正する法律」(同年法律第96号)(以下これらの法律を「金融3法」という。)が,国会において可決・成立し,健全性確保法において,銀行法26条(長期信用銀行法17条により長期信用銀行に準用)を改正し,平成10年4月1日以降,早期是正措置制度を導入する旨が定められていた。(甲22の1,甲146,乙100,弁論の全趣旨)
(2) 資産査定通達の発出等
ア 資産査定通達の発出
この早期是正措置の導入に伴い,金融機関が自己査定を行うための基準(自己査定基準)を策定することが求められた。
そこで,大蔵省大臣官房金融検査部(以下「大蔵省金融検査部」という。)は,平成9年3月5日付けで,各財務(支)局長,沖縄総合事務局長及び金融証券検査官に宛てて,「早期是正措置導入後の金融検査における資産査定について」と題する通達及び同通達別添の「資産査定について」と題する書面(以下併せて「資産査定通達」という。)を発出した。その中では,債務者の財務状況,資金繰り,収益力等による返済能力に基づき,債務者を「正常先」(「業況が良好であり,かつ,財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者」),「要注意先」(「金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者,元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか,業況が低調ないし不安定な
債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する先」),「破綻懸念先」(「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。具体的には,現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況で,自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸
念先とする」),「実質破綻先」(「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。具体的には,事業を形式的には継続しているが,財務内容において多額の不良資産を内包し,あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し,実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており,事業好転の見通しがない状況,天災,事故,経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは,これらに類する事由が生じており),再建の見通しがない状況で,元金又は利息について実質的に長期間延滞している先など」)及び「破綻先」(「法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先をいい,例えば,破産,
清算,会社整理,会社更生,和議,手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者」)の5段階に区分(債務者区分)し,これを前提に,担保等による回収可能性も考慮し,債務者ごとに貸出金を「Ⅰ分類」(「Ⅱ分類,Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産」),「Ⅱ分類」(「債権確保上の諸条件が満足に充たされないため,あるいは,信用上疑義が存する等の理由により,その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権等の資産」),「Ⅲ分類」(「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し,従って損失発生の可能性が高いが,その損失額について合理的な推計が困難な資産」であり,「金融機関にとって損失額の推計が全く不可能とするものではなく,個々の債権の状況に精通している金融機関自らのルール
と判断により損失額を見積もることが適当とされるもの」)又は「Ⅳ分類」(「回収不可能又は無価値と判定される資産」)に査定(資産分類)することとされていた。(甲1,弁論の全趣旨)
イ 全銀協Q&Aの送付
全国銀行協会連合会(以下「全銀協」という。)は,平成9年3月21日付けで,傘下の銀行の融資担当部長に宛てて,今後各銀行が自己査定を行ううえでの参考として,資産査定通達についての考え方をとりまとめた「『資産査定について』に関するQ&A」と題する文書(以下「全銀協Q&A」という。)を作成・送付した。(甲2,弁論の全趣旨)
ウ 4号実務指針の作成・公表
会計士協会は,平成9年4月15日付けで,銀行等監査特別委員会報告第4号として,「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(以下「4号実務指針」という。)を作成・公表した。
その中で,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いとして,「正常先債権」(「業況が良好であり,かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者に対する債権」),「要注意先債権」(「貸出条件に問題のある債務者,履行状況に問題のある債務者,赤字決算等で業況が低調ないし不安定な債務者に対する債権」),「破綻懸念先債権」(「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権」),「実質破綻先債権」(「法的,形式的な経営破綻の事実は,発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見込みがたたない状況にあると認められるなど,実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権」)及び「破綻先債権」(「
破産,清算,会社整理,会社更生,和議,手形交換所における取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権」)の5つの債権区分が示されていた。(甲3,弁論の全趣旨)
エ 9年事務連絡の発出及び全銀協追加Q&Aの送付
大蔵省は,金融証券検査官等に宛てて,平成9年4月21日付け事務連絡として,「金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金の査定の考え方」と題する事務連絡(以下「9年事務連絡」という。)を発出した。
全銀協は,これを受けて,いわゆる関連ノンバンク向け貸出金の査定について,同年7月11日ころ,傘下の銀行に対し,「『資産査定について』に関する『Q&A』」(以下「全銀協追加Q&A」という。)を作成・送付した。(甲4,乙111,弁論の全趣旨)
オ 不良債権償却証明制度の廃止
従前,銀行を含む金融機関の不良債権のいわゆる無税償却・引当(法人税基本通達9-6-1ないし9-6-11を指す。なお,同通達9-6-4ないし9-6-11は,平成10年の大蔵省令改正により,法人税法施行令96条に規定が置かれた。以下では,特に断りのない限り,法人税基本通達は,この改正前の通達を指すものとする。)については,「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達(平成5年11月29日蔵検第439号,平成6年2月8日蔵検第53号一部改正)により,国税庁との協議に基づき実施され,金融証券検査官が,Ⅳ分類及びこれに準ずるものとして証明した不良債権の金額は原則として法人税法の損金に算入することが認められていた(以下上記通達による不良債権の償却証明制度を「不良債権償却
証明制度」という。)ところ,大蔵省は,平成9年7月4日蔵検第296号通達により,不良債権償却証明制度を廃する旨の通達を発出した。(乙9,乙24,弁論の全趣旨)
カ 決算経理基準の改正
銀行においては,銀行法(昭和56年法律第59号)の施行に伴い,大蔵省が,銀行経営の健全性を確保する等の要請から,昭和57年4月1日蔵銀第901号「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」と題する通達を発出し,その中には,経理関係として,いわゆる「決算経理基準」(以下,下記平成9年7月31日の改正前の決算経理基準を「改正前決算経理基準」という。)が定められており,上記通達の発出以降,普通銀行は,この改正前決算経理基準に従い,会計処理を行い,また,原告を含む長期信用銀行においても,この普通銀行に関する決算経理基準に従い,その会計処理を行っていた。
大蔵省銀行局長は,原告を含む長期信用銀行及び普通銀行の代表取締役頭取に宛てて,平成9年7月31日蔵銀第1714号「『普通銀行の業務運営に関する基本事項等について』通達の一部改正について」と題する通達を発出し,その中で,資産査定通達の発出に伴い,改正前決算経理基準の中の「貸出金の償却」及び「貸倒引当金」の規定を改正した(以下改正された決算経理基準を「改正後決算経理基準」という。)。(甲183,甲231,乙42,弁論の全趣旨)
4 原告における自己査定基準の策定と関連親密先への貸出金に対する償却・引当の状況等
(1) 原告の関連親密先
原告は,平成9年度までに,リース,ベンチャーキャピタル(ベンチャー企業に対する資金提供等を行って株式公開まで導く業務),住宅金融,信販,不動産担保金融等の各種業務分野において,人的・物的に密接な関係を有すると位置づけていた「関連先」又は「親密先」(以下併せて「関連親密先」という。)を有し,これらの企業との連携によりその業務を展開してきた。原告内部において,関連親密先と位置づけられていたノンバンクには,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載の番号1のエヌイーディー株式会社(以下「エヌイーディー」という。),同番号9の第一ファイナンス株式会社(以下「第一ファイナンス」という。),株式会社ジャリック(以下「ジャリック」という。),平河町ファイナンス株式会社(
以下「平河町ファイナンス」という。)及び同番号10の株式会社日本リース(以下「日本リース」という。)が存在しており,また,長銀インターナショナルリース株式会社(以下「長銀リース」という。)や日本ランディック株式会社(以下「ランディック」という。)なども存在していた。
また,原告は,平成9年度までに,原告又は関連親密先が有する不稼働資産(いわゆる不良債権など収益を生じていない債権や不動産など)を移管するため,これらの資産を移管し保有させることや事業化を通じて収益を上げること等を目的とした受皿会社を設立し,原告が,受皿会社に対し,これらの不稼働資産の買取資金を融資するなどして,これらの不稼働資産を受皿会社に移管し保有させていた。
このような受皿会社は,別紙3「平成10年3月期における償却・引当額の状況」記載の番号2ないし8,11ないし14の各会社であり,平成9年度当時,原告は,これらの受皿会社についても,原告と密接な関連を有するグループ企業(関連親密先又は特定先と称していた。)であるか,又はその中核会社とされている各関連親密先と一体であると位置づけていた。(甲19,乙108,弁論の全趣旨)
(2) 原告の一般先に対する自己査定基準及び償却・引当の基準
原告は,早期是正措置の導入や中間とりまとめの公表等を受けて,平成8年以降,自己査定の基準及びこれに基づく償却・引当の基準に関する検討を重ねており,遅くとも平成10年3月ころには,これらについての内部基準を策定した。(弁論の全趣旨)
(3) 原告における関連親密先に対する自己査定の基準及び償却・引当の基準
他方,原告は,関連親密先・特定先については,「当行経営支援先ならびに特定関連親密先自己査定運用細則」(以下「自己査定運用細則」という。)及び「関連ノンバンクにかかる自己査定運用規則」(以下「自己査定運用規則」という。)を策定し,これらの関連親密先・特定先以外の一般先と区別した資産査定の基準及び償却・引当の基準を策定した。
具体的には,関連親密先のうち,平成8年4月の大蔵省検査において,原告の関連ノンバンクとされた先については,債務者区分を「関連ノンバンク」として,原告に母体行責任を負う意思があり,合理的再建計画が存在する場合には,当該年度の支援予定額をⅣ分類とし,それを超える支援予定額をⅢ分類とすること,母体行責任を負う意思があっても,再建可能性がない場合には,関連ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類の額を原告の貸出割合(シェア)によりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすることが定められ,また,関連ノンバンクとされなかった関連親密先については,債務者区分として「経営支援先」,「経営支援実績先」及び「特定先」という資産査定通達には明示されていない債務者区分を策定し,「経営支援先」については,原則Ⅱ分
類,支援予定額をⅢ分類,当期支援損計上予定額をⅣ分類として分類し,また「経営支援実績先」については原則Ⅱ分類として分類し,「特定先」については債務者区分を「正常先」又は「要注意先」とし,その債務者区分に応じて査定を行うこと,また,これらの貸出金のうちⅢ分類に分類されるものについて原則として償却・引当を必要としないことが内容とされていた。(甲6の1ないし4,甲19,甲63,甲64,弁論の全趣旨)
(4) 平成9年度における関連親密先等に関する債務者区分及び資産分類並びにこれらへの貸出金に係る償却・引当の状況等
原告は,平成10年3月期において,その自己査定基準及び償却・引当の基準に従い,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載のとおり,エヌイーディー及び第一ファイナンスについて「関連ノンバンク」であるとして資産査定通達に係る債務者区分を行わず,支援損又は損失確定額についてはⅣ分類として計上したが,その余の貸出金については,Ⅲ分類又はⅡ分類に資産分類し,償却・引当を実施しなかった。
また,日本リースについて「経営支援実績先」であるとして,原告の日本リースに対する貸出金の査定に当たっても,Ⅱ分類と分類して,償却・引当を実施しなかった。
さらに,受皿会社については,上記関連親密先と一体であるとして,その貸出金について,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載のとおり償却・引当を実施した。(甲6の1ないし4,弁論の全趣旨)
5 平成9年度における配当の実施状況
(1) 本件中間配当の決議・実施
原告は,平成9年11月25日開催の取締役会において,同年度(同年9月期)における中間配当として,1株につき3円,総額金71億7868万8924円を分配する旨の本件中間配当を行う旨決議した。上記取締役会には,D,E,F,G及びHが出席しこれに賛成した。
原告は,上記決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7564万6348円の金銭を分配した。(甲7,甲8)
(2) 本件決算配当の承認・実施
ア 平成9年度決算の取締役会における承認
原告は,平成10年4月28日開催の取締役会において,平成9年度(平成10年3月期)決算に係る営業報告書,貸借対照表,損益計算書,利益処分計算書案(以下「本件利益処分案」という。)及び付属明細書を承認し,これを会計監査人及び監査役会に提出する旨の承認決議をした。
本件利益処分案には,任意積立金2995億1618万4620円を取り崩して,当期未処理損失を処理し,利益処分額を86億7162万4655円としたうえで,このうち,1株につき3円,総額71億7864万7455円の本件決算配当を行う旨記載されていた。
なお,同期における原告の貸借対照表には,資本金3872億2900万円,法定準備金3539億2300万円,任意積立金3176億3000万円,当期未処理損失2716億1500万円及び剰余金460億1400万円が計上されていた。
上記取締役会には,被告A,D,E及びBが出席しこれに賛成した。(甲9,甲10)
イ 会計監査人による本件利益処分案の承認
原告の会計監査人である太田昭和監査法人(以下「本件監査法人」という。)は,原告から提出を受けた平成9年度決算案について検討し,これが適正である旨の監査報告書を提出した。(甲132,甲136,弁論の全趣旨)
ウ 本件利益処分案の株主総会への上程及び承認
原告は,平成10年5月25日開催の取締役会において,平成9年度定時株主総会において,本件利益処分案を決議事項として上程することを承認する旨決議した。上記取締役会には,被告A,D,E,C及びBが出席しこれに賛成した。
原告は,同年6月25日開催の定時株主総会において,D(同総会の議長)が上程した本件利益処分案を承認する旨決議(以下「本件決算配当決議」という。)した。(甲11,甲12)
エ 本件決算配当の実施
原告は,本件決算配当決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7233万6392円の金銭を配当した。(甲8)
6 原告の破綻,国有化
原告は,平成10年10月23日,金融再生法36条1項に基づき,破綻の認定を受け,特別公的管理の開始決定がされた。(乙1,乙77)
7 原告訴訟引受人による訴訟引受けに至るまでの経緯等
(1) 本件損害賠償請求権の譲渡
原告は,平成12年2月28日,被告らに対する本件訴訟に係る損害賠償請求権を原告訴訟引受人に譲渡し,同日付け内容証明郵便により,被告らに対して,上記譲渡を通知し,同通知は,同月29日にHを除く被告らに対し,同年3月2日にHに対し,それぞれ到達した。(甲40の1ないし8の各1,2,甲41ないし甲43)
(2) 訴訟引受け
原告は,平成12年4月12日,原告訴訟引受人に本件訴訟の引受けを命ずる旨の裁判の申立てを行い,当裁判所は,同年6月13日,原告訴訟引受人に本件訴訟の引受けを命ずる旨決定し,原告訴訟引受人が本件訴訟を引き受けた。
これを受けて,原告は,同月27日,当裁判所に対し,本件訴訟から脱退する旨の届出を行ったが,被告らは,原告の本件訴訟からの脱退について承諾していない。(当裁判所に顕著)
第5 争点
事案の概要に記載したとおり,本件は,原告が実施した,本件決算配当(原告の平成10年3月期の株主への配当)及び本件中間配当(原告の平成9年9月期の株主への配当)に関し,これに賛成した被告らに対し,本件決算配当については商法266条1項1号(Fについては商法266条1項5号)に基づく損害賠償責任が,本件中間配当については商法266条1項1号に基づく損害賠償責任がそれぞれ問われた事案であるところ,前提となる事実によれば,以下の事実が認められる。
平成8年6月21日に成立した金融3法により,早期是正措置の導入が決定され,平成10年3月期から,銀行等の金融機関においては,自己査定基準を策定し,これに従って自己査定したうえで,その結果に基づき貸出金等の適正な償却・引当を行い,事後的に会計監査人による会計監査や大蔵省(その後金融監督庁,金融庁)による金融検査によって,自己査定基準の適正性,償却・引当の適正性等について検査がされることになったこと,そのために,資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡及び全銀協追加Q&A(以下これらを併せて「資産査定通達等」という。)が発出あるいは公表され,これらによって銀行における資産査定の在り方が示され,そのうえで大蔵省銀行局長による通達である改正後決算経理基準が出される
に至ったこと,被告らは,原告の取締役として,これらの資産査定通達等を踏まえて,原告の自己査定基準を策定し,これに基づき原告の資産内容について自己査定をしたうえで平成10年3月期の貸出金等の償却・引当の処理を行い,その結果に基づいて,本件決算配当及び本件中間配当が実施されたこと,以上の事実が認められる。
ところで,原告らは,平成10年3月期においては,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が銀行等の金融機関における貸出金の償却・引当処理の基準として,商法32条2項の「公正なる会計慣行」(なお,以下,商法の規定中片仮名で表示された部分をひらがなで表示する。)となっており,しかもこれが唯一の「公正なる会計慣行」であったとしたうえで,被告らが関与して作成された原告の自己査定基準における償却・引当基準が上記のとおりの唯一の「公正なる会計慣行」に違反しており,配当可能利益が存しないにもかかわらず配当がなされたもので本件決算配当は違法であること,また,本件中間配当についても,平成10年3月期において配当可能利益がない状態が生ずるおそれが客観的に存在していたにもかかわらず配
当を行ったもので違法であると主張している。これに対し,被告らは,被告らが関与して作成された原告の自己査定基準は,資産査定通達等の趣旨に反するものではないと主張するとともに,原告らが主張する資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が当時唯一の「公正なる会計慣行」であったことを争い,いわゆる税法基準(法人税法で損金算入が認められる限度額において企業会計の費用又は損失を経理処理すれば足り,法人税法上容認される損金算入限度額を超えてまで費用として処理する必要はないとする会計処理方法,本件で問題とされる関連ノンバンクについては,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とする会計処理方法)が,平成10年3月期以前から,銀行の貸出金の償却・引当の基準について
の「公正なる会計慣行」であり,平成10年3月期においても税法基準が「公正なる会計慣行」として存続していたと主張している。以上のような事実関係を前提として,第3の当事者双方の主張を対比すると,本件訴訟における具体的な争点は,以下のとおりであるといえる。
① 商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容をどのように解釈すべきか。
② 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が平成10年3月期において,銀行等の金融機関における貸出金の償却・引当処理の基準として,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当し,しかもこれが唯一のものとされるためにはどのような要件を満たすことが必要か。
③ ②の要件との関係で,平成9年3月期以前の改正前決算経理基準のもとで,銀行等金融機関の不良債権の償却・引当に関する基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか。
④ 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が②の要件を満たしているといえるか。
⑤ 平成10年3月期において,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準に基づく原告の貸出金の償却・引当の結果がこれに違反しているといえるか。
以上のとおり,原告らの主位的主張は,平成10年3月期において資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとの点に尽きるものである。しかし,一方で,原告らは,予備的な主張として,仮に,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとはいえないとしても,被告らが主張する税法基準は,「公正なる会計慣行」となり得ず,当時の「公正なる会計慣行」は,平成14年法律第44号による改正前の商法(以下「平成14年改正前商法」という。)285条の4第2項における「取立つること能わざる見込額」(以下「取立不能見込額」という。)の判定に従い,債務者の資産状態,収益力,担保状況等からみて合理的な社会通念に従って行わなけ
ればならないとされていたものであるところ,平成10年3月期において原告が策定した自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当の結果はこれに違反していると主張しており,予備的な争点として,⑥仮に資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準が銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合,この点に関する当時の「公正なる会計慣行」は,どのようなものであったのか。そして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準による償却・引当が当時の 「公正なる会計慣行」に違反していたといえるか の点が争点になり得るというべきである。
第6 当裁判所の判断
1 争点①(商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・ 内容をどのように解釈すべきか。)について
(1) 銀行の貸出金の償却・引当の基準と商法32条2項の関係
本件で問題となる株式会社における貸出金(金銭債権)の償却・引当の基準については,平成14年改正前商法285条の4第2項(以下「旧商法285条の4第2項」という。)は,「金銭債権に付取立不能の虞あるときは取立つること能はざる見込額を控除することを要す」と規定しているところ,金銭債権に関する取立不能見込額について,どのような基準により判断されるべきかについては,商法に明示的な規定はない。そこで,その判断基準については,商法32条2項に「商業帳簿の作成に関する規定の解釈に付ては公正なる会計慣行を斟酌すべし」と規定されていることから,商業帳簿の作成に関する規定である旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」の解釈に当たっては,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌
して決めることになると解される。そして,原告を含む銀行は,いずれも株式会社であり,平成10年3月期における原告を含む銀行の貸出金の償却・引当に係る基準については,銀行法,長期信用銀行法及びそれらの施行令・施行規則に,その点に関する規定がないことからすると,結局,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌して決めることになるというべきであって,この点は,当事者間に争いのないところである。
(2) 商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容
ア 「公正なる」の意義・内容
商法32条2項の「公正なる」の意義・内容については,同条1項が「商人は営業上の財産及損益の状況を明かにする為会計帳簿及貸借対照表を作ることを要す」と規定していることからすると,商人の営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという商業帳簿を作成させる商法の目的からみて公正であることと解すべきことになる。そうであるとすれば,商人の営業上の財産及び損益の状況を明らかにする主要な目的は,商人(企業)の利害関係人(株式会社においては,当該会社の債権者,当該会社と取引をしようとする者及び株主)に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかにすることにあるというべきであるから,結局「公正なる」といえるか否かは,上記の目的に照らして,当該会計処理の基準(具体的な会計処理の理論あるいは方
法)が,社会通念上,合理的なものであるといえるかどうかによって決せられるというべきである(乙98の119頁参照)。
イ 「会計慣行」の意義・内容
次に,「会計慣行」の意義・内容については,その文言に照らし,民法92条における「事実たる慣習」と同義に解すべきであり,一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われている企業会計の処理に関する具体的な基準あるいは処理方法をいうと解すべきである。言い換えると,企業会計の処理に関する具体的な基準あるいは処理方法が,少なくともわが国の特定の業種に属する企業において広く行われていることが必要であり,また,相当の時間繰り返して行われていることが必要と解すべきである(乙98の119頁参照)。そして,当該会計慣行が特定の業種に属する企業において広く行われ,しかも,相当の時間繰り返して行われているという事実があってはじめて,当該会計慣行が「公正なる会計慣行」となり,こ
れによって当該会計慣行とされた会計処理の方法が,法改正等の手続を経ずに,商法32条2項を介して法的な強制力を持ち得ることになると解される。
ウ 「斟酌すべし」の意義・内容
また,商法32条は,「斟酌すべし」と規定しており,その趣旨は,「公正なる会計慣行」が商業帳簿の作成に関する商法総則の規定や株式会社の計算に関する規定の解釈の指針となるべきことを明らかにしたものというべきである。そして,「斟酌」とは,ある事情をくみいれて判断することであって,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,公正なる会計慣行をくみいれて判断することを要請しているものである。そうであるとすれば,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,「公正なる会計慣行」を斟酌することが要請されているとはいえ,他の事情を斟酌することが禁じられているわけではないことになり,結局,「斟酌すべし」とは,「公正なる会計慣行」が存在する場合には,特段の事情がない限り,それに従わなけれ
ばならないという意味に解すべきである。
(3) 新しい合理的な慣行が生まれようとしている場合と「公正なる会計慣行」 の関係について
なお,原告らは,「会計慣行」とは,既に行われている事実に限らず,新しい合理的な慣行が生まれようとしている場合には,それを含むと解すべきであると主張している。そこで検討すると,商法32条2項が「会計基準」という用語ではなく「会計慣行」という文言を用いて,企業会計の技術・実務の発展に伴い,立法作用によらないで企業会計の基準を変更し得ることを容認した趣旨からすると,企業会計の実務の実際の動向を考慮することが当然の前提になっていると解すべきである。そして, 一般論として考えてみても,前記の立法担当者の解説書(乙98の119頁)でも指摘されているとおり,「慣行」という以上は,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることが必要というべきであって,いかにその内
容が合理的なものであっても,そのことだけで直ちに「会計慣行」になり得ると解することはできないというべきである。
もっとも,前述のとおり,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,「公正なる会計慣行」を斟酌することが要請されているとはいえ,特段の事情があれば「公正なる会計慣行」以外の会計処理の理論や方法によることも許されると解すべきであり,原告が主張するような合理的な会計処理の方法が生まれようとしている場合には,これを後述の特段の事情のある場合に当たるとして,そのような新しい会計処理の方法によることも許されると解する余地はあるというべきである。
(4) 「公正なる会計慣行」は規範的な概念であり実務慣行とは異なるとする原 告らの主張について
原告らは,「公正なる会計慣行」とは,規範的な評価概念であり,現実の金融機関の決算処理の実務について,特段考慮すべきではないとして,あくまで銀行である原告の貸出金の償却・引当の基準が,公正性を有するか,すなわち商業帳簿の作成目的である商人の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らし,合理的かつ妥当なものであるかどうかが問われるべきであると主張し,例えば,医師の不法行為等が問題となる事件において,医師の客観的注意義務としての医療水準(本来あるべき基準)と単なる医療慣行(通常医師が現に行っている医療慣行)が区別されていることや盗難通帳における預金過誤払いの事件において,銀行が社会通念上求められるべき注意義務と銀行実務が必ずしも一致すべきものではないと指摘し,「公正なる
会計慣行」の内容を確定するに当たり,現実の金融機関の決算処理に関する実務の状況を考慮することが不当であると主張する。
しかしながら,商法32条2項の「公正なる会計慣行」は,企業会計の基準となるものであるが,その内容は,本来,個別具体的に法令として定め得るものであり,その内容とされた個々の処理基準が規範として作用し,個別的具体的な状況に応じてそれが変化するものではないというべきである。これに対し,原告らが指摘する注意義務の内容は,規範としての抽象的注意義務が既に存在することを前提としたうえで,当該個別具体的な状況に応じて異なり得る実際の具体的な注意義務の内容にほかならないというべきであり,両者は同一視できるものではない。換言すれば,原告らの指摘は,医師や銀行に対する不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求や契約上の注意義務違反を理由とする損害賠償請求のように,既に注意義務に関する抽象
的な規範が定立されている場合において,本来あるべき水準とされる現実的かつ具体的注意義務の判断に当たっては,現に行われている実務(慣行)を区別すべきであると考えるものであり,抽象的規範が存在することを前提として,具体的基準を解釈するに当たり,現に行われている実務の状況に依拠すべきではないということは当然のことというべきである。これに対し,商法32条2項は,「公正なる会計慣行」を会計処理の抽象的規範とすべきである,すなわち,この抽象的規範を定めるに当たって会計慣行を考慮して決定すべきであるとするものであり,商法32条2項そのものが金融機関の決算処理に関する一般的抽象的規範すなわち基準それ自体を定めたものとはいえないというべきである。そうであるとすれば,このような前提となる規範それ
自体の判断に当たっては,現実の金融機関の決算処理に関する実務の状況を考慮することが必要でありこそすれ,これを考慮することが不当とは到底いえないから,この点に関する原告らの主張は採用できない。
2 争点②(既に公正なる会計慣行が存在する場合にその内容を変更する新たな 会計慣行が唯一の「公正なる会計慣行」とされるためにはどのような要件を満 たす必要があるか。)について
以上1で述べたのは,「公正なる会計慣行」の解釈に関する一般論であり,未だ公正なる会計慣行が存在しない事柄について,新たに公正なる会計慣行が生まれる場面での解釈というべきである。これに対し,本件では,銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が問題となっているところ,この点については,既に公正なる会計慣行として改正前決算経理基準が存在し(後述するとおり,被告らがいわゆる「税法基準」に従った会計処理が貸出金の償却引当における「公正なる会計慣行」に当たると主張する点では原告らはこれを争っているものの,改正前決算経理基準それ自体が「公正なる会計慣行」に当たるとする点では当事者間に争いはない。),その改正により内容の変更がなされた場面での「公正なる会計慣行」が問題とされている。しかも,
本件で,原告らは,資産査定通達等で補充される改正後の決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たると主張しているのである。そこで,以下では,前記の「公正なる会計慣行」の解釈に関する一般論を踏まえ,どのような要件が満たされた場合に,資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるかについて検討する。
(1) 変更された処理内容が繰り返して行われることの要否
まず,以上の一般論のうち,「公正なる会計慣行」とされるためには,企業会計の処理に関する具体的な理論あるいは処理方法が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることが要求されるかについては,本件で問題となっている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準のように,既に通達等に基づく会計処理の運用が「公正なる会計慣行」(なお,その内容について争いがあることは前記のとおり)とされて存在している場合において,その改正手続を踏んだ上で,内容の変更がなされたときは,必ずしも,そこまでは要求されないと解すべきである。なぜならば,改正の内容が公正なものである以上,その変更は機動的になされる必要があるし,後記4(1)ア(ア)a及び4(1)イ(ウ)cで認定のとおり,企業会計原則及び改正前決
算経理基準において採用されている「継続性の原則」の趣旨からしても,その間に間隙を生ぜさせることは相当とはいえないからである。そうであるとすれば,改正内容が「公正」なものであり,改正手続自体が適正なものと認められるのであれば,必ずしもその内容が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われていなかったとしても,唯一の「公正なる会計慣行」に当たると認める余地はあるものというべきである。
そして,この点については,有価証券報告書提出会社については,企業会計審議会が公表した企業会計原則・同注解が企業会計に関する「公正なる会計慣行」に当たると解されているところ,平成10年大蔵省令第135号による改正後の「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下「改正財務諸表規則」という。なお,この改正後の財務諸表規則を「改正財務諸表規則」という。)1条2項により,企業会計審議会の作成・公表した企業会計の基準が,導入と同時に,原則として「公正なる会計慣行」となることを容認した趣旨からすると,企業会計原則・同注解の改正に当たっては,企業会計審議会が公表する会計基準で示された会計処理方法が,一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行うことまで要求されること
なく「公正なる会計慣行」となり得るとされていることが参考になるというべきである(甲98添付資料5,乙35の135頁,乙94の219頁,乙98の108頁参照)。もっとも,以下で述べるように,企業会計原則・同注解が改正により相当の時間繰り返し行われることなく「公正なる会計慣行」となり得るのは,上記の通り,改正財務諸表規則1条2項により包括的な委任規定が存することがその理由とされていることに留意する必要がある。
(2) 内容を変更することに伴う要件
次に,本件で問題となっている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準については,既に公正なる会計慣行として改正前の決算経理基準が存在していることからすると,資産査定通達等で補充された改正後の決算経理基準が広く会計上のならわしとして一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一の「公正なる会計慣行」とされるためには,改正前の公正なる会計慣行と改正後の会計慣行との間の内容変更の程度に応じて,従前の基準を変更することにより,企業会計の継続性の確保の観点から支障が生ずるような場合には,これに対する手当を講じる必要があるというべきである。なぜならば,従前の会計慣行が公正なものとして関係者に周知徹底され慣行として広く行われていたものであることからすると,その後に変更された内容が仮に「公正な
る」ものと評価できるとしても,変更自体が法規によらず,通達等を介して「会計慣行」の変更によってなされるものであり,本件で問題となる資産査定通達や9年事務連絡は,あくまでも行政組織内部の通達や事務連絡にすぎず,また,4号実務指針は会計士協会内部における監査上の指針であって,それらは当然に金融機関に一定の法的義務を課す性質のものではない以上,変更後の会計慣行が一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされるためには,会計処理に関する継続性の原則への配慮,ひいては後述するように,その内容が商法32条2項を介して法規範としての強制力を持つことからしても,変更が関係者にとって,いわば不意打ちにならないような手当が必要と解すべきだからである。そして,そのような手当がなされない場合
には,変更後の処理基準が内容的にみて「公正なる会計慣行」に当たるといえる場合であっても,これが一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされることはできず,従前の処理基準に従った処理もまた「公正なる会計慣行」として存続することになると解すべきである。
このことは,証拠(乙3,乙4,乙35,乙38,乙39,乙44)及び弁論の全趣旨によれば,企業会計の基準は,会計理論の発達,企業会計の技術・実務の発展,進化により変化するものであり,必ずしも唯一の基準が存在するわけではなく,企業会計の継続性の原則の趣旨からすると,複数の企業会計の基準が併存する場合があること(実際に従前の処理基準に従った処理の併存が認められている例として,後記3(8)イ(ウ)参照),企業会計原則・同注解が企業会計に関する唯一の「公正なる会計慣行」に当たるとの見解が有力視されるに至ったのは,前記改正財務諸表規則が定められた平成10年以降であり,他方,「公正なる会計慣行」は複数存在することがあり得ると解され,企業会計審議会の公表する基準であっても必ずしも直ちに「
公正なる会計慣行」となり得るものではないと解されていたところ,決算経理基準については,改正財務諸表規則のような法規による根拠付けがなされていないことからも裏付けられるというべきである。
(3) 商法32条2項を介して法規範となることに伴う要件
また,本件でも問題とされているように,銀行の貸出金 の償却・引当に関する基準が改正され,当該基準が,唯一,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」に当たることになった場合には,前記のとおり,この新たな銀行の不良債権の償却・引当に関する基準が,商法32条2項を介して法規範となり,商法290条1項の配当規制に影響を及ぼし,当該基準に反した処理をすることによって違法配当の問題が生じ得ることになり,改正が法規によってなされるものでないにもかかわらず,取締役であった被告らの民事責任及び刑事責任を生じさせ得ることからすると,新たな会計慣行について,一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一の「公正なる会計慣行」として強制力を生じさせるためには,改正手続が適正なものであることは当然
としても,新たな銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が新たに法規により企業会計の基準が定められた場合と同程度に一義的で明確なものであることに加え,前記のとおり,決算経理基準については,改正前財務諸表規則のような法規による根拠付けがなされていないことも考慮すると,当該基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,当該基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われた場合と同視しうる程度に,これが規範として拘束性を有するものであることの周知徹底を図ることが必要と解すべきである。
(4) 小括
以上検討したところによれば,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容を踏まえたうえで,原告らが主張するように資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が銀行の貸出金の償却・引当に関する基準として唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるためには,以下の要件を満たすことが必要といえる。すなわち,まず,当該貸出金の償却・引当に関する基準が,当該銀行の利害関係人に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして,社会通念上,合理的なものであることが必要である。そして,本件においては,従前から存した「公正なる会計慣行」である決算経理基準の改正という形で銀行の貸出金の償却・引当に関する基準の変更がなされていることからすると,改正手
続自体が適正で,改正の内容が公正なものであれば,変更された会計処理に関する基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることまでは要求されないというべきであるが,会計処理の基準の変更が法規によってではなく通達を介して新たな慣行によって行われるものである以上,その変更に伴って企業会計の継続性の確保の観点から支障が生じ,ひいては関係者への不意打ちになるような場合には,これに対する手当をすることが要求されるというべきである。また,本件で問題とされている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準の変更は,その変更された内容が唯一の「公正なる会計慣行」とみなされる場合には,改正が法規によってなされるものでないにもかかわらず銀行の取締役らの民事責任及び刑事責任を生じさせうるこ
とからすると,相当の時間繰り返して行われることなくこれを唯一の「公正なる会計慣行」とするためには,改正手続が適正なものであることは当然としても,新たな銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が一義的で明確なものであることが必要であり,さらに,当該基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,これが唯一の規範として拘束性を有するものであることの周知徹底を図ることが必要と解すべきである。
以上を整理すると,原告らの主張する資産査定通達等によって補充された改正後の決算経理基準が,銀行の不良債権の償却・引当に関する唯一の基準としての「公正なる会計慣行」に当たるとするためには次の要件を満たすことが必要と解すべきである。
① 当該銀行の利害関係人に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかに するという目的に照らして,社会通念上,合理的なものであること
② 変更に伴って企業会計の継続性の確保の観点から支障が生じ,ひいては 関係者に対する不意打ちになるような場合には,これに対する必要な手当 がなされていること
③ 改正手続が適正なものであること
④ 新たな基準が新たに法規により企業会計の基準が定められた場合と同程度に一義的で明確なものであること
⑤ 新たな銀行の決算処理に関する基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,当該基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われた場合と同視しうる程度に,これが唯一の規範として拘束性を有するものであることの周知徹底が図られていること
3 本件の事実関係(認定事実)
前記2で判断したとおり,平成10年3月期において,資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が,唯一の「公正なる会計慣行」であったとするためには,前記2の(4)で示された①から⑤までの要件を満たすことが必要と解される。そこで,以下では,これらの要件該当性を検討する前提として,早期是正措置の導入が決定され,その一環として資産査定通達等が発出され決算経理基準の改正に至った経緯とこれに対する大蔵省等関係者の対応状況,原告が前記決算経理基準の改正に至る経緯を踏まえて本件中間配当及び決算配当を実施するに至った際の被告ら等の関係者の対応状況,平成10年3月期における原告の自己査定基準に基づく実際の償却・引当の状況,その後の関係者の対応状況とこの間における銀行の資産査定をめぐる金融行政
の変遷等について,時系列に従って事実関係を整理することとする。
前記前提となる事実と証拠(各項末尾に摘示)及び弁論の全趣旨によって認められる事実関係は,以下のとおりである。
(1) 早期是正措置の導入に関する検討開始と原告における検討状況
ア 早期是正措置の導入に関する検討開始の状況等
(ア) 平成7年6月8日付け「金融システムの機能回復について」
大蔵省は,平成7年6月8日付け「金融システムの機能回復について」と題する指針(乙117)を公表した。
上記指針には,「検査・監督機能の一層の活用」と題して,検査・監督は,従来より金融機関経営の健全性を確保する上で大きな役割を果たしてきたが,いわゆるバブルの発生・崩壊という金融環境の激動期においては事前の経営チェック機能を必ずしも十分果たしえたとはいい難い面があること,近年の金融機関を巡る環境の変化に対応するため,検査・監督にかかる要員や研修の充実等に努め,検査・モニタリング機能の一層の活用を図ること,検査・モニタリングの結果,多額の不良債権の発生等が認められた場合には,時機を失することなくこれに対応し得るよう,客観的な指標に基づき金融機関経営の早期是正措置を求める措置の導入等について検討することが示されていた。(乙117の58頁)
(イ) 金融制度調査会による平成7年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」と題する答申
その後,株式会社大和銀行のニューヨーク支店における巨額損失事件が発覚したことなどにより,銀行に対するリスク管理,内部監督が社会的な問題となり,大蔵省検査等についての批判がされ,従来の銀行に対する保護的な事前指導行政から自己責任原則(市場を通じた銀行の評価と民間銀行の自主性の尊重)に基づく事後監督行政へと転換する議論・検討が一層進められた(甲231の2枚目,乙108の3頁)。
すなわち,大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会は,平成6年12月の東京協和信用組合,安全信用組合の破綻をはじめとして金融機関の破綻が相次いだことを受けて,平成7 年7月,金融システムの安定化のための諸施策を検討するべく金融システム安定化委員会を設置した。そして, 同委員会の報告に基づき,金融制度調査会は,同年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」と題する答申をした。その答申の中で,金融機関や預金者の自己責任原則の徹底と市場規律の十分な発揮を基軸とする透明性の高い金融システムを早急に構築していく必要があること,監督当局においても行政姿勢の転換が必要であり,市場機能の補完的役割を果たすことを基本として
,透明性の高い新しい行政手法の導入とともに,検査・モニタリング体制の整備・充実を図ることにより金融機関経営の健全性確保を促していく必要があることが指摘され,そのための具体的な金融機関経営の健全性確保のための方策として,「早期是正措置の導入」が挙げられた。そして,早期是正措置は,監督当局が最低限講ずる必要のある処分等の内容を明確化するものであり,当局の裁量の幅を狭め,行政の透明性確保にも資することとなること,早期是正措置の導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となるところ,検査・モニタリング体制の整備・充実が必要であるが,金融機関の自己責任原則の徹底等の観点からは,資産査定は先ず各金融機関自らが厳正に行うことが必要であることが指摘された(乙17の
1枚目左側4段目の(2))。(甲231,乙17,乙108)
(ウ) 平成7年12月26日付け「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」等
その後,金融検査・監督等に関する委員会は,同年12月26日,「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」(甲13)を公表し,その中で,金融行政金融機関の経営の健全性を確保するため,客観的なルールに基づき経営の早期是正を促すいわゆる早期是正措置を導入する必要があること,同時に,この制度が適切に機能するためには,金融機関自らの資産内容の的確な把握,監督当局の検査・モニタリング体制の整備は不可欠の前提であること,特に,資産内容の自己査定の重要性にかんがみ,これについては公認会計士による外部監査を活用していくことが求められることが基本的な認識として示された(1枚目)。
そして,金融機関の経営の健全性を確保するための監督手法として,早期是正措置を導入すること,これは,金融検査部局の検査等の結果に基づき,行政担当部局が業務改善命令等の措置を客観的なルールに則り厳正に実行していくものであること,が挙げられていた(2枚目)。
また,早期是正措置の導入に伴う新しい検査方法の確立について,早期是正措置の導入には,その基準となる自己資本の充実度等の正確な把握が不可欠であること,そのため,金融機関による自己査定及び外部監査の活用を前提とした新しい検査方法を確立すること,当局は,自己査定のための統一的な基準を示すことなどが挙げられた(3枚目及び4枚目)。
さらに,同日,今後の金融行政の転換について,金融機関の自己責任の徹底と行政当局における市場規律を基軸とした透明性の高い行政を行うことが肝要であり,そのため,当局の検査結果等に基づき自己資本の充実度等客観的ルールにより,業務改善命令等の措置を厳正に実行する早期是正措置制度を導入する必要がある旨の大蔵大臣の談話が公表された(甲14の1枚目)。(甲13,甲14,弁論の全趣旨)
(エ) 会計士協会による銀行等監査特別委員会の設置
会計士協会は,平成8年3月26日,前記(イ)の金融制度調査会からの答申「金融システム安定化のための諸施策」と前記(ウ)の「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」が公表されたことを受け,金融機関に係る監査業務について検討する特別委員会である「銀行等監査特別委員会」を設置することを決定した。
なお,上記特別委員会の委員長は,当時の会計士協会の副会長であったI(以下「I会計士」という。)が就任した。
イ 原告における早期是正措置に関する当初の検討状況
原告は,平成8年2月13日開催の常務会(D,E,F,C及びBが出席)において,「金融行政のあり方の根本的転換について」と題する資料(甲18の2)に基づく検討を行った。
上記資料によれば,自己資本の充実度等の客観的ルールに基づき,裁量を極力排除した行政命令の発動を厳正に実施する早期是正措置が導入されること,その導入に当たっての前提として,①金融機関自らによる自己査定を統一基準に基づき実施,義務付け,②その結果を公認会計士活用による外部監査でチェック,③当局検査は,自己査定や外部監査の結果を活用しつつ,その正確性や客観性を最終チェック及び④当局検査は,自己資本充実度及び自己査定正確度に関する格付けを行い,当該格付けに対応した弾力的検査手法を導入するといった4点を制度化し,客観性・正確性を確保することが示され,また,「当行経営への影響,課題」として,リスク管理体制,内部管理体制(含法令遵守状況)の組織内確立について資産の健全性の状況の適正
把握,管理システムの構築が指摘され,さらに,上記資料の添付資料(前記ア(ウ)の大蔵省発表原文とこれに注釈や原告の課題を記載した資料)には,早期是正措置の導入及び外部監査の活用を受け,MOF基準及び外部監査に耐え得る自己査定システムの構築が原告の課題とされることが指摘されていた。(甲18の1及び2,甲103添付資料1)
(2) 平成8年の大蔵省検査に対する原告の対応,当時の不良債権額等の把握状況,金融3法の成立と早期是正措置の導入の決定等
ア 平成8年4月における大蔵省検査の状況等
(ア) 平成8年4月8日会議における不良債権額把握の状況
原告は,平成7年ころから,近く大蔵省検査が実施されることを想定して資産査定に関する試算を行い,その結果について,総合企画部及び事業推進部が共同で,平成8年4月8日付け「円卓会議資料」と題する資料(甲168添付資料1)にまとめた。
上記資料には,「査定前」として,Ⅱ分類が2兆8672億円(一般先1兆1472億円,住専1300億円及び関連親密先1兆5900億円)であること,Ⅲ分類2115億円(一般先2115億円)及びⅣ分類2877億円(一般先1157億円及び関連親密先1720億円)の合計額は4992億円に達し,この4992億円について3年の期間(平成8年度2400億円,平成9年度1400億円,平成10年度1192億円)で償却する計画であること,他方,大蔵省検査による査定の結果,「査定後(最悪ケース)」として,Ⅱ分類は1兆9805億円(一般先1兆0822億円,住専1300億円及び関連親密先7683億円)であり,Ⅲ分類2603億円(一般先2115億円,関連親密先488億円)及びⅣ分類1兆1256億円
(一般先1807億円及び関連親密先9449億円)の合計額は1兆3859億円に達するが,できる限り,関連親密先の評価について検査官と協議し,査定後の「努力目標」に近づけること,「査定後(努力目標)」(もっとも可能性が高い分類)として,Ⅱ分類は2兆3719億円(一般先1兆1302億円,住専1300億円及び関連親密先1兆1117億円)であり,Ⅲ分類3334億円(一般先2115億円,関連親密先1219億円)及びⅣ分類6611億円(一般先1327億円及び関連親密先5284億円)の合計額は9945億円に達し,この9945億円を5年間で償却する計画(平成8年度2900億円,平成9年度2400億円,平成10年度2200億円,平成11年度1400億円,平成12年度1045億円)であることが記載
されていた(資料の2枚目)。
また,上記資料における「査定後(最悪ケース)」は,平成8年3月時点における関連親密先の資産について,清算価値をベースに,修正母体行主義により算定しており(甲116の120頁),「アポロリース,インターリース及び東海興業」に対する原告の貸出金についてもⅣ分類と想定していたが,当時,「インターリース」については日本信販株式会社の関連会社として業務を継続しており,経営破綻には至っていなかった(甲125の81頁)。
なお,上記資料には,「関連会社不良資産実態」として,長銀リース外8社の「不良資産」について,「実態ロス」(Ⅲ分類及びⅣ分類合計)が1兆2559億円,原告の貸出が1兆3256億円,「修正母体」による試算額が8437億円であることが記載されていた(上記資料添付別紙4)が,清算した場合における原告の損失負担額(プロラタ方式すなわち貸出残高の割合に応じた損失負担額)は5710億円であった(甲116の128頁,甲132の31頁)。
同日,上記資料の説明会(30分程度)が開催され,Hは,同説明会に出席したD,E,Fら常務以上の役員に対し,上記試算額について説明した。(甲116,甲121,甲125,甲129,甲131,甲132,甲167,甲168,弁論の全趣旨)
(イ) 平成8年の大蔵省検査後の原告の不良債権の検討状況
原告に対する大蔵省検査は,平成8年4月16日を検査基準日として,同月17日から同年6月12日まで実施され,資産査定については,同年5月7日から開始された(甲168添付資料2)。
その間,Hは,大蔵省検査における資産査定の途中経過の報告を受けて,原告の検査を担当した金融検査担当主任検査官のJ(以下「J主任検査官」という。)と面談し,関連ノンバンクの支援状況や受皿会社における事業化計画の状況等を説明して,分類額の圧縮について了解を求めたが,J主任検査官は,回収業務の状況について質問し,また,合理的な理由がない限り,分類額の圧縮に応ずることはできないと回答していた(甲168の23枚目,24枚目)。
大蔵省検査に係る資産分類の最終結果(甲169添付資料3)については,Ⅱ分類2兆5324億円(一般先1兆5420億円及び関連親密先9904億円),Ⅲ分類8960億円(一般先2451億円及び関連親密先5140億円),Ⅳ分類2029億円(一般先68億円及び関連親密先1961億円)であるというものであった。なお,関連親密先は「修正母体行方式にて残高上限」まで資産分類されていた。
その後,大蔵省金融検査部等は,同年10月4日付け示達(甲19)により,原告に対し,原告の関連会社の実態について,「ファイナンス業務を営む関連会社等が有する不良化した貸付債権について,簿価で受皿会社が譲り受け,その譲渡代金相当額を当行が融資している事例」が認められ,その結果,「これらの受皿会社においては,多額の含み損を抱える状況になっている」こと,「受皿会社を含めた関連会社等の相互関係や当行が実行した融資の資金フローについて,現状,いずれの所管部においても的確に把握されていないほか,関連会社等の支援については,一部を除きほとんど手が付けられていない状況」にあり,「関連会社等について,適切な管理に努めるとともに,抜本的な再建計画を早急に策定し,不良債権を計画的に処理して
いくことが必要である」ことを指摘した。その中で,別紙として,「親密・系列等の関係会社関係」として,ジャリック,エヌイーディーグループ(同記載番号1ないし8),第一ファイナンス(同記載番号9),日本リースグループ(同記載番号10ないし14)が記載されていた。
また,上記示達の中の「検査報告書」において,貸出金査定結果,分類額3兆6711億円,「特にⅢ・Ⅳ分類の合計額は,関連会社等を中心に1兆1166億円」にも達しており,3年間の処理方針が立てられていること(1頁),「関連会社等」について,「抜本的な再建計画を早急に策定し,不良債権を計画的に処理していくことが必要である」こと(16頁)が指摘されていた。(甲19,甲168)
イ 金融3法の成立と早期是正措置の導入決定,これを受けた原告の検討状況等
(ア) 金融3法の成立と早期是正措置の導入決定
その後,平成8年6月21日には,金融3法が,国会において可決・成立し,健全性確保法において,銀行法26条(長期信用銀行法17条により長期信用銀行に準用)を改正し,平成10年4月1日以降,早期是正措置制度を導入する旨が定められた。
健全性確保法における改正後の銀行法26条1項は「銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして,当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは,当該銀行に対し,措置を講ずべき事項及び期限を示して,当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め,若しくは提出された改善計画の変更を命じ,又はその必要の限度において,期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ,若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる」旨規定し,同条2項は「前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって,銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときに
するものは,大蔵省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ,大蔵省令で定めるものでなければならない」旨規定していた。(甲22の2,甲146,乙100,弁論の全趣旨)
(イ) 平成8年8月30日の常務会における検討状況
原告は,平成8年8月30日開催の常務会(D,E,F,C及びBが出席)において,総合企画部作成の同日付け「金融行政の転換と当行の対応について(内部管理体制の強化と早期是正措置)」と題する資料に基づき,審議・検討したが,その際,Fは,早期是正措置のための資産の自己査定について,プロジェクトチームを設けて対応していくとのことであるが,「実質的には,多額に抱えてしまっている不稼働資産をどの様な形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。その点は十分認識しておく必要がある。」と発言した。
上記資料(甲22の2)によれば,金融機関の自己責任原則に伴う当局の要請として金融機関に対する資産内容の自己査定要請があること,「早期是正措置の導入→自己査定の正確性と自己資本の充実について格付け,行政措置発動」があることとされ,また,資産自己査定・検査については,全取引先ごとに,企業・案件,資金使途,担保等の状況により,Ⅰ分類からⅣ分類までに自ら分類し,これを内部において検査する必要があること,ノンバンクは別途,当行系ノンバンク,非当行系で区分され,算出方法が修正母体行主義など,左記の一般業種と全く異なることが示されていた。(甲22の1及び2,乙100)
(3) 早期是正措置検討会における検討状況・「中間とりまとめ」の公表と当時における原告の対応,原告内部での不良債権の把握の状況等
ア 早期是正措置検討会における検討状況,中間とりまとめの公表等
(ア) 早期是正措置検討会の概要等
このような早期是正措置が導入されることとなったことを受けて,平成8年9月30日に大蔵省銀行局長の私的研究会として,早期是正措置検討会が発足し,早期是正措置の導入に向けて,その具体的内容の骨格と適正な財務諸表の作成に当たっての基本的考え方や実務指針等について検討し,同年12月には,後記(ウ)の中間とりまとめを作成・公表し,また,平成9年6月19日までに9回の会合が開催され,早期是正措置の導入に関する討論・検討が行われた。
なお,そのメンバーは,座長を国際経営コンサルタント株式会社顧問のK(以下「K」という。),商法学者,経済学者,日本銀行(以下「日銀」という。)の信用機構局長,会計士協会副会長兼銀行等監査特別委員会委員長であったI会計士のほか,株式会社さくら銀行(以下「さくら銀行」という。)の当時専務取締役であったL(以下「L」という。)等の銀行,信用組合の実務者が特別メンバーとして加わっていた。また,適宜,上記会合には,大蔵省金融検査部の企画官,管理課長等の大蔵省職員が説明等のために加わっていた。(証人K,証人L,甲15,甲138,乙115,乙116,弁論の全趣旨)
(イ) 会合における検討状況
a 平成8年11月21日開催の会合(第4回)における検討状況
平成8年11月21日に開催された早期是正措置検討会における会合においては,「償却・引当のあり方等」についての説明,討議が行われ,その中で,I会計士は,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する会計士協会で検討中のたたき台について説明し,その後の討論の中では,「これまでの償却・引当は税法基準に頼りすぎていたのではないか」,「有税でも必要な引当を行うべきとする考え方は判るが,税務会計と企業会計をできるだけ一致させていくべきではないか」といった意見が出された。(乙116)
b 平成8年11月29日開催の会合(第5回)における検討状況
平成8年11月29日に開催された早期是正措置検討会における会合においては,「資産の自己査定のあり方,位置付け等」についての説明,討議が行われ,その中で,当時の大蔵省大臣官房企画官のM(以下「M企画官」という。)は,「資産査定について(案)」(乙114)を資料と示して,その内容を説明し,その後,討議が行われた。
その際,特別メンバーである地方銀行の担当者は,一応今回の案に沿って,自己査定の基準(行内規程)を作成することとなるが,金融機関によってかなり判断に相違が生ずる可能性があり,その場合,各行独自の基準がそのまま認められるのかについて質問し,これを受けて,M企画官は,独自性を発揮するのは重要であるが,その結果が,当局が示す基準に整合しているかどうかについては十分にチェックすることとなると説明した。
その後,Kが,償却・引当の数値基準として,例えば米国の資産査定については,「substandard」(日本のⅡ分類にほぼ相当)について15パーセント,「doubtful」(日本のⅢ分類にほぼ相当)について50パーセントという目安があるが,日本の金融検査の場合に数値基準があるかどうかという質問を行い,M企画官は,Ⅳ分類は基本的に「loss」であり,償却・引当が妥当であると考えているが,Ⅲ分類については,検査のみから具体的な引当数値基準を判断するのは困難であり,当該金融機関の貸付先に対する見方等の判断に大きく依存し,清算した場合の損失額は算出できるが,それは,「ロス額」と相違し,どの程度,個別債権の引当を積むべきかについて指摘するのは困難であると説明した。
また,翁百合委員は,償却・引当及び資産分類の関係と税法との対応関係について質問し,例えば,自己査定の結果,本来の税法基準より引当金を多く無税で積みたいと考えた場合に,従前と同様の許可を受けて無税引当をするのか,そうであるとすると,自己査定の結果,経営者の判断により必要額を引き当てるという考え方とどのように整合性を取るのか,米国の場合,引当は有税,償却は無税となってわかりやすいが,この点はどのようになるのかという質問を行い,これを受けて,M企画官は,資産分類の考え方と税の考え方の関係は,税を横に置いて債権の健全性ということのみから判断していく仕組みである,実際に引当金を積んだときには有税と無税で効果が違う,いわゆる税効果会計はどうなんだという議論は当然あると思うが,
有税であるか無税であるかを外に置いて,それに左右されずに判定するというものであると説明した。
さらに,Kは,問題のある債権について金融機関側の判断と検査結果による判断の相違はどの程度あるのかという点を質問し,これを受けて,M企画官は,最終的には,金融機関側から資料の提出を受け十分議論して決定していること,また,当時大蔵省銀行局調査課長であったN(以下「N調査課長」という。)は,従前,資産査定と償却・引当とが必ずしも明確に結びついた形となっていないこと,監査の立場と検査の立場がかみ合っていないと意見の相違が生じ,検査の最終段階において,様々な問題が生ずること,米国の場合には,早期是正措置の導入以前から自己資本比率に基づく監督を実施し,その段階から資産査定と償却・引当ができるだけ結びつく形でルール化してきた経緯があると理解していること,資産査定と償却・引当に整
合性がある形であっても,個々の検査の場面で,金融機関側との意見が相違する,あるいは,公認会計士の考え方と検査の立場が相違することはあると思うが,早期是正措置検討会に出席した米国の公認会計士が説明していたように,そこは実務的に議論する中で,大きな隔たりが残ってどうしようもないということは少なく,かなり調整できるとの指摘もあり,議論の中で,いろいろ知恵を出していくことになると思うと説明した。
なお,特別メンバーであるLは,個別債権ごとに逐一査定することは実務的な負担が重く,ある程度くくった評価ができるような仕組みも許容すべきであり,自己査定の仕組みをどのように構築していくか,銀行間の格差が大きく,一挙に理想的な形までもっていくことはできないので,実際の適用に当たり,時間的な猶予について配慮してほしいとの意見を述べ,また,特別メンバーである信用組合の担当者からも,400を超える信用金庫全体を眺めれば自己査定が定着するのは相当時間がかかる,業界が全部足をそろえてこれをやっていくのはかなり難しく,方向性自体を否定するものではないが,実務的にみたときの負担を考慮する必要があるとの意見を述べた。(乙115,乙116,弁論の全趣旨)
c その他の検討状況等
また,早期是正措置検討会の会合の中では,地域金融機関,信用組合等から,定量的な基準が示されないと,償却・引当の基準となり得ないとの意見が出されていたが,各金融機関が個々の債権の回収可能性をもっとも認識しており,当局が一律の基準を示すことは不可能であること等から,後記(ウ)の「中間とりまとめ」においても,「機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではない」と指摘されるに止まり,定量的基準は示されず,各金融機関が実情に応じた自主ルールを作成すべきこととされていた。(証人K5頁,6頁,甲138の20頁,21頁)
(ウ) 「中間とりまとめ」の具体的な内容等
早期是正措置検討会は,平成8年12月26日付け「中間とりまとめ」を作成・公表した。
その中では,早期是正措置は今後の新しい金融行政の中核的手法となるものであることが示され,また,早期是正措置の導入に当たっては,金融機関が自らの責任において企業会計原則等に基づき適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提となること,各金融機関が行う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として重要な役割を果たすことになること,会計監査人においては,財務諸表の適正性についての深度ある監査を行うことが求められることが指摘されていた。次に,この早期是正措置の適時の発動の前提として,金融機関の資産内容の実態ができる限り正確かつ客観的に反映された財務諸表が作成され,これに基づき正確な自己資本比率が算出される
必要があること,適正な財務諸表の作成のためには,企業会計原則等に基づき適正な償却・引当が実施される必要があること,そのための要件として,例えば,企業会計原則注解18では,①将来の特定の費用又は損失であって,②起因事象が当期以前に存在し,③損失発生の可能性が高く,④その金額を合理的に見積もることができる場合,という考え方が示されているが,今後の早期是正措置の導入に当たり,各金融機関が更に適正かつ客観的に償却・引当を行いうるよう,会計士協会から償却・引当についての明確な考え方が実務上の指針(ガイドライン)として示されることが望ましいこと,などが示されていた。
また,償却・引当に関し,個別性の強い個々の債権の回収可能性の違いを無視して,機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではないこと,償却・引当の正確性,客観性等をできる限り確保する観点から,各金融機関においては償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備がすみやかに行われることが望まれることが示されていた。
さらに,各金融機関による償却・引当に当たっては,貸倒償却及び貸倒引当金の計上基準に関するガイドラインに従う必要があること,ただ,同ガイドラインについては,なお個別のケースに照らし判断するうえでの具体性を欠く部分があるため,各金融機関は自らの実情を踏まえつつ,より具体的・詳細な償却・引当ルールを自主的に作成し,これに基づいて導き出される個々の債権の回収可能性をもとに償却・引当を実施することが適当であることが示され,加えて,各金融機関が適正な償却・引当の実施を行っていくためには,有税による償却・引当を円滑に進めていく環境整備も必要であること,その観点から,有税償却・引当を行った場合の前払税金等の取扱いを定める税効果会計について,今後,検討が行われることが望ましいことが示
されていた。
この「中間とりまとめ」の中の「資産の自己査定について」の項においては,適正な償却・引当を行うためには,各金融機関は自らの資産内容の健全性を的確に把握する必要があること,資産の健全性を把握するための作業である資産の自己査定は,適正な償却・引当を行うための準備作業として位置づけることが適当であること,資産の自己査定は,各金融機関が有する資産を個別に検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って分類区分することであり,基本的には各金融機関の判断により行うものであるが,適度な統一性の確保という観点からは,各金融機関においてできる限り共通の基本的考え方が確保されていることが望ましいこと,当局がこれまでの検査(資産査定:Ⅰ~Ⅳ分類)における実務をもとに,自己査
定ガイドラインの原案を作成し,本検討会において検討を行った結果概ね了解が得られたので,こうした点を踏まえ,自己査定のガイドラインを作成することが適当であることが指摘され,この「自己査定のガイドライン」においては,正常先債権については,原則としてⅠ分類とする,要注意先債権については,原則としてⅡ分類とする,破綻懸念先債権については,担保等で保全されている部分を除き,原則としてⅢ分類とする,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」については,担保等で保全されている部分を除き,原則としてⅣ分類とするという考え方が示されていた。また,その中で,各金融機関においては,このガイドラインをベースに創意・工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成するこ
とはむしろ望ましいこと,各金融機関が自己査定ガイドラインよりも詳細な自己査定基準を作成する場合は,各金融機関は当局の検査等の際にその合理性,明確性等について説明を行うことが必要であること,「自己査定ガイドライン」は,これまでの検査における資産査定の考え方と基本的に同様である一方,今般,公認会計士協会から債権を正常先,要注意先等の5つの区分に分けてそれらに応じた償却・引当の計上に係る基本的な考え方が示されたことにより,両者は仕組みの大枠において一致が図られたものと考えられること,検査においても,各金融機関がガイドラインに沿って正確な自己査定や適正な償却・引当を行っているかどうかについてチェックする必要があることが示されていた。
この「中間とりまとめ」の「外部監査について」の項では,会計監査人(公認会計士又は監査法人)が行う財務諸表監査において,自己資本比率に関わってくる財務諸表上の数値の正確性などについて,内部統制の状況にも留意しつつ試査の程度を上げるなど,従来より深度ある監査を行うことが求められること,各金融機関が行う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として位置づけられることから,会計監査人が商法監査(会計監査)手続の一部である内部統制の評価を行う作業のなかで,各金融機関において自己査定基準・手続が適正に整備されているか,また,それに沿って自己査定が実施されているか,などについてもチェックすることは償却・引当に係る監査の機能を高める上で有効であることが示されていた。
この「中間とりまとめ」の早期是正措置の「基本的考え方」の項では,早期是正措置は,金融機関が自己責任原則に基づき経営改善への取組みを適時にかつ迅速に行うことを,行政当局が客観的指標に基づき促すことを目的としており,早期是正措置の具体的な発動基準は,金融機関の経営改善への取組みを効果的に促し得るようなレベルに設定する必要があることは当然であるが,他方,早期是正措置は金融機関を破綻に追い込むことを目的としたものではなく,制度導入時において多くの金融機関が達成不可能となるような基準を設けるべきではないこと,米国においては金融機関の不良債権処理に概ね目途がついたとされる平成4年末に早期是正措置が導入されたのと比べると,我が国においては,金融機関全体としては不良債権の処理が進ん
でいるもののなお状況は区々であり,制度導入時の環境は異なるとの見方があること,このような状況の下では,早期是正措置の導入により金融機関の貸し渋りが生じる等,実体経済に大きな悪影響が生ずることのないよう配慮することも必要であることなどが示されていた。
なお,「中間とりまとめ」の中の「自己資本比率(国内基準)の算定方法の見直し」の項(9頁)では,国際統一基準に従い,分子を自己資本(TierⅠ+TierⅡ)とし,分母をリスクアセット(甲121の120頁によれば,自己資本比率算定の際の分母となる数値であると認められる。)とし,分子を分母で割った数値(自己資本比率)を基準とすること,また,制度運営の基本的考え方として,是正措置の区分は,「第一区分:経営改善計画の作成・実施命令」,「第二区分:個別措置(注)の実施命令」,「第三区分:業務の一部又は全部の停止命令」が定められ,上記「第二区分」における「個別措置(注)」については,「増資計画の策定,総資産の増加抑制・圧縮」等が考えられるとされていた。また,「各措置区分の発動基準となる自己
資本比率の値」は,国際統一基準については「第一区分」は「8パーセント未満」,「第二区分」は「4パーセント未満」,「第三区分」は「0パーセント未満」とすることが定められていた。(甲15)
(エ) 「中間とりまとめ」に関する説明等
Kは,平成9年1月ころ,金融雑誌の取材を受けた際に,自己資本比率のバーについて,新制度スタート後3年間を経過期間と位置づけて実施状況を見極めたうえで平成12年度末までに基準値を見直すことを提言していること,現在,不良債権処理が峠を越したとしても,まだ29兆円もの残高があり,早期是正措置の尺度となる実質的な自己資本比率は厳しいものとなること,早期是正措置検討会に参考人として出席した米国監査法人の関係者は,日本の早期是正措置制度導入のタイミングは悪すぎると述べていたこと,平成9年度末までに増資,劣後債務の導入により自己資本の増強を図ったとしても,それを十分に調達し得る市場環境にはなく,結果的に深刻な貸し渋りが発生することも懸念され,早期是正措置の発動数値の決定に関しては
,金融システムや日本経済への影響を考慮しなければならないことを説明した。また,Kは,中間とりまとめにおける自己査定ガイドラインや償却・引当の考え方は定性的・抽象的な表現に止まり体制づくりに入れないのではないかとの質問を受けて,自己査定と償却・引当に関するガイドラインについて各金融機関の間の適度の統一性を確保するための目安にすぎないこと,各金融機関が自己責任原則に基づいて自らの実情と債権の個別性を踏まえて,主体的に自己査定の引当・償却を決めなければならないことを説明し,債務者区分ごとの貸倒実績率について各金融機関が過去のデータを有していないのではないかとの質問について,平成10年の開始時にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいが,しかし,その時点で不完全であっても,即「
落第」という機械的な裁定はできないこと,ある程度の趨勢は把握し得るし,公認会計士がチェックするので,必要な精度を確保し得ることを説明していた(乙19)。
さらに,Kは,当時において,早期是正措置の導入により不良債権処理に関する手当を完了させることは理論的にはあり得るが,そのような場合,多数の金融機関が業務改善命令や業務停止命令の対象となり,金融システムが大混乱に陥るため,いくつかの経過措置をとったこと,金融機関が自己資本比率をできるだけ改善する結果,分母におけるリスクアセットの圧縮すなわち貸し渋りに進み,日本経済に大変な影響を生じさせること,そのために,この貸し渋りをどのように防止するかについても考慮していた(甲138の13頁,14頁)。(証人K,甲138,乙19)
イ 自己査定体制検討プロジェクトチームの結成及び自己査定基準の検討状況と不良債権償却計画の検討状況等
(ア) 自己査定体制検討プロジェクトチームの結成
原告は,平成8年10月1日,早期是正措置導入の決定に伴い,資産の自己査定体制,手法,基準等の具体策を検討するため,D(当時頭取)の決裁により,自己査定体制検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を結成した。その担当役員は,B(当時常務)であり,アドバイザーとして,F,C(いずれも当時常務)及びH(事業推進部部長)が加わっていた。(甲23,甲99添付資料1,甲129の44頁)
(イ) 事業推進部による不良債権償却計画の検討状況
事業推進部は,平成8年10月29日付けで,「今後の不良債権処理について」と題する資料(甲24)を作成した。
上記資料によれば,「MOF検査査定結果」として,Ⅱ分類が2兆5324億円(一般先1兆5420億円及び関連親密先9904億円),Ⅲ分類が8960億円(一般先2451億円,住専1369億円及び関連親密先5140億円),Ⅳ分類が2029億円(一般先68億円及び関連親密先1961億円)であるとされ,関連・親密会社の実態不良資産の状況として,「MOF検分類状況」における「関連ノンバンク合計」のⅡ分類7164億円,Ⅲ分類5139億円,Ⅳ分類1961億円であること,他方,実態ベース(「MOF検分類に捕らわれずに現時点において当行として本音ベースで自己査定した場合の分類数字。但し,修正母体方式であるため当行残高が上限」)における関連ノンバンク合計のⅡ分類が3284億円,Ⅲ分類が84
8億円,Ⅳ分類が1兆0608億円であるとされていた。
また,上記資料によれば,関連親密先ノンバンクの不良債権については,修正母体行主義により原告の融資残高を上限とした場合の最終要処理額が1兆4275億円(当面処理額1兆1071億円)に達すること(№4),受皿会社の不良債権について,最終要処理額が2639億円(当面処理額337億円)に達すること(№5),これらの関連親密先の最終処理の合計額が1兆6914億円であること(№5)がそれぞれ指摘されており,これらの関連親密先の不良債権の償却について,原告が平成9年3月から5年の期間で支援(日本リースについては支援の再開を検討)を行うこと,その場合の償却額は,当面処理必要額として1兆0911億円,企業維持ベースとして合計2251億円,一部処理ベースとして合計5045億円,終了宣言
ベースとして1兆0131億円であること(№6)が想定されていた。
さらに,上記資料によれば,大蔵省に提出する予定の不良債権の償却計画(修正後のもの)として,Ⅲ分類7640億円(一般先1654億円及び関連親密先5986億円)及びⅣ分類2045億円(一般先53億円及び関連親密先1992億円)について,当初3年間(平成8年度ないし平成10年度)で,一般先を含む不良債権を5500億円処理することとされており(№9),その具体的な内容(№10)は,平成8年度2521億円(一般先1578億円及び関連親密先943億円),平成9年度1828億円(一般先810億円及び関連親密先1018億円),平成10年度1185億円(一般先254億円及び関連親密先931億円)というものであり,償却計画や実施スケジュールについて,償却財源と自己資本比率(国際統一基準
すなわちBIS基準8パーセント)の維持を考慮し,関連親密先を除く一般先の処理を義務的に行い(「must」),関連親密先の処理については,赤字決算を回避して企業を維持し,不良債権の増加を防止しながら,具体的な償却財源の状況(株価水準と株式含み益)に応じて,3年で一般先を含めて,5492億円から1兆0898億円までの処理をすること(№12)とされていた。
平成8年10月29日,Hは,Fに対し,上記資料に基づき,不良債権の償却計画を説明した。
その後,事業推進部は,同年11月11日付けで,上記資料を多少修正した「今後の不良資産処理について」と題する資料(甲26)を作成し,Hは,同日,Dに対し,上記資料に基づき,原告の不良債権の償却計画を説明した。
なお,これらの資料における「実態ベース」については,その時点における企業の清算価値を前提とした修正母体行主義により算定されたものであり(甲116の171頁),前記ア(イ)の円卓会議における資料の「査定後(最悪ケース)」と同様の趣旨で記載されていた(甲125の102頁)。(甲24ないし甲26,甲114,甲116,甲125,甲169,弁論の全趣旨)
(ウ) 原告内部の自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況等
その後も,原告内部において,自己査定基準及び償却・引当基準が検討され,事業推進部は,平成8年12月11日付けで,「早期是正措置の導入に伴う自己査定制度のあり方」と題する資料(甲27)を作成した。
上記資料によれば,「自己査定基準に係るMOF案の推移」(№2)として,大蔵省が自己査定について統一的なガイドラインの提示をしたが,実際にはガイドラインには具体的な数値基準を盛り込まず各行の裁量部分をある程度認めること,特に関連・親密については一律的な基準を作らず当初は個別行の事情により個別に対応する可能性も大きいことが記載され,次に,「当行の自己査定基準のあり方」(№3)として,関連親密先と一般先の基準を区分することにより関連親密先の要処理分類額の圧縮を最大限図り4パーセント(BIS基準8パーセント)をクリアーすること,Ⅲ分類基準の弾力化及びⅢ分類引当の段階化により償却引当負担の軽減,平準化を図ることとされ,具体的内容として,一般先については,Ⅰ分類(正常先),Ⅱ分
類(要注意先),Ⅲ分類(破綻懸念先),Ⅳ分類(実質破綻先及び破綻先)に分類し,分類に沿って償却・引当(Ⅲ分類は一定割合の償却・引当を行い,Ⅳ分類は全額の償却・引当を行う。)を行うこと(№3,№5),他方,関連親密先は概念的に破綻懸念先と実質破綻先に区別することは可能だが,支援先については合理的再建計画に基づき当行が支援を行うという点において,破綻懸念先と実質破綻先の区別は意味をなさないこと(№4),また,原告の支援先については支援計画における当期支援額(Ⅳ)は償却・引当を行い,翌期以降の支援予定額(Ⅱ)は対象外とされていた。
また,「当行自己査定基準による要処理不良債権額試算」の「関連親密先の自己査定の考え方」(№6)として,支援計画があるエヌイーディーについては,当該年度処理予定額をⅣ分類,次年度以降の処理予定額をⅡ分類と自己査定すること(支援計画で将来当行貸付金償却が明らかなものについてⅢ分類とせずⅡ分類とすることについて合理的な説明が必要),日本リースについては,本業の収益力で不稼働資産を抱えたまま企業維持が可能であり,徐々に(10年程度で)自力処理ができる場合,また含み資産の活用等により自力償却が見込まれる先は非分類とすること,第一ファイナンスについては,債権処理のために設けられたSPC等会社の実態がない先(物件整理以外に存在意義のない先)については,貸付金のロス,繰り欠をⅣ分類
資産の含み損をⅢ分類査定とすること(実態のない会社であり含み損,損失額が確定していないとの理由で説明できるか)が指摘されていた。
さらに,「主要論点別の問題点・課題」(№8,9)として,関連・親密先の別基準化がうまく行くかどうかが当行にとって今回新制度の最大のポイントであること,実質破綻先認定を最大限回避できるような自己査定基準の設定が不可欠であることが指摘され,会計上チェック基準ルールについて監査法人が会計士協会のルールを機械的に当てはめてくることはまずないと思われるがルールの決め方,縛り方如何によってはかなり影響が出てくること,自己査定内容と償却・引当実施額との関係については,ポイントはⅢ分類の償却をどうするかということ,即ちⅢ分類の中でも実態に即していくつかの段階に分けそれぞれ引当率を設定する等分離処理ができるかということ,同様に一般先と関連会社とを区分し,関連会社分については自己査定と
償却・引当との遮断を図ることができることがそれぞれ指摘されていた。
なお,上記資料には,株式会社日本債券信用銀行(以下「日債銀」という。)が大蔵省金融検査部から入手した「関連ノンバンク自己査定統一基準フローチャート」が参考資料3として添付され,同資料には,「系列ノンバンクとは,基本的には関連会社通達上の関連会社で貸金業を営む会社であるが,関連会社に該当しない場合であっても,各金融機関との間に何らかの関係があり,その会社の業況不振に対して,当該金融機関において実質的に責任があるとの経営判断を行い,いわゆる母体行としての支援を実施しているもの,あるいは今後実施しようとしているもの」という指摘がされ,また,フローチャートとして,系列ノンバンクに対する貸出金については,系列ノンバンクの体力について検討し(支援損計上の必要の有無,営業貸付金の
延滞率,債務超過(実質ベース)状態の有無,借入金の延滞又は金利減免・残高維持等の金融支援の有無),体力がある場合には,非分類とし,体力がない場合には,3年以内に不良債権の処理が可能であれば,非分類(単年度処理可能)又はⅡ分類(2,3年以内で処理可能)とし,3年以内に不良債権の処理が不可能であれば,再建計画に問題がない場合は支援損相当額をⅣ分類,その他をⅡ分類とし,再建計画の策定がない場合又は再建計画に問題がある場合は原則営業貸付金の査定結果を自行(庫)の貸出金にⅣ,Ⅲ分類の順に充当し,残額をⅡ分類とすること,なお,有価証券,不動産の含み損益等も勘案することが指摘されていた。(甲27,甲64添付資料3,甲132の47頁)
(エ) 平成8年12月19日常務役員フリーディスカッションにおける不良債権処理の検討状況
原告は,平成8年12月19日,原告の常務以上の役員が出席する「常務役員フリーディスカッション」と呼ぶ会議を開催し,事業推進部作成の同日付け「今後の不良資産処理について」と題する資料(甲169添付資料5)や総合企画部作成の同日付け「今後の決算・資本対策について」と題する資料(甲161添付資料4)に基づき,今後の不良債権の処理計画に関する討議・検討が行われた。
a 事業推進部作成の「今後の不良資産処理について」
上記資料(甲169添付資料5)によれば,MOF検査結果として,関連・親密のⅢ分類5140億円,Ⅳ分類1961億円の要処理合計額は7101億円とされ(№1),実態ベース要処理額として,関連・親密7社(エヌイーディー,日本リース及び第一ファイナンスを含む。)については,総資産8兆0228億円,延滞債権1兆5619億円,同ロス額9909億円,不動産等含み損6153億円,資本勘定1000億円のマイナス,最終要処理額1兆7603億円,当面要処理額7957億円との指摘がされていた。
また,上記資料によれば,平成8年度から平成10年までの3年間の償却計画としては,償却財源と自己資本比率(BIS基準8パーセント)を考慮し,株価に応じて,処理額5642億円,処理額7247億円及び処理額1兆2431億円の3種類の償却計画(№2)があると指摘され,5642億円の償却計画は,関連親密先の黒字決算を維持するため1695億円を処理するが,関連親密先の企業維持は事実上困難であること(担当者は,取引金融機関からの回収圧力により企業維持が困難となるおそれがある旨説明した。),7247億円の償却計画は,関連親密先の企業維持はギリギリ可能であること,1兆2431億円の償却計画は当面の目標レベルであるとされていた(甲169の24枚目,25枚目)。
上記資料における関連親密先の要処理額については,関連親密先が抱える不良債権とその含み損,不動産等含み損等の総額であり,最終的にこれらの会社が処理すべき不良資産であった(甲121の111頁)。
なお,Hは,上記資料を作成させた際,経営陣に危機感を持ってもらうため,前記(ウ)の同年11月11日付け資料よりも厳しい表現にするととともに,償却金額の水増しを指示し,担当者にそのような資料を作成・記載させ,これにより多額の償却財源を要することを原告の経営陣に強く印象づけようとした(甲169の25枚目,26枚目)。(甲121,甲169,弁論の全趣旨)
b 総合企画部作成の「今後の決算・資本対策について」
上記資料(甲161添付資料4)によれば,平成8年度から平成10年度までの不稼働資産処理内訳と正味自己資本比率試算として,以下の試算がなされていた。
まず,MOF検時提出計画における平成8年度から平成9年度の不稼働試算処理見込額は7785億円(Ⅲ5590億円,Ⅳ2045億円,買取二次損失分150億円+一般分非Ⅲ・Ⅳ分類追加処理必要額である「非」150億円),そのうち一般分は2583億円(Ⅲ2348億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),関連先は5202億円(Ⅲ3242億円,Ⅳ1960億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.60パーセント(含ファイナンス)又は4.17パーセント(除ファイナンス)であった。
「示達回答書計画」における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は5534億円(Ⅲ3480億円,Ⅳ1904億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),関連先は2892億円(Ⅲ1073億円,Ⅳ1819億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.10パーセント(含ファイナンス)又は3.65パーセント(除ファイナンス)であった。
関連親密企業維持ベース(株価2万3000円程度を想定)における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は7247億円(Ⅲ3747億円,Ⅳ2045億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),一般分(非分類追加分)は1305億円,関連先は3300億円(Ⅲ1340億円,Ⅳ1960億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.21パーセント(含ファイナンス)又は3.78パーセント(除ファイナンス)であった。
現実処理可能ベース(株価2万2000円程度を想定)における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は5642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ1780億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),一般分(非分類追加分)は1305億円,「関連先」は1695億円(Ⅳ1695億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,3.70パーセント(含ファイナンス)又は3.25パーセント(除ファイナンス)であった。
また,検討すべき対応策として,早期是正措置に向けて,不稼働資産を3年間で5500億円処理し,ファイナンス(増資)により1000億円を調達し,株式含み益3000億円を維持することを従前の認識としたうえで,追加的対応策として,ファイナンスの必達額は1000億円から1300億円であり,リスクアセットの1兆円から1.7兆円(3年間)の圧縮,収益積上(体質改善計画見直し)及び不動産の活用(本店売却益の計上)が必要であることが指摘されていた。なお,上記検討においては,最終的な結論は出されず,今後の株価の推移をみて,再検討することとされた(甲161の18頁)。(甲116,甲121,甲161,弁論の全趣旨)
(オ) 平成9年2月7日常務役員連絡会資料
総合企画部は,平成9年2月7日付けで,「今後の当行業務運営の基本的方向」と題する常務役員連絡会資料を作成し,同日開催された常務役員連絡会において,その説明を行った。
上記資料によれば,前提となる環境認識として,新規発生見込みを含めた今後の不良債権要処理額見込は最低7000億円から1兆円レベルで,かつ早期是正措置により平成9年度以降Ⅲ,Ⅳ分類資産は単年度での適正な償却・引当の実施が不可避であると指摘されていた。(甲28,乙100)
(カ) 平成9年2月14日常務会資料
検討チームは,平成9年2月14日付けで,「早期是正措置に係る資産自己査定について(MOF検討会での中間とりまとめを受けた中間報告)」と題する資料(甲99添付資料2)を作成し,同日開催された常務会において,この資料に基づく報告を行った。
上記資料によれば,早期是正措置発動に当たっては,自己資本比率(国際統一基準)を指標とすること,各金融機関は,自己の責任において適正な償却・引当を実施し,資産内容の実態を客観的に反映した財務諸表に基づき自己資本比率を算出すること,したがって,資産の自己査定は,適正な償却・引当の準備作業として重要な役割と位置付けることが指摘されていた(1枚目)。
上記資料によれば,「自己査定における課題と今後の検討ポイント」(4枚目)として,本番の平成10年3月期のBIS基準8パーセントクリアに向けて,当行自己査定基準および償却・引当のルール作成に当たっては,(ア)自己査定基準は一般先と関連親密先を区分して作成する。MOFガイドラインでは関連ノンバンクの記載なし,(イ)Ⅲ,Ⅳ分類基準に的を絞った検討。Ⅲ,Ⅳ分類の相当を占める関連親密先について,査定基準を慎重に作成,(ウ)Ⅲ分類の償却引当率の段階適用。個々の債権の回収可能性に着目して段階的(上限50パーセント)な引当率の設定を検討するとの指摘がされ,また,Ⅲ,Ⅳ分類の相当を占める関係会社については一般先と異なる基準を慎重に作成し,具体的にはMOF事務方において検討していたと思われる関
連ノンバンクの査定基準を参考にして,①支援損計上・金融支援の有無,②営業貸付金の延滞率,③実質面での債務超過状況,④不良債権処理に要する期間,⑤再建計画の有無等に着目してきめ細かな分類を行う方式を検討する旨の指摘がされていた。
さらに,償却・引当基準として,「Ⅳ分類の100パーセント償却・引当は当然で,Ⅲ分類の引当水準の設定がポイントであり」,具体的には,行政指導としての現行一律50パーセント引当を変更して,例えば15パーセントないし50パーセントと幅を持たせ,実体面と個別性を強調して個々の債権の回収可能性により引当率を決定する方式を検討するとの指摘がされていた。(甲99添付資料2,乙108)
(キ) 平成9年3月10日常務会資料
総合企画部は,平成9年3月10日付けで,「当面の業務運営の考え方と中期的展望~ビックバンへの戦略的対応~」と題する常務会資料(甲161添付資料10)を作成し,同日開催された常務会において,報告を行った。
上記資料によれば,早期是正措置への対応として,資産の自己査定による適正な償却・引当により不稼働処理を単年度実施するものとし(平成9年度見込み最小限3000億円),これを平成9年度決算に反映して自己資本比率(BIS基準)8パーセントを達成する必要があること,また,資産圧縮額とその資産圧縮計画として,平成11年度までに,貸出資産2兆5000億円の圧縮(平成8年度7500億円,平成9年度から平成11年度まで1兆7500億円),政策株式1兆円の売却及び不稼働資産1兆円の処理(平成8年度3000億円,平成9年度から平成11年度までの3年間で7000億円処理)により,4兆5000億円の資産圧縮が実施されることが指摘されていた。
なお,上記不良債権処理のうち,償却処理は,7000億円(平成8年度2000億円,平成9年度から平成11年度までの3年間5000億円)が予定されていた。(甲116の16頁,17頁,甲121の43頁,甲161添付資料10)。
(4) 資産査定通達の発出,全銀協Q&Aの送付,4号実務指針の公表,9年事務連絡の発出及び全銀協追加Q&Aの送付
ア 資産査定通達の発出
(ア) 資産査定通達の発出・内容
大蔵省金融検査部長は,資産査定通達を発出し,債務者区分を5段階で区分し,これを前提に担保等による回収可能性も考慮して,債務者ごとに貸出金をⅠないしⅣの4分類とするとしていたが, 同通達によれば,金融検査においては,従来から,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から,その保有する資産について,個々の資産を回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分し,査定を行っていること,一方,平成10年4月1日より,金融機関経営の健全性を確保していくための新しい監督手法である早期是正措置制度が導入されることとなるが,同制度は,金融機関が,企業会計原則等に基づき,自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸
表を作成することを前提としたものであること,金融機関が行う自己査定は,金融機関が適正な償却・引当を行うための準備作業として重要な役割を果たすこととなり,また,会計監査人は,財務諸表監査に際し,金融機関が行う自己査定等内部統制の状況についてもその有効性を評価することになること,金融検査における資産査定においては,通常,このようにして行われた金融機関の自己査定及び会計監査人による監査を前提とし,自己査定結果の正確性等をチェックすることとなることが指摘されていた。
また,資産査定通達によれば,早期是正措置検討会における検討を踏まえ,早期是正措置導入後の金融検査における資産査定が金融機関による自己査定等を前提としてより適切かつ統一的に行い得るよう,これまでの金融機関における資産査定の実務をもとに,改めて「資産査定について」を作成したので通知すること,検査に際しては,検査直前決算期(中間決算を含む。)等において金融機関が行う自己査定について,その基準が明確かどうか,またその枠組みが「資産査定について」の枠組みに沿っているかどうか等を把握し,金融機関の自己査定基準の枠組みが独自のものである場合には,「資産査定について」の枠組みとの関係を明瞭に把握するとともに,金融機関の自己査定基準の中の個別ルール(例えば,担保評価ルールや有価証券の
簡易な査定ルールなど)が合理的に説明できるものであるかどうか等をチェックすることとなることが指摘されていた。
さらに,上記「資産査定について」の中で,貸出金の査定に当たっては,その回収の危険性の度合に応じて,債務者の返済能力(財務状況,資金繰り,収益力等)を判定し,債務者の区分を行い,資金使途等の内容を個別に検討し,さらには担保や保証等の状況を勘案のうえ,貸出金の査定(資産分類)を行うこととされていた。
すなわち,債務者を「正常先」,「要注意先」,「破綻懸念先」,「実質破綻先」及び「破綻先」に区分して,この債務者区分に応じて,「正常先」に対する貸出金については,原則非分類とし,「要注意先」に対する貸出金のうち,一定の類型のもの(不渡手形,融通手形及び期日決済に懸念のある割引手形,赤字・焦付債権等の補填資金,業況不良の関係会社に対する支援や旧債肩代わり資金等,金利減免・棚上げあるいは元本の返済猶予など貸出条件の大幅な軽減を行っている貸出金等貸出条件に問題のある貸出金,元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題のある貸出金及び今後問題を生ずる可能性が高いと認められる貸出金,債務者の財務内容等の状況から回収について通常を上回る危険性があると認められる貸
出金)で,優良担保(預金等〔預金,掛け金,元本保証のある金銭の信託,満期返戻金のある保険をいう。以下同じ。〕,国債等の信用度の高い有価証券及び決済確実な商業手形等をいう。)の処分可能見込額(担保評価額を踏まえ,当該担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額をいう。)及び優良保証等(公的信用保証機関,金融機関及び金融機関が設立した信用保証会社等の保証,地方公共団体の損失補償契約等保証履行の確実性が高い保証(ただし,保証機関等の状況,手続不備等の事情から代位弁済が疑問視される場合及び自行(庫・組)が履行請求の意思がない場合を除く。),証券取引所上場の有配会社で,かつ保証者が十分な保証能力を有し,正式な保証契約による一般事業会社の保証,住宅金融公庫の「住宅融資保険」などの公的保険
のほか,民間保険会社の住宅ローン保証保険」などの保険等という。)により保全措置が講じられていない部分を原則Ⅱ分類とし,「破綻懸念先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分をⅡ分類,それ以外の部分をⅢ分類とし,「実質破綻先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分を原則Ⅱ分類,優良担保及び一般担保の評価額と処分可能見込額との差額及び保証による回収見込みが不確実な部分をⅢ分類,これ以外の回収の見込み
がない部分をⅣ分類とし,「破綻先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分並びに清算配当等が見込まれる部分をⅡ分類,優良担保及び一般担保の評価額と処分可能見込額との差額及び保証による回収見込みが不確実な部分をⅢ分類,これ以外の回収の見込みがない部分をⅣ分類とするとされていた。
(イ) 資産査定通達に関する説明等
大蔵省は,資産査定通達を発出した際に,これは各金融証券検査官がマニュアルにより検査を統一的に行い得るよう改めて作成したものであるが,各金融機関が行う自己査定について,共通の考え方を確保することに資するとして,全銀協等の関係金融団体を介して,その内容を各金融機関に公表し,また,金融雑誌において,大蔵省大臣官房企画官等が,その概要を説明した(乙20の29頁)。
上記通達を発出した当時の大蔵省金融検査部長O(以下「O金融検査部長」という。)は,金融雑誌の取材を受けて,「資産査定について」の原案に対するもっと詳細な当局基準が明らかにならないと,準備作業に入れないとの指摘もあったという点について,各金融機関の資産内容は規模,地域性,業種,時期などにより様々で,一律に適用できる詳細な査定基準を作成するのが難しいこと,自己査定の意義が金融機関における自己責任の徹底と信用リスク管理能力の向上にあり,各金融機関が,自らの実情に沿った詳細な基準を創意工夫により自主的に作成することが望ましいこと,検査官用のマニュアルとして検査における資産査定の統一を図ることを一義的な目的とする「資産査定について」を公表したのは,各金融機関が作成する自己査定
基準の基本的考え方についての「適度の統一性」の確保に資すると期待したことを説明した。また,自己査定の導入によって金融検査はどう変わるかという質問に対しては,金融検査の内容が大きく変わること,検査の基本的なチェックポイントは,例えば金融機関は自己査定基準を明定しているか,自己査定基準の枠組みが「資産査定について」のそれに沿ったものであるか,より詳細な資産区分概念などを持つなど独自色が強い基準を作成している場合には,「資産査定について」の枠組みとの関係を合理的かつ明確に説明できるかどうか,自己査定の体制がどうか,自己査定基準に沿って適切な自己査定が実施されているかどうか等であることを説明した。さらに,「資産査定について」で公表された分類方法は,従来の検査におけるそれと同一なのかと
いう質問については,基本的には変わらないこと,ただ,対外的に金融証券検査官用の資産査定マニュアルを公表したのは初めてのことであり,その理由が適度の統一性の確保と検査の透明性の向上にあることを説明した。また,自己査定体制が適正なものであるかどうかをチェックするため,平成10年4月以後早い段階で短期間のうちに全金融機関に対する検査が必要ではないかという質問に対しては,短期間に全金融機関に対して検査を実施するのは現実問題として難しく,過去の検査等を通じておおよそ把握している状況に応じて検査時期を計画したり,早期是正措置の導入までの間においても,各金融機関の体制整備状況等について把握するよう努めていきたいことを述べていた(乙21)。(甲1,乙20,乙21,乙119)
イ 全銀協Q&Aの作成,送付
全銀協の融資業務専門委員会は,傘下の銀行の融資担当部長に宛てて,全銀協Q&Aを送付したが,その中では,資産査定通達において定められた債務者区分,資産分類や担保等に関する解釈や具体的な適用事例が示されていた。
また,上記文書には,現時点での情勢を前提とした資産査定に係る一般的な考え方をまとめたものであり,将来にわたって固定されたものではなく,また個別金融機関の有する特殊性・地域性等は考慮されていない旨の指摘がなされていた。(甲2)
ウ 4号実務指針の作成,公表
その後,会計士協会は,平成9年4月15日付けで,4号実務指針を作成し公表した。なお,その際,公表方法はJICPAジャーナルにおける記者会見の方法によること,公表者名を会計士協会とすること,解説は特にせず,また,審議決定後の関係諸団体との調整は必要ないこととされていた(甲98添付資料2)。
4号実務指針によれば,早期是正措置の導入に伴い,銀行等金融機関(銀行のほか,信用金庫などの協同組織金融機関等を含む。以下同じ。)は,自ら資産の査定基準を定めて,その有する資産を検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に応じて分類区分すること(以下「自己査定」という。)が必要になったこと,自己査定は,貸倒償却及び貸倒引当金の適正な計上に資するものであること,銀行等金融機関は,自己査定基準を定めて,それに準拠して適正な自己査定が可能となるような内部統制を構築することが求められること,監査人は,貸倒償却及び貸倒引当金の監査を実施する際,自己査定基準が適正に整備され,自己査定の作業がその基準に準拠して実施されていることを確かめなければならないこと,監査人は,銀
行等金融機関の自己査定に係る内部統制が整備され,適切に運用されていることを確かめる必要があり,また,誤びゅう等の額が銀行等金融機関の自己資本比率に与える影響を十分考慮して監査上の危険性の許容水準を決定する必要があることなどから,より深度のある監査に努めることが求められることが指摘されていた。
また,内部統制の有効性の評価に当たっての留意事項として,銀行等金融機関は,それぞれ体系的な自己査定基準を作成することとされていることから,自己査定基準が文書化され,正式の行内手続を経て規程化されているか確かめること,自己査定基準に示す査定分類は,「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」(蔵検104号平成9年3月5日)の別添「資産査定について」と同一である必要はなく,より細かい分類であってもよいが,「資産査定について」の分類に整合し,分類の対応関係が確保されていることを確かめる必要があること,銀行等金融機関は,それぞれ,具体的かつ詳細な貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する規程を作成することとされていることから,当該規程が文書化され,正式の行内手続を経
て規程化されているか確かめ,また,当該規程は,本報告「6.貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱い」に整合し,かつ,それぞれの自己査定基準とも適切な連動が保たれているか確かめることが指摘されていた。
また,監査手続の適用については,査定の結果について,特に分類債権については,最終判断についての説明が付されており,判断と説明が整合しているかを確かめること,自己査定制度導入後の会計監査において,検査当局の検査結果は,監査上の参考として常に注意を払う必要があるが,検査時点の相違や頻度の相違等の理由から,当局の検査結果をそのまま監査判断の基礎として利用すれば足りるとはいえないことに留意する必要があること,監査人は,必要に応じて,銀行等の金融機関の了解のもとに,検査当局と可能な範囲内で直接情報交換を行うことが監査の効率化の観点から適当であることが指摘されていた。
さらに,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いとして,以下の監査上の取扱いに準拠して計上されている場合には,監査上妥当なものとして取り扱うことが示され,その準拠すべき監査上の取扱いとして,「正常先債権」,「要注意先債権」,「破綻懸念先債権」,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」のそれぞれの債権に区分すること,「正常先債権」及び「要注意先債権」については,債権額で貸借対照表に計上し,貸倒実績率に基づき貸倒引当金を計上すること,「破綻懸念先債権」については,債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し,残額のうち必要額を貸借対照表に貸倒引当金として計上すること,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」については,債権額から担保の処分
可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し,残額を貸倒償却するか又は貸倒引当金として貸借対照表に計上することとされ,また,貸倒実績率は正常先債権や要注意債権という分類毎の貸倒実績率によること,貸倒実績率の算定方法は種々考えられるが,その一例として,ある期間の期首(仮に3年間の推移でみる場合,該当する3年間を一つの期間とみた場合の期首)の該当する分類の債権残高を分母とし,その分母の額のうち期間内に毀損した額(貸倒償却及び貸倒引当金として計上した額の他,債権売却損等の損失額を含む)を分子として計算する方法があることとされていた。
なお,4号実務指針の適用される時期については,平成9年4月1日以降開始する事業年度に係る監査から適用するが,平成9年9月30日に終了する中間会計期間において銀行等金融機関が自己査定に係る内部統制を構築し,その旨を表明した場合には,当該中間会計期間に係る監査から適用するものとされていた。(甲3,甲60,甲98,甲159,乙119)
エ 9年事務連絡と全銀協追加Q&A
大蔵省は,金融証券検査官等に宛てて,平成9年4月21日付けで,9年事務連絡を発出した。
9年事務連絡によれば,その発出経緯については,関連ノンバンクに対する貸出金について,当面の方針として,当該貸出金の分類額が直ちに引当・償却に結びつけられるか否かは別にして,いわゆる母体行主義を前提とし,将来の親金融機関等の経営に与える影響等を総合的に把握することに重点を置き,査定を行っているが,最近においては,必ずしも母体行主義が貫徹されない例も散見され,さらに,平成10年4月から早期是正措置制度が導入されることに伴い,4号実務指針が公表され,この中では資産査定と企業会計における償却・引当とを極めて密接に関連づけていること等の状況の変化を踏まえ,改めて関連ノンバンクに対する貸出金の査定の在り方についてとりまとめられたものであるとされていた。
そして,金融機関等の関連ノンバンクの査定の基本的考え方として,関連ノンバンクに対する貸出金については,関連ノンバンクの体力の有無,親金融機関等の再建意思の有無,関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無(又はその進捗状況)等を総合的に勘案し査定すること,関連ノンバンクの体力の有無については,当該ノンバンクの資産状況,収益状況により判断し,具体的には,営業貸付金の査定結果や有価証券及び不動産等の含み損益の状況等を通じ把握した当該ノンバンクの資産の状況が実質債務超過であるかどうか,実質債務超過の場合には当該ノンバンクの償却前利益により概ね2年ないし3年で当該債務超過を解消できるかどうかを体力の有無の判断の一応の目安とすること,具体的な査定方法等としては,実質債務超過でない場合
,又は償却前利益により概ね2年から3年で実質債務超過の解消が可能であるなど自力再建ができる関連ノンバンク(いわゆる体力がある関連ノンバンク)に対する貸出金については,一般債務者に対する貸出金と同様に査定すること,概ね2年ないし3年で実質債務超過が解消できない関連ノンバンク(いわゆる体力がない関連ノンバンク)に対する貸出金については,実質債務超過の状況,親金融機関等の再建意思の有無,関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無(又はその進捗状況)等を総合的に勘案し査定することとされていた。
また,体力がない関連ノンバンクについては,(1)親金融機関等がいわゆる母体行責任を負う意思がない場合を前提として,①親金融機関等が関連ノンバンクを再建する意思がなく,かつ,いわゆる母体行責任を負う意思がない場合には,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建の見通しがない場合には,親金融機関等の当該ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果を親金融機関等の貸出金のシェアにより分類する(いわゆるプロラタ方式による分類)こと,②親金融機関等が関連ノンバンクを再建する意思はないが親金融機関等の貸出金額の範囲内において損失負担(プロラタ方式以上かつ貸出金全額以下)する意思がある場合において,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超
過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建の見通しがない場合には,親金融機関の当該ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とする。なお,経営の意思により債権放棄額が当該年度に確定しており,当該額が上記貸出金のシェアにより算定したⅣ分類額を上回る場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅢ分類とすることとされ,これに対し,(2)親金融機関等がいわゆる母体行責任を負う意思がある場合を前提として,①再建計画が作成されている場合において,再建計画に合理性がないと認められる場合には,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建計画に合理性がなく再建の見通しがない場合には,親金融機関
等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすること,①’再建計画が作成されている場合において,その他の場合には,親金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,全額をⅢ分類とする(ただし,この場合のⅢ分類の額は,当該ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類とⅢ分類の合計額を限度とすることができる)こと,なお,再建計画に沿って経営の意思により債権放棄額が当該年度に確定している場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅢ分類とする(経営の意思による債権放棄を当該年度に一括して行う場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅡ分類とすることができる)こと,②再建計画が作成されていないか又は検討中の場合に
おいて,関連ノンバンクの再建可能性が十分あると認められる場合には,原則として,親金融機関等の当該ノンバンクに対する貸出金の全額をⅢ分類とする(ただし,この場合のⅢ分類の額は,当該ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類とⅢ分類の合計額を限度とすることができる)こと,これ以外の場合は,親金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすることが示されていた。
その後,全銀協は,9年事務連絡の考え方に従い,全銀協追加Q&Aを作成し,同年7月11日ころ,傘下の銀行にこれを送付した。その中で,上記関連ノンバンクの体力の有無や査定方法の基準等が示され,またその点に関するフローチャートが添付されていた。(甲4,乙111)
(5) 平成9年度上期における原告の自己査定基準及び償却・引当基準の検討・策定状況,同上期における決算の検討状況等
ア 事業推進部における自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況,総合企画部における決算に関する検討状況等
(ア) 事業推進部作成の「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」
事業推進部は,平成9年5月9日付けで,「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」と題する資料(甲61添付資料2)を作成し,この資料に基づき,D,E,F,G及びHらに対し,検討チームの最終答申案について説明した。その際,事業推進部の担当者は,債務者区分については,大蔵省金融検査部原案等についても説明した(甲61の2枚目,甲99の18頁)。
上記資料は,後記イの常務会資料とほぼ同内容であったが,「当行案による自己査定見込額と前回MOF分類」(№14)と「早期是正措置対策」(№20)の点が付加されていた。
上記資料によれば,まず,「当行案による自己査定見込額と前回MOF分類」について,支援予定分(翌期以降の支援額)をⅢ分類とした場合,Ⅱ分類が9723億円となり,Ⅲ分類3969億円及びⅣ分類1872億円の合計額が5841億円となること,支援予定分(翌期以降の支援額)をⅡ分類とした場合,Ⅱ分類が1兆3488億円となり,Ⅲ分類204億円及びⅣ分類1872億円の合計額が2076億円となることが指摘され,また,参考として,前回MOF検によるⅡ分類が1兆0797億円であり,Ⅲ分類5140億円及びⅣ分類1961億円の合計額が7101億円であること(№14)が指摘されていた。
また,「早期是正措置対策」(№20)について,関連親密先の自己査定は「日本リースの扱い等無理をしているところがあること,償却・引当も引当率の考え方が会計士と相当議論になることは必至である」こと,会計士は,従来の会計監査との整合性から,大幅な査定や償却を要求することはないと思われるが,会計士協会の動向,他の銀行での状況等により会計士のスタンスが振れて全体として査定額,償却・引当額も増える可能性があること,時間をかけて処理すること(3か年による処理)に会計士の理解が得られる場合と得られない場合とに分けて,理解を得られる場合において各関連親密先の処理に関する合理的説明を準備すること,理解を得られない場合において前倒処理と自己査定・引当額の圧縮を図ることとされていた。(甲2
9の1及び2,甲61,甲99,甲103,甲105)
(イ) 総合企画部作成の「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」
総合企画部は,平成9年5月9日付けで,「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料(甲30)を作成し,これに基づき,D,F,G及びHらに対し,前記(ア)の事業推進部の説明と同じ機会に,決算等に関する説明を行った。
上記資料によれば,検討のポイントとして,早期是正措置をクリアし得る「不稼働処理必要額」の見極めとBIS比率8パーセント割れを回避しつつ,「必要不稼働処理」を可能とするリスクアセット,決算運営が挙げられ(1頁),「決算・BIS運営」として,同年9月期にリスクアセット21兆円を達成し,償却財源となるべき株式含み益がない(株価1万8000円)前提で,中期計画における不稼働資産の3000億円を償却した場合におけるBIS比率について試算し(2頁),また,日経平均株価の動向による不稼働資産の処理可能見込額を試算(株価が1万6500円から2万2000円までの場合において,1500億円から7000億円までの段階において不稼働資産の処理が可能)し,不動産売却益(1000億円)による償
却財源の状況が記載され(3頁),最終的に,償却・引当見込額(4598億円)と処理計画額(3454億円)がリンクしておらず,平成9年度処理額見込みとの調整が必要であること,支援対象である関連親密先(エヌイーディーほか2社)の償却・引当の必要額とその他の関連親密先のうち破綻懸念先及び破綻先の取扱いがポイントとなること(4頁)が指摘されていた。(甲30,甲64,甲99,乙108)
イ 常務会における原告の自己査定基準及び償却・引当基準の承認
D,E,F,C及びBは,平成9年5月23日開催の常務会において,検討チームの最終答申である同日付け検討チーム作成の「早期是正措置への対応について」と題する常務会資料(甲31の2)に基づき,原告の自己査定基準及び償却・引当基準について報告を受け,その内容を了承した。
上記資料の内容は,前記ア(ア)の事業推進部作成の資料とほぼ同内容であり,前記ア(ア)の「当行案による自己査定見込額」と「早期是正措置対策」の記載は除外されていた。
上記資料によれば,まず,「早期是正措置への対応の基本的考え方」(№1)として,各金融機関が自らの責任において自主的に定めた基準で適正に自己査定を実施すること,その結果に基づき,企業会計原則等に基づき自らの責任で適正な償却・引当を実施することが基本原則であり,そのための具体的基準について,MOF金融検査部のガイドラインで示された債務者区分等と平成9年4月(予定)の会計士協会のガイドラインで示される償却・引当の考え方は,いずれも定性的な内容であり,具体的基準の細目は,これらのガイドラインの趣旨に沿って別途個別に策定すること,具体的には,一般先自己査定基準,関連親密先自己査定基準及び国企所管先自己査定基準とこれらの基準ごとの各償却・引当基準を策定することが指摘されていた。
次に,「関連・親密先自己査定基準」(№9)として,MOFの考え方について,MOFガイドラインにおいては関連ノンバンクについて特に何の記載もないことからすると原則各金融機関の判断で自由に決められるという建前であるが,実態的には影響の大きさから敢えて決めなかったというのが真実に近いと考えられること,原告の基本認識について,「前回MOF検における関連・親密先のⅢ,Ⅳ分類は合計で7100億円と全体(除住専)の約74パーセントを占めており,これへの対応如何が今回の自己査定さらには早期是正措置対応の最大のポイントといえるから合理的説明が可能な範囲で最大限の圧縮が必要であること,一般先と関連・親密先とは別基準とすること,前回MOF検査結果については最大限尊重するが,当行の合理的基準
を優先すること,MOF金融検査部原案の考え方については極力取り込むこととするが,これを機械的に適用せず統一的基準で自己査定すること,償却・引当についても一般先と関連会社を区分し,当行の合理的基準によることとされていた。
また,「当行自己査定基準(案)」(№10)として,債務者区分のうち,「要注意先」及び「破綻懸念先」の区分については,残存不良債権の処理期間は,大蔵省金融検査部原案の3年ではなく,5年を基準とすること(国税の支援終了認定の目安),「実質破綻先」及び「破綻先」の区分については,原告の関連ノンバンクが法的に破綻することはなく,実質破綻先と破綻先との区別がつきにくいため,最終的に原告の支援の対象先かどうかで区分することが指摘され,「関連・親密先償却・引当基準」(№12)として,会計士協会,MOFの考え方について,いずれも関連親密先の償却・引当基準に関する具体的規定・考え方がないこと,当行の考え方について,関連親密先は一般先のように突然破綻するという偶発損失リスクは全くなく,当
行が完全にコントロールしている以上形式的には同一の債務者区分にあっても一般先とは異なる償却・引当基準を適用すること,具体的には,支援の有無等の実態に応じて個々に適切な償却・引当をすること(正常先及び要注意先は個別の償却の対象外とするが,破綻懸念先,実質破綻先及び破綻先については,当期支援予定額全額をⅣ分類として全額償却し,Ⅲ分類は,債務者区分に応じて12.5パーセントから50パーセントまでの引当を実施すること)が指摘されていた。(甲31の1及び2,甲99)
ウ 平成9年6月時点における中間決算に関する検討状況
D,E,F及びHは,平成9年6月12日,総合企画部作成の同日付け「97/上期決算運営について」と題する資料(甲162資料1)に基づき,同年度の中間決算に関する説明を受けた。
上記資料によれば,中間決算は黒字を維持すること,不稼働資産1000億円を処理すること,処理の財源として業務純益(使用可能額500億円)及び株式含み益の実現分又は不動産売却益(500億円)が考えられ,株価の状況により株式含み益が減少した場合(株価1万8000円台で株式損益が500億円程度の赤字)には,本店等の不動産売却益(500億円から1000億円程度)により不稼働資産処理の財源を賄うことが指摘されていた。(甲99,甲162,乙100)
エ 平成9年7月ころにおける事業推進部の関連親密先に対する自己査定基準の検討及び策定の状況
(ア) 自己査定試行(トライアル)用の基準
事業推進部は,原告の関連親密先に対する貸出金の査定基準として関連ノンバンクに係る自己査定(トライアル)運用規則(以下「トライアル運用規則」という。)及び当行経営支援先及び特定関連親密先自己査定(トライアル)運用細則(以下「トライアル運用細則」という。)を策定し,その後いくつか改訂して,平成9年7月10日には最終的な内容を決定した。
まず,基本的な趣旨・内容として,トライアル運用細則及びトライアル運用規則は,同年6月末を基準日とする自己査定試行(トライアル)を実施するに当たり,関連親密先に関する基準を定めるものであること,関連親密先や経営支援先について,通常の一般債務者と同様の基準で債務者区分・資産査定を行うことは適当ではなく,自己査定の趣旨を反映しつつ,対象先の特殊性を加味した査定基準を定めるものであること,経営支援先について,原告の支援が必要であり,同時に原告の支援がある前提では企業維持に懸念がなく,通常の債務者区分をあてはめることが適当ではないため,債務者区分を行わないこと,経営支援先に対する与信は企業維持が前提であり,原則Ⅱ分類とすること,ただ,当該年度の経営支援損については損失が明らか
であり,Ⅳ分類と査定することが定められていた(甲5の1)。
次に,トライアル運用規則において,関連ノンバンク(エヌイーディーが想定されていた。甲5の2「関連親密先自己査定フローチャート」参照)について,2,3年で実質債務超過額の解消が不可能であり,原告が母体行責任を負う意思があり,再建計画に客観的な合理性が認められる場合には,当期支援分をⅣ分類とし,支援予定残額をⅢ分類とし,それを超える部分をⅡ分類とすること(甲5の2の2頁,甲62の9枚目),再建計画が作成されていない場合(第一ファイナンスが想定されていた。甲5の2「関連親密先自己査定フローチャート」参照)には,与信先の営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金の割合(シェア)に応じてⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすること(甲5の2の2頁,甲62の6枚目)が定められており,また,ト
ライアル運用細則において,全銀協追加Q&Aにはないが,経営支援先,経営支援実績先及び関連親密特定先の債務者区分を設けて日本リースを経営支援実績先として全額Ⅱ分類とすること(甲62の7枚目,甲64の30頁,32頁),関連親密特定先について債務者区分に応じて正常先又は要注意先とし(甲62の6枚目),資産分類について担保相当分を非分類とし,その他をⅡ分類とすること,関連ノンバンクの関係会社を関連ノンバンク本体と一体であるとして同一の区分とすることが定められた(甲62の6枚目)。(甲5の1ないし3,甲62)
(イ) 被告らに対する説明状況等
FとHは,平成9年8月6日,事業推進部作成の同日付け「自己査定トライアル結果と平成9年度不良債権償却計画」と題する資料(甲62添付資料4)に基づき,同年6月を基準とする自己査定(トライアル)作業結果に関する報告を受けたが,その際,事業推進部の担当者から,関連親密先のⅢ分類の資産の引当について,さくら銀行が引当をしない方針を採っているとの説明があり,事業推進部においてこれに合わせて同様の方針を採ることとされた(甲62の16頁)。
なお,これらの基準は,株式会社日本興業銀行(以下「興銀」という。)の基準やさくら銀行の基準,さらには住友信託銀行株式会社(以下「住友信託」という。)の基準を参考とし(甲62の10頁,15頁,甲64の17頁,18頁,53頁,乙101の6頁,乙102,乙103),また大蔵省において原案が作成された「自己査定統一基準フローチャート」(甲27添付参考資料3)に基づき作成されていたが,その内容について相当自主裁量性が強く,公認会計士に認められない可能性もあること(甲62の11枚目)が指摘されていた。(甲62,甲64,乙101ないし乙103,弁論の全趣旨)
(6) 不良債権償却証明制度の廃止,改正後決算経理基準,早期是正措置の内容
ア 不良債権償却証明制度の廃止等
大蔵省は,平成9年6月には,不良債権償却証明制度を廃止するとの方針と,また自己査定結果を償却・引当に正しく反映するよう決算経理基準を改正するとともに,償却・引当が商法・企業会計原則に基づき行われるよう当局への有税償却の届出を廃止するとの方針を示し,同年7月4日蔵検第296号通達により,不良債権償却証明制度を廃する通達を発出した。(甲57,甲58,乙24)
イ 改正後決算経理基準の導入とその内容等
(ア) 改正後決算経理基準の導入
大蔵省銀行局長は,原告を含む各銀行の代表取締役頭取に宛てた通達により,改正前決算経理基準の中の貸出金の償却及び貸倒引当金の規定を改定し,これにより,平成10年3月期から改正後決算経理基準が適用されることになった。
(イ) 改正後決算経理基準の内容と貸出金の償却・引当に関する改正
前記(ア)の通達によれば,経営管理の項目には,新たに「資産の自己査定のあり方」として,銀行は預金者等から受け入れた資金を貸出金等の資産により運用しており,自らの資産内容の健全性を的確に把握することは銀行の責務であること,したがって,各行においては,商法,企業会計原則等及び第5に定める決算経理基準をも勘案し自己査定基準を作成し,各決算期(中間決算期を含む。)において,当該基準に基づき自らの資産を検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の度合に応じて分類区分することが必要であること,銀行による自己査定の体制は,基本的には銀行が自らの責任において定められるべきものであるが,当局として望まれる自己査定のあり方については「(別紙)資産の自己査定のあり方について」のとおりである
ので留意する必要があることが新たに設けられた。
また,資産査定通達の発出に伴い,改正前決算経理基準の経理処理の原則について,資産の評価は,自己査定結果を踏まえ,商法,企業会計原則等及び下記に定める方法に基づき各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施するものとすると改正し,また,貸出金の償却及び貸倒引当金についても改正し ,貸出金及び貸出金に準ずるその他の債権(以下「貸出金等」という。)の評価は次のような公正・妥当と認められる方法によるものとすることとして,(イ)貸出金等の償却について,回収不能と判定される貸出金等については,債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額(以下「回収不能額」という。)を償却する,(ロ)債権償却特別勘定への繰入れは,回収不能と判定される貸出
金等のうち上記(イ)により償却するもの以外の貸出金等については回収不能額を,最終の回収に重大な懸念があり損失発生が見込まれる貸出金等については債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額のうち必要額を,それぞれ繰り入れるものとすること,貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定(租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。以下同じ。)を除く。)は,貸出金等のうち上記(イ)により償却するもの及び上記(ロ)により債権特別勘定へ繰り入れるもの以外の貸出金等について,合理的な方法により算出された貸倒実績比率に基づき算定した貸倒見込額を繰り入れるものとすることと改正され,また各行が定める償却基準により償却するとするものが,少なくとも税
法で容認される限度額は必ず償却するものとすることと改正された。(甲59,甲183,甲231,乙23,乙81,乙118ないし乙120,弁論の全趣旨)
ウ 早期是正措置の内容
平成9年7月31日には,長期信用銀行法17条において準用される銀行法26条等の規定に基づき,長期信用銀行施行規則の改正(同日号外大蔵省令第61号)が行われた。
その内容(長期信用銀行法施行規則20条の2,3)については,原告のような海外拠点を有する長期信用銀行において国際統一基準に係る自己資本比率(いわゆるBIS比率)が用いられ,早期是正措置発動の基準及び措置の内容として,大蔵大臣は,自己資本比率が4パーセント以上8パーセント未満となれば,経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令を,同比率が0パーセント以上4パーセント未満となれば,自己資本の充実に資する措置に係る命令を,同比率が0パーセント未満となれば,業務の全部又は一部の停止の命令をそれぞれ発することができると規定されていた。
また,自己資本比率についても,銀行法14条の2が長期信用銀行法17条により準用されており,長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき,長期信用銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための大蔵省告示により定められ,その基準は,銀行法上の普通銀行と全く同一の基準であった。(甲139,甲146,甲231,弁論の全趣旨)
(7) 原告の自己査定トライアル,自己査定基準の策定と監査法人への説明,平成9年度決算に対する検討状況等
ア 平成9年8月1日の常務役員連絡会議
原告は,平成9年7月19日,スイスバンクコーポレーション(以下「スイス銀行」という。)との間で,証券業務等を目的とする合弁会社の設立,スイス銀行による原告に対する2000億円の増資引受け及び3パーセントの相互株式の持合を内容とする業務提携に関する基本合意を締結した。
これを受けて,同年8月1日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「中期シナリオの方向性へ向けた更なる加速と追加施策について」と題する資料(甲100添付資料⑤)に基づき,原告の経営全体の問題に関する検討が行われた。
上記資料によれば,今後の決算・BIS比率見通しとして,スイス銀行による資本注入,日経平均株価が平成9年度に2万円台であり,配当政策が平成11年3月期まで1株6円であるとの前提に立って,平成10年3月期において,不稼働資産5000億円(一般先2000億円,関連親密先3000億円)を処理し,リスクアセット21兆円の場合の自己資本比率9.07パーセントとなるとの試算がなされており,また,不稼働資産処理内訳のイメージについて,自己査定トライアル(速報ベース)による平成9年度要償却・引当見込額の試算として,一般先について1792億円(Ⅲ分類2397億円の50パーセントの額とⅣ分類593億円の合計額),関連親密先について3533億円(非支援先のⅢ分類額753億円の50パーセントの
額及びⅣ分類256億円の合計額と支援先のⅣ分類額2900億円との総額)すなわち総額5325億円の償却・引当を実施することが指摘されていた。
当時,Dは,スイス銀行との合意によるファイナンスが実施され,自己資本額が2000億円増加し,その結果BIS比率に余裕が生じて,その分中期計画の不稼働資産の処理額について3000億円の増額が可能となると考えた(甲116の41頁)。(甲100添付資料⑤,甲116,乙100)
イ 自己査定トライアルに基づく不良債権償却計画の検討状況
事業推進部は,トライアル運用細則及びトライアル運用規則等の自己査定基準に基づき,平成9年7月ころから,同年6月末を基準とする自己査定の試行(トライアル)を行い,これに基づき,同年9月2日付け「自己査定トライアルと97年度不良債権償却計画」と題する資料(甲32)を作成した。
上記資料によれば,自己査定作業の結果として,Ⅰ分類12兆7799億円,Ⅱ分類2兆9352億円,Ⅲ分類7150億円(そのうち関連親密先4359億円)及びⅣ分類2038億円(そのうち関連親密先1254億円)であること,Ⅲ分類とⅣ分類の合計額が9188億円(そのうち関連親密先5793億円)であることが示され,また,自己査定結果に基づく償却・引当試算として,今回の自己査定(トライアル)結果についてほとんどの銀行は,基本的には平成9年9月中間決算には反映させない方針であり,当面,自己査定結果と償却・引当との関連を厳密に考える必要はないが,平成9年12月基準による平成10年3月の本番実施時においては,今回のトライアル結果より大幅に減らすことは不自然・不可能であり,そういう意味では
今回のトライアルの出し方が平成10年3月期 の結果を事実上決めてしまうことになるので,今回のトライアル結果が本番実施時の最低ラインであり,事実上償却・引当予算から逆算的にⅢ,Ⅳ分類数字を決めざるを得ないことが指摘され,一般先・関連親密先を問わず,Ⅳ分類の資産(貸出金)について100パーセント,Ⅲ分類の資産について50パーセントの償却・引当を行った場合における償却・引当額は5613億円になり,Ⅲ分類の資産のうち関連親密先に対する部分について償却・引当を行わなかった場合には償却・引当額は3344億円となること,必要償却・引当額は計算上3300億円ないし5600億円となり,概ね平成9年度処理予定額5000億円の範囲内に収められる水準となっているが,裏を返せば本番実施時においてこ
れ以上自己査定額が積み上がる(含む会計士に否認されて増加する)と処理予定額を超えることになること,関連親密先の自己査定基準・方法はそれなりの無理をしていることもあり,相当の理論武装が必要となることが指摘されていた。
また,上記資料によれば,今回自己査定(トライアル)の問題点として,今回の自己査定トライアルは結果として概ねMOF査定額と同規模になっているが,実質的には事推所管先においてかなり無理をしているものであり,この点について今後他行動向,会計士のスタンス,更には平成9年秋の日銀考査の結果によっては平成10年3月の本番の際には修正せざるを得ない可能性もあること,関連親密先についてはMOFの関連ノンバンク通達に基本的に依拠しているものの,当行個別基準もそれなりに使って査定額の圧縮を図っていること,各行ともある程度関連親密先について弾力的な考え方で対応していく見込みであるが,当行の場合相当自主裁量性の強いものとなっておりこのあたり会計士に認められない可能性は十分あり得ることが指摘さ
れており,個別には,関連親密先のうち,エヌイーディーグループについて当該年度の支援損Ⅳ分類,残額をⅢ分類とし,日本リースグループについて本体を全額Ⅱ分類,グループ企業を正常先と要注意先に区別し,第一ファイナンスについて本来は貸出金全額ⅢⅣ分類であるが,含み損の部分で足きりとすることとされ,さらに,償却財源については,現実実態ベースではなお8000億円ないし9000億円残っており,年間5000億円では依然として財源不足との指摘もされていた。
なお,F,G及びHは,同月1日には,上記資料に基づき,担当者から説明を受けた(甲62の2枚目)。(甲32,甲62)
ウ 原告の自己査定基準に対する本件監査法人への説明と本件監査法人による了解
本件監査法人の原告の担当者であった公認会計士P(以下「P会計士」という。)及び公認会計士Q(以下「Q会計士」という。)は,平成9年9月2日,原告本店を訪問し,Hほか事業推進部のメンバーから,トライアル運用規則及びトライアル運用細則について説明を受けた。その際の主な説明内容は,債務者区分として「関連ノンバンク」以外の「関連親密先」を設けることの適否であったが,その点について,P会計士及びQ会計士は,おおむね上記自己査定の基準について資産査定通達等の許容範囲であると考え,その旨回答した。(甲64の56頁,57頁,甲132の52頁,甲136の48頁,65頁,68頁)
エ 平成9年度決算及び同期配当(本件中間配当及び本件決算配当)に関する検討状況等
(ア) 平成9年9月16日開催の常務役員連絡会議における検討状況等
D,E,F,C,B及びGは,平成9年9月16日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「97年度中間決算見込みについて」と題する常務役員連絡資料(甲162添付資料7)に基づき,同期における中間決算に関する検討を行った。
上記資料によれば,不稼働資産の処理財源として,使用可能業務純益が680億円(業務純益750億円)であること,株価の水準に応じて株式損益(株式3勘定尻)が127億円ないし481億円となること,不稼働資産は,業務純益及び株式損益を用いて,800億円ないし1000億円の処理が可能であることを前提に,平成9年上期決算主要項目の運営方針として,業務純益750億円を確保すること,株式損益について期末株価が1万8000円でも不動産売却益を必要しない利益を確保することとされ,不稼働処理として,不稼働資産の最低処理必要額を800億円とし,最大で1000億円を処理すること,ただ,関連先支援損の計上は,中間期においては必須としないこと及び支援完了でない限り「ディスクロ」に寄与しないことか
ら,中間期での計上を見送ることとされ,また,中間決算赤字と中間配当について,法律的見解として,中間決算を赤字とした上で中間配当を行うことは,黒字の場合に比べより取締役の期末配当可能利益の予測義務は重たくなるものの,期末の配当利益が確保される合理的根拠が存在する限り可能であるが,繰越利益は営業年度中に取締役会決定で取り崩すことができるのに対して,任意積立金の取り崩しは総会決議マターでありかかる性格のものを中間段階で前提にして配当を行うことは公正な会計慣行上妥当性に欠けるとの意見もあり,赤字決算の可能性を再検討した場合,中間決算を赤字とした場合であっても,中間配当は可能であるが,妥当性の点について疑問があること,中間期において不稼働資産の年間処理分(予定額5000億円)の早期処理
実施も不可能ではないが,剰余金(3433億円)を上回る水準の赤字幅(4000億円)となり,またBISの水準も8パーセント前後となり,個別処理案件の積上げも困難であり,現実的な選択肢となり得ないこと,また,他行動向も現状株式会社東京三菱銀行(以下「東京三菱」という。)を除き,中間では黒字としたうえで,年間での赤字を視野に入れた決算運営となる模様であること,以上を踏まえ,中間期において黒字決算を維持し,年間で赤字決算をすることが妥当であることが指摘されていた。(甲33,甲100,甲105,甲162,乙100)
(イ) 自己査定トライアル分類結果速報
原告は,平成9年10月16日,自己査定トライアルの結果について集計し,「自己査定トライアル分類結果速報」と題する資料を作成した。
同資料によれば,総資産額22兆8208億1500万円のうち,非分類12兆4761億0600万円,Ⅱ分類3兆0735億9300万円,Ⅲ分類7696億2500万円及びⅣ分類合計額1757億9300万円であること,平成8年4月の大蔵省検査における分類資産の額と比較した場合,Ⅱ分類は2937億2400万円増加し,他方,Ⅲ分類は1461億7300万円減少し,Ⅳ分類は337億5900万円減少していること(1枚目),関係会社の貸付金自己査定のトライアルと上記大蔵省検査の結果を比較した結果として,総貸出額は2兆6264億円(大蔵省検査時2兆2836億円)であり,貸出額が3427億円増加し,非分類が1914億円,Ⅱ分類が2821億円それぞれ増加し,他方,Ⅲ分類が214億円,Ⅳ分類が1
094億円それぞれ減少していること(4枚目)が指摘されていた。(甲104添付資料3)
(ウ) 中間決算案の承認と会計監査人への提出案に関する取締役会決議
被告A,D,E,F,C,B及びGは,平成9年10月28日開催の取締役会において,中間貸借対照表案及び中間損益計算書案を承認し,会計監査人に提出する旨の承認決議をした。なお,中間損益計算書案には,経常利益106億5800万円,税引前中間利益102億7700万円,中間利益100億5100万円が計上されていた。(甲34,甲65添付資料1)
(エ) 平成9年11月段階における同年度決算に係る検討状況等
a 平成9年11月12日の常務役員連絡会議における検討状況
D,E,F,C,B及びGは,平成9年11月12日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「97年度決算運営について」と題する常務役員連絡資料(甲163添付資料5)に基づき,同年度の決算に関する検討を行った。
上記資料によれば,単体赤字許容額として,決算配当を維持する場合に不稼働資産の処理に使用し得る剰余金額が3200億円程度(現状の配当原資及び利益準備金を除いたもの。将来の配当原資確保のためには2500億円ないし2800億円の赤字幅が限度)であること,無配当の場合でも自己資本比率8パーセントを維持するため,赤字許容額が3600億円程度であり,繰越損失について利益準備金及び資本準備金の取崩しが可能であることが指摘され,株価別不稼働処理可能額として,株価の水準(1万5000円から2万円まで)に応じて,おおむね3000億円ないし5500億円(赤字3200億円に不動産売却益1000億円を考慮した場合には,3700億円ないし7200億円)程度の不稼働資産の処理が可能であることが
記載され,「注」に自己査定トライアル結果に基づく処理額試算として,トライアル結果について,一般先1802億円(Ⅲ分類25パーセント,Ⅳ分類全額),関連先は862億円(Ⅳ分類のみ全額),合計額は2664億円であり,本査定想定について,一般先は2750億円,関連先は1150億円ないし2650億円,合計額は3900億円ないし5400億円であり,また,SBC向け今年度処理説明骨子として,今年度不稼働処理額が5000億円,自己査定トライアルの状況を踏まえた最低必要額は約3000億円(一般先2000億円及び関連先1000億円),さらに長銀リース及びランディックの支援完了を目指し,追加は2000億円であることが指摘されていた。
また,上記資料によれば,主要事項のリスク認識として,配当維持の選択は,赤字許容額が2500億円程度であり,株価次第で不稼働処理不十分のリスクがあること,これに対し,無配の選択は,不稼働処理可能額は拡大するが,他方,当時進められていたスイス銀行との資本提携の大幅遅延に伴う環境悪化が懸念されることが指摘され,また,不稼働処理額について当初予定の5000億円でも処理不十分とされるリスクがあること,総額5000億円の処理ができない場合には,不稼働資産の処理が遅れ,原告の格付け等環境が悪化し,資金調達面等激しいアゲインストとなるリスクがあるほか,スイス銀行への説明と乖離し,資本提携の枠組みに悪影響を及ぼすことも指摘され,当面の基本的対応方向として,年間処理予定額5000億円
は,現状株価では厳しい水準であるが,スイス銀行,アナリストへの説明内容(不稼働資産5000億円を処理する)や引当率の水準等を考慮した場合,下方修正により,不稼働資産処理額が5000億円に満たないとき,処理の遅れが顕在化する危険性(スイス銀行に対する説明内容と乖離した場合の提携の枠組みに対する悪影響や銀行の格付けが低下するおそれ)があり,現状では5000億円の不稼働資産を処理する方針とすることとされていた。
なお,Dは,5000億円の不稼働資産の処理を前提に,長銀リースのみの支援を完了する場合の処理額を3900億円,長銀リース及びランディックの支援を完了する場合の処理額を5400億円であると認識し(甲116の53頁),また,無配の選択は,スイス銀行によるファイナンス実施の観点から困難であること,今期(平成9年度)において一般先についての2500億円及び関連先についての867億円(当期支援額)の合計約3300億円の処理をしなければならない(「must」)が,無配・有配において,いずれを選択した場合でも,上記金額3300億円の処理は可能であることを認識し(甲116の57頁から59頁まで),さらに,これは日経平均株価1万4300円までを想定しており,1万4300円を株価が下回った
場合には,無配とせざるを得ないことを認識していた(甲116の61頁)。(甲36,甲65,甲66,甲89,甲100,甲105,甲116,甲163,弁論の全趣旨)
b 平成9年11月17日開催の常務役員連絡会における検討状況等
D,F,Eらは,平成9年11月17日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「自己査定トライアル(97/6基準)結果と今年度の償却・引当見込みについて」と題する常務役員連絡会資料(甲37)に基づき,平成10年3月期の償却・引当に関する検討を行った。
上記資料(平成9年6月末を基準として行われた自己査定のトライアルの結果を集計し,同時に分類資産ごとに倒産確率を基準とした償却・引当率を示したもの。乙100の23頁)によれば,一般先のうち正常先及び要注意先について貸倒引当金が最大でも546億円に達すること,一般先のうち債権償却特別勘定に組み入れられる部分(破綻懸念先,実質破綻先及び破綻先)について1644億円(Ⅲ分類25パーセント償却,Ⅳ分類100パーセント償却)に達すること,関連親密先については,原告との関係から倒産リスクがなく,継続企業として必要な支援を行っている以上,Ⅰ分類からⅢ分類までの資産について償却・引当を行わず,Ⅳ分類(当期支援額)に限り,全額(867億円)償却すること,平成10年3月期決算における自
己査定結果に基づく償却・引当試算として,トライアルの一般先に対する償却試算1644億円(Ⅲ分類及びⅣ分類合計額3919億円),査定案(試算)の一般先に対する償却試算2771億円(Ⅲ分類及びⅣ分類合計額4191億円),関連親密先については,長銀リース,ランディック及びエヌイーディーに対する支援を前提に,長銀リースのみの支援を終了する場合には,Ⅳ分類償却額1150億円,これにランディックの支援終了を加えた場合には,Ⅳ分類償却額2650億円であることとされ,おおむね合計3900億円ないし5400億円の償却・引当が見込まれていた。(甲36,甲37,甲62,甲65,甲66,甲89,甲101,甲103,甲104,乙100,弁論の全趣旨)
c 本件監査法人による内部統制監査と中間決算案に対する監査報告書の提出
本件監査法人は,平成9年10月ないし同年11月ころ,原告の自己査定に関する内部体制の整備状況について監査を実施したが,その際,自己査定基準に係る手引,与信監査制度に関する内部文書を閲覧し,原告の担当者からその説明を受けた。(甲136の4頁,49頁)。
また,本件監査法人の担当会計士であった公認会計士T(以下「T会計士」という。),P会計士及びQ会計士は,同年11月20日付けで,前記(ウ)の取締役会決議に基づき提出を受けていた原告の平成9年度中間決算案(中間貸借対照表及び中間損益計算書)について,中間監査の結果,これらの中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して原告の平成9年度の中間会計期間(平成9年4月1日から同年9月9月30日まで)に関する有用な会計情報を表示しているものと認める旨の監査報告書(甲7の17枚目)を提出した。(甲7,甲34,甲65,甲101,甲136)
(オ) 平成9年11月21日常務役員連絡会議における承認
D,E,F,C,B及びGは,平成9年11月21日開催の常務役員連絡会において,総合企画部作成の同日付け「中間配当実施について」と題する資料(甲65添付資料6)及び同日付け「平成9年度中間期決算発表(11/25)について」と題する資料(甲65添付資料12)に基づき,同年度の中間配当及び決算配当(いずれも1株3円)を行い,不稼働資産5000億円(一般先2500億円,関連親密先2500億円)を処理することを決定した。
上記「中間配当実施について」と題する資料によれば,剰余金(配当可能利益)額が3447億円,年間配当必要額が188億円であること,償却・引当の財源としては,日経平均株価が1万4300円(平成2年以降の最安値を基準)まで下落した場合に保有株式の損失見込額2050億円が発生するが,業務純益のうち1300億円及び不動産売却益1000億円から海外現地法人閉鎖等の臨時損失額100億円を控除した2200億円が考えられること,年間赤字額最大3200億円とした場合,最大3350億円の償却財源が見込まれることが指摘されていた。
また,「平成9年度中間期決算発表(11/25)について」と題する資料によれば,年間業績予想として,年間業務純益が1500億円であること,配当については,中間3円,期末3円とすること(12パーセント配当)とされ,また,補足説明として,年間不稼働処理見込額が5000億円であること,また平成10年3月期のBIS比率の見込みとして,ファイナンスが実施された場合には9.7パーセント程度,ファイナンスがない場合,リスクアセットを20兆円まで圧縮すれば,8.4パーセントであること(現状の21兆円を前提とした場合には8パーセントギリギリの水準)が指摘されていた。
なお,上記常務役員連絡会に先立つ同月20日,原告の法務部は,中間配当の可否について,期末の株価についてバブル崩壊後の最安値を採用していること,不稼働資産処理の必要最少額を3350億円とする点についても,自己査定試算額を基準としており,算定の不合理性はないことを挙げて,中間配当の実施に関しては,取締役の善管注意義務違反の問題はない旨回答した(甲65添付資料8)。(甲65,甲89,甲101,甲105,甲165)
(カ) 本件中間配当の承認決議
被告らは,平成9年11月25日開催の取締役会において,同年度の中間配当として,1株3円,合計額71億7868万8924円の金銭の分配を行う旨決議し,これに基づき,平成11年6月3日までに,71億7564万6348円の中間配当が実施された。
なお,中間貸借対照表には,剰余金3447億3000万円(任意積立金3176億3000万円,中間未処分利益270億9900万円)が計上され,中間損益計算書には,税引前中間利益102億7700万円,中間利益100億5100万円,前記繰越利益170億4800万円,中間未処分利益270億9900万円がそれぞれ計上されていた。
さらに,前記(エ)cのとおり,同年11月20日付け監査報告書が添付されていた。(甲7,甲8,甲34,甲65,甲101,甲105,甲165)
オ 自己査定運用規則及び自己査定運用細則
(ア) 平成9年12月15日の検討状況
D,E,F,C,B及びGは,平成9年12月15日,総合企画部作成の同日付け「長銀再生プラン~ディスカッションペーパー」と題する資料(甲105添付資料21)に基づき,検討を行った。
上記資料によれば,再生プランの前提として,平成10年1月のファイナンスを実施すること,平成9年度決算は現行の見通しであること(赤字2800億円,不稼働資産処理額5000億円),BIS比率10パーセントを維持し,国際業務を大幅に縮小して存続させること,再生プランの方向として,リスクアセットを平成12年3月期に15兆円まで圧縮すること,人員・経費等の削減を図ることとされ,また,今後の不稼働処理額について,「対外的」には,今年度処理額は5000億円(一般先2500億円,関連先2500億円)であり,一般先について当面の手当が完了したこと,関連先は2社の支援が完了し,エヌイーディーのみ継続支援をすることが指摘され,行内的には,今後の要処理額8000億円ないし9000億円である
こと,一般先(対象元本額1兆2000億円)については引当率7割であり,手当が完了したこと,関連先について貸出残高は3兆円に達するが,完全な不稼働資産は1兆円であり,今期の手当2500億円以外に残額1500億円から2500億円までの損失負担があることが指摘されており,また,現実には,関連親密先の損失を完全に一掃するには1兆円程度の規模の手当が必要であること,当面は一掃できる体力がなく,抱えて行かざるを得ないこと,そのうえで,3つのシナリオが示されており,シナリオ1として,追加の3000億円の処理を一気に実施する,すなわち法定準備金3000億円を使用し,いわゆる無配としてBIS基準8パーセントを放棄すること,シナリオ2として,処理一掃を目指した特別ファンドの設定(キャピタル益の追
求)であるが,現実には資金の制約があること,シナリオ3として財源を他に求めることが指摘されていた。(甲105添付資料21,甲117)
(イ) 平成9年12月16日開催の常務会における自己査定基準・償却基準の承認
平成9年12月16日開催の原告の常務会において,総合企画部作成の同日付け「早期是正措置導入に伴う自己査定の実施並びに自己査定基準・償却基準の概要について」と題する資料(甲102添付資料⑥)に基づき,自己査定基準及び償却基準に関する説明,検討が行われた。
上記資料によれば,自己査定実施の趣旨として,早期是正措置の導入に伴い,資産を個別に検討・分析の上,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに従い区分すると共に,これに基づき適切な引当・償却を行い今年度以降の決算に反映するものであることが挙げられ,自己査定基準及び分類方法のうち,関連ノンバンク査定基準として,関連ノンバンクについては,償却前利益によりおおむね2,3年で実質債務超過の解消が不可能な体力のない先及び経営支援(実績)先について,母体行責任を負う意思がある場合,基本的に当該年度支援額をⅣ分類,担保等による回収見込額をⅡ分類,残額をⅢ分類とすること(経営支援実績先は,原則全額Ⅱ分類)が指摘されていた。
また,上記資料によれば,自己査定の枠組み及び査定基準・償却基準の基本部分を頭取決裁とすること,自己査定手続の明細は,リスク統轄部担当役員(当時副頭取のEが担当)の決裁とすることとされていた。
その後,Dは,上記資料のとおり,「自己査定制度の制定及び自己査定の実施について」と題する回議文書について,回付を受け,これを決裁した。その内容は,自己査定制度の意義(早期是正措置の導入に伴い,資産内容の実態を客観的に反映した財務諸表を作成し,適正な償却・引当を行うことが求められ,そのための準備作業としての自己査定を実施すること),自己査定の基準日(6月末及び12月末を基準として年2回実施すること),自己査定の基本的考え方や分類方法(貸出金等について「正常先」から「破綻先」までの5つの「債務者区分」を行い,資金使途等の内容を個別に検討し,担保等の状況を勘案して,Ⅰ分類からⅣ分類までの4つの資産分類すること)等の基本的な事項であった。(甲102添付資料⑥,資料⑦)
(ウ) 自己査定運用規則及び自己査定運用細則の正式な策定
Eは,平成10年3月末ころまでに,平成9年12月29日付けで,事業推進部が策定した自己査定運用規則及び自己査定運用細則の策定に関する回議についてこれを決裁した。なお,Gも,回議を受け,これを承認した。(甲63,甲64)
(エ) 自己査定運用規則及び自己査定運用細則の内容
a 関連親密先についての債務者区分
まず,関連親密先について,一般先と同様の基準により債務者区分・資産分類を行うことは,原告の経営関与度の高さ等を勘案すれば適当ではないとして,全銀協追加Q&Aの趣旨を勘案する等して,「関連ノンバンク」,「経営支援先」及び「経営支援実績先」と呼ばれる債務者区分を設けることとされた。
このうち,「関連ノンバンク」について,大蔵省検査により原告関連ノンバンクと指定を受けている先で,そのうち体力がない(償却前利益によりおおむね2,3年程度で債務超過を解消し得る見込みがなく,実質的債務超過の状態が継続し,自力で再建の見通しが立たない場合)と認定された先であり,資産分類について一般先と異なる方法を採ること,また,「経営支援実績先」については,原告が支援を行いその支援が完了した先について業況が正常に復しているが,原告が特別の注意をもって管理をし,従来と同様のスタンスを維持していることから,この区分とし資産分類をⅡ分類とすること,上記各債務者区分に該当しない関連親密先(「特定先」)については,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」に分類し,原則として,その
債務者区分に従い資産分類を行うが,不動産の事業化を目的としている受皿会社及びその関係会社について,事業目的にかんがみ,保有資産の評価損と繰越欠損額の合計をⅡ分類とすること,関連親密先の関係会社については,原則として,関連親密先に準じて「正常先」又は「要注意先」に債務者区分し,それに応じた資産分類を行うが,「関連ノンバンク」に区分された関係会社のうち,不稼働資産の処理を本体と一体で行う会社については,本体の債務者区分(「関連ノンバンク」)に従い,それに準じた資産分類を行うことが定められていた。(甲6の1,甲6の4の「決裁事由」の第2項,第3項,第5項ないし第7項,第9項,第10項)
b 自己査定運用規則
自己査定運用規則においては,その中で,対象先は,原告の「関連ノンバンク」(平成8年4月の大蔵省検査において指定されたエヌイーディー,日本リース,ジャリック,第一ファイナンス及び平河町ファイナンス)であるとされ,この規則による特例として,まず,体力の有無について,実質債務超過の場合の体力の有無の判断は,償却前利益によりおおむね2,3年程度で債務超過を解消できるかどうかを目安として判断すること,体力がない(実質債務超過で,かつ,おおむね2,3年程度で償却前利益により解消できない)場合には,一般債務者と異なる基準により資産分類を行うこと,この資産分類基準は通常の債務者の資産分類とは異なることから,資産分類の前提となる債務者区分については,これを行わず「関連ノンバンク」と
すること,具体的な資産分類としては,例えば,原告に母体行責任を負う意思があり,合理的再建計画が存在する場合には,当該年度の支援予定額をⅣ分類とし,それを超える支援予定額をⅢ分類とすること,母体行責任を負う意思があっても,再建計画が作成されていない場合であり(甲6の2の2枚目の②及び同脚注6参照),かつ,当該「関連ノンバンク」の取引金融機関が原告のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類とし,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類とし,その他をⅢ分類とすること(甲6の2の2枚目脚注7参照)等が定められていた。(甲6の2,甲63)
c 自己査定運用細則
自己査定運用細則においては,その中で,「関連ノンバンク」に指定された先については,自己査定運用規則を適用すること,また,原告が指定する「経営支援先」,「経営支援実績先」及び「特定先」(原告の関連親密先)については,前記「自己査定制度の制定と自己査定実施について」に定められた債務者区分・資産分類とともに,次の査定基準を適用するとして,例えば,「経営支援実績先」については,日本リースが指定され,「関連ノンバンク」基準で体力がないと判断される先を除き,原告が過去に経営支援を行っていた先であるとされ,債務者区分を「経営支援実績先」,資産分類をⅡ分類とすることが定められ,また,「特定先」として,いくつかの受皿会社が指定されており,これらは,いずれも「正常先」又は「要注意先」
に区分し,原則として「債務者区分」に応じて資産分類を行うこと等が定められていた。(甲6の1)
(オ) 平成9年12月26日付け「2ヵ年計画(長銀再生2ヵ年計画)」
総合企画部が平成9年12月26日付けで作成した「2ヵ年計画(長銀再生2ヵ年計画)」と題する経営会議資料(甲105添付資料23)によれば,原告の改革方向を示す中期プランの見直しプランとして,バランスシートの健全化,関係会社の抜本的リストラ,顧客・商品戦略の再構築と業務運営の抜本的改革,思い切ったリストラの実施を骨子とする2カ年計画の提案がなされ,スイス銀行との提携(アライアンス)を前提に,原告グループの再編を進めることが指摘されていた。なお,同プランでも自己資本比率は8パーセント達成が前提とされ,平成9年度の不稼働資産処理の額は,5000億円とされていた。(甲105)
(8) 平成10年1月ころから同年3月までの状況
ア 大蔵省における自己査定に関する把握の状況
大蔵省金融検査部は,資産査定通達において,早期是正措置が導入されるまでの間における金融検査においても,金融機関の自己査定のための体制整備の進展状況等について把握するよう努められたいと示していたこともあり,また,前記(4)ア(イ)のとおり,O金融検査部長は,平成10年4月以降の一斉金融検査の実施は困難であり,できる限り早期是正措置の導入までに,各金融機関の体制整備状況等についても把握するよう努める旨述べていた。
そのため,大蔵省金融検査部は,平成9年度を各金融機関が自己査定に習熟するためのトライアル期間と位置づけて,その間において,各金融機関がどのような自己査定基準を策定しているかどうかについて予備的に検査し,そごがあれば,これを指摘して訂正させることも計画していたが,同年11月に,三洋証券株式会社の会社更生手続の申立て,株式会社北海道拓殖銀行の経営破綻や山一證券株式会社の自主廃業等により,金融システムが混乱に陥ったため,このような検査を実施するには至らなかった(乙81の3枚目から4枚目)。(証人R(以下「証人R」という。)9頁,甲1,乙21,乙81,弁論の全趣旨)
イ 各金融機関の自己査定の状況,預金保険法の改正と金融危機管理審査委員会による公的資金の導入
(ア) 各金融機関の自己査定の状況等
前記アの平成9年末の金融システムの混乱を受けて,預金保険法の改正等が国会において審議され,金融機関に対する資本注入制度の導入が検討されていた。そこで,大蔵省は,同年12月ころ,上記法改正のための国会における審議資料として,各金融機関の試行的な自己査定による数字(不良債権額)の提出を受けて,平成10年1月,これを国会に提出した。その際,各銀行には,自己査定基準と行内格付けといった債権区分が存在していたが,それ自体,ⅠからⅣ分類という分類より詳細な分類であり,しかもその内容が各行ごとに全くばらばらであったため,大蔵省の担当者(N調査課長)は,比較や集計ができず,各銀行に対し,Ⅰ分類からⅣ分類までに組み替えるよう指示し,各銀行が自主的にとりまとめた数字を国会に提出したが,
大蔵省において,前記法案審議資料として上記数字の組み替えを指示したにすぎず,各銀行が上記分類に沿って提出した数字の内容や相互の整合性をチェックすることまではしなかった(甲139の32頁,33頁)。(甲139,乙29,弁論の全趣旨)
(イ) 預金保険法の改正
その後,平成10年2月に,預金保険法が改正され(同年法律第4号),また,「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」(同年法律第5号)が施行され,これに伴い,銀行等の金融機関に対する公的資金の導入(資本注入)制度が設けられ,預金保険機構にはその審査を行う金融危機管理審査委員会(いわゆるS委員会)が設置された。
これを受けて,東京三菱を含む都銀9行,原告を含む長期信用銀行3行,信託銀行6行,地方銀行3行の合計21行が,経営の健全性の確保のための計画を提出して資本注入の申請を行ったが,金融危機管理審査委員会は,上記申請を行った21行に対し,自己査定結果とそれを裏付けるラインシート等の内部資料の提出を要求し,その提出を受けて,大蔵省金融検査部及び日銀考査局に対して,自己査定の結果についてチェックを依頼し,各銀行の経営改善計画の内容を確認して,公的資金の導入を決定し,総額1兆8156億円の公的資金が資本に注入され,その際,原告にも,公的資金1776億円が資本に注入された(甲116の80頁)。(甲105添付資料24,甲116,甲139,乙40,乙81,弁論の全趣旨)
(ウ) 銀行の有価証券評価に関する原価法の導入
改正前決算経理基準において,従来,銀行の保有する上場有価証券等の評価については,国債等を除き,いわゆる低価法(上場有価証券等の取得価格と時価の低い方の価格により評価する方式)が採用されていたが,大蔵省銀行局長は,各普通銀行代表者,各信託銀行代表者及び各長期信用銀行代表者に宛てて,平成10年2月27日蔵銀第468号「『普通銀行の業務運営に関する基本事項等について』通達の一部改正について」と題する通達を発出し,その中で,上記低価法によるべき旨の規定を削除した。
この結果,銀行において,上場有価証券等の評価に関して原価法(取得価格により評価する方式)を採用することが可能となり,いわゆる主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3行,信託銀行7行)のうち16行が,平成10年3月期の決算において,原価法を採用した。なお,11行は,前記(イ)の経営の健全性の確保のための計画において原価法によることを明らかにしており,また,同計画において低価法によることを明らかにしていた株式会社三和銀行,住友信託銀行,安田信託株式会社及び東洋信託銀行株式会社や資本注入の申請を行わなかった日本信託銀行株式会社も,原価法によることを明らかにした。
他方,興銀,東京三菱銀行及び三菱信託銀行株式会社は,従前のとおり,低価法を採用した。(乙38,乙39,弁論の全趣旨)
(エ) 金融機関の自己査定に対する大蔵省の対応
その後,大蔵省は,前記(ア)の各金融機関の自己査定の状況を踏まえて,金融機関の業態別(全銀協,地方銀行協会,第二地方銀行協会,信用金庫協会等)の説明会等において,担当職員が出席して説明をした。(甲138,甲139,弁論の全趣旨)
(オ) 早期是正措置の導入に伴う大蔵省の金融検査の方針
その後,大蔵省金融検査部長は,金融証券検査官等に宛てて,平成10年3月31日蔵銀第140号「新しい金融検査に関する基本事項について」と題する通達(以下「新検査通達」という。)(甲97添付資料1)を発出し,新しい金融検査に関する基本事項を示した。
新検査通達によれば,金融検査部においては,従来のきめ細かな事前指導を中心とする行政に即応したこれまでの検査体制・手法について抜本的な見直しを行い,検査の基本的な在り方を転換することとしたこと,新検査方式への転換に当たっての基本的考え方として,金融機関等における自己責任原則の徹底を前提として,金融機関等自らによる業務遂行上の管理体制の整備状況,その機能発揮の状況等について実態把握すること,特に,資産内容の健全性に関しては,早期是正措置の導入を契機として,金融機関等による自己査定,公認会計士による監査等を前提としつつ,商法,企業会計原則等を踏まえ,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態把握することが基本的考え方として示され,また,金融機関等の実態をより的確か
つ効率的・効果的に把握するため,公認会計士・監査役等の監査機能を検査において一層活用すること,早期是正措置の適用をも念頭に置いて,金融機関等の実態を的確に把握するため,金融機関等の経営実態に応じて検査頻度に繁簡をつけ,重点的・機動的な検査を実施すること,その際,日銀が実施する考査との間で,適切な連携の確保に十分配慮することが示され,さらに,新検査方式実施の要点として,資産内容の健全性に係る検査のため,早期是正措置制度に基づき,自己資本比率の水準いかんにより所要の措置が発動されること等を踏まえ,金融機関等による自己査定の正確性等について的確に実態把握すること,加えて,本部検査として,自己査定の正確性等の実態把握のため,被検査金融機関等の実施した自己査定について,個別債務者の自己
査定関連資料から抽出した資料に基づき,商法,企業会計原則等を踏まえ,その正確性及び自己査定結果による償却・引当の適切性につき実態把握すること,また役職員への質問・応答を通じた実態把握の具体的留意点として,被検査金融機関等における基本的融資方針,自己査定及び償却・引当についての内部統制の状況の説明を求め,資料及び臨店検査の状況等を勘案しつつ,自己査定基準,自己査定体制,自己査定結果,自己査定の基準と体制の定期的見直しの状況,償却・引当基準,償却・引当体制,償却・引当実績と体制の定期的見直し等の状況を確認することが示された。(甲97,乙25)
(9) 本件決算配当,平成10年3月期における原告の自己査定基準及び償却・引当基準による償却・引当の状況並びに各関連親密先の経営状況及び資産査定の状況等
ア 原告の関連親密先全体に対する償却・引当の状況等
原告は,平成9年12月末日を基準として,平成10年1月以降,資産査定を実施し,その内容については,リスク統轄部においてまとめられ,その結果について,平成10年4月24日付け「資産自己査定分析資料('97/12末基準)」と題する資料(甲104添付資料10)が作成された。
なお,被告A,D,E,C及びBは,平成10年4月24日開催の経営会議において,上記資料に基づき,不良債権処理に関する報告・説明を受けた。
上記資料によれば,①債務者区分別内訳として,関連会社についての債務者区分の状況は,「正常先」6829億円,「要注意先」9467億円及び「その他(関連会社等)」1兆0147億円(合計2兆6443億円)であること,②資産分類別内訳として,関連会社についての資産分類の状況は,非分類1兆2581億円,Ⅱ分類8644億円,Ⅲ分類4251億円及びⅣ分類967億円(合計2兆6443億円)であること(資料1枚目),自己査定トライアルの結果と比較した場合,Ⅱ分類が4911億円減少し,Ⅲ分類が675億円減少し,Ⅳ分類が100億円増加したこと(資料1枚目,3枚目),③償却・引当については,トライアル時において,一般先のⅢ分類2770億円(25パーセント引当)及びⅣ分類891億円(全額償却・
引当)についての償却・引当額は1583億円であり,関連親密先のⅢ分類4926億円(償却・引当なし)及びⅣ分類867億円(Ⅳ分類のみ全額償却・引当)についての償却・引当額は867億円であり,合計額は2450億円に達すること,他方,本番査定時において,一般先のⅢ分類2734億円及びⅣ分類1487億円についての償却・引当額は2171億円であり,関連親密先のⅢ分類4251億円及びⅣ分類967億円についての償却・引当額は2660億円(ランディックについて支援損を計上し,Ⅲ分類及びⅣ分類合計額1671億円全額償却)であり,合計額は5600億円に達していたことが,それぞれ指摘されていた(資料6枚目)。(甲104添付資料10)
イ 平成10年2月ころの本件監査法人による監査の状況
本件監査法人の担当であったQ会計士らは,原告の自己査定の内部統制の検証と自己査定結果の検証を実施し,その際,自己査定の手引,自己査定運用規則,自己査定運用細則等の自己査定基準に関する文書を入手して,検討を行った。
その際,Q会計士らは,4号実務指針に基づき,原告の上記自己査定基準と資産査定通達との整合性についてもチェックしたが,両者にそごはなく,上記自己査定基準は,資産査定通達の許容範囲内のものであると判断した。
すなわち,Q会計士らは,自己査定運用規則の中に当行が母体行責任を負う意思があっても,大幅な債務超過が相当期間継続しており,再建計画に客観的合理性が認められない場合において,当該支援対象ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類額を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残りをⅢ分類とすることや,「なお,当該ノンバンクの取引金融機関が当行のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類,その他をⅢ分類とすることができる」旨の同規則※7なお書の定め(以下「※7なお書」という。)も,貸出金シェアの場合には母体行責任を負う原告が他行の損失も負担するが,単独行であればその必要がないと理解されるので,全銀協追加Q&Aの許容範囲内と考え,ま
た,自己査定運用細則の対象は,基本的には,体力がある関連ノンバンクを対象とし,償却前利益2,3年で実質債務超過状態を解消し得るか,又は実質債務超過がない状態にあることから,基本的には,「破綻懸念先」に該当することはなく,「要注意先」以上であり,資産査定通達に照らし,当然資産査定はⅡ分類となること,さらに,自己査定運用細則の中の「特定先」については,銀行が積極支援する先は破綻に陥る可能性が極めて小さいと考えて,資産査定通達に係る「破綻懸念先」及び「要注意先」の定義に照らし,「特定先」を「要注意先」又は「正常先」と区分すること自体は,資産査定通達に照らし許容されると考えていた。(甲136の65頁ないし69頁)
ウ 平成10年3月期における原告の償却・引当額
原告は,平成10年3月期において,不良債権処理に係る損失として,6165億2800万円を計上した。その内訳は,「貸出金償却」514億9600万円,「債権償却特別勘定純繰入額」3330億6700万円,「株式会社共同債権買取機構への売却損」57億4500万円,「債権売却損失引当金繰入額」94億6200万円,「累積債務国向け債権等売却損」297億0200万円及び「取引先等支援損」1870億5400万円であった。(乙53)
エ 原告と各関連親密先の関係,平成10年3月期における経営・財務状況
(ア) エヌイーディー
a 原告とエヌイーディーの関係
エヌイーディーは,昭和47年11月,原告,株式会社第一勧業銀行(以下「第一勧銀」という。),商社及び証券会社の計4社が中心となって,ベンチャーキャピタルとして設立された株式会社であったが,その後,原告グループが,同社への出資比率及び融資残高の比率を増大させ,また,原告の出身者が多数同社の役員となるなど,資本,融資及び人的関係を強めるなどし,その結果,原告は同社を関連先と位置づけ,また,他の金融機関も,エヌイーディーが原告のいわゆる系列ノンバンクとみなし,平成8年4月の大蔵省検査において,原告の関連ノンバンクであると指定されていた。(甲19,甲76,甲150,甲152)
b エヌイーディーの平成10年3月期における経営状況と原告による支援計画
エヌイーディーは,バブル経済崩壊後,その不動産関連融資が不良債権化するなどして経営状況が悪化し(平成5年3月期時点の要処理債権額1236億円),平成6年3月期以降,原告から債権放棄等の支援(5年間で総額1900億円)を受けて,その不良債権の処理を進めたことから,平成9年3月時点において要処理債権額が767億円に減少する見通しであったが,結果的には,大幅な地価下落により不良債権額が増加し,2924億円の不良債権が残存することとなった(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№1)。
そこで,原告は,平成10年3月23日開催の常務会において,当初の計画を延長し,5年間(平成10年3月期から平成14年3月期まで)で,総額2951億円の支援を行い(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№3),不良債権3010億円を処理する修正計画を立案・了承し(甲38の1),この計画に基づき,国税当局と折衝して,新たに無税の承認(法人税基本通達9-4-2)を受けて,エヌイーディーの不良債権を処理し,同社の本業部門(ベンチャーキャピタル業)を不良債権部分から分離しこれを再建する計画(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№5)を実施する旨決定した。
なお,エヌイーディーには,平成6年3月期以前にその不良債権を簿価で譲り受けた受皿会社(別紙3「平成10年3月期における償却引当状況」記載番号2ないし8の各会社を含む。)が存在し,国税庁から簿価譲渡した不良債権をエヌイーディーに戻すべきであるとする指導も受け,当初の計画において,これらの会社の清算を優先する予定であったが,実際にはこの清算が進まず(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№1),そのため,上記修正計画においても,本体の不良債権の処理を優先し,受皿会社の清算を最後にすること,赤字増加回避のため,金利引下げを実施することとされていた(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№4)。(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理
について」,甲45の2添付の「長銀インターナショナルリース及びエヌイーディーの現状と対策」,甲45の2,甲76,甲150)
c 原告によるエヌイーディーの自己査定と償却・引当及び原告のエヌイーディーへの貸出金の債権放棄
原告は,平成10年3月期において,原告の貸出金及び支払承諾の合計額1717億4500万円について,エヌイーディーを「関連ノンバンク」に区分し,資産査定通達上の債務者区分については行わず,その資産のうち,Ⅳ分類201億8000万円(当期支援額),Ⅲ分類1515億6500万円(原告の貸出金1715億8500万円及び支払承諾額1億6000万円からⅣ分類額を控除したもの),Ⅰ分類40億2000万円(貸付有価証券残高)との査定を実施した。
また,原告は,同月31日開催の取締役会において,エヌイーディーへの貸出金のうち201億8000万円を放棄する旨の承認決議をした。(甲39,甲151)
(イ) エヌイーディーの受皿会社7社の状況
a 青葉エステート
青葉エステートは,昭和62年6月に設立された不動産及び融資を主たる業務とする株式会社であり,エヌイーディーの不良債権を簿価で譲り受けた受皿会社(原告のグループ企業であるエヌイーディーほか2社が出資)であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった(甲49の2の2頁,甲78添付資料一の1)。
平成10年3月期において,原告は,青葉エステートに対し,247億8400万円の貸出(エヌイーディーが保証予約)を行っていたところ,自己査定において,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」(甲6の4)記載の決済事由10項ただし書(以下「決済事由10項ただし書」という。)に基づき,債務者区分をエヌイーディーと一体として扱い,貸出金をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲49の2,甲74,甲78,弁論の全趣旨)
b ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ
ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ(以下「ユニベスト外4社」という。)は,エヌイーディーの不良債権を簿価で譲り受けるため,いずれも青葉エステートの全額出資により平成3年11月又は平成4年10月に設立された受皿会社であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった(甲78添付資料二の1ないし5,甲50の2,51の2,53の2,54の2参照)。
原告は,平成10年3月期において,ユニベスト外4社の貸出金(ユニベスト74億0300万円,グラベス31億9600万円,コーポレックス13億6200万円,プロクセル5億9600万円,日本ビゼルボ1億3100万円)について(エヌイーディーは保証予約),決済事由10項ただし書に基づき,これらの会社の債務者区分をエヌイーディーと一体であるとして扱い,貸出金をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲50の1及び2,甲51の1及び2,甲52の1及び2,甲53の1及び2,甲54の1及び2,甲78,弁論の全趣旨)
c エクセレーブファイナンス
エクセレーブファイナンスは,昭和60年12月に,他の金融機関から融資を受けてこれをエヌイーディーに融資するために設立された会社(平成10年3月期においてエヌイーディー全額出資)であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった。
エクセレーブファイナンスは,平成10年3月期において,原告から400億円の融資を受けて,これを全額エヌイーディーに融資しており,その資産(総額450億7400万円)の大半がエヌイーディーに対する融資金であり,同社の経営状況については,エヌイーディーに左右される状態であった。
原告は,平成10年3月期において,決済事由10項ただし書に基づき,同社の債務者区分をエヌイーディーと一体であるとして扱い,貸出金(400億円)をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲69の1の73頁,甲77,甲153の1枚目,6枚目,弁論の全趣旨)
(ウ) 第一ファイナンス
a 原告と第一ファイナンスの関係
第一ファイナンスは,昭和56年3月に設立されたファイナンスを行う株式会社であり,原告本体で行い得ない提携ローンやファクタリング等を主要業務としており,原告のグループ企業4社(ランディック,平河町ファイナンス,ジャリック及び外1社)が出資する原告のグループ企業であり,原告内部において,関連親密先と位置づけられていた。(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」)
b 原告による第一ファイナンスの処理計画
第一ファイナンスは,平成3年ころまで,ファクタリング業務のほか,ノンバンクへの貸出を行い,順調にその業容を拡大していたが,バブル経済の崩壊により,不良債権が増大し,平成7年7月に,総資産2288億円のうち含み損が657億円に達していた。原告は,同社の正常資産を平河町ファイナンスに移管し他の金融機関からの借入を維持し,原告のみが,第一ファイナンス本体に対する融資を行い,同社の残存不良債権を回収,処理し,最終的には同社を清算し原告が最終損失を全て負担することを計画し,この計画に基づき,同社の正常債権は,平河町ファイナンスに移管された(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」№1,甲46の1№1から№4)。
c 平成10年3月期における第一ファイナンスの状況と原告による自己査定及び償却引当等の状況等
平成10年3月期において,第一ファイナンス本体は実質債務超過状態(約138億円)にあり,損益も赤字の状態であったため(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」№1,№2,甲148の8枚目),原告は,最終的には同社を清算処理するほかないと考えていた。ただ,同社が債権の回収業務を継続しており,当面清算の必要はないとの理由により,原告は,同社を「関連ノンバンク」に債務者区分し,その貸出金1245億6000万円(同社の借入先は原告のみ)について,※7なお書に基づき,同社の資産をⅣ分類130億0700万円(同社繰越欠損額),Ⅲ分類400億0800万円(同社自己査定による営業貸付金Ⅲ分類,同社保有有価証券の含み損及び関係会社の繰越欠損の合計額),Ⅱ分類596億
9900万円(同社貸出金から,Ⅳ分類及びⅢ分類並びに優良担保部分を控除したもの)と査定し,Ⅳ分類額及びⅢ分類の一部(16億9300万円)の合計額147億円について引当を実施(有税による債権償却特別勘定への繰入れ)した。(甲147添付の資料7,弁論の全趣旨)
(エ) 日本リース
a 原告と日本リースの関係,日本リースへの支援の状況
日本リースは,昭和38年に,株式会社リコー,原告を含む各銀行,損害保険会社及び各メーカーの出資により設立された総合リース会社であるが,原告は,日本リース設立時の出資金融機関の一つであり,設立直後から日本リースとの取引を開始し,その後, 原告グループが日本リースの筆頭株主となり(甲94の4頁),原告の出身者が日本リースの代表取締役社長を含む主要役員の多くを占め,原告が融資残高においても第1位のシェアを占める(甲94の5頁)など,資本,融資取引,人的関係等において密接な関係を有しており,また,原告が平成8年3月末までに日本リースに損益支援を実施するなど,同社は,平成9年度当時,原告の系列ノンバンクであると位置づけられ,そのため,大蔵省金融検査部は,平成8年4月の
大蔵省検査の際に日本リースが原告の関連ノンバンクであると指定していた(甲80添付資料1)。(甲80,甲81,甲92ないし甲94,甲116,甲154,乙69,乙74)
b 日本リースへの原告による支援と日本リースの状況
原告は,平成3年以降,バブル崩壊により,不動産関連融資が不良債権化し,多数の不良資産を抱えて経営が悪化していた日本リースに対し,同社の不良資産の移管のため,受皿会社に買取資金を融資してこれを引き取るなどの支援を行っていたが,平成7年3月及び平成8年3月に,抜本的な処理として,不良債権を買い取る方式により総額約1600億円の損益支援(資金贈与)を実施し,また,原告が受皿会社に不稼働資産の買取資金を融資して不良資産を移管するなどの支援を実施した。
同社は,このような原告の支援を受けて,また,自力償却分を含め,平成9年3月期までに不良資産約3000億円を処理し,収益力の回復に努め,その結果,平成8年3月期において実力基礎収益(不良債権の処理に使用し得る償却前利益)は3億円の赤字(未収利息及び日本リースによる利息の追貸し分の利息収入を加えた計算上の利益が259億円)であったが,平成9年3月期における実力基礎収益は175億円(計算上の利益277億円)となり,平成10年3月期における実力基礎収益は182億円(計算上の利益261億円)となっていた(甲91の添付資料4)。
しかし,上記処理後も日本リースには多額の不稼働資産が残存し,平成8年3月期に582億円の債務超過状態にあり,また,要処理不稼働資産の額が,同年7月においても5000億円ないし6000億円に達するとか(甲81の6枚目),また,同期において,延滞債権額の含み損(3004億円),不動産等の含み損(2501億円)及び資本欠損553億円の合計6058億円の含み損が存在する等と指摘されていた(甲80添付資料2の平成8年12月29日付「今後の不良資産処理について」と題する資料8枚目「常務会フリーディスカッション資料」,甲94資料3№4)。(甲80,甲81,甲91,甲92,甲94,甲96)
c 平成10年3月期における日本リースの経営状況
日本リースは,平成10年3月期において,損益についてはおおむね年間の実力基礎収益175億円程度が見込まれていたが(甲81添付資料2),他方,資産については営業貸付金(9347億円)の含み損が7000億円に達し(甲81添付資料3),原告による支援がされても,不稼働資産の最終的な処理には相当期間が見込まれる状況にあった。
また,同年6月26日に住友信託と原告との合併に関する発表が行われ,住友信託と原告との間で合併交渉が進められ,これを受けて原告への資本注入が検討され,同年8月21日に経営改善計画が公表され,その中で,原告が,日本リースに対する貸出金を全額放棄し,同社は,他の金融機関からも一部債権放棄を受けるなどして,不良債権の含み損等6000億円の損失を処理するとの計画が示された。(甲48,甲81,甲120,甲129,乙75,乙76,弁論の全趣旨)
d 原告における日本リースの債務者区分と資産査定
原告は,平成10年3月期において,自己査定運用細則に基づき,日本リースを「経営支援実績先」に区分し資産分類をⅡ分類とし,その査定結果に基づき,原告の日本リースに対する貸出金(2556億8000万円)をⅡ分類として償却・引当をしなかった。(甲81)
(オ) 日本リース受皿会社
a 有楽エンタープライズ
有楽エンタープライズは,昭和60年6月に設立された日本リースグループの不動産会社であり,平成4年8月に,日本リースの不良債権に係る担保物件を取得した受皿会社である(甲83添付資料1)。
有楽エンタープライズは,平成10年3月期において,原告(借入額63億5000万円)及び日本リース(借入額130億1400万円)から融資を受けており,また,平成9年3月期における純損失額は2億8805万7489円であり,債務超過額(資本欠損)が30億5710万9105円に達していた(甲55の2の2枚目)。
有楽エンタープライズは,取得した物件(大阪市日本橋所在)の事業化(パチンコ業者向けテナントビルの建設)により収益をあげることを計画していたが,実際には,賃借人の選定が進まず,具体的な事業化計画の策定にまで至っていなかった(甲83の3枚目)。
原告は,平成10年3月期において,自己査定運用細則に基づき,有楽エンタープライズが「特定先」であるとして,その債務者区分を「要注意先」と区分し,原告の貸出金(63億5000万円)をⅡ分類とし,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」のとおり,償却・引当を実施した。(甲55の2,甲69の1の36頁,37頁,甲82,甲83,甲157,弁論の全趣旨)
b 四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート
四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート(以下「ビルプロ3社」という。)は,いずれも平成5年11月に日本リースの平成6年3月期における日本リースの大口融資先であった日本ビルプロジェクト株式会社及びそのグループ会社(以下「ビルプログループ」という。)に対する融資残高の圧縮を目的として,その不良債権に係る担保物件を債権簿価で買い取るため,設立された受皿会社(日本リース外2社出資)である。すなわち,平成5年7月にビルプログループが実質破綻したことに伴い,日本リースの取引金融機関から,日本リースのビルプログループに対する融資残高の圧縮が要請されたため,原告は,ビルプログループが開発を予定し日本リースが担保として融資をしていた担保物件(左門町物件,銀座八丁目物件,竜泉
物件及びN町物件と呼称された。)について,事業化計画を添付して物件の担保評価額を債権の簿価額までかさ上げして,ビルプロ3社への融資(四谷プランニング187億8000万円,木挽町開発115億5000万円,竜泉エステート166億9000万円)を実行し,この融資金により,ビルプロ3社に日本リースのビルプログループに対する貸付債権を買い取らせ,日本リースの融資残高の圧縮を実現していた。
平成10年3月期において,ビルプロ3社は,債務超過の状態にあったが,原告は,担保物件の事業化のめどが立ったなどとの理由により,自己査定運用細則に基づき,ビルプロ3社が「特定先」であるとして,その債務者区分を「要注意先」と区分し,原告の貸出金(四谷プランニング187億8000万円,木挽町開発115億5000万円,竜泉エステート166億9000万円)をⅡ分類とし,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」のとおり,償却・引当を実施した(甲156添付資料一の1,二の1,三の1)。(甲56の2,甲69の1の29頁,甲84ないし甲87,甲96,甲156,弁論の全趣旨)
オ 本件決算配当に関する検討,承認・実施等
原告は,平成10年4月28日開催の取締役会において,平成9年度(平成10年3月期)決算に係る営業報告書,貸借対照表,損益計算書,利益処分計算書案(本件利益処分案)及び付属明細書を承認し,これを会計監査人及び監査役会に提出する旨の承認決議をした。
本件利益処分案には,任意積立金2995億1618万4620円を取り崩して,当期未処理損失を処理し,利益処分額を86億7162万4655円としたうえで,このうち,1株につき3円,総額71億7864万7455円の本件決算配当を行う旨記載されていた。
なお,上記決算案を受領した本件監査法人において,T会計士,P会計士,Q会計士らが,上記取締役会決議に基づき提出を受けていた原告の平成9年度決算案(貸借対照表及び損益計算書)について,監査を行い,その結果,本件監査法人は,これらの財務諸表が一般に公正妥当と認められる財務諸表の作成基準に準拠して原告の同年度の会計期間(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)に関する有用な会計情報を表示しているものと認める旨の監査報告書を提出した。 また,本件監査法人による原告の平成9年度決算案の監査は,関与社員,公認会計士等20名,監査延べ日数825日(前年に比べると170日の増加),監査述べ時間6595時間を費やして行われており(甲136の2頁以下),この時点では,本件監査法
人として,原告の策定した自己査定基準が,資産査定通達,4号実務指針との関係で,さらには商法の規定との関係でも容認される内容であることを確認している。
原告は,同年5月25日開催の取締役会において,平成9年度定時株主総会において,本件利益処分案を決議事項として上程することを承認する旨決議し,同年6月25日開催の定時株主総会において,本件決算配当決議を行い本件決算配当決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7233万6392円の金銭を配当した。(甲8,甲11,甲12,甲132,甲136)
(10) 金融監督庁の発足と金融監督庁による平成10年3月期における金融検査の実施の状況等
ア 金融監督庁の発足
平成9年6月16日に,「金融監督庁設置法」(平成9年法律第101号)及び「金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下「関係整備法」という。)が国会において可決・成立し,同月20日に公布された。
平成10年6月22日,金融監督庁設置法及び関係整備法が施行され,金融監督庁が総理府の外局として発足し,これにより,金融監督庁は,民間金融機関等に対する検査・監督を所管し,従来,銀行法において,大蔵大臣の権限とされていた民間金融機関等の検査・監督権限について,その免許の付与,業務改善命令,業務停止命令,免許の取消し,合併認可等の全ての権限が,内閣総理大臣に移管された。そのうえで,金融検査・監督権限は,免許の付与及びその取消等の権限を除き,内閣総理大臣から法定委任を受けた金融監督庁長官にあるとされた。(乙1の1頁,3頁)
イ 金融監督庁による平成10年3月期決算に対する金融検査の実施
平成10年7月2日に,政府・与党がとりまとめた「金融再生トータルプラン(第2次とりまとめ)」において,「緊急的な措置として金融監督庁は日本銀行と連携しつつ,主要19行に対し,集中的な検査を実施」するとの方針が示されたことを踏まえ,金融監督庁は,同年3月期決算における各行の自己査定結果の報告に基づき,同年7月以降,日銀と連携して(金融監督庁による検査の分担が14行,日銀による考査の分担が5行),主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3行,信託銀行7行)に対する集中検査(以下「平成10年3月期金融検査」という。)を実施した(乙1の131頁,甲97の4頁)。
その際,金融機関等の財務内容の健全性について,早期是正措置の下で自己資本比率に基づき,必要な行政上の措置が適時に講じられることを確保するため,金融機関の自己査定と会計監査人による外部監査を前提に,早急に,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態を把握する必要があるとして,検査の重点事項の一つに,自己査定の正確性及び償却・引当の実施状況が挙げられ,平成10年3月期金融検査において可能な限り幅広く,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態把握すべきものとされていた(乙1の129頁,482頁)。
そして,主要19行の自己査定基準及び償却・引当基準の妥当性並びに自己査定の正確性等を重点として,金融検査が実施された(甲97の4頁,乙1の131頁)。
その結果,原告及び日債銀を除く主要17行について,自己査定結果と当局査定結果の乖離が生じていたことが明らかとなった。すなわち,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して5兆4061億円減少し,そのⅡ分類が3兆5842億円,そのⅢ分類が1兆5708億円,そのⅣ分類が2511億円,それぞれ当局査定結果により増加し,主要17行について1兆0413億円の償却・引当不足が存在した(乙1の131頁~133頁)。
また,当局の指摘事項として,主要17行における自己査定基準については,その内容の一部に問題が認められ,大半の銀行に改善を求めたが,総体としておおむね妥当であること,主な問題点は,上場有配企業等の子会社の債務者区分を,子会社の財務内容等を勘案せずに親会社に準じた債務者区分を行う規程となっていること,要注意先についてその財務内容等を勘案せず一律に,将来の一定期間の収益返済を控除していること,破綻懸念先以下の債務者について有価証券担保の時価から処分可能見込額を差し引いた額に対してⅢ分類とする規程となっていないことが挙げられており,さらに,主要17行における償却・引当の基準は,その内容の一部に問題が認められ,大半の銀行に改善を求めたが,総体として4号実務指針に整合し,おおむね
妥当であること,主な問題点には,関連ノンバンク等の償却・引当に関して一般の取引先と異なる基準を適用し,その一部を償却・引当の対象外としていること,実質破綻先債権等のⅢ分類について,全額償却する規程となっていないこと等が挙げられていた(乙1の513頁,514頁)。
他方,原告及び日債銀については,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して1兆8683億円減少し,そのⅡ分類が2298億円,そのⅢ分類が1兆3775億円,そのⅣ分類が2610億円,それぞれ当局査定結果により増加し,償却・引当の適切性については,自己査定が正確に行われていない,償却・引当の基準に問題があると指摘され,原告及び日債銀について8323億円の償却・引当不足があると指摘された(乙1の131頁,132頁,133頁)。(甲97,乙1)
ウ 原告に対する日銀考査の状況
日銀は,平成10年4月13日,原告に対し,同年3月期を対象とする日銀考査を申し入れ,原告の自己査定基準に関する資料の提出を受け,同年5月21日から,考査を実施した。
その際,考査を担当した日銀職員は,資産査定通達と全銀協追加Q&Aを参照にして,原告から提出を受けた自己査定基準に関する資料の適否を検討したが,自己査定運用細則において,債務者区分を「その他」としている点は資産査定通達における債務者区分に違反していること,このような基準は,恣意性が働くため,自己査定結果がゆがめられ,適切な償却・引当が実施されず,適正な財務諸表が作成されないとの問題があると認識し,それを原告側に指摘するなどした。(甲68)
エ 金融監督庁による原告に対する金融検査の概要等
金融監督庁は,原告の平成10年3月期(平成9年12月までの自己査定とそれに基づく償却・引当の数額に,平成10年3月までの後発事象による修正をしたものとなる。)を対象として,同年7月7日,原告に対する金融検査の実施を決定し,その旨原告に予告し,その際,主任金融検査官を務めたV(以下「V主任検査官」という。),金融検査官U(以下「U検査官」という。)ら原告の検査を担当した金融検査官は,同月9日に,原告との間で検査の抽出基準について意見調整をした。
その後,同年13日から立入検査が開始され(実質検査の開始同月16日),同年8月21日には,同年3月期を対象とした金融検査は,ほぼ終了したが,同日,原告が住友信託との合併に伴う日本リースに対する支援計画を発表したため,改めて,同年6月末時点における自己査定結果(同年9月中間決算における基礎資料)に基づく検査が実施された。(甲97)
オ 金融検査官による指摘,本件監査法人の担当会計士との面談状況等
(ア) 金融検査における金融検査官の指摘
V主任検査官は,平成10年7月以降の金融検査において,同月14日,原告側担当者に対し,自己査定ワークシートにおける債務者区分について,関連ノンバンク等を「その他」としているのは適当ではないと指摘し,これに対し,原告側担当者は,「その他」という債務者区分について内部において議論し,また,他行の動向を聴取し,同様の検討がされていたこと,日銀考査において日銀の担当者とも議論したが,その際,日銀内部において原告と同様の考え方をする者も,少数であるがいたことを説明した。また,V主任検査官は,原告側担当者に対し,債務者区分のポイントは貸出金が回収可能か否かであり,回収が可能(何十年も要するものは不可)であれば,状況に応じて正常先又は要注意先とし,それ以外は破綻懸念先以下に分類す
べきであると説明した。(甲97添付資料6)
(イ) 金融検査官と本件監査法人の担当者との面談状況
その後,同年8月20日,V主任検査官は,T会計士,P会計士及びQ会計士と面談し,その際,自己査定運用細則において,関連特定先を機械的に正常又は要注意先に分類することが誤りではないかと指摘し,P会計士は,資産分類が償却に結びついており,原告の経営により「グリップ」されている以上,破綻する先ではないこと,ロス認識として不動産は価値減算を考えるものではなく,長期的には回収可能性があることを説明した。
また,V主任検査官は,エヌイーディーに対する支援予定(Ⅲ分類)について引当がない点を質問し,P会計士は,経済的利益供与が貸倒引当の概念に該当しない,未払金の計上という方法があるが,企業会計実務の中で一般慣行として定着していない,原告の考え方も妥当の範囲内であると回答し,また,T会計士は,支援について現金供与もあり,貸出金の引当という考え方になじまないと説明した。(甲97添付資料9)
(ウ) 金融検査終了後の意見交換の状況
V主任検査官は,検査終了後の平成10年9月29日,B(当時頭取)と面談し,原告の自己査定と当局査定の差違について,「その他」の区分のような原告独自のものがあること,関連親密先の自己査定運用規則の中で,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」以外にないとしている点については,客観的には「破綻懸念先」が存在すること,自己査定において,返済に何年かかっても,事業継続が可能であるとして「要注意先」としており,意見の相違があったこと,原告の考え方は,現在の環境下では客観・妥当性のあるものといえないと指摘した。(甲97添付資料10)
カ 平成10年3月期金融検査における各関連親密先に対する資産査定及び償却・引当の不足額の指摘状況等
(ア) エヌイーディーに対する認定
U検査官は,エヌイーディーについては,原告による同社の支援計画について,2951億円の支援額はⅢ分類及びⅣ分類の合計額を上回り,計画どおり支援が実施されれば,同社は再建されるとして破綻懸念先に区分し,当期支援額201億8000万円をⅣ分類とし,Ⅲ分類を1543億6500万円(上記貸出金及び支払承諾額並びに貸付有価証券残高の合計額からⅣ分類額を控除),非分類12億2000万円(貸付有価証券残高40億2000万円から当該貸付に係る他行借入金28億円を控除したもの)と査定した。(甲69の1の41頁,甲151,甲152)
(イ) エヌイーディーの受皿会社7社に対する認定
U検査官は,青葉エステート及びユニベスト外4社について,いずれも実質破綻先と区分し,その貸出金全額(青葉エステート247億8400万円,ユニベスト74億0300万円,グラベス31億9600万円,コーポレックス13億6200万円,プロクセル5億9600万円及び日本ビルボゼ1億3100万円)についてⅣ分類と査定した。
他方,U検査官は,エクセレーブファイナンスについて,原告の同社への貸出金がエヌイーディーに全額貸し付けられ,エクセレーブファイナンスへの貸出金の回収可能性はエヌイーディーからの回収に全面的に依拠している以上,同社がエヌイーディーと一体であるとして,破綻懸念先に区分し,同社への貸出金400億円をⅢ分類と査定した。(甲69の1の73頁,甲78,甲153,弁論の全趣旨)
(ウ) 第一ファイナンスに対する認定
U検査官は,第一ファイナンスについて,破綻懸念先に区分し,Ⅳ分類477億4800万円(引当額,同社の営業貸付金のⅣ分類の額,上場有価証券含み損及び非上場株式含み損の合計額),Ⅲ分類203億9800万円(同社の営業貸付金のⅢ分類の額),Ⅱ分類445億6800万円(原告の同社貸出金からⅣ分類及びⅢ分類の合計額並びに優良担保額を控除したもの)と査定した(甲147の21頁,22頁,同添付資料1)。(甲46の1,甲71ないし甲73,甲147添付資料1)
(エ) 日本リース
原告の担当者(営業六部次長W)は,U検査官に対し,日本リースの債務超過額が1578億9600万円(甲69の1の103頁,甲81添付資料14),基礎収益力が約250億円(甲69の1の104頁,甲81の35頁)であると説明し,これに基づき,U検査官は,日本リースの債務超過の解消に6年程度かかると判断し,同社を体力のない関連ノンバンクとして,債務者区分を破綻懸念先と区分し,原告の日本リースに対する貸出金については,Ⅲ分類に資産分類した。(甲69の1の100頁,甲81)
(オ) 日本リース受皿会社
a 有楽エンタープライズ
U検査官は,有楽エンタープライズについて,同社を実質破綻先と区分し,原告の貸出金について担保による保全部分(20億6500万円)をⅡ分類とし,その残額42億8500万円はⅣ分類と査定した(甲157添付資料一)。(甲69の1の36頁,37頁,甲82,甲83,甲157,弁論の全趣旨)
b 四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート
U検査官は,ビルプロ3社を破綻懸念先に区分し,これらの貸出金については,その担保保全部分をⅡ分類とし(四谷プランニング20億9000万円,木挽町開発7億7300万円,竜泉エステート5億2800万円),その残額(四谷プランニング166億9000万円,木挽町開発107億7700万円,竜泉エステート144億1400万円)をⅢ分類と査定した(甲156添付資料一の1,二の1,三の1)。(甲56の2,甲69の1の29頁,甲84ないし甲87,甲96,甲156,弁論の全趣旨)
(11) 金融再生法の施行と原告の破綻
ア 金融再生法等の成立・施行
平成10年10月12日には金融再生法等が国会において可決・成立し,また同月16日には「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(同年法律第143号,以下「早期健全化法」という。)が国会において可決・成立した。
なお,早期健全化法3条2項は,「金融機関等は,金融再生委員会がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として,次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする」と規定し,この「措置」として,同条項1号は,金融再生法6条2項に規定する基準に従い金融再生委員会が定めるところにより,適切に資産の査定を行うことを規定し,また,同条項2号は,「金融再生委員会が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより,適切に引当等を行うこと」を規定する。
同月23日には,金融再生法,早期健全化法等が施行された。(乙1の4頁,弁論の全趣旨)
イ 原告に対する検査結果の通知と原告の破綻
原告は,平成10年6月以降の株価下落を受けて,同月26日に住友信託との合併構想を発表し,また,同年8月21日,合併を前提とした不良債権処理・経営合理化策を発表するなどしたが,その後も,株価の下落や金融債の販売減少が継続していた。
金融監督庁は,同年10月19日,前記の原告に対する金融検査の結果を通知した。その内容は,同年3月期における資産内容については,検査による資産査定に原告の償却・引当基準を適用して算出した追加償却・引当の要見込額が2747億円(当期未処理損失額)に達しており,同期における有価証券等の含み損額1684億円を前提としても,自己資本額(7871億円)を下回るが,同年9月期において検査結果を踏まえて原告が試算した自己資本額が1600億円となり,有価証券等の含み損額が5000億円に達するというものであった。
原告は,同月23日,金融再生法68条2項により,内閣総理大臣に対し,「その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められる」旨の申出をし,これに対し,原告の申出及び原告の検査結果による財務状況を踏まえ,同日,内閣総理大臣により,金融再生法36条1項による特別公的管理の開始の決定がされた。(甲97添付資料11,乙1の70頁,71頁)
(12) 金融検査マニュアルの公表,税効果会計の導入,4号実務指針改正の経緯等
ア 金融検査マニュアルの作成・公表
(ア) 金融検査マニュアルの検討状況
金融監督庁は,平成10年8月25日,検査部に「金融検査マニュアル検討会」を設置し,金融検査マニュアルに関する検討を行い,同年12月には「中間とりまとめ」(以下「マニュアル中間とりまとめ」という。)を作成・公表し,広くパブリックコメントを求めた。
マニュアル中間とりまとめの中には,「破綻懸念先」に係る「経営改善計画」については,「原則として5年以内」であること,「10年以内となっている場合」には,「経営改善計画等の進捗状況が計画どおり」すなわち「(売上高等及び当期利益が事業計画に比して8割以上確保されていること)」,「計画終了後の当該債務者区分が正常先となる計画であること」が示され,また,「特定債務者支援引当金」という勘定科目について,「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」こと,「なお,債権放棄の方法による支援に伴う
損失見込額を,特定債務者支援引当金として計上していない場合は,貸倒引当金として計上する必要があるので,別途貸倒引当金として計上しているかを検証する」ことが示されていた。
この中間とりまとめに対しては,その基準案をそのまま適用した場合には,破綻懸念先等に該当する中小企業が増加し,貸し渋りや資金の回収が拡大するおそれがあること(日本商工会議所等),要注意先について,基準を機械的に適用した場合,債務者にとって厳しすぎる結果となること(全銀協),破綻懸念先のうち金融支援先については,経営改善計画を策定中の債務者や10年超の長期の改善計画に基づいて着実に改善している債務者が破綻懸念先に追い込まれることのないよう,経営改善計画等については,当該債務者の事業の継続性が十分認められる計画となっているかどうかなど,計画期間にかかわらず総合的に判断すべきとする意見(全銀協)や計画期間はケースバイケースの個別判断が適当であること(個人会計士),償却・引当
に関する検査については,原案がそのまま平成11年7月以降適用される場合には,新基準への対応のため経過期間を設けるなど計画的引当が可能となるような措置を要望すること(第二地方銀行協会)等の指摘がされていた。(乙1の158頁,555頁,556頁,乙30の50頁,乙31)
(イ) 金融検査マニュアルの内容,公表
その後,金融検査マニュアル検討会は,上記(ア)のパブリックコメント等も踏まえ,平成11年4月8日付けで,その「最終取りまとめ」を作成し,公表した。
a 破綻懸念先の意義の改正
「破綻懸念先」については「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」であり,具体的には「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」とあったが,上記「債務者」の後に括弧書きとして「(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)」と付記し,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており」以下の部分が削除され,「現
状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり,従って損失発生の可能性が高い状況で,今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」と改められた。
なお,マニュアル中間とりまとめにおいて,「経営改善計画」について「原則として5年以内」,「10年以内」とされていた部分が「原則として概ね5年以内」,「概ね10年以内」と改められ,「(売上高等及び当期利益が事業計画に比して8割以上確保されていること)」とある部分も「概ね8割以上」と改められ,「計画終了後の当該債務者区分が正常先となる計画であること」についても,ただし書が付記され,「計画終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず,自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は,計画終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても差し支えない」と改められた。(甲136の38頁,39頁,乙1,乙30)
b 特定債務者支援引当金の新設
金融検査マニュアルにおいては,「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合」においては,「原則として,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上する」こと,また,「特定債務者に対する債権放棄,現金贈与等の方法による支援に伴う損失見込額については,特定債務者支援引当金を計上することが基本であるが,債権放棄の方法により支援を行っている場合において,当該特定の債務者区分が破綻懸念先で支援に伴う損失見込額が債権の範囲内であり,かつ,当該損失見込額が少額で特定債務者支援引当金を設定する必要性に乏しい場合など合理的な根拠がある場合は,個別貸倒引当金として
計上できる」ことが改正された。すなわち,「特定債務者支援引当金」という新たな勘定科目を新設し,支援が予定されている場合において,あらかじめその支援に必要な費用について引当金を計上すべきことが定められた。
なお,マニュアル中間とりまとめにおいては「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」とされていたが,これについても「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は」の後に「原則として」を付記し,その後の「当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」とある部分を「計上しなければならない」から「計上する」と改めた。(甲136の38頁,40頁,乙
1,乙30)
c 金融検査マニュアルにおける主な改正点
これらの改正の結果として,金融機関が支援を継続していることのみをもって要注意先と査定し得る余地があった部分について,この改正により金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については,経営改善計画等の計画期間が5年以内であり,計画の実現可能性が高く,計画終了後に当該債務者が原則として正常先となること等の一定の条件を満たす場合に限り,要注意先であると判断して差し支えないとすること,これらの条件を満たさない場合には「破綻懸念先」とすべきことが明示的に定められた。
また,経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,原則として,当該支援に伴い発生が見込まれる損失額を算定し,当該損失見込額に相当する額について,特定債務者支援引当金という勘定科目を設定し(又は貸倒引当金として),これを計上することが明示的に定められた。(甲136,乙1,乙30の49頁)
イ 税効果会計の導入に関する政省令の改正と銀行決算に与えた影響
(ア) 税効果会計の導入
企業会計審議会(平成10年政令第392号金融庁組織令24条参照)は,平成10年10月30日付けで,「税効果会計に関する会計基準の設定に関する意見書」を作成・公表し,連結財務諸表のほか(なお,連結財務諸表は,平成9年6月6日の連結財務諸表規則の改正により税効果会計を全面的に適用するとされていた。),個別財務諸表,中間財務諸表及び中間連結財務諸表を対象として,税効果会計に係る包括的な基準が示された。
これを踏まえて,同年大蔵省令第173号により,財務諸表規則,「連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という。)及び「中間財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表規則」という。)が改正され,個別財務諸表,連結財務諸表及び中間財務諸表における税効果会計の適用に関する規定が整備された。
すなわち,財務諸表規則8条の11において,「法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については,税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差違がある場合において,当該差違に係る法人税等の金額を適切に配分することにより,法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。」と規定され,連結財務諸表規則及び中間財務諸表規則においても同様の規定が定められている。
その適用については,財務諸表規則等の一部を改正する省令附則3条により,平成11年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から,税効果会計の適用が義務づけられた。なお,平成11年4月1日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち,同日以後に提出される有価証券報告書及び有価証券報告書に記載されるもの(すなわち,平成11年1月決算以後の決算期に係るもの)について早期に適用することも認められていた。(乙36)
(イ) 銀行決算に対する税効果会計の導入とその効果
その後,前記(ア)の早期適用として,平成11年3月期決算において銀行の決算に税効果会計が導入されたことに伴い,主要17行(都銀9行,長期信用銀行1行,信託銀行7行)は,約6兆6500億円の繰延税金資産を計上した。
また,主要17行は,不良債権を約10兆4000億円(個別債権処理額及び一般貸倒引当金繰入額の合計額)を処理し,そのため,多数の銀行が赤字決算を行ったが,それにもかかわらず,上記繰延税金資産の計上の効果として,平成10年3月期において2兆2400億円であった剰余金の額は,かえって,平成11年3月期において2兆6800億円に増加した。
そのため,税効果会計の導入により,会計と税務が切り離され,その結果,従来と比較して,有税による不良債権の処理すなわち償却・引当の自由度が高まったと評価された。(乙34,乙126,弁論の全趣旨)
ウ 4号実務指針の改正
会計士協会は,平成11年4月30日付けで,前記アの金融検査マニュアルの作成・公表を受けて,4号実務指針の一部を改正し,その中で,金融機関等の支援を前提として経営改善計画が策定されている債務者については,再建計画の実現可能性,その進捗状況及び今後の債務者の財政状態の回復の見込み等を総合的に判断し,自己査定が行われていることを確認すること,破綻懸念先債権については,「経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく」との文言が付加されたこと,「関連ノンバンクに対する債権」に関して,原則として関連ノンバンクが金融機関と同様の方法により自己査定及び償却・引当を行ったうえでの財政状態に基づいて査定を行う必要があること,経営支援先である関連ノンバンクに対する債権に係る今後の支援による予想損失
額について,債権放棄により支援を行う場合には貸倒引当金として,現金贈与等により支援を行う場合には特定債務者支援引当金として,それぞれ貸借対照表に計上しなければならないことが,改正の内容として定められた。(乙33,弁論の全趣旨)
4 争点③(平成10年3月期以前の改正前決算経理基準のもとで,銀行等金融 機関の不良債権の償却・引当に関する基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか。)について
2で検討したとおり,原告らの主張する資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が平成10年3月期における銀行等の貸出金の償却・引当の処理に関する基準として,「公正なる会計慣行」に該当し,しかもその内容が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされるためには,従前の「公正なる会計慣行」との関係で,変更される会計慣行の内容によって企業会計の継続性の観点からの支障が生ずるような場合には,これに対する手当をする必要があると解されるところ,既に述べたとおり,銀行等の金融機関の不良債権の償却・引当の処理に関する従前の「公正なる会計慣行」の内容がどのようなものであったかについては,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったか否かの点で当事者
間に争いがあるので,以下では,まず平成9年3月期以前の銀行等の貸出金の償却・引当の処理が実際にどのようにして行われていたのかを検討したうえで,当時の銀行等の貸出金の償却・引当の処理の基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか否かについて判断する。
(1) 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準の導入より以前の段階,すなわち,平成9年3月期までに存在していた銀行の貸出金に関する償却・引当基準)の内容等
ア 平成9年3月期以前から存在していた株式会社の決算業務に係る会計処理の諸原則
(ア) 企業会計原則
a 企業会計原則と商法32条2項の「公正なる会計慣行」
企業会計原則(甲98添付資料5)は,昭和24年7月9日付けで,企業会計審議会(当時において経済安定本部企業会計制度対策調査会)の中間報告として作成・公表され,また,これを解説した企業会計原則注解は,昭和29年7月14日付けで,企業会計審議会の中間報告として作成・公表された。その内容は,「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを要約したもの」であるとされており(乙94の219頁,乙98の108頁),企業会計原則は「法令によって強制されないでも,全ての企業が従わなければならない基準」(企業会計原則の前文)とされている企業会計の基本的な事項を定めたものとされている。
ところで,証券取引法193条の2は,証券取引所に上場されている有価証券の発行会社に対し,同法の規定により提出する貸借対照表,損益計算書その他の財務計算に関する書類については,その者と特別利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと規定し,監査証明の方法については,「監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書等により行う旨規定していた。そして, この監査報告書の作成に当たっては,会計監査人における監査証明に係る会計実務において,企業会計原則は,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に当たるとする解釈・運用が採られていた(乙98の106頁)。
また,昭和49年の商法改正(昭和49年法律第21号)により,商法32条2項が規定され,企業会計原則は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するとの解釈・運用が,会計実務において採られていた。
このような経緯を踏まえる限り,企業会計原則・同注解は,平成9年3月期以前から,企業の会計処理に関しては,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たるものであったというべきである。
なお,企業会計原則においては,真実性の原則(「企業会計は,企業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければならない」),明瞭性の原則(「企業会計は,財務諸表によって,利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し,企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない」),継続性の原則(「企業会計は,その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し,みだりにこれを変更してはならない」),保守主義(「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には,これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない」)等の諸原則が定められており,これらの諸原則は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」として尊重されなければならないと解される。(甲98,甲159,
乙3,乙44,乙94ないし乙96,弁論の全趣旨)
b 企業会計原則における「貸倒見積高」,「貸倒引当金」
企業会計原則第三の四(一)Dでは,受取手形,売掛金その他債権に対する貸倒引当金は,原則として,その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形式で記載することが定められ,同原則注解の注18には,将来の特定の費用又は損失であって,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができる場合には,当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとすることが定められている。 また,企業会計原則第三の五Cでは,受取手形,売掛金その他の債権の貸借対照表価額は,債権金額又は取得金額から正常な貸倒見積高を控除した金額とすることが定められている。
(甲98添付資料5)
(イ) 貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い
会計士協会は,監査委員会報告第5号として,昭和40年4月6日付け「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(昭和51年4月6日改正)(以下「委員会報告第5号」という。)を作成・公表した。委員会報告書第5号によれば,監査報告書における意見を付ける際の指標として,貸倒引当金について,例えば,企業が一定の算定基準を有していたとしても,その基準が合理的かつ客観的でないと認められるとき,又は明らかに不足あるいは超過していると認められるときは,除外事項とすること,ただし,企業が算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合を除いては,除外事項としないこ
とができるとされていた。そして,その趣旨は,適正な貸倒見積高の算定に当たっては,我が国の会計慣行とりわけ税法基準を多くの企業が採用しているという実情を踏まえたうえで,税の確定決算主義の立場等を考慮して,税法基準によって算出した貸倒見積高を計上している場合でも一定の条件のもとに一般に認められた企業会計の基準に準拠しているものとして取り扱うことができる旨定めたものであり,税法基準を採用している場合にはこれは継続して適用すべきことを要請しているものであるとされていた。(乙13,弁論の全趣旨)
なお,ここでいう税法基準とは,法人税法で損金算入が認められる限度額において企業会計の費用又は損失を経理処理すれば足り,法人税法上容認される損金算入限度額を超えてまで費用として処理する必要がないとするものであるが,本件では,銀行における貸出金の償却・引当の処理に関する会計実務とこの税法基準との関係が問題となるので,後に項を改めて検討することとする。
イ 銀行特有の規制,銀行特有の企業会計の基準
(ア) 銀行法による特殊な規制と大蔵省の監督権限
a 銀行法の規制
銀行法(昭和56年法律第59号。なお,平成10年法律第131号による改正前のもの)は,銀行経営の高度の公共性にかんがみ,一般大衆の預金の保護,信用維持等の観点から,銀行に対し,免許制,営む業務の限定,取締役の兼職の制限等,一般私企業にはない各種の規制を定めていた。 そして,原告については,長期信用銀行法により,銀行法の規制が準用されるか,又は銀行と同様の規制が設けられていた。
b 大蔵省による監督・規制権限
このような銀行経営の健全性及び適切性については,銀行の取締役等が,これを維持すべき職責を負うもの(銀行法1条2項参照)であり,このような観点から,銀行の取締役に銀行経営に専念させるべく,銀行法7条等の規制が設けられていると解されるが,銀行法は,従前(平成10年法律第131号改正前),大蔵省に銀行経営に対する広範な監督・規制権限を認めており,大蔵省によるこのような権限の行使を通じて,銀行経営の健全性及び適切性を確保することを定めていた。
すなわち,銀行の取締役の兼職については,大蔵大臣が認可する権限を有しており(銀行法24条1項),また,大蔵大臣に立入検査権限(同法25条1項),業務の停止等の権限(同法26条),免許取消等の権限(同法27条)を与えていた。 そして,大蔵省は,銀行経営の健全性及び適切性を確保する見地から,銀行免許の認可・剥奪権限(銀行法4条,27条),銀行取締役又は監査役の解任権限(同法27条)及び業務停止等の権限(同法26条)を有し,これらの諸権限を適正に行使するとともに,銀行それ自体の経営を監督・監視するため,その権限の行使を妨げた場合に刑罰(銀行法63条)による制裁を伴う資料提出権限(同法24条)及び立入調査権限(同25条)が認められており,大蔵省が銀行の経営に対する広
範な監督権限を有するなど,通常の株式会社と全く異なる規制が存在していた。
c 大蔵省検査
大蔵省は,銀行法上の大蔵大臣の立入検査の権限(銀行法25条)に基づき,平成10年3月期以前においては,銀行の経営の健全性を確保し,銀行業務の健全かつ適正な運営を期するため,一定期間(通常は2,3年に1回)ごとに,金融機関の経営状況全般についての検査を実施していた(甲69の2の4頁,5頁,甲97の4頁,乙115の7頁)。
この大蔵省検査において,金融証券検査官は,銀行の貸出金等の資産査定すなわち貸出金等の資産個別に検討して確実性の度合に応じ,4段階に分類する作業を実施していた。
その際の分類の方法については,昭和42年1月27日付け事務連絡銀検第28号「資産査定上の調整事項について」(昭和56年6月30日付け事務連絡銀検第131号改正,平成8年8月30日事務連絡最終改正)に従い(甲231添付資料2),非分類すなわちⅠ分類(「Ⅱ,Ⅲ及びⅣ分類以外の資産」),Ⅱ分類(「債権確保上の諸条件が満足に充たされないため,あるいは,信用上疑義が存する等の理由により,その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権及び何らかの理由により金融機関の資産として好ましくないと判定されるその他の資産」),Ⅲ分類(「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し,従って損失の発生が見込まれるが,その損失額の確定し得ない資産(Ⅲ分類額の50パーセント相当額は
正味自己資本査定上損失とする。)」)及びⅣ分類(「回収不可能又は無価値と判定される資産」)に分類するものと定められていた。
銀行等の金融機関は,このような金融証券検査官の実施した資産分類に沿って,その財務諸表を作成し,外部の監査を受けるなどして(甲139の19頁),決算業務及び会計処理を行っていた。(甲69の2,甲97,甲139,甲231,弁論の全趣旨)
(イ) 銀行特有の会計
このような銀行法による特殊な規制及び大蔵省の監督権限については,銀行における企業会計処理にも及んでいた。
すなわち,銀行は,毎営業年度ごとに,大蔵省令で定めるところにより,貸借対照表及び損益計算書を作成して,当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならないとされ(銀行法20条),さらに,銀行が商法第281条第1項(計算書類)の規定により作成する営業報告書及び附属明細書の記載事項は,大蔵省令で定めるとされ(同法22条),銀行の決算も大蔵省の監督下に置かれ,かつ,その決算書類(貸借対照表,損益計算書等)についても,大蔵省令において規定されていた。
また,本来,商法281条1項により毎決算期において株式会社が作成すべき貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書の記載方法は,「株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に関する規則」(以下「計算書類規則」という。)(昭和38年法務省令第31号。現平成14年法務省令第22号の商法施行規則)1条により,計算書類規則の定めるところによる旨規定されているが,銀行及び長期信用銀行が作成すべき商法第281条第1項に掲げる貸借対照表及び損益計算書の記載方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法については,「株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令」(昭和57年法務省令第42号)3条によ
り,計算書類規則2条1項の「貸借対照表及び損益計算書は,会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない」との規定すなわち明瞭性の原則を除き,計算書類規則の適用が排除され,それぞれ,銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)及び長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)の定めるところによる旨規定されていた。
これらの規制により,商法281条1項の毎決算期における貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書については,銀行法上の業務報告書により代置され,また,その記載方法についても,大蔵省令により定められていた。(乙6,弁論の全趣旨)
(ウ) 改正前決算経理基準
a 統一経理基準の沿革
前記のとおり,銀行における会計処理の業務は,法令により銀行経営の健全性及び適切性を確保するため,大蔵省の監督・規制下に置かれていたが,大蔵省は,このような法律上の規制に加えて,通達により,銀行の決算処理(会計処理)の業務を規制していた。
すなわち,大蔵省銀行局長は,昭和42年9月30日蔵銀1507号通達により,銀行が決算において従うべき会計の基準として,統一経理基準を示していたが,その後,数次の改正を経て,昭和50年7月7日蔵銀第1993号「銀行の経理基準について」と題する通達を発出し,新たな統一経理基準を示した。
その間,各銀行は,これらの統一経理基準に従い,決算業務を行っていたところ,会計士協会は,昭和51年10月付け「銀行業統一経理基準および財務諸表様式に係る監査上の取扱いについて」を作成・公表し,その中で,「昭和42年9月30日蔵銀1507号」として発せられた銀行業の統一経理基準について,今回の新通達『銀行の経理基準について』(昭和50年7月7日蔵銀第1993号,以下「現統一経理基準」という。)によって改正されるまでの間,数次にわたりその一部が改正されて今日に至っているが,各銀行はこれらの統一経理基準を銀行業における統一的な企業会計の基準として採用し,現在すでに会計慣行化しているものと考えられる旨述べて,現統一経理基準に基づく会計処理は,商法32条2項にいう「公正な会
計慣行」に合致しているものとして取り扱うことを明らかにして,統一経理基準が,銀行の決算経理の処理に関する「公正なる会計慣行」であるとの見解を表明した。(証人L23頁,甲228,乙6,乙7,乙81,乙120,弁論の全趣旨)
b 改正前決算経理基準の沿革等
その後,大蔵省銀行局長は,銀行法(昭和56年法律第59号)の施行に伴い,各普通銀行の代表者に宛てて,昭和57年4月1日付け蔵銀第901号「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」と題する通達を発出し,経理関係について,普通銀行が従うべき会計処理の基準として 前記統一経理基準を踏襲した改正前決算経理基準が発出され,普通銀行は,その経理処理を行うに当たり,改正前決算経理基準を遵守しなければならないものとされるに至った(乙6の7頁,乙11の21頁,乙81の4枚目)。
そして,普通銀行は,上記通達の発出以降,改正前決算経理基準に従い,会計処理を行っていたところ(甲60の51頁,甲122の82頁,甲133の141頁,甲136の9頁,同99頁,甲128の46頁,甲123の135頁),原告を含む長期信用銀行においては,固有の通達が発出されておらず,普通銀行に関する改正前決算経理基準を準用する取扱いが採られており(乙42の19頁),普通銀行と同様に,長期信用銀行においても,この改正前決算経理基準に従い,決算のための会計処理業務が行われていた。(証人L,甲60,甲122,甲123,甲128,甲133,甲136,乙6,乙11,乙42,乙81)
c 改正前決算経理基準における基本原則と「貸出金の償却」及び「貸倒引当金」の計上基準
改正前決算経理基準では,貸出金の償却として「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額を償却するものとする。なお,有税償却する貸出金については,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。」と定められ,また,貸倒引当金については,「貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定〔租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。以下同じ。〕を除く。)は,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとし,また,租税特別措置法第55条の2第7項の規定に係る貸倒引当金相当額を有税により繰り入れるものとする。」,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものと
する。なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。」と定められていた。(甲183,甲231,乙6)
なお,改正前決算経理基準においても,企業会計原則と同様に①真実性の原則,②明瞭性の原則,③継続性の原則,④保守性の原則等が定められている(乙6の7頁)。
(エ) 不良債権償却証明制度
a 不良債権償却証明制度の沿革
昭和25年以降,銀行を含む金融機関等の不良債権の損金処理,すなわち無税による償却・引当(法人税基本通達9-6-1ないし9-6-7に基づく処理)については,銀行と国税庁との協議に基づき実施され,金融証券検査官がⅣ分類及びこれに準ずるものとして証明した不良債権の金額は,原則として法人税法52条1項の「損金」に算入することが認められていた(乙5の40頁,乙6の13頁,乙9の350頁,乙11の24頁)。
なお,平成5年11月29日蔵検第439号「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,大蔵省による後記ウ(ア)の不良債権処理の方針を受けて,平成6年2月8日蔵検第53号一部改正通達が発出され,後記cのとおり,有税による償却・引当に関する内容が改正されたほかは,基本的には従前と同内容であった(乙9の350頁)。(乙5,乙6,乙9,乙11,弁論の全趣旨)
b 不良債権償却証明制度実施要領の内容
まず,金融機関等が必要な償却を行い,資産内容の充実を図ることは望ましいが,証明官の審査が厳に失し,あるいは寛に流れるときは本制度の本来の意義を失うおそれがあるので,税務当局との密接な連絡を保ちつつ,適正且つ慎重に審査を行うことが方針として示され,管轄及び証明官として,原告のような長期信用銀行においては,大蔵省金融検査部長が指名する上席金融証券検査官が証明手続を担当することと定められていた。
その証明内容については,直接償却の場合は,法人税基本通達「9-6-2」(回収不能の貸金等の貸倒れ)の貸金等の貸倒れの金額等についての証明を受けること,「間接償却」の場合は,法人税基本通達「9-6-4」(認定による債権償却特別勘定の設定)及び『9-6-7』(状況が変化した場合等の債権償却特別勘定の積増し)の債権償却特別勘定繰入れについてその金額等の証明を受けることがそれぞれ定められていた(乙9の351頁)。
証明手続については,各期末の償却予定債権の件数及び金額の概数並びに償却予定債務者明細(別添様式1)を,決算期末の2か月前の月の末日までに,大蔵省金融検査部審査課総括係宛てに提出することが定められており,具体的な提出書類としては,その証明内容ごとに,例えば,法人税基本通達「9-6-2 」(回収不能の貸金等の貸倒れ)の貸金等の貸倒れの金額の証明を受ける場合には,不良債権償却証明申請書及び不良債権明細表が提出書類と定められており,証明に当たっては,大蔵省金融検査部長の決裁を経て,正式発遣の手続がとられた(乙9の352頁,353頁)。
審査手続については,原則として,決算期末の月を審査の期間とすること,また,前回大蔵省検査後相当日時を経過している等の理由により必要と認める場合は,実地調査が行われること,申請債権について当期決算の概略(償却・引当の能力に重点を置く。),要償却債権の全貌(申請債権以外の要償却債権の有無及びその金額)等を調査事項とすること,実地調査に当たっては,金融機関に対し,貸出稟議書,信用調査資料,償却稟議書,申請債権に関する参考書類,当期決算予想表及び申請債権以外の不良債権一覧表を準備するよう求めることがそれぞれ定められていた。
具体的な査定基準としては,例えば,大蔵省検査の際にⅣ分類と査定された債権等について償却対象とし,回収不能額又は回収不能見込額を算定することが定められ,また,法人税基本通達9-6-4による債権償却特別勘定への無税繰入れに係る金額を証明する場合には,債務超過の状態が相当期間継続しているかどうか,事業好転の見通しがないかどうかを審査し,貸金等の額の相当部分(おおむね50パーセント)以上の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について判断すべきことが定められていた。
なお,上記事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないと定められていた(乙9の357頁)。
また,実際に,不良債権償却証明制度に基づき,銀行がその証明を受ける場合には,必要な資料を作成し,償却証明の申請を行い,債権償却特別勘定への繰入れが認められるかどうかについて質疑応答等を繰り返して,これが認められれば,金融証券検査官から期末までに債権償却証明の証明書が届けられた(証人X〔以下「証人X」という。〕6頁)。(証人X,甲131,乙9,乙11)
c 不良債権償却証明制度のもとにおける有税による償却・引当の取扱い
他方,有税償却・引当については,平成4年7月ころまでは,無税償却・引当と同様に大蔵省の承認を要したが,後記ウ(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」を公表した際,有税引当の活用を図るため,前記aの平成6年2月8日蔵検第53号一部改正通達により,以下の内容が定められた。
すなわち,まず届出制に改められ,有税引当等(有税引当及び有税直接償却)については,届出の受理に当たって,金融機関等の自主判断により行われるものであることに留意することとされ,また,届出があった際には,無税償却の適用がないかどうか等について聴取するものと定められ,その際には「不良債権有税引当等届出書」を作成し,無税償却・引当に関する提出手続に準じて,これを提出させることとされていた。
なお,不良債権有税引当等届出書の様式は,無税による償却・引当に係る不良債権明細表等と同様の様式であった。また,届出制に改められた後も,債権償却特別勘定への繰入れは,銀行による過剰引当が行われるなどの決算操作に利用されることを防止するため,有税による償却・引当についても,無税の場合と同様の資料を作成し,回収不能又はそれが見込まれる根拠やその金額について説明が行われる必要があった。 すなわち,この両者は,その説明を疎明する資料の有無,程度が多少相違するというものであるにすぎず,基本的には,銀行は,貸出金に関する償却・引当の根拠を十分に説明する必要があり,実質的には同様の手続であった(証人X5頁,33頁,甲136の9頁,乙118の9頁)。(証人X,
甲58,甲125,甲131,甲136の9頁,甲158,乙5,乙6,乙9,乙11,乙118)
そして,無税償却・引当の対象となるべき貸出金については,明示的に償却・引当が義務づけられていた。一方で,有税償却・引当については,その内容を当局に届け出る旨が定められているにすぎず,しかも具体的にどのような基準により償却・引当を実施すべきかについては明確な基準が存しなかったばかりか,有税償却・引当は,金融機関の自主的な経営判断で行うべきものとされ,無税償却・引当の場合のような不良債権償却証明制度のもとでの審査は行う必要がないものとされていた。その結果,有税償却は無税償却と異なり銀行の決算内容に負担を及ぼすこともあって,銀行は,もっぱら,無税償却・引当が可能な場合に償却・引当を行い,有税による償却・引当をほとんど行っていないのが実情であった。(証人L3頁,証人K8頁
,甲60,甲118,甲158の29頁,乙10の50頁,甲158の30頁,弁論の全趣旨)。
(オ) 小括
以上のような平成9年3月期以前に存在していた銀行の決算業務における会計処理の諸原則を前提とすると,平成9年3月期以前の銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の実務は次のようなものであったといえる。まず,基本的には,「公正なる会計慣行」であるところの企業会計原則・同注解によることになるが,銀行については,自己資本の充実と資産内容の健全化を図る観点から,企業会計原則・同注解よりも規制の厳格な改正前決算経理基準が発出されており,これに従うことになるところ,銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の基準としては,改正前決算経理基準のなかで無税償却・引当の対象となる貸出金については明示的に償却・引当を行うことが義務づけられていたが,有税償却・引当については,平成6年2月に通
達によりその活用を図るため届出制に改められはしたものの,その内容を銀行が自主的に当局に対し届け出る旨定められているにすぎず,具体的にどのような基準により償却・引当を実施すべきかについて明確な基準が存在しないという状況にあり,しかも,有税処理による損失計上は無税処理の場合と比べると銀行の決算内容に負担を及ぼすため,実際には,銀行は有税償却・引当をほとんど行っていないのが実情であった(甲158,乙10)。
そして,改正前決算経理基準のもとで,平成5年11月から通達により不良債権償却証明制度が採用されており,そこではより細かな銀行の貸出金に関する無税償却・引当の基準及び手続が定められていた。その結果,当時の銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の実務としては,不良債権償却証明制度によって補充された改正前決算経理基準に基づき,もっぱら税法上無税償却・引当が可能な場合に償却・引当を行うことが一般化しており,大蔵省検査において,銀行の貸出金がⅣ分類と査定された場合には,不良債権償却証明制度を介して回収不可能な貸出金として無税による償却・引当が可能となり,銀行としてもこのようなⅣ分類と査定された貸出金については,当期に全額の償却・引当を実施するものとされていた。このような経緯
から明らかなとおり,大蔵省検査によりⅣ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度を介して,義務的に貸出金の償却・引当を行う一方で,有税による償却・引当については,銀行の自主的な判断に委ねられた結果,実際には有税償却・引当はほとんど行われないという会計慣行が存在していたものといえる。
なお,前記認定のとおり,不良債権償却証明制度が採用される以前から,銀行の貸出金の無税による償却・引当については,銀行と国税庁の協議により実施され,金融検査官の証明により損金算入が認められており,上記のような会計慣行は,実際には,遅くとも資産査定通達が発出された昭和57年以降,会計慣行として定着していたものといえる。
ウ 銀行の不良債権処理に関する大蔵省の指針と銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務
(ア) 大蔵省による不良債権処理に関する指針
大蔵省は,バブル経済の崩壊以降,銀行の不良債権が増大する中,銀行に対して,不良債権を抱えている相手先企業であっても,将来の経済情勢の回復に期待し銀行が時間の猶予を与えることによって,本業の収益により徐々に穴埋めをさせることができるはずであり(乙2の88頁),いわゆるメインバンクである金融機関は,そのような企業の再建のために時間を貸すことが有効であるとするいわゆるソフトランディングの考え方に依拠して,平成4年から平成7年までの間に,以下のような指針を公表して,不良債権の処理方針を示した。
まず,大蔵省が平成4年8月18日付けで公表した「金融行政の当面の運営方針-金融システムの安定性確保と効率化の推進」と題する指針(乙15)によれば,不良資産の処理方針の早期確定とその計画的・段階的処理が急務であり,これにより国民の金融システムへの不安感を払拭するとともに,その安定性の確保に努めることが重要であること,個別問題の早期処理として,住宅金融専門会社,ノンバンク等の個別問題は,極めて多数の金融機関が関与し,利害関係が従来になく錯綜し,処理方針の早期確定と計画的・段階的処理に向けての一層の努力が要請されること,担保不動産の流動化として,不良資産の処理方針の早期確定と計画的・段階的処理を図り,併せて不動産の流動化に資するため,民間金融機関の協調による,担保不動産の
流動化のための方策につき早急な検討を行うこと,不良資産処理のための環境整備として,不良資産の処理が円滑に促進されるよう税務上の取扱いをも含め,必要な環境整備に努めることが指摘されていた。
次に,大蔵省が平成6年2月8日付けで公表した「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」と題する指針(乙16)においては,金融機関の資産内容悪化は,様々なレベルで金融機関に課題をもたらしていること,貸付債権のなかには,融資先企業の業績低下等により,通常に比べて留意を要する債権があることが指摘され,具体的には,その債権の性格ごとに以下のような留意事項が示されていた。
すなわち,「金融機関が,経営上の困難に直面した融資先に対して,金利減免等により支援を行っている債権」については,関係者の努力により元本が回収されるという前提で再建計画が実施されている貸出先に対するものであり,次に述べる破綻先債権,延滞債権と同列に扱うことはできないが,長期にわたって金融機関の収益を圧迫するという問題があること,「融資先が破綻しているか,又は延滞している債権」については,その一部につき回収不能が見込まれ,今後時間をかけて償却等により処理していく必要があるものであること,このような「破綻先債権,延滞債権のみならず,通常に比べて留意を要する債権や金利減免債権等」については,これらを同一視し,そのすべてについて償却等による処理が必要
であるかのように論ずることは適当ではなく,誤解を招くものであることが指摘され,金融機関においては,かつてなく厳しい経営環境のもとで,このような資産内容の実態に即した適切な対応を行っていく必要があり,償却等による処理が必要となるものについては,早期に処理方針を確定させ,計画的,段階的に処理を進めていくことが重要な課題であるとされていた。
また,上記指針の中の「不良資産の処理促進」については,不良債権についての償却・引当制度の活用として,いわゆる無税償却については,不良債権の実態に即した貸倒れ等の事実の認定を通じ,必要な償却を行うとの趣旨を徹底し,ノンバンク向け債権も含め,償却の一層の促進を図るとともに,そのための当局の体制についても引き続き充実強化に努めること,また,有税引当については,従来,金融機関は,貸倒れ又はこれに準ずる状況にある債権について償却・引当を行ってきたが,最近における不良債権の実態にかんがみ,引当制度の運用を改善し,貸倒れには至っていないものの回収に危険のある債権についても,金融機関自らの判断により,将来の回収についてのリスクに応じた必要な引当が行われるようにすることとしたこと,こ
れによって,回収不能とはまだ判定されていないが,リスクが高まっている延滞債権等についても,有税引当が行われることが期待されるが,他方で,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権については,この有税引当を行うことは,当面,企業会計上の合理性がないことになること,このような債権への対処としては,金利減免債権の流動化が検討対象となるところ,金利減免債権の流動化として,多額の不動産関連融資を抱えて資産内容が悪化し,経営上困難に直面しているノンバンク等について,関係金融機関は,金融システムの安定性確保の重要性を認識したうえで,長期的な展望のもとに,自主的に適切な対応を行っていく必要があること,これらのノンバンク等に対し,その再建計画の一環として金利減免
による支援が行われつつあるが,これら金利減免債権は,支援金融機関にとっては長期にわたって収益圧迫要因になり,財務体質の改善上問題があること,しかし,複数の金融機関による再建計画が実施されている場合に,金利減免債権をまったくの第三者に売却することは,再建計画の円滑な進捗を阻害することにもなりかねないことから,再建計画の円滑な進捗と関係金融機関の財務体質の改善を整合させるため,特別目的会社(再建計画の実行を管理する会社)を設立し,これに対して金融機関が抱えるノンバンク等向け金利減免債権が流動化することについて検討することとしたこと,これにより,金融機関は,金利減免債権を市場実勢価格で現物出資し,簿価(金利減免前の債権の帳簿価額)と時価(金利減免後の債権を市場実勢利率に基づく割引率
で現在価値に割り戻した市場実勢価額)との差額をロスカットすることとなるが,元本は回収されることが前提であることが指摘されていた。
そして,このような指針を受けて,平成6年2月8日付けで「不良債権償却証明制度実施要領について」の一部改正通達が発出され,有税による償却・引当に関して,金融機関等の自主判断により,改正前決算経理基準等に基づき,その内容を当局に提出したうえで,有税直接償却及び有税引当の実施がされることとなった。
その後,大蔵省が平成7年6月8日付けで公表した「金融システムの機能回復について」の中には,健全で活力ある金融システムは,我が国経済の安定的発展のため必要不可欠な前提であること,我が国経済が今後21世紀に向けて,豊かで創造的な経済社会を築いていくために,残された概ね5年の間に,金利減免等を行っている債権をも含め,従来の発想にとらわれることなく金融機関の不良債権問題に解決の目処をつけることとすること,このため,金融制度調査会においても基本的考え方について審議される予定であるが,大蔵省としては,当面次のような考え方により不良債権問題の早期解決に取り組み,金融システムの機能回復を図ることが示されていた。
また,その中で,「金融機関の自主的な経営健全化努力」として,行政としても,概ね5年の間に,金利減免等債権を含む不良債権問題の解決に目処をつけるため,所要の環境整備を図り,金融機関の真摯な経営努力を促すこと,その中で金融機関から金利減免等の支援を受けているノンバンク・住宅金融専門会社等については,再建計画の進捗状況の的確な把握が行われるとともに,必要に応じ再建計画の抜本的見直しを含む適切な措置が講じられるようにすること,金利減免等債権を含む不良債権の処理に際し,金融機関の体力や収益環境に応じて弾力的に対応できるよう,段階的な処理方策を検討すること,担保不動産の流動化等に向けた努力が一層要請されることが指摘されていた。
さらに,大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会の金融システム安定化委員会において,平成7年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」(乙17)が答申され,その中でも,不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできる限り早期にその処理に目処をつける必要があること,各金融機関は先ず自助による最大限の合理化努力や早期の引当,償却等の実施により,迅速にその処理を行っていく必要があることが指摘されていた。(乙2,乙11,乙15ないし乙17,乙99,乙117,弁論の全趣旨)
(イ) 銀行における関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務
a 金融慣行としてのメインバンク関係と母体行主義
我が国においては,従前,メインバンク制とかメインバンク関係と呼ばれる銀行と企業との間の取引慣行(金融慣行)が存在しており,その内容は,当該企業にとって,融資取引,預金取引,内国為替の取扱い,外国為替の売買といった銀行取引のいずれにおいても最大の取引シェアを誇る銀行はメインバンクと呼ばれ,このようなメインバンク関係として,当該企業が経営危機に陥った場合を含め,銀行がメインバンクとして企業の発展・成長に必要な設備投資等の資金を安定的に供給し,他方,当該企業においては,安定的な資金供給の見返りとして,あらゆる銀行取引において,メインバンクとの取引シェアを他の銀行よりも高く維持し,また,メインバンクは,当該企業の株式を取得し,その立場に基づき,従業員を当該企業の役員として
派遣するなど,当該企業の経営に実質的に関与し,さらに,当該企業が経営危機に陥った場合には,メインバンクは,その名声(信用)の維持,既存融資の回収の極大化,当該企業との取引の維持による営業基盤の維持拡大といった便益を考慮し,救済による便益がその費用(金利減免に伴う逸失利息,救済融資実行等による損失負担リスクの増大,救済活動に要する費用等)を上回ると判断する場合には,しばしば当該企業を救済する事例がみられた(甲115の127頁,甲116の95頁,乙7)。
このような金融慣行を前提に,バブル崩壊後,不動産関連融資を増大させていた銀行の関連ノンバンクが経営危機に陥っていたため,母体行によるこれらの関連ノンバンクの経営に対する事実上の支配を前提として,これらの関連ノンバンクを再建する母体行主義の慣行が行われていた。すなわち,前記(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」において示されるとおり,母体行による関連ノンバンクの支援計画について,当該関連ノンバンクに対する不良債権(金利減免等の貸出条件を緩和した債権)の処理もさることながら,その再建計画の円滑な進捗にも配慮し,再建計画の実行を管理する特別目的会社の設立及びこの会社への金利減免債権の売却を求めるなど,関連ノンバンクの支援,再建とこれに伴う不良債権の処理につ
いては,できる限り,母体行が関連ノンバンクを支援し再建させる手法が採られていた。
この背景には,各銀行は,相互にそれぞれの関連ノンバンクに融資し,各関連ノンバンクの資産(営業貸付金)状況のみを考慮して一斉に融資の回収をした場合には,関連ノンバンクが資金繰り破綻を起こして倒産し,その結果,母体行である親銀行の経営状況をも圧迫し,我が国の金融システム全体が崩壊するというシステミックリスク(銀行間取引の増大に伴い,ある銀行が破綻した場合に,それが他の銀行に波及し金融機関が連鎖的に倒産する現象を指す。甲115の126頁)が発生することを回避し,母体行がそれぞれの関連ノンバンクを支援し,また,このような母体行以外の銀行は,母体行である銀行の経営状況をも考慮して,当該関連ノンバンクに対する融資取引を継続するという母体行主義が行われていた(甲120の97頁,
99頁,甲123の158頁,甲129の116頁,乙101の2頁,甲69の106頁,乙106の18頁)。このような例は,株式会社富士銀行が芙蓉総合リースを支援した事例,株式会社三菱銀行がダイヤモンドリースを支援した事例,株式会社東海銀行(以下「東海銀行」という。)がセントラルリースを支援した事例が挙げられる(甲120の101頁)。
特に,このような母体行主義の考え方は,いわゆる住専処理について,農林系統金融機関が,設立母体である銀行に全面的な損失負担を求め(「完全母体行主義」などと呼ばれた。),他方,銀行は,プロラタ責任主義(貸出残高の割合すなわちシェアに応じて損失を負担する主義)を主張したが(乙2の149頁から150頁),最終的には,母体行である銀行が債権全額を放棄し(貸付残高を上限として責任を負担する修正母体行主義による責任負担),母体行以外の銀行が一定額の損失を負担する解決が図られたこと(乙2の155頁,甲115の104頁)からも裏付けられる。(甲68の16頁,同131頁,甲115の104頁,105頁,甲116,甲129の116頁,甲231,乙2,乙7,乙8,乙16,乙100,乙101
,乙104,乙110,H本人5頁)
b 大蔵省検査及び日銀考査における関連ノンバンクの資産査定に関する実務等
大蔵省検査及び日銀考査においても,このような母体行主義を前提とした査定が行われていた。
(a) まず,大蔵省検査においては,銀行が関連ノンバンクに多額の融資を行い,バブル経済の崩壊後,これが不良債権化したため,その実態の把握如何により査定結果が大きく変わり,銀行経営への影響が大きくなること,また,銀行は,母体行主義により,関連ノンバンクに対し,支援損(債権放棄)を計上するなどの支援を実施していたことから,検査に当たる金融証券検査官は,この問題を査定の場面においてどのように反映させるべきかについて疑問を持ち,大蔵省金融検査部においてその検討が行われた結果,平成6年4月12日付け「Ⅲ分類及びⅣ分類の査定の考え方等について」と題する文書(甲231添付資料8)により,銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定についての考え方が示された。
その中で,「貸金業を営む関連会社」について,銀行の貸出金残高が100存在し,関連会社の営業貸付金が500である場合において,再建方法として,他行の支援を求めず,親銀行が今後支援損を計上する,例えば,支援損100を3年間で計上することを予定しているときには,100をⅢ分類とすること,ただ,当年度の支援損が確定している場合には,例えば,Ⅳ分類33,Ⅲ分類67とすることが示されていた。
その後,平成7年4月13日付け「当面の貸出金等査定におけるⅢ分類及びⅣ分類の考え方について」と題する大蔵省管理課長発出の事務連絡(乙110,以下「7年事務連絡」という。)において,以下のような考え方が示された。
まず,「一般債務者」については,実質死に体(事業活動は継続しているものの,業況悪化が深刻な状態にあり,再建が困難)の状況にある場合,例えば貸出金残高が100,不動産担保の時価が50掛目0.7,評価35)である場合,Ⅱ分類35,Ⅲ分類15,Ⅳ分類50と査定する案(A案)と,Ⅱ分類50,Ⅳ分類50と査定する案(B案)が示されていた。
次に,「関連ノンバンク」については,体力がある場合(①償却前利益,②内部留保,③含み益,④純資産〔実質ベース〕等を勘案し,不良資産の処理が2~3年〔一応の目途〕で可能な場合)には,「一般債務者」に準ずることが示され,他方,体力がない場合(①償却前利益,②内部留保,③含み益,④純資産〔実質ベース〕等を勘案し,不良資産の処理が2~3年〔一応の目途〕で不可能な場合)には,再建計画の策定の有無により,査定方法が区別されることが示されていた。
この体力がない関連ノンバンクにおいて,再建計画が策定されていない場合には,原則として,「関連ノンバンク」の営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされ,例えば,営業貸付金(200)の査定結果が,非20,Ⅱ80,Ⅲ50,Ⅳ50であれば,関連ノンバンクに対する親銀行の貸出金(150)の査定が,Ⅱ50,Ⅲ50,Ⅳ50とそのまま反映されていた。
これに対し,体力がない関連ノンバンクにおいて,再建計画が策定されている場合(但し,検査官が妥当と判断したものに限る)には,再建計画が策定されていない場合と同様に,原則として,「関連ノンバンク」の営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされていたが,ただし,再建計画において,支援損等の計上が予定されている場合は,支援損相当額についてⅣ分類とし,その他をⅡ分類とすることも可とすることが示され,例えば,支援損75を5年間にわたり各年度15ずつ計上予定の場合には,営業貸付金200の査定結果が,非20,Ⅱ80,Ⅲ50,Ⅳ50であれば,関連ノンバンクに対する親銀行の貸出金150の査定が,Ⅱ75,Ⅳ75であるとされていた。
また,7年事務連絡では,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面考慮せずに査定を行うこととするとの方針が示されていた。
以上のとおり,7年事務連絡においては,関連ノンバンクの資産査定の結果については,他の銀行が当該関連ノンバンクに対する融資を行っている場合において,当該貸出残高を総貸出額で按分(プロラタ方式)して査定・分類するのではなく,そのまま関連ノンバンクの親銀行である銀行の貸出金の査定に反映させる仕組みが採用され,その限度において,関連ノンバンクの営業貸付金等の査定結果について,他の銀行の貸出金には反映させない取扱いが行われるとともに,他方,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面,考慮せず査定作業を行うこととすることが示されていた。(甲231,乙106の17頁,乙110,弁論の全趣旨)
(b) 次に,日銀考査については,日本銀行法(平成9年法律第89号)44条に基づき,第37条から第39条までに規定する業務を適切に行い,及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして,これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で,考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について,日銀が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約を締結することができ,日銀は,この考査契約に基づき,銀行の業務及び財産状況に関する考査(いわゆる日銀考査)を実施していた。
日銀考査においては,銀行の貸出金に関する査定として,「D分類」(Ⅱ分類に相当),「S分類」(Ⅲ分類に相当),「L分類」(Ⅳ分類に相当)に分類することが行われていたところ,従来銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定に当たっては,一般企業向け融資と同様に,そのノンバンク自体の支払状況や支払能力をベースに査定しており,銀行のノンバンクに対する融資額の範囲内で,D分類,S分類,L分類の分類を実施していたが,平成3年8月以降,親銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定に当たっては,関連ノンバンクの抱える不良債権の規模を査定し,関連ノンバンクに親銀行の融資額を超える不良債権が存在している場合には,その不良債権全額を親銀行本体の不良債権とみなすとの方針が採用され,これに基づく日銀考査
が実施されることとなった。すなわち,日銀考査において,認定不良債権額が親銀行の貸出金の総額を超える場合には,実際に存在しない「保証勘定」を設けて計数を調整し(乙106の18頁),他方,親銀行以外の銀行の関連ノンバンクに対する貸付金には,この不良債権額を反映させない仕組みが取られていた。
この方針による日銀考査の際には,親銀行に関連ノンバンクの経営を全面的に支援する意思を有するかどうかを確認して,その意思がある場合には,上記方針による考査が実施された。
このような日銀考査の方針の背景には,バブル経済の崩壊による不動産関連の倒産の増加により,関連ノンバンクに多額の不良債権が発生しており,後ろ盾となる親銀行が明確ではないまま,経営難に陥る例が多発した場合には,金融システム全体の混乱につながりかねないとの判断が存在していた。
なお,当時,多数の銀行は,支援意思を明確にして,日銀考査を受け入れており,その理由としては,親銀行以外の銀行債権者の融資金について,関連ノンバンクの不良資産を反映された場合には,融資の回収につながりかねないとの親銀行の判断があった。(甲68,乙8,乙106,弁論の全趣旨)
(ウ) 銀行の関連ノンバンクに対する支援の仕組み,税務上の取扱い
a 法人税基本通達9-4-2による支援の仕組み
法人税法37条1項は,内国法人が各事業年度において寄附金を支出した場合において,その寄附金の額は損金の額に算入しない旨規定しており,現金贈与,債権放棄,債務引受け等の損失負担は,原則として,法人税法上,課税対象として扱われることとなる。
しかし,親会社が子会社の整理のために行う債権の放棄,債務の引受けその他の損失負担については,一概にこれを単純な贈与と決めつけることができない面が多々認められるということであり,このようなものについては,その内容いかんにかかわらず,常に寄附金として処理すること等は全く実態に即さないといえること,また,一概に無利息又は低利貸付けといっても,そのことについて経済取引として十分合理的な説明がつくという場合には,子会社整理等の場合における損失負担等と同様に,常にこれを寄附金として取り扱うのは相当でないことから,法人税基本通達9-4-1及び9-4-2において,税務上も正常な取引条件に従って行われたものとして取り扱い,寄附金としての認定課税をしないことが明らかにされている(乙1
4の25頁)。
例えば,再建支援については,法人税基本通達9-4-2において,法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において,その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは,その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は,寄附金の額に該当しないものとすると定められている(なお,従来は,無利息貸付けのみが明示され,債権放棄,現金贈与等のいわゆる損益支援については明示されていなかったが,当然これも含まれるものであった。〔
乙14の34頁〕)。具体的に,このような子会社等の整理又は再建に関する損失負担が経済合理性を有するかどうか(すなわち無税扱いが認められるかどうか)については,①損失負担等を受ける者は,子会社等に該当するか,②子会社等が経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか),③損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由があるか),④損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか),⑤整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか),⑥損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっているなどの恣意性がないか),⑦損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負
担を重くし又は免れていないか)といった点が問題とされ,これらの点を総合的に考慮するものとされていた(乙14の25頁)。
ところで,バブル経済の崩壊以降,法人(支援者)が経営危機に陥った系列会社や取引先等の倒産等を防止するため又は整理するために,債権放棄等の損失負担等を行う事案が増加しているところ,損失負担等の額が寄附金に該当するかどうかが支援者の所得計算に多大な影響を及ぼすことから,国税庁において事前相談の制度が設けられた。すなわち,平成4年8月以降,中小企業の倒産が続出することを抑制・防止するため,銀行による取引先企業に対する金融支援を促す目的から,国税庁に「東京国税庁調査第一部調査課別室」が設置され,同別室において,金融支援の事前相談を受け付けて,適切な無税扱いを事実上承認する運用が行われていた(乙14の21頁,乙118の12頁)。
これを受けて,各銀行は,関連ノンバンクに対する金融支援を行う場合においては,事前に法人税基本通達9-4-2における要件を充足するものであるかどうかについて,上記①ないし⑦の要件を充足することを示す資料を開示して,事前に国税庁に相談を行い,国税庁は,場合によっては,その決裁を経て,銀行に対し,事実上の無税扱いの承認通知を行っていた(乙108の12頁)。例えば,原告は,平成6年6月すぎころ,当初10年の期間による日本リースに対する損益支援等を内容とする同社の再建計画を策定し,国税庁に対して,損益支援に関する無税扱いの承認を求めたが,国税庁は,10年の再建期間が長すぎると指摘し(甲154の12頁),その後,原告は,改めて,期間を5年とする日本リースの再建計画を策定し,国
税庁に提出する資料(甲154添付資料3)を作成してこれを提出し,同年11月ころ,国税庁から,事実上,無税扱いの承認を得た。
このように,銀行による金融支援が,形式上「寄附金」に該当する場合であっても,上記①ないし⑦の要件を充足する場合には,「寄附金」に当たらないとして損金算入することが認められ,これにより,金融支援が促されていた。(乙14,乙118,弁論の全趣旨)
b 金融支援先に対する不良債権の償却・引当に関する大蔵省における運用
このように,銀行による関連ノンバンクに対する支援が行われている場合には,不良債権償却証明制度等に基づき,親銀行(母体行)が再建のための支援を行っている支援先の貸出金について,延滞,破綻の事実が顕在化しておらず,償却・引当をすることはできないとする運用が,大蔵省において採用されていた。
まず,不良債権償却証明制度においては,法人税基本通達9-6-4の解釈・運用に当たっては,本来,債務超過の状態が相当期間継続しており,事業好転の見通しがないことという要件を充たす場合には,貸出金等の額の相当部分(おおむね50パーセント以上)の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について損金経理により債権償却特別勘定に繰り入れることができるとしてその額を証明していたが,他方,合理的な再建計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として,上記通達9-6-4の適用要件である事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないとされており,当然,金融証券検
査官は,銀行が支援をしている債務者の貸出金に関する償却・引当については,支援の有無や合理的再建計画の有無を前提に,その償却・引当の適否を判断していたものと思料され,このため,銀行が支援先に対して償却・引当を行うことについて,大蔵省金融検査部において,消極的な姿勢を示し,これを容易に認めない運用が採用されていた。
次に,大蔵省金融検査部は,一般的に,金融機関が支援を継続しながら,他方,貸出金に回収不能のリスクがあるとして償却・引当を行うことは,自己矛盾的であり,このような処理は採り得ないという見解を示していた。すなわち,前記(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」によれば,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権については,この有税引当を行うことは,当面,企業会計上の合理性がないことや再建計画が策定されている債権については引当金が要らないことが大蔵省銀行局の担当者の見解として示されていた(甲158の21頁)。また,大蔵省金融検査部審査課長補佐等を務めていたYは,その著作(乙10)の中で,「債務者に対して追加融資を予定している場合
,無税償却適状にならないことは当然であるが,このとき有税償却すれば追加融資自体が背任的な行為となるおそれがある点に留意する必要がある。逆にいえば,追加融資先を有税とはいえ償却することは,基本的には決算経理基準から見て問題となろう。」(52頁)と述べていた(なお,甲158の59頁によれば,同人は,刑事公判廷においては,支援先に対する償却・引当をしないという考え方自体必ずしも論理的ではないと供述するが,そのような自らの考え方自体が当時の大蔵省内においては少数派であったとも供述している。)。さらに,証拠(乙46)によれば,平成4年から平成5年にかけて,再建中である貸出先に対する貸倒れを認定することについて大蔵省が消極的な姿勢を示していたことが認められる。
このように,当時の大蔵省は,金融支援先に対する償却・引当をできる限り認めないものとする運用を採っていたといえる。(甲122,甲158,乙9ないし乙11,乙14,乙46,乙108,乙110,弁論の全趣旨)
c 銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の実務
このような大蔵省の運用・見解を背景として,銀行においても,関連ノンバンク向け貸出金については,再建を前提としている以上,これについて償却・引当をすることはできないとの実務が一般化していた。
すなわち,証拠(証人L10頁,12頁,20頁,37頁,証人K27頁,33頁,証人X12頁,13頁,E本人6頁,7頁,甲136の31頁,32頁,乙28の10頁,乙118の15頁,16頁,乙120の13頁,14頁)及び弁論の全趣旨によれば,一般的な銀行界の考え方として,①銀行が関連ノンバンクに対して支援を継続している場合には,当該関連ノンバンクが再建されることを前提としており,再建計画期間中における関連ノンバンクの破綻は通常想定し得ないこととされ,このような考え方は,Q会計士が,刑事公判廷において,「銀行が積極支援する債務超過状態のような財務内容の悪い関連ノンバンクであっても,銀行が積極支援すれば,再建計画がなくても再建計画が作成され,それが実行される可能性が極めて高
くて,破綻に陥る可能性が極めて小さい」と供述しており,このような考え方自体は,会計監査人においても,許容されていたことが窺われること,他方,②このような再建を前提として支援している関連ノンバンク向け貸出金について,銀行(母体行)が償却・引当を実施することは,関連ノンバンクが破綻するおそれがあることを前提に,回収不能見込額(関連ノンバンクの清算価値に基づき回収不能が予測される額)について有税償却・引当を実施するもので自己矛盾であり,それ以上,無税による支援を行うことや新規貸付けを行うことができなくなると考えられていたこと,すなわち,将来追加の与信をするということがあり得る先に対してあらかじめ引当金を積みながら貸出しをすることになると,新たな貸出しをするたびにそれに見合う過去と同
じ割合の引当金を積みつつ,新たに貸出しをすることになるが,実際貸出しを判断していく場合には,そのような合意に矛盾を感ずるのは自然な考え方であったこと(証人L20頁),また,③支援損の計上(債権放棄,現金贈与等)による支援が,単年度ではなく複数の事業年度に及ぶ場合であっても,あらかじめ支援予定額全額について,費用として引当をすることも,将来の再建支援額は確定したものではなく,支援による資産処分や経営改善の内容いかんにより支援総額や支援期間が変化し,場合によっては過剰支援・引当のおそれがあるため,将来の支援予定額の一部又は全部を引き当てることがほとんど行われていなかったこと,この点について,例えば,Q会計士は,刑事公判廷において,「平成9年3月期以前は,支援として意思決定した金額
について支援損に計上する,すなわち分割償却の処理が認められておったわけでございます。そして,翌期以降,支援するものについて,商法第287条の2の引当金を設定するという会計慣行が確立しておらなかったわけでございます。」と供述しており,このような支援損に係る引当金の計上には会計監査人も慎重であったことが窺われる。
以上の事実によれば,バブル経済崩壊以降平成9年3月期以前は,銀行界一般において,回収不能のリスクを見込んで関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当を実施し,あるいは将来の支援予定額の引当を実施することについては,これを行わないとする運用が,会計処理の実務として定着していたと認められる。
(エ) 小括
以上の事実を前提として,平成9年3月期までの銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務について検討すると,次のようにいえる。
以上のとおり,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当について,①母体行主義を前提としてシステミックリスクの発生を回避するため,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の査定結果を母体行の貸出残高を限度として又はその全額について,母体行に反映させる一方,関連ノンバンクの資産査定の結果を母体行以外の銀行の貸出金には反映させず,これにより,母体行以外の銀行の貸出残高の維持を図っていたこと,②前記イ(オ)のとおり,銀行の貸出金のうち,Ⅳ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度により全額無税償却が可能であり,平成9年3月期以前における会計慣行として,このⅣ分類の貸出金について当期における全額の償却・引当が義務づけられていたと解され,本来,関連ノンバンク向け貸出金
についても,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の内容を査定し,その査定結果(Ⅳ分類ないしⅡ分類)に応じて,各銀行ごとの貸出残高の割合(シェア)に応じてその査定結果を反映させるのであれば,当然,当時の会計慣行を前提に,Ⅳ分類と査定された銀行の貸出金について,当期における全額の償却・引当義務が発生するところ,関連ノンバンクの資産査定の結果が母体行の貸出金に反映される仕組みが採られていたため,仮に,不良債権償却証明制度により,このⅣ分類を全額償却・引当するとの義務を課した場合,明らかに過剰な償却・引当義務を課すことになるので,7年事務連絡においては,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,これを考慮せずに行うとして,査定の結果と償却・引当の義務を切り離したものと評価でき
ること,③このような母体行の貸出金にそのまま反映された関連ノンバンクの分類資産(不良資産)については,母体行が,合理的な再建計画を作成し国税当局において無税扱いに関する承認を受け,償却原資の提供すなわち債権放棄等の損益支援や新規貸付け等の支援をして,関連ノンバンクの経営の健全化を図ることが予定されていたこと,④最終的には,関連ノンバンクを再建し,それにより破綻が回避される以上,再建期間中における母体行及び母体行以外の銀行の貸出金については貸倒れのリスクが発生しないと考えられていたこと,⑤以上のような取扱いの結果,関連ノンバンクに対する貸出金については実際には償却・引当を行わないという会計実務は,メインバンク制とも相まって,平成9年3月期以前には,バブル経済崩壊以降相当長期間に
わたって行われていたこと,以上の事実がそれぞれ認められる。
そうであるとすれば,平成9年3月期までの銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務においては,不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準のもとでの貸出金の償却・引当に関する会計処理方法である税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当はしないとする会計慣行が存在していたといえる。言い換えると,銀行の貸出金のうちⅣ分類とされたものについては,当期に即時償却・引当をするとの会計慣行の例外として,このような関連ノンバンク向け貸出金に対する特別の取扱いが相当長期間にわたって存在していたというべきである。
エ 平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する実際の
会計処理方法が「公正なる会計慣行」に当たるといえるか。
前記イ及びウで認定したとおり,平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する実際の会計処理方法としては,いわゆる税法基準が採用されており,一般の貸出金に関しては,大蔵省検査によりⅣ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度を介して,義務的に貸出金の償却・引当を行う一方で,有税による償却・引当については,銀行の自主的な判断に委ねられた結果,実際には有税償却・引当はほとんど行われないという会計慣行が存在しており,さらに銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,銀行の貸出金のうちⅣ分類とされたものについては当期に即時償却・引当をするとの会計慣行の例外として,再建支援を前提とする限りは償却・引当をしないとする会計慣行が存在したことが認められる。
そこで,以下では,これらの会計慣行が,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」といえるかについて検討する。
(ア) 一般的な貸出金に関する税法基準に基づく会計処理について
前記認定の事実によれば,①会計士協会が委員会報告第5号において,税法基準によって貸倒引当金が計上されていれば特別な場合を除いて除外事項としないことができるとしていたこと,②昭和57年に発出された改正前決算経理基準については,銀行関係者もこれが商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」に当たると認識しており,本件においてもその点については当事者間に争いがないところ,この改正前決算経理基準において,貸出引当金については,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとされ,さらに債権償却特別勘定については税法基準によることが言及されていること,③いわゆる税法基準は,不良債権償却証明制度と結びついて,改正前決算経理基準の「貸出金の償却」と「貸倒引当金」の計上に関する細則的基準と
なっていたところ,不良債権償却証明制度は,銀行経営の健全性及び適切性を確保するための監督・規制権限を有する大蔵省の通達によって定められた制度であり,銀行の不良債権処理に関する手続全体を監督・規制し,過剰又は過少な償却・引当がなされないようチェックして適正な償却・引当を実施させることを目的としたもので,当時の大蔵省のもとでの銀行に対する事前指導による保護的な金融行政を前提とする限りは,銀行決算の健全性及び適切性を確保するという点で合理性を有する制度であったこと,④税法基準は,大蔵省による不良債権償却証明制度を介して銀行に対して適切な監督・規制が行われることを前提としており,そうであるとすれば,当該銀行の資産内容を正確かつ適正に反映するものと評価できるものであり,その意味では,税
法基準に従った会計処理は,当時の大蔵省による監督・規制に基づく事前指導的な金融行政を前提とする限りは,商法の商業帳簿の作成目的からみても銀行の財産状態及び損益状況を正確に反映しうるもので合理的なものといえること,⑤旧商法285条の4第2項の文言だけでは,いかなる場合に「金銭債権に付取立不能の虞ある」といえるのか,また,取立不能見込額をどのように算定するかが明らかでなく,企業会計原則にも貸倒金の計上基準についての指針はないところ,税法基準は,貸倒金額の証明に当たり,基準として明確な法人税基本通達を援用するものであり,基準として明確なものであること,以上の事実が明らかである。
そうであるとすれば,不良債権償却証明制度によって補充された改正前決算経理基準のもとでの銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理方法である税法基準は,大蔵省による事前の指導と規制のもとでの保護的な金融行政がとられていた当時の銀行の会計処理方法として,十分な合理性を有するというべきであり,これが平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」に当たるというべきである。
なお,以上の税法基準のもとでは,金融機関は,有税による償却引当を積極的に行ってはいなかったものである。この点については,大蔵省において,平成6年2月8日付通達で有税償却の活用を促していることは事実であるが,一方で有税償却については無税償却の場合のような明確な基準がなかったといえる。この点は,平成6年11月の時点で当時の大蔵省銀行局長が,回収不能とはまだ判定されていないが,リスクが高まっている延滞債権等について有税引当が期待されるとしながら,一方で,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権について有税引当を行うことは,当面企業会計上の合理性がないことになるとしていること(乙99)からも窺えるというべきである。結局,大蔵省においても有税
引当を行うか否かは,金融機関の自主的な判断にこれを委ねていたもので,税効果会計のような手当のないままで有税償却を行うことは金融機関の決算処理に負担が及ぶ可能性があったことからすると,税法基準のもとで,金融機関が積極的に有税引当を行っていなかったからといって,そのことを理由として税法基準が不合理なものと認めることはできないというべきである。
(イ) 銀行の関連ノンバンクに対する貸出金に関する会計処理について
次に,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関しては,不良債権償却証明制度,大蔵省検査及び日銀考査を前提として,母体行である銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続し,その再建を果たさせる以上,破綻リスクひいては貸倒リスクがなく,資産査定の結果,分類を受けなかった母体行以外の銀行において,その貸出金に対する償却・引当を不要として貸出残高の維持を行う一方,母体行において,償却・引当を不要とすることは,再建を絶対的な前提としたもので,破綻のリスクを考慮しないというものであり,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当について,いわば特別扱いを認めたものといわざるをえない。
しかしながら,このような銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する特別扱いを認める会計慣行は,①母体行は,関連ノンバンクに対し,法人税基本通達9-4-2による支援を通じて,最終的には,関連ノンバンクの営業貸付金に係るⅣ分類等の資産を処理して,これにより,母体行以外の各銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する回収不能のリスクを回避する一方,母体行以外の銀行は,関連ノンバンクの再建期間中において,母体行に対する信用を背景に,関連ノンバンク向け貸出を継続して資金繰り破綻を回避するものであるが,これは,要するに,システミックリスクの発生を回避するための手法であり,早期是正措置導入以前の大蔵省による事前の指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは,十分な合理性を有するも
のであったといえること,②このようなシステミックリスクの回避を目的として,大蔵省検査における関連ノンバンクの資産(営業貸付金)査定の結果を母体行の貸出残高を限度として全面的に反映させる一方,これに伴う過剰な償却・引当義務を解除するため,資産査定の結果と償却・引当を切り離したものであり,そのことについても合理性を認めることができること,③銀行の関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当を不要とする考え方は,基本的に,母体行による支援を前提とする以上,関連ノンバンクの破綻リスクが極めて小さいことに由来するものであるが,このような支援内容すなわち再建計画の合理性は,単に再建元である母体行のみならず,一般には,国税庁において無税扱いの事実上の承認を受ける際に,その合理性・実現可能性に
ついて審査が行われることが前提とされており,実際に,証拠(乙118の17頁)によれば,支援計画の実施状況及び債務者の財務状況について,銀行は毎年見直して国税庁に報告していたことや支援額や支援期間の圧縮を内容とする確認書を提出していたことが認められ,このような審査あるいは監視は継続的に行われていたことからすると,このような支援内容は,合理的かつ実現可能性の高い内容のものが承認されていたといえること,④7年事務連絡においても,再建計画の妥当性については金融証券検査官の判断に委ねられており,中立的な第三者であり,かつ,銀行経営の健全性及び適切性を維持するための監督・規制権限を有する立場の大蔵省において,このような再建計画が審査され,かつ,承認されていたものであること,以上の点を考慮
する限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金について,銀行による関連ノンバンクへの支援又は再建計画があることを前提にして,償却・引当を実施しないとする会計慣行は,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは,企業の財産状態及び損益の状況を明らかにする商業帳簿作成の目的からみても,合理的なものであったと評価することができるというべきである。
(ウ) 税法基準が「公正なる会計慣行」といえるかについての結論
以上のとおりであって,税法基準は,不良債権償却証明制度の運用において,銀行の経営の健全性及び適切性を維持するため,銀行を指導・監督・規制する権限を有していた大蔵省の担当者によって実際に行われていた指導・監督権限に基づき,銀行の資産内容の健全性と決算業務の適切性を図る見地から,無税償却・引当が可能な貸出金すなわちⅣ分類と査定された貸出金の償却・引当を義務づけていたものであり,当時において,「公正なる会計慣行」であったと評価できるというべきである。また,銀行が,関連ノンバンクに対する支援を継続して,関連ノンバンクの再建を図ることは,関連ノンバンクの破綻を防ぐだけでなく,ひいては金融システム全体の破綻を回避することに資するものであり,再建期間中における銀行の関連ノンバンク
向け貸出金に対する償却・引当をしないという会計慣行もまた,大蔵省の担当者による実際の監督・規制権限の行使を前提として,銀行会計の健全性を確保しようとするものであり,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする銀行に対する保護的な金融行政のもとでは,十分に合理性を有するもので,これが「公正なる会計慣行」であったと評価できるというべきである。
結局,平成9年3月における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準であったといえる。そして,その内容は,①銀行の貸出金については,原則として,大蔵省検査においてⅣ分類と査定された貸出金について,同額の無税による償却・引当の義務を負うこと,②銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当については,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とする(支援損の計上等を通じて,計画的段階的に処理する)というものであり,有税による償却・引当については,銀行の自主的判断に委ねられた結果,実際にはほとんど行われていなかったが,当時の保護的な金融行政のもとでは,大蔵省の事前指導・監督・規制によ
り銀行経営の健全性及び適切性を維持することにより,その内容の合理性が担保されていたと評価できるものである。
(2) 原告らの主張の検討
原告らは,①税法基準は,租税収入の確保という政策的観点に立って,税額の計算をし,課税の公平を図る目的で策定されており,そのような観点から,当該事業年度において,損失が生じたことが確実と認められるものについて損失計上が認められるものであり,他方,商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営成績を正しく表示し,もって株主及び会社債権者の利益を図る目的で策定され,両者の目的は全く相違しており,税法基準による会計処理が,商法32条2項の「公正なる会計慣行」となると解し得ないこと,②委員会報告第5号は,公表された当時,各企業の有する不良債権額が些少であり,「一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向
にある」ことを前提として,保守主義の観点からこれを容認したにすぎないものであり,これは,税法基準そのものを「公正なる会計慣行」と位置付けたものではなく,むしろ,委員会報告第5号によれば,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)となるとしており,税法基準は,企業の資産状態を正しく反映するものではないことを前提としていること,③平成4年8月18日付け「金融行政の当面の運営方針―金融システムの安定性確保と効率化の推進」は,不良資産処理の方針の早期確定とその計画的・段階的処理が急務であると指摘し,また,平成6年2月8日付け「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」は,「金融機
関自らの判断によりリスクに応じた必要な引当が行われるようにする。」ことを提言し,有税引当の概念を示し,これを受けて同日付け「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,有税引当及び有税直接償却を行うときの取扱いが明らかにされたことから,改正後決算経理基準の発出以前の段階において,行政当局は積極的に金融機関に不良債権の有税償却を求めていたこと,④改正前決算経理基準は,「貸出金の償却」について「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額」を償却すべきとしており,当然,有税償却を含む趣旨と解されること,また,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする。
なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と定め,有税引当を予定していること,すなわち,旧商法285条の4,企業会計原則に従い,回収不能見込額の償却・引当が義務づけられており,改正前決算経理基準における「貸出金の償却」の意義は,改正後決算経理基準における「貸出金の償却」の意義と同一であること,⑤法人税基本通達9-4-2は,債権放棄の対象である当該債権が実質的無価値ではない場合,本来寄附金認定される債権放棄について,経済合理性の見地から,損金算入を認める(寄附金と認定しない)ものであり,当該債務者に対する貸出金を回収不能と評価するか否かの判定基準とはなり得ないものであること,支援損の概念は,合理的な再建計画に基づき貸出先の事業が継続され,
その結果収益弁済が可能になる場合すなわち当該貸出金につき回収不能又は回収不能の見込みがない状況を前提とした概念であること,他方,貸出先の収益弁済が可能となる合理的な再建計画がない場合,合理的再建計画を前提とする回収不能又は回収不能の見込みがない状況にあるとの前提が成立せず,当該貸出金について回収不能のおそれがあり,関連ノンバンク向け貸出金については債権放棄による支援損の概念しかあり得ないとの被告らの主張は全く成立しないこと,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当が存在することを根拠として掲げて,以上の点等を考慮し,税法基準が,平成10年3月期より前の段階においても,商法32条2項の「公正なる会計慣行」となり得ないと主張している。そこでこれらの点について検討すると,以
下のようにいうことができる。
ア ①について
この点については,原告らが主張するとおり,法人税法22条4項は,法人税法における法人の各事業年度における「所得の金額」の算定の基礎となる「益金」と「損金」の額を計算するに当たり,「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」旨規定し,商法32条2項の「公正なる会計慣行」による旨を明らかにした趣旨と解され,原則として,いわゆる確定決算主義に従い,税法基準は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」により決定されるとするのが法人税法の基本的態度であると解される。
しかしながら,実際の実務の運用において,このような税法基準が,商法32条2項の「公正なる会計慣行」により全て決定されるとすることには無理があり,現実の問題としては,相互に影響することがあること自体は否定できない。すなわち,銀行の貸出金に対する償却・引当処理に関しては,有税であるか無税であるかを問わず,実際には大蔵省金融検査部による監督・規制下に置かれており,そのような状況を考慮した場合,税法基準が,銀行の貸出金に関する商法上の償却・引当の基準(商法32条2項の「公正なる会計慣行」)として現実に機能しているのは事実であって,税法基準に基づく会計処理方法が,大蔵省による保護的な金融行政のもとでは,商法上も十分な合理性を有していたことを否定することはできないといえる。
言い換えると,当時の保護的な金融行政のもとでは,銀行の償却・引当の実務・運用が,全て大蔵省検金融査部に事実上監督・規制されていたことからすると,銀行は,大蔵省金融検査部の検査を無視して,貸出金を査定し償却・引当を行うことは実際には考えられず,そのような不良債権償却証明制度を前提とする税法基準が,銀行の貸出金に関する償却・引当の実務すなわち会計慣行を形成していたことは明らかである(会計慣行となっていたこと自体は原告らも認めるところである。)。無論,税法基準が,当然に企業会計の基準となるものではないが,このような銀行における長期間にわたる実務処理の集積として,税法基準が銀行の会計実務として定着し,しかも大蔵省による指導・規制下におかれた金融行政のもとでは,銀行の貸出金の償
却・引当に関する現実的な会計処理方法として,商法上も十分な合理性を有していたというべきである。
また,税法と商法が本来目的を異にする点は,原告ら主張のとおりであるが,銀行の経営の健全性及び適切性の観点から,適正な決算処理を監督する趣旨で,大蔵省検査に依拠し,不良債権償却証明制度を介して償却・引当を行うとする不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準自体もまた,適正な決算処理を確保する趣旨においては,正確な銀行の財務状態及び損益状態の反映という商法の目的にも反していなかったと考えられる。
なお,有税による償却・引当は,償却・引当のコストに加えて同額の納税コストが発生し,銀行の決算を悪化させ,かえって,銀行経営の健全性を揺るがす事態を生せしめると考えられており,このような観点からも,税法基準による不良債権の償却・引当は,銀行の会計実務として定着しており,その内容は合理性を有していた,すなわち「公正なる」ものであったというべきである。
以上のとおりであって, この点に関する原告らの主張は,平成9年3月期以前において銀行の貸出金の償却・引当についての基準に関し税法基準に基づく会計処理方法(銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,再建期間中は償却・引当をしない等)が「公正なる会計慣行」として定着していたとの前記認定判断を覆すに足るものではない。
イ ②について
この点については,確かに,原告らが主張するように,委員会報告第5号は,税法基準による貸倒引当金が企業の実態に応じて経常すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)となると規定しているが,他方,前記(1)ア(イ)のとおり,委員会報告第5号は,我が国の会計慣行とりわけ税法基準を多くの企業が採用しているという実情を踏まえたうえで,一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向があるが,税の確定決算主義の立場等を考慮して,税法基準によって算出した貸倒見積高を計上している場合でも一定の条件のもとに一般に認められた企業会計の基準に準拠しているものとして取り扱うこと
ができる旨定めており,税法基準を採用している場合にはこれを継続して適用すべきことを要請していることからすると,その趣旨は,多数の金融関係者が反復継続して税法基準を採用していたことを考慮し,また,会計の一般原則である継続性の原則も踏まえたものと解することができるのであって,そうすると,この委員会報告第5号も,税法基準が「公正なる会計慣行」に該当することの根拠となり得るというべきあり,この点に関する原告らの主張は,前記認定判断を覆すに足るものではない。
ウ ③について
この点については,確かに,原告らの主張のとおり,これらの通達,指針等は,不良債権の処理の促進を要請し,有税による償却・引当を促す趣旨のものであること,特にⅡ分類と査定される貸出金についても有税引当を実施するよう促した趣旨であると解される(甲158の25頁)。
しかしながら,このような有税による償却・引当が勧奨された後も,実際には,銀行において有税引当等が行われたことはほとんどなく(甲158の30頁),これらの通達,指針等が銀行の会計処理の実務に実際に影響を与えたとは認められない。すなわち,前記のとおり,有税による償却・引当が,制度上,届出制に改められたものの,実際には無税による償却・引当と同様の説明が必要とされ,しかも要件自体が明確でなく,決算処理に負担を及ぼす可能性があるものでありながら,銀行の自主的な判断に委ねられていた結果,実際には,有税引当が行われることはほとんどなかったというのであるから,結局,有税引当は実務的に定着するには至らなかったものである。
また,前記のとおり,平成6年2月8日付け「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」についても,確かに,有税引当制度の運用を改善し,貸倒れには至らないが,回収に危険のある債権について将来の回収リスクに応じた必要な引当が促され,同日付け「不良債権償却証明制度実施要領について」と題する通達が発出されたところ,他方,上記指針は,金融機関の支援先に対する金利減免債権等については,元本が回収されるという前提で再建計画が実施されており,破綻先債権,延滞債権と同列に扱うことはできず,このような支援先に対する債権については有税引当の実施が,企業会計上の合理性がないとも指摘しており,結局,銀行の関連ノンバンク向け貸出金については,関連ノンバンクへの支援を前提とした再建可能性を考慮し
,また,再建計画が,国税庁による事実上の承認や大蔵省検査における金融証券検査官の判断を前提として,回収不能のリスクがないと考えられており,この点に関する運用は従前から変化がみられず,かえって,区別して取り扱われていることからみて,行政当局に見解の変更はなかったといえる。そうであるとすれば,この点に関する原告らの主張も前記認定判断を覆すに足るものではない。
エ ④について
この点についても,原告らが主張するように,改正前決算経理基準自体が,有税による償却・引当を認めていたこと,また,回収不能の判断については,改正前決算経理基準と改正後決算経理基準において,ほぼ同義に解し得ることは認められる。しかし,改正前決算経理基準において,回収不能見込額の算定が困難な場合,法人税基本通達9-6-5に従い,債権額の50パーセントを債権償却特別勘定に繰り入れて,その余の50パーセントを有税により繰入れを行うことができるとされていたが(乙118の8頁,9頁),このような要件を満たさない場合には,不良債権償却証明制度により,有税による償却・引当が大蔵省の監督・監視の下で厳格に運用されており,改正前決算経理基準の下では有税による償却・引当は義務化されていなかっ
たこと,他方,改正後決算経理基準の下では,有税による償却・引当が促されていたことを考慮すると,原告らの主張は,前記認定判断を覆すに足るものではない。
オ ⑤について
まず,原告らは,法人税基本通達9-4-2は,償却・引当の前提となるべき回収不能の判断基準となり得ないと主張する。確かに,法人税基本通達9-4-2は,それ自体,回収不能の判断基準として機能するものではないが,銀行が,国税庁の無税扱いの承認を受けて,関連ノンバンクに対する支援を継続している場合,最終的には,関連ノンバンクを再建して破綻を回避し得るものであり,それ自体,中立的な第三者であり,かつ,銀行経営の健全性及び適切性を監督・監視する大蔵省の認定を経たものであることからすると,銀行が法人税基本通達9-4-2による支援を継続している間においては,関連ノンバンクが破綻する事態には至らないものと評価する合理的な基準となるといえる。結局,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償
却・引当は不要ということになり,銀行としては,支援損を計上し,支援を継続する一方,償却・引当を不要とするものであり,その範囲で,償却・引当が不要な場合を示す合理的な基準として機能するものであると評価できる。そうであるとすれば,この点に関する原告らの主張も,前記認定判断を覆すに足るものとはいえない。
次に,原告らは,合理的な再建計画の存在により,関連ノンバンクが再建され,収益弁済が可能となることから,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当を実施しないことが妥当とされるのであれば,合理的な再建計画がない場合には,回収不能の見込みがない状況にあるとの前提が成り立ち得ないと主張する。
この点については,銀行の関連ノンバンクに対する支援については,証拠(乙9,乙110)及び弁論の全趣旨によれば,不良債権償却証明制度において,法人税基本通達9-6-4において,債権償却特別勘定への無税繰入れに係る金額を証明する場合には,債務超過の状態が相当期間継続しているかどうか,事業好転の見通しがないかどうかを審査し,貸金等の額の相当部分(おおむね50パーセント)以上の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について判断すべきとされるが,事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の
見通しがないと判断することが適当ではないと定められていたこと,また,7年事務連絡では,母体行による関連ノンバンクに対する支援の意思を前提として,合理的な再建計画が策定されている場合と策定されていない場合において,いずれも資産査定の方法は,原則として,関連ノンバンクの営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされ,また,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面,考慮せず査定作業を行うこととすることが明示されており,金融証券検査官が,大蔵省検査において,母体行の意思を確認し,母体行責任を負うことが確認された場合,銀行経営の健全性及び適切性を検査する金融証券検査官の判断のもと,いずれ母体行が適切な再建計画を策定し,それに
沿って,関連ノンバンクの再建が果たされることが期待されていたことが認められ,これらの事実に照らすと,単に再建計画がないことのみをもって,回収不能の見込みがないとの前提が成り立たないということにはならないというべきである。
5 争点④(資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準が,銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の基準としての「公正なる会計慣行」に当たるとするための要件を満たしているといえるか。)について
4で認定したとおり,平成9年3月期以前の銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準(以下,「旧基準」ともいう。)であり,関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当については,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とするものであったといえるところ,そのことを前提として,原告らの主張する資産査定通達等で補充された改正後決算経理基準(以下「新基準」ともいう。)が平成10年3月期において銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえるかについて検討することとする。
そして,そのための要件は,既に前記2(4)で指摘したとおりであるから,以下,まず,新基準の合理性及び改正手続の適正性(前記要件①及び③)について検討し,次に,新基準と旧基準の変更の程度・内容について検討した上で,変更にともなって必要な手当がなされているか(前記要件②)を検討し,その後に,新基準の一義的明確性(前記要件④)と新基準の関係者への周知徹底がなされていたか(前記要件⑤)について順次検討することとする。
(1) 新基準の合理性及び改正手続の適正性について
新基準が採用されるに至った経緯としては,前記3で詳細に認定したとおりである。すなわち,銀行に対するリスク管理,内部監督が社会的問題となり,大蔵省検査等についての批判がなされ,従来の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする銀行に対する保護的な行政から,自己責任原則に基づく事後監督行政への転換を求められるに至ったこと,そのため,金融制度調査会の金融システム安定化委員会,金融検査・監督に関する委員会,会計士協会により設置された銀行等監査特別委員会等での検討を経て,金融3法が成立し,早期是正措置の導入が定められたこと,その後,早期是正措置検討会での検討を経て,平成8年12月26日付けで「中間とりまとめ」が作成公表され,そこで銀行の貸出金の償却・引当に関する実務上の基準を定め
ることが必要であることが指摘されたこと,これを受けて,資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡,全銀協追加Q&Aが相次いで発出ないし送付され,これらを踏まえて改正前決算経理基準の改正に至ったこと,この資産査定通達等で補充された改正後決算経理基準により,早期是正措置導入後の銀行の貸出金の償却・引当に関する新基準が示されたこと,以上の事実が認められる。そして,以上のような改正の経緯に照らす限り,通達の改正手続自体は,必要な手順を踏んでおり,適正なものと認めることができるし,新基準の内容は(その詳細は既に認定したとおり),これを早期是正措置の導入という目的のもとでの銀行が自ら資産査定を行う際の貸出金の償却・引当の基準としてみると,後述するとおり,定量的な基準が示されて
いないなど内容の一義的明確性の点では問題が残るものの,新基準を唯一の「公正なる会計慣行」とするかどうかの問題と離れてみるかぎりは,会計処理の基準としては,一応の合理性を備えているものと認めることができる。
(2) 新基準による旧基準の変更の内容と程度について
前記3で認定した本件の事実関係を前提として,新基準と旧基準を対比すると以下のようにいえる。
ア 決算経理基準の改正,不良債権償却証明制度の廃止による変更
決算経理基準の改正により,旧基準においては,貸出金の償却・引当に関しては,税法基準によることが明示され,税法基準の限度額まで貸倒償却及び貸倒引当金の計上を実施することを義務づけるものであったものが,新基準のもとでは,旧基準が採用していた税法基準が採用されず,貸出先(債務者)の実態に応じて有税による償却・引当を実施すべきとするものであり,新たな基準に基づき貸倒損失及び貸倒引当金の計上を求めるものとされたといえる。
また,旧基準を補充していた不良債権償却証明制度は廃止され,その結果,新基準のもとでは,銀行はあらかじめ無税償却・引当の認定を受けられないことになり,一般事業会社と同様に自己責任により,無税による償却・引当を実施し,その後に行われる税務調査において,償却・引当に関する自己判断が否認される場合には,追徴課税をされることとなった。
イ 関連ノンバンクに対する貸出金の処理
旧基準のもとでは,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当は不要とされていたが,9年事務連絡によれば,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金の査定に当たっても,原則的には,銀行の貸出金のシェアに応じて関連ノンバンクの資産分類の結果を反映させるとともに,親銀行がこのようなプロラタ負担を超えて,関連ノンバンクの清算等に伴う損失を負担することにしている場合,又は関連ノンバンクについて合理的な再建計画が策定され,短期間(概ね2,3年程度)で再建が可能な場合以外は,親銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する査定に当たっては,原則をプロラタ負担とし,償却・引当を実施するよう指摘されていた。
ウ 旧基準から新基準に変更された当初の金融検査の結果
早期是正措置は,適正な財務諸表に基づく適正な自己資本比率の算出が前提とされるものであり,しかも,それは,各金融機関の自己責任において策定された自己査定基準を根拠として,貸出金の査定を行い,その査定結果に従い,必要な償却・引当を実施するというものであり,このような償却・引当の適切性も金融検査においては対象とされていた。
そして,このような金融検査の方針の下,平成10年3月期金融検査においては,新基準のもと各金融機関の貸出金等に係る償却・引当の額等についても厳格な検査が実施され,その結果,前記3(10)イのとおり,各金融機関の償却・引当不足額について指摘がされ,主要17行において,Ⅰ分類が5兆4061億円減少し,他方,Ⅱ分類3兆5842億円,Ⅲ分類1兆5708億円及びⅣ分類2511億円がそれぞれ当局査定結果により増加し,主要17行については1兆0413億円の償却・引当不足が指摘され,原告及び日債銀において,Ⅰ分類が1兆8683億円減少し,Ⅱ分類2298億円,Ⅲ分類1兆3775億円及びⅣ分類2610億円がそれぞれ当局査定結果により増加し,原告及び日債銀については8323億円償却・引当不足
が指摘された。
エ 新基準は税法基準を否定していないとする被告らの主張について
なお,この点に関し,被告らは,新基準は税法基準を否定するものではないと主張するが,そもそも,新基準導入の端緒となった早期是正措置の導入自体が銀行の自己責任による貸出金の償却・引当を念頭に置くものであり,従来の大蔵省の事前指導・監督・規制に基づく金融行政のもとで,不良債権償却証明制度を介して実施されていた税法基準とは相容れないものであるし,確かに,後述のとおり,新基準については,一義的明確性の点で疑問は残るものの,前記ア及びイで認定したとおり,実際の改正前決算経理基準と改正後決算経理基準の内容との対比,さらには関連する資産査定通達等の内容に照らしても,基本的な考え方において旧基準と新基準は異なるものであったことは認めざるを得ない。
オ 小活
以上,ア及びイで述べたとおり,新基準は,銀行の貸出金の償却・引当についての基準に関する従来からの会計慣行であった税法基準を離れ,新たな基準のもとで,有税による償却・引当をすべきとするもので,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金についても,できる限り関連ノンバンクの資産の実態に即して償却・引当を実施すべきとするものであり,いずれの点についても,有税による償却・引当は原則的には行わず,また関連ノンバンクについては,銀行が支援を継続する限り償却・引当は不要とする旧基準のもとでの「公正なる会計慣行」に比べて大幅な内容の変更を伴うものと認めざるを得ない。なお,このような大幅な変更は,旧基準が大蔵省の銀行に対する事前の指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでの基準であっ
たのに対し,新基準の導入自体が,そのような保護的な金融行政を見直し,銀行の自己責任による資産査定を義務づけようとしたもので,いわば180度の金融行政の転換を図るものであった以上当然のことというべきである(その意味では,被告らは早期是正措置の導入は,金融行政当局による監督手法の変更であると主張するが,監督手法の変更に伴い,必然的に銀行の会計処理方法の変更も促すものであったというべきである。もっとも,その変更が法令によらず,通達等によって行われた本件のような場合において,変更内容がただちに唯一の「公正なる会計慣行」となるためには,前記のような要件が必要であることは既に述べたとおりである。)。
そして,前記ウで認定したとおり,旧基準から新基準への過渡期ともいうべき平成10年3月期決算について,新基準のもとで行われた金融検査の結果,全ての銀行において償却・引当不足が指摘されているという事実に照らしても,旧基準と新基準に大幅な変更があったことが推認できるというべきである。
(3) 新基準の実施に伴う必要な手当の要否と有無について
ア 新基準による旧基準の変更
以上(2)で認定したとおり,旧基準と新基準の内容については,大幅な変更があったというべきである。そうであるとすれば,旧基準のもとでの銀行の貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」(その内容は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準である。)に代えて,新基準を,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行うことなく,直ちに唯一の「公正なる会計慣行」であると認めるためには,前記2(4)のとおり,変更に伴って企業会計の継続性の観点から支障が生じ,ひいては,その内容が法規範として強制力を持つ結果,関係者への不意打ちになるといった事態を避けるためにも,これに対する必要な手当(以下「セーフティネット」ともいう。)がなされていることが要件とされるというべきである。そこで,そ
のような手当が必要か否か,必要とした場合に本件においてそのような手当がなされていたといえるかについて検討する。
イ 有税による償却・引当を行うことに伴う問題点と対応策
前記認定のとおり,新基準のもとでは,旧基準のもとではほとんど行われていなかった貸出先(債務者)の実態に応じた有税による償却・引当を行うこととされているが,前記認定事実3(12)イと証拠(証人L,証人X,甲115の153頁,甲122の46頁,甲125の90頁から92頁まで,乙11,乙60,乙62)によれば,銀行が,貸出金の有税償却・引当を実施する場合,決算処理に与える影響が大きく,①税額分の資金運用益を確実に喪失する結果となり,例えば,1000億円を有税償却した場合,税率が50パーセントであるとすると,500億円の資金の運用益が喪失されること,②当時の税法においては,繰戻期間が1年と短期間であり,これを経過した場合,有税による償却・引当の額について税金の還付が受けられない結果
となって,無税化の利益が完全に失われること,③有税による償却・引当を実施した場合には,当該事業年度において,償却・引当額と同額の当期利益が減少するだけではなく,同額の税金支払が必要であり(甲125の90頁から92頁),その結果,償却・引当額の倍額のコストを必要とし,必然的に,同期において,自己資本額の減少すなわち自己資本比率の低下に直結し,特に早期是正措置の下では,銀行に対して致命的な結果をもたらしかねないこと,④さらには,銀行の決算を悪化させ,銀行の取締役に対する善管注意義務違反のほか,銀行経営の健全性を危殆に陥れるおそれがあったことが認められる。 そして,証拠(証人X32頁)によれば,銀行の決算業務においては,納税充当金まで含めて決算業務である以上,有税か無税かという
判断を抜きにして決算業務ができるものではなく,有税による償却・引当が銀行決算に与える影響は大きく,銀行は,銀行経営の健全性を確保するため,有税による償却・引当について消極的であり,また,銀行経営の健全性及び適切性を監督する立場にある大蔵省においても,不良債権償却証明制度の運用の下に無税による償却・引当を義務付けたうえで,このような銀行の実務を承認していたものと認められる。
ウ 税効果会計の導入の遅れ
このような有税による償却・引当に伴う,いわゆる税務会計と企業会計の乖離の問題については,従前から指摘がされ,これを解消する方法として,税効果会計の導入が考えられていた。
すなわち,証拠(乙35,乙36)によれば,企業会計審議会は,平成9年6月に,「金融商品の会計処理基準に当たっての論点整理」を公表し,その中で,金融商品の時価評価等の導入に当たって商法との調整が必要であると提言し,これを受けて,大蔵省及び法務省は,商法学者,会計学者及び実務家の参加を求めて,「商法と企業会計の調整に関する研究会」を立ち上げ,同年7月以降,同研究会において,その問題点が検討され,その後,同研究会は,平成10年6月16日付けで報告書が公表されている。
同報告書によれば,企業の利益は商法(企業会計)の手続を経て算出されるが,税務上の課税所得計算においては企業会計と異なる課税所得計算が行われるものであることから,課税所得と企業会計上の利益とに差違が生じ,減価償却費(耐用年数や償却方法の違い),引当金の繰入れ(損金算入額の制限),貸倒損失(事実認定時点の違い)等の損益の帰属期間の認識に差違があるため,将来の期間利益に対応すべき税額で当期に支払うべきものと当期の利益に対応すべき税額で将来支払うべきものが発生し,これらの税額を調整しないと,法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応せず,税引前当期純利益と税引後当期純利益の関係を歪め,適正な期間比較や企業間比較が困難となることが問題点として指摘されていた。また,これらの税額
の調整が図られないため,有税による貸倒償却や引当金の繰入れが阻害されるインセンティブとなっているとの指摘もされていた。
そこで,このような問題点の解消を図るため,一時差異に係る法人税額の期間帰属を企業会計に合わせることにより,企業会計上の利益が適正に表示されるよう調整する税効果会計の採用が必要であることが指摘されていた。
また,上記報告書の中では,企業会計において,繰延税金資産は前払税金に相当する税金を将来減少させる効果があり,繰延税金負債は未払税金に相当する税金を将来増加させる効果があると認められることから,一般的に資産性・負債性があると考えられていること,今後,商法の計算書類も含め個別財務諸表において税効果会計を採用することとなる場合には,企業会計上の基準を明確化することが必要であること,企業会計上の税効果会計に関する会計基準において,繰延税金資産及び繰延税金負債が法人税等の前払税金又は未払税金として資産性・負債性が明確にされるならば,商法上も公正な会計慣行を斟酌する立場から,企業会計上の基準と同様に,これらを貸借対照表に計上し得ることが指摘されていた。
さらに,①前記認定事実3(3)ア(イ)のとおり,早期是正措置検討会において,既に税効果会計の導入の必要性は指摘されており,また,同(ウ)によれば,「中間とりまとめ」の中においても,今後有税による償却・引当を円滑に進めていくための環境整備として税効果会計について検討を行うことが要請されていたこと,②早期是正措置検討会に委員として出席したL(当時は全銀協の一般委員長)は,当時,早期是正措置の導入により税法基準が採用されなくなった場合には,貸倒実績率に応じて償却・引当をするという考え方が全面に出てきて,銀行は有税か無税かを意識しないで対応せざるを得なくなり,決算処理上の負担が大きくなるので税効果会計の導入と平仄を合わせて早期是正措置を導入すべきと考えていたこと(証人L3頁),③早期是
正措置検討会の座長を勤めたKは,当時,早期是正措置の導入のさじ加減を誤ると,早期是正措置が一種のギロチン台のようなことになって,金融機関の経営危機,あるいは破綻を誘発しかねないので,当時の不安定な金融情勢に配慮しながら,ソフトランディングさせるという考え方が基本であったと述べていること(証人K12頁),④平成10年8月ころ,全銀協は,不良債権処理を促進する環境整備のため,無税償却基準の緩和を要望していたこと(乙60),⑤前記認定事実3(12)イのとおり,平成11年3月期決算における税効果会計の前倒適用が認められたこと,⑥税効果会計が銀行の平成11年3月期決算において導入されたことに伴い,主要17行(都銀9行,長期信用銀行1行,信託銀行7行)は,約6兆6500億円の繰延税金資産を計
上し,約10兆4000億円もの不良債権を処理したにもかかわらず,平成10年3月期において2兆2400億円であった剰余金の額は,平成11年3月期において,2兆6800億円にかえって増加し,有税による不良債権の処理すなわち償却・引当の自由度が高まったと評価されたこと,⑦このような税効果会計の導入が遅れた結果,無税償却・引当の慣行が併存し,他方,有税による償却・引当が義務化される方向が示された結果,各銀行を当惑させる状態にあったとの指摘もあること(証人K31頁,32頁),以上の事実が認められる。
エ 小括
以上の事実によれば,新基準で銀行の貸出金について,有税による償却・引当を義務づける方向が示された以上,旧基準に代えて新基準を唯一の基準としてその遵守を義務づけるためには,それに伴う決算処理に関する問題点を除去するためのセーフティネットとして,税効果会計の導入が同時に図られるべきであったといえる。それにもかかわらず,そのような手当が講じられなかったというべきであって,平成10年3月期においては,有税による償却・引当を義務づけるうえで,必要な手当てが不十分であったことは否定できないというべきである。
(4) 新基準の一義的明確性について
次に,新基準が,その内容において一義的に明確であったといえるか(前記2(4)の要件④参照)について検討する。
前記認定のとおり,新基準は,銀行の貸出金の償却・引当の基準に関し,貸出先(債務者)の実態に応じて,有税による償却・引当を義務付けるとともに銀行の関連ノンバンクに対する貸出金についても,できる限り関連ノンバンクの実態に応じて償却・引当をすべきとするもので,従来の税法基準によって補充された旧基準の大幅な変更を促すものであったといえるが,一方で,以下に述べるとおり,その一義的明確性の点では,いくつかの疑問点が指摘できる。
ア 改正後決算経理基準
改正後決算経理基準は,前記のとおり,回収不能が見込まれる貸出金について債権額から担保処分及び保証による回収可能額を減算した残額(以下「回収不能額」という。)を償却・引当すること,回収に重大な懸念があり損失発生が見込まれる貸出金については債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額のうち必要額について引当を実施すること,これらの貸出金以外の貸出金について,合理的な方法により算出された貸倒実績比率に基づき算定した貸倒見込額の引当を実施することが定められていたが,具体的かつ定量的な基準ではなく,資産査定通達等により補充されるものであった。
イ 資産査定通達
前記認定事実3(3)ア(イ)(ウ)(エ)と証拠(証人K,甲138)によれば,早期是正措置検討会においては,自己資本比率とこれに行政措置とを連動させる仕組み自体が,日本では全く未経験であり,当局が示す資産査定は金融機関の自己責任原則や主体性を阻害しないようにするため,大きな枠をガイドライン的に示すにとどめたこと,基準自体が定性的な内容であり,自己査定と検査との間に乖離が生じた場合,ともかくすりあわせながら一定期間試行的に行って定着させることを目的として早期是正措置を導入することとしたこと,償却・引当に関しては,米国では引当水準の目安が存在するが,これは目安に止まり,これ自体を行政措置の発動の根拠とすることは不適切であること,また,個別性の強い
個々の債権の回収可能性の違いを無視して,機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではなく,各金融機関が,自主的にこれを定めるとともに,また,償却・引当の正確性,客観性等を確保する観点から,償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備を行うべきことが基本事項とされており,定量的な部分が,金融機関のある程度自主性に委ねられていたこと,また各金融機関として平成10年の開始時点にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいが,その時点で不完全であっても,即「落第」という機械的な裁定はできないと考えられていたことが認められる。
また,前記認定事実3(8)アによれば,平成10年3月期決算における早期是正措置制度や自己査定制度の導入を踏まえて,大蔵省金融検査部は,各金融機関の自己査定体制の整備状況を検査し,平成9年度を自己査定の習熟度をみるためのトライアルの期間として,できる限り,大蔵省検査において,自己査定の整備状況をチェックし,問題点を指摘し訂正させることを検討していたことが認められ,大蔵省検査の中で,自己査定と資産査定通達の齟齬を解消していこうという姿勢を有していたことが窺われる。これは,当時大蔵省大臣官房審議官(銀行局担当)であったRが,その陳述書(乙109)において,資産査定通達や9年事務連絡は検査部内部の運用指針(ガイドライン)であり,検査官に対して一定の拘束力を持つのは当然としても,そ
れはあくまでも銀行法に基づく行政法上のものであること,それが金融機関において受け入れられ,結果として,優良な会計慣行(ベストプラクティス)として成熟化することが期待されていたこと,平成9年度(平成10年3月期)について,行政当局は,早期是正措置制度導入の準備期間であるとの意識を持ち,企業会計の実務面では金融機関の間でかなりの相違を生ずることを予測し,今後の金融検査や会計監査の中で是正と収れんを図るべきと認識していたこと,行政当局は,平成9年度に各行がガイドラインを参考にして自主裁量で作った自己査定基準について,大蔵省金融検査部が検査を実施し,不適切なものがあれば検査の際にその旨の指摘をして,将来に向けて是正して,ある程度の統一性を確保し,このような新しい手法に市場参加者全員が
慣れ,それが慣行となって徐々に統一性が出てきた段階で法規範性を持つに至ると認識していたことを述べ,また,当裁判所においても,証人として,資産査定通達が検査して議論する過程において共通の理解が相互に生まれれば,それがいわゆる商法でいう「公正なる会計慣行」となっていく可能性がある旨,資産査定通達等が実施され,ある程度議論されている過程の中で,市場で練られて成熟化していくと考えていた旨,検査を何回か重ねて議論をしていくうちに,段々と自己査定基準に関するばらつきが統一的な考え方に集約されていくというイメージであった旨供述していること(以上につき証人R6頁)からも裏付けられる。
これらの点を考慮すると,金融証券検査官は,金融機関が行う自己査定について,その基準が明確かどうか,その枠組みが「資産査定について」の枠組みに沿っているかどうか等を把握し,金融機関の自己査定基準の枠組みが独自のものである場合,「資産査定について」の枠組みとの関係を明瞭に把握し,金融機関の自己査定基準の中の個別ルールが合理的に説明できるものであるかどうか等をチェックすることが要請されており,その趣旨は,金融証券検査官が,金融検査の一環として,金融機関の自己査定の基準を検査し,「資産査定について」の枠組みに合致するかどうか,合致しない場合には,金融検査において,これを金融機関に指摘し,その是正を求めるものであり,基準の大枠すなわち定性的な基準を定めたうえで,次第に収れんを図
る趣旨とも考えることができる。
さらに,前記認定事実3(4)イのとおり,全銀協Q&Aによれば,現時点での情勢を前提とした資産査定にかかる一般的な考え方をまとめたものであり,将来にわたって固定されたものではなく,また個別金融機関の有する特殊性・地域性等は考慮されていないとされていたことからも,当初から一義的な基準として作用するというより,例えば,都市銀行,地方銀行,信用組合等一定の業態に応じて金融機関ごとに,基準として収れんされ,具体的かつ定量的な基準が形成されるまでの間のガイドライン的なものであったとみる余地もある。
以上の点を踏まえると,資産査定通達が,金融機関を明確に拘束する趣旨・内容のものであったといえるかについては多分に疑問があるというべきである。
ウ 4号実務指針
4号実務指針は,自己査定基準と資産査定通達の分類の整合性と対応関係を前提に,債権を分類して,その債権の分類ごとに必要な償却・引当をすべきことを定めるものであり,資産査定通達を前提にその償却・引当の抽象的かつ定性的な基準を示した指針であると認められる。
しかしながら,証拠(甲3,甲15,乙119,乙120)及び弁論の全趣旨によれば,4号実務指針は,会計監査における実務上の方針を示したものであるにすぎないこと,4号実務指針では,償却・引当すべき金額を具体的に算定することができなかったことが認められる。
すなわち,4号実務指針には通常の会計実務指針に存在する具体的な計算の規定と計算例がないこと,4号実務指針には債務者区分ごとに3年分の貸倒実績比率に基づき貸倒引当金を計上すべき旨定められているが,平成10年3月期において,銀行は4号実務指針公表後1年分の債務者区分ごとの貸倒実績率を有するにすぎなかったものであり(従前は債権分類ごとに貸倒実績を考慮していた。),4号実務指針でいう3年分の債務者区分の貸倒実績比率を用いることができず,適正な貸倒実績率による算定ができなかったこと,破綻懸念先についての債権額から担保回収見込額を控除した残額のうち必要額を引き当てるとされているが,その必要額の具体的な算定根拠がないことが認められる。
また,4号実務指針は,資産査定通達との関係において,債務者区分,資産分類,引当金算定の関係が必ずしも明確ではない。例えば,4号実務指針には債権区分の規定がなく,マトリックスを作成できないこと,資産査定通達では,破綻懸念先債権は,優良担保の処分見込可能額及び優良保証等により保全されている部分は非分類とし,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分をⅡ分類とし,残りをⅢ分類としているが,4号実務指針では,破綻懸念先債権は債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が認められる額を減算するとされ,優良担保と一般担保,優良保証と一般保証が区分されておらず,4号実務指針では,Ⅱ分類部分の引当が不要となる等の問題が存在していた。
さらに,前記認定事実3(3)ア(ウ)のとおり,「中間とりまとめ」においても,償却・引当の正確性,客観性等を確保する観点から,償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備を行うべきことが基本事項とされており,定量的な部分が,ある程度金融機関の自主性に委ねられていたこと,また各金融機関としては平成10年の開始時点にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいと指摘されるに止まっていたことから,結局,4号実務指針は,定性的な内容に止まり,定量的な償却・引当の基準として機能できたとはいえないというべきである。
加えて,前記認定事実3(4)ウのとおり,4号実務指針は,平成9年4月1日以降開始する事業年度に係る監査から適用するが,同年9月30日に終了する中間会計期間において銀行等金融機関が自己査定に係る内部統制を構築し,その旨を表明した場合には,当該中間会計期間に係る監査から適用することとされており,必ずしも平成9年9月期においては確実に適用されるとの前提に立っていなかったといえる。もっとも,この点に関しては,証拠(甲60の62頁,63頁)によれば,I会計士は,刑事公判廷において,弁護人から,4号実務指針が発表した途端に慣行になることがあるかとの質問に対し,「皆がそれを知り,皆が守ろうとすれば,それもまた慣行になるのじゃないでしょうか」と供述し,また,4号実務指針が財務諸表規則1条2
項,3項により一般に公正妥当と認められる企業会計基準とされており,当然に商法32条2項の公正なる会計慣行となり得る,4号実務指針は基準として一義的なものであり,会計慣行となり得るものである旨の供述していることが認められる。しかしながら,I会計士が供述した財務諸表規則は,遅くとも,平成10年11月24日号外大蔵省令第135号による改正後のものを指すと解されるが,上記改正前の財務諸表規則1条は,「大蔵大臣が法の規定により提出される財務諸表規則に関する特定事項について,その作成方法の基準として特に公表したものがある場合は,当該基準は,この規則に準ずる」ものとして,「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用される」旨規定していたにすぎず,上記改正により,1条2項が,「企
業会計審議会」により公表された会計基準は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当する」と規定したものであり,4号実務指針の公表当時,また平成10年3月期においては,企業会計審議会の公表する会計処理の基準であっても,立法的手当がされておらず,平成10年3月期において,財務諸表規則を根拠に4号実務指針が,財務諸表規則にいう「一般に公正妥当と認められる企業会計基準」であると解することはできず,上記財務諸表規則を介して,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たると解することもできない。
また,上記改正後の財務諸表規則1条2項,3項において,その主体は,いずれも企業会計審議会又は大蔵大臣(平成12年総理府令第116号により「金融庁長官」)であり,当然に,この中に会計士協会が含まれると解することもできない。もっとも,会計士協会の公表する監査委員会報告についても,一定の会計処理や情報開示を示している場合には,監査上妥当なものと取り扱うなどの方法により,間接的に会計的側面を有するものがあることも否定し得ないが,このような監査委員会報告が,基準として具体的かつ定量的な内容であることや事前に関係当局その他の関係者と十分な協議を経て関係者に会計基準として認識されるに至ったとみなし得ること等が必要であるというべきである。
さらに,証拠(甲136の18頁)によれば,Q会計士は,4号実務指針が全ての金融機関に一般的に適用されることを想定しており,規定の中に抽象的な部分も存在し,金融機関が実務を行うためには,それぞれの具体的基準を設けて運用する必要があったと供述し,上記の点も併せて考えると,4号実務指針が,具体的かつ定量的な基準として,償却・引当の基準を定めたとみることには,なお疑問が残るというべきである。
エ 破綻懸念先の概念等
また,特に,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する基準の変更の点については,資産査定通達の内容や4号実務指針からみても,以下の疑問点が指摘される。
(ア) 「破綻懸念先」の概念
まず,前記前提となる事実2(2)アによれば,破綻懸念先の概念については,「現状,経営破綻の状況にないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。具体的には,現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況で,自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」
とされていたが,従前の税法基準においては,①前記のとおり,母体行主義を前提としてシステミックリスクの発生を回避するため,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の査定結果を母体行の貸出残高を限度として又はその全額について母体行に反映させる一方,関連ノンバンクの資産査定の結果を母体行以外の銀行の貸出金には反映させず,これにより,母体行以外の銀行の貸出残高の維持を図っていたこと,②前記のとおり,母体行は,関連ノンバンクの分類資産(不良資産)について,合理的な再建計画を作成し,国税当局において無税扱いに関する事実上の承認を受け,償却原資の提供すなわち債権放棄等の損益支援や新規貸付け等の支援をして関連ノンバンクの分類資産を処理し,関連ノンバンクの経営の健全化を図る,すなわち再建することが予
定され,最終的に関連ノンバンクを再建し,それにより破綻が回避される以上,再建期間中における母体行及び母体行以外の銀行の貸出金については貸倒れのリスクが発生しないと考えられていたことを根拠として,不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準すなわち税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当をしないとする会計慣行が存在していたところ,「破綻懸念先」において,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先」として,母体行主義の下における関連ノンバンク向け貸出金の査定方法を前提とした表現が含まれている。
もっとも,「自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」とされていたが,証拠(甲136の39頁)と前記認定事実3(12)ア(イ)aによれば,金融検査マニュアルの策定・公表がされた際,その中で,「破綻懸念先」の意義について新たに「債務者」の後に括弧書きとして「(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)」と付記し,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており」以下の部分が削除され,「現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があ
り,従って損失発生の可能性が高い状況で,今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」と改められており,従前の会計慣行との比較において,「破綻懸念先」の意義が明確ではなかったことを踏まえて,このような改正が,金融検査マニュアルの中で行われたと考えられる。さらに,これを受けて,前記認定事実3(12)ウのとおり,平成11年4月に4号実務指針の内容も改正され,破綻懸念先債権については,「経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく」との文言が付加されている。これらの事実に照らすと,発出当初の4号実務指針には不明確な部分が存したことが明らかである。
(イ) 特定債務者支援引当金
銀行の関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当をせず,支援損すなわち支援に要する費用を計上するという慣行についても,4号実務指針で,このような計上が予定される費用について引当金を要するということが明確化されていたわけではなかった。
すなわち,前記認定事実3(12)ア(イ)b,cのとおり,平成11年になって初めて,銀行が関連ノンバンクに対して支援を実施している場合,新たに特定債務者支援引当金という勘定科目を設けて,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を費用の引当金として計上することが定められ,また,例外的に,支援の内容が債権放棄で,当該損失見込額が貸出金額の範囲内であり,かつ,当該損失見込額が少額で特定債務者支援引当金を設定する必要性に乏しい場合など合理的な根拠がある場合は,その支援額を個別貸倒引当金として計上し得ることが定められた。
このような金融検査マニュアルの定めは,新たに銀行が支援を継続している関連ノンバンクであっても,その支援に要する費用をあらかじめ計上することを義務づけて明確化し,さらに,例外的に,本来費用性の引当金と考えられる特定債務者支援引当金について,貸倒引当金の計上により代えることができると明示し,従来の銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の内容を整理し,明確化を図ったものと評価できるものであり,金融検査マニュアルの公表以前の段階においては,この点が明示的に定められていたと解することは困難であったといえる。
なお,この点に関しては,前記認定事実3(12)ウの4号実務指針の改正により,債権放棄により支援を行う場合には貸倒引当金として,現金贈与等により支援を行う場合には特定債務者支援引当金として,それぞれ貸借対照表に計上すべきことが定められ,従前明確ではなかった部分が明確にされたといえる。
オ 平成10年3月期における銀行(主要17行)の決算の修正
ところで,証券取引法24条1項,6項は,上場会社は,企業内容等の開示に関する省令(昭和48年大蔵省令第5号)の定めるところにより,事業年度ごとに,いわゆる有価証券報告書及び添付書類(「当該事業年に係る商法第283条第1項に規定するもので,定時株主総会に報告したもの,又は,その承認を受けたもの」すなわち貸借対照表,損益計算書等)を提出すべき旨規定し,また,同法24条の2は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等の記載すべき重要な事項の変更等があるときは,訂正報告書を提出すべきこと(同法7条準用),また,大蔵大臣は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは,提出者に対し,訂正報告書の提出を命ずること(同法9条1項準用)
,さらに,大蔵大臣は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等のうちに重要な事項について虚偽の記載があること等を発見したときは,提出者に対し,訂正報告書の提出を命ずること等(同法10条1項準用)を規定する。
また,財務諸表規則65条1項は,利益剰余金に属する剰余金又は損失金の貸借対照表における記載方法については,「利益準備金」(同条項1号),「任意積立金」(同条項2号)及び「当期未処分利益又は当期未処理損失」(同条項3号)の各区分に従い,当該剰余金又は損失金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならないと規定する。この「当期未処分利益又は当期未処理損失」の額は,「貸倒引当金繰入額又貸倒損失」の額が増減した場合には,当然それに伴い増減するところ(同規則87条,95条の4,95条の5,95条の6),これらの変更も,その額が多額に上る場合,当然,上記「重要な事項」に該当し,訂正報告書の提出等が必要となると解すべきである。
そして,新基準のもとでは,当然にこのような基準の変更がなされるべきところ,平成10年3月期において,そのことが必ずしも明確化されていなかったことを窺わせる事情として,主要17行において決算の修正が行われていないことが指摘できる。
すなわち,前記認定事実3(10)イによれば,主要17行において,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して5兆4061億円減少し,そのⅡ分類が3兆5842億円,そのⅢ分類が1兆5708億円,そのⅣ分類が2511億円,それぞれ当局査定結果により増加し,主要17行については1兆0413億円の償却・引当不足が存在していたと認められるところ,本来,このような貸出金に係る償却・引当不足額は,当然,費用として当期利益から除外されるべきであり,かつ,その額も1兆円にも及んでおり,証拠(乙34)によれば,主要17行の平成10年3月期決算において,8兆6151億円の赤字決算を行い,おおむね各銀行ごとには,最大100億円程度の黒字を計上した信託銀行や
最大約9000億円の赤字決算をした都銀が存在しており,上記不足額が各銀行ごとにどの程度存在していたかは明らかではないが,全体の当期損失額の8分の1にも達する更なる損失額が生じた以上,当然,新基準を厳格に適用することを前提とする場合には,このような不足額をすみやかに財務諸表に反映させ,訂正報告書の提出を求めるべきであったといえる。それにもかかわらず,これらの乖離が生ずること自体,基準としての明確性に問題があるというべきである。また,金融監督庁の対応の問題ではあるが,証拠(乙26)によれば,平成10年3月期金融検査の結果については,同期の決算を遡及的に修正することは無理であり,検査結果をどの決算期において反映すべきとの指摘を行わないことされている。結局,決算処理の是正を各銀行の自
主判断に委ねたものと解され,このことからも,新基準のもとでの実務が流動的な要素を含んでいたといえるし,いずれにしても新基準については,償却・引当の基準としての明確性に疑問があるといわざるを得ない。
カ 小括
以上によれば,旧基準と新基準を比較した場合,新基準は,①銀行の貸出金について有税による償却・引当を実施すべきとして従来の旧基準の変更を促し,②銀行の貸出金特に銀行の関連ノンバンク向け貸出金についても償却・引当をすべきとすることを促したものというべきであり,その範囲で,従前の会計慣行を変更することを目的としたものであるが,前記イのとおり,資産査定通達や4号実務指針には基準として明確ではない部分が存在し,特に定量的な基準の策定については各金融機関の自主性に委ねられている部分があること,特に,破綻懸念先の概念と特定債務者支援引当金の概念において,曖昧な点が残り,この点の変更が明確にされていなかったこと,金融当局においても新基準を厳格に適用して,銀行の決算の修正を図るまでの意
図があったとまでは思えないことなど,その基準としての一義的明確性や拘束性については,多分に疑問が残るものであったと認めざるを得ない。
(5) 関係者に対する規範として拘束性を有するものであることの周知徹底の有
無について
次に,原告らの主張するとおり,新基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たるとした場合には,商法32条を介して関係者に対し,法規範としての拘束性を有することになるところ,前記2(4)の要件⑤のとおり,これを認めるためには,新基準に拘束されることになる関係者に対し,新基準が一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が図られていることが必要と解すべきである。
そこで,以下,この点について検討する。
ア 基準の周知性
前記認定事実によれば,①早期是正措置の導入が決定された際,大蔵省は,その導入に関する各指針を金融雑誌誌上等において公表していたこと(前記認定事実3(1)ア),②資産査定通達の内容についても,同様に,金融雑誌誌上において公表し(前記認定事実3(4)ア(イ)),また,全銀協Q&Aの形で配布され(前記認定事実3(4)イ),各金融機関は,全銀協を介して,これらの基準の内容については知り得たこと,③9年事務連絡についても同様に全銀協追加Q&Aの形で配布され,同様に各金融機関は,全銀協を介して,これらの基準の内容については知り得たこと,④4号実務指針についても,JICPAジャーナル等の会計雑誌を介するなどして,その内容が公表されたこと,⑤改正後決算経理基準は,大蔵省銀行局長において,各銀行の代
表取締役頭取に宛てて発出され,その内容を当然に各銀行において知り得たことが認められ,新たな資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準は,基準として,一応の周知が図られたと評価することは可能である。
しかし,①税法基準の変更すなわち有税による償却・引当の義務化を促した点と,②銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の義務化を促した点については,以下の事情を考慮する限り,関係者の理解に対する手当が不十分であり,十分な時間的余裕もなく,関係者が理解し得る状態に達していたかどうかについては多分に疑問が残るところである。
イ 通達発出者の意図
新基準の中核をなす改正後決算経理基準は,大蔵省銀行局所管の通達であるところ,同通達発出当時の大蔵省銀行局の担当審議官であるRの証言によれば,R自身としては,同人が担当審議官を務めていた平成7年ないし平成10年は,銀行行政の転換期で,不良債権処理を余りに性急に行うことは大きな混乱を生ずるおそれがあり,いわゆるセイフティーネットの整備が必要と考えていたこと,新基準については,行政当局の作成した通達であり,通達の示すガイドラインを参考にして各銀行ごとに自己査定基準を作り,これに対し金融当局が何回か検査を行うことによって次第に統一的な考え方に収れんされていくものと考えていたこと(証人R11頁),平成10年3月期の時点では,新基準はマーケットや当事者の検証を経ていないもので,銀
行行政の目的で出された通達であり,未だ商法上の「公正なる会計慣行」にはなっていなかった(言い換えると通達で商法の会計基準が直ちに変更されるとは考えていなかった)と認識していたこと(証人R10頁,38頁)がそれぞれ認められる。
ウ 関係者の理解に対する手当
(ア) 平成10年3月期における原告を除く各銀行の実務
証拠(甲188ないし甲205)によれば,平成10年3月期において,都銀9行,原告を含む長信銀3行及び信託銀行7行は,その有価証券報告書において,貸倒引当金の計上基準としては,改正後決算経理基準に基づき,各行の自己査定基準及び償却・引当基準に従っていること,その内容は,おおむね4号実務指針に基づき,経営破綻先債権及び実質破綻先債権について債権額から回収可能見込額を控除してその残額について計上すること,破綻懸念先債権について債権額から回収可能見込額を控除してその残額のうち,債務者の支払能力を総合的に判断して必要な額を引当金として計上することを明らかにしていた。
しかしながら,証拠(甲136,証人L,証人X,H本人,乙102,乙103,乙118ないし乙120)によれば,①平成10年3月期より前に「特定債務者支援引当金」を計上したことがあった銀行は,東海銀行及び第一勧銀の2行にすぎず,平成10年3月期においても,Q会計士は,刑事公判において,平成10年3月期の大手19行のうち,長銀を除く18行で将来の支援予定額について,特定債務者支援引当金ないしは貸倒引当金を計上しなかったところは,18行中14行である旨供述しており(甲136の37頁),特定債務者支援引当金を計上した銀行は4行にすぎなかったこと,②平成9年5月19日,原告の総合企画部の担当者とさくら銀行の担当者が情報交換をした際,さくら銀行の担当者は,さくら銀行としては,関連
ノンバンクについては,母体行としてきちんと面倒を見て行くつもりであり実質破綻先等の債務者区分は不適切であり,債務者区分はしないつもりである旨述べ,平成9年7月14日の情報交換の際にも,債権放棄額確定分をⅣ分類(全額償却)とし,残りをⅢ分類とするがⅢ分類は損失の合理的推計ができないとして,引当は行わない旨述べたこと,また,さくら銀行は,平成10年3月期においても,上記方針に従い,支援予定の関連ノンバンクに対する貸出金については,債務者区分を実施せず,当期支援損をⅣ分類として全額償却したこと(証人L13頁,26頁,27頁),③興銀においても,平成10年3月期において,特定債務者支援引当金の勘定科目により,支援損予定額をあらかじめ計上していなかったこと(証人X,甲62),④住友信託
においても,直系ノンバンクⅢ分類債権償却の必要額は,支援の必要性等をその都度判断し,基本的には生かす企業として引当・償却を行わない様にしたいと考えられていたこと(H本人11頁,乙104)がそれぞれ認められ,これらの事実に照らす限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金については,多くの銀行において支援損を計上する以外には,特に個別の償却・引当を実施していなかったものと認めざるを得ない。
以上によれば,多くの銀行(上記18行中14行)は,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準に厳格に依拠したうえで,その貸出金の償却・引当を実施していたとは認められないというべきである。
(イ) 関係者の理解度
本件における新基準の変更内容について,実際に,関係者が,どの程度の理解をしていたかについては,①まず,資産査定通達等の導入に当たり,Kは,早期是正措置検討会において,自己査定と検査の結果に格差・乖離が生じた場合,相互にすりあわせて,一定の水準を探し求めること,また,有税による償却・引当を拡大するといっても,税効果会計も導入されず,どうなるのかといった指摘もあったが,すりあわせながら一定期間試行的に行って定着させるというのが了解事項であったと供述していること,そしてこのような供述内容は,前記認定事実3(3)ア(イ)bのとおり,M企画官が,自己査定基準において独自性を発揮するのが重要であるが,その結果が,当局が示す基準に整合しているかどうかについては十分にチェックすることとな
ると説明していたことやN調査課長が,個々の検査の場面で,金融機関側との意見が相違する,あるいは,会計監査人の考え方と金融検査の立場が相違することはあると思うが,検討会に出席した米国の公認会計士が説明していたように,そこは実務的に議論する中で,大きな隔たりが残ってどうしようもないということは少なく,かなり調整できるとの指摘もあり,議論の中で,いろいろ知恵を出していくことになると思うと説明していたことと符合すること,②前記認定事実3(10)オ(イ)のとおり,原告の会計監査を担当したP会計士等は,経済的利益供与が貸倒引当の概念に該当しない,未払金の計上という方法があるが,企業会計実務の中で一般慣行として定着していない,原告の考え方も妥当の範囲内であると回答し,また,他の担当会計士も,支援に
ついては現金供与もあり,貸出金の引当という考え方になじまないと説明していたこと,③証拠(甲136の23頁)によれば,Q会計士は,刑事公判廷において,平成10年3月期において,監査を行う公認会計士の側において,資産査定通達等が許容する解釈の幅に対する理解について影響があったのかどうかという弁護人の質問に対し,「平成10年3月期は,平成9年3月期以前の会計処理の継続という面もあったわけでございます。平成9年3月期以前に償却,引当をしなくてもいいというふうに認められた項目が,資産査定通達の解釈上,それが許容されるというふうに読める場合に,それを許容できないと,平成10年3月期に結論付けることは,なかなか難しかったのではなかろうかと,許容範囲内と判断できたのではないかというふうに思い
ます」と供述し,公認会計士においても,必ずしもこのような変更の内容については十分な認識・理解がなかったことが窺われること,④原告の元監査役であったZは,刑事公判廷において,平成10年3月期においても,従来銀行の貸出金の償却・引当の基準であった決算経理基準,不良債権償却証明制度,検査官の査定等が一体となった一つの基準が全然実質的には変わっていなかったと認識していた旨供述していること(甲135の46頁),Gも,当裁判所において,資産査定通達等の基準が銀行実務家において,「公正なる会計慣行」であると認識がなかった旨供述していること(G本人64頁),⑤証人Lは,当裁判所において,銀行の関連ノンバンク向け貸出金について,平成10年3月期にはどう対処をすべきかという明確な基準はなく,その
時の処理の仕方は,税法基準に則って処理するということをやっていた旨証言し(証人L11頁),また,平成10年3月期における企業会計処理の基準の変更については,当初早期是正措置は,平成10年の4月以降適用となっていたところ,平成10年の3月期から前倒しでやるということになり,準備が完全に整っていない金融機関もあるのではないかとの心配もあり,税効果会計が認められなかったというのに,その時期から実施するということになってかなり混乱はあったのではないかと思う旨証言していること(証人L17頁),さらに,この間,原告以外の銀行関係者においても,必ずしも,十分明確な理解がなかったこと,銀行界は,過去,税法基準に則って決算経理をしており税法基準に拘った考え方が銀行界一般には根強く残っていたこと
,そのため,早期是正措置が導入されたとはいえ,一番最初の段階で具体的なことがよく見えていない状況の中で,銀行が基準として考えるよすがとしては,税法基準が一番直近で目に見えた基準であったこと,したがって,税法基準をベースにして銀行が決算経理の処理をするということは,当時としては一般的な取組みの仕方ではなかったかと思う旨証言していること(証人L23頁),以上の事実が認められる。これらの事実からすると,平成10年3月期の段階においては,新基準がこれに拘束されるべき公認会計士,銀行関係者にとって,必ずしも,明確な基準といえないばかりか,その根幹の部分の内容について十分な理解が得られていなかったものと認めざるを得ない。
(ウ) 変更に対する時間的な余裕,習熟度
さらに,前記認定事実3(8)アのとおり,平成10年3月期における銀行の関連ノンバンク向け貸出金を含む貸出金に対する償却・引当は,各銀行間において,実際の状況にかなりばらつきがあったが,当初,このようなばらつきが生ずることは予想されており,大蔵省金融検査部は,平成9年度を各金融機関が自己査定に習熟するためのトライアル期間と位置づけて,その間において,各金融機関がどのような自己査定基準を策定しているかどうかについて予備的に検査し,そごがあれば,これを指摘して訂正させることも計画していたが,同年11月に,三洋証券株式会社の会社更生手続の申立て,株式会社北海道拓殖銀行の経営破綻や山一證券株式会社の自主廃業等により,金融システムが混乱に陥ったため,このような検査を実施するには至ら
なかったこと,また,大蔵省が預金保険法の改正等のための国会における審議資料として,各金融機関の試行的な自己査定による数字(不良債権額)を提出させた際にも,その内容が各行ごとに全くばらばらで,必要な数字の比較や集計ができず,各銀行に対し,Ⅰ分類からⅣ分類までに組み替えるよう指示したこと,さらに,その後においても,大蔵省は,平成10年1月以降,説明会において,このような「ばらつき」について統一化を図ることも試みたが,平成10年3月期決算は,平成9年12月末を基準としており,既にその時点では,平成10年3月期決算には時間的余裕がなかったことが認められる。
エ 小括
以上のとおりであって,新基準の内容については,一応の周知策はとられたと評価できるものの,前記(2)のとおり,新基準の内容が税法基準によって補充されていた旧基準の内容を大幅に変更するものであったにもかかわらず,新基準の内容自体に多分に曖昧な部分があったこともあって,平成10年3月期については,新基準を示した行政の当局者であるR審議官ですら,新基準が「公正なる会計慣行」になっていたとは考えていなかったばかりか,被告らを含む銀行関係者の多くの理解度,習熟度も前記認定の程度であり,旧基準による会計処理も許容されていると認識していた可能性があることが 窺える。そうであるとすれば,平成10年3月期については,いわば,旧基準から新基準への移行期ないしは過渡期とみざるを得ないもの
であり,その時点で,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が図られていたと認めることは到底できないというべきである。
(6) 新基準が平成10年3月期において銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」になっていたといえるかについての結論
以上(1)ないし(5)で検討したところによれば,新基準が示された経緯からすると一応手続的には適正であり,内容的にも新基準については一応の合理性を認めることができるというべきであるが,平成10年3月の時点で,企業会計の継続性を維持し,関係者への不意打ちを避けるといった観点からみて,旧基準から新基準への変更に必要な手当がなされているとは言い難いし,新基準の内容自体も一義的な明確性という点では多くの疑問が残るばかりか,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が関係者に対し図られていたと認めることもできないというべきである。
そうであるとすれば,平成10年3月の時点において,新基準が銀行の貸出金の償却・引当の基準として,唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとまで認めることはできないから,この点に関する原告らの主張は理由がないというべきである。
6 争点⑥(新基準が平成10年3月の時点で銀行の貸出金の償却・引当に関す
る唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合,この点に関する当時の会計慣行はどのようなものであったのか。そして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準による償却・引当が当時の「公正なる会計慣行」に違反していたといえるか。)について
原告らは,予備的な主張として,仮に新基準が平成10年3月の時点で銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合でも,被告らの主張する税法基準は当時の「公正なる会計慣行」とはいえず,当時の公正なる会計慣行は旧商法285条の4第2項における「取立不能見込額」の判定に従い,債務者の資産状態,収益力,担保状況からみて合理的な社会通念に従って行わなければならず,被告らが関与して原告が平成10年3月期において策定した自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当額はこれに違反していると主張している。この主張については,既に認定したとおり,平成10年3月期においても,税法基準によって補充された改正前決算経理基準(旧基準)は依然として「公正なる会計慣行」として存
続していたと認められるから,その観点からすると,原告らの主張は理由がないということになる。しかし,一方で,原告らの主張は,被告らが関与して原告が平成10年3月期に策定した自己査定基準に基づく原告の貸出金の償却・引当額は,その実質的な内容において当時の「公正なる会計慣行」に違反しているとの主張とみる余地もあるので,以下念のため,本件で問題とされている被告らが策定に関与した原告の平成10年3月期の自己査定基準に基づく関連ノンバンク等関係会社に対する貸出金に対する償却・引当の実態について検討することとする。
(1) 原告の平成10年3月期の自己査定基準と新基準及び旧基準との関係並びに自己査定基準に対する被告らの認識
ア 自己査定運用規則及び自己査定運用細則
原告らは,被告らが策定した自己査定基準すなわち「自己査定運用規則」及び「自己査定運用細則」が,不良債権の計画的な隠ぺいと不良債権処理の先送りを企図して,本来償却・引当義務を負うべき関連親密先に対して,償却・引当を不要とする目的により,これらの基準を策定したと主張するので,この点を検討すると,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,「自己査定運用規則」及び「自己査定運用細則」は,原告の関連親密先については,債務者区分を実施せず,「その他」と区分し,一律的な資産分類を行い,基本的には,当期支援損を計上する以外には,償却・引当を実施しないということを内容とするものであったことが認められる。
このような債務者区分は,新基準では,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当については,従来の慣行(一定期間における再建を実施し,これにより破綻回避を予定して,当期支援損を計上する以外には,償却・引当を実施しないとの慣行)を転換して,9年事務連絡の範囲内で,短期間の再建による破綻回避が行われる場合でない限り,関連ノンバンクの資産の実態に即して必要な償却・引当を行う義務を負うというものであったことからすると,そのような新基準の趣旨に照らす限り,その趣旨に反したものと認める余地があるし,また,前記認定事実3(10)ウ,オ,カのとおり,平成10年3月期の金融検査において,日銀の担当者及び金融証券検査官が,このような基準については資産査定通達等に反するとの指摘をしているこ
とからすると,客観的評価としては新基準に反していた可能性は高いというべきである。
しかし,一方で,平成10年3月期は,いわば旧基準から新基準への過渡期であり,新基準が未だ唯一の「公正なる会計慣行」にはなっていなかった以上,新基準に対しての違反は,通達違反の問題を生じさせるとはいえ,従来の「公正なる会計慣行」である旧基準(銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対しては,合理的な支援を継続する限り,償却・引当を実施しないとの会計慣行)が継続されていたものと認めざるを得ないから,以下のような基準を設けることも旧基準の範囲内であると解すべきである。
まず,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,「経営支援実績先」との区分を設けた点については,従前の税法基準を前提に検討した場合には,法人税基本通達9-4-2に係る支援先に対する支援が合理性を有するかどうかの判断基準として,「整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)」に従い,銀行による再建管理の実施先を想定し,合理的な再建計画の実施を前提に再建支援を行い,又は行い終えた先についてもその支援の継続,見直し,再開が必要となるとの観点から,通常先と異なる管理を継続する趣旨とみることができ,銀行の関連ノンバンク向け貸出金を一般の貸出金と区別して管理することを容認していた旧基準に照らし,容認できる区分といえる。また,前記認
定事実3(7)ウ,同(9)イによれば,本件監査法人もこの区分を了解している。そして,証拠(乙105の21頁,乙108の51頁から54頁,乙118の16頁,乙120の11頁)及び弁論の全趣旨によれば,当時の銀行による支援の形態として,いわゆる自転状態(<ア>含み損が残存しているが,含み損部分に見合う借入金の金利を本業の利益(償却前利益)によりまかなえる状態に達していること,<イ>期間損益が黒字であること,<ウ>キャッシュフロー(現金収支)が順調であり,借入金の約定返済に遅滞が生じていないこと)に達している場合に,さらに含み損を即時に処理し得る償却財源の提供すなわち損益支援を実施するときは,過剰支援となるおそれがあり,上記基本通達9-4-2において,「損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過
剰支援になっていないか)」という点との関係において,支援の合理性を否定されるおそれがあったことが認められるから,自転状態に達しているが,なお,銀行が,継続的な支援・管理を実施している先として「経営支援実績先」を観念する余地は十分あるというべきである。そうであるとすれば,旧基準に照らす限り,このような類型は許容できるというべきである。
次に,関連親密先であるノンバンクと一体とみなし得る子会社については,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,決済事由10項ただし書により,不稼働資産処理を本体で一体として行う会社については,本体の債務者区分に従い,それに準じた資産分類を行うとされていたものである。この点については,法人税基本通達9-4-1又は同基本通達9-4-2において,「支援者が行う子会社に対する支援の一環として,つまり関連会社の清算又は再建に伴う子会社の損失負担額を含めて支援者が子会社の支援を行う場合において,それが子会社の再建を図るために必要不可欠であると認められるときは,支援者の子会社に対する支援及び子会社の関連会社に対する支援等について,それぞれ法人税基本通達9-4-1又は同通達9-4-2に該当する
かを検討することとなる」こととされ(乙14の30頁),一定の場合において,法人税基本通達9-4-2が,支援を行っている先と支援先の関連会社の一体処理を許容していたこと,また,証拠(証人Xの28頁,29頁)及び弁論の全趣旨によれば,関連ノンバンク本体において,関連ノンバンクの関係会社(その孫会社等)を支援する場合,関連ノンバンクに新たなる損失が発生し,それも含めて,銀行が,支援計画を立てている場合においては,合理的な計画として,関連ノンバンクとその孫会社等の処理を一体的に行うことも許容されていたことからみて,原告において,一定の場合に,関連ノンバンクと孫会社等を一体とみることも,旧基準のもとでは許容されるものと考えられる。
また,※7なお書は,母体行責任を負う意思があっても,再建計画が作成されていない場合であり,かつ,当該「関連ノンバンク」の取引金融機関が原告のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類とし,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類とし,その他をⅢ分類とすることを定めている。この点,不良債権償却証明制度において,法人税基本通達9-6-4の運用に当たって,その要件である事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないとされているところ,銀行
が,再建のための支援を実施していない場合であっても,上記支援の内容が,損益支援などの再建のための抜本的な支援に限定されず,融資等の当面の企業維持を目的とした支援を含むものと解すると,旧基準による限り,償却・引当を実施することはできないと考えられ,また,損失が確定するまで無税による償却・引当も困難であり(有税による償却・引当が旧基準のもとで必ずしも義務とされていなかったことは,前記のとおりである。),このような運用も,旧基準においては,許容されていたというべきである。
イ 被告らの認識
また,原告らは,本件において,被告らは,平成10年3月期以前の段階において,原告の償却原資の状況からみて,償却不可能な不稼働資産を抱えていた結果,その存在を隠ぺいし,その処理を先送りするため,意図的にこのような自己査定基準を策定したと主張するので,検討する。
この点については,①前記認定事実3(2)ア(ア)のとおり,平成8年4月の大蔵省検査における原告の関連親密先の不良債権の試算として,Ⅲ分類及びⅣ分類の合計額が8437億円であると記載されているが,これは,修正母体行方式による査定結果であり,本来のプロラタ負担においては5710億円であるにすぎず,上記8437億円が単年度償却・引当すべき金額であったと考えられないこと,②前記認定事実3(2)イ(イ)のとおり,平成8年8月30日開催の常務会段階においては,未だ,早期是正措置検討会における「中間とりまとめ」すら作成・公表されておらず,この段階において,Fが「実質的には,多額に抱えてしまっている不稼働資産をどのような形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。
その点は十分認識しておく必要がある。」と発言していたとしても,それが,直ちに,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準に反することを承知のうえで,これを意図的に潜脱しようとした趣旨の発言とみることには無理があること,③前記認定事実3(3)イ(イ)のとおり,修正母体行主義により原告の融資残高を条件とした場合における関連親密先の不良債権について,その最終要処理額が1兆6914億円に達していたことは認められるが,その処理計画については5年間の期間が想定されており,従来の税法基準に照らし,当然許容される考え方,計画であったといえること,④前記認定事実3(3)イ(エ)のとおり,平成8年12月19日の常務役員フリーディスカッションにおいても,関連親密先の不稼働資産の処理計画について,3通りの
試算が行われているが,それ自体,可能な限り,原告内部において,不良債権の処理の早期化を進める趣旨の内容とみるべきであり,また,不良債権処理を進めるうえで,どのように償却財源を確保するかということは当然に検討されるべき課題であり,償却財源を検討しながら,不良債権処理額を検討することは不自然とはいえないこと,⑤前記認定事実3(3)イ(オ)のとおり,平成9年2月7日開催の常務役員連絡会資料によれば,「今後の不良債権要処理額見込は最低7000億円~1兆円レベル且つ早期是正措置により平成9年度以降Ⅲ,Ⅳ分類資産は単年度での適正な償却・引当の実施が不可避」との記載があり,単年度での1兆円規模の処理(償却・引当)が必要との趣旨にも読めなくはないが,その括弧書きには,「97年度不良債権要処理額見込
約3000~5000億円,98年度以降約1000億円/年~不確定要素」との記載があり,最終的には原告において1兆円規模の不良債権処理を要するものの,単年度においては,その一部を処理すれば足りるという趣旨とみることができること,そして,上記金額が,当時,原告が本来的には全額の償却・引当義務を負担しない(すなわち貸出金のシェアに応じたプロラタ方式により査定され,その場合に償却・引当義務を負うと理解される)関連ノンバンクの営業貸付金のⅣ分類,Ⅲ分類を含んだ金額であることからすると,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当をただちに行うような会計慣行が存在しなかった当時においては,上記1兆円という金額は一定期間において最終処理すべき金額を示したにすぎなかったとみるべきであり,
そうであるとすれば,上記1兆円は,単年度において直ちに償却・引当を要するものではなかったと認めるべきであること(乙100の15頁),⑥前記認定事実3(5)ア(ア)のとおり,平成9年5月9日付け「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」と題する資料においても,関連親密先の自己査定は,日本リースの扱い等無理をしているところがあること,引当率の考え方が会計士と議論になることが必至であり,個々の関連親密先の処理について,会計士に合理的な説明を行い,理解を得る必要があることや会計士の理解が得られる場合と得られない場合とに分けて試算する必要があることが指摘されており,外部監査における会計士の意見を尊重しようとする意図が認められること,特に会計監査人の理解が得られない場合も想定しており
,その場合には不良債権の処理額が積み上がることも当然予定していたと考えられること,他方,前記認定事実3(5)ア(イ)によれば,同日付け「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料(甲30)において,不稼働処理必要額の見極めとBIS比率8パーセント割れを回避しつつ,必要不稼働処理を可能とするリスクアセット,決算運営が挙げられているが,不良債権の処理を行ううえで,償却財源を配慮するのは,銀行決算において当然であり,また,総合企画部と事業推進部の試算が,4598億円(事業推進部)と3454億円(総合企画部)が相違する点も,異なる部署が個別に試算しており,この時点における数字の乖離が生ずることも,原告の正規の機関(取締役会,常務会,経営会議等)の承認・決
定を経ていない段階において当然であること(乙100の17頁,乙108の10頁),また,これらの数字は,いわゆる関連親密先に対する支援額に応じて異なるものであったこと(G本人27頁),⑦前記認定事実3(7)アにおいて,スイス銀行からのファイナンス実施により,増資される以上,当然償却財源に余裕が生じて,その分で不良債権処理を進めることを考えること自体,特に不自然な点はないこと,⑧前記認定事実3(7)イ,ウのとおり,平成9年9月2日付け資料によれば,償却財源の不足の点については,全体としての不良債権の処理には満たないことが指摘されていること(G本人35頁),相当の理論武装が必要となることや会計士に否認されるおそれについても,最終的には会計士に説明をして理解を得ることが前提であり,会計士の理
解が得られない場合には,最終的な償却・引当の増額も認識していたことも認められ,そのような事実に照らす限り,直ちに意図的に償却・引当の不足があるのにこれを潜脱しようとしたとは認められないこと(G40頁),⑨また,現に,Hほか事業推進部のメンバーは,Q会計士等に対し,原告の自己査定基準について債務者区分として「関連ノンバンク」以外に「関連親密先」を設けることの適否について見解を求めており,Q会計士等から,資産査定通達の許容範囲内との回答を得ていたこと,⑩前記認定事実3(7)エのとおり,本件中間配当に関する検討が行われた際も,D,E及びFは,いずれも赤字決算がないことを前提としていたとはいえ,従前の会計慣行に照らせば,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当は必要ではないと考え
ていたことが窺えるし,また,ほぼ一貫して平成9年度における5000億円の不良債権処理を想定していたことが認められること,⑪現に,平成9年度において,原告は,前記認定事実3(9)ウのとおり,最終的には6165億円の不良債権を処理していること,以上の各事実が認められる。
これらの事実と前記認定事実で詳細に認定した被告らの平成10年3月期の決算処理への対応に関する経緯を併せ考慮すると,被告らは,平成10年3月期の原告の不良債権の処理に関しては,新基準を厳格に適用した場合には,自己資本比率を8パーセント以上に維持することが困難になり,原告の今後の経営面で深刻な問題が生じ得る可能性があったことは認識していたというべきである。しかし,一方で新基準が平成10年3月期に初めて施行されるものであり,その内容自体旧基準を許容する解釈の余地を残している,あるいは,未だガイドラインであるとの認識もあって,原告の自己査定基準の検討に当たっては,原告にとって厳しい経営環境のもと,銀行の経営者としてのそれぞれの立場で,企業としての原告の維持・存続を図るべく,旧基
準との連続性ないしは継続性を保てるぎりぎりの線を模索していたとみるべきである。そして,前記認定のとおり,新基準がセーフティネットを欠き,その内容自体も一義的に明確といえず,さらに関係者への周知策も十分ではなかったことからすると,企業の経営者として,企業の維持・存続を図るため,新基準について独自の解釈をし(例えば,Dは,資産査定通達には日本リースを納めるボックスがなかったので,経営支援実績先という別のボックスを創出したと供述している。),できるだけ原告にとって有利な資産査定を行いたいと願ったこと自体にはやむを得ない一面があったというべきである。さらに,被告らとしては,そのような検討の過程で,会計士の指摘があればこれを変更することも考慮していたことが明らかであり,本件監査法人側か
らの回答では,許容範囲内とのことであったので,平成10年3月期の原告の不良債権の処理と関連親密先への支援損の計上を実施したものと認められる。 加えて,被告らが策定に関与した原告の自己査定基準(自己査定運用細則及び自己査定運用規則)は,当然,平成10年3月期においては,金融検査の対象となった際には,これを金融証券検査官に開示することを前提としており,被告らの経歴に照らしても,当初から,金融証券検査官に全く認められないような違法なものを策定するとは考えにくいし,自己査定基準自体は,Q会計士やP会計士にも開示され,その了解が得られていたものである。そして,原告の会計監査人が,いったんは原告の平成9年度決算案を新基準のもとでも許容されると判断したことは動かし難い事実である。そうであ
るとすれば,被告らの行った処理が,現時点での評価としては,客観的にみて資産査定通達等の新基準に反するものとみる余地はあるとしても,それ以上に,被告らにおいて意図的に新基準に反した処理をしようとした,あるいは旧基準からみても違法とされる会計処理を実施しようとした(商法違反の行為をする意図があった)と認定することには無理があるというべきである。
なお,原告らは,原告の当時の担当者が会計監査人に対し,関連ノンバンクの実態を説明せず,かえって,その実態を組織的に隠蔽したと主張するが,本件監査法人による原告の平成10年3月期決算の監査の実情は前記認定事実(10)オで認定したとおりであり,十分な時間をかけた監査がなされたことが窺われるところ,原告らが主張するような会計監査人に対する組織的な隠蔽行為がなされたことを認めるに足る証拠はない。
(2) 平成10年3月期における原告の貸出金の償却・引当が旧基準に適合しているといえるか。
ア エヌイーディー
前記認定事実3(9)エ(ア)bによれば,原告は,平成6年3月期以降,エヌイーディーに対し,債権放棄等の支援(5年間で総額1900億円)を実施していたが,大幅な地価下落により不良債権額が増加し,2924億円の不良債権が残存することとなったため,平成10年3月23日開催の常務会において,当初の計画を延長し,5年間(平成10年3月期から平成14年3月期まで)で,総額2951億円の支援を行い,不良債権3010億円を処理する修正計画を立案・了承し,この計画に基づき,国税当局と折衝して新たに無税の承認(法人税基本通達9-4-2)を受けて,エヌイーディーの不良債権を処理し,同社の本業部門(ベンチャーキャピタル業)を不良債権部分から分離して再建する計画を実施する旨決定した。
このようなエヌイーディーの状況をみると,原告による再建支援が継続される状況にあったから,税法基準に照らせば,支援先の関連ノンバンクについては再建を前提としていたものであり,実際に行われた以上に償却・引当を実施する義務があったとは認められない。
イ 青葉エステート他エヌイーディーの受皿会社6社
原告は,エヌイーディーの受皿会社7社について,決済事由10項ただし書に基づき,エヌイーディーと一体であるとして,本体と同様の査定をした。ところで,原告は,これらの受皿会社についても,エヌイーディーと一体として清算処理する予定であり,前記アの支援計画には受皿会社の清算も含まれていたこと,また,原告の受皿会社7社に対する貸出金のうち,エクセレーブファイナンスについては,その貸出金をエヌイーディーに転貸ししており,U検査官もエクセレーブファイナンスについては一括査定を行っていたこと,エヌイーディーが,エクセレーブファイナンスを除く残り受皿会社6社に対する原告の貸出金についても保証予約をしていた以上,受皿会社の査定をエヌイーディー本体と一体としてみることも可能であること,以上
によれば,原告が,これら受皿会社7社について,償却・引当を実施しなかった点は,旧基準に照らす限りは,これを逸脱していたとは認められない。
ウ 第一ファイナンス
前記認定事実3(9)エ(ウ)のとおり,原告は,最終的には第一ファイナンスの清算処理を検討していたが,同社が債権の回収業務を継続し,当面清算する必要がない状況にあったため,損失が確定していないことを理由に,※7なお書に基づき,ロス額が算定されるⅣ分類130億0700万円(同社繰越欠損額)及びⅢ分類の一部の合計額147億円についてのみ引当を実施(有税による債権償却特別勘定への繰入れ)した。
このような取扱いは,法人税基本通達9-6-4の運用に当たって,その要件である事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないと定められていることからすると,旧基準のもとでは許容の範囲内であったというべきである。また,税法基準において,有税引当は例外的であるところ,原告は,原告のみが融資先であり,他行との関係が問題とならないため,会計監査人の意見を受け容れて,有税による引当をあえて実施したものであり,いずれにしても旧基準のもとでの処理として,許容されないもの
であったとはいえない。
エ 日本リース及びその受皿会社
前記認定事実3(9)エ(エ)で認定したとおり,日本リースは,平成10年3月期において,損益についてはおおむね年間の実力基礎収益175億円程度が見込まれ,他方,同社の含み損(清算価値)が7000億円に達しており(甲81添付資料3),原告による支援がされても,不稼働資産の最終的な処理には相当期間が見込まれる状況にあったことは事実である。
ところで,原告は,日本リースを「経営支援実績先」に区分していたが,法人税基本通達9-4-2に係る支援先に対する支援が合理性を有するかどうかの判断として,このような基準を容認し得る余地はあるというべきである。また,日本リースは,いわゆる自転状態にあり,ノンバンクにとって最も重要なのは資金調達能力であるところ,当面原告が資金繰り支援(融資)を実施する限り,他行は原告の信用を根拠に融資を継続したと考えられるから,原告が,継続的な支援・管理を実施している「経営支援実績先」と日本リースを位置づけた以上,税法基準に照らし,一応破綻のおそれがないと考えて,Ⅱ分類とすることも許容されるというべきである。
また,有楽エンタープライズ及びビルプロ3社について,原告は,これを「特定先」として扱い,その債務者区分を「要注意先」として償却・引当を実施したが,同各社が日本リースの関係会社であり,しかも平成8年4月に行われた大蔵省検査において「親密・系列等の関係会社関係」とされていたことにも照らせば,旧基準を前提とする限り,原告が行った資産査定に基づく償却・引当が許容されないものであったとはいえない。
(3) 平成10年3月期当時の原告の体力からすると関連ノンバンクに対する貸出金についての償却・引当を行わなかったのは違法であるとする原告らの主張について
原告らは,関連ノンバンクが,銀行による支援が継続する限り破綻しないという考え方は,いわば銀行が無限に支援する財源を有していること,すなわち無限の支援体力を有することを前提とするものであるところ,平成10年3月期当時,関連ノンバンクの不良資産は優に1兆円を超えており,また,原告の支援体力は枯渇し,さらに,金融債の販売減少に伴い,資金繰り破綻の危険すら生じていたと主張している。この主張は,税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当はしないとする会計慣行のもとでも,平成10年3月期に関連ノンバンクに対する償却・引当を行わなかったことは違法であるとの主張とみる余地があるのでここで検討する。
この点については,前記4(1)ウ(ア)によれば,銀行の関連ノンバンクに対する支援の期間については,おおむね5年程度の期間が想定され,従来の指針において,計画的・段階的処理が要請されていたこと,すなわち,必ずしも,単年度において不良資産を一掃することが求められていたわけではなかったものである。さらに,前記認定事実3(7)オ(ア)によれば,原告の関連ノンバンクの不良資産の含み損等は1兆円に達し,当面,一掃できる体力がなく,抱えて行かざるを得ないものであったことが認められるものの,他方,同(オ)及び証拠(甲109添付資料6,甲122,乙108の39頁)及び弁論の全趣旨によれば,原告においてリスクアセットの圧縮が計画され(長銀再生2カ年計画),そこでは,約5兆円規模のリスクアセットの圧縮によ
り,自己資本比率8パーセントを維持しても,おおむね4000億円程度の自己資本額の減額が可能とされ,同額を不良債権の償却原資とすることが予定されていたこと,スイス銀行との提携により,業務純益をおおむね1300億円程度見込むことが可能とされていたこと,平成11年3月期において前倒適用された税効果会計の導入により,3000億円程度の繰延税金資産の計上が可能であったこと,その結果,数年程度不良資産を抱えたままの状態であっても,他方で相当額の償却財源が見込まれたこと,以上の事実が認められる。そして,当時の原告がおかれていた状況のもとでの経営判断として,そのような計画を建て,あるいはそのような見通しを持つこと自体が不合理であったとはいえないから,これらの事実に照らす限り,原告本体が平成1
0年3月期において破綻する蓋然性が高かったとはいえないというべきである。また,実際にも,前記認定事実3(11)イのとおり,原告の破綻認定と特別公的管理の開始の際に行われた金融監督庁の検査結果では,平成10年3月期においては,追加の償却・引当額2747億円を処理して,かつ,有価証券の含み損1684億円を前提としても,自己資本額は7871億円に達していたというのであるから,この時点では計算上は資産超過の状態にあったといえるものである(もっとも,平成10年9月期には大幅な債務超過に陥り,結局特別公的管理の開始が決定されているが,その間においては,平成10年6月以降の株価の下落,金融債の販売減少に伴う急激な資産内容の劣化,さらには新基準のもとでの清算価値による査定の見直しといったその後の
事情が存することが窺われる。)。そうであるとすれば,平成10年3月期においては,旧基準による資産査定を前提とする限り,原告には関連ノンバンクを支援する体力が残されていたと認定することができるというべきである。結局,この点に関する原告らの主張は採用できない。
(4) 小括
以上のとおりであって,被告らが関与して平成10年3月期に実施した原告の自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当の処理については,実施に至った経緯に照らす限りは,被告らにおいて,意図的に違法な会計処理をしようとしたとは認められないし,その内容を客観的に検討すると新基準の趣旨に反した処理がなされたとみる余地もあるが,償却・引当の処理の実態をみる限り,当時の「公正なる会計慣行」であった旧基準の許容の範囲内のものであったというべきである。そうであるとすれば,原告らが主張するように,新基準を前提として,平成10年3月期における原告の償却・引当の不足額すなわち当期未処理損失額が,原告の平成10年3月期における剰余金額460億1400万円を超えるものであったと認めることはできないこ
とは明らかである。
7 本件中間配当の違法性
前記5において判示したとおり,平成10年3月期においては,原告らが主張する銀行の貸出金に関する償却・引当に関する新基準(資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準)は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するものではなかったことが明らかであり,前記6で認定したとおり,当時の「公正なる会計慣行」である旧基準による限りは,平成10年3月期において,原告には本件決算配当及び本件中間配当を実施するに足る配当利益が存したというべきである。そうであるとすれば,本件中間配当が実施された際に,平成10年3月期において配当可能利益がない状態が生ずるおそれがあったと認める余地はないから,本件中間配当が違法であるとする原告らの主張は,その余の点について判断するまでもなく理由がない
ことが明らかである。
第7 結論(本件全体のまとめ)
1 本件の概要
以上認定説示したところから明らかなように,本件訴訟は,原告の前身である日本長期信用銀行が実施した平成10年3月期の本件決算配当及び平成9年9月期の本件中間配当について,平成10年3月期の貸出金の償却・引当に関する決算処理が,取立回収不能見込額の控除を要求する旧商法285条の4第2項に違反しており,実際には配当可能利益が存しないにもかかわらず行われたとして,これらの配当の実施に賛成した被告らに対し,商法290条1項違反(決算配当),もしくは商法293条の5第3項違反(中間配当)を理由として,商法266条1項1号に基づく損害賠償責任(ただし,被告Fについては,決算配当の承認決議以前に取締役を退任している関係で,決算配当については商法266条1項5号に基づく損害賠償責任)が問
われた事案である。
2 本件の争点と当事者の主張の概要
本件では,日本長期信用銀行が実施した平成10年3月期の貸出金の償却・引当に関する決算処理が,取立不能見込額の控除を要求する旧商法285条の4第2項に違反し,実際には配当可能利益が存しないにもかかわらず行われたか否かが争われ,取立不能見込額の判断の基準は,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌するものと解されるところ,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」がどのようなものであったのか,そして日本長期信用銀行が実施した決算処理が,その「公正なる会計慣行」に反していたといえるかが争点となった。
この点に関しては,原告らは,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」は,資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準(新基準)であり,日本長期信用銀行が実施した決算処理は,この基準に違反しており,当時日本長期信用銀行には配当可能利益が存しなかったと主張した。
これに対し,被告らは,新基準は,ガイドライン的性格を有し,各銀行の策定した自己査定基準とのすりあわせにより客観的な基準として収れんしていくことが予定されていたもので,平成10年3月期はその過渡期であり,それまでの銀行の貸出金の償却・引当の基準であったいわゆる税法基準によって補充された改正前決算経理基準(旧基準)が依然として「公正なる会計慣行」として存続しており,新基準は未だ唯一の「公正なる会計慣行」とはなっていなかったと主張し,一方で,仮に,唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとしても,日本長期信用銀行が実施した決算処理は,その解釈の範囲内であり適正なものであるとも主張した。
3 争点に対する当裁判所の判断の概要
以上のとおり,本件では,資産査定通達等によって補充された改正後の決算経理基準(新基準)が,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」であったか否かが最大の争点となった。すなわち,本件では,法令により取立不能見込額の解釈が定められたものではなく,行政内部での通達や事務連絡等による会計慣行の変更という形で新たな基準が示されている。その結果,その基準による処理が「公正なる会計慣行」と認められ,しかもそれが唯一のものということになると,これに反した会計処理は,商法違反ということにならざるを得ない。これは,実質的にみると法令によらず通達等で法改正が行われたのと同一の結果を招来することになるから,その当否が問題となり,平成10年3月期において
,新基準が唯一の「公正なる会計慣行」といえるかが争われたものである。
当裁判所のこの点に関する判断は,既に詳細に認定説示したところであるが,その概要は以下のとおりである。
まず,「公正なる会計慣行を斟酌すべし」とする商法32条2項の一般的な解釈論を検討し,その結果を踏まえて,本件のように既に通達等により「公正なる会計慣行」としての改正前決算経理基準が存在する場合において,これに代わる新たな会計慣行としての新基準が通達等の改正後ただちに唯一の「公正なる会計慣行」となるための要件について検討した。そして,原告らの主張する新基準が,平成10年3月期において唯一の「公正なる会計慣行」と認められるためには,改正手続が適正であることと,基準の内容が銀行の営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして合理的なものであることに加え,会計慣行の変更に伴って企業会計の継続性の点で支障が生じ,ひいては関係者への不意打ちとなるような場合には,これに
対する必要な手当(セーフティネット)を講じること,基準として一義的に明確なものであること,関係者に対し,これが唯一の基準となることの周知徹底が図られていること,以上の各要件が満たされていることが必要と判断した(前記第6の2,本判決26頁以下参照)。
次に,変更の対象となる旧基準の内容について,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったか否かについて争いがあるため,その点について検討し,いわゆる税法基準によって補充された改正前決算経理基準のもとでの会計慣行(具体的には,①大蔵省検査でⅣ分類と査定された銀行の貸出金については同額の無税による償却・引当義務を負うが,有税による償却・引当は銀行の自主性に委ねられた結果実際にはほとんど行われない。②銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,銀行が関連ノンバンクへの支援を継続する限り償却・引当は不要とする。)は,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは合理性を有するもので,「公正なる会計慣行」に当たると判断した(前記第6の4(1)エ(ウ),本
判決170頁参照)。
そのうえで,新基準が,前記の各要件に照らし,平成10年3月期において,唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるかについて検討した。そして,手続の適正性及び内容の合理性は一応認められるとした。しかし,旧基準から新基準への変更は,特に有税による償却・引当をすべきとする点と関連ノンバンクに対する貸出金についてもできる限り関連ノンバンクの実態に即して償却・引当をすべきとする点で大幅なものであるにもかかわらず,平成10年3月期においては税効果会計の導入がされておらず必要な手当が講じられていないといわざるを得ないし,さらに,新基準の一義的明確性や拘束性についても疑問が残るばかりか,新基準の関係者への周知徹底が図られていたとはいえないから,結局,平成10年3月期に新基準が唯一の「公
正なる会計慣行」となっていたとする原告らの主張は認められないと判断した(前記第6の5(6),本判決208頁参照)。
最後に日本長期信用銀行の平成10年3月期における決算処理における被告らの認識と,当時の「公正なる会計慣行」と認められる旧基準のもとでの決算処理の適正性について検討し,結論として被告らにおいて,商法違反に当たる行為をする意図があったとすることには無理があり(前記第6の6(1)イ,本判決214頁参照,日本長期信用銀行の平成10年3月期における決算処理については,現時点での客観的評価としては新基準に反しているとみる余地はあるが,旧基準を前提とする限りは,これを逸脱した違法なものとは認められないと判断した(前記第6の6(4),本判決223頁参照)。
4 結論
以上によれば,原告及び原告訴訟引受人の被告らに対する請求は,その余の
点について判断するまでもなく理由がないことが明らかである(なお,原告については,本件損害賠償請求権を原告訴訟引受人に譲渡したとして,第2回口頭弁論期日において訴訟脱退の申し出をしたが,被告らが承諾しなかったため,本件の当事者として残ったものであるところ,前記認定のとおり訴訟引受自体は有効と認められるから,その点からも請求の棄却を免れないというべきである。)。よって,原告及び原告訴訟引受人の被告らに対する請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 西 岡 清一郎
裁判官 山 口 和 宏
裁判官名島亨卓は転任のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 西 岡 清一郎
別紙1 原告らの主張
第1 「公正なる会計慣行」(商法32条)の意義・内容
1 資産査定通達等と「公正なる会計慣行」
(1) 「公正なる会計慣行」の規範的意味
ア 平成14年改正前商法(以下「旧商法」という。)285条の4の解釈と「公正なる会計慣行」
株式会社の取締役には,決算期ごとに法令及び定款に従い会社の財産及び損益状況を正しく表示した貸借対照表及び損益計算書を作成する義務が課せられ(商法281条の3第2項3号参照),また,株式会社が有する金銭債権については,債権金額をもって計上すべきもの(旧商法285条,285条の4第1項)とされるが,金銭債権に「取立不能の虞あるときは取立つること能わざる見込額を控除することを要す」(旧商法285条ノ4第2項)と定められているとおり,金銭債権に取立不能のおそれが生じているときはその取立不能見込額を控除しなければならない。
したがって,金銭債権につき取立不能のおそれが生じているときは,事実に反する会計処理は許されず,当該取立不能見込額を償却しなければならないが,仮にこれをしなかった場合,旧商法281条,285条,285条ノ4に反する。これは,売上(売掛金)の架空計上が認められないのと同様である。そして,商法32条2項に「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については公正なる会計慣行を斟酌すべし」と規定されていることから,商業帳簿の作成に関する規定である旧商法285条ノ4第2項の「取立不能見込額」の解釈に当たっても「公正なる会計慣行」に従わなければならない。
イ 「公正なる会計慣行」,「斟酌すべし」の各意義・内容等
この「公正なる」とは,営業上の財産及び損益の状態を明らかにするという目的に照らして「公正」という意味であり,上記目的に照らし,妥当かつ合理的と一般的に認められるものを指すと解される。そして,ここにいう「会計慣行」とは既に行われている事実に限らず,新しい合理的な会計慣行が生まれようとしている場合には,それも含まれる。
また「斟酌すべし」とは,公正な会計慣行がある場合は,それ以上に営業上の財産及び損益の状況を明らかにする会計基準があるなど特段の事情がない限り,それに従わなければならないという意味であって,その意味において,法規範性を有するものである。
ウ 企業会計原則及び同注解
この「公正なる会計慣行」に当たるものとして,一般に企業会計原則・同注解が挙げられ,「企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から,一般に公正妥当と認められたところを要約したものであり,必ずしも法令によって強制されないものでも,すべての企業がその会計を処理するにあたって従わなければならない基準である」とされている。同注解18において「将来の特定の費用及び損失であって,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができる場合には,当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする」とされ,また「発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失
については,引当金を計上することはできない」とされている。
エ 「決算経理基準」
また,当時の大蔵大臣の銀行に対する監督権限に基づき,大蔵省銀行局長は,昭和57年4月1日付け蔵銀第901号通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」(以下「基本事項通達」という。)を発出し,その「経理関係」の中において,銀行の決算の基準となるべき「決算経理基準」が定められ,長期信用銀行についても,この基本事項通達を準用する取扱いであった。そして,①原告を始めとする金融機関は,以後この「決算経理基準」に従い決算処理を行ってきたこと(決算経理基準が改正されるごとに,改正後の決算経理基準に従い決算処理を行ってきたということ),②決算経理基準の前身である銀行業統一経理基準(統一経理基準)について,日本公認会計士協会(会計士協会)の銀行監査特別委員会が昭和51年に公表
した「銀行業務統一経理基準及び財務諸表様式に係る監査上の取扱いについて」において,統一経理基準に基づく会計処理は商法32条2項にいう公正な会計慣行に合致しているものとして取扱うとしていたことに照らせば,金融機関の会計処理について,この「決算経理基準」をもって「公正なる会計慣行」に当たると解するのが相当である。したがって,平成10年3月期においては,平成9年7月31日付け銀行局長の一部改正通達によって改正された後の「決算経理基準」(改正後決算経理基準)が「公正なる会計慣行」となるといえる。
(2) 平成10年3月期における「公正なる会計慣行」の内容
ア 早期是正措置導入の意味
平成10年4月以降,長期信用銀行を含む金融機関の同年3月期決算をも対象として,経営の健全性確保のための金融当局による監督手法として早期是正措置が導入され,金融当局が,金融機関に対し,客観的指標である自己資本比率が8パーセント未満の場合,業務改善計画の提出等の是正措置を発動することができる旨定められた。この早期是正措置を実効あらしめるため,平成10年3月期決算から,金融機関は,自己査定基準を策定し,この基準に基づき,貸出金等の資産を回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従い自己査定し,その結果に基づき貸出金等の適正な償却・引当を行い,資産内容の実態を正確に反映した会計処理をすることが求められ,事後的に会計監査や金融検査において,自己査定基準の適正性・正確性,償却・引
当の適正性等について検査されることとなった。
平成6年12月の東京協和信用組合,安全信用組合の破綻,平成7年8月のコスモ信用組合,株式会社兵庫銀行,木津信用組合の破綻が続発するなか,金融制度調査会が平成7年12月22日に答申した「金融システム安定化のための諸施策」において,「金融機関経営の健全性を確保していくための新しい監督手法として,自己資本比率等の客観的な指標に基づき業務改善命令等の措置を適時に講じていく早期是正措置を導入することが適当であり,所要の手当を行い,必要な周知・準備期間を経た上でできるだけ早期に実施に移す必要があり」,「早期是正措置の導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となる。このため,検査・モニタリング体制の整備・充実が必要であるが,金融機関の自己責任原則の徹底
等の観点からは,資産査定は先ず各金融機関自らが厳正に行うことが必要である」と指摘され,また,平成7年9月には株式会社大和銀行ニューヨーク支店での不正経理が発覚し,大蔵省の金融検査・監督等に関する委員会も,同年12月26日,金融行政を保護的行政から市場におけるチェック機能を一層活用する行政へと転換すること及びその中核的手段として金融機関の経営の健全性を確保するため,客観的なルールに基づき経営の早期是正措置の導入を求め,その制度を適切に機能させるためには,金融機関自らの資産内容の的確な把握,監督当局の検査等が不可欠の前提であることを強調するとともに,「金融機関が,資産内容を自己査定し,外部監査によるチェックを受けた上で,その結果及び自己資本の充実度の状況を報告する。当局において,
これをモニタリングし,自己資本の充実度及び自己査定の正確性に関する評定を行う。なお,当局は,自己査定のための統一的な基準を示す。」ことの提言を行った。これらの提言を受けて,平成8年6月21日に成立した金融3法で早期是正措置制度の導入が決定されたものである。
早期是正措置制度の導入に当たり,同制度の具体的内容の骨格並びに適正な財務諸表の作成に関する考え方及び実務指針等を検討するため,平成8年9月30日に大蔵省銀行局長の私的研究会として「早期是正措置に関する検討会」(早期是正措置検討会)が発足し,大蔵省銀行局や同金融検査部を中心に法律学者や経済学者,会計士協会関係者,日本銀行(以下「日銀」という。)関係者,金融機関代表者等が参加して様々な検討が加えられて,同年12月26日に「中間とりまとめ」が公表されたが,その中で「早期是正措置の導入にあたっては,まず金融機関の自らの責任において企業会計原則等に基づき適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提となる。各金融機関が行
う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として重要な役割を果たすことになる。また,会計監査人においては,財務諸表の適正性についての深度ある監査を行うことが求められる。こうした一連の作業を経て作成された財務諸表が開示されることにより,金融機関経営の透明性の向上に資するとともに,市場規律による経営の自己規正効果が働くことになる。早期是正措置は,上記の市場規律を発揮させていくための補完的役割を果たすものとして位置づけられる」こと,とされており,早期是正措置導入の不可欠の前提として適正な自己査定,償却・引当を各銀行が行うことが予定されていた。
イ 早期是正措置導入を前提とした自己査定基準,償却・引当基準の整備
この「中間とりまとめ」の結果を踏まえて,平成9年3月5日に大蔵省から出されたものが資産査定通達であり,また同年4月15日に会計士協会から出されたものが4号実務指針であり,さらに同月21日に関連ノンバンクに対する貸出金の資産査定に関して資産査定通達の細則として発出されたのが9年事務連絡であり,資産査定通達の内容を全銀協が加盟金融機関用にQアンドA方式で補完したのが全銀協Q&A,9年事務連絡の内容をQアンドA方式で示したのが全銀協追加Q&Aである。また,不良債権償却証明制度は,平成9年7月4日付通達により廃止され,平成9年7月31日付けの銀行法施行規則の一部改正に伴い,改正後決算経理基準が平成10年3月期決算に適用されることとなった。
ウ 改正後決算経理基準の下での資産査定通達等による税法基準の排除
これらの資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡及び全銀協追加Q&A(資産査定通達等)を解釈するに際しては,税法基準をベースとしてはならない。そのことは,以下の①ないし⑦に述べる経緯から明らかである。
① 資産査定通達等の方向性を示した早期是正措置検討会において,償却・引当と資産分類との関係について,「『実質破綻先』については,今の法人税基本通達でいう『債務超過が1年以上に続いてロス額が40パーセントと見込まれる』ケースがこれに含まれると思われる。法人税基本通達によると40パーセントが一応の目処となっているが,35パーセントの場合どうなるか考えると,無税にはならないが35パーセントの場合でも実質破綻ということはあり得る。その場合は,有税になると思うが,現在はこの分類の考え方と税の考え方との関係は,税は横に置いて債権の健全性ということのみから判断していくという仕組みになっている。実際に引当金を積んだときには有税と無税では全然効果が違う,税効果会計はどうなんだという議論は
当然あると思う。ただ,私どもが今申し上げているのは,今の分類の考え方というのは,有税であるか無税であるかということは基本的に外に置いて,それに左右されないで判定をしてみるということである」と説明されている。
② 上記検討会の「中間とりまとめ」においても,「各金融機関が適正な償却・引当の実施を行っていくためには,有税による償却・引当を円滑に進めていく環境整備も必要である」とされ,資産査定通達等に基づく償却・引当には有税の償却・引当も含まれるとしている。
③ 全銀協追加Q&Aにおいては,体力がないノンバンクに対する貸出金の査定は,母体行責任を負う意思がある場合であっても,作成されている再建計画に合理性がない場合には原則として営業貸付金等の査定結果のⅣ分類額を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残額をⅡ分類とすべきとし,再建計画が作成されていないか又は作成中の場合には親金融機関等の収益力等から関連ノンバンクの再建可能性が認められる場合以外の場合は営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすべきとしているところ,この場合のⅣ分類は親銀行による支援を前提とする先に対するⅣ分類であり,仮に税法基準によるとすると無税償却の対象とならないと考えられるのであるが,これが資産査定通達等において全額償却・引
当すべきとされるⅣ分類とされていることから,資産査定通達等においては有税による償却・引当を前提としていると考えられる。
④ 資産査定通達等による自己査定,償却・引当を行うべく「決算経理基準」が改正されたが,貸出金の償却・引当について,上記改正前の「決算経理基準」(改正前決算経理基準)にあった「税法基準」の表現が削除され,改正後決算経理基準は自己査定基準,償却・引当基準により回収不能と判定される額を償却・引当すべきとされた。
⑤ 改正後決算経理基準の導入は,自己査定結果を償却・引当に正しく反映するようになされたものであるが,このことから,税法基準にとらわれていては,商法・企業会計原則に則った処理がなされないとして不良債権償却証明制度が廃止されたように,税法基準にとらわれた処理は商法・企業会計原則に則っているとはいえず,資産査定通達等の趣旨も満たさないものとして排斥されたことが窺われる。
⑥ 平成10年3月期末が目前に迫った平成10年3月20日の時点においても,全銀協が当局と協議のうえ作成した「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」において,改正後決算経理基準における償却・引当と税法上の償却・引当は基本的には無関係である旨明言された。
⑦ 上記⑥の「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」には「破綻懸念先債権に限らず,損失の発生が見込まれる債権については,必要額を引き当てることになる。このような取引先に対し,追加融資を行うか否かは,各行の経営判断であり,経理とは無関係である」とされており,仮に追加融資を行う先であるとしても損失の発生が見込まれる債権については必要額を引き当てなければならないとされている。
要するに,無税償却できない債権についても,改正後決算経理基準に従えば償却・引当をしなければならない場合があるとされていたことは疑問を容れる余地はない。
(3) 決算経理基準を補完する資産査定通達等の周知性,合理性
ところで,基本事項通達により,銀行決算の基準として「決算経理基準」が定められ,その中に貸出金の償却・引当の基準が示され,原告らを始めとする金融機関は,この「決算経理基準」に従って決算処理を行っていた。言い換えれば,「決算経理基準」が廃止されるまで,平成10年3月期決算を含む銀行の決算処理の際の拠るべき根拠規範は,この「決算経理基準」であり,原告も同様であった。
この「決算経理基準」は,平成9年7月31日付けの銀行法施行規則の一部改正に伴い,内容が一部改正されて平成10年3月期決算に適用される旨が大蔵省銀行局長から原告を始めとする金融機関の頭取宛てに通知されている。その主な改正内容は,平成10年3月期決算から自己査定制度が適用されることから,銀行が自己査定基準を作成し,その自己査定結果に基づいて適正な償却・引当をなすべきことや償却・引当のルールについての基本的考え方が示されたこと及び貸出金の評価の欄において,従来,税法に基づき有税・無税によって処理が分かれることが規定されていた部分を丸ごと削除し,これに代わって個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれるかどうかを判
断した上で,その必要額を償却・引当すべき旨の規定を置いたことである。
また,この新しい自己査定制度の開始に伴い,従来「税法基準」による償却・引当を実質的に支えていた不良債権償却証明制度は,平成9年7月4日付け通達により廃止された。それまで,多くの金融機関では,この不良債権償却証明制度において無税償却が認められた限度において,貸出金の償却・引当を行う傾向があったことは事実である(なお,そのような傾向や実務状況が即「公正なる会計慣行」という規範的意味を持ち得るものでないことは後記参照)。しかし,かかる制度が廃止され,それを前提に改正後決算経理基準における償却・引当基準も変更された以上,税法基準と自己の経営体力を適正かつ客観的に図るための会計処理に関連する償却・引当基準とは無関係となったことが明らかである。
以上のとおり,平成10年4月1日からの早期是正措置導入を前提としての各制度の創設,改廃状況を客観的に検討するならば,資産査定通達等は,金融機関の健全性を確保する目的で平成10年4月1日から導入された早期是正措置を有効に機能させるために必要な金融機関の資産内容の査定方法や適正な償却・引当の方法を明らかにしたものであり,それにより資産内容の実態を正確かつ客観的に反映した財務諸表を作成することを目指して策定されたものである。また,それらの内容は,「中間とりまとめ」の考え方を基礎として明確化され,しかも全銀協(全銀協Q&A,全銀協追加Q&A)や会計士協会(4号実務指針)を通して周知徹底が図られている。さらに,改正後決算経理基準は,資産査定通達等の公表を前提に改正され,その内容
は大蔵省から直接原告を含む金融機関に対して公表・送付され,適正な自己査定基準の策定が要請されている。
そして,各金融機関は,平成10年3月期決算における貸出金の償却・引当については,改正後決算経理基準に基づき,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定されなければならないとされた各行の自己査定基準,償却・引当基準に基づき貸倒引当金を計上するという会計基準を採用した。各金融機関の有価証券報告書に記載された平成10年3月期決算における貸倒引当金の計上基準についての表現は,各行によって若干の相違はあるが,内容及び用語の使い方からすれば,いずれも債権について自己査定を行い実務指針に従って貸倒引当金を計上している旨を明記している。
また,金融監督庁は,日銀と連携しながら,平成10年7月7日からいわゆる主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3項及び信託銀行7行)に対して,また,同月30日から地方銀行に対して,同年10月5日から第二地方銀行に対して,それぞれ一斉集中検査・考査を行ったが,それらの検査・考査においては,金融機関等の自己査定と公認会計士等による外部監査を前提に自己査定の正確性,償却・引当の適切性について,また,金融機関等の自己責任原則を前提にしたルール遵守体制,リスク管理体制の整備状況及びその機能発揮状況等について,その実態を把握することなどに重点が置かれていたところ,主要19行から原告及び株式会社日本債券信用銀行を除く主要17行に対する検査・考査結果の概要としては,自己査定基準及び償却
・引当基準とも,その内容の一部に問題があったため大半の銀行に改善を求めたとあるものの,総体としてはそれぞれ資産査定通達及び4号実務指針に対応しており,おおむね妥当であったとされている。
このように,①平成8年6月に金融3法が成立して以降,大蔵省銀行局や金融検査部を中心に法律学者や経済学者,会計士協会関係者,日銀関係者,金融機関代表者等が参加した「早期是正措置検討会」において様々な検討が加えられたうえで,同年12月に「中間とりまとめ」が公表され,これに基づいて平成9年3月5日に資産査定通達が,同年4月15日に4号実務指針がそれぞれ公表されるなど,平成10年3月期決算に向けた準備が進められ,同年4月1日から早期是正措置制度が実施されるまでの間に相応の準備期間が置かれていること,②各金融機関においても,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定すべきとされた自己査定基準,償却・引当基準を策定し,平成10年3月期決算においてこれら基準に基づいて自己査定,償却・引当の作
業を行ったこと,③主要17行に対する検査・考査結果,同期決算に用いられた自己査定基準,償却・引当基準が資産査定通達及び4号実務指針に対応しており概ね妥当であったとされていることにかんがみれば,平成10年3月期決算はあくまでも試行錯誤的なものにすぎなかったとか,貸出金等の償却・引当に関する基準は変更されていなかったとすることは,明らかに不当である。
そして,以上のような資産査定通達等の策定の経緯及び内容に照らせば,資産査定通達等における資産査定の方法,償却・引当方法等は,金融機関の貸出金等の償却・引当に関する合理的な基準であると認めることができるだけでなく,改正後決算経理基準の内容を補充するものとして,商法32条2項にいう「公正なる会計慣行」に当たると解することが相当である。そのうえ,早期是正措置制度は,金融機関が抱えている不良債権を早期に処理し,バブル経済の崩壊で低下したわが国の金融システムの機能回復を図るとともに,市場規律に立脚した透明性の高い金融システムを構築することにより,その安定化,健全化を成し遂げる目的で導入されるシステムであることを考えれば,この早期是正措置制度を有効に機能させるために策定された資産
査定通達等の趣旨に反する会計処理は許されないと解すべきであって,金融機関の貸出金等の償却・引当に関しては,資産査定通達等が唯一の合理的な基準であったと認められる。
(4) 資産査定通達等の規範性
原告らは,各行が自己査定基準,償却・引当基準を作成する際に,当然ながら資産査定通達等に一字一句合わせなければならないとか,これらに記載のない事項を基準化することは一切許されないなどと主張するものではない。問題は,どの程度の幅を超えた場合に,当該自己査定基準,償却・引当基準及びその適用が「公正なる会計慣行」の範囲を逸脱したと評価されるべきであるかということであり,原告らは,被告らが,貸出金の評価について,個々の債務者ごとに,適正な債務者区分・資産分類を行い,それを前提として各分類資産ごとに償却・引当を行うという資産査定通達等の定める基本的枠組みを逸脱するような理屈を作出して,資産査定通達等が許容しないような基準(「特定先基準」等)や償却・引当基準(関連先のⅢ分
類には償却・引当は行わない等)を策定したり,自己査定基準を正しく適用しないような処理(体力の存否,再建計画の合理性の有無等)をしたりしたことは,資産査定通達等で周知,徹底された当時の「公正なる会計慣行」に著しく反するものとして許されないと主張しているのである。
2 税法基準は平成10年3月期における「公正なる会計慣行」であったか
(1) 貸倒償却・引当に関する税法基準なるものについて
貸倒償却・引当に関する税法基準なるものについては,次の①ないし③のとおり整理できる。
① 法人税法33条2項が金銭債権につき評価損の計上を禁止していることから,法人がその有する金銭債権について回収不能を理由に貸倒償却できるのは金銭債権の全額が回収不能である場合に限られ,この場合担保物があるときはその担保物の処分後であること(法人税基本通達9-6-2)
② 一般の貸倒引当金(債権償却特別勘定等を除く)は税法で容認される限度額を必ず繰り入れることとし,その引当率は税法が定める法定繰入率である1000分の3であったこと(法人税法52条)
③ 債権償却特別勘定への繰入れは旧法人税基本通達9-6-4以下で認められる場合には全額繰り入れるものの,有税の場合も繰入れることができるとされていたこと
しかしながら,税法基準は,以下に述べる理由により,平成10年3月期において「公正なる会計慣行」であり得ないものであった。
(2) 税法基準が「公正なる会計慣行」であり得ない理由について
ア 税法基準の目的
そもそも税法基準は,租税収入の確保という政策的観点に立って,税額を計算し,課税の公平を図ろうとする目的で策定されている。すなわち,税法基準においては,税法の目的である租税収入の確保,課税の公平の観点から,損失の計上時期について明確性,統一性が要請されるため,当該事業年度に損失が生じたことが確実と認められるもの(債務の確定になじむ損失又は債権の消滅により生じる損失については,それらが確定したとき)に限定して損失計上が行われるべきものと解されている。
法人税基本通達9-6-2は,貸倒償却できる場合を金銭債権の全額が回収不能である場合に限定し,また旧法人税基本通達9-6-4は債権償却特別勘定の繰入れに関して「債務者に対して追加的支援を予定している場合」には「『事業好転の見通しがない』と判断することは原則として適当ではない」としているが,税法が無税で貸倒償却・引当できる場合をこのように限定しているのは,いずれも損失の計上について確定的なものを求める税法固有の目的に由来するものにすぎない(なお,追加的支援が全く予定されていない場合又は追加的支援が予定されていてもその支援の実効性が認められない場合には事業好転の見通しがないというべきであって,特定先基準とされた債務者はまさにそのような状況であった。)。
しかしながら,本件訴訟は,商法290条に定める配当可能限度額の有無に関する事件であり,商法の計算規定の適用が問題となる事案である。
商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営成績を正しく表示し,もって株主及び会社債権者の利益の保護を図ろうとする目的で策定されているものであるから,税法基準の目的とは明らかに異なる目的で策定されているのであり,税法基準で認められた会計処理方法が商法上当然に適法であるということにはならない。
したがって,税法基準が商法の計算規定上直ちに「公正なる会計慣行」になり得るものではなく,税法基準に基づく会計処理方法が企業の財政状態及び経営成績を正しく表示するという観点から見て,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するかどうかを検討することが必要不可欠である。
イ 委員会報告第5号
被告らは,会計士協会が昭和40年4月6日付けで,監査委員会報告第5号として公表した「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(委員会報告第5号)において,貸倒引当金の計上に関し,「算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合を除いて,除外事項(不適正意見)としないことができるとしている」ことをもって,税法基準が「公正なる会計慣行」であったと主張している。
しかし同報告は,それが公表された当時各企業の有する不良債権額は些少で「一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向にある」ことをあくまでも前提として,保守主義の観点からこれを容認したにすぎず,税法基準そのものを「公正なる会計慣行」と位置付けたものではない。かえって,委員会報告第5号によれば,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)とすることもなるから,これは,税法基準による引当が必ずしも企業の資産状態を正しく反映するものではないことを前提にしている。したがって,同委員会報告を税法基準
が「公正なる会計慣行」であることの根拠とする被告らの主張は失当である。
ウ 改正後決算経理基準
そもそも税法基準が「公正な会計慣行」になり得ないところ,改正後決算経理基準によって,平成10年3月期において税法基準が明らかに否定され,税法基準に基づく会計処理が許されなくなった。
すなわち,改正後決算経理基準は,前記(1)①(貸倒償却できるのは金銭債権の全額が回収不能の場合に限られていたこと)について,担保物の処分後でなくとも「担保の処分可能見込額」を減算した残額を償却する,前記(1)②(一般の貸倒引当金の引当率が税法の法定繰入率である1000分の3であったこと)について,「税法で容認される限度額」ではなく「合理的な方法により算出された貸倒実績率に基づき算定した貸倒見込額」を繰り入れる,前記(1)③(債権償却特別勘定の繰入れに関し,有税の場合も繰入れることができるとされていた)については,回収不能と判定される貸出金等については償却する以外のものについては回収不能額を,最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については債権額から担保の処分可能
額等を減算した額のうち必要額を,それぞれ繰り入れる,という内容に改正され,税法基準は,平成10年3月期決算においては否定され,もはや資産査定通達等との選択適用が認められる会計処理の原則でなくなったというべきである。実際,原告は,平成10年3月期決算の貸倒引当金に関し,決算経理基準の改正に伴い,同期決算から,他の金融機関と同様に,改正後決算経理基準に従い計上している旨を記載し,同期決算における金銭債権の償却・引当に関し,税法基準ではない会計基準によって計上する旨を表明しているのである。
エ 改正後決算経理基準の目的
改正後決算経理基準が,経理基準として税法基準を否定し,個別貸出金の回収可能性の程度・存否で判断する方法に明示的に切り替えた理由は,いわゆる税法基準による会計基準は,早期是正措置を導入した根本理由・目的と矛盾ないし反するものであったからである。
すなわち,平成10年4月から早期是正措置を導入する基礎となった平成7年12月22日付け金融制度調査会答申が「不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできるかぎり早期にその処理に目途をつける必要がある」とし,そのための方策として「ディスクロージャーの推進」,「早期是正措置の導入」を挙げ,かつ,「早期是正措置導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となる」と謳っていることから,早期是正措置導入の根本的目的は,不良債権の早期処理の実現及びそのためにそれまでの裁量的行政から透明性のある事後チェック方式へ転換することにあった。
これに対し,税法基準に基づく会計処理こそ不良債権処理を遅延させていた元凶であった。これは,金融機関自らが回収不能と判断したものはたとえ有税でも償却すべきにもかかわらず,税務に重点をおいた償却が結果的に不良債権処理を遅らせたことが指摘(早期是正措置検討会メンバー)されていたこと,そこで税法基準にはとらわれずに,健全性の観点から企業会計原則にのっとった償却を促すことを目的とした早期是正措置の導入を機に,不良債権償却証明制度が廃止されることになったとの指摘がされていたことから明らかである。そこで,不良債権償却証明制度の廃止を前提に,税法基準すなわち大蔵省との折衝による無税認定取得という行政裁量性の強い償却・引当システムという方法を改め,無税・有税にかかわらず,貸出金の回収可
能性の程度・存否の客観的判断による償却・引当システムが採用されることになったのである。
オ 改正後決算経理基準に係る質疑応答
改正後決算経理基準を受け,この改正内容が平成10年3月期から適用されることを前提に,全銀協は,大蔵省と協議の上「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」と題する解説(平成10年3月20日付)を各銀行経理担当部長に配布し,その中で,次のような質疑回答案を示している。
①[質疑事項3.]
決算経理基準「(3)資産の評価及び償却イ.貸出金及び貸出金に準ずるその他の債権の評価(イ)貸出金等の償却」の本文を直接償却の規定と考えると,法人税基本通達9-6-2の規定の趣旨と異なると考えられる。
すなわち,当該規定の「債権額から回収が可能と認められる額を減算した残高を直接償却する」という考え方は,従来からの会計慣行である法人税基本通達9-6-2の規定の「全額」及び「担保処分後」損金経理することができるとの文言に反することになると考えられるが,見解をご教示いただきたい。
[回答案]
決算経理基準における直接償却と税法上の直接償却は基本的に無関係である(ただし,実務的には,当該決算経理基準の但書により,担保処分後に直接償却することができる。)。
②[質疑事項7.]
平成9年3月5日付,大蔵省「資産査定について」中で,「消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,~破綻懸念先とする」とあるが,そのような破綻懸念先に対しても,今後,追加融資等の可能性がある場合においても,債権償却特別勘定を引当ててもよいのか。
[回答案]
破綻懸念先債権に限らず,損失の発生が見込まれる債権については,必要額を引き当てることになる。このような取引先に対し,追加融資を行うか否かは各行の経営判断であり,経理とは無関係である。
③[質疑事項16.]
各行が合理的に算定した貸倒実績率を使用して算定したいわゆる一般貸倒引当金については,税務上も無税として取り扱われるか。
[回答案]
改正後決算経理基準における貸倒引当率と税法上の貸倒引当率は基本的に無関係である。税法基準の限度内であれば,無税扱いされることは従来と同様である。
以上の内容をみれば,当時,全銀協が,決算経理基準と税法基準とは無関係であると認識していたことは明らかであり,平成10年3月期において償却・引当を行った支援先に追加融資を行うことは論理矛盾であるとか,決算経理基準の改正後も税法基準は生きており,これに従った償却・引当も許されていたというような被告らの主張は,失当である。
カ 改正後決算経理基準の導入以前における有税による償却・引当の要請
改正前決算経理基準は,一般の貸倒引当金の引当率に関しては税法が定める法定繰入率である1000分の3とし,債権償却特別勘定の繰入れに関しては「税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする」としていたが,そのような会計処理方法では不良債権問題が遅々として解決されないことから,行政当局等は指針等を示すことにより,各金融機関に対し,その改正前において,有税による償却をすることを求めていた。すなわち,大蔵省銀行局は,平成6年2月8日付けで「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」を公表し,「金融機関が不良債権の実態に即した必要な償却を行うとの趣旨を徹底し,償却の一層の促進を図るとともに,そのための当局の体制についても引き続き充実強化に努める。また,従来,金融機関は,
貸倒れ又はこれに準じる状況にある債権について償却・引当を行ってきたが,最近における不良債権の実態に鑑み,引当制度の運用を改善し,貸倒れには至っていないものの回収に危険のある債権についても,金融機関自らの判断によりリスクに応じた必要な引当が行われるようにする」ことを提言し,有税引当の概念が示され,これを受けて同日付けで「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,有税引当及び有税直接償却を行うときの取扱いが明らかにされたのである。
このように,平成6年2月時点で金融機関の貸金について,まず商法の計算規定や企業会計原則の観点から償却・引当が必要かどうかを判断し,その次に無税になるか有税になるかを判断するといういわば税法基準という呪縛からの解放が明確にされていた。
その後も,大蔵省は,平成7年6月8日付けで「金融システムの機能回復について」を公表し,「金融機関が,実態に即した決算対応を行い,自己資本の維持・充実等に配意しつつ不良債権について可能な限り前倒処理することを推進することにより,その資産内容を早期に改善し,内外の信頼確保に努めることを促す。また配当についても,横並びや経緯にとらわれることなく,経営実態に即した決定を促す」旨言明し,次いで,金融制度調査会は,平成7年12月22日付けで「金融システム安定化のための諸施策―市場規律に基づく新しい金融システムの構築―」を公表し,「不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできる限り早期にその処理に目処をつける必要がある。上記の不良債権額等の規模は,金融システム
全体としてみれば十分に克服しうるものであり,各金融機関は先ず自助による最大限の合理化努力や早期の引当,償却等の実施により,迅速にその処理を行っていく必要がある」旨を提言している。
このように,平成9年3月期以前においても,有税による償却・引当が求められていたのであり,無税適状にある債権額のみを償却・引当すれば足りるとする会計処理方法が「公正なる会計慣行」であったとまではいえないのである。このことは,以下の関係諸規定からも明らかである。
すなわち,改正前決算経理基準は,金融機関による「貸出金の償却」について「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額を償却するものとする。なお,有税償却する貸出金については,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と規定されているところ,この規定は,取立不能見込額には有税でも償却しなければならないものがあることを前提としている。また,改正前決算経理基準が,「貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定(租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。)を除く。)は,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとし,また,租税特別措置法55条の2第7項の規定に係る貸倒引当金相当額を
有税により繰り入れるものとする」とし,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする。なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と定めていたが,これは,回収不能のおそれがある貸出金等について有税であっても引当しなければならないとしていたことを示している。また,平成6年2月8日の不良債権償却証明制度実施要領通達の一部改正によれば,有税による償却・引当としては,有税直接償却と有税引当があるが,その対象とされる金額は,それぞれ「回収不能と認められる債権について,損失相当額」,「回収不能と認められる債権,最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる債権及び回収に危険のあると認められる債権にかかる損失見込
額」と定義されているところ,これらは平成14年改正前商法285条の4第2項にいう取立不能見込額と同義であるから,決算経理基準は取立不能見込額があれば有税でも償却・引当しなければならないことを規定していることになる。したがって,無税償却・引当のみをすれば足りるという会計処理が,決算経理基準に合致する公正なる会計慣行であったとはいえないのである。
また,不良債権償却証明制度実施要領通達は,平成9年7月4日付け金融検査部長通達蔵検第296号により,「金融機関等をめぐる環境変化等を踏まえ,今後は,金融機関が法人税基本通達等に基づき自ら行うことが適当と考えられる」との理由で廃止されたため,平成10年3月期決算においては,金融機関が自らの責任において,回収不能と認められる債権等について償却・引当を行うことが求められるに至った。
そして,改正後決算経理基準においては,それまでの「税法基準」に基づく償却・引当に関する会計処理の方法を削除し,個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれるかどうかを判断したうえで,その必要額を償却・引当すべきものとし,また,このように税法基準との関係に言及しなくなった改正後決算経理基準における「貸出金の償却」の定義も,有税償却に言及している改正前決算経理基準における「貸出金の償却」の定義も,「基本的には,商法,企業会計原則等に基づき貸出金の償却を行ってきており,定義が変わったわけではない」と解されていたことからすれば,改正前決算経理基準においても税法基準による無税償却相当の債権のみが回収不能と判定されていた
わけではない。したがって,平成9年3月期以前において,税法基準に従い無税適状にある債権のみ償却・引当をすれば足りるとする取扱いが貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」であったことはないというべきである。
キ まとめ
以上のとおり,平成9年3月期以前においても,税法基準は金融機関における貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」ではなかった。
仮に,税法基準が平成9年3月期まで貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」であったとしても,平成9年7月になされた不良債権償却証明制度の廃止及び改正後決算経理基準の導入は,平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度を有効に機能させるための手続整備の一環として行われたことが明らかであるから,平成10年3月期決算においては,早期是正措置制度を有効に機能させるために策定された資産査定や償却・引当のあり方等に関する資産査定通達等の趣旨に沿った会計処理を行うべきであった。また,資産査定通達等が回収不能見込みの債権にも無税償却できないものがあることを前提としていたこと,資産査定通達等が合理的な内容のものであること,そして,各金融機関が平成10年3月期決算において資産査
定通達等の趣旨に沿って策定された自己査定基準,償却・引当基準により決算を行ったことを総合的に考慮すれば,仮に,従来,税法基準が償却・引当の方法として許容されていたとしても,もはや平成10年3月期決算においては税法基準は「公正なる会計慣行」ではなくなったと評価すべきである。
(3) 法人税基本通達9-4-2について
ア 被告らの主張について
被告らは,関連ノンバンクは一般貸出先と異なり,原告らが支援する先であるため破綻がないから関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当の概念はなく,当該貸出金についての損失は法人税基本通達9-4-2による合理的な再建計画に基づき当期の支援手段として行われる債権放棄のみであるとし,債権放棄による損失は償却ではなく支援損であると主張している。
イ 債権放棄についての税務処理について
債権放棄は債権者の債務者に対する一方的意思表示により債権が法的に消滅することから,法人がこれを貸倒れとして損金経理していると否とにかかわらず,税務上もその消滅した時点において損金の額に算入するとしているものである(法人税基本通達9-6-1(4))。
ただし,その債権が「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」でなければその債権が実質的に無価値とはいえないことから,そのような債権の放棄は,法人税法37条6項にいう債務者に対する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」(法人税法37条6項)となって,会計上は全額損失等となる性質のものでありながら,税務上は,損金算入が制限されることになる(法人税法37条)。
他方,法人税基本通達9-4-2は,「例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等」「相当な理由があると認められるときは」,債権放棄により供与する経済的利益の額は寄付金の額には該当しないものとして損金算入を認めるものであるが(再建支援の手段としての債権放棄等が含まれることが明確化されたのは平成10年6月1日の基本通達の一部改正による),これは,相手先が「金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」ではないことから,当該債権放棄が相手先に「経済的な利益の贈与又は無償の供与」を行うことになるものの,その債権放棄が「合理的な再建計画に基づくものである等相当な理由があると認められるときは」,債権放棄すること
にそれなりの経済的合理性を有することから,税務上直ちに寄付金として取り扱うことは相当ではないとの趣旨によるものである。すなわち,法人税基本通達9-4-2は,合理的な再建計画に基づき事業が継続し事業継続による収益弁済により回収が見込まれる場合,すなわち,金銭債権が取立不能の状況にはない場合,あるいは仮に一部取立不能だとしてもその回収不能見込額が不明の場合を前提にしているものである。
ウ 金銭債権に関する償却・引当との関係について
被告らは,関連ノンバンク向け貸出金については,償却という概念は存在せず,債権放棄による支援損という概念で考えるべきであると主張するが,支援損という概念は,合理的な再建計画に基づき貸出先の事業が継続され,その結果収益弁済が可能になる場合を想定しているのであるから,当該貸出金につき取立不能ではない状況あるいは取立不能のおそれのない状況を前提とした概念ということになる。
したがって,この前提が成立しない場合,例えば,貸出先の収益弁済が可能となるような合理的な再建計画がない場合には,当該貸出金については取立不能のおそれがあるから,債権放棄による支援損ではなく,償却・引当が必要となる。
そして,金融機関自身の破綻が相次いだこと,平成9年4月に日債銀が関連ノンバンクを支援しきれずに破産せざるを得なくなったこと,同年11月には株式会社北海道拓殖銀行が破綻したこと等を考えれば,貸出先が関連ノンバンクであることの一事をもってその再建計画は合理的である,あるいはその再建が可能であると判断することは許されない。このことは,全銀協追加Q&Aにおいて,関連ノンバンクへの貸出金の資産分類について,親銀行が母体行責任を負う意思がある場合であっても,合理的な再建計画がない場合や,親銀行等の収益力から再建可能性が認められる場合以外には支援損以外のⅣ分類(当該関連ノンバンクの営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金のシェアにより親銀行に割り当てるⅣ分類)が生じるとしていたことか
らも明らかである。
平成10年3月期は,上記の状況であり,原告の関連ノンバンク向け貸出金について,合理的再建計画の有無や原告の収益力から再建可能性が認められるか否かにつき具体的な検討を行うことなく,原告の関連ノンバンクは,原告が支援するから破綻することはあり得ず,支援損の計上しかあり得ない,よって関連ノンバンクについては支援損のみ計上すれば足り,償却・引当をする必要はないとする処理が,「公正なる会計慣行」に基づく会計処理であったとは到底認められないものである。
3 「公正なる会計慣行」(規範)と単なる実務状況との質的相違
(1) 規範的評価と実務状況の乖離
ところで,本件訴訟では,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」(商法32条2項)を構成していたかが争点となるため,ともすれば,①資産査定通達等は「公正なる会計慣行」を構成するか,②平成10年3月期当時「公正なる会計慣行」は複数存在していたのかという規範的評価(法的判断)を飛び越えて,単に当時の各金融機関の決算処理の状況等を検討することによって「公正なる会計慣行」の内容を確定し,これと対比することにより原告の平成10年3月期決算処理の違法性の有無を判断することができるというような誤った考え方に陥りやすい。しかしながら,商法32条2項にいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」とは,ある業界において現に行われている単なる「会計慣行」を参考にせよという意味でない。同条項はあくまで規
範としての「公正なる」会計慣行に従うべきことを要求しているのであるから,単に当時の実務状況や金融機関の決算動向といった生の事実を認定してみても,それだけでは何の意味もない。
本件のような分野における規範と慣行との関係については,目新しい問題のようにみえるが,他の分野の訴訟においては,この問題が激しく議論されてきたばかりか,そのような議論を受けて,既に最高裁判所(以下「最高裁」という。)の立場も明確になっている。そこで,念のため,下記(2)において,規範と慣行を峻別する最高裁の考え方を整理する。
(2) 医療水準論(規範的評価)と医療慣行
規範的評価と実務慣行との本質的相違については,これが裁判上激しく争われ議論されてきた医療過誤訴訟におけるいわゆる医療水準(規範的評価)と医療慣行の関係を検討すれば容易に理解し得るものである。
最判昭和36年2月16日民集15巻2号244頁(東大輸血梅毒事件)は,既にいわゆる東大輸血梅毒事件において,「注意義務の存否は,もともと法的判断によって決定されるべき事項であって,仮に所論のような慣行が行われていたとしても,それは唯だ過失の軽重及びその度合いを判定するについて参酌さるべき事項であるにとどまり,そのことの故に直ちに注意義務が否定さるべきいわれはない」と判示していた。その後,未熟児網膜症に関する医療過誤訴訟が契機となって,注意義務の基準に関して様々な議論が学説上展開されたが,最高裁は,診療契約の「注意義務の基準となるべきものは,診察当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」と再三判示し(最判平成7年6月9日民集49巻6号1499頁,同様の判示とし
て最判昭和57年3月30日裁判集民事135号563頁,最判昭和63年1月19日裁判集民事153号17頁),診療当時の現に行われていた医療慣行とは区別された「臨床医学の実践における医療水準」という考え方を採用していた。そして,最判平成8年1月23日民集50巻1号1頁(医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項と医師の注意義務が争われた事件)は,医療水準(規範)と医療慣行との関係について,「医療水準は,医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから,平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく,医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって,医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない」と判示して医師の過失を否定し原判決を破棄して原審
に差し戻した。
以上から明らかなように,判例法上医師の注意義務の前提となる医療水準は,平均的医師が現に行っている医療慣行と必ずしも一致するものではなく,規範的判断として要求すべき水準として捉えられており,これと具体的医療行為との乖離の程度を検討して注意義務の有無は決せられるとする考え方が判例法上確定している。(最高裁判所判例解説民事編平成7年度〔下〕569頁参照〔上記最判平成7・6・9解説部分〕)。
(3) 盗難通帳による預金の過誤払い事件に対する近時の判例の判断枠組み
また,預金通帳等が盗難され偽造された印鑑等を使って金融機関において預金が過誤払いされている事件が多発し,現在集団訴訟が各地で起こされている。これらの訴訟においても,銀行側の拠るべき規範と銀行実務との乖離が焦点になっている。
判例(最判昭和46年6月10日民集25巻4号492頁)は,当座勘定取引契約による委託に基づく手形金の支払をする場合において銀行に要求される注意義務の水準と現に行われている銀行実務との関係について,「免責約款は,印影の照合にあたり必要な注意義務が尽くされるべきことを前提としているもので,右の義務を軽減緩和する趣旨と解すべきでないことは前叙のとおりであり,そして,ここにいわゆる必要な注意義務は,自己の財産の管理を銀行に委ねている取引先の信頼に沿うものとして,前示のごとく,銀行に対し社会通念上一般に期待されるところに相応するものでなければならない。したがって,現に行われている銀行業務の実情が必ずしもそのまま是認されるものでない」と判示している。
以上のとおり,実務の慣行(状況)は,あるべき規範そのものではなく,定立された規範と現に行われた行為と間の乖離があるかどうかが問われなければならない。上記の各分野における最高裁判決を前提に本件を捉えるならば,平成10年3月期に要求される「公正なる会計慣行」とは何か,資産査定通達等がその内容を構成していたかどうか検討したうえで,平成10年3月期に他行の会計処理がどうであったか(実務慣行)は,原告の会計処理の違法性の有無を決定するものではない。
(4) 被告らの主張に対する反論
被告らは,資産査定通達等は,内容が不明確である,特に,本件で問題となっている支援先に対する償却・引当をいかにすべきかについては,会計基準として実務に耐え得る指針は何ら示されていなかったと主張し,それを理由に資産査定通達等は「公正なる会計慣行」と認められないと主張する。しかし,資産査定通達は,支援先につき「自行として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の状況等について,客観的に判断し,今後破綻に至る可能性が大きいと認められる場合は破綻懸念先とする」と規定し,支援先であっても「今後破綻に至る可能性が大きいと認められる場合には破綻懸念先」として原則Ⅲ分類として必要額を償却・引当すべきであること,「実質破綻先」に該当する状況にある場合には原則Ⅳ分類
として全額を償却・引当すべきことを規定している。また,全銀協追加Q&Aにおいても,体力がない(償却前利益によりおおむね2,3年で実質債務超過の解消が不可能な)関連ノンバンクで,母体行責任を負う意思がある場合で,再建計画がある場合(さらには再建計画に合理性がない場合とその他の場合に分けられる。),再建計画が作成されていないか又は検討中の場合のそれぞれについて,資産分類の仕方を明記しており,少なくとも,Ⅳ分類となる資産について「回収不可能又は無価値と判定される資産」であるから,全額を償却・引当しなければならないとの指針が示されていたのである。したがって,支援先についても会計処理の基準として実務に耐え得るだけの指針が示されていたことは明らかである。
被告らは,「金融機関が平成10年3月期から資産査定通達等を参考にしてそれぞれ自己査定基準を策定したとしても,原告ら以外の各金融機関の資産査定通達等の受け止め方と自己査定基準の内容からみれば,原告ら主張の内容の慣行が成立していたとはいえない」と主張し,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」とは認められないと主張する。しかし,平成10年3月期決算において各金融機関は,貸倒引当金の計上について,改正後決算経理基準に基づき自己査定をしたうえで,破綻先債権,実質破綻先債権,破綻懸念先債権,要注意先債権に分類したうえで引当を行っており,金融監督庁の検査によれば,主要17行について自己査定基準,償却引当基準は資産査定通達,追加Q&Aと同様の関連ノンバンク9年事務連絡,実務指針とおおむね
一致していたと認められる状況にある。したがって,平成10年3月期において,各金融機関は資産査定通達等に準拠して償却・引当を行おうとしたことは明らかであり,その処理も概ね資産査定通達等に基づく処理と一致していたことが窺えるのであるから,被告らの主張は事実に反するものである。
被告らは,早期是正措置制度導入前から導入後の経緯をみても,資産査定通達等が平成10年3月期において「公正なる会計慣行」となっていなかったことは明らかであると主張し,導入前について,金融行政当局において,税法基準を否定する旨示達した事実がなく,換言すれば,税法基準による償却引当のみでは不十分であるとは明示しておらず,かつ,有税で償却引当をなすべき基準を明示していないこと,改正後決算経理基準の導入や債権償却証明制度の廃止は,従前の税法基準による償却・引当を否定するものではなかったと主張する。しかし,「決算経理基準」の改正は,それまでの税法基準に基づく償却・引当に関する会計処理の方法を削除し,個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり
損失の発生が見込まれるかどうかを判断した上で,その必要額を償却・引当すべきものとしているのであり,金融当局において税法基準を否定する旨示達したとみるのが相当である。
第2 原告が作成した(被告らが作成に関与した)自己査定基準,償却・引当基準の違法性(「公正なる会計慣行」違反)
1 自己査定基準,償却・引当基準の内容の違法性
(1) 特定先基準の違法性について
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙別添「特定関連親密先自己査定運用細則」(自己査定運用細則)により,日本リース関連会社その他事業推進部長が指定する先についてこれを「特定先」と位置付け,償却・引当の前提となる債務者区分について,当該貸出先の業況,財務状況あるいは返済状況の如何に関わりなく,「正常先」又は「要注意先」とした(以下このような債務者区分の設定を「特定先基準」という。)。そして,債務者区分を正常先又は要注意先とした場合は,当該先に対する資産分類は原則として非分類又はⅡ分類とされることから,すなわちその先に対しては償却・引当をしないことを意味することとなる。したがって,仮にこの「特定先基準」を認めれば,事業推進部長が特定先と認定しさえすれば,その先は,その経
営実態と関係なく正常先ないし要注意先となり,原則的に償却・引当が不要ということになる。
しかし,平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度は,金融機関が商法の計算規定等に基づき自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することを前提とするものであるが,償却・引当と連動している債務者区分を当該先の経営状態と関係なく経営者等の一存で決めることができるとすることは,すなわち償却・引当額を恣意的に増減することを認めることにほかならず,会社の財産及び損益状況を正しく表示した財務諸表の作成を求める商法の計算規定に反するものである。
特定先基準は,原告らが支援方針を決定している限り支援先は破綻する可能性がなく,したがって貸倒損失が生じないものであるから,貸倒れによる損失見込み額としての償却・引当の計上が不要であるとの理屈によるものである(支援ドグマ)。しかしながら,貸出先が事業を継続できるか否かは基本的には当該事業の収益力にかかるものであり,当該事業の収益力がなければ弁済原資となるべきキャッシュフローが生み出される状況にないのであるから,当該貸出先に対する貸出金が回収不能あるいは回収不能に陥るおそれは客観的に大であるというべきであって,支援方針を決定しているからといって支援の内容に客観的な実効性がなければ事業の収益力は何ら改善されるものではない。したがって,事業推進部長が特定先と認定するだけで,そ
の先の経営状態と関係なく,その先に対しては償却・引当を不要とすることが公正とはいえないことは明らかである。要するに,被告らは,特定先基準なるいわば「魔法の杖」を使って,必要な償却・引当を回避したものであり,これは,まさに経営者による恣意的な経理操作(粉飾経理)にほかならない。このように特定先基準は,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」に関する規定の解釈基準となる資産査定通達及び実務指針に反し,到底一般に公正妥当と認められる会計処理の基準であるとはいえないものである。
被告らは,「不良債権償却証明制度等実施要領について」において,「債務者に対して追加的支援を予定している場合」には「『事業好転の見通しがない』と判断することは原則として適当ではない」としていることを理由として,原告が支援を予定している先については事業好転の見通しがないとはいえないのであるから取立不能のおそれがないと主張する。
しかしながら,上記実施要領は,法人税基本通達9-6-4に基づく債権償却特別勘定の繰入れに関する規定であるから,そもそも実施要領の記載は,旧商法285条の4第2項の取立不能のおそれに関する解釈基準とはなり得ない。そのうえ,同記載から,そこでいわれている追加的支援とは事業を好転させる可能性があるものが前提となっていることは明らかである。しかし,原告が特定先と位置付けた債務者は,いずれも追加的支援が全く予定されていないか,あるいは追加的支援が予定されていても,その支援の実効性が全く認められないものであったから,同記載を根拠として,原告が支援方針であることのみをもって取立不能と認識する必要がなかったとするのは不当極まりない。
(2) 決裁事由10項ただし書の違法性について
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」記載の決裁事由10項ただし書(決裁事由10項ただし書)により,「『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼動処理を本体と一体で行う会社については『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」と定めるところ,その趣旨は,関連ノンバンクの関係会社は関連ノンバンクではないものの,原告が関連ノンバンクと一体として不稼働資産処理を行おうと考えている場合には,当該関係会社を単体として評価するのではなく,関連ノンバンクと一体のものとして考え,債務者区分を関連ノンバンクとするとともに,資産分類についても一体処理するとした関連ノンバンクに適用した資産分類に関する考え方と同様の考え方を当
該関係会社にも適用するというものである。そして,原告は,関連ノンバンクであるエヌイーディーにおいて当期債権放棄額をⅣ分類とし,残額をⅢ分類としたのに準じ,関連ノンバンクではない青葉エステート外エヌイーディーの関係会社を関連ノンバンクと債務者区分したうえで,これら関係会社向け貸出金につき全額Ⅲ分類とし,かつ,償却・引当を一切しなかった。
原告及びエヌイーディーは,平成6年3月期からエヌイーディーグループの再建計画を策定・実施し,その中で青葉エステート等のエヌイーディーの不良債権の受皿会社を清算する予定であったが,エヌイーディーの収益力の低下から,対外金融機関説明等を考慮し,エヌイーディー本体に対する債権放棄を優先させた結果,上記再建計画に盛り込まれていた関係会社の清算が実現できないまま平成10年3月期に至ったものであり,これら関係会社は,後記のとおり,平成10年3月期において,資産査定通達あるいは4号実務指針にいう実質破綻先であった。
そもそも,資産査定通達は,「資産査定とは,金融機関の保有する資産を個別に検討して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分することであ」るとして,資産査定においては,貸出先ごとに個別に検討して債務者区分を行ったうえで資産分類をすることを予定していることからすれば,関連ノンバンク等の関係会社を本体と一体として資産査定することは,同通達の趣旨に反するといわざるを得ない。しかも,関係会社とはいっても,それは本体の関連ノンバンク等とは別個の会社であって,個々の会社に対する原告の貸出金の額や担保の状況,返済状況等が全て異なっていることからすれば,それぞれの営業実態等を考慮,検討して資産査定すべきであり,関連ノンバンクの関係会社であることを理由に本体と一体として査定す
ることは合理性を欠くものといわざるを得ない。したがって,決裁事由10項ただし書は合理的な会計処理とはいえない。
また,金銭債権につき取立不能と見込まれるときは,その見込みを正確に反映した会計処理をすることが必要であり,これを取立不能ではないとする会計処理をすることは,売上(売掛金)の架空計上あるいは棚卸資産の架空計上をするのと同様であり,そのような会計処理が許されないのは当然であるところ,決裁事由10項ただし書は,関連ノンバンクの関係会社として不稼働処理を一体として行うとの一事をもって取立不能の見込みがあるか否かの検討を行わないとするに等しい規定であり,このような意味においても,同ただし書が合理的なものといえないことは明らかである。
(3) 「関連ノンバンクにかかる自己査定運用規則」(自己査定運用規則)※7なお書の違法性
原告は,自己査定運用規則※7なお書において,再建計画が作成されていない関連ノンバンクである第一ファイナンスについて「既に損失が確定しているとみなされる部分」のみをⅣ分類とし,損失が見込まれるものであってもそれが確定していないといえる部分はⅣ分類と査定していないと定めた。
第一ファイナンスは,最終的には清算を予定していた会社であり,清算に伴う損失が見込まれる状況にあったから,当然,その損失見込額全額をⅣ分類とすべきであった。にもかかわらず,原告は,清算手続がなされていないから損失が確定していないとの理由でⅣ分類としないこととしたのであるが,資産査定通達によれば,「回収不可能または無価値と判定される資産」であるⅣ分類は,「その資産が絶対的に回収不可能又は無価値であるとするものではなく,また,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,査定基準日において回収不可能又は無価値と判定できる資産」とされているのであるから,そのような理由でⅣ分類としないことが許されないことは明らかである。
なお,税法基準は,損失の計上について確定を要するとしているが,同基準は,租税収入の確保,課税の公平の観点から定められているものであるから,企業の財政状態及び損益状況を正しく表示しようとする商法計算規定に当然に整合性を持つものではなく,平成9年7月の決算経理基準の改正により税法基準が否定されたのであるから,税法基準を口実に,清算手続が終了していないという理由で損失見込額を取立不能見込額として計上しないとすることは許されない。
(4) 「経営支援実績先」との債務者区分を設け原則Ⅱ分類としたことの違法性
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙記載の決裁事由5において,「当行が経営支援を行ってきた先で,支援完了した先については,業況は正常に復しているものの,当行は引き続き特別の注意をもって管理を行っており,従来同様の当行スタンスを継続していることから,当該先の債務者区分は『経営支援実績先』として区分するものとした。資産分類については,原則Ⅱ分類とする」と規定した。
しかし,原告のいう支援完了した債務者のなかには,単に自転可能となっただけの債務者も含まれており,そのような債務者には,償却前利益で概ね2~3年程度で実質債務超過が解消できるとはいえない(体力がない)債務者も存在していた。また,「当行は引き続き特別の注意をもって管理を行っており,従来同様の当行スタンスを継続している」ことのみから,このような債務者について再建可能との判断ができるわけではない。したがって,原告が「経営支援実績先」との債務者区分を設け原則Ⅱ分類としたことは資産査定通達等に反するものである。
2 自己査定基準の策定目的の違法性
本来,自己査定基準は,当該金融機関の資産状態を正確に査定することを目的として策定されなければならないが,原告の策定した自己査定基準は,原告の資産状態を正確に把握するために策定されたものではなく,要償却・引当額を実態より圧縮することを目的として策定されたものである。
すなわち,被告らは,国際業務維持の目安となる自己資本比率8パーセント維持を目的として,原告の資産の実態とは関係なく,要償却・引当額を自己資本比率8パーセントが維持できる範囲内に圧縮するために自己査定基準を策定したものであり,それが,金融機関の経営の健全性を確保するため客観的なルールに基づき経営の早期是正を促すという早期是正措置の趣旨・目的,またその前提として金融機関が自らの財務内容を正確に資産査定するという自己査定制度の趣旨・目的に反することは明白である。このことは,以下に述べる自己査定基準の策定経過から優に認めることができる。
(1) 平成8年当時における自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況等
まず,被告らは,平成8年8月30日の常務会において,自己査定基準及び償却・引当基準を事業推進部及び総合企画部に策定させることを決定したが,その時点において,被告らは,原告の要処理不稼働資産が1兆円を超える額に達していること,原告の要処理不稼働資産処理原資が十分ではないことを知悉し,今後策定される自己査定基準,償却・引当基準により要処理不稼働資産額が正確に反映されることになれば,原告らは自己資本比率8パーセントを維持することが困難となりかねないことを認識していた。したがって,自己査定基準,償却・引当基準の策定に当たっては,原告の資産状態を正確に反映する自己査定基準,正確な要償却・引当額を算出する償却・引当基準ではなく,要償却・引当額を可能な限り圧縮することのできる自己査定
基準,償却・引当基準を策定することが必要であると認識していた。このことは,Fが,上記常務会において,「早期是正措置の為の資産の自己査定については,プロジェクトチームを作って対応していくということであるが,実質的には多額に抱えてしまっている不稼働資産をどの様な形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。その点は十分に認識しておく必要がある」と発言していたこと,同月19日の常務会において「今後,行政指導で自己査定が必要となっていくが,それを実態とどう調整していくかが非常に重要である」と発言していたことから十分に窺える。
その後,事業推進部は,前記の趣旨の自己査定基準を策定する前提として,原告の不稼働資産実態額及びそれを前提とする要処理額の把握を進めたが,その結果,原告の関連親密先である長銀リース,エヌイーディー,ランディック,第一ファイナンス,平河町ファイナンス,ジャリック,日本リース等に関して,平成8年の大蔵省検査において,Ⅲ分類5139億円及びⅣ分類1961億円の合計7100億円と査定されたが,その実態額はⅢ分類848億円及びⅣ分類1兆1626億円の合計1兆2474億円であり,他方,平成9年3月期及び平成10年3月期における関連親密先の不稼働資産処理の原資が約1500億円しかなく,不稼働資産の実態額が正確に査定されるような自己査定基準を策定し,それに基づいて自己査定を実施した場合は
,多額な償却・引当不足の表面化が予想される状況であった。Fは,平成8年10月29日に,Dは,同年11月11日に,いずれもHの説明により,上記状況を認識した。
事業推進部は,前記イの状況を前提として自己査定基準の内容を検討し,①関連親密先と一般先の基準を区分することにより,関連親密先の要処理分類額の圧縮を最大限はかり,自己資本比率の国際基準8パーセント,国内基準4パーセントを達成する,②Ⅲ分類基準の弾力化及びⅢ分類引当の段階化により償却・引当の軽減・平準化を図るという方針のもと,関連親密先に関しては,原告らが支援している先及び支援する方針としている先は,その業況等と関係なく債務者区分は要注意先,資産分類は原則Ⅱ分類とし,償却・引当はゼロとする,ただ当期支援分のみはⅣ分類とし全額償却するという基準を考案した。その基準は,関連親密先のⅣ分類を支援3社(長銀リース,エヌイーディー,ランディック),第一ファイナンス及び受皿会社9社のみ
とし,実態に則して査定すれば多額なⅣ分類査定が出ると思われる日本リースその他に対する貸出債権は全てⅡ分類とするものであった。さらに,受皿会社9社のⅣ分類についても,その償却・引当を適宜先送りする可能性を探ることが考えられていた。なお,事業推進部としても,①支援計画がある先(長銀リース,エヌイーディー,ランディック)について,支援計画により将来償却が明らかなものをⅢ分類とせずⅡ分類とすること,②エル都市開発,日比谷総合開発,長ビルの含み損をⅡ分類とすること,③第一ファイナンス及び受皿会社9社については含み損,損失額が確定していないという理由で償却・引当を先送りすること等には問題があることを認識していた。
(2) 平成9年2月7日の常務役員連絡会
D,Fらは,平成9年2月7日の常務役員連絡会において,総合企画部から,新規発生見込みを含めて今後の要処理不稼働資産見込額が最低でも7000億円から1兆円に達すること,早期是正措置の導入により平成9年度以降はⅢ分類及びⅣ分類は単年度での適正な償却・引当(従来と同様であればⅢ分類は50パーセント,Ⅳ分類は100パーセント)の実施が不可避であるところ,株価が1万8000円から2万円で推移すると仮定した場合,自己資本比率8パーセント,有配維持を前提とする限り,平成10年3月期の不稼働資産処理可能額は3000億円ないし5000億円にとどまらざるを得ない旨説明を受け,その際,上記被告らは,自己査定基準,償却・引当基準により算定される要償却・引当額について不稼働資産処理可能額の範囲
に圧縮する必要性を具体的に認識した。
(3) 平成9年度上期における自己査定トライアル(試行)の状況等
原告において,平成9年度上期において自己査定トライアルを実施する予定でいたが,この自己査定トライアル結果が本番自己査定結果をほぼ拘束すると考えられていたことから,事業推進部は,平成9年4月ころから,要償却・引当額を可能な限り実態より圧縮できる自己査定トライアル用自己査定基準,償却・引当基準を模索した。しかし,平成9年度から平成11年度までの3年間の不稼働資産処理財源を合計5000億円とする中期計画について,早期是正措置導入時の平成10年3月時点において,関連親密先だけで約1800億円の償却・引当不足が出るものと見込まれていた。
(4) 自己査定体制検討プロジェクトチームにおける最終答申等
D,F,H,Gらは,平成9年5月9日,総合企画部作成「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料に基づき,平成10年3月期の不稼働資産処理及び決算方針に関する協議をしたが,その結果,同期における関連親密先の不稼働資産の処理可能額は1994億円と想定されること,にもかかわらず同期の要償却・引当額は,最も甘くした債務者区分及び資産分類を前提として破綻懸念先のⅢ分類は12.5パーセントの引当,実質破綻先のⅢ分類は25パーセントの引当,Ⅳ分類は100パーセントの引当という償却・引当基準を適用しても合計2838億円までしか圧縮できず,関連親密先の不稼働資産処理可能見込額1994億円を844億円超過することから,要償却・引当額が上記1994億円
に収まるような自己査定基準,償却・引当基準を策定することを決定した。
検討チームは,上記方針を踏まえて,最終答申を作成したが,更に要償却・引当額を圧縮するため関連親密先のⅢ分類について償却・引当をしないこととした。そして,D,E,F,C,Bらは,平成9年5月23日の常務会において,上記最終答申を了承した。
(5) 自己査定トライアルの第一次集計結果と検討状況等
その後,自己査定トライアルの第一次集計速報値がまとまった平成9年9月1日時点において,F,G,Hらは,①基本的には自己査定結果に基づく償却・引当額を本番実施時において同トライアル結果より大幅に減らすことは不自然・不可能であること,同トライアルの結果が平成10年3月期の結果を事実上決めてしまうことになること,よって,同トライアル結果が本番実施時の最低ラインであり,同トライアル結果についても事実上償却・引当予算から逆算的にⅢ,Ⅳ分類数字を決めざるを得ないこと,②第一次集計値を前提として,関連親密先のⅢ分類にも50パーセントの償却・引当を行う,あるいは関連親密先のⅢ分類には償却・引当を行わないという二種類の償却・引当基準により試算をすると,Ⅲ分類及びⅣ分類の償却・引当合計額
は,前者は5613億円,後者は3344億円となり,おおむね平成9年度処理予定額5000億円の範囲内に納められる水準になっていること,③しかし,関連親密先の自己査定基準・方法等にはそれなりの無理をしていること,④同トライアルでは,事業推進部所管先においてかなり無理をして額を圧縮しているため,今後他行動向,会計士のスタンスによって本番の際には修正せざるを得ない可能性もあること,⑤関連親密先について,大蔵省関連ノンバンク通達に基本的には準拠しているものの,原告個別基準もそれなりに使って査定額の圧縮を図っている,各行ともある程度関連親密先については弾力的な考え方で対応していく見込みであるが,原告の場合相当自主裁量性の強いものとなっておりこのあたりが会計士に認められない可能性が十分あり
得ること,⑥原告の自己査定基準における債務者区分については,原告独自に「特定先」という区分を設定したこと,関連ノンバンク通達を適用するに当たり体力のない先を設定したこと,関連ノンバンク通達を適用するに当たり体力のない先を体力ありとして区分したこと等に問題があること,⑦その「特定先」区分設定により,要処理不稼働資産額を圧縮した先は,ランディック子会社(本来であれば一般先に準じて査定),日比谷総合開発・エル都市開発(本来であれば一般先に準じて区分,その場合は破綻懸念先あるいは実質破綻先に分類される可能性大),受皿9社(本来であれば一般先に準じて区分,その場合は破綻懸念先または実質破綻先に分類される可能性大)であること,⑧日本リースについては関連ノンバンク通達の適用を恣意的に行い,
本来「体力がない」関連ノンバンクであるにもかかわらず,事業会社の含み損を考慮せず,リース資産の含み損益の評価だけで「体力のある」関連ノンバンクとしたこと,⑨「特定先」については赤字・含み損を査定対象から除外したこと等の説明を受け,これを認識した。また,同トライアルでは,関連親密先のⅢ分類については,関連ノンバンクとして倒産リスクがない,との理由により償却・引当を行わないとしていた。
この償却・引当基準と関連親密先のⅣ分類は原則として当期支援分のみとするトライアル用の自己査定基準を併用すれば,関連親密先の償却・引当額は,当期支援額を調整することにより原告の償却・引当原資の多寡に合わせて自在に圧縮できることとなったのであるが,そのような基準が客観性を持ち得るはずがないものであった。
(6) 上記(1)ないし(5)の経過に係る原告の自己査定基準策定の目的等
以上の(1)ないし(5)の経過にかんがみれば,原告の自己査定基準及び償却・引当基準が,原告の資産状態を正確に反映する目的ではなく,要償却・引当額を実態より圧縮し,原告の償却・引当可能額に納めることを目的として策定されたものであることは明らかである。被告らは,この一連の過程を,事業推進部が単にシュミレーションしていたに過ぎない旨主張しているが,そもそも,原告の資産状態を正確に反映する自己査定基準,償却・引当基準を策定しようとしていたのであれば,上記のような数次にわたるシュミレーションなどする必要がない。その上,上記のような経過にかんがみれば,そのシュミレーションの目的が,可能な限り要償却・引当額を圧縮することにあったことに疑問を容れる余地はない。
(7) 被告らの主張に対する反論
被告らは,平成10年3月期において税法基準によることが認められていた,関連ノンバンク等支援先については償却・引当という概念が成立せず,単に支援損を計上すれば足りたという主張をしているが,上記(1)ないし(5)の経過をみると,当時,被告らがそのような考え方に立っていたとは到底認められない。当時,作成された各種資料には,大蔵省等が示した資産査定通達等と外形的な整合性を取りながら,実態より要償却・引当額を圧縮できる基準を策定しようと組織全体で腐心していた状況が顕著に窺えるのに,当時,被告らが,税法基準に従えば足りると考えていたことを窺わせる記載は皆無である。したがって,被告らの主張は,本件訴訟開始後に,始められたもので,原告の自己査定基準の策定当時,被告らが,税法基準で足りるとする
認識を有していたという主張は全く根拠がない。
また,原告内部の当時の資料において,財源効率の追求の観点から無税償却の積み上げを図るものの,有税引当も必要であるとして無税引当見込額のみならず有税引当見込額も試算していること,平成10年3月期の連結利益についてシミュレーションされているが,その中に,連結当期利益(有税処理2500の税効果考慮後)といった記載があることから,被告らが,平成10年3月期決算において,回収不能の見込みがある場合には無税償却できるか否かにかかわらず,償却・引当しなければならないこと,換言すれば,税法基準は回収不能見込の判断基準としては不十分であることを認識していたと認めるのが相当である。
第3 原告らの平成10年3月期会計処理による償却・引当不足額の発生と配当可能利益の不存在
1 日本リースについて
(1) 日本リースの状況
被告らは,日本リースに適用した「経営支援実績先」との債務者区分は,対象企業は,原告の重要な取引先であるが損益支援を実行した実績先であるから「損益支援が終了したから原告の手を離れた」と考えることはあり得ず,むしろ将来にわたり,資金繰り面,人事面,営業面,経営面の支援を継続するなど,なお「特別の経過観察」を必要とする先であるとの考え方から設けられた区分であるから,合理的であると主張する。しかし,そもそも債務者区分は資産分類の前提としての作業であり,貸出金等の価値の既存度合いを測るためのものであって,特別の経過観察を必要とする先か否かといったことを管理・把握するため設けるものではないのであるから,「経営支援実績先」との債務者区分を設けたことには,全く,合理性はない。
被告らは,①日本リースの実態として,原告による平成6年度末及び平成7年度末の損益支援の結果,その含み損部分に見合う借入金の利払いについては,本業の利益でカバーし,実態利益は,平成9年3月期175億円,平成10年3月期182億円となり,期間損益が黒字決算に復していること,②年間230億円の利益を挙げるための計画が具体化しており,本業の収益による不稼働資産の処理が進むとみられていたこと,③キャッシュフローが順調であり,平成9年11月の金融危機も原告の支援(損益支援はもとより,追加貸出等の支援等)なしで乗り切るなど,200近い金融機関からの借入金につき約定返済に一切延滞がないこと,④平成9年秋に他のリース会社と同様に,一時的に抑制したリース営業も,平成10年4月から再び増加
する計画を立てるなど活発な営業活動を展開していたこと,⑤子会社の日本リースオート等の上場によるキャピタルゲインの獲得が見込まれたこと等を理由に,全銀協追加Q&Aの「自力で再建の見通しが立たない」という要件には該当せず,「体力」があると判断して,同社向け貸出金をⅡ分類と査定したことが妥当であったと主張する。
しかし,日本リースには,支援終了後も7300億円の不稼働資産が残存し,うち約6500億円が回収不能見込みであり,しかも,このような不稼働資産を処理する財源は日本リースには存在していなかった。また,被告らが主張する日本リースの実態利益について,金利低下による偶発的要因の占める割合が多く,他方,同社は当時リース営業を抑制しており,将来的には収益が先細る状況にあり,日本リースに自転力があったとは到底いえない状況であった。さらに,日本リースは,平成9年11月の金融危機において,資金ショートを起こす危険が生じており,日本リースは,他行との交渉により,折返しの融資を確保したが,その理由は,原告及び日本リースが他行に対してその実態を隠ぺいしたことによるものであって,これが明らかとな
れば,当然,資金繰り破綻を生ずることが予想された。なお,日本リースの平成10年3月期における不良債権残高(回収不能の営業貸付金額)は,7229億円に達し,同社が自力で再建できる見込みは全く存在しなかった。
(2) 日本リースの償却・引当不足額
日本リースに対する貸出金2556億8000万円については,788億4400万円がⅣ分類となり,残額である1768億3600万円がⅢ分類となり,少なくともⅣ分類である788億4400万円の償却・引当を行わなければならなかったところ,全く償却・引当をしていないから,788億4400万円の償却・引当不足が生じているものである。
2 エヌイーディーについて
(1) 原告の償却・引当処理と問題点
原告は,エヌイーディーにつき自己査定運用規則により,「体力のない」関連ノンバンクであるが「合理的な再建計画が存在し,当行が母体行責任を負っても再建の意思を有する場合」に該当するとし,「経営の意思」により決定されている支援予定額(債権放棄)をⅣ分類とし,その金額のみを平成10年3月期の償却・引当額とした。なお,被告らは,支援ドグマを主張し,原告が策定したものであるから当然に再建計画に合理性があると主張するものであるが,再建計画は客観的に合理性のあるものでなければならないのは,自己査定運用規則が示すとおりである。
(2) 平成10年3月期に策定された再建計画に合理性がないこと
ア 平成10年3月期に当初計画を遥かに下回る額しか債権放棄が実施されなかったこと
原告が平成6年に策定したエヌイーディーの再建計画によれば,平成6年3月期から平成10年3月期にかけて支援総額1900億円(支援内容は債務免除等による損益支援)を実施するものであったが,平成9年3月末までに原告が支援(債務免除)した額は合計1051億円に止まり,当初計画に設定された総額との差額849億円が平成10年3月期において支援に必要な残額ということになる。
ところで,当初計画の実施後は残存要処理767億円の見込みであったが,大幅な地価下落によるロス率の増加,新規延滞の発生により2924億円のロスが残る見通しとなったことから(要するに,エヌイーディーの収益状況あるいは財務状況が当初計画の策定時点よりもさらに悪化したということ),平成10年3月期前に当初計画の見直しが行われ,その結果,支援期間を平成6年3月期から平成14年3月期までの9年間,支援総額を当初計画の1900億円から4001億円(うち1051億円は上記したとおり支援実施済み)に修正する旨の再建計画(以下,この修正後の再建計画のことを「修正計画」という。)が策定された。ただ,修正計画は国税庁の承認を得られなかった。
修正計画によれば,平成10年3月期に349億円を支援するというものであったが,しかしながら,同期に実施された支援額(債務免除額)は201億円に止まった。
すなわち,当初計画によれば平成10年3月期の必要な支援額は849億円残っていたにもかかわらず,しかも当初計画の策定段階と比べてエヌイーディーの収益状況あるいは財務状況がさらに悪化しているにもかかわらず,平成10年3月期での支援額(債務免除額)は201億円に止まったものである。
当初計画が国税庁の承認を得たことから「合理的な再建計画」であったことを前提とする限り,修正計画は,当初計画で支援に必要な残額849億円を平成10年3月期に実施することを前提としていないものであるから,それ自体不合理であることを示すものである。
イ 修正計画の支援予定額と実際の予定支援額とは異なるものであったこと
また,修正計画によれば,平成10年3月期ないし平成14年3月期の5年間に亘り2950億円を支援する内容であり,その支援額が経済合理性から税務上寄付金認定を受けない必要かつ相当額として国税庁の承認を得ることを意図していたが,実際には,上記5年間で1300億円の支援額しか予定していなかったもので,それ自体修正計画が実際には実行不可能で不合理なものであることを示すものにほかならない。
そもそも,修正計画は,「エヌイーディーは存在意義も無いし,経営状態も余りに酷い。できれば,直ぐにでも投げ出したい会社だ。けれども親である長銀が,子であるエヌイーディーを投げ出すと,長銀自体の信用にかかわる。だから,当面は,処理を先送りするしかない。ついては,無税償却の枠だけは確保しておかないといけない」ということで作成されたものであり,「長銀の無税償却を国税当局に認めてもらうために策定されたものであり,エヌイーディーの再建を目的とした合理的計画」ではなかったのである。
ウ 修正計画の実行によっても自転しないものであったこと
さらに,「98/3からの支援5か年計画(暫定)で3000億円の処理を実施した後でも最終利益は10億円程度の赤字。不良債権の処理が大半引当方式であり未引当の固定化債権が650億程度残り当該資産の金利負担を賄えない状況」であるとしているとおり,修正計画どおりに5年間で3000億円近い支援が仮に実行されたとしてもなお当期利益ベースで黒字化できる状況になかったものであって,しかも「再建計画5カ年計画表(収支計算)」(甲151の添付資料8の1)では「投資育成収益」として毎期30億円を見込んで計上しているものであるが,上記常務会資料にあるとおり「今後は店頭市場の低迷もあり20億円の確保は非常に厳しい水準」とされていた。
エ 合理的な再建計画ではない場合の具体的な償却・引当不足額について
以上アないしウのとおり,エヌイーディーの「再建計画に客観的な合理性が認められない」のであるから,「当該支援対象ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類額を貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とする」こととなり,その結果,原告のエヌイーディーに対する貸出金1715億8500万円のうち,755億9500万円がⅣ分類となり,少なくとも同額の償却・引当を行わなければならなかったところ,実際には201億8000万円について償却・引当をしただけであるから,その差額554億1500万円の償却・引当不足が生じている。
3 エヌイーディーと一体的処理基準(決裁事由10項ただし書)を適用した個社群について
(1) 青葉エステートについて
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」記載の決裁事由10項ただし書により,「『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼動処理を本体と一体で行う会社については『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」と定め,関連ノンバンクであるエヌイーディーにおいて当期債権放棄額をⅣ分類とし,残額をⅢ分類としたのに準じ,関連ノンバンクではない青葉エステート外エヌイーディーの関係会社を関連ノンバンクと債務者区分し,これら関係会社向け貸出金につき全額Ⅲ分類として,かつ償却・引当を一切しなかった。
前記のとおり,原告は,決裁事由10項ただし書を制定し,関連ノンバンクでないエヌイーディーの不良債権受皿会社を関連ノンバンクなる債務者区分とすることにより,取立不能額の分割償却あるいは計画償却を図ったものであり,損失の計上について人為的な操作を図り,経営者による意図的な経理操作(粉飾経理)を実施した。
青葉エステートは,平成8年3月末に46億3200万円,平成9年3月末に51億0300万円のいずれも大幅な経常損失を計上し,かつ従業員は全くなく,平成10年3月期において,事業継続の可能性が全くない状況であり,資産査定通達及び実務指針にいう実質破綻先に当たるものである。
よって,青葉エステートにつき,227億6100万円の償却引当不足が生じているものである。
(2) ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ(ユニベスト外4社)並びにエクセレーブファイナンスについて
ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスは,いずれも売上が皆無又は皆無に近い状況であり,平成9年3月期に大幅な経常損失を計上しており,かつ,従業員は全くなく,会社の実体すらない状況で,平成10年3月期において,資産査定通達にいう「実質破綻先」に当たるものである。
よって,ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスについては,償却・引当不足が生じていた。すなわち,ユニベストにつき73億7300万円,グラベスにつき31億8700万円,コーポレックスにつき13億5600万円,プロクセルにつき5億9600万円及び日本ビゼルボ1億3100万円並びにエクセレーブファイナンス400億円の各償却・引当不足が生じているものである。
4 第一ファイナンスについて
(1) 償却・引当の前提となる会社の状況について
第一ファイナンスは,平河町ファイナンスへの業務移管後,新規貸出を止め,その保有する不稼動債権の管理・回収のみを行う会社となったが,原告の内部資料には「第一ファイナンス及び受け皿2社の清算を検討-段階的な清算をイメージ(最終的な損失負担は,基本的に当行全額負担)」とされており,また,「将来的には当社清算を想定」,さらに「多額の含み損を抱えている上に,赤字体質であることから将来的に清算せざるを得ない」旨記載されており,第一ファイナンスについて最終的には清算を予定していた事実は明らかである。
このような業務状況を反映して,平成10年3月期決算において経常損益が45億9700万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同決算期の帳簿上の債務超過額は137億4800万円であった。
(2) 損失が見込まれる金額についてもⅣ分類とすべきであったこと
平成10年3月期における原告の第一ファイナンスに対する貸出金残高は1245億6000万円であったところ,同期における第一ファイナンスの帳簿上の債務超過額137億4800万円,同社の100パーセント子会社2社の債務超過額から子会社2社において計上していた貸倒引当金を控除した28億6600万円,同社保有の有価証券含み損313億4100万円及び同社の営業貸付金219億1700万円の合計698億7200万円に相当する額が,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のⅣ分類に当たるものである。
したがって,実際の引当額147億円と,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のうちⅣ分類に当たる698億7200万円との差額551億7200万円が償却・引当不足額となる。
5 特定先基準を当てはめた個社群について
(1) 有楽エンタープライズについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
有楽エンタープライズは,日本リースの貸付先であった末野興産の物件を取得するなど日本リースの末野興産向け貸出金を処理する機能を果たすために設立された不動産会社であった。
有楽エンタープライズは,大阪市中央区日本橋1丁目40番3号所在の物件にパチンコビルを建築し,パチンコ業者に一括賃貸することにより収益を上げること(いわゆる事業化)を計画していたものであるが,当該業者が平成8年9月に倒産したことにより事業化計画は頓挫し,平成10年3月末時点には上記土地を駐車場用地として暫定的に利用している状況にすぎず,また仮に事業化が実現したとしても「20年経っても経常利益はマイナスのままであり」「収益で借入金返済ができない」状況にあったものである。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,同社の平成9年3月期は経常損益2億8800万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また平成9年3月期の帳簿上の債務超過額は30億5700万円であったこと,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
有楽エンタープライズの上記アの状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。しかるに,原告は,有楽エンタープライズについて特定先基準により債務者区分を要注意先にとどめたことによって,同社向け貸出金63億5000万円に関して償却・引当額5600万円を計上したのみである。
しかしながら,有楽エンタープライズは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の有楽エンタープライズに対する貸出金63億5000万円から担保処分による回収見込額20億6500万円及び清算バランスによる回収見込額1500万円を控除した42億7000万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであって,上記償却・引当額との差額42億1400万円の償却・引当不足が生じているものである。
(2) 四谷プラニングについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
四谷プラニングは,日本リースの日本ビルプロヂェクト(ビルプロ)向け貸出金に関し,日本リースの決算対策のために設立された会社であり,ビルプロの取得に係る東京都新宿区左門町の土地(左門町物件)に関して日本リースのビルプロ向け貸出金を簿価で譲り受けて保有している会社であった。
ところで,左門町物件について実施を予定していた事業計画によれば,隣地を取得して整形地とした上で賃貸オフィス・マンションビルを建設するというものであったが,平成10年3月末現在暫定的に運送業者の配送センターの駐車場として利用されていた状況で,上記事業計画に関しては,平成9年9月における原告の認識としても,事業化の目処がないとしているものであり,計画どおりに事業化が実施される見込みは全くない状況であった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,四谷プラニングの平成9年3月期は経常損益1億8100万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また平成9年3月期の帳簿上の債務超過額は10億7200万円であり,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
四谷プラニングの上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,四谷プラニングについて特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金187億8000万円に関して償却引当額1億6400万円を計上したのみである。
しかしながら,四谷プラニングは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の四谷プラニングに対する貸出金187億8000万円から担保処分による回収見込額20億9000万円及び清算バランスによる回収見込額27億1000万円を控除した139億8000万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであり,上記償却・引当額との差額138億1600万円の償却引当不足が生じているものである。
(3) 竜泉エステートについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
竜泉エステートもまた四谷プラニングと同様,日本リースのビルプロ向け貸出金に関し,当該貸出金を担保権とともに譲り受ける受皿会社として設立された会社である。
同社については,担保権を有する東京都台東区竜泉2丁目の物件をパチンコ業者に賃貸する計画であり,定期賃借権の予約合意にまで至ったものの,近隣住民のパチンコ店建設に対する反対運動のため風俗営業許可や開発許可を取得できる目途が立っていない状態であり,また,担保権を有する東京都新宿区N町の物件もオフィスビル建設等の計画はあったもののいまだ具体化していなかった。このように,いずれの物件についても,今後それらの事業化が実現する具体的目途は立っていない状況にあった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,竜泉エステートの平成9年3月期は経常損益1億6100万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同期の帳簿上の債務超過額は9億6500万円であり,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
竜泉エステートの上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,竜泉エステートについて特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金149億4200万円に関して償却引当額1億3100万円を計上したのみである。
しかしながら,竜泉エステートは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の竜泉エステートに対する貸出金149億4200万円から担保処分による回収見込額5億2800万円を控除した144億1400万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであって,上記償却・引当額との差額142億8300万円の償却・引当不足が生じているものである。
(4) 木挽町開発について
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
木挽町開発もまた四谷プラニングと同様,日本リースのビルプロ向け貸出金に関し,当該貸出金を担保権とともに譲り受ける受皿会社として設立された会社である。
同社については,担保権を有する東京都中央区銀座8丁目の物件に隣地所有者と共同でビルを建設する計画があったものの,「出光興産との共同開発の合意そのものが締結されておらず,ビルプロによる事業化の見込みも全くなかった」ばかりか,立ち退きに応じない借家人もいて未だ具体化するには至っていなかったもので,上記事業計画に関しては,平成9年9月における原告の認識としても今後それらの事業化が実現する具体的目途は立っていなかった状況にあった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,木挽町開発の平成9年3月期は経常損益1億1300万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同期の帳簿上の債務超過額は6億7300万円であり,従業員もなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
木挽町開発の上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,木挽町開発について特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金115億5000万円に関して償却引当額1億0100万円を計上したのみである。
しかし,木挽町開発は実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告らの木挽町開発に対する貸出金115億5000万円から担保処分による回収見込額7億7300万円を控除した107億7700万円がⅣ分類となり,同額を償却・引当額として計上すべきであり,上記償却・引当額との差額106億7600万円の償却引当不足が生じているものである。
6 償却・引当不足額合計及び配当可能利益の不存在
特定先基準の違法性により,有楽エンタープライズにつき42億1400万円,四谷プランニングにつき138億1600万円,竜泉エステートにつき142億8300万円及び木挽町開発につき106億7600万円,決裁事由10項ただし書の違法性により青葉エステートにつき227億6100万円及びユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスにつき計526億4300万円,※7なお書の違法性により第一ファイナンスにつき551億7200万円,「合理的な再建計画」がないのにそれがあるとしてエヌイーディーにつき554億1500万円,再建可能性がなく体力がない関連ノンバンクであるのに「経営支援実績先」と債務者区分して資産分類をⅡ分類とした日本リースにつき788億4400万円,これら合計3078億240
0万円の償却・引当不足が生じているものである。
7 太田昭和監査法人(本件監査法人)の意見
被告らは,本件監査法人が,経営支援実績や特定先といった区分を設けることや原告の関連ノンバンクの子会社について一体処理することを容認し,これらの取扱いを資産査定通達等に照らして適正である旨の意見を述べていたと主張する。しかし,原告は,会計監査人に対し,当時,これらの関連ノンバンクやその子会社の実態を説明せず,かえって,その実態を組織的に隠ぺいしていた以上,このような虚偽の説明に基づく適正意見が被告らの主張を裏付けるものとなり得ない。
第4 仮に,資産査定通達等に商法32条2項を通じての法規範性が認められないとしても,平成10年3月期決算において,原告らが策定した自己査定基準,償却・引当基準に基づく下記の償却・引当額は,商法285条の4第2項にいう取立不能見込額としては不足しており,実際には配当可能利益は存在していない。
1 取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念に従って行うべきである。
債権の取立不能のおそれあるとき及び取立不能見込額は,債務者の資産状態,支払能力,取立のための費用及び手続の難易などを総合し,合理的な社会通念に従って総合的に判断すべきものとされているので,商法285条の4第2項における取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念に従って行わなければならない。したがって,取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念によって行うというのが「公正なる会計慣行」である。
2 資産査定通達等について仮に商法32条2項を通じての法規範性が認められないとしても,以下の考え方は,取立不能見込額の判定についての合理的な社会通念を示すものである。
(1) 売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能額となることは明らかなのであるから,債権額からこの回収可能額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるべきである。
(2) 売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,そもそも支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないのであるから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性を認めることができない。
(3) 取立不能見込額の判定は,当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきである。
(4) 取立不能見込額とは,見込額である以上,絶対的に取立不能な額だけではなく,また,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,決算作成時において回収不能と判定できる金額である。
3 自己査定基準,償却・引当基準が合理的な社会通念に反すること
(1) 特定先基準が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能であることは明らかであるから,債権額からこの額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるべきであり,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないので,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないというべきであり,これに対し,特定先基準は,貸出先の業況,財務状況あるいは返済状況の如何に関わりなく貸出金に対する個別の償却・引当を行わなくてよいとするものであり,不当である。
(2) 決裁事由10項ただし書が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,取立不能見込額の判定は,当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきであり,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないといえ,これに対し,決裁事由10項ただし書は,当該債務者を関連ノンバンクと一体として処理することを理由に当該債務者について当該関連ノンバンクに準じた資産分類を行うとしている点で不当である。
(3) ※7なお書が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,取立不能見込額とは,絶対的に取立不能な額だけではなく,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に決算作成時において回収不能と判定できる金額であり,これに対し,※7なお書は,Ⅳ分類すなわち「回収不可能又は無価値と判定される資産」(取立不能見込額)を既に損失が確定しているとみなされる部分のみに限定している点で不当である。
(4) 被告らの主張する税法基準が合理的な社会通念に反すること
被告らの主張する税法基準とは,原告らの関連親密先については支援損のみが問題となり関連親密先への貸出金は償却・引当の対象とはならない,償却・引当は無税適状の貸出金についてのみ行えば足りるところ,原告が支援する方針としている先については,法人税基本通達9-6-4の要件を充たさないので,関連親密先に対する貸出金は償却・引当をする必要がないというものである。
しかし,貸出金の回収不能見込額に関する合理的な社会通念は,前記2(1)ないし(4)のとおりであり,被告らの主張する税法基準は,このうち,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能額となることは明らかであるから,その債権額からこの額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるという合理的な社会通念,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないのであるから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないとの合理的な社会通念に反する。
また,税法基準が会計慣行であったとしても平成10年3月期における「公正な会計慣行」とはなり得ないことからすれば,税法基準は合理的な社会通念に反する。
4 償却・引当不足合計額及び配当可能利益の不存在
(1) 予備的主張における償却・引当不足額が問題となる会社
特定先基準の違法性により有楽エンタープライズ並びに四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート(ビルプロ3社)向け貸出金に係る償却・引当の不適切性,決裁事由10項ただし書の違法性により青葉エステート,ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンス向け貸出金に係る償却・引当の不適切性並びに※7なお書の違法性により第一ファイナンス向け貸出金に係る償却・引当の不適切性が明らかとなる(これらの会社の経営状況については,前記第3の1ないし3のとおり)。
(2) 償却・引当の不足額
平成10年3月期決算においては,有楽エンタープライズ及びビルプロ3社につき上記計429億8900万円,青葉エステート外5社につき計354億0400万円,第一ファイナンスにつき332億5500万円,その合計金額1116億4800万円の償却・引当不足が生じている。
すなわち,平成10年3月期決算においては,原告の有楽エンタープライズ外10社に対する貸出金に関し,損益計算書の貸倒引当金繰入額を合計1116億4800万円過少に計上し,その結果貸借対照表上の貸倒引当金を同額過少計上して,あたかも剰余金が460億1400万円であるかのような粉飾が行われたが,実際は剰余金がマイナス656億3400万円であり,法令上配当可能利益は皆無であった。
なお,第一ファイナンスに関しては,同期決算において,債務超過額137億4800万円,同社の100パーセント子会社2社の債務超過額から子会社2社において計上していた貸倒引当金を控除した28億6600万円及び同社保有の有価証券含み損313億4100万円の合計479億5500万円に相当する額が,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のⅣ分類に当たるものであり,実際の引当額147億円と,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のうちⅣ分類に当たる479億5500万円との差額332億5500万円が償却・引当不足額となる。
第5 各被告ごとの責任原因事実
1 本件決算配当について
(1) 被告A,D,E,B,Cについて
上記被告らは,平成10年5月25日開催の取締役会において,既述のように違法な本件期末配当にかかる利益処分計算書案を定時株主総会に議案として提出することを全員一致で決議し,その結果,同株主総会の承認を経て,平成11年6月3日までの間に,合計金71億7233万6392円の配当がなされたものであるから,上記被告らは,商法266条第1項第1号,同第2項により,同額を弁済すべき責任を負う。
(2) Fについて
ア Fの善管注意義務及びその違反
Fは,平成元年6月から平成10年4月1日まで,計算書類(損益計算書,貸借対照表及び利益処分計算書案)の最終作成権限を有する原告の取締役会の一員であった。そして,取締役は,法令及び定款に従い会社の財産及び損益状況を正しく表示した貸借対照表,損益計算書等の計算書類を作成する義務が課せられている(商法281条,同285条の4第2項,なお同281条の3第2項3号参照)。したがって,Fは,平成10年4月1日に取締役を退任するまで,原告の取締役として,資産査定通達等の「公正なる会計慣行」に従った自己査定基準等を策定するとともに,同基準等を正しく適用させ,本来必要な償却・引当を行うべき義務を負っていた。
ところが,自己査定基準策定目的の違法性で述べたとおり,Fは,原告の不稼働資産額の実態及び原告が平成10年3月期決算において本来必要な償却・引当ができない状況であることを十分に認識した上で,償却・引当財源内に圧縮すべく,本来必要な償却・引当を回避するような自己査定基準及び償却・引当基準の策定を提唱したものである。しかも,この提唱に沿った自己査定基準の具体的策定作業は,Fが実質的統括責任者であった事業推進部が中心となって行っており,Fは,適宜事業推進部担当者から報告を受け,指示・助言を与え,原告の違法な自己査定基準等策定に大きな影響力を有していた。そのうえ,実質的に,本件決算配当の実施を決定した平成9年11月11日,同月17日及び同月21日の各常務役員連絡会に出席して本件
決算配当の実施方針を了承するとともに,関連親密先の不稼働資産の償却・引当を合計2813億円に止めることを実質決定した平成10年3月23日の常務会に出席し,その方針を了承したものである。
上記一連の行為は,取締役として本来必要な償却・引当を行うべき義務に明らかに反するものであり,その結果として,平成10年3月期において配当可能利益があるとして,本件決算配当がなされるに至ったのであるから,同被告は,本件期末配当に関し,商法266条1項5号,254条3項により損害賠償責任を負うものである。
イ Fの主張に対する反論
Fは,①原告の自己査定基準等の適法性を主張するとともに,原告ら主張の各会議(平成9年11月11日の会議,及び同月17日の常務役員連絡会,平成10年3月23日の常務会)への出席は,直ちにFの善管注意義務違反を構成するものではない,②Fは,平成10年3月31日に原告らの取締役を辞任し,本件決算配当を決議した定時株主総会開催時(平成10年6月25日)及びそれに先立つ決算手続には一切関与しておらず,取締役在任期間中の言動を善管注意義務違反と評価しこれに期末配当による損害賠償責任を認めるためには,違法配当に故意が認められる場合に限られるべきであり,Fには,故意に違法配当を行う意思はなかったとして,在任中に善管注意義務違反はなく,かつ在任中の言動と退任後の決算に基づく配当との間の
因果関係も存しない,と主張する。
この点,上記①については,そもそも原告の自己査定基準等の内容(適用先の選定も含む)が違法か適法かの問題に帰着するが,その点については,前記のとおりである。また,原告ら指摘の各会議はいずれも本件期末配当実施の分水嶺ともいうべき重要な会議であり,原告の自己査定基準等の策定内容が違法と評価される限り,当該会議においてその方針を了承することが同被告の善管注意義務違反を基礎付けることは論を待たないというべきである。
また,上記②については,Fが平成10年4月以降の狭い意味での決算手続に参加していないからといって,Fが商法266条1項5号の責任が否定されるものではなく,本件決算配当の経過及びその間のFの果たした役割・内容にかんがみれば,Fの取締役在任中の言動,活動が,違法な本件決算配当実施に大きな影響を与えたことは明らかであり,損害との因果関係が認められることも明白である(この点について,刑事事件一審判決もFの違法配当罪を認定しているところである。)。
なお,Fは,損害結果と善管注意義務違反との間に因果関係を認めるためには,違法配当に故意が認められる場合に限ると主張する。この点,善管注意義務違反について,前記第2の2のとおり,Fの故意を認めることができることは明らかであるが,故意も過失も全くないというならばともかく,違法配当の故意がない限り結果との因果関係は認められない理屈はそもそも理論的に成り立たない主張である。
(3) 商法266条1項1号の法的性質論
ア 商法266条1項1号は無過失責任であること
商法266条1項1号の法的性質論に関し,違法配当を無過失責任と解すべきである。
すなわち,仮に一般の過失責任と解するならば,過失を前提とする具体的責任原因事実が規定されるはずであり,この点,例えば,株主権行使への利益供与(同項2号),他の取締役との利益相反行為についてはその旨の規定があるが,違法配当の場合,このような具体的違法な責任原因事実は規定されないまま,商法290条1項違反の利益配当議案を総会に提出したことのみをもって連帯弁済責任の根拠とする。このように,商法が配当議案の総会提出という抽象的,定型的な取締役の職務行為を弁済責任の根拠とし,当該取締役の違法配当議案の策定,決算案の取締役会承認といった具体的責任原因の内容を特定しないまま,一律に連帯弁済責任を要求しているのは,そもそも株主等への不当利得返還請求権の行使による損害の完全な回復は困難
であるゆえ,資本維持の必要上政策的に取締役に対し無過失責任を課したものである。
この点,被告らは,商法改正経緯,状況を挙げて,商法266条1項1号は一般の過失責任である旨主張するが,平成14年の商法改正の際,委員会等設置会社における執行役の違法配当責任について,後記のとおり,過失の有無の立証責任の転換がなされたが,一般の事業会社については,商法266条1項1号は特に改正されていない。しかも,衆議院及び参議院において,委員会等設置会社とそれ以外の会社との間で,規定が異なることの合理性に留意しつつ,引き続き検討する旨の附帯決議が付されていることからも,本件決算配当時点において,商法266条1項1号が無過失責任であると理解されていたことは明らかである。
イ 仮に,無過失責任でないとしても,被告らの主張する通常の過失責任ではなく,取締役が自己の無過失を立証した場合違法配当責任を免れるという立証責任転換規定にすぎないが,本件決算配当への関与について,被告らが無過失であったとはいえない。
(ア) 過失責任説と立証責任の転換
仮に,違法配当責任が無過失責任でないと解釈したとしても,それは立証責任の転換と結びついた過失責任に止まり,被告らが主張するような通常の過失責任(主張・立証責任は原告らに属する。)ではない。
すなわち,商法266条1項1号の責任を過失責任と解しても,違法配当議案の提出又は違法中間配当の実施が認められる限り,取締役に過失があることが推定されること,見通しを誤った中間配当の場合の293条ノ5第5項ただし書との対比から,無過失責任の立証責任は取締役に課すべきである。
(イ) 本件決算配当と被告らの無過失の不存在
以上のとおり,仮に商法266条1項1号が,過失責任を定めたものであるとしても,その主張・立証責任は,被告ら取締役にある。しかし,被告らは,自らの無過失についてほとんど説得力のある主張・立証を行っていない。
(ウ) 各被告の過失を基礎づける事実
a D,E及びF
上記被告3名は,原告の中枢経営陣として,違法な本件決算配当の決定における中心的な役割を果たしていた。これは,上記被告3名が違法配当に係る刑事責任を追及され,刑事第一審判決において,有罪とされていることからも明白である。
b Bについて
Bは,平成7年1月から平成10年8月まで常務取締役の職にあったが,①平成7年8月22日の大蔵省検査の対策会議や平成9年12月15日の長銀再生プランの会議に出席し,原告の処理すべき不稼働資産が1兆円以上あることを認識していたこと,②平成9年4月28日付けで事業推進部が分類資産額及び要償却・引当額を可能な限り圧縮し得る自己査定基準,償却・引当基準の試算を行った資料を検討し,検討チームの所管担当役員として同年5月23日開催の常務会に最終答申を提出していたこと,③平成10年4月24日開催の経営会議に出席し,平成10年3月期において,不稼働資産処理として不十分である旨の議論がリスク統括部長から出されたのを認識していたことから,Bの過失は明らかである。
c Cについて
Cは,平成9年当時,常務取締役の職にあったが,①同年5月23日開催の常務会には欠席したものの,配布資料である自己査定プロジェクトチームの最終答申を事後的に検討していたこと,②同年度の決算方針を再確認した同年11月12日及び同月21日開催の常務役員連絡会議に出席し,原告の不稼働資産が1兆円規模であるにもかかわらず,「配当先にありき」の方針が採用されたことを認識していたこと,③同年12月15日の長銀再生プラン会議に出席し,原告の処理すべき不稼働資産が1兆円以上あり,自己資本比率8パーセントを維持するという方針の下,本件決算配当に変更がないことを認識していたこと,④平成10年3月31日開催の常務会に出席し,総合企画部作成の「97年度決算着地見込み」と題する資料の説明を受
け,全体で6000億円程度の不稼働資産処理となる予定の報告を受けていたことから,Cの過失は明らかである。
d 被告Aについて
被告Aは,平成3年4月以降原告取締役会長の職にあったが,①昭和55年6月以降,常務取締役,取締役副頭取,取締役副会長等,原告の経営中枢部におり,原告がバブル経済に狂奔し,平成2年4月の大蔵省の総量規制実施後バブル経済が崩壊した結果多額の不稼働資産を抱えるに至った事情等を熟知していたこと,②取締役会長として,原告の経営会議・取締役会に出席しており,多額の不稼働資産処理を適法に進めるべく監視・監督する当然の義務と権限を有していたこと,③特に平成10年4月28日開催の臨時経営会議において,鈴木リスク統括部長が,平成10年3月期の自己査定額は約6500億円も少なく査定されているとして,同期の償却・引当額に,少なくとも約4000億円ないし約5000億円を加えるべきことを進言
したにもかかわわらず,これを黙殺し,同日開催の同年度決算を了承したことから,被告Aの過失は明らかである。
第6 本件中間配当について
1 中間配当における賠償責任成立の要件と本件争点
商法293条の5第4項,第5項は,違法な中間配当における損害賠償の責任を定めているところ,本件では,平成9年9月期中間配当について,これを承認した同年11月25日開催の取締役会決議の時点において,平成10年3月期決算で配当可能利益がない状態を生ずる「おそれ」が客観的に存在していたにもかかわらず,被告らは当該中間配当を行ったか否か,②被告らは当該予測を誤ったことについて過失がなかったか否かが問題となる。
2 争点①(本件中間配当に関する平成9年11月25日開催の取締役会決議の時点において,平成10年3月期に配当可能利益がない状態が生じる「おそれ」が客観的に存在していたか)
この点については,そもそも本件決算配当(平成10年3月期)が,平成9年9月期中間決算後の事情により突然生じたものではなく,原告内部において平成9年度中間期以前から少なくとも約8000億円ないし約9000億円の要処理不稼働資産が存在し,これにつき適正な償却・引当をすれば配当可能利益が皆無であるため,平成10年3月期の自己査定制度導入に合わせて1年以上も前から,不適正な自己査定基準・償却・引当基準が検討・策定されていたものである。したがって,平成9年11月25日の取締役会決議の時点において,平成10年3月期決算で配当可能利益がない状態を生ずる「おそれ」が客観的に存在していた。
3 争点②(本件中間配当に関する取締役会決議(平成9年11月25日)時点において,平成10年3月期末には,配当可能利益があると認識したことについて無過失であったか)
本件中間配当と本件決算配当の関連性からすれば,同期末に配当可能利益が不存在であったのに,平成9年11月25日の時点でその「おそれ」を誤ったことについて被告取締役らに過失がなかったということは事実上あり得ない。
(1) 本件中間配当決議当時の状況
ア 原告内部における1兆円近くにも及ぶ不稼働資産の存在及び被告らの認識状況
原告における不稼働資産が増加し,これが1兆円にも達することは,平成7年の時点で,Dらは認識し,平成9年11月25日の取締役会以前の各種会議においても事業推進部等関係各部から,これを示す関係資料が,数多くD,E,F,G及びHに提出されていた。
イ 本件中間決算決定当時における期末決算での配当可能利益不存在の「おそれ」に関する認識状況
平成9年度決算方針を実質確認した同年11月11日のDらによる会議に,総合企画部から提出された資料には,「今期配当維持」と「今期無配覚悟」の2つの選択肢が記載され,仮に無配として赤字決算を組んでも「但し,BIS比率8パーセント維持の観点からの赤字許容額は,3600億円程度」であって不稼働資産の完全処理は不可能であった。そこで,Dらは,スイス銀行からのファイナンス実施方針や原告の信用維持等を考慮し,同年度配当維持方針を実質決定した。
そして,この方針は,同月11日から同月21日までの間のファイナンス実施の先送り及び株式会社富士銀行の中間配当見送りという状況の変化にもかかわらず,同月21日の常務役員連絡会において,本件中間配当実施の方針が再確認された。
(2) 各被告の関与・認識状況
ア D,E及びF
上記被告3名は,平成9年11月11日の会議に出席し,この会議においてファイナンスを実施するためにも無配の選択肢は採れない旨のDの発言にE及びFも同意している。また同月21日の常務役員連絡会において中間配当実施方針を再確認している。
イ Gについて
総合企画部長であったGは,中間配当及び期末配当の方針に関する総合企画部資料を作成し,平成9年11月7日,部下とともに同月11日の会議のためこの資料をDに事前説明している。また,当然,同月11日の会議にも参加していたものである。
ウ Hについて
事業推進部長であったHは,平成9年5月9日,平成10年3月期の不稼働資産処理及び決算方針について,D,Fらとの会議に臨んだ。この会議では,事業推進部からは検討中の自己査定基準に基づく償却・引当見込額に関する資料,総合企画部からは,様々な考え方に基づく不稼働資産処理をシミュレーションした資料が提出され,要償却・引当額の更なる圧縮が可能な自己査定基準を作るべきことがFから指示された。
その後,自己査定トライアル実施を受けて,Hは,平成9年度決算方針について,F,Gらとの会議に出席した。この会議において,Hは,事業推進部の担当者に対し「(不稼働資産が)が現状実態ベースではなお8000~9000億円残っており,年間5000億円では依然財源不足である」と説明を行わせており,Hは,自己査定基準に基づく同期の償却・引当額は原告の不稼働資産の実態に即していないことを認識していた。
(3) 無過失に関する被告らの主張について
被告らは名目上予備的主張として「無過失」について様々な主張を行っているが,本件中間配当時と本件決算配当時の各時点において,原告の資産内容が一変(悪化)したというようなことはなく,実質的に,自己査定基準等に違法性はないから,その策定検討段階,自己査定トライアルに基づく本件中間配当及び本件決算配当の実施方針には過失はないというにすぎず,いずれも争点②の固有の主張となり得ない。
(4) 小括
以上のとおり,本件中間配当に関し,D,E,F,G及びHは,商法293条の5第5項により,原告ら請求額について連帯して賠償責任を負うものである。
以 上
別紙2 被告らの主張
第1 「公正なる会計慣行」(商法32条)の意義・内容
原告らは,資産査定通達等の趣旨を逸脱することが単なる通達違反ではなく,平成14年改正前商法285条の4第2項違反であると主張するために,商法32条2項を媒介にして,「資産査定通達等が平成10年3月当時,唯一の公正な会計慣行となっていた」と主張する。
これに対し,被告らは,上記主張の大前提となっている資産査定通達等(資産査定通達,4号実務指針,9年事務連絡,全銀協Q&A及び全銀協追加Q&A)が「公正な会計慣行である」ことを否認し,その余の点を検討するまでもなく,原告らの主張が失当であることを主張するものである。
1 「公正なる会計慣行」の意義,要件
公正な会計慣行と認められるためには,その会計手法が,①多くの者に②長年受け入れられてきたという事実ないし実績が必要である。①,②の要件を欠く中で,ある会計処理を直ちに,唯一の採り得る会計手法にするためには,立法によってこれを強制するしかない(その場合は,その会計手法が「公正なる会計慣行」になったのではなく,法律によって排他的な会計処理基準が定められたということである。)。
(1) 商法32条2項の立法趣旨
商法32条2項は,公認会計士の監査を会計監査人の制度として商法に導入するに当たり,その監査基準が,証券取引法と商法で一致しない場合に生ずる不都合を防止するため,商法と証券取引法との間における監査基準の根拠となる商業帳簿に関する規定の解釈を一致させる必要があったことから,昭和49年の商法改正により設けられた。その趣旨は,商業帳簿の作成に関する規定として,詳細かつ網羅的な規定を設けることは困難であり,また会計技術の進歩の迅速性にかんがみ,常に法規が対応していくのも困難であることから,商法には,基本的かつ重要な規定を設けて,それ以外の点について,「公正なる会計慣行」により,これを解釈し補充してゆくことが妥当であるというものである。
(2) 会計慣行の意義
このような商法32条2項の趣旨に照らすならば,「会計慣行」は,「事実たる慣習」(民法92条)と同義であり,一般的に広く会計上の習わし(慣習)として相当の時間繰り返し行われている会計処理の基準を指すと理解すべきである。
また,仮に「会計慣行」が会計上の「慣習」よりも広い概念であるとしても,従来一度も行われたことのない会計処理方法又は基準(新基準)が「会計慣行」と認められるためには,①新基準が法規範性を有するルールとして適用されることが関係者にとって明らかとなっていること,②新基準が実務に適用し得る程度に明確性を有していること(ないしは解釈についての共通認識が確立していること)が必要と解すべきである。
したがって,行政庁が,通達,事務連絡等を発出したことのみをもって,それが「会計慣行」となるものではなく,特に,公権力による一時的な政策的要請に基づく通達や事務連絡等の行政指導によって,従来存在しなかった基準をドラスチックに導入して,既存の基準に重大な変更を加え,あるいは未実施の基準を導入することで対象企業に過度の負担を強いる場合に,このような基準が直ちに「公正なる会計慣行」に該当すると解することは,経済社会における関係者の合意を本質とする「会計慣行」の概念に矛盾すると解すべきである。
(3) 「公正」の意義
商法32条2項の「公正」の意義は,当初,立法担当者等が「公正なる会計慣行」に該当していると解していた企業会計原則の中において,「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められるところを要約したもの」と定義され,経済社会において広く慣行として行われ,これがその社会の中で一般的に「公正妥当」なものとして受け容れられていたことからすると,経済社会において,関係者間で「公正」と評価され普遍性を獲得したものを指すと解すべきである。
したがって,「早期是正措置」とか「不良債権の早期処理」という公権力による一時的な政策課題を実現するための要請とは全く次元を異にする概念である。
(4) 「斟酌すべし」の意義
商業帳簿の作成に関する商法の規定の解釈に当たり,「公正なる会計慣行」としての企業会計原則を考慮すべきであるが,常に同原則に従った解釈をしなければならないものでなく,同原則以外に合理的な会計慣行も存在し得るから,このような別の会計慣行が存在する場合に,企業会計原則を考慮して,別の合理的と認められる会計慣行を採用することも可能であるということである。
これは,商法32条2項の立法過程において,最終的に「斟酌」という文言が採用された根拠として,①「依拠して」とした場合,当時,企業会計原則及び同注解は種々な分子を混入しており,商法の解釈指針としてそのまま採用するには整備が不十分であると考えられたこと,②「準拠しなければならない」と規定すると,必ず企業会計原則に従わなければならないと解釈される余地が生じ,いわば行政官庁の諮問機関である企業会計審議会に白紙委任するに等しく,立法作用として疑問があると指摘されていたことが挙げられていたことにも合致する解釈である。
これに対し,原告らは,「公正なる会計慣行」が一つしか存在しないことを前提とした主張をしているが,会計慣行は一つとは限らず,併存する複数の会計慣行が存在することもあり,この場合,いずれを採るかは企業の選択に委ねられ,仮に会計慣行が一つしかない場合であっても,これによらない正当な理由があるときは,これと異なる処理も許されるから,原告らの主張は失当である。
2 銀行業における貸出金の償却引当に関する会計慣行(税法基準)の存在
(1) 従来(早期是正措置の導入前)の銀行の貸出金に対する償却・引当処理の内容
平成9年3月当時,銀行業界では,大蔵省銀行局長通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」(昭和57年4月1日蔵銀第901号)の別紙第5の「決算経理基準」(改正前決算経理基準)が発出されており,各銀行は,具体的な償却・引当及び損金処理は,これを基準としていた。
ア 法人税法による一般の貸倒引当金
改正前決算経理基準は,一般の貸倒引当金について「税法で容認される限度額を必ず繰り入れる」と定めており,銀行は,法人税法に基づき,貸出金に対して,定率(法人税法施行令において,銀行の貸倒引当金の上限は1000分の3とされていた。)を乗じて算出した額の貸倒引当金を計上していた。
イ 債権償却特別勘定による繰入れ,不良債権償却証明制度
改正前決算経理基準は,債権償却特別勘定について,債権償却特別勘定への繰入れは,「税法基準」によるものと定めていたところ,債権償却特別勘定の繰入れに関する「税法基準」に関しては,法人税基本通達9-6-4ないし同9-6-6において詳細に定められていた。
この点,同9-6-4は,「債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し,事業好転の見通しがない」ため,「当該貸金の額の相当部分の金額につき回収の見込みがないと認められるに至った場合」には,「その回収の見込みがないと認められる部分の金額」につき,所轄税務署長の認定を受けて損金処理により債権償却特別勘定に繰り入れることができる(繰入額が損金となる)ものと定めていた。上記貸倒損失の認定について,金融機関の貸出金の場合には,税務当局ではなく,大蔵省大臣官房金融検査部(以下「金融検査部」という。)の金融証券検査官が回収不能又は最終の回収に重大な懸念があり,損失の発生が見込まれる貸出金であることを証明した金額に限り,税務上も損金として無税で経理処理することが認められてきた。これが不
良債権償却証明制度である。
この不良債権償却証明制度の下では,有税引当等についても「決算経理基準」等によりその内容を当局に提出するものとされていた。そして,この届出の受理に当たり,金融機関の自主判断により行われるものであることに留意するとされ,また,有税引当等については,決算経理基準等に基づき金融機関の自主判断により行われるものであるから,届出書の受理に当たっては無税償却の適用がないかどうか等について聴取するものとすると定められていた。従来,税効果会計等の有税処理の不利を緩和するための措置が採られていなかったため,銀行の不良債権の償却・引当は,「税法基準」により無税処理の要件を満たすものを中心に行われており,不良債権償却証明制度の下でも,有税による償却・引当が「金融機関の自主判断」により行われる
ことに留意するよう求めていた。すなわち,この当時金融機関における実務の取扱いは,原則として無税処理の要件を満たすものについてのみ処理が行われ,有税による償却・引当はあくまで金融機関の自主判断により行われるものであり,これが「公正なる会計慣行」となっていた。
ウ 支援先に対する取扱い
(ア) 法人税基本通達9-4-2
銀行の関連ノンバンク等支援先に対する支援損の計上に関する基準としては,法人税基本通達9-4-2(平成10年6月1日改正前)において定められ,これが銀行業界における会計慣行となっていた。
この趣旨は,業績不振の子会社等の倒産を防止するために,法人がやむを得ない措置として合理的な再建計画を策定し,これに基づいて新たな融資を行う必要がある場合には,その融資が無利息又は低利で行われたとしても,それは経済合理性を有しており,単に無利息又は低利というのみで,直ちに寄附金として取り扱うことは実態に即しないことから,上記通達により,税務上も正常な取引条件に従って行われたものと取り扱い,寄附金としての認定課税をしない旨を明らかにしたものであった。
同9-4-2は,実務上,既存債権について債権放棄を行う等の方法で子会社の財務体質の抜本的な改善を図る場合についても適用されていた。その後,平成10年6月1日の通達改正で,再建支援のための債権放棄等を寄附金としない旨明確化されたが,その前後を通じ,債権放棄等による関連親密先に対する支援額が損金として計上される点で特に変化がなかった。
(イ) 支援先に対する9-6-4該当性(回収不能の見込みがないこと)
このように,関連ノンバンクに対する支援損について,「税法基準」の法人税基本通達9-4-2による処理が行われる反面,同9-6-4の不良債権償却証明制度による処理を適用しないのが実務の取扱いであり,不良債権償却証明制度において,同9-4-2は列挙されていなかった。また,同9-6-4の適用に当たり「債務者に対して追加的な支援を予定している場合」には,原則として同9-6-4の「事業好転の見通しがない」と判断することは適当でないとされていた。
これは,銀行が再建を支援している積極支援先について,貸出金を延滞していないことが通例であり,法的破綻にも至っていないため,貸出金が回収不能となることは考えられず,「事業好転の見通しがない」と判断することも許されなかったことに基づくものである。不良債権償却証明制度による償却・引当の対象先は,ほとんどが法的破綻先であり,積極支援先について,母体行が単独で償却証明を得ることはおよそ考えられないことだった。
また,銀行が積極支援しながら,当該支援先に対する貸出金について回収不能であるとして有税引当することは,自己矛盾であるとか背任的な行為となるおそれがあるとの指摘がされており,これは,大蔵省における一般的な見解であり,かつ,銀行の実務であった。
(ウ) 将来分の支援損に対する引当等
上記(ア)のとおり,銀行は,関連ノンバンク向け貸出金について,法人税基本通達9-4-2により,国税当局から無税承認を受け,当期において,確定した支援損の額(債権放棄等の額)を計上していたが,翌期以降の支援予定額については引当を行うべき義務は存在せず,原則として引当を行わないものとされていた。
(2) 「税法基準」に従った処理が貸出金の償却引当における「公正なる会計慣行」であること
ア 税法基準が「公正なる会計慣行」とされる根拠
銀行が行っていた前記(1)の貸出金の償却・引当に係る処理は,①改正前決算経理基準の規定の存在,②長期間にわたり,同規定による会計処理の実務が積み重ねられていたこと,③会計士協会も,昭和40年4月6日以降,「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(以下「委員会報告第5号」という。)において,税法基準により貸倒引当金の計上がなされれば,除外事由としない(適正意見を付す)こととし,また,「銀行業統一経理基準及び財務諸表様式に関する監査上の取扱い」(昭和51年9月)のなかで,長年の実務において積み重ねられてきた実態を踏まえ,税法基準が会計慣行となっているとしていることから,商法32条2項における「公正なる会計慣行」となっていた。
他方,原告らは,平成9年3月期決算以前において,無税による償却・引当のみを行えば足りるとする会計処理が「公正なる会計慣行」になっていたといえない旨主張し,その理由として,①税法基準が租税収入の確保という政策的視点に立って,税額の計算をし,課税の公平を図ろうとする目的で策定されたものであること,②法人税基本通達9-6-2及び同9-6-4が,無税で貸倒償却・引当できる場合を限定しているのは,いずれも損失の計上について確定的なものを求める税法固有の目的に由来するものにすぎないこと,③他方,商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営実績を正しく表示しもって株主及び会社債権者の利益の保護を図ったものである以上,税法基準による会計処理方法が,商法上当然に適法なものであるといえないこ
とを挙げる。
しかし,「公正」とは抽象的な概念であり,かつ,絶対的なものではなく,社会経済の状況や企業会計の理論の発展状況に応じて変化するものである以上,実際に行われている会計処理の実務は,原則として,その時点における社会経済の状況や企業会計の理論等を反映していると考えられていることから,現実の会計実務の状況を確定し,そのうえで,正当性又は合理性を検討すべきである。そして,税法基準は,銀行の貸出金に対する償却・引当に係る一つの会計慣行として存在したものであり,銀行の貸出金に関する償却・引当の処理の実務として定着していたというべきである。
イ 原告らの主張に対する反論
原告らは,①改正前の決算経理基準が,有税による貸出金の償却・引当に関する定めを置いていたこと,②平成6年2月の不良債権償却証明制度実施要領通達の一部改正では,金融機関における不良債権処理を促進する目的から,無税による償却・引当だけでなく,有税による償却・引当制度の円滑な活用を図るためにその取扱いを整備したことに照らすと,平成9年3月期決算以前において,無税による償却・引当を行えば足りるとする会計処理が『公正なる会計慣行』になっていたと解することはできないと主張する。
しかし,改正前決算経理基準が有税による貸出金の償却・引当に関する定めを置いていたからといって,それはそのような方法も選択肢の一つであったということにすぎない。
そもそも,我が国の企業会計は,商法,証券取引法,税法の各規制が相互に影響又は牽制するいわゆる「トライアングル体制」であり,税法が企業の確定した決算を前提に法人税の納税義務を決定する(いわゆる確定決算主義)としていると同時に,企業決算も税法の運用を前提にした内容で確定され,両者は密接な関係をもっていた。
貸出金の償却・引当について税法上損金として認められるか,又は損金性を否認されて償却・引当部分につき法人税が課税されるかどうかは,銀行の決算内容に大きな影響を及ぼす。 仮に法人税の負担を50パーセントとすると,有税の場合は無税の場合の2倍の財源を要することになり,有税処理による損失計上は,無税処理の場合と比べて確実に銀行の決算内容を悪化させ,取締役の善管注意義務違反の問題を生じさせるおそれもあった。さらに,仮に,無税処理が,後日,税務当局から否認されれば,高率の加算税を含めた莫大な予算外負担が生じて経営を危殆ならしめるリスクがあった。
したがって,企業経営者は,軽々しく有税償却を行うことができなかった。特に,税効果会計が存在しなかった時点において,不良債権を確実に無税で処理できるかどうかは銀行経営上大きな関心事であった。このように,改正前決算経理基準の下,銀行の不良債権の償却・引当が,税法基準により,無税処理の要件を満たすものを中心に行われていたことは厳然たる事実であり,これを違法であったとか公正でなかったとか非難するのは現実から遊離した議論である。
また,委員会報告第5号は,「企業が算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積額に対して明らかに不足していると認められる場合を除いては,除外事項としないことができる」と規定していた。これは,金融機関において「税法基準」が「公正なる会計慣行」となっていたことを示す重要な証拠の一つである。
3 資産査定通達等による改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」と認められない理由
(1) 早期是正措置制度により,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となり得るものではないこと
早期是正措置制度は,経営の健全性確保のための金融行政当局による「監督手法」であり,その目的は専ら銀行法26条1項及び2項の定める経営改善計画提出命令,増資計画の策定等の個別措置及び業務停止命令等の措置を自己資本比率という客観的な基準により「適時」に発動できるようにすることにあったから,金融機関の不良債権を「早期」に処理するための制度でなかった。
したがって,経営改善計画の提出,個別措置あるいは業務停止命令を発動することが最大限なし得る処分であり,銀行がその処分に従わなかった場合には,銀行法28条により,業務停止命令,取締役・監査役解任命令,又は免許を取り消すことがあり,刑事処分としては同法62条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰を受けることが予定されていた。しかし,それが限界であり,これを超える制裁が定められていたものでもなく,必ずしも不良債権を「早期」に処理するための制度ということもできないし,さらに商法上の償却・引当その他の資産評価のあり方を変更するものともいえないものであった。
なお,自己資本比率の基準の策定は,銀行法14条の2により,大蔵大臣に与えられた権限であったが,これは同条に「銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準」という文言が使用されていることから明らかなとおり,銀行経営の健全性の判断の基準を定めるものであり,これを超えて商法上の会社の償却・引当等資産評価の基準を変更する趣旨を含んでいなかった。
そもそも,自己資本比率基準制度は早期是正措置導入より5年も前の平成5年に始まったものであり,時期的にみても,それが当時の商法285条以下の資産評価の基準を所与の前提としていたことが明らかであった。
また,平成6年10月に施行された行政手続法の趣旨からしても,早期是正措置制度上の施策は銀行法及び同施行規則等の法令に基づいて執行されるべきであり,安易に通達等の行政指導に依存したり,所掌事務の範囲を逸脱することは許されなかった。当時の金融検査部の所掌は,銀行法上の調査権及び検査権に基づく金融検査に関する事項にとどまるものであり(これに対し,早期是正措置の発動は,銀行局の所管であり,金融検査部には何の権限もなかった。),これを超えて商法上の資産評価の基準に関する事項(所管は法務省)を含まないことも明らかであった。
(2) 改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」となり得ない根拠等
ア 「公正なる会計慣行」たり得るものは,償却・引当額の算定・計上に当たっての具体的な会計処理の基準であり,抽象的な規範を示すにすぎない「決算経理基準」が,具体的な会計処理の基準となり得るものではないから,「決算経理基準」という通達上の文言が改正されたとしても,その改正後の通達上の指針が直ちに「公正なる会計慣行」となるわけではない。これは,商法32条2項の立法趣旨について「改正商法及び監査特例法等の解説」が,「企業会計原則が会計慣行と関係なく修正された場合,その修正部分がただちに会計慣行となることはない」と述べていることからも明らかである。
そもそも,「決算経理基準」は行政監督権を有していた大蔵省の通達にすぎず,それが銀行業界において決算の基準として広く行われてきたのは,いわゆる指導行政の下,その指導に従うことが事実上強制され,銀行業界もこれを広く受け入れ,毎年の決算でもその基準に従い処理されてきた結果,それが「公正なる会計慣行」と認められるに至ったことによるものである。よって,このような通達の改正すなわち「税法基準」の文言が削除されたことのみから,直ちに改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」となり得るものではなく,その通達に示された会計処理が,「公正なる会計慣行」となるための要件を満たすことが必要であり,反復・継続されていない会計処理の基準が「会計慣行」となるものではないのである。
改正前決算経理基準が1つの会計慣行として取り扱われていた主たる理由は,監督官庁から銀行に対する指示を行う通達であるからということではなく,既に発出から相当期間が経過し,また,各銀行において統一的な会計処理の基準として採用されていたことにあった。決算経理基準の内容に大きな変更が加えられた以上,少なくとも変更された部分については,上記と同様の段階に至るまでは,「公正なる会計慣行」として取り扱うべきではない。これは,改正後決算経理基準において,①自己査定基準の策定について,拠るべき基準として商法,企業会計原則等を挙げた外,「決算経理基準をも勘案し」という控えめな表現を用いた(決算経理基準に「従う」ことまで求めなかった)こと,②自己査定のあり方について「当局として望まれる自
己査定のあり方は,別紙1『資産の自己査定のあり方について』のとおり」という表現を用い,これがガイドライン的な性質のもので,法規範の定立ではないことを明確にしたこと,③資産の評価について,上記自己査定のあり方がガイドライン的なものであることを前提として,「自己査定結果を踏まえ」たうえで,商法,企業会計原則等及び決算経理基準に定める方法に基づき「各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施する」として,各行の自主性を尊重する方針を明らかにしたことからも明らかである。
また,決算経理基準を含む大蔵省の通達は,その後平成10年6月に通達をもって廃止され,その後,同様の内容のものが同年9月になって全銀協から各銀行に通知されたが,同通知本文においては「この基準によるほか,一般に公正妥当と思われる会計処理については,各行の判断で会計監査人と協議の上処理を行われますようご案内申し上げます」との記述があり,これは複数の会計処理方法が存在することを前提に,必ずしも同通知の内容に従った会計処理が行われなくとも,各行の自主判断及び会計監査人と協議の下で公正妥当と思われる会計処理が行われることを容認する内容のものであった。
イ 原告らは,資産査定通達等が改正後決算経理基準の内容を補充するものであると主張する。
しかし,資産査定通達等と改正後決算経理基準との間には,発出主体が相違し,これを無視して「補充」関係を認めることはできない。すなわち,改正後決算経理基準は大蔵省銀行局長が傘下の金融機関に宛てて監督行政の一環として発出したものであり,資産査定通達は大蔵省大臣官房金融検査部長が金融証券検査官等あてに発出したものであり,4号実務指針は会計士協会が会員あてに発した指針であり,9年事務連絡は大蔵省の管理課長が金融証券検査官あてに出したものであり,全銀協Q&A及び全銀協追加Q&Aは全銀協が会員あてに発出したものであった。よって,大蔵省銀行局長が発出した改正後決算経理基準について,明文の規定もなしに,金融検査部長や管理課長,会計士協会及び全銀協が発出した文書がこれを「補充」すること
はあり得ない。なお,改正後決算経理基準(を含む大蔵省通達)は,平成10年6月8日の廃止通達(蔵銀第1443号)によって廃止されたが,資産査定通達は,平成11年7月1日付「預金等受入金融機関に係る検査マニュアルについて」通達(金検第177号,金融監督庁検査部長発出)が発出されるまで存続しており,これは,資産査定通達が,形式的にも実質的にも銀行に対する指示文書としての性格を有さず,まして商法上の規範として銀行を直接的にも間接的にも何ら拘束するものではなかったことによるものであったと理解される。
したがって,改正後決算経理基準において,自己査定基準は「商法,企業会計原則等及び決算経理基準をも勘案して」作成するものとされていたが,「資産査定通達」や「4号実務指針」を基準とすべきことについては全く言及がなかったこと,銀行自身が自己責任において自己査定基準を定めるとされていたこと,「当局として望まれる自己査定のあり方については別紙1『資産の自己査定のあり方について』のとおりであるので留意する必要がある」という表現を用いることで,それが一種のガイドラインであり,銀行に対する新たな法的規範の定立を行う趣旨ではない旨示唆していたことから,改正後決算経理基準が,資産査定通達等により補充されることを予定していた,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」の一部になることを承認して
いたとまではいえない。少なくとも,従来の税法基準を排除してまで,資産査定通達等を取り込むことは予定されていなかったと解される。
ウ 原告らは,「平成9年7月の決算経理基準の改正によって,平成10年3月期においては税法基準が明らかに否定されており,税法基準に基づく会計処理が許されなくなったことは明白である」と主張し,①貸倒償却・引当及び債権償却特別勘定の繰入れについて,改正後決算経理基準において,貸出金等の償却について担保処分前でも処分可能見込額を減算した残額を償却すべきこと,②一般の貸倒金の繰入率が「税法で容認される額」から「合理的な方法により算出された貸倒実績率」に変更されたこと,③債権償却特別勘定の繰入れに関し,「最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については債権額から担保の可能額等を減算した額のうち必要額」を繰り入れるべきことが定められたことを挙げて,要するに従来存在して
いた「税法」や「税法基準」の文言が削除されたことを根拠として挙げる。
しかし,改正後決算経理基準においても,他の箇所には「税務基準」,「税法基準」又は「税法上の準備金」という概念が使用され,その全体をみれば,文言上,税法基準が全て否定されたということは到底いえないことは明らかである。 また,本件訴訟で問題となっている償却・引当の基準は,一般先に関する貸出金の評価及び償却の基準でなく,関連ノンバンク等の支援先に対する損金の計上の基準であり,改正後決算経理基準において「税法基準」の文言が削除されたことのみから,「税法基準が否定された」と即断することはできない。したがって,このような関連ノンバンク等の支援先に対する貸出金の償却・引当の基準について,税法基準を考慮することも当然許容されていたはずである。
エ 原告らは,改正後決算経理基準が税法基準を否定した理由として「税法基準による会計処理が,早期是正措置を導入した根本理由・目的と矛盾ないし反するものであった」ことを挙げ,また「税法基準に基づく会計処理こそ不良債権処理を遅延させていた元凶であった」ことを主張し,このような主張の根拠として,税務に重点をおいた償却が結果的に不良債権処理を遅らせたという意見が早期是正措置検討会メンバーの中にあったこと,税法基準にはとらわれずに,健全性の観点から企業会計原則にのっとった償却を促すことを目的とした早期是正措置の導入を契機に,不良債権償却証明制度が廃止されることになったこと,不良債権償却証明制度の廃止を前提に,税法基準すなわち大蔵省との折衝による無税認定取得という行政裁量性の強い償却
・引当システムという方法を改めたことを挙げる。
しかし,そもそも,早期是正措置の目的が不良債権処理の促進を直接の目的としていたという事実はなく,仮にそのような行政目的があったとしても,その目的の達成のための手段として「公正な会計慣行」を変更するためには,法令の制定が必要であり,単なる行政指導の手法である通達によって実現することは許されないはずである。仮に,このような法令によることなく,通達や事務連絡等の行政指導によって旧来の基準を改廃しようとする場合は,それが企業によって支持され,現実に履践され,商法32条2項の「公正なる会計慣行」として熟成するのを待つほかないというべきである。
オ 原告らは,改正後決算経理基準により税法基準が廃止されたと主張する根拠として,平成10年3月20日付け全銀協作成の「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」の中で「決算経理基準と税法基準とは無関係である」と解説していることを挙げる。
しかし,上記質疑事項は,「改正後決算経理基準の本文にある「債権額から回収が可能と認められる額を減算した残高を直接償却する」という考え方が従来からの会計慣行である法人税基本通達9-6-2の規定の「全額」及び「担保処分後」損金処理することができるとの文言に反することになると考えるが,見解をご教示いただきたい」というものであり,これに対する回答案が「決算経理基準と税法基準とは無関係」であるとされているのは,「決算経理基準」には,債権額から回収が可能と認められる額を減算した残額を直接償却すると定めてあるが,そのとおりに銀行が償却を実施したとしても,その金額は税法上の償却すなわち無税での償却になるとは限らない,税法基準である9-6-2は従来どおり存続しているから,担保処分後で
ないと損金処理(無税償却)は認めない,その意味で「決算経理基準」と税法基準とは無関係であるとの趣旨である。また,この回答案は,かっこ書きで「実務的には,当該決算経理基準の但書により,担保処分後に直接償却することができる」旨記載しているが,この記載の意味は,改正後決算経理基準の当該部分の本文で,「債権額」から「回収が可能と認められる額を減算した残額を償却する」とあるものの,ただし書で「担保が処分されていない等の事情により,償却することが適当でないと判定される貸出金等を除く」と規定し,税法の実務どおり,担保処分後でないと無税償却を認めないことが,改正後決算経理基準についても明らかであることを注記したものである。
以上からすれば,原告らが引用する「決算経理基準における直接償却と税法上の直接償却は基本的に無関係である」との記載は,原告らの主張とは逆に,改正後決算経理基準の下においても,税法基準が変更されることなく存在し,かつ,改正後決算経理基準も税法基準を意識した処理を認めているとの意味を有することが明らかである。
(3) 不良債権償却証明制度の廃止により税法基準が否定されるものでないこと
ア 不良債権償却証明制度の廃止の意義
不良債権償却証明制度の廃止は,早期是正措置制度が導入されることに伴い,改正後決算経理基準において「資産の評価は,自己査定結果を踏まえ,商法,企業会計原則等及び下記に定める方法に基づき各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施する」とされたことに基づく。
すなわち,平成10年3月期以降,各金融機関は自己責任によって自己査定基準及び償却・引当基準を作成し,それらに基づいた処理を行うこととなったが,その際,無税又は有税による処理の選択が,従来の不良債権償却証明制度の下における実務と異なり,各金融機関自身の自己判断に委ねられることとなったものであるが,このような趣旨を超えて,改正後決算経理基準において,各金融機関が税法基準により処理することを禁止されたと解することはできない。これは,現に,法人税基本通達9-4-2や同9-6-4,委員会報告第5号が,平成10年3月期においても特に変更されなかったことからも明らかである。
イ 実体的基準の変更のないこと
また,不良債権償却証明制度の廃止に伴い,「決算経理基準」においての「税法基準」文言が削除されたのであるが,これは,不良債権償却証明制度の手続や償却・引当額の実質的決定主体(従来,金融証券検査官が判定したものが,一般企業と同様に,国税庁の個別認定とされた。)という点での制度変更に応じた手当にすぎず,義務的な貸倒引当,償却の範囲を定める実体面について,何ら新しい基準を定立するものではなかった。
ウ まとめ
よって,平成10年3月期において,税法基準が「公正なる会計慣行」の1つであったこと,少なくとも税法基準に従った処理も複数の会計処理方法の中の1つとして許容されていたものである。
(4) 資産査定通達等の内容,規範性
ア 資産査定通達等のガイドライン性
中間とりまとめには,「早期是正措置の導入に当たり,各金融機関が更に適正かつ客観的に償却引当を行いうるよう,会計士協会より償却引当についての明確な考え方が実務上の指針(ガイドライン)として示されることが望ましい」との記載がなされており,以後実務上の指針について「ガイドライン」との表現を用い,適度の統一性の確保という観点からは,ガイドラインを作成することが必要であるとしたうえ,「自己査定ガイドラインは,あくまでもスタンダードとして位置付けられるべきものであり,各金融機関においては,このガイドラインをベースに,創意工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成することはむしろ望ましい」との記載がなされている。
したがって,資産査定通達等が,各金融機関がそれぞれの実情に沿った自己査定基準を創意工夫して策定する際の,ガイドラインとしての性格を有するものであったことは明らかである。
また,資産査定通達等は,その内容も明確でなく,解釈について共通認識が形成されていたものではないから,平成10年3月期においては会計処理実務における具体的基準として機能するものではなかった。そのため,資産査定通達等は,金融機関の資産査定,償却引当処理においてガイドラインとして用いられた(ただし,9年事務連絡については未公開である以上,ガイドラインとされることもなかった。)のみであり,その結果,各金融機関における自己査定,償却引当処理には,相当程度のばらつきが当然に生じるものであった。
イ 資産査定通達
(ア) 資産査定通達のガイドライン的・トライアル的性格
資産査定通達は,金融機関に対し,自己査定の「適度な統一性」を確保させるためのガイドラインにすぎず,各金融機関は自己責任原則に基づき,各金融機関の実情を踏まえて主体的に創意工夫を発揮して,自主的な自己査定基準を作成することが求められていた。
これは,早期是正措置制度自体が異常な環境下において導入され,かつ,税効果会計等の安全網(セーフティネット)が整備されていない状況下での導入であったため,早期是正措置の導入や自己査定実施のための環境整備に時間がかかることから,一定期間後の見直しが予定されていたことからも明らかである。そのため,導入後初年度の平成10年3月期において,各金融機関は,手探りで自己査定基準を策定し,その2年目以降,金融当局による検査や監査法人との論議等の中で,解釈のコンセンサスが得られ,またガイドラインの改正により解釈の幅が狭まっていくことが予想されたものの,あくまで平成10年3月期は,試行期間,過渡期であるにすぎなかった。
(イ) 資産査定通達策定者の意図
上記(ア)の性格は,資産査定通達策定者(早期是正措置検討会,大蔵省当局)も意図していたところであった。すなわち,早期是正措置検討会では金融システムへの影響を考慮して,ソフトランディングを指向しており,また大蔵省当局としても,早期是正措置制度は,銀行法に基づく措置にとどまり,これを超えて商法上の会計基準を変更する意図は有しておらず,各金融機関もそのように受け止めていたものである。
すなわち,早期是正措置制度導入に伴い,自己査定制度を導入し,その際,大蔵省から指針となるべき通達として資産査定通達が発出されたが,行政当局は,それらの通達等は,銀行法に基づく早期是正措置の発動の是非の判断基準を示すに止まると考えていた。これは,資産査定通達等の行政上の指針において,直ちに商法上の償却・引当の「法規範」となることは全く想定されておらず,そのように受け取られることのないような注記がなされていたことからも明らかである。
ウ 4号実務指針
4号実務指針は,早期是正措置検討会における議論を経て出されたものではなく,会計士協会が独自に作成して,公認会計士宛に発出したガイドラインであった。仮に金融機関が4号実務指針そのものに沿った償却・引当をしない場合でも,会計監査人の適正意見が得られない可能性があるというにとどまるだけであり,金融機関が4号実務指針に直接従うことが法的に義務づけられているわけではなかった。
また,平成10年3月当時,監査法人に勤務し公認会計士として金融機関の監査に関与していたaも,その意見書の中で,「4号実務指針には,資産分類(Ⅰ~Ⅳ)の規定がないという重大な欠陥があり,債務者区分,資産分類,引当金算定の関係が必ずしも明確にならず,資産査定通達と併せて解釈しても,債務者区分と分類区分のマトリックスを作ることはできませんでした」,「重大な欠陥,不備があり,償却引当額を計算することができないようなものでした。当時,金融機関の担当者と公認会計士は,従前の実務慣行に照らし合わせて協議しながら,4号実務指針(および資産査定通達)を解釈して償却引当額を算出しなければなりませんでした」と述べており,その内容が不明確であったことは明白である。
エ 9年事務連絡及び全銀協追加Q&A
9年事務連絡は,支援という要素を考慮して考えるべき関連ノンバンクの資産評価について,資産査定通達では明確な言及がないところから,追加して事務連絡の形で金融証券検査官あてに発出された大蔵省内の内部文書であり,金融機関及び公認会計士協会のいずれに対しても公表されたものではなく,ガイドラインたる性格さえ有しているものではなかった。
全銀協追加Q&Aは,大蔵省当局ではなく,全銀協から広報された例示方式によるガイドラインにすぎず,導入初年度において金融機関を法的に義務づけることはあり得なかった。また,全銀協追加Q&Aには,「現時点での諸情勢を前提とした関連ノンバンクの資産査定にかかる一般的な考え方をとりまとめたものであり,活用に際しましては,表面上の文書にこだわらず,あくまでも実質面を重視した解釈を行っていただく必要がありますので,念のため申し添えます」と記載され,その内容が一義的なものと呼び得るに足りるものではなかった。
(5) 各金融機関等の認識と平成10年3月期決算における各行の決算処理の実務等
ア 各金融機関等の認識
資産査定通達等が唯一の「公正なる会計慣行」であるとの原告らの主張は,資産査定通達等発出当時の金融機関及び金融当局関係者が実際に有していた認識と乖離するものであった。
(ア) 早期是正措置検討会における議論
早期是正措置検討会における議論においては,非常に短い時間で早期是正措置の全体の枠組みや定義付けを行わなければならなかった。その中で資産査定基準の内容については,他の問題と比較して時間的に細かい詰めがなされなかった。ただ,金融機関の関係者から具体的な基準を作るべきとの主張があったのに対し,それはそれぞれの銀行が創意工夫して自己査定基準を作っていくという考え方で対処するというのが同検討会のスタンスであった。
(イ) 「適度な統一性」の確保(中間とりまとめ)
早期是正措置検討会により発出された「中間とりまとめ」には,「自己査定ガイドラインは,あくまでもスタンダードとして位置づけられるべきものであり,各金融機関においては,このガイドラインをベースに創意・工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿った詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成することはむしろ望ましい」としつつ,「但し,適度な統一性の確保という観点から,各金融機関が作成する自己査定に関する基準は,原則として自己査定ガイドラインの資産区分概念に沿うことが必要である」と記載されている。この「適度な統一性」とは,各金融機関の自己査定基準が当局のガイドラインを参考にして創意・工夫を生かした自主的なものであることを求めてはいるものの,ガイドラインの一字一句沿うことを求めている
ものではなかった。少なくとも導入当初においては,各金融機関間のばらつきが当然予想されていたものである。
(ウ) 行政当局の認識
行政当局としても,早期是正措置が導入された平成10年3月期決算から直ちに資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となることは全く想定していなかった。
イ 平成10年3月期時点における継続的事実の積み重ねの不存在
前記第1(2)のとおり,本来,「公正なる会計慣行」(商法32条2項)と認められるためには,長年実務で受け入れられてきたという継続的事実の積み重ねが必要である。資産査定通達等が発出されたのは平成9年3月であり,平成10年3月期時点においては,何らそれらが会計処理基準として機能した実績が積み重ねられていないものであった。
(ア) 主要17行の決算処理の実務
この点,いわゆる主要17行(都市銀行9行,長期信用銀行1行及び信託銀行7行)は,平成10年に金融庁の一斉検査を受けたが,この結果について,①自己査定の正確性について,当局査定と自己査定との間の乖離が全行について認められ,関係会社について,その財務内容を勘案せずに正常先又は要注意先と区分した例や債務者区分を行わずその他と区分した例がみられ,また,他行の関連会社などについてその財務内容を勘案せずに非分類又はⅡ分類にとどめている例が存在し,②償却・引当の適切性について,自己査定が正確に行われていないほか,償却・引当の基準自体に問題が認められ,全行について,償却・引当の追加が必要であり,要追加必要額は1兆0413億円にも上り,③上記の指摘は全て「改善を要する」という形で指導
され,金融検査の結果を平成10年3月期に遡及して修正することは求められず,将来の決算期において修正していくことが指導されており,平成10年3月期において,主要17行が,多かれ少なかれ原告と同様の決算処理を行っていたことは明らかである。特に,関連ノンバンク向け貸出金については,当期に確定した額については,支援損として計上するものの,翌期以降の支援予定額については,引当金を計上しないという会計処理が,平成10年3月期当時においても,一般的であり,主要19行のうち,引当金を計上したのは4行のみで,原告を含む15行は引当金の計上を行わなかった。
資産査定通達は,全銀協を通じ「適度な統一性」を保持するためのガイドラインとしての性格を明示するために「自己査定基準作成に当たっての参考のために」とのコメントを付して,各行に配布されたが,これ以外に具体的に拠るべきものが金融当局側からは明らかにされておらず,従前の関連ノンバンク支援の特殊性に着目した決算処理の継続の是非についても明らかでなかったため,各行は手探りで自己査定基準を策定し,償却・引当を行った。このため,金融監督庁の検査では当然の帰結として,各行の償却・引当,支援損の計上等の決算処理結果にばらつきが出たものである。
以上のとおり,平成10年3月期決算において,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」と呼ぶに相応しい程度には各行に浸透せず,各行もそれぞれの決算処理が資産査定通達等の示す基準と大きく食い違っていたことに特に違和感をもたず,その意味で資産査定通達は,同期において,未だ「公正なる会計慣行」となっていたと到底いえない状況であった。
(イ) 金融検査マニュアルの導入
金融検査マニュアルは,平成11年4月に,金融証券検査官が,金融機関を検査する際の手引書として用いるために作成したものであるが,金融機関の管理体制の確認検査に重点を置いていることから,同年2月に,その策定に際してパブリックコメントが集められたが,全銀協を始めとする有力団体や会計士などから厳しい意見が寄せられ,その内容について,到底,関係者間に合意が成立しているとはいえない状況であった。このことからも,金融検査マニュアルよりさらに1年以上も前にパブリックコメント等の手続を一切行わないまま発出された資産査定通達等が提示する自己査定の基準は,平成10年3月時点においては,無論,平成11年2月の時点でも,なお関係者の支持を十全に受けていたとはいい難い状況にあったことが明らかで
ある。
ウ 原告らの主張に対する反論
(ア) 原告らは,各金融機関が,平成10年3月期決算における貸出金の償却・引当について,改正後の決算経理基準に基づき,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定されなければならないとされた各行の自己査定基準,償却・引当基準に基づき貸倒引当金を計上するという会計基準を採用したと主張している。
しかし,改正後決算経理基準には,「商法,企業会計原則等および決算経理基準をも勘案して自己査定基準,償却引当計上基準を作成実施するものとする」との記載はあるが「資産査定通達等」という文言も,「その趣旨の枠内で」という記載も全く存在しない。原告らの主張は,証拠に基づかない独自の解釈論にすぎず,失当である。
(イ) また,原告らは,主要18行の平成10年3月期有価証券報告書の抜粋を引用して,平成10年3月期決算における貸倒引当金の計上基準として,各銀行が「改正後の決算経理基準に基づき,資産査定通達,実務指針等に準拠するように定めた償却・引当基準によっている旨,有価証券報告書に記載していること」を説明する。
しかし,原告ら提出に係る各銀行別・有価証券報告書(18行分)において,「資産査定通達に準拠した」との記載は,18行中1行もないうえに,「実務指針に準拠した」との記載も,18行中7行(都銀2,信託5)が行っているにすぎない。このように,原告らの主張は,事実に反するものであり,失当である。
(6) 大蔵省検査(MOF検)におけるⅣ分類の意義の変更等
ア 従来のⅣ分類の意義
平成9年3月期まで行われた大蔵省検査(MOF検)における関連ノンバンクに関するⅣ分類額は,関連ノンバンクの第三債務者に対する貸出金の取立不能額を機械的に母体行の関連ノンバンクに対する貸出金にⅣ分類として反映させて算定された(修正母体行主義に基づく算定)。
このようなMОF検におけるⅣ分類額は,母体行主義に基づき,関連ノンバンクを「破綻させない」で母体行が責任をもって再建責任を果たすという考え方に基づくものである。
仮に,関連ノンバンクを「破綻させる」という「清算的」な考え方に基づくとすれば,銀行(母体行)の関連ノンバンクに対する「取立不能のⅣ分類」の額は,貸出金の割合に応じて算定される「プロラタ」方式によるはずであるが,そうなっておらず,関連ノンバンクの第三債務者に対する貸出金の取立不能額の全額がそのままⅣ分類とされている。
したがって,このMОF検における関連ノンバンクに関するⅣ分類額は,関連ノンバンクを「破綻させない」「母体行が責任をもって再建させる」という「再建的」な考え方に基づくⅣ分類額であり,「支援予定額」すなわち「関連ノンバンクの第三債務者に対する取立不能Ⅳ分類額(これは清算的なⅣ分類額)を解消させるために母体行が関連ノンバンクに対して損益支援すべき額の上限」を定めたものなのである。つまり,関連ノンバンクに対するⅣ分類額は,母体行の関連ノンバンクに対する貸出金の額につき,清算的な考えに基づいて「取立不能」であるとして査定したⅣ分類額ではなかったのである。
このように,関連ノンバンクに対するⅣ分類は,一般先に対するⅣ分類(銀行の貸出金に対する取立不能額を意味する。)と相違し,一般先と関連ノンバンクでは,同じ「Ⅳ分類」という言葉であっても,その意味が異なるものであった。
この当然の帰結として,MОF検における長銀の関連ノンバンクに対するⅣ分類は「即時償却・引当」を要するものではなく,複数年にわたって損益支援すべき額を意味するものであった(これにつき「分割償却」という言葉が用いられることがあるが,正確には「計画的,段階的損益支援」というべきである。)。
また,平成7年4月13日付け「当面の貸出金等査定におけるⅢ分類及びⅣ分類の考え方について」と題する大蔵省管理課長発出の事務連絡(以下「7年事務連絡」という。)もこのような考え方に従い,関連ノンバンクに対する銀行の「Ⅳ分類」につき,複数年度にわたる処理を認めている。
以上のとおり,このように,一般先に対するⅣ分類は「即時引当,償却」を意味するが,関連ノンバンクに対するⅣ分類はそもそも「即時引当,償却」を意味しない。関連ノンバンクに対するⅣ分類は「複数年にわたる損益支援の予定額」を意味するものであった。
イ 早期是正措置・自己査定制度導入後(平成10年3月期以後)のⅣ分類
早期是正措置・自己査定導入後は,資産査定の結果と引当・償却が密接に結びつくこととされた結果,「Ⅳ分類」という定義が「即時全額処理」を意味することとされた。従来の「資産査定」は数年ごとに行われるMОF検の概念であり,銀行の引当・償却と結びついていなかったが,平成10年3月期からは,自己査定の結果と引当・償却等の会計処理が連動する方向が示された。
このような自己査定の結果と引当・償却等の会計処理が連動する状況において,「Ⅳ分類」は「即時全額処理」ということになるので,従来のMОF検での査定において「関連ノンバンクに対するⅣ分類」とされてきたものについても,自己査定においてⅣ分類と査定し「即時全額処理(引当・償却)」を要することになるのか否かについて混乱が生じたものである。
しかし,この時点では,早期是正措置制度という新たな銀行監視の行政手法が採用されたものであって,銀行の関連ノンバンクに関する不良債権処理方針についての金融政策自体に変化があったわけではなく,関連ノンバンクについては母体行が責任をもって「損益支援により再建させていく」という考え方自体は維持された。つまり,関連ノンバンクにつき「即時破綻させる」という政策転換が行われたわけではなかった。
そこで,自己査定による「Ⅳ分類」は「当期中に処理を要するものである」という考え方と,関連ノンバンクに対する(従来のMОF検での)Ⅳ分類は全額即時引当,償却して関連ノンバンクを清算させるのではなく損益支援により再建を図るという考え方とを調和させるため,9年事務連絡が発せられ,また,これを敷衍した全銀協追加Q&Aにより,その内容が銀行に知らされ,関連ノンバンクに対する貸出金につき母体行責任を負う意思があり合理的な再建計画が存在する場合には,原則としてⅢ分類,当期の損益支援確定額を「Ⅳ分類」とするという方式がとられることになった。言い換えれば,従来であれば,7年事務連絡により,関連ノンバンクに対するものであれば,「MОF検Ⅳ分類(修正母体行主義のⅣ分類)」とされたものであっ
ても複数年の処理が可能であったが,平成10年3月期からは「自己査定Ⅳ分類」は分割処理を認めないものとされたので,この結果,複数年で処理すべき損益支援額を自己査定においてⅣ分類と称することができなくなったのである。
また,自己査定制度の下でのⅢ分類についても,一般先に対するⅢ分類は「取立不能の可能性」に基づくⅢ分類額であるのに対し,関連ノンバンクに対するⅢ分類は「将来の支援予定額」についてのⅢ分類額であり,同じⅢ分類という概念であっても,一般先に対するⅢ分類額については,そのうち,どれだけの額に引当金を計上するかという問題は,倒産確率など定性的,定量的なすべての要因を総合的に勘案して貸倒引当率を定めるものであるが,他方,関連ノンバンクに対するⅢ分類額については,そのうち,どれだけの額に引当金を計上するかという問題は,倒産確率に基づいて算定されるものではなく,損益支援計画に基づく経営判断の問題であると考えられたのである。
この結果,原告のみならず他行も同様に,平成10年3月期決算において,関連ノンバンクに対する貸出金につき,修正母体行主義により算定される従来の「MOF検Ⅳ分類額」については,即時全額引当・償却を要する取立不能の「自己査定Ⅳ分類」として計上することなく,原則としてⅢ分類とし,「当期に行うことが確定した損益支援予定額のみ」を「Ⅳ分類」とし,Ⅲ分類のうち,どこまで引当金を計上するかは経営の裁量の範囲とされたと解されるものである。
したがって,原告経営陣(被告ら)の「取立不能によるmustの即時引当,償却を怠っていたわけではない」,「たしかに,関連ノンバンクに対する損益支援をできる限り厚く行いたいが,それはmustの引当・償却を怠ったというものではなく,経営裁量としての損益支援をもっとやりたいと考えていたのだ」,「損益支援についても当期行うものはⅣ分類として当期中に(引当,償却によってではなく,損金計上などの方法で)処理する」という認識は,実体に根拠を有する当然のものであった。
(7) その他の原告らの主張に対する反論
ア 原告らは,平成4年8月に「金融行政の当面の運営方針ー金融システムの安定性 確保と効率化の推進」が,平成6年2月に「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」及び同「不良債権償却証明制度当実施要領について」が発出されたことから,「平成9年3月期以前においても,有税による償却・引当が求められていたのであり,無税適状にある債権額のみを償却・引当すれば足りるとする会計処理方法が「公正なる会計慣行」であったとまではいえないと主張する。
しかしながら,被告らも,平成9年3月期以前において,有税償却の途が建前として認められていたことまで否定するものではなく,ただそのような処理が銀行経営上極めて難しかったこと及び有税償却が建前として認められていたからといって,従前の無税償却を主とする税法基準による処理方法が否定されたとまでいえず,両者が併存していたと主張するものである。原告らの主張は,一つの慣行が公正なる会計慣行である場合,これと相違する他の慣行は「公正なる会計慣行」から排除され,また行政当局が指針を出した後,それと異なる慣行は「公正」でなくなるとする考えに立っていることが窺われるが,会計基準は民間の企業の中から生成発展するものであることに着目して,詳細な基準を法律や命令で定めることを避け,ただ「公正なる
会計慣行」を「斟酌」するべき旨の包括規定のみを置くにとどめた商法32条2項の立法趣旨を正確に理解しないものである。
「公正なる会計慣行」を理解するためには,複数の公正なる会計慣行が併存し得ること,その会計慣行は法律又は命令によって廃止することは別にして,単なる通達や指針では即時一括の廃止はできないこと,通達や指針により,公正なる会計慣行を変更するには,通達や指針の意向を汲んだ実務が会計慣行として熟成するまで待つほかないものである。
また,原告らは,旧商法285条の4第2項の取立不能見込額と改正前の決算経理基準における「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金」,「回収不能と認められる債権について,その損失相当額」とが同義であること,債権償却特別勘定の繰入について,「税法基準のほか,有税による繰入ができるものとする」等の指針が示されていることをもって,決算経理基準改正前から,有税引当を行うことも義務であった旨主張する。
しかし,まず,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」が何かは同条項だけでは明らかにならないがゆえに,義務的引当が必要となる範囲を明確に画するために,明確かつ詳細な指針が存する税法基準が貸倒引当金の算出根拠として機能していたのである。他方,有税部分は任意であり,明確な範囲を画する基準は存在せず,原告らは,「回収不能と認められる債権についてその損失相当額」等の通達上の文言が範囲を画するものとするが,「回収不能と認められる債権」は「取立不能見込額」と同様に「回収不能と認められる額」の具体的算定方法が明らかでない。「決算経理基準」における抽象的指針を引用して「取立不能見込額」と同義であると述べたとしても,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」は償却引当をしなければ
ならないことを述べたに止まり,具体的な基準は明らかとはならない。さらに,改正前決算経理基準における債権償却特別勘定への繰入が,「有税による繰入ができるものとする」とされているのは,有税による繰入が任意であることを示しており,この文言から義務的繰入が要求されると解するのは,矛盾した解釈である。
イ 原告らは,平成10年3月期においては,「原告銀行の関連ノンバンク宛貸出金について,合理的再建計画の有無や原告銀行の収益力から再建可能性が認められるか否かにつき具体的な検討を行うことなく,原告銀行の関連ノンバンクは原告銀行が支援するから破綻することはあり得ず支援損しかあり得ない,したがって関連ノンバンクについては支援損のみ計上すれば足り,償却・引当をする必要はないとする処理が,公正なる会計慣行に基づく会計処理であったとは認めがたい」等とも主張する。
しかし,被告らは原告の関連ノンバンクについて,合理的再建計画の有無や原告銀行の収益力から再建可能性が認められるかどうかについて具体的な検討を怠っていたわけではなく,単に原告が支援するから破綻することはあり得ないと主張しているわけでもない。
むしろ,被告らは,本件訴訟を通じ,日本リース,エヌイーディー等などに対する長期にわたる経営支援の実績を踏まえ,それぞれに再建計画が存在しこれに一定の合理性があったこと,原告の収益力から見て,これらの関連ノンバンクに対する支援は,原告が支援を続けることが可能であり,かつそれが原告の利益にも適うものであるとの判断に立ったものであることを縷々主張し,立証に努めてきた。その他の第一ファイナンス,ビルプロ3社,有楽エンタープライズ等についても,それぞれに支援をする合理的理由と再建可能性があったことを主張・立証してきたものであり,原告らのこの点に関する非難は,これらの支援の沿革を理解しない,全く的はずれなものである。
4 原告らの主張する「公正なる会計慣行」(規範)と単なる実務状況との質的相違に対する反論
原告らは,「規範」と「慣行」を峻別する例として,医療過誤や預貯金過誤払いの例を挙げて,「商法32条2項に言う『公正なる会計慣行を斟酌すべし』とは,或る業界において現に行われている「会計慣行」を参考にせよという意味ではない。同項はあくまで規範としての「公正なる」会計慣行に従うべきことを要求しているのであるから,単に当時の実務状況や金融機関の決算動向と言った生の事実を認定してみても,それだけでは何の意味もない。・・『公正なる会計慣行』の法的探求・評価と単に当時の実務状況,他金融機関の認識とは,全く法的性質を異にするものとして,厳に区別されなければならない」と主張する。
(1) 本件における「慣行」を論ずることの意義
しかし,本件訴訟において,「慣行」を論じる意味と医療過誤等において「慣行」を論じる意味は,「法的規範」との関係では明確な相違があり,本件においてそれらを引き合いに出すこと自体失当であるといえる。
ア まず,本件における議論の出発点は,旧商法285条の4第2項の「金銭債権に付取立不能の虞あるとき」の解釈にあるところ,同条項の文言のみでは,何らの解釈指針が示されていないがゆえに,「取立不能のおそれがあるとき」の判断基準について,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するものは何かが議論されるのであり,「会計慣行」そのものが,旧商法285条の4第2項の解釈における中間項として位置付けられるのである。
イ 他方,医療過誤において「法的規範」として問題となるのは,民法709条における「過失」である。
この「過失」の文言のみでは,いかなる場合に「過失あり」といえるのかは不分明である。そこで,「過失」の具体的内容を明らかにするために設定される中間項が「注意義務」である。
この「注意義務」を論じるうえでの「実務慣行」は,注意義務の内容を吟味する際の一つの重要な要素であることは事実であるが,「実務慣行」自体が「過失」の有無の判断における中間項となるわけではない。また,預金過誤払いにおける議論も同様であり,準占有者に対する支払いとして免責が認められるか否かという民法478条の「善意なりしとき」の解釈において,「慣行」自体が中間項として設定されるわけではないのである。
ウ 以上の対比から明らかなように,本件では,旧商法285条の4第2項という法的規範の解釈指針とするために,商法32条2項という条文に明記された「会計慣行」が何かが議論されているのであり,「公正なる会計慣行」たる「実務状況」は,商法32条2項を介して旧商法285条の4第2項の法的規範と直結するものである。
他方,医療過誤等において「過失」を論じるにおいては,中間項として設定されるのは「注意義務」であって「慣行」そのものではなく,またその中間項たる「注意義務」は,商法32条2項のように条文上明記された中間項ではない。ましてや,「実務状況」は,そのような性質を持つに過ぎない「注意義務」における,判断事情の一要素にすぎないのである。
したがって,本件において「会計慣行」を論じる意味と,医療過誤や預貯金過誤払い事件において「実務慣行」を論じる意味は全く異なるものであり,本件において,医療過誤や預貯金過誤払い事件における「慣行」の位置付けを引き合いに出すこと自体,全く的外れの主張なのである。
(2) 「過失」と「会計慣行」の相違点
ア また,「過失」と「会計慣行」の相違点については,そもそも,商法32条2項の「公正なる会計慣行」について,商法に詳細な規定を設けるのは,実際上困難であるばかりか,会計技術の迅速な進歩に対応することも難しいため基本的な規定のみを設け,その余は「公正なる会計慣行」に譲るのが適当であるとされたために包括的な規定が設けられたものである。このような趣旨からすれば,「公正なる会計慣行」については,その時々の社会的状況,会計学の進歩に応じて,逐次,規定の改正を繰り返すという方法によれば,商法上に詳細・具体的な規定を盛り込むことが可能なものである。
これに対して,「過失」は,そもそも,その行為者の置かれた具体的状況等によって,注意義務の存否,内容は自ずと異なるものであるから,法文に規定することができないものである。
イ さらに,商法32条2項においては,「公正なる会計慣行」という会計基準(ルール)自体に対して法規範性を付与するものであるのに対し,「過失」の概念は,当該個別具体的な状況における注意義務の存否,内容を決するという機能を有するのみである。「公正なる会計慣行」に該当し,法規範性が認められれば,一定の範囲の者に対して等しく拘束力を持つ(「斟酌」する必要が生じる)のに対して,「過失」においては,あくまでも当該個別事例について拘束力を持つのみである。
そのため,「公正なる会計慣行」に該当するものについては,当該会計基準(ルール)を適用する者の間においては,その適用結果(結論)にばらつきは生じないものであるのに対し,「過失」においては,その置かれた状況等によって注意義務の存否,内容という結論は個別に異なることとなる。
なお,「過失」についても,裁判例の集積により一定の行為基準的なものが形成されるという側面は否定できない。しかしながら,それらはあくまで事例判断の集積にすぎないのであって,それ自体が規範となるわけではなく,「公正なる会計慣行」とは全く法的性質の異なるものである。
(3) まとめ
以上のとおり,原告らが,「公正なる会計慣行」を定めるうえで,現実の会計実務を全く無視すべきであるとする主張が失当であることは明らかである。
第2 原告が作成した自己査定基準の適法性について
1 内容の適法性
前記第1のとおり,資産査定通達等が,平成10年3月期において,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たらないことは明らかであり,資産査定通達等が商法32条2項を介して旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」の法規範となることはない。したがって,仮に原告が行った会計処理が資産査定通達等に反する部分があったとしても,それは「通達」違反となるに止まり,商法違反となるものではない。
また,仮に,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」の一つであるとしても,原告が作成した自己査定基準は資産査定通達等の趣旨に反していない。資産査定通達は,金融機関の創意工夫により,実態を反映する自己査定基準を策定することを求めている。そして,関連親密先に対する貸出金については,資産査定通達等において明確な指針が示されていなかったため,原告は資産査定通達等及び追加Q&Aで示された趣旨及び考え方を参考にしつつ,税法基準をベースにした自己査定基準を策定した。
さらに,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」として認められ,かつ原告が作成した自己査定基準が資産査定通達等の趣旨を逸脱していたとしても,資産査定通達等は「唯一の」公正なる会計慣行ではなく,それに違反したことが直ちに違法となるわけではない。税法基準が平成10年3月期においても「公正なる会計慣行」であった以上,原告が策定した自己査定基準がこれに合致する限り,商法違反とはならない。
(1) 自己査定運用細則における「特定先区分」
原告らは,自己査定運用細則の「特定先」とされる区分につき,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」としたうえ,「債務者区分に応じた査定を行う」としている点について,「平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度は,金融機関が商法の計算規定等に基づき自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することを前提とするものであるが,償却・引当と連動している債務者区分を当該先の経営状態と関係なく経営者等の一存で決めることができるとすることは,すなわち償却・引当額を恣意的に増減することを認めることに他ならず,会社の財産及び損益状況を正しく表示した財務諸表の作成を求める商法の計算規定に反する」と主張する。
しかしながら,特定先に区分された企業(その対象先は長進,長銀システム開発等30社で,その具体名が細則中及びこれに添付の一覧表に明記されている)は,いずれも「当行の機能を補完するもの」として原告と密接な関係を有していた。そこで,決裁のための回議用紙2項に明記するとおり,「当行関連親密先等については,通常の一般債務者と同様の基準で債務者区分・資産分類を行うことは,当行の経営関与度の高さ等を勘案すれば適当ではない。今般,全銀協からの通知により,『関連ノンバンク』については,その特性に注目して通常の査定方法とは異なる自己査定方法が示された。当行としては,その趣旨に鑑み関連ノンバンクとともに,当行の特定関連親密先等について適切な査定を行うための基準を設ける」こととしたという経緯
がある。ここにいう「当行の経営関与度」というのは,この文書が社内向けのものであるところから細かく説明されてこそいないが,要するに,原告が資金,人事等万般にわたって密接な関係を有して事実上経営支配していたところであった。
したがって,このような先は,母体行である原告が積極的に支援する意思をもっており,客観的に経営破綻に陥る可能性は小さいと認められる債務者であったから,資産査定通達における破綻懸念先に区分する必要はなく,正常先又は要注意先に区分することとしたものである。
これに対し,原告らは,このような基準は,「原告銀行が支援方針を決定している限り支援先は破綻する可能性がなく,したがって貸倒損失が生じないものであるから,貸倒による損失見込額としての償却・引当の計上が不要であるとの理屈」になり,支援ドグマとでもいうべきものであるとして批判する。
しかし,原告らは,この議論の中で,原告が「特定先」に挙げた先については,原告がそれぞれの企業に対し長期にわたり密接な支援を行い,破綻を防ぐ努力を積み重ねてきた実績があったことを見落としており,親企業が長期間支援を続けてきた実績を持ち,そのうえで将来にわたり支援の意思を表明している場合は,普通はこれを信用して,支援の意思があることを認めるのが経済社会の常識である。よって,「特定先」に対する支援意思についても,少なくとも,過去における支援(損益支援に限らず,資金支援,経営支援等を含む)の実績が存在する限り,なおこれを肯定的に受け止めるのが相当であり,自己査定運用細則が示す30社の「特定先」は,上記のような実績を有する先であった。
(2) 決裁事由10項ただし書について
原告らは,決裁事由10項ただし書に「『経営支援先』又は『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼働処理を本体と一体で行う会社については,それぞれを『経営支援先』,『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」とした点が,「資産査定とは,金融機関の保有する資産を個別に検討して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分することである」とする資産査定通達の規定に反すると主張する。
しかし,資産査定通達が「資産を個別に検討する」ことを原則とすることと,ある特定の企業が他の企業の傘下にあることや密接な関係にあることを勘案することとは全く別のことである。例えば,業務内容が優れず,規模が小さい企業であっても,優良企業の関連子会社になれば,銀行を含む他の取引先は,親会社が救済又は支援をしてくれることを見越して高い信用力を持つことを認めるものであり,経済取引の自然の成り行きであって,これらの要素を資産査定の際に無視することはむしろ取引の実態にそぐわない。資産を査定する場合には,そのような要素を加味することが許されるのはむしろ自然なことである。取立不能かどうかを判断する場合についても全く同様なことがいえる。
以上の点からいって,決裁事由10項ただし書が不合理であると断定することはできない。
(3) ※7なお書きについて
原告らは,※7なお書きにおいて,「当該ノンバンクの取引金融機関が当行のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類,その他をⅢ分類とすることができる」と定めた部分について,資産査定通達によれば,「回収不可能又は無価値と判定される資産」であるⅣ分類は,「その資産が絶対的に回収不可能又は無価値であるとするものではなく,また将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,査定基準日において回収不可能又は無価値と判定できる資産」とされているのであるから,そのような理由で,清算に伴う損失見込額をⅣ分類としないことは許されないと主張する。
しかし,原告らの主張は,基本的に資産査定通達を唯一絶対の基準として,他の自己査定基準を判断するものであって,資産査定通達が金融証券検査官宛の内部通達で,法的拘束力を持たないか,仮に持つとしても他の基準を許さないものではないことを看過しているし,「回収不能かどうか」,「回収不能であることが確定するのはいつか」は,個別具体的に種々の要素を総合して判断すべきである。
そして,税法基準によれば,損失の計上について確定を要するとしていたものであり,当時税法基準も「公正なる会計慣行」として存続していたことを思えば,原告が第一ファイナンスのことを想定して策定して設けた前記なお書きも違法とまではいえないものであった。
(4) 「経営支援実績先」区分の合理性
これは,国税当局から「再建計画の合理性」と「損益支援の経済合理性」が認められ,損益支援につき法人税基本通達9-4-2による無税認定を受けたうえで,損益支援を実行し,この結果,自転可能な状態になった先を区分するため設定したものである。これは国税当局の無税認定の要件である「再建管理はなされているか」に従い損益支援後の銀行による再建管理の対象先であることを明確にするものである。対象先となる会社は,原告の重要な取引先であり,損益支援を実行した実績先である以上,「損益支援が終了したから長銀の手を離れた」と考えることはあり得ない。むしろ,将来にわたって資金繰り面,人事面,営業面,経営面の支援を継続するなど,なお「特別の経過観察」を必要とする先であり,このような考え方から設けられた
区分が「経営支援実績先」である。「経営支援実績先」は,損益支援の結果,「自転状態」に復しており,この先に対する貸付金の資産区分を原則として「Ⅱ分類」とすることは,資産査定通達における「破綻懸念先」や「要注意先」の区分の定義から考えても妥当である。すなわち,資産査定通達における一般先の債務者区分及び資産査定において,Ⅱ分類以下のⅢ分類債権の資産分類が行われるのは「経営改善計画等の進捗状況が芳しくない」債務者である「破綻懸念先」以下に区分された債務者であるが,損益支援が効を奏し,「自転可能」な状態になっている債務者については「経営改善計画等の進捗状況が芳しくない」とはいえず,経営支援実績先を債務者区分における「破綻懸念先」と同等と考えることはできない。
以上のことから,経営支援実績先について,一般先との比較において,「要注意先」と同等の債務者区分をすることが適当であるといえる。そして,資産査定通達においては,「要注意先」に対する貸出金については,担保等により保全されない債権はⅡ分類とされており(本文5頁),経営支援実績先の貸出金の資産分類を原則Ⅱ分類とすることは,何ら資産査定通達等の趣旨に反するものではない。
なお,後記の日本リースに加えて,平成10年3月末日現在では,ランディックと長銀リースが一括前倒しによる損益支援を終了し「自転状態」となったことから,「経営支援実績先」該当先は合計3社になっていた。
2 自己査定基準の策定目的の適法性
原告らは,被告らが平成8年8月30日の常務会で,自己査定基準及び償却・引当基準を事業推進部及び総合企画部に策定させることを決定した当時,原告の要処理不稼働資産が1兆円を超える額に達しており,自己資本比率8パーセントを維持することが困難となりかねないことを認識していたことを根拠として,原告の自己査定基準が「要償却・引当額を実態より圧縮し,原告の償却・引当可能額に収めることを目的として策定された」と主張する。そのうえで,「当時(平成10年3月期),被告らがそのような考え方(税法基準により関連ノンバンク等の支援先については支援損を計上すれば足りるという考え方)に立っていたとは到底認められない。当時作成された各種資料には,大蔵省等が示した資産査定通達等と何とかして外形的な整合性
をとりながら,実態より要償却・引当額を圧縮できる基準を策定しようと組織体で腐心していた状況が顕著に窺えるのに,当時,被告らが,税法基準に従えば足りると考えていたことを窺わせる証拠は皆無である。」と主張する。
しかし,当時,税法基準は銀行業界において広く行われ,これに従うこと自体に不自然な点はなく,その正当性を問題とする必要性はなかった。
また,このような状況の中で,資産査定通達等が発出されたが,その内容が当時の銀行業界で共有されていた支援損を巡る常識からやや乖離した内容のものであり,資産査定通達等に係る解説の中で,それがガイドラインにとどまる性質のものであることが強調され,自己査定基準について各銀行が自主性を発揮し,工夫を重ねて実情にあった無理のないものを作ることが推奨されており,原告が,資産査定通達の趣旨を尊重しつつも,自行の実情に適合した基準作りを目指すのはごく自然なことで,むしろそれは経営努力の表れでもあった。原告らは,被告らが要償却額・引当額を実態より圧縮することに「腐心」していたと主張するが,その「腐心」が当時適法とされていた税法基準の範囲内のことなら,何ら非難される筋合いのものではない。
実際のところ,本件に関連する刑事・民事の各事件の中で膨大な資料が証拠として提出されたが,平成10年3月又はそれ以前に作成された原告の内部資料について,違法な行為を行うことを前提として密議をこらすというような陰湿な場面を疑わせるものは存在しない。また,多くの関係者が様々な資料を作成しているが,「それは違法だから別の方法を探すべきだ」,「違法だから自分は荷担しない」というような発言がされた例もない。それだけでなく,平成10年3月の決算においては,長銀リース及びランディックの両社に対する前倒支援の結果,当初計画より1800億円近く多い額を前倒支援した。これは,義務的な支援の額を超えており,仮に,被告らが要償却・引当額を違法に「実態より圧縮」するために「腐心」する状況であったな
らば,義務のない支援に巨額な財源をまわすことなく,違法の可能性がある圧縮をそれだけ控えたはずである。
原告の平成10年3月期決算については,太田昭和監査法人(本件監査法人)による関与社員公認会計士等20名,監査延べ日数825日(前年比170日増),監査延べ時間6595時間という入念な監査が行われた。この監査においては,原告の自己査定基準等及び平成10年3月期決算における自己査定結果等に対する検討が,「深度ある」もの(4号実務指針参照)として入念に行われた。本件監査法人は,原告の自己査定基準策定経過においても,基準案の事前チェックを行った。原告も,自己査定基準作りの当初から,監査法人の踏むべき手順として予定に入れていた。
このような経過の中で,本件監査法人は,原告の策定した自己査定基準が,大蔵省のガイドラインたる資産査定通達との関係でも,また会計士協会の4号実務指針との関係でも,また商法の規定との関係でも,認容される内容のものであることを確認している。原告は,本件監査法人による検討結果を踏まえて,自己査定基準及びこれによる自己査定結果を適正なものであると受け止め,それを前提として決算を行ったのである。
商法監査において,特に金融機関における貸出金の償却・引当等については,監査に当たる会計監査人の意見が最も尊重されることは金融機関の実務の中で定着していた事実である。そして,会計監査人が適正意見を出せばその決算には重要な虚偽がないという考え方もまた経済社会の中で広く受け入れられてきた考え方であった。一方,大蔵省検査においては,従前,金融検査と償却・引当は連動しておらず,金融機関においては,償却・引当については,各行の経営判断と会計監査人の判断により必要とされる額を処理するのが実務であった。
3 再建計画の合理性と償却引当の関係
再建計画が合理的か否かは,その再建計画において行われる支援行為の適否の問題であり,償却の適否の問題ではない。なお,少なくとも平成10年3月期までは,必ずしも厳格な再建計画の作成を前提とする支援に限らず,人材の派遣,商材の提供,資金繰り支援等の多様な「支援」を予定している貸出先に対する貸付金を償却引当の対象とすることは矛盾と考えられており,この点について,法人税基本通達9-6-4の実施要領においても,追加融資等の支援を予定している先に対する貸出金については,無税償却適状にはないとの解釈指針を示していた。
被告らは,日本リース,エヌイーディー等の関連ノンバンクに対し,損益支援をする際,再建計画を策定しこれに沿って支援してきたが,原告らはこの再建計画に合理性がないと主張する。
しかし,被告らは,関連ノンバンクに対する支援を早期是正措置制度導入が決定される以前から実行しており,現に日本リース,長銀リース及び日本ランディックについては,平成10年3月までに前倒支援による支援完了に至っている。残るエヌイーディーについて,平成6年以降,計画的・段階的に支援を継続していたが,上記のとおり,中核3社について前倒しで支援完了に至り,平成10年4月以降は集中してエヌイーディーに対する支援を実行する予定であった。したがって,原告が支援していた重要な関連ノンバンクについて,再建計画が合理性をもたなかったというような事実はない。
第3 償却引当不足の不存在
1 日本リース
日本リースは,平成9年末時点において,①原告による平成6年度及び平成7年度の損益支援の結果,その含み損部分に見合う借入金の利払いについては,本業の利益でカバーし,実態利益は,平成9年3月期に175億円,平成10年3月期に182億円となり,期間損益は黒字決算に回復していること,②年間230億円の利益を上げるための「第5次中期計画」が具体化しつつあり,本業の収益により不稼働資産の処理が進む状態にあったこと,③キャッシュフローが順調で,平成9年11月の金融危機も原告の支援(損益支援はもとより,追加貸出し等の支援)なしで乗り切るなど,200近い金融機関からの借入金に係る約定返済に一切延滞はないこと,④平成9年秋に,他のリース会社と同様に一時抑制したリース営業も,平成10年4月から
は再び増加する計画を立てるなど,オリックスと並ぶリース業界のリーディングカンパニーとして活発な営業活動を継続していたこと,⑤子会社である日本リースオート,千代田情報機器の株式上場によるキャピタルゲインが見込まれていたこと等の状況を総合的に判断すれば,全銀協追加Q&Aの「自力で再建の見通しが立たない」という要件には該当せず,「体力あり」と判断し,上記「経営支援実績先」に該当する先として区分したうえ,同社向け貸出金をⅡ分類と査定することは妥当な取扱いであった。
2 エヌイーディー
原告は,日本リース,長銀リース,ランディック及びエヌイーディーの4社を,原告の事業展開の上で戦略上不可欠の中核的関連ノンバンクとして位置づけ,4社の破綻を回避すべく計画的段階的に支援を実行してきた。
その結果,平成8年3月に日本リースについて前倒支援を行って自転可能な状態に押し上げ,平成10年3月期には長銀リース及びランディックについて前倒支援を行って自転体制を構築した。
この結果,平成10年4月以降に要支援先として残るのはエヌイーディーのみとなった。同社については平成7年以降の再建計画に一定の修正を加えつつも,集中的に2950億円の損益支援を行うことで(この際税効果会計の導入等による財源増も見込まれ,支援の前倒しも十分可能であった),3000億円強の実質債務超過の相当部分が解消可能で,同社の消費者金融部門及びベンチャーキャピタル部門について年間10億円程度の収益も期待できた。
以上の状況の下,原告は,平成10年3月期において,自己査定基準に基づき,エヌイーディーに対する当期支援分201億8000万円をⅣ分類として支援損処理を行い,その余の将来支援予定分についてはⅢ分類として引当を行わなかった。この処理は,上記関連ノンバンク4社に対する支援を総合的,計画的に考える視点から行われ,全銀協追加Q&A及び当時の慣行に反するものではなかった。損益支援先であるエヌイーディーについて,取立不能を理由とする償却・引当をすることは,平成10年3月期当時,矛盾する行為であると認識され,また将来支援予定分について引当金を積む慣行も当時は存在せず,実際にも大手銀行17行中14行は引当を行わなかった。したがって,原告のエヌイーディーに対する貸出金についての上記処理は適
法なものであった。
3 エヌイーディーと一体的処理基準を適用した個社群について
(1) エヌイーディーのグループ会社
青葉エステートは,原告の関連ノンバンクであるエヌイーディーが,日本ランディック及び長銀リースとともに出資して設立したエヌイーディーの子会社であり,ユニベストほか4社は,いずれも,青葉エステートが100パーセント出資してエヌイーディーの不良債権を処理する目的で設立した同社の子会社であり,エクセレーブファイナンスは,エヌイーディーの資金調達窓口として,同社の100パーセント子会社として設立されたファイナンス会社であり,いずれも原告及びエヌイーディーが支援していた。
(2) 「税法基準」の適用による実質的処理
平成10年3月期当時は,企業会計原則注解18及び法人税基本通達9-6-4などの解釈として支援先に対する貸出金は償却引当が義務づけられていないとの考え方が一般に認められていたので,これら各社に対する貸出金を取立不能として償却引当をしなかった。
原告はこれら各社に対する貸出金については,エヌイーディーに対する支援計画において,エヌイーディーと一体として処理される会社として組み込み,国税当局から法人税基本通達9-4-2による無税認定による損金経理の承認を得ていた。したがって,国税当局はこれら各社に対する貸出金を実質的にはエヌイーディーに対するものとして策定した計画を合理的であると認めていたものである。なお,グループ会社の本体との一体処理は,法人税基本通達9-4-2による子会社等の再建等にかかわる損失負担の無税認定に係る事項であり,不良債権償却証明制度とは無関係である。
よって,これら各社についてエヌイーディー本体と一体で処理する基準を適用したのは,正当である。
(3) 資産査定通達のあてはめ
資産査定通達は当該債務者が実質破綻先であっても,担保及び保証によって保全された部分は,Ⅳ分類に分類査定されないものとしている。
仮に資産査定通達を原告らの主張するように解釈適用するとしても,青葉エステートほかの各社に対する貸出金は,いずれもエヌイーディーの保証があるから,Ⅳ分類に査定されない。
4 第一ファイナンスについて
(1) 清算「予定」について
関連会社支援において,清算が機関決定されていることと,清算「予定」であることは決定的違いがある。正式な機関決定がなされるまで追加融資等の支援を継続することにより支援先の継続的企業としての価値を維持し,その営業的価値に着目した企業に対し,法的清算処理が先行した場合よりも高値で営業譲渡をしたうえで(もしくはその目処をつけたうえで),清算に至るという過程を踏む場合を考えれば,それは明らかである。
(2) 損失発生の蓋然性の存否について
関連会社をどのように支援していくか,また,支援をいつ打ち切るかの判断については,まさに経営判断の問題である。当時の段階では,現に資金支援が続けられていることから,破綻,損失の発生の蓋然性は極めて低く,額の見積も困難である。むしろ,償却引当の時期を機関決定の時期とすることは判断基準として明確である。
(3) 第一ファイナンスの具体的状況
ア 原告は,平成10年3月期決算において,第一ファイナンスに対して約1246億円の貸出金債権を有していたところ,決算に先立つ自己査定において同社が原告自己査定基準の関連ノンバンク運用規則における「関連ノンバンク」であることから,同規則3(3)の「体力のない関連ノンバンク」に当たるものの,同社の取引先は原告だけで,同社をどのように再建又は整理するかの決定は翌年度以降となることから,公認会計士の指示に従い,既に確定しているとみなされるⅣ分類等合計147億円について償却・引当を行い,その余の貸出金については他の通常債権と併せて,一般貸倒引当金を計上するにとどめた。
イ 原告が,第一ファイナンスについて,単純に清算中の会社であることを前提とする処理をしなかった理由は次の点にあった。
(ア) 平成10年3月当時,第一ファイナンスは,提携先であった新京都信販の貸付先である個人から提携ローン割賦金を回収したり,大阪銀行等関西系銀行の関連ノンバンクの清算手続の中で回収を継続していたことから,同時点では原告の第一ファイナンスに対する貸出金の損失額は未だ確定し得ない状態にあり,当面は「破綻懸念先」としてⅢ分類にとどめ,これが確定した後に最終処理をすれば足りると考えられた。
(イ) 第一ファイナンスは,平成10年3月期に147億円の有税引当をしたことにより偶発的に大口債権のロスが発生する可能性も少なく,資産の含み損を抱えながらも当面の企業維持は可能であり,破産・清算会社からの配当,小口債権の回収に時間を要し,清算の時期・方法等は別途検討する予定であった。
(ウ) 債務超過の関連会社であっても,直ちに清算を行う義務が経営者ないし親会社にあるわけではなく,合理的な理由に基づき,親会社が関連会社を当面支援して存続させる選択をした場合には,破綻リスクは皆無であるから,これに対して有する債権について,直ちに償却・引当するか,あるいは清算時期,方法が確定した段階で引当・償却するかは経営者の裁量範囲内のことであると考えられていた。
(エ) 原告の平成10年3月期決算に関する会計検査に関与したQ会計士や平成10年7月の金融監督庁検査に関与したU検査官など,外部の関係者にも第一ファイナンスに関する上記処理方針は理解できるものであった。すなわち,U検査官が,「長銀においては母体行として面倒をみて,回収業務を当面継続することとしており」,「その回収が長銀の第一ファイナンスに対する貸出金の回収に若干でも寄与するという状況がある以上,実質破綻先とはしにくいと感じ,長銀の主張即ち『第一ファイナンスは回収業務を継続しており,新京都信販の提携ローンには個人相手で正常先も多く当分の間の清算はなく,それまで回収業務を継続するから実質破綻は行き過ぎである』という主張を容れざるを得ないと思いました。」と供述し,Q会計士も,資
産査定通達において,第一ファイナンスは破綻懸念先であり,最悪Ⅲ分類であったが,あえてⅣ分類として有税引当を行っており,非常に保守的な処理がされていると考えた旨供述しているところである。
(オ) 第一ファイナンスは,平成10年3月期に147億円の有税引当をした後の見通しとしては「今回の引当により当面必要な処理は一応完了。今後キャリングの赤字も最低限の水準に留まり,また偶発的に大口債権のロスが発生する可能性も少ない。資産の含み損は抱えながらも当面の企業維持は可能」であり,多額の含み損を抱えている上に,赤字体質であることから,「将来的には清算せざるを得ない」が,破産・清算会社からの配当,小口債権の回収に時間を要することもあり,「清算の時期・方法等は別途検討のこととしたい」とされていた。
上記「清算」の趣旨は,「時期・方法等は別途検討」という説明からも明らかなとおり,極めて幅のある内容であり,「せっかく回収業務でノウハウが蓄積されたわけですから,それを生かしたような業務に転換していく」,「もしも必要であれば営業貸付の清算も,そこで確定したものとしてやる」というような着地も考えられていた。
したがって,第一ファイナンスが,将来営業貸付業務については「清算」の方向であったにしても,その時期は未だ不確定で内容面でも純粋な法的「清算」に限られるものではなく,サービサー業務などに特化して存続することや他の関連会社と合併等による再編の中で一部の組織が残っていく可能性はあったのである。平成10年2月に策定された「2カ年計画」の中の「再編」はこのような不確定要素を多々含む柔軟かつ幅広いものであった。
ウ 一般に,債務超過の関連会社であっても,直ちに清算を行う義務が経営者ないし親会社にあるわけではなく,親会社が関連会社を当面支援して存続させる選択をした場合には,破綻リスクは皆無であるから,これに対して有する債権について,直ちに償却・引当するか,あるいは清算時期,方法が確定した段階で引当・償却するかは経営者の裁量範囲内のことであった。長銀の場合も,少なくとも平成10年3月時点ではなお,このような裁量内のこととして第一ファイナンスの問題は認識されていた。
したがって,第一ファイナンスが第三債務者に対して有していたⅣ分類相当の貸付金219億1700万円についても,これを直ちに長銀の第一ファイナンスに対する貸出金の査定に反映させることが強制されていたとはいえない。
このように,原告が同社を実質破綻先として扱わず,自己査定運用規則の※7なお書を適用して,処理をしたことには一定の合理性があったのである。そのうえで,公認会計士の指示に基づき,第一ファイナンスの確定していた損失に対応する147億円についてⅣ分類として引当処理をしていたのである。
(4) 保有有価証券の含み損の問題
第一ファイナンスにつき,実質破綻先でないことを前提とすると,同社が保有する株式等の含み損については,平成10年3月期の実務上,これを償却・引当の対象とする必要がなかったことは明らかである。
(5) まとめ
以上により,自己査定運用規則の※7なお書を違法であるとする原告らの主張及び551億円もの償却・引当不足であるとする原告らの主張がいずれも失当であることは明らかである。
5 特定先基準を当てはめた個社群について
(1) 「特定関連親密先(特定先)」区分の合理性
「特定先」と位置づけられている会社群は,原告のグループ機能を担っている直系関連会社群(長銀総合研究所など)と,関連ノンバンク支援の方策として関連ノンバンク保有不動産を引き取り事業化している関連ノンバンクの子会社群である。
「特定先」は,関連ノンバンクとは会社規模や業種が異なるものの,原告が,人的,資金的,経営的に特別の影響力(支配力)を持ち,母体行責任を負って,積極的に支援する方針を有している先である。
また,原告から幹部社員が派遣され,経営全般を掌握しているので,突発的破綻リスクはなく,これら「特定先」向け貸付金に偶発的貸倒損失が発生するリスクがないことは関連ノンバンクと全く同列であり,一般先とは異なる取扱いをする趣旨はそのままあてはまる。
したがって,「特定先」を「正常先」もしくは「要注意先」と同じ扱いとした原告の自己査定基準は,「特定先」の企業実態に即し,資産査定通達の趣旨にも反しない処理である。
(2) いわゆる「ビルプロ3社」について
ビルプロ3社に対する原告の貸出金は,日本リースを支援するために平成6年3月に実行されたものであり,この貸出金をもってこれら3社が,当時日本リースがビルプロに対して担保不動産付で有していた債権を買い取ったものである。
この対象不動産について,日本リースと原告が共同して事業化に取り組み,債権回収極大化に努めることとしていたものである。当時の不動産市況その他の経済環境の中では,ある程度時間をかけていかなければ事業の完成は難しい面があったものの,日本リースからの資金支援を継続しており,原告ヘの返済の遅滞もなく(日本リースの保証もあった),破綻の懸念もなかったので,日本リースに準じた評価として特定先に債務者区分し,結局要注意先と同じ扱いをしたものであって,正当である。
(3) 有楽エンタープライズについて
有楽エンタープライズは,日本リースが昭和60年6月に設立した日本リースグループの不動産会社であり,日本リースの母体行である原告が同社を支援するために融資した資金を元手に,同社から融資対象物件を譲り受けた上,事業化を目指す事業化会社であった。
日本リースは有楽エンタープライズの原告からの借入について延滞が生じないよう同社の資金繰りに十分注意するなどして,同社を支援しており,同社が事業化計画を中止したり,断念するおそれは極めて少なかった。
原告の有楽エンタープライズに対する貸出は,このように日本リースが有楽エンタープライズの事業化に対し確たる方針を持って臨んでいることを前提とした融資であり,日本リースに対する融資と与信リスクにおいて実質的に同等とみなせるものであった。従って原告が有楽エンタープライズを特定先に債務者区分し,結局要注意先と同じ扱いをしたことは正当である。
第4 原告らの予備的主張について
1 原告らの主張の問題点
原告らは,旧商法285条の4第2項のみでは具体的償却引当基準は導けないがゆえに,商法32条2項を通じて資産査定通達等の通達違反を旧商法285条の4第2項違反であると主張していたはずである。
しかるに,原告らの「資産査定通達で示された考え方は,旧商法285条の4第2項の取立不能見込額の範囲について『合理的な社会通念』を示すものである」との主張は,資産査定通達等の違反について,従前は,商法32条2項を通じて旧商法285条の4第2項違反があると主張していたものを社会通念を通じて旧商法285条の4第2項違反があると言い換えたにすぎないものである。
すなわち,別紙1の原告らの主張の第4の2(1)ないし(4)の要素は独自のものであり,他に何ら明確な判例,学説,実務慣行等の根拠が存在するわけでもない。また,これらの4要素のみを考慮した場合,例えば「当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきである」とする要件については,「自行として償却ないし撤退方針を決定しているかどうか」という資産査定通達の考え方や母体行による支援意思や支援計画の有無により資産分類を実施する9年事務連絡及び全銀協追加Q&Aの考え方とも矛盾し,相容れないものといわざるを得ない。
このような予備的主張に係る基準は,主位的主張に係る基準以上に不明確であり,失当であるといえる。
2 原告らが主張する「合理的な社会通念」は,平成10年3月期当時存在しなかったこと
(1) 旧商法285条の4第2項についての一般的解釈論
ア どのような債権が「取立不能の虞あるとき」に当たるかの判断基準は,債権の評価という,極めて評価的要素が高いものであるがゆえに,一律なものを定めることが困難という認識が一般的「社会通念」であった。
イ そして,「取立不能の虞あるとき」に当たるか否かの判断においては,個別的な債権につき個別的に判定する場合(個別判定法)のみならず,同種の集団的な金銭債権につき集団的に又は全部の金銭債権につき合理的に判定する場合(総合的判定方法)のいずれでもよいものとされていた。そして,集団的に判定する場合には,過去の取引不能の実績,同業者の取立不能の実績,得意先の変化,一般経済事情等の見通しなどを総合判断し,経験則に従って合理的判定するものとされていた。
ただし,いずれの場合でも,「取立不能の虞あるとき」の判定基準は,必ずしも明確ではなく相当の困難が伴うこと,認定には客観性があることが要請されることはもちろんであるが,取立不能見込額である限り,ある程度の主観的判断が入ることも差し支えないとされていた。
(2) 当時の慣行の存在
ア 総合的判定方法による貸倒引当金の計上
原告をはじめとする銀行業においては,「取立不能のおそれ」について,全債権について,法人税法に基づく1000分の3を乗じた額を貸倒引当金として計上している(前記総合的判定方法による「取立不能のおそれ」の算定)。
イ 税法基準による債権償却特別勘定の計上
前記アの貸倒引当金とは別個に,法人税基本通達9-6系により無税償却適状が認められるものについては,個別に債権償却特別勘定への繰り入れがなされていた。
ウ 支援先に対する貸出金については,無税償却適状態は認められないと考えられていたため,債権償却特別勘定への繰り入れはなされなかった。
「支援」(ここでいう「支援」は,必ずしも厳格な再建計画の作成を前提とする支援に限らず,人材の派遣,商材の提供,資金繰り支援等,多様な支援の形態をいう)を予定している貸出先に対する貸付金を償却引当の対象とすることは矛盾と考えられていた。法人税基本通達9-6-4の実施要領においても,追加融資等の支援を予定している先に対する貸出金については,無税償却適状にはないとの解釈指針が示されていた。
(3) まとめ
以上のとおり,原告らが主張する「社会通念」が平成10年3月期当時存在していたことを裏付ける文献上,実務上の根拠は何もない。結局,原告らの指摘する諸点はいずれも後視的な視点からの指摘にすぎず,当時金融機関の経営者の置かれていた実情とかけ離れた主張であって当を得ない。
第5 被告らの無過失
1 商法266条1項の性質-過失責任
商法266条1項1号に基づく取締役の損害賠償責任の性質は,過失責任であると解される。
これは,①無過失責任を課す旨明示されていないこと,②本来,商法290条1項に違反した配当は無効であり,会社が配当を受けた株主に対して不当利得に基づく返還請求権を有し,このような返還請求権の行使ができない場合でない限り,違法配当額を会社の損害とみて取締役に賠償させることは困難であるところ,同条項1号は,政策的に,会社の損害発生の有無が未定の段階で,損害賠償責任を取締役に負担させるものであり,いわば損害額についての推定規定であり,無過失責任を解する特別な理由がないこと,③同条項1号も株主による免除の対象とされていること,④同条項1号の立法過程からみても過失責任とみることが妥当であること,⑤企業会計の複雑性からみて,無過失責任と解することは取締役に酷な結果となること等から,根
拠付けられるものである。
2 過失がないことを基礎付ける事実
仮に,平成10年3月期において,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となっていたとしても,①平成10年3月期においては,税法基準が,未だ「公正なる会計慣行」であると一般に認識されており,客観的にみて,資産査定通達等が,同期において唯一の「公正なる会計慣行」となったことを認識することは不可能であり,②被告らは,税法基準により資産査定通達等が補充されるものと理解したところ,既に主張した経過に照らせば,そのような理解は当然のものであり,被告らが資産査定通達等が同期において唯一の「公正なる会計慣行」となったことを認識することは不可能であったことに照らせば,被告らには,税法基準が「公正なる会計慣行」であったと認識した点について,過失がなかったというべきである。
第6 被告Fの責任について
1 善管注意義務違反の不存在
(1) Fは,平成10年3月31日,取締役副頭取を辞任しており,本件決算配当を決定した取締役会当時,取締役ではなく,何ら本件決算手続に関与していない。
(2) 原告ら指摘に係るFが副頭取在任中に参加した諸会議は,業務執行の一環として適切な業務運営を行うために開催されたものであり,これらの会議に参加した事実を違法と評価することはできない。
(3) Fは,事業推進部担当の専務取締役ないし副頭取として,原告の資産健全化という原告の当該年度における重要業務の執行に注力し,まさに資産の健全化ないし不良債権処理に奔走していたのであり,同人に,貸出金評価の基準(公正なる会計慣行)に反する資産評価を行うとの認識はなく,いわんや配当可能利益が存在しないにもかかわらず配当することの認識はなかった。
Fは,金銭債権の資産評価ないし償却・引当に関し,銀行業界において一般に理解されていた考え方(会計慣行)を基礎として職務を行っていた。したがって,仮ににわかに会計慣行が変遷したとしても,会計上の「継続性の原則」に照らし,新しい会計慣行に従わなかったことを違法と評価することはできない。
2 取締役在任中の言動と決算手続との因果関係
(1) 決算手続の独自性
商法は,決算手続の独自性を認め,当該決算手続に関与した取締役の責任を定めているのであって,決算手続以前に退任した取締役は,当該決算手続について何らの権限も有しないのであるから,決算手続に基づく利益処分案の提案に関し責任を負わない。
(2) 退職後の後発事象等
原告における決算手続は,当該期終了すなわち期末の経過後に開始されること,決算経理基準に基づき期末後45日以内に,業務報告書が大蔵省に提出されるが,大蔵省は事前に配当内容等について細かい行政指導を行なうのが常態とされており,行政指導によって決算を変更する可能性も存在していたこと,このような護送船団方式による細かな規制は平成10年3月期決算の際も厳然として存在していたこと,原告の自己査定基準ないしこれにもとづく決算については,同年5月21日から同年6月12日まで実施された日銀考査においても,監査役及び会計監査人による監査報告書においても,何ら違法であるとの指摘はないこと,当期においては,決算手続の過程において業務純益が予想値より約180億円の上方修正となり,これを不稼動資
産処理財源に振り向けて追加したこと,貸出先の不渡り・会社更生法の適用申請などの後発事情による変動があったことなどの事実がある。
(3) 在任中の言動と配当との因果関係の不存在
Fは,利益処分案の作成に関与しておらず,またその予備段階ともいえる決算手続にも関与していない。
もとよりFには「違法配当」について故意はなく,仮にこのような退任取締役の在任中の言動に善管注意義務違反(過失)と評価される事実があったとしても,同人の在任中の言動と配当による損害との間には因果関係がない。
したがって,原告らの被告Fに対する本件請求は失当である。
第7 本件中間配当について
資産査定通達等が,平成10年3月期において,唯一の「公正なる会計慣行」となり得なかった以上,原告らの本件中間配当に関する主張がその前提を欠くことは明らかである。
仮に,資産査定通達等が唯一の「公正なる会計慣行」となり,平成10年3月期末において,原告に配当可能利益が存在しなかったとしても,被告らが中間配当を決議した平成9年11月25日の段階での資産査定通達等及び金融機関を取り巻く経営環境に対する被告らの認識を前提とすれば,被告らは,税法基準により,資産査定通達等の不明瞭な部分が補われると理解しており,平成10年3月期末において配当可能利益が存在しないおそれがない(商法293条の5第5項ただし書)と判断したことにつき過失はない。
1 本件中間配当を決議した平成9年11月25日の時点で,平成10年3月末に採るべき経理基準すなわち不稼動資産の処理基準に関する被告らの共通認識
(1) 本件中間配当決議が行われたのは,資産査定通達等が発出・公表されて,わずか約4か月の時点である。資産査定通達等はガイドラインの性格を有するものであり,基準として明確でなく,銀行が拠るべき基準を示すものではなかった。したがって,被告らは,資産査定通達等により,銀行の会計処理の基準が変更されるものとは認識していなかった。さらにいえば,銀行が支援している貸出先に関し一般先と同様な引当金を計上するとか,翌期以降の支援予定額について引当金を計上することが,商法上の解釈として求められているとの認識は全く有することができなかった。
(2) 早期是正措置が平成10年4月から導入されることは承知していたが,この制度も試行的な段階にあり,導入後の状況を見て見直しがなされると理解していた。早期是正措置の導入は,「監督手法」の変更であり「会計基準」の変更との認識はなかった。
(3) 平成9年7月31日に大蔵省の通達により「決算経理基準」が変更になっているが,これは早期是正措置導入以降の自己査定制度導入に伴う手続面の変更であり,不稼働資産の処理基準の変更を明確に示すものではなく,従来の税法基準による処理の実態を直ちに変更するよう求めるものではないと認識していた。
(4) 本件中間配当を決議するに際し,平成10年3月期決算において必要とされる償却・引当額の算出は,早期是正措置導入に伴って必要とされる自己査定基準を作成し(平成9年6月末時点の資産に対する自己査定トライアル基準を作成),その自己査定結果を踏まえて行なったものであり,その時点で銀行の資産状態を把握するに最も適切な方法であり,かつ,行政の考え方も取り入れた手順を採用したと認識していた。
2 中間配当を決議した平成9年11月当時の金融機関を巡る経営環境に関する被告らの共通認識
(1) 平成9年11月に入り,三洋証券株式会社の破綻に始まり,株式会社北海道拓殖銀行,山一證券株式会社と相次いで大手金融機関の経営破綻が発生し,本件中間配当決議を行った時期は,政府,監督当局,金融界を挙げて金融システムの維持と貸し渋り批判への対応に奔走していた時期であった。
(2) この時点で各金融機関にとっては自行が支援する関連ノンバンクについては計画的・段階的に支援をして再建させていく事が最も重要な経営課題の一つであると考えており(大蔵省も平成13年までに金融機関の不稼動資産を計画的・段階的に処理していくいわゆるソフトランディングを基本的な考え方として採用していた。),被告らも同様の認識であった。
したがって,この時点で,被告らには,支援先について将来の支援予定額を引当てる等の必要性は全く認識していなかった。あえてこの時点で支援している関連ノンバンクについて引当を行なう,又はその意思をマーケットに明示(例えば中間決算の発表時に公表)することは,母体行として支援を放棄したものと受け止められ,即座に他行からの関連ノンバンクに対する貸出金の回収などの事態が起こり,これが連鎖的に金融システム不安,崩壊に繋がるリスクがあった。これは原告に限らず全ての金融機関において同様の認識であると考えていた。
以 上
事件番号 :平成11年(ワ)第28164号
事件名 :損害賠償請求事件
裁判年月日 :H17. 5.19
裁判所名 :東京地方裁判所
部 :民事第8部
平成17年5月19日判決言渡
平成11年(ワ)第28164号 損害賠償請求事件
主文
1 原告及び原告訴訟引受人の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告及び原告訴訟引受人の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告
(1) 被告A,同D,同E,同B,同C及び同Fは,原告に対し,連帯して金7億円及びこれに対する同Cを除く被告らにつき平成11年12月30日から,同Cにつき同月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告D,同E,同F,同G及び同Hは,原告に対し,連帯して金3億円及びこれに対する平成11年12月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告訴訟引受人
(1) 被告A,同D,同E,同B,同C及び同Fは,原告訴訟引受人に対し,連帯して金7億円及びこれに対する同Cを除く被告らにつき平成11年12月30日から,同Cにつき同月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告D,同E,同F,同G及び同Hは,原告訴訟引受人に対し,連帯して金3億円及びこれに対する平成11年12月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告(当時の商号株式会社日本長期信用銀行)が,その取締役であった被告らに対し,以下の①及び②のとおり,被告らが商法の規定に違反した違法な配当実施に関与したと主張して損害賠償請求訴訟を提起し,その後,原告から本件各損害賠償請求権を譲り受けた原告訴訟引受人に訴訟引受けがなされた事案である。
① 被告A(以下「被告A」という。),同D(以下「D」という。),同E(以下「E」という。),同B(以下「B」という。),同C(以下「C」という。)及び同F(以下「F」という。)に対し,原告の平成9年度(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度)末(平成10年3月期)において,金71億7233万6392円を株主に配当したこと(以下「本件決算配当」という。)について,商法290条1項に違反し,配当可能利益が存在しなかったにもかかわらず,違法な本件決算配当が行われたとして,商法266条1項1号(Fについて商法266条1項5号)に基づき,上記配当額又は損害額の内金7億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(Cを除く被告らについて平成11年12月30日,Cについて同月
31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
② D,E,F,被告G(以下「G」という。)及び同H(以下「H」という。)に対し,原告の平成9年度中間期(平成9年9月期)において,金71億7564万6348円を株主に配当したこと(以下「本件中間配当」という。)について,商法293条ノ5第3項に違反し,同年度末において配当可能利益が存在しなかったにもかかわらず,違法な本件中間配当が行われたとして,商法266条1項1号に基づき,上記分配額の内金3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年12月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
第3 当事者の主張
1 原告及び原告訴訟引受人(以下「原告ら」という。)の主張
別紙1(原告らの主張)のとおり
2 被告らの主張
別紙2(被告らの主張)のとおり
第4 前提となる事実(証拠等で認定した事実については,各項末尾に証拠を摘示した。)
1 当事者
(1) 原告ら
原告は,商号を株式会社日本長期信用銀行として,長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に基づいて設立された長期信用銀行であったが,平成10年10月23日,「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号,以下「金融再生法」という。)36条1項に基づく特別公的管理の開始決定を受け,その後,株式会社新生銀行に商号変更された。
原告訴訟引受人は,預金保険機構の全額出資により設立され,預金保険機構からの委託等により破綻金融機関等からの貸付金債権等の買取り及びその管理・回収業務等を行う株式会社である。
(2) 被告ら
ア 被告A
被告Aは,昭和51年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年8月21日に退任するまでその地位にあった。その間の平成3年4月5日から平成10年8月21日まで取締役会長であった。
イ D
Dは,昭和61年6月27日に原告の取締役に就任し,平成10年9月28日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年4月28日から平成10年9月28日まで代表取締役頭取であった。
ウ E
Eは,平成元年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年4月28日から平成9年10月1日まで専務取締役,平成9年10月1日から平成10年8月21日まで取締役副頭取であった。
エ B
Bは,平成4年6月26日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年1月4日から平成10年8月21日まで常務取締役であった。
オ C
Cは,平成4年6月26日に原告の取締役に就任し,平成10年11月4日に退任するまでその地位にあった。その間の平成7年1月4日から平成10年8月21日まで常務取締役であった。
カ F
Fは,平成元年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年12月2日から平成9年10月1日まで専務取締役,平成9年10月1日から平成10年4月1日まで取締役副頭取であった。
キ G
Gは,平成6年6月28日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年6月から平成10年3月末まで,総合企画部長を務めていた。
ク H
Hは,平成7年6月29日に原告の取締役に就任し,平成10年4月1日に退任するまでその地位にあった。その間の平成8年2月から平成10年4月まで事業推進部長を務めていた。
2 原告の組織体制等
(1) 各会議体
原告には,商法上の取締役会の外,経営会議,常務会,常務役員連絡会などの各会議体が存在していた。
経営会議は,取締役会の前置機関として,原告の取締役会長が主宰し,取締役会への付議事項を議論する会議であり,常務会は,取締役頭取の諮問機関であり,会長を除く常務役員以上の取締役が構成員であって,業務執行について議論する会議であり,常務役員連絡会は,取締役頭取が招集する常務役員以上の取締役の意見交換,情報連絡の会議である。(乙100,弁論の全趣旨)
(2) 総合企画部,事業推進部
総合企画部は,原告における経営戦略(各業務戦略,資産負債構成,収益,重要投資等の計画)の企画・立案,これに関連した金融諸制度,資本市場の動向,他行の経営状況の調査等を行い,また,経営会議,常務会などの諸会議の事務局機能を担当し,さらに,経営方針に沿って,毎期・毎年の業務予算を作成し,全体としての進捗状況を管理する業務を行う部門であった。
事業推進部は,原告の不良債権の処理(いわゆる償却・引当,回収等)を実施する部門であり,不良債権の償却・引当処理を進めるほか,原告が支援していた関連ノンバンク等について,具体的な再建計画(事業化計画や不良債権処理のための財源を付与する損益支援の計画等)の立案・推進の業務を担当していた。(G本人,乙100,乙101)
3 平成9年度決算において導入された資産査定通達の概要等
(1) 早期是正措置の導入に至る経緯等
ア 早期是正措置の導入に対する検討等
金融検査・監督等に関する委員会は,平成7年12月26日,「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」と題する報告書を作成・公表し,その中で,金融機関(銀行)の経営の健全性を確保するため,自己資本比率による客観的な指標に基づき業務改善命令等の経営の早期是正を促すいわゆる早期是正措置を導入すること,そのためには,金融機関自らによる資産の査定(自己査定)とこれに基づく適正な償却(乙9ないし乙12によれば,貸出金等の債権に係る回収不能額について,直接貸借対照表から引き落とす貸倒処理をいうものと認められる。なお,法人税法上損金として処理し得る場合(無税)と損金として処理し得ない場合〔有税〕がある。)・引当の実施が前提となること,自己査定のための統一的基準を示す必要が
あることを指摘した。
その後,大蔵省(当時)銀行局長の私的研究会である「早期是正措置に関する検討会」(以下「早期是正措置検討会」という。)は,平成8年12月26日に「中間とりまとめ」を作成・公表し,その中には,自己査定については,従前の大蔵省による銀行法25条に基づく立入検査(いわゆるMOF検。以下「大蔵省検査」という。)における資産分類(Ⅰ分類ないしⅣ分類)に沿って,自己査定ガイドラインの原案を作成したこと,また,日本公認会計士協会(以下「会計士協会」という。)が示した債権の区分に従った償却・引当の計上に係る基本的な考え方により,資産査定と償却・引当の仕組みの大枠の一致が図られたこと,今後,各金融機関において,このガイドラインをベースに自己査定を行うべきことが記載されていた。(甲13ない
し甲15,乙18,弁論の全趣旨)
イ いわゆる金融3法の成立と早期是正措置の導入
また,平成8年6月21日には,「金融機関等の経営の健全化確保のための関係法律の整備に関する法律」(同年法律第94号,以下「健全性確保法」という。),「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」(同年法律第95号)及び「預金保険法の一部を改正する法律」(同年法律第96号)(以下これらの法律を「金融3法」という。)が,国会において可決・成立し,健全性確保法において,銀行法26条(長期信用銀行法17条により長期信用銀行に準用)を改正し,平成10年4月1日以降,早期是正措置制度を導入する旨が定められていた。(甲22の1,甲146,乙100,弁論の全趣旨)
(2) 資産査定通達の発出等
ア 資産査定通達の発出
この早期是正措置の導入に伴い,金融機関が自己査定を行うための基準(自己査定基準)を策定することが求められた。
そこで,大蔵省大臣官房金融検査部(以下「大蔵省金融検査部」という。)は,平成9年3月5日付けで,各財務(支)局長,沖縄総合事務局長及び金融証券検査官に宛てて,「早期是正措置導入後の金融検査における資産査定について」と題する通達及び同通達別添の「資産査定について」と題する書面(以下併せて「資産査定通達」という。)を発出した。その中では,債務者の財務状況,資金繰り,収益力等による返済能力に基づき,債務者を「正常先」(「業況が良好であり,かつ,財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者」),「要注意先」(「金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者,元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか,業況が低調ないし不安定な
債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する先」),「破綻懸念先」(「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。具体的には,現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況で,自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸
念先とする」),「実質破綻先」(「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。具体的には,事業を形式的には継続しているが,財務内容において多額の不良資産を内包し,あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し,実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており,事業好転の見通しがない状況,天災,事故,経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは,これらに類する事由が生じており),再建の見通しがない状況で,元金又は利息について実質的に長期間延滞している先など」)及び「破綻先」(「法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先をいい,例えば,破産,
清算,会社整理,会社更生,和議,手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者」)の5段階に区分(債務者区分)し,これを前提に,担保等による回収可能性も考慮し,債務者ごとに貸出金を「Ⅰ分類」(「Ⅱ分類,Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産」),「Ⅱ分類」(「債権確保上の諸条件が満足に充たされないため,あるいは,信用上疑義が存する等の理由により,その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権等の資産」),「Ⅲ分類」(「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し,従って損失発生の可能性が高いが,その損失額について合理的な推計が困難な資産」であり,「金融機関にとって損失額の推計が全く不可能とするものではなく,個々の債権の状況に精通している金融機関自らのルール
と判断により損失額を見積もることが適当とされるもの」)又は「Ⅳ分類」(「回収不可能又は無価値と判定される資産」)に査定(資産分類)することとされていた。(甲1,弁論の全趣旨)
イ 全銀協Q&Aの送付
全国銀行協会連合会(以下「全銀協」という。)は,平成9年3月21日付けで,傘下の銀行の融資担当部長に宛てて,今後各銀行が自己査定を行ううえでの参考として,資産査定通達についての考え方をとりまとめた「『資産査定について』に関するQ&A」と題する文書(以下「全銀協Q&A」という。)を作成・送付した。(甲2,弁論の全趣旨)
ウ 4号実務指針の作成・公表
会計士協会は,平成9年4月15日付けで,銀行等監査特別委員会報告第4号として,「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(以下「4号実務指針」という。)を作成・公表した。
その中で,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いとして,「正常先債権」(「業況が良好であり,かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者に対する債権」),「要注意先債権」(「貸出条件に問題のある債務者,履行状況に問題のある債務者,赤字決算等で業況が低調ないし不安定な債務者に対する債権」),「破綻懸念先債権」(「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権」),「実質破綻先債権」(「法的,形式的な経営破綻の事実は,発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見込みがたたない状況にあると認められるなど,実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権」)及び「破綻先債権」(「
破産,清算,会社整理,会社更生,和議,手形交換所における取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権」)の5つの債権区分が示されていた。(甲3,弁論の全趣旨)
エ 9年事務連絡の発出及び全銀協追加Q&Aの送付
大蔵省は,金融証券検査官等に宛てて,平成9年4月21日付け事務連絡として,「金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金の査定の考え方」と題する事務連絡(以下「9年事務連絡」という。)を発出した。
全銀協は,これを受けて,いわゆる関連ノンバンク向け貸出金の査定について,同年7月11日ころ,傘下の銀行に対し,「『資産査定について』に関する『Q&A』」(以下「全銀協追加Q&A」という。)を作成・送付した。(甲4,乙111,弁論の全趣旨)
オ 不良債権償却証明制度の廃止
従前,銀行を含む金融機関の不良債権のいわゆる無税償却・引当(法人税基本通達9-6-1ないし9-6-11を指す。なお,同通達9-6-4ないし9-6-11は,平成10年の大蔵省令改正により,法人税法施行令96条に規定が置かれた。以下では,特に断りのない限り,法人税基本通達は,この改正前の通達を指すものとする。)については,「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達(平成5年11月29日蔵検第439号,平成6年2月8日蔵検第53号一部改正)により,国税庁との協議に基づき実施され,金融証券検査官が,Ⅳ分類及びこれに準ずるものとして証明した不良債権の金額は原則として法人税法の損金に算入することが認められていた(以下上記通達による不良債権の償却証明制度を「不良債権償却
証明制度」という。)ところ,大蔵省は,平成9年7月4日蔵検第296号通達により,不良債権償却証明制度を廃する旨の通達を発出した。(乙9,乙24,弁論の全趣旨)
カ 決算経理基準の改正
銀行においては,銀行法(昭和56年法律第59号)の施行に伴い,大蔵省が,銀行経営の健全性を確保する等の要請から,昭和57年4月1日蔵銀第901号「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」と題する通達を発出し,その中には,経理関係として,いわゆる「決算経理基準」(以下,下記平成9年7月31日の改正前の決算経理基準を「改正前決算経理基準」という。)が定められており,上記通達の発出以降,普通銀行は,この改正前決算経理基準に従い,会計処理を行い,また,原告を含む長期信用銀行においても,この普通銀行に関する決算経理基準に従い,その会計処理を行っていた。
大蔵省銀行局長は,原告を含む長期信用銀行及び普通銀行の代表取締役頭取に宛てて,平成9年7月31日蔵銀第1714号「『普通銀行の業務運営に関する基本事項等について』通達の一部改正について」と題する通達を発出し,その中で,資産査定通達の発出に伴い,改正前決算経理基準の中の「貸出金の償却」及び「貸倒引当金」の規定を改正した(以下改正された決算経理基準を「改正後決算経理基準」という。)。(甲183,甲231,乙42,弁論の全趣旨)
4 原告における自己査定基準の策定と関連親密先への貸出金に対する償却・引当の状況等
(1) 原告の関連親密先
原告は,平成9年度までに,リース,ベンチャーキャピタル(ベンチャー企業に対する資金提供等を行って株式公開まで導く業務),住宅金融,信販,不動産担保金融等の各種業務分野において,人的・物的に密接な関係を有すると位置づけていた「関連先」又は「親密先」(以下併せて「関連親密先」という。)を有し,これらの企業との連携によりその業務を展開してきた。原告内部において,関連親密先と位置づけられていたノンバンクには,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載の番号1のエヌイーディー株式会社(以下「エヌイーディー」という。),同番号9の第一ファイナンス株式会社(以下「第一ファイナンス」という。),株式会社ジャリック(以下「ジャリック」という。),平河町ファイナンス株式会社(
以下「平河町ファイナンス」という。)及び同番号10の株式会社日本リース(以下「日本リース」という。)が存在しており,また,長銀インターナショナルリース株式会社(以下「長銀リース」という。)や日本ランディック株式会社(以下「ランディック」という。)なども存在していた。
また,原告は,平成9年度までに,原告又は関連親密先が有する不稼働資産(いわゆる不良債権など収益を生じていない債権や不動産など)を移管するため,これらの資産を移管し保有させることや事業化を通じて収益を上げること等を目的とした受皿会社を設立し,原告が,受皿会社に対し,これらの不稼働資産の買取資金を融資するなどして,これらの不稼働資産を受皿会社に移管し保有させていた。
このような受皿会社は,別紙3「平成10年3月期における償却・引当額の状況」記載の番号2ないし8,11ないし14の各会社であり,平成9年度当時,原告は,これらの受皿会社についても,原告と密接な関連を有するグループ企業(関連親密先又は特定先と称していた。)であるか,又はその中核会社とされている各関連親密先と一体であると位置づけていた。(甲19,乙108,弁論の全趣旨)
(2) 原告の一般先に対する自己査定基準及び償却・引当の基準
原告は,早期是正措置の導入や中間とりまとめの公表等を受けて,平成8年以降,自己査定の基準及びこれに基づく償却・引当の基準に関する検討を重ねており,遅くとも平成10年3月ころには,これらについての内部基準を策定した。(弁論の全趣旨)
(3) 原告における関連親密先に対する自己査定の基準及び償却・引当の基準
他方,原告は,関連親密先・特定先については,「当行経営支援先ならびに特定関連親密先自己査定運用細則」(以下「自己査定運用細則」という。)及び「関連ノンバンクにかかる自己査定運用規則」(以下「自己査定運用規則」という。)を策定し,これらの関連親密先・特定先以外の一般先と区別した資産査定の基準及び償却・引当の基準を策定した。
具体的には,関連親密先のうち,平成8年4月の大蔵省検査において,原告の関連ノンバンクとされた先については,債務者区分を「関連ノンバンク」として,原告に母体行責任を負う意思があり,合理的再建計画が存在する場合には,当該年度の支援予定額をⅣ分類とし,それを超える支援予定額をⅢ分類とすること,母体行責任を負う意思があっても,再建可能性がない場合には,関連ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類の額を原告の貸出割合(シェア)によりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすることが定められ,また,関連ノンバンクとされなかった関連親密先については,債務者区分として「経営支援先」,「経営支援実績先」及び「特定先」という資産査定通達には明示されていない債務者区分を策定し,「経営支援先」については,原則Ⅱ分
類,支援予定額をⅢ分類,当期支援損計上予定額をⅣ分類として分類し,また「経営支援実績先」については原則Ⅱ分類として分類し,「特定先」については債務者区分を「正常先」又は「要注意先」とし,その債務者区分に応じて査定を行うこと,また,これらの貸出金のうちⅢ分類に分類されるものについて原則として償却・引当を必要としないことが内容とされていた。(甲6の1ないし4,甲19,甲63,甲64,弁論の全趣旨)
(4) 平成9年度における関連親密先等に関する債務者区分及び資産分類並びにこれらへの貸出金に係る償却・引当の状況等
原告は,平成10年3月期において,その自己査定基準及び償却・引当の基準に従い,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載のとおり,エヌイーディー及び第一ファイナンスについて「関連ノンバンク」であるとして資産査定通達に係る債務者区分を行わず,支援損又は損失確定額についてはⅣ分類として計上したが,その余の貸出金については,Ⅲ分類又はⅡ分類に資産分類し,償却・引当を実施しなかった。
また,日本リースについて「経営支援実績先」であるとして,原告の日本リースに対する貸出金の査定に当たっても,Ⅱ分類と分類して,償却・引当を実施しなかった。
さらに,受皿会社については,上記関連親密先と一体であるとして,その貸出金について,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」記載のとおり償却・引当を実施した。(甲6の1ないし4,弁論の全趣旨)
5 平成9年度における配当の実施状況
(1) 本件中間配当の決議・実施
原告は,平成9年11月25日開催の取締役会において,同年度(同年9月期)における中間配当として,1株につき3円,総額金71億7868万8924円を分配する旨の本件中間配当を行う旨決議した。上記取締役会には,D,E,F,G及びHが出席しこれに賛成した。
原告は,上記決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7564万6348円の金銭を分配した。(甲7,甲8)
(2) 本件決算配当の承認・実施
ア 平成9年度決算の取締役会における承認
原告は,平成10年4月28日開催の取締役会において,平成9年度(平成10年3月期)決算に係る営業報告書,貸借対照表,損益計算書,利益処分計算書案(以下「本件利益処分案」という。)及び付属明細書を承認し,これを会計監査人及び監査役会に提出する旨の承認決議をした。
本件利益処分案には,任意積立金2995億1618万4620円を取り崩して,当期未処理損失を処理し,利益処分額を86億7162万4655円としたうえで,このうち,1株につき3円,総額71億7864万7455円の本件決算配当を行う旨記載されていた。
なお,同期における原告の貸借対照表には,資本金3872億2900万円,法定準備金3539億2300万円,任意積立金3176億3000万円,当期未処理損失2716億1500万円及び剰余金460億1400万円が計上されていた。
上記取締役会には,被告A,D,E及びBが出席しこれに賛成した。(甲9,甲10)
イ 会計監査人による本件利益処分案の承認
原告の会計監査人である太田昭和監査法人(以下「本件監査法人」という。)は,原告から提出を受けた平成9年度決算案について検討し,これが適正である旨の監査報告書を提出した。(甲132,甲136,弁論の全趣旨)
ウ 本件利益処分案の株主総会への上程及び承認
原告は,平成10年5月25日開催の取締役会において,平成9年度定時株主総会において,本件利益処分案を決議事項として上程することを承認する旨決議した。上記取締役会には,被告A,D,E,C及びBが出席しこれに賛成した。
原告は,同年6月25日開催の定時株主総会において,D(同総会の議長)が上程した本件利益処分案を承認する旨決議(以下「本件決算配当決議」という。)した。(甲11,甲12)
エ 本件決算配当の実施
原告は,本件決算配当決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7233万6392円の金銭を配当した。(甲8)
6 原告の破綻,国有化
原告は,平成10年10月23日,金融再生法36条1項に基づき,破綻の認定を受け,特別公的管理の開始決定がされた。(乙1,乙77)
7 原告訴訟引受人による訴訟引受けに至るまでの経緯等
(1) 本件損害賠償請求権の譲渡
原告は,平成12年2月28日,被告らに対する本件訴訟に係る損害賠償請求権を原告訴訟引受人に譲渡し,同日付け内容証明郵便により,被告らに対して,上記譲渡を通知し,同通知は,同月29日にHを除く被告らに対し,同年3月2日にHに対し,それぞれ到達した。(甲40の1ないし8の各1,2,甲41ないし甲43)
(2) 訴訟引受け
原告は,平成12年4月12日,原告訴訟引受人に本件訴訟の引受けを命ずる旨の裁判の申立てを行い,当裁判所は,同年6月13日,原告訴訟引受人に本件訴訟の引受けを命ずる旨決定し,原告訴訟引受人が本件訴訟を引き受けた。
これを受けて,原告は,同月27日,当裁判所に対し,本件訴訟から脱退する旨の届出を行ったが,被告らは,原告の本件訴訟からの脱退について承諾していない。(当裁判所に顕著)
第5 争点
事案の概要に記載したとおり,本件は,原告が実施した,本件決算配当(原告の平成10年3月期の株主への配当)及び本件中間配当(原告の平成9年9月期の株主への配当)に関し,これに賛成した被告らに対し,本件決算配当については商法266条1項1号(Fについては商法266条1項5号)に基づく損害賠償責任が,本件中間配当については商法266条1項1号に基づく損害賠償責任がそれぞれ問われた事案であるところ,前提となる事実によれば,以下の事実が認められる。
平成8年6月21日に成立した金融3法により,早期是正措置の導入が決定され,平成10年3月期から,銀行等の金融機関においては,自己査定基準を策定し,これに従って自己査定したうえで,その結果に基づき貸出金等の適正な償却・引当を行い,事後的に会計監査人による会計監査や大蔵省(その後金融監督庁,金融庁)による金融検査によって,自己査定基準の適正性,償却・引当の適正性等について検査がされることになったこと,そのために,資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡及び全銀協追加Q&A(以下これらを併せて「資産査定通達等」という。)が発出あるいは公表され,これらによって銀行における資産査定の在り方が示され,そのうえで大蔵省銀行局長による通達である改正後決算経理基準が出される
に至ったこと,被告らは,原告の取締役として,これらの資産査定通達等を踏まえて,原告の自己査定基準を策定し,これに基づき原告の資産内容について自己査定をしたうえで平成10年3月期の貸出金等の償却・引当の処理を行い,その結果に基づいて,本件決算配当及び本件中間配当が実施されたこと,以上の事実が認められる。
ところで,原告らは,平成10年3月期においては,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が銀行等の金融機関における貸出金の償却・引当処理の基準として,商法32条2項の「公正なる会計慣行」(なお,以下,商法の規定中片仮名で表示された部分をひらがなで表示する。)となっており,しかもこれが唯一の「公正なる会計慣行」であったとしたうえで,被告らが関与して作成された原告の自己査定基準における償却・引当基準が上記のとおりの唯一の「公正なる会計慣行」に違反しており,配当可能利益が存しないにもかかわらず配当がなされたもので本件決算配当は違法であること,また,本件中間配当についても,平成10年3月期において配当可能利益がない状態が生ずるおそれが客観的に存在していたにもかかわらず配
当を行ったもので違法であると主張している。これに対し,被告らは,被告らが関与して作成された原告の自己査定基準は,資産査定通達等の趣旨に反するものではないと主張するとともに,原告らが主張する資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が当時唯一の「公正なる会計慣行」であったことを争い,いわゆる税法基準(法人税法で損金算入が認められる限度額において企業会計の費用又は損失を経理処理すれば足り,法人税法上容認される損金算入限度額を超えてまで費用として処理する必要はないとする会計処理方法,本件で問題とされる関連ノンバンクについては,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とする会計処理方法)が,平成10年3月期以前から,銀行の貸出金の償却・引当の基準について
の「公正なる会計慣行」であり,平成10年3月期においても税法基準が「公正なる会計慣行」として存続していたと主張している。以上のような事実関係を前提として,第3の当事者双方の主張を対比すると,本件訴訟における具体的な争点は,以下のとおりであるといえる。
① 商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容をどのように解釈すべきか。
② 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が平成10年3月期において,銀行等の金融機関における貸出金の償却・引当処理の基準として,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当し,しかもこれが唯一のものとされるためにはどのような要件を満たすことが必要か。
③ ②の要件との関係で,平成9年3月期以前の改正前決算経理基準のもとで,銀行等金融機関の不良債権の償却・引当に関する基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか。
④ 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が②の要件を満たしているといえるか。
⑤ 平成10年3月期において,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準に基づく原告の貸出金の償却・引当の結果がこれに違反しているといえるか。
以上のとおり,原告らの主位的主張は,平成10年3月期において資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとの点に尽きるものである。しかし,一方で,原告らは,予備的な主張として,仮に,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」であったとはいえないとしても,被告らが主張する税法基準は,「公正なる会計慣行」となり得ず,当時の「公正なる会計慣行」は,平成14年法律第44号による改正前の商法(以下「平成14年改正前商法」という。)285条の4第2項における「取立つること能わざる見込額」(以下「取立不能見込額」という。)の判定に従い,債務者の資産状態,収益力,担保状況等からみて合理的な社会通念に従って行わなけ
ればならないとされていたものであるところ,平成10年3月期において原告が策定した自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当の結果はこれに違反していると主張しており,予備的な争点として,⑥仮に資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準が銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合,この点に関する当時の「公正なる会計慣行」は,どのようなものであったのか。そして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準による償却・引当が当時の 「公正なる会計慣行」に違反していたといえるか の点が争点になり得るというべきである。
第6 当裁判所の判断
1 争点①(商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・ 内容をどのように解釈すべきか。)について
(1) 銀行の貸出金の償却・引当の基準と商法32条2項の関係
本件で問題となる株式会社における貸出金(金銭債権)の償却・引当の基準については,平成14年改正前商法285条の4第2項(以下「旧商法285条の4第2項」という。)は,「金銭債権に付取立不能の虞あるときは取立つること能はざる見込額を控除することを要す」と規定しているところ,金銭債権に関する取立不能見込額について,どのような基準により判断されるべきかについては,商法に明示的な規定はない。そこで,その判断基準については,商法32条2項に「商業帳簿の作成に関する規定の解釈に付ては公正なる会計慣行を斟酌すべし」と規定されていることから,商業帳簿の作成に関する規定である旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」の解釈に当たっては,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌
して決めることになると解される。そして,原告を含む銀行は,いずれも株式会社であり,平成10年3月期における原告を含む銀行の貸出金の償却・引当に係る基準については,銀行法,長期信用銀行法及びそれらの施行令・施行規則に,その点に関する規定がないことからすると,結局,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌して決めることになるというべきであって,この点は,当事者間に争いのないところである。
(2) 商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容
ア 「公正なる」の意義・内容
商法32条2項の「公正なる」の意義・内容については,同条1項が「商人は営業上の財産及損益の状況を明かにする為会計帳簿及貸借対照表を作ることを要す」と規定していることからすると,商人の営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという商業帳簿を作成させる商法の目的からみて公正であることと解すべきことになる。そうであるとすれば,商人の営業上の財産及び損益の状況を明らかにする主要な目的は,商人(企業)の利害関係人(株式会社においては,当該会社の債権者,当該会社と取引をしようとする者及び株主)に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかにすることにあるというべきであるから,結局「公正なる」といえるか否かは,上記の目的に照らして,当該会計処理の基準(具体的な会計処理の理論あるいは方
法)が,社会通念上,合理的なものであるといえるかどうかによって決せられるというべきである(乙98の119頁参照)。
イ 「会計慣行」の意義・内容
次に,「会計慣行」の意義・内容については,その文言に照らし,民法92条における「事実たる慣習」と同義に解すべきであり,一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われている企業会計の処理に関する具体的な基準あるいは処理方法をいうと解すべきである。言い換えると,企業会計の処理に関する具体的な基準あるいは処理方法が,少なくともわが国の特定の業種に属する企業において広く行われていることが必要であり,また,相当の時間繰り返して行われていることが必要と解すべきである(乙98の119頁参照)。そして,当該会計慣行が特定の業種に属する企業において広く行われ,しかも,相当の時間繰り返して行われているという事実があってはじめて,当該会計慣行が「公正なる会計慣行」となり,こ
れによって当該会計慣行とされた会計処理の方法が,法改正等の手続を経ずに,商法32条2項を介して法的な強制力を持ち得ることになると解される。
ウ 「斟酌すべし」の意義・内容
また,商法32条は,「斟酌すべし」と規定しており,その趣旨は,「公正なる会計慣行」が商業帳簿の作成に関する商法総則の規定や株式会社の計算に関する規定の解釈の指針となるべきことを明らかにしたものというべきである。そして,「斟酌」とは,ある事情をくみいれて判断することであって,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,公正なる会計慣行をくみいれて判断することを要請しているものである。そうであるとすれば,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,「公正なる会計慣行」を斟酌することが要請されているとはいえ,他の事情を斟酌することが禁じられているわけではないことになり,結局,「斟酌すべし」とは,「公正なる会計慣行」が存在する場合には,特段の事情がない限り,それに従わなけれ
ばならないという意味に解すべきである。
(3) 新しい合理的な慣行が生まれようとしている場合と「公正なる会計慣行」 の関係について
なお,原告らは,「会計慣行」とは,既に行われている事実に限らず,新しい合理的な慣行が生まれようとしている場合には,それを含むと解すべきであると主張している。そこで検討すると,商法32条2項が「会計基準」という用語ではなく「会計慣行」という文言を用いて,企業会計の技術・実務の発展に伴い,立法作用によらないで企業会計の基準を変更し得ることを容認した趣旨からすると,企業会計の実務の実際の動向を考慮することが当然の前提になっていると解すべきである。そして, 一般論として考えてみても,前記の立法担当者の解説書(乙98の119頁)でも指摘されているとおり,「慣行」という以上は,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることが必要というべきであって,いかにその内
容が合理的なものであっても,そのことだけで直ちに「会計慣行」になり得ると解することはできないというべきである。
もっとも,前述のとおり,商業帳簿に関する規定を解釈するに当たっては,「公正なる会計慣行」を斟酌することが要請されているとはいえ,特段の事情があれば「公正なる会計慣行」以外の会計処理の理論や方法によることも許されると解すべきであり,原告が主張するような合理的な会計処理の方法が生まれようとしている場合には,これを後述の特段の事情のある場合に当たるとして,そのような新しい会計処理の方法によることも許されると解する余地はあるというべきである。
(4) 「公正なる会計慣行」は規範的な概念であり実務慣行とは異なるとする原 告らの主張について
原告らは,「公正なる会計慣行」とは,規範的な評価概念であり,現実の金融機関の決算処理の実務について,特段考慮すべきではないとして,あくまで銀行である原告の貸出金の償却・引当の基準が,公正性を有するか,すなわち商業帳簿の作成目的である商人の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らし,合理的かつ妥当なものであるかどうかが問われるべきであると主張し,例えば,医師の不法行為等が問題となる事件において,医師の客観的注意義務としての医療水準(本来あるべき基準)と単なる医療慣行(通常医師が現に行っている医療慣行)が区別されていることや盗難通帳における預金過誤払いの事件において,銀行が社会通念上求められるべき注意義務と銀行実務が必ずしも一致すべきものではないと指摘し,「公正なる
会計慣行」の内容を確定するに当たり,現実の金融機関の決算処理に関する実務の状況を考慮することが不当であると主張する。
しかしながら,商法32条2項の「公正なる会計慣行」は,企業会計の基準となるものであるが,その内容は,本来,個別具体的に法令として定め得るものであり,その内容とされた個々の処理基準が規範として作用し,個別的具体的な状況に応じてそれが変化するものではないというべきである。これに対し,原告らが指摘する注意義務の内容は,規範としての抽象的注意義務が既に存在することを前提としたうえで,当該個別具体的な状況に応じて異なり得る実際の具体的な注意義務の内容にほかならないというべきであり,両者は同一視できるものではない。換言すれば,原告らの指摘は,医師や銀行に対する不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求や契約上の注意義務違反を理由とする損害賠償請求のように,既に注意義務に関する抽象
的な規範が定立されている場合において,本来あるべき水準とされる現実的かつ具体的注意義務の判断に当たっては,現に行われている実務(慣行)を区別すべきであると考えるものであり,抽象的規範が存在することを前提として,具体的基準を解釈するに当たり,現に行われている実務の状況に依拠すべきではないということは当然のことというべきである。これに対し,商法32条2項は,「公正なる会計慣行」を会計処理の抽象的規範とすべきである,すなわち,この抽象的規範を定めるに当たって会計慣行を考慮して決定すべきであるとするものであり,商法32条2項そのものが金融機関の決算処理に関する一般的抽象的規範すなわち基準それ自体を定めたものとはいえないというべきである。そうであるとすれば,このような前提となる規範それ
自体の判断に当たっては,現実の金融機関の決算処理に関する実務の状況を考慮することが必要でありこそすれ,これを考慮することが不当とは到底いえないから,この点に関する原告らの主張は採用できない。
2 争点②(既に公正なる会計慣行が存在する場合にその内容を変更する新たな 会計慣行が唯一の「公正なる会計慣行」とされるためにはどのような要件を満 たす必要があるか。)について
以上1で述べたのは,「公正なる会計慣行」の解釈に関する一般論であり,未だ公正なる会計慣行が存在しない事柄について,新たに公正なる会計慣行が生まれる場面での解釈というべきである。これに対し,本件では,銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が問題となっているところ,この点については,既に公正なる会計慣行として改正前決算経理基準が存在し(後述するとおり,被告らがいわゆる「税法基準」に従った会計処理が貸出金の償却引当における「公正なる会計慣行」に当たると主張する点では原告らはこれを争っているものの,改正前決算経理基準それ自体が「公正なる会計慣行」に当たるとする点では当事者間に争いはない。),その改正により内容の変更がなされた場面での「公正なる会計慣行」が問題とされている。しかも,
本件で,原告らは,資産査定通達等で補充される改正後の決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たると主張しているのである。そこで,以下では,前記の「公正なる会計慣行」の解釈に関する一般論を踏まえ,どのような要件が満たされた場合に,資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるかについて検討する。
(1) 変更された処理内容が繰り返して行われることの要否
まず,以上の一般論のうち,「公正なる会計慣行」とされるためには,企業会計の処理に関する具体的な理論あるいは処理方法が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることが要求されるかについては,本件で問題となっている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準のように,既に通達等に基づく会計処理の運用が「公正なる会計慣行」(なお,その内容について争いがあることは前記のとおり)とされて存在している場合において,その改正手続を踏んだ上で,内容の変更がなされたときは,必ずしも,そこまでは要求されないと解すべきである。なぜならば,改正の内容が公正なものである以上,その変更は機動的になされる必要があるし,後記4(1)ア(ア)a及び4(1)イ(ウ)cで認定のとおり,企業会計原則及び改正前決
算経理基準において採用されている「継続性の原則」の趣旨からしても,その間に間隙を生ぜさせることは相当とはいえないからである。そうであるとすれば,改正内容が「公正」なものであり,改正手続自体が適正なものと認められるのであれば,必ずしもその内容が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われていなかったとしても,唯一の「公正なる会計慣行」に当たると認める余地はあるものというべきである。
そして,この点については,有価証券報告書提出会社については,企業会計審議会が公表した企業会計原則・同注解が企業会計に関する「公正なる会計慣行」に当たると解されているところ,平成10年大蔵省令第135号による改正後の「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下「改正財務諸表規則」という。なお,この改正後の財務諸表規則を「改正財務諸表規則」という。)1条2項により,企業会計審議会の作成・公表した企業会計の基準が,導入と同時に,原則として「公正なる会計慣行」となることを容認した趣旨からすると,企業会計原則・同注解の改正に当たっては,企業会計審議会が公表する会計基準で示された会計処理方法が,一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行うことまで要求されること
なく「公正なる会計慣行」となり得るとされていることが参考になるというべきである(甲98添付資料5,乙35の135頁,乙94の219頁,乙98の108頁参照)。もっとも,以下で述べるように,企業会計原則・同注解が改正により相当の時間繰り返し行われることなく「公正なる会計慣行」となり得るのは,上記の通り,改正財務諸表規則1条2項により包括的な委任規定が存することがその理由とされていることに留意する必要がある。
(2) 内容を変更することに伴う要件
次に,本件で問題となっている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準については,既に公正なる会計慣行として改正前の決算経理基準が存在していることからすると,資産査定通達等で補充された改正後の決算経理基準が広く会計上のならわしとして一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一の「公正なる会計慣行」とされるためには,改正前の公正なる会計慣行と改正後の会計慣行との間の内容変更の程度に応じて,従前の基準を変更することにより,企業会計の継続性の確保の観点から支障が生ずるような場合には,これに対する手当を講じる必要があるというべきである。なぜならば,従前の会計慣行が公正なものとして関係者に周知徹底され慣行として広く行われていたものであることからすると,その後に変更された内容が仮に「公正な
る」ものと評価できるとしても,変更自体が法規によらず,通達等を介して「会計慣行」の変更によってなされるものであり,本件で問題となる資産査定通達や9年事務連絡は,あくまでも行政組織内部の通達や事務連絡にすぎず,また,4号実務指針は会計士協会内部における監査上の指針であって,それらは当然に金融機関に一定の法的義務を課す性質のものではない以上,変更後の会計慣行が一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされるためには,会計処理に関する継続性の原則への配慮,ひいては後述するように,その内容が商法32条2項を介して法規範としての強制力を持つことからしても,変更が関係者にとって,いわば不意打ちにならないような手当が必要と解すべきだからである。そして,そのような手当がなされない場合
には,変更後の処理基準が内容的にみて「公正なる会計慣行」に当たるといえる場合であっても,これが一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされることはできず,従前の処理基準に従った処理もまた「公正なる会計慣行」として存続することになると解すべきである。
このことは,証拠(乙3,乙4,乙35,乙38,乙39,乙44)及び弁論の全趣旨によれば,企業会計の基準は,会計理論の発達,企業会計の技術・実務の発展,進化により変化するものであり,必ずしも唯一の基準が存在するわけではなく,企業会計の継続性の原則の趣旨からすると,複数の企業会計の基準が併存する場合があること(実際に従前の処理基準に従った処理の併存が認められている例として,後記3(8)イ(ウ)参照),企業会計原則・同注解が企業会計に関する唯一の「公正なる会計慣行」に当たるとの見解が有力視されるに至ったのは,前記改正財務諸表規則が定められた平成10年以降であり,他方,「公正なる会計慣行」は複数存在することがあり得ると解され,企業会計審議会の公表する基準であっても必ずしも直ちに「
公正なる会計慣行」となり得るものではないと解されていたところ,決算経理基準については,改正財務諸表規則のような法規による根拠付けがなされていないことからも裏付けられるというべきである。
(3) 商法32条2項を介して法規範となることに伴う要件
また,本件でも問題とされているように,銀行の貸出金 の償却・引当に関する基準が改正され,当該基準が,唯一,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」に当たることになった場合には,前記のとおり,この新たな銀行の不良債権の償却・引当に関する基準が,商法32条2項を介して法規範となり,商法290条1項の配当規制に影響を及ぼし,当該基準に反した処理をすることによって違法配当の問題が生じ得ることになり,改正が法規によってなされるものでないにもかかわらず,取締役であった被告らの民事責任及び刑事責任を生じさせ得ることからすると,新たな会計慣行について,一定時間繰り返し行われることなく直ちに唯一の「公正なる会計慣行」として強制力を生じさせるためには,改正手続が適正なものであることは当然
としても,新たな銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が新たに法規により企業会計の基準が定められた場合と同程度に一義的で明確なものであることに加え,前記のとおり,決算経理基準については,改正前財務諸表規則のような法規による根拠付けがなされていないことも考慮すると,当該基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,当該基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われた場合と同視しうる程度に,これが規範として拘束性を有するものであることの周知徹底を図ることが必要と解すべきである。
(4) 小括
以上検討したところによれば,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」の意義・内容を踏まえたうえで,原告らが主張するように資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準が銀行の貸出金の償却・引当に関する基準として唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるためには,以下の要件を満たすことが必要といえる。すなわち,まず,当該貸出金の償却・引当に関する基準が,当該銀行の利害関係人に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして,社会通念上,合理的なものであることが必要である。そして,本件においては,従前から存した「公正なる会計慣行」である決算経理基準の改正という形で銀行の貸出金の償却・引当に関する基準の変更がなされていることからすると,改正手
続自体が適正で,改正の内容が公正なものであれば,変更された会計処理に関する基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われていることまでは要求されないというべきであるが,会計処理の基準の変更が法規によってではなく通達を介して新たな慣行によって行われるものである以上,その変更に伴って企業会計の継続性の確保の観点から支障が生じ,ひいては関係者への不意打ちになるような場合には,これに対する手当をすることが要求されるというべきである。また,本件で問題とされている銀行の貸出金の償却・引当に関する基準の変更は,その変更された内容が唯一の「公正なる会計慣行」とみなされる場合には,改正が法規によってなされるものでないにもかかわらず銀行の取締役らの民事責任及び刑事責任を生じさせうるこ
とからすると,相当の時間繰り返して行われることなくこれを唯一の「公正なる会計慣行」とするためには,改正手続が適正なものであることは当然としても,新たな銀行の貸出金の償却・引当に関する基準が一義的で明確なものであることが必要であり,さらに,当該基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,これが唯一の規範として拘束性を有するものであることの周知徹底を図ることが必要と解すべきである。
以上を整理すると,原告らの主張する資産査定通達等によって補充された改正後の決算経理基準が,銀行の不良債権の償却・引当に関する唯一の基準としての「公正なる会計慣行」に当たるとするためには次の要件を満たすことが必要と解すべきである。
① 当該銀行の利害関係人に対し,営業上の財産及び損益の状況を明らかに するという目的に照らして,社会通念上,合理的なものであること
② 変更に伴って企業会計の継続性の確保の観点から支障が生じ,ひいては 関係者に対する不意打ちになるような場合には,これに対する必要な手当 がなされていること
③ 改正手続が適正なものであること
④ 新たな基準が新たに法規により企業会計の基準が定められた場合と同程度に一義的で明確なものであること
⑤ 新たな銀行の決算処理に関する基準に拘束されることになる関係者(銀行の取締役,公認会計士,税理士等)に対し,当該基準が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行われた場合と同視しうる程度に,これが唯一の規範として拘束性を有するものであることの周知徹底が図られていること
3 本件の事実関係(認定事実)
前記2で判断したとおり,平成10年3月期において,資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が,唯一の「公正なる会計慣行」であったとするためには,前記2の(4)で示された①から⑤までの要件を満たすことが必要と解される。そこで,以下では,これらの要件該当性を検討する前提として,早期是正措置の導入が決定され,その一環として資産査定通達等が発出され決算経理基準の改正に至った経緯とこれに対する大蔵省等関係者の対応状況,原告が前記決算経理基準の改正に至る経緯を踏まえて本件中間配当及び決算配当を実施するに至った際の被告ら等の関係者の対応状況,平成10年3月期における原告の自己査定基準に基づく実際の償却・引当の状況,その後の関係者の対応状況とこの間における銀行の資産査定をめぐる金融行政
の変遷等について,時系列に従って事実関係を整理することとする。
前記前提となる事実と証拠(各項末尾に摘示)及び弁論の全趣旨によって認められる事実関係は,以下のとおりである。
(1) 早期是正措置の導入に関する検討開始と原告における検討状況
ア 早期是正措置の導入に関する検討開始の状況等
(ア) 平成7年6月8日付け「金融システムの機能回復について」
大蔵省は,平成7年6月8日付け「金融システムの機能回復について」と題する指針(乙117)を公表した。
上記指針には,「検査・監督機能の一層の活用」と題して,検査・監督は,従来より金融機関経営の健全性を確保する上で大きな役割を果たしてきたが,いわゆるバブルの発生・崩壊という金融環境の激動期においては事前の経営チェック機能を必ずしも十分果たしえたとはいい難い面があること,近年の金融機関を巡る環境の変化に対応するため,検査・監督にかかる要員や研修の充実等に努め,検査・モニタリング機能の一層の活用を図ること,検査・モニタリングの結果,多額の不良債権の発生等が認められた場合には,時機を失することなくこれに対応し得るよう,客観的な指標に基づき金融機関経営の早期是正措置を求める措置の導入等について検討することが示されていた。(乙117の58頁)
(イ) 金融制度調査会による平成7年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」と題する答申
その後,株式会社大和銀行のニューヨーク支店における巨額損失事件が発覚したことなどにより,銀行に対するリスク管理,内部監督が社会的な問題となり,大蔵省検査等についての批判がされ,従来の銀行に対する保護的な事前指導行政から自己責任原則(市場を通じた銀行の評価と民間銀行の自主性の尊重)に基づく事後監督行政へと転換する議論・検討が一層進められた(甲231の2枚目,乙108の3頁)。
すなわち,大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会は,平成6年12月の東京協和信用組合,安全信用組合の破綻をはじめとして金融機関の破綻が相次いだことを受けて,平成7 年7月,金融システムの安定化のための諸施策を検討するべく金融システム安定化委員会を設置した。そして, 同委員会の報告に基づき,金融制度調査会は,同年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」と題する答申をした。その答申の中で,金融機関や預金者の自己責任原則の徹底と市場規律の十分な発揮を基軸とする透明性の高い金融システムを早急に構築していく必要があること,監督当局においても行政姿勢の転換が必要であり,市場機能の補完的役割を果たすことを基本として
,透明性の高い新しい行政手法の導入とともに,検査・モニタリング体制の整備・充実を図ることにより金融機関経営の健全性確保を促していく必要があることが指摘され,そのための具体的な金融機関経営の健全性確保のための方策として,「早期是正措置の導入」が挙げられた。そして,早期是正措置は,監督当局が最低限講ずる必要のある処分等の内容を明確化するものであり,当局の裁量の幅を狭め,行政の透明性確保にも資することとなること,早期是正措置の導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となるところ,検査・モニタリング体制の整備・充実が必要であるが,金融機関の自己責任原則の徹底等の観点からは,資産査定は先ず各金融機関自らが厳正に行うことが必要であることが指摘された(乙17の
1枚目左側4段目の(2))。(甲231,乙17,乙108)
(ウ) 平成7年12月26日付け「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」等
その後,金融検査・監督等に関する委員会は,同年12月26日,「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」(甲13)を公表し,その中で,金融行政金融機関の経営の健全性を確保するため,客観的なルールに基づき経営の早期是正を促すいわゆる早期是正措置を導入する必要があること,同時に,この制度が適切に機能するためには,金融機関自らの資産内容の的確な把握,監督当局の検査・モニタリング体制の整備は不可欠の前提であること,特に,資産内容の自己査定の重要性にかんがみ,これについては公認会計士による外部監査を活用していくことが求められることが基本的な認識として示された(1枚目)。
そして,金融機関の経営の健全性を確保するための監督手法として,早期是正措置を導入すること,これは,金融検査部局の検査等の結果に基づき,行政担当部局が業務改善命令等の措置を客観的なルールに則り厳正に実行していくものであること,が挙げられていた(2枚目)。
また,早期是正措置の導入に伴う新しい検査方法の確立について,早期是正措置の導入には,その基準となる自己資本の充実度等の正確な把握が不可欠であること,そのため,金融機関による自己査定及び外部監査の活用を前提とした新しい検査方法を確立すること,当局は,自己査定のための統一的な基準を示すことなどが挙げられた(3枚目及び4枚目)。
さらに,同日,今後の金融行政の転換について,金融機関の自己責任の徹底と行政当局における市場規律を基軸とした透明性の高い行政を行うことが肝要であり,そのため,当局の検査結果等に基づき自己資本の充実度等客観的ルールにより,業務改善命令等の措置を厳正に実行する早期是正措置制度を導入する必要がある旨の大蔵大臣の談話が公表された(甲14の1枚目)。(甲13,甲14,弁論の全趣旨)
(エ) 会計士協会による銀行等監査特別委員会の設置
会計士協会は,平成8年3月26日,前記(イ)の金融制度調査会からの答申「金融システム安定化のための諸施策」と前記(ウ)の「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」が公表されたことを受け,金融機関に係る監査業務について検討する特別委員会である「銀行等監査特別委員会」を設置することを決定した。
なお,上記特別委員会の委員長は,当時の会計士協会の副会長であったI(以下「I会計士」という。)が就任した。
イ 原告における早期是正措置に関する当初の検討状況
原告は,平成8年2月13日開催の常務会(D,E,F,C及びBが出席)において,「金融行政のあり方の根本的転換について」と題する資料(甲18の2)に基づく検討を行った。
上記資料によれば,自己資本の充実度等の客観的ルールに基づき,裁量を極力排除した行政命令の発動を厳正に実施する早期是正措置が導入されること,その導入に当たっての前提として,①金融機関自らによる自己査定を統一基準に基づき実施,義務付け,②その結果を公認会計士活用による外部監査でチェック,③当局検査は,自己査定や外部監査の結果を活用しつつ,その正確性や客観性を最終チェック及び④当局検査は,自己資本充実度及び自己査定正確度に関する格付けを行い,当該格付けに対応した弾力的検査手法を導入するといった4点を制度化し,客観性・正確性を確保することが示され,また,「当行経営への影響,課題」として,リスク管理体制,内部管理体制(含法令遵守状況)の組織内確立について資産の健全性の状況の適正
把握,管理システムの構築が指摘され,さらに,上記資料の添付資料(前記ア(ウ)の大蔵省発表原文とこれに注釈や原告の課題を記載した資料)には,早期是正措置の導入及び外部監査の活用を受け,MOF基準及び外部監査に耐え得る自己査定システムの構築が原告の課題とされることが指摘されていた。(甲18の1及び2,甲103添付資料1)
(2) 平成8年の大蔵省検査に対する原告の対応,当時の不良債権額等の把握状況,金融3法の成立と早期是正措置の導入の決定等
ア 平成8年4月における大蔵省検査の状況等
(ア) 平成8年4月8日会議における不良債権額把握の状況
原告は,平成7年ころから,近く大蔵省検査が実施されることを想定して資産査定に関する試算を行い,その結果について,総合企画部及び事業推進部が共同で,平成8年4月8日付け「円卓会議資料」と題する資料(甲168添付資料1)にまとめた。
上記資料には,「査定前」として,Ⅱ分類が2兆8672億円(一般先1兆1472億円,住専1300億円及び関連親密先1兆5900億円)であること,Ⅲ分類2115億円(一般先2115億円)及びⅣ分類2877億円(一般先1157億円及び関連親密先1720億円)の合計額は4992億円に達し,この4992億円について3年の期間(平成8年度2400億円,平成9年度1400億円,平成10年度1192億円)で償却する計画であること,他方,大蔵省検査による査定の結果,「査定後(最悪ケース)」として,Ⅱ分類は1兆9805億円(一般先1兆0822億円,住専1300億円及び関連親密先7683億円)であり,Ⅲ分類2603億円(一般先2115億円,関連親密先488億円)及びⅣ分類1兆1256億円
(一般先1807億円及び関連親密先9449億円)の合計額は1兆3859億円に達するが,できる限り,関連親密先の評価について検査官と協議し,査定後の「努力目標」に近づけること,「査定後(努力目標)」(もっとも可能性が高い分類)として,Ⅱ分類は2兆3719億円(一般先1兆1302億円,住専1300億円及び関連親密先1兆1117億円)であり,Ⅲ分類3334億円(一般先2115億円,関連親密先1219億円)及びⅣ分類6611億円(一般先1327億円及び関連親密先5284億円)の合計額は9945億円に達し,この9945億円を5年間で償却する計画(平成8年度2900億円,平成9年度2400億円,平成10年度2200億円,平成11年度1400億円,平成12年度1045億円)であることが記載
されていた(資料の2枚目)。
また,上記資料における「査定後(最悪ケース)」は,平成8年3月時点における関連親密先の資産について,清算価値をベースに,修正母体行主義により算定しており(甲116の120頁),「アポロリース,インターリース及び東海興業」に対する原告の貸出金についてもⅣ分類と想定していたが,当時,「インターリース」については日本信販株式会社の関連会社として業務を継続しており,経営破綻には至っていなかった(甲125の81頁)。
なお,上記資料には,「関連会社不良資産実態」として,長銀リース外8社の「不良資産」について,「実態ロス」(Ⅲ分類及びⅣ分類合計)が1兆2559億円,原告の貸出が1兆3256億円,「修正母体」による試算額が8437億円であることが記載されていた(上記資料添付別紙4)が,清算した場合における原告の損失負担額(プロラタ方式すなわち貸出残高の割合に応じた損失負担額)は5710億円であった(甲116の128頁,甲132の31頁)。
同日,上記資料の説明会(30分程度)が開催され,Hは,同説明会に出席したD,E,Fら常務以上の役員に対し,上記試算額について説明した。(甲116,甲121,甲125,甲129,甲131,甲132,甲167,甲168,弁論の全趣旨)
(イ) 平成8年の大蔵省検査後の原告の不良債権の検討状況
原告に対する大蔵省検査は,平成8年4月16日を検査基準日として,同月17日から同年6月12日まで実施され,資産査定については,同年5月7日から開始された(甲168添付資料2)。
その間,Hは,大蔵省検査における資産査定の途中経過の報告を受けて,原告の検査を担当した金融検査担当主任検査官のJ(以下「J主任検査官」という。)と面談し,関連ノンバンクの支援状況や受皿会社における事業化計画の状況等を説明して,分類額の圧縮について了解を求めたが,J主任検査官は,回収業務の状況について質問し,また,合理的な理由がない限り,分類額の圧縮に応ずることはできないと回答していた(甲168の23枚目,24枚目)。
大蔵省検査に係る資産分類の最終結果(甲169添付資料3)については,Ⅱ分類2兆5324億円(一般先1兆5420億円及び関連親密先9904億円),Ⅲ分類8960億円(一般先2451億円及び関連親密先5140億円),Ⅳ分類2029億円(一般先68億円及び関連親密先1961億円)であるというものであった。なお,関連親密先は「修正母体行方式にて残高上限」まで資産分類されていた。
その後,大蔵省金融検査部等は,同年10月4日付け示達(甲19)により,原告に対し,原告の関連会社の実態について,「ファイナンス業務を営む関連会社等が有する不良化した貸付債権について,簿価で受皿会社が譲り受け,その譲渡代金相当額を当行が融資している事例」が認められ,その結果,「これらの受皿会社においては,多額の含み損を抱える状況になっている」こと,「受皿会社を含めた関連会社等の相互関係や当行が実行した融資の資金フローについて,現状,いずれの所管部においても的確に把握されていないほか,関連会社等の支援については,一部を除きほとんど手が付けられていない状況」にあり,「関連会社等について,適切な管理に努めるとともに,抜本的な再建計画を早急に策定し,不良債権を計画的に処理して
いくことが必要である」ことを指摘した。その中で,別紙として,「親密・系列等の関係会社関係」として,ジャリック,エヌイーディーグループ(同記載番号1ないし8),第一ファイナンス(同記載番号9),日本リースグループ(同記載番号10ないし14)が記載されていた。
また,上記示達の中の「検査報告書」において,貸出金査定結果,分類額3兆6711億円,「特にⅢ・Ⅳ分類の合計額は,関連会社等を中心に1兆1166億円」にも達しており,3年間の処理方針が立てられていること(1頁),「関連会社等」について,「抜本的な再建計画を早急に策定し,不良債権を計画的に処理していくことが必要である」こと(16頁)が指摘されていた。(甲19,甲168)
イ 金融3法の成立と早期是正措置の導入決定,これを受けた原告の検討状況等
(ア) 金融3法の成立と早期是正措置の導入決定
その後,平成8年6月21日には,金融3法が,国会において可決・成立し,健全性確保法において,銀行法26条(長期信用銀行法17条により長期信用銀行に準用)を改正し,平成10年4月1日以降,早期是正措置制度を導入する旨が定められた。
健全性確保法における改正後の銀行法26条1項は「銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして,当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは,当該銀行に対し,措置を講ずべき事項及び期限を示して,当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め,若しくは提出された改善計画の変更を命じ,又はその必要の限度において,期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ,若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる」旨規定し,同条2項は「前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって,銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときに
するものは,大蔵省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ,大蔵省令で定めるものでなければならない」旨規定していた。(甲22の2,甲146,乙100,弁論の全趣旨)
(イ) 平成8年8月30日の常務会における検討状況
原告は,平成8年8月30日開催の常務会(D,E,F,C及びBが出席)において,総合企画部作成の同日付け「金融行政の転換と当行の対応について(内部管理体制の強化と早期是正措置)」と題する資料に基づき,審議・検討したが,その際,Fは,早期是正措置のための資産の自己査定について,プロジェクトチームを設けて対応していくとのことであるが,「実質的には,多額に抱えてしまっている不稼働資産をどの様な形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。その点は十分認識しておく必要がある。」と発言した。
上記資料(甲22の2)によれば,金融機関の自己責任原則に伴う当局の要請として金融機関に対する資産内容の自己査定要請があること,「早期是正措置の導入→自己査定の正確性と自己資本の充実について格付け,行政措置発動」があることとされ,また,資産自己査定・検査については,全取引先ごとに,企業・案件,資金使途,担保等の状況により,Ⅰ分類からⅣ分類までに自ら分類し,これを内部において検査する必要があること,ノンバンクは別途,当行系ノンバンク,非当行系で区分され,算出方法が修正母体行主義など,左記の一般業種と全く異なることが示されていた。(甲22の1及び2,乙100)
(3) 早期是正措置検討会における検討状況・「中間とりまとめ」の公表と当時における原告の対応,原告内部での不良債権の把握の状況等
ア 早期是正措置検討会における検討状況,中間とりまとめの公表等
(ア) 早期是正措置検討会の概要等
このような早期是正措置が導入されることとなったことを受けて,平成8年9月30日に大蔵省銀行局長の私的研究会として,早期是正措置検討会が発足し,早期是正措置の導入に向けて,その具体的内容の骨格と適正な財務諸表の作成に当たっての基本的考え方や実務指針等について検討し,同年12月には,後記(ウ)の中間とりまとめを作成・公表し,また,平成9年6月19日までに9回の会合が開催され,早期是正措置の導入に関する討論・検討が行われた。
なお,そのメンバーは,座長を国際経営コンサルタント株式会社顧問のK(以下「K」という。),商法学者,経済学者,日本銀行(以下「日銀」という。)の信用機構局長,会計士協会副会長兼銀行等監査特別委員会委員長であったI会計士のほか,株式会社さくら銀行(以下「さくら銀行」という。)の当時専務取締役であったL(以下「L」という。)等の銀行,信用組合の実務者が特別メンバーとして加わっていた。また,適宜,上記会合には,大蔵省金融検査部の企画官,管理課長等の大蔵省職員が説明等のために加わっていた。(証人K,証人L,甲15,甲138,乙115,乙116,弁論の全趣旨)
(イ) 会合における検討状況
a 平成8年11月21日開催の会合(第4回)における検討状況
平成8年11月21日に開催された早期是正措置検討会における会合においては,「償却・引当のあり方等」についての説明,討議が行われ,その中で,I会計士は,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する会計士協会で検討中のたたき台について説明し,その後の討論の中では,「これまでの償却・引当は税法基準に頼りすぎていたのではないか」,「有税でも必要な引当を行うべきとする考え方は判るが,税務会計と企業会計をできるだけ一致させていくべきではないか」といった意見が出された。(乙116)
b 平成8年11月29日開催の会合(第5回)における検討状況
平成8年11月29日に開催された早期是正措置検討会における会合においては,「資産の自己査定のあり方,位置付け等」についての説明,討議が行われ,その中で,当時の大蔵省大臣官房企画官のM(以下「M企画官」という。)は,「資産査定について(案)」(乙114)を資料と示して,その内容を説明し,その後,討議が行われた。
その際,特別メンバーである地方銀行の担当者は,一応今回の案に沿って,自己査定の基準(行内規程)を作成することとなるが,金融機関によってかなり判断に相違が生ずる可能性があり,その場合,各行独自の基準がそのまま認められるのかについて質問し,これを受けて,M企画官は,独自性を発揮するのは重要であるが,その結果が,当局が示す基準に整合しているかどうかについては十分にチェックすることとなると説明した。
その後,Kが,償却・引当の数値基準として,例えば米国の資産査定については,「substandard」(日本のⅡ分類にほぼ相当)について15パーセント,「doubtful」(日本のⅢ分類にほぼ相当)について50パーセントという目安があるが,日本の金融検査の場合に数値基準があるかどうかという質問を行い,M企画官は,Ⅳ分類は基本的に「loss」であり,償却・引当が妥当であると考えているが,Ⅲ分類については,検査のみから具体的な引当数値基準を判断するのは困難であり,当該金融機関の貸付先に対する見方等の判断に大きく依存し,清算した場合の損失額は算出できるが,それは,「ロス額」と相違し,どの程度,個別債権の引当を積むべきかについて指摘するのは困難であると説明した。
また,翁百合委員は,償却・引当及び資産分類の関係と税法との対応関係について質問し,例えば,自己査定の結果,本来の税法基準より引当金を多く無税で積みたいと考えた場合に,従前と同様の許可を受けて無税引当をするのか,そうであるとすると,自己査定の結果,経営者の判断により必要額を引き当てるという考え方とどのように整合性を取るのか,米国の場合,引当は有税,償却は無税となってわかりやすいが,この点はどのようになるのかという質問を行い,これを受けて,M企画官は,資産分類の考え方と税の考え方の関係は,税を横に置いて債権の健全性ということのみから判断していく仕組みである,実際に引当金を積んだときには有税と無税で効果が違う,いわゆる税効果会計はどうなんだという議論は当然あると思うが,
有税であるか無税であるかを外に置いて,それに左右されずに判定するというものであると説明した。
さらに,Kは,問題のある債権について金融機関側の判断と検査結果による判断の相違はどの程度あるのかという点を質問し,これを受けて,M企画官は,最終的には,金融機関側から資料の提出を受け十分議論して決定していること,また,当時大蔵省銀行局調査課長であったN(以下「N調査課長」という。)は,従前,資産査定と償却・引当とが必ずしも明確に結びついた形となっていないこと,監査の立場と検査の立場がかみ合っていないと意見の相違が生じ,検査の最終段階において,様々な問題が生ずること,米国の場合には,早期是正措置の導入以前から自己資本比率に基づく監督を実施し,その段階から資産査定と償却・引当ができるだけ結びつく形でルール化してきた経緯があると理解していること,資産査定と償却・引当に整
合性がある形であっても,個々の検査の場面で,金融機関側との意見が相違する,あるいは,公認会計士の考え方と検査の立場が相違することはあると思うが,早期是正措置検討会に出席した米国の公認会計士が説明していたように,そこは実務的に議論する中で,大きな隔たりが残ってどうしようもないということは少なく,かなり調整できるとの指摘もあり,議論の中で,いろいろ知恵を出していくことになると思うと説明した。
なお,特別メンバーであるLは,個別債権ごとに逐一査定することは実務的な負担が重く,ある程度くくった評価ができるような仕組みも許容すべきであり,自己査定の仕組みをどのように構築していくか,銀行間の格差が大きく,一挙に理想的な形までもっていくことはできないので,実際の適用に当たり,時間的な猶予について配慮してほしいとの意見を述べ,また,特別メンバーである信用組合の担当者からも,400を超える信用金庫全体を眺めれば自己査定が定着するのは相当時間がかかる,業界が全部足をそろえてこれをやっていくのはかなり難しく,方向性自体を否定するものではないが,実務的にみたときの負担を考慮する必要があるとの意見を述べた。(乙115,乙116,弁論の全趣旨)
c その他の検討状況等
また,早期是正措置検討会の会合の中では,地域金融機関,信用組合等から,定量的な基準が示されないと,償却・引当の基準となり得ないとの意見が出されていたが,各金融機関が個々の債権の回収可能性をもっとも認識しており,当局が一律の基準を示すことは不可能であること等から,後記(ウ)の「中間とりまとめ」においても,「機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではない」と指摘されるに止まり,定量的基準は示されず,各金融機関が実情に応じた自主ルールを作成すべきこととされていた。(証人K5頁,6頁,甲138の20頁,21頁)
(ウ) 「中間とりまとめ」の具体的な内容等
早期是正措置検討会は,平成8年12月26日付け「中間とりまとめ」を作成・公表した。
その中では,早期是正措置は今後の新しい金融行政の中核的手法となるものであることが示され,また,早期是正措置の導入に当たっては,金融機関が自らの責任において企業会計原則等に基づき適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提となること,各金融機関が行う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として重要な役割を果たすことになること,会計監査人においては,財務諸表の適正性についての深度ある監査を行うことが求められることが指摘されていた。次に,この早期是正措置の適時の発動の前提として,金融機関の資産内容の実態ができる限り正確かつ客観的に反映された財務諸表が作成され,これに基づき正確な自己資本比率が算出される
必要があること,適正な財務諸表の作成のためには,企業会計原則等に基づき適正な償却・引当が実施される必要があること,そのための要件として,例えば,企業会計原則注解18では,①将来の特定の費用又は損失であって,②起因事象が当期以前に存在し,③損失発生の可能性が高く,④その金額を合理的に見積もることができる場合,という考え方が示されているが,今後の早期是正措置の導入に当たり,各金融機関が更に適正かつ客観的に償却・引当を行いうるよう,会計士協会から償却・引当についての明確な考え方が実務上の指針(ガイドライン)として示されることが望ましいこと,などが示されていた。
また,償却・引当に関し,個別性の強い個々の債権の回収可能性の違いを無視して,機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではないこと,償却・引当の正確性,客観性等をできる限り確保する観点から,各金融機関においては償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備がすみやかに行われることが望まれることが示されていた。
さらに,各金融機関による償却・引当に当たっては,貸倒償却及び貸倒引当金の計上基準に関するガイドラインに従う必要があること,ただ,同ガイドラインについては,なお個別のケースに照らし判断するうえでの具体性を欠く部分があるため,各金融機関は自らの実情を踏まえつつ,より具体的・詳細な償却・引当ルールを自主的に作成し,これに基づいて導き出される個々の債権の回収可能性をもとに償却・引当を実施することが適当であることが示され,加えて,各金融機関が適正な償却・引当の実施を行っていくためには,有税による償却・引当を円滑に進めていく環境整備も必要であること,その観点から,有税償却・引当を行った場合の前払税金等の取扱いを定める税効果会計について,今後,検討が行われることが望ましいことが示
されていた。
この「中間とりまとめ」の中の「資産の自己査定について」の項においては,適正な償却・引当を行うためには,各金融機関は自らの資産内容の健全性を的確に把握する必要があること,資産の健全性を把握するための作業である資産の自己査定は,適正な償却・引当を行うための準備作業として位置づけることが適当であること,資産の自己査定は,各金融機関が有する資産を個別に検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って分類区分することであり,基本的には各金融機関の判断により行うものであるが,適度な統一性の確保という観点からは,各金融機関においてできる限り共通の基本的考え方が確保されていることが望ましいこと,当局がこれまでの検査(資産査定:Ⅰ~Ⅳ分類)における実務をもとに,自己査
定ガイドラインの原案を作成し,本検討会において検討を行った結果概ね了解が得られたので,こうした点を踏まえ,自己査定のガイドラインを作成することが適当であることが指摘され,この「自己査定のガイドライン」においては,正常先債権については,原則としてⅠ分類とする,要注意先債権については,原則としてⅡ分類とする,破綻懸念先債権については,担保等で保全されている部分を除き,原則としてⅢ分類とする,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」については,担保等で保全されている部分を除き,原則としてⅣ分類とするという考え方が示されていた。また,その中で,各金融機関においては,このガイドラインをベースに創意・工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成するこ
とはむしろ望ましいこと,各金融機関が自己査定ガイドラインよりも詳細な自己査定基準を作成する場合は,各金融機関は当局の検査等の際にその合理性,明確性等について説明を行うことが必要であること,「自己査定ガイドライン」は,これまでの検査における資産査定の考え方と基本的に同様である一方,今般,公認会計士協会から債権を正常先,要注意先等の5つの区分に分けてそれらに応じた償却・引当の計上に係る基本的な考え方が示されたことにより,両者は仕組みの大枠において一致が図られたものと考えられること,検査においても,各金融機関がガイドラインに沿って正確な自己査定や適正な償却・引当を行っているかどうかについてチェックする必要があることが示されていた。
この「中間とりまとめ」の「外部監査について」の項では,会計監査人(公認会計士又は監査法人)が行う財務諸表監査において,自己資本比率に関わってくる財務諸表上の数値の正確性などについて,内部統制の状況にも留意しつつ試査の程度を上げるなど,従来より深度ある監査を行うことが求められること,各金融機関が行う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として位置づけられることから,会計監査人が商法監査(会計監査)手続の一部である内部統制の評価を行う作業のなかで,各金融機関において自己査定基準・手続が適正に整備されているか,また,それに沿って自己査定が実施されているか,などについてもチェックすることは償却・引当に係る監査の機能を高める上で有効であることが示されていた。
この「中間とりまとめ」の早期是正措置の「基本的考え方」の項では,早期是正措置は,金融機関が自己責任原則に基づき経営改善への取組みを適時にかつ迅速に行うことを,行政当局が客観的指標に基づき促すことを目的としており,早期是正措置の具体的な発動基準は,金融機関の経営改善への取組みを効果的に促し得るようなレベルに設定する必要があることは当然であるが,他方,早期是正措置は金融機関を破綻に追い込むことを目的としたものではなく,制度導入時において多くの金融機関が達成不可能となるような基準を設けるべきではないこと,米国においては金融機関の不良債権処理に概ね目途がついたとされる平成4年末に早期是正措置が導入されたのと比べると,我が国においては,金融機関全体としては不良債権の処理が進ん
でいるもののなお状況は区々であり,制度導入時の環境は異なるとの見方があること,このような状況の下では,早期是正措置の導入により金融機関の貸し渋りが生じる等,実体経済に大きな悪影響が生ずることのないよう配慮することも必要であることなどが示されていた。
なお,「中間とりまとめ」の中の「自己資本比率(国内基準)の算定方法の見直し」の項(9頁)では,国際統一基準に従い,分子を自己資本(TierⅠ+TierⅡ)とし,分母をリスクアセット(甲121の120頁によれば,自己資本比率算定の際の分母となる数値であると認められる。)とし,分子を分母で割った数値(自己資本比率)を基準とすること,また,制度運営の基本的考え方として,是正措置の区分は,「第一区分:経営改善計画の作成・実施命令」,「第二区分:個別措置(注)の実施命令」,「第三区分:業務の一部又は全部の停止命令」が定められ,上記「第二区分」における「個別措置(注)」については,「増資計画の策定,総資産の増加抑制・圧縮」等が考えられるとされていた。また,「各措置区分の発動基準となる自己
資本比率の値」は,国際統一基準については「第一区分」は「8パーセント未満」,「第二区分」は「4パーセント未満」,「第三区分」は「0パーセント未満」とすることが定められていた。(甲15)
(エ) 「中間とりまとめ」に関する説明等
Kは,平成9年1月ころ,金融雑誌の取材を受けた際に,自己資本比率のバーについて,新制度スタート後3年間を経過期間と位置づけて実施状況を見極めたうえで平成12年度末までに基準値を見直すことを提言していること,現在,不良債権処理が峠を越したとしても,まだ29兆円もの残高があり,早期是正措置の尺度となる実質的な自己資本比率は厳しいものとなること,早期是正措置検討会に参考人として出席した米国監査法人の関係者は,日本の早期是正措置制度導入のタイミングは悪すぎると述べていたこと,平成9年度末までに増資,劣後債務の導入により自己資本の増強を図ったとしても,それを十分に調達し得る市場環境にはなく,結果的に深刻な貸し渋りが発生することも懸念され,早期是正措置の発動数値の決定に関しては
,金融システムや日本経済への影響を考慮しなければならないことを説明した。また,Kは,中間とりまとめにおける自己査定ガイドラインや償却・引当の考え方は定性的・抽象的な表現に止まり体制づくりに入れないのではないかとの質問を受けて,自己査定と償却・引当に関するガイドラインについて各金融機関の間の適度の統一性を確保するための目安にすぎないこと,各金融機関が自己責任原則に基づいて自らの実情と債権の個別性を踏まえて,主体的に自己査定の引当・償却を決めなければならないことを説明し,債務者区分ごとの貸倒実績率について各金融機関が過去のデータを有していないのではないかとの質問について,平成10年の開始時にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいが,しかし,その時点で不完全であっても,即「
落第」という機械的な裁定はできないこと,ある程度の趨勢は把握し得るし,公認会計士がチェックするので,必要な精度を確保し得ることを説明していた(乙19)。
さらに,Kは,当時において,早期是正措置の導入により不良債権処理に関する手当を完了させることは理論的にはあり得るが,そのような場合,多数の金融機関が業務改善命令や業務停止命令の対象となり,金融システムが大混乱に陥るため,いくつかの経過措置をとったこと,金融機関が自己資本比率をできるだけ改善する結果,分母におけるリスクアセットの圧縮すなわち貸し渋りに進み,日本経済に大変な影響を生じさせること,そのために,この貸し渋りをどのように防止するかについても考慮していた(甲138の13頁,14頁)。(証人K,甲138,乙19)
イ 自己査定体制検討プロジェクトチームの結成及び自己査定基準の検討状況と不良債権償却計画の検討状況等
(ア) 自己査定体制検討プロジェクトチームの結成
原告は,平成8年10月1日,早期是正措置導入の決定に伴い,資産の自己査定体制,手法,基準等の具体策を検討するため,D(当時頭取)の決裁により,自己査定体制検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を結成した。その担当役員は,B(当時常務)であり,アドバイザーとして,F,C(いずれも当時常務)及びH(事業推進部部長)が加わっていた。(甲23,甲99添付資料1,甲129の44頁)
(イ) 事業推進部による不良債権償却計画の検討状況
事業推進部は,平成8年10月29日付けで,「今後の不良債権処理について」と題する資料(甲24)を作成した。
上記資料によれば,「MOF検査査定結果」として,Ⅱ分類が2兆5324億円(一般先1兆5420億円及び関連親密先9904億円),Ⅲ分類が8960億円(一般先2451億円,住専1369億円及び関連親密先5140億円),Ⅳ分類が2029億円(一般先68億円及び関連親密先1961億円)であるとされ,関連・親密会社の実態不良資産の状況として,「MOF検分類状況」における「関連ノンバンク合計」のⅡ分類7164億円,Ⅲ分類5139億円,Ⅳ分類1961億円であること,他方,実態ベース(「MOF検分類に捕らわれずに現時点において当行として本音ベースで自己査定した場合の分類数字。但し,修正母体方式であるため当行残高が上限」)における関連ノンバンク合計のⅡ分類が3284億円,Ⅲ分類が84
8億円,Ⅳ分類が1兆0608億円であるとされていた。
また,上記資料によれば,関連親密先ノンバンクの不良債権については,修正母体行主義により原告の融資残高を上限とした場合の最終要処理額が1兆4275億円(当面処理額1兆1071億円)に達すること(№4),受皿会社の不良債権について,最終要処理額が2639億円(当面処理額337億円)に達すること(№5),これらの関連親密先の最終処理の合計額が1兆6914億円であること(№5)がそれぞれ指摘されており,これらの関連親密先の不良債権の償却について,原告が平成9年3月から5年の期間で支援(日本リースについては支援の再開を検討)を行うこと,その場合の償却額は,当面処理必要額として1兆0911億円,企業維持ベースとして合計2251億円,一部処理ベースとして合計5045億円,終了宣言
ベースとして1兆0131億円であること(№6)が想定されていた。
さらに,上記資料によれば,大蔵省に提出する予定の不良債権の償却計画(修正後のもの)として,Ⅲ分類7640億円(一般先1654億円及び関連親密先5986億円)及びⅣ分類2045億円(一般先53億円及び関連親密先1992億円)について,当初3年間(平成8年度ないし平成10年度)で,一般先を含む不良債権を5500億円処理することとされており(№9),その具体的な内容(№10)は,平成8年度2521億円(一般先1578億円及び関連親密先943億円),平成9年度1828億円(一般先810億円及び関連親密先1018億円),平成10年度1185億円(一般先254億円及び関連親密先931億円)というものであり,償却計画や実施スケジュールについて,償却財源と自己資本比率(国際統一基準
すなわちBIS基準8パーセント)の維持を考慮し,関連親密先を除く一般先の処理を義務的に行い(「must」),関連親密先の処理については,赤字決算を回避して企業を維持し,不良債権の増加を防止しながら,具体的な償却財源の状況(株価水準と株式含み益)に応じて,3年で一般先を含めて,5492億円から1兆0898億円までの処理をすること(№12)とされていた。
平成8年10月29日,Hは,Fに対し,上記資料に基づき,不良債権の償却計画を説明した。
その後,事業推進部は,同年11月11日付けで,上記資料を多少修正した「今後の不良資産処理について」と題する資料(甲26)を作成し,Hは,同日,Dに対し,上記資料に基づき,原告の不良債権の償却計画を説明した。
なお,これらの資料における「実態ベース」については,その時点における企業の清算価値を前提とした修正母体行主義により算定されたものであり(甲116の171頁),前記ア(イ)の円卓会議における資料の「査定後(最悪ケース)」と同様の趣旨で記載されていた(甲125の102頁)。(甲24ないし甲26,甲114,甲116,甲125,甲169,弁論の全趣旨)
(ウ) 原告内部の自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況等
その後も,原告内部において,自己査定基準及び償却・引当基準が検討され,事業推進部は,平成8年12月11日付けで,「早期是正措置の導入に伴う自己査定制度のあり方」と題する資料(甲27)を作成した。
上記資料によれば,「自己査定基準に係るMOF案の推移」(№2)として,大蔵省が自己査定について統一的なガイドラインの提示をしたが,実際にはガイドラインには具体的な数値基準を盛り込まず各行の裁量部分をある程度認めること,特に関連・親密については一律的な基準を作らず当初は個別行の事情により個別に対応する可能性も大きいことが記載され,次に,「当行の自己査定基準のあり方」(№3)として,関連親密先と一般先の基準を区分することにより関連親密先の要処理分類額の圧縮を最大限図り4パーセント(BIS基準8パーセント)をクリアーすること,Ⅲ分類基準の弾力化及びⅢ分類引当の段階化により償却引当負担の軽減,平準化を図ることとされ,具体的内容として,一般先については,Ⅰ分類(正常先),Ⅱ分
類(要注意先),Ⅲ分類(破綻懸念先),Ⅳ分類(実質破綻先及び破綻先)に分類し,分類に沿って償却・引当(Ⅲ分類は一定割合の償却・引当を行い,Ⅳ分類は全額の償却・引当を行う。)を行うこと(№3,№5),他方,関連親密先は概念的に破綻懸念先と実質破綻先に区別することは可能だが,支援先については合理的再建計画に基づき当行が支援を行うという点において,破綻懸念先と実質破綻先の区別は意味をなさないこと(№4),また,原告の支援先については支援計画における当期支援額(Ⅳ)は償却・引当を行い,翌期以降の支援予定額(Ⅱ)は対象外とされていた。
また,「当行自己査定基準による要処理不良債権額試算」の「関連親密先の自己査定の考え方」(№6)として,支援計画があるエヌイーディーについては,当該年度処理予定額をⅣ分類,次年度以降の処理予定額をⅡ分類と自己査定すること(支援計画で将来当行貸付金償却が明らかなものについてⅢ分類とせずⅡ分類とすることについて合理的な説明が必要),日本リースについては,本業の収益力で不稼働資産を抱えたまま企業維持が可能であり,徐々に(10年程度で)自力処理ができる場合,また含み資産の活用等により自力償却が見込まれる先は非分類とすること,第一ファイナンスについては,債権処理のために設けられたSPC等会社の実態がない先(物件整理以外に存在意義のない先)については,貸付金のロス,繰り欠をⅣ分類
資産の含み損をⅢ分類査定とすること(実態のない会社であり含み損,損失額が確定していないとの理由で説明できるか)が指摘されていた。
さらに,「主要論点別の問題点・課題」(№8,9)として,関連・親密先の別基準化がうまく行くかどうかが当行にとって今回新制度の最大のポイントであること,実質破綻先認定を最大限回避できるような自己査定基準の設定が不可欠であることが指摘され,会計上チェック基準ルールについて監査法人が会計士協会のルールを機械的に当てはめてくることはまずないと思われるがルールの決め方,縛り方如何によってはかなり影響が出てくること,自己査定内容と償却・引当実施額との関係については,ポイントはⅢ分類の償却をどうするかということ,即ちⅢ分類の中でも実態に即していくつかの段階に分けそれぞれ引当率を設定する等分離処理ができるかということ,同様に一般先と関連会社とを区分し,関連会社分については自己査定と
償却・引当との遮断を図ることができることがそれぞれ指摘されていた。
なお,上記資料には,株式会社日本債券信用銀行(以下「日債銀」という。)が大蔵省金融検査部から入手した「関連ノンバンク自己査定統一基準フローチャート」が参考資料3として添付され,同資料には,「系列ノンバンクとは,基本的には関連会社通達上の関連会社で貸金業を営む会社であるが,関連会社に該当しない場合であっても,各金融機関との間に何らかの関係があり,その会社の業況不振に対して,当該金融機関において実質的に責任があるとの経営判断を行い,いわゆる母体行としての支援を実施しているもの,あるいは今後実施しようとしているもの」という指摘がされ,また,フローチャートとして,系列ノンバンクに対する貸出金については,系列ノンバンクの体力について検討し(支援損計上の必要の有無,営業貸付金の
延滞率,債務超過(実質ベース)状態の有無,借入金の延滞又は金利減免・残高維持等の金融支援の有無),体力がある場合には,非分類とし,体力がない場合には,3年以内に不良債権の処理が可能であれば,非分類(単年度処理可能)又はⅡ分類(2,3年以内で処理可能)とし,3年以内に不良債権の処理が不可能であれば,再建計画に問題がない場合は支援損相当額をⅣ分類,その他をⅡ分類とし,再建計画の策定がない場合又は再建計画に問題がある場合は原則営業貸付金の査定結果を自行(庫)の貸出金にⅣ,Ⅲ分類の順に充当し,残額をⅡ分類とすること,なお,有価証券,不動産の含み損益等も勘案することが指摘されていた。(甲27,甲64添付資料3,甲132の47頁)
(エ) 平成8年12月19日常務役員フリーディスカッションにおける不良債権処理の検討状況
原告は,平成8年12月19日,原告の常務以上の役員が出席する「常務役員フリーディスカッション」と呼ぶ会議を開催し,事業推進部作成の同日付け「今後の不良資産処理について」と題する資料(甲169添付資料5)や総合企画部作成の同日付け「今後の決算・資本対策について」と題する資料(甲161添付資料4)に基づき,今後の不良債権の処理計画に関する討議・検討が行われた。
a 事業推進部作成の「今後の不良資産処理について」
上記資料(甲169添付資料5)によれば,MOF検査結果として,関連・親密のⅢ分類5140億円,Ⅳ分類1961億円の要処理合計額は7101億円とされ(№1),実態ベース要処理額として,関連・親密7社(エヌイーディー,日本リース及び第一ファイナンスを含む。)については,総資産8兆0228億円,延滞債権1兆5619億円,同ロス額9909億円,不動産等含み損6153億円,資本勘定1000億円のマイナス,最終要処理額1兆7603億円,当面要処理額7957億円との指摘がされていた。
また,上記資料によれば,平成8年度から平成10年までの3年間の償却計画としては,償却財源と自己資本比率(BIS基準8パーセント)を考慮し,株価に応じて,処理額5642億円,処理額7247億円及び処理額1兆2431億円の3種類の償却計画(№2)があると指摘され,5642億円の償却計画は,関連親密先の黒字決算を維持するため1695億円を処理するが,関連親密先の企業維持は事実上困難であること(担当者は,取引金融機関からの回収圧力により企業維持が困難となるおそれがある旨説明した。),7247億円の償却計画は,関連親密先の企業維持はギリギリ可能であること,1兆2431億円の償却計画は当面の目標レベルであるとされていた(甲169の24枚目,25枚目)。
上記資料における関連親密先の要処理額については,関連親密先が抱える不良債権とその含み損,不動産等含み損等の総額であり,最終的にこれらの会社が処理すべき不良資産であった(甲121の111頁)。
なお,Hは,上記資料を作成させた際,経営陣に危機感を持ってもらうため,前記(ウ)の同年11月11日付け資料よりも厳しい表現にするととともに,償却金額の水増しを指示し,担当者にそのような資料を作成・記載させ,これにより多額の償却財源を要することを原告の経営陣に強く印象づけようとした(甲169の25枚目,26枚目)。(甲121,甲169,弁論の全趣旨)
b 総合企画部作成の「今後の決算・資本対策について」
上記資料(甲161添付資料4)によれば,平成8年度から平成10年度までの不稼働資産処理内訳と正味自己資本比率試算として,以下の試算がなされていた。
まず,MOF検時提出計画における平成8年度から平成9年度の不稼働試算処理見込額は7785億円(Ⅲ5590億円,Ⅳ2045億円,買取二次損失分150億円+一般分非Ⅲ・Ⅳ分類追加処理必要額である「非」150億円),そのうち一般分は2583億円(Ⅲ2348億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),関連先は5202億円(Ⅲ3242億円,Ⅳ1960億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.60パーセント(含ファイナンス)又は4.17パーセント(除ファイナンス)であった。
「示達回答書計画」における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は5534億円(Ⅲ3480億円,Ⅳ1904億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),関連先は2892億円(Ⅲ1073億円,Ⅳ1819億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.10パーセント(含ファイナンス)又は3.65パーセント(除ファイナンス)であった。
関連親密企業維持ベース(株価2万3000円程度を想定)における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は7247億円(Ⅲ3747億円,Ⅳ2045億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),一般分(非分類追加分)は1305億円,関連先は3300億円(Ⅲ1340億円,Ⅳ1960億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,4.21パーセント(含ファイナンス)又は3.78パーセント(除ファイナンス)であった。
現実処理可能ベース(株価2万2000円程度を想定)における平成8年度から平成10年度の不稼働試算処理見込額は5642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ1780億円,「非」1455億円),そのうち一般分は2642億円(Ⅲ2407億円,Ⅳ85億円,「非」150億円),一般分(非分類追加分)は1305億円,「関連先」は1695億円(Ⅳ1695億円)であり,その場合の平成11年3月期における正味自己資本比率(TierⅠ)は,3.70パーセント(含ファイナンス)又は3.25パーセント(除ファイナンス)であった。
また,検討すべき対応策として,早期是正措置に向けて,不稼働資産を3年間で5500億円処理し,ファイナンス(増資)により1000億円を調達し,株式含み益3000億円を維持することを従前の認識としたうえで,追加的対応策として,ファイナンスの必達額は1000億円から1300億円であり,リスクアセットの1兆円から1.7兆円(3年間)の圧縮,収益積上(体質改善計画見直し)及び不動産の活用(本店売却益の計上)が必要であることが指摘されていた。なお,上記検討においては,最終的な結論は出されず,今後の株価の推移をみて,再検討することとされた(甲161の18頁)。(甲116,甲121,甲161,弁論の全趣旨)
(オ) 平成9年2月7日常務役員連絡会資料
総合企画部は,平成9年2月7日付けで,「今後の当行業務運営の基本的方向」と題する常務役員連絡会資料を作成し,同日開催された常務役員連絡会において,その説明を行った。
上記資料によれば,前提となる環境認識として,新規発生見込みを含めた今後の不良債権要処理額見込は最低7000億円から1兆円レベルで,かつ早期是正措置により平成9年度以降Ⅲ,Ⅳ分類資産は単年度での適正な償却・引当の実施が不可避であると指摘されていた。(甲28,乙100)
(カ) 平成9年2月14日常務会資料
検討チームは,平成9年2月14日付けで,「早期是正措置に係る資産自己査定について(MOF検討会での中間とりまとめを受けた中間報告)」と題する資料(甲99添付資料2)を作成し,同日開催された常務会において,この資料に基づく報告を行った。
上記資料によれば,早期是正措置発動に当たっては,自己資本比率(国際統一基準)を指標とすること,各金融機関は,自己の責任において適正な償却・引当を実施し,資産内容の実態を客観的に反映した財務諸表に基づき自己資本比率を算出すること,したがって,資産の自己査定は,適正な償却・引当の準備作業として重要な役割と位置付けることが指摘されていた(1枚目)。
上記資料によれば,「自己査定における課題と今後の検討ポイント」(4枚目)として,本番の平成10年3月期のBIS基準8パーセントクリアに向けて,当行自己査定基準および償却・引当のルール作成に当たっては,(ア)自己査定基準は一般先と関連親密先を区分して作成する。MOFガイドラインでは関連ノンバンクの記載なし,(イ)Ⅲ,Ⅳ分類基準に的を絞った検討。Ⅲ,Ⅳ分類の相当を占める関連親密先について,査定基準を慎重に作成,(ウ)Ⅲ分類の償却引当率の段階適用。個々の債権の回収可能性に着目して段階的(上限50パーセント)な引当率の設定を検討するとの指摘がされ,また,Ⅲ,Ⅳ分類の相当を占める関係会社については一般先と異なる基準を慎重に作成し,具体的にはMOF事務方において検討していたと思われる関
連ノンバンクの査定基準を参考にして,①支援損計上・金融支援の有無,②営業貸付金の延滞率,③実質面での債務超過状況,④不良債権処理に要する期間,⑤再建計画の有無等に着目してきめ細かな分類を行う方式を検討する旨の指摘がされていた。
さらに,償却・引当基準として,「Ⅳ分類の100パーセント償却・引当は当然で,Ⅲ分類の引当水準の設定がポイントであり」,具体的には,行政指導としての現行一律50パーセント引当を変更して,例えば15パーセントないし50パーセントと幅を持たせ,実体面と個別性を強調して個々の債権の回収可能性により引当率を決定する方式を検討するとの指摘がされていた。(甲99添付資料2,乙108)
(キ) 平成9年3月10日常務会資料
総合企画部は,平成9年3月10日付けで,「当面の業務運営の考え方と中期的展望~ビックバンへの戦略的対応~」と題する常務会資料(甲161添付資料10)を作成し,同日開催された常務会において,報告を行った。
上記資料によれば,早期是正措置への対応として,資産の自己査定による適正な償却・引当により不稼働処理を単年度実施するものとし(平成9年度見込み最小限3000億円),これを平成9年度決算に反映して自己資本比率(BIS基準)8パーセントを達成する必要があること,また,資産圧縮額とその資産圧縮計画として,平成11年度までに,貸出資産2兆5000億円の圧縮(平成8年度7500億円,平成9年度から平成11年度まで1兆7500億円),政策株式1兆円の売却及び不稼働資産1兆円の処理(平成8年度3000億円,平成9年度から平成11年度までの3年間で7000億円処理)により,4兆5000億円の資産圧縮が実施されることが指摘されていた。
なお,上記不良債権処理のうち,償却処理は,7000億円(平成8年度2000億円,平成9年度から平成11年度までの3年間5000億円)が予定されていた。(甲116の16頁,17頁,甲121の43頁,甲161添付資料10)。
(4) 資産査定通達の発出,全銀協Q&Aの送付,4号実務指針の公表,9年事務連絡の発出及び全銀協追加Q&Aの送付
ア 資産査定通達の発出
(ア) 資産査定通達の発出・内容
大蔵省金融検査部長は,資産査定通達を発出し,債務者区分を5段階で区分し,これを前提に担保等による回収可能性も考慮して,債務者ごとに貸出金をⅠないしⅣの4分類とするとしていたが, 同通達によれば,金融検査においては,従来から,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から,その保有する資産について,個々の資産を回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分し,査定を行っていること,一方,平成10年4月1日より,金融機関経営の健全性を確保していくための新しい監督手法である早期是正措置制度が導入されることとなるが,同制度は,金融機関が,企業会計原則等に基づき,自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸
表を作成することを前提としたものであること,金融機関が行う自己査定は,金融機関が適正な償却・引当を行うための準備作業として重要な役割を果たすこととなり,また,会計監査人は,財務諸表監査に際し,金融機関が行う自己査定等内部統制の状況についてもその有効性を評価することになること,金融検査における資産査定においては,通常,このようにして行われた金融機関の自己査定及び会計監査人による監査を前提とし,自己査定結果の正確性等をチェックすることとなることが指摘されていた。
また,資産査定通達によれば,早期是正措置検討会における検討を踏まえ,早期是正措置導入後の金融検査における資産査定が金融機関による自己査定等を前提としてより適切かつ統一的に行い得るよう,これまでの金融機関における資産査定の実務をもとに,改めて「資産査定について」を作成したので通知すること,検査に際しては,検査直前決算期(中間決算を含む。)等において金融機関が行う自己査定について,その基準が明確かどうか,またその枠組みが「資産査定について」の枠組みに沿っているかどうか等を把握し,金融機関の自己査定基準の枠組みが独自のものである場合には,「資産査定について」の枠組みとの関係を明瞭に把握するとともに,金融機関の自己査定基準の中の個別ルール(例えば,担保評価ルールや有価証券の
簡易な査定ルールなど)が合理的に説明できるものであるかどうか等をチェックすることとなることが指摘されていた。
さらに,上記「資産査定について」の中で,貸出金の査定に当たっては,その回収の危険性の度合に応じて,債務者の返済能力(財務状況,資金繰り,収益力等)を判定し,債務者の区分を行い,資金使途等の内容を個別に検討し,さらには担保や保証等の状況を勘案のうえ,貸出金の査定(資産分類)を行うこととされていた。
すなわち,債務者を「正常先」,「要注意先」,「破綻懸念先」,「実質破綻先」及び「破綻先」に区分して,この債務者区分に応じて,「正常先」に対する貸出金については,原則非分類とし,「要注意先」に対する貸出金のうち,一定の類型のもの(不渡手形,融通手形及び期日決済に懸念のある割引手形,赤字・焦付債権等の補填資金,業況不良の関係会社に対する支援や旧債肩代わり資金等,金利減免・棚上げあるいは元本の返済猶予など貸出条件の大幅な軽減を行っている貸出金等貸出条件に問題のある貸出金,元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題のある貸出金及び今後問題を生ずる可能性が高いと認められる貸出金,債務者の財務内容等の状況から回収について通常を上回る危険性があると認められる貸
出金)で,優良担保(預金等〔預金,掛け金,元本保証のある金銭の信託,満期返戻金のある保険をいう。以下同じ。〕,国債等の信用度の高い有価証券及び決済確実な商業手形等をいう。)の処分可能見込額(担保評価額を踏まえ,当該担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額をいう。)及び優良保証等(公的信用保証機関,金融機関及び金融機関が設立した信用保証会社等の保証,地方公共団体の損失補償契約等保証履行の確実性が高い保証(ただし,保証機関等の状況,手続不備等の事情から代位弁済が疑問視される場合及び自行(庫・組)が履行請求の意思がない場合を除く。),証券取引所上場の有配会社で,かつ保証者が十分な保証能力を有し,正式な保証契約による一般事業会社の保証,住宅金融公庫の「住宅融資保険」などの公的保険
のほか,民間保険会社の住宅ローン保証保険」などの保険等という。)により保全措置が講じられていない部分を原則Ⅱ分類とし,「破綻懸念先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分をⅡ分類,それ以外の部分をⅢ分類とし,「実質破綻先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分を原則Ⅱ分類,優良担保及び一般担保の評価額と処分可能見込額との差額及び保証による回収見込みが不確実な部分をⅢ分類,これ以外の回収の見込み
がない部分をⅣ分類とし,「破綻先」に対する貸出金については,優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外のすべての貸出金を分類し,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分並びに清算配当等が見込まれる部分をⅡ分類,優良担保及び一般担保の評価額と処分可能見込額との差額及び保証による回収見込みが不確実な部分をⅢ分類,これ以外の回収の見込みがない部分をⅣ分類とするとされていた。
(イ) 資産査定通達に関する説明等
大蔵省は,資産査定通達を発出した際に,これは各金融証券検査官がマニュアルにより検査を統一的に行い得るよう改めて作成したものであるが,各金融機関が行う自己査定について,共通の考え方を確保することに資するとして,全銀協等の関係金融団体を介して,その内容を各金融機関に公表し,また,金融雑誌において,大蔵省大臣官房企画官等が,その概要を説明した(乙20の29頁)。
上記通達を発出した当時の大蔵省金融検査部長O(以下「O金融検査部長」という。)は,金融雑誌の取材を受けて,「資産査定について」の原案に対するもっと詳細な当局基準が明らかにならないと,準備作業に入れないとの指摘もあったという点について,各金融機関の資産内容は規模,地域性,業種,時期などにより様々で,一律に適用できる詳細な査定基準を作成するのが難しいこと,自己査定の意義が金融機関における自己責任の徹底と信用リスク管理能力の向上にあり,各金融機関が,自らの実情に沿った詳細な基準を創意工夫により自主的に作成することが望ましいこと,検査官用のマニュアルとして検査における資産査定の統一を図ることを一義的な目的とする「資産査定について」を公表したのは,各金融機関が作成する自己査定
基準の基本的考え方についての「適度の統一性」の確保に資すると期待したことを説明した。また,自己査定の導入によって金融検査はどう変わるかという質問に対しては,金融検査の内容が大きく変わること,検査の基本的なチェックポイントは,例えば金融機関は自己査定基準を明定しているか,自己査定基準の枠組みが「資産査定について」のそれに沿ったものであるか,より詳細な資産区分概念などを持つなど独自色が強い基準を作成している場合には,「資産査定について」の枠組みとの関係を合理的かつ明確に説明できるかどうか,自己査定の体制がどうか,自己査定基準に沿って適切な自己査定が実施されているかどうか等であることを説明した。さらに,「資産査定について」で公表された分類方法は,従来の検査におけるそれと同一なのかと
いう質問については,基本的には変わらないこと,ただ,対外的に金融証券検査官用の資産査定マニュアルを公表したのは初めてのことであり,その理由が適度の統一性の確保と検査の透明性の向上にあることを説明した。また,自己査定体制が適正なものであるかどうかをチェックするため,平成10年4月以後早い段階で短期間のうちに全金融機関に対する検査が必要ではないかという質問に対しては,短期間に全金融機関に対して検査を実施するのは現実問題として難しく,過去の検査等を通じておおよそ把握している状況に応じて検査時期を計画したり,早期是正措置の導入までの間においても,各金融機関の体制整備状況等について把握するよう努めていきたいことを述べていた(乙21)。(甲1,乙20,乙21,乙119)
イ 全銀協Q&Aの作成,送付
全銀協の融資業務専門委員会は,傘下の銀行の融資担当部長に宛てて,全銀協Q&Aを送付したが,その中では,資産査定通達において定められた債務者区分,資産分類や担保等に関する解釈や具体的な適用事例が示されていた。
また,上記文書には,現時点での情勢を前提とした資産査定に係る一般的な考え方をまとめたものであり,将来にわたって固定されたものではなく,また個別金融機関の有する特殊性・地域性等は考慮されていない旨の指摘がなされていた。(甲2)
ウ 4号実務指針の作成,公表
その後,会計士協会は,平成9年4月15日付けで,4号実務指針を作成し公表した。なお,その際,公表方法はJICPAジャーナルにおける記者会見の方法によること,公表者名を会計士協会とすること,解説は特にせず,また,審議決定後の関係諸団体との調整は必要ないこととされていた(甲98添付資料2)。
4号実務指針によれば,早期是正措置の導入に伴い,銀行等金融機関(銀行のほか,信用金庫などの協同組織金融機関等を含む。以下同じ。)は,自ら資産の査定基準を定めて,その有する資産を検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に応じて分類区分すること(以下「自己査定」という。)が必要になったこと,自己査定は,貸倒償却及び貸倒引当金の適正な計上に資するものであること,銀行等金融機関は,自己査定基準を定めて,それに準拠して適正な自己査定が可能となるような内部統制を構築することが求められること,監査人は,貸倒償却及び貸倒引当金の監査を実施する際,自己査定基準が適正に整備され,自己査定の作業がその基準に準拠して実施されていることを確かめなければならないこと,監査人は,銀
行等金融機関の自己査定に係る内部統制が整備され,適切に運用されていることを確かめる必要があり,また,誤びゅう等の額が銀行等金融機関の自己資本比率に与える影響を十分考慮して監査上の危険性の許容水準を決定する必要があることなどから,より深度のある監査に努めることが求められることが指摘されていた。
また,内部統制の有効性の評価に当たっての留意事項として,銀行等金融機関は,それぞれ体系的な自己査定基準を作成することとされていることから,自己査定基準が文書化され,正式の行内手続を経て規程化されているか確かめること,自己査定基準に示す査定分類は,「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」(蔵検104号平成9年3月5日)の別添「資産査定について」と同一である必要はなく,より細かい分類であってもよいが,「資産査定について」の分類に整合し,分類の対応関係が確保されていることを確かめる必要があること,銀行等金融機関は,それぞれ,具体的かつ詳細な貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する規程を作成することとされていることから,当該規程が文書化され,正式の行内手続を経
て規程化されているか確かめ,また,当該規程は,本報告「6.貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱い」に整合し,かつ,それぞれの自己査定基準とも適切な連動が保たれているか確かめることが指摘されていた。
また,監査手続の適用については,査定の結果について,特に分類債権については,最終判断についての説明が付されており,判断と説明が整合しているかを確かめること,自己査定制度導入後の会計監査において,検査当局の検査結果は,監査上の参考として常に注意を払う必要があるが,検査時点の相違や頻度の相違等の理由から,当局の検査結果をそのまま監査判断の基礎として利用すれば足りるとはいえないことに留意する必要があること,監査人は,必要に応じて,銀行等の金融機関の了解のもとに,検査当局と可能な範囲内で直接情報交換を行うことが監査の効率化の観点から適当であることが指摘されていた。
さらに,貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いとして,以下の監査上の取扱いに準拠して計上されている場合には,監査上妥当なものとして取り扱うことが示され,その準拠すべき監査上の取扱いとして,「正常先債権」,「要注意先債権」,「破綻懸念先債権」,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」のそれぞれの債権に区分すること,「正常先債権」及び「要注意先債権」については,債権額で貸借対照表に計上し,貸倒実績率に基づき貸倒引当金を計上すること,「破綻懸念先債権」については,債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し,残額のうち必要額を貸借対照表に貸倒引当金として計上すること,「実質破綻先債権」及び「破綻先債権」については,債権額から担保の処分
可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し,残額を貸倒償却するか又は貸倒引当金として貸借対照表に計上することとされ,また,貸倒実績率は正常先債権や要注意債権という分類毎の貸倒実績率によること,貸倒実績率の算定方法は種々考えられるが,その一例として,ある期間の期首(仮に3年間の推移でみる場合,該当する3年間を一つの期間とみた場合の期首)の該当する分類の債権残高を分母とし,その分母の額のうち期間内に毀損した額(貸倒償却及び貸倒引当金として計上した額の他,債権売却損等の損失額を含む)を分子として計算する方法があることとされていた。
なお,4号実務指針の適用される時期については,平成9年4月1日以降開始する事業年度に係る監査から適用するが,平成9年9月30日に終了する中間会計期間において銀行等金融機関が自己査定に係る内部統制を構築し,その旨を表明した場合には,当該中間会計期間に係る監査から適用するものとされていた。(甲3,甲60,甲98,甲159,乙119)
エ 9年事務連絡と全銀協追加Q&A
大蔵省は,金融証券検査官等に宛てて,平成9年4月21日付けで,9年事務連絡を発出した。
9年事務連絡によれば,その発出経緯については,関連ノンバンクに対する貸出金について,当面の方針として,当該貸出金の分類額が直ちに引当・償却に結びつけられるか否かは別にして,いわゆる母体行主義を前提とし,将来の親金融機関等の経営に与える影響等を総合的に把握することに重点を置き,査定を行っているが,最近においては,必ずしも母体行主義が貫徹されない例も散見され,さらに,平成10年4月から早期是正措置制度が導入されることに伴い,4号実務指針が公表され,この中では資産査定と企業会計における償却・引当とを極めて密接に関連づけていること等の状況の変化を踏まえ,改めて関連ノンバンクに対する貸出金の査定の在り方についてとりまとめられたものであるとされていた。
そして,金融機関等の関連ノンバンクの査定の基本的考え方として,関連ノンバンクに対する貸出金については,関連ノンバンクの体力の有無,親金融機関等の再建意思の有無,関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無(又はその進捗状況)等を総合的に勘案し査定すること,関連ノンバンクの体力の有無については,当該ノンバンクの資産状況,収益状況により判断し,具体的には,営業貸付金の査定結果や有価証券及び不動産等の含み損益の状況等を通じ把握した当該ノンバンクの資産の状況が実質債務超過であるかどうか,実質債務超過の場合には当該ノンバンクの償却前利益により概ね2年ないし3年で当該債務超過を解消できるかどうかを体力の有無の判断の一応の目安とすること,具体的な査定方法等としては,実質債務超過でない場合
,又は償却前利益により概ね2年から3年で実質債務超過の解消が可能であるなど自力再建ができる関連ノンバンク(いわゆる体力がある関連ノンバンク)に対する貸出金については,一般債務者に対する貸出金と同様に査定すること,概ね2年ないし3年で実質債務超過が解消できない関連ノンバンク(いわゆる体力がない関連ノンバンク)に対する貸出金については,実質債務超過の状況,親金融機関等の再建意思の有無,関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無(又はその進捗状況)等を総合的に勘案し査定することとされていた。
また,体力がない関連ノンバンクについては,(1)親金融機関等がいわゆる母体行責任を負う意思がない場合を前提として,①親金融機関等が関連ノンバンクを再建する意思がなく,かつ,いわゆる母体行責任を負う意思がない場合には,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建の見通しがない場合には,親金融機関等の当該ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果を親金融機関等の貸出金のシェアにより分類する(いわゆるプロラタ方式による分類)こと,②親金融機関等が関連ノンバンクを再建する意思はないが親金融機関等の貸出金額の範囲内において損失負担(プロラタ方式以上かつ貸出金全額以下)する意思がある場合において,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超
過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建の見通しがない場合には,親金融機関の当該ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とする。なお,経営の意思により債権放棄額が当該年度に確定しており,当該額が上記貸出金のシェアにより算定したⅣ分類額を上回る場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅢ分類とすることとされ,これに対し,(2)親金融機関等がいわゆる母体行責任を負う意思がある場合を前提として,①再建計画が作成されている場合において,再建計画に合理性がないと認められる場合には,関連ノンバンクが実質的に大幅な債務超過の状況に相当期間陥っており,かつ,再建計画に合理性がなく再建の見通しがない場合には,親金融機関
等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすること,①’再建計画が作成されている場合において,その他の場合には,親金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,全額をⅢ分類とする(ただし,この場合のⅢ分類の額は,当該ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類とⅢ分類の合計額を限度とすることができる)こと,なお,再建計画に沿って経営の意思により債権放棄額が当該年度に確定している場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅢ分類とする(経営の意思による債権放棄を当該年度に一括して行う場合は,その金額をⅣ分類とし残額をⅡ分類とすることができる)こと,②再建計画が作成されていないか又は検討中の場合に
おいて,関連ノンバンクの再建可能性が十分あると認められる場合には,原則として,親金融機関等の当該ノンバンクに対する貸出金の全額をⅢ分類とする(ただし,この場合のⅢ分類の額は,当該ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類とⅢ分類の合計額を限度とすることができる)こと,これ以外の場合は,親金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金は,原則として,営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を親金融機関等の貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすることが示されていた。
その後,全銀協は,9年事務連絡の考え方に従い,全銀協追加Q&Aを作成し,同年7月11日ころ,傘下の銀行にこれを送付した。その中で,上記関連ノンバンクの体力の有無や査定方法の基準等が示され,またその点に関するフローチャートが添付されていた。(甲4,乙111)
(5) 平成9年度上期における原告の自己査定基準及び償却・引当基準の検討・策定状況,同上期における決算の検討状況等
ア 事業推進部における自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況,総合企画部における決算に関する検討状況等
(ア) 事業推進部作成の「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」
事業推進部は,平成9年5月9日付けで,「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」と題する資料(甲61添付資料2)を作成し,この資料に基づき,D,E,F,G及びHらに対し,検討チームの最終答申案について説明した。その際,事業推進部の担当者は,債務者区分については,大蔵省金融検査部原案等についても説明した(甲61の2枚目,甲99の18頁)。
上記資料は,後記イの常務会資料とほぼ同内容であったが,「当行案による自己査定見込額と前回MOF分類」(№14)と「早期是正措置対策」(№20)の点が付加されていた。
上記資料によれば,まず,「当行案による自己査定見込額と前回MOF分類」について,支援予定分(翌期以降の支援額)をⅢ分類とした場合,Ⅱ分類が9723億円となり,Ⅲ分類3969億円及びⅣ分類1872億円の合計額が5841億円となること,支援予定分(翌期以降の支援額)をⅡ分類とした場合,Ⅱ分類が1兆3488億円となり,Ⅲ分類204億円及びⅣ分類1872億円の合計額が2076億円となることが指摘され,また,参考として,前回MOF検によるⅡ分類が1兆0797億円であり,Ⅲ分類5140億円及びⅣ分類1961億円の合計額が7101億円であること(№14)が指摘されていた。
また,「早期是正措置対策」(№20)について,関連親密先の自己査定は「日本リースの扱い等無理をしているところがあること,償却・引当も引当率の考え方が会計士と相当議論になることは必至である」こと,会計士は,従来の会計監査との整合性から,大幅な査定や償却を要求することはないと思われるが,会計士協会の動向,他の銀行での状況等により会計士のスタンスが振れて全体として査定額,償却・引当額も増える可能性があること,時間をかけて処理すること(3か年による処理)に会計士の理解が得られる場合と得られない場合とに分けて,理解を得られる場合において各関連親密先の処理に関する合理的説明を準備すること,理解を得られない場合において前倒処理と自己査定・引当額の圧縮を図ることとされていた。(甲2
9の1及び2,甲61,甲99,甲103,甲105)
(イ) 総合企画部作成の「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」
総合企画部は,平成9年5月9日付けで,「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料(甲30)を作成し,これに基づき,D,F,G及びHらに対し,前記(ア)の事業推進部の説明と同じ機会に,決算等に関する説明を行った。
上記資料によれば,検討のポイントとして,早期是正措置をクリアし得る「不稼働処理必要額」の見極めとBIS比率8パーセント割れを回避しつつ,「必要不稼働処理」を可能とするリスクアセット,決算運営が挙げられ(1頁),「決算・BIS運営」として,同年9月期にリスクアセット21兆円を達成し,償却財源となるべき株式含み益がない(株価1万8000円)前提で,中期計画における不稼働資産の3000億円を償却した場合におけるBIS比率について試算し(2頁),また,日経平均株価の動向による不稼働資産の処理可能見込額を試算(株価が1万6500円から2万2000円までの場合において,1500億円から7000億円までの段階において不稼働資産の処理が可能)し,不動産売却益(1000億円)による償
却財源の状況が記載され(3頁),最終的に,償却・引当見込額(4598億円)と処理計画額(3454億円)がリンクしておらず,平成9年度処理額見込みとの調整が必要であること,支援対象である関連親密先(エヌイーディーほか2社)の償却・引当の必要額とその他の関連親密先のうち破綻懸念先及び破綻先の取扱いがポイントとなること(4頁)が指摘されていた。(甲30,甲64,甲99,乙108)
イ 常務会における原告の自己査定基準及び償却・引当基準の承認
D,E,F,C及びBは,平成9年5月23日開催の常務会において,検討チームの最終答申である同日付け検討チーム作成の「早期是正措置への対応について」と題する常務会資料(甲31の2)に基づき,原告の自己査定基準及び償却・引当基準について報告を受け,その内容を了承した。
上記資料の内容は,前記ア(ア)の事業推進部作成の資料とほぼ同内容であり,前記ア(ア)の「当行案による自己査定見込額」と「早期是正措置対策」の記載は除外されていた。
上記資料によれば,まず,「早期是正措置への対応の基本的考え方」(№1)として,各金融機関が自らの責任において自主的に定めた基準で適正に自己査定を実施すること,その結果に基づき,企業会計原則等に基づき自らの責任で適正な償却・引当を実施することが基本原則であり,そのための具体的基準について,MOF金融検査部のガイドラインで示された債務者区分等と平成9年4月(予定)の会計士協会のガイドラインで示される償却・引当の考え方は,いずれも定性的な内容であり,具体的基準の細目は,これらのガイドラインの趣旨に沿って別途個別に策定すること,具体的には,一般先自己査定基準,関連親密先自己査定基準及び国企所管先自己査定基準とこれらの基準ごとの各償却・引当基準を策定することが指摘されていた。
次に,「関連・親密先自己査定基準」(№9)として,MOFの考え方について,MOFガイドラインにおいては関連ノンバンクについて特に何の記載もないことからすると原則各金融機関の判断で自由に決められるという建前であるが,実態的には影響の大きさから敢えて決めなかったというのが真実に近いと考えられること,原告の基本認識について,「前回MOF検における関連・親密先のⅢ,Ⅳ分類は合計で7100億円と全体(除住専)の約74パーセントを占めており,これへの対応如何が今回の自己査定さらには早期是正措置対応の最大のポイントといえるから合理的説明が可能な範囲で最大限の圧縮が必要であること,一般先と関連・親密先とは別基準とすること,前回MOF検査結果については最大限尊重するが,当行の合理的基準
を優先すること,MOF金融検査部原案の考え方については極力取り込むこととするが,これを機械的に適用せず統一的基準で自己査定すること,償却・引当についても一般先と関連会社を区分し,当行の合理的基準によることとされていた。
また,「当行自己査定基準(案)」(№10)として,債務者区分のうち,「要注意先」及び「破綻懸念先」の区分については,残存不良債権の処理期間は,大蔵省金融検査部原案の3年ではなく,5年を基準とすること(国税の支援終了認定の目安),「実質破綻先」及び「破綻先」の区分については,原告の関連ノンバンクが法的に破綻することはなく,実質破綻先と破綻先との区別がつきにくいため,最終的に原告の支援の対象先かどうかで区分することが指摘され,「関連・親密先償却・引当基準」(№12)として,会計士協会,MOFの考え方について,いずれも関連親密先の償却・引当基準に関する具体的規定・考え方がないこと,当行の考え方について,関連親密先は一般先のように突然破綻するという偶発損失リスクは全くなく,当
行が完全にコントロールしている以上形式的には同一の債務者区分にあっても一般先とは異なる償却・引当基準を適用すること,具体的には,支援の有無等の実態に応じて個々に適切な償却・引当をすること(正常先及び要注意先は個別の償却の対象外とするが,破綻懸念先,実質破綻先及び破綻先については,当期支援予定額全額をⅣ分類として全額償却し,Ⅲ分類は,債務者区分に応じて12.5パーセントから50パーセントまでの引当を実施すること)が指摘されていた。(甲31の1及び2,甲99)
ウ 平成9年6月時点における中間決算に関する検討状況
D,E,F及びHは,平成9年6月12日,総合企画部作成の同日付け「97/上期決算運営について」と題する資料(甲162資料1)に基づき,同年度の中間決算に関する説明を受けた。
上記資料によれば,中間決算は黒字を維持すること,不稼働資産1000億円を処理すること,処理の財源として業務純益(使用可能額500億円)及び株式含み益の実現分又は不動産売却益(500億円)が考えられ,株価の状況により株式含み益が減少した場合(株価1万8000円台で株式損益が500億円程度の赤字)には,本店等の不動産売却益(500億円から1000億円程度)により不稼働資産処理の財源を賄うことが指摘されていた。(甲99,甲162,乙100)
エ 平成9年7月ころにおける事業推進部の関連親密先に対する自己査定基準の検討及び策定の状況
(ア) 自己査定試行(トライアル)用の基準
事業推進部は,原告の関連親密先に対する貸出金の査定基準として関連ノンバンクに係る自己査定(トライアル)運用規則(以下「トライアル運用規則」という。)及び当行経営支援先及び特定関連親密先自己査定(トライアル)運用細則(以下「トライアル運用細則」という。)を策定し,その後いくつか改訂して,平成9年7月10日には最終的な内容を決定した。
まず,基本的な趣旨・内容として,トライアル運用細則及びトライアル運用規則は,同年6月末を基準日とする自己査定試行(トライアル)を実施するに当たり,関連親密先に関する基準を定めるものであること,関連親密先や経営支援先について,通常の一般債務者と同様の基準で債務者区分・資産査定を行うことは適当ではなく,自己査定の趣旨を反映しつつ,対象先の特殊性を加味した査定基準を定めるものであること,経営支援先について,原告の支援が必要であり,同時に原告の支援がある前提では企業維持に懸念がなく,通常の債務者区分をあてはめることが適当ではないため,債務者区分を行わないこと,経営支援先に対する与信は企業維持が前提であり,原則Ⅱ分類とすること,ただ,当該年度の経営支援損については損失が明らか
であり,Ⅳ分類と査定することが定められていた(甲5の1)。
次に,トライアル運用規則において,関連ノンバンク(エヌイーディーが想定されていた。甲5の2「関連親密先自己査定フローチャート」参照)について,2,3年で実質債務超過額の解消が不可能であり,原告が母体行責任を負う意思があり,再建計画に客観的な合理性が認められる場合には,当期支援分をⅣ分類とし,支援予定残額をⅢ分類とし,それを超える部分をⅡ分類とすること(甲5の2の2頁,甲62の9枚目),再建計画が作成されていない場合(第一ファイナンスが想定されていた。甲5の2「関連親密先自己査定フローチャート」参照)には,与信先の営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金の割合(シェア)に応じてⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすること(甲5の2の2頁,甲62の6枚目)が定められており,また,ト
ライアル運用細則において,全銀協追加Q&Aにはないが,経営支援先,経営支援実績先及び関連親密特定先の債務者区分を設けて日本リースを経営支援実績先として全額Ⅱ分類とすること(甲62の7枚目,甲64の30頁,32頁),関連親密特定先について債務者区分に応じて正常先又は要注意先とし(甲62の6枚目),資産分類について担保相当分を非分類とし,その他をⅡ分類とすること,関連ノンバンクの関係会社を関連ノンバンク本体と一体であるとして同一の区分とすることが定められた(甲62の6枚目)。(甲5の1ないし3,甲62)
(イ) 被告らに対する説明状況等
FとHは,平成9年8月6日,事業推進部作成の同日付け「自己査定トライアル結果と平成9年度不良債権償却計画」と題する資料(甲62添付資料4)に基づき,同年6月を基準とする自己査定(トライアル)作業結果に関する報告を受けたが,その際,事業推進部の担当者から,関連親密先のⅢ分類の資産の引当について,さくら銀行が引当をしない方針を採っているとの説明があり,事業推進部においてこれに合わせて同様の方針を採ることとされた(甲62の16頁)。
なお,これらの基準は,株式会社日本興業銀行(以下「興銀」という。)の基準やさくら銀行の基準,さらには住友信託銀行株式会社(以下「住友信託」という。)の基準を参考とし(甲62の10頁,15頁,甲64の17頁,18頁,53頁,乙101の6頁,乙102,乙103),また大蔵省において原案が作成された「自己査定統一基準フローチャート」(甲27添付参考資料3)に基づき作成されていたが,その内容について相当自主裁量性が強く,公認会計士に認められない可能性もあること(甲62の11枚目)が指摘されていた。(甲62,甲64,乙101ないし乙103,弁論の全趣旨)
(6) 不良債権償却証明制度の廃止,改正後決算経理基準,早期是正措置の内容
ア 不良債権償却証明制度の廃止等
大蔵省は,平成9年6月には,不良債権償却証明制度を廃止するとの方針と,また自己査定結果を償却・引当に正しく反映するよう決算経理基準を改正するとともに,償却・引当が商法・企業会計原則に基づき行われるよう当局への有税償却の届出を廃止するとの方針を示し,同年7月4日蔵検第296号通達により,不良債権償却証明制度を廃する通達を発出した。(甲57,甲58,乙24)
イ 改正後決算経理基準の導入とその内容等
(ア) 改正後決算経理基準の導入
大蔵省銀行局長は,原告を含む各銀行の代表取締役頭取に宛てた通達により,改正前決算経理基準の中の貸出金の償却及び貸倒引当金の規定を改定し,これにより,平成10年3月期から改正後決算経理基準が適用されることになった。
(イ) 改正後決算経理基準の内容と貸出金の償却・引当に関する改正
前記(ア)の通達によれば,経営管理の項目には,新たに「資産の自己査定のあり方」として,銀行は預金者等から受け入れた資金を貸出金等の資産により運用しており,自らの資産内容の健全性を的確に把握することは銀行の責務であること,したがって,各行においては,商法,企業会計原則等及び第5に定める決算経理基準をも勘案し自己査定基準を作成し,各決算期(中間決算期を含む。)において,当該基準に基づき自らの資産を検討・分析して,回収の危険性又は価値の毀損の度合に応じて分類区分することが必要であること,銀行による自己査定の体制は,基本的には銀行が自らの責任において定められるべきものであるが,当局として望まれる自己査定のあり方については「(別紙)資産の自己査定のあり方について」のとおりである
ので留意する必要があることが新たに設けられた。
また,資産査定通達の発出に伴い,改正前決算経理基準の経理処理の原則について,資産の評価は,自己査定結果を踏まえ,商法,企業会計原則等及び下記に定める方法に基づき各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施するものとすると改正し,また,貸出金の償却及び貸倒引当金についても改正し ,貸出金及び貸出金に準ずるその他の債権(以下「貸出金等」という。)の評価は次のような公正・妥当と認められる方法によるものとすることとして,(イ)貸出金等の償却について,回収不能と判定される貸出金等については,債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額(以下「回収不能額」という。)を償却する,(ロ)債権償却特別勘定への繰入れは,回収不能と判定される貸出
金等のうち上記(イ)により償却するもの以外の貸出金等については回収不能額を,最終の回収に重大な懸念があり損失発生が見込まれる貸出金等については債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額のうち必要額を,それぞれ繰り入れるものとすること,貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定(租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。以下同じ。)を除く。)は,貸出金等のうち上記(イ)により償却するもの及び上記(ロ)により債権特別勘定へ繰り入れるもの以外の貸出金等について,合理的な方法により算出された貸倒実績比率に基づき算定した貸倒見込額を繰り入れるものとすることと改正され,また各行が定める償却基準により償却するとするものが,少なくとも税
法で容認される限度額は必ず償却するものとすることと改正された。(甲59,甲183,甲231,乙23,乙81,乙118ないし乙120,弁論の全趣旨)
ウ 早期是正措置の内容
平成9年7月31日には,長期信用銀行法17条において準用される銀行法26条等の規定に基づき,長期信用銀行施行規則の改正(同日号外大蔵省令第61号)が行われた。
その内容(長期信用銀行法施行規則20条の2,3)については,原告のような海外拠点を有する長期信用銀行において国際統一基準に係る自己資本比率(いわゆるBIS比率)が用いられ,早期是正措置発動の基準及び措置の内容として,大蔵大臣は,自己資本比率が4パーセント以上8パーセント未満となれば,経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令を,同比率が0パーセント以上4パーセント未満となれば,自己資本の充実に資する措置に係る命令を,同比率が0パーセント未満となれば,業務の全部又は一部の停止の命令をそれぞれ発することができると規定されていた。
また,自己資本比率についても,銀行法14条の2が長期信用銀行法17条により準用されており,長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき,長期信用銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための大蔵省告示により定められ,その基準は,銀行法上の普通銀行と全く同一の基準であった。(甲139,甲146,甲231,弁論の全趣旨)
(7) 原告の自己査定トライアル,自己査定基準の策定と監査法人への説明,平成9年度決算に対する検討状況等
ア 平成9年8月1日の常務役員連絡会議
原告は,平成9年7月19日,スイスバンクコーポレーション(以下「スイス銀行」という。)との間で,証券業務等を目的とする合弁会社の設立,スイス銀行による原告に対する2000億円の増資引受け及び3パーセントの相互株式の持合を内容とする業務提携に関する基本合意を締結した。
これを受けて,同年8月1日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「中期シナリオの方向性へ向けた更なる加速と追加施策について」と題する資料(甲100添付資料⑤)に基づき,原告の経営全体の問題に関する検討が行われた。
上記資料によれば,今後の決算・BIS比率見通しとして,スイス銀行による資本注入,日経平均株価が平成9年度に2万円台であり,配当政策が平成11年3月期まで1株6円であるとの前提に立って,平成10年3月期において,不稼働資産5000億円(一般先2000億円,関連親密先3000億円)を処理し,リスクアセット21兆円の場合の自己資本比率9.07パーセントとなるとの試算がなされており,また,不稼働資産処理内訳のイメージについて,自己査定トライアル(速報ベース)による平成9年度要償却・引当見込額の試算として,一般先について1792億円(Ⅲ分類2397億円の50パーセントの額とⅣ分類593億円の合計額),関連親密先について3533億円(非支援先のⅢ分類額753億円の50パーセントの
額及びⅣ分類256億円の合計額と支援先のⅣ分類額2900億円との総額)すなわち総額5325億円の償却・引当を実施することが指摘されていた。
当時,Dは,スイス銀行との合意によるファイナンスが実施され,自己資本額が2000億円増加し,その結果BIS比率に余裕が生じて,その分中期計画の不稼働資産の処理額について3000億円の増額が可能となると考えた(甲116の41頁)。(甲100添付資料⑤,甲116,乙100)
イ 自己査定トライアルに基づく不良債権償却計画の検討状況
事業推進部は,トライアル運用細則及びトライアル運用規則等の自己査定基準に基づき,平成9年7月ころから,同年6月末を基準とする自己査定の試行(トライアル)を行い,これに基づき,同年9月2日付け「自己査定トライアルと97年度不良債権償却計画」と題する資料(甲32)を作成した。
上記資料によれば,自己査定作業の結果として,Ⅰ分類12兆7799億円,Ⅱ分類2兆9352億円,Ⅲ分類7150億円(そのうち関連親密先4359億円)及びⅣ分類2038億円(そのうち関連親密先1254億円)であること,Ⅲ分類とⅣ分類の合計額が9188億円(そのうち関連親密先5793億円)であることが示され,また,自己査定結果に基づく償却・引当試算として,今回の自己査定(トライアル)結果についてほとんどの銀行は,基本的には平成9年9月中間決算には反映させない方針であり,当面,自己査定結果と償却・引当との関連を厳密に考える必要はないが,平成9年12月基準による平成10年3月の本番実施時においては,今回のトライアル結果より大幅に減らすことは不自然・不可能であり,そういう意味では
今回のトライアルの出し方が平成10年3月期 の結果を事実上決めてしまうことになるので,今回のトライアル結果が本番実施時の最低ラインであり,事実上償却・引当予算から逆算的にⅢ,Ⅳ分類数字を決めざるを得ないことが指摘され,一般先・関連親密先を問わず,Ⅳ分類の資産(貸出金)について100パーセント,Ⅲ分類の資産について50パーセントの償却・引当を行った場合における償却・引当額は5613億円になり,Ⅲ分類の資産のうち関連親密先に対する部分について償却・引当を行わなかった場合には償却・引当額は3344億円となること,必要償却・引当額は計算上3300億円ないし5600億円となり,概ね平成9年度処理予定額5000億円の範囲内に収められる水準となっているが,裏を返せば本番実施時においてこ
れ以上自己査定額が積み上がる(含む会計士に否認されて増加する)と処理予定額を超えることになること,関連親密先の自己査定基準・方法はそれなりの無理をしていることもあり,相当の理論武装が必要となることが指摘されていた。
また,上記資料によれば,今回自己査定(トライアル)の問題点として,今回の自己査定トライアルは結果として概ねMOF査定額と同規模になっているが,実質的には事推所管先においてかなり無理をしているものであり,この点について今後他行動向,会計士のスタンス,更には平成9年秋の日銀考査の結果によっては平成10年3月の本番の際には修正せざるを得ない可能性もあること,関連親密先についてはMOFの関連ノンバンク通達に基本的に依拠しているものの,当行個別基準もそれなりに使って査定額の圧縮を図っていること,各行ともある程度関連親密先について弾力的な考え方で対応していく見込みであるが,当行の場合相当自主裁量性の強いものとなっておりこのあたり会計士に認められない可能性は十分あり得ることが指摘さ
れており,個別には,関連親密先のうち,エヌイーディーグループについて当該年度の支援損Ⅳ分類,残額をⅢ分類とし,日本リースグループについて本体を全額Ⅱ分類,グループ企業を正常先と要注意先に区別し,第一ファイナンスについて本来は貸出金全額ⅢⅣ分類であるが,含み損の部分で足きりとすることとされ,さらに,償却財源については,現実実態ベースではなお8000億円ないし9000億円残っており,年間5000億円では依然として財源不足との指摘もされていた。
なお,F,G及びHは,同月1日には,上記資料に基づき,担当者から説明を受けた(甲62の2枚目)。(甲32,甲62)
ウ 原告の自己査定基準に対する本件監査法人への説明と本件監査法人による了解
本件監査法人の原告の担当者であった公認会計士P(以下「P会計士」という。)及び公認会計士Q(以下「Q会計士」という。)は,平成9年9月2日,原告本店を訪問し,Hほか事業推進部のメンバーから,トライアル運用規則及びトライアル運用細則について説明を受けた。その際の主な説明内容は,債務者区分として「関連ノンバンク」以外の「関連親密先」を設けることの適否であったが,その点について,P会計士及びQ会計士は,おおむね上記自己査定の基準について資産査定通達等の許容範囲であると考え,その旨回答した。(甲64の56頁,57頁,甲132の52頁,甲136の48頁,65頁,68頁)
エ 平成9年度決算及び同期配当(本件中間配当及び本件決算配当)に関する検討状況等
(ア) 平成9年9月16日開催の常務役員連絡会議における検討状況等
D,E,F,C,B及びGは,平成9年9月16日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「97年度中間決算見込みについて」と題する常務役員連絡資料(甲162添付資料7)に基づき,同期における中間決算に関する検討を行った。
上記資料によれば,不稼働資産の処理財源として,使用可能業務純益が680億円(業務純益750億円)であること,株価の水準に応じて株式損益(株式3勘定尻)が127億円ないし481億円となること,不稼働資産は,業務純益及び株式損益を用いて,800億円ないし1000億円の処理が可能であることを前提に,平成9年上期決算主要項目の運営方針として,業務純益750億円を確保すること,株式損益について期末株価が1万8000円でも不動産売却益を必要しない利益を確保することとされ,不稼働処理として,不稼働資産の最低処理必要額を800億円とし,最大で1000億円を処理すること,ただ,関連先支援損の計上は,中間期においては必須としないこと及び支援完了でない限り「ディスクロ」に寄与しないことか
ら,中間期での計上を見送ることとされ,また,中間決算赤字と中間配当について,法律的見解として,中間決算を赤字とした上で中間配当を行うことは,黒字の場合に比べより取締役の期末配当可能利益の予測義務は重たくなるものの,期末の配当利益が確保される合理的根拠が存在する限り可能であるが,繰越利益は営業年度中に取締役会決定で取り崩すことができるのに対して,任意積立金の取り崩しは総会決議マターでありかかる性格のものを中間段階で前提にして配当を行うことは公正な会計慣行上妥当性に欠けるとの意見もあり,赤字決算の可能性を再検討した場合,中間決算を赤字とした場合であっても,中間配当は可能であるが,妥当性の点について疑問があること,中間期において不稼働資産の年間処理分(予定額5000億円)の早期処理
実施も不可能ではないが,剰余金(3433億円)を上回る水準の赤字幅(4000億円)となり,またBISの水準も8パーセント前後となり,個別処理案件の積上げも困難であり,現実的な選択肢となり得ないこと,また,他行動向も現状株式会社東京三菱銀行(以下「東京三菱」という。)を除き,中間では黒字としたうえで,年間での赤字を視野に入れた決算運営となる模様であること,以上を踏まえ,中間期において黒字決算を維持し,年間で赤字決算をすることが妥当であることが指摘されていた。(甲33,甲100,甲105,甲162,乙100)
(イ) 自己査定トライアル分類結果速報
原告は,平成9年10月16日,自己査定トライアルの結果について集計し,「自己査定トライアル分類結果速報」と題する資料を作成した。
同資料によれば,総資産額22兆8208億1500万円のうち,非分類12兆4761億0600万円,Ⅱ分類3兆0735億9300万円,Ⅲ分類7696億2500万円及びⅣ分類合計額1757億9300万円であること,平成8年4月の大蔵省検査における分類資産の額と比較した場合,Ⅱ分類は2937億2400万円増加し,他方,Ⅲ分類は1461億7300万円減少し,Ⅳ分類は337億5900万円減少していること(1枚目),関係会社の貸付金自己査定のトライアルと上記大蔵省検査の結果を比較した結果として,総貸出額は2兆6264億円(大蔵省検査時2兆2836億円)であり,貸出額が3427億円増加し,非分類が1914億円,Ⅱ分類が2821億円それぞれ増加し,他方,Ⅲ分類が214億円,Ⅳ分類が1
094億円それぞれ減少していること(4枚目)が指摘されていた。(甲104添付資料3)
(ウ) 中間決算案の承認と会計監査人への提出案に関する取締役会決議
被告A,D,E,F,C,B及びGは,平成9年10月28日開催の取締役会において,中間貸借対照表案及び中間損益計算書案を承認し,会計監査人に提出する旨の承認決議をした。なお,中間損益計算書案には,経常利益106億5800万円,税引前中間利益102億7700万円,中間利益100億5100万円が計上されていた。(甲34,甲65添付資料1)
(エ) 平成9年11月段階における同年度決算に係る検討状況等
a 平成9年11月12日の常務役員連絡会議における検討状況
D,E,F,C,B及びGは,平成9年11月12日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「97年度決算運営について」と題する常務役員連絡資料(甲163添付資料5)に基づき,同年度の決算に関する検討を行った。
上記資料によれば,単体赤字許容額として,決算配当を維持する場合に不稼働資産の処理に使用し得る剰余金額が3200億円程度(現状の配当原資及び利益準備金を除いたもの。将来の配当原資確保のためには2500億円ないし2800億円の赤字幅が限度)であること,無配当の場合でも自己資本比率8パーセントを維持するため,赤字許容額が3600億円程度であり,繰越損失について利益準備金及び資本準備金の取崩しが可能であることが指摘され,株価別不稼働処理可能額として,株価の水準(1万5000円から2万円まで)に応じて,おおむね3000億円ないし5500億円(赤字3200億円に不動産売却益1000億円を考慮した場合には,3700億円ないし7200億円)程度の不稼働資産の処理が可能であることが
記載され,「注」に自己査定トライアル結果に基づく処理額試算として,トライアル結果について,一般先1802億円(Ⅲ分類25パーセント,Ⅳ分類全額),関連先は862億円(Ⅳ分類のみ全額),合計額は2664億円であり,本査定想定について,一般先は2750億円,関連先は1150億円ないし2650億円,合計額は3900億円ないし5400億円であり,また,SBC向け今年度処理説明骨子として,今年度不稼働処理額が5000億円,自己査定トライアルの状況を踏まえた最低必要額は約3000億円(一般先2000億円及び関連先1000億円),さらに長銀リース及びランディックの支援完了を目指し,追加は2000億円であることが指摘されていた。
また,上記資料によれば,主要事項のリスク認識として,配当維持の選択は,赤字許容額が2500億円程度であり,株価次第で不稼働処理不十分のリスクがあること,これに対し,無配の選択は,不稼働処理可能額は拡大するが,他方,当時進められていたスイス銀行との資本提携の大幅遅延に伴う環境悪化が懸念されることが指摘され,また,不稼働処理額について当初予定の5000億円でも処理不十分とされるリスクがあること,総額5000億円の処理ができない場合には,不稼働資産の処理が遅れ,原告の格付け等環境が悪化し,資金調達面等激しいアゲインストとなるリスクがあるほか,スイス銀行への説明と乖離し,資本提携の枠組みに悪影響を及ぼすことも指摘され,当面の基本的対応方向として,年間処理予定額5000億円
は,現状株価では厳しい水準であるが,スイス銀行,アナリストへの説明内容(不稼働資産5000億円を処理する)や引当率の水準等を考慮した場合,下方修正により,不稼働資産処理額が5000億円に満たないとき,処理の遅れが顕在化する危険性(スイス銀行に対する説明内容と乖離した場合の提携の枠組みに対する悪影響や銀行の格付けが低下するおそれ)があり,現状では5000億円の不稼働資産を処理する方針とすることとされていた。
なお,Dは,5000億円の不稼働資産の処理を前提に,長銀リースのみの支援を完了する場合の処理額を3900億円,長銀リース及びランディックの支援を完了する場合の処理額を5400億円であると認識し(甲116の53頁),また,無配の選択は,スイス銀行によるファイナンス実施の観点から困難であること,今期(平成9年度)において一般先についての2500億円及び関連先についての867億円(当期支援額)の合計約3300億円の処理をしなければならない(「must」)が,無配・有配において,いずれを選択した場合でも,上記金額3300億円の処理は可能であることを認識し(甲116の57頁から59頁まで),さらに,これは日経平均株価1万4300円までを想定しており,1万4300円を株価が下回った
場合には,無配とせざるを得ないことを認識していた(甲116の61頁)。(甲36,甲65,甲66,甲89,甲100,甲105,甲116,甲163,弁論の全趣旨)
b 平成9年11月17日開催の常務役員連絡会における検討状況等
D,F,Eらは,平成9年11月17日開催の常務役員連絡会議において,総合企画部作成の同日付け「自己査定トライアル(97/6基準)結果と今年度の償却・引当見込みについて」と題する常務役員連絡会資料(甲37)に基づき,平成10年3月期の償却・引当に関する検討を行った。
上記資料(平成9年6月末を基準として行われた自己査定のトライアルの結果を集計し,同時に分類資産ごとに倒産確率を基準とした償却・引当率を示したもの。乙100の23頁)によれば,一般先のうち正常先及び要注意先について貸倒引当金が最大でも546億円に達すること,一般先のうち債権償却特別勘定に組み入れられる部分(破綻懸念先,実質破綻先及び破綻先)について1644億円(Ⅲ分類25パーセント償却,Ⅳ分類100パーセント償却)に達すること,関連親密先については,原告との関係から倒産リスクがなく,継続企業として必要な支援を行っている以上,Ⅰ分類からⅢ分類までの資産について償却・引当を行わず,Ⅳ分類(当期支援額)に限り,全額(867億円)償却すること,平成10年3月期決算における自
己査定結果に基づく償却・引当試算として,トライアルの一般先に対する償却試算1644億円(Ⅲ分類及びⅣ分類合計額3919億円),査定案(試算)の一般先に対する償却試算2771億円(Ⅲ分類及びⅣ分類合計額4191億円),関連親密先については,長銀リース,ランディック及びエヌイーディーに対する支援を前提に,長銀リースのみの支援を終了する場合には,Ⅳ分類償却額1150億円,これにランディックの支援終了を加えた場合には,Ⅳ分類償却額2650億円であることとされ,おおむね合計3900億円ないし5400億円の償却・引当が見込まれていた。(甲36,甲37,甲62,甲65,甲66,甲89,甲101,甲103,甲104,乙100,弁論の全趣旨)
c 本件監査法人による内部統制監査と中間決算案に対する監査報告書の提出
本件監査法人は,平成9年10月ないし同年11月ころ,原告の自己査定に関する内部体制の整備状況について監査を実施したが,その際,自己査定基準に係る手引,与信監査制度に関する内部文書を閲覧し,原告の担当者からその説明を受けた。(甲136の4頁,49頁)。
また,本件監査法人の担当会計士であった公認会計士T(以下「T会計士」という。),P会計士及びQ会計士は,同年11月20日付けで,前記(ウ)の取締役会決議に基づき提出を受けていた原告の平成9年度中間決算案(中間貸借対照表及び中間損益計算書)について,中間監査の結果,これらの中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して原告の平成9年度の中間会計期間(平成9年4月1日から同年9月9月30日まで)に関する有用な会計情報を表示しているものと認める旨の監査報告書(甲7の17枚目)を提出した。(甲7,甲34,甲65,甲101,甲136)
(オ) 平成9年11月21日常務役員連絡会議における承認
D,E,F,C,B及びGは,平成9年11月21日開催の常務役員連絡会において,総合企画部作成の同日付け「中間配当実施について」と題する資料(甲65添付資料6)及び同日付け「平成9年度中間期決算発表(11/25)について」と題する資料(甲65添付資料12)に基づき,同年度の中間配当及び決算配当(いずれも1株3円)を行い,不稼働資産5000億円(一般先2500億円,関連親密先2500億円)を処理することを決定した。
上記「中間配当実施について」と題する資料によれば,剰余金(配当可能利益)額が3447億円,年間配当必要額が188億円であること,償却・引当の財源としては,日経平均株価が1万4300円(平成2年以降の最安値を基準)まで下落した場合に保有株式の損失見込額2050億円が発生するが,業務純益のうち1300億円及び不動産売却益1000億円から海外現地法人閉鎖等の臨時損失額100億円を控除した2200億円が考えられること,年間赤字額最大3200億円とした場合,最大3350億円の償却財源が見込まれることが指摘されていた。
また,「平成9年度中間期決算発表(11/25)について」と題する資料によれば,年間業績予想として,年間業務純益が1500億円であること,配当については,中間3円,期末3円とすること(12パーセント配当)とされ,また,補足説明として,年間不稼働処理見込額が5000億円であること,また平成10年3月期のBIS比率の見込みとして,ファイナンスが実施された場合には9.7パーセント程度,ファイナンスがない場合,リスクアセットを20兆円まで圧縮すれば,8.4パーセントであること(現状の21兆円を前提とした場合には8パーセントギリギリの水準)が指摘されていた。
なお,上記常務役員連絡会に先立つ同月20日,原告の法務部は,中間配当の可否について,期末の株価についてバブル崩壊後の最安値を採用していること,不稼働資産処理の必要最少額を3350億円とする点についても,自己査定試算額を基準としており,算定の不合理性はないことを挙げて,中間配当の実施に関しては,取締役の善管注意義務違反の問題はない旨回答した(甲65添付資料8)。(甲65,甲89,甲101,甲105,甲165)
(カ) 本件中間配当の承認決議
被告らは,平成9年11月25日開催の取締役会において,同年度の中間配当として,1株3円,合計額71億7868万8924円の金銭の分配を行う旨決議し,これに基づき,平成11年6月3日までに,71億7564万6348円の中間配当が実施された。
なお,中間貸借対照表には,剰余金3447億3000万円(任意積立金3176億3000万円,中間未処分利益270億9900万円)が計上され,中間損益計算書には,税引前中間利益102億7700万円,中間利益100億5100万円,前記繰越利益170億4800万円,中間未処分利益270億9900万円がそれぞれ計上されていた。
さらに,前記(エ)cのとおり,同年11月20日付け監査報告書が添付されていた。(甲7,甲8,甲34,甲65,甲101,甲105,甲165)
オ 自己査定運用規則及び自己査定運用細則
(ア) 平成9年12月15日の検討状況
D,E,F,C,B及びGは,平成9年12月15日,総合企画部作成の同日付け「長銀再生プラン~ディスカッションペーパー」と題する資料(甲105添付資料21)に基づき,検討を行った。
上記資料によれば,再生プランの前提として,平成10年1月のファイナンスを実施すること,平成9年度決算は現行の見通しであること(赤字2800億円,不稼働資産処理額5000億円),BIS比率10パーセントを維持し,国際業務を大幅に縮小して存続させること,再生プランの方向として,リスクアセットを平成12年3月期に15兆円まで圧縮すること,人員・経費等の削減を図ることとされ,また,今後の不稼働処理額について,「対外的」には,今年度処理額は5000億円(一般先2500億円,関連先2500億円)であり,一般先について当面の手当が完了したこと,関連先は2社の支援が完了し,エヌイーディーのみ継続支援をすることが指摘され,行内的には,今後の要処理額8000億円ないし9000億円である
こと,一般先(対象元本額1兆2000億円)については引当率7割であり,手当が完了したこと,関連先について貸出残高は3兆円に達するが,完全な不稼働資産は1兆円であり,今期の手当2500億円以外に残額1500億円から2500億円までの損失負担があることが指摘されており,また,現実には,関連親密先の損失を完全に一掃するには1兆円程度の規模の手当が必要であること,当面は一掃できる体力がなく,抱えて行かざるを得ないこと,そのうえで,3つのシナリオが示されており,シナリオ1として,追加の3000億円の処理を一気に実施する,すなわち法定準備金3000億円を使用し,いわゆる無配としてBIS基準8パーセントを放棄すること,シナリオ2として,処理一掃を目指した特別ファンドの設定(キャピタル益の追
求)であるが,現実には資金の制約があること,シナリオ3として財源を他に求めることが指摘されていた。(甲105添付資料21,甲117)
(イ) 平成9年12月16日開催の常務会における自己査定基準・償却基準の承認
平成9年12月16日開催の原告の常務会において,総合企画部作成の同日付け「早期是正措置導入に伴う自己査定の実施並びに自己査定基準・償却基準の概要について」と題する資料(甲102添付資料⑥)に基づき,自己査定基準及び償却基準に関する説明,検討が行われた。
上記資料によれば,自己査定実施の趣旨として,早期是正措置の導入に伴い,資産を個別に検討・分析の上,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに従い区分すると共に,これに基づき適切な引当・償却を行い今年度以降の決算に反映するものであることが挙げられ,自己査定基準及び分類方法のうち,関連ノンバンク査定基準として,関連ノンバンクについては,償却前利益によりおおむね2,3年で実質債務超過の解消が不可能な体力のない先及び経営支援(実績)先について,母体行責任を負う意思がある場合,基本的に当該年度支援額をⅣ分類,担保等による回収見込額をⅡ分類,残額をⅢ分類とすること(経営支援実績先は,原則全額Ⅱ分類)が指摘されていた。
また,上記資料によれば,自己査定の枠組み及び査定基準・償却基準の基本部分を頭取決裁とすること,自己査定手続の明細は,リスク統轄部担当役員(当時副頭取のEが担当)の決裁とすることとされていた。
その後,Dは,上記資料のとおり,「自己査定制度の制定及び自己査定の実施について」と題する回議文書について,回付を受け,これを決裁した。その内容は,自己査定制度の意義(早期是正措置の導入に伴い,資産内容の実態を客観的に反映した財務諸表を作成し,適正な償却・引当を行うことが求められ,そのための準備作業としての自己査定を実施すること),自己査定の基準日(6月末及び12月末を基準として年2回実施すること),自己査定の基本的考え方や分類方法(貸出金等について「正常先」から「破綻先」までの5つの「債務者区分」を行い,資金使途等の内容を個別に検討し,担保等の状況を勘案して,Ⅰ分類からⅣ分類までの4つの資産分類すること)等の基本的な事項であった。(甲102添付資料⑥,資料⑦)
(ウ) 自己査定運用規則及び自己査定運用細則の正式な策定
Eは,平成10年3月末ころまでに,平成9年12月29日付けで,事業推進部が策定した自己査定運用規則及び自己査定運用細則の策定に関する回議についてこれを決裁した。なお,Gも,回議を受け,これを承認した。(甲63,甲64)
(エ) 自己査定運用規則及び自己査定運用細則の内容
a 関連親密先についての債務者区分
まず,関連親密先について,一般先と同様の基準により債務者区分・資産分類を行うことは,原告の経営関与度の高さ等を勘案すれば適当ではないとして,全銀協追加Q&Aの趣旨を勘案する等して,「関連ノンバンク」,「経営支援先」及び「経営支援実績先」と呼ばれる債務者区分を設けることとされた。
このうち,「関連ノンバンク」について,大蔵省検査により原告関連ノンバンクと指定を受けている先で,そのうち体力がない(償却前利益によりおおむね2,3年程度で債務超過を解消し得る見込みがなく,実質的債務超過の状態が継続し,自力で再建の見通しが立たない場合)と認定された先であり,資産分類について一般先と異なる方法を採ること,また,「経営支援実績先」については,原告が支援を行いその支援が完了した先について業況が正常に復しているが,原告が特別の注意をもって管理をし,従来と同様のスタンスを維持していることから,この区分とし資産分類をⅡ分類とすること,上記各債務者区分に該当しない関連親密先(「特定先」)については,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」に分類し,原則として,その
債務者区分に従い資産分類を行うが,不動産の事業化を目的としている受皿会社及びその関係会社について,事業目的にかんがみ,保有資産の評価損と繰越欠損額の合計をⅡ分類とすること,関連親密先の関係会社については,原則として,関連親密先に準じて「正常先」又は「要注意先」に債務者区分し,それに応じた資産分類を行うが,「関連ノンバンク」に区分された関係会社のうち,不稼働資産の処理を本体と一体で行う会社については,本体の債務者区分(「関連ノンバンク」)に従い,それに準じた資産分類を行うことが定められていた。(甲6の1,甲6の4の「決裁事由」の第2項,第3項,第5項ないし第7項,第9項,第10項)
b 自己査定運用規則
自己査定運用規則においては,その中で,対象先は,原告の「関連ノンバンク」(平成8年4月の大蔵省検査において指定されたエヌイーディー,日本リース,ジャリック,第一ファイナンス及び平河町ファイナンス)であるとされ,この規則による特例として,まず,体力の有無について,実質債務超過の場合の体力の有無の判断は,償却前利益によりおおむね2,3年程度で債務超過を解消できるかどうかを目安として判断すること,体力がない(実質債務超過で,かつ,おおむね2,3年程度で償却前利益により解消できない)場合には,一般債務者と異なる基準により資産分類を行うこと,この資産分類基準は通常の債務者の資産分類とは異なることから,資産分類の前提となる債務者区分については,これを行わず「関連ノンバンク」と
すること,具体的な資産分類としては,例えば,原告に母体行責任を負う意思があり,合理的再建計画が存在する場合には,当該年度の支援予定額をⅣ分類とし,それを超える支援予定額をⅢ分類とすること,母体行責任を負う意思があっても,再建計画が作成されていない場合であり(甲6の2の2枚目の②及び同脚注6参照),かつ,当該「関連ノンバンク」の取引金融機関が原告のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類とし,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類とし,その他をⅢ分類とすること(甲6の2の2枚目脚注7参照)等が定められていた。(甲6の2,甲63)
c 自己査定運用細則
自己査定運用細則においては,その中で,「関連ノンバンク」に指定された先については,自己査定運用規則を適用すること,また,原告が指定する「経営支援先」,「経営支援実績先」及び「特定先」(原告の関連親密先)については,前記「自己査定制度の制定と自己査定実施について」に定められた債務者区分・資産分類とともに,次の査定基準を適用するとして,例えば,「経営支援実績先」については,日本リースが指定され,「関連ノンバンク」基準で体力がないと判断される先を除き,原告が過去に経営支援を行っていた先であるとされ,債務者区分を「経営支援実績先」,資産分類をⅡ分類とすることが定められ,また,「特定先」として,いくつかの受皿会社が指定されており,これらは,いずれも「正常先」又は「要注意先」
に区分し,原則として「債務者区分」に応じて資産分類を行うこと等が定められていた。(甲6の1)
(オ) 平成9年12月26日付け「2ヵ年計画(長銀再生2ヵ年計画)」
総合企画部が平成9年12月26日付けで作成した「2ヵ年計画(長銀再生2ヵ年計画)」と題する経営会議資料(甲105添付資料23)によれば,原告の改革方向を示す中期プランの見直しプランとして,バランスシートの健全化,関係会社の抜本的リストラ,顧客・商品戦略の再構築と業務運営の抜本的改革,思い切ったリストラの実施を骨子とする2カ年計画の提案がなされ,スイス銀行との提携(アライアンス)を前提に,原告グループの再編を進めることが指摘されていた。なお,同プランでも自己資本比率は8パーセント達成が前提とされ,平成9年度の不稼働資産処理の額は,5000億円とされていた。(甲105)
(8) 平成10年1月ころから同年3月までの状況
ア 大蔵省における自己査定に関する把握の状況
大蔵省金融検査部は,資産査定通達において,早期是正措置が導入されるまでの間における金融検査においても,金融機関の自己査定のための体制整備の進展状況等について把握するよう努められたいと示していたこともあり,また,前記(4)ア(イ)のとおり,O金融検査部長は,平成10年4月以降の一斉金融検査の実施は困難であり,できる限り早期是正措置の導入までに,各金融機関の体制整備状況等についても把握するよう努める旨述べていた。
そのため,大蔵省金融検査部は,平成9年度を各金融機関が自己査定に習熟するためのトライアル期間と位置づけて,その間において,各金融機関がどのような自己査定基準を策定しているかどうかについて予備的に検査し,そごがあれば,これを指摘して訂正させることも計画していたが,同年11月に,三洋証券株式会社の会社更生手続の申立て,株式会社北海道拓殖銀行の経営破綻や山一證券株式会社の自主廃業等により,金融システムが混乱に陥ったため,このような検査を実施するには至らなかった(乙81の3枚目から4枚目)。(証人R(以下「証人R」という。)9頁,甲1,乙21,乙81,弁論の全趣旨)
イ 各金融機関の自己査定の状況,預金保険法の改正と金融危機管理審査委員会による公的資金の導入
(ア) 各金融機関の自己査定の状況等
前記アの平成9年末の金融システムの混乱を受けて,預金保険法の改正等が国会において審議され,金融機関に対する資本注入制度の導入が検討されていた。そこで,大蔵省は,同年12月ころ,上記法改正のための国会における審議資料として,各金融機関の試行的な自己査定による数字(不良債権額)の提出を受けて,平成10年1月,これを国会に提出した。その際,各銀行には,自己査定基準と行内格付けといった債権区分が存在していたが,それ自体,ⅠからⅣ分類という分類より詳細な分類であり,しかもその内容が各行ごとに全くばらばらであったため,大蔵省の担当者(N調査課長)は,比較や集計ができず,各銀行に対し,Ⅰ分類からⅣ分類までに組み替えるよう指示し,各銀行が自主的にとりまとめた数字を国会に提出したが,
大蔵省において,前記法案審議資料として上記数字の組み替えを指示したにすぎず,各銀行が上記分類に沿って提出した数字の内容や相互の整合性をチェックすることまではしなかった(甲139の32頁,33頁)。(甲139,乙29,弁論の全趣旨)
(イ) 預金保険法の改正
その後,平成10年2月に,預金保険法が改正され(同年法律第4号),また,「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」(同年法律第5号)が施行され,これに伴い,銀行等の金融機関に対する公的資金の導入(資本注入)制度が設けられ,預金保険機構にはその審査を行う金融危機管理審査委員会(いわゆるS委員会)が設置された。
これを受けて,東京三菱を含む都銀9行,原告を含む長期信用銀行3行,信託銀行6行,地方銀行3行の合計21行が,経営の健全性の確保のための計画を提出して資本注入の申請を行ったが,金融危機管理審査委員会は,上記申請を行った21行に対し,自己査定結果とそれを裏付けるラインシート等の内部資料の提出を要求し,その提出を受けて,大蔵省金融検査部及び日銀考査局に対して,自己査定の結果についてチェックを依頼し,各銀行の経営改善計画の内容を確認して,公的資金の導入を決定し,総額1兆8156億円の公的資金が資本に注入され,その際,原告にも,公的資金1776億円が資本に注入された(甲116の80頁)。(甲105添付資料24,甲116,甲139,乙40,乙81,弁論の全趣旨)
(ウ) 銀行の有価証券評価に関する原価法の導入
改正前決算経理基準において,従来,銀行の保有する上場有価証券等の評価については,国債等を除き,いわゆる低価法(上場有価証券等の取得価格と時価の低い方の価格により評価する方式)が採用されていたが,大蔵省銀行局長は,各普通銀行代表者,各信託銀行代表者及び各長期信用銀行代表者に宛てて,平成10年2月27日蔵銀第468号「『普通銀行の業務運営に関する基本事項等について』通達の一部改正について」と題する通達を発出し,その中で,上記低価法によるべき旨の規定を削除した。
この結果,銀行において,上場有価証券等の評価に関して原価法(取得価格により評価する方式)を採用することが可能となり,いわゆる主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3行,信託銀行7行)のうち16行が,平成10年3月期の決算において,原価法を採用した。なお,11行は,前記(イ)の経営の健全性の確保のための計画において原価法によることを明らかにしており,また,同計画において低価法によることを明らかにしていた株式会社三和銀行,住友信託銀行,安田信託株式会社及び東洋信託銀行株式会社や資本注入の申請を行わなかった日本信託銀行株式会社も,原価法によることを明らかにした。
他方,興銀,東京三菱銀行及び三菱信託銀行株式会社は,従前のとおり,低価法を採用した。(乙38,乙39,弁論の全趣旨)
(エ) 金融機関の自己査定に対する大蔵省の対応
その後,大蔵省は,前記(ア)の各金融機関の自己査定の状況を踏まえて,金融機関の業態別(全銀協,地方銀行協会,第二地方銀行協会,信用金庫協会等)の説明会等において,担当職員が出席して説明をした。(甲138,甲139,弁論の全趣旨)
(オ) 早期是正措置の導入に伴う大蔵省の金融検査の方針
その後,大蔵省金融検査部長は,金融証券検査官等に宛てて,平成10年3月31日蔵銀第140号「新しい金融検査に関する基本事項について」と題する通達(以下「新検査通達」という。)(甲97添付資料1)を発出し,新しい金融検査に関する基本事項を示した。
新検査通達によれば,金融検査部においては,従来のきめ細かな事前指導を中心とする行政に即応したこれまでの検査体制・手法について抜本的な見直しを行い,検査の基本的な在り方を転換することとしたこと,新検査方式への転換に当たっての基本的考え方として,金融機関等における自己責任原則の徹底を前提として,金融機関等自らによる業務遂行上の管理体制の整備状況,その機能発揮の状況等について実態把握すること,特に,資産内容の健全性に関しては,早期是正措置の導入を契機として,金融機関等による自己査定,公認会計士による監査等を前提としつつ,商法,企業会計原則等を踏まえ,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態把握することが基本的考え方として示され,また,金融機関等の実態をより的確か
つ効率的・効果的に把握するため,公認会計士・監査役等の監査機能を検査において一層活用すること,早期是正措置の適用をも念頭に置いて,金融機関等の実態を的確に把握するため,金融機関等の経営実態に応じて検査頻度に繁簡をつけ,重点的・機動的な検査を実施すること,その際,日銀が実施する考査との間で,適切な連携の確保に十分配慮することが示され,さらに,新検査方式実施の要点として,資産内容の健全性に係る検査のため,早期是正措置制度に基づき,自己資本比率の水準いかんにより所要の措置が発動されること等を踏まえ,金融機関等による自己査定の正確性等について的確に実態把握すること,加えて,本部検査として,自己査定の正確性等の実態把握のため,被検査金融機関等の実施した自己査定について,個別債務者の自己
査定関連資料から抽出した資料に基づき,商法,企業会計原則等を踏まえ,その正確性及び自己査定結果による償却・引当の適切性につき実態把握すること,また役職員への質問・応答を通じた実態把握の具体的留意点として,被検査金融機関等における基本的融資方針,自己査定及び償却・引当についての内部統制の状況の説明を求め,資料及び臨店検査の状況等を勘案しつつ,自己査定基準,自己査定体制,自己査定結果,自己査定の基準と体制の定期的見直しの状況,償却・引当基準,償却・引当体制,償却・引当実績と体制の定期的見直し等の状況を確認することが示された。(甲97,乙25)
(9) 本件決算配当,平成10年3月期における原告の自己査定基準及び償却・引当基準による償却・引当の状況並びに各関連親密先の経営状況及び資産査定の状況等
ア 原告の関連親密先全体に対する償却・引当の状況等
原告は,平成9年12月末日を基準として,平成10年1月以降,資産査定を実施し,その内容については,リスク統轄部においてまとめられ,その結果について,平成10年4月24日付け「資産自己査定分析資料('97/12末基準)」と題する資料(甲104添付資料10)が作成された。
なお,被告A,D,E,C及びBは,平成10年4月24日開催の経営会議において,上記資料に基づき,不良債権処理に関する報告・説明を受けた。
上記資料によれば,①債務者区分別内訳として,関連会社についての債務者区分の状況は,「正常先」6829億円,「要注意先」9467億円及び「その他(関連会社等)」1兆0147億円(合計2兆6443億円)であること,②資産分類別内訳として,関連会社についての資産分類の状況は,非分類1兆2581億円,Ⅱ分類8644億円,Ⅲ分類4251億円及びⅣ分類967億円(合計2兆6443億円)であること(資料1枚目),自己査定トライアルの結果と比較した場合,Ⅱ分類が4911億円減少し,Ⅲ分類が675億円減少し,Ⅳ分類が100億円増加したこと(資料1枚目,3枚目),③償却・引当については,トライアル時において,一般先のⅢ分類2770億円(25パーセント引当)及びⅣ分類891億円(全額償却・
引当)についての償却・引当額は1583億円であり,関連親密先のⅢ分類4926億円(償却・引当なし)及びⅣ分類867億円(Ⅳ分類のみ全額償却・引当)についての償却・引当額は867億円であり,合計額は2450億円に達すること,他方,本番査定時において,一般先のⅢ分類2734億円及びⅣ分類1487億円についての償却・引当額は2171億円であり,関連親密先のⅢ分類4251億円及びⅣ分類967億円についての償却・引当額は2660億円(ランディックについて支援損を計上し,Ⅲ分類及びⅣ分類合計額1671億円全額償却)であり,合計額は5600億円に達していたことが,それぞれ指摘されていた(資料6枚目)。(甲104添付資料10)
イ 平成10年2月ころの本件監査法人による監査の状況
本件監査法人の担当であったQ会計士らは,原告の自己査定の内部統制の検証と自己査定結果の検証を実施し,その際,自己査定の手引,自己査定運用規則,自己査定運用細則等の自己査定基準に関する文書を入手して,検討を行った。
その際,Q会計士らは,4号実務指針に基づき,原告の上記自己査定基準と資産査定通達との整合性についてもチェックしたが,両者にそごはなく,上記自己査定基準は,資産査定通達の許容範囲内のものであると判断した。
すなわち,Q会計士らは,自己査定運用規則の中に当行が母体行責任を負う意思があっても,大幅な債務超過が相当期間継続しており,再建計画に客観的合理性が認められない場合において,当該支援対象ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類額を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残りをⅢ分類とすることや,「なお,当該ノンバンクの取引金融機関が当行のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類,その他をⅢ分類とすることができる」旨の同規則※7なお書の定め(以下「※7なお書」という。)も,貸出金シェアの場合には母体行責任を負う原告が他行の損失も負担するが,単独行であればその必要がないと理解されるので,全銀協追加Q&Aの許容範囲内と考え,ま
た,自己査定運用細則の対象は,基本的には,体力がある関連ノンバンクを対象とし,償却前利益2,3年で実質債務超過状態を解消し得るか,又は実質債務超過がない状態にあることから,基本的には,「破綻懸念先」に該当することはなく,「要注意先」以上であり,資産査定通達に照らし,当然資産査定はⅡ分類となること,さらに,自己査定運用細則の中の「特定先」については,銀行が積極支援する先は破綻に陥る可能性が極めて小さいと考えて,資産査定通達に係る「破綻懸念先」及び「要注意先」の定義に照らし,「特定先」を「要注意先」又は「正常先」と区分すること自体は,資産査定通達に照らし許容されると考えていた。(甲136の65頁ないし69頁)
ウ 平成10年3月期における原告の償却・引当額
原告は,平成10年3月期において,不良債権処理に係る損失として,6165億2800万円を計上した。その内訳は,「貸出金償却」514億9600万円,「債権償却特別勘定純繰入額」3330億6700万円,「株式会社共同債権買取機構への売却損」57億4500万円,「債権売却損失引当金繰入額」94億6200万円,「累積債務国向け債権等売却損」297億0200万円及び「取引先等支援損」1870億5400万円であった。(乙53)
エ 原告と各関連親密先の関係,平成10年3月期における経営・財務状況
(ア) エヌイーディー
a 原告とエヌイーディーの関係
エヌイーディーは,昭和47年11月,原告,株式会社第一勧業銀行(以下「第一勧銀」という。),商社及び証券会社の計4社が中心となって,ベンチャーキャピタルとして設立された株式会社であったが,その後,原告グループが,同社への出資比率及び融資残高の比率を増大させ,また,原告の出身者が多数同社の役員となるなど,資本,融資及び人的関係を強めるなどし,その結果,原告は同社を関連先と位置づけ,また,他の金融機関も,エヌイーディーが原告のいわゆる系列ノンバンクとみなし,平成8年4月の大蔵省検査において,原告の関連ノンバンクであると指定されていた。(甲19,甲76,甲150,甲152)
b エヌイーディーの平成10年3月期における経営状況と原告による支援計画
エヌイーディーは,バブル経済崩壊後,その不動産関連融資が不良債権化するなどして経営状況が悪化し(平成5年3月期時点の要処理債権額1236億円),平成6年3月期以降,原告から債権放棄等の支援(5年間で総額1900億円)を受けて,その不良債権の処理を進めたことから,平成9年3月時点において要処理債権額が767億円に減少する見通しであったが,結果的には,大幅な地価下落により不良債権額が増加し,2924億円の不良債権が残存することとなった(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№1)。
そこで,原告は,平成10年3月23日開催の常務会において,当初の計画を延長し,5年間(平成10年3月期から平成14年3月期まで)で,総額2951億円の支援を行い(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№3),不良債権3010億円を処理する修正計画を立案・了承し(甲38の1),この計画に基づき,国税当局と折衝して,新たに無税の承認(法人税基本通達9-4-2)を受けて,エヌイーディーの不良債権を処理し,同社の本業部門(ベンチャーキャピタル業)を不良債権部分から分離しこれを再建する計画(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№5)を実施する旨決定した。
なお,エヌイーディーには,平成6年3月期以前にその不良債権を簿価で譲り受けた受皿会社(別紙3「平成10年3月期における償却引当状況」記載番号2ないし8の各会社を含む。)が存在し,国税庁から簿価譲渡した不良債権をエヌイーディーに戻すべきであるとする指導も受け,当初の計画において,これらの会社の清算を優先する予定であったが,実際にはこの清算が進まず(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№1),そのため,上記修正計画においても,本体の不良債権の処理を優先し,受皿会社の清算を最後にすること,赤字増加回避のため,金利引下げを実施することとされていた(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理について」№4)。(甲38の2添付の「エヌイーディー(株)の処理
について」,甲45の2添付の「長銀インターナショナルリース及びエヌイーディーの現状と対策」,甲45の2,甲76,甲150)
c 原告によるエヌイーディーの自己査定と償却・引当及び原告のエヌイーディーへの貸出金の債権放棄
原告は,平成10年3月期において,原告の貸出金及び支払承諾の合計額1717億4500万円について,エヌイーディーを「関連ノンバンク」に区分し,資産査定通達上の債務者区分については行わず,その資産のうち,Ⅳ分類201億8000万円(当期支援額),Ⅲ分類1515億6500万円(原告の貸出金1715億8500万円及び支払承諾額1億6000万円からⅣ分類額を控除したもの),Ⅰ分類40億2000万円(貸付有価証券残高)との査定を実施した。
また,原告は,同月31日開催の取締役会において,エヌイーディーへの貸出金のうち201億8000万円を放棄する旨の承認決議をした。(甲39,甲151)
(イ) エヌイーディーの受皿会社7社の状況
a 青葉エステート
青葉エステートは,昭和62年6月に設立された不動産及び融資を主たる業務とする株式会社であり,エヌイーディーの不良債権を簿価で譲り受けた受皿会社(原告のグループ企業であるエヌイーディーほか2社が出資)であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった(甲49の2の2頁,甲78添付資料一の1)。
平成10年3月期において,原告は,青葉エステートに対し,247億8400万円の貸出(エヌイーディーが保証予約)を行っていたところ,自己査定において,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」(甲6の4)記載の決済事由10項ただし書(以下「決済事由10項ただし書」という。)に基づき,債務者区分をエヌイーディーと一体として扱い,貸出金をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲49の2,甲74,甲78,弁論の全趣旨)
b ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ
ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ(以下「ユニベスト外4社」という。)は,エヌイーディーの不良債権を簿価で譲り受けるため,いずれも青葉エステートの全額出資により平成3年11月又は平成4年10月に設立された受皿会社であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった(甲78添付資料二の1ないし5,甲50の2,51の2,53の2,54の2参照)。
原告は,平成10年3月期において,ユニベスト外4社の貸出金(ユニベスト74億0300万円,グラベス31億9600万円,コーポレックス13億6200万円,プロクセル5億9600万円,日本ビゼルボ1億3100万円)について(エヌイーディーは保証予約),決済事由10項ただし書に基づき,これらの会社の債務者区分をエヌイーディーと一体であるとして扱い,貸出金をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲50の1及び2,甲51の1及び2,甲52の1及び2,甲53の1及び2,甲54の1及び2,甲78,弁論の全趣旨)
c エクセレーブファイナンス
エクセレーブファイナンスは,昭和60年12月に,他の金融機関から融資を受けてこれをエヌイーディーに融資するために設立された会社(平成10年3月期においてエヌイーディー全額出資)であり,その業務等を一切エヌイーディーに委託し,実際に営業等を行っていなかった。
エクセレーブファイナンスは,平成10年3月期において,原告から400億円の融資を受けて,これを全額エヌイーディーに融資しており,その資産(総額450億7400万円)の大半がエヌイーディーに対する融資金であり,同社の経営状況については,エヌイーディーに左右される状態であった。
原告は,平成10年3月期において,決済事由10項ただし書に基づき,同社の債務者区分をエヌイーディーと一体であるとして扱い,貸出金(400億円)をⅢ分類とし,償却・引当を実施しなかった。(甲69の1の73頁,甲77,甲153の1枚目,6枚目,弁論の全趣旨)
(ウ) 第一ファイナンス
a 原告と第一ファイナンスの関係
第一ファイナンスは,昭和56年3月に設立されたファイナンスを行う株式会社であり,原告本体で行い得ない提携ローンやファクタリング等を主要業務としており,原告のグループ企業4社(ランディック,平河町ファイナンス,ジャリック及び外1社)が出資する原告のグループ企業であり,原告内部において,関連親密先と位置づけられていた。(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」)
b 原告による第一ファイナンスの処理計画
第一ファイナンスは,平成3年ころまで,ファクタリング業務のほか,ノンバンクへの貸出を行い,順調にその業容を拡大していたが,バブル経済の崩壊により,不良債権が増大し,平成7年7月に,総資産2288億円のうち含み損が657億円に達していた。原告は,同社の正常資産を平河町ファイナンスに移管し他の金融機関からの借入を維持し,原告のみが,第一ファイナンス本体に対する融資を行い,同社の残存不良債権を回収,処理し,最終的には同社を清算し原告が最終損失を全て負担することを計画し,この計画に基づき,同社の正常債権は,平河町ファイナンスに移管された(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」№1,甲46の1№1から№4)。
c 平成10年3月期における第一ファイナンスの状況と原告による自己査定及び償却引当等の状況等
平成10年3月期において,第一ファイナンス本体は実質債務超過状態(約138億円)にあり,損益も赤字の状態であったため(甲38の2添付の「第一ファイナンス(株)の処理について」№1,№2,甲148の8枚目),原告は,最終的には同社を清算処理するほかないと考えていた。ただ,同社が債権の回収業務を継続しており,当面清算の必要はないとの理由により,原告は,同社を「関連ノンバンク」に債務者区分し,その貸出金1245億6000万円(同社の借入先は原告のみ)について,※7なお書に基づき,同社の資産をⅣ分類130億0700万円(同社繰越欠損額),Ⅲ分類400億0800万円(同社自己査定による営業貸付金Ⅲ分類,同社保有有価証券の含み損及び関係会社の繰越欠損の合計額),Ⅱ分類596億
9900万円(同社貸出金から,Ⅳ分類及びⅢ分類並びに優良担保部分を控除したもの)と査定し,Ⅳ分類額及びⅢ分類の一部(16億9300万円)の合計額147億円について引当を実施(有税による債権償却特別勘定への繰入れ)した。(甲147添付の資料7,弁論の全趣旨)
(エ) 日本リース
a 原告と日本リースの関係,日本リースへの支援の状況
日本リースは,昭和38年に,株式会社リコー,原告を含む各銀行,損害保険会社及び各メーカーの出資により設立された総合リース会社であるが,原告は,日本リース設立時の出資金融機関の一つであり,設立直後から日本リースとの取引を開始し,その後, 原告グループが日本リースの筆頭株主となり(甲94の4頁),原告の出身者が日本リースの代表取締役社長を含む主要役員の多くを占め,原告が融資残高においても第1位のシェアを占める(甲94の5頁)など,資本,融資取引,人的関係等において密接な関係を有しており,また,原告が平成8年3月末までに日本リースに損益支援を実施するなど,同社は,平成9年度当時,原告の系列ノンバンクであると位置づけられ,そのため,大蔵省金融検査部は,平成8年4月の
大蔵省検査の際に日本リースが原告の関連ノンバンクであると指定していた(甲80添付資料1)。(甲80,甲81,甲92ないし甲94,甲116,甲154,乙69,乙74)
b 日本リースへの原告による支援と日本リースの状況
原告は,平成3年以降,バブル崩壊により,不動産関連融資が不良債権化し,多数の不良資産を抱えて経営が悪化していた日本リースに対し,同社の不良資産の移管のため,受皿会社に買取資金を融資してこれを引き取るなどの支援を行っていたが,平成7年3月及び平成8年3月に,抜本的な処理として,不良債権を買い取る方式により総額約1600億円の損益支援(資金贈与)を実施し,また,原告が受皿会社に不稼働資産の買取資金を融資して不良資産を移管するなどの支援を実施した。
同社は,このような原告の支援を受けて,また,自力償却分を含め,平成9年3月期までに不良資産約3000億円を処理し,収益力の回復に努め,その結果,平成8年3月期において実力基礎収益(不良債権の処理に使用し得る償却前利益)は3億円の赤字(未収利息及び日本リースによる利息の追貸し分の利息収入を加えた計算上の利益が259億円)であったが,平成9年3月期における実力基礎収益は175億円(計算上の利益277億円)となり,平成10年3月期における実力基礎収益は182億円(計算上の利益261億円)となっていた(甲91の添付資料4)。
しかし,上記処理後も日本リースには多額の不稼働資産が残存し,平成8年3月期に582億円の債務超過状態にあり,また,要処理不稼働資産の額が,同年7月においても5000億円ないし6000億円に達するとか(甲81の6枚目),また,同期において,延滞債権額の含み損(3004億円),不動産等の含み損(2501億円)及び資本欠損553億円の合計6058億円の含み損が存在する等と指摘されていた(甲80添付資料2の平成8年12月29日付「今後の不良資産処理について」と題する資料8枚目「常務会フリーディスカッション資料」,甲94資料3№4)。(甲80,甲81,甲91,甲92,甲94,甲96)
c 平成10年3月期における日本リースの経営状況
日本リースは,平成10年3月期において,損益についてはおおむね年間の実力基礎収益175億円程度が見込まれていたが(甲81添付資料2),他方,資産については営業貸付金(9347億円)の含み損が7000億円に達し(甲81添付資料3),原告による支援がされても,不稼働資産の最終的な処理には相当期間が見込まれる状況にあった。
また,同年6月26日に住友信託と原告との合併に関する発表が行われ,住友信託と原告との間で合併交渉が進められ,これを受けて原告への資本注入が検討され,同年8月21日に経営改善計画が公表され,その中で,原告が,日本リースに対する貸出金を全額放棄し,同社は,他の金融機関からも一部債権放棄を受けるなどして,不良債権の含み損等6000億円の損失を処理するとの計画が示された。(甲48,甲81,甲120,甲129,乙75,乙76,弁論の全趣旨)
d 原告における日本リースの債務者区分と資産査定
原告は,平成10年3月期において,自己査定運用細則に基づき,日本リースを「経営支援実績先」に区分し資産分類をⅡ分類とし,その査定結果に基づき,原告の日本リースに対する貸出金(2556億8000万円)をⅡ分類として償却・引当をしなかった。(甲81)
(オ) 日本リース受皿会社
a 有楽エンタープライズ
有楽エンタープライズは,昭和60年6月に設立された日本リースグループの不動産会社であり,平成4年8月に,日本リースの不良債権に係る担保物件を取得した受皿会社である(甲83添付資料1)。
有楽エンタープライズは,平成10年3月期において,原告(借入額63億5000万円)及び日本リース(借入額130億1400万円)から融資を受けており,また,平成9年3月期における純損失額は2億8805万7489円であり,債務超過額(資本欠損)が30億5710万9105円に達していた(甲55の2の2枚目)。
有楽エンタープライズは,取得した物件(大阪市日本橋所在)の事業化(パチンコ業者向けテナントビルの建設)により収益をあげることを計画していたが,実際には,賃借人の選定が進まず,具体的な事業化計画の策定にまで至っていなかった(甲83の3枚目)。
原告は,平成10年3月期において,自己査定運用細則に基づき,有楽エンタープライズが「特定先」であるとして,その債務者区分を「要注意先」と区分し,原告の貸出金(63億5000万円)をⅡ分類とし,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」のとおり,償却・引当を実施した。(甲55の2,甲69の1の36頁,37頁,甲82,甲83,甲157,弁論の全趣旨)
b 四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート
四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート(以下「ビルプロ3社」という。)は,いずれも平成5年11月に日本リースの平成6年3月期における日本リースの大口融資先であった日本ビルプロジェクト株式会社及びそのグループ会社(以下「ビルプログループ」という。)に対する融資残高の圧縮を目的として,その不良債権に係る担保物件を債権簿価で買い取るため,設立された受皿会社(日本リース外2社出資)である。すなわち,平成5年7月にビルプログループが実質破綻したことに伴い,日本リースの取引金融機関から,日本リースのビルプログループに対する融資残高の圧縮が要請されたため,原告は,ビルプログループが開発を予定し日本リースが担保として融資をしていた担保物件(左門町物件,銀座八丁目物件,竜泉
物件及びN町物件と呼称された。)について,事業化計画を添付して物件の担保評価額を債権の簿価額までかさ上げして,ビルプロ3社への融資(四谷プランニング187億8000万円,木挽町開発115億5000万円,竜泉エステート166億9000万円)を実行し,この融資金により,ビルプロ3社に日本リースのビルプログループに対する貸付債権を買い取らせ,日本リースの融資残高の圧縮を実現していた。
平成10年3月期において,ビルプロ3社は,債務超過の状態にあったが,原告は,担保物件の事業化のめどが立ったなどとの理由により,自己査定運用細則に基づき,ビルプロ3社が「特定先」であるとして,その債務者区分を「要注意先」と区分し,原告の貸出金(四谷プランニング187億8000万円,木挽町開発115億5000万円,竜泉エステート166億9000万円)をⅡ分類とし,別紙3「平成10年3月期における償却・引当の状況」のとおり,償却・引当を実施した(甲156添付資料一の1,二の1,三の1)。(甲56の2,甲69の1の29頁,甲84ないし甲87,甲96,甲156,弁論の全趣旨)
オ 本件決算配当に関する検討,承認・実施等
原告は,平成10年4月28日開催の取締役会において,平成9年度(平成10年3月期)決算に係る営業報告書,貸借対照表,損益計算書,利益処分計算書案(本件利益処分案)及び付属明細書を承認し,これを会計監査人及び監査役会に提出する旨の承認決議をした。
本件利益処分案には,任意積立金2995億1618万4620円を取り崩して,当期未処理損失を処理し,利益処分額を86億7162万4655円としたうえで,このうち,1株につき3円,総額71億7864万7455円の本件決算配当を行う旨記載されていた。
なお,上記決算案を受領した本件監査法人において,T会計士,P会計士,Q会計士らが,上記取締役会決議に基づき提出を受けていた原告の平成9年度決算案(貸借対照表及び損益計算書)について,監査を行い,その結果,本件監査法人は,これらの財務諸表が一般に公正妥当と認められる財務諸表の作成基準に準拠して原告の同年度の会計期間(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)に関する有用な会計情報を表示しているものと認める旨の監査報告書を提出した。 また,本件監査法人による原告の平成9年度決算案の監査は,関与社員,公認会計士等20名,監査延べ日数825日(前年に比べると170日の増加),監査述べ時間6595時間を費やして行われており(甲136の2頁以下),この時点では,本件監査法
人として,原告の策定した自己査定基準が,資産査定通達,4号実務指針との関係で,さらには商法の規定との関係でも容認される内容であることを確認している。
原告は,同年5月25日開催の取締役会において,平成9年度定時株主総会において,本件利益処分案を決議事項として上程することを承認する旨決議し,同年6月25日開催の定時株主総会において,本件決算配当決議を行い本件決算配当決議に基づき,平成11年6月3日までに合計金71億7233万6392円の金銭を配当した。(甲8,甲11,甲12,甲132,甲136)
(10) 金融監督庁の発足と金融監督庁による平成10年3月期における金融検査の実施の状況等
ア 金融監督庁の発足
平成9年6月16日に,「金融監督庁設置法」(平成9年法律第101号)及び「金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下「関係整備法」という。)が国会において可決・成立し,同月20日に公布された。
平成10年6月22日,金融監督庁設置法及び関係整備法が施行され,金融監督庁が総理府の外局として発足し,これにより,金融監督庁は,民間金融機関等に対する検査・監督を所管し,従来,銀行法において,大蔵大臣の権限とされていた民間金融機関等の検査・監督権限について,その免許の付与,業務改善命令,業務停止命令,免許の取消し,合併認可等の全ての権限が,内閣総理大臣に移管された。そのうえで,金融検査・監督権限は,免許の付与及びその取消等の権限を除き,内閣総理大臣から法定委任を受けた金融監督庁長官にあるとされた。(乙1の1頁,3頁)
イ 金融監督庁による平成10年3月期決算に対する金融検査の実施
平成10年7月2日に,政府・与党がとりまとめた「金融再生トータルプラン(第2次とりまとめ)」において,「緊急的な措置として金融監督庁は日本銀行と連携しつつ,主要19行に対し,集中的な検査を実施」するとの方針が示されたことを踏まえ,金融監督庁は,同年3月期決算における各行の自己査定結果の報告に基づき,同年7月以降,日銀と連携して(金融監督庁による検査の分担が14行,日銀による考査の分担が5行),主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3行,信託銀行7行)に対する集中検査(以下「平成10年3月期金融検査」という。)を実施した(乙1の131頁,甲97の4頁)。
その際,金融機関等の財務内容の健全性について,早期是正措置の下で自己資本比率に基づき,必要な行政上の措置が適時に講じられることを確保するため,金融機関の自己査定と会計監査人による外部監査を前提に,早急に,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態を把握する必要があるとして,検査の重点事項の一つに,自己査定の正確性及び償却・引当の実施状況が挙げられ,平成10年3月期金融検査において可能な限り幅広く,自己査定の正確性及び償却・引当の適切性について実態把握すべきものとされていた(乙1の129頁,482頁)。
そして,主要19行の自己査定基準及び償却・引当基準の妥当性並びに自己査定の正確性等を重点として,金融検査が実施された(甲97の4頁,乙1の131頁)。
その結果,原告及び日債銀を除く主要17行について,自己査定結果と当局査定結果の乖離が生じていたことが明らかとなった。すなわち,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して5兆4061億円減少し,そのⅡ分類が3兆5842億円,そのⅢ分類が1兆5708億円,そのⅣ分類が2511億円,それぞれ当局査定結果により増加し,主要17行について1兆0413億円の償却・引当不足が存在した(乙1の131頁~133頁)。
また,当局の指摘事項として,主要17行における自己査定基準については,その内容の一部に問題が認められ,大半の銀行に改善を求めたが,総体としておおむね妥当であること,主な問題点は,上場有配企業等の子会社の債務者区分を,子会社の財務内容等を勘案せずに親会社に準じた債務者区分を行う規程となっていること,要注意先についてその財務内容等を勘案せず一律に,将来の一定期間の収益返済を控除していること,破綻懸念先以下の債務者について有価証券担保の時価から処分可能見込額を差し引いた額に対してⅢ分類とする規程となっていないことが挙げられており,さらに,主要17行における償却・引当の基準は,その内容の一部に問題が認められ,大半の銀行に改善を求めたが,総体として4号実務指針に整合し,おおむね
妥当であること,主な問題点には,関連ノンバンク等の償却・引当に関して一般の取引先と異なる基準を適用し,その一部を償却・引当の対象外としていること,実質破綻先債権等のⅢ分類について,全額償却する規程となっていないこと等が挙げられていた(乙1の513頁,514頁)。
他方,原告及び日債銀については,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して1兆8683億円減少し,そのⅡ分類が2298億円,そのⅢ分類が1兆3775億円,そのⅣ分類が2610億円,それぞれ当局査定結果により増加し,償却・引当の適切性については,自己査定が正確に行われていない,償却・引当の基準に問題があると指摘され,原告及び日債銀について8323億円の償却・引当不足があると指摘された(乙1の131頁,132頁,133頁)。(甲97,乙1)
ウ 原告に対する日銀考査の状況
日銀は,平成10年4月13日,原告に対し,同年3月期を対象とする日銀考査を申し入れ,原告の自己査定基準に関する資料の提出を受け,同年5月21日から,考査を実施した。
その際,考査を担当した日銀職員は,資産査定通達と全銀協追加Q&Aを参照にして,原告から提出を受けた自己査定基準に関する資料の適否を検討したが,自己査定運用細則において,債務者区分を「その他」としている点は資産査定通達における債務者区分に違反していること,このような基準は,恣意性が働くため,自己査定結果がゆがめられ,適切な償却・引当が実施されず,適正な財務諸表が作成されないとの問題があると認識し,それを原告側に指摘するなどした。(甲68)
エ 金融監督庁による原告に対する金融検査の概要等
金融監督庁は,原告の平成10年3月期(平成9年12月までの自己査定とそれに基づく償却・引当の数額に,平成10年3月までの後発事象による修正をしたものとなる。)を対象として,同年7月7日,原告に対する金融検査の実施を決定し,その旨原告に予告し,その際,主任金融検査官を務めたV(以下「V主任検査官」という。),金融検査官U(以下「U検査官」という。)ら原告の検査を担当した金融検査官は,同月9日に,原告との間で検査の抽出基準について意見調整をした。
その後,同年13日から立入検査が開始され(実質検査の開始同月16日),同年8月21日には,同年3月期を対象とした金融検査は,ほぼ終了したが,同日,原告が住友信託との合併に伴う日本リースに対する支援計画を発表したため,改めて,同年6月末時点における自己査定結果(同年9月中間決算における基礎資料)に基づく検査が実施された。(甲97)
オ 金融検査官による指摘,本件監査法人の担当会計士との面談状況等
(ア) 金融検査における金融検査官の指摘
V主任検査官は,平成10年7月以降の金融検査において,同月14日,原告側担当者に対し,自己査定ワークシートにおける債務者区分について,関連ノンバンク等を「その他」としているのは適当ではないと指摘し,これに対し,原告側担当者は,「その他」という債務者区分について内部において議論し,また,他行の動向を聴取し,同様の検討がされていたこと,日銀考査において日銀の担当者とも議論したが,その際,日銀内部において原告と同様の考え方をする者も,少数であるがいたことを説明した。また,V主任検査官は,原告側担当者に対し,債務者区分のポイントは貸出金が回収可能か否かであり,回収が可能(何十年も要するものは不可)であれば,状況に応じて正常先又は要注意先とし,それ以外は破綻懸念先以下に分類す
べきであると説明した。(甲97添付資料6)
(イ) 金融検査官と本件監査法人の担当者との面談状況
その後,同年8月20日,V主任検査官は,T会計士,P会計士及びQ会計士と面談し,その際,自己査定運用細則において,関連特定先を機械的に正常又は要注意先に分類することが誤りではないかと指摘し,P会計士は,資産分類が償却に結びついており,原告の経営により「グリップ」されている以上,破綻する先ではないこと,ロス認識として不動産は価値減算を考えるものではなく,長期的には回収可能性があることを説明した。
また,V主任検査官は,エヌイーディーに対する支援予定(Ⅲ分類)について引当がない点を質問し,P会計士は,経済的利益供与が貸倒引当の概念に該当しない,未払金の計上という方法があるが,企業会計実務の中で一般慣行として定着していない,原告の考え方も妥当の範囲内であると回答し,また,T会計士は,支援について現金供与もあり,貸出金の引当という考え方になじまないと説明した。(甲97添付資料9)
(ウ) 金融検査終了後の意見交換の状況
V主任検査官は,検査終了後の平成10年9月29日,B(当時頭取)と面談し,原告の自己査定と当局査定の差違について,「その他」の区分のような原告独自のものがあること,関連親密先の自己査定運用規則の中で,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」以外にないとしている点については,客観的には「破綻懸念先」が存在すること,自己査定において,返済に何年かかっても,事業継続が可能であるとして「要注意先」としており,意見の相違があったこと,原告の考え方は,現在の環境下では客観・妥当性のあるものといえないと指摘した。(甲97添付資料10)
カ 平成10年3月期金融検査における各関連親密先に対する資産査定及び償却・引当の不足額の指摘状況等
(ア) エヌイーディーに対する認定
U検査官は,エヌイーディーについては,原告による同社の支援計画について,2951億円の支援額はⅢ分類及びⅣ分類の合計額を上回り,計画どおり支援が実施されれば,同社は再建されるとして破綻懸念先に区分し,当期支援額201億8000万円をⅣ分類とし,Ⅲ分類を1543億6500万円(上記貸出金及び支払承諾額並びに貸付有価証券残高の合計額からⅣ分類額を控除),非分類12億2000万円(貸付有価証券残高40億2000万円から当該貸付に係る他行借入金28億円を控除したもの)と査定した。(甲69の1の41頁,甲151,甲152)
(イ) エヌイーディーの受皿会社7社に対する認定
U検査官は,青葉エステート及びユニベスト外4社について,いずれも実質破綻先と区分し,その貸出金全額(青葉エステート247億8400万円,ユニベスト74億0300万円,グラベス31億9600万円,コーポレックス13億6200万円,プロクセル5億9600万円及び日本ビルボゼ1億3100万円)についてⅣ分類と査定した。
他方,U検査官は,エクセレーブファイナンスについて,原告の同社への貸出金がエヌイーディーに全額貸し付けられ,エクセレーブファイナンスへの貸出金の回収可能性はエヌイーディーからの回収に全面的に依拠している以上,同社がエヌイーディーと一体であるとして,破綻懸念先に区分し,同社への貸出金400億円をⅢ分類と査定した。(甲69の1の73頁,甲78,甲153,弁論の全趣旨)
(ウ) 第一ファイナンスに対する認定
U検査官は,第一ファイナンスについて,破綻懸念先に区分し,Ⅳ分類477億4800万円(引当額,同社の営業貸付金のⅣ分類の額,上場有価証券含み損及び非上場株式含み損の合計額),Ⅲ分類203億9800万円(同社の営業貸付金のⅢ分類の額),Ⅱ分類445億6800万円(原告の同社貸出金からⅣ分類及びⅢ分類の合計額並びに優良担保額を控除したもの)と査定した(甲147の21頁,22頁,同添付資料1)。(甲46の1,甲71ないし甲73,甲147添付資料1)
(エ) 日本リース
原告の担当者(営業六部次長W)は,U検査官に対し,日本リースの債務超過額が1578億9600万円(甲69の1の103頁,甲81添付資料14),基礎収益力が約250億円(甲69の1の104頁,甲81の35頁)であると説明し,これに基づき,U検査官は,日本リースの債務超過の解消に6年程度かかると判断し,同社を体力のない関連ノンバンクとして,債務者区分を破綻懸念先と区分し,原告の日本リースに対する貸出金については,Ⅲ分類に資産分類した。(甲69の1の100頁,甲81)
(オ) 日本リース受皿会社
a 有楽エンタープライズ
U検査官は,有楽エンタープライズについて,同社を実質破綻先と区分し,原告の貸出金について担保による保全部分(20億6500万円)をⅡ分類とし,その残額42億8500万円はⅣ分類と査定した(甲157添付資料一)。(甲69の1の36頁,37頁,甲82,甲83,甲157,弁論の全趣旨)
b 四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート
U検査官は,ビルプロ3社を破綻懸念先に区分し,これらの貸出金については,その担保保全部分をⅡ分類とし(四谷プランニング20億9000万円,木挽町開発7億7300万円,竜泉エステート5億2800万円),その残額(四谷プランニング166億9000万円,木挽町開発107億7700万円,竜泉エステート144億1400万円)をⅢ分類と査定した(甲156添付資料一の1,二の1,三の1)。(甲56の2,甲69の1の29頁,甲84ないし甲87,甲96,甲156,弁論の全趣旨)
(11) 金融再生法の施行と原告の破綻
ア 金融再生法等の成立・施行
平成10年10月12日には金融再生法等が国会において可決・成立し,また同月16日には「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(同年法律第143号,以下「早期健全化法」という。)が国会において可決・成立した。
なお,早期健全化法3条2項は,「金融機関等は,金融再生委員会がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として,次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする」と規定し,この「措置」として,同条項1号は,金融再生法6条2項に規定する基準に従い金融再生委員会が定めるところにより,適切に資産の査定を行うことを規定し,また,同条項2号は,「金融再生委員会が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより,適切に引当等を行うこと」を規定する。
同月23日には,金融再生法,早期健全化法等が施行された。(乙1の4頁,弁論の全趣旨)
イ 原告に対する検査結果の通知と原告の破綻
原告は,平成10年6月以降の株価下落を受けて,同月26日に住友信託との合併構想を発表し,また,同年8月21日,合併を前提とした不良債権処理・経営合理化策を発表するなどしたが,その後も,株価の下落や金融債の販売減少が継続していた。
金融監督庁は,同年10月19日,前記の原告に対する金融検査の結果を通知した。その内容は,同年3月期における資産内容については,検査による資産査定に原告の償却・引当基準を適用して算出した追加償却・引当の要見込額が2747億円(当期未処理損失額)に達しており,同期における有価証券等の含み損額1684億円を前提としても,自己資本額(7871億円)を下回るが,同年9月期において検査結果を踏まえて原告が試算した自己資本額が1600億円となり,有価証券等の含み損額が5000億円に達するというものであった。
原告は,同月23日,金融再生法68条2項により,内閣総理大臣に対し,「その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められる」旨の申出をし,これに対し,原告の申出及び原告の検査結果による財務状況を踏まえ,同日,内閣総理大臣により,金融再生法36条1項による特別公的管理の開始の決定がされた。(甲97添付資料11,乙1の70頁,71頁)
(12) 金融検査マニュアルの公表,税効果会計の導入,4号実務指針改正の経緯等
ア 金融検査マニュアルの作成・公表
(ア) 金融検査マニュアルの検討状況
金融監督庁は,平成10年8月25日,検査部に「金融検査マニュアル検討会」を設置し,金融検査マニュアルに関する検討を行い,同年12月には「中間とりまとめ」(以下「マニュアル中間とりまとめ」という。)を作成・公表し,広くパブリックコメントを求めた。
マニュアル中間とりまとめの中には,「破綻懸念先」に係る「経営改善計画」については,「原則として5年以内」であること,「10年以内となっている場合」には,「経営改善計画等の進捗状況が計画どおり」すなわち「(売上高等及び当期利益が事業計画に比して8割以上確保されていること)」,「計画終了後の当該債務者区分が正常先となる計画であること」が示され,また,「特定債務者支援引当金」という勘定科目について,「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」こと,「なお,債権放棄の方法による支援に伴う
損失見込額を,特定債務者支援引当金として計上していない場合は,貸倒引当金として計上する必要があるので,別途貸倒引当金として計上しているかを検証する」ことが示されていた。
この中間とりまとめに対しては,その基準案をそのまま適用した場合には,破綻懸念先等に該当する中小企業が増加し,貸し渋りや資金の回収が拡大するおそれがあること(日本商工会議所等),要注意先について,基準を機械的に適用した場合,債務者にとって厳しすぎる結果となること(全銀協),破綻懸念先のうち金融支援先については,経営改善計画を策定中の債務者や10年超の長期の改善計画に基づいて着実に改善している債務者が破綻懸念先に追い込まれることのないよう,経営改善計画等については,当該債務者の事業の継続性が十分認められる計画となっているかどうかなど,計画期間にかかわらず総合的に判断すべきとする意見(全銀協)や計画期間はケースバイケースの個別判断が適当であること(個人会計士),償却・引当
に関する検査については,原案がそのまま平成11年7月以降適用される場合には,新基準への対応のため経過期間を設けるなど計画的引当が可能となるような措置を要望すること(第二地方銀行協会)等の指摘がされていた。(乙1の158頁,555頁,556頁,乙30の50頁,乙31)
(イ) 金融検査マニュアルの内容,公表
その後,金融検査マニュアル検討会は,上記(ア)のパブリックコメント等も踏まえ,平成11年4月8日付けで,その「最終取りまとめ」を作成し,公表した。
a 破綻懸念先の意義の改正
「破綻懸念先」については「現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」であり,具体的には「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」とあったが,上記「債務者」の後に括弧書きとして「(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)」と付記し,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており」以下の部分が削除され,「現
状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり,従って損失発生の可能性が高い状況で,今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」と改められた。
なお,マニュアル中間とりまとめにおいて,「経営改善計画」について「原則として5年以内」,「10年以内」とされていた部分が「原則として概ね5年以内」,「概ね10年以内」と改められ,「(売上高等及び当期利益が事業計画に比して8割以上確保されていること)」とある部分も「概ね8割以上」と改められ,「計画終了後の当該債務者区分が正常先となる計画であること」についても,ただし書が付記され,「計画終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず,自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は,計画終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても差し支えない」と改められた。(甲136の38頁,39頁,乙1,乙30)
b 特定債務者支援引当金の新設
金融検査マニュアルにおいては,「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合」においては,「原則として,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上する」こと,また,「特定債務者に対する債権放棄,現金贈与等の方法による支援に伴う損失見込額については,特定債務者支援引当金を計上することが基本であるが,債権放棄の方法により支援を行っている場合において,当該特定の債務者区分が破綻懸念先で支援に伴う損失見込額が債権の範囲内であり,かつ,当該損失見込額が少額で特定債務者支援引当金を設定する必要性に乏しい場合など合理的な根拠がある場合は,個別貸倒引当金として
計上できる」ことが改正された。すなわち,「特定債務者支援引当金」という新たな勘定科目を新設し,支援が予定されている場合において,あらかじめその支援に必要な費用について引当金を計上すべきことが定められた。
なお,マニュアル中間とりまとめにおいては「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」とされていたが,これについても「経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は」の後に「原則として」を付記し,その後の「当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上しなければならない」とある部分を「計上しなければならない」から「計上する」と改めた。(甲136の38頁,40頁,乙
1,乙30)
c 金融検査マニュアルにおける主な改正点
これらの改正の結果として,金融機関が支援を継続していることのみをもって要注意先と査定し得る余地があった部分について,この改正により金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については,経営改善計画等の計画期間が5年以内であり,計画の実現可能性が高く,計画終了後に当該債務者が原則として正常先となること等の一定の条件を満たす場合に限り,要注意先であると判断して差し支えないとすること,これらの条件を満たさない場合には「破綻懸念先」とすべきことが明示的に定められた。
また,経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため,債権放棄,現金贈与等の方法による支援を行っている場合は,原則として,当該支援に伴い発生が見込まれる損失額を算定し,当該損失見込額に相当する額について,特定債務者支援引当金という勘定科目を設定し(又は貸倒引当金として),これを計上することが明示的に定められた。(甲136,乙1,乙30の49頁)
イ 税効果会計の導入に関する政省令の改正と銀行決算に与えた影響
(ア) 税効果会計の導入
企業会計審議会(平成10年政令第392号金融庁組織令24条参照)は,平成10年10月30日付けで,「税効果会計に関する会計基準の設定に関する意見書」を作成・公表し,連結財務諸表のほか(なお,連結財務諸表は,平成9年6月6日の連結財務諸表規則の改正により税効果会計を全面的に適用するとされていた。),個別財務諸表,中間財務諸表及び中間連結財務諸表を対象として,税効果会計に係る包括的な基準が示された。
これを踏まえて,同年大蔵省令第173号により,財務諸表規則,「連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という。)及び「中間財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表規則」という。)が改正され,個別財務諸表,連結財務諸表及び中間財務諸表における税効果会計の適用に関する規定が整備された。
すなわち,財務諸表規則8条の11において,「法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については,税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差違がある場合において,当該差違に係る法人税等の金額を適切に配分することにより,法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。」と規定され,連結財務諸表規則及び中間財務諸表規則においても同様の規定が定められている。
その適用については,財務諸表規則等の一部を改正する省令附則3条により,平成11年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から,税効果会計の適用が義務づけられた。なお,平成11年4月1日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち,同日以後に提出される有価証券報告書及び有価証券報告書に記載されるもの(すなわち,平成11年1月決算以後の決算期に係るもの)について早期に適用することも認められていた。(乙36)
(イ) 銀行決算に対する税効果会計の導入とその効果
その後,前記(ア)の早期適用として,平成11年3月期決算において銀行の決算に税効果会計が導入されたことに伴い,主要17行(都銀9行,長期信用銀行1行,信託銀行7行)は,約6兆6500億円の繰延税金資産を計上した。
また,主要17行は,不良債権を約10兆4000億円(個別債権処理額及び一般貸倒引当金繰入額の合計額)を処理し,そのため,多数の銀行が赤字決算を行ったが,それにもかかわらず,上記繰延税金資産の計上の効果として,平成10年3月期において2兆2400億円であった剰余金の額は,かえって,平成11年3月期において2兆6800億円に増加した。
そのため,税効果会計の導入により,会計と税務が切り離され,その結果,従来と比較して,有税による不良債権の処理すなわち償却・引当の自由度が高まったと評価された。(乙34,乙126,弁論の全趣旨)
ウ 4号実務指針の改正
会計士協会は,平成11年4月30日付けで,前記アの金融検査マニュアルの作成・公表を受けて,4号実務指針の一部を改正し,その中で,金融機関等の支援を前提として経営改善計画が策定されている債務者については,再建計画の実現可能性,その進捗状況及び今後の債務者の財政状態の回復の見込み等を総合的に判断し,自己査定が行われていることを確認すること,破綻懸念先債権については,「経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく」との文言が付加されたこと,「関連ノンバンクに対する債権」に関して,原則として関連ノンバンクが金融機関と同様の方法により自己査定及び償却・引当を行ったうえでの財政状態に基づいて査定を行う必要があること,経営支援先である関連ノンバンクに対する債権に係る今後の支援による予想損失
額について,債権放棄により支援を行う場合には貸倒引当金として,現金贈与等により支援を行う場合には特定債務者支援引当金として,それぞれ貸借対照表に計上しなければならないことが,改正の内容として定められた。(乙33,弁論の全趣旨)
4 争点③(平成10年3月期以前の改正前決算経理基準のもとで,銀行等金融 機関の不良債権の償却・引当に関する基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか。)について
2で検討したとおり,原告らの主張する資産査定通達等で補充される改正後決算経理基準が平成10年3月期における銀行等の貸出金の償却・引当の処理に関する基準として,「公正なる会計慣行」に該当し,しかもその内容が広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われることなく直ちに唯一のものとされるためには,従前の「公正なる会計慣行」との関係で,変更される会計慣行の内容によって企業会計の継続性の観点からの支障が生ずるような場合には,これに対する手当をする必要があると解されるところ,既に述べたとおり,銀行等の金融機関の不良債権の償却・引当の処理に関する従前の「公正なる会計慣行」の内容がどのようなものであったかについては,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったか否かの点で当事者
間に争いがあるので,以下では,まず平成9年3月期以前の銀行等の貸出金の償却・引当の処理が実際にどのようにして行われていたのかを検討したうえで,当時の銀行等の貸出金の償却・引当の処理の基準として,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったといえるか否かについて判断する。
(1) 資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準の導入より以前の段階,すなわち,平成9年3月期までに存在していた銀行の貸出金に関する償却・引当基準)の内容等
ア 平成9年3月期以前から存在していた株式会社の決算業務に係る会計処理の諸原則
(ア) 企業会計原則
a 企業会計原則と商法32条2項の「公正なる会計慣行」
企業会計原則(甲98添付資料5)は,昭和24年7月9日付けで,企業会計審議会(当時において経済安定本部企業会計制度対策調査会)の中間報告として作成・公表され,また,これを解説した企業会計原則注解は,昭和29年7月14日付けで,企業会計審議会の中間報告として作成・公表された。その内容は,「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを要約したもの」であるとされており(乙94の219頁,乙98の108頁),企業会計原則は「法令によって強制されないでも,全ての企業が従わなければならない基準」(企業会計原則の前文)とされている企業会計の基本的な事項を定めたものとされている。
ところで,証券取引法193条の2は,証券取引所に上場されている有価証券の発行会社に対し,同法の規定により提出する貸借対照表,損益計算書その他の財務計算に関する書類については,その者と特別利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと規定し,監査証明の方法については,「監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書等により行う旨規定していた。そして, この監査報告書の作成に当たっては,会計監査人における監査証明に係る会計実務において,企業会計原則は,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に当たるとする解釈・運用が採られていた(乙98の106頁)。
また,昭和49年の商法改正(昭和49年法律第21号)により,商法32条2項が規定され,企業会計原則は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するとの解釈・運用が,会計実務において採られていた。
このような経緯を踏まえる限り,企業会計原則・同注解は,平成9年3月期以前から,企業の会計処理に関しては,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たるものであったというべきである。
なお,企業会計原則においては,真実性の原則(「企業会計は,企業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければならない」),明瞭性の原則(「企業会計は,財務諸表によって,利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し,企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない」),継続性の原則(「企業会計は,その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し,みだりにこれを変更してはならない」),保守主義(「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には,これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない」)等の諸原則が定められており,これらの諸原則は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」として尊重されなければならないと解される。(甲98,甲159,
乙3,乙44,乙94ないし乙96,弁論の全趣旨)
b 企業会計原則における「貸倒見積高」,「貸倒引当金」
企業会計原則第三の四(一)Dでは,受取手形,売掛金その他債権に対する貸倒引当金は,原則として,その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形式で記載することが定められ,同原則注解の注18には,将来の特定の費用又は損失であって,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができる場合には,当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとすることが定められている。 また,企業会計原則第三の五Cでは,受取手形,売掛金その他の債権の貸借対照表価額は,債権金額又は取得金額から正常な貸倒見積高を控除した金額とすることが定められている。
(甲98添付資料5)
(イ) 貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い
会計士協会は,監査委員会報告第5号として,昭和40年4月6日付け「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(昭和51年4月6日改正)(以下「委員会報告第5号」という。)を作成・公表した。委員会報告書第5号によれば,監査報告書における意見を付ける際の指標として,貸倒引当金について,例えば,企業が一定の算定基準を有していたとしても,その基準が合理的かつ客観的でないと認められるとき,又は明らかに不足あるいは超過していると認められるときは,除外事項とすること,ただし,企業が算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合を除いては,除外事項としないこ
とができるとされていた。そして,その趣旨は,適正な貸倒見積高の算定に当たっては,我が国の会計慣行とりわけ税法基準を多くの企業が採用しているという実情を踏まえたうえで,税の確定決算主義の立場等を考慮して,税法基準によって算出した貸倒見積高を計上している場合でも一定の条件のもとに一般に認められた企業会計の基準に準拠しているものとして取り扱うことができる旨定めたものであり,税法基準を採用している場合にはこれは継続して適用すべきことを要請しているものであるとされていた。(乙13,弁論の全趣旨)
なお,ここでいう税法基準とは,法人税法で損金算入が認められる限度額において企業会計の費用又は損失を経理処理すれば足り,法人税法上容認される損金算入限度額を超えてまで費用として処理する必要がないとするものであるが,本件では,銀行における貸出金の償却・引当の処理に関する会計実務とこの税法基準との関係が問題となるので,後に項を改めて検討することとする。
イ 銀行特有の規制,銀行特有の企業会計の基準
(ア) 銀行法による特殊な規制と大蔵省の監督権限
a 銀行法の規制
銀行法(昭和56年法律第59号。なお,平成10年法律第131号による改正前のもの)は,銀行経営の高度の公共性にかんがみ,一般大衆の預金の保護,信用維持等の観点から,銀行に対し,免許制,営む業務の限定,取締役の兼職の制限等,一般私企業にはない各種の規制を定めていた。 そして,原告については,長期信用銀行法により,銀行法の規制が準用されるか,又は銀行と同様の規制が設けられていた。
b 大蔵省による監督・規制権限
このような銀行経営の健全性及び適切性については,銀行の取締役等が,これを維持すべき職責を負うもの(銀行法1条2項参照)であり,このような観点から,銀行の取締役に銀行経営に専念させるべく,銀行法7条等の規制が設けられていると解されるが,銀行法は,従前(平成10年法律第131号改正前),大蔵省に銀行経営に対する広範な監督・規制権限を認めており,大蔵省によるこのような権限の行使を通じて,銀行経営の健全性及び適切性を確保することを定めていた。
すなわち,銀行の取締役の兼職については,大蔵大臣が認可する権限を有しており(銀行法24条1項),また,大蔵大臣に立入検査権限(同法25条1項),業務の停止等の権限(同法26条),免許取消等の権限(同法27条)を与えていた。 そして,大蔵省は,銀行経営の健全性及び適切性を確保する見地から,銀行免許の認可・剥奪権限(銀行法4条,27条),銀行取締役又は監査役の解任権限(同法27条)及び業務停止等の権限(同法26条)を有し,これらの諸権限を適正に行使するとともに,銀行それ自体の経営を監督・監視するため,その権限の行使を妨げた場合に刑罰(銀行法63条)による制裁を伴う資料提出権限(同法24条)及び立入調査権限(同25条)が認められており,大蔵省が銀行の経営に対する広
範な監督権限を有するなど,通常の株式会社と全く異なる規制が存在していた。
c 大蔵省検査
大蔵省は,銀行法上の大蔵大臣の立入検査の権限(銀行法25条)に基づき,平成10年3月期以前においては,銀行の経営の健全性を確保し,銀行業務の健全かつ適正な運営を期するため,一定期間(通常は2,3年に1回)ごとに,金融機関の経営状況全般についての検査を実施していた(甲69の2の4頁,5頁,甲97の4頁,乙115の7頁)。
この大蔵省検査において,金融証券検査官は,銀行の貸出金等の資産査定すなわち貸出金等の資産個別に検討して確実性の度合に応じ,4段階に分類する作業を実施していた。
その際の分類の方法については,昭和42年1月27日付け事務連絡銀検第28号「資産査定上の調整事項について」(昭和56年6月30日付け事務連絡銀検第131号改正,平成8年8月30日事務連絡最終改正)に従い(甲231添付資料2),非分類すなわちⅠ分類(「Ⅱ,Ⅲ及びⅣ分類以外の資産」),Ⅱ分類(「債権確保上の諸条件が満足に充たされないため,あるいは,信用上疑義が存する等の理由により,その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権及び何らかの理由により金融機関の資産として好ましくないと判定されるその他の資産」),Ⅲ分類(「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し,従って損失の発生が見込まれるが,その損失額の確定し得ない資産(Ⅲ分類額の50パーセント相当額は
正味自己資本査定上損失とする。)」)及びⅣ分類(「回収不可能又は無価値と判定される資産」)に分類するものと定められていた。
銀行等の金融機関は,このような金融証券検査官の実施した資産分類に沿って,その財務諸表を作成し,外部の監査を受けるなどして(甲139の19頁),決算業務及び会計処理を行っていた。(甲69の2,甲97,甲139,甲231,弁論の全趣旨)
(イ) 銀行特有の会計
このような銀行法による特殊な規制及び大蔵省の監督権限については,銀行における企業会計処理にも及んでいた。
すなわち,銀行は,毎営業年度ごとに,大蔵省令で定めるところにより,貸借対照表及び損益計算書を作成して,当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならないとされ(銀行法20条),さらに,銀行が商法第281条第1項(計算書類)の規定により作成する営業報告書及び附属明細書の記載事項は,大蔵省令で定めるとされ(同法22条),銀行の決算も大蔵省の監督下に置かれ,かつ,その決算書類(貸借対照表,損益計算書等)についても,大蔵省令において規定されていた。
また,本来,商法281条1項により毎決算期において株式会社が作成すべき貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書の記載方法は,「株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に関する規則」(以下「計算書類規則」という。)(昭和38年法務省令第31号。現平成14年法務省令第22号の商法施行規則)1条により,計算書類規則の定めるところによる旨規定されているが,銀行及び長期信用銀行が作成すべき商法第281条第1項に掲げる貸借対照表及び損益計算書の記載方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法については,「株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令」(昭和57年法務省令第42号)3条によ
り,計算書類規則2条1項の「貸借対照表及び損益計算書は,会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない」との規定すなわち明瞭性の原則を除き,計算書類規則の適用が排除され,それぞれ,銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)及び長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)の定めるところによる旨規定されていた。
これらの規制により,商法281条1項の毎決算期における貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書については,銀行法上の業務報告書により代置され,また,その記載方法についても,大蔵省令により定められていた。(乙6,弁論の全趣旨)
(ウ) 改正前決算経理基準
a 統一経理基準の沿革
前記のとおり,銀行における会計処理の業務は,法令により銀行経営の健全性及び適切性を確保するため,大蔵省の監督・規制下に置かれていたが,大蔵省は,このような法律上の規制に加えて,通達により,銀行の決算処理(会計処理)の業務を規制していた。
すなわち,大蔵省銀行局長は,昭和42年9月30日蔵銀1507号通達により,銀行が決算において従うべき会計の基準として,統一経理基準を示していたが,その後,数次の改正を経て,昭和50年7月7日蔵銀第1993号「銀行の経理基準について」と題する通達を発出し,新たな統一経理基準を示した。
その間,各銀行は,これらの統一経理基準に従い,決算業務を行っていたところ,会計士協会は,昭和51年10月付け「銀行業統一経理基準および財務諸表様式に係る監査上の取扱いについて」を作成・公表し,その中で,「昭和42年9月30日蔵銀1507号」として発せられた銀行業の統一経理基準について,今回の新通達『銀行の経理基準について』(昭和50年7月7日蔵銀第1993号,以下「現統一経理基準」という。)によって改正されるまでの間,数次にわたりその一部が改正されて今日に至っているが,各銀行はこれらの統一経理基準を銀行業における統一的な企業会計の基準として採用し,現在すでに会計慣行化しているものと考えられる旨述べて,現統一経理基準に基づく会計処理は,商法32条2項にいう「公正な会
計慣行」に合致しているものとして取り扱うことを明らかにして,統一経理基準が,銀行の決算経理の処理に関する「公正なる会計慣行」であるとの見解を表明した。(証人L23頁,甲228,乙6,乙7,乙81,乙120,弁論の全趣旨)
b 改正前決算経理基準の沿革等
その後,大蔵省銀行局長は,銀行法(昭和56年法律第59号)の施行に伴い,各普通銀行の代表者に宛てて,昭和57年4月1日付け蔵銀第901号「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」と題する通達を発出し,経理関係について,普通銀行が従うべき会計処理の基準として 前記統一経理基準を踏襲した改正前決算経理基準が発出され,普通銀行は,その経理処理を行うに当たり,改正前決算経理基準を遵守しなければならないものとされるに至った(乙6の7頁,乙11の21頁,乙81の4枚目)。
そして,普通銀行は,上記通達の発出以降,改正前決算経理基準に従い,会計処理を行っていたところ(甲60の51頁,甲122の82頁,甲133の141頁,甲136の9頁,同99頁,甲128の46頁,甲123の135頁),原告を含む長期信用銀行においては,固有の通達が発出されておらず,普通銀行に関する改正前決算経理基準を準用する取扱いが採られており(乙42の19頁),普通銀行と同様に,長期信用銀行においても,この改正前決算経理基準に従い,決算のための会計処理業務が行われていた。(証人L,甲60,甲122,甲123,甲128,甲133,甲136,乙6,乙11,乙42,乙81)
c 改正前決算経理基準における基本原則と「貸出金の償却」及び「貸倒引当金」の計上基準
改正前決算経理基準では,貸出金の償却として「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額を償却するものとする。なお,有税償却する貸出金については,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。」と定められ,また,貸倒引当金については,「貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定〔租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。以下同じ。〕を除く。)は,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとし,また,租税特別措置法第55条の2第7項の規定に係る貸倒引当金相当額を有税により繰り入れるものとする。」,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものと
する。なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。」と定められていた。(甲183,甲231,乙6)
なお,改正前決算経理基準においても,企業会計原則と同様に①真実性の原則,②明瞭性の原則,③継続性の原則,④保守性の原則等が定められている(乙6の7頁)。
(エ) 不良債権償却証明制度
a 不良債権償却証明制度の沿革
昭和25年以降,銀行を含む金融機関等の不良債権の損金処理,すなわち無税による償却・引当(法人税基本通達9-6-1ないし9-6-7に基づく処理)については,銀行と国税庁との協議に基づき実施され,金融証券検査官がⅣ分類及びこれに準ずるものとして証明した不良債権の金額は,原則として法人税法52条1項の「損金」に算入することが認められていた(乙5の40頁,乙6の13頁,乙9の350頁,乙11の24頁)。
なお,平成5年11月29日蔵検第439号「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,大蔵省による後記ウ(ア)の不良債権処理の方針を受けて,平成6年2月8日蔵検第53号一部改正通達が発出され,後記cのとおり,有税による償却・引当に関する内容が改正されたほかは,基本的には従前と同内容であった(乙9の350頁)。(乙5,乙6,乙9,乙11,弁論の全趣旨)
b 不良債権償却証明制度実施要領の内容
まず,金融機関等が必要な償却を行い,資産内容の充実を図ることは望ましいが,証明官の審査が厳に失し,あるいは寛に流れるときは本制度の本来の意義を失うおそれがあるので,税務当局との密接な連絡を保ちつつ,適正且つ慎重に審査を行うことが方針として示され,管轄及び証明官として,原告のような長期信用銀行においては,大蔵省金融検査部長が指名する上席金融証券検査官が証明手続を担当することと定められていた。
その証明内容については,直接償却の場合は,法人税基本通達「9-6-2」(回収不能の貸金等の貸倒れ)の貸金等の貸倒れの金額等についての証明を受けること,「間接償却」の場合は,法人税基本通達「9-6-4」(認定による債権償却特別勘定の設定)及び『9-6-7』(状況が変化した場合等の債権償却特別勘定の積増し)の債権償却特別勘定繰入れについてその金額等の証明を受けることがそれぞれ定められていた(乙9の351頁)。
証明手続については,各期末の償却予定債権の件数及び金額の概数並びに償却予定債務者明細(別添様式1)を,決算期末の2か月前の月の末日までに,大蔵省金融検査部審査課総括係宛てに提出することが定められており,具体的な提出書類としては,その証明内容ごとに,例えば,法人税基本通達「9-6-2 」(回収不能の貸金等の貸倒れ)の貸金等の貸倒れの金額の証明を受ける場合には,不良債権償却証明申請書及び不良債権明細表が提出書類と定められており,証明に当たっては,大蔵省金融検査部長の決裁を経て,正式発遣の手続がとられた(乙9の352頁,353頁)。
審査手続については,原則として,決算期末の月を審査の期間とすること,また,前回大蔵省検査後相当日時を経過している等の理由により必要と認める場合は,実地調査が行われること,申請債権について当期決算の概略(償却・引当の能力に重点を置く。),要償却債権の全貌(申請債権以外の要償却債権の有無及びその金額)等を調査事項とすること,実地調査に当たっては,金融機関に対し,貸出稟議書,信用調査資料,償却稟議書,申請債権に関する参考書類,当期決算予想表及び申請債権以外の不良債権一覧表を準備するよう求めることがそれぞれ定められていた。
具体的な査定基準としては,例えば,大蔵省検査の際にⅣ分類と査定された債権等について償却対象とし,回収不能額又は回収不能見込額を算定することが定められ,また,法人税基本通達9-6-4による債権償却特別勘定への無税繰入れに係る金額を証明する場合には,債務超過の状態が相当期間継続しているかどうか,事業好転の見通しがないかどうかを審査し,貸金等の額の相当部分(おおむね50パーセント)以上の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について判断すべきことが定められていた。
なお,上記事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないと定められていた(乙9の357頁)。
また,実際に,不良債権償却証明制度に基づき,銀行がその証明を受ける場合には,必要な資料を作成し,償却証明の申請を行い,債権償却特別勘定への繰入れが認められるかどうかについて質疑応答等を繰り返して,これが認められれば,金融証券検査官から期末までに債権償却証明の証明書が届けられた(証人X〔以下「証人X」という。〕6頁)。(証人X,甲131,乙9,乙11)
c 不良債権償却証明制度のもとにおける有税による償却・引当の取扱い
他方,有税償却・引当については,平成4年7月ころまでは,無税償却・引当と同様に大蔵省の承認を要したが,後記ウ(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」を公表した際,有税引当の活用を図るため,前記aの平成6年2月8日蔵検第53号一部改正通達により,以下の内容が定められた。
すなわち,まず届出制に改められ,有税引当等(有税引当及び有税直接償却)については,届出の受理に当たって,金融機関等の自主判断により行われるものであることに留意することとされ,また,届出があった際には,無税償却の適用がないかどうか等について聴取するものと定められ,その際には「不良債権有税引当等届出書」を作成し,無税償却・引当に関する提出手続に準じて,これを提出させることとされていた。
なお,不良債権有税引当等届出書の様式は,無税による償却・引当に係る不良債権明細表等と同様の様式であった。また,届出制に改められた後も,債権償却特別勘定への繰入れは,銀行による過剰引当が行われるなどの決算操作に利用されることを防止するため,有税による償却・引当についても,無税の場合と同様の資料を作成し,回収不能又はそれが見込まれる根拠やその金額について説明が行われる必要があった。 すなわち,この両者は,その説明を疎明する資料の有無,程度が多少相違するというものであるにすぎず,基本的には,銀行は,貸出金に関する償却・引当の根拠を十分に説明する必要があり,実質的には同様の手続であった(証人X5頁,33頁,甲136の9頁,乙118の9頁)。(証人X,
甲58,甲125,甲131,甲136の9頁,甲158,乙5,乙6,乙9,乙11,乙118)
そして,無税償却・引当の対象となるべき貸出金については,明示的に償却・引当が義務づけられていた。一方で,有税償却・引当については,その内容を当局に届け出る旨が定められているにすぎず,しかも具体的にどのような基準により償却・引当を実施すべきかについては明確な基準が存しなかったばかりか,有税償却・引当は,金融機関の自主的な経営判断で行うべきものとされ,無税償却・引当の場合のような不良債権償却証明制度のもとでの審査は行う必要がないものとされていた。その結果,有税償却は無税償却と異なり銀行の決算内容に負担を及ぼすこともあって,銀行は,もっぱら,無税償却・引当が可能な場合に償却・引当を行い,有税による償却・引当をほとんど行っていないのが実情であった。(証人L3頁,証人K8頁
,甲60,甲118,甲158の29頁,乙10の50頁,甲158の30頁,弁論の全趣旨)。
(オ) 小括
以上のような平成9年3月期以前に存在していた銀行の決算業務における会計処理の諸原則を前提とすると,平成9年3月期以前の銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の実務は次のようなものであったといえる。まず,基本的には,「公正なる会計慣行」であるところの企業会計原則・同注解によることになるが,銀行については,自己資本の充実と資産内容の健全化を図る観点から,企業会計原則・同注解よりも規制の厳格な改正前決算経理基準が発出されており,これに従うことになるところ,銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の基準としては,改正前決算経理基準のなかで無税償却・引当の対象となる貸出金については明示的に償却・引当を行うことが義務づけられていたが,有税償却・引当については,平成6年2月に通
達によりその活用を図るため届出制に改められはしたものの,その内容を銀行が自主的に当局に対し届け出る旨定められているにすぎず,具体的にどのような基準により償却・引当を実施すべきかについて明確な基準が存在しないという状況にあり,しかも,有税処理による損失計上は無税処理の場合と比べると銀行の決算内容に負担を及ぼすため,実際には,銀行は有税償却・引当をほとんど行っていないのが実情であった(甲158,乙10)。
そして,改正前決算経理基準のもとで,平成5年11月から通達により不良債権償却証明制度が採用されており,そこではより細かな銀行の貸出金に関する無税償却・引当の基準及び手続が定められていた。その結果,当時の銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理の実務としては,不良債権償却証明制度によって補充された改正前決算経理基準に基づき,もっぱら税法上無税償却・引当が可能な場合に償却・引当を行うことが一般化しており,大蔵省検査において,銀行の貸出金がⅣ分類と査定された場合には,不良債権償却証明制度を介して回収不可能な貸出金として無税による償却・引当が可能となり,銀行としてもこのようなⅣ分類と査定された貸出金については,当期に全額の償却・引当を実施するものとされていた。このような経緯
から明らかなとおり,大蔵省検査によりⅣ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度を介して,義務的に貸出金の償却・引当を行う一方で,有税による償却・引当については,銀行の自主的な判断に委ねられた結果,実際には有税償却・引当はほとんど行われないという会計慣行が存在していたものといえる。
なお,前記認定のとおり,不良債権償却証明制度が採用される以前から,銀行の貸出金の無税による償却・引当については,銀行と国税庁の協議により実施され,金融検査官の証明により損金算入が認められており,上記のような会計慣行は,実際には,遅くとも資産査定通達が発出された昭和57年以降,会計慣行として定着していたものといえる。
ウ 銀行の不良債権処理に関する大蔵省の指針と銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務
(ア) 大蔵省による不良債権処理に関する指針
大蔵省は,バブル経済の崩壊以降,銀行の不良債権が増大する中,銀行に対して,不良債権を抱えている相手先企業であっても,将来の経済情勢の回復に期待し銀行が時間の猶予を与えることによって,本業の収益により徐々に穴埋めをさせることができるはずであり(乙2の88頁),いわゆるメインバンクである金融機関は,そのような企業の再建のために時間を貸すことが有効であるとするいわゆるソフトランディングの考え方に依拠して,平成4年から平成7年までの間に,以下のような指針を公表して,不良債権の処理方針を示した。
まず,大蔵省が平成4年8月18日付けで公表した「金融行政の当面の運営方針-金融システムの安定性確保と効率化の推進」と題する指針(乙15)によれば,不良資産の処理方針の早期確定とその計画的・段階的処理が急務であり,これにより国民の金融システムへの不安感を払拭するとともに,その安定性の確保に努めることが重要であること,個別問題の早期処理として,住宅金融専門会社,ノンバンク等の個別問題は,極めて多数の金融機関が関与し,利害関係が従来になく錯綜し,処理方針の早期確定と計画的・段階的処理に向けての一層の努力が要請されること,担保不動産の流動化として,不良資産の処理方針の早期確定と計画的・段階的処理を図り,併せて不動産の流動化に資するため,民間金融機関の協調による,担保不動産の
流動化のための方策につき早急な検討を行うこと,不良資産処理のための環境整備として,不良資産の処理が円滑に促進されるよう税務上の取扱いをも含め,必要な環境整備に努めることが指摘されていた。
次に,大蔵省が平成6年2月8日付けで公表した「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」と題する指針(乙16)においては,金融機関の資産内容悪化は,様々なレベルで金融機関に課題をもたらしていること,貸付債権のなかには,融資先企業の業績低下等により,通常に比べて留意を要する債権があることが指摘され,具体的には,その債権の性格ごとに以下のような留意事項が示されていた。
すなわち,「金融機関が,経営上の困難に直面した融資先に対して,金利減免等により支援を行っている債権」については,関係者の努力により元本が回収されるという前提で再建計画が実施されている貸出先に対するものであり,次に述べる破綻先債権,延滞債権と同列に扱うことはできないが,長期にわたって金融機関の収益を圧迫するという問題があること,「融資先が破綻しているか,又は延滞している債権」については,その一部につき回収不能が見込まれ,今後時間をかけて償却等により処理していく必要があるものであること,このような「破綻先債権,延滞債権のみならず,通常に比べて留意を要する債権や金利減免債権等」については,これらを同一視し,そのすべてについて償却等による処理が必要
であるかのように論ずることは適当ではなく,誤解を招くものであることが指摘され,金融機関においては,かつてなく厳しい経営環境のもとで,このような資産内容の実態に即した適切な対応を行っていく必要があり,償却等による処理が必要となるものについては,早期に処理方針を確定させ,計画的,段階的に処理を進めていくことが重要な課題であるとされていた。
また,上記指針の中の「不良資産の処理促進」については,不良債権についての償却・引当制度の活用として,いわゆる無税償却については,不良債権の実態に即した貸倒れ等の事実の認定を通じ,必要な償却を行うとの趣旨を徹底し,ノンバンク向け債権も含め,償却の一層の促進を図るとともに,そのための当局の体制についても引き続き充実強化に努めること,また,有税引当については,従来,金融機関は,貸倒れ又はこれに準ずる状況にある債権について償却・引当を行ってきたが,最近における不良債権の実態にかんがみ,引当制度の運用を改善し,貸倒れには至っていないものの回収に危険のある債権についても,金融機関自らの判断により,将来の回収についてのリスクに応じた必要な引当が行われるようにすることとしたこと,こ
れによって,回収不能とはまだ判定されていないが,リスクが高まっている延滞債権等についても,有税引当が行われることが期待されるが,他方で,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権については,この有税引当を行うことは,当面,企業会計上の合理性がないことになること,このような債権への対処としては,金利減免債権の流動化が検討対象となるところ,金利減免債権の流動化として,多額の不動産関連融資を抱えて資産内容が悪化し,経営上困難に直面しているノンバンク等について,関係金融機関は,金融システムの安定性確保の重要性を認識したうえで,長期的な展望のもとに,自主的に適切な対応を行っていく必要があること,これらのノンバンク等に対し,その再建計画の一環として金利減免
による支援が行われつつあるが,これら金利減免債権は,支援金融機関にとっては長期にわたって収益圧迫要因になり,財務体質の改善上問題があること,しかし,複数の金融機関による再建計画が実施されている場合に,金利減免債権をまったくの第三者に売却することは,再建計画の円滑な進捗を阻害することにもなりかねないことから,再建計画の円滑な進捗と関係金融機関の財務体質の改善を整合させるため,特別目的会社(再建計画の実行を管理する会社)を設立し,これに対して金融機関が抱えるノンバンク等向け金利減免債権が流動化することについて検討することとしたこと,これにより,金融機関は,金利減免債権を市場実勢価格で現物出資し,簿価(金利減免前の債権の帳簿価額)と時価(金利減免後の債権を市場実勢利率に基づく割引率
で現在価値に割り戻した市場実勢価額)との差額をロスカットすることとなるが,元本は回収されることが前提であることが指摘されていた。
そして,このような指針を受けて,平成6年2月8日付けで「不良債権償却証明制度実施要領について」の一部改正通達が発出され,有税による償却・引当に関して,金融機関等の自主判断により,改正前決算経理基準等に基づき,その内容を当局に提出したうえで,有税直接償却及び有税引当の実施がされることとなった。
その後,大蔵省が平成7年6月8日付けで公表した「金融システムの機能回復について」の中には,健全で活力ある金融システムは,我が国経済の安定的発展のため必要不可欠な前提であること,我が国経済が今後21世紀に向けて,豊かで創造的な経済社会を築いていくために,残された概ね5年の間に,金利減免等を行っている債権をも含め,従来の発想にとらわれることなく金融機関の不良債権問題に解決の目処をつけることとすること,このため,金融制度調査会においても基本的考え方について審議される予定であるが,大蔵省としては,当面次のような考え方により不良債権問題の早期解決に取り組み,金融システムの機能回復を図ることが示されていた。
また,その中で,「金融機関の自主的な経営健全化努力」として,行政としても,概ね5年の間に,金利減免等債権を含む不良債権問題の解決に目処をつけるため,所要の環境整備を図り,金融機関の真摯な経営努力を促すこと,その中で金融機関から金利減免等の支援を受けているノンバンク・住宅金融専門会社等については,再建計画の進捗状況の的確な把握が行われるとともに,必要に応じ再建計画の抜本的見直しを含む適切な措置が講じられるようにすること,金利減免等債権を含む不良債権の処理に際し,金融機関の体力や収益環境に応じて弾力的に対応できるよう,段階的な処理方策を検討すること,担保不動産の流動化等に向けた努力が一層要請されることが指摘されていた。
さらに,大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会の金融システム安定化委員会において,平成7年12月22日付け「金融システム安定化のための諸施策-市場規律に基づく新しい金融システムの構築-」(乙17)が答申され,その中でも,不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできる限り早期にその処理に目処をつける必要があること,各金融機関は先ず自助による最大限の合理化努力や早期の引当,償却等の実施により,迅速にその処理を行っていく必要があることが指摘されていた。(乙2,乙11,乙15ないし乙17,乙99,乙117,弁論の全趣旨)
(イ) 銀行における関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務
a 金融慣行としてのメインバンク関係と母体行主義
我が国においては,従前,メインバンク制とかメインバンク関係と呼ばれる銀行と企業との間の取引慣行(金融慣行)が存在しており,その内容は,当該企業にとって,融資取引,預金取引,内国為替の取扱い,外国為替の売買といった銀行取引のいずれにおいても最大の取引シェアを誇る銀行はメインバンクと呼ばれ,このようなメインバンク関係として,当該企業が経営危機に陥った場合を含め,銀行がメインバンクとして企業の発展・成長に必要な設備投資等の資金を安定的に供給し,他方,当該企業においては,安定的な資金供給の見返りとして,あらゆる銀行取引において,メインバンクとの取引シェアを他の銀行よりも高く維持し,また,メインバンクは,当該企業の株式を取得し,その立場に基づき,従業員を当該企業の役員として
派遣するなど,当該企業の経営に実質的に関与し,さらに,当該企業が経営危機に陥った場合には,メインバンクは,その名声(信用)の維持,既存融資の回収の極大化,当該企業との取引の維持による営業基盤の維持拡大といった便益を考慮し,救済による便益がその費用(金利減免に伴う逸失利息,救済融資実行等による損失負担リスクの増大,救済活動に要する費用等)を上回ると判断する場合には,しばしば当該企業を救済する事例がみられた(甲115の127頁,甲116の95頁,乙7)。
このような金融慣行を前提に,バブル崩壊後,不動産関連融資を増大させていた銀行の関連ノンバンクが経営危機に陥っていたため,母体行によるこれらの関連ノンバンクの経営に対する事実上の支配を前提として,これらの関連ノンバンクを再建する母体行主義の慣行が行われていた。すなわち,前記(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」において示されるとおり,母体行による関連ノンバンクの支援計画について,当該関連ノンバンクに対する不良債権(金利減免等の貸出条件を緩和した債権)の処理もさることながら,その再建計画の円滑な進捗にも配慮し,再建計画の実行を管理する特別目的会社の設立及びこの会社への金利減免債権の売却を求めるなど,関連ノンバンクの支援,再建とこれに伴う不良債権の処理につ
いては,できる限り,母体行が関連ノンバンクを支援し再建させる手法が採られていた。
この背景には,各銀行は,相互にそれぞれの関連ノンバンクに融資し,各関連ノンバンクの資産(営業貸付金)状況のみを考慮して一斉に融資の回収をした場合には,関連ノンバンクが資金繰り破綻を起こして倒産し,その結果,母体行である親銀行の経営状況をも圧迫し,我が国の金融システム全体が崩壊するというシステミックリスク(銀行間取引の増大に伴い,ある銀行が破綻した場合に,それが他の銀行に波及し金融機関が連鎖的に倒産する現象を指す。甲115の126頁)が発生することを回避し,母体行がそれぞれの関連ノンバンクを支援し,また,このような母体行以外の銀行は,母体行である銀行の経営状況をも考慮して,当該関連ノンバンクに対する融資取引を継続するという母体行主義が行われていた(甲120の97頁,
99頁,甲123の158頁,甲129の116頁,乙101の2頁,甲69の106頁,乙106の18頁)。このような例は,株式会社富士銀行が芙蓉総合リースを支援した事例,株式会社三菱銀行がダイヤモンドリースを支援した事例,株式会社東海銀行(以下「東海銀行」という。)がセントラルリースを支援した事例が挙げられる(甲120の101頁)。
特に,このような母体行主義の考え方は,いわゆる住専処理について,農林系統金融機関が,設立母体である銀行に全面的な損失負担を求め(「完全母体行主義」などと呼ばれた。),他方,銀行は,プロラタ責任主義(貸出残高の割合すなわちシェアに応じて損失を負担する主義)を主張したが(乙2の149頁から150頁),最終的には,母体行である銀行が債権全額を放棄し(貸付残高を上限として責任を負担する修正母体行主義による責任負担),母体行以外の銀行が一定額の損失を負担する解決が図られたこと(乙2の155頁,甲115の104頁)からも裏付けられる。(甲68の16頁,同131頁,甲115の104頁,105頁,甲116,甲129の116頁,甲231,乙2,乙7,乙8,乙16,乙100,乙101
,乙104,乙110,H本人5頁)
b 大蔵省検査及び日銀考査における関連ノンバンクの資産査定に関する実務等
大蔵省検査及び日銀考査においても,このような母体行主義を前提とした査定が行われていた。
(a) まず,大蔵省検査においては,銀行が関連ノンバンクに多額の融資を行い,バブル経済の崩壊後,これが不良債権化したため,その実態の把握如何により査定結果が大きく変わり,銀行経営への影響が大きくなること,また,銀行は,母体行主義により,関連ノンバンクに対し,支援損(債権放棄)を計上するなどの支援を実施していたことから,検査に当たる金融証券検査官は,この問題を査定の場面においてどのように反映させるべきかについて疑問を持ち,大蔵省金融検査部においてその検討が行われた結果,平成6年4月12日付け「Ⅲ分類及びⅣ分類の査定の考え方等について」と題する文書(甲231添付資料8)により,銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定についての考え方が示された。
その中で,「貸金業を営む関連会社」について,銀行の貸出金残高が100存在し,関連会社の営業貸付金が500である場合において,再建方法として,他行の支援を求めず,親銀行が今後支援損を計上する,例えば,支援損100を3年間で計上することを予定しているときには,100をⅢ分類とすること,ただ,当年度の支援損が確定している場合には,例えば,Ⅳ分類33,Ⅲ分類67とすることが示されていた。
その後,平成7年4月13日付け「当面の貸出金等査定におけるⅢ分類及びⅣ分類の考え方について」と題する大蔵省管理課長発出の事務連絡(乙110,以下「7年事務連絡」という。)において,以下のような考え方が示された。
まず,「一般債務者」については,実質死に体(事業活動は継続しているものの,業況悪化が深刻な状態にあり,再建が困難)の状況にある場合,例えば貸出金残高が100,不動産担保の時価が50掛目0.7,評価35)である場合,Ⅱ分類35,Ⅲ分類15,Ⅳ分類50と査定する案(A案)と,Ⅱ分類50,Ⅳ分類50と査定する案(B案)が示されていた。
次に,「関連ノンバンク」については,体力がある場合(①償却前利益,②内部留保,③含み益,④純資産〔実質ベース〕等を勘案し,不良資産の処理が2~3年〔一応の目途〕で可能な場合)には,「一般債務者」に準ずることが示され,他方,体力がない場合(①償却前利益,②内部留保,③含み益,④純資産〔実質ベース〕等を勘案し,不良資産の処理が2~3年〔一応の目途〕で不可能な場合)には,再建計画の策定の有無により,査定方法が区別されることが示されていた。
この体力がない関連ノンバンクにおいて,再建計画が策定されていない場合には,原則として,「関連ノンバンク」の営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされ,例えば,営業貸付金(200)の査定結果が,非20,Ⅱ80,Ⅲ50,Ⅳ50であれば,関連ノンバンクに対する親銀行の貸出金(150)の査定が,Ⅱ50,Ⅲ50,Ⅳ50とそのまま反映されていた。
これに対し,体力がない関連ノンバンクにおいて,再建計画が策定されている場合(但し,検査官が妥当と判断したものに限る)には,再建計画が策定されていない場合と同様に,原則として,「関連ノンバンク」の営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされていたが,ただし,再建計画において,支援損等の計上が予定されている場合は,支援損相当額についてⅣ分類とし,その他をⅡ分類とすることも可とすることが示され,例えば,支援損75を5年間にわたり各年度15ずつ計上予定の場合には,営業貸付金200の査定結果が,非20,Ⅱ80,Ⅲ50,Ⅳ50であれば,関連ノンバンクに対する親銀行の貸出金150の査定が,Ⅱ75,Ⅳ75であるとされていた。
また,7年事務連絡では,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面考慮せずに査定を行うこととするとの方針が示されていた。
以上のとおり,7年事務連絡においては,関連ノンバンクの資産査定の結果については,他の銀行が当該関連ノンバンクに対する融資を行っている場合において,当該貸出残高を総貸出額で按分(プロラタ方式)して査定・分類するのではなく,そのまま関連ノンバンクの親銀行である銀行の貸出金の査定に反映させる仕組みが採用され,その限度において,関連ノンバンクの営業貸付金等の査定結果について,他の銀行の貸出金には反映させない取扱いが行われるとともに,他方,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面,考慮せず査定作業を行うこととすることが示されていた。(甲231,乙106の17頁,乙110,弁論の全趣旨)
(b) 次に,日銀考査については,日本銀行法(平成9年法律第89号)44条に基づき,第37条から第39条までに規定する業務を適切に行い,及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして,これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で,考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について,日銀が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約を締結することができ,日銀は,この考査契約に基づき,銀行の業務及び財産状況に関する考査(いわゆる日銀考査)を実施していた。
日銀考査においては,銀行の貸出金に関する査定として,「D分類」(Ⅱ分類に相当),「S分類」(Ⅲ分類に相当),「L分類」(Ⅳ分類に相当)に分類することが行われていたところ,従来銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定に当たっては,一般企業向け融資と同様に,そのノンバンク自体の支払状況や支払能力をベースに査定しており,銀行のノンバンクに対する融資額の範囲内で,D分類,S分類,L分類の分類を実施していたが,平成3年8月以降,親銀行の関連ノンバンク向け貸出金の査定に当たっては,関連ノンバンクの抱える不良債権の規模を査定し,関連ノンバンクに親銀行の融資額を超える不良債権が存在している場合には,その不良債権全額を親銀行本体の不良債権とみなすとの方針が採用され,これに基づく日銀考査
が実施されることとなった。すなわち,日銀考査において,認定不良債権額が親銀行の貸出金の総額を超える場合には,実際に存在しない「保証勘定」を設けて計数を調整し(乙106の18頁),他方,親銀行以外の銀行の関連ノンバンクに対する貸付金には,この不良債権額を反映させない仕組みが取られていた。
この方針による日銀考査の際には,親銀行に関連ノンバンクの経営を全面的に支援する意思を有するかどうかを確認して,その意思がある場合には,上記方針による考査が実施された。
このような日銀考査の方針の背景には,バブル経済の崩壊による不動産関連の倒産の増加により,関連ノンバンクに多額の不良債権が発生しており,後ろ盾となる親銀行が明確ではないまま,経営難に陥る例が多発した場合には,金融システム全体の混乱につながりかねないとの判断が存在していた。
なお,当時,多数の銀行は,支援意思を明確にして,日銀考査を受け入れており,その理由としては,親銀行以外の銀行債権者の融資金について,関連ノンバンクの不良資産を反映された場合には,融資の回収につながりかねないとの親銀行の判断があった。(甲68,乙8,乙106,弁論の全趣旨)
(ウ) 銀行の関連ノンバンクに対する支援の仕組み,税務上の取扱い
a 法人税基本通達9-4-2による支援の仕組み
法人税法37条1項は,内国法人が各事業年度において寄附金を支出した場合において,その寄附金の額は損金の額に算入しない旨規定しており,現金贈与,債権放棄,債務引受け等の損失負担は,原則として,法人税法上,課税対象として扱われることとなる。
しかし,親会社が子会社の整理のために行う債権の放棄,債務の引受けその他の損失負担については,一概にこれを単純な贈与と決めつけることができない面が多々認められるということであり,このようなものについては,その内容いかんにかかわらず,常に寄附金として処理すること等は全く実態に即さないといえること,また,一概に無利息又は低利貸付けといっても,そのことについて経済取引として十分合理的な説明がつくという場合には,子会社整理等の場合における損失負担等と同様に,常にこれを寄附金として取り扱うのは相当でないことから,法人税基本通達9-4-1及び9-4-2において,税務上も正常な取引条件に従って行われたものとして取り扱い,寄附金としての認定課税をしないことが明らかにされている(乙1
4の25頁)。
例えば,再建支援については,法人税基本通達9-4-2において,法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において,その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは,その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は,寄附金の額に該当しないものとすると定められている(なお,従来は,無利息貸付けのみが明示され,債権放棄,現金贈与等のいわゆる損益支援については明示されていなかったが,当然これも含まれるものであった。〔
乙14の34頁〕)。具体的に,このような子会社等の整理又は再建に関する損失負担が経済合理性を有するかどうか(すなわち無税扱いが認められるかどうか)については,①損失負担等を受ける者は,子会社等に該当するか,②子会社等が経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか),③損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由があるか),④損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか),⑤整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか),⑥損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっているなどの恣意性がないか),⑦損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負
担を重くし又は免れていないか)といった点が問題とされ,これらの点を総合的に考慮するものとされていた(乙14の25頁)。
ところで,バブル経済の崩壊以降,法人(支援者)が経営危機に陥った系列会社や取引先等の倒産等を防止するため又は整理するために,債権放棄等の損失負担等を行う事案が増加しているところ,損失負担等の額が寄附金に該当するかどうかが支援者の所得計算に多大な影響を及ぼすことから,国税庁において事前相談の制度が設けられた。すなわち,平成4年8月以降,中小企業の倒産が続出することを抑制・防止するため,銀行による取引先企業に対する金融支援を促す目的から,国税庁に「東京国税庁調査第一部調査課別室」が設置され,同別室において,金融支援の事前相談を受け付けて,適切な無税扱いを事実上承認する運用が行われていた(乙14の21頁,乙118の12頁)。
これを受けて,各銀行は,関連ノンバンクに対する金融支援を行う場合においては,事前に法人税基本通達9-4-2における要件を充足するものであるかどうかについて,上記①ないし⑦の要件を充足することを示す資料を開示して,事前に国税庁に相談を行い,国税庁は,場合によっては,その決裁を経て,銀行に対し,事実上の無税扱いの承認通知を行っていた(乙108の12頁)。例えば,原告は,平成6年6月すぎころ,当初10年の期間による日本リースに対する損益支援等を内容とする同社の再建計画を策定し,国税庁に対して,損益支援に関する無税扱いの承認を求めたが,国税庁は,10年の再建期間が長すぎると指摘し(甲154の12頁),その後,原告は,改めて,期間を5年とする日本リースの再建計画を策定し,国
税庁に提出する資料(甲154添付資料3)を作成してこれを提出し,同年11月ころ,国税庁から,事実上,無税扱いの承認を得た。
このように,銀行による金融支援が,形式上「寄附金」に該当する場合であっても,上記①ないし⑦の要件を充足する場合には,「寄附金」に当たらないとして損金算入することが認められ,これにより,金融支援が促されていた。(乙14,乙118,弁論の全趣旨)
b 金融支援先に対する不良債権の償却・引当に関する大蔵省における運用
このように,銀行による関連ノンバンクに対する支援が行われている場合には,不良債権償却証明制度等に基づき,親銀行(母体行)が再建のための支援を行っている支援先の貸出金について,延滞,破綻の事実が顕在化しておらず,償却・引当をすることはできないとする運用が,大蔵省において採用されていた。
まず,不良債権償却証明制度においては,法人税基本通達9-6-4の解釈・運用に当たっては,本来,債務超過の状態が相当期間継続しており,事業好転の見通しがないことという要件を充たす場合には,貸出金等の額の相当部分(おおむね50パーセント以上)の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について損金経理により債権償却特別勘定に繰り入れることができるとしてその額を証明していたが,他方,合理的な再建計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として,上記通達9-6-4の適用要件である事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないとされており,当然,金融証券検
査官は,銀行が支援をしている債務者の貸出金に関する償却・引当については,支援の有無や合理的再建計画の有無を前提に,その償却・引当の適否を判断していたものと思料され,このため,銀行が支援先に対して償却・引当を行うことについて,大蔵省金融検査部において,消極的な姿勢を示し,これを容易に認めない運用が採用されていた。
次に,大蔵省金融検査部は,一般的に,金融機関が支援を継続しながら,他方,貸出金に回収不能のリスクがあるとして償却・引当を行うことは,自己矛盾的であり,このような処理は採り得ないという見解を示していた。すなわち,前記(ア)の「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」によれば,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権については,この有税引当を行うことは,当面,企業会計上の合理性がないことや再建計画が策定されている債権については引当金が要らないことが大蔵省銀行局の担当者の見解として示されていた(甲158の21頁)。また,大蔵省金融検査部審査課長補佐等を務めていたYは,その著作(乙10)の中で,「債務者に対して追加融資を予定している場合
,無税償却適状にならないことは当然であるが,このとき有税償却すれば追加融資自体が背任的な行為となるおそれがある点に留意する必要がある。逆にいえば,追加融資先を有税とはいえ償却することは,基本的には決算経理基準から見て問題となろう。」(52頁)と述べていた(なお,甲158の59頁によれば,同人は,刑事公判廷においては,支援先に対する償却・引当をしないという考え方自体必ずしも論理的ではないと供述するが,そのような自らの考え方自体が当時の大蔵省内においては少数派であったとも供述している。)。さらに,証拠(乙46)によれば,平成4年から平成5年にかけて,再建中である貸出先に対する貸倒れを認定することについて大蔵省が消極的な姿勢を示していたことが認められる。
このように,当時の大蔵省は,金融支援先に対する償却・引当をできる限り認めないものとする運用を採っていたといえる。(甲122,甲158,乙9ないし乙11,乙14,乙46,乙108,乙110,弁論の全趣旨)
c 銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の実務
このような大蔵省の運用・見解を背景として,銀行においても,関連ノンバンク向け貸出金については,再建を前提としている以上,これについて償却・引当をすることはできないとの実務が一般化していた。
すなわち,証拠(証人L10頁,12頁,20頁,37頁,証人K27頁,33頁,証人X12頁,13頁,E本人6頁,7頁,甲136の31頁,32頁,乙28の10頁,乙118の15頁,16頁,乙120の13頁,14頁)及び弁論の全趣旨によれば,一般的な銀行界の考え方として,①銀行が関連ノンバンクに対して支援を継続している場合には,当該関連ノンバンクが再建されることを前提としており,再建計画期間中における関連ノンバンクの破綻は通常想定し得ないこととされ,このような考え方は,Q会計士が,刑事公判廷において,「銀行が積極支援する債務超過状態のような財務内容の悪い関連ノンバンクであっても,銀行が積極支援すれば,再建計画がなくても再建計画が作成され,それが実行される可能性が極めて高
くて,破綻に陥る可能性が極めて小さい」と供述しており,このような考え方自体は,会計監査人においても,許容されていたことが窺われること,他方,②このような再建を前提として支援している関連ノンバンク向け貸出金について,銀行(母体行)が償却・引当を実施することは,関連ノンバンクが破綻するおそれがあることを前提に,回収不能見込額(関連ノンバンクの清算価値に基づき回収不能が予測される額)について有税償却・引当を実施するもので自己矛盾であり,それ以上,無税による支援を行うことや新規貸付けを行うことができなくなると考えられていたこと,すなわち,将来追加の与信をするということがあり得る先に対してあらかじめ引当金を積みながら貸出しをすることになると,新たな貸出しをするたびにそれに見合う過去と同
じ割合の引当金を積みつつ,新たに貸出しをすることになるが,実際貸出しを判断していく場合には,そのような合意に矛盾を感ずるのは自然な考え方であったこと(証人L20頁),また,③支援損の計上(債権放棄,現金贈与等)による支援が,単年度ではなく複数の事業年度に及ぶ場合であっても,あらかじめ支援予定額全額について,費用として引当をすることも,将来の再建支援額は確定したものではなく,支援による資産処分や経営改善の内容いかんにより支援総額や支援期間が変化し,場合によっては過剰支援・引当のおそれがあるため,将来の支援予定額の一部又は全部を引き当てることがほとんど行われていなかったこと,この点について,例えば,Q会計士は,刑事公判廷において,「平成9年3月期以前は,支援として意思決定した金額
について支援損に計上する,すなわち分割償却の処理が認められておったわけでございます。そして,翌期以降,支援するものについて,商法第287条の2の引当金を設定するという会計慣行が確立しておらなかったわけでございます。」と供述しており,このような支援損に係る引当金の計上には会計監査人も慎重であったことが窺われる。
以上の事実によれば,バブル経済崩壊以降平成9年3月期以前は,銀行界一般において,回収不能のリスクを見込んで関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当を実施し,あるいは将来の支援予定額の引当を実施することについては,これを行わないとする運用が,会計処理の実務として定着していたと認められる。
(エ) 小括
以上の事実を前提として,平成9年3月期までの銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務について検討すると,次のようにいえる。
以上のとおり,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当について,①母体行主義を前提としてシステミックリスクの発生を回避するため,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の査定結果を母体行の貸出残高を限度として又はその全額について,母体行に反映させる一方,関連ノンバンクの資産査定の結果を母体行以外の銀行の貸出金には反映させず,これにより,母体行以外の銀行の貸出残高の維持を図っていたこと,②前記イ(オ)のとおり,銀行の貸出金のうち,Ⅳ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度により全額無税償却が可能であり,平成9年3月期以前における会計慣行として,このⅣ分類の貸出金について当期における全額の償却・引当が義務づけられていたと解され,本来,関連ノンバンク向け貸出金
についても,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の内容を査定し,その査定結果(Ⅳ分類ないしⅡ分類)に応じて,各銀行ごとの貸出残高の割合(シェア)に応じてその査定結果を反映させるのであれば,当然,当時の会計慣行を前提に,Ⅳ分類と査定された銀行の貸出金について,当期における全額の償却・引当義務が発生するところ,関連ノンバンクの資産査定の結果が母体行の貸出金に反映される仕組みが採られていたため,仮に,不良債権償却証明制度により,このⅣ分類を全額償却・引当するとの義務を課した場合,明らかに過剰な償却・引当義務を課すことになるので,7年事務連絡においては,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,これを考慮せずに行うとして,査定の結果と償却・引当の義務を切り離したものと評価でき
ること,③このような母体行の貸出金にそのまま反映された関連ノンバンクの分類資産(不良資産)については,母体行が,合理的な再建計画を作成し国税当局において無税扱いに関する承認を受け,償却原資の提供すなわち債権放棄等の損益支援や新規貸付け等の支援をして,関連ノンバンクの経営の健全化を図ることが予定されていたこと,④最終的には,関連ノンバンクを再建し,それにより破綻が回避される以上,再建期間中における母体行及び母体行以外の銀行の貸出金については貸倒れのリスクが発生しないと考えられていたこと,⑤以上のような取扱いの結果,関連ノンバンクに対する貸出金については実際には償却・引当を行わないという会計実務は,メインバンク制とも相まって,平成9年3月期以前には,バブル経済崩壊以降相当長期間に
わたって行われていたこと,以上の事実がそれぞれ認められる。
そうであるとすれば,平成9年3月期までの銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する償却・引当の実務においては,不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準のもとでの貸出金の償却・引当に関する会計処理方法である税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当はしないとする会計慣行が存在していたといえる。言い換えると,銀行の貸出金のうちⅣ分類とされたものについては,当期に即時償却・引当をするとの会計慣行の例外として,このような関連ノンバンク向け貸出金に対する特別の取扱いが相当長期間にわたって存在していたというべきである。
エ 平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する実際の
会計処理方法が「公正なる会計慣行」に当たるといえるか。
前記イ及びウで認定したとおり,平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する実際の会計処理方法としては,いわゆる税法基準が採用されており,一般の貸出金に関しては,大蔵省検査によりⅣ分類と査定された貸出金については,不良債権償却証明制度を介して,義務的に貸出金の償却・引当を行う一方で,有税による償却・引当については,銀行の自主的な判断に委ねられた結果,実際には有税償却・引当はほとんど行われないという会計慣行が存在しており,さらに銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,銀行の貸出金のうちⅣ分類とされたものについては当期に即時償却・引当をするとの会計慣行の例外として,再建支援を前提とする限りは償却・引当をしないとする会計慣行が存在したことが認められる。
そこで,以下では,これらの会計慣行が,商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」といえるかについて検討する。
(ア) 一般的な貸出金に関する税法基準に基づく会計処理について
前記認定の事実によれば,①会計士協会が委員会報告第5号において,税法基準によって貸倒引当金が計上されていれば特別な場合を除いて除外事項としないことができるとしていたこと,②昭和57年に発出された改正前決算経理基準については,銀行関係者もこれが商法32条2項でいう「公正なる会計慣行」に当たると認識しており,本件においてもその点については当事者間に争いがないところ,この改正前決算経理基準において,貸出引当金については,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとされ,さらに債権償却特別勘定については税法基準によることが言及されていること,③いわゆる税法基準は,不良債権償却証明制度と結びついて,改正前決算経理基準の「貸出金の償却」と「貸倒引当金」の計上に関する細則的基準と
なっていたところ,不良債権償却証明制度は,銀行経営の健全性及び適切性を確保するための監督・規制権限を有する大蔵省の通達によって定められた制度であり,銀行の不良債権処理に関する手続全体を監督・規制し,過剰又は過少な償却・引当がなされないようチェックして適正な償却・引当を実施させることを目的としたもので,当時の大蔵省のもとでの銀行に対する事前指導による保護的な金融行政を前提とする限りは,銀行決算の健全性及び適切性を確保するという点で合理性を有する制度であったこと,④税法基準は,大蔵省による不良債権償却証明制度を介して銀行に対して適切な監督・規制が行われることを前提としており,そうであるとすれば,当該銀行の資産内容を正確かつ適正に反映するものと評価できるものであり,その意味では,税
法基準に従った会計処理は,当時の大蔵省による監督・規制に基づく事前指導的な金融行政を前提とする限りは,商法の商業帳簿の作成目的からみても銀行の財産状態及び損益状況を正確に反映しうるもので合理的なものといえること,⑤旧商法285条の4第2項の文言だけでは,いかなる場合に「金銭債権に付取立不能の虞ある」といえるのか,また,取立不能見込額をどのように算定するかが明らかでなく,企業会計原則にも貸倒金の計上基準についての指針はないところ,税法基準は,貸倒金額の証明に当たり,基準として明確な法人税基本通達を援用するものであり,基準として明確なものであること,以上の事実が明らかである。
そうであるとすれば,不良債権償却証明制度によって補充された改正前決算経理基準のもとでの銀行の貸出金の償却・引当に関する会計処理方法である税法基準は,大蔵省による事前の指導と規制のもとでの保護的な金融行政がとられていた当時の銀行の会計処理方法として,十分な合理性を有するというべきであり,これが平成9年3月期以前における銀行の貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」に当たるというべきである。
なお,以上の税法基準のもとでは,金融機関は,有税による償却引当を積極的に行ってはいなかったものである。この点については,大蔵省において,平成6年2月8日付通達で有税償却の活用を促していることは事実であるが,一方で有税償却については無税償却の場合のような明確な基準がなかったといえる。この点は,平成6年11月の時点で当時の大蔵省銀行局長が,回収不能とはまだ判定されていないが,リスクが高まっている延滞債権等について有税引当が期待されるとしながら,一方で,元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施されている先に対する債権について有税引当を行うことは,当面企業会計上の合理性がないことになるとしていること(乙99)からも窺えるというべきである。結局,大蔵省においても有税
引当を行うか否かは,金融機関の自主的な判断にこれを委ねていたもので,税効果会計のような手当のないままで有税償却を行うことは金融機関の決算処理に負担が及ぶ可能性があったことからすると,税法基準のもとで,金融機関が積極的に有税引当を行っていなかったからといって,そのことを理由として税法基準が不合理なものと認めることはできないというべきである。
(イ) 銀行の関連ノンバンクに対する貸出金に関する会計処理について
次に,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関しては,不良債権償却証明制度,大蔵省検査及び日銀考査を前提として,母体行である銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続し,その再建を果たさせる以上,破綻リスクひいては貸倒リスクがなく,資産査定の結果,分類を受けなかった母体行以外の銀行において,その貸出金に対する償却・引当を不要として貸出残高の維持を行う一方,母体行において,償却・引当を不要とすることは,再建を絶対的な前提としたもので,破綻のリスクを考慮しないというものであり,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当について,いわば特別扱いを認めたものといわざるをえない。
しかしながら,このような銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する特別扱いを認める会計慣行は,①母体行は,関連ノンバンクに対し,法人税基本通達9-4-2による支援を通じて,最終的には,関連ノンバンクの営業貸付金に係るⅣ分類等の資産を処理して,これにより,母体行以外の各銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する回収不能のリスクを回避する一方,母体行以外の銀行は,関連ノンバンクの再建期間中において,母体行に対する信用を背景に,関連ノンバンク向け貸出を継続して資金繰り破綻を回避するものであるが,これは,要するに,システミックリスクの発生を回避するための手法であり,早期是正措置導入以前の大蔵省による事前の指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは,十分な合理性を有するも
のであったといえること,②このようなシステミックリスクの回避を目的として,大蔵省検査における関連ノンバンクの資産(営業貸付金)査定の結果を母体行の貸出残高を限度として全面的に反映させる一方,これに伴う過剰な償却・引当義務を解除するため,資産査定の結果と償却・引当を切り離したものであり,そのことについても合理性を認めることができること,③銀行の関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当を不要とする考え方は,基本的に,母体行による支援を前提とする以上,関連ノンバンクの破綻リスクが極めて小さいことに由来するものであるが,このような支援内容すなわち再建計画の合理性は,単に再建元である母体行のみならず,一般には,国税庁において無税扱いの事実上の承認を受ける際に,その合理性・実現可能性に
ついて審査が行われることが前提とされており,実際に,証拠(乙118の17頁)によれば,支援計画の実施状況及び債務者の財務状況について,銀行は毎年見直して国税庁に報告していたことや支援額や支援期間の圧縮を内容とする確認書を提出していたことが認められ,このような審査あるいは監視は継続的に行われていたことからすると,このような支援内容は,合理的かつ実現可能性の高い内容のものが承認されていたといえること,④7年事務連絡においても,再建計画の妥当性については金融証券検査官の判断に委ねられており,中立的な第三者であり,かつ,銀行経営の健全性及び適切性を維持するための監督・規制権限を有する立場の大蔵省において,このような再建計画が審査され,かつ,承認されていたものであること,以上の点を考慮
する限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金について,銀行による関連ノンバンクへの支援又は再建計画があることを前提にして,償却・引当を実施しないとする会計慣行は,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは,企業の財産状態及び損益の状況を明らかにする商業帳簿作成の目的からみても,合理的なものであったと評価することができるというべきである。
(ウ) 税法基準が「公正なる会計慣行」といえるかについての結論
以上のとおりであって,税法基準は,不良債権償却証明制度の運用において,銀行の経営の健全性及び適切性を維持するため,銀行を指導・監督・規制する権限を有していた大蔵省の担当者によって実際に行われていた指導・監督権限に基づき,銀行の資産内容の健全性と決算業務の適切性を図る見地から,無税償却・引当が可能な貸出金すなわちⅣ分類と査定された貸出金の償却・引当を義務づけていたものであり,当時において,「公正なる会計慣行」であったと評価できるというべきである。また,銀行が,関連ノンバンクに対する支援を継続して,関連ノンバンクの再建を図ることは,関連ノンバンクの破綻を防ぐだけでなく,ひいては金融システム全体の破綻を回避することに資するものであり,再建期間中における銀行の関連ノンバンク
向け貸出金に対する償却・引当をしないという会計慣行もまた,大蔵省の担当者による実際の監督・規制権限の行使を前提として,銀行会計の健全性を確保しようとするものであり,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする銀行に対する保護的な金融行政のもとでは,十分に合理性を有するもので,これが「公正なる会計慣行」であったと評価できるというべきである。
結局,平成9年3月における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準であったといえる。そして,その内容は,①銀行の貸出金については,原則として,大蔵省検査においてⅣ分類と査定された貸出金について,同額の無税による償却・引当の義務を負うこと,②銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当については,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とする(支援損の計上等を通じて,計画的段階的に処理する)というものであり,有税による償却・引当については,銀行の自主的判断に委ねられた結果,実際にはほとんど行われていなかったが,当時の保護的な金融行政のもとでは,大蔵省の事前指導・監督・規制によ
り銀行経営の健全性及び適切性を維持することにより,その内容の合理性が担保されていたと評価できるものである。
(2) 原告らの主張の検討
原告らは,①税法基準は,租税収入の確保という政策的観点に立って,税額の計算をし,課税の公平を図る目的で策定されており,そのような観点から,当該事業年度において,損失が生じたことが確実と認められるものについて損失計上が認められるものであり,他方,商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営成績を正しく表示し,もって株主及び会社債権者の利益を図る目的で策定され,両者の目的は全く相違しており,税法基準による会計処理が,商法32条2項の「公正なる会計慣行」となると解し得ないこと,②委員会報告第5号は,公表された当時,各企業の有する不良債権額が些少であり,「一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向
にある」ことを前提として,保守主義の観点からこれを容認したにすぎないものであり,これは,税法基準そのものを「公正なる会計慣行」と位置付けたものではなく,むしろ,委員会報告第5号によれば,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)となるとしており,税法基準は,企業の資産状態を正しく反映するものではないことを前提としていること,③平成4年8月18日付け「金融行政の当面の運営方針―金融システムの安定性確保と効率化の推進」は,不良資産処理の方針の早期確定とその計画的・段階的処理が急務であると指摘し,また,平成6年2月8日付け「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」は,「金融機
関自らの判断によりリスクに応じた必要な引当が行われるようにする。」ことを提言し,有税引当の概念を示し,これを受けて同日付け「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,有税引当及び有税直接償却を行うときの取扱いが明らかにされたことから,改正後決算経理基準の発出以前の段階において,行政当局は積極的に金融機関に不良債権の有税償却を求めていたこと,④改正前決算経理基準は,「貸出金の償却」について「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額」を償却すべきとしており,当然,有税償却を含む趣旨と解されること,また,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする。
なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と定め,有税引当を予定していること,すなわち,旧商法285条の4,企業会計原則に従い,回収不能見込額の償却・引当が義務づけられており,改正前決算経理基準における「貸出金の償却」の意義は,改正後決算経理基準における「貸出金の償却」の意義と同一であること,⑤法人税基本通達9-4-2は,債権放棄の対象である当該債権が実質的無価値ではない場合,本来寄附金認定される債権放棄について,経済合理性の見地から,損金算入を認める(寄附金と認定しない)ものであり,当該債務者に対する貸出金を回収不能と評価するか否かの判定基準とはなり得ないものであること,支援損の概念は,合理的な再建計画に基づき貸出先の事業が継続され,
その結果収益弁済が可能になる場合すなわち当該貸出金につき回収不能又は回収不能の見込みがない状況を前提とした概念であること,他方,貸出先の収益弁済が可能となる合理的な再建計画がない場合,合理的再建計画を前提とする回収不能又は回収不能の見込みがない状況にあるとの前提が成立せず,当該貸出金について回収不能のおそれがあり,関連ノンバンク向け貸出金については債権放棄による支援損の概念しかあり得ないとの被告らの主張は全く成立しないこと,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当が存在することを根拠として掲げて,以上の点等を考慮し,税法基準が,平成10年3月期より前の段階においても,商法32条2項の「公正なる会計慣行」となり得ないと主張している。そこでこれらの点について検討すると,以
下のようにいうことができる。
ア ①について
この点については,原告らが主張するとおり,法人税法22条4項は,法人税法における法人の各事業年度における「所得の金額」の算定の基礎となる「益金」と「損金」の額を計算するに当たり,「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」旨規定し,商法32条2項の「公正なる会計慣行」による旨を明らかにした趣旨と解され,原則として,いわゆる確定決算主義に従い,税法基準は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」により決定されるとするのが法人税法の基本的態度であると解される。
しかしながら,実際の実務の運用において,このような税法基準が,商法32条2項の「公正なる会計慣行」により全て決定されるとすることには無理があり,現実の問題としては,相互に影響することがあること自体は否定できない。すなわち,銀行の貸出金に対する償却・引当処理に関しては,有税であるか無税であるかを問わず,実際には大蔵省金融検査部による監督・規制下に置かれており,そのような状況を考慮した場合,税法基準が,銀行の貸出金に関する商法上の償却・引当の基準(商法32条2項の「公正なる会計慣行」)として現実に機能しているのは事実であって,税法基準に基づく会計処理方法が,大蔵省による保護的な金融行政のもとでは,商法上も十分な合理性を有していたことを否定することはできないといえる。
言い換えると,当時の保護的な金融行政のもとでは,銀行の償却・引当の実務・運用が,全て大蔵省検金融査部に事実上監督・規制されていたことからすると,銀行は,大蔵省金融検査部の検査を無視して,貸出金を査定し償却・引当を行うことは実際には考えられず,そのような不良債権償却証明制度を前提とする税法基準が,銀行の貸出金に関する償却・引当の実務すなわち会計慣行を形成していたことは明らかである(会計慣行となっていたこと自体は原告らも認めるところである。)。無論,税法基準が,当然に企業会計の基準となるものではないが,このような銀行における長期間にわたる実務処理の集積として,税法基準が銀行の会計実務として定着し,しかも大蔵省による指導・規制下におかれた金融行政のもとでは,銀行の貸出金の償
却・引当に関する現実的な会計処理方法として,商法上も十分な合理性を有していたというべきである。
また,税法と商法が本来目的を異にする点は,原告ら主張のとおりであるが,銀行の経営の健全性及び適切性の観点から,適正な決算処理を監督する趣旨で,大蔵省検査に依拠し,不良債権償却証明制度を介して償却・引当を行うとする不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準自体もまた,適正な決算処理を確保する趣旨においては,正確な銀行の財務状態及び損益状態の反映という商法の目的にも反していなかったと考えられる。
なお,有税による償却・引当は,償却・引当のコストに加えて同額の納税コストが発生し,銀行の決算を悪化させ,かえって,銀行経営の健全性を揺るがす事態を生せしめると考えられており,このような観点からも,税法基準による不良債権の償却・引当は,銀行の会計実務として定着しており,その内容は合理性を有していた,すなわち「公正なる」ものであったというべきである。
以上のとおりであって, この点に関する原告らの主張は,平成9年3月期以前において銀行の貸出金の償却・引当についての基準に関し税法基準に基づく会計処理方法(銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,再建期間中は償却・引当をしない等)が「公正なる会計慣行」として定着していたとの前記認定判断を覆すに足るものではない。
イ ②について
この点については,確かに,原告らが主張するように,委員会報告第5号は,税法基準による貸倒引当金が企業の実態に応じて経常すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)となると規定しているが,他方,前記(1)ア(イ)のとおり,委員会報告第5号は,我が国の会計慣行とりわけ税法基準を多くの企業が採用しているという実情を踏まえたうえで,一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向があるが,税の確定決算主義の立場等を考慮して,税法基準によって算出した貸倒見積高を計上している場合でも一定の条件のもとに一般に認められた企業会計の基準に準拠しているものとして取り扱うこと
ができる旨定めており,税法基準を採用している場合にはこれを継続して適用すべきことを要請していることからすると,その趣旨は,多数の金融関係者が反復継続して税法基準を採用していたことを考慮し,また,会計の一般原則である継続性の原則も踏まえたものと解することができるのであって,そうすると,この委員会報告第5号も,税法基準が「公正なる会計慣行」に該当することの根拠となり得るというべきあり,この点に関する原告らの主張は,前記認定判断を覆すに足るものではない。
ウ ③について
この点については,確かに,原告らの主張のとおり,これらの通達,指針等は,不良債権の処理の促進を要請し,有税による償却・引当を促す趣旨のものであること,特にⅡ分類と査定される貸出金についても有税引当を実施するよう促した趣旨であると解される(甲158の25頁)。
しかしながら,このような有税による償却・引当が勧奨された後も,実際には,銀行において有税引当等が行われたことはほとんどなく(甲158の30頁),これらの通達,指針等が銀行の会計処理の実務に実際に影響を与えたとは認められない。すなわち,前記のとおり,有税による償却・引当が,制度上,届出制に改められたものの,実際には無税による償却・引当と同様の説明が必要とされ,しかも要件自体が明確でなく,決算処理に負担を及ぼす可能性があるものでありながら,銀行の自主的な判断に委ねられていた結果,実際には,有税引当が行われることはほとんどなかったというのであるから,結局,有税引当は実務的に定着するには至らなかったものである。
また,前記のとおり,平成6年2月8日付け「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」についても,確かに,有税引当制度の運用を改善し,貸倒れには至らないが,回収に危険のある債権について将来の回収リスクに応じた必要な引当が促され,同日付け「不良債権償却証明制度実施要領について」と題する通達が発出されたところ,他方,上記指針は,金融機関の支援先に対する金利減免債権等については,元本が回収されるという前提で再建計画が実施されており,破綻先債権,延滞債権と同列に扱うことはできず,このような支援先に対する債権については有税引当の実施が,企業会計上の合理性がないとも指摘しており,結局,銀行の関連ノンバンク向け貸出金については,関連ノンバンクへの支援を前提とした再建可能性を考慮し
,また,再建計画が,国税庁による事実上の承認や大蔵省検査における金融証券検査官の判断を前提として,回収不能のリスクがないと考えられており,この点に関する運用は従前から変化がみられず,かえって,区別して取り扱われていることからみて,行政当局に見解の変更はなかったといえる。そうであるとすれば,この点に関する原告らの主張も前記認定判断を覆すに足るものではない。
エ ④について
この点についても,原告らが主張するように,改正前決算経理基準自体が,有税による償却・引当を認めていたこと,また,回収不能の判断については,改正前決算経理基準と改正後決算経理基準において,ほぼ同義に解し得ることは認められる。しかし,改正前決算経理基準において,回収不能見込額の算定が困難な場合,法人税基本通達9-6-5に従い,債権額の50パーセントを債権償却特別勘定に繰り入れて,その余の50パーセントを有税により繰入れを行うことができるとされていたが(乙118の8頁,9頁),このような要件を満たさない場合には,不良債権償却証明制度により,有税による償却・引当が大蔵省の監督・監視の下で厳格に運用されており,改正前決算経理基準の下では有税による償却・引当は義務化されていなかっ
たこと,他方,改正後決算経理基準の下では,有税による償却・引当が促されていたことを考慮すると,原告らの主張は,前記認定判断を覆すに足るものではない。
オ ⑤について
まず,原告らは,法人税基本通達9-4-2は,償却・引当の前提となるべき回収不能の判断基準となり得ないと主張する。確かに,法人税基本通達9-4-2は,それ自体,回収不能の判断基準として機能するものではないが,銀行が,国税庁の無税扱いの承認を受けて,関連ノンバンクに対する支援を継続している場合,最終的には,関連ノンバンクを再建して破綻を回避し得るものであり,それ自体,中立的な第三者であり,かつ,銀行経営の健全性及び適切性を監督・監視する大蔵省の認定を経たものであることからすると,銀行が法人税基本通達9-4-2による支援を継続している間においては,関連ノンバンクが破綻する事態には至らないものと評価する合理的な基準となるといえる。結局,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償
却・引当は不要ということになり,銀行としては,支援損を計上し,支援を継続する一方,償却・引当を不要とするものであり,その範囲で,償却・引当が不要な場合を示す合理的な基準として機能するものであると評価できる。そうであるとすれば,この点に関する原告らの主張も,前記認定判断を覆すに足るものとはいえない。
次に,原告らは,合理的な再建計画の存在により,関連ノンバンクが再建され,収益弁済が可能となることから,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当を実施しないことが妥当とされるのであれば,合理的な再建計画がない場合には,回収不能の見込みがない状況にあるとの前提が成り立ち得ないと主張する。
この点については,銀行の関連ノンバンクに対する支援については,証拠(乙9,乙110)及び弁論の全趣旨によれば,不良債権償却証明制度において,法人税基本通達9-6-4において,債権償却特別勘定への無税繰入れに係る金額を証明する場合には,債務超過の状態が相当期間継続しているかどうか,事業好転の見通しがないかどうかを審査し,貸金等の額の相当部分(おおむね50パーセント)以上の金額につき回収の見込みがないと認められる部分の金額について判断すべきとされるが,事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の
見通しがないと判断することが適当ではないと定められていたこと,また,7年事務連絡では,母体行による関連ノンバンクに対する支援の意思を前提として,合理的な再建計画が策定されている場合と策定されていない場合において,いずれも資産査定の方法は,原則として,関連ノンバンクの営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ分類の順に充当することとされ,また,関連ノンバンクに対するⅣ分類と償却の関係については,当面,考慮せず査定作業を行うこととすることが明示されており,金融証券検査官が,大蔵省検査において,母体行の意思を確認し,母体行責任を負うことが確認された場合,銀行経営の健全性及び適切性を検査する金融証券検査官の判断のもと,いずれ母体行が適切な再建計画を策定し,それに
沿って,関連ノンバンクの再建が果たされることが期待されていたことが認められ,これらの事実に照らすと,単に再建計画がないことのみをもって,回収不能の見込みがないとの前提が成り立たないということにはならないというべきである。
5 争点④(資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準が,銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の基準としての「公正なる会計慣行」に当たるとするための要件を満たしているといえるか。)について
4で認定したとおり,平成9年3月期以前の銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準(以下,「旧基準」ともいう。)であり,関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当については,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,償却・引当を不要とするものであったといえるところ,そのことを前提として,原告らの主張する資産査定通達等で補充された改正後決算経理基準(以下「新基準」ともいう。)が平成10年3月期において銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえるかについて検討することとする。
そして,そのための要件は,既に前記2(4)で指摘したとおりであるから,以下,まず,新基準の合理性及び改正手続の適正性(前記要件①及び③)について検討し,次に,新基準と旧基準の変更の程度・内容について検討した上で,変更にともなって必要な手当がなされているか(前記要件②)を検討し,その後に,新基準の一義的明確性(前記要件④)と新基準の関係者への周知徹底がなされていたか(前記要件⑤)について順次検討することとする。
(1) 新基準の合理性及び改正手続の適正性について
新基準が採用されるに至った経緯としては,前記3で詳細に認定したとおりである。すなわち,銀行に対するリスク管理,内部監督が社会的問題となり,大蔵省検査等についての批判がなされ,従来の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする銀行に対する保護的な行政から,自己責任原則に基づく事後監督行政への転換を求められるに至ったこと,そのため,金融制度調査会の金融システム安定化委員会,金融検査・監督に関する委員会,会計士協会により設置された銀行等監査特別委員会等での検討を経て,金融3法が成立し,早期是正措置の導入が定められたこと,その後,早期是正措置検討会での検討を経て,平成8年12月26日付けで「中間とりまとめ」が作成公表され,そこで銀行の貸出金の償却・引当に関する実務上の基準を定め
ることが必要であることが指摘されたこと,これを受けて,資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡,全銀協追加Q&Aが相次いで発出ないし送付され,これらを踏まえて改正前決算経理基準の改正に至ったこと,この資産査定通達等で補充された改正後決算経理基準により,早期是正措置導入後の銀行の貸出金の償却・引当に関する新基準が示されたこと,以上の事実が認められる。そして,以上のような改正の経緯に照らす限り,通達の改正手続自体は,必要な手順を踏んでおり,適正なものと認めることができるし,新基準の内容は(その詳細は既に認定したとおり),これを早期是正措置の導入という目的のもとでの銀行が自ら資産査定を行う際の貸出金の償却・引当の基準としてみると,後述するとおり,定量的な基準が示されて
いないなど内容の一義的明確性の点では問題が残るものの,新基準を唯一の「公正なる会計慣行」とするかどうかの問題と離れてみるかぎりは,会計処理の基準としては,一応の合理性を備えているものと認めることができる。
(2) 新基準による旧基準の変更の内容と程度について
前記3で認定した本件の事実関係を前提として,新基準と旧基準を対比すると以下のようにいえる。
ア 決算経理基準の改正,不良債権償却証明制度の廃止による変更
決算経理基準の改正により,旧基準においては,貸出金の償却・引当に関しては,税法基準によることが明示され,税法基準の限度額まで貸倒償却及び貸倒引当金の計上を実施することを義務づけるものであったものが,新基準のもとでは,旧基準が採用していた税法基準が採用されず,貸出先(債務者)の実態に応じて有税による償却・引当を実施すべきとするものであり,新たな基準に基づき貸倒損失及び貸倒引当金の計上を求めるものとされたといえる。
また,旧基準を補充していた不良債権償却証明制度は廃止され,その結果,新基準のもとでは,銀行はあらかじめ無税償却・引当の認定を受けられないことになり,一般事業会社と同様に自己責任により,無税による償却・引当を実施し,その後に行われる税務調査において,償却・引当に関する自己判断が否認される場合には,追徴課税をされることとなった。
イ 関連ノンバンクに対する貸出金の処理
旧基準のもとでは,銀行が関連ノンバンクに対する支援を継続する限り,関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当は不要とされていたが,9年事務連絡によれば,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金の査定に当たっても,原則的には,銀行の貸出金のシェアに応じて関連ノンバンクの資産分類の結果を反映させるとともに,親銀行がこのようなプロラタ負担を超えて,関連ノンバンクの清算等に伴う損失を負担することにしている場合,又は関連ノンバンクについて合理的な再建計画が策定され,短期間(概ね2,3年程度)で再建が可能な場合以外は,親銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する査定に当たっては,原則をプロラタ負担とし,償却・引当を実施するよう指摘されていた。
ウ 旧基準から新基準に変更された当初の金融検査の結果
早期是正措置は,適正な財務諸表に基づく適正な自己資本比率の算出が前提とされるものであり,しかも,それは,各金融機関の自己責任において策定された自己査定基準を根拠として,貸出金の査定を行い,その査定結果に従い,必要な償却・引当を実施するというものであり,このような償却・引当の適切性も金融検査においては対象とされていた。
そして,このような金融検査の方針の下,平成10年3月期金融検査においては,新基準のもと各金融機関の貸出金等に係る償却・引当の額等についても厳格な検査が実施され,その結果,前記3(10)イのとおり,各金融機関の償却・引当不足額について指摘がされ,主要17行において,Ⅰ分類が5兆4061億円減少し,他方,Ⅱ分類3兆5842億円,Ⅲ分類1兆5708億円及びⅣ分類2511億円がそれぞれ当局査定結果により増加し,主要17行については1兆0413億円の償却・引当不足が指摘され,原告及び日債銀において,Ⅰ分類が1兆8683億円減少し,Ⅱ分類2298億円,Ⅲ分類1兆3775億円及びⅣ分類2610億円がそれぞれ当局査定結果により増加し,原告及び日債銀については8323億円償却・引当不足
が指摘された。
エ 新基準は税法基準を否定していないとする被告らの主張について
なお,この点に関し,被告らは,新基準は税法基準を否定するものではないと主張するが,そもそも,新基準導入の端緒となった早期是正措置の導入自体が銀行の自己責任による貸出金の償却・引当を念頭に置くものであり,従来の大蔵省の事前指導・監督・規制に基づく金融行政のもとで,不良債権償却証明制度を介して実施されていた税法基準とは相容れないものであるし,確かに,後述のとおり,新基準については,一義的明確性の点で疑問は残るものの,前記ア及びイで認定したとおり,実際の改正前決算経理基準と改正後決算経理基準の内容との対比,さらには関連する資産査定通達等の内容に照らしても,基本的な考え方において旧基準と新基準は異なるものであったことは認めざるを得ない。
オ 小活
以上,ア及びイで述べたとおり,新基準は,銀行の貸出金の償却・引当についての基準に関する従来からの会計慣行であった税法基準を離れ,新たな基準のもとで,有税による償却・引当をすべきとするもので,銀行の関連ノンバンクに対する貸出金についても,できる限り関連ノンバンクの資産の実態に即して償却・引当を実施すべきとするものであり,いずれの点についても,有税による償却・引当は原則的には行わず,また関連ノンバンクについては,銀行が支援を継続する限り償却・引当は不要とする旧基準のもとでの「公正なる会計慣行」に比べて大幅な内容の変更を伴うものと認めざるを得ない。なお,このような大幅な変更は,旧基準が大蔵省の銀行に対する事前の指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでの基準であっ
たのに対し,新基準の導入自体が,そのような保護的な金融行政を見直し,銀行の自己責任による資産査定を義務づけようとしたもので,いわば180度の金融行政の転換を図るものであった以上当然のことというべきである(その意味では,被告らは早期是正措置の導入は,金融行政当局による監督手法の変更であると主張するが,監督手法の変更に伴い,必然的に銀行の会計処理方法の変更も促すものであったというべきである。もっとも,その変更が法令によらず,通達等によって行われた本件のような場合において,変更内容がただちに唯一の「公正なる会計慣行」となるためには,前記のような要件が必要であることは既に述べたとおりである。)。
そして,前記ウで認定したとおり,旧基準から新基準への過渡期ともいうべき平成10年3月期決算について,新基準のもとで行われた金融検査の結果,全ての銀行において償却・引当不足が指摘されているという事実に照らしても,旧基準と新基準に大幅な変更があったことが推認できるというべきである。
(3) 新基準の実施に伴う必要な手当の要否と有無について
ア 新基準による旧基準の変更
以上(2)で認定したとおり,旧基準と新基準の内容については,大幅な変更があったというべきである。そうであるとすれば,旧基準のもとでの銀行の貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」(その内容は,税法基準によって補充された改正前決算経理基準である。)に代えて,新基準を,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返して行うことなく,直ちに唯一の「公正なる会計慣行」であると認めるためには,前記2(4)のとおり,変更に伴って企業会計の継続性の観点から支障が生じ,ひいては,その内容が法規範として強制力を持つ結果,関係者への不意打ちになるといった事態を避けるためにも,これに対する必要な手当(以下「セーフティネット」ともいう。)がなされていることが要件とされるというべきである。そこで,そ
のような手当が必要か否か,必要とした場合に本件においてそのような手当がなされていたといえるかについて検討する。
イ 有税による償却・引当を行うことに伴う問題点と対応策
前記認定のとおり,新基準のもとでは,旧基準のもとではほとんど行われていなかった貸出先(債務者)の実態に応じた有税による償却・引当を行うこととされているが,前記認定事実3(12)イと証拠(証人L,証人X,甲115の153頁,甲122の46頁,甲125の90頁から92頁まで,乙11,乙60,乙62)によれば,銀行が,貸出金の有税償却・引当を実施する場合,決算処理に与える影響が大きく,①税額分の資金運用益を確実に喪失する結果となり,例えば,1000億円を有税償却した場合,税率が50パーセントであるとすると,500億円の資金の運用益が喪失されること,②当時の税法においては,繰戻期間が1年と短期間であり,これを経過した場合,有税による償却・引当の額について税金の還付が受けられない結果
となって,無税化の利益が完全に失われること,③有税による償却・引当を実施した場合には,当該事業年度において,償却・引当額と同額の当期利益が減少するだけではなく,同額の税金支払が必要であり(甲125の90頁から92頁),その結果,償却・引当額の倍額のコストを必要とし,必然的に,同期において,自己資本額の減少すなわち自己資本比率の低下に直結し,特に早期是正措置の下では,銀行に対して致命的な結果をもたらしかねないこと,④さらには,銀行の決算を悪化させ,銀行の取締役に対する善管注意義務違反のほか,銀行経営の健全性を危殆に陥れるおそれがあったことが認められる。 そして,証拠(証人X32頁)によれば,銀行の決算業務においては,納税充当金まで含めて決算業務である以上,有税か無税かという
判断を抜きにして決算業務ができるものではなく,有税による償却・引当が銀行決算に与える影響は大きく,銀行は,銀行経営の健全性を確保するため,有税による償却・引当について消極的であり,また,銀行経営の健全性及び適切性を監督する立場にある大蔵省においても,不良債権償却証明制度の運用の下に無税による償却・引当を義務付けたうえで,このような銀行の実務を承認していたものと認められる。
ウ 税効果会計の導入の遅れ
このような有税による償却・引当に伴う,いわゆる税務会計と企業会計の乖離の問題については,従前から指摘がされ,これを解消する方法として,税効果会計の導入が考えられていた。
すなわち,証拠(乙35,乙36)によれば,企業会計審議会は,平成9年6月に,「金融商品の会計処理基準に当たっての論点整理」を公表し,その中で,金融商品の時価評価等の導入に当たって商法との調整が必要であると提言し,これを受けて,大蔵省及び法務省は,商法学者,会計学者及び実務家の参加を求めて,「商法と企業会計の調整に関する研究会」を立ち上げ,同年7月以降,同研究会において,その問題点が検討され,その後,同研究会は,平成10年6月16日付けで報告書が公表されている。
同報告書によれば,企業の利益は商法(企業会計)の手続を経て算出されるが,税務上の課税所得計算においては企業会計と異なる課税所得計算が行われるものであることから,課税所得と企業会計上の利益とに差違が生じ,減価償却費(耐用年数や償却方法の違い),引当金の繰入れ(損金算入額の制限),貸倒損失(事実認定時点の違い)等の損益の帰属期間の認識に差違があるため,将来の期間利益に対応すべき税額で当期に支払うべきものと当期の利益に対応すべき税額で将来支払うべきものが発生し,これらの税額を調整しないと,法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応せず,税引前当期純利益と税引後当期純利益の関係を歪め,適正な期間比較や企業間比較が困難となることが問題点として指摘されていた。また,これらの税額
の調整が図られないため,有税による貸倒償却や引当金の繰入れが阻害されるインセンティブとなっているとの指摘もされていた。
そこで,このような問題点の解消を図るため,一時差異に係る法人税額の期間帰属を企業会計に合わせることにより,企業会計上の利益が適正に表示されるよう調整する税効果会計の採用が必要であることが指摘されていた。
また,上記報告書の中では,企業会計において,繰延税金資産は前払税金に相当する税金を将来減少させる効果があり,繰延税金負債は未払税金に相当する税金を将来増加させる効果があると認められることから,一般的に資産性・負債性があると考えられていること,今後,商法の計算書類も含め個別財務諸表において税効果会計を採用することとなる場合には,企業会計上の基準を明確化することが必要であること,企業会計上の税効果会計に関する会計基準において,繰延税金資産及び繰延税金負債が法人税等の前払税金又は未払税金として資産性・負債性が明確にされるならば,商法上も公正な会計慣行を斟酌する立場から,企業会計上の基準と同様に,これらを貸借対照表に計上し得ることが指摘されていた。
さらに,①前記認定事実3(3)ア(イ)のとおり,早期是正措置検討会において,既に税効果会計の導入の必要性は指摘されており,また,同(ウ)によれば,「中間とりまとめ」の中においても,今後有税による償却・引当を円滑に進めていくための環境整備として税効果会計について検討を行うことが要請されていたこと,②早期是正措置検討会に委員として出席したL(当時は全銀協の一般委員長)は,当時,早期是正措置の導入により税法基準が採用されなくなった場合には,貸倒実績率に応じて償却・引当をするという考え方が全面に出てきて,銀行は有税か無税かを意識しないで対応せざるを得なくなり,決算処理上の負担が大きくなるので税効果会計の導入と平仄を合わせて早期是正措置を導入すべきと考えていたこと(証人L3頁),③早期是
正措置検討会の座長を勤めたKは,当時,早期是正措置の導入のさじ加減を誤ると,早期是正措置が一種のギロチン台のようなことになって,金融機関の経営危機,あるいは破綻を誘発しかねないので,当時の不安定な金融情勢に配慮しながら,ソフトランディングさせるという考え方が基本であったと述べていること(証人K12頁),④平成10年8月ころ,全銀協は,不良債権処理を促進する環境整備のため,無税償却基準の緩和を要望していたこと(乙60),⑤前記認定事実3(12)イのとおり,平成11年3月期決算における税効果会計の前倒適用が認められたこと,⑥税効果会計が銀行の平成11年3月期決算において導入されたことに伴い,主要17行(都銀9行,長期信用銀行1行,信託銀行7行)は,約6兆6500億円の繰延税金資産を計
上し,約10兆4000億円もの不良債権を処理したにもかかわらず,平成10年3月期において2兆2400億円であった剰余金の額は,平成11年3月期において,2兆6800億円にかえって増加し,有税による不良債権の処理すなわち償却・引当の自由度が高まったと評価されたこと,⑦このような税効果会計の導入が遅れた結果,無税償却・引当の慣行が併存し,他方,有税による償却・引当が義務化される方向が示された結果,各銀行を当惑させる状態にあったとの指摘もあること(証人K31頁,32頁),以上の事実が認められる。
エ 小括
以上の事実によれば,新基準で銀行の貸出金について,有税による償却・引当を義務づける方向が示された以上,旧基準に代えて新基準を唯一の基準としてその遵守を義務づけるためには,それに伴う決算処理に関する問題点を除去するためのセーフティネットとして,税効果会計の導入が同時に図られるべきであったといえる。それにもかかわらず,そのような手当が講じられなかったというべきであって,平成10年3月期においては,有税による償却・引当を義務づけるうえで,必要な手当てが不十分であったことは否定できないというべきである。
(4) 新基準の一義的明確性について
次に,新基準が,その内容において一義的に明確であったといえるか(前記2(4)の要件④参照)について検討する。
前記認定のとおり,新基準は,銀行の貸出金の償却・引当の基準に関し,貸出先(債務者)の実態に応じて,有税による償却・引当を義務付けるとともに銀行の関連ノンバンクに対する貸出金についても,できる限り関連ノンバンクの実態に応じて償却・引当をすべきとするもので,従来の税法基準によって補充された旧基準の大幅な変更を促すものであったといえるが,一方で,以下に述べるとおり,その一義的明確性の点では,いくつかの疑問点が指摘できる。
ア 改正後決算経理基準
改正後決算経理基準は,前記のとおり,回収不能が見込まれる貸出金について債権額から担保処分及び保証による回収可能額を減算した残額(以下「回収不能額」という。)を償却・引当すること,回収に重大な懸念があり損失発生が見込まれる貸出金については債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算した残額のうち必要額について引当を実施すること,これらの貸出金以外の貸出金について,合理的な方法により算出された貸倒実績比率に基づき算定した貸倒見込額の引当を実施することが定められていたが,具体的かつ定量的な基準ではなく,資産査定通達等により補充されるものであった。
イ 資産査定通達
前記認定事実3(3)ア(イ)(ウ)(エ)と証拠(証人K,甲138)によれば,早期是正措置検討会においては,自己資本比率とこれに行政措置とを連動させる仕組み自体が,日本では全く未経験であり,当局が示す資産査定は金融機関の自己責任原則や主体性を阻害しないようにするため,大きな枠をガイドライン的に示すにとどめたこと,基準自体が定性的な内容であり,自己査定と検査との間に乖離が生じた場合,ともかくすりあわせながら一定期間試行的に行って定着させることを目的として早期是正措置を導入することとしたこと,償却・引当に関しては,米国では引当水準の目安が存在するが,これは目安に止まり,これ自体を行政措置の発動の根拠とすることは不適切であること,また,個別性の強い
個々の債権の回収可能性の違いを無視して,機械的に一律の引当率を基準として示すことは適当ではなく,各金融機関が,自主的にこれを定めるとともに,また,償却・引当の正確性,客観性等を確保する観点から,償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備を行うべきことが基本事項とされており,定量的な部分が,金融機関のある程度自主性に委ねられていたこと,また各金融機関として平成10年の開始時点にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいが,その時点で不完全であっても,即「落第」という機械的な裁定はできないと考えられていたことが認められる。
また,前記認定事実3(8)アによれば,平成10年3月期決算における早期是正措置制度や自己査定制度の導入を踏まえて,大蔵省金融検査部は,各金融機関の自己査定体制の整備状況を検査し,平成9年度を自己査定の習熟度をみるためのトライアルの期間として,できる限り,大蔵省検査において,自己査定の整備状況をチェックし,問題点を指摘し訂正させることを検討していたことが認められ,大蔵省検査の中で,自己査定と資産査定通達の齟齬を解消していこうという姿勢を有していたことが窺われる。これは,当時大蔵省大臣官房審議官(銀行局担当)であったRが,その陳述書(乙109)において,資産査定通達や9年事務連絡は検査部内部の運用指針(ガイドライン)であり,検査官に対して一定の拘束力を持つのは当然としても,そ
れはあくまでも銀行法に基づく行政法上のものであること,それが金融機関において受け入れられ,結果として,優良な会計慣行(ベストプラクティス)として成熟化することが期待されていたこと,平成9年度(平成10年3月期)について,行政当局は,早期是正措置制度導入の準備期間であるとの意識を持ち,企業会計の実務面では金融機関の間でかなりの相違を生ずることを予測し,今後の金融検査や会計監査の中で是正と収れんを図るべきと認識していたこと,行政当局は,平成9年度に各行がガイドラインを参考にして自主裁量で作った自己査定基準について,大蔵省金融検査部が検査を実施し,不適切なものがあれば検査の際にその旨の指摘をして,将来に向けて是正して,ある程度の統一性を確保し,このような新しい手法に市場参加者全員が
慣れ,それが慣行となって徐々に統一性が出てきた段階で法規範性を持つに至ると認識していたことを述べ,また,当裁判所においても,証人として,資産査定通達が検査して議論する過程において共通の理解が相互に生まれれば,それがいわゆる商法でいう「公正なる会計慣行」となっていく可能性がある旨,資産査定通達等が実施され,ある程度議論されている過程の中で,市場で練られて成熟化していくと考えていた旨,検査を何回か重ねて議論をしていくうちに,段々と自己査定基準に関するばらつきが統一的な考え方に集約されていくというイメージであった旨供述していること(以上につき証人R6頁)からも裏付けられる。
これらの点を考慮すると,金融証券検査官は,金融機関が行う自己査定について,その基準が明確かどうか,その枠組みが「資産査定について」の枠組みに沿っているかどうか等を把握し,金融機関の自己査定基準の枠組みが独自のものである場合,「資産査定について」の枠組みとの関係を明瞭に把握し,金融機関の自己査定基準の中の個別ルールが合理的に説明できるものであるかどうか等をチェックすることが要請されており,その趣旨は,金融証券検査官が,金融検査の一環として,金融機関の自己査定の基準を検査し,「資産査定について」の枠組みに合致するかどうか,合致しない場合には,金融検査において,これを金融機関に指摘し,その是正を求めるものであり,基準の大枠すなわち定性的な基準を定めたうえで,次第に収れんを図
る趣旨とも考えることができる。
さらに,前記認定事実3(4)イのとおり,全銀協Q&Aによれば,現時点での情勢を前提とした資産査定にかかる一般的な考え方をまとめたものであり,将来にわたって固定されたものではなく,また個別金融機関の有する特殊性・地域性等は考慮されていないとされていたことからも,当初から一義的な基準として作用するというより,例えば,都市銀行,地方銀行,信用組合等一定の業態に応じて金融機関ごとに,基準として収れんされ,具体的かつ定量的な基準が形成されるまでの間のガイドライン的なものであったとみる余地もある。
以上の点を踏まえると,資産査定通達が,金融機関を明確に拘束する趣旨・内容のものであったといえるかについては多分に疑問があるというべきである。
ウ 4号実務指針
4号実務指針は,自己査定基準と資産査定通達の分類の整合性と対応関係を前提に,債権を分類して,その債権の分類ごとに必要な償却・引当をすべきことを定めるものであり,資産査定通達を前提にその償却・引当の抽象的かつ定性的な基準を示した指針であると認められる。
しかしながら,証拠(甲3,甲15,乙119,乙120)及び弁論の全趣旨によれば,4号実務指針は,会計監査における実務上の方針を示したものであるにすぎないこと,4号実務指針では,償却・引当すべき金額を具体的に算定することができなかったことが認められる。
すなわち,4号実務指針には通常の会計実務指針に存在する具体的な計算の規定と計算例がないこと,4号実務指針には債務者区分ごとに3年分の貸倒実績比率に基づき貸倒引当金を計上すべき旨定められているが,平成10年3月期において,銀行は4号実務指針公表後1年分の債務者区分ごとの貸倒実績率を有するにすぎなかったものであり(従前は債権分類ごとに貸倒実績を考慮していた。),4号実務指針でいう3年分の債務者区分の貸倒実績比率を用いることができず,適正な貸倒実績率による算定ができなかったこと,破綻懸念先についての債権額から担保回収見込額を控除した残額のうち必要額を引き当てるとされているが,その必要額の具体的な算定根拠がないことが認められる。
また,4号実務指針は,資産査定通達との関係において,債務者区分,資産分類,引当金算定の関係が必ずしも明確ではない。例えば,4号実務指針には債権区分の規定がなく,マトリックスを作成できないこと,資産査定通達では,破綻懸念先債権は,優良担保の処分見込可能額及び優良保証等により保全されている部分は非分類とし,一般担保の処分可能見込額及び一般保証による回収が認められる部分をⅡ分類とし,残りをⅢ分類としているが,4号実務指針では,破綻懸念先債権は債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が認められる額を減算するとされ,優良担保と一般担保,優良保証と一般保証が区分されておらず,4号実務指針では,Ⅱ分類部分の引当が不要となる等の問題が存在していた。
さらに,前記認定事実3(3)ア(ウ)のとおり,「中間とりまとめ」においても,償却・引当の正確性,客観性等を確保する観点から,償却・引当の必要額を算定するうえで参考とすべき過去の貸倒引当率等のデータ整備を行うべきことが基本事項とされており,定量的な部分が,ある程度金融機関の自主性に委ねられていたこと,また各金融機関としては平成10年の開始時点にできる限りの体制整備を終えていることが望ましいと指摘されるに止まっていたことから,結局,4号実務指針は,定性的な内容に止まり,定量的な償却・引当の基準として機能できたとはいえないというべきである。
加えて,前記認定事実3(4)ウのとおり,4号実務指針は,平成9年4月1日以降開始する事業年度に係る監査から適用するが,同年9月30日に終了する中間会計期間において銀行等金融機関が自己査定に係る内部統制を構築し,その旨を表明した場合には,当該中間会計期間に係る監査から適用することとされており,必ずしも平成9年9月期においては確実に適用されるとの前提に立っていなかったといえる。もっとも,この点に関しては,証拠(甲60の62頁,63頁)によれば,I会計士は,刑事公判廷において,弁護人から,4号実務指針が発表した途端に慣行になることがあるかとの質問に対し,「皆がそれを知り,皆が守ろうとすれば,それもまた慣行になるのじゃないでしょうか」と供述し,また,4号実務指針が財務諸表規則1条2
項,3項により一般に公正妥当と認められる企業会計基準とされており,当然に商法32条2項の公正なる会計慣行となり得る,4号実務指針は基準として一義的なものであり,会計慣行となり得るものである旨の供述していることが認められる。しかしながら,I会計士が供述した財務諸表規則は,遅くとも,平成10年11月24日号外大蔵省令第135号による改正後のものを指すと解されるが,上記改正前の財務諸表規則1条は,「大蔵大臣が法の規定により提出される財務諸表規則に関する特定事項について,その作成方法の基準として特に公表したものがある場合は,当該基準は,この規則に準ずる」ものとして,「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用される」旨規定していたにすぎず,上記改正により,1条2項が,「企
業会計審議会」により公表された会計基準は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当する」と規定したものであり,4号実務指針の公表当時,また平成10年3月期においては,企業会計審議会の公表する会計処理の基準であっても,立法的手当がされておらず,平成10年3月期において,財務諸表規則を根拠に4号実務指針が,財務諸表規則にいう「一般に公正妥当と認められる企業会計基準」であると解することはできず,上記財務諸表規則を介して,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たると解することもできない。
また,上記改正後の財務諸表規則1条2項,3項において,その主体は,いずれも企業会計審議会又は大蔵大臣(平成12年総理府令第116号により「金融庁長官」)であり,当然に,この中に会計士協会が含まれると解することもできない。もっとも,会計士協会の公表する監査委員会報告についても,一定の会計処理や情報開示を示している場合には,監査上妥当なものと取り扱うなどの方法により,間接的に会計的側面を有するものがあることも否定し得ないが,このような監査委員会報告が,基準として具体的かつ定量的な内容であることや事前に関係当局その他の関係者と十分な協議を経て関係者に会計基準として認識されるに至ったとみなし得ること等が必要であるというべきである。
さらに,証拠(甲136の18頁)によれば,Q会計士は,4号実務指針が全ての金融機関に一般的に適用されることを想定しており,規定の中に抽象的な部分も存在し,金融機関が実務を行うためには,それぞれの具体的基準を設けて運用する必要があったと供述し,上記の点も併せて考えると,4号実務指針が,具体的かつ定量的な基準として,償却・引当の基準を定めたとみることには,なお疑問が残るというべきである。
エ 破綻懸念先の概念等
また,特に,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に関する基準の変更の点については,資産査定通達の内容や4号実務指針からみても,以下の疑問点が指摘される。
(ア) 「破綻懸念先」の概念
まず,前記前提となる事実2(2)アによれば,破綻懸念先の概念については,「現状,経営破綻の状況にないが,経営難の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。具体的には,現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況で,自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう。なお,自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」
とされていたが,従前の税法基準においては,①前記のとおり,母体行主義を前提としてシステミックリスクの発生を回避するため,関連ノンバンクの資産(営業貸付金)の査定結果を母体行の貸出残高を限度として又はその全額について母体行に反映させる一方,関連ノンバンクの資産査定の結果を母体行以外の銀行の貸出金には反映させず,これにより,母体行以外の銀行の貸出残高の維持を図っていたこと,②前記のとおり,母体行は,関連ノンバンクの分類資産(不良資産)について,合理的な再建計画を作成し,国税当局において無税扱いに関する事実上の承認を受け,償却原資の提供すなわち債権放棄等の損益支援や新規貸付け等の支援をして関連ノンバンクの分類資産を処理し,関連ノンバンクの経営の健全化を図る,すなわち再建することが予
定され,最終的に関連ノンバンクを再建し,それにより破綻が回避される以上,再建期間中における母体行及び母体行以外の銀行の貸出金については貸倒れのリスクが発生しないと考えられていたことを根拠として,不良債権償却証明制度により補充される改正前決算経理基準すなわち税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当をしないとする会計慣行が存在していたところ,「破綻懸念先」において,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先」として,母体行主義の下における関連ノンバンク向け貸出金の査定方法を前提とした表現が含まれている。
もっとも,「自行(庫・組)として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の業況等について,客観的に判断し,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる場合は,破綻懸念先とする」とされていたが,証拠(甲136の39頁)と前記認定事実3(12)ア(イ)aによれば,金融検査マニュアルの策定・公表がされた際,その中で,「破綻懸念先」の意義について新たに「債務者」の後に括弧書きとして「(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)」と付記し,「自行(庫・組)としても消極ないし撤退方針としており」以下の部分が削除され,「現状,事業を継続しているが,実質債務超過の状態に陥っており,業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があ
り,従って損失発生の可能性が高い状況で,今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者」と改められており,従前の会計慣行との比較において,「破綻懸念先」の意義が明確ではなかったことを踏まえて,このような改正が,金融検査マニュアルの中で行われたと考えられる。さらに,これを受けて,前記認定事実3(12)ウのとおり,平成11年4月に4号実務指針の内容も改正され,破綻懸念先債権については,「経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく」との文言が付加されている。これらの事実に照らすと,発出当初の4号実務指針には不明確な部分が存したことが明らかである。
(イ) 特定債務者支援引当金
銀行の関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当をせず,支援損すなわち支援に要する費用を計上するという慣行についても,4号実務指針で,このような計上が予定される費用について引当金を要するということが明確化されていたわけではなかった。
すなわち,前記認定事実3(12)ア(イ)b,cのとおり,平成11年になって初めて,銀行が関連ノンバンクに対して支援を実施している場合,新たに特定債務者支援引当金という勘定科目を設けて,当該支援に伴い発生が見込まれる損失見込額を算定し,当該損失見込額に相当する額を費用の引当金として計上することが定められ,また,例外的に,支援の内容が債権放棄で,当該損失見込額が貸出金額の範囲内であり,かつ,当該損失見込額が少額で特定債務者支援引当金を設定する必要性に乏しい場合など合理的な根拠がある場合は,その支援額を個別貸倒引当金として計上し得ることが定められた。
このような金融検査マニュアルの定めは,新たに銀行が支援を継続している関連ノンバンクであっても,その支援に要する費用をあらかじめ計上することを義務づけて明確化し,さらに,例外的に,本来費用性の引当金と考えられる特定債務者支援引当金について,貸倒引当金の計上により代えることができると明示し,従来の銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の内容を整理し,明確化を図ったものと評価できるものであり,金融検査マニュアルの公表以前の段階においては,この点が明示的に定められていたと解することは困難であったといえる。
なお,この点に関しては,前記認定事実3(12)ウの4号実務指針の改正により,債権放棄により支援を行う場合には貸倒引当金として,現金贈与等により支援を行う場合には特定債務者支援引当金として,それぞれ貸借対照表に計上すべきことが定められ,従前明確ではなかった部分が明確にされたといえる。
オ 平成10年3月期における銀行(主要17行)の決算の修正
ところで,証券取引法24条1項,6項は,上場会社は,企業内容等の開示に関する省令(昭和48年大蔵省令第5号)の定めるところにより,事業年度ごとに,いわゆる有価証券報告書及び添付書類(「当該事業年に係る商法第283条第1項に規定するもので,定時株主総会に報告したもの,又は,その承認を受けたもの」すなわち貸借対照表,損益計算書等)を提出すべき旨規定し,また,同法24条の2は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等の記載すべき重要な事項の変更等があるときは,訂正報告書を提出すべきこと(同法7条準用),また,大蔵大臣は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは,提出者に対し,訂正報告書の提出を命ずること(同法9条1項準用)
,さらに,大蔵大臣は,同報告書及び添付書類である貸借対照表等のうちに重要な事項について虚偽の記載があること等を発見したときは,提出者に対し,訂正報告書の提出を命ずること等(同法10条1項準用)を規定する。
また,財務諸表規則65条1項は,利益剰余金に属する剰余金又は損失金の貸借対照表における記載方法については,「利益準備金」(同条項1号),「任意積立金」(同条項2号)及び「当期未処分利益又は当期未処理損失」(同条項3号)の各区分に従い,当該剰余金又は損失金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならないと規定する。この「当期未処分利益又は当期未処理損失」の額は,「貸倒引当金繰入額又貸倒損失」の額が増減した場合には,当然それに伴い増減するところ(同規則87条,95条の4,95条の5,95条の6),これらの変更も,その額が多額に上る場合,当然,上記「重要な事項」に該当し,訂正報告書の提出等が必要となると解すべきである。
そして,新基準のもとでは,当然にこのような基準の変更がなされるべきところ,平成10年3月期において,そのことが必ずしも明確化されていなかったことを窺わせる事情として,主要17行において決算の修正が行われていないことが指摘できる。
すなわち,前記認定事実3(10)イによれば,主要17行において,自己査定結果と当局査定結果を比較した場合,自己査定結果のⅠ分類が,当局査定結果と比して5兆4061億円減少し,そのⅡ分類が3兆5842億円,そのⅢ分類が1兆5708億円,そのⅣ分類が2511億円,それぞれ当局査定結果により増加し,主要17行については1兆0413億円の償却・引当不足が存在していたと認められるところ,本来,このような貸出金に係る償却・引当不足額は,当然,費用として当期利益から除外されるべきであり,かつ,その額も1兆円にも及んでおり,証拠(乙34)によれば,主要17行の平成10年3月期決算において,8兆6151億円の赤字決算を行い,おおむね各銀行ごとには,最大100億円程度の黒字を計上した信託銀行や
最大約9000億円の赤字決算をした都銀が存在しており,上記不足額が各銀行ごとにどの程度存在していたかは明らかではないが,全体の当期損失額の8分の1にも達する更なる損失額が生じた以上,当然,新基準を厳格に適用することを前提とする場合には,このような不足額をすみやかに財務諸表に反映させ,訂正報告書の提出を求めるべきであったといえる。それにもかかわらず,これらの乖離が生ずること自体,基準としての明確性に問題があるというべきである。また,金融監督庁の対応の問題ではあるが,証拠(乙26)によれば,平成10年3月期金融検査の結果については,同期の決算を遡及的に修正することは無理であり,検査結果をどの決算期において反映すべきとの指摘を行わないことされている。結局,決算処理の是正を各銀行の自
主判断に委ねたものと解され,このことからも,新基準のもとでの実務が流動的な要素を含んでいたといえるし,いずれにしても新基準については,償却・引当の基準としての明確性に疑問があるといわざるを得ない。
カ 小括
以上によれば,旧基準と新基準を比較した場合,新基準は,①銀行の貸出金について有税による償却・引当を実施すべきとして従来の旧基準の変更を促し,②銀行の貸出金特に銀行の関連ノンバンク向け貸出金についても償却・引当をすべきとすることを促したものというべきであり,その範囲で,従前の会計慣行を変更することを目的としたものであるが,前記イのとおり,資産査定通達や4号実務指針には基準として明確ではない部分が存在し,特に定量的な基準の策定については各金融機関の自主性に委ねられている部分があること,特に,破綻懸念先の概念と特定債務者支援引当金の概念において,曖昧な点が残り,この点の変更が明確にされていなかったこと,金融当局においても新基準を厳格に適用して,銀行の決算の修正を図るまでの意
図があったとまでは思えないことなど,その基準としての一義的明確性や拘束性については,多分に疑問が残るものであったと認めざるを得ない。
(5) 関係者に対する規範として拘束性を有するものであることの周知徹底の有
無について
次に,原告らの主張するとおり,新基準が唯一の「公正なる会計慣行」に当たるとした場合には,商法32条を介して関係者に対し,法規範としての拘束性を有することになるところ,前記2(4)の要件⑤のとおり,これを認めるためには,新基準に拘束されることになる関係者に対し,新基準が一般的に広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が図られていることが必要と解すべきである。
そこで,以下,この点について検討する。
ア 基準の周知性
前記認定事実によれば,①早期是正措置の導入が決定された際,大蔵省は,その導入に関する各指針を金融雑誌誌上等において公表していたこと(前記認定事実3(1)ア),②資産査定通達の内容についても,同様に,金融雑誌誌上において公表し(前記認定事実3(4)ア(イ)),また,全銀協Q&Aの形で配布され(前記認定事実3(4)イ),各金融機関は,全銀協を介して,これらの基準の内容については知り得たこと,③9年事務連絡についても同様に全銀協追加Q&Aの形で配布され,同様に各金融機関は,全銀協を介して,これらの基準の内容については知り得たこと,④4号実務指針についても,JICPAジャーナル等の会計雑誌を介するなどして,その内容が公表されたこと,⑤改正後決算経理基準は,大蔵省銀行局長において,各銀行の代
表取締役頭取に宛てて発出され,その内容を当然に各銀行において知り得たことが認められ,新たな資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準は,基準として,一応の周知が図られたと評価することは可能である。
しかし,①税法基準の変更すなわち有税による償却・引当の義務化を促した点と,②銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当の義務化を促した点については,以下の事情を考慮する限り,関係者の理解に対する手当が不十分であり,十分な時間的余裕もなく,関係者が理解し得る状態に達していたかどうかについては多分に疑問が残るところである。
イ 通達発出者の意図
新基準の中核をなす改正後決算経理基準は,大蔵省銀行局所管の通達であるところ,同通達発出当時の大蔵省銀行局の担当審議官であるRの証言によれば,R自身としては,同人が担当審議官を務めていた平成7年ないし平成10年は,銀行行政の転換期で,不良債権処理を余りに性急に行うことは大きな混乱を生ずるおそれがあり,いわゆるセイフティーネットの整備が必要と考えていたこと,新基準については,行政当局の作成した通達であり,通達の示すガイドラインを参考にして各銀行ごとに自己査定基準を作り,これに対し金融当局が何回か検査を行うことによって次第に統一的な考え方に収れんされていくものと考えていたこと(証人R11頁),平成10年3月期の時点では,新基準はマーケットや当事者の検証を経ていないもので,銀
行行政の目的で出された通達であり,未だ商法上の「公正なる会計慣行」にはなっていなかった(言い換えると通達で商法の会計基準が直ちに変更されるとは考えていなかった)と認識していたこと(証人R10頁,38頁)がそれぞれ認められる。
ウ 関係者の理解に対する手当
(ア) 平成10年3月期における原告を除く各銀行の実務
証拠(甲188ないし甲205)によれば,平成10年3月期において,都銀9行,原告を含む長信銀3行及び信託銀行7行は,その有価証券報告書において,貸倒引当金の計上基準としては,改正後決算経理基準に基づき,各行の自己査定基準及び償却・引当基準に従っていること,その内容は,おおむね4号実務指針に基づき,経営破綻先債権及び実質破綻先債権について債権額から回収可能見込額を控除してその残額について計上すること,破綻懸念先債権について債権額から回収可能見込額を控除してその残額のうち,債務者の支払能力を総合的に判断して必要な額を引当金として計上することを明らかにしていた。
しかしながら,証拠(甲136,証人L,証人X,H本人,乙102,乙103,乙118ないし乙120)によれば,①平成10年3月期より前に「特定債務者支援引当金」を計上したことがあった銀行は,東海銀行及び第一勧銀の2行にすぎず,平成10年3月期においても,Q会計士は,刑事公判において,平成10年3月期の大手19行のうち,長銀を除く18行で将来の支援予定額について,特定債務者支援引当金ないしは貸倒引当金を計上しなかったところは,18行中14行である旨供述しており(甲136の37頁),特定債務者支援引当金を計上した銀行は4行にすぎなかったこと,②平成9年5月19日,原告の総合企画部の担当者とさくら銀行の担当者が情報交換をした際,さくら銀行の担当者は,さくら銀行としては,関連
ノンバンクについては,母体行としてきちんと面倒を見て行くつもりであり実質破綻先等の債務者区分は不適切であり,債務者区分はしないつもりである旨述べ,平成9年7月14日の情報交換の際にも,債権放棄額確定分をⅣ分類(全額償却)とし,残りをⅢ分類とするがⅢ分類は損失の合理的推計ができないとして,引当は行わない旨述べたこと,また,さくら銀行は,平成10年3月期においても,上記方針に従い,支援予定の関連ノンバンクに対する貸出金については,債務者区分を実施せず,当期支援損をⅣ分類として全額償却したこと(証人L13頁,26頁,27頁),③興銀においても,平成10年3月期において,特定債務者支援引当金の勘定科目により,支援損予定額をあらかじめ計上していなかったこと(証人X,甲62),④住友信託
においても,直系ノンバンクⅢ分類債権償却の必要額は,支援の必要性等をその都度判断し,基本的には生かす企業として引当・償却を行わない様にしたいと考えられていたこと(H本人11頁,乙104)がそれぞれ認められ,これらの事実に照らす限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金については,多くの銀行において支援損を計上する以外には,特に個別の償却・引当を実施していなかったものと認めざるを得ない。
以上によれば,多くの銀行(上記18行中14行)は,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準に厳格に依拠したうえで,その貸出金の償却・引当を実施していたとは認められないというべきである。
(イ) 関係者の理解度
本件における新基準の変更内容について,実際に,関係者が,どの程度の理解をしていたかについては,①まず,資産査定通達等の導入に当たり,Kは,早期是正措置検討会において,自己査定と検査の結果に格差・乖離が生じた場合,相互にすりあわせて,一定の水準を探し求めること,また,有税による償却・引当を拡大するといっても,税効果会計も導入されず,どうなるのかといった指摘もあったが,すりあわせながら一定期間試行的に行って定着させるというのが了解事項であったと供述していること,そしてこのような供述内容は,前記認定事実3(3)ア(イ)bのとおり,M企画官が,自己査定基準において独自性を発揮するのが重要であるが,その結果が,当局が示す基準に整合しているかどうかについては十分にチェックすることとな
ると説明していたことやN調査課長が,個々の検査の場面で,金融機関側との意見が相違する,あるいは,会計監査人の考え方と金融検査の立場が相違することはあると思うが,検討会に出席した米国の公認会計士が説明していたように,そこは実務的に議論する中で,大きな隔たりが残ってどうしようもないということは少なく,かなり調整できるとの指摘もあり,議論の中で,いろいろ知恵を出していくことになると思うと説明していたことと符合すること,②前記認定事実3(10)オ(イ)のとおり,原告の会計監査を担当したP会計士等は,経済的利益供与が貸倒引当の概念に該当しない,未払金の計上という方法があるが,企業会計実務の中で一般慣行として定着していない,原告の考え方も妥当の範囲内であると回答し,また,他の担当会計士も,支援に
ついては現金供与もあり,貸出金の引当という考え方になじまないと説明していたこと,③証拠(甲136の23頁)によれば,Q会計士は,刑事公判廷において,平成10年3月期において,監査を行う公認会計士の側において,資産査定通達等が許容する解釈の幅に対する理解について影響があったのかどうかという弁護人の質問に対し,「平成10年3月期は,平成9年3月期以前の会計処理の継続という面もあったわけでございます。平成9年3月期以前に償却,引当をしなくてもいいというふうに認められた項目が,資産査定通達の解釈上,それが許容されるというふうに読める場合に,それを許容できないと,平成10年3月期に結論付けることは,なかなか難しかったのではなかろうかと,許容範囲内と判断できたのではないかというふうに思い
ます」と供述し,公認会計士においても,必ずしもこのような変更の内容については十分な認識・理解がなかったことが窺われること,④原告の元監査役であったZは,刑事公判廷において,平成10年3月期においても,従来銀行の貸出金の償却・引当の基準であった決算経理基準,不良債権償却証明制度,検査官の査定等が一体となった一つの基準が全然実質的には変わっていなかったと認識していた旨供述していること(甲135の46頁),Gも,当裁判所において,資産査定通達等の基準が銀行実務家において,「公正なる会計慣行」であると認識がなかった旨供述していること(G本人64頁),⑤証人Lは,当裁判所において,銀行の関連ノンバンク向け貸出金について,平成10年3月期にはどう対処をすべきかという明確な基準はなく,その
時の処理の仕方は,税法基準に則って処理するということをやっていた旨証言し(証人L11頁),また,平成10年3月期における企業会計処理の基準の変更については,当初早期是正措置は,平成10年の4月以降適用となっていたところ,平成10年の3月期から前倒しでやるということになり,準備が完全に整っていない金融機関もあるのではないかとの心配もあり,税効果会計が認められなかったというのに,その時期から実施するということになってかなり混乱はあったのではないかと思う旨証言していること(証人L17頁),さらに,この間,原告以外の銀行関係者においても,必ずしも,十分明確な理解がなかったこと,銀行界は,過去,税法基準に則って決算経理をしており税法基準に拘った考え方が銀行界一般には根強く残っていたこと
,そのため,早期是正措置が導入されたとはいえ,一番最初の段階で具体的なことがよく見えていない状況の中で,銀行が基準として考えるよすがとしては,税法基準が一番直近で目に見えた基準であったこと,したがって,税法基準をベースにして銀行が決算経理の処理をするということは,当時としては一般的な取組みの仕方ではなかったかと思う旨証言していること(証人L23頁),以上の事実が認められる。これらの事実からすると,平成10年3月期の段階においては,新基準がこれに拘束されるべき公認会計士,銀行関係者にとって,必ずしも,明確な基準といえないばかりか,その根幹の部分の内容について十分な理解が得られていなかったものと認めざるを得ない。
(ウ) 変更に対する時間的な余裕,習熟度
さらに,前記認定事実3(8)アのとおり,平成10年3月期における銀行の関連ノンバンク向け貸出金を含む貸出金に対する償却・引当は,各銀行間において,実際の状況にかなりばらつきがあったが,当初,このようなばらつきが生ずることは予想されており,大蔵省金融検査部は,平成9年度を各金融機関が自己査定に習熟するためのトライアル期間と位置づけて,その間において,各金融機関がどのような自己査定基準を策定しているかどうかについて予備的に検査し,そごがあれば,これを指摘して訂正させることも計画していたが,同年11月に,三洋証券株式会社の会社更生手続の申立て,株式会社北海道拓殖銀行の経営破綻や山一證券株式会社の自主廃業等により,金融システムが混乱に陥ったため,このような検査を実施するには至ら
なかったこと,また,大蔵省が預金保険法の改正等のための国会における審議資料として,各金融機関の試行的な自己査定による数字(不良債権額)を提出させた際にも,その内容が各行ごとに全くばらばらで,必要な数字の比較や集計ができず,各銀行に対し,Ⅰ分類からⅣ分類までに組み替えるよう指示したこと,さらに,その後においても,大蔵省は,平成10年1月以降,説明会において,このような「ばらつき」について統一化を図ることも試みたが,平成10年3月期決算は,平成9年12月末を基準としており,既にその時点では,平成10年3月期決算には時間的余裕がなかったことが認められる。
エ 小括
以上のとおりであって,新基準の内容については,一応の周知策はとられたと評価できるものの,前記(2)のとおり,新基準の内容が税法基準によって補充されていた旧基準の内容を大幅に変更するものであったにもかかわらず,新基準の内容自体に多分に曖昧な部分があったこともあって,平成10年3月期については,新基準を示した行政の当局者であるR審議官ですら,新基準が「公正なる会計慣行」になっていたとは考えていなかったばかりか,被告らを含む銀行関係者の多くの理解度,習熟度も前記認定の程度であり,旧基準による会計処理も許容されていると認識していた可能性があることが 窺える。そうであるとすれば,平成10年3月期については,いわば,旧基準から新基準への移行期ないしは過渡期とみざるを得ないもの
であり,その時点で,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が図られていたと認めることは到底できないというべきである。
(6) 新基準が平成10年3月期において銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」になっていたといえるかについての結論
以上(1)ないし(5)で検討したところによれば,新基準が示された経緯からすると一応手続的には適正であり,内容的にも新基準については一応の合理性を認めることができるというべきであるが,平成10年3月の時点で,企業会計の継続性を維持し,関係者への不意打ちを避けるといった観点からみて,旧基準から新基準への変更に必要な手当がなされているとは言い難いし,新基準の内容自体も一義的な明確性という点では多くの疑問が残るばかりか,広く会計上のならわしとして相当の時間繰り返し行われた場合と同視し得る程度に,新基準が唯一の規範として拘束性を有することの周知徹底が関係者に対し図られていたと認めることもできないというべきである。
そうであるとすれば,平成10年3月の時点において,新基準が銀行の貸出金の償却・引当の基準として,唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとまで認めることはできないから,この点に関する原告らの主張は理由がないというべきである。
6 争点⑥(新基準が平成10年3月の時点で銀行の貸出金の償却・引当に関す
る唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合,この点に関する当時の会計慣行はどのようなものであったのか。そして,被告らが関与して策定された原告の自己査定基準による償却・引当が当時の「公正なる会計慣行」に違反していたといえるか。)について
原告らは,予備的な主張として,仮に新基準が平成10年3月の時点で銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」といえないとした場合でも,被告らの主張する税法基準は当時の「公正なる会計慣行」とはいえず,当時の公正なる会計慣行は旧商法285条の4第2項における「取立不能見込額」の判定に従い,債務者の資産状態,収益力,担保状況からみて合理的な社会通念に従って行わなければならず,被告らが関与して原告が平成10年3月期において策定した自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当額はこれに違反していると主張している。この主張については,既に認定したとおり,平成10年3月期においても,税法基準によって補充された改正前決算経理基準(旧基準)は依然として「公正なる会計慣行」として存
続していたと認められるから,その観点からすると,原告らの主張は理由がないということになる。しかし,一方で,原告らの主張は,被告らが関与して原告が平成10年3月期に策定した自己査定基準に基づく原告の貸出金の償却・引当額は,その実質的な内容において当時の「公正なる会計慣行」に違反しているとの主張とみる余地もあるので,以下念のため,本件で問題とされている被告らが策定に関与した原告の平成10年3月期の自己査定基準に基づく関連ノンバンク等関係会社に対する貸出金に対する償却・引当の実態について検討することとする。
(1) 原告の平成10年3月期の自己査定基準と新基準及び旧基準との関係並びに自己査定基準に対する被告らの認識
ア 自己査定運用規則及び自己査定運用細則
原告らは,被告らが策定した自己査定基準すなわち「自己査定運用規則」及び「自己査定運用細則」が,不良債権の計画的な隠ぺいと不良債権処理の先送りを企図して,本来償却・引当義務を負うべき関連親密先に対して,償却・引当を不要とする目的により,これらの基準を策定したと主張するので,この点を検討すると,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,「自己査定運用規則」及び「自己査定運用細則」は,原告の関連親密先については,債務者区分を実施せず,「その他」と区分し,一律的な資産分類を行い,基本的には,当期支援損を計上する以外には,償却・引当を実施しないということを内容とするものであったことが認められる。
このような債務者区分は,新基準では,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当については,従来の慣行(一定期間における再建を実施し,これにより破綻回避を予定して,当期支援損を計上する以外には,償却・引当を実施しないとの慣行)を転換して,9年事務連絡の範囲内で,短期間の再建による破綻回避が行われる場合でない限り,関連ノンバンクの資産の実態に即して必要な償却・引当を行う義務を負うというものであったことからすると,そのような新基準の趣旨に照らす限り,その趣旨に反したものと認める余地があるし,また,前記認定事実3(10)ウ,オ,カのとおり,平成10年3月期の金融検査において,日銀の担当者及び金融証券検査官が,このような基準については資産査定通達等に反するとの指摘をしているこ
とからすると,客観的評価としては新基準に反していた可能性は高いというべきである。
しかし,一方で,平成10年3月期は,いわば旧基準から新基準への過渡期であり,新基準が未だ唯一の「公正なる会計慣行」にはなっていなかった以上,新基準に対しての違反は,通達違反の問題を生じさせるとはいえ,従来の「公正なる会計慣行」である旧基準(銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対しては,合理的な支援を継続する限り,償却・引当を実施しないとの会計慣行)が継続されていたものと認めざるを得ないから,以下のような基準を設けることも旧基準の範囲内であると解すべきである。
まず,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,「経営支援実績先」との区分を設けた点については,従前の税法基準を前提に検討した場合には,法人税基本通達9-4-2に係る支援先に対する支援が合理性を有するかどうかの判断基準として,「整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)」に従い,銀行による再建管理の実施先を想定し,合理的な再建計画の実施を前提に再建支援を行い,又は行い終えた先についてもその支援の継続,見直し,再開が必要となるとの観点から,通常先と異なる管理を継続する趣旨とみることができ,銀行の関連ノンバンク向け貸出金を一般の貸出金と区別して管理することを容認していた旧基準に照らし,容認できる区分といえる。また,前記認
定事実3(7)ウ,同(9)イによれば,本件監査法人もこの区分を了解している。そして,証拠(乙105の21頁,乙108の51頁から54頁,乙118の16頁,乙120の11頁)及び弁論の全趣旨によれば,当時の銀行による支援の形態として,いわゆる自転状態(<ア>含み損が残存しているが,含み損部分に見合う借入金の金利を本業の利益(償却前利益)によりまかなえる状態に達していること,<イ>期間損益が黒字であること,<ウ>キャッシュフロー(現金収支)が順調であり,借入金の約定返済に遅滞が生じていないこと)に達している場合に,さらに含み損を即時に処理し得る償却財源の提供すなわち損益支援を実施するときは,過剰支援となるおそれがあり,上記基本通達9-4-2において,「損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過
剰支援になっていないか)」という点との関係において,支援の合理性を否定されるおそれがあったことが認められるから,自転状態に達しているが,なお,銀行が,継続的な支援・管理を実施している先として「経営支援実績先」を観念する余地は十分あるというべきである。そうであるとすれば,旧基準に照らす限り,このような類型は許容できるというべきである。
次に,関連親密先であるノンバンクと一体とみなし得る子会社については,前記認定事実3(7)オ(エ)のとおり,決済事由10項ただし書により,不稼働資産処理を本体で一体として行う会社については,本体の債務者区分に従い,それに準じた資産分類を行うとされていたものである。この点については,法人税基本通達9-4-1又は同基本通達9-4-2において,「支援者が行う子会社に対する支援の一環として,つまり関連会社の清算又は再建に伴う子会社の損失負担額を含めて支援者が子会社の支援を行う場合において,それが子会社の再建を図るために必要不可欠であると認められるときは,支援者の子会社に対する支援及び子会社の関連会社に対する支援等について,それぞれ法人税基本通達9-4-1又は同通達9-4-2に該当する
かを検討することとなる」こととされ(乙14の30頁),一定の場合において,法人税基本通達9-4-2が,支援を行っている先と支援先の関連会社の一体処理を許容していたこと,また,証拠(証人Xの28頁,29頁)及び弁論の全趣旨によれば,関連ノンバンク本体において,関連ノンバンクの関係会社(その孫会社等)を支援する場合,関連ノンバンクに新たなる損失が発生し,それも含めて,銀行が,支援計画を立てている場合においては,合理的な計画として,関連ノンバンクとその孫会社等の処理を一体的に行うことも許容されていたことからみて,原告において,一定の場合に,関連ノンバンクと孫会社等を一体とみることも,旧基準のもとでは許容されるものと考えられる。
また,※7なお書は,母体行責任を負う意思があっても,再建計画が作成されていない場合であり,かつ,当該「関連ノンバンク」の取引金融機関が原告のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類とし,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類とし,その他をⅢ分類とすることを定めている。この点,不良債権償却証明制度において,法人税基本通達9-6-4の運用に当たって,その要件である事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないとされているところ,銀行
が,再建のための支援を実施していない場合であっても,上記支援の内容が,損益支援などの再建のための抜本的な支援に限定されず,融資等の当面の企業維持を目的とした支援を含むものと解すると,旧基準による限り,償却・引当を実施することはできないと考えられ,また,損失が確定するまで無税による償却・引当も困難であり(有税による償却・引当が旧基準のもとで必ずしも義務とされていなかったことは,前記のとおりである。),このような運用も,旧基準においては,許容されていたというべきである。
イ 被告らの認識
また,原告らは,本件において,被告らは,平成10年3月期以前の段階において,原告の償却原資の状況からみて,償却不可能な不稼働資産を抱えていた結果,その存在を隠ぺいし,その処理を先送りするため,意図的にこのような自己査定基準を策定したと主張するので,検討する。
この点については,①前記認定事実3(2)ア(ア)のとおり,平成8年4月の大蔵省検査における原告の関連親密先の不良債権の試算として,Ⅲ分類及びⅣ分類の合計額が8437億円であると記載されているが,これは,修正母体行方式による査定結果であり,本来のプロラタ負担においては5710億円であるにすぎず,上記8437億円が単年度償却・引当すべき金額であったと考えられないこと,②前記認定事実3(2)イ(イ)のとおり,平成8年8月30日開催の常務会段階においては,未だ,早期是正措置検討会における「中間とりまとめ」すら作成・公表されておらず,この段階において,Fが「実質的には,多額に抱えてしまっている不稼働資産をどのような形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。
その点は十分認識しておく必要がある。」と発言していたとしても,それが,直ちに,資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準に反することを承知のうえで,これを意図的に潜脱しようとした趣旨の発言とみることには無理があること,③前記認定事実3(3)イ(イ)のとおり,修正母体行主義により原告の融資残高を条件とした場合における関連親密先の不良債権について,その最終要処理額が1兆6914億円に達していたことは認められるが,その処理計画については5年間の期間が想定されており,従来の税法基準に照らし,当然許容される考え方,計画であったといえること,④前記認定事実3(3)イ(エ)のとおり,平成8年12月19日の常務役員フリーディスカッションにおいても,関連親密先の不稼働資産の処理計画について,3通りの
試算が行われているが,それ自体,可能な限り,原告内部において,不良債権の処理の早期化を進める趣旨の内容とみるべきであり,また,不良債権処理を進めるうえで,どのように償却財源を確保するかということは当然に検討されるべき課題であり,償却財源を検討しながら,不良債権処理額を検討することは不自然とはいえないこと,⑤前記認定事実3(3)イ(オ)のとおり,平成9年2月7日開催の常務役員連絡会資料によれば,「今後の不良債権要処理額見込は最低7000億円~1兆円レベル且つ早期是正措置により平成9年度以降Ⅲ,Ⅳ分類資産は単年度での適正な償却・引当の実施が不可避」との記載があり,単年度での1兆円規模の処理(償却・引当)が必要との趣旨にも読めなくはないが,その括弧書きには,「97年度不良債権要処理額見込
約3000~5000億円,98年度以降約1000億円/年~不確定要素」との記載があり,最終的には原告において1兆円規模の不良債権処理を要するものの,単年度においては,その一部を処理すれば足りるという趣旨とみることができること,そして,上記金額が,当時,原告が本来的には全額の償却・引当義務を負担しない(すなわち貸出金のシェアに応じたプロラタ方式により査定され,その場合に償却・引当義務を負うと理解される)関連ノンバンクの営業貸付金のⅣ分類,Ⅲ分類を含んだ金額であることからすると,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当をただちに行うような会計慣行が存在しなかった当時においては,上記1兆円という金額は一定期間において最終処理すべき金額を示したにすぎなかったとみるべきであり,
そうであるとすれば,上記1兆円は,単年度において直ちに償却・引当を要するものではなかったと認めるべきであること(乙100の15頁),⑥前記認定事実3(5)ア(ア)のとおり,平成9年5月9日付け「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理について」と題する資料においても,関連親密先の自己査定は,日本リースの扱い等無理をしているところがあること,引当率の考え方が会計士と議論になることが必至であり,個々の関連親密先の処理について,会計士に合理的な説明を行い,理解を得る必要があることや会計士の理解が得られる場合と得られない場合とに分けて試算する必要があることが指摘されており,外部監査における会計士の意見を尊重しようとする意図が認められること,特に会計監査人の理解が得られない場合も想定しており
,その場合には不良債権の処理額が積み上がることも当然予定していたと考えられること,他方,前記認定事実3(5)ア(イ)によれば,同日付け「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料(甲30)において,不稼働処理必要額の見極めとBIS比率8パーセント割れを回避しつつ,必要不稼働処理を可能とするリスクアセット,決算運営が挙げられているが,不良債権の処理を行ううえで,償却財源を配慮するのは,銀行決算において当然であり,また,総合企画部と事業推進部の試算が,4598億円(事業推進部)と3454億円(総合企画部)が相違する点も,異なる部署が個別に試算しており,この時点における数字の乖離が生ずることも,原告の正規の機関(取締役会,常務会,経営会議等)の承認・決
定を経ていない段階において当然であること(乙100の17頁,乙108の10頁),また,これらの数字は,いわゆる関連親密先に対する支援額に応じて異なるものであったこと(G本人27頁),⑦前記認定事実3(7)アにおいて,スイス銀行からのファイナンス実施により,増資される以上,当然償却財源に余裕が生じて,その分で不良債権処理を進めることを考えること自体,特に不自然な点はないこと,⑧前記認定事実3(7)イ,ウのとおり,平成9年9月2日付け資料によれば,償却財源の不足の点については,全体としての不良債権の処理には満たないことが指摘されていること(G本人35頁),相当の理論武装が必要となることや会計士に否認されるおそれについても,最終的には会計士に説明をして理解を得ることが前提であり,会計士の理
解が得られない場合には,最終的な償却・引当の増額も認識していたことも認められ,そのような事実に照らす限り,直ちに意図的に償却・引当の不足があるのにこれを潜脱しようとしたとは認められないこと(G40頁),⑨また,現に,Hほか事業推進部のメンバーは,Q会計士等に対し,原告の自己査定基準について債務者区分として「関連ノンバンク」以外に「関連親密先」を設けることの適否について見解を求めており,Q会計士等から,資産査定通達の許容範囲内との回答を得ていたこと,⑩前記認定事実3(7)エのとおり,本件中間配当に関する検討が行われた際も,D,E及びFは,いずれも赤字決算がないことを前提としていたとはいえ,従前の会計慣行に照らせば,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当は必要ではないと考え
ていたことが窺えるし,また,ほぼ一貫して平成9年度における5000億円の不良債権処理を想定していたことが認められること,⑪現に,平成9年度において,原告は,前記認定事実3(9)ウのとおり,最終的には6165億円の不良債権を処理していること,以上の各事実が認められる。
これらの事実と前記認定事実で詳細に認定した被告らの平成10年3月期の決算処理への対応に関する経緯を併せ考慮すると,被告らは,平成10年3月期の原告の不良債権の処理に関しては,新基準を厳格に適用した場合には,自己資本比率を8パーセント以上に維持することが困難になり,原告の今後の経営面で深刻な問題が生じ得る可能性があったことは認識していたというべきである。しかし,一方で新基準が平成10年3月期に初めて施行されるものであり,その内容自体旧基準を許容する解釈の余地を残している,あるいは,未だガイドラインであるとの認識もあって,原告の自己査定基準の検討に当たっては,原告にとって厳しい経営環境のもと,銀行の経営者としてのそれぞれの立場で,企業としての原告の維持・存続を図るべく,旧基
準との連続性ないしは継続性を保てるぎりぎりの線を模索していたとみるべきである。そして,前記認定のとおり,新基準がセーフティネットを欠き,その内容自体も一義的に明確といえず,さらに関係者への周知策も十分ではなかったことからすると,企業の経営者として,企業の維持・存続を図るため,新基準について独自の解釈をし(例えば,Dは,資産査定通達には日本リースを納めるボックスがなかったので,経営支援実績先という別のボックスを創出したと供述している。),できるだけ原告にとって有利な資産査定を行いたいと願ったこと自体にはやむを得ない一面があったというべきである。さらに,被告らとしては,そのような検討の過程で,会計士の指摘があればこれを変更することも考慮していたことが明らかであり,本件監査法人側か
らの回答では,許容範囲内とのことであったので,平成10年3月期の原告の不良債権の処理と関連親密先への支援損の計上を実施したものと認められる。 加えて,被告らが策定に関与した原告の自己査定基準(自己査定運用細則及び自己査定運用規則)は,当然,平成10年3月期においては,金融検査の対象となった際には,これを金融証券検査官に開示することを前提としており,被告らの経歴に照らしても,当初から,金融証券検査官に全く認められないような違法なものを策定するとは考えにくいし,自己査定基準自体は,Q会計士やP会計士にも開示され,その了解が得られていたものである。そして,原告の会計監査人が,いったんは原告の平成9年度決算案を新基準のもとでも許容されると判断したことは動かし難い事実である。そうであ
るとすれば,被告らの行った処理が,現時点での評価としては,客観的にみて資産査定通達等の新基準に反するものとみる余地はあるとしても,それ以上に,被告らにおいて意図的に新基準に反した処理をしようとした,あるいは旧基準からみても違法とされる会計処理を実施しようとした(商法違反の行為をする意図があった)と認定することには無理があるというべきである。
なお,原告らは,原告の当時の担当者が会計監査人に対し,関連ノンバンクの実態を説明せず,かえって,その実態を組織的に隠蔽したと主張するが,本件監査法人による原告の平成10年3月期決算の監査の実情は前記認定事実(10)オで認定したとおりであり,十分な時間をかけた監査がなされたことが窺われるところ,原告らが主張するような会計監査人に対する組織的な隠蔽行為がなされたことを認めるに足る証拠はない。
(2) 平成10年3月期における原告の貸出金の償却・引当が旧基準に適合しているといえるか。
ア エヌイーディー
前記認定事実3(9)エ(ア)bによれば,原告は,平成6年3月期以降,エヌイーディーに対し,債権放棄等の支援(5年間で総額1900億円)を実施していたが,大幅な地価下落により不良債権額が増加し,2924億円の不良債権が残存することとなったため,平成10年3月23日開催の常務会において,当初の計画を延長し,5年間(平成10年3月期から平成14年3月期まで)で,総額2951億円の支援を行い,不良債権3010億円を処理する修正計画を立案・了承し,この計画に基づき,国税当局と折衝して新たに無税の承認(法人税基本通達9-4-2)を受けて,エヌイーディーの不良債権を処理し,同社の本業部門(ベンチャーキャピタル業)を不良債権部分から分離して再建する計画を実施する旨決定した。
このようなエヌイーディーの状況をみると,原告による再建支援が継続される状況にあったから,税法基準に照らせば,支援先の関連ノンバンクについては再建を前提としていたものであり,実際に行われた以上に償却・引当を実施する義務があったとは認められない。
イ 青葉エステート他エヌイーディーの受皿会社6社
原告は,エヌイーディーの受皿会社7社について,決済事由10項ただし書に基づき,エヌイーディーと一体であるとして,本体と同様の査定をした。ところで,原告は,これらの受皿会社についても,エヌイーディーと一体として清算処理する予定であり,前記アの支援計画には受皿会社の清算も含まれていたこと,また,原告の受皿会社7社に対する貸出金のうち,エクセレーブファイナンスについては,その貸出金をエヌイーディーに転貸ししており,U検査官もエクセレーブファイナンスについては一括査定を行っていたこと,エヌイーディーが,エクセレーブファイナンスを除く残り受皿会社6社に対する原告の貸出金についても保証予約をしていた以上,受皿会社の査定をエヌイーディー本体と一体としてみることも可能であること,以上
によれば,原告が,これら受皿会社7社について,償却・引当を実施しなかった点は,旧基準に照らす限りは,これを逸脱していたとは認められない。
ウ 第一ファイナンス
前記認定事実3(9)エ(ウ)のとおり,原告は,最終的には第一ファイナンスの清算処理を検討していたが,同社が債権の回収業務を継続し,当面清算する必要がない状況にあったため,損失が確定していないことを理由に,※7なお書に基づき,ロス額が算定されるⅣ分類130億0700万円(同社繰越欠損額)及びⅢ分類の一部の合計額147億円についてのみ引当を実施(有税による債権償却特別勘定への繰入れ)した。
このような取扱いは,法人税基本通達9-6-4の運用に当たって,その要件である事業好転の見通しがないことを審査するに当たり,合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合や債務者に対して追加的な支援(融資,増資・社債の引受,債務引受,債務保証等)を予定している場合には,原則として事業好転の見通しがないと判断することが適当ではないと定められていることからすると,旧基準のもとでは許容の範囲内であったというべきである。また,税法基準において,有税引当は例外的であるところ,原告は,原告のみが融資先であり,他行との関係が問題とならないため,会計監査人の意見を受け容れて,有税による引当をあえて実施したものであり,いずれにしても旧基準のもとでの処理として,許容されないもの
であったとはいえない。
エ 日本リース及びその受皿会社
前記認定事実3(9)エ(エ)で認定したとおり,日本リースは,平成10年3月期において,損益についてはおおむね年間の実力基礎収益175億円程度が見込まれ,他方,同社の含み損(清算価値)が7000億円に達しており(甲81添付資料3),原告による支援がされても,不稼働資産の最終的な処理には相当期間が見込まれる状況にあったことは事実である。
ところで,原告は,日本リースを「経営支援実績先」に区分していたが,法人税基本通達9-4-2に係る支援先に対する支援が合理性を有するかどうかの判断として,このような基準を容認し得る余地はあるというべきである。また,日本リースは,いわゆる自転状態にあり,ノンバンクにとって最も重要なのは資金調達能力であるところ,当面原告が資金繰り支援(融資)を実施する限り,他行は原告の信用を根拠に融資を継続したと考えられるから,原告が,継続的な支援・管理を実施している「経営支援実績先」と日本リースを位置づけた以上,税法基準に照らし,一応破綻のおそれがないと考えて,Ⅱ分類とすることも許容されるというべきである。
また,有楽エンタープライズ及びビルプロ3社について,原告は,これを「特定先」として扱い,その債務者区分を「要注意先」として償却・引当を実施したが,同各社が日本リースの関係会社であり,しかも平成8年4月に行われた大蔵省検査において「親密・系列等の関係会社関係」とされていたことにも照らせば,旧基準を前提とする限り,原告が行った資産査定に基づく償却・引当が許容されないものであったとはいえない。
(3) 平成10年3月期当時の原告の体力からすると関連ノンバンクに対する貸出金についての償却・引当を行わなかったのは違法であるとする原告らの主張について
原告らは,関連ノンバンクが,銀行による支援が継続する限り破綻しないという考え方は,いわば銀行が無限に支援する財源を有していること,すなわち無限の支援体力を有することを前提とするものであるところ,平成10年3月期当時,関連ノンバンクの不良資産は優に1兆円を超えており,また,原告の支援体力は枯渇し,さらに,金融債の販売減少に伴い,資金繰り破綻の危険すら生じていたと主張している。この主張は,税法基準の下,再建支援を前提とする限り,銀行の関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当はしないとする会計慣行のもとでも,平成10年3月期に関連ノンバンクに対する償却・引当を行わなかったことは違法であるとの主張とみる余地があるのでここで検討する。
この点については,前記4(1)ウ(ア)によれば,銀行の関連ノンバンクに対する支援の期間については,おおむね5年程度の期間が想定され,従来の指針において,計画的・段階的処理が要請されていたこと,すなわち,必ずしも,単年度において不良資産を一掃することが求められていたわけではなかったものである。さらに,前記認定事実3(7)オ(ア)によれば,原告の関連ノンバンクの不良資産の含み損等は1兆円に達し,当面,一掃できる体力がなく,抱えて行かざるを得ないものであったことが認められるものの,他方,同(オ)及び証拠(甲109添付資料6,甲122,乙108の39頁)及び弁論の全趣旨によれば,原告においてリスクアセットの圧縮が計画され(長銀再生2カ年計画),そこでは,約5兆円規模のリスクアセットの圧縮によ
り,自己資本比率8パーセントを維持しても,おおむね4000億円程度の自己資本額の減額が可能とされ,同額を不良債権の償却原資とすることが予定されていたこと,スイス銀行との提携により,業務純益をおおむね1300億円程度見込むことが可能とされていたこと,平成11年3月期において前倒適用された税効果会計の導入により,3000億円程度の繰延税金資産の計上が可能であったこと,その結果,数年程度不良資産を抱えたままの状態であっても,他方で相当額の償却財源が見込まれたこと,以上の事実が認められる。そして,当時の原告がおかれていた状況のもとでの経営判断として,そのような計画を建て,あるいはそのような見通しを持つこと自体が不合理であったとはいえないから,これらの事実に照らす限り,原告本体が平成1
0年3月期において破綻する蓋然性が高かったとはいえないというべきである。また,実際にも,前記認定事実3(11)イのとおり,原告の破綻認定と特別公的管理の開始の際に行われた金融監督庁の検査結果では,平成10年3月期においては,追加の償却・引当額2747億円を処理して,かつ,有価証券の含み損1684億円を前提としても,自己資本額は7871億円に達していたというのであるから,この時点では計算上は資産超過の状態にあったといえるものである(もっとも,平成10年9月期には大幅な債務超過に陥り,結局特別公的管理の開始が決定されているが,その間においては,平成10年6月以降の株価の下落,金融債の販売減少に伴う急激な資産内容の劣化,さらには新基準のもとでの清算価値による査定の見直しといったその後の
事情が存することが窺われる。)。そうであるとすれば,平成10年3月期においては,旧基準による資産査定を前提とする限り,原告には関連ノンバンクを支援する体力が残されていたと認定することができるというべきである。結局,この点に関する原告らの主張は採用できない。
(4) 小括
以上のとおりであって,被告らが関与して平成10年3月期に実施した原告の自己査定基準に基づく貸出金の償却・引当の処理については,実施に至った経緯に照らす限りは,被告らにおいて,意図的に違法な会計処理をしようとしたとは認められないし,その内容を客観的に検討すると新基準の趣旨に反した処理がなされたとみる余地もあるが,償却・引当の処理の実態をみる限り,当時の「公正なる会計慣行」であった旧基準の許容の範囲内のものであったというべきである。そうであるとすれば,原告らが主張するように,新基準を前提として,平成10年3月期における原告の償却・引当の不足額すなわち当期未処理損失額が,原告の平成10年3月期における剰余金額460億1400万円を超えるものであったと認めることはできないこ
とは明らかである。
7 本件中間配当の違法性
前記5において判示したとおり,平成10年3月期においては,原告らが主張する銀行の貸出金に関する償却・引当に関する新基準(資産査定通達等により補充される改正後決算経理基準)は,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するものではなかったことが明らかであり,前記6で認定したとおり,当時の「公正なる会計慣行」である旧基準による限りは,平成10年3月期において,原告には本件決算配当及び本件中間配当を実施するに足る配当利益が存したというべきである。そうであるとすれば,本件中間配当が実施された際に,平成10年3月期において配当可能利益がない状態が生ずるおそれがあったと認める余地はないから,本件中間配当が違法であるとする原告らの主張は,その余の点について判断するまでもなく理由がない
ことが明らかである。
第7 結論(本件全体のまとめ)
1 本件の概要
以上認定説示したところから明らかなように,本件訴訟は,原告の前身である日本長期信用銀行が実施した平成10年3月期の本件決算配当及び平成9年9月期の本件中間配当について,平成10年3月期の貸出金の償却・引当に関する決算処理が,取立回収不能見込額の控除を要求する旧商法285条の4第2項に違反しており,実際には配当可能利益が存しないにもかかわらず行われたとして,これらの配当の実施に賛成した被告らに対し,商法290条1項違反(決算配当),もしくは商法293条の5第3項違反(中間配当)を理由として,商法266条1項1号に基づく損害賠償責任(ただし,被告Fについては,決算配当の承認決議以前に取締役を退任している関係で,決算配当については商法266条1項5号に基づく損害賠償責任)が問
われた事案である。
2 本件の争点と当事者の主張の概要
本件では,日本長期信用銀行が実施した平成10年3月期の貸出金の償却・引当に関する決算処理が,取立不能見込額の控除を要求する旧商法285条の4第2項に違反し,実際には配当可能利益が存しないにもかかわらず行われたか否かが争われ,取立不能見込額の判断の基準は,商法32条2項により,「公正なる会計慣行」を斟酌するものと解されるところ,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する「公正なる会計慣行」がどのようなものであったのか,そして日本長期信用銀行が実施した決算処理が,その「公正なる会計慣行」に反していたといえるかが争点となった。
この点に関しては,原告らは,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」は,資産査定通達等によって補充された改正後決算経理基準(新基準)であり,日本長期信用銀行が実施した決算処理は,この基準に違反しており,当時日本長期信用銀行には配当可能利益が存しなかったと主張した。
これに対し,被告らは,新基準は,ガイドライン的性格を有し,各銀行の策定した自己査定基準とのすりあわせにより客観的な基準として収れんしていくことが予定されていたもので,平成10年3月期はその過渡期であり,それまでの銀行の貸出金の償却・引当の基準であったいわゆる税法基準によって補充された改正前決算経理基準(旧基準)が依然として「公正なる会計慣行」として存続しており,新基準は未だ唯一の「公正なる会計慣行」とはなっていなかったと主張し,一方で,仮に,唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとしても,日本長期信用銀行が実施した決算処理は,その解釈の範囲内であり適正なものであるとも主張した。
3 争点に対する当裁判所の判断の概要
以上のとおり,本件では,資産査定通達等によって補充された改正後の決算経理基準(新基準)が,平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」であったか否かが最大の争点となった。すなわち,本件では,法令により取立不能見込額の解釈が定められたものではなく,行政内部での通達や事務連絡等による会計慣行の変更という形で新たな基準が示されている。その結果,その基準による処理が「公正なる会計慣行」と認められ,しかもそれが唯一のものということになると,これに反した会計処理は,商法違反ということにならざるを得ない。これは,実質的にみると法令によらず通達等で法改正が行われたのと同一の結果を招来することになるから,その当否が問題となり,平成10年3月期において
,新基準が唯一の「公正なる会計慣行」といえるかが争われたものである。
当裁判所のこの点に関する判断は,既に詳細に認定説示したところであるが,その概要は以下のとおりである。
まず,「公正なる会計慣行を斟酌すべし」とする商法32条2項の一般的な解釈論を検討し,その結果を踏まえて,本件のように既に通達等により「公正なる会計慣行」としての改正前決算経理基準が存在する場合において,これに代わる新たな会計慣行としての新基準が通達等の改正後ただちに唯一の「公正なる会計慣行」となるための要件について検討した。そして,原告らの主張する新基準が,平成10年3月期において唯一の「公正なる会計慣行」と認められるためには,改正手続が適正であることと,基準の内容が銀行の営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして合理的なものであることに加え,会計慣行の変更に伴って企業会計の継続性の点で支障が生じ,ひいては関係者への不意打ちとなるような場合には,これに
対する必要な手当(セーフティネット)を講じること,基準として一義的に明確なものであること,関係者に対し,これが唯一の基準となることの周知徹底が図られていること,以上の各要件が満たされていることが必要と判断した(前記第6の2,本判決26頁以下参照)。
次に,変更の対象となる旧基準の内容について,いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったか否かについて争いがあるため,その点について検討し,いわゆる税法基準によって補充された改正前決算経理基準のもとでの会計慣行(具体的には,①大蔵省検査でⅣ分類と査定された銀行の貸出金については同額の無税による償却・引当義務を負うが,有税による償却・引当は銀行の自主性に委ねられた結果実際にはほとんど行われない。②銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については,銀行が関連ノンバンクへの支援を継続する限り償却・引当は不要とする。)は,当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは合理性を有するもので,「公正なる会計慣行」に当たると判断した(前記第6の4(1)エ(ウ),本
判決170頁参照)。
そのうえで,新基準が,前記の各要件に照らし,平成10年3月期において,唯一の「公正なる会計慣行」に当たるといえるかについて検討した。そして,手続の適正性及び内容の合理性は一応認められるとした。しかし,旧基準から新基準への変更は,特に有税による償却・引当をすべきとする点と関連ノンバンクに対する貸出金についてもできる限り関連ノンバンクの実態に即して償却・引当をすべきとする点で大幅なものであるにもかかわらず,平成10年3月期においては税効果会計の導入がされておらず必要な手当が講じられていないといわざるを得ないし,さらに,新基準の一義的明確性や拘束性についても疑問が残るばかりか,新基準の関係者への周知徹底が図られていたとはいえないから,結局,平成10年3月期に新基準が唯一の「公
正なる会計慣行」となっていたとする原告らの主張は認められないと判断した(前記第6の5(6),本判決208頁参照)。
最後に日本長期信用銀行の平成10年3月期における決算処理における被告らの認識と,当時の「公正なる会計慣行」と認められる旧基準のもとでの決算処理の適正性について検討し,結論として被告らにおいて,商法違反に当たる行為をする意図があったとすることには無理があり(前記第6の6(1)イ,本判決214頁参照,日本長期信用銀行の平成10年3月期における決算処理については,現時点での客観的評価としては新基準に反しているとみる余地はあるが,旧基準を前提とする限りは,これを逸脱した違法なものとは認められないと判断した(前記第6の6(4),本判決223頁参照)。
4 結論
以上によれば,原告及び原告訴訟引受人の被告らに対する請求は,その余の
点について判断するまでもなく理由がないことが明らかである(なお,原告については,本件損害賠償請求権を原告訴訟引受人に譲渡したとして,第2回口頭弁論期日において訴訟脱退の申し出をしたが,被告らが承諾しなかったため,本件の当事者として残ったものであるところ,前記認定のとおり訴訟引受自体は有効と認められるから,その点からも請求の棄却を免れないというべきである。)。よって,原告及び原告訴訟引受人の被告らに対する請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 西 岡 清一郎
裁判官 山 口 和 宏
裁判官名島亨卓は転任のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 西 岡 清一郎
別紙1 原告らの主張
第1 「公正なる会計慣行」(商法32条)の意義・内容
1 資産査定通達等と「公正なる会計慣行」
(1) 「公正なる会計慣行」の規範的意味
ア 平成14年改正前商法(以下「旧商法」という。)285条の4の解釈と「公正なる会計慣行」
株式会社の取締役には,決算期ごとに法令及び定款に従い会社の財産及び損益状況を正しく表示した貸借対照表及び損益計算書を作成する義務が課せられ(商法281条の3第2項3号参照),また,株式会社が有する金銭債権については,債権金額をもって計上すべきもの(旧商法285条,285条の4第1項)とされるが,金銭債権に「取立不能の虞あるときは取立つること能わざる見込額を控除することを要す」(旧商法285条ノ4第2項)と定められているとおり,金銭債権に取立不能のおそれが生じているときはその取立不能見込額を控除しなければならない。
したがって,金銭債権につき取立不能のおそれが生じているときは,事実に反する会計処理は許されず,当該取立不能見込額を償却しなければならないが,仮にこれをしなかった場合,旧商法281条,285条,285条ノ4に反する。これは,売上(売掛金)の架空計上が認められないのと同様である。そして,商法32条2項に「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については公正なる会計慣行を斟酌すべし」と規定されていることから,商業帳簿の作成に関する規定である旧商法285条ノ4第2項の「取立不能見込額」の解釈に当たっても「公正なる会計慣行」に従わなければならない。
イ 「公正なる会計慣行」,「斟酌すべし」の各意義・内容等
この「公正なる」とは,営業上の財産及び損益の状態を明らかにするという目的に照らして「公正」という意味であり,上記目的に照らし,妥当かつ合理的と一般的に認められるものを指すと解される。そして,ここにいう「会計慣行」とは既に行われている事実に限らず,新しい合理的な会計慣行が生まれようとしている場合には,それも含まれる。
また「斟酌すべし」とは,公正な会計慣行がある場合は,それ以上に営業上の財産及び損益の状況を明らかにする会計基準があるなど特段の事情がない限り,それに従わなければならないという意味であって,その意味において,法規範性を有するものである。
ウ 企業会計原則及び同注解
この「公正なる会計慣行」に当たるものとして,一般に企業会計原則・同注解が挙げられ,「企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から,一般に公正妥当と認められたところを要約したものであり,必ずしも法令によって強制されないものでも,すべての企業がその会計を処理するにあたって従わなければならない基準である」とされている。同注解18において「将来の特定の費用及び損失であって,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができる場合には,当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする」とされ,また「発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失
については,引当金を計上することはできない」とされている。
エ 「決算経理基準」
また,当時の大蔵大臣の銀行に対する監督権限に基づき,大蔵省銀行局長は,昭和57年4月1日付け蔵銀第901号通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」(以下「基本事項通達」という。)を発出し,その「経理関係」の中において,銀行の決算の基準となるべき「決算経理基準」が定められ,長期信用銀行についても,この基本事項通達を準用する取扱いであった。そして,①原告を始めとする金融機関は,以後この「決算経理基準」に従い決算処理を行ってきたこと(決算経理基準が改正されるごとに,改正後の決算経理基準に従い決算処理を行ってきたということ),②決算経理基準の前身である銀行業統一経理基準(統一経理基準)について,日本公認会計士協会(会計士協会)の銀行監査特別委員会が昭和51年に公表
した「銀行業務統一経理基準及び財務諸表様式に係る監査上の取扱いについて」において,統一経理基準に基づく会計処理は商法32条2項にいう公正な会計慣行に合致しているものとして取扱うとしていたことに照らせば,金融機関の会計処理について,この「決算経理基準」をもって「公正なる会計慣行」に当たると解するのが相当である。したがって,平成10年3月期においては,平成9年7月31日付け銀行局長の一部改正通達によって改正された後の「決算経理基準」(改正後決算経理基準)が「公正なる会計慣行」となるといえる。
(2) 平成10年3月期における「公正なる会計慣行」の内容
ア 早期是正措置導入の意味
平成10年4月以降,長期信用銀行を含む金融機関の同年3月期決算をも対象として,経営の健全性確保のための金融当局による監督手法として早期是正措置が導入され,金融当局が,金融機関に対し,客観的指標である自己資本比率が8パーセント未満の場合,業務改善計画の提出等の是正措置を発動することができる旨定められた。この早期是正措置を実効あらしめるため,平成10年3月期決算から,金融機関は,自己査定基準を策定し,この基準に基づき,貸出金等の資産を回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従い自己査定し,その結果に基づき貸出金等の適正な償却・引当を行い,資産内容の実態を正確に反映した会計処理をすることが求められ,事後的に会計監査や金融検査において,自己査定基準の適正性・正確性,償却・引
当の適正性等について検査されることとなった。
平成6年12月の東京協和信用組合,安全信用組合の破綻,平成7年8月のコスモ信用組合,株式会社兵庫銀行,木津信用組合の破綻が続発するなか,金融制度調査会が平成7年12月22日に答申した「金融システム安定化のための諸施策」において,「金融機関経営の健全性を確保していくための新しい監督手法として,自己資本比率等の客観的な指標に基づき業務改善命令等の措置を適時に講じていく早期是正措置を導入することが適当であり,所要の手当を行い,必要な周知・準備期間を経た上でできるだけ早期に実施に移す必要があり」,「早期是正措置の導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となる。このため,検査・モニタリング体制の整備・充実が必要であるが,金融機関の自己責任原則の徹底
等の観点からは,資産査定は先ず各金融機関自らが厳正に行うことが必要である」と指摘され,また,平成7年9月には株式会社大和銀行ニューヨーク支店での不正経理が発覚し,大蔵省の金融検査・監督等に関する委員会も,同年12月26日,金融行政を保護的行政から市場におけるチェック機能を一層活用する行政へと転換すること及びその中核的手段として金融機関の経営の健全性を確保するため,客観的なルールに基づき経営の早期是正措置の導入を求め,その制度を適切に機能させるためには,金融機関自らの資産内容の的確な把握,監督当局の検査等が不可欠の前提であることを強調するとともに,「金融機関が,資産内容を自己査定し,外部監査によるチェックを受けた上で,その結果及び自己資本の充実度の状況を報告する。当局において,
これをモニタリングし,自己資本の充実度及び自己査定の正確性に関する評定を行う。なお,当局は,自己査定のための統一的な基準を示す。」ことの提言を行った。これらの提言を受けて,平成8年6月21日に成立した金融3法で早期是正措置制度の導入が決定されたものである。
早期是正措置制度の導入に当たり,同制度の具体的内容の骨格並びに適正な財務諸表の作成に関する考え方及び実務指針等を検討するため,平成8年9月30日に大蔵省銀行局長の私的研究会として「早期是正措置に関する検討会」(早期是正措置検討会)が発足し,大蔵省銀行局や同金融検査部を中心に法律学者や経済学者,会計士協会関係者,日本銀行(以下「日銀」という。)関係者,金融機関代表者等が参加して様々な検討が加えられて,同年12月26日に「中間とりまとめ」が公表されたが,その中で「早期是正措置の導入にあたっては,まず金融機関の自らの責任において企業会計原則等に基づき適正な償却・引当を行うことにより,資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提となる。各金融機関が行
う資産の自己査定は,適正な償却・引当のための準備作業として重要な役割を果たすことになる。また,会計監査人においては,財務諸表の適正性についての深度ある監査を行うことが求められる。こうした一連の作業を経て作成された財務諸表が開示されることにより,金融機関経営の透明性の向上に資するとともに,市場規律による経営の自己規正効果が働くことになる。早期是正措置は,上記の市場規律を発揮させていくための補完的役割を果たすものとして位置づけられる」こと,とされており,早期是正措置導入の不可欠の前提として適正な自己査定,償却・引当を各銀行が行うことが予定されていた。
イ 早期是正措置導入を前提とした自己査定基準,償却・引当基準の整備
この「中間とりまとめ」の結果を踏まえて,平成9年3月5日に大蔵省から出されたものが資産査定通達であり,また同年4月15日に会計士協会から出されたものが4号実務指針であり,さらに同月21日に関連ノンバンクに対する貸出金の資産査定に関して資産査定通達の細則として発出されたのが9年事務連絡であり,資産査定通達の内容を全銀協が加盟金融機関用にQアンドA方式で補完したのが全銀協Q&A,9年事務連絡の内容をQアンドA方式で示したのが全銀協追加Q&Aである。また,不良債権償却証明制度は,平成9年7月4日付通達により廃止され,平成9年7月31日付けの銀行法施行規則の一部改正に伴い,改正後決算経理基準が平成10年3月期決算に適用されることとなった。
ウ 改正後決算経理基準の下での資産査定通達等による税法基準の排除
これらの資産査定通達,全銀協Q&A,4号実務指針,9年事務連絡及び全銀協追加Q&A(資産査定通達等)を解釈するに際しては,税法基準をベースとしてはならない。そのことは,以下の①ないし⑦に述べる経緯から明らかである。
① 資産査定通達等の方向性を示した早期是正措置検討会において,償却・引当と資産分類との関係について,「『実質破綻先』については,今の法人税基本通達でいう『債務超過が1年以上に続いてロス額が40パーセントと見込まれる』ケースがこれに含まれると思われる。法人税基本通達によると40パーセントが一応の目処となっているが,35パーセントの場合どうなるか考えると,無税にはならないが35パーセントの場合でも実質破綻ということはあり得る。その場合は,有税になると思うが,現在はこの分類の考え方と税の考え方との関係は,税は横に置いて債権の健全性ということのみから判断していくという仕組みになっている。実際に引当金を積んだときには有税と無税では全然効果が違う,税効果会計はどうなんだという議論は
当然あると思う。ただ,私どもが今申し上げているのは,今の分類の考え方というのは,有税であるか無税であるかということは基本的に外に置いて,それに左右されないで判定をしてみるということである」と説明されている。
② 上記検討会の「中間とりまとめ」においても,「各金融機関が適正な償却・引当の実施を行っていくためには,有税による償却・引当を円滑に進めていく環境整備も必要である」とされ,資産査定通達等に基づく償却・引当には有税の償却・引当も含まれるとしている。
③ 全銀協追加Q&Aにおいては,体力がないノンバンクに対する貸出金の査定は,母体行責任を負う意思がある場合であっても,作成されている再建計画に合理性がない場合には原則として営業貸付金等の査定結果のⅣ分類額を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残額をⅡ分類とすべきとし,再建計画が作成されていないか又は作成中の場合には親金融機関等の収益力等から関連ノンバンクの再建可能性が認められる場合以外の場合は営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金のシェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とすべきとしているところ,この場合のⅣ分類は親銀行による支援を前提とする先に対するⅣ分類であり,仮に税法基準によるとすると無税償却の対象とならないと考えられるのであるが,これが資産査定通達等において全額償却・引
当すべきとされるⅣ分類とされていることから,資産査定通達等においては有税による償却・引当を前提としていると考えられる。
④ 資産査定通達等による自己査定,償却・引当を行うべく「決算経理基準」が改正されたが,貸出金の償却・引当について,上記改正前の「決算経理基準」(改正前決算経理基準)にあった「税法基準」の表現が削除され,改正後決算経理基準は自己査定基準,償却・引当基準により回収不能と判定される額を償却・引当すべきとされた。
⑤ 改正後決算経理基準の導入は,自己査定結果を償却・引当に正しく反映するようになされたものであるが,このことから,税法基準にとらわれていては,商法・企業会計原則に則った処理がなされないとして不良債権償却証明制度が廃止されたように,税法基準にとらわれた処理は商法・企業会計原則に則っているとはいえず,資産査定通達等の趣旨も満たさないものとして排斥されたことが窺われる。
⑥ 平成10年3月期末が目前に迫った平成10年3月20日の時点においても,全銀協が当局と協議のうえ作成した「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」において,改正後決算経理基準における償却・引当と税法上の償却・引当は基本的には無関係である旨明言された。
⑦ 上記⑥の「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」には「破綻懸念先債権に限らず,損失の発生が見込まれる債権については,必要額を引き当てることになる。このような取引先に対し,追加融資を行うか否かは,各行の経営判断であり,経理とは無関係である」とされており,仮に追加融資を行う先であるとしても損失の発生が見込まれる債権については必要額を引き当てなければならないとされている。
要するに,無税償却できない債権についても,改正後決算経理基準に従えば償却・引当をしなければならない場合があるとされていたことは疑問を容れる余地はない。
(3) 決算経理基準を補完する資産査定通達等の周知性,合理性
ところで,基本事項通達により,銀行決算の基準として「決算経理基準」が定められ,その中に貸出金の償却・引当の基準が示され,原告らを始めとする金融機関は,この「決算経理基準」に従って決算処理を行っていた。言い換えれば,「決算経理基準」が廃止されるまで,平成10年3月期決算を含む銀行の決算処理の際の拠るべき根拠規範は,この「決算経理基準」であり,原告も同様であった。
この「決算経理基準」は,平成9年7月31日付けの銀行法施行規則の一部改正に伴い,内容が一部改正されて平成10年3月期決算に適用される旨が大蔵省銀行局長から原告を始めとする金融機関の頭取宛てに通知されている。その主な改正内容は,平成10年3月期決算から自己査定制度が適用されることから,銀行が自己査定基準を作成し,その自己査定結果に基づいて適正な償却・引当をなすべきことや償却・引当のルールについての基本的考え方が示されたこと及び貸出金の評価の欄において,従来,税法に基づき有税・無税によって処理が分かれることが規定されていた部分を丸ごと削除し,これに代わって個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれるかどうかを判
断した上で,その必要額を償却・引当すべき旨の規定を置いたことである。
また,この新しい自己査定制度の開始に伴い,従来「税法基準」による償却・引当を実質的に支えていた不良債権償却証明制度は,平成9年7月4日付け通達により廃止された。それまで,多くの金融機関では,この不良債権償却証明制度において無税償却が認められた限度において,貸出金の償却・引当を行う傾向があったことは事実である(なお,そのような傾向や実務状況が即「公正なる会計慣行」という規範的意味を持ち得るものでないことは後記参照)。しかし,かかる制度が廃止され,それを前提に改正後決算経理基準における償却・引当基準も変更された以上,税法基準と自己の経営体力を適正かつ客観的に図るための会計処理に関連する償却・引当基準とは無関係となったことが明らかである。
以上のとおり,平成10年4月1日からの早期是正措置導入を前提としての各制度の創設,改廃状況を客観的に検討するならば,資産査定通達等は,金融機関の健全性を確保する目的で平成10年4月1日から導入された早期是正措置を有効に機能させるために必要な金融機関の資産内容の査定方法や適正な償却・引当の方法を明らかにしたものであり,それにより資産内容の実態を正確かつ客観的に反映した財務諸表を作成することを目指して策定されたものである。また,それらの内容は,「中間とりまとめ」の考え方を基礎として明確化され,しかも全銀協(全銀協Q&A,全銀協追加Q&A)や会計士協会(4号実務指針)を通して周知徹底が図られている。さらに,改正後決算経理基準は,資産査定通達等の公表を前提に改正され,その内容
は大蔵省から直接原告を含む金融機関に対して公表・送付され,適正な自己査定基準の策定が要請されている。
そして,各金融機関は,平成10年3月期決算における貸出金の償却・引当については,改正後決算経理基準に基づき,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定されなければならないとされた各行の自己査定基準,償却・引当基準に基づき貸倒引当金を計上するという会計基準を採用した。各金融機関の有価証券報告書に記載された平成10年3月期決算における貸倒引当金の計上基準についての表現は,各行によって若干の相違はあるが,内容及び用語の使い方からすれば,いずれも債権について自己査定を行い実務指針に従って貸倒引当金を計上している旨を明記している。
また,金融監督庁は,日銀と連携しながら,平成10年7月7日からいわゆる主要19行(都市銀行9行,長期信用銀行3項及び信託銀行7行)に対して,また,同月30日から地方銀行に対して,同年10月5日から第二地方銀行に対して,それぞれ一斉集中検査・考査を行ったが,それらの検査・考査においては,金融機関等の自己査定と公認会計士等による外部監査を前提に自己査定の正確性,償却・引当の適切性について,また,金融機関等の自己責任原則を前提にしたルール遵守体制,リスク管理体制の整備状況及びその機能発揮状況等について,その実態を把握することなどに重点が置かれていたところ,主要19行から原告及び株式会社日本債券信用銀行を除く主要17行に対する検査・考査結果の概要としては,自己査定基準及び償却
・引当基準とも,その内容の一部に問題があったため大半の銀行に改善を求めたとあるものの,総体としてはそれぞれ資産査定通達及び4号実務指針に対応しており,おおむね妥当であったとされている。
このように,①平成8年6月に金融3法が成立して以降,大蔵省銀行局や金融検査部を中心に法律学者や経済学者,会計士協会関係者,日銀関係者,金融機関代表者等が参加した「早期是正措置検討会」において様々な検討が加えられたうえで,同年12月に「中間とりまとめ」が公表され,これに基づいて平成9年3月5日に資産査定通達が,同年4月15日に4号実務指針がそれぞれ公表されるなど,平成10年3月期決算に向けた準備が進められ,同年4月1日から早期是正措置制度が実施されるまでの間に相応の準備期間が置かれていること,②各金融機関においても,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定すべきとされた自己査定基準,償却・引当基準を策定し,平成10年3月期決算においてこれら基準に基づいて自己査定,償却・引当の作
業を行ったこと,③主要17行に対する検査・考査結果,同期決算に用いられた自己査定基準,償却・引当基準が資産査定通達及び4号実務指針に対応しており概ね妥当であったとされていることにかんがみれば,平成10年3月期決算はあくまでも試行錯誤的なものにすぎなかったとか,貸出金等の償却・引当に関する基準は変更されていなかったとすることは,明らかに不当である。
そして,以上のような資産査定通達等の策定の経緯及び内容に照らせば,資産査定通達等における資産査定の方法,償却・引当方法等は,金融機関の貸出金等の償却・引当に関する合理的な基準であると認めることができるだけでなく,改正後決算経理基準の内容を補充するものとして,商法32条2項にいう「公正なる会計慣行」に当たると解することが相当である。そのうえ,早期是正措置制度は,金融機関が抱えている不良債権を早期に処理し,バブル経済の崩壊で低下したわが国の金融システムの機能回復を図るとともに,市場規律に立脚した透明性の高い金融システムを構築することにより,その安定化,健全化を成し遂げる目的で導入されるシステムであることを考えれば,この早期是正措置制度を有効に機能させるために策定された資産
査定通達等の趣旨に反する会計処理は許されないと解すべきであって,金融機関の貸出金等の償却・引当に関しては,資産査定通達等が唯一の合理的な基準であったと認められる。
(4) 資産査定通達等の規範性
原告らは,各行が自己査定基準,償却・引当基準を作成する際に,当然ながら資産査定通達等に一字一句合わせなければならないとか,これらに記載のない事項を基準化することは一切許されないなどと主張するものではない。問題は,どの程度の幅を超えた場合に,当該自己査定基準,償却・引当基準及びその適用が「公正なる会計慣行」の範囲を逸脱したと評価されるべきであるかということであり,原告らは,被告らが,貸出金の評価について,個々の債務者ごとに,適正な債務者区分・資産分類を行い,それを前提として各分類資産ごとに償却・引当を行うという資産査定通達等の定める基本的枠組みを逸脱するような理屈を作出して,資産査定通達等が許容しないような基準(「特定先基準」等)や償却・引当基準(関連先のⅢ分
類には償却・引当は行わない等)を策定したり,自己査定基準を正しく適用しないような処理(体力の存否,再建計画の合理性の有無等)をしたりしたことは,資産査定通達等で周知,徹底された当時の「公正なる会計慣行」に著しく反するものとして許されないと主張しているのである。
2 税法基準は平成10年3月期における「公正なる会計慣行」であったか
(1) 貸倒償却・引当に関する税法基準なるものについて
貸倒償却・引当に関する税法基準なるものについては,次の①ないし③のとおり整理できる。
① 法人税法33条2項が金銭債権につき評価損の計上を禁止していることから,法人がその有する金銭債権について回収不能を理由に貸倒償却できるのは金銭債権の全額が回収不能である場合に限られ,この場合担保物があるときはその担保物の処分後であること(法人税基本通達9-6-2)
② 一般の貸倒引当金(債権償却特別勘定等を除く)は税法で容認される限度額を必ず繰り入れることとし,その引当率は税法が定める法定繰入率である1000分の3であったこと(法人税法52条)
③ 債権償却特別勘定への繰入れは旧法人税基本通達9-6-4以下で認められる場合には全額繰り入れるものの,有税の場合も繰入れることができるとされていたこと
しかしながら,税法基準は,以下に述べる理由により,平成10年3月期において「公正なる会計慣行」であり得ないものであった。
(2) 税法基準が「公正なる会計慣行」であり得ない理由について
ア 税法基準の目的
そもそも税法基準は,租税収入の確保という政策的観点に立って,税額を計算し,課税の公平を図ろうとする目的で策定されている。すなわち,税法基準においては,税法の目的である租税収入の確保,課税の公平の観点から,損失の計上時期について明確性,統一性が要請されるため,当該事業年度に損失が生じたことが確実と認められるもの(債務の確定になじむ損失又は債権の消滅により生じる損失については,それらが確定したとき)に限定して損失計上が行われるべきものと解されている。
法人税基本通達9-6-2は,貸倒償却できる場合を金銭債権の全額が回収不能である場合に限定し,また旧法人税基本通達9-6-4は債権償却特別勘定の繰入れに関して「債務者に対して追加的支援を予定している場合」には「『事業好転の見通しがない』と判断することは原則として適当ではない」としているが,税法が無税で貸倒償却・引当できる場合をこのように限定しているのは,いずれも損失の計上について確定的なものを求める税法固有の目的に由来するものにすぎない(なお,追加的支援が全く予定されていない場合又は追加的支援が予定されていてもその支援の実効性が認められない場合には事業好転の見通しがないというべきであって,特定先基準とされた債務者はまさにそのような状況であった。)。
しかしながら,本件訴訟は,商法290条に定める配当可能限度額の有無に関する事件であり,商法の計算規定の適用が問題となる事案である。
商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営成績を正しく表示し,もって株主及び会社債権者の利益の保護を図ろうとする目的で策定されているものであるから,税法基準の目的とは明らかに異なる目的で策定されているのであり,税法基準で認められた会計処理方法が商法上当然に適法であるということにはならない。
したがって,税法基準が商法の計算規定上直ちに「公正なる会計慣行」になり得るものではなく,税法基準に基づく会計処理方法が企業の財政状態及び経営成績を正しく表示するという観点から見て,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するかどうかを検討することが必要不可欠である。
イ 委員会報告第5号
被告らは,会計士協会が昭和40年4月6日付けで,監査委員会報告第5号として公表した「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(委員会報告第5号)において,貸倒引当金の計上に関し,「算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合を除いて,除外事項(不適正意見)としないことができるとしている」ことをもって,税法基準が「公正なる会計慣行」であったと主張している。
しかし同報告は,それが公表された当時各企業の有する不良債権額は些少で「一般的にいえば貸倒見積高算定の基準として税法基準を採用している場合にはこの基準によって算出した金額は,適正な見積額を超過する傾向にある」ことをあくまでも前提として,保守主義の観点からこれを容認したにすぎず,税法基準そのものを「公正なる会計慣行」と位置付けたものではない。かえって,委員会報告第5号によれば,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積高に対して明らかに不足していると認められる場合には除外事項(不適正意見)とすることもなるから,これは,税法基準による引当が必ずしも企業の資産状態を正しく反映するものではないことを前提にしている。したがって,同委員会報告を税法基準
が「公正なる会計慣行」であることの根拠とする被告らの主張は失当である。
ウ 改正後決算経理基準
そもそも税法基準が「公正な会計慣行」になり得ないところ,改正後決算経理基準によって,平成10年3月期において税法基準が明らかに否定され,税法基準に基づく会計処理が許されなくなった。
すなわち,改正後決算経理基準は,前記(1)①(貸倒償却できるのは金銭債権の全額が回収不能の場合に限られていたこと)について,担保物の処分後でなくとも「担保の処分可能見込額」を減算した残額を償却する,前記(1)②(一般の貸倒引当金の引当率が税法の法定繰入率である1000分の3であったこと)について,「税法で容認される限度額」ではなく「合理的な方法により算出された貸倒実績率に基づき算定した貸倒見込額」を繰り入れる,前記(1)③(債権償却特別勘定の繰入れに関し,有税の場合も繰入れることができるとされていた)については,回収不能と判定される貸出金等については償却する以外のものについては回収不能額を,最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については債権額から担保の処分可能
額等を減算した額のうち必要額を,それぞれ繰り入れる,という内容に改正され,税法基準は,平成10年3月期決算においては否定され,もはや資産査定通達等との選択適用が認められる会計処理の原則でなくなったというべきである。実際,原告は,平成10年3月期決算の貸倒引当金に関し,決算経理基準の改正に伴い,同期決算から,他の金融機関と同様に,改正後決算経理基準に従い計上している旨を記載し,同期決算における金銭債権の償却・引当に関し,税法基準ではない会計基準によって計上する旨を表明しているのである。
エ 改正後決算経理基準の目的
改正後決算経理基準が,経理基準として税法基準を否定し,個別貸出金の回収可能性の程度・存否で判断する方法に明示的に切り替えた理由は,いわゆる税法基準による会計基準は,早期是正措置を導入した根本理由・目的と矛盾ないし反するものであったからである。
すなわち,平成10年4月から早期是正措置を導入する基礎となった平成7年12月22日付け金融制度調査会答申が「不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできるかぎり早期にその処理に目途をつける必要がある」とし,そのための方策として「ディスクロージャーの推進」,「早期是正措置の導入」を挙げ,かつ,「早期是正措置導入に当たっては,不良債権を勘案した,自己資本比率等の正確な把握が前提となる」と謳っていることから,早期是正措置導入の根本的目的は,不良債権の早期処理の実現及びそのためにそれまでの裁量的行政から透明性のある事後チェック方式へ転換することにあった。
これに対し,税法基準に基づく会計処理こそ不良債権処理を遅延させていた元凶であった。これは,金融機関自らが回収不能と判断したものはたとえ有税でも償却すべきにもかかわらず,税務に重点をおいた償却が結果的に不良債権処理を遅らせたことが指摘(早期是正措置検討会メンバー)されていたこと,そこで税法基準にはとらわれずに,健全性の観点から企業会計原則にのっとった償却を促すことを目的とした早期是正措置の導入を機に,不良債権償却証明制度が廃止されることになったとの指摘がされていたことから明らかである。そこで,不良債権償却証明制度の廃止を前提に,税法基準すなわち大蔵省との折衝による無税認定取得という行政裁量性の強い償却・引当システムという方法を改め,無税・有税にかかわらず,貸出金の回収可
能性の程度・存否の客観的判断による償却・引当システムが採用されることになったのである。
オ 改正後決算経理基準に係る質疑応答
改正後決算経理基準を受け,この改正内容が平成10年3月期から適用されることを前提に,全銀協は,大蔵省と協議の上「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」と題する解説(平成10年3月20日付)を各銀行経理担当部長に配布し,その中で,次のような質疑回答案を示している。
①[質疑事項3.]
決算経理基準「(3)資産の評価及び償却イ.貸出金及び貸出金に準ずるその他の債権の評価(イ)貸出金等の償却」の本文を直接償却の規定と考えると,法人税基本通達9-6-2の規定の趣旨と異なると考えられる。
すなわち,当該規定の「債権額から回収が可能と認められる額を減算した残高を直接償却する」という考え方は,従来からの会計慣行である法人税基本通達9-6-2の規定の「全額」及び「担保処分後」損金経理することができるとの文言に反することになると考えられるが,見解をご教示いただきたい。
[回答案]
決算経理基準における直接償却と税法上の直接償却は基本的に無関係である(ただし,実務的には,当該決算経理基準の但書により,担保処分後に直接償却することができる。)。
②[質疑事項7.]
平成9年3月5日付,大蔵省「資産査定について」中で,「消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,~破綻懸念先とする」とあるが,そのような破綻懸念先に対しても,今後,追加融資等の可能性がある場合においても,債権償却特別勘定を引当ててもよいのか。
[回答案]
破綻懸念先債権に限らず,損失の発生が見込まれる債権については,必要額を引き当てることになる。このような取引先に対し,追加融資を行うか否かは各行の経営判断であり,経理とは無関係である。
③[質疑事項16.]
各行が合理的に算定した貸倒実績率を使用して算定したいわゆる一般貸倒引当金については,税務上も無税として取り扱われるか。
[回答案]
改正後決算経理基準における貸倒引当率と税法上の貸倒引当率は基本的に無関係である。税法基準の限度内であれば,無税扱いされることは従来と同様である。
以上の内容をみれば,当時,全銀協が,決算経理基準と税法基準とは無関係であると認識していたことは明らかであり,平成10年3月期において償却・引当を行った支援先に追加融資を行うことは論理矛盾であるとか,決算経理基準の改正後も税法基準は生きており,これに従った償却・引当も許されていたというような被告らの主張は,失当である。
カ 改正後決算経理基準の導入以前における有税による償却・引当の要請
改正前決算経理基準は,一般の貸倒引当金の引当率に関しては税法が定める法定繰入率である1000分の3とし,債権償却特別勘定の繰入れに関しては「税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする」としていたが,そのような会計処理方法では不良債権問題が遅々として解決されないことから,行政当局等は指針等を示すことにより,各金融機関に対し,その改正前において,有税による償却をすることを求めていた。すなわち,大蔵省銀行局は,平成6年2月8日付けで「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」を公表し,「金融機関が不良債権の実態に即した必要な償却を行うとの趣旨を徹底し,償却の一層の促進を図るとともに,そのための当局の体制についても引き続き充実強化に努める。また,従来,金融機関は,
貸倒れ又はこれに準じる状況にある債権について償却・引当を行ってきたが,最近における不良債権の実態に鑑み,引当制度の運用を改善し,貸倒れには至っていないものの回収に危険のある債権についても,金融機関自らの判断によりリスクに応じた必要な引当が行われるようにする」ことを提言し,有税引当の概念が示され,これを受けて同日付けで「不良債権償却証明制度等実施要領について」と題する通達が発出され,有税引当及び有税直接償却を行うときの取扱いが明らかにされたのである。
このように,平成6年2月時点で金融機関の貸金について,まず商法の計算規定や企業会計原則の観点から償却・引当が必要かどうかを判断し,その次に無税になるか有税になるかを判断するといういわば税法基準という呪縛からの解放が明確にされていた。
その後も,大蔵省は,平成7年6月8日付けで「金融システムの機能回復について」を公表し,「金融機関が,実態に即した決算対応を行い,自己資本の維持・充実等に配意しつつ不良債権について可能な限り前倒処理することを推進することにより,その資産内容を早期に改善し,内外の信頼確保に努めることを促す。また配当についても,横並びや経緯にとらわれることなく,経営実態に即した決定を促す」旨言明し,次いで,金融制度調査会は,平成7年12月22日付けで「金融システム安定化のための諸施策―市場規律に基づく新しい金融システムの構築―」を公表し,「不良債権問題の早期処理は現下の喫緊の課題であり,今後5年以内のできる限り早期にその処理に目処をつける必要がある。上記の不良債権額等の規模は,金融システム
全体としてみれば十分に克服しうるものであり,各金融機関は先ず自助による最大限の合理化努力や早期の引当,償却等の実施により,迅速にその処理を行っていく必要がある」旨を提言している。
このように,平成9年3月期以前においても,有税による償却・引当が求められていたのであり,無税適状にある債権額のみを償却・引当すれば足りるとする会計処理方法が「公正なる会計慣行」であったとまではいえないのである。このことは,以下の関係諸規定からも明らかである。
すなわち,改正前決算経理基準は,金融機関による「貸出金の償却」について「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については,これに相当する額を償却するものとする。なお,有税償却する貸出金については,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と規定されているところ,この規定は,取立不能見込額には有税でも償却しなければならないものがあることを前提としている。また,改正前決算経理基準が,「貸倒引当金(債権償却特別勘定及び特定海外債権引当勘定(租税特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む。)を除く。)は,税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとし,また,租税特別措置法55条の2第7項の規定に係る貸倒引当金相当額を
有税により繰り入れるものとする」とし,「債権償却特別勘定への繰入れは,税法基準のほか,有税による繰入れができるものとする。なお,有税繰入れするものについては,その内容をあらかじめ当局に提出するものとする」と定めていたが,これは,回収不能のおそれがある貸出金等について有税であっても引当しなければならないとしていたことを示している。また,平成6年2月8日の不良債権償却証明制度実施要領通達の一部改正によれば,有税による償却・引当としては,有税直接償却と有税引当があるが,その対象とされる金額は,それぞれ「回収不能と認められる債権について,損失相当額」,「回収不能と認められる債権,最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる債権及び回収に危険のあると認められる債権にかかる損失見込
額」と定義されているところ,これらは平成14年改正前商法285条の4第2項にいう取立不能見込額と同義であるから,決算経理基準は取立不能見込額があれば有税でも償却・引当しなければならないことを規定していることになる。したがって,無税償却・引当のみをすれば足りるという会計処理が,決算経理基準に合致する公正なる会計慣行であったとはいえないのである。
また,不良債権償却証明制度実施要領通達は,平成9年7月4日付け金融検査部長通達蔵検第296号により,「金融機関等をめぐる環境変化等を踏まえ,今後は,金融機関が法人税基本通達等に基づき自ら行うことが適当と考えられる」との理由で廃止されたため,平成10年3月期決算においては,金融機関が自らの責任において,回収不能と認められる債権等について償却・引当を行うことが求められるに至った。
そして,改正後決算経理基準においては,それまでの「税法基準」に基づく償却・引当に関する会計処理の方法を削除し,個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれるかどうかを判断したうえで,その必要額を償却・引当すべきものとし,また,このように税法基準との関係に言及しなくなった改正後決算経理基準における「貸出金の償却」の定義も,有税償却に言及している改正前決算経理基準における「貸出金の償却」の定義も,「基本的には,商法,企業会計原則等に基づき貸出金の償却を行ってきており,定義が変わったわけではない」と解されていたことからすれば,改正前決算経理基準においても税法基準による無税償却相当の債権のみが回収不能と判定されていた
わけではない。したがって,平成9年3月期以前において,税法基準に従い無税適状にある債権のみ償却・引当をすれば足りるとする取扱いが貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」であったことはないというべきである。
キ まとめ
以上のとおり,平成9年3月期以前においても,税法基準は金融機関における貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」ではなかった。
仮に,税法基準が平成9年3月期まで貸出金の償却・引当に関する「公正なる会計慣行」であったとしても,平成9年7月になされた不良債権償却証明制度の廃止及び改正後決算経理基準の導入は,平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度を有効に機能させるための手続整備の一環として行われたことが明らかであるから,平成10年3月期決算においては,早期是正措置制度を有効に機能させるために策定された資産査定や償却・引当のあり方等に関する資産査定通達等の趣旨に沿った会計処理を行うべきであった。また,資産査定通達等が回収不能見込みの債権にも無税償却できないものがあることを前提としていたこと,資産査定通達等が合理的な内容のものであること,そして,各金融機関が平成10年3月期決算において資産査
定通達等の趣旨に沿って策定された自己査定基準,償却・引当基準により決算を行ったことを総合的に考慮すれば,仮に,従来,税法基準が償却・引当の方法として許容されていたとしても,もはや平成10年3月期決算においては税法基準は「公正なる会計慣行」ではなくなったと評価すべきである。
(3) 法人税基本通達9-4-2について
ア 被告らの主張について
被告らは,関連ノンバンクは一般貸出先と異なり,原告らが支援する先であるため破綻がないから関連ノンバンク向け貸出金について償却・引当の概念はなく,当該貸出金についての損失は法人税基本通達9-4-2による合理的な再建計画に基づき当期の支援手段として行われる債権放棄のみであるとし,債権放棄による損失は償却ではなく支援損であると主張している。
イ 債権放棄についての税務処理について
債権放棄は債権者の債務者に対する一方的意思表示により債権が法的に消滅することから,法人がこれを貸倒れとして損金経理していると否とにかかわらず,税務上もその消滅した時点において損金の額に算入するとしているものである(法人税基本通達9-6-1(4))。
ただし,その債権が「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」でなければその債権が実質的に無価値とはいえないことから,そのような債権の放棄は,法人税法37条6項にいう債務者に対する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」(法人税法37条6項)となって,会計上は全額損失等となる性質のものでありながら,税務上は,損金算入が制限されることになる(法人税法37条)。
他方,法人税基本通達9-4-2は,「例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等」「相当な理由があると認められるときは」,債権放棄により供与する経済的利益の額は寄付金の額には該当しないものとして損金算入を認めるものであるが(再建支援の手段としての債権放棄等が含まれることが明確化されたのは平成10年6月1日の基本通達の一部改正による),これは,相手先が「金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」ではないことから,当該債権放棄が相手先に「経済的な利益の贈与又は無償の供与」を行うことになるものの,その債権放棄が「合理的な再建計画に基づくものである等相当な理由があると認められるときは」,債権放棄すること
にそれなりの経済的合理性を有することから,税務上直ちに寄付金として取り扱うことは相当ではないとの趣旨によるものである。すなわち,法人税基本通達9-4-2は,合理的な再建計画に基づき事業が継続し事業継続による収益弁済により回収が見込まれる場合,すなわち,金銭債権が取立不能の状況にはない場合,あるいは仮に一部取立不能だとしてもその回収不能見込額が不明の場合を前提にしているものである。
ウ 金銭債権に関する償却・引当との関係について
被告らは,関連ノンバンク向け貸出金については,償却という概念は存在せず,債権放棄による支援損という概念で考えるべきであると主張するが,支援損という概念は,合理的な再建計画に基づき貸出先の事業が継続され,その結果収益弁済が可能になる場合を想定しているのであるから,当該貸出金につき取立不能ではない状況あるいは取立不能のおそれのない状況を前提とした概念ということになる。
したがって,この前提が成立しない場合,例えば,貸出先の収益弁済が可能となるような合理的な再建計画がない場合には,当該貸出金については取立不能のおそれがあるから,債権放棄による支援損ではなく,償却・引当が必要となる。
そして,金融機関自身の破綻が相次いだこと,平成9年4月に日債銀が関連ノンバンクを支援しきれずに破産せざるを得なくなったこと,同年11月には株式会社北海道拓殖銀行が破綻したこと等を考えれば,貸出先が関連ノンバンクであることの一事をもってその再建計画は合理的である,あるいはその再建が可能であると判断することは許されない。このことは,全銀協追加Q&Aにおいて,関連ノンバンクへの貸出金の資産分類について,親銀行が母体行責任を負う意思がある場合であっても,合理的な再建計画がない場合や,親銀行等の収益力から再建可能性が認められる場合以外には支援損以外のⅣ分類(当該関連ノンバンクの営業貸付金等の査定結果のⅣ分類を貸出金のシェアにより親銀行に割り当てるⅣ分類)が生じるとしていたことか
らも明らかである。
平成10年3月期は,上記の状況であり,原告の関連ノンバンク向け貸出金について,合理的再建計画の有無や原告の収益力から再建可能性が認められるか否かにつき具体的な検討を行うことなく,原告の関連ノンバンクは,原告が支援するから破綻することはあり得ず,支援損の計上しかあり得ない,よって関連ノンバンクについては支援損のみ計上すれば足り,償却・引当をする必要はないとする処理が,「公正なる会計慣行」に基づく会計処理であったとは到底認められないものである。
3 「公正なる会計慣行」(規範)と単なる実務状況との質的相違
(1) 規範的評価と実務状況の乖離
ところで,本件訴訟では,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」(商法32条2項)を構成していたかが争点となるため,ともすれば,①資産査定通達等は「公正なる会計慣行」を構成するか,②平成10年3月期当時「公正なる会計慣行」は複数存在していたのかという規範的評価(法的判断)を飛び越えて,単に当時の各金融機関の決算処理の状況等を検討することによって「公正なる会計慣行」の内容を確定し,これと対比することにより原告の平成10年3月期決算処理の違法性の有無を判断することができるというような誤った考え方に陥りやすい。しかしながら,商法32条2項にいう「公正なる会計慣行を斟酌すべし」とは,ある業界において現に行われている単なる「会計慣行」を参考にせよという意味でない。同条項はあくまで規
範としての「公正なる」会計慣行に従うべきことを要求しているのであるから,単に当時の実務状況や金融機関の決算動向といった生の事実を認定してみても,それだけでは何の意味もない。
本件のような分野における規範と慣行との関係については,目新しい問題のようにみえるが,他の分野の訴訟においては,この問題が激しく議論されてきたばかりか,そのような議論を受けて,既に最高裁判所(以下「最高裁」という。)の立場も明確になっている。そこで,念のため,下記(2)において,規範と慣行を峻別する最高裁の考え方を整理する。
(2) 医療水準論(規範的評価)と医療慣行
規範的評価と実務慣行との本質的相違については,これが裁判上激しく争われ議論されてきた医療過誤訴訟におけるいわゆる医療水準(規範的評価)と医療慣行の関係を検討すれば容易に理解し得るものである。
最判昭和36年2月16日民集15巻2号244頁(東大輸血梅毒事件)は,既にいわゆる東大輸血梅毒事件において,「注意義務の存否は,もともと法的判断によって決定されるべき事項であって,仮に所論のような慣行が行われていたとしても,それは唯だ過失の軽重及びその度合いを判定するについて参酌さるべき事項であるにとどまり,そのことの故に直ちに注意義務が否定さるべきいわれはない」と判示していた。その後,未熟児網膜症に関する医療過誤訴訟が契機となって,注意義務の基準に関して様々な議論が学説上展開されたが,最高裁は,診療契約の「注意義務の基準となるべきものは,診察当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」と再三判示し(最判平成7年6月9日民集49巻6号1499頁,同様の判示とし
て最判昭和57年3月30日裁判集民事135号563頁,最判昭和63年1月19日裁判集民事153号17頁),診療当時の現に行われていた医療慣行とは区別された「臨床医学の実践における医療水準」という考え方を採用していた。そして,最判平成8年1月23日民集50巻1号1頁(医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項と医師の注意義務が争われた事件)は,医療水準(規範)と医療慣行との関係について,「医療水準は,医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから,平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく,医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって,医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない」と判示して医師の過失を否定し原判決を破棄して原審
に差し戻した。
以上から明らかなように,判例法上医師の注意義務の前提となる医療水準は,平均的医師が現に行っている医療慣行と必ずしも一致するものではなく,規範的判断として要求すべき水準として捉えられており,これと具体的医療行為との乖離の程度を検討して注意義務の有無は決せられるとする考え方が判例法上確定している。(最高裁判所判例解説民事編平成7年度〔下〕569頁参照〔上記最判平成7・6・9解説部分〕)。
(3) 盗難通帳による預金の過誤払い事件に対する近時の判例の判断枠組み
また,預金通帳等が盗難され偽造された印鑑等を使って金融機関において預金が過誤払いされている事件が多発し,現在集団訴訟が各地で起こされている。これらの訴訟においても,銀行側の拠るべき規範と銀行実務との乖離が焦点になっている。
判例(最判昭和46年6月10日民集25巻4号492頁)は,当座勘定取引契約による委託に基づく手形金の支払をする場合において銀行に要求される注意義務の水準と現に行われている銀行実務との関係について,「免責約款は,印影の照合にあたり必要な注意義務が尽くされるべきことを前提としているもので,右の義務を軽減緩和する趣旨と解すべきでないことは前叙のとおりであり,そして,ここにいわゆる必要な注意義務は,自己の財産の管理を銀行に委ねている取引先の信頼に沿うものとして,前示のごとく,銀行に対し社会通念上一般に期待されるところに相応するものでなければならない。したがって,現に行われている銀行業務の実情が必ずしもそのまま是認されるものでない」と判示している。
以上のとおり,実務の慣行(状況)は,あるべき規範そのものではなく,定立された規範と現に行われた行為と間の乖離があるかどうかが問われなければならない。上記の各分野における最高裁判決を前提に本件を捉えるならば,平成10年3月期に要求される「公正なる会計慣行」とは何か,資産査定通達等がその内容を構成していたかどうか検討したうえで,平成10年3月期に他行の会計処理がどうであったか(実務慣行)は,原告の会計処理の違法性の有無を決定するものではない。
(4) 被告らの主張に対する反論
被告らは,資産査定通達等は,内容が不明確である,特に,本件で問題となっている支援先に対する償却・引当をいかにすべきかについては,会計基準として実務に耐え得る指針は何ら示されていなかったと主張し,それを理由に資産査定通達等は「公正なる会計慣行」と認められないと主張する。しかし,資産査定通達は,支援先につき「自行として消極ないし撤退方針を決定していない債務者であっても,当該債務者の状況等について,客観的に判断し,今後破綻に至る可能性が大きいと認められる場合は破綻懸念先とする」と規定し,支援先であっても「今後破綻に至る可能性が大きいと認められる場合には破綻懸念先」として原則Ⅲ分類として必要額を償却・引当すべきであること,「実質破綻先」に該当する状況にある場合には原則Ⅳ分類
として全額を償却・引当すべきことを規定している。また,全銀協追加Q&Aにおいても,体力がない(償却前利益によりおおむね2,3年で実質債務超過の解消が不可能な)関連ノンバンクで,母体行責任を負う意思がある場合で,再建計画がある場合(さらには再建計画に合理性がない場合とその他の場合に分けられる。),再建計画が作成されていないか又は検討中の場合のそれぞれについて,資産分類の仕方を明記しており,少なくとも,Ⅳ分類となる資産について「回収不可能又は無価値と判定される資産」であるから,全額を償却・引当しなければならないとの指針が示されていたのである。したがって,支援先についても会計処理の基準として実務に耐え得るだけの指針が示されていたことは明らかである。
被告らは,「金融機関が平成10年3月期から資産査定通達等を参考にしてそれぞれ自己査定基準を策定したとしても,原告ら以外の各金融機関の資産査定通達等の受け止め方と自己査定基準の内容からみれば,原告ら主張の内容の慣行が成立していたとはいえない」と主張し,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」とは認められないと主張する。しかし,平成10年3月期決算において各金融機関は,貸倒引当金の計上について,改正後決算経理基準に基づき自己査定をしたうえで,破綻先債権,実質破綻先債権,破綻懸念先債権,要注意先債権に分類したうえで引当を行っており,金融監督庁の検査によれば,主要17行について自己査定基準,償却引当基準は資産査定通達,追加Q&Aと同様の関連ノンバンク9年事務連絡,実務指針とおおむね
一致していたと認められる状況にある。したがって,平成10年3月期において,各金融機関は資産査定通達等に準拠して償却・引当を行おうとしたことは明らかであり,その処理も概ね資産査定通達等に基づく処理と一致していたことが窺えるのであるから,被告らの主張は事実に反するものである。
被告らは,早期是正措置制度導入前から導入後の経緯をみても,資産査定通達等が平成10年3月期において「公正なる会計慣行」となっていなかったことは明らかであると主張し,導入前について,金融行政当局において,税法基準を否定する旨示達した事実がなく,換言すれば,税法基準による償却引当のみでは不十分であるとは明示しておらず,かつ,有税で償却引当をなすべき基準を明示していないこと,改正後決算経理基準の導入や債権償却証明制度の廃止は,従前の税法基準による償却・引当を否定するものではなかったと主張する。しかし,「決算経理基準」の改正は,それまでの税法基準に基づく償却・引当に関する会計処理の方法を削除し,個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるかどうか,あるいは最終の回収に重大な懸念があり
損失の発生が見込まれるかどうかを判断した上で,その必要額を償却・引当すべきものとしているのであり,金融当局において税法基準を否定する旨示達したとみるのが相当である。
第2 原告が作成した(被告らが作成に関与した)自己査定基準,償却・引当基準の違法性(「公正なる会計慣行」違反)
1 自己査定基準,償却・引当基準の内容の違法性
(1) 特定先基準の違法性について
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙別添「特定関連親密先自己査定運用細則」(自己査定運用細則)により,日本リース関連会社その他事業推進部長が指定する先についてこれを「特定先」と位置付け,償却・引当の前提となる債務者区分について,当該貸出先の業況,財務状況あるいは返済状況の如何に関わりなく,「正常先」又は「要注意先」とした(以下このような債務者区分の設定を「特定先基準」という。)。そして,債務者区分を正常先又は要注意先とした場合は,当該先に対する資産分類は原則として非分類又はⅡ分類とされることから,すなわちその先に対しては償却・引当をしないことを意味することとなる。したがって,仮にこの「特定先基準」を認めれば,事業推進部長が特定先と認定しさえすれば,その先は,その経
営実態と関係なく正常先ないし要注意先となり,原則的に償却・引当が不要ということになる。
しかし,平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度は,金融機関が商法の計算規定等に基づき自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することを前提とするものであるが,償却・引当と連動している債務者区分を当該先の経営状態と関係なく経営者等の一存で決めることができるとすることは,すなわち償却・引当額を恣意的に増減することを認めることにほかならず,会社の財産及び損益状況を正しく表示した財務諸表の作成を求める商法の計算規定に反するものである。
特定先基準は,原告らが支援方針を決定している限り支援先は破綻する可能性がなく,したがって貸倒損失が生じないものであるから,貸倒れによる損失見込み額としての償却・引当の計上が不要であるとの理屈によるものである(支援ドグマ)。しかしながら,貸出先が事業を継続できるか否かは基本的には当該事業の収益力にかかるものであり,当該事業の収益力がなければ弁済原資となるべきキャッシュフローが生み出される状況にないのであるから,当該貸出先に対する貸出金が回収不能あるいは回収不能に陥るおそれは客観的に大であるというべきであって,支援方針を決定しているからといって支援の内容に客観的な実効性がなければ事業の収益力は何ら改善されるものではない。したがって,事業推進部長が特定先と認定するだけで,そ
の先の経営状態と関係なく,その先に対しては償却・引当を不要とすることが公正とはいえないことは明らかである。要するに,被告らは,特定先基準なるいわば「魔法の杖」を使って,必要な償却・引当を回避したものであり,これは,まさに経営者による恣意的な経理操作(粉飾経理)にほかならない。このように特定先基準は,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」に関する規定の解釈基準となる資産査定通達及び実務指針に反し,到底一般に公正妥当と認められる会計処理の基準であるとはいえないものである。
被告らは,「不良債権償却証明制度等実施要領について」において,「債務者に対して追加的支援を予定している場合」には「『事業好転の見通しがない』と判断することは原則として適当ではない」としていることを理由として,原告が支援を予定している先については事業好転の見通しがないとはいえないのであるから取立不能のおそれがないと主張する。
しかしながら,上記実施要領は,法人税基本通達9-6-4に基づく債権償却特別勘定の繰入れに関する規定であるから,そもそも実施要領の記載は,旧商法285条の4第2項の取立不能のおそれに関する解釈基準とはなり得ない。そのうえ,同記載から,そこでいわれている追加的支援とは事業を好転させる可能性があるものが前提となっていることは明らかである。しかし,原告が特定先と位置付けた債務者は,いずれも追加的支援が全く予定されていないか,あるいは追加的支援が予定されていても,その支援の実効性が全く認められないものであったから,同記載を根拠として,原告が支援方針であることのみをもって取立不能と認識する必要がなかったとするのは不当極まりない。
(2) 決裁事由10項ただし書の違法性について
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」記載の決裁事由10項ただし書(決裁事由10項ただし書)により,「『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼動処理を本体と一体で行う会社については『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」と定めるところ,その趣旨は,関連ノンバンクの関係会社は関連ノンバンクではないものの,原告が関連ノンバンクと一体として不稼働資産処理を行おうと考えている場合には,当該関係会社を単体として評価するのではなく,関連ノンバンクと一体のものとして考え,債務者区分を関連ノンバンクとするとともに,資産分類についても一体処理するとした関連ノンバンクに適用した資産分類に関する考え方と同様の考え方を当
該関係会社にも適用するというものである。そして,原告は,関連ノンバンクであるエヌイーディーにおいて当期債権放棄額をⅣ分類とし,残額をⅢ分類としたのに準じ,関連ノンバンクではない青葉エステート外エヌイーディーの関係会社を関連ノンバンクと債務者区分したうえで,これら関係会社向け貸出金につき全額Ⅲ分類とし,かつ,償却・引当を一切しなかった。
原告及びエヌイーディーは,平成6年3月期からエヌイーディーグループの再建計画を策定・実施し,その中で青葉エステート等のエヌイーディーの不良債権の受皿会社を清算する予定であったが,エヌイーディーの収益力の低下から,対外金融機関説明等を考慮し,エヌイーディー本体に対する債権放棄を優先させた結果,上記再建計画に盛り込まれていた関係会社の清算が実現できないまま平成10年3月期に至ったものであり,これら関係会社は,後記のとおり,平成10年3月期において,資産査定通達あるいは4号実務指針にいう実質破綻先であった。
そもそも,資産査定通達は,「資産査定とは,金融機関の保有する資産を個別に検討して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分することであ」るとして,資産査定においては,貸出先ごとに個別に検討して債務者区分を行ったうえで資産分類をすることを予定していることからすれば,関連ノンバンク等の関係会社を本体と一体として資産査定することは,同通達の趣旨に反するといわざるを得ない。しかも,関係会社とはいっても,それは本体の関連ノンバンク等とは別個の会社であって,個々の会社に対する原告の貸出金の額や担保の状況,返済状況等が全て異なっていることからすれば,それぞれの営業実態等を考慮,検討して資産査定すべきであり,関連ノンバンクの関係会社であることを理由に本体と一体として査定す
ることは合理性を欠くものといわざるを得ない。したがって,決裁事由10項ただし書は合理的な会計処理とはいえない。
また,金銭債権につき取立不能と見込まれるときは,その見込みを正確に反映した会計処理をすることが必要であり,これを取立不能ではないとする会計処理をすることは,売上(売掛金)の架空計上あるいは棚卸資産の架空計上をするのと同様であり,そのような会計処理が許されないのは当然であるところ,決裁事由10項ただし書は,関連ノンバンクの関係会社として不稼働処理を一体として行うとの一事をもって取立不能の見込みがあるか否かの検討を行わないとするに等しい規定であり,このような意味においても,同ただし書が合理的なものといえないことは明らかである。
(3) 「関連ノンバンクにかかる自己査定運用規則」(自己査定運用規則)※7なお書の違法性
原告は,自己査定運用規則※7なお書において,再建計画が作成されていない関連ノンバンクである第一ファイナンスについて「既に損失が確定しているとみなされる部分」のみをⅣ分類とし,損失が見込まれるものであってもそれが確定していないといえる部分はⅣ分類と査定していないと定めた。
第一ファイナンスは,最終的には清算を予定していた会社であり,清算に伴う損失が見込まれる状況にあったから,当然,その損失見込額全額をⅣ分類とすべきであった。にもかかわらず,原告は,清算手続がなされていないから損失が確定していないとの理由でⅣ分類としないこととしたのであるが,資産査定通達によれば,「回収不可能または無価値と判定される資産」であるⅣ分類は,「その資産が絶対的に回収不可能又は無価値であるとするものではなく,また,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,査定基準日において回収不可能又は無価値と判定できる資産」とされているのであるから,そのような理由でⅣ分類としないことが許されないことは明らかである。
なお,税法基準は,損失の計上について確定を要するとしているが,同基準は,租税収入の確保,課税の公平の観点から定められているものであるから,企業の財政状態及び損益状況を正しく表示しようとする商法計算規定に当然に整合性を持つものではなく,平成9年7月の決算経理基準の改正により税法基準が否定されたのであるから,税法基準を口実に,清算手続が終了していないという理由で損失見込額を取立不能見込額として計上しないとすることは許されない。
(4) 「経営支援実績先」との債務者区分を設け原則Ⅱ分類としたことの違法性
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙記載の決裁事由5において,「当行が経営支援を行ってきた先で,支援完了した先については,業況は正常に復しているものの,当行は引き続き特別の注意をもって管理を行っており,従来同様の当行スタンスを継続していることから,当該先の債務者区分は『経営支援実績先』として区分するものとした。資産分類については,原則Ⅱ分類とする」と規定した。
しかし,原告のいう支援完了した債務者のなかには,単に自転可能となっただけの債務者も含まれており,そのような債務者には,償却前利益で概ね2~3年程度で実質債務超過が解消できるとはいえない(体力がない)債務者も存在していた。また,「当行は引き続き特別の注意をもって管理を行っており,従来同様の当行スタンスを継続している」ことのみから,このような債務者について再建可能との判断ができるわけではない。したがって,原告が「経営支援実績先」との債務者区分を設け原則Ⅱ分類としたことは資産査定通達等に反するものである。
2 自己査定基準の策定目的の違法性
本来,自己査定基準は,当該金融機関の資産状態を正確に査定することを目的として策定されなければならないが,原告の策定した自己査定基準は,原告の資産状態を正確に把握するために策定されたものではなく,要償却・引当額を実態より圧縮することを目的として策定されたものである。
すなわち,被告らは,国際業務維持の目安となる自己資本比率8パーセント維持を目的として,原告の資産の実態とは関係なく,要償却・引当額を自己資本比率8パーセントが維持できる範囲内に圧縮するために自己査定基準を策定したものであり,それが,金融機関の経営の健全性を確保するため客観的なルールに基づき経営の早期是正を促すという早期是正措置の趣旨・目的,またその前提として金融機関が自らの財務内容を正確に資産査定するという自己査定制度の趣旨・目的に反することは明白である。このことは,以下に述べる自己査定基準の策定経過から優に認めることができる。
(1) 平成8年当時における自己査定基準及び償却・引当基準の検討状況等
まず,被告らは,平成8年8月30日の常務会において,自己査定基準及び償却・引当基準を事業推進部及び総合企画部に策定させることを決定したが,その時点において,被告らは,原告の要処理不稼働資産が1兆円を超える額に達していること,原告の要処理不稼働資産処理原資が十分ではないことを知悉し,今後策定される自己査定基準,償却・引当基準により要処理不稼働資産額が正確に反映されることになれば,原告らは自己資本比率8パーセントを維持することが困難となりかねないことを認識していた。したがって,自己査定基準,償却・引当基準の策定に当たっては,原告の資産状態を正確に反映する自己査定基準,正確な要償却・引当額を算出する償却・引当基準ではなく,要償却・引当額を可能な限り圧縮することのできる自己査定
基準,償却・引当基準を策定することが必要であると認識していた。このことは,Fが,上記常務会において,「早期是正措置の為の資産の自己査定については,プロジェクトチームを作って対応していくということであるが,実質的には多額に抱えてしまっている不稼働資産をどの様な形でその自己査定の中で考えていくかという,やや実態論が片方でより重要となる。その点は十分に認識しておく必要がある」と発言していたこと,同月19日の常務会において「今後,行政指導で自己査定が必要となっていくが,それを実態とどう調整していくかが非常に重要である」と発言していたことから十分に窺える。
その後,事業推進部は,前記の趣旨の自己査定基準を策定する前提として,原告の不稼働資産実態額及びそれを前提とする要処理額の把握を進めたが,その結果,原告の関連親密先である長銀リース,エヌイーディー,ランディック,第一ファイナンス,平河町ファイナンス,ジャリック,日本リース等に関して,平成8年の大蔵省検査において,Ⅲ分類5139億円及びⅣ分類1961億円の合計7100億円と査定されたが,その実態額はⅢ分類848億円及びⅣ分類1兆1626億円の合計1兆2474億円であり,他方,平成9年3月期及び平成10年3月期における関連親密先の不稼働資産処理の原資が約1500億円しかなく,不稼働資産の実態額が正確に査定されるような自己査定基準を策定し,それに基づいて自己査定を実施した場合は
,多額な償却・引当不足の表面化が予想される状況であった。Fは,平成8年10月29日に,Dは,同年11月11日に,いずれもHの説明により,上記状況を認識した。
事業推進部は,前記イの状況を前提として自己査定基準の内容を検討し,①関連親密先と一般先の基準を区分することにより,関連親密先の要処理分類額の圧縮を最大限はかり,自己資本比率の国際基準8パーセント,国内基準4パーセントを達成する,②Ⅲ分類基準の弾力化及びⅢ分類引当の段階化により償却・引当の軽減・平準化を図るという方針のもと,関連親密先に関しては,原告らが支援している先及び支援する方針としている先は,その業況等と関係なく債務者区分は要注意先,資産分類は原則Ⅱ分類とし,償却・引当はゼロとする,ただ当期支援分のみはⅣ分類とし全額償却するという基準を考案した。その基準は,関連親密先のⅣ分類を支援3社(長銀リース,エヌイーディー,ランディック),第一ファイナンス及び受皿会社9社のみ
とし,実態に則して査定すれば多額なⅣ分類査定が出ると思われる日本リースその他に対する貸出債権は全てⅡ分類とするものであった。さらに,受皿会社9社のⅣ分類についても,その償却・引当を適宜先送りする可能性を探ることが考えられていた。なお,事業推進部としても,①支援計画がある先(長銀リース,エヌイーディー,ランディック)について,支援計画により将来償却が明らかなものをⅢ分類とせずⅡ分類とすること,②エル都市開発,日比谷総合開発,長ビルの含み損をⅡ分類とすること,③第一ファイナンス及び受皿会社9社については含み損,損失額が確定していないという理由で償却・引当を先送りすること等には問題があることを認識していた。
(2) 平成9年2月7日の常務役員連絡会
D,Fらは,平成9年2月7日の常務役員連絡会において,総合企画部から,新規発生見込みを含めて今後の要処理不稼働資産見込額が最低でも7000億円から1兆円に達すること,早期是正措置の導入により平成9年度以降はⅢ分類及びⅣ分類は単年度での適正な償却・引当(従来と同様であればⅢ分類は50パーセント,Ⅳ分類は100パーセント)の実施が不可避であるところ,株価が1万8000円から2万円で推移すると仮定した場合,自己資本比率8パーセント,有配維持を前提とする限り,平成10年3月期の不稼働資産処理可能額は3000億円ないし5000億円にとどまらざるを得ない旨説明を受け,その際,上記被告らは,自己査定基準,償却・引当基準により算定される要償却・引当額について不稼働資産処理可能額の範囲
に圧縮する必要性を具体的に認識した。
(3) 平成9年度上期における自己査定トライアル(試行)の状況等
原告において,平成9年度上期において自己査定トライアルを実施する予定でいたが,この自己査定トライアル結果が本番自己査定結果をほぼ拘束すると考えられていたことから,事業推進部は,平成9年4月ころから,要償却・引当額を可能な限り実態より圧縮できる自己査定トライアル用自己査定基準,償却・引当基準を模索した。しかし,平成9年度から平成11年度までの3年間の不稼働資産処理財源を合計5000億円とする中期計画について,早期是正措置導入時の平成10年3月時点において,関連親密先だけで約1800億円の償却・引当不足が出るものと見込まれていた。
(4) 自己査定体制検討プロジェクトチームにおける最終答申等
D,F,H,Gらは,平成9年5月9日,総合企画部作成「97年度リスクアセット,決算・BIS比率,不稼働処理運営について」と題する資料に基づき,平成10年3月期の不稼働資産処理及び決算方針に関する協議をしたが,その結果,同期における関連親密先の不稼働資産の処理可能額は1994億円と想定されること,にもかかわらず同期の要償却・引当額は,最も甘くした債務者区分及び資産分類を前提として破綻懸念先のⅢ分類は12.5パーセントの引当,実質破綻先のⅢ分類は25パーセントの引当,Ⅳ分類は100パーセントの引当という償却・引当基準を適用しても合計2838億円までしか圧縮できず,関連親密先の不稼働資産処理可能見込額1994億円を844億円超過することから,要償却・引当額が上記1994億円
に収まるような自己査定基準,償却・引当基準を策定することを決定した。
検討チームは,上記方針を踏まえて,最終答申を作成したが,更に要償却・引当額を圧縮するため関連親密先のⅢ分類について償却・引当をしないこととした。そして,D,E,F,C,Bらは,平成9年5月23日の常務会において,上記最終答申を了承した。
(5) 自己査定トライアルの第一次集計結果と検討状況等
その後,自己査定トライアルの第一次集計速報値がまとまった平成9年9月1日時点において,F,G,Hらは,①基本的には自己査定結果に基づく償却・引当額を本番実施時において同トライアル結果より大幅に減らすことは不自然・不可能であること,同トライアルの結果が平成10年3月期の結果を事実上決めてしまうことになること,よって,同トライアル結果が本番実施時の最低ラインであり,同トライアル結果についても事実上償却・引当予算から逆算的にⅢ,Ⅳ分類数字を決めざるを得ないこと,②第一次集計値を前提として,関連親密先のⅢ分類にも50パーセントの償却・引当を行う,あるいは関連親密先のⅢ分類には償却・引当を行わないという二種類の償却・引当基準により試算をすると,Ⅲ分類及びⅣ分類の償却・引当合計額
は,前者は5613億円,後者は3344億円となり,おおむね平成9年度処理予定額5000億円の範囲内に納められる水準になっていること,③しかし,関連親密先の自己査定基準・方法等にはそれなりの無理をしていること,④同トライアルでは,事業推進部所管先においてかなり無理をして額を圧縮しているため,今後他行動向,会計士のスタンスによって本番の際には修正せざるを得ない可能性もあること,⑤関連親密先について,大蔵省関連ノンバンク通達に基本的には準拠しているものの,原告個別基準もそれなりに使って査定額の圧縮を図っている,各行ともある程度関連親密先については弾力的な考え方で対応していく見込みであるが,原告の場合相当自主裁量性の強いものとなっておりこのあたりが会計士に認められない可能性が十分あり
得ること,⑥原告の自己査定基準における債務者区分については,原告独自に「特定先」という区分を設定したこと,関連ノンバンク通達を適用するに当たり体力のない先を設定したこと,関連ノンバンク通達を適用するに当たり体力のない先を体力ありとして区分したこと等に問題があること,⑦その「特定先」区分設定により,要処理不稼働資産額を圧縮した先は,ランディック子会社(本来であれば一般先に準じて査定),日比谷総合開発・エル都市開発(本来であれば一般先に準じて区分,その場合は破綻懸念先あるいは実質破綻先に分類される可能性大),受皿9社(本来であれば一般先に準じて区分,その場合は破綻懸念先または実質破綻先に分類される可能性大)であること,⑧日本リースについては関連ノンバンク通達の適用を恣意的に行い,
本来「体力がない」関連ノンバンクであるにもかかわらず,事業会社の含み損を考慮せず,リース資産の含み損益の評価だけで「体力のある」関連ノンバンクとしたこと,⑨「特定先」については赤字・含み損を査定対象から除外したこと等の説明を受け,これを認識した。また,同トライアルでは,関連親密先のⅢ分類については,関連ノンバンクとして倒産リスクがない,との理由により償却・引当を行わないとしていた。
この償却・引当基準と関連親密先のⅣ分類は原則として当期支援分のみとするトライアル用の自己査定基準を併用すれば,関連親密先の償却・引当額は,当期支援額を調整することにより原告の償却・引当原資の多寡に合わせて自在に圧縮できることとなったのであるが,そのような基準が客観性を持ち得るはずがないものであった。
(6) 上記(1)ないし(5)の経過に係る原告の自己査定基準策定の目的等
以上の(1)ないし(5)の経過にかんがみれば,原告の自己査定基準及び償却・引当基準が,原告の資産状態を正確に反映する目的ではなく,要償却・引当額を実態より圧縮し,原告の償却・引当可能額に納めることを目的として策定されたものであることは明らかである。被告らは,この一連の過程を,事業推進部が単にシュミレーションしていたに過ぎない旨主張しているが,そもそも,原告の資産状態を正確に反映する自己査定基準,償却・引当基準を策定しようとしていたのであれば,上記のような数次にわたるシュミレーションなどする必要がない。その上,上記のような経過にかんがみれば,そのシュミレーションの目的が,可能な限り要償却・引当額を圧縮することにあったことに疑問を容れる余地はない。
(7) 被告らの主張に対する反論
被告らは,平成10年3月期において税法基準によることが認められていた,関連ノンバンク等支援先については償却・引当という概念が成立せず,単に支援損を計上すれば足りたという主張をしているが,上記(1)ないし(5)の経過をみると,当時,被告らがそのような考え方に立っていたとは到底認められない。当時,作成された各種資料には,大蔵省等が示した資産査定通達等と外形的な整合性を取りながら,実態より要償却・引当額を圧縮できる基準を策定しようと組織全体で腐心していた状況が顕著に窺えるのに,当時,被告らが,税法基準に従えば足りると考えていたことを窺わせる記載は皆無である。したがって,被告らの主張は,本件訴訟開始後に,始められたもので,原告の自己査定基準の策定当時,被告らが,税法基準で足りるとする
認識を有していたという主張は全く根拠がない。
また,原告内部の当時の資料において,財源効率の追求の観点から無税償却の積み上げを図るものの,有税引当も必要であるとして無税引当見込額のみならず有税引当見込額も試算していること,平成10年3月期の連結利益についてシミュレーションされているが,その中に,連結当期利益(有税処理2500の税効果考慮後)といった記載があることから,被告らが,平成10年3月期決算において,回収不能の見込みがある場合には無税償却できるか否かにかかわらず,償却・引当しなければならないこと,換言すれば,税法基準は回収不能見込の判断基準としては不十分であることを認識していたと認めるのが相当である。
第3 原告らの平成10年3月期会計処理による償却・引当不足額の発生と配当可能利益の不存在
1 日本リースについて
(1) 日本リースの状況
被告らは,日本リースに適用した「経営支援実績先」との債務者区分は,対象企業は,原告の重要な取引先であるが損益支援を実行した実績先であるから「損益支援が終了したから原告の手を離れた」と考えることはあり得ず,むしろ将来にわたり,資金繰り面,人事面,営業面,経営面の支援を継続するなど,なお「特別の経過観察」を必要とする先であるとの考え方から設けられた区分であるから,合理的であると主張する。しかし,そもそも債務者区分は資産分類の前提としての作業であり,貸出金等の価値の既存度合いを測るためのものであって,特別の経過観察を必要とする先か否かといったことを管理・把握するため設けるものではないのであるから,「経営支援実績先」との債務者区分を設けたことには,全く,合理性はない。
被告らは,①日本リースの実態として,原告による平成6年度末及び平成7年度末の損益支援の結果,その含み損部分に見合う借入金の利払いについては,本業の利益でカバーし,実態利益は,平成9年3月期175億円,平成10年3月期182億円となり,期間損益が黒字決算に復していること,②年間230億円の利益を挙げるための計画が具体化しており,本業の収益による不稼働資産の処理が進むとみられていたこと,③キャッシュフローが順調であり,平成9年11月の金融危機も原告の支援(損益支援はもとより,追加貸出等の支援等)なしで乗り切るなど,200近い金融機関からの借入金につき約定返済に一切延滞がないこと,④平成9年秋に他のリース会社と同様に,一時的に抑制したリース営業も,平成10年4月から再び増加
する計画を立てるなど活発な営業活動を展開していたこと,⑤子会社の日本リースオート等の上場によるキャピタルゲインの獲得が見込まれたこと等を理由に,全銀協追加Q&Aの「自力で再建の見通しが立たない」という要件には該当せず,「体力」があると判断して,同社向け貸出金をⅡ分類と査定したことが妥当であったと主張する。
しかし,日本リースには,支援終了後も7300億円の不稼働資産が残存し,うち約6500億円が回収不能見込みであり,しかも,このような不稼働資産を処理する財源は日本リースには存在していなかった。また,被告らが主張する日本リースの実態利益について,金利低下による偶発的要因の占める割合が多く,他方,同社は当時リース営業を抑制しており,将来的には収益が先細る状況にあり,日本リースに自転力があったとは到底いえない状況であった。さらに,日本リースは,平成9年11月の金融危機において,資金ショートを起こす危険が生じており,日本リースは,他行との交渉により,折返しの融資を確保したが,その理由は,原告及び日本リースが他行に対してその実態を隠ぺいしたことによるものであって,これが明らかとな
れば,当然,資金繰り破綻を生ずることが予想された。なお,日本リースの平成10年3月期における不良債権残高(回収不能の営業貸付金額)は,7229億円に達し,同社が自力で再建できる見込みは全く存在しなかった。
(2) 日本リースの償却・引当不足額
日本リースに対する貸出金2556億8000万円については,788億4400万円がⅣ分類となり,残額である1768億3600万円がⅢ分類となり,少なくともⅣ分類である788億4400万円の償却・引当を行わなければならなかったところ,全く償却・引当をしていないから,788億4400万円の償却・引当不足が生じているものである。
2 エヌイーディーについて
(1) 原告の償却・引当処理と問題点
原告は,エヌイーディーにつき自己査定運用規則により,「体力のない」関連ノンバンクであるが「合理的な再建計画が存在し,当行が母体行責任を負っても再建の意思を有する場合」に該当するとし,「経営の意思」により決定されている支援予定額(債権放棄)をⅣ分類とし,その金額のみを平成10年3月期の償却・引当額とした。なお,被告らは,支援ドグマを主張し,原告が策定したものであるから当然に再建計画に合理性があると主張するものであるが,再建計画は客観的に合理性のあるものでなければならないのは,自己査定運用規則が示すとおりである。
(2) 平成10年3月期に策定された再建計画に合理性がないこと
ア 平成10年3月期に当初計画を遥かに下回る額しか債権放棄が実施されなかったこと
原告が平成6年に策定したエヌイーディーの再建計画によれば,平成6年3月期から平成10年3月期にかけて支援総額1900億円(支援内容は債務免除等による損益支援)を実施するものであったが,平成9年3月末までに原告が支援(債務免除)した額は合計1051億円に止まり,当初計画に設定された総額との差額849億円が平成10年3月期において支援に必要な残額ということになる。
ところで,当初計画の実施後は残存要処理767億円の見込みであったが,大幅な地価下落によるロス率の増加,新規延滞の発生により2924億円のロスが残る見通しとなったことから(要するに,エヌイーディーの収益状況あるいは財務状況が当初計画の策定時点よりもさらに悪化したということ),平成10年3月期前に当初計画の見直しが行われ,その結果,支援期間を平成6年3月期から平成14年3月期までの9年間,支援総額を当初計画の1900億円から4001億円(うち1051億円は上記したとおり支援実施済み)に修正する旨の再建計画(以下,この修正後の再建計画のことを「修正計画」という。)が策定された。ただ,修正計画は国税庁の承認を得られなかった。
修正計画によれば,平成10年3月期に349億円を支援するというものであったが,しかしながら,同期に実施された支援額(債務免除額)は201億円に止まった。
すなわち,当初計画によれば平成10年3月期の必要な支援額は849億円残っていたにもかかわらず,しかも当初計画の策定段階と比べてエヌイーディーの収益状況あるいは財務状況がさらに悪化しているにもかかわらず,平成10年3月期での支援額(債務免除額)は201億円に止まったものである。
当初計画が国税庁の承認を得たことから「合理的な再建計画」であったことを前提とする限り,修正計画は,当初計画で支援に必要な残額849億円を平成10年3月期に実施することを前提としていないものであるから,それ自体不合理であることを示すものである。
イ 修正計画の支援予定額と実際の予定支援額とは異なるものであったこと
また,修正計画によれば,平成10年3月期ないし平成14年3月期の5年間に亘り2950億円を支援する内容であり,その支援額が経済合理性から税務上寄付金認定を受けない必要かつ相当額として国税庁の承認を得ることを意図していたが,実際には,上記5年間で1300億円の支援額しか予定していなかったもので,それ自体修正計画が実際には実行不可能で不合理なものであることを示すものにほかならない。
そもそも,修正計画は,「エヌイーディーは存在意義も無いし,経営状態も余りに酷い。できれば,直ぐにでも投げ出したい会社だ。けれども親である長銀が,子であるエヌイーディーを投げ出すと,長銀自体の信用にかかわる。だから,当面は,処理を先送りするしかない。ついては,無税償却の枠だけは確保しておかないといけない」ということで作成されたものであり,「長銀の無税償却を国税当局に認めてもらうために策定されたものであり,エヌイーディーの再建を目的とした合理的計画」ではなかったのである。
ウ 修正計画の実行によっても自転しないものであったこと
さらに,「98/3からの支援5か年計画(暫定)で3000億円の処理を実施した後でも最終利益は10億円程度の赤字。不良債権の処理が大半引当方式であり未引当の固定化債権が650億程度残り当該資産の金利負担を賄えない状況」であるとしているとおり,修正計画どおりに5年間で3000億円近い支援が仮に実行されたとしてもなお当期利益ベースで黒字化できる状況になかったものであって,しかも「再建計画5カ年計画表(収支計算)」(甲151の添付資料8の1)では「投資育成収益」として毎期30億円を見込んで計上しているものであるが,上記常務会資料にあるとおり「今後は店頭市場の低迷もあり20億円の確保は非常に厳しい水準」とされていた。
エ 合理的な再建計画ではない場合の具体的な償却・引当不足額について
以上アないしウのとおり,エヌイーディーの「再建計画に客観的な合理性が認められない」のであるから,「当該支援対象ノンバンクの営業貸付金等のⅣ分類額を貸出金シェアによりⅣ分類とし,残額をⅢ分類とする」こととなり,その結果,原告のエヌイーディーに対する貸出金1715億8500万円のうち,755億9500万円がⅣ分類となり,少なくとも同額の償却・引当を行わなければならなかったところ,実際には201億8000万円について償却・引当をしただけであるから,その差額554億1500万円の償却・引当不足が生じている。
3 エヌイーディーと一体的処理基準(決裁事由10項ただし書)を適用した個社群について
(1) 青葉エステートについて
原告は,平成9年12月29日付け回議用紙「自己査定運用細則ならびに細則制定の件」記載の決裁事由10項ただし書により,「『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼動処理を本体と一体で行う会社については『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」と定め,関連ノンバンクであるエヌイーディーにおいて当期債権放棄額をⅣ分類とし,残額をⅢ分類としたのに準じ,関連ノンバンクではない青葉エステート外エヌイーディーの関係会社を関連ノンバンクと債務者区分し,これら関係会社向け貸出金につき全額Ⅲ分類として,かつ償却・引当を一切しなかった。
前記のとおり,原告は,決裁事由10項ただし書を制定し,関連ノンバンクでないエヌイーディーの不良債権受皿会社を関連ノンバンクなる債務者区分とすることにより,取立不能額の分割償却あるいは計画償却を図ったものであり,損失の計上について人為的な操作を図り,経営者による意図的な経理操作(粉飾経理)を実施した。
青葉エステートは,平成8年3月末に46億3200万円,平成9年3月末に51億0300万円のいずれも大幅な経常損失を計上し,かつ従業員は全くなく,平成10年3月期において,事業継続の可能性が全くない状況であり,資産査定通達及び実務指針にいう実質破綻先に当たるものである。
よって,青葉エステートにつき,227億6100万円の償却引当不足が生じているものである。
(2) ユニベスト,グラベス,コーポレックス,プロクセル及び日本ビゼルボ(ユニベスト外4社)並びにエクセレーブファイナンスについて
ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスは,いずれも売上が皆無又は皆無に近い状況であり,平成9年3月期に大幅な経常損失を計上しており,かつ,従業員は全くなく,会社の実体すらない状況で,平成10年3月期において,資産査定通達にいう「実質破綻先」に当たるものである。
よって,ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスについては,償却・引当不足が生じていた。すなわち,ユニベストにつき73億7300万円,グラベスにつき31億8700万円,コーポレックスにつき13億5600万円,プロクセルにつき5億9600万円及び日本ビゼルボ1億3100万円並びにエクセレーブファイナンス400億円の各償却・引当不足が生じているものである。
4 第一ファイナンスについて
(1) 償却・引当の前提となる会社の状況について
第一ファイナンスは,平河町ファイナンスへの業務移管後,新規貸出を止め,その保有する不稼動債権の管理・回収のみを行う会社となったが,原告の内部資料には「第一ファイナンス及び受け皿2社の清算を検討-段階的な清算をイメージ(最終的な損失負担は,基本的に当行全額負担)」とされており,また,「将来的には当社清算を想定」,さらに「多額の含み損を抱えている上に,赤字体質であることから将来的に清算せざるを得ない」旨記載されており,第一ファイナンスについて最終的には清算を予定していた事実は明らかである。
このような業務状況を反映して,平成10年3月期決算において経常損益が45億9700万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同決算期の帳簿上の債務超過額は137億4800万円であった。
(2) 損失が見込まれる金額についてもⅣ分類とすべきであったこと
平成10年3月期における原告の第一ファイナンスに対する貸出金残高は1245億6000万円であったところ,同期における第一ファイナンスの帳簿上の債務超過額137億4800万円,同社の100パーセント子会社2社の債務超過額から子会社2社において計上していた貸倒引当金を控除した28億6600万円,同社保有の有価証券含み損313億4100万円及び同社の営業貸付金219億1700万円の合計698億7200万円に相当する額が,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のⅣ分類に当たるものである。
したがって,実際の引当額147億円と,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のうちⅣ分類に当たる698億7200万円との差額551億7200万円が償却・引当不足額となる。
5 特定先基準を当てはめた個社群について
(1) 有楽エンタープライズについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
有楽エンタープライズは,日本リースの貸付先であった末野興産の物件を取得するなど日本リースの末野興産向け貸出金を処理する機能を果たすために設立された不動産会社であった。
有楽エンタープライズは,大阪市中央区日本橋1丁目40番3号所在の物件にパチンコビルを建築し,パチンコ業者に一括賃貸することにより収益を上げること(いわゆる事業化)を計画していたものであるが,当該業者が平成8年9月に倒産したことにより事業化計画は頓挫し,平成10年3月末時点には上記土地を駐車場用地として暫定的に利用している状況にすぎず,また仮に事業化が実現したとしても「20年経っても経常利益はマイナスのままであり」「収益で借入金返済ができない」状況にあったものである。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,同社の平成9年3月期は経常損益2億8800万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また平成9年3月期の帳簿上の債務超過額は30億5700万円であったこと,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
有楽エンタープライズの上記アの状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。しかるに,原告は,有楽エンタープライズについて特定先基準により債務者区分を要注意先にとどめたことによって,同社向け貸出金63億5000万円に関して償却・引当額5600万円を計上したのみである。
しかしながら,有楽エンタープライズは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の有楽エンタープライズに対する貸出金63億5000万円から担保処分による回収見込額20億6500万円及び清算バランスによる回収見込額1500万円を控除した42億7000万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであって,上記償却・引当額との差額42億1400万円の償却・引当不足が生じているものである。
(2) 四谷プラニングについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
四谷プラニングは,日本リースの日本ビルプロヂェクト(ビルプロ)向け貸出金に関し,日本リースの決算対策のために設立された会社であり,ビルプロの取得に係る東京都新宿区左門町の土地(左門町物件)に関して日本リースのビルプロ向け貸出金を簿価で譲り受けて保有している会社であった。
ところで,左門町物件について実施を予定していた事業計画によれば,隣地を取得して整形地とした上で賃貸オフィス・マンションビルを建設するというものであったが,平成10年3月末現在暫定的に運送業者の配送センターの駐車場として利用されていた状況で,上記事業計画に関しては,平成9年9月における原告の認識としても,事業化の目処がないとしているものであり,計画どおりに事業化が実施される見込みは全くない状況であった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,四谷プラニングの平成9年3月期は経常損益1億8100万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また平成9年3月期の帳簿上の債務超過額は10億7200万円であり,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
四谷プラニングの上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,四谷プラニングについて特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金187億8000万円に関して償却引当額1億6400万円を計上したのみである。
しかしながら,四谷プラニングは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の四谷プラニングに対する貸出金187億8000万円から担保処分による回収見込額20億9000万円及び清算バランスによる回収見込額27億1000万円を控除した139億8000万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであり,上記償却・引当額との差額138億1600万円の償却引当不足が生じているものである。
(3) 竜泉エステートについて
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
竜泉エステートもまた四谷プラニングと同様,日本リースのビルプロ向け貸出金に関し,当該貸出金を担保権とともに譲り受ける受皿会社として設立された会社である。
同社については,担保権を有する東京都台東区竜泉2丁目の物件をパチンコ業者に賃貸する計画であり,定期賃借権の予約合意にまで至ったものの,近隣住民のパチンコ店建設に対する反対運動のため風俗営業許可や開発許可を取得できる目途が立っていない状態であり,また,担保権を有する東京都新宿区N町の物件もオフィスビル建設等の計画はあったもののいまだ具体化していなかった。このように,いずれの物件についても,今後それらの事業化が実現する具体的目途は立っていない状況にあった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,竜泉エステートの平成9年3月期は経常損益1億6100万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同期の帳簿上の債務超過額は9億6500万円であり,さらに従業員はなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
竜泉エステートの上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,竜泉エステートについて特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金149億4200万円に関して償却引当額1億3100万円を計上したのみである。
しかしながら,竜泉エステートは実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告の竜泉エステートに対する貸出金149億4200万円から担保処分による回収見込額5億2800万円を控除した144億1400万円がⅣ分類となり,その同額を償却・引当額として計上すべきであって,上記償却・引当額との差額142億8300万円の償却・引当不足が生じているものである。
(4) 木挽町開発について
ア 償却・引当の前提となる会社の状況について
木挽町開発もまた四谷プラニングと同様,日本リースのビルプロ向け貸出金に関し,当該貸出金を担保権とともに譲り受ける受皿会社として設立された会社である。
同社については,担保権を有する東京都中央区銀座8丁目の物件に隣地所有者と共同でビルを建設する計画があったものの,「出光興産との共同開発の合意そのものが締結されておらず,ビルプロによる事業化の見込みも全くなかった」ばかりか,立ち退きに応じない借家人もいて未だ具体化するには至っていなかったもので,上記事業計画に関しては,平成9年9月における原告の認識としても今後それらの事業化が実現する具体的目途は立っていなかった状況にあった。
このように事業化計画の実現が不可能な状況を反映して,木挽町開発の平成9年3月期は経常損益1億1300万円の赤字と借入金の弁済原資となるべきキャッシュフローを生み出す状況になく(いわゆる自転能力がない状況),また同期の帳簿上の債務超過額は6億7300万円であり,従業員もなく,会社としての事業活動の実態もない状況であった。
イ 債務者区分は実質破綻先と査定すべきであったこと
木挽町開発の上記状況は,資産査定通達あるいは実務指針にいう「法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの,深刻な経営難の状態にあり,再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている」ものであり,同社は「実質破綻先」に当たる。
しかるに,原告は,木挽町開発について特定先基準により債務者区分を要注意先に留めたことによって,同社向け貸出金115億5000万円に関して償却引当額1億0100万円を計上したのみである。
しかし,木挽町開発は実質破綻先であり,資産査定通達等に従い,原告らの木挽町開発に対する貸出金115億5000万円から担保処分による回収見込額7億7300万円を控除した107億7700万円がⅣ分類となり,同額を償却・引当額として計上すべきであり,上記償却・引当額との差額106億7600万円の償却引当不足が生じているものである。
6 償却・引当不足額合計及び配当可能利益の不存在
特定先基準の違法性により,有楽エンタープライズにつき42億1400万円,四谷プランニングにつき138億1600万円,竜泉エステートにつき142億8300万円及び木挽町開発につき106億7600万円,決裁事由10項ただし書の違法性により青葉エステートにつき227億6100万円及びユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンスにつき計526億4300万円,※7なお書の違法性により第一ファイナンスにつき551億7200万円,「合理的な再建計画」がないのにそれがあるとしてエヌイーディーにつき554億1500万円,再建可能性がなく体力がない関連ノンバンクであるのに「経営支援実績先」と債務者区分して資産分類をⅡ分類とした日本リースにつき788億4400万円,これら合計3078億240
0万円の償却・引当不足が生じているものである。
7 太田昭和監査法人(本件監査法人)の意見
被告らは,本件監査法人が,経営支援実績や特定先といった区分を設けることや原告の関連ノンバンクの子会社について一体処理することを容認し,これらの取扱いを資産査定通達等に照らして適正である旨の意見を述べていたと主張する。しかし,原告は,会計監査人に対し,当時,これらの関連ノンバンクやその子会社の実態を説明せず,かえって,その実態を組織的に隠ぺいしていた以上,このような虚偽の説明に基づく適正意見が被告らの主張を裏付けるものとなり得ない。
第4 仮に,資産査定通達等に商法32条2項を通じての法規範性が認められないとしても,平成10年3月期決算において,原告らが策定した自己査定基準,償却・引当基準に基づく下記の償却・引当額は,商法285条の4第2項にいう取立不能見込額としては不足しており,実際には配当可能利益は存在していない。
1 取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念に従って行うべきである。
債権の取立不能のおそれあるとき及び取立不能見込額は,債務者の資産状態,支払能力,取立のための費用及び手続の難易などを総合し,合理的な社会通念に従って総合的に判断すべきものとされているので,商法285条の4第2項における取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念に従って行わなければならない。したがって,取立不能見込額の判定は,債務者の資産状態,収益力,担保状況等から合理的な社会通念によって行うというのが「公正なる会計慣行」である。
2 資産査定通達等について仮に商法32条2項を通じての法規範性が認められないとしても,以下の考え方は,取立不能見込額の判定についての合理的な社会通念を示すものである。
(1) 売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能額となることは明らかなのであるから,債権額からこの回収可能額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるべきである。
(2) 売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,そもそも支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないのであるから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性を認めることができない。
(3) 取立不能見込額の判定は,当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきである。
(4) 取立不能見込額とは,見込額である以上,絶対的に取立不能な額だけではなく,また,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,決算作成時において回収不能と判定できる金額である。
3 自己査定基準,償却・引当基準が合理的な社会通念に反すること
(1) 特定先基準が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能であることは明らかであるから,債権額からこの額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるべきであり,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないので,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないというべきであり,これに対し,特定先基準は,貸出先の業況,財務状況あるいは返済状況の如何に関わりなく貸出金に対する個別の償却・引当を行わなくてよいとするものであり,不当である。
(2) 決裁事由10項ただし書が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,取立不能見込額の判定は,当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきであり,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないといえ,これに対し,決裁事由10項ただし書は,当該債務者を関連ノンバンクと一体として処理することを理由に当該債務者について当該関連ノンバンクに準じた資産分類を行うとしている点で不当である。
(3) ※7なお書が合理的な社会通念に反すること
合理的な社会通念によれば,取立不能見込額とは,絶対的に取立不能な額だけではなく,将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に決算作成時において回収不能と判定できる金額であり,これに対し,※7なお書は,Ⅳ分類すなわち「回収不可能又は無価値と判定される資産」(取立不能見込額)を既に損失が確定しているとみなされる部分のみに限定している点で不当である。
(4) 被告らの主張する税法基準が合理的な社会通念に反すること
被告らの主張する税法基準とは,原告らの関連親密先については支援損のみが問題となり関連親密先への貸出金は償却・引当の対象とはならない,償却・引当は無税適状の貸出金についてのみ行えば足りるところ,原告が支援する方針としている先については,法人税基本通達9-6-4の要件を充たさないので,関連親密先に対する貸出金は償却・引当をする必要がないというものである。
しかし,貸出金の回収不能見込額に関する合理的な社会通念は,前記2(1)ないし(4)のとおりであり,被告らの主張する税法基準は,このうち,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者に対する債権については,担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額のみが回収可能額となることは明らかであるから,その債権額からこの額を減算した残額が,取立不能見込額と判定されるという合理的な社会通念,また,売上,資産がほとんどなく,大幅な赤字,大幅な債務超過が続く債務者については,支援・再建の対象とされるべき事業自体が存在しないのであるから,金融機関が支援する方針であるというだけでは再建可能性は認められないとの合理的な社会通念に反する。
また,税法基準が会計慣行であったとしても平成10年3月期における「公正な会計慣行」とはなり得ないことからすれば,税法基準は合理的な社会通念に反する。
4 償却・引当不足合計額及び配当可能利益の不存在
(1) 予備的主張における償却・引当不足額が問題となる会社
特定先基準の違法性により有楽エンタープライズ並びに四谷プランニング,木挽町開発及び竜泉エステート(ビルプロ3社)向け貸出金に係る償却・引当の不適切性,決裁事由10項ただし書の違法性により青葉エステート,ユニベスト外4社及びエクセレーブファイナンス向け貸出金に係る償却・引当の不適切性並びに※7なお書の違法性により第一ファイナンス向け貸出金に係る償却・引当の不適切性が明らかとなる(これらの会社の経営状況については,前記第3の1ないし3のとおり)。
(2) 償却・引当の不足額
平成10年3月期決算においては,有楽エンタープライズ及びビルプロ3社につき上記計429億8900万円,青葉エステート外5社につき計354億0400万円,第一ファイナンスにつき332億5500万円,その合計金額1116億4800万円の償却・引当不足が生じている。
すなわち,平成10年3月期決算においては,原告の有楽エンタープライズ外10社に対する貸出金に関し,損益計算書の貸倒引当金繰入額を合計1116億4800万円過少に計上し,その結果貸借対照表上の貸倒引当金を同額過少計上して,あたかも剰余金が460億1400万円であるかのような粉飾が行われたが,実際は剰余金がマイナス656億3400万円であり,法令上配当可能利益は皆無であった。
なお,第一ファイナンスに関しては,同期決算において,債務超過額137億4800万円,同社の100パーセント子会社2社の債務超過額から子会社2社において計上していた貸倒引当金を控除した28億6600万円及び同社保有の有価証券含み損313億4100万円の合計479億5500万円に相当する額が,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のⅣ分類に当たるものであり,実際の引当額147億円と,原告の第一ファイナンスに対する貸出金のうちⅣ分類に当たる479億5500万円との差額332億5500万円が償却・引当不足額となる。
第5 各被告ごとの責任原因事実
1 本件決算配当について
(1) 被告A,D,E,B,Cについて
上記被告らは,平成10年5月25日開催の取締役会において,既述のように違法な本件期末配当にかかる利益処分計算書案を定時株主総会に議案として提出することを全員一致で決議し,その結果,同株主総会の承認を経て,平成11年6月3日までの間に,合計金71億7233万6392円の配当がなされたものであるから,上記被告らは,商法266条第1項第1号,同第2項により,同額を弁済すべき責任を負う。
(2) Fについて
ア Fの善管注意義務及びその違反
Fは,平成元年6月から平成10年4月1日まで,計算書類(損益計算書,貸借対照表及び利益処分計算書案)の最終作成権限を有する原告の取締役会の一員であった。そして,取締役は,法令及び定款に従い会社の財産及び損益状況を正しく表示した貸借対照表,損益計算書等の計算書類を作成する義務が課せられている(商法281条,同285条の4第2項,なお同281条の3第2項3号参照)。したがって,Fは,平成10年4月1日に取締役を退任するまで,原告の取締役として,資産査定通達等の「公正なる会計慣行」に従った自己査定基準等を策定するとともに,同基準等を正しく適用させ,本来必要な償却・引当を行うべき義務を負っていた。
ところが,自己査定基準策定目的の違法性で述べたとおり,Fは,原告の不稼働資産額の実態及び原告が平成10年3月期決算において本来必要な償却・引当ができない状況であることを十分に認識した上で,償却・引当財源内に圧縮すべく,本来必要な償却・引当を回避するような自己査定基準及び償却・引当基準の策定を提唱したものである。しかも,この提唱に沿った自己査定基準の具体的策定作業は,Fが実質的統括責任者であった事業推進部が中心となって行っており,Fは,適宜事業推進部担当者から報告を受け,指示・助言を与え,原告の違法な自己査定基準等策定に大きな影響力を有していた。そのうえ,実質的に,本件決算配当の実施を決定した平成9年11月11日,同月17日及び同月21日の各常務役員連絡会に出席して本件
決算配当の実施方針を了承するとともに,関連親密先の不稼働資産の償却・引当を合計2813億円に止めることを実質決定した平成10年3月23日の常務会に出席し,その方針を了承したものである。
上記一連の行為は,取締役として本来必要な償却・引当を行うべき義務に明らかに反するものであり,その結果として,平成10年3月期において配当可能利益があるとして,本件決算配当がなされるに至ったのであるから,同被告は,本件期末配当に関し,商法266条1項5号,254条3項により損害賠償責任を負うものである。
イ Fの主張に対する反論
Fは,①原告の自己査定基準等の適法性を主張するとともに,原告ら主張の各会議(平成9年11月11日の会議,及び同月17日の常務役員連絡会,平成10年3月23日の常務会)への出席は,直ちにFの善管注意義務違反を構成するものではない,②Fは,平成10年3月31日に原告らの取締役を辞任し,本件決算配当を決議した定時株主総会開催時(平成10年6月25日)及びそれに先立つ決算手続には一切関与しておらず,取締役在任期間中の言動を善管注意義務違反と評価しこれに期末配当による損害賠償責任を認めるためには,違法配当に故意が認められる場合に限られるべきであり,Fには,故意に違法配当を行う意思はなかったとして,在任中に善管注意義務違反はなく,かつ在任中の言動と退任後の決算に基づく配当との間の
因果関係も存しない,と主張する。
この点,上記①については,そもそも原告の自己査定基準等の内容(適用先の選定も含む)が違法か適法かの問題に帰着するが,その点については,前記のとおりである。また,原告ら指摘の各会議はいずれも本件期末配当実施の分水嶺ともいうべき重要な会議であり,原告の自己査定基準等の策定内容が違法と評価される限り,当該会議においてその方針を了承することが同被告の善管注意義務違反を基礎付けることは論を待たないというべきである。
また,上記②については,Fが平成10年4月以降の狭い意味での決算手続に参加していないからといって,Fが商法266条1項5号の責任が否定されるものではなく,本件決算配当の経過及びその間のFの果たした役割・内容にかんがみれば,Fの取締役在任中の言動,活動が,違法な本件決算配当実施に大きな影響を与えたことは明らかであり,損害との因果関係が認められることも明白である(この点について,刑事事件一審判決もFの違法配当罪を認定しているところである。)。
なお,Fは,損害結果と善管注意義務違反との間に因果関係を認めるためには,違法配当に故意が認められる場合に限ると主張する。この点,善管注意義務違反について,前記第2の2のとおり,Fの故意を認めることができることは明らかであるが,故意も過失も全くないというならばともかく,違法配当の故意がない限り結果との因果関係は認められない理屈はそもそも理論的に成り立たない主張である。
(3) 商法266条1項1号の法的性質論
ア 商法266条1項1号は無過失責任であること
商法266条1項1号の法的性質論に関し,違法配当を無過失責任と解すべきである。
すなわち,仮に一般の過失責任と解するならば,過失を前提とする具体的責任原因事実が規定されるはずであり,この点,例えば,株主権行使への利益供与(同項2号),他の取締役との利益相反行為についてはその旨の規定があるが,違法配当の場合,このような具体的違法な責任原因事実は規定されないまま,商法290条1項違反の利益配当議案を総会に提出したことのみをもって連帯弁済責任の根拠とする。このように,商法が配当議案の総会提出という抽象的,定型的な取締役の職務行為を弁済責任の根拠とし,当該取締役の違法配当議案の策定,決算案の取締役会承認といった具体的責任原因の内容を特定しないまま,一律に連帯弁済責任を要求しているのは,そもそも株主等への不当利得返還請求権の行使による損害の完全な回復は困難
であるゆえ,資本維持の必要上政策的に取締役に対し無過失責任を課したものである。
この点,被告らは,商法改正経緯,状況を挙げて,商法266条1項1号は一般の過失責任である旨主張するが,平成14年の商法改正の際,委員会等設置会社における執行役の違法配当責任について,後記のとおり,過失の有無の立証責任の転換がなされたが,一般の事業会社については,商法266条1項1号は特に改正されていない。しかも,衆議院及び参議院において,委員会等設置会社とそれ以外の会社との間で,規定が異なることの合理性に留意しつつ,引き続き検討する旨の附帯決議が付されていることからも,本件決算配当時点において,商法266条1項1号が無過失責任であると理解されていたことは明らかである。
イ 仮に,無過失責任でないとしても,被告らの主張する通常の過失責任ではなく,取締役が自己の無過失を立証した場合違法配当責任を免れるという立証責任転換規定にすぎないが,本件決算配当への関与について,被告らが無過失であったとはいえない。
(ア) 過失責任説と立証責任の転換
仮に,違法配当責任が無過失責任でないと解釈したとしても,それは立証責任の転換と結びついた過失責任に止まり,被告らが主張するような通常の過失責任(主張・立証責任は原告らに属する。)ではない。
すなわち,商法266条1項1号の責任を過失責任と解しても,違法配当議案の提出又は違法中間配当の実施が認められる限り,取締役に過失があることが推定されること,見通しを誤った中間配当の場合の293条ノ5第5項ただし書との対比から,無過失責任の立証責任は取締役に課すべきである。
(イ) 本件決算配当と被告らの無過失の不存在
以上のとおり,仮に商法266条1項1号が,過失責任を定めたものであるとしても,その主張・立証責任は,被告ら取締役にある。しかし,被告らは,自らの無過失についてほとんど説得力のある主張・立証を行っていない。
(ウ) 各被告の過失を基礎づける事実
a D,E及びF
上記被告3名は,原告の中枢経営陣として,違法な本件決算配当の決定における中心的な役割を果たしていた。これは,上記被告3名が違法配当に係る刑事責任を追及され,刑事第一審判決において,有罪とされていることからも明白である。
b Bについて
Bは,平成7年1月から平成10年8月まで常務取締役の職にあったが,①平成7年8月22日の大蔵省検査の対策会議や平成9年12月15日の長銀再生プランの会議に出席し,原告の処理すべき不稼働資産が1兆円以上あることを認識していたこと,②平成9年4月28日付けで事業推進部が分類資産額及び要償却・引当額を可能な限り圧縮し得る自己査定基準,償却・引当基準の試算を行った資料を検討し,検討チームの所管担当役員として同年5月23日開催の常務会に最終答申を提出していたこと,③平成10年4月24日開催の経営会議に出席し,平成10年3月期において,不稼働資産処理として不十分である旨の議論がリスク統括部長から出されたのを認識していたことから,Bの過失は明らかである。
c Cについて
Cは,平成9年当時,常務取締役の職にあったが,①同年5月23日開催の常務会には欠席したものの,配布資料である自己査定プロジェクトチームの最終答申を事後的に検討していたこと,②同年度の決算方針を再確認した同年11月12日及び同月21日開催の常務役員連絡会議に出席し,原告の不稼働資産が1兆円規模であるにもかかわらず,「配当先にありき」の方針が採用されたことを認識していたこと,③同年12月15日の長銀再生プラン会議に出席し,原告の処理すべき不稼働資産が1兆円以上あり,自己資本比率8パーセントを維持するという方針の下,本件決算配当に変更がないことを認識していたこと,④平成10年3月31日開催の常務会に出席し,総合企画部作成の「97年度決算着地見込み」と題する資料の説明を受
け,全体で6000億円程度の不稼働資産処理となる予定の報告を受けていたことから,Cの過失は明らかである。
d 被告Aについて
被告Aは,平成3年4月以降原告取締役会長の職にあったが,①昭和55年6月以降,常務取締役,取締役副頭取,取締役副会長等,原告の経営中枢部におり,原告がバブル経済に狂奔し,平成2年4月の大蔵省の総量規制実施後バブル経済が崩壊した結果多額の不稼働資産を抱えるに至った事情等を熟知していたこと,②取締役会長として,原告の経営会議・取締役会に出席しており,多額の不稼働資産処理を適法に進めるべく監視・監督する当然の義務と権限を有していたこと,③特に平成10年4月28日開催の臨時経営会議において,鈴木リスク統括部長が,平成10年3月期の自己査定額は約6500億円も少なく査定されているとして,同期の償却・引当額に,少なくとも約4000億円ないし約5000億円を加えるべきことを進言
したにもかかわわらず,これを黙殺し,同日開催の同年度決算を了承したことから,被告Aの過失は明らかである。
第6 本件中間配当について
1 中間配当における賠償責任成立の要件と本件争点
商法293条の5第4項,第5項は,違法な中間配当における損害賠償の責任を定めているところ,本件では,平成9年9月期中間配当について,これを承認した同年11月25日開催の取締役会決議の時点において,平成10年3月期決算で配当可能利益がない状態を生ずる「おそれ」が客観的に存在していたにもかかわらず,被告らは当該中間配当を行ったか否か,②被告らは当該予測を誤ったことについて過失がなかったか否かが問題となる。
2 争点①(本件中間配当に関する平成9年11月25日開催の取締役会決議の時点において,平成10年3月期に配当可能利益がない状態が生じる「おそれ」が客観的に存在していたか)
この点については,そもそも本件決算配当(平成10年3月期)が,平成9年9月期中間決算後の事情により突然生じたものではなく,原告内部において平成9年度中間期以前から少なくとも約8000億円ないし約9000億円の要処理不稼働資産が存在し,これにつき適正な償却・引当をすれば配当可能利益が皆無であるため,平成10年3月期の自己査定制度導入に合わせて1年以上も前から,不適正な自己査定基準・償却・引当基準が検討・策定されていたものである。したがって,平成9年11月25日の取締役会決議の時点において,平成10年3月期決算で配当可能利益がない状態を生ずる「おそれ」が客観的に存在していた。
3 争点②(本件中間配当に関する取締役会決議(平成9年11月25日)時点において,平成10年3月期末には,配当可能利益があると認識したことについて無過失であったか)
本件中間配当と本件決算配当の関連性からすれば,同期末に配当可能利益が不存在であったのに,平成9年11月25日の時点でその「おそれ」を誤ったことについて被告取締役らに過失がなかったということは事実上あり得ない。
(1) 本件中間配当決議当時の状況
ア 原告内部における1兆円近くにも及ぶ不稼働資産の存在及び被告らの認識状況
原告における不稼働資産が増加し,これが1兆円にも達することは,平成7年の時点で,Dらは認識し,平成9年11月25日の取締役会以前の各種会議においても事業推進部等関係各部から,これを示す関係資料が,数多くD,E,F,G及びHに提出されていた。
イ 本件中間決算決定当時における期末決算での配当可能利益不存在の「おそれ」に関する認識状況
平成9年度決算方針を実質確認した同年11月11日のDらによる会議に,総合企画部から提出された資料には,「今期配当維持」と「今期無配覚悟」の2つの選択肢が記載され,仮に無配として赤字決算を組んでも「但し,BIS比率8パーセント維持の観点からの赤字許容額は,3600億円程度」であって不稼働資産の完全処理は不可能であった。そこで,Dらは,スイス銀行からのファイナンス実施方針や原告の信用維持等を考慮し,同年度配当維持方針を実質決定した。
そして,この方針は,同月11日から同月21日までの間のファイナンス実施の先送り及び株式会社富士銀行の中間配当見送りという状況の変化にもかかわらず,同月21日の常務役員連絡会において,本件中間配当実施の方針が再確認された。
(2) 各被告の関与・認識状況
ア D,E及びF
上記被告3名は,平成9年11月11日の会議に出席し,この会議においてファイナンスを実施するためにも無配の選択肢は採れない旨のDの発言にE及びFも同意している。また同月21日の常務役員連絡会において中間配当実施方針を再確認している。
イ Gについて
総合企画部長であったGは,中間配当及び期末配当の方針に関する総合企画部資料を作成し,平成9年11月7日,部下とともに同月11日の会議のためこの資料をDに事前説明している。また,当然,同月11日の会議にも参加していたものである。
ウ Hについて
事業推進部長であったHは,平成9年5月9日,平成10年3月期の不稼働資産処理及び決算方針について,D,Fらとの会議に臨んだ。この会議では,事業推進部からは検討中の自己査定基準に基づく償却・引当見込額に関する資料,総合企画部からは,様々な考え方に基づく不稼働資産処理をシミュレーションした資料が提出され,要償却・引当額の更なる圧縮が可能な自己査定基準を作るべきことがFから指示された。
その後,自己査定トライアル実施を受けて,Hは,平成9年度決算方針について,F,Gらとの会議に出席した。この会議において,Hは,事業推進部の担当者に対し「(不稼働資産が)が現状実態ベースではなお8000~9000億円残っており,年間5000億円では依然財源不足である」と説明を行わせており,Hは,自己査定基準に基づく同期の償却・引当額は原告の不稼働資産の実態に即していないことを認識していた。
(3) 無過失に関する被告らの主張について
被告らは名目上予備的主張として「無過失」について様々な主張を行っているが,本件中間配当時と本件決算配当時の各時点において,原告の資産内容が一変(悪化)したというようなことはなく,実質的に,自己査定基準等に違法性はないから,その策定検討段階,自己査定トライアルに基づく本件中間配当及び本件決算配当の実施方針には過失はないというにすぎず,いずれも争点②の固有の主張となり得ない。
(4) 小括
以上のとおり,本件中間配当に関し,D,E,F,G及びHは,商法293条の5第5項により,原告ら請求額について連帯して賠償責任を負うものである。
以 上
別紙2 被告らの主張
第1 「公正なる会計慣行」(商法32条)の意義・内容
原告らは,資産査定通達等の趣旨を逸脱することが単なる通達違反ではなく,平成14年改正前商法285条の4第2項違反であると主張するために,商法32条2項を媒介にして,「資産査定通達等が平成10年3月当時,唯一の公正な会計慣行となっていた」と主張する。
これに対し,被告らは,上記主張の大前提となっている資産査定通達等(資産査定通達,4号実務指針,9年事務連絡,全銀協Q&A及び全銀協追加Q&A)が「公正な会計慣行である」ことを否認し,その余の点を検討するまでもなく,原告らの主張が失当であることを主張するものである。
1 「公正なる会計慣行」の意義,要件
公正な会計慣行と認められるためには,その会計手法が,①多くの者に②長年受け入れられてきたという事実ないし実績が必要である。①,②の要件を欠く中で,ある会計処理を直ちに,唯一の採り得る会計手法にするためには,立法によってこれを強制するしかない(その場合は,その会計手法が「公正なる会計慣行」になったのではなく,法律によって排他的な会計処理基準が定められたということである。)。
(1) 商法32条2項の立法趣旨
商法32条2項は,公認会計士の監査を会計監査人の制度として商法に導入するに当たり,その監査基準が,証券取引法と商法で一致しない場合に生ずる不都合を防止するため,商法と証券取引法との間における監査基準の根拠となる商業帳簿に関する規定の解釈を一致させる必要があったことから,昭和49年の商法改正により設けられた。その趣旨は,商業帳簿の作成に関する規定として,詳細かつ網羅的な規定を設けることは困難であり,また会計技術の進歩の迅速性にかんがみ,常に法規が対応していくのも困難であることから,商法には,基本的かつ重要な規定を設けて,それ以外の点について,「公正なる会計慣行」により,これを解釈し補充してゆくことが妥当であるというものである。
(2) 会計慣行の意義
このような商法32条2項の趣旨に照らすならば,「会計慣行」は,「事実たる慣習」(民法92条)と同義であり,一般的に広く会計上の習わし(慣習)として相当の時間繰り返し行われている会計処理の基準を指すと理解すべきである。
また,仮に「会計慣行」が会計上の「慣習」よりも広い概念であるとしても,従来一度も行われたことのない会計処理方法又は基準(新基準)が「会計慣行」と認められるためには,①新基準が法規範性を有するルールとして適用されることが関係者にとって明らかとなっていること,②新基準が実務に適用し得る程度に明確性を有していること(ないしは解釈についての共通認識が確立していること)が必要と解すべきである。
したがって,行政庁が,通達,事務連絡等を発出したことのみをもって,それが「会計慣行」となるものではなく,特に,公権力による一時的な政策的要請に基づく通達や事務連絡等の行政指導によって,従来存在しなかった基準をドラスチックに導入して,既存の基準に重大な変更を加え,あるいは未実施の基準を導入することで対象企業に過度の負担を強いる場合に,このような基準が直ちに「公正なる会計慣行」に該当すると解することは,経済社会における関係者の合意を本質とする「会計慣行」の概念に矛盾すると解すべきである。
(3) 「公正」の意義
商法32条2項の「公正」の意義は,当初,立法担当者等が「公正なる会計慣行」に該当していると解していた企業会計原則の中において,「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められるところを要約したもの」と定義され,経済社会において広く慣行として行われ,これがその社会の中で一般的に「公正妥当」なものとして受け容れられていたことからすると,経済社会において,関係者間で「公正」と評価され普遍性を獲得したものを指すと解すべきである。
したがって,「早期是正措置」とか「不良債権の早期処理」という公権力による一時的な政策課題を実現するための要請とは全く次元を異にする概念である。
(4) 「斟酌すべし」の意義
商業帳簿の作成に関する商法の規定の解釈に当たり,「公正なる会計慣行」としての企業会計原則を考慮すべきであるが,常に同原則に従った解釈をしなければならないものでなく,同原則以外に合理的な会計慣行も存在し得るから,このような別の会計慣行が存在する場合に,企業会計原則を考慮して,別の合理的と認められる会計慣行を採用することも可能であるということである。
これは,商法32条2項の立法過程において,最終的に「斟酌」という文言が採用された根拠として,①「依拠して」とした場合,当時,企業会計原則及び同注解は種々な分子を混入しており,商法の解釈指針としてそのまま採用するには整備が不十分であると考えられたこと,②「準拠しなければならない」と規定すると,必ず企業会計原則に従わなければならないと解釈される余地が生じ,いわば行政官庁の諮問機関である企業会計審議会に白紙委任するに等しく,立法作用として疑問があると指摘されていたことが挙げられていたことにも合致する解釈である。
これに対し,原告らは,「公正なる会計慣行」が一つしか存在しないことを前提とした主張をしているが,会計慣行は一つとは限らず,併存する複数の会計慣行が存在することもあり,この場合,いずれを採るかは企業の選択に委ねられ,仮に会計慣行が一つしかない場合であっても,これによらない正当な理由があるときは,これと異なる処理も許されるから,原告らの主張は失当である。
2 銀行業における貸出金の償却引当に関する会計慣行(税法基準)の存在
(1) 従来(早期是正措置の導入前)の銀行の貸出金に対する償却・引当処理の内容
平成9年3月当時,銀行業界では,大蔵省銀行局長通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」(昭和57年4月1日蔵銀第901号)の別紙第5の「決算経理基準」(改正前決算経理基準)が発出されており,各銀行は,具体的な償却・引当及び損金処理は,これを基準としていた。
ア 法人税法による一般の貸倒引当金
改正前決算経理基準は,一般の貸倒引当金について「税法で容認される限度額を必ず繰り入れる」と定めており,銀行は,法人税法に基づき,貸出金に対して,定率(法人税法施行令において,銀行の貸倒引当金の上限は1000分の3とされていた。)を乗じて算出した額の貸倒引当金を計上していた。
イ 債権償却特別勘定による繰入れ,不良債権償却証明制度
改正前決算経理基準は,債権償却特別勘定について,債権償却特別勘定への繰入れは,「税法基準」によるものと定めていたところ,債権償却特別勘定の繰入れに関する「税法基準」に関しては,法人税基本通達9-6-4ないし同9-6-6において詳細に定められていた。
この点,同9-6-4は,「債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し,事業好転の見通しがない」ため,「当該貸金の額の相当部分の金額につき回収の見込みがないと認められるに至った場合」には,「その回収の見込みがないと認められる部分の金額」につき,所轄税務署長の認定を受けて損金処理により債権償却特別勘定に繰り入れることができる(繰入額が損金となる)ものと定めていた。上記貸倒損失の認定について,金融機関の貸出金の場合には,税務当局ではなく,大蔵省大臣官房金融検査部(以下「金融検査部」という。)の金融証券検査官が回収不能又は最終の回収に重大な懸念があり,損失の発生が見込まれる貸出金であることを証明した金額に限り,税務上も損金として無税で経理処理することが認められてきた。これが不
良債権償却証明制度である。
この不良債権償却証明制度の下では,有税引当等についても「決算経理基準」等によりその内容を当局に提出するものとされていた。そして,この届出の受理に当たり,金融機関の自主判断により行われるものであることに留意するとされ,また,有税引当等については,決算経理基準等に基づき金融機関の自主判断により行われるものであるから,届出書の受理に当たっては無税償却の適用がないかどうか等について聴取するものとすると定められていた。従来,税効果会計等の有税処理の不利を緩和するための措置が採られていなかったため,銀行の不良債権の償却・引当は,「税法基準」により無税処理の要件を満たすものを中心に行われており,不良債権償却証明制度の下でも,有税による償却・引当が「金融機関の自主判断」により行われる
ことに留意するよう求めていた。すなわち,この当時金融機関における実務の取扱いは,原則として無税処理の要件を満たすものについてのみ処理が行われ,有税による償却・引当はあくまで金融機関の自主判断により行われるものであり,これが「公正なる会計慣行」となっていた。
ウ 支援先に対する取扱い
(ア) 法人税基本通達9-4-2
銀行の関連ノンバンク等支援先に対する支援損の計上に関する基準としては,法人税基本通達9-4-2(平成10年6月1日改正前)において定められ,これが銀行業界における会計慣行となっていた。
この趣旨は,業績不振の子会社等の倒産を防止するために,法人がやむを得ない措置として合理的な再建計画を策定し,これに基づいて新たな融資を行う必要がある場合には,その融資が無利息又は低利で行われたとしても,それは経済合理性を有しており,単に無利息又は低利というのみで,直ちに寄附金として取り扱うことは実態に即しないことから,上記通達により,税務上も正常な取引条件に従って行われたものと取り扱い,寄附金としての認定課税をしない旨を明らかにしたものであった。
同9-4-2は,実務上,既存債権について債権放棄を行う等の方法で子会社の財務体質の抜本的な改善を図る場合についても適用されていた。その後,平成10年6月1日の通達改正で,再建支援のための債権放棄等を寄附金としない旨明確化されたが,その前後を通じ,債権放棄等による関連親密先に対する支援額が損金として計上される点で特に変化がなかった。
(イ) 支援先に対する9-6-4該当性(回収不能の見込みがないこと)
このように,関連ノンバンクに対する支援損について,「税法基準」の法人税基本通達9-4-2による処理が行われる反面,同9-6-4の不良債権償却証明制度による処理を適用しないのが実務の取扱いであり,不良債権償却証明制度において,同9-4-2は列挙されていなかった。また,同9-6-4の適用に当たり「債務者に対して追加的な支援を予定している場合」には,原則として同9-6-4の「事業好転の見通しがない」と判断することは適当でないとされていた。
これは,銀行が再建を支援している積極支援先について,貸出金を延滞していないことが通例であり,法的破綻にも至っていないため,貸出金が回収不能となることは考えられず,「事業好転の見通しがない」と判断することも許されなかったことに基づくものである。不良債権償却証明制度による償却・引当の対象先は,ほとんどが法的破綻先であり,積極支援先について,母体行が単独で償却証明を得ることはおよそ考えられないことだった。
また,銀行が積極支援しながら,当該支援先に対する貸出金について回収不能であるとして有税引当することは,自己矛盾であるとか背任的な行為となるおそれがあるとの指摘がされており,これは,大蔵省における一般的な見解であり,かつ,銀行の実務であった。
(ウ) 将来分の支援損に対する引当等
上記(ア)のとおり,銀行は,関連ノンバンク向け貸出金について,法人税基本通達9-4-2により,国税当局から無税承認を受け,当期において,確定した支援損の額(債権放棄等の額)を計上していたが,翌期以降の支援予定額については引当を行うべき義務は存在せず,原則として引当を行わないものとされていた。
(2) 「税法基準」に従った処理が貸出金の償却引当における「公正なる会計慣行」であること
ア 税法基準が「公正なる会計慣行」とされる根拠
銀行が行っていた前記(1)の貸出金の償却・引当に係る処理は,①改正前決算経理基準の規定の存在,②長期間にわたり,同規定による会計処理の実務が積み重ねられていたこと,③会計士協会も,昭和40年4月6日以降,「貸倒引当金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」(以下「委員会報告第5号」という。)において,税法基準により貸倒引当金の計上がなされれば,除外事由としない(適正意見を付す)こととし,また,「銀行業統一経理基準及び財務諸表様式に関する監査上の取扱い」(昭和51年9月)のなかで,長年の実務において積み重ねられてきた実態を踏まえ,税法基準が会計慣行となっているとしていることから,商法32条2項における「公正なる会計慣行」となっていた。
他方,原告らは,平成9年3月期決算以前において,無税による償却・引当のみを行えば足りるとする会計処理が「公正なる会計慣行」になっていたといえない旨主張し,その理由として,①税法基準が租税収入の確保という政策的視点に立って,税額の計算をし,課税の公平を図ろうとする目的で策定されたものであること,②法人税基本通達9-6-2及び同9-6-4が,無税で貸倒償却・引当できる場合を限定しているのは,いずれも損失の計上について確定的なものを求める税法固有の目的に由来するものにすぎないこと,③他方,商法の計算規定は,企業の財政状態及び経営実績を正しく表示しもって株主及び会社債権者の利益の保護を図ったものである以上,税法基準による会計処理方法が,商法上当然に適法なものであるといえないこ
とを挙げる。
しかし,「公正」とは抽象的な概念であり,かつ,絶対的なものではなく,社会経済の状況や企業会計の理論の発展状況に応じて変化するものである以上,実際に行われている会計処理の実務は,原則として,その時点における社会経済の状況や企業会計の理論等を反映していると考えられていることから,現実の会計実務の状況を確定し,そのうえで,正当性又は合理性を検討すべきである。そして,税法基準は,銀行の貸出金に対する償却・引当に係る一つの会計慣行として存在したものであり,銀行の貸出金に関する償却・引当の処理の実務として定着していたというべきである。
イ 原告らの主張に対する反論
原告らは,①改正前の決算経理基準が,有税による貸出金の償却・引当に関する定めを置いていたこと,②平成6年2月の不良債権償却証明制度実施要領通達の一部改正では,金融機関における不良債権処理を促進する目的から,無税による償却・引当だけでなく,有税による償却・引当制度の円滑な活用を図るためにその取扱いを整備したことに照らすと,平成9年3月期決算以前において,無税による償却・引当を行えば足りるとする会計処理が『公正なる会計慣行』になっていたと解することはできないと主張する。
しかし,改正前決算経理基準が有税による貸出金の償却・引当に関する定めを置いていたからといって,それはそのような方法も選択肢の一つであったということにすぎない。
そもそも,我が国の企業会計は,商法,証券取引法,税法の各規制が相互に影響又は牽制するいわゆる「トライアングル体制」であり,税法が企業の確定した決算を前提に法人税の納税義務を決定する(いわゆる確定決算主義)としていると同時に,企業決算も税法の運用を前提にした内容で確定され,両者は密接な関係をもっていた。
貸出金の償却・引当について税法上損金として認められるか,又は損金性を否認されて償却・引当部分につき法人税が課税されるかどうかは,銀行の決算内容に大きな影響を及ぼす。 仮に法人税の負担を50パーセントとすると,有税の場合は無税の場合の2倍の財源を要することになり,有税処理による損失計上は,無税処理の場合と比べて確実に銀行の決算内容を悪化させ,取締役の善管注意義務違反の問題を生じさせるおそれもあった。さらに,仮に,無税処理が,後日,税務当局から否認されれば,高率の加算税を含めた莫大な予算外負担が生じて経営を危殆ならしめるリスクがあった。
したがって,企業経営者は,軽々しく有税償却を行うことができなかった。特に,税効果会計が存在しなかった時点において,不良債権を確実に無税で処理できるかどうかは銀行経営上大きな関心事であった。このように,改正前決算経理基準の下,銀行の不良債権の償却・引当が,税法基準により,無税処理の要件を満たすものを中心に行われていたことは厳然たる事実であり,これを違法であったとか公正でなかったとか非難するのは現実から遊離した議論である。
また,委員会報告第5号は,「企業が算定基準として税法基準を採用しているときは,税法基準によって計上した貸倒引当金が企業の実態に応じて計上すべき貸倒見積額に対して明らかに不足していると認められる場合を除いては,除外事項としないことができる」と規定していた。これは,金融機関において「税法基準」が「公正なる会計慣行」となっていたことを示す重要な証拠の一つである。
3 資産査定通達等による改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」と認められない理由
(1) 早期是正措置制度により,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となり得るものではないこと
早期是正措置制度は,経営の健全性確保のための金融行政当局による「監督手法」であり,その目的は専ら銀行法26条1項及び2項の定める経営改善計画提出命令,増資計画の策定等の個別措置及び業務停止命令等の措置を自己資本比率という客観的な基準により「適時」に発動できるようにすることにあったから,金融機関の不良債権を「早期」に処理するための制度でなかった。
したがって,経営改善計画の提出,個別措置あるいは業務停止命令を発動することが最大限なし得る処分であり,銀行がその処分に従わなかった場合には,銀行法28条により,業務停止命令,取締役・監査役解任命令,又は免許を取り消すことがあり,刑事処分としては同法62条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰を受けることが予定されていた。しかし,それが限界であり,これを超える制裁が定められていたものでもなく,必ずしも不良債権を「早期」に処理するための制度ということもできないし,さらに商法上の償却・引当その他の資産評価のあり方を変更するものともいえないものであった。
なお,自己資本比率の基準の策定は,銀行法14条の2により,大蔵大臣に与えられた権限であったが,これは同条に「銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準」という文言が使用されていることから明らかなとおり,銀行経営の健全性の判断の基準を定めるものであり,これを超えて商法上の会社の償却・引当等資産評価の基準を変更する趣旨を含んでいなかった。
そもそも,自己資本比率基準制度は早期是正措置導入より5年も前の平成5年に始まったものであり,時期的にみても,それが当時の商法285条以下の資産評価の基準を所与の前提としていたことが明らかであった。
また,平成6年10月に施行された行政手続法の趣旨からしても,早期是正措置制度上の施策は銀行法及び同施行規則等の法令に基づいて執行されるべきであり,安易に通達等の行政指導に依存したり,所掌事務の範囲を逸脱することは許されなかった。当時の金融検査部の所掌は,銀行法上の調査権及び検査権に基づく金融検査に関する事項にとどまるものであり(これに対し,早期是正措置の発動は,銀行局の所管であり,金融検査部には何の権限もなかった。),これを超えて商法上の資産評価の基準に関する事項(所管は法務省)を含まないことも明らかであった。
(2) 改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」となり得ない根拠等
ア 「公正なる会計慣行」たり得るものは,償却・引当額の算定・計上に当たっての具体的な会計処理の基準であり,抽象的な規範を示すにすぎない「決算経理基準」が,具体的な会計処理の基準となり得るものではないから,「決算経理基準」という通達上の文言が改正されたとしても,その改正後の通達上の指針が直ちに「公正なる会計慣行」となるわけではない。これは,商法32条2項の立法趣旨について「改正商法及び監査特例法等の解説」が,「企業会計原則が会計慣行と関係なく修正された場合,その修正部分がただちに会計慣行となることはない」と述べていることからも明らかである。
そもそも,「決算経理基準」は行政監督権を有していた大蔵省の通達にすぎず,それが銀行業界において決算の基準として広く行われてきたのは,いわゆる指導行政の下,その指導に従うことが事実上強制され,銀行業界もこれを広く受け入れ,毎年の決算でもその基準に従い処理されてきた結果,それが「公正なる会計慣行」と認められるに至ったことによるものである。よって,このような通達の改正すなわち「税法基準」の文言が削除されたことのみから,直ちに改正後決算経理基準が「公正なる会計慣行」となり得るものではなく,その通達に示された会計処理が,「公正なる会計慣行」となるための要件を満たすことが必要であり,反復・継続されていない会計処理の基準が「会計慣行」となるものではないのである。
改正前決算経理基準が1つの会計慣行として取り扱われていた主たる理由は,監督官庁から銀行に対する指示を行う通達であるからということではなく,既に発出から相当期間が経過し,また,各銀行において統一的な会計処理の基準として採用されていたことにあった。決算経理基準の内容に大きな変更が加えられた以上,少なくとも変更された部分については,上記と同様の段階に至るまでは,「公正なる会計慣行」として取り扱うべきではない。これは,改正後決算経理基準において,①自己査定基準の策定について,拠るべき基準として商法,企業会計原則等を挙げた外,「決算経理基準をも勘案し」という控えめな表現を用いた(決算経理基準に「従う」ことまで求めなかった)こと,②自己査定のあり方について「当局として望まれる自
己査定のあり方は,別紙1『資産の自己査定のあり方について』のとおり」という表現を用い,これがガイドライン的な性質のもので,法規範の定立ではないことを明確にしたこと,③資産の評価について,上記自己査定のあり方がガイドライン的なものであることを前提として,「自己査定結果を踏まえ」たうえで,商法,企業会計原則等及び決算経理基準に定める方法に基づき「各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施する」として,各行の自主性を尊重する方針を明らかにしたことからも明らかである。
また,決算経理基準を含む大蔵省の通達は,その後平成10年6月に通達をもって廃止され,その後,同様の内容のものが同年9月になって全銀協から各銀行に通知されたが,同通知本文においては「この基準によるほか,一般に公正妥当と思われる会計処理については,各行の判断で会計監査人と協議の上処理を行われますようご案内申し上げます」との記述があり,これは複数の会計処理方法が存在することを前提に,必ずしも同通知の内容に従った会計処理が行われなくとも,各行の自主判断及び会計監査人と協議の下で公正妥当と思われる会計処理が行われることを容認する内容のものであった。
イ 原告らは,資産査定通達等が改正後決算経理基準の内容を補充するものであると主張する。
しかし,資産査定通達等と改正後決算経理基準との間には,発出主体が相違し,これを無視して「補充」関係を認めることはできない。すなわち,改正後決算経理基準は大蔵省銀行局長が傘下の金融機関に宛てて監督行政の一環として発出したものであり,資産査定通達は大蔵省大臣官房金融検査部長が金融証券検査官等あてに発出したものであり,4号実務指針は会計士協会が会員あてに発した指針であり,9年事務連絡は大蔵省の管理課長が金融証券検査官あてに出したものであり,全銀協Q&A及び全銀協追加Q&Aは全銀協が会員あてに発出したものであった。よって,大蔵省銀行局長が発出した改正後決算経理基準について,明文の規定もなしに,金融検査部長や管理課長,会計士協会及び全銀協が発出した文書がこれを「補充」すること
はあり得ない。なお,改正後決算経理基準(を含む大蔵省通達)は,平成10年6月8日の廃止通達(蔵銀第1443号)によって廃止されたが,資産査定通達は,平成11年7月1日付「預金等受入金融機関に係る検査マニュアルについて」通達(金検第177号,金融監督庁検査部長発出)が発出されるまで存続しており,これは,資産査定通達が,形式的にも実質的にも銀行に対する指示文書としての性格を有さず,まして商法上の規範として銀行を直接的にも間接的にも何ら拘束するものではなかったことによるものであったと理解される。
したがって,改正後決算経理基準において,自己査定基準は「商法,企業会計原則等及び決算経理基準をも勘案して」作成するものとされていたが,「資産査定通達」や「4号実務指針」を基準とすべきことについては全く言及がなかったこと,銀行自身が自己責任において自己査定基準を定めるとされていたこと,「当局として望まれる自己査定のあり方については別紙1『資産の自己査定のあり方について』のとおりであるので留意する必要がある」という表現を用いることで,それが一種のガイドラインであり,銀行に対する新たな法的規範の定立を行う趣旨ではない旨示唆していたことから,改正後決算経理基準が,資産査定通達等により補充されることを予定していた,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」の一部になることを承認して
いたとまではいえない。少なくとも,従来の税法基準を排除してまで,資産査定通達等を取り込むことは予定されていなかったと解される。
ウ 原告らは,「平成9年7月の決算経理基準の改正によって,平成10年3月期においては税法基準が明らかに否定されており,税法基準に基づく会計処理が許されなくなったことは明白である」と主張し,①貸倒償却・引当及び債権償却特別勘定の繰入れについて,改正後決算経理基準において,貸出金等の償却について担保処分前でも処分可能見込額を減算した残額を償却すべきこと,②一般の貸倒金の繰入率が「税法で容認される額」から「合理的な方法により算出された貸倒実績率」に変更されたこと,③債権償却特別勘定の繰入れに関し,「最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については債権額から担保の可能額等を減算した額のうち必要額」を繰り入れるべきことが定められたことを挙げて,要するに従来存在して
いた「税法」や「税法基準」の文言が削除されたことを根拠として挙げる。
しかし,改正後決算経理基準においても,他の箇所には「税務基準」,「税法基準」又は「税法上の準備金」という概念が使用され,その全体をみれば,文言上,税法基準が全て否定されたということは到底いえないことは明らかである。 また,本件訴訟で問題となっている償却・引当の基準は,一般先に関する貸出金の評価及び償却の基準でなく,関連ノンバンク等の支援先に対する損金の計上の基準であり,改正後決算経理基準において「税法基準」の文言が削除されたことのみから,「税法基準が否定された」と即断することはできない。したがって,このような関連ノンバンク等の支援先に対する貸出金の償却・引当の基準について,税法基準を考慮することも当然許容されていたはずである。
エ 原告らは,改正後決算経理基準が税法基準を否定した理由として「税法基準による会計処理が,早期是正措置を導入した根本理由・目的と矛盾ないし反するものであった」ことを挙げ,また「税法基準に基づく会計処理こそ不良債権処理を遅延させていた元凶であった」ことを主張し,このような主張の根拠として,税務に重点をおいた償却が結果的に不良債権処理を遅らせたという意見が早期是正措置検討会メンバーの中にあったこと,税法基準にはとらわれずに,健全性の観点から企業会計原則にのっとった償却を促すことを目的とした早期是正措置の導入を契機に,不良債権償却証明制度が廃止されることになったこと,不良債権償却証明制度の廃止を前提に,税法基準すなわち大蔵省との折衝による無税認定取得という行政裁量性の強い償却
・引当システムという方法を改めたことを挙げる。
しかし,そもそも,早期是正措置の目的が不良債権処理の促進を直接の目的としていたという事実はなく,仮にそのような行政目的があったとしても,その目的の達成のための手段として「公正な会計慣行」を変更するためには,法令の制定が必要であり,単なる行政指導の手法である通達によって実現することは許されないはずである。仮に,このような法令によることなく,通達や事務連絡等の行政指導によって旧来の基準を改廃しようとする場合は,それが企業によって支持され,現実に履践され,商法32条2項の「公正なる会計慣行」として熟成するのを待つほかないというべきである。
オ 原告らは,改正後決算経理基準により税法基準が廃止されたと主張する根拠として,平成10年3月20日付け全銀協作成の「改正『決算経理基準』について(質疑応答編)」の中で「決算経理基準と税法基準とは無関係である」と解説していることを挙げる。
しかし,上記質疑事項は,「改正後決算経理基準の本文にある「債権額から回収が可能と認められる額を減算した残高を直接償却する」という考え方が従来からの会計慣行である法人税基本通達9-6-2の規定の「全額」及び「担保処分後」損金処理することができるとの文言に反することになると考えるが,見解をご教示いただきたい」というものであり,これに対する回答案が「決算経理基準と税法基準とは無関係」であるとされているのは,「決算経理基準」には,債権額から回収が可能と認められる額を減算した残額を直接償却すると定めてあるが,そのとおりに銀行が償却を実施したとしても,その金額は税法上の償却すなわち無税での償却になるとは限らない,税法基準である9-6-2は従来どおり存続しているから,担保処分後で
ないと損金処理(無税償却)は認めない,その意味で「決算経理基準」と税法基準とは無関係であるとの趣旨である。また,この回答案は,かっこ書きで「実務的には,当該決算経理基準の但書により,担保処分後に直接償却することができる」旨記載しているが,この記載の意味は,改正後決算経理基準の当該部分の本文で,「債権額」から「回収が可能と認められる額を減算した残額を償却する」とあるものの,ただし書で「担保が処分されていない等の事情により,償却することが適当でないと判定される貸出金等を除く」と規定し,税法の実務どおり,担保処分後でないと無税償却を認めないことが,改正後決算経理基準についても明らかであることを注記したものである。
以上からすれば,原告らが引用する「決算経理基準における直接償却と税法上の直接償却は基本的に無関係である」との記載は,原告らの主張とは逆に,改正後決算経理基準の下においても,税法基準が変更されることなく存在し,かつ,改正後決算経理基準も税法基準を意識した処理を認めているとの意味を有することが明らかである。
(3) 不良債権償却証明制度の廃止により税法基準が否定されるものでないこと
ア 不良債権償却証明制度の廃止の意義
不良債権償却証明制度の廃止は,早期是正措置制度が導入されることに伴い,改正後決算経理基準において「資産の評価は,自己査定結果を踏まえ,商法,企業会計原則等及び下記に定める方法に基づき各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施する」とされたことに基づく。
すなわち,平成10年3月期以降,各金融機関は自己責任によって自己査定基準及び償却・引当基準を作成し,それらに基づいた処理を行うこととなったが,その際,無税又は有税による処理の選択が,従来の不良債権償却証明制度の下における実務と異なり,各金融機関自身の自己判断に委ねられることとなったものであるが,このような趣旨を超えて,改正後決算経理基準において,各金融機関が税法基準により処理することを禁止されたと解することはできない。これは,現に,法人税基本通達9-4-2や同9-6-4,委員会報告第5号が,平成10年3月期においても特に変更されなかったことからも明らかである。
イ 実体的基準の変更のないこと
また,不良債権償却証明制度の廃止に伴い,「決算経理基準」においての「税法基準」文言が削除されたのであるが,これは,不良債権償却証明制度の手続や償却・引当額の実質的決定主体(従来,金融証券検査官が判定したものが,一般企業と同様に,国税庁の個別認定とされた。)という点での制度変更に応じた手当にすぎず,義務的な貸倒引当,償却の範囲を定める実体面について,何ら新しい基準を定立するものではなかった。
ウ まとめ
よって,平成10年3月期において,税法基準が「公正なる会計慣行」の1つであったこと,少なくとも税法基準に従った処理も複数の会計処理方法の中の1つとして許容されていたものである。
(4) 資産査定通達等の内容,規範性
ア 資産査定通達等のガイドライン性
中間とりまとめには,「早期是正措置の導入に当たり,各金融機関が更に適正かつ客観的に償却引当を行いうるよう,会計士協会より償却引当についての明確な考え方が実務上の指針(ガイドライン)として示されることが望ましい」との記載がなされており,以後実務上の指針について「ガイドライン」との表現を用い,適度の統一性の確保という観点からは,ガイドラインを作成することが必要であるとしたうえ,「自己査定ガイドラインは,あくまでもスタンダードとして位置付けられるべきものであり,各金融機関においては,このガイドラインをベースに,創意工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成することはむしろ望ましい」との記載がなされている。
したがって,資産査定通達等が,各金融機関がそれぞれの実情に沿った自己査定基準を創意工夫して策定する際の,ガイドラインとしての性格を有するものであったことは明らかである。
また,資産査定通達等は,その内容も明確でなく,解釈について共通認識が形成されていたものではないから,平成10年3月期においては会計処理実務における具体的基準として機能するものではなかった。そのため,資産査定通達等は,金融機関の資産査定,償却引当処理においてガイドラインとして用いられた(ただし,9年事務連絡については未公開である以上,ガイドラインとされることもなかった。)のみであり,その結果,各金融機関における自己査定,償却引当処理には,相当程度のばらつきが当然に生じるものであった。
イ 資産査定通達
(ア) 資産査定通達のガイドライン的・トライアル的性格
資産査定通達は,金融機関に対し,自己査定の「適度な統一性」を確保させるためのガイドラインにすぎず,各金融機関は自己責任原則に基づき,各金融機関の実情を踏まえて主体的に創意工夫を発揮して,自主的な自己査定基準を作成することが求められていた。
これは,早期是正措置制度自体が異常な環境下において導入され,かつ,税効果会計等の安全網(セーフティネット)が整備されていない状況下での導入であったため,早期是正措置の導入や自己査定実施のための環境整備に時間がかかることから,一定期間後の見直しが予定されていたことからも明らかである。そのため,導入後初年度の平成10年3月期において,各金融機関は,手探りで自己査定基準を策定し,その2年目以降,金融当局による検査や監査法人との論議等の中で,解釈のコンセンサスが得られ,またガイドラインの改正により解釈の幅が狭まっていくことが予想されたものの,あくまで平成10年3月期は,試行期間,過渡期であるにすぎなかった。
(イ) 資産査定通達策定者の意図
上記(ア)の性格は,資産査定通達策定者(早期是正措置検討会,大蔵省当局)も意図していたところであった。すなわち,早期是正措置検討会では金融システムへの影響を考慮して,ソフトランディングを指向しており,また大蔵省当局としても,早期是正措置制度は,銀行法に基づく措置にとどまり,これを超えて商法上の会計基準を変更する意図は有しておらず,各金融機関もそのように受け止めていたものである。
すなわち,早期是正措置制度導入に伴い,自己査定制度を導入し,その際,大蔵省から指針となるべき通達として資産査定通達が発出されたが,行政当局は,それらの通達等は,銀行法に基づく早期是正措置の発動の是非の判断基準を示すに止まると考えていた。これは,資産査定通達等の行政上の指針において,直ちに商法上の償却・引当の「法規範」となることは全く想定されておらず,そのように受け取られることのないような注記がなされていたことからも明らかである。
ウ 4号実務指針
4号実務指針は,早期是正措置検討会における議論を経て出されたものではなく,会計士協会が独自に作成して,公認会計士宛に発出したガイドラインであった。仮に金融機関が4号実務指針そのものに沿った償却・引当をしない場合でも,会計監査人の適正意見が得られない可能性があるというにとどまるだけであり,金融機関が4号実務指針に直接従うことが法的に義務づけられているわけではなかった。
また,平成10年3月当時,監査法人に勤務し公認会計士として金融機関の監査に関与していたaも,その意見書の中で,「4号実務指針には,資産分類(Ⅰ~Ⅳ)の規定がないという重大な欠陥があり,債務者区分,資産分類,引当金算定の関係が必ずしも明確にならず,資産査定通達と併せて解釈しても,債務者区分と分類区分のマトリックスを作ることはできませんでした」,「重大な欠陥,不備があり,償却引当額を計算することができないようなものでした。当時,金融機関の担当者と公認会計士は,従前の実務慣行に照らし合わせて協議しながら,4号実務指針(および資産査定通達)を解釈して償却引当額を算出しなければなりませんでした」と述べており,その内容が不明確であったことは明白である。
エ 9年事務連絡及び全銀協追加Q&A
9年事務連絡は,支援という要素を考慮して考えるべき関連ノンバンクの資産評価について,資産査定通達では明確な言及がないところから,追加して事務連絡の形で金融証券検査官あてに発出された大蔵省内の内部文書であり,金融機関及び公認会計士協会のいずれに対しても公表されたものではなく,ガイドラインたる性格さえ有しているものではなかった。
全銀協追加Q&Aは,大蔵省当局ではなく,全銀協から広報された例示方式によるガイドラインにすぎず,導入初年度において金融機関を法的に義務づけることはあり得なかった。また,全銀協追加Q&Aには,「現時点での諸情勢を前提とした関連ノンバンクの資産査定にかかる一般的な考え方をとりまとめたものであり,活用に際しましては,表面上の文書にこだわらず,あくまでも実質面を重視した解釈を行っていただく必要がありますので,念のため申し添えます」と記載され,その内容が一義的なものと呼び得るに足りるものではなかった。
(5) 各金融機関等の認識と平成10年3月期決算における各行の決算処理の実務等
ア 各金融機関等の認識
資産査定通達等が唯一の「公正なる会計慣行」であるとの原告らの主張は,資産査定通達等発出当時の金融機関及び金融当局関係者が実際に有していた認識と乖離するものであった。
(ア) 早期是正措置検討会における議論
早期是正措置検討会における議論においては,非常に短い時間で早期是正措置の全体の枠組みや定義付けを行わなければならなかった。その中で資産査定基準の内容については,他の問題と比較して時間的に細かい詰めがなされなかった。ただ,金融機関の関係者から具体的な基準を作るべきとの主張があったのに対し,それはそれぞれの銀行が創意工夫して自己査定基準を作っていくという考え方で対処するというのが同検討会のスタンスであった。
(イ) 「適度な統一性」の確保(中間とりまとめ)
早期是正措置検討会により発出された「中間とりまとめ」には,「自己査定ガイドラインは,あくまでもスタンダードとして位置づけられるべきものであり,各金融機関においては,このガイドラインをベースに創意・工夫を十分に生かし,それぞれの実情に沿った詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成することはむしろ望ましい」としつつ,「但し,適度な統一性の確保という観点から,各金融機関が作成する自己査定に関する基準は,原則として自己査定ガイドラインの資産区分概念に沿うことが必要である」と記載されている。この「適度な統一性」とは,各金融機関の自己査定基準が当局のガイドラインを参考にして創意・工夫を生かした自主的なものであることを求めてはいるものの,ガイドラインの一字一句沿うことを求めている
ものではなかった。少なくとも導入当初においては,各金融機関間のばらつきが当然予想されていたものである。
(ウ) 行政当局の認識
行政当局としても,早期是正措置が導入された平成10年3月期決算から直ちに資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となることは全く想定していなかった。
イ 平成10年3月期時点における継続的事実の積み重ねの不存在
前記第1(2)のとおり,本来,「公正なる会計慣行」(商法32条2項)と認められるためには,長年実務で受け入れられてきたという継続的事実の積み重ねが必要である。資産査定通達等が発出されたのは平成9年3月であり,平成10年3月期時点においては,何らそれらが会計処理基準として機能した実績が積み重ねられていないものであった。
(ア) 主要17行の決算処理の実務
この点,いわゆる主要17行(都市銀行9行,長期信用銀行1行及び信託銀行7行)は,平成10年に金融庁の一斉検査を受けたが,この結果について,①自己査定の正確性について,当局査定と自己査定との間の乖離が全行について認められ,関係会社について,その財務内容を勘案せずに正常先又は要注意先と区分した例や債務者区分を行わずその他と区分した例がみられ,また,他行の関連会社などについてその財務内容を勘案せずに非分類又はⅡ分類にとどめている例が存在し,②償却・引当の適切性について,自己査定が正確に行われていないほか,償却・引当の基準自体に問題が認められ,全行について,償却・引当の追加が必要であり,要追加必要額は1兆0413億円にも上り,③上記の指摘は全て「改善を要する」という形で指導
され,金融検査の結果を平成10年3月期に遡及して修正することは求められず,将来の決算期において修正していくことが指導されており,平成10年3月期において,主要17行が,多かれ少なかれ原告と同様の決算処理を行っていたことは明らかである。特に,関連ノンバンク向け貸出金については,当期に確定した額については,支援損として計上するものの,翌期以降の支援予定額については,引当金を計上しないという会計処理が,平成10年3月期当時においても,一般的であり,主要19行のうち,引当金を計上したのは4行のみで,原告を含む15行は引当金の計上を行わなかった。
資産査定通達は,全銀協を通じ「適度な統一性」を保持するためのガイドラインとしての性格を明示するために「自己査定基準作成に当たっての参考のために」とのコメントを付して,各行に配布されたが,これ以外に具体的に拠るべきものが金融当局側からは明らかにされておらず,従前の関連ノンバンク支援の特殊性に着目した決算処理の継続の是非についても明らかでなかったため,各行は手探りで自己査定基準を策定し,償却・引当を行った。このため,金融監督庁の検査では当然の帰結として,各行の償却・引当,支援損の計上等の決算処理結果にばらつきが出たものである。
以上のとおり,平成10年3月期決算において,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」と呼ぶに相応しい程度には各行に浸透せず,各行もそれぞれの決算処理が資産査定通達等の示す基準と大きく食い違っていたことに特に違和感をもたず,その意味で資産査定通達は,同期において,未だ「公正なる会計慣行」となっていたと到底いえない状況であった。
(イ) 金融検査マニュアルの導入
金融検査マニュアルは,平成11年4月に,金融証券検査官が,金融機関を検査する際の手引書として用いるために作成したものであるが,金融機関の管理体制の確認検査に重点を置いていることから,同年2月に,その策定に際してパブリックコメントが集められたが,全銀協を始めとする有力団体や会計士などから厳しい意見が寄せられ,その内容について,到底,関係者間に合意が成立しているとはいえない状況であった。このことからも,金融検査マニュアルよりさらに1年以上も前にパブリックコメント等の手続を一切行わないまま発出された資産査定通達等が提示する自己査定の基準は,平成10年3月時点においては,無論,平成11年2月の時点でも,なお関係者の支持を十全に受けていたとはいい難い状況にあったことが明らかで
ある。
ウ 原告らの主張に対する反論
(ア) 原告らは,各金融機関が,平成10年3月期決算における貸出金の償却・引当について,改正後の決算経理基準に基づき,資産査定通達等の趣旨の枠内で策定されなければならないとされた各行の自己査定基準,償却・引当基準に基づき貸倒引当金を計上するという会計基準を採用したと主張している。
しかし,改正後決算経理基準には,「商法,企業会計原則等および決算経理基準をも勘案して自己査定基準,償却引当計上基準を作成実施するものとする」との記載はあるが「資産査定通達等」という文言も,「その趣旨の枠内で」という記載も全く存在しない。原告らの主張は,証拠に基づかない独自の解釈論にすぎず,失当である。
(イ) また,原告らは,主要18行の平成10年3月期有価証券報告書の抜粋を引用して,平成10年3月期決算における貸倒引当金の計上基準として,各銀行が「改正後の決算経理基準に基づき,資産査定通達,実務指針等に準拠するように定めた償却・引当基準によっている旨,有価証券報告書に記載していること」を説明する。
しかし,原告ら提出に係る各銀行別・有価証券報告書(18行分)において,「資産査定通達に準拠した」との記載は,18行中1行もないうえに,「実務指針に準拠した」との記載も,18行中7行(都銀2,信託5)が行っているにすぎない。このように,原告らの主張は,事実に反するものであり,失当である。
(6) 大蔵省検査(MOF検)におけるⅣ分類の意義の変更等
ア 従来のⅣ分類の意義
平成9年3月期まで行われた大蔵省検査(MOF検)における関連ノンバンクに関するⅣ分類額は,関連ノンバンクの第三債務者に対する貸出金の取立不能額を機械的に母体行の関連ノンバンクに対する貸出金にⅣ分類として反映させて算定された(修正母体行主義に基づく算定)。
このようなMОF検におけるⅣ分類額は,母体行主義に基づき,関連ノンバンクを「破綻させない」で母体行が責任をもって再建責任を果たすという考え方に基づくものである。
仮に,関連ノンバンクを「破綻させる」という「清算的」な考え方に基づくとすれば,銀行(母体行)の関連ノンバンクに対する「取立不能のⅣ分類」の額は,貸出金の割合に応じて算定される「プロラタ」方式によるはずであるが,そうなっておらず,関連ノンバンクの第三債務者に対する貸出金の取立不能額の全額がそのままⅣ分類とされている。
したがって,このMОF検における関連ノンバンクに関するⅣ分類額は,関連ノンバンクを「破綻させない」「母体行が責任をもって再建させる」という「再建的」な考え方に基づくⅣ分類額であり,「支援予定額」すなわち「関連ノンバンクの第三債務者に対する取立不能Ⅳ分類額(これは清算的なⅣ分類額)を解消させるために母体行が関連ノンバンクに対して損益支援すべき額の上限」を定めたものなのである。つまり,関連ノンバンクに対するⅣ分類額は,母体行の関連ノンバンクに対する貸出金の額につき,清算的な考えに基づいて「取立不能」であるとして査定したⅣ分類額ではなかったのである。
このように,関連ノンバンクに対するⅣ分類は,一般先に対するⅣ分類(銀行の貸出金に対する取立不能額を意味する。)と相違し,一般先と関連ノンバンクでは,同じ「Ⅳ分類」という言葉であっても,その意味が異なるものであった。
この当然の帰結として,MОF検における長銀の関連ノンバンクに対するⅣ分類は「即時償却・引当」を要するものではなく,複数年にわたって損益支援すべき額を意味するものであった(これにつき「分割償却」という言葉が用いられることがあるが,正確には「計画的,段階的損益支援」というべきである。)。
また,平成7年4月13日付け「当面の貸出金等査定におけるⅢ分類及びⅣ分類の考え方について」と題する大蔵省管理課長発出の事務連絡(以下「7年事務連絡」という。)もこのような考え方に従い,関連ノンバンクに対する銀行の「Ⅳ分類」につき,複数年度にわたる処理を認めている。
以上のとおり,このように,一般先に対するⅣ分類は「即時引当,償却」を意味するが,関連ノンバンクに対するⅣ分類はそもそも「即時引当,償却」を意味しない。関連ノンバンクに対するⅣ分類は「複数年にわたる損益支援の予定額」を意味するものであった。
イ 早期是正措置・自己査定制度導入後(平成10年3月期以後)のⅣ分類
早期是正措置・自己査定導入後は,資産査定の結果と引当・償却が密接に結びつくこととされた結果,「Ⅳ分類」という定義が「即時全額処理」を意味することとされた。従来の「資産査定」は数年ごとに行われるMОF検の概念であり,銀行の引当・償却と結びついていなかったが,平成10年3月期からは,自己査定の結果と引当・償却等の会計処理が連動する方向が示された。
このような自己査定の結果と引当・償却等の会計処理が連動する状況において,「Ⅳ分類」は「即時全額処理」ということになるので,従来のMОF検での査定において「関連ノンバンクに対するⅣ分類」とされてきたものについても,自己査定においてⅣ分類と査定し「即時全額処理(引当・償却)」を要することになるのか否かについて混乱が生じたものである。
しかし,この時点では,早期是正措置制度という新たな銀行監視の行政手法が採用されたものであって,銀行の関連ノンバンクに関する不良債権処理方針についての金融政策自体に変化があったわけではなく,関連ノンバンクについては母体行が責任をもって「損益支援により再建させていく」という考え方自体は維持された。つまり,関連ノンバンクにつき「即時破綻させる」という政策転換が行われたわけではなかった。
そこで,自己査定による「Ⅳ分類」は「当期中に処理を要するものである」という考え方と,関連ノンバンクに対する(従来のMОF検での)Ⅳ分類は全額即時引当,償却して関連ノンバンクを清算させるのではなく損益支援により再建を図るという考え方とを調和させるため,9年事務連絡が発せられ,また,これを敷衍した全銀協追加Q&Aにより,その内容が銀行に知らされ,関連ノンバンクに対する貸出金につき母体行責任を負う意思があり合理的な再建計画が存在する場合には,原則としてⅢ分類,当期の損益支援確定額を「Ⅳ分類」とするという方式がとられることになった。言い換えれば,従来であれば,7年事務連絡により,関連ノンバンクに対するものであれば,「MОF検Ⅳ分類(修正母体行主義のⅣ分類)」とされたものであっ
ても複数年の処理が可能であったが,平成10年3月期からは「自己査定Ⅳ分類」は分割処理を認めないものとされたので,この結果,複数年で処理すべき損益支援額を自己査定においてⅣ分類と称することができなくなったのである。
また,自己査定制度の下でのⅢ分類についても,一般先に対するⅢ分類は「取立不能の可能性」に基づくⅢ分類額であるのに対し,関連ノンバンクに対するⅢ分類は「将来の支援予定額」についてのⅢ分類額であり,同じⅢ分類という概念であっても,一般先に対するⅢ分類額については,そのうち,どれだけの額に引当金を計上するかという問題は,倒産確率など定性的,定量的なすべての要因を総合的に勘案して貸倒引当率を定めるものであるが,他方,関連ノンバンクに対するⅢ分類額については,そのうち,どれだけの額に引当金を計上するかという問題は,倒産確率に基づいて算定されるものではなく,損益支援計画に基づく経営判断の問題であると考えられたのである。
この結果,原告のみならず他行も同様に,平成10年3月期決算において,関連ノンバンクに対する貸出金につき,修正母体行主義により算定される従来の「MOF検Ⅳ分類額」については,即時全額引当・償却を要する取立不能の「自己査定Ⅳ分類」として計上することなく,原則としてⅢ分類とし,「当期に行うことが確定した損益支援予定額のみ」を「Ⅳ分類」とし,Ⅲ分類のうち,どこまで引当金を計上するかは経営の裁量の範囲とされたと解されるものである。
したがって,原告経営陣(被告ら)の「取立不能によるmustの即時引当,償却を怠っていたわけではない」,「たしかに,関連ノンバンクに対する損益支援をできる限り厚く行いたいが,それはmustの引当・償却を怠ったというものではなく,経営裁量としての損益支援をもっとやりたいと考えていたのだ」,「損益支援についても当期行うものはⅣ分類として当期中に(引当,償却によってではなく,損金計上などの方法で)処理する」という認識は,実体に根拠を有する当然のものであった。
(7) その他の原告らの主張に対する反論
ア 原告らは,平成4年8月に「金融行政の当面の運営方針ー金融システムの安定性 確保と効率化の推進」が,平成6年2月に「金融機関の不良資産問題についての行政上の指針」及び同「不良債権償却証明制度当実施要領について」が発出されたことから,「平成9年3月期以前においても,有税による償却・引当が求められていたのであり,無税適状にある債権額のみを償却・引当すれば足りるとする会計処理方法が「公正なる会計慣行」であったとまではいえないと主張する。
しかしながら,被告らも,平成9年3月期以前において,有税償却の途が建前として認められていたことまで否定するものではなく,ただそのような処理が銀行経営上極めて難しかったこと及び有税償却が建前として認められていたからといって,従前の無税償却を主とする税法基準による処理方法が否定されたとまでいえず,両者が併存していたと主張するものである。原告らの主張は,一つの慣行が公正なる会計慣行である場合,これと相違する他の慣行は「公正なる会計慣行」から排除され,また行政当局が指針を出した後,それと異なる慣行は「公正」でなくなるとする考えに立っていることが窺われるが,会計基準は民間の企業の中から生成発展するものであることに着目して,詳細な基準を法律や命令で定めることを避け,ただ「公正なる
会計慣行」を「斟酌」するべき旨の包括規定のみを置くにとどめた商法32条2項の立法趣旨を正確に理解しないものである。
「公正なる会計慣行」を理解するためには,複数の公正なる会計慣行が併存し得ること,その会計慣行は法律又は命令によって廃止することは別にして,単なる通達や指針では即時一括の廃止はできないこと,通達や指針により,公正なる会計慣行を変更するには,通達や指針の意向を汲んだ実務が会計慣行として熟成するまで待つほかないものである。
また,原告らは,旧商法285条の4第2項の取立不能見込額と改正前の決算経理基準における「回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金」,「回収不能と認められる債権について,その損失相当額」とが同義であること,債権償却特別勘定の繰入について,「税法基準のほか,有税による繰入ができるものとする」等の指針が示されていることをもって,決算経理基準改正前から,有税引当を行うことも義務であった旨主張する。
しかし,まず,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」が何かは同条項だけでは明らかにならないがゆえに,義務的引当が必要となる範囲を明確に画するために,明確かつ詳細な指針が存する税法基準が貸倒引当金の算出根拠として機能していたのである。他方,有税部分は任意であり,明確な範囲を画する基準は存在せず,原告らは,「回収不能と認められる債権についてその損失相当額」等の通達上の文言が範囲を画するものとするが,「回収不能と認められる債権」は「取立不能見込額」と同様に「回収不能と認められる額」の具体的算定方法が明らかでない。「決算経理基準」における抽象的指針を引用して「取立不能見込額」と同義であると述べたとしても,旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」は償却引当をしなければ
ならないことを述べたに止まり,具体的な基準は明らかとはならない。さらに,改正前決算経理基準における債権償却特別勘定への繰入が,「有税による繰入ができるものとする」とされているのは,有税による繰入が任意であることを示しており,この文言から義務的繰入が要求されると解するのは,矛盾した解釈である。
イ 原告らは,平成10年3月期においては,「原告銀行の関連ノンバンク宛貸出金について,合理的再建計画の有無や原告銀行の収益力から再建可能性が認められるか否かにつき具体的な検討を行うことなく,原告銀行の関連ノンバンクは原告銀行が支援するから破綻することはあり得ず支援損しかあり得ない,したがって関連ノンバンクについては支援損のみ計上すれば足り,償却・引当をする必要はないとする処理が,公正なる会計慣行に基づく会計処理であったとは認めがたい」等とも主張する。
しかし,被告らは原告の関連ノンバンクについて,合理的再建計画の有無や原告銀行の収益力から再建可能性が認められるかどうかについて具体的な検討を怠っていたわけではなく,単に原告が支援するから破綻することはあり得ないと主張しているわけでもない。
むしろ,被告らは,本件訴訟を通じ,日本リース,エヌイーディー等などに対する長期にわたる経営支援の実績を踏まえ,それぞれに再建計画が存在しこれに一定の合理性があったこと,原告の収益力から見て,これらの関連ノンバンクに対する支援は,原告が支援を続けることが可能であり,かつそれが原告の利益にも適うものであるとの判断に立ったものであることを縷々主張し,立証に努めてきた。その他の第一ファイナンス,ビルプロ3社,有楽エンタープライズ等についても,それぞれに支援をする合理的理由と再建可能性があったことを主張・立証してきたものであり,原告らのこの点に関する非難は,これらの支援の沿革を理解しない,全く的はずれなものである。
4 原告らの主張する「公正なる会計慣行」(規範)と単なる実務状況との質的相違に対する反論
原告らは,「規範」と「慣行」を峻別する例として,医療過誤や預貯金過誤払いの例を挙げて,「商法32条2項に言う『公正なる会計慣行を斟酌すべし』とは,或る業界において現に行われている「会計慣行」を参考にせよという意味ではない。同項はあくまで規範としての「公正なる」会計慣行に従うべきことを要求しているのであるから,単に当時の実務状況や金融機関の決算動向と言った生の事実を認定してみても,それだけでは何の意味もない。・・『公正なる会計慣行』の法的探求・評価と単に当時の実務状況,他金融機関の認識とは,全く法的性質を異にするものとして,厳に区別されなければならない」と主張する。
(1) 本件における「慣行」を論ずることの意義
しかし,本件訴訟において,「慣行」を論じる意味と医療過誤等において「慣行」を論じる意味は,「法的規範」との関係では明確な相違があり,本件においてそれらを引き合いに出すこと自体失当であるといえる。
ア まず,本件における議論の出発点は,旧商法285条の4第2項の「金銭債権に付取立不能の虞あるとき」の解釈にあるところ,同条項の文言のみでは,何らの解釈指針が示されていないがゆえに,「取立不能のおそれがあるとき」の判断基準について,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に該当するものは何かが議論されるのであり,「会計慣行」そのものが,旧商法285条の4第2項の解釈における中間項として位置付けられるのである。
イ 他方,医療過誤において「法的規範」として問題となるのは,民法709条における「過失」である。
この「過失」の文言のみでは,いかなる場合に「過失あり」といえるのかは不分明である。そこで,「過失」の具体的内容を明らかにするために設定される中間項が「注意義務」である。
この「注意義務」を論じるうえでの「実務慣行」は,注意義務の内容を吟味する際の一つの重要な要素であることは事実であるが,「実務慣行」自体が「過失」の有無の判断における中間項となるわけではない。また,預金過誤払いにおける議論も同様であり,準占有者に対する支払いとして免責が認められるか否かという民法478条の「善意なりしとき」の解釈において,「慣行」自体が中間項として設定されるわけではないのである。
ウ 以上の対比から明らかなように,本件では,旧商法285条の4第2項という法的規範の解釈指針とするために,商法32条2項という条文に明記された「会計慣行」が何かが議論されているのであり,「公正なる会計慣行」たる「実務状況」は,商法32条2項を介して旧商法285条の4第2項の法的規範と直結するものである。
他方,医療過誤等において「過失」を論じるにおいては,中間項として設定されるのは「注意義務」であって「慣行」そのものではなく,またその中間項たる「注意義務」は,商法32条2項のように条文上明記された中間項ではない。ましてや,「実務状況」は,そのような性質を持つに過ぎない「注意義務」における,判断事情の一要素にすぎないのである。
したがって,本件において「会計慣行」を論じる意味と,医療過誤や預貯金過誤払い事件において「実務慣行」を論じる意味は全く異なるものであり,本件において,医療過誤や預貯金過誤払い事件における「慣行」の位置付けを引き合いに出すこと自体,全く的外れの主張なのである。
(2) 「過失」と「会計慣行」の相違点
ア また,「過失」と「会計慣行」の相違点については,そもそも,商法32条2項の「公正なる会計慣行」について,商法に詳細な規定を設けるのは,実際上困難であるばかりか,会計技術の迅速な進歩に対応することも難しいため基本的な規定のみを設け,その余は「公正なる会計慣行」に譲るのが適当であるとされたために包括的な規定が設けられたものである。このような趣旨からすれば,「公正なる会計慣行」については,その時々の社会的状況,会計学の進歩に応じて,逐次,規定の改正を繰り返すという方法によれば,商法上に詳細・具体的な規定を盛り込むことが可能なものである。
これに対して,「過失」は,そもそも,その行為者の置かれた具体的状況等によって,注意義務の存否,内容は自ずと異なるものであるから,法文に規定することができないものである。
イ さらに,商法32条2項においては,「公正なる会計慣行」という会計基準(ルール)自体に対して法規範性を付与するものであるのに対し,「過失」の概念は,当該個別具体的な状況における注意義務の存否,内容を決するという機能を有するのみである。「公正なる会計慣行」に該当し,法規範性が認められれば,一定の範囲の者に対して等しく拘束力を持つ(「斟酌」する必要が生じる)のに対して,「過失」においては,あくまでも当該個別事例について拘束力を持つのみである。
そのため,「公正なる会計慣行」に該当するものについては,当該会計基準(ルール)を適用する者の間においては,その適用結果(結論)にばらつきは生じないものであるのに対し,「過失」においては,その置かれた状況等によって注意義務の存否,内容という結論は個別に異なることとなる。
なお,「過失」についても,裁判例の集積により一定の行為基準的なものが形成されるという側面は否定できない。しかしながら,それらはあくまで事例判断の集積にすぎないのであって,それ自体が規範となるわけではなく,「公正なる会計慣行」とは全く法的性質の異なるものである。
(3) まとめ
以上のとおり,原告らが,「公正なる会計慣行」を定めるうえで,現実の会計実務を全く無視すべきであるとする主張が失当であることは明らかである。
第2 原告が作成した自己査定基準の適法性について
1 内容の適法性
前記第1のとおり,資産査定通達等が,平成10年3月期において,商法32条2項の「公正なる会計慣行」に当たらないことは明らかであり,資産査定通達等が商法32条2項を介して旧商法285条の4第2項の「取立不能見込額」の法規範となることはない。したがって,仮に原告が行った会計処理が資産査定通達等に反する部分があったとしても,それは「通達」違反となるに止まり,商法違反となるものではない。
また,仮に,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」の一つであるとしても,原告が作成した自己査定基準は資産査定通達等の趣旨に反していない。資産査定通達は,金融機関の創意工夫により,実態を反映する自己査定基準を策定することを求めている。そして,関連親密先に対する貸出金については,資産査定通達等において明確な指針が示されていなかったため,原告は資産査定通達等及び追加Q&Aで示された趣旨及び考え方を参考にしつつ,税法基準をベースにした自己査定基準を策定した。
さらに,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」として認められ,かつ原告が作成した自己査定基準が資産査定通達等の趣旨を逸脱していたとしても,資産査定通達等は「唯一の」公正なる会計慣行ではなく,それに違反したことが直ちに違法となるわけではない。税法基準が平成10年3月期においても「公正なる会計慣行」であった以上,原告が策定した自己査定基準がこれに合致する限り,商法違反とはならない。
(1) 自己査定運用細則における「特定先区分」
原告らは,自己査定運用細則の「特定先」とされる区分につき,債務者区分を「正常先」又は「要注意先」としたうえ,「債務者区分に応じた査定を行う」としている点について,「平成10年4月1日から導入された早期是正措置制度は,金融機関が商法の計算規定等に基づき自らの責任において適正な償却・引当を行うことにより資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することを前提とするものであるが,償却・引当と連動している債務者区分を当該先の経営状態と関係なく経営者等の一存で決めることができるとすることは,すなわち償却・引当額を恣意的に増減することを認めることに他ならず,会社の財産及び損益状況を正しく表示した財務諸表の作成を求める商法の計算規定に反する」と主張する。
しかしながら,特定先に区分された企業(その対象先は長進,長銀システム開発等30社で,その具体名が細則中及びこれに添付の一覧表に明記されている)は,いずれも「当行の機能を補完するもの」として原告と密接な関係を有していた。そこで,決裁のための回議用紙2項に明記するとおり,「当行関連親密先等については,通常の一般債務者と同様の基準で債務者区分・資産分類を行うことは,当行の経営関与度の高さ等を勘案すれば適当ではない。今般,全銀協からの通知により,『関連ノンバンク』については,その特性に注目して通常の査定方法とは異なる自己査定方法が示された。当行としては,その趣旨に鑑み関連ノンバンクとともに,当行の特定関連親密先等について適切な査定を行うための基準を設ける」こととしたという経緯
がある。ここにいう「当行の経営関与度」というのは,この文書が社内向けのものであるところから細かく説明されてこそいないが,要するに,原告が資金,人事等万般にわたって密接な関係を有して事実上経営支配していたところであった。
したがって,このような先は,母体行である原告が積極的に支援する意思をもっており,客観的に経営破綻に陥る可能性は小さいと認められる債務者であったから,資産査定通達における破綻懸念先に区分する必要はなく,正常先又は要注意先に区分することとしたものである。
これに対し,原告らは,このような基準は,「原告銀行が支援方針を決定している限り支援先は破綻する可能性がなく,したがって貸倒損失が生じないものであるから,貸倒による損失見込額としての償却・引当の計上が不要であるとの理屈」になり,支援ドグマとでもいうべきものであるとして批判する。
しかし,原告らは,この議論の中で,原告が「特定先」に挙げた先については,原告がそれぞれの企業に対し長期にわたり密接な支援を行い,破綻を防ぐ努力を積み重ねてきた実績があったことを見落としており,親企業が長期間支援を続けてきた実績を持ち,そのうえで将来にわたり支援の意思を表明している場合は,普通はこれを信用して,支援の意思があることを認めるのが経済社会の常識である。よって,「特定先」に対する支援意思についても,少なくとも,過去における支援(損益支援に限らず,資金支援,経営支援等を含む)の実績が存在する限り,なおこれを肯定的に受け止めるのが相当であり,自己査定運用細則が示す30社の「特定先」は,上記のような実績を有する先であった。
(2) 決裁事由10項ただし書について
原告らは,決裁事由10項ただし書に「『経営支援先』又は『関連ノンバンク』に区分された関係会社のうち,不稼働処理を本体と一体で行う会社については,それぞれを『経営支援先』,『関連ノンバンク』と債務者区分しそれに準じた資産分類を行う」とした点が,「資産査定とは,金融機関の保有する資産を個別に検討して,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に従って区分することである」とする資産査定通達の規定に反すると主張する。
しかし,資産査定通達が「資産を個別に検討する」ことを原則とすることと,ある特定の企業が他の企業の傘下にあることや密接な関係にあることを勘案することとは全く別のことである。例えば,業務内容が優れず,規模が小さい企業であっても,優良企業の関連子会社になれば,銀行を含む他の取引先は,親会社が救済又は支援をしてくれることを見越して高い信用力を持つことを認めるものであり,経済取引の自然の成り行きであって,これらの要素を資産査定の際に無視することはむしろ取引の実態にそぐわない。資産を査定する場合には,そのような要素を加味することが許されるのはむしろ自然なことである。取立不能かどうかを判断する場合についても全く同様なことがいえる。
以上の点からいって,決裁事由10項ただし書が不合理であると断定することはできない。
(3) ※7なお書きについて
原告らは,※7なお書きにおいて,「当該ノンバンクの取引金融機関が当行のみである場合には,既に損失が確定しているとみなされる部分をⅣ分類,担保等により回収が見込まれる部分をⅡ分類,その他をⅢ分類とすることができる」と定めた部分について,資産査定通達によれば,「回収不可能又は無価値と判定される資産」であるⅣ分類は,「その資産が絶対的に回収不可能又は無価値であるとするものではなく,また将来において部分的な回収があり得るとしても,基本的に,査定基準日において回収不可能又は無価値と判定できる資産」とされているのであるから,そのような理由で,清算に伴う損失見込額をⅣ分類としないことは許されないと主張する。
しかし,原告らの主張は,基本的に資産査定通達を唯一絶対の基準として,他の自己査定基準を判断するものであって,資産査定通達が金融証券検査官宛の内部通達で,法的拘束力を持たないか,仮に持つとしても他の基準を許さないものではないことを看過しているし,「回収不能かどうか」,「回収不能であることが確定するのはいつか」は,個別具体的に種々の要素を総合して判断すべきである。
そして,税法基準によれば,損失の計上について確定を要するとしていたものであり,当時税法基準も「公正なる会計慣行」として存続していたことを思えば,原告が第一ファイナンスのことを想定して策定して設けた前記なお書きも違法とまではいえないものであった。
(4) 「経営支援実績先」区分の合理性
これは,国税当局から「再建計画の合理性」と「損益支援の経済合理性」が認められ,損益支援につき法人税基本通達9-4-2による無税認定を受けたうえで,損益支援を実行し,この結果,自転可能な状態になった先を区分するため設定したものである。これは国税当局の無税認定の要件である「再建管理はなされているか」に従い損益支援後の銀行による再建管理の対象先であることを明確にするものである。対象先となる会社は,原告の重要な取引先であり,損益支援を実行した実績先である以上,「損益支援が終了したから長銀の手を離れた」と考えることはあり得ない。むしろ,将来にわたって資金繰り面,人事面,営業面,経営面の支援を継続するなど,なお「特別の経過観察」を必要とする先であり,このような考え方から設けられた
区分が「経営支援実績先」である。「経営支援実績先」は,損益支援の結果,「自転状態」に復しており,この先に対する貸付金の資産区分を原則として「Ⅱ分類」とすることは,資産査定通達における「破綻懸念先」や「要注意先」の区分の定義から考えても妥当である。すなわち,資産査定通達における一般先の債務者区分及び資産査定において,Ⅱ分類以下のⅢ分類債権の資産分類が行われるのは「経営改善計画等の進捗状況が芳しくない」債務者である「破綻懸念先」以下に区分された債務者であるが,損益支援が効を奏し,「自転可能」な状態になっている債務者については「経営改善計画等の進捗状況が芳しくない」とはいえず,経営支援実績先を債務者区分における「破綻懸念先」と同等と考えることはできない。
以上のことから,経営支援実績先について,一般先との比較において,「要注意先」と同等の債務者区分をすることが適当であるといえる。そして,資産査定通達においては,「要注意先」に対する貸出金については,担保等により保全されない債権はⅡ分類とされており(本文5頁),経営支援実績先の貸出金の資産分類を原則Ⅱ分類とすることは,何ら資産査定通達等の趣旨に反するものではない。
なお,後記の日本リースに加えて,平成10年3月末日現在では,ランディックと長銀リースが一括前倒しによる損益支援を終了し「自転状態」となったことから,「経営支援実績先」該当先は合計3社になっていた。
2 自己査定基準の策定目的の適法性
原告らは,被告らが平成8年8月30日の常務会で,自己査定基準及び償却・引当基準を事業推進部及び総合企画部に策定させることを決定した当時,原告の要処理不稼働資産が1兆円を超える額に達しており,自己資本比率8パーセントを維持することが困難となりかねないことを認識していたことを根拠として,原告の自己査定基準が「要償却・引当額を実態より圧縮し,原告の償却・引当可能額に収めることを目的として策定された」と主張する。そのうえで,「当時(平成10年3月期),被告らがそのような考え方(税法基準により関連ノンバンク等の支援先については支援損を計上すれば足りるという考え方)に立っていたとは到底認められない。当時作成された各種資料には,大蔵省等が示した資産査定通達等と何とかして外形的な整合性
をとりながら,実態より要償却・引当額を圧縮できる基準を策定しようと組織体で腐心していた状況が顕著に窺えるのに,当時,被告らが,税法基準に従えば足りると考えていたことを窺わせる証拠は皆無である。」と主張する。
しかし,当時,税法基準は銀行業界において広く行われ,これに従うこと自体に不自然な点はなく,その正当性を問題とする必要性はなかった。
また,このような状況の中で,資産査定通達等が発出されたが,その内容が当時の銀行業界で共有されていた支援損を巡る常識からやや乖離した内容のものであり,資産査定通達等に係る解説の中で,それがガイドラインにとどまる性質のものであることが強調され,自己査定基準について各銀行が自主性を発揮し,工夫を重ねて実情にあった無理のないものを作ることが推奨されており,原告が,資産査定通達の趣旨を尊重しつつも,自行の実情に適合した基準作りを目指すのはごく自然なことで,むしろそれは経営努力の表れでもあった。原告らは,被告らが要償却額・引当額を実態より圧縮することに「腐心」していたと主張するが,その「腐心」が当時適法とされていた税法基準の範囲内のことなら,何ら非難される筋合いのものではない。
実際のところ,本件に関連する刑事・民事の各事件の中で膨大な資料が証拠として提出されたが,平成10年3月又はそれ以前に作成された原告の内部資料について,違法な行為を行うことを前提として密議をこらすというような陰湿な場面を疑わせるものは存在しない。また,多くの関係者が様々な資料を作成しているが,「それは違法だから別の方法を探すべきだ」,「違法だから自分は荷担しない」というような発言がされた例もない。それだけでなく,平成10年3月の決算においては,長銀リース及びランディックの両社に対する前倒支援の結果,当初計画より1800億円近く多い額を前倒支援した。これは,義務的な支援の額を超えており,仮に,被告らが要償却・引当額を違法に「実態より圧縮」するために「腐心」する状況であったな
らば,義務のない支援に巨額な財源をまわすことなく,違法の可能性がある圧縮をそれだけ控えたはずである。
原告の平成10年3月期決算については,太田昭和監査法人(本件監査法人)による関与社員公認会計士等20名,監査延べ日数825日(前年比170日増),監査延べ時間6595時間という入念な監査が行われた。この監査においては,原告の自己査定基準等及び平成10年3月期決算における自己査定結果等に対する検討が,「深度ある」もの(4号実務指針参照)として入念に行われた。本件監査法人は,原告の自己査定基準策定経過においても,基準案の事前チェックを行った。原告も,自己査定基準作りの当初から,監査法人の踏むべき手順として予定に入れていた。
このような経過の中で,本件監査法人は,原告の策定した自己査定基準が,大蔵省のガイドラインたる資産査定通達との関係でも,また会計士協会の4号実務指針との関係でも,また商法の規定との関係でも,認容される内容のものであることを確認している。原告は,本件監査法人による検討結果を踏まえて,自己査定基準及びこれによる自己査定結果を適正なものであると受け止め,それを前提として決算を行ったのである。
商法監査において,特に金融機関における貸出金の償却・引当等については,監査に当たる会計監査人の意見が最も尊重されることは金融機関の実務の中で定着していた事実である。そして,会計監査人が適正意見を出せばその決算には重要な虚偽がないという考え方もまた経済社会の中で広く受け入れられてきた考え方であった。一方,大蔵省検査においては,従前,金融検査と償却・引当は連動しておらず,金融機関においては,償却・引当については,各行の経営判断と会計監査人の判断により必要とされる額を処理するのが実務であった。
3 再建計画の合理性と償却引当の関係
再建計画が合理的か否かは,その再建計画において行われる支援行為の適否の問題であり,償却の適否の問題ではない。なお,少なくとも平成10年3月期までは,必ずしも厳格な再建計画の作成を前提とする支援に限らず,人材の派遣,商材の提供,資金繰り支援等の多様な「支援」を予定している貸出先に対する貸付金を償却引当の対象とすることは矛盾と考えられており,この点について,法人税基本通達9-6-4の実施要領においても,追加融資等の支援を予定している先に対する貸出金については,無税償却適状にはないとの解釈指針を示していた。
被告らは,日本リース,エヌイーディー等の関連ノンバンクに対し,損益支援をする際,再建計画を策定しこれに沿って支援してきたが,原告らはこの再建計画に合理性がないと主張する。
しかし,被告らは,関連ノンバンクに対する支援を早期是正措置制度導入が決定される以前から実行しており,現に日本リース,長銀リース及び日本ランディックについては,平成10年3月までに前倒支援による支援完了に至っている。残るエヌイーディーについて,平成6年以降,計画的・段階的に支援を継続していたが,上記のとおり,中核3社について前倒しで支援完了に至り,平成10年4月以降は集中してエヌイーディーに対する支援を実行する予定であった。したがって,原告が支援していた重要な関連ノンバンクについて,再建計画が合理性をもたなかったというような事実はない。
第3 償却引当不足の不存在
1 日本リース
日本リースは,平成9年末時点において,①原告による平成6年度及び平成7年度の損益支援の結果,その含み損部分に見合う借入金の利払いについては,本業の利益でカバーし,実態利益は,平成9年3月期に175億円,平成10年3月期に182億円となり,期間損益は黒字決算に回復していること,②年間230億円の利益を上げるための「第5次中期計画」が具体化しつつあり,本業の収益により不稼働資産の処理が進む状態にあったこと,③キャッシュフローが順調で,平成9年11月の金融危機も原告の支援(損益支援はもとより,追加貸出し等の支援)なしで乗り切るなど,200近い金融機関からの借入金に係る約定返済に一切延滞はないこと,④平成9年秋に,他のリース会社と同様に一時抑制したリース営業も,平成10年4月から
は再び増加する計画を立てるなど,オリックスと並ぶリース業界のリーディングカンパニーとして活発な営業活動を継続していたこと,⑤子会社である日本リースオート,千代田情報機器の株式上場によるキャピタルゲインが見込まれていたこと等の状況を総合的に判断すれば,全銀協追加Q&Aの「自力で再建の見通しが立たない」という要件には該当せず,「体力あり」と判断し,上記「経営支援実績先」に該当する先として区分したうえ,同社向け貸出金をⅡ分類と査定することは妥当な取扱いであった。
2 エヌイーディー
原告は,日本リース,長銀リース,ランディック及びエヌイーディーの4社を,原告の事業展開の上で戦略上不可欠の中核的関連ノンバンクとして位置づけ,4社の破綻を回避すべく計画的段階的に支援を実行してきた。
その結果,平成8年3月に日本リースについて前倒支援を行って自転可能な状態に押し上げ,平成10年3月期には長銀リース及びランディックについて前倒支援を行って自転体制を構築した。
この結果,平成10年4月以降に要支援先として残るのはエヌイーディーのみとなった。同社については平成7年以降の再建計画に一定の修正を加えつつも,集中的に2950億円の損益支援を行うことで(この際税効果会計の導入等による財源増も見込まれ,支援の前倒しも十分可能であった),3000億円強の実質債務超過の相当部分が解消可能で,同社の消費者金融部門及びベンチャーキャピタル部門について年間10億円程度の収益も期待できた。
以上の状況の下,原告は,平成10年3月期において,自己査定基準に基づき,エヌイーディーに対する当期支援分201億8000万円をⅣ分類として支援損処理を行い,その余の将来支援予定分についてはⅢ分類として引当を行わなかった。この処理は,上記関連ノンバンク4社に対する支援を総合的,計画的に考える視点から行われ,全銀協追加Q&A及び当時の慣行に反するものではなかった。損益支援先であるエヌイーディーについて,取立不能を理由とする償却・引当をすることは,平成10年3月期当時,矛盾する行為であると認識され,また将来支援予定分について引当金を積む慣行も当時は存在せず,実際にも大手銀行17行中14行は引当を行わなかった。したがって,原告のエヌイーディーに対する貸出金についての上記処理は適
法なものであった。
3 エヌイーディーと一体的処理基準を適用した個社群について
(1) エヌイーディーのグループ会社
青葉エステートは,原告の関連ノンバンクであるエヌイーディーが,日本ランディック及び長銀リースとともに出資して設立したエヌイーディーの子会社であり,ユニベストほか4社は,いずれも,青葉エステートが100パーセント出資してエヌイーディーの不良債権を処理する目的で設立した同社の子会社であり,エクセレーブファイナンスは,エヌイーディーの資金調達窓口として,同社の100パーセント子会社として設立されたファイナンス会社であり,いずれも原告及びエヌイーディーが支援していた。
(2) 「税法基準」の適用による実質的処理
平成10年3月期当時は,企業会計原則注解18及び法人税基本通達9-6-4などの解釈として支援先に対する貸出金は償却引当が義務づけられていないとの考え方が一般に認められていたので,これら各社に対する貸出金を取立不能として償却引当をしなかった。
原告はこれら各社に対する貸出金については,エヌイーディーに対する支援計画において,エヌイーディーと一体として処理される会社として組み込み,国税当局から法人税基本通達9-4-2による無税認定による損金経理の承認を得ていた。したがって,国税当局はこれら各社に対する貸出金を実質的にはエヌイーディーに対するものとして策定した計画を合理的であると認めていたものである。なお,グループ会社の本体との一体処理は,法人税基本通達9-4-2による子会社等の再建等にかかわる損失負担の無税認定に係る事項であり,不良債権償却証明制度とは無関係である。
よって,これら各社についてエヌイーディー本体と一体で処理する基準を適用したのは,正当である。
(3) 資産査定通達のあてはめ
資産査定通達は当該債務者が実質破綻先であっても,担保及び保証によって保全された部分は,Ⅳ分類に分類査定されないものとしている。
仮に資産査定通達を原告らの主張するように解釈適用するとしても,青葉エステートほかの各社に対する貸出金は,いずれもエヌイーディーの保証があるから,Ⅳ分類に査定されない。
4 第一ファイナンスについて
(1) 清算「予定」について
関連会社支援において,清算が機関決定されていることと,清算「予定」であることは決定的違いがある。正式な機関決定がなされるまで追加融資等の支援を継続することにより支援先の継続的企業としての価値を維持し,その営業的価値に着目した企業に対し,法的清算処理が先行した場合よりも高値で営業譲渡をしたうえで(もしくはその目処をつけたうえで),清算に至るという過程を踏む場合を考えれば,それは明らかである。
(2) 損失発生の蓋然性の存否について
関連会社をどのように支援していくか,また,支援をいつ打ち切るかの判断については,まさに経営判断の問題である。当時の段階では,現に資金支援が続けられていることから,破綻,損失の発生の蓋然性は極めて低く,額の見積も困難である。むしろ,償却引当の時期を機関決定の時期とすることは判断基準として明確である。
(3) 第一ファイナンスの具体的状況
ア 原告は,平成10年3月期決算において,第一ファイナンスに対して約1246億円の貸出金債権を有していたところ,決算に先立つ自己査定において同社が原告自己査定基準の関連ノンバンク運用規則における「関連ノンバンク」であることから,同規則3(3)の「体力のない関連ノンバンク」に当たるものの,同社の取引先は原告だけで,同社をどのように再建又は整理するかの決定は翌年度以降となることから,公認会計士の指示に従い,既に確定しているとみなされるⅣ分類等合計147億円について償却・引当を行い,その余の貸出金については他の通常債権と併せて,一般貸倒引当金を計上するにとどめた。
イ 原告が,第一ファイナンスについて,単純に清算中の会社であることを前提とする処理をしなかった理由は次の点にあった。
(ア) 平成10年3月当時,第一ファイナンスは,提携先であった新京都信販の貸付先である個人から提携ローン割賦金を回収したり,大阪銀行等関西系銀行の関連ノンバンクの清算手続の中で回収を継続していたことから,同時点では原告の第一ファイナンスに対する貸出金の損失額は未だ確定し得ない状態にあり,当面は「破綻懸念先」としてⅢ分類にとどめ,これが確定した後に最終処理をすれば足りると考えられた。
(イ) 第一ファイナンスは,平成10年3月期に147億円の有税引当をしたことにより偶発的に大口債権のロスが発生する可能性も少なく,資産の含み損を抱えながらも当面の企業維持は可能であり,破産・清算会社からの配当,小口債権の回収に時間を要し,清算の時期・方法等は別途検討する予定であった。
(ウ) 債務超過の関連会社であっても,直ちに清算を行う義務が経営者ないし親会社にあるわけではなく,合理的な理由に基づき,親会社が関連会社を当面支援して存続させる選択をした場合には,破綻リスクは皆無であるから,これに対して有する債権について,直ちに償却・引当するか,あるいは清算時期,方法が確定した段階で引当・償却するかは経営者の裁量範囲内のことであると考えられていた。
(エ) 原告の平成10年3月期決算に関する会計検査に関与したQ会計士や平成10年7月の金融監督庁検査に関与したU検査官など,外部の関係者にも第一ファイナンスに関する上記処理方針は理解できるものであった。すなわち,U検査官が,「長銀においては母体行として面倒をみて,回収業務を当面継続することとしており」,「その回収が長銀の第一ファイナンスに対する貸出金の回収に若干でも寄与するという状況がある以上,実質破綻先とはしにくいと感じ,長銀の主張即ち『第一ファイナンスは回収業務を継続しており,新京都信販の提携ローンには個人相手で正常先も多く当分の間の清算はなく,それまで回収業務を継続するから実質破綻は行き過ぎである』という主張を容れざるを得ないと思いました。」と供述し,Q会計士も,資
産査定通達において,第一ファイナンスは破綻懸念先であり,最悪Ⅲ分類であったが,あえてⅣ分類として有税引当を行っており,非常に保守的な処理がされていると考えた旨供述しているところである。
(オ) 第一ファイナンスは,平成10年3月期に147億円の有税引当をした後の見通しとしては「今回の引当により当面必要な処理は一応完了。今後キャリングの赤字も最低限の水準に留まり,また偶発的に大口債権のロスが発生する可能性も少ない。資産の含み損は抱えながらも当面の企業維持は可能」であり,多額の含み損を抱えている上に,赤字体質であることから,「将来的には清算せざるを得ない」が,破産・清算会社からの配当,小口債権の回収に時間を要することもあり,「清算の時期・方法等は別途検討のこととしたい」とされていた。
上記「清算」の趣旨は,「時期・方法等は別途検討」という説明からも明らかなとおり,極めて幅のある内容であり,「せっかく回収業務でノウハウが蓄積されたわけですから,それを生かしたような業務に転換していく」,「もしも必要であれば営業貸付の清算も,そこで確定したものとしてやる」というような着地も考えられていた。
したがって,第一ファイナンスが,将来営業貸付業務については「清算」の方向であったにしても,その時期は未だ不確定で内容面でも純粋な法的「清算」に限られるものではなく,サービサー業務などに特化して存続することや他の関連会社と合併等による再編の中で一部の組織が残っていく可能性はあったのである。平成10年2月に策定された「2カ年計画」の中の「再編」はこのような不確定要素を多々含む柔軟かつ幅広いものであった。
ウ 一般に,債務超過の関連会社であっても,直ちに清算を行う義務が経営者ないし親会社にあるわけではなく,親会社が関連会社を当面支援して存続させる選択をした場合には,破綻リスクは皆無であるから,これに対して有する債権について,直ちに償却・引当するか,あるいは清算時期,方法が確定した段階で引当・償却するかは経営者の裁量範囲内のことであった。長銀の場合も,少なくとも平成10年3月時点ではなお,このような裁量内のこととして第一ファイナンスの問題は認識されていた。
したがって,第一ファイナンスが第三債務者に対して有していたⅣ分類相当の貸付金219億1700万円についても,これを直ちに長銀の第一ファイナンスに対する貸出金の査定に反映させることが強制されていたとはいえない。
このように,原告が同社を実質破綻先として扱わず,自己査定運用規則の※7なお書を適用して,処理をしたことには一定の合理性があったのである。そのうえで,公認会計士の指示に基づき,第一ファイナンスの確定していた損失に対応する147億円についてⅣ分類として引当処理をしていたのである。
(4) 保有有価証券の含み損の問題
第一ファイナンスにつき,実質破綻先でないことを前提とすると,同社が保有する株式等の含み損については,平成10年3月期の実務上,これを償却・引当の対象とする必要がなかったことは明らかである。
(5) まとめ
以上により,自己査定運用規則の※7なお書を違法であるとする原告らの主張及び551億円もの償却・引当不足であるとする原告らの主張がいずれも失当であることは明らかである。
5 特定先基準を当てはめた個社群について
(1) 「特定関連親密先(特定先)」区分の合理性
「特定先」と位置づけられている会社群は,原告のグループ機能を担っている直系関連会社群(長銀総合研究所など)と,関連ノンバンク支援の方策として関連ノンバンク保有不動産を引き取り事業化している関連ノンバンクの子会社群である。
「特定先」は,関連ノンバンクとは会社規模や業種が異なるものの,原告が,人的,資金的,経営的に特別の影響力(支配力)を持ち,母体行責任を負って,積極的に支援する方針を有している先である。
また,原告から幹部社員が派遣され,経営全般を掌握しているので,突発的破綻リスクはなく,これら「特定先」向け貸付金に偶発的貸倒損失が発生するリスクがないことは関連ノンバンクと全く同列であり,一般先とは異なる取扱いをする趣旨はそのままあてはまる。
したがって,「特定先」を「正常先」もしくは「要注意先」と同じ扱いとした原告の自己査定基準は,「特定先」の企業実態に即し,資産査定通達の趣旨にも反しない処理である。
(2) いわゆる「ビルプロ3社」について
ビルプロ3社に対する原告の貸出金は,日本リースを支援するために平成6年3月に実行されたものであり,この貸出金をもってこれら3社が,当時日本リースがビルプロに対して担保不動産付で有していた債権を買い取ったものである。
この対象不動産について,日本リースと原告が共同して事業化に取り組み,債権回収極大化に努めることとしていたものである。当時の不動産市況その他の経済環境の中では,ある程度時間をかけていかなければ事業の完成は難しい面があったものの,日本リースからの資金支援を継続しており,原告ヘの返済の遅滞もなく(日本リースの保証もあった),破綻の懸念もなかったので,日本リースに準じた評価として特定先に債務者区分し,結局要注意先と同じ扱いをしたものであって,正当である。
(3) 有楽エンタープライズについて
有楽エンタープライズは,日本リースが昭和60年6月に設立した日本リースグループの不動産会社であり,日本リースの母体行である原告が同社を支援するために融資した資金を元手に,同社から融資対象物件を譲り受けた上,事業化を目指す事業化会社であった。
日本リースは有楽エンタープライズの原告からの借入について延滞が生じないよう同社の資金繰りに十分注意するなどして,同社を支援しており,同社が事業化計画を中止したり,断念するおそれは極めて少なかった。
原告の有楽エンタープライズに対する貸出は,このように日本リースが有楽エンタープライズの事業化に対し確たる方針を持って臨んでいることを前提とした融資であり,日本リースに対する融資と与信リスクにおいて実質的に同等とみなせるものであった。従って原告が有楽エンタープライズを特定先に債務者区分し,結局要注意先と同じ扱いをしたことは正当である。
第4 原告らの予備的主張について
1 原告らの主張の問題点
原告らは,旧商法285条の4第2項のみでは具体的償却引当基準は導けないがゆえに,商法32条2項を通じて資産査定通達等の通達違反を旧商法285条の4第2項違反であると主張していたはずである。
しかるに,原告らの「資産査定通達で示された考え方は,旧商法285条の4第2項の取立不能見込額の範囲について『合理的な社会通念』を示すものである」との主張は,資産査定通達等の違反について,従前は,商法32条2項を通じて旧商法285条の4第2項違反があると主張していたものを社会通念を通じて旧商法285条の4第2項違反があると言い換えたにすぎないものである。
すなわち,別紙1の原告らの主張の第4の2(1)ないし(4)の要素は独自のものであり,他に何ら明確な判例,学説,実務慣行等の根拠が存在するわけでもない。また,これらの4要素のみを考慮した場合,例えば「当該債権に関する事情(債務者の資産状態,収益力,担保及び保証状況)のみに基づいて行うべきである」とする要件については,「自行として償却ないし撤退方針を決定しているかどうか」という資産査定通達の考え方や母体行による支援意思や支援計画の有無により資産分類を実施する9年事務連絡及び全銀協追加Q&Aの考え方とも矛盾し,相容れないものといわざるを得ない。
このような予備的主張に係る基準は,主位的主張に係る基準以上に不明確であり,失当であるといえる。
2 原告らが主張する「合理的な社会通念」は,平成10年3月期当時存在しなかったこと
(1) 旧商法285条の4第2項についての一般的解釈論
ア どのような債権が「取立不能の虞あるとき」に当たるかの判断基準は,債権の評価という,極めて評価的要素が高いものであるがゆえに,一律なものを定めることが困難という認識が一般的「社会通念」であった。
イ そして,「取立不能の虞あるとき」に当たるか否かの判断においては,個別的な債権につき個別的に判定する場合(個別判定法)のみならず,同種の集団的な金銭債権につき集団的に又は全部の金銭債権につき合理的に判定する場合(総合的判定方法)のいずれでもよいものとされていた。そして,集団的に判定する場合には,過去の取引不能の実績,同業者の取立不能の実績,得意先の変化,一般経済事情等の見通しなどを総合判断し,経験則に従って合理的判定するものとされていた。
ただし,いずれの場合でも,「取立不能の虞あるとき」の判定基準は,必ずしも明確ではなく相当の困難が伴うこと,認定には客観性があることが要請されることはもちろんであるが,取立不能見込額である限り,ある程度の主観的判断が入ることも差し支えないとされていた。
(2) 当時の慣行の存在
ア 総合的判定方法による貸倒引当金の計上
原告をはじめとする銀行業においては,「取立不能のおそれ」について,全債権について,法人税法に基づく1000分の3を乗じた額を貸倒引当金として計上している(前記総合的判定方法による「取立不能のおそれ」の算定)。
イ 税法基準による債権償却特別勘定の計上
前記アの貸倒引当金とは別個に,法人税基本通達9-6系により無税償却適状が認められるものについては,個別に債権償却特別勘定への繰り入れがなされていた。
ウ 支援先に対する貸出金については,無税償却適状態は認められないと考えられていたため,債権償却特別勘定への繰り入れはなされなかった。
「支援」(ここでいう「支援」は,必ずしも厳格な再建計画の作成を前提とする支援に限らず,人材の派遣,商材の提供,資金繰り支援等,多様な支援の形態をいう)を予定している貸出先に対する貸付金を償却引当の対象とすることは矛盾と考えられていた。法人税基本通達9-6-4の実施要領においても,追加融資等の支援を予定している先に対する貸出金については,無税償却適状にはないとの解釈指針が示されていた。
(3) まとめ
以上のとおり,原告らが主張する「社会通念」が平成10年3月期当時存在していたことを裏付ける文献上,実務上の根拠は何もない。結局,原告らの指摘する諸点はいずれも後視的な視点からの指摘にすぎず,当時金融機関の経営者の置かれていた実情とかけ離れた主張であって当を得ない。
第5 被告らの無過失
1 商法266条1項の性質-過失責任
商法266条1項1号に基づく取締役の損害賠償責任の性質は,過失責任であると解される。
これは,①無過失責任を課す旨明示されていないこと,②本来,商法290条1項に違反した配当は無効であり,会社が配当を受けた株主に対して不当利得に基づく返還請求権を有し,このような返還請求権の行使ができない場合でない限り,違法配当額を会社の損害とみて取締役に賠償させることは困難であるところ,同条項1号は,政策的に,会社の損害発生の有無が未定の段階で,損害賠償責任を取締役に負担させるものであり,いわば損害額についての推定規定であり,無過失責任を解する特別な理由がないこと,③同条項1号も株主による免除の対象とされていること,④同条項1号の立法過程からみても過失責任とみることが妥当であること,⑤企業会計の複雑性からみて,無過失責任と解することは取締役に酷な結果となること等から,根
拠付けられるものである。
2 過失がないことを基礎付ける事実
仮に,平成10年3月期において,資産査定通達等が「公正なる会計慣行」となっていたとしても,①平成10年3月期においては,税法基準が,未だ「公正なる会計慣行」であると一般に認識されており,客観的にみて,資産査定通達等が,同期において唯一の「公正なる会計慣行」となったことを認識することは不可能であり,②被告らは,税法基準により資産査定通達等が補充されるものと理解したところ,既に主張した経過に照らせば,そのような理解は当然のものであり,被告らが資産査定通達等が同期において唯一の「公正なる会計慣行」となったことを認識することは不可能であったことに照らせば,被告らには,税法基準が「公正なる会計慣行」であったと認識した点について,過失がなかったというべきである。
第6 被告Fの責任について
1 善管注意義務違反の不存在
(1) Fは,平成10年3月31日,取締役副頭取を辞任しており,本件決算配当を決定した取締役会当時,取締役ではなく,何ら本件決算手続に関与していない。
(2) 原告ら指摘に係るFが副頭取在任中に参加した諸会議は,業務執行の一環として適切な業務運営を行うために開催されたものであり,これらの会議に参加した事実を違法と評価することはできない。
(3) Fは,事業推進部担当の専務取締役ないし副頭取として,原告の資産健全化という原告の当該年度における重要業務の執行に注力し,まさに資産の健全化ないし不良債権処理に奔走していたのであり,同人に,貸出金評価の基準(公正なる会計慣行)に反する資産評価を行うとの認識はなく,いわんや配当可能利益が存在しないにもかかわらず配当することの認識はなかった。
Fは,金銭債権の資産評価ないし償却・引当に関し,銀行業界において一般に理解されていた考え方(会計慣行)を基礎として職務を行っていた。したがって,仮ににわかに会計慣行が変遷したとしても,会計上の「継続性の原則」に照らし,新しい会計慣行に従わなかったことを違法と評価することはできない。
2 取締役在任中の言動と決算手続との因果関係
(1) 決算手続の独自性
商法は,決算手続の独自性を認め,当該決算手続に関与した取締役の責任を定めているのであって,決算手続以前に退任した取締役は,当該決算手続について何らの権限も有しないのであるから,決算手続に基づく利益処分案の提案に関し責任を負わない。
(2) 退職後の後発事象等
原告における決算手続は,当該期終了すなわち期末の経過後に開始されること,決算経理基準に基づき期末後45日以内に,業務報告書が大蔵省に提出されるが,大蔵省は事前に配当内容等について細かい行政指導を行なうのが常態とされており,行政指導によって決算を変更する可能性も存在していたこと,このような護送船団方式による細かな規制は平成10年3月期決算の際も厳然として存在していたこと,原告の自己査定基準ないしこれにもとづく決算については,同年5月21日から同年6月12日まで実施された日銀考査においても,監査役及び会計監査人による監査報告書においても,何ら違法であるとの指摘はないこと,当期においては,決算手続の過程において業務純益が予想値より約180億円の上方修正となり,これを不稼動資
産処理財源に振り向けて追加したこと,貸出先の不渡り・会社更生法の適用申請などの後発事情による変動があったことなどの事実がある。
(3) 在任中の言動と配当との因果関係の不存在
Fは,利益処分案の作成に関与しておらず,またその予備段階ともいえる決算手続にも関与していない。
もとよりFには「違法配当」について故意はなく,仮にこのような退任取締役の在任中の言動に善管注意義務違反(過失)と評価される事実があったとしても,同人の在任中の言動と配当による損害との間には因果関係がない。
したがって,原告らの被告Fに対する本件請求は失当である。
第7 本件中間配当について
資産査定通達等が,平成10年3月期において,唯一の「公正なる会計慣行」となり得なかった以上,原告らの本件中間配当に関する主張がその前提を欠くことは明らかである。
仮に,資産査定通達等が唯一の「公正なる会計慣行」となり,平成10年3月期末において,原告に配当可能利益が存在しなかったとしても,被告らが中間配当を決議した平成9年11月25日の段階での資産査定通達等及び金融機関を取り巻く経営環境に対する被告らの認識を前提とすれば,被告らは,税法基準により,資産査定通達等の不明瞭な部分が補われると理解しており,平成10年3月期末において配当可能利益が存在しないおそれがない(商法293条の5第5項ただし書)と判断したことにつき過失はない。
1 本件中間配当を決議した平成9年11月25日の時点で,平成10年3月末に採るべき経理基準すなわち不稼動資産の処理基準に関する被告らの共通認識
(1) 本件中間配当決議が行われたのは,資産査定通達等が発出・公表されて,わずか約4か月の時点である。資産査定通達等はガイドラインの性格を有するものであり,基準として明確でなく,銀行が拠るべき基準を示すものではなかった。したがって,被告らは,資産査定通達等により,銀行の会計処理の基準が変更されるものとは認識していなかった。さらにいえば,銀行が支援している貸出先に関し一般先と同様な引当金を計上するとか,翌期以降の支援予定額について引当金を計上することが,商法上の解釈として求められているとの認識は全く有することができなかった。
(2) 早期是正措置が平成10年4月から導入されることは承知していたが,この制度も試行的な段階にあり,導入後の状況を見て見直しがなされると理解していた。早期是正措置の導入は,「監督手法」の変更であり「会計基準」の変更との認識はなかった。
(3) 平成9年7月31日に大蔵省の通達により「決算経理基準」が変更になっているが,これは早期是正措置導入以降の自己査定制度導入に伴う手続面の変更であり,不稼働資産の処理基準の変更を明確に示すものではなく,従来の税法基準による処理の実態を直ちに変更するよう求めるものではないと認識していた。
(4) 本件中間配当を決議するに際し,平成10年3月期決算において必要とされる償却・引当額の算出は,早期是正措置導入に伴って必要とされる自己査定基準を作成し(平成9年6月末時点の資産に対する自己査定トライアル基準を作成),その自己査定結果を踏まえて行なったものであり,その時点で銀行の資産状態を把握するに最も適切な方法であり,かつ,行政の考え方も取り入れた手順を採用したと認識していた。
2 中間配当を決議した平成9年11月当時の金融機関を巡る経営環境に関する被告らの共通認識
(1) 平成9年11月に入り,三洋証券株式会社の破綻に始まり,株式会社北海道拓殖銀行,山一證券株式会社と相次いで大手金融機関の経営破綻が発生し,本件中間配当決議を行った時期は,政府,監督当局,金融界を挙げて金融システムの維持と貸し渋り批判への対応に奔走していた時期であった。
(2) この時点で各金融機関にとっては自行が支援する関連ノンバンクについては計画的・段階的に支援をして再建させていく事が最も重要な経営課題の一つであると考えており(大蔵省も平成13年までに金融機関の不稼動資産を計画的・段階的に処理していくいわゆるソフトランディングを基本的な考え方として採用していた。),被告らも同様の認識であった。
したがって,この時点で,被告らには,支援先について将来の支援予定額を引当てる等の必要性は全く認識していなかった。あえてこの時点で支援している関連ノンバンクについて引当を行なう,又はその意思をマーケットに明示(例えば中間決算の発表時に公表)することは,母体行として支援を放棄したものと受け止められ,即座に他行からの関連ノンバンクに対する貸出金の回収などの事態が起こり,これが連鎖的に金融システム不安,崩壊に繋がるリスクがあった。これは原告に限らず全ての金融機関において同様の認識であると考えていた。
以 上
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.