解説記事2005年09月05日 【会計解説】 企業会計基準公開草案第5号「事業分離等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第8号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」について(2005年9月5日号・№129)
実 務 解 説
企業会計基準公開草案第5号「事業分離等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第8号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 布施伸章
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年7月29日に以下の公開草案を公表し、平成17年10月3日までコメントを募集している(脚注1)。
・企業会計基準公開草案第5号「事業分離等に関する会計基準(案)」(以下「本会計基準案」という。)
・企業会計基準適用指針公開草案第8号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」(以下「本適用指針案」という。)
これらは、平成15年10月に企業会計審議会によって公表された「企業結合に係る会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)を受けて、平成17年1月に公表した「事業分離等に関する会計基準の検討状況の整理」「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針の検討状況の整理」(以下合わせて「検討状況の整理」という。)に対して寄せられたコメントも参考として、審議を重ね、取りまとめられたものである。
本稿では、本公開草案の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく今後、変更される可能性があるが、最終的なものと同様の表現をしている場合があることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 事業分離(分離元企業)の会計処理
本会計基準案は、一般に事業の成果をとらえる際の「投資の継続・清算」という概念に基づき、実現損益を認識するかどうかという観点から、分離元企業の会計処理を考えている。これは、企業結合の会計処理を一般的な会計処理と整合させるために考えられた「持分の継続・非継続」という概念の根底にある考え方である。
この結果、分離した事業に対する投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、一般的な売却や交換に伴う損益認識と同様に、分離元企業において移転損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。これを判断するための観察可能な具体的要件として、本会計基準案では、一般的な売却や交換の会計処理の考え方を踏まえ、対価が移転した事業と異なるかどうかという「対価の種類」を用い、さらに、企業結合会計基準では、共通支配下の取引の会計処理を定めているため、これとの整合性を前提にして、分離先企業が子会社にあたる場合を手がかりに、分離元企業の会計処理を考えている。
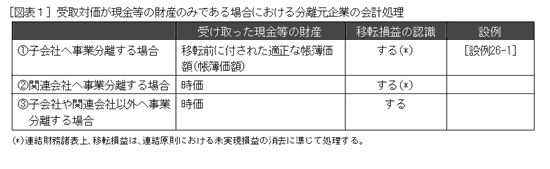
このため、本会計基準案は、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合、(2)分離先企業の株式のみである場合、(3)受取対価が現金等の財産と分離先企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、分離先企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。ここでは紙幅の関係により、(1)(2)の概要についてのみ記述する。
(1)受取対価が現金等の財産のみである場合
事業分離により、事業投資のリスクから免れるようになった場合に、投資は清算されたものとみなされるため、分離元企業が現金等、移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、通常、移転損益が認識される。
もっとも、企業結合会計基準における共通支配下の取引の会計処理の定めにより、分離先企業が子会社となる場合や子会社を分離先企業とする場合には、企業集団内における移転先の企業は移転元の帳簿価額により計上することとなる。したがって、共通支配下の取引又はこれに準ずる取引においては、基本的に移転損益を認識しないものの、分離元企業が受け取った現金等の財産の移転前に付された適正な帳簿価額が、移転した事業の適正な帳簿価額と異なる場合には、当該差額を移転損益として認識せざるをえないことになる([図表1]①参照)。
(2)受取対価が分離先企業の株式のみである場合
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合
企業結合会計基準からも明らかなように、この場合には、経済実態として分離元企業における当該事業に対する投資がそのまま継続していると考えられるため、親会社となる分離元企業において移転損益は認識されない。しかしながら、分離元企業の連結財務諸表上、移転した事業の適正な帳簿価額とこれに対応する分離元企業(親会社)の持分と差額(脚注2)は、連結原則における子会社の時価発行増資等に伴い生ずる親会社持分の増減額(持分変動差額)として取り扱うものとしている。
また、分離元企業は、分離先企業を取得する(既に子会社である場合の追加取得は「少数株主との取引」に該当する。)ため、連結財務諸表上、パーチェス法を適用し、分離先企業に対して(追加)投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との間に生ずる差額については、のれん(又は負ののれん)とすることとなる([図表2]①参照)。
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合
この場合、分離元企業による当該事業に対する投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見方と、投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見方がある。本会計基準案では、事業分離により、移転された事業に対する支配は失われても、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する事業投資を引き続き行っているとみられること等から、後者の考え方を採用している([図表2]②参照)。
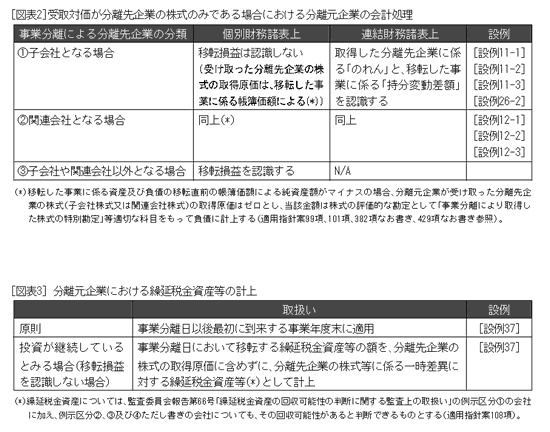
(3)分離元企業の税効果会計
本適用指針案では、分離元企業における繰延税金資産及び繰延税金負債(以下「繰延税金資産等」とする。)の計上について、[図表3]のようになるものとしている。
Ⅲ 結合当事企業等の株主に係る会計処理
1 被結合企業の株主に係る会計処理
企業結合により、保有していた被結合企業の株式が、結合企業の株式などの財と引き換えられた場合、被結合企業の株主にとって、その投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、交換損益を認識する場合と認識しない場合が考えられる。ここで、事業分離における分離元企業(例えば、吸収分割会社)と、100%子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業の株主(親会社)は、経済的効果が実質的に同じであることから、本会計基準案では、「検討状況の整理」と同様に、両者の会計処理を整合的なものとしている(脚注3)。
このため、本会計基準案では、分離元企業の会計処理と同様に、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合([図表4]参照)、(2)結合企業の株式のみである場合([図表5]参照)、(3)受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、被結合企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。
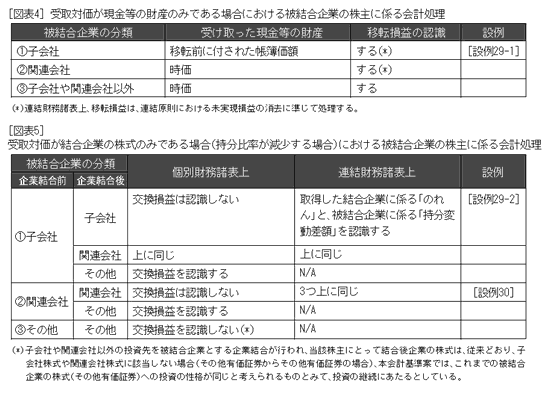
2 分割型の会社分割における分割会社の株主又は現金以外の財産の分配を受けた場合の株主に係る会計処理
いわゆる分割型の会社分割は、企業結合に該当しないが、本会計基準案では、当該分割会社の株主に係る会計処理や、株主が現金以外の財産(ただし、分割型の会社分割による新設会社又は承継会社の株式を除く。)の分配を受けた場合における当該株主の会計処理も定めている([図表6]参照)。
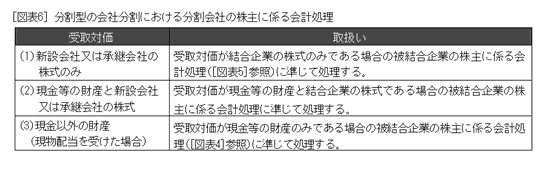
Ⅳ 企業結合の会計処理
企業結合の会計処理については、「検討状況の整理」の公表時に特にコメントを求めた7つの論点に関する本適用指針案における取扱いと「検討状況の整理」からの主な変更点を記載する。
1 「検討状況の整理」でコメントを求めた7つの論点への対応
論点1 適用指針の全般的な構成
「検討状況の整理」では、企業結合の会計上の分類毎(取得、持分の結合、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引)、かつ、代表的な企業再編の形式毎(合併、会社分割、株式交換及び株式移転等)に個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を示していた。コメント募集の結果、当該構成は支持されたため、本適用指針案でも同様の構成とし、さらに、適用指針の全体像をより把握しやすくするため、目次及び見出し番号を充実させている。
なお、企業結合の会計上の分類毎に適用される会計処理の概要は[図表7]のとおりである。
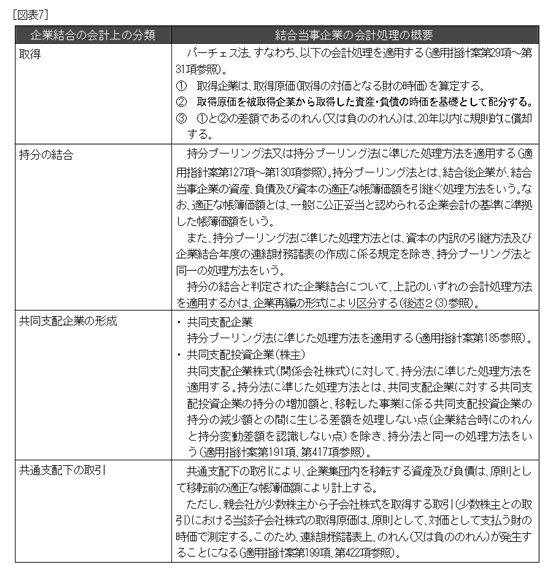
論点2 個別財務諸表に対する持分プーリング法の適用
「検討状況の整理」では、合併が持分の結合と判定された場合、当該合併に関する個別財務諸表上の会計処理は、みなし結合日に会計処理することが適当としつつ、関連する諸制度との調整を含め、引き続き検討することとしていた。
本適用指針案では、あるべき情報開示の観点と諸制度との調整結果を踏まえ、次のように会計処理することとしている(適用指針案第128項参照)。
(1)合併後の会社が連結財務諸表を作成する場合
① 連結財務諸表上の会計処理
企業結合会計基準の定めに従い、みなし結合日に合併の会計処理を行う。
② 個別財務諸表上の会計処理
合併期日に合併の会計処理を行う。また、以下の(2)の注記と同様の事項を注記することができる。
(2)合併後の会社が連結財務諸表を作成しない場合
個別財務諸表上、合併期日に合併の会計処理を行う。また、みなし結合日に合併したものとみなして算定した主要な損益計算書項目への影響の概算額を注記する。
論点3 取得と持分の結合の識別(特に潜在株式の議決権の行使の可能性の取扱い)
共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は、(1)対価要件、(2)議決権比率要件、(3)議決権比率以外の支配要件を順次判定し、すべての要件を満たした場合には「持分の結合」と判定し、1つでも要件を満たさなかった場合には、その時点で「取得」と判定することになる(適用指針案第7項参照)。
このうち、「検討状況の整理」では、議決権比率要件の判定にあたり、潜在株式の議決権行使の可能性については限定的に取扱うこととし、議決権比率要件で考慮されなかった潜在株式(例えば、特定の者に発行している潜在株式)については、議決権比率以外の支配要件で実質的に判定することとしていた。コメント募集の結果、当該取扱いは支持され、本適用指針案でも同様の取扱いとしている(適用指針案第19項~第21項、第25項参照)。
論点4 識別可能資産及び負債への取得原価の配分(企業結合が取得と判定された場合)
識別可能資産及び負債への取得原価の配分は、企業結合日における時価を基礎として行うが、「検討状況の整理」では、取得原価の科目別配分方法は、原則として示していなかった。コメント募集の結果も、取得原価の科目別配分方法を示すことについて、賛否両論があった。
本適用指針案では、取得原価の配分額の算定方法の基本的な考え方を示しているため(適用指針案第350項参照)、科目別の配分方法は特に示さないこととした。ただし、取得原価の配分額の算定に関する会計処理として、退職給付引当金への配分、被取得企業においてヘッジ会計が適用されていた場合の配分、被取得企業から新株予約権を承継した場合の配分を新たに示している(適用指針案第67項~第69項参照)。
論点5 研究開発費への取得原価の配分(企業結合が取得と判定された場合)
「検討状況の整理」では、取得企業が取得原価の一部を研究開発費等に配分する場合(企業結合会計基準三2(3)参照)とは、研究開発費等に係る会計基準との整合性の観点から、企業結合により取得した識別可能資産の企業結合後の使途が、取得企業において、同会計基準の定めにより研究開発費として処理すべき要件に該当する場合をいうものとしていた。コメント募集の結果、当該取扱いは基本的に支持され、本適用指針案でも同様の取扱いとしている(適用指針案第61項参照)。
論点6 共同支配企業の形成の判定のうち、契約要件の考え方
「検討状況の整理」では、共同支配企業の形成の判定規準として契約要件(共同支配投資企業となる投資企業が共同支配となる契約等を締結していること)を示していたが、コメント募集の結果、その内容については、おおむね支持された。
ただし、専門委員会における議論の結果、「検討状況の整理」において使用していた「拒否権」という用語は適当ではないと考えられたため削除するとともに、修正提案条項の要件も削除した。かわりに、本適用指針案では、ある重要な経営事項の決議の際に賛成しなくとも積極的に反対しない限りは、その決議事項につき賛成したものとみなすこととしている場合には、原則として、契約要件を満たしたことにはならないとした(ただし、共同支配企業への経営への関与の仕方が他の共同支配投資企業となる会社と異ならないと認められるような場合を除く。)(適用指針案第181項参照)。
論点7 注記事項
「検討状況の整理」では、企業結合に関連する以下の事項を注記することを提案し、これに対して様々な意見がよせられた。本適用指針案では、次のように取扱っている。
(1)企業結合年度の期首に企業結合が行われたものと仮定した当期の連結損益計算書への影響の概算額(企業結合会計基準四2(1)⑪及び適用指針案第361項参照)
「検討状況の整理」では、原則法による注記が困難な場合には、被取得企業の直前期の連結損益計算書の売上高及び利益情報による記載も認めていたが、当該方法は企業結合会計基準の趣旨とは必ずしも合致しないと考えられること等から本適用指針案では削除している。
また、「検討状況の整理」では、当該注記事項に関する基本的な考え方を示した「企業結合年度の期首に企業結合が行われたものと仮定した当期の連結損益計算書への影響の概算額」等の算定の考え方を添付していたが、本適用指針案では、これを適用指針に含めて示すこととした(適用指針案第318項~第319項参照)。
なお、当該注記事項が監査対象となるかどうかは別途検討されることになると思われる。
(2)重要な共同支配企業に対する投資情報の継続的開示(検討状況の整理第290項参照)
当該注記事項は、企業結合会計基準の解釈の範囲を超える可能性があるため、本適用指針案では削除している。
2 適用指針の検討状況からの主な変更点等
本適用指針案において、「検討状況の整理」から変更した主な事項及び主なコメントへの対応については、以下のとおりである(前述1を除く。)。
(1)全般的事項
本適用指針案では、「吸収合併存続会社」等、会社法で使用される用語を用いて記載することとした(適用指針案第5項等参照)。また、潜在株式の議決権行使の可能性の取扱い等、会社法上の制度と整合性のある記述とした(適用指針案第19項等参照)。
(2)取得の会計処理
企業結合が取得と判定された場合には、取得と持分の結合とを識別する規準と整合した形で取得企業を決定し、[図表7]で示したように、パーチェス法を適用する。
本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 企業結合年度の翌年度に繰延税金資産の回収見込額を修正した場合には、企業結合年度の判定をより重視するものとし、原則として、企業結合年度の翌年度の損益として処理し、企業結合年度における回収見込額の修正であることが明らかなときは、企業結合日におけるのれんの修正として処理することとした(適用指針案第74項参照)。なお、「検討状況の整理」では、回収見込額の修正は、原則として、企業結合日ののれんの額を修正し、それが企業結合の翌年度の状況変化が明らかな場合に限り、翌年度の損益とすることとしていた。
② 株式交換完全親会社等が取得した株式交換完全子会社等の株式に係る税効果は、原則として認識しない旨を示した(適用指針案第115項及び第123項参照)
③ 連結財務諸表の作成上、株式交換完全親会社等が取得原価の配分額の算定にあたり、みなし取得日を使用した場合の取得原価の算定日の取扱いを示した(適用指針案第117項、第126項など参照)。
④ 企業結合が取得と判定された場合には、パーチェス法の考え方を徹底するため、合併の場合においても、吸収合併消滅会社の土地再評価差額金は引継がないこととした(適用指針案第80項及び第81項参照)(脚注4)。
上記のほか、「検討状況の整理」へのコメント等において、のれんは本来、非償却資産として取扱うべきであるという意見があった。これは企業結合会計基準の定めに関するものであるが、再検討の結果、企業結合会計基準の定めを支持する旨の考え方が確認された(「コメント募集」3.参考資料)。
また、当該コメント等においては、のれんの非償却が認められないのであれば、企業結合日にのれんを全額償却し、その償却費を特別損失に計上することも容認すべきであるという意見も含まれていた。これについても検討した結果、「検討状況の整理」の取扱いが適当と判断されたため、その理由を結論の背景に追加記載した(適用指針案第369項、関連して第370項及び第371項参照)。
(3)持分の結合の会計処理
企業結合が持分の結合と判定された場合には、[図表7]で示したように、持分プーリング法又は持分プーリング法に準じた処理方法を適用する。本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 持分プーリング法が適用される場合と持分プーリング法に準じた処理方法が適用される場合を企業再編の形式により区分することとした。この結果、「検討状況の整理」では、親会社が異なる子会社同士の合併(持分の結合)の場合には、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することとしていたが、本適用指針案では持分プーリング法を適用することになる(適用指針案第127項、第129項参照)。
② 吸収分割が持分の結合と判定され、吸収分割会社から移転される事業の中に再評価した土地が含まれている場合には、持分プーリング法の考え方を徹底するため、会社分割の場合であっても、当該土地再評価差額金を引き継ぐこととした(適用指針案第158項参照)(脚注4)。
③ 吸収分割又は共同新設分割が持分の結合と判定された場合、「検討状況の整理」では、共同支配企業の形成に準じて、吸収分割会社等(分離元企業)の連結財務諸表上、当該関連会社株式に対して持分法に準じた処理方法を適用することとしていたが、本適用指針案では、持分法を適用し、のれん及び持分変動差額を認識することとした(適用指針案第152項参照)。
(4)共同支配企業の形成の会計処理
次の要件のすべてを満たし共同支配企業の形成と判定された場合(適用指針案第178項から第184項)には、[図表7]で示したように、持分プーリング法に準じた処理方法を適用する。
① 独立企業要件:共同支配投資企業となる投資企業は、複数の独立した企業から構成されていること
② 契約要件:共同支配投資企業となる投資企業が共同支配となる契約等(重要な経営事項の決定は共同支配投資企業全員の同意が必要である等の定めを含む。)を締結していること
③ 対価要件:企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること
④ その他の支配要件:上記以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと
本適用指針案では、前述のとおり、契約要件において、「検討状況の整理」で用いられていた「拒否権」という表現や修正提案条項の要件を修正した(適用指針案第181項参照)。
(5)共通支配下の取引等の会計処理
企業結合が共通支配下の取引に該当した場合には、[図表7]で示したように、原則として、移転元の適正な帳簿価額を基礎として会計処理し、少数株主との取引に該当する部分については時価を基礎として会計処理する。本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 共通支配下の取引の範囲について、「検討状況の整理」では、最終的な支配者を「同一の株主」としていたが、本適用指針案では、「同一の株主」の範囲を明確にし(緊密者・同意者が保有する議決権をあわせて支配の有無を判定する。)、連結範囲との整合性を図っている(適用指針案第201項参照))。
② 適用指針で取り扱う企業再編の形式の範囲を大幅に増やし、以下の例を示すこととした(適用指針案第202項参照)。
a 親会社と子会社との企業結合
・親会社(消滅会社)と子会社(存続会社)との合併(適用指針案第208項から第211項参照)
・事業譲渡(親会社の事業を子会社に移転した場合)(適用指針案第221項から第223項参照)
・会社分割において、対価に現金等の財産が含まれる場合(適用指針案第227項から第229項参照)
b 子会社と子会社との企業結合
子会社同士の合併を含め、5つの取扱いを示した(適用指針案第239項から第254項参照)。
このほか、単独で行った分割型の会社分割の会計処理も示している(適用指針案第260項から第261項参照)。
③ 資本の部の引継ぎに関し、以下の場合には、吸収合併存続会社は、原則として、資本の部の内訳を引き継ぐこととした。
・子会社が親会社を合併した場合(適用指針案第209項参照)
・子会社同士が合併した場合(支配の主体が個人・法人を問わない。適用指針案第244項、第251項参照)
また、以下の場合には、承継会社は、原則として払込資本を増加させるが、一定の条件を満たしたときは、分割会社の資本の部の内訳を適切に配分した額をもって計上できることとした。
・親会社が子会社に分割型の会社分割により事業を移転した場合(適用指針案第231項参照)
・単独で分割型の会社分割が行われた場合(適用指針案第261項参照)
脚注
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_ed/combination/combination.html)参照。
2 これは、分離元企業の事業の時価に増加した少数株主の持分比率を乗じた額(分離元企業の事業が移転されたとみなされる額)と移転した事業に係る適正な帳簿価額による純資産額に増加した少数株主の持分比率を乗じた額(移転した事業に係る親会社の持分の減少額)との差額にあたる。
3 さらに、本会計基準案では、被結合企業の株主が親会社である場合には、被結合企業の株式をすべて保有しているとき(被結合企業が100%子会社の場合)でも、それ以外のとき(被結合企業が100%子会社以外の子会社の場合)でも整合的な会計処理とするよう定めている。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)により、土地の再評価に関する法律が改正され、同法第7条の2及び第9条は削除されている。
企業会計基準公開草案第5号「事業分離等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第8号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 布施伸章
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年7月29日に以下の公開草案を公表し、平成17年10月3日までコメントを募集している(脚注1)。
・企業会計基準公開草案第5号「事業分離等に関する会計基準(案)」(以下「本会計基準案」という。)
・企業会計基準適用指針公開草案第8号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」(以下「本適用指針案」という。)
これらは、平成15年10月に企業会計審議会によって公表された「企業結合に係る会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)を受けて、平成17年1月に公表した「事業分離等に関する会計基準の検討状況の整理」「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針の検討状況の整理」(以下合わせて「検討状況の整理」という。)に対して寄せられたコメントも参考として、審議を重ね、取りまとめられたものである。
本稿では、本公開草案の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく今後、変更される可能性があるが、最終的なものと同様の表現をしている場合があることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 事業分離(分離元企業)の会計処理
本会計基準案は、一般に事業の成果をとらえる際の「投資の継続・清算」という概念に基づき、実現損益を認識するかどうかという観点から、分離元企業の会計処理を考えている。これは、企業結合の会計処理を一般的な会計処理と整合させるために考えられた「持分の継続・非継続」という概念の根底にある考え方である。
この結果、分離した事業に対する投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、一般的な売却や交換に伴う損益認識と同様に、分離元企業において移転損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。これを判断するための観察可能な具体的要件として、本会計基準案では、一般的な売却や交換の会計処理の考え方を踏まえ、対価が移転した事業と異なるかどうかという「対価の種類」を用い、さらに、企業結合会計基準では、共通支配下の取引の会計処理を定めているため、これとの整合性を前提にして、分離先企業が子会社にあたる場合を手がかりに、分離元企業の会計処理を考えている。
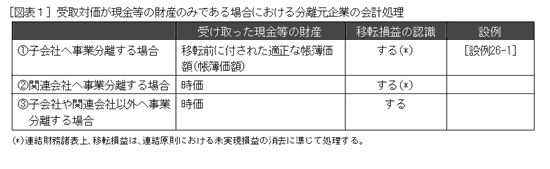
このため、本会計基準案は、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合、(2)分離先企業の株式のみである場合、(3)受取対価が現金等の財産と分離先企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、分離先企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。ここでは紙幅の関係により、(1)(2)の概要についてのみ記述する。
(1)受取対価が現金等の財産のみである場合
事業分離により、事業投資のリスクから免れるようになった場合に、投資は清算されたものとみなされるため、分離元企業が現金等、移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、通常、移転損益が認識される。
もっとも、企業結合会計基準における共通支配下の取引の会計処理の定めにより、分離先企業が子会社となる場合や子会社を分離先企業とする場合には、企業集団内における移転先の企業は移転元の帳簿価額により計上することとなる。したがって、共通支配下の取引又はこれに準ずる取引においては、基本的に移転損益を認識しないものの、分離元企業が受け取った現金等の財産の移転前に付された適正な帳簿価額が、移転した事業の適正な帳簿価額と異なる場合には、当該差額を移転損益として認識せざるをえないことになる([図表1]①参照)。
(2)受取対価が分離先企業の株式のみである場合
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合
企業結合会計基準からも明らかなように、この場合には、経済実態として分離元企業における当該事業に対する投資がそのまま継続していると考えられるため、親会社となる分離元企業において移転損益は認識されない。しかしながら、分離元企業の連結財務諸表上、移転した事業の適正な帳簿価額とこれに対応する分離元企業(親会社)の持分と差額(脚注2)は、連結原則における子会社の時価発行増資等に伴い生ずる親会社持分の増減額(持分変動差額)として取り扱うものとしている。
また、分離元企業は、分離先企業を取得する(既に子会社である場合の追加取得は「少数株主との取引」に該当する。)ため、連結財務諸表上、パーチェス法を適用し、分離先企業に対して(追加)投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との間に生ずる差額については、のれん(又は負ののれん)とすることとなる([図表2]①参照)。
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合
この場合、分離元企業による当該事業に対する投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見方と、投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見方がある。本会計基準案では、事業分離により、移転された事業に対する支配は失われても、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する事業投資を引き続き行っているとみられること等から、後者の考え方を採用している([図表2]②参照)。
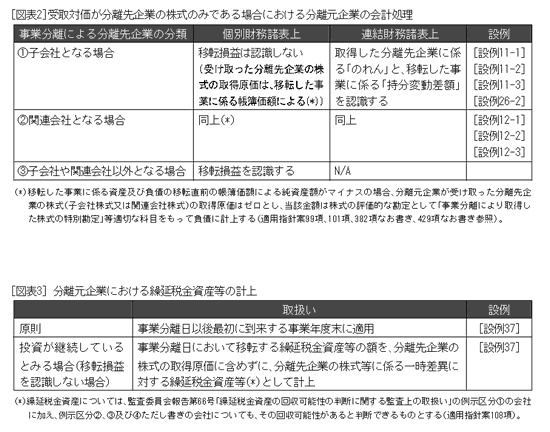
(3)分離元企業の税効果会計
本適用指針案では、分離元企業における繰延税金資産及び繰延税金負債(以下「繰延税金資産等」とする。)の計上について、[図表3]のようになるものとしている。
Ⅲ 結合当事企業等の株主に係る会計処理
1 被結合企業の株主に係る会計処理
企業結合により、保有していた被結合企業の株式が、結合企業の株式などの財と引き換えられた場合、被結合企業の株主にとって、その投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、交換損益を認識する場合と認識しない場合が考えられる。ここで、事業分離における分離元企業(例えば、吸収分割会社)と、100%子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業の株主(親会社)は、経済的効果が実質的に同じであることから、本会計基準案では、「検討状況の整理」と同様に、両者の会計処理を整合的なものとしている(脚注3)。
このため、本会計基準案では、分離元企業の会計処理と同様に、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合([図表4]参照)、(2)結合企業の株式のみである場合([図表5]参照)、(3)受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、被結合企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。
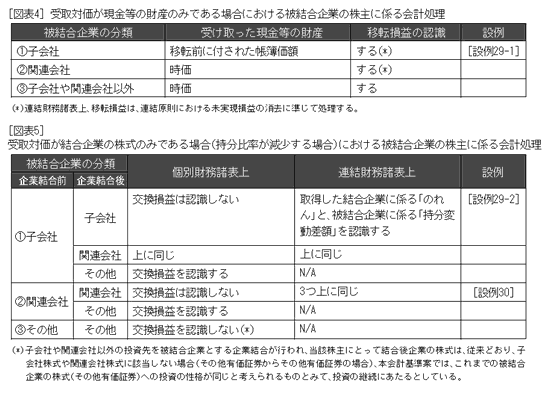
2 分割型の会社分割における分割会社の株主又は現金以外の財産の分配を受けた場合の株主に係る会計処理
いわゆる分割型の会社分割は、企業結合に該当しないが、本会計基準案では、当該分割会社の株主に係る会計処理や、株主が現金以外の財産(ただし、分割型の会社分割による新設会社又は承継会社の株式を除く。)の分配を受けた場合における当該株主の会計処理も定めている([図表6]参照)。
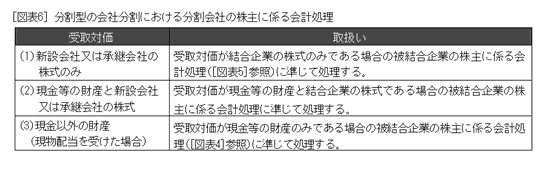
Ⅳ 企業結合の会計処理
企業結合の会計処理については、「検討状況の整理」の公表時に特にコメントを求めた7つの論点に関する本適用指針案における取扱いと「検討状況の整理」からの主な変更点を記載する。
1 「検討状況の整理」でコメントを求めた7つの論点への対応
論点1 適用指針の全般的な構成
「検討状況の整理」では、企業結合の会計上の分類毎(取得、持分の結合、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引)、かつ、代表的な企業再編の形式毎(合併、会社分割、株式交換及び株式移転等)に個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を示していた。コメント募集の結果、当該構成は支持されたため、本適用指針案でも同様の構成とし、さらに、適用指針の全体像をより把握しやすくするため、目次及び見出し番号を充実させている。
なお、企業結合の会計上の分類毎に適用される会計処理の概要は[図表7]のとおりである。
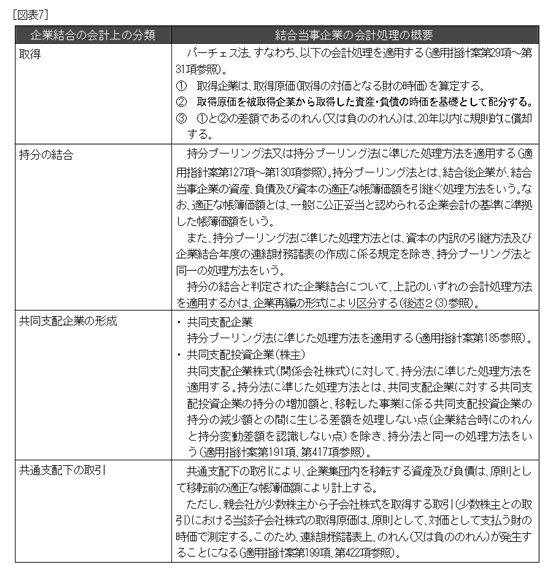
論点2 個別財務諸表に対する持分プーリング法の適用
「検討状況の整理」では、合併が持分の結合と判定された場合、当該合併に関する個別財務諸表上の会計処理は、みなし結合日に会計処理することが適当としつつ、関連する諸制度との調整を含め、引き続き検討することとしていた。
本適用指針案では、あるべき情報開示の観点と諸制度との調整結果を踏まえ、次のように会計処理することとしている(適用指針案第128項参照)。
(1)合併後の会社が連結財務諸表を作成する場合
① 連結財務諸表上の会計処理
企業結合会計基準の定めに従い、みなし結合日に合併の会計処理を行う。
② 個別財務諸表上の会計処理
合併期日に合併の会計処理を行う。また、以下の(2)の注記と同様の事項を注記することができる。
(2)合併後の会社が連結財務諸表を作成しない場合
個別財務諸表上、合併期日に合併の会計処理を行う。また、みなし結合日に合併したものとみなして算定した主要な損益計算書項目への影響の概算額を注記する。
論点3 取得と持分の結合の識別(特に潜在株式の議決権の行使の可能性の取扱い)
共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は、(1)対価要件、(2)議決権比率要件、(3)議決権比率以外の支配要件を順次判定し、すべての要件を満たした場合には「持分の結合」と判定し、1つでも要件を満たさなかった場合には、その時点で「取得」と判定することになる(適用指針案第7項参照)。
このうち、「検討状況の整理」では、議決権比率要件の判定にあたり、潜在株式の議決権行使の可能性については限定的に取扱うこととし、議決権比率要件で考慮されなかった潜在株式(例えば、特定の者に発行している潜在株式)については、議決権比率以外の支配要件で実質的に判定することとしていた。コメント募集の結果、当該取扱いは支持され、本適用指針案でも同様の取扱いとしている(適用指針案第19項~第21項、第25項参照)。
論点4 識別可能資産及び負債への取得原価の配分(企業結合が取得と判定された場合)
識別可能資産及び負債への取得原価の配分は、企業結合日における時価を基礎として行うが、「検討状況の整理」では、取得原価の科目別配分方法は、原則として示していなかった。コメント募集の結果も、取得原価の科目別配分方法を示すことについて、賛否両論があった。
本適用指針案では、取得原価の配分額の算定方法の基本的な考え方を示しているため(適用指針案第350項参照)、科目別の配分方法は特に示さないこととした。ただし、取得原価の配分額の算定に関する会計処理として、退職給付引当金への配分、被取得企業においてヘッジ会計が適用されていた場合の配分、被取得企業から新株予約権を承継した場合の配分を新たに示している(適用指針案第67項~第69項参照)。
論点5 研究開発費への取得原価の配分(企業結合が取得と判定された場合)
「検討状況の整理」では、取得企業が取得原価の一部を研究開発費等に配分する場合(企業結合会計基準三2(3)参照)とは、研究開発費等に係る会計基準との整合性の観点から、企業結合により取得した識別可能資産の企業結合後の使途が、取得企業において、同会計基準の定めにより研究開発費として処理すべき要件に該当する場合をいうものとしていた。コメント募集の結果、当該取扱いは基本的に支持され、本適用指針案でも同様の取扱いとしている(適用指針案第61項参照)。
論点6 共同支配企業の形成の判定のうち、契約要件の考え方
「検討状況の整理」では、共同支配企業の形成の判定規準として契約要件(共同支配投資企業となる投資企業が共同支配となる契約等を締結していること)を示していたが、コメント募集の結果、その内容については、おおむね支持された。
ただし、専門委員会における議論の結果、「検討状況の整理」において使用していた「拒否権」という用語は適当ではないと考えられたため削除するとともに、修正提案条項の要件も削除した。かわりに、本適用指針案では、ある重要な経営事項の決議の際に賛成しなくとも積極的に反対しない限りは、その決議事項につき賛成したものとみなすこととしている場合には、原則として、契約要件を満たしたことにはならないとした(ただし、共同支配企業への経営への関与の仕方が他の共同支配投資企業となる会社と異ならないと認められるような場合を除く。)(適用指針案第181項参照)。
論点7 注記事項
「検討状況の整理」では、企業結合に関連する以下の事項を注記することを提案し、これに対して様々な意見がよせられた。本適用指針案では、次のように取扱っている。
(1)企業結合年度の期首に企業結合が行われたものと仮定した当期の連結損益計算書への影響の概算額(企業結合会計基準四2(1)⑪及び適用指針案第361項参照)
「検討状況の整理」では、原則法による注記が困難な場合には、被取得企業の直前期の連結損益計算書の売上高及び利益情報による記載も認めていたが、当該方法は企業結合会計基準の趣旨とは必ずしも合致しないと考えられること等から本適用指針案では削除している。
また、「検討状況の整理」では、当該注記事項に関する基本的な考え方を示した「企業結合年度の期首に企業結合が行われたものと仮定した当期の連結損益計算書への影響の概算額」等の算定の考え方を添付していたが、本適用指針案では、これを適用指針に含めて示すこととした(適用指針案第318項~第319項参照)。
なお、当該注記事項が監査対象となるかどうかは別途検討されることになると思われる。
(2)重要な共同支配企業に対する投資情報の継続的開示(検討状況の整理第290項参照)
当該注記事項は、企業結合会計基準の解釈の範囲を超える可能性があるため、本適用指針案では削除している。
2 適用指針の検討状況からの主な変更点等
本適用指針案において、「検討状況の整理」から変更した主な事項及び主なコメントへの対応については、以下のとおりである(前述1を除く。)。
(1)全般的事項
本適用指針案では、「吸収合併存続会社」等、会社法で使用される用語を用いて記載することとした(適用指針案第5項等参照)。また、潜在株式の議決権行使の可能性の取扱い等、会社法上の制度と整合性のある記述とした(適用指針案第19項等参照)。
(2)取得の会計処理
企業結合が取得と判定された場合には、取得と持分の結合とを識別する規準と整合した形で取得企業を決定し、[図表7]で示したように、パーチェス法を適用する。
本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 企業結合年度の翌年度に繰延税金資産の回収見込額を修正した場合には、企業結合年度の判定をより重視するものとし、原則として、企業結合年度の翌年度の損益として処理し、企業結合年度における回収見込額の修正であることが明らかなときは、企業結合日におけるのれんの修正として処理することとした(適用指針案第74項参照)。なお、「検討状況の整理」では、回収見込額の修正は、原則として、企業結合日ののれんの額を修正し、それが企業結合の翌年度の状況変化が明らかな場合に限り、翌年度の損益とすることとしていた。
② 株式交換完全親会社等が取得した株式交換完全子会社等の株式に係る税効果は、原則として認識しない旨を示した(適用指針案第115項及び第123項参照)
③ 連結財務諸表の作成上、株式交換完全親会社等が取得原価の配分額の算定にあたり、みなし取得日を使用した場合の取得原価の算定日の取扱いを示した(適用指針案第117項、第126項など参照)。
④ 企業結合が取得と判定された場合には、パーチェス法の考え方を徹底するため、合併の場合においても、吸収合併消滅会社の土地再評価差額金は引継がないこととした(適用指針案第80項及び第81項参照)(脚注4)。
上記のほか、「検討状況の整理」へのコメント等において、のれんは本来、非償却資産として取扱うべきであるという意見があった。これは企業結合会計基準の定めに関するものであるが、再検討の結果、企業結合会計基準の定めを支持する旨の考え方が確認された(「コメント募集」3.参考資料)。
また、当該コメント等においては、のれんの非償却が認められないのであれば、企業結合日にのれんを全額償却し、その償却費を特別損失に計上することも容認すべきであるという意見も含まれていた。これについても検討した結果、「検討状況の整理」の取扱いが適当と判断されたため、その理由を結論の背景に追加記載した(適用指針案第369項、関連して第370項及び第371項参照)。
(3)持分の結合の会計処理
企業結合が持分の結合と判定された場合には、[図表7]で示したように、持分プーリング法又は持分プーリング法に準じた処理方法を適用する。本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 持分プーリング法が適用される場合と持分プーリング法に準じた処理方法が適用される場合を企業再編の形式により区分することとした。この結果、「検討状況の整理」では、親会社が異なる子会社同士の合併(持分の結合)の場合には、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することとしていたが、本適用指針案では持分プーリング法を適用することになる(適用指針案第127項、第129項参照)。
② 吸収分割が持分の結合と判定され、吸収分割会社から移転される事業の中に再評価した土地が含まれている場合には、持分プーリング法の考え方を徹底するため、会社分割の場合であっても、当該土地再評価差額金を引き継ぐこととした(適用指針案第158項参照)(脚注4)。
③ 吸収分割又は共同新設分割が持分の結合と判定された場合、「検討状況の整理」では、共同支配企業の形成に準じて、吸収分割会社等(分離元企業)の連結財務諸表上、当該関連会社株式に対して持分法に準じた処理方法を適用することとしていたが、本適用指針案では、持分法を適用し、のれん及び持分変動差額を認識することとした(適用指針案第152項参照)。
(4)共同支配企業の形成の会計処理
次の要件のすべてを満たし共同支配企業の形成と判定された場合(適用指針案第178項から第184項)には、[図表7]で示したように、持分プーリング法に準じた処理方法を適用する。
① 独立企業要件:共同支配投資企業となる投資企業は、複数の独立した企業から構成されていること
② 契約要件:共同支配投資企業となる投資企業が共同支配となる契約等(重要な経営事項の決定は共同支配投資企業全員の同意が必要である等の定めを含む。)を締結していること
③ 対価要件:企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること
④ その他の支配要件:上記以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと
本適用指針案では、前述のとおり、契約要件において、「検討状況の整理」で用いられていた「拒否権」という表現や修正提案条項の要件を修正した(適用指針案第181項参照)。
(5)共通支配下の取引等の会計処理
企業結合が共通支配下の取引に該当した場合には、[図表7]で示したように、原則として、移転元の適正な帳簿価額を基礎として会計処理し、少数株主との取引に該当する部分については時価を基礎として会計処理する。本適用指針案では、「検討状況の整理」から以下の点を変更している。
① 共通支配下の取引の範囲について、「検討状況の整理」では、最終的な支配者を「同一の株主」としていたが、本適用指針案では、「同一の株主」の範囲を明確にし(緊密者・同意者が保有する議決権をあわせて支配の有無を判定する。)、連結範囲との整合性を図っている(適用指針案第201項参照))。
② 適用指針で取り扱う企業再編の形式の範囲を大幅に増やし、以下の例を示すこととした(適用指針案第202項参照)。
a 親会社と子会社との企業結合
・親会社(消滅会社)と子会社(存続会社)との合併(適用指針案第208項から第211項参照)
・事業譲渡(親会社の事業を子会社に移転した場合)(適用指針案第221項から第223項参照)
・会社分割において、対価に現金等の財産が含まれる場合(適用指針案第227項から第229項参照)
b 子会社と子会社との企業結合
子会社同士の合併を含め、5つの取扱いを示した(適用指針案第239項から第254項参照)。
このほか、単独で行った分割型の会社分割の会計処理も示している(適用指針案第260項から第261項参照)。
③ 資本の部の引継ぎに関し、以下の場合には、吸収合併存続会社は、原則として、資本の部の内訳を引き継ぐこととした。
・子会社が親会社を合併した場合(適用指針案第209項参照)
・子会社同士が合併した場合(支配の主体が個人・法人を問わない。適用指針案第244項、第251項参照)
また、以下の場合には、承継会社は、原則として払込資本を増加させるが、一定の条件を満たしたときは、分割会社の資本の部の内訳を適切に配分した額をもって計上できることとした。
・親会社が子会社に分割型の会社分割により事業を移転した場合(適用指針案第231項参照)
・単独で分割型の会社分割が行われた場合(適用指針案第261項参照)
脚注
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_ed/combination/combination.html)参照。
2 これは、分離元企業の事業の時価に増加した少数株主の持分比率を乗じた額(分離元企業の事業が移転されたとみなされる額)と移転した事業に係る適正な帳簿価額による純資産額に増加した少数株主の持分比率を乗じた額(移転した事業に係る親会社の持分の減少額)との差額にあたる。
3 さらに、本会計基準案では、被結合企業の株主が親会社である場合には、被結合企業の株式をすべて保有しているとき(被結合企業が100%子会社の場合)でも、それ以外のとき(被結合企業が100%子会社以外の子会社の場合)でも整合的な会計処理とするよう定めている。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)により、土地の再評価に関する法律が改正され、同法第7条の2及び第9条は削除されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















