解説記事2005年11月28日 【ニュース特集】 個別計算書類に「株主資本等変動計算書」・「個別注記表」(2005年11月28日号・№140)
ニュース特集
会社法会計はこうなる!
個別計算書類に「株主資本等変動計算書」・「個別注記表」
新しい会社法の施行は、平成18年5月に予定されている。実務家は会社法の全体像を把握するために、会社法の細則を規定した法務省令案の公表を心待ちにしているが、法務省令案の公表は、11月下旬と予想されている。一方、会社法に関する解説書(雑誌・書籍)の公刊は相次ぎ、立法担当官によるブログが開設されるなど、会社法に関する情報は氾濫している。これらの情報から、法務省令(施行規則)が規定する計算書類の概要が見えてきた。
会社法に規定する計算書類はこれだ!
会社法435条2項は、「株式会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」と規定し、会社法444条1項は、「会計監査人設置会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)を作成しなければならない。」と規定している。
会社法に明示されている貸借対照表・損益計算書以外の計算書類は、法務省令で定められるものである。本誌が先週号(No.139)でお伝えしたように、法務省令(案)では、個別計算書類として、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」が明示されることが明らかとなった。また、法務省令(案)の連結計算書類には、商法特例法に規定されていた連結貸借対照表・連結損益計算書のほか、「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」が明示されることになる。会社法に規定する計算書類の概要は下図のように変更される。
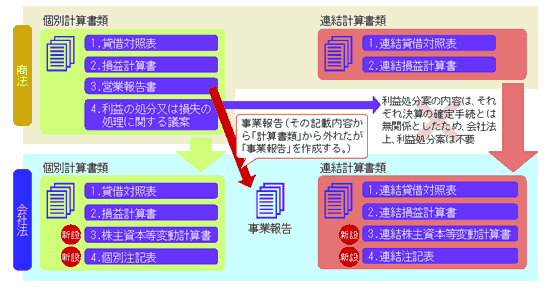
ASB待ちの「株主資本等変動計算書」
株主資本等変動計算書は、現行商法及び商法施行規則に見られないものである(新しい計算書類である。)。企業会計基準委員会(ASB)では、平成17年8月30日に、「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」(本誌No.130(2005.9.12)号34頁に掲載)を公表しているが、「連結株主資本等変動計算書等は、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するもの」と、作成目的を明らかにしている。
公表されている会計基準の適用指針(案)によれば、株主資本等変動計算書は、純資産の部に表示される①資本金②資本剰余金(資本準備金・その他資本剰余金)③利益剰余金(利益準備金・任意積立金等・その他利益剰余金)④自己株式⑤評価・換算差額等⑥新株予約権⑦少数株主持分(連結に限る)の各項目に区分して、当期における変動が表示されるものである。ASBは、12月初旬に「株主資本等変動計算書等に関する会計基準」を正式決定する予定であり、正式決定した会計基準の内容次第では、法務省令に規定する「株主資本等変動計算書」についても、調整を行う余地があるとしている。
「注記表」は、全ての注記を一覧で
「注記表」もこれまでの計算書類には見られないものである(新しい計算書類である。)。しかし、計算書類への注記については、有価証券の評価基準及び評価方法などの「重要な会計方針の注記(商規45条)」、担保に供されている資産(商規75条)などの「貸借対照表関係」など、多くの注記が行われてきた。商法施行規則に基づく注記のほか、「財務諸表等規則8条の14に規定された「継続企業の前提に関する注記」、新しい計算書類である「株主資本等変動計算書に関する注記」などを、各項目に区分し、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等との関連を明らかにしながら、一覧で表示するのが、新しい計算書類「注記表」だ。なお、公開会社でない株式会社は、注記の全部又は一部を省略することができる旨も法務省令に明示されることになりそうだ。
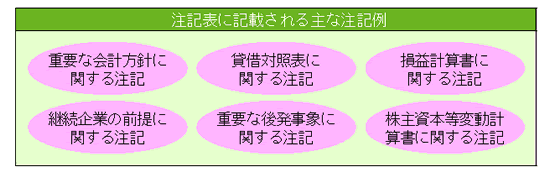
「営業報告書」は「事業報告」に
商法が計算書類と規定していた「営業報告書」は、会社法では、計算書類からはずれ、「事業報告」として作成することになる。立法担当官は、「営業報告書に記載される内容が必ずしも計算に関するものとはいえないことから、『計算書類』から除外した。」と説明している。
計算書類は、会計監査人の監査の対象であり、会計参与が作成権限を有するものである。会社法では、計算書類の範囲を明確(実態に即したもの)にすることが要請されていた。
一方、商法が計算書類と規定していた「利益処分案(又は損失処理案)」については、立法担当官が「剰余金の配当(会454条)、役員の賞与(会361条①)、資本の部の計数変動(会448条ほか)などに分解したうえで、これを決算の確定手続とは無関係に随時行うことができることと整理したため、会社法には、利益処分案は存在しない。」と説明している。
会社法では、利益処分案は不要となって、廃止されることになった。
会計基準に合わせ、B/S・P/Lも変わる!
貸借対照表・損益計算書の表示においても、会計基準の動向を踏まえて、変更が行われる。貸借対照表の「資本の部」は、その区分の名称を「純資産の部」に改めた上で、評価換算差額等・新株予約権の区分が設けられる。評価差額金は払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないことから、株主資本以外の項目として、純資産の部に新たな区分が設けられた。また、新株予約権者は、株主でも債権者でもないため、新株予約権は、新たな区分が設けられた。これらは、ASBが設定する「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(本誌No.128(2005.8.29)号12頁以下)に対応するものである。
さらに、損益計算書は、当期純利益金額までの計算となる。これまで、損益計算書は、当期純利益金額に前期繰越利益(損失)を加減して、当期未処分利益金額まで計算してきたが、これらについては、株主資本等変動計算書において表示されることになるため、損益計算書は、当期純利益金額までの計算で終わることになる。
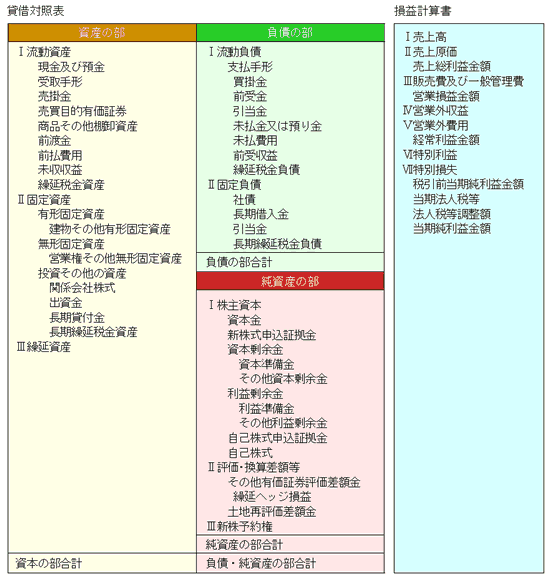
会社法会計はこうなる!
個別計算書類に「株主資本等変動計算書」・「個別注記表」
新しい会社法の施行は、平成18年5月に予定されている。実務家は会社法の全体像を把握するために、会社法の細則を規定した法務省令案の公表を心待ちにしているが、法務省令案の公表は、11月下旬と予想されている。一方、会社法に関する解説書(雑誌・書籍)の公刊は相次ぎ、立法担当官によるブログが開設されるなど、会社法に関する情報は氾濫している。これらの情報から、法務省令(施行規則)が規定する計算書類の概要が見えてきた。
会社法に規定する計算書類はこれだ!
会社法435条2項は、「株式会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」と規定し、会社法444条1項は、「会計監査人設置会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)を作成しなければならない。」と規定している。
会社法に明示されている貸借対照表・損益計算書以外の計算書類は、法務省令で定められるものである。本誌が先週号(No.139)でお伝えしたように、法務省令(案)では、個別計算書類として、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」が明示されることが明らかとなった。また、法務省令(案)の連結計算書類には、商法特例法に規定されていた連結貸借対照表・連結損益計算書のほか、「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」が明示されることになる。会社法に規定する計算書類の概要は下図のように変更される。
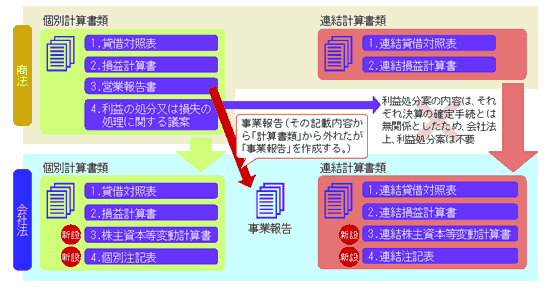
ASB待ちの「株主資本等変動計算書」
株主資本等変動計算書は、現行商法及び商法施行規則に見られないものである(新しい計算書類である。)。企業会計基準委員会(ASB)では、平成17年8月30日に、「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」(本誌No.130(2005.9.12)号34頁に掲載)を公表しているが、「連結株主資本等変動計算書等は、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するもの」と、作成目的を明らかにしている。
公表されている会計基準の適用指針(案)によれば、株主資本等変動計算書は、純資産の部に表示される①資本金②資本剰余金(資本準備金・その他資本剰余金)③利益剰余金(利益準備金・任意積立金等・その他利益剰余金)④自己株式⑤評価・換算差額等⑥新株予約権⑦少数株主持分(連結に限る)の各項目に区分して、当期における変動が表示されるものである。ASBは、12月初旬に「株主資本等変動計算書等に関する会計基準」を正式決定する予定であり、正式決定した会計基準の内容次第では、法務省令に規定する「株主資本等変動計算書」についても、調整を行う余地があるとしている。
「注記表」は、全ての注記を一覧で
「注記表」もこれまでの計算書類には見られないものである(新しい計算書類である。)。しかし、計算書類への注記については、有価証券の評価基準及び評価方法などの「重要な会計方針の注記(商規45条)」、担保に供されている資産(商規75条)などの「貸借対照表関係」など、多くの注記が行われてきた。商法施行規則に基づく注記のほか、「財務諸表等規則8条の14に規定された「継続企業の前提に関する注記」、新しい計算書類である「株主資本等変動計算書に関する注記」などを、各項目に区分し、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等との関連を明らかにしながら、一覧で表示するのが、新しい計算書類「注記表」だ。なお、公開会社でない株式会社は、注記の全部又は一部を省略することができる旨も法務省令に明示されることになりそうだ。
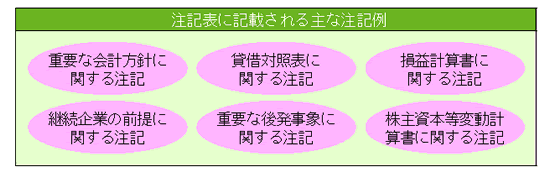
「営業報告書」は「事業報告」に
商法が計算書類と規定していた「営業報告書」は、会社法では、計算書類からはずれ、「事業報告」として作成することになる。立法担当官は、「営業報告書に記載される内容が必ずしも計算に関するものとはいえないことから、『計算書類』から除外した。」と説明している。
計算書類は、会計監査人の監査の対象であり、会計参与が作成権限を有するものである。会社法では、計算書類の範囲を明確(実態に即したもの)にすることが要請されていた。
一方、商法が計算書類と規定していた「利益処分案(又は損失処理案)」については、立法担当官が「剰余金の配当(会454条)、役員の賞与(会361条①)、資本の部の計数変動(会448条ほか)などに分解したうえで、これを決算の確定手続とは無関係に随時行うことができることと整理したため、会社法には、利益処分案は存在しない。」と説明している。
会社法では、利益処分案は不要となって、廃止されることになった。
会計基準に合わせ、B/S・P/Lも変わる!
貸借対照表・損益計算書の表示においても、会計基準の動向を踏まえて、変更が行われる。貸借対照表の「資本の部」は、その区分の名称を「純資産の部」に改めた上で、評価換算差額等・新株予約権の区分が設けられる。評価差額金は払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないことから、株主資本以外の項目として、純資産の部に新たな区分が設けられた。また、新株予約権者は、株主でも債権者でもないため、新株予約権は、新たな区分が設けられた。これらは、ASBが設定する「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(本誌No.128(2005.8.29)号12頁以下)に対応するものである。
さらに、損益計算書は、当期純利益金額までの計算となる。これまで、損益計算書は、当期純利益金額に前期繰越利益(損失)を加減して、当期未処分利益金額まで計算してきたが、これらについては、株主資本等変動計算書において表示されることになるため、損益計算書は、当期純利益金額までの計算で終わることになる。
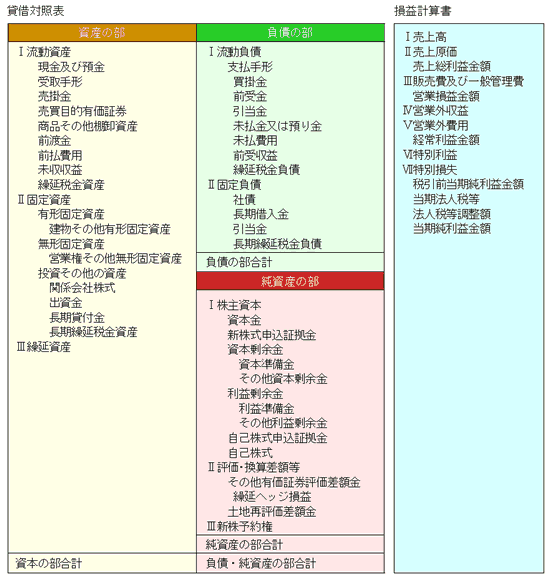
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















