解説記事2005年12月12日 【編集部解説】 国際的租税回避スキームで課税処分の取消判決(2005年12月12日号・№142)
解説
国際的租税回避スキームで課税処分の取消判決
「税負担回避目的であっても、本件契約は匿名組合契約」
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
東京地方裁判所民事38部(菅野博之裁判長)は、9月30日、オランダ王国の法人(原告)が匿名組合契約に基づき日本国内の関連会社から受領した金員(分配金)について、「本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合契約である。」・「匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約23条に規定する『一方の国の居住者の所得で前諸条に明文の規定がないもの』に該当するから、わが国に課税権がない。」などと判示し、『国内源泉所得』及び日蘭租税条約8条1項に規定する『企業の利得』に当たるとして行った法人税の決定等を取消した。
裁判所が国際的租税回避スキームと認識した上で、外形上の「匿名組合契約」であることを優先して課税処分を取消したものであり、課税庁には、本判決と同様の「処分証書の法理」による「航空機リース訴訟」の敗訴に次ぐ衝撃となる。本件については、課税庁側が東京高裁に控訴している。
1 事案の概要
日本ガイダント(以下「日本G社」という。)は、心臓ペースメーカー、血管カテーテル等の医療機器の販売を業とする企業グループであるガイダント・グループ(以下「Gグループ」という。)が、日本において医療器具を販売することを目的として、Gグループの外国会社が1000万円の資本金全額を出資して、日本において設立した会社である。日本G社は関連会社から日本国内における医療機器事業の営業を譲り受ける契約を締結した。その契約の対価は、約10億円と試算され、譲り受ける事業からは多大の収益が見込まれた。
日本G社は、契約の対価(約10億円)(「本件資金」)をGグループから調達することにしたが、Gグループの外国法人が日本G社の資本金として提供する場合には、日本G社が行う医療機器事業から生ずる利益の全額が日本G社(内国法人)の課税所得となってしまう上、日本G社の資本金が5億円を超えるときは、監査等の規制を受けることから、会社の運営コストの増加が見込まれた。
これに対し、Gグループの外国法人が日本G社との間に日本の商法上の匿名組合契約を締結し、本件資金を匿名組合出資金として、出資するという方法により日本G社に提供する場合には、日本G社が行う医療機器事業から生ずる利益のうち匿名組合契約に基づく利益分配金に相当する分は、日本G社の課税所得金額の計算上損金の額に算入されることから、日本G社には課税されない。しかも、日蘭租税条約の規定からすると、匿名組合がオランダから見ると日本にある恒久的施設となり、日本から見るとオランダにある恒久的施設となる組織を持ったものとして組成することができれば、匿名組合員(出資者)についても、上記の利益分配金がオランダにおいても日本においても課税されない可能性があることが見込まれた。
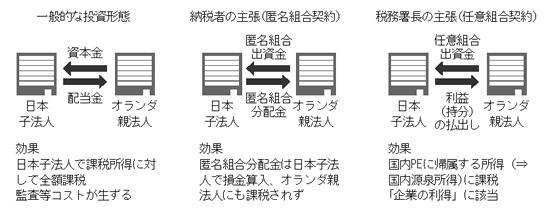
そこで、Gグループの中核企業であるGコーポレーションは、Gグループのオランダ法人GBVと日本G社との間において、オランダから見ると日本にある恒久的施設となり、日本から見るとオランダにある恒久的施設となる組織を持った匿名組合を組成させることにした。匿名組合契約書上、日本G社が「営業者」、GBVが「匿名組合員」であった。GBVは、日本G社の追加資本金9000万円及び、匿名組合出資金として9億7336万円余を日本G社あてに送金した。
GBVは、その保有する日本G社の全株式及び本件匿名組合契約に係る出資持分を現物出資してオランダにおいてGIBV(原告)を設立し、原告(GIBV)が本件匿名組合契約における匿名組合員ないし組合員の地位を承継した。
日本G社が本件匿名組合契約に基づいて原告に支払った「匿名組合分配金」は、次のとおりである。
平成7年12月期分 11億5113万円余
平成8年12月期分 12億2196万円余
平成9年12月期分 9億1140万円余
平成10年12月期分 12億3101万円余
匿名組合契約は、平成10年12月31日をもって終了した。
課税庁(税務署長)は、次頁3に掲載した主張を行い、上記匿名組合分配金(課税庁の主張では、「本件各利益の額」)を基に、①交際費等の損金不算入額、②寄附金の損金不算入額、③事業税認定損、の調整を行った後の課税所得金額について、原告が我が国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得であるとし、原告の本件各事業年度分の各法人税につき、「決定」し、無申告加算税賦課決定を行った。
原告は、課税所得金額等を0円とする異議申立て・審査請求をしたが、それぞれ棄却されており、上記の決定等の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 争点
本件の争点は、(1)本件契約は、商法535条に規定する匿名組合契約であるか、それとも民法667条1項の適用がある組合契約(「任意組合契約」)であるか、(2)原告が本件契約に基づき日本G社から匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約に規定するいずれの所得に該当するか、(3)平成7年12月期の組合持分譲渡に関する税額の計算、平成10年12月期の交際費等に関する税額の計算、並びに平成9年12月期及び平成10年12月期の寄附金の損金不算入額に関する税額の計算に、それぞれ誤りがあるかである。
なお、争点(3)については、結果として、本判決において判示されていないので、以下記述を省略する。
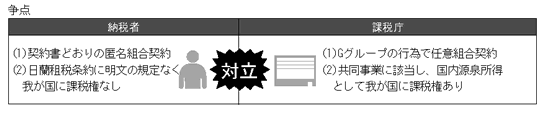
3 被告(税務署長)の主張
1. 争点(1)について
(1)本件契約書の各条項に関する検討によれば、少なくとも原告と日本G社との関係においては、本件事業に係る出資金その他の資産は、原告と日本G社の共有に属するということができ、本件契約において利益の分配とされている金員の支払は、単に原告の持分を払い出したに過ぎないというべきである。
そして、組合財産について共有関係が認められる以上、その基礎となる契約が、匿名組合契約ないしこれに準ずる契約に当たらないことは明らかである。
(2)商法上の匿名組合は、一般に、出資者にとっては投資の有利性と秘密性を享受することができ、営業者にとっては経営の自由度が確保できる制度として利用されている。
本件契約において、①原告が出資者の名称を秘匿することができる、②営業者とされる日本G社が経営の自由度を確保するために、匿名組合契約方式を採用しなければならない理由はない。
本件契約が匿名組合契約であるとすると、本件各利益は、利益分配金ということになるから、匿名組合員(原告)の課税所得としてわが国では課税されないのみならず、本件各利益は、日本G社の損金の額に算入されるから、日本G社においても課税されない。
しかも、原告は、オランダ課税当局に対し、日本G社は原告の固定的な機関となり、課税権は日本にある旨主張し、オランダ課税当局は、最終的には、原告が日本国内に恒久的施設を有していることを理由に、本件各利益に課税しないこととした。
したがって、原告は、本件契約が匿名組合契約であるとして、多大な租税負担軽減効果を得ている。
(3)GBVが増資という通常の方法ではなく、匿名組合契約に基づく出資という方法により、日本G社に事業資金を供給したのは、租税負担の軽減効果に着目したものにほかならず、GBVの匿名組合員としての地位を承継したとされる原告の租税回避の意図は明らかである。
(4)原告は、匿名組合員という名目ではあるが、単なる投資家ではなく、Gコーポレーションの統括の下に仕組まれた本件事業のスキームの重要な構成員とみるほかない。原告はGグループの構成員として、同グループの意思決定を通じて、日本G社と共同して本件事業を行っていたとみることができる。
(結論)本件契約の内容及び本件事業の実態を総合すると、本件契約は、匿名組合契約ないしこれに準ずる契約ではなく、原告と日本G社を構成員とし、日本G社を業務執行組合員とする任意組合契約に当たると解すべきである。
原告は匿名組合を選択した経済合理性などについて主張するが、原告が匿名組合を選択したのは、本件事業に係る投資リスクを限定等するためではなく、本件事業から生ずる所得に対するわが国及びオランダにおける課税を免れるためであったことは明らかである。
2. 争点(2)について
本件事業は、日蘭租税条約8条1項に規定する「事業」にあたるというべきであり、本件事業は、原告と日本G社との共同事業であり、原告の企業活動そのものであるから、本件事業から生じた所得である本件各利益は、日蘭租税条約8条1項にいう「企業の利得」に該当するというべきである。
本件各利益は、原告が日本国内に有する本件恒久的施設を通じて日本国内で行った本件事業から生じた所得であり、そのすべてが本件恒久的施設に帰属する。
本件各利益については、日蘭租税条約8条1項にいう「企業の利得」として、我が国に課税権があるというべきである。
4 判決
1. 争点(1)について
(1)本件契約書の各条項を検討して総合すると、本件契約書及び修正後の本件契約書は、日本G社を営業者、GBVを匿名組合員として日本の商法に基づいて設立される匿名組合について、日本G社及びGBVの権利義務等について日本G社及びGBVが合意した内容を取りまとめた書面であると認めるのが相当である。
(2)被告の前記各主張を検討しても、本件契約書及び修正後の本件契約書が商法上の匿名組合について日本G社とGBVが合意した内容を取りまとめたものであるという前記(1)の認定判断は覆ることはない。
(3)Gコーポレーションの傘下にあるGBV及びGBVの100%出資の子会社であった日本G社は、Gコーポレーションの意を受けて、日本及びオランダにおいてそれぞれ日本G社が行った医療機器事業から生じた利益のうち匿名組合契約に基づく利益分配金に相当する分についての課税を免れる目的で、GBVと日本G社の間に匿名組合契約を成立させ、また、日本の課税当局から本件契約が匿名組合契約であることを万が一にも否定されないようにするための措置として、GBVの匿名組合員の地位を日本G社の親会社ではない会社に承継させるために、原告を設立し、修正後の本件契約書を作成したということができる。
(4)上記のように、当事者間に匿名組合契約を締結するという真の合意がある場合には、それにもかかわらず、匿名組合契約を締結する主な目的が税負担を回避することにあるという理由により当該匿名組合契約の成立を否定するには、その旨の明文の規定が必要であるところ、法人税を課するに当たってそのような措置を認めた規定は存しない。したがって、当事者間に匿名組合契約を締結するという真の合意がある場合には、税負担を回避するという目的が併存することから、直ちに当該匿名組合契約の成立を否定することはできない。
もっとも、契約書上匿名組合契約を締結するとの記載があり、あるいは外観上匿名組合が存在する場合でも、実際の当事者間の法律関係、事業状況、経営実態等が契約書の記載の外観と異なるのであれば、匿名組合ではないという認定判断をする余地があることは当然である。しかしながら、本件の全証拠を精査しても、GBVと日本G社との間における真の合意が、GBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法以外の方法によって本件資金を日本G社に提供することであるとか、GBV又は原告と日本G社との法律関係や事業状況等が本件契約書に定められたものとは異なるものであるという事実を認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件においては、GBVと日本G社との間における合意は、前示のとおり、GBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法によって本件資金を日本G社に提供することであったと認めるほかない。
なお、本件資金を日本G社に提供するに当たって、GBVと日本G社との間においてどのような方法を採用するかは、両当事者間の自由な選択に任されている。税負担を回避するという目的それ自体は是認し得ないときもあろうが、税負担を回避するという目的から、本件資金を日本G社に提供する方法としてGBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法を採用することが許されないとすべき法的根拠はないといわざるを得ない。
〈結論〉本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合契約であると認めざるを得ない。
2. 争点(2)について
外国法人は、法人税法138条に規定する国内源泉所得を有するときは法人税を納める義務がある。しかし、租税条約において国内源泉所得について同条と異なる定めがある場合には、租税条約が優先する(法人税法139条)。したがって、租税条約において日本での課税の要件が満たされない限り、法人税を課することはできない。そして、当該外国法人がオランダ国内に本店を有する場合には、日蘭租税条約が適用されるので、その定めを検討しなければならない。
日蘭租税条約は、所得の種類を7条から22条まで定め、居住地国と所得源泉地国とに課税権を配分し、そのいずれにも該当しない所得については居住地国のみに課税権を認めている(23条)ところ、本件契約が任意組合を成立させる契約であれば、原告も日本国内において事業を行っていることになり、日蘭租税条約8条1項に規定する「他方の国にある恒久的施設を通じて当該他方の国において事業を行なう場合」に当たるから、日本国に課税権が認められる。しかし、匿名組合契約に基づき内国法人である営業者から外国法人である匿名組合員に支払われる分配金については、匿名組合では、匿名組合員が恒久的施設を通じて事業を行っているわけではないので、同項に該当せず、そのほか、日蘭租税条約7条から22条に掲げる所得のいずれにも該当しない。したがって、上記分配金は、日蘭租税条約23条に規定する「一方の国の居住者の所得で前諸条に明文の規定がないもの」に該当するというべきである。
そうすると、原告が本件契約に基づき日本G社から匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約23条に規定する所得に該当するから、我が国には課税権がない。
3. 判決のまとめ
以上によれば、被告は、原告の本件各事業年度分の各所得について法人税を課することはできないから、これを課することができるものとしてした本件各決定及び本件各賦課決定は、その余の点について判断するまでもなく、違法であるといわざるを得ない。
したがって、本件各決定及び本件各賦課決定は、全部取り消されるべきである。
5 本件事案の意義
1. 課税を免れる国際的租税回避スキーム
本件事案は租税回避スキームに対する課税について、裁判所が「契約締結の大きな目的が税負担の回避にある」と判示しながらも、外形上の匿名組合契約であることを優先して、課税処分を取り消した。
本件事案は、日本国内において多大な利益が見込まれるため、日本国内で課税されないことを目論んで日本子法人を「営業者」、オランダ法人を「匿名組合員」として、匿名組合契約を締結した。匿名組合契約により、分配金が損金に算入され、日本子法人は法人課税を免れることになった。オランダ法人も、日蘭租税条約に匿名組合分配金に関する明文の規定がないことから、国内源泉所得には当たらないとして、日本での国内源泉所得課税を免れることになった(本件判示)。本判決の内容からは離れるが、オランダ法人は、日蘭租税条約に基づき居住地(オランダ)においても当該分配金(利益)が課税されないことになった。匿名組合に対する課税と日蘭租税条約の規定の間隙をついた典型的ともいえる国際的租税回避スキームである。
また、課税庁が租税回避スキームと位置付ける航空機リーススキームは、課税の繰延という主な効果が見込まれたものだが、本件匿名組合契約スキームでは、日蘭租税条約の規定ぶりから、我が国の課税権が及ばないだけでなく、課税漏れが生じることになった。
課税庁は、匿名組合契約ではなく、グループとしての行為(任意組合契約)であると認定し、オランダ法人に対して国内源泉所得に対する課税を行ったが、菅野裁判長は、「本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合であると認めざるを得ない。」と判示し、我が国の課税権を否定し、課税処分を取消した。
2. 私法上の法律構成による否認
課税庁の「決定」は「私法上の法律構成による否認」という手法によるものである。本件では次の2つの視点から否認が行われている。①当事者の選択した法形式(匿名組合契約)と当事者間における合意の実質(共同事業)が異なるとして、取引の経済実体を考慮した実質的な合意内容に従って解釈し、その真に意図している私法上の事実関係を前提として法律構成をしたうえ、課税要件に当てはめた。②当事者間で行われた個々の契約(匿名組合契約)から離れ、全体をあらかじめ計画された一連のスキーム(Gグループの意思決定)として法律構成をしたうえ、課税要件を当てはめた。
本判決における裁判所の判断は、「私法上の選択可能性の自由」・「処分証書の法理」に基づくものである。このような対立は、航空機リース訴訟・映画フィルムリース訴訟・旺文社事件などでもみられるものである。
一方、本件事案は航空機リース訴訟と正反対の事実認定が行われている。航空機リース訴訟では、課税庁が任意組合を否認するものであったが、本件では、課税庁が契約書上の匿名契約を否認して、任意組合性を主張している。しかし、本件においても課税庁は、「処分証書の法理」の前に、敗れることになった。課税庁は精巧な租税回避スキームに対する課税の難しさ(司法判断の厳しさ)を、航空機リース訴訟と相まって、痛感したに違いない。
本判決に対して課税庁は東京高裁に控訴しており、最終的な決着はみられていない。国際的租税回避スキームの裁判例ということでも大変興味深い内容ということができる。
国際的租税回避スキームで課税処分の取消判決
「税負担回避目的であっても、本件契約は匿名組合契約」
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
東京地方裁判所民事38部(菅野博之裁判長)は、9月30日、オランダ王国の法人(原告)が匿名組合契約に基づき日本国内の関連会社から受領した金員(分配金)について、「本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合契約である。」・「匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約23条に規定する『一方の国の居住者の所得で前諸条に明文の規定がないもの』に該当するから、わが国に課税権がない。」などと判示し、『国内源泉所得』及び日蘭租税条約8条1項に規定する『企業の利得』に当たるとして行った法人税の決定等を取消した。
裁判所が国際的租税回避スキームと認識した上で、外形上の「匿名組合契約」であることを優先して課税処分を取消したものであり、課税庁には、本判決と同様の「処分証書の法理」による「航空機リース訴訟」の敗訴に次ぐ衝撃となる。本件については、課税庁側が東京高裁に控訴している。
1 事案の概要
日本ガイダント(以下「日本G社」という。)は、心臓ペースメーカー、血管カテーテル等の医療機器の販売を業とする企業グループであるガイダント・グループ(以下「Gグループ」という。)が、日本において医療器具を販売することを目的として、Gグループの外国会社が1000万円の資本金全額を出資して、日本において設立した会社である。日本G社は関連会社から日本国内における医療機器事業の営業を譲り受ける契約を締結した。その契約の対価は、約10億円と試算され、譲り受ける事業からは多大の収益が見込まれた。
日本G社は、契約の対価(約10億円)(「本件資金」)をGグループから調達することにしたが、Gグループの外国法人が日本G社の資本金として提供する場合には、日本G社が行う医療機器事業から生ずる利益の全額が日本G社(内国法人)の課税所得となってしまう上、日本G社の資本金が5億円を超えるときは、監査等の規制を受けることから、会社の運営コストの増加が見込まれた。
これに対し、Gグループの外国法人が日本G社との間に日本の商法上の匿名組合契約を締結し、本件資金を匿名組合出資金として、出資するという方法により日本G社に提供する場合には、日本G社が行う医療機器事業から生ずる利益のうち匿名組合契約に基づく利益分配金に相当する分は、日本G社の課税所得金額の計算上損金の額に算入されることから、日本G社には課税されない。しかも、日蘭租税条約の規定からすると、匿名組合がオランダから見ると日本にある恒久的施設となり、日本から見るとオランダにある恒久的施設となる組織を持ったものとして組成することができれば、匿名組合員(出資者)についても、上記の利益分配金がオランダにおいても日本においても課税されない可能性があることが見込まれた。
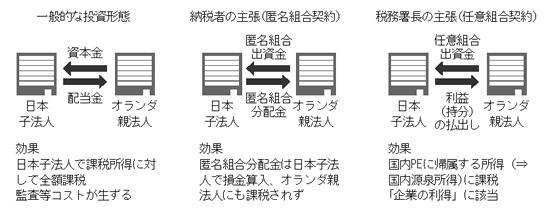
そこで、Gグループの中核企業であるGコーポレーションは、Gグループのオランダ法人GBVと日本G社との間において、オランダから見ると日本にある恒久的施設となり、日本から見るとオランダにある恒久的施設となる組織を持った匿名組合を組成させることにした。匿名組合契約書上、日本G社が「営業者」、GBVが「匿名組合員」であった。GBVは、日本G社の追加資本金9000万円及び、匿名組合出資金として9億7336万円余を日本G社あてに送金した。
GBVは、その保有する日本G社の全株式及び本件匿名組合契約に係る出資持分を現物出資してオランダにおいてGIBV(原告)を設立し、原告(GIBV)が本件匿名組合契約における匿名組合員ないし組合員の地位を承継した。
日本G社が本件匿名組合契約に基づいて原告に支払った「匿名組合分配金」は、次のとおりである。
平成7年12月期分 11億5113万円余
平成8年12月期分 12億2196万円余
平成9年12月期分 9億1140万円余
平成10年12月期分 12億3101万円余
匿名組合契約は、平成10年12月31日をもって終了した。
課税庁(税務署長)は、次頁3に掲載した主張を行い、上記匿名組合分配金(課税庁の主張では、「本件各利益の額」)を基に、①交際費等の損金不算入額、②寄附金の損金不算入額、③事業税認定損、の調整を行った後の課税所得金額について、原告が我が国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得であるとし、原告の本件各事業年度分の各法人税につき、「決定」し、無申告加算税賦課決定を行った。
原告は、課税所得金額等を0円とする異議申立て・審査請求をしたが、それぞれ棄却されており、上記の決定等の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 争点
本件の争点は、(1)本件契約は、商法535条に規定する匿名組合契約であるか、それとも民法667条1項の適用がある組合契約(「任意組合契約」)であるか、(2)原告が本件契約に基づき日本G社から匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約に規定するいずれの所得に該当するか、(3)平成7年12月期の組合持分譲渡に関する税額の計算、平成10年12月期の交際費等に関する税額の計算、並びに平成9年12月期及び平成10年12月期の寄附金の損金不算入額に関する税額の計算に、それぞれ誤りがあるかである。
なお、争点(3)については、結果として、本判決において判示されていないので、以下記述を省略する。
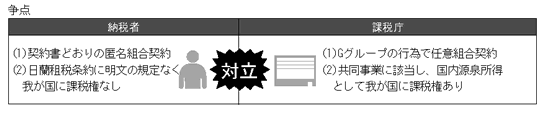
3 被告(税務署長)の主張
1. 争点(1)について
(1)本件契約書の各条項に関する検討によれば、少なくとも原告と日本G社との関係においては、本件事業に係る出資金その他の資産は、原告と日本G社の共有に属するということができ、本件契約において利益の分配とされている金員の支払は、単に原告の持分を払い出したに過ぎないというべきである。
そして、組合財産について共有関係が認められる以上、その基礎となる契約が、匿名組合契約ないしこれに準ずる契約に当たらないことは明らかである。
(2)商法上の匿名組合は、一般に、出資者にとっては投資の有利性と秘密性を享受することができ、営業者にとっては経営の自由度が確保できる制度として利用されている。
本件契約において、①原告が出資者の名称を秘匿することができる、②営業者とされる日本G社が経営の自由度を確保するために、匿名組合契約方式を採用しなければならない理由はない。
本件契約が匿名組合契約であるとすると、本件各利益は、利益分配金ということになるから、匿名組合員(原告)の課税所得としてわが国では課税されないのみならず、本件各利益は、日本G社の損金の額に算入されるから、日本G社においても課税されない。
しかも、原告は、オランダ課税当局に対し、日本G社は原告の固定的な機関となり、課税権は日本にある旨主張し、オランダ課税当局は、最終的には、原告が日本国内に恒久的施設を有していることを理由に、本件各利益に課税しないこととした。
したがって、原告は、本件契約が匿名組合契約であるとして、多大な租税負担軽減効果を得ている。
(3)GBVが増資という通常の方法ではなく、匿名組合契約に基づく出資という方法により、日本G社に事業資金を供給したのは、租税負担の軽減効果に着目したものにほかならず、GBVの匿名組合員としての地位を承継したとされる原告の租税回避の意図は明らかである。
(4)原告は、匿名組合員という名目ではあるが、単なる投資家ではなく、Gコーポレーションの統括の下に仕組まれた本件事業のスキームの重要な構成員とみるほかない。原告はGグループの構成員として、同グループの意思決定を通じて、日本G社と共同して本件事業を行っていたとみることができる。
(結論)本件契約の内容及び本件事業の実態を総合すると、本件契約は、匿名組合契約ないしこれに準ずる契約ではなく、原告と日本G社を構成員とし、日本G社を業務執行組合員とする任意組合契約に当たると解すべきである。
原告は匿名組合を選択した経済合理性などについて主張するが、原告が匿名組合を選択したのは、本件事業に係る投資リスクを限定等するためではなく、本件事業から生ずる所得に対するわが国及びオランダにおける課税を免れるためであったことは明らかである。
2. 争点(2)について
本件事業は、日蘭租税条約8条1項に規定する「事業」にあたるというべきであり、本件事業は、原告と日本G社との共同事業であり、原告の企業活動そのものであるから、本件事業から生じた所得である本件各利益は、日蘭租税条約8条1項にいう「企業の利得」に該当するというべきである。
本件各利益は、原告が日本国内に有する本件恒久的施設を通じて日本国内で行った本件事業から生じた所得であり、そのすべてが本件恒久的施設に帰属する。
本件各利益については、日蘭租税条約8条1項にいう「企業の利得」として、我が国に課税権があるというべきである。
4 判決
1. 争点(1)について
(1)本件契約書の各条項を検討して総合すると、本件契約書及び修正後の本件契約書は、日本G社を営業者、GBVを匿名組合員として日本の商法に基づいて設立される匿名組合について、日本G社及びGBVの権利義務等について日本G社及びGBVが合意した内容を取りまとめた書面であると認めるのが相当である。
(2)被告の前記各主張を検討しても、本件契約書及び修正後の本件契約書が商法上の匿名組合について日本G社とGBVが合意した内容を取りまとめたものであるという前記(1)の認定判断は覆ることはない。
(3)Gコーポレーションの傘下にあるGBV及びGBVの100%出資の子会社であった日本G社は、Gコーポレーションの意を受けて、日本及びオランダにおいてそれぞれ日本G社が行った医療機器事業から生じた利益のうち匿名組合契約に基づく利益分配金に相当する分についての課税を免れる目的で、GBVと日本G社の間に匿名組合契約を成立させ、また、日本の課税当局から本件契約が匿名組合契約であることを万が一にも否定されないようにするための措置として、GBVの匿名組合員の地位を日本G社の親会社ではない会社に承継させるために、原告を設立し、修正後の本件契約書を作成したということができる。
(4)上記のように、当事者間に匿名組合契約を締結するという真の合意がある場合には、それにもかかわらず、匿名組合契約を締結する主な目的が税負担を回避することにあるという理由により当該匿名組合契約の成立を否定するには、その旨の明文の規定が必要であるところ、法人税を課するに当たってそのような措置を認めた規定は存しない。したがって、当事者間に匿名組合契約を締結するという真の合意がある場合には、税負担を回避するという目的が併存することから、直ちに当該匿名組合契約の成立を否定することはできない。
もっとも、契約書上匿名組合契約を締結するとの記載があり、あるいは外観上匿名組合が存在する場合でも、実際の当事者間の法律関係、事業状況、経営実態等が契約書の記載の外観と異なるのであれば、匿名組合ではないという認定判断をする余地があることは当然である。しかしながら、本件の全証拠を精査しても、GBVと日本G社との間における真の合意が、GBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法以外の方法によって本件資金を日本G社に提供することであるとか、GBV又は原告と日本G社との法律関係や事業状況等が本件契約書に定められたものとは異なるものであるという事実を認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件においては、GBVと日本G社との間における合意は、前示のとおり、GBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法によって本件資金を日本G社に提供することであったと認めるほかない。
なお、本件資金を日本G社に提供するに当たって、GBVと日本G社との間においてどのような方法を採用するかは、両当事者間の自由な選択に任されている。税負担を回避するという目的それ自体は是認し得ないときもあろうが、税負担を回避するという目的から、本件資金を日本G社に提供する方法としてGBVと日本G社との間において匿名組合を組成するという方法を採用することが許されないとすべき法的根拠はないといわざるを得ない。
〈結論〉本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合契約であると認めざるを得ない。
2. 争点(2)について
外国法人は、法人税法138条に規定する国内源泉所得を有するときは法人税を納める義務がある。しかし、租税条約において国内源泉所得について同条と異なる定めがある場合には、租税条約が優先する(法人税法139条)。したがって、租税条約において日本での課税の要件が満たされない限り、法人税を課することはできない。そして、当該外国法人がオランダ国内に本店を有する場合には、日蘭租税条約が適用されるので、その定めを検討しなければならない。
日蘭租税条約は、所得の種類を7条から22条まで定め、居住地国と所得源泉地国とに課税権を配分し、そのいずれにも該当しない所得については居住地国のみに課税権を認めている(23条)ところ、本件契約が任意組合を成立させる契約であれば、原告も日本国内において事業を行っていることになり、日蘭租税条約8条1項に規定する「他方の国にある恒久的施設を通じて当該他方の国において事業を行なう場合」に当たるから、日本国に課税権が認められる。しかし、匿名組合契約に基づき内国法人である営業者から外国法人である匿名組合員に支払われる分配金については、匿名組合では、匿名組合員が恒久的施設を通じて事業を行っているわけではないので、同項に該当せず、そのほか、日蘭租税条約7条から22条に掲げる所得のいずれにも該当しない。したがって、上記分配金は、日蘭租税条約23条に規定する「一方の国の居住者の所得で前諸条に明文の規定がないもの」に該当するというべきである。
そうすると、原告が本件契約に基づき日本G社から匿名組合分配金という名目で受領した金員は、日蘭租税条約23条に規定する所得に該当するから、我が国には課税権がない。
3. 判決のまとめ
以上によれば、被告は、原告の本件各事業年度分の各所得について法人税を課することはできないから、これを課することができるものとしてした本件各決定及び本件各賦課決定は、その余の点について判断するまでもなく、違法であるといわざるを得ない。
したがって、本件各決定及び本件各賦課決定は、全部取り消されるべきである。
5 本件事案の意義
1. 課税を免れる国際的租税回避スキーム
本件事案は租税回避スキームに対する課税について、裁判所が「契約締結の大きな目的が税負担の回避にある」と判示しながらも、外形上の匿名組合契約であることを優先して、課税処分を取り消した。
本件事案は、日本国内において多大な利益が見込まれるため、日本国内で課税されないことを目論んで日本子法人を「営業者」、オランダ法人を「匿名組合員」として、匿名組合契約を締結した。匿名組合契約により、分配金が損金に算入され、日本子法人は法人課税を免れることになった。オランダ法人も、日蘭租税条約に匿名組合分配金に関する明文の規定がないことから、国内源泉所得には当たらないとして、日本での国内源泉所得課税を免れることになった(本件判示)。本判決の内容からは離れるが、オランダ法人は、日蘭租税条約に基づき居住地(オランダ)においても当該分配金(利益)が課税されないことになった。匿名組合に対する課税と日蘭租税条約の規定の間隙をついた典型的ともいえる国際的租税回避スキームである。
また、課税庁が租税回避スキームと位置付ける航空機リーススキームは、課税の繰延という主な効果が見込まれたものだが、本件匿名組合契約スキームでは、日蘭租税条約の規定ぶりから、我が国の課税権が及ばないだけでなく、課税漏れが生じることになった。
課税庁は、匿名組合契約ではなく、グループとしての行為(任意組合契約)であると認定し、オランダ法人に対して国内源泉所得に対する課税を行ったが、菅野裁判長は、「本件契約の締結の大きな目的が税負担の回避にあるとしても、本件契約は、匿名組合であると認めざるを得ない。」と判示し、我が国の課税権を否定し、課税処分を取消した。
2. 私法上の法律構成による否認
課税庁の「決定」は「私法上の法律構成による否認」という手法によるものである。本件では次の2つの視点から否認が行われている。①当事者の選択した法形式(匿名組合契約)と当事者間における合意の実質(共同事業)が異なるとして、取引の経済実体を考慮した実質的な合意内容に従って解釈し、その真に意図している私法上の事実関係を前提として法律構成をしたうえ、課税要件に当てはめた。②当事者間で行われた個々の契約(匿名組合契約)から離れ、全体をあらかじめ計画された一連のスキーム(Gグループの意思決定)として法律構成をしたうえ、課税要件を当てはめた。
本判決における裁判所の判断は、「私法上の選択可能性の自由」・「処分証書の法理」に基づくものである。このような対立は、航空機リース訴訟・映画フィルムリース訴訟・旺文社事件などでもみられるものである。
一方、本件事案は航空機リース訴訟と正反対の事実認定が行われている。航空機リース訴訟では、課税庁が任意組合を否認するものであったが、本件では、課税庁が契約書上の匿名契約を否認して、任意組合性を主張している。しかし、本件においても課税庁は、「処分証書の法理」の前に、敗れることになった。課税庁は精巧な租税回避スキームに対する課税の難しさ(司法判断の厳しさ)を、航空機リース訴訟と相まって、痛感したに違いない。
本判決に対して課税庁は東京高裁に控訴しており、最終的な決着はみられていない。国際的租税回避スキームの裁判例ということでも大変興味深い内容ということができる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















