解説記事2006年01月30日 【実務解説】 厚生年金基金からの脱退と年金制度(2006年1月30日号・№148)
実 務 解 説
厚生年金基金からの脱退と年金制度
税理士 江崎一恵
はじめに
厚生年金基金は、平成16年3月末現在で、1,357基金、加入員数約835万人となっています。中小企業が加入している総合型基金も574基金(加入員約500万人)あり、大企業中心の制度というわけではありません。基金に加入している事業所の中には、掛金の負担増と将来の給付の削減などの理由から、脱退を希望しているところも少なくないようですが、任意脱退をするには、基金の代議員や脱退事業所の被保険者の同意が必要であり、さらに多額の一括徴収金が必要なため、やむを得ず参加を続けているのが現状のようです。
事業所が基金から脱退しても、基金は将来、それまで加入員が積み立ててきた分について上乗せした年金を支払いますので、その運用不足分は基金を脱退しなかった残余の事業所が負担することになります。
従来は、脱退時に特別掛金を徴収することに関する法律的根拠がなく、脱退時の一括徴収金の制度を設けていない基金が多かったのですが、平成14年4月1日施行の厚生年金保険法の改正により、残余の事業所の負担が増加することとなるときは、基金は、増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める一定の計算方法のうちから規約で定めるものにより算定した額を、基金から抜ける事業所から掛金として一括徴収することができるようになりました。
一括徴収の対象となる理由や計算方法は、基金によって異なります。脱退時点で過去の全加入員の不足金を計算する基金、脱退時の加入員を基に計算する基金等があり、さらには、脱退しなくても、加入員が大幅に減少した場合には徴収する方式を採る基金もありますので、企業が脱退を希望している場合は、事前に規約の内容を確認することが肝要といえます。
また組織再編の場面においては、被合併会社が基金に加入しており、合併会社が加入していないような場合、合併を契機に基金からの脱退を考える会社もあるようです。そして、合併による脱退は任意脱退に該当しないことから一時金の支払は不要だと考え、合併の計画が固まった頃に脱退を申し出て、そこで初めて高額の納付金が必要であることを知って困惑するという話が仄聞されます。
このような基金脱退に関する会社からの相談、あるいは、基金の解散に伴う残余財産の分配金や代行返上の場合の一時金を受給する納税者の相談などに応じるためには、基金の仕組みを理解している必要があります。そして、その前にまず年金制度の基礎知識が必要であると考えて本稿を執筆しました。
Ⅰ 年金制度の概要
わが国の年金制度は、国民年金(基礎年金)を基礎とした下図のような3階建ての体系となっています。以下に簡単にそれぞれの年金制度について説明します。
1. 国民年金
国民年金は、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全国民が強制的に加入するいわゆる1階部分の年金で、老齢・障害・死亡に関して必要な給付をするのが目的です。
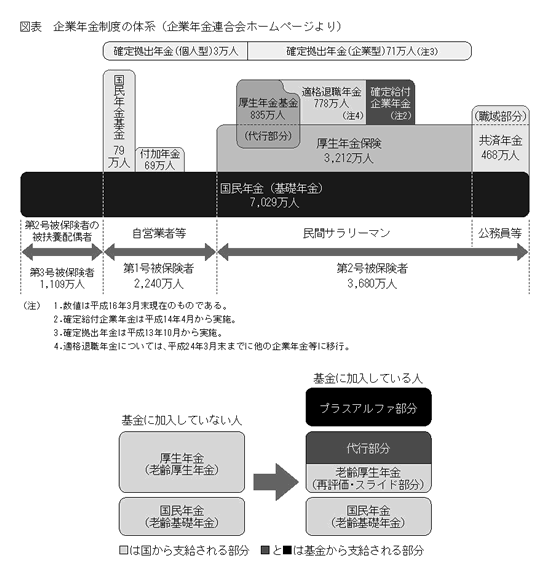
(1)被保険者の区分
被保険者の区分には第1号被保険者(自営業者、学生など)と第2号被保険者(厚生年金や共済年金などの加入者)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)があります。自ら保険料を納付しなければならないのは第1号被保険者のみです。
第2号被保険者の国民年金保険料は勤め先で徴収されている厚生年金保険料に含まれており、第3号被保険者の国民年金保険料は第2号被保険者が負担しています。
(2)課税関係
「老齢基礎年金及び付加年金」の給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35③一、31一)。「障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金」は非課税となっています(国年15条、25条)。
国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(所法74②五)。
2. 国民年金基金
国民年金の第1号被保険者を対象にした2階部分の年金で、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除の対象となります(所法74②五)。年金給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一)。
3. 厚生年金
厚生年金は民間の給与所得者が加入するもので2階部分に当たるものです。厚生年金の適用事業所で働く給与所得者は70歳まで厚生年金に加入し、給与の額に比例した保険料を事業主と折半で納めますが、20歳から60歳の間は自動的に国民年金にも加入しているとみなされるため、下位の標準報酬月額の場合、国民年金保険料よりも低い保険料負担で1階、2階部分の給付が受けられることになります。
老齢厚生年金の給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一)。障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金は非課税です(厚年41条②)。厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料は、社会保険料控除の対象になります(所法74②七)。
4. 退職共済年金
共済年金とは国家公務員、地方公務員、私立学校の職員のうち私立学校共済制度がある団体に所属する者が加入する制度で、退職共済年金は厚生年金と同じく2階建て部分を構成する年金です。厚生年金との相違点は職域加算という3階の部分の給付があり、この上乗せ給付までを入れると厚生年金と比べ割安な保険料率となっていることや遺族年金の遺族の範囲が厚生年金より広いことなどから、優遇を廃止し年金を一元化しようということが議論されています。
5. 厚生年金基金
厚生年金基金は昭和41年に始まった制度で、厚生年金の上乗せ、つまり3階部分を構成する企業年金です。厚生年金と違い加入は義務付けられておらず、事業所単位で加入を選択します。老齢給付について厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行うことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。基金の設立形態には、一企業で設立する単独設立、同一の資本系列の企業グループで設立する連合設立、同業種・同地域などの企業が集まって設立する総合設立の3種があります。
(1)拠出段階における課税上の取り扱い
厚生年金基金を設立すると、厚生年金保険料のうち、代行給付に見合う保険料を政府に納付することを免除され(免除料率)、これに上乗せ給付をするための掛金をあわせて、基金が徴収することになります。掛金の負担割合は、免除料率については事業主と加入者の折半ですが、上乗せ給付のための掛金については事業主の負担を増加することができます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。
(2)給付段階における課税上の取り扱い
①退職年金
加入者が受け取る退職年金は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一、31二)。
②退職一時金
厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で、同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるものは、退職手当等とみなされます(所法31二)。
③遺族一時金等
厚生年金保険法136条(準用規定)は、「第41条第2項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。」と規定しています。そして、同法第41条第2項(公課の禁止)は、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない」としていますので、遺族一時金等は非課税となります。
6. その他の企業年金
(1)確定給付企業年金
確定給付企業年金法(平成13年6月公布)に基づき、平成14年4月から実施された確定給付型の企業年金制度です。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがあります。年金資産の積立基準をはじめ、管理・運営にかかわる者(受託者)の責任が明確になっているほか、財務状況などの情報開示も事業主などへ義務づけられています。
(2)確定拠出年金
拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。積立不足ということがないため企業が追加拠出をする必要はありませんが、加入者にとっては運用のリスクを負い、給付額が定まらないため老後の生活設計を立てにくい面があります。しかし、途中で転職しても、自分の年金原資を転職先に移管して、通算した年金を受け取ること(ポータビリティ)が可能です。わが国では、確定拠出年金がこれにあたります。なお、アメリカでは401(k)と呼ばれる確定拠出型年金が普及しています。
(3)適格退職年金
厚生年金基金と並ぶ企業年金制度で、昭和37年に発足しました。年金原資を外部機関に積み立てるなど、法人税法で定める一定の条件を満たすことで国税庁長官に承認されます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があります。退職金の原資を社外積立によって平準化できることや、厚生年金基金に比べ少人数(15人以上)でも設立できるメリットがあります。
なお、平成14年度以降、新たな適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成24年4月から優遇措置が受けられなくなりますが平成23年度末までは確定給付企業年金等に非課税で移行することができます。
Ⅱ 厚生年金基金からの脱退
総合型厚生年金基金において、従来は脱退時に特別掛金を徴収することに関する法律的根拠がなく、脱退時の一括徴収金の制度を設けていない基金が多かったのですが、平成14年の厚生年金保険法の改正で、脱退する事業所から掛金を一括徴収することが規定されたのを機に、多くの基金で脱退時の特別掛金の一括徴収についての規定が整備されました。
1. 平成14年の改正
平成14年4月施行の改正厚生年金保険法では次の条項が追加されました。
厚生年金保険法138条(抄)
5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
厚生労働省令で定める計算方法とは(厚生年金基金規則第32条の3の2の要約)
① 未償却過去勤務債務のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額とする方法
② 積立金の額が最低積立基準額を下回る場合、下回る額のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額とする方法
③ ①、②のいずれか大きい額とする方法
※①については、繰越不足金等のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額を加算することができる。
2. 脱退時の一括徴収金の計算についてのイメージ
脱退時の一括徴収金の計算は基金によって計算根拠も違うため、実際には基金にて計算してもらうほかないのですが、加入員一人当たりの大まかな金額は例えば下記のように計算式でイメージできると思われます。
(【将来の年金給付のために積み立てられているべき額(数理債務、給付債務と表示されている)】-【純資産額】)÷加入員数
例えば給付債務1,200億円、純資産額800億円、加入員数2万人の基金の場合、
(1,200億円-800億円)÷2万人=200万円
脱退事業所の計算基礎となる加入員数が50人の場合、200万円×50人=1億円の特別掛金を一括納付することになります。
3. いわゆる「食い逃げ、足抜け」とは
この脱退時の一括徴収金を逃れるためにとられた方法が、いわゆる「食い逃げ、足抜け」といわれる方法で、それが基金に残った他の加入事業所の負担をさらに重くする結果となることが問題となっています。特に平成14年の厚生年金保険法改正前は、総合型厚生年金基金を任意脱退する場合の脱退時の一括徴収金が脱退時の加入員の人数に応じて算定される場合、その負担を軽減するために次のような手法により脱退をする事業所が多く見受けられました。
基金から脱退しようとする事業所は、先ず加入員である従業員をその基金に加入していない別会社へ順次転籍させます。この時点で転籍した従業員はその基金から脱退することになります。最後に社長だけが事業所に残った形となり、この社長の分に対応する一括徴収金のみを納付して基金を脱退するのです。この手法により、転籍した従業員にかかる一括徴収金の負担が不要となります。
4. 一括徴収金についての規約事例
脱退時の一括徴収金について法律で明文化されたといっても、個々の基金の規約においてこれを規定し、それを周知させなければ、改正条文は生かされません。脱退時の一括徴収金についての規定は基金によって様々ですので、加入している基金が、どのように規定しているかを確認しておくことが肝心です。ここで脱退時の一括徴収金について4つの基金の規約事例を見てみます。
(1)脱退時の一括徴収金が任意脱退の場合にのみ必要な規約事例
任意脱退時にのみ特別掛金を一括徴収する規約の場合、加入企業の合併、解散などの理由により基金を脱退することとなるときは、特別掛金の一括徴収はされません。このような規約は連合型の厚生年金基金においてその例がみられます。
事例(連合型S厚生年金基金)
(設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収)
第○条 基金は、設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が任意脱退の申出を行い、代議員会が認めた場合に限る。)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加する額として、次の各号に掲げる債務及び不足金を当該減少に係る設立事業所(以下、「脱退事業所」という。)の事業主から脱退時特別掛金として一括して徴収するものとし、当該脱退事業所の事業主に対し納入の告知を行う。
(1)未償却過去勤務債務
(2)繰越不足金
(3)基金の保有する固定資産の財政運営上の評価額が時価を上回る場合、当該上回る額
(4)資産計上した特例調整金
(5)脱退により財政運営上発生する不足金
2 脱退事業所の事業主は、前項の規定により納入の告知をされた脱退時特別掛金について、脱退日までに基金に納付しなければならない。
(2)脱退時の一括徴収金が脱退時の加入員を基に計算される規約事例
脱退時の一括徴収金が任意脱退以外でも徴収される規約の場合は、任意脱退はもちろんのこと、加入事業所の合併、解散のような場合においても特別掛金が一括徴収されます。しかし、一括徴収金の額が脱退時の加入員を基に計算される次のような事例の場合であると、いわゆる「食い逃げ」が理論上は可能かと思われます。
事例(総合型J厚生年金基金)
(脱退事業所に係る債務及び不足金の一括拠出)
第○条 この基金は、設立事業所が基金を脱退する場合(設立事業所でなくなった事業主の事業及び権利義務を継承する事業主が、引き続きこの基金の設立事業所の事業主として存続する場合を除く。)において脱退により生じる当該事業所に係る次の各号に掲げる債務及び不足金を特別掛金として、当該事業所から一括して徴収するものとする。
(1)過去勤務債務相当額
(2)繰越不足金
(3)資産額を時価評価した場合に生じる不足金
(4)財政上の不足金
上記各号の「債務及び不足金の額」は、次のように計算します。
(1)過去勤務債務相当額
脱退日現在における加入員の、脱退日の翌日の属する月の前月(以下「脱退日前月」という。)の標準給与の月額の12倍に、直前の決算日(脱退日の翌日の属する月が1月から9月までのときは前年3月末日、10月から12月までのときは当年3月末日をいう。以下同じ。)において責任準備金の算出に用いた特別掛金率と、脱退日前月末における残余償却年数に対応する別表○に定める年金現価率を乗じて得た金額。
(2)繰越不足金
脱退日の翌日の属する月の直前の決算日の繰越不足金の額を直前の決算日から脱退日前月末まで予定利率5.5%で付利した額に、標準給与割合を乗じて得た金額。
(3)資産額を時価評価した場合に生じる不足金
…(省略)…
(4)財政上の不足金
…(省略)…
(3)脱退時の一括徴収金が過去の加入員を含む加入員を基に計算される規約事例
上記とは異なり、脱退時の加入員ではなく、脱退事業所に従事したことのある全加入員を基に計算されるため、「食い逃げ」が不可能となります。
事例(総合型A厚生年金基金)
第○条 この基金は、この基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所でなくなる事業主の事業及び権利義務を承継する事業主が、引き続きこの基金の設立事業所の事業主として存続する場合を除く。)において、給付に要する費用に充てるため、当該減少する設立事業所(以下「脱退事業所」という。)に係る未償却過去勤務債務等の額を算出し、特別掛金として納入の告知を行い、脱退事業所から一括して徴収するものとする。
2.前項に定めるところにより、納入の告知を受けた脱退事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに次項に定める金額を納付しなければならない。
3.第1項の未償却過去勤務債務等の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1)脱退事業所がこの基金から脱退する日の翌日の属する月の前月末日(以下この条において「脱退基準日」という。)における特別掛金収入現価に、脱退基準日までの脱退事業所に従事したことのある全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額をこの基金設立以降の全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額で除して得た率を乗じて得た額
(2)脱退事業所が脱退する日の前年度(脱退日の属する月が4月から9月までの場合においては前々年度をいう。以下同じ。)の決算(その後財政計算を行っている場合は当該財政計算時とする。以下同じ。)において計上されている次のアとイに定める額の合計額が正となる場合には、当該合計額を、前年度の決算日までの脱退事業所に従事したことのある全加入員の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額をこの基金設立以降の全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額で除して得た率を乗じて得た額に当該決算日から脱退基準日まで年利5分5厘の複利により計算したその元利合計額
ア 資産勘定の資本金の額から負債勘定の基本金の額を控除した額
イ 移行調整金残高の額
(4)加入員が大幅に減少した場合には不足金を徴収する規約事例
事業所が未だ基金を脱退していなくても、加入員が大幅に減少した場合には積立不足分の一括拠出を求めている基金もあります。また、この基金は、「設立事業所の毎月末の加入員数が、直前の基金決算日の加入員数と比較して20%以上、かつ10人以上減少した場合は、加入員の大幅な減少に係る債務・不足金を一括して納めていただきます。」との説明を“基金だより”で行っています。
事例(総合型T厚生年金基金)
(一部営業譲渡等に係る債務及び不足金の一括徴収)
第○条 附則第○条第1項の規定にかかわらず、この基金の設立事業所が、次の各号に掲げる事由により加入員を脱退させた場合(以下本条、附則第○○条及び附則第○条において「一部営業譲渡等」という。)は、当該事由により脱退した加入員に係る附則第○条第1項第1号に定める継続基準に係る債務及び不足金の額と第2号に定める非継続基準に係る債務及び不足金の額のいずれか大きい額を、一部営業譲渡等に係る特別掛金として当該事業所から一括して徴収するものとする。
(1)この基金の設立事業所でない事業所へ事業の一部を営業譲渡した場合。
(2)この基金の設立事業所でない事業所に事業の一部を合併又は買収された場合。
(3)事業所を分割し分割後の事業所がこの基金の設立事業所とならない場合。
(4)設立事業所でない事業所へ加入員を転籍又は出向させた場合。
(5)設立事業所でない事業所からの出向社員を加入員としていた場合であって、当該加入員を出向元事業所へ復帰させた場合。ただし、当該復帰が、当該設立事業所と当該出向元事業所との間における事業の再編成による復帰である場合に限る。
(6)設立事業所の加入員を脱退させて、当該脱退加入員を設立事業所でない事業所からの出向社員又は派遣会社からの派遣社員として引き続いて当該設立事業所の業務に従事させた場合。
Ⅲ 脱退後の対応
基金への加入は、退職金制度あるいは福利厚生制度の一部ですから、退職金規程や就業規則に規定されているべきものです。基金を脱退するということは、従業員が受け取るはずであった上乗せ給付部分の年金が減額されるということですから、退職金規程や就業規則を変更しない場合には、上乗せ給付部分を会社が補填する必要があります。補填の方法としては、外部積立をしないで社内資金で退職時に支給をするか、他の制度へ加入するかということになります。他の制度としては確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済が考えられます。
退職金規程や就業規則を変更し、上乗せ給付部分を手当てしないという場合には、従業員に対する労働条件の不利益な変更ということになります。労働条件の不利益変更は一方的に事業主がしてよいというものではなく、上乗せ給付部分を手当てしないという合理的な理由の存在や加入員である労働者への十分な説明と同意が必要となります。また、これを機会に退職金規程を全体的に改正してしまう事例や退職金制度そのものを廃止し給料にその分を上乗せするような事例もあります。このように、基金を脱退した後の選択肢もたくさんありますので、その事業所の実情にあった制度を設計することが大切です。実際には、基金を脱退することについて加入員の同意を取り付ける際に、今後の制度の説明をすることになります。
Ⅳ 厚生年金基金にまつわる所得税の取り扱いについての留意事項
1. 基金の解散に伴う残余財産の分配金
基金の解散に伴う残余財産の分配金は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした裁決事例があります(平15-10-24裁決)。この裁決では、年金受給者である審査請求人(以下「請求人」)に対して支払われた、D社厚生年金基金(以下「本件基金」又は「基金」)の解散に伴う残余財産の分配金の全額が、一時所得とされるかどうかについて争われました。
国税不服審判所は、「本件分配金は、所得税法第30条第1項に規定する退職所得であると認めることはできないものであり、また、本件基金の解散という偶発的事由を発生原因とする一時金であり、所得税法第34条第1項の規定による一時所得に当たることとなる」と判断して、審査請求を棄却しました。裁決の要旨は以下のとおりです。
(1)基礎事実
請求人は、平成3年9月に満年齢57歳でD社を退職するに当たり、退職一時金9,642,400円を受け取りました。退職一時金の計算式によれば、この金額は、退職金総額14,669,000円から加算年金5,026,600円を控除した金額であり、加算年金の金額は、拠出加算年金現価相当額で、基金がD社に代わって請求人に支給する金額です。
請求人は、満年齢60歳を迎えた平成6年10月分から、基金の解散前である平成12年7月分までの加算年金を基金から受給しており、基金は平成12年9月29日に解散しました。基金の清算後の残余財産の金額を基準とした請求人の分配金の額は、9,404,250円です。本件分配金については、基金の規約に基づき、「一時金で受け取る方法」か「本件基金が厚生年金基金連合会に移管し、将来(又は現在)の年金に加算して受け取る方法」のいずれかを選択することを加入員に求めており、請求人は本件分配金を全額一時金で受け取る方法を選択しました。
(2)請求人の主張
・基金の解散に伴う残余財産の分配である本件分配金には、退職金の一部であり、基金に据え置いて積み立てた「拠出加算年金現価相当額」が含まれ、基金の原資は、それぞれの退職者の退職金とその運用益によって成り立っている。
・「加算年金受給残額」は、請求人が受給する加算年金のうち既に受給した加算年金を除いた、将来支給を受ける加算年金の額であって、本件基金の解散という偶発的事由に基づくものではなく、請求人の退職に基因して支払われた一時金に当たり退職所得である。したがって、一時所得とされる本件分配金の額から控除すべきである。
・退職所得の額として一時所得の額から控除すべき額は、加算年金年額675,500円を12で除し、支給期間である15年間の月数180か月から既に受給した月数70か月を控除した月数110か月を乗じた額6,192,083円と正確に計算される。
(3)関係法令等
所法第30条第1項の規定によれば、退職所得とは、退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいうとされ、同法第31条第2号においては、「厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で同法第122条に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの」を退職手当等とみなす旨規定しています。
また、所基通31-1の(1)では、厚生年金基金規約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)については、所法第31条第2号に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当すると定めています。
(4)審判所の判断
厚生年金基金が解散した場合、厚生年金基金連合会は、厚生年金基金から責任準備金の納付を受けて代行部分の給付義務を引き継ぐこととなり、上乗せ部分の給付については、年金給付を選択した者に係る残余財産の交付を受け、当該交付金を原資とした上乗せ部分の給付として年金又は死亡一時金及びその他の一時金を支給することとなるが、残余財産の分配金を一時金で受け取ることを選択した者については残余財産の交付がないことから上乗せ部分の給付はなくなることとなる。
本件分配金が請求人の退職に基因して支払われたものとして、所得税法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金であるといえるかどうかについて以下検討する。
イ)厚生年金基金の解散の場合に支払われる一時金については、基金の解散に基因して支払われるものであること、及び、既に退職した者についてだけでなく、退職の事実がなく引き続き勤務している者であっても支払われるものであり、当該一時金の支払が退職という事実と関係なく行われることからすれば、「退職に基因して支払われるもの」でないというべきである。
ロ)また、本件分配金の算定方法をみてみると、本件分配金の額は、厚生年金基金連合会に移管される基本年金部分としての最低積立基準額相当額に基づいた残余財産の額に応じて算定されているのに対し、請求人の主張する本件加算年金受給残額は、加入員期間の最終加算給与月額を基に算定されている点で、両者の算定方法は全く異なっており、両者の間に関連性がないことが認められるのであって、この点からも本件分配金が本来の退職一時金とその実質において同様のものであるとは認められない。
ハ)そして、退職所得とされる一時金は、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものの現価相当額、すなわち将来支給を受ける年金総額の前払いとしての支払であるのに対し、本件分配金は、上乗せ部分の給付原資に係る残余財産の分配であり、将来の年金給付の総額との関連性を有していないものであることから、本件分配金を退職手当等とみなされる一時金と解することはできない。
2. 代行返上の場合に受け取る一時金
代行返上とは、厚生年金基金が行っている老齢厚生年金に係る代行給付について、国にその支給義務を返上(移転)し、合わせて厚生年金基金の上乗せ部分(代行部分以外)の給付に係る支給義務を確定給付企業年金(基金型企業年金或いは規約型企業年金)に移行することです。厚生年金基金を解散した後に確定給付企業年金や確定拠出年金を導入することとは異なります。従って、「代行返上」といわれるのは、厚生年金基金から確定給付企業年金へ移行する場合だけです(企業年金連合会ホームページより)。
「厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度への移行に伴いプラスアルファ部分相当額を会社が一時金として支給した場合の取扱いについて」の事前照会では、東京国税局が、「年金受給権者に支給される基金一時金に係る課税関係については、照会に係る事実関係を前提とする限り、年金受給権者のうち、受給待期者の場合は退職所得、年金受給者の場合は、将来の年金給付の総額に代えて支給を受ける場合には退職所得となるが、そうでない場合は原則として一時所得となるとの取り扱いで差し支えありません。」と回答しています。
おわりに
国民年金法第1条は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定しており、国民年金は、その目的を達成するために必要な給付を行います。憲法第25条第2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定していますが、この憲法第25条と国民年金法について、通説はおおよそ次のように理解します。
憲法第25条第1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」として、すべての国民が生存権を保障されることを規定しています。しかし、生存権といっても中身が非常に抽象的であり、具体的にいかなるものが生存権なのかを明確にしなければ保障のしようがありませんので、第2項で、国に対し、社会保障制度や社会福祉制度を整備するように努力せよと命じています。すなわち、第1項は国民の権利に関する規定であり、第2項は国民の権利を実現するための国の責務を規定している訳です。国民年金受給権も直接的には第2項から導き出されるのでしょうが、前提として第1項(すべての国民の生存権の保障)があるわけです。
◇参考文献
坪野剛司編「新企業年金」日本経済新聞社
高澤留美子「厚生年金基金をやめる(ビジネスガイド2002年6月号)」(株)日本法令
新日本保険新聞社「保険税務のすべて」
大東文化大学法学部森稔樹ホームページ
厚生年金基金からの脱退と年金制度
税理士 江崎一恵
はじめに
厚生年金基金は、平成16年3月末現在で、1,357基金、加入員数約835万人となっています。中小企業が加入している総合型基金も574基金(加入員約500万人)あり、大企業中心の制度というわけではありません。基金に加入している事業所の中には、掛金の負担増と将来の給付の削減などの理由から、脱退を希望しているところも少なくないようですが、任意脱退をするには、基金の代議員や脱退事業所の被保険者の同意が必要であり、さらに多額の一括徴収金が必要なため、やむを得ず参加を続けているのが現状のようです。
事業所が基金から脱退しても、基金は将来、それまで加入員が積み立ててきた分について上乗せした年金を支払いますので、その運用不足分は基金を脱退しなかった残余の事業所が負担することになります。
従来は、脱退時に特別掛金を徴収することに関する法律的根拠がなく、脱退時の一括徴収金の制度を設けていない基金が多かったのですが、平成14年4月1日施行の厚生年金保険法の改正により、残余の事業所の負担が増加することとなるときは、基金は、増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める一定の計算方法のうちから規約で定めるものにより算定した額を、基金から抜ける事業所から掛金として一括徴収することができるようになりました。
一括徴収の対象となる理由や計算方法は、基金によって異なります。脱退時点で過去の全加入員の不足金を計算する基金、脱退時の加入員を基に計算する基金等があり、さらには、脱退しなくても、加入員が大幅に減少した場合には徴収する方式を採る基金もありますので、企業が脱退を希望している場合は、事前に規約の内容を確認することが肝要といえます。
また組織再編の場面においては、被合併会社が基金に加入しており、合併会社が加入していないような場合、合併を契機に基金からの脱退を考える会社もあるようです。そして、合併による脱退は任意脱退に該当しないことから一時金の支払は不要だと考え、合併の計画が固まった頃に脱退を申し出て、そこで初めて高額の納付金が必要であることを知って困惑するという話が仄聞されます。
このような基金脱退に関する会社からの相談、あるいは、基金の解散に伴う残余財産の分配金や代行返上の場合の一時金を受給する納税者の相談などに応じるためには、基金の仕組みを理解している必要があります。そして、その前にまず年金制度の基礎知識が必要であると考えて本稿を執筆しました。
Ⅰ 年金制度の概要
わが国の年金制度は、国民年金(基礎年金)を基礎とした下図のような3階建ての体系となっています。以下に簡単にそれぞれの年金制度について説明します。
1. 国民年金
国民年金は、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全国民が強制的に加入するいわゆる1階部分の年金で、老齢・障害・死亡に関して必要な給付をするのが目的です。
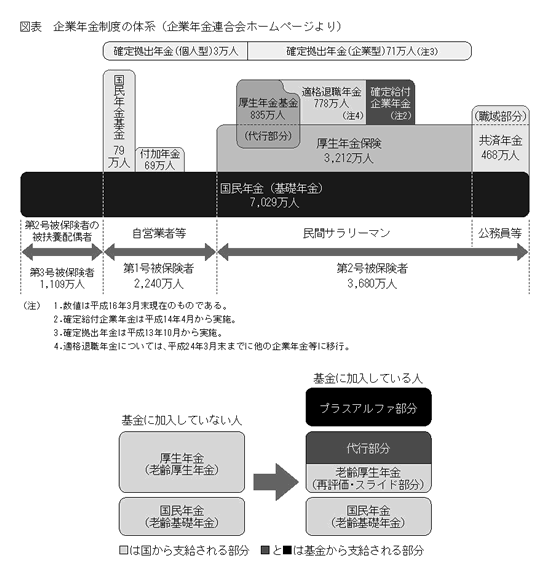
(1)被保険者の区分
被保険者の区分には第1号被保険者(自営業者、学生など)と第2号被保険者(厚生年金や共済年金などの加入者)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)があります。自ら保険料を納付しなければならないのは第1号被保険者のみです。
第2号被保険者の国民年金保険料は勤め先で徴収されている厚生年金保険料に含まれており、第3号被保険者の国民年金保険料は第2号被保険者が負担しています。
(2)課税関係
「老齢基礎年金及び付加年金」の給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35③一、31一)。「障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金」は非課税となっています(国年15条、25条)。
国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(所法74②五)。
2. 国民年金基金
国民年金の第1号被保険者を対象にした2階部分の年金で、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除の対象となります(所法74②五)。年金給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一)。
3. 厚生年金
厚生年金は民間の給与所得者が加入するもので2階部分に当たるものです。厚生年金の適用事業所で働く給与所得者は70歳まで厚生年金に加入し、給与の額に比例した保険料を事業主と折半で納めますが、20歳から60歳の間は自動的に国民年金にも加入しているとみなされるため、下位の標準報酬月額の場合、国民年金保険料よりも低い保険料負担で1階、2階部分の給付が受けられることになります。
老齢厚生年金の給付は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一)。障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金は非課税です(厚年41条②)。厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料は、社会保険料控除の対象になります(所法74②七)。
4. 退職共済年金
共済年金とは国家公務員、地方公務員、私立学校の職員のうち私立学校共済制度がある団体に所属する者が加入する制度で、退職共済年金は厚生年金と同じく2階建て部分を構成する年金です。厚生年金との相違点は職域加算という3階の部分の給付があり、この上乗せ給付までを入れると厚生年金と比べ割安な保険料率となっていることや遺族年金の遺族の範囲が厚生年金より広いことなどから、優遇を廃止し年金を一元化しようということが議論されています。
5. 厚生年金基金
厚生年金基金は昭和41年に始まった制度で、厚生年金の上乗せ、つまり3階部分を構成する企業年金です。厚生年金と違い加入は義務付けられておらず、事業所単位で加入を選択します。老齢給付について厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行うことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。基金の設立形態には、一企業で設立する単独設立、同一の資本系列の企業グループで設立する連合設立、同業種・同地域などの企業が集まって設立する総合設立の3種があります。
(1)拠出段階における課税上の取り扱い
厚生年金基金を設立すると、厚生年金保険料のうち、代行給付に見合う保険料を政府に納付することを免除され(免除料率)、これに上乗せ給付をするための掛金をあわせて、基金が徴収することになります。掛金の負担割合は、免除料率については事業主と加入者の折半ですが、上乗せ給付のための掛金については事業主の負担を増加することができます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。
(2)給付段階における課税上の取り扱い
①退職年金
加入者が受け取る退職年金は、雑所得のうち公的年金等に該当します(所法35条③一、31一、31二)。
②退職一時金
厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で、同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるものは、退職手当等とみなされます(所法31二)。
③遺族一時金等
厚生年金保険法136条(準用規定)は、「第41条第2項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。」と規定しています。そして、同法第41条第2項(公課の禁止)は、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない」としていますので、遺族一時金等は非課税となります。
6. その他の企業年金
(1)確定給付企業年金
確定給付企業年金法(平成13年6月公布)に基づき、平成14年4月から実施された確定給付型の企業年金制度です。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがあります。年金資産の積立基準をはじめ、管理・運営にかかわる者(受託者)の責任が明確になっているほか、財務状況などの情報開示も事業主などへ義務づけられています。
(2)確定拠出年金
拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。積立不足ということがないため企業が追加拠出をする必要はありませんが、加入者にとっては運用のリスクを負い、給付額が定まらないため老後の生活設計を立てにくい面があります。しかし、途中で転職しても、自分の年金原資を転職先に移管して、通算した年金を受け取ること(ポータビリティ)が可能です。わが国では、確定拠出年金がこれにあたります。なお、アメリカでは401(k)と呼ばれる確定拠出型年金が普及しています。
(3)適格退職年金
厚生年金基金と並ぶ企業年金制度で、昭和37年に発足しました。年金原資を外部機関に積み立てるなど、法人税法で定める一定の条件を満たすことで国税庁長官に承認されます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があります。退職金の原資を社外積立によって平準化できることや、厚生年金基金に比べ少人数(15人以上)でも設立できるメリットがあります。
なお、平成14年度以降、新たな適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成24年4月から優遇措置が受けられなくなりますが平成23年度末までは確定給付企業年金等に非課税で移行することができます。
Ⅱ 厚生年金基金からの脱退
総合型厚生年金基金において、従来は脱退時に特別掛金を徴収することに関する法律的根拠がなく、脱退時の一括徴収金の制度を設けていない基金が多かったのですが、平成14年の厚生年金保険法の改正で、脱退する事業所から掛金を一括徴収することが規定されたのを機に、多くの基金で脱退時の特別掛金の一括徴収についての規定が整備されました。
1. 平成14年の改正
平成14年4月施行の改正厚生年金保険法では次の条項が追加されました。
厚生年金保険法138条(抄)
5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
厚生労働省令で定める計算方法とは(厚生年金基金規則第32条の3の2の要約)
① 未償却過去勤務債務のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額とする方法
② 積立金の額が最低積立基準額を下回る場合、下回る額のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額とする方法
③ ①、②のいずれか大きい額とする方法
※①については、繰越不足金等のうち減少事業所が負担すべき額として合理的に計算した額を加算することができる。
2. 脱退時の一括徴収金の計算についてのイメージ
脱退時の一括徴収金の計算は基金によって計算根拠も違うため、実際には基金にて計算してもらうほかないのですが、加入員一人当たりの大まかな金額は例えば下記のように計算式でイメージできると思われます。
(【将来の年金給付のために積み立てられているべき額(数理債務、給付債務と表示されている)】-【純資産額】)÷加入員数
例えば給付債務1,200億円、純資産額800億円、加入員数2万人の基金の場合、
(1,200億円-800億円)÷2万人=200万円
脱退事業所の計算基礎となる加入員数が50人の場合、200万円×50人=1億円の特別掛金を一括納付することになります。
3. いわゆる「食い逃げ、足抜け」とは
この脱退時の一括徴収金を逃れるためにとられた方法が、いわゆる「食い逃げ、足抜け」といわれる方法で、それが基金に残った他の加入事業所の負担をさらに重くする結果となることが問題となっています。特に平成14年の厚生年金保険法改正前は、総合型厚生年金基金を任意脱退する場合の脱退時の一括徴収金が脱退時の加入員の人数に応じて算定される場合、その負担を軽減するために次のような手法により脱退をする事業所が多く見受けられました。
基金から脱退しようとする事業所は、先ず加入員である従業員をその基金に加入していない別会社へ順次転籍させます。この時点で転籍した従業員はその基金から脱退することになります。最後に社長だけが事業所に残った形となり、この社長の分に対応する一括徴収金のみを納付して基金を脱退するのです。この手法により、転籍した従業員にかかる一括徴収金の負担が不要となります。
4. 一括徴収金についての規約事例
脱退時の一括徴収金について法律で明文化されたといっても、個々の基金の規約においてこれを規定し、それを周知させなければ、改正条文は生かされません。脱退時の一括徴収金についての規定は基金によって様々ですので、加入している基金が、どのように規定しているかを確認しておくことが肝心です。ここで脱退時の一括徴収金について4つの基金の規約事例を見てみます。
(1)脱退時の一括徴収金が任意脱退の場合にのみ必要な規約事例
任意脱退時にのみ特別掛金を一括徴収する規約の場合、加入企業の合併、解散などの理由により基金を脱退することとなるときは、特別掛金の一括徴収はされません。このような規約は連合型の厚生年金基金においてその例がみられます。
事例(連合型S厚生年金基金)
(設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収)
第○条 基金は、設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が任意脱退の申出を行い、代議員会が認めた場合に限る。)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加する額として、次の各号に掲げる債務及び不足金を当該減少に係る設立事業所(以下、「脱退事業所」という。)の事業主から脱退時特別掛金として一括して徴収するものとし、当該脱退事業所の事業主に対し納入の告知を行う。
(1)未償却過去勤務債務
(2)繰越不足金
(3)基金の保有する固定資産の財政運営上の評価額が時価を上回る場合、当該上回る額
(4)資産計上した特例調整金
(5)脱退により財政運営上発生する不足金
2 脱退事業所の事業主は、前項の規定により納入の告知をされた脱退時特別掛金について、脱退日までに基金に納付しなければならない。
(2)脱退時の一括徴収金が脱退時の加入員を基に計算される規約事例
脱退時の一括徴収金が任意脱退以外でも徴収される規約の場合は、任意脱退はもちろんのこと、加入事業所の合併、解散のような場合においても特別掛金が一括徴収されます。しかし、一括徴収金の額が脱退時の加入員を基に計算される次のような事例の場合であると、いわゆる「食い逃げ」が理論上は可能かと思われます。
事例(総合型J厚生年金基金)
(脱退事業所に係る債務及び不足金の一括拠出)
第○条 この基金は、設立事業所が基金を脱退する場合(設立事業所でなくなった事業主の事業及び権利義務を継承する事業主が、引き続きこの基金の設立事業所の事業主として存続する場合を除く。)において脱退により生じる当該事業所に係る次の各号に掲げる債務及び不足金を特別掛金として、当該事業所から一括して徴収するものとする。
(1)過去勤務債務相当額
(2)繰越不足金
(3)資産額を時価評価した場合に生じる不足金
(4)財政上の不足金
上記各号の「債務及び不足金の額」は、次のように計算します。
(1)過去勤務債務相当額
脱退日現在における加入員の、脱退日の翌日の属する月の前月(以下「脱退日前月」という。)の標準給与の月額の12倍に、直前の決算日(脱退日の翌日の属する月が1月から9月までのときは前年3月末日、10月から12月までのときは当年3月末日をいう。以下同じ。)において責任準備金の算出に用いた特別掛金率と、脱退日前月末における残余償却年数に対応する別表○に定める年金現価率を乗じて得た金額。
(2)繰越不足金
脱退日の翌日の属する月の直前の決算日の繰越不足金の額を直前の決算日から脱退日前月末まで予定利率5.5%で付利した額に、標準給与割合を乗じて得た金額。
(3)資産額を時価評価した場合に生じる不足金
…(省略)…
(4)財政上の不足金
…(省略)…
(3)脱退時の一括徴収金が過去の加入員を含む加入員を基に計算される規約事例
上記とは異なり、脱退時の加入員ではなく、脱退事業所に従事したことのある全加入員を基に計算されるため、「食い逃げ」が不可能となります。
事例(総合型A厚生年金基金)
第○条 この基金は、この基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所でなくなる事業主の事業及び権利義務を承継する事業主が、引き続きこの基金の設立事業所の事業主として存続する場合を除く。)において、給付に要する費用に充てるため、当該減少する設立事業所(以下「脱退事業所」という。)に係る未償却過去勤務債務等の額を算出し、特別掛金として納入の告知を行い、脱退事業所から一括して徴収するものとする。
2.前項に定めるところにより、納入の告知を受けた脱退事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに次項に定める金額を納付しなければならない。
3.第1項の未償却過去勤務債務等の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1)脱退事業所がこの基金から脱退する日の翌日の属する月の前月末日(以下この条において「脱退基準日」という。)における特別掛金収入現価に、脱退基準日までの脱退事業所に従事したことのある全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額をこの基金設立以降の全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額で除して得た率を乗じて得た額
(2)脱退事業所が脱退する日の前年度(脱退日の属する月が4月から9月までの場合においては前々年度をいう。以下同じ。)の決算(その後財政計算を行っている場合は当該財政計算時とする。以下同じ。)において計上されている次のアとイに定める額の合計額が正となる場合には、当該合計額を、前年度の決算日までの脱退事業所に従事したことのある全加入員の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額をこの基金設立以降の全加入員(ただし、受給権を失権した者及び中途脱退者並びに権利義務の移転承継を行った者は除く。)の加入員期間中の報酬標準給与の月額の累計額で除して得た率を乗じて得た額に当該決算日から脱退基準日まで年利5分5厘の複利により計算したその元利合計額
ア 資産勘定の資本金の額から負債勘定の基本金の額を控除した額
イ 移行調整金残高の額
(4)加入員が大幅に減少した場合には不足金を徴収する規約事例
事業所が未だ基金を脱退していなくても、加入員が大幅に減少した場合には積立不足分の一括拠出を求めている基金もあります。また、この基金は、「設立事業所の毎月末の加入員数が、直前の基金決算日の加入員数と比較して20%以上、かつ10人以上減少した場合は、加入員の大幅な減少に係る債務・不足金を一括して納めていただきます。」との説明を“基金だより”で行っています。
事例(総合型T厚生年金基金)
(一部営業譲渡等に係る債務及び不足金の一括徴収)
第○条 附則第○条第1項の規定にかかわらず、この基金の設立事業所が、次の各号に掲げる事由により加入員を脱退させた場合(以下本条、附則第○○条及び附則第○条において「一部営業譲渡等」という。)は、当該事由により脱退した加入員に係る附則第○条第1項第1号に定める継続基準に係る債務及び不足金の額と第2号に定める非継続基準に係る債務及び不足金の額のいずれか大きい額を、一部営業譲渡等に係る特別掛金として当該事業所から一括して徴収するものとする。
(1)この基金の設立事業所でない事業所へ事業の一部を営業譲渡した場合。
(2)この基金の設立事業所でない事業所に事業の一部を合併又は買収された場合。
(3)事業所を分割し分割後の事業所がこの基金の設立事業所とならない場合。
(4)設立事業所でない事業所へ加入員を転籍又は出向させた場合。
(5)設立事業所でない事業所からの出向社員を加入員としていた場合であって、当該加入員を出向元事業所へ復帰させた場合。ただし、当該復帰が、当該設立事業所と当該出向元事業所との間における事業の再編成による復帰である場合に限る。
(6)設立事業所の加入員を脱退させて、当該脱退加入員を設立事業所でない事業所からの出向社員又は派遣会社からの派遣社員として引き続いて当該設立事業所の業務に従事させた場合。
Ⅲ 脱退後の対応
基金への加入は、退職金制度あるいは福利厚生制度の一部ですから、退職金規程や就業規則に規定されているべきものです。基金を脱退するということは、従業員が受け取るはずであった上乗せ給付部分の年金が減額されるということですから、退職金規程や就業規則を変更しない場合には、上乗せ給付部分を会社が補填する必要があります。補填の方法としては、外部積立をしないで社内資金で退職時に支給をするか、他の制度へ加入するかということになります。他の制度としては確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済が考えられます。
退職金規程や就業規則を変更し、上乗せ給付部分を手当てしないという場合には、従業員に対する労働条件の不利益な変更ということになります。労働条件の不利益変更は一方的に事業主がしてよいというものではなく、上乗せ給付部分を手当てしないという合理的な理由の存在や加入員である労働者への十分な説明と同意が必要となります。また、これを機会に退職金規程を全体的に改正してしまう事例や退職金制度そのものを廃止し給料にその分を上乗せするような事例もあります。このように、基金を脱退した後の選択肢もたくさんありますので、その事業所の実情にあった制度を設計することが大切です。実際には、基金を脱退することについて加入員の同意を取り付ける際に、今後の制度の説明をすることになります。
Ⅳ 厚生年金基金にまつわる所得税の取り扱いについての留意事項
1. 基金の解散に伴う残余財産の分配金
基金の解散に伴う残余財産の分配金は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした裁決事例があります(平15-10-24裁決)。この裁決では、年金受給者である審査請求人(以下「請求人」)に対して支払われた、D社厚生年金基金(以下「本件基金」又は「基金」)の解散に伴う残余財産の分配金の全額が、一時所得とされるかどうかについて争われました。
国税不服審判所は、「本件分配金は、所得税法第30条第1項に規定する退職所得であると認めることはできないものであり、また、本件基金の解散という偶発的事由を発生原因とする一時金であり、所得税法第34条第1項の規定による一時所得に当たることとなる」と判断して、審査請求を棄却しました。裁決の要旨は以下のとおりです。
(1)基礎事実
請求人は、平成3年9月に満年齢57歳でD社を退職するに当たり、退職一時金9,642,400円を受け取りました。退職一時金の計算式によれば、この金額は、退職金総額14,669,000円から加算年金5,026,600円を控除した金額であり、加算年金の金額は、拠出加算年金現価相当額で、基金がD社に代わって請求人に支給する金額です。
請求人は、満年齢60歳を迎えた平成6年10月分から、基金の解散前である平成12年7月分までの加算年金を基金から受給しており、基金は平成12年9月29日に解散しました。基金の清算後の残余財産の金額を基準とした請求人の分配金の額は、9,404,250円です。本件分配金については、基金の規約に基づき、「一時金で受け取る方法」か「本件基金が厚生年金基金連合会に移管し、将来(又は現在)の年金に加算して受け取る方法」のいずれかを選択することを加入員に求めており、請求人は本件分配金を全額一時金で受け取る方法を選択しました。
(2)請求人の主張
・基金の解散に伴う残余財産の分配である本件分配金には、退職金の一部であり、基金に据え置いて積み立てた「拠出加算年金現価相当額」が含まれ、基金の原資は、それぞれの退職者の退職金とその運用益によって成り立っている。
・「加算年金受給残額」は、請求人が受給する加算年金のうち既に受給した加算年金を除いた、将来支給を受ける加算年金の額であって、本件基金の解散という偶発的事由に基づくものではなく、請求人の退職に基因して支払われた一時金に当たり退職所得である。したがって、一時所得とされる本件分配金の額から控除すべきである。
・退職所得の額として一時所得の額から控除すべき額は、加算年金年額675,500円を12で除し、支給期間である15年間の月数180か月から既に受給した月数70か月を控除した月数110か月を乗じた額6,192,083円と正確に計算される。
(3)関係法令等
所法第30条第1項の規定によれば、退職所得とは、退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいうとされ、同法第31条第2号においては、「厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で同法第122条に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの」を退職手当等とみなす旨規定しています。
また、所基通31-1の(1)では、厚生年金基金規約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)については、所法第31条第2号に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当すると定めています。
(4)審判所の判断
厚生年金基金が解散した場合、厚生年金基金連合会は、厚生年金基金から責任準備金の納付を受けて代行部分の給付義務を引き継ぐこととなり、上乗せ部分の給付については、年金給付を選択した者に係る残余財産の交付を受け、当該交付金を原資とした上乗せ部分の給付として年金又は死亡一時金及びその他の一時金を支給することとなるが、残余財産の分配金を一時金で受け取ることを選択した者については残余財産の交付がないことから上乗せ部分の給付はなくなることとなる。
本件分配金が請求人の退職に基因して支払われたものとして、所得税法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金であるといえるかどうかについて以下検討する。
イ)厚生年金基金の解散の場合に支払われる一時金については、基金の解散に基因して支払われるものであること、及び、既に退職した者についてだけでなく、退職の事実がなく引き続き勤務している者であっても支払われるものであり、当該一時金の支払が退職という事実と関係なく行われることからすれば、「退職に基因して支払われるもの」でないというべきである。
ロ)また、本件分配金の算定方法をみてみると、本件分配金の額は、厚生年金基金連合会に移管される基本年金部分としての最低積立基準額相当額に基づいた残余財産の額に応じて算定されているのに対し、請求人の主張する本件加算年金受給残額は、加入員期間の最終加算給与月額を基に算定されている点で、両者の算定方法は全く異なっており、両者の間に関連性がないことが認められるのであって、この点からも本件分配金が本来の退職一時金とその実質において同様のものであるとは認められない。
ハ)そして、退職所得とされる一時金は、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものの現価相当額、すなわち将来支給を受ける年金総額の前払いとしての支払であるのに対し、本件分配金は、上乗せ部分の給付原資に係る残余財産の分配であり、将来の年金給付の総額との関連性を有していないものであることから、本件分配金を退職手当等とみなされる一時金と解することはできない。
2. 代行返上の場合に受け取る一時金
代行返上とは、厚生年金基金が行っている老齢厚生年金に係る代行給付について、国にその支給義務を返上(移転)し、合わせて厚生年金基金の上乗せ部分(代行部分以外)の給付に係る支給義務を確定給付企業年金(基金型企業年金或いは規約型企業年金)に移行することです。厚生年金基金を解散した後に確定給付企業年金や確定拠出年金を導入することとは異なります。従って、「代行返上」といわれるのは、厚生年金基金から確定給付企業年金へ移行する場合だけです(企業年金連合会ホームページより)。
「厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度への移行に伴いプラスアルファ部分相当額を会社が一時金として支給した場合の取扱いについて」の事前照会では、東京国税局が、「年金受給権者に支給される基金一時金に係る課税関係については、照会に係る事実関係を前提とする限り、年金受給権者のうち、受給待期者の場合は退職所得、年金受給者の場合は、将来の年金給付の総額に代えて支給を受ける場合には退職所得となるが、そうでない場合は原則として一時所得となるとの取り扱いで差し支えありません。」と回答しています。
おわりに
国民年金法第1条は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定しており、国民年金は、その目的を達成するために必要な給付を行います。憲法第25条第2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定していますが、この憲法第25条と国民年金法について、通説はおおよそ次のように理解します。
憲法第25条第1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」として、すべての国民が生存権を保障されることを規定しています。しかし、生存権といっても中身が非常に抽象的であり、具体的にいかなるものが生存権なのかを明確にしなければ保障のしようがありませんので、第2項で、国に対し、社会保障制度や社会福祉制度を整備するように努力せよと命じています。すなわち、第1項は国民の権利に関する規定であり、第2項は国民の権利を実現するための国の責務を規定している訳です。国民年金受給権も直接的には第2項から導き出されるのでしょうが、前提として第1項(すべての国民の生存権の保障)があるわけです。
◇参考文献
坪野剛司編「新企業年金」日本経済新聞社
高澤留美子「厚生年金基金をやめる(ビジネスガイド2002年6月号)」(株)日本法令
新日本保険新聞社「保険税務のすべて」
大東文化大学法学部森稔樹ホームページ
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























