解説記事2006年07月03日 【実務解説】 会計事務所職員のための経理実務 第5回 (2006年7月3日号・№169)
実務解説
会計事務所職員のための経理実務 第5回
税理士 竹内秀男
給与計算
1 サラリーマンの税金の仕組み
給料にかかる税金には、所得税と住民税があります。住民税は翌年からかかるため、1年目は納める必要がありません。所得税は1月1日から12月31日までの1年間の儲け(所得)に対して翌年3月15日までに確定申告をして納めるのですが、給与所得者(サラリーマン)の場合には、通常は確定申告がいりません。
会社が月々の給料から所得税を概算で天引きして、本人に代わって納める仕組み(源泉徴収制度)になっています。この源泉徴収は、その人の正しい所得税の金額ではないので、会社がその年の12月に年末調整という手続で正しい所得税の金額に計算し直してくれます。通常は納め過ぎの所得税が返されます。
2 毎月の定例事務
給与計算事務とは、社員の給与総支払額と控除額を計算し、各人が実際に受け取る差引支給額を計算して、本人に支給するまでの事務をいいます。月間スケジュールは図表1のとおりです。
(1)各人の給与から控除した(預った)所得税・住民税を、原則として翌月10日までに所得税は税務署に、住民税は各市区町村へ納付します。
(2)各人の給与から控除した(預った)健康保険料・厚生年金保険料に事業主負担を合わせた保険料を翌月末日までに納付します。
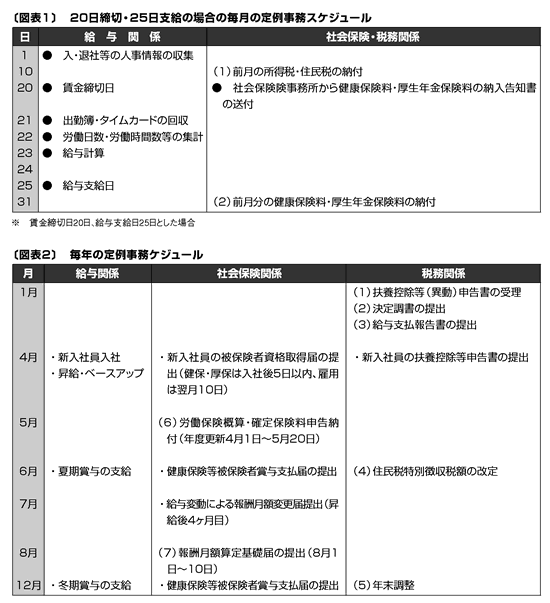
3 毎年の定例事務
年間スケジュールは図表2のとおりです。
(1)扶養控除等(異動)申告書の受理
各給与受給者(社員)から1月の給与支払日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
(2)法定調書の提出
給与や退職金、報酬、料金、不動産の使用料等の支払いの明細を記載した支払調書を作成し、1月31日までに税務署に提出します。
(3)給与支払報告書の提出
前年中に支払った給与について給与支払報告書(源泉徴収票と同時複写)を作成し、1月31日までに各給与受給者(社員)の住んでいる市区町村に提出します。
(4)住民税特別徴収税額の改定
住民税特別徴収税額は6月より改定します。
(5)年末調整
毎月の源泉徴収税額と、その年の給与の総額(年収)について納めなければならない所得税(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。
(6)労働保険料年度更新事務
労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料の申告納付を5月20日までに行います。
(7)標準報酬月額の定時決定
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定のため「報酬月額算定基礎届」を社会保険事務所に8月1日から8月10日までに提出します。
4 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
(1)健康保険
健康保険は、社員や社員の家族の健康を守ることを目的としています。具体的には、社員やその家族が業務外の原因による傷病にかかったり、出産や死亡などによって、家計から不時の出費を要する場合、その負担を軽くするため、医療費を負担したり、一定の金額を支給するというものです。
健康保険から支給されるものとしては、病気にかかったときやケガをしたときに保険証を提示して医療を受ける療養の給付が中心となっており、そのほかに、療養費、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、埋葬費などがあります。
保険料は被保険者(社員)の標準報酬月額と標準賞与額(平成15年4月から総報酬制が実施され、賞与からも同率で保険料が徴収されます)に保険料率を乗じた額で、事業主(会社)と被保険者(社員)が折半で負担することになります。
政府管掌健康保険の保険料率は、1,000分の82(組合管掌健康保険の保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で組合の理事会で決定し、厚生労働大臣の許可を得て定めることになっている)です。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険は、働く人が年をとったり、障害者となったり、死亡したときに、年金を中心とした長期の保険給付を行う制度です。対象となる保険事故は老齢、障害、死亡の3つで、これらに対して老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の給付がそれぞれ行われます。
保険料は健康保険と同じように、被保険者(社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じた額で、事業主(会社)と被保険者(社員)が折半で負担します。
保険料率は、平成16年9月まで1,000分の135.8、平成16年10月から毎年1,000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月以後、1,000分の183.0になります。
(3)雇用保険
雇用保険が行う失業等給付は、労働者が失業した場合に新しい勤務先が決まるまでの一定期
間、援助しようとするものです。また、超高齢
社会や少子化時代を反映して、高年齢者の継続
雇用や育児休業・介護休業した人を援助するた
めの給付も行っています。
保険料は被保険者(社員)に支払う給与に保険料率を乗じて得た額です。保険料率は、業種によって3つに分かれています。一般の事業は1,000分の19.5、農林水産業と清酒製造業は1,000分の21.5、そして建設業については1,000分の22.5となっています。このうち、一般の事業で働く被保険者(社員)が負担するのは1,000分の8、その他の事業で働く被保険者分(社員分)は1,000分の9となっています。そして残りを事業主(会社)が負担します。
(4)労災保険
労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に災害に遭い、ケガをしたり病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に一定の給付を行うほか、その被災労働者や遺族の生活を保護するための労働福祉事業を行うために設けられた制度です。
労災保険の給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遣族(補償)給付、葬祭料があります。なお、補償という文字がつく給付は、葬祭料を除いて、すべて業務上災害にかかる給付となっています。
保険料は働いている人に支払う給与に保険料率を乗じて得た額となります。保険料率は、災害の発生割合に応じて業種ごとに1,000分の5から1,000分の129と定められています。この保険料の負担はすべて事業主(会社)が行います。
5 源泉徴収(所得税)、特別徴収(住民税)
(1)源泉徴収(所得税)
① 源泉徴収制度
所得税は所得者自身がその年中の所得や税額を計算して申告し、その税額(所得税)を納める「申告納税制度」を原則としています。しかし、国民全員が確定申告をすると税務署の対応は困難となります。そこで給与の支払いを受ける人(給与所得者)などについては「源泉徴収制度」により、給与を支払う際にその支払いをする者(会社)が社員に支払う給与から一定の税額(所得税)を天引きしておき、これを定められた期日までに納付します。そして、源泉徴収された給与所得者の所得税は、原則として年末調整によって精算されます。
この源泉徴収をする給与の支払者(会社)を源泉徴収義務者といいます。
② 徴 収
源泉徴収は給与などを支払う都度行うことになっています。そして源泉徴収の税額を求めるために必要なのが「給与所得の源泉徴収税額表」です。源泉徴収税額表の適用区分は図表3のとおりです。
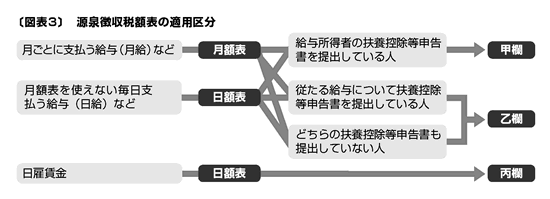
③ 納 付
源泉徴収した税額は翌月10日までに納付します。ただし、常時10人未満の給与所得者(社員)に給与を支払っている小規模な事業所では、税務署の承認を受けて次のような納期の特例制度があります。この場合、給与を支払うごとに源泉徴収を行い、納付日まで会社が預かることになります。
・1月から6月分……7月10日までに納付
・7月から12月分……翌年1月10日までに納付(一定の場合は1月20日)
(2)特別徴収(住民税)
① 住民税
住民税は都道府県と市町村(特別区)に納める地方税のことです。この都道府県民税と市町村民税(特別区民税)を合わせて一般に住民税といっています。
② 課税の方式
毎年1月1日現在にどこの市町村の住民基本台帳に記録されているかによって課税する市町村が決まります。そして、その市町村が税額を決定して通知することとなっています。このような課税方式は、所得税が所得者の申告によって納付する申告納税方式に対して、賦課課税方式と呼ばれています。
③ 普通徴収
普通徴収とは、納税者(基本的にはサラリーマン以外の者)が市町村の決定した税額を年4回(通常6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する方法です。
④ 特別徴収
特別徴収とは、給与の支払者(会社)が市町村からの税額通知書に基づいて、給与所得者(社員)に毎月の給与を支払う際にその給与から税額を徴収して納付する方法です。この場合、税額を徴収する義務を負う給与の支払者(会社)を特別徴収義務者といいます。
特別徴収した住民税は、徴収した月の翌月10日までに納付します。ただし、常時10人未満の給与所得者(社員)に給与を支払っている小規模な事業所では市町村の承認を受けて次のような納期の特例制度があります。この場合、給与を支払うごとに住民税の徴収を行い、納付日まで会社が預かることになります。
・6月から11月分……12月10日までに納付
・12月から翌年5月分……6月10日までに納付
6 給与計算
給料の明細書をみますと、所得税のほかに社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)が、天引きされています。給料から天引きされる社会保険料は、簡単に説明しますと次のように求めます。
(1)健康保険料と厚生年金保険料の金額は、あらかじめ決められた標準報酬月額(5月・6月・7月の給料の平均)を《健康保険標準報酬月額及び保険料額表》や《厚生年金保険標準報酬月額・保険料負担区分表》にあてはめて求めます。なお、健康保険料と厚生年金保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。
(2)雇用保険料の金額は、給料の金額を《雇用保険の一般保険料額表》にあてはめて求めます。
(3)給料の源泉所得税
会社に就職すると、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」という緑の用紙に、氏名、住所、配偶者の有無や扶養家族の人数などを記入して提出します。会社は、この「給与所得者の扶養控除等申告書」によって、扶養家族の人数をカウントします。次に、給料の金額から社会保険料を差し引いた金額を《源泉徴収税額表》にあてはめて、給料から天引きする所得税を求めます。
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1カ所にしか提出できないため、2カ所以上の会社から給料をもらっている場合には、2カ所目以降は《源泉徴収税額表》の乙欄の高い源泉所得税が天引きされることになります。
年末調整のポイント
1 年末調整
年末調整は、給与所得者について毎月(日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額(年収)について納めなければならない所得税(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。会計事務所の仕事としては、まず年末調整の資料を手際よく回収することがポイントになります。11月中旬頃にはクライアント(顧問先)には『年末調整についてのお願い』(必要書類一覧)を郵送して資料の準備をしてもらい、12月上旬にはコンピュータの入力を始めたいところです。また、『年末調整の作業一覧』により、資料回収のチェック、作業状況のチェック、源泉所得税の納付書のお渡し状況のチェック、法定調書・給与支払報告書・償却資産の申告書の提出状況のチェック等をするとよいでしょう。
(1)年末調整をする主な人
① 年初から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
② 中途就職し、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で前職の給与の金額や税額が証明できる人、ならびに前職がないことを証明できる人
(2)年末調整をしない主な人
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
② 本年中の給与等が2,000万円を超える人(所得税の確定申告が必要)など
2 年末調整の手順
年末調整の手順は、(1)1月から12月中に支給期日が到来した給料や賞与などの合計額を求め、(2)給与所得控除後の給与等の金額を求めます。そこから所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、損害保険料控除など)を差し引いて(3)課税給与所得金額を求めます。
そして、この課税給与所得金額をもとに所得税額の速算表を使って(4)年税額を算出し、そこから住宅借入金等特別控除を差し引くと(5)正規の年税額(平成18年は、年税額の10%〈最高12.5万円〉の定率減税が行われる。平成19年は廃止)が計算されます。この正規の年税額と源泉徴収した税額を比較し、年税額が源泉徴収した税額より小さければその分を還付し、年税額が源泉徴収した税額より大きければその分を追加徴収します(図表4参照)。
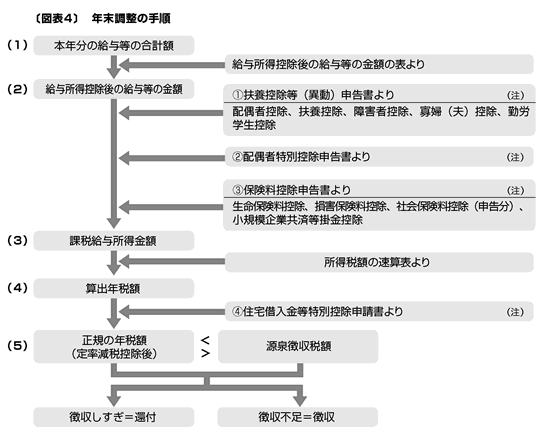
(注)給与等の支払いを受ける人から受理する書類
① 扶養控除等(異動)申告書
……配偶者や扶養親族などに関して記載するもの。中途入社で前職がある人はその会社の源泉徴収票を添付する。
② 配偶者特別控除申告書
……配偶者の年間の合計所得金額が76万円未満(給与年収141万円未満)の場合は配偶者特別控除が受けられる場合がある。
③ 保険料控除申告書
……生命保険料や損害保険料を記載するもの(控除証明書を添付)。本人が直接支払っている国民健康保険や国民年金、国民年金基金などの金額も記載する。
④ 住宅借入金等特別控除申告書
……年末調整により控除ができるのは2年目から。住宅借入金等特別控除証明書と借入金の年末残高証明書を添付。
なお、②と③はまとめて1枚の書式になっています。
3 支払調書・支払調書の合計表
給与や退職金、報酬、料金、不動産の使用料等の支払者は所定の提出期限までに、その支払いの明細を記載した支払調書などを作成し、所轄の税務署または市区町村に提出しなければなりません。支払調書などの主なものは図表5のとおりです。
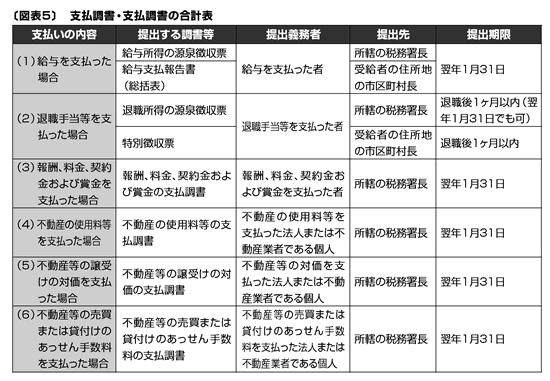
4 給与支払報告書
給与の支払いを受ける人(受給者)の住民税を市区町村が決定するためには、その受給者の前年中の所得金額がわからなければなりません。その資料となるのが給与支払報告書というもので、源泉徴収票と同時複写で作成されることになっています。
給与の支払者(会社)は、給与支払報告書を毎年1月31日までに各受給者の住所地(その年の1月1日現在)の市区町村長に給与支払報告書の総括表とともに提出します。
5 償却資産申告書
償却資産申告書は、事業で使用する減価償却資産にかかる固定資産税を計算するための資料として提出します。
土地や家屋にかかる固定資産税は、市区町村が把握し、税額計算から納付書の送付まで行うので申告は必要ありませんが、建物・自動車以外の減価償却資産の有無は、所有者にしか分からないので申告する必要があります。その内容は図表6のとおりです。
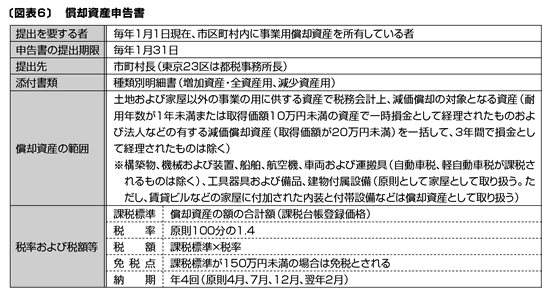
(たけうち・ひでお)
会計事務所職員のための経理実務 第5回
税理士 竹内秀男
給与計算
1 サラリーマンの税金の仕組み
給料にかかる税金には、所得税と住民税があります。住民税は翌年からかかるため、1年目は納める必要がありません。所得税は1月1日から12月31日までの1年間の儲け(所得)に対して翌年3月15日までに確定申告をして納めるのですが、給与所得者(サラリーマン)の場合には、通常は確定申告がいりません。
会社が月々の給料から所得税を概算で天引きして、本人に代わって納める仕組み(源泉徴収制度)になっています。この源泉徴収は、その人の正しい所得税の金額ではないので、会社がその年の12月に年末調整という手続で正しい所得税の金額に計算し直してくれます。通常は納め過ぎの所得税が返されます。
2 毎月の定例事務
給与計算事務とは、社員の給与総支払額と控除額を計算し、各人が実際に受け取る差引支給額を計算して、本人に支給するまでの事務をいいます。月間スケジュールは図表1のとおりです。
(1)各人の給与から控除した(預った)所得税・住民税を、原則として翌月10日までに所得税は税務署に、住民税は各市区町村へ納付します。
(2)各人の給与から控除した(預った)健康保険料・厚生年金保険料に事業主負担を合わせた保険料を翌月末日までに納付します。
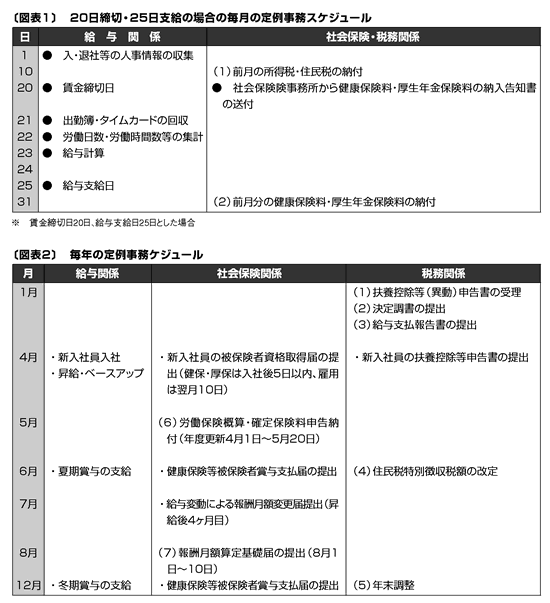
3 毎年の定例事務
年間スケジュールは図表2のとおりです。
(1)扶養控除等(異動)申告書の受理
各給与受給者(社員)から1月の給与支払日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
(2)法定調書の提出
給与や退職金、報酬、料金、不動産の使用料等の支払いの明細を記載した支払調書を作成し、1月31日までに税務署に提出します。
(3)給与支払報告書の提出
前年中に支払った給与について給与支払報告書(源泉徴収票と同時複写)を作成し、1月31日までに各給与受給者(社員)の住んでいる市区町村に提出します。
(4)住民税特別徴収税額の改定
住民税特別徴収税額は6月より改定します。
(5)年末調整
毎月の源泉徴収税額と、その年の給与の総額(年収)について納めなければならない所得税(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。
(6)労働保険料年度更新事務
労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料の申告納付を5月20日までに行います。
(7)標準報酬月額の定時決定
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定のため「報酬月額算定基礎届」を社会保険事務所に8月1日から8月10日までに提出します。
4 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
(1)健康保険
健康保険は、社員や社員の家族の健康を守ることを目的としています。具体的には、社員やその家族が業務外の原因による傷病にかかったり、出産や死亡などによって、家計から不時の出費を要する場合、その負担を軽くするため、医療費を負担したり、一定の金額を支給するというものです。
健康保険から支給されるものとしては、病気にかかったときやケガをしたときに保険証を提示して医療を受ける療養の給付が中心となっており、そのほかに、療養費、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、埋葬費などがあります。
保険料は被保険者(社員)の標準報酬月額と標準賞与額(平成15年4月から総報酬制が実施され、賞与からも同率で保険料が徴収されます)に保険料率を乗じた額で、事業主(会社)と被保険者(社員)が折半で負担することになります。
政府管掌健康保険の保険料率は、1,000分の82(組合管掌健康保険の保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で組合の理事会で決定し、厚生労働大臣の許可を得て定めることになっている)です。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険は、働く人が年をとったり、障害者となったり、死亡したときに、年金を中心とした長期の保険給付を行う制度です。対象となる保険事故は老齢、障害、死亡の3つで、これらに対して老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の給付がそれぞれ行われます。
保険料は健康保険と同じように、被保険者(社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じた額で、事業主(会社)と被保険者(社員)が折半で負担します。
保険料率は、平成16年9月まで1,000分の135.8、平成16年10月から毎年1,000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月以後、1,000分の183.0になります。
(3)雇用保険
雇用保険が行う失業等給付は、労働者が失業した場合に新しい勤務先が決まるまでの一定期
間、援助しようとするものです。また、超高齢
社会や少子化時代を反映して、高年齢者の継続
雇用や育児休業・介護休業した人を援助するた
めの給付も行っています。
保険料は被保険者(社員)に支払う給与に保険料率を乗じて得た額です。保険料率は、業種によって3つに分かれています。一般の事業は1,000分の19.5、農林水産業と清酒製造業は1,000分の21.5、そして建設業については1,000分の22.5となっています。このうち、一般の事業で働く被保険者(社員)が負担するのは1,000分の8、その他の事業で働く被保険者分(社員分)は1,000分の9となっています。そして残りを事業主(会社)が負担します。
(4)労災保険
労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に災害に遭い、ケガをしたり病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に一定の給付を行うほか、その被災労働者や遺族の生活を保護するための労働福祉事業を行うために設けられた制度です。
労災保険の給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遣族(補償)給付、葬祭料があります。なお、補償という文字がつく給付は、葬祭料を除いて、すべて業務上災害にかかる給付となっています。
保険料は働いている人に支払う給与に保険料率を乗じて得た額となります。保険料率は、災害の発生割合に応じて業種ごとに1,000分の5から1,000分の129と定められています。この保険料の負担はすべて事業主(会社)が行います。
5 源泉徴収(所得税)、特別徴収(住民税)
(1)源泉徴収(所得税)
① 源泉徴収制度
所得税は所得者自身がその年中の所得や税額を計算して申告し、その税額(所得税)を納める「申告納税制度」を原則としています。しかし、国民全員が確定申告をすると税務署の対応は困難となります。そこで給与の支払いを受ける人(給与所得者)などについては「源泉徴収制度」により、給与を支払う際にその支払いをする者(会社)が社員に支払う給与から一定の税額(所得税)を天引きしておき、これを定められた期日までに納付します。そして、源泉徴収された給与所得者の所得税は、原則として年末調整によって精算されます。
この源泉徴収をする給与の支払者(会社)を源泉徴収義務者といいます。
② 徴 収
源泉徴収は給与などを支払う都度行うことになっています。そして源泉徴収の税額を求めるために必要なのが「給与所得の源泉徴収税額表」です。源泉徴収税額表の適用区分は図表3のとおりです。
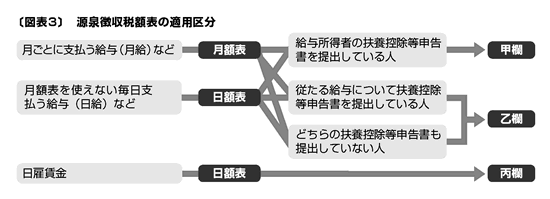
③ 納 付
源泉徴収した税額は翌月10日までに納付します。ただし、常時10人未満の給与所得者(社員)に給与を支払っている小規模な事業所では、税務署の承認を受けて次のような納期の特例制度があります。この場合、給与を支払うごとに源泉徴収を行い、納付日まで会社が預かることになります。
・1月から6月分……7月10日までに納付
・7月から12月分……翌年1月10日までに納付(一定の場合は1月20日)
(2)特別徴収(住民税)
① 住民税
住民税は都道府県と市町村(特別区)に納める地方税のことです。この都道府県民税と市町村民税(特別区民税)を合わせて一般に住民税といっています。
② 課税の方式
毎年1月1日現在にどこの市町村の住民基本台帳に記録されているかによって課税する市町村が決まります。そして、その市町村が税額を決定して通知することとなっています。このような課税方式は、所得税が所得者の申告によって納付する申告納税方式に対して、賦課課税方式と呼ばれています。
③ 普通徴収
普通徴収とは、納税者(基本的にはサラリーマン以外の者)が市町村の決定した税額を年4回(通常6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する方法です。
④ 特別徴収
特別徴収とは、給与の支払者(会社)が市町村からの税額通知書に基づいて、給与所得者(社員)に毎月の給与を支払う際にその給与から税額を徴収して納付する方法です。この場合、税額を徴収する義務を負う給与の支払者(会社)を特別徴収義務者といいます。
特別徴収した住民税は、徴収した月の翌月10日までに納付します。ただし、常時10人未満の給与所得者(社員)に給与を支払っている小規模な事業所では市町村の承認を受けて次のような納期の特例制度があります。この場合、給与を支払うごとに住民税の徴収を行い、納付日まで会社が預かることになります。
・6月から11月分……12月10日までに納付
・12月から翌年5月分……6月10日までに納付
6 給与計算
給料の明細書をみますと、所得税のほかに社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)が、天引きされています。給料から天引きされる社会保険料は、簡単に説明しますと次のように求めます。
(1)健康保険料と厚生年金保険料の金額は、あらかじめ決められた標準報酬月額(5月・6月・7月の給料の平均)を《健康保険標準報酬月額及び保険料額表》や《厚生年金保険標準報酬月額・保険料負担区分表》にあてはめて求めます。なお、健康保険料と厚生年金保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。
(2)雇用保険料の金額は、給料の金額を《雇用保険の一般保険料額表》にあてはめて求めます。
(3)給料の源泉所得税
会社に就職すると、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」という緑の用紙に、氏名、住所、配偶者の有無や扶養家族の人数などを記入して提出します。会社は、この「給与所得者の扶養控除等申告書」によって、扶養家族の人数をカウントします。次に、給料の金額から社会保険料を差し引いた金額を《源泉徴収税額表》にあてはめて、給料から天引きする所得税を求めます。
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1カ所にしか提出できないため、2カ所以上の会社から給料をもらっている場合には、2カ所目以降は《源泉徴収税額表》の乙欄の高い源泉所得税が天引きされることになります。
年末調整のポイント
1 年末調整
年末調整は、給与所得者について毎月(日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額(年収)について納めなければならない所得税(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。会計事務所の仕事としては、まず年末調整の資料を手際よく回収することがポイントになります。11月中旬頃にはクライアント(顧問先)には『年末調整についてのお願い』(必要書類一覧)を郵送して資料の準備をしてもらい、12月上旬にはコンピュータの入力を始めたいところです。また、『年末調整の作業一覧』により、資料回収のチェック、作業状況のチェック、源泉所得税の納付書のお渡し状況のチェック、法定調書・給与支払報告書・償却資産の申告書の提出状況のチェック等をするとよいでしょう。
(1)年末調整をする主な人
① 年初から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
② 中途就職し、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で前職の給与の金額や税額が証明できる人、ならびに前職がないことを証明できる人
(2)年末調整をしない主な人
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
② 本年中の給与等が2,000万円を超える人(所得税の確定申告が必要)など
2 年末調整の手順
年末調整の手順は、(1)1月から12月中に支給期日が到来した給料や賞与などの合計額を求め、(2)給与所得控除後の給与等の金額を求めます。そこから所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、損害保険料控除など)を差し引いて(3)課税給与所得金額を求めます。
そして、この課税給与所得金額をもとに所得税額の速算表を使って(4)年税額を算出し、そこから住宅借入金等特別控除を差し引くと(5)正規の年税額(平成18年は、年税額の10%〈最高12.5万円〉の定率減税が行われる。平成19年は廃止)が計算されます。この正規の年税額と源泉徴収した税額を比較し、年税額が源泉徴収した税額より小さければその分を還付し、年税額が源泉徴収した税額より大きければその分を追加徴収します(図表4参照)。
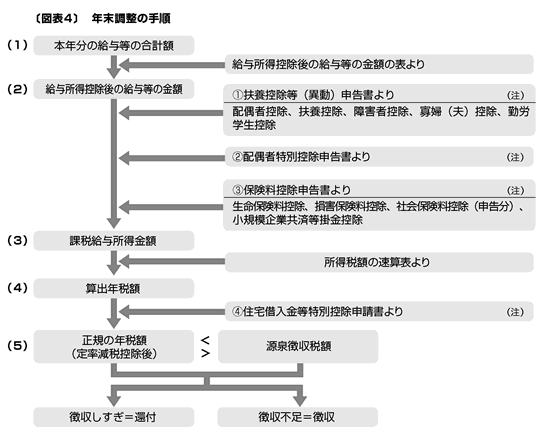
(注)給与等の支払いを受ける人から受理する書類
① 扶養控除等(異動)申告書
……配偶者や扶養親族などに関して記載するもの。中途入社で前職がある人はその会社の源泉徴収票を添付する。
② 配偶者特別控除申告書
……配偶者の年間の合計所得金額が76万円未満(給与年収141万円未満)の場合は配偶者特別控除が受けられる場合がある。
③ 保険料控除申告書
……生命保険料や損害保険料を記載するもの(控除証明書を添付)。本人が直接支払っている国民健康保険や国民年金、国民年金基金などの金額も記載する。
④ 住宅借入金等特別控除申告書
……年末調整により控除ができるのは2年目から。住宅借入金等特別控除証明書と借入金の年末残高証明書を添付。
なお、②と③はまとめて1枚の書式になっています。
3 支払調書・支払調書の合計表
給与や退職金、報酬、料金、不動産の使用料等の支払者は所定の提出期限までに、その支払いの明細を記載した支払調書などを作成し、所轄の税務署または市区町村に提出しなければなりません。支払調書などの主なものは図表5のとおりです。
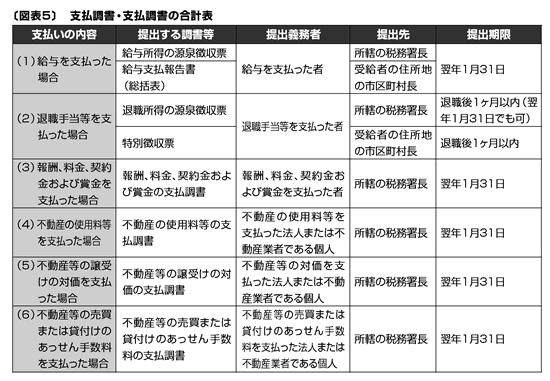
4 給与支払報告書
給与の支払いを受ける人(受給者)の住民税を市区町村が決定するためには、その受給者の前年中の所得金額がわからなければなりません。その資料となるのが給与支払報告書というもので、源泉徴収票と同時複写で作成されることになっています。
給与の支払者(会社)は、給与支払報告書を毎年1月31日までに各受給者の住所地(その年の1月1日現在)の市区町村長に給与支払報告書の総括表とともに提出します。
5 償却資産申告書
償却資産申告書は、事業で使用する減価償却資産にかかる固定資産税を計算するための資料として提出します。
土地や家屋にかかる固定資産税は、市区町村が把握し、税額計算から納付書の送付まで行うので申告は必要ありませんが、建物・自動車以外の減価償却資産の有無は、所有者にしか分からないので申告する必要があります。その内容は図表6のとおりです。
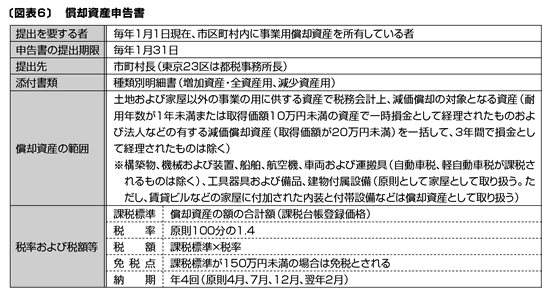
(たけうち・ひでお)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























