解説記事2006年11月20日 【会計基準解説】 「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)について(2006年11月20日号・№187)
実務解説
「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)について
企業会計基準委員会 研究員 波多野直子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、平成18年10月17日に、企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表した(脚注1)。本会計基準及び本適用指針については、平成18年6月6日に公開草案を公表し、平成18年7月20日まで広くコメントを募集した後、寄せられたコメントを検討し、当該公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。
本稿では、本会計基準及び本適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添える。
Ⅱ.本会計基準及び本適用指針の公表の経緯
1 これまでの我が国における関連当事者の開示
我が国における関連当事者の開示は、これまで、特定の会計基準に基づくものではなく、証券取引法上の規則に基づき行われてきた。平成2年6月、日米構造協議最終報告により米国財務会計基準書第57号「関連当事者の開示」(以下「SFAS第57号」という。)と関連当事者との取引の範囲を同様にすることとし、平成2年12月に有価証券報告書等の「企業集団等の状況」に「関連当事者との取引」の項が設けられた。
その後、平成9年6月に企業会計審議会により公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、「関連当事者との取引」を連結財務諸表の注記とする方針が示されたことを受けて、平成10年11月及び平成11年3月に連結財務諸表規則及び財務諸表等規則等が改正され、「関連当事者との取引」は、連結財務諸表又は財務諸表の注記事項となり、監査対象になった。また、監査上の実務指針として、平成11年4月に日本公認会計士協会監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第62号」という。)が公表された。
2 会計基準の国際的なコンバージェンス
このように、我が国における関連当事者の開示は、専ら証券取引法上の規則に基づいて行われてきた。しかし、関連当事者の開示に関する規定は、米国会計基準や国際財務報告基準などの国際的な会計基準では、会計基準の1つとして位置付けられている。また、関連当事者の定義や開示に関する取引範囲などについては、我が国の現行の財務諸表等規則及び連結財務諸表規則(以下「証券取引法関係規則」という。)と国際的な会計基準には差異が見られる状況にある。こうした中、関連当事者の開示が平成17年3月から開始したASBJと国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトの検討項目とされ、協議を行った。
このような国際的なコンバージェンスの観点に加え、いわゆる「純粋持株会社」(グループ全体の経営戦略の立案及び子会社管理に専念し、株式所有を通じて、実際に製造・販売などの事業活動を行う会社を支配する会社をいう。)の増加により、現行の実務による財務諸表提出会社と関連当事者との取引の開示では、事業会社である連結子会社と関連当事者との取引が開示されないため、関連当事者の取引の開示について見直しが必要ではないかという指摘もあった。
こうした状況を踏まえ、現行の証券取引法関係規則と国際会計基準第24号「関連当事者についての開示」(以下「IAS第24号」という。)及びSFAS第57号との比較検討等を行った上で、関連当事者の開示を会計基準として整備することとした。
Ⅲ.本会計基準及び本適用指針の概要
1 関連当事者の開示の目的
会社(連結財務諸表上は連結財務諸表作成会社及び連結子会社をいう。以下同じ。)と関連当事者との取引は、会社と役員等の個人との取引を含め、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。このため、関連当事者の開示は、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供するものでなければならないものとしている。
なお、会社計算規則上の開示では、業務執行者の事業運営のあり方が適切かどうかという観点を付加して独自の開示除外事項を設けていることや、連結財務諸表作成会社においても個別注記表(個別財務諸表での注記)のみでの開示を求めているなど、会計基準のコンバージェンスを踏まえた検討との関係では異なる要素が含まれているため、これらについては関係当局の当該規則に関する見解などを踏まえた実務に委ねられるものと考えられる。
2 関連当事者の範囲
(1)関連当事者の範囲の拡充
本会計基準では、関連当事者に該当する者として、①親会社、②子会社、③財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社、④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(以下「その他の関係会社」という。)並びにその親会社及び子会社、⑤関連会社及び当該関連会社の子会社、⑥財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者、⑦財務諸表作成会社の役員及びその近親者、⑧親会社の役員及びその近親者、⑨重要な子会社の役員及びその近親者、⑩上記の⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社、⑪従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)を掲げている(会計基準第5項(3))。
本会計基準では、現行の証券取引法関係規則において規定されているものに加え、⑧親会社の役員及びその近親者、⑨重要な子会社の役員及びその近親者、⑪従業員のための企業年金の3つについて、関連当事者の開示の充実を図る観点から国際的な会計基準を参考にして新たに追加している。
⑧親会社の役員及びその近親者については、親会社の役員の子会社に対する影響力が大きい場合もあることや、IAS第24号においては親会社の役員が関連当事者の範囲に含まれていることから含めることとしている。
⑨の重要な子会社の役員及びその近親者については、前述のとおり、純粋持株会社が増加していることから財務諸表作成会社が純粋持株会社の場合も考えられるが、このような場合、実質的に事業を行っている子会社の経営に従事している役員が当該子会社と取引を行い、連結財務諸表に重要な影響を与える場合も考えられるため含むこととしている。「重要な」が「子会社」に係るのか、「役員」に係るのか議論があったが、本会計基準では、関連当事者の開示の趣旨から、会社グループの事業運営に強い影響力を持つ者が子会社の役員にいる場合には、当該役員も関連当事者に該当することとし、重要性の判断を役員個人について行うものとしている。なお、役員の属する子会社を判断に全く考慮しないわけではなく、会社グループの中核となる事業活動を子会社に委ねている場合にあっては、当該子会社の役員のうち当該業務を指示し、統制する役員は、会社グループの事業運営に強い影響力を持つものと考えられる旨を記載している(会計基準第21項)。
⑪の従業員のための企業年金については、IAS第24号において従業員のための退職給付制度及びSFAF第57号において従業員の便益のための信託財産を関連当事者に規定していることを参考に追加されたものである。ただし、これが関連当事者に該当するのは、企業年金と会社の間で掛金の拠出(退職給付信託の設定を含む。)以外の重要な取引を行う場合に限られるものとしている。従って、我が国においては、関連当事者との取引として開示対象となるような取引は通常生じないものと考えられる。
開示対象となる場合の例として、厚生年金基金及び基金型の確定給付企業年金が個別指図による運用を行い、会社と直接取引を行う場合や、例外として認められている厚生労働大臣の承認を受けた場合の借入を基金が会社から行う場合において、これらの取引に重要性がある場合、退職給付信託における年金資産の入替え又は返還取引に重要性がある場合が考えられる。なお、海外子会社については、それぞれの国の企業年金制度に応じて、開示対象となる取引が存在するか否かを検討する必要がある(会計基準第23項)。
財務諸表作成会社の共同支配投資企業と、財務諸表作成会社及び連結子会社の共同支配企業は、「企業結合に係る会計基準」を踏まえた平成18年の証券取引法関係規則の改正等により、それぞれ④の「その他の関係会社」と⑤の「関連会社」に含まれることになっているので、基準上、明らかにしたものである(会計基準第5項(5))。
そのほか、役員等の近親者については、現行の証券取引法関係規則と同様、二親等以内の親族としている(会計基準第5項(8))。また、本会計基準では、関連当事者に該当するかどうかは、形式的に判定するのではなく、実質的に判定する必要があるとしている(会計基準第17項)。
(2)連結財務諸表と個別財務諸表での関連当事者の範囲の相違
上述のとおり、子会社は関連当事者に該当するものとされているが、連結財務諸表上、連結子会社については連結の範囲に含まれていることから、関連当事者から除かれるものとしている。なお、個別財務諸表で開示を行う場合には、重要な子会社の役員及びその近親者等は関連当事者に該当しないこととしている(会計基準第5項(3))。
3 関連当事者との取引に関する開示
(1)開示する取引の範囲
開示する取引の範囲については、連結財務諸表では、国際的な会計基準と同様に、新たに連結子会社と関連当事者との取引も開示対象としている(会計基準第6項)ため、現行の証券取引法関係規則と比較すると、2で述べた関連当事者の範囲の拡充と併せ、開示対象となる取引の範囲が拡大することになっている(図表1参照)。
なお、現行の取扱いと同様に、①関連当事者が第三者のために会社との間で行う取引や、②会社と第三者との間の取引で、関連当事者が当該取引に関して会社に重要な影響を及ぼしているもの(以上、会計基準第5項(1))、③無償取引や低廉な価格での取引(会計基準第7項)、④形式的・名目的に第三者を経由した取引だが、実質上の相手先が関連当事者であることが明確な取引(会計基準第8項)も開示する取引の範囲に含まれることを明示している。⑤連結財務諸表上これを作成するにあたって相殺消去した取引については現行の取扱いと同様に、開示する取引の範囲には含まれないことを確認している(会計基準第6項)。
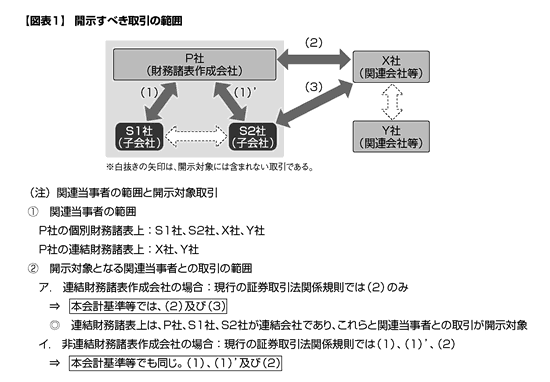
(2)開示対象外取引
現行の証券取引法関係規則と同様、①一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引と、②役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払いを、開示対象外の取引とした(会計基準第9項)。なお、資本取引については、現行の取扱いと同様、開示対象の取引に含めることとしているが、公募増資に関しては、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引(上記①)に該当するため、開示対象外の取引になるものとしている(会計基準第28項)。また、役員などの関連当事者が、会社の従業員としての立場で行っていることが明らかな取引(例えば、使用人兼務役員が会社の福利厚生制度による融資を受ける場合など)は、開示対象外としている(適用指針第5項)。
(3)開示対象期間
年度の途中において関連当事者に該当するようになる場合や、関連当事者に該当しなくなる場合には、現行の取扱いと同様に、関連当事者であった期間の取引について開示することとしている。例えば期末に子会社を取得(みなし取得を含む。)し、貸借対照表のみ連結している場合で、それ以前の期間においては当該会社が関連当事者に該当していた場合、子会社となる以前の当該会社との取引は連結財務諸表上相殺消去されていないため、連結上も関連当事者との取引の開示対象となる(適用指針第6項)。
(4)開示項目
重要な関連当事者との取引があった場合、現行の証券取引法関係規則と同様に、①関連当事者の概要、②会社と関連当事者との関係、③取引の内容(形式的・名目的には第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する。)、④取引の種類ごとの取引金額、⑤取引条件及び取引条件の決定方針、⑥取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高、⑦取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容、当該変更が財務諸表に与えている影響の内容、を開示することとしている(会計基準第10項(1)~(7))。
これに加え、本会計基準では、新たに、IAS第24号において開示されていることを参考に、⑧関連当事者との取引に関わる貸倒懸念債権や破産更生債権等に係る情報として、貸倒引当金繰入額や貸倒損失などの開示を追加している。この情報については、開示することにより信用不安を発生させる可能性もあるとの意見があったこと等を踏まえ、関連当事者の種類ごとに合算して記載することもできることとした。また、合算開示を行う場合、個別に開示されている重要な取引に係る債権に対するものを合算して記載する方法のほか、当該種類に該当するすべての関連当事者の貸倒懸念債権及び破産更生債権等に対する貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額等の合計額を、脚注の下に別途文章で記載することもできることとしている(会計基準第10項(8)及び適用指針の開示例1、図表2参照)。
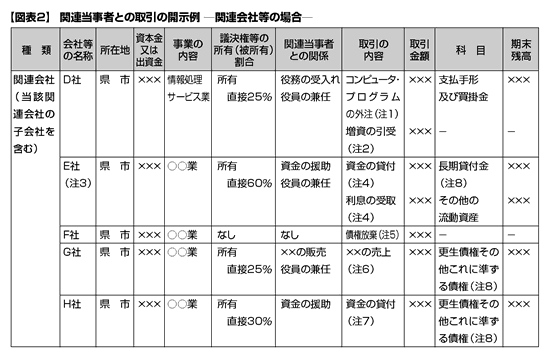
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)コンピュータ・プログラムの外注については、D社から提示された価格と、他の外注先との取引価格を参考にしてその都度交渉の上、決定している。
(注2)当社がD社の行った第三者割当増資を1株につき××円で引き受けたものである。
(注3)共同支配企業である。
(注4)E社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間3年、半年賦返済としている。なお、担保は受け入れていない。
(注5)債権放棄については、経営不振のF社の清算結了により行ったものである。
(注6)市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、取引条件を決定している。
(注7)資金の貸付については、×年×月より無利息としている。
(注8)関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)への更生債権等に対し、合計×××百万円の貸倒引当金を計上している。また、当連結会計年度において合計×××百万円の貸倒引当金繰入額を計上している。(※)
(※)会計基準第10項(8)なお書きにより、関連当事者の種類ごとに関連当事者に対する貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る情報を合算して記載する場合、上記のように表中の債権に対するものを記載する方法の他、表中に脚注番号を振らず、すべての関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)の貸倒懸念債権及び破産更生債権等に対する貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額等の合計額を脚注の下に別途文章で記載することもできる。
(5)関連当事者との取引に関する重要性の判断基準
本会計基準では、監査委員会報告第62号による現行の取扱いと同様に、関連当事者が法人である場合と個人である場合に分けて、重要性の判断基準を示している。現行の取扱いとの主な変更点は、①役員等の個人の関連当事者との取引に関する重要性の判断基準を100万円を超える取引から1,000万円を超える取引としたこと(適用指針第32項)、②会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む。)及びその近親者が他の法人の代表者を兼務し、当該役員等がその法人の代表者として会社と取引を行う場合については、関連当事者が法人である場合の重要性の判断基準を適用することとしたことなどである。②については、現行の取扱いでは、財務諸表作成会社の役員が、関連当事者に該当する関係会社等(親会社及び法人主要株主等、関連会社等、兄弟会社等)の代表者を兼務している場合に限り、その代表者として会社と取引を行うことは関係会社間における通常の商取引に該当すると考えられることから、法人との取引に属するものとして扱っているが、関係会社等以外の会社の代表を兼務し、その代表者として会社と取引を行う場合においても、会社間の通常の取引という観点からは関係会社等の代表者として取引する場合と同様と考えられることから変更したものである。ただし、会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む。)及びその近親者が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社と取引を行う場合においては、従来どおり、関連当事者が個人の場合の取引の判断基準により重要性を判断する(適用指針第33項)。
<関連当事者が法人の場合(適用指針第15項)>
① 連結損益計算書項目に関係する関連当事者との取引
イ 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費
売上高又は売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の10%を超える取引
ロ 営業外収益、営業外費用
営業外収益又は営業外費用の合計額の10%を超える損益に係る取引(その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する。)
ハ 特別利益、特別損失
1,000万円を超える損益に係る取引(その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する。)
ただし、ロ及びハに係る関連当事者との取引については、上記の基準に該当する場合であっても、その取引総額が、税金等調整前当期純損益又は最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益(当該期間中に税金等調整前当期純利益と税金等調整前当期純損失がある場合には、原則として税金等調整前当期純利益が発生した年度の平均とする。)の10%以下となる場合には、開示を要しないものとしている。
② 連結貸借対照表項目に属する科目の残高及びその注記事項に係る関連当事者との取引並びに債務保証等及び担保提供又は受入れ
イ その金額が総資産の1%を超える取引
ロ 資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等については、それぞれの残高が総資産の1%以下であっても、取引の発生総額(資金貸付額等)が総資産の1%を超える取引(ただし、取引が反復的に行われている場合や、その発生総額の把握が困難である場合には、期中の平均残高が総資産の1%を超える取引を開示することもできる。)
ハ 事業の譲受又は譲渡の場合には、譲受又は譲渡の対象となる資産や負債が個々に取引されるのではなく、一体として取引されると考えられることから、対象となる資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、総資産の1%を超える取引
なお、上記①及び②を個別財務諸表で関連当事者との取引を開示する場合に適用する場合には、連結損益計算書項目、連結貸借対照表項目、税金等調整前当期純損益は、それぞれ、損益計算書項目、貸借対照表項目、税引前当期純損益と、適宜読み替えるものとしている。
<関連当事者が個人の場合(適用指針第16項)>
関連当事者との取引が、連結損益計算書項目及び連結貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、1,000万円を超える取引については、すべて開示対象とすることとしている。
4 関連当事者の存在に関する開示
(1)親会社の情報
本会計基準では、親会社の存在の有無は、投資家が意思決定をするにあたって有用な情報と考え、IAS第24号やSFAS第57号と同様に、親会社の名称等の開示を新たに求めることとし、具体的には親会社の名称及び上場又は非上場の別の開示を求めている(会計基準第11項(1)、第38項及び適用指針第10項、図表3参照)。
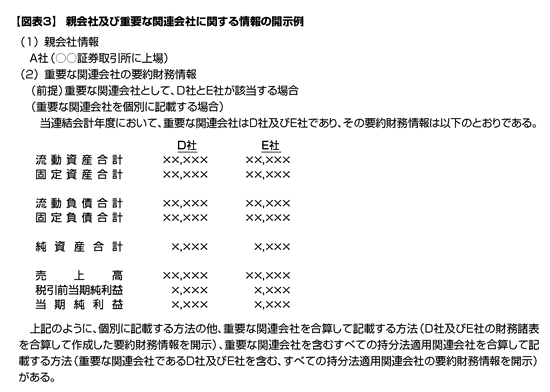
(2)重要な関連会社の要約財務情報
本会計基準では、重要な関連会社が存在する場合にも、これらの会社に関する情報が有用な情報であると考え、その名称と要約財務情報を開示することとしている。重要な関連会社の要約財務情報については、米国では会計原則審議会意見書第18号(APB第18号)「持分法による普通株式投資の会計」において、国際財務報告基準ではIAS第28号「関連会社に対する投資」及びIAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」において、共同支配企業を含む関連会社に関する要約財務情報の注記開示を求めており、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、我が国では関連当事者の存在に関する開示として、新たにこれを求めることとした(会計基準第39項)。
要約財務情報の記載項目としては、持分法投資損益(脚注2)(共同支配企業の場合は持分法に準ずる処理を適用した場合の投資損益)の算定に用いた財務情報(脚注3)をもとに、主な貸借対照表項目及び損益計算書項目を開示することとし、例えば以下の内容を記載することとしている。
① 貸借対照表項目:流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計
② 損益計算書項目:売上高、税引前当期純損益、当期純損益
要約財務情報の開示方法としては、①個別に開示する方法、②重要な関連会社の要約財務情報を合算して開示する方法、③持分法投資損益の算定対象としたすべての関連会社の財務情報を合算して開示(その旨及び重要な関連会社の名称を明記)する方法のいずれかを選択できることとしている(会計基準第11項(2)及び適用指針第11項、図表3参照)。
(3)重要な関連会社の要約財務情報における重要性の判断基準
要約財務情報の開示を必要とする関連会社の重要性は、以下のいずれかの場合に該当するかにより判断することとしている(適用指針第19項)。
① 各関連会社の総資産(持分相当額)が、会社の総資産の10%を超える場合
② 各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が、会社の税金等調整前当期純損益の10%を超える場合
ただし、②については上記の基準を満たす場合であっても、会社の最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益(当該期間中に税金等調整前当期純利益と税金等調整前当期純損失がある場合には、原則として税金等調整前当期純利益が発生した年度の平均とする。)の10%を超えない場合には、開示を要しないものとしている。なお、②を個別財務諸表上の開示に関して適用するときには、税金等調整前当期純損益は、税引前当期純損益と読み替えるものとしている。
Ⅳ.適用時期等
本会計基準及び本適用指針は、財務諸表作成会社において受入準備が必要であることを考慮し、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用するものとしている。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することもできるとしている(会計基準第12項)。
(はたの・なおこ)
脚注
1 本会計基準及び本適用指針の本文については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/kan_ren0720/)を参照のこと。
2 個別財務諸表上で関連当事者の開示を行う場合には、財務諸表等規則第8条の9で注記することが定められている、関連会社に対する投資に対して持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失を指す。
3 重要な関連会社に子会社があり、会社の持分法投資損益に当該子会社の利益(又は損失)持分相当分が含められている場合であっても、当該関連会社が非上場企業である場合などでは、この関連会社が連結財務諸表を作成していないことも考えられる。この場合には、実態等を勘案した上で、重要な関連会社の単独財務諸表を基礎に、当該子会社を連結したものとして調整した財務情報を開示する方法や、当該子会社に持分法を適用したものとして調整した財務情報を開示する方法などにより、開示対象となる重要な関連会社の要約財務情報にその子会社の財務情報の内容を反映することが考えられる。
「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)について
企業会計基準委員会 研究員 波多野直子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、平成18年10月17日に、企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表した(脚注1)。本会計基準及び本適用指針については、平成18年6月6日に公開草案を公表し、平成18年7月20日まで広くコメントを募集した後、寄せられたコメントを検討し、当該公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。
本稿では、本会計基準及び本適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添える。
Ⅱ.本会計基準及び本適用指針の公表の経緯
1 これまでの我が国における関連当事者の開示
我が国における関連当事者の開示は、これまで、特定の会計基準に基づくものではなく、証券取引法上の規則に基づき行われてきた。平成2年6月、日米構造協議最終報告により米国財務会計基準書第57号「関連当事者の開示」(以下「SFAS第57号」という。)と関連当事者との取引の範囲を同様にすることとし、平成2年12月に有価証券報告書等の「企業集団等の状況」に「関連当事者との取引」の項が設けられた。
その後、平成9年6月に企業会計審議会により公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、「関連当事者との取引」を連結財務諸表の注記とする方針が示されたことを受けて、平成10年11月及び平成11年3月に連結財務諸表規則及び財務諸表等規則等が改正され、「関連当事者との取引」は、連結財務諸表又は財務諸表の注記事項となり、監査対象になった。また、監査上の実務指針として、平成11年4月に日本公認会計士協会監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第62号」という。)が公表された。
2 会計基準の国際的なコンバージェンス
このように、我が国における関連当事者の開示は、専ら証券取引法上の規則に基づいて行われてきた。しかし、関連当事者の開示に関する規定は、米国会計基準や国際財務報告基準などの国際的な会計基準では、会計基準の1つとして位置付けられている。また、関連当事者の定義や開示に関する取引範囲などについては、我が国の現行の財務諸表等規則及び連結財務諸表規則(以下「証券取引法関係規則」という。)と国際的な会計基準には差異が見られる状況にある。こうした中、関連当事者の開示が平成17年3月から開始したASBJと国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトの検討項目とされ、協議を行った。
このような国際的なコンバージェンスの観点に加え、いわゆる「純粋持株会社」(グループ全体の経営戦略の立案及び子会社管理に専念し、株式所有を通じて、実際に製造・販売などの事業活動を行う会社を支配する会社をいう。)の増加により、現行の実務による財務諸表提出会社と関連当事者との取引の開示では、事業会社である連結子会社と関連当事者との取引が開示されないため、関連当事者の取引の開示について見直しが必要ではないかという指摘もあった。
こうした状況を踏まえ、現行の証券取引法関係規則と国際会計基準第24号「関連当事者についての開示」(以下「IAS第24号」という。)及びSFAS第57号との比較検討等を行った上で、関連当事者の開示を会計基準として整備することとした。
Ⅲ.本会計基準及び本適用指針の概要
1 関連当事者の開示の目的
会社(連結財務諸表上は連結財務諸表作成会社及び連結子会社をいう。以下同じ。)と関連当事者との取引は、会社と役員等の個人との取引を含め、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。このため、関連当事者の開示は、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供するものでなければならないものとしている。
なお、会社計算規則上の開示では、業務執行者の事業運営のあり方が適切かどうかという観点を付加して独自の開示除外事項を設けていることや、連結財務諸表作成会社においても個別注記表(個別財務諸表での注記)のみでの開示を求めているなど、会計基準のコンバージェンスを踏まえた検討との関係では異なる要素が含まれているため、これらについては関係当局の当該規則に関する見解などを踏まえた実務に委ねられるものと考えられる。
2 関連当事者の範囲
(1)関連当事者の範囲の拡充
本会計基準では、関連当事者に該当する者として、①親会社、②子会社、③財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社、④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(以下「その他の関係会社」という。)並びにその親会社及び子会社、⑤関連会社及び当該関連会社の子会社、⑥財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者、⑦財務諸表作成会社の役員及びその近親者、⑧親会社の役員及びその近親者、⑨重要な子会社の役員及びその近親者、⑩上記の⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社、⑪従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)を掲げている(会計基準第5項(3))。
本会計基準では、現行の証券取引法関係規則において規定されているものに加え、⑧親会社の役員及びその近親者、⑨重要な子会社の役員及びその近親者、⑪従業員のための企業年金の3つについて、関連当事者の開示の充実を図る観点から国際的な会計基準を参考にして新たに追加している。
⑧親会社の役員及びその近親者については、親会社の役員の子会社に対する影響力が大きい場合もあることや、IAS第24号においては親会社の役員が関連当事者の範囲に含まれていることから含めることとしている。
⑨の重要な子会社の役員及びその近親者については、前述のとおり、純粋持株会社が増加していることから財務諸表作成会社が純粋持株会社の場合も考えられるが、このような場合、実質的に事業を行っている子会社の経営に従事している役員が当該子会社と取引を行い、連結財務諸表に重要な影響を与える場合も考えられるため含むこととしている。「重要な」が「子会社」に係るのか、「役員」に係るのか議論があったが、本会計基準では、関連当事者の開示の趣旨から、会社グループの事業運営に強い影響力を持つ者が子会社の役員にいる場合には、当該役員も関連当事者に該当することとし、重要性の判断を役員個人について行うものとしている。なお、役員の属する子会社を判断に全く考慮しないわけではなく、会社グループの中核となる事業活動を子会社に委ねている場合にあっては、当該子会社の役員のうち当該業務を指示し、統制する役員は、会社グループの事業運営に強い影響力を持つものと考えられる旨を記載している(会計基準第21項)。
⑪の従業員のための企業年金については、IAS第24号において従業員のための退職給付制度及びSFAF第57号において従業員の便益のための信託財産を関連当事者に規定していることを参考に追加されたものである。ただし、これが関連当事者に該当するのは、企業年金と会社の間で掛金の拠出(退職給付信託の設定を含む。)以外の重要な取引を行う場合に限られるものとしている。従って、我が国においては、関連当事者との取引として開示対象となるような取引は通常生じないものと考えられる。
開示対象となる場合の例として、厚生年金基金及び基金型の確定給付企業年金が個別指図による運用を行い、会社と直接取引を行う場合や、例外として認められている厚生労働大臣の承認を受けた場合の借入を基金が会社から行う場合において、これらの取引に重要性がある場合、退職給付信託における年金資産の入替え又は返還取引に重要性がある場合が考えられる。なお、海外子会社については、それぞれの国の企業年金制度に応じて、開示対象となる取引が存在するか否かを検討する必要がある(会計基準第23項)。
財務諸表作成会社の共同支配投資企業と、財務諸表作成会社及び連結子会社の共同支配企業は、「企業結合に係る会計基準」を踏まえた平成18年の証券取引法関係規則の改正等により、それぞれ④の「その他の関係会社」と⑤の「関連会社」に含まれることになっているので、基準上、明らかにしたものである(会計基準第5項(5))。
そのほか、役員等の近親者については、現行の証券取引法関係規則と同様、二親等以内の親族としている(会計基準第5項(8))。また、本会計基準では、関連当事者に該当するかどうかは、形式的に判定するのではなく、実質的に判定する必要があるとしている(会計基準第17項)。
(2)連結財務諸表と個別財務諸表での関連当事者の範囲の相違
上述のとおり、子会社は関連当事者に該当するものとされているが、連結財務諸表上、連結子会社については連結の範囲に含まれていることから、関連当事者から除かれるものとしている。なお、個別財務諸表で開示を行う場合には、重要な子会社の役員及びその近親者等は関連当事者に該当しないこととしている(会計基準第5項(3))。
3 関連当事者との取引に関する開示
(1)開示する取引の範囲
開示する取引の範囲については、連結財務諸表では、国際的な会計基準と同様に、新たに連結子会社と関連当事者との取引も開示対象としている(会計基準第6項)ため、現行の証券取引法関係規則と比較すると、2で述べた関連当事者の範囲の拡充と併せ、開示対象となる取引の範囲が拡大することになっている(図表1参照)。
なお、現行の取扱いと同様に、①関連当事者が第三者のために会社との間で行う取引や、②会社と第三者との間の取引で、関連当事者が当該取引に関して会社に重要な影響を及ぼしているもの(以上、会計基準第5項(1))、③無償取引や低廉な価格での取引(会計基準第7項)、④形式的・名目的に第三者を経由した取引だが、実質上の相手先が関連当事者であることが明確な取引(会計基準第8項)も開示する取引の範囲に含まれることを明示している。⑤連結財務諸表上これを作成するにあたって相殺消去した取引については現行の取扱いと同様に、開示する取引の範囲には含まれないことを確認している(会計基準第6項)。
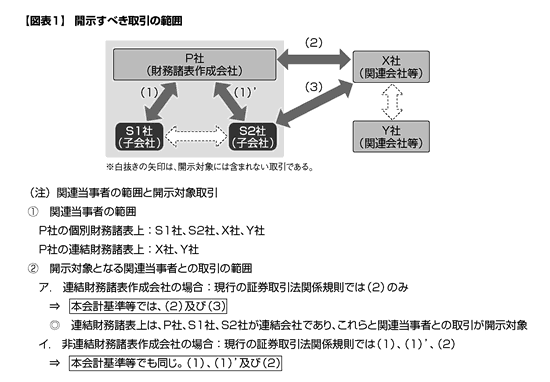
(2)開示対象外取引
現行の証券取引法関係規則と同様、①一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引と、②役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払いを、開示対象外の取引とした(会計基準第9項)。なお、資本取引については、現行の取扱いと同様、開示対象の取引に含めることとしているが、公募増資に関しては、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引(上記①)に該当するため、開示対象外の取引になるものとしている(会計基準第28項)。また、役員などの関連当事者が、会社の従業員としての立場で行っていることが明らかな取引(例えば、使用人兼務役員が会社の福利厚生制度による融資を受ける場合など)は、開示対象外としている(適用指針第5項)。
(3)開示対象期間
年度の途中において関連当事者に該当するようになる場合や、関連当事者に該当しなくなる場合には、現行の取扱いと同様に、関連当事者であった期間の取引について開示することとしている。例えば期末に子会社を取得(みなし取得を含む。)し、貸借対照表のみ連結している場合で、それ以前の期間においては当該会社が関連当事者に該当していた場合、子会社となる以前の当該会社との取引は連結財務諸表上相殺消去されていないため、連結上も関連当事者との取引の開示対象となる(適用指針第6項)。
(4)開示項目
重要な関連当事者との取引があった場合、現行の証券取引法関係規則と同様に、①関連当事者の概要、②会社と関連当事者との関係、③取引の内容(形式的・名目的には第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する。)、④取引の種類ごとの取引金額、⑤取引条件及び取引条件の決定方針、⑥取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高、⑦取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容、当該変更が財務諸表に与えている影響の内容、を開示することとしている(会計基準第10項(1)~(7))。
これに加え、本会計基準では、新たに、IAS第24号において開示されていることを参考に、⑧関連当事者との取引に関わる貸倒懸念債権や破産更生債権等に係る情報として、貸倒引当金繰入額や貸倒損失などの開示を追加している。この情報については、開示することにより信用不安を発生させる可能性もあるとの意見があったこと等を踏まえ、関連当事者の種類ごとに合算して記載することもできることとした。また、合算開示を行う場合、個別に開示されている重要な取引に係る債権に対するものを合算して記載する方法のほか、当該種類に該当するすべての関連当事者の貸倒懸念債権及び破産更生債権等に対する貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額等の合計額を、脚注の下に別途文章で記載することもできることとしている(会計基準第10項(8)及び適用指針の開示例1、図表2参照)。
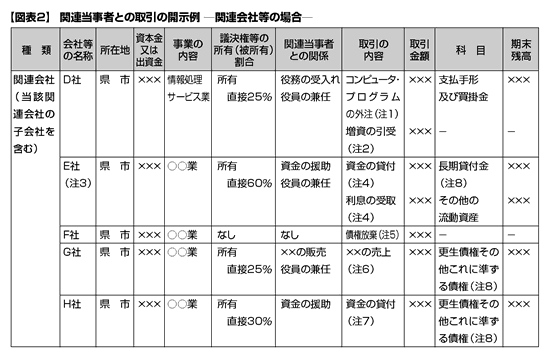
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)コンピュータ・プログラムの外注については、D社から提示された価格と、他の外注先との取引価格を参考にしてその都度交渉の上、決定している。
(注2)当社がD社の行った第三者割当増資を1株につき××円で引き受けたものである。
(注3)共同支配企業である。
(注4)E社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間3年、半年賦返済としている。なお、担保は受け入れていない。
(注5)債権放棄については、経営不振のF社の清算結了により行ったものである。
(注6)市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、取引条件を決定している。
(注7)資金の貸付については、×年×月より無利息としている。
(注8)関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)への更生債権等に対し、合計×××百万円の貸倒引当金を計上している。また、当連結会計年度において合計×××百万円の貸倒引当金繰入額を計上している。(※)
(※)会計基準第10項(8)なお書きにより、関連当事者の種類ごとに関連当事者に対する貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る情報を合算して記載する場合、上記のように表中の債権に対するものを記載する方法の他、表中に脚注番号を振らず、すべての関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)の貸倒懸念債権及び破産更生債権等に対する貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額等の合計額を脚注の下に別途文章で記載することもできる。
(5)関連当事者との取引に関する重要性の判断基準
本会計基準では、監査委員会報告第62号による現行の取扱いと同様に、関連当事者が法人である場合と個人である場合に分けて、重要性の判断基準を示している。現行の取扱いとの主な変更点は、①役員等の個人の関連当事者との取引に関する重要性の判断基準を100万円を超える取引から1,000万円を超える取引としたこと(適用指針第32項)、②会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む。)及びその近親者が他の法人の代表者を兼務し、当該役員等がその法人の代表者として会社と取引を行う場合については、関連当事者が法人である場合の重要性の判断基準を適用することとしたことなどである。②については、現行の取扱いでは、財務諸表作成会社の役員が、関連当事者に該当する関係会社等(親会社及び法人主要株主等、関連会社等、兄弟会社等)の代表者を兼務している場合に限り、その代表者として会社と取引を行うことは関係会社間における通常の商取引に該当すると考えられることから、法人との取引に属するものとして扱っているが、関係会社等以外の会社の代表を兼務し、その代表者として会社と取引を行う場合においても、会社間の通常の取引という観点からは関係会社等の代表者として取引する場合と同様と考えられることから変更したものである。ただし、会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む。)及びその近親者が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社と取引を行う場合においては、従来どおり、関連当事者が個人の場合の取引の判断基準により重要性を判断する(適用指針第33項)。
<関連当事者が法人の場合(適用指針第15項)>
① 連結損益計算書項目に関係する関連当事者との取引
イ 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費
売上高又は売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の10%を超える取引
ロ 営業外収益、営業外費用
営業外収益又は営業外費用の合計額の10%を超える損益に係る取引(その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する。)
ハ 特別利益、特別損失
1,000万円を超える損益に係る取引(その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する。)
ただし、ロ及びハに係る関連当事者との取引については、上記の基準に該当する場合であっても、その取引総額が、税金等調整前当期純損益又は最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益(当該期間中に税金等調整前当期純利益と税金等調整前当期純損失がある場合には、原則として税金等調整前当期純利益が発生した年度の平均とする。)の10%以下となる場合には、開示を要しないものとしている。
② 連結貸借対照表項目に属する科目の残高及びその注記事項に係る関連当事者との取引並びに債務保証等及び担保提供又は受入れ
イ その金額が総資産の1%を超える取引
ロ 資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等については、それぞれの残高が総資産の1%以下であっても、取引の発生総額(資金貸付額等)が総資産の1%を超える取引(ただし、取引が反復的に行われている場合や、その発生総額の把握が困難である場合には、期中の平均残高が総資産の1%を超える取引を開示することもできる。)
ハ 事業の譲受又は譲渡の場合には、譲受又は譲渡の対象となる資産や負債が個々に取引されるのではなく、一体として取引されると考えられることから、対象となる資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、総資産の1%を超える取引
なお、上記①及び②を個別財務諸表で関連当事者との取引を開示する場合に適用する場合には、連結損益計算書項目、連結貸借対照表項目、税金等調整前当期純損益は、それぞれ、損益計算書項目、貸借対照表項目、税引前当期純損益と、適宜読み替えるものとしている。
<関連当事者が個人の場合(適用指針第16項)>
関連当事者との取引が、連結損益計算書項目及び連結貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、1,000万円を超える取引については、すべて開示対象とすることとしている。
4 関連当事者の存在に関する開示
(1)親会社の情報
本会計基準では、親会社の存在の有無は、投資家が意思決定をするにあたって有用な情報と考え、IAS第24号やSFAS第57号と同様に、親会社の名称等の開示を新たに求めることとし、具体的には親会社の名称及び上場又は非上場の別の開示を求めている(会計基準第11項(1)、第38項及び適用指針第10項、図表3参照)。
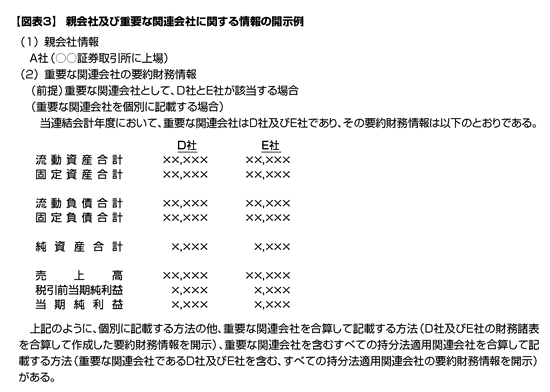
(2)重要な関連会社の要約財務情報
本会計基準では、重要な関連会社が存在する場合にも、これらの会社に関する情報が有用な情報であると考え、その名称と要約財務情報を開示することとしている。重要な関連会社の要約財務情報については、米国では会計原則審議会意見書第18号(APB第18号)「持分法による普通株式投資の会計」において、国際財務報告基準ではIAS第28号「関連会社に対する投資」及びIAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」において、共同支配企業を含む関連会社に関する要約財務情報の注記開示を求めており、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、我が国では関連当事者の存在に関する開示として、新たにこれを求めることとした(会計基準第39項)。
要約財務情報の記載項目としては、持分法投資損益(脚注2)(共同支配企業の場合は持分法に準ずる処理を適用した場合の投資損益)の算定に用いた財務情報(脚注3)をもとに、主な貸借対照表項目及び損益計算書項目を開示することとし、例えば以下の内容を記載することとしている。
① 貸借対照表項目:流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計
② 損益計算書項目:売上高、税引前当期純損益、当期純損益
要約財務情報の開示方法としては、①個別に開示する方法、②重要な関連会社の要約財務情報を合算して開示する方法、③持分法投資損益の算定対象としたすべての関連会社の財務情報を合算して開示(その旨及び重要な関連会社の名称を明記)する方法のいずれかを選択できることとしている(会計基準第11項(2)及び適用指針第11項、図表3参照)。
(3)重要な関連会社の要約財務情報における重要性の判断基準
要約財務情報の開示を必要とする関連会社の重要性は、以下のいずれかの場合に該当するかにより判断することとしている(適用指針第19項)。
① 各関連会社の総資産(持分相当額)が、会社の総資産の10%を超える場合
② 各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が、会社の税金等調整前当期純損益の10%を超える場合
ただし、②については上記の基準を満たす場合であっても、会社の最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益(当該期間中に税金等調整前当期純利益と税金等調整前当期純損失がある場合には、原則として税金等調整前当期純利益が発生した年度の平均とする。)の10%を超えない場合には、開示を要しないものとしている。なお、②を個別財務諸表上の開示に関して適用するときには、税金等調整前当期純損益は、税引前当期純損益と読み替えるものとしている。
Ⅳ.適用時期等
本会計基準及び本適用指針は、財務諸表作成会社において受入準備が必要であることを考慮し、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用するものとしている。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することもできるとしている(会計基準第12項)。
(はたの・なおこ)
脚注
1 本会計基準及び本適用指針の本文については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/kan_ren0720/)を参照のこと。
2 個別財務諸表上で関連当事者の開示を行う場合には、財務諸表等規則第8条の9で注記することが定められている、関連会社に対する投資に対して持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失を指す。
3 重要な関連会社に子会社があり、会社の持分法投資損益に当該子会社の利益(又は損失)持分相当分が含められている場合であっても、当該関連会社が非上場企業である場合などでは、この関連会社が連結財務諸表を作成していないことも考えられる。この場合には、実態等を勘案した上で、重要な関連会社の単独財務諸表を基礎に、当該子会社を連結したものとして調整した財務情報を開示する方法や、当該子会社に持分法を適用したものとして調整した財務情報を開示する方法などにより、開示対象となる重要な関連会社の要約財務情報にその子会社の財務情報の内容を反映することが考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























