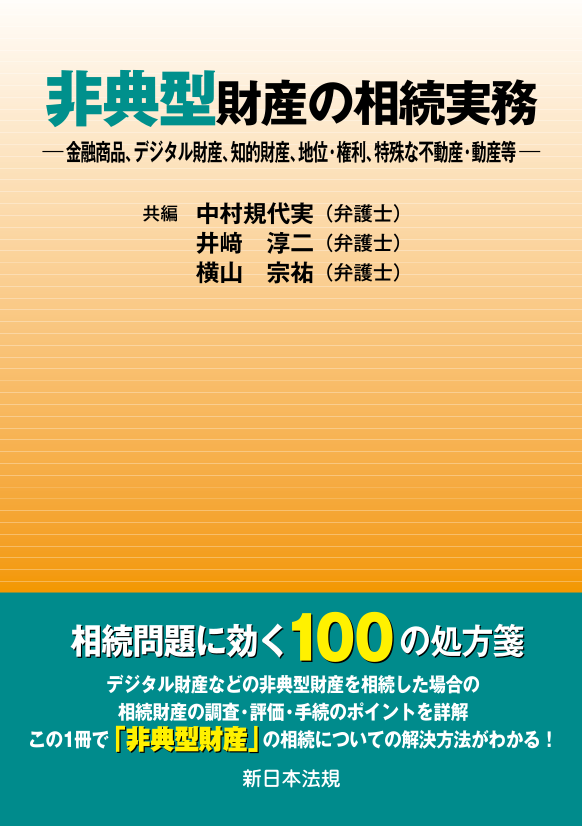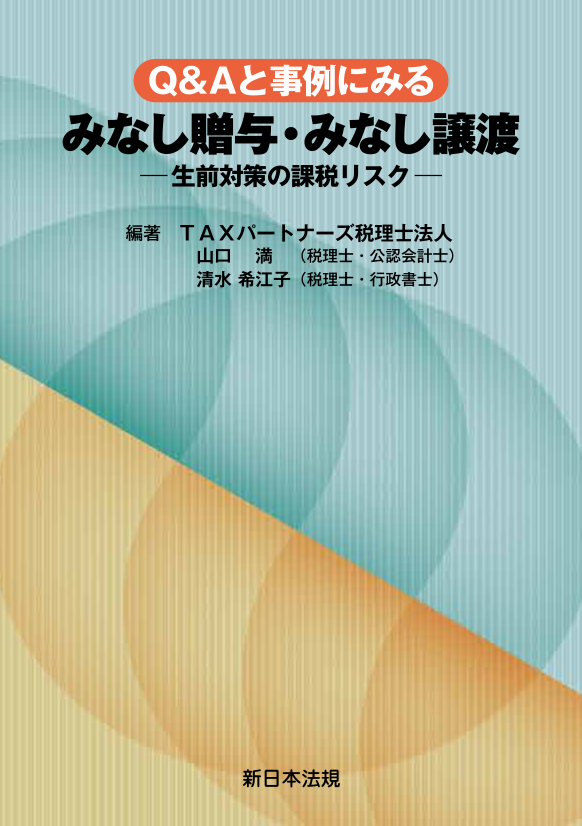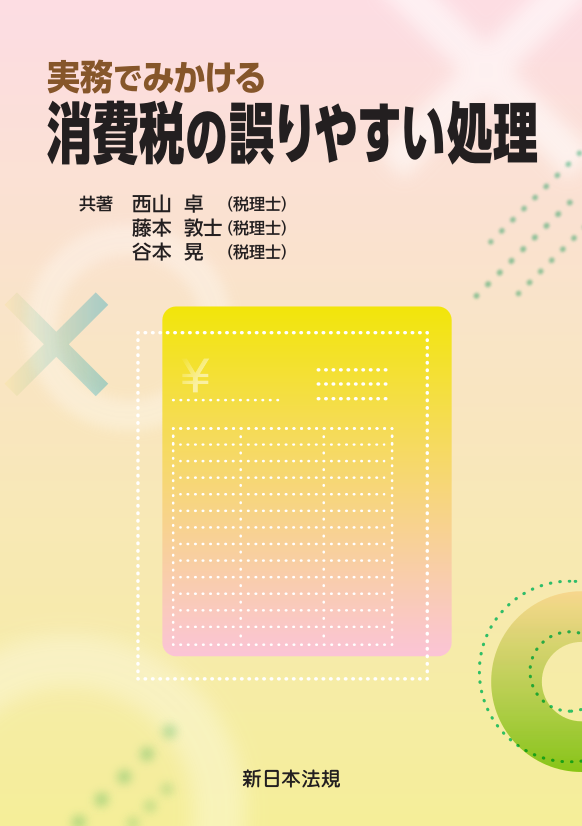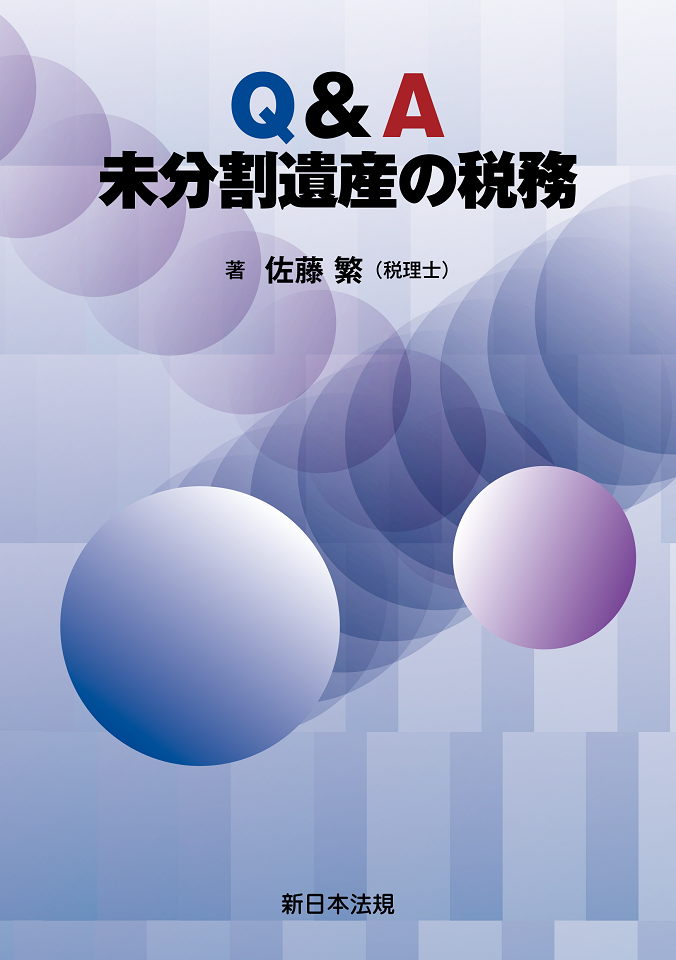解説記事2006年12月18日 【制度解説】 新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(2)(2006年12月18日号・№191)
実務解説
新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(2)
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 久保田修平
Ⅰ はじめに
今回および次回は、前回(本誌188号4頁参照)に述べた改正の概要の順に、各改正点の詳細および実務上のポイントについて検討する。
今回は公開買付制度の主要な改正点を中心に論じ、次回は公開買付制度のうち全部買付義務等ならびに大量保有報告制度および組織再編等における開示制度について触れることとする。
なお、改正された施行令および各内閣府令がそれぞれ平成18年12月8日および12月12日に公布され、改正法の施行時期は次のとおりとされている。
① 平成18年12月13日 公開買付制度、大量保有報告制度のうち重要提案行為等に係る部分および組織再編等における開示制度
② 平成19年1月1日 大量保有報告制度の大部分(①・③以外の部分)
③ 平成19年4月1日 大量保有報告制度のうち電子開示に係る部分
Ⅱ 強制的公開買付規制の対象となる取引の範囲の変更および明確化
1.市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けによる一連取引規制
新法は、市場取引や第三者割当てを組み合わせた脱法的な態様の取引に対応するため、一定の急速な買付けについては、個々の取引を細分化せず、一連の取引全体を規制対象とすることとした。
具体的には、次の場合に、その買付け等の全体について公開買付けが強制されることとなる(法27条の2第1項4号)(図表1参照)。
(a)3か月内(施行令7条2項)に買付け等または新規発行取得により10%(施行令7条3項)を超える株券等を取得し、かつ、
(b)そのうち特定売買等(立会外取引)または市場外取引による買付け等(公開買付けを除く)の割合が5%(施行令7条4項)を超える場合で、
(c)その結果、買付け等または新規発行取得の後の株券等所有割合が1/3超となるとき
また、上述の急速な買付けの場合の一連取引規制の適用にあたり、上記(a)の3か月内の10%の取得および(b)の5%の買付け等については、買付者およびその特別関係者(法27条の2第7項2号に定める実質基準の特別関係者に限る)による取得分が合算して判定されることとなる(法27条の2第1項6号、施行令7条7項)。
この場合、次の点に留意が必要である。
① 市場内取引による買付け等が入っても公開買付けの対象になること
② 当該3か月間に行われる買付け等は一体のものとして公開買付けの対象となること
③ 法令上、当該一連の買付け等を公開買付けを行うべき場合としているが、当該買付け等が規制される反射的効果として新規発行取得も規制される場合が生じること
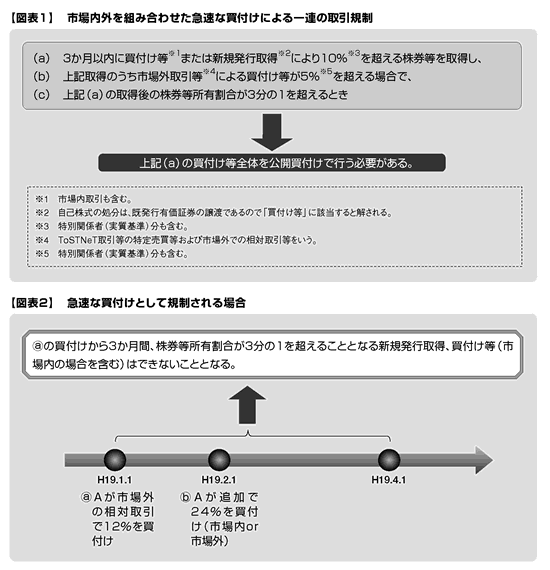
たとえば、図表2に掲げた例でいえば、Aが平成19年1月1日に市場外の相対取引にてB株式会社の12%の買付け((a))を行った場合、その後3か月の間、株券等所有割合が3分の1を超えることとなる買付け等((b))は市場内取引であったとしても公開買付規制の対象となり((b)の買付け等は市場内取引であっても公開買付規制が適用される)、また、(a)および(b)が一体の買付け等として全体を公開買付けによらなければならないこととなる((b)のみを公開買付けすればよいわけではない)。その結果、(b)の買付け等は3か月間できないこととなる。(b)が新規発行取得の場合も同様である。
上記規制に抵触しない方法として、平成19年1月1日に、Aが上記(a)の12%の相対取引による買付けと対象者(B株式会社)の24%の新株式の発行を合意し、当該相対取引は同日付で行い、新株発行については当該買付け後から3か月経過した同年5月1日に行った場合、本号の対象にならず公開買付規制の対象とならないかという問題が生じる。
この点、今回の改正の前後を問わず、新株発行の合意により株券等の引渡請求権を有する場合(施行令7条1項1号)に該当するなどとして、(a)の相対取引後の株券等所有割合の計算において当該新規発行株式分も合計すべきであるとの解釈もありうることから(その場合には、(a)の相対取引後の株券等所有割合が3分の1を超えることから法27条の2第1項2号に該当する)、合意内容については実務上慎重な検討が必要である。
なお、実務上は新設された法27条の2第1項4号の規制に目がいきがちであるところではあるが、たとえば32%の新株発行後に2%の市場外の相対取引を行うことは、本号の規制には該当しないが、法27条の2第1項2号に該当し、従来どおり公開買付けが強制されることとなるので、留意が必要である。
2.他者の公開買付期間中の大株主による急速な買集め行為規制
会社支配権に影響する買付けが競合する場合においては、株主・投資家がより複雑な投資判断を迫られること等の観点から、ある者が公開買付けを実施している間(施行令7条5項)に、株券等所有割合が3分の1を超える大株主が5%超(施行令7条6項)の買付け等(市場内の場合も含む)を行う場合には、公開買付規制の対象となった(法27条の2第1項5号)。
この点、第三者による公開買付けの開始時点では株券等所有割合が3分の1を超えていない者(株主)が、当該公開買付期間中に市場取引で買い増して3分の1を超えた場合には、その時点以降の買付け等につき、本規制が適用されると思われる(図表3参照)。
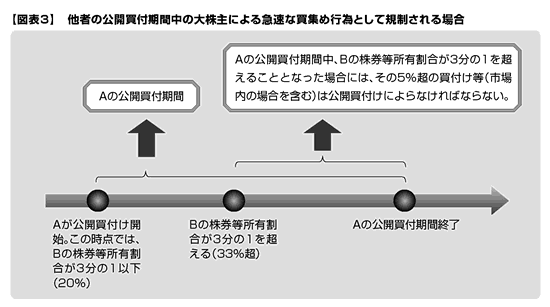
3.その他強制的公開買付規制の対象となる取引の変更
その他の改正点としては、50%超の株券等所有割合(旧法においては、顕在的な議決権ベースであったのが、潜在的な議決権も含まれることとなった)を有する株主による特定買付け等は公開買付けの適用除外とされた(施行令6条の2第1項4号)ことから、新株予約権付社債等の潜在的な議決権ベースで50%を超えている者が、株券等を特定買付け等により買い増すことが容易となった。
また、新株予約権や取得請求権付株式の権利を行使した場合(法27条の2第1項ただし書、施行令6条の2第1項11号)や、取得条項付株式または取得条項付新株予約権の取得事由発生によって株券等が交付される場合(施行令6条の2第1項12号)も公開買付けの適用除外として明記されている。
一方、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、全部買付義務が課せられた(法27条の13第4項1号)関係上、上記50%超の株券等所有割合を有する株主による特定買付け等を行う場合でも3分の2以上となる特定買付け等を行う場合(施行令6条の2第1項4号)には、公開買付けが強制されることとなる。
また、当該特定買付け等の対象となる株券等の所有者が25名未満であって、そのすべての所有者が公開買付けによらないことにつき同意している場合の特定買付け等の場合であっても、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、当該特定買付け等の対象となる株券等の所有者の全員の同意に加えて、当該特定買付け等の対象とならない株券等(「買付け等対象外株券等」)があるときは、
(a)当該特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意することにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会の決議が行われていること、または
(b)買付け等対象外株券等の所有者が25名未満であって、そのすべての所有者が当該特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意し、その旨の書面を提出していること
が必要となるので留意が必要である(施行令6条の2第1項7号、他社株公開買付府令2条の5第2項1号)。
Ⅲ 株主・投資者への情報提供の充実化・熟慮期間の確保
1.意見表明報告書の義務化
(1)意見表明報告書の提出
新法では、対象者は、公開買付開始公告から10営業日以内に意見表明報告書の提出が義務付けられた(法27条の10第1項、施行令13条の2第1項)が、意見表明報告書において記載される意見の内容は賛成反対だけでなく、中立や留保も許される。
もし、留保する場合には、その時点で意見が表明できない理由および今後表明する予定の有無等を具体的に記載することが必要となる(他社株公開買付府令第4号様式(記載上の注意)(3)c)。
意見表明報告書には、
① 公開買付者が対象者の役員、その依頼に基づき行う者で対象者の役員と利益を共通にする者、または対象者の親会社等の場合において利益相反を回避する措置を講じているときはその具体的内容
② 買収防衛策を含む「会社の支配に関する基本方針に係る対応方針」
の記載が必要となった(他社株公開買付府令第4号様式(記載上の注意)(3)d、(6))。
具体的な記載内容は今後の実務における集積が待たれるが、①の場合には、対象者の取締役会において特別関係者を除いて決議をした旨の会社法上適切な措置を取っただけに限らず、公開買付者の価格の妥当性を判断するために中立的な第三者からの意見聴取、社外取締役等による価格の妥当性の検討等の利益相反を回避する措置を行った場合には、そのプロセスを記載することになろう。
②の場合には、対象者がいわゆる買収防衛策を導入している場合には、その発動の有無および予定がある場合にはその具合的な内容を記載する必要があるが、公開買付者が突然対象者に対して公開買付けを開始する場面もあり、かかる場合には意見表明報告書を提出する段階では、当該買収防衛策の発動の有無を決めきれないことも想定される。
かかる場合においては、対象者としては、買収防衛策の発動の有無を検討中である旨を意見表明報告書に記載することになると思われる。このような意見表明報告書を提出した場合であっても、この時点では当該買収防衛策は発動される可能性が存する(少なくともこの時点では当該買収防衛策の導入した旨の決定は維持されている)ことから、対象者が「当該決定を維持する旨の決定」をしたとして、公開買付者は当該公開買付けを撤回することができる(施行令14条1項2号イ)と解する余地もあるように思われる。
また、開示すべき防衛策の範囲が大株主等への働きかけ等を含むのかなど、今後の実務で解消しなければならない論点もある。
(2)公開買付期間の延長請求等
対象者は、意見表明報告書に公開買付者に対して質問(法27条の10第2項1号)や、公開買付けの最短期間を30営業日まで延長することができることとなった(法27条の10第2項2号・3項)。
いわゆる敵対的な公開買付けに対して、上記質問や期間延長の請求が行われるものと思われるが、対象者が期間延長請求する旨およびその理由等を意見表明報告書に記載した場合には、対象者においてかかる延長請求をした旨および延長後の買付け等の期間の末日等(他社株公開買付府令25条の2)について、意見表明報告書の提出期限(公開買付開始公告から10営業日目)の翌日までに、当該公開買付開始公告と同じ方法により公告をする必要があるので(法27条の10第4項、施行令9条の3、他社株公開買付府令9条4項)、留意が必要である。
意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載された場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5営業日以内に、公開買付者は当該質問に対する回答、当該回答に至った経緯を時系列に記載し、対質問回答報告書を提出しなければならない(法27条の10第2項11項、施行令13条の2第2号、他社株公開買付府令第8号様式(記載上の注意)(3))。
公開買付者は、対象者からの質問に対して回答する必要がないと認めた場合には回答を拒絶または留保することもできるが、その理由を詳細に対質問回答報告書上記載する必要がある(他社株公開買付府令第8号様式(記載上の注意)(3)b)。
当該理由の「詳細」とはどの程度の記載が求められるのかについては、今後実務において検討されることになるが、当該質問に回答することが公開買付者の第三者に対する守秘義務に反するような場合、当該守秘義務に反してまで公開買付者が回答する義務を課すことは公開買付者にとって酷と思われることから、かかる質問に対する回答を拒絶等することは許されると解してもよいのではないだろうか。
なお、公開買付者が対質問回答報告書に記載した回答については、証券取引法上の民事責任および刑事責任(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科)を負うこととなる(法27条の20第1項4号、197条の2第6号)。
公開買付期間については、旧法では暦日ベースであったが、新法では営業日ベース(行政機関の休日は算入しない)で公開買付開始公告日から起算して20日以上で60日以内の期間となった(施行令8条1項)。なお、「起算して」という語が追加され、初日を期間に算入することが明確にされている。
2.公開買付届出書の記載事項の拡充
新法では、公開買付届出書(他社株公開買付府令第2号様式)の記載事項も大幅に改正された。
(1)買付け等の目的に係る拡充
「買付け等の目的」において、支配権取得または経営参加を目的とする場合には、支配権取得または経営参加の具体的方法やその後の具体的計画を記載するほか、支配権取得または経営参加後に予定する対象者の再編、重要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定・解職、役員構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更等の内容およびその必要性の記載が必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)a)。
たとえば、公開買付者が、対象者の株式等を100%取得し非公開化を目指している場合には、公開買付け終了後において、100%子会社化を目指すために株式交換またはその他のスキームにより対象者の株主に金銭を交付することを考えていること、100%にした後公開買付者または子会社と対象者との間で合併を行う予定であること、公開買付者の買収資金を対象者による借入れに借り換える予定であること等の記載が必要になると思われる。
また、純投資または政策投資が目的の場合でも、取得後の保有方針、売買方針および議決権行使方針ならびにその理由を、長期的な資本提携を目的とする政策投資の場合にはその必要性まで記載することが必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)b)。
特に、長期的な資本提携を目的とする政策投資の場合の必要性とは、いかなることを記載すべきかは「(記載上の注意)」からは明らかではなく、実務上悩ましい問題である。
また、いかなる目的の場合であっても、買付け等の後の発行者の株券等の追加取得の予定の有無、その理由およびその内容や、上場廃止の見込み等については記載が必要となる(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)c、e)。
(2)買付価格に係る拡充
買付価格については、「算定の基礎」だけでなく「算定の経緯」まで記載することとなった。
「算定の基礎」は、具体的な算定根拠について、買付価格が時価や公開買付者が最近行った取引の価格との相違がある場合には、その差額の内容について記載が必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)e)。
実務上、「算定の基礎」と「算定の経緯」にいかなる点を記載すべきかが問題となるが、「算定の基礎」の欄においては、算定根拠と算定した結果の時価との差額(買付価格と公開買付開始時点ないし直近数か月平均の対象者の株価とのプレミアムの有無等)について記載し、「算定の経緯」は、主に当該買付価格をどのように決定したかの価格決定プロセスについて記載することになろうかと思われる。
具体的には、「算定の経緯」においては、第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者の名称、意見の概要や当該意見を踏まえて買付価格を決定した経緯を具体的に記載することとなる(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)f)。
当該公開買付けが、
① 対象者の役員(いわゆるMBO)、
② 対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者、または
③ 対象者を子会社とする会社その他の法人(親会社による公開買付け等)
等の場合には、本来は対象者の全株主のために対象者の株式を高く購入するように公開買付者と交渉等をすべき対象者の経営陣が、できれば対象者の株式を安く購入したい公開買付者と一体となるため、利益相反的な状況が生じること、また公開買付者と他の株主との間に情報の偏在が生じている可能性が高いため、買付価格の公正性を担保するための措置を講じているときはその内容を記載しなければならない(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)f)。
このうち、②はいかなるケースが該当するかが明らかではないが、上記趣旨に鑑み、対象者経営陣とともにMBOを行うファンド等による公開買付け等が該当すると思われ、たとえば、公開買付者による公開買付けの端緒が対象者経営陣からの紹介であったという程度のものや当該公開買付けに関し対象者から賛同表明を得られるように交渉をした程度のいわゆる友好的な公開買付けの場合には、当該②には該当しないのではないかと思われる。
また、上記①ないし③に該当するケースでは、「公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容」の欄において、公開買付者が公開買付けの実施を決定した意思決定の過程や利益相反を回避する措置を講じているときはその措置を記載しなければならない(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(25))。
さらに、「価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これらに類するものがある場合には、その写し」を添付する必要がある(他社株公開買付府令13条1項8号)。
具体的には、「算定の経緯」の欄において、意見を聴取した第三者から受領した評価書等について公開買付届出書に添付する必要があり、かかる評価書等は公開買付届出書とともに公衆の閲覧に供されることとなる(他社株公開買付府令33条)。
(なかむら・さとし/くぼた・しゅうへい)
新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(2)
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 久保田修平
Ⅰ はじめに
今回および次回は、前回(本誌188号4頁参照)に述べた改正の概要の順に、各改正点の詳細および実務上のポイントについて検討する。
今回は公開買付制度の主要な改正点を中心に論じ、次回は公開買付制度のうち全部買付義務等ならびに大量保有報告制度および組織再編等における開示制度について触れることとする。
なお、改正された施行令および各内閣府令がそれぞれ平成18年12月8日および12月12日に公布され、改正法の施行時期は次のとおりとされている。
① 平成18年12月13日 公開買付制度、大量保有報告制度のうち重要提案行為等に係る部分および組織再編等における開示制度
② 平成19年1月1日 大量保有報告制度の大部分(①・③以外の部分)
③ 平成19年4月1日 大量保有報告制度のうち電子開示に係る部分
Ⅱ 強制的公開買付規制の対象となる取引の範囲の変更および明確化
1.市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けによる一連取引規制
新法は、市場取引や第三者割当てを組み合わせた脱法的な態様の取引に対応するため、一定の急速な買付けについては、個々の取引を細分化せず、一連の取引全体を規制対象とすることとした。
具体的には、次の場合に、その買付け等の全体について公開買付けが強制されることとなる(法27条の2第1項4号)(図表1参照)。
(a)3か月内(施行令7条2項)に買付け等または新規発行取得により10%(施行令7条3項)を超える株券等を取得し、かつ、
(b)そのうち特定売買等(立会外取引)または市場外取引による買付け等(公開買付けを除く)の割合が5%(施行令7条4項)を超える場合で、
(c)その結果、買付け等または新規発行取得の後の株券等所有割合が1/3超となるとき
また、上述の急速な買付けの場合の一連取引規制の適用にあたり、上記(a)の3か月内の10%の取得および(b)の5%の買付け等については、買付者およびその特別関係者(法27条の2第7項2号に定める実質基準の特別関係者に限る)による取得分が合算して判定されることとなる(法27条の2第1項6号、施行令7条7項)。
この場合、次の点に留意が必要である。
① 市場内取引による買付け等が入っても公開買付けの対象になること
② 当該3か月間に行われる買付け等は一体のものとして公開買付けの対象となること
③ 法令上、当該一連の買付け等を公開買付けを行うべき場合としているが、当該買付け等が規制される反射的効果として新規発行取得も規制される場合が生じること
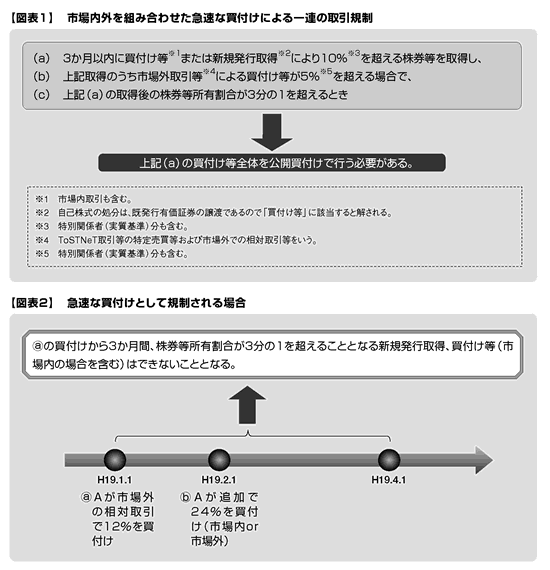
たとえば、図表2に掲げた例でいえば、Aが平成19年1月1日に市場外の相対取引にてB株式会社の12%の買付け((a))を行った場合、その後3か月の間、株券等所有割合が3分の1を超えることとなる買付け等((b))は市場内取引であったとしても公開買付規制の対象となり((b)の買付け等は市場内取引であっても公開買付規制が適用される)、また、(a)および(b)が一体の買付け等として全体を公開買付けによらなければならないこととなる((b)のみを公開買付けすればよいわけではない)。その結果、(b)の買付け等は3か月間できないこととなる。(b)が新規発行取得の場合も同様である。
上記規制に抵触しない方法として、平成19年1月1日に、Aが上記(a)の12%の相対取引による買付けと対象者(B株式会社)の24%の新株式の発行を合意し、当該相対取引は同日付で行い、新株発行については当該買付け後から3か月経過した同年5月1日に行った場合、本号の対象にならず公開買付規制の対象とならないかという問題が生じる。
この点、今回の改正の前後を問わず、新株発行の合意により株券等の引渡請求権を有する場合(施行令7条1項1号)に該当するなどとして、(a)の相対取引後の株券等所有割合の計算において当該新規発行株式分も合計すべきであるとの解釈もありうることから(その場合には、(a)の相対取引後の株券等所有割合が3分の1を超えることから法27条の2第1項2号に該当する)、合意内容については実務上慎重な検討が必要である。
なお、実務上は新設された法27条の2第1項4号の規制に目がいきがちであるところではあるが、たとえば32%の新株発行後に2%の市場外の相対取引を行うことは、本号の規制には該当しないが、法27条の2第1項2号に該当し、従来どおり公開買付けが強制されることとなるので、留意が必要である。
2.他者の公開買付期間中の大株主による急速な買集め行為規制
会社支配権に影響する買付けが競合する場合においては、株主・投資家がより複雑な投資判断を迫られること等の観点から、ある者が公開買付けを実施している間(施行令7条5項)に、株券等所有割合が3分の1を超える大株主が5%超(施行令7条6項)の買付け等(市場内の場合も含む)を行う場合には、公開買付規制の対象となった(法27条の2第1項5号)。
この点、第三者による公開買付けの開始時点では株券等所有割合が3分の1を超えていない者(株主)が、当該公開買付期間中に市場取引で買い増して3分の1を超えた場合には、その時点以降の買付け等につき、本規制が適用されると思われる(図表3参照)。
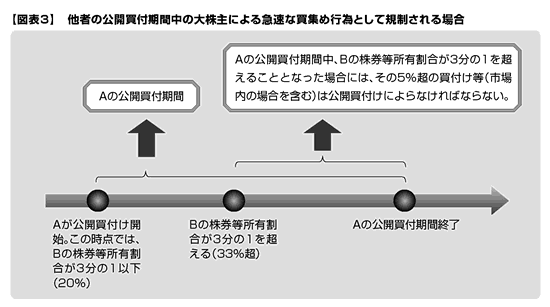
3.その他強制的公開買付規制の対象となる取引の変更
その他の改正点としては、50%超の株券等所有割合(旧法においては、顕在的な議決権ベースであったのが、潜在的な議決権も含まれることとなった)を有する株主による特定買付け等は公開買付けの適用除外とされた(施行令6条の2第1項4号)ことから、新株予約権付社債等の潜在的な議決権ベースで50%を超えている者が、株券等を特定買付け等により買い増すことが容易となった。
また、新株予約権や取得請求権付株式の権利を行使した場合(法27条の2第1項ただし書、施行令6条の2第1項11号)や、取得条項付株式または取得条項付新株予約権の取得事由発生によって株券等が交付される場合(施行令6条の2第1項12号)も公開買付けの適用除外として明記されている。
一方、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、全部買付義務が課せられた(法27条の13第4項1号)関係上、上記50%超の株券等所有割合を有する株主による特定買付け等を行う場合でも3分の2以上となる特定買付け等を行う場合(施行令6条の2第1項4号)には、公開買付けが強制されることとなる。
また、当該特定買付け等の対象となる株券等の所有者が25名未満であって、そのすべての所有者が公開買付けによらないことにつき同意している場合の特定買付け等の場合であっても、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、当該特定買付け等の対象となる株券等の所有者の全員の同意に加えて、当該特定買付け等の対象とならない株券等(「買付け等対象外株券等」)があるときは、
(a)当該特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意することにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会の決議が行われていること、または
(b)買付け等対象外株券等の所有者が25名未満であって、そのすべての所有者が当該特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意し、その旨の書面を提出していること
が必要となるので留意が必要である(施行令6条の2第1項7号、他社株公開買付府令2条の5第2項1号)。
Ⅲ 株主・投資者への情報提供の充実化・熟慮期間の確保
1.意見表明報告書の義務化
(1)意見表明報告書の提出
新法では、対象者は、公開買付開始公告から10営業日以内に意見表明報告書の提出が義務付けられた(法27条の10第1項、施行令13条の2第1項)が、意見表明報告書において記載される意見の内容は賛成反対だけでなく、中立や留保も許される。
もし、留保する場合には、その時点で意見が表明できない理由および今後表明する予定の有無等を具体的に記載することが必要となる(他社株公開買付府令第4号様式(記載上の注意)(3)c)。
意見表明報告書には、
① 公開買付者が対象者の役員、その依頼に基づき行う者で対象者の役員と利益を共通にする者、または対象者の親会社等の場合において利益相反を回避する措置を講じているときはその具体的内容
② 買収防衛策を含む「会社の支配に関する基本方針に係る対応方針」
の記載が必要となった(他社株公開買付府令第4号様式(記載上の注意)(3)d、(6))。
具体的な記載内容は今後の実務における集積が待たれるが、①の場合には、対象者の取締役会において特別関係者を除いて決議をした旨の会社法上適切な措置を取っただけに限らず、公開買付者の価格の妥当性を判断するために中立的な第三者からの意見聴取、社外取締役等による価格の妥当性の検討等の利益相反を回避する措置を行った場合には、そのプロセスを記載することになろう。
②の場合には、対象者がいわゆる買収防衛策を導入している場合には、その発動の有無および予定がある場合にはその具合的な内容を記載する必要があるが、公開買付者が突然対象者に対して公開買付けを開始する場面もあり、かかる場合には意見表明報告書を提出する段階では、当該買収防衛策の発動の有無を決めきれないことも想定される。
かかる場合においては、対象者としては、買収防衛策の発動の有無を検討中である旨を意見表明報告書に記載することになると思われる。このような意見表明報告書を提出した場合であっても、この時点では当該買収防衛策は発動される可能性が存する(少なくともこの時点では当該買収防衛策の導入した旨の決定は維持されている)ことから、対象者が「当該決定を維持する旨の決定」をしたとして、公開買付者は当該公開買付けを撤回することができる(施行令14条1項2号イ)と解する余地もあるように思われる。
また、開示すべき防衛策の範囲が大株主等への働きかけ等を含むのかなど、今後の実務で解消しなければならない論点もある。
(2)公開買付期間の延長請求等
対象者は、意見表明報告書に公開買付者に対して質問(法27条の10第2項1号)や、公開買付けの最短期間を30営業日まで延長することができることとなった(法27条の10第2項2号・3項)。
いわゆる敵対的な公開買付けに対して、上記質問や期間延長の請求が行われるものと思われるが、対象者が期間延長請求する旨およびその理由等を意見表明報告書に記載した場合には、対象者においてかかる延長請求をした旨および延長後の買付け等の期間の末日等(他社株公開買付府令25条の2)について、意見表明報告書の提出期限(公開買付開始公告から10営業日目)の翌日までに、当該公開買付開始公告と同じ方法により公告をする必要があるので(法27条の10第4項、施行令9条の3、他社株公開買付府令9条4項)、留意が必要である。
意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載された場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5営業日以内に、公開買付者は当該質問に対する回答、当該回答に至った経緯を時系列に記載し、対質問回答報告書を提出しなければならない(法27条の10第2項11項、施行令13条の2第2号、他社株公開買付府令第8号様式(記載上の注意)(3))。
公開買付者は、対象者からの質問に対して回答する必要がないと認めた場合には回答を拒絶または留保することもできるが、その理由を詳細に対質問回答報告書上記載する必要がある(他社株公開買付府令第8号様式(記載上の注意)(3)b)。
当該理由の「詳細」とはどの程度の記載が求められるのかについては、今後実務において検討されることになるが、当該質問に回答することが公開買付者の第三者に対する守秘義務に反するような場合、当該守秘義務に反してまで公開買付者が回答する義務を課すことは公開買付者にとって酷と思われることから、かかる質問に対する回答を拒絶等することは許されると解してもよいのではないだろうか。
なお、公開買付者が対質問回答報告書に記載した回答については、証券取引法上の民事責任および刑事責任(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科)を負うこととなる(法27条の20第1項4号、197条の2第6号)。
公開買付期間については、旧法では暦日ベースであったが、新法では営業日ベース(行政機関の休日は算入しない)で公開買付開始公告日から起算して20日以上で60日以内の期間となった(施行令8条1項)。なお、「起算して」という語が追加され、初日を期間に算入することが明確にされている。
2.公開買付届出書の記載事項の拡充
新法では、公開買付届出書(他社株公開買付府令第2号様式)の記載事項も大幅に改正された。
(1)買付け等の目的に係る拡充
「買付け等の目的」において、支配権取得または経営参加を目的とする場合には、支配権取得または経営参加の具体的方法やその後の具体的計画を記載するほか、支配権取得または経営参加後に予定する対象者の再編、重要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定・解職、役員構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更等の内容およびその必要性の記載が必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)a)。
たとえば、公開買付者が、対象者の株式等を100%取得し非公開化を目指している場合には、公開買付け終了後において、100%子会社化を目指すために株式交換またはその他のスキームにより対象者の株主に金銭を交付することを考えていること、100%にした後公開買付者または子会社と対象者との間で合併を行う予定であること、公開買付者の買収資金を対象者による借入れに借り換える予定であること等の記載が必要になると思われる。
また、純投資または政策投資が目的の場合でも、取得後の保有方針、売買方針および議決権行使方針ならびにその理由を、長期的な資本提携を目的とする政策投資の場合にはその必要性まで記載することが必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)b)。
特に、長期的な資本提携を目的とする政策投資の場合の必要性とは、いかなることを記載すべきかは「(記載上の注意)」からは明らかではなく、実務上悩ましい問題である。
また、いかなる目的の場合であっても、買付け等の後の発行者の株券等の追加取得の予定の有無、その理由およびその内容や、上場廃止の見込み等については記載が必要となる(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(5)c、e)。
(2)買付価格に係る拡充
買付価格については、「算定の基礎」だけでなく「算定の経緯」まで記載することとなった。
「算定の基礎」は、具体的な算定根拠について、買付価格が時価や公開買付者が最近行った取引の価格との相違がある場合には、その差額の内容について記載が必要である(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)e)。
実務上、「算定の基礎」と「算定の経緯」にいかなる点を記載すべきかが問題となるが、「算定の基礎」の欄においては、算定根拠と算定した結果の時価との差額(買付価格と公開買付開始時点ないし直近数か月平均の対象者の株価とのプレミアムの有無等)について記載し、「算定の経緯」は、主に当該買付価格をどのように決定したかの価格決定プロセスについて記載することになろうかと思われる。
具体的には、「算定の経緯」においては、第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者の名称、意見の概要や当該意見を踏まえて買付価格を決定した経緯を具体的に記載することとなる(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)f)。
当該公開買付けが、
① 対象者の役員(いわゆるMBO)、
② 対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者、または
③ 対象者を子会社とする会社その他の法人(親会社による公開買付け等)
等の場合には、本来は対象者の全株主のために対象者の株式を高く購入するように公開買付者と交渉等をすべき対象者の経営陣が、できれば対象者の株式を安く購入したい公開買付者と一体となるため、利益相反的な状況が生じること、また公開買付者と他の株主との間に情報の偏在が生じている可能性が高いため、買付価格の公正性を担保するための措置を講じているときはその内容を記載しなければならない(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(6)f)。
このうち、②はいかなるケースが該当するかが明らかではないが、上記趣旨に鑑み、対象者経営陣とともにMBOを行うファンド等による公開買付け等が該当すると思われ、たとえば、公開買付者による公開買付けの端緒が対象者経営陣からの紹介であったという程度のものや当該公開買付けに関し対象者から賛同表明を得られるように交渉をした程度のいわゆる友好的な公開買付けの場合には、当該②には該当しないのではないかと思われる。
また、上記①ないし③に該当するケースでは、「公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容」の欄において、公開買付者が公開買付けの実施を決定した意思決定の過程や利益相反を回避する措置を講じているときはその措置を記載しなければならない(他社株公開買付府令第2号様式(記載上の注意)(25))。
さらに、「価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これらに類するものがある場合には、その写し」を添付する必要がある(他社株公開買付府令13条1項8号)。
具体的には、「算定の経緯」の欄において、意見を聴取した第三者から受領した評価書等について公開買付届出書に添付する必要があり、かかる評価書等は公開買付届出書とともに公衆の閲覧に供されることとなる(他社株公開買付府令33条)。
(なかむら・さとし/くぼた・しゅうへい)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.