解説記事2007年01月15日 【編集部解説】 「減価償却制度の見直し」を検証する(2007年1月15日号・№194)
解説
「減価償却制度の見直し」を検証する
コスト・リカバリー制度と減価償却制度の融合
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
平成19年度税制改正の具体的内容で企業会計・税務申告の実務に最も大きな影響を与えることになるのが、「減価償却制度の見直し」である。「減価償却制度の見直し」では、①残存価額(取得価額の10%)の廃止、②償却可能限度額(取得価額の95%)の廃止、③技術進歩が著しいIT分野の3設備についての法定耐用年数の見直しが行われる。
実務的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、定率法の償却率に250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする方法)を導入する。
これらの「減価償却制度の見直し」は、米国で採用されているMACRS(コスト・リカバリー制度)の考え方を減価償却制度に反映させたものである。
Ⅰ 250%定率法とは?
代表的な減価償却方法のうち、定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法)では、残存価額(取得価額の10%)が廃止されることから、償却限度額の計算において90%を乗じることがなくなるが、償却率は(1/n、n:耐用年数)の算式で算定され、変更されない。
一方、定率法(当該減価償却資産の取得価額(期末簿価)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度として償却する方法)では、これまで、法定耐用年数経過時点において、残存する帳簿価額が残存価額(取得価額の10%)になるように、(1- 、n:耐用年数)の算式で算定されてきた。平成19年4月1日以後に取得をする原価償却資産について新たに導入される250%定率法では、(1/n×2.5、n:耐用年数)の算式で償却率が算定される。250%定率法の償却率を適用した場合には、現行の定率法を適用した場合に比べて、いずれも償却率が高くなり、設備投資の費用を早期に回収(償却)できるようになるが、耐用年数経過時点において、残存帳簿価額が0になることはない(残存価額を0とすると、理論上定率法の償却率は算定できない)。
、n:耐用年数)の算式で算定されてきた。平成19年4月1日以後に取得をする原価償却資産について新たに導入される250%定率法では、(1/n×2.5、n:耐用年数)の算式で償却率が算定される。250%定率法の償却率を適用した場合には、現行の定率法を適用した場合に比べて、いずれも償却率が高くなり、設備投資の費用を早期に回収(償却)できるようになるが、耐用年数経過時点において、残存帳簿価額が0になることはない(残存価額を0とすると、理論上定率法の償却率は算定できない)。
そのため、250%定率法では、250%定率法で計算した償却費が、法定耐用年数から経過年数を控除した期間内にその時の帳簿価額を定額法による償却(均等償却)すると仮定した償却額を下回るときに、償却方法を定額法に切り替えて減価償却費を計算する。この方法により、耐用年数経過時点において、備忘価額(1円)まで償却できることになる。
なお、減価償却資産の償却率は前頁下の表のとおり計算される。耐用年数2年では250%定率法により算定した償却率が1を超えるため、1.000として表示しているが、期中に事業の用に供した減価償却資産では、頭打ち(1.000に調整すること)を月数按分の前でするのか、後でするのかによって月数按分後の償却限度額が異なる場合も生じてくる。省令で償却率表を規定している現行の減価償却制度からすると、償却率表に1.000と記載され、1年分の償却限度額を計算したうえで(すなわち取得価額を基にして)月数按分計算が行われることになりそうだ(今号9頁参照)。
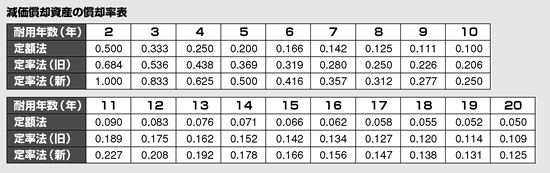
Ⅱ 法定耐用年数8年で250%定率法を適用すると
それでは具体的な例(取得価額100,000,000円、法定耐用年数8年(償却率0.312))にあてはめて250%定率法を検証してみよう。250%定率法は、定率法による償却から一定の時点で均等償却に切り替えて減価償却費を計算するところに特徴がある。実務的にはいつの時点から均等償却に切り替えることになるのかがポイントになってくる。
法定耐用年数8年(償却率0.312)の場合には、5年経過時点までは、現行の定率法と同じ計算方法で取得価額(期末簿価)に償却率(0.312)を乗じて減価償却費(償却限度額)を計算することになる(下記の表では法定耐用年数について償却率(0.312)を適用して計算している)。5年経過時点での残存簿価(154,149,526円)について、翌期以降(法定耐用年数-経過年数)で均等償却した各期償却額(51,383,175円)が6年目以降の定率法(償却率0.312)による償却額(48,094,652円)を超えることになるため、6年目より定額法に切り替え、6~8年の各期において、51,383,175円の減価償却費を計上し、耐用年数(8年)経過時点において、備忘価額(1円)を付すことになる。
期末簿価を上記の折れ線グラフで示している。5年経過時点までは一定の割合(償却率)で(スムーズな曲線で)償却していたものが6年目からは毎期一定額の償却で耐用年数経過時点において帳簿価額が備忘価額(1円)となるように、直線的な償却が行われることになる。
しかしながら、平成19年度税制改正大綱では、翌期以降(法定耐用年数-経過年数)で均等償却した各期償却額について、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて計算できるように、モデルケースを用いて、耐用年数ごとに一定の割合を定めておくこととしている(したがって、前頁の表を各法定耐用年数について作成し、均等償却への切替時点を検討する必要はない)。
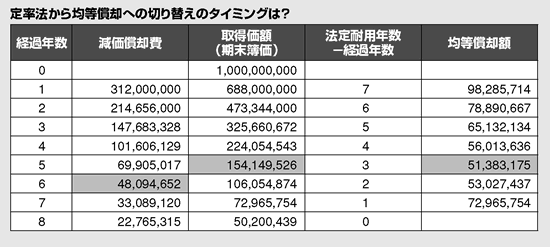
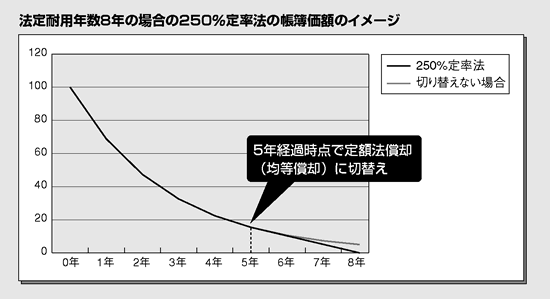
Ⅲ 既存の減価償却資産については
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、現行の償却方法・償却率を用いて償却限度額を計算することになるが、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却が進んだ資産については、翌事業年度以後5年間で均等償却することができる。
既存の減価償却資産については、設備投資の費用を早期に回収することにはならないが、減価償却資産の除却時の価値がほとんど残っていない実態に即して、取得価額の全額が償却できるように見直される。
Ⅳ 法定耐用年数の見直し
平成19年度税制改正に関する経済産業省意見では、世界における日本企業(シャープ)や韓国企業(サムスン電子など)の液晶パネルのシェアや設備投資を例にして、国際競争力を高めるための減価償却制度の見直しが要望されており、技術進歩や需要構造の変化に対応した減価償却制度の見直しが求められていた。
平成19年度税制改正大綱では、技術進歩が著しいIT分野の次の3設備について、法定耐用年数を短縮するとともに、平成20年度税制改正に向けて、減価償却資産の使用の実態等についてさらに調査・分析を進め、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討することとしている。
・フラットパネルディスプレイ製造設備
10年⇒5年に短縮
・フラットパネル用フィルム材料製造設備
10年⇒5年に短縮
・半導体用フォトレジスト製造設備
8年⇒5年に短縮
Ⅴ 新しい減価償却制度の特徴
減価償却制度の見直しでは、米国が採用しているMACRS(the Modified Accelerated Cost Recovery System)(以下「コスト・リカバリー制度」という)の考え方を部分的に反映させている。
コスト・リカバリー制度は、投資促進の観点から、資産の使用可能期間や残存価額とは関係なく、投下資金の回収期間(recovery periods)が定められる。会計と税務が乖離した(減価償却費の損金算入について確定決算主義が採用されていない)米国では、会計上の減価償却費から離れて税務上の償却額が計算されることになる。
我が国の平成19年度税制改正案は、資産の(法定)耐用年数の期間内において償却するという考え方を維持しており、全面的にコスト・リカバリー制度を導入したものとはいえないが、減価償却資産の耐用年数の期間中に定率法から定額法に切り替える減価償却方法となる250%定率法が、会計が本来予定していた減価償却方法とするには違和感もある(もちろん、我が国の減価償却の実態からすれば、税務会計の逆基準性を容認しなければならない。我が国の場合250%定率法も会計上の減価償却方法として認められることになると思われる)。
すなわち、新しい税務上の減価償却制度では、残存価額が廃止され250%定率法が導入されることで、(これまでの会計上の)減価償却の理屈にとらわれずに、実質的に設備投資の費用を早期に回収(償却)することになる。
また、平成19年度税制改正大綱を読むだけでは、減価償却について、確定決算主義(損金経理)を放棄するものとはなっていない。法定耐用年数の見直しについても、あくまで、当該減価償却資産の使用の実態に基づくもの(技術進歩や需要構造の変化の速さに対応したもの)ということになろう。
国際競争力の強化・経済活性化の視点からさらなる減価償却制度の見直しということになれば、我が国においても、企業会計と税務会計が減価償却制度において乖離することになるが、今回の減価償却制度の見直しは、減価償却という考え方(減価償却資産の取得価額を耐用年数の期間において、一定のルールに基づいて償却(費用化)すること)を維持したうえでの見直しと意義付けることもできる。
減価償却制度という枠組みは当面維持されることが予想され、税制改正大綱に検討事項として記述されているさらなる法定耐用年数や資産区分の見直しや制度の柔軟化(法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化)が、今後の注目点である。
なお、減価償却制度の見直しは、コスト・リカバリー制度の考え方を受け入れていることから(資産課税としての性格を踏まえ)、償却資産税(固定資産税)については、現行の評価方法が維持されることになった(耐用年数については法人税の例による)。(さじ・としお)
「減価償却制度の見直し」を検証する
コスト・リカバリー制度と減価償却制度の融合
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
平成19年度税制改正の具体的内容で企業会計・税務申告の実務に最も大きな影響を与えることになるのが、「減価償却制度の見直し」である。「減価償却制度の見直し」では、①残存価額(取得価額の10%)の廃止、②償却可能限度額(取得価額の95%)の廃止、③技術進歩が著しいIT分野の3設備についての法定耐用年数の見直しが行われる。
実務的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、定率法の償却率に250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする方法)を導入する。
これらの「減価償却制度の見直し」は、米国で採用されているMACRS(コスト・リカバリー制度)の考え方を減価償却制度に反映させたものである。
Ⅰ 250%定率法とは?
代表的な減価償却方法のうち、定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法)では、残存価額(取得価額の10%)が廃止されることから、償却限度額の計算において90%を乗じることがなくなるが、償却率は(1/n、n:耐用年数)の算式で算定され、変更されない。
一方、定率法(当該減価償却資産の取得価額(期末簿価)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度として償却する方法)では、これまで、法定耐用年数経過時点において、残存する帳簿価額が残存価額(取得価額の10%)になるように、(1-
 、n:耐用年数)の算式で算定されてきた。平成19年4月1日以後に取得をする原価償却資産について新たに導入される250%定率法では、(1/n×2.5、n:耐用年数)の算式で償却率が算定される。250%定率法の償却率を適用した場合には、現行の定率法を適用した場合に比べて、いずれも償却率が高くなり、設備投資の費用を早期に回収(償却)できるようになるが、耐用年数経過時点において、残存帳簿価額が0になることはない(残存価額を0とすると、理論上定率法の償却率は算定できない)。
、n:耐用年数)の算式で算定されてきた。平成19年4月1日以後に取得をする原価償却資産について新たに導入される250%定率法では、(1/n×2.5、n:耐用年数)の算式で償却率が算定される。250%定率法の償却率を適用した場合には、現行の定率法を適用した場合に比べて、いずれも償却率が高くなり、設備投資の費用を早期に回収(償却)できるようになるが、耐用年数経過時点において、残存帳簿価額が0になることはない(残存価額を0とすると、理論上定率法の償却率は算定できない)。そのため、250%定率法では、250%定率法で計算した償却費が、法定耐用年数から経過年数を控除した期間内にその時の帳簿価額を定額法による償却(均等償却)すると仮定した償却額を下回るときに、償却方法を定額法に切り替えて減価償却費を計算する。この方法により、耐用年数経過時点において、備忘価額(1円)まで償却できることになる。
なお、減価償却資産の償却率は前頁下の表のとおり計算される。耐用年数2年では250%定率法により算定した償却率が1を超えるため、1.000として表示しているが、期中に事業の用に供した減価償却資産では、頭打ち(1.000に調整すること)を月数按分の前でするのか、後でするのかによって月数按分後の償却限度額が異なる場合も生じてくる。省令で償却率表を規定している現行の減価償却制度からすると、償却率表に1.000と記載され、1年分の償却限度額を計算したうえで(すなわち取得価額を基にして)月数按分計算が行われることになりそうだ(今号9頁参照)。
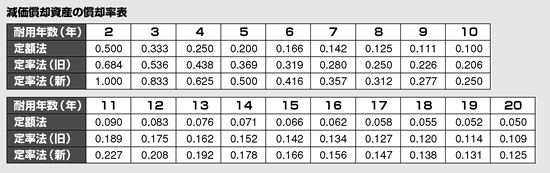
Ⅱ 法定耐用年数8年で250%定率法を適用すると
それでは具体的な例(取得価額100,000,000円、法定耐用年数8年(償却率0.312))にあてはめて250%定率法を検証してみよう。250%定率法は、定率法による償却から一定の時点で均等償却に切り替えて減価償却費を計算するところに特徴がある。実務的にはいつの時点から均等償却に切り替えることになるのかがポイントになってくる。
法定耐用年数8年(償却率0.312)の場合には、5年経過時点までは、現行の定率法と同じ計算方法で取得価額(期末簿価)に償却率(0.312)を乗じて減価償却費(償却限度額)を計算することになる(下記の表では法定耐用年数について償却率(0.312)を適用して計算している)。5年経過時点での残存簿価(154,149,526円)について、翌期以降(法定耐用年数-経過年数)で均等償却した各期償却額(51,383,175円)が6年目以降の定率法(償却率0.312)による償却額(48,094,652円)を超えることになるため、6年目より定額法に切り替え、6~8年の各期において、51,383,175円の減価償却費を計上し、耐用年数(8年)経過時点において、備忘価額(1円)を付すことになる。
期末簿価を上記の折れ線グラフで示している。5年経過時点までは一定の割合(償却率)で(スムーズな曲線で)償却していたものが6年目からは毎期一定額の償却で耐用年数経過時点において帳簿価額が備忘価額(1円)となるように、直線的な償却が行われることになる。
しかしながら、平成19年度税制改正大綱では、翌期以降(法定耐用年数-経過年数)で均等償却した各期償却額について、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて計算できるように、モデルケースを用いて、耐用年数ごとに一定の割合を定めておくこととしている(したがって、前頁の表を各法定耐用年数について作成し、均等償却への切替時点を検討する必要はない)。
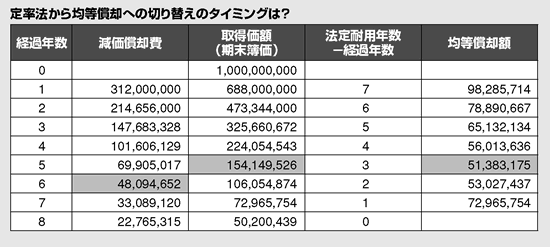
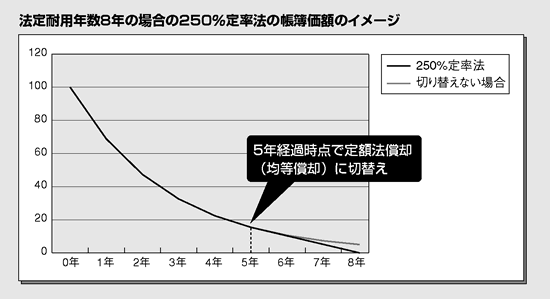
Ⅲ 既存の減価償却資産については
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、現行の償却方法・償却率を用いて償却限度額を計算することになるが、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却が進んだ資産については、翌事業年度以後5年間で均等償却することができる。
既存の減価償却資産については、設備投資の費用を早期に回収することにはならないが、減価償却資産の除却時の価値がほとんど残っていない実態に即して、取得価額の全額が償却できるように見直される。
Ⅳ 法定耐用年数の見直し
平成19年度税制改正に関する経済産業省意見では、世界における日本企業(シャープ)や韓国企業(サムスン電子など)の液晶パネルのシェアや設備投資を例にして、国際競争力を高めるための減価償却制度の見直しが要望されており、技術進歩や需要構造の変化に対応した減価償却制度の見直しが求められていた。
平成19年度税制改正大綱では、技術進歩が著しいIT分野の次の3設備について、法定耐用年数を短縮するとともに、平成20年度税制改正に向けて、減価償却資産の使用の実態等についてさらに調査・分析を進め、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討することとしている。
・フラットパネルディスプレイ製造設備
10年⇒5年に短縮
・フラットパネル用フィルム材料製造設備
10年⇒5年に短縮
・半導体用フォトレジスト製造設備
8年⇒5年に短縮
Ⅴ 新しい減価償却制度の特徴
減価償却制度の見直しでは、米国が採用しているMACRS(the Modified Accelerated Cost Recovery System)(以下「コスト・リカバリー制度」という)の考え方を部分的に反映させている。
コスト・リカバリー制度は、投資促進の観点から、資産の使用可能期間や残存価額とは関係なく、投下資金の回収期間(recovery periods)が定められる。会計と税務が乖離した(減価償却費の損金算入について確定決算主義が採用されていない)米国では、会計上の減価償却費から離れて税務上の償却額が計算されることになる。
我が国の平成19年度税制改正案は、資産の(法定)耐用年数の期間内において償却するという考え方を維持しており、全面的にコスト・リカバリー制度を導入したものとはいえないが、減価償却資産の耐用年数の期間中に定率法から定額法に切り替える減価償却方法となる250%定率法が、会計が本来予定していた減価償却方法とするには違和感もある(もちろん、我が国の減価償却の実態からすれば、税務会計の逆基準性を容認しなければならない。我が国の場合250%定率法も会計上の減価償却方法として認められることになると思われる)。
すなわち、新しい税務上の減価償却制度では、残存価額が廃止され250%定率法が導入されることで、(これまでの会計上の)減価償却の理屈にとらわれずに、実質的に設備投資の費用を早期に回収(償却)することになる。
また、平成19年度税制改正大綱を読むだけでは、減価償却について、確定決算主義(損金経理)を放棄するものとはなっていない。法定耐用年数の見直しについても、あくまで、当該減価償却資産の使用の実態に基づくもの(技術進歩や需要構造の変化の速さに対応したもの)ということになろう。
国際競争力の強化・経済活性化の視点からさらなる減価償却制度の見直しということになれば、我が国においても、企業会計と税務会計が減価償却制度において乖離することになるが、今回の減価償却制度の見直しは、減価償却という考え方(減価償却資産の取得価額を耐用年数の期間において、一定のルールに基づいて償却(費用化)すること)を維持したうえでの見直しと意義付けることもできる。
減価償却制度という枠組みは当面維持されることが予想され、税制改正大綱に検討事項として記述されているさらなる法定耐用年数や資産区分の見直しや制度の柔軟化(法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化)が、今後の注目点である。
なお、減価償却制度の見直しは、コスト・リカバリー制度の考え方を受け入れていることから(資産課税としての性格を踏まえ)、償却資産税(固定資産税)については、現行の評価方法が維持されることになった(耐用年数については法人税の例による)。(さじ・としお)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















