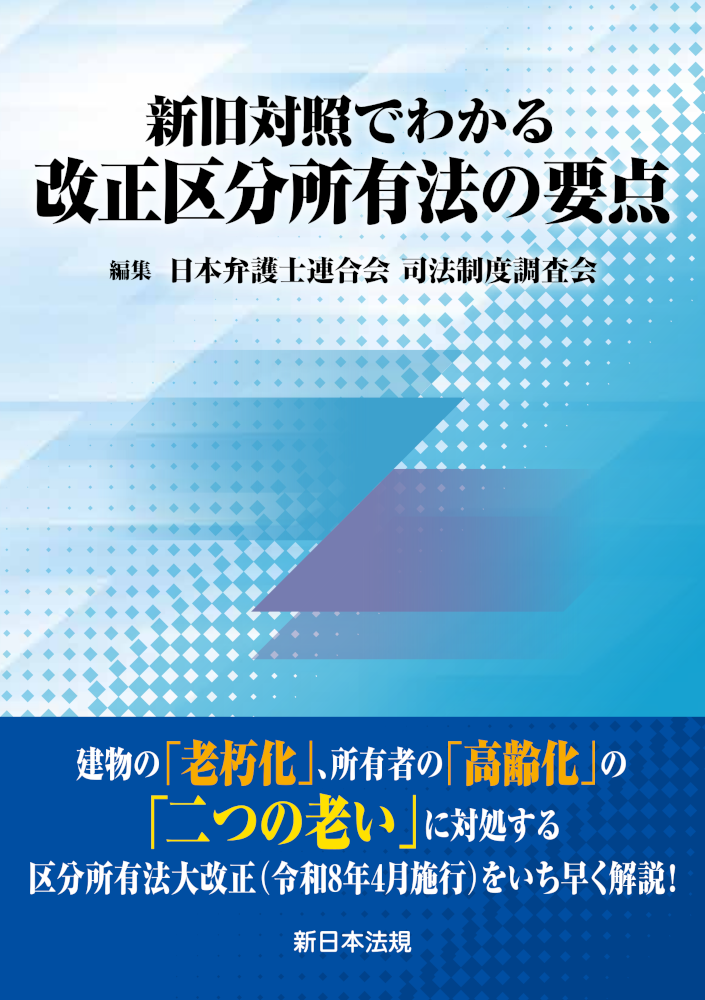解説記事2007年03月26日 【解説】 船舶リース税務訴訟でリミテッド・パートナーシップは任意組合との高裁判断(2007年3月26日号・№204)
船舶リース税務訴訟でリミテッド・パートナーシップは任意組合との高裁判断
森・濱田松本法律事務所 弁護士 増田 晋
Ⅰ はじめに
名古屋高等裁判所民事第4部(野田武明裁判長)は、平成19年3月8日、船舶リース税務訴訟の控訴審判決で、船舶賃貸事業の減価償却費等の必要経費を他の所得と通算することは適法とし、納税者の訴えを認めた名古屋地方裁判所民事第9部(加藤幸雄裁判長)平成17年12月21日判決(脚注1)を認容する判決を下した。
この控訴審判決で特筆すべきは、問題となった船舶リースのスキームの中に存在したケイマン諸島の特例リミテッド・パートナーシップ(“Exempted Limited Partnership”。以下、「ELPS」という)(脚注2)は、日本の租税法の適用上、民法の組合(民法667条。以下、「任意組合」という)として取扱われること、従って、ELPSのパートナーシップ財産(本件では船舶)の所有権はリミテッド・パートナーを含む全パートナーの共有として帰属することを明文をもって明らかにしたことである。
筆者の知る限り、本判決は、パートナーシップ形態による外国事業体の日本税法における取扱いについて初めて出された司法判断であり、又、最近国税不服審判所が幾つか下した外国パートナーシップの任意組合性を否定する裁決例(脚注3)をも否定するもので、大変に重要かつ貴重な判決である。
筆者は、本件の船舶リース税務訴訟についてアレンジャーの代理人として関与し、納税者代理人と共同して訴訟遂行をしてきた者であるが、本判決の重要性に鑑み、本事件の概要を控訴審での審理に焦点をあてて一早く読者に報告することが責務であると感じ筆をとった次第である。
Ⅱ 船舶リース事件と名古屋地裁判決
1.船舶リース事件の概要
問題となった船舶リースに出資した個人投資家に対し、国税当局が全国的に調査を進め追徴課税に踏み切ったのは、2002年のことである(脚注4)。本件船舶リースのスキームは概ね次頁の船舶リース賃貸事業の概要図のとおりであり、本件船舶リースをアレンジしたリース会社の関連会社が船を仕入れ、それを1口5000万円相当の共有持分に小口化して日本全国の個人投資家に売り、投資家はその共有持分権を日本の任意組合に出資し、同任意組合はケイマンのELPSのリミテッド・パートナーとして船を出資し、ELPSは裸傭船として船会社に船を賃貸し賃料を収受する法形式を取っていた。
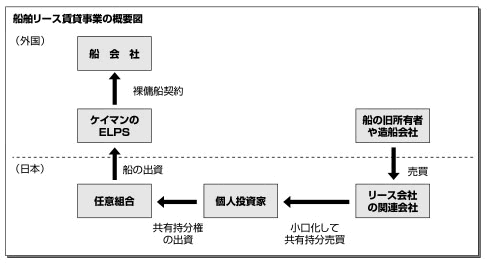
所得税法26条1項は船舶の貸付より生じる所得は不動産所得であるとし、所得税法69条1項は不動産所得より生じた損失は他の所得の金額から控除する旨定めているので、本件では原告となった組合員は組合参加時から船舶リースより生じる所得を不動産所得とし、他の所得と損益通算して所得申告をし、課税庁も当初数年間はこれに何らの異を唱えることはなかった。
しかしながら、2002年頃から課税庁は、本件の日本の組合は任意組合ではなく利益配当契約であると認定し、利益配当契約から生じた現金分配は雑所得にあたるとして、損益通算を否認して追徴課税を行った。
以下の名古屋地裁判決は、船舶リース事件の中でも最も先行した事件について出された判決であり、それ以外にも岐阜地方裁判所と名古屋地方裁判所で同種の案件が係属している。
なお、名古屋地裁での審理は日本の組合が任意組合であるか否か(より正確には、原告らが記名押印した組合参加契約が任意組合契約か否か)が争点となり、本件のELPSが日本の租税法上どのように扱われるかや、ELPSよりの損益や分配金の法的性質は一切争点とならなかった。その理由は課税庁が訴訟において、本件任意組合が本件ELPSより受ける損益の分配が不動産所得であることを認めたためである(脚注5)。
2.名古屋地裁判決の概要
(1)名古屋地裁判決は、基本的には船舶リース事件に先行した航空機リース事件の判決を踏襲するものである。従って、字数の関係上、詳細は筆者がこれまで公表している論文等に譲ることとするが(脚注6)、ここでも課税庁はいわゆる「事実認定による否認」を争点としたので、以下にポイントとなる点のみ簡単にまとめておく。
(2)名古屋地裁での主要な争点は、原告ら組合員が組合参加契約書に署名し、明らかに任意組合という法形式で船舶賃貸事業を行う旨選択しているところ、課税庁が「当事者の真意の探求」をして、他の契約類型(本件では利益配当契約)に引き直すことは許されるか、許されるとしてその限界は何か、という「事実認定による否認」の適用基準を示した点である。
名古屋地裁判決は、契約書が存在するにもかかわらず、文理解釈の原則又は処分証書の法理の適用されない場合の判断基準として、「当該契約類型や契約内容自体に着目し、それが当事者が達成しようとした法的・経済的目的を達成する上で、社会通念上著しく複雑、迂遠なものであって、到底その合理性を肯認できないものであるか否かの客観的な見地から判断」するとの基準を示し、そうではない場合(通常用いられることのない契約類型ではない場合)は、契約書に「使用された文言に則した文理解釈を中心として行うのが相当」、そうである場合(通常用いられることのない契約類型の場合)は、契約書等の外型的資料から離れた真意の認定が許されるとした。
加えて、租税回避目的との関係で、「このことは、動機、意図などの主観的事情によって、通常は用いられることのない契約類型であるか否かを判断することを相当とするものではなく、まして、税負担を伴わないあるいは税負担が軽減されること(本件各組合参加契約がこのような場合に該当するかについては、後に検討するとおりである。)を根拠に、直ちに通常は用いられることのない契約類型と判断した上、税負担を伴うあるいは税負担が重い契約類型こそが当事者の真意であると認定することを許すものでもない。なぜなら、現代社会における合理的経済人にとって、税負担を考慮することなく法的手段、形式を選択することこそ経済原則に反するものであり、何らかの意味で税負担を考慮するのがむしろ通常であると考えられるから、このような検討結果を経て選択した契約類型が真意に反するものと認定されるのであれば、それは事実認定の名の下に、法的根拠のない法律行為の否認を行うのと異ならないとの非難を免れ難いというべきである。」と判示し、航空機リースと同様の基準を示している。
(3)名古屋地裁判決は、その上で本件船舶リースの各契約や事実関係を検討し、詳細な事実認定を行い、本件船舶リースには経済合理性があり、用いられた任意組合という法形式も合理性があるので、「本件各組合参加契約等の内容を検討するに当たっては、使用された文言に即した文理解釈を中心として行うのが相当」とした。民法677条1項に定める任意組合の成立要件は、①複数の当事者が出資の合意をし、②各当事者が共同事業を営むことを合意したことであり、②の共同事業については、民法は業務執行者を選任して業務を委任する方式の任意組合を明文をもって認めているため(民法670条2項)、組合員は検査権と業務執行者の解任権さえ有せば②の要件は充足されるとするのが判例・通説である。本件では、組合参加契約は以上の要件を満たすものと認定された。
なお、課税庁の主張についても周到に検討した結果、そのほとんどは「動機等の主観的要素と効果意思とを混同し、本件各組合(参加)契約は、課税減少効果を目的とする契約であるとして、当事者の認識等をその動機等や経済的側面のみに着目してこれを理解し、動機等とは別の効果意思の検討を放棄するもの」といわざるを得ないとして一蹴している(脚注7)。
以上が、船舶リース事件の一審である名古屋地裁判決の概要である。
Ⅲ 控訴審の争点と名古屋高裁判決
課税庁は、原審が航空機リース事件に続き「事実認定による否認」の手法を排斥したため、控訴審では新たにELPSの日本の租税法上の取扱いを争点に加え、ELPSは任意組合ではなく、パートナーシップ財産はゼネラル・パートナー単独の所有となるので、原告ら組合員は減価償却費等を必要経費として使えないと主張した。名古屋高裁判決は、この争点を中心に十分に主張・立証がつくされた上で出された、初めての司法判断といえる。
1.ELPSの法的性質
組合員のこの点に関する主張は、本件ELPSは日本の租税法上任意組合として扱われるから、減価償却費等の必要経費はリミテッド・パートナーたる本件任意組合に直接帰属し、結局本件では任意組合が二層に成立していることになるので必要経費は各組合員に帰属するというものであった。課税庁はまずこれを争ったが(脚注8)、名古屋高裁は以下のとおりの判断を下している。
「以上によれば、ケイマンにおける特例リミテッド・パートナーシップを含むパートナーシップは、法人格を有せず、構成員間の契約関係という性質を有するものと認められる。そして、「共同で事業を行う人々の間に存在する関係」とは、①2人以上の当事者の間の、②各当事者が共同事業を営むことの合意を意味するものと解されるところ、我が国の民法の解釈としても、内部的に出資額以上の損失を負担しない当事者がいたとしても、組合契約の成立を妨げるものでないことは前記のとおりであるから、結局、ケイマン法に基づいて成立された特例リミテッド・パートナーシップである本件各パートナーシップは、我が国の民法における組合の要件を満たし得るものというべきである。」
2.パートナーシップ財産の帰属
次に、課税庁は、ケイマン法によればパートナーシップ財産はELPSのゼネラル・パートナーに帰属し、リミテッド・パートナーは本件船舶の共有持分権を有していないと主張し、ケイマン法の解釈が争点となったが、名古屋高裁は以下のとおりの判断を下している。
「これらの規定によれば(脚注9)、パートナーに属するリミテッド・パートナーも、ゼネラル・パートナーと同様、パートナーシップ財産を保有する主体であることが明示されているから、上記特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項のゼネラル・パートナーが「委託を受けて保有し、または保有する」というのは「受託して管理している」との趣旨であると解すべきである。したがって、本件各組合が本件各船舶を出資してリミテッド・パートナーシップを成立させたからといって、それによって、ゼネラル・パートナーが当然に本件各船舶の所有権を取得するものとはいえない。」
Ⅳ まとめ
名古屋高裁判決は、パートナーシップ形態による外国事業体の日本税法における取扱いについて初めて出された司法判断であり、これまでのELPSをめぐる投資実務を法的に確認するものとして、また、課税庁の独自の見解によって損なわれてきた法的予見可能性を回復するものとして、大変に意義のある判決といえる。
本判決では、この他にも、映画フィルムリースに関するパラツィーナ事件最高裁判決や外国税額控除制度の濫用に関する最高裁判決と本件の関係(射程)、及び、便宜置籍と船舶の所有権の関係なども判断されているが、別稿に譲ることとする。(ますだ・すすむ)
脚注
1 同判決の全文は、http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=7449&hanreiKbn=04に掲載されている。
2 日本の投資家が関与する国際的投資活動では、長年ELPSが投資ヴィークルとして多用されている。その状況や理由等については、石綿学「外国籍プライベート・エクイティー・ファンドの課税問題」(『ビジネス・タックス』有斐閣)484頁など参照。
3 例えば、米国の州リミテッド・パートナーシップに関して出された平成18年2月2日東京国税不服審判所裁判(本誌176号参照)などは、明確な判断は避けているがこの範疇に入るものと考えられ、又、刊行物未登載の裁決例もある。
4 大々的に新聞報道されたのは、2004年4月26日の朝日新聞や読売新聞の夕刊においてである。
5 課税庁がかかる訴訟対応を取った理由は推測するしかないが、本件では、1995年頃の組成当時アレンジャーが国税当局になした照会に対し国税当局がその旨を認めていた事実があり、又、国税当局としても訴訟で正面からリミテッド・パートナーシップの法的性質を争点とすることを避けたいとの意向が働いたものと思われる。
6 航空機リース事件は、名古屋高裁が平成17年10月27日に出した判決に対し、国が上告を断念して決着している(Lexis判例速報06年5月号92頁以下)。その原審は名古屋地判平成16年10月28日(判例タイムズ1204号224頁以下)。なお、航空機リース事件については、拙稿の「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断-航空機リース事件を素材として-」(「税理」2006年3月号)及び「航空機リースと租税回避行為」(『ビジネス・タックス』373頁以下、有斐閣)に詳しい検討をしている。
7 この引用は、航空機リース事件の名古屋高裁判決の判旨の一部である。
8 この点について課税庁はいろいろ主張しているが、それをまとめると「(ELPSは)日本法上の概念に照らしてみても、明らかに任意組合として取り扱われるというものではなく、むしろ匿名組合に近い性質を有している」というものである。しかしながら、課税庁はELPSが匿名組合だと断定はせず、最後まで何であるかを主張せず、又、ELPSが任意組合でないとして、そこからの所得や分配が何故雑所得となるのかも明らかにしていない。
9 これらの規定とは、ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項とパートナーシップ法21条1項本文であり、その和訳は以下のとおりである。
ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項(1991年改正法も同じ。):
「特例リミテッド・パートナーシップの財産で、1名または複数名のゼネラル・パートナーに譲渡され、帰属し、もしくはゼネラル・パートナーのために保有されているもの、または特例リミテッド・パートナーシップに譲渡され、もしくは同パートナーシップの名義に移転されたものは、ゼネラル・パートナーが、複数名の場合は共同して、パートナーシップ契約の定めに従って、特例リミテッド・パートナーシップの財産として、委託を受けて保有し、または保有するものとみなされる。」
特例リミテッド・パートナーシップ法によって準用されるパートナーシップ法21条1項本文:
「当初からパートナーシップの資本に持ち込まれ、または、購入されるなどして取得された、当該団体のためまたはパートナーシップの事業運営のための、すべての資産、権利および利益は、本法においてパートナーシップ財産といい、パートナーは、パートナーシップ運営のためにのみ、かつ、パートナーシップ契約に基づいてこれを保有および使用するものとする。」
増田 晋(ますだすすむ)
弁護士(日本及びカリフォルニア州)
森・濱田松本法律事務所パートナー、大宮法科大学院教授・慶応義塾大学法科大学院講師。
東京大学法学部卒業、University of Washington School of Law(LL.M)卒業。
【主な著書・論文】
「可動物件の国際的権益に関する条約および航空機議定書の概要と仮訳」(国際商事法務)、『ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務』(共著、有斐閣)、「「組合事業に関する租税回避防止」立法の問題点」本誌105号、「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)、「映画フィルムリースと航空機リースの違い」本誌167号他。
森・濱田松本法律事務所 弁護士 増田 晋
Ⅰ はじめに
名古屋高等裁判所民事第4部(野田武明裁判長)は、平成19年3月8日、船舶リース税務訴訟の控訴審判決で、船舶賃貸事業の減価償却費等の必要経費を他の所得と通算することは適法とし、納税者の訴えを認めた名古屋地方裁判所民事第9部(加藤幸雄裁判長)平成17年12月21日判決(脚注1)を認容する判決を下した。
この控訴審判決で特筆すべきは、問題となった船舶リースのスキームの中に存在したケイマン諸島の特例リミテッド・パートナーシップ(“Exempted Limited Partnership”。以下、「ELPS」という)(脚注2)は、日本の租税法の適用上、民法の組合(民法667条。以下、「任意組合」という)として取扱われること、従って、ELPSのパートナーシップ財産(本件では船舶)の所有権はリミテッド・パートナーを含む全パートナーの共有として帰属することを明文をもって明らかにしたことである。
筆者の知る限り、本判決は、パートナーシップ形態による外国事業体の日本税法における取扱いについて初めて出された司法判断であり、又、最近国税不服審判所が幾つか下した外国パートナーシップの任意組合性を否定する裁決例(脚注3)をも否定するもので、大変に重要かつ貴重な判決である。
筆者は、本件の船舶リース税務訴訟についてアレンジャーの代理人として関与し、納税者代理人と共同して訴訟遂行をしてきた者であるが、本判決の重要性に鑑み、本事件の概要を控訴審での審理に焦点をあてて一早く読者に報告することが責務であると感じ筆をとった次第である。
Ⅱ 船舶リース事件と名古屋地裁判決
1.船舶リース事件の概要
問題となった船舶リースに出資した個人投資家に対し、国税当局が全国的に調査を進め追徴課税に踏み切ったのは、2002年のことである(脚注4)。本件船舶リースのスキームは概ね次頁の船舶リース賃貸事業の概要図のとおりであり、本件船舶リースをアレンジしたリース会社の関連会社が船を仕入れ、それを1口5000万円相当の共有持分に小口化して日本全国の個人投資家に売り、投資家はその共有持分権を日本の任意組合に出資し、同任意組合はケイマンのELPSのリミテッド・パートナーとして船を出資し、ELPSは裸傭船として船会社に船を賃貸し賃料を収受する法形式を取っていた。
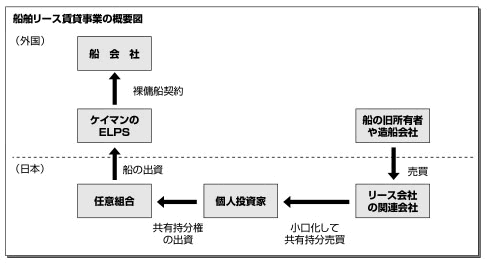
所得税法26条1項は船舶の貸付より生じる所得は不動産所得であるとし、所得税法69条1項は不動産所得より生じた損失は他の所得の金額から控除する旨定めているので、本件では原告となった組合員は組合参加時から船舶リースより生じる所得を不動産所得とし、他の所得と損益通算して所得申告をし、課税庁も当初数年間はこれに何らの異を唱えることはなかった。
しかしながら、2002年頃から課税庁は、本件の日本の組合は任意組合ではなく利益配当契約であると認定し、利益配当契約から生じた現金分配は雑所得にあたるとして、損益通算を否認して追徴課税を行った。
以下の名古屋地裁判決は、船舶リース事件の中でも最も先行した事件について出された判決であり、それ以外にも岐阜地方裁判所と名古屋地方裁判所で同種の案件が係属している。
なお、名古屋地裁での審理は日本の組合が任意組合であるか否か(より正確には、原告らが記名押印した組合参加契約が任意組合契約か否か)が争点となり、本件のELPSが日本の租税法上どのように扱われるかや、ELPSよりの損益や分配金の法的性質は一切争点とならなかった。その理由は課税庁が訴訟において、本件任意組合が本件ELPSより受ける損益の分配が不動産所得であることを認めたためである(脚注5)。
2.名古屋地裁判決の概要
(1)名古屋地裁判決は、基本的には船舶リース事件に先行した航空機リース事件の判決を踏襲するものである。従って、字数の関係上、詳細は筆者がこれまで公表している論文等に譲ることとするが(脚注6)、ここでも課税庁はいわゆる「事実認定による否認」を争点としたので、以下にポイントとなる点のみ簡単にまとめておく。
(2)名古屋地裁での主要な争点は、原告ら組合員が組合参加契約書に署名し、明らかに任意組合という法形式で船舶賃貸事業を行う旨選択しているところ、課税庁が「当事者の真意の探求」をして、他の契約類型(本件では利益配当契約)に引き直すことは許されるか、許されるとしてその限界は何か、という「事実認定による否認」の適用基準を示した点である。
名古屋地裁判決は、契約書が存在するにもかかわらず、文理解釈の原則又は処分証書の法理の適用されない場合の判断基準として、「当該契約類型や契約内容自体に着目し、それが当事者が達成しようとした法的・経済的目的を達成する上で、社会通念上著しく複雑、迂遠なものであって、到底その合理性を肯認できないものであるか否かの客観的な見地から判断」するとの基準を示し、そうではない場合(通常用いられることのない契約類型ではない場合)は、契約書に「使用された文言に則した文理解釈を中心として行うのが相当」、そうである場合(通常用いられることのない契約類型の場合)は、契約書等の外型的資料から離れた真意の認定が許されるとした。
加えて、租税回避目的との関係で、「このことは、動機、意図などの主観的事情によって、通常は用いられることのない契約類型であるか否かを判断することを相当とするものではなく、まして、税負担を伴わないあるいは税負担が軽減されること(本件各組合参加契約がこのような場合に該当するかについては、後に検討するとおりである。)を根拠に、直ちに通常は用いられることのない契約類型と判断した上、税負担を伴うあるいは税負担が重い契約類型こそが当事者の真意であると認定することを許すものでもない。なぜなら、現代社会における合理的経済人にとって、税負担を考慮することなく法的手段、形式を選択することこそ経済原則に反するものであり、何らかの意味で税負担を考慮するのがむしろ通常であると考えられるから、このような検討結果を経て選択した契約類型が真意に反するものと認定されるのであれば、それは事実認定の名の下に、法的根拠のない法律行為の否認を行うのと異ならないとの非難を免れ難いというべきである。」と判示し、航空機リースと同様の基準を示している。
(3)名古屋地裁判決は、その上で本件船舶リースの各契約や事実関係を検討し、詳細な事実認定を行い、本件船舶リースには経済合理性があり、用いられた任意組合という法形式も合理性があるので、「本件各組合参加契約等の内容を検討するに当たっては、使用された文言に即した文理解釈を中心として行うのが相当」とした。民法677条1項に定める任意組合の成立要件は、①複数の当事者が出資の合意をし、②各当事者が共同事業を営むことを合意したことであり、②の共同事業については、民法は業務執行者を選任して業務を委任する方式の任意組合を明文をもって認めているため(民法670条2項)、組合員は検査権と業務執行者の解任権さえ有せば②の要件は充足されるとするのが判例・通説である。本件では、組合参加契約は以上の要件を満たすものと認定された。
なお、課税庁の主張についても周到に検討した結果、そのほとんどは「動機等の主観的要素と効果意思とを混同し、本件各組合(参加)契約は、課税減少効果を目的とする契約であるとして、当事者の認識等をその動機等や経済的側面のみに着目してこれを理解し、動機等とは別の効果意思の検討を放棄するもの」といわざるを得ないとして一蹴している(脚注7)。
以上が、船舶リース事件の一審である名古屋地裁判決の概要である。
Ⅲ 控訴審の争点と名古屋高裁判決
課税庁は、原審が航空機リース事件に続き「事実認定による否認」の手法を排斥したため、控訴審では新たにELPSの日本の租税法上の取扱いを争点に加え、ELPSは任意組合ではなく、パートナーシップ財産はゼネラル・パートナー単独の所有となるので、原告ら組合員は減価償却費等を必要経費として使えないと主張した。名古屋高裁判決は、この争点を中心に十分に主張・立証がつくされた上で出された、初めての司法判断といえる。
1.ELPSの法的性質
組合員のこの点に関する主張は、本件ELPSは日本の租税法上任意組合として扱われるから、減価償却費等の必要経費はリミテッド・パートナーたる本件任意組合に直接帰属し、結局本件では任意組合が二層に成立していることになるので必要経費は各組合員に帰属するというものであった。課税庁はまずこれを争ったが(脚注8)、名古屋高裁は以下のとおりの判断を下している。
「以上によれば、ケイマンにおける特例リミテッド・パートナーシップを含むパートナーシップは、法人格を有せず、構成員間の契約関係という性質を有するものと認められる。そして、「共同で事業を行う人々の間に存在する関係」とは、①2人以上の当事者の間の、②各当事者が共同事業を営むことの合意を意味するものと解されるところ、我が国の民法の解釈としても、内部的に出資額以上の損失を負担しない当事者がいたとしても、組合契約の成立を妨げるものでないことは前記のとおりであるから、結局、ケイマン法に基づいて成立された特例リミテッド・パートナーシップである本件各パートナーシップは、我が国の民法における組合の要件を満たし得るものというべきである。」
2.パートナーシップ財産の帰属
次に、課税庁は、ケイマン法によればパートナーシップ財産はELPSのゼネラル・パートナーに帰属し、リミテッド・パートナーは本件船舶の共有持分権を有していないと主張し、ケイマン法の解釈が争点となったが、名古屋高裁は以下のとおりの判断を下している。
「これらの規定によれば(脚注9)、パートナーに属するリミテッド・パートナーも、ゼネラル・パートナーと同様、パートナーシップ財産を保有する主体であることが明示されているから、上記特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項のゼネラル・パートナーが「委託を受けて保有し、または保有する」というのは「受託して管理している」との趣旨であると解すべきである。したがって、本件各組合が本件各船舶を出資してリミテッド・パートナーシップを成立させたからといって、それによって、ゼネラル・パートナーが当然に本件各船舶の所有権を取得するものとはいえない。」
Ⅳ まとめ
名古屋高裁判決は、パートナーシップ形態による外国事業体の日本税法における取扱いについて初めて出された司法判断であり、これまでのELPSをめぐる投資実務を法的に確認するものとして、また、課税庁の独自の見解によって損なわれてきた法的予見可能性を回復するものとして、大変に意義のある判決といえる。
本判決では、この他にも、映画フィルムリースに関するパラツィーナ事件最高裁判決や外国税額控除制度の濫用に関する最高裁判決と本件の関係(射程)、及び、便宜置籍と船舶の所有権の関係なども判断されているが、別稿に譲ることとする。(ますだ・すすむ)
脚注
1 同判決の全文は、http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=7449&hanreiKbn=04に掲載されている。
2 日本の投資家が関与する国際的投資活動では、長年ELPSが投資ヴィークルとして多用されている。その状況や理由等については、石綿学「外国籍プライベート・エクイティー・ファンドの課税問題」(『ビジネス・タックス』有斐閣)484頁など参照。
3 例えば、米国の州リミテッド・パートナーシップに関して出された平成18年2月2日東京国税不服審判所裁判(本誌176号参照)などは、明確な判断は避けているがこの範疇に入るものと考えられ、又、刊行物未登載の裁決例もある。
4 大々的に新聞報道されたのは、2004年4月26日の朝日新聞や読売新聞の夕刊においてである。
5 課税庁がかかる訴訟対応を取った理由は推測するしかないが、本件では、1995年頃の組成当時アレンジャーが国税当局になした照会に対し国税当局がその旨を認めていた事実があり、又、国税当局としても訴訟で正面からリミテッド・パートナーシップの法的性質を争点とすることを避けたいとの意向が働いたものと思われる。
6 航空機リース事件は、名古屋高裁が平成17年10月27日に出した判決に対し、国が上告を断念して決着している(Lexis判例速報06年5月号92頁以下)。その原審は名古屋地判平成16年10月28日(判例タイムズ1204号224頁以下)。なお、航空機リース事件については、拙稿の「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断-航空機リース事件を素材として-」(「税理」2006年3月号)及び「航空機リースと租税回避行為」(『ビジネス・タックス』373頁以下、有斐閣)に詳しい検討をしている。
7 この引用は、航空機リース事件の名古屋高裁判決の判旨の一部である。
8 この点について課税庁はいろいろ主張しているが、それをまとめると「(ELPSは)日本法上の概念に照らしてみても、明らかに任意組合として取り扱われるというものではなく、むしろ匿名組合に近い性質を有している」というものである。しかしながら、課税庁はELPSが匿名組合だと断定はせず、最後まで何であるかを主張せず、又、ELPSが任意組合でないとして、そこからの所得や分配が何故雑所得となるのかも明らかにしていない。
9 これらの規定とは、ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項とパートナーシップ法21条1項本文であり、その和訳は以下のとおりである。
ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項(1991年改正法も同じ。):
「特例リミテッド・パートナーシップの財産で、1名または複数名のゼネラル・パートナーに譲渡され、帰属し、もしくはゼネラル・パートナーのために保有されているもの、または特例リミテッド・パートナーシップに譲渡され、もしくは同パートナーシップの名義に移転されたものは、ゼネラル・パートナーが、複数名の場合は共同して、パートナーシップ契約の定めに従って、特例リミテッド・パートナーシップの財産として、委託を受けて保有し、または保有するものとみなされる。」
特例リミテッド・パートナーシップ法によって準用されるパートナーシップ法21条1項本文:
「当初からパートナーシップの資本に持ち込まれ、または、購入されるなどして取得された、当該団体のためまたはパートナーシップの事業運営のための、すべての資産、権利および利益は、本法においてパートナーシップ財産といい、パートナーは、パートナーシップ運営のためにのみ、かつ、パートナーシップ契約に基づいてこれを保有および使用するものとする。」
増田 晋(ますだすすむ)
弁護士(日本及びカリフォルニア州)
森・濱田松本法律事務所パートナー、大宮法科大学院教授・慶応義塾大学法科大学院講師。
東京大学法学部卒業、University of Washington School of Law(LL.M)卒業。
【主な著書・論文】
「可動物件の国際的権益に関する条約および航空機議定書の概要と仮訳」(国際商事法務)、『ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務』(共著、有斐閣)、「「組合事業に関する租税回避防止」立法の問題点」本誌105号、「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)、「映画フィルムリースと航空機リースの違い」本誌167号他。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.