税務ニュース2004年05月17日 平和事件、最高裁で納税者側の上告を棄却(2004年5月17日号・№066) 過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」だけが争点に
平和事件、最高裁で納税者側の上告を棄却
過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」だけが争点に
最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、平成16年4月20日、同族会社に対する「無利息貸付に係る行為計算の否認」と過少申告加算税に係る「正当な理由」を争点としたいわゆる「平和事件」について、納税者側の上告を棄却し、同じく納税者側の上告受理申立てに対して不受理の決定を行った(平成11年(行ツ)第211号、平成11年(行ヒ)第168号)。国側の上告受理の申立てについては、上告審として受理することを決定した(平成11年(行ヒ)第169号)。
事件の概要
上告(申立)人Xは、遊技用パチンコ機器製造等を事業目的とするH社の代表取締役であり、有価証券の保管・運用等を事業目的としたN社の取締役を兼ねていた。XはH社の発行済み株式の73.5%及びN社の出資金の98%の出資持分を有していた。
Xは、平成元年3月10日、H社の株式3,000万株をN証券等を介してN社に総額3,450億円で譲渡した。N社の買取資金については、XがT銀行等から合計3,455億円余を年利3.375%で借入れ、N社に対して無期限・無利息・無担保で貸し付けたものである。Xは譲渡代金でもって、T銀行等に返済した。
これに対してY税務署長は、平成4年6月、X⇒N社の無利息貸付に対し所得税法157条の規定を適用し、この貸付によってXに利息収入が生じたものと認定して、平成元年分所得税について、雑所得の額141億円余とする更正処分及び過少申告加算税賦課決定を行った。平成2年分及び平成3年分についても同様の更正処分等が行われた。
これら各処分の取消し等を求めて、Xは前進手続を経て訴訟を提起した。1審(東京地裁平成7年(行ウ)第27号)は、請求を棄却した。控訴審(東京地裁平成9年(行コ)第70号)は、所法157条の適用を認めた上で、第1審の認定した利率について修正した。また、国税局勤務者が官職名を付して記載した解説書から、「正当な理由」があるとして、過少申告加算税賦課決定を取り消した。
納税者の上告棄却で本税部分は決着
「平和事件」については、納税者が上告及び上告受理の申立、国が上告受理の申立を行っていた。
納税者は、民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があるとして上告し、併せて、民事訴訟法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」・「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件」に該当するなどとの主張から上告受理の申立てを行っていた。
納税者の上告理由では、①所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)適用についての理由不備、②最高裁判例との相違についての理由不備、③適用すべき利率についての理由不備、④所得税法64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)1項不適用についての理由不備)を指摘していたが、最高裁は、「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条(上告の理由)1項又は2項に規定する事由に該当しない。」として斥けた。
納税者の上告受理の申立てでは、所得税法157条を適用した誤りなどを指摘しているが、最高裁は、「本件は、民訴法318条(上告受理の申立て)1項により受理すべきものとは認められない。」として斥けた。
国側の上告受理の申立ては、控訴審が過少申告加算税賦課決定処分を取り消した部分への不服であることから、「所得税法157条の適用」・「貸付金利子の認定における適正利率」など、課税所得・本税に関する部分は、控訴審の判決どおりに確定した。
国側は、「解説書の記載」が「正当な理由」とされることに危機感
国側の上告受理の申立ては、「本件は、民訴法318条1項の事件に当たる。」と判断され、上告審として受理された。
国側の上告受理申立ては、原判決が、国税当局に勤務している者が関与した著作物(「解説書」)の記載をもって、「税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解することは無理からぬところである。」と判示していることを原判決の誤りとして指摘している。また、その重要性を、「納税者の税務関係者が、本件解説書のような著作物に記載された解説を国税当局の見解と考えて過少申告に至れば、不注意によりその解説の趣旨を十分に理解していなかったとしても正当な理由があるということになりかねない。このような判断が一般化すれば、今後の課税実務に甚大な影響を与えるから、本件は通則法65条4項(「正当な理由」)の解釈適用に関する重要な事項を含んでいる。」としている。
ストック・オプション訴訟においても、平和事件と同様に、「解説書の記載」が争点の一つとなっており、また、下級審判決においては、従来の裁判例から見ても「正当な理由」に積極的な判断が見られている。課税当局の問題意識に対して最高裁が過少申告加算税を賦課しない「正当な理由」をどのように判断するかは、課税実務に大きな影響を及ぼすことになるだろう。
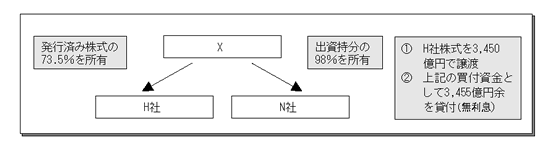
過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」だけが争点に
最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、平成16年4月20日、同族会社に対する「無利息貸付に係る行為計算の否認」と過少申告加算税に係る「正当な理由」を争点としたいわゆる「平和事件」について、納税者側の上告を棄却し、同じく納税者側の上告受理申立てに対して不受理の決定を行った(平成11年(行ツ)第211号、平成11年(行ヒ)第168号)。国側の上告受理の申立てについては、上告審として受理することを決定した(平成11年(行ヒ)第169号)。
事件の概要
上告(申立)人Xは、遊技用パチンコ機器製造等を事業目的とするH社の代表取締役であり、有価証券の保管・運用等を事業目的としたN社の取締役を兼ねていた。XはH社の発行済み株式の73.5%及びN社の出資金の98%の出資持分を有していた。
Xは、平成元年3月10日、H社の株式3,000万株をN証券等を介してN社に総額3,450億円で譲渡した。N社の買取資金については、XがT銀行等から合計3,455億円余を年利3.375%で借入れ、N社に対して無期限・無利息・無担保で貸し付けたものである。Xは譲渡代金でもって、T銀行等に返済した。
これに対してY税務署長は、平成4年6月、X⇒N社の無利息貸付に対し所得税法157条の規定を適用し、この貸付によってXに利息収入が生じたものと認定して、平成元年分所得税について、雑所得の額141億円余とする更正処分及び過少申告加算税賦課決定を行った。平成2年分及び平成3年分についても同様の更正処分等が行われた。
これら各処分の取消し等を求めて、Xは前進手続を経て訴訟を提起した。1審(東京地裁平成7年(行ウ)第27号)は、請求を棄却した。控訴審(東京地裁平成9年(行コ)第70号)は、所法157条の適用を認めた上で、第1審の認定した利率について修正した。また、国税局勤務者が官職名を付して記載した解説書から、「正当な理由」があるとして、過少申告加算税賦課決定を取り消した。
納税者の上告棄却で本税部分は決着
「平和事件」については、納税者が上告及び上告受理の申立、国が上告受理の申立を行っていた。
納税者は、民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があるとして上告し、併せて、民事訴訟法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」・「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件」に該当するなどとの主張から上告受理の申立てを行っていた。
納税者の上告理由では、①所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)適用についての理由不備、②最高裁判例との相違についての理由不備、③適用すべき利率についての理由不備、④所得税法64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)1項不適用についての理由不備)を指摘していたが、最高裁は、「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条(上告の理由)1項又は2項に規定する事由に該当しない。」として斥けた。
納税者の上告受理の申立てでは、所得税法157条を適用した誤りなどを指摘しているが、最高裁は、「本件は、民訴法318条(上告受理の申立て)1項により受理すべきものとは認められない。」として斥けた。
国側の上告受理の申立ては、控訴審が過少申告加算税賦課決定処分を取り消した部分への不服であることから、「所得税法157条の適用」・「貸付金利子の認定における適正利率」など、課税所得・本税に関する部分は、控訴審の判決どおりに確定した。
国側は、「解説書の記載」が「正当な理由」とされることに危機感
国側の上告受理の申立ては、「本件は、民訴法318条1項の事件に当たる。」と判断され、上告審として受理された。
国側の上告受理申立ては、原判決が、国税当局に勤務している者が関与した著作物(「解説書」)の記載をもって、「税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解することは無理からぬところである。」と判示していることを原判決の誤りとして指摘している。また、その重要性を、「納税者の税務関係者が、本件解説書のような著作物に記載された解説を国税当局の見解と考えて過少申告に至れば、不注意によりその解説の趣旨を十分に理解していなかったとしても正当な理由があるということになりかねない。このような判断が一般化すれば、今後の課税実務に甚大な影響を与えるから、本件は通則法65条4項(「正当な理由」)の解釈適用に関する重要な事項を含んでいる。」としている。
ストック・オプション訴訟においても、平和事件と同様に、「解説書の記載」が争点の一つとなっており、また、下級審判決においては、従来の裁判例から見ても「正当な理由」に積極的な判断が見られている。課税当局の問題意識に対して最高裁が過少申告加算税を賦課しない「正当な理由」をどのように判断するかは、課税実務に大きな影響を及ぼすことになるだろう。
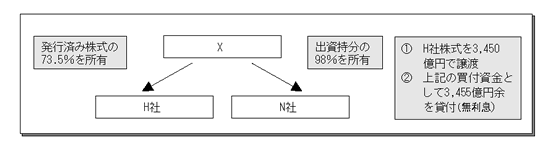
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















