解説記事2007年09月10日 【ニュース特集】 平成20年度における各省庁の税制改正要望は?(2007年9月10日号・№226)
キーワードは環境対策
平成20年度における各省庁の税制改正要望は?
先週号(本誌225号4頁参照)では経済産業省の平成20年度税制改正要望についてお伝えしたが、その他の各省庁の税制改正要望も出揃っている。当初、予定されていた消費税率の見直しを含む税制改正の抜本改革先送りが決定的となった今、注目すべき大きな税制改正は少ない印象だ。
しかし、例年とは違い、平成20年度税制改正要望では、キーワードの1つとして、“環境対策”が浮かんでくる。環境省だけでなく、国土交通省でも省エネ対策税制等を盛り込んでおり注目すべき点といえよう。また、昨年に引き続き議論となりそうなのが証券税制の特例の延長の可否だ。金融庁が要望しているが、自民党と公明党との意見が食い違うなか、参議院では民主党が第1党というねじれ現象も生じている。このため、現時点で平成20年度税制改正がどのようになるか予想もつかない状況だが、今回の特集では、経済産業省以外の省庁の主な税制改正要望事項を紹介する。
譲渡所得は当分の間、配当所得は恒久化を求める~金融庁
金融庁の平成20年度税制改正要望の目玉は、平成19年度税制改正で1年間延長が行われた証券税制の特例の延長だ。
具体的には、上場株式等の譲渡所得に係る優遇税率(10%)については、平成20年12月末で期限切れとなるが、当分の間、優遇税率の継続を求めている。また、上場株式等の配当所得の優遇税率(10%)も平成21年3月末で期限切れとなるが、長期・安定的な投資の促進、法人税と所得税との二重課税調整の必要性の観点から恒久化することを求めている。
民主党のマニフェストを意識? 証券税制の特例に関しては、平成19年度税制改正でも最後まで自民党と公明党との間で論点となった項目だ。最終的には「適用期限を1年延長して、廃止する。」との文言を税制改正大綱に明記することにより決着したものの、平成20年度税制改正でも議論が再燃することが予想されていた(本誌192号参照)。
しかし、今回の税制改正では、自民党と公明党との調整だけでなく、参議院第1党の民主党との調整も必要になる。
民主党では、先の参議院選挙のマニフェストにおいて、「資産性所得に対する課税標準の適正化を図りつつ、株式の長期保有に対する一定の配慮によって「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、健全な市場の発展に努めます。」と明記している。このため、金融庁の税制改正要望でも民主党のマニフェストを多少なりとも意識したものとなっているといえよう。
損益通算の拡大も求める 加えて、金融商品間の損益通算の拡大についても継続して求めている(図1参照)。上場株式等の譲渡所得と配当所得との間の損益通算を認めるほか、預金・債券等の利子所得および先物取引に係る雑所得についても、その対象範囲とすることを求めている。損益通算にあたっては、特定口座を最大限活用することも明記している。
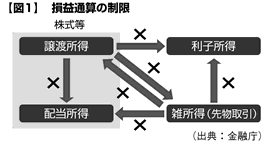
企業型確定拠出年金における個人拠出を容認 経済産業省の要望にもあるが、確定拠出年金に係る拠出制限の緩和を求めている(図2参照)。現在、企業型年金においては、個人拠出が認められていないなどの制約がある。
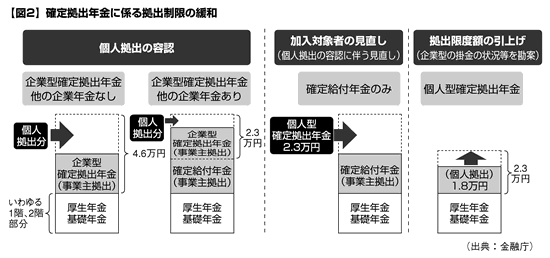
このため、①企業型確定拠出年金における個人拠出の容認、②個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し、③個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げを求めている。
その他では、企業年金等の積立金に対する特別法人税を撤廃することや現行の生命保険料控除・個人年金保険料控除の抜本的改組を求めている。
200年住宅促進税制の創設などを盛り込む~国土交通省
国土交通省の税制改正要望で目立つところでは、住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制の創設が挙げられる。
耐久性や耐震性を備えた質の高い住宅の供給および適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進する目的から、一定の基準に適合する認定住宅に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税負担を現行特例よりも軽減する特例措置を創設するというもの。「住宅の循環利用の促進に関する法律案(仮称)」を制定。住宅の循環利用に関する基本方針を国土交通大臣が策定し、その基本方針にそった計画を作成、認定することにより特例措置を受けられるというものである。
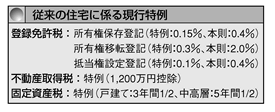
省エネ対策税制の拡充を 住宅に係る省エネ改修促進税制の創設も盛り込まれている。地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図ることを目的とし、既存住宅において一定の省エネ改修を行った場合に①省エネ改修に要した費用の10%相当額(上限20万円)の所得税額控除、②固定資産税を3年間、2分の1に減額する特例措置を求めている。省エネ改修については、窓の二重サッシ化や壁の断熱化等が想定されている。
また、地球温暖化対策として関連したところでは、エネルギー需要構造改革投資促進税制(特別償却30%、中小企業者等は税額控除7%との選択適用が可能)の対象設備に省エネ効果の高い窓等の断熱と空調、照明、給油等の建築設備から構成される「省エネビルシステム」等を追加することを求めている。
その他では、自動車グリーン税制の延長、住宅に係る耐震改修促進税制の適用要件の緩和、事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長、住宅取等資金に係る贈与税の特例措置の延長や拡充(住宅のバリアフリー改修等を追加)などを求めている。
国際競争力の観点からトン数標準税制の創設を また、平成19年度税制改正で先送りとなった外航海運におけるみなし利益課税(トン数標準税制)の創設も盛り込まれた。
トン数標準税制とは、運航している船舶のトン数(貨物を積むスペースの容積)からみなし利益を算出して課税する方式のこと。欧米・韓国等ではすでに導入されている。国土交通省では、国際的な競争力の観点(図3参照)から強くトン数標準税制の創設を求めている。
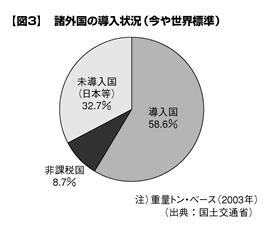
環境税以外にも地球温暖化対策税制を盛り込む~環境省
例年、税制改正での検討課題として挙がる環境税だが、今年も環境省と農林水産省が要望している。ただし、これまでの記載ぶりとは異なり、「与党における議論を踏まえて、環境税等地球温暖化対策を加速するために必要な税制上の措置について検討を急ぎ、その検討結果を踏まえて必要な措置を講ずること。」とされている。これは、昨年の議論が紛糾した際に、自民党の経済産業、環境、国土交通、農林の各部会長で合同部会をつくり、今後、税を含めた環境対策について検討を行うことにしたという背景を踏まえたものである。
また、環境省では、環境税の創設のほかにも、いくつかの地球温暖化対策に関する税制措置を要望している。
たとえば、京都議定書目標達成計画の達成のため、企業が京都メカニズムクレジットを購入した場合には、その購入費用を準備金とし、購入時点で全額損金に算入できるという措置の創設を盛り込んでいるほか、国土交通省と同じく省エネ住宅税制等やバイオ燃料関連税制の創設などを求めている。省エネ住宅税制等では、既存住宅の省エネ改修(複層ガラスの導入、断熱改修等)に対する所得税・固定資産税の減免措置等を挙げている。
地域力再生機構に係る税制上の特例措置を求める~内閣府
内閣府の税制改正要望で注目されるのが地域力再生機構(仮称)に係る税制上の特例措置の創設だ。同機構は、地方版の産業再生機構といえるもの。大田弘子内閣府特命担当大臣主催の研究会である「地域力再生機構(仮称)研究会」が8月7日に中間取りまとめを公表している。
同機構についても、産業再生機構と同様に、登録免許税の免除や法人事業税の資本割に係る課税標準の特例措置のほか、債権放棄等に係る税制上の措置を求めている。これは、事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合には、原則として法人税基本通達9-4-2に定める合理的な再建計画に基づく債権放棄に該当し、その損失は税務上損金に算入されるというもの。一方、債務免除を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)の再生手続開始の決定に準ずる事実等に該当し、債務免除の範囲内での過去の欠損金の損金算入が認められることになるというものだ。
厚労省では社会医療法人に係る非課税措置等 その他、厚生労働省では、平成20年度から都道府県が新たに見直す医療計画に基づき、地域において確保が困難な医療を担う社会医療法人の医療保健業を非課税とすることや改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための課税判定基準の見直し等を求めている。
平成20年度における各省庁の税制改正要望は?
先週号(本誌225号4頁参照)では経済産業省の平成20年度税制改正要望についてお伝えしたが、その他の各省庁の税制改正要望も出揃っている。当初、予定されていた消費税率の見直しを含む税制改正の抜本改革先送りが決定的となった今、注目すべき大きな税制改正は少ない印象だ。
しかし、例年とは違い、平成20年度税制改正要望では、キーワードの1つとして、“環境対策”が浮かんでくる。環境省だけでなく、国土交通省でも省エネ対策税制等を盛り込んでおり注目すべき点といえよう。また、昨年に引き続き議論となりそうなのが証券税制の特例の延長の可否だ。金融庁が要望しているが、自民党と公明党との意見が食い違うなか、参議院では民主党が第1党というねじれ現象も生じている。このため、現時点で平成20年度税制改正がどのようになるか予想もつかない状況だが、今回の特集では、経済産業省以外の省庁の主な税制改正要望事項を紹介する。
譲渡所得は当分の間、配当所得は恒久化を求める~金融庁
金融庁の平成20年度税制改正要望の目玉は、平成19年度税制改正で1年間延長が行われた証券税制の特例の延長だ。
具体的には、上場株式等の譲渡所得に係る優遇税率(10%)については、平成20年12月末で期限切れとなるが、当分の間、優遇税率の継続を求めている。また、上場株式等の配当所得の優遇税率(10%)も平成21年3月末で期限切れとなるが、長期・安定的な投資の促進、法人税と所得税との二重課税調整の必要性の観点から恒久化することを求めている。
民主党のマニフェストを意識? 証券税制の特例に関しては、平成19年度税制改正でも最後まで自民党と公明党との間で論点となった項目だ。最終的には「適用期限を1年延長して、廃止する。」との文言を税制改正大綱に明記することにより決着したものの、平成20年度税制改正でも議論が再燃することが予想されていた(本誌192号参照)。
しかし、今回の税制改正では、自民党と公明党との調整だけでなく、参議院第1党の民主党との調整も必要になる。
民主党では、先の参議院選挙のマニフェストにおいて、「資産性所得に対する課税標準の適正化を図りつつ、株式の長期保有に対する一定の配慮によって「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、健全な市場の発展に努めます。」と明記している。このため、金融庁の税制改正要望でも民主党のマニフェストを多少なりとも意識したものとなっているといえよう。
損益通算の拡大も求める 加えて、金融商品間の損益通算の拡大についても継続して求めている(図1参照)。上場株式等の譲渡所得と配当所得との間の損益通算を認めるほか、預金・債券等の利子所得および先物取引に係る雑所得についても、その対象範囲とすることを求めている。損益通算にあたっては、特定口座を最大限活用することも明記している。
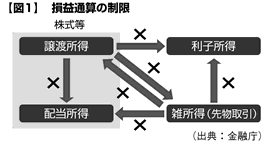
企業型確定拠出年金における個人拠出を容認 経済産業省の要望にもあるが、確定拠出年金に係る拠出制限の緩和を求めている(図2参照)。現在、企業型年金においては、個人拠出が認められていないなどの制約がある。
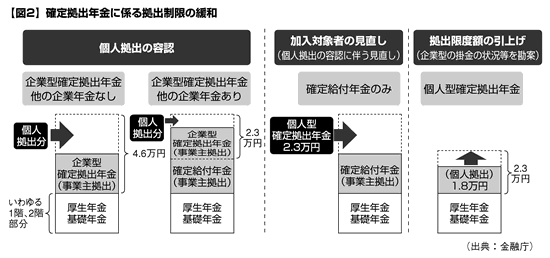
このため、①企業型確定拠出年金における個人拠出の容認、②個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し、③個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げを求めている。
その他では、企業年金等の積立金に対する特別法人税を撤廃することや現行の生命保険料控除・個人年金保険料控除の抜本的改組を求めている。
200年住宅促進税制の創設などを盛り込む~国土交通省
国土交通省の税制改正要望で目立つところでは、住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制の創設が挙げられる。
耐久性や耐震性を備えた質の高い住宅の供給および適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進する目的から、一定の基準に適合する認定住宅に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税負担を現行特例よりも軽減する特例措置を創設するというもの。「住宅の循環利用の促進に関する法律案(仮称)」を制定。住宅の循環利用に関する基本方針を国土交通大臣が策定し、その基本方針にそった計画を作成、認定することにより特例措置を受けられるというものである。
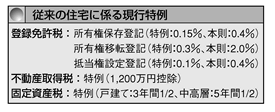
省エネ対策税制の拡充を 住宅に係る省エネ改修促進税制の創設も盛り込まれている。地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図ることを目的とし、既存住宅において一定の省エネ改修を行った場合に①省エネ改修に要した費用の10%相当額(上限20万円)の所得税額控除、②固定資産税を3年間、2分の1に減額する特例措置を求めている。省エネ改修については、窓の二重サッシ化や壁の断熱化等が想定されている。
また、地球温暖化対策として関連したところでは、エネルギー需要構造改革投資促進税制(特別償却30%、中小企業者等は税額控除7%との選択適用が可能)の対象設備に省エネ効果の高い窓等の断熱と空調、照明、給油等の建築設備から構成される「省エネビルシステム」等を追加することを求めている。
その他では、自動車グリーン税制の延長、住宅に係る耐震改修促進税制の適用要件の緩和、事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長、住宅取等資金に係る贈与税の特例措置の延長や拡充(住宅のバリアフリー改修等を追加)などを求めている。
国際競争力の観点からトン数標準税制の創設を また、平成19年度税制改正で先送りとなった外航海運におけるみなし利益課税(トン数標準税制)の創設も盛り込まれた。
トン数標準税制とは、運航している船舶のトン数(貨物を積むスペースの容積)からみなし利益を算出して課税する方式のこと。欧米・韓国等ではすでに導入されている。国土交通省では、国際的な競争力の観点(図3参照)から強くトン数標準税制の創設を求めている。
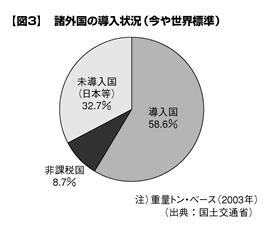
環境税以外にも地球温暖化対策税制を盛り込む~環境省
例年、税制改正での検討課題として挙がる環境税だが、今年も環境省と農林水産省が要望している。ただし、これまでの記載ぶりとは異なり、「与党における議論を踏まえて、環境税等地球温暖化対策を加速するために必要な税制上の措置について検討を急ぎ、その検討結果を踏まえて必要な措置を講ずること。」とされている。これは、昨年の議論が紛糾した際に、自民党の経済産業、環境、国土交通、農林の各部会長で合同部会をつくり、今後、税を含めた環境対策について検討を行うことにしたという背景を踏まえたものである。
また、環境省では、環境税の創設のほかにも、いくつかの地球温暖化対策に関する税制措置を要望している。
たとえば、京都議定書目標達成計画の達成のため、企業が京都メカニズムクレジットを購入した場合には、その購入費用を準備金とし、購入時点で全額損金に算入できるという措置の創設を盛り込んでいるほか、国土交通省と同じく省エネ住宅税制等やバイオ燃料関連税制の創設などを求めている。省エネ住宅税制等では、既存住宅の省エネ改修(複層ガラスの導入、断熱改修等)に対する所得税・固定資産税の減免措置等を挙げている。
地域力再生機構に係る税制上の特例措置を求める~内閣府
内閣府の税制改正要望で注目されるのが地域力再生機構(仮称)に係る税制上の特例措置の創設だ。同機構は、地方版の産業再生機構といえるもの。大田弘子内閣府特命担当大臣主催の研究会である「地域力再生機構(仮称)研究会」が8月7日に中間取りまとめを公表している。
同機構についても、産業再生機構と同様に、登録免許税の免除や法人事業税の資本割に係る課税標準の特例措置のほか、債権放棄等に係る税制上の措置を求めている。これは、事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合には、原則として法人税基本通達9-4-2に定める合理的な再建計画に基づく債権放棄に該当し、その損失は税務上損金に算入されるというもの。一方、債務免除を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)の再生手続開始の決定に準ずる事実等に該当し、債務免除の範囲内での過去の欠損金の損金算入が認められることになるというものだ。
厚労省では社会医療法人に係る非課税措置等 その他、厚生労働省では、平成20年度から都道府県が新たに見直す医療計画に基づき、地域において確保が困難な医療を担う社会医療法人の医療保健業を非課税とすることや改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための課税判定基準の見直し等を求めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























