解説記事2007年12月03日 【ニュース特集】 政府税調が「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」を答申(2007年12月3日号・№237)
抜本的税制改革のできる限り速やかな実施を要望
政府税調が「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」を答申
政府税制調査会(香西泰会長)は11月20日、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」(答申)を取りまとめ、11月26日には、福田首相に提出した。例年秋の審議についての答申は、「翌年度の税制改正に関する答申」と題して取りまとめられてきたが、今回の答申は、「あるべき税制について平成20年度改正事項とその他の事項とを区分することは困難」であるとして、「抜本的な税制改革に向けた基本的な考え方」を取りまとめたものである。
また、答申に盛り込まれた個々の事項についての実施のタイミングは、政府に委ねられているものの、「改革が遅れれば遅れるほど、解決困難な課題が膨れあがってしまう。」と明記するなど、できる限り速やかな実施を強く要望したものとなった。
今回の答申は、「消費税の増税」による財源の確保の必要性を示唆しているが、政治の状況は与野党ともに、平成20年度改正での消費税率の引上げは見送る方針となっている。消費税の増税抜きでの抜本的税制改革は事実上困難であることから、平成20年度税制改正で実施される事項は限定される。今回の答申は、平成20年度税制改正を含む中長期的視点からのあるべき税制の全体像ということになる。
1 答申からの平成20年度改正項目の判断は困難 答申の標題を「平成20年度税制改正に関する答申」とはせず、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」としていることからも明らかなように、答申は平成20年度税制改正というよりもこれまでの「中長期的視点からのあるべき税制」の議論を取りまとめたものである。今回の答申が指摘している事項については、財政状況や社会保障政策との整合性などの観点から一層の検討が必要であるなどと記述している反面、できる限り速やかな実施を求めており、税制としての方向性は示したものといえるだろう。
具体的には、「消費税の増税」は政治状況から困難であり、配偶者控除や扶養控除の見直し(給付付き税額控除への移行)も、社会保障政策との調整の視点から検討不足が指摘されている。経済のグローバル化に対応するための法人実効税率の引下げについても、(財源を考えれば)消費税率の引上げを含む抜本的税制改革の一環として実施されるべきテーマとなっており、平成20年度税制改正での実現は困難な事項となっている。答申に盛り込まれた個々の事項によっては、平成20年度税制改正で取り上げられるものもあろうが、全体像としては、中長期的に実施されるものと位置付けざるを得ない。
また、中長期的視点からの全体像のなかでも中核となる消費税の増税を含む抜本的税制改革が平成20年度税制改正での実施が困難となっていることから、平成20年度改正項目を答申から読み込むことは難しい。さらに、衆参の勢力がねじれた政治の状況が不透明さを増している。各事項の実施のタイミングについては、政府(政治)に下駄を預けた格好だ。
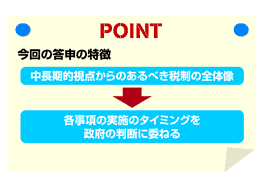
2 少子高齢化・グローバル化等の構造変化への対処を目指して 答申はまず、少子高齢化やグローバル化等の経済・社会の構造変化を踏まえ、①社会保障の安定財源確保、②いわゆる格差問題、③成長力の強化といった国民的課題が存在するとし、これらの解決のため、中長期的視点に立って、税体系全体のあり方について抜本的見直しを行っていくことが必要だとしている。
次に、答申は、目指すべき抜本的な税制改革には、「公平・中立・簡素」という3つの基本原則を踏まえつつ、①国民の安心を支える税制、②経済・社会・地域の活力を高める税制、③国民・納税者の信頼を得る公正な税制、との3つの視点(図表1参照)に立つことが必要であるとしている。
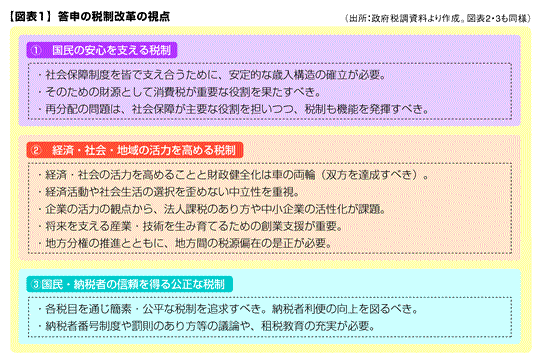
3 所得税の所得再分配機能のあり方の見直しを中核に 個人所得課税では、消費税の役割が重視される税体系となることや、個人住民税の比例税率化を踏まえ、所得税の所得再分配機能の役割を見直して(重視して)いくべきだとしている。
同時に、少子高齢化の進展、ライフスタイルや働き方の多様化に対応し、個々人や社会全体の活力を引き出す観点から、個人の経済・社会活動の多様な選択に対する中立性、国民にとってわかりやすい簡素な仕組みが課題となるとしている。
税率構造の見直しで所得税の累進課税を強化 具体的には、所得税の税率構造(税率・ブラケット幅)については、所得再分配機能が適切に発揮されるよう、見直すことが課題であるとしている。ブラケット幅を縮小等することで、所得税の納税者の大部分が5%または10%という低い税率が適用される構造(全体の80%程度)(図表2参照)を見直す方向性を示している。また、最高税率については、所得再分配の観点から(引上げの方向で)見直しを検討する必要があるとしている。
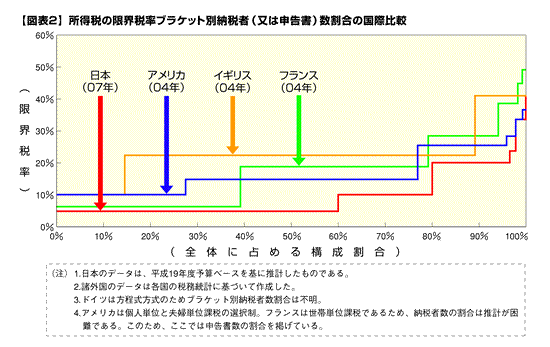
配偶者控除等は縮小の方向 また、男女共同参画やライフスタイルの多様化を踏まえた配偶者控除等(配偶者控除・配偶者特別控除)、扶養控除等(扶養控除・特定扶養控除)の見直しを検討すべきものとしている。配偶者控除等については縮小の方向で、扶養控除等については、成年者を扶養控除の対象から外すこと・特定扶養控除を縮小(廃止)する方向での検討が示唆されているが、少子化対策として、「給付付き税額控除」を活用することも考えられるとしている。
給与所得控除(概算控除)の上限設定を提言 給与への課税については、就業構造等の変化を踏まえ、給与所得控除の性格について今日の経済・社会状況に適合するよう再構築することが求められるとしている。勤務費用の実態を反映した見直しとして、給与所得控除に上限を設定する見直し(現行制度は概算控除の場合には収入金額の5%の給与所得控除が青天井で認められる)が適当であるとしている。
退職金課税については、現行の勤続20年を境に1年当たりの控除額が急増する仕組みや勤続年数が短期間でも退職金に係る所得の2分の1にしか課税されないという仕組みを見直し、全体として多様な就労選択に中立的な制度への見直しが必要であるとされている。勤続20年超の上乗せ部分(70万円-40万円)を縮小(廃止)する方向、ならびに2分の1課税を受けられる場合の要件設定および2分の1課税の圧縮割合の引下げの方向が示されている。
公的年金への課税については、年金以外に高額な給与を得ている場合の公的年金等控除について、世代間・世代内の公平性の観点から適正化を図ることを考慮すべきものとしている。公的年金等控除と給与所得控除とがダブルで適用される場合があることの見直しを求めるものであり、年金所得を雑所得とは別の所得区分とすることも考えられるとしている。
給付付き税額控除の可能性を議論すべき 所得税では、家族構成等の納税者の個々の事情に関し、一定額を所得から差し引く所得控除による対応を基本としてきている。他方で、税額控除は、税額から一定額を差し引く負担調整の仕組みであり、財政的支援としての性格が強い。所得控除は、高所得者ほど税負担軽減額が大きい(税負担軽減額は、高所得者ほど高い限界税率と所得控除額を乗じたものとなる)一方で、税額控除は、基本的に所得水準にかかわらず税負担軽減額を一定とすることができる。財政的支援の集中化や所得税の再分配機能の強化といった観点から、所得控除を改組して税額控除を導入するという考え方があり、検討を深めるべきである。
給付付き税額控除制度は、課税最低限以下の低所得者に対して、税額控除できない分を給付するという仕組みであり、低所得者支援、子育て支援、消費税の逆進性対応といった様々な視点から主張されている。持続可能で安心できる社会保障制度の構築とそのための安定的な財源の確保が重要な課題となっているなか、「給付付き税額控除」について、諸外国の事例も参考にしつつ、政策の必要性、既存給付との関係等の課題について、議論を行っていくことには意義がある。
既存給付との関係などの課題の整備に検討を要することからすれば、まさしく、中期的な検討課題という位置付けになろう。
ふるさと納税は寄附金税制を活用した仕組みを検討すべき 個人住民税の寄附金については、現行10万円の適用下限額を大幅に引き下げることが適当であり、納税者にとっての効果のわかりやすさという観点などから、現行の所得税額控除方式を税額控除方式とすることについて検討する必要がある。また、納税者が「ふるさと」と考える地方公共団体に対する貢献や応援が可能となる税制上の方策(「ふるさと納税制度」)が求められており、寄附金税制を活用した仕組みについて検討することが必要である。
4 法人課税の中核はグローバル化への対応と経済活性化 答申は、法人課税について、「経済のグローバル化等の経済・社会の構造変化に適切に対応するとともに、我が国経済の国際競争力を強化し、その活性化を図ることは、税制においても重要な課題である。」としている。具体的には、国際的なイコールフッティングを図るべきとの観点から要望されている法人実効税率の引下げと経済活性化を目的とした政策減税のあり方が検討課題になる。
法人実効税率の引下げは多数意見だが 法人実効税率の引下げについては、法人課税の国際的動向に照らして必要であるとの意見が多かった。しかしながら、厳しい財政状況にあることから、課税ベースの拡大を含めた対応が必要であるとしている。課税ベースの拡大についての具体的な記述はなく、現実的には、消費税率の引上げなどにより、財源の目途がたつことが、法人実効税率引下げの前提とも受け止められる(消費税が実質的に付加価値税の性格を有していることに着目すれば、法人税から消費税への移行は課税ベースの拡大とみることができる)。
政策減税の効果的な活用に重点 法人実効税率は、企業立地先や投資先の決定、利益移転に影響を与える一方、政策税制等も考慮した限界実効税率は、投資額の多寡に影響を与えるとの理論的整理がなされている。当面はわが国の持続的な経済成長のため、研究開発税制をはじめとする政策減税の効果的な活用に重点を置く必要がある。
「民間が担う公益」を支える公益法人税制 平成20年12月から公益法人関連三法が施行予定であり、いわゆる「新公益法人制度」がスタートする。これに伴い、税制面でも「民間が担う公益」を支える制度の構築が求められている。具体的には、新たに創設される公益社団(財団)法人については、公益目的事業の実施をサポートする措置を講じるべきである。新たに創設される一般社団(財団)法人については、多様な態様のものが現れることが予想され、態様に応じた措置を講じるべきである。特定公益増進法人のなかに公益社団(財団)法人を位置付け、寄附を行った個人・法人が寄附優遇を受けることができるようにするとともに、寄附を行うための環境整備を進めるべきである。
5 消費税は社会保障財源の中核を担うにふさわしい 消費税は、財貨・サービスの消費に幅広く等しく負担を求める性格から、勤労世代など特定の者への負担が集中せず、社会保障財源の中核を担うにふさわしいと考えられる。社会保障費に関しては、消費税率を引き上げていくことによって賄うとの姿勢を明らかにすること(「消費税の社会保障財源化」)について、選択肢の1つとして幅広く検討を行うべきである。
消費税については、「所得に対して逆進的」との指摘もあるが、社会保障を含む受益と負担を通じた全体で所得再分配に寄与しているという大きな意義を有している。
軽減税率(複数税率)については、制度の簡素化や事業者の事務負担等を考慮すれば、極力単一税率が望ましい。また、仮に軽減税率を導入する場合には、「インボイス方式」の導入が検討課題になる。
地方消費税は、税収の偏在性が少なく、安定的な基幹税目であり、重要な役割を果たしている。地方における社会保障関係費の大幅な増加が見込まれるなかで、地方消費税の充実確保を図っていく必要がある。
6 資産再分配機能等の回復を図ることが重要 相続税については、地価がバブル期以前の水準にまで下落し、相続税課税が発生する割合が4%程度まで減少するなど、その資産再分配機能や財源調達機能は低下している。高齢者世帯ほど資産蓄積が多くなっていることなどから、相続を機会に高齢者世代内の資産格差が次世代へ引き継がれる可能性も増してきている。
相続税を巡る環境の変化等からすれば、これまでの改正により大幅に緩和されてきた相続税の負担水準をこのまま放置することは適当ではなく、相続財産に適切な負担を求め、相続税の有する資産再配分機能等の回復を図ることが重要である。具体的には相続税の基礎控除の水準を引き下げることが適当である。最高税率を含む税率構造のあり方についても、格差の固定化の防止といった観点から検討する必要がある。
相続税の現行課税方式(法定相続分課税)は、必ずしも個々の相続人の相続額に応じた課税がなされないなどの問題(図表3参照)が指摘され、居住の継続に配慮した現行の各種特例は、居住等を継続しない他の共同相続人の税負担をも軽減する効果があるため、制度の趣旨や課税の公平からも問題がある(後述の事業承継税制の拡充についても同様の問題が指摘されている)。課税方式のあり方について、具体的かつ実務的な検討が必要である。
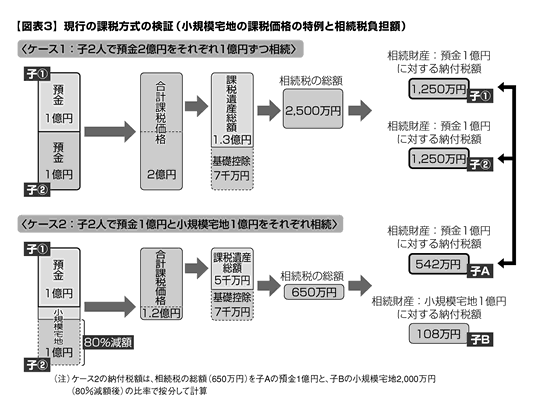
中小企業の事業承継においては、相続税負担について雇用確保や経済活力の維持の観点から一層の配慮が必要であるとの意見がある。一方で課税の公平性などの観点から十分な吟味が必要であるとの指摘もある。事業承継税制については、課税の公平性等の観点からも許容できる、経済活力維持のために真に効果的な制度とする必要がある。現行の各種特例を拡充することに関する前述の問題点にも留意しつつ、相続税制全体の見直しのなかでさらに検討を進めることが必要である。
上場株式等の軽減税率(10%)の廃止を引き続き答申に盛り込む 金融所得課税については、昨年度の答申において、上場株式等の配当や譲渡益の軽減税率(10%)を廃止すべきであるとしていたが、延長された経緯がある。政府税調は、今回の答申においても、上場株式等の配当や譲渡益の軽減税率(10%)について、「平成20年度税制改正では、税制が市場に歪みを与えることがないよう、昨年度の答申の方向に沿って対応すべきである。」とした。すなわち、軽減税率を再延長せずに、廃止(本則税率(20%)による課税)するように求めている。また、「軽減税率が廃止され、課税方式の均衡化が図られることを前提として、金融所得間の損益通算の範囲を本格的に拡大していくべきである。」としている。
政府税調が「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」を答申
政府税制調査会(香西泰会長)は11月20日、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」(答申)を取りまとめ、11月26日には、福田首相に提出した。例年秋の審議についての答申は、「翌年度の税制改正に関する答申」と題して取りまとめられてきたが、今回の答申は、「あるべき税制について平成20年度改正事項とその他の事項とを区分することは困難」であるとして、「抜本的な税制改革に向けた基本的な考え方」を取りまとめたものである。
また、答申に盛り込まれた個々の事項についての実施のタイミングは、政府に委ねられているものの、「改革が遅れれば遅れるほど、解決困難な課題が膨れあがってしまう。」と明記するなど、できる限り速やかな実施を強く要望したものとなった。
今回の答申は、「消費税の増税」による財源の確保の必要性を示唆しているが、政治の状況は与野党ともに、平成20年度改正での消費税率の引上げは見送る方針となっている。消費税の増税抜きでの抜本的税制改革は事実上困難であることから、平成20年度税制改正で実施される事項は限定される。今回の答申は、平成20年度税制改正を含む中長期的視点からのあるべき税制の全体像ということになる。
1 答申からの平成20年度改正項目の判断は困難 答申の標題を「平成20年度税制改正に関する答申」とはせず、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」としていることからも明らかなように、答申は平成20年度税制改正というよりもこれまでの「中長期的視点からのあるべき税制」の議論を取りまとめたものである。今回の答申が指摘している事項については、財政状況や社会保障政策との整合性などの観点から一層の検討が必要であるなどと記述している反面、できる限り速やかな実施を求めており、税制としての方向性は示したものといえるだろう。
具体的には、「消費税の増税」は政治状況から困難であり、配偶者控除や扶養控除の見直し(給付付き税額控除への移行)も、社会保障政策との調整の視点から検討不足が指摘されている。経済のグローバル化に対応するための法人実効税率の引下げについても、(財源を考えれば)消費税率の引上げを含む抜本的税制改革の一環として実施されるべきテーマとなっており、平成20年度税制改正での実現は困難な事項となっている。答申に盛り込まれた個々の事項によっては、平成20年度税制改正で取り上げられるものもあろうが、全体像としては、中長期的に実施されるものと位置付けざるを得ない。
また、中長期的視点からの全体像のなかでも中核となる消費税の増税を含む抜本的税制改革が平成20年度税制改正での実施が困難となっていることから、平成20年度改正項目を答申から読み込むことは難しい。さらに、衆参の勢力がねじれた政治の状況が不透明さを増している。各事項の実施のタイミングについては、政府(政治)に下駄を預けた格好だ。
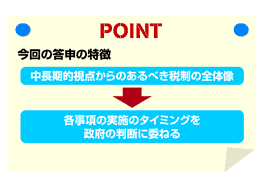
2 少子高齢化・グローバル化等の構造変化への対処を目指して 答申はまず、少子高齢化やグローバル化等の経済・社会の構造変化を踏まえ、①社会保障の安定財源確保、②いわゆる格差問題、③成長力の強化といった国民的課題が存在するとし、これらの解決のため、中長期的視点に立って、税体系全体のあり方について抜本的見直しを行っていくことが必要だとしている。
次に、答申は、目指すべき抜本的な税制改革には、「公平・中立・簡素」という3つの基本原則を踏まえつつ、①国民の安心を支える税制、②経済・社会・地域の活力を高める税制、③国民・納税者の信頼を得る公正な税制、との3つの視点(図表1参照)に立つことが必要であるとしている。
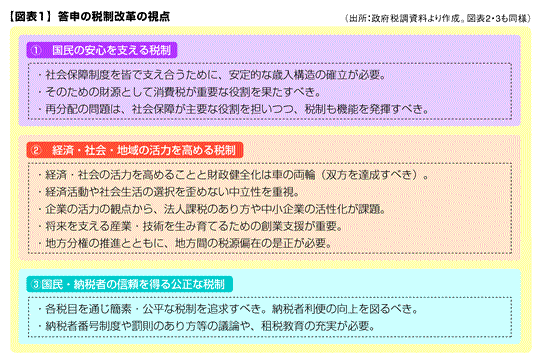
3 所得税の所得再分配機能のあり方の見直しを中核に 個人所得課税では、消費税の役割が重視される税体系となることや、個人住民税の比例税率化を踏まえ、所得税の所得再分配機能の役割を見直して(重視して)いくべきだとしている。
同時に、少子高齢化の進展、ライフスタイルや働き方の多様化に対応し、個々人や社会全体の活力を引き出す観点から、個人の経済・社会活動の多様な選択に対する中立性、国民にとってわかりやすい簡素な仕組みが課題となるとしている。
税率構造の見直しで所得税の累進課税を強化 具体的には、所得税の税率構造(税率・ブラケット幅)については、所得再分配機能が適切に発揮されるよう、見直すことが課題であるとしている。ブラケット幅を縮小等することで、所得税の納税者の大部分が5%または10%という低い税率が適用される構造(全体の80%程度)(図表2参照)を見直す方向性を示している。また、最高税率については、所得再分配の観点から(引上げの方向で)見直しを検討する必要があるとしている。
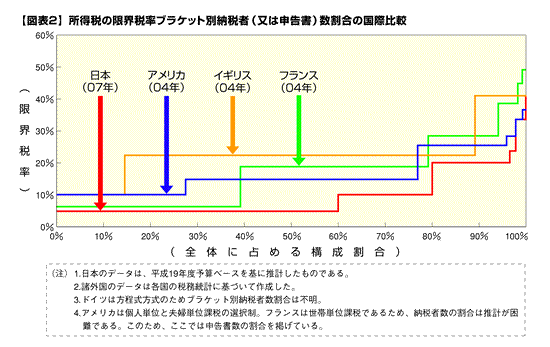
配偶者控除等は縮小の方向 また、男女共同参画やライフスタイルの多様化を踏まえた配偶者控除等(配偶者控除・配偶者特別控除)、扶養控除等(扶養控除・特定扶養控除)の見直しを検討すべきものとしている。配偶者控除等については縮小の方向で、扶養控除等については、成年者を扶養控除の対象から外すこと・特定扶養控除を縮小(廃止)する方向での検討が示唆されているが、少子化対策として、「給付付き税額控除」を活用することも考えられるとしている。
給与所得控除(概算控除)の上限設定を提言 給与への課税については、就業構造等の変化を踏まえ、給与所得控除の性格について今日の経済・社会状況に適合するよう再構築することが求められるとしている。勤務費用の実態を反映した見直しとして、給与所得控除に上限を設定する見直し(現行制度は概算控除の場合には収入金額の5%の給与所得控除が青天井で認められる)が適当であるとしている。
退職金課税については、現行の勤続20年を境に1年当たりの控除額が急増する仕組みや勤続年数が短期間でも退職金に係る所得の2分の1にしか課税されないという仕組みを見直し、全体として多様な就労選択に中立的な制度への見直しが必要であるとされている。勤続20年超の上乗せ部分(70万円-40万円)を縮小(廃止)する方向、ならびに2分の1課税を受けられる場合の要件設定および2分の1課税の圧縮割合の引下げの方向が示されている。
公的年金への課税については、年金以外に高額な給与を得ている場合の公的年金等控除について、世代間・世代内の公平性の観点から適正化を図ることを考慮すべきものとしている。公的年金等控除と給与所得控除とがダブルで適用される場合があることの見直しを求めるものであり、年金所得を雑所得とは別の所得区分とすることも考えられるとしている。
給付付き税額控除の可能性を議論すべき 所得税では、家族構成等の納税者の個々の事情に関し、一定額を所得から差し引く所得控除による対応を基本としてきている。他方で、税額控除は、税額から一定額を差し引く負担調整の仕組みであり、財政的支援としての性格が強い。所得控除は、高所得者ほど税負担軽減額が大きい(税負担軽減額は、高所得者ほど高い限界税率と所得控除額を乗じたものとなる)一方で、税額控除は、基本的に所得水準にかかわらず税負担軽減額を一定とすることができる。財政的支援の集中化や所得税の再分配機能の強化といった観点から、所得控除を改組して税額控除を導入するという考え方があり、検討を深めるべきである。
給付付き税額控除制度は、課税最低限以下の低所得者に対して、税額控除できない分を給付するという仕組みであり、低所得者支援、子育て支援、消費税の逆進性対応といった様々な視点から主張されている。持続可能で安心できる社会保障制度の構築とそのための安定的な財源の確保が重要な課題となっているなか、「給付付き税額控除」について、諸外国の事例も参考にしつつ、政策の必要性、既存給付との関係等の課題について、議論を行っていくことには意義がある。
既存給付との関係などの課題の整備に検討を要することからすれば、まさしく、中期的な検討課題という位置付けになろう。
ふるさと納税は寄附金税制を活用した仕組みを検討すべき 個人住民税の寄附金については、現行10万円の適用下限額を大幅に引き下げることが適当であり、納税者にとっての効果のわかりやすさという観点などから、現行の所得税額控除方式を税額控除方式とすることについて検討する必要がある。また、納税者が「ふるさと」と考える地方公共団体に対する貢献や応援が可能となる税制上の方策(「ふるさと納税制度」)が求められており、寄附金税制を活用した仕組みについて検討することが必要である。
4 法人課税の中核はグローバル化への対応と経済活性化 答申は、法人課税について、「経済のグローバル化等の経済・社会の構造変化に適切に対応するとともに、我が国経済の国際競争力を強化し、その活性化を図ることは、税制においても重要な課題である。」としている。具体的には、国際的なイコールフッティングを図るべきとの観点から要望されている法人実効税率の引下げと経済活性化を目的とした政策減税のあり方が検討課題になる。
法人実効税率の引下げは多数意見だが 法人実効税率の引下げについては、法人課税の国際的動向に照らして必要であるとの意見が多かった。しかしながら、厳しい財政状況にあることから、課税ベースの拡大を含めた対応が必要であるとしている。課税ベースの拡大についての具体的な記述はなく、現実的には、消費税率の引上げなどにより、財源の目途がたつことが、法人実効税率引下げの前提とも受け止められる(消費税が実質的に付加価値税の性格を有していることに着目すれば、法人税から消費税への移行は課税ベースの拡大とみることができる)。
政策減税の効果的な活用に重点 法人実効税率は、企業立地先や投資先の決定、利益移転に影響を与える一方、政策税制等も考慮した限界実効税率は、投資額の多寡に影響を与えるとの理論的整理がなされている。当面はわが国の持続的な経済成長のため、研究開発税制をはじめとする政策減税の効果的な活用に重点を置く必要がある。
「民間が担う公益」を支える公益法人税制 平成20年12月から公益法人関連三法が施行予定であり、いわゆる「新公益法人制度」がスタートする。これに伴い、税制面でも「民間が担う公益」を支える制度の構築が求められている。具体的には、新たに創設される公益社団(財団)法人については、公益目的事業の実施をサポートする措置を講じるべきである。新たに創設される一般社団(財団)法人については、多様な態様のものが現れることが予想され、態様に応じた措置を講じるべきである。特定公益増進法人のなかに公益社団(財団)法人を位置付け、寄附を行った個人・法人が寄附優遇を受けることができるようにするとともに、寄附を行うための環境整備を進めるべきである。
5 消費税は社会保障財源の中核を担うにふさわしい 消費税は、財貨・サービスの消費に幅広く等しく負担を求める性格から、勤労世代など特定の者への負担が集中せず、社会保障財源の中核を担うにふさわしいと考えられる。社会保障費に関しては、消費税率を引き上げていくことによって賄うとの姿勢を明らかにすること(「消費税の社会保障財源化」)について、選択肢の1つとして幅広く検討を行うべきである。
消費税については、「所得に対して逆進的」との指摘もあるが、社会保障を含む受益と負担を通じた全体で所得再分配に寄与しているという大きな意義を有している。
軽減税率(複数税率)については、制度の簡素化や事業者の事務負担等を考慮すれば、極力単一税率が望ましい。また、仮に軽減税率を導入する場合には、「インボイス方式」の導入が検討課題になる。
地方消費税は、税収の偏在性が少なく、安定的な基幹税目であり、重要な役割を果たしている。地方における社会保障関係費の大幅な増加が見込まれるなかで、地方消費税の充実確保を図っていく必要がある。
6 資産再分配機能等の回復を図ることが重要 相続税については、地価がバブル期以前の水準にまで下落し、相続税課税が発生する割合が4%程度まで減少するなど、その資産再分配機能や財源調達機能は低下している。高齢者世帯ほど資産蓄積が多くなっていることなどから、相続を機会に高齢者世代内の資産格差が次世代へ引き継がれる可能性も増してきている。
相続税を巡る環境の変化等からすれば、これまでの改正により大幅に緩和されてきた相続税の負担水準をこのまま放置することは適当ではなく、相続財産に適切な負担を求め、相続税の有する資産再配分機能等の回復を図ることが重要である。具体的には相続税の基礎控除の水準を引き下げることが適当である。最高税率を含む税率構造のあり方についても、格差の固定化の防止といった観点から検討する必要がある。
相続税の現行課税方式(法定相続分課税)は、必ずしも個々の相続人の相続額に応じた課税がなされないなどの問題(図表3参照)が指摘され、居住の継続に配慮した現行の各種特例は、居住等を継続しない他の共同相続人の税負担をも軽減する効果があるため、制度の趣旨や課税の公平からも問題がある(後述の事業承継税制の拡充についても同様の問題が指摘されている)。課税方式のあり方について、具体的かつ実務的な検討が必要である。
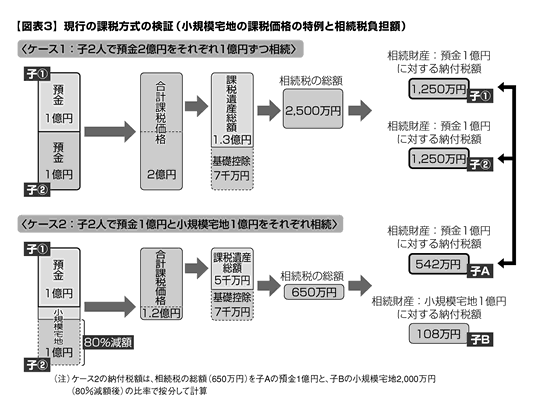
中小企業の事業承継においては、相続税負担について雇用確保や経済活力の維持の観点から一層の配慮が必要であるとの意見がある。一方で課税の公平性などの観点から十分な吟味が必要であるとの指摘もある。事業承継税制については、課税の公平性等の観点からも許容できる、経済活力維持のために真に効果的な制度とする必要がある。現行の各種特例を拡充することに関する前述の問題点にも留意しつつ、相続税制全体の見直しのなかでさらに検討を進めることが必要である。
上場株式等の軽減税率(10%)の廃止を引き続き答申に盛り込む 金融所得課税については、昨年度の答申において、上場株式等の配当や譲渡益の軽減税率(10%)を廃止すべきであるとしていたが、延長された経緯がある。政府税調は、今回の答申においても、上場株式等の配当や譲渡益の軽減税率(10%)について、「平成20年度税制改正では、税制が市場に歪みを与えることがないよう、昨年度の答申の方向に沿って対応すべきである。」とした。すなわち、軽減税率を再延長せずに、廃止(本則税率(20%)による課税)するように求めている。また、「軽減税率が廃止され、課税方式の均衡化が図られることを前提として、金融所得間の損益通算の範囲を本格的に拡大していくべきである。」としている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























