解説記事2008年04月14日 【ニュース特集】 事前照会に対する文書回答制度を確認しよう(2008年4月14日号・№254)
事前照会者名は原則非公開に!
事務運営指針が改正
事前照会に対する文書回答制度を確認しよう
国税庁は3月31日、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。改正事務運営指針では、事前照会者名が原則非公表とされたほか、対象取引に「将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なもの」が追加されている。さらに、文書回答の早期化(原則3か月以内の極力早期)等の改正が行われている。
今回の特集では、改正事務運営指針の内容および事前照会から文書回答までの具体的な手続等を確認する。
事務運営指針改正の背景と内容 改正された事務運営指針の内容は、昨年末に公表された与党税制改正大綱に明記されたもの。自民党税調での議論においては、従来の文書回答手続に対して、以下の改善要望がなされていた。
① 対象取引が実際に行われた、または確実に行われる取引等に限定され、取引の計画段階での課税関係の確認に活用できない。
② 照会者名の公表が文書回答手続の障害となっている。
③ 回答内容の早期公表により、商品開発に係る情報が他社に明らかとなり活用が躊躇される。
④ 取引の機動性確保の観点から迅速な回答を期待する。
公表延期期間を180日以内に延長 こうした要望に応じて、事務運営指針が改正されている。①~④に対する改正内容は以下のとおり。
① 「将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提示が可能なもの」を対象取引に追加(事務運営指針1(3))。
② 事前照会者名などの事前照会者を特定する情報は原則非公表(事務運営指針1(5)等)。
③ 相当の理由がある場合の公表延期期間を180日以内(改正前は120日以内)とする(事務運営指針6(2)ロ)。
④ 文書回答は原則3か月以内の極力早期に行うよう努める(事務運営指針6(1))。
事前照会から文書回答までの手続を確認 事前照会で文書回答を求める場合には、まず照会事案が文書回答の対象となるかを確認する必要がある。
事前照会が文書回答の対象となる要件は、事務運営指針1に掲げられており、事前照会者が行う取引等に係る国税に関する法令の解釈・適用その他税務上の取扱いに関する事前照会であること、申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であることなどが要件となる。
複数の選択肢について明確化された また、今回の事務運運営指針の改正により、仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくものではなく、実際に行われた取引等または将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る事前照会であることが要件とされたが、この「複数の選択肢がある事実関係に基づくものではなく」とは、1つの照会文書において前提としている事実関係が複数ではなく1つであることとなる。
事前照会における税務署の対応 次に、事前照会に対する文書回答までの手順を当局の処理と併せて確認していくことにする(表1参照)。
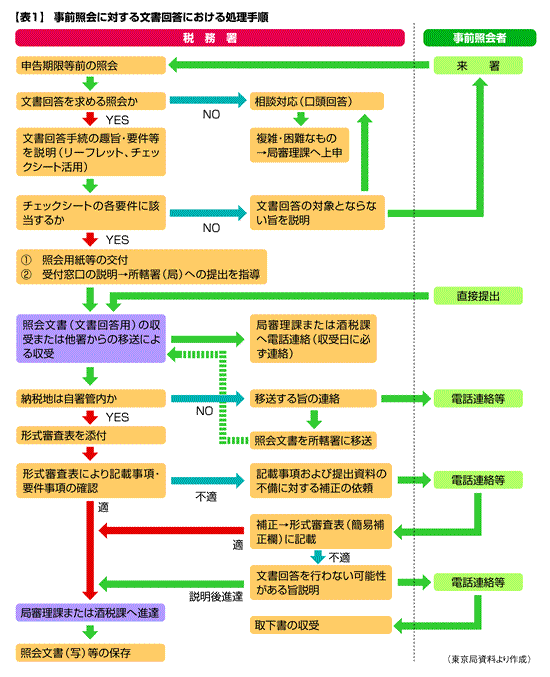
まず、事前照会者が税務署を訪れて事前照会を行う場合、税務署の担当者から文書回答を求めるかどうかを問われることになる。これに対して、文書回答を求めなければ、口頭回答(相談対応)での処理となる。
一方、事前照会者が文書回答を求めた場合は、チェックシート(今号7頁参照)により、照会内容の審査に必要な追加的な資料や翻訳文の提出に同意すること、照会内容および回答内容が公表されることに同意すること、回答内容の公表につき取引等の関係者の了解を得ることなどの各要件に該当するかどうかが確認され、その後、照会用紙の交付、受付窓口の説明(所轄署等への提出指導)が行われることになる。
なお、文書回答で照会窓口となるのは、法人税・消費税(法人)の場合、所轄税務署(調査部所管法人は国税局の調査審理(管理)課)となる。また所得税、相続税等の場合も、所轄税務署だが、同業者団体の窓口は局審理課等となる(表2参照)。
形式審査と口頭回答の関係 文書回答を求める照会の場合、照会用紙に照会者の住所・氏名を記載するが、税理士等の代理人を選任している場合には、税理士の住所、氏名の記載および押印も必要となる。
また、法令解釈・適用上の疑義の要約およびこれに対する事前照会者の求める見解の内容、照会事項に関係する取引等関係者の名称(実名)、取引等における権利・義務関係などの具体的な事実関係等を記載した書面の提出が必要となる。そのほか、事前照会に係る取引等に関するすべての契約書および審査に必要と思われる資料等の写し等関係書類、チェックシートも提出する必要がある(事務運営指針3(2))。
提出した照会文書は、税務署等の担当者により、形式審査が行われることになる。
具体的には、形式審査表(事務運営指針・別紙2)により、記載事項について、押印漏れはない、代理人・総代の委任状等の添付漏れはないなどについての適・不適が審査されるほか、要件事項に関して、他の事務運営指針等によって別途処理手続が定められているものでないかどうかなどが確認される。
形式審査等で提出された照会文書が文書回答の対象となる要件を満たしていないと判断された場合は、文書回答を行わない可能性が照会者に伝えられるが、その場合でも、口頭回答が可能な事前照会については、内容審査のうえ、口頭での回答が行われることになる。
なお、口頭回答における審理体制については、表2の口頭回答に係る部分を参照されたい。
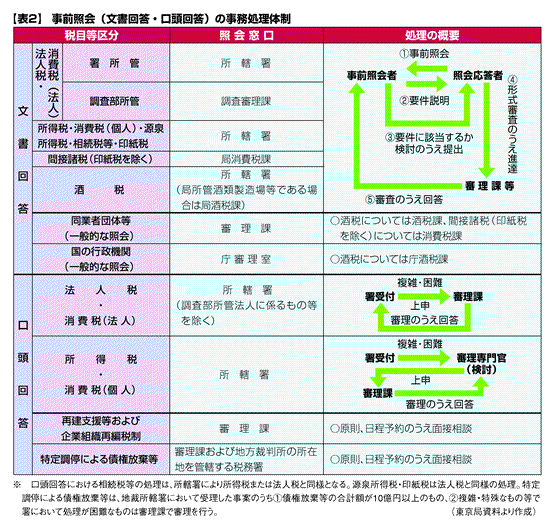 国税局での審理と回答の内容
税務署等での形式審査を経て国税局に送られた照会文書については、審理課等で再度、実務運営指針1(9)に掲げられている、実地確認や取引等関係者等への照会等による事実関係の認定を必要とするもの、同族会社等の行為または計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるものなどに該当しないかどうか確認がなされたうえ、実質審査が行われることになる。
国税局での審理と回答の内容
税務署等での形式審査を経て国税局に送られた照会文書については、審理課等で再度、実務運営指針1(9)に掲げられている、実地確認や取引等関係者等への照会等による事実関係の認定を必要とするもの、同族会社等の行為または計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるものなどに該当しないかどうか確認がなされたうえ、実質審査が行われることになる。
審査終了後、照会文書が受付窓口に到達した日から原則3か月以内の極力早期(例外あり)に、回答が行われることとなるが、その回答の内容は、事前照会者の求める見解の内容について①相当と認められる、②相当と認められないとの判断を示すもの、あるいは、同様の照会に対する税務上の取扱いが明らかになり、新たな見解を示すことがないものとなる。
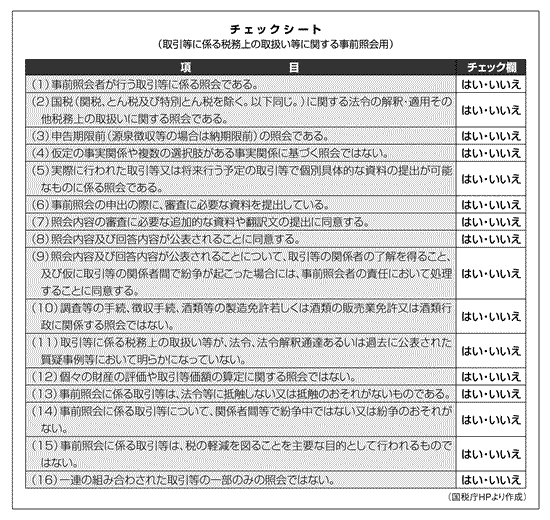
事務運営指針が改正
事前照会に対する文書回答制度を確認しよう
国税庁は3月31日、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。改正事務運営指針では、事前照会者名が原則非公表とされたほか、対象取引に「将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なもの」が追加されている。さらに、文書回答の早期化(原則3か月以内の極力早期)等の改正が行われている。
今回の特集では、改正事務運営指針の内容および事前照会から文書回答までの具体的な手続等を確認する。
事務運営指針改正の背景と内容 改正された事務運営指針の内容は、昨年末に公表された与党税制改正大綱に明記されたもの。自民党税調での議論においては、従来の文書回答手続に対して、以下の改善要望がなされていた。
① 対象取引が実際に行われた、または確実に行われる取引等に限定され、取引の計画段階での課税関係の確認に活用できない。
② 照会者名の公表が文書回答手続の障害となっている。
③ 回答内容の早期公表により、商品開発に係る情報が他社に明らかとなり活用が躊躇される。
④ 取引の機動性確保の観点から迅速な回答を期待する。
公表延期期間を180日以内に延長 こうした要望に応じて、事務運営指針が改正されている。①~④に対する改正内容は以下のとおり。
① 「将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提示が可能なもの」を対象取引に追加(事務運営指針1(3))。
② 事前照会者名などの事前照会者を特定する情報は原則非公表(事務運営指針1(5)等)。
③ 相当の理由がある場合の公表延期期間を180日以内(改正前は120日以内)とする(事務運営指針6(2)ロ)。
④ 文書回答は原則3か月以内の極力早期に行うよう努める(事務運営指針6(1))。
事前照会から文書回答までの手続を確認 事前照会で文書回答を求める場合には、まず照会事案が文書回答の対象となるかを確認する必要がある。
事前照会が文書回答の対象となる要件は、事務運営指針1に掲げられており、事前照会者が行う取引等に係る国税に関する法令の解釈・適用その他税務上の取扱いに関する事前照会であること、申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であることなどが要件となる。
複数の選択肢について明確化された また、今回の事務運運営指針の改正により、仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくものではなく、実際に行われた取引等または将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る事前照会であることが要件とされたが、この「複数の選択肢がある事実関係に基づくものではなく」とは、1つの照会文書において前提としている事実関係が複数ではなく1つであることとなる。
事前照会における税務署の対応 次に、事前照会に対する文書回答までの手順を当局の処理と併せて確認していくことにする(表1参照)。
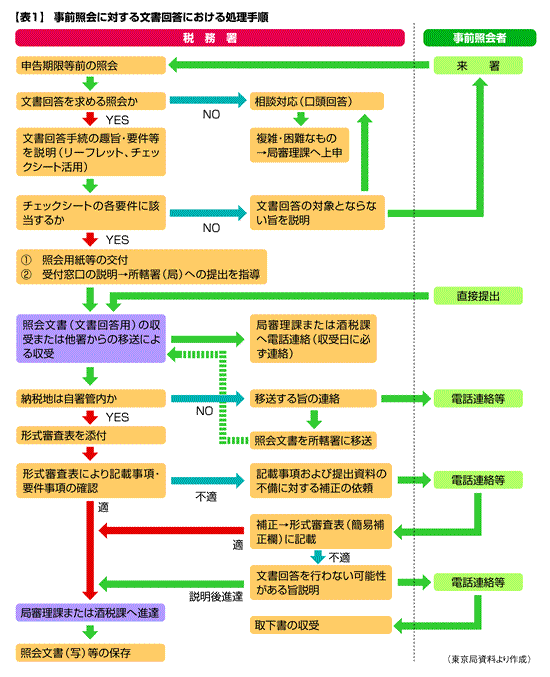
まず、事前照会者が税務署を訪れて事前照会を行う場合、税務署の担当者から文書回答を求めるかどうかを問われることになる。これに対して、文書回答を求めなければ、口頭回答(相談対応)での処理となる。
一方、事前照会者が文書回答を求めた場合は、チェックシート(今号7頁参照)により、照会内容の審査に必要な追加的な資料や翻訳文の提出に同意すること、照会内容および回答内容が公表されることに同意すること、回答内容の公表につき取引等の関係者の了解を得ることなどの各要件に該当するかどうかが確認され、その後、照会用紙の交付、受付窓口の説明(所轄署等への提出指導)が行われることになる。
なお、文書回答で照会窓口となるのは、法人税・消費税(法人)の場合、所轄税務署(調査部所管法人は国税局の調査審理(管理)課)となる。また所得税、相続税等の場合も、所轄税務署だが、同業者団体の窓口は局審理課等となる(表2参照)。
形式審査と口頭回答の関係 文書回答を求める照会の場合、照会用紙に照会者の住所・氏名を記載するが、税理士等の代理人を選任している場合には、税理士の住所、氏名の記載および押印も必要となる。
また、法令解釈・適用上の疑義の要約およびこれに対する事前照会者の求める見解の内容、照会事項に関係する取引等関係者の名称(実名)、取引等における権利・義務関係などの具体的な事実関係等を記載した書面の提出が必要となる。そのほか、事前照会に係る取引等に関するすべての契約書および審査に必要と思われる資料等の写し等関係書類、チェックシートも提出する必要がある(事務運営指針3(2))。
提出した照会文書は、税務署等の担当者により、形式審査が行われることになる。
具体的には、形式審査表(事務運営指針・別紙2)により、記載事項について、押印漏れはない、代理人・総代の委任状等の添付漏れはないなどについての適・不適が審査されるほか、要件事項に関して、他の事務運営指針等によって別途処理手続が定められているものでないかどうかなどが確認される。
形式審査等で提出された照会文書が文書回答の対象となる要件を満たしていないと判断された場合は、文書回答を行わない可能性が照会者に伝えられるが、その場合でも、口頭回答が可能な事前照会については、内容審査のうえ、口頭での回答が行われることになる。
なお、口頭回答における審理体制については、表2の口頭回答に係る部分を参照されたい。
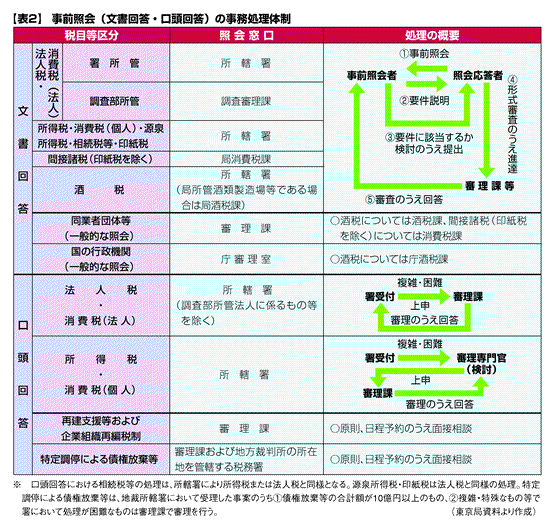 国税局での審理と回答の内容
税務署等での形式審査を経て国税局に送られた照会文書については、審理課等で再度、実務運営指針1(9)に掲げられている、実地確認や取引等関係者等への照会等による事実関係の認定を必要とするもの、同族会社等の行為または計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるものなどに該当しないかどうか確認がなされたうえ、実質審査が行われることになる。
国税局での審理と回答の内容
税務署等での形式審査を経て国税局に送られた照会文書については、審理課等で再度、実務運営指針1(9)に掲げられている、実地確認や取引等関係者等への照会等による事実関係の認定を必要とするもの、同族会社等の行為または計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるものなどに該当しないかどうか確認がなされたうえ、実質審査が行われることになる。審査終了後、照会文書が受付窓口に到達した日から原則3か月以内の極力早期(例外あり)に、回答が行われることとなるが、その回答の内容は、事前照会者の求める見解の内容について①相当と認められる、②相当と認められないとの判断を示すもの、あるいは、同様の照会に対する税務上の取扱いが明らかになり、新たな見解を示すことがないものとなる。
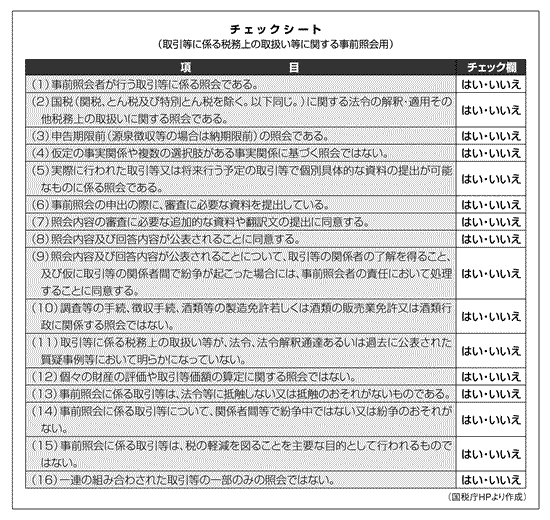
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















