解説記事2008年05月05日 【ニュース特集】 株主提案・買収防衛策を巡る内外機関投資家の動向(2008年5月5日号・№257)
株主提案・買収防衛策を巡る内外機関投資家の動向
新会社法への対応や相次ぐ株主提案が注目された平成19年株主総会を経て、平成20年総会は会社にとって昨年以上に票読みが難しくなりそうだ。海外の投資ファンドのほか、企業年金連合会などが会社に資本効率の改善などを求めて動き出しており、業績低迷企業には株主への説明責任を求めている。また、会社が提案する買収防衛策議案、株主による増配提案も焦点となりそうだ。会社には依然「モノ言う株主」ならぬ安定株主が多数いることもあり、直ちに会社提案が否決されることはなさそうだが、今後の内外機関投資家の動向いかんでは会社提案が否決される事態も見込まれる。
株主・会社間の「対話」の時代到来、会社提案・株主提案の焦点は?
「会社としての考え方を説明にあがりたい」――企業年金連合会(企年連)や運用会社、海外機関投資家が利用する議決権行使助言サービス会社には、こうした電話が5月以降ひっきりなしに鳴るという。総会決議に影響力のある機関投資家と水面下で対話を進めることで、会社が招集通知に記載する会社提案を可決しやすくするのが狙いだ。
従来は会社提案に反対する株主はごく一部であったが、昨年の総会では会社提案の否決事例が出たり(中西敏和「本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響」本誌226号5頁表1参照)、否決にまで至らずとも会社提案への反対比率が3割近くに達するなどの事例が散見された。取締役選任や増配等を求める投資ファンドによる株主提案も顕著に増加したものと捉えられている(216号4頁、今号4頁の表参照)。
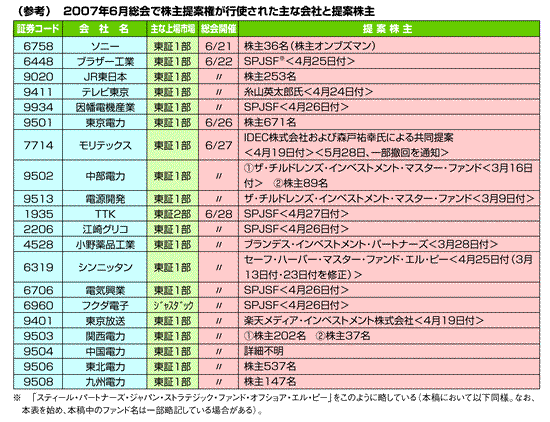
本年総会においても、買収防衛策など株主利益を制限する可能性のある議案には反対が増えそうだ。一般に買収防衛策は、会社の現経営陣の保身につながりかねず、株主提案の機会を奪うおそれがあるとみなされるからである。詳細は後述するが、すでにして表1のように、会社提案とは拮抗することになるであろう株主提案の動きもみられるところである。
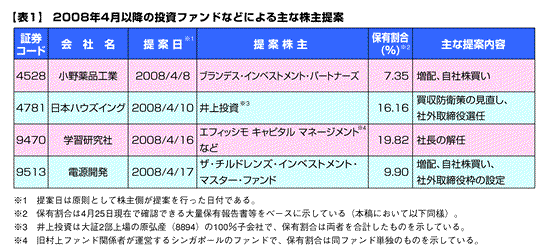
導入相次ぐ買収防衛策、昨年比で1.6倍に 議決権行使に関するデータを提供するガバナンスビジョンズによると、平成17年5月以降、今年3月末までに470社が買収防衛策を導入・更新した。「今年だけで4月23日時点までに89社が導入・更新しており、308社が導入した昨年1年間の同期比と比べても1.6倍のペースで増加している」(小林久仁子代表取締役)という。
買収防衛策の導入企業のうち、社外取締役がいない会社は約34%を占める。外国人持株比率の平均は14%で、外国人持株比率が5%未満の会社から、武富士、ローム、富士フイルムホールディングスなど50%を超える会社もある。
議決権行使助言サービス会社最大手のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)では、「外国人持株比率が5%に満たない会社や松下電器産業など時価総額が高く買収の危機に晒されていないところまでが導入しているのは過剰反応」(マーク・ゴールドスタインISSジャパン代表)と話している。
買収防衛策については、内外機関投資家は原則反対の立場といえる。企年連は3月24日、買収防衛策のルールを一部見直し(255号40頁参照)、ブルドックソースの最高裁判断以降増えている経済的対価を交付する条項の入った買収防衛策には原則反対する方針。買収者に現金などを支払うことは現金などを支払わない他の株主との関係で不公平になるとみている。
ISSや、同様に議決権行使助言サービス会社として知られるグラス・ルイスも、企年連と同じように買収者に現金などを支払う条項がある買収防衛策には反対の立場を採っている。両社ともガイドラインを年初に見直したため、同一内容を盛り込んではいないが、ISSでは社外役員の出席率の基準を追加した一方、グラス・ルイスでは独立委員会の社外役員の要件を過半数から全員に引き上げるなど、より厳格化している(後述参照)。このため、両社が反対を助言する買収防衛策は昨年に比べて増える見通しだ。
増配・社長解任など要求もなお改善求める 昨年総会から顕著な増加傾向にある株主提案。投資ファンドの保有銘柄を確認すると、本年総会以降、提案者や議案の種類が多様化する可能性があるといえる(表2参照)。
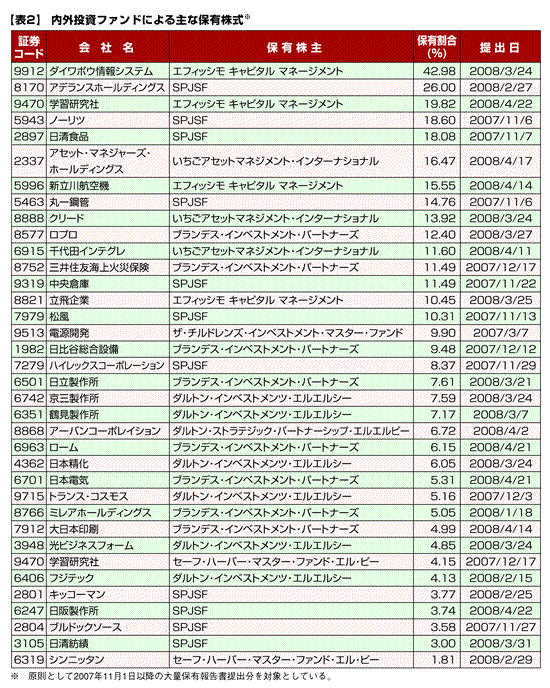
本年総会での株主提案の最大の焦点は剰余金の処分議案である。昨年の総会では2~10倍といったあまりにも大幅な増額要求であったので、他の株主の賛同を得られなかった面がある。が、本年総会では様相を改めて提案を行う事例がみられる。
たとえば、英投資ファンドのザ・チルドレンズ・インベストメント・マスター・ファンド(TCI)は電源開発に対し、昨年に引き続き株主提案をしているが(256号27頁参照)、今年の提案では、他の株主に複数の選択肢を用意することとしている。増配を求める提案において、昨年は1株当たり「期末30円配当を100円」とする提案を行っていた。本年総会に向けては、平成19年3月期実績で60円(中間配当30円、期末配当30円)、平成20年3月期中間配当で30円であるところ、株主提案では選択的に2通りを提示し、①期末配当50円(年間合計80円)、②同90円(年間合計120円)への増額を要求。加えて、「年間120円であっても電力5社同業平均にようやく並ぶ水準」(ジョン・ホーTCIアジア代表)と提案の合理性を主張している。
学習研究社では、エフィッシモキャピタルマネージメント(エフィッシモ)が現社長の解任議案を提案した。エフィッシモでは、「学研は平成19年3月期まで10期連続減収など業績不振で企業価値が大幅に毀損しているため」と説明している。
一方で、学研が明確な改善計画等を示せば、提案を取り下げるとしている。株主提案は、その可決だけが唯一の目的ではなく、経営陣に現状打開を迫る「カード」としても用いられているわけだ。
会社としては、海外の投資ファンドからの株主提案に備え、手続上の対応も必要になりそうだ。会社法では、株主が株主提案権を行使する場合、手続的には「株主総会の日の8週間前までに」とする定めを置いているが(303条・305条)、具体的な方法は定めていない。「株主提案する場合、何を会社に通知するのかのほか、通知の方法などを定款に定める必要もあるのではないか」(堀内勇世大和総研制度調査部次長)との指摘もある。
社外役員の独立性や株式持合いの復活を警戒、説明責任を
投資ファンド等によるこのような状況を踏まえた対応が、冒頭で紹介した企年連などへの電話につながっている。会社は内外機関投資家の動向を把握しておかないと、会社提案が否決されることになりかねず、円滑な総会運営に支障を来すことになるからだ。
もっとも、会社が株主と対話をすれば、会社提案に賛成してくれるわけではない。会社の利益と株主の利益が異なる場合が多いからである。「モノ言う株主」として企年連は、「会社が株主に納得できる説明責任を果たすかどうか」(年金運用部・木村祐基コーポレートガバナンス担当部長)をみており、会社との対話だけで議決権行使上、会社に有利になるわけではないと釘を刺す。
企年連、対話していない企業への訪問検討 企年連や運用会社は、会社に資本効率の改善を働きかけている。業績悪化の原因は会社の経営陣にあるとの判断からだ。
企年連は昨年2月、株主資本をいかに効率的に利用しているかを示す株主資本利益率(ROE)基準を導入した(202号18頁参照)。過去3期連続してROEが8%を下回っている会社には、業績低迷の納得がいく説明を求める。納得のいく説明が得られなければ、取締役の再任等に反対することで意思表示する方針だ。
企年連はさらに今年は7月以降、これまで接点がなかった企業への訪問にも乗り出す考えだ。どういった企業に訪問するかは今後詰める。「企年連が明確な基準を設けて訪問するのであれば、議決権行使のあり方が一変する契機になりうる」(関孝哉日本投資環境研究所首席研究員)と期待も大きい。
議決権行使助言サービス会社の視点 投資ファンドや年金基金など海外機関投資家の多くは、主にISSなどの議決権行使助言サービス会社の助言に基づき議決権行使をしていることもあり、助言会社の助言方針をみることでおおよその動向を把握できる。
ISSやグラス・ルイスは、社外役員の独立性や株式の持合いを疑問視。社内取締役だけでは経営陣への監視機能が乏しいからだ。また、銀行など安定株主が会社の株式を持ち合う必要性は薄れているとみている。
ISSは今年初め、社外取締役の取締役会への出席率を議決権行使の判断基準に加えた。出席率が75%を下回る場合、社外取締役の再任議案に反対を助言する。出席率が低い場合には経営陣を監視する役割を果たしていないとの判断である。マーク・ゴールドスタイン氏は、「鉄鋼業界など株式持合いについて、本来株主に還元すべき利益で競合他社の株式を取得するのは理解に苦しむ」と苦笑する。
グラス・ルイスは、日興コーディアルグループやIHIなど不祥事が起きた会社などの社外監査役の選任に独立性を求める。シニア・プロキシー・リサーチ・アナリストのフランク潤氏は、「形式的に社外でも、実態が独立していないと社外とは認めない。日本の会社は候補者の経歴など会社と独立しているかを判断するための情報開示が不十分」としている。
議決権行使、「行使結果の公表」からの脱却が課題 「議決権行使結果を公表するだけで満足しては何も生まない」――ガバナンスビジョンズの小林久仁子氏は憤る。
企年連を始め、日本の公的年金の多くが議決権行使の結果を議案ごとにウェブサイトなどで公表するのが一般的になった。小林氏は、行使の結果すら公表しなかったときに比べたら格段の進歩だが、これではまだ道半ばだという。行使結果を踏まえ、何が問題点なのか、翌年以降の議決権行使に活かしていくという発想が必要だからである。
海外の投資ファンドのターゲットになった会社には共通点がある。株主に十分な説明のないまま、現金・有価証券・不動産などの資産が豊富、株価が割安に放置されているなどだ。いずれかの株主と利益相反になりうる親子上場の問題を提起するファンドや長期的な運用をしているファンドもある。このため、投資ファンドが会社や市場に一定の規律や刺激を与えているのも事実である。
たとえば、米セーフ・ハーバー・マスター・ファンド・エル・ピーが昨年の総会で剰余金の増額を求める株主提案をしたシンニッタンでは、株主提案は否決されたものの、約30%の株主の支持を集めた。同社はその後、初めて約30%の配当性向を公表、剰余金の増額や自社株買いなどの株主還元策を実施した。株主の目にみえる成果があったのである。
一見すると、公的年金など保守的な国内機関投資家と海外の投資ファンドの議決権行使方針は対照的にみえるが、実は、会社の資本効率を高め、株価を上げたい点では共通しているものと考えられる。多額の資金を運用する公的年金では、株価の下落や配当抑制などで損失を被っている背景もある。ところが、国内機関投資家は会社とのこれまでの関係やマーケット・インパクトなどを理由に沈黙しているのが実態といえる。
本年総会において昨年の失敗に学んだ海外の投資ファンドの株主提案が可決されたり、会社の提案する買収防衛策が否決されたり、大規模な敵対的買収が成功するといった目にみえる変化が起これば、社外役員の独立性の厳格化や株式持合いの解消など会社側の対応も変わってくるであろう。国内機関投資家の主体的な議決権行使がカギを握ることとなりそうだ。
| コラム |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























