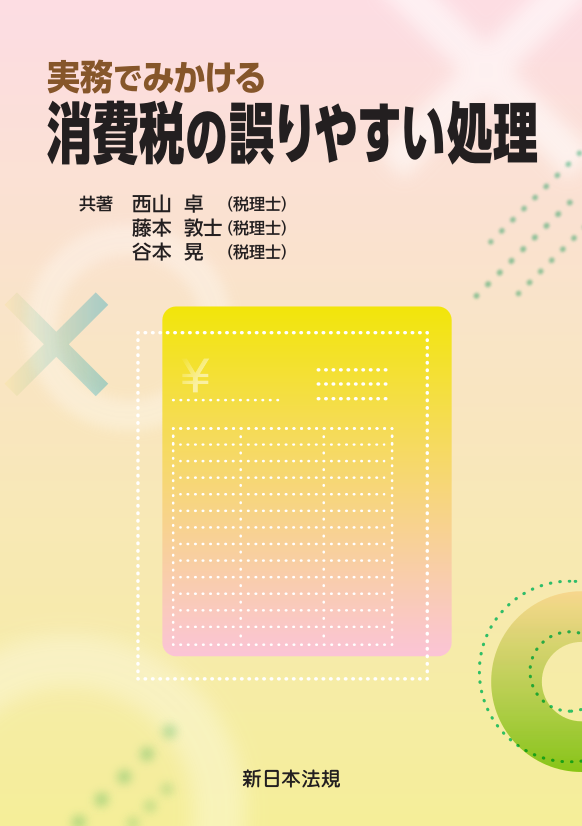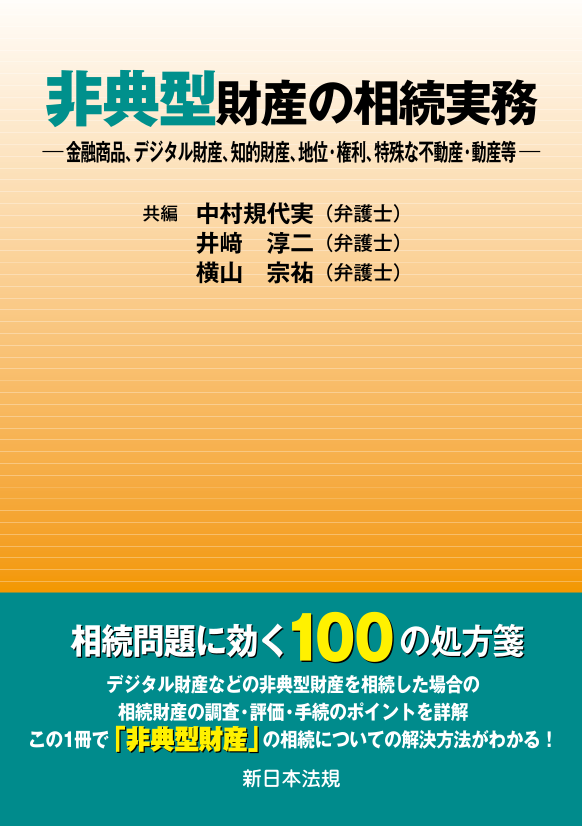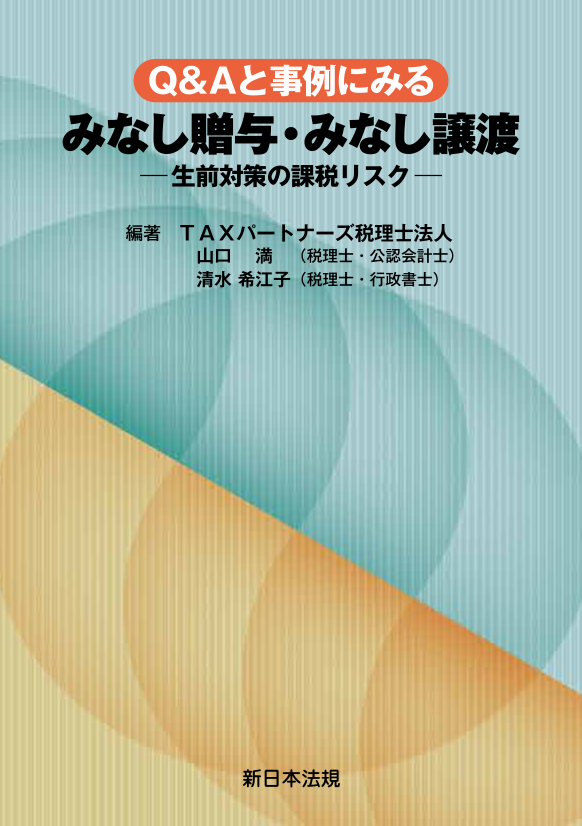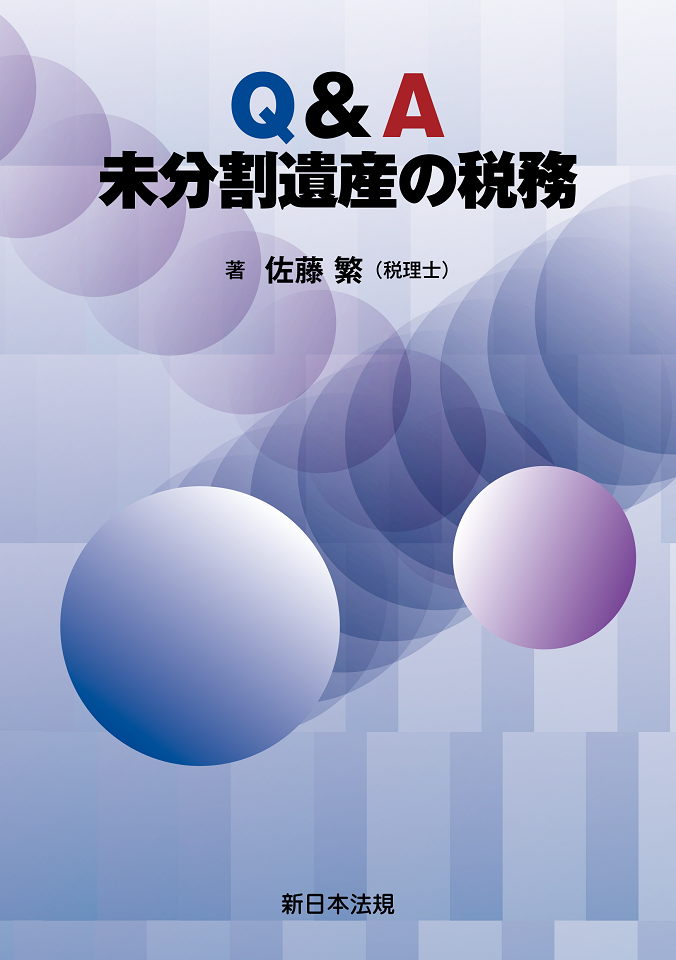解説記事2008年05月26日 【巻頭特集】 会社法がもたらした株主総会環境の変化と本年6月総会に向けての留意事項(2008年5月26日号・№259)
本年総会をどのように捉え、今後に活かすか
会社法がもたらした株主総会環境の変化と本年6月総会に向けての留意事項
三菱UFJ信託銀行(証券代行部門)理事/日本シェアホルダーサービス取締役会長 中西敏和
会社法が平成18年に施行され、3月期決算会社においては、その全面適用下での株主総会を昨年初めて迎えることとなった。本年6月総会は全面適用後第2回目の株主総会ということになるが、会社法の成立・施行とその全面適用がもたらした株主総会を巡る環境変化について、これをどのように捉え、どのように今後の会社の意思決定および株主総会の運営に活かしていくべきなのか。本年6月総会を目前に控えた今、これまでの環境変化を振り返りながら、将来的に進むべき方向性を含めてまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ 会社法全面適用がもたらした影響
本年6月総会における、またはこれ以降の株主総会に向けて検討すべき留意事項を述べる前に、まず会社法の全面適用による書類作成面および付議議案における影響について触れておく。
1 書類作成面での影響 平成19年6月の株主総会は、施行直後の経過的な対応が中心となった18年6月総会とは異なり、会社法全面適用直後の定時総会ということから、書類作成面で若干の混乱がみられた。営業報告書に代わって作成が求められた事業報告については、役員報酬に関する開示、社外役員に関する開示、会計監査人に関する詳細な開示に加えて、会社の業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針の開示の各事項がそれぞれ問題とされた。また、参考書類についても、役員選任議案について参考となる事項の記載、とりわけ社外役員の候補者に関する記載が問題とされた。
なかには役員報酬の開示のように、法令そのものの明瞭性が混乱を増幅したとの判断から会社法施行規則の改正に至ったものもある(平成20年4月1日施行のため、本年3月31日を事業年度末日とする事業報告については旧規則が適用される。松本真・小松岳志「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令』(平成20年法務省令第12号)の要点」本誌253号20頁参照)。
もちろん総会に先駆けて、モデルやひな型、さらには立案担当者を交えた解説書が発刊されたが、改めて実務における実例の重要さを認識された担当者も少なくないものと思われる。
これについては、図表1のとおり、19年6月総会の事例分析が行われ、その結果が紹介されている。本年総会に向けては、これら事例分析の結果を踏まえた対応が可能となり、担当者の負担は大幅に軽減されたものと思われる。ただ、社外役員の特定関係事業者との関係のように、趨勢が不明確な事項や事例が不十分な事項もあり、今後の事例の蓄積が待たれるところである。
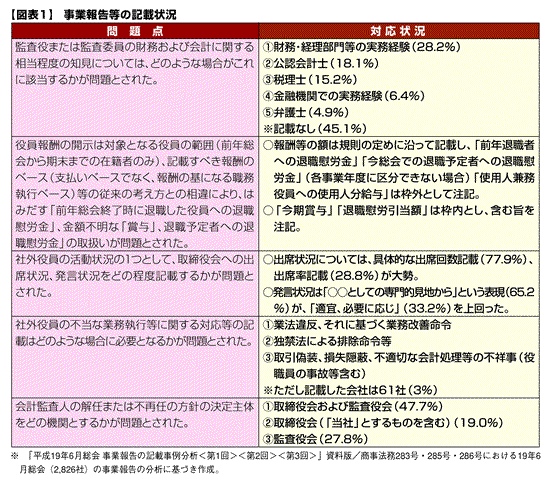
2 付議議案への影響 議案関係では、まず、利益処分案が廃止されたことにより、剰余金の配当が影響を受けた。形式的には議題の変更にすぎないが、事業年度に生じた利益の配分をベースにしたこれまでの考え方から、過去からの蓄積を含めた剰余金の処分をベースにした考え方へと変換が迫られた。後述するとおり、19年6月総会においては投資ファンドを中心とする株主からの増配提案が目立ったが、その一因ともなっている。
なお、剰余金の配当については、同じ剰余金を原資とする配当でも、利益剰余金と資本剰余金とでは課税関係で異なる取扱いが生じるという点について当初混乱がみられた。剰余金配当議案作成にあたっては、原資の違いについても考慮する必要がある。
利益処分案との関係でいえば、役員賞与も影響を受けた。こちらの方は会計処理の変更の後追い的な要素が強いが、役員賞与を単独で付議しなければならなくなったのを1つの契機として、役員賞与を廃止する会社が増えている(図表2参照。以下同様)。加えて、役員報酬関係では、ここ数年役員退職慰労金を廃止する会社が続出し、その結果、これらの廃止に伴い役員報酬改定という形で、株主総会で承認を受ける報酬枠の枠増しに動く会社が増加した。役員報酬については、一方で、すべての会社について事業報告での開示が求められるという問題があり、定例報酬の1本化という方向感がどのように受け取られるかについては、留意すべきである。
付議議案への影響という観点からは、会社法の施行を契機にストック・オプションへの関心が高まりつつある。ストック・オプションの付与は、旧商法のもとでは新株予約権の有利発行
と捉えられていたが、会社法のもとでは職務執行の対価として付与される新株予約権については、有利発行規制が及ばず、報酬としての規制を受けることになった。少なくとも対象が取締役や監査役の場合は、非金銭報酬としての新株予約権の付与と新株予約権の対価としての確定額報酬の支給決議を行うことで足りる。
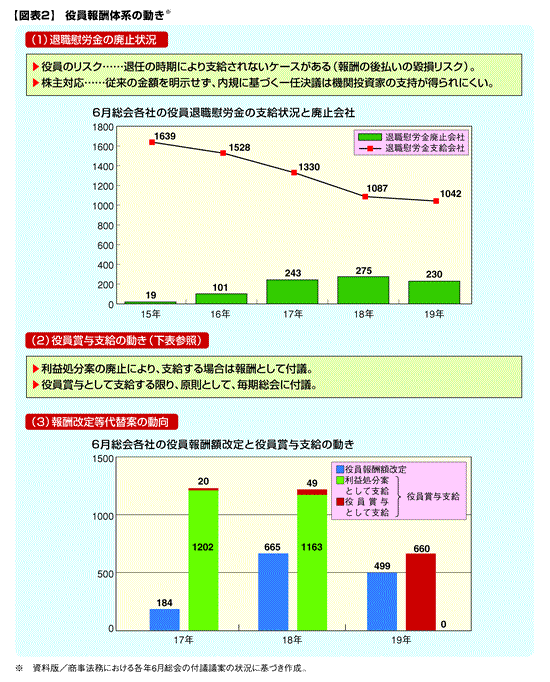
Ⅱ その他の特徴的な動き
次に、前年6月総会でみられた特徴的な動きを概観しておく(詳細については、拙稿「本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響」本誌226号4頁参照)。
1 全体的な動き 平成19年6月総会は、会社法全面適用への対応が大きな課題となったが、ここ数年みられた、株主総会を株主とのコミュニケーションの場として捉える基本的な考え方は維持され、集中日開催の回避(56.2%、前年比2.5ポイント低下)、総会時間の長時間化(平均所要時間55分、前年比3分増加)、出席株主・発言株主の増加といったところに反映されている。
また、来場する株主への歓迎姿勢も、手土産を手交する会社の増加(75.9%、前年比4.4ポイント増)、総会のビジュアル化を実施する会社の増加(65.8%、前年比6.8ポイント増)につながっており、その結果、都心のホテルや集会場を中心とする借会場を利用する会社の増加(51.6%、前年比1.9ポイント増)と会場予約の早期化という現象をもたらしている(以上、数値は2007年版株主総会白書・旬刊「商事法務」1817号による)。
このような動きのなかで着実に変化しているのが、総会における質問内容である。株価を主とし、業績、経営課題、株主還元策が中心となっており、いずれも具体的な質問が多い。来場株主にも、株主としての権利意識が高まりつつあることが感じられる。
ただし、このような動きは必ずしもすべての会社に共通した現象ではなく、一方で、社外株主の出席がほとんどなく、ビジュアル化や手土産とは無縁の会社が存在することも事実である。特に、次に述べる機関投資家対応と敵対的買収防衛策については温度差が強いといえる。
2 機関投資家の動き 機関投資家の動きは、かつては定足数の確保という観点からのみ捉えられがちであったが、上場各社の安定株主比率の低下に伴い、決議の成否という形でも問題となっている。
内外機関投資家の保有割合は年を追って増加しつつあるが、これと歩調を合わせるように、議決権行使に関する対応が厳しさを増している。加えて、自らの議決権行使に関する基準をメディア等を通じて公表する動きも活発化している。
その結果、機関投資家の保有割合が高い会社にあっては、その反対にあって議案が否決されたり、議案の取下げに至る会社も登場し始めている。もちろん、公表された数値でみる限り驚くに足りぬ数値ではあるが、事前に十分な票固めを行ったうえでの結果であり、その過程で議案の撤回または修正を余儀なくされた会社もあることが想定されるところから衝撃的ではある。
機関投資家の行動をいかに早い段階で捉え、全体の賛成票を固めるかが、機関投資家の比率の高い会社を中心に重要課題となっている。
加えて、19年6月総会では、いわゆる投資ファンドと称される株主からの提案が多数寄せられた。結果的にほとんどの会社で否決されたものの、相当数の支持を集めたところもあるといわれている。
それ以上に重要なのは、株主提案がなされたり、議案の成否が危ぶまれる都度、会社側は、会社提案の優位性なり妥当性なりを合理的に説明する必要があるということである。いいかえれば、買収攻勢が仕掛けられたのと似た形で、経営に対する姿勢と今後の経営計画が問われるということでもある。前述の個人株主の意識の高まりも、これと無縁ではない。
3 敵対的買収防衛策 平成19年6月総会では、敵対的買収防衛策は、図表3のとおり209社で導入のための総会決議が行われた。新聞報道によると、今年も相当数の会社で買収防衛策が付議されるといわれている。
その一方で、敵対的買収防衛策の効果に疑問を投げかける動きもあり、見直しを行う会社も出始めている。今いわれている「事前警告型買収防衛策」は、当初取締役会の決議によって行われるタイプからスタートした。その後、導入時点でも株主の意向を反映すべきという議論が強まり、株主総会決議型が主流となったという経緯がある。
ただ、株主総会決議型にしても、その多くは勧告型決議といわれるものであり、それ自体発動について特別の効力を生じさせるものではない。仮に、事前に定款変更を行って定款授権型としても、導入に際しては、会社からの独立性の高いメンバーによって構成された独立委員会の決定に従う必要があり、さらに株主意思の確認が必要という結論が出ることもある。
いずれにしても、これまでの衝撃的な事件の影響のもとに一人歩きした恰好となっており、自社の状況に合ったものを冷静に選択する時期に差し掛かったのではないかと思われる。
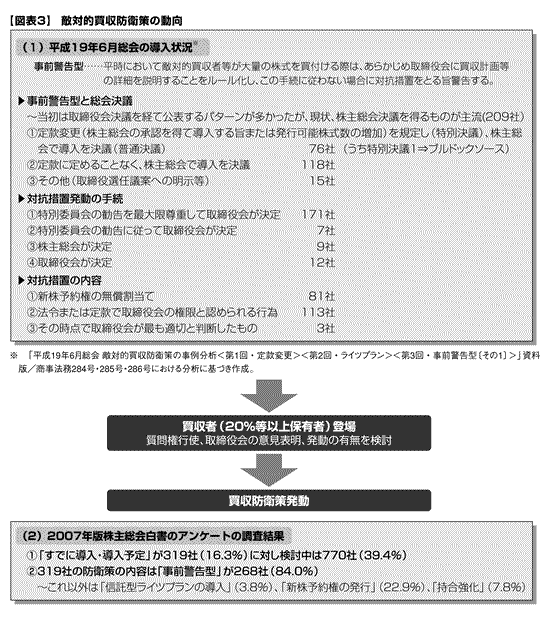
Ⅲ 本年総会に向けての留意事項
平成18年6月総会、19年6月総会と、会社法施行後2回の定時総会を経たことになるが、18年6月総会は全容が明らかでないまま緊急避難的に定款変更に目が向けられ、19年6月総会は全面適用に向けての対応に追われたという経緯がある。そういうなかにあって、本年総会を含め、今後検討すべき事項としては、役員報酬改革、剰余金処分権限の取締役会への委譲、および社外取締役の設置とそのために必要な役員責任軽減規定の創設等が挙げられる。
1 役員報酬改革 役員報酬については、個別開示の要請が強いなか、このまま個別開示を避け続けるならば、支給手続なり決定方針を明らかにし、恣意性が排除されるような仕組みであることを示すことが必要である。
株主総会で承認を得た報酬枠をベースにその配分は半ば取締役会(現実には代表取締役)に白紙委任したかのような現行制度について不透明感が強いとの指摘は従来からある。報酬枠の高低を含めて改めて議論するとすれば、その際に合理的な説明をするためにも、将来的には、業績連動型報酬やストック・オプション制度を組み込んだ複合型の報酬体系を組み込むことを検討すべきである。
事業報告の記載事項であるところから、役員報酬の決定方針については、記載がなくとも、質問があれば回答すべき事項であり、配分方法とその決定手続程度は説明をすべきものと思われる。
2 剰余金処分権限の取締役会への委譲 剰余金処分権限の取締役会への委譲は、18年6月総会で432社がそのための定款変更を行ったことからもわかるように(資料版/商事法務272号208頁参照)、関心が高い事項の1つである。
今後想定される四半期報告制度や会社法で導入済みの臨時計算制度を踏まえ、配当についての機動性を確保するためには、取締役会への権限委譲は早晩求められる課題といえる。配当を含めた剰余金の処分は、本来、経営の根幹に係る事項であり、株主総会のような場で議論するにふさわしい問題とはいえない。将来的には多くの会社が、取締役会に配当等の決定権限を委ねる方向に向かうものと思われる。
これとは別に、本年総会に向けては、取締役会に権限委譲しているかどうかにかかわらず、配当に関する考え方をより明確にする必要がある。事業報告に記載しない場合においても、質問があれば回答に応じるべき事項であり、そのための回答案を用意しておく必要がある。
3 社外取締役の設置等 ガバナンスの強化という観点からは、特に機関投資家を中心に、社外取締役の設置を求める声が強く寄せられている。
社外取締役については、特別取締役といった制度を設ける場合以外は、監査役会設置会社においては設置を義務付けられていない。しかし、内部統制システムの構築義務を始めとして、監査役会の監査機能とは別の意味で、取締役会の監督機能の強化という観点から期待が寄せられている。
また一方で、執行役員制度の導入という形で、社内の業務執行体制について、委員会設置会社のような意思決定と執行の分離を目論み、執行に専念する執行役員と執行と監督を兼ねる取締役執行役員といった構成に移行する会社が増えている。このような会社においても、監督機能の強化という観点から社外取締役を設置する動きがある。
委員会設置会社についてはいまだ移行例が少ないところから、第3の類型ともいえる執行役員制度の法制化とともに、社外取締役の機能をもう1度見直す時期かもしれない。
なお、社外取締役については、海外投資家への議決権行使助言機関であるISSが「取締役会への出席状況(書面決議を除く)が75%未満の場合は再選に反対」との考え方を示している(本誌257号7頁等参照)。候補者選定にあたっては、こういった点も考慮しなければならない。19年6月総会の分析結果でも、社外役員の取締役会への出席状況の記載については回数または割合を示す会社が多数を占めたが(図表1参照)、こういった基準が示されると、なおさらである。
Ⅳ 本年総会に向けての実務上の留意事項
1 株主構造の変化等に伴う対応 すでに述べたとおり、会社法全面適用への対応ということだけを捉えれば、19年6月総会でおおよその方向が示されたことは事実であり、本年6月総会においては、書類作成面では相当レベルが高まっていることが予想される。
一方で、株主構造の変化や株主行動の変化の波が強く寄せられており、それに向けての対応が引き続き大きな課題となる。そして、かつて安定株主比率が高い時代はほとんど関心が向けられなかった機関投資家の動きに従来以上に目が注がれ、プロ株主以外は一顧だにされなかった総会来場株主の動きにも目が向けられる時代となりつつある。
特に、内外機関投資家については、ICJのプラットフォームの利用や専門機関への株主判明調査の依頼といった事項を中心に、名義に登場しない機関投資家との接点を求める動きが活発化している。これまでの英文招集通知のWEBへの開示という待ちの姿勢から、積極的にアピールする動きへと変化しつつある。
本年は、投資ファンドを中心とする株主提案もやや沈静化するようであり、本稿が明らかにされる頃にはすでに株主提案権の行使期限が到来している。だからといって投資ファンドの要求が満たされたというわけではなく、現実に、役員選任議案への反対票を含めて実質的な対応を検討する動きもあるようである。
この場合、議決権行使基準等と照らし合わせて否決の可能性のある議案については、最後の最後まで必要な説明や票読みを行う努力が必要である。また、万が一、委任状勧誘といった形で組織的に反対活動が行われた場合に備え、株主名簿の閲覧・謄写請求等の動きには十分注意が必要である。
機関投資家と同様に、今後、議決権行使との関係で強い関心が寄せられると思われるのが個人株主である。現状、個人株主については、せっかく来場した株主に対しても、抽象的には歓迎姿勢を示すものの、質問でもなされない限り、その把握すらされていないのが実情と思われる。
いずれ、賛否が伯仲すると、総会来場の株主の動きは無視できないものとなり、場合によっては投票すら行う必要があるかもしれない。まず、株主総会の決議で投票を行うことが求められた際の対応とともに、来場した株主との接点を求めるための工夫(たとえば、アンケート用紙配付による出口調査等)も検討すべきである。
また、来場しない株主に対しても、議決権の行使比率を上げる努力は必要である。株主の議決権行使比率を引き上げるための方策として行われた、議決権行使書を返送した株主に対するQuoカードの提供が利益供与に当たるとされた裁判例が世間の耳目を集めたが(東京地判平成19年12月6日モリテックス総会決議取消請求事件。本誌240号66頁参照)、すべての事例について利益供与と認定されたわけではない。対象とされた事例のように、委任状勧誘合戦が行われているような場合には行うべきではないが、ただ単に定足数確保を目的としたケースについてまで問題とされているわけではなく、まさにケース・バイ・ケースである。
一方で、総会に来場する株主の活発な発言が増加している。質問内容が限定されるだけに頭打ちのきらいもみられるが、まじめな質問に対してはまじめに回答することが必要である。したがって、説明義務を超えた質問であってもまじめな質問である限り、応えられる範囲で応えるべきであり、トップが率先して行うべきである。
また、質疑応答において、株主が回答者を指名してくるケースがある。特に著名人を社外役員にしている場合はその傾向が強い。
もちろん指名に応じる必要はなく、あらかじめ社内で定められた役割分担に応じて所定の担当役員が議長の指名を受け、指名に従って回答するのが原則であることに変わりはないが、絶対的にタブーというわけでもない。ときに、社外役員自ら答弁した方が適切と判断されれば、議長に自らを指名するよう求め、その指名のもとに回答することもやぶさかではない。まさに「せっかくの機会でございますから……」である。
総会場に来た株主すべての顔がみえているわけではなく、安易に答弁するのは避けるべきであることに変わりはないが、いくつかの質疑が繰り返された後、相手を見極めたうえで指名を受け、参加すべきであろう。企業買収の活発化や敵対的買収に関する防衛論議、増配を中心とする株主提案といった動きに触発される形で個人株主が当事者意識を高めたことも事実である。そういった意味で株主総会は気が抜けない。
2 任意の開示事項への対応 会社法のもとでは、事業報告での任意の開示を規定した事項が少なくない。その典型ともいえるのが、剰余金の配当等を取締役会の権限とする旨の定款の定めがある会社に求められる権限の行使に関する方針(会社法施行規則126条10号)、株式会社の支配に関する方針を定めている場合に求められる基本方針の内容等(同規則127条)、役員報酬の額またはその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法およびその方針の内容の概要(同規則121条5号)等である。これらはいずれも関心の高い事項であり、将来的には任意であっても記載する方向で検討すべきものと思われる。
ちなみに、剰余金の配当を付議する場合、法文上は、①配当財産の種類および帳簿価額の総額、②株主に対する配当財産の割当てに関する事項、③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日の3つの記載が求められているが(会社法454条1項)、配当政策はその重要性から、参考事項として当然記載すべきであって、実例においてもほとんどすべての会社が記載している。これを、剰余金の配当が付議されない場合も含めて、事業報告に剰余金の配当方針として記載してはどうかということである。
また、買収防衛策の導入を決議した会社は、基本方針を含めてその詳細を議案として記載することが求められており、導入した会社については、以後事業報告に「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」として、当該防衛策の内容を開示すべきことは当然である。ただ、敵対的買収防衛策を導入するかしないかにかかわらず、支配する者のあり方に関する基本方針は、ほぼ各社とも企業価値の向上策を中心に定まっているものと思われるので、その方針と取組姿勢を積極的に開示してはどうかということである。
これらは、それぞれに対する株主の質問への回答であり、質問を受ける前に積極的に開示した方が得策ではないかと思われる。
3 その他の対応 最後にテクニカルな問題をいくつか述べる。まず、年々増加する一方の出席株主であるが、増えた原因は必ずしも一律ではない。何らかの事情で個人株主数が増えた、世間の関心を集めた、有名企業であるといったいくつかの共通する原因はあるが、それだけではないようである。要するに、読めないのである。
これに対して、会場を設営する側としては、総会当日用意した会場に、来場した株主すべてを着席させるのが原則であり、仮にできなければ急遽場所を用意してでも全員着席を願うほかない。
したがって、万が一の場合に備えて予備の会場は手配しておくべきである。そして、予備会場に最低限必要な機器は、本会場の状況がリアルタイムでわかるようなモニターと、予備会場の状況がタイムリーに議長および事務局に伝わるに必要な仕組みまたは体制である。当日、本会場に入りきれず、予備会場で発言を求める株主がいた場合は、議長にその旨を連携して指名を求め、議長の指名を受けて、議長に一時総会を中断させ、その間本会場に誘導して本会場の所定のマイクで発言させるということである。この手順をきちんと踏むことが重要である。
次に、総会場での投票である。会社が必要とする場合、これに備えることは当然であるが、総会場の雰囲気次第では、会社側が必要としないにもかかわらず、投票を求める動議が提出されることも考慮すべきであろう。総会場の多数の賛成があれば、これに従って投票の方法で採決を行う必要がある。
このような事態を避けるためにも、当日の総会場での多数を占めておく算段が必要である。大株主については、自ら出席してもらうか、包括委任状を貰い受け、意思表示をしてもらう必要がある。
なお、総会に出席する役員は通常、議決権行使書を手交したり、包括委任状を提出することなく、本人自らが出席という取扱いが多いが、採決の際、意思表示がないことを理由に除かれるおそれがあることに留意する必要がある。通常、問題となることはないが、まさに賛否が伯仲する場合には、その行方は重大である。定められた意思表示を忘れないようにしなければならない。
最後に、会社法がもたらした効果の1つとして挙げられるのは、インターネット開示による招集通知記載事項の一部省略とWEBサイトへの掲示による修正事項の周知である。
前者については時期的に困難ではあるが、後者については、何はともあれ、招集通知に記載しておくことであり、それを踏まえ、万が一修正が生じた場合には、時をはずさず、取締役会の決議を経て開示することである。
(なかにし・としかず)
会社法がもたらした株主総会環境の変化と本年6月総会に向けての留意事項
三菱UFJ信託銀行(証券代行部門)理事/日本シェアホルダーサービス取締役会長 中西敏和
会社法が平成18年に施行され、3月期決算会社においては、その全面適用下での株主総会を昨年初めて迎えることとなった。本年6月総会は全面適用後第2回目の株主総会ということになるが、会社法の成立・施行とその全面適用がもたらした株主総会を巡る環境変化について、これをどのように捉え、どのように今後の会社の意思決定および株主総会の運営に活かしていくべきなのか。本年6月総会を目前に控えた今、これまでの環境変化を振り返りながら、将来的に進むべき方向性を含めてまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ 会社法全面適用がもたらした影響
本年6月総会における、またはこれ以降の株主総会に向けて検討すべき留意事項を述べる前に、まず会社法の全面適用による書類作成面および付議議案における影響について触れておく。
1 書類作成面での影響 平成19年6月の株主総会は、施行直後の経過的な対応が中心となった18年6月総会とは異なり、会社法全面適用直後の定時総会ということから、書類作成面で若干の混乱がみられた。営業報告書に代わって作成が求められた事業報告については、役員報酬に関する開示、社外役員に関する開示、会計監査人に関する詳細な開示に加えて、会社の業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針の開示の各事項がそれぞれ問題とされた。また、参考書類についても、役員選任議案について参考となる事項の記載、とりわけ社外役員の候補者に関する記載が問題とされた。
なかには役員報酬の開示のように、法令そのものの明瞭性が混乱を増幅したとの判断から会社法施行規則の改正に至ったものもある(平成20年4月1日施行のため、本年3月31日を事業年度末日とする事業報告については旧規則が適用される。松本真・小松岳志「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令』(平成20年法務省令第12号)の要点」本誌253号20頁参照)。
もちろん総会に先駆けて、モデルやひな型、さらには立案担当者を交えた解説書が発刊されたが、改めて実務における実例の重要さを認識された担当者も少なくないものと思われる。
これについては、図表1のとおり、19年6月総会の事例分析が行われ、その結果が紹介されている。本年総会に向けては、これら事例分析の結果を踏まえた対応が可能となり、担当者の負担は大幅に軽減されたものと思われる。ただ、社外役員の特定関係事業者との関係のように、趨勢が不明確な事項や事例が不十分な事項もあり、今後の事例の蓄積が待たれるところである。
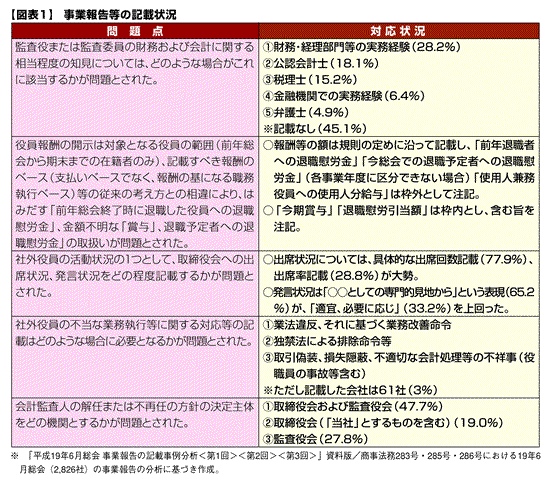
2 付議議案への影響 議案関係では、まず、利益処分案が廃止されたことにより、剰余金の配当が影響を受けた。形式的には議題の変更にすぎないが、事業年度に生じた利益の配分をベースにしたこれまでの考え方から、過去からの蓄積を含めた剰余金の処分をベースにした考え方へと変換が迫られた。後述するとおり、19年6月総会においては投資ファンドを中心とする株主からの増配提案が目立ったが、その一因ともなっている。
なお、剰余金の配当については、同じ剰余金を原資とする配当でも、利益剰余金と資本剰余金とでは課税関係で異なる取扱いが生じるという点について当初混乱がみられた。剰余金配当議案作成にあたっては、原資の違いについても考慮する必要がある。
利益処分案との関係でいえば、役員賞与も影響を受けた。こちらの方は会計処理の変更の後追い的な要素が強いが、役員賞与を単独で付議しなければならなくなったのを1つの契機として、役員賞与を廃止する会社が増えている(図表2参照。以下同様)。加えて、役員報酬関係では、ここ数年役員退職慰労金を廃止する会社が続出し、その結果、これらの廃止に伴い役員報酬改定という形で、株主総会で承認を受ける報酬枠の枠増しに動く会社が増加した。役員報酬については、一方で、すべての会社について事業報告での開示が求められるという問題があり、定例報酬の1本化という方向感がどのように受け取られるかについては、留意すべきである。
付議議案への影響という観点からは、会社法の施行を契機にストック・オプションへの関心が高まりつつある。ストック・オプションの付与は、旧商法のもとでは新株予約権の有利発行
と捉えられていたが、会社法のもとでは職務執行の対価として付与される新株予約権については、有利発行規制が及ばず、報酬としての規制を受けることになった。少なくとも対象が取締役や監査役の場合は、非金銭報酬としての新株予約権の付与と新株予約権の対価としての確定額報酬の支給決議を行うことで足りる。
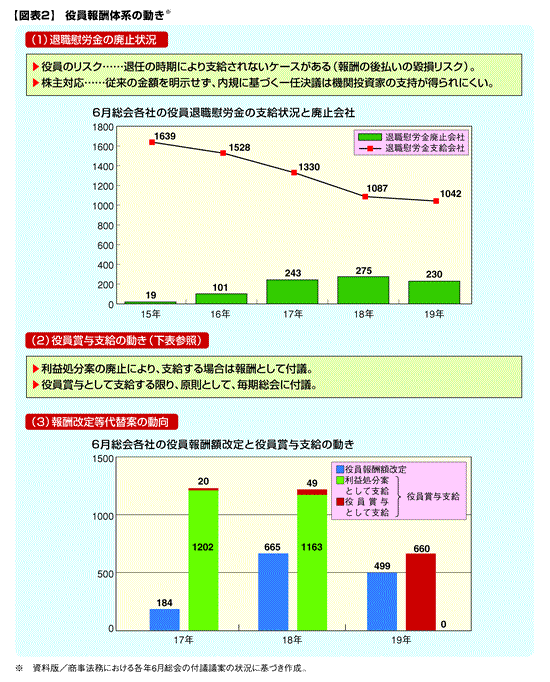
Ⅱ その他の特徴的な動き
次に、前年6月総会でみられた特徴的な動きを概観しておく(詳細については、拙稿「本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響」本誌226号4頁参照)。
1 全体的な動き 平成19年6月総会は、会社法全面適用への対応が大きな課題となったが、ここ数年みられた、株主総会を株主とのコミュニケーションの場として捉える基本的な考え方は維持され、集中日開催の回避(56.2%、前年比2.5ポイント低下)、総会時間の長時間化(平均所要時間55分、前年比3分増加)、出席株主・発言株主の増加といったところに反映されている。
また、来場する株主への歓迎姿勢も、手土産を手交する会社の増加(75.9%、前年比4.4ポイント増)、総会のビジュアル化を実施する会社の増加(65.8%、前年比6.8ポイント増)につながっており、その結果、都心のホテルや集会場を中心とする借会場を利用する会社の増加(51.6%、前年比1.9ポイント増)と会場予約の早期化という現象をもたらしている(以上、数値は2007年版株主総会白書・旬刊「商事法務」1817号による)。
このような動きのなかで着実に変化しているのが、総会における質問内容である。株価を主とし、業績、経営課題、株主還元策が中心となっており、いずれも具体的な質問が多い。来場株主にも、株主としての権利意識が高まりつつあることが感じられる。
ただし、このような動きは必ずしもすべての会社に共通した現象ではなく、一方で、社外株主の出席がほとんどなく、ビジュアル化や手土産とは無縁の会社が存在することも事実である。特に、次に述べる機関投資家対応と敵対的買収防衛策については温度差が強いといえる。
2 機関投資家の動き 機関投資家の動きは、かつては定足数の確保という観点からのみ捉えられがちであったが、上場各社の安定株主比率の低下に伴い、決議の成否という形でも問題となっている。
内外機関投資家の保有割合は年を追って増加しつつあるが、これと歩調を合わせるように、議決権行使に関する対応が厳しさを増している。加えて、自らの議決権行使に関する基準をメディア等を通じて公表する動きも活発化している。
その結果、機関投資家の保有割合が高い会社にあっては、その反対にあって議案が否決されたり、議案の取下げに至る会社も登場し始めている。もちろん、公表された数値でみる限り驚くに足りぬ数値ではあるが、事前に十分な票固めを行ったうえでの結果であり、その過程で議案の撤回または修正を余儀なくされた会社もあることが想定されるところから衝撃的ではある。
機関投資家の行動をいかに早い段階で捉え、全体の賛成票を固めるかが、機関投資家の比率の高い会社を中心に重要課題となっている。
加えて、19年6月総会では、いわゆる投資ファンドと称される株主からの提案が多数寄せられた。結果的にほとんどの会社で否決されたものの、相当数の支持を集めたところもあるといわれている。
それ以上に重要なのは、株主提案がなされたり、議案の成否が危ぶまれる都度、会社側は、会社提案の優位性なり妥当性なりを合理的に説明する必要があるということである。いいかえれば、買収攻勢が仕掛けられたのと似た形で、経営に対する姿勢と今後の経営計画が問われるということでもある。前述の個人株主の意識の高まりも、これと無縁ではない。
3 敵対的買収防衛策 平成19年6月総会では、敵対的買収防衛策は、図表3のとおり209社で導入のための総会決議が行われた。新聞報道によると、今年も相当数の会社で買収防衛策が付議されるといわれている。
その一方で、敵対的買収防衛策の効果に疑問を投げかける動きもあり、見直しを行う会社も出始めている。今いわれている「事前警告型買収防衛策」は、当初取締役会の決議によって行われるタイプからスタートした。その後、導入時点でも株主の意向を反映すべきという議論が強まり、株主総会決議型が主流となったという経緯がある。
ただ、株主総会決議型にしても、その多くは勧告型決議といわれるものであり、それ自体発動について特別の効力を生じさせるものではない。仮に、事前に定款変更を行って定款授権型としても、導入に際しては、会社からの独立性の高いメンバーによって構成された独立委員会の決定に従う必要があり、さらに株主意思の確認が必要という結論が出ることもある。
いずれにしても、これまでの衝撃的な事件の影響のもとに一人歩きした恰好となっており、自社の状況に合ったものを冷静に選択する時期に差し掛かったのではないかと思われる。
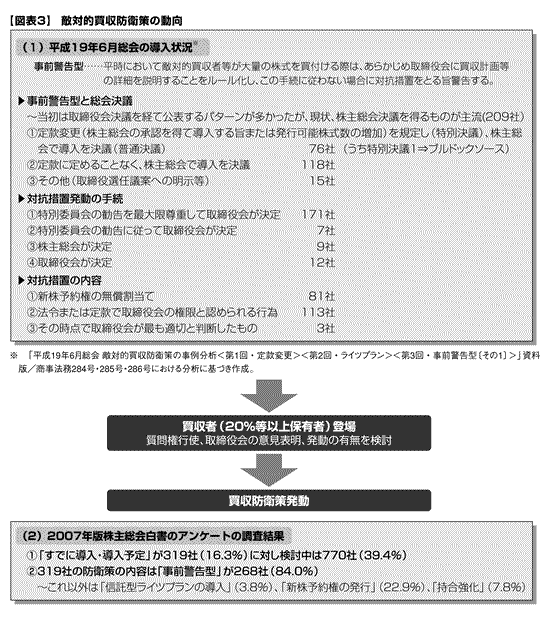
Ⅲ 本年総会に向けての留意事項
平成18年6月総会、19年6月総会と、会社法施行後2回の定時総会を経たことになるが、18年6月総会は全容が明らかでないまま緊急避難的に定款変更に目が向けられ、19年6月総会は全面適用に向けての対応に追われたという経緯がある。そういうなかにあって、本年総会を含め、今後検討すべき事項としては、役員報酬改革、剰余金処分権限の取締役会への委譲、および社外取締役の設置とそのために必要な役員責任軽減規定の創設等が挙げられる。
1 役員報酬改革 役員報酬については、個別開示の要請が強いなか、このまま個別開示を避け続けるならば、支給手続なり決定方針を明らかにし、恣意性が排除されるような仕組みであることを示すことが必要である。
株主総会で承認を得た報酬枠をベースにその配分は半ば取締役会(現実には代表取締役)に白紙委任したかのような現行制度について不透明感が強いとの指摘は従来からある。報酬枠の高低を含めて改めて議論するとすれば、その際に合理的な説明をするためにも、将来的には、業績連動型報酬やストック・オプション制度を組み込んだ複合型の報酬体系を組み込むことを検討すべきである。
事業報告の記載事項であるところから、役員報酬の決定方針については、記載がなくとも、質問があれば回答すべき事項であり、配分方法とその決定手続程度は説明をすべきものと思われる。
2 剰余金処分権限の取締役会への委譲 剰余金処分権限の取締役会への委譲は、18年6月総会で432社がそのための定款変更を行ったことからもわかるように(資料版/商事法務272号208頁参照)、関心が高い事項の1つである。
今後想定される四半期報告制度や会社法で導入済みの臨時計算制度を踏まえ、配当についての機動性を確保するためには、取締役会への権限委譲は早晩求められる課題といえる。配当を含めた剰余金の処分は、本来、経営の根幹に係る事項であり、株主総会のような場で議論するにふさわしい問題とはいえない。将来的には多くの会社が、取締役会に配当等の決定権限を委ねる方向に向かうものと思われる。
これとは別に、本年総会に向けては、取締役会に権限委譲しているかどうかにかかわらず、配当に関する考え方をより明確にする必要がある。事業報告に記載しない場合においても、質問があれば回答に応じるべき事項であり、そのための回答案を用意しておく必要がある。
3 社外取締役の設置等 ガバナンスの強化という観点からは、特に機関投資家を中心に、社外取締役の設置を求める声が強く寄せられている。
社外取締役については、特別取締役といった制度を設ける場合以外は、監査役会設置会社においては設置を義務付けられていない。しかし、内部統制システムの構築義務を始めとして、監査役会の監査機能とは別の意味で、取締役会の監督機能の強化という観点から期待が寄せられている。
また一方で、執行役員制度の導入という形で、社内の業務執行体制について、委員会設置会社のような意思決定と執行の分離を目論み、執行に専念する執行役員と執行と監督を兼ねる取締役執行役員といった構成に移行する会社が増えている。このような会社においても、監督機能の強化という観点から社外取締役を設置する動きがある。
委員会設置会社についてはいまだ移行例が少ないところから、第3の類型ともいえる執行役員制度の法制化とともに、社外取締役の機能をもう1度見直す時期かもしれない。
なお、社外取締役については、海外投資家への議決権行使助言機関であるISSが「取締役会への出席状況(書面決議を除く)が75%未満の場合は再選に反対」との考え方を示している(本誌257号7頁等参照)。候補者選定にあたっては、こういった点も考慮しなければならない。19年6月総会の分析結果でも、社外役員の取締役会への出席状況の記載については回数または割合を示す会社が多数を占めたが(図表1参照)、こういった基準が示されると、なおさらである。
Ⅳ 本年総会に向けての実務上の留意事項
1 株主構造の変化等に伴う対応 すでに述べたとおり、会社法全面適用への対応ということだけを捉えれば、19年6月総会でおおよその方向が示されたことは事実であり、本年6月総会においては、書類作成面では相当レベルが高まっていることが予想される。
一方で、株主構造の変化や株主行動の変化の波が強く寄せられており、それに向けての対応が引き続き大きな課題となる。そして、かつて安定株主比率が高い時代はほとんど関心が向けられなかった機関投資家の動きに従来以上に目が注がれ、プロ株主以外は一顧だにされなかった総会来場株主の動きにも目が向けられる時代となりつつある。
特に、内外機関投資家については、ICJのプラットフォームの利用や専門機関への株主判明調査の依頼といった事項を中心に、名義に登場しない機関投資家との接点を求める動きが活発化している。これまでの英文招集通知のWEBへの開示という待ちの姿勢から、積極的にアピールする動きへと変化しつつある。
本年は、投資ファンドを中心とする株主提案もやや沈静化するようであり、本稿が明らかにされる頃にはすでに株主提案権の行使期限が到来している。だからといって投資ファンドの要求が満たされたというわけではなく、現実に、役員選任議案への反対票を含めて実質的な対応を検討する動きもあるようである。
この場合、議決権行使基準等と照らし合わせて否決の可能性のある議案については、最後の最後まで必要な説明や票読みを行う努力が必要である。また、万が一、委任状勧誘といった形で組織的に反対活動が行われた場合に備え、株主名簿の閲覧・謄写請求等の動きには十分注意が必要である。
機関投資家と同様に、今後、議決権行使との関係で強い関心が寄せられると思われるのが個人株主である。現状、個人株主については、せっかく来場した株主に対しても、抽象的には歓迎姿勢を示すものの、質問でもなされない限り、その把握すらされていないのが実情と思われる。
いずれ、賛否が伯仲すると、総会来場の株主の動きは無視できないものとなり、場合によっては投票すら行う必要があるかもしれない。まず、株主総会の決議で投票を行うことが求められた際の対応とともに、来場した株主との接点を求めるための工夫(たとえば、アンケート用紙配付による出口調査等)も検討すべきである。
また、来場しない株主に対しても、議決権の行使比率を上げる努力は必要である。株主の議決権行使比率を引き上げるための方策として行われた、議決権行使書を返送した株主に対するQuoカードの提供が利益供与に当たるとされた裁判例が世間の耳目を集めたが(東京地判平成19年12月6日モリテックス総会決議取消請求事件。本誌240号66頁参照)、すべての事例について利益供与と認定されたわけではない。対象とされた事例のように、委任状勧誘合戦が行われているような場合には行うべきではないが、ただ単に定足数確保を目的としたケースについてまで問題とされているわけではなく、まさにケース・バイ・ケースである。
一方で、総会に来場する株主の活発な発言が増加している。質問内容が限定されるだけに頭打ちのきらいもみられるが、まじめな質問に対してはまじめに回答することが必要である。したがって、説明義務を超えた質問であってもまじめな質問である限り、応えられる範囲で応えるべきであり、トップが率先して行うべきである。
また、質疑応答において、株主が回答者を指名してくるケースがある。特に著名人を社外役員にしている場合はその傾向が強い。
もちろん指名に応じる必要はなく、あらかじめ社内で定められた役割分担に応じて所定の担当役員が議長の指名を受け、指名に従って回答するのが原則であることに変わりはないが、絶対的にタブーというわけでもない。ときに、社外役員自ら答弁した方が適切と判断されれば、議長に自らを指名するよう求め、その指名のもとに回答することもやぶさかではない。まさに「せっかくの機会でございますから……」である。
総会場に来た株主すべての顔がみえているわけではなく、安易に答弁するのは避けるべきであることに変わりはないが、いくつかの質疑が繰り返された後、相手を見極めたうえで指名を受け、参加すべきであろう。企業買収の活発化や敵対的買収に関する防衛論議、増配を中心とする株主提案といった動きに触発される形で個人株主が当事者意識を高めたことも事実である。そういった意味で株主総会は気が抜けない。
2 任意の開示事項への対応 会社法のもとでは、事業報告での任意の開示を規定した事項が少なくない。その典型ともいえるのが、剰余金の配当等を取締役会の権限とする旨の定款の定めがある会社に求められる権限の行使に関する方針(会社法施行規則126条10号)、株式会社の支配に関する方針を定めている場合に求められる基本方針の内容等(同規則127条)、役員報酬の額またはその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法およびその方針の内容の概要(同規則121条5号)等である。これらはいずれも関心の高い事項であり、将来的には任意であっても記載する方向で検討すべきものと思われる。
ちなみに、剰余金の配当を付議する場合、法文上は、①配当財産の種類および帳簿価額の総額、②株主に対する配当財産の割当てに関する事項、③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日の3つの記載が求められているが(会社法454条1項)、配当政策はその重要性から、参考事項として当然記載すべきであって、実例においてもほとんどすべての会社が記載している。これを、剰余金の配当が付議されない場合も含めて、事業報告に剰余金の配当方針として記載してはどうかということである。
また、買収防衛策の導入を決議した会社は、基本方針を含めてその詳細を議案として記載することが求められており、導入した会社については、以後事業報告に「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」として、当該防衛策の内容を開示すべきことは当然である。ただ、敵対的買収防衛策を導入するかしないかにかかわらず、支配する者のあり方に関する基本方針は、ほぼ各社とも企業価値の向上策を中心に定まっているものと思われるので、その方針と取組姿勢を積極的に開示してはどうかということである。
これらは、それぞれに対する株主の質問への回答であり、質問を受ける前に積極的に開示した方が得策ではないかと思われる。
3 その他の対応 最後にテクニカルな問題をいくつか述べる。まず、年々増加する一方の出席株主であるが、増えた原因は必ずしも一律ではない。何らかの事情で個人株主数が増えた、世間の関心を集めた、有名企業であるといったいくつかの共通する原因はあるが、それだけではないようである。要するに、読めないのである。
これに対して、会場を設営する側としては、総会当日用意した会場に、来場した株主すべてを着席させるのが原則であり、仮にできなければ急遽場所を用意してでも全員着席を願うほかない。
したがって、万が一の場合に備えて予備の会場は手配しておくべきである。そして、予備会場に最低限必要な機器は、本会場の状況がリアルタイムでわかるようなモニターと、予備会場の状況がタイムリーに議長および事務局に伝わるに必要な仕組みまたは体制である。当日、本会場に入りきれず、予備会場で発言を求める株主がいた場合は、議長にその旨を連携して指名を求め、議長の指名を受けて、議長に一時総会を中断させ、その間本会場に誘導して本会場の所定のマイクで発言させるということである。この手順をきちんと踏むことが重要である。
次に、総会場での投票である。会社が必要とする場合、これに備えることは当然であるが、総会場の雰囲気次第では、会社側が必要としないにもかかわらず、投票を求める動議が提出されることも考慮すべきであろう。総会場の多数の賛成があれば、これに従って投票の方法で採決を行う必要がある。
このような事態を避けるためにも、当日の総会場での多数を占めておく算段が必要である。大株主については、自ら出席してもらうか、包括委任状を貰い受け、意思表示をしてもらう必要がある。
なお、総会に出席する役員は通常、議決権行使書を手交したり、包括委任状を提出することなく、本人自らが出席という取扱いが多いが、採決の際、意思表示がないことを理由に除かれるおそれがあることに留意する必要がある。通常、問題となることはないが、まさに賛否が伯仲する場合には、その行方は重大である。定められた意思表示を忘れないようにしなければならない。
最後に、会社法がもたらした効果の1つとして挙げられるのは、インターネット開示による招集通知記載事項の一部省略とWEBサイトへの掲示による修正事項の周知である。
前者については時期的に困難ではあるが、後者については、何はともあれ、招集通知に記載しておくことであり、それを踏まえ、万が一修正が生じた場合には、時をはずさず、取締役会の決議を経て開示することである。
(なかにし・としかず)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.