解説記事2008年09月22日 【制度解説】 新しい公益法人制度と今後の課題(2008年9月22日号・№275)
解説
新しい公益法人制度と今後の課題
(社)日本経済団体連合会 総務本部 野村良寿
公益法人制度を巡っては、2006年6月に公益法人改革三法が成立し、本年12月1日から、新しい公益法人制度が開始する。従来の主務官庁の指導監督のもとで運営する形から、法人自らの自主的な運営を重視し、民間による自発的で多様な公益活動を推進する方向へと大きく舵が取られる。新制度施行まで半年を切り、既に多くの公益法人が新制度への対応作業を進めている。本稿では、新制度の概要について触れたうえで、実務に照らした新制度の課題について、採り上げることとする。なお、文中意見にわたる部分は、もとより筆者の私見にとどまる。
Ⅰ 新公益法人制度の概要
公益法人は、明治以来、民法34条(「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」)に基づき、主務官庁の指導監督のもと、運営が行われてきた。
しかし、小さく効率的な政府への転換、あるいは官から民への流れが進むなか、公益活動を担う主体としての民間の非営利活動への期待が高まってきた。また、政府の関連公益法人による不祥事や予算の無駄遣い等の問題も散見される。そこで、「民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、(中略)公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする」(公益認定法1条)新制度への移行が図られることになった(図表1参照)。
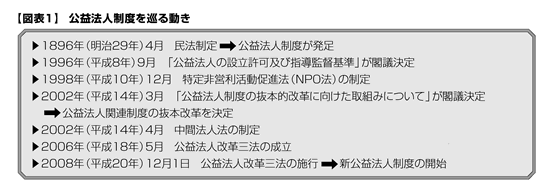
新制度を構成する法律は、(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」)、(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」)、(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」)の3法からなる。(1)一般法は、新制度のもとでの法人のガバナンス等、(2)公益認定法は、行政庁から公益認定を受ける際の認定基準、公益認定を受けた法人のガバナンス等について定めている。(3)整備法は、現行の公益法人が新制度下の法人に移行する際の要件、手続等を定めた法律である。
新制度で定められた公益法人の形態は、①一般社団法人、②一般財団法人、③公益社団法人、④公益財団法人の4つである。従来、公益法人の設立には政府の許可が必要であったが、新制度では登記のみで社団法人、財団法人を設立できる(一般法22条)。こうして設立された法人が一般社団・財団法人であり、一般法のもとで運営を行う。一般社団・財団法人のうち、行政庁から公益性があると認定を受けた法人が公益社団・財団法人となる。
公益性の認定については、現行制度においては実質的に主務官庁の指導監督を通じてなされていたが、新制度では、公益認定法に定められた公益認定基準に基づき、有識者で構成される第三者委員会である、政府の「公益認定等委員会」、あるいは都道府県の合議制の機関が行うことになる(公益認定法32条、50条)。
現行の公益法人については、本年12月の新制度の施行以降、自動的に「特例社団法人・財団法人」となり、主務官庁による監督、税制など、現行制度同様の扱いを受けるが、5年以内(平成25年11月末まで)に移行しなければ、解散となる(整備法46条)。この5年間に、行政庁から一般社団・財団法人への移行認可、あるいは公益社団・財団法人への移行認定を受ける必要がある。
なお、有限責任中間法人については、新制度の施行と同時に一般社団・財団法人となるが(整備法2条)、無限責任中間法人については、施行後1年以内に登記により一般社団・財団法人に移行する必要がある(整備法37条)。任意団体については、希望すれば、いつでも一般社団・財団法人へと移行できる。代表者の名義でしか権利義務を行使できない任意団体と異なり、一般社団・財団法人は、法人自身が不動産登記や金融取引など私法上の権利義務関係の主体となる。
Ⅱ 一般社団・財団法人と公益社団・財団法人について
次に、新たな公益法人制度のもとで制度化された、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人について、両法人の制度上の違いを比較しながら、解説する。
1 法人の実施事業 まず、各法人が実施する事業についての制約である。一般社団・財団法人については、その行う活動について、何らの制限も設けられておらず、法人の任意によるものとされている。公益事業のみならず、共益事業、収益事業を自由に行うことができ、事業の収支に関する制約もない。ただし、現行の公益法人から一般社団・財団法人に移行する法人については、「公益目的支出計画」を策定し、移行時点での法人の純資産相当額を公益目的のために費消することが求められている(整備法119条)。その間は行政庁の監督下で、公益目的事業を実施しなければならない。
一方、公益社団・財団法人については、公益認定法のもと、法人の目的、事業、機関、財務等について、厳格な基準が設けられており、そのすべてを満たさなければ、行政庁から公益認定を受けることができない。法人の実施事業に関しては、①公益認定法下で定義された公益目的事業を法人の主たる事業として行う(公益認定法5条1号)、②公益目的事業についてはその収入が費用を超えない(収支相償)(公益認定法5条6号、14条)、③法人の総費用の50%以上を公益目的事業に費やす(公益目的事業比率が50%以上)(公益認定法5条8号、15条)といった制約が課されている(図表2参照)。後述するが、公益目的事業の内容についても、詳細な要件が設けられている。
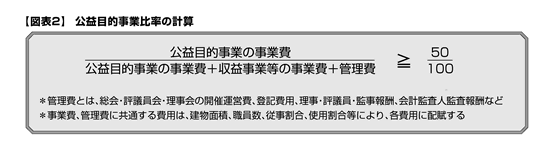
2 保有財産の扱い 現行の公益法人の指導監督基準で年間支出の30%以下に制限されている遊休財産の保有に関して、一般社団・財団法人については、この制限が撤廃された。保有する財産の内容や用途等に関する制約もない。
他方、公益社団・財団法人については、公益認定基準のもとで、①遊休財産の保有は公益目的事業に係る費用の1年分相当額以下とする(公益認定法5条9号、16条)、②公益目的事業の収入全額、および収益事業と共益事業の利益の2分の1以上を公益目的事業のために使用しなければならない(公益認定法18条)、③公益認定が取り消された場合、公益目的で取得した財産を国・地方公共団体や他の公益的団体に贈与しなければならない(公益認定法30条)、④株式会社等他の団体の事業活動を実質的に支配できる割合の株式等を保有してはならない(公益認定法5条15号)といった要件が要求されている。
3 法人の機関 一般法では、法人の運営に関する詳細なガバナンス規定が設けられており、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人ともに、これに基づいた機関の設置、運営が求められている。
法律上、社団法人については、社員総会、理事が、財団法人については、評議員、評議員会、理事、理事会、監事が必置の機関となった。これに加えて、公益社団・財団法人については、①同一親族である理事、あるいは同一団体に関係する理事の合計数が理事総数の3分の1を超えない(公益認定法5条10号、11号)、②理事、監事、評議員に対する報酬等が不当に高額とならないよう支給水準を定める(公益認定法5条13号)といった一段高い要件が設けられている。
なお、現行の公益法人制度では、同一業界に所属する理事の割合が法人の理事総数の3分の1を超えてはならないという規制があるが、新制度では撤廃された。
4 税 制 公益社団・財団法人については、寄附税制、法人税その他で一段高い優遇を受けることができる。
現在、主務大臣等から特定公益増進法人の認定を受けた公益法人に対しては、寄附者に対する税制上の優遇措置がある。ただ、特定公益増進法人の認定を受けた法人は、公益法人全体の3%程度に留まっている。新制度では、公益社団・財団法人となれば、自動的に特定公益増進法人として、寄附税制の優遇を受けることができる。寄附者に認められる損金算入限度額も従来の2倍程度まで拡大される。地方自治体が条例で指定した公益社団・財団法人に対する寄附金についても、寄附を行った個人が個人住民税の控除を受けることができるようになった。
法人税については、公益社団・財団法人は、新制度においても、現行制度同様、原則として収益事業のみに課税される収益事業課税が採られる。ただ、法人税率は、年800万円以下の所得については、現行同様22%であるが、それを超える部分は、一般の企業同様30%となった。
また、従来は、公益目的で行う事業であっても、税法上の収益事業(34事業)に該当すれば、課税対象とされたが、新制度では、税法上の収益事業のうち、行政庁の公益認定を受けた公益目的事業に該当する部分については課税対象から除外できる。さらに、収益事業に属する資産のうち、公益目的事業のために支出した金額は、みなし寄附金として非課税となる。
一方、一般社団・財団法人については、法人税法上、原則として普通法人とみなされ、30%の法人税が課される。
ただし、例外として、「非営利性が徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」については、公益社団・財団法人同様の収益事業課税が適用される。①剰余金分配を行わない、②解散時の残余財産を公益法人に贈与する、③同一親族である理事が理事総数の3分の1を超えないといった要件を満たせば、「非営利性が徹底された法人」とみなされ、(ア)会員に共通する利益を図る活動を主たる目的とする、(イ)定款等に会費の定めを行う、(ウ)主たる事業として収益事業を行っていない、(エ)定款に特定の個人団体に剰余金や残余財産を与える定めがないなどの要件を満たせば、「共益的活動を目的とする法人」とみなされる。
登録免許税や利子等にかかる源泉所得税については、公益社団・財団法人については現行制度同様非課税であるものの、一般社団・財団法人については課税されることになった。
Ⅲ 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の選択のポイント
以上のとおり、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人には、それぞれ特徴があり、各法人の実情に応じた選択が求められる。続いて、各法人が一般社団・財団法人、公益社団・財団法人を選択するうえでの判断の決め手となるポイントについて取り上げる。
1 一般社団・財団法人 一般社団・財団法人については、公益目的事業に関する制約もなく、法人の活動の自由度が高いことが最大の利点である。現行の公益法人から一般社団・財団法人に移行する法人については、「公益目的支出計画」の実施期間中は、行政庁の監督を受けるものの、計画終了後は行政庁の関与もなくなる。
税制に関しては、寄附税制に関する恩恵はないが、会費については、会員は損金で計上し、寄附枠を使うことはないので、会費を主な収入とする法人については関係が薄い。法人税についても、現行の公益法人については、指導監督基準等を通じて、既に「非営利性が徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」として求められる要件と同じ程度の運営をすることが要求されており、一般社団・財団法人を選択した場合でも、ほとんどの法人が収益事業課税の適用対象になるものと思われる。仮にどちらの要件も満たさず、普通法人同様の課税がなされても、課税範囲は拡大するが損益通算されるので、なかには有利に働く法人があるかもしれない。
他方、利子等に係る源泉所得税については、新たに課税されることになり、利息収入を元に運営している財団法人等にとっては、かなり重い負担となるだろう。不動産取得税、固定資産税、都市計画税についても、法人が保有する図書館、博物館、研究施設等の不動産等に対する非課税措置が、公益社団・財団法人については継続されるものの、一般社団・財団法人については平成25年度分までの適用となっている。仮に、本非課税措置がなくなる場合には、該当する固定資産を保有し、法人運営の基盤としている法人にとっては大きな懸念材料となる。
また、一般社団・財団法人については、行政の関与なく、登記のみにより設立できるため、類似・競合法人の設立を阻止できない。従来は、主務官庁による公益法人の厳格な設立認可、運営監督を通じて、一種の参入障壁ができ、同一業界内で類似・競合法人が新たに設立される余地は非常に限られていた。仮に、類似・競合法人の設立が進めば、公益法人間でも従来にはない企業同様の競争原理が働くこととなり、ややもすれば法人運営に影響を及ぼす惧れもある。
なお、現行の公益法人は、政府による各種許認可、補助金等の受け手としての一面も担ってきた。なかには、行政による公益認定を受けない一般社団・財団法人については、許認可、入札、当該法人役員の叙勲等において、公益社団・財団法人よりも不利な扱いを受けるのではないかと危惧する声もあるが、どちらの法人形態であっても扱いは変わらないというのが政府の見解である。
2 公益社団・財団法人 公益社団・財団法人については、行政庁から公益性を持った法人であるとのお墨付きを受けることで、「公益社団法人」「公益財団法人」という名称の独占ができると同時に、広く社会的な信用を得ることができる。税制面では、一般社団・財団法人よりも一段有利な恩恵を受ける。今回、公益社団・財団法人については、従来の特定公益増進法人を超える寄附税制の恩恵を受けることになり、広く社会から寄附を募りやすくなった。とりわけ、財団法人にとっては大きなメリットといえる。
一方、公益社団・財団法人に対しては、事業、財務など法人運営に関する制約が非常に大きい。収支相償、公益目的事業比率、遊休財産の保有制限等の公益認定基準を継続的に遵守していかねばならない。公益目的事業だけでなく、収益事業や共益事業についても、収益の2分の1以上は「公益目的事業財産」として公益目的に費消するなどの制約がある。この「公益目的事業財産」については、仮に公益認定が取り消された場合には、他の公益的団体、国・地方公共団体等に贈与することになっており(公益認定法30条)、財産の運用・活用を活動の糧とする法人にとっては大きなリスクとなる。
行政手続についても煩雑である。公益認定を受ける際の手続については、公益認定等委員会のホームページ(http://www.cao.go.jp/picc/)に掲載されているのでご覧いただきたいが、公益認定基準(図表3参照)を満たすことを証明する膨大な書類の作成、提出を求められる。認定後も、行政庁の監督のもと、毎年度、公益基準を満たしていることを証明する書類を提出しなければならない。定期的に実施される行政庁の立入検査についても、現行制度においては、主務官庁の行政官が行っているのに対し、新制度では、税当局のOB等を検査官として採用して充てる予定であり、財務をはじめ、法人運営に対して、従来以上の厳しいチェックが行われることが予想される。
実務面でも負担が増す。特に、各法人にとって負担が大きいのが、計算書類の作成である。公益法人会計基準に関しては、平成16年に全面的な改正が行われたが、新公益法人制度の発足に踏まえ、公益認定制度に対応したさらなる改正が行われた。各法人で平成16年改正基準への移行作業が進められてきた矢先であっただけに、各法人にとっての負担感は大きい。
今回の改正基準は、現行基準以上の仔細な情報開示を求めており、各法人に多大な事務負担を強いるものとなっている。たとえば、損益計算書は、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分し、さらに、その各事業毎に内訳表を作成する必要がある。収益事業等の利益の50%超を公益目的事業財産に繰り入れる法人については、貸借対照表についても、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分して作成しなければならない。
Ⅳ 新公益法人制度の課題と対応
新制度は、これまでの公益法人の活動実績、実態を十分に反映しておらず、民間の非営利活動を支援するという改革の趣旨から外れる部分が多いと批判されている。新制度発足を間近に控え、対応に苦慮している法人も多いようだ。
ここでは、各法人にとって、実務上影響が大きいと思われる新制度の課題を指摘するとともに、適宜、その対応について触れることとしたい。
1 理事会、評議員会の運営 新制度では、理事会、評議員会の議決に関して、本人出席による議決権行使が求められており、代理出席、委任状による出席は認められていない。これは役員会を定める一般法が新会社法の影響を多分に受け、会社の取締役同様、法人運営が理事、評議員の「個人」的な能力や資質に委任されているという考え方に基づいている。
しかし、公益法人のなかには、業界団体を中心に、企業、団体等の法人が会員を構成する公益法人も多い。法人会員の場合、理事、評議員等の役員に、企業、団体の上層部が就くケースがほとんどである。そのため、理事会、評議員会への本人出席が難しい場合が多く、代理出席や委任状提出を認め定足数を確保することがしばしばである。これは、理事、評議員の意思は、法人代表者である「個人」ではなく、会員としての「法人」の意思に基づいているという考え方に拠っている。
また、教育研究、文化芸術等の各種助成や顕彰等を目的とする法人など、各界の有識者を理事や評議員に委嘱する公益法人についても、日常多忙な有識者の出席を一堂に確保することは難しい。複数法人の理事、評議員を兼務する有識者も多いため、本人出席しか認められないとなれば、理事会や評議員会の開催日程の確保はより一層困難となる。
これに対し、スケジュールが確保しやすい人物を理事、評議員に任命すればよいではないかとの意見もある。しかし、本人の能力や資質よりもスケジュールの確保を優先して人選することになれば、法人運営の要である理事会や評議員会の形骸化にもなりかねない。理事、評議員の代理出席については、一般法等に明記されておらず、法改正の必要なく、行政庁の解釈の変更により、容易に見直しができる。民間による公益活動の促進をうたうのであれば、以上に触れたような各法人の活動実態を踏まえた制度設計が必要であり、理事会、評議員会の代理出席、委任状による出席を容認すべきではないか。
現行の体制では、理事、評議員の本人出席を確保する見通しが立たず、対応に悩まれている法人も多いであろう。理事を例に、議決権の代理行使について新制度の枠内で考えられる3つの対応策は以下のとおりである。
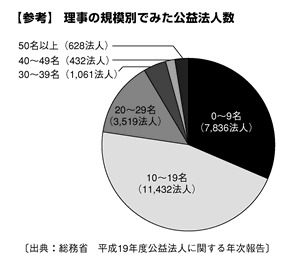
2 公益目的事業 公益社団・財団法人が主な事業として、あるいは、一般社団・財団法人が公益目的支出計画に基づき、実施する事業が「公益目的事業」である。「公益目的事業」とは、公益認定法2条4項において、①「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって」、②「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」という2つの要件を同時に満たすことが要求されている。前者については、公益認定法の別表で23項目(図表4参照)が列挙されており、現在の公益法人については、そのいずれかが該当するとされている。
一方、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」という要件については、内閣府公益認定等委員会が「公益目的事業のチェックポイントについて」(http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/003.pdf)を公表している。ここでは、(1)検査検定、(2)資格付与、(3)講座、セミナー、育成、(4)体験活動等、(5)相談、助言、(6)調査、資料収集、(7)技術開発、研究開発、(8)キャンペーン、○○月間、(9)展示会、○○ショー、(10)博物館等の展示、(11)施設の貸与、(12)資金貸付、債務保証等、(13)助成(応募型)、(14)表彰、コンクール、(15)競技会、(16)自主公演、(17)主催公演の17事業を公益目的事業の典型事業として取り上げ、各々の事業について、公益目的事業に該当するかの判断基準を解説している。
この17事業に該当しない事業については、①事業目的の要件として、不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないか、②事業の合目的性の要件として、受益の機会が一般に公開されているか、専門家が関与するなど事業の質を確保するための方策が採られているか、審査・選考において公正性が確保されているかといったチェックポイントが示されている。
ただ、このチェックポイントは、あまりに詳細に定義しすぎたため、柔軟性に欠け、公益法人の活動の実態、実績を十分網羅できる内容とはいえない。現在、公益法人が行っている公益的活動は多岐にわたっており、典型事業として掲げられた17事業の枠内でとても収まるものではない。各公益目的事業の括りは各法人が任意に設定できるものの、広範な事業を抱える法人にとっては、収支相償や公益目的事業比率など他の公益認定基準も勘案せねばならず、頭の悩ませどころである。
本来、本チェックポイントについては、公益目的事業をチェックする際の基本的な考え方(事業目的、事業の合目的性などのチェックポイント)を掲げたうえで、典型的な事業例を示した方が分かりやすかったのではないだろうか。実務上は、17の典型事業に沿って、各公益目的事業を設定するよりも、まず、各公益目的事業を設定したうえで、事業目的、事業の合目的性などの要件に照らして確認する方が現実的かと思われる。
また、チェックポイントでは、受益の機会が一般に開かれていることが求められており、共益事業は原則として公益目的事業から除くとされている。つまり、公益目的事業については、セミナーの参加費用、施設の貸与など、会員と非会員とで提供するサービスに差をつけることが許されていない。実際問題として、会員については、会費を徴収する以上、一般の方よりも一段上のサービスを提供できなければ、会員離れが生じる。わが国は欧米と異なり、寄附文化が根付いておらず、今後も、特に社団法人においては、会費が法人の運営財源の中心となると思われる。
チェックポイントにおいても、受益の機会が限定されている場合であっても、公益に直接貢献すると認められる合理的理由がある場合は、公益目的事業として認めるとする等、一定の配慮はなされているが、共益事業についても、公益目的事業として柔軟に認めていく必要があるのではないか。
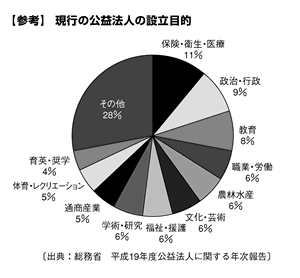
3 収支相償 公益認定基準では、公益目的事業について、その収入が適正な費用を超えないこと(収支相償)が要件とされている(公益認定法5条6号)。収支相償については、①個別事業毎、そして②法人の行う事業全体の2段階で要件を満たさなければならない。2段階で収支相償をみるのは、事業単位で直接定義できない部分についても、法人全体で判定を行うためである。
収支相償の要件が設けられた理由として、公益目的事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すべきものであるので、公益目的事業の遂行にあたって、持てる資源を最大限動員し、無償または低廉な対価を設定することで受益者の範囲を最大限拡大する必要があるからとされている。
しかし、いくら剰余金の分配を目的としない非営利法人といっても、常に事業が赤字でなければならないとすれば、法人を維持していくことはままならない。各事業毎に赤字を出していては、法人全体では相当規模の赤字を計上することになる。公益法人は、1つの事業を長期にわたって実施するケースも多く、その場合、期毎に収支の状況は大きく変動する。事業の実施期間全体で赤字であったとしても、必ずしも毎期赤字とはならないだろう。
収支相償の判定については、「経常収益-経常費用+特定費用準備資金の当期取崩額-特定費用準備資金の当期積立額」で算定した数値がゼロ以下とならなければならない。特定費用準備資金とは、将来(ただし、10年以内に)実施する特定の事業やイベントのために支出するために積み立てる資金である。これは、各事業が毎年、赤字では法人を維持できないという意見を踏まえて、収支相償の判定上、経常収支から控除することにしたものである。
しかし、特定費用準備資金に繰り入れるためには、①貸借対照表の特定資産に「○○事業実施積立資産」といった名称で計上する、②理事会等の承認なしに目的外で流用できない、③積立限度額・算定根拠等について備置・閲覧できるようにする等の厳格な要件をすべて満たす必要がある。勿論、予備費のように、将来の備えや資金繰りのために用いることはできず、かなり使い勝手の悪いものとなっている。
経理担当者にとっても、この複雑な収支相償の計算を事業毎、および法人全体で毎年度行わなければならず、かなりの負担となるだろう。
仮に、収支相償に違反したとしても、1、2年程度であれば、即時に公益認定が取り消されることはないともいわれているが、そもそも、収支相償の要件は本当に必要なのだろうか。公益目的事業財産への繰入規制や遊休財産の保有制限などで、公益の受益者の拡大は十分担保できると思われる。少なくとも、より簡便で分かりやすい判定方法へと見直す必要があろう。
4 公益目的支出計画 現行の公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合、「公益目的支出計画」を策定し、移行時の保有資産額を公益目的に使用することが義務付けられている(整備法119条)。本制度を巡っては、なぜこのようなことを行う必要があるのか、あるいは、制度が難解で分かりにくいといった声も多い。
今回の公益法人制度改革のきっかけの1つに、公益法人は公益的活動の担い手として、税制上の恩恵を受けているにもかかわらず、約20兆円にも及ぶ多額の財産が使われずに公益法人に滞留していることに対する問題意識があった。政治の場においては、税制上の恩恵も受けて蓄えた財産なのだから、事業の制約も行政庁の監督もない一般社団・財団法人に移行する法人については、その保有する財産に対して何の制約も課さないのは問題ではないかとの議論があった。なかには、課税すべきといった意見や国・地方自治体に贈与させるべきとの意見もあったようである。結局、一般社団・財団法人については、移行時点での純資産相当額を公益的活動に費消していく「公益目的支出計画」を策定させ、その計画が終了するまでの間は、行政庁の監督を受けることになった。
「公益目的支出計画」の詳細について解説する。「公益目的支出計画」で費消する移行時点の純資産相当額は「公益目的財産額」と呼ばれる。これは、貸借対照表の純資産額をベースに、土地、有価証券、美術品については時価評価し加減算を行う。そのうえで、基金の減算を行い、算出する。公益目的支出計画の実施期間中は、純資産を増やせないのかとの疑問が出されることがあるが、「公益目的財産額」とは、法人の「移行時点」の純資産相当額であって、移行後、純資産額が増えたからといって、「公益目的財産額」が増えることはない。
次に、公益目的支出計画において、「公益目的財産額」をゼロにしていくために行う公益的活動を「実施事業等」という。これは、①公益認定法上の「公益目的事業」、②従来の主務官庁が公益的な活動と認める事業、③他の公益法人、国・地方公共団体等に対する寄附が該当する(整備法119条2項1号)。①・②が「実施事業等」の中心になると思うが、これについては、法人の任意で事業を設定することができる。
このうち、事業収支が赤字になる事業を取り出し、その赤字額を合計し、「年間支出額」を算出する。「公益目的財産額」をこの「年間支出額」で割れば、公益目的支出計画の実施年数が算出される。黒字事業についても「実施事業」となりうるが、黒字分だけ「年間支出額」が減少し、その分、計画の実施期間が長期化する。会費については、事業収支の計算の際に、一般会費については収入に含める必要はないが、使途が特定される特別会費について会費規定でその旨定めた場合は、各事業の収入に含める必要があるので注意が必要である。
公益目的支出計画の実施期間中は、各法人は、各事業年度毎に、公益目的支出計画の実施報告書とともに、①実施事業等会計、②その他事業の会計、③管理業務等に係る法人会計の3つに区分した計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を行政庁に提出しなければならない(整備法127条)。
このように、一般社団・財団法人であっても、公益目的支出計画の「実施事業等」として、公益認定法上の「公益目的事業」に相当する事業が要求されたり、計算書類に厳格な区分経理が求められるなど、公益社団・財団法人並みの要件が課されており、行政庁が法人運営に大きく関与することになる。
一般社団・財団法人は、行政の関与を外し、民間の自発的な公益活動を促進するという今回の改革の理念をとりわけ具現化する制度であったはずである。しかし、実態は骨抜きとの感が否めない。公益目的支出計画については、公益法人への財産の滞留がきっかけとなっているが、これも補助金等の公的資金を受ける行政委託型法人が問題であって、会費・寄附等の民間資金によって運営してきた公益法人については、非難の対象とはならないはずである。新制度のもとで、各法人がより企業経営に近い、堅実な運営が求められているにも拘らず、公益目的支出計画を遂行するために、過去に蓄積してきた財産相当規模の事業を余計に実施しなければならないことは、計画終了後を含めた法人経営の継続性の観点からも問題が多い。
余談になるが、法人が保有する「土地」については、「公益目的財産額」の算定の際に、時価評価することが求められている。たとえば、高度経済成長期前から土地を保有する法人のなかには、取得時よりも大幅に地価が上昇し、法人の身の丈以上の公益目的支出計画を実施しなければならなくなる法人がでてくるかもしれない。
5 公益認定の体制 政府の公益認定等委員会は、移行法人については、5年間で公益認定の審査作業を行うことになる。仮に、現在、国所管の7,000弱の公益法人の半数が公益認定を希望した場合、再審査を除いても1日平均で2法人の審査を行うことになる。これに一般社団・財団法人に移行する法人の認可作業も加わる。申請書類が膨大で、非常勤の委員も多いなか、適切かつ円滑な審査を行っていくことは可能なのだろうか。
1つの懸念材料を指摘したい。公益認定に係る内閣府令では、公益認定を受けて公益法人に移行する場合の最初の事業年度に係る計算書類について、公益認定を受けた日の前日までと公益認定を受けた日以降とに区分して作成し、行政庁に提出することを求めている(公益認定法施行規則38条2項)。事業年度中に認定を受けた場合には、決算を2度行わなければならない。多くの公益法人は少数の経理担当者で切り盛りしているため、相当の負荷がかかることになる。
これに対して、公益認定等委員会は、法人の事務負担軽減のため、希望すれば、時期が近い場合には、公益認定日を4月1日に設定できるようにし、1事業年度中に複数の計算書類を作成しなくてすむよう配慮するとしている。しかし、多くの法人が4月1日の認定取得を目指して、申請が一時期に集中することが予想されるなか、公益認定等委員会の事務作業が追いつくのか懸念されるところである。
より深刻な問題を抱えるのは都道府県の合議制の機関である。地方は、国と比較して、新制度に関する体制、人員、専門性などに大きな差があることは否めない。こうしたなか、公益認定等委員会と各都道府県の合議制の機関との間で、整合性のある審査ができるのか不安視される。
Ⅴ おわりに
今回の公益法人改革は、公的な関与をできるだけ外し、民間による自主的な取組みを最大限尊重することが1つの主眼のはずであった。その意味では、新しい制度は、現行の公益法人の指導監督基準並み、あるいはそれ以下の簡便な制度となることが期待された。
しかし、公益認定基準をはじめ、制度的には非常に煩雑で難解な内容となり、計算書類をはじめ、各法人に非常に手間を課すものとなっている。法人運営の実態にそぐわない法律となったがために、収支相償や公益目的事業比率をはじめ、多くの例外措置を設けたこともこれに拍車をかけた。このままでは、各法人は、制度面での対応に時間をとられ、間接部門ばかりが肥大化し、本来推進すべき公益事業に経営資源を投下することができなくなる。現行の公益法人のほとんどは規模が小さく、少人数の担当者で新制度へ対応せざるをえない。そのため、特に、公益社団・財団法人については、要件が厳格で手続が煩雑だからという理由で選択しない法人も相当数あろうかと思う。そうなれば、新制度は絵に描いた餅となり、改革の意義も乏しいものとなろう。
公益法人改革三法の衆参両院の付帯決議では「法律の状況に変化が生じたときは、広く国民の意見を聴き、直ちに見直しを行うこと」がうたわれた。しかし、その後の政省令、ガイドライン等のパブリック・コメントなどでは、本稿でも触れた課題について、各方面から意見があがったものの、ほとんど採り入れられることはなかった。
今後、新制度を運用していくなかで、改善すべき点は早急に見直し、実態に沿った制度へと磨き上げていくことが必要だろう。勿論、各法人においても、今回の制度改革を機に、経営の質を高めつつ、公益の担い手として、わが国の経済社会の発展に向けて積極的な役割を果たしていかねばならない。今後、公益法人の大いなる活躍を期待したい。
(のむら・よしひさ)
新しい公益法人制度と今後の課題
(社)日本経済団体連合会 総務本部 野村良寿
公益法人制度を巡っては、2006年6月に公益法人改革三法が成立し、本年12月1日から、新しい公益法人制度が開始する。従来の主務官庁の指導監督のもとで運営する形から、法人自らの自主的な運営を重視し、民間による自発的で多様な公益活動を推進する方向へと大きく舵が取られる。新制度施行まで半年を切り、既に多くの公益法人が新制度への対応作業を進めている。本稿では、新制度の概要について触れたうえで、実務に照らした新制度の課題について、採り上げることとする。なお、文中意見にわたる部分は、もとより筆者の私見にとどまる。
Ⅰ 新公益法人制度の概要
公益法人は、明治以来、民法34条(「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」)に基づき、主務官庁の指導監督のもと、運営が行われてきた。
しかし、小さく効率的な政府への転換、あるいは官から民への流れが進むなか、公益活動を担う主体としての民間の非営利活動への期待が高まってきた。また、政府の関連公益法人による不祥事や予算の無駄遣い等の問題も散見される。そこで、「民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、(中略)公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする」(公益認定法1条)新制度への移行が図られることになった(図表1参照)。
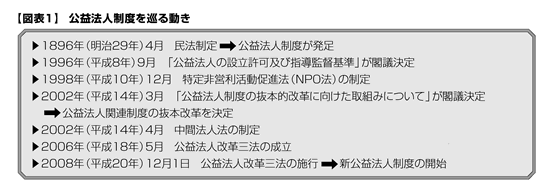
新制度を構成する法律は、(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」)、(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」)、(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」)の3法からなる。(1)一般法は、新制度のもとでの法人のガバナンス等、(2)公益認定法は、行政庁から公益認定を受ける際の認定基準、公益認定を受けた法人のガバナンス等について定めている。(3)整備法は、現行の公益法人が新制度下の法人に移行する際の要件、手続等を定めた法律である。
新制度で定められた公益法人の形態は、①一般社団法人、②一般財団法人、③公益社団法人、④公益財団法人の4つである。従来、公益法人の設立には政府の許可が必要であったが、新制度では登記のみで社団法人、財団法人を設立できる(一般法22条)。こうして設立された法人が一般社団・財団法人であり、一般法のもとで運営を行う。一般社団・財団法人のうち、行政庁から公益性があると認定を受けた法人が公益社団・財団法人となる。
公益性の認定については、現行制度においては実質的に主務官庁の指導監督を通じてなされていたが、新制度では、公益認定法に定められた公益認定基準に基づき、有識者で構成される第三者委員会である、政府の「公益認定等委員会」、あるいは都道府県の合議制の機関が行うことになる(公益認定法32条、50条)。
現行の公益法人については、本年12月の新制度の施行以降、自動的に「特例社団法人・財団法人」となり、主務官庁による監督、税制など、現行制度同様の扱いを受けるが、5年以内(平成25年11月末まで)に移行しなければ、解散となる(整備法46条)。この5年間に、行政庁から一般社団・財団法人への移行認可、あるいは公益社団・財団法人への移行認定を受ける必要がある。
なお、有限責任中間法人については、新制度の施行と同時に一般社団・財団法人となるが(整備法2条)、無限責任中間法人については、施行後1年以内に登記により一般社団・財団法人に移行する必要がある(整備法37条)。任意団体については、希望すれば、いつでも一般社団・財団法人へと移行できる。代表者の名義でしか権利義務を行使できない任意団体と異なり、一般社団・財団法人は、法人自身が不動産登記や金融取引など私法上の権利義務関係の主体となる。
Ⅱ 一般社団・財団法人と公益社団・財団法人について
次に、新たな公益法人制度のもとで制度化された、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人について、両法人の制度上の違いを比較しながら、解説する。
1 法人の実施事業 まず、各法人が実施する事業についての制約である。一般社団・財団法人については、その行う活動について、何らの制限も設けられておらず、法人の任意によるものとされている。公益事業のみならず、共益事業、収益事業を自由に行うことができ、事業の収支に関する制約もない。ただし、現行の公益法人から一般社団・財団法人に移行する法人については、「公益目的支出計画」を策定し、移行時点での法人の純資産相当額を公益目的のために費消することが求められている(整備法119条)。その間は行政庁の監督下で、公益目的事業を実施しなければならない。
一方、公益社団・財団法人については、公益認定法のもと、法人の目的、事業、機関、財務等について、厳格な基準が設けられており、そのすべてを満たさなければ、行政庁から公益認定を受けることができない。法人の実施事業に関しては、①公益認定法下で定義された公益目的事業を法人の主たる事業として行う(公益認定法5条1号)、②公益目的事業についてはその収入が費用を超えない(収支相償)(公益認定法5条6号、14条)、③法人の総費用の50%以上を公益目的事業に費やす(公益目的事業比率が50%以上)(公益認定法5条8号、15条)といった制約が課されている(図表2参照)。後述するが、公益目的事業の内容についても、詳細な要件が設けられている。
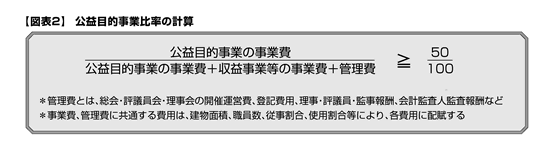
2 保有財産の扱い 現行の公益法人の指導監督基準で年間支出の30%以下に制限されている遊休財産の保有に関して、一般社団・財団法人については、この制限が撤廃された。保有する財産の内容や用途等に関する制約もない。
他方、公益社団・財団法人については、公益認定基準のもとで、①遊休財産の保有は公益目的事業に係る費用の1年分相当額以下とする(公益認定法5条9号、16条)、②公益目的事業の収入全額、および収益事業と共益事業の利益の2分の1以上を公益目的事業のために使用しなければならない(公益認定法18条)、③公益認定が取り消された場合、公益目的で取得した財産を国・地方公共団体や他の公益的団体に贈与しなければならない(公益認定法30条)、④株式会社等他の団体の事業活動を実質的に支配できる割合の株式等を保有してはならない(公益認定法5条15号)といった要件が要求されている。
3 法人の機関 一般法では、法人の運営に関する詳細なガバナンス規定が設けられており、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人ともに、これに基づいた機関の設置、運営が求められている。
法律上、社団法人については、社員総会、理事が、財団法人については、評議員、評議員会、理事、理事会、監事が必置の機関となった。これに加えて、公益社団・財団法人については、①同一親族である理事、あるいは同一団体に関係する理事の合計数が理事総数の3分の1を超えない(公益認定法5条10号、11号)、②理事、監事、評議員に対する報酬等が不当に高額とならないよう支給水準を定める(公益認定法5条13号)といった一段高い要件が設けられている。
なお、現行の公益法人制度では、同一業界に所属する理事の割合が法人の理事総数の3分の1を超えてはならないという規制があるが、新制度では撤廃された。
4 税 制 公益社団・財団法人については、寄附税制、法人税その他で一段高い優遇を受けることができる。
現在、主務大臣等から特定公益増進法人の認定を受けた公益法人に対しては、寄附者に対する税制上の優遇措置がある。ただ、特定公益増進法人の認定を受けた法人は、公益法人全体の3%程度に留まっている。新制度では、公益社団・財団法人となれば、自動的に特定公益増進法人として、寄附税制の優遇を受けることができる。寄附者に認められる損金算入限度額も従来の2倍程度まで拡大される。地方自治体が条例で指定した公益社団・財団法人に対する寄附金についても、寄附を行った個人が個人住民税の控除を受けることができるようになった。
法人税については、公益社団・財団法人は、新制度においても、現行制度同様、原則として収益事業のみに課税される収益事業課税が採られる。ただ、法人税率は、年800万円以下の所得については、現行同様22%であるが、それを超える部分は、一般の企業同様30%となった。
また、従来は、公益目的で行う事業であっても、税法上の収益事業(34事業)に該当すれば、課税対象とされたが、新制度では、税法上の収益事業のうち、行政庁の公益認定を受けた公益目的事業に該当する部分については課税対象から除外できる。さらに、収益事業に属する資産のうち、公益目的事業のために支出した金額は、みなし寄附金として非課税となる。
一方、一般社団・財団法人については、法人税法上、原則として普通法人とみなされ、30%の法人税が課される。
ただし、例外として、「非営利性が徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」については、公益社団・財団法人同様の収益事業課税が適用される。①剰余金分配を行わない、②解散時の残余財産を公益法人に贈与する、③同一親族である理事が理事総数の3分の1を超えないといった要件を満たせば、「非営利性が徹底された法人」とみなされ、(ア)会員に共通する利益を図る活動を主たる目的とする、(イ)定款等に会費の定めを行う、(ウ)主たる事業として収益事業を行っていない、(エ)定款に特定の個人団体に剰余金や残余財産を与える定めがないなどの要件を満たせば、「共益的活動を目的とする法人」とみなされる。
登録免許税や利子等にかかる源泉所得税については、公益社団・財団法人については現行制度同様非課税であるものの、一般社団・財団法人については課税されることになった。
Ⅲ 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の選択のポイント
以上のとおり、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人には、それぞれ特徴があり、各法人の実情に応じた選択が求められる。続いて、各法人が一般社団・財団法人、公益社団・財団法人を選択するうえでの判断の決め手となるポイントについて取り上げる。
1 一般社団・財団法人 一般社団・財団法人については、公益目的事業に関する制約もなく、法人の活動の自由度が高いことが最大の利点である。現行の公益法人から一般社団・財団法人に移行する法人については、「公益目的支出計画」の実施期間中は、行政庁の監督を受けるものの、計画終了後は行政庁の関与もなくなる。
税制に関しては、寄附税制に関する恩恵はないが、会費については、会員は損金で計上し、寄附枠を使うことはないので、会費を主な収入とする法人については関係が薄い。法人税についても、現行の公益法人については、指導監督基準等を通じて、既に「非営利性が徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」として求められる要件と同じ程度の運営をすることが要求されており、一般社団・財団法人を選択した場合でも、ほとんどの法人が収益事業課税の適用対象になるものと思われる。仮にどちらの要件も満たさず、普通法人同様の課税がなされても、課税範囲は拡大するが損益通算されるので、なかには有利に働く法人があるかもしれない。
他方、利子等に係る源泉所得税については、新たに課税されることになり、利息収入を元に運営している財団法人等にとっては、かなり重い負担となるだろう。不動産取得税、固定資産税、都市計画税についても、法人が保有する図書館、博物館、研究施設等の不動産等に対する非課税措置が、公益社団・財団法人については継続されるものの、一般社団・財団法人については平成25年度分までの適用となっている。仮に、本非課税措置がなくなる場合には、該当する固定資産を保有し、法人運営の基盤としている法人にとっては大きな懸念材料となる。
また、一般社団・財団法人については、行政の関与なく、登記のみにより設立できるため、類似・競合法人の設立を阻止できない。従来は、主務官庁による公益法人の厳格な設立認可、運営監督を通じて、一種の参入障壁ができ、同一業界内で類似・競合法人が新たに設立される余地は非常に限られていた。仮に、類似・競合法人の設立が進めば、公益法人間でも従来にはない企業同様の競争原理が働くこととなり、ややもすれば法人運営に影響を及ぼす惧れもある。
なお、現行の公益法人は、政府による各種許認可、補助金等の受け手としての一面も担ってきた。なかには、行政による公益認定を受けない一般社団・財団法人については、許認可、入札、当該法人役員の叙勲等において、公益社団・財団法人よりも不利な扱いを受けるのではないかと危惧する声もあるが、どちらの法人形態であっても扱いは変わらないというのが政府の見解である。
2 公益社団・財団法人 公益社団・財団法人については、行政庁から公益性を持った法人であるとのお墨付きを受けることで、「公益社団法人」「公益財団法人」という名称の独占ができると同時に、広く社会的な信用を得ることができる。税制面では、一般社団・財団法人よりも一段有利な恩恵を受ける。今回、公益社団・財団法人については、従来の特定公益増進法人を超える寄附税制の恩恵を受けることになり、広く社会から寄附を募りやすくなった。とりわけ、財団法人にとっては大きなメリットといえる。
一方、公益社団・財団法人に対しては、事業、財務など法人運営に関する制約が非常に大きい。収支相償、公益目的事業比率、遊休財産の保有制限等の公益認定基準を継続的に遵守していかねばならない。公益目的事業だけでなく、収益事業や共益事業についても、収益の2分の1以上は「公益目的事業財産」として公益目的に費消するなどの制約がある。この「公益目的事業財産」については、仮に公益認定が取り消された場合には、他の公益的団体、国・地方公共団体等に贈与することになっており(公益認定法30条)、財産の運用・活用を活動の糧とする法人にとっては大きなリスクとなる。
行政手続についても煩雑である。公益認定を受ける際の手続については、公益認定等委員会のホームページ(http://www.cao.go.jp/picc/)に掲載されているのでご覧いただきたいが、公益認定基準(図表3参照)を満たすことを証明する膨大な書類の作成、提出を求められる。認定後も、行政庁の監督のもと、毎年度、公益基準を満たしていることを証明する書類を提出しなければならない。定期的に実施される行政庁の立入検査についても、現行制度においては、主務官庁の行政官が行っているのに対し、新制度では、税当局のOB等を検査官として採用して充てる予定であり、財務をはじめ、法人運営に対して、従来以上の厳しいチェックが行われることが予想される。
【図表3】主な公益認定基準
| 公益認定法第5条<抜粋> 一 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 三 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 五 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 八 その事業活動を行うに当たり、……公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。 九 その事業活動を行うに当たり、……遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。 十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 十一 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 十二 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。 十三 その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 十五 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。…… 十六 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 十七 ……公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。 |
今回の改正基準は、現行基準以上の仔細な情報開示を求めており、各法人に多大な事務負担を強いるものとなっている。たとえば、損益計算書は、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分し、さらに、その各事業毎に内訳表を作成する必要がある。収益事業等の利益の50%超を公益目的事業財産に繰り入れる法人については、貸借対照表についても、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分して作成しなければならない。
Ⅳ 新公益法人制度の課題と対応
新制度は、これまでの公益法人の活動実績、実態を十分に反映しておらず、民間の非営利活動を支援するという改革の趣旨から外れる部分が多いと批判されている。新制度発足を間近に控え、対応に苦慮している法人も多いようだ。
ここでは、各法人にとって、実務上影響が大きいと思われる新制度の課題を指摘するとともに、適宜、その対応について触れることとしたい。
1 理事会、評議員会の運営 新制度では、理事会、評議員会の議決に関して、本人出席による議決権行使が求められており、代理出席、委任状による出席は認められていない。これは役員会を定める一般法が新会社法の影響を多分に受け、会社の取締役同様、法人運営が理事、評議員の「個人」的な能力や資質に委任されているという考え方に基づいている。
しかし、公益法人のなかには、業界団体を中心に、企業、団体等の法人が会員を構成する公益法人も多い。法人会員の場合、理事、評議員等の役員に、企業、団体の上層部が就くケースがほとんどである。そのため、理事会、評議員会への本人出席が難しい場合が多く、代理出席や委任状提出を認め定足数を確保することがしばしばである。これは、理事、評議員の意思は、法人代表者である「個人」ではなく、会員としての「法人」の意思に基づいているという考え方に拠っている。
また、教育研究、文化芸術等の各種助成や顕彰等を目的とする法人など、各界の有識者を理事や評議員に委嘱する公益法人についても、日常多忙な有識者の出席を一堂に確保することは難しい。複数法人の理事、評議員を兼務する有識者も多いため、本人出席しか認められないとなれば、理事会や評議員会の開催日程の確保はより一層困難となる。
これに対し、スケジュールが確保しやすい人物を理事、評議員に任命すればよいではないかとの意見もある。しかし、本人の能力や資質よりもスケジュールの確保を優先して人選することになれば、法人運営の要である理事会や評議員会の形骸化にもなりかねない。理事、評議員の代理出席については、一般法等に明記されておらず、法改正の必要なく、行政庁の解釈の変更により、容易に見直しができる。民間による公益活動の促進をうたうのであれば、以上に触れたような各法人の活動実態を踏まえた制度設計が必要であり、理事会、評議員会の代理出席、委任状による出席を容認すべきではないか。
現行の体制では、理事、評議員の本人出席を確保する見通しが立たず、対応に悩まれている法人も多いであろう。理事を例に、議決権の代理行使について新制度の枠内で考えられる3つの対応策は以下のとおりである。
| 対応1.理事の区分 現行の理事を、法律上の理事会を構成する「法律上の理事」と、それ以外の「事実上の理事」に分ける。「法律上の理事」については、常勤者など本人出席が容易な者とする。「事実上の理事」については、議決権は行使できないものの、法律上の理事会に出席し、意見を述べることは可能である。勿論、代理出席や委任状による出席も認められる。 ただ、「事実上の理事」に付与する名称によっては、「事実上の理事」が行った法律行為の効果が法人に帰属する表権代理(代表理事について一般法82条)の問題が発生する懸念がある。「事実上の理事」については、「法律上の理事」と誤認させるような名称(理事、理事役など)は避ける必要がある。また、「事実上の理事」を設けることについて定款に明記するか、理事会での議決を得ておいた方がよいだろう。 【参考】一般法82条(表見代表理事) 一般社団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 |
| 対応2.書面決議の活用 理事が各理事に対して事前に決議事項を送付・提案し、全理事の賛否を確認したうえで、理事会開催の際に書面(電磁的記録(電子メール等)による方法も可)で決議を行う。書面決議なので、理事会が定足数を満たしているかは問われず、代理出席も認められる。ただし、各議案について全員の賛成が求められる。 【参考】一般法96条(理事会の決議の省略) 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 |
| 対応3.理事会開催回数 法律上の理事会の開催を一般法上要請されている年2回に抑える(一般法91条2項)。法律上の理事会については本人出席を確保し、定足数を満たす必要がある。その他、事実上の理事会を開催することが可能であり、その際は定足数を満たしているかは問われず、代理出席、委任状による出席も認められる。 |
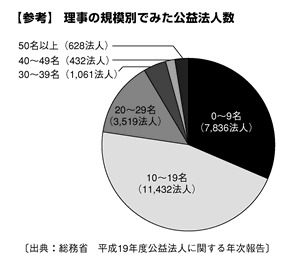
2 公益目的事業 公益社団・財団法人が主な事業として、あるいは、一般社団・財団法人が公益目的支出計画に基づき、実施する事業が「公益目的事業」である。「公益目的事業」とは、公益認定法2条4項において、①「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって」、②「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」という2つの要件を同時に満たすことが要求されている。前者については、公益認定法の別表で23項目(図表4参照)が列挙されており、現在の公益法人については、そのいずれかが該当するとされている。
【図表4】公益目的事業の要件
| 公益認定法別表(第2条関係) 一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 二 文化及び芸術の振興を目的とする事業 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 六 公衆衛生の向上を目的とする事業 七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 十一 事故又は災害の防止を目的とする事業 十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業 二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの |
この17事業に該当しない事業については、①事業目的の要件として、不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないか、②事業の合目的性の要件として、受益の機会が一般に公開されているか、専門家が関与するなど事業の質を確保するための方策が採られているか、審査・選考において公正性が確保されているかといったチェックポイントが示されている。
ただ、このチェックポイントは、あまりに詳細に定義しすぎたため、柔軟性に欠け、公益法人の活動の実態、実績を十分網羅できる内容とはいえない。現在、公益法人が行っている公益的活動は多岐にわたっており、典型事業として掲げられた17事業の枠内でとても収まるものではない。各公益目的事業の括りは各法人が任意に設定できるものの、広範な事業を抱える法人にとっては、収支相償や公益目的事業比率など他の公益認定基準も勘案せねばならず、頭の悩ませどころである。
本来、本チェックポイントについては、公益目的事業をチェックする際の基本的な考え方(事業目的、事業の合目的性などのチェックポイント)を掲げたうえで、典型的な事業例を示した方が分かりやすかったのではないだろうか。実務上は、17の典型事業に沿って、各公益目的事業を設定するよりも、まず、各公益目的事業を設定したうえで、事業目的、事業の合目的性などの要件に照らして確認する方が現実的かと思われる。
また、チェックポイントでは、受益の機会が一般に開かれていることが求められており、共益事業は原則として公益目的事業から除くとされている。つまり、公益目的事業については、セミナーの参加費用、施設の貸与など、会員と非会員とで提供するサービスに差をつけることが許されていない。実際問題として、会員については、会費を徴収する以上、一般の方よりも一段上のサービスを提供できなければ、会員離れが生じる。わが国は欧米と異なり、寄附文化が根付いておらず、今後も、特に社団法人においては、会費が法人の運営財源の中心となると思われる。
チェックポイントにおいても、受益の機会が限定されている場合であっても、公益に直接貢献すると認められる合理的理由がある場合は、公益目的事業として認めるとする等、一定の配慮はなされているが、共益事業についても、公益目的事業として柔軟に認めていく必要があるのではないか。
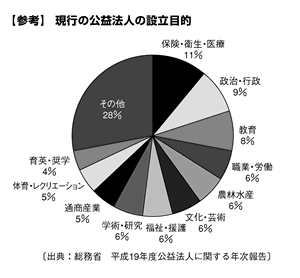
3 収支相償 公益認定基準では、公益目的事業について、その収入が適正な費用を超えないこと(収支相償)が要件とされている(公益認定法5条6号)。収支相償については、①個別事業毎、そして②法人の行う事業全体の2段階で要件を満たさなければならない。2段階で収支相償をみるのは、事業単位で直接定義できない部分についても、法人全体で判定を行うためである。
収支相償の要件が設けられた理由として、公益目的事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すべきものであるので、公益目的事業の遂行にあたって、持てる資源を最大限動員し、無償または低廉な対価を設定することで受益者の範囲を最大限拡大する必要があるからとされている。
しかし、いくら剰余金の分配を目的としない非営利法人といっても、常に事業が赤字でなければならないとすれば、法人を維持していくことはままならない。各事業毎に赤字を出していては、法人全体では相当規模の赤字を計上することになる。公益法人は、1つの事業を長期にわたって実施するケースも多く、その場合、期毎に収支の状況は大きく変動する。事業の実施期間全体で赤字であったとしても、必ずしも毎期赤字とはならないだろう。
収支相償の判定については、「経常収益-経常費用+特定費用準備資金の当期取崩額-特定費用準備資金の当期積立額」で算定した数値がゼロ以下とならなければならない。特定費用準備資金とは、将来(ただし、10年以内に)実施する特定の事業やイベントのために支出するために積み立てる資金である。これは、各事業が毎年、赤字では法人を維持できないという意見を踏まえて、収支相償の判定上、経常収支から控除することにしたものである。
しかし、特定費用準備資金に繰り入れるためには、①貸借対照表の特定資産に「○○事業実施積立資産」といった名称で計上する、②理事会等の承認なしに目的外で流用できない、③積立限度額・算定根拠等について備置・閲覧できるようにする等の厳格な要件をすべて満たす必要がある。勿論、予備費のように、将来の備えや資金繰りのために用いることはできず、かなり使い勝手の悪いものとなっている。
経理担当者にとっても、この複雑な収支相償の計算を事業毎、および法人全体で毎年度行わなければならず、かなりの負担となるだろう。
仮に、収支相償に違反したとしても、1、2年程度であれば、即時に公益認定が取り消されることはないともいわれているが、そもそも、収支相償の要件は本当に必要なのだろうか。公益目的事業財産への繰入規制や遊休財産の保有制限などで、公益の受益者の拡大は十分担保できると思われる。少なくとも、より簡便で分かりやすい判定方法へと見直す必要があろう。
4 公益目的支出計画 現行の公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合、「公益目的支出計画」を策定し、移行時の保有資産額を公益目的に使用することが義務付けられている(整備法119条)。本制度を巡っては、なぜこのようなことを行う必要があるのか、あるいは、制度が難解で分かりにくいといった声も多い。
今回の公益法人制度改革のきっかけの1つに、公益法人は公益的活動の担い手として、税制上の恩恵を受けているにもかかわらず、約20兆円にも及ぶ多額の財産が使われずに公益法人に滞留していることに対する問題意識があった。政治の場においては、税制上の恩恵も受けて蓄えた財産なのだから、事業の制約も行政庁の監督もない一般社団・財団法人に移行する法人については、その保有する財産に対して何の制約も課さないのは問題ではないかとの議論があった。なかには、課税すべきといった意見や国・地方自治体に贈与させるべきとの意見もあったようである。結局、一般社団・財団法人については、移行時点での純資産相当額を公益的活動に費消していく「公益目的支出計画」を策定させ、その計画が終了するまでの間は、行政庁の監督を受けることになった。
「公益目的支出計画」の詳細について解説する。「公益目的支出計画」で費消する移行時点の純資産相当額は「公益目的財産額」と呼ばれる。これは、貸借対照表の純資産額をベースに、土地、有価証券、美術品については時価評価し加減算を行う。そのうえで、基金の減算を行い、算出する。公益目的支出計画の実施期間中は、純資産を増やせないのかとの疑問が出されることがあるが、「公益目的財産額」とは、法人の「移行時点」の純資産相当額であって、移行後、純資産額が増えたからといって、「公益目的財産額」が増えることはない。
次に、公益目的支出計画において、「公益目的財産額」をゼロにしていくために行う公益的活動を「実施事業等」という。これは、①公益認定法上の「公益目的事業」、②従来の主務官庁が公益的な活動と認める事業、③他の公益法人、国・地方公共団体等に対する寄附が該当する(整備法119条2項1号)。①・②が「実施事業等」の中心になると思うが、これについては、法人の任意で事業を設定することができる。
このうち、事業収支が赤字になる事業を取り出し、その赤字額を合計し、「年間支出額」を算出する。「公益目的財産額」をこの「年間支出額」で割れば、公益目的支出計画の実施年数が算出される。黒字事業についても「実施事業」となりうるが、黒字分だけ「年間支出額」が減少し、その分、計画の実施期間が長期化する。会費については、事業収支の計算の際に、一般会費については収入に含める必要はないが、使途が特定される特別会費について会費規定でその旨定めた場合は、各事業の収入に含める必要があるので注意が必要である。
公益目的支出計画の実施期間中は、各法人は、各事業年度毎に、公益目的支出計画の実施報告書とともに、①実施事業等会計、②その他事業の会計、③管理業務等に係る法人会計の3つに区分した計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を行政庁に提出しなければならない(整備法127条)。
このように、一般社団・財団法人であっても、公益目的支出計画の「実施事業等」として、公益認定法上の「公益目的事業」に相当する事業が要求されたり、計算書類に厳格な区分経理が求められるなど、公益社団・財団法人並みの要件が課されており、行政庁が法人運営に大きく関与することになる。
一般社団・財団法人は、行政の関与を外し、民間の自発的な公益活動を促進するという今回の改革の理念をとりわけ具現化する制度であったはずである。しかし、実態は骨抜きとの感が否めない。公益目的支出計画については、公益法人への財産の滞留がきっかけとなっているが、これも補助金等の公的資金を受ける行政委託型法人が問題であって、会費・寄附等の民間資金によって運営してきた公益法人については、非難の対象とはならないはずである。新制度のもとで、各法人がより企業経営に近い、堅実な運営が求められているにも拘らず、公益目的支出計画を遂行するために、過去に蓄積してきた財産相当規模の事業を余計に実施しなければならないことは、計画終了後を含めた法人経営の継続性の観点からも問題が多い。
余談になるが、法人が保有する「土地」については、「公益目的財産額」の算定の際に、時価評価することが求められている。たとえば、高度経済成長期前から土地を保有する法人のなかには、取得時よりも大幅に地価が上昇し、法人の身の丈以上の公益目的支出計画を実施しなければならなくなる法人がでてくるかもしれない。
5 公益認定の体制 政府の公益認定等委員会は、移行法人については、5年間で公益認定の審査作業を行うことになる。仮に、現在、国所管の7,000弱の公益法人の半数が公益認定を希望した場合、再審査を除いても1日平均で2法人の審査を行うことになる。これに一般社団・財団法人に移行する法人の認可作業も加わる。申請書類が膨大で、非常勤の委員も多いなか、適切かつ円滑な審査を行っていくことは可能なのだろうか。
1つの懸念材料を指摘したい。公益認定に係る内閣府令では、公益認定を受けて公益法人に移行する場合の最初の事業年度に係る計算書類について、公益認定を受けた日の前日までと公益認定を受けた日以降とに区分して作成し、行政庁に提出することを求めている(公益認定法施行規則38条2項)。事業年度中に認定を受けた場合には、決算を2度行わなければならない。多くの公益法人は少数の経理担当者で切り盛りしているため、相当の負荷がかかることになる。
これに対して、公益認定等委員会は、法人の事務負担軽減のため、希望すれば、時期が近い場合には、公益認定日を4月1日に設定できるようにし、1事業年度中に複数の計算書類を作成しなくてすむよう配慮するとしている。しかし、多くの法人が4月1日の認定取得を目指して、申請が一時期に集中することが予想されるなか、公益認定等委員会の事務作業が追いつくのか懸念されるところである。
より深刻な問題を抱えるのは都道府県の合議制の機関である。地方は、国と比較して、新制度に関する体制、人員、専門性などに大きな差があることは否めない。こうしたなか、公益認定等委員会と各都道府県の合議制の機関との間で、整合性のある審査ができるのか不安視される。
Ⅴ おわりに
今回の公益法人改革は、公的な関与をできるだけ外し、民間による自主的な取組みを最大限尊重することが1つの主眼のはずであった。その意味では、新しい制度は、現行の公益法人の指導監督基準並み、あるいはそれ以下の簡便な制度となることが期待された。
しかし、公益認定基準をはじめ、制度的には非常に煩雑で難解な内容となり、計算書類をはじめ、各法人に非常に手間を課すものとなっている。法人運営の実態にそぐわない法律となったがために、収支相償や公益目的事業比率をはじめ、多くの例外措置を設けたこともこれに拍車をかけた。このままでは、各法人は、制度面での対応に時間をとられ、間接部門ばかりが肥大化し、本来推進すべき公益事業に経営資源を投下することができなくなる。現行の公益法人のほとんどは規模が小さく、少人数の担当者で新制度へ対応せざるをえない。そのため、特に、公益社団・財団法人については、要件が厳格で手続が煩雑だからという理由で選択しない法人も相当数あろうかと思う。そうなれば、新制度は絵に描いた餅となり、改革の意義も乏しいものとなろう。
公益法人改革三法の衆参両院の付帯決議では「法律の状況に変化が生じたときは、広く国民の意見を聴き、直ちに見直しを行うこと」がうたわれた。しかし、その後の政省令、ガイドライン等のパブリック・コメントなどでは、本稿でも触れた課題について、各方面から意見があがったものの、ほとんど採り入れられることはなかった。
今後、新制度を運用していくなかで、改善すべき点は早急に見直し、実態に沿った制度へと磨き上げていくことが必要だろう。勿論、各法人においても、今回の制度改革を機に、経営の質を高めつつ、公益の担い手として、わが国の経済社会の発展に向けて積極的な役割を果たしていかねばならない。今後、公益法人の大いなる活躍を期待したい。
(のむら・よしひさ)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















