解説記事2009年08月10日 【ニュース特集】 衆議院選挙公約にみる税制・法律改正項目等の詳細(2009年8月10日号・№318)
8月30日投開票に向けて出揃う
衆議院選挙公約にみる税制・法律改正項目等の詳細
第171回通常国会(1月5日召集)は延長後7月28日に閉会となる予定であったが、衆議院は7月21日、同日午後に開催された本会議において解散された。衆議院解散に伴う廃案の概況と廃案となったうち注目すべき法案については前号でお伝えしたところであるが(本誌317号4頁参照)、解散とともに注目されたのが、政党と有権者との契約とされる「マニフェスト」の取りまとめとこれに盛り込まれる選挙公約の内容である。年金・医療のあり方、少子化時代の子育て支援など生活に密着した施策が大きく報じられ、各方面からの分析・評価が加えられるなか、本稿では税制・法律改正項目等の詳細を確認しておく。
厳しい経済環境下、中小企業支援は各党がアピール 衆議院が7月21日に解散。定数480の解散時の内訳は、表1のとおりとなっている。
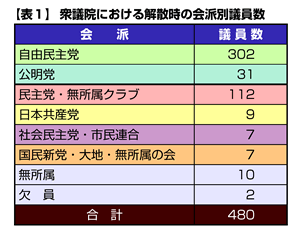
表中「会派」とは、議長に対して議員2名以上の届出により結成し、議案(国会提出法案等)の賛否など議院における活動を共にするものである。通常は政党がそのまま会派を結成するが、政党同士の場合、政党と無所属議員の場合、無所属議員同士の場合などもある。
なお、自由民主党・公明党の両会派が与党として連立政権を組んでいることは周知のとおりであるが、その他の会派が必ず与党に対立するわけではなく、本会議での投票行動をみると、(1)所得税法等改正法(平成21年法律第13号)の賛成会派は「自由民主党」「公明党」、反対会派は「民主党・無所属クラブ」「日本共産党」「社会民主党・市民連合」であったのに対し、(2)産業活力再生特別措置法等改正法(平成21年法律第29号)、独占禁止法改正法(平成21年法律第51号)、金融商品取引法等改正法(平成21年法律第58号)では「自由民主党」「民主党・無所属クラブ」「公明党」「国民新党・大地・無所属の会」の4会派が賛成、「日本共産党」「社会民主党・市民連合」が反対、(3)資金決済法(平成21年法律59号)では6会派が全会一致で賛成。各法律は結果的にすべて可決されている。
本稿では以下、解散時において各会派を結成していた中心政党としての「自由民主党」「公明党」「民主党」「日本共産党」「社会民主党」「国民新党」を取り上げ、8月18日公示・30日投開票となる本年衆議院議員総選挙における各党の選挙公約から、主に税制・法律改正事項として取り上げられた項目を確認していく。
「政権公約」「Manifesto」など様々な名称 各党の選挙公約を表2としてまとめた。
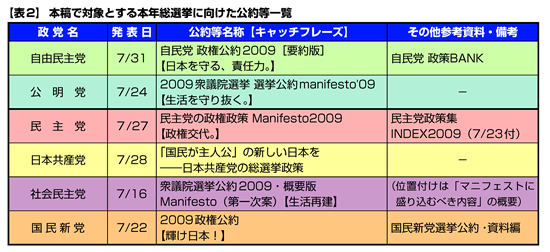
様々な名称がみられるが、「総選挙政策」と題する日本共産党を含め、いずれも総選挙での当選後、原則として任期中に果たすべき選挙公約と目されるものである。社会民主党においては「正式の公選法に基づくマニフェストは……公示日(8月18日予定)から配付開始」「今回発表したものは、法的には、『マニフェストに盛り込むべき内容』の概要」と表明しているところ、本稿では当該「第一次案」を対象とした(以下、総称して「公約等」という)。
また、政党によっては、公約等について、簡潔かつカラフルで手に取りやすく作成した要約版または概要版と呼ぶべきものと詳細な施策集とを別建てとし、分冊形式としている場合があるが、本稿で紹介する項目は選挙公約としてのものに絞っている(下掲・コラム欄参照)。
なお、選挙公約として政治的責任を負いながら実行されるべきものと捉え、財源については取り上げない。しかしながら傾向として触れておくと、天下りの禁止、公益法人・独立行政法人等の見直しをほぼすべての党が掲げ、まずは税金の無駄遣いをなくしていくとするほか、政治資金透明化の観点から、民主党・社会民主党・日本共産党が企業・団体献金の禁止、自由民主党・公明党・民主党・社会民主党が個人献金促進のための税制措置について言及している。
税制・法律改正等に係る個別項目の詳細 税および国と地方・地域に関係する項目について掲げたのが表3、経済成長政策や中小企業対策、その他法律の制定・改廃等の関係、温暖化対策についてまとめたのが表4である(与党に続く政党を民主党・社会民主党・国民新党、共産党の順とした。民主党ほか2党が「共に選挙を戦うにあたっての共通認識を整理」(7月31日・民主党幹事長定例会見発言)中のため)。
収載にあたっては、公約等に触れられている各党共通の課題を優先して洗い出し、できる限り各党横断的に取り上げたほか、記載のニュアンスを損なわないように要約している。
また、本誌読者に馴染み深いものと考えられる項目については極力収載する方針を採ったほか、公約等自体の分量も政党により相違していることから、政党ごとに収載項目の多寡が生じている。温暖化対策については、公明党・民主党・社会民主党の各欄で各党横断的な項目のほか、特徴的な項目のみを掲げるにとどめた。
各表を仔細にみれば、与野党を問わず共通して掲げられる施策も散見される状況であり、これらは特に留意しておきたい。
COLUMN
詳細版の位置付けが異なる? 自由民主党では、表2のように「要約版」とともに「政策BANK」を作成して個別具体的な施策の説明を行う。後者は「詳細版」と位置付けられており、選挙公約に包含されている(同様の分冊形式を採る例として、国民新党)。民主党の「政策集」はとりわけ詳細な説明を行うもので「公開会社法の制定を検討」するといった項目も存在するが、「党としての政策の考え方を取りまとめたもの」とされており、選挙公約とは位置付けられていない。
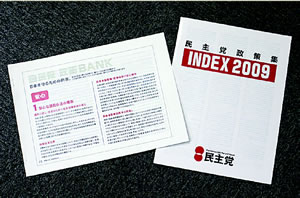
衆議院選挙公約にみる税制・法律改正項目等の詳細
第171回通常国会(1月5日召集)は延長後7月28日に閉会となる予定であったが、衆議院は7月21日、同日午後に開催された本会議において解散された。衆議院解散に伴う廃案の概況と廃案となったうち注目すべき法案については前号でお伝えしたところであるが(本誌317号4頁参照)、解散とともに注目されたのが、政党と有権者との契約とされる「マニフェスト」の取りまとめとこれに盛り込まれる選挙公約の内容である。年金・医療のあり方、少子化時代の子育て支援など生活に密着した施策が大きく報じられ、各方面からの分析・評価が加えられるなか、本稿では税制・法律改正項目等の詳細を確認しておく。
厳しい経済環境下、中小企業支援は各党がアピール 衆議院が7月21日に解散。定数480の解散時の内訳は、表1のとおりとなっている。
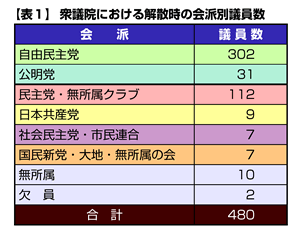
表中「会派」とは、議長に対して議員2名以上の届出により結成し、議案(国会提出法案等)の賛否など議院における活動を共にするものである。通常は政党がそのまま会派を結成するが、政党同士の場合、政党と無所属議員の場合、無所属議員同士の場合などもある。
なお、自由民主党・公明党の両会派が与党として連立政権を組んでいることは周知のとおりであるが、その他の会派が必ず与党に対立するわけではなく、本会議での投票行動をみると、(1)所得税法等改正法(平成21年法律第13号)の賛成会派は「自由民主党」「公明党」、反対会派は「民主党・無所属クラブ」「日本共産党」「社会民主党・市民連合」であったのに対し、(2)産業活力再生特別措置法等改正法(平成21年法律第29号)、独占禁止法改正法(平成21年法律第51号)、金融商品取引法等改正法(平成21年法律第58号)では「自由民主党」「民主党・無所属クラブ」「公明党」「国民新党・大地・無所属の会」の4会派が賛成、「日本共産党」「社会民主党・市民連合」が反対、(3)資金決済法(平成21年法律59号)では6会派が全会一致で賛成。各法律は結果的にすべて可決されている。
本稿では以下、解散時において各会派を結成していた中心政党としての「自由民主党」「公明党」「民主党」「日本共産党」「社会民主党」「国民新党」を取り上げ、8月18日公示・30日投開票となる本年衆議院議員総選挙における各党の選挙公約から、主に税制・法律改正事項として取り上げられた項目を確認していく。
「政権公約」「Manifesto」など様々な名称 各党の選挙公約を表2としてまとめた。
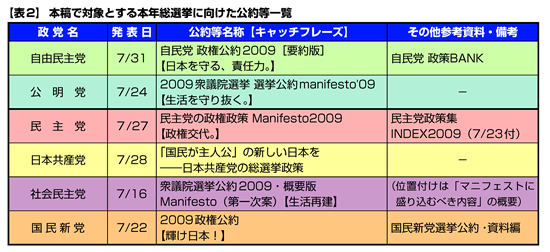
様々な名称がみられるが、「総選挙政策」と題する日本共産党を含め、いずれも総選挙での当選後、原則として任期中に果たすべき選挙公約と目されるものである。社会民主党においては「正式の公選法に基づくマニフェストは……公示日(8月18日予定)から配付開始」「今回発表したものは、法的には、『マニフェストに盛り込むべき内容』の概要」と表明しているところ、本稿では当該「第一次案」を対象とした(以下、総称して「公約等」という)。
また、政党によっては、公約等について、簡潔かつカラフルで手に取りやすく作成した要約版または概要版と呼ぶべきものと詳細な施策集とを別建てとし、分冊形式としている場合があるが、本稿で紹介する項目は選挙公約としてのものに絞っている(下掲・コラム欄参照)。
なお、選挙公約として政治的責任を負いながら実行されるべきものと捉え、財源については取り上げない。しかしながら傾向として触れておくと、天下りの禁止、公益法人・独立行政法人等の見直しをほぼすべての党が掲げ、まずは税金の無駄遣いをなくしていくとするほか、政治資金透明化の観点から、民主党・社会民主党・日本共産党が企業・団体献金の禁止、自由民主党・公明党・民主党・社会民主党が個人献金促進のための税制措置について言及している。
税制・法律改正等に係る個別項目の詳細 税および国と地方・地域に関係する項目について掲げたのが表3、経済成長政策や中小企業対策、その他法律の制定・改廃等の関係、温暖化対策についてまとめたのが表4である(与党に続く政党を民主党・社会民主党・国民新党、共産党の順とした。民主党ほか2党が「共に選挙を戦うにあたっての共通認識を整理」(7月31日・民主党幹事長定例会見発言)中のため)。
【表3】税、国と地方・地域に係る項目
政党名 | 内容(一部項目・要旨) |
| 自由民主党 | ▲消費税を含む税制の抜本的改革について平成21年度税制改正法附則に沿って平成23年度までに必要な法制上の措置を講じ、経済状況の好転後遅滞なく実施 ▲消費税の社会保障・少子化対策への特化、社会保障番号・カードの導入 ▲最大600万円の住宅ローン控除など住宅取得支援を継続・強化、住宅の長寿命化の推進とともに既存市場・リフォーム市場を整備 ▲国の出先機関の廃止、補助金・税配分の見直しなどの「新地方分権一括法案」を成立へ ▲中期プログラムに基づき税制の抜本的改革に取り組む際には地方消費税を充実、地方交付税を増額(地方交付税が地方の固有財源であることの明確化) ▲NPO法人などボランティア組織の育成・支援、「コミュニティ活動基本法」の制定による町内会・自治会・消防団などの団体の支援 |
| 公明党 | ▲一定の条件下、その時々の経済状況をにらみつつ2010年代半ばまでに段階的に実行する税制の抜本改革にあたっては、所得課税・法人課税・消費課税・資産課税等を含め税制全般について一体的に改革 ▲格差の是正や所得再分配機能の強化を図るため、所得税の最高税率の引上げや相続税の見直しを実行 ▲法人税については課税ベースを拡大しつつ実効税率を引下げ ▲生活支援や子育て教育支援等の観点から給付付き税額控除制度を導入 ▲消費税収の使途は社会保障給付および少子化対策の費用に限定、見直しに際しては複数税率の検討など低所得者への配慮措置 ▲税制全体のグリーン化の推進、自動車関係諸税の簡素化、税率のあり方の総合的見直し・負担軽減 ▲空き店舗対策などの商店街整備事業に取り組む商店街振興組合等に土地を譲渡した場合における特別控除の適用要件の緩和 ▲地方分権一括法の制定による出先機関の廃止・縮小、二重行政の是正 ▲地方の課税自主権の拡大(国と地方の税源比率を1対1とすることを目標)、地方消費税の充実 ▲NPOなどの非営利セクターに対する支援税制の認定要件緩和、寄付金控除制度の充実 |
| 民主党 | ▲租税特別措置の適用対象を明確化、その効果を検証できる仕組みをつくり、効果の不明なもの、役割を終えたものは廃止し、真に必要なものは「恒久措置」へ切替え ▲自動車関連諸税の暫定税率の廃止(将来的には、自動車重量税は自動車税として1本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止、ガソリン税・軽油引取税は表4参照) ▲相対的に高所得者に有利な所得控除から中・低所得者に有利な手当などへ切替え ▲中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%へ引下げ、いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置の廃止 ▲社会保険庁は国税庁と統合して「歳入庁」とし税と保険料を一体的に徴収、税と社会保障制度共通の番号制度を導入 ▲多様な賃貸住宅を整備するため、家賃補助や所得控除などの支援制度を創設 ▲リフォームを最重点に位置付け、バリアフリー改修・耐震補強改修、太陽光パネルや断熱材設置などの省エネルギー改修工事を支援 ▲国から地方への「ひもつき補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える「一括交付金」として交付 ▲国の出先機関の原則廃止、すべての国直轄事業における負担金制度の廃止(これに伴う地方交付税の減額は行わない) ▲認定NPO法人制度を見直し、寄付税制を拡充 |
| 社会民主党 | ▲消費税率は引き上げず、飲食料品分は実質非課税に ▲低所得者、子育て世帯に対する給付付き税額控除制度の検討 ▲高額所得者の最高税率を50%に戻し、基礎控除は現行38万円から76万円に ▲法人税の基本税率を34.5%に戻し、大企業の特別措置は大胆に縮小 ▲中小企業への法人税を11%に軽減、適用所得を引上げ ▲ガソリン税の暫定税率は廃止、環境面から抜本的に見直し ▲消費税と地方消費税の配分割合を1:1にするなど税源委譲により国と地方の税源配分を5:5に、削られた地方交付税を復元・増額 ▲国直轄事業の地方負担金を廃止 ▲NPO法・NPO税制を抜本改革し、NPOを支援 |
| 国民新党 | ▲現在30%に設定されている大企業法人税を35~40%台に引上げ、社会保障や国民の安心づくりに活用 ▲高額所得者の所得税の最高税率を現在の40%から50%に引上げ ▲消費税は増税せず全額を社会保障のための目的税に、食料・医療などの国民の安心な生活に必要なものについてゼロ税率化 ▲定率減税の復活、仕送り減税(自宅外通学者への仕送りに関する支出に係るもの)の創設、住宅ローン減税の拡充、中小企業の投資減税の新設、研究開発減税の新設を合わせて5か年で50兆円実施 ▲(年金等社会保障の見直しにおける)国税庁、社会保険庁の一元化および郵便局の利活用 ▲法人税・所得税・消費税を始めとする諸税を再検討し、税制における国と地方の比率を抜本的に見直し ▲地方交付税の復元(5か年で10兆円)、いきいき地方復活交付金(5か年計画で18.5兆円)の新設 |
| 日本共産党 | ▲他の先進国にならい「納税者憲章」を制定、消費税の免税点引上げや家族の労賃を必要経費と認めない所得税法56条の廃止など中小企業や零細企業を育てる税制に転換 ▲消費増税に反対、減税に踏み切り、その際に食料品などの生活必需品を非課税化 ▲所得税・住民税の最高税率を少なくとも1998年以前の水準(合わせて65%)に戻す ▲相続税の最高税率を元に戻す ▲証券優遇税制を直ちに廃止、税率を少なくとも20%に戻す ▲大企業の法人税率を1997年の水準まで段階的に引上げ ▲高齢者の所得税・住民税の増税について公的年金等控除の最低保障額を140万円に戻すとともに所得500万円以下の高齢者には老年者控除を復活 ▲中小企業を対象にした緊急の休業補償・直接支援を実施(中小貸し工場への家賃や光熱費などの固定費の補助、固定資産税の減免、大企業からの注文に応えるために行った設備投資の減価償却への助成など) ▲法人税にも累進制を導入、中小企業の一定範囲の所得について現行より税率を引下げ ▲自治体が実施している住宅リフォームへの助成制度を抜本的に拡充 ▲国庫負担金・補助金の廃止・縮減に反対、その改善・充実を求める ▲地方交付税の復元・増額 ▲国直轄事業負担金の抜本的な見直し ▲商店街の振興、農商工連携、伝統産業・地場産業の支援などについて地方自治体が主導的な役割を果たせるよう国の支援を抜本的に拡充 |
【表4】経済成長政策等、その他法律の制定・改廃等、温暖化対策に係る項目(次頁に続く)
政党名 | 内容(一部項目・要旨) |
| 自由民主党 | ▲農商工連携・産官学連携の推進 ▲ものづくり技術の開発、イノベーションの推進などによる産業の高付加価値化の実現 ▲BRICs・アジア諸国など各国市場を取り込むための投資環境整備・経済協力政策の推進 ▲小規模事業者共済の加入対象者の拡大 ▲商工会議所・商工会の組織機能強化のための早急な抜本的対策 ▲連帯保証人制度のあり方の見直し ▲不当廉売に対して断固対処するためのガイドラインの見直し ▲信用保証協会の緊急信用保証の拡大、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付・危機対応業務の実施、銀行等保有株式取得機構の活用などによる中小企業、中堅・大企業の資金繰り支援など金融システムの安定化 ▲空き店舗の活用や駐車場整備など商店街活性化の支援 ▲消費者庁の2009年9月中の発足、地方の消費者生活相談体制の強化、次期国会での消費者教育推進法(仮称)の成立 ▲消費者行政とのバランスをとった各種規制のあり方の見直しによる発展的経済活動の側面的支援、新たな立法時における規制の新設について国民の安心安全を確保するとともに自由で活力ある経済活動を阻害しない観点から引き続き十分な事前審査の実行 ▲新たな公益法人制度について5年間の移行期間でスムーズに移行できるよう引き続ききめ細かな対応、公益法人への委託等の廃止 ▲国会主導の政策立案のさらなる推進、議員活動の充実の観点から立法スタッフを拡充・強化 ▲太陽光発電の買取制度の導入、省エネ住宅・エコカー減税・エコポイントの推進、カーボンオフセットの本格的な推進を図る「低炭素社会づくり推進基本法」の制定 ▲わが国の2020年の温室効果ガスの削減量の目標を2005年比15%削減 |
| 公明党 | ▲産官学の連携強化・加速によるイノベーションの創出の促進 ▲現行の事業規制の抜本的な見直しによる民間事業活動のさらなる活性化 ▲アジア地域における内需拡大を総合的かつ集中的に推進する「アジア版ニューディール」に取組み ▲中小・小規模企業を一層支援するための財政面・税制面・制度面を含めた施策の強力な推進、商工会・商工会議所の組織機能の強化など ▲創業・経営革新・事業承継などに関するファンドの強化など ▲小規模企業共済の加入対象者の拡大 ▲緊急保証制度・セーフティネット貸付制度の十分な枠の確保や危機対応業務の機動的な対応、企業再生ファンドの拡充 ▲新会計基準対応(資産除去債務)における中小企業への負担軽減措置 ▲金融仲介機能が正常に機能するよう検査・監督を強化、金融機能強化法の積極的な活用等の推進 ▲企業再生支援機構による地域企業再生の円滑化の推進 ▲産業活力再生支援や企業立地促進などによる地域活性化の推進 ▲農商工連携500件、地域資源活用プログラム1,000件、新連携1,000件など新しい成長をもたらす取組みの積極的な支援 ▲エンジェル税制の活用やベンチャーファンドの拡充などベンチャー企業に対する資金調達や経営支援の強化 ▲事業承継に係るワンストップサービスを提供する「事業承継支援センター」による使い勝手のよい事業承継制度の運営 ▲中小企業再生支援協議会の機能強化、改正産業活力再生特別措置法の活用等による事業再生支援の強化 ▲中小小売商業振興法や地域商店街活性化法、中心市街地活性化法などの関係法制の抜本的な見直し、総合的な支援の拡充 ▲中小企業の経営基盤強化に資する知的財産活用の促進のため法整備や税制措置など戦略的にインフラ整備 ▲下請代金支払遅延等防止法の改正・執行強化、下請適正取引推進ガイドラインの活用などによる下請企業に過度な負担となる取引慣行の是正 ▲独占禁止法における課徴金や罰則の強化を受け国民目線での運用を図るためのガイドラインを策定、将来的には公平かつ公正、透明性の高い審判制度を構築など ▲暴力団・来日外国人犯罪組織などによる組織犯罪の取締りの推進 ▲消費者庁の早期スタートの推進、消費者教育に関する法整備の検討、適格消費者団体を始めとする消費者団体への情報提供、施設・資金などの支援など ▲投資家保護の観点からのFX取引等金融商品の取引に関する規制の見直し、金融資本市場が公正に機能するための規制の強化など ▲教育の質の向上、多様な人材の育成、職域の拡大など法曹養成制度の強化・充実 ▲裁判員制度について引き続き広報宣伝活動を実施、学校における法教育の普及・発展など ▲行政訴訟の体制整備を含めたさらなる改革の推進、より開かれた行政訴訟制度の創設 ▲弁護士「ゼロワン地域」の解消 ▲法テラスのスタッフ弁護士の大幅増員など ▲民事法律扶助のさらなる充実 ▲登記事項証明書の交付請求手数料の引下げ ▲「低炭素社会づくり推進基本法」の制定 ▲エコカー・エコ家電・太陽電池の「エコ3本柱」による環境と調和した経済の発展、価格の低減など ▲2020年に1990年比25%削減、2050年に同80%削減を目標 ▲税制抜本改革に向けて炭素税の導入を検討 ▲有価証券報告書における温室効果ガス排出量等の情報開示の推進 ▲電力の固定価格買取制度の拡充 など |
| 民主党 | ▲「次世代の人材育成」「公正な市場環境整備」「中小企業金融の円滑化」などを内容とする「中小企業憲章」の制定 ▲「中小企業いじめ防止法」を制定し、大企業による不公正な取引を禁止 ▲使い勝手のよい「特別信用保証」の復活 ▲政府系金融機関の中小企業に対する融資について個人保証を撤廃 ▲連帯保証人制度について廃止を含めたあり方の検討 ▲金融機関に対して地域への寄与度や中小企業に対する融資状況などの公開を義務付ける「地域金融円滑化法」を制定 ▲公正取引委員会の機能強化・体制充実による公正な市場環境の整備 ▲中小企業の技術開発を促進する制度の導入など総合的な企業支援策による「100万社起業」を目標 ▲消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報公開を企業に義務付ける「危険情報公表法」の制定、消費者の財産被害の救済と消費者団体訴訟制度を実効あるものとするため悪徳業者が違法に集めた財産を剥奪する制度の創設など ▲建築基準法などの関係法令を抜本的に見直し、住宅建設に係る資格・許認可の整理・簡素化等、必要な予算を地方自治体に一括交付 ▲定期借家制度の普及の推進、ノンリコース型ローンの普及の促進、リバースモーゲージを利用しやすく ▲2020年までに1990年比25%減、2050年までに同60%超減を目標 ▲将来的には、ガソリン税・軽油引取税は「地球温暖化対策税(仮称)」として1本化 ▲全量買取方式の再生可能エネルギーに対する固定価格買取制度の早期導入 ▲住宅用などの太陽光パネル、環境対応車、省エネ家電などの購入助成 など |
| 社会民主党 | ▲中小企業支援のための予算を4,000億円に倍増、経営・金融支援を拡充 ▲選択的夫婦別姓など民法改正を実現 ▲事業譲渡や経営形態変更の際、同じ雇用条件での継続雇用を実現 ▲裁判員制度の見直し ▲2020年までに1990年比30%、2050年までに同80%削減 ▲太陽光や風力発電の固定価格買取制度の導入 ▲環境税(CO2排出量に比例)の導入を目標、社会保障や温暖化対策などの財源に など |
| 国民新党 | ▲5か年で200兆円(追加財政支出150兆円、減税50兆円)の積極財政により経済成長と税収増、民間投資と消費への刺激拡大を通じて経済の活性化を実現 ▲困窮する中小零細企業の経営資金の返済について最長3年間の支払猶予制度を新設 ▲大企業による不公正契約(いわゆる下請いじめ)の是正など (他の政党の欄で掲げたものと同様の分野については特段の言及なし) ▲気候変動に関する基礎研究の充実(充分な科学的な検証なく温室効果ガス削減の目標設定や排出権取引の急拡大を進めること自体をゴールにすべきではない) ▲再生可能エネルギーを用いた発電機器の効率性・耐久性・低価格化のための積極投資、各家庭・事業者への一層の普及を図るための補助制度のさらなる充実 |
| 日本共産党 | ▲給付開始の早期化、助成率の引上げなど中小企業向け雇用調整助成金を抜本的に拡充 ▲緊急保証制度について全業種を対象化、審査条件を緩和、一般保証制度に導入された部分保証制度を廃止して全額保証に ▲違法な「下請切り」への指導監督を抜本的に強化、直ちに禁止 ▲EU制定の「小企業憲章」にならい、「中小企業憲章」を制定して中小企業の役割を明確化、国の政策の影響・効果を検証して中小企業政策に反映 ▲中小企業・地域経済に対する金融機関の貢献を義務付ける「地域金融活性化法」の制定、政府系金融機関の統廃合中止による公的金融制度の拡充 ▲独占禁止法を改正し、中小企業との取引・競争における大企業の地位の濫用を厳しく規制 ▲下請代金法を改正し、違反した企業名や事実の公表、損害賠償支払いの義務化などを措置 ▲公正取引委員会に中小企業の代表を加えるなど機能の拡充・強化 ▲業界団体・中小企業団体が大企業および大手の業界相手に「団体交渉」を行う権利を保障した「公正取引確保法」(仮称)を制定 ▲民法を改正し、選択的夫婦別姓制度の実現、再婚禁止期間・婚姻最低年齢の見直し、婚外子差別の禁止の推進 ▲2020年までに1990年比30%削減、2050年までに同80%削減 ▲二酸化炭素の排出量などに着目した環境税を導入 ▲自然エネルギーによる電力全般を全量買い入れる固定価格買取義務制度を導入 |
収載にあたっては、公約等に触れられている各党共通の課題を優先して洗い出し、できる限り各党横断的に取り上げたほか、記載のニュアンスを損なわないように要約している。
また、本誌読者に馴染み深いものと考えられる項目については極力収載する方針を採ったほか、公約等自体の分量も政党により相違していることから、政党ごとに収載項目の多寡が生じている。温暖化対策については、公明党・民主党・社会民主党の各欄で各党横断的な項目のほか、特徴的な項目のみを掲げるにとどめた。
各表を仔細にみれば、与野党を問わず共通して掲げられる施策も散見される状況であり、これらは特に留意しておきたい。
COLUMN
詳細版の位置付けが異なる? 自由民主党では、表2のように「要約版」とともに「政策BANK」を作成して個別具体的な施策の説明を行う。後者は「詳細版」と位置付けられており、選挙公約に包含されている(同様の分冊形式を採る例として、国民新党)。民主党の「政策集」はとりわけ詳細な説明を行うもので「公開会社法の制定を検討」するといった項目も存在するが、「党としての政策の考え方を取りまとめたもの」とされており、選挙公約とは位置付けられていない。
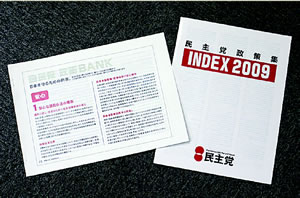
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























