解説記事2009年08月24日 【ニュース特集】 遺留分減殺請求の効力は相続開始時にまで遡及せず(2009年8月24日号・№319)
遺産分割に係る民法909条のような規定は存しない
遺留分減殺請求の効力は相続開始時にまで遡及せず
「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」との遺言により、審査請求人が承継した賃貸不動産に係る賃料の帰属が争われた審査請求事案で、国税不服審判所が、当該遺言の効力、遺留分減殺請求の効力、果実(賃料債権)の帰属について判断した(東裁(所)平20第139号)。審判所は、遺留分減殺請求について、遺産分割について相続開始時への遡及効を定めた民法909条のような規定が存しないことから、その効力が相続開始時にさかのぼるものではないとしている。
遺言書の検認から訴訟上の和解に至るまでの経緯
被相続人の相続に係る相続人・財産 被相続人(請求人の母)の相続に係る相続人は、被相続人の実子である請求人および養子2人(以下「Aら」という)の3名。被相続人の財産(土地8、建物2、預貯金6(計19,479,469円))のうち、1つの建物とその敷地の一部は、共同住宅および駐車場として賃貸されており、相続開始後の賃料等は、請求人、Aらなどの間での遺産分割協議により、請求人以外の名義の口座に入金された。
その後、「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」旨を内容とする被相続人の自筆遺言証書が家庭裁判所において検認された。
代償金1,200万円で和解 請求人は、Aらに対して、遺言書にかかわらず、AらがX土地(774㎡)を除くすべての土地および建物の所有権を取得するとともに被相続人の全債務を引き継ぎ、請求人はX土地を取得するとともに、Aらから代償金の支払いを受けるという遺産分割案を提示した。
一方、Aらは請求人に対し、遺留分減殺請求を行い、これにより、被相続人の相続財産が請求人とAらとの共有となった。Aらは、被相続人の債務に係るAらの連帯債務の解消等に関して、Aらは複数の案を示して解決したいと申し入れたが、請求人がこれに応じないとして、遺産に関する紛争の調停を申し立て、上記代償金の額について協議したが、調停は不成立に終わった。
最終的には、請求人が遺言書に基づく全遺産に対する権利の存在を確認または給付の履行を求めた訴訟において、Aらが支払可能な代償金の額として12,000,000円を提示し、請求人がこれを承諾したことで、和解に至っている(図表1参照)。
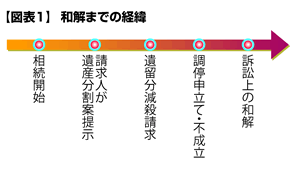 なお、この和解において、請求人およびAらは相続開始時以降、和解の成立時までの賃貸物件に係る賃料債権が、請求人に帰属しないことを確認している。
なお、この和解において、請求人およびAらは相続開始時以降、和解の成立時までの賃貸物件に係る賃料債権が、請求人に帰属しないことを確認している。
請求人による更正の請求に対して、一部減額する更正処分 請求人は当初、遺言書により相続した賃貸物件から生ずる相続開始以降の不動産所得の金額を請求人自身の所得として確定申告をしたが、上記和解により、賃貸物件に係る請求人の不動産所得は零円となったとして、原処分庁に対して更正の請求をした。
これに対して原処分庁は、遺産分割の確定までの期間に生じる不動産賃貸収入は、請求人にその法定相続分(3分の1)が帰属するとして、不動産所得の一部を減額する更正処分を行った。なお、請求人は本事案で当該更正処分の全部の取消しを求めている。
遺留分減殺請求等の効力、果実の帰属等に関する法令解釈 本事案において、審判所は、賃料債権帰属の法律関係として、①遺言の効力について、②遺留分減殺請求の効力について、③果実の帰属についての法令解釈を示している。
以下では、その内容を具体的にみていく。
遺言の効力について 遺産全部について共同相続人の1人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたとともに相続分が指定されたものと解すべきであり、また、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産全部が、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継されたものと解される(最高裁第二小法廷判決平成3年4月19日・民集45巻4号477頁参照)。
遺留分減殺請求の効力について 上記のとおり、すべての遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言により、当該遺産全部が、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継された後に、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合には、一般に遺留分減殺請求権は形成権であると解されるから(最高裁第一小法廷判決昭和47年7月14日・民集20巻6号1183頁参照)、遺留分減殺請求の意思表示により上記相続分の指定は遺留分を侵害する限度において直ちに失効し、当該相続人が取得した権利は、遺留分権利者の遺留分を侵害する限度において当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属することとなる(最高裁第二小法廷判決昭和51年8月30日・民集30巻7号768頁参照、最高裁第一小法廷判決平成10年2月26日・民集52巻1号274頁参照)。
したがって、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言がされた場合において、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、当該賃貸不動産を含むすべての相続財産は、当該相続人と減殺請求権を行使した遺留分権利者との共有財産となると解される。
また、遺留分減殺請求については、遺産分割について相続開始時への遡及効を定めた民法909条のような規定は存しないから、その効力が相続開始時にさかのぼるものではない(下線・編集部)。
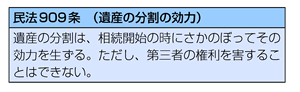 果実の帰属について
果実たる賃料債権は、賃貸物件を使用管理した結果生じるものであるから、遺産とは別個の財産というべきであって、その収取されるときにおける元物の持分に応じて単独ないし分割単独債権として確定的に帰属すると解するのが相当である。そうすると、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言により承継された当該賃貸不動産の賃料債権は、そのすべてが当該相続人の課税所得を構成し、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したことにより共有となった賃貸不動産から生じる賃料債権は、当然に分割されて共有者である当該相続人と遺留分権利者とがそれぞれの共有持分に応じて分割単独債権として取得するものであり、遺留分減殺請求のあった日以後に当該賃貸不動産から生じる賃料債権のうち遺留分を除く部分が当該相続人の課税所得を構成すると解される。
果実の帰属について
果実たる賃料債権は、賃貸物件を使用管理した結果生じるものであるから、遺産とは別個の財産というべきであって、その収取されるときにおける元物の持分に応じて単独ないし分割単独債権として確定的に帰属すると解するのが相当である。そうすると、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言により承継された当該賃貸不動産の賃料債権は、そのすべてが当該相続人の課税所得を構成し、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したことにより共有となった賃貸不動産から生じる賃料債権は、当然に分割されて共有者である当該相続人と遺留分権利者とがそれぞれの共有持分に応じて分割単独債権として取得するものであり、遺留分減殺請求のあった日以後に当該賃貸不動産から生じる賃料債権のうち遺留分を除く部分が当該相続人の課税所得を構成すると解される。
減殺請求の日の前日までは全額が請求人に帰属 上記の法令解釈に基づき、審判所は本事案について、本件遺言書が、「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」旨を内容とするものであることから、請求人は相続開始と同時に賃貸物件を含む被相続人の財産および債務のすべてを取得し、賃貸物件に係る賃貸人の地位も承継し、その後、遺留分権利者から減殺請求がされたことにより、請求人が受けた相続分の指定の効果は、Aらの遺留分(各6分の1相当額)を侵害する限度において直ちに失効し、請求人とAらとは、賃貸物件に対し、共有持分を取得する関係に立ったものと認定した。
そのうえで、賃料債権は、図表2のとおり単独ないし分割単独債権として確定的に請求人に帰属し、課税所得を構成すると認めるのが相当であると判断している(図表3参照)。
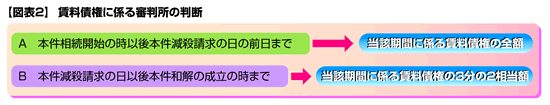
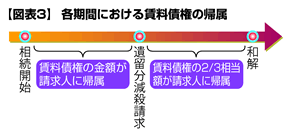 なお、審判所は、本事案における和解について、その経緯から被相続人の遺産の分割を行うことに当事者双方が合意して、賃貸物件の新たな権利関係を創設する趣旨のものであって、相続開始時にさかのぼって従前の権利関係に異動を来すものではないと解するのが相当とし、法律上遡及的な効力が生ずるものとは認められないとしている。
なお、審判所は、本事案における和解について、その経緯から被相続人の遺産の分割を行うことに当事者双方が合意して、賃貸物件の新たな権利関係を創設する趣旨のものであって、相続開始時にさかのぼって従前の権利関係に異動を来すものではないと解するのが相当とし、法律上遡及的な効力が生ずるものとは認められないとしている。
column
相続税の連帯納付義務に関する裁決事例では異なる判断 国税不服審判所は、相続税の連帯納付義務に関する裁決(裁決事例集No.71平18.6.26裁決)で、民法上の遺留分制度について、「これは、遺留分を侵害する被相続人の贈与、遺贈、相続分の指定等の処分行為を減殺請求で減殺することにより、遺留分権利者が、これらの処分行為がなければ相続財産となるものの一部を受け取るものであって、遺留分減殺請求権の行使により、相続時にさかのぼって取得するものと解される。」としており、本事案とは異なる判断をしていた(下線・編集部)。
遺留分減殺請求の効力は相続開始時にまで遡及せず
「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」との遺言により、審査請求人が承継した賃貸不動産に係る賃料の帰属が争われた審査請求事案で、国税不服審判所が、当該遺言の効力、遺留分減殺請求の効力、果実(賃料債権)の帰属について判断した(東裁(所)平20第139号)。審判所は、遺留分減殺請求について、遺産分割について相続開始時への遡及効を定めた民法909条のような規定が存しないことから、その効力が相続開始時にさかのぼるものではないとしている。
遺言書の検認から訴訟上の和解に至るまでの経緯
被相続人の相続に係る相続人・財産 被相続人(請求人の母)の相続に係る相続人は、被相続人の実子である請求人および養子2人(以下「Aら」という)の3名。被相続人の財産(土地8、建物2、預貯金6(計19,479,469円))のうち、1つの建物とその敷地の一部は、共同住宅および駐車場として賃貸されており、相続開始後の賃料等は、請求人、Aらなどの間での遺産分割協議により、請求人以外の名義の口座に入金された。
その後、「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」旨を内容とする被相続人の自筆遺言証書が家庭裁判所において検認された。
代償金1,200万円で和解 請求人は、Aらに対して、遺言書にかかわらず、AらがX土地(774㎡)を除くすべての土地および建物の所有権を取得するとともに被相続人の全債務を引き継ぎ、請求人はX土地を取得するとともに、Aらから代償金の支払いを受けるという遺産分割案を提示した。
一方、Aらは請求人に対し、遺留分減殺請求を行い、これにより、被相続人の相続財産が請求人とAらとの共有となった。Aらは、被相続人の債務に係るAらの連帯債務の解消等に関して、Aらは複数の案を示して解決したいと申し入れたが、請求人がこれに応じないとして、遺産に関する紛争の調停を申し立て、上記代償金の額について協議したが、調停は不成立に終わった。
最終的には、請求人が遺言書に基づく全遺産に対する権利の存在を確認または給付の履行を求めた訴訟において、Aらが支払可能な代償金の額として12,000,000円を提示し、請求人がこれを承諾したことで、和解に至っている(図表1参照)。
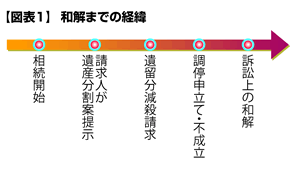 なお、この和解において、請求人およびAらは相続開始時以降、和解の成立時までの賃貸物件に係る賃料債権が、請求人に帰属しないことを確認している。
なお、この和解において、請求人およびAらは相続開始時以降、和解の成立時までの賃貸物件に係る賃料債権が、請求人に帰属しないことを確認している。請求人による更正の請求に対して、一部減額する更正処分 請求人は当初、遺言書により相続した賃貸物件から生ずる相続開始以降の不動産所得の金額を請求人自身の所得として確定申告をしたが、上記和解により、賃貸物件に係る請求人の不動産所得は零円となったとして、原処分庁に対して更正の請求をした。
これに対して原処分庁は、遺産分割の確定までの期間に生じる不動産賃貸収入は、請求人にその法定相続分(3分の1)が帰属するとして、不動産所得の一部を減額する更正処分を行った。なお、請求人は本事案で当該更正処分の全部の取消しを求めている。
遺留分減殺請求等の効力、果実の帰属等に関する法令解釈 本事案において、審判所は、賃料債権帰属の法律関係として、①遺言の効力について、②遺留分減殺請求の効力について、③果実の帰属についての法令解釈を示している。
以下では、その内容を具体的にみていく。
遺言の効力について 遺産全部について共同相続人の1人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたとともに相続分が指定されたものと解すべきであり、また、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産全部が、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継されたものと解される(最高裁第二小法廷判決平成3年4月19日・民集45巻4号477頁参照)。
遺留分減殺請求の効力について 上記のとおり、すべての遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言により、当該遺産全部が、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継された後に、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合には、一般に遺留分減殺請求権は形成権であると解されるから(最高裁第一小法廷判決昭和47年7月14日・民集20巻6号1183頁参照)、遺留分減殺請求の意思表示により上記相続分の指定は遺留分を侵害する限度において直ちに失効し、当該相続人が取得した権利は、遺留分権利者の遺留分を侵害する限度において当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属することとなる(最高裁第二小法廷判決昭和51年8月30日・民集30巻7号768頁参照、最高裁第一小法廷判決平成10年2月26日・民集52巻1号274頁参照)。
したがって、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言がされた場合において、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、当該賃貸不動産を含むすべての相続財産は、当該相続人と減殺請求権を行使した遺留分権利者との共有財産となると解される。
また、遺留分減殺請求については、遺産分割について相続開始時への遡及効を定めた民法909条のような規定は存しないから、その効力が相続開始時にさかのぼるものではない(下線・編集部)。
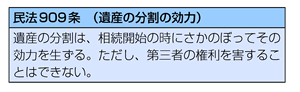 果実の帰属について
果実たる賃料債権は、賃貸物件を使用管理した結果生じるものであるから、遺産とは別個の財産というべきであって、その収取されるときにおける元物の持分に応じて単独ないし分割単独債権として確定的に帰属すると解するのが相当である。そうすると、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言により承継された当該賃貸不動産の賃料債権は、そのすべてが当該相続人の課税所得を構成し、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したことにより共有となった賃貸不動産から生じる賃料債権は、当然に分割されて共有者である当該相続人と遺留分権利者とがそれぞれの共有持分に応じて分割単独債権として取得するものであり、遺留分減殺請求のあった日以後に当該賃貸不動産から生じる賃料債権のうち遺留分を除く部分が当該相続人の課税所得を構成すると解される。
果実の帰属について
果実たる賃料債権は、賃貸物件を使用管理した結果生じるものであるから、遺産とは別個の財産というべきであって、その収取されるときにおける元物の持分に応じて単独ないし分割単独債権として確定的に帰属すると解するのが相当である。そうすると、賃貸不動産を含むすべての遺産を共同相続人の1人に相続させる旨の遺言により承継された当該賃貸不動産の賃料債権は、そのすべてが当該相続人の課税所得を構成し、遺言による相続分の指定に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したことにより共有となった賃貸不動産から生じる賃料債権は、当然に分割されて共有者である当該相続人と遺留分権利者とがそれぞれの共有持分に応じて分割単独債権として取得するものであり、遺留分減殺請求のあった日以後に当該賃貸不動産から生じる賃料債権のうち遺留分を除く部分が当該相続人の課税所得を構成すると解される。減殺請求の日の前日までは全額が請求人に帰属 上記の法令解釈に基づき、審判所は本事案について、本件遺言書が、「被相続人名義の全財産を請求人に相続させる」旨を内容とするものであることから、請求人は相続開始と同時に賃貸物件を含む被相続人の財産および債務のすべてを取得し、賃貸物件に係る賃貸人の地位も承継し、その後、遺留分権利者から減殺請求がされたことにより、請求人が受けた相続分の指定の効果は、Aらの遺留分(各6分の1相当額)を侵害する限度において直ちに失効し、請求人とAらとは、賃貸物件に対し、共有持分を取得する関係に立ったものと認定した。
そのうえで、賃料債権は、図表2のとおり単独ないし分割単独債権として確定的に請求人に帰属し、課税所得を構成すると認めるのが相当であると判断している(図表3参照)。
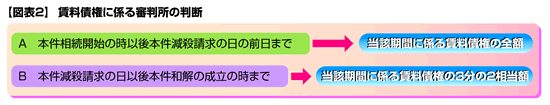
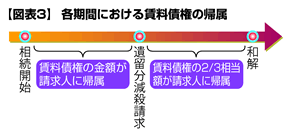 なお、審判所は、本事案における和解について、その経緯から被相続人の遺産の分割を行うことに当事者双方が合意して、賃貸物件の新たな権利関係を創設する趣旨のものであって、相続開始時にさかのぼって従前の権利関係に異動を来すものではないと解するのが相当とし、法律上遡及的な効力が生ずるものとは認められないとしている。
なお、審判所は、本事案における和解について、その経緯から被相続人の遺産の分割を行うことに当事者双方が合意して、賃貸物件の新たな権利関係を創設する趣旨のものであって、相続開始時にさかのぼって従前の権利関係に異動を来すものではないと解するのが相当とし、法律上遡及的な効力が生ずるものとは認められないとしている。column
相続税の連帯納付義務に関する裁決事例では異なる判断 国税不服審判所は、相続税の連帯納付義務に関する裁決(裁決事例集No.71平18.6.26裁決)で、民法上の遺留分制度について、「これは、遺留分を侵害する被相続人の贈与、遺贈、相続分の指定等の処分行為を減殺請求で減殺することにより、遺留分権利者が、これらの処分行為がなければ相続財産となるものの一部を受け取るものであって、遺留分減殺請求権の行使により、相続時にさかのぼって取得するものと解される。」としており、本事案とは異なる判断をしていた(下線・編集部)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















